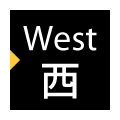安土-滋賀県
1917(大正6)年、山水絵巻の制作のために琵琶湖を巡っていた小杉未醒(放菴)は、安土城跡を訪れた際に、偶然、摠見寺第十一世住持、道規松岡範宗和尚と出会った。

安土城趾のある安土山
未醒は、松岡和尚に城跡を案内してもらい、翌日も安土の周辺を写生するために、その夜の宿泊先も紹介される。紹介された川魚料理屋「鮒幸」(当時は旅館もしていた)で食事をすませ、時間を持て余していると、再び松岡和尚が訪ねて来てくれた。そのときの様子を未醒は次のように述べている。
……やがて夕飯もすんで独り所在なく居るところへ、和尚さんまた来てくれました、昼は接待で色ある法衣であったが、夜は麻の黒衣、五十を越えた年配小柄ながら老健な禅僧の姿、その黒衣の袂からうまそうな柿の実を三つほど出して、これでお茶のみましょうと云いました、お寺の背戸に赤くなって居たものであろう。
あくる日小舟を賴んで内湖に出て、島と本土との間、茫々芦荻の中の水路を八幡まで行って見た、水路いく曲りところどころ漁村、むぐっちょが鳴いて居たり鷭が立ったり、この水郷の好風景を珍らしく、わが新発見の如くに人にも説き誇ったものです、その夜のあの、衣の袖からの柿三つが、なんとなく心に沁みて、この松岡範宗和尚との付き合いが始まる、時に関西地方への往復には立寄って寺の客となり、和尚も時に東京へ出ると、田端の私の宅を宿にする、……
小杉放庵「安土の老僧」『石』より

安土の水路
松岡範宗は、幼少時に名古屋の禅隆寺で得度し、その後、大徳寺および正眼寺で修行を積んだ僧侶であるという。千葉の円光寺、京都の竜安寺を経て妙心寺の塔頭・長興院の住職となり、1914(大正3)年、摠見寺の住職に兼任されて、翌年には専住となっている。松岡和尚は、安土城内の整備にも積極的に関わっており、1918(大正7)年に、安土保勝会が設立されると、その理事に就任する。

摠見寺の参道と仁王門
織田信長が安土築城にあたり、その菩提寺として開いた摠見寺は幕末に、本堂からの出火で三重塔や仁王門などを遺して焼失して以来、徳川家康邸の跡と伝えられる場所に仮の本堂を建てていた。

摠見寺の三重塔
そのため、古来の場所に本堂を再建することが松岡和尚の悲願であったが、摠見寺は檀家を持っていなかったため、松岡和尚は、しばしば上京し、当時、田端に住んでいた小杉放庵(未醒)の家を拠点として、織田信長のゆかりの人々に寺を再建する寄付勧進を願い歩いた。そして、放庵もまた、松岡和尚の信念に共感し、その事業の手伝いをするようになる。

摠見寺の本堂址
松岡和尚の思いに心を動かされたのは小杉放庵だけではなかった。
武藤伊八、山本勝蔵、伊庭慎吉、梅井孫三郎らといった歴代の安土村の村長や、多くの村の人々もまた、同じ思いで、摠見寺の再建に尽力したのであった。
放庵はたびたび、絵を描いては安土村の村長・伊庭慎吉に送り、寺の再建のための基金にしてもらっていたという。
結果的に、旧地に本堂を再建することはかなわなかった。
しかし、1933(昭和8)年10月15日から3日間、摠見寺にて盛大に営まれた信長公三百五十回忌にあわせ、1930(昭和5)年から1932(昭和7)年にかけて、仮本堂の大々的な改築や城跡内の石段の整備が行なわれた。

城址内の石段
松岡和尚と出会い、再建に携わってから16年の歳月を経て行なわれた、この仮本堂の改築について、小杉放庵は次のように述べている。
……年七十に近き老和尚が、二十年宿願成就の再建だから、たとえ結構の荘嚴、天正の昔の十が一に及ばずとも、嬉しかるべきわけ、……
小杉放庵「安土山日記」より
……めんめん十余年の助力積もって、ようやくにして今の伽監ができ上った、それは天下取りの右大臣信長公創建の規模には及ばずとも、ともかくにも名刹安土山摠見寺の復興、古稀七十に及んだ老僧、ここに念願かなって大満悦であった事です。
小杉放庵「安土の老僧」『石』より
松岡和尚と放庵にとっては、本質的な再建に勝るとも劣らない、心から喜ばしい出来事だったのである。
仮本堂の改築が成った1933(昭和8)年の4月中旬、34枚の襖絵を描く約束をしていた小杉放庵は摠見寺を訪れた。
襖絵の制作は、閑寂の中、改築された本堂で行なわれた。このときには、竹の林の中にぽっかりと白い月が浮かび上がる《竹林》と、松林にゆっくりと朝日が昇る《日の出》の2点が制作されたようである。それぞれ、襖4枚一組の画面で、いずれも渇墨による筆の動きが冴え渡り、余白の効果を十分に生かして、静寂な世界が作り上げられている。
また、この年の第11回春陽会展に出品されて好評を博した《石上》も、4枚一組の襖絵として仮本堂に納められた。広大な石の上に初老の男性が一人腰を下ろして佇んでいる情景を描いた作品である。
このときの安土滞在は、気心の知れた岸浪百草居や高倉観崖が合流し、楽しく充実したものとなった。しかし、一方で、死去したばかりの長年の親友・森田恒友のことが心から離れず、竹の絵を布施代わりに、松岡和尚に読経してもらったという。
小杉放菴は、その後も関西方面への旅行の折には、しばしば、安土に立ち寄っている。そして、二人の交遊は生涯変わらず、30年以上に渡り続くことになった。
1953(昭和28)年4月、享年84で松岡和尚が入寂すると、ちょうど、滞在中の東京で訃報を聞いた小杉放菴(当時は、主に新潟県の新赤倉の山荘で暮らしていた)は、すぐさま安土に駆けつけて葬儀に参列した。

安土城の天守閣址
……今又ここで三十年の親交を失う、老いの心傷みやすく、安土の松咲く花を見ても胸に迫って寂寞を覚えます。摠見寺再興の功によって再住妙心大和尚の僧位を受けて居たから、本山妙心寺の管長さんが葬儀の導師をつとめてくれました、葬儀終って暮れるまでと思って、ひとり古城の山に登る、天守閣の址から少し下って八角臺、夕かすみの湖上に比良の連峯竹生島たけ島伊吹山おぼろに出没する、この松の下に筵を布いてお酒のんだのは、何年前になるか、さよう三年目になる、四國へ行くとて立寄った、久しぶりでよう来てくれた事だと、あの剛毅な和尚が涙を落とした、年をとると気弱くなるものです、あくる日東京から四國同行の岸浪百草居、お弟子の内海かず子を連れて落ち合った、湖山の春景は八角臺の眺めが一番だからと、こゝで和尚と伊庭さんも一坐で昼の盃をあげた、竹生島の小謡など興に入っておもしろかったのだが、それがどうです、三年後の今日老放只ひとり、八角臺の松の根に腰掛けて居る、去年聖路加病院で百草居亡くなり、その少し前にかず子信州の旅先で亡くなり、こんどは和尚、みんなどこかへ行ってしまった。(二十八年)
小杉放庵「安土の老僧」『石』より

八角臺の址
放菴の妻ハルも、1938(昭和13)年に三男の三郎を亡くしてからは松岡和尚に帰依し、神道であった小杉家は、いつのまにか臨済宗を宗旨にしていたという。和尚の入寂は、放菴だけでなく、周囲の人々にも深い悲しみを与えたのである。
調査:1999年3月29日[小杉放菴記念日光美術館]