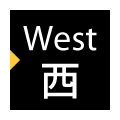茅野−長野県
1935(昭和10)年の6月3日から7日にかけて、小杉放菴は中川一政や岸浪百草居らと長野県を旅し、蓼科山麓を訪れた。
そのときのことを、中川一政は自らの著書で下記のように述べている。
……中央線茅野駅から低い小泉山、大泉山を眺めて放庵などと蓼科山麓へ行った。第一銀行の人が一つは山菜を食べさせる為め、一つは銀行のヒュッテの上の八子ヶ峰に放庵石といつか銀行の人々が言ひならわした岩があるから見せると言ふのである。……(中略)……放庵は放庵石にいちはやく辿りついて上った。高あぐらして雲でも呼ぶかと思うと、懐ころからそそくさとスケッチブックを取出して眼前に立ちはだかった蓼科を描き出した。……
中川一政『旅窓読本』より

「放庵石」と思われる石
小杉放菴もまた、同じときのことを、日記にのこしている。
三日
朝十時発茅野に向ふ、長野でのりかへ
塩尻でのりかへ 三時すぎ茅の着 先着
の酒井氏百草居永福、共に自動車に
のる 茅野の町をすぎ北東向し 瀧の湯
こさいの湯などをすぐ 親湯にて自動車
を捨て だら/\上り小一里、右に八つ岳近
く 蓼科の麓に 第一銀行の山荘あり
すべて西洋風の建築也 蒼茫として雲
来る 地は四千何百尺の由……(後略)
小杉放菴の『日記』(昭和10年6月3日の項)より

小杉放菴らが訪れた頃の第一銀行(現・みずほ銀行)山荘の絵葉書
五日
晴 ヤシ八子が峯に登る 大石峠より左の草
山也 石多し 銀行の人々其中の石を放庵
石と名づけ居る故 一度行き見よと誘はれ
て此度の遊となりたる也 頂上の大岩
それなるらし 八ガ岳の連峯 甲斐駒
など 大きな眺めなり 岩茸などとりつゝ九時
山荘にかへる、 岩茸のすの物にて一盃し
十時出立 途中の高原 小梨の多き
未だかくの如きを見ず、親湯にてひるめし、
十二時すぎ自動車 上川村にて他の三人写生
に行くとて別る、一時すぎ茅の発、七時
近く帰荘、七里の年寄達は英一と朝
の汽車にて東京に立ちたり
小杉放菴の『日記』(昭和10年6月5日の項)より

蓼科山を背景とした、「放庵石」と思われる石
ちょうど、この時期の日本の美術界は、帝展の松田改組により、大きな混乱のただ中にあった。放菴もこののち、その渦中に巻き込まれることになる。
調査:2009年7月4日[小杉放菴研究舎]