二〇二〇年

一月五日(日)祝祭の二日間



昨日は能楽初め、今日は演奏会初め。前者は中国の皇帝の徳を讃え、後者はキリスト教の神の愛を讃えるもの。どちらも外国のものなのに、すんなり受けいれているあたりが日本らしい。
能楽は、国立能楽堂の定例公演。
・能『西王母(せいおうぼ)』武田志房(観世流)
・狂言『財宝(さいほう)』山本東次郎(大蔵流)
二〇一六年から能楽を見始めたが、国立能楽堂の新年最初の公演に行くのは初めて。ロビーには鏡餅、能舞台には注連縄がはられて、清々しい。
通常の国立能楽堂の定例公演は、狂言が先で能が後だが、新年初の公演ということもあってか、今回は逆。『西王母』のアイも狂言と同じ山本東次郎で、しかも最初に登場、周の穆王(ぼくおう)の聖徳を讃えるので、全体に東次郎中心という感じで嬉しい。
聖王の御世を讃え、神仙の西王母が、三千年に一度しか花と実を結ばないという桃を捧げる話。続く『財宝』は、財宝という名の祖父(東次郎)に、孫三人が名前をつけてもらって御祝儀ももらい、酒宴になる狂言。
どちらも明朗でめでたい内容で、厳かな能から賑やかな狂言へと変わる流れが正月にあっている。
この日の楽しみはもう一つあって、四月からの新年度の主催公演予定表が手に入ること。中身は例年同様にもりだくさんだが、予算削減なのか、用紙が薄くなったのはさびしい。

続いて今日はミューザ川崎で、東京ユヴェントス・フィルハーモニー。指揮はもちろん坂入健司郎さん。
〈ベートーヴェン・ツィクルス最終回〜ベートーヴェン生誕250周年〉
・ブルックナー:テ・デウム
・ベートーヴェン:交響曲第九番《合唱》
合唱:東京ユヴェントス・フィルハーモニー合唱団
独唱:中江早希、谷地畝晶子、宮里直樹、大沼徹
演奏:東京ユヴェントス・フィルハーモニー
指揮:坂入健司郎
年末の風物詩の「第九」を、あえて正月に。しかしこうして聴いてみると、祝祭的な気分はむしろ正月のほうが出る。
ブルックナーのテ・デウムを前にもってくるというアイディアも秀逸。編成が似ているから合唱と独唱を無駄なく使えるという興行的な利点だけでなく、どちらも神への讃歌でありながら、ラテン語とドイツ語、教会音楽と世俗音楽、聖と俗の対照になる。
プログラムでテ・デウムの日本語訳に公教会祈祷文、シラーに許光俊さん訳の「おーい、ダチ公よ」(『クラシックを聴け!』掲載)を用いていたのは、聖俗の差を際だたせるためだろう。
そして、両方でケルビム(ケルブ)の一語が印象的に響くのも面白い。神の御稜威を際だたせる天使。
この対照が、マーラーの《千人の交響曲》を想わせる。第一部がラテン語の聖歌で、第二部がドイツ語による文学作品(シラーとゲーテ)。ブルックナーもマーラーも、「第九」の影響下に交響曲をつくり続け、その延長上にあろうとしたのだということを、あらためて実感。
演奏も、後期ロマン派風に濃密なブルックナー、古典派の澄明なベートーヴェンと、響きとリズムの違いが明確。後者はリズムに適切な呼吸感があるので、骨格が崩れない。音楽の鮮度が高い。どの楽章にも、ふっと悲壮な暗いパッションが顔を見せる箇所があるのが素敵。オーボエとホルンがソロをパシッと決めて、要所を締める。壮大に響いて、終楽章最後の豪快な加速も痛快。
一月七日(火)大野和士さんに聞く
二〇二〇年最初の外出仕事は、大野和士さんのインタビュー。年末に行なった山田和樹さんと同じく、音楽之友社のムック『世界の名門オーケストラ』のためのもの。
一月八日(水)三たび三谷幸喜
二〇二二年のNHKの大河発表。三谷幸喜脚本で、北条義時! これは面白そう。主演は小栗旬だが、『鎌倉殿の13人』という題なので群像劇らしく、いっそう楽しみ。大河は『草燃える』『太平記』『時宗』と、どういうわけか鎌倉の北条執権政府を描くのがやたらに上手な伝統がある。三谷テイストでその復活に大期待。
問題は、二〇二二年の日本と世界がはたしてどうなっているのか、見当もつかないことだが…。

夜はトッパンホールのニューイヤー・コンサート。
・グラウン:ヴァイオリン協奏曲イ長調(独奏:ダニエル・ゼペック)
・ハイドン:チェロ協奏曲第一番(独奏:ペーター・ブルンズ)
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集《四季》(独奏:山根一仁)
オーケストラは独奏者以外に十八人からなる、トッパンホールチェンバー・オーケストラ。
一曲目のグラウンでソロをとったゼペックが、二曲目以降ではコンサートマスター。おとなしかった弦楽が、ゼペックがコンサートマスターになったとたんにダイナミックなサウンドに一変したのは面白かった。
《四季》ではブルンズもチェロ・パートに参加。パワフルな演奏。もともとモダン楽器で人気を得た曲だけに、ピリオド楽器よりも合う部分があるのかも、などと考える。三月にビオンディ&エウローパ・ガランテが王子ホールで演奏するので、それを聴いてから、あらためて考えてみたい。
一月十二日(日)ミニとマキシ
昨日と今日と、二日続けてマーラーの交響曲。ただし演奏者は十五人対百六十人、客席は三百十五体三千八百と、強烈な差。しかしけっして多勢に無勢、隆車に向う蟷螂の斧とはならないところが、音楽というものの面白さ。


十一日 王子ホール
篠崎史紀&MAROカンパニー
・J・シュトラウスⅡ:
南国のバラ(シェーンベルク編曲)
宝石ワルツ(ウェーベルン編曲)
酒、女、歌(ベルク編曲)
・マーラー:交響曲第四番(ジモン編曲)
十二日 NHKホール
クリストフ・エッシェンバッハ(指揮)NHK交響楽団、マリソル・モンタルヴォ(ソプラノ)、 藤村実穂子(メゾソプラノ)、新国立劇場合唱団
・マーラー:交響曲第二番《復活》
どちらもN響のコンマスがリードしているのが面白いところ。
MAROカンパニーは、ヴァイオリンの﨑谷直人、オーボエの古部賢一、ホルンの福川伸陽など、強力な十五人編成。
新ウィーン楽派三人による編曲は、その面白さと複雑さが、実演だといっそうよくわかる。この編曲譜を売って活動資金にしようとしていただけあって、ありきたりのものではなく、それぞれが個性を発揮した、とても凝った編曲。
そしてマーラーの四番の、新しいクラウス・ジモン編曲版をようやくナマで聴くことができた。ホルンも入って、シュタイン版より響きが充実。
指揮者なしでコンマスの篠崎史紀がリードする。互いを聴き合い、息を合せて演奏しているのがよくわかる、客席から一人一人の顔も音もよくわかる音楽。指揮者がいないので思いきった動きなどはないが、音楽が呼吸して、緩急強弱と音色を自然に変化させながら、聴き手にも呼吸させる。その心地よさ。
そこがまったく逆だったのが、エッシェンバッハ指揮の《復活》。いかにもピアニスト出身らしい、ただピアノを大きくしたような、息をしない音楽。いや、息と無関係な音楽。それなのに強引に動くので、楽員は合わせるのに一苦労。さしものN響が乱れる場面もいくつか。
呼吸感がないということは「タメと開放」を感じにくい、不自然な、流れの悪い音楽になる。終楽章のヤマももう一つ決まらない。ソプラノ独唱のモンタルヴォは代役だからなのか、ギクシャクと動く指揮に律儀に合せようとして、ものすごく苦労していた。
コーダのオルガンがオケよりもずいぶん早く、ぶった切るように消えたが、聞いた話では、前日は逆にこぼれてしまったらしい。こういうのも、息と指揮が無関係だから、自然なタイミングがつかめないのだと思う。それでも新国立劇場合唱団は、ものすごく立派だった。
終演後はTBS、トーキョー・ブラボー・ソサエティが大活躍していたので、三千人くらいの方は満足されたはず。自分は、いま自分が聴きたいものはどんな音楽か、あらためて実感する、よい機会になった。
十七日にも紀尾井ホール室内管とウィーン・フィルのメンバーによる、シェーンベルク編曲版のワルツと《大地の歌》があるので、これはまたどうなるのか楽しみ。こちらは十四+歌手二人。
ほんとうは、十一日のマロ・カンパニーの前に、一橋大学兼松講堂で行なわれた、国立マーラー楽友協会によるマーラーの九番を聴きたかった。
そうすれば「九~四~二~大地」の四曲を、フルオケと室内楽版で交互に聴く形にできたのだが、しかし国立~銀座の移動時間を考えると、全曲聴くと間にあわない。
ロンド・ブルレスケまで聴いたところで飛び出す手も考えたが、それはなんというか、ブルックナーの九番をスケルツォまで聴いて帰るみたいな感じなので、あきらめた。
一月十五日(水) 偉大なる死物


十四時からオーチャードホールで日本オペラ協会の《紅天女》をみて、十九時からサントリーホールで、下野竜也指揮読売日本交響楽団。
《紅天女》はたしかに長かったが、終幕の梅の樹は美しかったし、最後の音楽はキャッチーでなかなか感動的だった。歌手も指揮者も真摯な熱演だった。
ただ自分が引っかかったのは、主人公の仏師が完成させたはずの天女像が最後までまったく出てこないのは、なぜなのだろうということだった。
樹齢千年、さらにこれからも生き続けたろう、偉大な梅の樹を切り倒して材料とし、愛する女性の生命を奪ってまで完成させた天女像。自然を破壊し、犠牲を出してまで完成させたことで、南北朝の騒乱を終息させたという天女像。
さまざまなものの生命を犠牲にして、像につくりかえ、固定すること。生命を奪うことになるが、同時に、有限のものをはるかな後世にまで永く残すこととなる。それは、あえていえば「芸術」というものの本質でもあるだろう。
生きて動いているものを、動かぬものにする。動かないのに、まるで生きて動いているかのようにみえる。
「生物を再現しうる死物」。
彫刻も絵も映画も、そしてマンガも。音楽を記号化した楽譜も、物語や芝居を文字化した書物もそうだろう。それが、有限の生命しかもたぬ人が生み出し、遺していく、芸術というもの。
その芸術というものが、この物語では偉大だが、同時に犠牲を伴うゆえに、罪深きものとなっている。
それはこの物語の主要テーマである、さまざまな二極対立、南朝と北朝、神と仏、精霊と人間、自然と人間、男と女、生と死、陰と陽、清と穢、その他もろもろの相反と矛盾を象徴している。
どちらも正しく、また正しくない。物語に出てくる楠木正儀は実在の人物で、「正しく死ぬ」ことのほうがよほど簡単な時代――父も兄もまさにそうして討死した――に、絶対矛盾を抱えたまま生き抜くことがどれほど難しいかを、体現したような生涯を送った人だった。
その矛盾と悲しみをすべて呑みこみ、後世に残るのが、天女像であるはず。
それをここで視覚化することの難しさは容易に想像がつくが、それでも挑んでほしかったと思った。「偉大なる死物」たる芸術の姿が眼前にあればこそ、ラストシーンは「固定されたもの」が喚起する幻であること、そして「いまここに生きて在ることの尊さ」を感じられたように思うから。
夜の演奏会のことは日経新聞の評に書くので省略するが、「偉大なる死物」の凄さに震撼させられる二時間だった。
一月十六日(木)横須賀へ
「音楽の友」の記事のためによこすか芸術劇場へいき、副館長さんに新シーズンの予定などをうかがう。
ここには二〇一七年三月十二日にも来たことがある。小ホールの「ベイサイド・ポケット」で《蝶々夫人》の短縮版をみた(可変日記に訪問記を書いた)。
 画像は、横須賀芸術劇場の公式サイトから
画像は、横須賀芸術劇場の公式サイトから大ホールの舞台にも入れてもらう。写真は自分が撮ったのではなくて公式サイトからだが、ここに見えるとおり、歌劇場式の馬蹄形の客席が美しいホール。客席千八百と規模も手頃。
新シーズンの目玉はなんといっても、十月十八日(日)に行われる、能の『隅田川』とブリテンのオペラ《カーリューリバー》の二本立て。
この二本が続けて観られるだけでも、私などには大御馳走だが、さらに出演者も素晴らしい。観世喜正、彌勒忠史、鈴木准に鈴木優人など、ワクワクするメンツである。
・能『隅田川』(演出:観世喜正)
シテ 観世喜正
子方 観世和歌
ワキ 森常好
ワキツレ 舘田善博
・オペラ《カーリュー・リバー》(演出:彌勒忠史)
狂女(テノール) 鈴木 准
渡し守(バリトン) 与那城 敬
修道院長(バス) 加藤宏隆
旅人(バリトン) 坂下忠弘
カーリューリバー・オーケストラ
鈴木優人(指揮、オルガン)
さて、このよこすか芸術劇場は一九九四年開場、その前は米海軍のEMクラブという休憩施設があり、さらにその前の一九四五年までは、帝国海軍の下士官兵集会所、すなわち水兵が休日に上陸したさいの宿泊施設があった。一九三八年完成の建物を、米軍が接収して使い続けていたそうだ。芸術劇場の裏側のメルキュールホテル横須賀(写真の右側の高層ビル)は、この集会所の塔のデザインを継承しているのだそう。

そして、よこすか芸術劇場の海側にあるのがヴェルニー公園。ここの一隅には帝国海軍の慰霊碑が集められている場所がある。戦艦長門や山城の碑があるのだが、そのなかでひときわ大きいのが、高尾型巡洋艦の艦橋を模した石碑。

しかしこれは不思議なことに、下部の碑文などがすべて剥ぎ取られていて、なんのためのものなのかよくわからない。正面に「國威顕彰」という文字だけが彫られている。
三年前にきたときにも不可解に思ったもの。今回もやはり気になった。帰宅後ネットで調べると、「東京湾要塞 三浦半島・房総半島戦争遺跡探訪」というサイト内に、情報が出ていた。
http://tokyowanyosai.com/sub/ibutu/sekihi/kinen-10.html
「昭和12年5月27日の海軍記念日に除幕されたもので、国際連盟脱退や軍縮条約廃棄という当時の社会情勢のなかで、海軍の偉業と意気を具象化したとのことである。塔の上部には羽を広げた金鵄が取り付けられていた」
敗戦により、「八紘一宇」などの碑板を剥ぎ取られ、しかし壊されはせずに、ここに置かれている。戦艦三笠、國威顕彰碑、よこすか芸術劇場、そして、港の大半を占めるアメリカ第七艦隊の基地。
日本の近現代史を、肌で感じることのできる場所。
一月十七日(金)再びミニ・マーラー

紀尾井ホール主催の演奏会。恒例となっている、新ウィーン楽派による室内アンサンブル編曲版をあつめたもの。
・ヨハン・シュトラウスⅡ:
入江のワルツ(シェーンベルク編曲)
酒、女、歌(ベルク編曲)
皇帝円舞曲(シェーンベルク編曲)
・マーラー(シェーンベルク&リーン編曲):大地の歌(メゾソプラノ:ミヒャエラ・ゼーリンガー、テノール:アダム・フランスン)
紀尾井ホール室内管弦楽団のメンバーに、首席指揮者のライナー・ホーネックなどウィーン・フィル四人を加えた、総勢十四人のアンサンブル。
前半のワルツは、さすがにウィーン風の艶麗かつ軽妙な味が出る。マーラーの《大地の歌》では、この作品の問題点である、第六楽章前半までの歌手と管弦楽の衝突――編成を小さくしても、基本はいじらない編曲なので、管弦楽をわざとぶつけていることが、いっそう明確になる――を、ホーネックは巧みにコントロールして、声を完全にはかき消さないようにしていた。このあたりは、歌劇場での豊かな経験のなせるわざだろうか。
一月二十三日(木)ヤーノシュカ

新宿文化センターで、ヤーノシュカ・アンサンブルのコンサート。
プログラムの解説を書いた。クラシックの素養を基礎に、エンターテイナーとして楽しませる四人組。
一月二十五日(土)歴史悲劇と私小説
サントリーホールで東京交響楽団の演奏会。指揮は飯森範親。
・ラッヘンマン:マルシェ・ファタール
・アイネム:「ダントンの死」管弦楽組曲(日本初演)
・リーム:道、リュシール(ソプラノ:角田祐子)(日本初演)
・R・シュトラウス:家庭交響曲
恐怖政治のもたらす狂気と惨劇の前半に対置される、私小説のような後半。
一月二十九日(水)奇妙な体験
日経新聞夕刊に、十五日にサントリーホールで行なわれた下野竜也指揮読売日本交響楽団の演奏会についての拙評が掲載された。
・ショスタコーヴィチ:エレジー
・ジョン・アダムズ:サクソフォン協奏曲(独奏:上野耕平)
・フェルドマン:オン・タイム・アンド・ザ・インストゥルメンタル・ファクター(日本初演)
・グバイドゥーリナ:ペスト流行時の酒宴(日本初演)
これはほんとうにいい演奏会だったので、空席があったのが残念でならなかった。とりわけ最後のグバイドゥーリナの「ペスト流行時の酒宴」。人の焦燥と狂騒が濃密な音響となって空間を満たしていく「死の舞踏的音楽」の凄さは、ナマでこそ十全に体験できるものだから。
こういう「生きた芸術」をもっと多くの人に聴いてもらえるように、体験してもらえるように、興味を持ってもらえるように、微力を承知でつとめるのが、私のような仕事の人間の役割だと、痛感した次第。
それはともかくとして、この作品への日経新聞の拙評は十五日に聴いて、二十三日の〆切までに書き、二十九日に掲載となったのだが、掲載までのわずか二週間のうちに、書いたことの意味合いと切実さがまるで変ってしまったことに、今になって気がつく。
「現代の地球と人類の情況そのもののような強烈な音楽」
じつはこれは、聴いたとき、書いたときには、自然破壊や戦争、政治的弾圧など、あらゆる危機の比喩、代表的な例として「ペスト」を一九六九年当時の作曲家が選んだのだろうと思い、そのつもりで「情況そのもの」とした。
だが、本日の夕刊を読んでくださった方の中には、これを「コロナウイルスの情況」のつもりで山崎が書いていると、思われた方もおられるかも知れない。いや、むしろそういう方のほうが多いのではないだろうか。
あれよあれよという間に、自らの言葉に思いもよらぬ別の意味合いと切実さが重なっていく、奇妙な体験。
それは、一種不可思議なやりがいを、自分に与えてもくれるのだが…。
二月一日(土)花の章とロット
東京芸術劇場で、読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹。

・マーラー:花の章
・ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲(独奏:ネマニャ・ラドゥロヴィチ)
・マーラー:交響曲第一番《巨人》
交響詩《巨人》が交響曲となるときに削除された《花の章》を、元の第二楽章の位置に戻すのではなく、あえて切り離して独立させ、初めに単独で演奏する。
このアイディアは納得がいくもの。現行版はやはり四楽章できちんとまとまっていて、編成の異なるこの楽章は異質なのだ。そしてこうすると、《花の章》冒頭のトランペット・ソロが、あのロットの交響曲のそれとよく似ていて、これまたロットからの影響だということが、よくわかる。
ハチャトゥリアンは、ネマニャの奔放なヴァイオリンがぴったりだけに快演。休憩後の《巨人》は、こってりと粘っこい熱演。
二月三日(月)ロトのダフクロ!
東京文化会館で東京都交響楽団の演奏会。指揮はフランソワ=グザヴィエ・ロト。

・ラモー:オペラ=バレ《優雅なインドの国々》組曲
・ルベル:バレエ音楽《四大元素》
・ラヴェル:バレエ音楽《ダフニスとクロエ》全曲(合唱:栗友会合唱団)
ロト本領発揮の快演。評を日経新聞に書く。
二月五日(水)神剣草薙
午後一時から国立能楽堂の定例公演。

・狂言『鶯(うぐいす)』野村萬斎(和泉流)
・能『草薙(くさなぎ)』藤井雅之(宝生流)
毎年恒例の企画《月間特集 近代絵画と能》の一つ。『草薙』は、東国征伐に出た日本武尊が駿河で火攻めにあったとき、天叢雲剣を振るって草を薙ぎ、窮地を脱したという説話を能にしたもの。五流のなかでも宝生流にしかないという、珍しい能。
終演後は紀尾井ホールに行き、某誌のためにトレヴァー・ピノックにインタヴュー。
二月六日(木)アークヒルズ界隈にて
六本木のANAインターコンチネンタルホテルで、午後四時から「音楽の友」のために札響の指揮者バーメルトにインタヴュー。
終了後に腹ごしらえをしてから隣のサントリーホールに行き、NHK交響楽団の演奏会。指揮はパーヴォ・ヤルヴィ。
・プロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲 第一番(独奏:レティシア・モレノ)
・ラフマニノフ:交響曲第二番
評を「モーストリー・クラシック」に書く。
二月七日(金)今日もサントリーホール
サントリーホールにて札幌交響楽団の東京公演。指揮はバーメルト。

・シューベルト(ウェーベルン編曲):ドイツ舞曲
・マーラー:亡き子をしのぶ歌(バリトン:ディートリヒ・ヘンシェル)
ベートーヴェン:交響曲第七番
昨日のインタヴューと合わせて、印象を「音楽の友」に書く。
二月九日(日)ピノックとヤマカズ
紀尾井ホールにて紀尾井ホール室内管弦楽団の定期演奏会。指揮はピノック。

・モーツァルト:交響曲第四十番
・モーツァルト:アヴェ・ヴェルム・コルプス
・モーツァルト:レクイエム
レクイエムには、望月万里亜(ソプラノ)、青木洋也(アルト)、中嶋克彦(テノール)、山本悠尋(バス)、紀尾井ホール室内合唱団も加わる。
清新で力強い音楽。終演後、関口台のキングレコードのスタジオに行き、山田和樹さんにインタヴュー。
五月の八日に東京都交響楽団と演奏する、三善晃の「反戦三部作」について話してもらう。

二月十一日(火)ポゴレリッチとヤマカズ
みなとみらいホールで、読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹。

・グリーグ:二つの悲しき旋律
・シューマン:ピアノ協奏曲(独奏:イーヴォ・ポゴレリッチ)
・ドヴォルジャーク:交響曲第七番
ポゴレリッチの緩急強弱自在のピアノとの共演を楽しむヤマカズ。一昨日のインタヴューはそのリハの後だったので、ネマニャに続けてポゴレリッチなんて、合わせるのが大変じゃないですかときいてみたら、「いやあ、面白いですよ~」と笑っていた。なるほどと納得(笑)。
アンコールは、曲の前にスピーチ。神奈川県立の希望が丘高校に入って、初めてデートというものをしたのが、みなとみらいだったという。そしてその頃に知った思い出の曲ということで、アザラシヴィリの無言歌を、慈しむように演奏。
二月十三日(木)『井筒』の陽炎

梅の花はいまがさかり。
能をはしごする。シテ方のホープと重鎮を一日に見られるので、楽しみにしていた。まず午後一時から、観世能楽堂で若手による観世会荒磯能。

・能『弓八幡』関根祥丸
・狂言『鬼の継子』野村太一郎
『弓八幡』は世阿弥作で、足利義持の将軍宣下を寿ぐためのものといわれる。
石清水八幡に奉納する弓を袋から出さないのは、治国平天下の象徴だからだというような詞があるあたり、いかにも戦乱が終息した新将軍の代を寿ぐ内容。
凛とした祥丸の舞と謡いは今日も見事だった。この人の身体の動きの線と円の滑らかさ、ピンと張った集中力の強さは傑出している。
続いて六時半から、国立能楽堂の定例公演。

・狂言『蟹山伏(かにやまぶし)』大藏基誠(大蔵流)
・能『井筒(いづつ)』豊嶋彌左衞門(金剛流)
これも《月間特集 近代絵画と能》の一つ。八十歳の金剛流の重鎮、豊嶋彌左衞門(前名は三千春で、昨年家名を襲名した)は、二〇一七年九月にここで『楊貴妃』をみて素晴らしかった。終盤、玄宗と幽明の境を異にして、死者の国に留まる悲しさが、抑制された動きからひしひしと伝わってきた。
それにしても世阿弥作の『井筒』は名作とされながら、ハードルの高い、近づきがたいものだと思う。約二時間のとても長い能なのに、動きはほとんどなく、シテとワキが前半に坦々と対話するだけで、途中にはドラマの起伏がまったくない。自分がナマでみるのはこれが三回目だと思うが、毎回、どうにかならないのだろうかと思うくらいに長く感じる。
国立能楽堂の主催公演にしては珍しいことに、演能中に帰っていく客が何人かいたのも、そのせいだろう。
おそらくは能をあまり知らない人が、ひとつ見てみようか、『井筒』は人気が高い作品らしいから、これに行ってみよう、という感じで来たのではないかと、勝手に想像する。しかし残念ながら『井筒』は、初心者お断りみたいな難しい能なのである。途中で帰った人はこれに懲りて、能は長くて退屈だからご勘弁、ということになるのだろう。
昭和後半の能楽研究の泰斗、表章(おもてあきら)は、『井筒』の評価が高まったのは、戦後に観世寿夫が登場して、「幽玄」がありがたがられるようになってからだと、どこかで述べていた。
自分は最近になって能に興味を持っただけだから、寿夫の実演を見ることはできなかった(映像は残っているが)。想像するに、静のなかに動が、動のなかに静がある、異常な緊張感で初心者すら惹きこむほどの芸だったのだろう。それなら『井筒』でも、間断するところなく集中させることができたかもしれないが、そんな天才はやたらにはいない。
豊嶋彌左衞門のような名手の芸を前にしても、私のような素人だと、その長さをもてあましてしまうのだ。
しかしそれでも、最後は見事なものだった。女の霊が井戸をのぞき込み、底の水に恋しい男の姿を見る場面で、我々の視界にもゆらゆらと陽炎が立って、目の前にいるのが男なのか女なのか、そのどちらでもあるような錯覚を起こさせた芸は、やはりすごいものだった。
ここで世阿弥は、『松風』とよく似た仕掛けをする。女の霊は、愛する男の装束をつけ、頭の形も真似ている。そのため、彼女が男の幻を目にする瞬間、彼女を見つめる我々も、男の姿を見ることになるのだ。
狂女の霊が目にしている幻覚を我々も共有させられる、その戦慄。
男そのものでもない。面は、顔はあくまで女なのだ。女でも男でもある人が、そこに陽炎のようにいる。その瞬間、見ている女と見られている男、二つのこの世ならぬ顔が渾然となって、主客の境目がなくなる。その揺らぎのなかに取り込まれ、霊の見ているものと、自分が見ているものが混じりあう。視点の複合。複眼の見、とでもいうか。
そして、原作の伊勢物語から引用した「筒井筒、井筒にかけし、まろがたけ」というこの部分の詞と節が、まことに美しく印象的で、鮮やかに浮かびあがる。
男と女、見る者と見られる者、外から見ている客、すべての輪郭があやふやになり、境界が消える、一瞬の陽炎。
その陽炎が、今夜も現出した。こういう瞬間のために、自分は能を見続けている。しかし『井筒』でそれに出会うためには、動きのない二時間が必要になる。初めての人には奨めにくいのに、名作。このあたりが能の難しさか。
二月十六日(日)室内オペラの魅力
王子ホールで、モーツァルト・シンガーズ・ジャパンによるモーツァルトの歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》全曲。

フィオルディリージ:針生美智子(ソプラノ)
ドラベッラ:小林由佳(メゾソプラノ)
グリエルモ:宮本益光(バリトン)
フェランド:望月哲也(テノール)
デスピーナ:鵜木絵里(ソプラノ)
アルフォンソ:黒田博(バリトン)
山口佳代(ピアノ)
ピアノ伴奏による小ホールでの上演、非常に楽しく、そしてこの歌劇の傑作ぶりをあらためて堪能した。
オペラにおけるモーツァルトのオーケストレーションの妙というのは、まさしく天才的としかいいようのないものだけれども、今日は山口のピアノの緩急強弱の変化とタッチのやわらかさが絶妙で、うまくそれを暗示していく。
この作品では、息づくように線を描く響きが甘美であるだけに、フルサイズだとそれにのめり込んでしまい、間延びしていく危険があるのだが、ピアノの響きではそうはならず、快速にキビキビと進行して、飽きさせない。そして、声と声の対応や絡みが明確に聞きとれる。歌手も無理をせずに歌える。
モーツァルトの真骨頂はやはりオペラにあると、つくづく思わせてくれた。
室内楽ホールでのピアノ伴奏によるモーツァルト歌劇は、面白い。モーツァルト・シンガーズ・ジャパンの来年の王子ホールでの登場もいまから楽しみだが、三月には第一生命ホールで、林美智子のドンナ・エルヴィーラを中心とする《ドン・ジョヴァンニ》がある。重唱のみのダイジェスト版というが、こちらも工夫して楽しませてくれそう。
仰々しい壮大さもオペラの魅力だが、逆に、モーツァルトやロッシーニ、ドニゼッティの喜劇、オペレッタなど、親密さで楽しむことも可能な作品がある。
日本語訳詞でやることも、けっして時代錯誤とは思わない。もちろんその場合は、泥臭さと粋の、きわどいバランス感覚が必要になるだろうが。
二月十八日(火)フォル・ジュルネ

東京国際フォーラムで、「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2020」の発表記者会見。テーマは第一回以来のベートーヴェン。
ホールCを使い、ステージにオーケストラ状に取材者が座り、指揮台の位置の会見者を見るという形式。
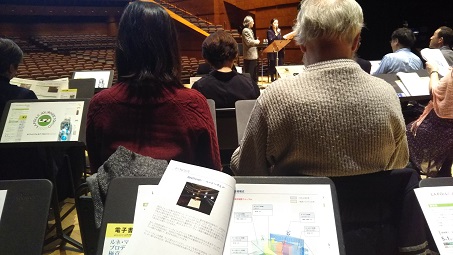
質疑応答では、コロナウイルス対策をとうするかという問いが出た。施設の消毒につとめるとのことだった。
終了後、神楽坂の音楽之友社に行き、同社ホールで「音楽の友」誌の特集「ホール主催事業を考える」座談会に参加。
二月二十二日(土)暗い影
昼から音楽之友社に行き、レコード芸術四月号の特集「21世紀のベスト・ディスク100」のための座談会に参加。

その後サントリーホールに行き、アンネ=ゾフィー・ムターのベートーヴェン生誕二百五十周年記念の演奏会シリーズの二日目、室内楽を聴く。
演奏を終えた四人が肩を抱きあう。見慣れた光景なのに、新型コロナウイルス感染のリスクが叫ばれはじめているだけに、その瞬間、会場の空気が一瞬凍り、暗い影がよぎったように思った。
評を日経新聞に書く。
二月二十三日(日)チームの可能性

ハクジュホールにて、カンマーオーケストラメロディアの演奏会。
このアマチュアの室内管弦楽団は、オーボエ奏者の町田秀樹さんが二〇一五年から主宰しているもの。町田さんは慶応の経済学部を出て銀行勤めをしたあと、二〇〇〇年にドイツに渡り、ミュンヘンのリヒャルト・シュトラウス音楽院でフランソワ・ルルーに学び、現在はミュンヘンを拠点に、プロとして活躍されている。ドイツの室内オーケストラのタッシェンフィルハーモニーの一員で、私がそのCDを紹介したことから、フェイスブックで連絡をくださり、今回聴かせていただくことになった。
・モーツァルト:セレナーデ第十番《グラン・パルティータ》第一楽章
・リヒャルト・シュトラウス:十三管楽器のためのセレナーデ
・ブラームス:交響曲第一番
メンバーには、慶応のワグネルやワセオケのメンバーも含まれているそうだ。現代日本のアマオケの演奏水準の高さを反映して、しっかりとした手応えのある演奏。演奏前に町田さんの話がある。これら三曲に共通して用いられている音型は、ワーグナーのマイスタージンガーなどにも登場する、ドイツ音楽の決まり文句のようなものだという。実際の音として聴かせてもらって、さらに納得。
町田さんはオーボエを吹きながら指揮をする。通常の指揮者の位置に楽員と向かいあう形で立つのではなく、半円形の横隊のなかでリードしているのが新鮮。
後半のブラームスでは、四三二二一の弦が下手側、管楽器が上手側に並ぶ。チラシには総勢三十二人の名があり、ステージいっぱいに並んで、力強く立奏。ただし必要以上に力んではいないので、この小ホールでも音が飽和することない。そのバランスがいい。アンコールはコンサートマスターがリードして、コーダをもう一度。
将軍とレギオンではない、チームとしての合奏。クラシックは、大衆の心を得やすいカリスマ音楽家の話題に終始しがちだが、それだけでは見えてこない、多様な魅力と可能性がある。そのことをあらためて感じる。
感染拡大への警戒が東京でも強まるなか、勇気をもって開催してくれたことに感謝。
二月二十四日(月)忘れていたものを
新型コロナウイルスが日ごとに大きな問題となってきている。
三月七日に鎌倉市の大船学習センターで「渋沢栄一とクラシック音楽」 という話をする予定だったが、感染拡大防止のために鎌倉市が年度内の市主催行事の一切を中止したため、消滅。
クラシックの演奏会にも、これから大きく影響が出てきそうだ。いつまで続くか、先が見えないのが困りもの。
個人的にも、なぜか今年は不意に予定が変わっていくことが多い。去っていく人、新たに声をかけてくれる人。終るもの、始まるもの。
ガラリと足元が崩れるようなことが起きたかと思えば、顔を上げたところに、誰かが笑顔で手をさしのべてくれていたりする。
二十五年ぶりくらいに声をかけてくれた人もいる。茅場町の事務所に毎日出勤していたあの頃、SNSどころかメールも携帯電話もなく、固定電話でしか連絡を取りあったことがなかったことに気がついて、生活様式の変化の大きさに呆然となる。打合せといえば、直接会って話すしかなかったのだ。
私自身は何も変化を求めることなく、時間に追われるまま漫然と立ちつくしているだけだが、まわりの人と景色が、どんどん移っていきつつある。去る者来る者、甦る者。何かが変る年。
こういうときは、初心に返ること。
「なくしたものを取り戻すことはできないけれど、忘れていたものを思い出すことはできますよね」と言ったのは、『タッチ』の上杉達也だったか。
そうだ、思い出そう。
ミュージックバードの『夜ばなし演奏史譚』が三月一杯で終了ときまった。最終回は来月二十九日放送のソッリマ特集だが、収録のほうは、二十二日の『巨匠「名盤」列伝』が最後となる。放送一月前の二十一日に録ってきた。
モーストリー・クラシックの連載と並行している『巨匠「名盤」列伝』、ラジオでの最後は誰にしようと思っていて、そうだ、この人がいると思い出した。
レジナルド・グッドオール。
こういうとき、俺にはやはりこの人しかいないなと(笑)。
モーストリー・クラシックの連載は、二〇〇九年の五月から、十年以上もいつのまにかやっているが、なぜかこの人のことはやっていなかった。私にとっては最も大切な指揮者の一人だけれど、世間的には「巨匠」といえるか?という思いがあったのだと思う。
その人をやることにした。
番組ではあえて、最高傑作の《トリスタンとイゾルデ》はかけずに、《指環》中心に構成して、〈ヴォータンの告別と魔の炎の音楽〉の、「さらばだ、勇ましきわが子」で終らせることにする。
グッドオールの《指環》をちゃんと聴くのは久しぶり。『クライバーが讃え、ショルティが恐れた男』を書いた二〇〇二年以来、十八年ぶりか。その年に、ミュージックバードの番組で特集を組んだ記憶があるので、この男について長くしゃべるのも、十八年ぶり。
しかし、よく憶えているものだ。このアクセント、このリズム、このフレージング、このダイナミクス。もう身体に入っている。鳴り出すと一瞬に甦って、身体を波動させてくれる。
エピソードも、拙著を読みかえすまでもなく、自然と口をついて出てきた。頭の中にその姿が見えるような気がしたのも、昔と同じ。ただ、自分の語りが少し、神田松之丞あらため神田伯山ぽくなっていた気がしたあたりは、二〇二〇年バージョンか(笑)。
ワーグナーしか指揮したくない、と言った男の音楽。あらためて聴いてみて、弱点は多々あるにしても、ワーグナーの音楽のツボ、波動を押えていることを再認識する。カルロス・クライバーが絶賛したのも、その点だろう。
それは「ワーグナーの毒」としかいいようのないものに、肉薄している。
いま、新たな仕事の一つとして、ナチス時代の音楽のありかたをいろいろ調べだしているのだが、グッドオールがその手でつかみだしてくれた「毒」は、二十世紀前半までの、つまりヒトラーが自殺する時点までのワーグナーの、本質をついているような気がしてならない。
イギリス人グッドオールを通じて、そこへ遡って行けるかもしれない。その灯火が、かすかに見える気がする。
昨日に帰ることで、明日が来るかもしれない。
明日がどうなるかは誰にもわからないけれど、まずは一歩を、グッドオールとともに。

ミュージックバードの『巨匠「名盤」列伝』では、指揮者名だけで副題はつけなかったが、今回だけはつけた。
「終りよければ、グッドオール」
やはりここへ帰らないと、なにも始まらないのだ(笑)。
二月二十七日(木)自粛開始
昨日の安倍首相による大規模イベントへの自粛要請を受け、クラシックにおいても、オーケストラやオペラ公演の中止が次々と発表されはじめた。
今日は某誌のためにクリスティアン・テツラフのインタヴューを行うことになっていたが、出演予定だった二十八日の読響の演奏会が中止になって急遽帰国、話が流れた。
三月十九日を目処に、自粛の効果を判断するとのこと。
三月九日(月)自粛自粛また自粛
三月上旬のクラシック公演、次々と自粛を余儀なくされる。東京・春・音楽祭のムーティの《マクベス》のマスターコースと本番、神奈川県立音楽堂の《シッラ》などなど、枚挙に暇がない。
出演者、主催者にとっては苦渋の選択で、金銭面はもちろん、精神面においても長く癒されることのない痛手となるだろう。早く収束することを祈るのみ。
自分の場合はこれまでのところ、講座が二つ延期になっただけ。それ以外は、中止公演でも原稿料をちゃんと払ってもらえているから、恵まれている。
どういうわけか、今月前半は原稿依頼が集中した。どうにもならず、〆切をとうに過ぎて、デッドラインぎりぎりになった仕事が担当さん六人分、つまり六人の方から切羽詰まった催促がいっぺんに来そうになったときは、さすがに海を見に行きたくなった。
しかし一つ一つ、とにかく仕上げていって、多大の迷惑をかけつつも何も落とさずにすんだのは、運がよかった。
三月十二日(木)空いた電車に乗って
日経新聞文化部で演奏会評を担当してくれていた岩崎記者が、三月末で埼玉支局デスクに栄転することになり、池田卓夫さんのお声がかりで、樋口隆一さん、江藤光紀さんとともに執筆者たちで送別会。恐いので、なるべく換気のよさそうな店を選んでもらい、天王洲で開催。
二週間ぶりぐらいに乗った丸ノ内線も銀座線も、そして山手線までも、帰宅ラッシュの時間帯なのにガラガラ。
これでは経済的には成り立たないだろうけれど、しかしウイルス禍が収束したとき、人の心をすりつぶすような満員電車や雑踏の毎日に戻りたいと人々は思うのだろうか、とも思う。これをきっかけにテレワーク化が進むなら、それはそれでいいことなのかもしれない。
SNSの普及がなかったら、このウイルス禍を乗りこえることは困難だったろう。もちろんそれなら、こんなに激烈な速度で感染が世界に広がることもなかったろう、ともいえるが。いずれにせよ、物理的な世界に匹敵するほどの重大性をネットの世界は獲得しようとしている。国際性はSNSが維持し、物理的な国境は閉鎖という日も来るかもしれない。
などと考えているうちに到着。空間に余裕はあるが人気店らしく満席の混雑。いるところには人がいる。美食と美酒だけは、SNS経由では味わえない。
参加者全員、平日夜は大概どこかの演奏会に行っているだけに、普段なら全員の都合の合う日はなかなか見つからないが、今月前半は何もないという異常な状況ゆえに集まることができた。
とはいえ、唯一敢然と来日、予定通り演奏したアンドラーシュ・シフのリサイタルに行った鈴木淳史さんだけは、品川駅近くでの二次会から参加になった。ワイワイと楽しい一夜。
三月十三日(金)『井筒』の古形

堂本正樹の『世阿弥』(劇書房/一九八六年)を読みかえしていたら、一月前に見て感想を書いた『井筒』に関して、巻末の「私的ノートを含んだ恣注」の七〇六頁に、面白い指摘があった。
『井筒』のシテは、現在は冠と老懸という髪の飾りだけが男風で、上衣は女の長絹だが、古い時代には男の直垂を着たりすることがあり、「形見の直衣身にふれて」のところで、男性風のカケリという狂いの動作をしたという。
「神憑り。または狂女の面をつけて舞う男博士の翔り。まことに激しい能になろう。月光の下で男装の女が恋しき男に憑かれてきりきりと狂うのである」
これなら、今の起伏に乏しい展開とは違って、緩急の変化がはっきりとつく。しかも、戦後すぐの『井筒』はほぼ一時間三十五分だったという。それが一九七九年の『能楽手帖』では一時間五十分となった。今は二時間かかるのが普通だ。「幽玄」とは極端に動きを抑制したものと理解され、ありがたがられるようになって、テンポが遅くなってきたのだ。
さらに堂本は、「極端に重々しく演じられる『檜垣』も、昔はこの『井筒』より軽かったらしいから驚きだ」とその典拠を示して、「狂乱物としてキリキリと演じられた『井筒』よりさらに軽い『檜垣』。……想像もつかない。ということは、現在の能全般がいかにスローモーになったかということでもある。そしてそのテンポを世阿弥以来の万古不易と信じ、疑わず受け入れる能評家の、素人弟子上がり的感性」と続ける。
能は、徳川時代に「武家の式楽」とされてから荘重志向が強まってテンポが遅くなったとされるが、『井筒』は昭和後半にさらに遅くなったというわけだ。
こののろさが、能を近づきがたいものにしているのは事実だろう。誰にでもすぐにわかるような大衆性を最優先すべきとは、私も思わない。楽しめる人とそうでない人がいるのは当然で、媚びる必要はない。
ただ現状の『井筒』は、あまりにも人を遠ざける。それにはそれだけの必然性があるのだろうが、令和の世には、また別のアプローチもあっていいのではと思わざるにいられない。
自然なテンポで舞い、カケリをして、きりきりと狂う井筒の女も見てみたい。もちろんそうなると、『松風』のシテと似てくる気もするが…。
三月十五日(日)時計は止まらない
ヨーロッパでの急激な感染拡大、感染クラスターの起きたクルーズ船、東京オリンピック開催をめぐる議論などのニュースを見ながら、去年の大河ドラマ『いだてん』の、嘉納治五郎の最期の様子をしきりと思い出す。そういえば、あの人は客船の船室で亡くなったのだ。
結局あのドラマは、途中で亡くなるにもかかわらず、役所広司演じる嘉納治五郎が真の主役だった。
生命の灯はつきても、時計は止まらない。明日へ。
三月十六日(月)ウルトラセブンと
近所のプールが二週間ぶりに営業を再開したので、早速泳ぐ。感染防止につとめつつ、少しずつ日常を取り戻す。
いまはただ、世界のウイルス禍が一日も早く収まることを祈るのみ。


少し前に届いていた本を二点。
まず青山通の『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』(新潮文庫)。
二〇一三年にアルテスパブリッシングから出て、ベストセラーとなった単行本の文庫化。
青山通とは、フェイスブック友達でもある青野泰史さんのペンネーム。最終回で印象的に使われたシューマンのピアノ協奏曲をきっかけに、クラシック音楽の面白さ、奥深さを発見していく、少年時代の物語。
文庫化で手軽になったので、このさいぜひ。文庫に追加された片山杜秀さんの解説や、木村元さんの一文も面白い。
(自分は二〇一三年六月十一日の可変日記に感想を書いている)
隣は、東京都交響楽団の演奏会プログラム「月刊都響」三月号。都響の三月分の演奏会四回も、首相の要請に応じてすべて中止となったので、会場ではついに一冊も配られることなく終った、幻のプログラム。
私の連載「オリンピックと音楽」の第十九回「バルセロナ・オリンピックとオペラ歌手の越境」も、ひっそりと載っている。
オリンピックそのものがどうなるかわからなくなってきたが、ともあれ連載は残り三回。第二十回はもう校了しているので、あと二回を粛々と書くのみ。最終回は『いだてん』話と決めているので、開催であれ中止であれ延期であれ、なんとでもうまく対応できる。時計は動く。
三月十九日(木)人の弱さと心の共振

今月二十八日の東京交響楽団のメンデルスゾーン編曲版マタイ受難曲、独唱者を日本人に変更し、最大限の感染予防と拡大防止のための対策を実施した上で、開催するとのこと。
払い戻しも可能なので、行く行かないはそれぞれの判断だが、私はこういうときだからこそ、ナマのマタイ(それも、ユダヤ人メンデルスゾーンが編曲したもの)が聴きたい。人間の弱さと孤独と愚かしさと無力と、そして、共振する心と心。だから嬉しい。
(しかし二十四日、感染者数が増大するなか、八月十三日に延期することが発表された)
三月二十一日(土)陽光と鳥の歌
久しぶりに上野駅へ。公園口改札が北側に移動していた。公園の大通りの正面となって、位置が思った以上に違う。東京文化会館に入るのにも、国立西洋美術館に面した扉からの方が近くなった。人の動線が大きく変わることになる。
十五日の東京新聞に「〈東京人〉東京クラシック音楽散歩 上野から世界へ羽ばたく」という短文を書いた。
発売中の『東京人』のクラシック特集に連動したもので、そこに書いた「音楽の聖地」としての上野公園の話である。
じつはこれを書いたときは、はたして今月は「花や絵とともに、美しい音を」楽しむことができるのか、演奏会があるのかどうか不安に思いつつ、希望を捨てずに願望をこめて、「ぜひ楽しんでほしい」と結んだ。
それから四日後の十九日、二〇二〇年の東京・春・音楽祭は、旧東京音楽学校奏楽堂でのトリオ・アコードによる「ベートーヴェン ピアノ三重奏曲 全曲演奏会」第一夜をもって、観客入りの演奏会を開始してくれた。
嘘つきにならずにすんでよかったと、まずはひと安心。
そしてその三日目の最終日、自分も聴きに行くことができた。先月二十三日以来、一月ぶりの演奏会通い復帰が、新聞のコラムの内容そのままに、奏楽堂と東京文化会館小ホールの組み合わせになったのは、感慨深い偶然だった。


奏楽堂は場所こそ移り、改修もされているが、基本は百三十年前の東京音楽学校開校時につくられた建物のまま。
幸田延や滝廉太郎に始まり、「運命」の全曲や「第九」の日本人による初演もされてきた舞台。そして麻布の南葵楽堂から寄贈された、徳川ライテイさんのパイプオルガンも、いまは一緒にいる。
当時は死病だった肺結核に斃れた、滝廉太郎の銅像が玄関脇にある。

東京・春・音楽祭は、海外の演奏家が参加するはずだった大きな公演がすべて中止になってしまい、満身創痍に近い状態だと思うが、そのなかでできるだけのことをしてくれているのは、頼もしい。
チケットはお客が自分でもぎる。プログラムも置いてあるのを取る。といった形で、お客もほとんど咳をしないし、接触にも気をつけている。これだけ互いに注意をすれば、現状ではまず問題はおきないのではないかと思う(一回だけ、思わずブラボーをかけた人がいたが、その瞬間の客席の緊迫感がすごかった)。
それよりも、昼間の暑い上野公園を、大勢でわいわい言いながら歩いたり走ったり、所在なげに噴水の回りに肩寄せあって座りこんだりしている人々の方が、よほど無防備で緊張感のない感じで、むしろ心配になる。


写真はフェイスブックの「東京・春・音楽祭」のページから
さて演奏会は十五時から、津田裕也、白井圭、門脇大樹の三人で第十、三、そして《大公》。
演奏会の冒頭、第十番の変奏曲から始まるはずなのに、ヴァイオリンの白井さんが二曲目のはずの第三番の頭をひきだしてしまい、顔を見合わせて止まるハプニング。
三人苦笑い。客席も思わず大笑い。間違いがあるのがナマ。本来なら困った話だが、今日は逆に嬉しくなる(笑)。
そして、最高に嬉しかったのは、《大公》の三楽章の素晴らしいアンダンテの終りで、上手の窓の外で突如として、絶妙のタイミングで野鳥がさえずってくれたこと。
窓から射し込む陽光と鳥の歌、そして終楽章の開始。これこそナマ。偶然にさえずった鳥たちの声は、天の配剤のように美しかった。
これから少なくともしばらくの間は、私は《大公》を実演であれ録音であれ聴くたびに、アンダンテの最後に、鳥たちの声の幻を聴くことになるだろう。
の声の幻を聴くことになるだろう。
それはnoiseなどではなかった。natureの贈り物だった。
しかし、virusもまた、人の営為を超えたnatureであることを思う。偶然がもたらすものは、はてしなく深い。

続いて、上野の音楽の灯を受け継ぐ、東京文化会館へ。
奏楽堂ではマスク着用を求められなかったが、東京文化会館は義務づけられていた。今日は受付でマスクをもらえたからよかったが、今後は自分で用意するようにしなければ。
十八時から小ホールで、「シューベルトの室内楽Ⅰ~鈴木大介(ギター)と仲間たち」を聴く。
ギター伴奏によるヴァイオリンとピアノのためのソナチネ、歌曲十曲、歌曲のギター独奏用編曲六曲、アルペジオーネ・ソナタ、ギター四重奏曲と、十五分休憩二回をはさんで計三時間のもりだくさんな演奏会。
かなり長く、演奏の凹凸もあったけれど、とにかく鈴木さんのシューベルト愛にみちたプロ。
なぜこんなにシューベルトの音楽にはギターが、オリジナルではないのにもかかわらず、合うのか。軽やかで弾力のあるリズムが、ギターのつまびく音、かきならす音に合うのか。気持ちよし。
一方で、《大公》を聴いた直後だと、ベートーヴェンの緩徐楽章から終楽章へとつなげる、暗から明への見事な変化と解放を、アルペジオーネ・ソナタも真似しようとしているのに、いかにもぎこちなく感じる。これが三年後、最晩年のヴァイオリンとピアノのための幻想曲になると、シューベルトならではの方法で見事に展開されるのだが、そうなったときには、もはやそのピアノ・パートをギターに置きかえるのは、おそらく無理。このあたり、ベートーヴェンの音楽がギター的でないのと関係するのか。
三月二十三日(月)酒宴と凱歌

グバイドゥーリナの《ペスト流行時の酒宴》を、ヤンソンス指揮コンセルトヘボウ管のCDで聴く。このコンビのライヴ録音をまとめた十四枚組のボックスの八枚目。二〇一一年のライヴ。
この八枚目は他に《ワルシャワの生き残り》と歌曲集《死の歌と踊り》、《タラス・ブーリバ》と、死神に憑りつかれたみたいな曲ばかりなのがすごい。
この曲を下野さんと読響で、サントリーホールで聴いたのが一月十五日。そして今からちょうど二か月前の一月二十三日に、日経新聞の評の原稿を書いたのだった。
夢のような昔(笑)。そして、一年前の今頃は、改元に向けて平成をふり返る各誌のための原稿に取りかかっていたことを思うと、さらに夢のような昔。

そしてそのあと、ミュージックバードのラジオ番組のために、「ベートーヴェンとアバドのヨーロッパ」というテーマを考えながら、そのためにアバドとベルリン・フィルの《田園》を聴く。二〇〇一年ローマのライヴ録音。
平成のEU精神を象徴する芸術家として、このところ気になり続けているアバド。そのEU精神は今、難民と経済格差からブレクジット、ウイルス禍と、崩壊の瀬戸際にある。
先日、あるFB友達の方たちが、《田園》の終楽章をどうとらえるか、という話をされていた。台風一過の晴天というのが普通だが、大破壊の後、もはや失われた理想郷を懐かしんでいるというとらえ方もできる。
たぶん、どちらも正しい。解釈の多義性、多面性こそ古典が永遠である理由。どうとらえるかは、そのときそのとき、演じる人、聴く人により千変万化する。そこに、今の世界が映る。世阿弥の能もそう。
古典は、今の自分を映す鏡なのだ。
一九四四年、敗戦直前のベルリンで、フルトヴェングラーとベルリン・フィルの《田園》を国立歌劇場(フィルハーモニーは直前に爆撃で破壊されていた)で聴いたある人は、一緒に演奏されたのがラヴェルの《ダフニスとクロエ》組曲だったこともあって、失われたギリシャの理想郷、遙かなるアルカディアがそこにあるようだったと、書いていた。
空襲下のベルリンに響いた昔の夢。
ではアバドは、生涯最後の全集で、その《田園》を、その終楽章をどうやっていたのかを、再確認したくなった。
異様なまでに力強い。あえていえば、「運命」の終楽章よりも、力強く肯定的な凱歌になっている。
「俺は人間を信じるよ」
そう言っているような演奏。
わかりました。信じましょ。
三月二十四日(火)演奏会と夜桜

上野の東京文化会館小ホールへ、東京・春・音楽祭の「N響メンバーによる室内楽 ベートーヴェン生誕250年によせて」を聴きに行く。すべてベートーヴェンの室内楽。
・アレグレット変ロ長調 作品番号なしの三九
・ヴィオラとチェロのための二重奏曲変ホ長調 作品番号なしの三二《二つのオブリガート眼鏡付き》 より 第一楽章
・ピアノと管楽のための五重奏曲
・七重奏曲
地味だが、なかなか聴けない作品もあり、ベートーヴェン・イヤーならでは。
休憩時間に上野公園に行き、夜桜を撮る。人は多少歩いているが、宴会などはない、静かな春の宵。

三月二十五日(水)響く言葉
新国立劇場の今季の目玉の一つで、四月の三回公演が完売となっていた《ジュリオ・チェーザレ》の中止が発表されたのは、一昨日のこと。
海外のキャスト、指揮者、スタッフの大半も来日して準備を続けていることが発表されていたが、やはり無理だった。
昨日、最後のリハーサルが行なわれたという。そこでの大野和士芸術監督の挨拶が、劇場から発表された。
「昨日夕方、最終的な要請を受け、四月十二日までの公演中止が決まりました。
しかし私の希望としましては、このプロダクションを、このキャストの皆さんで、将来、ラインアップに入れたいという希望を持っています。
ですから今日は決して最後ではない。そしてその日のために、今日、ハイライトのリハーサルを行って、私たちの劇場とこのプロダクション、そしてお客様とが強く結びつくことを企図して、キャストの皆さんのこれまでの成果を記録に留めたいと思います」
――今日は決して最後ではない。
心に響く言葉。
 写真はフェイスブックの新国立劇場のページから
写真はフェイスブックの新国立劇場のページから三月二十六日(木)春の中止
東京・春・音楽祭、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、明日以降の全公演中止が発表される。
今年はとくにスケールの大きな催しとなっていただけに、なんとも残念。
三月二十七日(金)ムター感染
アンネ・ゾフィー・ムターが昨日、新型コロナウイルスへの感染を、自らのフェイスブックで明らかにしたとのニュース。軽症ですむことを願うのみ。
感染経路はわからないようだし、サントリーホールで仲間と肩を抱きあうのを見てドキッとしたのは、先月二十二日の話。ひと月以上たっているから、今回の感染とは関係ない。しかし、これからは対人のさまざまなマナーが大きく変るのだろうと、あらためて思う。
四月六日(月)このごろ通信
毎日新聞の月曜夕刊に、三か月ごとに著者が交代する「このごろ通信」というコラムがある。四月からの三か月間、私が書かせていただくことになった。今日が一回目となる。
音楽好きに限定しない、一般読者向けのコラムなので、コンサート前後の出来事や、会場のことでも書こうと思っていたら、三か月のうちにはたしてコンサートに行く機会はあるのだろうかという、まったく想定外の事態になった。
早くも一回目からネタ切れの不安におびえつつ、なんとかやっていくつもり。
四月十五日(水)ターリヒ!
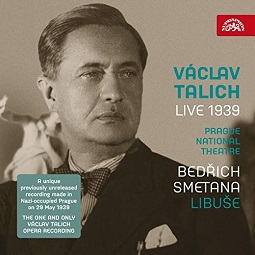
ヒストリカルのディスクで、久々に興奮するニュースをきく。
ターリヒ指揮チェコ・フィルによるスメタナの歌劇《リブシェ》抜粋。一九三九年五月二十九日プラハ国民劇場でのライヴがスプラフォンから出るという。
チェコ主要部が一九三九年三月にドイツの保護領となり、ナチスに支配された状況下で、ターリヒがチェコ人の誇りを保つためにこの年の五月に始めた音楽祭が「プラハ・音楽の五月」。いうまでもなくクーベリックが戦後に創始した「プラハの春」音楽祭の原型となったもの。
親衛隊の「金髪の野獣」、ハイドリヒがチェコに乗り込んでくる前の、まだ統制が比較的ゆるかった時期だからこそ可能になった音楽祭である。
このときの七月の《わが祖国》全曲の火の玉みたいな熱演は、ノルウェーに奇跡的に残っていた録音から二〇〇九年にCD化され、音質の限界を超えて、「ターリヒとは誰だったのか」を、本当の意味で教えてくれるものだった。
終演後、興奮した聴衆が思わず合唱してしまうチェコ国歌がしっかりと入っているのも、素晴らしかった。
その同じ音楽祭での《リブシェ》の第三幕の一部分が、これまた奇跡的に復元されて発売されるのだという。
ターリヒのオペラ録音が一部でも世に出てくるのは、これが初めて。しかもチェコの国民オペラとされる演目。
この音楽祭があまりに成功し、反独運動が勢いを増したこともあって、警戒したナチ当局は翌年から規模を縮小させ、《リブシェ》もこれを最後に、解放まで上演を許されなかったという。
いま、ちょうどこのへんの時代の中欧の音楽のことをあらためて調べだしているので、そこにこのような、背中をぶっ叩いて奮い立たせてくれるようなものが出てきてくれるのは、本当に嬉しい。
世界は病んでも、「夢は枯野を駆けめぐる」。
四月二十三日(木)岡江さんの訃報
女優の岡江久美子さんの訃報。新型コロナ・ウイルス感染のためという。
お会いしたことはもちろんないが、小中学校の先輩である。飾り気がなく、てきぱきと気働きがあるお人柄は、いかにも附小女子らしい雰囲気だと、勝手に好感を抱いていた。
ただ驚き、ご冥福を祈るのみ。
四月二十七日(月)恵比寿で散髪
不要不急の外出は自粛しているが、髪が伸びてどうにもならなくなってきたので、恵比寿の美容院に行く。
ひさびさに乗った山手線はガラガラ。原宿も渋谷も、真昼なのにホームや周囲に人がほとんどいない。異様な光景。
散髪するときはマスクをして、ひもは耳にかけずに、テープで止める。こうすればもみあげを切るのも簡単。しかしお客をたくさん入れるわけにはいかないから、経営も大変だろう…。
四月二十八日(火)グールド式
先週から、ミュージックバードの番組ナレーションの収録(六月放送分)を自宅で行っている。
先月に収録したニューディスク・ナビの五月放送分は、いつものスタジオでマスクをつけてしゃべったのだが、スタジオのあるTOKYO FMビル内で新コロ感染者が出たこともあり、四月中旬からは、社外の人間はテレワーク収録ということになった。
在宅勤務で大流行のZoomでしゃべって、ディレクターに収録してもらう出演者やゲストが多いようだが、うちは古いデスクトップ機でwebカメラなんて小じゃれたものはついてない(一応調達中)し、どうも音質などに不安がある。
ということで、自分でナレーション部分を自宅で録音してwavファイルにして送って編集をお願いする、「テレワークの元祖」グレン・グールド方式でいくことにした。
さいわい、つり下げ式の安いマイクは在庫があってすぐに配達してもらえた。机の脇に取り付け、録音ソフトを買い、ディスプレイを見ながらしゃべる。

古い木造家なので外の騒音がガンガン入る。向いのビル新築工事はこんな状況でもかまわず作業しているので、昼はとても無理だし、夜も早い時間はどんな邪魔が入るかわからない。その意味でも、自分だけの都合で勝手に時間を選び、中断再開の自由をもてる、グレン・グールド方式がよかった。
ということで、六月のウィークエンド・スペシャルの宅録版には、「テレワークの元祖~グレン・グールド再考」という番組をちゃっかり入れることにした。
以前からグールドは、「引きこもりの元祖」みたいな人と思っていたが、現在のような状況になると、その存在にものすごく積極的な意味と価値が加わってくる。特にワーグナーを自ら編曲してひいた一枚などは、預言的といってもいい。

しかし、ウィークエンド・スペシャル宅録の前日、先週木曜に最初に録ったニューディスク・ナビの一回目は、やはり大変だった。
ふだんは時間の管理をディレクターさんにまかせっぱなしにして、適当にしゃべっているのだが、初めてなので見当がつかない。そこで画面の録音タイムを視界の端に入れながら、曲目表やら資料やらを確認しながらしゃべると、中身に集中できない(笑)。
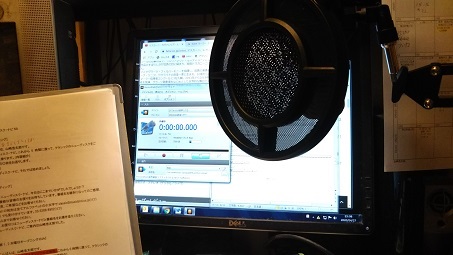
生放送なみに緊張しているのでミスはいつもより少ないのだが、本番以外の部分で、スタジオ収録の倍くらい時間がかかった。
そこでニューディスク・ナビの二回目は、一週五日分を昨夜、一昨夜と二日間に分けてノドと集中力の消耗を減らし、スタジオ同様に時計を見ず、話の内容だけに集中して、適当にしゃべってみた。これが正解。かえって時間もきちんと収まる。長年の習慣のおかげ(笑)。
面白いのは、手元にCDがあるとしゃべるのがはるかにラクだ、ということ。最初は画面上に種々の資料を展開して、適宜切り換えて読んでいたのだが、これはどうにも頭に入りにくく、なにより頭が回らなくなる。
それよりもCDのジャケ裏を見て冊子のページをめくり、と手を動かしながらやるほうが、何をどうしゃべるべきかという瞬時の選択に迷いが起きず、話のイメージが勝手に膨らんでいくのだ。
これにかぎらず、自分の場合は、家にこもるようになって、本やCDのような「形あるもの」への愛着と執着が、かえって増している。
ディスプレイ上の画像は、手にとれないものというだけでなく、どこまでいっても自分にとってはただの情報、「データ」でしかない。文章や音楽の世界に没入する、つまり「その場に遊ぶ」ことができるのは、「形あるもの」を手にとれるときだけ。触感の不可欠、とでもいうか。
触感と触覚の大切さを再確認できたのは、新コロによる怪我の功名か。
というわけで、だんだん宅録の見当もついてきた。残りのニューディスク・ナビ二週間分、がんばらねば。
五月三日(日)ベルティーニきたる!
外出自粛が続くなか、日本でもさまざまなオーケストラ、ホールなどの団体が無料のオンライン配信を始めている。
興味深いラインナップがならぶなか、強烈に心ひかれているのが、東京都交響楽団が公開を予定しているもの。

・第一四〇回定期演奏会Bシリーズ
一九八一年九月二十八日(月)東京文化会館
指揮/ガリー・ベルティーニ
マーラー:交響曲第六番《悲劇的》
https://www.tmso.or.jp/j/news/8896/?fbclid=IwAR2sLi15WRDCt6iudXuyAR2WK2lzVH4K7wPBkEsfJo9uvoIkU20mVdkzy1k
ベルティーニが都響と初めて演奏したマーラーで、その後の両者の長い関係のきっかけになった演奏会だ。
柴田南雄はクラウス・プリングスハイムと東京音楽学校による昭和九年の日本初演を聴いて、自分も音楽をやって生きていきたいと思うようになって以来、この曲に特別の思い入れをもっていたが、その柴田が絶賛した演奏だった。
大学一年生だった自分も聴きに行き、強烈な衝撃を受けたもの。もちろんこの曲の実演初体験だった。どういうわけか一階正面の最前列に近い席だった。
記録によると、ベルティーニは幻想交響曲などを演奏した十八日が初登場で、このマーラーは十日後。十八日に行った音楽同攻会の友人や先輩が「ベルティーニは面白い」と口々に語っていたので、かなり期待して行った記憶がある。
前半のモーツァルトのファゴット協奏曲では、聞いていたとおりに暴れまわるベルティーニの奇天烈な指揮ぶりが可笑しくて、吹き出すのが恐くて、顔をあげられなかった。
マーラーではそれに慣れて、突如足をそろえた瞬間に革靴の踵がカチーンと音を立てるとか、ハンマーの箇所は指揮棒を両手で握って頭上に掲げ、思い切りふり下ろしたとか、コーダの直前の静かな箇所で夜九時になり、客席のあちこちで時報のアラームが鳴り出した(デジタルの腕時計が流行りだしたころで、これみよがしに時報を鳴らしている人がたくさんいた時代だった)など、演奏の激しさとともに、昨日のように憶えている。
柴田南雄も文句を言っていたアラームは、この録音でも聞こえるのだろうか。当時、ラジオなどでやったような記憶はないので、完全に三十九年ぶりに再会することになる。いわば、十八歳の自分との再会。
パンドラの箱というか、玉手箱というか、聴いてみるのは正直な話、ちょっと恐いが楽しみ。
五月六日(水)地方自治の本義
今回の新コロ禍は、内務省が消滅して以来初の全国的国難、つまり局地的な災害でもなければ、権限を政府に一任すべき外交問題でもない、全国同時多発の国難となった。そしてGHQの置き土産である地方自治制度が、初めて真の意味で存在意義を問われている観がある。
政府と政党が、お肉券など旧来の発想と手法にとらわれて後手後手に回るうちに、頼りにならないからと都道府県が独自に動き出しているあたりは、ちょっと黒船以後の幕末の幕府と雄藩の関係を思わせたりもする。
オリンピック(と万博)は、当初考えられていたような「高度成長期の夢よもう一度」という懐古的イベントではなくて、(やるにせよやらないにせよ)今回も変革期に位置するものになりそうだ。少しでもよい方向に向かうことを。
五月八日(金)山田和樹、三善晃の反戦三部作を語る

https://www.tmso.or.jp/j/archives/special_contents/2020/20200508/
本来なら今夜七時から、山田和樹さんが指揮する三善晃の「反戦三部作」演奏会が、東京文化会館で東京都交響楽団により行われていたはずだった。
上にリンクした記事は、その宣伝のために今年の二月九日に私が行なったインタヴューをまとめたもので、演奏会の前に都響のサイトで公開されるはずだったが、中止となったために封印されていたもの。演奏会が予定されていた本日、初公開となった。
お話をうかがいながら、山田さんのなみなみならぬ思いを感じて、私もとても楽しみにしていた演奏会だった。

後半、「三善晃はなぜ三部作の初めの二曲に、キリスト教的なタイトルをつけたとお思いですか」とたずねると、一瞬虚をつかれたような表情になり、しかしすぐに目をキラッと輝かせて、「いい質問ですねえ」と笑ってくれた。
ほんの少しだけ考えたのち、出てきたお答えは、まあ見事なもの。
「タイトルの由来」という見出しがついた部分のことだが、こういう問答ができる瞬間こそ、まさしくインタビュアー冥利につきる場面である。だからこそ、夢と消えてしまったことは本当に残念。
敗戦から七十五年、チラシの「この声が、聴こえるか――」という言葉もとても印象的。
いつか必ず、実際の音となることを信じて。
〈公演中止〉第903回定期演奏会Aシリーズ
東京文化会館
指揮/山田和樹
合唱/東京混声合唱団、武蔵野音楽大学合唱団
児童合唱/東京少年少女合唱隊
三善晃:レクイエム(1971)
三善晃:詩篇(1979)
三善晃:響紋(1984)
この日記をフェイスブックに載せたところ、岩城宏之指揮によるレクイエムの一九七二年の初演を聴かれた方から、当日はケルビーニのレクイエムと組み合わされていたと教えていただいた。
初演時はキリスト教音楽のレクイエムと対置させていたのだ。
自分がキリスト教的なタイトルについての質問を思いついたのも、インタヴューの直前にピノック指揮紀尾井ホール室内管のモーツァルトのレクイエムの美しい演奏を聴いて、これはやはり、キリスト教徒のためのものだなと感じたのが、きっかけだった。
五月十二日(火)一九八一年への旅
都響ラジオ #3 歴代指揮者シリーズ③
今日から公開になった、ベルティーニと都響の一九八一年の《悲劇的》。
いい演奏だったんだ、やっぱり(笑)
テンポ感のよさ、前へ前へと進む推進力。技術とか精度とかスタミナとか、弱点を色々指摘することは可能だろうが、とにかく聴く者をぐいぐいと惹きこむ力が凄い。
音も予想以上によくて、鑑賞に支障なし。この前年、一九八〇年十一月十日の若杉弘の《復活》がやはり素晴らしい演奏(私の《復活》初体験だった)で、評判の高さから翌年にLP化されたことがあったが、どういうわけか、真価のまったく伝わらない、むしろ誤解させてしまうような貧弱な音質になっていた。
その悲しい記憶があったのでこの《悲劇的》もとても不安だったのだが、まったくの杞憂。これならよくわかるはず。
心配された(でも少し楽しみにしていた)コーダ直前の腕時計の時報音も、ほとんど聴きとれなかった。二時間三十八分十秒のところに入っている「ピー」というような高い音が、あるいはそれかもしれないが、知らない人はまったく気にならないはず。
しかし、それよりも自分にとって面白いのは、音を聴いていると、あの日のベルティーニの指揮ぶりが眼前に甦ってくることだ。
第二楽章で猛烈に動きまわり、もぐり込んだと思ったら、次の瞬間に指揮棒を高く掲げて直立したり。そういった激しい動きがちゃんと音に出ているから、三十九年前の映像が浮かんでくる。
終楽章の初めの方には盛大に足音が入っているし、二回のハンマーの「グッとためてドカーン」という響きには、両手で指揮棒を頭上に掲げ、気合一閃ふり下ろしたあのジェスチャーが、見事に反映されている。
そして、物哀しい夢のような、第三楽章。ある意味ではこれがいちばん懐かしかった。
こんなのを聴いていたのか、痩せっぽちだった十八歳の、俺。
三十九年後の今になって気がつくことだが、六〇年代の演奏様式の主流である重戦車系とも、七〇年代の端正だけど薄い響きとも、そして八〇年代後半のやたらに遅くて濃厚な音とも異なる、五〇年代的な感覚の弾力をもった、よい意味で「季節外れ」な音楽づくりが、自分の波長にピタリと合ったのだと納得できたのは、大きな収穫だった。
なおこの《悲劇的》の日本初演は、三日の日記で触れた通り、クラウス・プリングスハイムと東京音楽学校による、一九三四年の演奏会。二回目は、四十一年後の七五年にギーレンとN響。続いて七七年に渡邉曉雄と都響が演奏し、七八年にはアマオケ初演として、東大オケが演奏している。
マーラーの実演が急激に普及していったのが七〇年代後半、というよりも昭和五十年代であり、アマオケの隆盛と底辺拡大ともリンクしていたことが、この演奏史には端的に表れている。

東京文化会館のアーカイブにある、当日の文字の多いチラシ(と思ったらプログラムだった)も、よく憶えている。
学生1500円とあるので、おそらくこれで聴いている。
http://i.t-bunka.jp/pamphlets/11799

1983年、二十歳の俺。後輩から、爆弾魔の手配写真みたいですねといわれたっけ(笑)
五月十九日(火)お祝い返しは微笑に
一昨日から新たに購入したパソコンへの引越。二〇一二年から八年使ってきたウィンドウズ7から、ようやく10へ。
前のPCはシステムに異常があって、10にアップグレードできなかった。CD‐ROMの古いソフトには読めないものもあるが、一部は工夫すれば起動できるようで、どうにかなりそうだ。
なかでも捨てたくなかったのが、『グローセス・ゼンガーレキシコン』というドイツのCD‐ROM。歌手大事典、その名のとおり、十六世紀以来の名のある歌手一万四千五百人の経歴を掲載した、世界最大級の歌手事典である。実際、これほど広範囲に詳細なものはない。

ところが二十年前のソフトなので読めない。PCの進歩で置き去りにされてしまったのだ。買い換えるかと思って新版を探したところ、二〇〇三年に書籍で第四版が出ているという。手元のCD‐ROMは一九九七年の第三版の書籍を元にしているが、第四版は二万人に歌手が増えているという。
問題は、新版がとても高価なこと。古本でも六万円以上かかるし、重くてかさばる大冊となると、これからの時代、抱えておくのもためらわれる。電子書籍やオンライン化はされていないらしい。
というわけで、CD‐ROMを何とか使えないかと検索したところ、起動方法がわかった。貴重な資料がただのゴミとならずにすんだ。こういうところ、ネット社会は本当に便利。
五月二十三日(土)果しなき流れの果に
外出自粛で変化の少ない毎日のうちにうっかりしていたが、四月にこのサイトが十五周年を迎えていた。
このような、前世紀じみた「ホームページ」を閲覧される奇特な方がたくさんおられるはずもなく(笑)、ほとんど私用の公開備忘録と化しているが、維持できるかぎりは続けていこうと思う。
ついでに、最近の仕事などから。
感染防止のために休止していた朝日カルチャーセンターの講座は、六月から再開。延び延びになっていた三月分の講座をまず行い、七月からは新たな講座「頭文字Kの名指揮者」となる。
朝カルでもオンライン講義が増えているが、これらは講師のITレベルに合わせ(笑)、旧来の対面式でやる。もちろん、感染対策は万全に行うそうだ。
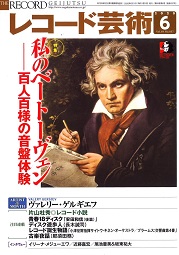

発売中の「レコード芸術」六月号に書いた記事のうち、自分が特に気に入っているのは、先取りレヴューのエベーヌ四重奏団によるベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集(八十四~八十五頁)。
この全集は掛け値なしに凄い、素晴らしいものだ。
今年はクス四重奏団のサントリーホールのブルーローズでのライヴ盤(このホールの音響はマイクを通すと、生で聴くより格段によくなり、演奏の印象まで一変させると実感する盤。エベーヌの三枚目も同様だった)とか、カザルス四重奏団の三分冊セットとか、演奏スタイルも曲順構成と分割法もそれぞれに異なって魅力的な弦楽四重奏曲全集がすでに登場しているが、なかでもエベーヌ盤は、まさに「日下開山」となるべきものだ。
昨年七月の東京公演のとき、この全集についてインタヴューさせてもらったとき、かれらは本番翌日に六時間のパッチセッション(本番の三倍ものパッチ!)をやってきた後だったのに、本当に真摯にこちらの質問に答えてくれた。
そのインタヴューは「レコード芸術」三月号に掲載されているので、それもぜひ読んでいただきたいが、この全集の演奏をいっそう深く味わうためのキーワードが、四人それぞれの言葉の端々に込められていたことに、完成したセットを拝聴したとき、あらためて気がついた。
世界の七都市で録音した七回のコンサートからなる全集。「七つの海」や「七大州」を連想させる通り、まさに世界をめぐる「ベートーヴェン・アラウンド・ザ・ワールド」。
意地の悪いいいかたをすれば、このグローバルで雄大な発想は、「コロナ前」の平成時代らしいもの、ともいえる。そして現状の世界においては、非常に困難な現実に直面した理想、ともいえる。
実際、七枚目をパリで録りおえた一月二十七日(モーツァルトの誕生日でヴェルディの命日で、アウシュヴィッツが解放された日)の直後、世界の都市はコロナ禍に呑みつくされ、次々と封鎖されていった。あらためて始まるはずだった各地でのかれらのベートーヴェン・ツィクルスは、すべて中止に追い込まれた。
その悔しさと悲しみの深さは、私などには想像がつかないものだろう。
この全曲盤は、レコード会社主導ではなく、かれら自身が企画して資金集めをし、その責任において実現させたもののようだ。低価格に抑えられているのも、今年春のツアーの会場で直売することを意識したためなのではないかと思う。その意味でも、ツアーができなかったことは大変なのではないだろうか。
しかし、これが芸術というものの、畏敬すべき偉大さなのだろうが、「コロナ前」の思想に基づいてつくられたこのセットには、それにもかかわらず、「コロナ後」を生きるすべての人たちに向けたメッセージ、エベーヌの四人のメッセージと、かれらを通して顕現したベートーヴェンのメッセージが、はっきりと刻み込まれている。
そう、永遠の預言のように。
少なくとも私の場合は、この七枚九時間弱の音楽の流れに、このところずっと励まされ、勇気づけられ、気力を与えてもらっている。
人類の悠久の歴史、地球的規模の空間すらも超越する時間を凝縮したような、小松左京の『果しなき流れの果に』流にいえば、時の流れの果にあって宇宙の真理となりうるような、四つの弦楽器の、果しなく広大にして、緊密なる対話。
そして、この九時間弱の音楽のクライマックスに置かれた九秒弱の沈黙の、すべてを呑みこんだ無の、果しなき長さ。
私が感じたそのメッセージがどのようなものであったかを、つまりはその無がなんであったかを、「レコード芸術」六月号に書いた。
そして、六月三十日から七月三日にかけてのミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」では、全曲を放送しながら、お話をする。
ベートーヴェンの弦楽四重奏曲には、SPの時代から数多の名盤がある。そのすべてが、その当時の演奏スタイルを象徴しながら変遷し、通り過ぎていく。解釈の可能性がつきることがないというのが、偉大な古典の証明だ。
エベーヌ盤は、二〇二〇年という世界史において特筆すべきものとなった年を象徴する、今後も聴き継がれ、語り継がれていくべき録音だと思う。


小松左京の『果しなき流れの果に』は、四十年ぶりに読み返したときの感想を二〇一九年二月七日の「可変日記」に書いた。
文庫は新装版の表紙(左)もファンタスティックで好きだが、生頼範義が描いた昔の表紙(右)も忘れがたい。
五月二十八日(木)機械任せの文字起し
そろそろ原稿締め切りに追われだす。インタヴューの文字起し、いつも大変なので、楽をしようと無料の文字起しアプリを使ってみた。これが使えると作業がものすごく楽になる。
なになに、音声ファイルを読ませるべし。
待つことしばし。出た!
「夫婦夫婦がAFTA不協和音進むふっふっふんふんふんふんふんふんを不老不死風紋ふらふらあふれる自然あふれるふんふん、ふん風評がUFOを配布し負傷FNS風評ふらふら夫婦で住む主婦FF3冬氏をフ外相を推するんです風の主婦主婦らがFIS防府UF分ふんふん、ふんふんとフワフワのふんふんふんふんふんふんふんふん。豆腐、上田房夫SFO35分、噴射古墳はふっふっふっふっふっふっ不安、恐怖と不安です夫婦は主婦層はフンフンAFTA不法ふふふふふふふふふふふふふふ。アフガン紛争ふんふんふんふんと抱負を婦人服冬冬分FFを増やす菅さん。オフィス本。紛争を手法のSUフランス風にはふさふさ夫婦で逡巡する案IFC SF TOEFL普通交付税の不交付―TOWA IFOふんふん、ふんSFA FAの星コースを進む。FFF牛のふんふんと夫婦像を紛争を防ぐシステム不安を踏んだ紛争はふさふさ古筆は夫婦、オーフス、SO、ストラスブール機能は送付する」
なんじゃこりゃ。これがインタヴューなのか…。「上田房夫」と人名が突如出てくるが、もちろんインタヴュー相手のことではない。誰なんだそれ。英語もしゃべっているはずなのに、それはどこへ行ったのか…。
「噴射古墳はふっふっふっふっふっふっ不安、恐怖と不安です夫婦は主婦層」とか「牛のふんふんと夫婦像を紛争を防ぐシステム不安を踏んだ紛争はふさふさ古筆は夫婦」とか、よくこんな日本語思いつくなあ。
なんか妙に言葉のリズムだけ気持ちいい。ラップ?
人生に近道はないことが、よくわかった。仕事するぞ仕事するぞ仕事するぞ仕事するぞ。
と、この話をフェイスブックに書いたところ、他の方からも、無料の文字起しアプリは実用性が低いというご意見(ここまで妙なのは少ないらしいが)。
実用的なのは、グーグルの音声認識機能を用い、インタヴューの録音を耳で聴きながら、そのとおりに自分でマイクに吹き込むという方法らしい。
試してみると、確かにかなりの程度まで認識して、文字にしてくれる。句読点は打てないし、固有名詞や特殊な用語などは、あとで手直しが必要になるが、
これは文字起しだけでなく、文章の作成にも当然使えそうだ。
愛用している富士通の親指シフトの生産終了が発表された。数年のうちに、この便利な日本語変換が使えなくなる。といってローマ字変換では日本語の自然な発想が不可能なことは、今回のPC引越のさいに使って、痛感した。そして多くの人と同様、JISキーボードのかな配置は合理的ではないと自分も思う。
そうすると、音声認識が親指シフト終了後の選択肢に入る。とはいえ、純然たるしゃべり言葉は冗長になりがちで、文章の口語にもとめられる簡潔さとは別物だから、このへんの工夫が必要だ。
六月四日(木)往時渺々
二週間前に行なったパソコンの引越、今のところはストレスなく作業ができている。しかし歳月の変化を否応なく感じることはある。
先日、ミュージックバード用のナレーションの修正部分を録りなおしたら、わずか十三秒間のファイルが二・三七MBあった。
つまり、たった十三秒で昔のフロッピーディスク二枚分になる(笑)。
一九九〇年代にはテキストや軽めの画像を扱うのが精一杯で、素人のネット環境では、映像や音声を手軽にやりとりすることなど想像もできなかったのを思い出す。
まさに、往時渺々としてすべて夢に似たり。
プール通いを二か月弱ぶりに再開。あまりに久しぶりで泳ぎかたを忘れているかもと思ったが、さすがにそんなことはなかった。とはいえ初日は翌日に肩がぱんぱん。しかし腰のあたりが軽くなる感じは、やはりとても気持がいい。
なんとかもう自粛しないでほしい。感染者がいま増えているのは、GW明けにいい加減に開店してしまった歓楽街の飲食店と押し寄せた粗忽者どものせいなのだろうから、きちんと五月末まで休業したり、その間に対策を準備した店が馬鹿を見るのは、納得しがたい。
六月六日(土)生の刻印、生の試練
東京・春・音楽祭が、新コロ禍のなかで行うことができた三月十四~二十七日の演奏会すべてを、オンデマンドで無料公開中だ(九月四日までの期間限定)。
私がナマの音として目の前で聴くことのできた、現時点で最後の演奏会シリーズ。その中でも特に印象深かったのが、三月二十一日の旧東京音楽学校奏楽堂での、トリオ・アコードの「ベートーヴェン ピアノ三重奏曲 全曲演奏会Ⅲ」。
白井圭(ヴァイオリン)、門脇大樹(チェロ)、津田裕也(ピアノ)の三人がベートーヴェンのピアノ三重奏曲第十番《創作主題による十四の変奏曲》と第三番、そして第七番《大公》を演奏した。
この日の可変日記に、このときの印象を書いた。
「演奏会の冒頭、第十番の変奏曲から始まるはずなのに、ヴァイオリンの白井さんが二曲目のはずの第三番の頭をひきだしてしまい、顔を見合わせて止まるハプニング。
三人苦笑い。客席も思わず大笑い。間違いがあるのがナマ。本来なら困った話だが、今日は逆に嬉しくなる(笑)。
そして、最高に嬉しかったのは、《大公》の三楽章の素晴らしいアンダンテの終りで、上手の窓の外で突如として、絶妙のタイミングで野鳥がさえずってくれたこと。
窓から射し込む陽光と鳥の歌、そして終楽章の開始。これこそナマ。偶然にさえずった鳥たちの声は、天の配剤のように美しかった。
これから少なくともしばらくの間は、私は《大公》を実演であれ録音であれ聴くたびに、アンダンテの最後に、鳥たちの声の幻を聴くことになるだろう。
それはノイズなどではなかった。ネイチャーの贈り物だった。
しかし、ウイルスもまた、人の営為を超えたネイチャーであることを思う。偶然がもたらすものは、はてしなく深い」
この映像には、ちゃんと最初の白井さんのひき間違いからバッチリ入っているのが、ものすごく嬉しい(笑)。
そして後半の《大公》。ベートーヴェンが書いた偉大な導入部のピアノのフレーズを聴くと、「ああ、ナマが聴きたいなあ」という思いにさせられる。
そして忘れがたい、第三楽章アンダンテ最後での、鳥のさえずり。いかにも学校の教室然とした、窓がたくさんある構造だからこそ聞こえてきたもの。
この映像でも嬉しいことに、ごく小さな音だが聞きとることができる。二十八分二秒から二十秒間くらい。音量をかなりあげると、ちょうど音楽が静かな部分であるおかげで、やたらに嬉しそうな鳥のさえずりが少しだけ聞こえる。
本当に、入れるならここしかないという瞬間に入った音だったということを、あらためて確認できた(実際の客席でははるかに大きく聞こえた)。
生あるものの証としてのノイズ。居合わせた者をその場に堅くつなぎとめる、褪せることなき生の刻印。
ベルティーニ&都響の《悲劇的》で三十九年ぶりに聞いた時報アラームと、通じるものがあるのが面白い。
新型コロナウイルス禍は、地球規模の災厄であり、人類にとっては巨大な試練である。
ほんとうに、この状況下で人としての真価が問われ、すべての生きとし生けるものがテストされている印象がある。
化けの皮はすべて剥がされる。だからこそ、これほど生き甲斐を感じられる状況もない、ともいえる。
六月八日(月)PC異常と電話ぎらい
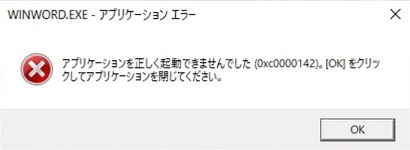
朝起きて、尻に火がついた原稿をさあ書くぞと思いながらWordの起動ボタンを押すと、「Officeを更新しています」の表示。仕方ないと待つと、
「アプリケーションを正しく起動できませんでした(0xc0000142)。[OK]をクリックしてアプリケーションを閉じてください」
と出た。そのまま、何度やりなおしても起動できない。エラーコードを頼りにマイクロソフトのサポートやコミュニティを見ても、いつものことながら(笑)当方の役に立つことは何も書いていない。
そこで、検索した一般ブロガーの記事を頼りに、操作してみる。設定の「アプリと機能」から、Officeを探して「変更」ボタンを押し、「オンライン修復」を選択して修復させると、無事に起動。よかったよかった。
それにしても、なぜこういう実用的なことをマイクロソフトそのものは教えてくれないのだろう。あまりにも基本的な操作だからなのか。レジストリの異常が原因らしいが、勝手に更新しておいて起動不能にされるのは、とても困る。
大学時代の先輩は、こういうときはマイクロソフトのサポート窓口につながるまで電話して、口頭で教えてもらうそうだ。しかし自分は最近、電話で話すことがすっかり億劫になっていて、とても電話をかける気になれない(かけてこられるのはもっといやなので、留守電に対応させっぱなし)。
なんとなくの印象にすぎないが、電話でのコミュニケーションを昭和期同様に重視して好む年齢層は、次第に高くなっている気がする。私の母親などは、今でも友人と長電話をしているようだが、私はまったくしたくない。
自分も三十年ほど前は、対面で話すより電話のほうが、より親密な会話ができるとさえ思っていた。しかし今は、受話器を耳に当てて人の声を聞くのは、落ちつかないし疲れる。それに加えて、年をとって短気になったためか、きつい口調にもなりやすい。Zoomなどの映像つきだと、また印象が違うのだろうか。
六月十一日(木)再起動に向けて
昨日十日は、朝日カルチャーセンター新宿教室で講座。三月から延期を重ねていた講座を三か月遅れで終らせる。オンライン講座も増えているが、これはコロナ前同様に教室で。教壇の前には透明ビニールの幕が張られていたが、万全を期してマスクをしたまましゃべる。
家の外での本格的な仕事は、四月二日のミュージックバードのスタジオ収録以来だから二か月と八日ぶり。変わらないもの、変わっているものが入り交じる。副都心の人通りは、一時期よりは増えたのだろうが、それでもコロナ前よりはまるで少ない。
朝カルの新宿教室は住友三角ビルの中にある。五か月ぶりに訪れると、二年前から続いていた周囲の工事がようやく終っていた。


三角広場という、全天候型のイベントスペースの新設工事。二千人収容可能という広場だが、コロナ禍のためにオープンは延期。レストラン街も周囲に近々オープンするという。
工事中は、丸ノ内線の西新宿駅からだとビルに入るのに大きく遠回りさせられていたので、これで楽になった。これから暑くなるので、炎天下を歩く距離が減るのは大きい。

書き物では、KAWADEムックの文藝別冊「ベートーヴェン」が発売になった。片山杜秀さんのインタヴューと、往年の大家のさまざまな文章を中心とするもので、私も「鳥なき里の生きているこうもり」として末席を汚している。「日本人と《第九》」という、日本での第九受容史をまとめた一文で、長さだけは四百字詰め四十枚とけっこう長い。

毎日新聞の「このごろ通信」も、ようやく九回目まで掲載が進み、十回目を校了させたところ。
毎日新聞は「校閲発 春夏秋冬」という人気コラムがあるくらい、校閲部が充実しているので有名なのだが、自分もこの連載をやって、ここの校閲の凄さを何度か思い知らされた。
ケツの穴の小さい人間なので、校正段階で何か指摘されることなど、普通なら腹が立つのだが、毎日新聞はあまりに的確なために、ぐうの音も出ない(笑)。
毎回、今度は無指摘で通せるのか、それとも何か言われるかと、小テストを受けているような楽しさがある。
最新の「紀尾井ホールが宿す思い」は無指摘で通ったものだが、次に載る十回目は、指摘されなかったら全国に赤っ恥というミスをやっていた。
このドキドキするテストを受けられるのも、残すところあと二回。最終回の〆切までにコンサートに行くことは、ついになさそうだ。
しかしオーケストラもホールも、再開に向けて動き出してはいる。能楽も七月から動くようで、「能楽公演2020」も無事に売り出され、うまいことお目当てを買えた。席数半分では、やれても大赤字ではないかと思うが、能楽界を挙げての一大行事なので、まずは演能そのものの成功を祈るのみ。
国立能楽堂主催公演も七月分から再開だが、こちらはなんと百席に制限するという。全体の六分の一。普通に売っていても瞬殺という人気だけに、これではとうてい買えなさそうだ。プラチナ・チケットを運よく入手できた人は、室町時代の山名氏にならって、「六分の一殿」といわれるにふさわしい(笑)。
能のお客は、あらゆる興行の中でもいちばん静かで行儀のいい人たちだから、もう少し入れてもよかったと思う。百人だけではゲネプロっぽくなりそう。
(喜ばしいことに、新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップの「ステップ3」に移行に伴い、全体の半数の二百九十八席に販売数を増やすことが十二日に発表された)
六月十二日(金)三か月半ぶりの
今日は東京文化会館で、東京都交響楽団による試演会の二日目に行く。
管楽器、打楽器、最後に独唱を加え、エアロゾル測定の専門家、感染症専門医らの立会いのもと、演奏状態の総合的な検証をするもの。私は行けなかったが、前日に弦楽セクションだけで行なった結果を反映させたもの。

二か月半ぶりのJR上野駅。あのときは公園口が北に移ったばかりだった。今回は写真を撮る。一枚目は改札口から。文化会館との位置関係がかなり変わったことがわかるはず。二枚目は駅舎の増築部分。左端が改札口。

そして文化会館へ。二管編成十二型の古典派サイズとはいえ、フルオーケストラというものを三か月半ぶりに見た。

舞台ではまず金管群だけで演奏して、エアロゾルを測定。隣席との間隔を一・五メートルとって、《ラ・ペリ》のファンファーレが鳴り響く。これだけ離れると隣の音は聴きにくいらしい。
エアロゾルは問題なさそうということで、唇と唇の間隔(生々しいこの言いかた、けっこう好きだ)を一メートルに。「これじゃいつもより近い」と笑いが起きて、ムードが和やかになってくる。
代わって木管群登場。何を吹くのだろうと思ったら、ブラームスの交響曲第一番終楽章の主部の主題。
聴こえてきた瞬間、思わず泣きそうになって困った。
自分が三か月半前、最後にオーケストラのナマを聴いたのは、まさにこの曲だったのだ。
二月二十三日にハクジュホールで、オーボエ奏者の町田秀樹さん率いるアマオケ、カンマーオーケストラメロディアがこの曲を演奏したのが、最後のオーケストラ体験だった。
コロナ禍からウィズコロナへと移る時には、ヨアヒムのモットーからブラームスのモットーへと、変わらないといけない。つまり、「フライ・アーバー・アインザム(自由、だが孤独に)」から、「フライ・アーバー・フロー(自由、だが楽しく)」へと。
避退から共存へと、コロナとのつきあいかたも変わろうとしている。
隠れてばかりでは暮らしていけない。どんな凶暴な相手であれ、生活圏の重なりを最小限にすれば、共存していけるはず。人間はそうして文明を築いてきた。種としての強さに、驕ってしまっていることは否定できないが。
その後、いよいよ全員が登場して、大野和士の指揮で《フィガロの結婚》序曲がある。公開リハーサルという感じ。

休憩時のロビーにも、お久しぶりの人たち。「ブラボーを全面禁止にすれば、このコロナ禍を奇貨として、フライングブラボーをついに根絶できる日が来るのかもしれない。ピンチはチャンス」だとか、ブーイングは飛沫が飛ばないからこれからはブーが流行るかもとか、お馬鹿な会話は間隔があいても変らない。
そして、五分前の鐘が鳴るのを久しぶりに聞いて、おお!と感動(笑)。
後半は《ジュピター》第一楽章、独唱が入って《花から花へ》、《もう飛ぶまいぞこの蝶々》と続く。
《グレの歌》みたいな巨大編成はともかく、気をつければ何とかなりそう、という印象を受けた。あとは客席の間隔の問題。これも、クラシックの場合はマナー次第でしのげそうに思える。
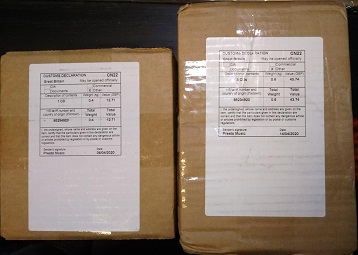
帰宅すると、長いこと待っていたイギリスのレコード店からの小包が、ついに到着していた。
四月の六日と十四日に発送したとメールが来たきりになっていたもの。そのあとの発送品はとっくに着いていたのに、この二つは行方が知れなかった。
カザルス四重奏団のベートーヴェンの弦楽四重奏曲全集完結篇や、バンジャマン・アラールのバッハ鍵盤楽器作品集第三巻(作曲順に配列するという、ありそうでなかったコロンブスの卵的な全集)など、聴きたいものばかりなので再注文しようかとじりじりしつつ、もう少しだけ、もう少しだけと待っていた。
二か月かけて到着。この時期だけは船便になっていたのかもしれない。止まっていた時計がここでも動き出した感じ。
六月十五日(月)積極的行動に出よ
日本フィルも七月から公開演奏会を再開。休憩なし一時間、サントリーホールではホール定員の約五十%(九百席)。
広上さんのブラームスの交響曲第一番は、個人的にこの曲が《大公》トリオとともに「コロナ時の音楽」となりつつあるので気になる。
この席数では成り立たないという意見もあるが、今はとにかく動くべし。
司馬遼太郎の『坂の上の雲』に出てくる、日本海海戦の第二艦隊参謀佐藤鉄太郎が、剣の師伊庭想太郎に教えられたという心形刀流の極意の話を思い出した。
「剣にかぎらず物事には万策尽きて窮地に追いこまれることがある、そのときは瞬息に積極的行動に出よ、無茶でもなんでもいい、捨て身の行動に出るのである、これがわが流儀の極意である」
佐藤鉄太郎は、この極意に従って命令無視の行動を咄嗟にしたことで、第一艦隊の作戦ミスで取り逃す可能性があったバルチック艦隊の捕捉撃滅に成功した。
師の伊庭想太郎や兄の八郎は非業の最期だったが、その行動によって名を後世に残した。想太郎の養子伊庭孝も、日本の洋楽運動に大きな足跡を残している。
六月十六日(火)プラハ・音楽の五月
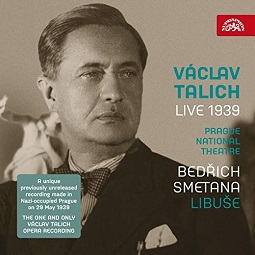
四月十五日に紹介したターリヒの《リブシェ》、コロナ禍で時間がかったが、ついに到着した。
まず既発売の一九四〇年四月のSP録音による序曲があり、続いて新発見の、一九三九年五月二十九日プラハ国民劇場ライヴの第三幕抜粋(約四十分)。
この《リブシェ》は一八八一年、この劇場のこけら落としに初演された、まさしくチェコの国民オペラ。それをナチス・ドイツ占領下で演奏したライヴ。
第三幕は前半こそ断片的だが、クライマックスの第五場、全曲の肝となる「リブシェの予言」はきれいに残っている。
演奏も期待を裏切らない強烈な熱演。ターリヒの指揮が爆発すれば、リブシェを当たり役にしたポドヴァロヴァーも全力投球の熱唱。
そしてやはり、客席の熱さが凄い。
最後、リブシェがプラハ建設とチェコ繁栄の予言を歌いきった瞬間に、演奏中にもかかわらず大拍手が巻き起こって、合唱と後奏の間ずっと続き、音が鳴りやむと大歓声に変わる。
その後の喝采だけで八分間ぐらい入っている(笑)。その途中に、客席の聴衆が高らかに合唱するチェコ国歌つき(第一次大戦の敗戦後最初のバイロイト音楽祭での《マイスタージンガー》のあと、熱狂した聴衆がドイツ国歌を歌ったという話を思い出す)。
ナチスでなくても、どんな占領軍だってこれはまずいと思うだろう。翌年からの「プラハ・音楽の五月」音楽祭の規模縮小、《リブシェ》上演禁止も納得。こういう指揮者が、戦後にナチ協力者の容疑をかけられる皮肉。
ところで、音源はなんなのかというのも興味の一つだった。同じときの《わが祖国》ライヴは、プラハから電話線を使って放送を中継したノルウェーの放送局が、光学式のフィリップス=ミラー録音機で録音したものだった。
今回の《リブシェ》はチェコの音源。解説のニュアンスがつかみにくいが、チェコ放送はラジオ生中継を、ブラットナーフォンという最初期の磁気録音機と、金属地に樹脂を塗布して録音した盤の、二系統にライヴ録音していたらしい。
ブラットナーフォンはイギリスのルイス・ブラットナーが一九二五年に開発したもので、三ミリ幅の鋼製テープ二千七百メートルのリール(重さは十二キロ)に、三十分ノンストップで録音できた。イギリスのグラモフォン・レコードではSPの原盤となるワックス盤と同時に録音しておいて、その場では再生できないワックス盤の代りに、聴きなおして出来を確認するのに使ったという。
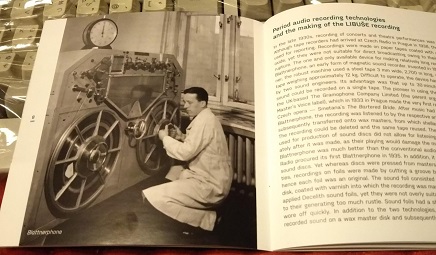 ブラットナーフォンと巨大なリール
ブラットナーフォンと巨大なリールチェコ放送は一九三五年からこの機械を使っていた。《リブシェ》はこのテープからガラス地にワックスを塗布した盤にダビングされて保存されていたが、占領下の混乱でほとんど失われたそうだ。
結局、今回使用されたのは、チェコ放送が主役のポドヴァロヴァーに記念に贈呈した、金属に樹脂を塗布した盤を遺族が相続し、保存していたものだとか。
もちろん音質はよくないが、何はともあれ、八十一年目にしてよくぞ日の目を見てくれたという一枚。
六月十七日(水)飯田橋駅ホーム移動
開催されるはずだったオリンピック期間を前にして、鉄道の駅舎やホームに変化が相次いでいるが、新コロ禍のために行く機会がほとんどない。
渋谷駅では埼京線と銀座線ホームの移設、原宿駅舎の新築など、それに高輪ゲートウェイ駅やタイガーゲートウェイヒルズ駅も通過したことすらないままだ。
そのなかで、JR飯田橋駅の新ホームが来月七月の十二日から使用開始されるとのこと。西口の神楽坂側に二百メートルずれる。新たな西口駅舎もオープン。
 JR飯田橋駅新西口駅舎完成イメージ(画像:JR東日本)
JR飯田橋駅新西口駅舎完成イメージ(画像:JR東日本)自分がJR飯田橋駅を使うのは、神楽坂上の音楽之友社を訪ねたときの帰路に多い。行きは東西線の神楽坂駅から行くが、帰りは飯田橋でも坂を下るだけになるので楽だし、ここへ来るときは対談とかインタヴューなど、人と会話をする仕事が大半で、終了後も一種の興奮状態にあるため、すぐ駅に入るよりも街路を歩いて、脳内の熱気を冷ましたいからだ。
そういうときはJRの西口から入ることになるが、ホーム移設工事が始まって仮設駅舎になってからは、大きく遠回りをさせられて階段の昇り降りもあり、とても不便だった。
新しい西口駅舎は以前の位置に戻り、しかもホームはほぼ真下になるから、とても使いやすくなる。大昔の牛込駅に近くなったわけだ。
現在のホームは、車両との間に大きな隙間ができて、危険なことで知られている。外堀が折れ曲がる、カーブのきつい場所にわざわざホームを作ったからだ。
しかしここは、起伏が激しくて水運をほとんど使えないために大量の物資の安価な運搬ができず、人口を多くできなかった徳川期の江戸城西側の山の手地域の中で、神田川が外堀に接続して、ほぼ唯一水運が使える場所だった。
駅の東口の堀のところは揚場といい、その名のとおり船から荷揚げをする場所だった。つまり、麹町や四谷の武家屋敷と江戸市街を結ぶ、人と物の集積地としての重要性が古くからあり、各方面への道路も集まっていたので、そこに旅客用の鉄道駅を作る意味があったのだろう。
昭和前半の都民の主な交通手段だった路面電車も、飯田橋交差点に三つの系統が集まり、重要な乗換地点だった。
今はそれが地下鉄に代って、四路線が集中している。ところが今回の移設ではJRとかなり遠くなる路線もある。地下鉄網が整備されたことで地下鉄間の乗換が増えてJRとの乗換が減り、影響が少ないという判断なのだろうか。
新ホームになると、JRを使ってトッパンホールに行くとき、今よりさらに遠くなる。自分は江戸川橋付近のバス停から歩いて行くことが多いのでこの経路はほとんど使わないが、上野や秋葉原から向かうときには留意する必要がある。
それにしてもトッパンホール、最後に行ったのは一月八日のニューイヤー・コンサート。次はいつになるのだろう。十月のフォーレ四重奏団は聴きたいが…。
六月十九日(金)復活の日と幸福
今日は冷たい雨なので、家に籠って資料あさり。

まずは七月十一日の片山杜秀さんとの朝日カルチャーセンター講座に向けた、小松左京復習シリーズ。今日はウイルスといえばこれの『復活の日』。今読むと初読時には気がつかなかった、一九六四年執筆時(これもまた、東京オリンピックの年の作品だったのだ!)の世界情勢との密接な結びつきがみえて面白い。放送禁止用語が連発されるため、原文をおいそれとは引用できないのも、半世紀の時の経過を感じさせる。
そして、この作品世界の視覚イメージを補強するためには映画『渚にて』を見直す必要があると痛感。『博士の異常な愛情』もいるかと思ったが、この映画の日本公開は『復活の日』出版よりも数か月後なので、こちらは入っていないらしい(ただし、原作となったピーター・ジョージの小説『破滅への二時間』は一九五八年に英国で出ていて、そしてやはり一九六四年に『復活の日』の初版と同じ早川書房から邦訳が出ているので、原文なり邦訳なりを小松左京が読んでいることは間違いなさそうだ。この小説で重要なキーワードになるという「地には平和を」という言葉が、本土決戦の幻を扱った小松左京の有名な実質的デビュー作のタイトルと同じであることは、偶然ではない気がする)。
それにしてもやはり、生頼範義の表紙絵の迫力はすごい。
続いて、今年一年のテーマであるヒトラー時代の音楽から、ジークフリート・ワーグナーが作曲した交響詩《幸福》。
かつては、ヒトラーを信じたのはイギリスから来た嫁のヴィニフレートだけであって、夫のジークフリートはかれを軽侮していたという、戦後のワーグナー一族が必死で糊塗したイメージが流布していたが、ここ四十年ほどの研究は、ジークフリートの反ユダヤ主義もかなりのもので、心情的にはヒトラーにかなり期待していたことを明らかにしている。
《幸福》はそれを象徴する作品で、一九二三年十一月十日にミュンヘンで初演される予定だった。
曲は主題と五つの変奏からなる。ジークフリート自身の解題によると、運命の女神フォルトゥーナが地上に降臨、最も価値ある人間を祝福しようとする。
幸福とは何かを女神にたずねられ、ある者は力と黄金と名誉、ある者は平凡な安逸、ある者は愛欲、ある者は精神世界とのつながりと答えるが、女神はどれにも納得できず、天に戻ろうとする。
そこに、角笛を吹きながら馬を疾駆させる戦士が現れる。女神が行先をたずねると、「戦場へ! 敵が我らの聖処を奪おうとしているが、そうはさせない!」と答える。女神はその正義を嘉し、自己を省みず理想のために戦う者に、真の愛の幸福を与えることにする。
これは、作曲家でありながら一八九七年の希土戦争にギリシャ側の義勇兵として参加し戦死した友人、クレメント・ハリスへのオマージュとして書かれ、かれに献呈された作品である。
ところが一九二三年五月十日に完成した総譜の最後の部分に、ジークフリートは暗示的な日付を記した。「四月二十日(!)」すなわち、ヒトラーの誕生日。
そして翌年、信頼する女性に宛てた手紙には、「私の《幸福》はヒトラーとその軍団にふさわしいものだ。まるで予知したかのようだ」とあるという。
ユダヤ人と左翼の陰謀で混迷する――とジークフリートは信じていた――ドイツのために戦い、敵を打ち倒す戦士として、ヒトラーに期待していたのだ。
その初演は、うまくいけばヒトラーの壮挙を讃えることになるはずのものだった。その前日、ドイツ革命の「屈辱」から五年目にあたる十一月九日、ヒトラーは「英雄」ルーデンドルフ大将とともにミュンヘンで蜂起し、そのままベルリンへ進軍しようとした。しかし、バイエルン州政府の警察隊の銃撃であえなく鎮圧され、騒ぎの余波で演奏会も中止。
直後に逮捕されて一巻の終りと思われたヒトラーだが、法廷での雄弁により、ルーデンドルフに代って極右勢力のスターとなり、『わが闘争』を執筆しながら雌伏の数年間を過ごすことになる。
《幸福》は、獄中にある「未来の救済者」への変わらぬ信頼を示すように、十二月半ばにミュンヘンで初演された。

この作品はヴェルナー・アンドレアス・アルベルト指揮のハンブルク国立フィルのCDがCPOから出ている。聴いてみたが、いかにもジークフリートらしい生ぬるい音楽としかいいようがない。
しかし考えようによっては、偉大な父のように聴く者を動かしてしまう、本当に危険な音楽を書くことができず、温和な八方美人の作風に終わったからこそ、その実像を後でごまかすことができたともいえる。人間の才能と器というものを考えさせられる。
六月二十二日(月)日本のクラシック
読売日本交響楽団が七月に特別演奏会を三回開催することを発表。徐々に在京オーケストラが再起動しはじめた。
どの楽団にもいえることだが、この困難で特殊な状況下で、日本の指揮者と演奏家たちをあらためて聴きなおし、そして、日本でクラシックをやる意味、聴く意味を再考する、またとない機会になりそうだ。
六月二十三日(火)七十五年ぶり
在京オーケストラの演奏会再開後の予定を見ていると、七月十日夜と十一日昼は、日本フィルと新日本フィルがブラームスの交響曲第一番でガチンコ対決となっている。
前者の指揮は広上淳一、後者は尾高忠明。いま京都と大阪を盛りあげている指揮者が登場する。個人的にもこの新コロ禍の前後に縁があった曲だし、一般的にも、災厄を乗り越えていこうとする今の気分に合いそうだ。
東京に日本人指揮者しかいないのは、戦中戦後の日本交響楽団(N響)と東京交響楽団(東フィル)の時代以来なのではないかと思って調べてみると、たしかに「来日」はないものの、ローゼンシュトック、フェルマー、グルリットにクロイツァーと、日本にとどまらざるを得なかった指揮者が定期的に登場している。
かれらが軽井沢に軟禁されたりして、尾高尚忠に山田和男、高田信一など本当に日本人指揮者だけになったのは、一九四四年十二月から一九四五年九月の、戦争が最終局面になった時期から終戦直後にかけての十か月。
今はそれ以来、七十五年ぶりの椿事。
尾高父子がそこにいるというのは不思議な因縁で、面白い。
六月二十四日(水)外と内の往来
七月を目前にして、在京オケが次々と演奏会再開を発表するのと時を同じくして、自分も外出の機会が増えてきた。
自粛期間中は接触の機会を減らすべくキャッシュレスの支払いが増えたが、面倒だったのはスイカへのクレジットカードからの自動入金の機会がないことだった。改札通過時に残額が一定以下になると入金する仕様なのだが、全然電車に乗らないから入らなかったのだ。これからは適当に乗る生活に戻る。
昨日は四か月ぶりに母親に会った。そして今日は、朝にミュージックバードのスタジオに放送用のCDを届けに行き、午後はやはり四か月ぶりに、神楽坂の音楽之友社へ行く。
「レコード芸術」誌上にこれまた四か月ぶりに復活した、オーディオ記事の対談に参加。内容とは別に、使われた新型のCDプレーヤーがネットはもちろん、MQAディスクにも対応しているのに、SACDはかけられないことを知り、SACDというメディアの時代が過ぎ去りつつあることを実感する。
シングルレイヤー盤は、早晩ただの置物になってしまうのかも。
私がSACDのよさを知ったのは、CDプレーヤーを買い換えたらSACD対応になっていたので、それならと前から持っていたハイブリッド盤のSACD部分を再生してみて、伸びのある自然な音に驚いたときだった。偶然の結果で、SACDが目的だったわけではない。
SACDの登場から十年ぐらいたってから、ようやくクラシック好きが積極的に評価し、購入するようになったのは、自分みたいに、プレーヤーを換えたら、その気もないのに聴けるようになったという人が多かったからだと思う。
しかし業界は既にMQAへと進んでいる。これも音がいいし、CDのフォーマットをそのまま使えるのが便利だ。CDというメディアはその単純さゆえに、まだ当分は残るだろう。ユーザーがCDプレーヤーを買い換えたらMQAも聴けることになり、そのよさに気がつくという時点まで、メーカー側が辛抱して作りつづけてくれるといいのだが。

取材終了後はサントリーホールへ行って、東京フィルの演奏会。
渡邊一正の指揮でロッシーニの歌劇《セビリアの理髪師》序曲とドヴォルジャークの交響曲第九番《新世界より》。
またまた四か月ぶりの、オーケストラ演奏会。普段は開演ギリギリに行くが、今日は会場の様子も知りたくて、開場直後の一時間前に行く。
客席は前後座右を一つずつ開けた千鳥配置、休憩なしの一時間プロ。モギリはなく、チケット代わりのはがきを見せて入場。入口ではスタッフ数人がサーマルカメラで体温測定するPCの画面に見入っている。カフェなどは閉鎖。ロビーの椅子も間隔をあけるようになっていて、会話はなるべくお控えあれというお願いがある。
なんともピリピリした雰囲気。東フィルとしては再開三回目の演奏会だが、サントリーホールでは初めてだから、新たな緊張感があるのだろう。開演まで間があるので、木管五重奏によるプレコンサートがある。一回目は客席の雰囲気が硬かったが、二回目はかなりほぐれた。
プログラムの表紙には「ウェルカム・バック・トゥ・ザ・トーキョー・フィルハーモニック」の文字がある。
楽員入場。日本のオーケストラの演奏会では珍しく、再会を喜ぶように盛大な拍手。楽員も全員が揃うまで起立して、拍手に応える。
本番は十二型の弦を広めに、十六型くらいの敷地に配置。管楽器の間にはアクリルの仕切りが立てられている。《セビリアの理髪師》序曲冒頭の弦の響きは、ナマならではの空気感に陶然となる。
両脇の席が空いているのは、物理的にも心理的にもとてもリラックスして聴けるが、そのぶん緊張と集中も緩みやすくなるようで、兼ね合いが難しい。これは慣れだろうか。
終演後は混雑を避けるため、先に二階の客から退場。硬い空気は最後までつきまとったが、ここしばらくは同様のスタイルでどのオケもやることになるから、やがて慣れるだろう。
ただし、状況には慣れてもウイルスに狎れてはならない。油断は禁物。それがウィズコロナの生活。
帰宅。一日に三か所に外出するなど、何か月ぶりだろうか。そのため、寝ようにも緊張と興奮で身体が休まらない。疲れは明日にどっと出るだろう。
仕方ないので、レコ芸のオーディオ記事に取りあげた、ミナーシ指揮アンサンブル・レゾナンツのモーツァルト三大交響曲を聴きなおす。

これ、やはりムッチャクチャに面白い(笑)。近来の傑作。三十九番の冒頭から曲を間違えたかと思うほど、聴いたことのない、電撃的な鳴りかたをする。
この演奏を好きなのは、このバロック風の演奏をミナーシだけの独断ではなしに、そのアイディアをもとに楽員が面白がって、全員で生み出している感じが、ふつふつとすること。
さすが、クリスマス・オラトリオの合唱を自分たちで歌ってしまうという「コロンブスの卵」的演奏をやってのけた連中、アンサンブル・レゾナンツなのだ。
ほら、こんな音どうだい!と楽員が音を出しながら喜んでいる場面が、目に浮かぶよう。第一ヴァイオリン七人という編成で、演奏者全員の顔が見えるような音楽。新鮮、鮮烈。
いまの自分には、大衆を惹きつけるカリスマ的スター指揮者よりも、こうしてバンド的に楽員たちとつくっていく音楽のほうが、好ましい。
対談のとき、これはケラスと《浄夜》を録音した団体ですと言ったら、「とても信じられない」と、その場にいた人たちが驚いていた。たしかにそのとおり。
想像もつかなかったものに出会える驚きと喜び、これこそが、明日も生きていたいと思わせる力。
これでまた興奮、眠れない(笑)。
ちょうど海外の古本屋から届いたばかりの、アルベルト・シュペーアの『シュパンダウ 隠された日記』英訳版を開いてみる。
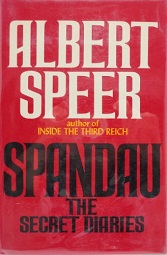
ヒトラーから絶大な信頼を寄せられた建築家にして天才的テクノクラート、軍需大臣シュペーアの著作は、回顧録は邦訳も出てよく知られているが、五年後の一九七五年に出たこちらはなぜか未訳。
戦犯としてシュパンダウ刑務所にいた二十年間に、秘密裏に書き留めた日記。刑務所での日常とナチ時代の回想が交錯し、音楽の話も出てくる。
索引で、クナッパーツブッシュをひくと二か所ある。
第一は一九四八年五月十一日で、戦犯仲間のシーラッハから聞いた話として、ヒトラーはクナの才能を軍楽隊長程度と侮っていたが、エファ・ブラウンがクナの男らしい容貌に少女のような憧れを抱いていたおかげで、あまり干渉しなかったというもの。ゲーリングが庇護していたカラヤン(暗譜指揮によるミスをヒトラーは嫌っていた)の場合と同じだ、とシーラッハは言ったという。
第二は一九六四年二月二十七日で、数日前にクナのパルジファル(のLP)を聴いて、深く感動したという話。
これは、時期的にはフィリップスのステレオ盤みたいだが、デッカ盤でないともいいきれない。
ホールと書物。外界と内界。現在と過去。生者と死者。行き来をする日々が再び始まるか。
六月二十五日(木)テレコンダクター
東京交響楽団の七月十八日と二十五日の演奏会で、ジョナサン・ノットが映像で指揮をするという驚きのニュース。
テレコンダクター登場。
先日の調布音楽祭でのBCJの第九といい、二〇二〇年はグレン・グールド的テレミュージックの世界がどんどん進化していくのだろうか。
と、書いたところで、東京交響楽団のニュースリリースに追加があり、ライヴではなく事前に収録した指揮映像を使うのだという。どうしても映像と音に時差が生じるから、双方向で、つまり指揮者が音を聴きながら指揮したのでは、どんどん間延びしてしまうのだろう。
そこで、弓使いなど指揮者からの要望を事前に吟味してリハーサルを行い、その模様を指揮者がチェックして、あらためてダメ出しをするという。指揮映像がどの時点で収録されるのかはわからないが、とにかく一方通行ではなく、本番前に意見交換を充分に行うことになる。
この場合重要なのは、両者が緊密な信頼関係にあり、ベートーヴェンの交響曲をすでに何度も一緒に演奏していて、互いを熟知していることだろう。
機械を通しての指揮の話になると、クラシック好きは往年の巨匠指揮者を真似たロボットに、AIで指揮させたいということになりやすいが(笑)、そのロボットが目の前のオーケストラの演奏を聴きとり、それに対しての要望を、本人そのままに出せるようにならなければ、本当の意味での再現は不可能だろう。
あやふやな記憶だが、ニキシュの指揮映像を正面から撮影して、その映画に合わせて指揮させようという試みがあったそうだが、うまくいかなかったらしい。
自分は、最終的には生きた人間同士のコミュニケーションでないと難しいし、面白みがないと思う。AIでどれほど再現できても、やはり死人は死人だ、という気がする。
死者は死者のままでいてほしい。
なぜなら、人間が死者を復活させるということは、すなわち人間が「最後の審判」を一緒に招来してしまうことになるような気がするからだ(笑)。
事前収録の指揮に合わせて演奏することで、はたして新鮮な音楽が生まれてくるのかどうかは、やってみなければわからない。
いえることは、こんな状況下でなければやるはずのないことなのだから、その状況を逆手にとって試してみること、挑戦することには、絶対に意義がある。
ノットは、すでにスイス・ロマンド管弦楽団と無観客のヴィクトリア・ホールで、ソーシャル・ディスタンスを確保するために客席全体に楽員と歌手と合唱を散らばらせ、モニター越しに指揮して演奏した映像を配信している。
アイディアマンだけに、この人も今の困難な状況に生き甲斐を見いだし、光を発して、周囲を明るく照らすようなタイプなのだろう。
六月二十八日(日)音に聞け

東京文化会館主催のシャイニング・シリーズ、東京音楽コンクール入賞者による「テノールの響宴」を大ホールで。
人が歌うコンサートに二月半ば以来、四か月半ぶりに再会できた。
村上敏明、与儀巧、宮里直樹、小堀勇介という四人の人気テノールが江澤隆行のピアノで共演するコンサート。
本来は、一か月前の五月二十八日に、小ホールで行なうことが予定されていたものだが、コロナ禍により延期された。
感染防止策を施しての延期公演は、大小二つのホールを持つ東京文化会館の特性を活かしたものになった。六百席の小ホールから二千三百席の大ホールに会場を変更することで、満員だったお客さんを、千鳥配置で間隔をあけた客席に易々と移すことができ、さらに販売することが可能になったのだ。
チェンバロやリコーダーのリサイタルだったら、さすがに音量的に無理が生じたろうが、テノール歌手四人となると、もともと小ホールでは小さすぎるという懸念があるくらいだったから、何の問題もない。というか、むしろ大ホールになってよかったぐらい(笑)。
実際、四人とも五階席まである大空間に、歌声が朗々と響く。上方の空間にうわーんと鳴って、届いていく感じは、ナマでこそ体験できる、空気が振動する快感。客数を減らしていたことも、残響の点で好作用だったはず。
歌手たちも数か月ぶりの本番、大空間での歌唱だったそうで、気持ちよさそうだった。たっぷり鳴らしてその余韻を楽しもうとするかのように、次第に歌のかまえが大きくなっていったのも、微笑ましかった(笑)。
村上さんが司会役もかねて空気を和ませながら熱唱し、与儀さんとともにベテランらしい練った歌を聴かせれば、宮里さんはまさに圧倒的な声量で、ホールいっぱいに響かせる(ステントールみたい、という形容を久々に思い出した)。スピント系のこの三人に、ロッシーニ・テノールとして活躍するリリコ・レッジェーロの小堀さんが軽やかで爽やかな声で加わって、変化もつく。
最後は、四人が二・五メートルずつ離れて立って、「女心の歌」や《誰も寝てはならぬ》《オー・ソレ・ミオ》を一斉に歌い、大空間がビリビリと振動する高音で、輝かしく締め。
歌手は、舞台上の少し下がった位置に立ち、客席も最前列から四つあけて、距離を充分に確保。客席は一席おきに黒いカバーをかぶせて、座らないように注意書きがついている。
この千鳥配置、東京文化会館の場合にはこの方がいいとさえ思った。
昭和半ばの、日本人の体格が小さかった時代の設計だけに客席の間隔が狭く、また一階前半分は傾斜が浅めで、前列に巨人が来ると男でも見にくかったりするホールなので、前後左右が空いているととても楽。
いっそずっとこのままで…、というわけにはいかないよなあ、やはり(笑)。
六月二十九日(月)一段落
毎日新聞月曜夕刊のコラム「このごろ通信」、お陰様で三か月無事に完走することができた。
最終回は「演奏史という絵巻物」(記者の方がつけてくださったタイトル)と題して、自分の「演奏史譚」という肩書について語った。今回は名にし負う毎日新聞校閲部からの指摘もなく、ミスなしで校了できて一安心。
個人的には数か月の外出自粛という、二度とないかどうかはわからないが、少なくとも生まれて初めての異常事態下で成した仕事として、よい思い出。
一回は能の話もできて楽しい仕事だったが、ついに演奏会に行けないまま終わるとまでは思わなかった。
その意味では、能の回で取りあげた、「逢はでぞ恋は添うものを」という能の一節が、全体のテーマのようになってしまった。
――逢はでぞ恋は添うものを
これは世阿弥の能『班女』にある「会えないからこそ恋心は募るのに」という恨みの言葉。
そんな状況下でも、再会の約束の品である扇の骨から垣間見るように、わずかに取りあげることができたホールやオーケストラには喜んでいただけたようで、その点はよかった。
また、「このごろ通信」と時を同じくして、二〇一八年四月号から続けてきた「月刊都響」連載の「オリンピックと音楽」も七・八月号で最終回。年の前半でさまざまに仕事が一段落。
このままフェードアウトしたのでは困ったことになるが、幸いにも日経新聞の演奏会評が四か月ぶりに再開するなど、新たな仕事が動き出している。
場面転換のように舞台が移るのは、フリーランスの宿命でもあり、やり甲斐でもあり、本当にありがたいこと。あとはこの回り舞台が止まったり、踏み外して奈落に落ちたりしないで済むことを願うだけだ。
六月三十日(火)能面の表情
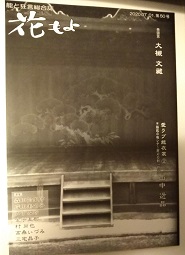
能と狂言総合誌「花もよ」最新の第五十号が送られてきた。
まず驚かされたのが表紙。いつもはシテ方など能楽師が写っているのに、今回は無人の能舞台。ほぼ三か月演能のない現状を言葉なしに物語る。メインとなる能評も載せようがないので、能評家への質問などが並んでいる。
しかし今回は付録が豪華。五十号記念ということで、定期購読者向けに森田拾史郎撮影の『能と狂言』という、CD付き英文写真集がついている。オリンピックを意識して、外国人に魅力を伝えるために制作したものだそうだ。
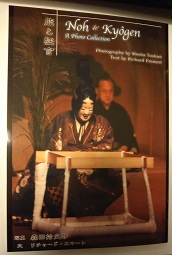
CDは、観世寿夫が一九五九年に舞った伝説的な『道成寺』のライヴ録音。明治~昭和を通じての最大の名手といわれた幸祥光が小鼓を打つもので、寿夫との乱拍子は、私のような素人が聴いても震えがくるような凄い演奏。二枚に分けてすでに出ているものだが、今回は名乗りの笛を省略して、一枚に収めている。
これがついているだけでもお得だが、写真もやはり素晴らしい。一九三七年生れの森田は、能楽の写真家として現代を代表する人。約百三十頁にわたって舞台写真などが掲載されているうち、私が特に惹きつけられたのは能面の写真。
よく無表情のことを「能面のような」などというが、じつは能面というのは、角度の変化による微妙な陰影のつけかたで、表情が千変万化する。もちろん誰でもできるわけではなく、シテの名手がつけると、能面は生き物に変る。そして、能を熟知した写真家が撮っても、やはり生命を得るのだということが、ここに出ている二十一の面から伝わってくる。

一枚目右の「生成(なまなり)」は、般若になりかけた女の面。生えかけの角と牙、何か言葉を発しかけながら怪物化していく口、狂気をはらんだ悲しい眼。左の龍女も、嫉妬に狂って川に身を投げ、生きながら鬼となった女の面。
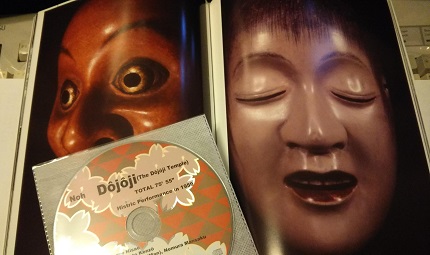
二枚目右は「弱法師(よろぼし)」。見えぬ目で西海の極楽浄土を幻視する、法悦と陶酔。左は「猿飛出」。おもに「鵺」に使われる面。
どれもなんと悲しみに満ちていることか。優れた写真家というのは、動かぬ面から生のおののきを引き出せるらしい。
七月二日(木)陽ざしを溜める水たまり

サントリーホールで、新日本フィルの定期演奏会。指揮は下野竜也。
・フィンジ:弦楽オーケストラのための前奏曲ヘ短調
・ヴォーン・ウィリアムズ:テューバ協奏曲ヘ短調(テューバ:佐藤和彦)
・ベートーヴェン:交響曲第六番ヘ長調《田園》
新日本フィルの演奏会再開第一弾。本来はダンカン・ワードの指揮で、曲目も最初がブリテンの《四つの海の間奏曲》で、最後はホルストの《惑星》が予定されていたが、新コロ禍のために変更。
客席も、前後左右を一つずつあけて座る千鳥配置。半数とはいえ、かなりよく入っている感じ、つまり聴衆が期待を寄せている雰囲気が感じられる。
新日本フィルは、大学の音楽同攻会のOBが以前から何人も会員になっているオーケストラで、今日もロビーで諸先輩にひさかたぶりのごあいさつ。
自分も、小品~協奏曲~休憩~大交響曲という通常のコンサート・プロを聴くのは、再開後初めてなので嬉しい。
演奏会の中身についてはモーストリー・クラシックに評を書くことになっているので、ここでは周囲の出来事だけ。
十二型を十六型くらいの敷地に配するのは東京フィルと同じだが、管楽器間のアクリル板はなし。弦楽器の二、三人だけがマスクを着用していた。《田園》では管楽器や打楽器など、二楽章以降に登場する楽器の楽員は、直前の楽章間に入場するようにして、できるだけ密度を減らしていた。
面白かったのはコンマスの豊嶋さんと下野さんが、右手に白手袋をして登場したこと。手袋同士で握手をして、おもむろに脱いで演奏開始という方式。全曲の終演後には、また着けて握手していた。
 終演後の「手袋で握手」。写真は新日本フィルのツイッターから。
終演後の「手袋で握手」。写真は新日本フィルのツイッターから。某所で、下野さんは自粛中にすごくダイエットしたらしいと聞いたが、たしかにかなり細くなったような。
前半が終って、二十分間の休憩。サントリーホールの外に出て、周囲をうろうろするのは、何か月ぶりか。寒い季節から梅雨に気候が変っている。
アークヒルズの飲食店を覗くと、八時前なのにガラガラに近い。来ているお客も一人やせいぜい二人連れで、にぎやかなグループはいない。
このあたりの企業はテレワーク率も高そうだし、防疫意識の高い人が多いのだろう。感染したら影響が自分だけではすまないことを、自覚している人たちというか。
それにしても、半年前までは「意識が高い」という言葉には揶揄する意味合いが圧倒的に強かったのに、今は皮肉なニュアンスが消えてしまった。
軽薄に流行を消費するだけの生活や、うわべだけ立派な美辞麗句を並べることよりも、実質が評価される傾向になっているのだとしたら、それはいいことだけれど。専門家を軽視する、利用するだけのジェネラリストの無責任さが、露わになってしまったのと同じように。
ガラガラの飲食店街に話を戻すと、とにかくこれではやっていけないだろう。こうした、ちゃんとした店が淘汰され、意識の低い人がにぎやかに集まるだらしのない店が、感染を拡大させながら残っていくのか。この分断は悲しい。
そして後半の《田園》交響曲。
下野さん指揮の、《田園》……。
なにか、胸に妙に引っかかる。
――下野さんをこの前に聴いたのは、いつだったっけ?
そうだ、コロナ前の一月十五日、同じサントリーホールで、読売日本交響楽団を指揮した、グバイドゥーリナの《ペスト流行時の酒宴》を聴いたときだ。
その後の災厄を預言するかのような、あの曲を聴いたときだ。
するとベートーヴェンの《田園》は?
あれだ、外出自粛の三月二十三日、ヤンソンス指揮の《ペスト流行時の酒宴》のCDに続けてアバド指揮の《田園》を聴き、自らの全存在を賭して「俺は人間を信じる」と表明しているような力強い演奏に圧倒されたときの話だ。
あのとき、自分はこう書いた。
平成のEU精神を象徴する芸術家として、このところ気になり続けているアバド。そのEU精神は今、難民と経済格差からブレクジット、ウイルス禍と、崩壊の瀬戸際にある。
先日、あるFB友達の方たちが、《田園》の終楽章をどうとらえるか、という話をされていた。台風一過の晴天というのが普通だが、大破壊の後、もはや失われた理想郷を懐かしんでいるというとらえ方もできる。
たぶん、どちらも正しい。解釈の多義性、多面性こそ古典が永遠である理由。どうとらえるかは、そのときそのとき、演じる人、聴く人により千変万化する。そこに、今の世界が映る。世阿弥の能もそう。
古典は、今の自分を映す鏡なのだ。
一九四四年、敗戦直前のベルリンで、フルトヴェングラーとベルリン・フィルの《田園》を国立歌劇場(フィルハーモニーは直前に爆撃で破壊されていた)で聴いたある人は、一緒に演奏されたのがラヴェルの《ダフニスとクロエ》組曲だったこともあって、失われたギリシャの理想郷、遙かなるアルカディアがそこにあるようだったと、書いていた。
空襲下のベルリンに響いた昔の夢。
ではアバドは、生涯最後の全集で、その《田園》を、その終楽章をどうやっていたのかを、再確認したくなった。
異様なまでに力強い。あえていえば、「運命」の終楽章よりも、力強く肯定的な凱歌になっている。
「俺は人間を信じるよ」
そう言っているような演奏。
あの体験を、偶然にも下野さんが実演で再現してくれている。
内面の核となる昨日の体験が、一昨日と今日の外界によって、前後から包むように再現されていく、驚きと歓び。
《惑星》のような大編成の作品が防疫上の問題でできないので、十二型の準二管編成で、そしてヘ調で前半と揃えるという、まずはその意味合いが大きいのだろうが、とにかく下野さんは大自然への讃歌を選んだ。
《惑星》から《田園》に転じるというのも、暗示的で面白い。宇宙から地上に降りてくる。
そういえば、小松左京の『復活の日』で、昆虫以外の地上の生物をすべて滅ぼしたあのウイルスの原型は、宇宙から来たものだったっけ。
だがそれよりも、映画『スターウォーズ』の主人公ルーク・スカイウォーカーという名が、ジョージ・ルーカスの宇宙への憧れを暗示したものだという、大昔に読んだ解釈が頭に浮かんでくる。
ルークはルーカスの変形。ジョージの語源はギリシャ語のゲオルゴスで、意味は農夫。農夫とは「大地を歩む者」、すなわちアースウォーカー。その大地から翔んで空へ、宇宙へ。
しかし《田園》は、アースウォーカーの世界。踏みしめて、嵐のあとの水たまりを見る。
今度は、司馬遼太郎が『坂の上の雲』に書いた一節を思い出す。
「あたりまえのことをいうようだが、有能とか、あるいは無能とかいうことで人間の全人的な評価をきめるというのは、神をおそれぬしわざであろう。ことに人間が風景として存在するとき、無能でひとつの境地に達した人物のほうが、山や岩石やキャベツや陽ざしを溜める水たまりのように、いかにも造物主がこの地上のものをつくった意思にひたひたと適ったようなうつくしさをみせることが多い。
日本の近代社会は、それ以前の農業社会から転化した。農の世界には有能無能のせちがらい価値基準はなく、ただ自然の摂理にさからわず、暗がりに起き、日暮れて憩い、真夏には日照りのなかを除草するという、きまじめさと精励さだけが美徳であった」
――陽ざしを溜める水たまり。
まさに、それ。
七月五日(日)読響再始動の俊英
 写真は読売新聞オンラインから。
写真は読売新聞オンラインから。東京芸術劇場で、読売日本交響楽団の演奏会再開第一弾となる特別演奏会に行く。指揮者は鈴木優人。
・マーラー:交響曲第五番から第四楽章アダージェット
・メンデルスゾーン:管楽器のための序曲
・モーツァルト:交響曲第四十一番《ジュピター》
休憩なしで一時間強のプロ。一曲目が弦楽、二曲目が管楽器と打楽器、三曲目がフルオーケストラと編成が変る。
ただし三曲目には出てこない、一曲目あるいは二曲目だけのメンバーもいて、舞台上での密を避けなければならない状況下で、できるだけ多くの楽員が登場できるように工夫してある。それ以外にも趣向を凝らした選曲で、さすが鈴木優人らしい。それについては追々触れる。
楽員たちは黒シャツ黒パンツ。さらに舞台への入退場のときだけ全員が烏天狗風の黒マスクをつけるので、なんというか、ジャパニーズ・ニンジャ(笑)。
最初がアダージェット。ヴィスコンティの映画『ベニスに死す』の、恋情とコレラ禍、エロスとタナトスの交合。
自分はこの曲というとどうしても、三十七年前に見た二十世紀バレエ団のジョルジュ・ドンがここでこう動いた、ここはこう回った、などの残像が、いまも脳裏に浮かんでくる。
弦は八型で八八六五四。対向配置だがコントラバスを中央に横一線に並べる。奏者一人に譜面一台。少ない編成で離れているから、響きがダンゴにならずに澄明によく鳴る。久しぶりの合奏なのに音が濁らないあたり、あらためて在京オケ御三家のポテンシャルの高さを感じる。
あまり濃密にならないのが自分の好みにも合う。音程が揃わないのをヴィブラートでごまかした、濁った厚い音は、もう二十世紀に置いてきてほしい(笑)。
メンデルスゾーンの作品は初めて聴くもの。弦楽が退場して管と打に交代。
管楽器は東フィルや新日本フィルと比べていちばん間隔が広く、一・五メートルくらいあけていた。その隙間に次の列の楽員がいて、千鳥配置になっている。ヒナ壇を高くあげて、高低差もつけていた。響きの一体感をカバーする意味もあるのではないだろうか。
曲の後半、打楽器が派手に鳴り響くと音楽が爆発。ベートーヴェンとマーラーを結ぶ、過程のような音楽。特殊楽器を含めて管楽器たくさん(数えとけよ)。
メインの《ジュピター》は、驚いたことに六型の少人数。しかし堂々と、キビキビと俊敏に鳴り響かせてしまった。六六五四三。コントラバスは移動して、下手側のチェロの後ろ。大空間なのでヴィブラートをかける、ある種の折衷型。
活力にみちて、コーダでは音楽が堰を切ってあふれだすような瞬間がきた。ここでも読響のポテンシャルを実感。
アンコールつきで、ラモーの《未開人の踊り》。マーラーから溯っていき、バロックの快活へ。
鈴木優人は四月に読響の「指揮者/クリエイティヴ・パートナー」に就任したが、五月の定期が中止になったため、今日がお披露目。
鈴木は曲間の配置換えのときに場つなぎでスピーチ。活動再開、新たなスタートということで、ドの音で始まる三曲を揃えたとのこと。作曲者の頭文字がすべてMだったのは偶然だとか。
その一方で自分が感じたのは、今日の「陰の主役」はベートーヴェンでないのか、ということだった。ドの音で始まるハ調はベートーヴェンが得意としたものだし、マーラーの五番もメンデルスゾーンの曲も、疑いなくベートーヴェンを意識している。《ジュピター》は調性といい終楽章の堂々たるフーガといい、ベートーヴェンの出現を予告したような曲。
鈴木は昨年十二月にNHK交響楽団に客演したときも、メシアン~ブロッホ~コレッリ~メンデルスゾーンという選曲により、「陰の主役」としてそこにいないバッハの影を感じさせるという、面白い仕掛けをしてくれた。
今回はそれがベートーヴェン。残念ながら実演では、めっきり影が薄くなってしまったその記念年を、透かし細工のように感じさせる工夫が楽しい。
そして、前回も今回も、ポイントにメンデルスゾーンがいるというのがとても嬉しい。
ユダヤ人であることもあって、ワーグナーに比べて、ドイツ音楽史において不当に軽視されてきたメンデルスゾーン。しかしその存在は、バッハ・ベートーヴェンとマーラー以降をつなぐ、重要なアクセスポイントになりうるのだ。
鈴木優人と読響、相性がよさそうでこれからが楽しみ。選曲と演奏の双方で、はじけるアイディアに期待。
 写真は日テレNEWS24から。
写真は日テレNEWS24から。七月十日(金)交響清祓祝典楽
 新日本フィルのフェイスブックから。
新日本フィルのフェイスブックから。すみだトリフォニーで新日本フィルの演奏会。指揮は尾高忠明。
・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番変ホ長調《皇帝》(ピアノ:清水和音)
・ブラームス:交響曲第一番ハ短調
本来はピアニストのフォークトが指揮も兼ねていた演奏会。それが、七十五年前の敗戦前後、日本に自国人指揮者しかいなかった時期の指揮者陣の一人、尾高尚忠の遺児に代わったというのも、個人的な興味として聴きたかったところ。
《皇帝》もブラームスの一番もさんざん聴いてきて、耳にタコができている自分なのに、今日は新鮮に聴けた。
十二型を広めに配置、出演者は握手の代りに肘を合わせるなど、ソーシャル・ディスタンスが保たれていたが、最後の尾高さんのスピーチにもあったとおり、本拠地を持つオーケストラ、つまり練習段階から一貫して同じホールで演奏するオーケストラの強みを、明確な輪郭と、かちっと存在感のある響きに感じた。
感動的だったのは、終楽章のホルン・ソロを上間善之(東京交響楽団首席)がバシッと決めると、それまで不安定だった管楽器群が、人が変わったみたいに生彩を放って、歌いはじめたこと。
ブラ一なんて今さら、と思うクラシック好きも多いのだろうが、この瞬間の音楽にはなにかこう、あたりが祓い清められるような気がした。
むかし、ワーグナーの名訳者として知られる高木卓は《パルジファル》のBühnenweihfestspielを「舞台清祓祝典劇」と訳した。一般的な「舞台神聖祝典劇」の意味不明さよりも私は好きなのだが、それに従えば、交響清祓祝典楽。
こういう瞬間が不思議なのは、その曲を生まれて初めて実演で聴いたときの記憶がよみがえることが多いこと。
自分がこの曲をナマで初めて聴いたのは一九八三年二月、チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィルがヘルクレスザールで演奏したときだった。
当日朝に購入した席は最前列中央、指揮者のお尻の真下。
前半のハイドンではにこやかだったチェリが、後半のこの曲の入場のときには鬼のように厳しい顔つきで入ってきて、前半の雰囲気のままに笑いかけた第二ヴァイオリンのトップが、その表情を見てどうしていいかわからなくなり、憮然として席についたのを、昨日のように覚えている。
気迫のこもった開始。濃密な音楽が進み、そして終楽章。
たっぷりと間をとった終楽章のホルン・ソロの、山麓の野にこだましていくような広闊さと、そこからの強大なエネルギーの奔流。
今日のホルンが似ていたかどうかは、じつをいうとあまり問題ではない。
それよりも、三十七年前に自分の肉体と感性に、初めてその響きが沁みこんできた瞬間の感覚を呼び覚ましてしまうくらいに、その音に瑞々しい、新鮮なおののきがあったということ。
帰路、ふだんならJR駅の北口へ急ぐだけだが、今日は寄り道。
南口の駅ビルのテルミナにあるヨドバシカメラに行って、webカメラを買いたい。コロナ禍の初期、まともな商品がすべて品薄になるなかで手に入れたものがあまりに性能が低くて、百六十分のVHSに三倍で録画して二回ダビングしたみたいな画質なので、明日の片山杜秀さんとのオンライン講座のために、もう少しまともなものがほしい。
ホールを出て、東武ホテルレバント東京の前を通る。行きに気がついたことだが、通路際のいつも明るいビュッフェ形式のレストランが真っ暗。コロナ禍でビュッフェができずに定食形式に変え、人が少ないのでディナーを休んでいるらしい。コロナ禍のもたらした闇。
階段を降りて北斎通り(昔の本所割下水)に出て、右へ折れて長いガード下をくぐり、駅の南側に出る。
すると線路際の南側が歓楽街、いわゆる「夜の街」になっていることを、ひさしぶりに実見した。二十年以上前の送電線業界にいたころ、取引先の若い社員さんたち七、八人と、このへんの女の子のいる店で接待で飲んだことがあったのを思い出す。間違いなくそれ以来。
女の子や客引きの男性たちが、気だるげに立っている。雰囲気でわかるのか、こちらには話しかけてこない。かれらも、駅の方から歩いてくるお客たちも、全体に若くてマスクをしていない。近年、こういう場所で圧倒的に多数派だった、自分と同年配かそれより上のオジサン、オジイサンたちがほとんどいない。
通り抜けて、改札の前からテルミナの二階に上がり、ヨドバシカメラに入る。十時の閉店まで三十分くらいという時間帯のせいか、人が少ない店内をパソコン用品売場へ。
この駅ビルそのものはとても古い。一九六一年営業開始だから、自分が生まれる前からある。
おもちゃ売場と、その背後の古いコンクリの壁を見たとき、またフラッシュバックが起きた。
六才頃に祖父に連れられて、この駅ビルにあった模型店にきたことがあった。家の近くの自由が丘のおもちゃ屋などでは扱っていない、千分の一スケールくらいの旧帝国海軍の軍艦の特殊なプラモデルを売っていると雑誌の広告で知り、頼んで連れてきてもらったのだ。
喫水線より上だけの、今から思えば数年後に始まるウォーターライン・シリーズの原型のようなシリーズ。
残念ながら赤城などの空母や戦艦の売れ線はほぼ品切で、ちょびた鉛筆のような駆逐艦ばかりいくつか買ってもらったこと、それらが飾ってあったガラスのショーウィンドウ、蛍光灯の白々しい照明などが、頭に浮かんできた。そして、帰りに国電のホームから見上げた駅ビルの窓から、夜の闇に向けて白々しい光が輝いていたこと。
webカメラは外国製ばかりだが、在庫が戻りつつあるのか、適当なものが買えた。そしてホームへ。今は駅ビルのホーム側の窓はふさがれていて、光が漏れることはない。
 錦糸町の駅ビル、テルミナのサイトから
錦糸町の駅ビル、テルミナのサイトから家の最寄り駅に着き、近くの飮み屋街を通る。金曜の十時過ぎだから、活気は多少戻っている。ここでも、マスクをしない若い男女が歩きながら無防備に歓声をあげて集団で歩いている。
やはり中高年男性の酔客がいない。人の密度は薄いけれど、世代構成は二十年ほど前までに戻ったかのよう。
近年の超高齢化社会の街角の様子が、一変してしまった。かれらは家にこもっているか、出てもそそくさと戻るのだろう。警戒を続ける人だけでなく、自粛するうちにただ出無精になったという人もいるだろう。
高齢層を主要な顧客にしてきた日本の消費社会は、変わるのかもしれない。高齢の聴衆が多いクラシックの演奏会は、コロナ禍が収束しても、これまでのような人出が望めなくなるかもしれない。平日午後の演奏会に聴衆がたくさん入り、それがメインとなった近年の状況も、変わるのかも。
その後のビジネスモデルを、どう再構築するか。近い将来に起こる、避けることのできない問題だったとはいえ、一気に五年ぐらいタイムテーブルが早まってしまった気がする。
七月十一日(土)初オンライン講座
午後は東京文化会館に行き、東京二期会のスペシャル・オペラ・ガラ・コンサート「希望よ、来たれ!」。これについては日経新聞に書く。
夜は片山杜秀さんと、朝日カルチャーセンター新宿教室のオンライン講座「昭和音楽史」。五月のゴールデンウィークにこれまで同様に新宿の教室で話すはずだったものが、延期の上オンラインに切り換える形で実現した。
初めて自宅のPCからZOOMを使ってしゃべる。慣れないので緊張したが、お陰様で無事終了。
疲れた(笑)。受講者の反応が見えない、聞こえないというのは、慣れないととてもやりにくかった。
対面講座では反応や空気が伝わってくるから、話題をそろそろ切り換えるか、逆にノッているならもっと展開させてやるかという判断ができるが、それがわからない。飲み屋で二人きりで馬鹿話をしているわけではないので、自分たちの感覚だけで進行を決めてしまうわけにもいかない。内容や気分は、それに近いのだが(笑)。
ラジオの場合は、完全に顔の見えない不特定多数が相手だから、言ってみれば自分をリスナーとしてしゃべる。顔を出さずに聴覚だけなので、集中しやすい。
しかし講座となると受講者が絞られていて、ある程度具体性があるだけに、反応がわからないのがもどかしい。まあ、片山さんは大学のオンライン講義で「暖簾に腕押し」状態でやり続けて免疫ができたとおっしゃっていたので、慣れなのだろうとは思うが。
それはともかく、自分としてはいつものように、片山さんの鉄砲玉のような言葉にわくわくびくびくしながら、楽しくしゃべることができた。
二〇二〇年と一九七〇年、二つのベートーヴェン記念年を並べ、万博と小松左京を入り口にするというのは私が考えたことだが、それを片山さんはジャンプ台にして、ユートピアとディストピアという、音楽上の対比に見事に持っていってくれた。
オンラインではあっても、こういうライヴな化学反応こそ、本当に片山さんとしゃべっているときの醍醐味。それはまあ、なんとかつくれたと思う。
一九七〇年の万博は最後のユートピアだったが、その数年後には『日本沈没』がベストセラーになり、そして『ノストラダムスの大予言』で、一九九九年に世界が滅亡するという話が世を席巻する。
ほぼ同時期に石油ショックが起きたのが大きかった。アメリカの衰退で世界秩序が乱れ、石油が枯渇して資源の奪い合いになり、一九九九年に世界戦争で滅亡するという図式に説得力が生じたのだ。松本零士の『ワダチ』、つのだじろうの『メギドの火』とか、そうした世界観に基づいたマンガも読んだ。
そして何より、プラモデルや塗料が原油値上げのあおりで値段が一気に高騰したのが、プラモ命の子供にとってはあまりにも切実で過酷で、まさに世界の終りという感じだった(笑)。
十歳前後、ようやく自意識が確立され始めた年代に、四十歳まで生きられないと宣告されたショックは大きかった。片山さんも自分も、このショックがその後の世界観の基礎になっている。それですごく気が合うのだと思う。
こうした終末ブームは、超能力も含めて、すべてオカルトブームでくくれるともいえる。万博の理想主義、科学万能主義がゆらいだあと、七〇年代前半はその反動で、オカルトブームに包まれた。
さて、オンライン講座の利点は、時間延長がしやすいこと。対面式では時間割を過度に無視することはできない。教室は次の講座のために速やかに明けわたさねばならないし、受講者にもその後の予定があるだろうから、十分間ぐらいの延長が限界だ。しかしオンラインなら、ある程度の融通が利く。受講者は途中で抜けてもかまわない。終了後一週間以内なら、好きな時間に何度でも見なおすことができるので、当日は途中でやめて、残りはあとで見るということが可能だ。
ということで、今回は三十分延長したが、実をいえば片山さんがエンジン全開になったところだったから(笑)、あと一時間はできたろう。
こういう判断をその場でしようとするときに、受講者のその時点での雰囲気がわからないのが、オンライン講座の難しさなのだ。
話としてはさらに膨らませられそうな部分もあったので、もし次ができたら、延長を初めから予告して途中で小休止をとるなど、適切な構成を考えたい。
終了後、二人して残念に思っているのが、『日本沈没』のラジオドラマ版に触れるとこまで行けなかったこと(笑)。これはまたいつかやりたい。
追記:お陰様で早速にオンライン講座の次回開催が決まった。九月十二日(土)の十八時三十分から。できるだけ多くの方に見ていただきたいので、朝カルに相談して、非会員の一般の方でも税込二千七百五十円に下げてもらった。
そのために規定の時間は一時間となったが、これは文中にあるとおり、大幅延長でいくつもり。
七月十二日(日)東京都交響楽団
サントリーホールで東京都交響楽団の演奏会。指揮は大野和士。
・コープランド:市民のためのファンファーレ
・ベートーヴェン:交響曲第一番ハ長調
・デュカス:舞踊詩《ラ・ペリ》より「ファンファーレ」
・プロコフィエフ:古典交響曲(交響曲第一番)
休憩なしで一時間強のプロ。現状では金管と打楽器がたくさん出てくるような大編成作品はできないので、ファンファーレでかれらを登場させるというのは、うまい工夫。
二曲の交響曲はともに二管編成の十二型という、密集を避けるために適切と考えられている古典派サイズ。ただし都響は間隔を他よりも狭めにとっていることもあって、音の密度が濃い。
そして、ベートーヴェンとプロコフィエフ、編成が同じでも後者の音のつくりは強靱そのもの。楽器の強度と安定性、奏者個々の技術が、百二十年ではるかに進歩して、それをあてにして書いていることがよくわかる。十日のブラームスもホルンとトロンボーン以外の基本は二管編成だが、各楽器のソロの存在感が質量ともに増していることがよくわかった。オーケストラを構成する要素が、時代とともに安定性を高めていく。このあたりは、十二型という同じ大きさだからこそ明瞭に聴きとれた。
七月十三日(月)日本フィル

サントリーホールで日本フィルの演奏会。指揮は井上道義。
・バッハ:トッカータとフーガ ニ短調
・バッハ:主よ人の望みの喜びよ
(右二曲はオルガン独奏:石丸由佳)
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調(ヴァイオリン:前橋汀子)
中止になった四月の演奏会の前半分を休憩なしで行なったもの。そうすることで、ソリストの前橋に通常の演奏会ではできない脚光をあて、前橋がオーケストラと共演するアンコールを二曲つけて、結局は一時間半近いプログラムに。
一曲目はベートーヴェンのロマンス第二番で、井上の伴奏ピアノに途中からオーケストラが参加。二曲目はサラサーテのツィゴイネルワイゼン。
過度の自粛を嫌う井上は、素手で堂々と共演者たちと握手。その意志と信念がすべてにあらわれた一夜だった。
七月十四日(月)読売日本交響楽団

サントリーホールで読売日本交響楽団の演奏会。指揮は原田慶太楼。
・コープランド:市民のためのファンファーレ
コープランド・静かな都市(イングリッシュ・ホルン:北村貴子、トランペット:辻本憲一)
ハイドン:交響曲第百番《軍隊》
これも休憩なしの一時間プロ。アンコールがあって、シューベルトの軍隊行進曲をエルネスト・ギローがオーケストレーションしたもの。
俊英として注目を集める原田、初めて聴けた。輪郭のはっきりした力強さ、ダイナミックな音楽が魅力的。外国人指揮者のいないコロナ禍において、大忙しになりそう。
N響以外の在京オーケストラの演奏会が再開され、ここまでいくつか通った。感染防止策は手さぐりだし、曲目も間に合わせではあったが、それぞれの個性がかなり出て面白かった。
ここからは、この状況下で何ができるか、しっかりと考えたプログラムが組まれていくはず。客席半分、編成も大規模は無理、外国人アーティストの来日は望めない状態が少なくとも数か月は続くなかで、どのように工夫していくか。
それは、来月以降に見えてくるはず。困難と戦いながら、どんな風景をみせてくれるのか、期待するのみ。ただし、関係者全員の身心の健康を強く願う。
七月十五日(水)ひさかたぶりの
日経ホールにて、千葉交響楽団のメンバーによるオンライン用の無観客(観客無制限、ともいうそうだ)演奏会の映像収録に、このオーケストラの音楽監督山下一史さんの話の聞き役として参加。

楽屋をあてがわれ、用意された弁当を食べての長時間収録は、何年ぶりか。スーツにネクタイというのも久しぶり。
この室内楽用ホールには、月一回程度の自主公演シリーズがあるが、海外のアーティストが来られないことなどで休演続き。その空いたスケジュールを活用して収録することになったもの。楽員も山下さんも、これが活動自粛以来数か月ぶりの実演だそうで、楽しそうだった。
大企業がこのような形でオーケストラを支援するのは、素晴らしいと思う。
オンライン講座「日経アートアカデミア」内の「ベートーヴェンと現代」シリーズ第二回となるもの。
曲は「七重奏曲」「交響曲第六番第一楽章(弦楽四重奏版)」、そして山下さん指揮の「コントルダンス(三曲)」。

演奏収録が終ってから対談を収録。
七月十六日(木)クラシックと怪談
今年はコロナ禍で季節を感じにくい。梅雨の雨量がやたらに多いせいもある。自分が子供の頃は、夏休みになると昼にテレビで再放送される『日本怪談劇場』などの怪談話が楽しみだった。
ということで、納涼系のお化け話を。
少し前に、紀尾井ホールのことをネット検索していて知った話。ホールそのものの話ではなく、ホールが建つ前にあった、大正十年建築(岡田信一郎設計)の和洋折衷の超豪華な邸宅のこと。
一部は明治、さらに江戸期の尾張藩邸時代のものも混じっていたというこの建物、あまりに貴重だというので、その主要部分は数年間の調査と工事をへて、現在は南平台の日本製鐵の所有地に移築復元されている。
その調査と解体移築のさい、いろいろ幽霊話があったらしい(解体した建材と一緒に南平台へ霊も移動したそうだ)。ネットで検索すると、すぐにいくつも出てくる。
それらを読むと、ネットの噂話にはよくあることだが、それぞれ独自の改変や推測が混じって、何が事実なのかはわかりにくくなっている。こういうときは、大元にさかのぼるしかない(もちろん、それが真実とは限らないが)。その大元は実話怪談を集めた現代百物語、『新耳袋』の第九巻に載っているという。

買って読んでみた。あえてここには載せない。ご自身でお読みあれということにする。
この話以外のものも実話だという。だからホラー小説のように盛り上がるわけではなく、坦々と恐いものが続く。
関西の話が多く、小松左京の有名な短編『くだんのはは』の元ネタになった、神戸空襲の前に出現して破局を予言したという、人の言葉をしゃべる牛、件(くだん)の現代版があったりする。
しかし何より驚いたのは、朝比奈隆をめぐる怪談が三つ載っていること。登場するのはブルックナーの交響曲第七番、ベートーヴェンの《合唱》と、いかにもこの人らしい選曲。
自分は知らなかったが、朝比奈ファンには有名な話なのだろうか。
中身はこれもバラさない。ご興味があればぜひ。
七月二十日(月)公演は絶対にやります

新国立劇場・情報誌「The Atre」八月号に掲載された、オペラ芸術監督大野和士のインタビュー(ききては井内美香さん)を読む。
いい言葉がたくさん。
新国立劇場でも防疫のための検証をさまざまに行ない、十月の《夏の夜の夢》上演のための助走を開始しているそう。外国人歌手が来日不能の場合にそなえ、「初日をきちっと開けられるような実力のある日本人のカバー歌手の方々に、十分に準備」してもらう。演出家マクヴィカーの助手は「いざとなったらスカイプでもやる」と言っているとのこと。その場合は日本に演出補をおき、リハーサルの映像を見ながらやりとりをしていく。
芸術家も聴衆も観光客も「好きな時に好きに国境を越えていたボーダーレスな世界が、今後は違ってくる」。水際対策でストップするのが今は理性的な判断。「そうすると、これまでやっていた形でのオペラ上演に代わるアイディアが必要で、それなくして元に戻ることだけを直線的に目標にすることはもうできなくなってくるのでは、と思いますね」
会員へのメッセージから。
「皆さんに一番お伝えしたいことは、新シーズンはできる限り公演中止は考えないということです」
感染拡大のために劇場の閉鎖を余儀なくされるような事態にならない限り、
「それ以外では公演の中止はしない。どのような形であれ、公演は絶対にやります。それが一番強く、皆さんにお伝えしたいことです」
新国立劇場のオペラ部門は、この未曾有の危機的状況において、有事に最高の人物、唯一無二の人材を芸術監督にいただいているのかもしれない。
この会報誌は、会員以外には三百円で頒布されている。このインタビュー、ぜひ多くの方に読んでもらいたい。
七月二十一日(火)次の昭和音楽史は
片山杜秀さんとのオンライン講座「昭和音楽史」、お陰様で第二回開催決定。お題は「カラヤンとグールド」。昭和期におけるスタジオ録音による「レコード芸術」(月刊誌じゃなくて)の盛衰について考えてみる。
第一回は通常の対面講座からの転用だったため、オンラインにしてはかなり高い、というのがネックだったが、朝カル側と相談して、今回は非会員の方でも二千七百五十円になった。
受講料を下げたぶん、規定の時間は六十分となるが、ここは「時間を大幅に延長する可能性がございます。あらかじめご了承ください」ということで(笑)。
県外移動や海外渡航による制限はありません。一週間以内ならご都合のいい時間に何度でも見られるので、ぜひ。
・紹介文から
新型コロナ・ウイルス禍により、今年前半はコンサートやオペラ公演の大半が中止されました。平成期に質量ともに大きな向上を遂げてきた日本の実演界が、いまは未曾有の危機に直面しています。この状況下で思い出すのが昭和の時代、演奏会以上に大きな関心と人気を集めていた、レコードというメディアのこと。それはいつでもどこでも、手軽に鑑賞できるものでした。
カラヤンやグールドなど、ライヴとは異なるスタジオ録音のレコードに力を注いだ音楽家や、演奏家の存在を排した電子音楽など、「完成品としての音楽演奏」という理想を追いかけた昭和のクラシック音楽界のことを、その原型となった劇映画の手法との比較などから、考えてみます。
七月二十四日(金)始原にして終末
ひさびさに、半蔵門のミュージックバードのスタジオで番組収録。スケジュール表を見ると、スタジオでは四月二日の「ニューディスク・ナビ」が最後だったので、ほほ四か月ぶり。
内容は、九月末放送の「ウィークエンド・スペシャル」。ところが、ようやくスタジオで録れると思ったら、これがこの番組の最終回となってしまった。
最後のテーマは「シリーズ・初演者の録音」。これはもともと「夜ばなし演奏史譚」の特集だったのだが、その途中の三月で番組が終わることになり、まだまだやりたい曲があるということで「ウィークエンド・スペシャル」に移させてもらったものだった。
それなのに、こちらも終わり。作曲者と初演者(おもに指揮者)の関係、いわば母親と産婆の関係から、作品を立体的に眺めるという試みは、二十世紀の演奏史をとらえなおす意味でもけっこう面白く、次から次へと題材が見つかり、CDを集めている最中だったので、個人的にとても残念。
運が悪いというか、番組二つを終らせてしまう、デステーマなのか。
ちょうどいいので、オルフの作品をカラヤンが初演した《時の終りの劇》を最後にかけることにする。審判の日を扱ったこの作品が一九七三年の夏、『日本沈没』や『ノストラダムスの大予言』と同じ年、終末ブームのなかに生まれていたというのは、面白いシンクロナイズ。
この「ウィークエンド・スペシャル」の放送開始は二〇〇七年十月だった。奇しくも自分は、番組の始まりと終わりに出演したことになった。
「ニューディスク・ナビ」のほうは、リモート収録を今後も継続する予定なので、次のスタジオ収録は、はたしていつのことやら…。
七月二十五日(土)東京エクペリメント
 ノットの指揮映像。東京交響楽団のツイッターから
ノットの指揮映像。東京交響楽団のツイッターから十四時からサントリーホールで、東京交響楽団の演奏会。
指揮:ジョナサン・ノット(ベートーヴェンに映像にて出演)
・ストラヴィンスキー:ハ調の交響曲
・ベートーヴェン:交響曲第三番変ホ長調《英雄》
コロナ禍のクラシック界において、センセーショナルな話題となってきた事前収録による映像指揮を含む演奏会、ようやく体験できた。
編成は八八六四三の八型。ストラヴィンスキーもベートーヴェン同様、ヴァイオリンが左右に分かれる対向配置。
再開後はどこのオーケストラも、楽員入場時から盛大な拍手という、外来オケ同様の習慣ができているが、今日の東響は開演前に楽員が三々五々席についている。アメリカ式に少し似たスタイルで、「さあいよいよ入場です」みたいな瞬間をつくらない。そのため、コロナ前に戻ったかのように、コンサートマスターのニキティンが入場するまで、拍手は起こらなかった。
たしかに、非常時だからとすべてに気を張りすぎると長続きしない。有事のなかでも、平凡な日常に少しずつ戻していったほうが、長期戦に備えることができる。真意はわからないが、そうした回帰のための工夫なのかも、と感じた。
そして、今日はそれ以外の要素があまりにも異常事態なのだから(笑)、リラックスできるところはリラックスしたほうがいい。
(あとで聞いた話では、ストラヴィンスキーの曲は演奏経験が少ないのに、感染防止のために楽屋での事前練習が禁じられていたため、開演前の舞台で少しでもさらっておこうとした楽員が多く、あのような形になったのだという)
前半のストラヴィンスキーのハ調の交響曲は指揮者なし。ノットは三楽章の交響曲とか、ストラヴィンスキー作品も得意だから、その解釈が多分に反映されているはずだが、実質的にはコンサートマスターによるディレクション。
とはいえ、古典派とも両大戦間の新古典主義とも一味違うものだけに、たやすくはない。二十世紀前半のアメリカにおいて独自の発展を遂げて大完成された、シンフォニー・オーケストラという機能的な演奏組織と興行形態のために書かれたものだからだ。
シンフォニー・オーケストラというシステムは、鉄製の響板をもつグランドピアノがニューヨーク・スタインウェイによって完成され、ヨーロッパに逆輸入されて普及したのと同じように、旧世界に影響を及ぼした。
これはスター指揮者が統率する、機械化された大工場のようなオーケストラというのが定型なので、そのために書かれた音楽は、指揮者なしでやるには向いていない(ストラヴィンスキーの場合はさらに、作曲者・創造者という立場で指揮して初演して、スター指揮者という再現芸術家を凌ごうとしたから、ひねくれている)。
考えようによっては、エロイカをオケにまかせ、こちらを事前映像で指揮する手もありそうだが、それはおそらく、いくらなんでも無理だったのだろう。この曲で必要なのは、双方向性が確保された上での指揮芸術なのだろうから。
さてエロイカ。四台の大きなモニターが運び込まれ、方陣を組む。ただし客席に向けられた一台だけ、楽員に近い他の三台から少し離れているので、一辺が他の三辺から浮いたような四角形。
白い壁をバックに、タキシードを着たノットの腰から上の映像が映る。冒頭、オーケストラを立たせて拍手を受けさせる映像に、客席がほほえむ。
バン!バン!という最初の二つの和音が、気魄のこもった澄んだ音で響いて、お、これはいい感じになるぞ、と予感させる。実際、気合の入った、そして自発性に富んだ、気持のいい演奏になった。
もちろん、映像は拍子とアクセント、きっかけを出すだけで、その場その場の響きやバランスのコントロールはできない。八型ゆえの響きの純度、テクスチュアの明快さは魅力的だったが(個人的にはベートーヴェンはもう、十二型以下の編成で聴きたい)、総奏になると木管と金管の強さに圧倒されてしまう。自発性があるからこその奔馬ぶりが出る。
また、ときにフレーズの最後の間がつまるのは、オーケストラの音を聴かずに指揮しているからか。本当に何も聴いていないのか、それとも誰かが指揮に合わせてピアノをひいているのか、いずれにしても現実の響きとはどうしても異なるだろう。
(これもあとで聞いた話だが、四年前にユンゲ・ドイツフィルを指揮したときの映像に基づいて指揮していたという。ということは、オーケストラのほうが動いて、帳尻を合わせるために間がつまったのかもしれない)
そうした弱点にもかかわらず、オーケストラには確かなライヴ感があった。川崎に続いて二回目の演奏という慣れもあるのだろう。終楽章の各パートの呼応と波動は見事だったし、コーダでのノットの思い切った加速も、自らの表現として音にしてみせた。
今日はLBブロックから聴いた。ここの席だとコンマスの背中越しに映像が見えるので、映像とコンマス以下の楽員の動きとの関係がわかりやすかった。
そこで見ながら思ったのは、これはやはり共演を重ねて熟知しているからこそのことだし、さらにそれ以前に、同じ時代の響きのセンスを共有していることが大きいだろうということ。昔の指揮者の映像をいきなり出してきても、鳴らしかたのギャップは埋まらないように思う。
とにかく面白かったし、考えさせるヒントに満ちた、トーキョー・エクペリメントだった。
今回のように、同じ指揮映像を見ながら演奏を繰り返すことを、実演の自死行為と考える人もいるかもしれない。
しかし、今日の演奏はけっして「音ゲー」の実演版ではなかった。つまり、画面の表示に合わせて正確にボタンを押せば正しい音が出て高得点になる、というようなものではなかった。それが目的にはなっていなかった。
結局これは、同じ楽譜を毎回誠実に音にして演奏を繰り返すという、クラシック音楽演奏において当然とされてきたことと、最終的には同じ地平にある行為なのではないだろうか。
紙の上の音符に加えて指揮も映像として不完全に固定されることは、再現芸術としての程度の差にすぎないと、いえなくはないだろうか。
固定された不完全さと不即不離の関係にあって、そこに有限の生命を与える。古典の再現芸術の奥深い不思議。
いってみれば、「ベートーヴェンの楽譜に基づいてノット指揮東京交響楽団が演奏する」のがいつものスタイルだが、今回は「ベートーヴェンの楽譜とノットの指揮映像に基づいて東京交響楽団が演奏する」エロイカだった。
肝心なのは、本番の昂奮のなかで、よくも悪くも即興的な部分が出てきていたことだ。そうした要素は、おそらく実演を重ねれば重ねるだけ強まる。つまり、そこでは「再現芸術」の成分が増すのではないかと思えたのが、「楽譜と演奏」というクラシックの永遠の問題を考える補助線にもなりそうな気がして、ものすごく刺激された。
再現芸術の枠組みというのが、実はフレキシブルなものなのだと気がつくことができたのは、大収穫だった。
夢想してみる。数百年後に今回のノットの指揮映像が発掘され、ベートーヴェンの《英雄》を指揮しているところだと解読され、未来のオーケストラが映像に合わせて演奏してみるなんてことになったら、どんな音が出てくるのだろう。
これもまた、再現芸術の一つの可能性なのだ。
指揮者は作曲家と同様に、いるのだがいない。いないのだが、いる。
留守と言え
此処には誰も居らぬと言え
五億年経ったら帰ってくる
(高橋新吉『るす』)
(自らネタばらしをすると、文中の「トーキョー・エクスペリメント」は、「フィラデルフィア・エクスペリメント」が元ネタ。太平洋戦争最中の一九四三年、ステルス実験をした米海軍の駆逐艦が、なぜか二千五百キロを瞬間移動したという都市伝説である)
七月三十一日(金)能楽公演2020


「能楽公演2020~新型コロナウイルス終息祈願」の五日目を見に、国立能楽堂へ。
この公演は能楽協会が中心となって開催するもので、二十七日から八月七日までの二週間のうち、平日の十日間に行なわれる。シテ方五流派をはじめとして三役の人間国宝・重鎮が連日出演する、能楽界が総力を挙げた豪華なもの。
本来は五輪の時期に合わせ、「東京2020 オリンピック・パラリンピック能楽祭」として開催されるはずだった。しかし大会が一年延期されたために、名称を変えて単独で行なわれることになった。客席は前後左右をあけた千鳥配置なので入場者は半数以下になる。収支の勘定はもちろん、楽屋内外の感染防止策も大変だろうに、敢然と開催してくれたことに感謝するのみ。
本来なら国立競技場の観客で千駄ヶ谷駅周辺は大混乱だったはずだが、延期ということで閑散としている。酷暑期の十四時開演ということできついかと思ったが、梅雨が長びいて温度は高くない。席の前後左右があくのも、客としては楽。無責任な立場からいえば、とても見やすい日となった。
しかしロビー上方の照明は、医療関係者への感謝を示す青い光になっている。そのことを忘れてはならない。


さて今日の番組。
・舞囃子『鷺』 野村四郎
・狂言『月見座頭』 山本東次郎
・能『道成寺』 金剛龍謹
個人的には二月十三日以来、五か月半ぶりの能楽。
自分にとってのこの日のポイントは、舞囃子(能の終盤あたりのシテの舞と謡を、面をつけない紋付袴姿で、地謡と囃子とともに演じるもの)と狂言は、五十六年前の一九六四年に開催された「オリンピック能楽祭」にも参加していた大ベテラン、野村四郎と山本東次郎がそれぞれの主役であること。能は、京都を拠点としているために東京では見る機会が限られる金剛流の『道成寺』であること。
開演。舞囃子の演者が、換気のために開けられたままの切戸口から登場する。
居並んだ全員を見て、この時期によくもまあこれだけお爺さんばかりそろったものと驚き、感心し、感謝する。
シテの野村四郎、小鼓の幸清次郎、太鼓の三島元太郎の三人が一九三六年、地頭の坂井音重が一九三九年、笛の一噌庸二が一九四〇年、大鼓の亀井忠雄が一九四一年。六人とも太平洋戦争開戦前の昭和十一~十六年の生れで、野村、三島、亀井の三人が人間国宝。
野村とは幼なじみの、八十年近いつきあいになるだろう重鎮がずらりと並ぶ。前回のオリンピックのときには二十代、駆け出しだった面々だ。
活動自粛のため本番が数か月も途絶えると、高齢になるほど筋力や体力の維持が困難になるように思うが、その不安を気魄ではねのけていく。
能の舞の動きは象徴化され、けっして具象的なものではないのに、今日の舞にはたしかに鷺がいた。
翼を広げ、片足で立つ鳥が、紋付袴姿の人間の向うに見える。美しく澄みきった、儚き幻。
続いて狂言『月見座頭』。
今の自分は、狂言への関心は能に比べると高くない。ただ、山本東次郎(一九三七年生)と五歳下の則俊の兄弟が共演する舞台はできるかぎり見たいと思っていて、それが『月見座頭』のような傑作となれば、見逃すわけにはいかない。
この狂言は、三年前の二〇一七年九月十五日に国立能楽堂の定例公演でも見ている。作品についてはそのときの可変日記にまとめたので、引用する。
旧暦八月十五日の中秋の名月の晩を舞台とする話。
狂言の中でも『月見座頭』は不思議な深さを持つ話として有名なので、楽しみにしていた。
下京に住む盲目の座頭が、月見に浮かれる人々をよそに、野辺で虫の声を聞いて心を慰めている。そこに上京に住む裕福な男が月見に通りかかる。座頭に気がついて声をかけ、歌を詠みあって気が合ったので、酒を酌み交わす。謠と舞に興じたあと、二人はそれぞれの住居に帰ることにして別れる。
ところが、上京の男が突如として邪心を起こす――声を変え、座頭をからかってやろう。幸せな気分で歩いている座頭にわざとぶつかり、言いがかりをつけて地べたに押し倒し、逃げ去る。
座頭は同じ男とわからぬまま、よい男もいればひどい男もいると、泣きながら見えぬ目で落とした杖を探して拾い、くしゃみをして惨めな気持で帰っていく。
説明しようもない、無垢の善意と無意味な悪意の共存。不条理な表裏一体の感情。つくられたのは江戸時代らしい。六月に見た『蜘盗人』にあふれていた、邪心を打ち消してしまうほどの善意と幸福の、その裏に潜むものをむき出しにしたような。
目の見えない座頭相手だから、自分の身元を知られずにすむ「上京の男」は、無垢の善意を示せるし、同時に無意味な悪意をぶつけることもできる。
善意と悪意、どちらかが嘘なのではなく、表裏一体の人間性。互いが互いを際立たせあう。
現代のSNSを連想する。そこでは人間が世間様に対してつけている能面の下の、奥底にある原始的な感情や欲望が露出してしまうことがある。悪意はその典型だし、はたまたその逆も。
相手には見えず、自分にだけ見えることもあれば、自分には見えず、相手にだけ見えることもある。目明きのつもりの自分も、じつは見えないことばかり。
『月見座頭』が描く不條理は、まさにそうしたもの。
前半、上京の男に一つ舞ってくれと所望された座頭は、能の『弱法師』の一節を舞った。『弱法師』は盲目の男を主人公とする傑作の一つ。だからこそ座頭はそれを舞い、謡う。(引用ここまで)
三年前は、シテ(下京に住む盲目の座頭)が則俊で、アド(上京に住む裕福な男)が東次郎だったが、今回は逆。
東次郎の座頭は、盲目で貧しいが教養は豊か、という雰囲気が強く出る。長袴をはいて出たのは、足元のおぼつかなさを示すためか。足さばきが難しいだろうに、『弱法師』も見事に哀しく舞う。
それは、浄土につながる西海が見えたように思った瞬間、道行く人々に突きあたって転ばされ、盲目の境遇に引き戻される弱法師の場面。
盲目のはずの座頭が、こんな舞まで巧みにこなしてみせる。舞えといったのは上京の男なのだが、その瞬間、かれはどう思ったか。
この舞にこそ、上京の男が唐突に抱く善意の裏返しの悪意の、その芽があるのかもしれない。
偶然にも五日前に、視覚障碍のあるマッサージ師がボランティアの帰りに駅のホームから転落、電車にはねられるという痛ましい事故があった。ホームに人が少なく、誰も注意していないという状況で起きたらしい。悪意はないが善意もない「不在の事故」を、重ね合わさずにはいられなかった。
後半は『道成寺 古式』。金剛流の若宗家、金剛龍謹がシテ。
出演者が多い曲ということもあって、感染防止を強く意識した演能だった。
まず地謡の人数が少ない。一列五人に減らしている。金剛流は初見なのでわからないが、観世流や喜多流でみたときは他の曲同様に二列八人だったし、宝生流は二列六人だった。
また、地謡も五人の鐘後見(釣りひもを操作して、鐘を上下させる役)も、口を四角い布で覆っていた。このためもあってか、地謡はちょっと迫力不足に感じた。
舞台に大人数が出る時間をなるべく減らすため、本来なら舞台に出ずっぱりの出演者が、出番のときだけ舞台に出る。鐘後見五人は、鐘を固定させたらいったん退場して、上下させる直前に再び入場する。ワキも寺僧一人だけは初めからいるが、ワキツレ二人は鐘が落ちた後、寺僧と言葉を交わす場面になって、おもむろに橋懸から入る。アイも初めは一人だけで、相棒の方は鐘が落ちる前に入る。
出番でなくとも初めから控えているというのが、無理を承知の能の美学。それが崩れる。人の出入りによって、シテを恒星とする惑星系になるべき能舞台の秩序が乱れる。そのことがよくわかった。今回は非常時でしかたないとして、やらないほうがよいことなのだとよくわかったのが、個人的には収穫だった。
さて金剛流の『道成寺』。いままで見た宝生流や観世流との違いを際立って感じたのは、乱拍子の身体のつかいかたと足さばき。素人にはその違いを具体的に述べることはできないが、とにかくかなり違う。
それと、何度も視線を送って、鐘への執着が強調されたのも印象に残った。観世や宝生では象徴化されて仄めかされるその執念が、わかりやすく示される。このあたりは上掛かり(京都風)の二流派に対し、下掛かり(奈良風)の金剛流の特徴なのか。
小書の「古式」では、前ジテの面が中年から若い女の面に代わり、後ジテは赤頭のかつらをつける。この赤頭が他流派のような鮮やかな赤ではなく、西洋人の赤毛のような、茶系の強い自然な色であることも面白い。より本物っぽい、とでもいうか。
シテの金剛龍謹は一九八八年生まれと若く、現宗家の金剛永謹の息子。自分は永謹の豪気で男性的な能が好き。龍謹もその芸風を受け継いで柄が大きく、楽しみな人。二歳上の宝生流宗家、宝生和英とウマが合うらしく、異流派での共演を積極的に行なっているのもいい。
鐘が上がったときの、とぐろを巻く大蛇が鎌首をもたげたような首の動き、寺僧に襲いかかるときのキレのよさなどが印象に残った。
乱拍子のとき、主鐘後見をつとめる父永謹が、食い入るように足元を見つめていた。
舞囃子「鷺」
シテ 野村四郎
笛 一噌庸二
小鼓 幸清次郎
大鼓 亀井忠雄
太鼓 三島元太郎
地謡 野村昌司 中島志津夫 坂井音重 藤波重彦
狂言「月見座頭」
シテ 山本東次郎
アド 山本則俊
後見 山本凜太郎
能「道成寺 古式」
シテ 金剛龍謹
ワキ 宝生欣哉
ワキツレ 野口能弘 則久英志
アイ 山本泰太郎 山本則孝
笛 杉市和→杉信太朗
小鼓 幸正昭
大鼓 山本哲也
太鼓 前川光長
後見 松野恭憲 廣田幸稔 工藤寛
鐘後見 金剛永謹 豊嶋幸洋 宇高徳成 惣明貞助 田村修
地謡 宇高竜成 豊嶋晃嗣 今井清隆 種田道一 山田純夫
狂言後見 山本則秀 山本則重 若松隆 山本凜太郎
八月一日(土)観世九皐会


矢来能楽堂にて観世九皐会の定例会。四月の定例会がコロナ禍で延期されたもの。当初の日程では関根祥丸の桃々会と重なってしまい、見られないはずだったが、両方とも後日に延期されたために、来ることができた。
防疫のために席は左右を空けて百席限定。能二番、狂言一番に仕舞がいくつかというのが九皐会公演の基本的構成だったが、途中に消毒をする入替制にして二部に分割。十五時からの第二部に行く。
地謡は能も四人のみ。アクリル板(二枚つながりで、直角に曲げて立てる)で互いを仕切り、飛沫を防止していた。
・仕舞『歌占 クセ』小島英明
・仕舞『東岸居士 キリ』観世喜之
・狂言『茶壺』山本泰太郎
・能『菊慈童』永島忠侈
昨年九月に『檜垣』の素晴らしい演能を見せてくれた永島忠侈。しかしコロナ禍による数か月の活動停止は、高齢のシテ方にとって、体力の維持を難しくしたのかも知れなかった。
八月三日(月)削りの鉄則

夜はオペラシティでBCJのマタイ受難曲。とにかく素晴らしかった。
人の弱さといやらしさ、ちっぽけさを歌ったこの作品が、コロナ禍においてこれほど切実に響くとは。
この作品の肝である「自分たちは今、取り返しのつかないことをしでかしている最中なのだ」という思いを、あらためてひしひしと実感する三時間。
この曲には、イエスが死んだ直後に地震で死者が復活し、「げにかの人は神の子なりき」と感嘆される場面がある。
そこは、カール・リヒターの旧盤などはまさに天上からの光で満たされるような、すさまじい説得力の響きになっていて、全曲中最大の力点がおかれている。
BCJの演奏が好きなのは、人間たちの行動と思いをきわめて劇的に描く一方で、そこをそれほどには強調していないことだった。神の子だと信じるかどうかは聴くものにまかされている。押しつけてはこない。
問題は人間たちなのだ。
今回は感染防止のために合唱をオケの前に出した、普段のBCJとは裏返しの配置が思わぬ効果を生んだと感じた。
もちろん、オーケストラが最後部に広がるため響きが散漫になる傾向があり、一長一短はあった。音響体としては通常配置のほうが一体感が出るが、今回の配置のほうが音のドラマとしての切迫感、迫真感があったのだ。
 BCJのツイッターから。
BCJのツイッターから。リハ中の写真で、飛沫を防ぐためにオケが後ろで歌手が前にいる。通奏低音のチェロの後ろには幅広のアクリル板。
本番での歌手はもう少し前に出ていたと思う。客席は前2列をあけていた。

当日のステージマネージャーがツイッターに配置図を公開してくれている。指揮者は合唱の飛沫が来る位置より離れていた。ソロは指揮者の真横なので、危険が少ない。そのぶんソロは首を横に回して指揮を見ないといけないので(そのときは発声しない)、大変そうだった。
客席を半分に減らしたために、昼夜の二回公演。三時間の長丁場を二回というのは大変だったはずだが、見事な公演。
それにしても、合唱を聴くのは二月の紀尾井町ホール以来。オペラシティに行くのはなんと昨年十一月以来。まさに失われた半年という感じ。
この演奏を、鈴木優人指揮東京交響楽団のメンデルスゾーン編曲版と聴き比べてみたかったと、あらためて思った。大人数のアマチュア合唱団が歌うメンデルスゾーン版は、十九世紀の市民社会のためのオラトリオとしての位置づけを明確にしてくれたはずだ。しかし現状ではアマチュア合唱団の練習と本番は感染リスクが大きすぎ、中止となったのだ。
ところでBCJの直前には、遅れに遅れていた厚い原稿をようやく出すことができて、一安心。
担当さんが悲鳴をあげているのを知りながら、四千四百字といわれた原稿を時間を余計にかけて六千字も書き、さらに一時間半かけて千六百字削るって、一体どういう神経なのか…(笑)
こういうときの鉄則。
・自分が面白いと思う箇所から削る。
・うまく書いたつもりの導入部はすっぱりと捨て、いきなり本題で始める。
どちらもひとりよがりなだけだから。導入というのは、しばしば自分自身が本題に入るための助走に過ぎず、読者には関係なかったりする。
でも、そう割り切れるまでには時間がかかる。もったいなくて、いつか使えるかもと思い、削った部分も一応取っておくが、あとで思い出すことなんて絶対にない(笑)。
八月四日(火)かなわねばこそ
先月三十一日に続いて、「能楽公演2020~新型コロナウイルス終息祈願」の七日目を見に国立能楽堂へ。

・舞囃子『葛城 大和舞』本田光洋
・狂言『川上』野村萬
・能『安宅 勧進帳 滝流之伝』観世銕之丞
銕之丞の『安宅』は、この人らしい力強さが、無駄な力みなしに、自然に発揮されたものだった。進行も澱みなく、リズムよく運ばれて心地よい。最後の「滝流之伝」の舞も勇壮。
野村四郎は著書の『狂言の家に生まれて』(白水社)で、この「滝流之伝」という小書を「弁慶一人を勇者に仕立てた歌舞伎の『勧進帳』を能のほうに逆輸入したような感じで、すごく派手な演出」だとし、「立派で大きく、しっかりした体形で声もよく出る人であれば」似合うと書いている。その意味では、銕之丞はぴったり。

ただしこの小書の場合、関をぬけた後で義経の境涯を地謡が語る、クセという部分を抜くことになっているという。
野村は「このクセは義経主従が命がけで平家を滅ぼしたにもかかわらず、讒言により兄頼朝に追われ流浪する運命を嘆く優れた詞章のクセで、上手に謡えば、聞いている人を深く感動させる力があります」と述べている。「義経と主従の絆というようなものが、ひしひしと伝わる文章になって」いるのに、これは歌舞伎には採り入れられていない。
自分も、二〇一八年九月に国立能楽堂の公演で、宝生流の武田孝史による『安宅』を見たとき、それまではわからなかったこのクセの素晴らしさ、能ならではの素晴らしさを教えられた気がした。
以下は、そのときの可変日記から。
なるほど、と思わされたのは関所をどうにか抜けて、弁慶が義経に無礼を詫びたあとの場面。平家を滅ぼしながら讒言によって陥れられた悲運の境遇への嘆きが、地謡によって謡われていく。ここで義経主従は動きも表情も殺し、一切感情を出さずに座っているだけ。一幅の絵と化したように停止する。
この部分がこれまではとても長く、正直退屈に感じられたが、今日は違った。字幕つきで地謡の歌詞がよくわかるおかげもあり、動きのない場面ゆえに、その向こうの世界に思いを馳せたくなる。
見事に切り抜けられたからこそ、そこまでして切り抜けねばならない主君の境遇の不運を思う。感情と行動が激発した関所抜けの場面から、無言の回顧と内省へ。激動から静止へ、有から無への変化と対照にこそ、能の醍醐味がある。直前の義経の詞「げにや現在の果を見て過去未来を知るという事」を受けて、ここでは時間の進行が止まって、来し方行く末の無限の時空とつながっている。
能舞台の上の時空を停止させて、そこにはない、その前後の時空へと広げ、多層化させる。これこそ能の魔術。
平家と戦って駆け抜けた海と山、大地の思い出。讒言による栄光からの没落と逃避行。神も仏もないのか。はたしてこの先、主君の未来には何があるのか。
義経は言う。「かなわねばこそ憂き世なれ」
このクセを抜いて、代りに豪傑弁慶が派手に舞う「滝流」は、まさに歌舞伎的なのだ。「落人の存在とその悲哀」というのが『安宅』を語るのに「いちばん大切で適切な言葉」だと考える野村は、だから「滝流」が好きではないという。
自分も『安宅』の弁慶は万夫不当の豪傑というより、義経に従う十人の武者のなかで、沈着冷静で智略と豪胆さをかねそなえた将校的存在だと思う。
富樫が通過を許す理由は、主人をあえて打擲するという弁慶の行動ではない。歌舞伎と違い、それでも許さないと言っている。通さざるを得なくなったのは、弁慶の背後にいる武者たちの、決死の気魄にたじろいでしまったからなのだ。
弁慶が、強力の格好をさせた主人を打つことまでしなくてはならない。その苦しみと情けなさを他の武士たちも共有したからこそ、山を動かすほどの気魄が火を吹いたのだろう。
関を通れたのは弁慶一人の力ではなくて、全員の力を結集できたゆえだが、しかしそれは結局、武者たちにとっては恥ずべきことだった。だから、関を遠ざかって小休止したとき、我に返ったかれらは「夢のさめたる心地して」泣くのだ。
なるほどと思い、それなら自分もクセがあるほうが好きだと思いつつ、今日の場合は「滝流」でよいのかもと思う。
なぜなら防疫のために、本来は九人いるはずの同山(同行の山伏)が五人に減らされていて、弁慶の存在感が相対的に大きくなっていたからだ。主従十一人が舞台に居並んでこそ、あのクセは活きてくるのかもしれない。
早く、同山全員が出られる日が来てほしい。
地謡も三十一日同様に一列五人だったが、口を隠す布はつけていなかった。そのためか響きの弱さは感じなかった。むしろ、少ないために響きが明快になり、詞章が聞きとりやすかったかも。アイやツレは通常通りに舞台にとどまり、細かく出入りをすることもなかった。
一方で、出入り口には以下の張り紙があった。
配役変更のお知らせ
八月五日 能「西行桜」シテ梅若実は、体調不良により観世銕之丞が代役を勤めます。
八月六日 能「船弁慶」は都合により、前シテ金剛永謹、後シテ金剛龍謹にて勤めます。
長期間の公演自粛による影響もあるのだろうか。銕之丞は連日の演能となる。
八月十二日(水)日傘の新調など

写真は、今年のコロナ酷暑をしのぐためのグッズ。
右下は冷感マスク。ポリエステル九とポリウレタン一という材質で、涼しいというよりも、不織布のように内部に熱がこもる不快感がないのがとても楽。耐用性もある程度ありそう。
その左上に晴雨兼用傘を二本。
中央の大きいのはドイツのクニルプス社製。一九二八年に折り畳み傘を発明した会社なんだそうな。ドイツの傘なんてゴツそう、と思ったが、その前の軽量日傘が三年目でもうシャフトがきしみだしたので、しっかりしたメーカーにしたいと思った。三百八十グラムは確かに軽くないが、広げたときには重心が絶妙なので重さを感じない。ボタンで自動開閉できるのも楽だし、機構もしっかりしていそう。おもに日傘として使うので、涼しげな青と白のストライプにした。
左上の紺色の細いのは、その補助役に用意したもの。使うかどうかわからないが降るかも、くらいの時に鞄にいれておくには、クニルプスは重すぎる。こちらはとにかく軽い。百十六グラム。そのぶん華奢なので、あくまで万一の保険。降雨時メインなので暗めの紺。
八月十三日(木)日経アートアカデミア
日経新聞のオンライン講座「日経アートアカデミア」というのがある。
その「ベートーヴェンと現代」シリーズ第二回は、千葉交響楽団の音楽監督山下一史と楽員による室内楽作品演奏。
曲は「七重奏曲」「交響曲第六番第一楽章(弦楽四重奏版)」、そして山下さん指揮の「コントルダンス(三曲)」。
自分は演奏前に交響曲を中心に山下さんにお話をうかがう役を仰せつかった。
日経新聞本社には日経ホールという小ホールがあり、月一回程度の自主公演シリーズがあるが、海外のアーティストが来られないことなどで休演続き。その空いたスケジュールを活用して、七月に無観客の日経ホールで収録した。メンバーも山下さんも、活動自粛以来数か月ぶりの実演だそうで、楽しそうだった。

税込千円で一週間視聴できるので、とりわけ千葉方面在住の方は(笑)ぜひ。
なお第一回は片山杜秀さんの講演、同氏と一柳慧さんの対談、飯野明日香さんのピアノ演奏と、こちらも豪華版。
八月十五日(土)
三十六度のくそ暑さの中、音楽同攻会OB会の打ち合せに呼ばれて早稲田大学へ。二〇一七年十一月にOB会の総会でしゃべって以来だから三年ぶり。

コロナ禍に加えて夏休み期間なので建物や大隈庭園は閉まっている。しかしなんとなく学生(?)がうろうろしているのは昔と同じ。

かつて第二学生会館があったところ(今は大隈記念タワーというのが建っている)から、正門脇の通用門を見る。キャンパス内には知らない高いビルがニョキニョキ。建物の様式にさっぱり統一感がないあたりがいかにも早稲田。

一九八〇年代に部室があった大隈講堂裏と、その脇の元予備校のビル(今はエクステンションセンター)。その隣の文具のサンワと、一軒置いて隣の立ち食いそば屋は昔のままに存続。サンワとそば屋の間にある靴屋はまったく記憶にないのだが(笑)、昔からあったか?
渋谷駅東口行きのバスに乗って帰る。途中にも喜久井町キャンパスとか、いつのまにか増殖していた。
八月十七日(月)白昼のカルメン

酷暑の午後、新百合ケ丘の昭和音大のなかにあるテアトロ・ジーリオ・ショウワで、藤原歌劇団の《カルメン》。
オペラ全曲をみるのは、二月十六日の王子ホールでの、モーツァルト・シンガーズ・ジャパンによる《コジ・ファン・トゥッテ》以来。オーケストラ伴奏と合唱つきとなると一月十五日の、日本オペラ協会の《紅天女》以来。
本来は四月にやるはずだったが八月に延期し、演出も感染防止を意識したものに変更された。
具体的には、舞台最後列の高いヒナ壇に合唱をならべ、前にオーケストラ。最前部の空いた部分で独唱とダンス。独唱とダンスは舞台衣装をつけているが、装置は椅子と可動式の小さな壁が四枚あるだけ。ほとんどセミステージ形式上演に近い。
歌手、合唱、ダンサー、そして指揮者はフェイスガードをつけている。大げさにも感じられるが、大きな団体のなかでは自粛後最初のオペラ全曲公演となるだけに、万全を期したスタイルとなるのは仕方のないところ。ここでつまずいたら終わりなのだ。様子を見ながら各団体で回数を重ねて、緩められるところを緩めていくことになるのだろう。
発声によって、明らかにフェイスガードに響いてしまい、ビリビリとヴィブラートがかかったり、それほどでもなかったりするのが興味深かった。
 写真は藤原歌劇団のツイッターから
写真は藤原歌劇団のツイッターから岩田達宗のこの演出は、原型になった二〇一七年の初演の舞台をみている。そのときは、社会の底辺に暮らす登場人物の中で、まだしも兵士(ホセが最初に属している集団)が恵まれた階層だと明快に示されていたことに、とても説得力があった。だからホセはその所属を失いたくない。しかしカルメンに誘惑されたことでそれを失い、といって根無し草の盗賊団にも共感できず、故郷にも満足できず、身の置き所を失って破滅していく。その流れが明確だった。
ところが、合唱と独唱が前後に分離され、演技のからみをできるだけ削らざるを得ない今回は、登場人物を社会や集団のなかに位置づけることができない。
ただ、個人対個人のドラマだけがあるということになる。
それによって、うまくいくところとそうでないところが出てきて、それが《カルメン》という作品の構造を浮き彫りにしてくれたのが面白かった。
第一幕は、全体に収まりが悪い。ここでは、さまざまな人間が行き交い、深浅の関係を持つ、街そのものが大きな役割を果たしている。それなのに今回は雑踏を描きようがない。ホセもカルメンも、その街角の群衆のなかから存在が浮かびあがるはずなのに、そこが希薄になる。
ただ、この街で(というより、このオペラ全体において)いかなる集団にも属さない闖入者のミカエラだけは、街がなくとも存在が映える。だからホセとの二重唱は、舞台の制約を超越して美しい。
彼女が体現する故郷の山野や母の愛などの居心地のいい共同体は、初めからイメージの中にしか存在しないから、制約を越えることができるのだ。
第二幕も、冒頭のジプシーの踊りから闘牛士の登場にかけては、酒場の群衆とのからみがないと、本当の熱気がわいてこない。エスカミーリョも常に大衆の讃仰の中にある存在だから弱くなる。
対してこの幕の後半は独唱たちだけでつくられる場面だから、うまくいきそうなのに、しかしそうでないのが面白い。それぞれの思いと行動がバラバラの方向を向いたまま、相殺しているようなもどかしさが残る。
それが、逆にからみあって活かしあうのが第三幕。特にその終わりのアンサンブルは、全曲のなかでも白眉となる冴えを、台本と作曲の双方がみせている。
ここではそれぞれの欲望と感情と立場が衝突しあい、からみあい、その緊張のなかで互いを輝かせあう。そのドラマの素晴らしさ。二幕にはいなかったミカエラが、実はそのすべてを結んでいる。
なぜなら、ミカエラが体現する家族や故郷との結びつきは、カルメンや他のジプシーが持ちようのないものだから。捨てられたのか捨てたのかはそれぞれだろうが、かれらは仲間というあやふやなものにすがるしかない。だからかれらはミカエラの存在にいらつき、それをごまかすように、俺たちは根無し草じゃない、仲間と一緒で自由なのだと叫んで、犯罪に突き進んでいく。
ミカエラへのいらつきの表れかた、反応のしかたが役によって異なることが、それぞれの立場を明確にし、からみ合わせるのだ(しかし実はミカエラもホセの母に引き取られた孤児であり、ホセの母とホセを失えば、元の木阿弥になるのかもしれない)
第四幕もうまくいく。ここでは群衆も他のキャラもみな第三者にすぎない。闘牛士の行進までがどんなに盛り上がろうと、すべては遠景。カルメンとホセの破局のドラマだけが真実。
ホセの最後の「俺を捕まえてくれ、俺がカルメンを殺したんだ」というような歌詞のところで、しかし誰も他に出さなかったのは大正解。
捕まえにきた兵士も、惨劇に驚くエスカミーリョや群衆の姿もいらない。最後の音楽は、かれらのことなど何も描いていないのだ。ただホセと、死体となったカルメンだけ。
この演出では、ファム・ファタールを暗示するような赤い月がここまでずっと後方のスクリーンにあるのだけれど、ここだけは白い、白けた昼の太陽が出た。
――白けた太陽と、女の死体と、すべてを失った男。
それが一瞬、《マノン・レスコー》終幕にオーバーラップして、その幻影に私の心がおののく。
まわりにあるのは闘牛場ではなく、見渡すかぎりの砂漠と、白い太陽だけ。喉の渇き。デ・グリューにとっても、ホセにとっても。
やっぱオペラも素敵。
八月二十一日(金)鎖国下のクラシック
NHK交響楽団が九月公演でのパーヴォ降板を正式に発表。現状を鑑みれば仕方のないところで、代役は山田和樹と広上淳一。
山田がペルトを武満に変えたのは、日本ではできるかぎり邦人作品を入れたいという思いのあらわれだろう。以前にインタビューしたとき、かれはそう語っていた。海外に邦人作品を紹介することも大切だが、日本のクラシック好きも、聴いている人は限られている。
武満の《弦楽のためのレクイエム》なんて有名曲すぎる、もっと新しく未知の作品をやれという意見も当然出るだろうが、これだってちゃんと聴いたことのない人は、マニアとまでいかない層には、実はけっこういると思う。
それにしても、九月の在京オーケストラの指揮者陣を一覧にしてみると、本当に七十五年前の終戦直後以来の特殊な状況が復活してしまったと思う。海外の指揮者の名前がそのままになっているところもまだあるが、おそらくは難しい。
NHK交響楽団:山田和樹、広上淳一、下野竜也
東京フィル:小林研一郎、(バッティストーニ→渡邊一正)
東京交響楽団:飯森範親、原田慶太楼、井上道義、大友直人、(ブランギエ→尾高忠明)
日本フィル:山田和樹、小林研一郎、園田隆一郎、原田慶太楼
読売日本交響楽団:小林研一郎、尾高忠明、鈴木優人
東京都交響楽団:大野和士、梅田俊明
新日本フィル:秋山和慶、矢崎彦太郎、沼尻竜典
東京シティ・フィル:井田勝大、高関健
六月下旬から在京のオーケストラが徐々に活動を再開した頃、私はこの日記に「この困難で特殊な状況下で、日本の指揮者と演奏家たちをあらためて聴きなおし、そして、日本でクラシックをやる意味、聴く意味を再考する、またとない機会になりそうだ」と書いた。まさにそのときが来ている。鎖国下のクラシック。
ただ九月はシーズン初めの時期だからか、どのオケの人選も手堅い感じ。一回りすると、さらに若い人たちにもチャンスがいきそうだ。
あとは、聴衆の側の根強いヨーロッパ(特にドイツ語圏)志向&信仰が、変るかどうかなのだろうが……。
八月二十二日(土)BCJのヨハネ

バッハ・コレギウム・ジャパンがコロナ禍中のケルンで録音したヨハネ受難曲が九月二十日に緊急発売される。これは楽しみ。
「CD録音セッションは、ライブ・ストリーミングの前後一両日、ヨーロッパの各国が順次国境を閉鎖しフライトも次々のキャンセルされていく、大変緊張した雰囲気の中で行われました。ホテルのカフェやレストランも徐々に営業場所を狭めていき、最終日には、ついに警察官がホールに現れ、直ちに立ち退いて建物を閉鎖するよう求められました。しかし幸い、その警察官もBCJの演奏を聞いて下さっていたことから私たちの活動を理解してくださり、1時間だけ猶予が与えられたのでようやく最後まで収録することができたのです。
皮肉なことに、ヨハネ受難曲は、このような緊迫した雰囲気の中で演奏するのに誠に相応しい受難曲と言わざるを得ません。イエス・キリストの逮捕と処刑という緊迫した物語を、マタイ受難曲より遙かに劇的に映し出したこの音楽は、私たちが今回経験した大きな苦難に際し、この世に生きることの意味を、改めて考え直すことを私たちに迫るかのようです」
~バッハ・コレギウム・ジャパン音楽監督 鈴木雅明~バッハ・コレギウム・ジャパン公式ホームページより
八月二十四日(月)百十年目のベートーヴェン
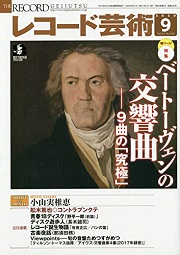
発売中の「レコード芸術」九月号の特集は、『ベートーヴェンの交響曲 ――9曲の「究極」』。
生誕二百五十年のベートーヴェンの交響曲について、さまざまな切り口のディスク紹介を中心に盛りだくさん。
俊英指揮者、坂入健司郎さん(鎖国下の演奏界において、活躍が期待される一人)の「ベートーヴェンの交響曲を指揮すること」という、演奏現場からの寄稿もある。面白いのでぜひ。
自分は「ベートーヴェン交響曲録音の110年」と題した録音史と年表を書いた。一九一〇年に大オデオン弦楽合奏団(指揮者不詳)が《運命》全曲を録音してから、今年は百十年目。編集者に多大の迷惑をかけつつ、原稿は百十の百倍の一万一千字(これは偶然)。
この特集で紹介されている新録音のなかで、ほかに海外盤Reviewの「今月のイチオシ」でも音楽エッセイストの鈴木淳史さんが紹介していて、特に期待をそそるのがサヴァール指揮ル・コンセール・ド・ナシオンによる、第一~五番のSACD三枚組。
日本でも九月十日発売予定だが、待ちきれなくてドイツのJPCに注文した現物が、七月二十三日発送から一か月かけて到着。英米からの航空便は七~十四日くらいで届くようになったが、まだものによっては時間がかかるらしい。まあ、今年の春には三月に向うが出して、四か月後の七月に着いたCDもあったから、その最長記録に比べれば(笑)。

届いたのは他に、ティーレマンとシュターツカペレ・ドレスデンが昨年のザルツブルク・イースターで演奏した《マイスタージンガー》(ツェッペンフェルト、フォークト他)。それとフラ・ベルナルドが出した「CARA SPOSA」というヘンデル・アルバム。ORFの既発売音源からで、チェンバロ・デュオのル・プティ・コンセール・バロックが中心。最後にジャルスキとスピノジによる二〇〇六年の《リナルド》の〈CARA SPOSA〉のアリア。
この二つも日本では未発売なので、早く手に入れられて嬉しい。ミュージックバードでも十月には紹介できる。
八月三十日(日)将門=逆髪?
最近、半蔵門駅近くの山下書店の棚が面白くて、ミュージックバードへ行くたびに覗いている。目利きの店員さんがセレクトしているなあ、という感じ。
前からそうだったのだろうけれど、コロナ禍の前はお客が多くて通路を歩きにくく、じっくり見る余裕がなかった。最近は空いているので行きやすい。もちろん、このままだと店の存続にかかわるだろうから、このあたりは難しいところ。自分が行くときだけ空いていて、それ以外は混んで売れているというのが理想だが、そうはうまくいかない。
そこで先日買ったのが、関幸彦の『英雄伝説の日本史』(講談社学術文庫)。帯の惹句に「かくて義経は成吉思汗に、道真は天神様になる」とある通り、英雄伝説の変貌の過程を追うもの。

まだ途中だから感想はおくけれど、メインの章立てが「道真と将門」「田村麻呂と頼光」「為朝と義経」という二人ずつになっているのは納得のいく組み合わせで、だから読む気になった。
ここで書きたいのは「道真と将門」のこと。近代以前の日本ではこの二人、つまり菅原道真と平将門が対になっていたということを自分が知ったのは、ほんの数年前のことだった。
なぜ気がつかなかったというと、将門が武士で道真は公家で、武士と公家は決定的に違うという思い込みのためだ。
近代日本のステロタイプな分類を信じこみ、武士がカッコいいと思っていた。公家は文弱で卑怯で形式主義で女々しく優雅なのに対し、武士は剛健で勇敢で実質重視で雄々しく無骨。
日本男児たるもの、心はサムライたるべしというような、昭和大衆社会の典型的な、いわば講談社的美学にはまっていた。だから、公家の陰険な宮廷劇の敗者である道真には感情移入しない。
死後に怨霊になって大暴れしたとはいえ、幽霊の復讐というのは四谷怪談のように、現実的な力がない女性がやるもので、何か男らしくない感じがした。
自分自身はちっとも男らしくない、貧弱で卑怯な人間なのに、それでもこういうマチズモを振りかざすのが当然だったのが、昭和という時代だった。
そして将門は、武士のなかでも社会の革新者という存在の先駆けというイメージがあった。
これは中学二年で見た、大河ドラマの『風と雲と虹と』とか、その後に読み始めた司馬遼太郎の歴史小説とか、いやそれ以前に当時の全般的な、革新偏愛の歴史観の影響だろう。
それは英雄史観とでもいうべきもの。時代の激動期に登場し、社会を変革する英雄を中心に、歴史を物語るやりかた。時勢の変化を体現する者としての英雄。
もちろん、当時の極端な左翼の人たちは英雄否定の民衆史観みたいなものを掲げていたけれど、物語としての魅力は比較にならなかった。何かPTA的な、ヒステリックな感じもした。
それはともかく、この英雄史観も道真と将門を切り離してしまう。将門は頼朝以降の、社会を変革する板東武者の元祖なのだ。ヨーロッパから維新とともに入った近代の英雄像、「高貴な野蛮人」のイメージがそこに重ねられる。東洋的な豪傑から西洋的な英雄へと、人気の対象が変わる。信長や龍馬など、憧れの歴史変革者たちの、早すぎた元祖。
ところが、こうした近代的英雄観のフィルターを外して中世を眺めなおすと、道真と将門はセットになっている。
それを知ったのは四年前、樋口州男著の『将門伝説の歴史』(吉川弘文館)を読んだときだった。二〇一六年三月十一日の可変日記に書いている。
「面白いのは、将門を死後すぐに伝説化させていく人びとが、最近の研究ではどうやら、道真を怨霊化させることで自分たちの復権を、少なくとも憂さ晴らしをもくろんだ、道真の不遇の遺児たちと弟子に連なる人脈らしいと、みえてきていること。
左遷されたかれらは、将門が暴れた常陸などの遠国で吏人、つまり事務方をやっていたらしいのだ。中央で身につけた文筆能力をもつかれらが書きとめないかぎり、僻陬の地の反乱者の伝記、すなわち『将門記』などが、きちんとした形で残るはずはなかった。
伝説の裏の、なまなましい現世の人間たちの思いと恨み」
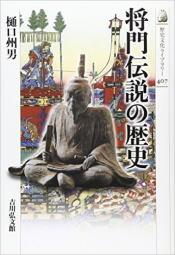
道真と将門の死後の伝説化に力を注いだのは、道真の不遇の子孫や弟子たちだった。怨霊も反乱も、為政者に対する抗議という点では同じなのだ。
道真が死んだのは九〇三年。将門は九四〇年で、三十七年も離れている。これも二人を一緒にイメージしにくい理由の一つだが、ここで重要なのは、道真が宮廷に祟りをなす怨霊としてはっきりと認識されるようになるのは、何年もたってからだということ。
醍醐天皇の東宮保明親王が亡くなったのが九二三年。親王は道真を左遷した藤原時平(九〇九年没)の甥にあたっていたため、道真の祟りという噂が出て、帝は二十年ぶりに道真の追放を解いて、正二位を追贈する。
しかし、父保明の跡を継いで東宮となった慶頼王(時平の外孫)も、二年後に五歳で没する。その後も台風・洪水・疫病と災厄が続く。
怨霊の存在が決定的になったのは九三〇年、内裏の清涼殿に落雷し、大納言藤原清貫など公卿・官人に複数の死者が出た事件だった。清貫はかつて道真追放に関与し、配流先の太宰府を訪ねて道真の動向を探った人物だったので、道真の怨霊が雷神になって復讐したと考えられるようになった。惨事を目の当たりにした醍醐帝は病となり、三か月後に崩御。
一方、将門が関東で源氏や平氏の豪族との武力抗争で世を乱しはじめるのは九三五年のこと。道真の雷神が出現して五年しかたっていないから、同時代の事件といっていい。だから道真の祟りと将門の反乱がセットになるのは不思議ではない。将門の生年は不明だが九〇三年という説があり、だとすると道真の生まれ変わりのような気配にもなる。
道真と将門がセット。ここでそういえばと思い出したのが、能の『雷電』。二〇一七年六月七日にこの能を見たときの当日記から、以下引用。
「叡山の秋の夜。天台座主の法性房尊意(ワキ)を訪ねて、菅原道真の幽霊(シテ)が現れる。幼少時の学問の師である法性房に、旧恩を感謝する幽霊。しかしその真意は、これから雷神となって内裏に行き、自分を陥れた貴族どもを蹴殺してやる。高い法力を持つ法性房に助けを頼みに来ても、どうか邪魔をしないでくれという依頼だった」
しかし尊意が聞き入れないので、道真は鬼に変じて内裏を襲い、尊意が法力でこれを鎮めるという話で、元ネタは太平記や北野天神縁起にある。
奇妙なのは、実在の尊意が道真より二十一歳も年下で、「幼少時の学問の師」にはなりえないことだった。
それをなぜ結びつけたか。結び目に将門がいる。『英雄伝説の日本史』によると、尊意は将門の乱で調伏祈願を行なった。霊験あらたかに将門は翌月討たれたが、相討ちになったかのように、尊意も二か月後に入滅した。
この強敵同士の相討ち話をヒントに、将門を道真に置きかえたのが『雷電』だとすれば納得がいく。能は怨霊を退けて万々歳で終わるが、引き換えに尊意も生命を落とすことが、物語の裏に予感されているのだろう。それを恐れて、道真は旧師を止めに現れたとも考えられる。
さらに頭に浮かんだのが、『蝉丸』。蝉丸伝説を元に自由な創作を加えたこの能についての考察は、二〇一九年九月二十日の日記に書いている。
この能の蝉丸は道真、逆髪は将門の暗喩と考えることはできないだろうか?
時代は醍醐帝の御代。蝉丸はその第四皇子だが盲目。この蝉丸を逢坂の関に連れてきて、置いていくのが藤原清貫(前述のとおり、のちに道真の怨霊の雷撃で殺される人物)。罪もなく追放された蝉丸は文句も言わず、泣きながらそこに暮らす。
そこに来た逆髪は、蝉丸の姉にあたる皇女。しかし不思議なことに、登場のときは「延喜第三の皇子」と、男であるように名乗る。髪の毛が逆立っていて、ときに正気を失うために宮廷を放逐され、東に進んで逢坂にたどりついた。
女か男かはっきりせず、垂れるべき髪は逆立ち、正気と狂気が入れ替わる。
「それ花の種は地に埋もつて千林の梢に上り、月の影は天に懸つて万水の底に沈む、これらをばみないづれか順と見、逆なりと言はん」
何が順で何が逆か、決められるのか。
「我は皇子なれども、庶人に下り、髪は身上より生ひ上つて星霜を戴く、これみな順逆の二つなり、面白や」
こうした逆髪の言葉が、賜姓皇族となって板東に下った一族から出て、そこで反乱を起して逆賊となり、新皇を名乗って王朝を築こうとした将門を意識したものとすれば、一々腑に落ちる。
唯々諾々と配流地に留まる蝉丸と、慰みを求めて東国に下る、行動的な逆髪。道真と将門、公家と武人の違いが、そこに反映されていないだろうか。
蝉丸は伝説上の人物だが、逆髪は能作者の創作とされる。坂神の言い換えといわれるが、サカガミという響きの大元には、マサカドがあるのではないか。
皇国史観の戦時中、能界は『蝉丸』の演能を自粛したという。醍醐帝を悪者として描いているからだそうだが、隠された反逆者としての逆髪の存在も、ひょっとしたら問題だったのではないか。
もちろん、すべては妄想。しかし次に『蝉丸』に接する機会があったら、こんなことを意識して見るのが楽しみ。
追記:十月頃、たまたま『日本の聖と賎 中世篇』(野間宏、沖浦和光/河出文庫)という対談本を読んでいたら、中世の大和国奈良坂にあった、北山宿という非人宿、夙(しゅく)の話が出てきた。

般若寺坂(吉川英治の『宮本武蔵』に登場する般若坂のことだ)とも呼ばれるこの坂の上には、奈良豆比古神社という古い神社があり、毎年十月に地元の人による翁舞の神事があることで知られている。三人の翁が舞うもので、能の『翁』の古態とも目される。この神社の縁起というのが面白い。
天智帝の子、施基皇子の子である春日王は、逆髪が生えて白癩を患ったため、都を出てこの地に隠棲した。春日王の二人の子、浄人王と秋王(安貴王)は、市に出て自ら削った弓矢を売ったり散楽(猿楽)をしたりして稼ぎ、父を養った。孝養の甲斐あって春日王の白癩は快癒し、このことが上聞に達して弓削の姓を賜り、市人から弓削夙人と呼ばれたという。
奈良豆比古神社の翁舞の三人は春日王と二人の王子のことで、そして浄人王は猿楽の元祖となったという。
もちろん、由緒を飾るための伝説で、実在の人物の名をそれらしく借りただけで、史実ではないだろうが、逆髪の王子とくれば、否が応でも『蝉丸』との関連を思う。
そこで、ネタ元として紹介されている『能楽風土記』(藪田嘉一郎/檜書店)を入手してみたら、やはり藪田も、この伝説を奈良坂から逢坂に移したのが『蝉丸』の元ではないかと推察していた。
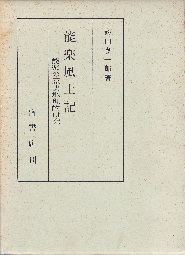
能作者が、何の根拠もなく逆髪を創作したと考えるよりは、坂という境界の地にまつわる悲運の皇子という共通点をもつ春日王を蝉丸に組み合わせたと考えるほうが、説得力がある。
かたや琵琶法師の祖、かたや猿楽の祖という二人であるのも面白い。そしてそこに、道真と将門のイメージも重ねる。逆髪という言葉が「逆をなす者」を連想させるからだ。
そのとき、将門同様に簒奪を企んだ人物として、弓削道鏡もイメージされていたかもしれない。道鏡には天智天皇の子の志貴皇子の落胤とする説があり、これは春日王と同じだ。しかも道鏡の弟は弓削浄人というのである。
どれが先で、どれが後なのかはさっぱりわからないが、蜘蛛の巣のように伝説がからみあっていて、妄想すると実に楽しい。
九月一日(火)《フィデリオ》(一)

新国立劇場で二期会《フィデリオ》ゲネプロ。大植英次指揮、深作健太演出。
感想は三日の初日後に。ともあれよくもわるくも、いろんなことを考えさせてくれる舞台だった。
オペラパレスの《フィデリオ》といえば、二〇一八年五月の飯守泰次郎指揮、カタリーナ・ワーグナー演出の舞台の毒気が、いまも身体から抜けない(笑)。
あのアンチ・クライマックスの、「寝取られ」の鳥肌が立つような嫌悪感は、しかしそれゆえにこそ劇場的昂奮、マゾヒスティックな劇場的快感につながっていたから、自分が生涯ただ一度、拍手しながらブーイングしたものだった(詳しくは同年五月二十日の日記に書いた)。
今晩の出演者のうち、ドン・フェルナンド(黒田博)とロッコ(妻屋秀和)が共通していたことが、いっそうあの舞台を思い出させた。
とにかく《フィデリオ》は考えさせるオペラ。この作品にからんで、最近聴いたCDで面白かったのが、ズヴェーデン指揮ニューヨーク・フィルがデッカ・ゴールドから発売した、デイヴィッド・ラング作曲の歌劇「プリズナー・オブ・ザ・ステート」。
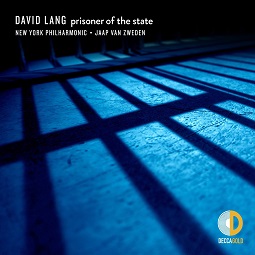
二〇一九年六月のこの作品、ストーリーは《フィデリオ》そのまま。国事犯、正確には国事囚と訳せるタイトルは《フィデリオ》のロッコの歌詞から採られた(今夜の字幕にも国事犯とあった)。
この作品の歌詞に納得のいかない魅力を感じたラングは、ベートーヴェンの音楽を一切使わずに、筋書と歌詞を借りて手を加え、自らの音楽をつけた。固有名詞をやめて看守とか助手とか、いつの時代にも場所にもいる抽象的な存在にし、人物を減らして本筋だけにし、そして最後に独自の合唱を加えて、いわば《フィデリオ》の批判的再話とした。
こういうものをつくりたくなる要素が《フィデリオ》にはある。面白くないだのなんだのと色々いわれるオペラだが、これだけ何かを語らずにいられない作品は、ベートーヴェンの作品でも珍しいかもしれない。言葉は言葉を呼ばずにはいられない、ということか。

最後の写真は、新国立劇場のもぎりのあたり。コロナ禍で七か月ぶりに訪れたオペラパレス、本番では検温とか連絡先記入とか、入場に時間がかかりそうなので、見られる方は時間に余裕を持って行かれたほうがよさそう。
九月三日(木)《フィデリオ》(二)

新国立劇場で二期会の《フィデリオ》初日。大植英次指揮、深作健太演出。
深作は二年前の二月に二期会で《ローエングリン》を演出している。
これはローエングリンにバイエルン国王ルートヴィヒ二世を重ね合わせ、国王ハインリヒをビスマルク、エルザをオーストリア皇妃エリーザベトに見立てていた。破綻していく現実の人生の最後に、ルートヴィヒが少年時代に憧れた《ローエングリン》の世界の夢を見る、といった印象だった。
ここで十九世紀後半のドイツ史を扱った深作が、《フィデリオ》では二十世紀のドイツ史を作品に重ねた。
冒頭、通常の序曲の代わりに深作は、レオノーレ序曲第三番を置いた。そしてその音楽に合わせて、ナチス・ドイツの強制収容所に入れられていたフロレスタン(ユダヤ人ではなくてドイツ人の政治犯らしい)をレオノーラが危機一髪で救いに来るという、《フィデリオ》そのもののあらすじを演じさせた。
名指揮者クレンペラーはレオノーレ序曲第三番について「ベートーヴェンは、この序曲のなかで、物語全体をくりかえしている」と述べていた。そしてこの曲を第二幕第二場の前に置くことにより、個人の運命の問題をここで人類全体の問題にまで高めてみせたベートーヴェンの意図を、より効果的に示すことができると考えていた。
深作も、この曲はオペラ全体の短縮版だと考えたのだろう。それを冒頭に置くことによって、序曲がオペラの物語をくりかえすのではなく、オペラが序曲の物語をくりかえす形にした。
この問題提起は面白い。序曲に登場する強制収容所は、アウシュヴィッツのような絶滅収容所を暗示するとともに、ナチス・ドイツそのものをも暗示する。
そして深作演出でのオペラは、ナチス支配の終わりと解放に始まって、「ベルリンの壁」が象徴する、冷戦下の東ドイツでの秘密警察国家の復活と崩壊(ここまで第一幕)、イスラエルによる分離壁とトランプによる国境壁の建設、そしてそれを取り払った戦後七十五周年記念式典の場へと進んでいく。はてのない圧政のくりかえしと、つかのまの解放。
ここで、ドイツ知識人二人の言葉を思い出す。
まずトーマス・マン。マンは「ドイツ人の自己解放の祝祭劇」である《フィデリオ》がナチス専制下の十二年間にドイツで上演禁止にならなかったのは、おかしいと考える。そして、「ヒトラーのドイツで《フィデリオ》を聞き、両手で顔をおおうことなく、会場から外に飛び出しもしなかったとは、何という鈍感さであろうか」と、ドイツにとどまって《フィデリオ》を演奏したり聴いたりしていた人々を、激しく非難した。
続いてアドルノの一言。
「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」
ナチズムが去っても、すぐにスターリニズムが来る。冷戦が終わって「ベルリンの壁」が崩壊しても、同時多発テロが起きる。そしてユダヤ人はパレスチナ人の生活を分断する分離壁をつくり、アメリカ人はメキシコからの不法入国を防ぐ国境壁をつくろうとする。
このような野蛮な愚行のくりかえしのなかでも、われわれは《フィデリオ》を上演し続けなければならず、その理想をあきらめてはならない。
この発想はとても面白かったのだけれど、残念なことに、舞台上に演じられるドラマとの関連が、また登場人物たちとの関連が、音楽と物語が先に進めば進むほど、どんどん希薄になっていった。
コロナ禍において三密を避けるため、演出プランは一から練り直しになったという。歌手同士、そしてそこに合唱団の動きをからめられなかったのは、致命的な障壁だったのだろう。映像と字幕で補おうとしたが、すればするほど、歌手たちのドラマとの乖離は広がった。
第一幕のレオノーラの大アリア《来れ、希望よ》のところで、ケネディ大統領の西ベルリン訪問の映像が出たのは、たしかによく合っていた。
全体主義の荒野に孤立する「自由主義の砦」西ベルリンの運命は西側諸国全体の運命でもある、ということを意味する「イッヒ・ビン・アイン・ベルリナー」という、このときのケネディの言葉には遠い理想への、苦くも力強い希望がこめられていたのだから。
偶然にも初日の二日前、チェコの上院議長が台湾の国会で、ケネディにならって「私は台湾人だ」と演説した。
スカッとするような言葉だけれど、中国は猛反発し、いやがらせを始めた。当然そうなることを予想しての、覚悟があっての言葉だったろう。
オペラはプロパガンダの場ではないのだから、政治的主張をそこまであからさまにしてほしくはない。ただ、オペラの中の出来事も二十世紀の歴史も、そうなりうるだけの切実さを内包していることは、示してほしかった。ここからはみなさんの考えかた次第です、と思わせるところまでは、行ってほしかった。
第二幕にはイスラエルの分離壁が登場した(深作が自らそう説明している)。池田卓夫さんが喝破したとおり、当初の予定どおり指揮者がエッティンガーだったら、イスラエル人であるかれは、この演出をはたして受け入れただろうか。
受け入れないだろうと私は思うが、諾否いずれにせよ、エッティンガーにとって簡単ではない決断になったはずだ。
しかし指揮者は大植に代わったので、問題は起きなかった。問題は起きなかったが、なにか、世界史的な事件のニュース映像をテレビ越しに安全な日本から眺めているような気分が全体に否定できなかったのは、こういうところなのだ。
エッティンガーにとって切実な問題となることは、我々にとっても切実な問題となる(現時点でそうだと思うか、明日そうなりうると思うかは、人それぞれとしても)。
被害者が時と所を変えれば加害者となる、少なくとも容疑者になる問題は人類共通で、誰も傍観者たりえない。「アウシュヴィッツ以後」に《フィデリオ》を見る人は、ドイツ人にかぎらず、誰もがそれを意識する必要がある。オペラ本編では、そこに切り込んでほしかった。
レオノーラははたして常に「民衆を導く自由の女神」なのか。ドン・ピツァロははたして常に悪魔の手先なのか。イスラエルの分離壁を出すなら、この疑問を提示してほしかった。
この問題の切実さをプロパガンダでなしに、人類共通のものとして実感させるには、舞台上の歌手たちと合唱の動きによるほかないと思う。
私は、読み替え演出の最大の意義は、切実さをより効果的に、新鮮な驚きとともに感じさせることだと思っている。
もちろん、読み替えればすべて切実になるわけではない。伝統的演出でも切実さを感じさせることは可能だ。現に六百五十年前から基本が変わらない能でも、シテの力で切実さは発現する。
ただ、読み替えでは意外さが新鮮さを生み、切実さが増す可能性が高くなる。
前述のように、コロナ禍のためにそのような演出を徹底できなかったのだとすれば、まことに残念。
九月五日(土)祝福の音

山田和樹指揮日本フィルの演奏会。
ここ何年か、九月のシーズン開始は日本フィルが先頭を切って、ヤマカズの指揮で行なうというのが、東京のオーケストラ・シーンの恒例になっている。
自分の場合は、直前の八月下旬から九月初旬にかけて松本の音楽祭に行き、空気のいいところでサイトウ・キネンを聴き、穂高神社に詣でて夏が終わり、そしてヤマカズで東京の秋が始まるというパターンが続いていた。
今年は松本の音楽祭がない夏。つまり個人的には、夏のない夏。
しかしこうして秋の行事は、例年通りに来てくれた。まだこれからも異常事態は続くけれど、その渦中にわずかでも日常が見つかるのは、嬉しいこと。
そしてそれにふさわしい、いい演奏会だった。
・ガーシュウィン:アイ・ガット・リズム変奏曲(ピアノ:沼沢淑音)
・ミシェル・ルグラン:チェロ協奏曲(チェロ:横坂源、ピアノ:沼沢淑音)
・五十嵐琴未:櫻暁(おうぎょう)
・ラヴェル:バレエ音楽《マ・メール・ロワ》
オーケストラは十型で十八六四三。
初めのガーシュウィンはピアノを指揮者の正面に縦に置き、オーケストラとの一体感を重視したスタイル。二曲目のルグランの独奏チェロは指揮者の脇に出たが、書法の問題なのか、オーケストラの響きのなかでチェロの音が映えにくい。三十分強の曲を長く感じた。
ソロのアンコールは、四本のチェロを伴奏とする《鳥の歌》。その前奏でオケの首席がソロをとったのだが、これが目の覚めるような、叙情的な横坂の響きとは別の、ピンと張りのある、気持のいい音。びっくりして見なおしたら、今日の首席はなんとゲストの伊東裕。そりゃうまいに決まっている(笑)。
終演後、横坂が伊東も立たせようとしたのに、ソロ・アンコールであることを意識してか、遠慮して立たなかったのも謙虚で気持ちよし。
後半は五十嵐琴未の新作。桐朋出身の若い作曲家だそうで、異常事態の中でこういう人にチャンスを与えたのが素敵。
「桜の夜明け」というタイトルだと、自分は能の『西行桜』の「待てしばし、待てしばし、夜はまだ深きぞ」「白むは花の影なりけり」とか、春の宵が過ぎるのを認めまいとするイメージを持つが、ここではむしろ、やがて来る払暁と開花を暗夜に待ち望む、「花の影より、明け初めて」の曲想だった。
そして《マ・メール・ロワ》。この演奏が抜群に素晴らしかった。
十型という弦の少なさが、曲によく合っていた。音が澄んで抜けがよく、明快な輪郭で鮮明に響く。
いつものこのホールなら十型では響きが弱くなるはずだが、今日は音を吸ってしまう人間が半分しかいないために充分に響く。コロナ禍が生んだ妙なる音。
なんといっても終曲の《妖精の園》が圧倒的だった。眠り姫の静かな目覚め。生への回帰。五感にゆっくりとよみがえる、光と色と音と香りと、大地と生命の感触。
《子供と魔法》後半にも通じる、自然と生命への讃歌。共生の感覚。
ラヴェルのオーケストレーションはまに魔術的。最後は《ボレロ》の一部分であるかのように、オルガン的な澄んだ響きになった。そのハーモニーの美しさ。
失礼を承知で書くが、日本フィルってこんなにいいオーケストラだったのだと思い知らされた(笑)。
何年前だったか、ヤマカズさんにインタビューしたとき、「サントリーホールっていうのは、護られてる気がするホールなんです。この舞台の上なら必ずうまくいく、大丈夫だという気になれるんです」という意味のことを語っていた。
今日はそれを客席でも実感した。
祝福された場所と人が響かせた、祝福された音楽だったとしか、この《マ・メール・ロワ》は形容のしようがない。
寿福増長、遐齢延年の音楽。
いつか、「もっとよい世の中」が来たら、山田和樹と日本フィルのコンビによる、《子供と魔法》全曲が聴いてみたいもの。
九月六日(月)踊る音

芸術劇場で、大野和士指揮東京都交響楽団によるサラダ音楽祭のメインコンサート。サラダとはSaLaD、Sing and Listen and Dance~歌う!聴く!踊る!の意。
ラヴェルのピアノ協奏曲第二楽章(独奏:江口玲)とペルトのフラトレス(独奏:矢部達哉)では、新潟のりゅーとぴあを拠点とする、金森穣率いるノイズム・カンパニー・ニイガタのダンスが加わり、音楽に明確な肉体性が付与される。男女の愛と別れを描いたらしい前者、金森の肉体と衣装が金剛力士像を想わせて東洋的な雰囲気が漂う後者。
対して後半はミヨーのバレエ音楽《屋根の上の牡牛》を、あえてオケだけで。前半とは逆に、あるべき具体的な肉体を取り除くことで、オーケストラが肉体を暗示する面白さ。都響のメカニズムの高さが威力を発揮。
九月八日(火)漂う音

サントリーホールで尾高忠明指揮読売日本交響楽団の演奏会。
・グレース・ウィリアムズ:海のスケッチ
・モーツァルト:ピアノ協奏曲第二十三番イ長調(独奏:小曽根真)
・ペルト:フェスティーナ・レンテ
・オネゲル:交響曲第二番
小曽根との闊達なピアノ協奏曲を中央に、他の三曲はほぼ弦楽のみ(ペルトにハープ、オネゲルにトランペット一本がいるだけ)。
イギリスの女性作曲家グレース・ウィリアムズ(一九〇六~七七)は、つねに海の近くに住んだ人だそうだが、その海のイメージは、しかし底知れぬ不安にみちている。
それはこの曲が一九四四年、第二次世界大戦末期につくられたものだからなのか。終曲はとてもきれいだったが、ものいわぬ戦死者の霊が無数に光りながら海面を漂って消えていく、精霊流しのような場面を想像したりした。
後半のペルトとオネゲルも、弦の響きは夢幻的に美しく、そして憂いと嘆きに満ちている。その短くない時間をへて、オネゲルの最後に短く、しかし高らかに鳴りわたったトランペットの響きは、めったやたらに印象的だった。
それは凱歌なのか、それとも、最後の審判のラッパなのか。
六日と合わせて、オーケストラが音で表す肉と霊。躍動と沈潜。まことに対照的な二日間で愉快だった。
その後、サントリーホールから二十一時半頃に帰宅しようとして、去年まではラッシュ並みに混んでいた渋谷行きの銀座線があまりに空いているのに、今さらながら驚く。
これは、旧に復することがあるのだろうか。個人的には、今のままのほうが楽だが。
海外からは鎖国、客席は半済という状況下で行なわれた、在京オケの演奏会を五日から三つ聴いた。
奏者の間隔は広めで、十二型か十型の室内オケ・サイズなのは相変わらず(後方のプルトや三番以下の管打の人たちの出番は、どうなっているのだろう…)だが、このスタイルで活動再開した七月頃に比べると、響きの一体感や連携性、鳴りのよさがぐんと増してきていて、さすがプロの集団という印象を受けた。
曲目も、最初は練習も手さぐりという状況下のため、とりあえずは慣れた名曲でという印象だったが、今はこんなときだからこそ聴けるというものも増えてきて、制作陣と指揮者の腕の見せどころのようになってきている(一方で、あとどのくらい続くのかわからないだけに、根をつめすぎず、適度に心を休めてほしいと切に思う)。
九月十一日(金)
すみだトリフォニーで矢崎彦太郎指揮新日本フィル。
・ビゼー:カルメン組曲第一番
・サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲第三番ロ短調(独奏:三浦文彰)
・プーランク:シンフォニエッタ
九月十二日(土)
紀尾井ホールで紀尾井ホール室内管弦楽団演奏会(指揮者なし、コンサートマスターは玉井菜採)
・グリーグ:《ホルベアの時代から》
マーラー(シュタットルマイア編曲):交響曲第十番〜第一楽章アダージョ(弦楽オーケストラ版)
ゴリホフ:ラスト・ラウンド~第一楽章
ブラームス:弦楽五重奏曲第二番ト長調
夜は、片山杜秀さんとの朝日カルチャーセンターのオンライン講座「昭和音楽史」。たくさんの方にご覧いただき、無事に終えることができた。
二回目ということで、受講者の反応が見えないのにも慣れて、制限時間いっぱいの二時間半(笑)、リラックスして進めることができた。回線が混雑していたのか、不調でユーチューブの映像が乱れることがあったのは残念だったが。
後半の「冷戦スパイ小説系の話題」が特にご好評をいただいたので、我々二人が消されないうちに、第三回でも時間をさかのぼる形で続けたい。
九月十三日(日)

東京芸術劇場で鈴木優人指揮読売日本交響楽団演奏会。
・ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調(独奏:郷古廉 カデンツァ:第一楽章/ブゾーニ、第二~三楽章/郷古オリジナル、第三楽章/クライスラー版を基にしたもの)
・ベートーヴェン:交響曲第六番ヘ長調《田園》
九月十四日(月)思わぬ訃報
東京交響楽団は十二日後の二十六日の演奏会から、ソーシャルディスタンス仕様の市松模様の再配置ではなく、「ご購入いただいたチケットの座席で鑑賞していただ」くようにするとのこと。つまり通常に復帰。とはいえロビーでの密集、とりわけ売店前で飲食しながらの会話などは、まだ難しいのではないか。
オーケストラなど、出演者が楽屋での密を避けるために人数が制限されることなど、舞台側の問題はまだ残るが、少しずつ進んでいきそう。
同業の音楽ライター、オヤマダアツシさん(山尾敦史さん)が、九月三日に亡くなられていたことを知る。
近年は大切なフェイスブック友達として、楽しいやりとりを何度もさせていただいた。手術直前の書き込みを最後に、まったく書き込みをされておらず、心配していたのだが、当たらなくていい不安の予感が当たってしまった。
最後にお会いしたのは、七月二十五日の東京文化会館での小曽根真さんの演奏会の帰り道。おだやかで優しい笑顔がいまも目に浮かぶ。
幸い、フェイスブックでのお言葉は消えずに残っている。
オヤマダさん、今度はあちらのフェイスブックで友達になってください。その日まで、しばしさようなら。
九月十六日(水)
午後に「レコード芸術」十一月号のピアノ特集のために那須田努さん、満津岡信育さんと鼎談。
夜はサントリーホールで大野和士指揮東京都交響楽団の演奏会。「矢部達哉・都響コンサートマスター三十周年記念」
・ベートーヴェン:ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための三重協奏曲ハ長調(ヴァイオリン:矢部達哉 チェロ:宮田 大 ピアノ:小山実稚恵)
ベートーヴェン:交響曲第三番変ホ長調《英雄》
九月十八日(金)我と心の闇深く
原稿仕事の遅れが続き、日記を書いている場合ではないのだが、いろいろあって書かずにいられないので、営業時間外の投稿ということでご容赦(フリーランスに営業時間外などないが)。ただし必要最小限のことだけ。


国立能楽堂の定例公演。
・狂言『菊の花(きくのはな)』佐藤友彦(和泉流)
・能『天鼓(てんこ)』豊嶋彌左衞門(金剛流)
豊嶋彌左衞門の『天鼓』がもう絶品。名作といわれながら自分はなぜか理解できなかったこの能、三回目にして初めて真価を知った。
後漢の時代、前場は皇帝の命で理不尽に子を殺された老父が嘆き、後場は皇帝の命で豪華な弔いを受けることになった子が、亡霊になって喜ぶ。
殺されたのに、弔われたぐらいで何で喜んでいるのだろうと現代人は思うわけだが、しかるべく弔ってやれば怨霊は必ず鎮まるという、中世的な怨霊観で納得すべき話なのだろう。
前半の子を失った父の悲嘆、後半の少年の歓喜、彌左衞門さんは明快に演じわけてくれた。声の響きのなんともいえぬ魅力、そして後場の舞の見事さ。
素人には単調なくり返しに思えることも少なくない舞が、変化を重ねて飽きさせず、調子を高めていくものだということが、はっきりとわかった。囃子とわずかにずらすことで、どんと響く足拍子。
装束の洗練された美しさもさすが京都の金剛流。柳の緑、夕景と紅葉の紅、そして足元は川面の藍と、月光を受けて金色にきらめく波。簡素な能舞台の上で、装束の色彩の動きが舞台装置にも背景にもなる、その豊潤なイマジネーション。
彌左衞門さんの能は、いつも最後にありえないような変化(へんげ)を感じさせてくれる。
初めて見た『楊貴妃』では、深い愁いをたたえた絶世の美女に変じた。二回目の『井筒』では、男か女かわからない、両者が重なりあう異様な幻像に。そして今日は、水面を叩いてはしゃぐ少年の姿になった。
この、視界がぐんにゃりと歪んで、別のものが見えてくる瞬間こそ、能ならではの醍醐味。
それにしても作者不詳の『天鼓』、詞章が美しくも劇的。前場の、子を殺された老父の嘆き。
「恨むまじき人を恨み、悲しむまじき身を歎きて、我と心の闇深く、輪廻の波にただよふ事生々世々のいつまでの、思のきづな長き世の、苦の海に沈むとかや」
――恨むまじき人を恨み、悲しむまじき身を歎きて、我と心の闇深し。
自分は、できれば闇を呪うよりも、闇に灯をともすことを選びたい。
今日のような舞台は、まさしく心の闇に灯をともしてくれる。そう、『羽衣』の天人がいう、あの言葉。
「世の憂き人に伝ふべし」。
九月十九日(土)
すみだトリフォニーで沼尻竜典指揮新日本フィルの演奏会。
ストラヴィンスキー:バレエ音楽《カルタ遊び》
リスト:ピアノ協奏曲第一番変ホ長調(独奏:實川風)
サン=サーンス:交響曲第三番ハ短調《オルガン付き》(オルガン:石丸由佳)
前日に編集者から来たメールに名前が載っていたピアニストの顔が、フェイスブックの「知り合いかも」に突然何人もあがっていたりするのは、さすがに気味が悪いものがある。ただの偶然ならいいが…。
ネット時代の人間は基本的に丸裸で、ビッグブラザーにお目こぼししてもらっているだけ、終わりなき執行猶予の日々を生きているだけ、ということなのか。まあ、そんなに悪いことはしていないと自分では思っているが。せいぜい〆切を守れないくらい(ダメ)。
九月二十四日(木)七か月ぶりの銀座

銀座の王子ホールで「MAROワールド」。「まろ」ことN響の第一コンサートマスター、篠崎史紀をリーダーとするアンサンブルの演奏会。
・ベートーヴェン:セレナーデ ニ長調
・ベートーヴェン:七重奏曲 変ホ長調
篠崎史紀(ヴァイオリン)、鈴木康浩(ヴィオラ)、伊東裕(チェロ)、菅沼希望(コントラバス)、近藤千花子(クラリネット)依田晃宣(ファゴット)、日高剛(ホルン)という、俊英も交えた強力なメンバー。
王子ホールへは、というより銀座に来ることそのものが、七か月ぶり。最後は二月十六日のモーツァルト・シンガーズ・ジャパンによる《コジ・ファン・トゥッテ》のときだった。
春の時期に比べれば人出は増えているのだろうが、浅草とともに東京のインバウンドの中心地だっただけに、地上の銀座通りに出ると、他の場所よりもいっそう人と車の少なさを感じる。台風で大雨となる可能性もあったから、それもあるのだろう。


三越前のライオンもマスクをつけていた。また山野楽器の一、二階が長いことあいていたが、そこにauの5Gショールームとショップが入っていた。帰宅後にネットで調べると、明後日オープンなのだそう。銀座通りをはさんだ三越側から写真を撮ると、午後二時前なのに車がなく、一人しか通行人がいない写真が撮れてしまった。写真外側の左右には車がいたので、偶然のタイミングにすぎないのだが、それが簡単に撮れてしまうほどに活気がないのはたしかである。
演奏会は夜七時開始予定だったが、入場者数制限のために十四時開始の回を追加し、昼夜二回公演となった。自分は昼の回に行く。
篠崎、鈴木、伊東の三人による前半のセレナーデ、全員による後半の七重奏曲とも、充実の演奏。七重奏曲のカデンツァでは伊東や近藤など若手にも腕をふるわせるのがまろ流。
七重奏曲は七月に日経ホールで、千葉交響楽団のメンバーが無観客で収録したものを、関係者として客席で聴かせてもらったのに続き、今年二回目。実演を聴く機会がこれまでなかったのに、今年ならではの現象か。
ベートーヴェン初期の大ヒット作で、日経ホールでの対談で山下一史さんがお話されていたように、若書きなのにとても成熟した音楽。セレナードやディヴェルティメントのような、いかにも貴族の館に向いた十八世紀的な音楽は、もうベートーヴェンの手中に収まっていた、これ以上の先はなかった、ということなのかも。
とはいえ、この多楽章という形式に、ベートーヴェンは長い時と経験をへて、いっそうの自由さと深遠さをもって、後期の弦楽四重奏曲群において回帰していくことになる。
その原点。そして変ホ長調という調性はエロイカや《皇帝》と同じで、中期の充実も予告しているのだろう。
休憩時にチーフ・プロデューサーの星野桃子さんと七か月ぶりに話をする。主催公演の柱である海外アーティストが来られないためキャンセル続き。公演数が多いため、払い戻しの対応をするホール附属のチケットセンターがてんてこまいの状況なのだそう。
入場者数の制限はようやく緩和されたが、出入国についての見通しが当分は立たないだけに、クラシックの興行界の苦難はまだ続く。
九月二十五日(金)悲運の御曹司の能

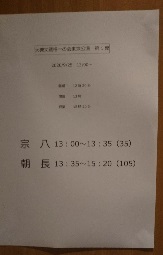
昨日に続いて銀座へ。昨日よりは銀座線も街も混んでいる。
観世能楽堂での「大槻文蔵 裕一の会 東京公演」十三時からの第一部に行く。市松模様で入場者が制限されているのがもったいない、素晴らしい演能だった。
・狂言『宗八』野村万作
・能『朝長』大槻文蔵
能『朝長』は源義朝の次男で、平治の乱で敗走中に傷を追い、十六歳で落命した源朝長を扱う修羅能。
悪源太義平が兄、頼朝と義経が弟となる。戦やぶれて京を退き、東国へ逃れようとする父や兄に従ったが、途中で膝に受けた矢傷が重くなり、美濃の青墓の宿で没した。
世阿弥の実子、十郎元雅の作といわれている。元雅は『隅田川』を型通りのハッピーエンドにせず、救いのない話にするなど、近代的な劇作のセンスを持った人だった。能楽研究者の西野春雄は「元雅ほど無常の人間世界を見据え、人間の心の動きを的確に描き、詩情を劇化し得た作者はいない」(『岩波講座 能・狂言 Ⅲ能の作者と作品』岩波書店)と述べている。『朝長』の一族敗亡の悲嘆、生々しく陰惨な死の描写などには、たしかにこの人らしい雰囲気がある。
元雅は能作者としての優れた才能を持つ反面、演技者としては目立つ存在ではなかった(父の世阿弥は追悼文で絶賛したが、しかし他には同時代で誉めている人がいないという)。
対照的に、能作の才はないがシテとして傑出していた従兄弟の三郎元重(音阿弥。元雅が生まれる前に、世阿弥の養子になっていたと考えられている)が将軍義教の寵愛を受け、観世三代目の太夫になって華々しく活躍するのを横目に、父とともに人気を失い、ついには父に先立って、三十代前半で若死にした。
現実における不遇と作品内容の暗さに関連があるのかどうかは、推測の域を出ない。しかし、特に『朝長』は、自らと父の一座の悲運の未来を、預言したかのようにさえ思える作品なのだ。
父から源氏の嫡流として扱われ、後に武家の棟梁となった異母弟の頼朝はもちろん、世に勇名を轟かせた兄義平や弟義経に比べても、朝長の知名度は低く、影が薄い。その死も壮烈な斬り死になどではない。敗走中に膝に受けた矢傷で動けなくなり、父の足手まといになるのを嫌って、父に頼んで殺してもらった(能では自ら切腹する)という人である。
英雄豪傑ではない、人間的な弱さを持った主人公が選ばれている。そして朝長の死だけでなく、三日後に裏切られて討たれる父義朝とその忠臣鎌田政清、捕らえられて処刑される兄義平、その前に捕らえられていた弟頼朝のことも語って、一族の敗亡を描く物語となっている。
さらにこの能の独創性は、前シテと後シテを別人にして、朝長の死にざまを本人の幽霊とは別に、その世話をした青墓宿の長者、つまり宿場の女将にも語らせたことだという。
世阿弥が大成した修羅能、夢幻能のパターンは、現世の人間に化身して前場に登場した幽霊が、後場では本人となって出て、その死を客観的視点と主観的視点で立体的に語る。『朝長』はさらに一歩進めて完全な別人の男女とし、両者の視線と感情が交錯するドラマとしたのだ。
前場のシテは青墓宿の長者(義朝の愛妾の一人)となり、朝長の墓の前でワキ(宝生欣哉)と出会う。ワキは朝長の乳母子だったが、今は嵯峨清涼寺の僧となり、旧主の墓参りに来たという。
そこで長者は朝長の最期の様子を僧に語ってきかせる。落武者たちのあわただしい到着。深夜に念仏を唱える朝長の声が聞こえたあと、その切腹を義朝に告げる鎌田政清の声。義朝が駆けつけると、
「御肌衣も紅に染みて、目も当てられぬ有様なり」
紅に染みて、という詞章の響きが喚起する鮮血のイメージがものすごい。こういう生々しさは、やはり元雅ならではの詞章だろうと思う。
そしてここでは、長者は太刀持ちの男(トモ)と侍女(ツレ)を伴っており、ワキも侍僧を二人連れている。この人たちがただいるのではなく、それぞれの立場から芝居の登場人物のように語り、行動するところも、様式化・抽象化された世阿弥の能よりも、後世の歌舞伎に近い感覚になっている。
このあたりは元雅の代表作『隅田川』で、本来は舞台の登場人物ではない地謡の声を、念仏を唱える住民の合唱のように使用した、独創的なセンスと共通するものを感じる。
ただし面白いことに、金春・金剛・喜多の下掛りの流派の『朝長』では、トモとツレは出てこず、シテ一人だけの形になっているという。
これは同じく元雅の『弱法師』が、現行版ではシテとワキしか出ないのに、父世阿弥による写本ではシテの妻や僧侶が出るようになっていて、より芝居的なものだったという現象と似ている。長く演能が途絶えたこの曲を江戸期に蘇演したさいに、簡素化してドラマを凝縮したものが現行版だと考えられている。
多人数の一座を有機的に活用しようというのが、元雅の作劇の基本的姿勢だったのではないだろうか。そこで『朝長』ではさらに、オリジナルの前シテと後シテは、別の役者二人が演じたのではないかと考える研究者もいるという。
その場合は、青墓宿の長者も後場に残り、僧たちの供養に立ち会う形になる。物語としての筋はたしかに通るが、そうすると前場と後場で違う役をシテが演じわけるのを楽しむ面白味はなくなるわけで、そこが弱点になる。
後場は長者の宿に移り、僧が観音懺法を読誦して弔うところに、朝長の霊(後シテ)があらわれる。年配の女性から若武者へ、大槻文蔵の気配の変化が見事。
シテは途中から床几に座って謡う。これは馬上での戦場の様子をあらわす。左膝を射られる瞬間、左袖を巻き上げ、左手に持った扇子を膝に突きたてる。衝撃が走る。修羅能ならではの、抽象の靄を一瞬に突き破ってくる具象の凄まじさ、その痛み。
続いて床几を立って床に座ると、最後は扇子で左から右に腹を切る。ここもまた、瞬間に噴出する写実性。
前場後場の変化の大きさなど、この能が『実盛』『頼政』とともに「三修羅」と呼ばれて、修羅能中の三大難曲とされることも、素人ながらに納得がいった。
梅若実が地頭なので、地謡も期待どおりの美しさだった。野村太一郎の落ちついたアイも好き。
世阿弥とはまた別の、陰惨に深くえぐる魔力を持つ元雅の能、もっと見たい。『朝長』『隅田川』『弱法師』『盛久』は見たが、これからもくり返し見たい。『朝長』の有名な小書「懺法」はもちろん、『弱法師』の古い形も見たい。さらに元雅作の可能性が高いという『重衡』『維盛』『唐船』も見たい。
見たい能、まだまだたくさん。
・狂言『宗八』野村万作、野村裕基、石田幸雄
・能『朝長』
シテ/大槻文藏
ツレ/武富康之 トモ/齋藤信輔
ワキ/宝生欣哉 ワキツレ/御厨誠吾、野口琢弘
アイ/野村太一郎
笛/松田弘之 小鼓/観世新九郎 大鼓/亀井忠雄 太鼓/三島元太郎
地謡/梅若実、梅若紀彰、山崎正道、角当直隆、川口晃平
後見/赤松貞友、観世淳夫
九月二十六日(土)両隣に電球
サントリーホールで東京交響楽団の演奏会。ブランギエが指揮してイブラギモヴァがソロの予定だったが、コロナ禍で尾高忠明と川久保賜紀に変更。
・リャードフ:交響詩《魔法にかけられた湖》
・ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第一番イ短調(独奏:川久保賜紀)
バルトーク:管弦楽のための協奏曲
演奏の感想はさまざまな方が書いておられるので、卑近な話だけ。
一週間ほど前に入場制限が緩和され、今日から客席が市松模様から通常に戻った。とはいえ、緩和直前まで販売数を半分で停めていたため、販売再開後の日数に余裕がなかったから、入りは半分を少し超えた、というくらいか。
売りかたの都合か、隣りあって五、六人座っているところと、一列ずらっと空いている部分がまだらにある感じ。
自分としては左右に人が座るのは半年ぶり、大ホールでは七か月ぶりの体験。サントリーホールだと、昭和中期までのホールと違って席幅に余裕があるから、思ったほど狭苦しくは感じない。
ただ開演直後は、人間て熱を出すものなんだよな、と思い出す。人ひとりいると百ワットの電球一個くらいの熱が出ると聞いたことがあるが、なるほどたしかに、両隣にすぐ電球があって(笑)、そして風の抜けが悪い感じがした。
自分も含め、駅から歩いてきてすぐに着席しているから、発する熱量が開演直後は高いのだろう。途中から感じなくなった。この「最初は両隣に電球」の感覚は、慣れるまで少し時間がかかるかも。
しかし基本的には、これでクラスターが起きることはまずないのではないか、という印象。恐さは感じなかった。ただし飲み物の売店とか、クロークはどうするのかとかは、寒さの到来とともに考えなければいけないだろう。
それと、これは能楽堂や繁華街でも感じることだが、高齢者の割合が減った。前にも書いたが、クラシック界では五年後くらいに起きるはずだったことが、一気に早まった感がある。
九月二十七日(日)「シテ一人主義」
二十五日の『朝長』のところで、下掛りの三流派ではシテ以外のツレとトモが削られ、登場人物が減らされているという話を書いた。そして『弱法師』でも、元雅のオリジナルの詞章を世阿弥が筆写したと考えられる古本では、現行版よりやはり人数が多いと書いた。
これについて、堂本正樹の『世阿弥』(劇書房)を読みかえしたら、こんなことが書いてあった。
「登場人物を整理し、主人公一人に絞る傾向は『葵上』『弱法師』などにも見える。前者は近江猿楽の、後者は元雅の原作だが、現行のスッキリした形にしたのは、最晩年の世阿弥であろう。その点現代の能を支える「シテ一人主義」過重への水路を開いたのも、世阿弥だった。素人の稽古がしやすいこの形式は、やがて桃山期以降の、大名素人能隆盛の基礎ともなり、ひいては能の遊芸化と通俗化の歪曲をも促す。能が演劇としての健全な発展を止める原因の一つは、世阿弥の「演者の自儘」の責任でもあった」(五百六十六頁)

『葵上』や『弱法師』などの登場人物を整理したのが世阿弥だというのは、あくまで堂本独自の推測。世阿弥が自作においてシテとワキの関係だけに凝縮されたドラマを好んだのは確かだろう。しかし、だからといってこれらの作品の改変まで世阿弥の仕業だとするのは、多数派の意見ではないようだ。
この推測の当否はともかくとしても、シテ一人に絞れば素人の稽古がしやすいというのはなるほどと思う。また、上演が途絶えていた『弱法師』を綱吉の命で江戸城内に復活するにあたっては、人数を制限する必要があったかも知れない。戦国の動乱期に、人数を少なくして演能しやすくしていた可能性もありうる。
江戸期に「武家の式楽」となって儀式化され、武士の習い事としての需要も増すにつれ、能は「シテ一人主義」に偏重し、「演劇としての健全な発展を止め」たのだろう。
そのぶん、芸術としての深化と純化を増した部分もあるから、一概に是非は決められないのだろうが。
九月二十八日(月)第九の合唱団
在京オーケストラによる年末の第九、合唱団変更の発表が続く。東京交響楽団は新国立劇場合唱団、新日本フィルは二期会合唱団に。
大人数のアマチュアは練習も含めて感染リスクが高いだけに、少数精鋭のプロの合唱団に代えられている。新国合唱団は読売日本交響楽団の第九にも例年どおり出演するので大忙し。交響楽団と第九を歌いそうなプロの合唱団というと、あとは東京オペラシンガーズや藤原歌劇団合唱部、東京混声合唱団とかだろうか。
九月二十九日(火)《リナルド》記者会見

鈴木優人がプロデュースするBCJオペラシリーズの第二弾、ヘンデルの歌劇《リナルド》記者会見を、オンラインで見る。移動時間のロスを考えると、オンラインはたしかに便利。
鈴木優人はコロナ禍という特殊状況のなかで、ピリオドだけでなくモダン・オーケストラの演奏会でも、最も活躍している若手指揮者。ピンチにおいて大きなチャンスを得て、鮮やかに結果を出しつつある。
コロナ禍のため主要キャストは日本在住の歌手に変更され、演出にも制限があるとはいえ、三年前の第一弾《ポッペアの戴冠》も、セミ・ステージ形式ながら優れた上演だったので、今回も期待している。
これまでは入場制限のため販売を止めていたが、緩和により再開するという。十月三十一日に神奈川県立音楽堂、十一月三日に東京オペラシティのコンサートホールと、二回公演。
十月三日(土)千葉笑いの本場へ
千葉交響楽団の定期演奏会を聴きに、千葉へ行く。
八月十三日に日経ホールで行なわれたオンライン講座、日経アートアカデミア「ベートーヴェンと現代」第二回の収録に参加した。
千葉交響楽団が出演してベートーヴェンを無観客で演奏するもので、自分は音楽監督の山下一史さんの対談役をおおせつかった。
その縁でご招待いただいたので、千葉の町を見たかったこともあり、喜んで聴きに行くことにした。
自分は千葉県とは縁が薄い。生まれ育ったのは目黒区の南西端で、田園都市線で県境をまたぐといえば西の神奈川県に入るときで、大きな川は玉川のイメージしかない。
すみだトリフォニーがあるおかげで、隅田川をわたる機会は近年になって増えたが、錦糸町から千葉県まではまだ距離がある。それを今回は千葉市まで進む。隅田川、旧中川、荒川、中川、新中川、江戸川。県境までの川の多さと、ひたすら続く平野。
千葉県に入り、船橋を過ぎて、津田沼を通る。自分は津田沼というと一九七〇年代後半に駅前に大型店舗が林立して大発展した町、というイメージしかないのだが、駅や線路まわりはずいぶんと古びた、くすんだ感じなのに驚く。四十年前の大発展のあとは、再開発の機会がなかったのかも。

千葉駅に到着。ここもホーム周辺は昔懐かしい感じ。ただ駅ビルの内部は近年改装したらしく、今風に清潔で明るい。
初めての駅なので、一時間近く早めについて周囲をうろついてみる。面白いのは、駅前広場のようなものがないことだった。並行して走る京成千葉駅(かつては国鉄千葉駅前という、やけくそみたいな駅名だった)のほうにも、ロータリー風のものはない。

どうやら東口の幅広の階段を降りたところにバスのターミナルがあるので、これが駅前広場に相当するらしいのだが、階段のまん前に千葉都市モノレールの駅舎が大きく立ちはだかっているため、視界が開けずに暗い。便利は便利だが、もう少し工夫できなかったのかと思う。
演奏会の会場は千葉県文化会館といって、そのモノレールの一号線終点、南端の県庁前駅から行く。バスもあるが、せっかくだからモノレールに乗ってみる。


このモノレール、地上からはかなりの高さ。高所恐怖症の人は乗る気になれないかも。

降りて東に向かうと、県立図書館。茶と白の塗りわけが昭和後期風モダンで、懐かしい感じ。

その脇のコンクリの階段がこれまた懐かしい感じで、これを登っていくらしい。お茶の水駅から秋葉原駅への斜面を下って以来、ずっと平地ばかりを通ってきたが、ひさびさに山の手という感じになる。南に行けば県立千葉高校という表示もある。こういう旧制中学以来の名門校は、だいたい城跡にあるものだから、この山もそれなのだろう(あとで確認したら、亥鼻城という千葉氏の本城があったらしい)。登っていくと天守閣らしきものが見えた。これは近代のもので、千葉市立郷土博物館。

文化会館の入り口までは、階段をけっこう登る。バリアフリーなどは考えないあたり、いかにも昭和の建物。


その点は古いが、しかし内部はここも昭和モダニズムの懐かしさがあり、自分の好み。ホール内は木の質感で温かみがある。大高正人の設計で一九六七年開場、千八百席と人数も多すぎず、バランスがいい。昔のホールらしく残響は少なめだが、山の斜面を利用して建てたことにより、客席の傾斜が大きくて、舞台が近くて見やすい。


どうせ無味乾燥な多目的ホールだろうと思いこんでいて、来る前に調べていなかったのだが、いい感じのホール。
戦後に地方公共団体が建てはじめたホールの先駆である、神奈川県立音楽堂や世田谷区民会館や東京文化会館など前川國男の業績を踏まえた、文化への思いが伝わってくる。戦後民主主義の文化国家建設への思いが、まだ生きている感じ。
日本のホールは、一九六〇年代開場と七〇年代のそれとでは、同じ昭和でも、ホールの雰囲気にかなり大きな差があると思う。七〇年代以降は効率優先で、はっきりいって精神的に貧しい。
たぶん石油ショックあたりで思想が変わって、土建屋行政の気配が濃厚になって、四角いビル風の、多目的ならぬ無目的ホールの精神的な貧困が生まれる。
国全体がそれなりに豊かになって、しかしお金の使いかたがよくわからず、一億総中流意識が広まるなかでの、広まったからこその、平等の不公平が生んだ精神的貧困なのかもという気もするが、これは機会をあらためて、また考えてみたいテーマ。
話を戻して、今日の千葉県文化会館。客席は市松模様に制限されているが、なんであれ完売は気持ちいい。お客さんが学校の先生とか、いかにも地方都市の教養層という雰囲気なのも快い。東京ではもう味わうことがむずかしい、昭和の教養主義の香気がまだ濃厚にある。
曲目はベートーヴェン・プログラム。
・ピアノ協奏曲第五番変ホ長調《皇帝》
・交響曲第三番変ホ長調《英雄》

中期の変ホ長調の人気作二曲。日経アートアカデミアで演奏した初期の傑作、七重奏曲と同じ調性。この曲目で指揮が音楽監督の山下一史、ピアノが河村尚子とくれば、売れないわけがない。制限なしで売りたかったろう。
編成は十型、管楽器の音量バランスがとりにくかったようだが、とにかく気持のこもった熱演で、聴いているほうも嬉しくなった。
最後に、山下さんがスピーチ。オンライン講座をぜひ見てくださいと宣伝してくれて、私の名前まで忘れずに出してくれた。ありがたいかぎり。
終演後は、モノレールには乗らずにその西の海側にあるJRの本千葉駅から千葉駅へ。十五分に一本程度なので、千葉駅との往復に意外と時間を食う。ぜひまた来てみたいが、次も時間の余裕を充分にみておかなければ。
ところで、自分は千葉と聞くと反射的に「千葉笑い」という言葉が頭に浮かんでくる。たぶん司馬遼太郎の『街道をゆく』かなにかで読んだのだろう。
江戸時代、大晦日の夜に千葉寺(せんようじ)に集まった近隣の住民が、顔を隠して不平不満をいいあい、笑って新年を迎える習慣のことだとか。近年は民間行事として復活しているらしい。
その千葉寺は千葉県文化会館のさらに南にある。ここもいつか行ってみたい。
十月四日(日)夏の夜の夢

新国立劇場で『夏の夜の夢』。感想は日経新聞に書く。
十月六日(火)峡谷から星たちへ

サントリーホールで、読売日本交響楽団による「サントリー音楽賞受賞記念コンサート」。
メシアンの《峡谷から星たちへ》。カンブルランが指揮するはずだったが、コロナ禍の入国制限のために来日できず、鈴木優人が代役。ピアノは児玉桃。
ソーシャル・ディスタンスを保った形でこの大曲の響きをコントロールするのは容易ではないだろうと思うが、鈴木の指揮は見事なものだった。
十月七日(水)中世の女たち
国立能楽堂の定例公演。
・狂言『金藤左衛門(きんとうざえもん)』山本泰太郎(大蔵流)
・能『江口(えぐち)』梅若万三郎(観世流)


狂言と能、どちらも女性が活躍する内容になっている。
能とテーマ的に関連のある狂言を選ぶかどうかは時と場合によって異なり、無関係なことも多い。しかし、山本東次郎家では関連性を意識して組み合わせる場合が多く、自分としてはそのほうが喜劇と悲劇の対照でテーマが立体化され、狂言の印象も強まるのでありがたい。
今回も中世の女性について、『江口』と見事な関連をもっていた。
狂言『金藤左衛門』は、山賊の金藤左衛門が山道で待ち伏せしていると、里帰りをしようとみやげ物を抱えた女が一人で通りかかる。金藤は薙刀で脅して荷物を奪う。追い払われた女が腹にすえかねて戻ってきてみると、金藤は薙刀を脇において、盗品の品定めに夢中。こっそり近づいた女は薙刀を盗むと、今度は逆に脅しにかかる。金藤は盗品を取り戻されるばかりか、薙刀に脇差、着ていた小袖まで奪われてしまう。
油断した男が女の機転にやりこめられるというのは、狂言の定型の一つだ。近世から現代にかけての感覚だと、弱い女が強い男に思わぬ逆襲をするところに面白みがあるということになる。
しかし、網野善彦の『中世の非人と遊女』を読むと、近代日本の「男性社会」では常識的なこうした発想は室町以降、現代に近づくにつれて固定化されていったものらしいことがわかる。

網野は、十六世紀の宣教師フロイスの報告に、日本女性の識字率の高さや財産権の所有、旅行や行動の自由が特筆されていることを紹介して、
「ここでのべてきたような女性のあり方は、早くも古代から家父長制が確立し、その下にあって女性の社会的地位は低く抑圧され、自由を奪われていたとする従来の「常識」とはかなりかけはなれており、実際、最近の家族史の研究は、すでにこの「常識」を大きく崩しつつある」
『金藤左衛門』に登場する女も働き者で、母親に贈るための小袖などを手に入れ、たった一人で山道を歩くという、かなり自由そうな存在である(ただし字は読めない)。
しかもフロイスが見た戦国時代には、こうした自由が主に商工業に携わる都市部の女性に限定されてきていたが、鎌倉時代まではもっと広範囲の、さまざまな職種や階層で女性の権利が認められていたという。
能『江口』の遊女も、江戸時代の遊廓に閉じ込められた奴隷的な娼婦とは異なる自由な存在(もちろん、その自由は不安定と表裏一体だろうが)で、朝廷との関係も持ち、けっして被差別階級ではなかった。統率する長も女性だった。
現在の大阪府東淀川区にあった江口の里は、淀川と神崎川の分岐点にある川湊で、京都から西国への船路の中継点となり、西の尼崎にあった神崎の遊女宿とともに、鎌倉時代までは二大歓楽街として栄えた。
江口と神崎の遊女は、朝廷の五節の舞には、貴族の息女から選ばれる舞姫に仕える役割を持っていた。上皇や天皇、高位の公家の寵愛を受け、その子を生む遊女もいた。朝廷の女房になった遊女もあるという。
さらには、勅撰和歌集に歌が収められるほどの文才を発揮した遊女もいた。世阿弥作と考えられる『江口』は、まさしくその代表的な一例、新古今和歌集に収められた西行法師と遊女妙(たえ)の問答歌を題材にしたものである。
西行が難波の天王寺に参詣する途中、雨に降られて江口の長(遊女の統率者)に宿を借りようとしたが断られた。そこで歌を詠んだ。
「世の中を厭ふまでこそ難(かた)からめ仮の宿りを惜しむ君かな」
晴れを待つまでの一時の宿借りを断られたので、「世を捨てて出家することは難しいだろう、浮世に執着するあなたには」というような嫌味を歌にしたのだ。
すると江口の君が歌を返す。
「世を厭ふ人とし聞けば仮の宿に心留(と)むなと思ふばかりぞ」
遁世したというのなら、浮世に執着するなと思っただけですよと返して、やりこめたのだ。
先の狂言『金藤左衛門』も、山賊にしては妙に理屈好きで言い訳してばかりの男を女がやりこめる話だったので、ここが似ている。
世阿弥はこの話を、西行を著者に仮託した『撰集抄』(せんじゅうしょう)という仏教説話集で知ったらしい。そして世阿弥の時代にはすっかり廃れていた江口の旧跡を訪ねた旅僧が、江口の君の幽霊に出会うという夢幻能に仕立てた。
後場では、遊女たちが舟に乗り、旅船に漕ぎよせて男たちを誘ったという「川逍遥」の場面を、幽霊が再現する(この部分の舟歌は父の観阿弥作らしい)。
やがて詞章は、輪廻をくりかえす罪障の苦しみからの解脱を説きはじめる。
遊女は、実は普賢菩薩の化身だった。正身をあらわし、舟を白象に変えて、西方の空に消える。
「光とともに白妙の、白雲にうち乗りて、西の空に行き給ふ」
ここに遊女の名の妙、そして西行の字を読みこんだのが世阿弥らしい趣向。
この普賢菩薩の化身というのは、前述の『撰集抄』にある別の遊女話、平安時代の性空上人の話を借りたもの。
性空が、普賢菩薩の生身の姿を見たければ神崎(異説あり)の遊女の長を拝めという霊夢を見て、その宿を訪ねたという話だ。
性空が遊女の長の舞と遊女たちの謡を目にしながら、目をふさいで心をすますと、白象に乗った普賢菩薩の姿と謡が心に浮かぶ。
目を開けると遊女、閉じると菩薩だったという、煩悩即菩提の具現化のような話を用いて、歌舞の華やかさとその空虚無常を表裏一体にした能に仕上げたのが世阿弥の才覚で、傑作の傑作たる所以。
しかし殷賑を極めた江口の里も、南北朝の騒乱後は遊女どころか、人家もないような野に変じて、「仮の宿」としての現世の無常が強調される。
遊女の社会的地位も、室町時代には低下し、賤視の対象となる。ふたたび網野善彦の『中世の非人と遊女』から引く。
「室町・戦国期以降、天皇をはじめ、それまでの多少なりとも呪術と結びついた神仏の権威は、決定的に低落していく。そのことが、遊女や巫女など、「聖なるもの」の権威に依存するところ大であった女性の芸能民、宗教民の社会的地位を低落させ、かつての「聖別」は賤視の方向への差別に転化したことについては、すでに明らかにされている」
こうしてみると『江口』は、「遊女」が「娼婦」の意味だけではなく、言葉どおりの「遊び女」たりえた、失われたよき時代への挽歌のようでもあり。室町時代には女性の猿楽一座もあったのに、いつしか男性しか許されなくなっていく。
一方で、穢れの苦しみを強調しておいてから救ってやるという、仏教のマッチポンプ的な作用も思う。
ただ、美しく、深い能とはいえ、正直にいって長すぎると感じたのも事実。同じ世阿弥の『井筒』にも感じる長さ。現代人との時間感覚の差か。
梅若万三郎のシテは、以前にも『西行桜』で見たが、とりわけ荘重に、時間をかけて演じる人なので、その長さがきわだつ。予定表には九十分とあったが、百五分くらいかかったように思う。
最後の、遊女が普賢菩薩に変じるところ。ここは作り物や装束に頼らず、詞章だけで語られるために、その実感がとても難しい。シテのオーラと演技力がすべてということになるのだろう。いつか、息をのむような変身を実感できる舞台に接してみたい。
山本東次郎のアイ、梅若実が地頭をつとめる謡、囃子方は人間国宝がそろって見事なものだった。

この写真は銕仙会のサイトから、2015年の演能。
三人の遊女が舟に乗り、川逍遥をしている場面。
中央がシテの江口の君、左側の遊女は棹をさして舟を漕いでいる。
なお今回の国立能楽堂公演では、このような舟の作り物はなく、人の動きだけで暗示した。
十月八日(木)熊倉優
サントリーホールで新日本フィルの演奏会。指揮は熊倉優。
・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲(独奏:竹澤恭子)
・チャイコフスキー:交響曲第四番

熊倉優は一九九二年生まれ。桐朋学園大学出身の新鋭。コロナ禍で海外の指揮者が来られないなか、若手にチャンスが回るのは素晴らしいこと。
チャイコフスキーの終楽章は暴れ馬のような爆速の演奏になったが、元気がよくて楽しかった。
十月九日(金)定型を離れて
宝生能楽堂にて、銕仙会の定期公演。
・能『蟻通(ありどおし)』大槻文藏
・狂言『雁大名(がんだいみょう)』野村萬
・能『鳥追舟(とりおいぶね)』鵜澤久

 傘と灯明を持つ宮守。銕仙会のサイトから。
傘と灯明を持つ宮守。銕仙会のサイトから。『蟻通』は紀貫之(ワキ:殿田謙吉)が登場する能。大雨の降る闇夜に和泉国を通過中、貫之の乗馬が伏したまま動かなくなってしまう。
困りはてていると、灯明と傘をもった宮守の老人(シテ)が現れる。宮守は、馬が動けないのは蟻通明神の神域を下馬せずに通った咎めだと告げる。
灯明の明かりで鳥居や社殿の存在に気づいた貫之が和歌を手向けると、馬は立ち上がることができた。宮守は神楽を舞い、和歌の徳を称える。
冷たい雨の降る夜だったので、宮守の姿にリアリティを感じる。しかし宮守が後場で神の正体を現したりせずに、そのままの姿で舞う簡素な構成が珍しい。
狂言の『雁大名』は、都での長い訴訟に勝った大名が、祝いの酒宴の肴に初物の雁を買おうとするが金がない。太郎冠者と一芝居をうち、雁屋からまんまと雁をだまし取る。こうした話は失敗に終わることが多いのに、悪が勝つという意外な展開。
『鳥追舟』は薩摩国が舞台。訴訟のために十年も都に出ていた大名(ワキ:森常好)が、ようやく勝ちを収めて帰国する。先の狂言とそのままつながっているようなのは、前後の能との関連をあまり意識しない野村家にしては意外。
その国元では、留守を預かっていた家臣(ワキ:大日方寛)が慢心して専横のふるまいとなり、大名の妻(シテ:鵜澤久)と子(子方:谷本康介)に、田を荒らす鳥を追う舟に乗る卑賤な仕事をさせる。そこに帰国した大名が怒って家臣を斬ろうとすると、長く留守にしたほうも悪いと妻が説得し、許された家臣は改心して忠誠を誓う。
舟の作り物が出たり、二人のワキ(片方がワキツレになるのではなく、同格)が活躍するなど、芝居風の強い能。きれいごとのハッピーエンドなのが、大衆の嗜好に合わせて残虐性の強い説教節などとは対照的だ。最後に舞台に残って留めの足拍子を踏むのがシテでも大名でもなく、改心した家臣というのが印象的。
三番とも、何らかの形で定型とは異なるのが面白かった。

シテと子方が鳥追舟に乗り、家臣がその脇に立つ。銕仙会のサイトから。
十月十三日(火)隔たりを越え

池袋の芸術劇場で、落合陽一×日本フィル プロジェクトVOL.4《__する音楽会》。回を重ねるたびに舞台上方のスクリーンが大きくなり、視覚的情報の質と量が増加している。
もともと、耳が不自由など障碍をもつ人にも音楽を楽しんでもらおうという目的で始まったシリーズだが、今年は健常者の聴衆も困難のなかに。
十月十六日(金)人生足別離
日経BP社発行の「DAZZLE」第七十号の見本誌が送られてきた。


この雑誌は発行元によると「医師、企業経営者・管理職、各界のプロフェッショナルなど、エグゼクティブ女性に特別にお届けしているライフスタイル誌。二〇〇九年の創刊以来、ファッションやビューティー、ジュエリー&ウォッチ、カルチャー、旅など、確かな目でセレクトした情報を隔月でお届けしています。 (購読・購入申込はお受けしておりません)」という「上質でラグジュアリーなライフスタイル誌」。
とても高級な服飾、宝飾、香水、旅行などの記事と広告が並び、代金は無料。つまり「ぶらあぼ」などと同じく広告収入だけで成り立つフリー雑誌。それなのに大判の百三十頁フルカラーという豪華版。十年以上同じ体裁で続いたので、安定した評判を得ていたのだろう。
こういうラグジュアリーな世界には何の縁もない自分(この雑誌が送られているという「エグゼクティブ女性」には、ついに一度もあったことがなかった)なのに、なぜか二〇〇九年四月号の創刊から十一年にわたり、コラムの「MUSIC」欄を担当してきた。気がつくと、他の「MOVIES」とか「THEATER」などのコラムの執筆者は全員女性でそろっているのに、自分は(ここでも〆切に遅れ放題だったのに……)替えられることもなかった。ありがたいかぎり。
しかし、コロナ禍のために状況は一変した。緊急事態下では広告も記事もつくりようがないわけで、六月号を出したあとで八月号は休み。そして十一月号(十月と十二月の合併号)を最後に、休刊することになった。先が見通せないというよりも、会社本来のBtoBの方針に戻して、という理由らしい。
これがその最後の号。来日公演はまだ恐くて紹介できないので、BCJをメインに。
一つの業界に関わる年月が長くなるにつれ、発端から終焉まで、ゆりかごから墓場までつきあえた仕事が増えてくる。
人生足別離。明日は明日の風が吹く。
(記事写真は全部載せると怒られそうなので、部分だけ)
午後はすみだトリフォニーで、外山雄三指揮新日本フィルの演奏会。一九三一年生まれ、日本人指揮者の現役最長老にして足腰はしっかり。狂言で現役バリバリの野村萬・万作兄弟(一九三〇及び三一年生まれ)を連想する。
演奏の感想は諸先達に譲るとして、客席で気がついてしんみりしてしまったのが、プログラム掲載の曲目解説の執筆者のお名前。
もはやこの世では言葉を交わすことがない方のご遺稿。思わぬ場所でこういうものに出会うことは、それすなわち一場の夢幻能。ただ合掌。
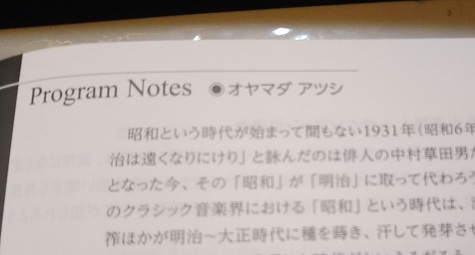
十月十八日(日)角田鋼亮
サントリーホールで日本フィルの演奏会。指揮は角田鋼亮、ヴァイオリン独奏は辻彩奈。
・バッハ:シャコンヌ
・バッハ:ヴァイオリン協奏曲第一番
・バッハ:ヴァイオリン協奏曲第二番
・ブラームス:交響曲第四番

角田は若くしてセントラル愛知交響楽団の常任指揮者をつとめる、期待の星の一人。高い評判を以前から聞いていたのだが、タイミングが合わず、ようやく今日聴くことができた。
豊かな音楽性。今年は日本人指揮者をまとめて聴くよい機会となった。七十~五〇歳代の世代が大なり小なり斎藤メソッド的というか、リズムに弾力のない音づくりをするのに対し、若い世代はより柔軟で流麗なセンスに優れているように思える。
角田もその代表格のようで、今後が楽しみ。ただ、ブラームスの終楽章のパッサカリアでは、コントラバスとチェロのリズムにもっと注意を向けてもいいのではと思った。最初にヴァイオリン・ソロでシャコンヌを演奏して、オスティナート・バスを演奏会のポイントにしただけに、聴衆にもそれをわかりやすく示してほしかったと思う。
ムーティが昨年春のマスタークラスのとき、若い指揮者はヴァイオリンに気をとられてコントラバスを忘れやすい、と注意していたのを思い出した。
十月二十二日(木)蝋燭の能
国立能楽堂の企画公演。シーズン一回の「蝋燭の灯りによる」公演。
・謡講 井上裕久(シテ方観世流)
・能『鉄輪(かなわ)』武田孝史(宝生流)

能の『鉄輪』は、女の丑の刻まいりを扱ったもので、鬼女の面で頭に鉄輪を乗せ、その上に蝋燭を灯したスタイルが有名。女の嫉妬を具現化した、いかにも能らしい能として上演される機会が多いのだが、なぜかタイミングが合わず、いままで見ることができなかった。
陰陽師の安倍晴明(ワキ)が出てくるというのも、人気の理由の一つだろう。ただ、捨てた前妻(シテ)の呪いに苦しむ下京の町人からの依頼で御祓をするというあたり、朝廷に仕える身分にしてはずいぶん安っぽい感じがする。
舞台が暗すぎて、ドラマそのものが薄闇に沈んだようなもどかしさが残る。鬼女の鉄輪の上にある蝋燭、これをほんとうに灯すことができれば、闇との対比で効果が出たと思うのだが、そうはできないので暗いだけ。前回の『調伏曽我』でも護摩壇の炎がほんとうに燃え上がっていたら違うだろうと感じたが、それと同じ。闇の中に煌めいて揺らぐ炎のイメージこそ、正であれ邪であれ、この二つの能の重要な要素なのではないか。
もちろん、そこをリアルにやったのでは、能ではなくなってしまうのかも知れず、むずかしい。
明るい照明の舞台で、闇と炎を脳裏にイメージするのが、やはり適切な見かたなのだろうか。通常の形で『鉄輪』をあらためて見てみたい。
十月二十三日(金)横のものを縦に
最近は、横書きのほうが文章を速く、楽に書ける気がして、残り時間が苦しいときなど、そうすることが増えていた。
ところが今朝、この二週間どうにも筆が進まず困りはてていた大仕事を、ひょっとしたらと縦書きの書式に直したら、これが不思議。どんどん進みはじめた。
じつは夢見のおかげ。どうにも進まずにあきらめ、ふて寝した明け方に、原稿を書いている夢をみた(笑)。
いつもなら、目覚めたあとで夢のなかのようには現実の原稿が進んでいないことを思い、あれが現実だったらと情けなく思うだけなのだが、今回はその前にまず、夢のなかでは縦書きのフォーマットで書いていて、構成を考えたりしていたことが気になった。そこで同じようにしたら、書けるようになった。
文脈、段落のつながり、そして、見通せなかった各ブロックや全体像が頭の中で見えてくる。言葉の最良の意味で「俯瞰的に」、地平線まで見える感じ。
基本的には、掲載媒体の縦横に合わせて書くことにしているのだが、流れ重視で談話的な、話し言葉に近い感覚の文章にしたいときは、縦書きで掲載されるものでも、最近は横書きにしていた。書き出してしまえば滑らかに進んで、あまり推敲の必要がない。しかしそのぶん、だらだらした文章になる。
今回は長いので、流れのあるほうがよいかと思った。指先を痛めるのもさけたいので、変換精度の高いグーグルの音声入力を使おうとも考えた。それなら横書きだと思ったのだが、大間違いだった。
二十枚を超すような日本語の文章は、読むときだけでなく、自分の場合は書くときにも縦書きでないとダメなようだ。
ところで書式は、これは縦横どちらの場合も、二十字×四十行×二段、四百字詰原稿用紙四枚分がA4用紙一枚に入るようにしている。
この仕事を始めた四半世紀前は、四百字詰原稿用紙×枚数で依頼されるのが主流だったからである。最近は、紙のメディアでもこの習慣が残っているのは、原稿料の計算のときくらいで、依頼そのものは字数指定でくることが多い。
だから一行二十字にこだわる理由はなくなってきているのだが、長年の習慣のせいなのか、日本語を書くにはこれが書きやすい。四百字詰原稿用紙の書式というのは、人類の叡智の結晶じゃないかと思っている(笑)。
十月二十四日(土)愛の証
青山の銕仙会能楽研修所にて、観世流シテ方柴田稔主催の「青葉乃会」。
銕仙会能楽研修所を初めて訪問。表参道の交差点から南東に歩く。コンクリ打ちっぱなしの建物は一九八三年竣工。
今風のつくりなのに、靴を脱いで下駄箱に預けるという、昔ながらの日本式になっているのが面白い。見所も畳敷。これらは能楽マンガ『花よりも花の如く』の「連雀能舞台」のモデルになっているので、初めて見た気がしない。
能舞台は階段を上がった二階にある。見所は約二百席で小さめ。いままで来なかった理由は、自由席の公演が多くて、席取りが億劫だったため。今回は指定席なので買ってみた。
 写真は銕仙会のサイトから
写真は銕仙会のサイトから曲は『定家』ただ一つ。しかし二時間かかる。金春禅竹の傑作。
この曲については、二〇一八年九月十五日の欄に書いたので、それを参照のこと。そのときは浅見真州がシテで、後場では「痩女」の面をかけた。容色の衰えた老婆の面が、愛欲と妄執の凄まじさをあらわしていた。「妄執のはてなき苦しみ。その裏の、陶酔のはてなき喜び」。

能楽研究者の三宅晶子は『世阿弥は天才である』(草思社)で、「これだけ愛されれば本望である、という女としての最高の悦びを表現した曲」だとする。
「これほどの想いをかけられるとは、女に生まれてこんな幸せなことはない。恋しい男からここまで想われるのであれば、地獄に堕ちることも厭いはすまい」
「後悔はしていない。今の醜い姿を見てくれ、これこそ愛の証、自分の生きたことの証であるのだと、そういうことが言いたいのでなければ、こんなところで舞ったりはしないだろう」
「皇女の誇りと愛される女の自信があるからこそ、醜い姿を曝して舞えるのだ。受動に始まって受動に徹することで、それを能動に変えてしまった女の生き方が、凝縮して表現されてこそ、〔序の舞〕が面白くなる」
しかし今回のシテの柴田は、「痩女」ではなく「泥眼(でいがん)」の面を用いていた。生身の人間ではないが、気品のある高貴な美しい女の面で、醜く衰えてはいない。女が考える「愛の証」と、男が考える「愛の証」の違いがそこに示されているようで、興味がつきない。
 写真は「能楽師・柴田稔 Blog」から
写真は「能楽師・柴田稔 Blog」から三宅の本は一九九五年に上梓されたものだが、ここで三宅は、シテの存在が希薄に感じられることが割合多く、
「なんのために〔序の舞〕を舞っているのか、その意味が見出せないのである。そういう場合演者は、もしかすると式子内親王を定家に愛された女としか見ていないのではないだろうか。愛される存在である女の感情を、女の真実にまで立ち入ってつかみ取り、表現し切るまでのことを、男である能役者はあまりしないのかもしれない。そこまですると能でなくなると思っているのだろうか」という。
そして、「世阿弥は男の理想としての女を描く。それは非常に美化された姿であるといってよい。だから見ていて気持ちがいいし、男の演者には演じやすいであろう」ものなのに対し、禅竹の描く女性像は「あまりにもずばりと現実の女そのものを描くので、ギクリとしてしまうほどだ。どうもこと女に関しては、世阿弥よりも禅竹の方が実態をよく知っていたのではないだろうか」と結んでいる。
醜さこそ「愛の証」と言いきれるか、それとも「愛の証」は美しくと願うか。
多面的な解釈が可能であることが『定家』の傑作の証なのは、疑いないが。
十一月八日(日)永遠なるものの比喩
悪戦苦闘した大仕事、ムックの『至高の名指揮者』はついにタイムオーバー。自分にあきれつつ、昨日あたりから心身のリハビリ。
そこで、このところくり返し聴いているCDがある。オーストリアの指揮者フェリックス・モットル(一八五六~一九一一)のピアノ・ロール。
モットルはバイロイトで活躍したワーグナーの直弟子三人(ほかはカール・リヒターとヘルマン・レヴィ)の一人で、ワーグナーは《マイスタージンガー》を初演したリヒター、《パルジファル》を初演したレヴィとならんで、《トリスタン》のスペシャリストとしてモットルを評価していた。
三人とも残念ながら録音は遺していないが、モットルだけはピアノ・ロールを遺した。このtacetの二枚組には十曲八十九分が入っている。すべてワーグナーで、《ローエングリン》《パルジファル》《トリスタン》《マイスタージンガー》の前奏曲や抜粋をピアノ編曲してひいている。
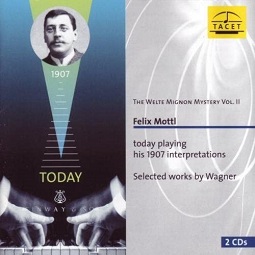
tacetの再生技術はかなり優れているようで、音の流れに自然な生命感があるのがありがたい。
とはいえピアノ・ロールはピアニストのタッチそのものは伝えてくれないようなので、ピアニストの芸術を判断するのに適しているかどうかは疑問。しかし指揮者のピアノの場合は、そのリズムや呼吸感、フレージングを感じとることはできる。
モットルの場合、それがなんとも気持がいい。ゆったりとしたテンポで音楽を慈しみながら、深く呼吸させ、大きく波動させて、幻のカール・リヒターと、録音があるカール・ムックやクナッパーツブッシュのあいだをたしかにつないで、偉大なワーグナー指揮者たちの系譜の存在を感じさせてくれる。
たとえば、二枚目の最後に入っている《パルジファル》第一幕の「場面転換の音楽と聖杯騎士の入場」がまさにその典型。
しかもピアノの音だけというのが、今の自分の、少し疲れた耳と心にちょうどよい。抽象化されたワーグナー、墨絵のワーグナー、点描のワーグナー。
水面に絵の具を垂らしたように、自分の白く乾いた心にポツリと落ちたピアノの点が、オーケストラの響きのイメージとなって、ふわっと透明に広がっては消えていく。
一瞬あとには、影が残るだけ。実体のない、蜃気楼のようなオーケストラの響きと、人の歌声。
もちろん、自分が元のオペラの響きをある程度憶えているからこそ、ふくらむイメージ。知らない人が聴いても面白いとは思えない。
たとえば五曲目の〈エルザの夢〉なんて、私の耳にはオーケストラとエルザとハインリヒと合唱の響きがたしかに聴こえてくる(いや、場面さえ見える)けれど、聞こえない人には、幽霊を見たとでも私が言っているようにしか思えないだろう。
聞こえてくるもの、与えられるものだけがすべてではない。
「すべて移ろい行くものは、永遠なるものの比喩にすぎず」
比喩の悦楽、とでもいうか。たぶん、能が教えてくれた愉悦。
二枚目の最初には、《トリスタン》の愛の二重唱が入っている。抽象化された、現世においては存在を許されない甘美な一体感。欠けている半身についに出会えたという喜びと愛おしさと、身を焦がす苦しみ。
このピアノ・ロールから四年後、ミュンヘンの宮廷歌劇場で《トリスタン》第1幕の指揮中に、モットルはピットに倒れて死ぬ。
その男が百十三年前にひいたピアノの比喩が鳴る。
十一月九日(月)不帰橋と仮の宿

現世回帰のリハビリ、マンガ本を買ってきて読む。吉田秋生の新作『詩歌川百景』第一巻。『海街diary』のスピンオフ作品。『海街…』最終巻の最後に収められた短編からつながるもの。いわくありげな登場人物が多いので、その相関関係を頭に入れるのに時間を食ったけれど、やはり面白い。
前作の開始時点からは十二年以上後の話で、子供はそれぞれに大人になり、大人は老い、世を去った人もいる。止まらない時間のなかで、出会いと別れをくり返し、死者を偲び、今を生きる人々。人生足別離。
それを象徴するのが、舞台となる山形県北部の温泉を流れる二つの川の一本、詩歌川(うたがわ)にかかる不帰橋(かえらずのはし)。死者がわたることのできない、現世と彼岸を隔てる橋という意味で、過去がけっして戻らないことを象徴しているよう。
とはいえ、『海街…』のヒロインがここから鎌倉に引っ越すことで物語が始まっていったことが示すように、この河鹿沢温泉には過去のしがらみに満ち、澱んだ雰囲気がある。
『海街…』には、山に囲まれた鎌倉と地形がそっくりだという台詞があった。しかし鎌倉はその向うに広い海が光っているのに、河鹿沢にはない。主人公と仲間の若者たちの青春は、この澱んだ、山あいの谷の町にある。その苦味が物語の基調にあるのが、前作との違い。
不帰橋に話を戻すと、そのたもとに崇徳上皇の「瀬をはやみ 岩にせかるる滝川の われても末に 逢はむとぞ思ふ」の碑がある。
これは藤原定家が「小倉百人一首」に入れた、いつかの再会を願う悲恋の歌。
定家が出てきてやっと気がついたが、ヒロインの名前「妙(たえ)」は、いうまでもなく新古今和歌集で西行と歌を交わした江口の君、遊女妙からとられているのだろう。
「世を厭ふ人とし聞けば かりの宿に心とむなと思ふばかりぞ」
それでも人は、生きて在る以上は「仮の宿」こと、現世に執着せずにはいられない――それがどんなに、わずかな歳月にすぎないにしても。江口の君はそのことを、その歓びと哀しみを知っている。なるほど、男をやりこめる江口の君とヒロインは似ている。自らも葛藤を抱えながら、菩薩のような存在。
そう思うと、物語の舞台が温泉旅館であること、ヒロインの祖母の大女将が芸者あがりであることなど、仕掛けはあちこちに。登場するたくさんの女性たちのなかで、ほぼヒロインだけがベタで塗られたみどりなす黒髪なのも、意味深。
こんなことは、能の『江口』に興味を持ってその背景や周囲を調べていなければ、まるでわからなかった。『江口』の世界にわずかでも触れているから、その機微に実感が、生身の温もりがわく。そうでなければ、ただのトリビアにすぎなかったろう。能に感謝。
というわけで(?)、CDで『江口』後場を聴く。オペラの全曲盤と一緒で、舞台を知らないとイメージしにくいのだが、舞台を知ってから聴くと、視覚がないことでかえって、無限のイメージがわく。日本語というのもいい(笑)。観世寿夫がシテを謡う一九六二年の録音。

十一月十一日(水)フォーレの二乗
届いたまま未聴のディスクを聴く。
エベーヌ弦楽四重奏団などとともに、現代世界最高の室内楽団と思う、ドイツのフォーレ四重奏団(ピアノ四重奏)。
結成二十五周年記念の最新盤は、原点に帰るかのように、団体名の由来となったフォーレのピアノ四重奏曲二曲と、歌曲五曲のピアノ四重奏編曲版。レーベルはBERLIN CLASSICS。
かれらのデビュー盤は一九九九年録音のARS MUSICI盤で、フォーレの一番がドヴォルザークのピアノ四重奏曲第二番と組み合わされていた。写真の左側。右側がそれから二十一年後の二〇〇〇年五月の再録音。

せっかくだから聴き比べてみる。初めの三楽章の所要時間はさほど変わらないが、表情の彫琢の深さが段違いに増している。そして終楽章は旧盤八分二十七秒に対し七分四十一秒と速い。表現が濃密で、時間差以上にスピード感が違う。二〇一四年にトッパンホールで初めて聴いたときの、ブラームスの一番の終楽章のコーダの激烈さに度肝を抜かれたことを思い出した。
表現が確信に満ち、力強い。そして完璧な四人のバランス。ピアノというまったく異質な楽器が入っているのに、弦楽四重奏のような一体感を、立体感と両立させて表出できるのがかれらのすごさ。
二十一年の歳月が血となり肉となっている。重ねた年輪の芳しさ。録音のよくないDG盤しかないブラームスも、これなら再録音してほしいと思う。
二番も同様に素晴らしく、そしてこれまで同様、実演では粋なアンコール・ピースになるだろう歌曲たちも素敵。〈われらの愛〉〈ゆりかご〉〈夢のあとに〉〈月の光〉〈マンドリン〉。特に〈マンドリン〉のセンスのよさにききほれる。
コロナ禍がなければ、十月初めにトッパンホールで、ホールの開館二十周年とかれらの結成二十五周年を祝う二つのコンサートで、これらの曲が演奏されていたはずだった。まことに残念。
これはイギリスから届いたCD。一時期は船便で二か月かかるのが当然だった荷物も、十月半ばには旧に復して、航空便で十日、八日と次第に縮まり、このディスクにいたっては十月二十七日発送で十一月三日着、たった六日で届いた。しかしヨーロッパの感染拡大で、また日数を食うようになるのかも。不安。
十一月十二日(木)われ永遠に立つ
十一月前半は、私的な「コロナ禍におけるピリオド演奏強化週間」。日本のピリオド楽器演奏、HⅠPの水準向上と広がりに、目を瞠らされた四回の演奏会。



・二日 モンテヴェルディ:聖母マリアの夕べの祈り 濱田芳通指揮ラ・ヴォーチェ・オルフィカ、アントネッロ(東京カテドラル)
・三日 ヘンデル:歌劇《リナルド》 鈴木優人指揮バッハ・コレギウム・ジャパン(東京オペラシティ コンサートホール)
・十日 ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第四番、交響曲第九番《合唱》ほか 川口成彦(フォルテピアノ)、渡辺祐介指揮オルケストル・アヴァン=ギャルド、クール・ド・オルケストル・アヴァン=ギャルド(みなとみらいホール)
・十一日 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第一番、第二十三番《熱情》、第二十九番《ハンマークラヴィーア》 小倉貴久子(フォルテピアノ)(東京文化会館 小ホール)
 東京カテドラルのルルドの泉にあるマリア像
東京カテドラルのルルドの泉にあるマリア像一六一〇年のモンテヴェルディの教会音楽、一七一一年のヘンデルのオペラ、一八二四年のベートーヴェンの交響曲と、ほぼ百年おきで規模を拡大していく声楽入りの大曲が三回、それも年代順に進行するというのが、ひさびさに「東京で勝手に音楽祭」になって楽しかった。
まずはモンテヴェルディ。東京カテドラル聖マリア大聖堂で音楽を聴くのは四回目だが、そのうち三回が《聖母マリアの夕べの祈り》で、あと一回もモンテヴェルディのミサ曲《イン・イロ・テンポレ》と、モンテヴェルディしか聴いていない。マリアだからマリア、そしてこの教会の大空間も曲にふさわしい。
この曲を初めてナマで聴いたのは二〇〇七年、くしくも同じ場所と団体による演奏で、今はなき目白バ・ロック音楽祭(面白い試みだった!)の一つだった。
しかし十三年をへて、とにかく上手くなっているのが嬉しい驚き。濱田のつくる響きが濃密に波動するのは、以前と基本的に変わらないと思う。四十七人という合唱は、残響の多いこの空間ではかなりの規模。二〇一七年に聴いたコントラポントとヴォーカル・アンサンブル カペラは十二人編成で、それでも充分に楽しめたが、その四倍の人数。
二〇〇七年のときは響きが混濁してしまい、独唱と合奏も音程が不安定だったりすることがあって、正直なところ困惑したのだが、今回はまるで違う。響きの純度があがり、全体の演奏の安定度も高い。声楽はソロをとるときだけマスクを外すが、合唱はつけたまま。それだけきちんとした唱法を身につけているということなのだろう。こうなると、空間全体に響きがふわーっと広がって、熱い渦を巻く。官能的でさえある。音楽的・宗教的な法悦。
続いてヘンデルの《リナルド》。四時間の長さを飽きさせない、楽しい上演。これまた、鈴木優人指揮のオケも歌手も上手い。
バロック・オペラは教会音楽と対照的に合唱を用いない。歌手たちの妙技と存在感だけで物語を語る。日本人だけになった歌唱陣、しかし森麻季、中江早希、藤木大地、大西宇宙など、見事なもの。
アリアのくり返しも装飾や仕種の変化で飽きさせない。能の序の舞のくり返しが、名手が舞えば同じことにはならないことを思い出す。過去のひからびた美学を安易に現代化するのではなく、芸の力で血と肉をあたえる工夫。
砂川真緒の演出は、全体をオタク青年が楽しむコンピューター・ゲームのようにした。キリスト教対イスラム教という深刻な現代的課題を、あくまでゲームの中の出来事にすることで、その重さを軽減していた。
そしてベートーヴェンの第九。八八六四三のオケと二十八人の合唱。たしかにみなとみらいの大空間を圧倒する音量ではない。しかしこれも響きの純度が高いので、明確に音が通る。ヴィブラートたっぷりの混濁した大音響に呑まれるのではなく、耳をすますことの心地よさ。歌詞もよく聴きとれる。
前半の《プロメテウスの創造物》序曲に続くピアノ協奏曲第四番では、いままでどうしてもタイミングが合わず、やっとナマを聴けた川口成彦のフォルテピアノがソロ。潤いのあるタッチ、俊敏で微妙な陰影と色彩の変化など、このところの大活躍が納得できる魅力。
面白かったのは舞台上方に大型スクリーンを吊り、演奏を大写しにしていたこと。アイドルのスタジアム・コンサートの手法で、遠いものを近く感じさせ、同じ空間にいるという実感を補強できる。大型ホールでピリオド楽器を聴くにも有効な手法だろう。《リナルド》でもこれをやっていたら、さらに楽しめたかもしれない。本格的な舞台上演の場合はともかく、セミステージ方式の場合は、やってみる価値があるのではないだろうか。
ここでもオケ、声楽ともに水準が高く、澄んだ響きで安定性もかなり高い。そして若い人が多いのに感心。BCJやオーケストラ・リベラ・クラシカのメンバーが多いが、ホルンは福川伸陽などN響、新日本フィル、千葉響の団員がナチュラル・ホルンを吹いている。
かつては、モダンとピリオドを対立の構図でみる人が多かったが、時代は変わり、モダン楽器をおもに演奏する演奏家でも、ピリオド楽器と奏法の知識をもつ人が増えている。
ヨーロッパでそうなっているように、時代によって楽器や奏法を変えることが自然になっていくのだろう。TPOに応じて衣装を替えるようなものだ。そしてそれは、厳格である場合、多少ルーズにする場合など、状況によって変化する。
第九の前にプレトークをした池辺晋一郎は、あまりこうした時代の潮流を理解しておらず、相変わらずの対立の構図でしゃべっていて、あまり益がなかった。ただ、ピリオド楽器演奏を「時代劇みたいなもの」と形容したのは面白かった。
歴史劇は時代考証をする。戦国時代の日本人にスーツとネクタイを着せたら、それは読みかえ演出だ。同じように、リュリやラモーの鍵盤楽器作品を現代のピアノでひくのも、読みかえだ。
読みかえ演出は大好きだし、大いに意義があると思うが、その面白さを深く味わうためには、時代考証を意識した演出も知っておいて損はない。
モダン楽器で何も考えずに演奏するのは、長篠の合戦の織田方の火縄銃三段撃ちを、火縄銃なんて時代後れで不便だから重機関銃にすればいいじゃんと、それで武田の騎馬隊を一斉射撃するようなものなのかもしれない。

そのことを強く感じたのが、小倉貴久子が三台のフォルテピアノを使いわけてひいた、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ三曲だった。曲間にマイクを使って小倉自ら楽器を説明してくれるので、とてもわかりやすい。
一七九四年完成の第一番では、アントン・ヴァルターの一七九五年製(レプリカ)。五オクターヴと音域が狭く、ウィーン式(跳ね上げ式)アクションで響きが軽い。チェンバロに近い音。しかしベートーヴェンはこの楽器を用いて、四楽章と交響曲を想わせる規模の構成とし、若々しい覇気を感じさせる。
一八〇五年完成の第二十三番《熱情》は、一八〇〇年頃のブロードウッドの五オクターヴ半の楽器で。膝でレバーを操作したヴァルター製に対し、現代同様のペダルがつくようになった。ベートーヴェンはこれとほぼ同じ機構をもつエラールを用いて、第二十一番《ワルトシュタイン》から第二十六番《告別》までの中期の傑作群を書いている。
イギリス式シングルエスケープメントの響きは、はるかに重い。低音がガシャンというような、独特の機械的響きで鳴る。柱時計の鐘の、あの鉄の響きのような感じ。難聴がいよいよ進んだ作曲家は、こういう低音を聴きながら作曲していたのかと思うと感慨深い。
一八一八年完成の第二十九番《ハンマークラヴィーア》は、一八四五年製のJ・B・シュトライヒャー。六オクターヴ半の音域をもつ、作曲家が没して十八年後の楽器をあえて用いるのは、作曲家と同時代の六オクターヴの楽器一台では、このソナタを演奏できないから。
ベートーヴェンが前半二楽章を作曲しているときには、ナネッテ・シュトライヒャーの六オクターヴの楽器を用いていたが、途中でブロードウッドの楽器が届き、後半二楽章はそれを用いて作曲された。問題なのは、同じ六オクターヴでも二台の楽器の音域が異なっていたこと。ブロードウッドのほうが少し低い。そのため、全曲を一台で演奏するには六オクターヴ半の楽器が必要になる。
現世の楽器の制約を超え、理想の未来の楽器のために作曲しようとしていた後期のベートーヴェンを、端的に示すような話。
一八四五年製の楽器ならそれが可能になる。金属棒が二本入っていて木製のフレームを補強し、弦の高い張力に耐えられるようになっている。それだけに強い響きだが、ウィーン式(跳ね上げ式)アクションなので軽い響きでもある。
後半をブロードウッドで書いたとき、イメージされていたのは先ほどの、あのガシャンという低音だったのかもしれないな、などと考えながら聴く。
いずれにしても、現代のコンサートグランドの交差弦の濁った低音の響きが生理的に苦手な自分にとっては、平行弦の澄んだ響きは、耳に心地よかった。
外へ出ると、西洋美術館のロダン作の「地獄の門」が目に入る。
聖マリア大聖堂に始まって地獄の門に終わる「コロナ禍におけるピリオド演奏強化週間」。

永遠の物のほか物として我よりさきに造られしはなし
しかしてわれ永遠に立つ
汝等こゝに入るもの一切の望みを棄てよ
十一月十三日(金)かれらは来た
読売日本交響楽団、十二月公演には指揮者ヴァイグレ来日。第九の歌手二人も来日。入国後十四日間の隔離措置をへて登場とのこと。
コロナ禍では第九はできない、と最初はいわれていたけれど、公演数の多い第九がある十二月だからこそ、隔離期間があっても外国人演奏家の登場が可能になるという、面白い事態(欧州の感染拡大も関係あるかも)。一公演だけの予定だったピアニストのアームストロング(船長ではない)は来日せず。
あとは、日本の感染状況があまりひどくならないことを祈るのみ。
夜はサントリーホールで、ゲルギエフ指揮ウィーン・フィル。
噂どおりの凄いものだった(笑)。
・ベートーヴェン:序曲《コリオラン》
・チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲(チェロ:堤剛)
・R・シュトラウス:交響詩《英雄の生涯》
来日早々の福岡でのオンライン記者会見で、「距離をおいたのではウィーン・フィル伝統の響きはつくれない」と宣言したとおり、舞台上ではソーシャル・ディスタンスをとらない密集隊形。すり鉢状の階段ステージがその密集度をいっそう高める。
アレクサンドロス大王のマケドニア・ファランクスを想わせる、誇り高きフィルハーモニカー。
 ツイッターのサントリーホール公式アカウントから
ツイッターのサントリーホール公式アカウントから十五‐十三‐八‐十‐八。ヴィオラが少ないのは、渡航直前の検査で陽性反応が出た奏者と、その濃厚接触者を外したためだそう。
一曲目の《コリオラン》は、自分にはあまりにも響きが重くて、リズムの弾力に欠けて感じられ、二〇二〇年のベートーヴェンとしてこれはちょっと…と思ったが、それが後半のシュトラウスになると、そのままで有無を言わせぬ説得力をもった魅力的音楽になるのがすごい。やはり十九世紀後半から二十世紀半ばまでのドイツ音楽では別格の存在。
二曲目のロココ変奏曲は、録音でも実演でも自分がどうしても集中を保つことができない苦手な作品なので感想省略。
シュトラウスは、ウィーン・フィルにとって自家薬籠中の音楽。かれの音楽は、ウィーン・フィルとシュターツカペレ・ドレスデンという歌劇場を母体とするオケがその再現者として無上の存在であることが示すように、本質的に劇場のもの。そしてゲルギエフも、交響曲よりは劇場の指揮者。
その相性のよさが見事に作用して、響きが波うつように、美しく綾をなす。ファランクスのなかからすっと姿をあらわしては、また戻っていくソロや声部の、なんとあでやかなこと。
大概は冗長に感じられるこの曲を、一瞬も停滞させることなく、物語を面白く聴かせる語りくちのうまさと色彩美。
ウィーン・フィル史上初の女性コンサートマスター、ダナイローヴァのソロもつややかで、素敵に美しかった。男性楽員がグレーのスラックスで揃えるなか、黒のパンツスーツが印象的。
アンコールはリラックスして《皇帝円舞曲》。ただ自分はこの曲に「美しき落日」のようなものをイメージしてしまうので、いろいろ考えさせられたが。
有機的音響体としてのウィーン・フィルというオーケストラの特別さを、あらためて思い知らされたコンサート。「美しき過去」をそのままに、今にとどめようとするオーケストラ。
自らを「超一級の伝統芸能」だとする割り切りが、よくも悪くもすごい。ヨーロッパ文明の「芸術家」のありかたとしては、けっこう異質な自己定義ではないかと思うが、それで有無を言わせないレベルに達している。だからこそ日本のクラシック好きは、とりわけかれらを好むのかもしれない。
舞台上だけでなく、客席もびっしり満員。ウィーン・フィルが帰る母国では歌劇場も演奏会も閉鎖中で、しばらくは日本公演が最後の演奏機会になる。
たしかに今回の来日は特例だらけ。どんな力が動いたのか、想像もつかない。これがどのような意味を持つ公演だったのかは、一年後、さらに数年後にわかっていくことだろう。
ただ、日本のクラシック界の閉塞状況に突破口を開けられるのは、やはりウィーン・フィルとサントリーホールの組み合わせしかなかったのだろうとも思う。
一九五六年以来、六十五年間で三十六回目の来日。こんなに来日している交響楽団はほかにない。史上初めてヨーロッパから来たオーケストラ、そして前年来日のシンフォニー・オブ・ジ・エアは消滅しているから、現存最古の来日オーケストラ。SP時代から日本のファンに愛されてきたクラシック音楽のシンボル。
サントリーホールも一九八六年以来、日本のクラシック興行界のシンボル。
日本のクラシック音楽受容と消費の歴史において「ウィーン・フィル」が担ってきた意味、それが今回の来日公演実現によって、また一段と深まったように思う。もし小澤征爾が指揮していたら、さらにすごいことになっていただろう…。
無事を祈るのみだが、ただ、ネット世論がかまびすしい世の中ではむずかしいこととは重々承知の上で、「三歩進んで二歩下がる」ことをくり返していく覚悟への寛容さも大切かな、と思っている。
このあと、十四日間の隔離措置が必要とはいえ、欧州からの来日音楽家が少しずつ登場してくる。新国立劇場の《アルマゲドンの夢》《こうもり》の出演者とスタッフ、そして何人かのピアニストや指揮者たち。この流れが、少しずつ広くなっていくことを。
話はそれるが、今年の東京の第九、新国立劇場合唱団は読響、N響、東フィル、東響と四つのオケと共演。よくバッティングしなかったもの。
十一月十五日(日)モノオペラ的ルチア
日生劇場でオペラ『ルチア~あるいはある花嫁の悲劇~』。
田尾下哲の演出は、コロナ禍のなか、感染防止のためにドニゼッティの《ランメルモールのルチア》を短縮して、ソーシャル・ディスタンスを保つようにしたもの。客席は市松模様、オーケストラは弦と木管だけにして、ホルンを含む金管はピアノで代用。弦も六五四三二くらいに縮小。
舞台に立つのはルチアと黙役の亡霊のみ。他の役はいっさい姿をみせずに、舞台左右の黒いスクリーンの背後で、いわゆる陰唄(カゲウタ)で歌う。
音楽もルチアの歌う場面以外の大半をカットして、百四十分を休憩なしの九十分に縮める。つまりルチアだけがほぼ出づっぱりで、シェーンベルクの《期待》やプーランクの《人間の声》などのモノオペラに似た、孤独な女の心理劇という趣になる。
コロナ禍を逆手にとった、コロナ禍だからこそ可能なスタイルで、こういうチャレンジ精神は大いに買う。
もちろん、本来はそうでないドラマをそうするのだから、無理や齟齬はあちこちに出る。しかし新たな説明的ナレーションや字幕を加えることをいっさいせずに、ただ短縮するだけにした態度は潔くて、好ましい。
ルチアにまとわりつく亡霊は、ルチアの内心の不安や恐怖が具現化したもの。ドラマを動かし、悲劇を招き寄せる、宿命のような存在。
ルチアは舞台上の、箱のような灰色の部屋の中にいる。閉鎖病棟のようでもあり、霊廟のようでもあり。
 日生劇場のサイトから
日生劇場のサイトからいうまでもなくルチアの閉塞と孤立を示しているのだが、同時に歌手が大きなメガホンの中にいる形になるので、日生劇場のデッドな音響のなかで、歌いっぱなしのルチア役の声を援護する役割ももっている。これはうまい工夫。
通常の上演以上に、主役ルチアの出来にすべてがかかってくるが、森谷真理の歌と演技は圧倒的に素晴らしかった。
この人の存在を初めて意識したのは、去年六月の二期会の《サロメ》のゲネプロだった。昔の日本のプリマドンナに多かった、顎にヴィブラートをぶら下げたような猛女型の発声ではなく、ピンと張りのある声がまっすぐに伸びて、こちらの心に刺さってくる。
凄少女(せいしょうじょ)、とでもいうべき歌唱がサロメにぴったりだったのだが、今日のルチアも同様にはまり役。サロメのごときルチア。狂乱の場の迫力は、演出上のすべての無理も疑問も呑みこんで、ひっさらっていくものだった。
個人の意見としては、エドガルドだけは離れた場所に姿をみせてもいいのではないかと思った。ルチアが心を許す現世の人間はエドガルドだけであり、かれに嫌われ、呪われたことでルチアの自我が一気に崩壊し、惨劇に突っ走っていく。
そのエドガルドを、ソーシャル・ディスタンスを完全に保った位置に出すことで、じつはルチアとは真の意味で心を通わすことが終始できておらず、互いの思い込みが誤解を生み、悲劇になるというやりかたも、あるのではないかと思った。たとえば愛の二重唱も、手紙をとおしてのやりとりのようにするとか。
しかし、こんな余計なことを考えさせてくれるものこそ、自分にとってはいい舞台。コロナ禍のなかでの芸術表現として、とても面白かった。
NISSAY OPERA 2020 特別編
オペラ『ルチア~あるいはある花嫁の悲劇~』
全1幕 原語[イタリア語]上演 日本語字幕付
原作:ガエターノ・ドニゼッティ作曲 オペラ『ランメルモールのルチア』
指揮:柴田 真郁
演出・翻案:田尾下 哲
管弦楽:読売日本交響楽団
ルチア 森谷 真理
エドガルド 吉田 連 ※
エンリーコ 加耒 徹
ライモンド 妻屋 秀和
アルトゥーロ 伊藤 達人
アリーサ 藤井 麻美
ノルマンノ 布施 雅也
泉の亡霊(助演) 田代 真奈美(両日)
十一月十六日(月)BCJの第九実演
オペラシティで、BCJによる年末の第九公演が急遽決定。十二月二十七日に昼夜二回公演。
東京では、こういうときだからこそ第九をしっかりやらねば、という感じになってきてるのが面白い。ちょっと、岡田暁生さんの『音楽の危機』への、現場からの反撃のようでもあり(笑)。
ピリオド楽器による第九は、個人的には何度でも聴きたい。コロナ禍における日本クラシック界の顔になったといってもいい鈴木親子とBCJによる第九は、一年の最高の締めくくりかも。
十一月十七日(火)至高の指揮者たち

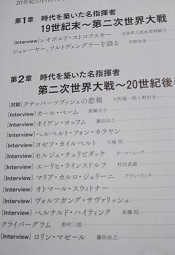
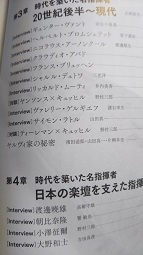
「至高の指揮者たち:20~21世紀の名指揮者が語る音楽と指揮芸術」
明日十八日に発売予定のこのムック、はっきりいって必買・必読だと思う。
一九六五年から二〇一六年まで半世紀の「レコード芸術」「音楽の友」に掲載された、名指揮者たちのインタヴュー記事などをあつめたもの。どういう人たちが出てくるかは目次写真(下手で失礼)をご覧あれ。
私は総論的に、ハンス・フォン・ビューローからバーンスタインあたり、二十世紀半ばまでの指揮者の物語を九十枚書いた。後半は山田治生さん、日本人指揮者は奥田佳道さんが担当されている。
もちろん大指揮者たちの肉声を伝える記事がメインで、拙稿は添え物に過ぎないが、演奏史譚らしき仕事が少しはできたかなと思っている。
どんどん売れると続篇ができて、今回時間切れで書ききれなかった部分――ああ情けない――も、ひょっとしたら書かせてもらえるかもしれない……ので、立ち読みせずにぜひ買ってください!
十一月十八日(水)いまここで

新国立劇場の藤倉大作曲のオペラ《アルマゲドンの夢》、とても面白かった。
H・G・ウェルズの短編を原作にふくらませた物語は、ポピュリズムが生みだした独裁者の専制に翻弄される平凡な男と、かれが愛した女の死を描く。まさに現代的な題材。
休憩なし百分という時間に猛烈な情報量の音楽と物語が凝縮されているので、正直言って一回では、全貌はとてもつかめない。ただ、その目まぐるしさは映像を効果的に多用する舞台とあいまって、まさに今のもの、と感じられる。
一回でつかみきれずとも、とにかく嬉しいのは、「いまここで生まれている」ものに立ち会っている空気が、劇場全体にみなぎっていること。
音楽も舞台もいま生まれている。そのことへのすべての出演者、スタッフの充実感が、舞台から放射してくる。劇場って、これだよね!という感じ。予定調和ではない鮮度、みずみずしさへの歓び。
こういう感覚を新国立劇場で味わうのは、久しぶりという気がする。これは大野和士さんの大きな功績。
就任最初の《魔笛》も、前回の《夏の夜の夢》も、劇場的快感に満ちた素敵な舞台ではあったが、他の劇場で上演済のプロダクションだったから、自分にはどうしても「美しい過去をなぞっている」印象を受けずにはいられなかった。
そこが《アルマゲドンの夢》は決定的に違う。完全な初演で、なにもかもがピチピチと新鮮にはねている。こういうものがコロナ禍につくられたことに感謝。
クラシック音楽には、すでに定評のある名作の先刻承知の「感動」が、新たに再現される瞬間に立ち会う歓びもある。
五日前のウィーン・フィル来日公演はまさにそれだった。コロナ禍で忘れかけていたそれを呼び戻してしまう、まさに「Verweile doch, du bist so schön!」という叫びを現実化させようとするかのような再現、惰性とは完全に無縁の、永遠なる再現。
再現と創造。たてつづけに、音楽芸術の対照的な二つの側面の美しい実例に接することができて、とても嬉しい。
ところで、このオペラに出てくる独裁者は、二十世紀から現代まで、世界のあちこちにいるステロタイブな独裁者。
ニューズウィーク日本版のサイトで『「コロナで民主主義が後退する」という予想が当たらなかった三つの理由』というのをたまたま読んでいたら、啓発的な言葉に出会った。以下引用。
独裁的指導者は危機の深刻度を否定したり情報を隠したり、疑似科学的な解決策に飛び付いた。ブルガリアの政治学者イワン・クラステフいわく「危機が独裁主義者を利するのは、自らつくり上げた危機のときだけだ。彼らが必要とするのは打倒すべき敵であり、解決すべき問題ではない」。
現在の混乱が各国の政治に与える究極的な影響は読めない。だが、未来は民主主義の危機が叫ばれた1年前より、はるかに開けて見える。
(引用終わり)
このクラステフの「危機が独裁主義者を利するのは、自らつくり上げた危機のときだけだ。彼らが必要とするのは打倒すべき敵であり、解決すべき問題ではない」という言葉。なるほどという感じ。現代においては、独裁主義者だけでなくポピュリズムが頼りの政治家すべてに言えそうだが。
オペラのジョンソンは、戦争という危機をあおっていた。コロナ禍に対しては、かれはどうするのだろう。
十一月十九日(木)インクが滴る感じ
サントリーホールで、鈴木優人指揮読売日本交響楽団の演奏会。
シャリーノ:夜の自画像
シューベルト:交響曲第四番《悲劇的》
ベリオ:レンダリング

五月に予定されながらコロナ禍で中止となった演奏会(鈴木優人のクリエイティヴ・パートナーの就任お披露目となるはずだった)の曲目から、マティアス・ヘフス独奏のベーメのトランペット協奏曲をシャリーノ作品に入れかえたもの。
ソリストが消えて華やかさは減じたけれど、一八一〇~二〇年代オーストリアと一九八〇年代イタリア、一世紀半の時間を行き来するプログラムとしての統一感が出て、より面白くなった。
シャリーノの曲について鈴木は「弦のハーモニクスを巧みに用い、今までない手法で文字通り音によって絵を描いています。インクが滴る感じは東洋の水墨画に近い印象で、日本的な美学を感じるものです」と読響のサイトで語っている。
「インクが滴る感じ」というのは、ナマで音を聴くと、ものすごくよく納得できる。音が音の膜を透けてゆくような感じ。強い色彩が混ざるのではなく、透明度の高い、淡い音と音が漂い、浸透しあう。ナマでないと、この空気の幽かな振動の快感は感覚しにくい。
そしてシューベルト。一九七〇年代の新古典主義的スタイルだと、端正だが平面的で重い響きになりやすいのだが、鈴木の響きはピリオド演奏の経験を踏まえて、輪郭がはっきりして動感がある(奏法そのものはモダン的)。シャリーノやベリオと同じ音感覚ではないので、コントラストがはっきりと出る。これは、二〇二〇年の音感覚で両者をとらえなおした、現代ならではのアプローチ。
ベリオのレンダリングは、シューベルトが生涯最後に書きかけた未完の交響曲D九三六Aの空白部分を、ベリオ独自の音楽でつないだもの。鈴木は『ベリオは陶器の欠けた部分を「金継ぎ」するようにティシュー(織物)を用いて埋め、作曲しました。この継ぎ目の部分では、チェレスタを用いてピアニッシシモの弱音で鳴らすなど、タイムスリップするかのような音楽を書いています。夢のような部分で響きのグラデーションが美しいのです。全体としてベリオの謙虚さと技が光りつつ、シューベルトの感動的な音楽が浮かび上がります』と語っている。
白昼夢のように、シューベルトの晴朗な音楽のそこかしこに、それを夢幻的に歪めたベリオの音楽がチェレスタの響きとともに闖入したかと思うと、突如として正気に戻る。夢と現を彷徨する音楽。
過去のクラシック音楽を現代に演奏する行為、そのもののカリカチュアのようでもあって、とても面白い一夜だった。
しかし残念なのは、お客さんが少なかったこと。満席入場が可能なのに、制限されているかのような客席。保守的なお客さんに好奇心の愉悦を思い出してもらうには、どうしたらいいのか。これは自分も自らの課題として考えつつ、とにかく挑戦を続けてほしいと願うのみ。
三十日にはよみうり大手町ホールで、鈴木優人と読響のアンサンブルによるヴィヴァルディの《四季》とケージの曲を入れ子にした一夜がある。これも十八世紀と二十世紀の対話で、とても楽しみ。
十一月二十日(金)船弁慶


国立能楽堂の定期公演。十一月の公演からはほぼ満席入場(一列目のみ空席)が可能になり、びっしりのお客さん。とはいえ能楽はクラシック以上に静かで行儀のいいお客が多いので、あまり不安は感じない。
ただ、併設の展示室は休憩時は閉鎖、開演前も入場制限ありとのことなので、なかなか入る機会がなさそう(来月の特集に合わせて「勧進能」特集なので、覗いてみたいのだが)。
終演後も先月までは行なっていた時差退場をせず、自由退場となったが、そのために出口手前の狭い通路にかなりの密集状態となる。夜公演はどうしても帰宅を急ぐ人が多いので、次回以降は時差退場になるかも。
・狂言『延命袋(えんめいぶくろ)』茂山七五三(大蔵流)
・能『船弁慶(ふなべんけい) 重キ前後之替・舟唄替之語(おもきぜんごのかえ・ふなうたかえのかたり)』片山九郎右衛門(観世流)
『船弁慶』は観世信光の人気作で演能機会が多いが、自分が見るのは二回目で四年ぶり。シテ以外の登場人物の演技場面も多い、いかにも信光らしく芝居風味の強い能。
後半が派手に盛り上がるので、能を初めて見る人、歌舞伎好きの人が見るには最適の曲だろう。最初に『井筒』を見るというのは登山初心者が高山に挑むようなものだし、歌舞伎の原作となった『安宅』や『石橋』だと、どうしても大衆向けにわかりやすく劇的に改変された歌舞伎版と比べてしまうので、地味に見えてしまう。
その点で『船弁慶』は、能ならではの独自性と、わかりやすさを兼ねそなえている。昭和に能楽の外国客演が増えはじめたころ、やたらに『船弁慶』ばかりやるので、他のものはないのかと目の肥えた外国人からいわれたそうだが、それくらいに初心者にも楽しめるものなのだ。事実、私の前列の和服のご婦人方は能をあまり知らないようだったが、終演後に「楽しかった!」と喜びあっていた。
この能は、シテが前場と後場で別人を演じることに特徴がある。前場は義経の愛妾静、後場は平知盛の怨霊。女と男、緩と急、優美な舞と憤怒の襲撃との落差が大きく、両方の要素を一回で楽しむことができる。
今回は特に後場が激動的。「流レ足」という、怨霊が水面を滑るような動きも楽しかった。
ただ、この能の本当の独自の魅力は、前場と後場、つまり静と動との中間の場面にあると思う。シテが舞台にいない場面(笑)なのだが、そこに最高の劇的瞬間がくるというあたりが、ワキを重視した観世信光ならではの作劇法なのだ。
静が義経の前で別れの舞を舞って退場したあと、主従は大物浦から西国へ船出しようとする。船頭役のアイが急速な囃子にあわせて舟の作り物をもって走ってくる。一行が乗り込んでしばらくは、晴天のもとでの和気あいあいとした航海。
ところが六甲山から吹き下ろす風が、突然に嵐の気配をもたらす。荒れだす波と風、懸命に漕ぐ船頭。しかしどうもおかしい。義経の家臣が思わずもらす。
「妖怪(あやかし)がついているのではないか」
「いけない、船上で不吉なことを口にしてはならない!」と弁慶がたしなめる。耳にした船頭も激怒する。海上ではそのような一言が、本当に幽霊を呼び寄せてしまうからだ。
すると、水底から平家一門の亡霊が次々と波間に現れる。
六甲山の麓には清盛一代の「夢の都」福原があり、公達が数多く討たれた一ノ谷古戦場がある。壇の浦に滅んだ平家の亡魂が故地を慕って水底を進み、福原の沖に漂っていても、何の不思議もない。
この、次第に不安と緊張が高まっていく場を、三間四方の何もない能舞台に、弁慶や船頭の問答だけで描いていく、イマジネーションを喚起する力が凄い。
能を見るのは、こういう無限の想像力が沸騰する瞬間に出会うためだと、自分は思っている。
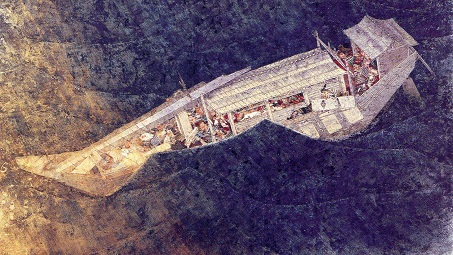 前田青邨『大物浦』
前田青邨『大物浦』そして、能のこの力に惹かれ、見事に視覚化してみせてくれたのが、画家の前田青邨だ。
その『大物浦』は、義経一行の船が波風に翻弄されながら、あやかしの世界に捉えられる瞬間を描いている。左手の舳先を包む金色の光は、あやかしの光なのである。
その行く手には何がいるか。それを描いたのが『知盛幻生』という絵。知盛や幼い安徳天皇など一門の亡霊が、白い波涛となって航路を阻む。白は平氏の色なのだ。
 前田青邨『知盛幻生』
前田青邨『知盛幻生』能では知盛の亡霊が去って終わるが、義経一行が勝ったわけではない。必死で霊をふりきり、陸地に戻っただけだ。航海は失敗し、軍勢は散り散りとなり、義経はわずかな手勢だけで潜伏と逃避行を重ね、奥州へ落ちていくことになる。
この破局の発端が、能の詞章では、義経が静に未練を残したことのようにも感じられるのも面白かった。
能の最初の場面で、弁慶が静に別行動を告げに行ったのに、義経の口から聞かねば納得できないと、静は義経に会いに来てしまう。
義経自らに説得された静は、しかたなく宿に下がるが、その悄然たる姿をみた義経のほうが、未練気を起す。
今日は波が荒いから出航を一日待とうと、家臣から弁慶に告げさせるのだ。
こういうことだけ、弁慶に直接言えずに人に言わせる義経が面白い。
しかし弁慶は、さては静への未練だなと義経の下心を言下に見抜き、だめだだめだ、屋島の戦いでは嵐をついて船出して、見事に勝ったではないかと船出を進言する。
結局、義経は弁慶に同意するのだが、このような未練心を起した時点で、義経から武運は去っているのだろう。戦えば必ず勝って、平家を鮮やかに滅ぼした軍事の天才は、もはや二度と輝くことがないのだ。
はっきりは書かないけれど、文脈に匂わせるあたりが、能の詞章の面白さ。
そう考えてみると、前半の狂言『延命袋』は、義経の破滅を見事に予告するものだった。
男は、妻があまりに口やかましいので離縁したいと思っているが、何しろ弁の立つ相手なので言い出しにくい。
そこで、実家に里帰りしたときをねらって、太郎冠者に離縁状を持っていかせることにする。しかし手紙を見た妻は怒り狂い、男の口から聞かねば承知しないと、家まで戻ってきてしまう。
しかたない、離縁の印に何でも持っていけと男が言うと、妻は袋を出し、男にかぶせて連れていってしまう。
他人まかせは身の破滅。
こうして、狂言と能をうまくつなげる工夫が、国立能楽堂の企画の面白さ。
十一月二十二日(水)成人式
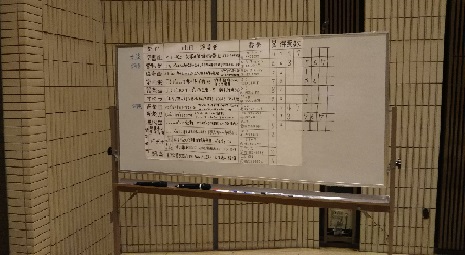
音楽之友社にて、レコード・アカデミー賞の選考会。
ビデオ・ディスクの月評は数年前から担当しているが、この賞の選定に関わるのは今回が初めて。「レコード芸術」の執筆者としてようやく成人して、選挙権を与えられたというところか。
そういえば自分がレコ芸を読み始めたのは一九八〇年のことだから、今年は四十周年ということになる。
例年は会議室に年二回集まり、一回目に部門賞を各部門の月評担当者が決め、二回目は全員で投票して大賞から銅賞までを選んでいるのだそうだ。しかし今年は防疫のために部門賞は担当者間のメールや電話のやりとり、つまりテレワークで決定し、大賞を決定するための投票のときのみ全員が集まることになった。
今日がその選考会。三密を避けるために、会場は空間に余裕のある音楽の友ホールとなった。
今年は三部門にエラス・カサドが選ばれるという驚きの事態で、投票する者としてはまことに面白い。ビデオ・ディスクは特別部門の一つで、大賞選定の対象には入っていないので、いわば遊軍的に気が楽な立場である。
大方の予想通り、評が割れて決選投票をくり返すことになった。細かい経緯は来月発売の「レコード芸術」に譲る。自分が最初から推していたカサドの第九が選ばれたので、なんとなく嬉しい。
十一月二十五日(水)レハールとパリ


昨日と今日は、日生劇場で二期会による《メリー・ウィドウ》。
昨日はゲネプロ、今日は別キャストのゲネだったものを有料のプレヴュー公演に切り換えたもので、当然のことに音楽面には生煮えの部分があったので、歌唱と演奏についての感想は控える。
それよりも作品。今回もあらためて感じたのは、レハールがこの作品で、オッフェンバックの音楽の魅力を自己流に咀嚼して、じつにうまく書いていること。なぜオッフェンバックかといえば、この作品の舞台、というよりも影の主役が、パリだから。
我々日本人はかつての「ドイツ音楽絶対史観」の影響か、オペレッタといえば「音楽の都」ウィーンのものと思いこみがちだが、オペレッタの淵源はパリ、そこで大活躍したオッフェンバックの諸作にある。
ウィーンの人々にとっても(パリ以外のすべての都市の住人と同様に)、「十九世紀の首都」パリ、歓楽と美食の都、享楽と頽廃の「大淫婦」パリは、流行の発信源として憧れの存在なのだろう。
《メリー・ウィドウ》は、その「パリ憧憬」を巧みに利用した作品なのだ。そのパリの雰囲気を出すのに最適なのが、オッフェンバック風にリズムが弾んで呼応しあう、軽快で洗練された音楽。パリにある小国ポンテヴェドロの公使館に出入りするフランス人たちのアンサンブル場面のやりとりなどで、レハール独自の旋律美と粘っこさを加えながら、それはさかんにつかわれる。終幕のフレンチ・カンカンのもろな引用は、その最もわかりやすい例。
ストーリーも、原作となったコメディ『大使館付随員』を書いたのは、オッフェンバックのヒット作群の共同作詞者の一人、アンリ・メイヤックなのだ(ついでにいうと、メイヤックとアレヴィのコンビは《こうもり》の原作戯曲も書いていて、さらにビゼーの《カルメン》の作詞者でもある)。オッフェンバックを借りてこないほうが不自然なくらい。
そしてそこに、ポンテヴェドロ出身のヒロイン、ハンナが歌う東欧風で土俗的な〈ヴィリアの歌〉を挿入して対比させる。じつにうまくできている。
ハンナもダニロも(ツェータ男爵も)パリ式の生活に合わせようとしつつ、地方出身者の純朴と頑固を捨てきれない。それがヴァランシェンヌやカミーユ、カスカーダ、サン・ブリオッシュなど享楽的なパリ人の洗練されたふるまい(不倫の火遊びも含めて)と対比される。
面白いのは、せっかくのパリなのに、公使館とハンナ邸という「地方出身者の領域」に舞台を限定していること。さらに今回の眞鍋卓嗣演出はすべて公使館内に収めたので、パリの伊達男もマキシムの美女も外界から入ってくるという設定がより明確になった。ここは、パリなのにパリになりきれていない場所なのだ。
そして第二幕で、ハンナの故郷が公使館内に再現され、男を惑わす妖精ヴィリア(アダンの《ジゼル》やプッチーニの《妖精ヴィッリ》にも出てくる女妖)の歌を歌うと、故郷から飛来したように、男女の恋の妖精が出現する。
この妖精たちがハンナに手を貸して、ダニロとの恋を真面目に成就させることになる。しかも、キューピッドというのはどこの国でもいたずらものなのか、ひらひらと恋のゲームを楽しんでいたはずのカミーユとヴァランシェンヌまで、本気にさせてしまう。
ここでカミーユが歌う〈バラのつぼみが〉は、後年の《微笑みの国》の〈君はわが心のすべて〉を予感させる、情熱的な愛の歌。
これを「レハールのテノール」リヒャルト・タウバーみたいな歌手が歌えば、それは完璧な恋の魔法になるに違いない(レハールとタウバーが出会うのはもっと後の話だけれど、この歌を聴くと、レハールの音楽はタウバーに歌われることを待っていたとしか、思えなくなる)。
恋の妖精を出したのは真鍋さんの素晴らしいアイディアだが、もっと思いきって活用すればよいのにとも思った。第一幕と第二幕で二回、ハンナとダニロは二重唱でいい感じになるのに、意地が邪魔をして、あと一言が言えない。
このもどかしさが、この演出ではどちらのキャストとも、あまりうまく表現できていなかった。ふと動きが止まって見つめあい、ぷいと離れるだけではわかりにくい。主役をここで動かしたくないのなら、男女の妖精に何らかの感情表現をさせたりしてもよかったのではないか。
あと、カミーユと逢い引きしていたヴァランシェンヌが、発覚寸前でハンナに入れかわるところも唐突な印象。二人の関係にハンナも(ニェーグシュ同様に)気づいていて、それとなく注視していたとか、伏線を張ったほうがよかったのではないか。ここも、妖精に手を貸させることも可能だったのでは。
そんなこんなは感じたけれど、すれっからしが住むパリに、森と泉の土地から純情な恋の妖精が現れてドラマを動かすという設定は、作品の構造を考えるヒントとしても、とてもありがたかった。
十一月二十六日(水)そこにエベレストがあるから

紀尾井ホールで、サクソフォンの須川展也によるソロ・リサイタル。バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ三曲を一夜で吹くもの。
須川さんには九月に「音楽の友」のためにインタヴューしたさい、この三曲とリサイタルについてのお話をうかがっていた。コロナ禍の合間に録音したCDも聴かせてもらった。
パルティータだけ三曲で一夜というのは、ヴァイオリンのイブラギモヴァが二〇一一年十一月にハクジュホールで演奏したのを聴いたことがある。
そのときの可変日記に、「第一番のあとに休憩を入れ、第二番と第三番を休みなしで演奏するようにした。そうして、シャコンヌの大難所を山登りの頂上のようにして前半は緊迫感を高めていき、一転して第三番は表現の余裕と幅を広げ、いわば下山中の、雄大なアンコールに」と書いている。
須川さんの設計もそれに似ている。第一番はバロック・ヴァイオリンの奏法や装飾を参考にし、第二番はよりエモーショナルに、そして休憩後の第三番はジャズ的なアドリブも交えてと、大きな山をつくる。
しかし実演で聴くと、サクソフォンでの「登山」がいかに大変な、超人的な行為なのかが、ものすごくよくわかる。肺と指の限界に挑むような行為で、原曲のヴァイオリンよりもさらに大変だろう。須川さんほどの世界的名手が、息も絶え絶えになりそうな危険をかわし、しかし途切れることなく音楽を進め、難所の連続を懸命に乗りきっていく。これはセッション録音には聞こえてこない、ライヴならではのチャレンジ。
完成度という点ではもちろんセッションが上なのだが、この偉大な挑戦、登頂の瞬間に立ち会っているという一期一会の感激は、なにものにも代えがたい。
ただ感謝。

十一月二十八日(土)西洋文明の象徴


今日から三日連続で演奏会通い。
東京文化会館で東京都交響楽団。沼尻竜典の指揮で、《タンホイザー》序曲ではおそらく今年初めての生のワーグナーの響きを聴き、ブラームスの交響曲第四番での衒いのないひたむきな演奏に好感を抱きつつ、考えさせられたのは、モーツァルトの二十番の協奏曲でソロをひいたガヴリーロフ。
奔放といってもいいほどに強烈につけられる緩急強弱のコントラスト。強打の連発の次の瞬間には、一気にダッシュして繊細な弱音へ。
これほど自己主張の激しい芸術家というものを目のあたりにするのは、コロナ禍の今年では初めてかも。疑いなく日本人からは絶対に出てこないタイプだと、日本の音楽家を聴き続けてきた今年だけに痛感する。
そして、この激烈な表現を思いどおりに現実化させる、グランドピアノという楽器のことを思う。
他の楽器でこういうことは可能だろうか。オーケストラはこれほど急激に動くことはできないだろう。音の跳躍は、ピアノが打楽器の一種である打鍵楽器だからこそ。
一個人の表現と主張を巨大に増幅し、東京文化会館の大空間に鳴りわたらせる楽器。その機構の精巧さと強靱さ、高い安定性と均質性が、それを可能にする。一人で世界と対峙することすら可能にしそうな楽器。
いろいろな意味で、西洋文明を象徴する楽器。工業化、資本主義化、帝国主義化が進む十九世紀の西洋世界で生まれるべくして生まれた、獰猛なまでの力をもつ楽器。
指の動きによって操作される鍵盤、キーボードというものが、パソコンを初めとして、現代の知的作業では欠かせぬものになっていることも思う。
都響スペシャル2020(11/28)
ワーグナー:歌劇『タンホイザー』序曲
モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466
ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 op.98
スカルラッティ : ソナタ ニ短調 K.1 L.366
モーツァルト : 幻想曲 ニ短調 K. 397
(ピアノ/アンドレイ・ガヴリーロフ)
指揮/沼尻竜典
ピアノ/アンドレイ・ガヴリーロフ
十一月二十九日(日)革命と戦争の時代

さいたま芸術劇場で鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパンによる『ベートーヴェン「運命」とハ長調ミサ曲』。
前者は一八〇八年、後者はその前年の作品。プロイセンもオーストリアも屈伏させられていた、ナポレオン絶頂期の頃の音楽。どちらも異様なまでに執拗に横溢する、怒りにも似た、煮えたぎるエネルギーに満ちた、ベートーヴェン中期の音楽。ピリオド楽器の限界を超えて噴出してくる。
ミサ曲は音楽好きのエステルハージ候ニコラウス二世の委嘱で書かれたが、粗野なまでに革新的な音楽を侯爵は理解できずに酷評し、献呈を受けることすら拒否したという。
この日は、ステージが狭く密集を避けるため、前日のオペラシティでの公演では三十三人だった編成(ソプラノのみ九人)の合唱を減らし、二十四人で歌うことを、後半開始前に鈴木雅明が告げる。そしてその前に、ハイドンがエステルハージ候の委嘱でつくったミサ曲の終曲〈アニュス・デイ〉を、三十三人のフル編成で歌う。なぜそれがハイドンではできるかというと、オーケストラの編成が弦楽合奏のみで小さいから。
これはいかにも宮廷音楽風で、エステルハージ候お気に入りだったのも納得。対照的に、その枠組みをぶち壊すように強烈な、個人の芸術としてのベートーヴェン。革命の時代、一介の士官が皇帝に成り上がる時代そのもののよう。
ところで、さいたま芸術劇場に来るのは昨年四月のBCJによるマタイ受難曲以来なので、一年七か月ぶり。ここといえば楽しみの一つが、ホール向かいにある十万石まんじゅうの店。久々に休憩時間に寄ると、なんと謝恩セールで全品二割引。大喜びで買って帰る(笑)。


十一月三十日(月)クリエイティヴな
よみうり大手町ホールで、『鈴木優人プロデュース「四季」&ケージ』。
昨日の埼玉ではオルガンをひいていた鈴木優人が、今日は読売日本交響楽団と登場。とても面白い、創造的で示唆に満ちたコンサートで、「クリエイティヴ・パートナー」という読響でのポストの意味が、わかる気がした。
ここで鈴木はプロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノを担当し、コンサートマスターの長原幸太以下弦楽器十人、打楽器二人の読響アンサンブルと共演。
曲目はヴィヴァルディの《四季》と、ケージの諸作を入れ子で演奏するという意欲的なもの。これについて、プログラム掲載の大西穣の一文が示唆に富んでいて面白い。
ヴィヴァルディ作品では「当時の習慣に倣い、鳥のさえずりや激しい嵐をはじめとする自然の題材はそれぞれ音によって表現されており、音の風景画が目指されている」
対してケージは、「テクノロジーや現代文化を自然の一つとして見出し、作品中に取り入れることを追求した」
そして「理想的な自然を描写した作曲家、音に自然を組み込んだ作曲家。時代の異なる二人の作品世界へ交互に触れれば、西洋音楽の自然観の変遷に、深く向き合えることだろう」

ステージの左半分にはさまざまな小道具が持ち込まれ、ケージが生きた二十世紀アメリカの、豊かな消費生活を送る家庭の居間が再現されている。舞台下手のこの居間でケージの《リビングルーム・ミュージック》などが演奏され、ヴィヴァルディは上手のステージで、普通の演奏会風に演奏される。
そしてたしかに、両者の「自然」の相違が面白い。外界の自然音を楽器で模倣し、音楽作品に仕立てるヴィヴァルディに対し、居間のラジオやピアノ、缶や本を楽器として用いるケージ。人に媚びない十八世紀の外界と、テクノロジーの力で人を安楽に過ごさせる二十世紀の居間との対照。
両者が最も近づいたのは、ケージの《リビングルーム・ミュージック》で缶や本を叩く音と、ヴィヴァルディの《冬》でのスタッカートで凍てつく寒さを表現した第一楽章から、屋外の氷雨と室内の暖かさを対照させた第二楽章へとつながる流れだった。
ここでヴィヴァルディが、厳しい外界と安楽な居間を共存させて、このコンサート全体を三百年前に総括しているという玄妙さが、なんとも嬉しかった。
それにしても、この自然観の変遷を考える上で重要なポイントは、モダンピアノという楽器を知らないヴィヴァルディと、モダンピアノを基本に音楽をつくっているケージ、という違いではないか。
ヴィヴァルディのオーケストラには、打楽器はない。通奏低音を担当するのは撥弦楽器のチェンバロと、擦弦楽器のチェロとコントラバス。はじいたりこすったりするが、「叩く」ことはない。
これが十八世紀後半になるとオーケストラは軍楽隊の楽器、つまり打楽器を金管とともに導入し、響きを多様化させ、幅を拡げる。その変化と、ピアノの普及と発展の時代が重なるのは暗示的。
一昨日と昨日に聴いたモーツァルト、ベートーヴェン、ワーグナー、ブラームスというドイツ・オーケストラ音楽の王道は、ピアノの発展と軌を一にする。
何でも模倣でき、暗示できる、ピアノという万能の中性楽器。オーケストラが楽器を多様化させて「自然」を取り込むとき、ピアノもそれを抽象化させて取り込む。
ケージは、そのピアノの抽象性と均質性、論理性に、飽きた人。プリペアド・ピアノを用いて、それを崩そうとする。
しかし、それでもその音楽の基本にあるのはピアノ。叩く音が基本にある。缶や本を叩いて楽器にするのも、ピアノの音を変化させたものという意味で、プリペアド・ピアノの延長にある。
ピアノのビートが音楽の基本になっていくとき、二十世紀後半のジャズやポップスは、リズム楽器としてドラムスを必要とするようになっていく。ということは……。
ここからはほとんど妄想になってまとまらないけれど、とにかく刺激し、脳を活性化してくれる、クリエイティヴなコンサートだった。これからも楽しみ。
 読売日本交響楽団のサイトから
読売日本交響楽団のサイトから撮影=青柳聡/©読響
プロデュース、指揮、チェンバロ、ピアノ:鈴木優人(指揮者/クリエイティヴ・パートナー)
独奏ヴァイオリン:長原幸太(コンサートマスター)
ヴァイオリン:小田透、川口尭史、對馬哲男、肥田与幸
ヴィオラ:鈴木康浩(ソロ・ヴィオラ)、二宮隆行
チェロ:髙木慶太、木村隆哉
コントラバス:小金丸章斗
打楽器:西久保友広、野本洋介
ケージ:私たちの春が来る
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』第1番「春」
ケージ:「ヴァイオリンと鍵盤のための6つのメロディ」から
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』第2番「夏」
(休憩)
ケージ:「リビングルーム・ミュージック」から“メロディ”
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』第3番「秋」
ケージ:クレド・イン・アス
ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集『和声と創意の試み』第4番「冬」
一柳慧:イン・メモリー・オヴ・ジョン・ケージ
十二月三日(木)今日の日のように
夜に新国立劇場で《こうもり》。
指揮者と主役の歌手たちは、来日後十四日間待機をして海外から登場。大スターはいないけれど、適材適所で好感度の高い公演。
ツェドニク演出の舞台は二〇〇六年初演の十五年選手だが、来月上演のマダウ=ディアツ演出の《トスカ》とともに、新国立劇場のレパートリーでは最も頼りになる、安心の出来。
野球にたとえれば、劣勢の四回に登板して三イニングを無得点に抑え、相手の勢いを殺いで逆転の呼び水となる、仕事の確実な中継ぎ投手みたいなプロダクション。十五年間で六回目の公演というのが、その着実な人気を物語る。
今回の五公演のうち、唯一の夜公演に行くことにした。十時終演は楽ではないが、やはりオペラは夜公演のほうが、歌手のコンディションがよくなると思う。
第二幕クライマックスのドゥイドゥ・ワルツに、心をぐっと鷲掴みにされた。
 写真は新国立劇場のサイトから
写真は新国立劇場のサイトからBrüderlein, Brüderlein und Schwesterlein
Wollen alle wir sein, stimmt mit mir ein!
Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein,
Lasst das traute Du uns schenken
Für die Ewigkeit, immer so wie heut,
Wenn wir morgen noch dran denken!
Erst ein Kuss, dann ein Du, Du, Du immerzu!
兄弟に 兄弟そして姉妹に
私たちはなりましょう いいですね!
兄弟に 兄弟そして姉妹に
親しげな「君(ドゥー)」という呼び名を贈りましょう
いつまでもずっと 今日の日のように
明日もまたそう思い続けましょう!
まずキスを 続いて君(ドゥー)を 君 君 君といつまでも!
(オペラ対訳プロジェクトのサイトから)
「まずキスを 続いて君(ドゥー)を」
シラーの『歓喜に寄す』にも似た親愛の歌は、ウィルス感染が拡大する日本、欧米の大半の歌劇場が閉鎖されている現在の世界において、しかし、ブラック・ジョークでも皮肉でもない。
人の切実な願いの歌。
かなわぬ夢であっても、求めてやまぬ願いの歌。
「いつまでもずっと今日の日のように」
永遠のものなどないと知っているからこそ、そう願う。
かつてブルーノ・ワルターは、「ベルリン人のくせに、どうしてウィーン子よりも上手に演奏できるんだ」と、ウィーン・フィルの楽員に嫉妬させたくらい、このワルツを、情感豊かに指揮してみせたという。
その演奏はこの地上から消えてしまったが、余韻はそこかしこに残っている。
ファルケを歌ったミッテルハマーは声量に乏しいのが惜しかったけれど、そのハイバリトンの歌声には、全盛期のフィッシャー=ディースカウみたいに響く、美しい瞬間があった。
一日も早い平安を。
コロナと戦うすべての医療従事者に、感謝を。
十二月四日(金)久しきワーグナー

調布市文化会館 たづくり くすのきホールにて、「わ」の会コンサートvol.6 Befreiung:解放。
指揮者の城谷正博を中心に、ワーグナーの抜粋をピアノ伴奏で歌手が歌うコンサート。今回は日本ワーグナー協会創立四十周年記念事業として、太田麻衣子の演出もつく豪華版。
曲は、友清崇のアルベリヒ、今野沙知恵、花房英里子、藤井麻美のラインの乙女による《ラインの黄金》第一場に始まり、大塚博章のヴォータン、池田香織のブリュンヒルデによる《ワルキューレ》第三幕後半が続く。後半は《タンホイザー》第三幕の抜粋が、片寄純也のタンホイザー、小林厚子のエリーザベト、大沼徹のヴォルフラム、池田香織のヴェーヌスで歌われる。合唱パートは基本的に省略だが、最後の部分だけ他の歌手や助演者が全員参加して歌った――ここで、教皇の杖が緑なしたことをあらわすためなのか、能楽用の老松が描かれた幕が背景に下りてきたのは、能楽好きとして「お願いだからそれはやめて~」と叫びたくなったが(笑)。
 写真は「オペラ・エクスプレス」のサイトから
写真は「オペラ・エクスプレス」のサイトから伴奏は二台ピアノ(木下志寿子・三澤志保)で、演出も簡素とはいえ、ひさびさに聴く歌入りのワーグナーが、耳に心地よい。池田香織と片寄純也の日本人離れした力強い声を筆頭に、二時間を楽しませてくれた。
池田と片寄、それに大沼は来年二月の二期会の《タンホイザー》公演でも同じ役を歌うので、期待がふくらむ一夜。
十二月五日(土)夜討曽我その一
昼は国立能楽堂にて、観世流の観世九皐会所属のシテ方佐久間二郎能の会「三曜会」。メインとなる能『夜討曽我』を一週間後に川崎能楽堂でもみるので、感想はそのときにあわせて。
夜はサントリーホールで、東京交響楽団の演奏会。指揮は鈴木雅明。
・モーツァルト:ピアノ協奏曲第二十一番ハ長調(ピアノ:児玉桃)
・シューベルト:交響曲第八番ハ長調《グレート》
元々は指揮者がミケーレ・マリオッティ、ピアノがロベルト・コミナーティだったが、コロナ禍による渡航制限で交代となったもの。キビキビとした演奏。
十二月六日(日)消えるもの残るもの
大学時代に在籍したサークルで、今の稼業のきっかけとなった音楽同攻会が、現役学生の人数不足のため大学の公認を取り消され、部室を退去させられるという。OBの先輩たちが現役から状況を聞く場に、短時間だけだが同席。
残念ではあるが、これは時代の流れだろう。むしろ、今までよく継続できたものだと思う。
続いて梅若能楽学院会館に行き、「梅若会トライアル公演 梅若の狂と鬼」。
・仕舞 蝉丸:土田英貴
鉄輪:梅若長左衛門
野守:山崎正道
船弁慶:角当直隆
・独吟 弱法師:梅若実
・能『葵上 古式』梅若紀彰、小田切康陽、山中が晶、大日方寛、御厨誠吾、山本則重、松田弘之、飯田清一、亀井実、林雄一郎
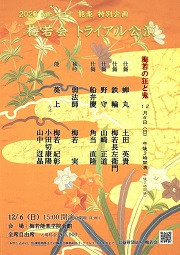
観世流の梅若家の本拠地である梅若能楽学院会館は中野坂上駅が最寄駅で、山の手通り沿いに北上したところにある。途中の大久保通りが谷底にあたり、中野坂上駅も、あるいは北の東中野駅も山の上になるので、帰路は必ず坂を登らなければならない。真夏はけっこうつらそうな地形。中央線も丸ノ内線も、中野区と杉並区では駅付近は平らという印象があるが、ここはそうではなかった。
建物は山の手通りからちょっと入ったところで、夜だとわかりにくそう。一九六一年開場で、設計は大江宏。国立能楽堂を設計したのと同じ人だが、こちらのほうがモダンで凝っている感じ。外壁はコンクリートの灰色。
堂本正樹は一九六三年二月にここで結婚式の披露宴をしたそうで、出席した三島由紀夫は入口のガラス扉を自動ドアと間違えて、おでこをぶつけたという。
これがその入口か、と思いつつ入る。
堂本はこの話を『回想 回転扉の三島由紀夫』で、二年後に三島が『憂国』を映画化したときの章で述べている。
堂本は映画の演出を担当した。映画での能舞台の使用は二人の考えという。
実際の撮影はセットだったが、直前のリハーサルは、赤坂にあった橋岡能舞台で行なった。それが梅若能楽学院会館だったらさらに感慨深かったところだが、ともあれ、三島の在世当時からそのままに現存する能楽堂は意外と少ない。ここと矢来能楽堂、あとは行ったことのない杉並能楽堂くらいだろう。
能舞台は二階で、一階は上階への階段が二つ。窓際に食堂風にテーブルがならぶ。披露宴の会食はここでやったのだろうか。窓はル・コルビジェ風に広く、棧は細め。磨いたコンクリと木材が共存した、いかにも一九六〇年前後の雰囲気。
そう大きくない空間に人が多く、写真を撮る余裕はなかった。いくつかのサイトに無人時の写真が掲載されている。

 写真は中野区公式観光サイト まるっと中野から
写真は中野区公式観光サイト まるっと中野から能舞台の見所は三百席。感染防止で席数が半分に制限されて完売、自由席というので不安だったが、中正面に座れた。
現行版と異なる原典版に従い、前場に破れ車の作り物と青女房(ツレ)が出る「古式」の小書をやっと見られた。わかりやすくはなるが、どうしても必要というものでもなく、詞章の想像力だけで充分という意見もなるほどと思う。
梅若実が地頭とあったので楽しみだったのだが、体調不良で降板。かれが地頭のときの地謡は例外なく見事なので、とても残念。独吟はテープとなる。
席が近く、二階に舞台があるせいか、足拍子の振動がどんと伝わってきた。
十二月七日(月)言葉を音にすること

東京オペラシティリサイタルホールで松平敬のバリトンリサイタル「声のひとり旅」。
日本現代音楽協会主催の音楽祭〈現音 Music of Our Time 2020〉の一環として、演奏家が企画する演奏会を公募して開催する「ペガサス・コンサート・シリーズ」の一夜。
FBフレンドでもある松平さんが、無伴奏の作品ばかり十一曲を歌うというもの。喉の負担も大きいだろうし、無伴奏歌曲では変化もつけにくいだろうから、一時間ちょっとぐらいだろうかと勝手に予想してきたら、休憩を含めてほぼ二時間という、通常の演奏会の長さ。
しかも一九四四年の早坂文雄の《うぐひす》に始まって、委嘱新曲の初演となる鈴木治行の《区区》まで、さまざまな唱法やテクニック、ときにパフォーマンスを駆使して、飽きさせないどころかワクワク楽しませるという、松平さんならではのリサイタルだった。
早坂が第二次世界大戦中にこんな実験的な曲を書いていたことにも驚かされたし、川島素晴の《月に憑かれたエチュードⅡ》は、シェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》のパロディで、その全二十一曲の歌詞を抜粋しながら、二十一種類の唱法で歌うという超絶技巧の曲。《区区》では、新国立劇場の《紫苑物語》の平太役で用いられて話題となった、ホーミー唱法の不思議な響きも登場。
言葉を音にする、響きにする、という行為のもつ、無限のアイディアの泉を味わうような一夜。
十二月九日(水)ハーモニーの推進力
サントリーホールで読売日本交響楽団の演奏会。指揮は常任指揮者のセバスティアン・ヴァイグレ。来日後十四日間の自主隔離を行なっての登場である。
三月と七月に予定されていた来日が中止となったため、じつに一年三か月ぶりの読響との共演。
・モーツァルト:ピアノ協奏曲第二十五番(独奏:岡田奏)
・ブルックナー:交響曲第六番

ヴァイグレが最も得意とするのは、ワーグナーに始まる十九世紀後半以降のドイツ音楽ではないかと感じている。
それはまさに前回の来日時、二〇一九年九月十日にサントリーホールで演奏した、ロットの交響曲を聴いたときに思ったことだ。可変日記にこう書いている。
「二月にパーヴォ指揮N響でも聴いたので、一年に二回ナマを聴けたが、演奏の印象はかなり異なるのが面白い。
簡単に言えば、パーヴォの演奏はマーラーから帰納したロットで、ヴァイグレのはワーグナー+ブラームスから演繹したロット。だから、第三楽章スケルツォは、前者ではマーラーそのもののように聴こえたのに、後者はそこまでいかず、「これをいじって、マーラーはあの音楽にしたんだな」と感じさせる。
(略)ヴァイグレの指揮は確信に満ち、作品を細部まで熟知しているように感じさせた。読響との息も合ってきた感じ。ワーグナー+ブラームス風の音楽が、語彙といい文法といい発音といい、指揮者の音楽言語と合うのだろうとも思った」
「ワーグナー+ブラームス」と書いているが、ヴァイグレの場合は特にワーグナーである。
今夜のブルックナーの交響曲も、まさしく「ワーグナーから演繹したブルックナー」だと感じた。
どこがワーグナー的なのか。
その演奏を聴きながら頭に浮かんできたのは、我が最愛の指揮者、イギリス最高のワーグナー指揮者、レジナルド・グッドオールの言葉だった。
かれは、ブリテン後期の音楽に興味がない理由をこう語っている。
「(ブリテンの音楽に欠けているのは)第一にハーモニー、基本的なハーモニーへの感覚だ。ハーモニーはそれ自身がリズムを内部に持ち、音楽を推進させるんだ」
さらに、ヴェルディに興味がない理由は、こうだ。
「ヴェルディには一番上の声部しか、メロディしかない。私にはまるで興味がもてない。《女心の歌》なんて、ほんとに節だけだ。ハーモニー的には、どうしようもない。
《トリスタン》冒頭の、低音を考えてみるがいい。最初は何の意味もない。ところがそこに和声が、ハーモニーが加わると、それはすべてを語りはじめる。何か雰囲気が、そこに生まれる。だから私は、ワーグナーが好きなんだ」
この二つの言葉は、ワーグナーの魅力を考える上で、非常に示唆に富んでいると思う。もちろん全面的に正しいとは思わない。ブリテンにはブリテンの、ヴェルディにはヴェルディ独自の魅力があると私も思う。しかし、かれらになくてワーグナーにあるもの、その魅力の本質的な急所を、たしかにグッドオールは突いているとはいえると思う。
そして、ヴァイグレのブルックナー演奏に感じたのも、まさにこれだった。グッドオールのいう「ハーモニーはそれ自身がリズムを内部に持ち、音楽を推進させる」こと。メロディやリズムよりも、ハーモニーが次の響きを導き、音楽を進行させていく。
こういう流儀、演奏法こそ、「ドイツ的演奏」の一つの流れといえるのかもしれない。そして、この方法論をワーグナーより前の、前期ロマン派や古典派などに適用しても、あまり面白い音楽にはならない気がする。
何か、大きなヒントをもらった気がする一夜。
ワーグナーにおけるハーモニーの重要性を意識する上では、四日の「わ」の会を体験したことも大きな意味があった。
ピアノ伴奏にするといっそう明確になるが、ワーグナーのオーケストラ・パートは、歌手をまったく助けようとしていない。絶対にただの伴奏にならずに、ハーモニーを構成している。歌のヒントになって補助するような声部がないところも多く、歌が独立して、ハーモニーの一部をなさないといけない。ものすごくたいへん。その点、池田と片寄は、一人で声部を構築する力がきわだっていた。
その歌の困難さは、七日に松平さんがただひとりで音程とリズムをとって音楽を形成してみせた、二十世紀後半以降の無伴奏歌曲のたいへんさの、原型になるのかもしれない。
その意味で、この三つの演奏会もまた「勝手にツィクルス」になっていた。
十二月十二日(土)二つの『夜討曾我』
神田伯山の登場と活躍で、久方ぶりに注目されつつある講談。
講釈師という商売は「冬は義士、夏はお化けで飯を食い」といわれる。冬は忠臣蔵、夏は怪談で稼ぐという意味。
十二月は討入りの時期だけに、昔は講談だけでなく、テレビでも映画やスペシャル・ドラマがならんだものだが、最近はめっきりやらない。忠臣蔵という字を読めない人も増えているという。
復讐譚は「半沢直樹」はじめ、これからもドラマの基本形の一つであり続けるだろうが、もはや忠臣蔵の物語そのものには感情移入しにくくなってしまった。昔は大河ドラマの定番の一つだったが、いまは視聴率が取りにくそうで、信長さえ出てくれば喜ばれるのとは対照的。
逆に、昭和までの日本人は、なぜあんなにも忠臣蔵が好きだったのかというほうが、いまとなると不思議でさえある。
いかなる精神構造が、あの臥薪嘗胆の仇討物語を必要としていたのか。その詮索はまたの機会として、昔はとにかくみな、仇討物語が大好きだった。
その祖型は、鎌倉時代の曽我兄弟の仇討である。さまざまなジャンルで脚色されながら愛され続け、江戸歌舞伎では、正月は必ず『寿曽我対面』などの曽我物という恒例が生まれたほどである。『助六』もそのヴァリエーションの一つだ。
歌舞伎に先行して、能でも物語のさまざまな場面を描いた曲が、室町期につくられている。現行は『調伏曾我』『小袖曾我』『夜討曾我』『禅師曾我』と四作あり、さらに廃曲も多く、『伏木曾我』『虎送』『和田酒盛』は近年復曲されており、ほかに『大磯』もあって、この物語の人気の高さがうかがえる。
このなかで演能機会が多いのは、『小袖曾我』と『夜討曾我』。前者はいよいよ仇討行に出発する曾我兄弟が母に別れを告げる話で、後者は仇討直前と直後、一人生き残った弟の五郎時致が奮戦の後に生け捕りとなる話。
門出を舞う前者は正月に向きそうで、後者は討入り話だけに、十二月に向いているのだろう。それが理由か、今月は二回みることができた。どちらも土曜日。
一回目は五日に国立能楽堂で、観世流の観世九皐会所属のシテ方佐久間二郎能の会「三曜会」。二回目は十二日に川崎能楽堂の主催公演で、同じく観世流の梅若実をシテとするもの。
日付は前後するが、二回目の川崎公演のほうがシンプルな形だったので、こちらから話をする。
川崎能楽堂に行くのは初めて。ここに行けることも、今回のチケットを購入した動機の一つだった。川崎市が建てた能楽堂で、JR川崎駅の東口、つまりミューザ川崎の反対側にある。
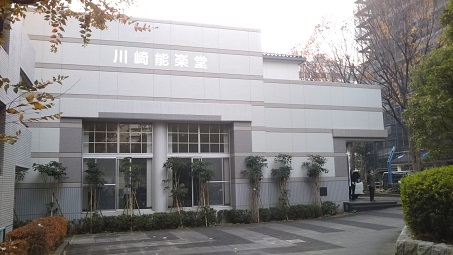
サンスクエア川崎というURのマンションの敷地の一角にある、こじんまりした建物。一九八六年開場で、席数は百四十八とかなり小さい。
そういえば、この近くに九龍城の不気味な内部を再現したゲームセンター「電脳九龍城」があったはずと検索してみたら、昨年十一月に閉店していた。残念。
あきらめて川崎能楽堂に入る。一九八六年開場。ロビーはほんのわずかしかなく、内装も公立の学校のような感じ。バブルに向かい始めた昭和六十年代の成金感覚と、それと対照的な五十年代の地味さとがせめぎあい、渦を巻いてしまい、何か居心地の悪さを呼んでいるような。
ホールに入ると、能舞台上部の屋根はなく、四隅の柱も下部の一メートルほどがあるのみで、橋懸も短い。席数も百四十八と少ないので、本番よりも稽古能などが主な目的なのだろう。
 川崎市文化財団のサイトから
川崎市文化財団のサイトから困ったのは、見所の座席が子ども向けで狭小なこと。隣席が身体の大きなご老人だったので、とりわけコロナ禍ではかなりのストレスとなる。何事も経験してみなければわからないが、次に来る機会はあまりなさそう。
気をとりなおして、公演開始。
・狂言『清水』三宅近成
・能『夜討曽我』梅若実

『夜討曾我』は現世の人間しか出てこない現在能で、出演者全員が面をかけない。シテ方が八人、狂言方が一人で、ワキがまったく出ないのが珍しい。一時間ほどの短い能。
通常は、シテが曽我兄弟の弟の五郎時致、ツレは兄の十郎祐成、従者の団三郎と鬼王、五郎と戦う古屋五郎と御所五郎丸。ほかに立衆の縄取が二人。ただし今回は、兄の十郎がシテになっている。
前場は、富士の巻狩での曽我兄弟の宿所。夜襲での仇討を決意した兄弟が、母のもとに形見の品を届けるために故郷へ帰れと、従者の団三郎と鬼王(この二人も兄弟)に命じる。
死ぬ覚悟でついてきたのに、ここで生きて帰ることはできないと、従者二人はその場で刺し違えて死のうとする。かれらを説得して形見を渡し、涙で見送る兄弟。ここで前場は終わり。
狂言方のアイが使番として登場し、兄弟を狼藉者として討ち取るよう、武者たちに告げる。
後場は、仇討を遂げた後の五郎の戦いの場面。十郎は出てこない。松明を掲げた五郎が登場し、乱戦ではぐれた兄が、先に討ち取られたことを嘆く。討手の古屋五郎と戦い、二つに切り捨てる。
これを見た御所五郎丸は一計を案じ、女物の薄衣をかぶって待ち伏せる。現れた五郎は疲れはて、五郎丸を女と誤認して見逃す。五郎丸は後ろからつかみかかり、一回転しながらも五郎を押さえこんで、生け捕りにする。
シテが兄の十郎になっているのは、演じるのが梅若家の当主、梅若実だから。近年は足腰に問題があるらしく、シテをつとめる機会が少ない。六日も休演だったので不安だったが、今日は無事に登場してくれた。杖をつき、歩くのはやはり大変そう。しかし舞台に入った後は葛桶に座っているだけなので問題はない。さすがの存在感。後場は、ツレとなった五郎役の角当直隆による斬組み。
先に書いたように、一週間前の五日にも、佐久間二郎能の会「三曜会」で『夜討曽我』を見ていた。

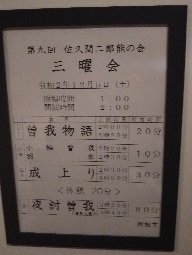
佐久間二郎の会は、若さを活かした、わかりやすい能が中心になっている。ここではシテの五郎を佐久間が演じ、十郎は永島充。敏捷な佐久間と沈着冷静な永島、キャラクターの対照がいい。
こちらを後にしたのは、「十番斬」という小書きがついて、大がかりになっているため。アイと後場の間に、曽我兄弟が討手十人を斬る場が挿入されている。これは『十番斬』という廃曲からとったもの(幸若舞の同名の曲を舞台化して挿入したもの、というほうが近いのかも)で、観世流にしかない小書という。
斬組み(チャンバラ)が派手になるだけでなく、ドラマとしても、こちらのほうが面白い。
仇討後、駆けつけた討手十人(曽我物語に従って、全員に名がある)と戦う曽我兄弟。二人は背中合わせに互いを守りあい、次々と倒すが、やがて舞台と橋懸に分断され、五郎は敵を追って去る。
十郎一人となったところに、新田忠常役のワキ方、福王和幸が登場。本来はワキのいない能にスペシャルゲストという感じで、とてもカッコいい役になっている。ハンサムな福王はぴったり。
疲弊した十郎は新田に刀を折られる。勝負はついたと、とどめを刺さずに去ろうとする新田。その袖に十郎はすがりつき、首をとれという。烏帽子を首に見立て、新田は刀で打ち落とすと小脇に抱えて退場。十郎も切戸口から出る。
ここから通常の後場につながる。登場した五郎の「十郎殿十郎殿、何とてお返事はなきぞ、十郎殿…」という呼びかけが、十郎の最期を見たばかりだけに、いっそう哀れに感じられる。
かれを追って現れた古屋五郎を演じるのは、くしくも一週間後に五郎を演じる角当直隆。金色の側次(そばつぎ)を着た姿が堂々として、いかにも強敵という感じなので、緊迫感が高まる。
その古屋が斬られたところに、御所五郎丸役の長山耕三が登場。
囃子に合わせて女物の薄衣をかぶるさいの、気合の入った所作もタイミングも見事に決まっていて、御所の強い覚悟が伝わってくる。その覚悟が示されることにより、本来は卑怯な策略なのに、そうせねば倒せない相手だからなのだと、納得させられてしまう。
能の斬組みは、「幽玄」の芸術性に比べて低く見られがちだが、時代劇のチャンバラとも歌舞伎の立回りとも違う、独自の特別な魅力をもっている。
それは、一つ一つの所作に込められた気魄がもたらす、高い緊張感。武士というのは本当にこういう雰囲気だったのかもしれないと、想わせてくれるのだ。
全体の構成もよかった。初めに仕舞で『小袖曽我』出陣の男舞を佐久間と永島が舞い、能につなげる。
野村萬斎がシテの和泉流狂言の『成上り』は、刀が竹筒にすり替えられることが『夜討曽我』のアイの「大藤内」での刀と竹筒の取り違えに通じ、また最後に太郎冠者がすっぱに転がされる動きが、能の最後の五郎丸と五郎の格闘の動きに通じる。
こういうふうに、同じ要素のコミカルな面とシリアスな面が裏表に重なると、心地よい深さが生じる。狂言と能の関係はこのようであってほしい。
第九回 佐久間二郎能の会「三曜会」
・おはなし「曽我物語」立川四楼
・仕舞『小袖曽我』佐久間二郎・永島充
・仕舞『羽衣』観世喜之
・狂言『成上り』野村萬斎
・能『夜討曽我 十番斬 大藤内』佐久間二郎
十二月十三日(日)倭寇と航海の能

矢来能楽堂にて、観世九皐会の十二月定例会の第二部を見る。
・仕舞『車僧』小島英明
・仕舞『柏崎 道行』永島忠侈
・仕舞『猩々』佐久間二郎
・能『唐船』桑田貴志
例年は能二番と狂言一番と仕舞というのが定例会の基本の構成だが、いまは防疫のために二部に分け、その間に消毒を行なっている。その第二部。
能の『唐船』が目当て。中世日本の倭寇を題材としているのが特徴である。年長と年少の子方がそれぞれ二人ずつ、四人も必要なので、いつでもやれる能ではないらしい。
舞台は九州箱崎。同地の武士何某(ワキ:舘田善博)は、十三年前に捕らえた中国の祖慶官人(シテ:桑田貴志)に牛飼いをさせている。
そこへ唐船に乗った祖慶官人の息子二人が到着。父を救うべく、身代金として宝物を持ってきたのである。武士何某は承諾したところに、祖慶官人が二人の子を連れて、牛飼いから帰ってくる。日本でも子供をつくっていたのだ。
中国の子と再会を喜ぶ祖慶官人。故国に帰る船に乗り込もうとするが、武士何某は、日本の子二人は牛飼いをつがせるために行かせないという。離れたくないと取りつく四人の子に囲まれた祖慶官人は、途方に暮れて座り込んでしまう。
 写真は銕仙会のサイトから。
写真は銕仙会のサイトから。そのさまを見た武士何某は態度を和らげ、全員での帰国を許可する。乗り込んだ船の上で、喜んで舞う祖慶官人(狭い船の作り物の中で、その場だけで舞うのが面白い)。
最後は帆が張られて、出帆したことを示す。五人が船に乗り合わせて、七福神の宝船を想わせる。
 写真は銕仙会のサイトから。
写真は銕仙会のサイトから。帆と柱のついた唐風の船の作り物や、牛飼いをあらわす紅白の紐など、舞台装置も華やかな芝居仕立ての能。
世阿弥の息子十郎元雅が、永享二(一四三〇)年に吉野の天河大辨財天社に詣でて、所願成就を願って尉面(じょうのおもて)を寄進したさいに、この能を舞って奉納したたという説がある。
 天河大辨財天社のサイトにある尉面
天河大辨財天社のサイトにある尉面尉面の裏に、元雅の寄進の言葉とともに「唐船」と墨書されていることがその根拠なのだが、しかしこの能を舞ったと断言できる証拠はないらしい。
将軍義教に疎まれ、苦境にあった元雅が、南朝の本拠地、吉野の神社に詣でていることは、後世の人間にとっては歴史のロマンだ。南朝方と近かったのではないかと考える人もいる。
証明はできないにしても、山深い吉野と航海の能という対照の面白さに、元雅の心境を結びつけていくことは、歴史小説的には愉しい想像。
十二月十五日(火)地域文化の花と幹
このところ愛聴しているCD。ヘンゲルブロック指揮のバルタザール=ノイマン合唱団による『ヨーロッパのクリスマス』。ヨーロッパ各国のクリスマス・キャロルを十六の言語で歌ったものだ。
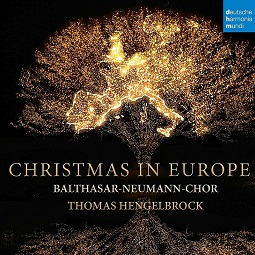
この合唱団をナマで聴いたのは二〇一八年十二月八日、ヘンゲルブロックとともにNHK交響楽団の定期に登場したときだった。
バッハ・プログラムで、管弦楽組曲第四番、シェーンベルク編曲の前奏曲とフーガ《聖アン》、合唱が参加してマニフィカト(クリスマス用挿入曲つき)。
さらに無伴奏合唱によるアンコールで、クリスマス・オラトリオの第五十九曲と、十五世紀フランスの聖歌〈久しく待ちにし、主よとく来たりて〉(ヒッレルード編)。
すべてが何らかの意味でクリスマスに関わっているという凝ったプログラムで、とりわけ印象的だったのが、最後の聖歌だった。バッハとシェーンベルク、「ドイツ音楽」の歴史に画期をなした二人の作曲家を並べたプロを、その最後に十五世紀のラテン語聖歌に帰すことで、ヨーロッパ音楽五百年の歴史をクリスマスをポイントに俯瞰していた。
そしてこのときは、アマチュアだというバルタザール=ノイマン合唱団のうまさにも驚かされた。
このクリスマス・アルバムは、そのラテン語の〈久しく待ちにし、主よとく来たりて〉を始まりにおく。これだけで自分にはとても嬉しいが、これは始まり。
そこからフランス、北欧、東欧とロシア、イベリア、オランダとイギリス、イタリアと各地域をめぐり、最後にブルックナーによるラテン語、レーガーによるドイツ語聖歌で終わる。
二十三曲を十六の言語で、各地域のローカル色を唱法や伴奏にあらわして、その変化していくさまが、アニメーションのように美しく、心地よい。
多彩な地域文化の花と枝の、その幹と根としてのクリスマスを歌って、今年の八月に録音されたアルバム。分断と閉鎖のなかにあるヨーロッパの、希望のちいさな灯火。ジャケットも素敵。
「土にはやすき 人にあれやと」
十二月十六日(水)音楽よ、俺を
ミューザ川崎で東京交響楽団の演奏会。指揮は正指揮者就任が決定している原田慶太楼。
・藤倉大:海
・ブリテン:歌劇「ピーター・グライムズ」より、四つの海の間奏曲
・ニールセン:序曲「ヘリオス」
・エルガー:エニグマ変奏曲


音にしっかりした肉体感、躍動感があるのが原田の魅力。二十世紀のオーケストラ作品には不可欠なものだが、五十代以上の日本人指揮者でこのセンスをもっている人は少ない。若い世代ならでは楽しみな要素。一方で脂肪がつきすぎることはなく、響きはあくまでしなやか。
十一か月ぶり、ほぼ一年ぶりのミューザ川崎。その音響のよさを、久々だけにあらためて実感する。澄んだハーモニーが美しく鳴りわたる。やはり関東随一のホール。ここを本拠地とする東響は幸せだと思う。そういえば、来シーズンの読売日本交響楽団は、いつも使っているみなとみらいが長期改修に入るため、ミューザ川崎で四回演奏する。できるだけ聴いてみたい。
ところで今夜は、四月にノット指揮で行なわれる予定だった演奏会の振替公演。ブリテンとニールセンは、ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》の代わりに入ったもの。
プログラムの曲目解説の担当者にその変更の痕跡が示されていて、新規の二曲は奥田佳道さんが書かれているが、藤倉作品は作曲家本人、そしてエルガーは、亡きオヤマダアツシさんの遺稿となっている。
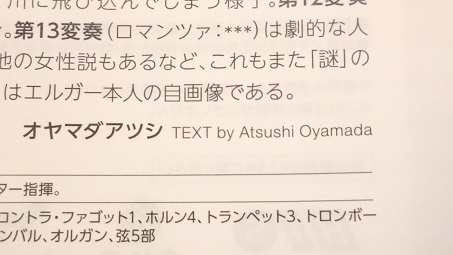
イギリス音楽をとりわけ愛されたオヤマダさんだから当然といえば当然で、ということは、いつかウォルトンが演奏される機会にも、オヤマダさんの解説を読めるんでしょうね、などと隣席の山田治生さんと休憩時にしゃべる。
そうしてエニグマ変奏曲が始まったのだが、ここには〈ニムロド〉があることを、その響きが始まるまで、すっかり忘れていた。
いうまでもなく、亡き人の追悼に演奏されることもある曲。
いや、まいった。
オヤマダさんを喪ったその年の暮に、その人が解説を書いたイギリス音楽を、よりによってニムロドを、聞かされるなんて。ミューザは、オヤマダさんのお家にも近かったはずだ。
コロナ禍第一波のさなかだったため、われわれはその死をあとで知り、葬儀にも出ていない。きちんとお別れをいうことができていない。
このニムロドは、その代わりにいま響いているような気がしてならない──演奏者も関係者もあずかり知らない、自分だけの勝手な思い込みだけれども。
──いや、自分にはこんな大仰な音楽は似合わないから、いいよ。
オヤマダさんなら、そう言って微笑むかもしれないとも思う。途中からは、天井を見上げているしかなかった。
さようなら。
音楽よ、俺を泣かすな。
十二月十八日(金)邯鄲

国立能楽堂の定例公演。《月間特集 所縁の能・狂言‐勧進能‐》。各流派・各家がさまざまな勧進能で演じた曲をとりあけるもの。今回は「寛延勧進能」。
・狂言『悪坊(あくぼう)』大藏彌太郎(大蔵流)
・能『邯鄲(かんたん) 盤渉(ばんしき)』観世銕之丞(観世流)
十二月十九日(土)
夜は片山杜秀さんと、朝日カルチャーセンター新宿教室のオンライン講座「昭和音楽史」。
十二月二十日(日)

池袋の東京芸術劇場で、セバスティアン・指揮読売日本交響楽団によるベートーヴェンの《合唱》。
十二月二十一日(月)新しい生活様式
午前中はオンラインにて尾高忠明さんにインタヴュー。来年三月十一日の埼玉会館でのN響との演奏会について。
昼過ぎにミュージックバードに行き、片山杜秀さんと恒例の年末特番を収録。
ミュージックバードの番組は、四月下旬から宅録で行なっていたので、スタジオのマイクの前でしゃべるのは八か月ぶり。片山さんと対面でお会いするのも昨年十二月二十八日の朝日カルチャーセンター新宿教室の講座以来だから、ほぼ一年ぶり。
しかし片山さんとは朝カルのオンライン講座で一昨日二時間半もお話したばかりだし、五月と八月にも同じ講座でご一緒しているので、長くお会いしていないという感じがまったくない。
宅録といいオンラインといい、新しい生活様式がすんなり混じり込んでいる。
しかし物心両面の変化の大きさは、ありようはまるで違うが、九年前の東日本大震災とならぶもの。番組で一年をふり返りながら、あらためて実感する。
十二月二十二日(火)花は根に帰るなり

昼はトッパンホールで、川口成彦のフォルテピアノによるランチタイム・コンサート。ソレールに始まり、アルベニスの擬古典風組曲、そしてグラナドスが近代風にアレンジしたスカルラッティのソナタ集。美しい響き。
夕方五時からは国立能楽堂で観世流の久習會。
・能『和布刈(めかり)』荒木亮
・狂言『塗附(ぬりつけ)』三宅右近
・能『春栄(しゅんねい)』荒木亮


『春栄』のシテは宮内美樹がつとめるはずだったが、癌のために十一月二十日に急逝。師の荒木が代役となって『和布刈』と合わせて演じた。
二番ともワキ方(福王和幸)の仕舞がある、珍しい能。
能の後に地謡が歌う附祝言が型どおりの縁起のいい詞ではなく、追悼の意を込めた『忠度』の「花は根に帰るなり。わが跡弔いて賜び給へ。木陰を旅の宿とせば。花こそ主なりけれ」だったのは、強く印象に残った。
――花こそ主なりけれ。
十二月二十三日(水)
サントリーホールで、庄司紗矢香とヴィキングル・オラフソンによるデュオ・リサイタル。素晴らしい音楽。評を日経新聞に書く。
十二月二十五日(金)夢の記憶

大野和士と東京都交響楽団による《くるみ割り人形》全曲。素晴らしかった。
都響はこの曲を二年前にもミンコフスキとミューザ川崎で演奏している。あのときの「踊る音楽」とは異なる、硬質で雄弁、凄まじく気合の入った、ダイナミックなシンフォニック・バレエ。
自分はチャイコフスキーの交響曲にまったく興味がなく、オペラとバレエにこそその天才を感じる人間だが、情景を描写するそのオーケストレーションの素晴らしさ、そうしてモダンさが、鮮明に聴きとれる。ストラヴィンスキーやマーラーは、こういうチャイコフスキーがいてこそ、出てくるのだろうと思う。
クリスマスのバレエ公演としては定番だが、オーケストラ曲としてこれだけの水準で聴くことができる機会は、そうない。十四型の都響の鳴りも輝かしい。有機的音響体としての底力をみせつける。こういう高度な「オーケストラ芸術」はなんとかして守っていかなければならないと、あらためて感じる。
隣席(といっても間隔はあけてある。田んぼの向こうの「お隣」という感じ)の柴田克彦さんと「大野さんはやはり劇場の人ですねえ」と、うなずきあう。まさしく交響的なドラマ。客席の照明を明るいままにしてあるので、プログラムに寺西基之さんが書かれた場面説明を読みながら聴くと、作曲者と演奏者の語りくちのうまさがよくわかる。
事前録音の新国立劇場合唱団による女声合唱も、人がいないまま響くことで幻想性がまして、むしろこれで正解なのではないかと思ったり(笑)。もちろん、録音と実演をきっちり合せられる、大野の精確なテンポ感覚があればこそだが。
都響がコロナ禍で第九を避けたゆえに実現した、息をのむ名演。去年の十二月にはゲルギエフのあの《マゼッパ》を聴いたんだった、と思いだしたり。
最後のところ、大野がどう解釈して指揮していたのかはわからないが、自分には、さーっと朝の光と風が入ってきて目が覚めて、お菓子の国が夢のなかに去っていくように思えた。
一場の夢。
ちょうど一週間前に国立能楽堂でみた『邯鄲』の、いつみても見事な、夢からの目覚めの場面を連想する。
すべてが夢だったと気づく虚しさと、しかしその記憶は消えることなく自分の胸に残るだろうという充足感の、不思議な混淆。
音楽の実演というものも、まさにそれだよな、と思う。
十二月三十一日(木)今年最後の八日間
仕事納めなど夢のまた夢、今年もまた年越し原稿を食べながら暮れようとしている。仕事があるだけましなのだとは理解しつつ、まさしく貧乏暇なし。
そんな生活でも、「今年最後」となる日々の行事が徐々に増えた。
二十四日は今年最後の音楽之友社での仕事で、朝から「stereo」誌のためにスピーカー九種を聴きくらべ。

試聴用に持参したヘンゲルブロックの「ヨーロッパのクリスマス」から、〈久しく待ちにし、主よとく来たりて〉を聴く。時間の関係で最初の数分だけに抑えないといけないのだが、いいスピーカーだと、私もお相手のオーディオ評論家の井上千岳さんも編集さんも、誰も止めようといわずにこの曲は最後まで聴いてしまう。それくらいにいい曲と編曲と歌。しかし原稿〆切が一月三日なのはつらい(笑)。
夜は今年最後のサントリーホールで、BCJの《メサイア》。なんとアンコールに鈴木優人編曲の〈久しく待ちにし、主よとく来たりて〉が歌われ、この日は朝から晩までこの歌づくし。

会場でサントリーホールの人とお話ししたら、年末年始のコンサートが中止になったため、今年はゆっくり休めてしまうとのこと。お互い複雑な笑いをうかべるしかない。
二十五日は今年最後のインタヴュー仕事。エラス・カサドというのが嬉しい。しかしコロナ禍のためPC越しのインタヴュー。限られた時間にもかかわらず誠実に、饒舌に語ってくれて大助かり。その日の夜は今年最後の東京文化会館で、すでに触れた大野と都響の《くるみ割り人形》。
今年はメサイア、くるみ割り、第九とクラシックの年越し御三家が聴けた。これでフンパーディンクの《ヘンゼルとグレーテル》があれば四天王だったが、それはまたいつかの機会に。
二十六日は今年最後の国立能楽堂。狂言『米市』では山本東次郎一家が賑やかに、能『鞍馬天狗 天狗揃』では宝生流の稚児五人と天狗八人が舞台に並び、華やかに年の締め。

二十七日は今年最後のコンサートへ。オペラシティでBCJの第九。コロナ禍の一年で、おそらく最も実演を聴いたのが鈴木二代とBCJだったから、これで締められるのは嬉しい偶然。三十二人の合唱が澄んだハーモニーで、星雲の彼方に届けとばかりに壮大に轟いた。

少し前に「音楽の友」特集のために昨年十二月から今年十一月までに通った演奏会などを集計したところ、クラシック八十四回、能楽十七回、その他二で計百三回。前年度は二百二十八と可変日記に書いているので、半分以下に減った。もちろんコロナ禍のため。
二十八日は今年最後の水泳。
二十九日は今年最後の番組収録。自宅でニューディスク・ナビのナレーション部分を録る。宅録はすっかりニューノーマルになった。
三十日は今年最後のミュージックバード行き。番組用のCDを届ける。年下の人たちが「正ちゃん帽」という呼び方を知らないのに、ジェネレーションギャップを実感(笑)。でも、ボンボンつきのニット帽って、ほかに呼称がないと思うのだが。「ケムール人みたいなの」といおうとして、それはもっと通じないだろうと思ってやめる。昭和は遠くなりにけり。ケムール人は二〇二〇年の未来から一九六六年の現代に来たのだったが…。
今年最後の買い物がドイツから到着。十月末にはイギリスからの航空便が五日で届くまで輸送状況も回復していたが、今回は十八日かかったから、ふたたび悪化しているのだろう。中身は、スイスのザンクト・ガレンにあるバッハ財団のアンサンブルによるクリスマス・オラトリオと第九、そしてベルンでのヴェンツァーゴ指揮の《カルメン》。
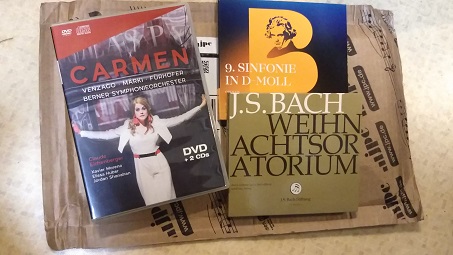
《カルメン》はDVDとCDが同梱されていることに惹かれた。CDはニューディスク・ナビで放送できる。近年は、ミュージックバードで使えるCDかどうかを購入時のポイントに考えるクセがついている(笑)。そして、ビゼーのオリジナル・スコアを用いているというのも大きな魅力。ヴェリズモ風に直截な現行版よりも凝ったスコアで、コスキー演出版をROHのライヴビューイングでみたことがあるが(面白かった)、CDはこれが初めてではないか。
その夜は今年最後の原稿提出を、「レコード芸術」編集者あてに。
そしてむかえた今日。年賀状はとても無理なので越年決定。
新日本フィルのジルヴェスター・コンサートの指揮者がPCR検査で陽性になったために演奏会中止。楽しみにしていたお客さんは残念だろうし、指揮者や楽員、すべての関係者の無念と落胆はいかばかりのものか、想像にかたくない。
今年は奇跡的にオーケストラ内のクラスターが起きずにすんだが、今後はクラシックのコンサートも、関係者の感染による影響が増大することは避けられないだろう。この問題もまた越年。東京の陽性者が今日はついに千三百人を超すという。来年は感染拡大防止のため、ふたたび開催自粛を要請される可能性もある。
クラシック界も不安はつきないが、闇を呪うよりも、灯を点してくれる人たちを紹介するのが私の仕事。
今年一年もお世話になりました。すべての人に、とりわけ、コロナ禍と戦うすべての医療関係者に感謝。
皆様よいお年をお迎えください。来年こそ。
Homeへ