二〇二一年
一月五日(火)渋谷で実演初め


二〇二一年の実演初め。オーチャードホールで、マキシム・パスカルの指揮で二期会の《サムソンとデリラ》のゲネプロと初日本番。歌手は別キャスト。感想は十七日に後述。
ゲネと本番のあいだに時間があったので、一年以上ぶりに渋谷駅の周囲をうろつく。再開発で大きく変わりつつある。東横線の旧地上ホームの脇の眼鏡模様が再現され、渋谷ストリームという高層ビルへの通路には、かつての線路が二本埋めこまれていた。自分も子どものころから何度この上を通ったかわからないが、そこを歩くのは新鮮。位置を移した新しい銀座線ホームは、鯨に呑みこまれたピノキオがゼペットじいさんに再会する場面を思い出す。



一月六日(水)小菅優のベートーヴェン
すみだトリフォニーで小菅優&新日本フィルのベートーヴェン演奏会。指揮は角田鋼亮。《エグモント》序曲、ピアノ協奏曲第一番、第五番《皇帝》。
小菅の充実ぶりを示す、気魄のこもった、間然するところのない、素晴らしいピアノ。
一月八日(金)コロナ禍の演奏会
昨日の緊急事態宣言を受けて、一~二月のクラシックの演奏会、オペラの公演予定について、気がついた範囲での宣言前後の変更を、順不同でおぼえがき的にまとめ。
・N響、読響、都響、東響、日本フィル、東京シティフィル、以上六つの在京オケの一月の演奏会は予定通り開催。
・新日本フィルも予定通り。なお一月十五、十六日の演奏会は既発表のとおり、指揮者が上岡敏之から佐渡裕に変更。
・東フィルは、一月十一日の演奏会は予定通り。二十二日と二十四日の定期は、休憩を入れずに予定の全プログラムを演奏し、二十二日の夜公演の終演時間は午後八時。
・なお東響は、二月十一日のジェルメッティが来日不可能。代役は調整中。
・新国立劇場
《トスカ》は予定通りのキャストとスタッフで上演。カッレガーリ(指揮)、イゾットン(トスカ)、メーリ(カヴァラドッシ)、ソラーリ(スカルピア)は日本へ入国し、リハーサル参加に備えて十四日間の待機期間中。
《フィガロの結婚』は入国制限の変更により、出演者を以下のとおり変更して上演。伯爵夫人:ガンベローニ→大隅智佳子。フィガロ:モラーチェ→ソラーリ(トスカのスカルピア役)
また、それぞれの夜公演(二月三日と九日)については、開演時間の変更を検討中。
・王子ホール
一月二十七日の公演につき、ホルンのトゥーニス・ファン・デァ・ズヴァールトが来日不可能となったため、ファウストとメルニコフの出演により、曲目を変更。二月二日のイッサーリスは来日不可能のため公演中止。
・オペラシティコンサートホール
一月十七日の《エリアス》につき、歌手が既発表の変更に加えて、イムラーが加耒徹に交代。
・トッパンホール
一月中の全公演を、夜八時終演となるようにする。二十一日のメルニコフについても、これを前提に調整中。
・東京二期会
二月十七日からの《タンホイザー》指揮者を、コーバーからヴァイグレに変更。ヴァイグレは三か月日本に滞在。
一月十日(日)翁とバッハ
能楽初め。矢来能楽堂で観世九皐会の一月定例会の第一部。
・能『翁』永島充 小島英明 山本則孝 山本泰太郎 竹市学 幸正昭 後藤嘉津幸 船戸昭弘 柿原弘和
・狂言『成上り』 山本東次郎 山本凜太郎 山本則俊
能『翁』は翁の永島充、千歳の小島英明、三番三の山本泰太郎の中堅三人が、いずれもあたりを祓うような気合の入った動きで年の初めの神事にふさわしく、小気味がよかった。
小鼓の頭の侍烏帽子が打っているうちにずり下がってきてしまい、後見が後ろから直すがすぐゆるんでしまう。最後に地謡の観世喜正が退場時に一気に紐を締めなおして解決。
『成上り』は十二月五日に和泉流の野村萬斎でみたばかりだが、最後に縄ですっぱを縛ろうとするドタバタがある和泉流に対し、大蔵流はそれがなくて短い。
山本東次郎の太郎冠者のもつ太刀を、寝ているあいだに杖にすり替えるすっぱの役は弟の山本則俊。ほんの短い場面なのに両者の呼吸が絶妙で楽しい。前にみたときもこのコンビだったから、これは兄弟でしかやりたくないものなのかも。
夜は王子ホールで、ヴァイオリンの篠崎史紀率いるMAROカンパニー。総勢十三人でバッハの協奏曲を六曲。老練、中堅、俊英、三世代が入れ換わりでソロをとっていく。楽しく頼もしい。
一月十一日(月)ニューイヤー
池袋の東京芸術劇場で、熊倉優指揮の日本フィルによるニューイヤー・コンサート。
一月十二日(火)インバル
東京文化会館でインバル指揮東京都交響楽団による演奏会。トリスタンの前奏曲と愛の死、ブルックナーの交響曲第三番の初稿。
一月十三日(水)ジュスタン・テイラー
王子ホールでジュスタン・テイラーのゴルトベルク変奏曲。変奏ごとにパウゼをおいて、思いきって意欲的な表現。アグレッシブに若さがきらめく。アンコールのフランス作品がとても魅力的で、これはいつかまとめて聴いてみたいもの。
一月十五日(金)いつのまにか短くて

国立能楽堂の定例公演。
・狂言『松囃子(まつばやし)』石田幸雄(和泉流)
・能『弱法師(よろぼし)』朝倉俊樹(宝生流)
『弱法師』を事前に告知することなく短縮するという事件があった。
元々の予定では、狂言と休憩もあわせて十八時半開演で二十時四十五分終演予定と、チラシに書かれていた。それが緊急事態宣言後、休憩をなくして二十時に終演させるという発表があった。
不思議だったのは、現在の休憩時間は二十五分なので、それを削っても二十時二十分までかかるはずだということ。どうやって解決するのかなと前から気になっていた。当日掲示された時間割を見ると、八十分かかるはずの『弱法師』が六十分(実際にはさらに短く、五十~五十五分だった)になっていた。
初心者の私はあれ? もうここまで進んだがこんなに速い展開だったっけと不審に思っただけだったが、会場におられたFBフレンドは詳しい方なので、詞章のうちの「クリ」「サシ」「クセ」の三か所を省いたことにすぐに気がつき、終演後に猛抗議をされたという。
四分の一ものカットをして二十時に終らせることに必然性があるかどうかの議論はここではおくが(発売済の公演は変更しなくてもいいという例外がせっかく認められているのだから、このような短縮は必要ないと自分は思うが)、それよりも問題はカットをすること、どのようなカットをするかの告知を、事前にしなかったこと。知らない人はこういう能なのかと思ってしまうことになる。
気にかかるのは、二月十九日の定例公演でも、十八時三十分開演を十七時三十分に早めると発表していること。
緊急事態宣言の期間延長もあると見越してのことなのだろうが、これも前のチラシの終演予定が「午後九時十五分頃」とあったのが、現在サイトに掲載された修正後のチラシでは「午後八時頃」となっていて、約十五分短くなっている。
大槻文藏の『砧』はとても楽しみにしているものなので、変なカットはせず、休憩を短めにするくらいにしてほしい。
いやな予感がするのは、抗議を受けたせいなのか、十九日になってサイトに掲載されたお知らせのなかに「感染予防のため、通常とは異なる上演の形態で演じられる場合がございます」という文言があること。
この一言で「だから何でもありだっていってあるじゃん」とならないことを、強く願う。
一月十六日(土)ゲルシュタイン
紀尾井ホールでゲルシュタインのピアノ・リサイタルを聴く。
一月十七日(日)国民音楽の人びと

オペラシティで、鈴木雅明指揮のBCJによるメンデルスゾーンのオラトリオ《エリアス》。
この作品については、二〇一六年九月十一日に大井剛史指揮日本フィル他のサントリーホール公演を聴いたときの感想を可変日記に書いた。「劇的な書法の充実、漲る生命力において、疑いなくメンデルスゾーンの代表作」ということを再確認。「奇跡」のスペクタクルを音だけで表現し、想像させようとする、その意欲。
今回は八型のピリオド楽器、合唱三十四人という編成だったので、十四型のモダン楽器のオーケストラと約二百人のアマチュア合唱団だった四年前とは、見た目の印象は大違い。
一八四六年イギリスでの初演の合唱団は二百七十一人だったというから、ヘンデルが確立した、近代市民社会における「国民音楽としてのオラトリオ」というスタイルには、日本フィル版が近かったかもしれない。
しかし響きの純度が高いことで、メンデルスゾーンの音楽は今回のほうがよくわかった。音が濁らないので、広がり豊かに雄大に響くという点では、むしろ三十四人のプロの合唱のほうが上だった。
このひと月でBCJを聴くのは三回目となる。十二月二十四日にサントリーホールで《メサイア》、二十七日にオペラシティで「第九」、そしてこの《エリアス》。奇しくも「国民音楽としてのオラトリオ」の歴史を追う形になった。
その確立者であるヘンデル、そのエッセンスを交響曲という、自らが不滅の地位に昇らしめたジャンルに取り込んで、さらに一歩進めた「国民音楽としての交響曲」を生みだしてのけたベートーヴェン。そして、ヘンデルがイギリスで達成したことをドイツで、より発達したオーケストラを用いて再現しようとしたメンデルスゾーン。
三曲を続けて聴けたのが面白く、その間の一月五日にオーチャードホールで、もったいぶらず、軽快俊敏な演奏でサン=サーンスの音楽の新たな魅力を引き出したマキシム・パスカルの指揮で二期会の《サムソンとデリラ》を、GPと本番で二回見られたのも、ありがたかった。
《サムソンとデリラ》も《エリアス》同様に旧約聖書が題材で、やはり奇跡を音で描こうとする。ここに出てくる神はユダヤ教の、嫉妬深く短気で独善的で不寛容な畏怖すべき存在。人間に対してとてもわかりやすい形で干渉してくる。そこにあるのはキリスト教の愛ではなく契約。その荒々しさ。
善悪と正邪、敵味方の区別が画然としていて、曖昧さや迷いを許さず、まったく容赦がない。
英雄サムソンを色仕掛けでたぶらかしてその力を奪うデリラは、邪神ダゴンを信じる異教徒であり、イスラエル人を憎悪し、復讐を企む敵である。サムソンに対しては愛情どころか憐憫の情も、最初から最後まで、かけらすらない。
その意味で、敵将ホロフェルネスに近づいて酒で眠らせ、首を落としてイスラエルを救う寡婦ユディトとは、敵味方が変わっただけの、鏡のような存在の女。首の代わりに髪を切る点だけが違うが、それは捕らえたサムソンに、さらなる屈辱を与えるため。
観客の共感も同情も、いっさい寄せられることを拒む、全身これ悪という存在(聖書のデリラは金でつられて恋人を裏切るだけの、もっと小者のようだが、オペラでは、男性という存在そのものを憎んでいるような凄味がある)。
そして、物語のキモとなるサムソンを誘惑する場面が、三幕構成の中央の第二幕に置かれていることや、初めに女の仲間の男が出てきて、女と対話するところなどが、《パルジファル》の第二幕に似ているのが面白かった。
これはゲネプロのデリラ役が池田香織で、先月彼女の見事なワーグナー歌唱を聴いたばかりだったというのもある。デリラ役での妖艶な歌声も素晴らしかったが、自分のなかではそれが、クンドリーの姿と二重写しになっていた。
しかし、いうまでもなくデリラとクンドリーはまるで違う。なによりも、クンドリーは味方になったり敵になったりする。時に応じて毒にも薬にもなる他人という存在の捉えがたさを、二重人格という形で体現していて、ただひたすらに邪悪でしかないデリラとは違う。
一面的なデリラはいかにも古代的で、複雑なクンドリーはより近代的、ともいえる。
しかしそれよりも考えてしまうのは、ワーグナーがクンドリーを、イエスの受難を笑ったがゆえに呪われたユダヤ人だとしていること。
時として味方、時として敵とは、ワーグナーにとっては同時代のドイツのユダヤ人そのもののことではないか。
ユダヤ人でありながらキリスト教に改宗してドイツの国土と文化を愛し、旧約(ユダヤ教の聖典)の世界と新約(キリスト教独自の聖典)の世界を重ね、最後にエリアスとイエスを重ねた――過去を救うために現代を回心させ、現代を救うために過去を回心させた、という歌詞によってエリアスは歴史化され、永遠化されて、イエスに重なる――オラトリオを書いてみせるメンデルスゾーンは、その典型なのではないか。
あまりに新奇なために忘れられていた「第九」を蘇演、真価を理解させたのはドレスデン時代のワーグナーだとされているが、これはワーグナー一流の自己宣伝で、じつはその前にメンデルスゾーンもライプツィヒ(ワーグナーの故郷)で「第九」を蘇演していたという。
仲間にして敵。油断ならぬライバル。
その象徴であるクンドリーも、みなもろともに最後に救済される舞台清祓祝典劇《パルジファル》(ワーグナーにとっての国民音楽)の初演の指揮を、ユダヤ人ヘルマン・レヴィにゆだねる、ワーグナーの複雑。
というわけで今度は《パルジファル》に浸りたくて、その実演に行きたくてしょうがない。「東京・春・音楽祭」のイースターでの上演が、どうか実現しますように!
一月十九日(火)読響の首席指揮者たち

サントリーホールで読売日本交響楽団の演奏会。指揮は常任指揮者のセバスティアン・ヴァイグレ。
R・シュトラウス:交響詩《マクベス》
ハルトマン:葬送協奏曲(ヴァイオリン:成田達輝)
ヒンデミット:交響曲《画家マティス》
コロナ禍の中、二か月連続でほとんどの演奏会を振りつづけるという、字義通りの「常任指揮者」としての活動で、オーケストラとも聴衆とも篤い信頼関係が醸成されつつあるヴァイグレ。
その最も得意とする近代ドイツ音楽、それもナチスに運命を翻弄された三人の作曲家を集めるという好プログラムで、楽しみにしていたもの。
腰の据わった、明解で実体感のある、立体的な響き。とりわけナチス時代の2曲、ハルトマンとヒンデミットが充実した演奏だった。
国内亡命を決意したハルトマンの、自らの心を埋葬するかのような、やり場のない憤懣がふつふつとたぎる前者。独奏ヴァイオリンの成田達輝が、何かにとりつかれたような、といいたくなる高い集中力で電撃的にひききった。
後者はフルトヴェングラーの「ヒンデミット事件」のきっかけになったことで知られる曲。オペラの音楽を転用、編曲した三つの楽章には、『イーゼンハイムの祭壇画』からとられた副題がつけられている。金管や打楽器を含めて、有機的音響体としてのバランス、一体感が素晴らしい。指揮者とオーケストラの見事な協同作業。
ドイツ的な堅固さに加えて、金管や打楽器には心地よい軽捷さがあって、それが音楽に動感や高低の落差をあたえていた。このあたりは隣席の朝日新聞の吉田純子さんが喝破されたとおり、カンブルラン時代の余韻の好作用だと思う。そこにはたしかに、メシアンの「アッシジ」の響きを思い出させる瞬間があった。

そのカンブルランの新譜がドイツから到着。現在首席指揮者をつとめるハンブルク交響楽団が自主制作したもの。メゾのカトリーナ・モリソンを独唱に、ベリオの《フォークソング》、モンサルバーチェの《五つの黒人の歌》、ファリャの《恋は魔術師》。公開の演奏活動ができない昨年十一月に、ライスハレでセッション録音したもの。到着まで日数がかかるかと思ったら、以外に速く発送から八日で着いてくれた。
まだ少し聴いただけだが、ドイツの放送オケとも読響とも異なる、太めの輪郭の響きがするのが面白い。四月予定の読響への再登場が無事に実現することを願うばかり。
ところで、読響の演奏会は十九時に始まって、終演は二十一時近く。すでに販売中の公演は緊急事態宣言下の営業時間短縮要請の例外となるという政府の通達にしたがって、無理な短縮を主催者もホールもしないのはありがたいかぎり。
これは公演の主催者よりも親会社や、会場を貸すホール側の意向に左右されるようで、サントリーホールや東京文化会館の演奏会は当初発表どおりの開催時刻だが、ホールや団体によっては開演時間を早めたり、休憩をなくしたり、曲を減らしたりしている。
一月二十一日(木)メルニコフ

トッパンホールでメルニコフのピアノ・リサイタル。フォルテピアノとモダンピアノ、三台を作品の時代で使いわける素晴らしい趣向。
一月二十二日(金)バッティストーニ
サントリーホールでバッティストーニ指揮の東京フィルの演奏会。日経新聞に評を書く。
一月二十四日(日)四つの序曲
十四時から東京芸術劇場で飯森範親指揮東京ニューシティ管弦楽団、十八時からミューザ川崎で下野竜也指揮東響をはしごで聴く。
前者はモーストリークラシックに評を書く。後者は前半がベルクのヴァイオリン協奏曲、後半がベートーヴェンの《フィデリオ》絡みの序曲四曲をいっぺんに演奏するという、下野ならではの選曲が愉しい。ミューザの音響ならベルクも細部まで鮮明に響いて気持ちよし。
一月二十六日(火)デュオⅠ
一月二十七日(水)デュオⅡ

二夜続けて王子ホールでイザベル・ファウストとメルニコフのリサイタル。線は細いが美しい。
一月三十日(土)景清、復讐の仮託
国立能楽堂特別公演。
・能『誓願寺(せいがんじ)』金剛永謹(金剛流)
・狂言『節分(せつぶん)』井上松次郎(和泉流)
・能『大仏供養(だいぶつくよう)』観世喜正(観世流)
主に見たかったのは景清物の『大仏供養』。二〇一九年八月の観世会荒磯能で野村昌司のシテで見たのが初見で、今日は二回目。
そのときの可変日記を引用する。
「直面で演じるチャンバラもの。悪七兵衛景清が主人公。主君の平家が滅亡した後、再建された南都東大寺大仏殿の落慶法要に列席する源頼朝を暗殺しようとする話。
前場は母に別れを告げる場面、後場は春日神社の神職に変装して、掃き清めながら頼朝に近づくが、狩衣の下に着込んだ鎧を見破られて失敗、討手一人を切り倒し、後日を期して逃走する。
能屈指の名作『景清』の前日談だが、あのような深みはない、単純な武勇譚」
後半は多数の源氏方を相手にした大チャンバラにもできそうなのだが、一人を斬るだけで拍子抜けみたいにあっさりしているのが特徴の能。景清(シテ:観世喜正)が掃きながら頼朝(子方:観世和歌)に近づいていって、直前で臣下(ワキ:安田登)に止められる、その一瞬の緊迫こそが見どころ。喜正は動きにキレがあって、さすがにうまい。
それにしても景清は不思議なキャラクターで、平家滅亡後の活動と生涯がいろいろと語られるわりには、軸となる物語がなく、断片的なエピソードばかりなのだ。江戸期の文楽や歌舞伎では一本の戯曲にまとめられるが、中世にその原型らしきものはない。
この『大仏供養』も『景清』とは結びつかない。『景清』で効果的に謡われる「麒麟も老いぬれば駑馬に劣るが如くなり」という詞が、まだ壮年期の物語のはずの『大仏供養』にも使われるあたり、『大仏供養』は『景清』を意識して後世に書かれたのではないかと感じるが、それ以上にはつながってこない。
そもそも、頼朝が東大寺を訪れたときに暗殺未遂事件が起きた記録はないという。しかし完全な創作とも思いにくい。自分はなんとなく、能と同時代の室町期の事件をヒントに、前時代の豪傑景清に仮託したのではないかと思っている。
それは能(猿楽)が隆盛を迎え、さかんにつくられていた世阿弥の壮年期、永享元(一四二九)年九月のこと。六代将軍足利義教が南都を訪れ、東大寺正倉院で名香蘭奢待を切り取った。
ところがその直前、楠木五郎左衛門尉光正なる僧形の者が奈良に潜伏、義教襲撃を企てたかどで幕吏に捕縛されるという事件が起きた。
京に連行のうえ、見物人が蝟集する六条河原で斬首されたが、そのさいに遺偈一首と辞世の和歌三首を書き、その態度が素敵だと評判になったと、伏見宮貞成親王が書き記している。
この楠木五郎左衛門尉が南朝の忠臣楠木一族の本当の末裔なのかどうかははっきりしないらしいが、一般の人は当然、南朝の遺臣が足利将軍に復讐しようとしたと考えただろう。
といって、おおっぴらに南朝方を賛美するような能はつくれないので、前時代の話にしたのではないか。景清という謎の多いヒーローは、そうしたさまざまな話の仮託先となることで、つくりあげられたのではないか。
一月三十一日(日)悲しみの静
国立能楽堂にて、東京能楽囃子科協議会主催の別会能。
・能『乱 置壺 双ノ舞』観世清和、片山九郎右衛門 福王和幸 松田弘之、観世新九郎、亀井忠雄、小寺佐七
・連調『出端』三島元太郎、金春惣右衛門
・一管『鳥手」中谷明
・舞囃子『二人静』野村四郎、梅若万三郎 小野寺竜一、大倉源次郎、安福光雄
・一調『土車』岡久広 柿原崇志
・狂言『末広』山本則俊、山本則重、山本則秀 熊本俊太郎、大村華由、柿原光博、梶谷英樹
・舞囃子『砧』観世銕之丞 寺井久八郎幸正昭、亀井実
・能『龍虎』宝生和英、金剛龍謹 森常好、舘田善博、梅村昌功 山本泰太郎、藤田貴寛、鵜澤洋太郎、佃良勝、桜井均
別会能、つまり特別公演をうたうだけあって、人間国宝や宗家、若宗家などが集う豪華なメンバー。
デュオがテーマらしく、『乱』では観世清和と片山九郎右衛門、連調『出端』では太鼓の三島元太郎と金春惣右衛門、舞囃子『二人静』では野村四郎と梅若万三郎、そして文字どおり龍虎が相搏つ能『龍虎』では、宝生和英と金剛龍謹が異流共演した。
強く印象に残ったのは舞囃子の『二人静』。面と装束をつけず、紋服と袴のままで長老二人が舞い謡うものだが、残された女の深い悲しみが、静かに舞台に満ちていった。
二月二日(火)三十八年前のあの壁

小田急線黒川駅のまん前にある読響の練習所で、セバスティアン・ヴァイグレにインタヴュー。
これからの二週間ほどは、「レコード芸術」や「音楽の友」から依頼されたインタヴュー仕事がいくつか。対面もあればオンラインのZoomもあって、入国禁止直前の一月三日までに来日したアーティストとホール関係者から話を聞く。ヴァイグレは十一月下旬から三か月日本にいることになるという。
少し早めに入って、二期会の《タンホイザー》のオーケストラ・リハーサルを一時間ほど聴かせてもらった。
聴きながら突然頭に浮かんだのが、ヴァイグレはホルン奏者としてベルリン国立歌劇場に入団して、八〇年代初めの来日公演で初めて日本に来た、と前に語っていたこと。
自分が《タンホイザー》を生まれて初めてナマで見たのは一九八二年だったかの、ベルリン国立歌劇場来日公演の《タンホイザー》だった。
ひょっとしたらヴァイグレはあのとき参加していたのだろうかと思い、インタヴューでたずねてみると、八三年が初来日で、たしかにスイトナーの指揮で《タンホイザー》を吹いたという。
どうやら私の記憶違いで、八三年が正解。それはともかく、それから三十八年後にその人の指揮で《タンホイザー》を聴くというのは、時間が螺旋を描きながら戻ってきた感じで、愉しい。

レコ芸の編集長、浜中充さんのツイッターから
しかし、その旧東独時代の話をしはじめたときのヴァイグレの目と声に宿った陰惨の影は、すごいものだった。
その一瞬、自分が一度だけ訪れた東ベルリンの、あの独特の白けた、乾いた空気がよみがえった気がした。
くしくもそれも八三年。五月に横浜で《タンホイザー》をみる数か月前の観光旅行のときだった。住民たちには越えることが不可能な国境が、目に見える灰色の壁として、立ちふさがっている町。
当時はまだブランデンブルク門の下の壁が東側にはなく(あるいは低くて)、そこから向こうが見えた。見えるのにくぐることのできない、異界への門。その数年後に警備兵が門を走り抜けて西に亡命する事件が起きて、東側にも高い壁ができ、見通せなくなったと聞く。
私権が厳しく制限され、レコードなどほとんど手に入らないあの警察国家に、その崩壊など予想もできぬまま暮らしていた人が、目の前にいる。
そして目に見える壁の崩壊から三十二年後、ウィルスという目に見えぬ壁に隔てられた世界。
二期会の《タンホイザー》は、いろいろなことを考えながら見ることになりそう。インタヴューは五月下旬発売の六月号に掲載予定。
二月三日(水)ドラマとディスタンス
新国立劇場で《トスカ》。指揮者と主役三人は入国制限直前に来日、待機期間をへて無事に登場。
再演を重ねてきたマダウ=ディアツ演出は空間の広がりがあって、特に第一幕最後のミサの場面にナポリ王妃マリア・カロリーナが登場する場面が毎回楽しみなのだが、今回は防疫のために合唱がディスタンスをとったため、視覚的にも聴覚的にも焦点が定まらず、盛りあがりを欠いた。理解できる措置とはいえ残念。
二月六日(土)大人の義経

観世能楽堂で日本能楽会の東京公演。この会は重要無形文化財「能楽」の技能保持者として文化庁の総合認定を受けた能楽師を構成員とする一般社団法人。
つまりは人間国宝やそれに準ずる能楽師ばかりが出てくるという重鎮の会。
いくつもの舞囃子や仕舞、連吟や一調に続いて、狂言と能。
・狂言『箕被』野村萬 能村晶人
・能『船弁慶 白波之伝』浅見真州(野村四郎の代演)、豊嶋彌左衛門、粟谷明生 福王茂十郎、村瀬慧、村瀬提(矢野昌平の代演) 山本泰太郎 藤田次郎、飯田清一、柿原弘和、梶谷英樹 後見:武田孝史(浅見真州の代役) 地頭:本田光洋
『船弁慶』はシテ方の異流共演で、観世流の浅見真州が前シテの静、金剛流の豊嶋彌左衛門が後シテの平知盛、喜多流の粟谷明生が義経というもの。そして地謡は本田光洋を地頭に金春流のシテ方が担当している。
前シテは日本能楽会会長の野村四郎の予定だったが、都合により浅見が代演。主後見の浅見がシテに回ったので宝生流の武田孝史に交代。しかしこれでシテ方五流がすべて舞台にいることになった。
もちろん私のような素人には、異流共演によってどんな面白さや問題が生じているのかはわからない。
通常は子方がやる義経を、大の大人の粟谷明生がやるというのが面白かった。子方が足りないときにままあることだそうだが、静役のシテにとっては、恋慕の相手が子方では感情移入しにくいという難点を避けることができる。そこで一度見たいと思っていた。この配役をおそらく自分で決めた四郎が予定通り静を演じていたら、どんな感じだったのだろう。しかし前場はともかく、後場は子方のほうが貴人という雰囲気が出る。粟谷もなんとなくやりにくそうだった。
いちばん楽しみにしていたのは後場の豊嶋彌左衛門の知盛。波を滑るように動き、水を払うように足が動く。金剛流は所作に歌舞伎的な豪快さとケレンがあって、見ていて楽しい。
二月八日(月)ハルモニア・ムンディ達
六週間滞日中のイザベル・ファウストに、三重協奏曲(三重県の曲にあらず)のディスクについてなどを、レコード芸術のために対面でインタヴュー。
年末にはエラス・カサドにもインタヴューできた(日本にいたがZoom)ので、セッションに参加した指揮者とソリストの一人から話をうかがえたのは立体的で愉快。
サンプル盤を一足先に聴かせてもらったが、期待を裏切らぬ見事な出来。鮮度の高い演奏の活力にくわえて、ピリオド楽器だからこそ実現した、適切なバランスで透明度の高い響きが素晴らしい。
この録音に参加しているメルニコフが先月二十一日にトッパンホールで行なったチェンバロからコンサートグランドまで四台の鍵盤楽器を用いた演奏会での、フォルテピアノによる《さすらい人幻想曲》の鮮烈な音楽にも通じるもの。
自分はこの曲、モダンピアノだと濁ってうるさいだけで、さっぱり好きになれなかったのだが、フォルテピアノの音響だと、まさに目からウロコが落ちるように曲本来の魅力が鮮明に現前した。同様に三重協奏曲(三重県の曲にあらず)もモダン楽器の強大な響きで聴くとあまり面白くない曲なのに、ピリオドだとワクワクさせられる。
少なくとも十九世紀前半までは、作曲者が耳にしていた楽器の響きは、曲そのものと不可分の関連性をもっていると痛感させられる、実演とディスク。
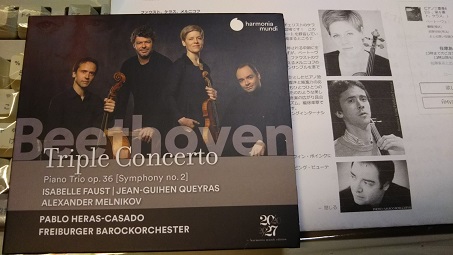
ところでCDの下にあるのは、インタヴューの資料にHMVのサイトからプリントアウトした、大公トリオの紹介文。これを目にしたファウスト、ケラスの若さに「十五歳の少年みたいだわ!」と大喜び。この紙をわざわざスマホで撮影していた。自分には目の前のファウストのほうが、よほど少女のような純粋な感性をもっているように思えたが(笑)。
彼女にもエラス・カサドにも、そして二人の話の端々にうかがえるハルモニア・ムンディというレーベルにも、心地よい茶目っ気が感じられる。そのユーモア精神は、つきることのない好奇心と鋭敏な感受性と、表現への意欲のあらわれ。先細りするレコード業界を照らす「良心のともしび」のように思えて、まことに温かく頼もしい。
二月十日(水)フィガロの呼吸


昨日今日と二日続けて《フィガロの結婚》をみる。といっても九日は新国立劇場でのフル編成版、十日は王子ホールでモーツァルト・シンガーズ・ジャパンのピアノ伴奏による二時間強の抜粋版と、サイズはかなり違う。
正直に書くが、どちらがよりモーツァルトの天才を感じさせたかといえば、圧倒的に後者だった。
前者は、指揮者が一生懸命に振れば振るほど音楽の間が詰まってしまい、硬直した、平板なアンサンブルになっていった。モーツァルトの音楽、とりわけ《フィガロ》の音楽の、その難しさと恐ろしさを、逆説的に痛感するしかなかった。
対して後者には指揮者がいない。ピアノを後方に置いて、歌手たちは前で演技する。
重唱のタイミングを合わせるには互いの歌をよく聞き、そして息を合わせ、リズムの弾みを利用するほかない。
面白いことに、そうなるとだからこそ音楽は自然に呼吸し、心地よく跳ねる。音楽が、自然に円を描いて廻る。
そのなかから、前日は他の音楽の中に埋もれたまま流れ去ってしまった、モーツァルトにしか書けない、悪魔的に美しく温かいフレーズが、遠心力でふわっと浮きでてきて、こちらの心を鷲掴みにする。そして、あっという間に後ろ姿を見せて消える。その天才。
一年前の《コジ・ファン・トゥッテ》に続いて、山口佳代のピアノは、たった一人でこの作品のオーケストラを暗示する、絶妙に音楽的なものだった(しかも今年は美声まで披露)。
二人のダンサーが助演して、その音の動きをドラマとともに視覚的に拡げて見せたのも、単調になることを防ぐ、うまい工夫だった。
歌う人数が多くなる場面では横一列になるのだが、そのときの配列によって、モーツァルトの音楽の動きが、はっきりと目に見える。
指揮者なしで、互いを聴くだけでアンサンブルをつくらなければならないことが、モーツァルトの書法を透かし絵のように見せてくれる、その面白さ。
そしてそのなかから、座長的存在の宮本益光が歌うアルマヴィーヴァ伯爵の孤立のドラマが、はっきりと見えてくる。
味方と思っていたマルツェリーナ一派も、自分たちの都合でついていただけ。
ロッシーニの《セビリアの理髪師》の当初の題名が「アルマヴィーヴァ」だったというのとは少し違う意味で、この作品もまた「アルマヴィーヴァ」。
この二公演の合間の十日昼には、朝日カルチャーセンターの新宿教室でブルーノ・ワルターと協奏曲の話をした。
弾き振りによるモーツァルトの協奏曲のオーケストラとピアノの一体感。《皇帝》でのギーゼキングとの無縁といってもいいほどのズレ。そしてブラームスの一番で、精神的に不安定なホロヴィッツのピアノを一緒に呼吸をさせて支え、圧倒的なクライマックスへとピアニストとオーケストラと聴衆を連れてゆく、その見事さ。
優れたオペラ指揮者は、優れた協奏曲指揮者でもある。
こういう音楽の呼吸が大好きだからこそ自分は音楽を聴きはじめ、ずっと聴いてきて、これからもたぶん聴きつづけ、一緒に息をしていく。

その幸福を指揮者なしの《フィガロの結婚》が味わわせてくれた。そこから見えるのは、自分が求めるのがある種の室内楽的快感、合奏の快感だということ。
そして自分が好きな指揮者とは、指揮者なしではコントロールできないような大規模の音楽の場合でも、基盤となる呼吸の一貫性をあたえ、室内楽的快感をもたらしてくれる人だということ(誤解されがちだが、トスカニーニはその頂点にいる芸術家だと自分は思っている)。
モーツァルト・シンガーズ・ジャパンは、去年二月の《コジ・ファン・トゥッテ》も素晴らしく愉しいものだった。小屋芝居的な感覚が、大劇場では味わいにくい魅力を明確にしてくれた。
そしてあのときは、翌月に新国立劇場の中劇場で、新国立劇場オペラ研修所の研修公演で《フィガロの結婚》をみられるのを、楽しみにしていたのだった。いうまでもなく、そういう、親密さを維持できる空間のほうが、モーツァルトの魅力を感じやすいからだ。ところがコロナ禍で中止になってしまった。
その新国立劇場オペラ研修所の公演、今年の演目はチマローザの《悩める劇場支配人》。これも中劇場の大きさが活きそうな演目なので楽しみ。
ついでに、自分が三月に楽しみにしているものを書くと、その前の五日と六日には国立劇場の小劇場で、面白そうな公演がある。「詩歌をうたい、奏でる ―中世と現代―」と題して、両日とも前半は『梁塵秘抄』などの今様や白拍子、乱舞、乱拍子を復元。
後半は現代音楽で、五日はケージ作曲の《RENGA(連歌)》(一九七五‐七六)、六日は大岡信の『ベルリン連詩Ⅱ』に川島素晴など三人が音楽をつけた新作初演で、独唱はFBフレンドでもある松平敬さん。
つまり、日本中世の歌や舞の再現と、現代の視点による連歌の再創造の組み合わせ。能楽と時代を同じくする文化。五日は行けないが、六日はなんとしても行くつもり。
あと二十一日には紀尾井ホールで、オーケストラ・ニッポニカによる「1964年前後・東京オリンピックの時代」。
・古関裕而:オリンピックマーチ(一九六三)管弦楽原典版
・入野義朗:交響曲第二番(一九六四)
・三善晃:管弦楽のための協奏曲(一九六四)
・團伊玖磨:交響曲第四番(一九六五)
これだけまとめてナマで聴ける機会は少ないのでこれも楽しみ。
渡航禁止措置と緊急事態宣言の影響で三月の公演はかなりの変更がありそうだが、これらはどうか実現しますように。
二月十二日(金)N響の東欧プロ
東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は熊倉優で、スメタナ、シマノフスキ、ドヴォルザークの東欧プロ。
シマノフスキのヴァイオリン協奏曲第一番の独奏イザベル・ファウストは、甘美にして怜悧な、期待通りの美しさ。熊倉は全体の造型力、構成力など未成熟なところがあったけれど、一九九二年生まれだからまだまだこれから。コロナ禍でのこの経験は今後に生きてくるはず。
二月十三日(土)ムーティのテノール

東京文化会館小ホールで、フランチェスコ・メーリのテノール・リサイタル。六百五十席の空間(満員)で、絶頂期にある世界トップクラスの歌手の歌声を聴ける幸せ。純度の高いまっすぐな響きの快感、高い知性と見事なコントロール。
歌曲から始めて、後半にオペラ・アリア、そしておなじみの名歌をならべた十曲ものアンコール(四十五分以上あったと思う。レオンカヴァッロの〈マッティナータ〉ではピアノの弾き語りまで披露)と、次第に熱量を高め、より自由で開放的なスタイルへともっていく、全体の設計と展開の見事さ。
曲の構成も巧みで、即興性も交えつつ絶対にフォルムが崩れない。《ルイザ・ミラー》や《愛の妙薬》《椿姫》のアリアなんて、まあお見事なものだった。この知的なコントロール能力こそ、ムーティが絶大な信頼を寄せ、メーリもそれに応え続ける、原動力にちがいない。
トスカニーニと、かれが最も信頼したテノール、アウレリアーノ・ペルティレとの幸福な関係を連想する。余計な響きの贅肉がついておらず、音程にブレがないというのも、指揮者にとっては大きな恵みだろう。
《トスカ》の二つのアリアは、新国立劇場のオペラ公演でも聴いたばかりだったが、ちょっと表現に締まりのない指揮者のもとでは聴けなかった、細かな動きと音色のニュアンスの変化を加えていて、ああ、本当はこういうふうにフレーズをとりたかったのね、と納得できるものだった。もちろん、ホールがより適切な大きさということもあるだろうが、ムーティやトスカニーニなら喜んで許すだろう、という動きだった。
ピアノの浅野菜生子もメーリの歌に鋭敏に反応して、見事な共演だった。
嬉しかったのはレハールの《ほほえみの国》の〈君はわが心のすべて〉をイタリア語で朗々と歌ってくれたこと。
この歌はレハール最高のヒット・ナンバーといってよく、早くから各国語に訳されて歌われてきた。帰宅後、この歌の創唱者であるリヒャルト・タウバーが一九四六年にレハール指揮のベロミュンスター管と共演した演奏会のライヴCDを引っ張りだし、思わず聴く。

ヒトラーに厚遇されたレハールと、ユダヤ人としてドイツを逐われ、イギリスにいたタウバー。九年ぶり、そして翌々年に亡くなる二人の生涯最後の共演がこの演奏会。トリを飾るのはもちろん〈君はわが心のすべて〉。
しかしなぜかここでタウバーは、英語訳詞で歌いはじめて、続いてドイツ語、フランス語と言葉を変えていく。
言語を超え、恩讐を超え、ということか。メーリのイタリア語版を聴いたら、これが聴きたくてたまらなくなった。
二月十四日(日)ふる雪の色
渋谷のセルリアンタワー能楽堂で金剛流の定期能。
・狂言『鐘の音』茂山逸平、茂山あきら、茂山千五郎
・能『雪』豊嶋彌左衛門(シテ) 殿田謙吉(ワキ) 松田弘之(笛)、曽和正博(小鼓)、國川純(大鼓)
能『雪』は五流のうち金剛流にしかないという珍しい曲。小規模だが美しい。旅の僧が摂津国野田で降雪に足止めされていると、雪の精が女の姿で現れる。
雪女的な恐ろしい存在ではなく、融けて消えてしまうはかなさと、それでも消えぬ煩悩の愚かしさ、すなわち人間の妄執を象徴する雪。
「土に落ち身は消えて、古事のみを思ひ草、仏の縁を結べかし」
「古事」は「ふること」と詠んで、昔のことと雪が降ることをかけている。
もうなんといっても、豊嶋彌左衛門の謡いの美しさに聞きほれる。セルリアンタワー能楽堂は二百一席と小さくて、しかもコロナ禍で半分しか客を入れていないため、じつによく響く。
その声の艶やかさ、色っぽさとやわらかさの素晴らしさ。
こういう「男の色気」というのは、壮年を過ぎた老境にいたってこそ、よく獲得できるもののような気がする。
面が微笑んでいるように見えたのも、豊嶋の芸なのだろう。
老い木の花、老い木の彩り、老い木の微笑み。
昨夜の四十歳のテノールと今夕の八十一歳のシテ。洋と和、壮と老、それぞれの美を二日続けて堪能できる幸福。
二月十七日(水)《タンホイザー》
二期会の《タンホイザー》。昨日のゲネプロに続けて本番を見る。日経新聞に評を書く。
二月十八日(木)めぐろの日本フィル
午後は新橋でミュージック・ペンクラブの音楽賞選定会議。コロナ禍の年ならではの選択になったと思う。
夜はめぐろパーシモンホールで日本フィルの特別演奏会。東横線都立大学駅から北に山を登った位置にあるこの目黒区のホールには、特別の思い入れがある。
以前もここに書いたが、ここにはかつて東京都立大学があった。自分は小学生の頃、家のある緑が丘から深沢の学校までバス通学をするのに、この大学の塀沿いにある二つのバス停を使って、毎日乗り換えをしていた。
いろいろな思い出があるので、地縁のない人にはめんどくさいだろうこのホールに、行く機会があればできるだけ利用し、周囲をうろつく。

今回も早めに行き、大井町線の緑が丘駅(殺風景な駅舎に建て替えられていた…)から昔の自宅(塀の一部だけが残っていて、懐かしかった)の前を通り、緑が丘交番の前からバス通学路を歩いて、都立大学駅に向かう。バスのルートは変更され、本数も少ないが、途中のバス停の位置は昔のまま。思いのほか、周囲の景色も変わっていない。

駅付近で早めの夕飯をとり、坂道を登って十八時からのコンサートに向かう。都立大学跡地の北東角の交差点の「つ久し」という和菓子屋は五十年前のままに残っているが、あとは大きく変化。


めぐろパーシモンホールは二〇〇二年開場、千二百席と手頃な大きさで、椅子の背もたれがバネ仕込みのリクライニングになっていたり、ぜいたくなつくり。客席の傾斜が強めなので舞台が近く、木質の内装も落ち着きがある。
これまでは二期会のヘンデルやカニサレスのギターだったので、反響板を設置した状態は今回初めて見聞したが、見た目も音も品がいい。


さて曲はオール・ベートーヴェンで、指揮は高関健。
・バレエ音楽《プロメテウスの創造物》終曲
・ピアノ協奏曲第三番(独奏藤田真央)
・交響曲第六番《田園》
前半は藤田真央のピアノの素晴らしさに感激。柔軟な身体そのままの繊細なタッチが生みだす色彩の変化、しかしひ弱さとは無縁の、敏捷に跳躍する弾力。とにかく音楽が新鮮で、ピアノという楽器の音を聴く歓びをもたらす。
アンコールにひいた、モーツァルトのピアノ・ソナタ第九番の第二楽章も、なんとも優美で素敵な音楽。
今月と翌月にかれのリサイタルを二回聴く予定で、モーツァルトのソナタがあることもあり、とても楽しみになった。メインにリヒャルト・シュトラウスのピアノ・ソナタをすえたリサイタルなど、この演奏力がなければ成り立たないだろう(笑)。
後半の《田園》もとてもいい演奏。眼鏡をとった高関さんの、衒いのない誠実な指揮が、曲のよさと生命力を自然に紡ぎだす。編成は十四型と再会直後よりも大きくなってきたが、木管がきれいに浮き出て、バランスが心地よい。上手側に置いた第二ヴァイオリンとヴィオラの内声部をしっかりと響かせることで、響きの構造と動きが視覚化されて効果的。
《田園》で終わる構成、能楽風に言えば「田園留め」の構成を、珍しくも日本フィルは三月五、六日の定期でもやる。
指揮はカーチュン・ウォン、ショスタコーヴィチがドレスデン空襲の惨禍と内心の苦悩を反映させて書いた弦楽四重奏曲第八番の室内交響曲版に始まり、リヒャルト・シュトラウスが敗戦直後に書いたオーボエ協奏曲(独奏:杉原由希子)につなげて、そして《田園》。
東京大空襲と東日本大震災の時期にふさわしい、鎮魂と再生のプログラム。今度は《田園》がどんなふうに響くのか、これも楽しみにしている。
二月十九日(金)『砧』の夫婦愛
国立能楽堂の定例公演。
・狂言『塗附(ぬりつけ)』髙澤祐介(和泉流)
・能『砧(きぬた)』大槻文藏(観世流)
『砧』の大槻文藏のシテと、梅若実を地頭とする地謡が素晴らしかった。
こういう演能にたまに出くわしてしまうので、能楽堂通いがやめられない。年に何回あるかどうかの、たぶん一生忘れられない『砧』。
梅若実が地頭となるときの地謡は、他とはまるで違う。高音が秀麗なまでに美しく響いて高空へと飛翔、息が途切れそうになった瞬間にジェットコースターか急流下りのように一気に流れ落ち、鐘のような、澄みきった残響となる。よどみない絶妙な呼吸の緩急もじつに音楽的。
しかもその技巧や美音が、ただそれ自身のために存在するのではなく、詞章の響きを明快に伝え、能のドラマそのものを実感させることと、完璧に結びついているのが凄い。
ただ声に聞きほれているだけで、詞の中身が切々と伝わってくるという、響きと意味の驚異的な合一。
今回は他の七人の地謡も梅若会で固めていたためか、特に統一感があった。
そして大槻文藏。前場は都から三年も帰らぬ夫の芦屋某(ワキ:福王茂十郎)を九州の家で待つ夫人役。面も美しく、装束にも華やぎがあり、若々しい。
夫の帰郷がさらに遅れることを知らされ、裏切られたと思いこむところでは、瞋恚の噴出(前に見た野村四郎は、うなじから強い怒気を発していた)よりも、花の茎が折れてしまったような、まさしくしぼむように生命の火が消えていく。退場。
ここで夫の下人(アイ:三宅右近)が登場して、夫人が病み衰えて亡くなったこと、ようやく帰り着いた夫がその死を哀れみ、霊を呼び出して、その弔いをすることを告げる。右近は無駄な力みがなく、坦々と落ちついているのにだれず、話の内容が自然に耳に入ってくる。絶妙の運び。円熟の芸。
いよいよ後場。ここからの大槻文藏が本当に凄かった。
国立能楽堂は橋掛りが舞台から斜め後方に向かって架けられているので、正面の前方の席からは角度的に揚幕の奥の鏡の間まで見える。
幕があがり、鏡の間の暗がりにその立ち姿が見えた瞬間、本当に冥界の闇の底から女の霊が実体をとって浮かびあがっているようだった。ぞっとする。
そして、自分がこの話の要点を勘違いしていたことに気がつく。恨みを抱いて死んだ妻が何らかの祟りをなすので、夫が弔いをするのだろうと思いこんでいたのだが、そうではなかった。妻は祟ってなどいない。
ようやく帰郷して妻の最期の様子を知った夫が、閨怨、すなわち孤閨の恨みに凝り固まって死んだのでは、地獄に落ちて苦しんでいるに違いないと憐れんで、自ら進んで弔いをするのだ。
その弔いによって、妻の霊が現れる。地獄の責め苦の痛みを語ったのち、捨て去りにした夫への恨み言を口にする。そして夫ににじり寄り、ついに怒りを露わにする。
その姿に夫が無言で手を合わせる。夫の悔恨と愛情には偽りがないと思えたのだろう、次の瞬間、妻の霊は苦しみから解放され、成仏がはじまる。
ここのシテの動きと地謡の連携が本当に見事だった。「夢ともせめてなど思ひ知らずや、怨めしや」に合わせ、激情にかられて床をはたくシテ。ところが「法華読誦の力にて、幽霊まさに成仏の、道明かになりにけり」と読経のように地謡が調子を変えた瞬間、すーっとシテの背筋が伸びた。
不思議なことに、能面の表情からも険しさが消えたようにみえた。この世に縛りつけていた妄執の鎖が解け、重さが消えて漂いはじめたようにみえた。
――あ、救われたんだ。
わずかな姿勢の動きが確信させる。
ここでの地謡の音色変化の瞬間は《タンホイザー》第三幕のクライマックス、エリーザベトの名が二回叫ばれた直後に弔いの合唱が聞こえ、魔から聖へと雰囲気が一変する、あの魔術的な転換の妙に通じるものだ。
重力から解放されたように立ち上がった妻の霊は、夫の傍を離れ、橋掛りを静かに退場していく。
「開くる法の華心、菩提の種となりにけり」
――さらば。
シテは横へ進んでいるのに、その姿は浄土へ上昇していくように思える。目に見えるのは水平方向の動きなのに、心に感じるのは垂直方向なのだ。
視覚と感覚にねじれを生じさせるシテの芸。現実が虚構へとねじれる、想像力の魔術。
目に見えるもの、姿を現しているものがすべてではない。その向こうへと感覚が羽ばたく瞬間。
これがあるから能はたまらない。
くすんだ、抑えた響きでドラマを支えた囃子方も素晴らしかった。
二月二十日(土)レーベルの本

ONTOMO MOOK『迷うもまたよし!クラシック・レーベルの歩き方』が発売になった。
メジャーとマイナー各社、消えたものまで含めて、百五十五のレーベルをその分野を得意とするレコ芸執筆陣が新たに書きおろし。どんなアーティストがいたか、代表盤は何か、何年に創業し、その後どのような吸収統合、改編をしていったかなどを一冊で調べることのできる、まさに保存版。
税込二千七百五十円と、ムックとしては高めだが、それだけの中身と最新情報がつまっているものだと思う。
自分は大物ではワーナー・クラシックス、ほかにいくつかのヒストリカルなどを担当した。こういうものは書く人間にとっても、きちんと経緯を調べなおしたりして得るものが多い。なかでも「あのレーベルはいまどこへ 日本編」は書いていて面白かった。
一九八〇年代以降の話にしぼったが、一九八七年に日本のクラシック・レーベルが雨後の筍のように急増していることが面白い発見だった。CDの普及とバブル景気がその大きな要因。
ポニーキャニオンとならんでその代表格が、ファンハウス・クラシックス。広上淳一などがメインだったが、そのなかにカザルスホールの一九八七年開場記念シリーズでのホルショフスキと、オーチャードホールの一九八九年こけら落としの尾高忠明指揮東フィルの《復活》ライヴがあった。
一九八六年のサントリーホール開場をきっかけに、東京に豪華なコンサートホールが出来はじめたのも、昭和末期から平成へのまさにこの時期。見事にリンクしている。
懐かしくなって、手元になかったこの二種を、これを機会に中古で買いなおした。三月十三日から朝カルオンラインで始まる片山さんとの「音楽の殿堂としてのホール」シリーズでは、最後のほうでこれらについても触れるはず。
こうやって、先の仕事につながる材料が偶然に出てきて、連鎖反応のように次々と見つかっていくときが、資料調べの何よりの醍醐味。

二月二十一日(日)旅の始まり
王子ホールで、カルテット・アマービレの演奏会。六年越しとなるベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲ツィクルスの第一回で、第三番、第十一番、第七番の三曲。
ヴァイオリンを対向配置にし、チェロは下手奥。今回から挑戦した配置だそうで、これからの発展が楽しみ。
二月二十二日(火)十六型
東京文化会館で東京都交響楽団の演奏会。指揮は大野和士。
・武満徹:夢の時
・ブラームス:アルト・ラプソディ(メゾソプラノ/藤村実穂子、男声合唱/新国立劇場合唱団)
・マーラー:交響曲第四番(ソプラノ/中村恵理)
本来は《復活》が予定されていたが、防疫のために曲目変更。しかしマーラーではコロナ禍以後初めての十六型。
二月二十六日(金)藤田!
彩の国さいたま芸術劇場の音楽ホールで藤田真央のピアノ・リサイタル。
・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第六番
・モーツァルト:ピアノ・ソナタ第十四番
・ブラームス:二つのラプソディー 作品七十九
・リヒャルト・シュトラウス:ピアノ・ソナタ ロ短調


軽やかなタッチで俊敏多彩な音楽。日本人ピアニストの演奏で、モーツァルトのソナタをこれだけワクワクしながら聴ける日が来るとは。
後半のシュトラウスも、この曲をメインにしてホールをいっぱいにできるピアニストは藤田だけだろう。演奏も生彩にみちた素晴らしいもの。いまの日本で、何をおいても聴くべきピアニスト。
夜の与野本町は周囲が暗く、帰路もなんとなく寂しいのでためらうのだが、そんなことを忘れさせる、生きた音楽。
二月二十七日(土)高崎芸術劇場とCD
高崎芸術劇場に群馬交響楽団を聴きに行く。

新幹線や高速道路を使うと落下傘で降りたみたいなもので、目的地の周囲しかわからない。在来線だと地理関係や距離感がよくわかる。渋沢栄一の故郷深谷を経由して進む、利根川沿いの関東平野は本当にまっ平ら。

高崎はパスタの町として有名なので、コンサート前に有名店「はらっぱ」駅ビル店でペペロンチーニを食す。なるほど美味。たっぷりとかかった粉チーズが、唐辛子の利いた辛くて猛烈に熱いスープに熱せられて、食べているうちにパリパリと固まってくる。その食感の変化が快感。にんにくがものすごくたくさん入っているが、マスクをかけているのでご容赦(笑)。


高崎芸術劇場は二年前に開場したばかりだけに秀麗なホール。旧市街とは駅の反対側にある。多目的ホールということもあってか、ロビーやホール内の雰囲気は大阪のフェスティバルホールになんとなく似ている。一方で、闇夜に煌々と照り映えるまばゆさは群馬音楽センターの美風を受け継いでいるし、ペデストリアンデッキで駅と直通になっているのはミューザ川崎のそれの拡大版という感じ。内外の長所をうまく受け継いでいる。


演奏会は群響定期独特の十八時四十五分開始。終わると二十一時前。二十時で町が暗くなる現在の東京と違い、緊急事態宣言の出ていない群馬は、高崎駅前の店がまだ開いている。しかし基本的に二十一時閉店が大部分のようで、あれよあれよというまに人気がなくなる。


帰りは大宮まで新幹線にしたが、二階建て車両の一階の客席には、自分一人しかいなかった……。

さて今回の目的は新しい高崎芸術劇場を初訪問し、その芸術監督大友直人が指揮する群馬交響楽団を聴いてみたいというのがメインだが、現地でしか売っていない群響の自主制作盤を購入し、ミュージックバードの新譜紹介番組ニューディスク・ナビで放送したいというのも、大きなポイントだった。
きっかけは、ニューディスク・ナビで紹介した新譜のなかに、高崎芸術劇場の音楽ホール(大ホールとは別の、四百十二席の室内楽ホール)でセッション録音されたものが二枚あったこと。
ニューディスク・ナビは一日六時間、月~金に週五回、計三十時間で毎週二十五枚強の新譜CDを放送する番組で、二〇〇七年十月からやっているから、だいたい一万八千枚くらいのCDを紹介してきた。新譜ばかりだから脈絡はないが、たまに何枚かで関連性が見つかることがあって、そういうときは楽しくなる。

高崎録音の二枚もそうだった。一枚目は、アルディッティ弦楽四重奏団がシャリーノやリゲティなどこの半世紀ほどの作品をあつめたマイスターミュージックの一枚。二〇一九年十一月二十二と二十三日のセッション録音で、二十三日には演奏会もあり、細川俊夫の《パッサージュ(通り路)》が世界初演された。
これは高崎芸術劇場がケルン・フィルハーモニーと共同委嘱した新作。高崎芸術劇場はこの年の九月二十日にオープンしているから、開場記念の委嘱だったのだろう。
このCDにはその初録音が含まれているのが大きなウリなのだが、じつはオープン二か月目のこの頃、高崎芸術劇場はスキャンダルの舞台となっていた。十八日に館長の菅田明則と副館長の佐藤育男が、劇場備品の入札を巡って、官製談合防止法違反などの容疑で逮捕されたばかりだったからだ。
真実は法廷で明らかになるだろうが、ともかく菅田館長は二十七日に辞任。そして翌二〇二〇年一月十日、新館長に児玉正蔵、新設の芸術監督に大友直人が就任して、新体制がスタートする。
群響の音楽監督として新ホール建設にも尽力しながら、なぜか開館直前に任期満了で退任してしまった大友が、形を変えて高崎に戻ってくることになった(退任の背景は私も仄聞しているが、噂話のレベルなのでここには書かない)。
二枚目のALMの「荒井里桜 in concert」は、大友の肝煎りで開始された、高崎芸術劇場による「T‐Shotシリーズ」の第一弾となるCD+DVD。才能ある若手を実演・録音・録画で紹介するもので、メインは二〇二〇年十月十二~十四日に音楽ホールで収録されたセッション録音のCD。しかしDVDに入っている大友群響と共演したシベリウスの協奏曲は、DVDなのでラジオでは著作権の関係で放送できない。静止画像で音がメインなので、やってもかまわない気がするが、そうはいかない。
調べると、この演奏は二〇二〇年三月二十一日、コロナ禍のために無観客公演となり、FM群馬が放送した第五百五十六回定期演奏会のもの。大友さんが高崎に捲土重来してすぐに、コロナ禍が来てしまったのだ。そしてこれは、当日のエルガーの交響曲第二番と合わせて十二月にCD二枚組の自主制作盤として発売され、会場や事務局で売っているという。
これは放送できる。開館とスキャンダルの時期のアルディッティ、再出発の荒井里桜の盤との間の、コロナ禍の記録。
こういうものを買わずして、なんのための演奏史譚か(笑)。
と思っていたら、うまいことに二月末に大友さんが指揮する定期と東京公演がある。それなら、まだ行ったことのない高崎芸術劇場を実地体験し、大友さんとオーケストラと聴衆のあいだの空気も知りたい、ということで(〆切的にかなりヤバい時期にもかかわらず)行くことにした。
写真にあるのがそれ。領収書をもらったら群響理事長名義、すなわち群馬県知事名義だった。
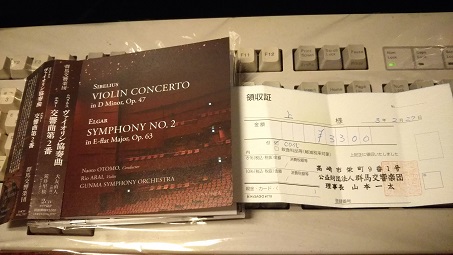
三月一日(月)平家物語強化月間始まる
世田谷パブリックシアターの小劇場、シアタートラムで木ノ下歌舞伎の『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』をみる。


今年の三月は、自分的には平家物語強化月間となっている。
三月は東京大空襲と東日本大震災の月であり、また卒業の月でもあり、「壊滅と別離の月」というイメージがある。
自分の場合は学校教師のようにそれが毎年制度化されているわけではないが、それでもいくつもの記憶が重なっているし、今年も、そしてきっと来年以降も、なんらかの別れがきては、それもあわせて思い出すだろう。
生きているかぎりはくり返し。人生足別離。
壇の浦の戦いで平家が滅亡したのは、三月二十四日。壊滅と別離の三月は、平家物語の諸行無常の響きを聴くのにぴったりの月といえる。
尤もこれは旧暦で、新暦では五月二日にあたるそうだが、やはりイメージ的には三月下旬、桜が咲くか咲かないかくらいの時期のほうがあう。
今月の国立能楽堂の主催公演は四回とも『吉野静』『巴』『景清』と能三番に茂山の新作狂言『維盛』と、平家物語の登場人物を主役とする作品がならぶ。
また、野村萬斎が芸術監督をつとめる世田谷パブリックシアターでは、下旬に『子午線の祀り』を公演するほか、シアタートラムでの貸し公演では木ノ下歌舞伎による『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』が二月末から三月上旬にかかった。コロナ禍で上演できるか不安だったが、幸いにしてすべて実現した。
その開幕となったのが、木ノ下歌舞伎の『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』。
木ノ下歌舞伎とは「歴史的な文脈を踏まえつつ、現代における歌舞伎演目上演の可能性を発信する団体」。古典歌舞伎を自由に補綴・監修して現代化するもので、十五年にわたり好評を得ている。これまでは京都や横浜の劇場が主であるために見る機会を得なかったが、今回は世田谷なので気軽に行くことができた。
客席は市松模様で半分しか入れないため、採算は苦しいだろうが、それでも開催してくれたことに感謝。
前半は通常の現代劇スタイルで、鳥羽法皇と崇徳天皇の対立に始まる源平争乱の歴史を、壇の浦の平家滅亡までざっとおさらい。続いて『義経千本桜』のストーリーを、歌舞伎スタイルを適宜とり入れながら追い、「渡海屋・大物浦の段」では、かなり歌舞伎風になる。
原作の歌舞伎は、能の『船弁慶』に描かれた大物浦の平知盛の亡霊の来襲を、じつは死んでいなかった知盛による変装と復讐だったとした点に特徴がある。しかし結局は再び敗れて、知盛は滅亡をくり返すことになる。
つまり、当事者による歴史の再現、歴史の反復。木ノ下歌舞伎はこの「歴史のくり返し」にポイントを置いた。
再現といっても前とは違う。今や義経主従も鎌倉方に追われる敗者だし、なによりも、全員が前回のことを憶えているというだけでも違う。違うはずなのに、しかしくり返し。
入水にあたって安徳天皇が辞世「いまぞ知る みもすそ川の流れには 浪のそこにも都ありとは」を詠む場面は、全体の冒頭にも置かれているので、都合三回反復されることになる。
やり直してもやり直しても、結局はやってくる滅亡の時。
二回目の入水での知盛は、白と銀の死装束の鎧姿で出陣したのに、最期の場面では赤青黄など多色のぼろをまとっていた(背中には東京オリンピック2020のエンブレムもあったような)。
安徳帝の懇願(つまりご聖断…)で戦闘を停止したあと、薙刀にすべての死者たちの装束を結わえつけてもらい、それを碇の代わりに海に放り込み、その重さに引きずられて自らも海に沈んだ。
壇の浦での一回目の入水では普通に碇を投げ込んでいたから、二回目の入水は面子やしがらみや、死者の無念の一切を一緒に持っていって終わりにする、という覚悟だったのかもしれない。
このくり返しで知盛は、義経は、何かを学んだのだろうか。学んで、賢くなっているのだろうか。
われわれも歴史に学ぶことなく、愚行をくり返す。何度壊滅し何度別れても、またくり返す。
そのたびに、平家物語は諸行無常の鐘の音とともに甦る。「波の下にも都のさぶろふぞ」とうそぶく。
三月は平家物語強化月間。壊滅と別離の月。『吉野静』『巴』『景清』『子午線の祀り』と見る。楽しみ。
三月三日(水)即物的に明るく
国立能楽堂の定例公演。
・狂言『折紙聟(おりかみむこ)』深田博治(和泉流)
・復曲能『吉野静(よしのしずか) 前入(まえいり)』赤松禎友
個人的平家物語シリーズの二回目。
国立能楽堂の紹介文には「吉野山で再会した静御前と源義経の家臣・佐藤忠信は吉野の衆徒を欺き、義経を落ち延びさせるために共謀します。今回は、現在観世流では上演されない前場を復曲しての上演です」とある。
『吉野静』を見るのは二〇一七年三月の「東京若手能」に続いて二回目。前回も三月で、シテは宝生流の和久荘太郎だった。
そのときの日記に、
「能でいえば『船弁慶』のあと、大物浦で難破して吉野に潜んだ義経一行。しかしここにも危険が迫ったことを知って、平泉に向けて北陸に脱出する。その時間を稼ぐために吉野に残る佐藤忠信と静御前の奮闘(刀をとるわけでないが)を描いたのが、『吉野静』。
一応はハッピーエンドとはいえ、その底には義経との今生の別れへの二人の思いがあるはずと望んだりするのは、当方の勝手な思い込みか」
と書いている。
話としては大物浦のあとだから、物語の時間としては偶然にも『義経千本桜―渡海屋・大物浦―』に続く形になる。
復曲された前場はあまり印象に残らなかった。後場は四年前と同じで、ハッピーエンドにどうも納得がいかないもどかしさが残るのも、同じだった。
義経記での静は、吉野山に入ろうとする義経から都に帰れと命じられる。しかし都まで彼女を護るために義経がつけた郎党に裏切られ、財宝を奪われて置き去りにされる。吉野山をさまよううちに蔵王権現にたどりつくと、縁日でさまざまな芸が奉納されている。老僧に諭されて彼女も白拍子舞を捧げると、その美しさと上手のゆえに衆徒に正体を気づかれて捕らえられ、脅迫に屈して義経主従の吉野入りを白状してしまう。すると一転して労られ、都につきそいつきで送り届けられる(その後、鎌倉の頼朝の元に連行される)。
佐藤忠信のほうは、吉野山中まで義経に同行していたが、衆徒の襲来を覚った義経に殿軍を志願して、脱出の時間を稼ぐことにする。大奮戦して脱出(ここを劇化した能『忠信』も別にある)、京都の恋人の家に潜伏するが、心変わりした女の密告で北条義時に追捕され、壮絶な最期を遂げる。
二人とも、信頼した者に裏切られて苦しんでいる。物語の主人公である義経にしても兄に裏切られ、最後は藤原泰衡に裏切られて討たれるのだから、義経記をまとめたのは、よほど人間不信の強かった人々だったのかもしれない。落ち目になった途端に、他人の心は離れる。猜疑の目を向けられ、見捨てられ裏切られ、坂道を転げ落ちるほかない。
しかし『吉野静』は悲嘆の影に目をそむけ、二人はひたすら活発に、流言蜚語の計略や白拍子舞の芸をつくして、主君逃走の時間稼ぎという役割を明るく演じきる。自己犠牲の悲壮感も、再び会えぬ義経への思いもない。役目を首尾よくはたした静は、晴々と都に向かう。
死者に無念と苦悶を語らせることで、妄執を解こうとする夢幻能『二人静』に対し、生者の外面的行動のみがあって、内面の心理の綾は語られない。都合の悪いことには目をつむった、極端に即物的な現在能。それがもどかしさの原因らしい。
三月六日(土)カーチュン・ウォン登場
サントリーホールで日本フィルの演奏会。指揮はカーチュン・ウォン。
ショスタコーヴィチ(バルシャイ編):室内交響曲作品一一〇a
R・シュトラウス:オーボエ協奏曲(オーボエ:杉原由希子)
ベートーヴェン:交響曲第六番《田園》
カーチュン・ウォンは一九八六年シンガポール生まれ。二〇一六年のマーラー国際指揮者コンクールで優勝し、二〇一八年からニュルンベルク交響楽団の首席指揮者をつとめている。外国人の入国が困難な時期だが、夫人が日本人なので往来が可能らしく、各地に客演して日本でも評価を高めている。
本来はインキネンが指揮して、前半に《田園》、後半にシュトラウスの協奏曲と「ティル」という構成だったが、ウォンは「ティル」をショスタコーヴィチに替え、曲順を変更した。
ドレスデン空襲の惨禍に触発されて生まれた弦楽四重奏曲第八番を原曲とする室内交響曲に始まり、敗戦後の惨状のなか、従軍中のアメリカのオーボエ奏者の提案がきっかけでつくられた古典派風のオーボエ協奏曲をへて、自然への讃歌である《田園》へと、明確なストーリーを設定したのだ。
こういうセンスからして只者ではないし、指揮も評判通りの優れたもの。指揮棒を持たずに俊敏な動きでオーケストラに指示を出し、生彩豊かな音楽を引き出していく。弦楽器はピアノ配置で、チェロを上手側の前列に置く。そうして、その低弦の明確な響きを基本にしてハーモニーを整え、音楽を推進させる。
これはグッドオールがいう、ハーモニーが音楽を推進させる、ワーグナーの魅力に通じるものだった。つまりこの響きは、《田園》の劇的な自然描写がワーグナーに大きな影響を与えていることを、つよく実感させたのだ。
終演後の喝采も盛大だった。一言しゃべらせて、というしぐさで客席を静めたウォン、「また、秋に」と日本語で語りかけて、一層の拍手を浴びた。
十二月に再登場、コロナ禍で昨年中止されたマーラーの五番を振る。楽しみ。

続いて半蔵門の国立劇場の小劇場へ。特別企画公演「詩歌をうたい、奏でる ―中世と現代―」第二夜を見る。
前半は、日本中世の公家たちの宴会での歌謡を再現。楽器を用いずに人の声で楽器の響きを再現する、邦楽伝統の「唱歌(しょうが)」、いわゆる口三味線で白拍子や乱拍子、今様などを歌う。十二音会の歌。
・『五節間郢曲事(ごせちのあいだのえいきょくのこと)』 より
乱拍子『思之津(おもいのつ)』、朗詠『令月(れいげつ)』、今様『蓬莱山(ほうらいさん)』、乱舞『万歳楽(まんざいらく)』、白拍子『水猿曲(みずのえんぎょく)』、乱拍子『白薄様(しろうすよう)』
人の声だけなのに、雅楽の合奏のように響く瞬間があるのが面白い。
後半は現代音楽《ベルリン連詩Ⅱ》。中世の連歌の伝統に倣って、一九八七年に西ベルリンで大岡信と谷川俊太郎、アルトマンとパスティオールの四人が共作した連詩、『ファザーネン通りの縄ばしご ベルリン連詩』の部分を歌詞とするもの。作曲も川島素晴、フェルム、桑原ゆうの三人が「連曲」している。
曲名に「Ⅱ」がつくのは、一柳慧が一九八九年に発表した交響曲《ベルリン連詩》に続くもの、という意味である。
雅楽の伶楽舎と西洋楽器のアンサンブル東風が演奏し、歌は観世流シテ方の坂真太郎が日本語詩、バリトンの松平敬がドイツ語詩を歌う。指揮の川島素晴をはさんで舞台上手に洋楽、下手に邦楽。
能謡を雅楽が伴奏するのは、正統的な邦楽ではありえないことだろうが、それが実現する面白さ。ということは、自分がなんとなく聴いている異国の音楽も、本来はありえないはずの楽器や奏法の共演が現代音楽で実現しているのかも、なんてことを考える。
前半の背景は宮中の殿舎風だったが、後者は冷戦時代の西ベルリンでつくられた連詩ということで、西側から見た「ベルリンの壁」の風景が再現されている。
 写真は桑原ゆうさんのブログから。
写真は桑原ゆうさんのブログから。二月のヴァイグレのインタヴューのさいに、一九八三年に見た東西ベルリンの独特の空気と光景を思い出したばかりだったので、不思議な縁を感じる。
コンクリート壁面の落書きはもっとくすんだ色合いだったし、自分が見た二月のベルリンの空は、どんよりと曇っているだけだった記憶があるが、それは当時の両ベルリンの町への印象が重なっているのかもしれない。
三月九日(火)寿夫の『井筒』CD


能と狂言総合誌「花もよ」第五十四号が届く。その魅力の一つは付録のCD。今号は待望の観世寿夫の『井筒』。
一九六三年、世阿弥生誕六百年の年にビクターが発売した、上下巻各三枚組のLP『能』に収録されていたもの。
当時の名手が集う五流五番立てのステレオ録音で、横道萬里雄の詳細な解説がついていた。自分が知るかぎり、ビクターは観世流武田太加志の『高砂』、宝生流近藤乾三の『安宅』などを単発でCD化しただけで、あとは出ていない。
なかでも気になっていたのがこの『井筒』なので、LPの板起しながらCDで聴けるのは嬉しい。
能のレコードは、舞台を知らずに楽しむのは難しい。しかし舞台を見てからなら、音だけでイメージをふくらませられるぶん、DVDなどの映像ソフトとはまったく別種の魅力がある。この点、オペラの全曲盤とよく似ている。
・能『井筒 物着』(観世流)
シテ:観世寿夫、ワキ:松本謙三
笛:一噌正之助、小鼓:幸祥光、大鼓:吉見嘉樹
地謡:観世寿夫、観世静夫、野村四郎、若松宏光
三月十一日(木)「頼む」と「励め」
大河『青天を衝け』を楽しんでいる。
深谷の農民と江戸の大名の生活の大きな違い、いわば下部構造と上部構造の違いをうまく視覚化してくれている。そこに落語の世界そのままのような、江戸の長屋暮らしの風景が、平岡円四郎を通じて垣間見えるのも楽しい。
近年の大河の美術は凄いものばかりだが、今回は脚本と俳優がそれに負けていない。安っぽい激情ですべてを口で説明するとか、もったいぶっているだけで中身のない言葉や演技もないのが嬉しい。
第三回だったか、将軍家慶から「徳川を頼む」と言われる慶喜と、高島秋帆から「お前も励め」と言われる栄一。「頼む」と「励め」、自分を認めたおじさんの一言の違いが、二人の運命の違いそのものになる。こういうのは大好き。
今日は浦和でNHK交響楽団を聴く。先月の高崎での群響に続き、湘南新宿ラインで通う。今回も初訪問のホールを体験するのが目的の一つ。

浦和の埼玉会館は一九六六年落成、五十五年目と年輪を重ねたホール。神奈川県立音楽堂や東京文化会館と同じ前川國男の設計だが、茶色の外観といい木質のホール内装といい、それらとは雰囲気が異なる。しかし品のよいモダニズムが往年の教養主義の余香を感じさせる点は、やはりいかにも六〇年代らしい美点。


 この画像は埼玉会館のサイトから。
この画像は埼玉会館のサイトから。映画『砂の器』クライマックスの演奏会シーンに使われたホールというのも、あの作品が好きな人間には嬉しい。
千三百席の大ホールのほかに五百席の小ホールもある。
現在の建物は二代目で、初代は一九二六年落成というから、日本の公会堂ではかなり早い。日比谷公会堂よりも早く、東日本では日本青年館に次ぐという。
建設の中心人物は渋沢栄一。曾孫の尾高忠明さんの指揮をここで聴くのは、なかなかに意義深い。
東日本大震災十年目の当日ということで冒頭に〈ニムロッド〉が演奏され、アンコールもグリーグの〈過ぎにし春〉。心に沁みる演奏だった。
高崎に続いて浦和でも、ラフマニノフのパガニーニ狂詩曲が演奏された。クライマックスに鳴り響く「怒りの日」。
浦和の街並みは、駅前を除くと昭和五十年頃そのままの、懐かしい雰囲気。
帰宅しようとすると、宇都宮線の人身事故の影響で湘南新宿ラインのダイヤがめちゃくちゃ。よりによってこの日か、と思いつつ、京浜東北線に乗って帰る。
高崎のときの帰りも二十一時過ぎなので新幹線に乗った。今回は二回とも、帰りは湘南新宿ラインに乗れない巡り合わせになった。
三月十三日(土)巴御前、後藤新平
国立能楽堂の普及公演。
・解説・能楽あんない「巴の見たこと、語ること」佐伯真一
・狂言『墨塗(すみぬり)』善竹十郎(大蔵流)
・能『巴』種田道一(金剛流)
個人的平家物語シリーズの第三回。
シテ(種田道一)は木曽義仲につき従って戦った武勇の女、巴。
木曽出身の旅の僧(ワキ:高井松男)が義仲最期の地粟津を通ると、神社に巫女がいる。彼女は実は巴の幽霊で、僧が弔うと生前の鎧姿で現われ、義仲最期の模様を語る。世阿弥ではない、後世の誰かが複式夢幻能の型通りに作ったものだが、凡庸に終わることなく、場面を喚起する力と、感情の表出が豊かな名作。
平家物語では、騎馬が泥田にはまって動けなくなり、あえなく雑兵に討たれる義仲だが、ここではいったん去ったはずの巴が戻ってきて敵を追い払い、義仲が望みどおりに自害する時間を稼いだことになっている。この、嘘か本当かわからない最後の奮戦を再現してみせる、巴の幽霊の執着が悲しい。
金剛流は動きにケレンがあって、見ていて楽しい。橋掛りまで敵を追っていく場面では、薙刀の軸を手の中でくるくると回転させて刃をきらきら光らせる。これが合戦での白刃のきらめきのように見える、その工夫が面白かった。
夜は自宅から、片山杜秀さんとの朝日カルチャーセンターのオンライン講座、「音楽の殿堂としてのホール」。
これは「昭和音楽史」シリーズの一環なのだが、今回は上野の奏楽堂から帝国劇場、日本青年館と昭和に入ったところで時間切れ(笑)。
終盤に片山さんから後藤新平の名を出る。青年館や日比谷公会堂と関わりがある後藤は、台湾や満州など旧植民地で活躍し、大正期のロシア音楽界と日本のつながりの、パイプのような役割を果たしている。面白い。
片山さんと二時間半も楽しくおしゃべりをして、それでお金までもらえるなんて、なんと幸福な仕事なのだろう…。
三月十四日(日)
東京芸術劇場で読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹。
・コープランド:エル・サロン・メヒコ、ガーシュイン:ピアノ協奏曲ヘ調(ピアノ:清水和音)
・ヴィラ=ロボス:ブラジル風バッハ第九番
・レスピーギ:交響詩《ローマの松》
三月十五日(月)
サントリーホールで東京都交響楽団の演奏会。指揮は尾高忠明。
・武満徹:系図-若い人たちのための音楽詩-(語り:田幡妃菜 アコーディオン:大田智美)
・エルガー:交響曲第一番変イ長調
三月十七日(水)『街の灯』が明るくて

すみだトリフォニーホールで、「新日本フィルの生オケ・シネマ チャップリン《街の灯》」を見る。
一九三一年に公開されたチャップリンの名作『街の灯』を、竹本泰蔵指揮の新日本フィルのナマ伴奏と合わせて見るもの。古今東西さまざまな名作映画のサウンドトラックからオーケストラ部分を除去し、代わりにナマ演奏するという方式は近年の流行となっている。
もともとはサイレント映画の復活上映で使われて、やがてトーキー実用化後の映画にも応用された手法だと思う。『街の灯』はトーキー時代の作品だが、サイレント映画に近い。サイレント育ちでセリフを嫌ったチャップリンが、自ら作曲した音楽とわずかな擬音だけをサウンドトラックに入れたからである。
その音楽を、より豊かなオーケストラ・サウンドで聴くことができる。映像もデジタル修復されてとても明るく鮮やかだが、問題はその鮮明さにあるように感じた。チャップリンを初めとする出演者のメーキャップの濃さが露わになるし、サイレント用の身ぶりや表情の大仰さも鼻についてしまう。
薄暗く輪郭のぼやけた画面でこそ、雰囲気が出る気がする。むずかしい。
ところで、緊急事態宣言が再発令された一月八日以降に売り出された公演の販売数は席数の五十%以下となっている。そこで興味深いのは、席割が去年のように一律の市松模様ではなく、主催者によって違うこと。
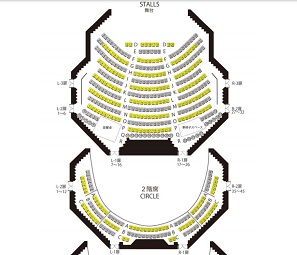
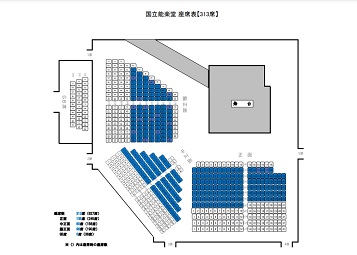
二月に売り出された世田谷パブリックシアターの『子午線の祀り』は、左右はあけずに前後の列だけをあけている。国立能楽堂は二月売出しの三月公演では機械的な市松模様だったが、三月売出しの四月公演では、舞台に近い前半分を最前列だけあけて売っている。
いずれも宣言が解除されて残席を売り出すときに、問題が少ないように配慮したもの。複数で行く人が隣席を連番で買うにはこのほうがいい。
ただ世田谷パブリックシアター方式だと、解除後に全席を販売したときに、あとで買った人が前の列を買える可能性があり、そこが難しい。
宝塚は早くから、四月の国立能楽堂と同じく前半分のみだそうだ。たしかに、宝塚で前列が後から買えるなんてことになったら、暴動になりかねない(笑)。
こういう配分などは、さまざまに経験を重ねて、それぞれの実情にあわせて改善されているらしい。
三月十九日(金)三たび景清

近所の高遠桜は早くも満開。二本あったうちの一本は、根が広く張りすぎて道路との間の擁壁を破壊しつつあり、安全上の理由で今年の開花直前に伐採されてしまったが、残る一本はすこぶる元気。枝と枝が重なった前よりも風景がすっきりして、むしろ今のほうが爽やかでいい感じかもしれない。
最近、各地で桜並木の伐採が相次いでいるのは、ソメイヨシノの寿命が短いせいらしいが、根が張って舗装を持ち上げたりする危険もあるそうだ。桜は地上の枝ぶりと同じ直径に根を張るので、けっこう始末に困るという。住宅街の家の庭に松や梅はあっても桜がないのは、この根の広がりの問題が大きいのだろう。

夕方からは国立能楽堂の定例公演。
・狂言『蜘盗人(くもぬすびと)』野村萬(和泉流)
・能『景清』浅見真州(観世流)

個人的平家物語シリーズの第四回。
『景清』は平家物語を題材とする能のなかでも傑作の一つで、大好きな作品。
国立能楽堂の紹介文を引用すると、
「日向に流罪となった平家の武将・悪七兵衛景清の元を訪れた娘の人丸に、盲目となった景清は屋島の戦を語ります。親子の情愛、人間模様を寂々と描く名作です」
この能を見るのは三回目。いずれも国立能楽堂の定例公演である。
・二〇一六年六月 塩津哲生(喜多流)
・二〇一七年十二月 梅若玄祥(観世流)
今回を含めて、三人のシテ方はそれぞれの個性を発揮して景清を舞った。シテによる個性の差が自分などでもこれほど強く感じられた能は、ほかには例がないと思う。
この能が現在能で、シテが若き日の力を失った老人であるという設定が、演じ手の感情移入と表出をさせやすいのかもしれない。死の時点で時計が止まった夢幻能の死者たちや女性の役よりも、より身近で共感しやすいのではないか。
二〇一六年の塩津版についての印象。
「合戦。上陸した景清が、逃げる敵の三保谷十郎を追う。相手の兜の後ろの錏(しころ)をつかんで引けば、錏がちぎれて三保谷は一目散。離れたところでふりかえり、「お前の力は強いなあ」と感心すると、「なんの。お前の首こそ強いなあ」と景清がにっこり破顔する。男と男の、戦場の会話。生命が輝いた瞬間の、屋島の太陽。盲いた景清が、再び見ることのないもの」
続いて、二〇一七年の梅若版の印象。
「去年の六月、喜多流の塩津哲生で同じ『景清』を観たときには、景清と錣を引きちぎられて逃げる三保谷四郎の、生命を賭した男と男の勝負の爽快さと、輝く記憶の鮮明さが印象的だったが、玄祥の景清はむしろ、主家の頽勢を逆転しようとした侍の命懸けの覚悟と、それでも敗北を阻止できなかったことへの口惜しさを、全身にみなぎらせたことで際立っていた。だから屋島の記憶は、今となってもよき思い出どころか、ひたすら苦い。
その闇を見せぬため、涙しながらも景清は早く行けと娘をうながす。しかしなお、去ろうとする娘の行く手に杖を出して立ち止まらせ、後ろから肩に手を当てて名残を惜しむ。未練。孤独。老残。このあたりのリアリズムは玄祥ならではなのか」
今回の浅見真州の景清は、主家滅亡後もおめおめと生き残り、老残の身をさらしていることを、ひたすらに恥じいっている男のようだった。忸怩たる思いをときに制御できなくなり、突如として短気を起こす。正気に返れば、そんな自分も情けない。自己嫌悪の悪循環のなかに、それでも生きてしまっている男である。
屋島の思い出も、とてもではないが誇らしげに語ったり、口惜しさを思い出したりできる対象ではない。惨めな現在の境遇へのコンプレックスが先に立って、含羞とともに控えめに語る。
しかし、それでも語らねばならない。平家の物語を語って聞かせることで、口を糊しているからである。そのことも恥ずかしい。
盲目の景清は、平曲を語る琵琶法師たちの元祖となったといわれる。能の景清も琵琶こそ持たないが、「日向の勾当」と名乗って法師の格好をしている。景清の「さすがに我も平家なり。物語はじめて御慰みを申さん」という詞には、平家方の一員という意味に加えて、平曲の琵琶法師という意味も重なっている。
英雄たちの興亡の間近にいた者が生き残り、以後はその生涯を語って暮らすという生きかたは、常陸坊海尊が源義経の股肱の臣でありながら、衣川の合戦には参加せずに生きのび、それから数百年も生きて、義経主従の話を語り続けたという伝説と似ている。
これは、のちの『義経記』の原型になる義経の物語を口誦で語っていた旅芸人たちが、海尊本人だと偽称、あるいは誤認されたのだろうと考えられる。静御前の墓が日本各地にあるのも、静の物語を語る女芸人が行き倒れになったのを、後世になって静本人だと伝説化されたのだろうと考えられている。
盲目の景清が日向に流罪になったというのも、史実としては証明がなく、平家物語などにも書かれていない。これもやはり、日向にいた平曲の琵琶法師が、後世に誤解されたのかも知れない。
ただ景清が海尊と違うのは、傍観者の語り部に終わることなく、自らも英雄伝説の主人公に昇格したことである。
景清は平家滅亡後に主君の仇を討つべく、鎌倉や奈良で頼朝を狙いつづけ失敗しつづけ、通っていた女に裏切られて捕らえられる。しかし観音の利生により、首を刎ねられたのに生きかえり、盲目も治る、というような伝説だ(女に裏切られて鎌倉勢に襲われるのは、義経記の佐藤忠信の最後にそっくり)。
だが、口承文芸として存在したこの伝説は後世に伝わらずに失われたらしい。田代慶一郎は、『謡曲を読む』(朝日選書)に以下のような推測を書いている。
「『義経記』『曾我物語』の二篇は、世にもてはやされた結果、ついには口承世界を脱して文字に書き留められ、その形を後世にまで残したが、これらの物語の形成期には、同じように語り出され語りつがれながらも、結局途中で流産してしまった英雄伝説も少なからずあったに違いない。謡曲に先行した景清伝説なるものも、『平家物語』に源を発しつつ次第にそこから独立して成長して行き、広く民間に普及しながらも、ついに口承世界を脱することのなかったそういう英雄伝説の一つだったのではないか」
この失われた口承文芸の一部分が脚色され、幸若舞――「舞」といいながら語り物が主――として残った。そこから近松門左衛門が物語を拡大して浄瑠璃『出世景清』の題でまとめ、浄瑠璃のドラマを近代化し、新紀元を画した。これは同じ浄瑠璃の『壇浦兜軍記』など、さまざまな景清物の原型となったとされる。
そうした英雄物語と比べて謡曲の『景清』は、より人間的であるがゆえに見る者の共感を誘い、深い感銘を残す。
三月二十日(土)
新国立劇場で、大野和士指揮の《ワルキューレ》。
三月二十一日(日)春待ち人に
「惜しみても惜しみても、去り行く春を留むる手立て無かりけれども、惜春の思いを忘れめや、夏秋冬とたつきを重ね、再び巡り来る暖かな良き日、春待ち人になるこそうれし、春待ち人になるこそうれしと、この世慈しむ目出度さよ」
(山本東次郎作の狂言一調『うれしき春を』より)



大雨の下、国立能楽堂へ行き山本東次郎家の「山本会別会」をみる。
自分は、能に較べると狂言への関心は今の時点では薄いが、大蔵流の山本東次郎家は特別に愛好している。
人間という、弱くて卑怯で狡猾で愚鈍で矮小で、じたばたするくせにあっという間に死んでしまう、情けないほどにちっぽけな生き物への、無限に大きな愛をかれらの舞台に感じるからだ。
その代表が二〇一七年六月二十九日に国立能楽堂の蝋燭能でみた『蜘盗人(くもぬすびと)』。蝋燭の薄闇のなかに中世の幻が現れたような、一場の夢のような、人間という存在への愛おしさに満ちた舞台だった。
その一方で『月見座頭』のような、ほんの気まぐれであるだけに救いがたいほどに暗い、人の悪意がむき出しになった狂言も見せてくれる。
それは、現当主の四世山本東次郎(一九三七年生)の人柄が、弟の則俊、甥の泰太郎、則孝、則重、則秀、さらに泰太郎の子凜太郎などの一族や弟子たちの協力により、舞台の隅々にまで浸透しているもののように思う。
その一家が狎れあうことなく、団結してつくりあげる特別公演が山本会別会。
初めに能の『翁』。喜多流シテ方の香川靖嗣の翁、凜太郎の千歳、則孝の三番三。『翁』は「能にして能にあらず」といわれるだけに、土俗的な宗教性や芸能性を色濃く残している点が魅力だが、さらに「三社風流(さんじゃふりゅう)」という小書(特殊演出)がつく。
風流を「ふうりゅう」とよむと、上品な味わいを意味するが、「ふりゅう」は反対に派手な大仕掛け。この場合は仮装行列のようなもので、狂言方の三番三の場の後半になったところで、神仏が華やかに登場する。「三社風流」は天照大神(東次郎)、春日明神(則俊)、八幡大菩薩(泰太郎)と三柱の神仏が出て、舞台の祝言性をさらに高める。
しかもここで、三番三は特別に本物の鎧を着て舞う。鎧は重さが二十キロもあるそうで、立っているだけでも大変そう(しかし一九八八年に東次郎がこの小書を復曲したさいの鎧は五十キロあったという)。二〇一九年四月に横浜能楽堂で東次郎が再演したとき、日程が会わずに行けなかったが、それをまたやるというので楽しみにしていた。
世に仇なすものから具足で身を護り、天下泰平、国土安穏、五穀豊穣を祈る三番三。天皇家の天照大神、藤原氏の春日明神、源氏の八幡大菩薩と、王家公家武家の三大勢力の祖先神がセットになっているのは、いかにも中世という感じ。
休憩後、則重の子で五歳の則光がシテをつとめる狂言『しびり』、凜太郎が鷺を真似て舞う復曲狂言『鷺』、大勢が出てきて能のパロディを楽しく賑やかにやる『業平餅』(「急ぎ候ほどに、知らぬ里に着きにけり」という、ワキの謡の定型的詞章のパロディが愉しい)と続き、東次郎が自作の狂言一調『うれしき春を』で太鼓の三島元太郎と共演して締め。
当日のプログラムに寄せた東次郎の挨拶文に、こうあった。
「狂言には『天下治まり、目出度い御代なれば」という科白がたびたび出てまいります。ついこの間まで当たり前に思っていたこの言葉が、幾多の戦乱や疫病を乗り越え、必死に狂言を伝えてきた者たちにとって、どれ程真剣な願いであったかを改めて考えます。一年前は公演を催すことすらできませんでした。また無観客での心の満たされない公演も経験しました。本日はこうして多くのお客様の前で舞台を勤められますことを衷心より有り難く、幸せに思っております」
当日は緊急事態宣言のために客席は市松模様で五割以下。満員ではないのが残念だったが、第二次世界大戦がもたらした惨禍も肌で知っている東次郎の思いと願いは、能楽堂の空間を温かく満たしていたと思う。
この日はオーケストラ・ニッポニカによる一九六四年オリンピック前後の音楽という貴重な演奏会もあり、身が二つあればという思いだったが、山本会を選んだのは間違いではなかった。
『うれしき春を』にあるとおり、過ぎた春を惜しんでいるばかりよりは、またやってくる暖かな良き日、春を待つ人になるほうが心嬉しい。
春が来るごとに、若い凜太郎や則光はすくすく育ってやがて花を咲かせ、さらなる未来につないでいく。そうして、三番三も翁も永遠に生き続けていく。
山本会別会、次は満員の客席の一人として見たい。
三月二十二日(月)コロナ禍の「祀り」



世田谷パブリックシアターで木下順二の戯曲『子午線の祀り』を見る。
個人的平家物語シリーズの第五回。野村萬斎が主役平知盛と演出を兼ねるこの舞台は二〇一七年七月に初演され、自分も同月二十日に見に行った。
四年ぶりの再演となる今回は、若村麻由美の影身の内侍、成河の義経、村田雄浩の阿波民部重能など、主要キャストはほぼそのまま。しかしコロナ禍という事情のため、三十一人いた役者を十七人に減らし、セットも変更。
上下二段の舞台と複数の移動可能な階段で構成されていた前回に対し、今回は別の作品からの転用という三日月形の半円が主なセット。鎧の草摺のようにも見える階段に対し、三日月は兜の鍬形のようでもある。

二〇一七年の舞台。壇の浦の平家勢 撮影=細野晋司 スパイスの紹介ページから

二〇二一年の舞台。壇の浦の平家勢 撮影=細野晋司 ステージナタリーの紹介ページから。
三日月盤の上を走り回りながら薙刀を振るう能登守教経(松浦海之介)最後の奮戦の殺陣などは、迫力とスピード感があった。だが人数が減ったため、壇の浦の開戦前の平家勢の「群読」は、前回の大人数の密集による力強い昂揚が見事なものだっただけに、肩すかしに感じられた。
台本をかなり縮めたことの影響も小さくなかった。前回は二十分の休憩を含めて三時間五十分かかったが、今回は各幕二十分ずつ短縮して三時間十分。
たしかに、前回は自分もやや長すぎると思った。しかし二割もカットしてしまうとさくさく進みすぎて、ストーリーを追うだけの感じが強くなる。人物描写が表面的で浅薄になり、台詞の奥に広がる心のときめきや動揺を感じにくくなる。複数の人間の運命が弄ばれていく歴史大ロマンという、平家物語ならではの宿命の重みと深みが薄れてしまうのだ。
今回の舞台で改善された部分もあり、たとえば最後の知盛入水の部分は、海の果てしなき深さと、蒼空までの遠さを感じさせた。
もう少しカットを控えめにし、人数を元に戻した、コロナ後の三回目の上演を期待したい。それだけの古典的名作であると、今回もたしかに感じた。
三月二十四日(水)濱田滋郎さん急逝
音楽評論家、スペイン文化研究家の濱田滋郎さんが二十一日に八十六歳で急逝されていたことを知る。
稼業の大先達であり、若いころからご文章を愛読してきただけに、思いはつきない。
二年前の一月、「レコード芸術」の人気連載「青春18ディスク」のために十代のころのお話をうかがえたのは、私にとっても大切な思い出である。日比谷高校を座骨神経痛で一年で中退され(あの坂を登って通うのがつらくてねえ、でもレコード屋には行ける座骨神経痛でしたと笑っておられた)、ご自身言われるところの家事手伝い、今でいえばニート生活のなか、独学でスペイン語とギターを学ばれ、スペイン音楽のレコードの解説文の翻訳をきっかけに世に出られた。
そのころのお話をうかがうなかで、当時のご自宅が大田区田園調布、中学校が久ヶ原、そして大岡山の古物屋でSP盤を偶然に見つけて買った話などは、自分も同じ東急沿線の緑が丘で、中坊時代の行動範囲がかなり重なっていたから、三十年近く時代が違うとはいえ、地元の風景が目に浮かんでとても楽しいものだった(大岡山を「おおおかやま」ではなく「おーかやま」と呼ぶ、地元民ならではの読みかたも懐かしかった)。
最後にお会いしたのは昨年十一月、音楽の友ホールで行なわれたレコード・アカデミー賞選定会議のときだった。終了後、「素敵なご文章を本当にありがとうございました」と、私がご著書の『約束の地、アンダルシア』(アルテスパブリッシング)をレコ芸八月号で紹介したことへのお礼のお言葉をくださった。
しかし素敵なのは拙文ではなくご著書のほう。次のご本も楽しみにしております、とお話ししたのだったが……。いまはご冥福をお祈りするのみ。
宣伝になって恐縮だが、前述の『青春18ディスク』はムックになって購入可能。濱田先生のお話、ぜひお読みあれ。久石譲さん、仲道郁代さん、ヤマザキマリさん、恩田陸さん、片山杜秀さんなどほかの語り部も豪華。
私はなぜかギター系担当で(笑)、荘村清志さんの回も担当した(これもものすごく楽しいインタヴューだった)。また昔のレコ芸の特集「人生の50枚」も転載され、私もその末席を汚している。

三月二十七日(土)
十四時からすみだトリフォニーで新日本フィルの演奏会。鈴木秀美の指揮で、ベートーヴェンの三重協奏曲と交響曲第五番。
十八時からはサントリーホールで東京交響楽団の演奏会。井上道義の指揮でベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番(独奏:北村朋幹)とショスタコーヴィチの交響曲第六番。
三月二十八日(日)『黄金の日日』再び
四月からNHKのBSで、一九七八年の大河ドラマ『黄金の日日』が、修復の上で再放送されるとこと。
『黄金の日日』は、全編のDVDを購入している唯一の大河ドラマ(ほかにも欲しいものはあるが、昔のは総集編しか残ってない)。しかし新たに修復しての放映となると、毎週見るしかない。
能の宗家の家を扱った『俺の家の話』(すごく面白かった。コロナ禍のマスクを能面とプロレスのマスクマンにつなげて、すべてを夢幻能のように。マスクだけで中身がないという主人公は悲しかったが、誰もがそうなのかもしれない)が終って悲しかったが、四月からは『青天を衝け』と並行してこれを見よう。
四十三年の歳月を隔てて、ともにテーマ音楽が尾高さん指揮というのも面白い因縁(しかも『黄金の日日』の曲と演奏は大傑作)。
三月二十九日(月)モーツァルト!
王子ホールで、藤田真央の「モーツァルト ピアノ・ソナタ全曲演奏会」の第一回。「清らかな始まり」と題して、ハ長調の作品ばかりでそろえた。
・ピアノ・ソナタ第七番
・フランスの歌〈ああ、お母さん聞いて〉による十二の変奏曲
・ピアノ・ソナタ第十六番
・六つのウィーン・ソナチネ第一番
・ピアノ・ソナタ第一番
・ピアノ・ソナタ第十番
これまでに聴いたモーツァルトの演奏が素晴らしかったので楽しみにしていたが、期待を上まわる見事な快演。
軽やかに弾み、俊敏に音色を変え、まさに玉を転がすような推進力と活力をもったモーツァルト。正直にいって、日本のピアニストがこれほどに柔軟で快活な魅力にみちたモーツァルトを聴かせてくれる日が来るとは思ってもいなかった。
全五回の第一回。これからもほんとうに楽しみ。なんとしても聴きに行く。
四月三日(土)お豆腐狂言

紀伊國屋サザンシアターで、狂言の茂山千五郎家による「お豆腐の和らい」。
茂山千五郎家は二世と三世の茂山千之丞を主な作者として、新作にも力を入れている。そのうちの三本をまとめて公演するもの。
・『ニンジャカジャと大名、そしてちょっとタロウカジャ』茂山童司(三世茂山千之丞)作・演出
・『維盛』帆足正規作、二世茂山千之丞演出
・『妙音へのへの物語』二世茂山千之丞作・演出
茂山千五郎家らしい、にぎやかで楽しい関西風の舞台。謡いながら何人かが手で囃す箇所は、会場によっては客席の手拍子が盛大に加わるのだろうと思った。東京の観客はおすましなところがあるので、今回そうはならなかったが。
先月からの平家物語強化月間の続きとして『維盛』を見たいと思っていたのだが、どういうわけか途中で睡魔に襲われてしまい、語ることができず。
四月六日(火)2+1
新国立劇場で《夜鳴きうぐいす》《イオランタ》の二本立てを見たあと、ハクジュホールで「N響チェンバー・ソロイスツ」。後者は日経新聞に評を書く。
終演後はひさびさに代々木八幡駅前の「なつめ」で夕食。鶏ささみとアボカドの焼きレモンのドリア。美味。

四月七日(水)還暦の東京文化会館
ようやく〆切機雷原を潜り抜け、六日から浮上してコンサート通い再開。
午後に国立能楽堂で『熊野』、夜に東京文化会館で「東京文化会館バースデーコンサート」と、昨日に続いてはしご。コロナ禍は相変わらずだが、クラシックや古典芸能の公演に関してはコロナとの共存態勢が整ってきたようで、忙しいのはありがたいこと。『熊野』の話は後日に譲って、ここでは上野の話。


六十年前の一九六一年四月七日に開館した、その還暦を祝うもの。赤いちゃんちゃんこは着ていなかったが、代わりに東京春祭の桜色の幟に包まれていた。
佐渡裕指揮東京都交響楽団の演奏で、ワーグナーの《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第一幕への前奏曲とヴェーゼンドンク歌曲集(メゾソプラノ:藤村実穂子)、ドヴォルザークの交響曲第9番《新世界より》というプロ。
佐渡が都響を振るのは珍しい。欧州から帰国したばかりの大野和士が待機期間に引っかかったためらしい。しかし佐渡は最後のスピーチで、自分が翌月の五月に生まれたこと、開館直後の四月末から旧師のバーンスタインがニューヨーク・フィルと初来日して演奏したことなどを話して、つながりを納得させる。
ということは、アンコールは《キャンディード》序曲でドンと盛りあげるかなと思ったら、バーンスタインのディヴェルティメントからのワルツと、ストラヴィンスキーのグリーティング・プレリュードで、ユーモアを交えて終らせた。ダイナミックな音楽。
ヴェーゼンドンクの藤村さんの歌が見事の一言。最初はやや響きが硬くてフリッカっぽかったが、次第に調子を上げ、「トリスタン」の音楽や「剣の動機」が木霊する、ワーグナーならではの冥い官能の世界に引きずり込んでくれた。月末に大野&都響で歌う《大地の歌》への期待がいやが上にも高まる。
それにしても木管をはじめとして、都響の響きがきれいなこと。やはりこのホールで育ってきたオーケストラだけに、ここでの鳴らしかたを熟知していると実感する。そして、自分の耳もやはりここの響き、残響少なめのすっきりした響きが原点なのだということを、あらためて感じた。
《新世界より》の第二楽章を聴きながら、そういえば自分が生まれて初めて東京文化会館に来たときに聴いたのも、この曲だったと思い出す。
高三の自分が初めて自分で買ったコンサート。一九八〇年十一月二日、マゼール指揮ウィーン・フィル。第二楽章後半の弦首席だけの室内楽になるところが、息をのむようにきれいだった。それから四十一年たった今日の都響もまた、きれいだった。
《新世界より》は、六十年前の落成披露演奏会でも演奏された曲目だった。ただし都響はまだなかった。
金子登指揮の東京藝術大学音楽学部の管弦楽研究部(現在の藝大フィルハーモニア管弦楽団)が、チャイコフスキーの《弦楽のためのセレナーデ》、モーツァルトのピアノ協奏曲第二十三番(独奏:安川加寿子)、そして《新世界より》を演奏したのだった。
このことは、「東京・春・音楽祭2021」のプログラムに寄稿するために調べて知ったことだった。てっきりNHK交響楽団かと思っていたら、そうではなかったのが面白かった。N響はシュヒターの指揮で、当日昼の落成式典で演奏しただけ。

しかし考えてみれば、藝大オーケストラは日本最古の交響楽団として、交響楽運動揺籃の地、上野の東京音楽学校奏楽堂で数多の名曲を日本初演してきた「和製パリ音楽院管弦楽団」なのだから、奏楽堂から東京文化会館へと上野の「オーケストラの宝灯」を受け渡す者として、最適の存在なのだった。
そしていまはここに都響がいる。四十年後の百歳のバースデーコンサートを自分が聴くことはたぶんないだろうが、都響はいるだろう。そのとき響くのは、どんな《新世界より》なのだろう。
四月八日(木)来日音楽家の春


午後、東京文化会館小ホールのホワイエで東京・春・音楽祭の記者会見。バブル方式でホテルに自主隔離中のムーティもリモートで登場。写真左のモニターにこの後映し出されたが、肖像権の関係で撮影禁止。
今回はストリーミング配信に力を入れている。そのなかでも、ムーティのイタリア・オペラ・アカデミーが無料で聴講できるのが素晴らしい。
一昨年の《リゴレット》は一日だけ、指揮者と歌手それぞれのマスタークラスを聴講させてもらったが、ものすごく面白かったし勉強になった(感想を二〇一九年三月三十日の日記に書いた)。
今年はコロナ禍で無観客だが、代わりに無料でネット配信される。これはイタリア側の厚意で実現したそう。時間割はまだ発表になっていないが、時間の許すかぎり視聴したいと思う。
ほかにもいろいろな話があったうち、海外の音楽家来日実現の経緯について。
入国禁止となっていた二月から、春祭は単独で動き出したそうだ。最初に外務省にきくと、まずは他の省庁に働きかけてくれ、ウチが動くのは話がすべてまとまってからの最後だ、といわれた。それなら文化庁にきこうと思ったが、どこが担当なのかがまずわからない。以前から別のことでつきあいのあった文化庁の人にきいてみると、ここが担当ではないかと紹介してくれた。
そこでやっと話が進み出した。来日できるのは「公益性の高い者」。しかし公益性が高いとはどういうことなのか、具体的な基準はない。文化庁が窓口になって他の省庁と話を進めてくれるが、どこまで進んでいるのかはわからない。
前例のない事態だけに、とにかくこれを機会にやりかたをつくろうということで、申し入れる側も文化庁の側も試行錯誤で時間がかかる。話がまとまる前に時間切れでいくつかの公演が中止となるなか、どうにかムーティたちの来日が可能になった。
新国立劇場も同時期に春祭とは連携なしに動いていたようで、前後して指揮者と歌手の来日が認可されたという。
結果論で揚げ足を取るのは簡単だが、先例主義を基本とする人たちが話をまとめるのは、とにかく大変だったろう。
──道は初めからあるものではない。不屈の意志と勇気と、探究心をもった生き物の足跡がやがて道になる。
そんなことを思った。情報が限られているので、あくまでも現時点の感想に過ぎないが。
四月十日(土)ムーティと三谷礼二さん
昨夜のムーティによる《マクベス》についての講演、自分はきけなかったが、《リゴレット》第二幕終盤の「avrai」をバリトンが引き延ばすのがけしからん、という話があったという。
これは八日の記者会見(歪められていない真のヴェルディを知るために大切なのは、スコアと手紙とトスカニーニだ、と言っていた)でも話していて、ムーティにとっては大切なポイントになる話。
一昨年のオペラ・アカデミーをみたときは、ちょうどここを若手指揮者に教えていて、とても面白かった。そしてそのとき私が思い出したのは、亡き恩師の三谷礼二さんが一九六七年か六九年のヨーロッパ・オペラ行脚で体験したという、カプッチッリの物凄いリゴレットの話だった。これについては、二〇一九年三月三十日の日記に書いている。
ムーティの《リゴレット》の指揮は素晴らしかったし、カプッチッリみたいな「avra~~~~~~~~~~~~~~ⅰ」も、かなうものならいつか聴いてみたい。それが客であることの快感だ。
そして、特別に無料で公開されているイタリア・オペラ・アカデミーのネット中継をみる。やはり面白くためになる。
以前にも書いたが、ムーティはスカラ座に君臨した時代はどういうわけか、歌手の高音などの部分的な問題以前に音楽そのものが硬直していて、自分も苦手だった(トスカニーニの一九四八年以後の録音に顕著な硬直とよく似た弱点)。
しかしスカラ座を追われて(人間不信になるような、とてもつらい経験だったらしい)、ローマに移って東京春祭によく来るようになったあたりから、七十年代のフィレンツェ時代までのような伸縮性と弾力のある、情熱的な音楽を取り戻したように思う。その響きには、ほんとうにヴェルディ演奏における人間国宝的な価値がある。
――後期の作品とは違って、《マクベス》のような初期作品では当時の楽器の性能から、金管は音の減衰を早めにして、ひっぱらないように。ピリオド・スタイルの発想。
――指揮法はパスタをつくるときのように腕で円を描いて、そのなかに拍子が入っている(それより前に言っていた、イタリア流では手首のやわらかな動きが大切というのは、この拍子の表出にかかわるのかも)。刻んだり、派手に動いたりしてはいけない。それが「トスカニーニ流だ」というあたり、一般的な思い込みとは違っていて、じつに面白い。でも納得。
――マクベス夫人のアリアに入って、いよいよ歌いまくるムーティ。ムーティはデ・サバタとカラスの演奏が最高だといっていたけれど、ここはレナータ・スコットの歌と声と表現を頭の中で鳴らしてやると、すごくしっくり来る感じ。
十六時二十分で配信終了。歌手リハは配信がないのか、それとも今日はやらないのかは不明。BGMにして仕事しようと思ったが、聞きほれてしまってとても無理(笑)。若いオーケストラの反応がじつに俊敏で鋭敏なのも気持ちよい。
トスカニーニのオケ・リハ録音もそうだが、歌手なしの優れた演奏って、ヴェルディの書いたオーケストラの表現がいかに凄いかを明確にわからせてくれて、じつに啓示的で勉強になる。もちろん、歌手のパートをなんとなく頭の中で鳴らせるぐらいの知識は必要だろうが。
明日からも楽しみだが、社会生活との折り合いをどうつけるかが課題。
三谷さんの思い出に触れてから三ツ橋 敬子指揮のNHK交響楽団を聴きにサントリーホールに行くと、最後に鳴り響いたのはなんと、マダム・バタフライの愛の二重唱。
森谷真理も福井敬もN響もよかった。三谷演出最大の成功作は、もちろんこのオペラ。こういう符合というのはなんというか、たまらないものがある。そういえば今年は没後三十年。
四月十一日(日)レクイエム
東京・春・音楽祭、ムーティのオペラ・アカデミーをネットで楽しむ(ムーティの歌唱についての主張は主張として、まずはあのダイナミックで熱く、きわめて雄弁で劇的なヴェルディの響きに触れてみることが何よりも大切だと思う。トスカニーニの人気と評価が高かった理由は「楽譜に忠実」というスローガンを掲げたからではなく、物凄い音楽をつくっていたから、というのと同じこと)のと並行して、東京文化会館での演奏会通いもようやく開始。
今日は大ホールでシュテファン・ショルテス指揮東京都交響楽団、東京オペラシンガーズほかによるシューベルトの交響曲第四番《悲劇的》とモーツァルトのレクイエム。
いかにもドイツの歌劇場の楽長として実績を積んできた人らしい、しっかりした力感のある音楽。日本人指揮者の端正な拍節感にこのところ聞きなれていたので、低音から波動するようなその響きが新鮮。
ただ、指揮者の思いと客席の雰囲気にはズレがあったように感じた。
まずショルテスは、シューベルトの交響曲を昔風に、かなり重厚に演奏した。独唱四人が黒一色の服でそろえたレクイエムは、途中のラクリモーサではなく最後のコムーニオにクライマックスを置いて、じっくりと描いていった。
こういうあたり、今日が東日本大震災から十年と一か月、という日付の厳粛さを意識したように感じたのだが、客席の側が必ずしもそうではなくてカジュアルな雰囲気なのに、指揮者が少しとまどっている印象も受けた。
もちろん、主催者側が特にそのように告知したわけでもなし、日本人の大部分は非キリスト教徒なのだから、どのような心持ちでこの演奏会に臨もうと、聴衆の自由なのだけれども。
四月十二日(月)フォーコ!
 写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから
写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページからムーティのオペラ・アカデミー、東京文化会館に移って、歌手も合唱も入ったトゥッティのリハーサル。空間と編成が大きくなったぶん、ムーティのエネルギー放射もさらに強まって、ますます元気そう。ほんとにすげえ(笑)
全アンサンブルがそろったことで、ますます元気になってきている感じ。これが本物の「歌劇場のディレットーレ」という人種なだろう。
「fuoco!」と叫んだあと、「日本語ではなんて言うんだ?」とたずね、長原コンマスが「炎」と教えると「ホノオ~!」と迫力たっぷりに叫んでから、「自分も日本語を勉強しないといけないね」と笑わせる。
トスカニーニもリハーサルで「fuoco!」と叫んだときは凄かったし、それに応えてNBCの弦が、火の出るような音を出したのを思い出した。トスカニーニは本当に怖い声だったが(笑)。
第一幕のフィナーレ。まさしく「勇将の下に弱卒なし」という感じ。これは本番がとてもとても楽しみ。
 写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから
写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから夜は東京文化会館小ホールで、フォルテピアノの川口成彦と古楽オーケストラ《ラ・ムジカ・コッラーナ》の演奏会。
オーケストラといってもヴァイオリン二、ヴィオラ、チェロ、ヴィオローネという弦楽器五人の最小サイズ。
曲はモーツァルト、C・P・E・バッハ、ベートーヴェンの古典派プロ。フォルテピアノは十九世紀前半に日進月歩の勢いで大発展した楽器なので、数年の違いで機構も響きも音量も音域も大きく異なる。ここで川口が使用したのは、今回の作品群にふさわしい年代の一八九五年頃のヴァルターの楽器のレプリカ。
響きがかなりチェンバロに近く、ピリオド楽器の弦楽五重奏相手でも、ときにソロが聞こえにくいほど音量が小さい。しかしその繊細さを活かした多彩な表現が見事で、とくにベートーヴェンのピアノ協奏曲第二番ではエコーのようにくすんだ音を出すなど、とても面白かった。
四月十三日(火)七十五年、七十九歳
 写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから
写真はフェイスブックの東京・春・音楽祭のページから昨日に続いて東京文化会館小ホールで「都響メンバーによる室内楽」。コンサートマスターの山本友重など弦楽器奏者七人によるアンサンブル。
前半のドヴォルジャークの弦楽五重奏曲も、都響の特色そのままのがっちりと立体的で明快な、シンフォニックな響きが気持ちよかった。しかし今回のお目当ては後半のR・シュトラウス作品で、弦楽六重奏による歌劇《カプリッチョ》の前奏と、《メタモルフォーゼン》の弦楽七重奏版(レオポルト編曲)。
《メタモルフォーゼン》は偏愛する曲だが、よい演奏に接する機会はなかなかない。「二十三の独奏弦楽器のための習作」と副題にあるように、単純な弦楽五部の合奏ではなく、二十三人の独立性が高い点に特徴があるが、それだけにうまく演奏しないと混濁して、単調な音楽に終始する可能性があるためだ。
七重奏だと響きの厚みは減るが、テクスチュアが明快になるので、とりわけ今夜のように高水準の演奏だと、音楽の構造が透かし絵のように浮かびあがる。シュトラウスは下書きの段階では七重奏で曲の途中まで書き、その後で二十三重奏に拡大したという。この下書きを元に最後まで編曲したのがレオポルト版で、近年演奏や録音の機会が増えている。
自分が聴くのも三回目で、最初は二〇一四年の同じ「東京・春・音楽祭」で、シュトラウスをテーマとするマラソン・コンサートで、ウェールズ弦楽四重奏団を中心とするメンバーのものだった。
今回は先に《カプリッチョ》の前奏が取りあげられたので、二作品の相似がいっそう露わになる。
オペラの「改革者」グルックの時代を舞台に、そこから始まるワーグナーなどドイツ・オペラの黄金時代を愛おしむような《カプリッチョ》。ミュンヘン、ドレスデン、ベルリン、ウィーンなどが空襲を受け、伝統ある大歌劇場が軒並み灰塵と化した悲しみのなかに書かれた《メタモルフォーゼン》。両者の精神は、たしかにひとつながり。
後者の最後、ついに姿を現す《英雄》交響曲の葬送行進曲のテーマ。変容を重ねてたどりつく、輝かしき過去の世界への挽歌。一九四六年に初演されているので、今年は七十五周年。
家ではトスカニーニのCDを聴く。
ムーティの情熱にあおられて、その流祖(ムーティはトスカニーニのアシスタントだったヴォットーに学んだので、自らをその孫弟子と位置づけている)の演奏を聴きたくなった。
やはりイタリア・オペラ、それもミラノ・スカラ座を指揮した盤が聴きたい。ということで一九四六年五月十一日の、スカラ座再建記念演奏会のライヴ。
スカラ座もドイツ各地の歌劇場同様、一九四三年八月の空襲で大きく損壊し、公演が不可能になっていた。しかし終戦一年後に修復され、そのこけら落としを指揮したのが、一九二九年以来十七年ぶりの帰還となったトスカニーニだった。
イタリア・オペラ黄金の一世紀を彩るロッシーニ、ヴェルディ、プッチーニ、ボーイト四人の傑作オペラの聞きどころを集めた演奏会。
ロッシーニの《ウィリアム・テル》のバレエ音楽での圧倒的な生命力、ヴェルディの《ナブッコ》序曲の燃えたぎるようなカンタービレ。
強く大きく響いて安定してはいるが、そのぶん重いNBC響とはまるで違う、澄んで軽やかなスカラ座の弦の響き。叩くのではなく跳ねるそのリズムの躍動。
ヴェルディのテ・デウムは、トスカニーニが作曲家直伝でイタリア初演を指揮した作品。ここでソロを歌うテバルディは、この日がスカラ座デビュー。
一九一五年以降、じつはプッチーニ作品をあまり指揮しなくなっていくトスカニーニが、唯一好んでいたのが《マノン・レスコー》。ここではその第三幕。トスカニーニの指揮で聴くと、まるでフランス・オペラのように優美軽快に響くのが興味深い。トスカニーニに抜擢され、ファルスタッフを生涯に千二百回歌ったバリトン、スタービレがレスコー役なのも嬉しい。
この第三幕のラストでは、名テノールのジーリが楽譜にない高音を高らかに歌いあげて歓喜をあらわす映画が残っている。同じことをやったテノールは聴いたことがないが、面白いことに名ソプラノのオリヴェロがマノンを歌ったとき、同じ叫びを追加して喜びを表現した。
もちろんトスカニーニは、ムーティ同様にそんなことは許さない(笑)。その代わりにオーケストラが、歓喜の激情を爆発的に響かせる。
しかし三種とも一度聴いただけで忘れられなくなるような、オペラ的快感と感興にみちた演奏。
最後は《メフィストーフェレ》プロローグの、轟然たる響きの奔流で締め。二〇一六年の東京・春・音楽祭で、ムーティが素晴らしいナマを聴かせてくれたのを思い出す。
いくつかのレーベルから出ているが、今回聴いたのはスキラ社発行のCDつき書籍。スカラ座の歴史的録音を用いて、公演ポスターを表紙にしたこのシリーズは、CDケースとは違った紙製ならではの親密さがあり、音も聴きやすく、写真が何枚も入っているのが嬉しい。


トスカニーニ生誕百五十年の二〇一七年に出たもの。そういえばこのスカラ座演奏会も、《メタモルフォーゼン》初演と同じく今年が七十五周年。そして奇しくもこのときトスカニーニは、今のムーティと同じ七十九歳。
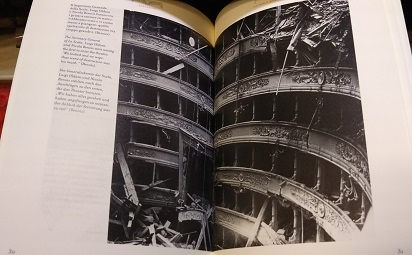
四月十六日(金)オペラ・アカデミー
今日は若手指揮者の出番はなく、完全にムーティの指揮によるトゥッティのリハーサル。自主隔離中からZoomで歌手たちとはリハーサルをしていたそうなので(八日のリモート記者会見時もそのあとに歌手リハがあると言っていた)、言葉の指示はほぼオケ相手にだけ。
四月十七日(土)井伊大老となぜか二部
 大河ドラマ「青天を衝け」の公式ツイッターから
大河ドラマ「青天を衝け」の公式ツイッターから大河ドラマ『青天を衝け』で岸谷五朗が演じた井伊直弼のキャラクターは、史実に近いかどうかは別として、その性格づけがとても面白かった。
まがい物、その地位にふさわしくない者として信頼されていないという不安を抱えた、自分に自信のない男。
三十過ぎまで部屋住みの庶子として無為のまま趣味に生きてきた人物が、兄の死によって世子となり、当主となった。しかしその家は、徳川将軍家の譜代筆頭という特別の家柄。大老という特別の役職につけるけれど、逆にいえば老中などの実務経験なしに、いきなり幕閣の頂点をやるしかない、特別の家柄。
大老になって突然降ってわいたみたいに登場させるドラマが多いなか、今回は老中首座の阿部正弘の在世中から、その他大勢の大名の一人として顔を出していたのがよかった。そんな男が、阿部急死後の混乱のなかで、得意の茶の湯を通じて将軍家定の信任を得る。そうしていきなり大老として、幕政の表舞台に立たされることになる。
家定もやはり、将軍のまがい物という不安を抱えていたので、似た者同士の二人は共感し、依存しあう。そのため、譜代筆頭としての井伊の高い忠誠心と義務感は、家定という個人に向けられる。家定のひねくれた意志を忠実に実行する役を引き受けることになる。
これが、やはり高い忠誠心の持ち主である慶喜との決定的なズレ。慶喜の忠誠心は徳川将軍家という「機関」に対してのものであり、特定の個人に向けたり、その結果として派閥抗争をしたりすることは愚かだと思っている。これが井伊には理解できない。
井伊の小心者ぶりが、反動として安政の大獄という陰惨な恐怖政治、密偵政治の呼び水となるというのは、一つの解釈として面白かった。
ただ、いきなり次の回で桜田門外の変になったのは、急ぎすぎで惜しい。
あと一回、安政の大獄の暗黒とその残虐な弾圧をじっくりと描いたほうが、恐怖政治が攘夷熱で日本中を沸騰させ、ついには幕府崩壊を招く結果になることを意識させられたように思う。
安政の大獄は昭和後期のドラマなら、戦前戦中の特高や憲兵の陰険と残虐を肌で知る新劇人などがそこらじゅうにいたから、放っておいても陰惨な雰囲気が出たが、今はそうはいかない。
特に、橋本左内の描写があれだけで終ったのはもったいない。松平春嶽との妖しい関係を、風呂で背中を流す場面でせっかく暗示したりしていたのだから。
左内と春嶽だけでなく徳川斉昭と藤田東湖、慶喜と平岡円四郎など、幕末独特の大名と腹心の家臣の篤い関係も描いていただけに、井伊と長野主膳(『花の生涯』で佐田啓二が演じたのが有名だが、自分は『翔ぶが如く』で数回だけ出てきた伊藤孝雄の悪役ぶりが好きだった)の関係も描いてほしかった。
自分が奔走して家定の後継に据えた家茂との微妙な関係も、もっといろいろ描けたように思う。
井伊の狂言好きという一面を描いてくれたのは嬉しかったが、これも急ぎすぎて説明不足の描写に終わってしまった。
このとき井伊家から扶持を受けていた茂山千五郎家の現当主が、ドラマでも狂言『鬼ヶ宿』の一部を演じていた。
茂山家のユーチューブ・チャンネルでは、井伊家と茂山家との関係がわかりやすく説明されている。
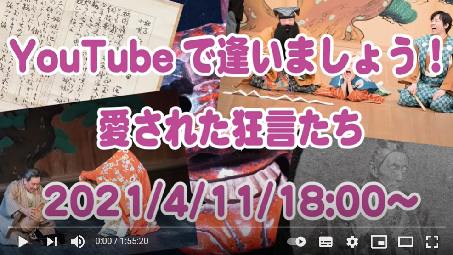 YouTubeで逢いましょう!〜愛された狂言たち〜
YouTubeで逢いましょう!〜愛された狂言たち〜千作という別名ができた由来が、井伊家と禁裏への出演時に名前を使いわける必要からというのは面白かった。『鬼ヶ宿』もここで通して見ることができる。これは井伊が本当に自ら作って茂山家に下された作品で、初演は桜田門外の変の二週間ほど前だったという。
男が久しぶりに恋人の家を訪ねると、女はとっくに愛想を尽かしていて、男など邪魔なだけ。外へ酒を買いに行かせてしこたま呑ませ、歌わせ舞わせて、男をいい気分に酔わせたところで、女は突如として鬼となって襲いかかる。男はあわてて逃げていく。
愛憎の感情がどこかで入れ替わってしまい、気持がずれていく男女関係、ひいては人間関係の機微を示そうとしたらしいこの狂言を、安政の大獄の最中に面白がってつくっていたという井伊の心理。
このへんは、やはり大河でじっくりやってもらいたかった。
この日は昼と夜で演奏会をはしご。
まず東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は鈴木雅明。
・ハイドン:交響曲第九十五番
・モーツァルト:オーボエ協奏曲(独奏:吉井瑞穂)
シューマン:交響曲第一番《春》
夜は十八時からサントリーホールで東京交響楽団の演奏会。指揮は原田慶太楼で「正指揮者就任記念コンサート」。
・ティケリ:ブルーシェイズ
・バーンスタイン:セレナード(ヴァイオリン:服部百音)
・ショスタコーヴィチ:交響曲第十番
ところで最近のクラシックのコンサートでは、防疫のためにチケットの半券は自分でもぎり、プログラムも積んであるところから自分でとる形式が多い。
問題なのは、東京交響楽団のプログラムだけ、一部とろうとしてなぜか二部とってしまうことが多いこと。
今日は休憩中に隣席の奥田佳道さんがプログラムを読んでおられたので、
「自分、なぜか二部とっちゃうんですよね」と言った。
すると奥田さんがぷっと噴き出し、手にもったプログラムを見せてくれた。
やはり二部あった。
なぜこうなるんでしょうと、同病相哀れむ。二年前なら一部は読まずに戻しに行くが、今は防疫上そういうわけにはいかないので、しかたなく持ちかえる。
原田の「東京交響楽団正指揮者就任記念コンサート」、ハイカロリーでエネルギッシュ、若い力にみちた気持のいい演奏会だった。これからも楽しみ。
たくさんのお客さんも同じ思いで、最後は一般参賀にスタンディングオベーション。希望の光は人を笑顔にする。
でもプログラムは二部。

四月十九日(月)『熊野』と中世の京都
能の『熊野』と京都の話。この能は十日前の七日に国立能楽堂で見たばかり。
《月間特集 日本人と自然 春夏秋冬》
・狂言『土筆 (つくづくし)』善竹彌五郎(大蔵流)
・能『熊野(ゆや) 村雨留(むらさめどめ)』観世銕之丞(観世流)
まず「くまの」ではなく「ゆや」と読むのが初心者には難しい。シテ方五流のうち喜多流だけは『湯谷』と書くので読みやすい。ただどちらにしても、この能の主人公である才色兼備の女性の名前だとは、なかなか想像しにくい。
平家全盛期の京。平宗盛(ワキ)は遠江国池田の宿の長、熊野(シテ)を愛人として京に呼び寄せている。
「宿の長」というのは宿場の遊女の統率者を意味する。昨年十月七日の日記で『江口』について書いたことだが、応仁の乱ぐらいまでの中世日本では、女性の財産権や旅など行動の自由がかなりの程度認められていて、近世の父系制社会とは様相がかなり異なっていたらしい。熊野もそのような地位にある女性である。
しかし熊野の老い先短い母が、最期に一目あいたいから帰って来いと手紙を書いて、縁者の朝顔(ツレ)に託して京に上らせる。
朝顔から手紙を見せられた熊野は狼狽し、宗盛に帰国の許可を願うが、花見の宴をするから待てと許されない。そして宗盛邸から牛車に同乗し、清水寺に向かう。駘蕩たる春の都の景色を讃じつつ、目に入る寺々に母の無事を祈る熊野。
宴が始まり、客をもてなす熊野は、宗盛の所望で舞を舞う。そのとき俄か雨が降りだし、花を散らすのを見た熊野は、筆をとって短冊に歌を記す。
「いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん」
この歌に感心した宗盛は、突如として帰国を許す。都に帰るまでお供をしていては、そのあいだに宗盛の気が変るかも知れないと、花見の場からそのまま帰国の途につく。
俗に「熊野松風に米の飯」、つまり能の『熊野』と『松風』は毎日食べる米飯と同じように飽きのこない名曲といわれる。特に有名なのは、宗盛邸から清水寺までの道行の場面。
舞台には牛車を模した作り物が置かれて、熊野役のシテはその中に立って乗っていることを暗示する。動作は手や面の動きなどほんのわずかに抑えられ、道中の景色も熊野の心理も、地謡とシテが謡う詞章によって語られるだけ。言葉がほぼすべてのイメージを喚起していく、まさに能ならではの魅力に満ちた場面。
少し前に読んだ二冊の新書に中世の京の地理が書かれていたので、以前よりも雰囲気を頭に浮かべやすくなった。
桃崎有一郎の『「京都」の誕生 武士が造った戦乱の都』(文春新書/二〇二〇)と伊藤正敏の『寺社勢力の中世―無縁・有縁・移民』(ちくま新書/二〇〇八)の二冊。
中世の京都は、桓武天皇が建設した平安京とは異なる姿になっていた。それは寺社と武家が手を加えたものだった。
そもそも平安京は、計画どおりには機能していなかった。摂関期の頃に実際に市街となっていたのは東半分の左京だけで、しかも四条より北側に人口が集中していた。平安京の北東の四分の一ほどの部分しか、都市の態を成していなかったのだ。あとは湿地などのため、人が住むには適していなかった。南端の九条大路にある羅城門(羅生門)が、鬼が棲みつくほどに荒廃したのも当然である。
放置された西半分の右京に代わって発展したのは、鴨川を渡った東岸から東山にかけてだった。桓武帝が洛中、つまり平安京の内部には東寺と西寺以外の寺社の建立を禁じたためにその周縁、なかでも鴨川の東岸地帯に大きな寺社が建つことになったからである。
当時の寺社とその周囲は貴賤を問わず人が集まる、賑やかな場所だった。特に大きいのは祇園社(現在の八坂神社)と清水寺で、前者は比叡山延暦寺、後者は南都興福寺の支配下にあり、それぞれの「京都支店」として張りあっていた。
この二つの社寺と洛中を結ぶのは、四条と五条(現在の松原通)から東に伸びて鴨川を渡る二つの橋だった。
室町時代に鴨川に架かっていた橋は、藪田嘉一郎の『能楽風土記』(檜書店/一九七二)によると、祇園橋と清水橋とも呼ばれた四条と五条の二つしかなかった。当時の橋は官製ではなく、民間の拠出金で作られて管理されており、その勧進元は寺社、すなわち祇園社と清水寺だった。両社寺に大きな財力があるからこそ、橋を架けることができたのである。
橋の周囲の河原(現在のような堤はなく平坦で、鴨川も浅かった)には、芸人を含むさまざまな賤業の下層民が住み、かれらも両社寺の支配下にあった。このように社寺は宗教的権威に加えて、巨大な経済力も擁する存在だったのである。
さらに鴨川東岸の開発には寺社勢力だけでなく、王家と武家も加わった。
まず、寺社地域の北側の白河一帯は藤原摂関家の別荘地となっていたが、ここを白河帝が譲り受け、「国王の氏寺」たる法勝寺と御所の白河北殿を建立し、院政の根拠地とした。
また、反対の南側の山沿いには鳥辺野という墓地が広がっているが、ここと五条橋のあいだの六波羅を開発して拠点としたのが、伊勢平氏の清盛である。
さらに平家は平安京の南端にも勢力を拡大し、湿地帯で公家の別荘などしかなかった西八条を開発(どうやって地盤を改良したのかは不明らしい)、洛中での新たな拠点とした。
能『熊野』の副主人公たる平宗盛は、清盛の三男。腹違いの十歳上の長兄小松重盛も次兄基盛も清盛に先んじて亡くなっていたため、清盛没後は平家の棟梁となった。もともと宗盛は清盛の正妻時子の嫡男なので、血筋の正統性は重盛よりも高かった。
母時子の権勢は強く、西八条の土地というのは清盛ではなく時子の所有だったという。まだ女性の権利が認められていたことの表れである。
前述の『能楽風土記』は、能の名曲に出てくる人名や地名、古歌や故事を実証的に解きほぐしていく名著で、それによると宗盛邸は八条高倉、いまのJR京都駅の東側あたりにあった。熊野の道行はここから始まって五条で鴨川を渡り、清水寺に向かったものと推定している。
ただし詞章に八条付近の描写はない。「四条五条の橋の上、老若男女、貴賎都鄙、色めく花衣、袖を連ねて行末の、雲かと見えて八重一重、咲く九重の花盛り、名に負ふ春の景色かな」という、じつに美しい響きでイメージを拡げる謡で、鴨川の二つの橋から始まるのである。
それゆえ、室町時代の十五世紀半ばにつくられたこの能では、出発地を六波羅に想定しているのではないかと考えることも不自然ではない。
それから東の清水寺へと向かう道に入る。熊野は沿道にあるさまざまな寺や堂に、母の無事を祈っていく。
この能には死と葬送のイメージがさまざまに織り込まれて、母を思う熊野の切迫感を強調している。『能楽風土記』によると、六波羅と字をあてる前は「六原=ロクハラ」で、ロクとは墓地のこと。六道の辻も同様の連想を呼ぶ。鳥辺山とはもちろん鳥辺野のこと。
さらに清水寺の北側には湯屋谷という地名がある。ユヤダニ、イヤダニは各地にあるが、多くは墓所を指すという。熊野(湯谷)という主役の名からして、これに通じている。元になった平家物語では、宿の長者の娘の名は侍従で、熊野というのは母の長者の名なのだが、能はあえてそれを変えている。
このように、この能からは中世の京都のありようが見えてくるようで、まことに愉しい。
一方、人の心理があまり書き込まれていないこの詞章から、男女の恋愛関係の機微を読み解いてみせたのが田代慶一郎の『謡曲を読む』(朝日選書/一九八七)で、これも面白いのだが、長くなりすぎたので次の機会にして、CDの話。


きわめつけの名曲で、耳からイメージさせる割合が大きいだけにレコード向きなのだろう。写真上段は観世元正がシテで、一九六六年のステレオ録音。囃子方や地謡も充実していて、純度の高い響きに聞きほれる。下段右は観世寿夫がシテで、一九七三年のモノラルの放送音源。左は梅若実がシテで、これは囃子方のいない、謡曲としての録音。
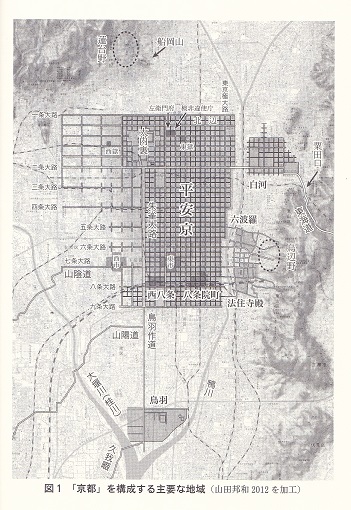

桃崎有一郎『「京都」の誕生 武士が造った戦乱の都』(文春新書/二〇二〇)掲載の地図。
左京しかない平安京と、鴨川の対岸に白河院が開発した白河、平家が開発した六波羅と西八条など。
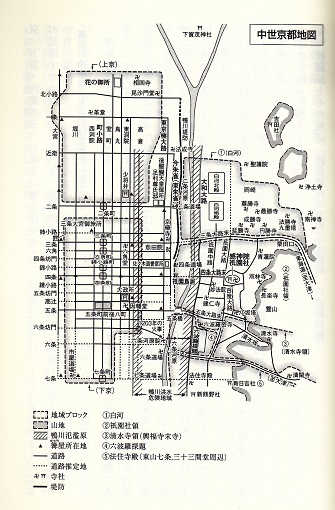

伊藤正敏『寺社勢力の中世―無縁・有縁・移民』(ちくま新書/二〇〇八)掲載の地図。
都市の中央にあるべき朱雀大路ではなく(それは西端になった)、今朱雀(東朱雀)小路と鴨川を中央にして発展した、鎌倉~室町期の京都。
江戸の町が大川(隅田川)を中央にして、東へ発展したことを想起させる。なお、この地図では三条と五条に橋があるとなっている。
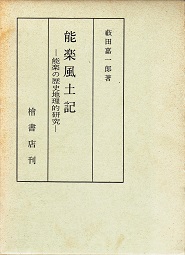 藪田嘉一郎『能楽風土記』(檜書店/一九七二)
藪田嘉一郎『能楽風土記』(檜書店/一九七二)四月二十日(火)生者と死者と、

「レコード芸術」の五月号が発売された。自分は月評のほかに今月は三つの記事に参加した。
・特集「新時代の名曲名盤五〇〇④」の選者
・エラス=カサドのインタヴュー
・「レコード誕生物語」第四十一回「ワルター指揮/ふたつのマーラー:交響曲第九番」
生者と死者の芸術をバランスよく扱えるのは、今の自分の仕事の姿勢として、とてもありがたいこと。ワルターのマーラーの九番の話は、「演奏史譚」らしきものがどうにか書けたかと思っている。
それにしても今月は、三つの仕事全部が表紙に載っている。二十五年以上「レコ芸」に書いてきて、これは初めてのことかもしれない。ちょっと嬉しい。
四月二十一日(水)演出の鮮度
新国立劇場で《ルチア》。ジャン=ルイ・グリンダ演出のプロダクションは二〇一七年三月初演のもの。
四年ぶり二回目となる今回は、コロナ禍のために演技も変更され、合唱もディスタンスをとる。コロナ禍のこの劇場では通例となっている、この合唱のディスタンスというのが意外に曲者で、オペラの舞台ならではの昂揚感をかなり削ぐ。
あやふやな記憶だが、演技も防疫のためという以上に細部が変更されていたと思う。初演時のルチアは男装をすることや槍への執着などで、従属的な弱い女性であることを嫌悪していた。その主体性への願いを男性たちが否定することが発狂という悲劇につながるのだが、今回はそうした要素がかなり薄められていた。
殺したアルトゥーロの首を、槍の穂先に突き刺して立つショッキングな場面もなし。残酷という判断かもしれないが、狩の獲物の鹿の首の剥製を壁一面に掲げるというアシュトン家の伝統、男らしさの証明をルチアもやろうとしたのだという、哀しいつながりが消えてしまう。
やはりオペラ演出の細部――しかしその細部にこそ主張が宿っている――は、演出家のいない再演では鮮度が薄れて、わかりにくくなるのだなと感じる。
スカップッチの指揮はやや強引。楽譜にある超高音も軽々と出した、ローレンス・ブラウンリーのエドガルドがききものだった。
四月二十二日(木)受け継ぐもの
能とコンサートをはしご。
午後は国立能楽堂の企画公演。
・狂言『木六駄』茂山千五郎
・復曲能『泰山木』観世清和、金剛永謹
『木六駄』は、雪の降る峠道を牛十二頭に越えさせる牛飼いを、一人芝居で演じる茂山千五郎の芸がみもの。
『泰山木』は金剛流の『泰山府君』に基づいて、ワキ方の福王茂十郎などが復曲したもの。二十年前の初演時には、世阿弥時代を再現して、ワキやシテも地謡とともに歌うスタイルだったそうだが、今回は通常の地謡のみ。
観世宗家と金剛宗家が共演し、両宗家秘蔵の能面を交換してかけた。豊臣秀吉が愛した金剛宗家所蔵の「雪の小面」、世阿弥がかけたという観世宗家所蔵の赤鶴作の「小癋見」。さらに徳川秀忠からの拝領品として観世宗家に伝わる狩衣を金剛宗家が着用した。
夜はミューザ川崎で、ムーティ指揮東京春祭オーケストラの演奏会。
モーツァルトの《ハフナー》と《ジュピター》、二曲の交響曲のみ。反復をしても休憩入れて一時間半で終わる。
普通ならもう一曲欲しいくらいだし、そもそもモダン・オケでモーツァルトの交響曲だけの演奏会というのは食指が動きにくいのだが、聴いてみればとんでもない、お腹いっぱいの濃密な、長く忘れないだろう音楽体験だった。
東京・春・音楽祭でムーティが《ハフナー》を指揮するのは二度目で、二〇一〇年に《カルミナ・ブラーナ》の前座として自分も聴いている。そのときの演奏にはピンと来なかった。
しかし今日は違う。ものすごく充実している。たぶんそれは、同じ東京春祭オーケストラといいながら、出す音楽がまるで違っているから。あのときも東京の各オーケストラの首席クラスがそろっていたはずだが(コンマスは堀正文だったらしい)、もっと硬直した音楽だった。
それに比べて、今日のオーケストラの俊敏でにこやかで優美で、明快なアクセントで生き生きとしていたこと! ムーティの即興的な動きにも瞬時に、愉しげに反応する。
大野和士が「モーツァルトの音楽はそのオペラを演奏したことがあるオーケストラかどうかで表現の豊かさがまるで違ってくる」と言っていたけれど、まさにそれだろう。
かれらはモーツァルトのオペラをムーティと演奏したわけではないが、二週間近くヴェルディのオペラを一緒に演奏してきた。喜怒哀楽のドラマを小さな音型やフレーズの動きや陰影に込められることを、身体にたたき込んでいる。その音楽語彙の豊富さ、自在さ。シンフォニーしか演奏していないオーケストラには容易に出せない、ドラマをはらんだ動きとアクセント。
《ハフナー》でそのことの重要性がとりわけ発揮されたのは、最後のたたみこみのところだった。ここはいうまでもなく、《フィガロの結婚》のコーダなどと似たしめくくりをしている。さまざまな楽器がそれぞれの音を多彩に鮮やかに響かせたその一瞬に、自分の頭の中に《フィガロの結婚》のあの数時間に及ぶ騒動のはての大団円が、映像となってなだれ込んできた。
これにはびっくりした。あまりの情報量の色彩と言葉の横溢に、自分の脳が溺れそうになった。
わずか十秒くらいの音楽が、数時間の音楽のイメージを召還してしまうこと。開かれた窓のように、広大な空間に脳内でつながってしまうこと。世界への窓のような十秒間。一瞬のなかに数時間が入っている、数時間が一瞬として知覚される、そういう無茶なことが脳のなかでは起りうる。それだけの活気に、オーケストラは満ちていたのだ。
とはいえ、ムーティのモーツァルトの響きは、ヴェルディのときのそれとはまるで違う。まさしくトスカニーニ的だったヴェルディに対し、モーツァルトは優美に、カラヤン風のレガートで響く。
もちろんカラヤンの水平レガートそのものではなく、もっと波動して歌うイタリア風のカンタービレで、ヴィットリオ・グイのモーツァルトを想起させるものだけれど、しかし、これはこれでムーティなりのカラヤンとウィーン・フィル、そしてザルツブルクの町へのオマージュなんだろうと感じる。
音が澄んでいるので、各声部が立体的に鳴る。とりわけ第二ヴァイオリンが雄弁。ピアノ配置なのに鮮明に聞こえるのに驚く。対向配置でなくとも、やりかた次第だと思い知らされる。
《フィガロの結婚》そのままの人間讃歌だった《ハフナー》に対し、《ジュピター》はだいぶ趣が違った。いや、自分には違うとしか聞こえなかった。
第一楽章がすすむうち、なんと寂しくて、哀しい、しかしとてつもなく偉大な音楽なのだろうと思った。
孤高にして孤独な英雄の音楽。第二楽章も第三楽章も寂寥感は変わらない。
そして終楽章、ジュピター音型による雄大なフガートが築く音の神殿は、壮麗にして堂々、わき出る泉のような生命力をもつが、人類が死に絶えた場所に建っているような、空漠たる虚しさがある。
廃墟ではない。荒涼としてもいない。誰にも毀つことのできない、永遠に壮麗な大神殿。しかし無人。
なんという寂しい、哀しい光景をムーティは見ているのだろう、と思った。
若い世代に偉大な音楽の伝統を伝えていくことを自らの「ミッション」、使命としているこの人は、その心の中に、はてしなく暗くて深い絶望を抱いているのだと、そんな気がした。
それが、カラヤンの響きのイメージをまとっている、ということも感慨深かった。いささか俗っぽく、現世的ではあったにせよ、いやそれゆえにこそ、華やかな栄光に彩られた、二度と戻ることのない、失われた時代への追憶。
聴きながらずっと、『クレンペラーとの対話』の結びに引用された、聖書の「伝道の書」第一章十七~十八節の語句が頭に浮かんでいた。
「われ心をつくして智慧を知らんとし、狂気と愚痴を知らんとしたりしが、これもまた風を捕うるがごとくなるをさとれり。
それ智慧多ければ悲しみ多し、知識をますものは悲しみをます」
預言者のごとく、絶望的なビジョンを心にみながら、この人は熱く音楽の価値を説き、言葉と指揮棒で人を動かそうとすることをやめない。
来年のオペラ・アカデミーは《仮面舞踏会》。我が最愛のヴェルディ・オペラのひとつ。
必ず無事に実現しますように!
四月二十四日(土)しばしの別れ

緊急事態宣言による無理心中みたいな休業要請で劇場やホールが閉められる前日に、ギリギリで実現した日本フィル演奏会。ギリギリの日程で来日できたラザレフが指揮する、ダイナミックでカラフルなグラズノフとストラヴィンスキー。
昨年二月の九州公演以来、東京では二〇一九年十一月以来となる将軍ラザレフと日本フィルの再会。ナマの音楽の喜びをかみしめさせてくれるコンサートだった。この特別な午後にプレトークをやらせてもらえたのは、本当に光栄なこと。
特別な状況だけに、十五分間の話の内容には困らなかった。でも、何もなさすぎて話題に困るくらいに平穏な日々の演奏会のほうが、ほんとうは望ましいとつくづく思い知った機会でもあった。
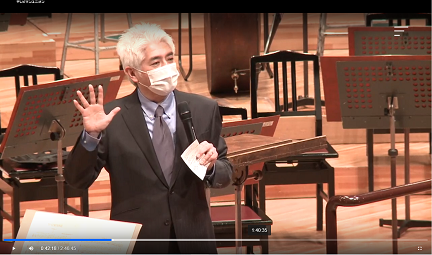

日本フィルのアーカイブ配信からスクリーンショット
五月九日(土)フモレスケ交響曲の夢

ミューザ川崎で、井上喜惟指揮のマーラー祝祭オーケストラほかによるマーラーの交響曲第三番。
昨年来のコロナ禍により、マーラーの合唱入りの交響曲(二、三、八)の全曲演奏は、日本でもプロアマ問わず途絶えている。
そのなかでおそらく本邦初の公演となったのが、名古屋のアマチュア、東海グスタフ・マーラー交響楽団による四日の第三番。マーラー祝祭オーケストラはそれに続くもので、首都圏では初のはず。
このような難事に挑戦できるあたり、日本のアマオケの意気軒昂ぶりの証明だし、演奏水準もそれにふさわしく高いものだった。
自分にとっては二十四日サントリーホールのラザレフ&日本フィル以来、十五日ぶりのコンサート。二週間あくと感覚が狂う。その間に気温が上昇したせいもあり、コロナ禍のホール内が換気のためにとても冷えるということを、すっかり忘れて薄着で来てしまった(ずっとエアコン全開だから、どこのホールも電気代がかさんでいることだろう……)。
そしてミューザは、二十二日のムーティ指揮の東京春祭オーケストラによるモーツァルト演奏会以来。
席についてステージを眺めただけで、あのときのオーケストラの活力と喜びに満ちた響きと姿の記憶がよみがえってくる。きわめて俊敏で有機的な音響体であると同時に、一人一人の顔がはっきりと見えた、個が織りなす集団の悦楽。
ムーティはオーケストラをイタリアに持ってかえりたいと言ったそうだが、けっしてお世辞ではなかったと思う。ほんとうに見事だった。
一方、今日のマーラー祝祭オーケストラはプロのトレーナーも奏者に含んでいるが、基本はアマチュア。プロの俊英を選りすぐった東京春祭オーケストラとは立ち位置が異なる。とはいえ、この大曲を演奏できる力と真剣さを持っている。
近年の日本のプロオケの充実をさまざまな意味で支えているのは、アマオケ活動の広がりと厚みと、そこに集う人びとの熱意。優れたホールで二つを続けて聴いたことで、日本のオーケストラ運動の隆盛の基礎にプロとアマの相関関係があることを実感した。
井上喜惟さんの指揮は奇をてらうことなく、じっくりと音にしていく。特徴的だったのは第三楽章のトランペット(指定はポストホルン)と第四楽章のベルを舞台上手脇の三階客席に置き、上空から音が降ってくるようにしたこと。
ヴィンヤード(ワインヤード)型のホールを、舞台の平面だけでなく高低差も用いて、立体的な音響空間として活用するのは、カンブルランが読響時代に何度も楽しませてくれたやりかた。最近はこういうのを聴く機会がなかったので、再会が嬉しかった。
第一楽章のトロンボーンやこのポストホルンなど、マーラーがソロ楽器にかなりきつい役割を負わせていることも、あらためて実感。奏者たちはこれらを見事にこなした。
ところで第三番、大曲だけにプロもおいそれと演奏できる作品ではないので、実演を聴くのは二〇一七年十二月のマイスター指揮読売日本交響楽団以来、三年半ぶり。
そしてこの一年ほどは、コロナ禍で演奏できるマーラーはかぎられ、第四番しか聴いていない。二月に大野和士指揮都響、四月に尾高指揮新日本フィル。さらに偶然ながらコロナ禍直前に最後に聴いたマーラーも、昨年一月の篠崎史紀とMAROカンパニーによる室内アンサンブル版の第四番だった。
第四番ばかり聴きつけた耳で第三番を聴くと、二曲の結びつきが深いことをいっそう強く感じる。構想のみに終わったフモレスケ交響曲の材料を分割し、拡大したのがこの二曲だけに、当然のこと。
共通するのはベートーヴェンの後期に範をえた、長大な緩徐楽章をクライマックスにもつこと。第三番の第六楽章が弦楽四重奏曲第十六番の第三楽章、第四番の第三楽章が《フィデリオ》第一幕の四重唱と、ともに「本歌取り」をしている点も似ている。
しかし終わりかたは第三番が感動的。第七楽章として構想していた『少年の魔法の角笛』の〈天上の生活〉を外し、ベートーヴェンの第三十二番のピアノ・ソナタみたいな終わりかたにした。本歌である弦楽四重奏曲第十六番にしても、ベートーヴェンには三楽章で終える案もあったという(そうしていたら、人類滅亡後の地上に響く音楽みたいになったのにと言ったのは、エベーヌ四重奏団のチェリストだった)。
そして〈天上の生活〉は、第四番の終楽章になった。天国で幸せにしているのはイエスであれ聖人たちであれ、みな悲惨な死にかたをした人ばかりだよ、と暗示するこの曲は、音楽そのものは魅力的(三番の第五楽章とあちこち似ている)なのだが、続けて聴くとどうしても、第三楽章の感動に水をかける感じになる。
しかも実演だと、楽章前の歌手の入場のタイミングの難しさに加え、終演後はまるで歌手が全曲でソロを歌ったみたいに拍手が集中しがちなのが、どうもいま一つ納得がいかないなど、盛り上がりを妨げる印象がさらに強くなる。
もちろんこのアンチクライマックス、皮肉な盛り下げこそが、いかにも『少年の魔法の角笛』の精神にかなっていて、マーラーの結論とも考えられる。
第三番の、戒律に背いてしか生きられない弱い人間でも、信仰さえ強ければ天国の道は開かれる、という第五楽章〈三人の天使は歌う〉に続いて始まる終楽章の大団円は、第四番のアンチクライマックスへの過程にすぎないともいえる。
フモレスケ交響曲に含めるつもりだった〈この世の生活〉、貧しい子供の餓死を描いた歌曲に始まり、〈三人の天使は歌う〉と〈天上の生活〉では、戒律を破って晩餐に参加しているような使徒でも信仰さえ捨なければ天国に行けるし、そもそも天国にいる聖人たちもみなまともな死にかたはしていないけど、今はたらふく食べているよと説く(悪人正機説とは違うが、なんとなくそれっぽい)。
〈この世の生活〉をプロローグに、第三番と第四番を連作で取りあげるフモレスケコンサートをいつか聴いてみたい気がしてきたが、音楽だけで百六十分くらいかかるから、難しいか(笑)。
五月十二日(水)東京の演奏会再開
宣言延長下でも東京の舞台公演やクラシックの演奏会は再開できるということで、まずはよかった。
映画館などは閉まったままで分断されるのは、合理的な説明がされていないだけに納得しにくいが、動員力が劇場公演とは桁違いで、若年層が多めな気もするから、そういうことが背景なのか。
ともあれ、十四日間待機で来日していたアーティストと関係者の努力が無駄にならないですみそうなのはよいこと。
六月六日東京文化会館でのサーリアホのオペラ《オンリー・ザ・サウンド・リメインズ》も無事に上演できそうということで、とても嬉しい。
なにしろ能の『経正』と『羽衣』が題材になっているというのだから、私などは見ないわけにはいかない(笑)。
しかも台本が自由な翻案ではなく、エズラ・パウンドとフェノロサによる謡曲の英訳(おそらく一九一六年に出版されたもの)だというのも興味深い。これはアーサー・ウェイリーやドナルド・キーンの業績に先行する最初期の英訳。キーンによるとパウンドの訳は「ときどき原文と無関係」らしいが(笑)、それだけに英語詩として美しいという。
田代慶一郎の『謡曲を読む』という本は、能の台本である謡曲を文学作品として読んでみようという面白い本だが、それによると、謡曲に文学的価値があると評価したのはウェイリーやキーンなどの外国人が最初で、日本人でそう考えたのは三島由紀夫ぐらいだったという。パウンドとフェノロサはその先人ということになる。その意味でも聴くのが楽しみ。
能楽そのものも国立能楽堂はじめどうやら公演できそう。今年見た能では二月の『砧』の印象がずば抜けていて、そこでシテをつとめた大槻文藏の銕仙会での『玄象』、そして地頭として超絶的な地謡をきかせてくれた梅若実の『西行桜』が今月に予定されているので、中止にならなくてほんとうによかった。
五月十三日(木)諸行無常の響きあり
オーチャードホールが二年後に東急本店と合わせて建てかえられるというニュースが流れる。平成元年、一九八九年開場だから、三十年と少し。
隣接の東急本店が古いので、あおりをくったかたちか。それにしても、日本人はほんとうにスクラップ&ビルドが好きだ。式年遷宮みたいなものか。
一九八二年開館の五反田のゆうぽうとホールも二〇一五年に閉館して取り壊したし、一九八三年開館の赤坂プリンスホテルの地上三十九階の新館も二〇一二年に閉館して取り壊し。バブル直前からバブル中の時期に建った東京の建物には、無性に壊したくなる何かがあるようだ。土地の区画がまとまった大きさで一括に処理できるので、建て直しが簡単ということなのか。産廃と化す建材の無駄はすごそうだが。
東急というのは鉄道そのものも、新玉川線を最後に新しい路線を敷設していないのに、接続を変えたり駅を次々と地下化したり、路線が半世紀でこんなに変化してしまった会社は、東京の私鉄で他にないように思う(私の少年時代そのままに近いのは、池上線沿線くらいだ)。立ち止まることができない企業体質なのだろう。泳いでいないと死んでしまうサメ類みたいというか。渋谷の駅周辺も巨大怪獣みたいなビルが続々と建っている。東急だけでなく、東京には「再開発してないと死ぬマン」がたくさん住んでいる(笑)。
建替えとはいえ、元のままではないだろう。本体も旧来のデパートという業態そのままではないだろうし、劇場もヒカリエにシアターオーブがある。松濤の高級住宅街を後背地とするこの土地をどう考えていくか、二年後の話ならもうアイディアは固まっているのだろうが。
その後に出たNHKの報道によると、銀座の複合施設「GINZA SIX」を手がけたルクセンブルクの会社と共同で行なうもので、「これまでの百貨店の業態と異なる新たな施設を目指したい」というから、オーチャードホールのようなものが残るかどうかもわからない。
この日記の二月二十日、ムックのレーベル本の紹介で、ファンハウスがかつて発売した、一九八七年のカザルスホールと八九年のオーチャードホールのこけら落としのライヴ盤について触れていた。いま前者は一般には非公開となり、後者もどうなるか。ファンハウス・レーベルもとうにない。諸行無常の響きあり。
五月十四日(金)能『玄象』
宝生能楽堂で銕仙会公演。
・狂言『入間川(いるまがわ)』野村萬
・能『玄象 替之型・早装束(げんじょう かえのかた・はやしょうぞく)』大槻文藏

シテは悪左府頼長の息子で、琵琶の名手として知られる藤原師長。奥義を究めるべく入唐を志す師長は、その直前に須磨浦を訪れる。
宿を借りた塩屋の老夫婦の奏でる琵琶と琴があまりに素晴らしいのに驚くと、じつは村上天皇と梨壺女御の霊が身をやつした姿だという。
師長の入唐を思い止まらせるために現われた村上は後場で貴人の装束となる。遺愛の玄象(絃上)とともに渡来した青山、獅子丸の三面の琵琶の銘器のうち、獅子丸を奪っていた龍神に命じて返却させ、師長に渡す。
琵琶をめぐる能だが琵琶が演奏されないのは、青山が出てくる『経正』などと同じ。金剛流にシテが本物の琵琶を奏でる小書もあるという。今回の「替之型」では琵琶の模型が登場。観世流以外の曲名は『絃上』で、ケンジョウとよむ。


舞台写真は銕仙会のサイトから
五月十五日(土)『熊野』の真情
能『熊野』についての話の続き。
この曲は「熊野松風に米の飯」(「に」を「と」や「は」とすることも多い。いずれにしても米飯と同等という意味)といわれるほど親しまれている。
明治から昭和戦前の知識階級には、趣味教養の一つに謡を嗜む人が少なくなかった。有名な例として、ワキ方下掛宝生流の宝生新に教わった夏目漱石がいる。自分をモデルにした『吾輩は猫である』では、謡に熱中する姿をパロディにしている(後架とは便所のこと)。
「後架の中で謡をうたって、近所で後架先生と渾名をつけられているにも関せず、一向平気なもので、やはりこれは平の宗盛にて候を繰返している。みんながそら宗盛だと吹き出すくらいである」
この「これは平の宗盛にて候」というのは『熊野』冒頭のワキの詞。『熊野』が謡の愛好者によほど親しまれていればこその描写だ。
『熊野』の詞章は美しい。謡うと心地がよいだろうことは字面からもうかがえる。しかし、ドラマとしての価値はどうか。演劇評論家の堂本正樹は『「熊野・松風と米の飯」などという言葉があるが、「熊野」は「松風」に比べてさまで名作ではない。風情や景色中心で、人間的な深みに欠けるのである』(『能・狂言の芸』/東京書籍/一九八三)とする。

維新の混乱期に能を衰滅から救い、明治の名人といわれた初世梅若実も『「松風」みたいなものが好きでして、同じ熊野松風と申しましても、「熊野」の方ははじめあんまり好みませんでした』と息子の二世実が、白洲正子がまとめた『梅若実聞書』で回想している。
しかし「後に京都に参りまして、方々見物して歩き、四条五条の橋からずっと清水のあたりまで、今も昔も変わらぬあののんびりした景色に接しまして、それから好きになったと申しておりました」という。
「熊野」の道行の場面に描かれた風景を自分の目で見て、つまりその「風情や景色」を実感してようやく曲が好きになれたとは、裏返せばそれ以外には魅力が少ないということだ。堂本が述べるとおり、人間の感情や心理、対話といった劇的な要素については、『松風』のような深みを欠いていると初世実も感じていたのだろう。
『熊野』で奇妙なのは、主な登場人物がシテの熊野とワキの平宗盛の二人なのに、相手に抱いている感情がほとんど述べられていない点にある。
なぜそうなっているのか。熊野はホステスとして権力者の宗盛に雇われているにすぎないのだから、(肉体関係があっても)宗盛への特別な感情などないと割り切って考えるのが、いちばん簡単だ。故郷の老身の母のことが心配で、気まぐれな雇い主から早く解放されたいだけ。国文学者の三宅晶子は「彼女は信心篤い孝行娘であり、プロの自覚をしっかり持った、りっぱな遊女なのだ」とする(研究十二月往来「能の中の女性像―〈熊野〉の場合―」/『銕仙』四五五号)。
うららかな京の春景色、満開の桜とは裏腹の、母との死別への不安。同じ能の『隅田川』の有名な詞、「人間憂いの花盛り」そのものの、景色の陽光と心理の暗闇のコントラストによって見せる能、ということになる。
だがそれだけでは、女性としての魅力を能舞台では出せないと考えた人が、昔のシテ方にいた。十四世喜多六平太によると、喜多流の伝書には、湯谷(喜多流の表記)には、東国に残してきた好きな男がいると思って舞え、という意味のことが書いてあるという。
そんなことは詞章には書かれていないと六平太も否定しつつ、舞台で舞うときには、母を思う気持の表現だけではしんみりとするばかりだが、そこに故郷の若い恋人に逢いたいという慕情を込めることで、女性らしい花やかさを出せるのはたしかだという。
伝書のいうことを隠し味として加えることで、演技に華が出るというわけだ。
「伝書というものは、然し、読みようがわるいと、却って迷いを起こすもので、そこまで達しないものが文字に現われた通りを半可通に鵜呑みにしたりすると、それこそおかしなことを信じ込んでしまうことがあります。そこが伝書の尊さでもあり、また危険なところでもあり、生兵法が大傷のもとになるわけで、よく面授を受けなければならないと申されるのも、ここのことです」(六平太芸談)
恋人がいると説明したら捏造になる。しかし帰郷を妙に嬉しがる、女性の愛らしさを見た観客が、あれ、湯谷にはひょっとしたら別に男がいるのか? と想像して面白がるだけなら、それはそれで観能の醍醐味なのである。
この想像で曲に「人間的な深み」が出る、ということも可能だろう――下衆の勘繰り、セクハラめいたものだが。
何はともあれ、受け取る側がそれぞれに想像の翼を広げられることが、能の面白さなのだ。
それにしても、熊野には他に好きな男がいるのではないかという憶測が生じるのは、第一には熊野の宗盛への感情がいかなるものなのか、詞章では何も説明せず、被支配関係の下で、ごくビジネスライクに接している――花見の宴になればホステス役を見事につとめる、とか――ことが大きい。
それに加えて、歴史上の平宗盛というのがさっぱり魅力のない人間なので、あんなダメ人間に惚れる女などいるわけがない、という印象がつきまとうことも大きいだろう。
平家物語などでの宗盛は、意気地なしのくせに驕慢、無能のくせに強欲で、名家をつぶしてしまう愚昧な跡取り息子の典型として描かれている。
前述の『吾輩は猫である』の一文も、便所でうなる謡がよりによって「これは平の宗盛にて候」と、屁みたいな男の名を名乗るからことさらにおかしいのだ。しかも実際は「これは平宗盛なり」と昂然とした詞なのに、ていねいな口調に間違えているのも珍妙だ。
このパワハラ男への、無言の抵抗をする女性として熊野を演じたシテがいたという。能楽評論家の戸井田道三が見た、二世梅若実だ。
『春の花・都大路・牛車に乗った美女というような派手で優美な世界は後景にしりぞいて、宗盛というわがままな権力者に対する無力な一女性の抵抗の姿勢が前面にのり出して来た感があった。牛車のつくりものの中で、シテはウタイにつれて所どころ車外を眺めて悲しみに顔を曇らせるのが、普通の演出である。(略)それなのに、全然、そとを見ようともしないのである。そして「四条五条の橋の上、四条五条の橋の上、老若男女、貴賎都鄙、色めく花衣(略)」の老にあてて、すいと顔をあげてそとを見た。(略)群衆の中に自分の老母と同じ老女だけを見て、他はあってもなくても同じように無関心な対象でしかなかったのである。(略)熊野を人権無視に対して抵抗する人間としてとらえた梅若実の斬新さに、能にもこれだけ近代的演出が可能なのだと教えられた』(『能 神と乞食の芸術』せりか書房/一九八九)

ちなみに、戸井田も『松風』はおもしろいが『熊野』は「それほどおもしろい能ではない」ものと考えていた。一九五九年に来日したフランスの文化人二人が『熊野』を見せられて、死ぬほど退屈と評したのも当然と思っていたが、二世実のこの近代性に目を開かされたらしい。
これも堂本正樹がいう「人間的な深み」だろう。じつは堂本も同じときの『熊野』を見ている。ところが、この実の近代的解釈には気がつかなかったというのだから面白い。戸井田がこう感じた舞台を、堂本は「この能が梅若実の人間苦の極限を描く芸風と違いすぎるので、さまで熱心に見なかったらしい」と自分で認めている。いつもの「人間的な深みに欠ける」能だとしか思わなかったのだ。
能は、見る人それぞれなのだ。シテの二世実本人がどう考えて舞っていたのかだって、わかりはしない。
また逆に、熊野が宗盛に惚れているという解釈もありうる。戸井田が続けて見た梅若実の息子、五十五世梅若六郎(三世梅若実)の熊野がそうだったという。
「六郎の熊野は、しんそこから宗盛が好きで、宗盛のわがままをむしろよろこんでいる女のなまめかしさがあった。だから国に残した老母の病気に思いをはせながら、なお都の花見にも心ひかれ、そういう矛盾した自分が悲しいという女であった。(略)熊野がおそれているのは権力者の変わりやすい気分ではなく、むしろ自分の気持なのであった。もし、いまをはずして宗盛の気が変わることがあれば、自分の気持もまたぐらついて老母を見捨ててしまうのではないか、とおそれているのである。六郎の女らしい女としての熊野は、そうわたしに見えたのである」(前掲書)
これも、堂本が見ていたらどう思ったか、興味深いところだが、残念ながら何も書いていない。見なかったのだろうが、見てもやはり何も感じなかったかもしれない。しかし戸井田はそう見た。
せっかく男女二人が舞台にいるのだから、そのあいだに恋愛感情があると考えたほうが、この能が面白くなるように私は思う。
もちろんこれは私が男だから、男に都合よく考えるのかもしれない。熊野の「女らしさ」や「花やかさ」という美は、熊野本人の溌剌たる生命力がもたらすものであって、宗盛だの東国の若い男だのへの恋心のためなどではない、と思う人もいるだろう。
三宅晶子は「いつもいつも、女が登場すれば恋愛とは限らない」と、熊野の恋愛感情をばっさり否定している。
ここまで紹介した喜多六平太と二人の梅若実は、いずれも「人間的な深みに欠ける」詞章からはうかがい知れない熊野の人間造型を、シテの芸の力で感じさせようとした。
ところが、熊野と宗盛の恋愛感情を謡曲そのものに読み取ろうとしたのが、田代慶一郎の『謡曲を読む』(朝日選書/一九八七)である。

田代によると、近代日本の能の研究者や愛好家は、謡曲を実際の舞台公演と分離することはできない、つまり謡曲はあくまで能の台本であって、独立した文学として読むことはできないと考える人が主流だったという。野上豊一郎や戸川秋骨などである。
謡曲を独自の文学作品として高く評価したのは外国人、アーネスト・フェノロサとエズラ・パウンド、アーサー・ウェイリー、ドナルド・キーンなどの英米人だった。かれらは英訳して世界にその価値を紹介した。
日本には長詩の伝統がなく、和歌や俳句のような短い詩しかないと日本人自らが思いこんでいたなかで、謡曲こそが長詩だと発見したのは、かれらだったのである。しかもパウンドとウェイリーは日本を訪れたことがなく、実際の能を目にすることもなかった。謡曲を読むことだけで、その価値を認めたのである。
田代も謡や舞、面と装束をつけ、囃子方を伴う実際の上演とは切り離して、文学として謡曲を読む。それは後世、特に江戸時代に加えられた可能性のある演出の変更を排して、できるだけ原初の精神に迫ろうとする試みでもある。
世阿弥や娘婿の金春禅竹――『熊野』の作者の可能性が高いとされる――の時代に生じた上演上の変化の一つに、地謡の発展があった。本来はシテとワキの対話で進んでいたものに、その謡を補強するために地謡が一緒に謡うようになり、やがては地謡だけが謡うクセという部分が増えていったのである。現在地謡が謡っている部分には、元はワキが謡っていた詞もあれば、シテが謡っていた詞も含まれている。
田代は『熊野』の地謡の部分を、推測を交えて熊野と宗盛の対話に復元してみる。たとえば、詞章に挿入される漢詩の詩句を、興に乗った宗盛が朗詠している場面とみなすのだ。
この発想はものすごく面白いだけでなく、とても参考になった。『熊野』にかぎらず他の能の地謡の部分もこのように考えてみれば、対話劇、心理劇としての彫琢がさらに深まるだろう。
そして田代は、言葉には出ない熊野の無意識の情念として、宗盛への愛情があると考える。
なぜ言葉に出ないかといえば、二人の地位と立場において、言わずとも明白なことだからだ。白楽天の『長恨歌』などに、帝王による美女溺愛のさまだけが描かれ、女性からの感情の描写が省かれているのと同じだという。
肝心なのは、この謡曲における宗盛は平家物語の情けないダメ男ではなく、豪宕磊落な英雄的人物として設定されていると田代が考えることである。「これは平宗盛なり」という誇らしげな名乗りには、力強い自信がみなぎっている。歴史小説の主人公が、史実よりも美化されたり英雄化されたりするのと同じく、ここでの宗盛は熊野が惚れるにふさわしい、たくましい男なのだ。
この魅力的な男と魅力的な女の「恋するもの同士の微妙な心理的駆け引き」が『熊野』のドラマだと田代は考える。
「宗盛の熊野への愛は決して権力者の一方的な寵愛ではなく、女の心を捉えている自信に裏付けられた余裕ある愛情なのだ。熊野を手元に置いておこうとする宗盛の強引さは一面において愛情の表現であるように、熊野の執拗すぎる帰国の願いには甘えがある」
しかし、田代の解釈には納得するところも多いが、強引に感じられるところもある。解釈の一つではあるが、それ以上ではないと自分は感じる。
圧倒的な説得力を持つには、まず宗盛を演じる立派な風采のワキが必要だ。つまり、宗盛を玄宗皇帝か藤原道長か足利義満かと見紛う「帝王」に思わせてしまえるワキだ。
次に、謡の最後の最後、「東に帰る、名残かな」のところで、都の宗盛への名残惜しさを突如として覚えて、自分が宗盛を愛していると初めて自覚する、そんな演技のできるシテと、そんな語感を込められる地謡も必要だろう(これを可能にできれば、この春をおそらく最後に都を西へ落ち、滅び去っていく宗盛と平家一門への挽歌ともなるだろう)。
前述のごとく、地謡の詞を主役たちの対話ととらえなおす試みは、能のドラマを考える上でほんとうに示唆に富んでいると思う。しかし、想像力を飛翔させる最後のカギはやはり、実演の舞台の上にあるような気がする。
いろいろな『熊野』論を見てきて面白いのは、宗盛と熊野の関係の解釈の可能性に何らかのロマンを求めがちな男たちに対して、すでに触れたように、三宅晶子がばっさりと割り切っていることだ。
「二人が雇用関係にあるのは歴然たる事実で、だからこの二人にとっては、愛情は問題ではない。熊野は命令とあらば花見にも出かけ、宴席で酌をして、歌い舞うのは当然である。彼女はそれを専門の職業とする、いわばプロなのだから」
先の『謡曲を読む』の引用で、熊野の「執拗すぎる帰国の願い」を、田代慶一郎は恋人への「甘え」とみていた。しかし三宅はこれを「自分が気に入られている自信の裏付けがあるからだろう」と冷静に考える。
甘えではなく、自分の価値への自信。
自分が男であるだけに、なるほどなあと思わされる。これこそ男が自分に都合よく誤解しやすい女心だろう。
ところでこの謡曲は、金春禅竹作の可能性が高いと考えられている。しかし自分は、どうもそう思いにくかった。『定家』のような曲では女性の微妙な心理の襞にふれ、植物的に湿った、独特の官能を詞に込めることを好む禅竹にしては、あまりにもあっさりしているように感じられたからだ。
まさしく三宅晶子が「あまりにもずばりと現実の女そのものを描くので、ギクリとしてしまうほどだ。どうもこと女に関しては、世阿弥よりも禅竹の方が実態をよく知っていたのではないだろうか」と『世阿弥は天才である』(草思社)と書いた禅竹にしては、である。
しかし今回、その三宅の『熊野』論を読んで、その違和感が解けた気がする。女の実態をよく知る禅竹が、熊野の恋心を書かなかったということは、つまりそんなものはまったく存在していない。ただの雇用関係なのかもしれない。
竹を割ったようなこの三宅の解釈に比べると、戸井田道三と田代慶一郎は、やはり考えすぎと思えてくる。
戸井田が見た梅若実と六郎、それぞれの解釈というのも、戸井田の思い込みによるところが大きい可能性もある。堂本正樹が二世実による同じ舞台を見ていながら、そうした解釈にまったく気がつかなかったと書いているように。
作品の本質そのものが奥深くてはかり知れず、無限の可能性と多面性をもっているものこそが、古典芸術のなかでも傑作となるが、『熊野』はそこまでの本質を持っていないのだろう。だからこそ解釈をしようとすると、独善的になったり考えすぎになったりしやすい。
やはりあくまでも、景色の陽光と心理の暗闇のコントラストだけを味わうべき能なのかもしれない。
だがそれでもなお、何か未知の艶なるものに新たに出会えるかもしれないと、明日も飽きずに舞台を見に行くのが、古典芸術の悦楽である。
(文中に出てくる三宅晶子の論考はここで読める) http://www.tessen.org/archive/files/2011/02/172.pdf
五月十六日(日)
サントリーホールで、NHK交響楽団の演奏会。指揮は尾高忠明。
ハイドン:チェロ協奏曲第二番(チェロ:辻󠄀本玲)
モーツァルト:四つの管楽器と管弦楽のための協奏交響曲(オーボエ:吉村結実、クラリネット:伊藤圭、ファゴット:水谷上総、ホルン:福川伸陽)
ドビュッシー:神聖な舞曲と世俗的な舞曲(ハープ:早川りさこ)
パヌフニク:交響曲第三番《神聖な交響曲》
五月二十一日(金)夢は覚めにけり
国立能楽堂の定例公演。
《月間特集 日本人と自然 草木成仏》
・狂言『蝸牛(かぎゅう)』茂山逸平(大蔵流)
・能『西行桜(さいぎょうざくら) 素囃子(しらはやし)』梅若実(観世流)
国立能楽堂の主催公演は、四月から六月まで三か月連続で「日本人と自然」を特集のテーマにしている。昨年の同時期に予定されながら、コロナ禍ですべて中止となった企画を復活させたもの。シテ方などに一部交代はあるが、ほとんどは昨年のまま。
残念なことに今年も緊急事態宣言で四月末から五月上旬の二公演が中止されたが、幸いにも宣言延長後は再開され、今日も予定通り。コロナ禍前は十八時半だった開演時間を、九月までは一時間早めることが宣言前の三月の時点で発表されていた。二十一時前後の終演だと、帰宅して風呂に入ったりするうちに日付が変わってしまう。それが一時間早いだけでだいぶ気分が違うので、助かっている。
今日は『西行桜』。梅若実の本格的なシテを久しぶりに見られる。それにふさわしく共演者もベテランが多く豪華。
国立能楽堂のページにある作品説明を引用する。
「大勢の花見客の去った夜、西行の庵に老桜の精が現れます。西行の歌に着想を得て、歌人と花の精との心の交流を描いた世阿弥作の夢幻能です」
まず西行(ワキ:福王茂十郎)に仕える能力(アイ:茂山七五三)が登場。京の西山に隠棲する西行の庵室にある桜の老木が花盛りとなったが、今年は主人が花見客を禁ずると命じたことを告げる。
そこにワキツレ四人(福王和幸ほか)が花見客の里人として登場。花を見たいので中に入れてくれと、能力を通じて頼む。はるばる来たのだからと西行は許すが、浮世が厭わしいから山に隠れているのに、群衆に押しかけられるのは桜の咎だと、歌を詠む。
「花見んと群れつつ人の来るのみぞ、あたら桜の、科には有りける」
ここで地謡が「あたら桜の蔭暮れて、月になる夜の木の本に、家路忘れて諸共に、今宵は花の下臥して、夜と共に眺め明かさん」と謡うと、里人は退場し、舞台には西行一人となる。
すると桜の老木から老桜の精(シテ:梅若実)が現れる。自ら「夢中の翁」、夢の中だと名乗って、西行を諭す。
「浮世と観るも山と観るも、ただその人の心にあり、非情無心の草木の、花に浮世の科はあらじ」
西行に納得させると、都の桜の名所を数え、舞う。そして、明けていこうとする春の夜を惜しむ。
ここの詞章が美しいことでこの能は名高い。「惜しむべし惜しむべし、得難きは時、逢ひ難きは友なるべし、春宵一刻価千金、花に清香月に影。春の夜の、花の影より、明け初めて」とか、「待て暫し、待て暫し、夜はまだ深きぞ」など、名調子が続いていく。

古歌を巧みに織りこんだ言葉遊びの妙などから、世阿弥の作とみるのが定説だが、『能楽手帖』の天野文雄は、「破格な構成は世阿弥らしくなく、禅竹の作かもしれない」と述べている。
この本には禅竹作と推定する曲がたくさんあって、いくらなんでも多すぎる気もするが、『西行桜』の芝居風の構成が世阿弥らしくないというのは、なんとなく理解できる。
また、天野はさらに面白いことを述べている。
「現在は、老桜の精が作り物の内に姿を現わしたときには、花見客はすでに切戸口から退場しているが、これは比較的近年の改変。花見客が残る形が「惜春」という主題にふさわしい」
これは意外な指摘だった。西行の不快を知って、花見客はそそくさと退場してしまうのかと自分は思っていた。先の国立能楽堂の解説に「大勢の花見客の去った夜」とあるとおり、それが現代の一般的な解釈だが、元はそうではなかった。
客は一緒に寝ているのだという。たしかに、「家路忘れて諸共に、今宵は花の下臥して、夜と共に眺め明かさん」と、ここに一泊すると謡っているのだから、すぐに帰ってしまうのはおかしい。
客と雑魚寝をしながら夢を見て、「浮世と観るも山と観るも、ただその人の心にあり」と西行は覚る。
だとするとこの西行は、自分が思っていたほど厭世的な人物、桜を独占したいと思う偏狭な人物に終わることなく、遁世することで浮世をあるがままに受けいれた人物、という印象になる。
老桜の精が謡う各地の桜の名所は、つまりは貴賤群集がさんざめく場所でもある。西行は今さらそこに加わる気はないだろう。しかしその賑わいを、人生の短い春を生きる人々を、愛おしく思う。
春宵一刻価千金。誰の時間も、容赦なく過ぎていく。
「花を踏んでは同じく惜む少年の、春の夜は明けにけりや、翁さびて跡もなし、翁さびて跡もなし」
梅若実の老桜の精は、驚きに満ちたものだった。
面をつけず、直面で演じたのだ。
老桜の精も老人とはいえ、精や霊や神や鬼など人ならぬものの場合は、面をつけるのが通例と聞いている。現にプログラムにある梅若玄祥時代の写真も、尉の面をつけている。
ところが今日は直面。装束も老木らしい黒系ではなく、『鷺』を演じるときのような白色系。
理由はわからないが、視界の狭い面をつけると足元がおぼつかないという現実的な問題があったのではと思う。右手で杖をつくのは予想していたが、左手にも長めの杖を握った。スキーのように二本の杖で立ち、歩く。異例だが、老桜の太い根や垂れ下がった枝とも想える。
最近の実は、おそらく股関節に支障があるらしく、歩行に苦労している。地頭を謡うときも小型の椅子に座っている。
今日は両手に杖をつく形だから、通常のように舞うことはできない。しかし不自由な身体から放射されるオーラはすごいものだった。怒りにも似た気魄。謡の声と節の美しさは絶品。
あれっと思ったのは、「待て暫し、待て暫し、夜はまだ深きぞ」を地謡が謡ったこと。これは本来シテが謡って、明けようとする夜を留めようとするものだ。
これを地謡が謡うと、直前の「鐘をも待たぬ別れこそあれ」の言葉に従い、夜明けとともに去ろうとする老桜の精を、西行が惜しんで、待てしばしと言っているようにもとれる。
しかし耳を貸すことなく、後見に支えられて橋掛りを半ばまで来たシテは、ふり返って謡う。
「夢は覚めにけり」
その後、幕前まで来たところで、もはや足に力が入らないのか、杖をついたまま前に進めず、足袋が滑って、むなしく足掻いているような形になった。楽屋からあわてて人が飛び出してきて、両側から介助する形で幕に入る。
痛々しい、という人もいるかもしれない。しかし私はその執念に心打たれる。
――夢は覚めにけり
西行の思い。老桜の精の思い。作者の思い。素顔をさらす梅若実の思い。虚と実のさまざまが重なって層をなし、結晶したような一言だった。
 プログラム掲載の写真。これは面をつけている。(吉越研撮影)
プログラム掲載の写真。これは面をつけている。(吉越研撮影)五月二十二日(土)『青天を衝け』月間
池袋の東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は原田慶太楼。
・グアルニエーリ:弦楽器と打楽器のための協奏曲[日本初演]
・ピアソラ:バンドネオン協奏曲《アコンカグア》(バンドネオン:三浦一馬)
・ヒナステラ:協奏的変奏曲
・ファリャ:バレエ組曲《三角帽子》第一番
晩年はアルゼンチンに亡命して同地で没したファリャも含めて、ブラジルとアルゼンチンのラテンアメリカ・プロ。
生誕百年のピアソラが軸になるとはいえ、これだけ挑戦的な選曲を思いきってして、成果を残せるのが今のN響。あえて定期を停止し、「令和以降のN響」を模索するための一年としたチャレンジ精神がお見事。
ラテンな熱い旋律が濃厚に歌われて、後半はノリノリのリズムで驀進して、グシャグシャの爆発でイェーイヒューヒュー、みたいな単純な曲が一つもないのがすばらしい(笑)。バルトークを範としつつ、熱帯の蒸れた空気を加えたようなブラジルのグアルニエーリ。夜の闇と空気、そして官能のピアソラ。ヒリヒリした響きに都会的な真昼の乾いたセンスを感じさせるヒナステラ。そして響きに生々しい力がみなぎるファリャ。
原田の特長たる肉体感の豊かな音楽。骨格があって肉づきがあって、そして俊敏に躍動する。
感心したのは、弦を対向配置とし、チェロを第一ヴァイオリンの後ろにおいたこと。二十世紀作品ならピアノ配置の弦のほうが演奏しやすいし指揮しやすい気がするが、あえてそうしないことで、響きに鮮明な立体感と遠近感、そして互いに聴きあおうとする集中力が出ていたのが見事。
特に合奏協奏曲的なグアルニエーリとヒナステラでは、首席を中心に各パートの実力が高いN響の美点が、生き生きと発揮される。どのパートも巨大音響装置の部品の一つではない。
三浦の音を慈しむようなバンドネオンも印象的。アンコールは大河ドラマ『青天を衝け』のエンディング「大河紀行」の音楽。
五月のN響演奏会は十五、十六日が尾高忠明指揮(モーツァルトの協奏交響曲とパヌフニクの交響曲第三番が素敵だった)、二十六、二十七日は広上淳一指揮で故尾高惇忠(ドラマはおだかじゅんちゅう、こちらはおたかあつただ)の交響曲が演奏される。三回合わせて『青天を衝け』月間だったことが、このアンコールでわかった(笑)。
そのしみじみとした音を聴きながら連想したのは、渋沢栄一と同時代を生きた薩摩藩士、村田新八のこと。
岩倉具視の欧米視察使節団に加えられるほどの才幹でありながら、下野する西郷隆盛を慕って薩摩に帰り、西南戦争に参加して城山で戦死した人。欧州旅行中に風琴(アコーディオン?)を手に入れて、帰国後も愛奏したという人物。
自分は三十一年前の『翔ぶが如く』で演じた益岡徹が、城山での最後の夜に風琴を弾き、おもむろに火にくべて、その炎をじっと見つめている場面が大好きだが、バンドネオンを聴いていたらそれを思い出した。
西洋で見たもの聞いたもの、個人の思いはさまざまにあったろうに、大西郷への恩義に殉じることを選んだ男。
『青天を衝け』のいいところは、当時の人が男も女も身分や立場にしばられて生きていることをしっかりと描いて、そこで自己を貫くには、それぞれにさまざまな道があることを示していることだと思う。
どれが正解というのでもない。それぞれがその役割をまっとうし、どんな人生の絵を描くか。
武士というのは、とにかくやせ我慢をしなければならない。義に殉じなければ武士ではない。慶喜はもちろん、幕府も水戸も薩摩も長州も、さらには百姓なのに武士になりたがった土方歳三のような男も、すべて。
栄一は、かれらの生きざまと死にざまを見つめつつ、武士の世の中ではない、人がもっと自由に人生の絵を描ける世界を求めていくはず。
幕末から明治へ、これからも楽しみ。
家に帰ると、ファリャがアルゼンチンで世を去ったという話から、亡命時代にファリャが指揮したライヴCDのことを思い出した。
スペインの名ソプラノ歌手、コンチータ・バディア(一八九七~一九七五)の生誕百年記念盤。バルセロナ生まれで、グラナドスやファリャから信頼された彼女も、スペイン内戦を期に一九四五年までアルゼンチンにいた。そして亡命してきたファリャと交流を深めた。

残っているのは一九四二年ブエノスアイレスのラジオ番組の録音三十分弱。ファリャ自らの指揮で《三角帽子》や《はかなき人生》の一部をバディアが歌う。
澄んで艶のある美声、そして意外なほどに濃密な語り口のファリャの自作指揮が聴ける。
五月二十七日(木)「ただいま」
ミューザ川崎にて東京交響楽団の演奏会。指揮はジョナサン・ノット。
・ベルク:室内協奏曲(ピアノ:児玉麻里、ヴァイオリン:グレブ・ニキティン)
・マーラー:交響曲第一番《巨人》
十四日間待機をへて登場したノット。昨年末の「第九」は聴けなかったので、自分にとってはずいぶん久しぶり。
映像で登場した昨年七月のテレコンダクター以来、リアルな実演では、一昨年十一月にマーラーの交響曲第七番を聴いて以来、ということになる。
ベルクとマーラーの初めにかけては、楽員との息がもう一つ合わず、のりきれない印象だったが、次第に感覚を取り戻して、最後は盛りあがった。カーテンコールでノットが「ただいま」と書かれた本拠地へのあいさつの白布を広げた瞬間は、なかなかに感動的だった。
 東京交響楽団の公式ツイッターから
東京交響楽団の公式ツイッターから六月二日(水)花を盗むのは誰

国立能楽堂の定例公演。《月間特集 日本人と自然 花鳥風月》の一つ。
・狂言『花盗人(はなぬすびと)』山本東次郎(大蔵流)
・能『吉野天人(よしのてんにん) 天人揃(てんにんぞろい)』山階彌右衛門(観世流)
国立能楽堂のサイトの解説。
花盗人「桜の花を折った盗人を捕まえてみると、漢詩や和歌を口ずさむ教養のある人物でした。風雅なやりとりや酒宴の場が楽しい曲です」
吉野天人「吉野山を訪れた花見の衆が出会った美しい女性は、吉野の桜に心引かれて舞い下りた天人でした。満開の桜の中、大勢の天人が花に戯れ舞い遊びます」
時季遅れだが桜でそろえた狂言と能。『花盗人』は東次郎のシテと泰太郎のアド、ほかに花見客六人と山元東次郎家勢ぞろいの賑やかな狂言。東次郎のちゃっかりしたシテが愉快。
『吉野天人』も「天人揃」の小書がつくことで、シテの山階彌右衛門のほか、天人が合わせて六人も出る華やかな能。
狂言には花見客がたくさん、能には天人が象徴する桜の木がたくさん。
プログラム掲載の村上湛の解説によると、『吉野天人』は観世十郎元雅の『吉野琴』の改作だが、実質は「江戸時代の新作能と考えるのが妥当」だという。
元雅の『吉野琴』のワキは紀貫之。大海人王子時代の天武天皇が、吉野山中に逃れて琴をひくと天女が現われ、「五節の舞」を舞った過去が回想される。
「五節の舞」は壬申の乱勝利の奇瑞になったとされる故事なので、南朝に近かったと考えられる元雅が、その勝利を願う底意を込めた能とみることもできる。歴史サスペンスのような楽しい想像。
しかしその後は上演が途絶え、番外曲となった。江戸中期、稀曲の復活を好んだ綱吉の命で蘇演されたころに、現行の『吉野天人』に改作されたらしい。
残された詞章は冒頭の次第のみで、あとは別物。ワキはただの「都の者」となり、天武天皇伝説は省かれ、ドラマ性や歴史性を消した、ひたすらに叙情的・幻想的な、単純な能となった。
天女が複数出て華やかな「天人揃」の小書は、天野文雄の『能楽手帖』によると江戸後期頃の考案だそう。能は六百年の歴史があるといっても、意外と近年の工夫が加えられている。
現代のダンスなどなら、群舞は主役を引き立てるようにつくられるけれど、能の相舞はまったく同じ振付になる。それだけに、シテに確固とした力量や存在感がないと難しいと感じた。
六月四日(金)三十九年後の邂逅


べしゃべしゃと雨が降り続け、まさに梅雨としかいいようのない天候の下、東京文化会館でサーリアホのオペラ《オンリー・ザ・サウンド・リメインズ‐余韻‐》のリハーサルを見学。
ゲネプロではないが、それに近い通し上演。休憩含めて二時間強。以下、ネタばれなしで感想を書く。
能の『経正』と『羽衣』の詞章の英訳(フェノロサの遺稿をエズラ・パウンドがまとめたもの)を歌詞に用いた、「オールウェイズ・ストロング」と「フェザー・マントル」の二部構成(タイトルは直訳ということらしい。平経正はおよそ、黄金バットみたいな「強い。絶対に強い」キャラではないから、名前負けの感も出てくるが…)。「オンリー・ザ・サウンド・リメインズ」というのは、『経正』の詞章「声は幽(かすか)に絶え残つて」あたりから採られているらしい。
独立した能が二本だから、第一部と第二部の内容に直接のつながりはない。第一部は幽霊、第二部は天女、いずれも現世の人間がこの世ならぬものに出会う、いかにも能らしい幽玄な話。
その意味では似たような話で、どちらも同じ二人の歌手、カウンターテナーとバリトンがシテとワキの役を歌う。しかし少しずつ違い、二本続けてみると、相違ははっきりとわかる。そして、最後にはちゃんとカタルシスがある(少なくとも、自分はカタルシスを味わった)。
淡い色と淡い色を並べると、色の個性がはっきり見えるみたいな。ならぶことで互いの特徴が見えてきて、より深めあう、とでもいうか。わかりやすい声高な主張を抑えて、見者に感じさせ、想像させ、考えさせるというこのあたりは、まことに能的。
能公演の多くが、一回が二曲あるいは三曲からなっていることもヒントにあるのかも知れない。
簡素な編成は能に倣っているが、音楽と舞台は能の模倣ではない。「幽玄」をオペラとして表現するにはどうするかを深く考慮し、咀嚼したもの。
とはいえ『羽衣』で私が偏愛する二つの詞、「世の憂き人に伝ふべし」と「いや疑いは人間にあり。天に偽りなきものを」が、きちんとドラマのポイントとして活かされているのは嬉しかった。
六日の本番ではより完成度を高めてくるだろうから、再見がとても楽しみ。
ところでプログラムには、現代の能楽研究の第一人者である天野文雄も文章を寄せ、フェノロサとパウンドの業績について説明している。
天野が二年前に上梓した『能楽手帖』(角川ソフィア文庫)は、現在上演される能のうち、復曲も含めた主な二百曲の解説本。あらすじだけでなく上演時間、作者の推定、改編の歴史や現在の演出の主なヴァリエーションなど、実演を見るときに必要な情報を最新の知見により、文庫サイズでコンパクトにまとめた素晴らしい本だが、あとがきに面白いことが書いてあった。

明治頃から、謡曲(能の詞章)は「綴れ錦(つづれにしき)」だと言われるようになった。「数々の古典から美辞麗句を取ってきて縫い合わせた古い錦のようなもので、そこには部分の美しさはあるが、全体はこれという脈絡のないものという、謡曲に対する揶揄」で、坪内逍遥あたりが言い始めたことらしい。逍遥はさらに「婆さまのチャンチャン」のようなものとまで言ったという。
文明開化で西洋のシェークスピアや近代戯曲に触れた逍遥たち、明治の教養人が能をひたすらに古くさく思ったのは、仕方のないことかもしれない。
少し前に読んだ野村光一の対談集『音楽を語る 3』(音楽之友社)で、辰野隆が西洋音楽を讃える一方で「日本の音楽なんてものは簡単なものですよ。あんなものは」と笑い、「田舎の単線の汽車みたいでね。淋しいものだ」と一九五五年に言っているのと同じ感覚(しかも、この部分の小見出しは誰の言葉なのか、『邦楽の「間」はマヌケの「間」』と、さらに強烈なものになっている)。

かくいう自分とて、つい七年ほど前まで似たような印象だった。
しかしその自分が、いま共感しているのは次の文章。
「能を実際に観劇することのなかったイェーツやパウンドを感動させたことも文学としての能の普遍的な魅力を物語っているであろう。
これらの戯曲すなわち能の数々は豊麗な表現と高潔な感情を合わせた、まさしく日本文学史における際立った傑作であり、曖昧さや引喩、それに言葉遊びに満ちたセリフは初めての観客には流れる節々を聞き取る以上は困難でもあるが、とは言え、決して机上のドラマではなかったのである」
これは、ドナルド・キーンの『能・文楽・歌舞伎』(吉田健一訳/講談社学術文庫)の一文。
さらにキーンは「数ある舞台芸術の中でも観客に最も多くを求めるのがおそらく能であろう」という。
感覚的にわかりやすいものを求め、美味しいものを消費するだけの、安直で独善的な現代の観客にはおよそ合わない、いわば注文の多い舞台芸術、能。
しかし、「能の意図するところは表面的な楽しみを追うことではなく、個を越え深淵へと向かい、究極的には人の心に触れんとするものである」
自分は、キーンが外国人だからありがたがるのではない。
それよりもこの人こそが、ラウリッツ・メルヒオールという不世出のヘルデンテノールを教えてくれることで、オペラの世界への扉を三十九年前に開いてくれた恩師だ、ということを思い出すのだ。
三十九年前はオペラ、今度は能。
自分の人生における、先導者としてのこの人の存在の大きさを思う。
──キーンさん、やっぱりここにもいてくれたんですね。
書物を通じてよき師に出会うことは、自らの心に灯をともすようなもの。
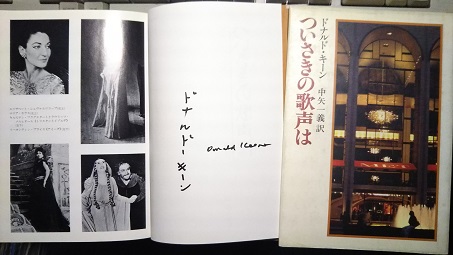
六月六日(日)冥界から天界へ
Dデイとオーメンの日、六月六日に雨ざーざー降ってきて、午後も雨が残る今日。東京文化会館でサーリアホのオペラ《オンリー・ザ・サウンド・リメインズ‐余韻‐》の本番。
やはりリハーサルとは気の入りかたも音響と照明の完成度も違い、作品と舞台が伝えようとするものがはるかに明快になっていた。
能の『経正』と『羽衣』。
ともにこの世には長く留まれない者と出会う人間の物語だが、前者が観客に残すもどかしさ、わだかまりが、後者の春の夜の月の光の中に解けていく、そのカタルシスが今日ははっきりとわかった。
それは前者を支配する、死しても消えぬ人間界の妄執や迷妄が、後者の天人の「いや疑いは人間にあり。天に偽りなきものを」の言葉をきっかけに、天界へ向けて浮き上がるようにほどけていく、その気持のよさ。
全体に冥界から現世、現世から天界へという、まるで『神曲』のような一つの流れ、上昇気流がつくられている。
原作の能の『経正』を見るときに大変なのは、目の前に経正役のシテがいて舞っているのに、「姿は見えずに声だけ聞こえるぞ」というワキのセリフを信じて、本当は見えないんだと全力で想像しなければならないこと(笑)。暗闇の空間に灯火の炎が揺らめくと輪郭だけがときどき朧に見えたりするとか、そんな光景を脳内に作らなければならない。
しかしオペラなら具現化できる。障子に映る人影のように、経正を見せないでいることができる。琵琶を通じてのシテとワキの心の触れあいを、性愛を暗示するものとしたのもよし。当時の仁和寺の法親王と稚児ならばそういう関係で当然だし、法親王に仕える行慶僧都と同様の関係でも不思議はない。
中間部であまりに動きが少なくて眠気を誘ったのは、悪い意味で「いかにも能的」といえるかも(笑)。
ただ能では、一ノ谷で戦死した経正が修羅道に落ちていて、その醜い姿を見せたくないために消えるというのがポイントなのだが、フェノロサ/パウンドの訳文と今回の舞台は、そこがわかりにくくなっていた。
平家物語のつきることのない魅力の源泉は、王朝物語と軍記物と仏教説話、貴族と武士と僧侶の三世界の微妙な力関係にこそある。これは平家ものの修羅能が見事に舞台化した要素で、自分などは能に興味を持ったからこそ、その点に気がつくことができた。
平経正はまさにその典型で、殺生で穢れた武士階級の出身なのに、名門の公家の子弟のように名寺の稚児として育ち、教養豊か。典雅な王朝世界に生きたいと欲しながら、戦場で生命の取りあいをして死ぬ。そうして修羅道に落ちた、その慙愧と無念。
シテの背景にあるこの感覚は、謡曲では自明のものとして直接説明してはいないから、英語世界の人が理解するのは難しいのかもしれない。苦しみだして、いきなりハラキリ(明治から昭和にかけ、日本人の特徴と考えられていたもの)。
だから、最後がもどかしい。割りきれない悪夢のような、むずむずする感じが残る(地謡として舞台の外、ピットの中にいたコーラスが、ここで突如として舞台にあがり、劇に参加したことの意味はよくわからなかった。修羅の世界の住人たちなのか)。
しかしこのもどかしさを、人の不安と猜疑が生む苦悶ととらえて、第二部へ向けての準備としたのは見事。
死んで姿形を失った冥界のものが、夢の中でなんとかこの世に出てこようともがいた第一部に対し、第二部は現世の話で、放置すればやがて失われてしまう美しいものを天界に返し、褒美としてその模倣、永遠なるものの比喩としての現実の舞踏(芸術すべての象徴か)を得るという話。
第二部は音楽もはるかに多彩で華やかで、生命力も豊かになる。二十台のスピーカーを用いたエレクトロニクスの効果もより鮮やかで、妙なる天人の声のこの世ならぬ不思議さも、絶妙のエコーの付加であらわされていた。
初めの部分だけ、コーラスが舞台の上に立ち、ドラマに参加したのも面白かった。全曲の中でここだけはワキツレ、ワキと一緒に舞台に出たワキ方が歌う部分なので、たしかにオペラの合唱のようになるのが正しい。そしてそのあとはピットに入って、地謡の役割に徹する。
「ときどき原文と無関係」とキーンがいうだけあって(笑)、後半の設定は少し能と違っていた。能では天人はあくまで一人だし、そして太陽が出ている時間(印象としては午後遅く、夕焼けになる直前)のはずだが、このフェノロサ/パウンド訳では天人は十五人に分身し、月光の空に舞う。元の詞章のイメージを自由にふくらませた感じ。
今回の演出はこの違いを効果的に活用した。天人役の歌手が苦しみだすところで、同じ扮装のダンサーが登場する。まるで天人の魂(ダンサー)と肉(歌手)がもう分裂しはじめているかのように。ところが羽衣を返してやると、活力を取り戻した天人は完全に二人に分身し、漁夫を驚かせる。そうして舞が始まり、さらに数も増えていくことが暗示される。
ラスト、はるか天空に輝く月の中で舞っているようなシルエットが、とても美しかった。舞う姿がそのまま最後に月に吸い込まれていく最後は、能では『融』が有名だが、月宮殿の天人たちがそうであっても不思議はない。「世の憂き人に伝ふべし」といわれたダンスを、歓喜して踊りつづける漁夫白龍。
五時過ぎの終演後に外へ出ると雨が上がり、日が長い時期だけに爽快な青空となっていた。
六月七日(月)エルサレムSQ(一)
昨日のサーリアホのオペラ、何はともあれ歌手もスタッフも作曲家も日本に来れたのが、じつにありがたかった。経済面と精神面の負担は、呼ぶ方も来る方も並大抵ではないだろうが…。
サーリアホは待機期間中に転倒して足を痛め、四日のリハの時点では車椅子だったが、本番の日は杖をつきながらも自ら歩いていて、一安心。カーテンコールでもきちんと立って答礼していた。
十四日間ものホテルでの待機は、ストレスたまるだろう…。
ところで能がらみのオペラは、今年は細川俊夫の《二人静》の日本初演も八月に予定されている。
併演がマーラーの《大地の歌》のコーティーズ編曲による室内オーケストラ版という、私などには夢のように楽しみな二曲の組み合わせで、しかも演奏者が超豪華。
結構な人数になるだろうアンサンブル・アンテルコンタンポランが無事に来られるのだろうかという不安はあるが、なんとか実現してほしいもの。
昨日開幕したチェンバーミュージック・ガーデンは、交代や中止、日程順延などの変更が一部にあるが、大半は予定通り公演される。八月のサマーフェスティバルもサントリーホールの実行力で実現することを祈るのみ。
夜はそのサントリーホールに行き、小ホール、ブルーローズでのチェンバーミュージック・ガーデンから、エルサレム弦楽四重奏団によるベートーヴェンの全曲ツィクルス第二夜を聴く。第二番、第八番《ラズモフスキー第二番》、第十三番(終楽章は大フーガ)。
六月八日(火)エルサレムSQ(二)
昨日に続き、ブルーローズでエルサレム弦楽四重奏団によるベートーヴェンの全曲ツィクルス第三夜。第四番、第十番《ハープ》、第十五番。
六月十日(木)エルサレムSQ(三)
ブルーローズでエルサレム弦楽四重奏団によるベートーヴェンの全曲ツィクルス第四夜。第三番、第九番《ラズモフスキー第三番》、第十四番。
エルサレム弦楽四重奏団は昨年にこの恒例のツィクルスをやるはずだったが、コロナ禍で一年延期。来日後十四日間の待機をへての登場。
アメリカ型のクァルテットの系譜を継ぐ、大ホール向けの音量とエネルギー。高くて安定感のある技術力。ユダヤ系らしさは、緩徐楽章での濃厚な祈りの歌となって発揮された。
六月十一日(金)拒絶と普遍
東京芸術劇場でNHK交響楽団の演奏会。指揮は下野竜也。
・フィンジ:前奏曲
・ブリテン:シンフォニア・ダ・レクイエム
・ブルックナー:交響曲第〇番
鎮魂交響楽に無効交響楽。委嘱元から演奏を断られた前者と、作曲者が無効の烙印を押した後者。フィンジの作品も生前に演奏されなかった点がブルックナーと同じ。下野ならではの凝ったプログラム。「拒絶音楽会」とでもいうか。
自分は前の晩に、ブルーローズでベートーヴェンの弦楽四重奏曲第十四番を聴いていた。これは演奏者から「演奏不可能」として断られ、ベートーヴェンの生前には初演されなかったという難曲なので、今日に続けると、演奏者、委嘱者、作曲者と三者三様に拒絶された楽曲が偶然にそろって愉快(どれも好きな作品であるし)。
ヴォーン・ウィリアムズを想わせる叙情的なフィンジ作品から、そのままブリテン作品の不安と危惧に満ちた開始につなげる工夫がうまい。両大戦間の平和から戦争の時代へ。シャープで鋭敏な演奏だけに、これを皇紀二千六百年記念祝典で歌舞伎座で演奏していたら、みんなどんな顔して聴いたのだろうとか、そもそも当時の日本のオケの技術でまともに演奏できたのだろうかとか、いろいろイメージがふくらむ。
後半のブルヌル。ブルックナー開始もブルックナー休止もちゃんとあって、やっぱりブル太郎飴の一つという感じなのだけれど、第三楽章スケルツォの低音の刻みがロッシーニみたいだったり、第四楽章の主題や動きがオペラ風にドラマチックなのが楽しい。リンツからウィーンに引っ越してきて、宮廷歌劇場でいろんなオペラ聴いたのが思わず入り込んでしまった、みたいな。だから本人は無効としたのかもしれないが、このブルックナー的でないところが自分は好き。
下野は作品を熟知した、確信感にみちた指揮ぶり。前半二楽章でのルフトパウゼは、NHKホールよりも残響豊かなので効果的だったし、硬質のサウンドもサントリーホールより音が広がらないので明確だった。東京芸術劇場の音響が活きていた。
ただ、一階平土間の客が百人いるかどうか、ひょっとしたらオーケストラよりも少なかったかもしれないのは、演奏がよかっただけに残念。自分も含めて、開演直前に不安げに周囲を見回すお客が多かった。これまでN響とは縁の薄い池袋地区で、平日で十八時半開始というのが足を引っぱったのか。
当然、男子トイレのブルックナー行列はなかった。残念ではあったが、しかし演奏は真剣で気魄に満ちていた。
帰宅後、ネットでフェロノサ/パウンド訳の謡曲の英文を検索してみる。ヴァージニア大学図書館のサイトにあった。
これを見ると、あくまで記憶に頼ってだが、サーリアホのオペラは一部の改変(「TSUNEMASA」を「Always Strong」にしたり、琵琶の「青山」SeizanをBlue Mountainに変えるなど)はあるが、ほぼ原文を歌詞として用いている。
英語という、事実上世界の公用語となった言語による一九一六年のテキストを尊重し、それに音楽を新たにつけたという意味で、この作品は「能のオペラ化」というより「英語謡曲のオペラ化」なのだろう。能の上演における瑣末な表面を模倣するのではなく、始源にさかのぼって、より普遍化された神話から、新たなオペラを生みだそうとする試み。
そこに込められたフィンランド人作曲家としての自負は、民族楽器カンテレの使用に現われている。
『経正』の修羅の苦しみを単純化しているのも、フェロノサ/パウンド版によるもの。死者が姿を見られるのを嫌うのは、むしろ黄泉のイザナミ的な感覚か。
羽衣伝説は世界共通だけに、『羽衣』はより普遍性を持ちやすい。
フェロノサ/パウンド版は月宮殿の天女と、太陽の下にある人間界を対比させることで日の本の国、すなわち「日本」を意識させようとする気配があるが、オペラはそうした、日本を強調する要素を削除していたように思う。
また、詞章のラスト。
「天の羽衣、浦風にたなびきたなびく。三保の松原浮島が雲の、愛鷹山や富士の高嶺。かすかになりて、天つ御空の霞にまぎれて失せにけり」
これは松の木、愛鷹山、富士山の高さと、天女がぐんぐんと上昇して天空の霞に消えていくさまを、簡潔に固有名詞を並べるだけでイメージさせ、とても素敵だ。フェロノサ/パウンドもこれを英語にしているが、オペラはここが日本人以外にはわかりにくいとみたのか、かなり省略してあったと思う。
それにしても、パウンドが手を入れた詩の言葉はさすがに美しい。
「ただ今ここにて奏しつつ。世のうき人に伝ふべし」は、
「No, come here to learn it. For the sorrows of the world I will leave this new dancing with you for sorrowful people」
になる。「学べ」という一言があるので、漁夫は踊りを真似しはじめる。
「いや疑は人間にあり。天に偽なきものを」は、
「Doubt is fitting for mortals; with us there is no deceit」
相手を「死すべき者」と見下すことで、「私たち」という言葉に昂然たる気配が出る。「doubt」と「deceit」の対照もさすが。
出版の前にパウンドは、フェロノサの未定稿を自らの師である詩人イェーツに見せている。
そのスタイルに大きな影響を受けて、イェーツは戯曲数本を書きあげた。その代表作が『鷹の井戸』。一九一六年ロンドンでの初演では伊藤道郎が鷹役を演じた。一九三九年には日本でも上演。
一九四九年には横道萬里雄が翻案して新作能『鷹の泉』とし、一九六七年にはより演劇的要素を強めた能『鷹姫』に改作した。この『鷹姫』は、近年上演機会が多い。サーリアホを見たところで、あらためて見てみたいものだ。
ケルト伝説によるこの『鷹姫』の登場人物の一人は、英雄ク・フーリン。日本でク・フーリンといえば山岸凉子の傑作『妖精王』。『妖精王』といえば夏至の前の夜。今年は六月二十日の夜。あと八日。晴れますように。

『TSUNEMASA(経正)』
http://jti.lib.virginia.edu/japanese/noh/PouTsun.html
『FEATHER MANTLE(羽衣)』
http://jti.lib.virginia.edu/japanese/noh/PouHago.html
六月十二日(土)善知鳥
国立能楽堂で普及公演。《月間特集 日本人と自然 花鳥風月》
・解説・能楽あんない 能・狂言の鳥 竹本幹夫(早稲田大学名誉教授)
・狂言『千鳥(ちどり)』善竹忠重(大蔵流)
・能『善知鳥(うとう)』金井雄資(宝生流)
『善知鳥』は、殺生を生業としたために、死後地獄に落ちて苦しむ者をシテとする能で、同様の話の『阿漕』『鵜飼』とあわせて「三卑賤」と呼ばれる。生きるために手を汚さねばならない階層の苦しみ。
芝居風のリアリズムとスケールの大きな幻想性が結びついて、想像力の翼を羽ばたかせる能。
……なのだが、もう一つ集中できないまま終わる。宝生流の品のよさか。
六月十五日(火)時の果てに鳴る音
ブルーローズで、小菅優プロデュースの武満徹「愛・希望・祈り」~戦争の歴史を振り返って~の第一夜。
・武満徹:《二つのメロディ》より第一曲アンダンテ
・武満徹:カトレーンⅡ
・メシアン:世の終わりのための四重奏曲
《世の終わりのための四重奏曲》が凄まじい演奏だった。
時の終点、「審判の日」の暗闇に鳴り響く、時の進行が完全に止まったかのような濃密な音楽。小菅のピアノはもちろんのこと、吉田誠のクラリネットもベネディクト・クレックナーのチェロも凄かったが、最後を飾る金川真弓のヴァイオリン・ソロが圧巻。来日できなかったアレクサンダー・シトコヴェツキーの代役とはとても信じられない出来。
十七日の第二夜もものすごく楽しみ。こちらもストラヴィンスキー、武満、アイヴズ、ショスタコーヴィチと選曲が素晴らしい。
六月十六日(水)ピアノの万華鏡(一)
ブルーローズで、バスバリトンのクレシミル・ストラジャナッツ、フォルテピアノの小川加恵、ヴァイオリンの水谷晃によるリート・リサイタル。昨夜の濃密とはまた別の魅力の、気持のいい時間。
シューベルト、シュポーア、シューマン夫妻、十九世紀半ばまでのロマン派の音楽。二十世紀音楽とモダン楽器の組み合わせによる強靱で自己主張のきつい音響よりも古い時代の音を、人の自然な発声と一八三五年製フォルテピアノ、ガット弦のヴァイオリンが奏でていく。
ストラジャナッツの無理なく、豊かに響く美声が耳と身体に心地よい。シューベルトの〈夜と夢〉での弱音の、見事なブレスコントロール。すっくと立つ息の柱。空気になじむピリオド楽器の音。
シュポーアのヴァイオリンつきの〈魔王〉というのが貴重だったが、アンコールにシューベルト版が出ると、やはり後者の偉大さを再確認してしまう(笑)。父と子、死に神の声色の使いわけがさすがに巧み。
もう一曲のアンコール、〈浜辺の歌〉の日本語の美しさにも感服。ストラジャナッツは二週間待機をしながらも、十一日の岐阜サラマンカホールの公演は無観客で配信のみになったそうで、ブルーローズ公演だけでも有観客で実現できて何よりだった。
なおこれは「フォルテピアノ・カレイドスコープ」というシリーズの第二日。初日は佐藤俊介などが来日できず中止となったが、あと二回ある。
第三日はホフマン(一七九五年製)と N・シュトライヒャー(一八一八年製)の二台、第四日はエラール(一八六七年製)と、まさに万華鏡のごとく十九世紀のさまざまなピアノが出てくる。
以下のyoutubeは、十一日岐阜のためのストラジャナッツのリハーサルから。
https://www.youtube.com/watch?v=izygidO_uqg
六月十七日(木)円環の四時間
ディスクユニオン新宿店、現在の紀伊國屋書店のビルから、建て替えが完了したビルに移転(元の場所に復帰)。三階なので昇降もラク。七月九日から。
自分は次の朝日カルチャーセンターの講義が十四日なので、そのときに行けそう。新宿もだんだん人出が戻り、紀伊國屋書店のエレベーターも再び混雑して乗るのがたいへんになりそうだったから、あれに乗らないですむのは大助かり。
一方、紀伊國屋ビルの方は耐震補強工事のため、地下名店街の九店が七月十五日で閉店するそう。
夜はブルーローズで、小菅優プロデュースの武満徹「愛・希望・祈り」~戦争の歴史を振り返って~の第二夜。これも素晴らしいものだった。
全体のアンコールとして、最後に〈聞かせてよ愛の言葉を〉を置くのは、武満徹と大戦との関わりを考えれば当然に予想できるのだが、しかしそれが現実の音として響くことで、頭で考えた理屈を跳びこえ、耳から心に啓示のごときものとなって生命の光輝と熱をもたらす、その見事さ。
二晩、四時間の音楽がそこで円環となり、一つの小宇宙をなしていく。その最後の成立の瞬間に今まさに立ち会っているという、時間の芸術としての音楽ならではの歓喜。
そして、鳴りやんでしまえばすべては幻。残るのは光と温もりの記憶だけ。某紙に評を書くので、あとはそちらに。
六月十八日(金)
国立能楽堂の定例公演。
《月間特集 日本人と自然 花鳥風月》
・狂言『箕被(みかずき)』大藏彌右衛門(大蔵流)
・能『松風(まつかぜ)』狩野了一(喜多流)
六月二十二日(火)
オペラシティコンサートホールで、NHK交響楽団の「ミュージック・トゥモロー2021」。指揮は杉山洋一。
・西村朗:華開世界~オーケストラのための(二〇二〇)[NHK交響楽団委嘱作品・世界初演]
・間宮芳生:ピアノ協奏曲第二番(一九七〇)[第十九回尾高賞受賞作品](ピアノ:吉川隆弘)
・細川俊夫:オーケストラのための《渦》(二〇一九)[第六十八回尾高賞受賞作品]
六月二十三日(水)
ブルーローズで、「フォルテピアノ・カレイドスコープ Ⅲ」。ベートーヴェンのチェロ作品を集めた一夜。チェロは酒井淳、フォルテピアノは渡邊順生。前半は一七九五年製ホフマン、後半は一八一八年製シュトライヒャーを使用。
・チェロ・ソナタ第一番
・モーツァルトの《魔笛》より「恋人か女房か」による変奏曲
・チェロ・ソナタ第四番
・チェロ・ソナタ第五番
六月二十四日(木)十五分早く
明日二十五日、日生劇場での藤原歌劇団の《蝶々夫人》初日、開演を十五分早めて十八時十五分開演に変更とのこと。
留守電が入っていたので、また都議選関係だろうと思ったら、そうではなくて変更の電話連絡だった(笑)。
三十分繰り上げられたのを知らずにいったら、たぶんただ遅刻するだけだが、十五分前だとちょうど着く頃だから、着いた途端に「まもなく開演です」と急かされて、大慌てになる可能性が高い時間差。日生劇場の二階席などだと、たどりつくのにけっこう時間かかって心臓に悪いので、先に教えてもらって助かった。
しかし正直、十五分遅くなるとゾンビの群れが霧とともに夜の日比谷に出てくるとかいうわけではなし、やる側も見る側も、効果に比べて負担ばかりが大きい変更という気がする。
六月二十五日(金)慶応三年生まれ
コンサートとオペラのはしご。
まず十四時からサントリーホールのブルーローズで「フォルテピアノ・カレイドスコープⅣ」。川口成彦(フォルテピアノ、一八六七年製エラール)、原田陽(ヴァイオリン)、新倉瞳(チェロ)。
素晴らしく気持のよい演奏会だった。初めのグリーグのピアノ三重奏断章とラヴェルのヴァイオリン・ソナタまでは暖気運転という感じだったが、前半最後のフォーレのピアノ三重奏曲から三人が本領発揮。
生命力と多彩な語り口、そしてなんといっても平行弦ピアノとガット弦の弦楽器二梃の共鳴が生み出す、聴くものを吸いこむような、澄んだハーモニーの美しさ。ピリオドによる近代フランス室内楽は、こんなにも魅力的に響くのかと、目からウロコが落ちるような驚き。
透明度の高い三枚の薄布が、風に吹かれて揺れ動き、さまざまに重なって色彩を変化させていくような、淡く爽やかな音のグラデーション。空気と調和する謙虚な音。相手を受けいれる余白と余裕、耳を傾ける気遣いをもった、マナーのよい音の快感。
曲よりも演奏よりもまず、その響きに耳をひたすのがどうしようもなく心地よい。もちろんそれは、奏者たちが優れた音程感、機械的ではない相対的なそれをもって楽器を奏で、対話し、共存させているからだ。
青薔薇の音響はモダン楽器だと強く響きすぎるが、平行弦とガット弦の澄んだ音に関しては理想的な、日本有数のホールではないだろうか。
後半は、没後百年のサン=サーンス。
まずは川口のソロで、バッハの無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータから二曲を、サン=サーンスがピアノ用に編曲したもの。
こういう編曲があることなどまったく知らなかったが、ただピアノに置き換えるだけでなく、「合いの手」みたいな音や声部をロマン派風に加えているのが面白い。聴くうちにバッハの時代、サン=サーンスの時代、そして川口と私たちの時代と、時間が多層化され、歴史化される愉悦。
川口が昨年年末のランチタイムコンサートでも、グラナドスが編曲したスカルラッティのソナタ五曲という珍品を取りあげて、やはり多層化の快感を味合わせてくれたのを思い出した。
昔と今、彼と我、という主観的な把握が、第三者の時間を挟むことによって相対化され、それぞれの位置と距離感がより明快な、歴史となる。
続いて新倉の《白鳥》。エンドピンを用いずガット弦でひく。この人はかつて「Jクラ」の典型的な売り方をされた人と記憶するが、それからスイスに渡り、真摯に学んだという。誠実な姿勢と心持ちがそのまま音になっていると感じた。
最後のピアノ三重奏曲第一番では、フォーレで聴いた爽快なグラデーションが再来した。
 サントリーホール公式アカウントのツイッターから。
サントリーホール公式アカウントのツイッターから。今回用いられた一八六七年製エラールはサントリーホール所有の楽器で、チェンバーミュージック・ガーデンにピリオド楽器のコンサートが加わるきっかけになったもの。リストも弾いたことがあるといわれるこの楽器を、福澤諭吉の孫でフランス文学者の福澤進太郎がパリで購入し帰国、その妻となったパリ音楽院出身のギリシャ人歌手、福澤アクリヴィが大切に使っていたものという。
 福澤アクリヴィのCD
福澤アクリヴィのCDトスカニーニと同い年、明治ゼロ年にあたる慶応三年生まれの楽器。
そういえばこの年は、正岡子規・尾崎紅葉・斎藤緑雨・夏目漱石・南方熊楠・幸田露伴・宮武外骨という、やたらに豪華な明治人たち(満年齢が明治と一緒なのでわかりやすい人たち)の生まれた年でもある。
坪内祐三が『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』というとても面白い本にしていた。ただ、この著者によくあることだが、途中で書くのに飽きてしまったために、盛大な竜頭蛇尾に終わるのが残念でしたが。その坪内も昨年急逝。
ふり返れば素晴らしき人ばかり。そして楽器は、さまざまな人の想いを鍵盤に重ねて生き続けていく。
慶応三年生まれの平行弦ピアノ。これからもその澄んだ響きをたくさん青薔薇で聴けますように。
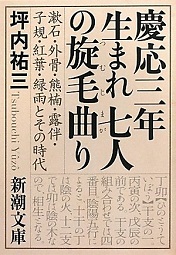
続いて、日生劇場の藤原歌劇団の《蝶々夫人》初日へ。
十八時十五分の開演まで一時間半以上あるので、日比谷劇場街をうろつきながら腹ごしらえをすることに。日比谷シャンテの地下二階にレストラン街があるので、そこで物色。
以前なら十七時前だと開けている店が少なくて選択肢がかぎられたが、今は二十時閉店のためかどこも早くからやっているので、この点は助かる。
このレストラン街、初めて来たがいい感じ。ほとんどの店の店内が通路側から見えるようになっていて、雰囲気や混み具合がすぐにわかるのが開放的でいい。
それに、自分はいま東京随一の劇場街にいるのだという、ある種の昂揚感を、街路を歩くよりもひしひしと感じられるのが快感。それは周囲の人々(ほとんど女性)が、これから舞台や映画を見るのか見たあとなのか、その期待や興奮を上気した表情にあらわしているから。ここはこの時間帯には、特にそういうお客が来るレストラン街らしい。
朝日カルチャーセンターのオンライン講座で片山さんと続けている「音楽の殿堂としてのホール」、次の九月は日比谷劇場街をメインにするつもりなので、この雰囲気を味わえたのはありがたい。
経験的に、こういう劇場的興奮が包んでいる空間にある店というのは、気配に張りがあって、気持のいい店が多い。迷ったあげくに自分が入ったのは「五穀」というほかにもあるチェーン店だが、やはり美味だった。すぐ顔に出るので公演前にはアルコールを避けているが、このご時世でノンアルコールビールがおいしくなったのはありがたい。アルコール入りよりお腹が膨れないのも助かる。

十七時半過ぎに地上に出ても、まだ全然明るい。日比谷シャンテ前にあるゴジラ像、五年前に「帝都クラシック探訪」の取材で片山さんと来たときにはキンゴジかなにかのゴジラだったが、今は最新のシン・ゴジラに変わっていた。一九三二年発祥の銀幕と舞台の東宝、というビルの文字が誇らしげ。劇場街の大半が小林一三の東宝というのが日比谷の特色。

日生劇場はそのなかで、ほぼ唯一の非東宝の劇場。しかし非日常的な夢の場としては、やはり重要な一つ。
ここで舞台公演を見ることが脳にもたらす独特のワクワク感は、小六で見た劇団四季のジョン万次郎のミュージカル以来、今も変わらない。一九六三年開場、自分と同い年の劇場内の雰囲気は、コロナ禍の困難のためか少しすさんでいる気もするが、人が戻ってくればワクワク感もすぐに戻るだろう。
故粟國安彦の演出は一九八四年初演のオーソドックスなもので、二年後につくりなおされた川口直次の美術は、地方への移動公演も考慮して組みやすく作られていますが、美しく効果的なもの。
蝶々さんの、ここではない夢の国アメリカへの一途な憧れの背景となる、今いるところ日本への強烈な嫌悪と絶望の念を、舞台に視覚化してしまうことは可能だけれど、それは心地よくないと思うお客さんもたくさんいるだろう。
自死へと突っ走っていく、幕末から敗戦までなら理解しやすかったろう蝶々さんの心情――日本社会を厭いつつ、じつのところ彼女は日本的封建主義の美学の体現者。むしろそれゆえに、封建主義の建前の陰にある、性搾取という獣性を憎むのだ――が現代日本人には遠くなっているのと同様、「フジヤマ、ゲイシャ、ハラキリ、カブキ」的な日本景色と文化も、もはや我々の周囲からは遠くなっている。すべてを過去の風景と人々、彼岸の夢としたほうが楽かもしれない、などとも考える
しかし、どんなにその心情に共感しづらかろうと、クライマックスで思いつめていく蝶々さんを描く歌と音楽のドラマの力だけは不変の、普遍的に強く訴えるもの。ヒロイン役の小林厚子は声が疲れているのか本調子ではなかったが、放射するオーラはやはり大したものだった。

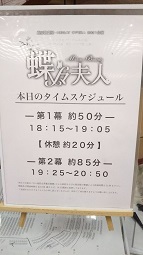
六月二十六日(土)バブル式演奏会
東京芸術劇場で、一年半ぶりのタケシことアラン・ギルバートの指揮で東京都交響楽団の演奏会。十六型で濃厚に響かせるアメリカン・プロ。アイヴズはパロディ要素を抑えて正々堂々の演奏。来週のペッテションも楽しみ。
指揮者は袖から出ると階段で客席に降り、指揮台手前でまた階段を上がる。じつにバリアフルなカーテンコール。
通常の十四日間待機ではなく、バブル方式の隔離で一週間ほど前に来日。他者との接近が制限されているため、このような形なのだとか。舞台上に通路をつくる必要がないので、弦楽器のディスタンスも平均してとれる。プログラムによれば七月十八、十九日のハーディングも来日可否の判明は一週間前頃とあるので、やはりバブル方式らしい。欧州の音楽界が動き出すとみな忙しくなって、短期間ですむこの方式でしか、来日しようがなくなるのかも。
 東京都交響楽団のツイッターから。
東京都交響楽団のツイッターから。六月二十七日(日)平家物語の後始末
昼は観世能楽堂に行き、観世流シテ方の「奥川恒治の会」へ。
・仕舞『忠度』観世喜正
・仕舞『佛原』観世喜之
・仕舞『船弁慶』小島英明
・狂言『茶壺』野村万蔵、野村万之丞、能村晶人
・能『大原御幸』
奥川恒治(建礼門院)、伊藤嘉章(後白河法皇)、永島充(阿波ノ内侍)、坂真太郎(大納言ノ局)
殿田謙吉(ワキ)野口能弘、大日方寛、野口琢弘(ワキツレ)
野村拳之介(間)
杉信太朗(笛)、飯田清一(小鼓)、亀井広忠(大鼓)

まず三つの仕舞が、一ノ谷の敗北、権力者の寵を得ることの虚しさに気づいて出家する白拍子、滅亡後の怨霊化と、平家と周囲の人々の姿を三様に描く。
能『大原御幸』は、壇の浦の戦いから一年後の晩春、出家して大原に隠棲した建礼門院の許を後白河法皇が訪ねる場面を平家物語に従って描いたもの。夢幻能ではなく現実能で、平家物語をそのまま舞台化、芝居化したような趣である。
この能については、白洲正子の『謡曲平家物語』での解釈が鋭い。

寂しく静かに一門の菩提を弔って暮らす建礼門院に対して、後白河法皇一行は「九重の、花の名残を尋ねてや、青葉を慕ふ山路かな」という出の謡からして、物見遊山の気分だと指摘する。「花の名残」や「青葉を慕ふ」という詞は、
「自然の風景にことよせて、盛りを過ぎた女の美しさを謳っており、傷心の女院を慰めに行くというより、好奇心が先に立っているらしい。それが遊び好きの法皇や宮廷人のほんとうの気持だったであろう。順を追うにしたがって、それは次第に明らかになっていく」
その後も詞章には、法皇の下心が見え隠れするという。法皇の和歌「池水に汀の桜ちりしきて 波の花こそ盛りなりけれ」も引用される。
「露にまみれた夏草も、乱れた青柳も、波に翻弄される浮草も、そしてこの御製も、見ようによっては入水した女のなまめかしさを歌っており、法皇の心がそそられて行くさまを形容しているように見える」
女院と再会した法皇は、都落ちから西海での日々の過酷な思い出を、仏教の六道にたとえて語らせる。さらに、安徳帝の最期の様子も語らせる。つらい記憶と向きあう女院の気持など気にせず、というよりもわざと踏みにじり、いたぶるかのようでさえある。白洲はいう。
「女院が一番忘れたい過去のことを、改めて聞くというのは残酷極まりないことだ。法皇はほのかな恋心を、女院が受けつけないと知って、かわりにこのような難題を持出されたのかも知れない。が、女院が生死の境で体験したことは、世間の人々も聞きたい所であった。いってみればこの場合の法皇は、大衆の代表者で、別に法皇だけが残酷というわけではない」
興味本位で独善的な大衆の、代弁者としての法皇。私たちの代表だ。
女院はけなげに一門の入水を語る。二位の尼に抱かれ、「今ぞ知る御裳濯川の流れには 波の底にも都ありとは」と辞世の句(木ノ下歌舞伎の『義経千本桜』で三度くり返されたもの)を詠んで、海中に沈む安徳帝の最期。
二位の尼と幼帝、そして平知盛の入水の場面を舞台で演じる能は、『碇潜(いかりかづき)』の禅鳳本による演出がある。しかし『大原御幸』は直接にではなく、過去の記憶として女性に語らせる。
語りだけだから派手ではない。だが、それだけに味わいが深い。
陽光にきらめく清水、瑞々しく繁る青葉、閑寂の大原。そこで語られる、武士たちが首を取りあい、一門が入水する酸鼻な戦場の記憶。
静寂の現在のすぐ後ろに、叫喚の過去がある。明るく緑なす山の真下に、人を呑みこむ暗い海が波うつ。坦々と進む表面の裏に、壮大な歴史劇がある。
現在能なのに、背後には無数の人々の思いと盛衰の物語が渦巻いているのだ。
物語を締めくくるにふさわしい能。
もういちど白洲正子を引くと、平家物語や源平盛衰記の描写に従えば浮草のような素質をもち、その頼りなさが魅力となっているような女院の人間臭さが、この能では清浄無垢な尼僧に昇華されている――ふれなば落ちん風情を、美しい風景描写の奥に、たくみにかくしながら――という。
「女院を美化することによって、この世では達することのできなかった、成仏の境地に至らせた。ここでも謡曲は平家物語の後始末をやってのけたのである」
能になったことで平家物語は生彩と魅力を増し、不滅の輝きを得ている――そう自分が感じていたことを「後始末」の一語でスパッと言いきってくれていて、膝を叩きたくなる。
夜はサントリーホールのブルーローズへ行き、チェンバーミュージック・ガーデンの楽日で、ピアノ三重奏のヘーデンボルク・トリオ演奏会。
ヘーデンボルク三兄弟は母親が日本人で、ヴァイオリンとチェロの二人はウィーン・フィルの団員としても活躍中。二十一日の予定だったのがコロナ禍の渡航制限で来日が遅れ、今日に延期されたもの。ともかく実現できてよかった。
・ベートーヴェン:ミュラーの《私は仕立屋カカドゥ》による変奏曲
・ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲第五番《幽霊》
・ブラームス(キルヒナー 編曲):弦楽六重奏曲第一番(ピアノ三重奏用版)
バランスのとれた気持のいい演奏で、特にブラームスの弦楽六重奏曲第一番をキルヒナーがピアノ三重奏に編曲したものは珍しさをこえて印象的だった。
キルヒナーは、シューマンやブラームス、クララ・シューマンと懇意だった作曲家。フォーレ四重奏団がシューマンとあわせて録音したピアノ四重奏曲のCDで知っていたが、編曲もうまい。
作曲家本人以外の編曲は、オリジナリティ重視の二十世紀中にはとかく軽視される傾向があったが、現代では柔軟にその価値を認めることができるようになったのだろう。一九九〇年代初めの頃、カザルスホールでデ・レーウ、ベス、ビルスマが《浄夜》のシュトイアマン編曲によるピアノ三重奏版を演奏してくれたときには、録音がほとんどなかった記憶がある。しかし今はけっこうCDが増えてきた。オリジナルとはまた別の魅力があるからである。それと同様、このブラームスもピアノ・トリオの新たなレパートリーとして、これからも聴いてみたくなるものだった。
アンコールにはサン=サーンスの《白鳥》が演奏された。直前にあいさつした長兄ヴィルフリート・和樹が、演奏できる喜びを話そうとして泣きだしてしまった。「音楽の都」ウィーンに暮らす音楽家にとって、演奏の機会を奪われることがどれほどの苦しみかを実感する。
六月二十九日(火)ヴァイグレ再び
サントリーホールで読売日本交響楽団の演奏会。指揮は四か月ぶりに再度来てくれたヴァイグレ。自分は十五日のミューザ川崎に続いて今回二回目。
・グルック(ワーグナー編曲):歌劇《オーリードのイフィジェニー》序曲
・フランツ・シュミット:歌劇《ノートル・ダム》から間奏曲と謝肉祭の音楽
・フランツ・シュミット:交響曲第四番
フランツ・シュミットの二曲が貴重。歌劇場人らしくダイナミックな動作で振った《ノートル・ダム》と、重厚な交響曲との対照が面白い。後者はアイヴズの《答えのない質問》みたいな暗いトランペット・ソロが印象に残る。
七月四日(日)第十雄洋丸事件を知る

「乗りものニュース」の『災害派遣で船撃沈、「第十雄洋丸事件」の顛末 東京湾業火漂流20日間、その時海自は』から
フェイスブックを見ていたら、一九七四(昭和四十九)年十一月九日に「第十雄洋丸事件」という事件があったことを知る。
プロパンやナフサなど五万八千トンを積んだ日本最大のLPG・石油混載タンカー、第十雄洋丸に貨物船パシフィック・アレスが東京湾内で衝突、ナフサに引火して両船の乗組員三十八名が死亡。
漂流を開始した両船が、横須賀港に衝突して大爆発し、市内を焼き払う恐れが出たため、海上保安庁と民間船がいったん千葉側に曳航。
その後、第十雄洋丸を東京湾外に曳航して処分することにしたものの、途中で爆発が起きて曳航索が切れ、黒潮に乗って再度の漂流を開始。
ここで海上自衛隊に災害派遣が要請され、撃沈を目的として護衛艦四隻、潜水艦一隻、哨戒機十機が出動。
二日間かけて護衛艦の砲撃と哨戒機の爆撃で上部タンクの残留ナフサを焼き払ったのち、潜水艦の雷撃で撃沈。火災発生から二十日後のことで、ウィキペディアによると沈没地点は犬吠埼灯台の東南東、約五百二十キロの海域。
いかにも大事件なのに、自分はまったく知らなかった。
一九七四年といえば石油ショックの翌年、経済の混乱に加えて『日本沈没』に『ノストラダムスの大予言』の書籍と映画が大ヒット、超能力などテレビやマンガでオカルトブームが起き、『大地震』や『エアポート75』、『タワーリング・インフェルノ』などハリウッド製のパニック映画の大作が次々と公開されようとしていた年。
まさにそんな年に、東京湾内を漂流する巨大タンカーが横須賀を襲うかもしれないなんて、パニック映画そこのけの事件が起きていた。
戦車や軍艦のプラモデルばかり作っていた小学六年生の自分が、憶えていないのが不思議だ。しかし、今よりも自衛隊アレルギーが桁違いにきつい時代だったから、いかに災害派遣とはいえ、東京湾のすぐ外で自衛隊が商用船を火器で撃沈する話は、マスコミによってはあまり話題にしたくなさそうな気もする。ともかく家でも学校の友達とも、話題にした記憶がない。
まあ、自分自身をもてあました、今でもあまり思い出したくない時期でもあった。自我がうまく形をとれず、言語化できず、周囲に対してだけでなく、自分自身に対してもうまく説明できなかった、思春期前の暗い秋と冬。それで耳に入ってこなかったのかも知れない。
七月十一日(日)水戸訪問(前)
水戸へ行き、生まれて初めて水戸芸術館に入り「1964 音風景」を聴く。
送電線工事をやっていた一九九〇年代半ばには、水戸の北側にある那珂に現場があり(あとで聞くと、故オヤマダアツシさんのご実家の近くだったらしい)、同時期にその北西約五十キロの栃木県の大田原にも大きな現場があったので、この二つを結ぶ一般道を何度も往復した。
だから、茨城県北西部の雰囲気は知っているけれど、那珂までは常磐自動車道をひた走るだけなので、途中の水戸までの地勢や雰囲気はまるで知らない。
常磐道沿いには元請(東電から仕事を請けて、我々下請に発注する会社)二社の資材置場もあり、谷和原と谷田部インターで降りて通ったが、これも落下傘的にインターから資材置場までの道を知っているだけなので、東京との「地表の連続性」はよくわかっていない。
一般道や在来線の線路を走ってこそ、そういうものは実感できる。今回往復に乗った「ひたち」と「ときわ」は、特急とはいえ在来線の線路を走るので、雰囲気はわかる。
 東京駅より特急ひたちで出発
東京駅より特急ひたちで出発私の高校は文京区白山にあったのに、かなりの生徒が千葉や埼玉から通っていた。同級生がいた松戸、柏、我孫子、さらに茨城県の取手を通る。駅前の徒歩圏に住んでいるとはかぎらないから、ここから毎日通うのは大変だったろう。自分も含めて、すべての友人が帰宅部だったのは校風だけでなく、通学時間が長くかかるので余裕がないことも大きかったのだろう。
土浦通過。高校のころ小学校からの友人に誘われて、ここからバスに乗って自衛隊武器学校を見学に行ったのを思い出す。駅前の丸井を妙におぼえているが、十年以上前に閉店したらしい。
水戸駅の手前で庭園の脇を通る。有名な偕楽園だという。電車の中からだが、もう見学した気になる(笑)。
水戸駅到着。まず腹ごしらえ。駅ビルの「エクセル」で食べる。昔は駅ビルのレストランというと、一見の観光客相手の高いだけで美味しくない店が少なくなかった気がするが、最近はSNSによる情報拡散のせいもあってか、ちゃんとした店がほとんどだと思う。駅にあるということは、その町の顔の役割も果たすのだから当然のこと。だから初めての町では、駅ビルから探すことにしている。
今日は「蕎麦処まち庵」で「夏野菜のぶっかけそば」。梅と大根おろしがたっぷりのっていて、つゆをかける前に藻塩と柚子胡椒だけで食べてみる。美味。

満足して外へ。城下町、つまり数百年以上の歴史のある大きな町では、駅は城から遠いことが多い。旧市街の町外れにしかつくれなかったためだが、水戸は駅北口の目の前が城跡という珍しいパターン。水戸城南側の堀を兼ねていた、千波湖の東半分を埋め立てた場所につくられたからである。
しかし、そのため近いが低い(笑)。本丸跡にある水戸一高などははるか崖の上。自分の水戸についてのイメージは、恩田陸の『六番目の小夜子』や『夜のピクニック』のモデルとなっている同校ぐらいなので、外から眺めてみたかったが、かんかん照りの陽ざしの下では、とても歩いて登る気にはなれない。

黄門トリオ 背後の右手奥の建物はかつての丸井だそう
ペデストリアンデッキ上の黄門トリオの写真を撮ったのち、階下のバス乗り場へ。水戸芸術館は旧市街にあり、バス停四つ目なので歩くにはちょっと厳しい。四つの系統が通る場所なので、あまり待たずに乗れる。
旧市街も城と同じ台地上にあるので、バスは坂道を登る。国道50号であることに気がつく。自分が栃木や群馬県内でさんざん車で走った、北関東を長くつなぐ国道がここまで来ている。芸術館最寄りの泉一丁目というバス停は水戸随一の京成百貨店の真ん前で、いかにも目抜き通りの中心地という感じ。
かつては京成百貨店と地元の伊勢甚百貨店が向かい合わせに建っていた場所だという。現在は伊勢甚が撤退した跡地に京成が移転し、その京成の跡地に、水戸市の新市民会館が再来年四月の開館をめざして建設中。二千人の大ホールと五百人の中ホールをつくるそうで、交響楽団やオペラ公演などが行なえる。

建設中の新水戸市民会館。ウルトラセブン風の宇宙からの侵略ではなく、
高度成長期の工事現場から怪獣が出てくるのがウルトラマン風。成田亨風の塔がその予感を与える
水戸芸術館は、その新市民会館のすぐ裏にある。有名な塔がみえてきた。現物は、思った以上に成田亨っぽい。

成田亨っぽい水戸芸術館の塔。上まで登れるそうだが行きそこねた

なんというか、デザインと銀色、赤白の配色が成田亨のウルトラマンぽい景色
広々とした緑の広場を、低めの建物と回廊が威圧感なく囲んで、ぜいたくで気持のいい空間。西池袋にある自由学園明日館のたたずまいを連想する。三十年経っているが、古びた感じがしない。


エントランスの頭上にパイプオルガンがあるのが面白い。オルガン・コンサートでは、ここがホールに早変わりする。じつに教会的な空間。
コンサートホールATMは六百二十~六百八十席で、空間に余裕と親密さが共存する、これも気持のいい場所。
 水戸芸術館のサイトから
水戸芸術館のサイトからコンサートの話は後に譲って、脱線。
送電線建設の仕事で那珂と大田原の現場を車で往復していたころ、途中や現場付近で見かけて気になっていたのが、那珂近くの「風車弥七の墓」と、大田原付近にある「那須与一の墓」、そして国宝の「那須国造碑」と二つの侍塚古墳。
とくに国造碑と古墳は不思議。今はただの内陸部の農村地帯としか思えぬ地域に、これほどのものがある。古代においてあの地域はどのような重要性をもっていたのか。しかし、これら遺物の脇を流れる那珂川が関東第三の大河で、はるかに南流して水戸も通過していることは、何かを解く鍵なのだろう。
と、今ならそんなことを考えて見に行くが、毎月通過していたあの頃はヒストリカルのディスクと仕事のことで頭がいっぱいで、ちょっと車を停めて見にいこうかとか、そんな気にはついにならずじまいだった(笑)。
ところが今、わざわざ行こうとするにはとても面倒な場所なわけで、まさに後悔先に立たず。
七月十一日(日)水戸訪問(後)
水戸行きの主目的であるコンサート、「1964 音風景」は、東京オリンピックの年につくられた音楽作品五曲からなるもの。といってもオリンピックとは直接の関係はなく、一九六二年の初来日で話題をあつめたケージなど、ゲンダイオンガクが活力と希望に満ちていた時代の、ある一年という感じ。六〇年代後半のカウンターカルチャーにつながる「自由」を求めた音楽。

・湯浅譲二:ホワイト・ノイズによる〈プロジェクション・エセムプラスティック〉
・高橋悠治:クロマモルフⅡ
・ジョン・ケージ:〈ピアノのための電子音楽〉より
・一柳慧:弦楽四重奏曲第一番
・テリー・ライリー:インC
アンサンブル・ノマド
磯部英彬(エレクトロニクス)
片山杜秀(企画監修・おはなし)
冒頭に湯浅譲二が片山さんと登場し、自作について語る。
このテープ作品は、あらゆる周波数の音からなるホワイト・ノイズから、さまざまな周波数の音を取り出して響かせるもの。当時影響を受けていた鈴木大拙の説く禅の思想、「一即多、多即一」によるところが大きいという。
虫の声のような高音に始まり、響きあうように波紋が拡がっていくさまを、今日は作曲家の提案により、図形楽譜を大きなスクリーンに表示しながら再生。たしかに視覚的なイメージがあると変化が聴きとりやすい。さらに今回は途中のパウゼを十五秒から十秒に短縮した、作曲五十七年目にしての「改訂版初演」。
続いて高橋悠治がクセナキスに影響を受けて書いたピアノ独奏曲、プリペアド・ピアノの音を電子的に変調するケージ作品、四人の奏者が大きくディスタンスをとる一柳慧の弦楽四重奏曲と続く。曲間には片山さんの解説もたっぷりと。そして後半は今日本にいるというテリー・ライリーの傑作《インC》。
五十七年前の作品ばかりとはいえ、湯浅の臨席が象徴するように、ケージ以外の四人は現存・現役である。一九六四年にケージは五十二歳になるが、現存の四人は湯浅の三十五歳が最年長で、一柳三十一歳、ライリー二十九歳、高橋二十六歳。時代も若く、作曲家も若い。
作曲者臨席で演奏された、再現芸術ではなく再生芸術であるテープ音楽に始まり、難技巧の曲も易々とひきこなす演奏力を持った作曲家が、自分で演奏することを念頭に書いたろうピアノ曲が続く。
それが、ケージ以降は演奏者の判断にゆだねた要素が出てきて、他者による再現芸術という度合いが増してくる。この流れに沿った選曲と配列が巧妙で、面白かった。
しかし、前半の一柳作品までは、作曲そのものには偶然性や確率といった、個人の意志ではない手法が入っているのだろうけれど、内攻的で、聴いていて息がつまるような閉塞感があった。
これが《インC》になると開放感、さまざまな可能性と選択肢のある、開かれた印象の音楽になる。ミニマルな音の連なりが生む、響きのうねりに身をゆだねるのが心地よい。
この作品が現在までさかんに演奏され続ける、傑作の傑作たる所以は、この再現芸術としての開かれた可能性にこそあるのかも、などと考える。
二時間半、たっぷりと聴いて終演。
「今日の音楽は、わからない人がほとんどだろうね」と近くの席で休憩時に言っていた地元のおばあさんも、しかし最後までおとなしく聴いていた。
ホール内でも雷鳴が聞こえていたが、終演後に出てくると大雨。それほど待たずにバスに乗れたのはよかったが、駅に着くと外に出る気になれず、夕食もまた駅ビルで食べる仕儀となる。
肉を食べる気になれず、「キッチン寅家」でオムライス。「奥久慈の卵を使用した」の一言が決め手で選んだが、そのとおり卵が新鮮で、ベタベタせず食べやすく美味。

ケチャップたっぷりのオムライスとポテトフライで、「うわ腹にもたれそう」と一瞬思ったが、
どれも鮮度が高くすんなりと食べられた
ここであらためて、片山さんによるプログラム掲載の解説や、水戸芸術館のフリーペーパー「vivo」掲載のインタヴューなどを読む。いうまでもなく面白い。プログラム解説の高橋悠治の《クロマモルフⅡ》についての一節など、片山節全開で楽しい。
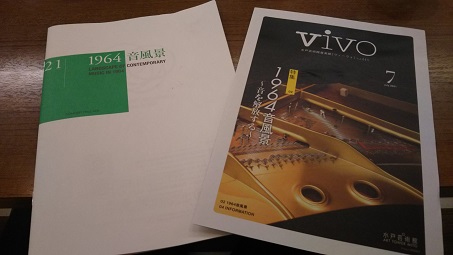
「クセナキスは(略)ピアノ曲なら12の音程のミクロな組み合わせではなく、88の鍵盤のマクロな確率論的統制を主張した。高橋のピアノ曲はその流れに位置するが、クセナキスの、まるで騒乱状態か激甚災害かというその種の音楽に比べると、風かゲリラか流れ者かという佇まいを感じさせる」
騒乱のクセナキス、風来坊の高橋悠治(笑)。
ところで、突然大雨になることの多い今年の梅雨に重宝しているのが、クニルプスの自動開閉折りたたみ傘。昨年に日傘兼用で買ったものは三百八十グラムと少し重かったが、今年は二百三十グラムという軽量版が出たので新たに買った。
華奢かと思ったが台風でもないかぎり問題なし。ボタン一つで閉じることもできるのが、ものすごく便利。水はけがとてもいいので、たたんだときに少し振るだけですぐ乾く。専用のドライバッグに入れれば、そのまま鞄にしまえる。

クニルプスの傘とドライバッグ。赤い丸がトレードマーク
コンサートのとき、ホールの傘立てに立てたり外したりの時間を食わないのがとても楽。国立能楽堂やNHKホールのように傘立てのない会場に行っても無問題。忘れるかも、盗られるかもというストレスもない。長い傘を持って歩くことがまったくなくなってしまった。
晴雨兼用で遮光機能までついているから、梅雨明けの真夏にも持ち歩くことになりそう。ほんとに便利。
帰路の特急は「ときわ」。途中でいくつかの駅に停まるので、行きよりも時間がかかる。日が長い時期なので、東京直前まで景色を見られるのがありがたい。柏駅のあたりで、夕暮れの東の空にきれいな虹がかかった。

七月十四日(水)パイプオルガンと光

 サントリーホールの公式ツイッターから
サントリーホールの公式ツイッターからサントリーホールでパイプオルガンを聴く。「石丸由佳オルガン・リサイタル ―J・S・バッハと夢見る宇宙―」と題した、オルガン演奏にくわえてプラネタリウム投影、科学者の佐治晴夫の講演つきの演奏会。
サントリーホールでのプラネタリウム投影は初の試みなのだそうで、私の席からだともう一つ不鮮明だったが、青や緑の光はそれだけでも涼やかできれい。
前半はバッハ四曲に『さらば宇宙戦艦ヤマト』の《白色彗星》。パイプオルガンが本気を出すと、フル・オーケストラに優るとも劣らぬ大音響が出る。《白色彗星》の重低音の迫力もすごかった。たしかこの曲、映画ができたころは技術的に実演での演奏は不可能だったときいた記憶があるが、今日はバリバリ響いた。
佐治さんのお話も面白かった。惑星探査機ボイジャー一号の銅製レコードにバッハの前奏曲を収録することを提案された方だそう。
一九七七年に打ち上げられ、太陽圏を出て飛び続けるボイジャーは、電池が切れる二〇二五年ごろまでは、今も信号を送ってくるという。お話の途中にはボイジャーが送ってきた最新の「宇宙の音」の「日本初演」もあった。深海の底のようなゴーッという音を聴くと、そのあまりにもはるかな距離と凄まじい孤独のイメージに、そら恐ろしくなる(笑)。
五十億年後に赤色巨星化した太陽に呑みこまれて地球が消えたとき(弥勒菩薩が五十六億七千万年後に降臨したとき、もう地球はないのだ…)、人類が生きた証は、飛び続けるボイジャーの積み荷だけになるだろうというお話は壮大、まさに宇宙的で、パイプオルガンの響きにぴったりだった。
プログラム掲載の佐治さんの文章によると、一九三五年東京生まれの佐治さんが初めてプラネタリウムに行ったのは、一九四二年のこと。佐治さんはこの年四月のドーリットルによる東京初空襲のさいの、超低空を飛ぶB‐25爆撃機の姿を見られたそうだが、この事件を受けて灯火管制が始まるなか、小学校の担任が当時東京唯一のプラネタリウム、有楽町の東日天文館に連れていってくれたという。戦時下にもかかわらず、「星の知識は戦場でも役立つ」という理由で投影が続けられていたそうだ。
その「畏怖を感じるほどの美しさ」に圧倒された一週間ほどのち、お父さんから「まもなく東京は火の海になる。その前に、東京に数台しかないパイプオルガンを聴いておきなさい」といわれて、お兄さんとともに日本橋三越本店のウーリッツァーを聴きにいかれた。
軍服を着たオルガニストが演奏したのは軍艦マーチなどの軍歌だったが、その重厚で壮麗な音に感動していると、
「突如、遠い星空の彼方から光のカケラが舞い降りてくるような楽曲になったとき、兄が耳元でささやいたのです。「バッハだよ」。オルガンとバッハ、宇宙との衝撃的な出会いでした」
火の海になる東京の予感と、プラネタリウムとパイプオルガンが眼と耳に啓示してくれるもの。そして、虚空をどこまでもいつまでも飛び続けるボイジャー。
時空を超越するイメージの足元の、切実で過酷な現実。
人がなぜ大聖堂をつくるのか、なぜそこにパイプオルガンをつけるのか、それがいま、コンサートホールにある意味は何か。
いろいろなことを、果しなき流れの果まで考えさせてくれる演奏会とお話。
七月十六日(金)感染拡大
二期会の《ファルスタッフ》初日中止。関係者にコロナの感染者が出たという。新国立劇場の高校生向け《カルメン》中止に続き、こんな事態が当たり前になってくるのか……。
七月十九日(月)平日のファルスタッフ
二期会の《ファルスタッフ》、面白かった。日経新聞に評を書くので詳細は省くが、とりわけ才人ペリーの演出がとても楽しかった。この傑作オペラのここがこうなるのか、あそこはああなるのか、次はどうする? おおそうくるとは…、とワクワクしながら見た。
この、新制作のオペラならではのワクワク感をひさびさに味わえた、才気あふれる舞台。個人的には第二幕のフォード禿げ部隊と、最後に客席を映しだす鏡が大好き(笑)。
それにしてもこの公演、なぜ平日月曜の昼にやるのかと思ったら、元は「海の日」の祝日午後の公演だったのに、オリンピックが一年延期で「海の日」が二十二日になってしまったためとのこと。人に教えられるまで、まったく気がつかなかった(笑)。
七月二十二日(木)仙台から、仙台へ

今日は「フェスタサマーミューザKAWASAKI」の開幕日で、知り合いのほとんどはノットと東京交響楽団の演奏会に行かれたようだ。
しかし自分は、サントリーホールへ行く。アークヒルズに入ろうとするところで、オリンピックのボランティア用ユニホームを着た女性とすれ違う。
目的は十七時からのパスカル・ヴェロ指揮仙台フィルの東京公演。仙台を本拠とする企業、アイリスオーヤマの主催によるもの。自分は東京生まれの東京育ちだが、父も母方の祖父も仙台人で、墓も仙台にある。つまり父祖の地のオーケストラなので、聴きにいかないわけにはいかない(笑)。
ヴェロは東日本大震災をはさんで二〇〇六年から十八年まで常任指揮者をつとめ、現在は桂冠指揮者の称号を贈られている、特別に縁の深い人。その人がこの公演のためだけに十四日間待機でやってきた。仙台では公演せずにこの東京公演だけというのはもったいない話で、八、九割うまっていた客席には、仙台から来たファンもたくさんいたようだ。
東京でしかやらない理由はおそらく、メインであるサン=サーンスの《オルガン付》交響曲に必要なパイプオルガンをもつコンサートホールが仙台にはないため。没後百年の作曲家のこの代表曲を、ヴェロに思いっきりやってもらおうという趣向だったのだろう。オルガンは東北学院大学でオルガニストをつとめる今井奈緒子がひく。
演奏も、特別の機会にふさわしい力演だった。フランスの指揮者らしい華やかさと快活な生命力、適度なケレン味が心地よく、ヴェロが仙台で安定した人気を誇った理由の一端がうかがえた。アンコールもあえて曲を変えずに、《オルガン付》のクライマックスをくり返して、サントリーホールのパイプオルガンの威力を再び堪能させる。
仙台フィルの充実を喜びつつ、やはり本拠地の雰囲気を一度味わいたいなと思う。次の定期は九月で、カーチュン・ウォンが客演してラフマニノフのピアノ協奏曲第二番(独奏は上原彩子)と交響曲第二番をやるそう。これならとても聴いてみたい人と曲だが、折悪く片山さんとのオンライン講座の当日。オンラインだから仙台から参加する手もあるが、慣れないことをするのは恐い。ともあれいつか、墓参りとあわせて行きたい。
七月二十七日(火)三人翁

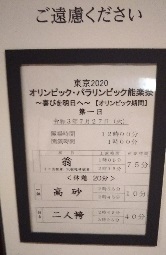
国立能楽堂で行なわれている能楽協会の「東京2020オリンピック・パラリンピック能楽祭~喜びを明日へ~」。オリンピック期間の五日間のうちの初日に行く。
本来は昨年の予定だったが、オリ・パラ延期のために昨年は「能楽公演2020」と名を変えて開催。今年も期間を短縮して開催。酷暑の時期の平日の昼間、周辺が観客と野次馬で大混雑となるだろう国立競技場のすぐ近くということでためらいがあったが、五輪が無観客と決まったので、安心して行くことにする。
競技場周囲の道路が封鎖されている関係でバス停の位置が変わっていたり、警官が各所に立っていたりするが、千駄ヶ谷駅付近の通行人はそれほど多くない。
初めに金春流の『翁 十二月往来 父尉延命冠者』。『翁』は神事的・呪術的気配の濃い、由来不明の不思議な曲。猿楽の原点のような曲で、まさしく辺りを祓うような厳粛さには摩訶不思議な魅力があって、年に一回は見たくなる(現在の各流派では年始に取りあげる)。
『翁』には「能にして能にあらず」という形容が必ず使われるが、この言葉は天野文雄の『能楽手帖』によると、元は『鉢木』の前場を評する言葉として江戸後期に誰かが言い出したのが、明治になって『翁』の不思議な魅力を説明するのに転用されたのだという。
今回は「十二月往来」と「父尉延命冠者」の二つの小書(特殊演出)つき。前者は本来シテ一人の翁が三人に増え、毎月の風物を言祝ぐ詞が追加される。後者は、現在は割愛される父尉と延命冠者の二役を復活させたもの。父尉は翁役のシテ、冠者は千歳役の狂言方が兼ねる。
寺社の神事の一環として生まれたらしい『翁』の、古態に近いらしいこれらの小書を見たいというのが、今回の観能の主な動機。
そのあと、野村萬がシテの狂言『二人袴』。九十一歳で現役というだけでも驚くべきことだが、洒脱で生き生きとした芸も健在。楽日にも一歳下の弟、野村万作の狂言『舟渡聟』がある。今回はこの兄弟の存在そのものが「寿福増長の基、仮齢延年の法」たる芸能の象徴、「翁」そのもののようでもあり。
・能『翁 十二月往来 父尉延命冠者』
翁・父尉 金春憲和
翁 髙橋忍、金春飛翔
三番三 茂山千五郎
千歳・延命冠者 茂山忠三郎
笛 藤田貴寛
小鼓 幸正昭、後藤嘉津幸、船戸昭弘
大鼓 安福光雄
地頭 本田光洋
・一調『高砂』
謡 金春安明
太鼓 金春惣右衛門
・狂言『二人袴』野村萬、能村晶人、野村万禄、野村万之丞
七月二十九日(木)訃報・浅見真州
観世流シテ方の重鎮、浅見真州が十三日に亡くなっていたとのニュース。
今年は十月に傘寿記念の「浅見真州の会」で老女物の大曲『姨捨』を舞う予定と知り、楽しみにしていたのだが、かなわぬ夢になった。合掌。
八月三日(月)能楽堂の脇正面
国立能楽堂にて能楽協会主催の「東京2020オリンピック・パラリンピック能楽祭 ~喜びを明日へ~」の楽日。
・仕舞『玉之段』金剛永謹
・狂言『舟渡聟』野村万作
・能『道成寺』金剛龍謹
メインは金剛流若宗家の金剛龍謹による『道成寺』。この大曲も『翁』同様に年に一度は見たくなる。
くしくも去年の「能楽公演2020」以来なのでちょうど一年ぶり。そのときも金剛龍謹がシテだった。ただし昨年は「古式」という小書がついたが、今年はなし。茶系のおとなしめの装束で、大蛇もより人間的というか。『翁』は平日昼ということもあるのか寂しい入りだったが、こちらは演目の人気もあってか、満席に近い盛況。
今回は初めて脇正面から『道成寺』を見てみた。
能楽堂の座席がホールと違うのは、正面席が三種類あることである。
能舞台正面の底辺に面した「正面」、左辺に面した「脇正面」、両者のあいだから斜めに見る形の「中正面」。
チケット代はこの順に安くなる。とはいえ視野の点では、中正面でも正面に近い席は柱があまり気にならず、脇正面より見やすいので、割安なお得感がある。

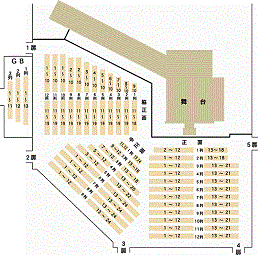
自分はこれまで、正面かそれに近い中正面で見ることにこだわってきた。能楽に通いはじめたころ、ためしに脇正面を買ってみたら、舞台を真横から見る形になり、まるでオペラを舞台袖で見たときのようなもどかしさを感じたからだ。
初めて見る曲(作品)の場合は、それだと内容がつかみきれない。ときどき、高校生の集団が割安の脇正面席で見学していることがあるが、あの位置で初めて能を見て能を好きになれる人は、少ないのではないかと思う。むしろ舞台からわざと遠ざけられているような疎外感をおぼえて、能嫌いを増やすだけなのではないか。それともあれは、能をよく知っている学生たちばかりなのだろうか。
一つの曲の内容がよくわかるまで、あるいは同じ曲でも流派が違う場合は、正面側で見る。そう決めてきたが、『道成寺』はこれが七回目くらいでシテも二回目なので、今回は脇正面で見てみた。
結論をいえば面白かった。乱拍子も横から見るとこうなるのかとか、シテの動きと鐘の高さ(段階を踏んで少しずつ下げている)の関係もよくわかる。進行の段取りはよく見えるが、それだけにある種の関係者視点というか、客観的になって、ドラマに入り込むことは難しい。
ただ、正面とはまるで別の魅力があることもよくわかった。舞台上のドラマが遠くなる反面、橋掛りがぐんと近くなるのだ。能でも狂言でも橋掛りの上での演技は多いが、それが親密なものになる。今回はアイの野村萬斎も目当ての一つだったので、鐘が落ちた後のやりとりなどは間近で楽しむことができた。
国立能楽堂の橋掛りは他の能楽堂よりも長いので、チャンバラの多い能、盗賊や天狗や鬼がたくさん出て橋掛りにならんで一斉に謡うものなどは、次の機会には脇正面で迫力を楽しんでみたい。
そして、近さというだけでなく、橋掛りの意味合いも正面席とは違ってくるというのも発見だった。正面から見るときの橋掛りは、異界との架け橋、遠くへ去るものなのだが、脇正面での橋掛りは、舞台上の世界が自分に近づいてくるものとなる。まさしく歌舞伎における花道と同じ意味合い。橋掛りを正面に寄せたのが、歌舞伎の花道なのだ。
野村四郎(幻雪)によると、歌舞伎の『勧進帳』の最後の飛び六方は、金剛流の『安宅』にある型を採り入れたものだという。いつか金剛流の『安宅』を、脇正面から見てみたいもの。
ただし金剛流は京都が本拠で、東京で見る機会はかぎられるので、コロナ禍が収束して京都に行ける日が来たら、というところか。
八月五日(木)ひたひたと来てる
JR四谷駅上のアトレ内のスターバックスを覗くと、従業員に感染者が出たために一時休業。感染拡大、ひたひたと近づいてきている。
八月七日(金)あなたはわたし
東京文化会館で二回公演が予定されていた《マイスタージンガー》が四日に続き、関係者に感染者が出たために今日も公演中止となってしまった。
待機期間をへて参加した海外の歌手たちも含め、公演実現に尽力した関係者の口惜しさはいかばかりかと思う。損失額もたいへんなものだろう。十一月に新国立劇場でも公演があることがまだしも救いとはいえ、そちらには参加できない歌手もいる。
そして、心ならずも陽性となった方たちが重症化せず、あまり悩まないことを祈るばかり。これは先日の二期会の《ファルスタッフ》も含めて、これまで中止となった、そしてこれから同様の事態に見舞われるかもしれないすべての実演興行にいえることだが、現在の日本の状況では、生活しているかぎり誰が感染しても不思議ではない。
あなたはわたし。わたしはあなた。
話を変えて、その東京文化会館が六月六日に実現してくれた、サーリアホのオペラ《オンリー・ザ・サウンド・リメインズ‐余韻‐》。台本となったのは、フェノロサの遺稿をエズラ・パウンドが一九一六年にまとめて出版した英訳による謡曲。
まとめる前にエズラ・パウンドは、フェノロサの草稿を、自らが助手をしていたアイルランドの詩人、ウィリアム・バトラー・イェーツに見せていた。謡曲と能に興味を抱き、霊感を受けたイェーツは、『鷹の井戸』という戯曲を書き、一九一六年にロンドンで初演、翌年に出版している。
この戯曲は日本でも一九三九年に軍人会館(のちの九段会館)で初演された。一九四九年には能楽研究者の横道萬里雄が翻案して、新作能『鷹の泉』とした。一九六七年に改訂して『鷹姫』と名を改め、現代まで上演が続けられている。
サーリアホのオペラを見て、あらためてこの『鷹の井戸』や『鷹姫』を見てみたいなあと思っていたが、今年はなんと幸いなことに、どちらも上演が予定されていることに気がついた。
今月末には、この作品に愛着を持って何度も上演してきた梅若実玄祥が、舞台生活七十周年を記念して、新作能楽舞踊劇『鷹の井戸』を観世能楽堂でやる。
能楽評論家の村上湛が台本を書き、梅若の実子である藤間勘十郎が演出と作詞・振付。梅若以外の出演は、ダンサーの上野水香と大貫勇輔。
続いて十一月に、金春流シテ方の山井綱雄が国立能楽堂で新作能『鷹姫』をやる。流派をこえて宝生流や観世流など五流派すべてのシテ方が参加し、演出はシェークスピア劇演出家として活躍する木村龍之介。
なんというか、こういう「劇場が呼んでいる」状況では、ラッパに応えるのが礼儀というもの(笑)。やりくりして行くことにする。
コロナよ邪魔するな。クー・フーリンが呼んでいる!


八月八日(日)喜正の『融』
矢来能楽堂で観世九皐会の定例会第一部。
・能『融(とおる) 思立之出・舞返(おもいたちのいで・まいがえし)』観世喜正
矢来観世家の若先生こと喜正がシテのこの日は、観客のアンケートで決めたリクエスト曲をやる。最多得票で一位となったのが『融』。じつは自分も、一月に『翁』を見に来たときに投票、三つ書けるうちの一つに『融』を選んだので、十四日すみだの大河リクエスト曲『花神』同様に願いがかなって嬉しいし、となれば行かないわけにはいかない(笑)。
こういうリクエストは、ふたを開けたら一位ではない曲、本人がやりたかった曲が取りあげられるケースも意外とある気がする。しかし喜正は真摯に結果に応えた上に、これまでにもたびたび勤めた曲ではあるけれど、「小書の都合で前段の謡い所を省略することが多く、全編通しで演じたことがありませんでした。今回は謡いの省略なしでさせていただこうと思います」と覚悟を示していた。
そのとおり、通常なら併演されるはずの仕舞や狂言をなくし、『融』一曲に集中して九十~百分の会。客のほうも自ずと気合いが入る。そして期待を裏切らない、凛として気持のいい演能だった。
それにしても『融』をつくった世阿弥は、やはり凄い。ここしばらく世阿弥ではない能を続けて見ていたので、ひさびさにその詞と構成と響きに触れると、格の違いを痛感する。その洗練、その格調の高さ、その奥深さ。
真に優れた夢幻能は、型を踏襲しただけの凡百の夢幻能とはまるで違う。何よりワキの位置づけ。凡作では、前場と後場のはじめに説明的な詞をしゃべってあとは座っているだけということになりかねないが、世阿弥のははるかに主体的。
能の主人公はあくまでシテだが、その主人公を夢の幻に見る人物、小説などの語り部としての「わたし」というワキの主体性がはっきりしている。ワキ(今回は森常好)にとっても、やりがいのある曲なのではないか。
その象徴が、シテとワキが謡い交わす二重唱的な歌いかたの多用。その対話のリズムと響きの絡みあいの、官能的といってもいい音楽的な美しさ。現世の人間(ワキ)と冥界の幽霊(シテ)の心の波長が合って、不思議な共振を起して、有りえない心の交感が生じて、ワキはシテの幻影を見る。
その、静かな水面に波紋が生じて、だんだんと大きな渦になって両者を巻き込んでいくような、その過程を描き出すことが、世阿弥は空前絶後にうまい。
『融』の主題は、まさにその相異なる者同士の交感。本来の伝説では、廃墟にとりついて生者を憎み、生命を奪う悪霊のような存在だった源融の霊を、世阿弥はワキの夢のなかで風雅な遊びをし続ける、幻想的な存在に造りかえた。
その発想の種になるのが、唐の詩人賈島と韓愈の推敲の故事。この二人の心の交流を、融の霊と僧の関係と二重写しにすることで、美しい交感劇が生まれる。
老人「鳥は宿す池中の樹」
僧「僧は敲く月下の門」
老人「推すも」
僧「敲くも」
老人「古人の心」
両者「今目前の秋暮にあり」
呼応するリズムの美しさ。「池中の樹」は賈島の名詩「題李凝幽居」の一節。池の水面に樹が映ることで、あたかも水中に樹があるかのように見える。
この水面に映る影を、世阿弥は現実に対する幻影、霊界の象徴として描くことを好む。夢幻能の後場はすべて、水面に映る幻の世界の出来事のようなもの。
幻を映し出す鏡として、眼下に沈む水面と対になるのが、頭上に輝く月面。後場に登場する融の霊は、前場の老人とは一変して、生前の典雅な形姿で華やかに舞い、謡い遊ぶ。その姿は月光に照らしだされ、最後には天界の月面へと吸い込まれていく。
後場の舞がほんとうに見事。「舞返」という小書がつくと、五段で構成される早舞がさらに三段増える。現代の通常の能の上演では、舞を三段に短縮するのが一般的で、それでも私のような素人は単調に感じて退屈することが少なくないのだが、それを計八段やって、まったく飽きさせない。それどころか惹きこんでいく。終りに向けて次第に加速していく、勢いと集中力の素晴らしさと美しさ。
いま五十歳の喜正の、心技体の充実を実感。
チラシにある「中将」の面が用いられていた。動かない面を名手がつけると、爽やかに微笑むように、さまざまな表情を見せる。能の不思議。
それにしても、『融』に響く「交感する心と心のおののき」の快感は、まことに凄い。心の襞と襞がむき出しに触れあうような、切なくて震えるような、しかし心の奥底からわき上がる歓喜。
なんであれ芸術というのは、このおののく歓喜を媒介してくれるもの、なのかもしれない。
この「交感のおののき」は、これからもさまざまな人と芸術が体験させてくれるだろう。それに反応できる感受性を失いたくないと、切に願うのみ。
八月九日(月)恋のおののき
九日は仙台フィル以来、十八日ぶりにオーケストラを聴く。すみだトリフォニーホールでの「新日本フィル・シンフォニック・ジャズ・コンサート Special Guest 上原ひろみ」。五月に予定されていたのが緊急事態宣言で延期となったもの。実現できて何より。
沼尻竜典の指揮で、オリンピック開会式にも登場したジャズ・ピアニストの上原ひろみがゲスト。前半はオーケストラのみでバーンスタインと上原の作品、後半は上原のピアノを独奏にその自作を演奏する構成。
本プロが終わったところで楽員がひきあげたので、アンコールなしかと思ったら上原一人が戻ってきてソロのアンコール。二曲目には新日本フィルのコンマス西江辰郎と第二ヴァイオリン首席のビルマン聡平が加わってトリオで演奏。満席に近い聴衆のほとんどは上原目当てだったようなので、大盛り上がりとなった。
個人的に聴けて嬉しかったのは、前半の『ウエスト・サイド物語』からのシンフォニック・ダンス。
この曲は、だれずに演奏するのが意外と難しい。ビート主体で器楽的にやられると騒々しいだけで形にならず、聴いていて途中で飽きる。今回はそれが実にうまく、流麗につながって、ミュージカル全曲の「歌のない短縮版」のようにまとまっていた。
それは、歌がないのに歌が聞こえるような演奏だったから。防疫のため楽員による「マンボ!」の掛け声はなかったのだが、演奏そのものが歌を感じさせた。〈サムフェア〉では、
Hold my hand and we're halfway there. 手を握ってよ、もう途中だよ
Hold my hand and I'll take you there. 手を握ってよ、君をそこへ連れていくよ
この切なく願う恋の言葉が、弦楽から聞こえてくるようだった。
そのあとも、ダンス・パーティの場面の音楽からは〈マリア〉の恋の歌が聞こえてきたし、〈クール〉にもジェット団の「ボーイ、ボーイ」のささやきが聞こえる。そして〈フィナーレ〉では、この悲しみをこらえるような音楽が、〈サムフェア〉と〈アイ・ハヴ・ラヴ〉の歌の旋律の組み合わせからできていると明快に聞きとれることで、この音楽の意味するところ、内包するドラマが伝わってくる。
勝手な推測だが、沼尻は『WSS』全曲の音楽とドラマが大好きで、ものすごくよく知っているのではないだろうか。
音楽の表層ではなく、ドラマとその響きをイメージしているから、このミュージカルを不滅のものたらしめている「恋する心のおののき」が、このダンス曲集からも伝わってくる。全曲への愛が、歌のない舞曲から恋の歌を引っぱりだす、というか。
いつか沼尻指揮の『WSS』全曲の舞台版を聴いてみたい(この作品は演奏会形式だと生きてこないので)
八月二十一日(土)どこかでエンゼルは
新国立劇場で《スーパーエンジェル》をみる。何も予習せず舞台だけ見たが、「異端」とか「天使」といった用語の前提条件がなにもわからず、舞台上で何が起きているのかつかみきれなかった。
五人の天使を信仰する新興宗教の誕生物語みたいに思えたのだが、そういうものでもなかったらしい。
天使はいつでも見守ってくれている、みたいな歌詞が途中で出てきてからは、頭の中で森永製菓のCMのエンゼルの歌が鳴りっぱなしになってしまい、その歌詞とメロディの強さで、目の前の音楽が耳に入りにくくなってしまった。
「だァれもいないと思っていても どこかでどこかで エンゼルは いつでもいつでも ながめてる」で始まる『エンゼルはいつでも』、作詞がサトウハチローで作曲が芥川也寸志という。
八月二十二日(日)野村幻雪の訃報
観世流シテ方の野村幻雪(四郎)の訃報。七月に浅見真州が亡くなって驚いたばかりなのに。
八十四歳と八十歳。不思議はないとはいえ、能舞台でつい先日まで姿を見ていたので意外な気がする。そういえば二月に見た『船弁慶』は、幻雪が急病で静を降板、真州が代役となったものだった。
幻雪の最後の能は五月の国立能楽堂の『鷺』だったそうだが、見損ねた。自分が最後に見たのは、面をつけず紋服と袴で舞う舞囃子ばかりで、昨年七月の「能楽公演2020」での『鷺』と、今年一月の東京能楽囃子科協議会公演での、梅若万三郎との舞囃子『二人静』だった。
面をつけないだけに、シテ本人と役柄と、両者が二重写しになっているような感覚を味わいながら見ることになる。
『鷺』については、
「能の舞の動きは象徴化され、けっして具象的なものではないのに、今日の舞にはたしかに鷺がいた。
翼を広げ、片足で立つ鳥が、紋付袴姿の人間の向うに見える。美しく澄みきった、儚き幻」
また『二人静』については、
「面と装束をつけず、紋服と袴のままで長老二人が舞い謡うものだが、残された女の深い悲しみが、静かに舞台に満ちていった」
と書いている。
どちらも印象深かったが、偶然にも今日はこれからサントリーホールで細川俊夫の『二人静』を見ようとしているだけに、その姿が強く思い出されてくる。
「思い返せば、古も、恋しくもなし。憂き事の、今も恨みの衣川、身こそは沈め、名をば沈めぬ」
過去など恋しくはない。衣川にその身は果てようと、名は朽ちはしない。
能を見はじめてたった五年半なのに、意外と多くの能楽師が逝ってしまった。五年というのは人の一生において、けっして短くない期間なのだなと思う。
世を去る人がいるぶん、育っている人もいる。しかし、いなくなったという事実は画然としていてわかりやすいが、芸の成長・成熟というのは曖昧模糊としていて、わかりにくい。見る人によって意見もわかれる。しかもその成長曲線は常に変動していて、一定ではない。
こちらの好奇心や感受性も、年をとるごとに衰えて硬直化してくる。我々の乗っている船はけっしてさかのぼることができず、川を下ることしかできないが、艫に座って後ろを見て、評価の定まった過去を懐かしんでいるほうが、ぬくぬくと心地よい。
しかし、幻雪と山本東次郎の対談『芸の心』(笠井賢一編/藤原書店)の一節を思い出す。
野村「古典というとただ古くて完成されたというイメージになる。私は伝統という言葉が大好きです」(略)
野村「伝統というのは要するに過去、現在、未来です。この全部が集まって、過去も現在も未来も集まって伝統になる。これが伝統の定義だ」(略)
山本「書物と違って、生きてるんですよね」
野村「そう、生きてるということなんですよ。東次郎さんも、私もそれぞれに伝統という荷物を背負って生きている。とりわけ東次郎さんは代々の狂言の大きなものを背負っていま歩いてます。それで、未来へ向かってます。前のものを背負いながら現代を生きて、次の世代に受け渡していこうと」

あれは『安宅』だったか、年若のシテの後見をつとめ、流れ出る顔の汗を何度も拭いてあげた能のあと、微笑みを浮かべたまま、満足げに長く座っていた姿も思い出す。
いまはただ感謝。
八月二十七日(金)ヘビとえんぜる

二期会の《ルル》のゲネプロを新宿文化センターで。音楽も舞台もとても充実した舞台。
ワイマール時代のドイツ表現主義が産み落とした作品と、現代ならではの問題意識をもつカロリーネ・グルーバーの演出の、見事な交合。偉大なる頽廃芸術。男性社会における性的搾取の犠牲者、魂なき性人形=ヘビとしてのルル。
細川俊夫の《二人静》では、女に憑依した静の霊が舞い、この《ルル》では、分裂を余儀なくされたルルの魂が踊る。
霊も魂も、呼びかたを変えれば、すなわちエンゼル。いま、アフガニスタンで起きようとしていることの影。
僕の天使、とオペラの最後に叫ぶ作曲家アルヴァ。「ある天使の思い出に」書いたヴァイオリン協奏曲を形見として、《ルル》を未完のまま置き去りに遺すベルク。その符合。
新国立劇場のオペラ《スーパーエンジェル》は、私には成功作とは思えなかったが、しかし、腑に落ちない天使というイメージを召喚してくれた。その何枚ものの翼の羽ばたきが、私の心に、ざわざわと波紋を起していく。
ばらばらの公演と作品が勝手につながって、互いの陰影を濃くしていく。コロナ禍以来、体験しにくくなっていたこの実演の連環が、恐るべき天使の姿で現われる。その快感と痛み。
八木重吉の詩、「花になりたい」を思い出す。
えんぜるになりたい
花になりたい
八月二十九日(日)戯曲と音楽、小鯛焼

上野の東京藝大奏楽堂にて、ベートーヴェンの音楽劇《エグモント》。
ゲーテの戯曲『エグモント』の半分ほどを上演し、ベートーヴェンの劇音楽を演奏するもの。
同日に神奈川県立音楽堂でEICの演奏会も二期会の《ルル》もあって、身が三つあればというところだったが、劇音楽は元の戯曲と組み合わされてこそ真価がわかるし、さらにピリオド楽器だし、ということでこちらを選択。
歌曲や合唱曲、オペラなどでは親しんできたゲーテだが、戯曲を舞台で見たことはない。シェークスピアに比べると、日本での上演機会は少ないと思う。なかでも『エグモント』はまれだろう。それだけにあきらめることができなかった。
『エグモント』は一七八九年一月、フランス革命勃発の半年前にマインツで初演されたもの。八十年戦争と呼ばれるスペインからのオランダ独立戦争(一五六八~一六四八)勃発の直前、フェリペ二世が派遣した総督アルバ公により処刑されるオランダの貴族、エグモント伯が主人公。ヴェルディの《ドン・カルロ》の原作となったシラーの戯曲と同時代の題材で、ドニゼッティの《アルバ公》の前日譚のような話。
最後は処刑されてしまうが、その死が以後本格化する独立戦争の魁となる、それを予見して主人公が死を受けいれるという展開は、メル・ギブソンの映画『ブレイブハート』の主人公、スコットランド独立の英雄ウィリアム・ウォレスの話に似ている。
エグモント役の細貝光司など、文学座を主体とする俳優十三人が、クレールヒェン役のソプラノ歌手中江早希、鼓笛隊役の打楽器奏者一人とともに出演。舞台中央に置かれたオーケストラの前面で、簡素な衣装と小道具で演技をする。
戯曲全体の半分ほどの抜粋だそうですが、ベートーヴェンの付随音楽とのつながりはよくわかる。
序曲だけが突出して演奏頻度が高く、他の部分は続けて聴いてもあまり魅力を感じない音楽ですが、こうして聴くと意味あいが変わってくる。間奏曲が二部構成になっているのは、前の幕の雰囲気を受けて、次の幕の予告をするため。
処刑前夜に牢獄でまどろむエグモントが、夢を語るセリフにつけられた〈メロドラマ〉は、セリフと呼応して初めて劇的効果が鮮明になる。作曲翌年の一八一〇年にゲーテはお膝元のワイマールの劇場でベートーヴェンの音楽を用いて上演し、〈メロドラマ〉について「ベートーヴェンは、途方もない天才性をもって、私の意図を汲み取ってくれた」と絶賛しているそうだが、なるほどと納得。
自由や正義といった概念は、集団心理に弄ばれる平時の人間には、何がそれにあたるのかが見えにくい。弾圧を受けた人間には、それが奪われているがゆえに、具体的なものとして存在する。悲劇。
台詞にはPAが入っているとはいえ、マスクをつけての語りはやりにくいだろうが、俳優たちは最善をつくした。
渡辺祐介率いるオルケストル・アヴァン=ギャルドは、若手奏者によるピリオド楽器オーケストラ。去年十一月にみなとみらいで川口成彦とのピアノ協奏曲第四番、交響曲第九番《合唱》などの快演を聴かせてもらったが、今日もピリオドならではのすっきりした、鮮度の高い響きで、生き生きと好演。モダンもピリオドも当然に使いわけられる若い世代が育っているのは心強い。
コロナ禍での一年延期にもめげず、こうした貴重な機会をつくってくれた東京藝術大学演奏藝術センターに感謝。
あらすじは正直単純で、シュトルム・ウント・ドラングの熱情だけみたいな感じだが、やはり役者たちが目の前で演じてくれると、ドラマの肉付きが違う。シェークスピアの史劇の影響をさまざまに深く受けているのもよくわかった。
クレールヒェンの生き方は、何もなければ彼女と結婚して平凡に暮らすはずだった若者、ブラッケンブルグとの関係で明確になる。エグモントの正義も不倶戴天の敵アルバ公の、もう一つの正義と対話することで相対化される。そして、二つの正義のあいだでおろおろと手を拱いて見ているだけの、アルバ公の庶子フェルディナンドとの処刑前夜の対話で、エグモントの死の決意は固まっていく。
これらを受ける形で間奏曲などの音楽が響く。こういう展開を見ることができたのは幸いだった。
ところでこのゲーテの戯曲も、今月下旬のエンゼルチクルスの一つだとわかったのも面白かった。
ゲーテはヒロインとしてエグモントと恋仲になる平民の娘クレールヒェン(これがクララの愛称だと、今回初めてわかった)を置き、二つの歌を歌わせた。
彼女は兵士となって独立のために戦いたいが、女だからできない。エグモントが投獄されると、かれを救い出して自由のために戦おうと市民たちに語りかける(ここでは突然メガホンを使った)が、アルバ公率いるスペイン兵を恐れて、婦女子のいうことなど誰も耳を貸さない。
自らの無力に絶望した彼女は毒を仰いで死ぬが、その直前、死にゆくエグモントを自由な世界に連れて行く、天使の幻影を語る。あきらかに、自らがそうなることを願って死ぬ。
エグモントは彼女の死を知らずに処刑されるが、前夜のまどろみのなかで自らと人々を導く自由の女神の幻影を見る。女神はクレールヒェンの姿をしている。
『ファウスト』の「永遠にして女性的なるもの、われらを引きて昇らしむ」のグレートヒェン=マリアの萌芽であり、ワーグナーのゼンタやエリーザベトの原型となる、聖女幻想。
いかにも、男性社会の産物(笑)。
自由の女神という言葉を聞いた瞬間、先日の《ルル》の最後で作曲家アルヴァがルルに、ニューヨークの自由の女神みたいな格好をさせ、「僕の天使」と叫んだのを連想した。あれは青いドレスに赤い頭飾りと靴と、ひどいセンスのものだったが(笑)。そういえばアルヴァと父シェーンはルルをミニョンと呼ぶ(男たちはみな、彼女に勝手な名をつけて呼ぶのだ)けれど、あれももちろんゲーテから来たのだろう。
ゲーテ~ワーグナーの聖女幻想の陰画としての、ヴェーデキント=ベルクの《ルル》。
そういえば今日の《エグモント》のオーケストラ編成は第一ヴァイオリン六、六五四三二だったが、二期会の《ルル》も六五四四二と、チェロが一人多いだけで同規模だった。
しかし下手側に窮屈に押し込められ、上手側はあふれるほどの金管群、さらに背中の下手端にははみ出した打楽器群がいるという挟み打ち。もちろんモダン楽器。百二十年間のオーケストラの発展肥大と頽廃を実感させる響きの差で、これもまた愉快。
ところで《エグモント》十五時開演の前に、藝大から少し遠回りして桜木の和菓子店、桃林堂へ。
藝大に行くならここで菓子を買えと、山の神(古い奏楽堂が使われていたころの藝大生。古い校舎の廊下にはときに、明らかにこの世の人ではない学生も歩いていたという……)に命じられた。
自分が学生のころから変わっていない昭和の建物。もちろん会計は現金のみ。近年の名物という、竹籠入りの小鯛焼などを買って帰る。五個で千八百円、鯛焼にしては高いが、なるほどまるで異なる上品な美味。縁起物だし、これは差し入れなどによさそう。

東京藝大奏楽堂(たぶん幽霊は出ない)

当日の進行。黒字が演劇、赤字が音楽。

前日のリハーサル。オルケストル・アヴァン=ギャルドのツイッターから。

これは本番の舞台写真。最後の場面。中央の黒い処刑台に進もうとするエグモント。上手側にアルバ公とフェルナンド。下手にオラニエ公。処刑台のまわりに市民と兵士たち。最後方に天使クレールヒェン。
中江早希さんのツイッターから。

場面に応じてマスクを使いわけた。これはエグモントがスペインで誂えた華麗な服を、クレールヒェンに見せに来た場面(独立と自由を願いつつ、貴族としてはスペイン宮廷文化に依存しているという、簡単ではない内面が見える場面)
中江早希さんのツイッターから。

《ルル》のゲネプロ。ピット内の配置がよくわかる。

上野桜木の桃林堂

桃林堂の菓子。美味い。
九月一日(水)パイプオルガンの魅力
オペラシティで鈴木優人のオルガン・リサイタル。バッハ、スウェーリンク、メンデルスゾーン、ブクステフーデ。
コロナ禍で海外アーティストの来日がごくわずかになるなか、コンサートホールの巨大パイプオルガンの演奏会は、自分にとって新たな出会いといえるもの。
現代の東京には優れたパイプオルガンを持つホールがいくつもあるが、これまではオーケストラ演奏会の楽器として聴くことが多かった。ランチタイムなど短時間のオルガン・コンサートをやるホールも多いが、何か中途半端な感じで、行く機会がなかった。オーケストラ曲の編曲などホピュラー路線が多いのも、二の足を踏んでいた理由である。
しかし八月にサントリーホールで聴いて、単独で演奏するときの音量やパワーの凄さ、そして何よりもファンタジーの大きさに、蒙を啓かれた。もっと聴いてみたいと思っていたところに、うってつけのこのコンサート。ドイツ・オルガン音楽の王道から選んだプログラムを、鈴木優人が解説しながらひいてくれる。
ファンタジアを得意とし、幻想曲のマエストロと呼ばれているというブクステフーデの、自由に飛翔するようなイマジネーションの大きさが、特に印象に残った。壮麗な響きの色彩の豊富さ、重低音の威力など、ナマでこそ実感できる。
九月八日(水)背中を叩く音楽
遅れていた一回目のワクチンをようやく六日に打ってもらい、翌日は予想通り風邪の症状のようなだるさと微熱で一日寝て過ごし、今日は無事に回復して朝日カルチャーセンターの講座で、グールドとバーンスタインの話。
レジュメに使ったのは、三十年くらい前に書いたままお蔵入りしている単行本用の原稿の抜粋。こういうあんちょこがあると、ほんとうに便利でいい(笑)。ありがとう昔の俺。
〆切に遅れている原稿もたった二本になったので(ダメ)、聴けずに我慢していたCDを聴く。クレンペラーが一九六二年にフィラデルフィア管に客演したときの《田園》&《英雄》のステレオ。
この客演の他の演奏会は少し前に正規発売されたが、この演奏会だけは保存音源の状態不良とかで発売されなかったのだが、別の音源が見つかったそうで、めでたく日の目を見た。

いいなあ、このエロイカ!
この曲についてはフィルハーモニアとの一九五九年セッション録音が自分の刷り込みになっている。対向配置の面白さ(一九八〇年ごろにはクレンペラーかクーベリックくらいしか録音ではなかったし、実演ではまずありえなかった)、木管を強調した独特のバランス、各声部の呼応による遠近感と立体感、堂々として、絶対に崩れない全体の骨格、遅いテンポでもリズムは弾ませることができ、呼吸感がつくれることなど、自分がそれから四十年間にわたって音楽を聴く上でのポイントを教えてもらった、たたき込んでもらった盤だった。
ただ惜しむらくはセッション録音のため、リズムにこめる気魄とか、微妙な即興的変化とか、集中力や推進力とかは乏しかった。そういうものは一九六〇年のウィーン芸術週間ライヴでこそ教えてもらったが、そちらはしかしモノラルだったので、たとえば終楽章の変奏曲での立体感などは想像するほかなかった。
それがこれはライヴでステレオ。クレンペラーの《英雄》のステレオ・ライヴは、たぶんこれしか残ってないのでは。
明快で、しかし硬くならない絶妙の立体感と、豊かな呼吸感。フィラデルフィアの木管の歌いぶりの艶やかさ。葬送行進曲の真に迫るドラマ(近年は聴く機会の増えたホルンによる運命動機の暗示、すでにクレンペラーがはっきりと浮かびあがらせていたことに驚く)。
すべてが、自分がさんざん慣れ親しんできたリズム、間とバランス、緩急強弱で響くのに、そこに新鮮な生彩と弾力が加わっているという驚きと感激。四十年前に聴いたものと似ているのに、初めて出会う音楽。
年取ったといっている場合じゃない、立て、そこから出てこい、と呼びかけてくる音楽。明日からも歩いていけ、と背中を叩く音楽。
――わかりました。まずは原稿やらせてください。
九月十三日(月)スポーツ的快感
重陽の節句のあたりから、東京のクラシック界は一気に動きはじめた。週末は大小さまざまなものが立て込んで、どれを選べばいいのか悩ましい。どうすれば最適の組み合わせが見つかるのか、ほとんどパズルを解くような感じ。
悩ましいけれど、しかしありがたいこと。海外からの来日は限定され、販売席数にも制限がある困難な状況下にもかかわらず、それぞれに特徴を発揮した、意欲的な公演が続いた。
オペラは二本、九日に東京文化会館で二期会の《魔笛》、十二日にオペラパレスで藤原歌劇団の《清教徒》。前者にとっては原点みたいな作品、後者にとっては近年の看板であるベルカント・オペラと、それぞれに得意のレパートリーだけに充実感のある公演だった。
《魔笛》はギエドレ・シュレキーテの颯爽とした指揮が気持ちよかった。バレリーナを想わせる身のこなしで、軽快で爽快な音楽をつくりだす。陰鬱で鈍重に演奏した《魔笛》くらい苦手なものはないので、大いに共感。
《清教徒》は、アルトゥーロ役の澤﨑一了が、作曲者が書いたとおりの超高音をスパン!と何度も決めたのに驚愕。日本のテノールでこんな人が出るとは。
フィギュアスケートの四回転ジャンプがすべてきれいに決まるのを目の当たりにしたような。それだけがすべてではないけれど、ベルカント・オペラにはこうしたスポーツ的要素もある。「芸術点」とはまた別の価値を持っているのだ。
九月十六日(木)丸木砂土の時代
土曜日のオンライン講座「光は日比谷より」のための資料から、秦豊吉の評伝『行動する異端―秦豊吉と丸木砂土』(森彰英/TBSブリタニカ/一九九八)。
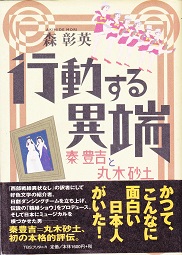
秦豊吉(一八九二~一九五六)は東京生まれ、一高・東大法学部から三菱商事に入り、一九二〇年から二六年までベルリン支店に勤務。大学在学中からドイツ文学の翻訳を行なっており、帰国後の二九年に翻訳した『西部戦線異状なし』が大ベストセラーとなる。
三三年に三菱商事を退社し、東京宝塚劇場の支配人となる。三五年に日本劇場に日劇ダンシングチームを設立。戦後は帝国劇場社長となり、五一年に越路吹雪などによる帝劇ミュージカルスを創始、現在の東宝ミュージカルの基礎を築く。
クラシック界とはあまり結びつかないが、父の弟が七代目の松本幸四郎だったり、公職追放を受けていた四七年に新宿帝都座でストリップの元祖、額縁ショウを始めてみたりと、一筋縄ではいかない面白い人。
そのもう一つの顔のほうに、面白い一文があった。もう一つの顔とは、戦前のエログロナンセンスの時期と戦後のカストリ雑誌時代に艶笑譚などを書くのに用いた、丸木砂土(サド侯爵のもじり)という筆名。ワイマール期のベルリン三菱時代に要人接待などで用いた遊興街の思い出を帰国後に書いたなかに、こんな文章があった。
「フリードリッヒ街の外れにある「アドミラル・パラスト」は気軽に楽しませてくれ、女も選べる安直なダンスホールだった。ここの売り物は氷上で芝居と舞踏を見せるショウだが、ステージが終わると、それまでロシア風の冠り物に赤い靴で氷上にいた女優たちが、夜会服に着替えて廊下に並んでいる。この中からお好みの相手を選んで踊り場に出るのである」
東ベルリンにあるアドミラル・パラストは、空襲も市街戦も生き残った貴重な劇場建築。四四年からはフィルハーモニーを爆撃で喪失したフルトヴェングラー&ベルリン・フィルがシュペーア軍需相の肝煎りで演奏会を行ない、戦後には五五年の再建までベルリン国立歌劇場が仮住まいしたことで、クラシック好きにはおなじみの建物。
アイススケートのリンクが売りだったのは二三年までで、その後はレヴュー劇場、オペレッタ劇場となったようで、現在も同様のようだが、敗戦直後の混乱期の大元の姿が、丸木砂土によって紹介されている。
十五年戦争の直前と直後の時期にだけ姿を現わす、丸木砂土という仮面とその時代精神(エログロ流行の一方で左翼がさかんな時代。すさんだ心の両面か)。なかなか面白い。

現在のアドミラル・パラスト。公式サイトから。
九月十九日(日)ペレアスから
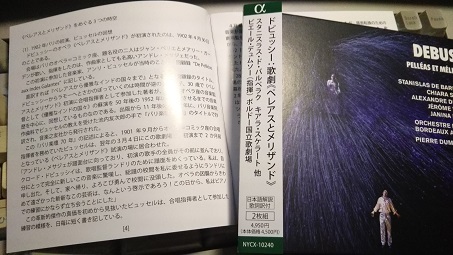
デュムソー指揮ボルドー国立歌劇場によるドビュッシーの《ペレアスとメリザンド》全曲CDが、ナクソス・ジャパンより発売された。
おそらくはアバド以来三十年ぶりのこのオペラのセッション録音。ミンコフスキが初演、金沢と東京にも持ってきてくれた美しいプロダクションによるもの。本来は俊英デュムソーの指揮で劇場で再演するはずだったものを、コロナ禍で不可能になったのを奇貨としてレコーディングに切り換え、そのままのメンバーでセッション録音したもの。舞台上演とはまた別の魅力と美がある。
国内盤のライナーノーツを担当した。「《ペレアスとメリザンド》をめぐる3つの時空」と題して、一九〇二年の初演に合唱指揮者として立ち会い、初演者メサジェに続いて指揮を担当したアンリ・ビュッセルの回想から初めて、二〇一八年、ドビュッシー逝去と第一次世界大戦休戦百年の記念の年に行なわれたミンコフスキの舞台上演、そして二〇二〇年のデュムソー指揮のこの録音と、三つの場面を述べている。
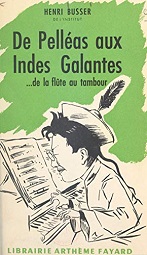
ネタ本としたビュッセルの回顧録の原題を直訳すると、『ペレアスから優雅なインドの国々まで』。一九〇二年ペレアスでの指揮者デビューから、一九五二年にパリ・オペラ座の音楽監督として《優雅なインドの国々》蘇演を大成功させるまでの五十年間を中心に回想したもの。
ミンコフスキの三十年間の指揮キャリアは逆に、「ラモーからドビュッシーまで」。この対照の面白さ、そしてメサジェとビュッセル、ミンコフスキとデュムソーの関係の相似の面白さをポイントにして、出演者紹介も含めて五千字書かせてもらった。
国内盤は輸入盤よりも高いが、山下賢司さんによる新規の日本語対訳もついている。
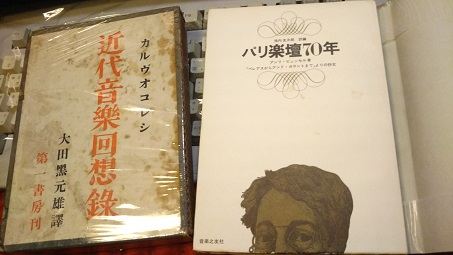
写真は、右がビュッセル回顧録を弟子の池内友次郎が抄訳した『パリ楽壇70年』(一九六六年)。四半世紀前になんとなく買っておいた本が今役立つとは思いもよちなかった。左は、たぶんそれと一緒に古賀書店で買った同時代の音楽評論家・音楽学者のカルヴォコレシの『近代音楽回想録』(大田黒元雄訳、一九三八年)。この人もペレアス初演を見ていて、ダンディから意見を聞いていたりとか、使えるかなと思ったが、文章の焦点がぶれるので今回は不参加に。でも、次は俺の番だと言っている気がする。
九月二十六日(日)幻想と巨人
一昨日からコンサート三連発。二十四日は王子ホールでMAROワールド。清水和音を招いてのブラームス・ナイト。ピアノ四重奏曲第一番での、なんか退場者がいて、四人だけでどんなに懸命に走り回っても音楽のフィールドを埋めきれない、みんながボールのある場所に集まってしまってパスを送る相手がいない、みたいなもどかしさがピアノ五重奏曲では見事に解決。五人が適切なポジションを得て協同して、陣形ががっちり安定して立体的な響きになるだけでなく、パスだのドリブルだのとそれぞれの個人技の見せ場も出てくるという違いが面白い。
ブラームスの書法の成熟か。そしてシェーンベルクが前者をオーケストレーションしたのは、この兵力不足の隙間にこそ自分が援軍を出す意義があると考えたからかも、などと考えながら聴く。
昨日のスダーン指揮東京交響楽団と今日の沼尻竜典指揮NHK交響楽団は、前者の幻想交響曲と後者の《巨人》の、親子関係みたいな相似が楽しかった。サントリーホールと芸術劇場と会場が違うのに、どちらも舞台奥右にティンパニ二セットがならんでいるという既視感。
失恋が人生最大の重大事件になっているという「青さ」も似ている。続篇《レリオ》で生への回帰をはかる前者と、プロローグのような《さすらう若人の歌》をもつ後者、どちらも語ったり歌ったりの具体的な言葉をもつ姉妹篇をもち、交響曲では言葉にならない思いを音でぶちまけようとする共通性も面白い。
ただ、ぐちゃぐちゃに終わる前者に対し、教養小説のように、あるいはベートーヴェンのように、苦悩を克服して凱歌をあげる後者。ライン川をはさんだそんな違いはあれ、前者がなければ後者はたぶん存在していない。〈花の章〉を含んだ改訂前の五楽章版だと、その親子関係はさらに濃厚だったかもしれない、などと考えながら聴く。
こんなふうに、曲についていろいろ、意味のあることもないことも、とにかく考えさせてくれる、想像の翼を広げてくれるものこそ、自分にとってはいい演奏会なのだと思う。
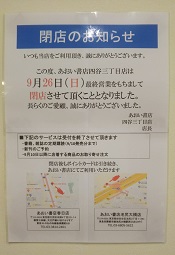
帰路、今日で閉店する四谷三丁目のあおい書店に寄る。
ここが閉まると、四谷三丁目駅と四谷駅の周辺には本屋が皆無ということになる。二十年前には二つの駅あわせて大小六店はあったのに、ついにみな消える。
本は、なんといっても店頭での邂逅こそが楽しみなものなのに、その喜びを味わう場が近所になくなった。
一つくらい新たに開店してほしい…。
九月二十七日(月)ワクチン二回目
二回目のワクチン。一回目が遺物混入騒ぎで延期となったため、間隔はモデルナの規定ギリギリの三週間。前回は接種会場(国立新美術館)でずいぶん待たされたが今日ははてきぱきと進む。担当者が増えたのか、手際がよくなったのか。
九月二十八日(火)副反応
二回目の副反応は一回目とほぼ同じで翌日はだるく、少し発熱。元に戻るのに夜までかかり、前回より長かった。
九月二十九日(水)挑め
サントリーホールへ行き、読売日本交響楽団の定期を井上道義の指揮で。宮田大の独奏でゴリホフのチェロ協奏曲《アズール》の日本初演を聴けたのが嬉しかった。本来はイラン・ヴォルコフが指揮するはずの演目をそのまま引き受けた、今年七十五歳の井上の冒険心に感服。
コロナ禍の非常事態において、読響がなるべく予定の曲目を変えないように努め、それに応えられる出演者を探しているのは、本当に素晴らしいこと。時間がかぎられているだけに容易なことではないはず。来月のアデスのピアノ協奏曲もソリストのヴィキングルが来日中止になったが、若いチャクムルが敢然と引き受けてくれたおかげでそのまま演奏できるという。挑戦なきところに進歩なし。
メインのショスタコーヴィチの交響曲第九番は、音楽が井上の心身と一体化している点で、バーンスタインとマーラー作品の関係を想わせる。軽妙ではない、重く陰影の深い演奏。
九月三十日(木)今の日本で聴くべきは


国立能楽堂で能楽座の公演。人間国宝や名手が流派をこえて集った豪華な公演なのに、いつも平日午後なのがもったいない。今回で一区切りというためか、特に重量級の曲が集まっていた印象。大槻文藏が鷺、梅若実玄祥が帝の能『鷺』がメイン。
緊急事態宣言解除を待って、王子ホールでの藤田真央のモーツァルト・ツィクルス第二回が、いよいよ明日発売。
今の日本で聴くべきは、藤田真央のひくモーツァルトのソナタ。個人的にはそう思っている。前回第一回の明るく快活なハ長調プロから、今回は一転して短調プロへ。
十月一日(金)十五年目
ミュージックバードの番組「ニューディスク・ナビ」の十一月放送分の収録を完了。この番組もいつのまにか十五年目に入っている。
十月二日(土)深き山にすみける月を

喜多能楽堂にて「塩津能の會」。喜多流の塩津哲生がシテをつとめる能『伯母捨』がメイン。
百三十五分、現行曲では最長という大曲。
能の世界には、最奧の曲として「三老女」がある。老女をシテとする『檜垣』『関寺小町』『姨捨』(喜多流のみ『伯母捨』と書く)の三曲。
昭和中期までは文字通りの秘曲で、舞台にかかることは本当に希少だったそうだが、近年は増えてきて、東京では年に二、三回はかかるようになってきた。
とはいえ、国立能楽堂や各流派や家が主催する定期公演の類にはかからない。シテ方が個人で主催する会で、特別の機会に特別の覚悟で取りあげられるだけ。そのため、自分が能を見始めたころにはどこでやっているのかわからず、気がついたときには売切れということが多かった。アンテナの張りかたがわかった最近は、ようやく発売前に気づけるようになったが。
増えたといっても、今でもシテ方なら誰でもやれる曲ではない。宗家以外は各流派の長老クラスにしか許されない。その人たちでも一つの曲を舞えるのは生涯にただ一度、ということがほとんど。
プログラムにある塩津のあいさつに、その思いがよく出ている。
「伯母捨」だけは特別だ、大変な曲だ、と先人からよく聞かされていましたが、これほどまでとは知らず、今はもう観念しております。
永きに亘り習得したものは総て捨て去らねば、有害以外の何物でもないとさえ、思えて参りました。稽古を積めばなんとかなる、の信念の前に最後に大きな壁が立ち塞がった感じで一人、もがいております。
すでに老女物の『卒都婆小町』『鸚鵡小町』、そして『檜垣』と三つを勤めている七十六歳の塩津にして、この言葉。どれほど別格に難しいかがよくわかる。
しかしこのように長く精進を重ねて、老境に至って初めて、そしておそらくただ一度挑戦できる、生涯の目標になる曲がある能というのは、本当に素晴らしい芸術、奥の深い芸術だと感じる。
実際に見てみて、たしかに『伯母捨』は、ほんとうに凄い作品だった。
これほど深い境地を描いた作品が六百年前に書かれていて、それが受け継がれて、代々の芸術家が自己の生涯を賭けて実際の舞台にかけ、今も眼前にかかっているという、歴史の凄み。
自分自身も六十近くになって、まだこんな凄いもの、奥深いものに初めて出会えることが、たまらなく嬉しい。
古今集のよみ人知らずの歌、「わが心なぐさめかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」が物語の主題となる能だが、私は西行の歌、「深き山にすみける月を見ざりせば思ひ出もなき我が身ならまし」をむしろ思った。
浮世の俗事、喜怒哀楽の記憶のすべてを忘れ、深山にかかる澄んだ月の光景だけが、心にある。
まさしく、澄みきった月のような能。
姥捨てが題材ときくと深沢七郎の『楢山節考』のような話かと思うが、そのような生々しい話ではない。捨てられた老女の思いをひたすらに純化して美しく描きつつ、最後に人の業の深さをしぼり出すところに、この能の凄さがある。
老女が誰であるのか、また山に置き捨てられる具体的な経緯などは、詞章の本文には含まれていない。この作劇法が興味深い。それらはアイが語るところにしか含まれていないので、狂言方にとっては腕の見せどころとなる、重要な役である。しかもその内容は、流派や家によって異同があるという。
今回は大蔵流の山本東次郎で、かれによるアイ語りを聴けるのも、この公演を楽しみにした理由の一つだった。大蔵流では、甥に捨てられた伯母は山で亡くなるが、執心によって石となる。甥は自らの行為を悔いて出家するという内容。
東次郎は、故野村幻雪(四郎)との対談『芸の心』(笠井賢一編/藤原書店)で、こう語っている。
「父は『姨捨』は能で言わないことを間狂言で言ってしまうところに意味がある、残酷な内容だからあまり生々しくてはいけないし、それでいてちゃんと伝えなければいけないところがむずかしいんだという話はしていました。稽古されたのは二十五、六の時だったかな。寿夫さんにその話をしたら、「あれはシテの方は一切言わないことをあえてリアルな狂言の語りで聞かせることがすごく大事なんだと僕は思うよ」と言ってらっしゃいました」
東次郎のいう「語りが生になってはいけない」「生々しさをどう覆い隠すか」に重きをおいた語り、ズシリと来るものだった。
後場で老女の霊は、中秋の名月の美を讃えて荘重に謡い、舞う。
その白衣は、まるで月の光そのもののように冴え冴えと輝く。澄みきって清い月光を浴びる老女の姿であり、同時に、夜空をまぶしく照らす月、そのもののようにも見えてきた。
シテ自らが舞台装置となる。何もない能舞台に、輝く月球のイメージを喚起してみせる。能ならではの、すさまじき想像の翼。
しかし、老女の霊はそれでもなお、悟りを開いているわけではない。現世への執着が消えていない。この能の真の凄味が明らかになるのは、ここからである。
月光は、世をあまねく照らす弥陀の光明の象徴だ。だが、月は不変ではない。満ち欠けもあって、その周期が時の移ろいを象徴する。
こう思いいたった瞬間、老女は有為転変の現世への執着を思い出してしまう。
「返せや返せ昔の秋を、思ひ出でたる妄執の心。やる方もなき今宵の秋風、身にしみじみと。恋しきは昔、しのばしきは閻浮の秋よ友よと」。
歳月が過ぎ、友がみな死に絶えても、現世を恋い慕い、霊となってとどまりつづける老女の妄執。
姥捨ての行為の是非だとか、甥への恨みとか、そんなものは一切語られない。
昔と同じように秋の名月を愛でても、周囲にもはや友は一人もいない。時間の経過から置き捨てられた、老残の孤独の淋しさをただ嘆くのだ。
「わが心なぐさめかねつ更級や姨捨山に照る月を見て」
悟りきれぬ凡夫の哀しさ。「深き山にすみける月」以外に思い出などあるものかといいながら、現世を捨てきれぬ愚かしさ。その煩悩に触れることが、この能を哀しく奥深いものにする。
最後、白々と明けていく朝の気配とともに、ワキの旅人は去っていく。舞台にひとり置き去りにされた老女の霊は救われることなく、ふたたび石と化す。
「今もまた姨捨山とぞなりにける」
座り込んだシテが、最後はほんとうに石となっていくように見えた。
見上げるその面は、ついに月に届きえぬ無力と永遠の孤独に、泣いているように見えた。
ただただ、身震いするほど凄かった。
第十三回 清能会 塩津能の會
・舞囃子『安宅』 塩津圭介
松田弘之(笛)、林大輝(小鼓)、亀井洋佑(大鼓)
・狂言『福の神』 山本則俊、山本則重
・能『伯母捨』
塩津哲生(シテ)
森常好(ワキ)、舘田善博、梅村昌功(ワキツレ)
山本東次郎(アイ)
松田弘之(笛)、林吉兵衛(小鼓)、亀井忠雄(大鼓)、小寺真佐人(太鼓)
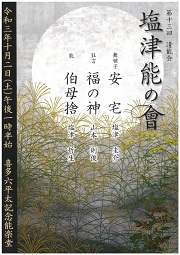
ほんとうにこのチラシそのもの、足元には秋草が生えていて、 全身に月光を浴びている、ときには月そのものに見える、輝くように美しい装束だった。装束を背景にも舞台装置にも用いて、月光の野を脳内にイメージさせる、能の力は凄いと思った。
十月五日(火)夢の解剖
世田谷美術館で「夢の解剖―猩々乱」をみる。砧公園の一角にある世田谷美術館のエントランスの空間を舞台として、能の『猩々乱』を公演するもの。オペラやバレエの演出家として国際的に活躍するイタリア人、ルカ・ヴェジェッティが「演出をする」のがポイント。
美術館閉館後の夜八時開演。砧公園、私には砧緑地という古い呼称がしっくりくる。同じ世田谷区の深沢にある私の出た小学校から直線距離で三キロ強、小学生を遊ばせるのに最適の空間なので、一年に一、二回くらい遠足に行った記憶がある。個人的に懐かしい。
昼間の公演なら、小学校から半世紀ぶりに歩いてみることも試したかった。だが夜の世田谷の住宅街の暗くて細い道なんて、慣れないと迷って遭難しかねないのであきらめ(笑)、最寄りの用賀駅から北西に歩く。それでも片道二十分はかかったから、一・五キロはあったか。
世田谷の夜道を歩き、さらに暗く人気のない砧公園を抜けていくのは、なかなかのスリル。やっと北端の美術館にたどりつくと正面は閉まっていて、案内を頼りに脇の入口から入る。
 夜の砧公園を歩く
夜の砧公園を歩く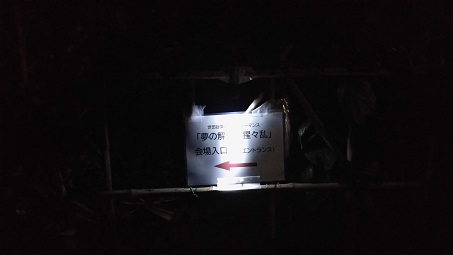 美術館脇に浮かびあがる案内板
美術館脇に浮かびあがる案内板舞台となるエントランスには、月球を模した丸いライトを載せた篝火のようなスタンドが四つ。これが能舞台の四隅の柱の位置にあり、内側が三間四方というのは演能が始まってわかった。後方の二階への階段の踊り場の上にも一つあり、そこに囃子方三人が座る。

開演前に客席からみたエントランス。正面奥の踊り場から右上に2階への階段がある
シテは左奥の白い壁面に影を映して登場する
配られたキャスト表を見て、地謡が観世銕之丞一人なのに驚く。通常の能では八人、少なくとも四人はいるのだから。
しかしこの疑問は二階からお調べ(開演前に、姿を見せずに囃子方が試奏するもの)が聴こえてきて氷解した。磨いた大理石の空間の反響と残響が強烈で、能舞台ではありえない大音量で響く。地謡が何人もいたら、混濁するだけだろう。
お調べが止み、囃子方が二階から階段を降りてきて、踊り場に着席して開演。エントランスの照明が落とされ、五つの月球が暗い空間に浮かびあがる。
 世田谷美術館の案内PDFから
世田谷美術館の案内PDFから中国の富裕な酒屋の主人に扮したワキ(森常好)が出てきて次第を語り、ワキ座に着く。大理石の硬く冷たい床の上に四十五分間じかに座っている。
続いて、猩々役のシテ長山桂三が奥の通路から入場。通路の壁には横から強い光があてられ、白い壁にシルエットが映る。これは、月面を背に黒い影が浮かぶ場面をイメージさせたように感じた。
 世田谷美術館のサイトから 撮影:今井智己
世田谷美術館のサイトから 撮影:今井智己そして、川中から現われた猩々が美酒に酔い、水上を舞い遊ぶ場面となる。ただそれだけで、ほとんどストーリーもドラマもないことが、この能の特徴。
能狂言は歌舞伎と同じく、日本古来の舞台芸術の伝統として、現在も原則的には照明の変化を演出としては用いない。蝋燭能や屋根のない野外公演以外は、どこもかしこも同等に明るい。しかし今回は照明の方向や光量が限定され、陰翳が濃くなるところが蝋燭能に似ている。
夜の月光の下で舞う場面なのだから、たしかにこのほうがイメージしやすい。シテが月そのものになりきった三日前の『伯母捨』の豊かな想像性は能ならではの魅力だが、わかりにくいと感じる人もいるだろう。それよりもイメージしやすい。ただし、演能中に光量や方向を変化させることは慎んでいる。
爪先立ちで横に流れ、水上を滑るさまを示す流レ足、波を蹴立てる乱レ足など、水と戯れる猩々のほろ酔い気分を、能舞台よりもはるかに滑りやすそうな磨いた大理石の床面にもかかわらず、シテの長山さんは軽々と動いていて、さすが。月下で美酒に歓び、酔い、嬉しげに舞い謡う幻獣の姿がユーモラスに、しかし品格を保って描かれていく。
照明の変化を最小限に控えていることが端的に示すように、ヴェジェッティは『猩々乱』という曲そのもの、囃子や謡や舞などの進行にはいっさい手を加えない。通常の演能そのまま。ただ、能舞台という平面から、美術館のエントランスという立体的な場所に移しかえて、その空間いっぱいに能の響きを展開させる。これだけで十分に異化の面白さがある。
銕之丞の地謡の声は二階から、姿を見せぬまま降って響いてきて、シテの謡と唱和する。そのときには奥の白い壁面に地謡のシルエットが浮かびあがる。水面のシテと月面の地謡が、謡いあうかのようであり、あるいは、地謡がシテの影法師、分身として応えているかのようでもある。これは地謡が一人しかいないからこそ可能になるイメージ。
高さの概念、空間の概念というのは、『道成寺』の頭上の鐘を例外として、通常の能では詞が脳内にイメージさせるだけだが、ここではより明快になる。
といってもエントランスを使ってだから、写実的な高低の表現ではなく、イメージをふくらませるための見立てというほうが近い。その意味では能の魅力の源泉である、抽象と具象の微妙なバランスでの共存をこの演出は守っている。ヴェジェッティという人は能のことをとても深く理解しているのだろうと思った。
十日前の九月二十五日にサントリーホールで東京交響楽団を指揮したスダーンが、幻想交響曲で舞台袖からオーボエや鐘を響かせたとき、もっと遥かな遠さをイメージさせた、絶妙の音響センスを連想した。
これは水平方向だが、カンブルランがサントリーホールのP席とかオルガン席とか二階客席とか、ヴィンヤードの空間を巧妙に使って立体的な音響効果をあげていたこと、最近そういうものに出会う機会が少ないことを思い出し、懐かしくて嬉しくなった。
そういうものに似た、あえていえば西洋的な空間使用のセンスのよさが、この「夢の解剖―猩々乱」にもある。
そしてこの空間がもたらす、もう一つの西洋的なもの――それは残響の多さ。囃子がとにかく響く。高い空間の壁という壁に反響して、こちらを全方向から包み込むように響く。能楽堂ではありえない音響だが、音に溺れるような響きは、この世ならぬ妖精が月下に舞うという場面にぴったりの幻想性、ある種のトランス状態といってもいい感覚をもたらす。
日本の木造建築では、風呂場でもないかぎりこんなに豊かな残響はなかっただろう。これは個人的な推測にすぎないけれども、昔の日本のホールの残響が短めだったのは、そもそも近代までの日本人が長い残響になじんでいなかったからではないかと思っている。
立体的な音響、また全身を包むような反響、西洋からきたこれらの感覚の、その原型は、カトリックの大聖堂の空間が恍惚的にもたらすそれなのではないか。
そして、その大聖堂で発展した音楽と美術という二つの芸術が、近代になるとコンサートホールと美術館という別々の空間に展示されるようになった。
西洋的なこれらの要素のただなかに、『猩々乱』という夢幻能が置かれる。能はもともと寺社で上演されていた。その能に西洋的なセンスを加えることで、日本と西洋のそれぞれの舞台芸術の個性が露わになり、画然と浮かびあがる。まさしく「夢の解剖」。
偶然にも今年は、能と西洋芸術の出会いの場をいくつか見ることができた。
六月のサーリアホのオペラ《オンリー・ザ・サウンド・リメインズ》は『経正』と『羽衣』の謡曲の英訳を用いたが、能の単なるオペラ化ではなかった。『経正』は修羅能の要素を薄め、死者が姿を見られることを嫌う「見るなのタブー」を前面に出した。それによってオルペウスの冥府下りやイザナギの黄泉国行きのような、死せる恋人の探索と失敗という伝説に近くなった。『羽衣』はいうまでもなく、世界各地に羽衣伝説、白鳥伝説としてさまざまに伝わるものの一つ。
つまり、地球のどこかでいつかに生まれて世界に伝播し、変形されていった普遍的な伝説の、その一つの変奏として謡曲を見ていた。
また、八月の細川俊夫の『二人静』は、西洋のオーケストラと歌に、能の謡と舞を組み合わせていた。異質なものが唐突に出会う、その居心地の悪さ。
しかし、キリスト教を背景とする芸術と仏教を背景とする芸術がここで出会うことで、ここには書かれていない、だが難民問題の背景にあるイスラム教のことを、それが不在であるがゆえに意識してしまう。そこに響かないものの響き、声なきものの声、とでもいうか。
これらの試みがどこまで成功しているかの判断は、見る人によって異なるだろう。少なくとも自分にとっては、自分の立ち位置、居場所の再確認を鋭く求めてくるように感じられて、とても嬉しい。
十月六日(水)虚実のにじみ


新国立劇場の《チェネレントラ》、すごくよかった。七時に始まって劇場を出たのが十時半。あと一時間早いと楽だけれど、夜公演は勤労者が行きやすいように七時という割り切りか。
音楽面がとても充実しているのに加えて、粟國淳の演出もすごく考えさせる。ある映画会社(そのデザインは三〇~五〇年代のハリウッドのように見えた)が『チェネレントラ』という映画を撮っているという、ハリウッドお得意のバックステージ物みたいな感じになっている。
うまいのは、アリドーロを演じる俳優が映画監督も兼ねているという設定にしたこと。プロデューサーにあたるドン・ラミーロとは、同じ映画人でも別種の権力をもたせることで、アンジェリーナを主演女優に抜擢するという役割に、さらに説得力がました。
まあ、劇中劇の手法自体は珍しくないが、とても面白かったのは、映画スタジオという現実と映画の中の虚構との境目が、画然としていないこと。どちらなのか、わざとよくわからなくしてある。つまり、虚実の境目がにじんでいる。「わかりやすさ」をまず求める現代の消費者がイライラしそうな、虚実のにじみ。
これはおそらく、オペラのなかでドン・ラミーロとダンディーニが入れ替わっていて、「もつれた糸」のような混乱を起していることがヒントなのだろう。
しかしこの虚実のにじみは、オペラという芸術そのもののことではないかと、途中で思った。
オペラにおける音楽の重要性は、芝居の合理性とはしょっちゅう対立する。芝居として合理的にやるなら、長いアリアで高音を出したり技巧を延々と披露したり、みんなでいっぺんに歌って重唱したりするのはおかしい。芝居という現実と音楽という虚構の境目がにじんで共存しているのが、オペラという芸術。
ロッシーニだと、ヴェルディ以降よりもいっそう、音楽の虚構性というか自律性というか、そういうものがきわだっている。だから、オペラという芸術の特異性、虚実のにじみを示すのに、ちょうどよい実例になる。
ドン・ラミーロのアリアの最後をアンコールしたのは、二十世紀以降のオペラ上演では珍しいことだが、二回目の公演からやっているらしい。バルベラの歌が素晴らしいことが最大の理由としても、しかしアリアのアンコールほど、オペラの虚構性を強調するものはない。
その意味でこのアンコールは、演出の一部になっている。虚構ならではの魅力が、現実を突き破って輝く。
もちろんそれだけでは、ただののど自慢大会になるから、ドラマとしての現実性もなくてはならない。虚実のにじみ、虚実の皮膜にこそ、オペラの真実がある(アンジェリーナの最後のアリアは、詩と技巧が結びついて、まさに現実と虚構の絶対矛盾を超越する、虚実の皮膜にある真実と思える。だからこれにアンコールはない、なんて気がするが、ここはもう少し考えたい)。
ヴェルディやワーグナーやプッチーニなど、十九世紀後半から二十世紀に活躍したオペラ作曲家は、虚構性をできるだけ現実性の陰に隠そうとした。大いなる幻想の時代、ロマン派の時代。その二面性に自覚的に向きあったのが、卓越した実務的歌劇場人でもあったリヒャルト・シュトラウスか。
何はともあれ、音楽的にとても充実していて、しかも深く考えさせてくれる舞台とくれば、オペラにこれ以上何を望むべき。
十月九日(土)沖澤のどか
東京芸術劇場で、読売日本交響楽団の演奏会。指揮は山田和樹が予定されていたが、入国制限のために帰国できず、沖澤のどかに交代。
・シベリウス:《フィンランディア》
・ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第一番(独奏:ペーター・レーゼル)
シベリウス:交響曲第二番
あわてず騒がず、幅広い呼吸でスケールの大きな演奏。沖澤はほんとうに楽しみな人。
十月十日(日)永島充の『井筒』
矢来能楽堂で、観世九皐会の十月定例会の第二部。
・仕舞『當麻』永島忠侈
・仕舞『半蔀』観世喜之
・仕舞『土車』鈴木啓吾
・能『井筒』永島充
十月十二日(火)藤田はモーツァルト
王子ホールで、藤田真央のモーツァルトのピアノ・ソナタ全曲演奏会第二回。
副題に「限りない哀愁と苦悩」とある今回は、ハ長調で揃えた第一回とはうってかわって短調ばかり。
軽捷にしてダイナミック、暗い情熱が渦巻くような、見事な演奏。
十月十五日(金)春栄の兄は
国立能楽堂の定例公演。
・狂言『小傘(こがらかさ)』野村萬斎(和泉流)
・能『春栄(しゅんえい)』今井泰行(宝生流)
兄弟愛を描く直面の現在能。子方が弟なので、シテももう少し若いほうが説得力が出そう。
十月十六日(土)京都で能見物
十六日と十七日は四年ぶりに京都と大阪に行ってきた。
主目的は前者の金剛能楽堂と後者の大槻能楽堂で能をみること。公演がうまく二日続きになったので行くことにした。
どちらも通常の主催公演ではなくて、「日本全国 能楽キャラバン!」として特別に開催されたもの。
これはコロナ禍の「萎縮効果を乗り越え,文化芸術に対する需要喚起や業界全体の活性化を図る」ため、「我が国の文化芸術水準を向上させるような公演等を支援」する、文化庁の「大規模かつ質の高い文化芸術活動を核としたアートキャラバン事業」の一環。
クラシックも大小の特別演奏会や、オーケストラの地方公演などを行なっている。しかし内容の多彩さと面白さは、能楽のほうが一枚上手という印象。
「全国20地域・35会場・71公演というかつてない規模で日本全国をまわる能楽の祭典」が、来年の一月末までに行なわれる。たくさんの地方公演に加えて、本拠地でも大規模な企画をしてくれているのが、私には特にありがたい。
観世宗家は『安宅』と『正尊』、シテ方が合わせて二十五人ぐらい出る二本立てをやるし、銕之丞家は「次世代へとこの新作能を受け継いでいくため、今回の上演では若手能楽師も多数出演予定」と謳う新作能『鷹姫』を取りあげる。矢来観世は、喜正が『道成寺』と『熊野』を舞う(喜正は、夏の『融』でも自らの基礎を固めなおそうとするかのような気合の入った能を見せてくれたので、これらもとても楽しみ)。
ほかにも金春流が「三老女」のなかでも最奥の秘曲『関寺小町』を本田光洋が舞うなど、流派や能楽堂がそれぞれに趣向を凝らしている。
そのなかで、金剛流の本拠地である京都の金剛能楽堂は「京都能楽紀行」四公演をやり、大阪の観世流の大槻能楽堂は「大槻文藏三番能 復曲の名曲を観る」三公演をやる。うまいことに、それぞれの第一回が十六、七日と続くことになったので、行ったことのない関西の能楽堂とその公演を見学しようと考えた。
いうまでもなく、能は奈良と京都を中心に近畿で発展したもの。江戸時代以降は能が「武家の式楽」となったため、四座一流の太夫は全員江戸に居住するようになり、現在も金剛流以外の宗家は東京を本拠としている。しかし能を見はじめると、いろいろな意味で京都が今もその「源泉」であると実感する(端的にいえば、装束のなんともいえないセンスのよさ、など)。それで、一度向こうの雰囲気を味わってみたかった。

というわけで一日目は京都。東京七時四十二分初ののぞみで九時五十七分着。感染者が減って私のような旅行者が増えているようで、駅前の各地の寺社行きのバス乗場はすでに行列。
自分は洛中を歩くが、陽がつよくて暑いくらい。東本願寺の西側、新町通を北上していく。烏丸通と堀川通という2本のメインストリートの間にある新町通は、今は細い道だが、伊藤正敏の『寺社勢力の中世―無縁・有縁・移民』(ちくま新書/二〇〇八)の記述に心惹かれた。
「中世の京を見ていこう。京都の人であっても、京都の中心部を、遺跡という目で見ながら歩いたことはないだろう(略)。
まずは商家と工房が建ち並ぶ町小路(現在の新町通)である。ここは洛中一番の高台、山の手にある通りで、鴨川の氾濫があってもこのあたりは絶対の安全地帯である。自動車の通行量が多い道路ではないから、四条通の四条新町を北上して徒歩で散歩できる。東西を見ればここが最高所であることがわかるだろう。(略)本来の幅二十五メートルが五メートルにまで狭くなっているが、古代・中世の道路の真上を歩くことができる。風情ある町並みである。京都の穴場中の穴場である。都市を指す「町」という言葉は、この町小路が元祖なのだ。町小路と平安京東西道路が交差する場所を三条町・六角町・四条町など「○○+町」と呼ぶ。(略)
町小路には土倉が立ち並び、祇園会の山鉾を出す「有徳人」と呼ばれる金持が多くいた。洛中では内裏も武家屋敷も、鴨河原よりは水害の危険が少ないけれども、町小路よりはずっと危険な東京極~東洞院の間にあった。京では商人・職人が一番偉いのだ」

町小路沿いの五条町、四条町、六角町、二条町などには、さまざまな商品の「日本最大の市場」があったという。今は眠ったように静かな道だが、ところどころ茶屋四郎次郎・同新四郎屋敷や三井両替店などの跡を示す駒札が立っていて、往時を偲ばせる。

真平で直線でこの道を三キロほど北上すると二条を越え、京都御苑に面した丸太橋通りへ。洛中の南北の半分ぐらいを歩いた感じか。右折して御苑に入り、閑院宮邸跡を覗きながら蛤御門(意外と小さい)まで来ると、金剛能楽堂まではあと少し。


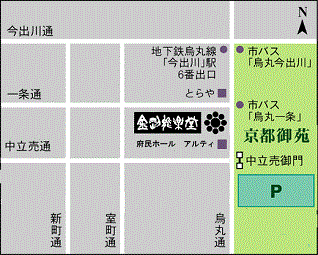

下長者町通を西に歩いて新町通に戻り、角の麺処晃庵で、茄子の忘れ煮うどんを食べる。手頃な値段なのに品がよくて美味。関東とは出汁も違うが、水と土の質がそもそも違う気がする。
歩き疲れたので中立売門の中のベンチで時間をつぶし、開演の十四時まであと少し。自由席だというので、開演三十分前に向かう。

京都御所に面した一等地。南隣に京都府立府民ホールのアルティがある。これは一九八八年開場で五百六十席の室内楽ホール。十五時から京都アルティ弦楽四重奏団の演奏会がある。十七時開演ならはしごができたが、そこまでは都合よくいかない。




金剛能楽堂は二〇〇三年開場で、その前の能楽堂は四条室町に明治の初め頃からあったという。内部の能舞台はそこから移築されたというから、百五十年ほど経っている。
明るくて余裕のある造りの建物。ホワイエに面した庭の池には錦鯉かたくさんいる。四百十二席、正面の最後列がボックス席になっているのが個性的。感染対策で一席ずつあけて座れるので楽。

・対談 高井大輔(貴船神社禰宜)、金剛永謹
・能『鉄輪』 廣田幸稔
「京都能楽紀行」は『鉄輪』『田村』『土蜘蛛』『草紙洗』と、京都を舞台とする曲を集め、演能前に曲にゆかりの寺社の宮司や禰宜、公家の話を聞くもの。
第一回は、貴船神社での丑刻参りが主題の『鉄輪』。
じつは前日の午後に、いきなり金剛能楽堂から電話がかかってきた。時期が時期だけに中止の告知かもとヒヤリとしたが、「他のお客から貴船神社でやるのかという問い合わせがあったので、金剛能楽堂でやると念のために連絡している」とのことで、胸をなでおろした。
貴船神社、上京からでも十キロ以上はある山中だから、たしかに間違えたら大変だろう(笑)。丑刻参りは通いではきつそう。
『鉄輪』は人気があって上演機会も多いが、お化け屋敷風のおどろおどろしさで見せる感じが強くて、ドラマとしては表面的なものに思える。

十六時過ぎに終演、少し北の今出川駅から地下鉄烏丸線に乗り、四条駅で降りて四条通を東に歩く。河原町のあたりに國友銃砲火薬店という看板があり、大筒といえば近江国友村! さすが京の都!と一人で興奮する(馬鹿)。

宿は大阪梅田の大阪新阪急ホテルなので、阪急京都線で梅田駅へ。急行で四十五分ほどかかり、途中で暗くなる。エスカレーターが右に立つように変わり(境目はやはり府境だろうか)、地下街の大きさと繁華に、大阪に来たと実感。地下街でパスタを食してホテル入り。
十月十七日(日)大阪で能見物
この日のメインは十四時からの大槻能楽堂での公演。前後にたっぷりと時間がある。しかし前夜からの雨が朝まで残って最高気温が急激に下がる予想だったので、朝はホテルで朝食をとった後しばらくのんびり。どこへ行くとも決めていなかったが、四年前に来たときに道を間違えて茶臼山に行けなかったことを思い出し、とりあえずその近くの大阪市立美術館に行くことにして、九時半ごろチェックアウト。
梅田駅から地下鉄御堂筋線で天王寺駅に行き、あとは徒歩。予報よりも雨は早く上がって晴天となり、昨日同様に汗ばむ陽気の中を歩く。


一九三六年開場の大阪市立美術館は広い天王寺公園の一角。上町台地の上にあって西側が低地。通天閣を下に見る。
 写真はあべの経済新聞から
写真はあべの経済新聞から大阪市立美術館では特別展「聖徳太子 日出づる処の天子」をやっていた。六二二年に亡くなっているので、来年が没後千四百年の記念年。近接する四天王寺が太子の創建した寺であるだけに、格別の縁がある。
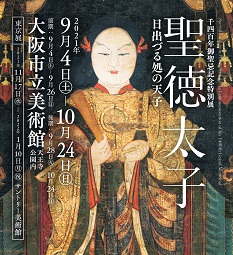

各地から集められた、太子の像や画が並ぶ。聖徳太子というと、自分には昔の一万円札の、あの徳高げな人のイメージが強いのだが、意外にも多くの像や画の太子は、幼年であれ壮年であれ、眉をしかめた厳しい表情をしている。このポスターはその典型的なもの。
解説によると、これは物部氏との戦争で、勝利を四天王に祈願しているときの表情なのだという。それがどの年代のものにも転用されていったらしい。
慈愛や寛容から遠く、怨敵打倒を祈る厳しく鋭い顔。これこそがむしろ太子のイメージらしい。展示の最後には山岸凉子の『日出づる処の天子』の原画数枚もあって、繊細な美しさに息をのまされるが、その妖しく美しく、恐ろしい厩戸王子の顔が、これらの展示と自然につながっているのに驚かされる。このイメージから、漫画の厩戸は創造されたのだ。

大阪市立美術館の北側にあるのが、茶臼山。大坂冬の陣では徳川家康の本陣となり、夏の陣では真田幸村の本陣となった山。


山頂を示す石標。標高は二十六メートル。こちらには三葉葵の紋があり、反対側には六文銭の紋が描かれている。
スマホで茶臼山の地図を見ていたら、北へわずか二百メートル行ったところに幸村戦死の地、安居天神が表示されているのを見つける。こんな近くにあったのか。


小さな社殿の脇に、座り込んだ幸村の像。疲れて立つ気力もなく、討たれる直前の姿らしい。
幸村というのは本人が知らない、後世の人がつけた名前らしいが、それゆえにこそ人々の思いがつまっている感じがする点で、聖徳太子という名と似ている。
ところでこのあたりは坂道が多く、土地の高低が入り組んで起伏がはげしく、山の手らしい地形になっている。安居天神の西側は崖のように低くなり、いかにもミサキのように張り出したここは、神社のような聖地があるのにふさわしい。
東京の西側の、坂道の多い地域に生まれ育ってきた自分のような人間は、真っ平らな市街地というのが、あまり落ちつかない。こういう高低の入り組んだ地形の方が安心する。
平地と違って道や区画の変更が簡単ではなく、地形の高低に影響されるので、昔の雰囲気が残りやすいのだ。茶臼山も安居天神も、空襲で大きな被害を受けたのにもかかわらず、この地形だからこそ四百年前と変わらない気配がある。

その安居天神の真東に大きな石鳥居が見えた。いうまでもなく四天王寺西門、西方浄土につながるとされた石鳥居に決まっている。
物部氏を倒して勝利を得た聖徳太子がお礼に四天王を祀って建てた寺。あの厳しい祈りの結果として生まれた寺。道はつながっている。呼ばれるように接近する。

石鳥居に向かって谷町筋を横断しようと歩いているとき、少し左側のビルの看板が見えた。
金剛組。西暦五七八年創業、現存する世界最古の企業。
四天王寺建立のために百済から招かれた宮大工、金剛重光が創業したもの。看板を見ただけで感動した。

そして石鳥居へ。能『弱法師』で盲目の俊徳丸が「仏法最初の天王寺の石の鳥居ここなれや。立ち寄りて拝まん、いざ立ち寄りて拝まん」と謡う鳥居。

「釈迦如来 転法輪処 当極楽土 東門中心」とある扁額。

一九五九年再建の五重の塔。


四天王境内を北に歩き、石舞台や亀の池、一六二三年建立と現存のなかでは圧倒的に古い六時堂の脇を抜ける。写真は亀の池。
大槻能楽堂は北へまっすぐ上町筋を二キロほど行けばよいので、歩くことにする。

半分ほど来たところにあったのが近鉄の大阪上本町駅。モデルガンマニアだった中学生の頃、このあたりにあった上六ガン&ホビーという店が、模型雑誌に六研製の短機関銃ベルグマンの広告を出していて、十四万円だかの値段に驚愕しつつ、憧れたのを唐突に思い出す。

そして大槻能楽堂に到着。一九三五年にこの地に建てられ、八三年に建て直して、さらに昨年大改修を終えたばかり。


四百四十八席、勾配があって見やすい客席。

大槻能楽堂では「日本全国 能楽キャラバン!」の一環で開催された「大槻文藏三番能 復曲の名曲を観る」の第一回を見た。
・狂言『舟渡聟』(和泉流)
野村又三郎、伊藤泰、野村信朗
・復曲能『維盛』(観世流)
大槻文藏(平維盛の霊)、齊藤信隆(武里)、谷本康介(六代御前)
福王和幸(滝口入道)、野口隆行(那智の浦人)
貞光智宣(笛)、清水晧祐(小鼓)、山本哲也(大鼓)、上田悟(太鼓)
能楽界では一九七八年に観世寿夫が亡くなった後の八〇年代に、番外曲の復曲がさかんに行なわれるようになった。
中心になったのは、東京では浅見真州と梅若実玄祥、大阪では大槻文藏に福王茂十郎など。寿夫の次の世代、当時四十代のシテ方(福王はワキ方)で、研究者や演劇関係者など、能楽師以外の協力者も得て実現した。
『維盛』もその一つで、世阿弥の実子である観世十郎元雅の作の可能性が高いという。弔いの場面で手に持つ鉦を鳴らす音を入れるのは『隅田川』と同じで、いかにも音楽的効果を重視する元雅らしいという印象を受ける。
かつて平維盛(シテ)が入水した那智の海を、遺児の六代(子方)が滝口入道(ワキ)に伴われて訪れる。海に出ていた舟人を呼ぶと、維盛の舎人として入水を見届けた武里(ツレ)だった。武里から父の最期の様子を聞いた六代が、入水したあたりの沖まで出て弔いたいというと、今日は波が荒れているから、浜辺で弔いなさいと武里に止められる。
後場では、六代が滝口入道や武里とともに弔いをはじめると、維盛の霊が軍体(甲冑姿)であらわれる。そして、お前が仏門に入ってくれたことで、自分も修羅道から救われたといって消える。
シテの平維盛の霊は後場にしか出てこないのだが、武里を前シテとして演じることも古くからあったという。初めて蘇演したときには両方を試したようだが、今回は武里をツレにまかせて、後場にも残らせる方式。
ドラマとしてはこのほうが自然だが、武里と話した六代が、まるで父を見るような心地がすると言っていたり、波が荒れて舟は出せないといいながら、自分はその直前まで入水地点に一人で舟で出ていたりするなど、前場の武里をめぐる詞章には、維盛の霊の化身のような気配が濃厚に込められている。いつかはその形式でも見てみたいもの。
今回が初めてだから思い込みかもしれないが、開始時間がアバウトだったり、東京の能よりもやわらかい空気が、舞台にも客席にもあるように感じた。

十四時開演で終わると十六時過ぎ。大槻能楽堂の東南側は、冬の陣の真田丸があったあたり。今回はなぜか聖徳太子・幸村紀行みたいになってしまったので見に行きたい気もするが、暗くなる前に北側の難波宮跡公園を抜け、大阪城の東を回ることにする。
復元された難波宮の大極殿跡から大阪城を望む。

JR大阪城公園駅の前から、西の天守閣をふり返る。まだ時間はあったが早めに新大阪駅へ。なぜか新大阪駅名物でもある赤福を土産に買い、十九時四十五分初ののぞみで東京へ。
自由席三両が満杯という、コロナ禍前のような混雑。経済活動を旧に復しつつ、感染を抑えられるとよいが。
十月二十二日(金)渋沢栄一をめぐり
大河『青天を衝け』もいよいよ第四コーナーの明治編。
栄一と喜作の再会シーン、よかった。葛藤劇があってこそ、「お前の友は、生きてまた会おうと言っていたぞ」という土方歳三の別れの言葉が生きてくる。そして、土方の「友」、近藤や沖田が土方より先にあの世に行ってしまっていたことの重さも、あらためて感じる。
このドラマの土方がいつも一人ぼっちだったこと、無名の部下は連れていても近藤や沖田は一度も出てこないままで、まるでかれらは初めから先に死んでいるみたいだった、というのは、計算づくの演出だったのだろう。
一切弁解しない、言葉にすればその瞬間に嘘になると知っている慶喜もいい。大政奉還を宣言したとき、無言の家康が映ったのも素敵だった。
愛人問題をどうやら正面から扱おうとしているのには驚いたが、現代人の美意識に安易に媚びないこれまでの描き方からすれば、不思議はないのかも。このあともどうなるか楽しみです。
さて本題。十一月二十日に大船で「渋沢栄一とクラシック音楽」というテーマの講座をやる。いかにも便乗企画っぽいですが、もともとは放映前の昨年三月にやるはずだったもの。コロナ禍で延期になって、絵に描いたような便乗企画となった(笑)。
でもまあ、受講者の方には「渋沢栄一のイメージ」が明解になっているだろうから、やりやすくはなったかも。
十月二十四日(日)来日指揮者三人
来日オーケストラはさすがにまだほとんどないが、海外の指揮者や独奏者は、公演回数が複数ある人を中心に、無事に来日するケースが秋から増えてきた。
二十二日から三日間、在京オケに縁の深い外国人指揮者の組み合わせを続けて聴く。
N響のブロムシュテットはペール・ギュントにドヴォルザークの八番、ディスクでも名盤をつくっている二曲の組み合わせ。前者を実演でこれほど格調高い響きで聴く機会はそうない。とりわけ〈オーセの死〉の悲痛と慟哭。日本フィルのラザレフはショスタコーヴィチの十番での推進力にみちた陰惨。「ソ連」を肌で知っている人だからこその慄然か。


興味深かったのは東響のノットのモーツァルトのレクイエム。ジュスマイヤー版を基本としつつ、〈ラクリモーサ〉は独唱が装飾的に歌うフィニッシー版を採用。最後に「アーメン」が二回歌われたあと、ミサで使うような小さな鐘が鳴らされる。まだアルファ・レーベルにいたころのクルレンツィスが録音したこの曲で、〈アーメン・フーガ〉を挿入した後にやはりチャイムが鳴らされたのとよく似ている。これはどういう根拠なのだろう(ミサでは「聖別」の前に注意を喚起するために鳴らしたりするらしいが)。
個人的には、ちょうど一週間前に大槻能楽堂でみた復曲能『維盛』で、弔いの鉦が効果的に使われたことと連環し、脳を活性化してくれたのが嬉しかった。
たしかに〈ラクリモーサ〉の後、曲の気分は変わる。ジュスマイヤー作曲の部分が続いたあと、モーツァルトの音楽が戻る最後の〈聖体拝領唱〉の前に、リゲティの《ルクス・エテルナ》が挿入される。
乱反射しながら、宇宙の彼方へと永遠に伸びていく光を想起させる響き。しだいに遠くなる。七月にサントリーホールで聴いた、虚空を飛び続けるボイジャー一号からの響きを思い出す。
再び小さな鐘が鳴らされ、一呼吸置いてモーツァルトの〈聖体拝領唱〉へ。リゲティと同じ歌詞なのに、〈入祭唱〉そのままのこの音楽は、五十億年の彼方ではなく、いまここにいる死者を見つめ、安息を願っている。
十月二十六日(火)充実の『道成寺』

観世能楽堂で観世喜正の『道成寺』。能楽キャラバンの一環で、観世九皐会の特別公演。
喜正にとって十回目となる今回は、披き以来二十五年ぶりという小書をつけない基本形。まさに初心に立ち返った喜正のシテは、期待通りのすばらしさ。
前九回の経験を踏まえつつ磨きなおされた、鮮度の高さ。それは、落ち着きこそがスピード感につながるという、矛盾のなかから生まれる鮮明さと緊迫感。
乱拍子で大役をつとめる小鼓が女性の大山容子だったのは、能楽の未来を見すえた起用なのだろう。気合の入った見事な鼓。女声による掛け声にも違和感はない。師の大倉源次郎が後見役で見守り、床几をしっかり支えていたのも、頼もしい思いがした。
鐘入りのあと、アイ二人のやりとりやワキによる昔語りは、どうかするとだれてしまいやすいのだが、今日の野村万蔵と野村拳之介は緊張感に満ちてリズムよく、長く感じない。
後場のシテは、身体よりも腕の動きで毒蛇を暗示する巧みさに感服。鬼の型通りに笞(しもと)を振るうのではなく、肘をあげることで、尻尾の先が襲うように見える。柱巻でも、左腕の動きが柱に巻きつく蛇身のように見えた。それにしても、般若の面の形相の恐ろしいこと。
十月二十八日(木)早く退場したい…

国立能楽堂で「狂言ござる乃座」の第六十四回、野村万作卒寿記念の『唐人相撲』。ブロムシュテットは九十四歳、野村万作は九十歳。
中国に渡った日本の相撲取りが、皇帝の命で廷臣約三十人と次々と戦い、勝ち抜いて帰国の許しを勝ち取る話。総計三十九人が舞台に出る、能狂言ではおそらく最大人数の狂言。賑やかで楽しい。
インチキ中国語の響きとやりとりが楽しいのだが、将来的にはポリコレ的に問題になって、上演しにくくなるのかも。
今回は萬斎が行司役の通辞。大蔵流とはラストが少し違い、皇帝まで倒した騒ぎと混乱のなかを相撲取りが脱出する大蔵流に対し、万作家では皇帝が最後に帰国を許し、「再見再見、一路平安」(また会おう、道中無事で)と、ちゃんとした中国語で一同が見送った。
ところで上演中、近くのお客のスマホか何かが十五分毎くらいに、大音量で何事かしゃべることをくり返すという椿事があった。何を知らせているのかよくわからない。しかし前にも同じものを聞いた記憶がある。
終演後、分散退場で順番がくるのを待っているときに、その客の近くの女性客が関西弁で怒りだした。一回ならともかく、繰り返しされるのはたしかに困る。
切りかたがわからないんだからどうしようもない、というような弁解をされたらしく、「わからないなら外へ出て行けばいいじゃないですか」とキンキン声が聞こえてくる。操作法がわからないという困惑も理解できないではないし、しかし関西からわざわざこの公演のために来た人なら、頭に来るだろうとも思う。
どちらも、笑って楽しむためにチケットを買って、ここに来たのに。
退場の順番がくるのを、ただじっと座って待つ。いたたまれない……。
十月二十九日(金)生を実感させる人
サントリーホールで鈴木優人指揮の読売日本交響楽団。
ライマンの《シューベルトのメヌエットによるメタモルフォーゼン》とアデスの《イン・セブン・デイズ》はともに日本初演と、鈴木優人ならではの選曲。
後者はピアノ協奏曲で、ヴィキングル・オラフソンがひくはずだったが日程の都合で来日中止。一九九七年生まれの若いチャクムルが果敢に引き受けてくれたおかげで、実演で聴くことができた。そのチャレンジ精神に感謝。アンコールに鈴木と連弾でブラームスのワルツをひいたのも愉しかった。
メインのシューベルトの「グレイト」もいい演奏。澄んだ響きで力まず、弾力と推進力があってもたれない。
考えさせられたのは、旋律を長く歌わせずに、短い音型の反復と弾力によって曲全体を形成するスタイルに、アデスに通じるものを感じさせたこと。無機的にならずにリズムが息づくのは、二十世紀音楽よりもバロック音楽から得た感覚なのだろう。
鈴木は来月には読響とブルックナーの《ロマンティック》を二日間やる予定になっている。ブルックナーはシューベルトからも大きな影響を受けているので、この方法論の延長でブルックナーの響きをとらえてくれるなら、ブルックナーがあまり得意ではない自分にも楽しめるかもしれない。
ところが、残念なことに二日間とも仕事と重なってしまい、聴くことができない。しかし十一日のトッパンホールのバッハの平均律第一巻は行くつもりだし、十二月の読響アンサンブルとのダウランド、ヴィヴァルディ、デュティユーにシェーンベルクの《月に憑かれたピエロ》という、日本ではおよそこの人しかできなさそうな曲目のよみうり大手町ホールの演奏会も聴きたいと思っている。
脳を活性化してくれる人は、自分にとっては生を実感させてくれる人である。
十月三十日(土)鶴のどんでん返し

東京芸術劇場で《夕鶴》。日経新聞に評を書く。一幕が終わったときには、正直これをどう論じたらいいのかと途方に暮れた。しかし二幕で納得。痛快!
十月三十一日(日)歴史と寓話

総選挙に投票後、久々に神奈川県立音楽堂に行き、ブルーノ・ジネール作曲の歌劇《シャルリー~茶色の朝》日本初演を見る。
普通なら副都心線から東横線、JRというルートだが、前日に池袋まで同路線を往復したとき、行動制限の減った休日で傍若無人な人たち(他人の邪魔をすることで自身の存在を確かめているわけだから、じつは他人にすごく依存しているわけだが)が増えている印象を受けたので、渋谷を経由するのを避け、銀座線から新橋で東海道線を使って往復。
予想通りこちらは人が少なめ。あとで考えたらハロウィンだったから、渋谷を避けたのはまちがいなく正解だった(京王線でいやな事件が起きたことも帰宅後に知った)。
しかしやっぱり、桜木町から紅葉坂を登っていくのはなかなかつらい(笑)。坂下で横断する十六号線の交通量が休日で少なかったのはまだよかったが。
早めに着き、折よく雨もあがったので裏手の横浜能楽堂を外から覗く。内部の能舞台は一八七五年製で関東地方最古の能舞台だし、客席まわりもシックでとても好きな能楽堂なのだけれど、山の上という立地が難物で、あまり来れない。
掃部山公園に入り、井伊直弼の銅像を見る。井伊がここに住んでいたわけではなく、横浜開港のきっかけをつくった恩人ということで建てられたらしい。
神奈川県立音楽堂に入る。前川國男設計で一九五四年に建った傑作。急勾配の客席、その下の空間を利用したホワイエと細い桟の大きなガラス窓、木質のホール内とごまかしのきかない音響など、七年後のレーモンドの群馬音楽センターに強い影響を与えていることをあらためて感じる。

ジネールの《シャルリー》はソプラノ歌手にヴァイオリン、チェロ、クラリネット、ピアノ、パーカッションという六人だけで演じられる、四十五分ほどのポケット・オペラ。一九九八年発表のフランク・パヴロフのベストセラー小説『茶色の朝』をそのまま歌詞にしている。モノオペラだが、奏者たちも合唱として歌い、脇役として舞台に顔を出す。
前の日に池袋で《夕鶴》を見たばかりなので、両者の共通点が面白かった。ともに原作をそのまま歌詞とする「ペレアスとメリザンド」方式であり、また前者は経済的搾取による人間疎外、後者は全体主義による人権抑圧と、それぞれの時代において切実だった、そして普遍的な社会派的テーマを明確に持っている。
《シャルリー》は短いので、前半には同じ編成でヴァイルの『三文オペラ』から二曲とシャンソン二曲、シュルホフによる〈ジンガレスカ〉、デッサウの《ゲルニカ》、そしてジネールの《パウル・デッサウのゲルニカのためのパラフレーズ》が演奏された。
ワイマール時代の音楽的象徴というべき『三文オペラ』、そのヴァイルがナチスに逐われてパリで一九三四年と翌年に作ったシャンソン(公演後のトークセッションでジネールが語ったところによると、この時代のフランスの反ユダヤ主義は、じつはドイツ以上に激しく、ヴァイルはすぐに渡米したという)。続いて強制収容所で死んだユダヤ系チェコ人、シュルホフのジプシー風の音楽という、絵に描いたような禁じられた音楽「頽廃音楽」、そしてピカソの「ゲルニカ」に触発されたデッサウの音楽と、それに基づくジネールの音楽。ジネールの祖父と父はスペイン内戦の敗北でフランスに逃げた亡命スペイン人だったそうだ。
特定の時代と場所、個人に強く結びついた前半のこれらと、いつの時代でもどこの場所でも、誰の身にも起こりうる事態を描いて普遍的な《シャルリー》。
つまり歴史と寓話が並列され、同じ編成による一連の音楽として響くことで、互いを裏づけあい、肉づけあい、輪を描く。この構成はとても優れていた。

話がそれるが、先日『レコード芸術』の月評のために、三大テノールのローマでの第一回コンサートとドキュメンタリーのブルーレイをみた。そのドキュメンタリーによると、一回目の前には、あんなビッグヒットになるとは誰も夢にも思っていなかったそうだ。
とりわけ予想外の莫大な利益を得たイギリス・デッカが、その金を使って始めたのが「頽廃音楽シリーズ」だったというのが意外で面白かった。シュルホフを聴きながら、そのことも思い出した。
配布されたプログラムも原作者や作曲者、出演者のメッセージ、演出家のノート、沼野雄司さんと小沼純一さんの作品解説など、コンパクトながら盛りだくさんの内容で、とても充実している。
小沼さんの言葉、「こうした作品を公共ホールが積極的に公演することに意味があるとわたしは考えている。また勇気を感じている」に、激しく共感。
そしてこのプログラムには「速報」として、大いなる明日への希望(笑)も最後に載っていた。
──ビオンディによるヘンデルの《シッラ》、明二二年十月末に上演決定。
二〇二〇年の二月末の上演予定で、あとは幕を開けるだけという状態にこぎつけていながら、コロナ禍で三日前に中止に追い込まれたオペラが、二年八か月後に戻ってくるという。
そのときが、「もっとよい世界」になっていますように!
十一月八日(月)ヴェルディの…

サントリーホールでムーティ&ウィーン・フィル。なんといってもアンコールのウンリキこと《運命の力》序曲。
本プロではガッチリとした音響体、いかにもシンフォニー・オーケストラだったウィーン・フィルが、一瞬に正体のウィーン国立歌劇場管弦楽団に早変わりして、オペラの音楽を奏でる。沸きたつような、その音のうねりの快感。
来年の東京春祭では、我が最愛のヴェルディ・オペラの一つ、《仮面舞踏会》をやってくれるはずだ、ということを思い出して今から熱くなる。
そういえばムーティ、「ラ・フォルツァ・デル・デスティーノ」と曲名を告げるとき、その前に「ヴェルディの」と、日本語の「の」を入れていたように聞こえた。会場にいた知人たちもそう聞いたというので、空耳ではなかったよう。
十一月九日(火)
ひねもす原稿書き。
十一月十日(水)アバドとEU精神
午後に朝日カルチャーセンター新宿教室で「アバドとルツェルン音楽祭管弦楽団」。EU精神の体現者としてアバドを考える。受講者の反応もよい感じ。帰路は毎回恒例のコメダにより、ピスタチオのミニシロノワール。最近はピスタチオを推す企業が多い。
十一月十一日(木)ゲートウェイへ
木曜日はインタヴューのため、目的地まで山手線に乗る。最近電車内でいやな犯罪を起こす男が多いのは、コロナ禍で車内が空いているせいもあるのかも、などと考える。混んでいたらやりにくいだろう。だからといって、前みたいに混むのもいやだが。そして、昔は暴れるといえば車を使うやつが多かったのに、いまはもうお金がなくて、車なんて買えないのかもしれない。そもそも電車しか知らず、車への執着もないのかも。
自分の父ぐらいの年代、戦前生まれの年代が、マイカーにすごく執着していたのとは対照的。なんというか、車を持つことがかれらの自己実現の一つだったのだろう。あの世代や少し後の世代の人たちは、そのこだわりを捨てられぬまま乗り続け、なかにはブレーキのつもりでアクセルを踏んでしまう人が出る。


生まれて初めて、目的地の高輪ゲートウェイ駅で降りる。なんにもない駅。周囲も工事中。地方の新興駅に来たような雰囲気で、とても山手線の沿線とは思えない。新駅といえば、日比谷線のタイガーゲートウェイヒルズ駅もまだ行ったことがないので、いつか降りたい。
インタヴューを終えスマホを見ると、拙稿を待っている人から、もうデッドラインで印刷所に待ってもらっている状態だから、十三時を目途に掲載の可否を決めるぞという最後通告のメールが午前中に入っている。いま十二時四十分。お願いだから十五時まで待ってくれないかとメールして許しをもらい、文章を頭で考えながら帰宅。無我夢中でキーを叩きまくり、とにかく仕上げて十五時二十五分に出す。
しばらく放心状態、あるいは放電状態の後、バスに乗ってトッパンホールへ。鈴木優人による平均律第一巻全曲。こういうとき、普通なら途中で意識を失うはずだが、バッハの音楽はこちらを眠らせない。脳のどこかを覚醒させる。音量やダイナミクスではなく、音の連なりが覚醒を求める、不可思議なバッハの力。
なぜかこのあと十三日にアンデルシェフスキによる二巻抜粋、十六日にアファナシエフによる一巻抜粋と、六日間で三回平均律という平均律強化週間になっているので、演奏のことはこれらを聴いてから。
十一月十二日(金)リエンツィの力

たまっていたメールの返事を出す。新しく買ったマスクが来た。白一色にあきたので黒の千鳥格子にしてみたが、どんなものやら。
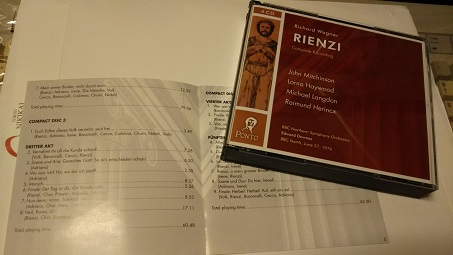
買い損ねていて、ようやく手に入れたダウンズ指揮の《リエンツィ》CD四枚組を聴きはじめる。この作品の舞台上演は大幅にカットするのが通例で、百五十~百八十分くらいだが、ノーカットを謳うこの演奏(元は放送録音)は二百七十六分くらいある。比較的長いホルライザーのCD三枚組でも二百十八分だから、さらに六十分近く長い。二幕のバレエ音楽だけで三十九分もある。
たしかに、オランダ人以降よりははるかに単純な音楽だが、若書きの瑞々しくストレートな力と新鮮な熱気が宿っていて、ドイツの歌劇場では第二次世界大戦までとても人気が高かったというのもよくわかる。
作曲家本人の考えは考えとして、大衆とワーグナーの結びつきを考える上で無視できない作品。そしてその大衆には、ヒトラーその人も入っている。
東京春祭でいつかやってほしい。日本でぜひ指揮してほしいとヴァイグレにいったら、けっこう乗り気だった。プラハだったか東欧でも指揮したと、けっこう経験があるようだった。イタリア・オペラみたいな要素もあるし、ワーグナーの出発点として、そこからどこまで発展、複雑化させていったかを知ってもらうことができる、などと目を輝かせながらしゃべっていた。日本では、一九九八年に若杉弘が藤沢で日本語訳詞版を上演したのが最後のようだから、ぜひ二十一世紀最初の上演をやってほしいもの。
とはいえ、これのノーカット版の日本語字幕なんてつくったら死んじゃいますよ、無理無理、と広瀬さんは前に笑っていたが。
十一月十七日(水)西田の渋沢
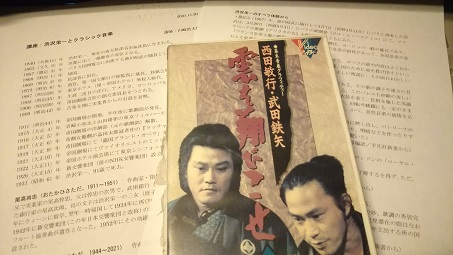
二十日に大船でやる講座「渋沢栄一とクラシック音楽」の準備を、珍しく早めにすすめる(←ふだんからそう心がけるようにしましょう)。
栄一が幕末の渡仏でみた《アフリカの女》の話から尾高忠明まで、我ながらけっこう面白い内容になりそう。写真は当日のレジュメと、資料用のVHS。もともとこの講座は昨年の三月に予定していたもので、『青天を衝け』放映の一年前にやるつもりだったから、その時点では栄一はともかく尾高惇忠たちはイメージがつかみにくいだろうと思い、一九七八年にTBSが二時間枠で放映したドラマ『雲を翔びこせ』を少し見てもらおうと考えていた。
栄一が西田敏行、妻の千代が池上季実子、父が大滝秀治、喜作が武田鉄矢、尾高惇忠が柴俊夫、尾高長七郎がCharで、尾高平九郎が川崎麻世。
ほかに慶喜が片岡仁左衛門、平岡円四郎が田村高廣、土方歳三が中山仁など。テレビ黄金時代なので、一場面しか出てこない役も妙に豪華。円四郎を暗殺する水戸藩士がなぜか横尾忠則。ナレーションが渥美清というのもいい感じ。
西田敏行と武田鉄矢は、あんまりクラシックと関係ありそうには見えないが、武州の百姓姿は今の役者たちよりもさまになっている(笑)。ここから西洋へ行く、ということの突拍子のなさは、むしろ感じてもらえるかも。ただし洋行シーンはまったくなし……。
十一月十八日(木)文庫本とCD
十一日から十八日までの八日間はバッハ国際強化週間のようになっていて、十一日に鈴木優人の平均律第一巻全曲@トッパンホール、十三日にアンデルシェフスキによる第二巻十二曲@紀尾井ホール、十六日にアファナシエフによる第一巻八曲(+モーツァルト)@王子ホールと平均律大会が続いたのち、十七と十八日はイザベル・ファウストによる無伴奏ヴァイオリン全曲@オペラシティ。


新鮮な意欲で挑む鈴木のチェンバロ、繊細入念にして豊麗多彩、楽器の可能性と美しさを堪能させたアンデルシェフスキのピアノ(フーガが始まるときの、ぐーっと音楽が起動してくる感じが何度聴いてもたまらない魅力)、陰惨暗鬱、地の底でうごめくような遅いテンポのアファナシエフの打楽器的なピアノときて、オペラシティの広い空間を静かに、しかし豊潤に満たしていくファウストのヴァイオリン。
その語り口の豊かさ、謙虚に空気になじむ心地よい響き。たった一挺の小さな楽器が織りなす世界の広大さ。休憩なしで三曲七十五分とアンコールぶっ続け、その間舞台上では一度も調音せず、鳴るのはただバッハの音のみ。前奏曲とフーガの組み合わせばかり聴いたあとだと、ソナタもパルティータも構成が新鮮に感じられる(笑)。ちなみに初日は二階正面、二日目は一階十列目あたりで聴いたが、面白いことに印象はより遠い初日のほうがよく、広がりを感じた。大きい空間に響かせることを意識しての演奏だから、ということなのかもしれない。
それにしても、東京各地の四つのホールの主催公演でバッハが続く珍しさ。単独の来日なら日程の調整も自主隔離もやりやすいことが、「ひとりバッハ」シリーズの理由の一つか。同時に、コロナ禍で活動が停まるなか、バッハに立ち返った音楽家も多かったせいもあるだろう。平均律全曲はやらないと言っていたシュタイアーも、第二巻全曲のCDを出す。
ところでそのCD界、衛星ラジオで新譜紹介番組をやっているので肌で実感することだが、このところ新録音の絶好調が続いている。といってももちろん、巨大オーケストラの大交響曲全集とかではない。逆。コロナ禍で生みだされた、室内楽的なスタイルの名演が中心。
それがCDという、流行りものと金儲けの匂いが大好きな人たちにとっては、とうの昔にオワコンとなっているパッケージに、とても合っている。CDの魅力である手軽さ、軽便さ。そして八十分という、一晩の演奏会に似た長さに合った編成とプログラム。
個人的には、そのつくりにすごく愛着を感じる。文庫本に感じてきたのと似た親愛の情、といってもいい。大きくて重いLPにも、形のない配信にもない、コンパクトに手のひらに乗るもの、ポケットに入る形あるものへの、愛おしさ。
これほど売れなくなってもCDにこだわり、つくっている人たちも、似た思いを共有していることを、最近はよく感じる。とくに、フランスのレーベルや音楽家たちがそうだ。紙の手触りが表紙となるデジパック、軽いけれど華奢なパッケージへのこだわりも、そのへんから来ているのではないか。
九〇年代あたりのメジャー・レーベルの、いかにもマスプロな、CDなのに背伸びした重厚長大系とは、かなり感じが違う。
ハルモニア・ムンディやエラートにはそんなディスクがたくさんあるが、そのなかから最近のお気に入りをあげる。

まずはハルモニア・ムンディ。左上。カシオリとミナーシ指揮アンサンブル・レゾナンツによるベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番とヴァイオリン協奏曲のピアノ独奏版。
この面子なら個性あふれる演奏になるに決まっているが、特に第四番のピアノは、ベートーヴェン時代の手稿譜を調べて、作曲家が独自に加えていたやたらに難しい装飾を再現して、聴いたこともないようなヴィルトゥオジティックな演奏を展開している。モダン楽器に金管とティンパニだけピリオドというアーノンクール・スタイルで、しかし音量バランスは慎重に調整して、平行弦ピアノみたいな澄んだ響き。ヴァイオリン協奏曲のピアノ版も、これはたいがい大味な感じで飽きるのだが、千変万化のピアノの響きで新鮮な音楽になっている。例のティンパニ入りカデンツァも、こうやってくれて初めて納得がいくというか。
上右はエラートで、カウンターテナーのジャルスキーとギターのティボー・ガルシア。これは期待をはるかに上まわる美艶のきわみみたいな音楽。ガルシアの滴るような瑞々しさをもった美音のギターにジャルスキーの妖しい声が絡み、ちょっと凄い世界になっている(笑)。選曲と構成も素晴らしい。
下左は、廉価盤レーベルのブリリアント。シャリーノなど現代音楽の紹介者として活躍するアンジウス指揮の室内オーケストラによるワーグナー・アルバム。まずヴェーゼンドンク歌曲集を低声用のヘンツェ編曲版で、さらになんとボイト訳のイタリア語歌詞で、ミンガルドに歌わせている。
マティルデ・ヴェーゼンドンクとコジマ、ワーグナーをめぐる二人の女にちなんだ選曲で、ポイントになるのは、ワーグナーが二人のどちらかと過ごしているときに書いた短い旋律を、シャリーノがふくらませた《パレルモの煩悶》。ヴィスコンティの映画『ルートヴィヒ』に使われた、あの悩ましい旋律も使われる。
ブリリアントはこれ以外にも、このところイタリア系の音楽家による、妙に意欲的なディスクがさりげなく出ている。ソッリマがひいたエルガーのチェロ協奏曲もさすがの面白さだった。
おしまいは、下右の日本のスリーシェルズ。冨田勲の映像音楽を集めた演奏会のライヴ録音。ビッグⅩとか勝海舟とか徳川家康とかキャプテンウルトラとかの主題歌が、ナマ音のオーケストラで響く快感。きょうの料理を真剣に演奏しているのも大好き。そして、マイティジャックの主題歌を聴衆も一緒に歌うアンコールは、ほんとうに熱い(笑)。ライヴといっても録りっぱなしではなく、低音などを強めた爆音系のマスタリングをしているのがいい。
どれも、作り手のこだわりがこちらの心にも灯をともす、素敵な文庫本のようなCDたち。
十一月二十日(土)大船往復
大船での講座「渋沢栄一とクラシック音楽」、おかげさまで無事に終了。
しかし往路でアクシデントがあった。新橋駅で、銀座線から東海道線へ乗り換えようとJRの改札を十一時半頃に通ったところ、茅ヶ崎駅で車両故障のため東海道線の運転見合せ、お急ぎの方は横須賀線へ、というアナウンスが運よく耳に入る。このへんの接続はさっぱりわかっていないのだが、どうやら横須賀線も大船を通るらしいと知り、地下五階のホームまでエレベーターで降りる。折よく発車しようとする列車に間に合った。
土日に演奏会や講座のために近県に行くときは、遅延に遭遇することがけっこうあるので、余裕をもって出ることにしている。それに加えて、路線に選択肢のある駅にいるときにわかったのは運がよかった。結局、東海道線の運転再開は十三時近かったそうで、それからでは十四時の講座開始ギリギリの到着になったかもしれなかった。
帰りは、大船駅のホームに降りるとちょうど電車がいたので急いで乗る。やれよかったと一息つくと、東海道線ではなく湘南新宿ラインと判明。新宿からでも帰れるので、運賃が余計にかかった以外は大きな問題はなかったが、似たような路線がいくつも通る駅というのは、なかなかにわかりにくい。
十一月二十一日(日)
レコード・アカデミー賞の第二次選定委員会のために音楽之友社へ。
一時間ほどで無事に終了。大賞銀賞銅賞決定まで計十回投票となる大激戦だったが、面白い上に納得の結果となった。
十一月二十三日(火)能の「私」
国立能楽堂で、観世流シテ方の長山桂三主催の桂諷會の公演をみる。
昨年七十七歳で亡くなった父の長山禮三郎の一周忌追善と銘打たれている。そのためにメインである二番の能だけでなく、仕舞や舞囃子、狂言など前後に演じられる曲もすべて、死者の弔いや冥界での様子、そして親子の深い情愛が描かれたもので揃えられている。
観世喜正、鵜澤久、観世淳夫、観世銕之丞、山本順之、大槻文藏、故人とゆかりの深いシテ方六人による仕舞と舞囃子は、いずれも故人に捧げようという強い集中力と気魄が感じられる、気持のよいものだった。
とりわけ、大槻文藏が舞って喜正が地頭をつとめた『融』の「この光陰に誘はれて、月の都に、入り給ふよそほひ、あら名残惜しの面影や」の謡いには、心を打つものがあった。
能はまず、桂三の十六歳の息子凜三による『敦盛』。初面、すなわち初めて面をつけて舞う能。
十六歳の少年が十六歳で討死した敦盛を舞うというのが珍しい。少年ならではのしなやかな形姿が説得力を生む。
もちろん、かつてある劇評家が、十七歳の少女の役を同い年の女優が演じるのを見て、それは単なる事実であって演劇ではないと評したという話に似て、経験を積んだシテ方が演じる敦盛とは、まだ比較にならないだろう。それは私のような素人がみてもわかる。
しかし、あえていえば、それでいいのだと納得もした。
十六歳で死ぬ、つまり人生がそこで停まってしまうことを惜しんだり、残念に思うのは、そのあとの人生を生きた者だからこそだろう。何が失われたか、どんな可能性があったかを、自らの経験に照らし合わせて実感できるからだ。
この能のワキは熊谷次郎直実、一ノ谷で敦盛の首を取った当人である。自分の息子と同年代の少年を殺してしまったことの罪深さを実感できるのは、かれが大人で、その後の人生を生きてきたからこそだ。
十六歳の少年自身には、その年で死んでしまうことのもったいなさは、ほんとうのところはわからないだろう。かれの経験はそこまでしかないのだから。
夢幻能の多くは、シテが演じる死者を夢現の境で見るワキは、シテとは関係の薄い後世の仏僧である。しかし『敦盛』のワキは直接に縁のある、殺した当人である点に特徴がある。
その罪悪感が、敦盛と似た年頃の、貧しい草刈りの若者たちに出会ったとき、その草笛の音を、合戦前夜に平家陣営から聞こえた名笛の音のように錯覚させ、かれを夢幻の世界に連れていく。
この能の主役、「私」という語り手はあくまでワキなのだと、よい意味で実感させてくれた。
そしてこの日のクライマックスである長山桂三の能『砧』。
兄の長山耕三がツレとなり、侍女の夕霧を演じる。兄の方が若い娘の役なので高く、弟が﨟󠄀たけた夫人の役なので低く声を出す。兄弟だが師が違い、耕三が師の観世喜之や兄弟子の永島忠侈に似た、細めの透明度の高い響き、桂三は師の銕之丞に似た膨らみのある響きと、声の響きの質そのものが違うのが面白い。
来年三月には兄耕三が父の三回忌追善で同じ『砧』を舞うそうで、そのときには弟桂三がツレとなり、声の高低が入れ替わる。そのときはどんな響きの二重唱になるのか、興味深いところ。
自分がこれまで見た『砧』とのいちばんの違いは、幽霊となった後場でも、前場の生前の姿と同じ面(深井という面だろうか)をかけていたことだった。他では亡者の苦しみを示す「痩女」とか、不気味な形相の面に変わっていたのだが、今回はそのまま。
つまり、夫であるワキの記憶のなかにある生前の気品にみちた姿のまま、死者となって現われたのだ。
妻の死を知って急ぎ帰国したワキを演じた宝生欣哉が、「無慙やな」に始まる詞に、孤独のなかに死なせてしまった妻を哀れに思う感情をかなり強く込めたのと、その姿は呼応していた。
妻は地獄で責め苛まれる苦しみを嘆いて、夫の薄情をなじる。その怒りをシテは強く表出するが、それはあくまでも、夫の後ろめたさが反映されたもの。
ここでも、主役である「私」はやはりワキなのだ。夫は自分の記憶にある妻の姿しか、イメージすることができない。そしてその姿と表情は、弔いによって成仏していく、そのときの姿でもある。
『敦盛』も『砧』も、シテとワキの関係が深いからこそ生じる、ワキの主体性の強さ。誤解のないように書くが、それは、シテが弱いからではなく、存在感を発揮するからこそ印象づけられるもの。世阿弥が仕掛けたドラマツルギーを、それぞれに実感できた能二番だった。
十一月二十四日(水)藤田真央
「藤田真央がソニークラシカルとワールドワイド契約 来年秋にモーツァルトのピアノ・ソナタ全集をリリース」
これはほんとうに嬉しく、楽しみ。
だから言っただろう、「今の日本で聴くべきは、藤田真央のひくモーツァルトのソナタ」!
十一月二十六日(金)ヴェンツァーゴ

今夜のサントリーホールの読売日本交響楽団の演奏会は、幸せをかみしめる嬉しい時間をもたらしてくれた。
ついに実演で聴けた、ヴェンツァーゴのブルックナー。
細かく波動し呼吸し、うねり、音の綾をつむぐ。響きは澄んでいるが、洗練されているとはいいがたい。ドイツ風のがっちりと構築された音響体でもない。
流動する音の綾が想わせるのは、川や池や、水面に映る青空と白雲や、草原がひろがる牧歌的な風景。トリオでは人々が楽しげに踊る。威圧的ではなく気持のいい風が吹く、ひろびろとした緑野。
といっても音楽のつくり方は、けっして茫洋とはしていない。細かく抑揚と緩急をつけ、光と色が綾なす織物のような音楽を求めて、指揮棒の動きは俊敏に変化する。その要求を次第に身体に取り込み、実音化していった適応力の高さは、さすが読響。
終演直後、指揮台を降りると前にまわり、指揮台の手すりをつかんで、まずは楽員に対して深々と感謝の一礼。その姿が、じつに美しかった。
そしてクルッと振り向いた瞬間、両手を広げて客席の拍手に応え、破顔一笑。意外とお茶目そうな素顔がここで出た。こちらまで幸福感に満たされる瞬間。
CPOレーベルのブルックナー全集の第一弾、第四番と第七番が二〇一一年に出て、聴いて驚いてからちょうど十年。
じつに三十三年ぶりという来日を実現してくれた関係者に、心から感謝。そしてできれば、これからも継続的に呼んでくれますように。現代ではまったく独自のブルックナー演奏のスタイルだけに、もっともっと聴いてみたい。
今夜は、実演でこそわかる美点がたくさんあった。ベルン響と録音したこの第三番は、あの全集のなかでは方向性がちょっと曖昧なものだったが、実演は、同じベルン響との録音が大成功した第九番に近い感じだった。オルガン・サウンドが美しく、それもブルックナー風の階段状のデュナーミクではない、ワーグナー風の、歌いまわしのあるオルガン・サウンド。ワーグナーの影響がここかしこに聞こえる演奏になっていた。
このブルックナーは、本来なら二〇二〇年四月に演奏されるはずだった。自分はこのときのプログラムに寄稿させてもらったが(なにしろ、ヴェンツァーゴがいいなんて妙なことを言うプロの書き手は、日本では俺ひとりくらいだから)、コロナ禍で幻の演奏会となっていた。
しかし一年半をへて、ついに昨夜実現した。個人的な話だが、今月は、昨年三月にやるはずだった大船での「渋沢栄一とクラシック音楽」をやり、そして四月に聴くはずだったヴェンツァーゴを聴けて、停まっていた時間がようやく本格的に動き出した気がする。
十二月五日(日)闇に響く音


横浜能楽堂で、みなとみらいホール主催による「ミュージック・イン・ザ・ダーク」。
これは館長の新井鷗子さんの紹介文によると、「視覚障がいのある演奏家との合同メンバーによるアンサンブルが、照明をすべて消した暗闇の空間で演奏し、視覚以外の感覚を通して音楽を享受するコンサート」。これまではみなとみらいの小ホールでやっていたが、五回目となる今年は長期改修中のため、横浜能楽堂が会場。さらに初めて、西洋楽器ではなく和楽器の尺八と琴が演奏される。
まずは能楽堂へ。先日の神奈川県立音楽堂の隣なので、桜木町駅からだと掃部山を登らなければならない。フェイスブックでフレンドの方からバスが楽と教えてもらったので、今回はそれを選択。横浜駅東口のバスターミナルから一〇三系統で最寄りの「戸部一丁目」バス停へ。たしかにぜんぜん楽。本数も多いし十分ほどでつく。横浜駅から乗るときは屋外に出ずにすむので、雨や盛夏にはこれにかぎりそう(混むかもしれないが)。
横浜能楽堂は二十五年前の一九九六年開場だが、能舞台ははるかに古く由緒がある。百四十六年前の一八七五年製で、最初は根岸にあった。一九一九年に駒込に移され、染井能楽堂の名で知られる。ここは小津安二郎の映画『晩春』に出てくることで有名。持ち主を替えながら震災と戦災を生き残り、今は横浜に建つ。
メインの出演者は、藤原道山とかれが率いる尺八アンサンブル、風雅竹韻。型八人の尺八奏者。
開演。道山が一人舞台中央で《アメイジング・グレイス》を吹きはじめると、照明が完全に落とされて、文字通りの暗闇になる。
いや、空のない暗闇ってこんなに暗いとは。忘れていた(笑)。目が慣れてきても、せいぜい前席の背もたれがおぼろに見えるだけ。あとはいつまでたっても真っ暗。席が市松模様で前後左右があいているので、人の気配をほとんど感じない。しかたがないので、思わず目をつぶってしまう。
座って肘掛けに腕を下ろして、姿勢が安定しているからいいが、立ち上がれといわれたら、どうなるだろう。何もないところにこの闇のなかで立たされたら、たぶんへたり込んでしまう。少し動いただけで、北を向いているのか南を向いているのか、たちまちわからなくなって、不安で仕方なくなるにちがいない。
曲の終りで照明がつく。続いて風雅竹韻のうち四人が登場。道山が能舞台の後座中央、下手の橋掛りに二人、上手の脇座あたりに二人が距離をとってならぶ。再び消灯。暗闇のなかから、尺八五重奏による《鶴の巣籠》が聞こえてくる。
尺八合奏の響きはオルガンみたいで、かなり魅力的。新井さんの文に「体中の感覚を研ぎ澄ませて漆黒の闇に身を委ねてみるとき、音楽はより雄弁になにかを語りかけてくるかもしれません」とあるとおり、たしかに音の圧をより強く感じる。ものすごく存在感がある。
やがて、能舞台だけでなく客席後方から、三つの扉の位置からも尺八が聞こえてきて、闇のなかで八本の尺八の響きに八方から包囲されるかたちになった。
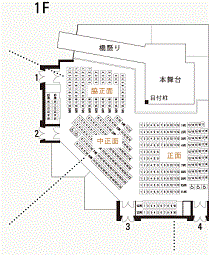
闇に響く音。『公演のサブタイトルである「闇に響く音」とは、尺八演奏家の藤原道山さんが、「暗闇」という二つの漢字には両方とも「音」という部首が含まれていることに発想を得て創案してくださいました』。なるほど、暗にも闇にも字のなかに音が入っている。もちろん響の字にも。
その後は点灯した状態で尺八合奏が二曲あって、休憩。
後半には、筑波大学附属視覚特別支援学校高等部のソプラノ二人と、筝の澤村祐司も出演。
三人は視覚障碍者。前半に「闇に響く音」を体験したあとだけに、かれらが常にあの闇の中で音を聴き、奏でていることを、痛切に実感する。新井さんが「このコンサートが、音楽とは、音とはなにか、そして視覚障がいについて考える契機となれば幸いです」と書かれているとおり。
その術中にずぶりとはまる俺。

 中江早希さんのツイッターから
中江早希さんのツイッターから偶然だが、その前の二日間には、シェーンベルクが月光を音に描いた曲を続けて聴いていた。
三日には鈴木優人指揮の読響アンサンブルと中江早希が歌い語る《月に憑かれたピエロ》。後方のスクリーンに映し出された、青白かったり紅に染まったり、遠ざかったり近づいたりする月が、見事な演奏とあいまって効果的だった。ここでのピエロの陰惨な苦しみは、夢幻能でシテが語る地獄の苦しみとそっくり。
四日にはデスピノーサ指揮のNHK交響楽団による《浄夜》。これは視覚効果なしに、輝いてゆらめく月光が音で描かれる。耽美的な月夜。
これらに続けての「闇に響く音」。
まさに、「月夜ばかりと思うなよ」な体験(笑)。
家に帰ってきて、エベーヌ四重奏団の新譜、「ラウンド・ミッドナイト」をまた聴く。デュティユーの《夜はかくの如し》とシェーンベルクの《浄夜》を、メルラン作の《ナイト・ブリッジ》でつなぐ。神秘の闇夜から耽美の月夜へと世界をつなぐ、ジャズのスタンダードを用いた橋掛り。
ああ、月は明るく温かく、しかし醒めてこちらを見おろしている。

十二月九日(木)滑り込みセーフ
いくつかのコンサートを備忘録的に。
十一月三十日王子ホールでのフルートのパユとチェンバロのバンジャマン・アラールは、後半のバッハのフルート・ソナタ三曲のうち、とりわけト短調のBWV一〇二〇が、完璧なバランスと波のように呼応しあう生命力で圧倒的だった。
以前、ラ・プティットバンドのメンバーとして来日、ブランデンブルク協奏曲第五番で目がさめるように鮮やかなソロを聴かせてくれたアラールは、いまハルモニア・ムンディでバッハの全鍵盤音楽を、楽器をひきわけながら年代順に録音するという、まさに「コロンブスの卵」的偉業に取り組んでいる。
来年二月にも単独で再来日、浜離宮朝日ホールでオール・バッハ・プログラムをひく予定になっているけれど、これは無事の実現を祈るほかない。とにかく、入国制限開始直前に聴けただけでも幸いだった。
そしてその前日、入国制限が開始される午前零時の二十分前にヘルシンキを離陸していて、奇跡的に入国できたのがピアノ四重奏のフォーレ四重奏団。
このものすごい四人を何も知らずに初めて聴いてぶったまげたのは、七年前の十二月十二日のトッパンホールでのこと。そのときは招聘元のパシフィック・コンサート・マネージメントがホールを借りての主催公演だったが、その日のあまりの大成功がきっかけで二年後の二〇一六年からは、トッパンホール主催公演シリーズの重要メンバーとなり、二年に一度のペースで来日してきた。
しかし二〇二〇年秋の来日はコロナ禍で中止、延期された今年も、ギリギリのところで実現。今回のトッパンホール公演は七日と九日、招聘元とホールが一回ずつ開催する二回。


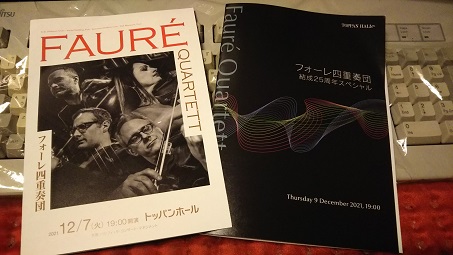
今回からヴァイオリンとヴィオラが立奏するスタイルに代わって驚く。しかしそれがさらなるアグレッシヴな応酬を生みだし、視覚的にも聴覚的にも正解。
どういう理由で始めたのかは知らないが、同じく立奏していたアルテミス弦楽四重奏団のメンバーが、「ヴァイオリンやヴィオラを座ってひくのは無理な姿勢で、健康によくない」と言っていたのも思い出した(関係ないが、フォーレ四重奏団は二〇一六年の来日時にヴァイオリンのエリカ・ゲルトゼッツァーがホテルで転倒して靱帯を傷め、松葉杖で移動していたこともあった)。
四人がそれぞれの位置で明確に存在を主張し、同時に音響体としての一体感も完璧。個人と全体の理想的な協働関係。ドヴォルジャークもムソルグスキーもフォーレもブラームスも、はじけるような生命力と濃密な響きにみちている。初めて聴いた二〇一四年のときはアンコールで〈卵のからをつけたひなの踊リ〉だけを演奏し、「いま全曲を編曲している最中」と期待させ、二〇一六年に全曲を聴かせてくれた《展覧会の絵》は、さらに表現の振幅と力強さを増していた。
やっぱりピアノのモメルツのコントロールが凄い。一人だけ異質な楽器を使っているのに、出しゃばらず控えすぎず、絶妙のバランス感覚でアンサンブルをつくる。
それと、今回痛感したのが、ゲルトゼッツァーのヴァイオリンの強い響き。ヴァイオリンは本来ならもう一人、つまり弦楽四重奏の形態になったほうが響きは安定する。先日、ある日本のアンサンブルでブラームスのピアノ四重奏と五重奏を同じ演奏会で聴いたとき、後者ではバランスがそろって立体的ないい音楽だったのに、前者は響きがぐちゃっとしたまま薄く、何かが欠けたままの音楽になったことがあった。
つまり、足らなかったのは第二ヴァイオリンだった。普通だとヴァイオリン一本では、ヴィオラとチェロの連合軍に負けてしまいやすいのだ。
しかしフォーレ四重奏団はそうはならず、完璧なバランスを実現している。
そこで思い出したのが、二〇一八年にインタヴューしたときのゲルトゼッツァーの言葉。
自分は、普通ならポップスでしか使わないような強いスチール弦を使っていると言っていたのだ。
もちろん、それだけが理由ではないだろうけれど、そうした工夫をさまざまに重ねることで、普通ならバランスを取ることが難しいピアノ四重奏というジャンルで、前人未到といってもいい業績を四半世紀にわたって重ねているのだろう。
これだけ勁烈な表現をとりながら、けっして濁ったり割れたり、汚い響きを出さないのも本当に凄いこと。白刃をわたるような、ギリギリの真剣勝負の連続。
対してアンコールはロマンティック。九日のシューマンの四重奏曲のアンダンテ・カンタービレは十八番だし(全曲も二〇一八年に聴かせてくれた)、七日は一曲目、九日は締めの三曲目にひいたフォーレの《夢のあとに》も、ため息が出るくらい素敵。この曲では二日間とも、演奏後にゲルトゼッツァーが涙ぐんでいたのも印象的。
まさしく、夢のような二夜。
十二月十日(金)柳とモビール
能とオーケストラをはしご。


午後は観世能楽堂で大槻文藏をシテとする『遊行柳』。人間国宝が顔をそろえる強力な囃子方に支えられた、シテ大槻、地頭梅若実という、唯一無二のコンビによる舞と謡の絶美のコラボ。
最後、「露も木の葉も、散り散りになり果てて、残る朽木と、なりにけり」のところで動きを停めたシテは、本当に柳の枯木、朽ち果てた残骸になりきってみせた。
思わず息をのむ。長い歳月が一瞬のうちに流れ去っていくような、「悠久の一瞬」が舞台に現前する。
こういう瞬間を体験するために、自分は能を見続けている。見事に謡いきった梅若実が、入場よりも二時間後の退場のときのほうがはるかに元気になっていたのは、とても嬉しかった。まさしく遐齢延年の芸術。
晩はカーチュン・ウォン指揮日本フィルの演奏会。首席客演指揮者となって初登場、とても楽しみにしていたもの。
・アルチュニアン:トランペット協奏曲 変イ長調(トランペット:オッタビアーノ・クリストーフォリ)
・マーラー:交響曲第五番 嬰ハ短調
もともとトランペット吹きだったというウォンとクリストーフォリは、ウマが合うらしい。さっきの大槻&梅若のコンビを連想する。アルチュニアンを軽快に吹ききったクリストーフォリは、そのままマーラーでもトップを吹く。前半のカーテンコールの最後、指をグルグル回す「巻き」のポーズをして、もう急がないとダメなんだよ、と聴衆に教えたクリストーフォリが可笑しい。
そしてマーラー。三月に聴いて、この人の才能に驚かされた《田園》では、
「弦楽器はピアノ配置で、チェロを上手側の前列に置く。そうして、その低弦の明確な響きを基本にしてハーモニーを整え、音楽を推進させる。
これはグッドオールがいう、ハーモニーが音楽を推進させる、ワーグナーの魅力に通じるものだった。つまりこの響きは、《田園》の劇的な自然描写がワーグナーに大きな影響を与えていることを、つよく実感させたのだ」
と自分は可変日記に書いた。マーラーでは明確に違う。ヴィオラが前列。そしてハーモニーを基礎にするのではなく、各パートがモビールのように揺れ動いて次の動きを生みだすマーラー独特の音響体を、じっくりと克明に描いていく。
この数年、自分はこの曲では苦手なタイプの演奏に続けて出会っていた。ものすごい音圧で、雑に鳴らしまくるだけとか、人の呼吸とまったく無関係に、身体の外で揺れまくる演奏とか(誰の指揮かは書かないが)。
今夜は、ようやく耳と身体に素直に入ってくる演奏を聴けた。クレンペラーがいうように長すぎる曲なのに、もてあますことなく聴けた。次回の第四番と伊福部作品、それ以降のマーラー・シリーズも楽しみ。
十二月十一日(金)ぱらいそへ
午後に芸術劇場でデスピノーサ指揮NHK交響楽団。
・チャイコフスキー:ロココ風の主題による変奏曲(チェロ:佐藤晴真)
・ムソルグスキー(ラヴェル編曲):組曲《展覧会の絵》
代役で登場したデスピノーサ、自分はかなり好きなタイプ。すっきりした明るいサウンド、歯切れのいい抑揚でリズムが軽快。明確な滑舌と響きは、まさにイタリア語のそれを想わせる。五日に聴いたバルトークのピアノ協奏曲第三番(独奏:小林海都)やシェーンベルクの《浄夜》に続いて、《展覧会の絵》も泥くささのない、明快な音楽が心地よい。
その《展覧会の絵》、フォーレ四重奏団の編曲版の四日後にオーケストラ版を聴けてしまうのが、東京の音楽界のありがたいところ。
デスピノーサのこの曲の響きは、とても都会的で洗練されている。しかし華やかでも美麗でもない。バルトークに通じる機能的な陰惨さ、スタイリッシュなグロテスクとでもいうか。金管や木管の皮肉な口調や抗議と呪詛の声に、清潔な現代的大都市の底辺で、絶望的な貧苦にあえぐ人々の、愚かな騙しあいが見えるような。
ラストの〈キエフの大門〉の荘厳な栄光に輝く音楽は、悲惨なまま死んでしまったかれらを迎え入れる、ぱらいそのようだった。
いや、別に隠れ吉利支丹の話ではないので普通に天国でいいのだが、なにかぱらいそといいたくなる、過酷で陰惨な生活の果ての天国。ぼろぼろの身なりの痩せこけた人々が、雲の道を光の門へと歩いていくような。
そう、マーラーの交響曲第四番の終楽章そのもののよう。あの天国にいる聖人たちは悲惨な死にかたをした人ばかり。貧苦に死んだ人々のほうが行きやすそうな、悪人正機説みたいな天国。
デスピノーサは年明けも日本に残り、今度は読売日本交響楽団を指揮してラヴェルの《クープランの墓》や《ボレロ》を振るそうなので、どんな感じになるのか、これは来年早々の楽しみ。
十二月十五日(水)年の瀬へ
月刊誌「音楽の友」新春恒例のコンサート・ベストテンのために、昨年十二月から今年十一月までに通った各種公演の数を合計すると、オーケストラ八十六、その他演奏会五十、オペラ二十三、能楽四十二、演劇など五で、計二百六。
昨年よりはるかに増えて、コロナ禍前の数字にけっこう近づいた。ただし大規模公演は少なく、室内楽などの割合が増えている感じ。
ただ聴いたり見たりしているだけの気楽な立場ではあるが、演奏者、出演者への敬意をもち、できうる限り真摯に舞台に接すること。ないものねだりや揚げ足取りの感想は誰でもいえるから、自分はやらない。これを忘れないように思っているが、あまり多いと感性が磨耗して、いい加減な態度になる危険が出てくる。このくらいの数が自分には限界か。
会場ごとの数は調べていないが、いちばん多いのはやはりサントリーホールだろうか。
そのサントリーホール、日程を見なおしたら、十日に聴いたカーチュン・ウォン指揮日本フィルの演奏会が、今年最後の訪問だったのかもと気づく。
もう、どのホールも次の機会が年内最後の訪問となる、そんな時期になってしまった。今年もお世話になりましたと、心の中でお礼していくことにしよう(サントリーホールはどうしよう…)。
ところでそのサントリーホールでは、昨夜の読売日本交響楽団の演奏会で、終演後の拍手の最中にP席で男二人が、鑑賞時のマナーをめぐって殴りあい、流血騒ぎになったのだとか。
終演後の退場時に客同士が鑑賞時のマナーが原因でもめるというのは、残念ながら時々あった。しかし、まだ公演の一部といっていいカーテンコール中に騒ぎを起こすのは、あまりにも傍迷惑。
P席にいる成人の男性客というのは、かなりのコンサート好きが多いのではないかと思う。しかし完売公演の今回は、小林愛美を聴きたいという子供たちも多かったようだから、親御さんも含めて、コンサートに慣れていない方たちもホール全体にはたくさんいただろう。当事者の一人が「ド素人のくせに」というような言葉を口走ったらしいのは、そういう人たちを意識して、ケンカ相手が実際にド素人かどうかとはかかわりなく、思わず出た言葉のようにも思う。
これが「抱きあえ、諸人よ! 全世界に口づけを!」の第九のあとだったら強烈なブラックユーモアだが、独ソ戦の最中に書かれたプロコフィエフの交響曲第五番のあとだったとのこと。
コロナ禍前よりも周囲の他人の行動に敏感になっているのに、年末に向けて大人数で行き交う機会が増えてきているので、もめごとが起こりやすいのかもしれない。東京は二年近く、人が少ないのに慣れてしまったから。急に人込みだらけになって、戸惑いがストレスになっている要素もありそうだ。自分も短気な人間なので、気をつけねば。
十二月二十九日(水)年の瀬二週
この数年聞くことがなかった、「火の用心」の年末夜警の方々の声と拍子木が今年は昨日から聞こえる。年の瀬が来た、という実感がわいてきてありがたい。寒いなかご苦労さま。
自分はまだ書き物の仕事を積み残してしまっていて、明日にでも仕上げないといけないが、ともあれ外出の必要のある仕事は、今日でおしまい。
さまざまな締めくくりが一気にやってきたような、年末の二週間だった。
まず十八日土曜。上の前歯四本の差歯がボロリと落ち、歯抜け爺状態に。少し前から不安だったが、突如として終りが来た。
十九日。日曜に診てくれる先生が近所にいるとネットで判明し、急遽予約して行く。直感的に相性がよさそうと思ったので、応急処置だけでなく作り直しもお願いする。年内にできますよとのことで大助かり(もちろん、突然の高額の出費は痛いが)。この通院のため、楽しみにしていたさいたま芸術劇場でのBCJのメサイアは断念。埼玉といえばの、十万石饅頭を買って帰る野望もついえる。
二十日。歯抜けのままミュージックバードで片山杜秀さんとの年末特別番組の収録。二〇〇三年からやっているので、もう二十年近い。しゃべる二人は白髪が増えたくらいしか変わらないが、制作スタッフは入れ代わりを重ね、今年は新しいディレクター。といってもニューディスク・ナビでずっと一緒にやっている方なので、手法は多少変わってもよどみなく、気持ちよく四時間分の収録完了。

二十四日。今年最後の音楽之友社訪問で「レコード芸術」誌のオーディオの仕事。日にちが日にちなので、編集者のご厚意により、男四人でケーキを食してから試聴開始。《久しく待ちにし》をバルタザール・ノイマン合唱団の名唱で聴いたところまではクリスマスにぴったりだったが、仕上げにソプラノのサラ・アリスティドの『エーテル』(今年聴いたなかで最も鮮烈なコンセプト・アルバム)をかけたら、プーランクのスターバト・マーテルの「肉体が滅びる時には」の真に迫る歌唱で終わってしまい、これでいいのかという気持に満たされる。

夜は芸劇の大野和士&都響で、今年の「第九」聴き納め。十一月の指揮者なし六型のトリトン晴れた海のオーケストラに始まり、ピリオド楽器のBCJをへて堂々たるモダン演奏にいたる。
二十五日。四半世紀使ってきた冷蔵庫が壊れる。夜は朝日カルチャーセンターで三か月に一度の片山さんとのオンライン講座。今回は片山さんが次のお仕事の都合で新宿教室から、私もwebカメラを換えたら一気に画像が鮮明になったので、二人とも明るい場所でしゃべることになる。六十近いおっさんがこんなに屈託のない顔で笑っておしゃべりして、それでお金までもらえるなんて、なんと有難い仕事だろう。

二十六日。冷蔵庫を新宿に見に行く。年内二十九日に配送してくれるとのことで、年を越さずにすんで大助かり。続いて目黒の喜多能楽堂に行き、今年の能楽見納め。


平家の亡霊たちが壇の浦での滅亡を再現する能『碇潜(いかりかづき)』。金春禅鳳による戦国時代の大がかりな演出を再現した舞台なので見てみたかった。前場では三人の漁師が、敵武者二人を両脇に抱えたまま海に飛び込む、能登守教経の壮烈な最期を再現する。入水後、橋掛りの一の松まで進んだところでふり返り、弔ってくれという三人が、ほんとうに波間に立ってこちらを見つめる舟幽霊みたいに見えて、ぞっとする。
それにしても、今年は能、木ノ下歌舞伎、子午線の祀り、平家琵琶と、いったい何度「波の下にも都のさぶらふぞ」と孫の安徳帝を抱えて海に飛び込む二位尼の場面を舞台で見たり聴いたりしたか。とにかくその機会の多い一年だった。
帰宅すると、一昨日注文したスピルバーグ版の『ウエスト・サイド・ストーリー』のサウンドトラックCD(ドゥダメル指揮)が届いていた。
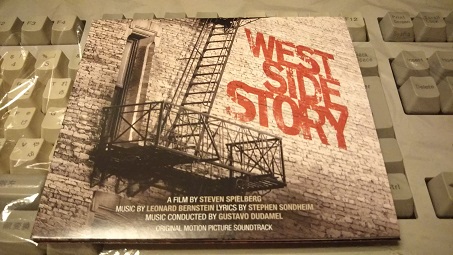
二十七日。このところ具合の悪い家猫を病院に連れていくと、どうやらお別れが近いことが判明する。すべてが年内に片がつくように動く今年だが、これだけは年を越したい。できるだけ、苦しませない形でせいぜい悪あがきをしたい。カルペ・ディエム。
夜、紀尾井ホールでオピッツとスダーン指揮愛知室内オーケストラによるベートーヴェンのピアノ協奏曲全曲演奏会の第一夜。八型のオーケストラもピアノも歯切れがよく、気持ちいい。古典派はこのくらいの編成で聴きたいし、紀尾井ホールの音響もまさに最適。
二十八日。午後に新しい差歯が無事に入る。安定性を増すために六本分。仕事が速くて躊躇なく、一気にやってくれるのが気持ちいい。
夜はオピッツの第二夜。四番にヴァイオリン協奏曲ピアノ版に皇帝という、恐ろしくヘビーなプログラム。だが今夜も気持よし。これで今年のコンサート聞き納め。今年は面白いことに、最初に聴いた演奏会も小菅優のひく一番と皇帝(とびきり見事な演奏だった)だったので、うまく初めと終わりがつながって、円環が閉じた感じ。
二十九日。今年最後のニューディスク・ナビ収録。『ウエスト・サイド・ストーリー』新録を軸に、国内盤で再発されたオリジナル・ブロードウェイ・キャスト盤と六一年のサウンドトラック盤、さらに八五年イスラエル・フィルとのマーラーの九番のSACDなどを組み合わせて、バーンスタイン特集みたいな一週間にした。明快なテーマをもたせて一年の収録をしめくくれるのは嬉しい。
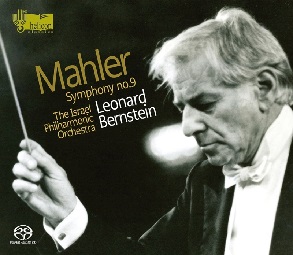
夕方、冷蔵庫が到着。年末年始にあるのはとても助かる。
夜、家猫の写真が一枚もないのに気がついて撮る。ひどいピンぼけだが、この子らしい表情なのでよしとする。とにかく猫らしく勝手に生きぬいてほしい。
チャメ、一緒によい年を迎えよう。

Homeへ