二〇一〇年
一月一日 新春ハイドン三昧
元旦。今日もCD三昧。
まずは年末に到着したネマニャ・ラドゥロヴィチの小品集を聴く。
ネマニャのヴァイオリンそのものは予想通り素晴らしい。ただ、ムード音楽風の弦楽五重奏の伴奏が微妙で、個人的にはピアノ伴奏で聴きたい気がする。しかし誰がいいのかとなるとまた難しい…。
次はルーデンス・トゥルクのヴァイオリンとオリヴァー・シュニーダーのピアノによるメンデルスゾーン作品集。一八三八年のヴァイオリン・ソナタ ヘ長調と、一八二三年のヴァイオリンとピアノと弦楽オーケストラのための協奏曲。
後者は十四才のときの作品だが、面白い。今年はホフシュテッター指揮のオルフェオ盤でも聴いた。十四才のメンデルスゾーンがつくった曲はシンフォニアの九~十三番など、名曲とはいえないにしても結構な魅力がある。
トゥルクの鋭い切り込みもいいが、やはりシュニーダーのピアノが俊敏に冴えまくっている。
ニケのドビュッシー初期作品集はひとまず後日のお楽しみにして、思わず惹きこまれたのが、リコーダーのボスグラーフのヴィヴァルディ協奏曲集。
どうも音質が苦手なブリリアントというのが引っかかって聴いていなかったのだが、これはいい。鮮やかな響きと素晴らしいスピード感。音質も聴きやすい。
ルーヴル宮音楽隊のチェンバリスト、フランチェスコ・コルティと共演したヘンデルのソナタ集が同レーベルから出ているので、一緒に買ったのだが、思わぬ収穫。ソナタ集も聴くのが楽しみ。
しかし、何よりも時間をかけて聴いてしまったのは、昨年末から聴き続けるノリントンのロンドン・セット。
ノリントン好きの私がいってもなんだろうが、これは掛け値なしの傑作セットだ。かめばかむほど味が出るという、近年のノリントンにしては珍しい(残念ながら)演奏。
かれの録音としては、ベートーヴェンの全集とベルリオーズのレクイエム以来の出来、といってもいいのではないか。
このセットのノリントンは、楽想によってかなり遅めのテンポをとるのだが、それがものすごく効果的。音楽のふところが大きいのだ。シュトゥットガルトの連中のうまいこと。
そこらじゅう、新鮮な発見に満ちた四枚。
ミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」は二月一杯まで収録がすんでいるので、次は三月第一週。ここを勝手にウルトラ・ハイドン週間にしようなどと思ったり。フィゲイレドに、カザルス・クァルテットに、クリスティアン・ヤルヴィに、そしてノリントン。
グロース・ドイッチュラント師団というか、パイパー・カンプグルッペというか、JV44というか、松山三四三航空隊というか。
なんだか、こんなに素晴らしいCDばかり元旦にそろってしまって、逆にこれから一年がちょっと不安になる。
MXTVの番組を録画して観る。画面がかなり白い。正面の真下に今までなかったフットライトがあったが、あれが効きすぎのような…。
一月三日 湯島天神とその台地
このところずっと、元旦の初詣は近所の須賀神社に行き、もう一つはどこか有名どころに二日か三日に行くというパターンになっている。
今年は湯島天神。べつにどこか受験するわけではないのだが。
やはり受験生とその母父が多く、午後遅い時間なのに長い行列になっている。
並ぶのを面倒がった子供にヒスを起こし、「いいわよ。じゃ帰りましょう」と帰っていく母親。我慢もさせず自分がカリカリするところを見せてしまって、受験に勝たせることなんてできるのか? とも思うけれど、しょせんは他人事。
それから、あとで本堂で祈祷してもらおうという母親に、「名前呼ばれんのが恥ずかしい」といやがる中学生男子。
そうなんだよなあ、思春期の男子って自意識のバランスが取れなくて、そんなことが妙に恥ずかしかったりするんだよなあ、と懐かしくも微笑ましい。
ともあれ並んでいる人たちの感じは、全般に好ましかった。
去年は神田明神に行ったが、湯島天神はそこから近いのに、参拝者の雰囲気が異なるのが面白い。こちらは文京区風、山の手風とでもいうか。
湯島台というのか本郷台というのか、地続きの台地の上にあるのに、神田明神が千代田区、湯島天神が文京区と分れるのには、それだけの意味があるらしい。
もともとの神田明神は大手町、平将門の首塚近くにあったそうで、沖積層の低湿地の神様である。湯島台の台上に移っても氏子は低湿地の人たちだし、その気質は変わらないのかも。
湯島天神に話を戻すと、境内が意外に小さい。江戸時代からこの区画だったようだ。つまり、大きな神域ではなく、この小さな一角だけが「聖地」だった。
地形を眺めるとなるほどと思う。この台地の東北側は、不忍池のある低湿地。つまり、縄文時代には入り江だった場所で、そこに張り出した陸地の角に、湯島天神がある。
まさしく御崎、岬の聖地。ということは縄文遺跡もあるのだろうかと思って、帰宅後『アースダイバー』の地図を見てみると、やはりその通りだった。
今まで行った場所でいえば、代々木八幡と同じようなもの。
こういう縄文遺跡のある場所が、天神とか八幡とか、比較的新しい神様になっているのも暗示的。もともと古い聖地として認識されていて、誰を祀ったのかはあとからきた話なのだろう。
いまの神田明神の場所も、すぐ北側が入り江の入口で岬の位置にあたるから、明神が移転してくる前から、すでに何らかの聖地だったのではないか。
湯島の花街の跡も面白かった。
湯島天神のある高台から不忍通りまで西から東へ下る坂の途中に、ラブホテルやら料亭(料理屋)といった、「花街のなれのはて」が並んでいる。
このあたりは、江戸期には中間など幕府の下級奉公人の居住区だったから、明治以降に花街にされたものだ。
やはりここでも花街は、円山町や神楽坂、荒木町と同じく、坂の高低差を利用して人工的につくられている。そして坂下の低湿地は池之端や広小路まで続く、自然発生的な飲み屋街。円山町と宇田川町などの関係と同じだ。明治・大正期の「三業地」づくりの鉄則を、ここでも確認する。
ただ、湯島の坂は東に向いているせいか、妙に広々として明るく、他の三業地跡にある、暗く入り組んで湿った雰囲気は少ない。
ところでその東西の坂(というよりもきつい階段)の一つは実盛坂という。平家物語に出てくる老武者、斉藤別当実盛の塚だか家だか「首洗いの井戸」だかが坂の下の南側にあったとする伝説があるそうだ。
実盛は埼玉県の妻沼あたりの長井の庄を拠点としたのだから、史実性は低そうだ。しかし、茨城県の岩井を拠点とした将門の首塚(の一つ)が遠く東京の大手町にあるのと、民間伝承として形が似ている。ともに低湿地にあるのも面白い。弥生や古墳時代以降の「聖地」のあり方なのかもしれない。
各地にあるさまざまな首洗いの池とか井戸とか、戦死した勇者の首を洗う水場の伝承がどんな位置にあるのか調べてみたら、何か見えるのかも。山の手の焼場が谷間奥の水源にあることを思うと、弔いと水源の関係は深い。
それにしてもここから北の本郷台、向ヶ丘、上野の山付近はほんとうに洪積台地と沖積低地が正面衝突したような場所で、高低差が急で大きい。
こうして行ってみると、今の東大農学部の場所にいた一高生が、『嗚呼玉杯』で「栄華の巷低く見て」と歌ったのは比喩的な表現ではなく、実際に根津の遊廓跡や池之端仲町などの歓楽街を見下ろす位置にあったからだ、ということが実感できる。それに、戊辰戦争で官軍が前田屋敷にアームストロング砲をすえて上野の山の彰義隊を砲撃したのも、低湿地をまたぐ格好になって、当然の配置だということも。
やはり東京の高低差は面白い。少し暖かくなったら、続いて根津遊廓跡や鴬谷や下谷万年町など、上野付近の「谷町」の悪所跡めぐりをしたいと思った。
一月八日 神田明神と成田山、団十郎
湯島天神詣のことで知人と、
「日本の有力な神社って、天津神と天皇家の祖先神以外はオオナムチ以来、ほとんど怨霊神では」なんて話になった。
いうまでもなく天神は菅原道真、明神は平将門。死後あるいは生前に平安時代の藤原政権を脅かした人々である。ほかにも平安時代は怨霊神のオンパレードだし、より古いオオナムチなど国津神も、きちんと祀らないと祟るという印象がつよい点で、怨霊神の元祖だ。
そんなことをネットでダベっていて、目に留まったのがウィキペディアの「神田明神」の「伝説」の項にある一節。
この神田明神を崇敬する者は成田山新勝寺を参拝してはいけない事と云われている。これは当時の朝廷から見て東国(関東)において叛乱を起した平将門を討伐するため、僧寛朝を神護寺護摩堂の空海作といわれる不動明王像と供に現在の成田山新勝寺へ使わせ平将門の乱鎮圧のため動護摩の儀式を行わせた。即ち、成田山新勝寺を参拝することは平将門を苦しめる事となるので、神田明神崇敬者は成田山の参詣をしてはならないとされている。
神田明神と成田山が不倶戴天の関係にあるなんて話、恥ずかしながらまったく知らなかった。
あらためて「弘法大師」という存在の凄さを感じる。怨霊を抑えられるほどの超自然的な力をもつ「科学」真言呪法を体現する超人。と同時に、なんとも古代的な宗派とも思うが。
気になったのが、歌舞伎の市川団十郎のこと。成田屋という屋号が象徴するように、元禄年間に活躍した初代の団十郎は成田近くの出身で、成田山を篤く信仰するだけでなく、芝居でも不動明王にたびたび扮し、その化身となることで、江戸での成田山人気の旗振役になった。
これもネットで知った情報だが、このとき江戸市内で成田山信仰の中心になったのは深川の永代寺で、成田山からここまではるばると御本尊が運ばれて「出開帳」をするのに時期を合わせて、団十郎が不動明王を演じたそうだ。
ここからは根拠のない私の想像だが、ということなら将門と新勝寺の由来は由来として、神田明神と成田不動の対立をあおったのは、神田と深川の、町人どうしの対抗意識なのではないだろうか。
家康の江戸入部早々からの町人地としての伝統をもつ神田っ子にしてみれば、深川の賑わいなど、
「川向うの新開地の連中が、田舎の神様かついで浮かれてやがる。てやんでェ。明神様の仇なんぞ拝んでたまるかい」
というところだろう。
江戸三大祭といえば神田祭と山王祭の二つは必ず入るが、残り一つは深川八幡祭と浅草三社祭のどちらを入れるか、意見が分かれるという。深川も浅草も江戸城から遠く、繁華街としての歴史が浅いからだろう。
もちろん、新開地だからこそ荒っぽく猥雑な活気に富むわけで、代々の市川団十郎は、深川、ついで浅草の二つの新開地の活力と経済力を象徴する大衆的人気者だったといえるのでは。そういえば浅草寺には九代目の『暫』の像がある。
想像は想像として話を戻すと、では団十郎やその一門は、神田明神との関りを避けるのだろうか? 神田明神下に住む銭形平次の役を市川家の役者がやることは、じつはあり得ないことなのか?
歌舞伎での将門は、すでに死んで悪鬼怨霊と化している話が多いらしい。代りに妻や遺児が妖術を用いてその怨みを晴らそうとするが、主役のヒーローに倒される。将門は怨念が肉親によって継承されているだけの、観念上の敵役にすぎない。生身の将門を演じることを避けている気配があるのが面白い。
将門が主役の大河の『風と雲と虹と』にも、歌舞伎役者は一人もいなかったような気がする。
真山青果は新派で上演するために一九二五年に『平将門』を書いており、一九六〇年に前進座が改編して上演したこともある。前進座にとっては、毛沢東の革命理論風に農民起義の英雄として、将門をとらえなおすというアカい意図のほかに、市川宗家がやれない芝居をやる、という意義もあったのかも。
一月九日 「振り向くな君は美しい」
国立競技場に、全国高校サッカー選手権の準決勝を観に行く。
ここ数年、高校とクラブチームが合同で戦う、高円宮杯の準決勝を同じ会場で十月に観ている。今年のプレーはとても面白くて、人の少ない客席で気楽に、わずか千円で見るには申し訳ないようなものだった(十月十日の欄参照)。それでもっと観てみたくなり、ならば伝統ある正月の高校サッカーの準決勝の雰囲気も知っておきたくなった。高校サッカーでは国立競技場で行うのは準決勝と決勝と開幕戦だけで、ここで戦うことは格別の栄誉とされているのである。
また、今年の高円宮杯では高校チームがすべて敗退して準決勝にはいなかったので、レベル低下がいわれる高校チームのサッカーを、素人なりにクラブチームと比較してみたいとも思った。
ナマで観戦したのは、第一試合の山梨学院大付属と矢板中央のみ。日差しの強い暖かい日だったとはいえ、下半身をジーンズだけにしたのが失敗。寒さで膝が笑いそうになったので、次の青森山田対関大一高は家に帰って、テレビ観戦。
この数試合だけですべてを判断することなどもちろんできない。だが、高円宮杯の横浜Fマリノス対三菱養和の一戦にくらべると、見た目の面白さが一段落ちるという印象は否めなかった。
ピッチ全面を広く使い、人もボールも大きく動いてつながって、意外性と爽快感にみちていたクラブチーム同士の試合に対し、今日の試合はボールがつながる快感が少なかった。狭い範囲内でゴチャゴチャして、ピンボールのように選手に当ったり転がったりする場面が大半なのは、正直面白くない。
山梨の二点も、ゴール前のピンボールでボールが跳ねているうちに入った感じで、草野進が野球の本塁打を形容していったところの「観客を一瞬に置き去りにしていくような」、呆然とさせられるシュートの快感は少なかった。
両軍がつくる小さなボックスにしばられず、自在に抜けだしたり切り裂いたりできる攻撃のタレントがいない、ということなのか。
近年は小学生の年代からクラブに人材が集中し、ユースチームに進めずにあぶれた選手が高校に行く、という状況だそうだ。もちろん、高校で飛躍的に伸びて年代別の代表に選ばれる選手も、青森山田のボランチ柴崎を筆頭に何人かいるのだが、かつての高校サッカー全盛期にくらべて層が薄いことは避けられない。
今日の四チームのうち、高円宮杯では青森山田のベスト十六が最高で、矢板中央はその予選の関東プリンスリーグで負け越して二部降格、山梨学院と関大一高は参加していないという状況に、そのまま反映されていたようだった。
テレビで観た二試合目は、ロスタイムを含めた最後の数分間で、関大一高が二点差を追いついてPK戦に持ちこんだ。こうした劇的な展開は甲子園同様、高校生の年代だけが放つ輝きで、高校サッカーの醍醐味これにありという試合。その後のPK戦も、三本止めて勝った青森山田のキーパー櫛引は凄かったし、興奮させられた。
これが大観衆のいるコクリツが生む、マジックなのかも知れない。
だが冷静に考えてみると、両軍で十人蹴って五本しか入れられない、それもキーパーがコースを読めば止められる程度のシュートが大半というのは、どうなのだろう。
高円宮杯もPK戦だったが、あのときは両軍十本のうち入らなかったのは三本だけ、しかも外した理由も異なった。
うち二本はバーにあてて外したものだった。キーパーに方向を読まれても止められない位置と強さという厳しさを求めて、結果的に外した。それを延長まで戦って消耗した体力で、なお蹴ろうとしたのだから、大した意志と自負だと思う。もう一人は遠藤のコロコロを真似しようとして機を逸し、正面に蹴ってしまったのだが、これも結果はともかく、魅せるサッカーを求めたプレーだった。
だが、観客数に関しては高校サッカーが五、六倍も多く、学校の応援団は大勢で賑やか。
山梨学院にはチアリーダーもブラスバンドもいた(ここは野球も強くて応援しがいのある学校だけに、応援団も人が集まるのに違いない)。
勝っても負けてもスタンドの一部を埋めたかれらが迎えてくれるわけで、これはクラブチームでは味わえない充実感。高校サッカーを一つの到達点と考えるなら、これでいいのだろう。
テレビ中継などマスコミの注目度も、クラブチームとは段違いだ。
そんな歓声はプロになってから浴びればいい、騒がれるのはむしろ本人のためにならない、ユースは成長の過程の、時期の一つにすぎないというクラブの考え方にも、一理あるとは思うけれど。
最後はちょっと居心地が悪かった。
試合後の三位表彰式に続き、競技場全体に、大会歌『振り向くな君は美しい』(日テレの高校サッカーの番組で流れるあの歌)が流れるのだ。敗者に向けた歌だから、いま負けたばかりのチームの表彰式にはぴったりではあるのだが、これがなんとも気恥ずかしい。
阿久悠と三木たかしの一九七六年の歌で、読売新聞主催で主会場を大阪から東京に移したその年の大会から使われているらしい。歌詞といい曲調といいアレンジといい、もろに青い三角定規の『飛び出せ青春』主題歌などに似た、七〇年代の青春ソング。勝者ではなく敗者の美しさを称えるという感覚は、まさにあの時代の青春ドラマの世界。
日テレの学園ドラマは大好きだったけれど、その世界観が三十年後の現実界に響くのはどうにもずれた感じで、自分には正視できない。
高校野球の歌なら『栄冠は君に輝く』はもちろんのこと、『振り向くな君は美しい』と同じ阿久悠が翌七七年につくった『君よ八月に熱くなれ』も、べつに照れくさくない。
これらは行進曲だから、土俗的、原始的で時代に左右されない昂揚力で、恥ずかしさなど吹っ飛ばしてしまうのか。
ところが『振り向くな君は美しい』だと、七〇年代後半の一種いじけた気分に加えて、当時の日テレが他局よりも強く発散していた、「アメリカのショービジネスの影響と古い和風とが、まだらに混じっている昭和日本の興行界」の気配をいまに甦らせてしまう(いま思えば当時の「一種いじけた気分」も、ヴェトナム後のアメリカから輸入したものだった)。それが歴史の中に去ることをよしとせず、中途半端に現世に留まっているから、気恥ずかしい。
この大会歌の古臭さが、全国高校サッカー選手権自体が時代後れになりつつある状況と、妙にリンクしてしまった。
国立競技場そのものも、サッカー場としては時代後れで、聖地にはなりきれていないし…。
「振り向くな昭和は遠くなりにけり」
ところで、いまどきの子供の名前シリーズ。というか、私と同世代の親がつけた名前シリーズ。
山梨学院大附属には加部未蘭(かべみらん)というフォワードがいた。ACミランにちなんでのもの。負傷の影響で最後の二十分ほどしか出てこなかったが、ガタイがよくスピードもあり、二年生なので来年が楽しみな好選手。
また、すでに敗退した広島観音には、竹内翼というフォワードがいたそうだ。もちろんあの『キャプテン翼』。
この人の両親は徹底していて、かれの兄は「達也」といって野球をやり、姉は「梢(こずえ)」というが、バレーボールではなく陸上をやっているという。
それにしても、こういう名前の選手がちゃんと強豪チームでフォワードなど、目立つ位置にいるのには感心する。
考えてみれば、その競技に関してよほど傑出していないかぎり「名前負け」の印象を自他ともに感じてしまうだろうから、ほかの競技に移ったり、止めてしまったりするのかも知れない。
つまり、名前負けしない選手しか、残れなかったのかも。
ずいぶんときつい賭け、という気が。
一月十四日 カッレくんが来た
数日前にネットでダベっていて、ふとしたことでバラの話題になったのだが、途中で本題とは無関係に、当方の頭に突然勝手に思い浮んだことが一つ。
――「白バラ赤バラ」とくれば、「カッレくん」だよなあ。
『名探偵カッレくん』。
小学三、四年生のころ岩波少年文庫で読んで、大好きだった三冊シリーズの少年探偵物。「五・六年生以上向け」とあったのを、「まだ難しいかも」などと怯えつつ読んで、夢中になった。
スウェーデンの児童作家、リンドグレーンの作品。この作者というと『長くつ下のピッピ』シリーズが飛び抜けて有名だが、自分にとってはカッレくんと、あとは『やかまし村』シリーズである。
主人公カッレは名探偵に憧れる少年。ほかに男女二人の友達と一緒に「白バラ軍」を組んで、ライバル三人の「赤バラ軍」とバラ戦争ごっこをするのも、かれの重要な生活である。
そして偶然に本当の犯罪に巻き込まれ……という話なのだが、何より気に入っていたのは、バラ戦争ごっこの描写だった。東京郊外の住宅地にはありえない、高く古い石壁と、木の扉と塀の街に展開されるそれにとても憧れた。
バラ戦争という不思議に優雅な名前自体、これで知ったのだった。
小学校の頃以来、読みかえしたことはないのだが、数年前にもいちど思い出したことがあった。
引越をしたときに処分してしまっていたので、買いなおそうと思ったのだが、ネットで検索しても絶版で、古本もなかった(子供向けの本は傷みが激しく美品が少ないため、状態に神経質な人が多い日本の古書界では、まともには取り扱われない。たまに出ても高価になる)。
ところがあらためて検索すると、素晴らしいことに三年ほど前に三冊とも復活していたらしい。欣喜雀躍して注文、今日届いた。



新版は昔の箱入のハードカバーから、ソフトカバーになっている。そして何よりもあの、少年文庫独特のくすんだ青や緑、赤の単色の表紙の雰囲気が好きだったのだが(いかにも夜中に抜けだして冒険している、という雰囲気だった)、これも白表紙の色刷に変っている。
とはいえ、表紙絵と挿絵は懐かしい、昔のまま(いま見るとエーヴァ・ラウレル画とあるから、原作の流用らしい)。特に二冊目の『カッレくんの冒険』と三冊目の『名探偵カッレとスパイ団』の表紙の、この画だ……。
カッレ、アンデス、そしてエーヴァ・ロッタ(この女の子の、二語の名前というのが当時は不思議でならなかった。いまこうして書いていても、泣きたくなるくらいに懐かしい)。
ネット上の読者の感想などを読むと、どうやらずいぶん長いこと絶版状態だったらしい。復活させたのはきっと、自分も子供時代に親しんだ記憶をもつ編集者なのではないだろうか。
新版には、映画監督の山田洋次が一文を寄せている。助監督時代にカッレくんを映画化したくてシナリオ化したこと、許諾を得ようとしてうまくいかなかったこと、そして五十年後のいまも、映画化の夢をもっていることが書いてある。
『寅さん』の場面設定の一部は『カッレくん』から借りた、という驚きの一言もあるから、かれの思いは本物だ。
さらに、知人から教えられたのだが、早川書房から数年前に邦訳が出たスウェーデンの作家スティーグ・ラーソンのベストセラー推理小説『ミレニアム』三部作の主人公は、カール・ミカエル・ブルムクヴィストといって、カッレくんと同じ名前を与えられているという。
すっかり忘れていたが、カッレくんという奇妙な響きの名は、カールの愛称なのである。また、今回買ってみて知ったことだが、『名探偵カッレくん』の原題は『名探偵ブロムクヴィスト』というのだ(でもこれは、少年探偵だとはっきりわかる邦題の方が、個人的には好き)。
ともあれ、買っただけで安心してはいけないので、近々に読むつもり。いずれは『ミレニアム』も。
一月十五日 遥かなる山元村
佐野眞一の『遠い「山びこ」─無着成恭と教え子たちの四十年』(新潮文庫)を読みおえ、今井正監督の映画『山びこ学校』をみる。
前者は一九九二年に公刊されたドキュメンタリー。副題のとおり、作文集『山びこ学校』に関った人々、特に山形県南村山郡山元村の村立山元中学校の教師として文集を指導した無着成恭と、その生徒四十三人の人生を追いつつ、『山びこ学校』のなりたちと、その後の四十年間を丹念に掘り起した労作。
生徒は昭和十年四月から翌年三月までの生れで、中学で無着の担任の下で学んだのは二十三年四月から二十六年三月。
GHQによる学制改革で新制中学が生れて、二年目にあたる。戦前なら大半が小学校を出ただけで働いていたはずが、改革により就学期間が三年延長された、戦後民主主義教育の第一世代に属している。一年上の昭和九年生れに、よくも悪くも血気盛んな言論人が少なくないことを思うと、かれらはまさに新時代の申し子だったといえる。
生徒の綴方(作文)をまとめた文集を学内で発行しはじめたのは二十四年七月で、その一編、江口江一の「母の死とその後」が文部大臣賞を受賞して教育界の話題となったのが、二十五年十一月。それらの抜粋が『山びこ学校』として一冊にまとめられて出版されたのは、ちょうど生徒たちが卒業する二十六年三月。
学制改革が実施されたばかりで、学校体制が固まる直前の混沌期に生れた、みずみずしく力強いこの本は、二年間で十二万部というベストセラーになる。
背景にあるのは、山村暮しの絶対的な貧困。朝から晩まで真面目に働いても金が残らない、どうにもならない貧困。昭和の末には大方は解消される絶対的貧困が、まだあった時代。
山元村の大半を占める山林には農地改革の恩恵も及ばず、地主と小作の搾取関係が戦後もそのまま続いていた。自作農の耕地も猫の額で、収入は限られる。
その勤勉と貧困の生活を、子供の素直な濁りのない目でしっかりと見すえ、懐疑を感情論や印象論に偏らせないために数量的に把握し、綴方に記録する。
この客観的な把握が、貧困や格差を解消するための第一歩となる――なるはずなのだが、それは当然、親などの大人にとっては都合の悪い欺瞞や、恥ずべき事実を露にする。しかも『山びこ学校』として出版されたことで、全国にまで知られてしまうことになった。
親たちが「貧乏綴方」と呼んで嫌がるそれを指導した無着成恭は、共産党員ではなかったが、保守的な農民にとってはアカそのものだったろう。対して無着の方も、戦後民主主義教育の旗手という村の外からの遇像化の声に応えようとするうち、村から浮いた存在になっていく。
結局、村の教育委員会から辞任勧告を受けて、『山びこ学校』出版三年後の二十九年春に退職。東京に出て、駒沢大学仏教学部に学ぶ。
そして卒業後の三十一年春から、吉祥寺の私立明星学園の教師となる。マスコミで活躍する教育タレントという一面が拡大するのは、この明星学園時代。
一方、子供たちも成長するにつれて、現実の困難に直面していく。転校生一人を除く四十二人の卒業生のうち高校に進学したのは、男子四人のみ。そして早世した五人を除いた三十七人のうち、四十年後にも山元村に留まっていたのは、わずか五人。他はみな、生活の場を余所に求めるしかなかった。
それは日本の政治社会が第一次産業をなおざりにして、二次と三次に重点をおき、経済大国の道をかけのぼった――それ以外に敗戦後わずか四半世紀で絶対的貧困をほぼ撃退し、有史以来初の一億総中流意識を現出させる方法などなかったのだから、当時としては正しい選択だったと思うが――高度成長の時代の縮図、そのものである。同時に、左翼が存在基盤を失い続ける四十年間でもあった。
映画の方は『山びこ学校』出版前から企画が開始されていたが、二十六年十月に山元村で撮影開始、出版から十四か月後の二十七年五月に一般公開された。
冒頭の画質音質が悪いのにびっくり。どうやら、こんなプリントしか残っていないらしい。独立プロは弱小で原版散逸の危険が高いから、仕方ないのだろう。
製作には、脚本を書いた八木保太郎のプロダクションと、日教組が共同で名を連ねている。
佐野本によると、八木は当初二百万円しか資金を用意できなかったが、県教組経由で山形県に働きかけ、六百万円を借り出すことに成功した。といっても県が直接に出資することはできないので、県の口利きで荘内銀行が県教組傘下の学校生協に融資し、それを八木プロが無担保で借りる、という迂回方式だった。
さらに、行政とは対立関係の日教組に対しても協力を仰いだ。日教組は全国五十万の教職員に一人十円のカンパ指令を発し、総計五百万を出資した。
八木プロと日教組の連名になっているのはこのためで、そしてこれは、体制側と日教組が呉越同舟の形で協力したことの証でもある。この作品のために設立された、山形県知事を会長とする後援会には、常任理事に県総務部長と県教組委員長という、行政と教組の実力者がともに顔をそろえていた。
佐野によると、この頃は行政当局と日教組の溝が深まる直前の、一種の無風状態の時期だったという。だからこそ呉越同舟が可能になったのだが、それだけこの題材が魅力的であり、また、左右どちら側からも、利用価値が高いと見なされたためでもあった(後援会をとりしきった県総務部長と県教組委員長の二人が、のちに国政選挙に打って出て、それぞれ自民党と社会党の代議士になりおおせたという事実は、じつに象徴的だ)。
この無風状態下の呉越同舟の話、三年後の『ここに泉あり』が同じ方式を群馬で再現しようとして失敗し、行政側の援助を得られずに挫折の危機に瀕したことと較べると、とても面白い。
さて映画の中身だが、木村功演じる無着成恭以下、生徒まですべて実名で登場するのにもびっくり。『ここに泉あり』は仮名だったのに、こちらは遠慮なし。
山元村にロケ隊が乗り込み、無着はもちろん、村民や中学の全面的協力でつくられた映画は、すべてをできるかぎり、現実に即してやろうとしたのだ。教室のセットを山元中学の雨天運動場内につくり、在校生が生徒役で参加し、無着がつねに立ち会う形での撮影で、生活綴方運動そのままのリアリズムなのである。
しかも脚本の八木は「『山びこ学校』は無着の花の部分で、映画では、それを咲かせた幹の部分を描き出したい」と考えて、無着の日記をもとに、綴方の背景にある生徒の家族の姿、生活、さらに無着の両親(滝沢修と北林谷栄が演じている)なども、きれいごとではなくリアルに描いていく。綴方が生徒の家庭に起した軋轢など、佐野本に書かれている出版当時の問題は、ほとんどがこの映画のなかで、すでに描かれている。
プライバシーなんて概念のない時代だから可能だったのだろうが、文章よりもよほど直接的なイメージ形成力をもつ映像でこれをやったら、たとえ公開期間は短くとも、「再現」という映画の虚構――それはやはり虚構なのだ――が、現実を上書きすることになりかねないのではないか。
『山びこ学校』が、その創造者であるはずの教師と生徒の以後の人生を、その強すぎる影響力によって逆に呪縛していくこと――これが佐野本の主題だ――に、この映画はかなり力を貸しているように思えてならなかった。
映画の強調点として目をひいたのは、「おひかり様」なる地元の新興宗教を、迷信としてつよく排除しようとしていること。そういえば「迷信」という言葉自体、かつてはよく聞いたのに、最近はあまり耳にしない。左翼性が強かった時代ならではの言葉なのだろうし、また、左翼と新興宗教の対立が根深いもので、そのために後者が保守政党と結びついていく因果関係を、あらためて思う。
モノクロ画面の効果もあって、役者はみなそれらしく見える。主な子役は東京からわざわざ山元中学に転校して参加したそうだが、なかでも藤三郎役の子供はいかにも賢く沈着、リーダーシップと存在感を持ち、なるほどこれが「級長」なる人種かと、納得させられる(それだけに、実在の佐藤藤三郎が成人後も山元村に残り、儲からない農業を懸命に続けつつ文章を書き、ついには無着に対する、最も辛辣な批判者になっていくという現実の重さが、ズシリとくる)。
無着役の木村功も、純朴明朗で無邪気な若さと、強い説得力をもつ情熱的理想家という役柄に見事になりきっている。
面白いのは、その教師像が日本テレビの学園ドラマの熱血教師たちと、妙に似ていること。熱血漢で着飾らないが汗臭さのない爽やか系で、無私無欲で、異性に対する勘だけ変に鈍いとか、そっくりなのだ。どうも、この木村功の無着を原型にしたような気がしてならない…。
一月十八日 平河天神の由来
東京FMでミュージックバードの番組収録をおえ、近くの平河天満宮に行く。
東京で天神様といえば、年始に行った湯島天神、小学六年のときだったか母親に連れられて行った亀戸天神、この二つが有名で規模も大きい。それに較べると平河天神はマイナーだが、ここも霊験あらたかなのだそうだ。
付近が平河町という地名なので、そこから平河天神なのだろうと思い込んでいたが、由来をみると逆らしい。この神社が慶長年間に江戸城東北の平川門外からここに移されてきたので、貝塚という地名を平河町に変えたのだそうだ。
旧地名が貝塚とは嬉しい。やはり縄文時代の遺跡跡に神社があるのだ。ビルに囲まれていて、あまり高地っぽく感じないのだが、南の永田町に向かって緩やかな坂になっており、下は沖積層の入江だった。神社の東側の通りをおりた、いまの首都高の三宅坂ジャンクションと最高裁にはさまれた三角の土地は、江戸時代には谷町と呼ばれていて(出たぞ谷町。もちろんこれも消えた地名)、たしかに低い。また、神社の西には貝坂という坂があって、旧称を残している。
それから、移転前の神社のこと。大元は、太田道灌が古い江戸城内の北側につくったのが始まりだという。平川門の南の皇居東御苑に天神堀や梅林坂など、いかにもそれらしい地名があるが、どうやらその近くにあったらしい。
それが家康時代になって城郭を拡張、その付近まで本丸としたために、平川門外に移された。さらに、本丸の北から東側をまわり南の日比谷入江(当初は丸の内のあたりまで海だったのだ)に注いでいた、その名を平川という大河の流れを東に向け、最終的には日本橋川と神田川の二本にとつけ変えてしまう数度の大治水工事の過程で、もう一度移転させられて現在の位置になったのである。
初詣がきっかけで、神田と深川など、江戸の町ごとの新旧の差に興味が出てきた。なんとなく、幕末の江戸の規模のことしか頭になかったのだが、三田村鳶魚がいう通り、それは二百五十年にわたって発展を続けた結果であって、その過程にはさまざまな変化がある。偶然にも平河天神は、草創期の江戸の段階的発展を反映して、この地にきた神社だった。
太田道灌時代の天満宮が、江戸城内のどんな場所にあったのか、近々に見に行こうと思う。
一月十九日 恩師の訃報
中学校時代に国語を教わった山本先生が、昨年七十九歳で亡くなられていたことを友人から聞く。
丸顔で眼鏡、穏やかな人柄で生徒から親しまれた先生だった。うちの中学のことを最も古くから知る一人で、ときどき授業の本筋から外れて話される挿話や雑談に温かなユーモアがあって、それを聞くのが楽しみだった。
北杜夫の『どくとるマンボウ青春期』も教えてくれた。私が憶えているのは、学生が教師をからかう話。
教師が授業に行くと教室は無人。「寒いので七番教室に移ります」と黒板に書いてある。急いで七番に行くとやはり無人。「都合で三番に移ります」とある。この調子で、生徒のいる教室を求めて学校中をさまよう教師を、生徒たちは屋上から眺めている、というやつだ。
これを先生の語りで聞くとさらに愉快で、先年松本高校校舎を訪れたときは、まず屋上をさがしてしまった(じつはこの校舎はすべて三角屋根で、平らな屋上なるものはなさそうなのだが)。
友人にも、先生の話をきっかけに大好きになり、文庫本をたえず持ち歩いてボロボロにして、すでに七、八冊は買いかえたという猛者がいる。
杜甫の「国破山河在 城春草木深」を扱ったときも忘れられない。終戦直後に真夏の緑がまぶしいのを見て、「クニヤブレテサンガアリ」とはこういうことかと痛感したという話を、妙に鮮やかに憶えている。お年を考えると敗戦の頃十四歳前後で、授業を聞く私たちと同年齢だったから、強く共感を誘う何かが、その語りくちと表情にあったのだろう。
定期テストのとき、用紙の最後に問題に見せかけて「落ちついてゆっくり考えてみましょう」みたいなアドバイスが必ずついていたのも、よき思い出。
いまはご冥福を願うのみ。
一月二十日 貝塚の青松寺
午後からジャパンアーツの新春懇親パーティ。なぜか私のような者にまでお声がかかったので、ホテルオークラへ。
ある人に、
「可変日記、ときどき読むんですけど、音楽の話があまり出てこないで、戦争の話とか延々と続くじゃないですか。ああいうの、別のブログにしてくださいよ。CDとかの話が読みたいんですから」
といわれる。
コーヒーを頭からかけてやろうかと思ったが、ま、他人にしてみれば欲しい情報しか欲しくないのは、普通だ。ブログで特定のテーマに関係した日記だけを拾い読みできるシステムがあるのは、読み手にとっては不要なテーマも多いから、ということだろう。
書く方も読む方も、誰もがさまざまな趣味をもつ。だがクラシック関係の物書きのサイトには、CDや演奏会の情報や感想、業界のゴシップに集中してほしいという考えは、閲覧者にとって当然のことかも知れない。その方が有用だからだが、うーん……。
三時頃に失礼して、暖かいのでホテルの東南を散歩することにする。行くときは反対の溜池山王駅から登っていったのだが、オークラの建物は尾根から東南側の斜面にあり、特に宴会場は斜面の下方なので、虎の門駅からの方がはるかに近かったと気がつく。
徳川秀忠夫人お江を荼毘に付した場所とされる、我善坊谷という谷を見ようと思ったのだが、ちゃんと調べず適当に歩いたため、江戸見坂というずっと北側の坂を通り、谷間の桜田通りまで降りてしまった。
このあたりの高低差はきついので、また登る気にはなれない。しかたなく神谷町駅から帰ることにしたが、歩く途中で案内の看板を見たら、東側の山に、愛宕神社と青松寺があると書いてある。
青松寺って、市来竜夫と吉住留五郎の碑があるとこじゃないか、こりゃいいとこに来たと急に元気が出て、行先変更。
市来竜夫とはインドネシア独立戦争で独立軍に参加して戦死した旧日本軍軍属で、『快傑ハリマオ』の主人公大友道夫のモデルだと、私が推測している男だ。
青松寺は東京タワーの近くだと思い込んでいたのだが、愛宕山の一角だった。
だがここにもいきなり行ったため、結局、顕彰碑は発見できず。
それにしても、青松寺は面白い寺。
戦前は、爆弾三勇士(肉弾三勇士)の銅像と墓(銅像がそのまま墓碑だそうだから、遺骨もその下にあったのだろう)で有名だった。かれらは佐賀人なのに、なぜか縁もゆかりもないこの東京の寺に葬られ、顕彰されたのだ。
その頃は、門前付近の目立つ場所にあったらしい。戦後、反軍国主義の風潮によって撤去され、今はばらばらになり、一人の銅像と墓だけが寺の墓地の北端に移されているという。
そうして戦後の一九五八年、インドネシアのスカルノ大統領が来日したさい、かれの直筆の碑文による市来竜夫たちの顕彰碑が、その青松寺にできた。
日本とインドネシアが国交回復をし、児玉誉志夫や瀬島龍三など、右翼とそれに親しい商社マンが戦後補償事業の巨額の利権をもとめて暗躍していた時期。それと関係があるのかどうかは不明だが、市来竜夫は、岩田愛之助という戦前の大物右翼の門下生だった。
青松寺から尾根伝いに愛宕神社へ。講談の曲垣平九郎で有名な参道の石段、直に見下ろすとすさまじい急傾斜。登りより降りが怖い。
かつての稼業柄、鉄塔に登った経験で高いところはわりと平気なのだが、ここを手すりを使わずに降りるのは、さすがに足がすくみそうになった。
帰宅後、顕彰碑の場所を知りたくて、青松寺のことをネットで調べるとすぐ見当がついた。ところが、それよりも面白い発見が寺の歴史にあった。
一四七六年に太田道灌がつくった寺だそうで、創建当初の場所はここではなかった。一六〇〇年に家康の命で遷されるまで、麹町の貝塚にあったのだという。
麹町の貝塚。驚いた。
二日前の日記に書いた通り、平河天神に行って、平河町がかつてそう呼ばれていたことを知ったばかりなのだから。
平河天満宮も太田道灌が、一四七八年につくったもの。麹町貝塚の地に遷されたのは、一六〇七年。
貝塚という縄文時代からの由緒をもつ場所(貝塚はゴミ捨て場所というのと聖地というと、二つの説があるらしいが)には、たしかに神社よりも寺と墓地がある方がしっくりくる。
しかし寺というのは墓地をもつぶん、神社よりも大きな用地がいる。それを立ち退かせて空いた土地を武家と町人の屋敷地にし、その一角に七年後に天満宮を遷した、ということではないだろうか。
平河天満宮と青松寺。まるで無関係と思っていた二つの場所が、こんな形でつながってくる。
考古学者の森浩一がいうとおり、現地に行ってみるという行為は、たしかに思わぬ発見をもたらすものらしい。
こういう偶然、司馬遼太郎いうところの「あなたはこんなところにいたのか」の発見の快感は、たまらなく愉しい――というより、大げさにいえばこれこそ、自分にとって、いま生きている根拠そのものみたいなもの。
何をいわれようと、この日記はこういう、他人にとってはおよそどうでもいい快感を書きちらす場にしよう。
「ゼーアドラー号とか昔から好きなので、アトランティス号の話は面白かったです」と、嬉しいことを言ってくれる方もいる(ほんの一握りだろうが)。いずれにせよ、このスタイルでいつのまにか五年近くも書いてきたのだから、私の気ままに興味のない方は、とっくに読まなくなっているはず。
というわけで、これからも「戦争の話とか延々と」書き続けるつもり。と同時に、更新に関してはできるだけさぼらないように、とも思うのだけれど……。
一月二十一日 音楽の国のアリス
先日、『カッレくん』と再び出会えた岩波少年文庫。さらにもう一つ、懐かしい再会をした。
『音楽の国のアリス』(ラ・プラード 光吉夏弥訳)
どんな本かは、訳者あとがきから。
「アリスという名のひとりの少女が、『ふしぎの国のアリス』で名高いもうひとりのアリスのように、小さなからだになって、音楽の国という、どこよりもふしぎな国へ出かけ、しんせつな楽器達の案内で、オーケストラのいろいろの楽器や、音楽についてのいっさいのことを学びます」
ルイス・キャロルが書いたシリーズではなく、同名の少女を主人公にした本。
まあ、いわゆるパチモンだ。
読んだのは小学六年生の頃で、学校の図書室から借りた。結構長く手元にあった記憶があるから、夏休みなどに借りたのかも知れない。
劣等生で、なかでも音楽の授業がいちばん嫌いな自分が、どういうわけか、これを読みたくなった。
楽器もできないやつがなぜこんな本を読むんだろうという疑問と鬱屈は、人にいわれる以前に、自分の中にあった。そのムズムズする気恥ずかしさは、この本を読んでいるときの光景と一緒に、いまでもそのまま思い出せる。
答えはわからない。ハーモニカやリコーダーを吹く授業は大嫌いだったけれども、オーケストラの響きやそれを構成する楽器のことに興味があったから、としかいいようがない。
結局、今の自分のありかたを、それと知らずにここで選択していた気もする。その意味で、私にとってクラシックとの関係の、どうやら原点になる本。
だが、それきりずっと会えなかった。図書室にあるだけで近所の本屋にはなかったから、買えなかったのだ。
私が借りたのは、今回入手したのと同じ、初期の岩波少年文庫の装丁だった。手元の本には一九五六年初版、一九六〇年第五刷、定価百六十円とある。
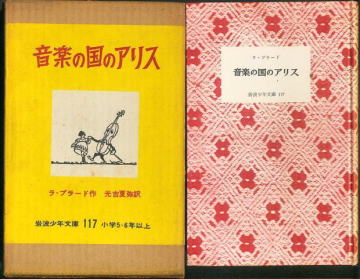
上の写真は左が外箱、右が中身。図書室の本は中身だけだったから、この段ボールの中央に色紙を貼っただけの簡素な外箱を目にしたのは、今回が初めて。
私が読んだ一九七〇年代の岩波少年文庫は、別の装丁になっていた。下にある『西遊記』がそうで、唯一手元に残してあったこれは、一九七三年の第十七刷。
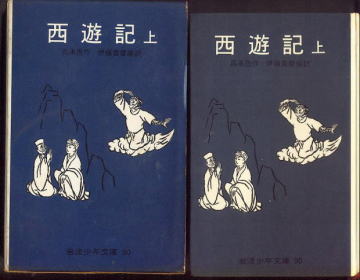
この色合、この表紙と外箱こそ、本屋でなじんだ岩波少年文庫。『カッレくん』シリーズもこんな感じだった。
『音楽の国のアリス』は、新装丁になっていたのかどうか。とにかく長いこと絶版で、いまも復刊していない。英文の原著も同様らしい。アリスの名を借用している点、著作権的にかなり微妙な気もするから、あるいはそれが問題なのかも知れない。
数年前にも思い出し、古書店サイトを検索したことがあるが、まるで引っかからなかった。そんな本はなかったんじゃないかというくらい、きれいさっぱり。
一度でも古本が出れば書名が記録に残るはずのアマゾンのサイトにもない。つまりアマゾンでは、この本が売られたことがない。『カッレくん』について書いたように、児童書の古本は汚損している率が高いから、日本のように保存状態に神経質な国では、売り物にならないのかも知れない。
ところがそれが、特に目的もなく行った中野の「まんだらけ」にあった。ご覧のとおり、径年変化はあるが、箱つきのほぼ美品。それもたった八百四十円。
我が目を疑うとはこういうことかと、思い知った。手にとる前に、たしかにあの『音楽の国のアリス』だと、何度も確認しなければならなかったから。
三十五年たって、とうとう買えた。
今回初めて知ったが、オリジナルは一九二五年刊という古いもの。著者はニューヨーク交響楽団の第一ヴァイオリン奏者。このオーケストラのボスで、ヤング・ピープルズ・コンサートの指揮者として名高いウォルター・ダムロッシュの推薦文付というのが、いかにもである。
アメリカでは長くベストセラーだったそうで、きっと少年時代のバーンスタインも読んだにちがいない。
それから、巻末の文庫目録を眺めていたら、懐かしい書名の中に、タイトルをどうしても思い出せなかった少年探偵ものがあるのを発見。
『オタバリの少年探偵たち』!
爆撃を受け、家族がそこで死んだ家のガレキの上で戦争ごっこをしている少年たちが主人公という、なんともすさまじい話だった。さっそく調べると、これは嬉しいことに新版で復活している。
もちろん注文。糸でつながったように甦る岩波少年文庫たち。
あと、『ヴィーチャと学校友だち』というのも懐かしい。戦後間もないソ連の少年たちの話で、ピオネールとかコルホーズといった言葉をこれで知った。これは復刊していないようだ。まあ、あたりまえか…。
一月二十三日 ボッケリーニの五重奏
いまごろになって、ブリリアント・レーベルのラ・マニフィカ・コムニタが演奏する、ボッケリーニの弦楽五重奏全曲シリーズの素晴らしさを知る。
バロックとロマン派の中間にある、古典派というスタイルのリズム感覚と呼吸感を、しっかり形にして聴かせてくれるような印象。聴いたのは第五集だが、これは全部買わねば。
ヴィヴァルディの《四季》他もとても面白かった。こうした廉価レーベルでは音場感や活力のない音質のものも少なくないので敬遠していたのだが、これらのイタリア録音はとても優秀。かつてのCACTUSレーベルのメンバーによるものらしい。
一月二十六日 スカイツリーと江戸城
ミュージックバードの番組収録は、半蔵門のFM東京ビルの四階にあるスタジオでいつもやっているのだが、皇居の向うに、押上に建設中のスカイツリーが見えることに気がついた。
高層建築は、ある日突然視界に入ることが多い。ネットにいくつかある進捗記を見ると、すでに二百五十メートルを超えている。その伸びが妙にワクワクさせるのが、塔なるものの不思議な魅力。
完成時の高さは六百三十四メートル。その暁には七、八十キロ離れた、神奈川県の小田原市あたりからも眺めることができるそうだ。冬至の日の影の長さは最長で三・四キロというから、上野や新小岩あたりまで伸びるらしい。
場所は、東武伊勢崎線の業平橋駅と押上駅のあいだ。東武や京成の鉄道用地のあたりで、建設の主体は東武だそうだ。
収録後、よく晴れて暖かいので散歩。押上はあらためて訪問することにして、今日は江戸城へ。
まずは大手町の将門首塚から。このあたりは平らな低地。一五九〇年の家康の江戸入城のころ、大手門北側の大手堀のあたりを平川という川が流れ、丸の内まで来ていた日比谷入江という内海に注いでいた。初めは首塚の近くにあった神田明神は、西に平川、南に入江と、二辺に水を控える低湿地に鎮座していた。
その後、江戸城拡張に伴って、平川天神と同様に二回動座している。
初めは一六〇三年、家康が征夷大将軍となって江戸が名実ともに天下人の首府となった年に、駿河台に遷された。ここで高地の神社となったわけだ。
駿河台は元の名を神田山というが、山を削ってその土を日比谷入江の埋立に用い、台地状になったところに駿河出身の家臣の屋敷が置かれたので、駿河台とよばれることになったという。
二回目はこの時期に行なわれていた、神田山を南北に分断する神田川の開削工事が進むなかで、今の湯島台の地に一六一六年に遷された。この神田川が江戸中期までは江戸府内(町奉行の管轄範囲)の北の境界だったから、神社はその外へ遷されたことになる。神田明神とその東側の土地が外神田と呼ばれたのは、このためらしい。
続いて大手門から皇居東御苑に入り、三の丸、本丸、天守閣跡。本丸御殿跡は充分に広いようでもあり、意外に狭いようでもあり。何もない更地を囲んで樹木が茂っているため、イメージしにくい。
復元図などにはこれだけの木は書き込まれていないが、元はなかったのか、省略されているだけなのか。本丸だけでなく、城全体に曲輪の外縁を白塀ではなく樹木がめぐっていることが、近世の人工の城塞という気配を薄れさせる。
天守閣の東には宮内庁書陵部の建物があって、ここまでが本丸の台上にあり、そこから梅林坂を降りると、低地の平川門に至る。
もちろんこのあたりの地形は徳川家によって大改造されているのだろうが、太田道灌時代の天満宮は、この書陵部のあたりにあったのではないだろうか。ここなら洪積台地の張り出しで、坂下に沖積層の低湿地を見下ろす「聖地」、つまり現在の神田明神や湯島天神、さらに九段坂上の田安門付近にあった田安明神(筑土神社)などと似ているからである。
それが梅林坂下や天神堀のあたりにあったのでは、平川が氾濫するたびに水浸しになりそうだ。
平川門と隣の不浄門を見学。大奥の女性の出入はこの門にかぎられていたそうだが、たしかにここからは男社会の二の丸も三の丸も通らずに大奥へ直に行けるのだから、当然といえば当然の規定か。
平川門で東御苑を出て、竹橋を歩いて北の丸公園に登る。公園といっても日比谷公園や代々木公園のように整備されたものではなく、原始的、原生林的な、放置された雰囲気が濃いのが面白い(もちろん、そんなわけはないのだが)。
公園内の国立近代美術館や科学技術館の中を観るには時間が足りないので、外観だけ。ダビデの星で埋まった後者の外壁は強烈。「中の池」という、武蔵野の自然の淵に戻りつつあるような池をすぎて、国立近代美術館附属の工芸館へ。
ここは、かつての近衛師団司令部の建物がそのままに用いられているのがウリである。一九一〇年というからちょうど百年前の洋風建築で、大震災にも空襲にも無事だった。床面や内装は現代化されているが、外観や玄関ホールは往時のまま。すぐ向いを首都高が走っていて、雰囲気に落ちつきがないのが玉に傷とはいえ、移築されずに元の位置にそのままあることには、別の歴史的意義がある。
千鳥ヶ淵の南縁を歩き、イギリス大使館の脇から麹町地獄谷を抜け、帰宅。
二月一日 『クラシック迷宮図書館』
片山杜秀さんの『クラシック迷宮図書館』を読む。
『レコード芸術』の音楽書書評欄『片山杜秀のこの本を読め!』の、一九九八年から二〇〇三年までの六年間の原稿を主体にしたもの。月一冊なので、七十冊強の音楽書が扱われている。
いうまでもなく面白く、刺激的。と同時に、日本の出版界ではこんなにもたくさんの「音楽書」が、毎月毎月出ていたのかということに驚く。ごくわずか、刊行数年後のものもあるが、大半は数か月以内の新刊を取りあげているのだ。
部数減少を補うべく、とにかくたくさんの種類の本を出し続けている(一冊百部と十冊十部なら、どちらも合計百部で数は一緒という方式。もちろん、そうは問屋が卸さないが)、近年の日本の出版事情のおかげもあるにせよ、小説などに較べれば選択肢ははるかに限られる。それでこんなに読み物として面白い評を重ねたのだから、すばらしい。
それにしても、取りあげられた本の四分の一くらいは、新刊だったにもかかわらず私が知らない、その存在に気がつきさえしなかったものである。
音楽家の評伝や自伝に傾きがちな自分の関心の偏向を恥じつつ、ここでの片山さんの選択には、有名音楽家についてのファンブックの類の、クラシック本としては比較的メジャーで華やかな、いかにも書店で平積みされそうな本が少ないことにも気づく。新刊なのにいきなり棚に入ってそのままみたいな本が、むしろ多い気がする(たとえば、アーサー・M・アーベルの『我、汝に為すべきことを教えん』。この著者と書名だけで興味を持つ読者が、はたして何人いるか)
ここで片山さんが重視しているのは、その本がいかに売れそうな、多くの人が興味をもちそうな「テーマ」を選んだかよりも、いかに個性ある「主張」をしているかだ。
その主張(ときに著者が自覚していない矛盾そのものであったりする。秋山邦晴の「戦後民主主義的史観」とか)が、片山さんならではの視点と把握で、一冊の中から、活力にみちた文体によってグワッとつかみだされる。
肝心なのは主張の正当性ではない。それは二の次だ。説得力のあるもの、いかにもトンデモなもの、その違いは片山さんの好意的な形容や皮肉な言い回しなどの使い分けで見当がつくけれども、とにかくそれは二の次だ。主張の独創性、斬新さ、勢いの強さ。それらを選び、キモを鷲づかみにし、読者の前に放りだす。
片山さんに釣りあげられて、漁船の甲板に放りだされた魚がビシャビシャ水を飛ばして跳ねるのを、自分が呆然と眺めているような気がしてくる――水槽は自分で用意してこいと言われたのに、忘れて漫然と乗っている自分。水槽に入れてやらなければ、その「主張」という名の魚は、弱って死んでしまうのだが。
どうでもいいことを一つ。
「そういえば平田昭彦という俳優が日比谷の濠端の帝国劇場に出演中のおり、一ファンとして楽屋を訪ねたまだ中学生の私に、「ぼくは映画育ちでしょう。ひとつき毎日、舞台で同じ台詞をやっていると飽きてしまって、ほんとうはじつにつらいのです」と真顔でいっていたことがあった。そのあと帝劇の地下で鰻を食べた。なつかしい」
と二百五十二頁にある。これはおそらく、私も見に行った『サウンド・オブ・ミュージック』に、平田がトラップ大佐の友人役で出ていたときの話ではないかと思うが、作品名より、「そのあと帝劇の地下で鰻を食べた」という記憶の方が重視されているのが、愉しい。
二月十三日 ドイツのスター・テノール
一九六〇年のライヴ盤は、隣接権が公有になる来年が勝負と思っていたが、意外と今年から発売され始めている。
演奏や発売の年月日から五十年たてば公有になると勘違いして、フライングで発売したケースもあるように聞くが(法的な期限は月日に関係なく、すべてその年の大晦日までは公有にならない)、権利が切れる前に、少しでも独占の利益を得ようというものもあるようだ。なんであれ正規発売はありがたいことだから、大歓迎。
たとえばオルフェオのウィーン国立歌劇場シリーズでは、クロプカール指揮の《売られた花嫁》と、ワルベルク指揮の《密猟者》。
特に後者は、このころ妙にウィーンでプッシュされていた「期待の新鋭楽長」ワルベルクの存在証明となるもので、出るのは嬉しいけれど、いまとなってはウィーンでもどれくらい売れるのだろう。ともかく、ゼーフリート&クメントのコンビにこだわりがあるらしい。
次に、ケルン歌劇場の《ドン・ジョヴァンニ》ドイツ語版(DG)。HMVのサイトでは扱っていなくてタワーにしかない盤だが(付記 数日後にHMVでも売られるようになった)、いつものようにタワーのサイトでは気がつかず、店頭で発見。
サヴァリッシュの指揮、プライ、ヴンダーリヒ、グリュンマーなどの豪華メンバー。ツェルリーナは二十二歳のマティスで、プレミエ十日前のオーディションで抜擢されたという。
オスカー・フリッツ・シューの演出とカスパール・ネーアーの装置が素晴らしかったそうで、プライとサヴァリッシュの自伝がともに印象強く回想している記念的上演なのだが、謎が一つ。
サヴァリッシュの自伝を読むかぎり、最後の六重唱をカットして、ドン・ジョヴァンニの地獄落ちで止めた演出だったように書いてあるのだ。
「オスカー・フリッツ・シューとカスパール・ネーエルと私が、ケルンで『ドン・ジョヴァンニ』の新演出をしたとき、私たちはドン・ジョヴァンニの破滅をもって結末とし、《ドラマ》からいわば《ドラマ・ジョコーゾ(喜劇・滑稽劇)》を作り出している残りの部分を削ってしまいました。ある非常に優れた人々が結末は上演されなければならないといい、その他のそれよりも劣ったともいえない人々が、この作品はドン・ジョヴァンニの抹殺によって終幕とすべきだと主張したとしても、私はその両者に対し拍手喝采することでしょう。そして私にはどちらがより正しいのかわからないと、正直に告白するでしょう」
(『ヴォルフガング・サヴァリッシュ自伝』真鍋圭子訳/第三文明社)
六重唱カットは、原典主義が広まる以前の十九世紀には広く行なわれていた慣習だが、一九六〇年の時点でやったのでは当然論議の的となるだろう。
ところが、CDには最後の六重唱もちゃんと入っているのだ。
音質は変らないようだから、編集で他の録音をつないだとも思えない。カットした場合とつけた場合と、日によって二つのヴァージョンがあったのだろうか?
これはすぐに解決しそうにないので、後日をまつ。
ここではそれより、ドイツ語訳詞のこと。翌年秋のベルリン・ドイツ・オペラ再建記念公演でフリッチャイが指揮したこの作品もドイツ語訳詞だったし、五年前のベーム指揮のウィーン国立歌劇場再建公演もそうだった。音楽祭以外の通常の歌劇場での上演では、まだほんとうにドイツ語が当然だったのだ。
アメリカ人歌手の集団が西ドイツの歌劇場を席巻する直前、ギリギリの時期でもある。アメリカ人だらけの六〇~七〇年代の西ドイツのオペラ上演って、どこか近年の大相撲みたいなものだったのかも、と思ってみたり。
この盤はドイツ語訳詞だけに、ドイツ・ローカルの発売である。CD化の最大の理由はヴンダーリヒの存在らしい。日本ではドイツ・オペラというと芸術性優先で、そのミーハー性には目がいきにくいけれども、どこの国にもそうした要素は濃厚にあるわけで、なかでもテノールは、やはり「オペラの華」なのだ。
SP時代のタウバーやヴィトリシュ、ロスヴェンゲ、戦後のショック、アンダース、そしてヴンダーリヒ。一九七〇年代以降では、ペーター・ホフマンただ一人が、かれらに近いスター性をもっていたのかも知れない。かれらの魅力はドイツ語歌詞を歌っているときにこそ、十全に発揮された。
先に触れたオルフェオ盤で歌っているクメントも、ウィーン人にとっては懐かしいテノールなのだろう。
他国人が客観的にみれば同時代のヴンダーリヒの方が魅力的だろうが(私は地味なりにクメントの歌も好きだが)、自分の町の歌劇場の歌手は、理屈を越えた親愛の対象なのだろう。当時のウィーン人は、バリトン歌手でもプライよりヴェヒターを好んだにちがいない。
そんな地域性がまだ残っていた時代のライヴ盤。イタリア語やフランス語の原語歌唱が当然になって親密度が薄れていくなか、ヴンダーリヒは早逝し、クメントはレパートリー公演の汎用テノール、そして脇役へと転じていく。
二月二十一日 群響と指揮者たち
雑誌『音楽之友』昭和三十年五月号を読んでいたら、昨年十月十六日と十七日のこの日記で取りあげた映画、『ここに泉あり』関連の記事が数本あった。
野村光一と今井正の対談「今井正と音楽と映画を語る」では、指揮者役が近衞秀麿から山田耕筰に交替したいきさつを今井が語っている。以前から群響と関係があった近衞と話がついていたのだが、
「撮影の直前になって近衛さんから手紙が参りましてね、どこかの映画会社と近衛さんを主人公とした、ある音楽映画を作るという契約をされたので、そのために非常に残念だけれども、出られないというのです。それで大変困りましてね、山田さんにその事情もよくお話してお願いしたのですがね、自分は何か昔オーケストラを日本で広めるときに非常に苦労した、そういうものが、形は違うけれども、この中に何か同じような形のものとして出ていて、自分達としてもこういう映画は作られた方がいいと思うから出てやろうというふうなお話で出て頂いたのです」
主演映画の企画が本当にあったのか、それとも「映画にはノータッチで」という群馬県知事や井上房一郎との密談に従った口実なのかはわからないが、いずれにしても近衞から降板を申し出たことは間違いない。そして私の知るかぎり、このような映画はつくられていない。
創設当初の指揮者で、音楽監督的存在だった山本直忠が「群馬交響楽の実際」と題して、楽団最初の三年間の活動をふり返っているのも、丸山勝廣と対立して去った側の回想ということで貴重。
当方の予想通り、無理なプロ化を推進して土地の音楽家を追い出したあげく、赤字ばかりでプロ楽員に逃げられ続ける丸山のマネージメントを、「素人」だときつく批判している。
「も早昔の群響には戻り得ないと思う。只唯一の望みはマネジャーに人を得る事と、地元から優秀な若い指揮者が出て、もう一度地元の人々を育て上げて第二次群響を作る日の来る事である」
映画公開当時の群響が移動音楽教室で食いつなぐだけの、明日をも知れぬ団体に落ちぶれていたことを思えば、このサジを投げた言葉も、あながち恨みから出たものとばかりはいえない。
この号にはそうした地元密着型の一例として、札幌放送交響楽団がその指揮者の西田直道(N響のコントラバス首席をつとめた西田直文の父)によって紹介されている。群響とは異なるスタイルなので、これも参考になる。
放送交響楽団といっても、N響とかバイエルン放送交響楽団のような放送局丸抱えではない。当時NHKでは、東京、大阪、名古屋以外の各地方の中央局に専属オーケストラをおき、その定員を二十名としていた。札幌のものは札幌放送管弦楽団(札管)といい、戦時中の一九四二年に設立、当初は定員十名だったが戦後に倍に増員された。
この二十人が、当時札幌では唯一のプロの音楽団であった(といっても一年契約の不安定な立場だったという)。そしてかれらを中心にアマチュアを加えて増員し、NHKが資金援助をしていたのが札幌放送交響楽団だった。人数は書かれていないが、どうにか二管編成が可能になったとあるから、四五十人か。
この交響楽団は一九四八年設立、その半数は一九三七年に結成され、戦時中に霧消した札幌新交響楽団という市民オーケストラの出身だという。
NHKの放送管弦楽団を核に、エキストラを入れて交響楽団をつくる方式は名古屋などでも行なわれたらしいが、札幌は放送交響楽団と名乗るぶん、それだけNHKとの関係が強かったのかも知れない。定期演奏会は春秋の年二回(無料)だけで、もっと増やしたいがNHKの経済事情では無理だという。
しかしアマチュア(いうまでもなく、当時のかれらの演奏水準は現代とは較べものにならないほど低かったろう)を加えてでは、難度の高い曲はやれない。西田は札管と仙台放送管弦楽団の数回の合同演奏が相当の成果をあげた経験から、プロでなければこれ以上の地方交響楽団の成長は見込めないと述べている。アマチュア音楽家にオーケストラは、あまりに荷が重すぎるというのである。
群響の丸山と同じ結論に達しているわけだが、しかし人口で高崎の十倍ほどもある札幌でさえ、プロ化には人材と財力が足りない。西田の結論としては「どうしてもNHKの強力かつ積極的な参加が必要となって来る」。NHKに放送管弦楽団の規模を拡大してもらい、五六十名の団体とするのが夢だ、と結んでいる。
それから二三年後の一九五七年か五八年に、群響が北海道に演奏旅行を行なった。『ここに泉あり』のヒットで有名になった賜物で、丸山が高田富與札幌市長を表敬訪問すると、
「札幌の文化向上に、まず市民会館の建設を手がけ、これを完成させた。そして次の仕事を考えたとき、交響楽団が頭に浮び、係にその設立準備を命じたところ、調査の結果、札幌ではムリだとの答えがかえってきた。それであきらめていたが、高崎にあることを知り、高崎でできたことが札幌にできないことはないはずだと思っていたのだが……」
と端的に話してくれた。大都市札幌でできないことが、高崎ででき、小都市が大都市を刺激している。
夢中で過ごした十年間だったが、今まで考えなかった群響の存在意義を、予期しない所で聞かされた。このときの印象は強烈だった。
群響は育っていたのだ。
(『愛のシンフォニー』丸山勝廣/講談社)
この刺激のおかげか、札幌交響楽団が「札幌市民交響楽団」として発足したのは、一九六一年のことである。おそらく札幌放送交響楽団の楽員たちも参加したことだろう。
ところがこのとき、群響の首席チェロ奏者など中堅の楽員五六人が、札響に移籍する事件が起きた。
しかし丸山は恨み言をいわず、
「こちらが悪いんですよ。食えるほどの給料が出せない。かれらには女房、子供がいるんですから」
と平静を保ったという(『泉は涸れず』毎日新聞社刊の崔華國の一文による)。
いがみあってもしかたがない、と考えたのだろう。それどころか一九六二年には丸山の発案により、群響、札響、京都市交響楽団の三大地方オーケストラがそれぞれの本拠地を訪問しあう「三市交響楽団特別演奏会」が開始されている。
話を五八年頃の群響の北海道楽旅に戻すが、丸山によれば指揮者として同行したのは、若き小澤征爾だったという。
渡欧前の無名時代で、渡邉暁雄の仲介で斎藤秀雄が丸山の依頼を受け、弟子の指揮者を推薦したうちの一人だったのである。小澤にとって桐朋学園のオーケストラ以外で初めて指揮したのが群響だというのだから、その縁は浅くない。安中や館林、赤城山など、県内各地の移動音楽教室にも同行した。
しかし偶然にもその時期の斉藤の弟子には、山本直忠の息子、直純もいた。
直忠がアマチュア時代の群響を指揮していたころ、中学生の直純もリハーサルについてきて、弦楽器や管楽器を手当たり次第に鳴らす。ところが何をやっても子供の直純の方がうまく、あげくに「おじさんたちの音はきたないなア」とやるので、楽員たちは悔しがったそうだ。
小澤によると、かれが群馬に行った頃は直純も久山恵子も他の仕事で忙しく、何もなかった自分が選ばれたというのだが、やはり父のことがあって、直純は群響と距離をおいたのではないか。
このころ、何かの拍子に小澤が山手線の中で、
「私の終生のライバルは、直純ですよ」
と言った瞬間の目の輝きが忘れられないと、丸山は『愛のシンフォニー』に書いている。
それから三十余年の後、丸山は一九九二年二月二十八日に亡くなった。
群響は堂々たる本物の交響楽団になっていた。翌月の晦日、楽団葬が群馬音楽センターで行われ、小澤はバッハのアリアを指揮した。
続いて直純が登場、『ここに泉あり』ゆかりの山田耕筰の《赤とんぼ》を指揮しただけでなく、その後の多数の参会者による献花の間、ベートーヴェンの葬送行進曲をくり返し指揮したという。
仇も恨みももはや遠い日のかなた、という思いだったのかもしれない。
三月二日 東新宿とモンテヴェルディ
ソプラノ歌手のロベルタ・マメリを聴きに大久保のルーテル教会に。
数年前、ヴェネシアーナ(ヴェネクシアーナ)の一員として来日したときに初めて聴き、もう一人のソプラノのエマヌエラ・ガッリとともに艶のある美声で酔わせてくれたが、今回は経験をかさねて歌も存在感もさらに一回り大きくなり、素晴らしいものだった。
ところがそこに向う途中、副都心線の東新宿駅のひどいつくりにがっくり。
副都心線の各駅はみな開業前の見込の乗降数を上回っている(地方延命策でつくる道路や飛行場とは事情が違うから、鉛筆をなめていないらしい)のに、この東新宿駅だけが下回っているという話は聞いていた。
今回使ってみて、なるほど利用する人が少ないわけだと、よくわかった。
まず、乗降ホームが深い。急行をやりすごすために上下線が縦二段になっていて、底の池袋行は地下はるか。しかもエスカレーターや階段の位置が各階で離れていて、通路を行ったり来たり、無駄に歩かされる。
やっと改札階まで登ると、改札が一箇所しかないのでそこまで歩く。
さらに地上への出口がわずかで、どれも改札から遠い。肝心の、明治通りと大久保通りの交差点にはたった一箇所、しかもエレベーターのみ。副都心線にこれから乗る客はバラバラに到着するが、降りる客はいっぺんに降りるから、とても混雑する。
余裕をもって駅に着いたはずが、地上に出るのに十分近く空費して、気がつけば開演ギリギリ。
たしかに、乗降客の見込が少ない駅の場合は、立退きの補償だのなんだの、コストがひどくかかる地上出口をいくつも新設するのは難しいだろう。明治通り沿いに用地を近年になって確保するのが大変だろうことは、容易に想像がつく。
公共性の観点から駅そのものはつくらないわけにはいかなかったのだろうが、しかしこんな構造では不便で、いっそう使わなくなるにきまっている。
知っているかぎりの地下鉄の駅で、最低級ではないか。新設線は大江戸線もそうだが、用地とコストの兼ね合いが困難で、構造が複雑になるのは避けられないにしても、もう少しうまくできなかったのだろうか。なんともいえず、非人間的な回り道なのだ。
大地震で緊急停止して、停電で真っ暗な中を一番底のホームから地上まで、徒歩で急いで登らなければならない状況とか、想像するだに恐ろしい。
北隣の西早稲田駅もやはり使いづらいから、基本的に副都心線は、渋谷、新宿三丁目、池袋の三つのターミナルと、その先の直通の私鉄各線への移動にしか使いたくないような気がする。
この三つは既設駅の施設や出口を利用しているから、不快感が少ないのだ(とはいえ渋谷の地下駅なども、東横線が直通になってその大量の乗降客が往来するようになったら、かなり殺伐として、いやな雰囲気になりそうな気がするが)。
やっと出てきた東新宿の地上。明治通りも大久保通りも妙にだだっぴろくて、荒涼とした雰囲気。
目的地とは反対方向だが、駅の東側には、高齢化と過疎化がはなはだしく進行し、「都心の限界集落」(すげえ……)という異名をもつ、戸山団地がある。
あくまで個人的な印象だけれども、戸山とか箱根山のあたりは、高齢化がまださほどではなかった三十年前に初めて行ったときから、すでにとても暗い場所、あえていえば「闇が深い」、光と音を夜の闇が吸い取ってしまうような場所と、霊感など薬にするほどもない自分でさえ感じた場所だった。いったい、いまはどうなっているのだろう。
ともあれ、次の機会にはどんなに混雑しようと、山手線の新大久保駅から行くことにする。
ここからはCD話。
ネットの情報だが、ORFから、モンテヴェルディの《オルフェオ》のヒンデミット編曲・指揮による一九五四年ウィーン・ライヴが出る。
当時では珍しく、現代楽器ではなくピリオド楽器を用いた先進的な上演で、器楽アンサンブルは(そうとは名乗らなかったが)ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスが担当し、その非公式なデビューとなったものだという。オルフェオ役のシニンベルギの装飾歌唱も、高く評価された。
ウィーン・コンツェントゥス・ムジクス絡みだから発売されたのだろうが、個人的にこれはとても嬉しい。
なぜかというと、この上演を吉田秀和がみていて、絶賛しているからだ。
かれの一九五三~五四年の米欧旅行記『音楽紀行』のなかで、特に印象的なことの一つに、ヨーロッパでモンテヴェルディの音楽を初めて知り、その素晴らしさに驚嘆していることがある。
「ともかくモンテヴェルディをきいたのは、ぼくにとって、本当に『体験』だった。つまり、単に新しい体験というだけでなくぼくの精神はこれを聞く前にもってなかった拡がりを増し、今後来るものに対する新しい触覚を拓かれたような気がした位だ」
これはローマでゲディーニ編曲の《マニフィカト》を聴いたあとの感想で、その後にウィーンで、この《オルフェオ》をみている。
「帰って来てから、ぼくはまだまだ知らない天才たちの名が次々と出てくる《音楽史》というものについて、恐ろしくて学校で講義なんかできなくなってしまった」ともある。
のちの『名曲300選』が、古典派以前に多くの(正直なところいささか多すぎる)ページを割いたのは、このときのショックへの答なのだろう。
音楽学者以外の一般の日本人にモンテヴェルディの名を知らしめたのは、この『音楽紀行』が最初だったのではないかと思えるのだ。
ということで、いま書いている『一九五四/五五』では、その後のピリオド演奏隆盛の原点の一つみたいな話にできるから、なんとかこの吉田のモンテヴェルディ体験の話を入れたかったのだが、適当な音源がなかった。
ゲディーニ版の《マニフィカト》は、カンテッリが一九五六年にニューヨーク・フィルを指揮したライヴがあるので、いざとなれば強引にそれでやるかと考えていたのだが、このヒンデミット盤がでるなら、いうことなし。
ORFのショップ・サイトで一部がサンプルで聴けるが、それで聴くかぎり、ひどくドライな表情と運び方が、いかにもヒンデミットらしくて可笑しい。古楽復興運動と作曲における新古典主義が実際に結びついているドキュメントというのは多くない気がするから、貴重な証言だろう。
入手が待ち遠しい。
三月七日 明治神宮前〈原宿〉
二日の当欄に書いた副都心線の話をネット仲間とおしゃべりしていて、その副都心線の「明治神宮前」駅が、今日七日から日曜だけは急行が止り、それとともに駅名も「明治神宮前〈原宿〉」に変ることを教えてもらった。
原宿を走っていることに気がつかない人もいるからというが(いかにもゆとりの人向け、なんていったら怒られるんだろうけれど)、面白い改名の仕方だ。
たしかにこの駅はJRより明治神宮から遠く、特に副都心線のホームの位置は明治通りの下、ラフォーレ原宿の脇という、いかにも今の原宿らしい場所なのだから当然といえば当然なのだが、駅名で〈〉(ヤマカッコ、と呼ぶらしい)がついている例は珍しい。「溜池山王」とか都営の「馬喰横山」「若松河田」とか、かなり強引な地名合体に較べて〈原宿〉は、いかにも追加という扱いである。
いっそ「原宿」だけにすればと思うのだが、いきなりそれはまずい、ということか。明治神宮にしてみれば、自社の名がついた駅が消えるのはいやだろうし。
「明治神宮前原宿」にしなかったということは、段階的に変化させる気なのかも。次は「原宿〈明治神宮前〉」で、最後は「原宿」。
昔の特撮ドラマ『宇宙猿人ゴリ』が、悪役がタイトルだから視聴率が低いんだということで、
『宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン』
になり、やがて
『スペクトルマン』
になったのと同じだ(ちがうか)。
あれはたしか、映画『猿の惑星』が話題になった時期だったので、便乗で猿人をタイトルにしちゃったんだったような(ボスがゴリで部下がラーというのも、安易なネーミングで好きだった)。
そういえば昭和四十年代後半は、猿人だのイエティだのヒバゴンだの、ちょっとあとのオリバー君だの、妙にみんな猿人好き、ケムクジャラ好きだった時代のような気がする。『スターウォーズ』のチューバッカも、その文脈で感情移入しやすかったのだ。
閑話休題。
ところで気になるのは、これはなんとアナウンスするのだ、ということ。
「次はめいじじんぐうまえ、かっこ はらじゅく かっことじ。お降りの~」
とかいうんだろうか?
あのお姉さんの声で「かっことじ」は聞いてみたい気もする(バカ)。
ならばいっそ、
「めいじじんぐうまえ、かつまた はらじゅく」
「めいじじんぐうまえ、されど はらじゅく」
「めいじじんぐうまえ、じつは はらじゅく」
「めいじじんぐうまえ、いつかは はらじゅく」
「めいじじんぐうまえ、めざせ はらじゅく」
とかはどうか。
おりよく、今日はオーチャードホールでゼッダ指揮の東フィルによる《ギョーム・テル》抜粋を聴きにいったので、アナウンスも確認してみる。
答は 「めいじじんぐうまえ はらじゅく」
ただこれだけ。残念。
日本語よりも、ローマ字表記のMeijijingumae"Harajuku"の方を読んでいる感じか。
ただし電車内のアナウンスは、「はらじゅく」の方の声量をやや抑え、アクセントを少し平板にすることで、〈〉の中の文字ですよ、ということを示そうとしていた。えらい。
演奏会は大いに満足。これがフランス・オペラであるという意識を、合唱の扱い、オケの音色、リズムやフレージングのアクセントにまで徹底してあるのが、さすがゼッダだった。
これをもしドイツ語訳でやると、いかにもシラーという感じになるのだろう。ケーゲルの一九五三年の放送録音がCD化されているから、買うことにする。
それにしてもオーチャード、今日のように雨だとちょっと困るホール。
傘立の数が足りないので、あとについた客は、傘をビニール袋に入れて客席に持ちこまなければならない。三十年前ならそんなこと当り前だったが、さすがに現代では、こういうことはホール全体のイメージを貧しくするのではないか。早めに行けばいいんだともいえるが、傘立を確保するために早出するなんて、もうそれだけで心貧しい気がする。
おそらくは入口前の空間が狭く、消防法の関係などで傘立が増やせないのではないかと思うのだが、なんとかしてほしいところ。
そういえば三十年前で思い出したが、あのころのホールやホテルの傘立って、鍵が最初からなくて使用できない箇所がやたらに多かったという記憶がある。
あれは一体、なんだったのだろう。イタズラで抜く奴でもいたのだろうか。それとも、今でも同様になくなるが、簡単に新品の鍵に代えているだけなのか。
いずれにせよ、ああいう現象がなくなっただけ、日本は豊かになったということかも。
三月十日 ウィーンの俊英たち
クリスティアン・ヤルヴィ指揮トンキュンストラー管弦楽団の、ベートーヴェンの第九(マーラー編曲版)を聴く。
年初に聴いたこのコンビのハイドンのパリ・セット同様、好調で躍動感のある演奏。マーラーの改変の様子もよく聞きとれる。終楽章のソプラノ独唱に問題があるのが残念。
このコンビはいいと思っていたら、すでに昨年夏でヤルヴィは退き、コロンビア生れのアンドレス・オロスコ=エストラーダが新シーズンから首席指揮者になっているという。一九七七年生れというからまだ三十代前半。そういえばウィーン放送交響楽団も、ドゥ・ビリーから一九八〇年生れのコルネリウス・マイスターに交代する。
オーケストラの財務状況も関係ないわけではないだろうが、ウィーンでは世代交代が加速している。エストラーダはどんな指揮者か知らないが、マイスターはウィーンでもかなり嘱望される存在だと聞いたことがある。
数年前に新国立劇場で《フィデリオ》を指揮したときには、初めての日本のオーケストラを前に焦ったか、上滑りしている印象があったけれど、若いだけに日々成長しているはず。このオーケストラとのCDもオルフェオからアイネム作品集が早くも出ているので、じっくり聴いてみるつもり。エストラーダも近々に耳にしたい。
三月十一日 万国ロッシーニ博覧会
七日に続いてゼッダ指揮東フィルのロッシーニ演奏会。オペラシティでのスターバト・マーテルは、期待を上回る見事さだった。独唱陣には凹凸があったけれど、オーケストラと合唱の充実が補って余りある。
ゼッダの指揮は入神の域。ロッシーニに関して、音楽とその様式の魅力、美しさをここまで音にできる人が、いまの世界に他に何人いるだろう。澄んだ明るい響きと、敏捷な波動の素晴らしさ。
この人がすごいのは、二十世紀の楽器と奏法を用いながら、しかもけっして小さくない編成を用いながら、作品が十九世紀前半のものであると、その響きではっきりと示せること。時代様式の把握と提示のツボを、これ以上ないほど的確に押さえている。そうすることで、作品そのものの美しさが前面に出てくる。
言葉の真の意味での、謙虚の美学。それが年輪を重ねることで、見事な花を咲かせている。《ギヨーム・テル》がフランス・オペラの先駆けとなる優美さを持ち、《スターバト・マーテル》がヴェルディを予告する情熱的な音楽であることを、同じオーケストラと合唱(それも日本の…)を用いて、ここまで明確に描き分けられることに、圧倒された。
巨大戦艦ではない巡洋戦艦。ドイツ風にいえばポケット戦艦のような、軽捷の魅力。
オペラシティの音響もどんぴしゃだった。けっして万能のホールではないが、二十一世紀に行った演奏会のなかで、忘れられない響きのいくつかがこのホールで聴いたものであるのは、やはりそれだけの魅力がここの音響にある、ということだろう。
家に帰って、ケーゲル指揮の《ヴィルヘルム・テル》のCDを聴く。ドイツ語版。約百十分の短縮版で、序曲がなくドラマ主体、バレエ音楽も省略。それらを積極的に採用したゼッダの抜粋法とは好対照で、ここで早くもフランス式とドイツ式のオペラ観の相違が出ている。
歌手ではアルノルト役のゲルト・ルッツェがいかにも昔のドイツのテノールの発声法で、私はとても好き。聖トーマス教会の受難曲では福音史家歌いとして活躍した人だそうで、ラミンやリヒターの指揮で歌った録音も残っている。
だがなんといっても面白いのは、ケーゲルの指揮。各幕しめくくりのアンサンブルが行進曲風のリズムで、クライマックスは軍楽隊みたいな威圧的な音響(ワーグナーの《リエンツィ》序曲の終盤のような)になる。この感じは誰よりも初期のカラヤンに似ているもので、ドイツの青年指揮者の一つのスタイルなのかも知れない。かれらなりの新即物主義なのだろう。第三帝国型トスカニーニ、なんていったら怒られるだろうが(ケーゲル指揮では一九五四年の《オテロ》ドイツ語版も出ているので、これも聴いてみるつもり)。
とにかく、ゼッダのときに響いた音楽とはまるで別物になっているのが、なんとも愉快。これはなるほど《ギヨーム・テル》ではなくて、《ヴィルヘルム・テル》だ。
スターバト・マーテルもドイツ語圏の演奏が聴きたくなったので、メスナー指揮のザルツブルク音楽祭の一九四八年ライヴを注文。この指揮者だとケーゲルよりぬるい感じになるだろうが、テノールがローレンツ・フェーエンベルガーというのが楽しみ。
このようにイタリアとフランスに加えてドイツ風やら、一九七〇~八〇年代の無国籍風やら比較して、いろいろと考えてみたくなるのが、ゼッダが残してくれた大きな果実。契機を与えてくれるものは、なんであれ偉大だと思う。
三月十二日 カッレくんを読む
『カッレくん』三部作を読みおえる。
第一作『名探偵カッレくん』の魅力は色褪せていなかった。新版につけられた一文で、山田洋次は助監督時代にこの第一作を読んで、
「まるで映画を見ているかのように行間から楽しいイメージがうかびあがった」という。
「虫眼鏡のレンズ越しに見えるやや湾曲したカッレ少年の真剣な表情のクローズアップ。それがこの映画のファーストカット。以下小説をたどるにつれて次々と映画の場面がうかんできて本をおく間も惜しいようなありさまだった」
たしかにこの第一作の書法は、きわめて映画的なのだ。
主観と客観、モノローグと対話、近景と遠景、静と動などの変換と対照が、一瞬に、鮮やかに行われる。そのモンタージュの見事さ。
そして文章自体、簡潔な描写なのに、人物の心理や人柄をその行動、表情そのものが語るように書いている。だから、映像を見ているような感じになる。
たとえば、エーヴァ・ロッタの母親のいとこにあたる「エイナルおじさん」出現の場面のやりとり。
「それに、またたいへんかわいらしい娘がいるんだね」と、エイナルおじさんはいって、エーヴァ・ロッタのほっぺをつねった。
「いやっ、よしてよ、痛いわよ」と、エーヴァ・ロッタはさけんだ。
「そうだよ、痛くしてやったんだよ」と、エイナルおじさんはいった。
エーヴァ・ロッタは会った瞬間からエイナルに嫌悪感をもっているが、エイナルはそれを察して、どんどん嗜虐的になる。こういう、やたらに触るオヤジはよくいるし、それは少女にしてみれば、虫酸の走る思いでしかない。カッレとアンデスはこの場に居合わせているが、憧れのエーヴァ・ロッタがこんな目にあっているのに、相手が大人だから手の出しようがない。かれらについては何も書いていないのに、二人の悔しい顔がこの一節の背後に目に見える気がする。
この視覚的な叙述法には意味があり、カッレが観察を好む、名探偵かぶれの少年であることと結びついている。犯罪とは無縁の平和な田舎町、リルチョーピングの食料品店の息子であるカッレは探偵気取りで、町に異常がないか、怪しい人物や車がいないか、四六時中その目でチェックしていて、気がついたことはすぐメモにとっている。そしてかれの頭の中には、ホームズにとってのワトスンのような「架空の聞き手」がいて、かれの名推理をほめそやしてくれる。
他人から見れば馬鹿げた一人遊びが、遠い大都会で起きて、この町を通りすぎていくだけのはずの悪事を露顕させ、犯人逮捕につながる大手柄をカッレにたてさせることになる。
だがこの作品の面白さは、カッレを内気で空想癖をもつただの推理オタクにせず、友達とにぎやかに遊ぶ明朗な少年でもあるとしていること。
この内向と外向のバランスがとれているからこそ『名探偵カッレくん』は傑作になったし、映画的でもあるのだ。
続編『カッレくんの冒険』は、正編と対をなすもの。いろんな点で好対照になっている――というより、かなり意図的にそうしてある。
この対照ぶりは、大ヒットして奔馬のように作者の手を離れつつある第一作のカッレ像を、手綱を締めて軌道修正するべく、五年もたってから続編を書いたのではないかと、そんな気もした。
前作から一年後の(でも、歳は同じ十三歳。ピーターパン現象だ)カッレは、探偵ごっこから遠ざかっている。あんな手柄はまぐれ当りで、自分が得意なのは架空の事件だけ、現実の事件にはもう首をつっこんではいけないと、あの事件をむしろ契機にして自覚するようになっている(ひょっとしたら、当時のスウェーデンにはカッレにかぶれた少年探偵が続出して、親を心配させるようなことが起きていたのかも知れない)。
その代りにカッレが打ち込むのは、バラ戦争遊び。「バラ戦争のほうが、ほんとうはありがたいのだ!」と、カッレは「架空の聞き手」にいう。
そのバラ戦争は、悪態をついて取っ組みあうだけのものだった前作に較べて、ずっと大がかりで、手の混んだものになっている。「戦場」は夜の住宅街だったり、無人の大きな屋敷だったり。このあたり、現実の子供には不可能な、でもできたらいいなと思わせずにはおかない、絶妙のさじ加減でリンドグレーンは舞台を設定し、展開させてみせるから、いま読んでもワクワクさせられる。
『カッレくん』といえばバラ戦争、という私の印象をつくったのは、まちがいなくこの『カッレくんの冒険』だ。
そして、このバラ戦争の過程で、カッレたちは大人の犯罪を目撃し、巻き込まれ、生命の危機に瀕し、助けあって虎口を脱する。そのすべてが探偵ごっこではなしに、バラ戦争がきっかけで起きる。
最後にカッレは、「もう探偵ごっこはやめるつもりだ」と「架空の聞き手」に別れを告げる。子供は子供だけに許される輝きを楽しみなさいという作者のメッセージは説教くさいが、代りがバラ戦争なら、逆らう子供はいないだろう。
原著のデータを見ると、第一作は一九四六年に書かれている。第二次世界大戦終戦の翌年。
それにしては戦争の影がどこにもないことに驚いたが、考えてみればスウェーデンは武装中立のまま参戦しなかったから、あろうはずがない。同じ北欧でもデンマーク、ノルウェー、フィンランドは大国と隣接しているため戦争の嵐に巻き込まれたのに、真中のスウェーデンは無風地帯だった(ウィーン・フィルがフルトヴェングラーと一緒に一九四三年にストックホルムに演奏旅行したさい、豊富な食料と物資に感激した、なんて話があったのを思い出す)。
それどころか、十九世紀初めのナポレオン戦争を最後に、スウェーデンは二百年近く対外戦争のない、ほんとうに珍しい国。だから一九四六年の少年に破壊と殺戮の影がなくても、不思議はない。
さらにいえば、『カッレくん』の物語では、国の状況から身近な環境まで、すべてが無風状態にある。
舞台のリルチョーピングがどこにあるかはわからないけれども(ストックホルムの南西約百キロあたりにリンチェピングとかノルチェピングといった都市があるから、そのへんか。ただしもっと田舎町っぽい)、そこは山田洋次の言葉を借りれば「寛容さといたわりの気持ちを大切に生きている優しい市民がこの街の住人なのであり、都市生活とはこのようでありたいという一種のユートピア」で、犯罪などほとんどない。
作中の季節はつねに夏。冬の厳しい北欧では日の長い夏こそが遊びの季節であり、夏休みは二か月半もあって、いやな学校から解放された子供たちには、自由な時間がいくらでもある。
そして今回初めて気がついたが、とても不思議なことに、カッレとその友達には兄弟姉妹がいるのかいないのか、まったく登場しない。当時、一人っ子はまだ多くなかったと思うが。さらに、友達もみな同い年で対等。つまり長幼による面倒な緊張関係がまるでなく、大人に対する子供、という単純な関係しかない。ここも無風状態。
こうした何重もの無風状態が生む安楽さが、作品の背景にある。カッレたちは何の不安も屈託もなく、退屈を嫌い、冒険を求めて走り回る。現実の子供が憧れずにはいられない、ユートピア。
第三作だが、これは正直途中で飽きてしまった。あまりに活劇調なのも、リルチョーピングの外に出てしまうことも、そして初めて六歳の小さな子供を登場させたのも、すべて変化をつけるためなのだろうが、無風状態の快楽あってこその『カッレくん』なのだ。冒頭の、町の古城でのバラ戦争の場面はとても面白いのに、物語がリルチョーピングから出てしまってからは、魔法が解けたようにわざとらしい活劇になる。
でも、次の言葉。
「エーヴァ・ロッタが、ついさっき予言したように、いつかみんなが哀れな四十じいさんや四十ばあさんになっても、あのすばらしい夏の遊びのことは忘れずに覚えていることだろう。(略)そうなんだ、バラ戦争はたしかに、永遠に夏休みやそよ風やきらきら照る太陽と結びつく遊びなのであった!」
その通り!
三月十五日 ベルリン・フィル・プレイズ・モーツァルト
二十一年前に買い損ねたCDの中古を新宿ディスクユニオンで発見、購入。
『ベルリン・フィル・プレイズ・モーツァルト』(R32C‐1168)。RCAの国内盤である。
ベルリン・フィルが指揮者なしでモーツァルトの交響曲第四十番、《リンツ》に《フィガロの結婚》序曲を演奏したもの。このオーケストラが指揮者抜きで録音した、最初の一枚だろうといわれているもの。
国内盤発売の時期が面白かった。一九八九年七月二十一日。その広告を前月発売の『レコード芸術』で見たのは、四月のカラヤンのベルリン・フィルの芸術監督辞任が発表されてから、まだ数か月という時期だった。後任もまだ決まっていなかった(アバド選出は十月)。
それだけに、指揮者なしの録音というのがじつに意味深いものに思えたのだ。オレたちはカラヤンに頼らずともやれるぜ、といわんばかりのようで。
今回あらためて調べて気がついたが、カラヤンが急逝したのは七月十六日のことである。偶然にもその五日後、騒ぎのさなかに店頭に出たことになる。
急逝後に指揮者なしのベルリン・フィルを聴くなんて、考えようによっては追悼演奏みたいにもとれるが、当時は誰もそうは感じなかったと思う。末期の両者の仲がきわめて険悪で、ついに決裂にいたったのは周知のことだったから。
少し後でANFが出したライヴ盤に、ベルリン・フィルがベーム追悼のために指揮者なしで演奏したモーツァルトの二十五番(だったと思う)のライヴ録音が入っていたことがあった。それとは対照的に思えたのが、この盤だった。
そんな因縁つきの盤だから買う気でいたのだが、どういうわけか入手しそこねた。ごく普通の国内盤なのに見つけられず、まもなく廃盤になってしまった。
今回現物を見て、その理由が想像できた。当時はなぜかソニー盤だと思い込んでいたのだ。当時の、カラヤンべったりのソニーからこんな盤が出るなんて面白いと思っていたのだが、それが大間違いだった(これは私だけではないようで、知人の一人もソニーだと思っていたという。「ジャパン・アズ・ナンバーワン」意識の総仕上げみたいに、「ソニーがとうとうカラヤン&ベルリン・フィルと契約!」と喧伝されていたため、グラモフォン以外ならソニーだろうと思い込んだのかも知れない。ベルリン・フィルのRCA盤はこれが初めてだったから、結びつかなかったのだろう)。
当時はネットで検索なんてできないから、店頭で現物を探すだけ。それなのにレーベルを間違えているのでは、なかなか見つけられない。正直、あの頃の国内メジャー盤にはほとんど興味がなかったから、他のレーベルなどおざなりにしか見なかったし。
しかも、この年の発売分の国内盤を扱った『レコ芸』イヤーブック一九九〇年版を見るとよくわかるのだが、CD買換え需要にバブル景気が重なって、各社の発売点数はすさまじい量に達している。大型店といえども陳列棚はかぎられるから、よほどの人気盤でないかぎり、アイテムごとの仕入数は少なかったはず。
だのに、国内盤なのだからどこかで見つかるさとタカをくくったのが失敗で、とうとう買えずじまい。
それから二十一年目にやっと買えた。
解説をみると、録音年月は一九八七年の十月二十一日から二十四日。西ベルリンにあるエイズに感染した子供のための治療センターに売上を寄付するチャリティ盤だそうだ。このセンターの存在を知った楽員たちが、自発的に録音したものだという。原盤もマイナー・レーベルではなくRCAだとあるので、録音からまもなく西ドイツ国内向けに発売され、日本側がそれを知って二年後に発売した、というところなのかも。
ベルリンのエイズ撲滅チャリティは、歌手の参加するコンサートのライヴ盤が毎年ドイツRCAで出て、近年は日本にも輸入されていた。レーベルが同じだから、そうした盤の始まりだったのかも知れない。
だから、帝王に対するプロテストというほどのものではないのだろうが、楽員の自主性が強調される点には、間接的にカラヤンとの不仲が感じられる。カラヤンが辞任したからこそ日本でも発売が可能になった、なんてことも考えられなくはない。
録音の時期としてはカラヤンとの録音が減り、レヴァインなどとグラモフォンに録音していたころ。名盤主義に拘泥しつつも、レコードとは通過する一瞬の記録でしかないということが、日本人にもやっとはっきりしはじめていたころ。
そして演奏も、まさに過ぎた時代のものだ。荘重様式で重々しく威厳があり、弾力のないインテンポで、面白味などは薬にするほどもない、ひからびたモーツァルト。指揮者の個性というものがないから、この時代のオーケストラのこうした特性がむき出しになっている(まあ、日本ではいまでもこういうモーツァルト演奏の方が主流派だけれども)。
だから演奏自体は好みではないが、ドキュメントとしてはとても面白い。
一九八〇年代後半という一時期のクラシック・シーンを、ベルリンから東京まで、いろいろと思い起こさせてくれる盤だった。
なお、知人にアメリカ盤も存在することを教えてもらった。ドイツと日本だけではなく、多国籍な発売だったのだ。アマゾンのサイトによると日本より三週間遅れ、一九八九年八月十日発売となっている。アメリカでもカラヤン辞任後、没後というのが面白い。ドイツ盤のデータもわかれば面白いが。
三月十七日 謎の「荒法師」
時代劇専門チャンネルの『草燃える』完全版再放送は快調に進行中。やはり面白く、とても苦いドラマ。
折よく新書で出た脚本の中島丈博の回想で、かれにとって初めての大河である『草燃える』は波に乗って快調に書けたとあり、問題が続出したその後の大河とは状況が違ったとあったが、たしかにその好調は観る方にも伝わってくる。
印象的なのは、番組の最後で画面が消えた後に、誰かの叫び声だけが響く形で終ったりすること。だまされて政子を取りあげられた伊東十郎役の滝田栄の叫びが残る回なんて、じつに見事だった。
こういうことが可能なのは、男優たちの発声の基本がしっかりしていて、個性ある声色で美しく響き、それぞれに節回しをもっているからだろう。八〇~九〇年代のやたらに怒鳴る発声は、こういう古典的発声法へのアンチテーゼだったのだろうけれど、じつに無駄なことをしたものだという気がする。
完全版のおかげで、この作品の義経郎党の特異な描き方も明確になった。
きちんとつき従っているのは、東北弁でおよそ世事に疎い佐藤継信、忠信兄弟だけ。あとは黒沢年男、佐藤蛾二郎、かたせ梨乃などが演じる京の盗賊が西国での合戦で郎党として加えられ、梶原景時たち板東武者を鼻白ませる。
特に黒沢年男が演じる、苔丸という役が面白い。もとは紀州熊野の漁師だったという設定は、いかにも伊勢三郎義盛や駿河次郎などと似ているのだが、かれらだと『義経記』などで義経の股肱、忠臣というイメージが出来上がってしまっているから、その身分の怪しさ、いかがわしさが見えなくなる。なぜ武士たちがかれらを蔑み嫌うのかが、わかりにくくなってしまうのだ。それを苔丸たちに変えてしまうことで、いかにも平家政権末期の世相が生んだ、体制外の連中という雰囲気にしている。
ところが、さらに面白いことが一つ。このドラマに弁慶がいないのは以前の日記でも触れたが、にもかかわらず、一ノ谷と壇の浦のときだけ、弁慶のまがいものみたいな男が義経の背後にいるのだ。
かれは苔丸の仲間の「鞍馬の荒法師」として義経の郎党に加わり、合戦場面では褐色の布で顔を包む僧兵スタイルで、馬上で長刀をふるって活躍する。
ところが合戦では苔丸たちよりも義経の近くにいるのに、平時になると目立たない。ほぼ何もしゃべらない。そして戦闘終了とともに画面から消える。壇の浦の回では、「荒法師」という役名だけがクレジットタイトルにある(笑)。
つまり、中島丈博の脚本上ではどうでもいい役なのに、合戦場面の映像でだけ目立つ存在なのである。
これは何なのか。
勝手な想像だが、ひょっとしたら、この合戦場面を『歴史への招待』といった歴史番組に流用することを考慮して、こんな映像にしたのではないだろうか。
流用するときは画面をぼかしたりするのが常だ。長い鍬形の兜をかぶった大将の脇に僧兵のシルエットが見えれば、誰だって義経と弁慶主従だと思うだろう。むしろ、弁慶がいなければ源平合戦の絵面としていかにも物足りない。あえて外した『草燃える』はそれでいいが、他の番組に流用するときにはそれでは困る。
合戦場面は経費を食うから、使い回しの適用度を下げたくなかったのかも。
この「荒法師」とは逆に、苔丸たちのように特徴的な人物が合戦場面で義経の近くにいないのも、かれらがいると流用の邪魔になるという判断だったのでは。
馬鹿らしいといわれるだろうが、それくらい、この弁慶まがいの「荒法師」は奇妙な登場の仕方をしている。
三月十八日 線と点 チェコが気になる
本屋で見かけて、気になったオビ。
『テンプル騎士団の古文書』(レイモンド・クーリー/ハヤカワ文庫)なる、ダヴィンチコード系のミステリー二巻本が棚にフェイスされていた。
そのオビにはどこかの書店の店員さんの推薦コピー(本屋大賞が人気まだまだあるから、きっと効果があるのだろう)がついている。その下巻。
「なにより読み進めるうちに線が点となるこの構成力! すごい作品だ!!」
うーん、「線が点となる」のは、構成力がないからでは?
初めはつながっていたものがバラバラになるミステリーって、そりゃたしかに別の意味で「すごい」だろうが…。
誰も疑問に感じなかったのか?
未読なので作品について語る資格はないが、一般の方のブログの感想をいくつかみると、「初めは面白かったが…」というのがある。あるいはほんとうに「線が点になる」ものかも知れず、これはけっこう正直なコピーなのかも…。
入手した新譜から。
ヴィオラのタムスティのシューベルト・アルバムは素敵な一枚。
それから、スプラフォンが最近押しているパヴェル・ハース四重奏団は、生命力が豊かでいいクァルテット。
新譜のプロコフィエフで感心して、ヤナーチェクとパヴェル・ハースを一曲ずつ録音した二枚も買ったが、特に両者の一番を収めた二枚目がいい。
ゲンダイオンガク風に甲高くなったりきしんだりせず、響きのコクとリズムの弾力を保って、鋭敏に鳴らせる点が魅力的で、まさに二十一世紀の四重奏団という気がする。ハースの作品は数年前の来日公演でも演奏したそうで、これは聴いてみたかったものだ。
チェコという国の音楽家たち、大木正興さんが亡くなってからは強力な推薦者もおらず、最近はどちらかといえばマイナーだけれど、弾力のあるとてもいい若手が、着実に育っている気がする。
これから注目してみようと思う。
三月二十日 コジ・ファン・トゥッテ
サントリーホールのホール・オペラ、『コジ・ファン・トゥッテ』を観る。
ダ・ポンテ三部作の中でモーツァルトの書法が一段と成熟して、官能と人間の暗い本性がほのめかされた作品だが、ラヴィアの演出は南イタリアの艶笑コメディという陽気な一面を強調して、陰翳は少なめ。
前二作の演出では非常に効果的に用いられていた「闇」が、ここではほとんど姿を見せなかったことが、今回のコンセプトを象徴している。
布類も木製の家具類もすべて生成りの自然色を基本として、人為的な彩色は抑えられている。闇に対置される光が、前二回の演出では人為の象徴であったことを思うと、今回は「理性対野性」が対立するのではなく、自然な野性が素直に、即興的に存在する世界、ということなのかも知れない。
代りに、コンメディア・デッラルテのプルチネッラの仮面をつけた人々が野次馬的に登場し、主役たちのドラマを見物している。ここに「外と内」の関係があるのだろうかとも思ったが、一度観ただけでは、この野次馬の位置づけと意味は正直よくわからなかった。
指揮のルイゾッティがつくる躍動感にみちた指揮は、この自然な野性の世界とぴったりと合っていて、やはり素晴らしい。ただ、この音楽にはもう少し翳があってもいい、とは思った。
ところでサントリーホールでの「ホール・オペラ」は、今回で一段落となるそうだ。偶然にも私は第一回のクーン指揮の《ラ・ボエーム》も観ている。音楽のことより、P席にスリットの入ったゴム・スクリーン(正式にはなんと呼ぶのだろう)を張り、そのスリットから合唱が首だけ出したり引っ込めたりして第二幕を歌ったこと、第三幕もたしかオルガン席脇の通路を使って歌ったことなどを憶えている。
以後は長く遠ざかって、二〇〇四年に久しぶりに《トスカ》を聴いた。
そのときはシコフが聴きたくて買ったのだが、ほとんど何も期待していなかった指揮者のつくる音楽が、見事な呼吸感とスケールの大きさをもっていることに驚き、「ひょっとしたらクラシック半世紀の暗黒時代は終ったのかも」と感じたのが、二十一世紀の演奏に興味を抱く契機の一つだった。
いうまでもなく、その指揮者がルイゾッティだった。翌年が《ラ・ボエーム》(第三幕の四重唱でのトランペットの肺腑をえぐる響きはいまも耳に残っているし、きっと一生忘れまい)、そして二年後から始まったダ・ポンテ三部作。
一九九三年当時とは東京のホール事情も大きく変ってしまい、現状でのサントリーホールは、人間の声を聴くときには東京最高の会場ではないと思う。ホール・オペラは歴史的使命をすでに果たしたのだろう。
思い出は思い出。一つの祭が終った。
三月二十一日 コンダクターなし
東京オペラシティにて、アンスネスがモーツァルトのピアノ協奏曲を弾き振りするノルウェー室内管弦楽団の演奏会。
アンスネスの演奏はCDで聴けたとおりの、ぽかぽかと温かいモーツァルト。個人的にはもう少し弾けた俊敏なモーツァルトが聴きたいけれど、これはこれで完成度の高い、立派な「クラシック」。
曲目は弾き振りによるピアノ協奏曲二曲(第二十三番と二十四番)の間に、交響曲《ハフナー》とグリーグのホルベルク組曲。
私は何となく他の二曲もアンスネスが指揮するのかと思い込んでいたのだが、そうではなかった。ステージ中央に指揮台はない。その代りに、コンサートマスターの席に座った音楽監督が、ヴァイオリンを弾きながら指揮をした。
「指揮をした」といっても、弾き振りのときによくある、自分の演奏の合間には素手で拍子をとる、というような動作はしない。第一ヴァイオリンにそんなヒマはほとんどないから、アイコンタクトによっている。
だから遠目に見ているだけだと、室内管弦楽団が「指揮者なし」で演奏しているように見える。
だがそうではない。音楽監督はたしかに指揮をしていたのだ。それは演奏後、音楽監督がステージの袖に引っ込んではまた出てきて拍手に応えるというクラシックではおなじみの、指揮者ならではの特権的な動作をしたことで示された。
舞台に残ったままの他の楽員とは、立場が違うのである。指揮者、いわゆるコンダクターではないけれど、彼女はたしかに音楽監督、ミュージック・ディレクターなのだった。
コンダクトとディレクト、その作業は区別される。イギリスではコンサートマスターのことを「リーダー」と呼ぶけれども、コンダクターの絶対的権威性が確立される以前には、リーダーも共同で演奏を「ディレクト」していたのかも。
近年、たとえばプラハ室内管弦楽団とか、指揮者なしでコンサートマスターの名がCDに大きく表記されているスタイルがよくあるけれど、それがどういうことなのか、実際の演奏会で目にしてよくわかった。
まあ、ここでの音楽監督はイザベル・ファン・クーレン、ソリストとして名を知られた人だから、ややコンダクター的な色合が他のディレクターたちよりも強かった可能性もあるが。
いずれにせよ、オーケストラという労働者の集団がいて、コンダクターという芸術ヒーローがいて、背後には資本家がいるというような、近代資本主義的な大交響楽団、アメリカ型の交響楽団とは異なる、ディレクションの形。
ところでその演奏、特にグリーグの曲などは高水準で、かれらだけの演奏会も一度聴いてみたいと思った。
三月二十二日 警察日記とファウスト
CSで放映された映画『警察日記』を観る。
一九五五年二月三日封切で、『ここに泉あり』がその九日後だから、ほとんど同時期の作品。この年のキネマ旬報のベスト・テンでは前者が六位、後者が五位と並んで高い評価を受けている。なお一位は『浮雲』で二位が『夫婦善哉』という、日本映画の黄金時代。
主演が森繁久彌なのに、日活映画というのが珍しい。
前年に映画製作を再開したばかりの日活は、ライバル各社から俳優とスタッフを引き抜いて陣容を整えようとした。対抗して各社が結んだのが有名な五社協定で、それで封じ込められた日活が石原裕次郎や小林旭などのスターを育てて独自の社風を築いていく、という流れになるのだが、この『警察日記』は引抜作戦が功を奏した、再開間もない時期の作品。
この時期の森繁が『三等重役』(五二年)や『次郎長三国志』シリーズ(五二~五四年)での喜劇役者としての成功にあきたらず、芸域を広げるべく新たな役柄を求めていたことは、群響の丸山勝廣の『この泉は涸れず』に書かれている。
『ここに泉あり』の製作がきまったとき、丸山がモデルのマネージャー役は、当初は二枚目の鶴田浩二がやるはずだった。しかし所属の松竹の都合で降板、水木洋子が小国英雄に代って新しい脚本を書く段階では、森繁が予定されていた。
今井正がその出演を熱望し、森繁自身も今井と仕事をすることで「森繁のカラから抜けだせる」と、大いに乗り気だったのだという(それにしても、小国脚本は鶴田を念頭にしていたのだから、完成版とはまるで別物だったのだろう)。
だがこれは実現せず、小林桂樹が代役となった。東宝がどうしても許可しなかったためで、東宝争議のとき組合側で活動した人間が『ここに泉あり』のスタッフに加わっていたこと、また松竹専属の岸恵子が出演する関係から松竹系列での公開が決まっていたこと、この二つが問題だったのだという。
森繁は、切望した仕事を泣く泣くあきらめた。それからまもない日活での活動は、こうしたことが伏線に違いない。
『警察日記』は、まさに森繁が望み通りカラを破った最初の作品となったが、それが『ここに泉あり』と封切時期が間近になったのは、偶然ながら愉しい。
ただし、森繁が日活で活動したのは五五年の前半のみで、五月の『次郎長遊侠伝 天城鴉』を最後に、六月には永井荷風原作の鳩の街を舞台にした『渡り鳥いつ帰る』(監督も『警察日記』と同じ久松静児)で、東宝に復帰している。そして九月の『夫婦善哉』で、役者として決定的な評価を得ることになる。
さてその『警察日記』。子役の二木てるみの好演もあり、日活再開後の最初のヒット作になったという(好評を受けて十一月には『続警察日記』がつくられたが、もちろん森繁は出なかった)。
会津磐梯山の麓、猪苗代湖畔の架空の町、横宮の警察署を舞台に、警官と民衆がさまざまに織りなす人情喜劇。
物語はいかにも昭和の東北を舞台にしたものだ。『青い山脈』や『三等重役』(面白いことに三本とも脚本を井出俊郎が担当している)のような明朗喜劇が、陽光きらめく南国を舞台にするのとは図式的に対照的で、東北の農村は暗く貧しい。大陸からの引揚者もいる(満蒙開拓団に東北の貧しい農民が新天地を求めて数多く参加したことは、佐野眞一の『遠い「山びこ」』に書かれていた)。
そして犯罪は、この貧困が原因で起きる。捨子、万引、無銭飲食、仏像泥棒、そして身売り(映画の中で娘が売られるのは愛知県一宮の紡績工場ということになっているが、現実には芸妓や娼妓になる方が深刻だったろうし、周旋屋が暗躍して搾取する余地も大きかったはず)。横宮は鉄道駅があるため、農民にとっては東京への出口となる町だから、そうした犯罪が集まることになる。
この映画の中で警官が扱うのは、根は善良な人々が貧しさのために犯すこうした罪だけで、凶悪犯はいない。
貧困という病根を絶てば人々は幸福に暮らせるが、現場の警官のできることには限りがあるから、その範囲でかれらは精一杯努力する。ここでの警官は社会の監視者としての「官憲」ではなく、じつに戦後民主主義的な、護民官みたいに心優しい人たちなのである。
貧困という社会的題材を扱いながら、民衆に寄り添う存在として意図的に警官を位置づける。『山びこ学校』の教師が民衆の自覚を促すことで、同じ東北の農村の苦しさからの脱却につなげようとしているのとは対照的だ。
しかし、多くの問題が単純なハッピーエンドではなく、次善の策、問題はあるけれどもひとまず可能な方法で対策されているのも興味深い。
身売りから救われた娘は、母や弟妹を養うために年の離れた金持の後添いになると決める。捨子をした母親は、子供が裕福な旅館に引きとられるのを確かめて身を引き、東京に職を求める。
貧しい馬子は、創設早々の自衛隊に入る。そして、息子五人を戦死させて頭がおかしくなり、いまだに戦中同様の国民服を着た元校長先生の、万歳のかけ声と日の丸の旗に送られる。
かれら、娘も母も馬子もみな汽車に乗り、故郷を離れなければならない。
ここで、貧困から逃げることが結局は「自由からの逃走」となり、別の苦しみを抱えてより不幸になる可能性が暗示されている。貧者が代償なしに幸福を得ることは容易ではないのだ。
しかし、その悲しみを理解し見守るものとして、警官たちがいる。ラスト、かれらを乗せた汽車を山道から見送る若い警官(三国連太郎)はその象徴だ。
はっきりいって「こんな警官ばかりならいいなあ」というユートピアである。
原作の小説を書いた伊藤永之助のことはろくに知らないのだけれども、ウィキペディアをみると昭和初期はプロレタリア文学、共産主義が弾圧された時代には農村を舞台にした作品を書き、戦後は社会主義作家クラブの中心として活動したとある。そういう作家が、警察官を権力の走狗として軽蔑するのではなく、人情あふれる護民者として理想化している。
田中角栄の周囲には、元は社会主義の運動家だった人が少なからずいた、という話を連想する。
地方の不便さを減らし、貧苦から脱却させるために、公共事業で道路と鉄道を整え、中央の富を分配する。体制側の政党が地方民衆の生活を楽にし、代りに票を得て左翼を抑え、選挙に勝つ。
高度成長と五五年体制による、上からの日本型社会主義。その萌芽を、一九五五年につくられたこの映画が暗示しているように思うのだ。
税を軽減してもらおうと農民が役人に説明する場面や、通産大臣に出世した酒屋の次男坊が故郷を視察に訪れ、芸者を呼んで馬鹿騒ぎをする場面がある。
それらは喜劇らしく戯画化されているけれど、事の是非についてはやはり言挙げせず、判断を保留する。こうした必要悪の体制と権力が、地方の生活水準上昇の導入者、水先案内人となっていくのだ(地元に錦を飾るのが通産大臣だというのが、また意味深い)。
戦後民主主義の夢想の中に、現実的着地点がかいま見える人情映画。
ところで、前述の正気を失った元校長を演じているのは、東野英二郎。『ここに泉あり』では、警察署長だったのに公職追放を受け、楽団の経理に落ちぶれる役だった。社会的地位がありながら敗戦で人生を狂わせた堅物の老人、というのが東野の十八番だったらしい。
話はかわって、CD話。
ハルモニア・ムンディから出たイザベル・ファウストのバッハの無伴奏、渋くてコクがある響きで、素晴らしい。
今までこの人の録音、たとえばベートーヴェンのソナタ全集などはもう一つピンとこなかったのだが、ピアニストなどの共演者が、私好みではなかったせいなのかも知れない。
でも、これはいい。渋いのにリズムの弾力があり、絶妙の浮遊感がある。音がへばりつかず、浮いているのだ。といっても、地に足のつかない不安定さというのではない。自らの意思と力で空中にあり、自在に動き、弾む音楽。
日本のクラシック好きにはベタッと粘る音が好きな人が多いから、そういう人は落着きがない演奏と感じるかも知れない。しかし私にはこれこそが、今を生きる音楽である。
シュタイアーのゴルトベルク変奏曲も素晴らしかったし、ハルモニア・ムンディの好調は、じつに嬉しい。
三月二十八日 見事な《ラ・ボエーム》
横浜でホモキ演出の《ラ・ボエーム》を観る。非常に刺激的で面白かった。
全幕を通しで上演し、すべてが雪の積もった路上で展開される。雪景色、なんて美しいものではなく、石畳を凍てつかせる、大都市の暗く淋しい、薄く積もるだけの雪。どれほどに着飾り、暖かい部屋に住み、愛を語ろうと、登場人物全員の足元に冷たく過酷な孤独と荒廃と、利己主義が広がることを暗示する。
第二幕だけでなく、第四幕もクリスマスのパーティに設定し、両者を残酷に対照させた着想がすばらしい。二度の宴会でそそり立つクリスマス・ツリー(いろんな意味が込められているのだろう)。ところがこの二つの、カフェとレストランでの宴会の間の、恐ろしい落差。大雑把にいうと、仲間内→宴会→仲間内→宴会、という幕構成になって、各幕が起承転結の役割を担う。
最大のポイントは第四幕。本来ならボヘミアンたちは前と変わらず貧乏なままなのだが、この演出では功成り名遂げ、金と欲にまみれた生活を送っている。
そのかれらが裕福な客たちと高級レストランで開くパーティに、街娼に落ちぶれたムゼッタと瀕死のミミがやってきて…という展開になる。
このとき、男と女の間には、絶望的な格差が生じている。
オペラは砂糖漬けのお涙頂戴の物語だが、その物語構造の内部には、この差別と偽善が確かに存在しているのだ。
設定は現代に変えてあり、それによって社会と人間の問題が過去の場所、特定の人物や職業に限定されるものでなく、普遍的な問題であると示すのだが、しかしその正当性を考えるには、いったんミュルジェの原作小説『ボヘミアンたちの生活』にたちかえるとわかりやすい。
自身がボヘミアン生活をしていたミュルジェは、その体験をもとにこの小説を書き、さらに戯曲化して富と名声を得ることに成功した。
それを正当化するためか、かれは序文に、貧苦と無名の反市民的生活をへて、まもなく社会的に認められる成功者こそが本物のボヘミアンであり、才能も運もなく成功できずに、反市民的生活そのものが目的化してしまうような連中は、見せかけだけの偽ボヘミアンだと、自画自賛する意味のことを書いた。
その点、壁にペンキをぶちまけたり、カフェでズボンを下ろして下着を見せたりなど、善良な市民が眉をひそめることを前半でくり返すこの演出の芸術家たちは、第四幕で見事に人気者になれたのだから、確かに本物のボヘミアンである。
一方、著書にサインを求めてきたウェイトレスをだまして強姦しようとするなど、名声を得てもかれらの根の下劣さ、身勝手さが抜けていないことも、ホモキは示しておく(このあたり、かれらがふざけて口にする歌詞を利用して、別の意味を持たせる工夫が見事だった)。
この男たちに対して、ミミとムゼッタは、かれらの雌伏時代のお相手というだけ。その成功と反比例するように、社会の最下層に沈んでいく。彼女たちはグリゼット、お針子と呼ばれる存在で、芸術家ではなく、ボヘミアンではない。
考えの足らない私はこれまで、主役の貧しい男女全員がボヘミアンだと思い込んでいたのだが、そうではないのだ。
このオペラのタイトル「ボヘミアンたち」は、芸術家の卵である男性たちのみを指していて、グリゼットを含めてはいない。そのことを、ホモキは襟首をつかむようにしてわからせてくれた。
そしてミュルジェの規定に従えば、成功しなければ本物ではないのだから、このボヘミアンたちは、不遇に終ってはならないのだ。
この第四幕には、細かい仕掛けが色々とあった。以下は、私一人が上演中に確認したものだけでなく、信頼する友人知人から得た情報に基づいている。
まず、ホモキが意地悪なのは、ロドルフォの出世作の小説が何であるかをわかるようにしたこと。作品名は『ミミ』。表紙には、かれがミミに贈ったボンネットの絵が書かれている。
彼女を題材にした小説で成功したロドルフォにとっては、それは甘美な思い出というだけ。
だが、そこに本物の、瀕死のミミが現れる。短く刈られたその髪は、彼女が体だけでなく心も病んで、何かの施設(知人はそれを「ヴィスコンティ通りの、あるいはそういう名の避病院あるいは更正施設」だと喝破した。卓見だろう)に強制的に収容されていたことを暗示している。そこから逃げたところを、けばけばしい身なりで街娼暮しをするムゼッタに助けられ、連れてこられたのだ。
ロドルフォは同じ人間、一人の女性に対してした残酷な仕打の結果を、ここで見せつけられる。ミミを救おうと行動するムゼッタに対し、ロドルフォとマルチェッロは札束をふりかざすことしかできず、ムゼッタをあきれさせる。
コッリーネとショナールは、もっと世渡り上手に、偽善的に行動する。コッリーネは自らの財布をのせた盆をショナールに渡し、パーティの裕福な参加者たちから義捐金をつのるように促す。さらには外套を、チャリティの売物にする。有名人の外套だから、高く売れる。そしてそれらの金を、ムゼッタに渡す。
本の表紙を見て、往時のボンネットのことを回想しつつ、ミミはこと切れる。
しかし金持連中にとっては、死なれては迷惑なだけ。金を放りだし、遺骸に抱きついて悲しむのはムゼッタ一人。ロドルフォはその名を叫びながら、事態に直面することを避け、置き去りにして逃げていく。ほかの全員がそそくさと続き、ためらいを見せたマルチェッロも、ムゼッタの街娼姿に怯え、背を向ける。
ラスト、雪の路上に放りだされたミミの亡骸の傍ら、散らばる紙幣の中に、膝を抱えてすわりこむムゼッタ。
いうまでもなく、ここで断罪されているのはミュルジェではなく、ボヘミアンやその流れを受け継ぐ反市民的ポーズをとる芸術家たちだけではない。かれらに眉をひそめつつ、かれらが起こした混乱に乗じて略奪に加わる第二幕の群集や、有名になったかれらにへつらう、第四幕の偽善的な賓客も間接的な共犯だし、そしてそれは客席の私たちも、誰しも多かれ少なかれ身に覚えのあることだろう。「本物のボヘミアン」は、人の醜い心を戯画化した、私たちの代表なのである。
男たちそれぞれの立場に応じた反応の描写も冴えに冴えていたが、ここでムゼッタを残したことが印象的だった。
彼女をもっとしたたかな女性として行動させ、ミミを一人にすることも可能なのに、逆に寄り添わせた。男社会(それに甘んじ、それを利用する女性もそこに含まれる)の身勝手と偽善を強調しているともとれるし、また人間性の、はかなくも最後の希望として残したとも、とれなくはない(彼女を待つのも、おそらくミミと同じ運命なのだが)。
そういえば、アーンの喜歌劇『シブレット』には、老いたロドルフォが出てきて、若い男女たちの恋を成就させようと努力するという。
たしかにロドルフォの将来は、『カッレくん』を読みなおす大人がカッレの将来、それも必ずしも明るくない将来を想像せずにはいられないのと同じく、考えてみたくなるものがある。
ここで逃げ出すロドルフォは、小デュマの小説『椿姫』で、ヒロインの臨終に間に合わず、その骨を無縁墓地から掘り出させて改葬したアルマンと、結局のところは似たようなものと思ったり。
ムゼッタが第四幕のパーティで貴族のパトロンをうまく見つけて、彼女の出自でも可能な最高の出世、つまりヴィオレッタのような高級娼婦になっていったりするのも、それはそれで面白い。そして彼女も、ミミから伝染した結核で死ぬ。
ならば《ラ・ボエーム》と《椿姫》を続けて上演して、ムゼッタとヴィオレッタ、そしてマルチェッロとジェルモンを同じ歌手が歌うなんて、いいかも。
マルチェッロ=ジェルモンとしては、そりゃ息子に「あの女はやめとけ」と止めるだろうというもの(笑) ロドルフォなど他の「本物のボヘミアン」は、当然周囲の貴族とかの役で。
オペラの設定は《ラ・ボエーム》が一八三〇年頃、《椿姫》が一八五〇年前後だから、男たちについては年代のズレがちょうどいい。
ただ、ムゼッタ=ヴィオレッタはかなりの年増になって、一歩間違えると豊志賀になりそうだ。
《ボヘミアン淪落の女の真景累ヶ淵》
そして、最後はミミとヴィオレッタと豊志賀の亡霊が…、なんて。
四月一日 飲み会馬鹿話
エイプリルフール。大学時代のサークルの同級生三人で飲み会。いつも同様に馬鹿な話を数時間。
『滝山コミューン1974』の話。あの六、七〇年代の日本型社会主義の時代において団地をコミューン化する、西武電鉄と革新勢力の奇妙な共犯関係とか、団地ってまさにソ連型社会だなあとか、その原型は一九四〇年体制にあるんだろうかとか、そりゃあれはソ連の計画経済を真似してんだから似てて当然だろうとか、戦後の『山びこ学校』や『ここに泉あり』の世界は、その一九四〇年体制への反動として毛沢東的農民革命への左翼のシフトを意味してんだろうかとか、さらにそれが失敗して左翼が都市回帰したとき、ちょうど六、七〇年代の団地全盛期とかさなって、『滝山コミューン』の時代がくるんじゃないかとか、そのとき自民党は都市部をあきらめて地方への左翼浸透をつぶすべく、社会主義的な政策と資金を地方に重点投入して、地方を支持基盤にしたんだよなあとか、そんなことをごちゃこちゃしゃべったあげく、ぽんと出たのが森繁の話。
森繁がただのコメディアンではなく役者として認められた一九五五年の二本、『夫婦善哉』と『警察日記』。
森繁の前者の関西弁はうまいなあと一人がいう(森繁は大阪人なので当然)。でも後者での東北弁は、関東人のオレが聞いてもおかしいと思うぜ、などと私が言ったら、もう一人が「その映画知らない。どんなの?」という。
社会主義の小説家の作品の映画化で、福島の田舎町を舞台に戦前風の「オイコラ」型官憲ではない、護民官みたいな理想的な警官がいっぱい出てきて、貧しい市民をなんとか助けようとするユートピア話だよ、なんて説明すると、
「てことは、『砂の器』のあの駐在みたいなもの?」
これには、おお!と思った。
『砂の器』が書かれたのは、一九六〇年から翌年にかけて。
警察署と駐在で規模は違うが、たしかに『警察日記』と『砂の器』の警官は、戦後民主主義的な警官という意味で、似ている(もちろん、『砂の器』の三木謙一が乞食の父子を助けるのは、戦前という設定だが)。
そして、これをお読みの方はすでに気がつかれているだろうが、『砂の器』の身元不明の被害者は、東北弁みたいな方言をしゃべっていたことが当初の捜査の大きな鍵になる。だがそのズーズー弁は予想に反し、東北とは反対方向の出雲弁だと判明する。
まさか、森繁の東北弁が嘘くさいからそれを思いついたというのはないにしても、人情派の警官が東北弁をしゃべるという『警察日記』のイメージを、清張が利用した可能性はないとはいえない。あの時代の映画がもっていた影響力の大きさは、そのまま『砂の器』の重要なファクターでもあるわけだし。
さらにいえば、森繁が演じた警官はあの映画で、貧しさに苦しむ母子を助け、子供に養い親を見つけてやり、仕事を求めて東京に向う母親を駅で見送る。父子を助けた三木謙一も、子を託児施設に、父を癩病院へ、やはり両者を引き裂く形で(当時では仕方のないことだったが)対策している。
『砂の器』は人の出自、戦前と戦後、地方と都市などのさまざまな断裂を背景にした物語だが、そこに、一過的なユートピアとしての戦後民主主義の一つの象徴である『警察日記』をはさむと、清張の「意地の悪さ」がさらに見えてくるような気がしないでもない。
酔った上での馬鹿話だから、これで終りなのだが。
帰宅後、前半の団地話について別の方から、藤森照信が紹介した「住いの五五年体制」なる説を教えてもらう。
戦後、爆発的に増大する都市部の若い勤労世帯に住いを供給した二つの柱、住宅公団の団地と住宅金融公庫の融資。
二つとも法律が整備されたのは一九五五年で、前者は革新系政党が、後者は自民党が対抗しあって立法化したものだから、「住いの五五年体制」なのだ。
公団と公庫の背景に、こういう左右の対抗関係があったとは知らなかった。団地は社会主義、持家は資本主義。当然といえば当然だ。
昭和四十年代まではまだみんな貧しかったから、低廉な団地がリード。五十年代に懐が温かくなり、終身雇用と年功序列制が社会全般に広まるにつれ「庭付一戸建」への(現代では不思議なほどの)憧れが燃え上がり、たとえ通勤二時間圏でも公庫を利用して購入し、均質集中型の団地を出てバラバラになり、革新より保守を望むようになる。
一九八〇年代後半の首都圏での革新勢力の弱体化は、それと軌を一にする。そしてその頃から、郊外のモータリゼーションとファストフード化が急速に進行する。なるほど…。
四月二日 ブッダと上野の夜桜
東京・春・音楽祭の《パルジファル》演奏会形式を聴く。
シルマー指揮による、すっきりと澄明な響きが心地よい。感動的というのではないのだが、変にご大層くさく鈍重にやられるよりは百倍もいい。
妙な話だが、クレメンス・クラウスが指揮した一九五三年バイロイト・ライヴの録音を、久々に聴きかえしてみたくなった。四半世紀前に聴いたときには、こちらがクナッパーツブッシュに感情移入しすぎていたためか、同じ年の《指環》に較べて薄味の凡演としか思えなかったのだが、いまの自分ならまた違った感想を持つのではないかと、シルマーの指揮を聴きながら感じたからである。
歌手も実力派をそろえていて、なかでもミヒャエラ・シュスターの、今にも折れそうなもろい心に苦しみながら、懸命につっぱっているクンドリは、体格のいい猛女型の歌唱に慣れていただけに、新鮮で印象的だった。没入型の演技も鮮やかで、これは舞台で観たかった。
外題役のブルクハルト・フリッツも役にあった声でよかったが、最後のソロの途中で声が裏返りそうになり、後半を抑えてしまったのが惜しかった。こういうとき、聴いている方もヒヤヒヤして、集中できなくなるのが困りもの。
数年前、《オランダ人》から《ローエングリン》までを順番に東京で聴けたことがあったが、今回も新国立劇場での《ジークフリート》《神々の黄昏》にこの《パルジファル》と、バイロイトで初演された三本を続けて聴くことができた。
こうして聴くと、いかにも《パルジファル》は実用的に、歌手の負担が過大にならないように書かれていることがよくわかって面白い。現実の歌劇場のための作品であり、対して《指環》は、いかにも「夢の劇場」のための作品なのだ(だからこそカルショーたちデッカ・ボーイズは、現実の歌劇場ではあり得ない《指環》がレコードで可能だと、夢を追うことができたのだろう)。
一方、楽劇理論の提唱と実践を開始して以後、表面的には離れていたキリスト教と人間との問題に、前半生の歌劇作品以来、最後の作品で久しぶりに関わったのも興味深い。死ぬことを禁じられたクンドリは、オランダ人にイヴの原罪を重ねたような存在である(そういえば《マイスタージンガー》の二人の女性の名がイヴとマグダラのマリアからとられているのは、どういう暗喩なのだろう?)。
そして、たしかにパルジファルは『ヴァーグナーとインドの精神世界』ではないけれど、ブッダじみている。欲を去って涅槃に至る。ワーグナーがブッダを主役に構想したという《勝利者》は、どんな話だったのか。さらにニーチェとゾロアスター。近視眼的な意味でのキリスト教と西洋人の関係を、客観化しようという十九世紀ヨーロッパの動き。このあたりはさっぱり詳しくないが、調べだせば奥ははてしなく深そうだ。
幕間に上野公園を歩く。夜桜とその下で飲み騒ぐ人々。ぼんぼりだけが闇の中に仄かに光って、人々は青い影となって服装もわからない。離れて眺めると、現代と特定することのできない、時代から浮遊しているかのような幻想的場面。
東京・春・音楽祭の来年は《ローエングリン》。パルジファルの息子の話ということになる。指揮は今年のバイロイトで同じ作品をふるネルソンス。これもいまから楽しみ。
それにしても、こうした声楽入りの大編成の場合、東京文化会館の音響は適度に抜けて響いて、素晴らしいと思う。オペラの舞台公演ではここまで良さは出ないから、やはり後方の反響板を含めての効果なのだろうか。
四月三日 マーラーと土手の桜
午後から紀尾井ホールで紀尾井シンフォニエッタの演奏会。
ホール開館と楽団結成十五周年を記念するもので、《春の声》とモーツァルトのピアノ協奏曲第二十六番《戴冠式》にマーラーの交響曲第四番。指揮は高関健で、ソプラノの天羽明惠とピアノの田部京子が出演。
前半はいま一つノリが悪かったが、舞台からあふれんばかりに編成を拡大したマーラーは、細部まで血がかよい、各声部が生き生きと動いて鳴る見事な演奏。高関の、この作曲家の音楽への共感の深さがよく伝わってきた。アンコールに天羽明惠をまじえて《ラインの伝説》を演奏したのも、珍しいが的を射た選曲。
帰りは、上智大学脇の土手の桜の下を四ツ谷駅まで。晴れた青空と見下ろす土手の緑と、降りかかる桜花。
四月四日 佐村河内と池袋西口の桜
東京の演奏会は、会場も団体もバラバラなのに不思議なシリーズとなって、思わぬ興趣を味合せてくれることがある。
おとといからの三日間は、ちょうど桜の時期ということも相まって、まさしく味わいのある音の連鎖だった。
今日は午後から、池袋芸術劇場で佐村河内守(さむらごうちまもる。かわちのかみではない)の交響曲第一番。
ワーグナー~マーラー~佐村河内。
佐村河内は私と同じ一九六三年、広島生れ。被爆二世で重度の抑鬱神経症に不安神経症、頭の中で絶えず轟音が鳴り続ける頭鳴症を患い、三十五歳で全聾に。
人前に出るには前もって数日間にわたって薬を大量に摂取し、体調を整えなければならないという。作曲は独学で、オーケストラ音楽、ゲーム、テレビ音楽などを手がけ、交響曲第一番は四十歳のときの作品。
とまあ、波瀾に満ちた人生を余儀なくされている人だ。その自伝的著作『交響曲第一番』は、許光俊さんが紹介したこともあってクラオタには有名である。
「ハンディキャップ・クラシック」なんて言葉があるくらい、クラシックの世界では何らかの障碍に苦しむ人に脚光が当たる傾向が特に日本では強く、その物語性と純粋な音楽的な価値との判別が、とても難しい。正直なところ、音楽がすべてで、それを聴くまでは何ともいえないというのが私の気持で、自伝は読まずにおいた。ゲーム音楽も聴いていない。
だが、一切のお世辞抜きで、今日聴いた交響曲第一番からは、壮絶な、本物の感銘を受けた。本人によるとヒロシマの原爆をテーマとした「祈り」の音楽で、全三楽章を演奏すると七十分もかかるそうだが、今日は二年前の広島での世界初演と同様、第二楽章を省いて約四十分。
二つの楽章を通じ、重苦しい、鬱々とした音楽が耳鳴りのように響き続け、うめき、さけび、さいなみ、打ちのめし、最後にいたって壮大な祈りとなる。
言葉にするとじつに嘘くさく、こけおどしじみてしまっていやなのだが、耳に響くその音楽にはどうにもならない真実味と説得力と、肺腑をえぐる迫力があって、心底圧倒された。
健常者の同情や好奇心を超え、現代に生きる人間の心を揺り動かす力がある。たしかに、他の作曲家から受けた影響はあるだろう。だが、日本の作曲家で、こんなふうに天地を圧するように、轟然とオーケストラを鳴り響かすことができる人が、いったい何人いるだろう。後期ロマン派の巨大交響曲の流れをくむ、ティラノサウルス的な作品。その凄さは、ナマでこそ体験すべきもの。
この曲を自分の意思で選んで、演奏した大友直人は入魂の指揮ぶりだったと思うし、オーケストラの集中も素晴らしかった。終演後に指揮者が客席の作曲者を舞台上に招いたとき、歩いてくるかれを見たコンマスの大谷康子さんが涙をぬぐっていたが、あれは嘘いつわりのない、本心の涙だったろうと思う。
今年、京都では全楽章版が演奏されるらしい。評判は広まっていく。
今日は桜を見られないかと思ったが、芸術劇場の前に数本あった。
広場だけれど公園ではないから、宴会をするスペースはない。花の下に待ち合わせをする人と、行き過ぎる人だけ。
ワーグナーもマーラーも、上野の夜桜もお堀の桜も美しかった。
だが、いま花の下に立つありがたさをどこよりも感じたのは、今日の音楽と、雑然たる池袋のビルの谷間。
(二〇一四年二月八日の附記:この作品は佐村河内守本人の作曲ではなく、作曲家新垣隆が、佐村河内の構成案と指示の下に作曲したことが明らかになった。新垣は健常者であり、ここに書いたことの基礎的事実が崩れたことになるが、当時の私のいつわりのない心境として、原文には手をふれずにおくことにする)
四月五日 モーツァルトと素手
昨日、一昨日の演奏会を通じて感じたことを二つ。
どちらもメインの曲(マーラーと佐村河内)には深い充実を感じたが、それとは見事なまでに対照的に、前半のモーツァルト――《戴冠式》と《ジュピター》――は単調な、退屈な演奏だった。二十世紀後半の形骸化した新古典主義の影響は、残念ながら日本ではまだ根強い。
もう一つは、高関も大友も指揮棒を用いず、素手で指揮していたこと。
いつのまにか日本の指揮者には、素手で指揮する人が増えている。小澤征爾、井上道義。飯森範親もそうだった気がするが、どうだったか。
基本的に日本を最大の拠点として、オペラよりも演奏会がメインの人たち、という気がする。
素手の指揮はストコフスキーを代表格に、二十世紀英米の演奏会で流行した習慣のように思う。オペラでは歌手たちのために指揮棒を用いるのが普通だ。
日本の指揮者たちは、いつごろ、どうして指揮棒を用いなくなったのか? そして先にあげた人々の多くが桐朋、斉藤メソッドを学んだ人であることには、意味があるのか?
いうまでもなく、斉藤自身は指揮棒を用い、タタキやシャクイなど、指揮棒の動きを重視する人だった。
ごく大雑把にいえば、指揮棒をもつ右手が拍子、素手の左手が表情。リズム楽器とメロディ楽器を明確に分割した、二十世紀以降のポピュラー音楽と通底するものがある気もする。
もちろん、ただの思いつきの暴論。
四月七日 大都会のハクビシン
ネットを通じて知り合った方で、神宮前にお住いの人がいる。
一軒家で、以前から屋根裏にネズミや野良猫が棲むことがあったのだが、最近はなんとそこに、ハクビシンが暮らしているという。
猫ぐらいの大きさというから、かなり大きい。ウィキペディアをみると、けっこう昔から郊外の農村部にはいたようだが、最近は山手線沿線でも、夜に電柱に登っていたとか電線の上を走っていたとか、目撃例が非常に増えている。
四谷でも、若葉町あたりで見たと聞いた。池袋でも見たというし、テリトリーを都市部に広げつつあるらしい。
近所では野良猫がめっきり減ったが、そのうち野良ハクビシン、ノラビシンが問題になるのかも。
先月二十二日の日記で触れたシュタイアーのゴルトベルク変奏曲をまた聴く。虚飾のない、言葉の真の意味で豊麗をきわめたもの。すばらしい!
四月八日 灯火管制のない町に
フルトヴェングラーとウィーン・フィルによる、一九四三年五月のストックホルム公演のライヴを聴く(M&A CD‐八〇二)。
『名探偵カッレくん』を読みなおし、スウェーデンが第二次大戦中に中立だったことを思い出して、そこでの戦時中の録音が聴きたくなった。
この戦争で最後まで中立だったヨーロッパの国にはスウェーデンのほか、スイス、スペイン、ポルトガル、アイルランド(とトルコ)がある。当然ながら交戦国間のスパイ戦や秘密外交が行われた。ストックホルムがこの時期を描くスパイ小説の舞台となることも珍しくない。
一九四六年の『名探偵カッレくん』にも、唯一戦争を感じさせる記述として、
「長年、バラ戦争をやってきた。インディアンと白人のものすごい戦争もやってきた。世界大戦中は連合国軍のスパイにもなった」
という一節がある。
その戦時中のストックホルムに、フルトヴェングラーは単身、あるいはベルリン・フィルやウィーン・フィルと、一九四二年と翌年に四度にわたり客演している。スイス各地とともに、かれが訪れることのできる貴重な中立都市だった。
ただし、ドイツ大使館は滞在中のかれを監視するよう命じられていた。四二年一月の最初のストックホルム訪問で、ユダヤ人指揮者のドブロウェンと会食したときには、若い参事官がこうしたことをやめるよう、フルトヴェングラーに懇願したという。しかしかれは「ここはスウェーデンで、ドイツではない」と取りあわなかったという。
三度目の訪問となる一九四三年五月のウィーン・フィルとのシューベルト演奏会は、同年十二月のストックホルム・フィルを指揮した《合唱》とともに、戦時中では貴重なベルリン以外での録音記録となるもの。ただし全曲が残っているのは《グレート》のみで、最初の《ロザムンデ》序曲は失われ、《未完成》は第一楽章のみ。アンコールの《皇帝円舞曲》も前半しか現存していない。
フルトヴェングラーの戦時下のライヴは、その異常なまでの切迫感と迫力で、特別な人気を誇る。《グレート》なら、一九四二年十二月のベルリン・フィルとの録音がその好例だ。
五か月後のストックホルム・ライヴには、あれほどの凄味はない。平和な中立国での演奏だからと簡単にいいきれるものではないけれど、もの足らなく思う人もいる。しかも磁気録音を実用化していた同時期のドイツ録音と異なり、アセテート盤で音質的にも劣る。それやこれやで、話題になることの少ない演奏だ。
だが今回聴きなおしてみて、これはこれでベルリン盤と異なる美しさをもつ、魅力的な演奏だと感じた。
それはなんといっても、ウィーン・フィルの魅力によるところが大きい。澄んだ響き、上品な、貴族的というより王朝的な、抑制を忘れない艶と優美が戦前のSP録音と共通して、まさに『未完成交響楽』のウィーンを想起させるのだ。ウィーン・フィルといえども、こうした優美な軽妙さは一九五〇年代には次第に失われ、二十世紀後半は粘っこくて直截的な、弾まない響きになっていく。それがここに、より戦前に近い形で残っているのだ。《未完成》第一楽章には《グレート》よりはっきりとそれが出ているし、《皇帝円舞曲》前半も、アンコールらしく自発的な熱気とうねりが増しているけれど、軽さと弾力が音楽の基礎をなすことは変らない。
同じウィーン・フィルでも、「ウラニアのエロイカ」や亡命直前のフランクとブラームスなどだと、切迫感と劇性が前面に出ていたと記憶する。その意味で、このストックホルム・ライヴは貴重だ。
ウィーン・フィルの楽団長シュトラッサーは、このときの思い出を『栄光のウィーン・フィル』(ユリア・セヴェラン訳/音楽之友社)に書いている。
「聴衆の中には、多くの亡命者たちもいた。私たちの国からスウェーデンまで落ち延びることに成功した人たちである。どんなにこの人たちが辛い目に遇ってきたか、この燈火管制のないストックホルムでどんなにホームシックに悩まされていたか、私たちにはよく察せられた。私たちがアンコールに応えて〈青きドナウ〉を弾いた時、多くの聴衆の中から啜り泣きが起こった」
《青きドナウ》はこの日ではなく、二日後の《英雄》などの演奏会で演奏されたものだが、このシューベルト演奏会からも、ユダヤ人が大半を占めるだろう亡命ウィーン人を涙させる要素は、たしかに聞きとれると思う。一方、楽員たちは灯火管制のない街の夜景に、平和のまばゆさをおぼえたのだろう。
思いと思いの交錯する町。ディア・オールド・ストックホルム。
四月九日 ムーティのダンディズム
東京・春・音楽祭でムーティ指揮のカルミナ・ブラーナを文化会館で。
強く、硬く力を込めて弾まない音楽。合唱は先日の《パルジファル》とほぼ同じのメンバーのはずなのに、澄明さが消えて一つの塊のように響く。
時流に媚びずに自己のスタイルを貫くのが、この指揮者のダンディズム。それはそれで立派。
以前から評判だけを耳にしていたバリトンのリュドヴィク・テジエ、やっとナマで聴けた。やわらかく豊かな美声。
四月十七日 直葬なる言葉
昨日の日経新聞の夕刊を読んで、直葬という言葉を知る。
通夜や告別式といった葬儀を省いて、いきなり焼いて骨にしてしまうこと。一般的には「ちょくそう」とよむ。「じきそう」の方が仏教用語ふうの印象になるし、そうよむ人もいる。しかし、元々は行倒れや身寄りのない人を対象にした葬場関係者の業界用語、符牒らしいから、口語的によむのが妥当だろう。
焼場に行くと、端に一つだけ小さい炉があって、それはそうした死者のためのものだと、前に葬式を出したときに葬儀屋さんから聞いた。そこを用いて簡単に手短に、事務的に処理する意味が直葬という響きに込められているのだろう。
しかし、最近はそれが一般の人にも広がりつつあるそうだ。
たしかに集団就職などで地方から出てきた人で、退職後は友人知人が少ない、田舎とももはやほとんど縁がない、少子化で子や孫も少ない、さらに独立して遠くにいる、という人が仰々しい葬式を望まなくても不思議ではない。生前には一度も会っていない程度の関係の人に、単なる義理で来てもらうことに疑問を感じる人も少なくないだろう。
葬式や法事はもともとムラ社会で発展してきて、江戸時代に檀家制度によってシステム化され、一億総中流意識の時代にみんなが同じようにやるようになったものだから、それらがことごとく崩壊した今、肉親や少数の友人だけがお別れをして、「焼く」という最小限の行為があれば、充分かも知れない。おひとりさま社会にふさわしいスタイルである。
それにしても驚いたのは、都内ではすでにこの直葬が三割を占めると記事に書いてあったこと。
自分の周囲での経験がないからこそ、直葬という言葉を私は知らなかったのだが、直葬の場合、よほど縁のある人以外はそもそも死去したことにすら気がつかないのだから、その増加が私の目につかなくても当然だ。
葬儀屋さんも坊さんも大変だ。超高齢化社会で葬儀産業は成長一方かと漫然と思っていたが、それだからこそ社会の変化に応じた経済の論理が浸透して、合理化が求められているらしい。
実際、ネットで見ると、葬儀会社の方が営業活動の一つとして直葬を提案しているものが目につく。たしかに劇的なコストダウンで競争力を高められるのだから、必然的な選択なのかも。
そう思いつつ本屋であらためて眺めてみると、「葬式はいらない!」みたいな新書がけっこう多いことに気づく。「坊主はずし」が進行しつつある。
告別式は、宗教と無関係なセレモニーでもいいわけで、有名人でも葬儀は密葬にして、一般向けには日をあらためて、無宗教の「お別れの会」という形を見受ける。今後は宗教色のない「葬教分離」がますます進むのだろう。
しかし、それでは寺は維持できない。寺とは何なのか、墓とは何なのか、今後は何を経済的基盤としていくのか、待ったなしで再確認される時代。
夜、あるオーケストラの演奏会に行ったところ、プログラムに「遺贈ご寄附のお願い」という紙がはさまっていた。
メメント・モリ。
四月十八日 断弦。初台から内藤新宿へ
午後からオペラシティで、ブッフビンダーのピアノ・リサイタル。ベートーヴェンのソナタの第十番、《熱情》《ハンマークラヴィーア》。
演奏はまあ、いかにもブッフビンダーだったが(なんなんだ)、印象に残ったのは《ハンマークラヴィーア》の第一楽章途中で高音の弦が切れたこと。
楽章後にブッフビンダーが立ち上がって弦をいじってみたがどうなるものでもなく、やや間をおいて調律師が登場、聴衆が見守るなかで修理。ブッフビンダーは舞台に残りたがったが、時間がかかったのでいったん引っ込む。
隣席の寺西基之さんが、
「ツィメルマンなら調律自分でやるそうだから、こんなとき自分でなおすかも」
とおっしゃるので、
「自分でなおしたあと、いまのはケージの《四分三十三秒》でした、とスピーチしたら受けるでしょうねえ」
などといっているうちに再開。
しかしアイスランドの噴火、来日演奏家にも影響が出るのだろう。ブッフビンダーも帰国が大変かも。ラ・フォル・ジュルネの時期には落ち着くといいが。
終演後。オペラシティからの帰路は、なるべく歩くことにしている。今日はまだ日没前なので、前から気になっていた場所へ寄ってみることに。
甲州街道を四百メートルほど新宿に戻って、西参道入口の交差点を越えて、すぐの南側。ここに古い寺が二つある。
正春寺と諦聴寺。新宿は空襲で焼き払われていて、ほとんどの寺が戦後の再建だが、この二つはかなり古そう(ひょっとしたら戦前かと思ったが、知人によればこの一帯も丸焼けのよし)。
首都高速とその入出路が空中で巨大にからみあう、現代的な光景の真下に寺があるのが、いかにも面白い。
正春寺で寺の案内板を読むと、徳川家の忠臣、土井家所縁という意外な歴史をもつ寺だった。
土井利勝の弟、昌勝の正室と娘が、それぞれ秀忠と家光の乳母(ともに複数いた乳母の一人)をしており、昌勝の孫を住職に一六二〇(元和六)年、湯島の専西寺の別院として建立したという。湯島の本院は天和の大火で焼失、以後はこの初台に一本化された。
秀忠の乳母の方は初台局といい、彼女がこの初台の地名の元になったとも、逆にこの地を拝領したからその名になったとも、由来ははっきりしないようだ。
(太田道灌が連絡用に設置した一連の烽火台のうち、最初の一つだから初台だという、かなりコジツケくさい説もある。道灌の名が出てきた時点でマユツバの雰囲気になるが、それにしても武州、上州での道灌は、弘法大師や聖徳太子なみの人気者である。江戸の守神という役割にこの人ほどふさわしい人はいない。どうして神に祀られなかったのか、不思議)
娘の方は梅園局と呼ばれ、出家して正春院、現在の寺名の元になった。
面白いのは当初は天台宗だったのに、四年後の一六二四年に浄土真宗(東本願寺派)に改宗していること。
家康の青春時代、三河一向一揆に家臣の半分が参加してしまい、鎮定にとても苦労したという話がある。あるいは土井家も元は門徒で、一揆後は家康に遠慮して天台宗に変え、さらに再び戻したのかも、などと妄想すると愉しい。東本願寺派なら徳川家との関係もよいのである。
ただ、よく考えると初台局の夫が利勝の弟というのは年齢的に無理がある。利勝が秀忠の六歳上でしかないのだから。文字どおり母子ほどに年が離れた夫婦になってしまう。利勝の養父利昌の弟あたりと考える方が自然だ。
そうした疑問も含め、利昌という人も興味深い。さして有力な家ではないようだが、秀忠の乳母を出したり、家康のご落胤という噂のある利勝を養子にし、実子の元政(元昌?)をさしおいて跡継ぎに据えたりしている。
軍事や外交や内政ではなく、奥向に関して家康が深く信頼した人物、一族なのかも。歴史小説の主題にもなりそうな。
ほかにこの寺には、幸徳秋水の内妻でやはり大逆事件に連座して刑死した、管野スガの墓があるという。例の市ヶ谷富久町のあそこで処刑されて、ここに葬られたわけだ。
さらに隣の諦聴寺も、一八五〇(嘉永三)年まで四ツ谷にあって、その年に移転してきたのだという。ぽつぽつとつながる地縁。
この二寺から二百メートルほど東に歩くと、箒銀杏(ほうきいちょう)なる古い巨木に遭遇した。
掲示板によると樹齢二百年、渋谷区の名のある樹木の中で、初代がそのまま現存する唯一の例だそうである。空襲にも焼け残った木なのだ。
幕末の切絵図では甲州街道沿いの先の二寺の東に、銀杏天神なるものがある。現物は樹下の祠といったところで、社殿などはないが。
景色はまるで変っても、いま自分は往時の古街道の上そのものに立っているのだと思うと、ちょっと嬉しい。
また、このあたりは甲州街道の北側より南側を歩いた方が周囲が広々として、よほど気持がいいことも発見する。
北側はビルの真下のため、崖下を歩いているような感じなのだが、南側は斜面の上を歩くことになるので、視界が広いのだ。
かつてその下には、玉川上水の水と緑があった。明るい雰囲気は、江戸時代の甲州街道から受け継いだものなのかも知れない。これからはなるべく南側を歩くことにしよう。
北側に、佐鳴予備校があることにも気がついた。静岡を拠点とする学習塾チェーン。富士宮や沼津や三島、掛川など、この県のどこの工事現場に行っても、街角で見かけたマークが懐かしい。どうせなら甲州街道の内藤新宿ではなく、東海道の品川につくればよかったのに…。
四月十九日 政治的な問題
アウディーテのフルトヴェングラーRIAS録音集が国内盤化されるのに合せて、同社の社長が来日。関口台のキングレコードのスタジオにて、このセットのマスタリングをどのように行なったかの説明会が開かれる。
当時のベルリンの不安定な電気事情から、オリジナルのテープには電圧の変化による速度の増減があり、音程が揺れている。それがどんなものか、どう修正するか、またノイズは除去するが演奏ミスはあえて修正しないとか、などといった話を実例とともに聞く。
実例として提示されたものには、今回のボックスとは無関係の、別の指揮者による音源もあった。しかしこれらについては、何を聴いたか、何を見たか、口外しないでほしいとのこと。放送局のアーカイヴズのテープはライバル会社との争奪戦になっていて、その勝敗には政治的な力もからんでいるからだという。
四月二十日 蔵書を電子書籍に
自分が所有する書籍をPDF化、大雑把にいえば電子書籍化してくれるサービスが始まっているそうで、手数料は一冊百円だという。
本を送ると、背表紙を切り離し、ページごとにスキャンしてデータに変換してくれる。だから現物の本は壊される。リサイクルされるか焼却されるか、いずれにしても現物は消える。
心ひかれる感じはしないでもないが、手元の本を裁断するというのが、ちょっとというか、かなり引っかかる。
そうか、そうして電子書籍は生れるのか、とも思ったり。テキストデータが存在しない古い書物の場合、一冊が背表紙を切り取られてバラバラにされ、中身をスキャンされ、棄てられているのだ。
残るのは紙屑。肉から離れて霊だけ残る、なんて考えると宗教っぽい。
電子書籍化の波は止められないし、遠からず私も日常的に用いるのだろうが、そのある部分はそうしてつくられる。
もちろん、出版社も古本店も、売れ残った本は単なる不良在庫として日常的に裁断処分しているわけで、しょせん物は物。大量消費社会に生きる個人の、身勝手な感傷にすぎないが。
ただし、友人に指摘されて気がついたが、私が見たサービスは、今のところは発行後五年以内の書籍にしか対応していないという。紙が古いと読取エラーの発生率が高いからだそうだ。
基本が二十六しかないラテン文字よりも、漢字仮名混淆の日本語は元々はるかに読み取りにくい。旧仮名ならいっそうひどいはず。
現時点では利用範囲は狭そう。
四月二十二日 懐かしのチクロ
ブラジル製の粉末ジュースから甘味料サイクラミン酸(通称チクロ)が検出され、回収処分となったというニュースがあった。チクロは、日本では発がん性があるとして一九六九年に食品衛生法で使用禁止となっているのである。
チクロってまだあったんだ、というのが最初の感想。
一九六九年といえば私が小学校に入る年で、たしかにこのころ、少年誌か漫画誌かで「チクロはこんなに怖い!」というキャンペーンが展開されていて、その名がある種の恐怖とともに刷り込まれた記憶がある。
そのあと、高校生のときにニーヴン&パーネルの『インフェルノ~SF地獄編~』を読んで、これは現代アメリカ人がダンテの神曲風の地獄を旅するという話なのだが、そのなかにチクロ反対運動をした罪で、罰としてぶくぶくに太らされている女性というのが出てきた。
現代アメリカ人にとって、微々たる発癌性よりも肥満の危険の方がはるかに大きいのに、安価で有用だったチクロを禁止して、肥満化を促進してしまった、というのが彼女の罪だった。
チクロは毒じゃないのかあ、と幼時の刷込がゆらいだのだが、そのころからさまざまな新しい人口甘味料が普及しはじめ、問題の正当性など考える機会はなかった。このニュースで、今も禁止なのだと久しぶりに思い出した次第。
ところが、これも友人からの指摘で、チクロはヨーロッパなどでは禁止されたことがなく、いまも菓子などに使われていることを知る。
禁止運動はアメリカや日本など局地的なもので、ヨーロッパ諸国は重大な危険があるとは考えなかったのだ。
ニーヴン&パーネルは、チクロは当時さかんになりはじめていたアメリカの消費者運動(ウーマンリブ運動とかにも似た)の、ヒステリックな反応の犠牲者であるような書き方をしていた。それが日本にも輸入された結果だったのかも。
四月二十六日 芝と隼町
数か月前からの予定に従い、山の神が胆石の手術で入院。
四十年前に山の神の母親が同じ胆嚢除去をしたときには、開腹手術で一月も入院したそうだが、今は内視鏡手術で入院わずか五日。このへんの進歩は本当にありがたい。
病院は西新橋の慈恵医大附属で、行ってみて驚いたのは、入院棟が芝の青松寺のまさに門前であったこと。
市来竜夫と吉住留五郎の顕彰碑、わざわざ機会をつくるまでもなく、見に行くことができそうだ。
病院と虎ノ門駅を結ぶ愛宕下通り、このあたりが往時の日比谷入江なる海だったと想いながら歩く。
西側のホテル・オークラのある高地から降りる斜面には、汐見坂とか江戸見坂とか、いかにも入江を見下ろす雰囲気の名前の坂がある。まあ、江戸初期はすでにかなり浅くなっていて、埋め立てるのもそんなに大工事ではなかったのでは、とは思うが。
金比羅神社とか塩釜神社とか、海に縁の深い神社も近くにある。といってもこれらは、埋立のはるか後に讃岐の京極家と仙台の伊達家が自邸内に勧請したものだから、入江との直接の関係はないはずだが、埋立地だけに水はけはよくなかったろうし、品川湊から上方、領地への海運の安全を祈るなんて意味合いもあったのかも。
それにしてもこのあたりをぐるりと回ってみる機会、いままでなかった。
周りをそこらじゅう地下鉄が走っているのに、意外と接続がうまくできていなかったり、駅間が遠かったり、じつは交通の便があまりよくないのである。
平らに見えて、じつは北西から南東へと、複数の山と谷が波状に並行していることが地下鉄のルートの制約となり、各線の接続を難しくしているようだ。こういうことは歩いてみるとよくわかる。
手術は明日で、今日は朝の入院手続と夕方の手術説明がある。その合間にFM東京へ行って、ミュージックバードの番組を収録。
FM東京は平河町にあるので、偶然にも青松寺の旧所在地の麹町貝塚の近くと現所在地を往復することになった。知人に教わったことだが、同じく芝の増上寺も、元は麹町貝塚にあったという。貝塚の跡地に寺がいくつもあったわけだ。
そういえば、赤坂の山王日枝神社は、元は江戸城内の紅葉山にあったが、城郭の拡張に伴って最初に移転したのは、は隼町だったのだそうだ(その後、明暦の大火で焼けて現在地に再移転)。
隼町というと国立劇場だが、江戸時代の隼町は北の街道沿いの町人地のこと。FM東京のあたりは、かつての神域だったのかも知れない。
四月二十七日 手術
山の神の手術は無事成功。「電源コードみたいに赤と青に色分けされているわけじゃないし、別々の部品に分れているわけでもないので、大変です」と偽悪的に説明してくれた先生、さすがの腕前。
市来・吉住の顕彰碑も見つけた。寺の右側、精進料理店とのあいだの細い道を入ったところ。竹藪に囲われてあり。
五月九日 一戦終えて
午後、今月下旬発売の月刊誌類の原稿をようやくすべて入稿。
『レコ芸』はひさびさに特集に関わったので、今月は量が多かった。
担当さんからは
「私が片山さんと川本三郎さんの十一日の対談を見に行けるかどうかは、山崎さんにかかってるんですからね」
とクギを刺されていたが、この雑誌については八日夜で完了したので、まあ大丈夫かと。あとは、担当さん自身の頑張り次第だろう、たぶん(無責任)。
それにしても特集、一九八〇年代特有の弾力のない、遅くて、フォルムの崩れた――これがいちばん問題――演奏を聴きかえすのはしんどかった。
音楽シーン自体は懐しさにくわえ、一九七〇年代よりもよほど面白く、何よりも現代につながる要素が多く出ているので、温故知新の効果は、書く方にとっても大きかったのだが。
これから十九日までは、月刊誌もラジオ収録もない、フリーハンドの十日間。
休日前夜と一緒で、「さあ、単行本の原稿を一気に仕上げよう! いっそ2冊ぶんいくか!」とか「さあ、たまってる本とDVDを片づけよう! 死ぬ気で読むぜ!」とか、毎月夢はふくらむが、結局はゴロチャラと、自堕落なキリギリス生活のくり返し。
まずは停滞した「可変日記」の更新。
日差しの弱い日があったら、鴬谷~金杉通り~吉原~下谷万年町貧民窟跡とか蔵前~押上スカイツリー~玉ノ井遊廓跡といった、墨田悪所めぐりもしたい。
再オープンした上野学園の石橋メモリアルホールは万年町のすぐ近くなので、ガラ・コンサートにあわせて行こうかと思ったが、あいにく別の演奏会とバッティング。
最近気にかかるのは、大佛次郎。
かれについて書いた海野弘の『秘密結社の時代‐鞍馬天狗で読み解く百年』を読んだのがきっかけだが、これはタイトルこそ面白いものの、新書でもどうかというくらいに踏込の浅い本だった。
執筆当時の世相を反映した時代小説であるのが(特に戦前の)大佛次郎作品の特徴だと指摘していながら、
「「江戸日記」は帝人事件の裁判のニュースが派手に報道されているときに書かれた。当時の読者はやはり、帝人事件と重ねていたのではないだろうか」
これで止めてしまい、大佛の内心に本気で踏み込んでいこうとはしない。
本質と直面せずに、多くの事象と戯れていくことが海野弘の魅力であるとは承知しているし、私自身共感できる部分もあるが(笑)、これではいくらなんでももどかしさが先に立つ。
それで、かえって興味がわくことになり、海野も参考資料に挙げていた朝日選書の『大佛次郎‐その精神の冒険』(村上光彦)を、古本で読む。
厚さは似たようなものだが、密度はずんと濃い。読むにつれ、三田村鳶魚とか野村胡堂とか、司馬遼太郎とか山田風太郎とかのあいだに大佛次郎をはめると、ジグソーパズルが埋まって、一つのマンダラになりそうな気がしているが…。
これはもう少し。
『大佛次郎の「大東亜戦争」』という新書も去年出ていた。これも読まねば。
あとはたまっているCD。ポンド安でイギリスのCD店から買い、ちょっと聴いて、凄くよさそうだったもの。
ウィグモア・ホールのライヴ・シリーズから、ペレーニ、イヴラギモヴァ、エリアスQ、ピノックのリサイタル。セガン指揮LPOのドイツ・レクイエム。ネルソンスの《火の鳥》に、Ⅴ・ペトレンコのタコ八。
それに一九八三年のLP以来、二十七年ぶりに初めて全部がCD化された、DANACORDの『GREAT SINGERS & MUSICIANS IN COPENHAGEN 1931‐1939』六枚組。
こんなものが、今になってCD化されるとは。
五月十日 三段跳びの小掛!
小掛照二さんが昨夜、七十七歳で亡くなったとネットのニュースで知る。
三段跳びの元世界記録保持者であり、その後もJOCの副会長など、陸上界の要人だった。
この人のご長男は義郎君という。そのかれと私は小中学校が同じで、しかも小学校六年間と中学一年の七年間、クラスまでずっと一緒という関係だった。
個人情報保護の声が喧しい現代では考えられないが、当時は名簿が生徒全員に配布され、住所と電話番号はもちろん、両親の名前と職業まで載っていた。
小学校に入って早々、茶の間でその名簿を眺めていた亡父が「小掛照二! おい、あの三段跳びの小掛の息子がお前と同じクラスにいるじゃないか!」と興奮しながら話しかけてきた場面は、なぜか鮮明に覚えている。
戦前生れの世代の人にとって三段跳びという種目は、陸上の中でも、ひときわ輝いていたのだ。
一九二八年アムステルダムの織田幹雄に始まり、三二年ロサンゼルスの南部忠平、三六年ベルリンの田島直人まで、三大会連続で五輪の金メダルを獲得するという、日本が世界に誇る「お家芸」だったからだ。戦争でその伝統が途絶え、さらに敗戦のためにあらゆる面で自信を失った日本人にとって、小掛さんは二十年ぶりに登場した希望の星だったのだ。
そんなことなど知るよしもなく(一九六九年頃に日本のお家芸といえば、男子体操や女子バレーのことだったのだ)、きょとんとする私に、父は「小掛照二が仙台で三段跳びの世界新記録を出したとき、それを客席で見ていたんだ」と、誇らしげに語った。
へえ、とそのときは聞いていただけだったが、いまウィキペディアを見ると、たしかに小掛さんは一九五六年の秋に仙台市の宮城陸上競技場で行われた日本陸上競技選手権兼メルボルン五輪の最終予選会で、世界新記録を樹立したとある。しかも十六m四十八㎝、それまでの世界記録を二十五㎝も上回る、驚異的な世界新記録だったそうだ。
そんなものを目の前で見せられたら、一生忘れられないのも当然だ。小掛さんは父と同じ一九三二年生れで、同い年の親近感もあったろう。当時、父の方は仙台で税務署勤めだったはず。
だが、残念ながら四十日後のメルボルンでは負傷による練習不足がたたって、小掛さんは八位に終り、二十年ぶりの金メダルはならなかった。
このあたりの不運は、一九五二年ヘルシンキ五輪での、水泳の古橋広之進にも似ている(こうした挫折が敗戦後にお家芸の分野で重なったからか、一九七〇年代あたりまで「本番に弱い日本人」というのが、スポーツではきまり文句のように言われていた)。
しかし、日本人最後の三段跳びの世界記録保持者という栄光は、消えることがない。我が父だけでなく、他の同窓生の親たちもほとんどが「三段跳びの小掛」という名前に対して、特別の輝きを感じていたようだ。
その息子たちが同級生になったのは、十三年後。私もかれも劣等生だったためか、けっこう仲がよかった。
お宅に呼ばれたこともある。父君にも会った。そして車で、原宿のキディランドに連れて行ってくれたのだが、そのときの驚きは忘れられない。郊外のおもちゃ屋や模型店しか知らない小学生には、世の中にこんなにおしゃれで、燦然と光り輝く店があるなんて、想像もつかなかったからだ。
いま思えば、そのとき「父が仙台の新記録に居合わせたそうです」とか、気の利いたことを言えば、きっと照れながら喜んでくれたろう。だが、そんなところにまるで心が回らないのが、劣等生の劣等生たるゆえんである。
義郎君は体格が大きく、いかにもスポーツマンの息子らしく頑丈そのものだったのに、高校一年のときに友人のバイクに同乗していて投げ出され、あっけなく逝ってしまった。
一九七八年、いまから三十二年前のことだから、くしくも今年は三十三回忌ということになる。
息子さんにあの世で再会されただろうか。ご冥福を祈る。
五月十二日(前) 吉原から鳩の街まで
午後からうまく時間が空いたので、隅田川の沿岸地域を歩く。
日比谷線で三ノ輪まで行き~吉原~日本堤~桜橋~鳩の街~押上スカイツリーと歩いて、地下鉄で移動して蔵前の御米蔵跡を見学するコース。
三ノ輪駅から六百米ほど南東に下っていくと、かつての新吉原遊廓跡。
あとで考えたら、次の南千住駅まで乗って、小塚原刑場跡から泪橋をわたって山谷ドヤ街を抜けて南下するという、もっとスペクタクルなルートもあったのだが、これはまたの機会に。
それにしても吉原こと新吉原、現在の千束四丁目は電車では不便なところ。
原型の元吉原は江戸初期、まだ正規の城下町が日本橋から新橋までしかなかった時代に、その北東の外縁、現在の日本橋人形町二丁目と日本橋富沢町のあたりにつくられた。ところが開幕後の急激な人口増加でその周囲まで都市化が及んで風紀取締上不都合となり、半世紀ほど後の明暦の大火(一六五七年)の前後に、現在の場所に移転した。
元吉原と同様に市街の外縁に、しかも同じ轍を踏まぬよう、可能な限りの辺鄙な場所に移した。
浅草寺と千住宿の中間、日光街道からも隅田川からも離れた、幅四百米、奥行三百米ほどの長方形の区画。水田地帯の真中にぽつんとあるので、浅草田圃とも綽名された。
現在では周囲の田畑は余さず宅地化されているが、駅はどれも遠く、普通はバスかタクシーで行くことになる。浅草から歩く人もいるだろうが、雨のときなどはかなり面倒なはず。
今は西側の地下をつくばエクスプレスが通過しているから、いっそ「吉原駅」をつくったら面白かったろうが、そうはしなかった。僻地化政策は幕府以来、現在も継続しているらしい。
時代劇でおなじみの吉原大門、傾城町の唯一の出入り口が、江戸城とは反対の東北、鬼門に向いているのは、疑いなくわざとそうしているのだろう(元吉原も大門は北向だった)。
しかもその大門と表通りの日本堤(現在の土手通り)とを結ぶ五十間道は、くの字に曲げられて、大門が日本堤からは直に見えないようにしていた。この湾曲は現在もそのまま残っているし、さらには傾城町の境界も道となって残っているし、内部の道もほぼそのまま。明治後も遊廓として、周囲から切り離されてきたからだろう。
吉原が凄いのは、こんな不便な場所にあるにもかかわらず、現役の性風俗産業の町、日本最大のソープランド密集地であることだ。最盛期より減ったが、今も約百五十軒あるという。
玉の井や鳩の街、洲崎パラダイスは売妨法施行で衰滅して宅地に変ったし、新宿二丁目やゴールデン街などはほぼ飲み屋街になったのに、ここはソープばかりである。
飲み屋が少ないのは交通不便だからだろうが、それほど不便なのに風俗店が衰えなかったのは、とても不思議。
このあたりは京浜工業地帯における川崎堀之内の位置を考えてみると、都心との関係より、北側の千住の工場街との関係で考えた方がよいのだろうか。いずれにせよ、素人には謎。
面白いのはそれらの店もきちんと昔の傾城町の区画の中にだけあって、今は塀も堀もなくなっているのに、その外に広がりはしていないこと。維新後の公娼制度も、売妨法後の条例も、その区画を守らせてきたからだろうか。おかげで、前述のごとく今も境界が歴然としている。
しかしその区画内も、現在の条例では新規出店はもちろん、建物の建替さえできないので、やがて消滅の運命にある。
性風俗産業は不滅とはいえ、草食系の若い人がこういうところで遊びたがるとは思えない。お客は次第に高齢化して、減少しているのではないだろうか。
どの店も朝十一時くらいから営業していて、ボーイさんが店頭に立っているのだが、三時ごろにその前を歩いているのは、ほんとに私一人。ボーイさんと目を合せないように歩く(笑)。いかに平日とはいえ、これでは苦しいだろう。
たくさんのソープランドの中に「オペラ」の姉妹店「セリアオペラ」というのがあって、オペラ好きを笑わせる。
ソープが消えたとき、吉原は初めて歴史遺跡となるのだろうし、その日はそんなに遠くない気もする。
吉原大門跡から土手通りをわたり、土手通りと並行して走る、山谷堀の跡を南東にくだって隅田川へ。
土手通りは、この堀の脇の日本堤という堤の道の後身。山谷堀はいつできたのかはっきりしないそうだが、江戸初期に隅田川(幕府の正式呼称は浅草川)上流の氾濫をせき止め、浅草や下谷の水はけをよくするために掘られたという。
大川(隅田川)から山谷堀へ屋形船で入って上るというのが、いちばん贅沢な吉原行きの方法だったとか。
堀跡は大門付近では遊歩道程度の幅だったが、下るにつれて堀幅が広がり、途中からは山谷堀公園という公園になる。左手は現在の今戸一丁目。この付近は、安易には口にできない歴史をもつ。
隅田川との合流点の右手には、待乳山聖天(まつちやましょうてん)という寺が、小さな丘の上に。
さらにその西の浅草六丁目は旧名を猿若町といい、天保十二(一八四〇)年に歌舞伎の江戸三座が堺町、葺屋町、木挽町から移転させられて集められ、芝居町を形成していた。
町人文化の爛熟期である幕末の三十年ほどは、浅草寺の裏に遊廓も芝居町もまとまっていたわけで、このあたりが一大遊興地域となっていたわけだ。根岸の里や向島に商人が別宅や妾宅や隠居所をつくったのも、自然が豊かだという以外にこうした遊興地に近いという、脂粉くさい理由もあったのだろう。
江戸の町人地は地形上の制約から、東北方向へ、千住宿へと発展していた。しかし維新で武士階級が消えて、発展のエネルギーは山の手へと方向転換する。
隅田川の岸に到着。行く手には建設中のスカイツリーが、否が応にも大きく目に入る。川を少し遡って桜橋で渡河。
この橋は人道橋で車が通らないので、スカイツリーをゆっくりと眺められる。隅田川の左岸に着くと、弘福寺と長命寺の二つの寺が並ぶ。後者は桜餅で有名。桜橋というのはこのあたりが墨堤の桜の名所だからだろうが、桜餅が食えることもあるのだろう、きっと。
墨堤通りを五百米ほど朔行し、右折して鳩の街通りに入る。
この細い商店街は、戦後に赤線として有名だったところ。ここから一キロほど北東の東向島に、大正年間に発展した玉ノ井という私娼街があったが、その一帯が空襲で灰になったあと、娼家は焼け残った家を求めて、向島の他の地域に移った。その一つがこの鳩の街通り。それまでは普通の商店街だったらしいが、疎開で空家が多かったので、それらを名目上はカフェーに改造して私娼街とした。
それらは警察の指導で、風俗店であることがはっきりわかるように、アール・ヌーボー風の装飾を入口や窓まわりに施し、モザイク・タイルを貼ってある。ただし、商店街の表通り側ではなく、裏側に向けて設置して目立たないようにしてあった。このあたりは吉原大門を鬼門に向け、道を曲げる感覚と似ている。
カフェー百軒、三百人の娼婦が女給という名目でいたというから、かなりの規模。といっても一軒に娼婦三人だけの計算だから、普通の二階建ての民家でやっていけたわけだ。一九五八年の売妨法施行で廃業して民家に戻ったが、タイル貼りの建物は現在も数軒残っている。しかし取壊中の家もあるし、往時の痕跡はまもなく消えてしまいそうだ。
森繁久彌が『警察日記』と同じ年に主演した東宝映画に、鳩の街を舞台にした永井荷風原作の『渡り鳥いつ帰る』というのがある。いつか観てみたいもの。
興味深いのは、商店街の表通りと住宅街の雰囲気が、わが家近くの余丁町のまねき通りという商店街(俳優の遠藤憲一はここが大好きで、四半世紀も住んでいるとか)などと似ていること。
鳩の街の方が道幅も狭く戦前のまま、対して余丁町は空襲で焼けて戦後の再建のはずだが、景色に共通性があるのだ。
大正頃に町割ができて、震災後に本格的に形成された、当時のいわゆる「勤め人」の家族向け、あまり裕福ではない市民層向けの、密集した町並。その同質性が類似を生むのかも知れない。(続く)
五月十二日(後) 鳩の街から蔵前まで
四百米ほどで水戸街道にぶつかって、鳩の街通りは終り。余裕があれば玉ノ井か京島も歩きたかったが、くたびれたのでファミレスで一休みしたあと、そのまま南下して押上のスカイツリーに向う。
桜橋通りが京成押上駅の東で京成線と交差する踏切の脇には、撮影場なる広場があり、ツリーが上から下までよく見える。今日の高さは三百六十八米。
しかし六百三十四米の完成時には近すぎて、全体を見るにはつらくなりそう。撮影場はだんだん遠ざかるのだろうか。
なんにせよ、巨大すぎてもう一つ実感のない塔。
押上駅前の交差点に出て「おっ」と驚いた。
北十間川という、江戸の掘割そのままの川が流れていたことだ。京成橋という橋がかかっている。
かつて江戸の町中を結んだ掘割は、さきの山谷堀のように埋められたり、首都高がかぶさったりして、ほとんどが原型をとどめていない。それがここに残っていて、眼下を流れている。
スカイツリーの真下に、思わぬ江戸の名残。隅田川も江戸の川だが、一直線に護岸されて脇を首都高が走るその景色には感じられないものが、北十間川にはあった。もちろん、これもコンクリで護岸された現代の川なのだけれど、街中のむきだしの川に縁がなくなって久しい西東京の人間にとっては、それだけでとても新鮮なのである。
ちなみに北十間川は西隣の東武業平橋駅の駅前も流れていて、東武橋というのがかかっている。京成橋と東武橋、この即物的な命名法は嫌いではないが、傾城橋と豆腐橋とか言いかえてしまう方が、江戸っ子っぽいかも。
ともあれ、むきだしの川に出会う可能性など、まったく予期していなかったので、不思議なほど元気がわいてきた。
ということでもう一か所まわることにし、都営浅草線に乗って蔵前まで行き、浅草御蔵跡を見る。幕府の米蔵がかつてここにあり、札差が幅を利かせた場所。
御蔵跡には下水道局や郵便局、都立蔵前工業高校などがあるが、とにかくだだっ広い。東京港沿いの埋立地にも近いものがあって、水辺の倉庫街というのは、用地の使い方に共通性があるらしい。
蔵前橋から総武線の鉄道橋までの御蔵跡の岸辺は「隅田川テラス」という遊歩道になっていて、護岸壁に蔵を模したナマコ壁模様が描かれている。
向島あたりの川岸に散見したテント村は、ここにはまったくなかった。
浅草橋駅へ出て、総武線~中央線で帰宅。休憩入れて三時間弱の墨江歩き。とにかく東東京はまっ平ら。
五月十三日 『ピアノ大陸ヨーロッパ』
西原稔の『ピアノ大陸ヨーロッパ』を読む。この著者は同じアルテスで『クラシックでわかる世界史』を出している。音楽社会史、音楽思想史では定評のある人だけに記述は手堅い。
前作は縦長の判型が長すぎるように感じたが、こちらは普通の選書サイズで、手にとりやすい。
十九世紀の音楽市場を語るのに、当時の工業化社会、市民社会を象徴する楽器であるピアノに焦点を当てた本は、岡田暁生の『ピアニストになりたい!』や西原自身の『ピアノの誕生』など、日本でも数冊出ている。
その中でこの本のポイントは、タイトルのごとく、パリ、ウィーン、ロンドン、ベルリン、ライプツィヒ、プラハ、さらにはイタリアやスペインなど、諸都市と諸国の消費状況の特徴をそれぞれに記述していることにある。
十九世紀前半までの各都市の相違がかなり大きかったからこそ、この着眼点に意味があるのだが、その差を小さくしていくのが鉄道だというのが面白い。
いうまでもなく、鉄道もピアノ同様に工業化社会の象徴の一つなのだ。鉄道網がヨーロッパに敷かれていった十九世紀の半ば、ピアノも鉄製フレームに交差張弦という完成形に近づき、その強大で輝かしい響きを採用したメーカーだけが、生き残る。現代のピアノはそうした淘汰による、標準化の産物なのである。
対して十九世紀前半は、従来の地方性を引き継ぎつつ、さまざまな個性と可能性がまだ残っていた時代だった。
五月十五日 指揮の三態
この一年ばかり、紀尾井シンフォニエッタの演奏会に通っている。
二管編成、五十人弱という規模だからこそ、「オーケストラとは何か」を考えさせてくれるのがありがたい。
オーケストラ全体と楽員個人の関係、個々の役割が大編成の場合よりも見えやすい。室内楽、合奏団の延長上にあるものとしてのオーケストラ。(大交響楽団はむしろ巨大なピアノに似ているときがある。アメリカ風のヒーロー、ヴィルトゥオーゾ・ピアニストとオーケストラ指揮者は、だから似ているのかも)
今日はライナー・ホーネックが指揮して、ハイドンのヴァイオリン協奏曲第一番、モーツァルトの交響曲第二十九番、そしてシューベルトの「グレート」というプログラム。
ウィーン・フィルのコンサートマスターであるホーネックが、三曲でそれぞれ指揮のスタイルを変え、「指揮の三態」を見せてくれたのが面白かった。
まずハイドンの協奏曲では、典型的な弾き振りスタイル。通常の指揮者の位置に指揮台をおかずに立ち、ヴァイオリンのソロを弾きながら、手の空いたときに指揮をとる。
続いてモーツァルトの交響曲ではコンサートマスターの席に座り、第一ヴァイオリンの一人としてリードする。手指は使わずに動作や目で合図し、演奏で引っ張っていく。いわば、指揮者なしでオーケストラが演奏するときのスタイル。
後半のシューベルトでは編成が大きくなるので、指揮台を置き、その上で指揮棒を振る、普通のオーケストラ指揮者のスタイル。
演奏の印象は、やはりコンマスの席からリードするのに慣れているからか、モーツァルトがいちばんよかった。
精度はややルーズにはなるのだが、ヴァイオリンを中心に全部の弦がしなやかに歌って、自発性を感じさせる。弦の響きに輝きというか、豊麗さが加わってくる。前にも書いたが、日本人が演奏するモーツァルトは平板単調で退屈なことが少なくないのだが、これはまるでそうではなかった。
後半のシューベルトはひた押しに進める演奏で悪くはないが、全体に響きが硬い感じ。最初のハイドンの場合はその硬いオケと、やわらかいソロの対照と混合が面白い。
いずれにせよ、指揮台上からのコンダクトとリーダー席からのディレクト、英語圏では用語を使い分けられているスタイルがオーケストラの演奏に及ぼす影響の違いを、一人の指揮で聴けたのはとても参考になった。
ところで紀尾井シンフォニエッタ、秋からのベートーヴェン・チクルスはボッセ、コープマン、リープライヒ、下野、ヘンヒェンという陣容。派手ではないがこれも楽しみ。
東京のオーケストラはなぜかベートーヴェン・チクルスが流行のようで、ほかにもいくつかあると聞く。これをきっかけにリズムに弾力のあるスタイルが日本の古典派演奏にも広まっていくのなら、個人的には大歓迎。
五月十八日 幻の千駄ヶ谷文化会館
午後、信濃町の民音音楽博物館のライブラリーへ本を借りに行く。
途中、須賀町の本性寺の前を通ったので、ここの毘沙門堂にお参り。
空襲で四ツ谷の大半が焼けた中、この本性寺の山門と毘沙門堂は奇跡的に焼け残った。南寺町と呼ばれて寺が多いこの一帯でもほぼ唯一の、元禄頃の建物。
毘沙門像は、太田道灌時代から江戸城にあって家康が引き継いだものを綱吉の側室が拝領して、ここに堂を建立したとある。北向きになっているのは、北方の伊達政宗を抑えるために家康が向けたことに由来するという。
さて、ライブラリーへ。歩いて行ける距離にある上に、私のように信者ではない一般人でも利用でき、この種の図書館としては珍しく、蔵書の館外貸出もしてくれる。しかも利用者の大半は楽譜が目的なので、音楽書は他の人が借りていることも少ないし、入手難でマニアの間では有名な本も、気軽に貸してくれる。
以前は竹中労の『呼び屋』を借りた。これは出版直後に版元の、弘文堂――かつては東の岩波、西の弘文堂といわれた人文書の名門だが、騒動があって児玉誉士夫、渡邉恒雄、中曽根康弘の影響下におかれ、渡邉恒雄の弟が社長をしていた――がいったん倒産したため、店頭にほとんど並ばなかったという本だ。
今日は、「盤鬼」西条卓夫の『名曲この一枚』と、野村光一の『音楽を語る 三』を借りる。
これらも『呼び屋』同様、古本が少ない(特に前者)。三冊とも新書サイズなので汚損率が高く、単行本主体の古本市場ではまともに扱われにくいからか。
個人的に必要度が高かったのは『音楽を語る 三』。
『音楽を語る』は、一九五〇年から五五年にかけて、野村光一が『音楽之友』誌上で行なった対談を集めた三冊のシリーズ。一と二は入手したが、三は買えていない。
このシリーズ、対談相手に音楽好きの文化人が多いのが面白い。第一回は私が最近こだわっている大佛次郎だし、大岡昇平や河上徹太郎が諸井三郎の「スルヤ」について語ったり、杉村春子がオペラを手伝っていた時代の話をしていたり。
第三巻では辰野隆の回に、日本初の撃墜王、バロン滋野の話が出てきたのに驚いた。滋野男爵はもとは音楽家で、若くして愛する妻を失い、傷心の身でパリに音楽留学したが、途中で戦闘機乗りに転じて第一次世界大戦中のフランス空軍に加わり、軍功を挙げてレジョン・ドヌール勲章を与えられた人だ。辰野とは音楽家時代に交流があったという。
その滋野、亡妻を愛惜するあまり、遺骨をぜんぶ舐めてしまったと辰野は語っている。すごい話だが、愛機にも妻の名をつけたくらいだから、本当なのかも知れない。
ほかに目をひいたのは、建築家の前川國男の話。
音楽関係では神奈川県立音楽堂と東京文化会館の設計で有名な人だが、対談はちょうど前者を完成させ、後者に取りかかろうという一九五五年なので、後者の話がメインになる。
後者は当時、ミュージックセンターとカタカナで呼ばれていた。野村が、上野の竹の台というロケーションはなかなかいいんじゃないでしょうかと水を向けると、意外にも前川自身はそうは思っていないと答える。
「わたしはむしろ新宿御苑に千駄ヶ谷寄りの入口があるんですよ、あの辺につくりたいといって大分主張したんですが、非常な困難がありまして、どうしてもダメだから諦めろといわれて」
新宿御苑の、千駄ヶ谷門の内側。たしかにそこなら用地はあるし、千駄ヶ谷駅からも近い。あの文化会館の建物があそこに出来ていたら、という気はする。
上野の欠点は、
「中央線のヒンターランドから外れていることと、なに分にも現在があの通り猥雑だもんですからね」
この「中央線のヒンターランド」という思考が、なんだかとても愉しい。前川國男は、戦後東京のポイントを中央線においていたらしい(そういえば、当時のかれの事務所も四ツ谷駅前にあった)。
しかし上野公園は都のものだが、新宿御苑は国有だから都の建物を建てるのは難しいだろうし、戦後の一般へ開放した後も、内閣や皇室のさまざまな行事のために他の公園よりも高い閉鎖性を確保してある場所だけに、公共ホールをつくるわけにはいかなかったのだろう。
千駄ヶ谷なら、東京体育館などがある線路の南側でもよさそうな気がするが、いまの東京体育館は一九五六年八月に完成したというから、ミュージックセンターの話が具体化したときには、すでに体育館用地に決まってしまっていたのかも知れない。
あるいは将来のオリンピック招致をにらんで、中央線の南側のあの一帯は代々木練兵場跡まで含め、「体育会系」で固めるというような構想があったのかも。
五月二十日 大佛次郎への一歩
大佛次郎のこと。
すでに触れた海野弘の『秘密結社の時代』、村上光彦の『大佛次郎‐その精神の冒険』、小川和也の『大佛次郎の「大東亜戦争」』、川西政明の『鞍馬天狗』といった選書、新書を読みちらしただけで、肝心の著作はごくわずかしか読んでいない状態で、あえて書く。
どの本も大佛の小説を年代順に追いながら、世相とからめつつその変遷を追ったもの。特に戦前は、同時代の事件や気分と関連性、連想性の高い作品が多かったようだ。
少し前に出た山本七平――私の出た小学校が戦前に青山にあった頃の、大先輩にあたる――の『昭和東京ものがたり』(日経ビジネス人文庫)が、昭和初期の東京の勤め人家庭の「知足安分」の生活と、同時代の出来事に対する気分や心情など、年表ではわかりにくい要素を年ごとに書いてくれていて、これを合わせて読むと参考になった。
大雑把にいえば、昭和五年までは大正元年以来の「軍縮時代」が続いて、軍人たちは肩身が狭く、将校が町へ出るにも遠慮して平服の背広に着替えるような雰囲気だった。しかし大恐慌による不況の悪化が社会を不安定にし、テロを招く。
翌年の満州事変で世の中が変りはじめるが、その時代の人には、戦争が十五年ずっと続いたという実感はなく、むしろ軍需景気で社会が活性化されて雰囲気は明るくなり、失業が減り、女性の就業機会も増える結果となった。
好景気は貧富の差を拡大し、冷害に苦しむ東北では女性の身売りが増え、左翼が弾圧され、軍人が威張りだすなど、社会不安の要因はましていたが、昭和十年ごろまでは明るさが続いていた。
左と右、貧と富、明と暗、洋と和、ペンと剣、理想と現実、さまざまな対立がせめぎ合い、奇妙に共存し混合していたのが、昭和初期の世相という。
そうした対立の共存は現代にもあるけれど、西洋化と大衆化の度合いが限定的だった当時はより相違の落差が大きく、輪郭が明確だった。鮮度も高く、矛盾のコントラストがきつかったのである。
そのなかで、この時代の各層に共通していたのは、政治家の汚職や資本家の搾取に対する強い反感。インテリ層を中心とする左翼がロシア革命に鼓舞されて活性化したのがきっかけとなり、対抗して右翼も熱さを増していく。
軍人を含む極右勢力も、権力者の腐敗を憎悪する心情は極左と共通していた。かれらの場合は「君側の奸」を除いて天皇と自分たちを直結させようとして、テロになる。
極左極右のどちらであれ、あるのはヒロイズムやニヒリズムといった、自己陶酔。しかし大半の一般人は、その独善的な冒険主義に眉をひそめている。
この、矛盾のコントラストがつよい昭和初期という時代に、大佛次郎ほどふさわしい作家はいない気がする。
一高~東大の超エリートコースを歩みつつ、それを外れて大衆文芸の作家になる。フランスの文学と音楽を愛好し、国際色豊かな横浜のホテル・ニューグランドの一室を仕事場にハイカラな生活を送りつつ、最大の成功作は髷物の『鞍馬天狗』。学歴にふさわしく左翼思想の洗礼を受けつつ、尊皇の気持は忘れない。世紀末風のニヒリズムに強く惹かれつつ、健全なヒューマニズムを讃える。
選良と大衆、洋と和、左と右、悲観と楽観など、たくさんのさまざまな対立が共存しているのが大佛次郎という人間であり、その作品らしいのだ。
たとえば、作家歴を通じて書き続けた鞍馬天狗の人物像も、一定していない。
年齢は次第に若返る。倒幕のために手段を選ばなかったのが、途中から正道を行く。やたらに人を斬る時期もあるが、やがて殺生を厭うようになる。ときには幕府内の腐敗を正して、結果的に幕府を助けることまでする。維新後は新政府に加わらず、その専横を嫌う。藩組織に属さない自由人で、反骨とヒューマニズムの人であることだけが変らない。
同時代の、同じく「国民作家」と讃えられた吉川英治の人と作品には、このような矛盾は少ない。野村胡堂は、一高~東大中退で大衆作家という経歴に共通点があるが、かれはその西洋志向をクラシック音楽という趣味に封じ込め、作品には露出させなかった。
ところが大佛次郎の場合は、時代小説の一方に多くの現代小説があり、そこにはハイカラでモダンな都市生活が描かれているという。
その最初の作品『白い姉』の主人公が女性で、昭和六年に書かれたというのが面白い。満州事変で世が明るくなり、女性の社会進出が加速する最初の年に、ブルジョワのモガとモボが活躍するモダンな小説――そこには西洋世紀末風の、滅びの予感も描かれている――を書いて成功させた。戦争が加速させる資本主義的な消費社会の隆盛と、不安。世相をつかみとる勘が冴えているから、かれは国民作家なのだ。鎌倉の自宅を出て、横浜のホテル・ニューグランドの一室を仕事部屋にするのも、この年からだという。
この時期、仲がよかったのが久米正雄というのも心に残る。この可変日記で以前『学生時代』を紹介した久米も、一高~東大を出て漱石門下というエリートコースにいながら、大衆文芸が登場した大震災後から通俗小説を書きはじめ、純文学から離れている。戦時中は文壇活動が主体で執筆量が減り、そのことをなじった高見順に対して、「僕は間違って小説家になった」と答えたという。大佛の方は書き続けていたけれど、この久米と、さまざまな悲しみを共有していたように思えてならない。
西洋的な大衆消費社会にどっぷりつかってしまった現代では、もはやこんな問題は時代後れという人もいるだろう。しかし、日本人のくせにクラシックなどにかかわっている自分には、大佛の内面に無関心でいることはできないのである。
その後の現代小説では、ついに軍国主義化が進んで息苦しくなる社会状況が、当局を刺激しない程度に批判され、そして戦後の代表作『帰郷』につながる。
このあたりは村上光彦の『大佛次郎‐その精神の冒険』がきちんと紹介している。雑学的に感心したのは、昭和三十年に書かれた『風船』の主人公の名前が、「村上春樹」だということ。実在の作家の方はその六年前に生れているから、もちろん偶然の一致。
それから、その二年後から翌年にかけて書いた、『橋』という作品。主人公の大内田良平は戦艦大和が沖縄に特攻出撃した際の護衛艦の艦長で、元海軍少将。三人の旧部下が戦後もかれを敬愛して、「三銃士」と自称して訪ねてくる。テレビで森繁久彌がやった向田邦子の『だいこんの花』みたいである。ドラマの放映は一九七〇年からだから、『橋』の設定を参考にしたのかも知れない。
さて、これらの現代小説の大半は長く入手困難だったそうだが、近年は未知谷という出版社が、シリーズで果敢に復刊してくれている。これからいくつか読んでみるつもり。
五月二十一日 天狗の最期、土方の最期
もう少し、大佛次郎のこと。
いろいろと紹介書を読みつつ頭を離れなかったのは、司馬遼太郎との関係。
ほとんど見えないのだ。
司馬が「少年倶楽部」の愛読者で吉川英治や山中峯太郎に夢中だったことは、本人が随筆に書いている。ということは『角兵衛獅子』などの『鞍馬天狗』シリーズも読んでいるに違いないのだが、それについてどう語っていたか、私の記憶にはないのである。
しかし、大佛の作品の内容を知れば知るほど、司馬への影響を思わずにはいられない。
たとえば大佛の代表作の主人公、鞍馬天狗。もちろん架空の人物だが、維新回天期の実在の人物で、その自由人的位置が鞍馬天狗に近い存在といえば、坂本龍馬だろう。作者は龍馬がモデルだとは言ってはおらず、当初の構想でもそこまで考えていなかったと思うが、次第に意識したことは疑いないだろう。
なぜなら『鞍馬天狗』シリーズには西郷、桂、勝、益満など実在人物が登場するが、龍馬はただ一作品にしか登場しない。しかもその登場は、よりによってシリーズ最終作『地獄太平記』においてである。つまり、実在の龍馬が登場したときに架空の天狗は消えると、小川和也は喝破している。
対して司馬は、その坂本龍馬そのものを主人公とした『竜馬がゆく』で圧倒的な好評を博し、戦後型の「国民作家」の地位を確立する。
司馬が創造したのは一九六〇年代という、熱い時代にいかにもふさわしい竜馬像だが、この作品の初めの方で、寝待の藤兵衛なる泥棒が、かなり無理な形で無名時代の竜馬の子分格になっている。
主人公の武士の協力者に盗賊をすえるのは、大佛が好んで用いた手法なのである。『赤穂浪士』の蜘蛛の陣十郎、『鞍馬天狗』の黒姫の吉兵衛など、枚挙に暇がないほどに出てくる。意地や義理に縛られがちで窮屈な侍に、自由な批評精神をもった反骨の盗賊を組合せるのだ。
司馬はその時代小説の典型的手法を借りた。だが、架空の人物である藤兵衛は話が進むにつれ、次第に存在が小さくなる。司馬がこの作品を、かれ独自の歴史小説――時代のうねりそのものが主人公であるような――へと発展させていくにつれ、架空の人物は動けなくなるのだ。
このほかにも、物語性の強い、つまり時代小説の性格が濃く残っている六〇年代の維新ものには、大佛作品を意識した気配がある。
大佛が『鞍馬天狗』の中で、新撰組の近藤勇を敵役ながら、男の中の男として魅力的に描いたのに対し、司馬は『燃えよ剣』で、それまでは近藤の陰に隠れがちだった、土方歳三を主人公にしてみせた。任侠映画の主人公のようにカッコいい土方に対し、近藤への司馬の共感は薄い。これ以降、一般の人気も土方の方がずんと高くなった。
また『十一番目の志士』の主人公、天堂晋助が京都で「たった一人の長州藩」として神出鬼没の活躍をするあたりは、読者が鞍馬天狗を連想することを、司馬は当然に意識しているはずだ。
百姓あがりで虚無的、しかし野獣的な性欲と生命力をもつ天堂は、爽快な天狗の陰画のような存在だ。かれを追う新撰組を、近藤ではなく土方が率いてくるのも、意図的なものだろう。
(ところで個人的好みをいえば、人柄が場面ごとに都合よく変ってしまって設定にぶれのある竜馬より、土方や天堂の方が融通が利かないぶん、よほど素敵だ。ただし『十一番目の志士』の方は、作者が興味を失ったかのように唐突に終るのが残念だが)
司馬が大佛について語らないのは、吉川英治などと違って、大佛が六〇年代にも現役の作家で、大先輩であると同時にライバルであったからかも知れない。
そして大佛の方も、矛盾が共存した昭和初期を象徴する作家にふさわしく、大衆小説ではない、ノンフィクションの歴史物語を六〇年代に書く。フランスを舞台にした『パリ燃ゆ』と、未完の『天皇の世紀』である。
後者の最後の主要人物が、その数年前に司馬が『峠』で書いて一躍知名度を高めた河井継之介だったというあたり、大佛と司馬の、維新期をめぐる複雑な相関関係が表れているかのようだ。
なお、これらにはもちろん鞍馬天狗は登場しない。
『天皇の世紀』に天狗を出せたら、気楽でいいだろうとはしゃべっており、また――『パリ燃ゆ』のコミューンの市街戦で、クラマノフスキーとかテングノフスキーとかと名乗る人物が勇敢に戦って死ぬ。戊辰戦争の官軍の軍服、白帯に日本刀を差したこの男が、本当にポーランド人だったのかどうか、埋葬のさいに疑問に思われた――と、天狗の最期らしきものまで語ったこともあるという。
あくまで戯れ言なのだが、じつは大佛自身はけっこう本気だったのでは、と思えてならない。
維新後の同志の堕落に失望する鞍馬天狗にとって直後のパリ・コミューンは、たしかにこれ以上ない死に場所だ。
それに、どこの誰とも知れずに死ぬのも、いかにも天狗らしい。
五稜郭での最後の日に、
「新撰組副長土方歳三」
と、もはやこの世のどこにもない組織の肩書をあえて名乗って死ぬ、『燃えよ剣』の土方歳三のあの最期に匹敵する、見事な場面になったかも知れない。
天狗、パリ・コミューンに消ゆ。
西洋化し続ける近代日本に生きて、その動きがもたらす希望と失望をともに作品に込めた、大佛次郎という作家の人生を総括する戯言ではあるまいか。
五月二十二日 墓の起源?
我家には猫が二匹と半分いる。
半分とは、上半身だけがいるとかそういうのではない(それはキモい)。近所の飼猫が夜明けから日暮まで来て、ウチをねぐらに朝飯と昼飯を食っているという意味。
飼主が日中不在で、メス猫なのに出たがりで人を恐れないため、いつのまにか昼は私の部屋に居ついてしまった。
夜が明けると自宅を出て、我が寝室の窓を叩いて鳴いて当方をたたき起こし、朝飯をもらうとパトロールに出て、数時間後に戻ってきて私の布団で寝る。そして、日暮時になると自宅へ帰っていく。
飼主さんと当方で打合せしたことではなく、その猫が自分でそう決めて日課にして、人はただ従うのみ。女王の風格とでもいおうか。名はチャメ。
しかしそいつのことはいい。ここでの話題は家猫のオス、フク。
こいつがやたらにネズミをとる。今年になって早くも三匹屠った。
一晩かけてなぶり殺しだから、ほんとうに後生の悪い奴(いたう罪な作り給ひそ)。お楽しみが終ると、前にいた野良猫と同じく、人間に見せるために玄関先に置いていく。
かくして翌朝、私が埋葬の役目を仰せつかる。
生き物は、人も動物も土に還るべきと思うので、庭に掘って埋める。
塀際の適当な位置に穴を掘るが、庭といっても猫の額みたいな狭さ。
「適当な位置」といっても、この数になると「あれ、ここはもう掘ってなかったっけ」てなことになってくる。そろそろやばい。
で、思った。次は石なり枝なり、なにか目印を地面において、間違えないようにしなければと。
で、さらに思った。これが墓の始まりじゃん、と。
――墓標って、記念や弔いよりまず、場所をわからせるためについてんだ。
話がいきなりでかくなるが、日本の古墳には、誰が入っているのかわからないものがたくさんある。というか、天皇陵でさえ確実なものの方が少ない。
かつて、群馬県太田市で送電線工事の仕事をしたとき、現場の鉄塔のすぐ脇に天神山古墳というのがあった。
長さ二百十メートル、東日本最大、全国でも三十位内に入るという、巨大な前方後円墳。
ところがこれも、誰が葬られているのかわからないのである。
毛野の国の首長であることは疑いないにしても、名前は何なのか、いくつで死んだのか、どんな人生だったのか、具体的なことは何一つ伝わっていない。
ただ、大きな目印が残るだけ。
個人の墓など、原則的には、その人を直接に知る人が存命の間だけあればいいと私は思う。
偲ぶ人たちのための目印。つまり、私が間違って前のやつを掘返してしまい、イザナギ・イザナミ神話を追体験しないようにするため(笑)につける、ネズミの墓標と同じ。
先祖をきちんと祀るなんてことができたのは、古い時代には一部の特権階級だけだったはず。それは義務という以上に権利としての意味が大きかったろう。
天神山古墳など、まさにそれ。ところがそれさえ、もはや誰が入っていたのかはわからないのだ。
それを、現代人が全員、ペットの分まで含めて、過去への弔いを未来永劫に背負っていったとしたら、いったいどうなるのだろう。形は大切だが、どこかでキリがなければ。
最終的には、ただの地面ということでいい。東京なんて、山手線の中や隅田沿岸は誰かの墓や、誰かが死んだ場所の上に家やビルが建っている可能性がかなり高いわけだが、それで当り前だと思う。
明日は我身。みな土に還る。
雑談だが、埋葬がらみでウィキの「もがり」の項目を見たら、万葉集では「殯宮」を「あらきのみや」と読むそうだ。
神泉の隠亡谷の上に荒木山(後の渋谷円山町)があったというのは、ただの偶然だろうけれど…。
さて、大小はあっても墓は墓。
次はもっと運のいい生涯を送れよ、などと思いつつ、ネズミ用の穴を掘る。
墓標はなにがいいだろう。
すごく小さな前方後円墳でも、盛ってみようか。
五月二十三日 ネトピル!
CDでネトピル指揮プラハ響の《我が祖国》を聴く。
若き血のたぎる快演。すさまじく熱い歌とリズム、気迫、うねりと間合いの見事さ。〈ブラニーク〉終曲の猛スピードのたたみ込み、もう一度聴きたくなったが、脳の血管が切れそうになるので少し我慢(笑)。
やはりいま聴くべきはチェコ人か。来日してほしいもの。
五月二十六日 パリの二人
二十一日の日記で触れた鞍馬天狗とパリ・コミューンの関係で、むかし空想したことを少し。
パリに行くなら、函館にいた土方歳三の方も可能性があるかも知れない。フランスは幕府に肩入れしていたのだから、落城寸前の五稜郭からフランス軍艦で脱出して、近代軍学を学びに行くとか、沖田のための薬を探しに行くとか。
フランス軍に参加して、コミューンを武力制圧する側に回り、鞍馬天狗と最後の対決をする。そこで二人はどんな問答をするのか。そして天狗の死にざまに、土方は何を学ぶのか、なんて。
五月二十八日 新宿と自信不足の時代
今日は夕方から新宿界隈へ。
夜に新宿文化センターでワセオケを聴くのが主行事だが、山の神が洗濯機を買い換えるので、まずは、歌舞伎町近くの家電量販店へ。
じつは昨日も下見に行っていて、そのときには「翌二十八日までの値段」というのがついていた。せっかくだからと別のカメラ量販店まで行ってみると、その方が七、八千円高かった。これなら電器店と思ったが、戻るのも面倒だし、どうせ翌日に新宿に出る用事もあるので、あわてて買わずに一日あけた方が後悔もないからと、そのまま帰った。
ということで今日。ところが家電店につくと、まだ五時頃なのに値札が明日の二十九日からの価格というのに変っていて、それが七、八千円も上がっている。
「昨日は明日まで変らないと聞いたんだけど」と店員さんに言うと、前の価格でいいという。「他店さんを調べて、調整しているんです」とのこと。他店が高かったら自店も価格を上げるという、そういう調整なのだ。
昨日見ておいて、ほんとによかった。というわけで前の価格で買えたからいいのだが、正直な話、昨日の店内の活気はカメラ店の方がはるかにあった。店内が狭いぶん、「ドン・キホーテ」同様に煽る効果もあるのだろうけれど、それだけでない客数の差があるように感じた。
そのあと某雑誌をみると、ばっちりのタイミングで家電店の話が出ていて、新宿では結局、競合の効果でカメラ店が売上を伸ばしていて、家電店は目標に達してないとある。
もちろん、長い目で見なければ意味がない。家電店は新宿駅西口にも大型店舗を建設中と、大拡張戦略が続いているのだが、これが一段落したとき、正念場になるのかも。
靖国通りから四季の道に入り、ゴールデン街をうろつく。歌舞伎町から東へ続く大きな窪み、すなわちオオクボなる低湿地のなかである。
ゴールデン街は戦後に非合法の売春地帯「青線」として繁盛し、売妨法施行後は、多くがスナックなど小さな飲み屋に転業した。ジャーナリストや作家が集まることで知られている。
我が荒木町にも、小規模ながら柳新道通りという、よく似た小道がある。
芸者遊びをするための三業地の傍らにつくられた私娼街(シモの方はこっちでお手軽に、というわけだ)で、その後はほとんどが小さな飲み屋になった。いまもごくわずかだけ風俗店が残っている。通りの雰囲気だけでなく、客に週刊誌記者などが多かったことも、ゴールデン街と共通しているのが面白い。
かっぱ池(ムチの池)周囲の斜面や低地にあった三業地が衰退したあと、現在の飲食店街としての荒木町のイメージの原型になったのは、この「四ツ谷のゴールデン街」柳新道通りらしい。いまはメイン・ストリートとなっている杉大門通りや、車力門通りの南半分は、当初は普通の住宅が多かったそうだ。
新宿に話を戻して、ゴールデン街から新宿文化センターへ。
このへんがオオクボ低湿地の東端で、南と東は山になる。まだ時間があるのでそちらに登ってみる。
崖の上には西向天神、そして寺がいくつかならんで、抜弁天にいたる。山の手の鉄則、崖上に寺と神社、斜面に墓地、下の谷間に町という地形がここにも。
新宿文化センターがなんとなくジメっとしているのは、地形的に当然なのだ。
四半世紀前にジャパンアーツでバイトしていた頃は、このホールでしょっちゅう演奏会やオペラ公演があり、来る機会が多かった。リヒテルも演奏したし、一九八四年に三谷礼二さんが演出した二期会の《椿姫》もここで公演された。
地理的には厚生年金会館よりもさらに新宿駅から遠くて不便だったが、一九七九年開場というから、当時はその新しさが魅力だったのだろう。
いまはほとんど来る機会がない。いったい何年ぶりなのか、はっきりしないくらいだ。昭和女子大学人見記念講堂や、五反田の「ゆうぽうと」などと同様、大学生時代の一九八〇年代前半には新築であんなに通ったのに、まったく行く機会のなくなったホールの一つだ。
バブルの狂騒的繁栄の直前、昭和末期に建てられたこれら多目的ホールは、デザインも内装もとにかく「普通」だ。貧相ではないが、華やかさや個性もない。
金はできたのだがどう使っていいかわからない、豪華なのは成金じみて恥ずかしいし、世間体もあるから適当に控え目に、そして汎用性を高くという、一億総中流意識の時代ならではのもの。
本当に渋いものをつくろうとすれば、見た目だけ豪華なものよりもよほど金がかかるわけだが、もとよりそんな覚悟もないから平凡なものができる。
自信不足。ひとことでいえばそれだろう。当時のスポーツの「本番に弱い日本人」というのと共通する、黒船以来の精神構造だ。
そのためらいの感覚が麻痺して、狂奔したバブルの数年間は、一種の精神革命だったと思う。建物も消費生活も、あれを境に大きく変容した。
バブル時代は嫌いだし、懐かしさを覚えるのは、この新宿文化センターが象徴する、昭和五十年代の総中流意識の時代のほうだ。しかし、純粋に現存の建物として見た場合、人見やゆうぽうと同様、魅力が乏しく平凡なのは否定できない。
一億総中流意識は、自信不足という特性ゆえに、様式美には縁が薄かった。
その平凡さゆえに、愛おしく懐かしいのだけれど。
さて、こんなオヤジの繰言は、若い学生諸君にとってはどうでもいいこと。
ワセオケは現役の団員が三百人いるそうだ。こんなクラブは、体育会でも少ないのではないか。客席も大盛況。
ワセオケをナマで聴くのも、一九八三年に文学部の記念会堂で大学創立百年を記念して、岩城宏之指揮により行われた《千人の交響曲》のアマチュア日本初演以来、二十七年ぶり。
昔と較べて技術水準がどうだとかいえるほど、私の記憶力は強くない。やや気になるパートもあったが、さかんに活動していること自体が頼もしい。
家に帰って、届いたCDを聴く。
カペラ・アムステルダムという合唱団が歌う、スウェーリンクの聖歌集。
ハルモニア・ムンディの新譜の聞きどころを集めたサンプル盤に入っていた一曲を聴いて、即座に購入したもの。
ジュネーヴ詩篇歌、すなわちフランス語訳による詩篇集。オランダ人の作曲家が、わざわざカルヴァン派のフランス語訳に音楽をつけているのが面白い。
詩としての美しさ、言葉の響きの美しさがその理由だろうというが、それが納得できるCD。
陶然と酔わせる響き。声部が波うつように織りなす、音の綾。スウェーリンクはカトリック、プロテスタント双方のための聖歌を書いているのだそうだ。最後はオランダの多数派であるプロテスタントに改宗したが、内心ではカトリックへの共感も捨てていなかった、とか。
カペラ・アムステルダム、他のCDも聴かねば。指揮のダニエル・ロイスはCDではストラヴィンスキーとかマルタンとか、冷たく鋭角な二十世紀音楽を聴いていたので、このスウェーリンクのやわらかな響きは意外で、嬉しい発見。
五月三十日 アリヴェデルチ
家の近くに、私の大好きなペペロンチーノが食べられる喫茶店があった。
このパスタはもともと賄い飯だそうだが、まさにそんな感じ。ガーリックと塩胡椒だけで単純だから、もたれないし飽きない。週に二回は食っていた。
ぜんぜん専門店とかじゃない。団塊のオジサンが早期退職して始めたような、ただの喫茶店のパスタ。
正直、具材が多い場合は扱いかねている感じがあって(笑)、だからこそペペロンチーノしか食べなかったのだが、それに関しては天下一品だった。出来にかなりムラがあって、混んで忙しいときの方が見事なアルデンテになったりするあたりも、楽しみだった。
ところが今日、前を通りかかると「二十六日で閉店しました」の貼紙があり、早くも内装屋さんが中を壊している。
先週食べたときには、そんなこと書いていなかったのに。いま思えば、オヤジさんが何かいいたそうな顔をしていた気もしないでもない。
会うは別れの初め、仕方がない。開店から十年ほどたっていたから、いつかはと思っていたけれど、まさかこんなに突然とは。
しばらくはあの味を思い出すことになるだろう。単純なつくりかただから、自分で真似してみる手もあるが…。
景気の動向とどのような関係があるのか、新宿通り沿いのビルの一階にある店が、このところ次々と閉店している。昔風の洋品店とか、四谷、信濃町、曙橋界隈で、ただ一つ残っていたゲームセンターとか。
ゲーセンなんて今はまったく縁がないが、学生時代には昔の家や学校の近くのあちこちで、かなりの時間を費やした。それらの店も大半が、いやおそらくすべて閉店している。すでに終って久しい風俗の一つ。若い人向けの店は、今はどんなものがあるのだろう。早稲田あたりをうろついてみれば、わかるだろうか。
ともあれ、アリヴェデルチ、ペペロンチーノ。
五月三十一日 サロネンの境地
サントリーホールで、サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団の演奏会。
サロネンの指揮のもと、オーケストラが精妙な響きをつくりだす。近年の来日ではあまり評価が高くなかった楽団も、この指揮者がリードすると見違える。
前半のムソルグスキーとバルトークもお得意の曲目でさすがだったが、後半の幻想交響曲は精妙にしてグロテスク、熱気と緊張にみちた見事な演奏だった。
一九五〇年代前半生れの世代の指揮者は荘重と俊敏の過渡期にあって、もう一つグッとこない――見かけに較べて、リズムの動きが表面的で、弾力が足りない――人が多いのだが、サロネンはその淀みから抜けだして、独自の高い境地に至りつつあると思える。
指揮ぶりが意外に地味なのは、じつは重要な要素なのかも。
六月二日 「こん・ばん・は」
CSテレビで『ドリフ大爆笑』の初期の番組を観ている。
一九七七年二月開始、私が中学二年のときに始まった月一回の番組。「もしもシリーズ」の「威勢の良い銭湯」をもう一度見たいのだが、ギャグそのものよりゲストやその歌、そして当時の風俗そのものが懐かしい。
この頃のフジテレビは、かなりひどい低迷期にあったはず。漫才やバラエティ中心の「軽チャー路線」に切換え、さらにトレンディドラマで黄金時代を迎えるのは、一九八〇年以降のこと。その直前の、垢抜けない自信不足の時代。
さて、その中の一九七九年六月頃の放映分で、志村けんが天気予報のネタをやっていた。ギャグ自体は面白くないのだが、「おっ」と思ったのは、最初に「こん・ばん・は」と挨拶したこと。
――そういえば、こういう挨拶をするお天気お姉さん(おばさん?)、たしかにいた…。
およそ何でも調べられるネット検索だが、探しかたが悪いのか、この人の情報は見つからない。バブル以降になると、「お天気お姉さん」が関心と憧れの対象になって情報も増えるが、それより前には、関心を持つ人も少なかったらしい。
六月四日 スピノジ、《事故》と《罠》
ジャン=クリストフ・スピノジと新日本フィルの演奏会を、サントリーホールで聴く。
プログラムのメインがハイドンの交響曲二曲、それも百番代ですらなく、第八十三番《雌鳥》と第八十二番《熊》なのだから、通常の日本の交響楽団ではまず考えられない構成。そのせいか、一日だけの公演なのに空席が目立つのは残念だったが、内容はとても愉しかった。
前半と後半のそれぞれ初めにおかれたモーツァルトとロッシーニの序曲とアリアよりも、ハイドンが何といっても聴きごたえがあり、仕掛けにみちた「楽しいハイドン、愉快なハイドン」だった。昨年ブリュッヘンが指揮したときとは段違いに快活に音楽が飛び跳ねて、日本のオーケストラでもこんな風にやれるということが素直に嬉しかった。
ただし標題は《雌鳥》より《事故》、《熊》よりも《罠》の方がよかったかも知れない(笑)。
「事故」というのは、第一楽章でオーケストラがクナのライヴなみにぐちゃぐちゃになったこと。近くで見ていた人の話だと、どうやら汗か何かが目に入って指揮が続けられなくなり、演奏が乱れたらしい。楽章終了後に第一ヴァイオリンの女性からハンカチを借りてじっくりと汗を拭き、それから返していた。さらに第一ヴァイオリン後方の楽員が楽譜を床に落す事故もあった。
休憩後の後半は指揮台に立つなり「これで大丈夫だ」と大きな白いハンカチを客席に見せ、笑いを誘う。《熊》の終楽章は、終ったかと思って客席が拍手しはじめると、コーダをこれでもかと何度も反復してフライングを誘う《罠》。
あざといといえばあざとく、悪ふざけといえば悪ふざけ。けれど、面白い。
六月八日 HMV渋谷店の閉店
HMV渋谷店が八月で閉店すると、ネットのニュースで見る。銀座のインズの店舗もその前になくなるらしいし、新宿高島屋からも撤退したそうだ。数年前に予感したことが現実になってしまった。
ポップスのCDがこれだけ売れない以上、ビル丸ごとというサイズのメガストアが競合して存続することは、困難になっている。海外ではとうに大部分が姿を消しているのだから、日本はよく続いた方だ。再販制度で在庫を回せる日本式だからこそだろう。外資系だったHMVもタワーも、気がつけばともに国内資本。「ガラパゴス化」で存続しているのだ。
しかしそうなると、再販制度の及ばない、原則的には買取になる輸入盤などはかなり仕入れにくくなる。売上の大半を占めるJポップは当然ながら国内盤だけだから品揃えに問題はないが、その利点を持ってしても、いよいよどうにもならなくなったのだろう。町の小さなレコード店も続々と閉店している。
それにしても、移転縮小ではなく渋谷から完全に撤退とはさびしい。HMVがツタヤに売却される話があるが、駅前にそのツタヤの店舗があるから、不要になるのか。
閉店前に一度行ってみるつもり。
六月十七日 一夜の幸福
片山杜秀さんと久々に飲む。愉快。
帰宅後、山の神に「片山さんと飲んできた後は、いつも幸せそうな顔をしている」と言われる。そうかも知れない。
六月十八日 《カルメン》の空間
新国立劇場で《カルメン》を観る。
演奏や演出云々より、あらためてこの作品は、本当に大きな舞台とハコに向いたものだと思う。
これはあくまで「感じ」であって、具体的な根拠があるわけではない。ただ、ドラマと音楽が大きな舞台を求め、それを満たすだけの「社会」を含んでいると感じられるのだ。
少し前に上演した《愛の妙薬》や《リゴレット》などの「イタリア・オペラ」は、それをもたない。本質的に旅回りの一座向けの作品のように思える。
といっても《カルメン》の初演は、パリ最大のオペラ座ではなくてオペラ・コミークで、この劇場は当局の規定によりレチタティーヴォが使えず、台詞をしゃべる形式でなければならなかった。しゃべったのでは歌うことに較べて響かないから、小空間向きということになる(オペラ・コミークの客席そのものは千七、八百で新国立劇場とほぼ同じ)。
ここに《カルメン》の矛盾がある。
ビゼーは、小空間には収まりきらない音楽、あるいはその可能性をもつ、その意味で未完成な劇場作品をつくって、直後に死んでしまった。最初に絶賛を受けたのがオペラ・コミークではなく、続くウィーン宮廷歌劇場での上演のときだったのは、ひょっとしたら、その特性が活きる大空間での上演だったという理由もあるのではないか。そしてこのときは、大空間向けにギローの補作によるレチタティーヴォがつけられていた。
世界に広まった原型はこのギロー補作版だが、パリでは一九五九年に至るまでオペラ・コミーク版の上演が同劇場で続けられ、オペラ座が上演することはできなかった。しかしその年の十一月、レイモン・ルロー演出のレチタティーヴォ版によるグラントペラ風の絢爛豪華な舞台がオペラ座で上演され、ようやくレチタティーヴォ版が採用された。
二百五十人の出演者、十五頭の馬と、極端に大規模なもので、今度はやりすぎの感もあるが、大好評で七〇年まで再演されている。
潔癖症的な原典主義が流行った二十世紀後半には、他人の補作を排してオペラ・コミーク版に似た原典版に戻す動きも起きたが、録音ではともかく実演では、今でもレチタティーヴォだけは適宜用いているケースが多い。新国立劇場もそうだった。作品の本質的なスケールに、それが合っているだろう。
もちろん、オペラ・コミーク版を芝居として徹底的に練り込んで、新国立劇場の中劇場くらいの空間で行う上演も、いつかは観てみたいが。
六月二十一日 イヴァン・フィッシャー
イヴァン・フィッシャー指揮のブダペスト祝祭管弦楽団の演奏会を、オペラシティで聴く。
曲目はオール・ブラームスで、ハンガリー舞曲に始まってヴァイオリン協奏曲(独奏レンドヴァイ)、交響曲第四番。
ハンガリー風と言っていいのかどうかわからないが、ゴツゴツした独特のリズムのアクセントが面白い。リズムに弾む感じがないのは、一九五一年生れという指揮者の年代にふさわしいのだが、そこにアクセントがついているから、ノリがいいのか悪いのか判断のつきにくい、じつに個性的な音楽になっている。
アンコールで演奏されたロッシーニの《楽器の序奏を伴う変奏曲》では、レンドヴァイが飛び入り風に参加するなど愉しかった。同曲のCD録音にもレンドヴァイが加わっているらしく、これは買って聴いてみようと思う。
六月二十三日 コネリーの弟
フランスの録音技師シャルランの一連の録音が輸入盤で再入荷(再発売?)されるそうで、そのなかにカラヤンの兄ウォルフガングがオルガン合奏で録音したバッハの《フーガの技法》がある。
持っていないので買うつもりだが、それでカラヤン兄弟の関係、さらにアダムとイヴァンのフィッシャー兄弟のことなどを考えていて、そういえはショーン・コネリーに弟のニール・コネリーというのがいて、007のパチモンみたいな、しょうもないスパイ映画やってたなあ、なんてことを思い出す。
こういう、どうでもいい話題にかぎって記憶回路が迅速に働き、『ドクター・コネリー/キッド・ブラザー作戦』という題だったと頭に浮かぶ。
ジェームズ・ボンドじゃなくて、ただの俳優のコネリーの、その弟がスパイまがいの活躍をするという話だった。ボンドの名を出すと原作者の著作権がからんで面倒だから、出さなかったのだろう。それだけでもいい加減な映画だとよくわかる。そもそも、肝心の弟コネリーが情けない鬚をはやした、魅力も演技力もさっぱりという人だった。
『ロシアより愛をこめて』のボンドガール、ダニエラ・ビアンキや『サンダーボール作戦』のアドルフォ・チェリがいたのは覚えていたが、ネットで検索するとM役のバーナード・リーやミス・マネペニー役のロイス・マクスウェルまで出ていたらしい。
昔、深夜のテレビで一度見たきりだからそこまで注意していなかったが、最後の場面で「よくやったな。お兄さんもほめてたぞ」とか言っていたのは、すると本物のMだったのか。そういう役者が集められていたということは、制作者やスタッフもボンド映画の関係者だったのだろうか。
ボンド映画って、どんなにヒットしようが話題になろうが、こういうB級の根が抜けないところがいいのかも。
六月二十六日 鹿鳴館の仏花
オペラシティでダブルヘッダー。
十四時から新国立劇場でオペラ《鹿鳴館》、十八時半からコンサートホールで山形交響楽団演奏会。
《鹿鳴館》、池辺晋一郎の音楽よりも考えさせられたのは鵜山仁の演出。
伊藤博文などの名士貴顕が舞踏会に登場する歌詞に合わせて、ヒョットコとオタフクの面をつけた着物姿の日本人が猿のような踊りをする。天皇家の紋である菊を黒い花瓶に入れて、仏花のイメージを重ねる。日本人の心身の醜さを揶揄しつつ、特権階級への憎悪を露わにする、いまどき珍しいくらいの左翼風。
鵜山は文学座の演出家。この戯曲はもともと文学座が初演したのに、『喜びの琴』事件で三島と決裂して以後、文学座は上演の機会をもたないという。
これまで観た《ナクソス島のアリアドネ》でも《カルメン》でも、オペラでは設定とト書きを遵守していた鵜山が、ここで「いかにも『鹿鳴館』らしい」演出をしなかったことと、そのことが関係しているとまでは思わないが、ともかくかなりアクの強い舞台だった。
池辺は三島の原作に沿ってオペラ化をしたのだから、舞台も穏当にその線でよかったのではないかと思うのだが。
和と洋の文化の粋が鮮やかに、美しく対照されるのではなく、薄暗く、薄汚れている。
鹿鳴館に和服の壮士が乱入する場は、和洋の対照のグロテスクで滑稽な一面を象徴する光景になりうるのに、壮士は登場しない(そういえば池辺の音楽も、邦楽などは採用しない純西洋型だった)。
設定を離れるのなら、いっそ現代化してしまうのもありだなあと思った。
三島は、進駐軍時代に急激にアメリカナイズされる日本の状況を見て、その原型としての鹿鳴館時代を思ったという。
たとえば《ばらの騎士》の時代設定を一九一一年に移すなど、作曲された時代に合わせることで、その創作の背景となった社会状況をあぶり出そうとするのが近年の演出法の流行だが、それにならって進駐軍時代にすれば、いやらしさがはっきりと出るだろう。
あるいは、戦後の日本型社会主義に限界が来て、弱肉強食のアメリカ式資本主義が称えられた小泉時代に、開国と文明開化の時代を重ねることも可能だろう。鹿鳴館への憧れは、美食とブランド信仰の原型だ。鹿鳴館は六本木ヒルズか。
前半は地方のさびれた駅前商店街、鹿鳴館はロードサイドの大型ショッピングセンターにする、というのもありか。
何にせよそれは、二回目か三回目の演出でいい。
舞台前縁にならべられた、仏花を想わせる菊の花瓶は、終演後の喝采のときに思わぬ威力を発揮した。
ステージ後方に若杉弘の遺影が大きく映されたのだ。観客も出演者も、その遺影に拍手。
仏花のお陰で、舞台が仏壇になった。
隣席の知人に、「あれはそのためだったんですねえ」と言ったら、ゲラゲラ笑ってくれた。
「第二試合」は、河村尚子の弾いたショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第一番が、目の覚めるような快演。勢いにまかせた観はあるけれど、彼女のよい面が素直に出ていた。
会場は超満員。山響も一年前同様の好調ぶり。
七月四日 鳥越神社というトポス
上野学園の石橋メモリアルホールへ行き、上野学園大学管弦楽団を聴く。
音大の学生を中心にしたオーケストラだが、同大の教授陣が出演して、指揮が下野竜也、モーツァルトのオーボエ協奏曲の独奏が広田智之、グリーグのピアノ協奏曲の独奏が田部京子という、なかなか豪華なもの。
曲はほかにマイスタージンガー前奏曲と大学祝典序曲、アンコールに威風堂々第一番。
新築のホールは席数五百、二階正面で聴いた響きはすっきりして好み。パイプオルガンは旧ホールから引き継いだもので、大きさの割に天井が高いのがいい。
この新しいホールを聴きたいというのが第一の目的だが、第二の目的は、この近辺がかつて下谷万年町と呼ばれた貧民窟跡なので、それを見てみること。四ツ谷鮫ヶ橋、芝新網町とならんで、明治期に東京三大貧民窟と呼ばれた町である。
ただし、万年町とは明治以降の名で、江戸時代には山崎町とよばれていた。当時から貧民層の居住地だったらしい。
もちろん、現代にその痕跡はない。万年町には一丁目と二丁目があったが、一丁目はすべて昭和二年に地下鉄銀座線の上野電車庫(現検車区)になった。上野学園はその一丁目のすぐ東隣、ただし戦前は区が変って浅草区の神吉町だったところ(いまはまとめて東上野四丁目)。
二丁目の方は戦後しばらくは長屋のままで、泥棒長屋だの、おかま長屋だのと呼ばれる路地があったという。
一九四〇年生れの唐十郎はこの万年町二丁目育ち。少年時代の男娼たちとの交流の思い出(なんたって「おかま長屋」だ)を、『下谷万年町物語』という戯曲と小説にしている。
私は残念ながら小説しか読んでいないが、昨年再演された戯曲を見に行った知人は面白かったそうだ。現在この二丁目は一丁目と切り離され、北上野一丁目となっている。
その北上野一丁目も歩いてみたが、やはりごく普通の町並。
このあたりは、地名は下谷とはいいつつも西の浅草まで続く、空の広い平野。山の手の谷町のように、地形そのものが社会を記憶してくれるわけではない。道幅が広がり、建物が変れば、雰囲気はまったく変る(その意味で、平地なのに今も区画が歴然と生きている吉原は、ほんとうに珍しい例だろう)。
その平らな地域を南南東にくだって、鳥越神社へ向う。
五月十二日に吉原~押上~蔵前と散歩したときに、どういうわけかあちこちでその名を見かけて、妙に気にかかったのが、「鳥越神社」という名だった。
その名のとおり台東区鳥越にある神社で、歩いた地域のなかでも蔵前はその近くだから不思議はないが、遠い山谷堀あたりでその名を見たので気にかかった。
そこで帰宅後に本やネットで調べてみたら、なんと六五一年創建、旧名を白鳥神社といい、江戸では浅草寺につぐ古い歴史を持つ寺社の一つなのである。
しかも祭神のヤマトタケルに加えて八幡太郎義家と、輝かしい武人にまつわる由緒をもち、かつては広大な敷地に囲まれ、古社にふさわしく「鳥越山」の上にあったという。
ヤマトタケルと八幡太郎義家は、天皇の血を引いて夷を平らげる、つまり後世の征夷大将軍の原イメージをつくったといってもいい英雄だ。ところが徳川幕府は、その由緒を考えれば奇妙なほどに、この神社を大切にしなかった(面白いことに徳川家が強くこだわるのは、かれらよりも太田道灌に関りをもつ寺社だったらしい)。
家康から家光の時代にかけ、鳥越山は何度も削られ、池沼や御米蔵の埋立に用いられてついに平地となり、二万坪ともいわれた広い社領の大半は武家地に召し上げられ、江戸時代から現代まで、川の脇にただ本殿を残すのみ。
なんだかとても妙な神社。
いったいなんだ、と気にかかりだしていたところ、本屋で目にしたのが塩見鮮一郎の『弾左衛門とその時代』と『江戸の非人頭 車善七』。そこに、江戸初期の鳥越神社周辺がどんな場所だったのかがずばりと書いてあった。
以下は、主にその二冊から得た知識。
鳥越神社の東、浅草に向う街道が鳥越川をまたぐ場所に、鳥越橋がかかっていた。いまの「蔵前一丁目」と「柳橋二丁目」の二つの交差点のあいだの信号のところである。
江戸の最初期、家康が入部して間もない頃、この橋と神社の中間の北岸に、幕府の御仕置場(処刑場)がつくられた。
元は、つまり後北条氏の頃は、現在の日本橋本町三丁目にあったという。江戸城と城下町を拡張するため、鳥越に移したのだ。なお、移転した後も神田明神や日枝神社の神輿は死穢を嫌い、処刑場跡には入らなかったという。
それが鳥越橋のたもとに移ったため、この橋は俗に「地獄橋」と呼ばれたという。その移転に前後して、元の刑場の近くにいた長吏頭の弾左衛門も、やはり鳥越に移されてきた。さらに、それまで大川端のどこかにいた非人頭の車善七も、ここに土地を与えられた。長吏も非人も処刑の下働きを職務の一つとする、被差別民である。さらに、長吏の支配下にある猿飼頭も、いつからかは不明だが、鳥越神社の近くに住んでいた。
前述のように、神社は死穢を嫌う。しかしなぜか鳥越山のふもとに、刑場とそれにかかわる人々が置かれた。そして山は、どんどん削られて消えてゆく。
ここで処刑された最も有名な罪人は、盗賊の高坂甚内である。その墓は刑場に近い鳥越神社の南、その名も甚内橋の南岸につくられ、瘧(おこり)の病に効くとされ、現在は神社になっている。
甚内橋は旧名を猿子橋といい、近くに猿飼が住む猿屋町があった。その一角には、猿飼頭の加賀美太夫にちなむ加賀美稲荷がいまも残っている。
移転から半世紀ほどのち(塩見の推定では一六四五年頃)、御仕置場はさらに北の山谷堀に移され、長吏頭と猿飼頭も合わせてその北側に移転した。
御仕置場は町域の外縁、川向うの街道沿いに置くものときまっていたらしい。江戸の町が大きくなり、鳥越橋を渡った右側に幕府の御米蔵ができたから、その隣の刑場は都合が悪くなったのだろう。
興味深いのは、このとき幕府が御仕置場と長吏たちだけでなく、鳥越神社を含む鳥越町全体を、山谷堀の北岸に移そうとしたことである。
鳥越町の住人は新たに新鳥越町をつくって住み、山谷堀にかかる橋は、新鳥越橋と呼ばれることになった。鳥越神社もそこへ移転するはずだったが、懸命に運動して故地に残り、同じ鳥越山にあった熱田神社が新鳥越町に移転した。長吏頭と猿飼頭は新鳥越町の東隣、寺に囲まれた「新町」に住んだ。
山谷堀あたりで私が鳥越の名を目にしたのは、このためだったらしい。
それからさらに十五年ほど後の一六六〇年頃(吉原が移転してから数年後)、御仕置場はもっと北、千住宿に近い小塚原に移され、幕末までそこにあることになる。ただし長吏頭たちはそのまま「新町」に住み続けた。非人頭はかれらとは別に、いつの頃からか、新吉原の区画の裏に屋敷を構えていた。
なお、有名なドヤ街は新鳥越町の北、浅草山谷町に形成されることになる。
これらの事実それぞれがどんな因果関係にあるのか、私にはわからない。差別問題にかかわることなので、安易な憶測は許されない。
ただ、先日自分が山谷堀と蔵前を歩いたのは、特別な理由もない選択だったのだけれど、じつはどちらも近くに刑場があったわけで、これはすごい偶然。
さて、その鳥越神社に突然ついた。
小雨だった天気が、社に入ると同時に本降りになる。
拍子抜けするほど由緒を感じにくい、聖地性や存在感の希薄な神社。白鳥山、鳥越山と呼ばれた山だか丘だかは影も形もなく、まっ平ら。
同じ平地でも、帰りがけに見た浅草橋駅のすぐ北にある銀杏岡八幡の方が、よほど由緒ありげで奥深く見えた。
この奇妙な「何もなさ」、縄文以来のミサキの聖地性を奪われた平板さ、空白感こそが、逆に鳥越神社千四百年の歴史の重さを物語っているのではないか。
しばらく気にかかりそうな場所。
七月九日 池袋の砂漠と大地
池袋の芸術劇場へ、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団の演奏会(名曲シリーズ)を聴きに行く。
ハイドンの《天地創造》の序奏、ヴァレーズの《砂漠》(電子音なし)、マーラーの《大地の歌》という、とても変ったプログラム。そのヘンテコも興味をひいたが、何よりも《砂漠》があるのがいちばんの理由。
いま書いている『一九五四/五五』本の一話に、一九五四年十二月パリでの世界初演の話題が入るので、ナマで体験してみたかったのだ。シェルヘン指揮のその初演が聴衆の非難と嘲笑の声にみちたスキャンダラスなものとなったことは、ターラのCDで確かめられるし、さらにその半年ほど前に吉田秀和が作曲家と会って対話している。当時のゲンダイオンガクのありようを考えるときの、典型的なドキュメントなのである。
さて演奏会、カンブルランは《天地創造》の序奏を《砂漠》の前だけでなく後にも演奏することで、カオスに始まって砂漠世界をへてカオスに戻る、という構成にしていた。その発想はわかるが、音楽的な関連性はもう一つ腑に落ちない。
後半の《大地の歌》では、独唱とオーケストラのバランスの悪さが気になって集中できなかった。テノールのミヒャエル・ケーニッヒはパリ国立オペラの《消えた男の日記》を歌った歌手だが、その巨大な体躯にもかかわらず、声が埋没してまるで聞こえてこない。アルトのエカテリーナ・グバノヴァはまだしも声が響いたが、それでも充分ではない。
上手側の二階席から斜めに見下ろす位置の席だったから、正面とは声の響きが違うかも知れない。あらためて考えてみると《大地の歌》をナマで聴くのはこれが初めて。独唱を強調したCDのバランスに慣れてしまっていたから、物足りなく感じた可能性も高い。歌手の力量、指揮者のバランス調整、会場の音響の問題も大きいだろう。別の演奏をもっと聴いてみなければ断定はできないが、マーラーはかなり鳴らしにくい音楽をつくったまま、自らは聴くことなく死んでしまったのではないか、という気がする。
初演者であり、実演経験も数多く――あるいは誰よりも多く。少なくとも日の目を見た録音の数はずば抜けている――重ねていたワルターは、いったいどんなバランスで鳴らしていたのだろう。
邪推は控えねばと思いつつ、この曲の室内楽版(シェーンベルクの試みをライナー・リームが一九八三年に補筆したもの)の録音が近年になって、作曲者のオリジナルでないものにしては異例なほどに多いのは、単に編曲がよくできているからだけでなく、レコードでこの作品に親しんだ世代の音楽家や聴衆にとって、原曲よりも自然なバランスに聞こえるからじゃないか、なんてことを考えてみたい誘惑にかられる。
七月十二日 藤村中佐というひと
有馬哲夫の『CIAと戦後日本』(平凡社新書)を読んでいる。
著者は公開されたアメリカの公文書を駆使して、『日本テレビとCIA』とか『原発・正力・CIA』など、戦後秘史ものを得意とする人。特に後者は、私もかつて送電業界にいて、業界の奇妙な部分をいくつか体感したり見聞したりしただけに、面白かった。
今回の本のテーマは『保守合同・北方領土・再軍備』という副題のとおり。
中心になるのは海軍再建を悲願とした野村吉三郎なのだが、その周辺の人物として、私には懐かしい名前が出てきた。
海軍中佐、藤村義一。
戦時中にドイツ、スイスの日本大使館に赴任し、敗戦数か月前にスイスでアメリカ情報局OSSの責任者アレン・ダレス(のちのCIA長官)と接触し、独自の和平工作を行おうとしたが失敗した、という話で有名な人。
なぜ懐かしいかというと、この人を主人公にしたドキュメンタリードラマを、三十年ほど前にテレビで観たから。
あの頃のテレビでは、再現ドラマとドキュメンタリーをまぜた、ノンフィクションの歴史番組が流行っていた。
両者が入れ子になって、自由に行き来する構成もあった。以前可変日記で紹介した、小澤征爾を野村義雄が演じる『ボクの音楽武者修行』がそうだし、野口英世に関するかなり辛口の番組(実はその業績は大したものではなく、それを本物にしようとする焦りと功名心が原因で黄熱病にかかって死ぬ、というような話)とか、芦田伸介が山田耕筰をやった『大いなる朝』(フルトヴェングラー指揮の《運命》を聴きながら、息子に「この指揮者はドイツでユダヤ人を助けているそうじゃないか。お父さんはなぜそうしないの」とか、戦争協力をなじられる)とかは放映時に観た。おもにテレビマンユニオンが得意にしたスタイルである。
その一つに、藤村の和平工作の話があったのだ。藤村を演じたのは仲代達矢。
冒頭、番組のディレクター(萩元晴彦か?)が、放映当時の西ベルリンのティアガルテン近くの芝生の前に立ち、
「三十ん年前、いまは何もないこの場所に、日本大使館がありました。一九四ん年、一人の帝国海軍中佐が、武官としてここに赴任します」
というようなことをしゃべると、その後方の舗道を紺色の軍服にコートを着た仲代(長身でとても似合っていた)が歩いてきて、何もない芝生にむかって身を半回転させ、かつてはそこにあったはずの玄関に入ろうとすると、その瞬間にドラマ・パートがスタート。
ドキュメンタリーからドラマへの切り換えには、よくこの手法が用いられていた。しかしこのときは緑の芝生の脇の当世風のディレクターの服と、仲代の軍服の対照があまりにも鮮やかで見事だったから、いまも目に焼きついている。おかげで一九八三年に初めて西ベルリンに行ったとき、旧日本大使館跡を探しに行ったりしたくらいだ。
といいつつ、タイトルや主人公の名前などは忘れていた。しかしいまは凄いことに、そうしたことがネットで全部わかる。番組名は『緊急暗号電、祖国和平せよ』。一九七五年十二月十八日に、日本テレビが放映したものだそうだ。
この話はもともと、一九五一年の『文藝春秋』に「痛恨! ダレス第一電」という記事を本人の藤村義一(戦後は義朗と改名)が発表して評判になったのが世に出た最初で、その後も藤村は折に触れて語り続け、四半世紀後のテレビ番組に至るらしい。
しかしこうした秘話ものにはよくあることだが、その回想には本人による潤色があり、しかも年月を経るにつれて、その度合いが濃くなっているという。
その点をきちんと検証した、素晴らしいサイトがある。大堀さんという方がつくられた『日瑞関係のページ』の「藤村義一 スイス和平工作の真実」だ。こんなことタダで読ませてもらっていいんでしょうか? といわずにいられないほどしっかりした検証で、これを読むとその虚実と変化がよくわかる。
OSS側は藤村の話をとりあえず聞いただけなのに、ワシントンが交渉を承認したと話を大げさにして本国に伝えたこと、最初の記事ではダレスとは直接には接触していなかったのが、のちには会見したと変ること、など。
大堀さんは、これを藤村の自己顕示欲の強さが影響したとみて、「どうして藤村は事実を本国に報告しなかったのか?そして戦後は少しでもそれを正そうとしなかったのか?」と疑問を呈している。
ところが今回の『CIAと戦後日本』を読むと、戦後の記事や談話には、別の目的もあったではないかと思えてくる。
どうやら藤村は戦後CIAのエージェントか、少なくとも協力者になったらしい。スイスで藤村と接触したとされるOSS側の日本問題の主任ポール・ブルームは横浜生れで、戦後に再来日してCIAの初代日本支局長となるのだが、一方でかれは藤村と共同で会社を設立し、同じ住所に住んだというのだ。
野村吉三郎への協力にも、CIAが関係している。参院補欠選に出馬した野村のために、松下電器などの財界から選挙資金を集めるのが藤村の仕事だった。
こういう人物なのだから、日米講和条約締結の年――アメリカは野蛮な帝国主義の国で、ソ連は平和を愛する国と素朴に信じる人が少なくなかった時代――に発表された「痛恨! ダレス第一電」という記事には、自尊心を満足させる目的の一方で、アメリカの印象を好転させる意図も含まれていたのではないか。
右記サイトによれば、その記事で強調されているのは、アメリカ側には早期停戦のための交渉の用意があったのに、日本の本国政府が無能であったために実を結ばなかった、ということである。
これを素直に読めば、アメリカへの好感度は高まる。当時の日本政府がダメだから停戦できず、その結果としてソ連参戦や原爆投下を招くことになったわけであって、アメリカは信頼すべき相手だったのだ、という印象を読者に与える(実際、のちにテレビで観た十二歳の私の感想も、そんなものだった)。
藤村が、実際より交渉の日付を一か月前にずらしているのも、ワシントンが交渉を承認した、ダレスと直接会った、などのつくり話も、それだけアメリカ側が真剣だったと思わせる効果がある。アメリカにとってはその方が好都合で、事実を正したりされては、逆に損なのだ。
なお大堀さんは、ブルーム(サイトではブルンと表記)の回想に事実と相違する点があることから、かれが本当にスイスで藤村の交渉相手だったのかどうか、疑わしいとしている。
口裏を合わせ、藤村の話に箔をつけてやる理由は、仕事のパートナーだからというより、プロパガンダ作戦へのCIA日本支局長としてのサポートと考えた方が自然ではないか。上司のダレスの承認も当然得ていただろう。(ついでにもう一つ。『CIAと戦後日本』にはブルームの写真があるが、説明には一九四一年にドナルド・キーンが撮ったとある。五一年の誤植という気もするけれど、いずれにせよ、ブルームとキーンにどんな縁があったのかも、大いに気になる)。
さらに考えると、これは有馬哲夫のこれまでの著作にも関係するのだが、日本テレビが一九七五年という時点で、この話を蒸し返す番組を放映したことには、何か理由があったのだろうか? スポンサーは、どこの企業だったのか?
などと邪推しながら、もう一度『緊急暗号電、祖国和平せよ』を観てみたい。
たしかラストは、こんな感じ。
――日本政府から交渉の許可が出ず、仲代演じる藤村は呆然とする。そこでドキュメンタリーに移り、初めて本物の藤村義朗(義一)老人が登場、交渉の舞台だったベルン郊外の湖畔のホテルかレストランの席について外を眺め、
「緑がきれいでした。子供たちが遊んでいた。自然の美しさが目にしみました」
とか、挫折の日の思い出を語る。
この前の、交渉が失敗する過程がもう一つ盛りあがらなかった記憶――まあ、中学一年生の記憶だが――があるが(いま考えれば、関係者の多くが存命だったのだから、ぼかさなければならない要素が大きかったはず)、ここはとても印象的だった。
その印象的な場面を、裏事情を邪推しながら、もう一度観たい。
テレビマンユニオン・ドキュメンタリードラマ大全集とか発売されたら、けっこう買う人がいると思うのだが…。
七月十三日 ろくでなし三国志
本田透の『ろくでなし三国志』(ソフトバンク新書)、まだ途中だがとても面白い。現代に媚びた言い方をすれば、三国志の「ゼロ年代新解釈」か。
たしかに著者がいうとおり、後世の東晋以下の南朝や南宋の「力はないけど俺らが正統。負けていても俺らの勝ち」という「脳内勝利」の尊王賤覇思想の元祖は、「引きこもり妄想男」諸葛孔明なのだ(笑)。より古い春秋時代の周室も似ているけれど、かれらは「脳内勝利」を歴史に対して叫ぶことはしなかった。
しかも、後年の諸政権と較べてさらに凄いのは、言い出しっぺのくせに、その主張の根拠がおそろしくあやふやなことである。それが孔明の凄さ。
まあ、孔明の新解釈が鮮やかにきまりすぎて、他の英雄たちの記述はそれに引きずられてしまったような感じだが、この孔明論はナルホドと感心するばかり。
七月十四日 谷中と日暮里のあいだ
川本三郎さんと片山杜秀さんとの第二回対談を聴きに、千駄木の古書店へ。
前回は都合がつかず残念だったが、今日は聴けた。評判どおりの愉しさ。
会場の「古書ほうろう」も、落ち着いたいい感じの書店。
書棚のあいだに置かれた椅子に座ってお話を聴いたが、ふと見あげると、『一九六〇年 夏 ソビエト』という題の古書がある。タイトルを見た瞬間に身体が反応して、中身もろくに見ず購入。
著者は岡野喜一郎といい、駿河銀行の頭取家の人で、当時は常務。慶応出身で美術にも造詣が深かったようだ。
こんな絵に描いたような「資本家」の人でも、一九六〇年のソ連へ視察旅行に行けたらしい。思わぬ発見。読むのが楽しみ。
いままでほとんど行く機会のなかった千駄木や日暮里など、東京の北北東地域に行けたのも面白かった。
私は東急沿線生れで、三十七年間住んでいた。山手線に乗るなら渋谷から、京浜東北線に乗るなら大井町からという感覚が、心身にこびりついている。
こういう人間が山手線に乗ると、西は池袋、東は上野が北限で、大塚から鴬谷までの部分はほとんど縁がない。大塚から鴬谷までの部分を乗った回数は、たぶん今までの人生の全合計で十指にみたないし、各駅で乗降した回数となると、二進法、つまりゼロかイチ。
ということで今日は貴重なチャンス。行きは西日暮里で降り、帰りは日暮里から乗るルートをとった。すると、二つの駅とも地形に共通点がある。
どちらの駅からも会場は南側にあたるが、必ず山越えになるのだ(西日暮里は切通を抜ける)。そして、この山で隔てられるためか、駅の南側にはバブル以降の再開発の波があまり及ばず、心地よい古さがある。
その典型が日暮里駅の南側の、有名な「夕焼けだんだん」のある谷中銀座の商店街で、昭和の匂いたっぷりでじつに魅力的なのだが、北の山の稜線を越えた崖の下にある日暮里駅(重要なターミナルなので、モダンな新建築になっている)との結びつきは、どうも弱そう。
谷根千という名が象徴するように、谷中は根津、千駄木とともに、南の上野につながる町なのだ。北の山上には寺と墓地が広がって、日暮里と分断している。
この地形に興味がわいた。
あとで調べてみると、山手線の東北部分の線路は鴬谷から日暮里まで、上野台地の北縁に沿って、その崖の下をずっと走っている。
この地形の制約から、日暮里の市街は北を流れる隅田川がつくった低い平野に広がることになり、南の谷中とは関係が薄くなる。
さらに日暮里から西も、上野台地から西北へと尻尾のようにのびる、細長い山脈の北の崖下を走るのだ。これは王子の飛鳥山まで延びて、京浜東北線などはそれに沿って、王子駅へ向う。
山手線は、田端駅の西につくられた切通で山脈を横切り、西南の駒込へ向う。
鴬谷から駒込へのこの景色を、昼間に見てみたい。うまいことに四日後に上野へ行く用があるので、そのときを利用するつもり。
七月十八日 山手線の山陰
午後から上野の東京文化会館で、二期会によるオペラ版《ファウストの劫罰》を観る。よくわからなかった。
終演して、外に出たのが五時頃。この時間になれば日射は和らいでいるし、日が長いので日没までには時間がある。
夏場に歩くには早朝以外にはこの時間が最適ということで、上野公園の北を歩いてみる。鴬谷駅まで行き、四日前の日記に書いた通り、上野台地の崖下を行く山手線に乗るつもり。
まずは文化会館から北西に。西洋美術館、国立博物館の前を歩き、芸大の前へ出る。黒田清輝記念館のところで右折して、北上。
このへんには空襲を免れた、古い建物が残っている。閉鎖された京成線の博物館動物園前駅の入口も、昭和初期のモダニズム建築でいい感じだが、それよりも驚いたのは、国際子ども図書館。
いまはこんな新しげな名前だが、旧称は帝国図書館。日本の図書館の総本山、国会図書館の前身なのである。
一九〇六年完成で、百年たっている。国立博物館で最古の表慶館よりも二年古く、和洋折衷ではない純粋な西洋建築。
これが、白灰色の柱と壁面にベージュのレンガを施して、じつに洒落た、しかも堂々とした立派な建物なのだ。恥ずかしながら、こんなにセンスよく美しい建物だとは全然知らなかった。
中も見てみたくなったが、それは次の機会にゆずって、上野中学と文化財研究所の間をぬけ、寛永寺の霊園に到着。
上野台地の北端を占めるここは、かつて徳川家の霊廟で、いまは一面の墓地。
外からのぞいただけだが、いかにもいわくありげな立派な石垣もあって、きっとそれが霊廟なのだろう。
西から東へ三つ並ぶうちの第二霊園には、道路に面して四代将軍家綱の霊廟の勅額門という、立派な赤門が現存していた。家綱が死んだのは一六八〇年だが、ネットで見るとこの勅額門は家光の上野霊廟からの転用らしく、とすると一六五一年頃のものということになる。
帝国図書館と家綱の勅額門、この二つを見ただけでも来た甲斐があったが、まだまだ明るい。
寛永寺霊園前の道を東へ行き、北へ曲がって忍岡中学(上野中学と、こんなに近接して中学が二つあるのも面白い)の前を通り、JRの線路をまたいで北の崖下へ降りる、凌雲橋へ。
鴬谷駅の南口はその手前、崖上にあった。池上線や旧目蒲線の改札みたいに小さな入口。とても天下の山手線の入口とは思えない(崖下の北口も同様で、乗降客の少なさを示していた)。
凌雲橋(汽車の煙をまたぐからか?)をわたり、その脇の階段をくだって、鴬谷駅前の街へ。
話には聞いていたが、ほんとうにラブホテルばかり。迷路みたいな狭い路地にラブホテルが密集している。
ネイティブ・ジャパニーズじゃないお姉さんたちとか、日本人らしきおじさんやお兄さんがホテル前や曲り角、そして駅の北口改札前に、人待ち顔でたくさん立っている。
いや強烈。先日の吉原よりも、湿った淫靡さでは上だ。駅のすぐ前、線路際にむき出しで、これだけ固まっているのがすごい。他のホテル街は、もう少し人目につきにくいところにあると思うが…。
駅前に三島神社というのが江戸時代からあるはずだが、ラブホテルに囲まれてどこにあるのか見えない(笑)。
しかも、線路の向うの南の崖上は寛永寺の霊園で、見渡すかぎりの墓と塔婆。鮫ヶ橋の崖下を連想してしまった。これで、山手線の駅なのである。
このホテル街の起源というのが、あまりよくわからない。
江戸時代の、坊さんがお稚児遊びをするための茶屋に由来するという人もあるし、それに神社の脇に岡場所があっても不思議はないが、いずれにせよ規模は小さかったのではないか。
ホテル街が駅の真ん前ということは、駅が一九一五年に出来たあとに形成されたと見る方が自然だと思う。
連込み旅館が露出した場所に、あえて幹線鉄道の駅をつくるとは思えないからである。たとえどんなに薄い、見え見えのものであっても、その種の施設には覆いを一枚かけて日陰におくのが、大正までの日本の美学のように思うのだ。
しかし関東大震災後の東京では、歴史的由来や地理的条件などを持たない、それまで住宅地だった場所にも、サカサクラゲの旅館街が忽然と出現してしまうことがあった(千駄ヶ谷鳩森とか、大久保とか)。
鴬谷ホテル街も、その例の一つという気がする。あるいはもっと新しく、戦後の産物かも。戦後しばらくの上野駅の公園口近辺が猥雑で、女装した男娼などの稼ぎ場だったという状況に、関係がある気がしないでもない。
鴬谷駅から山手線の北回りで、新宿まで乗る。鴬谷から日暮里、西日暮里、田端、駒込は駅が崖下や谷間にあり、乗降客も少ない。南を山に遮られて、山手線の山陰という雰囲気だった。
といってもこの印象は、日曜で通勤客が少ないことも大きいはず。人が一気に増えたのは巣鴨からだが、これは逆に、とげぬき地蔵の参拝者なのだろう。
七月二十四日 炎天下の早早戦に酔う
炎天の下、酷暑の神宮球場に行く。
夏の高校野球の西東京大会準決勝、早稲田大学高等学院対早稲田実業学校の一戦。つまり、早早戦である。
高校野球の試合をナマで見たことがなく、こんな機会でないと、なかなか真夏に行く気にならないと思った。
準々決勝の四試合から神宮球場で(ただし一試合だけは第二球場。そこで負けて本球場に行けなかった一チームは、ちょっとかわいそう)、大きなスタンドでゆったり見られるのもよいと思った。
しかし、関係者以外で予選を観に行く物好きは少ないのか、観戦のための情報が意外なほどにネット上に上がっていない。とりあえず入場券が大人七百円ということはわかった。試合開始の十二時半頃につくと内野は満席で、外野のみ。
外野は空いているが、話題性もあって普段よりは多いのではないか、と勝手に想像する。席につくと、第一試合の日大三高対日大鶴ヶ丘が五対五で延長戦に入り、まだ試合中。
そう、この日の準決勝は第一試合が日大系、第二試合が早稲田系のダブル兄弟校対決で、どうなっても決勝は日大対早大の系列校の組合せになるのである。
鶴ヶ丘 〇〇〇〇〇二〇三〇〇〇〇〇一
日大三 〇〇一〇三〇〇一〇〇〇〇〇〇
ということで、延長十四回、六対五で鶴ヶ丘(この地名、いったいどこなのだろう)が勝つ。終ったのは二時頃。
十回から十二回まで見ていたが、灼熱の直射日光の下で飲んだビールが悪く回り、焼きそばを食べたら軽い熱中症らしくクラクラときた。そこで終盤は涼しいスタンド裏に退避して、汚いコンクリの上に死人のように転がってしのぐ。
早早戦の開始直後にやっと蘇生して、スタンドに復帰。
私は大学からの人間なので、どっちに座ってもいいのだが、一緒に行った友人が学院出身なので、そっちの一塁側へ。
まあ、何をどう考えても早実の戦力が上だから、大して関係もないのに早実を応援するのは勝馬に乗るみたいでいやだし、実力に劣る学院が珍しくがんばって勝ち残ったからこそ、じつに四十一年ぶりという対決がベスト4という高レベルで実現したわけだし、それに、男子高出身者としては、女がいるようなチャラチャラした高校の応援なんぞできるか(バカ)ということで、一人で来たとしても男子高の学院の応援席に行くことになったろう。
それに、これは客席で友人から教わったのだが、学院の校歌は「都の西北」なのだ。学院は旧制の予科を前身とする直属校だから、その点が早実や早稲田高校とは違うのだ(予科というのは国立の旧制高校に相当する。一高が東大の駒場になったように、新制では大学の教養課程に近いのだが、学院は逆に新制高校に「格下げ」する形で存続したのだ。その名残で第二外国語があったりする)。
だから大学からの人間としては、学院を応援している方が気持いい。
しかし、やっぱり不思議な光景。
両者とも大学野球部と同じ白にエンジのユニフォーム(胸のWASEDAの校名のSの位置が少し違うとか、ほとんど「間違い探し」レベルの差しかない)を着て、「かっせ、かっせ、わーせーだ」と応援席から声がかかる。
それになんたって「紺碧の空」。この応援歌は、早稲田系列すべて共通。
イニングの初めに歌うこともあるが、点を取ったときにスタンドで合唱するのがきまりで、そのときの方が当然ながら熱唱になる。
早稲田実業 〇二一〇二〇一〇一 七
早大学院 〇〇〇二〇〇一〇〇 三
早実が七点取ったので得点時の「紺碧の空」を七回聞かされたが、学院ナインも奮闘して四回、七回と得点したので、そのときはこちらが声をかぎりと「紺碧の空」を聞かせてやる。変なステレオ、あるいは遅れすぎのエコー(笑)。
さらに学院の方は劣勢ながら「都の西北」も三、四回歌って、「お前らこれはまだ歌えねえだろう」と見せつけた。そのときには当然、外野のオヤジたちも右手を前に出して声を合わせる。
しかしまあ、スポーツがあまり強くないので応援にも統制がない学院より、早実の方がブラバンからチアリーダーから応援団まで、しっかりしていたのは仕方がない。そしてかれらは当然、早稲田大学の応援法をモデルにしている。
その大学の応援団には、名物の「コンバットマーチ」というのがある。
これは「一試合に一回限り」が原則だと、昔は聞いた。現実にはそんなに厳しくないというが、応援も気合が入った激しい振付なので、いずれにしてもやたらに使えるものではない。
ギリギリの勝負どころの得点チャンスで使う、「伝家の宝刀」なのである。現在進行形の試合の中で、いつこれを使うかを判断するのが、応援団長の腕の見せ所になるわけだ。
早実がちゃんと伝統に従って、一度しか使わなかったのは見事だった。
一点差につめ寄られた直後の五回表の攻撃で、一点を取って、さらにもう一点をねらって突き放そうという場面。
ここで、「ダダダダンダタン ダダダダンダタン」とそのイントロが響いた瞬間、「おお、きたッ!」と反対側のスタンドにいるくせに、思わず心が騒ぐ。
ナポレオンが、最終決戦部隊である老親衛隊をついに戦場に投入してきたときみたいな、その鼓笛隊の音が聞こえてきたときみたいな、そんな瞬間(バカ)。
実際、そこで見事に追加点をとって、試合の行末をほぼ決めた場面になったのだから、ここで勝負をかけた応援団長、「敵ながら天晴れ」というしかない。
こんな嗜虐的快感を味わえるのも、早早対決の醍醐味。
学院の方は覚えているだけでも二回、普通にコンバットマーチを鳴らしてしまっていた。それじゃあ、ただの高校野球の応援だよ(苦笑)。
だが、統制がとれてなくて、黄色い声がなくて野太い声ばかりで、ファウルボールが来ただけでみんなで喜んだりしている学院の連中もとても楽しそうで、とても素敵だった。
最後は点差が開いたとはいえ、学院ナインの奮戦によってちゃんと試合になったし、だからこそ相手がコンバットマーチを使う場面にもなったのである。
一方のチームに肩入れして、友人とゴチャゴチャ言いつつ観るというのは、やはりいい。
それで相手に「紺碧の空」を歌われるのは、ちょっとあれだけれども(笑)。
終了後、勝者の早実応援団が敗者に対してエールを送ったが、それがやっぱり「フレー、フレー、ワッセッダ」。なんか変(笑)。
学院の生徒たちは「紺碧の空」を歌って、エールに代えていた。これは兄弟校ならではで、ちょっとジーンとくる。
外野席、酷暑はともかくとして、のんびり見られたのは心地よかった。プロ野球だと外野席は応援がうるさすぎて、こんなにゆったりできない。
また来てみたいものだが、次の早早対決、いったいいつあることやら。
準決勝二試合を見るかぎり、おそらく甲子園には早実が行くだろう。今年はテレビの高校野球を、いつもより熱心に見ることになれそうだ。
しかし、中学の同級生で、いまは息子が出た都立高校を熱心に応援している男がいった、「高校野球の醍醐味は地方予選」という言葉にも納得した。日常の生活を送りながら、地元で行なわれる予選を応援に行く。あまりにも華やかな甲子園とは、別の充実がある。
それにしても、早稲田人の愛校心は学校そのものより、「都の西北」や「紺碧の空」という歌への愛、連帯感によるものが大きい気がすると、帰宅後あらためて思う(OBの人間的紐帯の現実的な強さでいえば、慶応の三田会のほうが、ご承知のとおり、問題にならないくらいに稲門会より強い)。
旧制高校出身者の、寮歌への愛着に似ているのかも知れない。それを歌っている瞬間は、たしかにつながっている感じがするのだ。
酷暑の早早戦をわざわざ見にいった甲斐は、これらの歌を本気で、照れずに歌える連中の姿を見られたことにあった。
せっかくだから秋の六大学野球も見にいこうとも思うが、斉藤の最後のシーズンだけに、変に混んでくたびれそうな気もするし、さてどうしたものか…。
八月四日 菅野=原家の謎
東海大に、東海大相模出身の菅野智之という速球派のピッチャーがいる。
開催中の世界大学野球選手権の日本代表ではリリーフ役のはずだったが、斉藤と並ぶ先発エースの沢村が負傷欠場となったため、準々決勝の台湾戦に先発して見事コールド勝ち。
この菅野、東海大相模では春の選抜で甲子園に出ているが、そのときは大先輩の原辰徳の甥というので話題を呼んだ。原の妹の子供なので姓が違うという。
じつは、私の昔の仕事仲間にも菅野さんという人がいて、原辰徳と義理の親戚になったという話を聞いた。
ならば、この菅野さんはきっと、菅野投手の親戚(大伯父)なのだと考えたくなるのだが、謎が一つ。
菅野投手はテレビなどで「すがの」と読まれるのだが、知人の菅野さんの方は「かんの」と名乗っていたのである。
個人的には、松山三四三航空隊の三〇一飛行隊長、菅野直と同じ「かんの」の方がピンと来るのだが、「すがの」という読みもたしかに少なくない。
親戚間で、何らかの事情で読みを変えているのか? それとも、まさかと思うが、菅野投手と菅野さんはどちらも原の親戚ではあるけれど、たまたま字が同じなだけで読みは違う、別の家なのか?
菅野投手がプロで活躍すれば、この謎が明らかになる日がくるか?
八月五日 死者と生者の思い出に
WALHALLが出した、ミトロプーロス指揮メトロポリタン歌劇場の《蝶々夫人》の、一九五六年ライヴを二十年ぶりくらいに聴く。
いや、これはほんとに凄い。
ミトロプーロスの演奏では、一九五七年ザルツブルクの《エレクトラ》とこの一九五六年の《蝶々夫人》の二つが、永遠に残るべき大傑作なのではないか。
ミトロプーロス&メトの《蝶々夫人》は、ラジオ放送が一九五六、五八、六〇年と一年おきに三度行われていて、どれも録音が残っている。頻度の高さは人気の高さの証明だが、そのなかでも初年度の演奏は、その後の二度の中継のきっかけになっただけに、とりわけ燃焼度が高い(ちなみに主役は三回とも異なり、アルバネーゼ、ステッラ、カーステン)。
先日、一九六〇年盤が同じWALHALLから初CD化されたばかりだ。それも悪くない演奏なのだが、八〇年代前半に出たMOVIMENTO MUSICAのLPの、初年度の演奏には及ばなかった。指揮も歌手もオケも、完全燃焼にいたっていない。
その五六年盤がやっとCD化されたのである。その出来を思えば、いままで入手しやすい形でCD化されなかったのがむしろ不思議でしょうがない(ディスコグラフィには以前にもCDが出たとあるが、私はその盤を見たことがない)。
何が凄いって、オケの一つ一つの音型やフレーズが、生き物のように指揮に反応してふくらんで、有機的にからみあっていくのが凄い。
パニッツァやパピの好調時のメトの上演と似たケミストリー、化学反応が、指揮者とオーケストラの間に起きている。手垢にまみれたプッチーニの感傷的音楽から、ハッとするほど電撃的な響きが、随所で聞こえてくる。
歌手もケミストリーを共有していて、自然に、自発的にきっかけとフレージングを読んで、見事に指揮にのっていく。
デ・パオリスとかチェハノフスキーとか、黄金の三〇年代以来のヴェテランが脇を固めているから、それがプラスしているのだろう。ピンカートン役のバリオーニだって、普段からは考えられないくらいにうまく歌っている(一人だけ、シャープレス役のブラウンリーが遅れがちだが、わずかな瑕瑾にすぎない)。
これは、直前にリーダーズ・ダイジェスト用に、準全曲を数日かけてセッション録音していたことがよかったのかも知れない。あの録音(LIVING STAGEがCD化している)自体は生気に欠けてまるで面白くないのだが、表現を徹底するための、格好のリハーサルになったのに違いない。
そして、あらためてその真価に驚かされるのが、外題役のアルバネーゼ。
生来のセンスに加えて、トスカニーニとの共演で学んだ朗唱法のカンタービレとリズムの感覚が、ここで全面的に活用されている。
ここでの彼女の歌は、ミトロプーロスとの共犯関係(ある種、作曲の領域にまで踏み込んでいく、という意味で)のなかで、その瞬間瞬間に生れているのだ。
お互いにフレージングのうねりを読みあいながら、音楽に生命と官能を吹き込んでいく、名人同士の対局。ピットの中と舞台の上と、指揮者と歌手がアイコンタクトと全身の感覚で切り結ぶ、火花の散る緊張感と、そして一体感。
ソロとオケのこの交響こそ、オペラのライヴを聴く最大の醍醐味。グールドなら「エクスタシー」と呼ぶだろうもの。
四半世紀前に三谷礼二さんにこの録音を聴いてもらったときのことを、思い出してしまった。
うん、この指揮は凄いよ、と同意してもらえて、とても嬉しかったこと。
その一方、アルバネーゼはキーキー声なんて一般的な悪評を鵜呑みにした私が「なんか変な声ですけど」とわかったように言うと、「いや、この蝶々さんはすばらしいと思うけどなあ…」と、私の目をじっと見ながら微笑まれたこと。
不思議だった。
皮相な聴きかたでは悪声にしか聞こえないこの歌手の、いったい何を、この人はほめるのか。悪口をいっておけば他人と一緒で波風がたたない歌手について、平然と自分の意見を口にできるのは、何に拠るのか。
そして、生意気な若造を怒鳴りつけたりせず、うながすように微笑むのは、どういうことなのか。
この疑問につまずいて、そして、私の音楽鑑賞歴は次の段階へと進んだ気がする。見つけたつもりの答が正しいどうかはわからないが、とにかく、それがいまの自分につながっている。
恥かしい記憶もひっくるめ、この録音にかかわったすべての死者と生者と、すべての思い出に感謝。乾杯。
八月六日 ベートーヴェンの弟子
練習曲で有名なチェルニーの、交響曲第一番を聴いている。ハ短調で、いかにもベートーヴェン風の大仰な曲なのに、中身がなんにもないのがすごい(笑)。作品番号七八一というのもすごいが。やっぱりこの人はヘン。でもなぜか好き。
八月八日 地元の甲子園球児
夏の甲子園、東東京代表の関東一高に四谷四丁目と荒木町の出身者がいるそうだ。商店街の横断幕に、誇らしげに書かれている。
子供の少ない地域だけに珍しい。高校野球に詳しい友人によると、二人はエースとセンター、堂々たるレギュラーだという。ともに地元の四谷中学だが、野球に関してはリトルシニアの新宿シニアに所属していたから、中学の野球部には入っていなかったのでは、とのこと。
現代の甲子園球児はシニア出身が多くなっているそうだ。シニアは中学生でも硬球を用いるので、高校に入ってから硬式を始めるよりも有利らしい。
サッカーはさらに進んで、高校生でも学校チームよりクラブ・チームが上位になっている。少子化の時代、頂点にプロ組織があるスポーツでは、これが当然の流れかも。
プロ野球も、以前の東京大阪二極集中型から、数球団が政令指定都市に分散して好結果を招いたのだから、サッカー・クラブのようにユース年代を取りこんだ下部組織までつくればさらに経営基盤が安定しそうだが、「甲子園」という一大産業があるかぎり、難しいか。
ついでにいえば相撲部屋も、東京に固まらずに地方都市を拠点にすれば、なんて思うが、こちらは「限界競技」になりつつあるだけに…。
八月十日 シニアの時代
四谷四丁目を歩いていたら、関東一高の二人のほか、早実の控え投手にも四谷四小~四谷中の地元出身がいるという懸垂幕が出ていた。
かれもやはりシニア出身だが、関東一高の二人とはチームが違っていて、杉並シニア。ほぼ地元の新宿シニアに較べて遠いから、情報の入りかたに時差があったらしい。
何はともあれ、三年前の四谷中学には三人も未来の甲子園球児がいたわけだ。しかもおそらくは野球部には入っていなかった、という状況が面白い。クラス対抗の野球大会とかあったら、すごい戦いになってそうだが…。
八月十二日 ユンケルとミカド
ネットでの無駄話で知ったトリビア。
アメリカに旅行に行った友人にきいたが、北米にもユンケル黄帝液があるのだという。
そうか、ユンケルがアメリカにも進出している関係もあって、イチローがそのCMキャラなのだなと納得。
それにしても黄帝、「イエローエンペラー」と訳しているのだろうか? 人種差別っぽい感じがするのはなぜ?(笑)
すると別の友人から、ヨーロッパには「ミカド」という菓子があると教えられる。グリコのポッキーの洋名だそうだ。
向うにはミカドという細い竹の棒を使って遊ぶ家庭ゲームがあって、ポッキーがその棒に似ているから、ミカドと名づけて売り出したらしい。
ここからただの妄想。
甲子園出場の京都外大西、じつは「京都外国人大学西高校」という校名の外国人ばかりの学校で、選手がみんなキューバ人だったら強いだろうにとか、馬鹿なことを考える。
暑い。
八月十三日 キャンディード
日経新聞に載る『キャンディード』の批評を書く。七日にオーチャードで観てきたもの。
カーセンらしい、饒舌かつ意地悪な演出。しかし、意地悪なやつでなければ表することのできない、作品への愛憎を取り混ぜた敬意。
書き切れなかった細部のこと。
日本人にはとても理解しきれないほど多種多様なパロディが仕掛けられていたようだが、わかったいくつかは好き。
まず、懐かしのSFドラマ『タイムトンネル』のタイムトンネルみたいなのが出てきた。奥中央の消失点を目指し、同じ図形が、小さくなりつつ無数に並ぶ。
本家は楕円で、舞台は四角いブラウン管の形になっているが、時空を超えて旅をするキャンディードには、まさにぴったりの装置。世紀半ばの子供たちにとっては、テレビそのものが時空を超える装置だったことも重ねているのだろう。
そして何度もタイタニックが登場するのだが、ウィキによれば『タイムトンネル』で主人公が時間旅行を始めるきっかけが、タイタニックに乗り合わせてしまった友人を救うためなのだそうだから、どうやらそれも重ねているらしい。もちろん、映画やミュージカルの『タイタニック』も入っているのだろうが。
キャンディードたちが絞首刑になる場面では、執行人がエド・マーロー(伝説的なニュース・キャスター)の番組しめくくりの挨拶、「グッドナイト・アンド・グッドラック」を執行の合図にした。これは噴いた。
「シェル・ショックで頭をやられたヴェトナム帰りが見つけた油田だから、社名はシェル石油にしよう」というギャグも、馬鹿馬鹿しくて好き。
初めの方に出る、ウェストファリアならぬウェスト・フェイリャーの領主の容姿はケネディ風。そればかりか声色と口調も、ちゃんとケネディの有名な大統領就任演説の真似だった。こういうコダワリも好き。
あと、映画『タクシードライバー』とか『フォレスト・ガンプ』など、さらに色々と重ねていたのだろうが、とてもつかみきれず。
二十世紀北米の消費生活への、深い愛着と激しい不信。
ところで公演プログラムには、一九五六年十二月のブロードウェイ初演の直前に、バーンスタインがニューヨーク・タイムズに寄稿したエッセイ「キャンディードかオムニバスか?」が転載されていて、面白かった。
新聞掲載は十一月十八日。バーンスタインはその一か月前の十月七日に、ABC系列で放映されたフォード社提供のテレビ・シリーズ「オムニバス」で、「アメリカのミュージカル」と題する番組のホストをつとめたばかりだった。
ヨーロッパ風のオペレッタからアメリカのミュージカルが生れる歴史とその特性を、演奏を交えつつ紹介する番組で、そこでバーンスタインは「アメリカのミュージカル」について、かなり独特の定義をしたのだ。
かれによるとそれは、ブロードウェイ・ミュージカルと同義なのである。だから舞台はニューヨーク、言葉もこの大都市のもので、そして音楽には、アメリカ独自の音楽であるジャズがとりいれられていなければならない。
ミュージカルの名にふさわしいのは、ガーシュウィンやポーターの諸作や『ガイズ・アンド・ドールズ』、そしてバーンスタイン自作の『オン・ザ・タウン』などである。
そうでないものはすべて、オペレッタになる。つまりハマースタインが歌詞を書いた『ショー・ボート』『オクラホマ!』『南太平洋』『王様と私』や、当時大ヒット中の『マイ・フェア・レディ』などの名作群は、ミュージカルではなくオペレッタだという。外国はもちろん、同じアメリカでも南部や西部を舞台にして方言を用いたら、ミュージカルではないのだ。エキゾチックな魅力、異郷の風土と社会の魅力で惹きつけるものは、すべてオペレッタなのである。
この分類は前述のように、一般的ではない。普通は右の諸作も、すべてミュージカル・コメディの範疇におく。
ところがバーンスタインは、そうしない。『キャンディード』もミュージカルではないことになる。プログラムの関西弁で訳されたバーンスタインの言葉を引用すると「これがオペレッタの一種であることは明白」で、「オペレッタとか、コミック・オペラとか、なんと呼ばれようと、それは俺らが決めることやない」
創作者としてのバーンスタインが面白いのは、初演早々に人気をえた舞台作品はすべて「ミュージカル」、つまりニューヨークを舞台にして、ジャズをとりいれたものだったことだ。『ファンシー・フリー』『オン・ザ・タウン』『ワンダフル・タウン』、そして『ウェストサイド物語』。
逆に何らかの意味で「エキゾチック」なものには、この『キャンディード』やホワイトハウスを舞台にした『ペンシルヴァニア・アヴニュー一六〇〇番地』など、不幸の影がつきまとっている。
カーセンが『ウェストサイド物語』をやったら、どんなものになるのだろう。
この作品の方は疑いの余地なく、不滅の名声につつまれているが、しかし現代では映画版の呪縛が強すぎて、クローズアップのできない実演では、観客が舞台の広さをもてあますことが少なくない。
それを新解釈で、饒舌に埋めつくした舞台を見てみたい。
私はまるで不案内なのだが、ブロードウェイでミュージカルの名作が再演されるときは、いまでもト書きどおりのオーソドックスな舞台だけなのだろうか。
八月十四日 早実のコンス
甲子園二回戦、早実と中京大中京の試合を見る。早実、点とりすぎ。
早実には安田権守という選手がいる。権守という名は「こんす」と読み、本人の祖父が「守り神になるように」とつけたのだそうだ。
なぜか高校野球には、ユースのサッカーよりも変った名前が少ない。
保守的な家庭が多いということなのかどうかは知らないが、そのなかで貴重な存在が二年で三番を打つこのコンス君。かれに与えた初回の死球をきっかけに、相手投手が我を忘れたようだった。
テレビだと応援の音声が抑えられているのでわかりにくいが、早実の応援団は七点とった一回と十二点とった五回の二回、コンバットマーチを使ったようだった。あれだけのビッグイニングだから、当然か。
さて、三回戦ではなんと、関東一高対早実の東京対決が実現。願ったり叶ったり。四谷中勢の直接対決まで見られれば愉しいが。勝敗は、関東一高の白井投手の出来次第という気がする。
八月十七日 東西東京対決
東京対決は関東一高が打ち勝つ。早実はやはり、前の試合で勝ちすぎたか。四谷中学OB対決は実現せず。早実の一人は甲子園では出てこなかったので、何か故障があったのかも。
八月十八日 東京終戦
関東一高は千葉の成田に敗れ、ベスト8で終る。神田明神より成田権現か。
八月二十日 映画『大番』のこと
先日CSで放映した映画『大番』四部作を観おえる。
とても面白かった。加東大介は昔から大好きな役者だが、その代表作。
それまで加東は脇役専門だったのが、一九五七年から翌年にかけて連続的に公開されたこの『大番』の主役、ギューちゃんこと赤羽丑之助に抜擢され、生涯最大の当り役になった。
加東の主演作というと、自らの兵役体験を元にした『南の島に雪が降る』も佳作で、とても好きな作品。体験者でなければ真似できない、指導できない日本兵の挙措動作の本物っぽさも魅力の一つなのだが、もちろん、なんたって役者と物語がいい。しかし、あくまであれは加東大介本人として出演しているわけで、役ではない。その意味で四作、合計七時間半の『大番』のもつ意味は大きい。
原作は獅子文六が同時期に週刊朝日に連載した小説で、愛媛県の田舎町の貧しい百姓の息子が東京に出て、兜町で相場師として浮沈をくり返しながら、ついに名と財をなしていくという、典型的な立志伝もの。
無学無教養、女にはだらしないが人に憎まれず、豆タンクのように精力的な商売でチャンスをつかむ主人公の造型が、見事にツボを押さえている。
そして、株は世の景気とそのまま連動するものだから、昭和初期の動乱と敗戦をへて朝鮮戦争にいたる時代を背景に、社会と個人の命運の変化をたくみに重ね合わせる物語がうまい。
こういうふうに経済を描いた小説というのは、それまで日本にはあまり例がなかったらしい。
山本夏彦だったか、戦前の一般家庭、勤め人の家庭は貯金も郵便局にするのが当然で、会社をやっている人以外、銀行にはおよそ縁がなかったと書いていた記憶がある。銀行でさえそうなら、株式はそれ以上に堅実とは無縁の、怪しい世界だったろう。相場師というのにも山師、バクチ打ちのような投機的印象だけがあったのではないか。
そんな妖怪的な印象が、戦後の大衆消費社会の進行で変化しはじめ、神武景気などの好景気もあって、手は出さないまでも証券業界への関心が高まっていく。そんな時代の読者に、「一歩だけ前」の題材を提供したわけで、原作が大ヒットしたのは当然だ。
映画も、ヒット作が必ず持っている、ワクワクするような活気が画面に充満しているし、配役が適材適所。
加東大介の主人公を支える、愛人で待合の女将が淡島千景。仕事面の女房役が仲代達矢。伝説的相場師で、今は没落して物乞い同然だが、主人公に貴重なヒントを与える「チャップリンさん」が東野英治郎(この人は私が何の映画を観ても「落魄した老人」の役ばかりなのが可笑しい)。
原作が途中の時点で映画の公開がスタートしたため、読者ばかりか、原作者までが加東や淡島のイメージに引きずられるようになって困ったそうだ。それくらい、役にはまっているのである。
さらに、個人的に嬉しかったのは、淡島千景演じる「おまきさん」の待合というのが、荒木町にあったという設定であること。まさしく窪地の底、階段の下に待合の建物がつくられているのだ。
基本的にはスタジオのセットだが、一場面ロケをした箇所があって、まだ三業地が残っていた、昭和三十年代前半の荒木町の姿が映っていた。
それから、明らかに水野成夫をモデルにした財界人を山村聡が演じているのだが、荒木町の芸者あがりの二号の家に住んでいる設定になっている。実際の水野も、四谷近辺のお妾さんの家に住んでいたそうで、ここまでモロに真似しちゃっていいのか、と心配になるくらい。
ウィキペディアによると、『大番』は一九六二年から翌年にかけてフジテレビ(水野のテレビ局だ…)が連続ドラマにしていて、そちらでは渥美清が主人公を演じ、出世作になったという。
たしかに渥美清も、この役にはピッタリだろう。観てみたいが、フィルムが現存するのかどうか。
二人のギューちゃん、映画の加東とテレビの渥美は、一九六一年製作の『南の島に雪が降る』のなかでは、短時間ながら共演していた。面白い縁。
うまいことに『大番』は、原作が小学館文庫で復刊されてまもない。原作にも興味が出たので購入。
獅子文六という作家自体も、往年の人気にもかかわらず、今は著作の大半が姿を消している人だが、その人となりにさまざまな点で惹かれるので、評伝『獅子文六の二つの昭和』(牧村健一郎著)を読んでみるつもり。
八月二十八日 本屋の平積み
曙橋の商店街に行く。ここは、四谷近辺の町では「住宅地の商店街」の雰囲気がある。
本屋も昔風の小型店なので、狭い面積に棚が高く立ちならび、本が所狭しとつまっている。今日は月末だから、中央の平積みスペースには、附録つきの女性月刊誌が何種類も、高く積み上げられていて壮観。ブランド小物を附録にするのが大ブームらしい。
学年誌その他で見慣れてきたからなのか、「附録つき平積み」の光景には、なぜか「本屋に来た」というワクワク感と安心感があって嬉しい。
時代がどんなに変っても、大型書店やコンビニにはない光景だからか。
八月二十九日 オランダの光学式録音機
少し前に、ネトピルの珍しい盤でもないかと思って、チェコのCDショップのサイトを覗いた。
思ったとおり、ネトピルの以前の録音などがあったので嬉しかったが、それ以上に気になったのが、『ターリヒ一九三九年ライヴ』という、二枚組。
ターリヒがチェコ・フィルとプラハの放送管弦楽団の合同オケを指揮して《我が祖国》とスラヴ舞曲の第二組曲を演奏した、一九三九年六月のプラハでのライヴなのだ。もちろん、世界初登場の貴重な音源。
勇んで注文して、今日届いた。とるものもとりあえず聴く。
演奏は素晴らしい。さらに、この演奏会がいかなる状況で行われたものかも解説書に詳述されていて、ターリヒがチェコ音楽界に占める歴史的位置の重要性について、大いに示唆を受けた。さっそく『レコード芸術』編集部にメールして、十一月号の「海外盤試聴記」に取りあげてもらうことにする。
ということで演奏とその経緯はその記事の方に書くことにするが、ほかにもう一つ、その録音のことがとても面白かった。これは記事に書ききれるかどうかわからないので、ここに書いてしまう。
このライヴ録音は、チェコには現存しない。電話線を使って放送を中継したノルウェーの放送局が録音を保存していたため、それを音源として七十年後に甦ることになったという。
録音に用いられたシステムは、フィリップス=ミラー録音機。アメリカ人技師のミラー博士が一九三一年に開発、オランダの電機メーカー、フィリップスが一九三六年に商品化したもので、当時いくつかあった、光学式の録音再生システムの一つである。
セルロイド製の専用フィルム「フィルミル」に針で音溝を刻んで録音し、非接触の光学式で再生するもので、二十五~八千ヘルツの音域をカバーし、十五分間の連続使用が可能だった。再生ノイズもなく、当時では磁気テープ録音よりも優れた、最高の録音方式だったという。
しかし機械は大変に高価で、燃えやすくて管理の大変なセルロイド・フィルムを使用するという難点もあり、導入したのは限られた放送局のみ。ノルウェー以外にはスイス、ポーランド、ルクセンブルク、ニューヨークのWQXR、そしてBBCくらいだという。
ドイツのオランダ侵攻後、英空軍がアイントホーフェンにあるフィリップスの工場を爆撃したことで供給が停止し、そのまま商品としての生命を終えたが、ノルウェーでは一九五〇年まで使用していたそうだ。
このCDで録音機の詳細を初めて知ったが、私などは、それとは知らずにその音をたくさん聴いているにちがいない。
最大の例は、オーパス蔵の相原さんが指摘された通り、戦前戦中のメンゲルベルクなど、一連のアムステルダム・ライヴである。フィリップスの本拠だけに、この機械が使用されたとみて疑いない。
どうりで、コンセルトヘボウのライヴはノイズが少なく、そして大曲がまとめて残っていたわけだ。
ニューヨーク・フィルやBBC交響楽団のライヴのなかにも、WQXRとBBCという二つの放送局が用いたものが含まれている可能性が高い。いずれ機会があったら、注意して聴いてみよう。
こんなものが出てくるなんて、やっぱりチェコは、古今とわずに要注目の国。
九月一日 獅子文六の小説世界へ
獅子文六の小説『大番』を、小学館文庫で読む。
まず、厚い文庫二冊で計千二百頁もあるのに、すらすら読みきれたのに感心。この人の文章の軽妙なリズムはすごい。
読点が多用されるため、初めはうるさく感じたのだが、読んでいるうちに「隙間」が目に入らなくなり、意味のとりやすさがきわだってくる。「待っている」を「待ってる」とするなど、「い」の省略癖も同様。
映画版よりも、株取引の実際や、主人公の仕事の具体的な内容がしっかりと書かれていてわかりやすい。
戦前の株取引は、現在よりはるかに投機的色彩が強い。その浮沈の激しさは、成り上がりの主人公の生涯を面白く物語るのに最適だし、前にも書いたが、株価くらい、政治経済の変動に敏感で、また即座に反応するものはないわけだから、満州事変以後の歴史的事件を、無理なくストーリーに織り込める。そして、手の届かない名家の美しい女性への永遠の憧れと、水商売の女たちとの身勝手な関係の好対照。週刊誌に連載中から大人気だったのも、納得である。
若いときは実用一点張りで吉原の色街に通うが、少し金ができて知恵をつけると芸者遊びになり、荒木町、さらに格を上げて赤坂や築地の一流花街へ。しかし戦後は、和風の形式主義をわずらわしく感じるようになり、気楽な銀座のクラブ通いに。現代では想像のつきにくい「女遊び」の実態と変化が描かれているのもありがたい。戦前に鳩森にいた文六は、荒木町をよく知っているのだろう。
さらに、主人公の故郷である愛媛県の鶴丸町なる田舎町の様子と風俗も、じつに魅力的。実際の名は岩松町(現在は宇和島市津島町岩松)といい、牧村健一郎の『獅子文六の二つの昭和』によると、文六の二番目の妻の故郷で、戦後の混乱を逃れて昭和二十年冬から三年間、文六の一家が暮らした場所だという。
横浜と東京しか知らない都会人の文六が、初めて暮らした田舎町。その南国の気風と習俗を文六は深く愛するようになって、作品にとりいれたのである。
先日観た映画版の鶴丸町は、実際にこの岩松にロケしたもの。この町そのものを舞台にした獅子の作品には、ユーモア小説の傑作とされる、『てんやわんや』がある。面白そうなので買ってみる。
獅子文六その人の人生にも、ますます興味がわいてきた。少し前に読みちらした大佛次郎とも近いものを感じる。ともに国際色豊かな横浜生れのインテリで、特にフランス文学の造詣が深いのにエリートコースを外れていて、昭和期の大衆小説の名手として大成功しながら、屈折した内面をもっている。
大佛が獅子文六の名を知ったのは、ある日突然にその著書が本人から送られてきたときのことで、「こういう文学を少なくとも、あなたはわかってくれるでしょうから」という献辞と署名が、フランス語で書かれていたという。
牧村健一郎は、この本を昭和十一年発行の文六最初の長編小説『金色青春譜』と推測している。これは鎌倉や軽井沢などの避暑地を舞台に、私大卒で仕事にあぶれた若者と有閑マダムたちが展開する軽快なコメディだそうだ(題はいうまでもなく、『金色夜叉』のもじり)。
フランス語でそういう献辞を書いたことは、文六が、同時代の「モダン」な通俗小説の書き手としての大佛に抱いていた、親近感のあらわれだろう。
ということで、先の『てんやわんや』に加えて、自伝的作品の『娘と私』、そして以前から気になっていた『海軍』も買うことにする。『海軍』は戦時中の大ベストセラーだが、それゆえに戦争協力小説として、敗戦後の文六の人生に長く暗い影を投げかけたものだ。
しかしすべて絶版なので、古本で文庫を注文。そんなに古いものでもないのにそれなりの値段がついている。絶版後も多少の人気があるということか。
九月四日 『大番』のタネの一部
獅子文六話の続き。
文六の基本は私小説ではなく、創作小説の書き手だったが、実体験をタネにふくらませるのがうまかったようだ。
『大番』のなかに、主人公が終世憧れ続ける、可奈子という女性が出てくる。故郷鶴丸町の第一の素封家の令嬢で、旧藩主の華族、鍋島伯爵家に嫁ぐが、海軍士官の夫は戦死、戦後は財産の大半を失って、大磯に逼塞することになる。映画では原節子が演じ、夫の伯爵は、片山杜秀さんが偏愛する平田昭彦だった。
実際の文六の方はというと、岩松にいるときに借りて住んだのが町の素封家の屋敷の離れで、好人物の当主と親しく交流した。東京に戻って数年後、娘が外交官と結婚するが、その人物は岩松の旧藩主、宇和島伊達家の、その分家の出だった。また、二人の妻に先立たれた文六の再々婚の相手は、子爵の娘で、松方正義公爵の孫の未亡人。戦後は大磯に暮らしていたという。
自分の再々婚も娘の結婚も、昭和二十六年。『大番』はその五年後に始まる。実体験から得た知識を、巧みに、そして読者がよりわかりやすく共感しやすい、面白い物語へと翻案したらしい。素晴らしい手腕だと思う。
九月六日 帰れなかったドイツ兵
また獅子文六の話。
牧村健一郎の書いた評伝『獅子文六の二つの昭和』を読んでいて、とても驚いたことが一つ。
文六が一九六九年の死の直前に書いた手記に、戦時中に箱根にいたドイツ兵たちの話を描きたいという、実現しなかった構想があるそうなのだ。
これは以前に可変日記で触れた、一九四二年に横浜港で爆沈したドイツの仮想巡洋艦トール号と輸送艦の、乗組員の生存者百人のことである。
かれらは終戦まで、箱根芦之湯の温泉旅館、松坂屋に軟禁状態にあった。松坂屋へ滞在したときに主人からその話をきいた文六は、老いによる筆勢の減退や体力の低下を忘れて、
「猛然と創作欲が湧いた。大ユーモア小説となる材料で、久し振りに、そういう仕事がやってみたくなった」
若く頑健な身体をもてあますドイツ兵たちと、戦争で男の減った温泉街に暮らす女たち。そこにはさまざまな珍騒動が起き、二十八人の女性が妊娠して、町の大問題にもなったという。
文六に興味を持つ以前から、私が興味を持っていた話を、文六が書こうとしていた。無関係だと思っていた二つの話題が、突然に連関する。
こういう瞬間は、心底愉快。
この箱根のドイツ兵については最近、『帰れなかったドイツ兵』という荒井恵美子のドキュメンタリーが光人社NF文庫で出ているので、読んでみようと思ったところだった。しかしそれはそれとして、ユーモア小説の大家、文六が描いていたとしたら。読んでみたかったもの。
前にも紹介したが、漫画家黒田硫黄の『あたらしい朝』も、かれらをあつかった話である。
黒田がこの逸話を知ったのは、箱根にある「アルカリ硫黄泉という湯が出るところ」の旅館に、エネルギー補充に行ったさい、館内の展示室にあるドイツ兵たちの写真と説明を見たときだという。
その旅館こそ、文六も泊まった松坂屋にちがいない。
さらにこの旅館をめぐっては、ここをモデルにして西武と東急の「箱根戦争」を描いた『箱根山』という作品を、文六はすでに書いているそうだ。
これも面白そう。松坂屋にもいつか行ってみたいが、ひとまずは『箱根山』を読みたい。調べると九〇年代にも文庫で再刊されていたらしいが、いまは絶版で古本も高い。安いのが出てくるのを待ってみる。
九月十日 『てんやわんや』と京都
獅子文六の『てんやわんや』を読みおえる。
これはほんとうに面白い。二十九歳の独身男、犬丸順吉という主人公が、敗戦四か月後の昭和二十年十二月、関東から愛媛県の「相生町」なる田舎町に移って過ごす、一年間を描いたユーモア小説。
その相生町の人々、風俗、景色の描き方がすばらしいのだ。
戦争の被害もなく、豊かで陽気な、南国の別天地は、読者をなんとも愉しい気分にさせる。読んでいる間じゅう、その一隅に自分の身があるような気がした。作品の中に小宇宙が出現している。こういう仮想現実的な快感を味わうのは、久しぶりだった。
九月一日の日記で触れたとおり、文六の二番目の妻の故郷で、昭和二十年十二月から三年間、文六が妻と娘の三人で暮した、岩松町がそのモデルである。
『大番』では鶴丸町という名で、主人公の故郷になっていたが、『てんやわんや』は東日本の都会人が訪問する設定だけに、未知の土地への他県人の驚きが、わかりやすく描いてある。
そして、その驚きがやがて深い親愛に変っていくさまが、巧みに読者の共感を誘う。人気のよさが、闘牛、鉢盛料理、山奥の村のマレビト信仰、燈籠焼き、大鰻、秋祭り、牛鬼といった行事をとおして、明朗に描かれていく。
この「別天地」の物語の愉しさは、時代を超えて読まれるだけの力をもったものだと思うけれども、当時の日本全体の状況、すなわち敗戦直後の大混乱と荒廃が、相生町の魅力をいっそう高める、効果的な背景になっていることはいうまでもない。
主人公は、元議員の出版社社長の、書生あがり。戦時中は、社長の伝手で情報局に務めていた。大した仕事はしていないが、下っ端なりのうまみはあった。そのため、戦犯にされるぞと社長に脅されて、身を隠すために、社長の故郷に近い相生町へ逃れることになる。
一時的に身を置いていた湘南の社長の別荘から、沼津発の汽車と船で愛媛へ向うが、延着はあたりまえ、何日かかるのか見当もつかない、「旅行の困苦が、徳川時代に勝る」敗戦直後の旅行である。
この旅の描写は真に迫っているが、これはまさしく昭和二十年十二月に疎開先の湯河原から妻と娘を連れて岩松に向った、五十二歳の文六の体験そのものなのだろう。自身、戦時中に小説『海軍』を書いたために戦犯になるかもという不安を抱えての岩松行きだったから、その気分が主人公に重ねられている。
それはまた、空襲の被害が東京周辺に留まらないことを、その目で確かめていく旅でもあった。
「静岡や、浜松の惨憺たる焼跡」に続いて、名古屋では「車窓に名古屋市の廃墟が展開され、金の鯱も、天守もなくなった城が、遠く見えた」。
「大阪、神戸の焼跡は、暗夜と、車内大満員のために、よく見えず、焼跡はもう飽きたから、見えない方がいい」
そうして岡山県の宇野から四国高松へわたり、汽車で宇和島駅へ。
「やっと全二日間の汽車旅に解放されて、改札口へ行くと、私は再び沼津駅へ舞い戻ったのではないかと、錯覚を起こした。夜目にも、ナマナマしいバラックの駅なのである。
まさか、私の旅の最後の駅――この四国の果ての町まで、戦禍が及んでいようとは、夢にも思わなかった。孫悟空が億千万里を飛行したつもりでも、やはり仏の掌中にあった――あの驚きと、落胆とが、私の心を襲ったのは、いうまでもない。日本の狭さ、と今度の戦争の大きさが、痛切に胸へくると共に、こんな地方に隠れたって、果して大網を脱れうるかと、心細くなってきたのである」
そして宇和島からバスで二時間。険しい山道を登って峠を越すと、眼下に盆地がひらけていた。
「それは、山々の屏風で、大切そうに囲われた、陽に輝く盆地であった。一筋の河が野の中を紆り、河下に二本の橋があり、その片側に、銀の鱗を並べたように、人家の屋根が連なっていた。いかにも、それは別天地であった。あの険しい、長い峠を防壁にして、安全と幸福を求める人々が、その昔、ここに居を卜した――そういう感じが、溢れていた」
四国の果ての宇和島までに及んだ戦禍と人心の荒廃を脱して、陽に輝く別天地へ。この、暗から明への見事な描写があってこそ、相生の魅力が生きてくる。
ところで、暗い焼跡ばかりのこの旅行のなかで、一瞬、異彩を放つ町がある。
「京都――一軒も焼けていない大都市。ツキアイというものを知らないのは、損であるか、得であるか、しかし、線路の紅殻塗りの家から、幸福そうな灯が漏れていた」
京都は無傷という事実を、今さらながらに強く感じる一節だった。京都は、戦後の焼跡だらけの日本において、特別の意味をもったのではないか。
そしてそれは、いまも継続している気がする。
『てんやわんや』とほぼ同時期に書かれた、大佛次郎の『帰郷』においても、京都は特別の意味をもっていた。
爆撃で焼けた横浜などは、
「安楽にしている者は少ない戦後の町の生活で、大部分はバラック小屋同然の板の家なのである。生きる苦しみが各戸に充満して、赤ん坊が泣き、女が甲高く叫び、配給の行列が続き、どうにも出来ない問題が山のように積もっているはずなのだ」とあり、
「日本中、戦災を受けたどこの都市へ行っても、同じことだろうが、この街には個性なんて、まだ出来ていないのだ」
と画家が語る台詞もある。
しかし、京都は違う。
「戦争の果てに日本に残ったのは、実に京都、奈良だけだといってもよいのである」
「町なかに柳の老樹が幅を利かせて、八百屋の店の屋根などに、かぶさるように枝を垂れているのを見かけることがあった。古い日本の町で、それも戦災を受けなかったところでないと現在は見られない風景なのである」
「古い屋並が揃っている裏通りを見つけ出しては、懐かしい心持ちを湧かしていた」
『帰郷』は大佛の代表作の一つで、昭和期には幅広い層に読まれ、二回も映画になっている。個人的には、冒頭の戦時中のマラッカの場面の見事な描写――大佛は、同盟通信の嘱託として南方諸地域を視察した昭和十八年後半に、実際に占領下のマラッカを見ている――に較べ、戦後日本の部分は、「偶然の出会い」を多用する大佛の癖が、物語の真実味を削いでいるのが残念だが、全体として優れているのはいうまでもない。
京都はマラッカ、東京、鎌倉とともに重要な舞台となる。この作品の取材で訪れた大佛は、以後は毎年の滞在が習慣となり、次作の『宗方姉妹』にも登場させる。大佛自身が、戦後日本で京都の魅力の虜になった、その一人だったわけだ。
『帰郷』のクライマックスは、その京都の、金閣寺の場面である。
ここでは『てんやわんや』の一節と逆のことを感じずにはいられない。
――この金閣が、『帰郷』のわずか二年後、昭和二十五年に焼失してしまう、昔の金閣なのだということを。
焼けなかった京都が特別の意味をもちはじめた戦後に、金閣は闇夜に紅蓮の炎を巻きあげて輝き、焼け落ちた。
三島の『金閣寺』を、久々に読みなおしてみようと思う。
ところで『てんやわんや』と『帰郷』は、単に同時期という以上の因縁をもっていることを、牧村健一郎の『獅子文六の二つの昭和』で知った。
文六は昭和二十二年十月に岩松から東京に帰ってきて、翌二十三年春から戦後最初の新聞小説を毎日新聞に書くことにした。ところが連載一か月前の三月、戦争協力の容疑により、公職追放の仮指定を受けてしまう。本人と周囲が奔走して異議申立がとおり、指定は解除されたのだが、この騒動のために連載は半年間、延期になった。
その穴埋めに急遽書かれたのが、大佛の『帰郷』だったのだという。そしてその終了後、同年十一月に始まったのが、『てんやわんや』なのだそうだ。
獅子と大佛、しばらくは読み続けることになりそう。
九月十一日 ホール落語
落語を日経ホールで聴く。
いつかナマで聴きたいと思いつつ、機会がなかった。覚えているのは、ある高校の学園祭で落研(?)の人がやっているのを見たくらい。プロのは聴いた記憶がない。
で、ふだんは演奏会でお世話になっている日経ホールから、なぜか落語にご招待いただいたので、これは縁と。
三遊亭圓歌と桂米團治の二人会。
とても愉しかった。テレビに較べると舞台は遠いし、残響がふえて聞きとりにくい部分も出てくるのだが、周囲の人々と笑いを共有しながら味わう演者との相互通行の感覚は、ナマならではのもの。
「山のあなあなあな」の圓歌は八十一歳、現代落語界では重鎮である。
米團治は、米朝の息子。圓歌と米朝は若いときから親交があるそうで、圓歌は花をもたせようというのか、トリを年下の米團治に譲っていた。
なお、ホール落語でも寄席と同様、演目の予告はない。落語家が最後に自分で告げるだけ。プログラムには出演者の脇に括弧のついた空欄があって、そこに客が自分で書き込むようになっている。
テレビ、ラジオやCDでは考えられない、何が出るのかわからない面白さ。珍しい噺を突然に取りあげたときとか、通にはたまらない瞬間なのだろう。
・桂まん我 野ざらし
・三遊亭圓歌 中沢家の人々
・三遊亭小円歌 三味線漫談(先代文楽や志ん朝、志ん生、三平などの出囃子の再現あり)
・桂米團治 七段目
圓歌の「中沢家の人々」は、麹町の家に自分の両親、先に亡くなった最初の妻の両親、そして後妻の両親、老人六人と一度に同居した経験を落語にしたもの。
近年はこの噺しかやっていないというが、さすがにとても可笑しい。
今日は三十五分だったが、完全版は六十五分あるそうで、DVDかCDが欲しくなった。
同年代の先代林家三平ほどではないにしても、やはり古典には強くない人だから、噺家としての位置づけは難しいのだろうが、話芸そのものは見事なもの。
米團治はそれを受ける形で、マクラを「中川家の人々」(本名が中川明)として父米朝との話をしつつ、芝居狂のドラ息子が登場する「七段目」へ。
歌舞伎の名セリフがいくつも出てくるが、團十郎のあの鼻にかかった声色の真似をしたりして、これも笑った。
米朝と自分との関係を、噺のなかの謹厳な父とドラ息子との関係になぞらえてあるのが、自虐的でいい。
なるほどと思ったのは、圓歌を聞いているときにはビートたけしのしゃべりを思い出し、米團治を聞いているときにはさんまの一人小芝居を思い出したこと。
古典・新作にかかわりなく、落語の話芸は漫談の基本なのだろう、やっぱり。
演題が事前に伏せられているのと同じく、拍手が短いのもよかった。幕が降りきったら、それでパッとおしまい。
歌舞伎もそうだが、このあっさり感が古い時代の日本の拍手なのである。
ご承知のとおり、クラシックの拍手は出たり入ったり、やたらに長い。心からの喝采ならいいが、なんとなく形骸化していることもある。ときにはアンコール目当てみたいな雰囲気もあって、複雑な気持にもなる。
それに較べて、本番の間だけがすべてという和風の割切った感覚は、これはこれでいい。歌舞伎の客席からの掛声などは、本番中に凝縮して練り上げられてきた、観客側の「芸」なのだろう。
ともあれ、落語を聞く機会を増やしたいと思った。
九月十二日 ロイヤル・オペラと横浜
横浜の神奈川県民ホールでロイヤル・オペラの《椿姫》。
ヴィオレッタがゲオルギューからヤオに交代ということは事前に発表されていたが、開幕前にわざわざオペラ・デレクターの女性が出てきて陳謝。
一九八三年に初めて欧州に行ってコヴェント・ガーデンで《トスカ》を見たさい、そのときもパヴァロッティがアラガルに交代して、開幕前にディレクターらしき人がしゃべったのを思い出した。
当日の朝、天井桟敷の券を買いに劇場前の券売所まで行くと、予想に反してすんなりと買えてしまい、おかしいなと思ったら、パヴァロッティ降板がすでに発表されていたのである。
アラガルはその時点で知名度もある、地力のある歌手だし、お客も、こういうときはリキをいれて声援するので、かなりの熱唱となり、結果的にはけっして損をしなかった(ちなみに外題役はジョーンズ)。パヴァロッティがそのまま歌っていたら、当日券を入手できなかった可能性が高かったのだから、むしろこの交代は感謝すべきことだったろう。
また、そのおかげで、まだ平土間と上階(四階以上だったか)の入口が別で、内部も行き来できないようになっていた時代の、古いコヴェント・ガーデンに行く機会を得られたのだ。
「この席の入口はあっちだ」と、正面階段上の係員に、階段下の脇の小さなドアを教えられたときは驚いたし、幕間に下の様子を見にいこうにも通路がなく、四階だったかのスタンドでコーヒーを飲むしかないと知ったときには、なるほどこれがイギリスの階級社会の一端かと、身をもって納得したものだった。
この歌劇場で冷遇されていたグッドオールは、天井桟敷のさらに上の清掃員用の部屋に、レッスン室をあてがわれていた。そこでワーグナーを教えるので「ワルハラ」と綽名されたという話がある。
この話を読んだとき、普通の劇場以上に天井桟敷が「差別」されているコヴェント・ガーデンの、そのさらに上階(エレベーターなし)というのだから、それがどのような扱いを意味するものか、現場を知っていたおかげで、容易に想像することができた。
その後、パリ、ベルリン、ミュンヘンなどいくつかの歌劇場をまわったが、上下階に連絡のない建物は、他にはなかった。この「差別」は、さすがに英国内でも評判が悪く、現在は改修されたそうだが、いまでもこの歌劇場というと、この構造とパヴァロッティ降板のことが強く印象に残っている。
それから二十七年後のロイヤル・オペラ来日公演でも、やはり交代劇とディレクターの釈明。
しかしそれ以上に驚いたのは、第二幕の開幕前のこと。再びディレクターが登場してきた。ヤオが不調のため、アイリーン・ペレスに交代するという話。たしかに大アリアのカバレッタで完全に抜けてしまう音があったとはいえ、降りるほどに悪いとは思わなかった。
さてそのペレス、歌手としての柄は小さめではあるけれど、スコットを思わせる集中力の強い響きと歌は、好感度の高いものだった(帰宅後に調べたら、数年前にザルツブルク音楽祭プロダクションの《フィガロの結婚》でこの人の伯爵夫人を聴いていることが判明したが、どんな歌だか、まったく覚えていない…)。
終演後は、近くのホテルニューグランドで夕食。
現在は隣にニューグランドタワーが増築されているが、本館はほぼ戦前のままに残されている(きっと米軍は占領後に接収することをもくろんで、当初から爆撃を禁じていたのにちがいない)。
戦前の洋風建築らしくコンパクトな印象だが、品のよさはさすが。現在のフロントはタワーの方にあるが、往時のフロントとロビーは、本館の玄関正面の階段を登った二階にあり、現在は宴会場の受付になっている。この二階は天井も高く広々としていて、実にいい感じ。
一九三〇年代の大佛次郎はこの本館の三一八号室を仕事部屋として、長逗留していたという。客船が欧米旅行の花形だった時代の国際色豊かな横浜でも、特に外国人客の多いこの高級ホテルで、まだ見ぬ西洋の匂いに触れていたのだった。
一九四〇年に単行本化された『新樹』という短編には、名前こそないが、それだけにこのニューグランドそのものだとはっきりわかるホテルが登場する。「大体このホテルには、外国航路の汽船の送迎の客が一夜を泊るか春秋の根岸の競馬の折に上方筋の神戸、大阪の客が集まってくる程度で、日本人の長逗留の客は珍しかった。殆ど全部が外国人である」とあって、戦前の客層がよくわかる。
正面の大階段は「ホテルの中の大通りといつてもよい」とあって、「大通り」には「メインストリート」とフリガナがされている。
さらに主人公の「初老に近い品のいい紳士」は、大佛と同じ三一八号室に、独りで長逗留している設定だ。
大佛の現代作品にはこのように、本人の周囲を活用しているものがある。『夜の真珠』や『明るい仲間』といった中編では、酒場マスコットが主な舞台となるが、これも日本大通りの近くにあった、大佛行きつけの実在の店であり、そのマスターや四匹の飼い猫、常連客たちが、ほとんどそのままの容姿と性格で作品に登場している。
だがこのマスコットは、四匹の猫とともに一九四五年五月の横浜空襲で灰になってしまって、残念ながら現存しない。そこで代りに、往時の片鱗をとどめるニューグランド本館で「大佛次郎の横浜」を想う。
九月十四日 『海軍』の魅力と影響
獅子文六の『海軍』を読みおえる。
真珠湾奇襲攻撃のさい、二人乗りの特殊潜航艇五隻に乗って真珠湾に潜入、戦死して「軍神」となった九人の若者の一人、谷真人中尉(モデルは横山正治。死後、二階級特進して少佐)の、二十二年の生涯を描いたもの。
正確には獅子文六の、ではなく、岩田豊雄の、である。これを書いたとき、作者は戯作者的なペンネームを使わずに、あえて本名を用いたからだ。
かれの執筆歴のなかでも重大な意味を持つ作品らしいだけに、もともと、いずれは読む気でいた。ところが、あることがあって、何をおいても最優先で読もうと決意した。
あること、というのは、『てんやわんや』の新潮文庫版の巻末につけられた評論家、大井広介による解説のなかに、こんな一節を読んだことだ。
「『悦ちゃん』『南の風』『おばあさん』それぞれ受け、戦争中は『海軍』を書いた。私は『海軍』を読んでいない。読んでいたらからんでいたかも知れない。まあ素通りしたがいいだろう」
なんとも、いやな書きかた。
この解説には、昭和二十六年六月という日付がある。講和前の、戦後民主主義の時代だ。いかにもその時代らしい、きめつけともいえる。「私は大衆に追従せぬ貴族主義者を持って任じている」というこの人、本名を麻生賀一郎といって九州の炭鉱王、麻生太吉の孫であり――麻生太郎は従兄弟の子にあたる――坂口安吾によると戦前から「堂々たる大邸宅」に住んでいたというこの人が、戦時中にどんな生活をしていたかは知らない。
ただ、こういう、自分は戦争に批判的だった、という意味の物言いをする人が戦後には意気さかんで、それがそのまま戦後育ちの、戦時中にはまだ子供だったから自分は無実で、一方的な被害者だ、というような理屈を振りかざす世代に受け継がれていったことに、いやな感じを受けるだけである。
一方、『海軍』の作者文六は、当事者であることから逃がれようがない。
戦記物というよりも、海軍兵学校の生徒生活を主題にしたこの小説は、昭和十七年後半に朝日新聞朝刊に連載され、即座に大評判をよび、単行本化されて大ベストセラー、翌十八年の大詔奉戴日(十二月八日)には映画版が公開されて、やはり大ヒットした。
牧村健一郎の『獅子文六の二つの昭和』によると、哲学者の木田元が二十年春に兵学校に入学した背景には、この『海軍』の影響もあったという。
中学時代に新聞での連載も単行本も読み、さらに映画も観た木田は、
「『海軍』で海兵にあこがれたのは確かです。海兵の友人たちも『海軍』に感激していた。この小説の影響力はものすごかった」と語ったそうだ。
そうした小説を書いたことに、戦後の文六は消えない苦しみを感じていた。
文学座時代の神山繁があるとき、
「『海軍』を読み、映画を見て感激した若者が海軍を志願しましたね」
と話しかけると、いつもなら気の利いた答えをすぐに返す文六が、このときにかぎって、黙って目を伏せるだけだったという。
その『海軍』。作品そのものについての感想をいえば、きわめて出来のよい、見事に美しいもの、というほかない。
べつに、狂った時代の読者にしか理解できないような、特殊な物語ではない。普通に、設定も人物も物語もとてもうまく書けた、読者を引き込める作品なのである。いま読んでも、読者はそこに描かれた組織と個人との、清々しく美しい関係に感激させられるはずだ。
ただ、その作品世界がその出来のよさゆえに、戦時という特殊状況において、現実とあまりにも強く結託した。それが結果的に大いなる不幸となり、著者にも関係者にも読者にも、深い心の傷跡を刻むことになった。
一人の、わずか二十二歳で戦死した下級将校の生涯を描いただけなのに、題名は大仰にも『海軍』。これが、作品の主題を見事にいいあらわしている。
帝国海軍の、歴史や戦闘全体が扱われるわけではない。一人の人間を海軍軍人たらしめる、組織全体の精神、いわゆる「ネイビー・スピリット」が、一人の若者の生と死を通して描かれるのだ。
その精神の象徴にして、源泉となるのは、江田島の海軍兵学校での教育。
小説のほぼ半分は、鹿児島生れの主人公が成長して、兵学校の受験を突破して入学、そこで教育を受け、卒業して、ハワイに練習航海するところまでに割かれている。なかでもその主眼は、兵学校での生活だ。
「校内に入れば、朱と白の生徒館、緑の大芝生、遠く鬱蒼たる松並木を透かして能美島の山影――まず、その環境の美しさに驚く。その環境の塵一つ止めぬ清浄さに驚く。その中に、誰一人佇んだり、逍遥している者のないのに驚く。やがて、白い作業服を着た生徒たちが、汚れなき童貞の挙止を以て、一糸乱れざる規律を行動していることに驚く。どこやらか、鐘の音が聴えてきそうな錯覚を起す。戒律的なもの、童貞的なもの、没我的なもの――環境と人間のすべてに亘って、トラピストの院内に入ったような印象を、受け勝ちなのである」
この、修道院や禅寺のような清浄峻厳な環境で、信仰ではなく、軍人としての信念を鍛え、磨いていく若者たち。
この作品の特徴、そして面白味は、主人公のその後、つまり少尉に任官して、本物の軍人になってからの生活や訓練、さらに、特殊潜航艇の艇長となって真珠湾攻撃に参加し、戦艦を撃沈し、生還かなわず戦死するあたりの細部を、ほとんど描いていないことにある。
戦時中のため、軍人生活の実際も訓練も、特殊潜航艇そのものも真珠湾攻撃の前後も、すべて機密事項でわからないことだらけ。たとえわかっても書くことを許されない状況だったので、文六は、主人公自身の視点からその様子を描くことを、断念したらしい。
代りに、主人公の幼なじみで親友、しかし健康に恵まれずに兵学校受験に失敗して中学も中退、家出して画家になろうとする副主人公、牟田口隆夫の目から、その部分は語られることになる。
苦肉の策だったのだろうが、結果的にはこのことが、物語の効果を増すことになっている。
つまり、多分に文六自身が投影されているらしい副主人公の目から主人公を描いたことで、初めて主人公が魅力的な、女も男も惚れずにいられない人間性を獲得できたからだ。
友情に厚く、純粋で、自己犠牲を厭わず、しかし「サイレント・ネイビー」の伝統に従って、任務のことは一切語らない、信念の男。
人間的魅力というのはあくまで他人が判断するものだから、視点が交代したおかげで、主人公のそれが明白になる。
同様に、死者のことを語れるのは、生き残った者たちだけなのだ。死者は自らを、自らの死を語り得ない。
語り部となる副主人公は、作者と、読者の代理となるのである。ここのところが実にうまく書けているので、同時代の読者に大きな影響を与えたのは、当然の結果に思えるのだ。
そして、後世の読者である私もまた、影響を受ける。
といっても、もはや若くもないし――偶然にも『海軍』を書いたころの文六とほぼ同年配になっている――子供もいない。それに、自分であれ子供であれ、誰かを入れようにも、もはや海軍兵学校は存在しない。
せめて、もう少しいろいろ知りたい。ということで、文六が『海軍』のあとに書いた『海軍随筆』、それに映画版のVHSビデオ(DVDにはなっていない)などを手に入れることにする。
それから、外からではなく内部の、つまり、兵学校生徒だった人の回想も読みたい。手近なところで立ち読みしたら、豊田穣が三四三航空隊の飛行隊長、鴛淵孝の生涯を描いた『蒼空の器』に、兵学校時代のことが書かれていた。
豊田と鴛淵は兵学校出身、六十八期の「同期の桜」で、『海軍』の谷真人(横山正治)の一期下だから、ほぼ同年代である。ちょうどよい。
というわけで、『蒼空の器』を買ってきちんと読むことも決定。
九月十六日 真人が行く、真人が行く
映画『海軍』を観る。
獅子文六の小説『海軍』は二回映画化されているが、これは昭和十八年製作の一回目の方で、田坂具隆監督による松竹映画(なお二回目は、三十八年製作で北大路欣也主演の東映映画)。
昭和十八年十二月八日、開戦二周年を記念して公開された。一年前の同日には山本嘉次郎監督の東宝映画『ハワイ・マレー沖海戦』が封切られており、それに続く戦意高揚映画の大作。
まず、配役のこと。
主人公の谷真人(演じたのは山内明)の中学時代の恩師を、東野英治郎が演じていたのが面白かった。戦後の映画では落魄した役ばかり私が観てきた東野が、敗戦前の、落魄前の姿をやっと観せてくれた(笑)。配属将校役が笠智衆というのもいい。全体に重苦しいこの映画のなかで、かれの出演シーンだけは剽軽さがあって楽しくなる。また、副主人公の牟田口隆夫(演じるのは志村久)の父は、小沢栄太郎。
戦後の映画やテレビでおなじみの東野も笠も小沢も、このころから既に「立派な大人」の役をやっていたのだ。当時はまだ、四十歳前のはずである。現代劇をやれる新劇系の役者の歴史が浅く、ヴェテランがいなかったこともあるのだろうか。主人公の母親を演じる滝花久子(田坂監督夫人)にしても、実年齢がまだ三十六歳とは思えない、老けた雰囲気。
さて、映画自体。平野国臣の和歌「我が胸の燃ゆる想いに比ぶれば煙は薄し桜島山」をカンタータ風に合唱で歌わせて(音楽は内田元)、煙を吹く桜島で始まるあたりは重厚で、期待をもたせる。
しかし、その後はもう一つ。
真珠湾奇襲とその大勝利が起した国民的昂奮を受けて生み出された傑作が、映画では『ハワイ・マレー沖海戦』であるとすれば、小説では『海軍』といえる。それを映画にして、『ハワイ・マレー沖海戦』の感激をもう一度、ということだったのだろうが、正直、そこまではいかなかったようである。
ただし、現存するフィルムはGHQによる接収などの影響で、ラストの約二十分が失われている。だから私の感想は、あくまで途中までのものにすぎない。
『ハワイ・マレー沖海戦』の成功は、ストーリーの破綻、浅薄な人物描写などにお構いなく、航空機と空母と特撮を中心に、映画としての、映像としての効果を、ひたすら追求した点にあった。『海軍』の場合は、原作が存在することが足かせになったようだ。
ストーリーをひどく中途半端にしか追えていないことが、原作好きにとってはもどかしい。
まず、江田島の海軍兵学校は現物を撮影しながら、機密保持のためなのかどうか、生徒のシーンがとても少ない。
校庭で輪形になり、速足行進でぐるぐる回る軍歌演習の場面くらいだが、これには規律だった動きの美しさは少ない。
カッター競漕の場面もあるが、これは『ハワイ・マレー沖海戦』の予科練の場面にも出てきたから、新味がない。原作にある通り、江田島名物の「棒倒し」を撮影してほしかった。
文六は戦後の『娘と私』のなかでも、
「私は、今でも、あの学校のことを、忘れられない。あのような純白で、清冽な雰囲気を、曽て、いかなる学校でも、感じたことはない。規律嫌いの私が、規律の守り方、守らせ方を、あんなに美しく感じたことはない」と、愛惜を込めて書いているが、残念ながら画面からはその清冽さを感じにくい。
副主人公の牟田口が、ただの脇役になり下がってしまい、主人公ばかりが描かれるのも、原作の妙味を損っている。もっとも、ビデオのケースには、本編にない潜水学校での牟田口のシーンのスチル写真が載っている。時間の都合でカットされたのか、それとも、失われたラストの巻にあったのか。
それ以外も、描写をかなり端折っているのだが、対照的に、やたらに多くて長いのが、鹿児島の旧跡に参詣する場面。東郷平八郎や大山巌の生誕地、島津斉彬を祀る照国神社などにお参りして、頭を下げるシーンが断続的に何度もある。
主人公が中学生、兵学校生徒、そして軍人と進むにつれ、参拝の姿勢が美しくなっていくことでその成長を描こうとしているのかも知れない(生涯最後の帰郷で、東郷平八郎の墓所に詣でているのは暗示的だ)が、あまりにくどい。
もっとも、こんな場面が多くて重苦しいのは、ガダルカナル島撤退、山本五十六戦死、アッツ島玉砕などが続いて、戦況の厳しさが国内でも隠せなくなった、公開時期のせいもあるのだろう。
こんなふうに不平ばかりを並べつつ、私がなおこの映画への希望を捨てないのは、失われたラストへの期待である。
手元の松竹製のVHSビデオは、真珠湾に潜む谷真人の特殊潜航艇が、空襲終了後に浮上し、潜望鏡で湾内をのぞき、「ちきしょう、アリゾナ型が一隻まだ残ってやがる」とつぶやく場面で、唐突に終る。
戦時中は、戦艦アリゾナを撃沈したのは特殊潜航艇の魚雷攻撃だと信じられていた。だからこれを撃沈、その戦果と戦死が日本で発表され、海軍葬へ、と場面がつながっていくはずだ。
ビデオは百十四分だが、ウィキペディアのこの映画の項には百三十二分とあるので、十八分ほど短い。
このあとの場面について、一九七七年に出た季刊映画宝庫第二号「ヒコーキ・戦争映画」特集号の記事「戦争映画にまつわる戦史と戦闘」で、小学生でこの映画を観たという斉藤忠直が触れている。
中学生のときに読んだ以下の一節を、私は久々に思い出した――そのときは、これがどんな映画か、まるで知らなかったけれど。
初めて戦争映画らしいものを見たのは、おふくろにつれられていった戦時中の『海軍』。九軍神の日比谷公園での国葬の日、目が悪くてついに憧れの海軍士官になれなかった牟田口隆夫が、他の八人とともに真珠湾に散って軍神となった、親友の谷真人の柩車を目の前にして、「真人が行く、真人が行く」と涙をボロボロこぼしながら、つかれたようにつぶやき、追いかけようとするシーンが、なぜか今もすごく印象に残っている。
私は、このシーンが観たいのである。それを観ないうちは、この映画をあきらめることができないのだ。
九月十九日 トンネルは三本
チリ落盤事故、無事救出を願ってやまないが、救出用トンネルの掘削は三本同時進行とか。どれがトム? ディックとハリーは? と考えた私は、映画『大脱走』の見すぎ。
九月二十日 『娘と私』
獅子文六の『娘と私』を読みおえる。
深く、忘れがたい名作。文六の作品の中で、「文学的」な意味でも評価が高いということがよくわかる。
文六は一九二二(大正十一)年、二十九歳のときにフランスのパリへ遊学し、三年後、身重のフランス人妻をともなって帰国する。『娘と私』は帰国の翌月、横浜で娘が誕生する場面に始まる。
当時の文六は父の遺産を食いつぶすだけの、無名の存在だった。新劇活動を志し、本名の岩田豊雄で戯曲の翻訳などを行ない、やがて一九三七年、自らが名付けた文学座結成の中心人物の一人となることになるが、そうした活動では当然ながら、満足な収入にならない。
娘が五歳のときに妻は、ストレスによる心身の不調で帰国、そのまま亡くなってしまう。幼い娘を抱えての男やもめ、苦闘のうちにやがて作家として名を成すようになり、愛媛県岩松出身の女性と一九三四年に再婚、戦争と岩松移住の時期をへて帰京、妻が亡くなり、娘が結婚する一九五一年までの生活と創作を回顧する、自伝にかなり近い小説。
ユーモア小説の大家として知られる文六、しかし岩田豊雄としての実像は、明朗快活どころか、無愛想な、とっつきにくいものだったという。文学座の役者たちにとっては、妥協のない、とても怖い先生だった。
意地悪く醒めた目で事象を見る、人間観察の達人だからこそ、ああした乾いたユーモアを描けたのだろう。『娘と私』は、その岩田豊雄の一面を強く出して書かれたものである。『てんやわんや』や『大番』で親しんだ、岩松の人と町と自然も、ここでは獅子文六自身の目でとらえなおされる。というより、ここに描かれた実体験を原型にふくらませて、あのユーモアになるという手の内を、明かしてみせてくれている。現実と虚構との落差が生む立体感、遠近感の奥深さ。
坦々とした描写だが、その行間には生きること、生活すること、つまりは人間であることへの、やるせないような愛が満ちていて、文庫本にして六百頁の厚さ――それも昔の文庫だから、字はかなり小さい――を、まったく長いとは感じさせない。現在は絶版なのが、ほんとうに惜しい作品。
ところでこの作品、NHKの「連続テレビ小説」の第一作の原作だったということはよく知られているが、今回読んでみて、なるほどと思った。
男性が主人公だし、ウィキペディアによると番組のつくり方もその後の作品とはかなり違うらしいが、しかし戦争とか伴侶の死とか子役とか家庭中心の描き方とか、「連続テレビ小説」でウケる要素が、すべて揃っているのだ。「大河ドラマ」で信長・秀吉・家康の時代が確実に受けるのと同様に、かつての「連続テレビ小説」には、戦争と敗戦が欠かせなかった。その始まりだったのである。
それにしても、獅子文六をまだまだ読みたい。『悦ちゃん』も『箱根山』も。こうなったら、毒を食らわば皿まで。とうとう、獅子文六全集(十六+別巻)をネット古書店で購入してしまう。
約一万二千円ナリ。
以下は、ただの思いつきのメモ。
獅子文六が本名の岩田豊雄で『海軍』を書き、海軍兵学校の魅力を広く知らしめたのに似て、大佛次郎も本名の野尻清彦に近い、野尻草雄の名で『一高ロマンス』を書き、第一高等学校の寮生活の魅力を紹介して、受験生たちの憧れをかきたてた。
海兵も一高も、ある種の人たちが「エリート教育の理想」として、称揚してやまない、失われた名門である。軍人教育とバンカラでは正反対だが、生徒全員が寮生活である点は共通する。
本当に理想の教育だったのかどうか、私に判断する能力はないが、両校の美点を、文六と大佛が分担するようにして書いたのは面白い。
ただし、文六が外部の大人の目で書いたのに対し、大佛は一高在学中に、在校生の実体験として書いた。その点は大いに異なっている。
九月二十二日 「っ」のともだおれ
大佛次郎に獅子文六、このところ昭和初期の大衆小説を読んでいて、とても気になることが一つ。
かれらの文章は、基本的にとても平易である。口語文で用語は簡単。旧かな表記になっている場合でも、見た目の印象は、現代文とほとんど変らない。
しかし、前述のように気になることが一つある。
「どなたかいらっしゃるんですか」
顔を真白にぬって、あくどい媚を振りまくので気味が悪いようだった女が、この言葉を耳にはさんでこうたずねると、
「うむ、俺のいい人が」
と、笑いながら答えて、祇園のお盆のくばり物らしい芸子の名をそめ抜いた団扇で膝を打たれていた。
「嘘ばっかし。あんた、泊まっていらしってもいいんでしょう」
これは、大佛次郎の『鞍馬天狗 天狗廻状』の一節。原文の初出は、一九三一年から三二年にかけて報知新聞夕刊に連載されたもので、引用は、一九八九年の徳間文庫版から。
気になるというのは、最後の「泊まっていらしっても」の「いらしっても」である。これは「いらしても」の引用ミスでも、原本の誤植でもない。大佛作品に頻出する用法だからだ。戦前昭和を舞台にした現代小説でも使われているから、江戸言葉でもない。
このことが気になっていたら、獅子文六もやはり使うことに気がついた。ところがさらに不思議なのは、文六は「いらっしても」というように書くのである。「し」をはさんで「っ」の位置が前後に異なるのだ。
昔は、こういうふうにしゃべっていたのか? それならそれでよいとして、なぜ二人の「っ」の位置が異なっていて、統一がないのか?
しかも、前述の引用の一行目のように「いらっしゃる」も用例があり、これは文六も同じように併存させている。
わずか六、七十年前の言葉なのに、謎なのだ。片山さんがこの話を面白がって調べてくれたが、「いらせらるる」が転訛したもので、江戸時代から「いらっしゃった」「いらっしった」と「いらしった」の三つの用法が共存していて、統一のないまま戦前にいたったようだ。文六の「いらっした」は、「いらっしった」をつめたもの、ということらしい。
「いらっしった」は、江戸期の町人がいいそうだし、「いらっした」「いらしった」は、木暮三千代とかが口にしても自然そうだし、昭和期の山手言葉には、そんな響きがあった気もする。
だが、自分で口にしようとすると、ひどく違和感がある。つまり子供の頃、半世紀近く前にはすでに、私の周囲やテレビでは「いらし」に変っていたわけだから、「いらっし」と「いらしっ」も、戦後二十年ほどで滅んだように思える。
明確な理由、原因はあるのだろうか?
九月二十五日 ボッセに感動
ゲルハルト・ボッセ指揮の紀尾井シンフォニエッタによる、ベートーヴェンの交響曲第一番と《エロイカ》を聴く。
掛け値なしに素晴らしかった。ボッセが若き日に身につけた新即物主義と、のちにあらためて学んだピリオド奏法の、幸福な結婚。時代が一回りして、この結びつきが可能になったのだが、それを体現してみせるには、並外れて柔軟な精神と肉体が必要なわけで、この老練の指揮者は、まさしく希有の存在といって過言ではない。
日本のオーケストラでこんなエロイカを、こんなに俊敏で壮大で革命的で、しかも虚しくて悲しいエロイカを聴けるとは。明日もう一度、聴きにきたいくらいだが…。
九月二十六日 ナマでカズ・ダンス
国立競技場で、サッカーJ2のFC横浜対カターレ富山を観る。
今年は国立でのJ1が少ないので、観てみようと思った。
バックスタンド側は空いているかと思ったが、これが大間違い。横浜のファンで客席がかなり埋まっている。日曜日で子供連れが多い。正面スタンドの席は空いているので、少し高くてもそちらの方にしておけば気楽に観戦できたのだが、あとのまつり。
こういう混み具合って、入口でチケットを買うときに確認できるんだろうか。次はダメもとできいてみよう。
試合は、早くも五十八分で横浜が三対〇にする、ワンサイド・ゲーム。正直、J1にくらべるとぬるい感じだし、子供連れの人たちと一緒に動くと気疲れしそうだから、七十分過ぎたら早めに帰ろうと考えはじめたのだが、その七十分に、横浜のカズが、交代で登場。
キャプテン・マークまで巻いている。国立での試合だし、観客は多いし、ワンサイドだしということで、しめに出てくるかもと思っていたら、やっぱり。
周囲の観客は大歓声で迎える。三点ゴールしたときよりも、明らかに沸いている。プロの興行としては、これで正しいのだろう。
そしてその四分後、ゴール正面でカズが倒されてフリー・キックのチャンス。なんとカズが自ら蹴って、見事にゴールのなかへ。
スタンドは大興奮。横浜の選手も全員で大騒ぎ。そして、カズ・ダンス。
バックスタンドからは背中が小さく見えただけだが、スクリーンには大写しになっていたし、現場で目撃したという事実はかわりない。これで来た甲斐はあった、早く帰らないでよかった、と感謝しつつ帰宅。
十月一日 江田島の輝き、その影
豊田穣の小説『蒼空の器』を読む。
帝国海軍の戦闘機パイロット、鴛淵孝少佐の二十五年の生涯を描いたもの。
この人を有名にしたのは何よりも、終戦の年の正月に精鋭パイロットを選抜して編成された、新型戦闘機紫電改を駆る松山三四三航空隊、その戦闘七〇一飛行隊の隊長としての活躍である。一九六三年の東宝映画『太平洋の翼』で加山雄三が演じた、滝大尉のモデルだ。
だからこの小説も、呉爆撃に来襲した数百機の米艦載機を、五十四機で迎撃して六十機以上を撃墜、損失十機以下という大戦果を挙げて、松山に紫電改ありと勇名を轟かせた、一九四五年三月十九日の、三四三航空隊のデビュー戦から始まっている。
この空戦の最後に、帰艦する敵機を追尾して、土佐沖の米機動部隊の只中に単機でまぎれ込んだ鴛淵の紫電改が、敵の旗艦、空母エセックスの艦橋を銃撃して猛将ハルゼーに一泡ふかせ、一瞬に機をひるがえして脱出する場面がある。
あまりにも鮮やかで、鞍馬天狗のようにカッコいいこの話は、作者の創作だろう。しかし、ヒーローの物語の幕開けとして、じつに効果的である。
その後は、時間をさかのぼって、中学卒業までの長崎の少年時代、江田島の海軍兵学校時代と続く。作者自ら、主人公の江田島生活がこの物語の「白眉」だと語るとおり、江田島時代は長く、文庫本約五百二十頁のうち、半分近い約二百四十頁に及んでいる。それに較べ、ラバウルから豊後水道上空までの戦場時代は、四分の一の約百三十頁にすぎない。
この点、意識的になのか無意識的なのか、この物語は獅子文六(岩田豊雄)の『海軍』によく似ている。
主人公の性格も共通する。明朗で誠実で、爽やかな好青年。はにかみ屋で多弁を好まない。海兵では劣等生ではないがトップクラスでもない、平凡な生徒。
その平凡な生徒が戦場で立派に戦えるのは、鋼のような信念の力であり、その信念を鍛練し身につけさせたのが、江田島の教育。
そこで江田島時代が、物語の大半となるわけだ。
だが、ただ一度の実戦経験のみの『海軍』の主人公、谷真人(事歴や人柄は、モデルの横山正治そのままだから横山としてもいいが、ここでは二小説の主人公の比較だから、谷としておく)はそれでよいとしても、約二年も最前線にいた鴛淵の場合、疑問が残らないでもない。
鴛淵は一九四二年八月にラバウル航空隊に着任して実戦に参加、一九四四年初頭までここで戦った。
下級指揮官の戦死率は高い。鴛淵の海兵同期三百人のうち、三分の二が戦死した。飛行士の場合はさらに高い。「ラバウルのリヒトホーフェン」といわれた笹井醇一(鴛淵の一期上、谷真人と同期)や同期の大野竹好など、鴛淵に優るとも劣らぬ優秀な戦闘機乗りが次々と戦死するなか、鴛淵は、連日の激戦を十五か月戦い抜き、ラバウルから生還する。
一九四四年前半は内地で搭乗員練成にあたり、十月に前線に戻って台湾とレイテで空戦、足を負傷して内地で治療ののち、一九四五年一月に新編の三四三航空隊に参加。三月後半から四か月間を戦うも、終戦二十日前の七月二十五日、豊後水道上空で撃墜され、戦死。
性急な自己犠牲を選ばず――九軍神はもちろん肉弾三勇士、神風攻撃隊など、いたずらに美化されて悪用される危険が高い――粘り強く生きて戦い続ける「平凡」の力。それでもついに訪れる、死と祖国の敗北。また、合間の内地の期間には何を体験し、何を思ったか。
小説としては、このあたりも書き甲斐がありそうなのだが、作者は江田島時代ほどの重きを置かない。
戦場と銃後での、人間くさい感情や出来事に接して生きる鴛淵を、あまり書きたくなかったようなのだ。江田島時代のまま、純粋な青年として死んでゆく。
じつは鴛淵孝という人は、童貞のままで死んだという説が有力である。
部下たちなど周囲の人々は、そう思っていたという。『蒼空の器』本文では、なぜかはっきりとは書いていないが、背表紙には「壮烈、果敢、質実、至純にして穢れを知らず逝く」とあって、そのことが暗示されている。
現代のように、三十代の童貞や処女が珍しくない時代とは違う。金を出して女を買うことが当り前だった頃である。しかし鴛淵はここでも信念にしたがって、童貞をつらぬいたらしい。
この点も、『海軍』の谷真人と同じなのだ。副主人公の牟田口隆夫は、中尉となった谷に再会したとき、谷には中学時代と変らない「童貞の匂い」が薫っていると感じ、対して自分がすでに「清浄ではない」と感じる。
童貞という言葉には、禁欲の修行者の清いイメージが込められている。先月十四日のこの日記に引用したが、『海軍』には、江田島の説明に「白い作業服を着た生徒たちが、汚れなき童貞の挙止を以て、一糸乱れざる規律を行動していることに驚く」という一節もあった。当時では一般的な感覚だったようだ。
若い軍人のなかには「戦場に行く身に女は無用」と考えて結婚しない者も、少なくなかった。かれらは「軍人半額二十五年」、まもなく死ぬのだから、若い未亡人をつくることはない、と考えた。鴛淵や谷はさらに極端に、生涯不犯の誓いをたてて神秘的な強さを誇った「毘沙門天の化身」上杉謙信に倣うかのように、芸者を抱くことさえしなかった。
一九三五年から三九年、つまり鴛淵の思春期に朝日新聞に連載され、圧倒的な支持を集めた吉川英治の『宮本武蔵』の影響も、大きいのだろう。
剣に生きるための求道的な禁欲、ヒロインお通への頑なな拒絶に共感した青年は、少なくなかったはずである(とはいえ、吉川英治は吉野太夫との関係をぼかしながらも書いていて、武蔵が童貞だったとは考えにくいが)。
だがそうした思い込みも、実社会で青年らしい潔癖や気後れが薄れていくうちに忘れ、戦場と死を目前にして、生の証しを性に求める人も増えたろう。むしろそれが、自然である。
ところが鴛淵は二十五歳で戦死するまで、一途に、一本気に純潔を守った。こうした毅然たる、汚れなき個性を描くには、江田島に重点をおくしかない、と作者は考えたのかも知れない。
『蒼空の器』と『海軍』の相似点は、これにとどまらない。物語の構造そのものにも、似ているところがある。
それは、同級生が副主人公として存在していることだ。かれは生き残って、若き英雄の生と死を、その輝きに気後れしつつ、見つめている。
『海軍』では、もちろん牟田口隆夫がそれにあたる。『蒼空の器』の場合、それは作者の豊田穣自身だ。
豊田も鴛淵と同期で海兵に入学、四号生徒(娑婆でいうところの一年生)のとき、同じ分隊で起居をともにした。だから四号時代の話が長く、生彩に富んでいるのは当然のことで、ここには作者も友人の一人として登場する。任官後も、同期の飛行学生として操縦訓練を霞ヶ浦で受け、豊田は艦爆の操縦士となった。
だが、その後の二人の戦歴は、対照的といっていいほどに異なる。
鴛淵に遅れること半年、一九四三年四月、豊田は初めて最前線に出た。ところが最初の出撃で接敵前に撃墜され、漂流ののち、捕虜となってしまう。ハワイからアメリカ本土に送られ、終戦までの二年半を、無為と失望のうちに過ごすことになったのである。
鴛淵のような軍功に恵まれず、名誉の戦死もせず、それどころか、日本の軍人としては不名誉な捕虜として生き残ってしまい、戦後に作家となる豊田。
谷や鴛淵の死を光、とすれば、影、ともいうべき豊田の生。
しかも、豊田はアメリカで酒巻和男と一緒にいたらしい。酒巻は豊田や鴛淵と同じ海兵六十八期、谷と同じく特殊潜航艇で真珠湾攻撃に参加しながら、ただ一人生き残って捕虜になった。「軍神」になりそこねた上に、「捕虜第一号」となる不運を背負って、生きた人である。
ついでにいえば、谷真人は中学四年で海兵に合格したため一期上になったが、年齢は鴛淵たちと同じだった。
予想以上に、この人々の生死はからみあい、複雑な光彩を放っている。
ヒーローではない豊田穣の人生に、興味がわく。調べてみると直木賞受賞作の『長良川』とか『海兵四号生徒』とか、自伝的作品がいくつかあるらしい。それらを読んでみることに決定。
十月三日 好きな席から
秋晴れで気候もよい。ということで、国立競技場のFC東京対湘南戦を観戦。
日照も弱く、涼しくてラク。国立はやはりこの時期に限る。
席はビジター側ゴール裏の斜め上。ここはピッチ全体がコンパクトに視野に収まるので、見やすい。また、攻防が左右の横方向に動く正面スタンドやテレビ桟敷に較べ、上下の縦方向に動くので展開や連動ぶりがわかりやすく、迫力やスピードも間近に感じられるので、個人的にはいちばん好きな場所である。
ただし、ビジターのファン席なので、ホーム側のユニホームなどは禁止。手拍子や応援歌は強要されないが、礼儀として湘南側の応援をする。
試合は三対〇でFC東京勝利。大黒、平山、石川、リカルジーニョ、森重、徳永、中村北斗、今野と有名タレント揃いで(W杯前は長友もいた)、ほとんどの時間で湘南を圧倒できるチームなのに、降格争いをしていて、これが十一試合ぶりの勝利というのが、ホントに不思議。監督交代でチーム全体に活が入った後の試合だから、特にそう感じるのだろう。
大黒、石川、リカのゴールも、各々のスタイルを活かした見事なものだった。苦戦続きなのに最後まできちんと応援する湘南ファンも、皮肉でなく立派。
十月四日 『長良川』
豊田穣の『長良川』を読む。
一九七〇年度下半期の直木賞受賞作。豊田が中日新聞の記者生活をしながら、一九六一年から同人誌『作家』に書き綴った連作で、受賞後に第二部の四編が書き足され、翌年完結した。読んだのは第二部も合せた光人社NF文庫の完全版。
解説の進藤純孝によると、直木賞よりも芥川賞にふさわしいという意見があったそうだ。たしかに文学的な私小説、ウジウジジメジメとした話だから、芥川賞的な性格も濃い。
ただ、背景に戦争があるだけに、より多くの人々の運命が描かれている点で、直木賞向きと考えられたのだろうか。特に表題ともなった「長良川」の章は、織豊期から江戸、戦後の混乱期をへて現代への長い時代と、墨俣から満洲までの大きな空間での、多数の人生が個人の運命のうちに込められていて、そのスケールは大衆小説的ともいえる。
ところでこの章、個人的には墨俣一夜城、川衆、嫁が隠れ切支丹で処罰されたことや伊勢湾台風の災害など、登場するキーワードが、例の『武功夜話』とその隠匿と発見をめぐる物語に似ているのが面白かった。中部地方の古い郷士出身の階層にとっての歴史的大事件が、共通しているということなのだろうけれど。
連作はどれも、現在の日常生活のなかでの出来事をきっかけに、「私」(武田と名づけられている)の捕虜時代の体験がフラッシュバックしてくる、という構成をとっていて、大きな断層があるようでじつは合せ鏡のように連続している、戦時と現代が重ねられる。
その調子は暗い。だがその暗さは、生きていくことに付随する暗さだから、けっして独りよがりなものではない。いわば生のリズムがつくる暗さだから、読ませる力がある。だから、七百頁近い厚さを一気に読んでしまった。
この出世作から二十年後に、作者自身はその後の著作をふりかえって「未だに「長良川」を抜くことが出来ないでいるような気がしている」と書いているが、あるいはそうなのかも知れない。
作中、戦死した同期の戦闘機乗りの母親に会った主人公は、彼女の本心を想像する。
「――私の息子も、あなたのように、生き残ってくれればよかった。だのに、あの子は死んでしまった。でも、あの子には、国家のために死んだという名誉が残っています。捕虜になって帰ってきたあなたには、何も残されていない……」
『蒼空の器』で予感したように、豊田の生は暗い。しかし、凡愚で、現実の泥をすすっている中年の自分には、共感できる部分が大きい。
続いて、同じ豊田穣の、より自伝的な『海兵四号生徒』にとりかかる。
十月七日 秀作『海の紋章』
豊田穣の『海兵四号生徒』と『海の紋章』を読む。
前者は江田島での四号生徒(一年生)時代を、後者はその後の最上級生時代から、艦爆乗りとなってソロモンに向け出撃する直前までを描く、自伝的小説。
ただし主人公は、前者が盛田修平なのに対し、後者は『長良川』と同じ武田竜平になっている。前者の最後に、捕虜生活と敗戦、帰国を結末としてつけているので、『海の紋章』は続編ではないという位置づけなのかも。
『海兵四号生徒』の方が直木賞受賞直後に書かれ、一九七一年に映画化されている(渡辺篤史主演の大映映画。未見)から、知名度は上かも知れないが、作品としての面白さ、味わい深さは『海の紋章』がはるかに高い。
豊田文学の暗さが、純粋たるべき生徒時代よりも、迷いの多い士官時代に合うからだろう。『海兵四号生徒』の江田島の描写は、咆哮と鉄拳、体育会系の色合いが強く、『蒼空の器』の爽快さや『海軍』の清浄さだけではない一面が押し出されるが、どうも収まりが悪い。
対して、『海の紋章』はうまくできている。海兵卒業後、士官候補生となっての練習航海で満洲帝国へ。任官後の戦艦伊勢乗組。霞ヶ浦での飛行訓練、宇佐、富高、鹿屋、佐伯と、九州各地の基地での急降下爆撃の訓練。そして空母飛鷹に乗り、トラック島からラバウルの最前線へと、大日本帝国内の各所での移動に、若き精神の彷徨が重ねられているのだ。
主人公は『蒼空の器』の鴛淵とは対照的に、女を知らずに死ぬのは空しいと考える。大塚の三業地で童貞を捨て、延岡の芸者から、異性との情愛を学ぶ。
各地の一流料亭での芸者遊びは、士官ならではの特権。しかし、芸者はあくまで芸者であって、その関係は刹那的なものでしかない。性の道具としての女。
一方で、予科練出身の下士官たちとの微妙な関係。操縦士として腕利きであればあるほど、かれらは上官である士官に対して、複雑な感情を抱く。その思いを圧倒できるほどの技術的、あるいは人格的な優越を示せない、武田の胸中。そして起きる、いくつかの事件。
どれも人間として共感しやすいものであり、英雄譚である『蒼空の器』には、描かれなかったものだ。
面白いのは、『海の紋章』では鴛淵孝らしき人物が、影が薄いこと。
海兵の一号生徒のときに大淵として出てくるが、卒業後、その存在は消える。霞ヶ浦の場面にもいない。豊田の別作品での回想でも、ラバウルに到着した後、同島にいた同期の飛行士たちが次々とあいさつに来るのに、鴛淵は出てこない。
何らかの悪感情やわだかまりがあったとは書いていないし、おそらく偶然の行き違いだったのだろうが、『海の紋章』の四年後に『蒼空の器』を書いたとき、戦場での鴛淵の実在感がいま一つ希薄になったのは、海兵卒業後のこうした微妙な距離のためだったのかも知れない――逆に、だからこそ、『蒼空の器』を英雄譚にできた、とも考えられるわけだが。
さていよいよ、捕虜時代を描いた自伝第三部、『割腹』へ。
十月十日 捕虜第一号
酒巻和男の『捕虜第一號』(新潮社)を読む。
真珠湾攻撃に参加した五隻の特殊潜航艇の艇長の一人で、ただ一人生き残って米軍の捕虜となり、他の九人が戦死して九軍神となるなか、日本人捕虜第一号という不名誉な呼び名を与えられ、重い十字架を背負うことになった、酒巻和男少尉の回顧録。
昭和二十四年初版なので、記述の大半は十六年十二月の出撃から、二十一年正月に帰国するまでの丸四年の捕虜生活。帰国後、結婚してトヨタに勤めはじめたところで終る。
冒頭部分には真珠湾攻撃の模様やそれに至るまで、また特殊潜航艇の実際などが詳しく語られていて、『海軍』に書かれなかった部分を補完する形になっている。敗戦で日本人の心理は大きく変化していたとはいえ、その部分――岩田豊雄は、戦争が終ったら書き足そうと書いていたが、敗戦で不可能になった――を読んでみたいという読者の欲求は大きかったろうから、それに応えたこの本が、かなり売れたのもよくわかる。
一方で、日本全体が捕虜のようになってしまった占領下において、捕虜生活の第一号である人への関心の高さも、売れる背景だったろう。酒巻は二年前の二十二年にも、講演をもとにした『俘虜生活四ヶ年の回顧』を出している。
ただし、酒巻の記述はきわめて冷静で文学的誇張を避けており、それは捕虜時代の回想でも一貫されている。「確実、静粛、迅速」が海軍将兵のモットーだったそうだが、酒巻がそのとおりの、きわめてすぐれた実務的能力の持ち主らしいことが、その文章からうかがえる。
その点、真珠湾で戦死した九人の戦友たちとも、変ることはなかったのではないか。数奇な偶然が九人を軍神にし、一人を捕虜第一号にと分けてしまった。
捕虜生活の後半をともにした、海兵同期の豊田穣に関する記述は、ほとんどなかった。長編小説「井伊大老」を書いていた「大野中尉」が豊田を指すようだ。
それにしてもこの本、その後は復刊された形跡がない。著者の要望だろうか。
十月十一日 『割腹』と『トレイシー』
豊田穣の『割腹 ――虜囚ロッキーを越える――』『月明の湾口』を読み、続いて、中田整一の『トレイシー 日本兵捕虜秘密尋問所』を読む。
『割腹』は以前に触れたように豊田の自伝第三作、『月明の湾口』は真珠湾、マダガスカル、シドニーでの特殊潜航艇の奮戦を描いたもので、搭乗員のなかには海兵同期の酒巻和男、広尾彰、伴勝久の三人も登場する。あとがきの『特殊潜航艇と私』には、酒巻との戦後の関わりも書かれている。
これらのあとに、『トレイシー』を読んだのは、衝撃だった。
半年ほど前に出たときは、本屋で見かけただけで買わなかったのだが、豊田穣の捕虜生活に関心を持ち出してから、そういえばあの本も内容的に関係があるのではないか、と思い出した。そこで、ちょっと立ち読みしてみて驚き、あわてて買ってきた。
題名のとおり、トレイシーとはアメリカ軍がカリフォルニアに設置した捕虜尋問センター。尋問だけでなく宿舎内での盗聴も活用して、軍事情報を収集した。この本は、公開された米公文書を調査して、トレイシーやその他の場所で日本人捕虜が、「何をしゃべったか」を解明したものである。
その捕虜の一人に「大谷誠」という海軍中尉が登場する。
これは、豊田穣が捕虜時代に用いた偽名と同じで、経歴にも共通点がいくつかあるので、本人とみて疑いない。
ところが、『トレイシー』の著者はそれに気がつかない。というより、おそらくは気がつかないふりをしている。他の事項ではきちんとリサーチをしている著者が、気づかなかったはずはないのだ。
なぜとぼけたかといえば、大谷誠から米軍が得た情報としてこの本に書かれている内容が、かなり重要なものであるからだろう。大谷が豊田穣だと明かしてしまえば、死者に鞭打つことになると考えたのだろうと、私は思う。
だから私も、それが何であるかをここで書くのは、控えることにする。
ただ、『長良川』や『海の紋章』『割腹』でのいくつかの暗示的記述の向うにあるものが『トレイシー』で見えた、腑に落ちたように感じられたことは、書かずにいられない(それらの符合を細かく解明すれば、新書一冊くらいの量になるだろう)。
そして、私はそれを知ったことで、豊田を軽蔑するどころか、むしろ、弱き人間として、男として、共感するところが深まったことも、書かずにいられない。
『海軍』に始まった「読書の旅」が、この『トレイシー』で、やっと一つの終点に至ったと感じる。
まとめてしまえば、「男はつらいよ」という一言になってしまうのだが。
十月十二日 酒巻和男と豊田穣(一)
「海兵読書の旅」は一段落といいつつ、酒巻和男と豊田穣、二人の捕虜の物語を備忘録的にまとめてみる。
酒巻は一九一八年十一月、豊田は一九二〇年三月生れ。海兵では同じ六十八期生で、分隊は違ったが、第二外国語が同じ支那語のクラスだったので、そこで親しくなったという。また、酒巻とともに特殊潜航艇で真珠湾攻撃に参加、九軍神の一人となった広尾彰は、四号時代に豊田と同分隊で親しかったので、間接的な縁もあった。
一九四一年四月、少尉任官と同時に酒巻と広尾は特潜乗組員に任命され、愛媛県三机湾(偶然にも、獅子文六が戦後に移住した岩松から遠くない)で、「甲標的」という暗号名で呼ばれた二人乗りの小型潜航艇の猛訓練に参加しはじめた。その少し後、豊田は飛行科学生として霞ヶ浦航空隊に入隊、赤トンボに乗って操縦訓練を開始している。
その年の十一月十八日。酒巻たち特潜乗組員は、イ号潜水艦五隻(それぞれに特潜一隻が載せられている)に分乗し、真珠湾に向けて、呉の軍港を出航した。
出撃前夜、酒巻と広尾は二人だけで呉の町を歩いた。「僕等は純潔を守ろう」と広尾が言い、二人は待合の前を素通りした。そして香水を買った。特潜で発進するとき、軍服にかけるためである。
同じころ、豊田の方は霞ヶ浦で、童貞のまま死ぬべきか、死ぬ前に女を知っておくべきか、悶々と迷っていた。
そして十二月八日。真珠湾内で広尾は戦死。酒巻は湾外で座礁した特潜から、同乗の稲垣兵曹とともに脱出したが、稲垣は波にのまれ、酒巻一人が海岸に打ち上げられた。そのまま失神しているうちに、米兵にとらえられて捕虜となった。
ホノルルに連行された直後は、米兵に射殺されるつもりであった。
だから、堂々と官姓名を隠さずに名乗り、「立派に死んだと日本海軍省に打電してくれ」と告げたが、もちろんアメリカ側は殺そうとはしなかった。
そのため酒巻の名は、見せしめと復讐のために殺された勇敢な軍人としてではなく、捕虜第一号として、伝わることになったのである。
この事実は、かなり早くに日本海軍も把握したらしい。
開戦を霞ヶ浦で迎えた豊田は、劈頭の大戦果にわく訓練生活のなかで、どうも酒巻が捕虜になったらしいという噂を、同期生から聞いた。翌年三月七日、九軍神という半端な人数の発表があったことで、その事実は決定的となった。
海軍省報道局は特潜攻撃隊から酒巻の痕跡を消し、九人にした。集合写真などからも、その姿だけが切除されている。
「酒巻は自決してくれんかな。捕虜を出したら六十八期の恥だ」と、思いつめた表情で口にする同期生もいたという。
「生きて虜囚の辱めを受けず」で有名な戦陣訓は、東条英機が陸軍大臣時代に公布したものだから、海軍には関係なかったが、同じ感覚は不文律として、それ以前から軍人の常識となっていた。
しかし、豊田は酒巻に対して、なぜか怒る気にはなれなかったという。小さな潜航艇では、敵に囲まれて自決できずに捕虜になることもあるだろうと、同情の気持ちが強かったという。
とはいえ、自分も捕虜になるつもりは毛頭なかった。一年後、同じ憂き目にあおうとは、思ってもいなかった。
一九四二年二月下旬、酒巻の身柄はハワイから米本土に移された。サンフランシスコに上陸、ロッキー山脈を越え、ウィスコンシン州マッコイのキャンプに到着したのは、九軍神発表の二日後、三月九日のことだった。
日本軍が勝ち続けていた時期だけに、まだ日本兵の捕虜は酒巻一人で、かれは抑留された日系移民(インタニー)たちとともにおかれていた。移動は頻繁で、五月二十日には、かれらとともにテネシー州のフォリスト・キャンプに、ついで七月一日に、ルイジアナ州のリビングストン・キャンプに移された。
ここには米本国のほかハワイ、パナマなどの邦人抑留者を合せ、千二百五十人がいた。「珍しい石を入念に磨いたり、木の根を繊細に彫刻したりしながら」時節をじっと待つインタニーに、見守られているように酒巻は感じたという。
九月ごろ、新しい日本人捕虜がいると新聞に載った。そして十一月十五日、酒巻はインタニーと別れ、その新たな捕虜たちと合流した。
約五十人、その三分の二は、六月にミッドウェーで沈んだ空母飛龍の機関員だった。退艦命令の届かない艦底の機関室にいたかれらは、自力で脱出したものの友軍に見捨てられる格好になり、二週間の漂流のすえに、米軍に捕えられたのである。
一か月半後の一九四三年元旦、飛龍の機関士官など十六名に移動命令が出た。リビングストンに残った酒巻は、かれらがサンフランシスコ湾内のフォート・マクドーエル・キャンプに行ったと書いている。が、実際には、この日から運用を開始した米軍の捕虜秘密尋問センター、トレイシーに連れていかれ、尋問と盗聴により情報を収集されていたのである。
酒巻がそれを免れたのは、情報源としてはもはや利用価値がないと見なされていたためだろうか。かれらは二月下旬にリビングストンに、重巡古鷹の生存者など新たな仲間を加えて帰還した。
三か月後の五月二十二日、捕虜全員がウィスコンシン州のマッコイ・キャンプに移動した。
酒巻にとっては、二度目の滞在ということになる。ここに一九四五年六月まで二年以上滞在するうちに、米軍の大攻勢で日本人捕虜は増加しつづけ、ついに二千名をこえるほどになった。
その多数の新参者の一人に、豊田穣がいた。
再会は、一九四四年四月八日のことだった。豊田は大谷誠と偽称していたが、「六十八期でよく肥えて柔道が強い」という情報をあらかじめ得ていた酒巻は、きっと豊田だと確信して、酒保でビール一本を用意してかれを迎えた。そして、二人きりのわびしいクラス会となった。
(続く)
十月十三日 酒巻和男と豊田穣(二)
豊田穣が、ガダルカナルのルンガ泊地攻撃に向う途中にサボ島北方で撃墜されたのは、酒巻と再会する一年前の、一九四三年四月七日のことだった。
霞ヶ浦のあと、一九四三年一月まで九州各地の基地で訓練を続け、急降下爆撃機の操縦士となった豊田は、三月に空母飛鷹に乗組み、トラック島経由でラバウルに向った。トラック島では戦艦大和に対する爆撃訓練なども行ない、そして四月にラバウルに移って、ガダルカナルへの航空攻撃を主体とする「い号作戦」に参加した。これは連合艦隊司令長官の山本五十六がラバウルの陣頭で指揮する、劣勢挽回のための総力作戦だった。
その最初の出撃で、豊田の操縦する九九式艦爆は、爆撃前に敵戦闘機に撃墜され、海上に着水した。脱出した豊田と同乗の下士官は、鱶につきまとわれながら一週間漂流し、ニュージーランド軍の哨戒艇に発見され、米軍の捕虜となった。
捕虜になった豊田が、大谷誠という偽名を用いたのは、米軍に対する攪乱というよりも、日本にいる家族たちへの配慮だったのではないか。
捕虜第一号、酒巻の名が伝わったときの同期生の拒否反応を思えば、自分の姓名が国内に知られる可能性を豊田が嫌っても、不思議ではない。
近くにいた同期生が海面への「突入自爆」を確認していたため――豊田は不時着水のつもりだったが、上空からは突入に見えた――、豊田は戦死と見なされ、故郷では殉国の英雄扱い。父は立派な墓を建て、戦後に帰国した豊田は自分の墓を見、さらには直前に亡くなった母が、あの世で息子に会うことを楽しみにしていたと、聞かされることになる。
だが、それでも、「捕虜の出た家」という汚名のもと、戦時の両親に肩身の狭い思いをさせるよりは、ずっと「孝行」だったはずだ。
その後、豊田はニューカレドニア島に送られ、ついで五月下旬から翌年二月までハワイのオアフ島にいて、その初めの五か月は、フォード島の海兵隊の拘置所に入れられていた。
そこでは、太平洋地域情報センターの情報将校から、かなり厳しい尋問を受けている。豊田によれば、米軍は山本長官の生死を確認したがっていた。四月十八日にブーゲンビル島で撃墜した一式陸攻に、「フィフティシックス」が乗っていたのかどうか、戦死したのかどうか、その確報を欲していたのである。
他の捕虜から聞いて豊田は山本の死を知っていたが、あえて黙秘を続けた。それで鉄格子つきの暗黒の独房「アイスボックス」に二週間入れられたが、六月五日に山本の国葬が日本で行われたことが判明して、独房から解放された。
豊田が、捕虜を犯罪者なみに扱うのは条約違反の虐待だと非難すると、代償に英和辞典一冊と、エンタープライズ見物の権利を得ることができた。どちらも、豊田の方から要求したものである。
この空母が真珠湾にいることを豊田が知っていたのは、少し前にエンタープライズ乗組の戦闘機パイロットが、日本の飛行士の捕虜がいると聞いて、豊田に会いにきたことがあったからである。
豊田は、空母瑞鶴の零戦乗りと思われていたので、それを聞いた米パイロットが、南太平洋海戦で自分たちと激闘した相手に会いたいと、やってきたのだった(そのかれが、豊田のいうように本当に単なる興味本位で来たのか、それとも何らかの確認や情報収集の任務を負っていたのかは、大いに疑問であるが)。
異例にも要求は認められ、豊田は米軍少尉の軍服を着て、空母を見物させてもらった。頭の固い尋問担当の情報将校とは対照的に、空母の副長コクスン中佐は同じ飛行機乗りのせいか、親切だった。当初は禁じられていた飛行甲板と格納庫も、副長の好意で見ることができた。
「副長室に帰ると、コクスン中佐が日本の空母とどこが違っていたか、と訊いた。彼の狙いはこれだったのである。私はすべての問いに、両国の空母の構造はよく似ている、と答えた」
硬軟を巧みにとりまぜて懐柔する、米軍の情報収集法の一端が、ここにある。
一定の尋問が終ると、豊田たちはインタニーの抑留キャンプ内に、区画されて住まわされた。捕虜の食事を作ってくれる一世から、酒巻の噂を聞いた。
「あの人は、殺せ殺せと叫ぶので舌を噛んで死んではいけんというので、MPが歯医者につれていって、歯を全部ぬいてしもうたそうですけん。ハワイの病院にいたんじゃが、もう本土に送られたいう話ですのう」
そのため、半年後にマッコイ・キャンプで酒巻と再会したとき、まずその歯を見ずにいられなかった。丈夫そうな白い歯だった。豊田がその噂をいうと、酒巻は堅いパンにかぶりついて、自分の歯だと証明した。
こうした類の噂、流言蜚語は、捕虜収容所にはつきものだったという。
二月、豊田は他の捕虜とともにハワイから船でサンフランシスコに運ばれた。そこから救急車の、窓のない真っ暗な車内に押し込められ、方角も時間もわからないままに旅をし、やがて、
「ヨーロッパの風景を思わせるルネッサンスふうの赤レンガ建物の玄関に私たちは立っていた。(略)避暑地に建てられたホテルか別荘というのが、この赤レンガの印象であった」
イギリス貴族の別荘のようなこの収容所を、豊田は「ロンドン塔ホテル」と呼んだ。「多くの日本人捕虜がこのホテルを通過したが、このように優雅な呼び名をつけたのは私一人であったようだ」
豊田たちはここで一か月ほどを過ごした。囚人じみた自由のない生活で、「ここでは最終的に、捕虜の名前、身分、捕獲された場所などが、分厚いファイルにタイプされた」という。
それから三十二年後の一九七六年、豊田はアメリカを訪れ、自らの捕虜時代の故地を訪ねて回っているのだが、そのときにも、この「赤レンガ・ホテル」だけはカリフォルニアのどこにあるのか見当もつかなかったので、放置している。
建物も、目的も、豊田の回想では霧のなかにあるようで、かえって不思議に強い印象を残すこの収容所こそ、戦後に至るまでその存在が秘匿された、日本兵捕虜の秘密尋問所、トレイシーである。
サンフランシスコの東方六十キロ、バイロン・ホット・スプリングスにあるこの尋問所を、終戦までに二千三百名の日本人捕虜が、その正体を知らないままに「通過した」のである。
(続く)
十月十四日 酒巻和男と豊田穣(三)
トレイシーからの解放は、その人物が情報源から、ただの捕虜になったことを示している。
四月にここを出た豊田たちはロッキーを越えてマッコイ・キャンプに運ばれ、迎えに出た酒巻と再会した。
酒巻は、最古参の捕虜ということもあって英語がうまく、実直な人柄で米兵からも信頼され、連絡係や下士官兵のまとめ役をつとめていた。
捕虜という未知の境遇に日本兵は動揺し、統率は乱れがちだったし、捕虜に進級はないから、同期の豊田が中尉なのに酒巻は少尉のままとか、難しい立場だったが、かれはよくその職務をはたした。
他の捕虜から、自分の名が日本で噂になっていることも知っていたが、
「それについてとくに悩んでいる様子はみせなかった。よく食い、野球に熱心で、キャンプ内の面倒をよく見て、マージャンで勝つと大声をあげて笑った」
感傷やニヒリズムとは無縁のようにみせていたが、一方で、いつもは無表情な顔をしていることが多かった。
「彼が愉快そうに哄笑するのは、トンカツを三人分平らげた時とか、麻雀で、大物をつまみ上げた時に限るので、その他の時には、この得意の無表情な顔をしているのである。つまり太平洋戦開始の日、若くして捕虜となり、その後苦労をなめ続けて来た彼には、体の片隅に子供子供した所が残っている外は、青年壮年の華やかな時代を知らぬ間に飛び越えた、初老じみたものがもうきざし始めているのかも知れなかった」
マッコイ・キャンプにいるとき、近くのラ・クロスの町に真珠湾攻撃の特潜二隻が運ばれてきたことがあった。国債を売るための宣伝に、米国内を巡回していたのである。収容所長は酒巻を呼んで、「ユーのミゼット・サブマリンが来ているから、希望すれば外出許可を出す」と言ったという。捕虜たちの用事で町に買い出しに行くことを許されるほど、酒巻は米兵から信頼されていたが、この話は断った。その快活さは、感情のある種の遮断によって、そこに自他を寄せつけないことで、保たれていたのだろう。
マッコイ・キャンプから一九四五年六月にテキサス州のケネディ・キャンプに移動、そこで敗戦を知り、同年十二月に帰国の途に着くまでの間に、捕虜の待遇は悪化の一途をたどり、捕虜のなかにも積極的な親米派が出現して、他の人々を貶めるような行動をした。
そのために、酒巻も豊田も辛酸をなめることが少なくなかったが、そのような苦しい境遇においても、酒巻が胸襟を開いて、豊田に本心を見せることはなかった。仲が悪いわけではなく、よく冗談もいいあい、内務でも助けあってきたが、打ち解けはしなかった。
口に出さずとも、互いの腹の底でわかっているはずだという、「サイレント・ネイビー」そのものの態度を、酒巻はその無表情とときおりの哄笑で、仲間に対しても貫きとおしたのだ。
一方、豊田の方はマッコイ・キャンプに到着してまもなく、退屈をまぎらすために小説を書きはじめた。恋愛小説と歴史小説『桜田門以前』を書いて、捕虜たちの「人気作家」となったが、原稿は帰国のさいに没収されてしまったという。
一九四六年一月四日、酒巻と豊田たちは、三週間の航海のすえ、復員船で浦賀沖に到着、祖国の土を踏んだ。
「捕虜第一号」酒巻の帰還は巷の噂になっていたそうで、復員業務に従事していた海兵同期の生存者が、迎えに出ていた。しかしそのかれも、戦死したはずの豊田が一緒にいたのには驚いていた。
二百八十八名の海兵六十八期のうち、七割の二百名が戦死。生存者は、八十八名。うち捕虜となったのは、酒巻と豊田ともう一人の、三名だった。
復員後、酒巻は徳島へ、豊田は岐阜へ帰郷した。まもなく豊田が名古屋の新聞社に記者の職を得たのに対し、酒巻が無為のままにいたのは、捕虜としての知名度の差もあったろう。酒巻は、身の危険さえ感じつつ、興味本位の世間に翻弄されることを恐れ、家族にさえ、捕虜という「異常な過去」を語らずにいた。
その年の十一月、豊田はデスクから、酒巻を取材することを命じられた。十二月八日、開戦五年目の日に、特潜攻撃の回想記を載せようというのである。
そこで岐阜から、二日がかりで徳島の農村にある酒巻の家を訪ねた。かれは歓待してくれたが、特潜の取材と聞くと、口をつぐんでしまった。ただ一人の生存者として、語りたくなかったらしい。
豊田は二日間ねばり、記事にしないという条件で、概要を聞き出した。
帰宅した豊田は、友情と信義にもとると悩みつつも、歴史的価値の高さを優先して、「あれから今日まで」という記事にまとめた。これは好評で、豊田は局長賞を得たが、新聞を送った酒巻からは、約束を破るとはけしからん、貴様との長い友情もこれまでだ、という抗議の手紙が来た。
しかし、新聞を読んだある女性から、豊田自動織機(のちのトヨタ自動車)の人事部にいる伯父が、酒巻さんのような苦労をした方にぜひ来てほしいといっている、という電話が新聞社にきた。
そこで豊田が酒巻に手紙を書くと、かれは岐阜の豊田の家に来て、一泊した。その晩、おれのことを理解してくれるのは、こいつ一人しかいない、と豊田は思ったという。
生涯の朋友であるはずの海兵同期の中にさえ、捕虜となった仲間を「特殊帰還者」などと蔑む者が、戦後になっても、いたからである。
トヨタには、マッコイで一緒だった陸軍伍長がいたこともあり、酒巻は「小市民として」新生を期し、勤めはじめた。
このころ、酒巻は、自身の体験を自らで語っておこうと考えたらしい。翌四七年に『俘虜生活四ヶ年の回顧』という講演を行なって本にまとめ、さらに一九四九年に新潮社から『捕虜第一號』を出して、ひとくぎりとした。
その後の酒巻は英語力を活かして輸出課長、さらにブラジル・トヨタの社長を務めるなど、企業人として成功した。数年に一度は豊田と会い、旧交を温めていたらしい。
その豊田は、一九七一年に『長良川』で直木賞を得て、作家として独り立ちした。戦記物の第一人者として活躍し、八〇年代には六十八期の戦死者二百名の人となりと戦歴を回想する、『同期の桜』とその完結編を書き、「紙の慰霊碑」とした。「捕虜となって生き残った私の、義務でもあると考えた」からである。
豊田は一九九四年に没し、酒巻は五年後、一九九九年にその生涯を終えた。
(了)
引用・参考文献
『捕虜第一號』酒巻和男 新潮社
『海の紋章』豊田穣 集英社文庫
『割腹』豊田穣 集英社文庫
『同期の桜』豊田穣 光人社NF文庫
『同期の桜〈完結編〉』豊田穣 光人社
『月明の湾口』豊田穣 文藝春秋
『戦争と虜囚のわが半世紀』豊田穣 講談社
『長良川』豊田穣 光人社NF文庫
『トレイシー』中田整一 講談社
十月二十二日 予告された浪費の記録
この「はんぶる」の来訪者カウンターが、一週間ほど前に三十万を超えた。
いい加減な更新、自分勝手な内容の日記にもかかわらず、お読みくださっている皆様に、心よりお礼を申し上げます。
日頃のご愛顧に感謝ということで、何か新コーナーをつくろうと思い、十六日に始めたのが「気になるディスク」、またの名を「予告された浪費の記録」。
初めは副題をより長ったらしく「約束された無駄遣いの記録」にしようかと思っていたが、友人から「マルケスですか?」と突っこまれ、なるほど、『予告された殺人の記録』のもじりの方が、いかにもエエカッコシーでいいなと思いなおして、変えた。
目的は、発売予定の盤から自分が注目する盤、注文したがまだ入手していない盤をあげるコーナー。当然ながら、売れ線など意識しない個人的な選択である。そしてまだ聴いていないのだから、いい演奏かどうかもわからない。
つくってみて、あらためて気がついたが、これは、ネットで買うのがメインになったからこそ、初めてコーナーとして成立している。
つまり、発見から入手までに、多かれ少なかれタイムラグがあるのが当然だからこそ、内容を評価する義務から逃れることができて、「買うつもり」だけで、紹介できるのだ。
以前のように、店頭で買うのが主体だったころは、予定などあまりチェックせず、発見即ち無駄遣い、まさに「サーチ&デストロイ」(破壊されるのは、我が財布の中身だけれども…)だった。
そうして買った盤を紹介する場合、手元にあるのだから、少しは聴いて判断しよう、という重荷を背負うことになる。
それでは、物理的にも心理的にも圧迫感がきつくて、毎日更新するなど、絶対に不可能だ。
また、楽しめなかった盤の場合、面白くなかっただの、出来が悪いだのと批判したり、嫌味や皮肉を書きつらねたりするのは、現在の自分の趣味ではない。そうして、読者と「復讐の快感」を共有するのも一つの方法だし、昔はそんな書き方もしたが、いまはなるべくやりたくない。といって、面白かった盤だけ選んで紹介するのでは、数はぐっと減る。
いずれにしても、このサイトを習慣的にチェックしてくれている人に、ほぼ毎日、わずかでも変化を提供するものにというもくろみは、実現できなくなる。
だが、手元にない盤、「買うつもり」にすぎないものなら、無責任にやれる。
ネット社会というのは、こんなところでも、現実から浮遊した気楽さを与えてくれるのだ。いいことなのか、悪いことなのか、よくわからないけれど。
といいながら、夜にレコード店に行くと、ネットでは気がつかなかった盤をいくつか見つけて、購入してしまう。
ネットが強い店、店頭陳列に強みのある店、そして円高によってぐっと買いやすくなった海外のショップ・サイト、それぞれの個性が魅力的で、浪費の道は、まだまだ先が長そうだ。
俵孝太郎さんがいわれたとおり、蒐集家の行き着く先は、玩物喪志。
だが、久遠劫より今まで流転せる苦悩の餓鬼道はすてがたく、ダウンロードやストリーミングだけで暮らす安養のネット浄土は、いまだ恋しからず候、候。
十月二十三日 黙示録の土曜日
サントリーホールで、尾高忠明指揮の日フィルを聴く。メインはウォルトンのオラトリオ《ベルシャザールの饗宴》。
ちょうど一週間後には、大友指揮東響のエルガーのオラトリオ《生命の光》を聴く予定なので、ときならぬイギリス・オラトリオ週間。
バーナード・ショーのいう「レクイエムを聞いて背筋をゾクゾクさせている」イギリス紳士淑女の気分になれるか。
それにしても、《ベルシャザールの饗宴》て、なんなのだろう。
ユダヤ人たちの「バビロン捕囚」の嘆きに始まって、かれらを苦しめるバビロン王、ベルシャザールが堕落した豪勢な饗宴を開いていると、いきなり手が出現して、王の破滅を預言する言葉を書く。
その夜、王は死に、バビロンは二つに分裂して弱体化する。そして、神罰によるバビロンの崩壊と滅亡を喜んで、ユダヤ人たちが神への讃歌を絶叫する。
この讃歌がなんとも、けたたましい。
聴きながら、福田恆存が訳したD・H・ロレンスの『現代人は愛しうるか 黙示録論』のことが、頭に浮かんでいた。
現世の弱者、貧者たちが、権力と富をもつ者(その象徴がバビロン=ローマの栄華)をうらやみ、嫉妬し、その破滅が黙示録のなかに預言されていることを来世の救いとし、その滅亡のさまに、ゾクゾクするような復讐と勝利の快感を味わう。ヨハネ黙示録の正体はそれだと、炭鉱夫を父にもつロレンスは喝破する。
三十年近く前に読んだきりだから、かなりいい加減な記憶だが、このオラトリオの結末の「勝利の讃歌」の、脅迫的なリズムによる絶叫は、歌詞も音楽も、双方がその黙示録論を思い出させた。
今日の演奏が、ドライできつい響きのもの――誇張抜きで、途中で左耳がキーンと耳鳴りした瞬間もあった――だったことも、歌詞の内容にふさわしい、音楽の暴力性をわかりやすくする作用をしたのだろう。
プログラム掲載の日本語訳(訳者名の記載なし)から、一部を引用する。
そこで、我らの力なる神に向かって高らかに歌え、ヤコブの神に向かって、喜びの声を上げよ。
地の王たちが嘆き悲しみ、地の商人たちは泣きわめいて、その衣服を引き裂くとはいえ。
彼らは泣き悲しみ、いたく嘆く。大いなる都もひとときのまに、そのさばきが下されたことを。
(略)
ヤコブの神に向かって、よろこびの声をあげよ。
バビロンの栄華は、地に墜ちたからである。
ハレルヤ!
帰宅後に調べると、この歌詞(ウォルトンの友人シットウェルが書いたもの)は、前半の題材こそ旧約聖書だけれど、後半の讃歌は、ヨハネ黙示録からとったものらしい。やはり、黙示録そのものと結びついていたのだ。
ならば、このバビロンは歴史上のバビロンを指すと同時に、黙示録でいうところの「大淫婦バビロン」、黙示録が書かれた時代の信者たちにとって、燃えるような嫉妬と憧憬の対照だった栄華の都、ローマの暗喩でもある。さらに後世の人にとっては、過去の存在ではなく、つねに現世の、権力者(地の王)と資本家(地の商人)を呪詛しつづけるものだと、ロレンスは指摘していたはずだ。
さらに面白いのは、このオラトリオと『黙示録論』が、ほとんど同時期に書かれていたことだ。
オラトリオは一九二九年から三一年に書かれて三一年に初演、黙示録論は一九二九年に書いて、三〇年発表。
両者に直接の関連はないだろうが、背景の時代精神は一緒なのだ。
一九三〇年前後。第一次世界大戦の結果、既存の政治体制が搖らぎ、大衆が、社会を大きく動かしはじめた時代。一方では、二〇年代のアメリカに出現した、大量消費社会の沸騰。その象徴である、ハリウッドを光源とする、映画文化の普及(そういえば、『ハリウッド バビロン』という、醜聞史の本もあった)。
そして、ロシア革命の影響が西欧を揺るがした時代。ロレンスがいうような、富者を打倒する「最後の審判」が弱者に与える「復讐の快感」は、共産主義者が叫ぶ「革命」の概念に、よく似ている。
イギリスでは、そうした急進的なマルクス主義の暴力性を嫌う人々が、漸進的な社会主義であるフェビアン協会をつくって活動し、かれらと関係の深い労働党が、政権を握っていた。だが、世界大恐慌の波及で方針は揺らぐ。
教会にとっては、共産主義こそ最強の「反キリスト」であり、かれらもまた、ハルマゲドンの接近を意識するようになる。また、共産主義に暴力的に対抗できるものとして、同時にそのヴァリエーションとして、ファシズムが敗戦国に台頭してくる。
この混乱、沸騰、イデオロギーの戦国時代みたいな社会状況が、ヨハネ黙示録に注目する人を増やしたのか。ロレンスやウォルトンは、その一人だったのか。
フランツ・シュミットが《七つの封印を有する書》を書いたのも一九三五~三七年、ナチス・ドイツの圧迫が強まる、オーストリアにおいてだった。
じつをいうと、黙示録のことは少し前から、気にかかっていた。
というのも、来月に日経新聞で批評する予定になっている、メッツマッハー指揮新日本フィルの二つの演奏会。
その曲目が、じつに暗示的で面白い。
・十一月二日
ブラームス:悲劇的序曲
ハルトマン:交響曲第6番
チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」
・十一月六、七日
マーラー:交響曲第6番「悲劇的」
「悲劇的」二つに「悲愴」一つというタイトル。そしてそれよりも気になるのが、交響曲第6番が三つで「666」。
映画『オーメン』でおなじみ、黙示録の「獣の数字」だ。
メッツマッハーはいったい、何をあらわそうというのか(笑)。
柴田南雄が、「第六」といえばベートーヴェンの「田園」、という人もいるだろうが、自分にとってはマーラーの「悲劇的」こそ「第六」だ、といっていた記憶があるが、それも思い出してみたり。
と、黙示録が気にかかっていたところへ、今日のウォルトン=ロレンス。
マーラーを聴くのは再来週六日、同じ土曜日の予定。気がついたら「黙示録の土曜日」が、いきなり幕を開けていた。
そして、その中間の土曜日には、ヨハネはヨハネでも、黙示録ではなく福音書の方にもとづくという、エルガーのオラトリオ《生命の光》の日本初演がある。黙示録の狭間で、どんな印象を与えてくれるのか、これも楽しみだ。
ロレンスはたしか、キリストは精神的強者であり、その愛は、その強靱さにもとづくものなのだから、黙示録の「弱者の復讐劇」は、キリストの愛の精神とは何の関係もない、というようなことをいっていたはず。
そして《生命の光》が扱うのは、まさにそのキリストの「愛の力」らしい。
なんとも見事な、偶然のシリーズ。
東京って、とても面白い町だとあらためて思う、クラオタが一人。
十月二十九日 ハクビシンを見た!
深夜、二階の我が部屋。窓の外で、ギシギシと物音がする。
近所の猫でも来たかと窓を開けると、目の前の電線の上を、イタチのようなものが、長い尾をたててバランスをとりながら、歩いていく!
少し先の電柱に到達すると、ささっと別の電線に乗りかえ、視界から消えていった。
南元町あたりで見たという話をネットで呼んでいたし、前々から何となく気配はあったが、とうとう、この目で見た。都会のハクビシン。鼠やカラスを襲うだけにして、猫は襲わないでほしいが…。
近年は山手線内の古い住宅の屋根裏などに住みつき、野外での樹上生活を、そのまま電柱と電線に置きかえて、棲息しているらしい。変化する都市の生態系。
十月三十日 人生の光(生命の光)
大友直人指揮東京交響楽団、東響コーラスなどによる、エルガーのオラトリオ《生命の光》。
予想どおり、とても充実した演奏だった。日本初演の作品を、全員が暗譜で歌った東響コーラスの努力はそれだけでも称賛に値するし、それにふさわしい結果が、練れた響きと確かな骨格にあらわれていた。
大友&東響は二〇〇二年から〇五年にかけてエルガーのオラトリオ《神の国》《使徒たち》《ゲロンティアスの夢》を演奏して好評を得ており、今回は、いわばシリーズの完結編。
とはいえ、《生命の光》は前述の三作品に先んじて書かれたもので、エルガーがまだ地方的作曲家という境遇に甘んじていた頃の作品。
大傑作ではないが、しかし、実に堂に入った、立派な響きの作品だった。
オラトリオ第一作でここまで書けるのは、エルガー個人の力というより、二世紀の伝統をもつ、イギリス・オラトリオ界そのものの厚みがなせる業という部分もあるのではないか。
ベートーヴェンの交響曲、あるいはその後継者としてのワーグナーの楽劇をヒエラルキーの頂点とする、ドイツ・ロマン派中心の音楽観では、市民音楽、国民音楽としてのオラトリオの重要性は見えなくなってしまうが、イギリスでのその歴史は、再検証の価値がありそうだ。
オラトリオは自分たちの言葉で歌える点で、オペラよりも自由な存在だった。ヘンデルにしても、オペラからオラトリオへの転回を、経済的破綻、撤退といった消極的な意味合いで捉えがちだけれども、イギリスの音楽界、興行界から見れば、もっと積極的、肯定的に考えることができるのではないか。少なくとも演奏史に関しては、そこには豊かな歴史があるはずで、だからこそ英語のオラトリオは、イギリスの「国民音楽」と位置づけられるに至ったのだろう。
ハイドンが晩年に、その代表作である《天地創造》と《四季》を書いたのも、ロンドン滞在でヘンデルのオラトリオに接した影響だという。作曲と初演はウィーンで行われたが、前者の台本はもともと、イギリス人がヘンデルのために書いた英語のもので、それをドイツ語訳したものだった。後者も、前者の独訳を担当したスヴィーテン男爵が、英語の叙事詩をオラトリオ化したものである。
この男爵はそれ以前に、モーツァルトにヘンデルの《メサイア》や《アレクサンダーの饗宴》の編曲を依頼していたことでも名高い。
オラトリオの先進国はイギリス、という印象が、当時はあったのではないか。しかもヘンデルは、イタリア主導の音楽界において国際的に活躍した、貴重なドイツの先達だった。そして、オペラはイタリア語でなければならないが(ハイドン自身のオペラも基本的に伊語)、オラトリオは自分たちの言葉でよい。
メンデルスゾーンなどは、この流れを引き継ぐ人だったように思える。結局、ウェーバー、マルシュナー、ワーグナーによるドイツ語の歌劇運動がドイツ音楽の主流になることで、オラトリオの比重は軽くなってしまうが。
さて、《生命の光》の物語は、いかにも福音書らしい話。
盲目の若者がイエスに出会い、その奇蹟によって目が見えるようになる。
しかし、パリサイ人たちはそれを「ありえないこと」とし、イエスは預言者だと断言した若者を、虚言で世を惑わす者として、国外追放に処してしまう。
それでも若者は、イエスを神の子と信じる。
イエスを「世の光」とたたえる、祈りの合唱で終り。
キリスト者の方はよく知っている話なのだろうが、いかにも聖書らしい「例え話」だ。
盲目は、いうまでもなく、キリスト教に出会っていない状態を指す。
視力の獲得は、その教えを信じることによって、その人生が光であまねく照らされること(THE LIGHT OF LIFEは、「人生の光」と訳すこともできると大友はプレトークで語ったが、意味としてはその方が妥当な訳だろう)
ポイントは、キリスト教の信仰を得て開眼したことによって、社会から、共同体から、追放されること。
現世利益とは無縁で、社会的弱者であることを運命づけられるけれども、信仰による孤高の精神的強者として、愛と寛容の心をもって世を生きぬくことができるようになる、ということ。
ロレンスの論にしたがって大雑把にいえば、ここで、では自分を迫害したものを、その無知ゆえに赦すか、最後の審判での復讐を願って呪うかで、福音書の世界と黙示録の世界とにわかれる。
このオラトリオは、福音書の世界にとどまるわけだ。
ただ、こうした孤高の信仰は、きわめて内省的な、パーソナルなものではないかと思えるだけに、それを大管弦楽と百五十人の合唱団に四人の独唱で、教会ではない世俗の演奏会場で、壮大に響かせることには、なにか「市民社会」そのものの矛盾、という気がしないでもない。
ヴィクトリア朝の偽善的道徳観そのもの、とも考えたり。
この音楽の真下で、黙示録のどろどろした怨念の世界が、渦巻いているような感じがするのだ。
プログラムの等松春夫さんの一文によると、この作品から四年後にエルガーは《ゲロンティアスの夢》でイギリス楽壇の寵児となり、楽界の期待に応えて「使徒三部作」にとりかかる。
イエスの受難とその後を描く連作で、その初めの二作が前述の《使徒たち》と《神の国》。
エルガーはこの三部作を「ニーベルングの指環」のように、三夜連続で演奏することを考えていたという。エルガー自身は、イギリスでは少数派のカトリックだったが、「使徒三部作」は多数派にあわせて、イギリス国教によっており、完成していれば、イギリス国民音楽の頂点をなしたかも知れなかった。
しかし三作目は、ついに書かれなかった。《神の国》初演から、二十八年間も生きていたのに、である。
その三作目というのが、なんと《最後の審判》だったというのが面白い。
エルガーは黙示録の音楽を構想しながら、ついに書けなかった。
交響曲のような純器楽、標題性をもたない純粋音楽に関心が移ったこと、次第に信仰心が薄れたことなどが理由として推測されているが、本当のところは、よくわからない。
ところで、《生命の光》の終曲の讃歌の歌詞は、こんなふうに始まる。
「世の光」である主よ! あなたをたたえて、天使たちと、大天使たちが声あげ、さらに、天のすべての大軍が加わります。
たとえ人間の賛美の歌声が弱く、調和を欠くその歌声では讃えきれずとも、天が声をあげ、神から御子に与えられた栄光を、高らかにたたえます。
(カペル=キュア作詞 秋岡陽訳)
人間は弱くても、大天使たちと天の大軍が代りに歌ってやるという。
弱き人間の代行者となる、神の軍勢。
やはり、かなり黙示録風で、その背中が見えるようだ。
もちろん、この部分の音楽もそうだ。
独唱より、合唱と大管弦楽の比重が増したロマン派以降のオラトリオやカンタータ的な音楽は、その形式自体が、黙示録の世界に近くなるのかも知れない。
ヴェルディのレクイエムでいちばん印象的なのは〈怒りの日〉の音楽だし、マーラーの《復活》も、もろに最後の審判を音化したものだし。
教会を脱けつつある近代人に、宗教を補強するものとして、あるいはその代りとしての、黙示録的オラトリオ? 当時のオカルト・ブームの流れの一つ?
大衆社会が台頭する両大戦間が、一つのクライマックスとなるのか。《ベルシャザールの饗宴》があって『黙示録論』があって、一方でエルガーは書けずにおわって、「千年帝国」が登場して、フランツ・シュミットの《七つの封印を有する書》がうまれて。
話は飛ぶが、日本のように宗教音楽の伝統のない国で、最初に流行した「オラトリオ」が、ショスタコーヴィチの《森の歌》だったことは、どんな位置関係になるのか?
十一月一日 早慶が優勝決定戦へ
六大学野球の早慶戦、一つ勝てば優勝をきめていた早稲田が、慶応に連敗して同率で並ばれ、両校による優勝決定戦が行なわれることになる。
早慶による優勝決定戦は、一九六〇年秋以来、奇しくも、ちょうど五十年ぶりのことだそうだ。
そのときのことは、私も一九六〇年の『らいぶ歳時記』十一月六~十二日の項に書いているが、「伝説の早慶六連戦」と呼ばれる、大熱戦になった。
まず、リーグ戦での対決を二勝一敗で早稲田が制し、慶応に同率で追いついて優勝決定戦となったが、延長十一回、日没による同点引分が二試合続いて(学生野球の聖地にプロがきては困るという理由で六大学が反対し、当時の神宮にはナイター設備がなかった)、三試合目、リーグ戦を含めると六戦目で早稲田が勝って、ようやく勝負がついた。
このとき、早稲田のエースの安藤元博は、一つ負けた以外の五試合、延長を含めた計四十九回をただ一人で投げぬいて三勝を挙げ、「鉄腕」と讃えられた。
今はナイター設備があるし、延長無制限だから、再試合になることはない。だが、記憶に新しい「再試合」といえば、甲子園で斉藤祐樹が勝った試合だから、どうしても因縁づけたくなってしまう。
いずれにせよ、斉藤が有終の美を飾るのには、最高の舞台だが……。
海軍話にかまけているうちに、可変日記には書き忘れたが、先月十四日、神宮へ東京六大学野球を見にいった。
夏に高校野球の早早戦をみて、大学野球にも興味が出たのと、毎年恒例にしていた、国立でのユース・サッカーの高円宮杯準決勝戦を、悪天候で見にいかなかった(選手たちはもちろん、雨のなかで戦ったが)ので、その代りという意味合いもあった。
早稲田対立教、慶応対明治の二試合。二戦目の日曜日、斉藤が登板しない日ということもあって席には余裕があり、バックネット裏の指定席という、プロ野球では経験のない好位置で見ることができたので、面白かった。
大学野球は現役時代、まだ立教に長嶋一茂がいるときの早立戦以来、四半世紀ぶり。だが、二番手で登板した大石のキレのいい速球(最速百五十一キロ)、そして九回裏二対二の同点から、四番山田の、レフトへ美しい放物線を描いたサヨナラ本塁打など、バックネット裏からだと、とても見応えがあった。
しょせん、レベルの低いアマチュアじゃないかという人もいるだろうが、気持ちの入ったプレーの素敵さに変りはないし、それを低価格で、余裕のある観客席で、のんびりと眺められる。
同じ神宮で、プロの阪神戦でも見ようと思ったら、スタントは人だらけで応援は賑やか、なんとも落ちつかない。
それよりはるかに快適だし、年をとったせいか、学生ならではのナインとベンチの一体感とか、攻撃開始時に一、三塁コーチ席につく選手の全力疾走とか、そんなことが見ていて嬉しくなる。
またナマで見てみたいが、しかし早慶戦となると、ほぼ満員だろうとためらっていたら、優勝決定戦まで実現。
先日の早立戦に続く慶明戦での、慶応打線の振りの鋭さに「これは、早稲田の三投手も苦労しそう」といういやな予感があたって、斉藤、福井、大石の三人とも打ち込まれてしまった。
仕切り直しの決定戦は、どう考えても斉藤がピシッと抑えるしか勝機はない。舞台は、少なくとも舞台だけは、これ以上ないくらいに整っているのだ。
それにしても、私が現役の頃は法政明治の全盛期で、早稲田も弱い(創立百周年のときに、桐生高校からきた木暮などががんばって突然優勝したが、「御祝儀優勝」みたいな感じがぬぐえなかった)が、学業優先の慶応はさらに輪をかけて弱く、早慶戦はただのお祭りで、実体は消化試合、というのがほとんどだった。
ほんとうに時代は変った、というか、めぐった。半世紀ぶりの決定戦、ともかく、いい試合になることを祈るのみ。
十一月二日 ナマのメッツマッハー
メッツマッハーと新日フィルの「獣の数字」シリーズ、第一日をサントリーで聴く。
この指揮者は正直、CDでの印象はイマイチだったのだが、ナマだとかなり違って、とても好きなタイプ。
リズムがちゃんと下まで落ちないで、上滑りしているようにCDでは聴こえたのだが、ナマでは逆に、軍楽隊ふうに強拍が強調される。この軍隊調はケーゲルや初期カラヤンに顕著だったもので、しかも筋肉質の、輪郭線の太い緩急強弱の描きわけは、クレンペラーなど、戦前の新即物主義の様式に通じている。
つまり、あえていえば、きわめて古風な、「ドイツ風」の指揮者なのだ。ハンブルク歌劇場やバンベルク響など、現代音楽シンパなのに非放送局の団体で名声を得てきたあたりも、この人が「どんな複雑な曲でもさらりと振れる」ような、器用なタイプではないことを物語っているのかも知れない。
だが、ハンブルク時代からかれを聴いている知人によると、ここ数年で急速によくなったということだから、CDとの差は録音とナマの差だけでなく、本人の成長による部分もあるようだ。
ハルトマンの交響曲第六番は特に素晴らしく、メッツマッハーの主張が奈辺にあるのか、よく示されていると感じた。静と動、平穏と闘争の音楽がめまぐるしく交錯し、入れ替わる。
チャイコフスキーの《悲愴》のは、それに較べれば古典的な交響曲だから、楽章単位、あるいはそれを二部か三部に分ける程度で、しかしやはり明確にその陰陽が区別される。ドライに、しかし機械的にならずに、強弱のコントラストをはっきりとつけるあたり、新即物主義の再来を感じる。
スケルツォではイチニ、イチニと足踏みしながら指揮したり、まさに軍楽。
「交響曲の父」、ハイドンが軍楽用の各種打楽器を大胆に導入したナポレオン戦争のころから、交響曲というのは硝煙の臭いのする、血なまぐさい要素をはらむようになったわけで、チャイコフスキー、マーラー、ハルトマンは、ハイドン将軍の正統な後継者たちだった、ということなのかも知れない。
六日のマーラーも大いに楽しみになったが、最近の録音も聴いてみなければ。
十一月三日 優勝決定戦
早慶の優勝決定戦、NHKがテレビ中継していたので、最後まで観てしまう。
楽勝で終れず、ノーヒットノーランも消えるあたりが、いまの斉藤なのか。でも、ゲームをつくったのはかれだし、中押しのタイムリーを自分で打って、慶応のエースの一人、福谷にショックを与えたことが慶応の継投策を狂わせ、最後には登録したピッチャーがいなくなる結果を導いたわけで、功績は大きい。
反撃した慶応の総力戦も凄かったし、学生野球ならではの波瀾の展開も最高。そして、何たって最後の、大石の百五十三キロの高めのストレート。大石達也というより、上杉達也みたいな豪速球。ほれぼれさせられたが、斉藤が楽勝していたら、この「剛球一直線」はなかったのだから、終りよければすべてよし。
一方で、これが四年生にとっては「最後の早慶戦」であることを、二人の監督が強く意識し、かれらの思いを汲みあげて勝利に活かそうと、苦心の采配をしているのもよくわかった。
うまくいかないこともあったのは、乱戦だけに仕方がない。しかし、最終回、エラーがらみで早稲田に決定的な追加点を与えた投手――野手で登録されていた急造投手――が、いったん次の投手が出てきたのに続投することになったのは、かれが四年生だからこそだろう。それに応え、懸命の投球で後続を断って、仲間に声をかけられていた場面は、敵ながらこちらも胸が熱くなった。
やっぱり、学生スポーツには学生スポーツのよさがある。来季も行ってみたいが、慶応の主戦投手が二人とも二年生だったことを考えると、早稲田は苦戦必至かも。
ただ、高校の早早対決で投げ合った早実の鈴木と学院の千葉の両エースが、きっと来年大学に入るだろう。いきなりの活躍は難しくても、楽しみが入れ替わりながら、受け継がれていく。
しかし今日の神宮外苑は、超満員の野球の早慶戦に大学ラグビーに、サッカーのナビスコ杯。天気もよかったし、信濃町も千駄ヶ谷も外苑前も、駅は人で凄まじかったことだろう。
夜は新宿に、早大生が繰り出しているはず。昔は、コマ劇場前の噴水でみんなで泳ぐ(バカ)ときまっていたが、あの噴水のない今は、どうするのだろう?
十一月五日 日本アマゾンの十年
日本のアマゾンのサイトに、開業十周年と出ていた。まだ十年しかたっていないのか、ということに驚く。
目黒から引越して、文筆業専業になったのが二〇〇〇年の夏なのだが、それよりも後にできたことになる。もっと前のような気がするのだが、私の記憶もいい加減なものだ。
友人に教えられたが、アマゾンのサイトでは自分の購入記録を、最初までさかのぼることができる。それを見ると、日本アマゾンで最初に買ったのは二〇〇〇年の十一月、それ以前は載っておらず、なるほどこのころに開店したらしい。
米英のアマゾンをすでに使っていたから、デザインが同じなのはわかりやすかった。今は何でも扱っているが、当時は本を買うサイト、と私は考えていた。
ついでに見てみると、米国のアマゾンは一九九八年、英国のは一九九九年に買った記録が残っていて、自分が内外のネットで物を買うようになったのが、大体このあたりからだとわかる。
そんな程度の古さでしかないのか、十年て、思った以上に長い歳月なんだなと思うと同時に、そんな長期間の記録が一つ一つきちんと残り、集積されているアマゾンやほかの商業サイトって、やはり少し恐ろしい気もする。
たしかにそれは事実なのだろうし、サイトにとっては、血の通った人間のことではなく、無量大数の顧客データのなかの、一つに過ぎないわけだろうけれど。
十一月六日 悲劇的、悲しみの聖母
「黙示録の土曜日」三週が無事に終了。メッツマッハーの《悲劇的》は予想どおり、激烈な闘争とつかのまの平穏と、そして敗滅の音楽だった。
英雄は打ち倒され、神の国が来るかどうかは、わからぬままに終る。
緩徐楽章を第三楽章にした曲順も、個人的には賛成。マーラー本人の意図はどうあれ、第一、第二と二つの楽章で激闘し、心身ともに消耗しきって、第三楽章で戦場を離れて安息と感傷の時間を過ごし、そして終楽章で最後の戦いへ、という時間の流れの方が、自分には共感しやすいからである。
(話はそれるが、ブルックナーで、もし第八番と第九番も第七番までと同様に、アダージョを先にしてスケルツォを後に配置していたら、曲のありがたみは大きく減っていたのではないか。特に第九番が、あのスケルツォで終っていたら、聴く方はどう感じるのだろう。補作だろうとテ・デウムだろうと、終楽章をつけずにいられないにちがいない)
終演後、すみだトリフォニーから新宿に移動してタワーレコードへ。
フリットリの歌う、ボッケリーニのスターバト・マーテルを見つけて購入。イタリア・ソニー。こんな盤、いままで気がつかなかった。考古学者の森浩一のいう通り、やはりフィールドワークは大切である。
友人たちによると、数か月前から売っていた由。たしかに『オペラ御殿』の棟梁日誌には、今年の三月十日の項に早くも紹介されている。何か既視感がある気がしたのは、ミン吉棟梁のこの日誌を読んでいたかららしい。そこにもあるように、日本のアマゾンのサイトがなぜか既に扱っていて、他店の担当者がそれを知って、出入りの輸入業者に依頼して、仕入れたのだとか。
日本の小売店は、それぞれに輸入業者が異なるために、マイナー盤やローカル盤の場合、けっこう店によってアイテムや入荷時期、価格に差が出る。
まあ、マニアにとってはみんな同じではつまらないし、相違を見つけることが楽しみであったりもするので、結構なことなのだが。
十一月十日 見たら死ぬディスク(笑)
「気になる盤」で紹介した、一九六〇年ライヴのサンツォーニョ指揮の《ファヴォリータ》(WALHALL)が他の盤とともに到着した。
こうした盤は厳密には、二〇一一年元旦にならないと隣接権が切れて公有にはならないはずだが、ラテン的気楽さか、海外ではフライングで発売してしまっているらしい。
日本の小売店が扱っていないのは、輸入業者のほうで、来年まで止めているためなのだろうか。日本には神経質なお客もいそうだから、自衛策なのかも。たかが数か月、されど数か月である。
ところでこの《ファヴォリータ》は、三十年ほど前にメロドラムがLPしたきり、CD化されなかった音源である。
私が一九六〇年の録音をすべて集めようなどと、馬鹿なことを思いたったのはCD時代になってからだが、その頃にはもう中古盤すら見なかった。海外のサイトなどにも見当たらず、まあ大げさにいえば「幻のLP」だったのである。
そういうLPは他にも何種かあって、たとえばバイロイトでのマゼール指揮の《ローエングリン》のメロドラムのLPも、その一つだった。
これは発売当初の一九八〇年代に代々木のジュピターで購入したが、一九六〇年というだけで後に必要になるとは夢にも思わず、売却してしまった。そしてそれきり、やはり再会できなかった。
この種のイタリア盤は、廃盤にもかかわらずディスクユニオンなどでは二束三文に近いから、なかなか処分する人が出ないのか、それとも、出る機会はあっても安いので、すぐに売れてしまうのかわからないが、当方がそう頻繁に行くわけではないこともあって、見かけないままに十年以上の歳月がすぎてしまった。
それで、あまりに発見できないので、もし店先で出会うことがあったら、それはオレが死ぬときじゃないか、などと冗談で考えるようになった。
初めは冗談でも、長く続くと、何となく、ほんとうにそんな気になってくる。愚かな話だが、ユニオンでオペラのLP棚を見るとき、変にドキドキしたりするようになってきた。
だが、マゼールの《ローエングリン》は二〇〇五年にCD化され、そして《ファヴォリータ》も今年CD化され、LPを探す必要はなくなった。
呪いは解けて、死なすにすんだ。ほっとしている。
ところが、じつは今、CDで長いこと再会できない盤があって、これが新たな呪いになりそうなのだ。
それが何かは、書くまい。どこそこの店にありましたよ、と教えられたりしたら困るから。ただ、別のレーベルが再発して、一日も早く、呪いの解ける日が来るのを神に祈るのみ。
十一月十三日 千葉南部のキョン
TBSの「情報7days ニュースキャスター」で、動物のキョンが、千葉南部で一万頭も繁殖し、農作物を食い荒らして害獣化していることを紹介していた。閉鎖された動物園(行川アイランドか?)から逃げたのが、きっかけとか。
私の年代には『がきデカ』の、「八丈島のキョン!」のギャグが懐かしいキョンだが、実物は悪魔を想わせるヤギの顔とツノに、恐ろしく不気味な鳴き声。
都会のハクビシンといい、変っていく生態系。いまの日本にはどちらも天敵などいないから、どんどん繁殖するのだろう。気味悪~。
知人は、ジビエ(フランス料理に用いる、野生の鳥獣肉)の材料にすれば、新たな千葉名産になるのではと言っていたが、さて。
十一月十五日 革命の暴力
新国立劇場で、《アンドレア・シェニエ》を観る。再演だが、私は初めて。
演出のフィリップ・アルローは今年の開幕の《アラベッラ》の人だが、《シェニエ》の方が、ずっとよかった。主役たちの運命をもてあそぶ、フランス革命の血を流させずにはおかない暴力性が、わかりやすく描かれていたからである。
はてない復讐と没正義の権力闘争が、無数の死者を生む。黙示録的な「貧者の復讐」がいかなる事態を招きうるかを、フランス革命がまず示し、十九世紀が始まったのだと、あらためて思う。
歌もスタイルはそれぞれだが、この作品に必要なパワーがあって気に入った。指揮のシャルランも、前回の《トスカ》よりもこの作品の方が合っている。イタリア・オペラではあっても、ことパリが舞台となると、指揮も演出も、フランス人ならではの利点が活きるのかも。
こういう、社会と個人の運命が巧みに結び合わされた歴史ドラマは、高校生が見るにもよいのではとも思った。だが、日本人キャストだけでこの重量級の作品をやるのは、ちょっときついか…。
十一月十六日 偶発ステレオ
「気になる盤」に紹介したが、トスカニーニの一九五一年のヴェルディのレクイエム、RCAで出ている有名な音源だが、そのステレオ版を売っているサイトがある。
ステレオといっても正規の機材によるものではなく、いわゆる偶発、アクシデンタル・ステレオ。
当時のNBC放送はメインの中継ラインのほかに、別のマイクからの予備のラインがあって、それも録音されていた。二つのマイクは位置がわずかながら異なっていたので、両者の録音をシンクロさせることができれば、原始的なステレオ録音が生れる。
ということで二種の録音を用い、ステレオ化したもの。
この別ラインによる偶発ステレオはSPにも例があり、エルガーの自演盤やデューク・エリントン楽団などはCDにもなっている。トスカニーニとNBC響の場合も、話そのものは以前から知られていて、ラテン・アメリカ向けに、スペイン語のアナウンスを加えて放送していた別ライン録音を組みあわせて、一九四二年三月十四日のエル・サロン・メヒコのステレオ録音をつくってみた人がいるそうだが、このレクイエムのことは、今回初めて知った。
定位などは怪しいが、たしかにステレオで聴こえて、かなり楽しめる。
トスカニーニというと、オーパス蔵が発売したイギリスHMV原盤のトスカニーニものはかなり音が違い、最近の《オテロ》などは、カルショーが『レコードはまっすぐに』でカラヤン盤の制作時に触れていた、あの冒頭の重低音がしっかり入っているのに驚かされた。
これはRCAのCDでは、よく聴こえないものなのだ。HMV盤はじつは別ライン録音で、RCA音源と合わせると偶発ステレオになる、なんてことだったら愉しいが…。
十一月十八日 福井大石斉藤対菅野
明治神宮野球大会、早稲田大学対東海大学による決勝戦を神宮へ観に行く。
先発の福井は前回見たときと同様に立ち上がりが不安定で、二回に失策がからんで一点を失う。対する東海大のエース菅野はさすがの好投手で、とても点を取れそうになかったが、六回裏につかんだワンチャンス、二死満塁から四番山田が二点タイムリーを打ち、二対一と逆転。
直前の六回表、一死二、三塁のピンチを、福井がしのいだのが大きかった。ここで一点でも中押しされて二点差になっていたら、今日の菅野の出来からして、そのまま押し切られていたはず。
まさに、ピンチの後にチャンスあり、という勝負事の鉄則そのもの。結局、菅野が早稲田に許したのはこの二点だけだから、ほんとうに大きかった。山田は前回見たときにも、立教相手にサヨナラ本塁打を打っていて、まさに四番にふさわしい活躍だった。
逆転後の七回表に登板した大石が、またよかった。七、八回の二イニング、打者六人から五三振を奪う快投。
普段はこの大会の観客数は知れたものらしく、外野席を閉鎖して、入れるのは内野席のみ。私はヘタレにも「一塁側の早大席は混むだろう」と思って、東海大側の内野席にいた(結局は東海大側も満杯になり、混むのは一緒だったが)。
大石のボールを見た瞬間、周囲の客席が一気に意気消沈する気配を感じて、ひそかに快哉を叫ぶ(イヤな奴)。
この投球に勢いづけられたか、早稲田は八回にもチャンスをつかんだが、ここは菅野がふんばり、センター伊志嶺(ロッテが一位指名)の気迫のこもったファインプレーもあって、無得点。
そして九回表、斉藤がマウンドへ。
正直、大石を降ろすのはもったいないし、危険な気がしたけれど、それを納得させてしまうのが、斉藤という男なのだろう。
大石が降りて、ひょっとしたらとふたたび期待し始めた東海大側応援席。学生たちは「ハンカチだ」と馬鹿にし、斉藤が投球練習で二球ほどワンバウンドを投げると野次を飛ばしていたが、斉藤の第一球をみただけで、また意気消沈してしまったのが愉快だった。
個人的に嬉しかったのは、最後がサードゴロだったこと。
そのサードは、七回から守備固めに入っていた後藤。斉藤とは早実からのチームメートで、早実では主将だった。
ところがこの後藤、先日の早慶の優勝決定戦で、大きなミスをしていた。守備固めで一塁に入ったのに、なんでもないファールフライを落球、命拾いしたそのバッター(慶応の控え捕手)がチーム初安打を放ち、慶応の大反撃のきっかけをつくってしまったのである。
そのかれが、今日は最後にゴロを拝みどり、一塁へ投げて、ゲームセット。
きれいに終るもんだなあ、と。
斉藤自身はここまで二つ三振をとっていたから、三者三振で締める気だったはずだが、そうはいかなくて、それで後藤に、今日初めての守備機会がきて、そしてかれらの大学野球が、というか七年間のチームメートとしての関係が、終る。
野球選手としての実力云々ではなく、斉藤という人間の「力」(運、というよりも、何かもっと能動的なパワー)を感じた試合だった。
しかし、じつは八回のピンチをしのいだあたりでは、同時に東海大の菅野を応援していたり。
三人のドラフト一位投手を擁する相手に対し、菅野はたった一人。悪役を引き受けて、百五十キロのストレートを投げ続ける姿は、とても格好よかった。
まだ三年生、かれには来年がある。
東海大の応援も、面白かった。
ここには立派なチアリーディング・チームがいるはずだが、ほかの試合と重なったのか、今日の応援はさびしくも、野郎どもばかり。
そしてチャンスになったら、学ラン姿の応援団に代って、男五人でユニホーム着たのが登場して、TOKAIと一字ずつ書いたパネルもって、ニコニコ笑いながら、ダンスしていた。
女子チアリーディングの代役だったのか。これを見られただけでも、三塁側にいた甲斐があったというもの(笑)。
思ったことが、もう一つ。
この大会には、大学だけでなく高校も参加していて、午前の決勝戦で、日大三高が鹿児島実業に勝って優勝していた。
日大三高は、今年の夏も早実と都大会決勝を争っていたし、四年前、高校時代の斉藤が有名になるきっかけになった、都大会決勝の大激戦の相手でもあったから、長いこと、安定して強い。三高だけでなく、日大系列は、ほかにも二高、鶴ヶ丘、藤沢など、強いところが多い。
それなのに、日本大学そのものの野球部はひどく弱い。いまも二部に落ちていて、成績不振の責任をとって監督がシーズン中に辞任とか、ゴタゴタが数年続いている。
先日の慶応野球部のナインには、日大の付属高校の出身者が何人かいた。なぜかれらは日大でなく、慶大に進んでしまうのか? どうして、高校と大学の連繋が悪いのか?
今日見た東海大には菅野など、系列高の出身者が何人もいたから、日大のことがいっそう気になった。
東海大、早大とならんで学生数の多さを誇るマンモス大学、日大の不思議。けっこう偏差値の高い系列校もあるから、もともとつながりが弱いのか?
十一月二十日 高崎で群響を聴く(前)
去年、群馬交響楽団とその生みの親である丸山勝広のことを調べて、可変日記にも書いたことがあった(十月十六、十七日、十一月六日など)。
しかし、群響をその本拠地高崎の音楽センターで聴いたことは一度もないし、高崎という町自体、きちんと歩いたことがない。九〇年代前半、太田や大間々など群馬県の各地の現場に出張したし、前橋に長く勤務したこともあったが、高崎にはほとんど縁がなかったのである。
そこで、トゥルノフスキーが定期を指揮するという機会に、日帰りで聴きに行ってみることにした。
送電線の仕事に行くときには車ばかりだった(事務所や現場が駅から遠く、山の中の場合もあったから、車でないとどうにもならなかった)が、今回は電車。それも新幹線ではなく、往復とも在来線の高崎線を使うことにする。
新幹線に乗らないのはコスト節約の意味もあるが、時間はどうせたっぷりあるし、また、車で行ったとき、高速道路しか使わなかったために、落下傘でいきなり目的地に降りるようなもので、そこまでの景色の変化や、東京からの距離の感覚を肌で知ることができなかった、という反省があるからだ。
新幹線も高速道と同じで、やはり落下傘になる。遠距離ならともかく、高崎なら在来線の急行でも片道二時間弱。そこで、『ここに泉あり』の時代と、ほぼ同じ経路を体験してみることにした。
行きは新宿から、湘南新宿ライン経由の直通なので、乗り換えもなく簡単。午後に出て三時頃に高崎に着き、夜の演奏会までに街を見てまわる計画。
高崎線というと、私の子供時代には、日本一の殺人的なラッシュで有名だったが、今はそうでもないらしい。それなりに客が多かったのは、熊谷まで。東京まで毎日の通勤通学をするとしたら、大体このあたりが限界か。
熊谷のすぐ次の籠原駅で、車両数を十両から五両に減らす作業があり、数分待たされる。半分にしてもいいほど乗客数が激減するわけで、雰囲気はいかにも地方路線じみてくる。深谷、本庄――本庄って、こんなに遠いのか――、群馬県との県境に沿って、西北西へ。
そして高崎駅に到着。直前に『ここに泉あり』を観なおしていたので、小さな駅舎と、駅前の闇市が頭にあったが、六十年後の現代に、そんな景色があるはずもない。駅は大きく、背後の階上には新幹線のホームがあり、駅前には、仙台駅風のペデストリアンデッキがある。
市街の中心部は駅の西、烏川との間にある、高崎城址の周辺に広がっている。現代では前橋が県行政の中心、高崎が県経済の中心というイメージが固定しているが、高崎城は江戸初期に井伊直政が築いた由緒をもつ立派なもので、戦前は陸軍第十五連隊の駐屯地、戦後は市役所などの公共施設がある場所となっている。
今夜の演奏会場である音楽センターはそこにあるのだから、市中の主要な場所を与えられているわけで、高崎市における群響の重要性がよくわかる。
しかし、今日は音楽センターへ行く前に、まずは群響発祥の地である、ラメーゾンという喫茶店に向かう。それは市の北部、田町北交差点の南西角にある。
かつての中山道とおぼしき古い国道沿いの、大きなビルなどない町並みだが、丸山勝広の『この泉は涸れず』(本田書房)によると、戦前には高崎の目抜き通りだったそうだ。
だが敗戦直後の一九四六年初めには、戦前に高級店として知られた山徳呉服店のショーウィンドウに、高価な着物や帯の代りにゴム長が干してあるほど、物のない状況になっていた。
その山徳呉服店の向いに、「市内最大のデパートであった」熊井呉服店の一棟があった。戦時中は疎開した肥料会社が借りていたが、東京に引き上げて空いたのを、戦前のように品物が豊富な時代はもう二度とこないだろうからと、呉服店の熊井社長が、群響に気前よく貸してくれたのだそうだ。
建物は三階建てで、二階を高崎市民オーケストラ(群馬フィルハーモニーオーケストラと改称。通称群響)の練習場、三階を和室の集会所(楽団のプロ化後は県外から来た楽員の合宿所)とし、一階を、楽団長となった井上工業社長、井上房一郎の提案で、喫茶店とした。
その喫茶店が、ラメーゾンである。正式には、フランス帰りの井上の命名で、「ラ・メーゾン・ド・ラ・ミュージック(音楽の家)」という。
開店は、同店のホームページによると一九四七年九月一日とあり、丸山の回想では一九四六年十月だという。どちらが正しいのか私には判断できないが、その草創期の印象を、丸山が活写している。
「この店ができたときにはすばらしかった。けい光灯の間接照明だが電球がなく東京まで買いに行った。お客さんがドアの外からのぞいていて中に入ってこない。戸まどいしているのである。まだまだ世間は混乱状態で町はよごれていた。当時のラ・メイゾンのもつふん囲気は町の中できわだっていた。(略)二十一年から二十二年にかけてとにかくこの建物の二階からはオーケストラが、階下の喫茶店ではクワルテットや、芝居までが演じられたのである。
そして町の空気とはそぐわない明るい灯の下で、コーヒーなどをすすりながら毎晩十時十一時まで、文化人といわれるような人が集まって、だべっていた。
『パリではこんなふうにしているうちに夜が明けてくるんだよ』と井上さんのいった言葉が耳に残っている」
――パリではこんなふうにしているうちに夜が明けてくるんだよ。
この井上の言葉は、私にはとても印象的に響く。この店を、地方にはそぐわないほどの、洗練された都市文化の灯にしようとしたのは、誰よりも井上房一郎だったのだ。その思いがこの一言に、痛いほどに込められている。
ラメーゾンでの最初期の活動には、楽団指揮者の山本直忠を院長に附属音楽院を開設、歌とピアノなどを教えたり、教養講座と名打って、井上自身が講師役となってフランス絵画の講義をするなど、まずは畑を耕し、底辺を拡大しようとする動きが含まれていた。
のちの高崎哲学堂運動に通じる、こうした啓蒙活動こそが井上の考えていたもので、楽団をプロ化して性急に拡大をはかる丸山の、多分に誇大妄想的な目標とは、ずれていたのである。
その後、プロ化によってアマチュア楽員が手を引いたとき、井上がかれらとともに別楽団をつくる動きまで起きた。結局は分裂にいたらず、井上は群響の会長に戻ったが、丸山と井上の齟齬という火種は、その後もくすぶり続け、一九六三年の訣別に至ることになるのである。
しかし、井上なしでは、つまり丸山だけでは、今日の群響はありえなかった。そのことは、これから高崎市街を回るにつれて、強く感じるようになる。
熊井社長の予想に反し、東西冷戦のおかげで戦後経済の回復は急激だった。
熊井呉服店も売場を拡張することになり、楽団の練習場は一九五四年頃に移転を余儀なくされ、いまの音楽センターの付近にあった、旧十五連隊の兵舎に移った。指揮者が足に力を入れると、床が抜けてしまうボロ家だったそうだ。
ラメーゾンは田町に残った。
といっても、残念ながら当時の場所にはない。群響がいた元の建物は西隣、いまの近藤ビルの位置にあったという。一九六二年に現在の地に移転、建物は一九八八年に改装したものだそうだ。
そのラメーゾンに到着。奥の喫茶部に入って、コーヒーとケーキを注文。喫茶部はあまり大きくなく、持ち帰り用の販売がメインのようだが、老舗らしく落ち着いた雰囲気が心地よい。
『ここに泉あり』に出てくる喫茶店、「ラララ」とその建物は、ラメーゾンをそっくり再現していたというから、それを頭に描きつつ、元の用地を眺める。
周囲は、小規模な商店ばかり。戦前に高崎市で一、二を競ったという熊井呉服店も山徳呉服店も、見当たらない。ネットで調べたくらいでは、現存するのかどうかよくわからない。
後者は創立者の山田徳蔵がつくった、洞窟観音山徳公園にその名が残っているが、店舗そのものは時代の大波に、呑まれてしまったのだろうか。
現在の高崎市内の大型百貨店はスズランといい、これは本店が前橋で、高崎店は一九六八年に開業したものである。
(続く)
十一月二十日 高崎で群響を聴く(中)
ラメーゾンを出ていったん西に進み、すぐ南に折れる。古い商店街らしいアーケード街を抜け、また西に行くと、音楽センターが見えてくる。
演奏会にはまだかなりあるが、明るいうちにいちど見ておこうと思った。
センターの入口に面した北側は公園になっていて、高崎城のわずかな遺構、乾櫓と東門がある。
一九六一年に音楽センターが開場したとき、丸山が言葉を選んだという「昭和三十六年ときの高崎市民之を建つ」の碑が前庭に建てられた。
その建設費が、当時の市の年間予算八億の四割を超す、三億三千万という巨額なものであり、市民の賛同と募金活動なくしては、不可能なものだったからである。前庭が公園化されたためか、碑はあまり目立たない、木の陰にあった。
正面から眺めたあと、上から見ると白いザリガニのような、音楽センターの独特の建物の周囲を回ってみる。
音楽センターの西側から南側にかけては、シンフォニーロードという道路が走っている。これは一九九四年にできた新しい道路で、それ以前には西側のシティギャラリーの用地と合せ、そこに高崎市立第二中学校があった。
映画『ここに泉あり』が製作された一九五五年前後の群響の高崎でのホームグラウンドは、この二中の講堂(体育館)だった。当時の二中の校舎は、高崎連隊の旧兵舎を流用していたというから、木造の講堂も同様のものだったろう。
前橋で演奏するさいには、一九三〇年落成の群馬会館というホールが使えた。これも客席数は四百程度で、しかも音響はひどく悪かったが、その程度のホールすら、当時の高崎にはなかったのだ。
(市北部の本町に、一九一八年落成の高崎市公会堂という洋館があったが、戦時中から鉄道省や市庁舎に転用されたままで本来の目的には使えず、一九五〇年には火災で半焼してしまった。初期の群響が用いて、『ここに泉あり』にも出演した燭台つきの古ピアノは、もともとはこの公会堂の備品だったという)
そんな町が、楽員が二、三十人程度しかいないオーケストラのために、演奏会を主な用途とする二千人収容のホールをいきなりつくった。『ここに泉あり』の成功と好評がなかったら、ありえなかったに違いない。
市議会では、音楽ホールよりも体育館の方が先だという、ごく当然の意見も根強かった。
そこで両者を兼ねるような構造で、五千人収容の大公会堂という折衷案も出たが、多目的ではどっちつかずでよくないという丸山の意見を採用した住谷啓三郎市長が押し切って、「音楽センター」という、当時の公共建築では異例の、限定的名称をもつホールが誕生した。
ほぼ同時期に、東京都が上野に「ミュージックセンター」を建てる計画を立てていたから、あるいは名称のヒントは、そこから得たのかも、という気がする。
しかし、日本の首都と人口十万の地方都市とでは、文化を取りまく状況がまるで異なるのだから、その意気の高さは見上げたものだ。しかも東京さえ、結局は「東京文化会館」という曖昧な名前になったのに、高崎は「音楽センター」で貫徹したのだから、すばらしい。
ちなみに東京文化会館は一九六一年四月、群馬音楽センターは同年七月の開館で、来年ともに五十周年を迎える。
シンフォニーロードに沿って音楽センターの南に出て、そのまま駅の方へ。
群馬県は、一人当たりの保有台数が全国一位という自動車王国だから、高崎の町をこんなに歩きまわる人間も、少ないにちがいない。高低差のない平地続きで道もわかりやすく、歩きやすい町なのだから、もったいない気がする。
駅前のワシントン・ホテルの角を右に曲がって南下、八島町交差点にある高崎市美術館へ。
目的はこの美術館の隣にある、旧井上房一郎邸。美術館経由で見学できるようになっている。
この邸宅は、建築家アントニン・レーモンド(一八八八~一九七六)の事務所兼自宅「笄町の自邸」のデザインを写して、アレンジをくわえたものである。
レーモンドはチェコ生れのアメリカ人で、帝国ホテル建設の際に有名なライトの助手として来日、その後独立して、戦時中をのぞく四十年間、日本を拠点に活動した。東京文化会館の設計者、前川國男もその下で働いた経験があるという。そのレーモンドが一九五一年に麻布笄町に建てたのが「笄町の自邸」で、その原型は臨時の現場事務所だったという、木造平屋建ての簡素なものである。
翌年、自宅を火事で失った井上房一郎は、レーモンド邸の無駄のない、美しいデザインにほれ込んだ。それを写し、和風の生活様式に合せてアレンジして、自邸を建てなおした。
日本建築の美点を西洋建築にとりいれたレーモンドのモダニズムは、曲線のない、直線と斜線だけで構成されている。華美な装飾は一切なく、細い丸太で組んだむき出しの柱と梁に板を張りつけた、「小屋」と呼びたくなるような、単純な質素さ。窓とガラス戸が壁面の大部分を占め、非常に風通しがいい。西洋風に自然を遮断するのではなく、自然とともにある、優しい建物。窓やガラス戸の棧がとても細くて繊細に感じられるのも、印象的だ。
井上は、桂離宮の「発見者」として名高いブルーノ・タウトを高崎に招き、庇護したことで知られるが、この家の質素と繊細の美学は、まさしくタウトのそれに通じているのだろう。
もちろんそれはいうまでもなく、贅を極めた者の質素である。
美術館も見て外に出ると、暗くなってきている。しかし日の短い時期だけに、六時の開場にはまだ一時間半ほどある。
普通の食い物屋が、夜の開店前の半端な時刻なので、途中にあったガストで適当に食べ、市街をもう一度歩く。
暗い。
まだ五時過ぎで、かなりの店が閉まっている。この早さは、やはり地方都市らしい。昼はそれなりに賑わっていたアーケード街も、人通りがなくさびしい。
北へ抜けて西側、柳川町のあたりはスナックやパブが密集する飲み屋街のようだが、その種の店はまだ開店前で、酔客のための運転代行業の車がポツポツ停まっている以外は、やはり人気がない。
昼の街と夜の街の隙間の時刻の、無人の闇。
柳川町の西を南へ戻ると、道は城跡と市街の境界をなす、三の丸跡の水堀に沿う形になる。街灯しか明りのない、堀脇の道を進む。
八階建ての百貨店スズランが、夜空に大きな黒い影をつくっていた。
少し人恋しくなって中に入ると、内部はとても明るく、広い。外と内の落差の大きさに、ちょっと呆然。このデパートは窓が少なく、外に光をもらさないようになっているのだ。
店内を抜けて南に出る。また、無人の夜のさびしい闇に包まれる。
ところが、少し歩くと右前方に、闇の中にひときわ明るく、内部の光を外に放射している建物が、見えてきた。
そして、どこから出てきたのかというほどの数の人々が、そこへ向かって、歩いている。
群馬音楽センターだった。
闇の中の灯。
この鮮やかな効果には、驚いた。
霊感や宗教心などまったくない私でさえ、ここが祝福された場所、何者かが嘉みするホールだと、感じないわけにはいかないくらい、効果的な光景だった。
冷静に、その明るさの理由を考えてみる。一階と二階のロビーの正面全部がガラス窓になっていて、中の照明の光が、そのまま素通しで外を照らすためだ。
窓の広さと、そして、その細い桟。
曲線を用いず、多数の直線と平面を組みあわせて構成する、立体物。精巧な折紙細工、折鶴のような、繊細な立体物。専門的には折板構造というのだそうだ。
ああ、これもアントニン・レーモンドが設計したものなのだと、いま初めて思う。昼にはわからなかったその魅力が、旧井上房一郎邸を見た経験を通して、夜の闇の中で、初めてわかってきた。
(続く)
十一月二十日 高崎で群響を聴く(後)
チケットを取り出し、ホールへ入場。モギリが扉のところではなく、いったんロビーに入って、左右の二か所に別れているのが面白い。この方が、人の流れをスムーズにできるのだろう。
階段をあがって二階へ。この階段はうねるような曲線で、たくさんの丸穴があき、直線の建物の中でコントラストをつくっている。アルミなどの軽い建材が普及する以前だからなのか、素材の重量感と繊細さの同居が、じつに面白い。
二階ロビーは天井が高く、広々。昼にはガラス面から、外光がたっぷり入るのだろう。客席との間の壁面には、レーモンド自身の手になるという、個性的でカラフルな抽象的模様が描かれている。
私が子供のころ、一九六〇年代には、あちこちでこういう模様を見かけた。今となってみると古い印象だが、しかし暗い外に向かって、鮮やかな色彩を放射していたのは、他ならぬこの壁面である。その効果は、夜の闇にこそ映える。
一階ロビーへ降りて、客席に入る。自分の席はA席で、十列目の二十一番。思ったより前で舞台に近く、かなり左。すぐ前がB席、左がC席で、後者は自由席だ。それなら前半後半で位置を変えることも可能だろうから、C席にすればよかったと、このときになって気がつく。
椅子は古い劇場だけに小さいが、前の席との高低差があるので、舞台は見やすい。後方をふりかえると、客席は二段に別れておらず、かなりの勾配をつけた、一つの斜面にしてある。
二段にしないのは、二千人級の日本の大型ホールとしては、かなり珍しい構造だろう。横も扇形に広がっているから、これならどの席からでも、舞台はとても見やすく、近く感じられるのではないだろうか。新国立劇場を連想する。
そしてその斜面の下に生じる空間を利用して、ロビーの一階奥に事務所やトイレなどを設置している。この無駄のなさが、レーモンド流なのだ。
たしかに、あとで演奏を聴いた印象では、残響の少ないドライな音響で、これは音楽ホールとしては弱点だ。しかし、これほどの見やすさ(前席に無神経な大男が座っているときの不快感は、平らなホールでは誰もが味わっているはずだ)をもち、舞台と客席に近接感のあるホールは、多くない。
開演前の舞台では、渡辺和彦さんが前説をされていた。定期演奏会の恒例となっているらしい。休憩中もロビーでお姿を見かけたが、私はこういう単独行のとき、誰とも話をしたくない勝手な性分なので、声をかけずに失礼する。
今年八十二歳の首席客演指揮者、トゥルノフスキーの演奏は、新即物主義の系譜を引き継ぐ、背筋の伸びるような緊張感をもつ、見事なもの。前半がモーツァルトの《皇帝ティートの慈悲》序曲、ハイドンの《ロンドン》、後半がドヴォルジャークのスラヴ舞曲第一集。スラヴ舞曲は、アンコールの第九番で発揮された闊達な躍動感が、本プロの八曲にもあったら、さらによかったろうが…。
客席のマナーも洗練されていて、好感度の高いものだった。群響六十年の歴史は、さすがに伊達ではない。
終演後、人込みにまじって外に出て、いま一度、闇に浮かぶ音楽センターの姿を、眺める。
この建物を実現した最大の功労者は、疑いなく丸山勝広だ。
かれの情熱、それを支えた高崎市民、そして高崎市長住谷啓三郎の実行力がなければ、画餅に終ったにちがいない。
しかし、こうしてその場所を体験してみると、設計者のレーモンド、そしてかれを強力に推薦した井上房一郎の功績もまた、非常に大きなものであることが痛感される。
私の手元にある丸山の回顧録二冊は、いずれも井上と最終的に決裂した一九六三年より、あとに書かれたものである。
だから、ギクシャクはしながらも、政治経済の両面で事務長の丸山の後ろ楯だったはずの会長、井上の寄与が、実際よりも軽く書かれている可能性が高い。
音楽センターの構想も、丸山は一人で思いついたように書いているのだが、そうではないと、感じられてならない。
旧井上房一郎邸に掲示されていた井上の経歴には、一九五四年秋頃から井上が音楽センター建設を提唱した、というように書いてあった。
たぶん、どちらか一人の考案ではないのだろう。言い出しっぺが誰であるにしても、関係者間でダベっているうちに、具体的になっていったのではないか。
音楽センターは、最終的には二千人収容のホールのみに落ち着いたが、当初の構想では、複数の施設からなる、音楽文化の総合的な「センター」だった。
「でき得る限り大勢の人を収容し、ひとりひとりの負担額を少なくしなければならない。芸術家をそのつど宿にとめては経費がかさむ。宿泊施設ももちたいものだ。県下の先生方がそこに自由に寝泊まりし、研究できるような資料室やレコード鑑賞室も必要だ。各国大・公使館を通じ、その国独自の民族的な楽器を寄贈してもらい、生徒たちにみせる音楽博物館的な要素もほしい」(この泉は涸れず/本田書房)
こんな構想を、丸山は自分の頭の中で考えついたという。
だが、結局それは、群響が終戦直後に熊井呉服店の一棟を借りて始めた、「ラ・メーゾン・ド・ラ・ミュージック」での啓蒙活動を、より大規模に焼き直したもの、といえるのだ。
そしてそのころ、中心にいたのは丸山ではなく、井上だったはずである。
闇の中の灯。
闇に明るく光を放つ、群馬音楽センター。その姿に、敗戦間もない高崎の暗い夜に煌々と輝く、ラメーゾンのまばゆい照明が、私の頭の中で二重写しになる。
もちろん、独断専行型の丸山が無謬のマネージャーではなかったように、県下有数の建設会社を引き継いで、何不自由なく育った井上も、完全無欠の聖人君子ではなかったろう。批判の余地はそれぞれ大いにあったろうと思う。
だが、金儲けのためではなしに、文化活動に注いだ情熱の熱さと強さは、どちらも本物。その何よりの証が群馬交響楽団であり、群馬音楽センターである。
二人のうちどちらが欠けても、高崎のオーケストラ運動は少なくとも数十年、遅くなっていたにちがいない。
ホール建替の話があるという。絶好の立地だけに、再開発もしたくなるのだろう。土木工事で富を地方に再分配してきた、「土建屋の国」戦後日本らしい、いかにもな発想ではあるのだけれど…。
シンフォニーロードを歩き、高崎駅に着く。事故があったとかで、高崎線は遅れていたが、特に混んでもおらず、発車後は順調に走ってくれた。夜の埼玉を抜け、東京へ、東京へ。
面白かった。
ラメーゾン、旧井上房一郎邸、群馬音楽センター、演奏会。そしてその合間に歩いた、昼と夜の高崎の町と道。
気ままな散歩だったのに、どれもがそれぞれのメロディを奏で、見事なコントラストとハーモニーをなし、軽やかなリズムで交響して、楽しませてくれた。
高崎交響楽。今日はおしまい。
十一月二十一日 イージートーン賛
数日前から、リーボックのイージートーンというスニーカーを買って、履いている。高崎へもこれで出かけた。
使っている友人の感想にとても説得力を感じたので、自分も試してみたところが、これが、歩くのにとてもいいのだ。
足の裏、指の付け根の拇趾球(ぼしきゅう)と踵の二か所に厚めのクッションがついていて、履くと爪先が浮く。クッションが通常の三倍の柔らかさで、やや不安定なため、脚と臀部に負荷をかけて鍛えることができる。
と書くと、普通の靴よりも歩き疲れそうな感じがするが、私自身の感想ではまったく逆。むしろ、歩くのがはるかに楽に感じられ、疲れない。
初めこそ、たしかにふくらはぎや腿の裏、臀部に張りを感じるのだが、すぐに筋肉がついて、感じなくなる。履くと、ケツの穴がしまる感じがして、自然に姿勢もよくなるようだ。ここ数年、ひどくなっていたふくらはぎの冷えも感じなくなったから、それだけ血行もよくなっているということなのだろう。
しかし、それ以上にありがたい副産物が、クッションの柔らかさによる、歩きやすさである。
アスファルトの舗道の上を歩いても、足の裏への衝撃は、土や芝生を歩くときのように軽い。これまでは、長く歩くとまず足の部分がくたびれて、足裏が痛くなり、足全体を重く感じるようになったのだが、イージートーンだと、かなり歩いてもそうならない。そのぶん腿が疲れているのだろうが、その疲れはむしろ、心地よく感じるのである。
トレーニング云々より、鉄とコンクリの現代都市を歩くためにぴったりの靴、そう感じる。似たような靴が各社で出ていて、履き較べたわけではないけれど、私はこれで文句なし。
歩くのが愉しくてしかたないので、散歩にも精が出そう。買ったのはカジュアルなタイプだが、上部が本革でシックなタイプも追加で買おうかと、思案中。
十一月二十三日 顕在化した浪費の記録
各所に注文したCDがどっと到着。現実化する、予告された浪費の記録。さっと聴いたものでは、エドナ・スターンのピアノ協奏曲集とタベア・ツィンマーマンのソナタ集が出色の出来。特に前者のオーベルニュ管の呼吸感はお見事で、あえてモダン・ピアノを用いたスターンの響きも繊細で、美しい。
さて次は何を聴こう。イブラギモヴァか、パドモアか、クライツベルクかフェッロか…。わきたつ心、ふるえる財布。
十一月二十四日 フェッロのケルビーニ
あるサイトに「新譜」として出ていたフェッロ指揮シュトゥットガルト歌劇場のケルビーニのレクイエム、到着した現物を見ると、一九九六年のライヴ録音。この翌年まで音楽監督だったのだから、当然か。発売はドイツのANIMATOという、日本の店頭ではあまり見かけないレーベル。
でも、聴いてみると、これが思わぬ拾い物の名演。フェッロの柔らかめの音楽性にケルビーニって、ピッタリなのだと納得。
興味が出たので、このレーベルが出している、フェッロとシュトゥットガルト国立歌劇場の管楽セクションによる「オペラのバンダ」二枚、それにコッホの旧録音の再発売で、フェッロ指揮カペラ・コロネンシスによる、ケルビーニの《ハイドンの死に寄せる歌》と交響曲というのを、注文してみる。こういう発見は愉しいが、ふるえる財布。
夜は紀尾井でコープマンのチェンバロ・リサイタルを聴く。愉快。
十一月二十五日 『あたらしい朝』完結
戦時中に箱根山にいたドイツ兵を題材にした、黒田硫黄の『あたらしい朝』第二巻(完結編)を読む。
後半は明らかに書き急ぎすぎで、多くの伏線が未発展のままに終っている。もったいないが、病気で中断を重ねて、数年がかりの執筆だから、仕方のないところか…。
十一月二十六日 紀尾井のコープマン
紀尾井シンフォニエッタのベートーヴェン交響曲シリーズ、コープマン指揮で第二番と《田園》。
ピリオド奏法をとりいれた点では、前回のボッセと共通しているのだが、ボッセの厳しさに対し、愉悦感が先に立つ。それはいいのだけれど、前回があまりに見事な演奏だっただけに、雑な部分が気になる。響きがやや硬めに感じられたのは、前回はボッセがドイツから連れてきたコンサートマスターだったのに対し、今回は日本人だったからか。小編成だけに、違いは大きいのかも。
ともかく、どうしても前回と比較してしまうので、損である。
十一月二十七日 講座とスピーチ
朝は早稲田大学エクステンションセンターのオペラ講座で、広上淳一さんのお話を聞く。
沼尻竜典、尾高忠明、そして広上と指揮者の講話が続いたあとに、来週は自分がしゃべる番で、これはきつそう。
午後はグランドパレスで行われた、宇野功芳さんの八十歳祝賀会へ。数十名の参加者は宇野さん自ら選ばれたそうで、記者や編集者、レコード会社の社員が大部分を占め、同業者は数人。
みなさんピアノや歌を披露するなか、何の芸もない私はスピーチ。
ところが、どういうわけか、ここ二十年ないほどにあがってしまい、話はメロメロに。惨めな気分で帰宅。
十二月一日 ルイサダ
椿山荘で盛大に行われた、キング・インターナショナルの創立二十周年記念パーティに参加したあと、池袋の芸術劇場でジャン=マルク・ルイサダのリサイタルを聴く。
前半はショパンのマズルカ、ノクターン、スケルツォ三曲、後半はシューマンのダヴィド同盟舞曲集とショパンのワルツ四曲。
即興性と詩情の豊かな、さまざまな意味でいかにもフランス人らしいピアノ。演奏も面白かったが、それと同時に聴衆がかもし出す、会場全体の雰囲気を好もしく感じた。
華美でなく、服装も気配も控えめ。昭和後期の、大衆教養主義の時代を思い出させるような雰囲気。
主催のアイエムシーミュージックは大手ではないが、地道な活動で近年の評判の高い興行主。ショパン・コンクールの上位入賞者だがメジャーな市場から外れている、というような実力派ピアニストを招き、日本各地をツアーさせて、ファンを掘り起こす方式が話題になった(会場売りのCDも、記念の意味を含めてよく売れるそうだ。全体の規模が小さいクラシックCD市場では、これが馬鹿にならない)。
RCAと録音契約があり、テレビでの知名度も高いルイサダは、その中では大物格。チケットも相応に高めだが、おそらくは、アイエムシーが結びつきを強めてきた客層が、大半だったのではないだろうか。
十二月三日 自由が丘、遠い町
クラシカ・ジャパンの番組『クラシカ・ラウンジ』にほぼ一年ぶりに出演することになり、収録。
前回までは赤坂の本社で撮ることが多かったが、今回は、東急大井町線の等々力駅近くにあるスタジオ。
生れてから四十年近く大井町線の緑が丘に住んでいて、友人も東急沿線の住人が多かった。だから等々力駅にも親しみがあるが、降りるのは久しぶり。相変わらず小さい。最近は、等々力や隣接する九品仏、尾山台などは無人駅に近いこともあるらしい。住人の高齢化が進んで、通勤通学の乗降客も減る一方なのかも。
大井町線に、急行なんてものがあるのにも驚かされる。かえってそのために前後の接続が不便になっている気がするのは、都営新宿線の急行と同じ。
駅を出た周囲の家並みは、三、四十年前と同じように背が低くて建てこんでいて、ほとんど変っていないことに驚く。駅前なのに店舗も少ない。
目黒通り沿いにある東北新社のスタジオは、この辺では珍しいような大きなビルで、とても目立っていた。
番組五本を撮りおえて駅に戻り、自由が丘で東横線に乗りかえる。自由が丘駅の構造や内装が、十年前とはまるで変ってしまっていて、ウラシマ状態。
自由が丘の町も、最寄りの繁華街でありながら、どういうわけか子供のころから愛着を持てない町、安心感のない町だったが、ますます遠くなってしまった。
原武史が重松清と対談した『団地の時代』で述べていたことだが、自由が丘にしても緑が丘にしても、周囲はともかくとして駅自体は谷間にあるのに、平然と「丘」と名づけてしまった、自然に反した嘘くささにみちた駅。そのハリボテっぽさが、自分の違和感の原因なのかどうかは、わからないけれど。
原武史は、将来は自分が育った西武線沿線に帰りたいと言っているが、そう思えるのが少しうらやましい。
私は、東急沿線に帰りたいとは思わないから。ただ、旧目蒲線や池上線のように東急の中でも古い路線なら、嘘くささはなさそうな気もする。
いったん家に帰ってから、夜はオペラシティで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルのシューマン演奏会の初日を聴く。
十二月四日 オペラ講座とパーヴォ
午前中は、早稲田大学エクステンションセンターのオペラ講座。
時間がなくてタクシーに乗ったら、行先を「早大正門」と言う私を早稲田の関係者とみて、運転手さんが、先日の明治神宮野球大会の決勝を球場へ観に行ったという話をはじめる。おお、私も行きましたよ、と答えて会話がはずむ。
この大会、ふだんは内野席しか客を入れないのだが、あまりに観客が来たためか、あの日の終盤には、外野席にも百人くらいの人がいた。かれもその一人だったそうで、勝負を決めた七回の四番山田の逆転打は見たという。「あそこでカットボール(菅野の得意球)はないよ」と野球講釈を聞いているうちに到着。
年一回この講座でしゃべっているが、今年はここまで沼尻、尾高、広上と、現在活躍中の指揮者の方々が講師として登場しているので、昔の日本のオペラ指揮者などを、《椿姫》にからめて話す。
一九六八年、近衞秀麿が藤原歌劇団の《椿姫》を指揮したライヴ(オケは東フィル。オペラ指揮者としての近衞の実務的能力の高さが示された、貴重な実例)や、若杉弘指揮の《こうもり》など。
面白かったのは講義後、受講した方から、「最近はDVDばかりなんですが、音だけ聴くというのも、やはりいいもんですねえ」とか、「画も出るんだと思って、スクリーンずっと見ちゃいました」などと声をかけられたこと。言い方は違うが、いずれにしてもオペラ・ファンにCDを聴く習慣が、かなり少なくなっていることを実感した。
いまの自分はむしろ、DVDなど視覚ソフトには、劇場空間と異なるためのもどかしさを感じることが多くて、CDで耳に集中することが多いのだが、明らかに少数派になりつつある。
午後はオペラシティで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィルのシューマン演奏会を、昨夜に続いて聴く。
示唆に富んだ、充実した音楽。四番と《春》、二番と《ライン》という分けかたは、CDの《春》&《ライン》というカップリングとは異なっている。
これは副題つきを一日にまとめると、日本ではその日だけ売れてしまう(笑)という興行上の都合らしいのだが、幻想曲ふうに即興性の強い第四番にはじまって、凝ったオーケストレーションの《ライン》で終る、シューマンの成熟がよくわかる、すぐれた曲順になっていた。
もちろん、その変化を目に見えるように聴かせてくれる、ヤルヴィと楽員の能力があってはじめて、活きる曲順だが。
フル・オーケストラ相手だと、バトン・テクニックの鮮やかさばかり印象に残って、さっぱり感銘のなかったパーヴォの本領に、ここで触れることができた。
この人は俊敏と荘重、それぞれのスタイルを作品とオーケストラの規模に合わせて、使い分けてしまうのだ。ただし後者、大交響楽団を用いた場合には、どうも外形だけで、中身が伴わないように感じられたが、ドイツ・カンマー・フィルハーモニーとの俊敏様式には、そのような作為的なものを感じない。もう少し、余裕がほしいということは可能だが、それはより年輪を重ねてからでいい。
前にも書いたが、パーヴォに限らず、いまの自分には、巨大化しすぎて動きの鈍い肉食竜を想わせる大交響楽団より、小型で俊敏な室内管弦楽団の方が、はるかに刺激的で面白い。
それにしても、見事なまでに、先日発売されたCDには入っていないものの多い、《ライン》の実演だった。
第四楽章での、霧にかすむ大聖堂を想わせるような、神秘的で荘厳な、圧倒的というほかない見事な響きの「空気感」がマイクに入らないのは、これは当然のことだから、かまわない。仕方がない。
問題は、どんな音質でも聞きとれるはずのリズムの弾力、呼吸感が、セッション録音のCDには、ほとんどないことである。同じように動いているのに、ガチャガチャとせわしく騒々しく、単調に感じられてしまう。演奏の説得力が、まるで違ってしまっている。
これはベートーヴェンの交響曲全集のCDにも、同じことを感じた。ライヴで収録したDVDが最近話題なのも、実演の方がすぐれているからに違いない。近々に購入してみなければ。
十二月八日 坂が呼ぶ、川が呼ぶ
本を二冊。まずは横関英一の『江戸の坂 東京の坂』(ちくま学芸文庫)。
坂道ファン(笑)のバイブルともいわれる古典的名著だそうだが、私が知ったのはつい最近。
購入した理由は内容に加えて、四日のオペラ講座のさい、大学の音楽同攻会の大先輩に教えていただいたから。
講座の世話役的立場ながら、絶対に出しゃばらない、立派な方なのだが、講座のあとに昼食をご馳走していただきながらお話を聞くと、妙に坂道にお詳しい。たとえば、「汐見坂というのは江戸城内にもあって…」なんて感じ。
「あの梅林坂の近くですね!」とか、当方も思わず応戦する(バカ)わけだが、その理由をうかがうと、先輩の御父君が『江戸の坂』なる本を書かかれたほどの坂道研究家だからという。そして、中の写真は自分が撮ったんだ、といわれる。
「古い本なのに、最近もちくまが復活させたいといってきて…」
などといわれるので、これは読んでみなければと興味がわき、調べてみると、たしかに復活したばかり。横関先輩のお父さんは、真山青果の助手をされながら、坂道研究にいそしんでおられたらしい。というわけで、さっそく注文。
もう一つは本屋で見つけたもの。
塩見鮮一郎『賤民の場所 江戸の城と川』(河出文庫)
右の本と題名が似ているが、浅草弾左衛門ものでなじみ深い塩見鮮一郎が、鎌倉時代頃からの、江戸の川と城の関係を書いた話。徳川家が大改造する以前の江戸の地形に触れているのが、嬉しい。
作者も作者、話も話とくれば、これも読まずにいらりょうか(笑)。
というわけで、江田島話が一段落したら、江戸の坂と川が、自分をまた呼んでいる気がする。読むのが楽しみ。
読み終えたら、イージートーンを履いて実見に出かけるつもり。
そういえばこの靴、山の神にも薦めて買わせると、やはり好評。彼女が通っている整体師さんが、みるみる筋肉のメリハリがついてきたのに驚いて、自分も買うと言い出したそうである。
十二月十七日 権田原、南無八幡
外苑東通り、神宮外苑と赤坂御用地の間に、「権田原」(ごんだわら)という交差点がある。青山、赤坂というオシャレげな地域の間近に、妙に百姓っぽい地名が印象的。
ネットで調べると、一九六〇年代にはこの付近の森が、オカマな人々の「ハッテン場」として、活況を呈したそうだ。戦後すぐの上野公園北部から、こっちへ移ってきたらしい。
まあ、その話は、いい。
権田原という地名の語源の話。
よく聞くのは、付近に権田とか権太とかいう姓か名前をもつ人が住んでいて、それが元になったというもの。
しかし、そういう名前の人が、確かにこの付近に住んでいたかどうかははっきりしない。地名から逆にその由来を類推したような気配が濃厚だ。
だからよくわからない。ところが、横関英一の『江戸の坂』を読んでいると、面白い説が載っている。
権田原交差点を東に曲がると、明治記念館と東宮御所の間の、急な坂をおりることになる。
この坂はいま「安鎮坂」(あんちんざか)と名づけられている。しかし昭和半ばまでは「権田坂」(ごんだざか)とも呼ばれていた。
古い坂の名なんて流動的で、基本的には全部「通称」だから、人によって時期によって、色々あるわけだ。坂の上の方を「権田坂」、下半分を「安鎮坂」とする切絵図もある。
いずれにしても、その坂を底まで下ると、すぐにまた急な登りになって、迎賓館の脇をあがっていく。こちらは「鮫河橋坂」。むかし、この坂をミニバイクでおりてきたビートたけしが、スピードを出しすぎて安鎮坂に入る右カーブを曲がり切れず、標識に激突して、瀕死の事故を起したことで知られている。
この、向いあう二つの坂の最下部のあたりに、かつて鮫河橋(鮫ヶ橋)という橋があった。北から川が流れていて、そこにかかっていた橋である。
鮫河と呼ばれる、その上流の川沿いにも道があって、それは鮫ヶ橋谷町の、貧民窟へと入る道。私が、何度も歩いた道だ。いまは川が消え、道だけが残る。
一方、川の下流の南はというと、すぐに赤坂御用地の中になるので、一般人は入れない。「鮫河橋門」という門があって、その先には池があるはずだが、外からは見えない。谷町から流れてきた鮫河は、その池に流れ込み、そこからさらに南東の元赤坂町を抜け、最終的には、溜池に流れ込んでいた。
ここが、なんとなく妙な場所。
貧民窟から出てきた川が、そのまま御用地に入るのが、不自然なのだ。
この御用地の前身は、ほぼすべて紀伊徳川家の中屋敷。だから、天下の御三家の庭に、貧民窟の生活排水が流れ込んでいたことになるのである。
さて、ここでやっと『江戸の坂』が出てくる。じつはこの鮫ヶ橋から元赤坂へと流れる川と池の土地、江戸初期には、紀州家のものではなかったという。
当初の紀州家の屋敷は、この土地をはさんで、その北(いまの迎賓館)とその南(東宮御所など)の、二つの高所に別れていたのだそうだ。
例の明暦の大火で、江戸市中の大半を焼失し、その後の「再開発」によって多数の寺社や大名屋敷が移転する騒動のなかで、紀州家は二つの用地の間の低地も併呑して、現在の、ひとつながりの大きな用地になったのだという。
それ以前、この川沿いの土地には一ツ木村の町人が住み、「誉田坂」という坂があって、四谷、千駄ヶ谷と赤坂、芝を結ぶ街道として、賑っていたという。
あの低い部分だけ、当初は町人地だったというのは、現地を知るものにとっては「なるほど!」と腑がおちるが、さて横関が注目するのは、「誉田」の読み。
語源は応神天皇の諱、誉田別尊(ほむたわけのみこと)に由来するから、「ほむた」あるいは「ほんだ」と読む。
ところが、応神天皇陵とされる、大阪の誉田御廟山古墳のそれは「こんだ」と転訛している。「こんだ」はさらに「ごんだ」「ごんた」と転訛する例があるので、のちの「権田坂」もやはり、「誉田坂」の転訛ではないか、と見るのだ。
一般的な説ではないようだが、説得力がある。
では、失われた「誉田坂」と現存する「権田坂」の名は、何からきたか。応神天皇とくれば誉田八幡。八幡様が近くにあったから、にきまっている。
しかしこれも、今はない。横関は古文書を引用して、鮫ヶ橋付近に「放生池」(ほうじょういけ)という池があって、そのほとりに、放生庵という庵があり、そこに、八幡太郎義家の兜を祀る、正八幡宮があったと書く。
正八幡は応神天皇ではないとかいった細かい詮索はひとまずおいて、八幡宮とくれば誉田、というわけだ。「誉田坂」と「権田坂」は、東西からその八幡宮に向かう坂なのである。
では、その八幡宮のある池は、どこにあったのか、という問題。御用地内に現存する、大きな池のことだとも考えられるが、鮫ヶ橋の近くということでは、今の「みなみもとまち公園」にあったという、池だか沼だかの方が適している。
今日、あらためて見に行ってみると、公園の案内板には、かつてここには池や沼があって、そこから出た水が溜池にまで注いでいたが、のちに水田となり、さらに、四谷の外堀工事で出た残土をつかって埋め立てられて、町人地になった、とあった。
おそらく、ここに放生池があって、小さな八幡社があったのだろう。
しかし、山や岡の上の「ミサキ」ではなく、低地の池の畔に八幡様というのは不自然な気がする。源義家の兜があったから、というだけなのか。水辺なら、竜神など水神の方がふさわしい。
これも、現地で別の説を知ることができた。
この公園の西端、鮫ヶ橋谷町からの通りに面して、「せきどめ稲荷」がある。ここで川を「堰止め」ていたのを、「咳止め」にかけて、咳よけの神様にしたのは、いかにも江戸っ子らしい、半分やけくそみたいな洒落。
おそらく、埋立地の土地を乾かすために、川の水が流れ込まないように堰をつくったのだろう(南の紀州屋敷に流れ込まないように、という説明も見たことがあるが、そっちを止めてしまったら水が流れなくなって、一帯全部が池になってしまう)。
その「せきどめ稲荷」に掲示された説明の一つに、ここに「鮫ヶ淵」という淵があり、源義家が通ったさいにその乗馬が落ちた。馬はあがってきたが、鎧だけが沈んで、その淵のヌシ(つまり水神)になったという伝説が、書かれていた。
あちこちで似た話を読んだ気がする。たとえば中央区の兜町の鎧橋にも、義家が鎧を水中の龍神に奉じて、無事に渡河したという伝説がある。すぐ近くの鮫ヶ橋谷町の奥の、いまの若葉公園のところにも「鎧ヶ淵」という池があった。
借りたり借りられたり、みんなごっちゃになっているのだろうが、ともかく、龍の化身とされる「馬」や、水辺に多い「鎧」というキーワードによって、水神と義家が結びつき、そこから、池の畔の八幡様というものが出てくるらしい。
ところが、その八幡宮が、いまは影も形もない、というのがまた面白い。
前にも鳥越神社の話で書いたが、徳川家って、先祖であるはずの義家や八幡様に対して、やはり関心が薄そうだ。
由来や祭神がよくわからなくなった聖地には、とりあえず稲荷社か八幡社をつくる、というのが庶民の通例だ。古墳などは大概そうなっているし、鮫河橋では「せきどめ稲荷」こそが、八幡宮のはるかな後裔かも知れないが、幕府の方は、そんな民間信仰はどうでもいいらしい。
塩見鮮一郎の『江戸の城と川』を読んでいてもあらためて思うのが、徳川家の太田道灌へのこだわりの強さ。義家への関心の低さとは対照的で、源義家でも平将門でもなく、非業に死んだ道灌こそが江戸城の守護神という気がする。
これも、理由を考え出すと、いろいろ楽しそうな。
十二月十九日 年末放談と片山さん新刊
片山杜秀さんと、ミュージックバード毎年恒例の「年末放談」収録。
小澤征爾の松本での復帰演奏は、コバケンにスタイルがそっくりだとか、そんな話題を音楽含めて六時間。
片山さんが今年の一枚に選ばれたシチェドリンの管弦楽のための協奏曲第四番と第五番、きれいな響きなのにニヒルという、この作曲家らしい曲も面白いが、驚いたのは、演奏がキリル・カラビッツ指揮のボーンマス交響楽団だったこと。
カラビッツは興味を寄せている指揮者の一人で、このオケとのハチャトリヤン(ONIX)を買ったばかり。しかしかれの演奏を探したとき、このシチェドリンには気がつかなかったのである。
CDを見たら理由がわかった。国内用の帯には「カラボウツ」とある。さらにHMVのサイトには「カラビツ」とあった。これでは「カラビッツ」で検索しても出てこない。英字で検索するという当然のことをさぼってはいけないと、あらためて痛感。
収録後は他の方も交えて、五人で忘年会。「海老蔵はいっそ名前を返上して、生島新五郎を復活させたら、とても似合うんじゃないか」とか、ブラックな話で盛りあがる。
片山さんが「食べるラー油」を知らなかったのは、意外。恐るべき博学のひとなのに、不思議なところに穴がある。
片山さんの新刊『ゴジラと日の丸』を読み始める。週刊「SPA!」に連載されたコラムをまとめたもので、音楽も含めた広範囲の「片山アイテム」博覧会。いまさらながら面白い。
十二月二十一日 道灌と将門の境界
横関英一の『江戸の坂 東京の坂』と塩見鮮一郎の『江戸の城と川』を、途中まで読む。
後者はもちろんだが、前者にも、家康入部以前、大改造以前の江戸と関東の川の姿への関心があるのが愉しい。坂の脇や下には水路があることも珍しくないのだから、当然といえば当然。
また、坂の名前は時代によって変化していくことが多いから、それを考察することで、江戸の各時代の町並みの変遷を描く結果になるのも嬉しい。
『江戸の城と川』の方は、奈良時代から家康入部前までの関東の川の流路(江戸周辺だけでなく、利根川や荒川などの上流もまるで異なっていた)を、地図を多数挿入して、わかりやすく書いているのが魅力。もちろん、地図も文章も推測による部分が大きいので、信じ込んではいけないだろうが、とにかく明確なイメージをつかめるのはありがたい。
太田道灌が随所に登場して、江戸と関東でのかれの存在の大きさ(弘法大師のような)が示される。道灌が扇谷上杉の居城川越を中心に、関東の西半分を勢力圏としていて、江戸、岩槻、蕨などのゆかりの城が、東方の敵に備える境界線の川沿いにあったこともよくわかった。
考えてみると、時代はまるで違うが、もう一人の「関東のヌシ」である平将門は、逆に関東の東半分が勢力圏になるから、分けあっている形になるわけだ。そして、平川をはさんで向いあう江戸城と将門首塚は、両者の勢力圏の境界であると同時に、山手と下町の境界でもある。
そういえば、道灌というひとは、なんで神に祀られていないのだろう…。
十二月二十四日 テレビ収録
MXテレビの正月番組を収録。今回はセットではなく、背景はデジタル合成。ライトグリーンのビニール幕の前に座るだけで、画面ではそれらしくなる。自分で体験してみると、妙に感心する。
十二月二十九日 キーンさんと
「モーストリー・クラシック」の取材で、ドナルド・キーンさんに初めてお会いする。場所はキーンさんのご自宅。
いうまでもなく、戦前メトへの、そしてマリア・カラスよりも前のオペラ世界への目を開いてくれた大恩人として、三十年も私淑してきた方だ。
編集のTさんからお話をいただいて以来、心待ちにしていた。内容はメトのこと、ヨーロッパの歌劇場のことなど。一九二二年生れで今年八十八歳になられるが、頭脳の明晰さに圧倒される。
帰宅後、キーンさんの自叙伝『私と20世紀のクロニクル』を読みなおす。古典から近代に至る日本文学研究と紹介の業績はもちろんとして、谷崎潤一郎以下の昭和の文人たちと交流し、歌右衛門が活躍した時代の歌舞伎を見、さらに若いときには、米軍の情報将校としてアッツ島や沖縄などの激戦地へ足を踏み入れ、日本機の神風攻撃の恐怖も、間近に体験されている。
むろんそんな話は本題ではないから、まったくできなかった。けれど、歴史そのものともいえる方と、一瞬でも時間を共有できたことに感謝。
あつかましく、『ついさきの歌声は』を持っていってサインをお願いする。カタカナと英語で書いてくださった。
最高の年の瀬。雑誌の記事は、二回に分割する予定らしい。
Homeへ