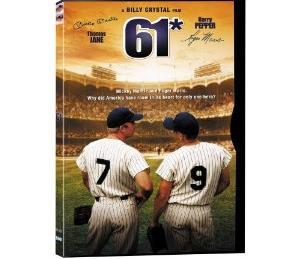二〇一一年
一月一日 五十一年前
新年。昨日、つまり二〇一〇年の大晦日をもって、一九六〇年に制作された録音の、著作隣接権の占有が日本やECで切れた。公有となったわけで、今年は、一九六〇年の録音がさまざま出てくるはず(昨年後半から始まってはいるが)。
一九九五年、占有期間が二十年から五十年に延びた年から、待ちに待った十六年。ここ数年の不安は、そのときまでパッケージ・メディアが存命かどうかということだったが、どうにか間に合った。
ところで、今回の『ゆく年くる年』は『昼のプレゼント』みたいでバラエティ色がつよく、ありがたみなし。この番組だけはただただ厳粛であってほしいのだが…。正月は遠くなりにけり。
一月四日 「宇野功芳、一九六七年バイロイト来日公演の思い出を語る」
今年の聴きぞめ、新国立劇場の《トリスタンとイゾルデ》。
同じ列の十個くらい右が皇太子殿下だった。東京文化会館やサントリーホールでの皇族席は二階上手になることが多いが、意外にも一階中央の、客席から見えにくい位置。全幕をご覧になっていた。
前奏曲が終って上がりはじめた紗幕がセットの船の舳先にひっかかり、メリメリと音を立てたときには、肝が冷えた。どうにか外れたものの、その後も、重そうな歌手が舳先に立つたびにグラグラ揺れて、今にも折れそう。
この船、到着前に難破して、全員遭難するかもと思う。オペラにならない。
さて、皇太子殿下ご臨席の関係で、音楽ジャーナリズム関係者は、一階後方の下手に集められていた。新国の目玉公演だけに、いつもより人数が格段に多い。
私の前の席は、宇野功芳さん。
三幕の開演前、大野和士がピットに出てくるまで少し間があいたので、雑談。マルケ王の話になる。
宇野「ぼくが最初に見たマルケ王は、ホッターだったんだよ。よかったよ~。イゾルデがニルソンで」
私 「へえーー。あれ、ということは、バイロイトの大阪公演ですか。大阪まで行かれたんですか」
宇野「そうそう。よくおぼえてないんだけど、あんとき、旅館に雑魚寝させられたんだよなあ」
私 「は?」
宇野「日本間に、三人で寝せられてさ。評論家のSと、ニッポン放送のなんとかというプロデューサーと。他人と一緒なんて、今なら絶対イヤだけど、なんかそんなことにされたんだよ」
私 「はあ」
宇野「そしたら朝起きたときにさ、Sが横向いて、壁をひっつかんで寝てるんだよ。こんなふうに」
と、猫が両手で引っかくようなポーズ。
宇野「あんな寢方をする人、いないよなあ。なんだかそんなことばっかり、おぼえてんだよねえ…」
いかに大先達の貴重な思い出話とはいえ、S氏が大阪の旅館でどんな格好で寝てようと、およそどうでもいいのだが、さすが人気漫談家、牧野周一の息子さんだけあって、その部屋の様子が、ありありと目に浮かぶ名調子なのである。
指揮者が出てきたので、おしまい。
一月七日 日本人の第九、二十五年
『オペラ御殿』のミン吉棟梁に教えられ、山田一雄の一九六〇年録音の第九終楽章が、タワーレコードから復活することを知る。
これは珍しい音源で、一九六〇年八月に二十五センチ盤で発売されて以来、再発されたことがあるのかどうかも疑わしい。しかし、キングの自社制作初のステレオ録音という、貴重な意義のある盤。
当時の山田は夏精(かせい)と名乗っていたから、オリジナル・ジャケットにもそうある。もともと山田は本名の和男を用いていたが、離婚問題などのゴタゴタから一九五九年に改名、六八年に一雄に改名するまで、この名を用いていた。
こういうことは、後世になるとわかりにくくなる。この盤でテノールを歌っている石井昭彦という人も、演奏家大事典にその名がないので不思議に思っていたが、ネットで調べたら、のちに養子に入って藤沼と改姓したそうで、なるほどその姓で事典にもちゃんと載っていた。
ところで、この盤について当時の雑誌類を読み返していたら、田辺秀雄が『レコード芸術』に書いた評に、とても興味深いことが書いてあった。
田辺が日本コロムビアにいた戦時中、山田和男指揮の日本交響楽団(現在のN響)の演奏で第九の全曲を企画したが、終楽章のマイクアレンジにミスがあり、発売にはいたらなかった。しかし田辺はそのテスト盤を、一九六〇年当時も秘蔵している、というのだ。
橋本國彦指揮東京交響楽団(現在の東フィル)による、終楽章だけの録音は知っていた(ロームの日本SP名盤復刻選集Ⅳに収録)が、山田一雄に、戦時中の全曲盤があったとは驚き。現存するのなら、いうまでもなく邦人初の第九全曲録音ということになる。
ほかに資料はないかと思って、日本SP名盤復刻選集Ⅳを見ると、クリストファ・N・野澤さんの解説に、山田和男指揮日響の第九のラジオ放送が、一九四三年の一月五日と十一月二十八日に行われたことが書いてあった。
当時、このように長大な作品の場合、NHKの放送をコロムビアが商業用レコードに録音することは珍しくなかった。戦時中に独立のセッションを組むのも難しいだろう。山田のコロムビア盤は、この二つの放送の、どちらかと同じものとみて間違いない。
ちなみに、橋本のビクター盤も同じ一九四三年、十月に発売されている。戦況が悪化しつつあった昭和十八年に、ともに録音されていたわけだ。どちらも訳詞によるもので、山田の一月の放送はバリトン独唱を担当した谷田部勁吉の訳、橋本盤は尾崎喜八訳と異なっていた(今回のタワー盤では、歓喜の歌の部分だけ、岩佐東一郎訳が用いられている)。
さらに調べると、ネットには「山田一雄の世界」というありがたいサイトがある。驚いたことに、ディスコグラフィの欄に、山田&日響の録音の終楽章が、LP化されていたことが書かれている。
日本コロムビアのDX一〇〇〇一~四という四枚組(?)で、一九四三年十一月二十八日のNHKでの録音で、一月の放送とは独唱の二人と合唱団が交代(玉川学園合唱団など)し、谷田部訳ではなく、尾崎訳が用いられているそうだ。
このセットがどんなものなのか知らないが、近衞指揮新響のマーラーの第四番第四楽章も収められているそうだから、N響の録音集とか、日本のオケのSP録音集とか、そんなものだろうか。
いずれにしても素直に考えると、これこそが山田の第九の一部分だろう。この日の全曲のテスト盤が、田辺秀雄の手元で戦災を免れた。終楽章のLP化に用いられたのが、そのテスト盤なのかどうかまでは、現時点では不明だが。
田辺氏は残念ながら昨年亡くなられているが、ご遺品の中に、ひょっとしたらまだその全曲が眠っているのかも。
古雑誌をひっくり返すのは楽しい。
それにしても、幻の山田盤はともかくとして、邦人初の第九全曲録音て、誰なのだろう。
思いつくのは近衞と岩城。近衞秀麿指揮の読売日本交響楽団の学研盤が一九六八年九月六~十三日、岩城宏之指揮N響のコロムビア盤(邦人初の交響曲全集の一環)が一九六八年十二月二十日。どちらが先に発売されたか知らないが、このあたりか、それとも前に何かあるか。
この二種も、なぜかそろって一九六八年で、前述の戦時下の録音から、偶然にもちょうど二十五年後の録音になる。
冷戦の下で国力を回復した日本がGNPで西側第二位になり、それなりに豊かさが実感されはじめた時代だ。どちらも今はなき、新宿厚生年金会館でのセッション録音なのも面白い。いうまでもなく新宿こそ、日本の「一九六八年」を象徴する場所なのだから。
アッツ島玉砕、山本長官戦死の年と、四半世紀後の、繁栄と騒乱と暗殺と若者風俗の年の、日本人の第九、四種。太平洋とベトナム、どちらも国外に戦争があった。
そしてそのあいだに位置するのが、六〇年安保の年の山田の終楽章、一部日本語の和洋折衷盤というのも、なにか暗示的だ。
と、自分で書いているうちに、聴きくらべたくなってきた(笑)。
一月九日 伊達直人現象
年末のニュースをきっかけに、全国各地に伊達直人出現。模倣善。
一時のブームになってしまうのは、評価の難しいところだけれど、最初の人がヒーローのタイガーマスクではなく、その正体である伊達直人を名乗ったセンスは、大好き。作品の中身を知らなければ思いつかないだろう。テレビアニメにもマンガにも、リアルタイムで接していた私には、それだけで嬉しくなる。
まさしく大悲劇に盛りあがったあとに来る、アニメ版のラストもよかったが、対してマンガ版の、ヒーローらしからぬ唐突な最期こそ、味わいが深かったなあと、久しぶりに思い出す。
トラックに跳ねられそうになった子供を助けて、身代りになる伊達直人。最後の力を振りしぼって、懐中から取り出したマスクをドブ川に放り込み、タイガーマスクを死なせずに、伊達直人だけで死んでゆく。
この、名もなき者であることを選択する行為が伊達直人を象徴する。それだから(テレビのエンディング・テーマ『みなし児のバラード』の歌詞……)、その名による寄付に共感させられるのだ。
昼のテレビ番組でも、あの死にっぷりが紹介されていた。やはりあれは、誰にとっても印象深いのだろう。
一月十二日 吉原の引手茶屋
福田利子の『吉原はこんな所でございました』(ちくま文庫)を読む。
吉原の引手茶屋、「松葉屋」の女将の養女になった著者の、ほぼ江戸期そのままに近かった戦前の遊廓時代から、戦後の赤線、売妨法後の特殊浴場街へと、移り変っていった吉原の様子の見聞記。
現場の体験談だけに、堅苦しく理屈で割り切るのではなく、実情を具体的に、ユーモアで包んで描いてあるのが大きな魅力。場の空気を肌で知る者なればこそ書けるもの。一九三七年頃の遊廓街の配置図や、戦前の写真が収められているのもありがたい。
引手茶屋という稼業がまず興味深い。歌舞伎や時代劇の、吉原の大門を入ってすぐ、大通りの両側にならんでいるのが引手茶屋で、これらは遊廓ではない。
高級遊廓への入口なのである。
遊廓は大見世、中見世、小見世、それ以下の河岸見世と、格式と規模によって分れている。そのうち、中以下の遊廓は客が直接に見世へ行く。通りを歩く客に声をかけて見世に呼び込むのは、妓夫太郎の仕事である。
だが、大文字楼、角海老、稲本などの大見世は、まるで違う。引手茶屋を経由しなければ、登楼することができない。
客――もちろん一見お断りで、馴染以外は紹介者が必要――はまず引手茶屋にあがり、大見世の花魁の用意ができるまで、茶屋の座敷で酒食と、芸者や幇間の歓待を受ける。
相撲や芝居の升席や棧敷席などの上席を、相撲茶屋や芝居茶屋を通して借りるのによく似ている。第三者が仲介することが、江戸期の格式の証だったらしい。
この前近代的なシステムがまだあるのは相撲だけ。引手茶屋は戦後、遊廓がカフェーと呼ばれる特殊飲食街(いわゆる赤線)に変ったときに、不要となった。
松葉屋も料亭(料理屋)に商売替えしたが、赤線内はカフェーしかできないとお上にいわれて、半年だけカフェーをやった。本格的に料亭として再出発したのは、一九四八年春だった。
その頃に面白い話がある。歌舞伎の籠釣瓶の冒頭、吉原大門前で花魁道中が行なわれるが、背景の引手茶屋のうち、上手側の暖簾に松葉屋の名が入ったのは、一九四七年東劇での上演からだという。
戦前は「西の宮」という老舗の名を書くときまっていたが、関東大震災で廃業していた。それで、松葉屋に馴染の深い中村吉右衛門が、その再出発を励ます意味を込め、その名に変えたのだそうだ。
また、売防法施行で一九五八年にカフェーが廃業。その場所で新たに特殊浴場を始めた業者の大半が、他地域からの新規参入だった、という話も興味深い。
松葉屋は料亭として続き、はとバスのコースに入り、お座敷芸や花魁ショーを見せる観光スポットとなったが、周囲がソープランド街では難しい部分もあり、一九九八年に廃業。
その七年後に著者は没し、松葉屋の跡地はマンションになっているという。
一月十五日 軽チャーな人々
たけしをメインにしたテレビ番組、Nキャスを観ていたら、横沢彪の葬式を映していた。
ところが、漫才ブームや「ひょうきん族」で縁の深かったはずのたけしは、何も言わない。他の出演者も、その話題をたけしには振らない。山の神によると、さんまやタモリが、その死についてコメントしたところも見てないそうだ(見逃しただけかも知れないが)。
一九八〇年代のフジテレビ黄金時代を築いた人々にしては、不可解。何かあったのだろうか?
一月十九日 去りゆく兎
知人のスマートフォン。普通の写真を3D化した画面をみせてもらった。むかし懐かしい立体シールにそっくり。ビニール製で厚みがあって、指紋みたいな模様のあるヤツのことだ。3D以外に、アニメーション風の動きを示すのにも用いられていた。
数歳年長の知人は即座に同意してくれたが、隣にいた三十代くらいの男性は、立体シールそのものを知らず。
正月からトシを感じる年男(虎ばかり流行って、兎はどこに…)。
一月二十日 去りゆく店
HMV池袋店が、都内ではHMV唯一のクラシック売場の残る店舗になっていたが、改装で消えたという。
ポップスなどの売場が、これまでのクラシック売場にすべてまとめられ、クラシックはコンピレーションものなどだけになるそうだ。
九〇年代にはさんざん通いつめたし、コピー時代の「はんぶる」を配布してくれたのも、公衆の前で音楽の話を初めてしたのも、この池袋店だった。
当時はあのフロアを、中央部以外はすべてHMVが占めていたが、二十年後のいま、ついにその一角だけに。
秋葉原の石丸電気も、昨年春のレコードセンター閉店に続き、ソフト本店も三月末で閉店して、ソフト事業そのものから手を引いてしまうらしい。駅の反対側にタワーレコードができ、人の流れが変わったのが大きいのだろう。
八〇年代にセゾン文化(タワーもHMVも、ことクラシックに関しては、その支流という傾向が強い)とは別のところで、大型レコード店の快感を初めて教えてくれた石丸と秋葉原の街。まあ、当時とは主要店舗が何度も変っているので、すでに感傷のようなものはないけれど。
一月二十九日 アジアカップ決勝
試合後に長友が高々と掲げた、香川の白い十番のユニホーム、かっこよかった…。韓国戦の後は川島が脱いで、前に突き出して見せた黒い一番が素敵だった。なぜか今回は、そんなポーズがやたらに印象に残る。
それにしても、前任の岡田監督が目指しながら、放棄せざるを得なかった攻撃的で敏捷なサッカーが、多少の変化はあるとはいえ、基本的には同様のメンバーで、わずかの期間にかなりの程度まで――点は入らなくても、以前のようなストレスは感じなかった――実現できたというのは、いったい何の差なのだろう。
Homeへ
二月一日 赤線地帯
CSで放映された、久松静兒の『渡り鳥いつ帰る』と溝口健二の『赤線地帯』を観る。
前者は可変日記で触れた「鳩の街」、後者は吉原の、赤線を舞台にした話。
一九四六年、昔ながらの遊廓の営業が禁じられ、すべてカフェーと呼ばれる特殊飲食店となり、一階にはボックス席やダンスホールが、形だけつくられた。娼婦たちは女給として契約し、名目的には客との自由恋愛だった。ただし特殊飲食店を出せるのは、昔からの遊廓街に限られていて、江戸以来の囲い込み政策が継承されていた。その地域を警視庁が赤線で囲って表示したので、赤線という名称になった。
吉原のほかには新宿二丁目、洲崎、千住、玉ノ井、亀有、新小岩、そして向島の鳩の街などがあったという。
一九五八年まで、十二年だけ存在した赤線の女たちと男たちは、映画監督にとって魅力的な素材だったらしい。ほかに川島雄三の『洲崎パラダイス 赤信号』も有名で、久松作品が一九五五年、他の二つが五六年と、すべて売妨法が国会を通過する前後につくられている。
三作品とも、人間の、滑稽で哀しい生と性を描きつつ、ロケやセットで、赤線や周囲の景色を記録してくれている。
特に『渡り鳥いつ帰る』は、往時の隅田川や木橋や、その流域の町々の風景を丁寧に画面に収めていて、ありがたい。
考えてみれば私がみた他の久松作品、『警察日記』も『南の島に雪が降る』の二作でも、猪苗代や東南アジア(のつもり)の自然が、人間たちとともに、重要な被写物になっていた。
撮影は三作とも別の人なので、これは久松自身の志向と見ていい。巨匠とはされていない監督だが、この点はとても好きである。映画自体の出来は、溝口はいうまでもなく、川島にも及ばないが。
さて、赤線は占領下の日本が生んだ徒花であり、カフェーや娼婦は、戦後の和洋の風俗の雑交を象徴したのだろう。戦前の遊廓とも、高度成長以後の特殊浴場とも異なる、赤線だけの風情があったらしい。遊廓時代に較べると娼婦の身分は自由だが、敗戦直後の貧苦は、特殊浴場の頃とはくらべものにならない。
赤線の消滅と高度成長の本格的な開始の時期が重なるのは、偶然ではないのかも知れない。
先月十二日の可変日記で触れた福田利子の『吉原はこんな所でございました』(ちくま文庫)にも、赤線時代独自の特徴が書かれている。
「そのころの娼婦たちは、かつてのおばさんに花魁たちが手とり足とりして教えられたほどには仕込まれてはいませんで、お客も自分で連れてこなければならなかったりで、ある面で昔の花魁たちよりは大変なところがありました。それだけに、お客を馴染にさせるのにどんな手だてがあるのか、“媚び”についても自分なりの工夫がいった、と聞いています。ですから、一生けんめいな、いじらしいところがあったでしょうし、それでいて吉原や玉の井、洲崎などの昔からの土地の臭いを身につけている……。赤線地区の娼婦たちが戦後派の作家たちに愛されたのも、あの時代特有の臭いのせいではないかしら、と昭和二十年代の吉原の姿を追いながら、そんなことを思っております」
そういえば、五木寛之の『青春の門 自立編』には新宿二丁目の赤線と、インテリ娼婦のカオルが出てくるんだっけ、と思いだす。一九八〇年代の佐藤浩市主演の映画は昔みたことがあるが、原作をきちんと読んだことはない。
主人公は五木より少し年下の一九三五年生れという設定だそうだから、早大生として二丁目に出入りしたのは、一九五三、四年のはず。
新宿二丁目も、内藤新宿の宿場女郎以来の長い歴史を持つ岡場所だが、福田の先の文では「昔からの土地の臭い」を持つ地域に含めていない。
宿場町の埃っぽさが消えず、さらに国鉄の駅や繁華街、そして何よりも、闇市に近いがゆえの人の出入りが、空気を渇かし、現代化させていたからか。
ともあれ、いまさらながらに読んでみるつもり。
二月四日 耳かっぽじって聞きやがれ
新国立劇場の「夕鶴」、歌手も指揮も(まあ演出も)よい出来で、総合的にかなりの水準と思ったが、特に効果的で印象に残ったのは、字幕をやめたこと。近年は日本語作品でも字幕が普通になっているだけに、新鮮な体験だった。
歌詞を聞きとろう、聞きとらせようと努めることが、ドラマへの没入を高める結果になった。音楽と言葉の関連にも、あらためて気がつかされた。これは、視覚全盛の現代において、忘れかけた重要な要素といっていいのではないか。
日本において、劇場の字幕によって、オペラのファン層が拡大したことは、どうにも否定できない事実。レコード界でも、手軽なDVDの登場によって、オペラのソフトが売れるようになった。
どちらもポイントは、視覚面からの直接的な情報の拡大ということにある。そのぶん、真剣に耳で聴く機会が減り、安易になっているのかも知れない。
二月六日 体幹と長友
体幹の重要性をくり返し説く長友に影響され、両肘と爪先で体を支える体幹トレーニングをやってみる。簡単だが、これは効きそう。
それにしてもマツコ・デラックスは、「守備の人」という印象がまだ強かったW杯の時点で長友に目をつけていたわけで、サッカーに興味はないといいつ、男を見る目はさすがに確かだ…(笑)。
二月七日 昭和五十年代の始まり
原武史『「鉄学」概論』(新潮文庫)を読む。
NHK教育テレビの番組テキストの文庫化なので、堅苦しく体系的な本ではなく、随論といった感じで、さまざまな話題が出ている。
鉄道会社が、沿線に住宅地を開発して経営安定をはかる方策の話(第五章)。東急の田園都市構想、西武の学園都市構想は知っていたが、小田急の中央林間駅が、同社の林間都市構想の名残だとは、知らなかった。もとは中央林間都市駅と名づけられたのだが、都心から遠すぎて成功せず、一九四一年に中央林間に改称したのだそうだ。林間の都市というと、軽井沢の別荘地みたいな感じにしたかったのだろうか。他社との差別化をはかるためとはいえ、どうにも無理がある。
第四章「西の阪急、東の東急」では、東急が渋谷駅や目黒駅をターミナルではなく、ただの通過駅にしようとしていることを批判する視点が、さすがに鋭い。
この場合のターミナルというのは、山手線に接続する駅にある、行き止り型のホームのことだ。東急の幹線路線はそれをなくして通過型のホームにし、山手線内の地下鉄に乗り入れる動きを進めているのである。
東急の目黒駅は地下化され、南北線に乗り入れる形に変ったし、東横線の渋谷駅も二〇一二年度には地下に移り、副都心線に乗り入れる。駅名が「終点」として路線の「顔」ではなく、通過点の一つに過ぎなくなるから、路線のイメージがぼやけてしまう、と原は指摘する。田園都市線などは、ずっと前からそうだ。
二十三区内で四本以上のホームをもつ大型の行き止り駅は、東急では蒲田だけだろう。そして蒲田は山手線ではない。
ターミナル駅がさまざまな意味で私鉄の「顔」だ、というのはよくわかる。
しかしこれは、国鉄が悪い先例をつくったわけだ。東京の旧国鉄の駅に、行き止り型のホームはない。全国すべての路線の原点となるはずの東京駅も、幅も深さもある立体的な巨大駅だが、視覚的には通過駅なのだ。
私が初めてヨーロッパに行ったとき、都市の外と結ぶ長距離線の駅がみな、堂々たる行き止り構造のホームになっているのを、とても素敵に感じたものだ。蒸気機関車の煙を逃がさなければならない時代にできたためか、屋根が非常に高くて雄大なのも気持ちよかった。着いたときも出ていくときも、毎日の通学や通勤ではない、「旅」という非日常的な体験をしている気分が、それだけで盛りあがってきた。
だがJRの東京、上野、新宿、品川、どれも旅情を欠いている。遠距離旅行の終始点としての「顔」という雰囲気をかろうじてもつのは、上野駅の浅草口ぐらいだろう。
東急はその私鉄版みたいなものか。
その東急が乗り入れる地下鉄も、地上の風景と切り離されたもの(たとえば半蔵門駅は、通過する乗客にとって、地上の半蔵門という実体とは関係のない、記号としての駅名に過ぎない)だから、やはり「顔」がないことが、第六章「都電が消えた日」で語られる。
こうしてみると、東急もJRも地下鉄も、どこまでもひとつながりの、長い不透明のチューブになることを目指しているようだ。
第八章「乗客たちの反乱」も面白い。一九七三年春、国鉄労組の順法闘争によるノロノロ運転に怒りを爆発させた通勤客のサラリーマンが、まず三月に高崎線上尾駅、四月には首都圏三十以上の駅で大暴れし、電車や駅を破壊して、運行をマヒさせた騒動のことが語られる。
何者かが煽動した組織的なものではなく、自然発生の大暴動だったことが、事件の特徴だった。その高い破壊衝動は、サラリーマンたちが大学紛争などで身につけた闘争力の余韻とも考えられるが、それが政府、体制にではなく、国鉄労組へ向けられたことに、この事件の特異性があった。六〇年代には労働者としての共感から、国鉄労組の闘争に理解を示していたサラリーマンたちは、この時点から、自らの生活を妨害するものとして、反対の立場に立ったのである。
それは、分裂と抗争をくり返してきた革新運動の終焉の、一つの現れだった。学生運動が衰退して、過激派の爆破事件や連合赤軍事件で一般の支持を完全に失った、その直後のことなのである。孤立した国鉄労組のストは、一九七五年の八日間に及ぶ「スト権スト」を最後の光芒として行なわなくなり、国鉄民営化の伏線となる。
これは、私の実体験と照らして、とても納得がいった。小学生時代(一九六九~七五年)の私は東急バスで通学していて、仲間も大半は東急、京王や小田急のバスや電車の利用者だったから、国鉄の春闘はテレビでしか知らない。
そして、原も書くように、私鉄の春闘は完全なストなので、電車が動かない。ノロノロ運転を我慢する必要はなく、学校が休みになるだけのことだった(西武線だけは最初からストがなかったが、西武沿線から通う生徒はいなかった)。
だが、そうしたスト休校は、一九七五年に入った中学ではしていない。「首都圏国電暴動」のあとの時期から、私鉄の春闘ストもなくなったのではないか。
想像すれば、この暴動の衝撃と、同年秋の石油ショックによる大不況で、私鉄労組はストができなくなってしまったのではないだろうか。
私は近頃、日本に関しては一九六〇年代、七〇年代という区分より、やはり昭和四十年代、五十年代の方が、時代の気分がより伝わるのではないか、という気がしている。
六〇年代というと、六〇年安保に始まって所得倍増、東京五輪があってビートルズにGS、学生運動の拡大という輝かしい時代になる。そして、連合赤軍と石油ショック、終末論の流行で陰惨に始まる七〇年代とは対照される感じだ。暗部を切り離すことができるのである。
これに対して昭和四十年代というと、ビートルズと学生運動に始まって、ヴェトナム戦争と反戦運動、万博と公害の激化、革新運動の衰退と景気後退で終る、という感じ。反抗の時代というべき激しさに、明暗の両面があった感じになる。
また、アメリカの影響がとても強く、明暗とも気分が連動している。その追随性の強さは、映画に代って全盛期を迎えた民放テレビのもつ、即時的、直接的な伝播力によるものだろう。
次の五十年代は、ある種の無風状態、安定状態。対イラン問題などでアメリカの権威が失墜していくなか、日本はどんどん経済力をアップさせて、アメリカに追随していた気分に、大きなズレが生じてくる。
都市のサラリーマンにはまだまだ心情左翼が多いのだけれど、家庭をもって懐も暖かくなったぶん、気分はだんだん利己的になっていて、保守に近づきつつある。自民党による富の再分配で、地方も豊かになる。
そうして、「一億総中流」という意識が支配的になってくる。それなりに豊かだけれど、身についた貧乏性がまだ抜けきらず、基本的には質素。レーガンのドル高政策のおかげで、摩擦を起こすほどに輸出はやり放題。金はたまるが輸入はしにくいので、土地投機に向う。
これが六十年代初めのプラザ合意でドル安円高になると同時に、貯めた金と高い地価を担保にした借金を、湯水のように遣いはじめる。
といっても、遣いかたを知らない貧乏人あがりの成金だから、熱に浮かれたようにめちゃくちゃな浪費をし、憧れの没落貴族の娘を買うようにアメリカを買いあさり、バブルという昭和の終点に、まっしぐら。
原による首都圏国電暴動の解釈は、昭和四十年代の終りと昭和五十年代の始まりを告げる事件のように思えて、示唆に富んでいた。
二月十日 『箱根山』三国志
獅子文六の『箱根山』を読む。
西武の堤康次郎と東急の五島慶太が繰り広げた箱根開発合戦、「箱根山戦争」を背景に、箱根の老舗の温泉旅館を舞台にして、一九六一年三月から十月に、朝日新聞に連載された小説。
西武が西郊鉄道、そのグループ会社の駿豆鉄道(現在の伊豆箱根鉄道)が函豆鉄道、対する箱根登山鉄道が箱根横断鉄道、小田急が南部急行、背後にいる親会社の東急が関東急行などと、一応は仮名になっているのだが、そのトップの顔ぶれと人柄を含めて、ほとんど現実を丸写しにしているのが面白い。どこまでホントでどこからがウソか、よくわからない書き方をしているだけに、現代なら抗議が出るかも知れない。
そして、この小説がうまいのは、西郊鉄道対関東急行の横綱対決だけでなく、それを横目に、小涌谷に常春苑というヘルス・センターをつくって箱根進出をもくろむ、氏田観光の北条一角という第三の勢力をおいていること。箱根を舞台にした三国志にしてあるのである。
これも虚構ではなく、実際に小涌園をつくって箱根に進出した、小川栄一率いる藤田観光がモデルなのだそうだ。芦ノ湖を真ん中にした三者の配置、性格の描き分けなど、モデル自体が個性豊かなおかげとはいえ、文六の筆も冴えて、ワクワクさせられる。
といっても、残念なことに現実に即しすぎたせいか、この三者をあまりあくどく動かすわけにもいかなかったらしい。かれらは背景にとどまって、メインは箱根最古の温泉場、足刈にある二軒の温泉宿、玉屋と若松屋の競争を、文六ならでは人の悪いユーモアで描いている。
これもモデルがあり、足刈とは芦之湯(古名を芦刈の湯という)のことで、玉屋と若松屋は松坂屋と紀伊国屋という、江戸時代から現在まで続く二軒の旅館のことである。
文六は一九五五年から毎年夏を松坂屋で家族と過ごすのを習慣とし、長く逗留して小説の執筆も行なっていた。自らが暮した風土を作品に取り込むのは、『てんやわんや』でもおなじみの手法で、何気ない描写にも実感がこもる。
電鉄という現代的な企業の競争と、温泉宿という古来の商売の競争を重ね合わせることで、欲と見栄という人間のエネルギーの源泉の、愚かしくも微笑ましい不変性を浮彫りにしている。
文六が紹介する、「ケンカばかり」の箱根の歴史も面白い。
最初は元箱根と箱根町。元箱根の方が箱根権現の門前町として古い。ところが江戸幕府がここに宿場と関所をつくろうとしたとき、権現社の権威をタテに協力しなかったため、頭に来た幕府が三島よりに新たな町をつくった。それが箱根町で、宿場として繁盛したものだから、元箱根の住民は面白くなく、不和が続く。大正期に乗り出してきた堤康次郎は、元箱根側の不満を利用して土地を買占め、以後は元箱根の方が賑やかになる。
さらに強羅と宮城野、仙石と元箱根も仲が悪い。これらの意地の張り合いに、堤と五島の競争が絡む。そしてこれらの対立とは別に、明治から昭和初期にかけて宮ノ下に富士屋ホテルを築く山口家、戦後の小涌園の藤田観光と、箱根の中腹に進出してくる勢力。
地図などで地形や高低差を想像しながら、その地政学(というほどでもない)を考えるのが楽しい。
なお、松坂屋というのはもちろん、横浜港内の爆発事故で艦を失ったドイツ海軍の将兵が、戦時中から数年間滞在した旅館のことでもある。
晩年の文六は、かれらと箱根の女たちとの騒動を小説化しようとして、はたせずに死んだ。しかし、この『箱根山』にもそのあらましが短く語られている。規律正しく生活しながらも、かれらが日本兵とは少し違ったのは、
「女に対して、たいへん軍規が寛大なのである。艦長のB大尉からして、少し怪しかったが、下士官から水兵となると、公然と、女漁りに狂奔した。彼等に許可された散歩区域は、芦ノ湖畔から宮ノ下であるが、その辺で会った女に、ことごとく盟邦精神を発揮した」
B大尉のモデルは、指揮官のブルーンズ大尉だろう。これは小説だから事実を面白おかしく誇張しているのだろうが、あまりにも善良無害に描かれていた新井恵美子の『帰れなかったドイツ兵』の兵士たちとは異なる、生々しい男たちの姿である。当時の松坂屋の若主人だった松坂康が全集の月報に寄せた一文にも、
「これら青い目の水兵たちが、欲望の門を開こうとしてかもし出す連日連夜の珍談、奇談は獅子文学の好材料たることうけ合いだった」とある。
この小説の主役の一人である勝又乙夫は、そうしたドイツ兵と旅館の女中とのあいだに生れた。頭脳明晰、体格もよくて性格も真面目という、できすぎのキャラクターだが、その乙夫(おとお。父親がオットーと名づけたがったのを、日本側でこう変えてしまった)の風貌が、大鵬に似ているとあるのは、いかにも一九六一年夏前後という連載時期らしい。
ウクライナ人の父と日本人の母を持つ大鵬が、二十一歳になったばかりで大関から横綱へと駆けのぼった、まさにそのころなのだ。読者は、大鵬そのものを頭に描いて読んだことだろう。
このように時代風俗に密着しすぎたことが、獅子文六の作品が没後まもなく、急速に忘れられた原因の一つだったのかも知れない。しかし今となってみると、半世紀前の日本の記録として、新たな価値を持ちつつある。
二月十一日 電球色の蛍光灯
仕事部屋の蛍光灯を、机のスタンド以外、ぜんぶ電球色に変えてみた。
まずは気持いい。落ち着くし(仕事部屋で落ち着いていていいのか、という疑問は、この際おく)、体感温度も一度ほど上がったような気がする。
それにしても、直管の蛍光灯四本をいっぺんに交換すると、こんなにも馬鹿みたいに明るくなるとは。色の違いよりもまず、それに驚く。
ダメになったやつから一本ずつ変えるのって、結局はだらだらと明るさを損しているのかも。
毎年とはいかずとも、二年に一度くらいは全部変えるようにすると心機一転、気持よいかも。
友人でも、蛍光灯を電球色にしている人は意外と多い。LEDにも電球色があるそうだが、どんな感じなのだろう?
二月十二日 箱根山の祖父
母方の祖父の話。
私が以前従事していた送電線工事の仕事は、もともとはこの祖父の始めたものである。
大正から昭和へ替わるころに、祖父が岳南組(現在の岳南建設)に入り、送電線工事を担当して、やがて独立したのが始まりなのだが、不思議だったのは、祖父の前職が東京市の水道局であること。
なんでいきなり水道から送電線に移ったのか、理由を知らなかったのだが、母親と獅子文六の『箱根山』の話をしていたら、そのヒントが。
母によると、岳南組が箱根で温泉関係の仕事を請け負った、それが祖父の、岳南組での最初の仕事らしいのである。
岳南組とは、御殿場出身の勝又春一が起した建設会社で、当初は御殿場など北駿地域から、山梨県あたりの仕事が中心だった。御殿場は箱根山の西北側、仙石原への入口にあるから、やはり地縁で箱根の工事を得たのだろう(勝又という姓自体、『箱根山』にも出てきたように、県境をまたいで箱根にも多い。勝俣とか勝間田とか字は色々あり、文六が書いたように元は山梨地方の姓ともいう)。
温泉関係というのだから、引湯の配管工事などだったのかも知れず、それなら水道局にいた祖父にはぴったりである。そこから、岳南組の主要業務である、送電線工事に転じたのだろう。
ちょうど堤康次郎が箱根土地を設立して、強羅を買い占めていたころだから、この工事も関連するのかも知れない。
少し面白くなって、家にあった勝又春一の伝記を読む。残念ながら箱根の仕事の話はない。代りに、岳南組の満洲進出当時の話に目がいく。
この満洲進出では、春一と同じ静岡県出身で、満洲事変のときに仙台第二師団長として勇名を轟かせた、多門二郎中将との関係が、岳南組にとって何らかの重要性を持っていたらしい。
祖父は、岳南組の満洲支店にいたことがある(支店長だったともいうが、よくわからない)のだが、仙台出身だから、第二師団との関係においては、その地縁も少しは役に立ったかも知れない。
祖父と孫といえば、吉川英治の孫が大麻で逮捕されたなんてニュースを見る。
それとは関係ない話だが、吉川英治の著作権は、来年いっぱいで切れる。講談社の吉川英治文庫とか、どうなるのだろう。
二月十四日 トロイアの人々
おとといの《影のない女》に続き、ゲルギエフ指揮マリインスキー劇場の《トロイアの人々》を観る。
サントリーホールでのただ一回の演奏会形式だが、ゲルギエフが上演を熱望したというものだけに、素晴らしい演奏だった。ドイツ語やイタリア語に較べ、フランス語というのは帝政ロシア以来の伝統なのか、ロシア人にとって違和感が少ないのかも。
それにしても今回の演目は国がバラバラだが、古代的、アジア的な専制国家における為政者の宿命と人間疎外、というテーマが共通しているようにも思える。《トゥーランドット》もそうだし、《パルジファル》のアンフォルタスも、存在そのものはかなり異教的だし。
終演後はかなりの降雪。ゲルギエフ寒気団の来襲か。
二月十五日 パルジファル
昨日がすごすぎて、今日の《パルジファル》第三幕はもう一つ。ゲルギエフの呼吸感が、ワーグナーの音楽となるとどうしても浅く感じられる。
グルネマンツ役のルネ・パーペは、歌も容姿もさすがの存在感だが、マリインスキーの座付の歌手のなかでは浮いてしまう感じ。演奏会形式でも、目線や身ぶりの演技を初めパーペはしていたのに、パルジファル役の歌手が楽譜に首を突っこんだままで余裕がないのに気づくと、自分も演技をやめてしまった。
でも、ローエングリンにタンホイザーと、キリスト教がらみの作品だけでそろえてあったのは納得。後者では、響きにベルリオーズとの関連性を感じられたのが収穫。
二月十六日と十七日 箱根山へ
一泊で箱根山へ。松坂屋に泊まり、仙石原や元箱根、箱根神社、ロープウェーで駒ヶ岳山頂の箱根元宮などを回り、宮ノ下の富士屋ホテルで食事して帰京。
戦前からのもの、高度成長期のもの、そのままのものと失われたもの、さまざまだったが、山の入り組んだ地形に、明治以後のデベロッパーたちのさまざまな情熱がこもっていて、面白かった。残雪が多くて、思うように歩けなかったのが惜しかった。
二月十八日 西武と東武、あと東急
古代専制国家シリーズ、NHKホールで《トゥーランドット》を観る。
帰りは渋谷駅で副都心線に乗ると、乗入先の西武線が運行見合せとかで副都心線も一本運休し、ホームにいたその車両が、そのまま次の東武線乗入れとなる。
乗る方はただ待つだけだが、気になったのは、車両が西武のものだったこと。乗入れ先で地上に出ると、それが東武の線路を走ることになるわけだ。
いずれやりくりをして西武に戻すのだろうが、副都心線では、乗入れ先の事故や故障のたびに、こうしたことが日常的に起きるのか。もう開発競争をしているわけでもなかろうから、ガチのライバルではないにせよ、不思議な感じ。
これで来年に東急東横線にも乗入れると、やりくりはさらに複雑に。原武史のいうとおり、ますます個性が薄くなる。
二月二十一日 大河の脚本家たち
脚本家の大野靖子が亡くなった。
『国盗り物語』『花神』と、黄金時代の大河ドラマの功労者の一人で、そして私見では、司馬作品の脚色がいちばん上手だった人。余計なことをせずにツボを押え、複数の作品を巧みに組みあわせ、群像劇にする手法が、見事だった。
『花神』などは、本放送時に視聴率がとれなかったのに、現存する総集編は高い評価を受けている。橋田寿賀子の「ホーム大河」の方が、大野の群像劇よりも視聴率がとれたのは、知人も言っていたとおり、戦後日本の大いなる不幸。
同じ知人によると、『元禄太平記』のホンを書いた小幡欣治も先日亡くなったそうだ。こちらは、江守徹所蔵のビデオから全作品が復元される可能性が出てきたときだけに、さらに惜しい。
それにしても大河ファンとしての自分は、ここ三年ほど、八〇年代の阪神ファンみたいな状態が続いている。開始して一か月もたつと、もう次の年の大河しか楽しみがないのだ(笑)。まあ、『坂の上の雲』が年末にあるから、救われているが……。
Homeへ
三月四日(金) 三十三年目の…
テレビCMの森三中の「キャンディーズ」、ちゃんとキャンディーズになってるのが、なんだか悲しい(笑)。彼女たちの「キャッツアイ」はあくまでパロディだったのに。
老いたる者の過ぎし青春の思い出をもてあそばないでくれ~と嘆いていると、同級生の友人から「そんなものは見たことがない。そんなものはやってない!」と、思いっきり現実から目を背けた意見がくる(笑)。
やはりあれには、冗談では済まない何かを、同世代の男は感じるらしい。
四月から、NHK衛星で『新選組血風録』が始まるのだが、大丈夫なのかこれで、と思わざるを得ないキャスト。ここまでマイナーだと、「大化けするかも」とかかえって期待したくなる。
そんな奇跡は起きないに決まっているが、四十五年前には栗塚旭だって島田順司だって無名だったんだし、と、観るまでは希望を捨てないのが、時代劇馬鹿。
と、ここまで書いて自分で驚いたが、NET版の『新選組血風録』って、四十五年も前の作品なのか。一九六五~六六年放映。そこからもう一度四十五年さかのぼると一九二〇年、大正時代だ。そのあいだに関東大震災と第二次世界大戦。
つくづく戦後の平和は長い。そして、ありがたきもの。
三月五日(土) スポーツの春
だいぶ春めいてきたので、そろそろ国立か神宮で何か観たいと検索。
Jリーグは来月までお預けだが、プロ野球は、ヤクルト対阪神のオープン戦が十七日にある。平日の昼なら、シーズン中ほど賑やかではないだろうから、これに行こうかと計画中。天気次第か。
国立競技場のJリーグは、今年は秋にJ2の横浜FCのゲームが三つもある。「カズダンスat国立」の再現を期待、というところか(去年、この目で見たのは、ちょっと自慢)。特に、古巣ヴェルディとの一戦があるのがいい。これでもしカズがきめたら、両軍のサポーターが拍手するかも。いまから楽しみ。
三月九日(水) 金八の昭和五十年代
TBSでやっていた「金八先生」第一回を偶然見てしまう。
一九七九年十月。景色、電車、日本建築の建物とその内装、服、髪型……。何もかもみな懐かしい昭和五十年代、一億総中流幻想のあのころ。
それにしても、この画面のなかの東京の風景は、調和がとれてなくて、さっぱり美しくない。美というものが何らかの犠牲の上に成り立つものだとすれば、昭和五十年代というのは、犠牲が最小限ですんでいた時代だからこそ、美しくなくていいんだ、と思ったり。
この時代は、現実の建材そのものが安っぽかったから、セットでもかなり真似できるらしい。しかしそれだけでなく、小道具のそろえ方、なにげない配置、そのあたりの真実味は、まさしく「ドラマのTBS」。金八の狛江の下宿の部屋の雰囲気とか、びっくり。
若き武田鉄矢は、表情もしぐさも、ナインティナインの岡村に瓜二つ。というか、岡村がこの影響を受けたのか。
アイドルたちもいま見ると、さっぱりそれっぽくないのが新鮮。三原議員は、スッピンの方がきれいかも。小林聡美も出ている。
最終回スペシャルへ向けての再放送らしい。一日二本だから、第一シリーズ二十六本でちょうど、放映日直前の金曜日までとなる計算か。
三月十一日(金) 東日本大震災
地震。
月刊誌類の〆切が一段落、何にも仕事をせずにゴロゴロしていた。
遅い昼飯を四谷のピザ屋で食い、低空に黒灰色の雲がかかるのを、なぜか何度も見上げた。本屋に入り、二階で新書を立ち読みしていたとき、揺れ始めた。
大きいが、船に乗っているような長い周期の揺れ。途中から激しさを増し、長く続く。棚の本がいっせいに転がり落ちる。店員さんが落ち着いて非常口をあけてくれたので、お礼を言いつつ(こういうときは妙に冷静なものらしい)外へ。
三栄通りは、ビルから出てきた人だらけ。「まだ揺れてるよね」という声を聞きつつ、自宅へ。
なにしろ古い家だけに心配だったが、外から見るかぎりは変化なし。山の神に声をかけると、中も大丈夫だが仏壇だけが落ちて壊れたという。身代わりか。
仕事部屋の戸をあけて中に入ると、床に積み上げてあった本とCDの山が崩れて、足の踏み場なし。先程の本屋と同じ光景が広がるのに苦笑い。
組立式の本棚は二つとも横に大きく傾いでいたが、幸いにも前には倒れていなかったので、中段から下の本はそのまま残っている。あとで考えると、振動の方向が南北だけで、東西ではなかったのがよかったらしい。直そうと元の方向へ押していたら、長く大きな余震が来た。
本棚を押えながら、そういえば他家の猫が私の部屋に入り込んで寝ていたはずだが、どうしたろうと気になる(あとで山の神にきいたら、外を走って逃げるのを見かけたというので、ひと安心)。
その後もくり返す余震におびえつつ、震源は東北地方で、大災害らしいとテレビで見る。山の神はとても料理をする気がないというし、家を空けて外へ食べに出る気にもならないし、緊張からかそれほど腹も減らないので、カップ麺を買いにいく。
三栄通りは、夜というのに人だらけ。こんな形容は不謹慎かもしれないが、お祭のようにたくさんの人が出て、歩きまわっている。電車の回復待ちで残っている会社員が、あきらかに妙な興奮状態になっている。高らかに笑ったり、大声で話したり(あとで知人に聞くと、飲み屋なども大賑わいだったらしい)。この光景は、長く忘れないだろう。
三栄公園脇の公衆電話は、こんなときでもつながるらしく行列。
コンビニも長蛇の列だが、百円スーパーに行くとこちらはさほどでもない。まだ残っていたカップ麺を買って帰る。
食べてみると、百円カップ麺の方が、普通のものよりも味が素直で非若者には食べやすいという、意外な発見。そのうち、外に隠れていた家猫も帰ってきた。
仕事部屋を片づけ、パソコンまでの通路をとりあえず確保。ところが、一月ほど前から不調だったモデムがついに完全に壊れ、ネット接続が不可能になる。
テレビでは気仙沼の闇と火災。一九六〇年がらみでチリ地震津波を調べ、吉村昭の『三陸海岸大津波』を読んだことがある。三陸のリアス式海岸ではその地形ゆえに大津波になりやすく(同時に、その地形ゆえに海産物が豊富で、漁村ができるのだが)、チリ地震以前の明治と昭和初期にも、沖合の地震で大きな被害が出ている。地元では津波を「よだ」と呼ぶらしい。地震の後、海底で「ドーン、ドーン」という砲撃音のような轟きが聞こえ、そして津波が来る、という描写が恐ろしかった。
今回はどうなのだろう。被害が少ないことを祈るが…。
寝る。余震と興奮で眠りが浅い。
三月十二日(土) その翌日
呆然とテレビを見る。三陸海岸はもちろん平野まで襲う、近代では未曾有の大津波。仙台の親戚たちが気になるが、連絡がつかない以上、ジタバタしても始まらない。大半は海から遠い地域なので、大丈夫だろうとは思うが。
原発もおかしい。送電業界にいたから東電独特の言い回しを多少は知っているので、気になる。今はなんの関係もないとはいえ、祖父と父がその下請で食わせてもらった恩義があるから、自分までは一蓮托生だとは思っているが。
今日は、新国立劇場のオペラ研修所卒業公演に行く予定だった。中止を知らせるファックスがくる。昨日はまさに公演の途中に地震が起き、そのまま中止になったという。明日は幕を開けるので、来てほしいと書いてあるが…。
三月十三日(日) その翌々日
研修所公演、申し訳ないが、とても出かける気になれず。他のいくつかの公演も中止の報が電話やファックスでくる。
夜になって、明日からの計画停電、輪番停電をテレビで知る。関東の鉄道はかなり停まるらしい。調整をする時間もないほどの緊急事態ということか。
三月十四日(月) 街へ出よ
計画停電初日。前夜発表のため、知らなかった人も少なくないらしい。鉄道の運休、間引き運転による通勤通学への影響の方が今日は大きそう。
クラシカ・ジャパンの番組打合せを予定通りやるというので、赤坂へ。赤坂の町は人込みこそいつもより少ないが、人々の表情は普通で、その中にいると当方も落ち着く。こういうときだけに、見知らぬ同士も気をつかいあうし、それが互いの心を癒してもくれる。
家でテレビやネットにかじりついているより、外で働いたり、多数の人と接する方が、心は健康でいられそうだ。
無料レンタルのモデム、プロバイダーに連絡すると新品に交換してくれるという。ただし現在の交通事情のため、いつ届けられるか不明だそう。
船酔いみたいな感覚が続いていたが、これは地震酔いというそうな。
「ニューディスク・ナビ」などのミュージックバードの番組では、一か月以上前に収録したものなので、何ごともないように私がしゃべっている。
三月十五日(火) ネット難民カフェへ
クラシカ・ジャパンの収録、停電や運休を考慮して中止もありうるという話だったが、スタジオを等々力から赤坂に変更してやるというので、駆けつける。
雑誌等の〆切のない時期なので、ネットは見られない方が精神衛生上好都合と思っていたが、メールは見ないとまずいので、インターネット・カフェを生れて初めて利用する。
面倒だからと携帯電話のメールは使わずにパソコンだけに一本化してきたが、こういうときは不便。ネットカフェでは読めるだけで発信できないし。
フィレンツェ歌劇場の来日公演が、市長の帰国命令により途中で打ち切り。
三月十七日(木) 七日目
モデムが到着。おどかされたわりに、意外に早かった。都内の道路はものすごく空いているが、流通システムの基盤は揺るぎないようだ。
神宮のプロ野球オープン戦は中止。
四日の日記に「つくづく戦後の平和は長い」なんて書いていた。地震はそれから一週間後。思わず苦笑い。
三月十八日(金) ミューザ川崎
ミューザ川崎のホールの現状が公開され、天板が落ちた被害の凄さに驚く。公演中でなくて、本当によかった。
九段会館は古いから仕方ないと思ったし、日比谷や上野が大丈夫なのにも感心したが、それに較べてこれは、どういうことなのだろう。
関東では好きな音響のホールだが、天井を補強するとなれば、あるいは音に変化が出るかも。もちろん、安全には代えられないが。
三月十九日(土) 本郷台と根津谷
小中学校の同級生の墓参り。場所は本郷の、東大赤門前の喜福寿寺。
今年はちょうど十年目、例年は六、七人の仲間で来るのだが、今年は震災の影響で自分一人。他の人の分まで、線香を松明みたいに焚いたので、お墓の中の人はかなり煙たかったにちがいない。
一人で楽しいのは自由に歩きまわれることなので、ついでに周囲を回り、寺の裏手にある旅館、鳳明館を見る。
この鳳明館の本館は、驚いたことに明治三十年代の木造建築である。官製のコンクリートならともかく、民間の木造で空襲どころか、関東大震災さえ乗りこえているというのが凄い。
本郷にはこれ以外に、明治三十八年の木造三階建ての下宿、本郷館も現存している。本郷台の地盤が固かったことで地震の被害は少なかったのだろうが、よく火災を免れたものだと驚く。
しかも、老朽化で閉鎖された本郷館と異なり、鳳明館は現役の旅館なのだ。今回の地震もまったく平気だったようで、回りを眺めながら、こういう強運の建物に、いつか泊まってみたいと考える。
笠智衆主演の『好人好日』で、主人公の数学者が東大近くの古旅館に泊まっているところに、三木のり平が泥棒に入る場面があったが、その建物がこの鳳明館に似た感じだったような気がする。
万定フルーツパーラーという、アール・デコ風の古い「モダン」な建物(昭和初期だとか)も、素敵だった。
次に旧制一高跡を見る。いまの東大農学部の位置にあった。一高というと、建物が現存することから駒場の印象も強いが、あちらは一九三五年の移転で、一高史の中では最後の十五年ほどを占めるにすぎない。「向ヶ丘」とか「向陵」と呼ばれ、半世紀弱の長い歴史を持つのは、この本郷の方である。
あらためて歩くと、東大のすぐ隣とはいえ、道路を隔てて、あくまで別の用地という印象がいまだに残っている。かなり広い。中の建物は、農学部が来たときにまったく変えてしまったようだ。
その脇を抜けて根津の谷におりて、下町風の生活空間を、夕闇の中で歩く。
不思議に温かい。町の運命、人の運命なんてものを考える。明治の建物が残る本郷台とは異なり、根津谷の町並みはすべて戦後のもの。
一高ができる前、ここには遊廓があった。それが消えて普通の町になり、震災と戦災で二度消えて、いままた、人が暮らしている。
人は戻る。三陸の漁村もそうだろう。
来年はできれば早めにきて、もっとゆっくり本郷を回ってみよう。
そのときには、友人たちもみな、いつものように墓参りに集まるはず。
三月二十日(日) 仙台より
仙台南部に住む亡父の妹弟五人、家族も家財も全部無事と判明。名取市の一人が心配だったのでひと安心。電気も復旧したという。
ただ、ウチの墓石が倒れて割れたそうだ。宮城沖地震では無事だったが、さすがに今回はもたなかった。落ち着いたら直しにいかねば。
三月二十二日(火) 全日本対前日本
一週間後のサッカー、日本代表によるチャリティ試合のメンバー発表。
海外組がほとんど戻ってくるのも嬉しいが、Jリーグ選抜にも、かつての代表メンバーが多く含まれている。
言葉遊びをすれば、全日本対前日本。元日本ならもう全日本ではないが、前日本はいつ返り咲くともわからない。だから、そこに勇気と夢がある。
カズがいるのが嬉しいのも、かれが、元日本を拒否して前日本であり続けるサッカー馬鹿の、シンボルだから。
三月二十三日(水) 雑感
田園都市線~半蔵門線で通勤している女性にきくと、節電による影響で女性専用車両はなくなっているが、いままでの慣習のまま、ラッシュ時にはやはり女性がほとんどらしい(ごく一部、勇者も乗車中)。
エスカレーターの右を、自然に空けるみたいな感じか? こういう心理って、なにか面白い。
水道水を幼児に飲ませないようにというお達しが出て、たちまち水のペットボトルが売り切れる。近所を見るかぎり、幼児にではなく、自分が飲むために買っていく人が大半のようだった。
そういう人たちは、自らの行為が、買いそこねた乳幼児の母親や妊婦に非常な精神的不安を与える、人間として恥ずべきものであるということが、わかっているのだろうか。最低。
癪にさわるので、いつもは浄水器で漉した水でつくるコーヒーを、あえて水道水のままで淹れてみる。まずい(笑)。
クラオタ話。こんなときこそ「一九五四/五五」を進めよう。
ムラヴィン&レンフィルのタコ十、フルヴェン&ウィーン・フィルのマタイ、クレツキ&イスラエルのマラ九、ターリヒ&チェコ・フィルの《わが祖国》と、続けて聴く。
民族の魂の絶叫という感じで、なんとも強烈。みんな一九五四年四~六月の録音で、このシンクロがじつに面白い。
三月二十四日(木) 中止と再起
四月の東京・春・音楽祭の《ローエングリン》、出演者がそろわないため中止と知らせが来る。
一方、二十六日の東京交響楽団は外国人抜きで、曲目変更して演奏会。これは行こうと思う。生者があまり萎縮していては、死者の弔いにならない気がするから。
三月二十六日(金) 電気の東西
今回の電力不足の騒ぎまで、日本の東西で電気の周波数が違うなんてこと、まったく忘れていた。
そういえばたしかに三十年ほど前までは、「これは50Hz用だから」とか、電気製品そのものに区別があって、買うときに注意する必要があった。
しかしいまは、器具の方で周波数に応じて切り換えてくれるので、消費者は気にしなくなり、忘れたのだ。(西日本で使う方が電気の効率がいいらしいとか、その程度か)
で、そんな明治の亡霊が残っていたことに愕然となったのだが、そこで思い出したのが、二十年ほど前に静岡の富士宮市で、高圧送電線の付替工事をしたときのこと。
東西の電力会社の境界は、静岡県では富士川だった。川の東西で差が端的にあらわれるのが周波数の相違だが、それだけではない。
送電線工事に用いる工具や器具のいくつかが、まったく違うのだ。たとえば東日本が、凸と凹の組合せにしているとすると、西日本は逆に、凹と凸の組合せにしてある。
必要があってのことではなく、お互いの意地で、わざと変えてあるのだ。
だから、静岡県内の工事会社は、両方の工具をそろえなければならない。
我々が富士宮でやったときには、これはすべて東電の管内だが、だから東日本用の工具だけでいいかというと、そうはいかない。東西でつながっている場合もあるので、作業場所によっては西側の工具が必要になるのだ。
とにかく無駄。 いまは知らないが、二十年前までは、新設、つまり新たに作る送電線の場合でも、こんな「意地による相違」がそこかしこに残っていた。
こんな無駄は早く統一した方がいい。簡単ではないけれど、周波数も。
明治時代はしかたがないとしても、一九四〇年に総力戦体制で日本の電力会社を統合したときに、統一の動きを踏み出せなかったのだろうか。
電力会社側は、「電力の鬼」松永安左衛門などが統合に大反対していたそうだが、それはそれとして、互換性だけは高めてくれればよかったのに。
今度のことが、そのきっかけになってくれれば、と思う。
三月二十八日(日) ぞうさん計画
計画停電がなくて不公平な地区。土日と休日の午後八時から、四時間くらい停電してみたらどうか。すると他にすることがないので、来年には子供がたくさん生れて、社会が活性化し、復興の速度が上がるかも。計画停電による増産計画。
三月二十九日(月) 雑感
来月十日の東京・春・音楽祭、中止の《ローエングリン》に代るチャリティ演奏会の指揮者はメータ。フィレンツェ歌劇場来日公演が中止になったとき、自分は残って日本のオーケストラと支援演奏会をやりたかったと言った男が、わざわざ再来日して指揮。しかも、こんなときにあえて「第九」。イスラエル・フィルがなぜかれを心底信頼するのか、初めて本当にわかった気がする。
サッカー。前半は代表が代表たる所以を見せ、メンバーの変った後半は一世一代のカズダンス。現役だけが発揮できるクオリティのなかでの、あのシュート。感謝感謝。
知人の娘さんの大学に、入試時の「受験生は前進」という案内板が残っていたそうだ。
ひるまず進め受験生。ただの「表示」が、偶然にも素晴らしい「標語」になった例(笑)。一緒に「試験官先頭」もあったらおかしいのにって、それは「指揮官先頭」。戦闘指揮の鉄則。これは、大学よりも東電に必要な標語かも。「菅先頭」は、ちょっと不安…。
三月三十日 書店にて
本屋に行く。「あれ、この月刊誌、こないだ前のが出たばっかりじゃなかったっけ」と、何度も思う。
二週間ばかり「普通の毎日」が抜け落ちていることに気がつく瞬間。
Homeへ
四月二日(土) 日本中が
今日、四谷三丁目のスーパーの前に、白人の旅行者らしき男女が五、六人。
こんなに外人がいないのは戦時中以来といわれる今の東京に、普通の雰囲気でウロウロしている白人旅行者って、いったい何者だろう。サルコジ大統領と一緒にフランスの特務機関でも来日したのだろうか。あるいはマスコミ関係?
それにしても外人が珍しいなんて、ほんとに万博あたりの時代みたいだ。
昨日、一九五五年に竹山道雄が書いた『ヨーロッパの旅』を読みかえしていたら、ヨーロッパ人は「ヒロシマは誰でも知っていて、日本中があのようだったと思っているらしい」とあった。
ヒロシマをフクシマにかえれば、いまもそのまま通用しそうだ…。
四月三日(日) 月に雄叫び
『新選組血風録』。演出が清水一彦だったので、トンデモない出来ではなかった。昔のNET版の主題歌「花の嵐か血の雨か、今宵白刃に散るは何」とか「月に雄叫び血刀かざし」の歌詞そのままの場面があったのは、きっとわざとなのだろう。こういう稚気は大好き。しかしやはり役者は弱い。土方役の永井大は、近藤勇の写真にそっくりだ。
前の『新選組!』のときは、清水一彦が演出の回はリズムがよくて面白く、画面も凝ったアングルや光を使う。それに対して伊勢田雅也の回はすべてが平板、ときまっていた。『江』はその伊勢田がメインだけに、案の定の出来(脚本も想像以上のものだが)。清水の下の世代では、『篤姫』の佐藤峰世も好き。
大河って、個人的には演出次第。
四月九日(土) ようこそ
三月十四日発送、というメールが来たきりになっていた、イギリスのCD便。
半ばあきらめていたら今日突然到着。震災後の混乱のなか、まさか被災地に行ってはいないにしても、どこかで置き去りになっていたのだろう。誰にとも知れず、頭を下げてみる。
中身はヴィルデ・フラングのグリーグのヴァイオリン・ソナタなど。沁みる。
四月十一日(月)うまれた時が
気がつくと、なぜか『昭和ブルース』を口ずさんでいる。
「うまれた時が 悪いのか
それとも俺が 悪いのか
何もしないで 生きてゆくなら
それは たやすいことだけど」
(山上路夫作詞・佐藤勝作曲)
オリジナルは一九六九年発売だそうだが(二番以降の歌詞が闘争歌っぽくなるのは、その時代状況のせいらしい)、私の頭にあるのはもちろん、一九七四年のドラマ『非情のライセンス』の天知茂の歌。
この歌や『昭和枯れすすき』が流行って、終末ブームが起きた石油ショック後の世相は、いまの状況への予行演習だった気もする。
新国立劇場の《ばらの騎士》も、指揮や主役級が大きく入れ替わる事態に。
仕方ないと思いつつ、オックス男爵役のフランツ・ハヴラタがそのままとはいうことに、喜びよりもむしろ驚く。
新国立劇場のサイトに、かれの言葉が出ている。
「ヨーロッパはじめ、世界各地で大震災チャリティーコンサートが開かれています。でも、私にとっては、遠く離れたところで歌うのではなく、日本に来て、歌うことが本当のチャリティーなんです」
かっこいい。
四月十三日(水) ハヴラタとドミンゴ
二時から新国立劇場の「ばらの騎士」と、七時からサントリーホールのドミンゴ演奏会のダブルヘッダー。
初台が終演六時十五分、京王新線~都営新宿線で市ヶ谷、南北線に乗りかえて六本木一丁目に、六時四十三分着。
問題なく移動できたが、余震で地下鉄が止まったり遅れたりしたらアウトだったから、あとから思えば危険な賭け。
ハヴラタの歌う「オックス男爵のワルツ」、ドミンゴの「オテロの死」、どちらも名人の十八番。
すでにオックスを六百回歌っているというハヴラタ、齢七十を過ぎてなお「オテロの世界チャンピオン」というしかないドミンゴ。
名人ならではの「くずし」も含め、かれらの旺盛なショーマンシップと、いま敢えて日本に来て(たぶん、周囲の制止をふりきって)歌うという使命感の強さは、表裏一体の「本物のプロ意識」なんだろうと、あらためて痛感する。
こういうときには、やや泥臭いぐらいのそれが、ありがたい。
ドミンゴはほんとうに好調だった。前半は「オテロの死」以外は、《シモン》《イル・トロヴァトーレ》に《リゴレット》と、バリトンのパートばかり。たしかに響きはバリトンぽくないのだが、ナマで聴くと鳴りのよさは一級品。バリトンとかテノールといった声種の区別をこえた、「ドミンゴ」という唯一無二の声種としかいいようがない。
おそらくは共演のソプラノ歌手が交代したための曲目変更で、《リゴレット》第三幕の二重唱があったのが嬉しい。
ヴェルディが書いた、最も霊感豊かな音楽の一つなのに、ナマだとなかなかいい演奏が聴けないが、今日は興奮した。こういう、バリトンとしてのパワーが必要な曲になると、ドミンゴは苦しいのだけれど、伴奏がそれをカバー。演奏会形式でオケがガンガン鳴ったほうが、この曲はいいのかも知れない。
後半はレハール、カールマンなど、シルバー・エイジのウィンナ・オペレッタが中心。
個人的にツボにはまったのは、スッペの《詩人と農夫》序曲。
いわゆる通俗名曲のこの曲、いまの東京の「普通の」演奏会で聴く機会は、ほとんどない。
それを四十八にもなって、いまここでまじめくさった顔で聴いている自分の姿を考えたら、なんだか猛烈に可笑しくなってきて、演奏中に噴き出しそうになって困った。
四月十六日(土) 早起き野球
四月中は計画停電の影響で、神宮も国立も、平日の昼にプロの野球やサッカーがある。
どれか一つ観にいこうと日程を見ていたら、東都大学野球が、その余波で開始時間が早まり、平日朝九時からやっているのを発見。
東都大学リーグは東京六大学に較べてかなり不利な扱いを受けていて、六大学が土日月を確保するのに対し、火~金の平日。しかも六大学が火曜にずれ込んだときには、順延を余儀なくされる。試合開始も一時間早く、例年は朝十時から。
中央大出身の澤村拓一が、斉藤祐樹にライバル意識を燃やすのもむべなるかなという状態なのだが、今年はさらに早まって、朝九時開始なのだ。
しかし野球ファンも団塊を中心に高齢化しつつあることを考えると、プロ野球も猛暑を避けて、早朝開始というのもいいかも知れない。
四月十八日(月) 帝国主義の妄想
クラシックの演奏家、フランス人とイギリス人はかなりの高率で来日してくれている(特に前者)が、ドイツとイタリアは壊滅的(特に後者)。
一緒に戦争する仲間を間違えた気がする、なんて冗談もあるが、もちろんこれは、個人の意志の問題だけではなく、各国の原子力に対する態度と関連が深い。
原子力を推進する国は、そういえばかつての帝国主義の列強が多い。帝国主義に出遅れた無粋な田舎者が肩寄せあったのが、三国同盟。なのに日本だけが懲りずに「エネルギーにおける新帝国主義」に参加しようとしたのだろうか…。
妄想は妄想として、ともかく来てくれる音楽家に感謝。英仏人とて葛藤のなかった人はいないだろうし、ドイツ語圏にもハヴラタとともに《ばらの騎士》に参加した、指揮のマイヤーホーファーやベーンケのような人がいる。来ない人を一々あげつらっても仕方がない。
夜はサントリーホールで、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団。
敢然と日本に来たフランス人カンブルランの《ボレロ》は、通俗に流れず、多彩な楽器編成の面白さを入念に示していく演奏で、素晴らしかった。
四月二十日(水) 平日昼のプロ野球
神宮球場でヤクルト対中日のゲームを観る。思ったとおり内野は空いていて、楽だった(外野は平日でもけっこう入っていて、スーツ姿の観客が意外なくらいに多かった)。
ただ私の指定席は位置が半端で、防護ネットの枠が打席にかかって見にくい。現代ならもっと邪魔にならない建材もありそうで、改良してほしいところ。
ゲームは〇対〇の九回裏ヤクルトの攻撃、無死一、二塁で送りバント。処理した投手が無人の三塁へ投げてしまいボールが転々、二塁走者が帰ってサヨナラ。
投球前、遊撃の関心が明らかに二塁の方へ、併殺プレーに向っていて、三塁手が妙に孤立して見え、「あれ、彼が前へ出たら、誰がカバーするの?」と思った瞬間の出来事だった。テレビより遠いのに、こういう陣形の乱れがわかるのは、ナマの面白さ。
一塁側にいたので、負けた直後の中日ベンチがよく見えたが、停電になったみたいに選手の姿が一瞬に消え、グランドから引き上げるナインも暗闇に吸い込まれるみたいで、野次馬としてはじつに面白かった。プロとして恥ずかしい負け方だけに、当然か。
それにしても、四月下旬というのに、スタンドを吹き抜ける風の冷たいこと。日本列島全体が北へ動いたというか、黒潮から外れてしまったような感じ。
四月二十一日(木) ヤマトと轟天号
まさにいまこそ、コスモクリーナーDが必要だ。行け、ヤマト、十四万八千光年の彼方、イスカンダルへ! などと考えていたら、
「冷凍砲さえあれば原発処理はすぐ済むぞ!」
月刊「映画秘宝」の、このバカな一言に感動して(というか、私と同類のバカがいることに感動して)思わず購入。
たしかに『海底軍艦』轟天号のあの冷凍砲なら、第一原発など、あっという間に丸ごと氷づけにできるわい。
しかし、こんな子供時代の超兵器を思い出すなんて、それだけ自分の心が荒んでいるのだろう。
四月二十二日(金) 身銭は切らないが
ご存じの方は何をいまさらだろうが、クレジットカードのポイント、義捐金に換金できることに気がつく。しかも交換率は、金券化するときより高いようだ。
こうしたポイント、ふだんの私はほとんど利用することがないので、喜んで義捐金に。
ネットで簡単にできるし、フトコロも痛まない。ま、それでは義捐金とはいわない、という気もするが。
四月二十三日(土) 国立の木霊
むかし、新潟育ちの知人から、こんな話を聞いた――その家から線路までは十キロ以上離れていて、普段は汽車の汽笛などまったく聞こえないのだが、冬にかぎって、聞こえてくることがあった。
厚く低くたれ込めた雪雲に反射して、届いてしまうらしいのだ。そしてそういう雲は、きまって大雪を降らせる。だから、晩に布団の中で汽笛が聞こえると、ああ、明日は大雪だ、と思いながら眠るのだそうだ。
我が家は、国立競技場から直線で約一・五キロの距離にあるのだが、ときに、その応援や歓声が聞こえることがある。初めは近所のテレビの音かと思ったが、どうもそうではない。それで、かつて聞いた新潟の雪雲の話を思い出し、やはり曇や雨で雲が厚く低いとき、風向によって届くのだと、気がついた。
といっても、基本的には代表戦とか浦和レッズとか、サポーターがよほど元気な連中のときだけ。
ところが今日は、ガンガン聞こえる。大雨の中、鹿島と横浜のサポーターが懸命に応援しているらしい。熱い。
突然のすごい悲鳴と大歓声にネットを見ると、マリノス追加点。今日はほんとによく響く。
雨ぐらいでなぜ来ないと、自分を呼んでいるような気が…(自意識過剰)。
四月二十六日(火) ドナウの音楽
「気になるディスク」に書いた、ピアニストのウルズレアサの『ルーマニアン・ラプソディ』、現物が来たので聴いてみると、じつにオモロイ。
エネスコ、コンスタンティネスク、バルトークを民俗音楽風にやるのは予想通りとして、シューベルトの「三つのピアノ曲」までもが、まるでジプシー音楽みたいなのはびっくり(笑)。
さすが、コパチンスカヤと組むピアニスト。
四月二十七日(水)ブオン、ブオン
DVDが出ていなかったF1映画『グラン・プリ』、ブルーレイでいきなり出ると知る。現実のカーレースにはまったく興味ないのだが、マシンの迫力と様式美を見事に両立させたこの映画は、むかしテレビで夢中になったので、もう一度観てみたい。
有名な冒頭の画面三十六分割に聞こえてくるテーマ音楽と、一瞬に響きわたる排気音。英国が緑、仏が青、伊が赤、日本が白と、国別に色が指定されているのも、クラシックでいい雰囲気だった。
子供時代、プラモデルをつくるのに愛用した塗料のパクトラタミヤの「ブリティッシュグリーン」「フレンチブルー」「イタリアンレッド」という色名が『グラン・プリ』に出てくるF1マシンのナショナル・カラーのことだと知ったときは、妙に嬉しかった。「ジャーマングレー」だけは、開戦初期までのドイツ軍の装甲車両の色で、意味が違っていたが。
Homeへ
五月一日 蒐集らせん階段
一九六〇年という一年間のクラシックのライヴ録音を網羅して、小宇宙を形成してみようと思いたってから、二十年ぐらいたっている。
元旦にも書いたが、今年は一九六〇年から五十一年目、つまり著作隣接権が消滅して、誰でもライヴ録音をCD化できる年ということで、ここ十五年にないペースで「一九六〇年物」が出ている。
「らいぶ歳時記」にまとめているのだが、今年は追加アイテムが多いので、早くも疲れてきた。
いったい何種類あるのか、数えていないのでわからないが、リストの字数は現時点で四十二万六千六百五十八。四百字詰原稿用紙で、千六十六枚が字でびっしり埋まるという量(サイトに載っているものはそれより少し短縮してある)。
正直、自分にももうよくわからなくなっている。あまりに典拠資料が多いので一々載せなかったのも、いまになると失敗だった。
たとえば、今日リストに加えたばかりの、一月八日のチェリビダッケ指揮ミラノRAI響の《田園》。
これに関連して、昔の私は、一週間後の十五日の《ジュピター》などの録音へのコメントに、こう書いている。
「チェリビダッケ(1912生)は当時フリーだったが、ローマに居を構えていたのでイタリア各地のオーケストラに客演する機会が多かった。1週間前の8日には、このオーケストラとベートーヴェンの《運命》と《田園》も演奏している(録音は未確認)。」
いま読み返してみて、今年初登場した《田園》の録音の存在を、何年も前にすでに予感していた「昔の自分」に、自分で感心しつつ、なかばあきれる。しかしここで問題は、いったいどうやってこの事実を「昔の自分」は調べたのか、ということ。
まったく、おぼえていない…。
チェリの評伝ならいいが、当時の雑誌類だとしたら、断片的すぎて、どれのことやら見当もつかん…。
「一九六〇年」、さすがに数が増えすぎた。膨大すぎて、なにがなんだかよくわからない。
フリーペーパー「はんぶる」の原点に立ち返って、「ウィーン/60」、つまり、ウィーンとその後背地のザルツブルクを中心に限って、そのしばりの中から外を眺めるかたちにしないと、まとまりがつかないだろう…。
とすれば、結局は、最初の構想が正しかったわけで、二十年かけて、
「ふりだしにもどる」
過ぎたるは及ばざるがごとし。
これだけを知るのにかかった二十年という歳月は、まあ、無駄ではないだろうけれど。
自分も来年元旦には、数えで五十。人生五十年で、らせん階段を一回り。降りているのか昇っているのかは、うーん。
五月二日 樅の木は残った
「日本映画専門チャンネル」で『阿修羅のごとく』を放映していた。大河ドラマの『草燃える』と同じ昭和五十四年だそうだ。両方とも、なんとも「苦い」ドラマ。こういうのを観ると、昭和五十年代前半は、やはりそれなりに成熟した時代だった気がする。
もちろんその成熟は表面的なものにすぎず、昭和五十年代後半、一九八〇年代になると、大量消費の急流の中で一気に享楽化、幼児化してしまうのだが。
衛星のNHKプレミアムでは、大河の古い総集編をハリウッドの技術で修復した、デジタルリマスター版をシリーズで放映している。並行して、CSの「時代劇専門チャンネル」でも、修復前の総集編を放送している。
『新・平家物語』のリマスター版は、鮮やかすぎてびっくり。やや平板になった気はするが、光の輝きが違う。
平治の乱で、清盛役の仲代達矢が士卒を励まして叫ぶ、
「しかも思え、ときしも年号は平治、ところは平安の都、われらは平氏! 奮えや人々!」
この伝説的名調子、大鎧の金物と錦がキラキラと光って、効果倍増。
舞台や映画出身の役者が大半を占めた一九七〇年代までは、発声と台詞回しが隅々までしっかりしている。こういう台詞回しの美しいドラマを観ていると、大河以外のNHK時代劇も懐かしく思い出す。平賀源内が主人公の『天下御免』、その前の徳川吉宗の『男は度胸』など。
『男は度胸』は吉宗よりも、敵役の山内伊賀亮が子供心に印象に残っているのだが、ウィキペディアで見ると寺田農だそうだ。一九七〇年の放映だけに、反体制の革命家という存在が、自然に熱いオーラをまとっていたのかも。
『樅の木は残った』の回では、宮城県柴田郡柴田町の郷土資料館に、全五十二話中五十一話の録画テープが保存されていたという話が紹介された。NHKに本放送はもちろん残っていないから、現時点では現存する唯一のもの。
まだホームビデオが普及する前の時期なのに役場が録画していたのは、たまたまこの町にビデオテープの製造工場があったからだという。『樅の木は残った』は現地ロケを行い、大河のなかでもご当地町おこしの先駆けになった作品(だから、仙台人の祖父や父はとりわけ喜んでいた)だが、そのお陰ともいえる。
しかも東日本大震災の前にNHKに届き、被災もなく修復作業中という。
モノクロだろうとなんだろうと、まさしく『樅の木は残った』の題にふさわしい、嬉しい話。
五月三日 国盗り物語
昨日に引き続いて、大河の『国盗り物語』総集編を観る。デジタルリマスター版ではないが、本放送で観たきりでその後は観たことがなかったから、新鮮。
織田信長伝としては、もはや否定された解釈も含めて、自分の年代の「聖書」みたいな作品だったと実感。
駆け足の総集編だけでも、『梟の城』『尻喰え孫市』『功名が辻』『播磨灘物語』などが見事にはめ込んであって、絢爛たる司馬遼太郎絵巻になっていることがわかる。のちの『花神』とともに、脚本の大野靖子は素晴らしい仕事をした。
熱田神宮に全編が残っていたとか、そんな奇蹟を祈る。
五月四日 男子高校生の日常
このところ、『男子高校生の日常』というギャグマンガにはまっている。
展開も設定もいい加減、はっきり言って、第一巻の出来が素晴らしくて、あとはムラのあるマンガだが、平凡な三流男子高の帰宅部って、自分も含めて、たしかにこんなふうにバカだったなあと。
おたくマインドのある人向き。最近四巻が出た。
五月九日 九段会館と日本遺族会
東日本大震災で天井が落ちて死傷者が出た九段会館が閉館になるという。運営元の日本遺族会が国に返還するらしい。
あとはどうなるのだろう。東京では貴重な帝冠様式建築だし、内装も雰囲気がある――私が入ったのは高校の何か行事のときだから、三十年も前だが。
戦後六十六年、門外漢には、現在の実体がどのようなものなのか、想像しにくくなっている日本遺族会と切り離されることは、吉なのか凶なのか。
うまく補修と保存へと道がつけばよいのだけれど、立地がいいだけに、再開発したがる人も多そうだ…。
五月十二日 その名はダナス
台風一号なるものの存在を、きちんと認識させられる年というのも、珍しいと思う。
そういえば、アメリカでは番号ではなくて人名をつけていて、「キャサリン台風」というのがあったと思い出した。しかしあれは三号の「C」ではなく「Kathleen」、十一号なのだそうだ。ただし日本とは判定に相違があって、日本では台風九号だと、ウィキにある。
日本人は車でもクラシック音楽でも、型番より愛称を好む(カローラとか、運命とか)傾向が欧米より強いとされるのに、台風は「伊勢湾台風」を例外に、番号好き。災害だからなのか。
ところが、日本を含む太平洋湾岸諸国は、国際的な台風委員会というのが共通した名称をつけていると、友人が教えてくれた。
気象庁のサイト内の「台風の番号と名前」に出ている。各国が提出した名前を順番につける方式だそうだが、順番に法則性が見えなくて、親しみにくい。
この憶えにくさは試験に最適だから、きっと気象予報士の受験者は丸暗記するのだろう。水兵リーベ式の暗記法が、やっぱりあるのだろうか。
国によって名称の背景に差があって、プラピルーン(雨の神)とか、雨や風の名前がけっこうあるのに、日本がそういうのを避けているのは、いかにも不吉を嫌う、言霊の幸わう国。
コップ台風なんて「コップの中の嵐」にしようというシャレか。しかしそれで死ぬ人はちょっとバカみたいだぞ。
韓国は基本的にかわいい感じで、フィリピンのが全体に畏怖的というか、悲観的。特に「ダナス」(経験すること)というのは、意味を深く考えると怖くて眠れなくなりそうな…。
五月十四日 三十五年前のドミンゴ
NHKのドミンゴの番組を観る。
初来日の一九七六年、NHKホールでの《道化師》のアリアをやっていた。興味深いことに、もちろんいい声なのだけれども、まだ若いだけに鳴りすぎる感じで、その後の澄明感がない。いまよりもずっとバリトンぽい響きなのだ。ちょうどオテロを歌い始めたころだから、そうしたことも関係するのかも知れない。
この時期をへて、節制を重ねて無駄がとれ、響きが澄んできて、現在がある。
立派。
五月二十一日 地獄の天使
ハワード・ヒューズ監督・製作の映画、『地獄の天使』を観る。
ヘルズ・エンジェルズといえばアメリカの暴走族だけれど、この映画の原題が元になったのだろうか。これは第一次世界大戦の空戦物。ストーリーは辛口だがつけたりみたいなもので、実機を使った空戦シーンが異様な迫力。
大金持で飛行機好きのヒューズが、湯水のように資金を投じた結果である。第一回アカデミー賞作品賞を受賞した、航空映画の先駆けである一九二七年の『つばさ』を上回る映像を目指し、ヒューズが入れ込みすぎて、あまりに現場に口を出すために監督が次々と降板、とうとう自分で監督になったという映画。自分でスタント操縦をして失敗、大怪我で長期の撮影中断もあった。
前半は、ロンドン空襲に来るツェッペリン飛行船の執拗なメカ描写が印象的。宮崎駿の巨大メカ描写の源流には、直接的にか間接的にか、疑いなくこの映画のツェッペリンの場面がある。『スターウォーズ』にも、それはありそう。
一九三〇年の映画なのに、約三十分がカラー撮影というのにも驚く。カラー・フィルムの技術が存在していたということは頭ではわかっていても、現実にみせられるのは重みが違う。飛行船が撃墜されて炎上する、巨大な火の玉がカラーなのが強烈。
逆に、サイレントの部分が残っているのも面白い。撮影中にトーキーが実用化されたため、役者を取り替えて大半を撮影しなおしたのだそうだ。両大戦間の映画の革新的進化の流れが、この一本に凝縮されている。
後半は、双発の重爆撃機による爆撃シーンと、死人が三人出たという大空戦。弾薬集積基地に爆弾を落とすと、時間差をおいて次々と誘爆、ついに全体が吹っ飛ぶというシークエンスは、『青島要塞爆撃命令』の原型のようにも思える。
この重爆が撃墜される場面では、素人目にも異常なきりもみ降下が映るが、やはり引き起こせずに本当に墜落、死者を出したらしい……。
映画屋の夢というか、悪夢というか。
五月二十二日 蜂と筍
今年はアシナガバチが大量発生と聞いて数日前から警戒していたが、さっそく巣を玄関のひさしの裏につくろうとしていたのを発見、駆除。
風向や気候の関係なのか、来ない年はまるで来ないし、来る年には三つ四つつくられる。発見が数日遅れるとそれなりの大きさになって面倒なので(作業バチの数も比例して増える)、これからも気をつけねばならない。
面白いのは、我が家では人間がよく通る場所、玄関や窓がある、東南に面した壁面にだけ、巣がつくられること。
お互いに共存の難しい場所ばかりなのだ。今日の場合も巣自体は目に入らなかったが、ハチが頭上で警告の羽音をたてたので気がついた。いきなり刺されるほどの近さでなくてよかった。
また、ハチが来る年には竹もよく生える気がする。あまり早く取るとすぐあとに生えてキリがないで、適当に伸びるのを待つのだが、これも目を離すと、たちまちニョッキリ。果てしなき永遠の繰り返し。
年々歳々蜂筍相似たり。
五月二十八日 二号来たる
台風一号に続き、珍しく二号も接近。
プロ野球の開幕戦で二本ホームランを打ったら、「このペースだと今年は二百六十本打ちますね」(まだ百三十試合の時代)と語るバカなアナウンサーがいるだろうか、と笑ったのはホイチョイだが、今年の台風は、ほんとに全部日本に来そうな気がする。
友人いわく、二号って、なんか後ろめたい感じと。
五月二十九日 元禄太平記
少し前に録画しておいた、『元禄太平記』総集編を観る。
赤穂と吉良の塩田をめぐる経済的対立をとりいれたのが、当時は斬新な解釈といわれたけれど、いまみると、それはそれとして、物語の核になる「忠臣蔵」部分は、カラー版の大河では初めてだったからか、ごくオーソドックスにつくってある。そしてそれがよかったのだろう。
何度みても、甲府宰相綱豊(家宣)役の木村功がいい。『新・平家』の義朝も似合っていたし、いい役者だったとあらためて思う。
森繁の水戸光圀は厭味な感じが、水戸は水戸でも(懐かしいフレーズ)、むしろ烈公斉昭のような。放映時に翌月曜日の『水戸黄門』で、東野英治郎が決定版的人気を博していたことを考えると、この人物造型はさらに味わい深し。
これで一躍人気が出た江守徹の内蔵助は、幸四郎、松緑といった歌舞伎役者のオーソドックスな型をとりいれつつ、うまく現代化している。表情、声の出し方がのちの鹿賀丈史によく似ているのが面白い。というより、鹿賀が真似したのだろうけど。
もう一つ存在が軽いのは、堀部安兵衛の関口宏と、架空の人物である柳沢兵庫の竹脇無我。この兵庫というのは柳沢吉保の兄の子という設定で、堀田隼人と月森十兵衛を合わせたような人物。十兵衛から思いついて、同じ柳生家の別の有名人の名をとったのだろうか。
まあ、本放送時には何よりも清水一学役の三善英史の、壮絶なまでの大根ぶりが話題になっていたから、この二人の軽さは目立たなかったのかも。
その一学、さすがに総集編では一言しかしゃべらせていないのはいいとして、その巻き添えか、吉良家中のもう一人の強敵だった、辻萬長演じる小林平八(この話では平八郎ではなく、平八)も一場面しか出てこないのは、個人的にはとても印象的で好きだったので、残念。
江守徹が持っていたという本編のビデオ、うまく修復されて世に出てほしい。討入の回は歴代の大河のなかでも、いちばんの出来だったと思う(この頃の大河は、室内戦の狭い殺陣と演出が、とにかく上手だった)。
それに、松の廊下事件を知らせる早駕籠の、江戸から赤穂の旅程を描くだけで一回の大半を費やすという驚くべきことをやった、第十九回「嵐の中の人々」。
早駕籠に乗った使者の焦燥と疲労困憊(休むことなくエッホエッホとずっと揺られっぱなしなので、ひどい船酔いになる)と、何も知らない赤穂の城内との、静と動の対照が、とても見事だったという記憶がある。
五月三十日 我が内なるエイハブ船長
ハリウッド映画『白鯨』を、初めて真剣に観てみた。
クラシック関係で最近は一九五四、五五年のことばかり調べているのだが、その関係で、同時期の映画をいくつか観なおしている。
特に、ビキニ環礁での第五福竜丸事件がらみの観点で『ゴジラ』を観て、それからアメリカの原水爆怪獣もの。
ゴジラ、それも第一作のゴジラは、作中で宝田明がいうように水爆そのものであり、地震や台風のような天災そのものであり、また、日本を焼き尽くし、原爆を投下したB29のようでもある、人間の手の及ばない存在。
どんな砲火もはねかえす。
銀座を火の海にして、セイバー戦闘機の攻撃も気にせず、海に悠然と引きあげていくゴジラの後ろ姿を見ながら、「チキショー、チキショー」と悔し涙を流す少年が映るが、あれは震災や空襲に対して、日本人がさんざん流してきた涙。
オキシジェン・デストロイヤーなる、危険すぎて発明者が自らの生命とともに滅ぼしてしまうほどの、水爆なみの超兵器でしか、倒せなかった。
これに対し、アメリカの怪獣は、普通の新兵器を使えば倒せる。
『原子怪獣現わる』の水爆実験で目覚めた古代の肉食竜リドサウルスも、『放射能Ⅹ』の放射能で巨大化したアリも、普通の人間が工夫することで倒せる。
有史以前から人間が道具を開発し、集団による連繋を工夫することで、一対一では倒せないマンモスを狩り、クジラを捕ってきた延長上に、怪獣もいる。
核兵器は、余計な副産物もあるけれども、原則的には便利な最新の「道具」の一つであって、現にリドサウルスを倒すのにも、放射性アイソトープを用いた新型弾(劣化ウラン弾みたいなものか?)が使われる。
この時代が面白いのは、こうした映画を生み出す核兵器開発競争と並行して、というかコインの両面として、原子力平和利用の動きが出ていること。
ウォルト・ディズニーは、原子力平和利用の積極的な宣伝者だった。
『ゴジラ』と同じ一九五四年の映画、『海底二万浬』には、そうした要素が色濃くある。
ジュール・ヴェルヌの原作のナウティルス号は、海水中の塩分を用いて発電したエンジンを使っているのに、ディズニー版のノーチラス号は、明らかに原子力を思わせる、未知の危険な新エネルギーで駆動している。
これは、同時期に就役した米海軍の世界最初の原子力潜水艦、その名もノーチラス号を宣伝する意味も兼ねている。
そしてディズニーは数年後、映画と現実の二つのノーチラス号が出てくるテレビ番組『わが友原子力』をつくった。原子力の平和利用を宣伝する映画である。
で、『白鯨』。
一九五六年製作のこの映画は、設定が十九世紀の一八四一年だから原子力とは関係ないのだが、上にあげた同時期の諸作と並べてみると、言外のメッセージがあったように思えてくる。
白鯨モーヴィ・ディックは、人間の傲慢を叩きつぶす神罰のような存在であるという点で、ゴジラによく似ている。
『海底二万浬』との関連も面白い。ヴェルヌは『白鯨』を意識していて、主人公は生物学者と捕鯨船の銛打ちで、最初はモーヴィ・ディックのごとき謎の巨大生物が、何度も目撃されているという話から始まる。
その生物が、じつは潜水艦ナウティルス号、人間のつくった「道具」だった、という展開で、そこにディズニーは、さらに原子力平和利用を暗示した。
『白鯨』の映画はそれに対して、その原型である、神が自らの手でつくったような、巨大なクジラを登場させる。
この映画の脚本を担当したのはSF作家のブラッドベリで、この人は『原子怪獣現わる』の原案になった短編『霧笛』の作者である。
当時のアメリカで、正面から核兵器反対をとなえたら、「原爆の父」オッペンハイマー博士のように公職を追放される危険が大きかったことを考えると、この『白鯨』の映画は、精一杯の寓話だったのかも知れない。その点で、『海底二万浬』と好対照の位置にあるのだ。
寓話性を絶対に強く意識しているはずだ、と思ったのは、グレゴリー・ペック演じるエイハブ船長とかれの捕鯨船ピークォッド号が、モーヴィ・ディックに対して僣越にも攻撃を仕掛け、一人を残して全滅させられる場所の設定。
その地名が、台詞には、気がついただけで二回出てきた。
ビキニ環礁なのだ。
メルヴィルの原作が、たまたまそこに設定したというだけにしても、ちょっとびっくりした。
ラスト、銛打ちたちの乗るボートを口で噛み砕き、尾ヒレで打ち砕き、そして巨体をピークォッド号に激突させて沈める、怒れるモーヴィ・ディックの白い背には、溺死したエイハブ船長の死体が、ロープで縛りつけられたまま。
いま、フクシマ以後の日本でこれを観るのは、我が内なるエイハブ船長の姿を見せつけられるようで、かなり効く。
エイハブ船長を演じたグレゴリー・ペックという人も、ちょっとというか、かなり、面白い。
『ローマの休日』の脚本を、赤狩りで追放されたトランボが友人の名を借りて書いているのを、ペックは承知していたらしいし、その三年後に『灰色の服を着た男』という、現代アメリカの精神的荒廃と危機の予感を描いた映画の中で、戦争で従軍中に「ローマ」で愛人をつくり、子供までできてしまったアメリカのサラリーマンを演じて、自ら『ローマの休日』の陰画のようなことをやっている。
(ところでこの作品では、現代の光景から、戦時中の場面がフラッシュバックしてくるという手法が用いられている。同様の手法で書かれた豊田穣の『長良川』は、おそらくこの映画かその原作かに影響を受けたのではないだろうか)
この『灰色の服を着た男』と同じ年に公開されたのが、『白鯨』。
ペックはこの作品の全権利を所有していたというから、たぶんこの作品には、かれの考えが反映されているだろう。
さらにその三年後には『渚にて』という映画で、核戦争後で滅亡間近の地球を回るアメリカ潜水艦(そういえば、これは原子力潜水艦にきまっている)の艦長役もやっている。
赤狩りにはあっていないが、当時のアメリカでは、危険なまでのリベラル思想の持ち主だったらしい。
『ローマの休日』はじめ、ヒット作や話題作に続けて主演しながら、一九五〇年代のアカデミー賞にノミネートすらされなかったのは、単にかれが大根だっただけだから、なのだろうか。まあ、これは「陰謀論は蜜の味」だけれど。
ともかく、ペックのきちんとした評伝も読みたいと思ったが、日本で出ているのは『ローマの休日』のフォトブックみたいなのばかり。
アメリカでは何冊か出ているが、どれがいいのだろう…。
Homeへ
六月一日 ルセのクープラン
石橋メモリアルホールに、クリストフ・ルセのチェンバロによるチャリティ演奏会を聴きに行く。
津波の一週間後、楽器製作者のデュコルネが発案し、ルセの賛同を得て一晩だけの来日を決めたという。使用されたチェンバロはいうまでもなくデュコルネ製で、このためにわざわざ空輸された。
演奏会の決定後、原発災害の甚大さがどんどん明白になったことを、二人がどのように思ったかは、わからない。わかるのは、それでもかれらは来た、ということ。
曲目はルイとフランソワ、二人のクープランの組曲を交互に。知人も言っていたが、《威厳》とか《小さな風車》とかの曲名をもつフランソワよりも、アルマンドとかサラバンドとか、舞曲の名前が無機的にならぶルイの曲の方が、ルセの演奏ではより純音楽的に充実して響き、奥深く感じられた。
六月二日 ミキエレットと肉体
新国立劇場のミキエレット演出の《コジ・ファン・トゥッテ》。
とても楽しんだ(生きた空間を、新国の舞台では久々に見た)けれど、面白いのは、震災でも来てくれたオリジナルの歌手たちが痩せているのと対照的に、代役で来てくれた歌手は「体格がいい」こと。元の歌手の写真などを見ても、声楽的にはともかく、視覚的には原案とは、あるいはかなり変わっているようだ。
この演出では肉体のしなやかな動きをかなり重視しているので、残念。フィオルディリージが陥落する肝心の場面がほかよりも弱くなってしまったのは、演技力と容姿の問題が大きそう。
六月五日 伊上勝と西村俊一
井上敏樹と竹中清の『伊上勝評伝』を読む。徳間書店刊。
伊上勝というのは、子供番組を中心に昭和期に活躍した、テレビ・ドラマの脚本家。『快傑ハリマオ』のほか、『遊星王子』『隠密剣士』などを宣弘社の社員として書いたことを、後輩の阿久悠の回想などで知っていたので、大いに興味があった。
伊上勝の息子で、自身も脚本家として活躍する井上敏樹の回想を頭に、あとは竹中清が関係者に行なったインタビューを並べたもので、評伝というよりは証言集、知人の回想集というつくり。
とはいえ、初期の『仮面ライダー』の大部分や『赤影』の全部を書き、『悪魔くん』『闘え!ドラゴン』、そして一九七〇年代の東映特撮物でも大活躍したということは知らなかったから、とても感心させられた。著者の竹中はもちろん、どちらかといえばこちらに関心があって執筆したようである。
六〇~七〇年代の特撮物の脚本というと、上原正三や金城哲夫などウルトラ・シリーズの脚本家の評価が高く、東映のそれはまともに評価されない。よくもわるくも活劇の面白さに徹していて、深読みさせる余地などないからだろう。
私は、どちらかといえば東映の単純さの方が好きだったから、それを確立したのが伊上勝だったというのは、自分がのちに『ハリマオ』にのめり込んだことと合わせて、感慨深い。
ただ、『ハリマオ』や『隠密剣士』では、プロデューサーの西村俊一の考えも多く入っていたはずである。これらに色濃い西村の「少年倶楽部」風のロマンと、伊上の無国籍風の活劇とが組み合わさっていたことが、その面白さの一因のように思えるのだが、残念ながらこの評伝に西村俊一のことは、なぜかほとんど出てこない。
八〇年代に入って、スランプと深酒でほとんど書けなくなった伊上の、最後の大きな仕事が『水戸黄門』で、その放映を子供のようにはしゃいで観ていたと、井上敏樹の回想にある。この作品が、宣弘社を離れた西村プロデューサーの最高のヒット作だったことを思うと、『遊星王子』に始まった一つの円環の終り、と思えてならない。
竹中はともかく、井上が西村をまったく知らないとはどうも思えず、あるいは故意に伏せているのかも、という気がするが、これはもちろんただの憶測。
ところで、井上は平成の仮面ライダー・シリーズの脚本家として大活躍しているそうだ。私はまったく観ていないのだけれど、ご承知のとおり平成ライダーといえば、サブカル系の人が高く評価しているシリーズだ。
ウルトラ・シリーズに隠れて、後世から評価されない昭和ライダーを書いていた脚本家の息子が、その点で対照的な平成ライダーの脚本家だというのは、とても面白い。そう思って井上の回想を読みなおすと、また一段と味わい深い。
六月六日 メトのゲネプロ
メトロポリタン歌劇場のメンバーによる記者会見(記者席も満員の盛況)を聞いたあと、東京文化会館での《ランメルモーアのルチア》ゲネプロを観る。
第二幕に入る前に、第三幕のエドガルドの長大なアリアをオーケストラだけで演奏。始める前に「セミトーン」、つまり半音下げることをノセダが説明していたので、とにかくそれで一度演奏しておきたかった、ということか。
ダムラウの赤ん坊が客席にいて、ママの狂乱の場などで叫んだり。ノセダがピットにその子を呼び、指揮棒を振りまわさせるとオーケストラがわっと大喜び。このへんはいかにもアメリカン。
それにしても情熱的な、息の長い旋律美と血のたぎるようなリズム。この曲もトスカニーニの指揮で聴いてみたかったものの一つ。
六月七日 メトのラ・ボエーム
NHKホールでメトロポリタン歌劇場来日公演の《ラ・ボエーム》。
ゼッフィレッリの舞台は、ミラノやウィーンで半世紀近く上演されている名演出を原型にした、王道中の王道。NHKホールでは舞台が遠く感じられるのは仕方がない。
歌手では、フリットリがやはり飛び抜けている。個人的にはネトレプコより彼女が聴けて嬉しかった。たしかに、よい意味で貫祿がありすぎて、弱さが売り物のミミには合わない気味もある。ミミという役にはどうも共感できないという本人の思いが、出てしまうのかも知れない。しかし音楽性の高さ、深い表現力は、生半の歌手の及ぶところではない。
声は以前より滑らかさが失われて、太くなってきているが、イタリア・オペラには、こうした声が合う作品がいくらでもある。オリヴェロ、スコットなど、イタリアのプリマ・ドンナの進む道を彼女も歩んでいるのだろう。今後も楽しみ。
六月十一日 四谷三丁目の喫茶クラウン
五日に書いた井上敏樹と竹中清の『伊上勝評伝』の話。
東映のプロデューサー、阿部征司の回想にこうあった。
「僕はね、伊上さんが原稿を書くときに使っていた、四谷三丁目の喫茶店〈クラウン〉に行くのは嫌いじゃなかったんですよ。伊上さんが目の前で原稿書いてるのを、ただ見ているだけなんだけどね。それもそんなに嫌いじゃなかった。仕事場にしていたアパートは、四谷三丁目の交差点近くにあるのは知っていたんですが、肝心要のアパートの名前を伊上さんは言わないんですよ」
ここを読んだときは、伊上もかつてご近所さんだったのかと感慨があった。自宅は別にあったが、仕事部屋は四谷三丁目に借りていたのだという。
ただし喫茶店クラウンは現存しない。山の神によると、風月堂(交差点の東南角の南寄りにある)の向って右、信濃町寄りにあったという。いまは普通のビルが建っているが、当時は喫茶店が二軒ならんでいたわけだ。
六月十三日 七時間半
獅子文六の『七時間半』と『可否道』を読んだ。
前者は昭和三十五年に「週刊新潮」、後者は昭和三十七年から翌年にかけ「読売新聞」に連載したもの。文六の後期の長編で、以前触れた『箱根山』はこの間の昭和三十六年に書いていて、全集ではこの三作で第九巻を構成している。
昭和二十年代の諸作のような勢いや集中力はないが、当時の風俗を巧みにとりいれて物語に織っていく、練達の手腕に衰えはない。
まずは『七時間半』。
『七時間半』というのは、東京大阪を結ぶ特急「つばめ」の所要時間のこと。ただし作品内ではそのままではさしさわりがあるのか、「ちどり」と名前を変えてある。じつは、東京大阪間の特急の最短所要時間は連載中に、六時間半に縮まっている。時代の変化の速度がどんどん増していることは文六にとってやりにくかったろうが、ともかく、新幹線以前の、食堂車があった時代の特急の話。
その一本、午後十二時半に東京を発車して、夜の八時に大阪へ到着する車内が舞台である。
首相から学生まで、さまざまな階層の人が乗り合わせるものだから、グランドホテル形式の群像劇にする手もあったろうが、文六はそこまで手の込んだことはせず、食堂車のコックとウェイトレスの恋に「ちどり・ガール」と呼ばれる客席係(もちろん実際はつばめガール。スチュワーデスのような客室乗務員)の美人をからめて主役三人とし、あとは脇役にしぼりこんでいる。安保前後の騒然たる時期の連載だけに、岸信介らしき首相や、全学連らしき連中も登場。
品川操車場の朝の発車準備に始まり、東京から大阪までの車内や停車駅や沿線の様子を、時間の進行に合わせてかなりていねいに描いているので、小説とはいえ、鉄道好きには貴重な記録なのではないだろうか。
まだ読んでいないが、文六は横浜駅のシュウマイ売りをヒロインにした作品もその前に書いているはずだから、かなりの「鉄ちゃん」だったのだろう。
食堂車に「つばめガール」と、新幹線時代になれば消えることが当時から予感されていたものに着眼したのはさすが。
私は食堂車を、子供時代の仙台行きの特急でかすかに憶えている。五、六時間かかったから、たいがい一度は行くことになった。
それは祖父が一緒の場合が多かった。行きたがらない母とは対照的で、孫に甘いためもあったろうが、戦前の銀座などを知る明治人の、ハイカラ好きの名残もあったと思う。オートミールという、街中ではホテルにしか置いていないようなものを好んで注文するのが、祖父のこだわりだった。
そうした気分を思い出しつつ読んだ。そういえば「旅の食堂、日本食堂」なんてラジオCMも、旅にいざなうような感じで好きだったっけ(小説では「全国食堂」と名を変えているが)。
人気の安定した獅子の作品だけに、これも翌年に映画化されている。川島雄三監督、フランキー堺、団令子、白川由美という、いかにもそれらしい配役で『特急にっぽん』というタイトル。いつか衛星などで観てみたい。
六月十四日 可否道
昨日に続いて、獅子文六の『可否道』の話。
昭和三十七年から翌年にかけ「読売新聞」に連載したもので、当時の世相をじかに反映している点では、『七時間半』よりも『箱根山』よりも楽しめる。
可否というのは珈琲同様、コーヒーの中国語表記の一つ。茶道のごとくコーヒー道をうち立てようとする初老の男が、主要人物の一人なのである。
この男が、開通間もない丸ノ内線の四谷三丁目駅近くに屋敷をかまえているという設定も、個人的には面白かった。伊上勝の喫茶クラウンといい、たまたまご近所の話が続く。
文六は、本名の岩田豊雄の名で幹事をつとめる文学座が、信濃町駅と四谷三丁目駅の間の、大正天皇生母の柳原二位局邸跡にアトリエをおいていることもあって、この辺をよく登場させる。以前に触れた『大番』には荒木町の花町が登場したし、一儲けしたその主人公が邸宅をかまえたのも、信濃町付近だった。
さて、手間をかけてコーヒーを美味しく淹れる儀式を真剣にやるのは、いかにも大正~昭和初期のモダンな時代の日本のコーヒー好きを想わせる。たしかに昭和五十年代くらいまでは、そんな気分を受け継いだ喫茶店も愛好家も、数多く残っていた。
そういえば、LPやそれを勿体ぶって再生する「儀式」というのも、当時はたしかに存在していた。いまでも、吉祥寺とか中央線沿線の喫茶店や住宅には、わずかに残っていそうな気がする。いかにも中央線文化という感じ。四谷も中央線が走っていることを考えると、戦前の山手文化から戦後の中央線文化に引き継がれた気分、というところか。
しかし、茶道のように格式化しよう、家元制度化しようというのは、当然ながら無理だらけ。すでに時代からずれ始めている。その滑稽が、ちょうど出回り始めた、家庭向けインスタントコーヒーの手軽さと対比させられる。本格的に始まった大量消費社会が浮き彫りにする人間と世間の身勝手が、喜劇的に描かれる。
さすがなのは、大量消費社会の登場をコーヒーに加えて、草創期のテレビ業界によって描いていること。民放テレビの番組とCMくらい、大量消費社会を象徴するものはないのだ。
ヒロインの坂井モエ子は新劇の脇役女優だが、テレビの連続ドラマで人気が出て、CMで活躍するほどになっている。
「以前は、人に顔を知られるのは、映画俳優が一番だったが、このごろでは、テレビ・タレントである。なにしろ、家庭へ侵入してくるから、親しみの度がちがう。それも、坂井モエ子のように、長期の連続ドラマに、よく出演すると、まるで、聴視者の家族の一員のような、待遇を受ける。茶の間の観客というのは、役者の芸の巧さよりも、ナジミの深さで、人気を湧すので、彼女のファンは、世間の想像以上に、多いのである」
既存の舞台や映画では考えられなかった、お茶の間直結型の人気タレントというのが、テレビを通じて生まれるようになったのだ。そして、それを可能にするくらいにテレビが一般家庭に普及した、史上最初の時期なのである。それはテレビだけでなく、冷蔵庫、洗濯機、そしてインスタント食品などで、家庭環境が激変しつつある時代だった。「道」などをのんびりと追求する余裕などない。
文六の作品は次々とドラマ化されていたから、テレビの制作現場の雰囲気もよく知っていたのだろう。赤坂のTBSらしきテレビ局の内外と業界人の様子も、面白おかしく描かれる。
消費社会の大波は、新劇の劇団と俳優にも及ぶ。赤坂檜町にある劇団「新潮」というのが出てくる。檜町なら場所的には六本木の俳優座が近いが、しかし文六が書くなら文学座のことと、読者が想像するのを百も承知で、新劇人の生態に触れる呼吸が憎らしい。
「この劇団は、数人の幹部俳優が中心となって、運営されているのだが、どれも、新劇三十年の経歴の所有者であって、技術の点では水準を抜いていても、もう五十を越したジイさんバアさんであるから、理想だの、情熱だのに、カッカと燃え上る連中ではない。彼等とても、三十年前には、カッカと燃え上ったことがあるだけに、そういう所業を、何か、幼稚なものと考える傾向がある」
作品の連載中、文学座には分裂騒動が起きて、退団者が劇団「雲」を結成している。この偶然も面白い。
六月二十一日 夏至の妖精王
本屋に行くと、「山岸涼子ベストセレクション『妖精王』Ⅰ」が出ていた。
大好きで、むかしから何度も読んでいるから買いはしないが、「夏至に発売する」という粋な計らいに心が騒ぐ。
そう、夏至といえば『妖精王』。「君はこのぼくを頼りにしなさすぎるよ」――ああ、クーフーリンの言うとおり。久々に行こう、ニンフィディアへ。
というわけで、夏至の夜明けに読了。久々に読みなおすと「純粋すくすく美少年が、業を背負った女軍団を無邪気に征服」という構図が前よりもよくわかる。「愛されたい」という欲は悪なのか? 山岸涼子は、なぜこんなに自分の「オンナ」を嫌悪するのだろう。対極に耽美的な少年愛があって、いまのBL(ボーイズラヴ)につながるのか。さすが「二十四年組」と呼ばれる女性マンガ家の一人だけあって、このあたりはもはや古典と呼ぶにふさわしい。
マブは、モーガン・ル・フェイとグィネヴィアを混ぜたような。アーサー王物語を骨子に、古今東西のさまざまなファンタジーを面白がってぶち込んで、やはりよく出来ている。
六月二十二日 節電
真夏日。このぐらいの暑さになると、例年なら近所で盛大に室外機の音が響くはずだが、今年は静か。
やはりみな気をつけているらしい。その心がけ自体は素晴らしいのだけれど、やりすぎになりそうな気もする。
三月の震災直後と、この夏とでは、同じ電力の不足でも、その性質がかなり異なっている。三月は突然の事態で、全体量が足りなくなり、朝や夜の食事時の使用量さえ賄えない可能性があったから、一日すべてで節電を心がける必要があった。休ませていた発電所を稼働させるのに、最低二週間は要したからである。
いまはそれがフル稼働していて、たとえ例年のごとく、湯水のように遠慮なく電気を使ったとしても、足りないのは、酷暑期の平日の午後数時間だけだ。
他の時間帯は充分な余裕があるはず。
六月二十八日 破産と再生
大リーグのドジャースが破産手続を申請というニュース。フィラデルフィア管弦楽団に続く名門の破産。
私などは「破産」という言葉だけで、死亡宣告のような感じを受けるのだが、どちらも活動は続けている。再生のためのショック療法として破産するわけで、日本では民事再生、昔の会社更生といった手続にあたる。
ショッキングな用語を避け、なるべくソフトにというあたりが、言霊信仰。
六月二十九日(一) ジンジャーエール
近くのコンビニで、ウィルキンソンのジンジャーエールを売っていたので買ってみる。ほんとうにショーガ味が効いて辛いが、うまい。友人にきいてみると、意外なくらいファンが多い。かれらはこれまでビンで飲んでいたという。ペットボトルでの発売を喜んでいた。
ゼロカロリーになったのは好悪が分かれそうだが、個人的にはこの方がいい。
たしかに、人口甘味料の独特の味は口に残るのだけれど、糖分たっぷりのどろりとした重さは、もっと苦手だ。
六月二十九日(二) 猫と鏡
猫が鏡を見ている。
後ろに座った私も鏡を見て、鏡の中で目と目とが合う。その瞬間、ぱっと振りかえって、現物の私の目を猫が見る。
鏡の中の像が現実の反映であることを理解しているわけで、やっぱり猫って頭がいいと思う。ならば、自分の顔もわかっているのだろうか…。
ところで、犬は大きいのから小さいのまで色々な種類があるが、猫にはそこまでのヴァラエティがない。体長はどれも似たようなものだ。
ネコ科にはトラやライオンまでいるわけで、結局、飼いならすことができたのがこの小さい種類だけだった、ということなのだろうか。
六月三十日 福島原発行動隊の歌
リタイア組四百人が志願して、福島の原発事故収束作業に参加するという。それぞれ一家言ある人が集まるのだから、難しい部分もあるだろうが、ほんとうに立派だと思う。
その名は福島原発行動隊。
どうしても《民族独立行動隊の歌》を思い出すのだが、語呂もあうし、きっとそのもじりなのだろう。ただし、歌詞は《国際学連の歌》の方が合いそう。
東大音感合唱団による一番の訳詞。
労働にうちきたえて 実らせよ学問を
平和望む人のために
ささげよう我が科学
我等の友情は 原爆あるも たたれず
闘志は火と燃え
平和のために 戦わん
団結かたく 我が行く手を 守れ
「原爆あるも」を「原発あるも」に変えれば、まさにぴったり。
学生時代の無私の情熱と正義感を、ひとまずイデオロギーを捨象して半世紀ぶりに甦えらせるのなら、すばらしい。かつてのそれが無駄ではないことの、何よりの証明ではないか。
Homeへ
七月二日(土) アラールと扇風機
シギスヴァルト・クイケンのラ・プティット・バンドによる、バッハ演奏会を聴きにオペラシティへ。
ブランデンブルク協奏曲の、二、六、五、三番の四曲と三重協奏曲。クイケン自身のひくヴィオロンチェロ・ダ・スパッラも大活躍だったが、個人的にはチェンバロのバンジャマン・アラールの清々しい演奏が、いちばん印象に残った。この人はアルファからバッハの独奏曲を出しているので、近々聴いてみるつもり。
夕方、初台から歩いて帰る途中、新宿のヨドバシカメラに寄る。扇風機、売れているとは聞いていたが、ほんとうに売場がほぼカラになっていた。いまどきおよそ見ないような、昔風の銀色のタイプが二台残っていただけ。その代わりか、パソコン売場には、USBで回す小型扇風機がいっぱいあったが…。
七月四日(月) 朝からドラマ
朝、外がガヤガヤするなと思ったら、いきなりドラマの撮影が始まった。
「観念しろ、須藤!」
犯人の追跡と逮捕の場面らしい。この付近がよほど好きな製作プロダクションがあるらしく、土日の夜などはしょっちゅうだが、平日の朝は珍しい。
七月五日(火) 爽快人間と十三日
ビールのCMで、『妖怪人間ベム』の替え歌で「爽快人間の歌」をやっているが、けっこう好き。妖怪人間の三本指が問題とかで、再放送できなかった時代が長かったから、知っている年齢層はけっこう高めに限られる気もするが。
ベムというと思い出すのは、村の大人が十三日の夜になると、呪いのために全員怪物に変身してしまう話。
子供は人間のままなので、親たちは自分が正気を保っている昼のうちに、かれらを村の外へ逃がしておくのだが、ある子供たちだけが残ってしまう。
はじめは何の変化もなく、子供たちは居間にいて、母親が台所で夕食をつくっている音を聞いているのだが、知らないうちに母親は怪物になっていて、子供を殺すために包丁を研いでいるのだ。
この、自分の親が、何よりも頼りにしている親が、目を離したすきに怪物となって自分を襲うという展開、まさにこの世に身の置き所のなくなる展開が、子供心にはトラウマになるほど、恐ろしかったのだ。
七月六日(水) グレアム・グリーン
およそ文学的素養のない私だが、最近はグレアム・グリーンに、猛然と興味がわいている。
占領下のウィーン(第三の男)、第一次インドシナ戦争のベトナム(おとなしいアメリカ人)、キューバ革命前のハバナ(ハバナの男)、コンゴ動乱直前のベルギー領コンゴ(燃えつきた人間)と、冷戦の摩擦点に傍観者として滞在し、小説にする男。イギリス情報部との謎めいた関係、キリスト教と共産主義。
とりわけ自分にとっては、「一九五五年」に出した、ベトナムが舞台の『おとなしいアメリカ人』が引っかかる。
そこで小説のほか、二回の映画化のDVDを購入。さらに、『コンゴ・ヴェトナム日記』も入手してみる。
七月八日(金) 夕映えの空に
偶然、夕焼け空を見ることができた。今日は雲の配分が絶妙で本当に美しく、幸福感。「夕映えの空に神は在る」という話、嘘じゃないと思ったり。
七月十日(日) 日経の書評
日経新聞に『フルトヴェングラー家の人々』の書評を書かせてもらった。何よりも、すぐ上の書評者が原武史、その上の本の著者が佐野眞一だったのは、私が強い関心をもっている二人なので、偶然とはいえ素直に嬉しい。
七月十四日(木) 綴方教室の滝沢修
日本映画専門チャンネルの高峰秀子特集で、山本嘉次郎の映画『綴方教室』を観る。右傾化の進んでいた昭和十三年という時点で、まだこれだけ社会派的な映画を撮れたことに感心する。
教師役の滝沢修はじめ、配役の柱になっている新協劇団は、同じ築地系の新築地劇団(この作品を演劇化して好評を得ていた)とともに、二年後に一斉検挙されて解散しているから、これがギリギリの時期の作品なのだろう。
その視点、リアリズムなど、今井正の映画『山びこ学校』への影響は大きいのではないか。しかもそこで滝沢修が、教師無着成恭の父親役になっているのが愉快。
七月十五日(金) 水戸黄門終了
テレビの『水戸黄門』が低視聴率のために打ち切りになるという。民放の連続時代劇の、いよいよ終り。
というより、日本映画の歴史が始まって以来、連綿とつくられてきたプログラム・ピクチャーとしての時代劇の終り。
七月十六日(土) 本郷館解体
来年春の友人の墓参りのとき行こうと思っていた本郷館(築百年の木造三階建下宿)、今月一杯で取り壊しとか。人が住まなくなって傷みも加速しているだろうから、限界か。今月中に行くしかないのだが…。
七月十八日(月) 女子サッカーW杯
朝は人並みに女子サッカーW杯決勝。歓喜と興奮。けっして勝負を投げない闘争心に感動。
勝敗を決する五番目のキッカーは澤だと思いこんでいたが、そうではなくて十一番目だったというニュース。キーパーより後にしてしまうことで、不安をユーモアに変えた監督の掌握術に感心。それがあの落ち着きにつながったのか…。
七月十九日(火) 長い話
友人とネットでやりとりしていて、相手が「褌より長いメール」が得意、という話が出る。
褌より長い。昔なつかしい、古い日本人の言い回し。
子供の頃、祖父が寝床で私と妹に物語を聞かせてくれていたとき、妹が「もっと長い話」ばかりをせがんだ。それでめんどうくさくなった祖父が、「空から長~い褌が垂れていて、その端っこをお前がつかんでいる」と、「長い話」をしたのを思い出した。
七月二十日(水) おとなしいアメリカ人(一)
グレアム・グリーンの『ザ・クワイエット・アメリカン』を読む。この作品、あとで述べるが、邦題がややこしい。
オリジナルは、一九五五年に出版された。翌年に田中西二郎訳で早川書房から出た邦題は『おとなしいアメリカ人』。
ヴェトナム戦争でのアメリカの失敗を予見したような作品として名高い。
一九五一年から翌年にかけて、第一次インドシナ戦争下のヴェトナムが舞台。独立をめざすホーチミンのヴェトナム民主共和国(ヴェトミン)と、日本敗退後の復権を求める旧宗主国フランスが、一九四六年末から戦いを続けている。
開戦当初は、近代兵器で武装した仏軍が圧倒的に優勢で、ヴェトミンは北部山岳地帯にこもってゲリラ戦をするほかなかった。しかし一九四九年に中国で共産党が勝利し、国境越しにヴェトミンに支援を開始すると、戦意の低い仏軍は各地で敗退、完全に掌握するのは都市部周辺だけと、敗色濃厚になっていく。
作品のなかで、グリーンはフランスの空軍将校に語らせている。
「あなたはジャーナリストです。われわれが勝てないことは、ぼく以上によく知っているでしょう。あなたはハノイとのあいだの道路が毎晩、中断され破壊されてることを知ってる。あなたはフランスが毎年、サン・シール(陸軍士官学校)の一学年に相当する将校を失ってることを知ってる。五〇年には、フランスは壊滅に瀕していました。ド・ラットルが、どうにか二年間、フランスの命脈をたもたせた――それだけです。しかし、ぼくらは職業軍人です。政治家たちがやめろというまでは戦いつづけなくちゃならない。たぶんやつらは寄り集まって、緒戦の頃に話し合いがついたと同じ講和条件で折り合うでしょう。この数年間の戦争は全部ナンセンスになるわけだ」
ジャン・ド・ラトル・ド・タシニー将軍は、一九五〇年に着任すると、ハノイからトンキン湾の間に「ド・ラトル・ライン」と呼ばれる要塞線を築き、ヴェトミンの伝説的名将、ボー・グエン・ザップの攻勢を食い止めた総司令官。しかし一九五一年末に癌のためにその地位を降り、パリに戻って翌年初めに没すると、戦況は坂を転げ落ちるように、悪化の一途をたどり始める。
小説は、ちょうどド・ラトルの退場と病死の前後、つまり植民地支配の「終りの始まり」に設定されている。
このころ、フランス正規軍――といっても、頼りになるのはドイツ兵主体の外人部隊だったが――はハノイ周辺の争奪戦に奔走していたので、サイゴン(現在のホーチミン市)を中心とする南部は、ヴェトナム人の軍閥が割拠し、叛服常ならぬ姿勢を見せていた。
その軍閥の一つに目をつけ、フランス軍ともヴェトミンとも対立する民族資本主義の「第三勢力」に育て、共産主義の防壁に仕立てようと画策したのが、アメリカである。
フランスに対しても、戦費の大半を負担するなど支援を怠らなかったが、一方では旧来の植民地主義に見切りをつけていた。アジアでも中南米でもアフリカでも、旧植民地を英仏蘭に代って直接に統治するのではなく、表面的には民族自決の原則を尊重しながら、実質的な傀儡政権をおくのが、その基本戦略だった。
さて、小説の主人公ファウラーは、中年のイギリスの新聞特派員。帝国主義の落日を皮肉な目で傍観している。かれの国も古きヨーロッパの同僚として、植民地を失い続けているのだが、仏領インドシナでは、少なくとも当事者ではない。
その前に現れるのが、アメリカ経済使節団の一員、オールデン・パイル。
この男は、いわゆるヤンキー風ではない。つまり、陽気で人懐っこく、騒々しくてマッチョな、あるいは放蕩無頼気取りだったりの、カウボーイの末裔ではない。そんな同国人に眉をひそめる、おとなしくて謙虚な、ハーヴァード出身のきわめて優秀なインテリ青年で、童貞。
その姿は「ひょろ長い脚、クルーカットの頭、キョロキョロした学生らしい眼つき、どう見ても有害なことのできそうな男とは思えない」。当時のテレビドラマや雑誌広告のイラストに描かれたような、爽快で健全な若者なのだろう。
そして、物質文明の頂点をきわめる、豊かで清潔なアメリカに育った。「ロングアイランドで海水浴をしている彼、どこかのアパートの二十三階で、同僚たちと一緒にうつした写真のなかの彼。摩天楼と急行エレヴェーター、アイスクリームとドライ・マティニのカクテル、ミルクを飲みながら喰べる昼食、ビジネス特急の車中のチキン・サンドウィッチ――そうした世界にこそ、この男は属しているのだ」
だから「おとなしいアメリカ人」なのである。だがパイルは、頭につめた最新の知識と理論の正しさを、「正義」を、現実の世界で実証してみたいと燃える、無邪気な世間知らずの冒険好きだった。
主人公はいう。
「おれはあれほどごたごたを起こしておきながら、それをあれほど善意の動機からやった男を見たことがない」
この、当時のアメリカそのものみたいな男が、ヴェトナムに「第三勢力」を、という最新理論を鵜呑みにしたのが、悲劇の発端。こんな青二才のインテリのアメリカ人が、本当にサイゴンに来ていたかどうかはわからない。しかし、あえて戯画的にそう描くことで、アメリカの無邪気な善意の危うさを、よりわかりやすくしているのだろう。
パイルが軍閥の一つ、テエ将軍(トリン・ミン・テ。実在の人物)一派を支援するためにプラスチック爆弾を渡すと、それが共産ゲリラの仕業に見せかけた、サイゴン市内での無差別テロに使われていくのである。
この爆破テロは、一九五一年から五三年にかけ、実際に頻発したものだった。
グリーンがさすがに世界的な文士なのは、物語をこうした、大上段の政治状況だけで語ってはいないこと。パイルは、主人公の愛人であるヴェトナム女性に恋をし、主人公に対してフェアに「恋の決闘」を申しいれ、その財力と情熱と純粋さと正直さ――すべて、ヨーロッパ人の主人公が持ちあわせないもの――によって、女性を奪うのである。
大状況だけでは、いかに壮大であっても、特定の時代の特定の地域だけの物語になりかねない。しかしそこに、きわめて矮小で卑小で人間くさい「三角関係」が、その寓話として重ねられることで、普遍にして不変の人間喜劇が生まれる。
物語は倒置法の一種で、結末が先に語られる形で始まるが、そこでパイルは何者かに暗殺され、女性は何事もなかったように――アジア的神秘そのもの――主人公のもとに戻っている。この、とってつけたようなハッピーエンドも、グリーンらしい苦い後味を残す(おそらく、新たな苦しみの始まりにすぎない)。
パイルの戯画的な人物造型に象徴されるように、グリーンのアメリカ嫌いは全編に徹底している。しかしその独立自助のプロテスタンティズムも資本主義も消費社会もデモクラシーも、原型はグリーンの母国イギリスにこそあるのだ。だからそれは単純ではない、複雑で深刻な近親憎悪なのである。
作者が一九五五年にこの作品を書き上げたとき、フランス軍は前年にディエン・ビエン・フーで乾坤一擲の勝負を挑んで大敗北、ついに統治を投げ出し、ヴェトナムは米中ソの超大国の都合のまま、南北に分割されていた。
南の「第三勢力」の指導者となったゴ・ディン・ジエムは、各地の軍閥を吸収した。テ将軍もその傘下に入って、次を狙う人物と目されたが、何者か(ゴ一派だといわれる)に暗殺された。
ゴ政権の背後で糸を引いていたのは、CIAの誇る闘士、エドワード・ランズデール空軍大佐だった。ランズデールは生前のテ将軍との関係も深く、まさにパイルのような役割を果たしたから、かれがパイルのモデルだと考える人もいる。
が、ランズデールがインドシナに着任したのは一九五四年以後なので、直接のモデルではないらしい。四十歳台で、無邪気で罪のない若者でもない。
愉快なのは、アメリカで没後翌年の一九八八年に出たランズデールの評伝の副題が、『ジ・アンクワイエット・アメリカン』であること。おとなしくないアメリカ人、というわけだ。
このことが象徴するように、グリーンの小説は、当然ながら以後のアメリカ人が強く意識する対象になった。
その意識が生み出したものも面白かった。それは次項に。
七月二十一日(水) おとなしいアメリカ人(二)
昨日に続いて、グレアム・グリーンの『ザ・クワイエット・アメリカン』話。
グリーンの小説は、文学性と同時に高い娯楽性をもつ作風ゆえに、いくつも映画化されている。いちばん有名なのはもちろん『第三の男』で、もともとは映画の脚本の叩き台として、書きおろしたものだ。
『ザ・クワイエット・アメリカン』も映画化されている。それも、アメリカで二回だから、アメリカ人の関心の強さが示されている。ただし公開時の邦題が、小説の邦題と異なるのがわかりにくい。
昨日の初めに「ややこしい」と書いたのはこの問題である(原題はすべて『ザ・クワイエット・アメリカン』)。
一九五八年製作のマンキーウィッツ監督の一回目は『静かなアメリカ人』。邦題をつけるとき、原作が日本語訳されていることに気がつかなかったのか。
とはいえ、これは直訳で類推できるからまだいい。二〇〇二年のフィリップ・ノイス監督の再映画化の邦題は『愛の落日』という、意味不明のものになった。言い訳のように、あとに小さく「クワイエット・アメリカン」とついている。

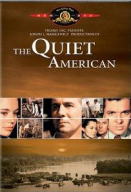

二作とも、原作と異なる部分がある。もちろん、映画化では珍しくない話で、映画との関係が密接な『第三の男』でさえ、グリーン自身による脚本は原作よりもはるかに出来がよい。さらにアメリカ市場を意識して、主人公とその友人はイギリス人からアメリカ人に変えられ、主人公の失恋に終る有名な映画のラストも、原作とは異なるものだった(グリーンもこのラスト改変は、監督の判断が正しいと認めている)。
しかし『ザ・クワイエット・アメリカン』の場合、その改変が、製作年代の風潮を色濃く反映しているのが興味深い。
凄いのは一九五八年版である。原作の三年後の製作なのに、ラストにどんでん返しが勝手に加えられているのだ。
殺されたアメリカ人(この映画ではわざと名前がない)は、じつは諜報活動にはまったく無関係で、すべてが共産主義スパイの謀略だったと判明する。ヒロインのフォンは、主人公ファウラー(この二人の名は原作通り)の不実をなじり、かれとは復縁しない。打ちのめされた主人公は、虚脱状態でサイゴンの夜の雑踏に独りで消えていく。
つまり、若きアメリカ人は善良にして無実。対する共産主義者は邪悪な悪魔であり、傍観者を気取っていたイギリス人は、その悪魔に利用された間抜け、という構図になっているのである。
アメリカ人の観客は溜飲を下げただろうが、グリーンは激怒した。
ハヤカワepi文庫の若島正の解説によると、「この小説と作者を意図的に攻撃しているような映画」で「支離滅裂」とこきおろしたそうだ。しかしハリウッドの契約では、内容の改変に関して原作者が異議を唱える権利はなかったので、どうにもならなかった。
たしかにこの改変は、原作のアメリカ批判をぶち壊した。原作への反駁を目的にした映画、といってもおかしくない。
東西冷戦下、スプートニク・ショックで威信を傷つけられたばかりの、一九五八年のアメリカで公開するには、こうするほかなかったのだろう。南ヴェトナム政府の全面協力で現地ロケを行なったとあるから、ゴ政権とアメリカ顧問団への恩義もあったのか。
結末の評価はともかく、現地協力のおかげで、原作とほぼ同時代(撮影はわずか五、六年後)のヴェトナムが、モノクロだがたっぷりと映っているのはありがたい。カオダイ教の不思議な本山も登場する。
一九五一年から五五年まで、作者が四度にわたりヴェトナムを訪れ、サイゴンだけでなく最前線の状況まで現実に経験しているのが原作の強みなのだが、それに近い景色を映像で見られるのだ。
一つ面白いのは、現地ロケ以外の場面が、ローマのチネチッタで撮影されていること。経費の高いハリウッドを脱出して、安いローマで撮影するランナウェイ方式が流行っていたとはいえ、なぜヴェトナムの話をイタリアで撮るのか。これも深読みしたくなる。
イタリアもヴェトナム同様、防共のためにアメリカが資金を湯水のように投入した国なのだ。共産党が強い国だけに、物質的繁栄で民衆が不満を覚えないことが大切だと、アメリカは考えた。撮影隊がドルをこの二国に落とすことの背後には、政治的意義もあったはずなのだ。
映画の中身だけでなく、その製作の事情にも、「第三勢力」扶植に忙しいアメリカの自己正当化が見えかくれする。
俳優は、主人公がマイケル・レッドグレーヴ。アメリカ人はオーディ・マーフィ。ローマで撮影したためか、フォンはイタリア女性のジョルジア・モル。
オーディ・マーフィはご承知のとおり西部劇スターで、その前は第二次世界大戦に従軍して輝かしい戦功をあげ、多数の勲章を得た、本物の英雄だった人。原作の青二才のインテリとは正反対の、敏捷なカウボーイ風である。出身もボストンではなく、テキサスに変えられている(役者のテキサス訛りの問題もあるのかも)。裏表のない善良な情熱を感じさせるには、純朴な役者の方がいいと考えられたのか。
次の『愛の落日』は、一回目から四十四年後の二〇〇二年製作。
こちらは、原作を大きく歪めるような暴挙はしていない。大筋では忠実に従っている。半世紀前の光景をカラーでよく再現しているようだ。視覚面でのクライマックスとなる、サイゴンのオペラハウス前での大爆破テロ(一九五二年一月に実際に起きた)も、一回目同様に現実の場所で再現している。
この二〇〇二年版の特徴は、原作や一回目の映画の時点ではまだわからなかった、一九六〇年代のヴェトナムへのアメリカの全面的な軍事介入の失敗を、反省する視点をもっていること。
そこで、ここでのオールデン・パイル(今回はちゃんと名前がある)は、原作よりも謀略的な人間に描かれている。
一見無鉄砲なその行動の背後には、つねに冷たい計算がある。現地語を知らないふりをしているが、じつは流暢に話せる。裏にあるのはまさにランズデール大佐のような、一級の工作員の顔なのだ。原作では名前があがるだけのトリン・ミン・テ将軍も、その協力者としてクローズアップされる。
ただそのぶん、無垢な善意でごたごたを起こしてしまう、原作のパイルの「善意の狂気」の恐ろしさは後退している。それより、工作員としては一流でも、人間観察では素人だったというねじれが、その失敗につながることになるのだ。
そのパイル役はブレンダン・フレイザー、主人公役はマイケル・ケイン、フォンはドー・ハイ・イエン。老マイケル・ケインが、さすがの存在感を発揮する。
しかしこの映画の製作は、二〇〇一年の九・一一同時多発テロとイラクへの軍事介入という、「愛国的な」時期に重なってしまった。それで、原作に忠実だったことが災いしてお蔵入りしかけ、マイケル・ケインらの奔走により、ようやく公開が実現したという。
半世紀をへてなお、『ザ・クワイエット・アメリカン』は、アメリカ人のノドに刺さった小骨のような作品なのだ。戦後アメリカの本質を、一面でついているからだろう。
ところで『ザ・クワイエット・アメリカン』の情報を本やネットで調べているうち、『ジ・アグリー・アメリカン』、つまり「醜いアメリカ人」という、似たような題名の小説や映画があることに気がついた。
サーカーンという、明らかにヴェトナムをモデルにした、南北に分れた東南アジアの小国が舞台。主人公は南サーカーンに赴任したアメリカ大使。現地人を援助して北の共産主義勢力の陰謀と闘う、というような話らしい。
原作小説はアメリカ人のウィリアム・J・レデラーとユージン・バーディックの共著で、グリーンの小説の三年後、一回目の映画と同じ一九五八年に出たベストセラーだという。
映画は五年後の一九六三年製作、監督はジョージ・イングランド、主人公の大使がマーロン・ブランドで、現地の「第三勢力」のリーダーは、なんと岡田英次がやっているそうだ。
これまた『侵略』なる、面白みのない邦題なのが残念な、ヴェトナムへの本格介入の直前につくられた映画。一作目の『静かなアメリカ人』と同様、日本盤DVDが出ていないので、アメリカ盤を注文してみる。
どのようなものか、楽しみ。
七月二十二日(金) 聖杯と御苑
「和製バイロイト音楽祭」こと、『パルジファルとふしぎな聖杯』を観に、新国立劇場へ。
タイトルをちゃんとおぼえていなかったので、予定表に「子供パルジファル」と書いておいたら、「なに、子供がパルジファルやるの?」と山の神。いくら仕事でも、お遊戯を見る気はない。子供向けのパルジファル。
開演十分前について、中劇場への階段を上がっていたら、なんと二階のバルコニーから金管が、「聖杯の動機」を鳴らしている。さすが和製バイロイト。正面からは登り坂(階段)だし、客席も扇型だし。でもこのシャレがわかるのは、大きなワーグナー・キッズだけだろう。
昨年までの《指環》ではオケも舞台上にいたけれど、今年は十五人編成でピットに入っている。いっそフタをして完全にバイロイト風にすればと思ったが、楽器を演奏する姿を生で見てもらう機会は貴重だから、しかたのないところ。
グルネマンツがマツコみたいなオカマなのが面白かった。「花の乙女」が「お菓子の乙女」になってるのは、子ども向けのアレンジ。
最後は、第一幕の聖杯騎士団の合唱の音楽を使って、客席の子供と聖杯踊り、じゃないグレイルダンス。見よう見まねで即座に反応できる子供って、やっぱりすごい。
《指環》では客いじりが少なかったので、この方が子供は楽しめるだろう。その点で明らかに進歩している。ワーグナー・ファンもこの聖杯踊り、みんなで踊ってみたら面白いのに。
初台から歩く帰り道、新宿御苑へ回り道。ウチへは新宿口から大木戸口へ抜ければいいので、ときどき利用する。
台風が過ぎたあとだが快晴ではない。雲が多く、気温も七月とは思えないほどに低く、それがよかった。
苑内は風がひんやり、空気が心地よく澄んでいて、ほとんど高原のような雰囲気。涼しく暗い林を抜け、広い芝生に。
その真ん中で寝ころがった。身体がグンと伸びて、これ以上ないほどに贅沢な気分(たった二百円だけど)。
見上げる空の広いこと。あまりの解放感に、たとえこの瞬間に心臓が止まっても、何の悔いも不安もなく目を瞑れるだろう、などと考えたり。
七月二十三日(土) 国立のサッカー
国立競技場で、J1のカシワ対カシマを観る。柏が好調だけに三万人も入っていたが、今夜も風が涼しいのでとても快適。今年の柏はなるほど、したたかで強い。二対一で勝利。
目当ての北嶋が、間近でゴールしてくれたのが嬉しかった。鹿島は後半に大迫が交代で出てきたが、まだ高校生みたいに迫力と存在感がなかったのが残念。
七月二十四日(日) アナログ放送終了
「ご覧のアナログ放送の番組はきょう午後に終了しました」
仕事部屋のテレビはDVDとゲーム専用の、十年前のブラウン管式。地上波はアンテナなしの劣悪な画面をときどき見ていただけなので、今回も一切対策もせず。というわけで、午後は上記の案内が出ている(各局とも個別に制作した画面なので、相違あり)。明日はどうなるのだろう。
七月二十五日(月) 砂嵐とゴースト
ケーブルテレビでは、デジアナ変換でアナログテレビでも、二〇一五年まで見られるようになっているという。
それで集合住宅などでは、未契約の世帯でもついでに見られるケースが多いようだが、何も接続していない私のテレビは、完全に白黒の砂嵐。
でも、なぜかNHKだけかすかに映像がうつる。デジタル幽霊。じっと見ていれば、そのうち話しかけてくるか。
七月二十七日 早早対決、今年はなし
早稲田の高等学院、ベスト8で敗退。決勝までいかないと、二年連続の早早戦は実現しなかったとはいえ、惜しい。日大は昨年と同じ兄弟高対決。早実は今年も、安田コンス(権守)に期待。
七月二十八日 醜いアメリカ人
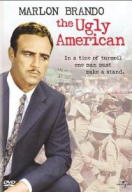
マーロン・ブランド主演のカラー映画『ジ・アグリー・アメリカン』を観る。二十一日の日記で触れたDVD。
ヴェトナムがモデルらしき、南北に分れた東南アジアの小国サーカーン。ブランド扮するマクホワイトは第二次世界大戦中、パイロットとして従軍してこの地域に不時着、現地のゲリラに協力した。そのとき親交を結んだ、抗日と独立の英雄デヨングを演じるのが、岡田英次。
マクホワイトはその後アメリカでジャーナリストをしていたが、大使に選ばれて赴任することになった。
北の工作員が、反米世論を形成するべく謀略を各所で仕掛けている。マクホワイト夫妻も首都ハイドーの空港に到着、専用車に乗り込んだとたん、滑走路になだれ込んだデモ隊に包囲されてしまい、すんでのところで軍隊に救われる。
この部分の映像が面白い。明らかに、六〇年安保のニュース映像を下地にしているからである。
道路を斜行するジグザグデモ。空港の柵を境に警官隊と揉みあい叩きあい、乗りこえて乱入するデモ隊。
このへんは全学連が国会に突入したときの映像にそっくりだし、大使を乗せた車が囲まれて動かなくなるところは、大統領報道官ハガティの車が羽田空港外で進退不能になり、海兵隊のヘリで救助されたハガチー事件、そのまんまだ。
さらに目を引くのは、デモ隊はほぼ全員が男性なのに、車を囲む場面には若い女が一人だけいて、その彼女が後方からの圧迫で車に押しつけられ、恐怖の叫びをあげるカットが一瞬挿入されていること。これが樺美智子圧死事件を意識していることも疑いない。そういえば少し前の場面で、犠牲者(謀略で殺されたのだが)の似顔絵を描いたプラカードを掲げて行進しているのも、やはり似たような映像を、当時のニュースで見た。
これを観ると、日本人ほどではないにせよ、アメリカ人にとっても六〇年安保の騒動が、それなりに大きな事件だったことをあらためて思う。現職大統領の訪日という重要な外交行事が中止になったのだから当然なのだが、原因は反米勢力による煽動だという意識が、アメリカでは強かったこともうかがえる。
この場面から実感するのは、原作が出版された一九五八年から、映画が公開された一九六三年までの五年間に、アジアなど第三世界では、大変動がいくつも起きていたこと。
一九五九年元旦にはキューバ革命、一九六〇年には韓国の四月革命と六〇年安保、アフリカ諸国の独立があった。キューバは急速にソ連に接近して一九六二年のキューバ危機になり、韓国では軍事クーデターで親米派の朴正煕が実権を掌握し、アフリカでも動乱が頻発した。
一九五八年前後の小康状態から、米ソが第三世界で陣取合戦を激しく争う「熱い冷戦」に入っていたのである。南ヴェトナムでも、解放戦線がテロとゲリラ活動を開始していた。
原作は未読だが、このような状況だけに、映画の方が、直接的な危機感が高まっているのではないか。
ロケはタイで行なわれている。国王が君臨する仏教国であることなど、風俗はタイそのものだが、「事件は、近年の歴史を元に書かれているが、タイの政治や歴史を反映したものではない」という断り書きが冒頭に入る。
さて、ブランド演じるマクホワイト大使は赴任後、民衆のリーダーとなっているデヨングと個人的に再会、旧交を温める。しかし二人は、アメリカの援助で建設中の道路「フリーダム・ロード」をめぐって、相容れない立場にそれぞれが立っていることを知る。
道路の目的は経済発展の促進で、物質的繁栄と自衛力が育つことが対共産主義の防壁になると、いかにもアメリカ的大義を掲げるマクホワイト。
それに対しデヨングは、首相クエン・サイが私腹を肥やす結果にしかならないという。戦争を挑発する道路で、戦車を売りつけるための、侵略的なアメリカの軍事的冒険だと非難する。
デヨングの政敵クエン・サイは、第三世界諸国の伝統的な権力者の典型として描かれている。おそらくは家柄と財力に恵まれ、旧宗主国への留学経験があると思しき、西欧の文物に通じたインテリ。
自国の民衆をまるで信用していない。そのために独裁的で、要職を親族で固めるあたりは、キューバのバティスタや韓国の李承晩、南ヴェトナムのゴ・ディン・ジエムなど、民衆の怨嗟の的となって失脚した人々に似ている。妨共のためにそんな連中の後ろ楯となり、結果的にさらに堕落腐敗させてしまうのが、当時のアメリカがくり返した失敗だった。
不幸なことに、マクホワイトですら、アメリカか共産主義かの、偏狭な正邪の図式にとらわれていた。民族独立と、冷戦に巻き込まれない平和を願うデヨングの真情を理解できず、反アメリカならば共産主義者と決めつけてしまう。
かれが共産主義勢力と対決する姿勢を鮮明にしたことが、ソ連や中国、北サーカーンの工作員と、デヨングが接近する結果を招く。デヨングは武装蜂起し、民衆を味方にして圧倒的な勢力となり、クエン・サイに政権移譲を迫る。
ところが、ここで意外な展開になる。クエン・サイがマクホワイトとの会見の場で、とても有能な政治家であることを明らかにするのだ。デヨングが中立で、共産主義者に騙されているだけという、マクホワイトが認めようとしなかった真実の証拠を提示する。
武器支援は受けるが、北側の軍事介入は許さないというデヨングとの約束を無視して、北側は蜂起に合わせ、国境付近にパラシュート部隊を降下させていた。そして革命の成就後、ただちにデヨングを暗殺して政権を乗っ取る計画だった。これらすべてをクエン・サイは察知、お人好しのアメリカ人に教えて、アメリカ第七艦隊の出動を確約させる。そして赤化工作を排除できるなら、デヨングと連立政権を組んで民主的改革を行なう用意があると、したたかな政治力を見せる。
政情不安な国のアメリカ大使のスタッフに軍人もCIAも皆無で、軍事面はさっぱりという設定にはいかにも無理があるのだが、これは「平和外交」の映画的演出なのだろう。
また、撮影に協力してくれたタイ側に花を持たせる意図もあるに違いない。デヨング役は日本人の岡田英次だが、クエン・サイはタイ人の、ククリット・プラモートがやっているのだ。面白いことにこの人、王家の血を引く本物の政治家兼作家で、一九七五年には現実にタイの首相になったという人物である。
しかし、結局デヨングは落命する(このあたり、トリン・ミン・テ将軍がモデルらしく思われる)。その後サーカーンがどうなったのかは映画では描かれず、結末はマクホワイトの述懐が、まず大使館で記者相手に、続いて米議会のテレビ中継で(審問のために召喚されたのだろう)、行われる場面になる。
誤りを自覚したマクホワイトは、アメリカの論理を押しつけてはならない、彼地の革命家の、民族自決の意志を誤解してはならない、と話す。
――その意志は、二百年前にアメリカを独立させた人々がもっていたのと同じ理想と情熱だ。二百年前の初心を忘れたとき、アメリカは憎悪の対象となるだろう。
この「醜いアメリカ人」の警告は、家庭で中継を見ていた一般市民が、どうでもいいとばかりに途中でテレビを消してしまうことで、しり切れトンボに終る。最後に、《アメリカ・ザ・ビューティフル》の旋律が一瞬響く皮肉も効果的。
かなり暗い幕切れ。しかしアメリカで一九六三年四月にこの映画が公開されて七か月後、南ヴェトナムでゴ・ディン・ジエムが米軍事顧問団の支持を得たクーデターにより暗殺され、米軍の軍事介入の動きが次第に不可避になっていく現実の方が、もっと暗い。
現在の中東やリビアの情勢を見ても、独善的な価値観の押しつけは変っていないようだ。同時に、昭和初期の大日本帝国が、もっと拙劣な手法でアジア諸国を傷つけたことも忘れてはならないが。
岡田英次はとてもがんばっていた。セリフの大半が現地語(タイ語)ではなく英語だから、日本人でも大丈夫だったのか。四年前の映画『二十四時間の情事』以後、国際的に活躍していた時代の記録の一つである。
Homeへ
八月一日 痛快人間
イスラエル・フィルの歴史的演奏を収めたヘリテージ・シリーズ、モントゥーとパレーのライヴ盤が実に痛快。
八十八歳と九十歳の、フランスの粋な爺さん二人。
前者は亡くなる三か月前の指揮とは、とても思えない。初共演なので、ベートーヴェンの交響曲第四番にエルガーのエニグマ変奏曲、ラヴェルの《ダフニスとクロエ》第二組曲と、モントゥーの名刺代りの愛奏曲が選ばれているのもいい。
モノラル録音に若干のステレオ感を加えていて、純潔主義者は嫌いそうだが、私はこれはありだと思う。
八月五日 松田選手に
一瞬の晴れ間が見えると、セミが一斉に鳴きだす。鳴きやむと曇り空。
夏雲に 鳴けよ響けよ ただ七日
雲はれて 鳴けよ響けよ 蝉時雨
(一句よんでどうする…)
八月六日 「原爆を許すまじ」を聞いたことがありますか
ふるさとの街やかれ
身よりの骨うめし焼土に
今は白い花咲く
ああ許すまじ原爆を
三度許すまじ原爆を
われらの街に
(原爆を許すまじ 作詞浅田石二/作曲木下航二)
CSの日本映画チャンネルでは、新作公開に合わせて新藤兼人特集。
なかでも、『原爆の子』と『第五福竜丸』は、もともとこの時期にはぴったりだし、特に今年は、フクシマ以後の八月ということで意味が大きい。
で、『第五福竜丸』を観ていた。
一九五四年、アメリカの水爆実験による第五福竜丸被爆事件を、ドキュメンタリー・タッチで描いた劇映画。
坦々と、抑制したリアルな表現を続けるなかで、情感面でのクライマックスを形成するのが、この事件をきっかけに始まった広島の原水禁で、反核歌《原爆を許すまじ》が合唱される場面。
思わず一緒に歌っていたら、隣で観ていた山の神が、
「これは何の歌? ねえ、何の歌?」
と、しつこくきいてくる。
「え? まさか《原爆を許すまじ》を知らないの?」
驚いてききかえす。
「知らない。聞いたこともない」
一九五四年に、(やはりこの事件をきっかけにして)できたこの歌、年上の山の神は子供時代に、当然に歌っているはずと思っていたら、歌っていないどころか、聞いたことさえないという。
愕然としたわけだけれども、あらためて考えてみれば、自分もこの歌、学校で習ったわけではないし、回りで歌っている人もいなかった。
プロの歌手で初めて聞いたのは、フォーク歌手のピート・シーガーの一九六三年カーネギー・ホールのライヴ盤で、アメリカ人の聴衆に対して、シーガーが日本語でこの歌を歌っていた録音。
そしてそれは確実に、自分が二十歳をすぎてからの体験。
有名なはずなのに、少なくとも東京では、聞く機会、歌われる機会がずいぶんと限られている歌なんだと、あらためて考える。
知らない人の方が、ひょっとしたら多いんだろうか?
なぜ?
共産党系の中央合唱団がつくって、うたっていた歌だからなのか。
自分が物心ついたころ、原水爆反対運動は共産党系と社会党系に分裂して、激しいがまったく不毛な抗争のさなかにあったが、そのことが関係しているのだろうか。中ソ寄りの社会党は、共産圏の核は容認するという方針だったから、こんな反核歌は認められなかったのか。
何にしても、不思議。
たしかにセンチメンタルで、いかにも戦後民主主義全盛期の歌だから、当事者意識より被害者意識が強く、四番などはあきらかに教条主義的な歌詞で、げんなりさせられる部分もあるけれど、人の心を動かす力をもっている歌だとは思う。それだけに、もったいない気がする。
それにしても『第五福竜丸』、やっぱりいい映画。
被爆した船員のなかでただ一人命を落とすことになる、久保山愛吉役の宇野重吉が、あまりにもはまっている。
南雲中将といえば『トラトラトラ』の東野英治郎しか浮かばないように、久保山といえば宇野重吉。
前述のように、坦々と悲劇を描いていくのだけれど、それだけに、水爆の死の灰が船に降り注ぐ場面で、久保山が、体についた灰を、何気なくペロリとなめてしまう一瞬は、何度みても心臓が縮むような恐ろしさ。
ところで《原爆を許すまじ》のこと、年長の方のご意見をうかがうと、どうやら、一九五〇年代前半あたりの生れを境に、それより前の世代は知っているのが当然で、それ以後は逆に知らないのが当然、という感じになるらしい(いうまでもないが、厳密な統計などではなく、ただの印象論)。
当り前に世に広まっていた歌が、ある時点から、ひどく特殊なものになっているのが興味深い。ショスタコーヴィチの《森の歌》などと、現象的には似ているのだろう。
反対運動の分裂は一九六三年だから、それまでの十年間が「普及期」だったということなのか。
八月七日 ソ連と日本、地味とウルトラ
片山杜秀さんから《原爆を許すまじ》などの、面白い情報を教えていただく。
まず、ソ連時代のグルジアだかアゼルバイジャンだかの作曲家が《ヒロシマ》というバレエを書いていて、その冒頭には、この歌のメロディがそのまま使われているという。
ソ連などの旧共産圏では、日本の歌の一つとして、かなり知られたのだろう。本国の日本では、ある時点から特殊化されていたことを思うと、皮肉だが。
続いて、映画『第五福竜丸』は、冒頭の出港時の漁船員の笑顔など、林光の音楽も合わせ、全編がソ連映画の手法を想わせること。
黒澤明が日本アメリカ映画代表なら、新藤兼人は日本ソ連映画代表にあたるのではないか、といわれる。
面白い。すると、今井正は日本ネオレアリズモ代表だろうか。
それから、日本の社会主義勢力が参照するのはアメリカではなく、まずソ連の原子力だったこと。
原爆はもちろん、原発もソ連が積極的に採用したことが、日本の左翼勢力の核への態度に、大きく影響してきた。
ヒロシマの原爆は日本とアメリカの問題だが、フクシマの原発はチェルノブイリとの比較、日本とソ連の歴史比較になるのでは、といわれる。
これも感服。《原爆を許すまじ》の認知度の極端な上下はそのせいだ。また、自民党が採り入れた、東京に蓄積された富を公共事業によって地方へ再分配するという、戦後の日本型社会主義。その一つに原発建設も含められるが、この「日本列島改造」は、ソ連の「自然改造」の模倣なのである。
未開の大地と森林を開拓し、ダムや発電所や工場など重工業を建設する「自然改造」は、ソ連の有名な「五ヶ年計画」の手法だ。日本も戦前に満洲でそれを真似、戦後に本土へ持ち込んだ。
そういえば、《原爆を許すまじ》を生んだ「うたごえ運動」、それが世に広まるきっかけとなったソ連映画『シベリヤ物語』も、まさしく「自然改造」を賛美する映画だった。
ところが日本の左翼が惹かれたのは、それよりも天然色で描かれた大自然と、そこに生きる人々の、力強い合唱の歌声だった。このズレがそのまま、その後の日本の左翼が抱え込む矛盾となる。
さらに、東電が一九六七年につくった宣伝映画『黎明‐福島原子力発電所建設記録 調査篇‐』が、インターネットで簡単に見られるのを教えていただいた。間宮芳生の音楽がプロコフィエフ風で、まるでソ連の五か年計画の記録映画みたいだという。
これ、たしかに五か年計画っぽい。雄大な自然と、それを改造し克服する、人間と科学の力。まさに二十世紀的。
福島第一原発の津波被害の原因の一つになったといわれる、台地を二十メートルも削って用地を低くしてしまった工事も、誇らしげに描かれている。
個人的にはこの映画、別の感慨もあった。一九六七年、この時代の作業現場の色使いの地味さがまた、いかにもという感じで、懐かしいのである。
薄いカーキとかベージュとかライトグレーといった、ぼやけた色の、汚れの目立たない制服や工具、作業車の色。兵隊の略帽みたいなキャップなど。
自分の仕事は発電所ではなく、そこから出る送電線の方だったが、同じ東電の工事だから、雰囲気は共通する。
この時期、つまり私が小学校に入る前後の頃、父は現場に行きっぱなしで、数週間に一度帰宅するだけだったが、そのとき着ていた作業服とか、車(白いライトバン)とか、うっすらと記憶がある。
映画の工事現場は、それと同じ雰囲気をもっているのだ。そして、自分が作業現場に出た昭和の末にも、部分的にはまだ残っていた。だから、懐かしい。
その直後、バブルになると俄然、危険防止とか若い人にもアピールしようとかで、すべてが鮮やかで明るい原色に変わる(褪せにくい染料の進歩なども含め、とにかく金満になった)。
今年、記者会見ですっかりお馴染みになった東電の青い作業服は、八〇年代あたりからと記憶する。この映画の頃は、色は茶系で、デザインは米軍の軍服そっくりだったのだ。
戦場とちがって工事現場では、人間が土や草にまぎれてわかりにくいと、事故に巻き込まれる危険が増す。だから、派手な色を着た方がよいのだが、バブルより前の時代には、ヘルメットだけは白色とか黄色とか目立つ原色にするものの、作業服は中間色にしていた。
派手なのは自分たちの分に合わない、という自戒が、たしかにあったのだ。
この、建設関係者の一種軍隊的な、無個性で地味な色彩感覚は、たしかに高度成長期までの、そして一億総中流幻想の時代までの、特徴といえる。
あと、この映画は『ウルトラQ』や、『ウルトラマン』と同時期にあたる。そのせいか、あそこに出てくる建設現場とも、雰囲気がよく似ている。
台地に発破をかけるシーン、あそこから土を噴きあげながら出現したら、まんま、ウルトラシリーズの怪獣だ。
そういえば、建設現場に怪獣が出現する話が、この二作品には、けっこう多かったのではないか。
あれも時代の反映なのだろう。自然改造の障碍の象徴としての、怪獣。
これは東宝怪獣映画とも違うし、次の『ウルトラセブン』とも違う。
『セブン』には、侵略者としての宇宙人とか人類とか、もっと冷戦と第三世界的な、ヴェトナム戦争の反映みたいな話が多かった。経済から政治へ、地方から世界へ、みたいな変化があったのか。
ウルトラセブンが、日本の防衛を代行する、最強無敵のアメリカ第七艦隊の暗喩だとはよく指摘されることだが、ではウルトラマンは、何の暗喩だったのか。これも考えてみると面白そう。
などなど。最近は片山さんがあまりにお忙しいので、飲みにはいけないのだけれど、こんな思いつき話をネットでやりとりしているだけでも、本当に愉快。
八月九日 WAVE自己破産
CDショップのWAVEが自己破産、というニュースを知る。
近年はセゾングループを離れて、転々としていたけれど、とうとう終り。
今年の春までは、店舗数もそれなりにあったらしいが、自分が見たのは、赤坂見附駅上のベルビー赤坂が改装した何年か前に、短期間あった店が最後。CD棚のダークグレーの配色に六本木店や池袋店と共通したものを感じて、嬉しかった記憶がある。
自分が通いつめたのは六本木店で、ついでロフト一階にあった渋谷店。東横線沿線の人間には便利だったからである。この頃の思い出は『クラシック・ヒストリカル108』の序章に書いた。渋谷では、クアトロの店も忘れられない。はす向かい近くにあった最初のHMV、そして宇田川町のフリスコ、この三つを何度回遊したことか。
しかし、いま思いかえしてみると、西武百貨店ではなく、明治通りの向いのビルにあった時期の池袋店、これも妙に印象が強い。WAVEにはやはり、発祥の地である池袋の水が合うのだろうか。
六本木店の記憶が青山ブックセンター六本木店(終夜営業)と組み合わさっているように、池袋店の記憶も、西武百貨店地下の書店、リブロと組み合わさっている。
八〇年代に隆盛したセゾン文化とオタク文化(風俗という方が合いそうだが)の主な後背地となったのは、どこよりも西武沿線だった気がするが、西武は東急の自由が丘とか、京王の下北沢&吉祥寺のような、郊外の「自領」の中に消費拠点をつくらず、「国境」の池袋に集中する点に特徴があった。
あるいはセゾングループでは、渋谷に対する「郊外拠点」が池袋だったのか。
八月十日 ヴェンツァーゴ!
MDGから出たヴェンツァーゴ指揮バーゼル響のブルックナー交響曲集、第四番と第七番の二枚組を聴く。とても気持ちがいい。
スケールは大きくない。おそらく人数もそんなに多くなく、中規模だろうと思うが、その澄んだ響きと中庸のテンポ感がじつにいい。爽やかに呼吸している。
全集の完成が楽しみだし、この人の活動にも関心を払っていこう。都合よく、デュッセルドルフ響の《ライン》も出るという。
一九四八年生れ、日本ではそれほど注目されたことのないヴェテランだが、大きな実りの時期を迎えている気がする。その点、同い年のカンブルランにも似ているのかも。
八月十一日 マーケットの記憶
吉田秋生『海街diary』四巻が出ていたので喜んで買う。あと、七尾和晃の『闇市の帝王』(草思社文庫)。
敗戦直後の混乱のさなか、大金をもって中国大陸から東京に乗り込み、マーケットやキャバレーを経営して「東京租界の帝王」と呼ばれた、王長徳の評伝。
正直、本書だけではその正体がつかみきれず、どこまでがハッタリなのかわからない謎が残るのだが、目を瞠らされる記述も多かった。
『闇市の帝王』というタイトルは、正確とはいえない。駅前などの焼跡に自然発生する露店の闇市ではなく、二、三階建てで、個人店が長屋のように密集して入る「マーケット」を建設、家賃をとるのが、王長徳の主な仕事だった。本文中で著者が王の言葉として書く通り、「闇市とマーケットは違う」のだそうだ。
たとえば、渋谷駅前。
王長徳が土地を入手してマーケットをつくったのは、東口の、いまバスターミナルとなっているあたりから、東急文化会館の土地(いまはヒカリエを建設中)だった。五島慶太の東急は、王から土地を購入したのだという。
個人的に驚いたのは、王が新橋、荻窪などにつくった同種のマーケットが、東横線の学芸大学駅と、自由が丘駅にもあったということ。
学芸大学駅近くのは、駒沢通りのバス停、三谷停留所脇の三角地。たしかに昔から、車で通るたびに何か不自然な土地だと感じていたが、あれが「三谷マーケット」の跡だったとは。
そして自由が丘は、駅前の自由が丘デパートこそ、それだというのである。
デパートといっても、いわゆる百貨店のことではない。駅正面口の右手、東横線の線路西側に沿って都立大学駅方向へ細長く伸びたビルのことだ。地下一階、地上は三階(部分的には五階まであるらしい)、食料品店や雑貨屋などさまざまな個人商店が、長屋状に延々とならぶ。
自由が丘は、私にとって生まれてから四十年近く、最寄りの繁華街だった街である。自由が丘デパートも、子供の頃には母の買い物につきあって、しょっちゅう通り抜けた。
日曜に家族で駅近くの映画館に行き、帰りにこのデパート三階のレストランで食事をするという、テレビ隆盛以前の郊外の家庭では典型的だったろう、「休日の過ごし方」をした記憶もある。
私が物心ついたときから半世紀近く、現在までほとんど変りなく存在する、雑然とした商店街ビル。これが闇市の次の段階である「マーケット」だったのだ。
子供の頃には、ある大きさのビルの中に、業種の異なる小店舗がいくつも入って、マーケットと称する場所が、自由が丘にも緑が丘にも、いくつかあった。わさわさと賑わう気分が好きで、いまでも場所と外観をありありと思い出せる。
しかしそれらはまもなく(一九七〇年代に)、マンションなどに建てかえられた。縦横に充分な大きさのある土地だったからだ。自由が丘デパートが現存しているのは、線路脇の細長い区画だからではないか。同じような細長い「マーケット」は、隣の都立大学駅の、自由が丘方向の線路沿いの東側にも、残っている。
国電の駅前だけでなく、郊外の私鉄駅の商店街にまで戦勝国民の力が及んでいるとは、思いもよらなかった。
といっても、王の名は直接には残っていないそうだ。かれはさまざまな事情から、表には出なかった。自由が丘デパート(日本で初めて、デパートという名称をつけた商業施設だそうだ)公式の創業者は、山田三樹となっている。しかし、「山田三樹も晩年は都議などを務めるものの、かつては戦後の、いわば愚連隊のひとりとしても知られていた」という。
その山田の背後に王がいた、ということらしいのだが、ただし一九五〇年代後半には、王は渋谷や学芸大学と同様、自由が丘のマーケットも手放していた、とある。
いまの自由が丘デパートの建物の正確な年代は知らないが、それより古いものには思えない。戦後すぐに王が各地に建てたマーケットは、どれも木造二階のバラックだったから、これは王が手放したあとに、山田三樹が建てなおしたものなのではないだろうか。
さらに、他の場所とはちがって、住人には王の存在がまったく記憶されていないそうだ。だから現在の自由が丘デパートに関しては、直接ではなく間接的な関係なのではないか。
国電の駅前の大半が焼野原となった戦後、不法占拠の形で露店や屋台の闇市ができる。やがて、ヤクザや華僑など、顔役の仕切でマーケットに整理される。そして、東京五輪前後からの都や民間の再開発で、駅前ビルに入ったり、地下街に入ったり、近くの土地に移ったり。
それだけではない。郊外の私鉄駅周辺でも戦後に住人が増えていくとき、平場の商店街だけでなく、数階建てのマーケットのビルがつくられることがあった。
現代東京の繁華街は、さまざまな形でさまざまな人がかかわって、偶然と故意の双方の作用により、いま私たちが目にする、「清潔」な姿に至っている。
その始まりに焼野原と、闇市とマーケットがあった。その実態は、忘却の霧の中に消えつつある。混乱のせいでもあるが、それよりも関係者が、そのどさくさ紛れの、美しいことばかりではない思い出を他人に語らず、忘れようとしているせいが大きい。
著者がマーケットの借り手の証言を得ようにもごくわずかで、大半は見つからず。見つかっても会うのを断られたり、もう忘れていたり、去年亡くなっていたり。小松左京の傑作『牛の首』を思わせる。
時間も人も連続しているのに、まるで遠い昔のよう。その向うの闇。
王長徳を通じて、「繁華街の始まりの闇」のことを考えさせられた。
八月十二日 米アマゾンの送料
アメリカのアマゾン、一年ほど前は送料がとても高くついたが、一時的な値上げだったらしく、最近は、それほどでもないことに気がつく。石油高騰で燃料費が高かったからなのか、日本アマゾンへの誘導策だったのか。円高のおかげで、ダメ人間はますますダメ人間に…。
八月十三日 偏見
夜中にコンビニへ買い物。真夏で好きなこと(数少ない)の一つは、深夜二時頃でも何となく人が街をうろうろしている、独特の開放感。
でも、飼い主と散歩するシベリアン・ハスキーは好きではない。顔つきがほとんどオオカミだから。眼がいや。狡猾で獰猛(ほら、ケモノ偏だらけだ)。夜中には見たくない。
八月二十日 史上最大の第七戦をみる
一九六〇年ワールドシリーズ第七戦、ピッツバーグ・パイレーツ対ニューヨーク・ヤンキーズのテレビ中継の完全版DVDを観戦する。
見事なシーソーゲームで十対九、MLB一世紀の歴史の中で唯一、サヨナラ本塁打で世界一が決まった、「史上最大の第七戦(ザ・グレーテスト・セブンス・ゲーム)」とも呼ばれるビッグゲーム。