四月一日(日)おほむたから
ついに発売された山田一雄交響作品集のCDを聴く。
《おほむたから》は、やはり異形の傑作。秋にナマで聴いたときよりはずっと冷静に聴けるが、マーラーの交響曲第五番の葬送行進曲がときにむき出しに、ときに逆回しのように(作曲当時の日本に磁気録音テープの逆回しなどないが)、バラけて響き、聲明と重なる。
あらためて強く感じるのは、近代日本の精神と社会の基盤の、解体と崩壊を弔う音楽だということ。西洋音楽に象徴される欧化運動と、皇国日本の解体。液状化などという言葉を安易に使えば、怒られるだろうけれど…。
ともあれ、昭和十九年の日本には、こういう音楽があったということ。
四月三日(火)中劇場のモーツァルト
今日はミュージックバードの収録のあと、午後に新国立劇場中劇場で、日本人キャストによる《ドン・ジョヴァンニ》演奏会形式公演。
歌うのは、四月十九日から始まるオペラパレス公演のカバーの歌手たち。不測の事態が起きないかぎり、影の存在に終るかれらに歌ってもらおうという、尾高忠明の発案。昨年の《コジ》に続く二回目。
昨年同様、オケは四‐三‐二‐二‐二の弦楽(東フィルの首席クラスの選抜)にピアノという編成で、指揮と伴奏チェンバロは、ヘッドコーチの石坂宏。
ステージの手前に歌手が指揮者を挟んで一列に並び、奥にオーケストラ。背面に字幕が出て、その背景の色の変化が、ほぼ唯一の装置。
結果からいえば、とても楽しめた。昨年の《コジ》よりもずっとよかった。そして、《ドン・ジョヴァンニ》という作品の特性が露わになっていて、学んだ点も多かった。
まず、弦楽とピアノという編成。ピアノが管、打楽器の代役となるのだが、この方式、《コジ》だと響きにひどく違和感があったのに、《ドン》では少なかった。編曲法や演奏の違いもあるのかも知れないが、《コジ》の音楽の方が管楽器の音色の配置に関して、モーツァルトがあまりにも天才性を発揮していてピアノには置き換えられないのに、《ドン》はそこまでいっていない気がする。
その代り、弦楽、特に低弦が雄弁。なかでも今日は、首席チェロの服部誠という人が素晴らしかった。十三人のなかでもダントツに光っていたが、モーツァルトがまた、それにふさわしいオーケストレーションをやっている。
次に、演奏会形式のこと。これも《コジ》には合わなかった。これは、本公演がミキエレット演出の細かい動きをともなうものだったという、比較の問題もあるけれど、もともと、音楽が複数の人物の人間関係の変化に重点をおいているだけに、動きや演技がないとつまらない。
これが《ドン》は違う。アリアが連続する形式だけに、歌手が他の役を意識せず、自分だけで完結した身振りや表情をすれば事足りる。アンサンブルの場面さえ、音楽がそうした性格をもっている。
さらに、舞台上演より好ましいと思う部分さえあった。それは歌手の出入りのこと。今日は、幕の途中から登場する場合があるだけで、歌手が途中で退場して入りなおしたのは、始めと終りしか歌わない騎士長以外には、第二幕途中でドン・ジョヴァンニが一度やっただけ。あとは歌うとき立ち、終れば椅子に座る、という動きだけだった。
《ドン》の舞台上演は、歌手のアリアごとの入退場が、だんだん馬鹿らしくなってくるのだ。歌い終ると、後奏のところで歌手が退場。だから客席が拍手するのは、たいがいの場合、無人の舞台に対してになる。それが途切れると次の歌手が入って、またアリア。そしてまた無人の舞台への拍手、という繰り返しが虚しくなる。これが今日はなかった。ちゃんと歌手に拍手できる。
指揮者をはさんで下手に貴族、上手に平民(と騎士長)という席の配置も、作品中の階級社会を一目瞭然にしていて、単純だが効果的だった。
そして、客席約一千という中劇場の規模が、モーツァルトに、日本人歌手に、じつに合っている。先日の藤原の《フィガロ」も、東京文化会館の大空間ではなくここだったら、歌手の印象もかなり違ったろう、と思わざるを得なかった。
何年か前にも書いたことだが、中劇場をもっと活用して、日本人キャストと小編成のオケと、ごく簡便な装置によるオペラ公演(モーツァルトだけでなく、ワーグナー以外のほとんどのオペラ)を、廉価に数多くやることができたら、オペラというものがより日本の観客にとって日常的で、親しく愛すべきものになるだろうにと、いつも思う。
残念ながら、そんな予算がどこにもあるわけないのだが。
ともあれ、平日午後の一回かぎりの公演、というのがとてももったいなく思える、いい公演だった。
終演後の京王線は、暴風雨のため二十分遅れ。六時前の混みだす時間だが、上りだし、早退の人が多いのか車内はガラガラ。ただ、帰りに吹いた突風で愛用の傘が壊れたのは悔しい。
十年以上使ってきたから、お役御免と思うことに。ご苦労さま。
さて今週は今日から演奏会強化週間。今日が《ドン・ジョヴァンニ》、明日が《オテロ》、明後日が《タンホイザー》とオペラ三連発で、一日あけて土曜は、オーケストラ演奏会二つのはしご。
座りっぱなしなので、腰が痛くならないといいが…。
四月四日(水)オテロと川口とルメイ
新国立劇場の《オテロ》。これはいかにも、大空間向けの作品。
オテロ役のフラッカーロ、前に歌ったグールドのような英雄的な声ではなく、泣きのヴィブラートが入る。しかしそれがいかにも、イタリアのテノールの歌うオテロで、好き嫌いは別にして、「イタリアの山羊の声」の伝統に則ったものだと感じる。
指揮のレイサム=ケーニック、二十年ほど前にヌオヴァ・エラなどのCDでよく見かけた名前なので、懐かしい。まさか、今になって初めてナマで聴くとは思わなかった。ぐちゃっとした響きも、一九九〇年前後の感じ。
話はかわって、日経新聞の「私の履歴書」はいま蜷川幸雄。数日前は、隣に倉田保昭の文章も載るという濃い紙面だった。さて、蜷川は戦前戦中の少年時代を埼玉県川口市で過ごしたという。あの鋳物工場の町。
そのなかで目を引いたのは、川口は空襲がなかったから、戦前の鋳物工場がそのまま戦後も操業したという説明。『キューポラのある街』の風景は、戦前から変っていない、というのだ。
どうして米空軍は、鋳物工場を放っておいたのだろう。
下町を焼き払ったのは、町中に工場が混じっていて、軍需を下支えしているから、という理屈だったはず。
割れやすい鋳物じゃ戦車はつくれないにしても、鋳物が軍需物資にまるで含まれないとは思えない。
あれだけ綿密な調査と計画をたてて、破壊する地域、残す地域を分けたとされる米戦略空軍が、鋳物工場が密集する川口を無傷で放置したのは、たまたまの偶然なのか? それとも、何か理由があったのか?
残念ながら、蜷川はこのようなことには関心がないようで、触れていない。でも気になる。
以下は、陰謀論じみた妄想。
アメリカの戦略爆撃の司令官、カーチス・ルメイが戦後になって、なぜか日本から勲章をもらった――自衛隊育成の功績というのが表向きの理由だが、特に何もしていないらしい――真相は、ひょっとしたら「川口を爆撃しなかったから」だったりして?
そのおかげで吉永小百合の代表作(未だに)『キューポラのある街』がつくれたと、日活が運動してたりして?
映画はちょうど五十年前の一九六二年公開、受勲は六四年で、辻褄は合う…。
四月五日(木)凶気の調律
近くの本屋で以下の本を見つけたのだが、怖くて(笑)買えなかった。
『ジョン・レノンを殺した凶気の調律A=440Hz 人間をコントロールする「国際標準音」に隠された謀略(超知ライブラリー73)』
紹介文に「A=440Hzから、A=444Hz(C=528Hz)へ。「愛の周波数528」がもたらす驚異のパワー」とある。著者名がホロウィッツというのは、いかにも説得力ありげ(笑)。
どちらにせよ、より低いバロック・ピッチの方が、自分の耳には心地よいが。
夕方からは東京文化会館で、東京・春・音楽祭の《タンホイザー》。
水準の高いキャストにNHK交響楽団という、この音楽祭らしい豪華版。N響のオペラ演奏が聴けるだけでも貴重だ。
ただし今年は、アダム・フィッシャーの指揮が緊張感に乏しく、一昨年の《パルジファル》に続いてゲストのコンサートマスターをつとめたペーター・ミリング(シュターツカペレ・ドレスデンのかつての名コンマス)が冴えず、直率のヴァイオリンに乱れが生じるなど、オーケストラはもう一つだった。
歌手は舞台後方に崖のように高い段を組み、合唱団とともに一列に並ぶ。その背景に書き割りのような映像と字幕。
通常よりも一段下げたオーケストラとは高低差があるので、分離は明快だったが、上と下に響きが広がるから、歌手は歌いにくいのではないかと思った。
歌手のなかではヴォルフラム役のマルクス・アイヒェが整った歌いくちで、いちばん印象に残った。
四月七日(土) 時計仕掛けのストラヴィンスキー
インキネン&日フィル@サントリーとインバル&都響@東京文化会館の演奏会を二つはしご。
互いに打ち合せたみたいな時間設定。日フィルはふだん十四時なのに今日は十六時開演で十八時前に終り、都響も土曜だから十八時開演でもよさそうなのに、十九時。空いた一時間は、サントリーから上野への移動と、軽い食事にぴったりで無駄がない。これより短かったら慌ただしく危険だし、長かったらもてあまして面倒になって、いずれにせよ一つに絞ってしまったはず。
近年の東京は土日に演奏会が集中するだけに(これで秋に池袋の芸劇が再開すると、どんなスケジュールになるのだろう…)、こういう設定はありがたい。逆に、はしごできてしまうだけにあきらめがつかない、ともいえるが(笑)。
曲目は、前者はシベリウスのクオレマとマーラーの交響曲第五番、後者はストラヴィンスキーのペトルーシュカ&火の鳥と、なんとも武闘派な二本立て。
アンコールにハルサイ全曲なら面白いが、などといいつつ会場へ。
マーラーの直後にストラヴィンスキーの二つのバレエを続けて聴けたのは、学ぶものが大きく有意義だった。
インキネンのマーラーはこれまで同様に澄明な響きで、見栄やケレンをさけてすっきりと、しかし現代の演奏らしい推進力をもって進めるもの。
対してインバルは、世代的にも二十世紀後半風で、推進力がなく冷静な、よくも悪くもスタジオ録音のレコードのような演奏(とても踊れそうにない)。しかしその音楽は、時計細工のように精緻。
インバルの棒、都響のテクニック、文化会館のクリアな音響、すべてがあいまって、ストラヴィンスキーがこの初期の二作においてすでに、後期ロマン派や国民楽派の影響を脱した、じつにモダンなオーケストレーションに到達していることが、よくわかった。
前半のペトルーシュカは三管編成の一九四七年版なので、新古典主義の雰囲気が濃くなっていた。対して火の鳥は四管編成の一九一〇年オリジナル版。別動隊のバンダが二階下手から吹く、大がかりなもの。版が違うのはインバルの意図だとしても理由はわからないが、両者の響きにはかなりの差があった。その差で変化をつけようとしたのだろうか。
前者が新古典主義風なのに、後者は巨大。巨大だが、後期ロマン派型の過剰浪費ではなく、精細で巧妙な大型機械を想わせる。つまり「マシン・エイジ」の音楽。機関銃やガソリン・エンジンなど、直後の第一次世界大戦で大活躍する機械類のような。
直前に聴いたマーラーが、かれなりに未来を見つつも、作品も演奏も、技がかかったり、かからなかったりのプロレス性が色濃かったのとは、明確に異なる。ストラヴィンスキーはまさしく二十世紀の、マシン・エイジの音楽。
その後のかれの新古典主義が、現代のバロック演奏とは概念の異なる時計細工になることも、無理なく納得できた。
帰宅後、あえてロト&ラ・シエクルのピリオド演奏の火の鳥を聴きかえしてみる。やはりとても面白く、刺激的。喚起するイメージもはるかに豊か。
音楽の姿としては、インバルよりもロトがはるかに好きだけれど、この演奏だと、マシンとしての高い論理性は背後に隠れがちになる。矢澤孝樹さんはこれを評して「むしろ精巧な、魔法を吹き込まれた寄木細工のような」とおっしゃったが、いい得て妙。
四月九日(月) 『政宗』のジェームス三木
CSで大河の『独眼竜政宗』を、ほぼ二十五年ぶりに見ている。
ジェームス三木の脚本は、近年の大河の、子供向けマンガのような、薄っぺらな人物造型とは比較にならないもの。
たとえば、殿山泰司の演じる修験者の長海法印。殿山がやっているという時点ですでにインチキ臭いし、明らかにそうなのだが、他の登場人物は、そのことをあからさまに口にしたりはしない。
それは「言わずと知れたこと」で、見ていればわかるからだ。しかし、インチキはインチキなりに存在価値、利用価値があることが皆わかっているから、百も承知で、言葉の上では尊重しておく。
こういう、現実社会においても当り前にあることが、近年の大河では「わかりにくい」と判断されるのか、みんなむき出しである。あまりに単純で薄い。
とくに感心させられるのは、岩下志麻演じる、政宗の母。男の脚本家は女性を偶像化しがちといわれ、竹山洋などはまさにそうだが、ジェームス三木は違う。冷めた目で、長所と短所が複雑にからんだ、善悪いずれともつかない性格を、シニカルに描く。
ここまで冷めていて、女性に理想など求めないからこそ、この脚本家は「女たらし」になれたのか。それとも逆に、女性遍歴の果てに、この冷めた視点にたどりついたのか。おそらくはその両方なのだろう。
勉強のために(何のだ)、話には聞いていても読んだことのない『仮面夫婦』を古本で買ってみることに。女性カタログ「春の歩み」が楽しみ。
四月十日(火) 日生劇場記者会見
帝国ホテルで行われた、日生劇場開場五十周年記念公演の記者会見に行く。
目玉はライマンのオペラ二本の日本初演で、今年の秋に《メデア》、来年の秋に《リア王》。下野竜也指揮読売日本交響楽団の演奏で、歌唱担当は二期会。
記念公演に日本初演の作品をもってくるあたり、この劇場らしい、六〇年代の精神を受け継ぐ印象。開場のときにベルリン・ドイツ・オペラの来日公演があったことはよく知られているが、あれも現代作品を必ず含むなど、その後に続く時代の豪華な引越公演とはやや性格を異にする、実験精神に富んだものだったように感じられるから、形だけそれを真似するよりも、こうした新制作こそがふさわしいだろう。
このような音楽をしっかり聴かせてくれるということでは、下野ほど信頼できる指揮者も少ないから、その点も万全。
ここからは個人的な話だが、日生劇場は自分と「同い年」なので、記念行事には自然と関心が向く。
自分が明確に記憶しているという意味での最初の日生体験は、一九七四年に劇団四季がやった子供向けのミュージカル『ジョン万次郎の夢』だった。小学校の鑑賞教室のようなもので、ちょうどこの年の大河が『勝海舟』だったから、みんなけっこう熱心に観ていた。(ちなみに大河では小澤幹雄が演じたそうで、おぼろにその画面も憶えている)
その後は、そんなに頻繁に訪れているわけではないけれど、曲線の多い優美な内装など、貸しホールとは異なる、劇場の温もりを感じさせてくれる数少ない場所として、好感を抱いてきた。
だから、この記念公演も成功を祈る。
四月十三日(金)アルミンクのチェコ音楽特集
今日はアルミンク指揮の新日本フィル@トリフォニー。スークの《おとぎ話》にドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲(独奏マティアス・ヴォロング)、ヤナーチェクの《イェヌーファ》組曲(ブレイナー編)というチェコ・プロ。
こうして続けて聴くと、ヤナーチェクというのは独創性な天才だとつくづく思う。国民楽派が、よくも悪くも集団催眠なのに、この人の作曲法とオーケストレーションは、意識の覚醒を求めてくる。ものすごく面白くて、モダン。ある状況から生れてくるのではなく、その唐突な出現によって局面を変えてしまう、だから天才。アルミンクも、こういう曲の方が冴える。
前半はシュターツカペレ・ドレスデンとバイロイト音楽祭の第一コンマスという、ヴォロングの滑らかな美音が見事だった(先日の《タンホイザー》のコンマスがペーター・ミリングだったので、SKDの新旧コンマス聴き較べ)。元々はスロヴァキア生れでウィーン・フィルのティボール・コヴァーチの予定だったが、いつのまにか変っていた。
アルミンクは来週十九日にサントリーで、チェコに続いてイタリア・プロを聴く予定。カゼッラの《スカルラッティアーナ》(独奏原田英代)、レスピーギの《古風な舞曲とアリア》第三組曲と《ローマの松》という、戦間期の新古典主義~マシン・エイジの作品なので、これも楽しみにしている。
それも含め、今日からは八日間で七回の演奏会強化週間。
明日は紀尾井シンフォニエッタのコダーイ、ヨアヒム、リスト、バルトークのハンガリー特集、明後日はノリントン&N響のベートーヴェン(これは日経で批評予定)、明々後日はカンブルラン&読響のドビュッシー&ストラヴィンスキー(ペトルーシュカの一九四七年版をもう一回)、そしてオーストリアのショパン弾き、インゴルフ・ヴンダーのモーツァルト、リスト、ショパン。一日おいて前述のアルミンク、翌日はレ・ヴァン・フランセのニールセン、ミヨー、プーランク。
ノリントンとヴンダー以外は、「二十世紀前半、欧州諸国の音楽」という一貫したテーマがなぜか偶然にあるという、楽都(?)東京の面白さ。
華やかなビッグネームの来日演奏家が続くよりも、こうしたプログラムが組めて、聴きに来る客がいる、ということの方が、土中に伸びた根の強さと広がりを感じられて、好もしい。
四月十四日(土)ハンガリーの人々
紀尾井シンフォニエッタのハンガリー・プロに行く。
とても面白かったが感想は後回しにして、まず気になったのが指揮者、ガーボル・タカーチ=ナジの今のポスト。
その名の通り、タカーチ四重奏団のヴァイオリン奏者だったが、一九九二年に離脱して、現在は指揮活動が増えているらしい。そのかれが二〇一〇年から首席指揮者兼芸術監督をつとめているのが、ハンガリー国有鉄道交響楽団。
国鉄響なんてオケがあるのだ。旧共産圏ならではの組織らしいが、いまでも存続しているのが面白い。
このオケをJRで呼んで、改装なった東京駅で駅コンやって、例の「鉄オタクラシック」の曲とか演奏したら、矢澤孝樹さんとか満津岡信育さんとか、「鉄ちゃんクラちゃん」の人たちに大受けするんじゃないかと思う。
指揮者も、ヨアヒムの協奏曲(とんでもない曲で大笑い)とか聴くかぎり、イケイケ調で指揮できる人だし。
さて今日の演奏会。
・コダーイ 夏の夕べ
・ヨアヒム ヴァイオリン協奏曲第2番「ハンガリー風」(独奏はバルナバーシュ・ケレメン)
・リスト 夕べの鐘(弦楽合奏版)
・バルトーク 弦楽のためのディヴェルティメント
最初と最後が、独立国としてのハンガリーに生きた二十世紀人の二人、途中が独立を知らず、ドイツ語圏に生きた十九世紀人の二人。音楽語法の違いに、そのことが如実に現れている。あえていえば前者はハンガリー語の響きで作曲しているし、後者はドイツ語で作曲している。
面白さでいえば、何よりもヨアヒムの協奏曲。十九世紀に「ハンガリー風」というと「ジプシー風」と混ざってしまうわけで、そのとおり終楽章は「フィナーレ・アラ・ツィンガーラ」、はっきりとジプシー風とうたっている。
これがまあ、私のなかにある「アカデミックな芸術家」というヨアヒムのイメージをひっくり返すような、妙ちきりんな曲だった。ブラームスのハンガリー舞曲などの旋律や音型と、パガニーニなど名人系の協奏曲をくっつけたみたいな、派手で俗っぽい曲。両端楽章のコーダの騒々しさなんて、思わず爆笑しそうになったくらい。なのに、ドイツ語圏の作品らしく、オーケストレーションは妙に凝っている。
ヨアヒムとは、こういう名人性、芸人性を持つ人だったのかと目からウロコが落ちたが、どうやらこれは、演奏のスタイルによるところが大きかったらしい。極端なメリハリをつけた、快速の爆演だったのだが、帰宅してナクソスのNMLでキム・スーヤン独奏のナクソス盤などを聴くと、のんびりとしてメリハリも脈絡もない、つまらない曲でしかない。
どちらが正統派なのか、判断する知識が私にはないが、「ハンガリー風」「ジプシー風」の形容にふさわしく、曲への熱い共感に満ちていたのは、文句なしに今日の紀尾井の演奏。ケレメンが超絶技巧を駆使して、分散和音みたいな妙な音型やら重音やらを猛スピードで弾き、それをオケが煽りに煽ったからこそ、曲を面白く感じることができた。
ドイツの目から見た、エキゾチシズムの、芸人の音楽としてのハンガリー風。そのイメージのままにあえて作曲した若きヨアヒムは、どんな心境だったのだろうと、考えずにいられない。
アンコールがまたエンターテインメントなもので、パガニーニのカプリース第一番のあと、バルトークの四十四の二重奏曲からピツィカートを、ケレメンとタカーチ=ナジの共演で。
指揮者もヴァイオリニストだからこその芸当で、ここだけコンマスの楽器を借りて弾くという趣向で、愉しませた。
休憩後は美しいリストのあと、バルトーク。複雑で陰気で、なんとも苦い音楽に「ディヴェルティメント」と名づける陰鬱なユーモアは、ヨアヒムの「芸人音楽」と正反対のようでいて、じつは、同質の暗闇のなかから生れてくるのかも知れない。
ハンガリーという国の歴史と人々を考えるきっかけをくれる、刺激的で面白い演奏会だった。
四月十五日(日)ノリントンの倍管
日経新聞の批評のため、ノリントン指揮NHK交響楽団を聴きに行く。ベートーヴェンのフィデリオ序曲と三重協奏曲に、エロイカ。
このコンビを聴くのは二〇〇六年の初共演以来。そのときはオペラシティのコンサートホールだったので、ノンヴィブラートのピュアトーンにもぴったりだったが、今日は巨大なNHKホール。
そのため、反響板やエロイカでの倍管など、いくつかの音響的工夫が加えられていた。三重協奏曲の独奏のヴァイオリンとチェロがヴィブラートを多用したのも、おそらくはそのためだろう(前回の庄司紗矢香はノンヴィブラートに挑戦していた)。
ただし、プログラムを見ると、木管楽器を倍の人数にする倍管は、サントリーホールでのブラームスの交響曲第二番でもやるらしい。NHKホール公演でも、ベートーヴェンの第四番やティペットの一番は指定の二管編成のままのようだから、曲によって判断するということか。
四月十六日(月)カンブルラン絶好調
カンブルラン&読売日本交響楽団のサントリーホール演奏会。
後半の《ペトルーシュカ》がすばらしかった。インバルは時計細工を聴かせてくれたが、これは機械仕掛けの人形が魔法で生命力を得たような、絶妙のファンタジー。ストラヴィンスキーのオーケストレーションのマジックを堪能。この曲は一月にハーディング&新日フィルでも聴いているので、今年だけで早くも三回目(すべて一九四七年版)。どれもそれぞれに個性的で面白かったが、これは一頭地を抜く出来だった。
前半のドビュッシー二曲のうち、後半の《おもちゃ箱》も、やや長すぎとは思ったが印象的。《遊戯》といいこの曲といい、ドビュッシーの晩年のグロテスクな、シニカルなユーモアは不思議。
一曲目の、音の匂いだけが漂うような《牧神》と合わせ、カンブルランは絶好調。見るたびに身のこなしがしなやかになってきている気もするが、初めからこうだったか?
四月十七日(火)『仮面夫婦』
山下典子の『仮面夫婦』を読んだ。
これを読むかぎりジェームス三木は、脚本の才能はすごいがそれ以外は、身勝手で気まぐれで嫉妬深く暴力的な、最低の人格。といっても、離婚訴訟中の奥さんが書いたものだけに、犬も食わないものがさらに腐敗した感じで、丸飲みはとても出来ない。自己弁護と正当化の色合いが強い(ウィキによると、この著書をめぐってジェームス三木が妻と出版社を相手に名誉毀損の訴えを起こし、被告が五百万円の和解金を支払ったとある)。
期待の「春の歩み」は、思ったより抑えた文章。当時はその内容を紹介した雑誌などで、もっと生々しい描写を読んだ気がする。続編の『夫婦戦争』にそういうものが出ているらしいが、人間の醜さばかり感じるので、もう充分。
ちなみに記された女性は百七十三人、夫人は七十六番目(時系列)。大したもんだ。梵天丸も、斯くありたい。梵天丸というより煩悩丸という感じだが…。
夜は紀尾井で、インゴルフ・ヴンダーのピアノ・リサイタル。
ショパン・コンクールに入賞した、珍しいオーストリア人であるとか、第二位ながらグラモフォンと契約したとか、興味をひく点がいくつかあった。しかし今日聴いたかぎりでは、音の少なさをもてあましていたような本プロのモーツァルト、リスト、ショパンより、アンコールのホロヴィッツの《風変りな踊り》にスクリャービン、モシュコフスキーの《花火》など、音符のつまった音楽の方が、伸び伸びと、難技巧を楽しんで弾けるようだった。
コンサートグランド、強大にして精巧なピアノが二十世紀に大完成してからのレパートリーに強い人、という印象。
四月十八日(水)いまさらながら、野球とベースボールと
「可変日記」二〇一一年分の日記を一つのページにまとめる。長いが、検索がしやすいので。
個人的には八月二十日の日記の、一九六〇年のワールド・シリーズ最終戦「史上最大の第七戦」完全版DVDの話が気に入っている。
試合展開と結果は先刻承知でも、一試合丸々の時間と映像を体験することが、こんなにワクワクするものだとは。マントル&マリスのMM砲のすごさ、ロベルト・クレメンティの伝説的悪球打ちが、目の前に。
ヤンキーズの大エース、ホワイティ・フォードの投球が見られないのは残念だが、かれが投げていればヤンキーズ圧勝にきまっていて(シーズン中の成績が今一つなので先発三番手に回されたが、投げた二試合、第三戦と第六戦は連続完封だった。翌年も一完封して、シリーズ三試合連続完封の偉業を達成した)、この十対九の大熱戦にはならなかったのだから、仕方のないところ。
それにしてもこんな映像、よく残っていたもの。
いま見ると、この時点ですでに大リーグのテレビ中継は、打席を外野からの望遠で撮っていたことに感心。
いまでは忘れられていることだが、日本のテレビは長いことネット裏からのカメラだったので、ベース付近の球筋などはよくわからなかった。アメリカ流の外野からの画面が中心になったのは、ようやく昭和五十年代になってからだったと記憶する。
初めは中継側の技術的な制約もあったのかも知れないが、それよりも球筋を研究されるとかサインを盗まれるとか、せこい理由の反対が大きかったのだ。
スコアボードからの望遠カメラでサインを盗むなど、スパイ活動をする球団があるという噂があったのもこの時期で、スポーツの本質的な部分とは無関係なせせこましさが、「プロ野球」につきまとっている時代だった(まあ、だからこそ現代とは違った意味で熱く、面白かったともいえるが)。
さらに古い、テレビ映像が現存しない時代(一九六〇年前後とか)となると、映画用のニュース・フィルムしかないのだが、これはまた、一塁側か三塁側からのアップの画面ばかり。ロングで投手と打者を同じ画面に映すことをせず、それぞれのカットを切り換えるものだから、もう一つ様子がわからない。
ひょっとしたら、あの投打のアップは同じ一球の前後ではなく、別々のボールのときに、カメラの角度を変えて撮っていたのではないだろうか。時間と空間を勝手に操作する、いかにも映画的な「まやかし」で、迫真感がないのは、そのせいなのかも。
「史上最大の第七戦」の映像に感激するのは、こうした昭和日本のテレビやニュース映画に慣れてしまった目に、投げる、打つ、守る、走る、というベースボールの躍動を連続して自然に映写した半世紀前の画面――その自然さは高度なテクノロジーに支えられている――が、どうしようもなく新鮮だからだろう。
四月十九日(木)イタリア、戦間期の音楽
サントリーホールでアルミンク指揮新日本フィルの演奏会。先週のチェコ・プロに続いてイタリア・プロ。どちらもかつてのハプスブルク帝国の版図だが、そうした意味合いは薄そう。
近代イタリア音楽、国民音楽のゴッドファーザーとでもいうべき、ヴェルディのルイーザ・ミラー序曲で始めて、あとはカゼッラの《スカルラッティアーナ》(独奏は原田英代、素晴らしかった)、レスピーギの《古風な舞曲とアリア》第三組曲と《ローマの松》という、二十世紀の戦間期の作品。
カゼッラとレスピーギの個性の違いが明確なのが面白かった。カゼッラは五曲で約二十分の作品にD・スカルラッティの旋律が八十八も用いられるという、ストラヴィンスキーのコラージュ手法の影響らしい、新古典主義の曲。
ストラヴィンスキーだけでなく、六人組やラヴェル、ファリャなどのスペイン趣味やジャズ的感覚も採り入れた、いかにもこの時代らしい曲。汎ラテンというか汎地中海というか、国際都市パリの流行に敏感な、耳聰い人という印象。
これに対してレスピーギは、はるかにイタリア国民楽派ふう。この人は新古典主義より古代趣味。神経質で病的な近代と対照的な、厳粛で骨太で重厚な、たくましい古代。《古風な舞曲とアリア》にも、東方や北方志向の、古代専制帝国への憧憬を感じる。
地中海という明るい海でつながる交易国家ではなく、アジアやガリアやゲルマンやブリテンを討ち平らげる、無敵の征服国家。その意味で、第三組曲の最後の曲が明白にバッハのオルガン曲のフーガを模していたのは、単に厳粛で高度な技法の模倣というだけでなく、意味深で面白い。
《ローマの松》は舞台裏からのトランペットに鳥の声の録音、さらに二階のLD席に展開したバンダ、舞台背面上方のオルガンと、まさに人員と資材とテクノロジーを総動員した国家総動員型(笑)の、豪勢なマシン・エイジの国民楽派。
四月二十一日(土)テツラフのヨアヒム、江戸東京たてもの園
十四日に話題にしたヨアヒムのヴァイオリン協奏曲第二番《ハンガリー風》、テツラフとダウスゴー&デンマーク国立響の中古盤が到着したので聴く。これは先日の紀尾井での演奏に近いテンポで、イケイケのイメージも近いので◎。
このディスクの、普通の人にとってのメインであるはずのブラームスはこれから聴くところだが、しかしこの二曲、あまりつながりはない気がする(笑)。
このディスクの評判をほとんど聞かないのは、ブラームスを聴きたい人にとって、ヨアヒムの曲が「始末に困る」からなのでは…。
義母の墓参りの帰路、小金井の江戸東京たてもの園に寄る。
初めて行ったのは昨年秋の初めで、まだ日差しが強く暑かったが、今日は適度に曇って動きやすい。土曜日の割には混んでいなかった。
たてもの園は、敷地そのものが東京都の形を模しているのが面白い。東側に下町、中央に山の手、西側に多摩地域の建物が移築されている。時代もこれを反映する形で、人口密度の高い東側は、社会の変化や災害などで入れ替りが激しいだけに震災以降の建物が多く、西側は江戸以来の農家も混じる。
西側と中央部は前回に見学したので、今回は東半分。いかにも江戸期の名主屋敷らしい大きさをもつ農家の天明家を見たあと、東側に出る。いちばん南にある都電は、幼児期におぼろに憶えている内装だけでなく、木の床と油の臭いが懐かしい。
その北には震災後に建てられた「看板建築」と呼ばれる店舗が立ち並ぶ。正面の見かけだけは擬洋風だが、中身は普通の日本建築。
化粧品屋とか文具、荒物に乾物、生花など、それぞれの店内が再現してあるのが楽しい。ただし、西側と違って、建物の中に上がれないのが残念。強度の問題なのか、あるいは下町の家らしく通路も狭く階段も急なので、多くの見学者が入るのに無理があるからか。それでも、店舗兼住宅の裏に貸間が建てられていて、江戸期の「裏だな」の長屋を思わせる貸間が昭和にもあったことがわかるなど、やはりとても面白い。
さらに北には、中心部を外れた街道沿いに生き残った、江戸末期・明治の和風の商店や旅館などが並び、最北には有名な子宝湯(銭湯)が大きく構えている。このあたりも、中に入れるのは子宝湯くらいなのが残念。
西半の山手の住宅や多摩の農家、それに二二六事件の舞台ともなった雄大な高橋是清邸などは、実際に中を歩くことでその広さや高さといった間取り、そして生活感を学べる面白さがあった。そちらももう一度歩いてみたかったが、東半だけでもその広さにくたびれたので、またの機会に。ここは飽きない。
四月二十三日(月)海のかなたのローマ
南川高志の『海のかなたのローマ帝国 古代ローマとブリテン島』を読む。
紀元前五五年のカエサルの侵攻に始まり、四一〇年の統治放棄まで、五百年になんなんとするローマン・ブリテンの実態に、英国の歴史学と考古学の最新の研究に基づいて迫ろうとするもの。
同時に、研究史も紹介される。ブリテン島の「ローマ化」の意義が、歴史学者から俄かに高く評価されるようになったのは、ヴィクトリア女王時代末期の帝国主義的状況においてだったこと。逆に一世紀後、植民地の大半を失った二十世紀末になって、その過大評価を批判する動きが、ポストコロニアル理論の隆盛とともに、若い考古学者から起きたこと。
『第九軍団のワシ』以下のサトクリフのローマン・ブリテン・シリーズが書かれたのは、ちょうどその中間の、二十世紀半ばである。
ブリテンの原住民は独自の文字を持たず、記録がローマ側に限られるから、歴史学はローマ側の見地に偏らざるをえない。ローマ化の影響力の評価が振子のように揺れるのも、そのことが大きい。
つまるところ、ブリテンでのローマ化は、ごく局地的なものだったようだ。都市がまだなかったこの島に、ローマ人は初めてそれを建設した。が、ローマ化はその内部と周囲だけで、農村に暮らす原住民に及ぶことは少なかった。原住民の言語までがローマ化されたフランスやスペインと較べるまでもなく、都市名以外にはラテン語の痕跡がほとんど残っていないことが、それを示している。
ローマ化は面ではなく、点だった。とはいえ、都市は現在のイングランドの隅々におかれ、ロンドンを中心にしてローマ流の道路で結ばれたから、点と線のあつまりという方が近い。
そしてその都市は、規模自体は大陸に較べて小さいものだったとはいえ、広場にバシリカ、闘技場や浴場など、ローマ流の生活様式をきちんと守っていた。その内部でのローマ化に関しては、きわめて濃厚だったのである。
都市の内と外のこの格差、落差が面白い。サトクリフのシリーズは、この雰囲気をかなりよく物語化しているように思う。南川の記述の通りなら、執筆時点の歴史学の大勢はそうではなかったはずだが、サトクリフはそうした帝国主義的な建前論によることなく、二十世紀のインドやアフリカの植民地の実情、本音を鋭く見抜いて、そこから過去を見通したから、あそこまで書けたのではないか。
南川の本に戻ると、都市とともに、あるいはそれ以上に深くローマ化されていたのは、ローマ軍団の要塞、砦だった。
その実例として紹介される、イングランド北部のウィンドランダという要塞の話が、とても面白い。この要塞は、ハドリアヌスの長城の数キロ南を並行して走る、ステインゲイト道に面している。
長城が一二〇年代に建設される以前、八〇年代のアグリコラ総督時代から、要塞線として同種の役割を果たしたのが、このステインゲイト道だった。ウィンドランダは、東西に数珠つなぎとなった街道沿いの要塞の一つで、ほぼ中央に位置している。
この要塞の遺跡近くから、木板文書なる貴重な遺物が大量に出土したのだ。それは紙の代りに薄い木板に、灰とゴムを混ぜたインクで書いた書類である。
そこには、北辺の要塞に暮らすローマ兵たちの活動ぶりをうかがわせる内容が書かれていた。戦力報告書、物資の注文書、休暇願、出入りの商人の紹介状、さらには別の要塞の司令官夫人が、ウィンドランダの司令官夫人を自身の誕生祝いに招く招待状、などなど。
なんら現代人と変わらない、千九百年前の人間の仕事と生活の記録が、几帳面に文書として残されているのだ。
こういう話を読むと、何をどう批判しようと、ローマとは「文明の光」だったと、痛いほどに感じられる。あやふやな伝説に彩られた中世の闇と霧の向うに、叡知の光が照らす古代世界があったのだ(もちろん、これは一面的な見方にすぎないが)。
こうした木板が腐らずに残ったのは、北国の寒冷な気候と痩せた土壌のおかげだという。そのような辛い、温暖な地中海からはるかに離れた地域にまでローマ帝国は来て、膨大な人員と物資を投入した要塞線を築いて、属州ブリタンニアを防衛していたのだ。前述のように、その支配の実態が点と線にすぎなかったにしても、人間のエネルギーの凄さと広大さに、興味のつきない時と空間。
こんな文書を残せるほどに人間は賢く、同時に、いったんはそれを失うほどに愚か。
四月二十七日(金)トリフォノフ
サントリーホールで、「チャイコフスキー国際コンクール優勝者ガラ・コンサート」の協奏曲編。
ヴァイオリンのセルゲイ・ドガージンがモーツァルトのヴァイオリン協奏曲第三番、チェロのナレク・アフナジャリャがドヴォルジャークのチェロ協奏曲、ピアノのダニール・トリフォノフがショパンのピアノ協奏曲第一番を、アンドレイ・ヤコヴレフ指揮のモスクワ交響楽団と演奏した。
はっきりいって、トリフォノフ一人だけ「カテゴリー」が違う。
甘美にして軽妙華麗、エレガントな響き。「ネコが踏んでも音が出る」と揶揄されるほどにメカニズムの完成度が高いだけに、プロのピアニストでも大半は似たような音色しか出ないのがモダン・ピアノ。ひと握りの選ばれた人だけが、ピアノ独自の魅惑的で、多彩な音色と軽捷な響きを紡ぎだすことができる。
トリフォノフはその一人。かのファツィオリを愛奏のも、さもありなん。
だから、ドガージンもアフナジャリャも、先日のヴンダー同様にカテゴリーが「U‐23」に思えるのに対し、今年二十一歳のトリフォノフはフル代表。
先日の室内楽編も後半はかれの独奏だったのだから、聴いておけばよかった。
指揮者とオケは正直、かなり問題があったが、それよりも指揮のヤコヴレフ、ヤク戦闘機をつくった同名の技術者と関係があるのだろうかということが気になる。といいつつ、顔はゴルバチョフの片腕だった、アレクサンドル・ヤコヴレフに似ている気もする…。
四月二十九日(日)空虚な拍手
新国立劇場《ドン・ジョヴァンニ》。やはり、アリアのあとで誰もいなくなった舞台に拍手するのは、虚しい。
Homeへ
五月二日(水)敬虔と捨鉢
ヴェンツァーゴのCPOブルックナー・シリーズ第三弾、ノーザン・シンフォニアとの交響曲第二番を聴く。予想以上にオモロイ。
既発の四と七、〇と一の演奏と、たしかに違う。ヴェンツァーゴは最初のセットの解説に「ブルックナーが金太郎飴なんてとんでもない。曲ごとに異なるサウンドがある」と宣言しているのだが、まさに有言実行、今回も違う。
このシリーズの特長である「解像度の高い、鮮明な響き」はずっと共通しているのだけれども、バーゼル響による四と七の自然体の爽快感、タピオラ・シンフォニエッタによる〇と一の前期ロマン派的な澄明な俊敏さと、今回のノーザン・シンフォニアとの第二番との違いは「得体の知れない感じ」に満ちていること。冒頭の、まるでシベリウスみたいな妙な響きの始まり方から、もうたまらない。
室内楽的に、克明に描けば描くほど、この曲は内省的な祈りの歌と外向的な祭りの踊りに分裂していって、それが頻繁に変化し、入れ替わる。敬虔と捨鉢の複雑な、いや猥雑な共存。
こんな躁鬱病のような曲だとは、初めて知った。聴く前は〇と一と同じラインかと想像していたのだが、その斜め上方を飛び越えていくヴェンツァーゴ。恐れ入りました。
これまでは二曲をセットにしていたのに、今回が一曲だけなのは、第二番の特異性を示しているのか。
残るは三五六八九の五曲(と〇〇)。どうなるか、つまらない予想は役に立たないと思い知らされたので何も考えないことにするが、こんなに多彩な変化をもったブルックナー全集は、疑いなく史上初となるだろう。楽しみ。
ところで、今回のオーケストラであるノーザン・シンフォニア。本拠地はイングランド北東部、ニューカッスル近郊のゲイトヘッド。ニューカッスルは、サトクリフのローマン・ブリテン・シリーズですっかり馴染になった、ハドリアヌスの長城の東端の都市なので、その意味でも親しみがわく。
五月五日(木)二年ぶりのLFJ
十一時から十三時まで、「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」(LFJ)で、クラシックソムリエをつとめる。昨年はプログラムの大幅変更の余波でこの仕事がなくなったので、二年ぶりの東京国際フォーラム。
初日はホールA以外にもチケットに売れ残りがあると聞いたが、三日目は例年同様、残っているのはホールAだけ。いったんすべてキャンセルになって、新たに売り出す形になった昨年の混乱の余波で、出足が遅れただけなのではないか。
クラシックの会場としては大きすぎるけれども、当日に「来てみた」お客の受け皿として、五千人収容のホールAの当日券は、絶対に必要だ。そして、そのような方の多くが初心者であることを思えば、有名曲が主体なのもよい。
ただ、本当は、ホールAだけのLFJ体験ではもったいないと、ソムリエ席で質問を受けつつ毎年思うのも事実。相談してくださる方の大半が、他は売切でホールAしか買えなかった方なのだ。
いつもとは異なる珍しい曲、アンサンブルや合唱、デュオに独奏、そうした多様な音楽の面白さ、愉しさに触れてみることが、もう少し手軽にできたら、この祝祭の場に、より深い親しみを感じていただけるはずで、素晴らしいのだが。
いまは、その段差がかなり大きい。それには五百~千人規模のホールが複数必要で、会場的にも経費的にも、無理なのだろうけれど。
この日の夜は「スーパームーン」、月が地球にいちばん接近するのと満月が重なって、普段より三割も明るく大きいという。
たしかに大きい。ウサギもはっきりと見える。
学生の頃、男三人で虚しく西湘バイパスをドライヴして、途中で停めて浜に歩いて出たことがあった。
すると、頭上に大きな満月がまぶしいほどに光を放っていて、それが波頭に反射してきらめき、声を上げてしまうくらい美しかった。
その少し前に教育テレビで放送した、フリードリヒ演出のバイロイトの《ローエングリン》でのローエングリン登場の場面にそっくりだったのに驚いた。満月にペーター・ホフマンの白鳥の騎士のシルエットが重なり、月光が波頭をきらめかせるのだ。
その後あんな満月は見たことがなく、見間違いや思い込みだったのかと思っていたが、今日のスーパームーンはそっくりだ。あの日もこれだったのだ。
五月七日(月)NJPと隅田西岸散歩
新日本フィル(NJP)の記者会見。会場はすみだトリフォニー脇の東武ホテルレバント東京。
二〇一二~一三年シーズンは創立四十周年と、音楽監督アルミンクの十年目にして最後の年を兼ねている。その内容が紹介されたあと、二〇一三年秋以降の新体制が発表された。
インゴ・メッツマッハーがコンダクター・イン・レジデンスに就任。ダニエル・ハーディングも現在のミュージック・パートナー・オブ・NJPの契約を延長する。ともに期間は二〇一五年夏までの二シーズンで、一シーズンに四演目六公演を指揮するのも同じ。どちらのポストも公式にはアルファベット表記だが、ここではカタカナで書いておく。
オーケストラが特定の作曲家をコンポーザー・イン・レジデンスに任命するのはよくあるが、その指揮者版か。音楽監督は客演指揮者の人選や選曲の責任者であり、アルミンクもそうしているが、メッツマッハーはそこまでは関わらない。記者会見の資料によると、定期演奏会の指揮と同時に「楽団員の求めに応じて音楽的アドバイスを行」なったりするという。首席指揮者、プリンシパル・コンダクターといった一般的なポストとはどう違うのか、そのへんはよくわからない。
個人的には音楽監督にまでなってほしかったけれど、ともあれメッツマッハーは好きな指揮者だけに、大歓迎。いずれはこのコンビで新国立劇場のピットにも入ってほしいが…。
午後二時から一時間半ほどで終り。今日は七時から、トリフォニーで四十周年記念演奏会を聴く予定だが、夕食をとる以外に三時間ほど間がある。
戻るには半端。休日明けの月曜では図書館なども確実に休み。日差しは強いが暑くはない。どこかを歩こうと考え、まだ行ったことのない、南千住は小塚原の刑場跡に決める。
あとで考えたら、半蔵門線から東武伊勢崎線に乗り入れて北千住へ出れば近い上に、途中の東向島(玉ノ井)や鐘ヶ淵などの場所も通れたのだが、東京の東側の交通にまるで疎いために思いつかず、浅草橋から都営浅草線で浅草まで行き、隅田川沿いに北へ歩くことにした。
助六で有名な花川戸をすぎ、浅草寺裏の浅草六丁目へ。このあたりに幕末の三十年間、歌舞伎の江戸三座などが集められて芝居町となった、猿若町があった。
川沿いに中村勘三郎の「平成中村座」のノボリ。知らなかったが、江戸の芝居町の近くにあるらしい。
一面まっ平らなこのあたりでは珍しい小山に鎮座する、待乳山聖天に参詣。平成中村座はその先、山谷堀公園が隅田川にぶつかる位置に建っていた。
隅田川の少し上流には謡曲『隅田川』の題材となった梅若伝説の舞台、古代以来の橋場の渡しがある。そこに近いのも興趣があるが、しかしそれよりも、市川団十郎を頂点とする猿若町と、浅草弾左衛門が支配した新町との、境界の位置にあるという意味深さに感心する(団十郎と弾左衛門の対立については塩見鮮一郎の『弾左衛門とその時代』に詳しい)。
さらに、この山谷堀にかかっていた橋のたもとに、三代将軍家光の頃の刑場があったことを思い出す。偶然にも、今日はそこから、刑場の次の移転先である小塚原までを歩こうとしている。ただし、正確な場所が思い出せなかった。
(あとで調べたところ、少し上流の、いまは吉野通りが通っている吉野橋、旧称山谷橋の浅草側、遍照院という寺があるあたりの、江戸後半に「砂利場」と呼ばれた場所が、それだった。なお江戸の刑場は市街地の拡大にともない、日本橋の北側~鳥越橋~山谷橋~小塚原と、東北方向へ三度も移された)
かつて新町と呼ばれた、今戸一丁目と二丁目を歩く。皮革業が多い。今戸神社にお参り。ここには白山神社が合祀されている。少し歩いて熱田神社。この神社はかつて、南の蔵前近くの鳥越山にあった。鳥越橋の刑場が家光時代に山谷橋へ北上するのにあわせて、熱田神社もこの新鳥越町へ移転した。
吉野通りに沿って歩く。やがて、いわゆる山谷のドヤ街。
マンモス交番の奥に、いろは会の商店街アーケードが見える。屋根には「あしたのジョーの町」という横断幕が掲げられているが、薄暗い路上に男が何人も座り込む光景に気後れして、入らずに吉野通りへ戻る。旅館とホテルの周囲には、近年の流行らしく白人の旅行者も多い。
明治通りとの交差点が有名な泪橋。渡ると南千住駅手前の巨大なガード。小塚原刑場の跡は、日比谷線と車庫への引込線の線路用地になっている。そのあたりを眼下にしながら跨線橋を渡る。
線路の北には、刑死者を弔った回向院がある。寺内に吉田松陰や橋本左内の墓や首切地藏もあるらしいが、見学時間は四時半まで。すでに過ぎていた。
残念と思いつつ門の脇を見ると、吉展地藏が建っていた。
私の生れた年に起きた、誘拐殺人事件の被害者を弔うためのものだ。二年後の犯人逮捕まで、遺体が他人の墓の中に隠されていたということだけを憶えていたので、その墓がここだったのかとこのときは思ったが、帰宅後に調べると、五百メートルほど西北の、日光街道沿いの円通寺の墓地だったそうだ。
その円通寺には彰義隊の墓と上野から移築された黒門があるし、少し南には吉原の遊女の投げ込み寺だった浄閑寺がある。このあたりもいつか訪れたい。
南千住駅の少し先には、おばけ煙突で有名な千住火力発電所の跡地があると案内図に出ているが、これも次の機会に。
江戸と東京の社会の、人の生と死の影が色濃く刻まれた地域から、錦糸町へ。
この時点では北千住経由で戻れることを思い出していたが、時間に余裕もあるので、まだ乗ったことのないつくばエクスプレスで、秋葉原を経由することに。
秋葉原にはすぐに着いたが、驚いたのは駅の深さ。もう少し掘れば黄泉の国なんじゃないかというくらいに深い。JRへ乗り換えるのに、長いエスカレーターを何度も昇る。高速と低速の二種があるのも、この深さなら当然だろう。
錦糸町に着いてから夕食。スカイツリーが見える店でパスタを食べたが、見事にはずれ。スープの多さ、フェットチーネの太い麺、いずれも、ゆであげを失敗してもごまかせるような工夫だが、失敗から逃げている料理とは結局、初めから失敗している料理なのだった。
いよいよ四十周年記念演奏会。昼の記者会見での小澤征爾の映像コメントによると、桂冠名誉指揮者であるかれが本来振るはずで、病のため断念したという。そこで登場したのがハーディング。
R・シュトラウスの《町人貴族》組曲とワーグナーのヴェーゼンドンク歌曲集(独唱は藤村実穂子)、後半はマーラーの《巨人》と、ドイツ後期ロマン派でそろえた、とても長いプロ。
正直、前半は長過ぎ。《町人貴族》は尻上がりに艶としなやかさが出てきたけれど、曲がどうにも単調で、苦手。ヴェーゼンドンクの藤村は格調高く、締まった響きの安定性の高さも見事だったが、音楽があまりにソリッドで硬い。
後半のマーラーが面白かった。粗さも目立ったとはいえ、久しぶりにマーラーらしいマーラーを聴いた気がした。舞台裏からの冒頭のトランペットの遠近感もいいし、なんといっても全体の響き。
マーラーの響きの構造は、村上春樹との対談本で小澤征爾が言っていた通り、一般的なドイツ音楽の構造とは、まるで異なっている。ピラミッド型の重層構造ではないから、その響きは、音量の大小とは無関係に、鳴り方そのものが薄い。平面的なのだ。
ただ、平面とはいっても複雑怪奇で、各声部が、ミミズやゴカイなどの環形動物が無数に絡みあってモゾモゾと動き、うねるような、グロテスクなゾワゾワ感をもっている。このゾワゾワ感を出さずに響きを妙に整理すると、生命力を失って面白くない、さんざん聴きあきたマーラーになってしまう。
近年ではアバドとテンシュテットが、このゾワゾワ感を出せるマーラー指揮者だ。そしてハーディングも、おそらくアバドに学んで、それができる。
今回の演奏ではピリオド奏法にも通じる、音の減衰を早めにさせて響きを濁らせないフレージングによって、無数の環がうねる空間をつくりだしていた。
ホルン全員が立ち上がった最後の最後で、響きが混濁してグチャグチャになってしまったあたりは改善の余地があるだろうけれど、ハーディングと新日本フィルのマーラーは、今後も楽しみ。
五月十一日(金)フラング突然の降板
オペラシティでの東京交響楽団の演奏会で、珍しい事態に遭遇した。
予定の演目は《フィンランディア》とニールセンのヴァイオリン協奏曲に、再びシベリウスで交響曲第一番。
ところが、開演時刻に楽団長が登場。独奏のヴィルデ・フラングがゲネプロの後、猛烈な吐き気と腹痛でホテルの部屋を出られない状態となり、開演三十分前にキャンセル。急な話でどうしようもなく、やむなく一曲省いてシベリウス二曲だけの、まるで「ラ・フォル・ジュルネみたいな」プロ(ただし曲間に十分の休憩あり)に変更し、そして希望者には払戻しに応じることを舞台から告げた。
払戻しは苦渋の決断だろうが、躊躇なく、潔く決めた姿勢は立派。終演後に結構な数のお客さんが申し出ていた。珍しい曲だけに、それが目当てという北欧音楽好きも少なくなかったろう。
急遽独り舞台になった指揮のロウヴァリ(名前はサンットゥ=マティアス。こういうカタカナ表記、自分は好きではない)は、一九八五年生れのフィンランド人。粗削りなところも多いが、ユーゲントリッヒャーぶっ壊れ系という感じで、ゴツゴツとした鋭い響きが、私は面白かった。近くにいた知人は「ヒドイ。大学生以下」と怒っていたけれども…。アンコールは交響曲第一番から第三楽章を再演。八時二十分ごろ終演。
帰宅後に思ったのは、かなりクセの強い指揮者だけに、無事に公演が行なわれたとして、フラングとの相性はどうだったのだろうということ。本当に急病なのかと疑うのは、下衆の勘繰りだが。
今日のプログラムは、明日も川崎で再演されることになっている。どうなるのか。ともあれ、五日後の十六日にはハクジュホールでフラングのショート・リサイタルを聴く予定なので、それまでには快復してほしいもの。
五月十二日(土)代役は上原彩子
東京交響楽団のことが気になってサイトを覗くと、昼頃に「急告」が出た。
今日もフラングは体調不良で降板、代って上原彩子が登場して、ラフマニノフのピアノ協奏曲第二番を弾くという。
昨日の今日でラフマニノフ。上原の十八番とはいえ、偉いとしかいいようがない。土曜なのに午後二時開演などではなく、夜六時なのが救いか。
野次馬根性丸出しで調べると、フラングと上原は事務所が異なるから、マネージャー・サイドとは無関係に、オーケストラに対する男気ならぬ「女気」での代役なのだろう。
そういえば上原彩子は十八、十九日と日フィルの演奏会に出て、ラザレフ指揮で同じラフマニノフの、第三番をひくのだった。こちらは自分も聴く予定。
五月十六日(水)フラング登場
ハクジュホールで、ヴィルデ・フラングのヴァイオリン・リサイタル。
午後三時開演。モーツァルトのソナタ第二十五番、ブラームスのハンガリー舞曲の十一、十七、二番のヴァイオリン編曲、プロコフィエフのソナタ第二番という、休憩なしのショート・プログラム。もう一度、夜七時半からくり返される。三百席しかないホールで収入を確保するには、適切な方法だろう。
いかにもノルウェー人らしい長身長髪に白い肌。温和な顔つきだが芯は強く、頑固そう。表情に陰はなく、身のこなしも演奏も特に病後には見えなかったが、数日たっているだけにわからない。
ホールの空間規模にふさわしい澄んだ響きのモーツァルトと、それを完全に逸脱した、強大にして強靱なプロコフィエフとの対比が強烈で、面白かった。
後者はフルート・ソナタの編曲だが、編曲を提言して初演したのがオイストラフということが象徴するように、二十世紀の大ホールと大人数の聴衆のための、強い響きの音楽になっている。ヴィブラートを多用し、高いモダン・ピッチで、金属的なまでに鳴りわたり、やはりマシン・エイジと呼びたくなる音楽。
フラングはこの音楽を真っ向から、猛烈な勢いでひききった。シベリウスとプロコフィエフの協奏曲を収めたデビュー盤での、後者の演奏もよかったから、相性がいいらしい。ピアノのミハイル・リフィッツも、ブゾーニ・コンクール優勝が伊達ではない、弱音から強音までコントロールの行き届いた演奏。
微妙な天候が続いてエアコンも難しいのだろう、冷房が効きすぎ。「この寒さもノルウェー風か」といったら、隣席の飯尾さんが笑ってくれた。
ところで、今日いちばん印象に残った光景は、ホールへ行く途中。
JRの原宿駅から西へ、代々木公園の南側の遊歩道を歩いて行ったのだが、道が下りになる直前の南門あたりの木陰の遊歩道に、中高年の男性が百人以上、強い日差しを避けるように、びっしりと隣り合って、所在なげに座っている。例のブルーシートのハウスが見えたからそうなのだろうが、密集して座っているのが印象的。道路脇に、業務用らしき白いワゴンが何台も停車していたが、これらはこの光景に関係あるのだろうか。
原宿駅からも代々木八幡駅からも離れた、通行人も車も少ない、都会の隙間の場所の、平日の真っ昼間。
五月十八日(金)《ポーランド》
サントリーホールで、ラザレフ指揮日本フィルの演奏会。ラフマニノフのピアノ協奏曲第三番とチャイコフスキーの交響曲第三番《ポーランド》。
前者の独奏は上原彩子。十二日に川崎で演奏したのは第二番で、今日は三番。過剰な情緒を排し、決然とした力強い演奏。客席も沸いていた。
後半の《ポーランド》は、実演ではなかなか聴けない曲。《白鳥の湖》と同時期の作品で、西欧風の洗練と一種の「社交性」が感じられ――マナーを意識しているといえばいいのか――舞曲による五楽章の組曲という雰囲気もある。チャイコフスキーが古典派以前を意識した四つの組曲をつくるのは少し後のことで、その先駆けという意味もあるのか。それだけに散漫にもなりやすい。
ラザレフは的確にその性格を音にしていて、終楽章を盛り上げる演出も、この人ならでは。終演後はスコアを高々と掲げて、作品こそが素晴らしいのだという身振りをしていた。
五月十九日(土)《嘆きの歌》
トリフォニーでアルミンク指揮新日フィルを聴く。前半がドヴォルジャークの《金の紡ぎ車》、後半がマーラーの《嘆きの歌》。
ボヘミアつながりで、どちらも死者の復讐という、陰惨な民話的物語を描いている。前者は金の紡ぎ車が、後者は人骨でできた笛が、非業の最期を遂げた死者の嘆きを響かせて、罪を犯した強欲な生者を断罪するのだ。
ロマン派の音楽は、古典派までの神話や聖書に代って、こうした北方的な血なまぐさい民話を、好んで題材にするようになった。二曲合わせることでそれが明解になる。アルミンクのこうした選曲のセンスには、いつも感心させられる。
それにしても《嘆きの歌》、なんと無駄に編成がでかいこと。
SATBの四人の独唱や舞台裏のバンダも加わる。終演後の拍手のときに表に出てきたバンダが二十人ほどもいたのには、驚くやら呆れるやら。怖いもの知らずの若者が、ベルリオーズの誇大妄想を真似てみたような作品。
作曲から二十年も後にようやく初演できたとき、第一部カットとともに、バンダなしで演奏できるように改訂したというのも、納得がいく。
独唱の扱いも興味深い。オラトリオでよくあるように、特定の役柄を特定の歌手にあてることをしない。まるでオーケストラのなかの楽器にフレーズを受け渡しさせるように、歌詞を各声部に自由に振り分けている。合唱も含めて、全員が「語り」を分担しているのだ。そして、その中で少年の声だけは死者の嘆きの声という役割に固定して、無伴奏できわだたせる。
とても交響的な「オーケストレーション」で、オペラ的でもオラトリオ的でもない。このあたりもやはりベルリオーズ風で、劇的交響曲の一種ともいえそう。
かれがオペラを書かなかった理由の一端を感じた。交響曲の人なのだ。
アルミンクの演奏が劇的な表情づけを抑制したものであったことも、この印象を強めたのだろう。
五月二十五日(金)アダムスの歌
大学の同級生二人と渋谷で飲む。焼鳥屋のあとの二次会は、このメンバーではおそらく初めてのカラオケ。
といってもきっかけは、グループサウンズのアダムスというグループが歌ったという、《旧約聖書》なる歌が実在するのかどうかを確かめるためだった。
結果はたしかに存在し、友人の一人が歌う。妙な歌。私は《風のフジ丸》が歌いたかったがなかったので、《快傑ハリマオ》などを歌う。しかし声が出ない。
五月二十六日(土)大地の歌
サントリーホールでスダーン指揮東京交響楽団を聴く。モーツァルトの《ハフナー》交響曲とマーラーの《大地の歌》の二曲。
十一日のフラング騒動以来の東響。今日も「メゾソプラノ不調のため、《大地の歌》は一、三、五楽章のみの演奏とします」となったらどうしようなどと思っていたが、もちろん無事に全曲。
十九日が新日の《嘆きの歌》だったので、マーラーの「声楽つき大作」の最初と最後を、くしくも一週間おきで聴くことに。これが東京の面白さ。
野心的で、よくも悪くもひたむきな若さにみちていた前者と、老練にツボを押えている後者。そうした違いはあるけれど、その編成が与える表面的なイメージを裏切ってくる点では、共通している。つまり、前者はオラトリオのようでそうではないし、後者はオケ伴の歌曲集のようにとれるのに、違う。どっちも「交響曲」。骨の髄までのシンフォニストの作品だと、よくわかる演奏だった。
《大地の歌》をナマで聴いたとき、録音との違いで何よりも印象に残るのは、独唱とオケのバランスの悪さだ。歌とオケが重なり、しょっちゅう交通事故のように衝突するので、声が聞きとれない。ワーグナーが巨大編成と声のバランスを巧妙にとり、響かせるのとは正反対。
まるでオペラ的ではない。声が楽器の一つにすぎない点も、交響曲。
初めてナマを聴いたときは、マーラーが実演を体験できなかったためなのか、と思った。実音を聴いていたら、理想と現実の差を考慮して、響きを整理したのではないかと。
初演者で、この曲を十八番として何度も演奏したワルターは、この問題をどう処理したのだろう。ウィーン・フィルならオペラの手練だけに、ある程度勝手に調整しそうな気がするが、音がバカでかくてピット経験のないニューヨーク・フィルを指揮したときなど、いったいどうやっていたのか、とても気になる。
そして、シェーンベルク編曲(リーン補作)の室内管弦楽団版が一時流行したのは、この弱点を補正する意味もあるのではと思っていた。帰宅して、手元にウェルザー=メスト指揮のIPPNW盤があったので聴いてみたが、たしかにこの編曲は、単に小編成というだけでなく、巧みに響きを間引いてあって、実演でも歌は明解に聞きとれそうだ。
しかし今日は、これはこのままでいいのだ、聞きとれないようにやるべきなのだと、聴いて理解できた気がする。
なぜなら、声とオケが衝突するのは第五楽章までで、第六楽章は違うからだ。ここだけは、声とオケのバランス調整と交代がきちんと、オペラやオラトリオ風に書いてある。ゆったりとして音量が抑え目という単純な問題だけでなく、音が重ならないように配慮してあるのだ。
この変化は明確に意図的なもので、この楽章だけでそれまでに匹敵する長さであることを考えると、この曲もまた、マーラー好みの二部構成なのだろう。
そうして思い返すと、五楽章までほとんど、声は叫んでいた。大編成のオケが咆哮するのに懸命に張り合って叫び、虚しく敗れて、かき消されていた。それが終楽章で変わる。
苦闘と葛藤をへての諦念。
外界の喧騒にふりまわされて、内面の感情――喜怒哀楽のなんであれ――を持てあまして叫べば叫ぶほど、葛藤がますばかり。それが第六楽章で、外界も内面も穏やかに、一つの世界として、自然に調和する。詠嘆調でハッピーエンドとはいえないけれど、ここにはある種の解決と生の解放と、広がりがある。
マーラーはちゃんと構成して、このバランスにしてある。だから、オケつきの連作歌曲ではなく、オーケストラを主体にした本気の交響曲なのだ。ただしロマン派の、概念としての「交響曲」。純器楽で編成そのものは古典的な、次の第九番とは対照的で、まさに好一対。
終楽章がそれまでの楽章を否定するという意味では、むしろこの《大地の歌》こそが、まさに「第九」の名にふさわしいのかも知れない(おお友よ、この調べではなく!)。凱歌ではない点で、「第九」の陰画だが。
それからオーケストレーション。巨大なのに細密。その併存(映画的なモンタージュではなく、巨大な響きと同時に細部が併存する)は、きわめて絵画的な、音画といっていいものだった。
スダーンの演奏は派手ではない。しかし、こういうことをわからせてくれる演奏とは、もちろんいい演奏に決まっている。メゾ独唱のレンメルトも、さすがの存在感。
というわけで、曲の構造はよくわかったが、テノールがまるで報いられるところのない、ひどくかわいそうな役回りだという思いは、変わらない…。
五月二十八日(日)怪我の功名
吉田秀和さんの訃報をネットで知る。二十二日に亡くなられていたよし。畏れ多くてご挨拶する機会はなかったが、長年の愛読者として、合掌。
自分が書きつづけている一九五四/五五年の話は、吉田さんの『音楽紀行』を最大の史料とするものである。早く完成させようとあらためて思う。
一九六〇年の新譜を「らいぶ歳時記」に載せるためにデータづくり。なかで疑問が生じたのが、ICAが出したDVD「TREASURES OF THE RUSSIAN BALLET」。
一九五六~六三年にソ連のバレエ団が訪英したさいの名場面集(BBCテレビのスタジオ録画)で、そのなかにレニングラードのキーロフ・バレエによる一九六〇年七月の《石の花》第一幕があるので購入したのだが、面白いエピソードでもないかと史料をみてもまるで当りがなく、どうもおかしい。
結局、翌年の一九六一年六月の欧州ツアー(その途中でヌレエフが亡命したことで名高い)の誤表記と判明した。
普通ならこの段階で「使えん!」で終りになるのだが、にしてはなぜか、頭の中に「一九六〇年にレニングラードのバレエ団が…」というキーワードが、別にある気がしてならない。
思いうかぶ本をいくつか引っぱりだして、わかった。
一九六〇年六月から七月にかけて、かれらは日本に初めて来ているのだ。かの「赤い呼び屋」神彰率いるアートフレンドの招きで。《石の花》も《白鳥の湖》などとともに全幕を公演している。
おお、きれいに一年違いの六、七月なら、ちょうどいい。この間違いDVDを使って「らいぶ歳時記」で来日公演とアートフレンドの話をしよう。六〇年安保で客が少なかった話、とかも。
ありがとうICA! よくぞよくぞ、間違えてくれました。正しい表記なら自分は買わなかったし、六〇年話へとりあげるにも牽強付会の臭いが強くなる。
どんなものであれ、きっかけさえあればぶち込むのが「らいぶ歳時記」の基本方針。「小宇宙」みたいになるのが楽しくてたまらない。そのぶん、多すぎて訳がわからなくもなっているが…。
というわけで、大島幹雄による神彰の評伝『虚業成れり』を読む。あらためて面白い。
ソ連の音楽家の招聘に先鞭をつけたのは、一九五五年にオイストラフを呼んだ小谷正一だが、かれはなぜかこれ一回で共産圏と手を切り――それがなぜなのかは、かれの評伝『無理難題「プロデュース」します 小谷正一伝説』などにも説明されていない。じつはかなり気にかかっている――マルセル・マルソーなど、西側からの招聘に専念する。代って台頭したのが神彰とアートフレンド。かれらは一九五七年にボリショイ・バレエ団の初来日を実現し、翌年にはボリショイ・サーカスを招いて、より広範囲の大衆を動員することに成功する。
面白いのは、ボリショイ・サーカスという日本名が、アートフレンド側の勝手な命名だったということ。正式には「ゴスダルトベンヌィ・ソビエツキィ・ツィルク」、国立ソ連邦サーカス団という硬い名前で愛称などなかったのに、前年に呼んだバレエ団にあやかって名づけたのが、一般化してしまったそうだ。
ついでに、アートフレンド出身のプロデューサー、康芳夫の自伝『虚人魁人康芳夫』も読みかえす。
アートフレンドとソ連のつなぎ目に、シベリア帰りでじつはソ連のスパイだった、Aという男がいたこと。宏池会初代事務局長でアートフレンドの理事だったというから、田村敏雄のことらしい。
さらに、波の大きい興行稼業のなかで確実な収入源となっていたボリショイ・サーカスを、神が失った原因。それは、旭川の映画館経営を皮切りに北海道一円を仕切っていた、本間誠一の本間興業の仕掛けだったという。
六〇年代、ソ連と中国の関係悪化が表面化し、激しくなっていた時代に、神が中国に接近し始めたことを利用して、本間はソ連に、神が中国に寝返ったと信じ込ませることに成功し、ボリショイ・サーカスの興行権を奪ったのだそうだ。
中ソ対立の激化が日本の左翼と関係業界の勢力図に分裂と変化をもたらしたことは、労音がモデルと思しき山崎豊子の小説『仮装集団』の主要なテーマ。その現実版のような話。
五月二十九日(月)ダムバスターズ
サッカーをろくに知らない母親との、ピントのズレた会話。
「U‐23、エジプトに負けた」
「えっ、カズがゴールしたんでしょ?」
「……。カズは、U‐45日本代表だ」
「?」
「……。」
デヴィッド・パリー指揮ロンドン・フィルの、エリザベス女王即位六十周年記念「テムズ川ダイアモンド・ジュビリー・ページェント公式アルバム」を試聴。
グリーンスリーヴスやらルール・ブリタニアやら木星やらニムロドやら威風堂々やらダニーボーイやら、さらにジェームズ・ボンドのテーマまで、イギリスの愛国的旋律てんこもりのお買得盤(こういうとき、やっぱりブリテンはいないのか…)。
個人的なツボは、エリック・コーツのダムバスターズ・マーチ。ボールトの愛奏曲でもあったこれは、一九五五年の戦争映画『暁の出撃』(ザ・ダムバスターズ)のテーマ曲。曲もいいのだが、映画そのものがまた見たくなってしまった。
これについては、何年か前の可変日記に、イギリス製の廉価DVDを買ったときに書いている。第二次世界大戦中、ドイツのルール地方のダムを破壊した、英空軍爆撃機隊の実話の映画化。
いまは国内盤でリマスター版が出ている。買いたい気もするが…。
夜はサントリーホールで、ヘンゲルブロック指揮のハンブルク北ドイツ放送交響楽団の演奏会。
関心の高さを如実に反映してか、客席には同業の方々がとても多かったが、空席も少なからず。一般のお客さんに根強いピリオド・アレルギーもあるのだろうが、まだその名が浸透していないことも大きいのだろう。
この指揮者をナマで聴くのは初めて。長所と短所が両刃の剣のようになっている人と感じたが、その部分で一月に聴いたかれの古巣、フライブルク・バロック・オーケストラの音楽性にとても似たものを感じたのが面白く、興味がわいた。ドイツ人指揮者としては、かなり珍しいタイプだとも思う。
このあたりを、日経新聞の評に書くつもり。
Homeへ
六月一日(金)ラルテ・デル・モンド
メストレ&ラルテ・デル・モンドをオペラシティで聴く。
やっとナマでメストレを聴けた。あいまいさのない、決然とした演奏は好み。筋肉質のダンサーのようにしなやかな身のこなしと、ときおり見せる含羞の表情は、前夜に偶然読み返した『トーマの心臓』の登場人物が大人になったかのようでもあり。
この演奏会への興味はこれ以外にもあって、ラルテ・デル・モンドがどういう団体なのかを見たかった。
今回は主宰者のヴェルナー・エールハルトがコンサートマスター。四‐三‐二‐一‐一の弦にチェンバロで、ヴァイオリンが向って左に固まるピアノ型配置。CDや宣材映像では四‐四‐二‐二‐二でヴァイオリンを対向配置にしていたのとは異なって、第一ヴァイオリン主体の響きになっていた。
ピッチは低めでノンヴィブラート。しかし楽器はモダン。純粋な古楽アンサンブルに較べて、ツアーの演奏会でも調整に手間取らない、実用性重視の折衷型。
同一のメンバーでバロックから現代曲までこなせ、またホールの大小にも柔軟に対応できるし、必要に応じて臨時の増強も容易というわけで、ドイツではこのスタイルの方が多数派なのだろう。
シュトゥットガルトや北ドイツなど、フル編成の放送交響楽団にも、こうした柔軟性をそなえた団体が増えている。小編成アンサンブルと兼業の楽員も少なくないのではないか。これがノリントンやヘンゲルブロックなど、古楽出身の指揮者を交響楽団が受けいれる下地になっているのだと思う。
聴きながら、三日前に聴いたヘンゲルブロックとの共通性を思う。
ラルテ・デル・モンドのエールハルトはかつて、コンツェルト・ケルンのコンサートマスター兼アーティスティック・リーダーだった。指揮者抜きで演奏するときにはかれが中心になった。それと同じことを、フライブルク・バロック・オーケストラにいたヘンゲルブロックもやっていたのだろう。
二人は、いわば野球の「プレイング・マネージャー」のように、コンマスの席から統率(ディレクト)していた。
専業の指揮者として、指揮(コンダクト)をはじめたヘンゲルブロックだが、よくもわるくも、いまもその気配が多分に残っているのではないか。
六月四日(月)ローエングリン
新国立劇場の《ローエングリン》。最愛の音楽作品の一つを聴きながら、ひどく退屈したことに自分で驚く。
外題役のフォークトの声は甘美で、しかもとてもよく響く。終幕までなみなみと出ていた。声質、声量、スタミナ、加えて容姿も傑出している。惜しむらくは単色で表情に変化がなく、感情の表現に欠けるのだが、とにかく、これだけのローエングリン歌いが世界に何人もいないのはたしか。
他の歌手も役柄にあっていた。だがシュナイダーの指揮が平板で動感に欠け、面白くない。この作品は、単純な君臣関係ではない、中世の封建制ならではの複雑で微妙な力関係に男女の感情を絡めた独唱と、その絶え間ない勢力の変化を感じ取って反応する合唱の織りなすドラマが、じつに面白いと思うのだが、そうしたものがあまり伝わってこない。
第一幕の、権力抗争のさなかに魅力的で力強い神秘的英雄が突如出現して、人々を熱狂の渦に巻き込んでしまう危険性(ジーク・ハイルならぬハイル・ジーク!)、第二幕で、猜疑心の毒がしだいに回っていって、無垢の正義なるものへの凡人の不安と不信がましていき、第三幕ですべてを失う愚かしさ、それらのドラマに血が通わない。音楽が、聞き古した陳腐なものに感じられてしまう。
演出も、こうした力関係の変化と心理の動きを明快に視覚化したものではなかった。ワーグナーが巧妙に音楽に仕込んだ歌手の出入りと微妙にずれていて、ドラマを動かすキッカケの役をワーグナーが与えたテルラムントやオルトルートの進退に、メリハリがない。いるべき瞬間にいず、いなくていいときにいる感じ。
衣装がまた妙だった。どうやらローエングリンは蝶か鳥で、エルザが花に擬されているらしい。むかし森進一が歌った「花が女か 男が蝶か」という歌を思い出す。
その他の男女の登場人物と合唱の扮装も、あからさまにではないが、どこか虫や鳥や花を想わせるデザイン。しかし全体にまとまりがなく、落ち着きがない。これは、そのように意図してのことかも知れないが。
第一幕のエルザの服はあまりに妙でカッコ悪く、かわいそうなくらいだった。半端な長さと形のスカート、首の後ろの灰色の物体(知人が旅客機用の空気枕と形容した。うまい)とか、すべてが「女として開花しきっていない」半端なつぼみを暗示しているのだろうと思うが、いくらなんでもカッコ悪すぎ。
いやなので細かくは書かないが、第三幕初めの舞台装置は、あまりに下品。
それから、金管と木管が肝心なところでコケ続けたのは、まるで六〇年代の日本のオケを聴いているかのようだった。
余話として、印象的なハプニング。
終演後のカーテンコールというか、その前の、袖から歌手が一人ずつ出てきて中央で拍手を受けるとき。
オルトルート役が下手から登場。すると、なぜかエルザ役も反対の上手から歩いてくる。
ご承知の通り、順番は重要性の低い方が先だから、この場合はエルザ役のメルベートが誤り。しかし中央で鉢合わせとなれば、格の低いオルトルート役のレースマークが譲るしかない。
苦笑いして一歩下がった彼女、メルベートが拍手を受ける間、ハインリヒ王役のグロイスベックの影に隠れていた。続いてレースマークが拍手を受けたあと、メルベートに何か声をかけようとしたのだが、メルベートはぷいと横を向いて視線を合わさない。ミスを恥じて困っている表情ではなく、ひどく不機嫌そうだった。結局最後まで、視線を合わせようとせず。わざと、レースマークにいやがらせをしたのかとさえ思えてくる。
何があったのか知らないが、共演者への不満を舞台上でここまで隠さない光景は、珍しい。色々あった公演の、締めくくりにふさわしい出来事。
六月六日(水)アベベとパーヴォ
サントリーホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮フランクフルト放送交響楽団。
前半のリストのピアノ協奏曲第一番はバトン・テクニックも鮮やかで響きもゴージャスなのだけれど、作品のせいもあってか、それ以上のものがない音楽。
独奏がアベベ=沙良・オットだった、というのだけが印象的。いや、裸足だったということなのだが…。袖から出てきて、ひな壇を軽々と風のように駆けあがる裸足の美少女アリスは素敵だった。
ところが、後半のマーラーの交響曲第五番では圧倒された。
大交響楽団のポテンシャルの高さが十全に発揮されると、いかに物凄い響きが出るかということを見せつけるような演奏。すごかった。
基本になるのは濁りのまったくない、異様に透明度の高い弦の響き。二年前、ドイツ・カンマーフィルとの《ライン》第四楽章で、霧のなかにおぼろに浮かび上がる大伽藍のまぼろしを音で描いたのには心底驚いたが、あのときもそのキャンバスと絵具になったのは、濁りがないがゆえに自由自在にぼかしを加えたりなくしたりできる、弦の響きだった。
フランクフルトの弦は、その前に《皇帝》とブルックナーの七番を聴いたときは重たくて抜けの悪い印象だったから、やっとパーヴォの指向が浸透したのか、それとも曲によって変えるのか。
もやっとしがちな音響のサントリーホールで、音がこんなにきれいに隅々まで鳴りわたるのだから、しかも実在感のない響きになりやすい二階中央でこれだけ充実して響くのだから、楽員の力量と、それを引き出す指揮者の能力に驚く。
とにかく透明で見通しがいいから、色々なものが遠近感豊かに聴こえてくる。ケレンもはったりもなくスピーディに進めているのに、その多彩にうごめく響きはマーラー特有の「ゾワゾワ感」にみちていた。管も素晴らしかった。第一楽章のトランペットも見事だったが、なんといっても第三楽章のホルンソロの、まさに満場を圧する響き!
六月十日(日) 走れエルトマン
四時からオペラシティで、ソプラノのモイツァ・エルトマンのリサイタル。
とても満足。歌そのものはあまり変化や緩急の効かない直球派なのだが、前半のメンデルスゾーンとモーツァルトの歌曲、後半のリリコ・レジェロ・ヤヤ・キツメのオペラアリア、という曲目が声質にぴったりであることと、オペラシティという適度に大きな空間がその表現と声量に合っていることが、伸び伸びと歌える結果に結びついたように思う。
ピアノのフーバーがうまい。アリアでも見事。
一つ隣の舩木さんはベルリンでエルトマンの《ルル》を見てとてもよかったそう。それはたしかに見てみたい。
個人的には、アンコールの最後にレハールの《ジュディッタ》のアリアを歌ってくれたのがツボ。
新宿まで歩く帰り道、「マイネ・リッペン、ジー・キッセン・ゾー・ハイス」のフレーズと、エイトマンの歌の「ひびけとどろけ、鋼鉄の男」のフレーズが、頭のなかで心地よく混じり合う。
六時過ぎだが、夏至直前ということでまだ明るく、甲州街道で樹齢二百年の箒銀杏の、葉を青々と茂らせた元気な姿に挨拶。
六月十四日(木) 折衷式のこと
「気になるディスク」に、ドイツの室内管弦楽団、マナコルダ指揮カンマーアカデミー・ポツダムによるシューベルトの交響曲第三番と《未完成》を載せる。
もちろんまだ聴いていないのだが、モダン楽器に一部ピリオド楽器を交え、ピリオド奏法を採用した、折衷式の演奏らしい。
一日に聴いたラルテ・デル・モンドもそうだが、こうしたモダンとピリオドの折衷が、ドイツでは主流になりつつあるようだ。シュトゥットガルト室内管弦楽団など二十世紀後半に隆盛した「バロック音楽演奏のためのスタイル」よりもピリオド重視だが、基本的な精神は変わらず、その延長にあるスタイル。
十九世紀後半に確立された大型ホールでの音楽興行のシステムに順応させるには、純粋な古楽器よりも効率がいいのだろう(大交響楽団も容易に採用できる)けれど、面白いのは、英仏伊蘭ではあまり多くない、ドイツ独自の現象のような気がすること。
このへん、突っ込んでみるといろいろと考えられそうだ。前述のシステムが、同時期に確立した、ドイツ中心の音楽史観と密接に関わっていることとか…。
そういえば現代イタリアのロッシーニ・ルネッサンスも、純粋なピリオドではなく折衷である点、ドイツと似ている。
十九世紀半ばから「自国民の音楽」として芸術音楽を位置づけ、音楽界の主流となったドイツとイタリア。後者のヴェルディ以後の歌劇場システム、前者の、メンデルスゾーン~シューマン~ブラームスの流れの、古典を吸収して、再生産する演奏会システム。そこへの折衷。
「なんちゃってピリオド」などと嫌う人も少なくない折衷式だが、私は、いいものもあればダメなものもあるという誤差を認めた上で、好きだ。二十世紀後半の「新古典主義」的な、弾力を欠いた無味乾燥の演奏よりは、よほどいい。
気になるのは、ドイツと興行システムが似た、さらに資本化されたアメリカ。あそこでは前期ロマン派以前って、いまどんなふうにやるのが主流なんだろう。
六月十六日(土) 世界の天秤
家猫のワサビ、腺ガン手術四か月目の検査。血液検査とレントゲンでは異常なしとのこと。よかったよかった。病気の前よりも太りつつあることが、いちばん問題と指摘される(笑)。
閑話休題。診察を待つ間、大きな段ボール箱を抱えた、三十歳くらいの兄ちゃん登場。
新宿駅南口のルミネ前で、飛べなくなっていたカラスを保護したよし。野生だから興奮するし、仲間のカラスが守ろうとしたりして、つかまえるのが大変だったそうだ。色々調べて、野生動物を処分などせず無料で治療してくれると知り、新宿七丁目の抜弁天のこの病院まで、タクシーできたという。
診察はタダといっても、タクシー代は自弁。「デートへ行く途中だったけど、見捨ててしまったら何かが崩れてしまう気がして…」と兄ちゃん。
治療後、このカラスまだ若いから、このまま放しても大丈夫らしいです、と嬉しそうな顔をして出てきて、段ボールに入れたまま、南口までまたタクシーで戻って行った。
えらい。えらいやつもいればそのぶんダメなやつもいて、帳尻があってしまうのが「世界の天秤」なのかも知れないけが、とにかくえらい。
六月十八日(月)銀二参上
「一九五五」の話はクライバーン、ショパン・コンクール、そして「ハンガリー動乱直前のシフラ」の話を書き終え、ジリジリと進んでいる。次はスカラ座で活躍するプリモウォーモ、ジュゼッペ・ディ・ステファノが主人公のつもりだったのだが、うまい切り口が見つからず、ただの事実の羅列になりそうで、もう一つ面白そうにない。
いっそこの話はやめちまうか、と思いつつ山根銀二の『音楽の旅』(一九五五~五六年の欧州と共産圏の旅行記)を読みかえしたら、当時のスカラ座を、山根の視点で描けることに気がつく。
というか、はっきり言えば、タイトルが先に浮かんできた。
「銀二参上 ~山根銀二の音楽の旅」
カラス絶頂期のこの年にヴィスコンティ演出とバーンスタイン指揮の《夢遊病の女》、ゼッフィレッリ演出の《イタリアのトルコ人》、ヴィスコンティ演出とジュリーニ指揮の《椿姫》、そして《ノルマ》をスカラ座で、さらにはカラヤンとの《ルチア》もベルリンで見たなんて日本人は、山根夫妻くらいだろう。この年のバイロイトと、ウィーン国立歌劇場の再建記念公演もほぼすべて見ている。凄いし、しかも嬉しいのは、ここに挙げた公演のほぼすべてが録音として残っていることだ(《トルコ人》だけは同時期のセッション録音)。
そしてそれらに触れる前に、まずはかれが気にいらなかったという、一九五五年四月六日ローマでのストラヴィンスキー自作自演の《エディプス王》の話。
これもRAIレーベルがCD化している。「バッチリそのCDが出ていて、しかも手元にあると気がつくとき」こそ、この仕事をしていて、何よりもゾクゾク来る瞬間だ。
あと、ダルムシュタットへ現代音楽を聴きに行ったら、なぜか指揮がストコフスキー(笑)で、しかも少し遅刻したら指揮者の厳命のせいで、前半まったく入れてもらえなかった。客席にたどりついた後半も指揮者への憤懣が収まらず、乙にすました指揮姿に腹が立ち、最後のリタルダンドの妙に多い《牧神》が「たまらなくいや」だった、という話も愉快。
これも、まさにその五月三十一日のフランクフルトでの《牧神》がGUILDから出ている。山根が聴けなかった前半のメシアンの《聖体秘蹟への讃歌》も、M&Aから出ていた。
パズルが、ばんばんはまってくる。
早速、《エディプス》と《牧神》を聴きなおしてみる。前者は荒っぽい。そして後者は、たしかにやたらに引きずる演奏で、これを聴きながら山根がプリプリ怒ってたかと思うと、いっそう愉しい。
翌日、ドイツの高名な評論家シュトゥッケンシュミットから、
「山根さんですか? お姿を見かけて、そうではないかと思っていました。昨日は私も締め出されていました。あなた怒ってましたねぇ…」と話しかけられたという。前年に訪欧した吉田秀和と親しく交流したシュトゥッケンシュミット、次に来た日本人評論家が、この喧嘩っ早い江戸っ子だったのだから、面白かったことだろう。
しかしいま、山根の文章を素直に受け取りにくくしているのは、この人が進歩的文化人、つまり戦後の言論界を支配した左翼知識人の、一典型だからかも知れない。大正から昭和初期に一高~東大に学び、新人会にも属した山根は、マルクス主義を最新の科学と信じた世代の知的エリートのひとりだった。
そのかれが、このように資本制ヨーロッパ諸国の音楽と演奏をあれこれ論じるのは、友人が指摘したように「場違い」な印象さえある。
だが、この『音楽の旅』で描写が生き生きとしているのは、まさにその「場違いな」西側諸国の部分なのだ。
そこを読むと、大正デモクラシーと教養主義の時代の人だけに、けっして教条主義や左翼小児病ではない、さすがの知性と鑑賞眼を持っていることがわかる。ヴィーラント・ワーグナーを評価せずにフェルゼンシュタインの天才を認めるあたり、けっしてイデオロギー(社会主義的リアリズム)からだけではない、かれなりに筋の通った主張。
それに対し、おしまいの三分の一を占める東独、ソヴェト、中国の部分は型にはまった報告調で、まるで面白くない。素直な知性と感受性の眼が、「かくあるべし」の建前でふさがれている感じだ。これもこの本の重要な特徴で、資本制の豊かな社会に生きる戦後の左翼知識人の難しさを考える、好例になっている。
などと、友人とやりとりしながら書いているうちに、骨格ができあがってしまったようだ。書くぜ、銀二参上。
六月十九日(火)北欧の合唱曲
オペラシティでスウェーデン放送合唱団。台風が接近中で緊張が高まるなか、行きはまだ雨が弱い。都営新宿線もみな早退けしたのか、普段は混み合う六時過ぎなのに空いていて、むしろ快適。帰りも、雨は強いが風がさほどではないうちに帰れたので助かった。
さてダイクストラとこの合唱団(三十三人)のコンビ、前回の来日を聴き逃したので今日は楽しみだった。この指揮者はショーマンシップと芸術性の程よいバランスが好きで、ジェンツ時代から注目していたが、あっという間に偉くなってしまった。今年まだ三十四歳。
前半は北欧の合唱曲、後半はラフマニノフの《連祷》から一~九曲。《連祷》はさすがの純度の高さが、やや西側風に洗練されすぎて、もう少しロシア風の粗さと強さが欲しい気も。なにか、録音で聴くのと似たような響きになって、ナマで人の声を聴く醍醐味に不足するように思うのは、贅沢な要求なのだろうが。
前半はヤン・サンドストレム、マントゥヤルヴィ、アルヴェーン、ヴィカンデルと、アルヴェーン以外は聞いたことのない作曲家の曲が並ぶ。サンドストレムの曲はサーミ語で歌われている。サーミ語って何?と思えば、ラップランドの言葉だとか。その素朴な民謡に、鳥の声など自然の響きの模倣をあわせたもの。なかなかに美しい。
でも、やっぱりアルヴェーンの二曲、《夕べ》と《そして乙女は輪になって踊る》が飛び抜けていた。ハーモニーの神秘的な深さと広がりが生む充実感は、ラフマニノフまで含めて、他の作曲家にはないもの。これは何度でも、自分の耳と身体をその響きに浸したい感じ。アンコールで、武満徹編曲の《さくらさくら》(ジェンツ時代のダイクストラを彷彿とさせるもの)などに続いて、最後にもう一度《そして乙女は輪になって踊る》を歌ったのは、かれらもこの曲に手応えを感じているからだろう。
家に帰って調べると、かれらの新譜の「ノルディック・サウンド2」が今日の前半とほぼ同じで、アルヴェーンの二曲が入っている。これは買おう。
六月二十二日(金)突然カサッツァ
今日の東京のクラシック界の夜七時はなぜか「イタリアのとき」。
サントリーホールでは、老ゼッダが東フィルと、『パーセル:「アブデラザール」組曲/ケルビーニ:交響曲ニ長調/ベリオ:フォーク・ソングズ/メンデルスゾーン:交響曲第四番「イタリア」』
紀尾井ホールでは、ブルネロ指揮紀尾井シンフォニエッタが、『レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア第三組曲/ボッケリーニ:チェロ協奏曲第五番/ソッリマ:チェロと弦楽のための「イタリアへの旅」より/マリピエロ:ヴィヴァルディアーナ/ストラヴィンスキー:プルチネルラ組曲』
そしてオペラシティではミラノ・クラシカ合奏団&森麻季(ソプラノ)の『珠玉のバロック音楽』。ヴィヴァルディの「夏」「冬」、ジェミニアーニとコレッリの合奏協奏曲など。
自分的には前の二つも聞き逃したくないものなのだが、最後のミラノ・クラシカ合奏団へ行くことにした。
どんな団体か知らないし、正直、外したかもと思っていたのだが、会場でもらったプログラムを見ると、なんと驚いたことに、ヴァイオリン独奏&コンマスがエンリコ・カサッツァ、と書いてある。
カサッツァは合奏アンサンブルのラ・マニフィカ・コムニタのリーダーで、ブリリアント・レーベルにボッケリーニの弦楽五重奏曲集などを録音しているヴァイオリニスト。TACTUS原盤の《四季》は愛聴盤なので、それがここでナマで聴けるとは、嬉しい驚き(これも会場で気がついたことなのだが、十三時半開始のアフタヌーン・コンサートで「春」と「秋」を演奏しており、一日で全曲になるという趣向だった)。
カルミニョーラやオノフリの強烈な個性にくらべれば小粒だが、艶のある美音と冴えるテク、そして自然な呼吸感は、CDで聴く通りの見事なものだった。
ジャンルカ・カプアーノがチェンバロをひきながら指揮するミラノ・クラシカ(四‐四‐二‐二‐一の弦にチェンバロという編成。ピリオド楽器)も、明るい響きと生命力が豊かで、好ましいアンサンブル。
チェロのトップが飛び抜けてうまいぞと思ってプログラムを見ると、オノフリが全幅の信頼を寄せているアレッサンドロ・パルメリだった。うまくて当り前。
カサッツァとパルメリ、こんなところで会えるとは。会場で見た印象では、この二人は海外ツアー用の補強メンバーではないかと思うが、とても満足。バロック・アンサンブルの来日には、ときどきこうした「嬉しい事故」がある。
休憩時に外へ出て近江楽堂の前に行くと、チェンバロの渡邊孝が、CDリリースを記念してゴルトベルク変奏曲を演奏していた。できればこれも聴いてみたかった。重なりすぎだよ、東京の金曜日。
六月二十三日(土)新世紀の土地と路線
横浜のみなとみらいで、プレトニョフ指揮のロシア・ナショナル管弦楽団の演奏会(感想を語れるほどの強い印象を得られなかった)を聴いたあと、帰宅のためにみなとみらい線のホームに降りる。
ところが「日吉駅で人身事故発生のため運転見合せ」のアナウンスが流れる。
かなり時間がかかりそうなので、とりあえず地上へ出る。横浜駅まで二キロはないようなので、歩くことにする。
横浜みなとみらい21の再開発地区を歩くのは初めてなので、面白い。
ランドマークタワー周囲の繁華をすぎると、近隣の高層マンションのためらしきショピングセンターがあったり。元が海浜地区だから、まっ平でただっ広い。
新高島駅のあたりは更地も多いが、日産の本社があり、横浜BLITZというライヴハウスと劇団四季のキャノン・キャッツ・シアターもある。開演前の夕方なので人がたくさんつめかけていたが、日没後はかなりさびしそう。
横浜駅に到着。昔ながらの習慣で東海道線の品川経由で新宿へと思ったが、いまは湘南新宿ラインの方が直通で速い。
行先が「小金井」とあるので新宿から中央線に入るルートもあるのかと思ったら、そうではなく、宇都宮線の小山駅の次に小金井駅というのがあるのだった。中央線の方は武蔵小金井。
元が貨物線だけあって、途中のルートも在来線とはまるで違うのが楽しい。横浜の次は新川崎、武蔵小杉、大崎、恵比寿、渋谷、新宿。三十五分ほどで到着。
六月二十七日(水)山響とトリフォノフ
山形交響楽団毎年恒例の東京公演、題して「さくらんぼコンサート」。十年目の今年は、創立四十周年記念も兼ねる。
昨年は行けなかったが、自分も今回が三回目で、毎年楽しみにしている。十人に一人あたるさくらんぼ(プログラムに通し番号が打ってあって、末尾の数字が休憩時に発表される数字と一緒だと、一箱だか一袋だかもらえる)も楽しみなのだが、それ以上に、飯森範親と山響の演奏がじつに気持ちよくて、お客の反応も温かく、幸福感を味わえるから。このコンビはほんとにいい状態が続いている。
オペラシティで、五十人強の二管編成(弦は十‐八‐七[八?]‐六‐四)を聴くというのも、今の自分の志向にぴったり。今日は西村朗の《弦楽のための悲(ひ)のメディテーション》、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番(独奏ダニール・トリフォノフ)、そしてブラームスの交響曲第二番。
西村の作品は、一度ぼーっと聴いたくらいで論じられる曲ではないので、感想省略。後半のブラームスは、この編成にふさわしい、すっきりと軽快な演奏。後期ロマン派風の重層型の音響ではなく、シューマンの水平型の響きからとらえたブラームスとでもいうか。ブラームスはピリオド式と二十世紀型演奏様式の境界に位置する作曲家だと思うので、こういうアプローチも大いにありだと思う。自分的には、中身もないのに大仰に演奏されるよりもよほど好き。
だが、真に圧倒的だったのはチャイコフスキーの、そのピアノを弾いたトリフォノフ。ほんとうに凄かった。
コンサートに通ううちに経験的に自覚したことだが、自分はモダン・ピアノのピアノ協奏曲というのが得意でない。批評の仕事のときはもちろん別だが、そうでないときは、気がつくと「意識が遠のいている」、すなわち「寝ている」ことが少なからずある。「いかにもピアノらしい音」に、さっぱり魅力を感じないためらしい。
しかしトリフォノフは、とうてい寝るどころではなかった。眼を見開いたままで、そしてそれ以外の全身を耳にして全曲を聴かざるを得ない、驚異的な演奏。
すべての音、フレーズ、パッセージに美とスリルがある。電撃が走るように躍動し、飛び跳ね、歌い、変化していく。迫力ある低音から夢幻的な高音まで、音色も強さも自由自在。第一楽章の二つのカデンツァ的な部分で、ぐっとテンポを落として沈潜するなど、気分の落差と対照も鮮烈。
素晴らしいのは、これだけ豪快なスピード感を発揮しながら、叩きつけるような、威圧的な響きを一切出さないこと。力みがまったくない。この人の体つきは独特で、ピアニストらしくない。面白いことに、その演奏姿はヴァントが指揮する姿勢にとてもよく似ている。腕を完璧に脱力しているのが、この軽捷な響きにつながるのだろう。細いけれど、しなやかで俊敏な筋肉。
暴力的にならず、不健康にもならず、その音楽が生と生命と肉体への、力強い肯定になっているのが嬉しい。だから幸福感が豊か。
ショパン・コンクールのライヴ盤を聴いたときは、やや美音と軽やかなリズムに耽りすぎるというか、推進力を失う弱点が目立ったが、去年のルービンシュタイン、チャイコフスキーの両コンクールを連覇したあたりから、その欠点が消えたらしい。一九九一年生れ、今年まだ二十一歳だから、伸びるのも当然。
自分としては今後、絶対聴き逃せないピアニストの一人になった。
終演後、今年も私はさくらんぼ外れ。隣席の某氏(思わぬ騒動になってもいけないので名を秘す)は見事当選。
山響を愛するものの端くれとして、いつか山形へ演奏会を聴きに行きながら、さくらんぼも山ほど食ってやろう。
六月二十八日(木)ブルネロ&サイ
マリオ・ブルネロ&ファジル・サイの「ソナタの夕べ」@紀尾井ホール。
ともに紀尾井には縁が深いけれど、コンビを組むとは思いもよらなかったし、ブルネロは先日の紀尾井シンフォニエッタを指揮した演奏会を聴き損ねたし、などなどとても楽しみにしていた演奏会。
結果は昨夜の山形交響楽団に引き続いて、大満足。幸せ一杯胸一杯。二人の偉才ががっぷり四つに組んで、「デュオ」という形式の面白さ、愉しさを存分に味あわせてくれるものだった。
曲目は、前半がシューベルトのアルペジョーネ・ソナタとサイの「四つの都市‐ピアノとチェロのためのソナタ」、後半がフランクとドビュッシーのソナタ。
前半も後半も、「ロマン派の王道」的な曲に、ジャズ的な自由なリズムの扱いを加えた近代的な曲を続けるという構成で、これが見事にはまっていた。憧憬とロマンを悩ましく熱く歌う曲と、ひとひねりした曲との対照。これは西欧の洗練と、非西欧の野性との組合せでもある。
特にサイの自作。四つの都市とはトルコのスィヴァス、ホパ、アンカラ、ボドルム。私などはアンカラ以外、名前さえ聞いたことがないが、それそれの性格と民謡の違いで四楽章を構成する。
「スィヴァス」では中東風の物哀しい歌、「ホパ」ではロックのように激しいカルカス・ダンス、「アンカラ」では重苦しくうめくような低音と、懇願する高音。自分の生れ故郷の町にこういう音楽をあてるサイの内面が興味深い。
そして夏の保養地「ボドルム」では、歓楽街に聴こえるスウィング・ジャズ。しかし途中で口論が起こり、チェロとピアノが互いを非難し、殴りあうような音で唐突に終る(笑)。
アイヴズの弦楽四重奏曲で、四つの楽器が殴りあうやつがあるが、あれはたしか、最後は全員で山に登って一応の解決をみていた。サイのは決裂で終り。まあ大団円になるよりも、「終りなき日常」を生きる感じがしていい。
EU加盟を目指すほどヨーロッパ化されたイスラム国、西と東の混交する地域としてのトルコが、象徴されているような曲だった。それが、トルコ帝国の膨張を食い止めた城塞都市、ウィーンの音楽家シューベルトの作品に続いて響く妙。
それにしても、二人の楽器の響きがじつにいい。鳴った瞬間に消えていく、美しき空気の振動。身ぶりも顔の表情も豊かに動くサイ、苦行僧のようなブルネロと、演奏姿は対照的なのだが、音楽の表現の彫りは、ともに深い。
ブルネロのチェロは歌うというより、言葉を語るような多様な表現力をもっている。サイのピアノも、鋭さとロマン性の共存が見事。アグレッシブな表現も随所にあって、様式の枠を超えた部分もあるかも知れないが、その表現は言葉の最良の意味において「ロマンティック」なものだった。
何よりも感心させられたのは、サイの音量と音質のコントロール能力。チェロが響くための「余白」を空間に必ず残していて、バランスが完璧なのだ。両者の対話のドラマは、それぞれに響きつつ、調和し、ときに対立することで生れる。しかし完璧な音量バランスが、そのときどきの関係はどうあれ、互いを尊重しあっていることを雄弁に示す。
恐ろしく耳がいい。この人も「ピアノの枠を超えられるピアニスト」だと思った。それに紀尾井ホールの音響が、こういう音楽には絶好のもの。
アンコールもよく考えられていて、西欧と非西欧の組合せになっていた。《冬の旅》の第一曲を見事な「語り」で聴かせたあと、ガーシュウィンの前奏曲第一番でジャジーに。そしておしまいにバッハのコラール《主イエス・キリストよ、われ汝の名を呼ぶ》の真摯な祈りで両者を昇華する、お見事な構成。
なるほど、これが言葉の真の意味での「デュオ」だと、思い知らせてくれた演奏会。感謝。
なお「演奏者の要望」により、公演は録音されていた。CD化は未定だそうだが、ぜひ発売してほしい。
六月二十九日(木)過剰なり世紀末
ハーディング指揮新日本フィル@サントリーホール。《タンホイザー》序曲とヴェヌスブルクの音楽に、エルガーの交響曲第二番という二曲。終ってみると、とても納得のできるプログラム構成。
エルガーの曲が、いかにも第一次世界大戦前の「過剰」な音楽で、R・シュトラウスなどと同時代のものだということが、ハーディングのつくるサウンドだととてもよくわかる。頽廃はしてない(いかにもヴィクトリア朝風に、隠しているだけかも知れないが…)けれど、編成も音符も曲想も演奏時間も、とにかく多くて長くて、過剰。
その原型をつくったのがワーグナー。パリこそがこの時代の「首都」であることを考えれば、そのパリのために書いたヴェヌスブルクの音楽は、ワーグナーと英仏の「栄華の巷」とをつなぐ音楽。
ハーディングは、弦の澄んだハーモニーとしなやかな流動感の美しさがきわだつ。対向配置で立体感がよく出ていた。
それにしても、新日で最近かれが振ってるのは、《火の鳥》にマーラーの九番に《巨人》と、徹底して近代曲。
来週も《英雄の生涯》。今度はR・シュトラウスの「過剰」を味わえる。その前の《未完成》も、R・シュトラウスとどう関連づけるのか、楽しみ。
六月三十日(土)天皇の世紀!
なんとテレビ版「天皇の世紀」(大佛次郎原作)が、時代劇専門チャンネルで七月十六日から放映開始だそうだ。一九七〇年代前半、石油ショック前のテレビ絶頂期の、伝説の番組。
まず、時代劇専門チャンネルでは山本薩夫・今井正・篠田正浩・佐藤純彌などが監督したドラマ版が放映される。
続いて八月半ばに日本映画専門チャンネルで、第二部のドキュメンタリー版を四十年ぶりに放映するという。
これは片山杜秀さんも大好きだったという番組で、伊丹十三が語りで、テレビマンユニオンが得意とした「ドキュメンタリードラマ」の走りなのだ。
ドキュメンタリーと再現ドラマが入れ子になる、テレビならではの構成。
これをきっかけに、テレビマンユニオンのドキュメンタリードラマがまとめて復活したりしたら、嬉しい。
ともあれ、必見!
Homeへ
七月四日(水)万世橋駅のまぼろし
万世橋駅の遺構が整備されるという。中央線のお茶の水と神田のあいだ、かつてその跡地に交通博物館があった場所の駅である。
一九一二年、明治四十五年に開業してから、万世橋~東京間が七年後に開通するまでは、中央線の行き止まり、ターミナル(始発・終点)駅として高い重要性があった。
以前、三遊亭圓生の思い出話を読んでいて、須田町あたりは圓生が駆け出しの頃(明治の末から大正)に、東京でいちばん賑やかな場所だったと書いてあったのに驚いた記憶がある。江戸期以来の多町(たちょうと読む)の青物市場に加えて明治期に繊維問屋街ができ、その玄関となる万世橋駅の周辺に、飲食店街や寄席などが集中したためらしい。
いまでも中央線の車内から、往時のホームや駅舎の姿が想像できるくらいに形が残っているのだが、それをさらに整備してくれるらしい。
消しゴムをかけるように、過去の姿をどんどん消していってしまう東急とは対照的な(私の思い出のつまった東横線渋谷駅の櫛形のホームは、来年にも消えてしまうのだ…)、近年のJRの復古ムードはなかなか好き。
秋葉原駅の総武線や神田駅の中央線のホームが、まさに「屋上屋を架した」無理な形なのに較べて、万世橋駅は、収まるべきところに収まっている美しさがありそうで、楽しみだ。
と、ここまで書いて、秋葉原駅のあの構造は、金剛型などの旧帝国海軍の戦艦の、あとで無理やり高くした艦橋の不格好さに似ていると思いつく。ああなったのは昭和七年だというから、時期的に近いことも気分を似させるのだろう。
地下のつくばエクスプレスのホームから総武線ホームまで一気に駆け上がるなんて、まさに戦艦の艦底から艦橋最上部まで登るような気分だ。それにくらべ、万世橋駅は近代化改装前の低い艦橋のような、自然で美しいフォルムの鉄道駅を想わせずにいないから、憧憬をかきたてるのかも知れない。
でもやっぱり、駅前の軍神広瀬中佐の銅像は戻ってこないのだろうな。万世橋駅といえば、それなのだが…。
七月七日(土)ハーディングと両国駅
午後二時から、ハーディング指揮新日本フィル@トリフォニー。
曲目は《未完成》と《英雄の生涯》。
前者は、もう一つ方向性の見えない演奏で、睡魔に襲われかける。しかし隣席の見知らぬご老人がいびきをたて始めたため、当方は俄然目がさえる。とはいっても、演奏に集中できない点では、寝ているのも隣に気を取られるのも、似たようなもの。
シューベルトでは、ノンヴィブラートで音の減衰の早いピリオド・スタイルが現在では珍しくない。ハーディングもドイツ・カンマーフィルやマーラー・チェンバー管などで、そうした経験を積んでいるはずだ。ボッセやブリュッヘン、スピノジと共演してきた新日本フィルの方も、その様式を身につけている。なのに今回は、二十世紀風のスタイル。
ならば「あえてピリオド風にしない」ことに意味を感じさせてほしいのだが、それが自分には聴きとれなかった。R・シュトラウスと関連づけるなら、モーツァルトの作品の方がいいのでは、などと考えているうちに終了。
しかし後半、《英雄の生涯》は「プロレスなら新日」の評判に違わぬ、見事で豪快な格闘技だった。現代の演奏らしくフォルムのしっかりした演奏で、充実した響きがホールに充満。
時間的にはブルックナーやマーラーの長いやつの半分くらいしかないのに、そこへこれだけ音を詰め込んでしまうR・シュトラウスの「過剰」ぶりも凄いし、細密かつ精妙に描き出したハーディングもさすが。第二ヴァイオリンを上手に、その背後にヴィオラ、中央にチェロという配置も、立体的で効果的。R・シュトラウスの音楽にこの配置がこんなにはまるとは、少し驚いた。
終演後、土砂降りを心配した雨はまだ弱かった。四時前でせっかく明るいのだからと、次の両国駅で途中下車して、駅舎を見にいく。
突然、ナンチャッテ鉄ちゃん。
トリフォニーへ行くとき、総武線の脇下に見えていつも気になっていたのが、この両国駅の駅舎である。幻の万世橋駅と違って、こちらはどう見てもかなり古い建物が現存して、いまも利用されているからだ。
ウィキペディアの記述によると、この駅舎は関東大震災後の一九二九年に建てられ、ほぼそのままで現在に至るというのだから、八十年を超す長寿建造物。よくぞ再開発されなかったものだ。
その時点では、総武線というのは隅田川を渡れず、ここがターミナルだったそうだ。なるほど駅舎の背後には、行き止まりの頭端式ホームが今の総武線と並行して残されていて、往時を偲ばせる。
関東大震災の破壊の結果、区画変更が可能になって鉄道用地が確保され、お茶の水駅と結ばれたのは一九三二年(秋葉原駅の高架はこのときにできた)。
駅舎にいい雰囲気がただようのは、ターミナルだからに違いない。始発・終点駅には、かならず特有の風情(旅への憧れと、帰郷への焦りがないまぜになったようなもの)があるのだ。
駅前のロータリーもひなびて、今風に発展していないのが好ましい。
構内を歩いてみると、白塗りでかなり現代化されており、往時の暗さがないのはちょっと残念(勝手な意見)。
一階部分の頭端式ホームへつながる側には飲食店が入っていて、その店内なので、歩いてみることはできなかった。
むかし懐かしい、鉄道駅の顔をとどめる両国駅。できるだけ長く、このままであってほしいもの(身勝手な意見)。
七月十日(火)バッケッティ登場
「レコード芸術」のために、ピアニストのアンドレア・バッケッティにインタビュー。札幌のPMFに登場したのを機会に、帰国前日に東京で行なったもの。
機関銃のようにしゃべる。五分で通訳の方がクタクタ。十五分で記事が埋まるくらいにしゃべった(笑)。しかし論理は明晰。頭切れるなぁ。
移籍したソニーにはゴルトベルク変奏曲、本人四種めの録音を入れるという。そのあたりの理由も、レーベルが変る経緯もちゃんと聞いてきたので、まとめるのが楽しみ。
七月十一日(水)圓生の『江戸散歩』
四日の日記で、三遊亭圓生が、震災前は須田町が東京でいちばん賑やかだったといっていると書いたら、友人から初耳でビックリしたという感想をもらう。
この話は、圓生の『江戸散歩』(朝日文庫、上下二巻)に出てくる。自分もこれを読んだときは驚いたし、文庫解説の川本三郎も「知らなかった」と述べている。あの川本が知らないくらいだから、ほとんど知られていない話だろう。
よい機会なので、自分も久しぶりに読みかえしてみることにした。先の記述は上巻二百十一頁に出ている。
「神田というてェとあの須田町というところに電車の停留所がありました。あすこがね、昔は東京一の盛り場でした。と云って、みなさん信用しないかも知れない。本当なんです」
「ここンところの交差点の人てえのはなかった。電車が止まってもうぞろぞろ人でいっぱいでした。(略)あと何処へ行ったって、銀座へ行ったって何処へ行ったって、そんな事はないんです。須田町だけはまァひどい人通りでした」
ここでの「電車」とはもちろん、市電のチンチン電車のこと。須田町は東西南北の各方向から来る市電が接続する乗換地点だったので、人の乗り降りが多かったらしい。その真ん前に、新宿方向から延伸してきた中央線の万世橋駅ができ、ターミナルとなったので、さらに混雑したのだろう。
圓生は一九〇〇年(明治三十三年)生れ、東京を市電が走りはじめるのはその三年後で、八、九歳頃から義太夫、ついで噺家として芸の世界に入ったから、市電が東京の交通を大きく変えたその時期に、東京各地の寄席を巡り始めたのだ。
圓生の家は、新宿の柏木(現在の西新宿)という、当時としてはかなりの僻地にあったから、市電と国電がなければ、子供の足では大変だった。
万世橋駅前に軍神広瀬中佐と杉野兵曹長の銅像ができた、その除幕式のときにも駅前の白梅亭という寄席に出ていたので、土砂降りの雨のなかで礼拝する海軍将校たちの姿を見ているという。
駅前といっても銅像の建立は一九一〇年で、万世橋駅の開業は一九一二年だから、銅像の方が先である。駅よりも前に須田町交差点が発展していたのだ。
明治末~大正における須田町の隆盛には、江戸以来の経済と商業の中心である日本橋と京橋、神田、それに下谷と浅草を加えた本来の意味の「下町」(川向うは含めない)の内部に、鉄道と駅が入っていなかったことが大きいのだろう。
東京駅開業の一九一四年の時点で、北は上野、南は東京、西は万世橋、東は川向うの両国、この四駅に囲まれた地域、すなわち下町には市電しかなかった(秋葉原駅はあったが、貨物専用で旅客は乗れない)。この状況下において、須田町には下町地域を走る市電交通の扇の要として、高い重要性が生じたのだ。
事態を一変させるのが、一九二三年の関東大震災の破壊と再建である。
区画整理で鉄道用地が確保され、一九二五年に上野~東京間が開通(半円だった山手線が丸い円になった)、七年後にはお茶の水~両国間も開通して、下町にも縦横に鉄道が走ることになった。
大震災が、現代の原型となるモダン都市、東京を生む契機になったのだ。交通網の発達が、江戸以来の下町への一極集中から、周辺への増殖をもたらした。
圓生の『江戸散歩』には、東京駅の辺りが「三菱が原」と呼ばれて、夜には歩きたくない物騒な場所だったこと、明治の末期までの銀座はそれほど華やかではなかったこと、日比谷の交差点は何もない寒い場所だったこと、などが回想されている。いずれも、震災後に東京の新しい顔となる地域である。山手線が走っていたのも、武蔵野の田園地帯がほとんどだった。
それに対し、震災前の下町には日本橋に魚河岸が、神田多町に青物市場が、また繁華街として浅草があり、その裏手には絢爛たる色彩に輝く吉原があった。
その活気と華やぎは、江戸の昔からそのまま引き継がれていたものだ。圓生が明治末期と大正の東京を語りながら『江戸散歩』と名づけたのは、当時の東京には江戸の気配が、まだ色濃く残っていたからに違いない。
そのなかで、須田町の繁栄には、江戸でも昭和でもない、圓生の少年時代だけの一瞬の輝きが込められている。だからこそ、読む者はその回想の鮮やかな意外性に、瞠目せざるを得ないのだ。
震災後の一九二九年、道路拡張にともなって須田町交差点は南に移転。乗降客の減った万世橋駅は、一九四三年に休止された。
・駅と路線の開業、開通年
上野駅 一八八三年(明治十六年)
両国駅 一九〇四年(明治三十七年)
有楽町駅 一九一〇年(明治四十三年)
万世橋駅 一九一二年(明治四十五年)
東京駅 一九一四年(大正三年)
神田駅 一九一九年(大正八年)
秋葉原駅 一九二五年(大正十四年)、ただし貨物駅は一八九〇年(明治二十三年)開業
御徒町駅 一九二五年(大正十四年)
浅草橋駅 一九三二年(昭和七年)
万世橋~東京は一九一九年(大正八年)
上野~東京は一九二五年(大正十四年)
お茶の水~両国は一九三二年(昭和七年)
山手線の上野~新宿~新橋は一八九一年(明治二十四年)
七月十二日(木)ヴェリズモ二本立て
二期会公演の《カヴァレリア・ロスティカーナ》&《道化師》の二本立てのゲネプロを見に、東京文化会館へ。
ゲネの段階だから、歌手の感想は書かない。オーケストラもまだ調整段階のようだった。
田尾下哲の演出が、二作の対照を明快にしたのが面白い。《カヴァ》は十九世紀の因襲的なムラ社会、《道化師》は二十世紀の大衆消費社会での物語。前者が閉鎖的な人間関係の中で起きる事件、後者がその共同体に外からやってきた旅芸人たちの話という相違を、より明確化していた。
ただし前者は、シチリアの農村というよりは石造りの、モノクロームな舞台。農村の猥雑で下世話な感じは、極力抑えられていた。カトリックの禁欲的道徳観や倫理性の支配を強く感じる。全体が閉鎖的な修道院内で展開されている印象。
この点で面白かったのは、指揮者カリニャーニが(ゲネプロなのに)進行を止めて要求した二つのこと。
舞台裏で歌う教会の聖歌をくぐもった響きにするよう合唱団に求めたのは、舞台上の合唱との対照を明確にするためなのだろうが、その瞑想性、厳粛性を強調しようという意味にも感じられた。
また、間奏曲の後半で響くオルガンの音量を、当初の数倍に大きくして、ホール全体が教会であるかのように、包み込むように響くように求めた。南欧独特の午睡の、けだるいまどろみのようだともいう人もいるこの間奏曲に、より宿命的な重さをもたせる結果になっていた。
決闘に行く直前、それまで不倫だ酒だと現世の快楽をむさぼっていたトゥリッドゥは、死を覚悟して突然反省したかのように、母親にサントゥッツァのことを頼んでいく。この部分、ただの手前勝手なお涙頂戴のようにも解釈できるだろうが、かれのなかに眠っていた、あるいは目を背けていた、キリスト教的な罪の意識と愛が、ここで甦ったと考えることもできる。ある種の回心。逆に、それに縛られて死ぬ、ともいえるが、間奏曲のオルガンの響きは、それと結びついているようにも感じられた。
続く《道化師》は、元の設定を百年後に移した一九六〇年代、アメリカのハリウッドやテレビの価値観が大衆社会を支配している時代という設定。ドサ回りのテレビ女優ネッダは、ハリウッドでの華やかな成功と名声に憧れている。間男シルヴィオはプロデューサーらしい。
たくさんの細かな動きで焦点がぶれるというか、ポイントが目立たなくなる弱点はあったけれど、この「見立て」は面白かった。
最後の「これで喜劇は終りです」をオリジナル通り、トニオにいわせるのがこの演出のキモ。カニオが絞り出すようにこの言葉をいうのが現代の上演では常識になっているが、もとは陰謀の仕掛け人である、トニオの言葉だった。
これは、初演のときの歌手の力関係にも原因があったようだ。一八九二年の初演は、有望な若手のデビュー作を、これまた有望な指揮者トスカニーニや有望なテノールのジロー(ジラウド)によって上演するものだったけれど、一人だけ重鎮として参加していたのが、トニオ役のヴィクトル・モーレル。
ヴェルディのヤーゴやファルスタッフを創唱した、大バリトン。作曲者と個人的に仲がよかったので、わざわざ出てくれたらしい。だからトニオは、まさにヤーゴのような陰険な策謀家で、プロローグに登場して、最後もしめるという、座頭的位置を与えられていた。
ところがこの最後の言葉は、かなり早い段階からカニオがいうようになった。作品が世に広まって、人気テノールがこぞって歌うようになってからだろうが、誰が最初はわからない。吉田光司氏のご教示によると、初版譜ではトニオの言葉なのだが、レオンカヴァッロの生前に出たいくつかの版では、すでにカニオが言うようになっているという(異版の問題では、ペッペという役名を北イタリア風にベッペにする譜もあるそうだ)。
たしかに、一九〇七年にレオンカヴァッロが監修者として参加した世界初の全曲録音でも、カニオが語っている。作曲者がこの変更を自ら認めているわけだ。同時代のプリモ・ウォーモ、ゼナテッロやカルーソーあたりは、きっと自分で口にしていたろう。
それ以後、録音では大半がカニオ。ただし池田卓夫氏によると、一九七九年のムーティ指揮のEMI盤は、初版通りトニオが語っているという。ちょうどムーティがゴリゴリの原典主義者として物議を醸した時期だけに、さもありなんという印象。ムーティは九二年にフィリップスに再録音しているが、こちらはパヴァロッティがカニオ役だけに、どうなっているのか興味深い。
手元にあるもので面白かったのは、一九三六年のメトロポリタン歌劇場のライヴ。カニオ役のマルティネッリがいうのは予想通りとして、そのあと別の人間が高笑いする。トニオ役のリチャード・ボネッリらしい。これはとても効果的(さすがにパピが指揮している盤だぜと、我田引水)。
考えてみると、この最後の言葉は非常に重要で、歌手の力関係で取り合いになるのも当然だと思う。これを口にする方は一種の自律性、自らの行動を言語化することができるが、いえない方は衝動や本能に振り回されたまま、ということになるからだ。
カニオがいえばオテロのようになれるし、トニオがいえばヤーゴのようになれる。逆にいえば、同時にオテロとヤーゴが存在することが許されない。
初演のときのように、明確にトニオ役の歌手が格上という公演はほとんどなくて、大概はカニオ役の方がスターだろうから、カニオが口にすることになるのは当然だし、レオンカヴァッロもそのあたりの劇場事情をわかっていたから、異版を認めたのだろう。
その意味で、カニオのセリフに続けてトニオが高笑いというのは、うまく折り合いをつけたケースなのだ。
ただし同じ歌劇場の同じマルティネッリ主役の公演でも、一九三四年や四一年の録音でトニオを歌うティベットは高笑いをしていないから、ボネッリ個人の選択によるものらしい。
余談。《道化師》初演指揮者のトスカニーニは、その後も各地で指揮しているが、あるとき、「イタリアの栄光」とたたえられた人気バリトン、バッティスティーニとこのオペラで共演することになったという。
バッティスティーニは、後世のバスティアニーニ以上の二枚目バリトンで、マスネがかれのために《ウェルテル》の外題役をバリトン用に書き換えたくらいの人気スター。
そういう人物が出る以上、《道化師》のプロローグを歌うのはかれ以外にいないことになるが、本編の方では、醜いトニオなんて役は歌いたがらず、二枚目のシルヴィオを歌う、といいだした。
しかしトスカニーニは、プロローグをシルヴィオが歌うのは作曲者の指定に反するだけでなく、ドラマとしてもおかしいからと、これを拒否した。結局、バッティスティーニは降板したという。
トスカニーニという人が本来戦っていたのは、ペッペとベッペの混在とか、こうしたイタリアの歌劇場ならではの、あまりにも現場主義的ないい加減さであって、原典主義をふりかざしたのは、専らそのためだったはずだ。ところがアメリカでは、メディアにそれが極端な受け取られかたをして……と書いてくと、まさに今回の十九世紀イタリア的《カヴァ》と、二十世紀アメリカ的《道化師》の相違にも通じてくる。
このように、いろいろと発想の翼を広げさせてくれただけでも、今回の田尾下演出は、私にはとても面白かった。
最後にもう一つ余談。カリニャーニがこだわった《カヴァレリア・ロスティカーナ》間奏曲後半のオルガン。
カラヤン指揮フィルハーモニアのモノラルの旧録音の方でオルガンをひいているのは、あのデニス・ブレイン(伝説的ホルン奏者)である。
カラヤンたっての希望によるものだそうだ。演奏も、ステレオ再録音より断然すぐれている。
七月十七日(火)阿部、川路、三郎助
録画しておいたテレビ・ドラマ版『天皇の世紀』第一回「黒船」を見る。
監督:山本薩夫、音楽:武満徹、語り:滝沢修、というトリオが、私にはもうたまらない。演出は少し重厚にすぎるけれど、これはこれでよし。
ペリーが来航前に琉球に寄る場面で、いきなり現代の米軍基地が映って、一九七一年放映時の沖縄が返還前で、ヴェトナム戦争の後方基地にされていたことに重ねるあたり、そして米国側でも幕府側でも、軍人や侍の横暴と傲慢、いやらしさが強調されるあたり、左翼人山本薩夫ならでは。
老中阿部正弘が田村高廣、勘定奉行川路聖謨が木村功というキャストは渋いけれど、説得力高し。私の知るかぎり、大河ではこの二人の人物、納得できる配役を見たことがないだけに、嬉しい。徳川斉昭が三島雅夫というのも、いかにも。
藤岡重慶が、浦賀奉行所与力の中島三郎助というのもよい。旺盛な好奇心、知識欲という日本人の長所が、軽佻浮薄という短所と表裏一体であることが、黒船上でのかれの描写に象徴される。
ご承知の方も多かろうが、この中島という与力は、じつに面白い人物なのだ。ペリーの黒船を最初に応接した下級役人だが、素敵なのは、このクラスの人物は大半が歴史に一瞬顔を見せただけで退場するのに、そうではないこと。それどころか、維新史の最後にも登場する。
西洋の科学力に驚き憧れ、一念発起して造船術や操船術を懸命に学び、与力の地位から出世して幕府の軍艦方の一人となる。開明派だが最後まで忠誠を貫き、榎本武揚とともに五稜郭までいって徹底抗戦。最後は榎本に対して降服をすすめながら自らは幕府に殉じることを選び、息子二人とともに砦を死守して、降服二日前に戦死。
つまり、「幕末」の最初と最後の双方に顔を出す、ほぼ唯一の人物(ほとんどは途中で死ぬか、途中参加だから)。よき幕臣、よき日本人の典型みたいな男。
この第一回ではそこまでは説明しないが、そこまでわかっていて登場させていると、想像がつく。歴史好きの骨が震えるドラマ。あと十二回見るのが楽しみ。
それに続いて、ドキュメンタリーに変った第二部は八月十三~十七日に全二十六回を集中放映するそうだ。三十分番組だが、ちゃんと第一部の続き(第一部は水戸天狗党壊滅のあたりまでらしい。武田耕雲斎:加藤嘉というのがまた、たまらん…)からになっているらしい。つくり手の執念を感じる。
七月十八日 真夏に冬のパリ
新国立劇場で、高校生のためのオペラ鑑賞教室《ラ・ボエーム》を高校生にまじって観る。
真冬の大都市の寒さ、それ自体が若者たちの孤独な心象を象徴する話だけに、真夏の上演だと感情移入しにくい気も。
本公演と同じ粟國淳の演出は安定したもので、第二幕冒頭のスクリーンの絵がそのまま現実の舞台に転換していく瞬間の見事さには、客席の高校生たちが息をのんでいるのがはっきりと感じられた。こういう、ナマならではのマジックは、この種の公演には不可欠。
ただ、石坂宏の指揮がとても堅実で、四角四面すぎるように感じられた。作品も作品だし、客席も客席なのだから、もう少しドラマに引きこむハッタリがあってもよかったのでは。もちろん、若い層に媚を売って羽目を外しては、誰のためにもならないことは、承知しているが。
七月二十日(金)松陰の密航失敗
『天皇の世紀』の第二回「野火」を見る。吉田松陰の黒船密航失敗を描く話。
原作の文体にも似た、坦々とした演出(下村尭二)は重すぎるけれど、理論よりも行動派、現場主義者としての松陰という観点から、原田芳雄を選んだのは納得(それでもやっぱり、個人的には松陰といえば『花神』の篠田三郎、だが)。
それよりも演出家(本人ではなく俳優が演じる形式)を登場させてドキュメンタリードラマの形にしていたのが、まるで第二部の予告のようで、面白かった。脚本の石堂淑朗の発想だろうか。
印象的なのは、密航に失敗して黒船から追い返され、下田の浜で茫然とする松陰たちの前で夜が明けていく場面の、武満徹の音楽の圧倒的な美しさ。短いけれど、武満ってすげェ、というほかない響きのマジックだった。
これも含めて、松陰の密航失敗の一幕って、なぜか名場面になるようだ。『花神』では、黒船上で密航を断られた松陰が金子(岡本信人!)にあきらめろと諭し、通訳の米人に対して悲しげに、しかしさわやかに微笑むときの、あの篠田三郎の表情が忘れがたいし。青春の挫折というのは、画になりやすいのか。
しかし、じつは最高なのは次回予告。主役である中村翫右衛門の高島秋帆もよさそうだが、それよりもちらりと映った伊藤雄之助の鳥居耀蔵は、「耀甲斐」どころか本物の「妖怪」にしか見えない。なんじゃありゃ(笑)。これは期待度最大!
七月二十一日 ファウスト交響曲
スダーン指揮東京交響楽団のサントリーホールでの演奏会へ行く。
曲目は、マーラーの《さすらう若人の歌》とリストのファウスト交響曲。今シーズンのテーマであるマーラーの声楽作品に、その先輩格を組み合わせている。
マーラーの独唱はバリトンのホルツマイア。表情を細かくつけた個性的な表現で、オケ伴よりもピアノ伴奏で小ホールで聴くのに向いている気がした。
スダーンの指揮は、二曲ともかれらしい、やわらかめの響きできっちりした音づくり。このコンビをサントリーホールで聴くときに気になる弱点、つまり響きのコシの弱さは相変わらずだが、音楽のつくりはわかりやすい。
リストはやっぱり長すぎて、聴く方の緊張が続かないが、この過剰さこそがロマン派。スタイルといい規模といい、ベルリオーズとの関連を強く感じる。
リストは、ショパンと重なる前半生のパリ時代にはピアノ独奏曲ばかりつくっていたのに、一歳上のショパンが没する前の年にドイツのワイマールにきてからは、交響詩や交響曲などの標題的な分野の管弦楽曲に猛然と力を注ぎはじめた。
大管弦楽の時代である後期ロマン派の始まりを告げるかのようであり、その原型となるベルリオーズの流儀を、ドイツ語圏に接ぎ木するかのようでもあった。
スダーンの指揮で聴くと、ドイツの堅牢な力強さよりもフランスに近い、華麗さと神秘性を強く感じた。唐突だが、メシアンが思い浮かんだりもした。
それに、最後の神秘の合唱(歌いだす直前に東響コーラスが、静かに素早く入場したのが効果的だった)も、シューマンやマーラーが同じ詩につけた旋律に較べて、あまりドイツ語らしくない抑揚なのがよくわかって、面白かった。
リストという存在を十九世紀ヨーロッパ諸国の音楽の「扇の要」と考えると、面白い景色が見えそうだ。ハンガリー狂詩曲などは、国民楽派の隆盛に先駆けるものだったわけだし…。
七月二十三日(月)死とシューベルト
「気になるディスク」にカザルス四重奏団のシューベルトを取りあげる。先日のカンマーアカデミー・ポツダムとオルフェオ・バロック管弦楽団の交響曲CDなど、なぜか今年は、シューベルトを見直す年になりそうな気がする。
まだ自分は聴けていないのだが、すでに「気になるディスク」に紹介したアルカント四重奏団による弦楽五重奏も「レコード芸術」編集部のモトヒロ氏によると、恐ろしいほどの名演らしい。
モトヒロ氏は、レコ芸の吉田秀和担当で、亡くなる前日に最後の原稿を受けとった人だが、「アルカントのこれを吉田さんが聴いたら、なんといったんだろうと思う、もうそういう話が聞けないと思うと、ほんとにつまらない」としみじみ言っていた。あまりに突然いなくなってしまったので、いまでも携帯に吉田さんから電話が入りそうな気がする、とも。
これから自分はきっと、アルカントのシューベルトを聴くときいつも、この話を思い出すだろう。
七月二十五日(水)グラモフォン王朝
「レコード芸術」特集の仕事で、千勝泰生氏にインタビュー。ポリドールからドイツ・グラモフォンに出向、八〇年代から九〇年代前半、「グラモフォン・ダイナスティ」と呼ばれた時代のDGを、マーケティング担当として内部からご覧になっていた方。
とっても面白かった。A&R部門のヘッド、ギュンター・ブレーストのもと、多士済々のプロデューサーたちがカラヤン、バーンスタインなど綺羅星のごときアーティストたちとCDをつくっていた時代。その人となり、裏話など、あまりに生彩豊かで面白いので、編集のモトヒロ氏が急遽内容を組み直し、増ページすることにしたくらい。
ロック登場以降パッとしなかったクラシックが、CD時代にビッグ・ビジネスになっていく、その興隆期の「祝祭の日々」と、やがて硬直化しての衰退、まさに王朝の興亡史のような物語である。
とくにガツンと来たのは、当時のDG体制を背後から、黒幕のようにまとめていた、私などは今まできいたことのないある人物の存在とその人となり。この話は、「レコ芸」が出たときのお楽しみということで。うまくまとめられるといいが。
当時の自分は「アンチDG」だと思っていたが、「アンチ巨人もまた熱烈な巨人ファン」という論法で行けば、DGファンなのかもと、つくづく思った。
余話の一つとして、千勝さんがヨーロッパで立ち会った、あるセッションのスケジュール表を見せていただいた。
一九七九年六月、カルロス・クライバー指揮ミラノ・スカラ座、コトルバスやドミンゴなどによる《ラ・ボエーム》全曲。クライバーの評伝にも紹介されているが、目の前にそのセッションに立ち会ったという人がいて、配役や詳細な録音日程の一覧があると、実感が違う。
しかしある朝、クライバーのホテルの部屋がもぬけの殻になっていて、一巻の終り。いつもこんな調子だったとか。
他の契約を無駄にしないために一九八〇年二月に録音されたのが、アバド指揮ヴェルディのレクイエムだそうだ。
これは以前、別の機会に知ったことだが、同じ頃のアバド指揮の《アイーダ》も、合唱団が《ドン・カルロ》をフランス語で歌うのを拒否したために、直前に変更したという話だった。大曲の録音にはこんなことも多かったらしい。
七月二十七日(月) アイーダ
七月二十八日(火) 研修所のコジ
二日続けて新国立劇場へ。二十七日は日中親善公演の演奏会形式による《アイーダ》、翌日はオペラ研修所公演の《コジ・ファン・トゥッテ》。
どちらも短縮版。特に後者はアリアの大半を抜いた、アンサンブル場面のみ。話の筋は通るしサクサクと進んで、正直その長さを持てあますことも少なくないこの作品を、退屈することなく聴けた。
ただ、両日ともオペラ的感興とでもいうか、人間のドラマに接した、という気があまりしなかった。完全な舞台上演ではないからではなく、広上淳一と天沼裕子の指揮に、ヒトの息吹、つまりは歌を感じにくかったからかも知れない。
七月二十九日 左内と主膳
『天皇の世紀』の第四回「地熱」と第五回「大獄」を見る。演出に今井正が登場、画面の緊張感がまるで違うものに。
外交と将軍継嗣の二つの問題がからんで京都の重要性が増していくなか、ライバルとなる橋本左内と長野主膳を、田村正和と天知茂がやるという配役が素敵。
当時の有力諸侯には、この二人のような懐刀となる人物(国学者とか医者あがりとか)がいて、方針決定や具体的な運動はかれらが担っていた。同じように京都の貧乏公家に接近して攘夷を説く連中もいる。大半が微禄あるいは富裕な商家農民の出身で、下から、あるいは野からのエネルギーを上層が吸い上げる形で時代が動いていることを象徴する。
理路整然たる弁舌の才と爽やかな情熱をもち、汚れ仕事もあえてやる田村の橋本左内の魅力には、鞍馬天狗が重ねられているかのようで、沈着冷静な天知の長野と好対照。
この対決に木村功の川路聖謨、三島雅夫の水戸斉昭、そして近藤勇を得意にした中村竹弥の井伊直弼、まったくしゃべらない伊丹十三の岩倉具視がからんで、ほれぼれ。
「大獄」では水戸家への密勅をめぐって、血で血を洗う抗争がついに始まる。切支丹狩りなどに用いられてきた、江戸期の陰湿残虐な密偵政治の手法がここで爆発。左内も松陰も刑死。その牽引役となるのが長野主膳で、天知はぴったり。
時間の関係か、ここまでのことをやる――幕府崩壊を早めることになる――長野の内面にはほとんど触れない。こういうふうに、わかりやすくできないことはできないままに、安易に単純化せずに見る側に歴史的知識と、そして何よりも想像力を要求してくるあたりが、私などにはたまらなく嬉しいのだけれど、視聴率はとれそうにない(笑)。
書き忘れたが、第三回「先覚」も面白かった。商家出身の洋式砲術の先駆者高島秋帆(中村翫右衛門)と、その開明を憎んで弾圧する鳥居耀蔵(伊藤雄之助)の対決。
ドラマ版『天皇の世紀』では登場人物の来歴を細かく描いたり、説明したりすることをしていないので、役者が短い場面のなかで、その人物の雰囲気をどれほど匂わすことができるかが勝負になる。その点、翫右衛門も伊藤も――今さらながらに――上手い。後者の陰気で不健康な人物像は、今だと本田博太郎の演技に似ている。というより、本田がこのあたりから学んだのだろう。
鳥居の陰惨な密偵政治の描写と雰囲気に、なんともいえない迫真性と説得力があふれているのは、翫右衛門も伊藤も、戦前の左翼弾圧と特高警察の時代をくぐり抜けているからではないか。
原作の大佛次郎は、まさにその「昭和維新」の時代に『鞍馬天狗』を書いていたわけだし、『天皇の世紀』とそのTVドラマもまた、新左翼と学生運動の嵐の時期のものだ。幕末と戦前と一九六八年の三つの時代が、共鳴しあっているのだろう。
七月三十一日 足袋の人、田口
野球の田口が引退。こんな時期に聞くのは不思議だが、MLBの選手獲得期限を過ぎたからとのこと。松井のケースもそうだが、浪人というのがアメリカ野球には当り前に存在している。
どうでもいい話だが、田口って、一人だけ足袋はいて野球やってるみたいに見えるのが好きだった。足の大きさとかストッキングの長さとかの関係なのだろうが、あの姿はもう見られない。
Homeへ
八月一日(水)帯の不合理とシュッツ
オリンピックで日本柔道不振。
柔道の前開きの胴着に帯というのは、スポーツの合理性だけで考えれば、おかしなものはないだろうか。乱れやすく、ほどけやすい。外国人選手で乱れたまま闘う人もいるのは、いい方に解釈すればその不合理への、スポーツマンとしての本能的な抗議のような気もする。
ほかにこういう競技はあるだろうか。障碍物競争の障碍は、それがなければ障碍物競争にならないし、サッカーも、キーパー以外が手を使ったらサッカーにならない。それらは不合理ではなく、競技の特質に結びついた「制限」だ。
柔道の場合、スポーツとしてみれば、床が畳でなくともいいように、胴着と帯でなくともいい気がする。相撲のまわしと違い、相手の帯を握ったら反則なのだから、むしろない方が間違いがない。
伸縮する襟のついた、筒状のかぶる服の方がいいような気がするが、ダメなのか。民族衣装にこだわる理由は、国際スポーツにはないはず。サッカーだって、イギリスの民族衣装を着てはいない。現在の胴着の乱れた着方を見ていると、柔道がJUDOになる流れのなかでは、いずれ避けられない気が。
とはいえ個人的には、スポーツとして不合理な、余計な儀式性(所作とか姿勢とか服装とか)があってこその「武道」だと思っているけれども。
このへんはつきつめていくと、文楽だろうがクラシックだろうが、伝統や文化とは何か、不合理で非効率なものに価値はあるか、という問題につながるかも。
買ったまま聴けていなかった、ヒリアー指揮によるシュッツの、受難曲などの宗教的物語音楽を集めた四枚組「The Complete Narrative Works」を聴く。
素晴らしい。ひんやりした合唱と独唱の響きがたまらない。《十字架上の最後の七つの言葉》など、きわめて簡素であるがゆえに、イエスの嘆きと苦しみと祈りが突き刺さってくる。どれも一時間に満たない長さの三つの受難曲も、今の自分には、バッハのそれよりも身近で、理解しやすく感じられる。これはお買い得で、絶対オススメ。
「踏むがいい」
八月二日(木)未完のファシズム
片山杜秀さんの『未完のファシズム』(新潮選書)を読む。面白い。
欧州の第一次世界大戦は、近代国家間の戦争が、国力全体の多寡によって決まる、長期間の総力戦とならざるを得ないことを明白にした。
このとき、国力にも資源にも恵まれない「持たざる国」である日本の、帝国陸軍の俊英たちは、いわば「どうにもならない」この事態に対して、どう方策を考えたか。そのことを小幡敏四郎の「包囲殲滅」、石原莞爾の「世界最終戦論」、中柴末純の「戦陣訓」、酒井鎬次の「電撃戦論」などなど、さまざまな軍人の思想を比較することで示していくもの。
稀覯本に近いものも少なくないだろうかれらの著書を掘り起こし、要点をわかりやすく紹介する片山さんの筆は、いつもながらに鮮やか。
結論を先に言ってしまえば、結局かれらはみな、現時点の国力と戦力で日本が列強と戦えば最終的に必ず負ける、と気づいていたらしい。優秀で冷静な頭脳の持ち主なら、それが当然の結論だろう。
しかし、かれらは軍人であるかぎり、必敗とは口が裂けても言えない。負けるとはけっして言わない「やせ我慢と強がり」こそが、軍人を軍人たらしめる要素だからだ。
物の見方や対策のたて方はそれぞれに異なるのだが、この一点だけは、絶対に共通する。それを丹念に明らかにしていく点に、私はこの本の醍醐味を見た。片山さんいうところの「密教」であるこのつらい真実を隠して、かれらは「顕教」である自らの理論を展開していく。
どれもみな、小が大を倒すための戦法である。とても小気味がいい。しかし前提として、大、すなわち敵が必ず数を頼みに油断していて、司令部は愚かで将兵は士気が低く、動きが鈍く、装備は旧式でなければならない。
そういう相手でなければ、大兵力に勝てるわけがないのだ。しかし、西洋の列強にそんなことはありえない。たとえ緒戦でそんな状況をつくれても(真珠湾奇襲のように!)、現代の総力戦はそれだけでは終らない。だから、実際は戦わずにすむようにせよ、あるいは緒戦の勝利を活かして早期に講和してもらえ、というのが「密教」なのだ。戦いたくないと敵国に思わせるための「顕教」で、そこまでは軍人の仕事だが、「密教」の実現は政治家の領分ということになる。
この言外の真実を「顕教」の行間に察してもらわなければいけないのに、そうならない不幸。威勢のいい言葉だけが一人歩きして、軍の仲間も世間も、そして本人までも酔い痴れていく。それが太平洋戦争の無残な敗戦と多数の死を招く。
石原の満州事変は、少壮参謀に危険な「火遊び」の味を教え、小幡の包囲殲滅至上主義は文字通りの「馬鹿の一つおぼえ」と化して作戦を硬直させ、中柴の不合理な精神論は性急な玉砕を招いて将兵を無駄死にさせ、酒井の機甲部隊は先見的だが、当時の日本の工業力ではまがい物しかつくれない(もしうまくつくれても、海軍の機動部隊同様、補充のきかない「使いきり」だったろう)。
このなかで「取りあえず今は戦うな」とはっきりと口にし、ソ連式の統制経済で日本と植民地を将来的に――数十年単位で――重工業化しようとする長期的国家構想をもったのは唯一人、石原莞爾だが、一種の無責任体制である明治憲法下では「分をわきまえず政治に容喙する軍人」として、面白いことに軍内部からも嫌われ、排斥される。
明治憲法の政治体制に対する片山さんの見方にも、なるほどと唸らされた。この無責任体制は、憲法の埒外にいる「元勲」たちが舵を取ったときにはうまくいったが、かれらが死に絶えたときに機能しなくなった、というのだ。
そういえば元勲の大半は武士や志士、すなわち軍人あがりの政治家だった。ところが明治以降の教育制度は、軍人を軽蔑する官僚や政治家を育て、両者の分裂を深くするばかりだった。
(天皇を含めた)誰にも強大な独裁権がない体制。ファシズムたりえぬ体制。それが書名の「未完のファシズム」だ。
恐ろしいのはこの体制が、辺境の下位の軍人が勝手に戦争を起こしても止められない、無責任なものであることだ。中途半端にそれぞれの権益だけがある。
悪名高き「統帥権」にしても、軍部が国家全体を積極的に支配しようとするものではなく、単に、体制内のナワバリを守るためだけに使う言葉だ。この点は、意外に見落としやすいのではないか。
それが、司馬遼太郎のいう「関東軍名物の火遊び」をくり返させることにつながっていく。
読み終えて思ったのは、どの「顕教」も現実の「持てる国」には歯が立たない空論であることは、太平洋戦争を待たずともノモンハンで学べたのではないか、ということ。
ノモンハンでかれらを襲ったソ連の機甲部隊は、「想定外」に強力だったはずだ。だのに、そのことに目と耳を閉ざした、恐るべき愚かしさ。
「どうにもならない」ことがそこで明らかになったのに、メンツと既得権益を守るために知らんぷりをし、かれらは国民との無理心中の道を突っ走った。
この本に出てこない辻正信は「顕教」の空虚なプリンスなのか。
老朽化した無責任体制内部の組織が、保身のための単なる利権集団に墮してしまう悲劇は、無様なパロディとして、平成の日本でもくり返されている。
遠くない将来に新たな震災が日本を襲ったとき、フクシマが平成のノモンハンだったと、思わずにすむようにしたい。
八月十七日(金)複合する時間
三週間ぶりに演奏会へ行く。ハクジュホールにて荘村清志と福田進一という、日本を代表するギタリスト二人を中心とする「Hakujuギター・フェスタ2012」の一日め(全三日間)。
このフェスタは毎年好評で、今年がすでに七回め。この二人の登場に加え、私も大好きなこのホールがクラシック・ギターにぴったりなのと、ひとひねりした多彩なプログラムが飽きさせないからだろう。
今年のテーマはロンドン五輪にあわせ「英国の伝統と革新‐シェイクスピアからビートルズまで」。一日めの今日は、まず二人が登場して十六世紀ごろのリュート曲をプロローグに演奏。
続いて第一部は、ピリオド楽器のつのだたかし(リュート)、杉田せつ子(ヴァイオリン)、坪田一子(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、上薗未佳(ヴァージナル)というメンバーで、ダウランドなどシェイクスピア時代の音楽を演奏。
ギターとはみな縁戚だけれど、調弦も演奏も面倒で音量が小さいという、不合理だらけの「古楽器」が生む、繊細で謙虚な音の美しさ。会場の空気を圧するのではなく、空気と触れあうような、微妙な響きが好ましい。
とりわけ、ヴァージナルとリュート、リュートとヴィオラ・ダ・ガンバの組合せの二重奏という、一見単純なのに、恐ろしく奥の深い響きに惹かれた。スカーフでヴァイオリンを首に固定する、オノフリ直伝のスタイルの杉田さんのヴァイオリンも、「ケンプのジグ」などで生き生きと愉しい音楽を披露。
最後にテノールの望月哲也が加わり、シェイクスピア作品に登場する歌曲を三曲。ドイツ系リリック・テノールという印象が強かったが、こういうのも上手。
後半は出演者が替り、福田進一のギター伴奏で望月哲也が歌う、二十世紀イギリスの歌曲。
二十世紀半ば、ピーター・ピアーズとジュリアン・ブリームという素晴らしいコンビが登場したことで、ブリテンはもちろんウォルトンなどが、ギター伴奏のテノール歌曲の傑作をいくつも書いた。
日本で演奏される機会はごく少なく、福田は何十年も前からやってみたかったそうだが、望月の出現によって、やっと演奏する機会を得たそうだ。納得。
これが前半と好対照で、面白かった。ピアーズ&ブリームのコンビがダウランドなどの歌曲を甦らせ、その刺激で現代の作曲家が新作を書く。ブリテンの「中国の歌」などは李白や白居易の漢詩を歌詞にしていて、いうまでもなくマーラーの「大地の歌」の影がかすかにある。これが象徴するように、まるで擬古典的ではない、あくまで二十世紀の書法によるものだが、ともかくテノールとギターの組合せが「イギリスの音楽」として、バロックと現代を結んでいる。
一方では、このコンビの成功が過去そのものへの関心を高め、直後に隆盛するオリジナル楽器復興運動の呼び水になったろうことも想像できる。それが、前半のピリオド演奏につながる。
二十世紀半ばのある演奏を軸にして、過去と現代の作曲、大昔と昨日と今日の演奏が、さまざまに環をなしてつながっている。種々の「時間」が多重に複合して流れて回り、共鳴しあう面白さ。その表層に「いま」がある。
望月&福田のコンビがアンコール曲にダウランドの「流れよ、わが涙」をブリテン編曲版で取りあげて演奏会を終らせたのは、山田治生さんが「秀逸」と評したとおり、「複合する時間」の環を象徴するものだった。
――そうだ、「クラシック音楽」の醍醐味の一端はこの、時間の多重な複合にこそあるのだ。
なんだかそんな気がしてきて、とても嬉しくなった。
荘村、福田、つのだなどの出演者がマイクで演奏曲を説明するのも、和やかでよい感じ。くり返すが、こういう音楽を適切なホールで聴けるのは幸せだ。
八月十八日(土)ひとの芸
ハクジュホールのギター・フェスタ、二日め。
後半の古沢巌&荘村清志によるダウランド~ヘンデル~ケルト・スピリッツ(加藤昌則編)、福田進一を加えたビートルズ・ナンバー(同じく加藤編)も、ブリテン諸島のメロディの豊穣さを味あわせてくれてよかったが、圧巻は前半のヴィアゾフスキーのソロ。
弦をはじく、こする、滑らせる、指先から多彩な音色と響きの小宇宙が繊細に紡ぎだされて、奥深く遠近感豊かな、緻密にして遠大な表現に驚かされる。
昨夜からの合奏つづきの合間にギター・ソロを聴くと、その凝集力と思索性の高さに呑まれる。
同じ独奏楽器でも、グランド・ピアノやオルガンは、楽器自体が強大な響きを出す。そのための剛性の強い安定したメカニズムをもっているけれど、ギターはそうではない。ピアノたちは人間の力に反応して機械的に増幅してくれるが、ギターはそこまで親切で確実な道具ではない。人の指先の「芸」がいのち。
その意味で、昨夜のリュートなどのピリオド楽器にとても近いということを、ヴィアゾフスキーは痛感させてくれた。曲はヴァイス、ヴァシリエフ、モンク、アサドの作品。
八月十九日(日)松本日帰りと夜の歌
日経新聞の仕事で、松本のサイトウキネン・フェスティバルへ日帰り。
東京同様のかんかん照りで、盆地の松本はたまらない暑さ。少し足を伸ばせば上高地の冷気が待っているけれど、金も暇もなし。松本には例年八月末近くに来るが、もう少し楽な気がする。
十六時開演だが、余裕を見て新宿十時発で十二時半着のスーパーあずさ。新宿のホームで東条碩夫さんに遭遇し、松本では階段の上り口で片山さんに出会う。なぜみなこれを選ぶのだ(笑)。
駅を出てまず、片山さんと一緒に駅前のタワーレコードへ。こんなとこまで来てコイツラは、と笑われそうだが、ほかでは在庫切れでここにしか残っていない輸入盤を買ってきてくれと、友人に頼まれたのだ。小さい店で国内盤ばかりなのに、たしかに売っていた。一九八七年録音。あるいはほぼそれ以来、ずっと店頭にあったんじゃあるまいか(店はもっと新しいので、別の店の在庫が回ってきたんだろうけど)。無事購入。
由緒正しい独立店などならともかく、全国共通のチェーンストアの棚に残っているというのも不思議な気がするが、だからこそ他県からでも在庫を知ることができたのだろうし、面白い。
そのあと、古本屋に行くという片山さんにくっついて歩いていたら、東条さんに再会。メシを食おうという話になり、市民芸術館わきの蕎麦屋に行ったが、有名店なので直射日光のなか、何人も行列して待っている。あきらめて近くのレストラン&カフェへ。
結局、東条さんと私は外へ出る気にもなれず開場までそこにいたが、片山さんは果敢に古本屋へ行かれた。
演目《火刑台上のジャンヌ・ダルク》の感想は仕事なので省略。十七時半頃に終って、十八時三十五分松本発の電車に乗る。
行きは今年も、かつて二年近く滞在した塩山の現場事務所跡を、その近くの踏切を通過したときに眺めた。
帰りは、今年は日帰りパターンなので回れなかったが、来年が例年のように平日の終演が遅い日で一泊パターンになるなら、長野回りで上田へ出て無言館――戦没画学生の作品を集めた美術館――を見に行きたいな、などと考えつつ帰京。
ところで、その無言館館主の窪島誠一郎が書いた、戦没作曲家尾崎宗吉の評伝『夜の歌』が出たそうだ(これはヴェトナム在住の友人に教えてもらった。日本の本の情報を海外から教えてもらうというのも、ネット時代ならでは)。
大震災の昨年、私が最も心動かされた音楽は山田一雄の《おほむたから》と尾崎宗吉のチェロとピアノのための小品、《夜の歌》だった。ともに敗戦直前、近代日本が崩壊するときに書かれた挽歌。
さすがの片山さんもこの本の出版はご存じなかったので、教えてさしあげた。さも自分で見つけたみたいな顔で、偉そうに(笑)。
その片山さんによると、ナクソスからもヤブロンスキー指揮で山田一雄作品集がでるそうで、《おほむたから》ももちろん収録。この発売も待ち遠しい。
八月二十三日(木)南チロルという場所
「気になるディスク」に、南チロルの温泉町メランのサロン・コンサートを当時の楽譜と楽器で再現した「メランの湯治音楽」というCDを載せる。
南チロルは現在イタリアに属しているが、かつてハプスブルク帝国領で、いまもドイツ語の強い地域。その帰属をめぐってオーストリアとの間に紛争が起きたこともあった。友人のご教示によると、今はメラーノとイタリア風に呼ばれるこの町も、その昔は皇妃エリーザベトお気に入りの保養地だったとか。
実際の演奏会とその録音が行われた町も、ドイツ語ではトプラッハ、イタリア語ではドッビアーコと呼ばれる、同じ南チロルの町だ。近年は、この地にゆかりの深いグスタフ・マーラーの名を冠した音楽週間が開かれることでも知られる。
オーストリアの放送局であるORFが録音を担当しているのは、この地域でのドイツ語の強さを示すのだろう。CDの曲目がウィンナ・ワルツとイタリア・オペラの名曲になっているのは、文化面での両属性の反映にちがいない。
ドッビアーコ/トプラッハは近年、グラモフォンのCDの録音場所として聴く機会が多い。どういう理由があるのかは知らないが、アバドやかれに近いイタリアの音楽家、マーラー室内管弦楽団などが登場する。この「メランの湯治音楽」を指揮しているシュタイネッカーも、同楽団のチェロ奏者出身である。
アバドはここに独伊の接点、さらには汎ヨーロッパ的な可能性を見ているような気もする。それが過去に向かえばハプスブルク帝国や皇妃エリーザベトへの追憶となり、未来へ向かえばEC的理想世界になるか。その結び目に「マーラー」があるような。
ひねた目で見れば、そんな理想主義ではなく、単に保養地として開発したいデベロッパーが関わっているだけ、かも知れないけれども。
マーラー室内管の出身者がつくったこのアルバムには、さまざまな過去と現在と未来がつまっている気がする。
八月二十七日(月)トリフォノフ!
待望のトリフォノフの新譜を聴いた。すげぇ。ナマにくらべると少し音がくぐもり、金属的になるのは仕方ないこととして、チャイコフスキーの協奏曲第一番は予想通り、圧倒的な躍動感。
激情と沈潜の鮮烈な入れ替わり。こういうテクニックの持ち主は、往々にして細部の追求に走って骨格を失い、軟体動物みたいな音楽になりかねないのだが、かれは構築力があって、骨組みがしっかりしている。激情と沈潜の両者に没入しながら自分の背中を冷静に見ているような、主観と客観の驚異的両立。
繊細微妙に変化するタッチのゾクゾクする玄妙さと、圧倒的なスピード感で敏捷に跳躍する響き。特に、電撃の走るようなトレモロの凄さは、今まで誰にも聴いたことがないような威力。しかも、ちっとも力任せじゃないのが凄い。まさに「トレモロの魔神」。
とにかく現時点でのトリフォノフは、希有の「音づくり」である。若い筋肉の鋭敏な柔らかさ、敏捷さ、それがすばらしい。十年後、二十年後にどんなピアノを弾くのか、それはわからないが、現時点ではモダンピアノ独特の臭みというものを完全に超越している。それが凄い。
音が「ガン!」じゃなくて「バッ!」と一瞬に跳ねていく俊敏さ(だからピアノ臭くない)は、まさに体操の金メダルクラス。おそろしく鋭敏で敏捷な、知性に満ちた筋肉。軽やかさがあって。
この曲は、一八九一年のカーネギー・ホールのこけら落としに、作曲家自らが指揮した事実に象徴されるように、いかにも二十世紀アメリカ的な大衆消費社会向きの、大ホールの大聴衆のための大音量の大技巧、大旋律の大協奏曲、の典型曲のように演奏されてきた。
ところが、トリフォノフにはそのようなイメージとは異なる「軽み」と敏捷さがある。大ホール向けの轟音とは別のピアニズムが、ここに花開いている。
マリインスキー・レーベルなのに、ゲルギエフと楽団が完全に引立て役で、あくまでトリフォノフが主役というつくりなのも当然。しかしオーケストラも有機的に連動していて、正直、いつものゲルギエフのスタイルよりも好きだ。
後半のソロ曲も鮮烈。協奏曲は一度ナマを聴いているだけに、あのときの衝撃を再確認する感覚で聴いたが、こちらは初聴きだけに、何処へ行くのかという予測不可能ぶりに鳥肌が立つ。チャイコフスキーの《ショパン風に》、ショパンの舟歌、最後のシューマン(リスト編)の《献呈》もすばらしいけど、圧倒的なのはシューベルトの歌曲のリスト編曲版。
異様な切迫感が、不思議な広がりと余裕(夜の深い暗闇と、死による解放のような…)のなかに展開されるドラマチックな《魔王》、一転して憧れと希望に満ちた《春の想い》の歌心、《ます》の軽やかな明るさときて、《水の上で歌う》でロマンチシズムが大爆発。
音に音が連なり、重なっていく、ただそれだけの動きが生む快感を、これだけの凄さで聴かせてもらったのは、ものすごく久しぶり。たぶん、トスカニーニのなにかを聴いて以来の、音による官能とエクスタシー。
そしておしまいに《白鳥の歌》からの《都会》。不安と戦慄に満ちた重低音。シューベルトの絶望とリストの暗闇が時代を超越して、どろどろと渦巻きながら炸裂する。
シューベルト歌曲のリスト編曲版を、ロシアのピアニストたちは伝統的に得意にしてきた気がする。そこには何か、ロシア文学の雄渾な流れと共通するものを感じるのだけれども、その「シューベルト/リスト」の伝統の、精華を聴かせてもらった気がする。やはり今年はシューベルトなのだ。♪なじかは知らねど。
トリフォノフのナマも、早くまた聴いてみたい。ヴァントの指揮みたいな姿勢で、完璧に脱力した腕から出る響きは、さらに純度が高い。
高速スライダーを投げる投手みたいなもので、この柔軟な筋肉を十年も二十年も維持できるとは思えないから、とにかくいま聴かなければ!
八月三十日(木)携帯にご注意
盗撮事件で逮捕される大人が多い。これだけ日常化すると、自分みたいなオヤジが携帯を手に持ったまま、街中や特にエスカレーターあたりに立つと、非常に危険な誤解を受ける可能性が高くなる。夏場は薄着でポケットが少ないので、携帯を手に持つクセがあるのだが、早急にやめないといけない。おかしな世の中。
しかもこうして書くこと自体、捕まったときのための言い訳を用意してるようにさえ見える……。
正直な話、私なぞはカメラまるで使わないので、カメラなし携帯の方がいい。カメラがつく前の携帯がとても軽かったことを考えると、今の技術ならもっと軽くできるはず。軽薄短小大好き人間。
カメラのレンズに見えて、じつは水鉄砲という携帯もいいかも。捕まえた方がびっくり。セミのおしっこみたいのが出る。なづけてセミション。セミホ。
八月三十一日(金)ドイツのソニー
「気になるディスク」に、ソル・ガベッタがマゼール&ミュンヘン・フィルと共演したショスタコーヴィチを載せる。
新録音を眺めていると、ソニーがクラシックに関するかぎり、完全にドイツの会社になっているのが面白い。アメリカ録音は、ヨーヨー・マがクロスオーヴァー的なアルバムをつくるくらいだろう。
ドイツ・グラモフォンのほうがよほどアメリカ色が濃くて、いつのまにか入れ替わっている。まあDGはアジア色も濃く、グローバル戦略というべきか。
Homeへ
九月一日(土)モンポウづくし
オペラシティのモンポウ演奏会へ。コンサートホール開館十五周年記念公演、そして今年はフェデリコ・モンポウ没後二十五周年にあたるそうだ。
午後三時に始まって三部構成、約三時間の長い演奏会。モンポウといえばピアノ独奏曲という印象が強いのだが、さまざまな編成の作品が演奏された。
第一部は村治佳織によるギター独奏曲と、遠藤真理と三浦友理枝によるチェロとピアノのための作品。第二部は三浦のピアノ独奏、鈴木優人のオルガン独奏、そしてアントニ・ロス・マルバ指揮、幸田浩子のソプラノと新国立劇場合唱団、オルガンによる《魂の歌》。
第三部ではマルバ指揮東京フィルによるオーケストラ曲で、ピアノ曲をロザンタールが編曲した《街道、ギター弾き、老いぼれ馬》、ソプラノ独唱による歌曲集《夢のたたかい》、そして与那城敬のバリトンと合唱を加えた宗教曲《インプロベリア》。
モンポウはオーケストレーションが苦手だったらしく、あとの二曲もマルバとマルケヴィチが手を加えたもの。
この作曲家らしい、繊細で内省的な音楽をたっぷりと聴けたが、そのなかで性格が異なり、強い印象を残したのは最後の《インプロベリア》。
受難日のミサの「とがめの交唱」に音楽をつけたもの。十字架にかけられるイエスが、人の忘恩をとがめ、なじる。
教会にこうした文言があることも知らなかったが、エジプトから救い出してやったのに、ファラオを紅海に沈めてやったのに、放浪中は食物をくだしてやったのに、その恩義を忘れて私を十字架にかけるのかという詞は、ちょっと意外な気がした。神の業績は神の子の業績、ということなのか…。
九月二日(日)小さなエゴのメロディ
片山杜秀さんの『線量計と機関銃』(アルテスパブリッシング)を読了。
縦横無尽に知識の海を駆けめぐり、現代日本を語るキーワードをひょいひょい釣り上げていく漁獲力、そしてそれを調理する料理力に今回も圧倒される。
ミュージックバードで月一回放送されている「片山杜秀のパンドラの箱」でのお話をほぼそのままに活字へ起こしたもので、それでこれほどの論理構成ができているのが凄い。過去のさまざまな事象と対照させつつ、三・一一以後の日本社会の問題を鮮やかに語っている。
先日取りあげた『未完のファシズム』のテーマ、「持たざる国の課題」は、戦後六十年を過ぎた平成日本にも形を変えて生きている。過去と現代の合せ鏡。その意味で、二冊とも読んだ方がそれぞれをより深く理解できる。
それにしても、登場する音楽の演奏家の大部分は、私などは名前さえ知らない人ばかり(笑)。
さて、このなかで特に印象的だったのは、吉田秀和が一九七三年秋の石油ショックについて、安保以上の事件だと書いていたということ。
安保闘争や学生運動というのは、保革のどちらであれ、主張と手段の正否はどうあれ、根本にあるのは個人的な欲ではなかった。しかし石油ショックによって起きた、トイレットペーパーの不足の噂と買占め、価格上昇を見込んだ売惜しみなどは、個人の物欲が醜くむき出しになったものだった。
現実に飢餓に近い終戦直後とは違う。高度成長で物は豊かになったのに、心は比例しておらず、その貧しさ、利己主義がここで曝露されてしまった。それが吉田に衝撃を与えたのである。
石油ショックに前後して起きた、価値観が崩壊するような、足元が崩れるような「終末ブーム」は、子供だった私もはっきりと覚えている。いや、ようやく自我に気がつきだした十歳の子供が初めて体験した、大騒動の感覚だった。
「人類の進歩と調和」を謳った万博から一転、光化学スモッグやヘドロに象徴される公害問題、連続爆破事件などのテロ、恐怖のイメージしかない「新宿」など、社会不安が自分にも少しずつ見えていたところへ、石油ショックが来た。
これは子供の生活範囲では、大好きだったプラモデルの価格が石油高騰の波をもろに受けてどんどん値上がりする、切実な問題としてあらわれた。しかしそれ以上に、どうやら世界が有限らしいという恐怖の方が、大きかった。
この一九七三年秋というのは本当に不思議な時期で、もともと小松左京の『日本沈没』の大ブームが種をまいていたところで現実の石油ショックが起き、さらに『大予言』がベストセラーになって、二十六年後の一九九九年に世界が滅亡するという話が広まった。石油ショックでは三十年後に石油が枯渇するという予想もあって、ちょうど一九九九年と年代が近かったから、迫真感がました。
これらがシンクロし、共振して、終末ブームが起きた。「パニック映画」が次々とヒットし、「少年マガジン」にも永井豪の「バイオレンスジャック」や、松本零士の「ワダチ」など、終末を扱ったマンガがいくつも載った。一九七二年から「少年サンデー」に連載された梅図かずおの「漂流教室」も、もちろん忘れてはならない終末物だ(これらと同時につのだじろうの「うしろの百太郎」がオカルトホラーブームを巻き起こし、ユリ・ゲラーなどの超能力ブームや映画『エクソシスト』のヒットなどにつながることも、時代の気分をよく示している)。
この終末ブームは、当時小学生から中学生くらいの年代の心理に、深甚な影響を及ぼしている。一学年下の片山さんも間違いなくその一人だろう。
その影響はあとにも残った。一九七四年秋のアニメ『宇宙戦艦ヤマト』の、あと一年で人類が滅亡する地球という設定も、前年の終末ブームの反映にほかならない。二十年後のオウム真理教事件も、疑いなく終末ブームとオカルトブームが一世代に投げかけた影の、落し子だ。
誤差を承知でいうが、それらに共通する気分、前提として「地球規模、世界規模の人類の融和と共存は不可能」という絶望があったと思う。大人数の協力は無理なので、災害のさなかに取り残された少人数の集団がどうして生き残るか、いわば「ノアの方舟に乗るにはどうしたらよいか」がテーマだった。
その物語には当然、ある範囲の実力主義(超能力への憧憬はその埋め合わせだろう)、さらには利己主義を正当化する性質がひそんでいたといえなくもない。「大きな物語」が大災害とともに消滅したあとに生き残る、「小さな物語」としての実力主義と利己主義。小さな自己実現の幻想。
話がまた飛ぶが、終末ブーム世代が成長する七〇~八〇年代に、社会的地位と高収入が両立する職業として、弁護士と開業医がもてはやされていたのは、まさに「小さな自己実現」としての実力主義と利己主義の現れだった気がする。
人間性を云々することなく「試験に合格すればなれる」という基準が、受験戦争下の大衆社会ではとてもわかりやすかったのだ(官僚も同じか)。
吉田秀和は、物が飽和した社会におけるトイレットペーパーの買占めと売惜しみという現象に、この利己主義を既成事実化し、正当化する社会の端緒をみて、嫌悪したのではないか。吉田も炯眼、その一言を掬う片山さんもさすが。
残念なことに、バブルとその崩壊をへて、現在の高齢化社会の歪みと、そして原発公害に至る現象は、利己主義正当化の流れ以外の何ものでもない。
きっかけは石油ショック、か。
九月三日(月)ヤマカズ21
サントリーホールで日フィルを聴く。「山田和樹 コンチェルト・シリーズ」と名打たれた演奏会の第一回。
日フィルの正指揮者に就任した「二十一世紀のヤマカズ」こと、山田和樹が自ら企画したものという。
今日はピアノの小山実稚恵を独奏に、ラヴェルの協奏曲と「左手」、サン=サーンスの《死の舞踏》とラフマニノフのパガニーニ変奏曲。三つの協奏曲がすべて一九三〇年代の作品なのがいい。
ラヴェルの二曲をナマで続けると、いかに性格が異なるかが明瞭になって、とても勉強になった。小編成でジャズ風味をとりいれた軽妙な前者に対して、後者は編成がはるかに大きく、響きは後期ロマン派や国民楽派風に重厚で濃厚。作曲を並行して進めていたからこそ、意図的に対照的させたのだろう。
山田と小山の音楽性には後者の方が合っていて、硬さもとれたのか、鳴りがぐんとよくなっていた。その延長上にラフマニノフがあって、豊麗な色彩感、情感にみちた旋律など、とても楽しめた。
九月四日(火)乱歩と『新青年読本』
一九七三年、石油ショックに始まる終末ブーム最中の秋から年明け。小学五年生の私は、突然ラジオを聞きはじめた。
FMの音楽番組ではなくAM。野球中継でも若者向け深夜放送でもない(それらを聴くのは中学生になってから)。
ニッポン放送の平日夜九時から十五分間放送される、『日本沈没』のラジオドラマを聞き出したのだ。
夏頃から、カッパブックス版の原作がクラスで評判になっていた。何ページ目だかの、セックスシーンと火山の噴火を組み合わせたイラストが、色気づきはじめた男子小学生たちのリビドーを刺激したことも大きく、何かといえばタイトルとそのページ数を叫んでいた。
そのドラマをラジオでやっていると、クラス仲間の、三段跳びの小掛照二氏の息子に教わって、何人かで聞きはじめたのだ。映画が年末、テレビドラマは翌年秋だから、それらに先んじていた。
正直、内容を理解できていたとはいえない。地鳴りの効果音に群衆の悲鳴が重なり、「頭痛にノーシンがお送りする…にっぽん ちんぼつ」と入る、冒頭のナレーションしか覚えていない。
途中からは、そのあと十時までに放送されるほかの番組の方が面白くなり、それらだけ聞くようになった。
当時はまだ、一人のパーソナリティが数時間を担当するワイド番組ではなく、十分か十五分の長さの独立した帯番組が四つか五つ続く、古いスタイルだった。「西に東にその名も高く」の「豪傑マンの歌」で始まる『愛川欽也のラジオ劇画 立川文庫』、九時四十分からの『欽ちゃんのドンといってみよう!』こと、略して『欽ドン』(これは大ヒット中で、七五年にはテレビ番組に発展する)。
そして九時五十分からの十分間が「あなた、いくつ顔をお持ちですか。え、ウチヅラにソトヅラに…(略)。この男、素顔は一つ。仮面は、世間の悪徳の数だけ」のナレーションで始まる、『オリベッティ劇場 怪人二十面相』だった。
しかし『怪人二十面相』といいながら少年探偵団ものではなかった。江戸川乱歩の少年向けではない作品を自由に脚色していて、たしか聞きはじめた頃が『孤島の鬼』で、『芋虫』も聞いた。「ことうの おに」「いもむし」といったタイトルコールが、それだけで不気味だった(ウィキペディアによると、小山田宗徳の声だったらしい)。
そういえば、夏木陽介が明智を演じて七二年にNHKが放映した『明智探偵事務所』も、少年探偵団ものではないのに二十面相(米倉斉加年)が登場した。オープンタイプの空色のフォルクスワーゲンで逃げる二十面相の姿が、おぼろな記憶にある。昭和三十年代の映画やラジオで少年探偵団ものが大人気だったから、その世代が成長した七〇年代にも、広く支持を得るのに二十面相が欠かせなかったのかも知れない(とはいえこの番組、低視聴率で叩かれていたけれども)。
話をラジオ番組に戻す。
私はこの番組がきっかけで、乱歩に興味をもった。思春期の始まり、エログロを面白がりだす年齢だったからだ。『孤島の鬼』に伏せ字を見つけて妙にゾクゾクしたりした。『陰獣』や『人間椅子』は、そのタイトルに興奮した。しかし所詮は平凡な子供、情けないことに文章が難しすぎ、ポプラ社の少年探偵団もので満足するだけの結果に終った。
ただそのときに、乱歩のデビュー作や『陰獣』などの代表作が、おもに「新青年」という戦前の雑誌に掲載されたことを知った。なにか怪しげな存在として、「新青年」の名をおぼえたのである。
以上が長い前書き。ここから本題。
獅子文六を読みはじめて、かれの初期の執筆先も「新青年」であることを知った。陰惨な探偵小説雑誌と思っていたのに、パリ帰りのかれのようなモダンな作家も書いたことを意外に思った。
そして文六の全集で当時の作品を読んでいると、「新青年」はユーモア小説も載せれば探偵小説も載せる、当時の都市モダニズムの象徴みたいな雑誌らしいことがわかってきた。ほかにも後世に名を残す書き手がたくさんいたらしい。
少し前、少年倶楽部全盛期に編集長をつとめた加藤謙一の『少年倶楽部時代』を読んで面白かった。そこで「新青年」でも適当な参考書を探したら、『新青年読本』(「新青年」研究会編/作品社)というのがよさそうに思えたので、古書を購入して読んでみた。
A5判で三百三十六頁、そのうち約百頁は一九二〇年から五〇年までの「新青年」全巻の総目次にあてられ、あとは複数の著者がこの月刊誌三十年の歴史を、五つに区分して語っている。
初めは創刊から一九二四年まで。意外にも当初は地方の農村に住む堅実な青年向けで、堅い修養訓話、海外移民の勧めなどがメインだった。そこから脱皮をくり返すのが「新青年」の歴史だそうで、以後の隆盛の萌芽となる海外探偵小説の翻訳も、すでに載せられていた。
第二は二四年から二七年までの探偵小説時代。二三年に乱歩が『二銭銅貨』で華々しくデビューしたのをきっかけに、海外名作の翻訳に加えて、小酒井不木、甲賀三郎、夢野久作、横溝正史などの邦人作家の作品が次々と紹介された。「乱歩が載る探偵小説雑誌」のイメージは、この時期を指しているわけだ。
一方で谷譲次(本名長谷川海太郎、ほかに筆名は牧逸馬、林不忘)が自身のアメリカ体験による『めりけんじゃっぷ』連作を発表、モダニズムの先鞭をつけてもいる。岩崎昶などによるアメリカ映画の紹介と評論も、特徴となっていた。
第三は二七年から三七年まで。つまり昭和二年から十二年で、この時代が都市モダニズム誌としての絶頂期。きっかけは編集長が創刊以来の森下雨村から横溝正史に交替したこと。
横溝は「新青年を英語に翻訳すれば、モダンボーイである」という意味のことを就任直後に書いたそうだ。
戦後の『犬神家の一族』『八つ墓村』の因襲的なおどろおどろしい代表作のイメージからは意外だが、横溝も典型的なモボだったのだ。金田一耕助が戦前にアメリカに渡ってカレッジを卒業したという原作の設定は忘れられがちだが、まさしくモダニズムの残り香なのである。
背景には、東京の消費社会の発展と拡大がある。二四年の関東大震災の結果、近代都市化が加速し、浅草に代って銀座がモダンな繁華街として急伸するなか、その中心となったのは、山の手に住む勤め人(今でいうサラリーマン)などの新しい中間層だった。
「新青年」はそのなかでも、私立大学生とOBを主な読者とした。探偵小説とユーモア小説を柱に、ファッション、映画、スポーツなどをセンスよく紹介する「デパート雑誌」。パリとアメリカの娯楽文化がその光源で、獅子文六や久生十蘭、小栗虫太郎が華やかに活躍するのはこの時期のことである。
一方で、乱歩や谷譲次はほとんど書かなくなっていた。誌面の変化もあるが、かれらが売れっ子になり、「キング」や新聞など大部数の世界で活躍するようになったかららしい。百万部以上を売るそれらに較べ、「新青年」は三一年の絶頂期でも三万部という。本当に、都市部の限られた読者のものだったのだ。
第四は、三七年から四五年まで。日中戦争に始まる軍国主義と戦時体制の下、誌面は窮屈になっていく。探偵小説が書きにくくなったため、軍事小説は当然として、秘境冒険ものもメインになるという展開は、とても興味深い。
第五は、四五年から五〇年まで。探偵小説に柱を戻すものの活力は失われ、新興の「宝石」などに読者を奪われる。
最後に連載していた横溝正史『八つ墓村』が未完のまま終刊になり、「宝石」に掲載誌を移して完結したという話は、時代の変化を象徴している。
以上のように、『新青年読本』は雑誌の歴史を都市文化と社会情勢の変遷に重ね、枝葉に触れつつ巧みに紹介する。多数の図版で、視覚的イメージもつかみやすい。紹介された作家たち、特に久生十蘭やユーモア小説のウッドハウスなどはきちんと読んでみたくなった。
一九八八年刊行で、戦後民主主義的言説や生硬なフェミニズムに古さを感じる部分もあるが、関係者が生存していた時代だけに、実感のこもった証言は貴重。
その後の「新青年」再評価の流れを紹介した鈴木貞実の一文も面白い。八〇年創刊の「ブルータス」はその精神の継承を謳うという。自分にはおよそ縁遠い雑誌だが(笑)、ほかにも八〇年代は二〇年代論が流行した時代だそうだ。
特に松山巖の『乱歩と東京』が面白そう。次はこれを買って読むことに。
九月六日(木)岩城メモリアル
モーストリークラシックの公演評のため、オペラシティで岩城宏之生誕八十年メモリアルコンサート。オーケストラアンサンブル金沢(OEK)をホスト・オーケストラとして、ゲスト多数の三部構成、三時間十五分の長丁場。井上道義、外山雄三、天沼裕子、山田和樹(ヤマカズ21)、渡辺俊幸が指揮。
外山雄三指揮で黛敏郎のスポーツ行進曲(例の日テレのアレ)をナマで聴き、ジュディ・オングのあの手を広げた有名なポーズと衣装をナマで見て、ヤマカズ21指揮OEKの伴奏で《魅せられて》を聴く機会があるとは思わなかった。
それにしてもヤマカズ21、大忙し。私も松本の「ジャンヌ・ダルク」に日フィル演奏会と、三週間で三回聴いているし、その間には話題のクセナキスの《オレスティア》もあった。単発の特別演奏会の多い、夏の音楽祭から演奏会シーズン開始の端境期だからこそだが、伸びるときにはこういう状況を切り抜ける必要があるのだろう。音楽好きの関心も、ここでぐんと高まったと思う。
今日指揮台に立った五人の指揮のなかでも、その若さにもかかわらず、音色と音響の精緻さにおいて際だっていた。東混を指揮した《水ヲ下サイ》の仕上げもさすがだった。
九月九日(日)夢遊病の女
新国立劇場オペラパレスで上演された藤原歌劇団の《夢遊病の女》を見る。
良演。特筆すべき感想なし。
九月十二日(水)乱歩と東京
松山巖の『乱歩と東京』を読む。
副題に「1920 都市の貌」とあるように、乱歩の作品を年代順に追いながら、その舞台となる東京の発展と変化、世相とからめていくもの。著者は芸大出身の建築家なので、当時の建物や街路への言及が多いが、それを入り口として、その変容が象徴する急激な近代都市化、生活環境と人間心理の砂漠化(たとえば『屋根裏の散歩者』や『人間椅子』の背景に、西洋化した住居と日本人の生活心理のズレと不安を見る)を、独創的な発想と資料渉猟によって読み解いていく。
第一章では、明智小五郎が初登場した『D坂の殺人事件』が取りあげられる。
その主要人物に共通する特徴として、著者は人間関係の希薄さをあげる。明智と語り役の「私」は地方出身と思しき独身の下宿住いで、特に親しくはない。行きつけの喫茶店で顏を合わせたとき探偵小説などの趣味的な話をするだけの、表面的な――現代的な――関係なのだ。
著者はここに、一九二五(大正十四)年の作品発表(もちろん「新青年」に掲載)当時の東京における、地方出身者の急激な増大の影響を見る。
それまでは一%程度の人口増加率は、一九一七年に突然、十四・五%に跳ねあがっていた。数にして実に四十二万人。その後も、平均して四、五%の高い増加率が、昭和初年まで維持された。もちろん、第一次世界大戦による好景気がきっかけである。
この結果、一九一二(大正元)年に約二百八十万だった東京の人口は、その後の二十年でほぼ倍増する。昭和初期の都市大衆社会の拡大の基盤には、こうした新規の流入層がいたのだ。
流入者が増えた東京の、希薄な人間関係の具体的な現れとして「東京人の目つきが以前より険しくなり、その反面、喧嘩が著しく減った」という意味の柳田國男の指摘を著者が引用するのは、じつに鮮やか。「江戸の華」だった喧嘩という肉体的な社交が、無言で険しい視線のやりとりに変化する。そして探偵小説は、その無言の観察と想像の闇から生れる。
そういえば、仙台の農家の次男坊で、高等小学校を出て地元で代用教員をしていた祖父が、にわかに東京に出て働きはじめたのは、まさに一九二〇年頃のことだった。乱歩の東京は、祖父の東京でもある。そして祖父が浅草よりも銀座を好み、やがて東京の西郊に家を構えたことは、この本が描く東京の変遷に沿う。
建築との絡みでは、乱歩の代表作『陰獣』と、同潤会アパートとの関連を指摘する第五章が面白い。作中の容疑者である大江春泥は、東京各所の貧民窟に転々と住居を借りていくのだが、その九か所すべてが、同潤会アパートの建設地に近いのである。
震災後、西洋のモダンな集合住宅を模してつくられた鉄筋コンクリートの同潤会アパートには、災害対策というだけでなく、貧民地域の生活環境を改善する役割も期待されていたのだ。
そのことが、まさに探偵小説のように鮮やかに謎解きされる快感。全編このような調子で、とても面白かった。さすがに名著といわれるにふさわしい。
ところでこの本、単行本を古書で買った。文庫にもなっているので、文庫偏愛者としてはそちらを選ぶつもりだったのだが、アマゾンのカスタマーレビューに「写真や図版が多いので単行本がいい」という意味のことが書いてあったので、なるほどと従うことにした。
あとで、在ヴェトナムの友人からも同様のアドヴァイスをもらったが、たしかにその通り。モノクロで影の多い古住宅の写真だから、文庫サイズでは見にくいだろう。原書はA5判である。
一九八四年初版で、発行所はPARCO出版。このデータも考えさせる。
四日の日記でも触れたように、八〇年代に起きた二〇年代論ブームの一つなのだ。そして出版社は、まさにこの時代を象徴するセゾン文化そのもの。
それまでのような、澁澤龍彦的というか唐十郎的というか新宿風というか、アングラな露悪趣味が強かった二〇年代への関心が、よりアカデミックな場所で展開された八〇年代。「戦前=軍国主義=暗黒」というステロタイプな左翼思考が力を失い、また同時に権威や正統への堅苦しい執着も薄れて、傍流やマニアックな対象を「面白がる」ことが許されはじめた時代。飽食感はまだないが、何となく懐が温かくなっていた時代。
一方では、大正以来の民間建築が、まだ街に残っていた最後の時代。この『乱歩と東京』に見える建物たちは、八六年刊行の藤森照信の『建築探偵の冒険』に出てくる建物と同様、バブル期の再開発によってほとんど姿を消している。
不幸にも、バブル景気の「手品の種」は土地という不動産だったわけで、その上に建つ古い建物たちは、土地の「有効利用」を阻む障碍物にすぎなくなった。そして、まさに砂上の楼閣のごとく、消えていったのだ。その貴重な観察記録。
戊辰の役、日露戦争、太平洋戦争と、近代日本は四十年毎の戦争で変質したという説がある。戦争ではないが、バブル突入もやはり変質期だったのか。
九月十四日(金)オルガンつきの至福
武蔵野市民文化会館の小ホールで、ソプラノのサンドリーヌ・ピオーの歌曲リサイタル。ピアノは名コンビのスーザン・マノフ。この秋、最も楽しみにしている演奏会の一つだったが、その期待を裏切らない、素晴らしい一夜。
フォーレ、メンデルスゾーン、ショーソン、R・シュトラウス、ヴァンサン・ブーショ、プーランクにブリテンというプログラムは、昨年のアルバム『夢のあとに』と、曲順は異なるがほぼ同じ。フランス語とドイツ語の歌詞を交互に歌いわけ、そして最後に英語と、自在にそれぞれの響きの澄んだ美しさと余韻の違いを味あわせてくれた。
純音楽的、といってもいい前半の四人の作品の歌唱に対し、ブーショに始まる後半はモノドラマ的な表情やしぐさをまじえ、より物語性を増す。この対照が鮮やか。マノフのピアノがまたお見事で、歌の背後の景色を次々と変化させつつ、遠近感豊かに描きだしていく。
そして、何よりも満員の客席の息をのませたのは、最後のブリテンの《彷徨いつつ思う》。ここでピオーは、ピアノに向いて歌うことで声をその弦に共鳴させる手法を用いるのだが、「小ホールなのにパイプオルガンがある」この会場の贅沢な特長を活用して、ピアノばかりか上方のオルガンのパイプにも共鳴させ、木霊のように摩訶不思議な反響の、いやとうてい言葉では形容できない、神秘的で奇蹟的な音の世界をつくりだしたのだ。
これぞナマの快感、醍醐味。あとでマノフに話を聞いてきた友人によると、リハのときにこのオルガンの存在に気づいて、さっそく試したのだという。
このあとに歌う予定のハクジュも王子ホールも、オルガンはついていない。武蔵野まできてよかった。ピオー・リサイタル《オルガンつき》。
演奏会後も友人たちと吉祥寺で愉しい会話と、美味い料理と酒を堪能。幸福。
九月十五日(日)はしご
トリフォニーでアルミンク指揮新日本フィルによるブラームスのドイツ・レクイエム。つづいてサントリーホールでシナイスキ指揮の東京交響楽団の、モーツァルトのピアノ協奏曲第二十七番(独奏ラーンキ)とショスタコーヴィチの交響曲第四番の演奏会。
良演。特筆すべき感想なし。
九月十七日(月)「モンサルヴァート家の人々」
二期会の《パルジファル》を東京文化会館で観る。クラウス・グート演出、飯守泰次郎と読売日本交響楽団の演奏。
病院やサナトリウムを思わせる、二階建ての装置。回り舞台を一貫して使用して、さまざまな登場人物の境遇と心理を事細かに描いていくことで、わかりやすい、飽きさせない演出だった。
物語の始まりを一九一四年のドイツにしたのが秀逸。いうまでもなく夏に第一次世界大戦が始まる年だが、同時に、その元旦はワーグナーの著作権が没後三十年で切れて、ドイツ各地で《パルジファル》が堰を切ったように上演され始めた日でもあった。著作権と同時に、作曲者によるこの作品のバイロイト以外での舞台上演の禁止条項も効力を失った、最初の日だったからである。
救済の約束の拡散と、凄惨な近代戦の二つが始まった年なのである。傷病兵、入院患者のような扮装をした聖杯騎士団は、第一幕後半の聖堂に入る舞台転換の音楽の、例の鐘が鳴り響く場面で、ラッパ式の蓄音機を前に椅子に座り、行儀よく聴いている。これはたぶん、トーマス・マンの『魔の山』の、結核療養所の患者たちが集会室にそろって蓄音機を聴く場面のパロディなのだろう。『魔の山』の物語の終りは第一次世界大戦の開始に設定されているから、うまく符合する。そしてマンの、ワーグナーに対する複雑な愛憎入り交じる感情は、そのままこの演出の基礎の一つを成している。
マンが育った、十九世紀的なドイツの市民社会が崩壊し、大衆社会と全体主義が到来する、ある「二十世紀の神話」として、物語は描かれる。父王ティトゥレルとその一族(アンフォルタスとクリングゾル)の物語は、『ブッテンブローク家の人々』ならぬ、『モンサルヴァート家の人々』のようでもある。
そういえば、ワーグナーの著作権が切れることは、ワーグナー家の収入基盤が失われて、バイロイト音楽祭の運営が不安定になることを意味する。その財源不足を補い、さらには毎年開催できるようにしてくれた――それまでは二年やると一年休み――のが、ナチス・ドイツだった。《パルジファル》の聖地の外への拡散は、この悲劇の始まりに位置する事件でもある。ドイツの演出家が《パルジファル》に近代ドイツの歴史と社会を重ねたくなるのは、物語構造の共通性だけでなく、もっと皮膚感覚の部分で、さまざまに似た匂いがあるのだろう。
バルセロナ、チューリヒの歌劇場との共同制作とのことだが、舞台も歌手の演技も、違和感なく視覚化してくれたことに感謝。
歌手ではアンフォルタス役の大沼徹、グルネマンツ役の山下浩司がとても充実した歌と演技を披露したし、パルジファル役の片寄純也も健闘した。
飯守泰次郎の指揮は、悠揚迫らぬテンポで、日本のワーグナー好きにはとても受けがいいが、私はやはり苦手。聖金曜日の音楽の叙情性などはさすがと思うけれど、フレーズの抑揚にメリハリが足りず、単調すぎると感じられた。純音楽的演奏ということもできるのだろうが…。
家へ帰って、ヤノフスキ指揮のペンタトーン盤の第三幕を聴きなおす。ケレン味なしに、最後などはわざとあっさりとやっているが、精妙な響きには鮮やかさと艶があり、美しい。
九月二十日(木)FOR ALL
ユニバーサルの新譜「最新決定盤ベートーヴェン・ベスト」。
バレンボイム指揮のベートーヴェンの交響曲全集につけたこの邦題、正直もう少し考えるべきだったと思う。
原題は「BEETHOVEN FOR ALL」。あのウェスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラがこのタイトルのもとに演奏するということには、とても切実な意味と願いと祈りが込められているはずで、これを「万人向け」という意味にとって「ベスト」と訳したのかも知れないが、ちょっと違うと思う。
国際情勢が緊迫し始めた今日の極東アジアにおいて、我々もけっして無関係ではなく…。
九月二十二日(土)ピノックのモーツァルト演奏会
紀尾井ホールで、ピノック指揮紀尾井シンフォニエッタによるモーツァルト演奏会。交響曲第三十六番「リンツ」、クラリネット協奏曲(独奏パトリック・メッシーナ)、交響曲第三十九番。
良演。特筆すべき感想なし。
九月二十四日(月)後ろ姿の美しき
スクロヴァチェフスキ指揮の読売日本交響楽団@サントリーホール。
後半の《トリスタンとイゾルデ》をヘンク・デ・フリーヘルが編曲した「オーケストラル・パッション」が圧倒的だった。聞きどころを約六十分、声楽抜きでまとめたものだが、ワーグナーのオーケストラ・マジックに心を揺さぶられた。
客観性を保って精妙に響かせていくミスターSのタクトに、献身的に応える読響の素晴らしいこと(あのコーラングレ!)。一週間前の同じオーケストラの響きとはまるで異なる、抑揚のはっきりした、言葉をしゃべるように歌うフレージングが生む立体感。
ワーグナーがどれほど巧妙に天才的に魔術師的に詐欺師的にものすごい音楽を書いたか、世にも稀な音の染物師にして織物師であったかが、声楽抜きのフル・オーケストラによって、明快になる。
なぜか《トリスタン》は、トルソのような上演の方が、その偉大さがよくわかる気がしないでもない。ワーグナー自身がほんとうに言ったのかどうか知らないが、これをそのまま舞台上演しても、出来の悪いパロディにしかならないというのは、ある程度まで真実のようだ。
現世には存在し得ない、あまりに巨大で儚い美と生の戦慄は、不完全な形の演奏にこそ、その影が、その暗示が、その例え話が、その木霊が、見えたり聴こえたりするような気がする。
少なくとも自分には、何年か前の「青いサカナ団」の縮小版とか、先日聴いたアンサンブル・カルペ・ティエムのCDとか、今日のミスターSの「オーケストラル・パッション」とかの方が、この世ならぬその後ろ姿を垣間見ることができた気がする。
ボダンツキ指揮の戦前メトのライヴ録音も、あの音質とカットの多さが、やはりトルソといえるし(笑)。
今日は前半一曲目の《魔弾の射手》序曲も精妙にして深い、聞き応えのある名演。《トリスタン》が海なら、その予告編であるこちらは森。二曲目のスクロヴァチェフスキのクラリネット協奏曲は、作品自体には自分はあまり集中できなかったけれど、今年七十歳の独奏ストルツマンの色気のある響きに感服。見た目も若いが、隣の指揮者が八十九歳だけに、さらに若く見える。
ともかく読響、カンブルランとスクロヴァチェフスキという二人のマエストロと継続的な関係を保っていることが、なんとも幸福。耳の至福。
九月二十九日(土)突然ジュウラニアン
久生十蘭、面白すぎ。こんな日本人離れした想像力をもつ作家がいたとは。
『新青年読本』に啓発されて、久生十蘭の小説を読んでみたのだが、驚いた。私は今まで、夢野久作や小栗虫太郎などを立ち読みするたびにその文体との相性の悪さを感じて挫折し、十蘭もかれらと似たようなものだろうと敬遠していたのだが、まるで間違っていた。この人の文体は、自然で恐ろしく蠱惑的である。
読んだのは、ちくま文庫版の「怪奇探偵小説傑作選〈3〉久生十蘭集」。
パリの安宿で食いつめた、日本人高等遊民の成れの果てを描く『黒い手帳』の暗いユーモア、箱根の芦ノ湖の華族の屋敷を舞台とする『湖畔』の頽廃美、欧州行き豪華客船が舞台の『予言』の映画的展開、オホーツクの孤島での『海豹島』の異形、中落合の聖母病院近くの洋館を舞台とする『ハムレット』の心理的迷宮などなど、全十三編(プラス一)、まさに万華鏡的に変化する名品ばかり。
戦前と戦後の作品が七対六とほぼ同数で、戦争という巨大な悲劇を間にはさんでなお、「新青年」的モダニズムの精神が継続していることが素晴らしい。
ジュウラニアンなる、熱狂的ファンが存在するだけのことはある。当時の日本人の中のほんとうにごく一部、大河の一滴くらいの割合なのだろうが、その怪奇趣味と国際感覚が混淆したモダニズムは凄い。
『新青年読本』に、日本の戦後の大衆小説が「外国」を取り込むのは五木寛之の『青年は荒野をめざす』以後のことだとあったが、その三十年も前に、十蘭はここまで進んでいたのだ。
「大衆」の範囲そのものが戦前と戦後で異なるとはいえ、トーキー映画の発展でパリやアメリカがとても身近になった時代だからこそ、谷譲次や獅子文六、そして十蘭のような渡航経験をもつ作家たちの活躍の場が「新青年」に開けたのだろう。大佛次郎が現代ものを書き出すのも、この頃ではなかったか。
付け焼き刃の俄かジュウラニアンと化して、いろいろ読みたくなる。とりあえずは東京を舞台に、日本、フランス、ヴェトナムを結ぶ『魔都』と、パリを舞台にした『十字街』の二大長編を買ってみる。この二作については、海野弘が解題本を一冊書いているので、それもあとで読んでみるつもり。
谷譲次もまだまるで読んでないし、ものをろくに知らない人間で、ほんとによかったと思う。この谷譲次こと長谷川海太郎は、その兄弟と併せて、存在そのものが面白そうだ。
十蘭も長谷川兄弟も、モダニズム全盛期の「新青年」の名編集長、水谷準と旧制函館中学の先輩後輩だったようで、このあたりの函館人脈の国際性というのも面白そう(少しあとに田中清玄や亀井勝一郎もいる)。
その国際性に関して、今回の短編集で気になったのが『地底獣国』の背景。
一九三九年の作品なのだが、当時のソ連におけるスターリンの粛清と恐怖政治の心理と気分がかなり正確に書いてあって、同時代の日本でも、実情がこんなにちゃんとわかっていたのかと驚いた。
そしてそれが知識自慢ではなく、物語の骨格をなしている。考えようによっては、日本の特高警察の手口をソ連に当てはめただけなのかも知れないが、それが正鵠を射てしまうあたりが、十蘭のすぐれた国際感覚の証明なのではないか。
当時の日本人はあんな無茶な戦争をやったくらいだから、よほど無知で夜郎自大な人たちのように思いがちなのだが、そうではなく、世界での位置をとてもよくわかっている(軍人も、エリートなら必ず海外での留学経験を持っていた)。
わかっていながら、なぜあの戦争になったのか。そんなことまで考えてみたくなる。
いずれにせよ、これからのジュウラニアン生活が楽しみ。
九月三十日(日)ホルン交響曲《英雄》
オペラシティでスクロヴァチェフスキ指揮の読響演奏会。ベートーヴェンの交響曲第二番&第三番《英雄》。
音がやや重く感じられたのは、三日連続で東京~横浜~東京という日程の最後だけに、ちょっとお疲れだったのかも。
しかし、低弦の雄弁で澄んだ響きは素晴らしく、それを基礎に骨格を構築し、細かく変化に富んだ抑揚をつけて各声部が立体的に、手応え確かな響きで鳴るのは快感だった。
白眉はエロイカの葬送行進曲の、その後半。深い悲劇性をはらむ演奏だった。これは初日の演奏を聴いた友人の斉藤啓介氏が指摘していたことだが、ホルンの「運命動機」を鮮やかに浮かび上がらせた効果は、今日も素晴らしかった。
その余韻か、スケルツォの最後でもホルンが遠雷のように、あえていえば「審判のラッパ」のように聞こえたのも、新鮮な体験。ベートーヴェンがこの曲のホルンに込めた意味を再考してみたくなった(となれば、終楽章のコーダのホルンはどうなるのだろうと期待したのだけれども、もう一つピンとこなかった。これも疲労のせいか?)。
ただし個人的にはベートーヴェンを、いかにエロイカとはいえ、十六型(だと思う。コントラバス八本だった)で鳴らすのは、大味な気がした。NHKホールならともかく、オペラシティだし。
とはいえ、前述の葬送行進曲の後半では弦の音が澄みきって、ただただ豊かで有機的な響きになって、そんなことを忘れさせたから、集中力の問題なのかも知れないが。
Homeへ
十月二日(火)まぼろしの東京駅
『新青年読本』や『乱歩と東京』やらを読んでいるうちに、同じように八〇年代に出た、過去を探検する本で思い出したのが藤森照信の『建築探偵の冒険』。
単行本は一九八六年、手元のちくま文庫版も八九年初版と、四半世紀前の古い本なのだが、いまはなぜか、あまり古い気がしない。
内容の面白さもあるが、たぶん、何よりもこの表紙絵(単行本も文庫も同じ)のせいだろう。
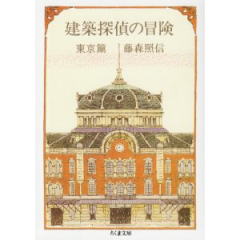
旬の話題だけにあちこちで見かける、復原された東京駅の丸の内駅舎の中央部分。それが描かれているので、妙に新鮮な感じがするのだ。
ところがこの絵の発表は二十六年前。安野光雅が辰野金吾の設計図から描き起こして、一九一四年の完成から四五年の空襲による被災まで存在した、往時の駅舎を再現したもの。
この絵が描かれた時点では、夢のまた夢の、失われた姿だった。
藤森は、本書内に転写した辰野の図面の下に「この絵に基づいて復原してほしい」と書き込んでいる。いまの読者は、まさにその通りに実現したと思うわけだが、当時そう書いた藤森は、はたしてその実現の可能性を信じていたろうか。
それどころか、本書の「全長335メートルの秘境」の章を読むと、取り壊して再開発される危険の方が、よほど大きかったことがわかってくる。国鉄にとってはそれが「宿願」だったらしいのだ。
まずは戦後まもなく、二十五階建ての高層ビルにする計画を出した。しかし巨大鉄骨の製造技術がないため、鉄筋コンクリート製二十五階建て(笑)という、「持たざる国」にふさわしい無謀な計画だったおかげで、話はつぶれた。
続いて七七年、日本の技術力でも高層建築が可能になった時代になって、美濃部都知事が国鉄の要望を容認し、いまの駅舎は「明治村にでも」移したらという恐しい提案をした。幸いにも激しい反対運動が起きて、国会まで勝負がもつれた挙句、再開発は一応延期になった。
その後、藤森たちの活躍もあって、時代の浅い近代の歴史的建造物にも、ようやく保存の機運が生じた。藤森が名づけた民家の「看板建築」(震災後にたてられた小規模な商店で、日本建築だが正面だけが張りぼての西洋風になっている)も、現地での保存は無理でも「江戸東京たてもの園」などに移築されて、生き長らえるようになった。
そうして東京駅も、この本から二十六年たって往時の駅舎が復原されたのだから、素晴らしい。藤森も感無量なのではないかと思う。
藤森は、往時の東京駅のデザインは、大の相撲好きの辰野博士が横綱の土俵入を写したもの、と確信しているという。
「大銀杏のような派手な屋根、両手をいっぱいにはり広げググッと腰を割った低い姿勢、クイッとアゴをあげ皇居を見据える中央玄関――そういわれるとそんな気になるでしょう」
「東京駅は、わが駅界の不世出の横綱です。それに、年をとって自然にハゲたわけじゃなくて、アメリカ部屋のB29に無理やり引っこ抜かれただけで、手当てをすれば生えてきます。あの八角ドームの大銀杏を結い直し、もう一度、皇居に向かって土俵入りをさせてあげるのが昭和という御代の締めくくりの仕事ではないでしょうか、みなさん!」
はたして大銀杏の横綱がそこにいるのかどうか、自分も近いうちに確かめに行きたいと思っているが、それはそれとして、この「全長335メートルの秘境」の章、いま読むと、また別の感慨もわいてくる。
章の後半に展開される「細部発見の紙上ツアー」、ここにあるのが、この復原によって逆に失われてしまった、私にとってはオリジナルよりよほど親しくなじんでいる、戦後昭和の東京駅の姿だからだ(笑)。
被災の結果、戦後の東京駅は八角ドームと三階部分を取り去ったが、これは本来、あくまで応急の修理工事だった(だから国鉄は建替えを望んだのだろう)。
工事を担当したのは、海軍航空隊に応召されていた技師たちで、復員のさい、飛行場に残っていた資材をいただいてきた。そして、物資が極度に不足した大戦末期の資材と工法を用いて、「五年持てばいい」という話でつくったという。
だから屋根は貧弱なスレート貼り、骨組みは太い角材が足りないので、代りに薄板をボルトで組み合わせて用いるという、戦中の飛行機倉庫そのまま。しかも内部のドームの材料は、零戦などでお馴染みのジュラルミン製(!)だという。
これが五年どころか、四十年後の八六年にもほぼそのまま使われていた。藤森はそこに「紙上ツアー」させてくれるのである。
日露戦争の「勝利」を記念してつくられた、「駅界の不世出の横綱」としての東京駅復活も素敵だけれど、「持たざる国」を象徴する、昭和後半の「まにあわせ」東京駅も、どこかに残しておいてもよかったような…。
ま、滅びしものは常に美しい、という繰り言にすぎないのだけれど。
十月十一日(木)グライムズ
随所で評判の新国立劇場の《ピーター・グライムズ》、やっと見てきた。なんか、ブログが炎上しちゃった人の話みたいだった。その今日性と普遍性と神話性に生命を与えた演出に、乾杯。
「ブログが炎上」といっても、これは私の個人的感想で、ヴィリー・デッカーの演出はそういう意味での「現代的」なものではなく、抽象化された、まさに神話的なものだった。北の、暗く荒涼とした海と漁村といった具象性はないが、そのぶん、観客側で勝手な想像を膨らませられるので、今日的ともなりうるのだ。物語自体が《ヴォツェック》や《軍人たち》よりもずっと、そうした今日性を保っているのだろう。ピーターが、自らを追いつめるものとして挙げる村人の「噂話」は、ネット社会における匿名の「真実」や「正義」の暴力によく似ている。
そして、孤立する側と秩序の側のどちらにも引け目と短所があり、それを忘れるために、かれらは興奮し、激怒する。「正しさ」が相対的なものでしかない世界を、演出は巧みに際立たせていた。
借りたプロダクションの場合、演出家本人は来ずに助手が代役ということも多いが、今回はデッカー本人が来ていたらしい。そのためか、合唱の一人一人の動きに精彩があって、見事な出来。新国の合唱は、最近の公演では響きとアンサンブルにどうも以前の冴えを失っているように感じていたが、動きの刺激が歌の方にも好作用をしたのか、今日は公演の主役になっていた。
十月十三日(土)合奏版クロイツェル
「気になるディスク」で紹介した、ヴァイトハースとカメラータ・ベルンによるベートーヴェンの弦楽四重奏曲第十一番《セリオーソ》と《クロイツェル・ソナタ》、現物が届いたので早速聴いた。
トニェッティ編曲の《クロイツェル・ソナタ》は、先日ブラッハーとマーラー室内管弦楽団の盤を聴いたばかりだが、あちらが独奏も合奏も硬質でキツメの音楽(いかにもベルリン風)なのに対し、躍動感と多彩な響きの変化があって、個人的にはずっと好み。《セリオーソ》も活力豊かで、これはよい買い物。
それにしてもこの編曲、トニェッティ本人の録音がないらしいのが面白い。色々と録音のある人なのに、不思議。
十月十四日(日)《パウルス》
鈴木雅明指揮BCJによるメンデルスゾーンのオラトリオ《パウルス》をオペラシティで聴く。素晴らしい公演で、さまざまなヒントを与えてくれた。
ここ数年、ナマの演奏会を聴く回数が増えて、いちばん教わったのは、オラトリオという形式のもつ重要性かも知れない。録音を通してでは、何だか大編成の単調な音の塊という印象が強く、自分には親しみのない聖書の物語が多いこともあって、縁遠かった。通常のドイツ中心の音楽史観では、それほど重視されていないこともある。
しかし、ナマでその規模と響きの大きさを身体で感じ、合唱と独唱と管弦楽のやりとりを目で見てみると、これが北方のプロテスタンティズムが生んだ十八~十九世紀の市民社会と、密接に関連するものだと実感するようになってきた。
ヘンデルのいるロンドンが、まずその震源。ヘンデルがイタリア語のオペラから英語のオラトリオに転じたのは、ロンドンの市民社会にこの形式の方が合っていたから。オペラだけだったらいったん忘れられた可能性も高かったと思うが、オラトリオは時代を越え、作曲者の死後もイギリスの市民社会に根づいた。
その影響は、プロテスタント圏を中心にドイツの市民社会にも及んでいった。なかでもメンデルスゾーンは、まさにドイツ市民のためのオラトリオ作家になろうとした人だった。晩年の代表作《エリヤ(エリアス)》、未完の遺作《キリスト》、寿命が尽きなければさらに増えていたはずで、ワーグナーのドイツ・オペラ運動と拮抗する、ドイツ・オラトリオの雄になっていたかも知れない。
一八三六年デュッセルドルフで初演の《パウルス》は、その第一作。パウルスとはキリスト磔刑後に入信し、使徒となって殉教した聖パウロのドイツ語表記。
ヘンデル風の壮麗さと同時に、バッハの受難曲の厳しさを併せようとしているのが、とても面白い。登場人物が異教徒の迫害をうける場面の音楽は、福音史家風のテノールといい合唱の迫力といい、もろに受難曲風なのだ。ヘンデルはドイツ人とはいえ、そのオラトリオはあくまでイギリス産。ではドイツ伝統のオラトリオはないのか、そうだ、バッハの受難曲があるじゃないか、とメンデルスゾーンは考えたのではないか。
この初演より七年前の、有名なマタイ受難曲の蘇演そのものが、ドイツの市民社会のための音楽形式を探す過程で、二十歳のメンデルスゾーンが見つけたものだったのでは、という気がしてきた。
重要なのは、この蘇演が通常のコンサートホールで行われたこと。受難曲を教会ではなく演奏会場でやるのは、現代人が思うよりも、はるかに大きな発想の転換だったはずだ。
そして、バッハがあくまで教会のために書いた受難曲を世俗の演奏会場に引っぱりだしたことには、ヘンデルのオラトリオのような市民のための作品がドイツにも存在していることを示す意味があったのではないか。
バッハが「神の子」の受難を描いたのに対し、《パウルス》は受難を人間がなぞるものとしての、使徒の殉教を描く。神の受難から人の殉教への人間化と、教会から演奏会への音楽の俗化との照応。刑死を覚悟でエルサレム行きを決意するパウルスの言葉には、いかにもドイツ人好みの自己犠牲、英雄死の悲壮美が満ちている。
その一方で、ヘンデルの壮麗さもばっちりとりいれる。最後は合唱、独唱、大管弦楽すべてによる壮大な総奏。この機能的な「総動員」こそ、市民社会から国民国家への発展を予言するもの。しかもオーケストラは百年前よりもはるかに進歩拡大しているし、旋律美も明快。第四十二曲だったか、「お身を大切に」と人々が歌うところ、バッハならフーガにしそうなのに、SATBの独唱が順繰りにその旋律を歌いわけたところなどは、じつにロマン派的で、美しい処理。主や聖霊の言葉が厳かなバスではなく、女声合唱やソプラノ・ソロで清げに歌われたのも、やはりロマン的で微笑ましかった。
ピリオド楽器による純度の高い演奏もとてもよかった。モダン楽器なら高すぎ大きすぎ強すぎ、威圧的に響くだろうバランスが、とても適切だった。特にナチュラルホルンやトランペット、オフィクレイド(佐伯茂樹さんが吹いた)などの金管が、とかく弱点になりがちな音程の精度にも問題なく、謙虚な響きだったのが、じつに心地よし。もちろん合唱と独唱も澄んだ響きで、さすがの出来。
さて二週間後には、尾高忠明&東響でウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》を聴く予定。ヘンデルから二世紀、メンデルスゾーンから一世紀をへて、第一次世界大戦後の二十世紀のモダンな大衆社会に生れた、弱者が富者への復讐を絶叫する、黙示録のオラトリオ。
二年前の二〇一〇年十月に尾高&日フィルでこの曲を聴いたのが、オラトリオが気になりだすきっかけの一つだった。今度はどう聴こえるか、楽しみ。
十月十五日(月)ワーグナーの合唱のオラトリオ性
メンデルスゾーンのオラトリオに関連した思いつき。
オラトリオは作曲家と市民社会との結びつきを示すもので、その社会とは、キリスト教を道徳の基盤とする共同体。だからオラトリオの題材は、旧約なり新約なりの聖書の世界になる。言葉と宗教性をもつものだけに、作曲家のアイデンティティを、明確に示すことになる。だがオペラのように自由な題材を選べないことが、やがて足かせになっていく。
ひるがえってワーグナーの作品を考えてみると、そこに出てくる「合唱」というのは、キリスト教社会に属していることが多い。合唱が大活躍する前期の歌劇ではそれが顕著で、《さまよえるオランダ人》《タンホイザー》《ローエングリン》、どれもキリスト教の倫理に背いた破戒者を主人公に、合唱はその周囲の、因襲的なキリスト教社会と秩序を象徴している。《ローエングリン》の外題役は破戒者ではないが、ヒロインのエルザは「本質を知りたい」という、あらゆる科学の萌芽となる根源的欲求をもつ、よくいえば人文主義者の原型的女性で、それゆえ最後は共同体に不利益をもたらす。
しかし北欧神話世界を描いた《ニーベルングの指環》で、状況は変る。最初に歌詞が書かれた《神々の黄昏》の第二幕以外、合唱が活躍する場面はない。
ワーグナーは、合唱という無個性な集団を排除し、独立した個人だけを出そうと考えた。その意志は、ラインの乙女とワルキューレに個々の名前を与えたことに象徴される。
なるほどと思う一方、合唱の排除と、非キリスト教の世界を扱ったことは、けっして無関係ではあるまい。やはり合唱の重要性が小さい《トリスタンとイゾルデ》は中世の伝説だが、ここにもキリスト教の存在は、ほとんど感じられない。倫理も背徳の意識も、特定の宗教との関係性は薄い。より抽象化された、人間同士の関係においての、近代的な感覚だ。「いつの時代にもありうること」「つねにいま起きていること」という点、《トリスタン》も「伝説」ではなく「神話」なのだ。
これに対し、後期でも合唱が活躍する作品では、とたんにキリスト教の色彩が濃厚になる。《パルジファル》の合唱はいうまでもなく聖杯騎士団だし――一方で、花の乙女たちは名無しの集団に戻ってしまった――、《ニュルンベルクのマイスタージンガー》の市民の合唱の歌詞には、キリスト教やら聖人やらにちなむ内容が、かなりの割合を占める。
合唱とはつまるところ市民の聖歌隊である、という原則が、ワーグナーにも強く存在していたように思える。オラトリオ的な市民音楽の感覚、ともいえるのではないか。
この視点から各国オペラの合唱の位置づけを考えてみると、面白いかも。
十月十六日(火)浪費と後悔のためでなく
九月十三日の「気になるディスク」で紹介した、ジョナサン・ビスとエリアス弦楽四重奏団のシューマンとドヴォルジャークのピアノ五重奏曲集(ONYX)を聴く。特に後者が素晴らしい。
刺激的でない、コクのある渋めの響きなのに、風のような爽快感、通気性の良さがあって、苦手のドヴォルジャークの音楽をこんなに楽しめるとは。爽やかなロマンの美。曲自体もたしかに傑作だと教えてもらった。
このほか、ヴァイルとターフェルムジーク・バロック管の《イタリア》と《エロイカ》も、ピリオドとは思えぬ確かな骨格と、抑揚と句読点の打ち方が見事な演奏で◎。あと、ポール・ルイスのシューベルトも予想通りの「激烈なるシューベルト」で、とても面白かった。
夜はトリフォニーでエフゲニー・スドビンのピアノ・リサイタル。スカルラッティやスクリャービンなど、ホロヴィッツが得意とした作曲家が並ぶ。魔性というより、明晰で澄んだ、知的な演奏。
十月十八日(木)若松監督の死
映画監督の若松孝二氏の死去を知る。十二日夜にタクシーにはねられたという話を十六日のニュースで見て心配していたが、十七日に亡くなられた。
私が間近でお話をうかがえたのはほんの数回だが、訥弁の中にも鋭く、感性豊かな言葉が光って、鮮やかな印象となって残っている。最後にお会いしたのは二か月ほど前の八月。
監督が一流の役者にしたといっていい井浦新(ARATA)のこと、七〇年前後の新宿ゴールデン街の思い出、そしてなによりも、撮ることのなかった原発批判の映画の構想、そのラストシーン…。
現役のままで逝かれたことは本望だろう、取りあえずは、そう信じる。
十月二十日(土)言葉のないオラトリオ
池袋の東京芸術劇場で、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団演奏会。
オール・ラヴェルで、前半が《マ・メール・ロワ》、後半が《ダフニスとクロエ》全曲。表現をぐっと抑制した前半とは対照的に、後半は色彩と音響のマジック全開。ラヴェルの天才的オーケストレーションを堪能させてもらう。カンブルラン、絶好調が続いている。
それにしてもこの曲、全曲だと合唱が大活躍。ピットにとても入りそうもない大編成の管弦楽といい、まさに綜合芸術としてのバレエ。
これだけたくさん歌うのに、まったく歌詞がないのも凄いことだと思う。「はじめに言葉があった」というキリスト教の論理重視から離れた、「言葉のないオラトリオ」のようにも感じられた。
それは、新国立劇場合唱団の好演のたまものだが、新装なった芸術劇場のホールの音響の変化も、有利に作用したように思う。改装前は視覚的にも音響的にもやや冷たく感じて、正直それほど好きになれなかったが、今日は電灯色のような温かさを、艶を消した壁面にも、そしてその響きにも感じた。
パイプオルガンを覆い隠す形で反響板を設置したことが、音の実在感を増すことにつながっているようだ。
これからは、このホールに来ることが楽しみになりそう。
十月二十四日(水)ロマン派二夜
朝は、青山葬儀所で行われた若松監督の葬儀に行く。六百人が参列したそうだが、過度の演出もなく、しめやかに。
夜は紀尾井ホールで、ペーター・レーゼルとクァルテット・エクセルシオの演奏会(シューベルトの《死と乙女》とシューマンのピアノ五重奏曲)。昨夜も浜離宮朝日ホールでバリトンのローマン・トレーケルと原田英代のドイツ・リート(シューベルト、ブラームス、シューマン)の夕べを聴いているので、二夜続きで「ドイツ・ロマン派がっしりの夜」。
二晩とも、一音たりともゆるがせにしない、正攻法の解釈。なかでは、トレーケルの《詩人の恋》が漆黒の狂気といった風情で、ひきこまれた。アンコールのメンデルスゾーンの《歌の翼に》も、私などは女声の印象が強かったのだが、バリトン歌唱にも黒光りするような美しさがあることに驚く。
十月二十五日(木)大人の音楽
「気になるディスク」に、ウィスペルウェイ三回めのバッハの無伴奏チェロ組曲全曲を取りあげる。また無伴奏か、などと思いつつ聴きだしたら、あまりに深くて豊潤な、素晴らしい音楽に驚嘆したため。
モダン・ピッチより全音低いカンマー・ピッチ(ヴェルサイユ・ピッチとも同じ)によるチェロの響きが、実にいい。これだけ低いピッチでも、音が濁ったりぶれたりせず、滑舌よく明晰に語りかけてくる、技術の物凄さ。
たった一台の楽器が生み出す、作品、作曲家、演奏家自身との対話。聴きての心の水面に、静かに起こる波紋。
五十歳記念の、十四年ぶりの録音だという。つまり私と同学年なのだが、ここにあるのは、本物の大人の音楽だ。
若者でも老人でもない、大人(オトナと読んでもタイジンと読んでもよし)、すなわち賢者の音楽。クラシックの演奏では、案外聴くことの出来ないもの――すぐれた若者や老人は、たくさんいるけれど。
三十代でも八十代でもない、五十代の大人がつくる音楽の、ちから。
十月二十七日(土)奏法をめぐって
本日の日経新聞朝刊の最終面文化欄の記事「ベートーベン 奏法の変遷」に、私のコメントを紹介していただいた。
ありがたいことだが、字数制限の中で要約された形だと、私の言いたかったこととは少しニュアンスが変っている。
そこで、コメントの元になったメールに書いた該当部分を、ここに引用しておく。ほとんど推敲せずに書いたので、言葉足らずでわかりにくい部分もあると思うがご容赦を。ごくわずか、原文の字句を変更している。
(ベートーベンは)古典派のしめくくりでもあるけれども、同時にロマン派の始まり、元祖でもある。ロマン派というのは現代の演奏会、興行システム(オーケストラの規模、ホールの大きさなども含め)を決定づけているもので、いわばベートーヴェンを目標にして、それらが成り立ってきた、拡大発展されてきたといってもいい。「精神的な大きさ」をそのまま「物理的な大きさ」におきかえてしまってよかった、幸福な幻想の時代ですね。
だから、倍管も含めた巨大な編成、ロマン派風の演奏も大いにありえた。アメリカにおける交響楽団の組織の発展は、その代表ですね。
ヤンソンス&バイエルン放響などは、その十九、二十世紀的なシステムをそのまま受け継いでいる。サントリーホールやそれ以上の大きなホールには、それがあっている。
その一方に、それをやりすぎと考えて、ピリオド様式がベートーヴェンでも八〇年代くらいから隆盛してきた。
ただ、その実践を通じて、ベートーヴェンには時代を超えてしまっている部分も大きくあって、純粋なピリオド楽器だと、その大きさを表現しきれないところもあると、わかってきた。
物理的な限界が、精神面での表現の限界にもつながってしまうという弱点ですね。
ヤルヴィがやっているような、モダンの室内オケがピリオド様式をとりいれるという折衷様式は、その点で現在の一つの「落しどころ」かな、と思っています。純粋主義者には、中途半端と嫌う人もいますけれど。
ホールの大きさ、あえていえば聴衆の教養のもち方、それらに応じて変化していいのでは、と思っています。
十月二十八日(日)黙示録の饗宴
サントリーホールで尾高忠明指揮の東京交響楽団定期演奏会。曲目的に、この数か月でいちばん楽しみにしていた演奏会の一つ。共演はローマン・トレーケル(バリトン)と、東響コーラス。
・武満徹:波の盆(TV音楽の演奏会用編曲版)
・マーラー:リュッケルトによる五つの詩
・ウォルトン:オラトリオ《ベルシャザールの饗宴》
どれも好きな曲だし、尾高さんの得意とするジャンルなので期待していたが、実際に聴くと、予想以上に三曲の関連性がよくわかった。選曲センスの勝利。
それは《ベルシャザールの饗宴》は当然として、他の二曲にも「最後の審判」を想起させる部分があることだった。
《波の盆》は、ハワイ移民の日系一世を主人公とする一九八三年のテレビ・ドラマ。この時期の武満の音楽はとても甘美で、この音楽のメイン・テーマも、アメリカのスタンダード曲やイギリス民謡のようにわかりやすく、親しみやすい。ハワイ移民が主人公ということを意識しているのだろうが、印象的だったのは、第四曲〈夜の影〉の、太平洋戦争を回想する場面で派手に鳴り響くマーチ。
もろにアメリカンな、ゴージャスな響きで、終戦直後の思春期の武満が全身で感じただろう、進駐軍、マッカーサー、星条旗、そういったものの、キラキラとカラフルに輝く力強いイメージが、一瞬に噴き出してくるようだった。
それがタイトル通りの、不安げな夜の響きの中に唐突に挿入されるのは、甘美なアイヴズという趣で面白かったのだけれども、あとでウォルトンの作品に似たような響きを聴いているとき、あのマーチも最後の審判の音楽、神のラッパなのじゃないか、と思い浮かんだ。
最後の審判といっても、「法事だけ仏教」の無宗教の日本にふさわしく、キリスト教的でも預言的でもない。「黙示録の神の軍勢」は、二十世紀後半の日本人が想像できる範囲では、戦後民主主義の時代に思い知った、アメリカの圧倒的なパワーと物量に、おきかえられるのではないか。約十八分のなかの、ほんの数十秒のあのマーチには、それくらいの力があった。それは、黒船以来百五十年の、アメリカと日本の力関係を象徴するものともいえた。
続く《リュッケルトによる五つの詩》での「審判のラッパ」は、終曲の〈真夜中に〉の最後に出てくる。夜中に一人であれこれ思い悩んでも解決策の見つからない、人類の苦しみ。それを詩人リュッケルトは、神の手に委ねることにする。
そのとき、《復活》交響曲の終楽章のハルマゲドンを想わせる、神のラッパが高らかに鳴り響く。
日本的に変形されたもの、次に十九世紀ロマン派の詩人と音楽家が黙想したものときて、いよいよ黙示録音楽の本家本元、《ベルシャザールの饗宴》。
これはやはり、ウォルトンの大傑作。一九四七年にカラヤンが「この五十年間で最高の合唱曲」といったというのも、むべなるかな。ヘンデル以来二百年のイギリス国民音楽としてのオラトリオの歴史をしめくくる、総決算。
ここで歌っているのはもはや、ヘンデルやエルガーの曲の場合のような、キリスト教的道徳を賛美する市民ではない。現世の強者と富者を呪い、うらやみ、神が圧倒的な力でかれらを滅ぼすことを願って、弱者たちが絶叫する。
二年前、同じ尾高指揮日フィルの演奏会で、何の予備知識もなくこの作品を初めて聴いて、旧約聖書が題材と解説にあるのに、後半がそこから離れた、D・H・ロレンスの『黙示録論 現代人は愛しうるか』に出てくるヨハネ黙示録の、弱者の怨念と神による復讐の世界そのものであることに、とても驚いた。
このことはこの「可変日記」の二〇一〇年十月二十三日の欄に書いたので繰り返しは避けるが、とにかく《ベルシャザールの饗宴》とロレンスの『黙示録論』が、同じ一九三〇年前後に生れているということが、非常に面白かった。
まったくの偶然のシンクロなのに、両者が互いを説明しあい、より生々しく、切実なものへ深めあっている。早い話、福田恆存訳の『黙示録論』を読んでいなかったら、《饗宴》を聴いても、ただ壮大な音楽と思っただけだろう。旧約聖書に黙示録をくっつけた、つまり伝説上のバビロンと預言上の大淫婦バビロン、過去と現在=未来の二つの都を重ねあわせた、ヌエのような音楽だと、私などはとても気がつきもしなかったろう。
精神的強者キリストの「愛の宗教」とは無縁の、精神と物理両面の弱者たちの怨嗟と復讐の願望を描く書としての、ヨハネ黙示録。そのことが、この二作を並べると痛いほどよくわかる。
その二つが片やアメリカの物質文明と大恐慌、片やロシア革命にファシズム、ポピュリズムの醜さがむき出しになった一九三〇年に登場する、面白さ。
ヤコブの神にむかって喜びの声をあげよ。
地の王たちが嘆き悲しみ、
地の商人たちが泣きわめいて衣服をひきさいているときに。
ヤコブの神にむかって喜びの声をあげよ。
バビロンの栄華は崩壊したのだから。
ハレルヤ!
(三浦淳史訳)
今日は自分にとって二回目の体験だったし、大友直人のエルガー・オラトリオ・シリーズで経験を積んでいる東響コーラスが、さすがに純度の高い響きを聴かせてくれたので、ウォルトンの仕掛けをいくつか楽しむ余裕がもてた。
ほんとうに、最後のハレルヤ・コーラスの、禍々しく血なまぐさく、暴力的なこと! 二百年前のヘンデルのハレルヤ・コーラスから遠く隔たった、陰惨なパロディ。最後は大編成のオーケストラ、二百人の合唱、両サイドの高所にずらりと並んだバンダ、そしてパイプオルガンがごうごうと鳴り響き、耳をつんざく。
最後、ベートーヴェンの《運命》終楽章のあのしつこい「勝利の終結」を、これでもかと真似してみせた、ウォルトンのブラックユーモアも凄かった(笑)。
演奏会のあと、溜池山王駅へ歩いているときに頭に浮かんだ、昔の大河ドラマの一場面。
「リバノの山の杉の木のように、
高くそびえて見える人がいたとしても、
ごくわずかの時が過ぎ去れば、
そこには何も残りはしない。
かれらは一瞬のうちに、
泡のように消えてしまうだけだ。
何も恐れるな、助左。
主のお恵みを!」
(NHK大河ドラマ『黄金の日々』第三十七話「反逆」より。秀吉の伴天連退去令で追放されるフロイスが、刑死を覚悟で切支丹とともに日本にとどまる決意をのべたあと、主人公にかける言葉。脚本:市川森一)
これが弱者の怨念と復讐ではない、強きキリスト者の信念なのだ。きっと。
偶然だが、この作品の、大河史上でも屈指の傑作といわれるテーマ曲(池部晋一郎)の指揮も、若き日の尾高さんなのだった。不思議な環。ということで、DVDを引っぱりだして見る。
それにしても、空席が多かったことが残念。他会場での他の団体の公演とさんざんぶつかる日程で、しかも一日だけの公演とは、何ともったいない!
Homeへ
十一月六日(火)武器学校と三式中戦車
本屋をうろうろしていたら、目についたのが月刊「丸」の表紙。
自衛隊の土浦駐屯地の武器学校に保存されている、旧帝国陸軍の三式中戦車。陸軍が終戦直前にようやく完成させた、「M4シャーマンとどうにか戦える」戦車だが、本土決戦用に国内に温存され、実戦には出なかった。で、現存する一台が武器学校にある。

表紙はその写真なのだが、私にはものすごく懐かしい。いまから三十四年前の高一のころ、ガンマニアの友達に誘われて、常磐線とバスを乗り継いで、はるばる現物を見に行ったことがあるからだ。
戦車の陳列場所は昔と変ってないらしく、私もこの表紙とほとんど同一の構図で写真を撮った記憶がある。
しかし、あの頃と現代では、武器学校の見学のしかたは、かなり異なっているようだ。行ったのは春休みの平日だったと思うが、受付で姓名住所を書くだけで中に入ると、見学者は自分たち二人だけで、展示室内には監視員もおらず、完全な放置状態で自由に、というより勝手気ままに見て歩けた。
兵舎風、というかその類を転用したのではないかと思われる木造の火器展示室に入ると、古今東西の重機関銃や対戦車ライフルやバズーカやらの重火器が、細いチェーンを一本、引金の穴に通しただけで無造作に置いてあった。ピストルなどの軽火器はガラスケースの中で、手では触れなかった記憶があるから、重いものは盗難の危険度も低いと考え、むき出しにおいてあったのだろう。
無人だから触り放題。持ってみようとしたら、ものすごく重かった。こんなものを担いで山野を歩かされるのでは、おれはとても兵隊になれないと思った(当時はガリガリに痩せていて、五十キロなかった)。
外におかれた戦車数台の周囲も、やはり自分たち男子高校生二人のみ。
そこに「世界の戦車」とかそんな雑誌で見ていた三式中戦車の現物が、シャーマンの隣に座っていた。
吸いよせられるように砲塔に登ると、ハッチが開いているので内部に入った。エンジンや細かい装備はなくなっていたように思うが、砲架周囲のハンドルが残っていたので、思わず回すと砲塔が旋回しはじめた。写真の右側にある屋根の柱に砲身がコツンと当たったので、あわてて戻した(当時の屋根はもっとチャチで古びていて、あちこちさびていた)。
これは面白いと、隣のシャーマンにも乗りこんでみたら、すべて電気式でボタンしかなく、動かせなかった。日本のは手動式だから動かせる、という事実に気づいて、子供心に悲しくなった。
よくないイタズラだが、時効ということで勘弁してもらう。貴重な車両を傷つけたりしなくてよかった。
そのあと一、二年して、バカな武器ヲタ(オレラじゃないっス)が火器展示室のチェーンを切断、盗難事件を起し、その後は警備が厳重になったらしい。
この「丸」の記事にも「今回は特別に戦車の内部にカメラが入りました」みたいなことが書いてあるから、今は三式中戦車にも近づけないのだろう。
当然といえば当然。あの頃が牧歌的すぎた。武器学校を出ると、離れた平地に現用の74式戦車がいたので、またふらふらとそこへ行こうとしたら、そこは訓練用の敷地だったらしく、武器学校内とはうってかわって、警備兵がすっ飛んできて連れ戻された(もらろん、口調は優しかったが)。警備が緩いのは平日で見学者の少ない、武器学校の中だけだったのだろう。
出ると腹が空いたが、駐屯地の外はなにもなかった。そこで門前の自動販売機で友人が甘酒を買ったが、一口飲んだたけで「まずい!」と叫んで捨ててしまった。なによりも、なぜ奴が甘酒などを突然買ったのかが不思議だったが。
土浦駅前に出て、数少ないビルの一つの丸井デパートの食堂に入り、アイスを載せたホットケーキを食べた。いかにも地方都市という雰囲気だった土浦駅も、その後は行ったことがないが、今は様変わりしていることだろう。
十一月七日(水)よき人、よき奈良
NHKのBSプレミアムで放映された渋谷実監督の映画『好人好日』を録画して、久々に観る。騒がれることは決してない地味な作品だが、ひそかに愛するひとの少なくない、佳作。
主役の、世界的数学者だが変人という役(岡潔がモデル)を演じる笠智衆がいい。帝大近くの本郷の旅館として出てくるのが、現存する鳳明館がモデルかもと思っていたが、そうではなかった。坂下にある、ボロい下宿。なのに「飛雲閣」と、名前だけ立派なのが可笑しい。ここに登場する三木のり平がまたいい。
しかしなんといってもこの映画の大きな魅力は、一九六一年の奈良の景色を、鮮明なカラー映像で見られること。空の青と野山の緑、樹木の濃緑のなかにまぎれて浮ぶ、黒い甍の町。若草山あたりから眺めた遠景の場面に、特にひかれる。
ところで、NHKの番組サイトには渋谷監督のこともきちんと紹介してある。だが、代表作の一つが『気違い部落』だというのは、歴史的事実なのだが、やはりこういうところには書いていない。
問題になるのはタイトルだけで、中身は差別的なものではないだけに、残念。
話はそれるが、私は上原善広の著作の愛読者だが、「路地」を中上健次の小説に基づいて、被差別部落を指す用語にしていることは、どうも賛成できない。既成概念に染まっていない新たな用語がいるのなら、新規の造語をしてほしい。
これでは、部落を集落と言い換えねばならなくなったように、いまも古い街にはそこら中に、普通に残っている路地、露地を、公開の場ではそう呼べなくなってしまう可能性がある。
現在の消防法では、すり抜けるのがやっとの狭い路地は、次第に消えていくだろう。そうして、部落という古くからの集団生活の単位が、現代社会では村や町といった行政上の単位に包含されて具象性を失ったように、路地もまた何を指すのかわかりにくい、歴史的用語になっていくのだろうけれど、そのことと言葉として使えなくなるのは、問題が違う。
十一月八日(木)傑作『十字街』
久生十蘭の『魔都』と『十字街』、やっと読了。
時間を食ったのは、前者を寝床で読むと必ず「寝落ち」してしまい、進めなかったため。
『魔都』は十蘭初期の作品であるためか、後年のあの異様に澄んだ描写力がまだ身についてないようで、文章に無駄が多く、くどい。進まないので、寝てしまう。舞台となっている一九三四年の東京というのも、面白そうな場所がいくつか出ているのに、細部の描写にこだわるわりに、映画的にシーンが浮かぶような創造力をもってない。ストーリーも、最後はどうもまとまらなかったような印象。
一方、『十字街』は、これはとても面白かった。まごうかたなき傑作。こちらは五一年、早すぎる晩年の作品だけに、そこに出てくる三四年パリの景色と生態の、まあ生き生きと寒々と黒々と広々とうねうねと、不気味にうごめいていくこと。十蘭の三〇年代初期のパリ体験が、時間をへて見事に昇華され、空間がそのままドラマと化している。
この本を片手に、登場するパリの街角を歩いてみる愛読者がいるというのも、当然だ(もちろん、自分もいつかやってみたい)。自らのパリ生活体験をこれほどに巧みに、私小説ではない小説へ活用できた人は、少ないのではないか。
この、無慈悲でしかし蠱惑的なパリを舞台に、物語のテーマである三四年にフランスで現実に起きた「スタヴィスキー事件」が、どうやら十蘭の人生観の原点の一つと思しき、一〇年に起きた日本の大逆事件、そして『十字街』が五一年に朝日新聞に連載される二年前の下山事件と、徐々にネガになりボジになりしながら、三重写しのドラマになっていく。
この、三つのミステリアスな謀略事件が黙示するのは、顔も人格もない権力というものの、身勝手で得体の知れない、果てしない悪意と限度のない残忍さ。
それは底無しの闇のように人の五感を奪い、裸踊りをさせ、轢殺する。
それにしても戦後民主主義の時代、フランスが「自由の国」として、知識層を中心に日本人の憧れの対象になっていた五一年に、権力の醜さと一般人の無力はフランスでも同じという話を書く十蘭、フランス帰りのこの男の、なんたる人の悪さ! なんたる小説的批評力!
当時の日本人はきっと、居心地の悪さをまず先に感じたのではないか。
それに、パリをかなり知っている人でなければ、地図を見ながらでないとイメージがつかみにくい。新聞連載時の読者は、きっと置いてきぼりだったろう。
私が読んだのは朝日文芸文庫版だが、これは詳細なパリの略図がついていて、参照しながら読み進められるので、とても助かった。作者の年譜も詳しく、とても親切な、本好きのための本。
というわけで二冊読みおえ、買っておいた海野弘の「久生十蘭 ――『魔都』『十字街』解読」に、ようやく取りかかる。十蘭自身とこの二作の人物や舞台のモデルなどを語ってくれる本のようなので、楽しみ。
ところでアマゾンで「久生十蘭」と検索したら、大量の作品が「¥0 Kindle版」で並んでいた。ああ、こういう時代なのか。たしかに著作権切れているし。価格の有無(誰がもらうにせよ)が作者への「敬意」とは無関係になるのが、ネットの世界だ。でも…。
前述の『十字街』の朝日文芸文庫版などは、地図に年譜に橋本治の解説と、現代に「よい商品」として成立させるための工夫を、手間と金をかけてこらしている。だが無料の電子書籍版はたぶん、テキストが放り出してあるだけだろう。解説には別に著作権があるわけだし。
何か、本の墓場。巨大な、宇宙的規模の本の無縁墓地。我々はその埋葬者名簿と墓碑銘を、無料で読める。というのはセンチな感想にすぎないが。
夜は紀尾井ホールで、ジャンルカ・カシオーリのリサイタル。ノクターンをテーマに、シューベルト、自作、リスト、現代のコッラ、ドビュッシー、ショパンが並ぶ。作曲年代の限界を超えて巨大な前衛性を示した、最後のショパンのスケルツォ第一番が、猛烈に面白かった。
十一月十日(土)オペラ講座開始
晩秋の恒例行事となっている、早稲田大学エクステンションセンターの「オペラ総合講座」、私がコーディネーターを担当する後半五回、「ワーグナーとヴェルディのあとで」がスタート。
最初の二回は自分が担当する。一回目の今日は、フランスのオッフェンバックとビゼーをテーマに。
ワーグナーとヴェルディとフランスのグラントペラとの関係、そしてそれらの本流とは異なる傍流だが、ユーモアと悲劇を組み合わせて、シリアスなだけではないドラマを、歌と話し言葉の混合によってつくりだした二人の作曲家のこと。
いったん帰宅して、音楽同攻会の現役とOBの合同総会へ。私事で早退け。
十一月十二日(月)グラスハープ
夜はサントリーホールで、ゲルギエフ指揮マリインスキー管弦楽団そのほかによる、《ランメルモールのルチア》演奏会形式。
ゲルギエフの浅い呼吸感だと、どうもドニゼッティの熱い旋律線に、生命が吹き込まれない。ルチア役のナタリー・ドゥセ(デセイ)は、コンディションがよくなかったようだが、さすがのコントロールで独り舞台。珍しいグラスハープの演奏を、ステージ上でたっぷりと見、聴けたのは嬉しく、貴重な経験。
終演後の客席では、たくさんの人がスタンディング・オベーションしていた。
十一月十五日(木)さよならだけが人生だ
東京文化会館でソフィア国立歌劇場の《カヴァレリア・ルスティカーナ》《ジャンニ・スキッキ》二本立て。
悲劇と喜劇という組合せは、人生のコインの両面のようで、面白い。《スキッキ》は三部作の中でも単独に上演される機会の多い作品で、戦前のメトでは《道化師》と併せたライヴも残っている。コヴェント・ガーデンでは《サロメ》との二本立てがあったというが、さすがにこれはどうか。
土曜日のオペラ講座はヴェリズモ期がテーマなので、直前にナマを観られるのは、それだけでありがたい。水曜にも新国立劇場の《トスカ》を見るつもりだったが、これは私事でキャンセル。
夜、飼い猫のワサビが逝く。
二週間ほど前、腺ガンが再び悪化して腹水がたまり、長くないことを獣医の先生に教わって、覚悟をして一緒の時間を過ごしてきたから、ショックはない。ただ喪失感。
ワサビの生きざまと逝きざまは、先代のハナ同様、見事なものだった。私がオペラから帰ってきたのを待っていたように、膝の上に乗せたら数分のうちに、静かに逝ってしまった。
膝の上で寝るのが小さいときから大好きだったから、できればその形でみとりたいと思っていたのだが、どうやら彼女も、そのように決めていたらしい。
わずか六年の寿命は短すぎるが、これも定め。楽しい時間をありがとう。
しばしの別れ。長く生きると、向うで待ってくれている人やネコがだんだん多くなって、再会の楽しみが増していく。
十一月十六日(火)十蘭の政治陰謀小説

海野弘の『久生十蘭』を読みおえる。
副題に「『魔都』『十字街』解読」とあり、十蘭の長編二本を中心とする。
プロローグは十蘭の故郷、函館にある十字街という交差点から。
一九〇二年、阿部正雄としてここで生れ育ち、函館中学に入ったが問題を起して中退。一年ほど東京へ出て戻った十蘭は、十八歳で函館新聞の記者となり、二十六歳までをこの町で過ごした。
ところが、演劇の仕事を志して記者をやめ、上京して以後は、亡くなるまで二度と帰郷しなかった。作品で函館に言及したことも、ただの一度もないという。
自分を語らないことで有名な十蘭は、故郷も抹殺しているのである。
ところが面白いのは、「十字街」が函館の実際の地名であることだ。
かれの小説ではパリのコンコルド広場を指すこの言葉は、十字路を意味する地名としては、現代では北海道以外、ほとんど使われていない。思わぬところで十蘭の「お里が知れる」のが愉しい。そこから話を始める海野も、さすがに見事。
十蘭の実家は、この十字街から坂を登った、函館山の中腹の元町にあった。函館の旧市街で、近くにロシア正教やカトリックなどの教会の尖塔が建ちならぶ、ハイカラ色の濃い地域だそうだ。
獅子文六が横浜、横溝正史が神戸の生れであることなどを考えあわせると、明治生れで都会的モダニズムの発信者であるためには、国際的な港町の空気を吸って育つことが重要な条件だったのだろう。
十蘭の二歳下で函館中学の後輩にあたる水谷準は、昭和初期の「新青年」名編集長として十蘭や獅子を育てた人だが、故郷函館について、「北海道のうちでは非常に文化的というか、横浜と同じ感じのね、なんか雰囲気のあるところなんです。東京へきてわかったんですが、東京のほうがむしろ田舎の感じがしました」と、『新青年読本』のインタビューのなかで語っている。やはり函館中の後輩である田中清玄も、音楽がさかんで西欧風のモダンな雰囲気があちこちにあったと語っているそうだ。
そして、長谷川海太郎(すなわち谷譲次、林不忘、牧逸馬)以下の四兄弟。その父で函館新聞社長の淑夫は、父親のいない十蘭にとっても、親代りの存在だったらしい。
この「長谷川家の人々」もじつに面白い。淑夫が出身地の佐渡で中学教師をしていたとき、思想面で多大な影響を与えた教え子が北一輝だった。また、長男海太郎は大杉栄と交流があったが、そのアメリカ遊学中に大杉は殺される。作家として成功したあとは、父の縁で北一輝と交流した。ただし父の方は、北よりも大川周明に傾倒していたという。兄弟の三男、長谷川濬(しゅん)はその大川の周旋で満洲へ行き、満映で甘粕正彦の下で働き、その最期をみとる。
縁深きかれらのことを何も語らなかった十蘭も、「長谷川家の人々」の一人なのである。この兄弟については川崎賢子の『彼等の昭和』という評伝があるそうなので、いつか読んでみたい。
さて、海野はその十蘭を、三〇年代に遅れてきたモダニズム青年として位置づける。二つの長編『魔都』と『十字街』をモダン都市小説と見ると同時に、「政治陰謀小説」として読み解く。
二〇〇八年出版の『久生十蘭』は、旧著の『モダン都市東京―日本の一九二〇年代』、『陰謀と幻想の大アジア』につながるものだというのだ。

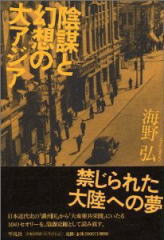
『大アジア』はとても面白い本だったが(文庫化されないのが不思議)、東京の二〇年代論の古典として名高い『モダン都市東京』はさぼっていたので、この機会にこれから読むつもり。
だが今の時点でも、「二〇年代のモダン都市は、西欧のモダン都市と同時代的ではあるが、風俗的コピーでもある。三〇年代に入ると、日本のモダニズムが成熟したともいえるが、政治や社会の大きな波と対決しなければならなかった」と海野が書く意味は、よくわかる。
最新の西欧近代文明への憧れが、文化風俗にあらわれたのが日本のモダニズムだ。それは、社会運動の場合はマルクス主義にあらわれる。国際政治運動の場合は、列強の帝国主義に対抗する、あるいはその変形としての、大アジア主義――ツラニズムやら日ユ同祖論やら国柱会やらを含む――にあらわれる。
二〇年代から三〇年代にかけては、それらが交雑しながら、生臭さとキナ臭さをましていく。しかし結局、どれもまだ――あるいは永遠に――根をおろせない表層的なもの、すなわち幻想の、陰謀じみたものに終って、敗戦のカタストロフを迎えることになる。
国際性への憧れが、軽妙に乾いて明るいモダニズムから、熱いがどろどろと暗い、大アジア主義の自己陶酔的陰謀に変質していく三〇年代にあらわれたのが、十蘭の『魔都』というわけだ。
『魔都』は入り組んだ話だが、根本的には、三四年の東京――銀座のようなモダンな地域と、築地の待合のような古い場所が光と影をなす魔都――で、自堕落で身勝手なモボやモガが起す、安南(ヴェトナム)皇帝とかれにまつわる利権をめぐる騒動である。
そのモボやモガには、明らかなモデルがあることを海野は指摘していく。久我侯爵の分家の男爵家を素行不良で廃嫡された長男、真珠王御木本幸吉に勘当された長男、ジャズ歌手川畑文子、など。
安南皇帝、すなわち仏領インドシナの皇帝も、現実の存在を元に自由な想像を加えた人物。作中の宋龍王は、皇位を狙う甥の存在に脅かされつつ、日本名を名乗って日本に愛人をもち、享楽的な生活を送る。これは実在の、パリで遊んでいたバオダイ帝と、その大叔父で日本に亡命したクオンデの二人の存在と行状をごちゃ混ぜにしてフィクションにし、他国の皇族のイメージを混ぜているようだ。
海野はそこで満州国の皇帝と弟を挙げているけれど、朝鮮の李王家もいたし、大アジア主義の時代の日本には、外国人の皇子が何人か滞在していたのだ。
そしてこの騒動の真犯人として、仏印に進出して利権を得ようともくろむ、新興コンツェルンの暗闘がからめられる。
当時、化学工業を足場に、第一次世界大戦の大戦景気で巨利を得て発展した、日窒、森、日曹、理研など、財閥系ではないコンツェルンが実在していた。十蘭は日窒と森らしきコンツェルンを出し、ボーキサイト(アルミニウムの原料)の採鉱権をめぐって、争わせる。
きっと似たような暗闘と陰謀が、アジア諸国でも国内でもたくさんあって、十蘭の情報網(新聞記者出身だからか、強力なものだった)に入っていたのだろう。
そこに、右翼の大化会や、「陸軍機密費問題」事件に登場する金貸しの乾新兵衛、相場師島徳蔵、談合屋前田栄次郎など、疑獄や乗っ取り、抗争事件で悪名を馳せた実在の組織・人物の名前をもじった、架空の連中をからませる。
海野の推定とは違うが、作中の夕陽新聞なる興行好きの新興夕刊紙には、佐野眞一の『巨怪伝』に描かれた、正力松太郎の読売新聞の姿がちらついてならなかった。「ゆうよう」と読ませているし、読売が部数を激増させて業界一位に躍進する原動力となった戦術の一つが、夕刊の重視だったからだ。
最後には、鶴見の土建屋=ヤクザ=右翼(当時は三位一体だった)が抗争の挙句に市街戦の様相を呈した二五年の鶴見騒擾事件と、二年前で記憶も鮮やかな二・二六事件を二重写しにしてみせる。
皇帝を人質にとって東京の中心地にたてこもったヤクザが、同じヤクザとの銃撃戦(ヤクザ相撃つ)の末に全滅する、強烈なパロディ。十蘭の描写が逃げるような駆け足になるのは、連載時の三八年では、さすがに危険すぎるネタだったからか。
ここに挙げた以外には、牽強付会気味で無理を感じる推定もあるのだが、とにかくさまざまに裏づけをされていくと、とても面白い。八日に書いた通り、小説としての出来はもう一つという評価は変わらないが、「政治陰謀小説」としての読みには、ワクワクさせられる。
アジアをめぐるさまざまな利権と陰謀に手を出すうちに、目先の欲と面子に縛られて後戻りできなくなり、ついには、モダニズムの卸し元、アメリカとの戦争に突き進むことになる日本。
その自縄自縛の絶望的な予感が、「新青年」に連載されたこの小説に読みとれると、理解することができた。
続く後半は『十字街』の解読。
十蘭のパリ体験、物語のテーマであるスタヴィスキー事件の実際などが語られていくなかで、面白かったのは獅子文六との、微妙なライバル関係。
フラン安で日本人が暮らしやすく、楽天的だった二〇年代の獅子のパリと、不況と円安で生きにくく、閉塞的な三〇年代の十蘭のパリとの違いが、そこに影を落としているようにも思う。
十一月十八日(日)肉は消えても
朝、江古田の蓮華寺にある哲学堂動物霊園にて、ワサビを荼毘に付す。
あまりに穏やかな顔つきで、まさしく眠っているような様子なので、山の神は焼きたくないと言うが、もちろんそうはいかないと、彼女もわかっている。
車で向う途中、鶴巻町の早大通りに面した獣医さんの前を通る。
六年前、大学の野良猫保護のボランティア・サークルがこの病院に預けたのをもらってきたのが、ワサビである。
体毛がサビ、すなわち色々な毛色がメチャメチャに混ざっていて、「こういうタイプは性格もきつくて騒々しいので、嫌われます」と先生が言ったので、もらうことにしたのだった(ノラをもらいに来る人って、よくも悪くもそうした義侠心を発揮したがるクセがあるのを、先生は先刻ご承知だったのかも)。
その通り、最初のうちはきかん坊の暴れん坊、手がつけられなかったが、二年後にオスのフクが仔猫で来ると、見事なまでの「保護者」に変身して、ムチャをしなくなった。
外で野良猫と喧嘩をしたフクのうなり声を聞くやいなや、一目散に飛び出していって、自分より一回り大きい相手にも飛びかかっていく――この場面を見たときは、自分ははたしてこんな勇気が持てるだろうか、いや、持たなければいけないのだがと、教えてもらった。
新目白通りをへて新青梅街道へ入り、早めに到着。
ペットの弔いをどうするかは人それぞれだろう。ウチでは焼いてもらい、遺骨を家にしばらく置いてから、霊園に収めることにしている。哲学堂では先代のハナも焼いてもらったので、二匹目。
ここはあまり商売臭くなく、きちんとやってくれるのが気に入っている。ハナを遺骨にしたあと、当方の気持が不思議なくらいに楽になったことは、六年たってもよく憶えている。
荼毘を待つあいだに周囲を歩くと「みずのとう」こと、野方配水塔が隣にあった。一九二九年完成の、江戸川乱歩の小説の舞台になりそうな、天文台を想わせるモダンなデザインが印象的な給水塔。
同じデザインのものが板橋の大谷口にもあり、むかし日大板橋病院へ見舞いに行く途中に、バスから眺めて驚いた。あちらは先年建てかえられたらしいが、野方はそのまま残っているので嬉しい。ただ、ほんとにただ建っているだけで、ぶっきらぼうというかなんというか。
古い住宅街だが、土地は高低が入り組んで、その中を妙正寺川と江古田川が縫うように蛇行し、蓮華寺のほかに哲学堂公園などに樹木も多く、武蔵野らしい、じめっと湿った雰囲気が漂っている。
一時間半後、遺骨を拾って壺に入れ、抱いて帰宅。
十一月二十日(火)吉田秀和追悼本
『吉田秀和――音楽を心の友と』という追悼本が、音楽之友社からONTOMO MOOKで出た。「レコード芸術」の二回の特集をベースに、そのフルカラー化と、全著作紹介、インタビューなどの資料を補強したもの。

不肖私めも声をかけていただいて、少しだけ書いている。片山杜秀さん、矢澤孝樹さん、広瀬大介さんなどの見事な追悼文の末席を私も汚しているのだが、こうして読んでみると、生前にご挨拶さえしていない、ほんとうに一介の「読者」の立場からえらそうに書いた失礼な奴、おれ独りなんじゃないのか……。
読者がものを書くなという意味ではもちろんなく、この本のありようとしては異質、ということだ。他の方はみな、多かれ少なかれ、故人とご縁のあった人たちばかり。畏れ多いとはこのことだ。
まあ、書く段階でその予感があったので、パソコンの前で呻吟するばかりで長いこと何も書けず、書いては消しをくり返し、担当のモトヒロ氏から「もう校了間近で、こんなこと言いたくないけど出してないの、山崎さんだけなんですが」と最後通告をだされ、いっそ
思いがあふれて何も書けません。
と真ん中に一行だけで、あとは白紙の一ページという「禁じ手」にしてもらおうかとも思ったが、ギリギリのところでようやく書くことができた。
というわけで、拙文はほんとに文字通り、どうしようもなく拙い出来だが、本自体は、この偉大な才能の生涯を振り返る上で、基本資料となるものだと思う。
ただ一つだけ自慢できるのは、版元の友社にさえなかったというバーンスタインの『音楽のよろこび』の翻訳本の現物を貸したのは、おれだ。
といっても、この本の元になったテレビ番組『オムニバス』のDVDの解説を書かせてもらうのに必要で買ってあったというだけで、手前勝手な偶然にすぎないが。
手前勝手といえば、私と故人の、間接的ながら数少ないご縁といえば、ヨーゼフ・ホフマンのこと。
「レコード芸術」のHMVの広告にコラムを書かせてもらっていたころ、ホフマン賛を書いたとき、かれを「空虚な名人芸」と批判した故人に不満を述べたことがあった。まことに若気の至りで、HMVの判断で実名はカットされたが、わかる人にはわかったようである。
それから二十年、このムックにも転載された担当のモトヒロ氏の思い出によると、最後の原稿を受け取る少し前、レコ芸の「ピアニスト特集」を読まれた故人は、「内田光子などが入ってなくて、その代りにホフマンが二十二位とは、どういう投票なんだ」と不審だったらしい。困ったモトヒロ氏は「一般の読者ではなくライターの投票なので、マニアックな人もいますから」と答えたという。
すいません、そのマニアックなヤツ、おれと谷戸基岩さんのたった二人でした(笑)。ああ、最後までおれはマニアとしてだけ御大に関わったのだなぁと、つくづく思った。
話は戻って、そのあとに書かれた故人最後の原稿には、その投票で一位をとったホロヴィッツと、それにからんでハイフェッツのことが取り上げられている。どちらもナマを聴かれた演奏家。ハイフェッツはただ一度だったそうだが、とにかくその印象から、話は書かれている。
完全な自意識過剰で書くが、御大が録音でしか知らないホフマンについて一言も触れず、ヴィルトゥオーゾのなかでもナマを聴いたホロヴィッツとハイフェッツにだけ話をしぼったのは、明らかに意図的な、一種の決意表明だったのではないかという気がする(ホフマンを挙げた奴に対するメッセージだったとまでは、いかに自意識過剰な私も、そうは思わないが)。
その意味は、わずかな実演経験しかもたない私でも何となくはわかるが、それでも語り続けるのが自分の仕事。
ひるがえって考えてみると、故人がそのハイフェッツをただ一度聴いた直後、『音楽紀行』に書いた言葉は、最後の文章での書き方とはかなり違う。これは、何に由来するのか、なんてことを考えだしてようやく、このムックに載せた拙文に取りかかることができた。そこに、ほんとうの意味での、自分の仕事との関わり――きわめて一方的なものだが――を見いだせる気がしたからである。
手前勝手なことばかりをしているうちに、迂回した形でもご縁をもてたのは、本当にありがたいこと。
――失礼だけが人生だ。
十一月二十一日(水)ヤマカズ&日フィル
日フィルの正指揮者になったヤマカズ21、山田和樹の話ではない。元祖の山田一雄のこと。以前からその録音の復活に力を注いでいるタワーレコードが、生誕百年記念として、日フィルとのライヴ録音集をリリースする。
文化放送とフジテレビの専属だった、いわゆる旧日フィルとの演奏。一九六五年から七二年にかけての録音で、ショスタコーヴィチの五番にプロコフィエフの七番、R・シュトラウスのアルプス交響曲などの初登場のレパートリーが嬉しい。しかもすべてステレオ録音。
五六年の創立当初から、自前でステレオ録音のアーカイヴをつくっていた(放送目的だけなら当時はモノラルで充分)文化放送と日フィル関係者の、努力と先見の明に感謝しなければならない。
そして、旧フジテレビの河田町の事務所を明けわたすとき、すべてのテープがあやうくただの産業廃棄物になるところだったと聞くが、それを阻止して、きちんと管理保存した関係者にも、感謝。
十一月二十六日(月)ヤンソンス
サントリーホールで、ヤンソンス指揮バイエルン放送交響楽団の来日公演。
曲はベートーヴェンの交響曲第四番と《英雄》。私はこの日しか聴かないが、四回にわたる交響曲全曲チクルスの第一日となるもの。
前者は第一ヴァイオリン十二人、後者は十四人と編成を抑えたことに象徴されるように、ナマは予想以上に、ピリオド様式を意識した演奏だった。
というより、現代ヨーロッパの楽員には、古典期の作品にはそれにふさわしい奏法があることが、程度の差はあれ、自明の態度となっているのだろう。澄明な響きと、音の減衰を速めにして、重く引きずらない。楽員が自然にそのように反応するようになっているのだと思う。
その一方で、近代のオーケストラならではの機能性、安定性、均質性は、十全に発揮され、弦も管もトップクラスの水準にある。
その意味で、一種の折衷様式といえる演奏だった。その点は好ましいのだけれど、ベートーヴェンの音楽の凄さを味わえたかというと、それは別。
インテンポで快速に運ぶ一方で、強弱の一瞬の変化を細かくつけて工夫している。だが、呼吸感があまりない。そのため、ベートーヴェンらしい遠近感、パースペクティヴの広がりが少なく、単調に感じられた。
十一月二十七日(火)ヴァルガ
ウィーン・フィルのソロ・チェロをつとめる、タマーシュ・ヴァルガにインタビュー。
ついたばかりで疲れているようだったが、今年のバイロイト音楽祭への出演についてたずねたら、俄然しゃべりだしてくれた。経緯、祝祭劇場の「神秘の裂け目」のなかの印象、共演したティーレマンのことなど。まとめるのが楽しみ。
十一月二十八日(水)ヤンセン
夜は紀尾井ホールでジャニーヌ・ヤンセンのヴァイオリン・リサイタル。
ベートーヴェンの《春》、ドビュッシーとフランクのソナタ、サン=サーンスの序奏とロンド・カプリチオーソ。アンコールはドビュッシー、シマノフスキ、フォーレの三曲。
艶のある美しい音色に心地よく酔う。
Homeへ
十二月二日(日)山梨の峠道
朝、笹子トンネルで崩落事故の一報をネットで知る。
二十年前、塩山の送電線建設現場にいたころは、毎週のように往復したトンネル。約四キロと長いだけに、あの中で崩落となると怖い。
(追記 九人もの方の犠牲がのちに判明した。ご冥福をお祈りする)
この事故に関連して、塩山在住の矢澤孝樹さんとフェイスブックでやりとりしているうちに、はからずも昔の山梨通いのころを思い出す。
自分が通っていた一九九〇年頃には、勝沼インター付近の法面の土砂崩れのため、中央道が一週間ほど使えなくなったことがあった。ちょうどその朝、東京から向っていて通行止になり、途中でおりて二十号に入ったら大渋滞。
おとなしくそのまま行けばいいのに、適当に山道に入って、三時間くらいかかって山を越え、塩山にたどりついた。ぐるぐると巡るうちに突然、山間の村に入ったりして面白かったが、あとで考えると、あのあたりで道を知らずに山越えするなんて、遭難しても不思議じゃない、無謀な話だった。
なぜあんなことができたかを考えてみると、当時の自分が山道の法則というか「生態」みたいなものを、皮膚感覚で覚えていたからだろう。自分が関わっていた百万ボルト送電線というのはデカいだけに、現場は人里離れた山中にあった。そこで毎日、車で山道を行けるとこまで行き、あとは小一時間徒歩で登山(クマ除けにぶら下げたカウベルをガランガラン鳴らしながら。ひとりマーラー)していたのである。それで、このときも地勢を見ながら走れば何とかなるべぇくらいで行ってしまったのだが、実際は運がよかっただけだろう。
また別の機会には、塩山から静岡の富士宮の現場へ応援に行くことになり、南へ山越えしたこともあった。
日の暮れかけた夕方、妙な名前の村だなぁと思いながら通過したのが、上九一色村。それから数年後、オウム真理教事件で世にその名を知られることになる。
十二月三日(月)ベートーヴェン六叉街
ブリュッヘンとヤンソンスが出した、二つのベートーヴェン交響曲全集を、CDで少しずつ聴いている。まるで似ていない両者、じつに面白い対照だ。
ピリオド楽器を用い、作曲上のカオスも演奏面の限界もすべてそのまま抱えこんで、さまざまなアイディアを音にしてみせるブリュッヘン。一方、モダン楽器を用いて、音の早い減衰などピリオド的なセンスをとりいれつつ、近代の合理性と機能性を最大限に活用し、止揚しようとするヤンソンス。
前者は有限の裡に垣間見る永遠、後者は永遠に向けて進み続ける有限、とでもいうか。どちらが好みかときかれればブリュッヘンに決まっているが、好き嫌いの問題ではない、演奏行為というものの面白さと偉大さ――そして、虚しさ――が、この両者の対照に、端的に顕れているように思える。
さらに去年出た、シャイーとティーレマンの全集も併せると、もっと面白い。作曲者のメトロノーム指定を守り、トスカニーニの直進にカラヤンの流麗、ガーディナーの意欲、三世代の代表的ベートーヴェン演奏を咀嚼して次を目指した前者と、アナクロといっていいのかどうかよくわからないが、どろどろした後者。
これらさまざまの可能性と有限性の十字街に立つ、ベートーヴェン。
こう書いたところで、久生十蘭が自作に『十字街』と名づけた理由に気がついた。人間の真偽と善悪と美醜のすべてが行き交い、姿を見せては消える場所として、久生十蘭は「十字街」という題名を(故郷の地名から)考えつき、パリのコンコルド広場に象徴させたのだろう。
凱旋門へもルーヴルへも、生臭い政治と経済の舞台へも、ノートルダム寺院へも、そして死体置場(モルグ)へも、上へも下へも右へも左へも、すぐに行ける「世界でいちばん美しい」十字街、調和のとれたコンコルド広場。
ベートーヴェンの九つの交響曲は、まさに音楽のコンコルド広場なのか。
ベートーヴェンも偉いが十蘭も偉い。
函館にある「十字街」もそんな場所なのか、確かめに行ってみたくなった。久生十蘭ならぬ、若き新聞記者阿部正雄は、そこに何を見たのか。
それにしても、コンコルド広場の周囲は十蘭の時代とそんなに変っていないだろうが、函館の十字街は、はたして面影だけでも残っているものなのやら。
日本の街並みくらい、人間の有限性を見せつけるものはないのかも(笑)。
もう一つ、バレンボイムの「ベートーヴェン・フォー・オール」の交響曲全集もあったことを思い出す。あれもまた、演奏自体はごくオーソドックスで好みとは違うけれど、その普遍性にこそ意味が見出される。
一連の「ベートーヴェン・フォー・オール」のシリーズを聴いて、遅まきながら私もバレンボイムへの認識を革めた。たしかにどれも仕上げは粗い。しかし芸術家としてのその存在の大きさと重さ、ウェスト=イースタン・ディヴァン・オーケストラの運動の意義の重さが、実感できた。ユダヤ=キリスト=イスラム、この問題が新しくて古い、切実にして永遠の命題であることが、ベートーヴェンを通して暗示されているのだ。
これで十字街から五叉街になった。
さらに日本では、飯守泰次郎と東京シティ・フィルの全集が四月に出ていた。かつてベーレンライター新版を用いて録音したコンビが、ピリオド風味を捨ててマルケヴィチ校訂版に基づいて録音したもの。これも好き嫌いを超えて、日本の交響楽運動の保守反動的な一面を代表する、六つめの全集。
六つのセットすべてが、それぞれの指揮者の、現代世界に対する明快な意志表明、存在証明になっているのが面白い。単に「こうやってみた」という解釈の問題ではなく、現代へとつながる時間の流れ、すなわち「歴史というものに対する態度」がそこで問われている。それを明確にすることで、自己のアイデンティティを明らかにしている。
だから、名盤とか珍盤とかいった、従来の価値基準では量ることのできない、「現代に留めおくモノ」という意味の、それぞれの存在を賭けた「レコード」になっている。
それが、シャイー盤が出た昨年十月からヤンソンス盤発売の今年十二月まで、わずか十四か月に六つも揃ったというのが、実に愉快。
今までにも全集は数知れずあるし、時期的に接近して出たものもいくつもあるだろうけれど、音楽的な個性の相違、優劣といった差ではない、こんなに立ち位置と方向性の違う六つ、六叉街に立つベートーヴェンは、珍しいのではないか。
などと書いていると、友人から「ここには米国のオケが一つもない」という、素晴らしい指摘を受けた。
歴史をことさらに意識せず、進歩という、時間の経過のうちの良い面しか見ないことによって、十九世紀末~二十世紀にかけての、大オーケストラ運動があった。だから歴史のないアメリカも、そして日本も参加し、本家を上回る水準すら達成できたわけだが、二十一世紀になると…。
そうして考えると、ここにロンドンとベルリンのオケがいないのも面白い。ロンドンは当然だからおくとして、ヨーロッパ本土においてはベルリンが、二十世紀アメリカと資本制度の橋頭堡みたいな都市だったことが、偶然ながら端的に象徴されているのかも。
十二月四日(火)ドラミング・ライヴ
オペラシティで行なわれた、コリン・カリー・グループによるライヒの「ドラミング」ライヴに行く。
コンピューターなら完璧に再現できそうな音楽を、人力でやることの愉しさと充実感。聴いている側は音の雨のなか、時間の感覚がなくなるが、演奏者はきちんと把握している。《ラインの黄金》のニーベルハイムの金床の音はこれを予告していたわけで、ワーグナーの先駆性に感心したり。
それにしても、ふだんのクラシックの演奏会とは異なる、比較的若くてイマっぽい聴衆で満員。終演後の「フオー」とか「イェーイ」みたいな歓声も新鮮。
十二月六日(木)アルマヴィーヴァ…
新国立劇場で《セビリアの理髪師》。最後のアルマヴィーヴァのアリアがないのはごく普通のことなのだが、一度あの快感を味わってしまうと、クリープのないコーヒーどころか、メインディッシュ抜きでコーヒーが出てきたような、拍子抜けした気分になる。
モンタナーロの流れがよく間延びしない指揮、日本歌手陣も好演したのに、我ながら客というのは身勝手なもの。
十二月七日(金)暗さと明るさの裏に
ハーディング指揮新日本フィル定期@トリフォニーに行く。
開演二時間前の五時過ぎに、東北で震度五弱、東京で四の地震があった。三・一一にもハーディングが指揮して、話題になったことを思い出す。遅れてくる人が心もち多かった気もするが、大きな混乱はなく定刻の七時十五分過ぎに開始。
今回ハーディングは、先月二十八日にサントリー、今日明日にトリフォニーで二演目を振るが、曲が巧みに関連づけられている。二十八日はチャイコフスキーの交響曲第四番に《春の祭典》、今日明日はショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第一番と交響曲第十番。
つまり帝政末期、革命寸前の混乱期、そしてスターリン晩年から没後の「雪どけ」と、四曲でロシア史の流れを追うようになっているのだ。
残念ながら二十八日は紀尾井のヤンセンに行って聴けなかったので、演奏面における関連づけについては語れないが、今日だけでもとても面白かった。
ジダーノフ批判の波及を恐れて七年間抽斗にしまわれ、ほとぼりのさめた一九五五年に初演された協奏曲と、五三年のスターリンの死の直後に着手され、その年のうちに初演された交響曲。両者の語法の類似を如実に感じることができた。
協奏曲の独奏はコンサートマスターの崔文洙。モスクワ音楽院でクリモフに学んだそうで、つまりは初演者オイストラフの孫弟子。もう少し音色に多彩な変化がほしいと思う箇所もあったけれど、技術はさすがのもの。崔は、後半の交響曲でもコンサートマスターとして登場した(前半は西江辰郎)ので、第三楽章でのソロなどが協奏曲と同質の響きになるのが暗示的で、面白かった。
ハーディングの指揮するショスタコーヴィチは、都会的な、鋭利な暴力性と嗜虐性にみちたもの。特に交響曲はテンポを遅めにして、その陰惨をじっくりと描き出す。第一楽章の暗鬱、第二楽章の狂躁、第三楽章の嘲笑と猜疑、第四楽章の凱歌なんだかどうだかよくわからない熱狂、みな血なまぐさく、凶暴な破壊衝動に裏づけられている。安易に標題性を求めるつもりはないが、スターリン時代の都会人の気分は、まさにこうしたものだったのではないか。
いつ果てるとも知れない陰鬱な音楽に辟易したか、寝落ちするお客も少なくなかったけれど、私は佐村河内守の交響曲第一番を客席で聴いていたときの気分を思い出した。
トゥッティになると響きが混濁して飽和するが、この場合はこれでいい。それでなお、不思議に透き通った緊張と切迫感が維持されるのが、ハーディングの只者ではないところ。
ともかく暗い。スターリン死後の状況を象徴することになったエレンブルグの小説『雪解け』には、主人公がこの曲の初演をラジオで聴いて、新時代の到来を実感する場面があるそうだが、曲自体はちっとも開放的でも愉しげでもないというのが、面白い。
むしろスターリン圧政時代にこそ、前向きで威勢がよく、力強く景気のいい、社会主義リアリズムにふさわしい《森の歌》などが書かれていたわけだ。
あの曲はあの曲でけっこう好きだが、それはそれとして、強者の論理を景気よくふりかざす人は信用しがたいというのは、いつの時代でも一緒なのだろうな、などと考えてみたり。
前半の最後に崔文洙によるソロのアンコールがあったこともあり、終ったのは九時半頃。約二時間十五分、ずしりと重い演奏会。
十二月十日(月)勘三郎の理髪師
亡くなった中村勘三郎の棺に六代目菊五郎の衣装がかけられていることを、日経新聞に載った野田秀樹の見事な追悼文で知る。新しい歌舞伎座の舞台の板の端切れを、棺の中の遺骸の足が踏んでいることも。
NHKでやっていた追悼特番では、抜粋で『髪結新三』をやっていた。自分も観た十二年前の歌舞伎座の舞台なので懐かしく、嬉しかったり悲しかったり。家主の富十郎との爆笑の掛け合いが記憶に鮮やかだが、二人とももういない。
ろくに観劇経験もないなかでこの舞台が印象に残っている理由は、ほかにもある。勘三郎と夫人の調髪をしている美容師さんに、私もカットをしてもらっているからだ(まったくの偶然)。
野田の文には、遺骸が紋付袴をつけていることも書かれていたが、髪はどうなっているのだろう。放射線治療のあととはいえ、まさかマゲはつけていまい。
ICUのなかでの数か月間、病状を何も知らされていない美容師さんはもちろん近づけなかった。おそらくは夫人か看護師が整えていたのではないか。
きっと美容師さんは、棺の中の勘三郎の最後の調髪をしたのではないか。根拠はないが、絶対にそういう気がする。
勘三郎一家が、そうした出入の人(と呼んでいいかどうかわからないが)にも細やかな心配りをするらしいことは、十年以上同じ人に髪を切ってもらってきた自分も、仄聞している。
その人が独立して店をかまえたとき、場所を変えたとき、華やかに店頭を飾るのは、必ず勘三郎一門の生花だった。
自分もそろそろ髪を切りにいかなければならないのだが、ちょっと会うのがつらい。お互い男、店先で泣くわけにもいかねぇし。
十二月十一日(火)駒場にて
東大駒場キャンパスでの「『線量計と機関銃』刊行記念トークショー 麻木久仁子と片山杜秀の年忘れ時事放談」を聴きに行く。
一週間後にミュージック・バードの年末恒例の片山さんとのクラシック放談の収録があるので、その予習をかねて。
会場は東側のコミュニケーションプラザ北館というところの二階。東大OBのアルテスの鈴木さんによると、かつての駒場寮の跡地だという。一高時代からの建物は時計台のある本校舎と左右の講堂と図書館、それに柏葉の校章のついた正門くらいになってきているようだ。
昭和の始め、普通選挙法が施行されるや否や、不景気のなかで議員はポピュリズムの陥穽にはまり、調子がいいだけの選挙目当ての無責任な公約が横行する。そうしてわずか数年で、二大政党とも民衆の信頼を失う。軍部が台頭する直前のこの状況と現在との類似を片山さんが例を挙げて述べると、麻木さんが現代との結びつきをわかりやすく加える。
選挙直前、タイムリーすぎてきわどい話も出たが(笑)、参考になった。
十二月十二日(水)期日前投票
期日前投票に行く。衆院の選挙区と比例、都知事と最高裁判事、二枚ずつ透明ケースに入った四枚四色の用紙をいっぺんに渡され、記入場所は前の二枚と後の二枚との二か所にわかれ、書き終わると全部をもって、四つならんだ箱に「この色はこれ」というように入れていく。
当日の投票会場だと、前の二つが終ってから、あらためて後の二つにかかるはずだが、期日前投票の場所は狭いのでこうなる。普通にやればどうということはないが、「間違って違う用紙に書いてしまったら」「間違って別の箱に入れてしまったら」といった心配をしだすと、けっこう心が騒いで落ち着かなくなる。パニック障害の人なんか、これはけっこう危険な罠になりかねない気が……。
当選者をあてる勝馬投票券ではないので(時々そんな気になる)、死票になるのはかまわないが、せっかく行って無効はいやだ(笑)。
十二月十三日(木)江ノ島より
待望の『海街diary』の五巻、やっと読んだ。
「おれらはいなくなるけど それで終わりじゃねーんだもん」
そうだ、街も日本も世界も。
人の死と、残された者の思いを描いてきたこの作品の意味は、大震災以後、さらに深くなっているように思う。
十二月十八日(火)年末放談
年末恒例、片山杜秀さんとのミュージック・バードの特別番組『クラシック放談2012』無事収録完了。
夜の十時前から深夜二時半まで、今年は初めての深夜収録。終了後は築地の寿司か六本木の焼肉か、なんて話が最初は出ていたが、明日もあるし眠いので、ただちに解散。お互い来年は五十歳。
最初の放送は二十三日。今年もリスナーに楽しんでいただける番組になるといいが。ケージ生誕百年記念で《四分三十三秒》が番組自主音源で全曲(笑)かかるラジオ番組なんて、世界にそう例はないはず。普通なら放送事故扱いだ。
片山さんとの対談は阿吽の呼吸でやれるので、お世辞抜きで毎年愉しい(片山さんがどうお思いかはわからないというか、片山さんにカバーしてもらっているところが大きいが)。今年の締めはこれしかないという曲も、山田一雄の《おほむたから》で一瞬に一致。
それにしても片山さんの忙しさは半端ではない。自分なら間違いなく三回くらい死んでいる。
十二月十九日(水)イマドキのキカイ
こわれもの話二題。
まずは洗濯機。数字表示にエラーが出て修理にきてもらう。買って二年半、実費かと思ったら購入店の三年保障に入っていたので、助かる。
古い日本家屋なので、洗濯機を浴室内に置くようになっているのだが、湯気と湿気が電子機器にはよくないらしい。
修理の人によると、最近の洗濯機はエラーが出やすく、つまりは壊れやすく出来ているそうだ。あまり頑丈につくるとモーター部分からの発火など、大事故になるまで使いがちなので、それを避けるためだという。
そういう意味で、購入店独自の長期保障、それも五年などのものに入っておいた方が間違いないのだとか。
最近はネット通販の方が安いので、そちらに目が行きがちだけれど、ネットはほとんど、普通の一年保障だけ。高くてかさばる、買い換えが面倒なものは、やはりリアル店舗の方がよいのかも。
次は、ゲーム機のプレイステーション2。画面がブラックアウトすることが増えてきた。発売数か月後の二〇〇〇年初夏に買ったものだから、もう十二年半も使っているわけで、むしろ、よくこんなに長く働いてくれたもの。不具合が多いとされた初期型だけに尚更だ。
こちらは洗濯機のような必需品ではないから、どうするか考える。
一は、これを期にゲームからすっぱり足を洗って、思索と読書と執筆に振り向ける案。五十男にはこれがふさわしいかも。いずれにせよ近年はもう、サッカーゲームくらいしかしていないのだし。
二は、携帯ゲーム機に移る案。ゲーム業界全体の動向に沿う形だが、老眼には画面が小さすぎ、不器用な人間には操作も細かすぎるので、これは絶対無理。
三は、PS3に買い換える案。発売当初は高いし重いし電気は食うしで、興味がなかったのだが、現行機種は初期型よりも小型軽量化され、価格も大きく下がっている。『メタルギア』シリーズなどはやはりやってみたいし、ブルーレイディスクの再生機にも使える。
PSの『ガンパレード・マーチ』や、『奏(騒)楽都市OSAKA』のような懐かしいゲームも、自分がもういちど遊ぶことはまずないにしても、ダウンロードで安く買うことができる。ただしPS2のソフトは遊べないらしい。
結局、煩悩を減らすことはあきらめ、PS3を買うことに。
それにしてもPS3が出てから、もう六年も経っているのか。今回調べていて気がついたが、PS~PS2~PS3の代替わりのサイクルは、ともに六年だった。つまり、もう次のPS4が出てもいい年数になっていることになる。話が出てこないのは、据置型のゲーム専用機の時代そのものが終っているからか?
そういえば、CDもDVDも、いつのまにかとても古いメディアになっているのだった。
十二月二十日(金)イマドキのバッハ
バッハのCDを二枚続けて聴く。
まずはアマルコルドとラウテン・カンパニーによるモテット集(DHM)。アマルコルドはライプツィヒの聖トーマス教会合唱団OB五人のアンサンブルなのだが、女声を助演にくわえたモテット、軽々と生き生きと歌われているのにちょっとびっくり。「元祖バッハ本舗」トーマス教会の出身者でも、今はこういうバッハを歌う時代なのだ。
次はガイヤールとプルチネッラによるアリア集(アパルテ)。「気になるディスク」の十一月二十六日に取りあげたもの。ガイヤールのピッコロ・チェロの柔和な歌いくちに、ピオー、クリストフ・デュモー、ゴンザレス・トロと、バロック・オペラの名手と俊英三人がそろった独唱。喜びも哀しみも祈りも、いかにもフランス風のバッハというか、草書体の流麗な響きで、さらに気持いい。
嬉しい驚きなのは、二曲入っているシュープラー・コラールのサックバット。
聴きての心を瞬時にとらえる、響きと音色の見事に豊かな膨らみ、何だか知らないがめったやたらに巧いヤツが吹いているぞと思って調べると、一九八五年トゥールーズ生れの、ファブリス・ミリシェーという若手。
あのスローカーやベッケも成しえなかった、ミュンヘン国際音楽コンクールのトロンボーン部門第一位(二〇〇七年)獲得という快挙も、なるほどと納得できる演奏。
検索すると、年明けにちょうど来るらしい。聴いてみたくなってきた…。
十二月二十一日(金)げんしけん二代目
フェイスブックで友人たちの熱烈な推薦を受けた『三月のライオン』を買おうと、本屋に入った。だが、先に『げんしけん』十三巻「二代目の四」が平積みされているのが目に入ってしまい、毎度のように流されて、こちらを買ってしまう(ダメ)。
でもやはり面白い。一度終った話を五年後に連載再開するという無理(作品の中の時間は連続している)をやっているのに、この「二代目」の方がはるかにおもろい。
自分はこの三十年アニメをほぼまったく見ていないし、マンガやゲームも通り一遍のものしか知らないが、大学(中央大の多摩校舎がモデル)のオタク・サークルのもてない男どもを描いた「初代」の前半は、いわゆるクラオタとして似たような陰気な生活をした自分にも、とても共感できるコメディだった。
さらにその後半は新しい学年が加わって前面に出てきて、図式的なオタクキャラの上級生が背景に下がるにつれて物語性がまし、共感性よりも人間ドラマとして面白くなっていった。
そのさらに下の学年を描く「二代目」は、腐女子や「オトコの娘」(おとこのこ、女装の美少年)が増殖して、ますますドラマが愉快で深い。クラシック関係では、アニオタよりも腐女子との遭遇率がかなり高いので、参考(?)になる。
同性のオタクを描くよりも、異性のキャラ(腐女子)を描いた方が物語として動きと照れ臭さが出て面白いのは、どんな創作も一緒なのかも。
それだけに、女性キャラはつくりものめく部分もあるけれど、それが楽しい。この巻で登場した今野なんて娘は自分が大好きなタイプだが、あきらかに「男にとって都合がいいキャラ」(笑)。
とにかくおもろい。「……ダメだ この人……腐ってやがる……」大笑い。でも一方に、「周りの人間に裏で情報通ヅラされんのは疲れんだよ」なんて、深いセリフもポンと出てきて(やるなあ、笹原妹)。
初代から引っぱり続けたコイバナ(恋話)もいよいよケリがつきそうで、次巻で大団円か? 早くも待ち遠しい。そのあいだに『三月のライオン』読もう。
十二月二十二日(土)読響の第九
池袋の東京芸術劇場で、カンブルラン&読響の「第九」。今年の演奏会納め。
年の瀬に「第九」を聴くなんて、ワイケルト&N響(一九八〇年)以来、三十二年ぶりのこと。でもこのコンビは聴き逃せないと思った。
曲目は「第九」一曲だけで短め。やはり面白かった。ピリオド風ではないが、重厚ドイツ風でもない。フランス近代、現代音楽の流れから見なおした、大仰さのない、明るく爽快なベートーヴェン。
白眉は第二楽章。普段は単調な体操のようで飽きるこの楽章が、こんなに精妙な仕掛けと発見にみちているとは! 終楽章の後半も、大規模声楽曲の指揮を得意とするだけあって、変化に富んだ見事なコントロール。改装後の芸術劇場の音響も、合唱にぴったり。さわやかに今年の締め。
しかし、これだけの公演回数が超満員とは大したもの。年末の第九の人気というのは、こんなに安定しているのか。客席のマナーがやや不安だったが、今日は演奏会慣れした、好ましいものだった。独唱陣のテノールが交替していたが、N響もそうだとか。テノール御難続き。
十二月二十三日(日)ドイツの「国立歌劇場」表記のこと(改訂版)
(一月二日追記 バイエルン州などのフライシュタート〈自由国、共和国〉表記に関し、その歴史について、友人の景山優理子さんから非常に有益なご教示をいただきましたので、それに基づいて後半部分を書き直しました。景山さん、ありがとうございます)
「レコード芸術」一月号を読んでいたら、例の「ドイツの歌劇場、国立歌劇場か州立歌劇場か」の表記問題に関して、海外楽信欄で城所孝吉さんが、実に説得力のある説を述べている。
結論からいえば、ドイツでも国立歌劇場と呼ぶべき、というもの。その論拠となる部分を、まるまる以下に引用する。
Staatという言葉は、ドイツの行政機関を表す言葉としては「国家」、「国立」という意味しかなく、「州」という訳は適切でない(Staatが「州」という意味で使われるのは、アメリカ合衆国等、外国の自治体のみ。ドイツ国内の行政区画としての州はLandと称される)。実際ドイツには、よりランクの低い小規模劇場としてLandestheater(州立劇場)が存在し、StaatsoperやStaatstheaterと呼ばれる大劇場は――実際には州の資金により運営されているとはいえ――「国立(歌)劇場」と訳されるべきなのである。
なるほど、と深く納得。合衆国やオーストラリアなどのstateの訳語として使うときしか、Staatには「州」の意味はないわけだ。
そして、現代ドイツの行政区画の用語の訳語としては、Staat=国家、Land(Bundesland)=州(連邦州)が妥当。ポイントは、Staatに「ドイツの連邦州」という意味はない、ということ。
ヴァイマル時代に宮廷歌劇場そのままにStaatsoperとして国費で運営していたものが、戦後の西ドイツでは各州の負担に変った。中央集権では軍国主義化しやすい自国民の性格を恐れ、反対意見を確保するためだろうが、そのことと、名称とは別の問題というわけだ。
単純だが明快、目からウロコの落ちるような見事な説明。
Staatを英語のstateに訳してしまうと、そこに「国」と「州」(アメリカ風の)の、両方の意味が生じる。それで、州がお金を出しているのだから「州立歌劇場」を選ぼうよ、というのが「国立ではなく州立」表記問題の始まりだったと思うが、これはあくまで英語の考えかた。ドイツでの行政区画としての「州」は、Landなのだ。
私のような素人はあちらの説を見ては「ほおほお」、こちらの説を聞いて「へえ~」と右往左往しているばかりだが、これはかなり、強く説得された。よほど強力な反論が出てこないかぎり、自分も今後は国立歌劇場と記すことにしたい。
と、いうようなことをフェイスブックに書いたら、友人たちから興味深く、示唆に富んだレスをいただいた。
なかでも面白かったのは、バイエルン州は特例的にFreistaat Bayernと名乗っている、ということ。
ドイツの連邦州(Bundesland)の一つなのに、アメリカ式のStaatを用いているわけだ。
この場合は、Frei、自由という言葉と一体になっていることに意味があるのだと思う。これは、オレンジやアイルランドなどが用いた「自由国」のドイツ語訳であると同時に、中世以来の伝統をもつ自由都市、ハンブルクなどのFreistadtをもじった言葉だろう。
この名称、自由という言葉がついているからてっきり私は戦後、この地域を統治したアメリカ占領軍主導でつくられた用語なのかと思った――アメリカは西ベルリンの自軍管轄地域にも「自由ベルリン放送」や「自由ベルリン大学」など、「自由」とついた組織を好んでつくっているので――が、そうではないそうだ。
一九一八年の第一次世界大戦敗北によってドイツ第二帝国が崩壊、共和制に移行した直後、連邦を構成する諸邦(Staat)のうち、バイエルンやザクセンなど数邦が、市民自治を謳って名乗った名称なのだという。
その後ヴァイマル憲法が制定され、諸邦は州(Land)に改編されたが、バイエルンとザクセンのフライシュタートは、そのまま使われつづけた。
そして、第二次世界大戦後に西ドイツ(ドイツ連邦共和国)が成立して連邦州が復活したさい、バイエルンは旧称を採用した。さらに東ドイツ(ドイツ民主共和国)が解体してドイツが統一されたときに、ザクセンとテューリンゲンもフライシュタートと名乗った。
こうした経緯を考えると、フライシュタートというのはあくまで理念的な名称で、バイエルンもザクセンも、実務的にはブンデスラントの一つである。たとえば州議会は、他州と同様にLandtagと呼ばれている。
だからバイエルンもザクセンも、シュターツオーパーのシュターツは他地域同様に州を意味せず、(ドイツ)国立を指していると考えられる。いや、理念としてのバイエルン国の、ザクセン国のという意味だというなら、それゆえにこそ国立歌劇場と訳すべきで、州という下位の言葉など、なおさら使わない方がよい。
結局は、英語のstateも「国」の意味合いが強いのにもかかわらず、合衆国の場合に「州」という、より下位の用語で訳してしまったことが、混乱の発端なのだろう。連邦なのだから「邦」とでも訳しておけばよかったのではないか。
十二月二十四日(月)社長シリーズ指揮者編
クラオタのためのトリビア。そしてすぐに忘れるので、自分の備忘録。
ミュージック・バードの「ニューディスク・ナビ」で、メナヘム・プレスラー(ボーザール・トリオのピアニスト)がコンサートホール・レーベルに録音したピアノ協奏曲集を取りあげるべく、関連情報を調べていて気がついたこと。
ショパンの二番をデイヴィッド・ジョセフウィッツという、ほぼ無名の指揮者が指揮している。こんな人、情報あるのかなと思いながらホームズの『コンダクターズ・オン・レコード』を開くと、マイナー・レーベルの指揮者に異様に強い(笑)この本には、ちゃんと出ていた。
一九一八年ハリコフ生れ、スイスをへてアメリカに移り、ボストンで化学と音楽を学ぶ。四六年に兄弟でコンサートホール・レーベルを設立。その後も同様の会員制レコード会社を多数設立。自レーベルに多くの指揮録音を残した、なんてことが書いてある。
なんと、コンサートホールの創立者がオーナーの特権で指揮していたのだ。実際の演奏会にはほとんど出たことがないとあるから、世間的には指揮者として認められていなかったらしい。
モントゥー、シューリヒト、ミュンシュなどにコネをもち(たしかにコンサートホールに録音している)、プロデューサーとしてかれらの指揮を間近に見ることで、プロの指揮者としてのマナーを身につけた……そうな。
よほど腕利きの下振りがついていた気もするが、ともかく伴奏指揮だけでなく、《運命》や《新世界より》、ヨハネ受難曲などの録音があるそうだ。
十二月二十七日(木)笑顔の力
先日、片山さんとの対談を拝聴した麻木久仁子さんが、じつは乳癌などの治療を続けられていたことを、ネットのニュースで知る。
当日は厚かましく打ち上げまでお邪魔させもらったのだが、あのチャーミングな笑顔の背後で闘病をされていたことなど、まるで気がつかなかった。手遅れだが、頭が下がる。
また、例の不倫騒動のあと、むしろ被害者のはずの麻木さんの仕事が減っていることに、どうも納得いかなかったのだが、脳梗塞と闘われていたのだそうだ。
十二月二十九日(土)PSのご隠居
プレイステーション2の日本国内での出荷終了というニュースを知る。
十九日の日記に書いた通り、うちでは発売三か月後の二〇〇〇年六月頃に買ったPS2がおかしくなったので、PS3に買い換えたばかり。偶然にも、機種そのものの寿命とほぼ重なったようだ。何か嬉しい符合。感謝と祝福を。
ゲーム機としては引退したが、パソコンのディスプレイの高さの調整用にその下に置いているので、ディスプレイ台として隠居生活を送ってもらう予定。これもPS3が、上に物をおけない仕様のおかげだ。
十二月三十日(日)フォルクスオーパーの『サウンド・オブ・ミュージック』
おそらく今年最後のCD便が到着。JPCからの、ヤノフスキの《タンホイザー》と、ウィーン・フォルクスオーパーの『サウンド・オブ・ミュージック』。前者は新年の楽しみに取っておき、後者を早速聴く。
二〇〇五年、フォルクスオーパーの舞台上演のライヴで、ドイツ語訳詞。
一九五九年のブロードウェイ初演から四十六年目にして、オーストリアでは最初の本格的なプロダクションとなった公演だそうだ。つまり、引越公演や小規模公演はあったのだろうが、大規模な自主制作はこれが初めてというわけ。ちなみに映画からは四十年目、マリア・フォン・トラップ生誕百年の節目の年。
なぜこんなに遅れたかというと、国外逃亡者を主役とするこの作品が、オーストリア人にとって屈辱的なものだから、ということらしい。占領時代の映画『第三の男』をウィーン子が嫌うというのと、似たような意味か。
トラップ一家を主役にした映画『菩提樹』が、ミュージカルよりも前の一九五六年に西ドイツでつくられているのとは対照的で、日本人にはわかりにくい、オーストリア(あくまでナチス・ドイツの被害者という立場をとる)と、東西冷戦下の西ドイツとの違いがここにある。ちなみに西ドイツでは初演後まもなく上演されており、そのディスクもあった。
さてこのCD、JPCのサイトに何の情報もなかったので、見たら指揮がエリック・カンゼルなのにまずびっくり。
ヴォン・スターデとのテラーク盤も録音しているこの指揮者を、アメリカからわざわざ招いたのだ。オーケストラの響きとあいまって、ミュージカルよりもオペレッタよりの、甘美でゴージャスな響きになっているのが、いかにもな感じで微笑ましい。
ヒロインのマリア役のサンドラ・ピレスはオーストリアの国民的人気歌手だそうだが、メアリー・マーティンやジュリー・アンドリュースの清純派系の声になれた耳には、コケットな声質とねっとりしたフレージングで、冒頭はやや違和感が残る。これまでに聴いたオーストラリア版の歌手や東宝版の大地真央のCDがジュリー・アンドリュースを意識していたのに、あえて違う個性派。ただ、その個性ゆえに〈マイ・フェイヴァリット・シングス〉は実にうまい。これはオリジナルの舞台版なので映画版と違って、修道院長との二重唱になっている。
〈ドレミの歌〉は〈ツィーディーイーの歌〉になっている(ツェーデーエーでもなかった)。しかしこれを聴いていると、映画版のあの、やたらにのど自慢なボーイ・ソプラノの声がなくて、それを思わず頭の中で鳴らしている自分に気がつく。〈エーデルワイス〉の後半も、会場を揺るがす客席全体の合唱になったりはしない。
『ウェストサイド物語』もそうだが、映画版のミュージカルは出来がよければよいほど、そのあまりに強いイメージ固定力が、その後の舞台公演にとって障碍になることを、あらためて確認。
十二月三十一日(月)新春かくし芸大会
新年のテレビの番組表を見て、『新春かくし芸大会』がないことに気がつく。
二〇一〇年が最後だったのだそうだ。たしかに近年はチラ見してもまるでつまらなかったから(メーキングを番組の最中にやってしまったり)、当然といえば当然なのだろうが。
七〇年代のナベプロ専制期。高橋敬三の司会にハナ肇の銅像コント、いかりや長介の「南京玉すだれ」などなど。何が楽しいのかよくわからない(暗記に苦労したという点では「かくし芸」なのだろうが)英語や中国語のドラマ。そして番組テーマソングの《一月一日》。
自分にとっては『レコ大』よりも『紅白』よりも夢中になれる、年に一度の楽しみだった。広いスタジオいっぱいに人気タレントや歌手が居並ぶオープニングの華やかさ…。昭和は遠くなりにけり。
制作はフジテレビだったが、フジが低迷していた七〇年代が絶頂で、八〇年代にフジの人気が急上昇するのと反比例してナベプロがダメになるにつれ、どんどんつまらなくなっていった。考えると、いろいろ象徴的な番組。
Homeへ