二〇一三年
一月一日(水)州営国立歌劇場?
明けましておめでとうございます。謹んで皆様のご健康とご多幸をお祈りします。
去年十二月の二十三日の可変日記に書いた「国立歌劇場か州立歌劇場か」の問題は、多くの方から反応をいただいた。
自分はドイツ事情に詳しい方々のご意見を拝聴しているばかりで、自力で見つけたことなど何もない。
基本にたちかえると、現代ドイツの行政区画の用語の訳語として、Staatは国家、Land(Bundesland)は州(連邦州)で、シュタートにドイツの連邦州という意味はない、という城所さんの解説が実に明快だった、という一点につきる。
しかし、用語はそうであっても、現実には歌劇場を国ではなく連邦州が運営しているのだから、「国立」は実情に合わないという意見にも、説得力がある。
これはたしかに無視できない視点で、たとえばあのFreistaat Bayern、直訳すればバイエルン自由国(共和国)だが、この言葉だけ放り出したら混乱を招く。実質的には「バイエルン州」であり、私も通常は、簡単にそう書くと思う。フライシュタートは理念としての名称にすぎない。「ドイツ連邦共和国の連邦州の一つであるところのバイエルン自由国」と書けば誤解は減るだろうが、いちいち書いていられないし。「自由国バイエルン連邦州」では、何が何だかわからない。
これと同様に、現代ドイツのシュターツオーパーも、多分に理念的な言葉なのだろう。理念と現実の、どっちをメインに訳すか、という問題だと思う。
これも教えていただいたことだが、フィルハーモニア・フンガリカが特例的に西ドイツ直営だったとき、Bundesorchester、つまりBundes(連邦の)とついていたそうだ。これに対して、シュターツオーパーはブンデスオーパーとは呼ばれない。しかし同時に、ランデスオーパーでもない。どちらでもない、理念上の名称なのだ。
宮廷がなくなっても、「カンマーゼンガー(宮廷歌手)」が名誉ある称号として残っているのと似ているのかも。
ただ、「国立」と書くと国費で運営されているような誤解を招く、という意見もよくわかる。英国のRoyal、これは別に王室が運営しているのではなく、「王室公認」という程度の権威づけの言葉だが、現在のシュターツは、これと似たものになっている。
グッドオール伝を書いたときは、この差にこだわってコヴェント・ガーデンを「王室歌劇場」とした。この方式だと、シュターツオーパーも「国家歌劇場」とか、高い格付けを意味する言葉にする手もある。ただこうすると、それこそ「ソ連邦英雄」みたいに、全体主義の国のような、圧政的な語感が生じるのが、現代日本の難しいところだ。
どれと簡単に決められるものではないが、私は国立歌劇場を使おうと思う。州立歌劇場は、シュタートに連邦州の意味がない以上、意訳の度合が強すぎるし、国家歌劇場は、語感が硬すぎるから。
まあ、州営国立歌劇場とすれば、実質も伝わるけれど、これは市営プールか何かみたいで、誰もがいやだろう……。
一月二日(水)ヤノフスキのワーグナー

初詣はいつものように、近所の須賀神社。聴き初めは、ヤノフスキの《タンホイザー》全曲盤(ペンタトーン)。
ヴェヌスブルクのバレエ音楽のない、ドレスデン版。この方がヴァージョンとしてまとまっているという考えか。
R・D・スミスの外題役の存在感がいま一つ軽いとか、ステンメは相変わらず深くていい声だけれど、エリーザベトにはちょっと重くてこもるとか、完璧な独唱陣とはいわないが、しっかりとした陣容。ゲルハーヘル(ゲアハーハーという読みもあるが、なんか取組直後の力士インタヴューみたいだ…)のディースカウそっくりの美声とフレージングは、謹厳で理屈っぽいヴォルフラムにぴったり。
ヤノフスキの指揮するオーケストラと合唱は、期待を裏切らぬ高い充実度。この人のもたれないテンポ設定とハーモニー感覚の冴え、しなやかに綾をなして、長い呼吸線で歌う弦、そして自然な緩急を加えつつ、さりげなく横に揺れて弾むリズムが、いつものように素晴らしい。
重戦車でも軽戦車でもない、つまり大仰でも敏捷でもないけれど、バランスの整った傑作中戦車のもつ、美しいフォルムと高性能。
とくに今回の「バイロイト・テン」のシリーズで気に入っているのは、各幕の最後の音だ。ほとんどの場合で引っぱらずに、フッ…と力を抜いて、あっけない終りかたをする。クライマックスへのもっていきかたが上手な指揮者なのに、リキをいれたまま汚い音で終らせて、熱演を演出するようなことをしない。
その、最後の最後にひっ外してくる、ギリギリのところで我に返させる、ある種のヒトの悪さが、なんとも実にワーグナーらしい印象を与える。その面白さ。そう、ワーグナーって本当はこういう、興ざめした顔を一瞬に見せる人だよな、といいたくなるような。
そしてそれが、敬愛するクレンペラーを想起させずにはおかない。クレンペラーの何が好きといって、そのヒトの悪さであるわけで(笑)。
いまからちょうど三十年前の一九八三年二月、共産圏のど真ん中の孤島、西ベルリンのドイツ・オペラで《ローエングリン》を聴いたときにはもっと軽い感じで、こういう存在の指揮者になるとは、思いもよらなかった。《指環》再録音と上野での実演が、ほんとうに楽しみ。
(ちなみにそのベルリンの舞台、装置と衣装は五〇~六〇年代のヴィーラント・ワーグナーのバイロイト音楽祭と、まったく同じものだった。残念ながらまるで輝きを失っていて、貴重なものを見たというありがたさは、まるでなかったが。あれはワーグナー没後百年の記念上演だったが、今年は生誕二百年)
一月三日(木)明王と明神、天神
母親、妹、山の神とのランチのあと、山の神と深川の富岡八幡へ。
しかし夕方なのに参拝者の行列があまりに長いので、挫折して隣の深川不動にお参りして帰る。十数年前に元旦に来たときも、やはり同様だった。不動堂の行列がいつも短く、近くにあるだけに、ついそちらを頼ってしまう。
二〇一〇年一月の可変日記に、将門を祀る神田明神と、その鎮圧のために護摩祈祷をした成田山が、仇敵同士とされていることを書いた。
そして、その成田山の本尊の不動明王像が「出開帳」、つまり江戸まで出張して知名度を高めたのが深川の永代寺(現在の深川不動)だったことから、この問題には将門を祭神とする神田と不動明王を守護神とする深川、つまり家康以来の下町と明暦の大火を契機に発展した川向うという、新旧二つの町人地のライバル関係が象徴されているのではないかと、妄想してみた。
さらに、その不動明王の人気と関係が深いのは市川團十郎である。何となく神田といえば落語や捕物帳の世界で、歌舞伎とは結びつきが薄い感じがするのは、この対立のせいなのだろうか。
などを思い出しつつ地図を見ると、深川と同じ新開地でも、武家屋敷の多い本所になると、江戸期の武士が尊崇した太田道灌と縁の深い天神が祀られ、亀戸天満宮となっている。またその西側には、かつて道灌が江戸城内に鬼門鎮護のために建立したという、法恩寺(当初は本住院)もある。家康入部によって移転、神田、谷中をへて元禄八年にここへ来たというから、やはり武家地では道灌と天神がセットになっているらしい。
深川の明王、神田の明神、そして本所の天神。神様とは、氏子が育むエネルギーこそが実体などと、また妄想。
一月六日(日)三月のライオン
友人方がこぞって絶賛のマンガ、『三月のライオン』第一巻を読む。なるほどとても面白く、続きはさらに面白くなりそう。「家族の喪失と崩壊と、新たな構築」がテーマの一つになっている点が、『海街diary』と共通する。あと七巻(以下続巻)も読めるのが嬉しい。
それにしても、作者が心をこめて選んだ、予告カットと第一回のあかりねえちゃんのワンピースの柄(スクリーントーン)が、偶然にも『よつばと!』のとうちゃんのパンツの柄と同じだったという巻末の話は、どちらも大好きな作品だけに、大爆笑。
一月八日(火)将門、道灌、團十郎
三日の日記に書いた、江戸の明王、明神、天神の話。
騎虎の勢いで、前に書いたことも合わせながら妄想をひろげると、武家が尊崇した太田道灌は、関東の西半分の山手側の、武蔵野の神様。
かれは洪積層を川が削ってできた断崖の上に城を造ることを好む。それは中沢新一が『アースダイバー』で指摘した、「ミサキ(御崎)」にあたる場所。縄文以来の遺跡、聖地だったことが多い。
もはや由来のわからないそういう聖地を含む城内に、道灌は自らが崇拝する天神と山王を祀る。江戸城の場合は平河天神と日枝神社が、その後身。
それに対して、東半分の低湿地の町人地を象徴したのが、大手町の、かつては日比谷入江の海辺だった場所にある、将門の首塚。
神田明神も元々はそのあたりで、その村人=のちの下町の神田っ子を氏子にしていた。ところが江戸の大開発にともなって移され、最終的に北の神田山、いまの湯島台地の「ミサキ」に定まって、半高地の神様みたいになっていく。
やがて、埋立地が発展した新開地の深川が、元禄あたりから殷賑を極めるようになると、成田山からきた不動明王とそれを尊崇する市川團十郎が、埋立地の守護神として人気を集めていく。相撲が興行として発展するのも、ここ。永代寺と富岡八幡。時期によっていくつかある芝居町はつねに別の場所にあるけれど、城東の低地にあることは、共通する。
しかし同じ新開地でも、北側の本所は武家地であるので、亀戸天満宮と道灌創建の法恩寺が鎮座する。
道灌とゆかりが深く、江戸早々からの伝統を持つ神田明神と日枝神社の大祭は将軍家と縁が深く、「江戸三大祭」に含められる。一方、浅草と深川の祭は新開地の悲しさ、どちらが「江戸三大祭」の最後の一つに入るのかを、相争って結論がでない。とはいえ、ともに新興の町人地としてのエネルギーは巨大で、しかもどちらも團十郎に関係が深いのが、面白いところ。
時代劇などを通じて我々のもつ「江戸のイメージ」は、実は化政文化以降の、幕末のそれであることが多い。それ以前の、とりわけ明暦の大火以前、また家康の入部以前の江戸というのは、曖昧模糊としていて、わからないことだらけ。
たしかなのは大半が湿地で、それに囲まれたわずかな地域に人が住んでいたらしい、ということだけ。
将門と道灌は、その「古江戸」を象徴し、二人にゆかりのある(と後世が見なした)寺社や遺跡は、「大江戸のできるまで」の変遷の様を示唆してくれる。
対して團十郎は、イメージができあがってから、いわば時空の変化が止まった「大江戸」の住人の象徴。同じ名前が代々襲名されていくことで、その継続性を象徴する(一人一人の人生は、かなり浮沈が激しいが)。
将門、道灌、團十郎。
時間を超えて江戸を象徴する、三人。(最後のひとりは江戸期だけで八人もいて時間を超える。そういえば将門も七人いたという。あれは影武者によって空間を超えるケースか)。
三人とも非業の死を遂げている。将門以外は怨霊神というわけではないが、後世の人にはかれらの霊験を考える上で、それも意味があったのだろう。
一月十二日(土)本所散歩、音の自然
今日は演奏会通い初め。
メッツマッハー&新日本フィルをトリフォニーで聴くが、その前にいい機会だし天気もいいので、武家地、本所の亀戸天満宮と法恩寺を訪問。どちらも蔵前通り沿いにあるので、錦糸町駅から歩く。城東らしく、地形はまったいら。

天満宮は受験直前で混んでいるかと思ったが、参拝の行列も短く、それらしい若者もほとんどいない。初詣にきてしまったのだろうか。自分にとっては(受験もないのに)小学六年生で母親に連れてこられて以来、約四十年ぶり。藤棚が懐かしい気もするが、記憶にあるのはむしろ『男はつらいよ』の一場面のはず。

天満宮はいうまでもなく大きな神社だが、法恩寺も予想以上の堂々たる規模をもつ大寺だった。
元禄八年に移転してきた時には二十の子院が周囲にあったそうで、現在も四つが存在し、門前の参道に並んでいる。
寺内には道灌の墓所(拝み墓)もあって、武家にとっての道灌の存在の大きさを実感させた。この寺は川向うへ移る武家への、幕府からの餞だったのではないか。もともとは江戸城内の鬼門を鎮護するための祈祷所として道灌が建てたものだそうで、幕府成立直後の慶長十年に神田柳原(今の神田須田町二丁目)へ、続いて谷中清水町(池之端四丁目)へ移されたというから、次第に遠ざかりながらも、方角的には常に江戸城の鬼門を護っていたわけだが、本所移転により、東方の武家地を鎮める役割へと変った。
残念ながら大震災と東京大空襲で焼き払われているので、建物そのものに風情は感じないが、これは向島から深川にかけての隅田川東岸全体にいえること(司馬遼太郎が『街道をゆく』でこの地域を歩いたとき、江戸期の残り香がまったく消えているため、何も書きようがなくてさじを投げていたのを思い出した)。
それにしても寺社って南を向いているものだから、正面から撮ろうとすると北のスカイツリーが必ず写るのがご愛嬌。
ついでに、両国駅で大震災前から使われていた、頭端式(行きどまり式)のホームも撮る。現在の総武線と並行する形で現存している。震災前は西側に用地がなくて線路が墨田川をわたることができず、両国駅が東方からの玄関駅だった。その事実を教えてくれるホーム。

友人のご教示によると、一九八二年までは房総方面行きの急行の発着ホームとして使われ、夏休みには大いに賑わっていたそうだ。三十年後の今は使われることなく、ベンチなどは残っているが、乗降客の姿はない。このホームへ通じる部分の駅舎は、飲食店に貸されている。
駅舎はその左の、行きどまりの先にある白い建物(一九二九年完成。今年で八十四歳)。
この駅舎と旧ホームを合わせて、歴史的建造物として修復、再現してくれないかなと思ったりする。再開発から取り残されたおかげか、震災前と昭和初期の雰囲気がこれだけ残っている駅も、そう多くないのではないか。国技館とか江戸東京博物館とか、全体が歴史記念物だらけの町なのだし。それこそ、江戸東京博物館の外部展示室にするとか。
肝心の演奏会も、とても楽しめた。メッツマッハーは一昨年の初登場の鮮やかさに較べて昨年は停滞気味に感じられ、気がかりだったが、今日はよかった。
骨太で明確な輪郭の響き、強くたくましいリズムと生命力、静と動の鮮やかなコントラスト、この人の魅力が復活。
ヨハン・シュトラウスの《ウィーンの森の物語》、ヤナーチェクの《利口な女狐の物語》組曲(マッケラス編)、R・シュトラウスのアルプス交響曲、というプログラム。
いうまでもなく、大自然への讃歌という意味合いの曲を並べているのがミソ。町の近郊の森から、村の外の大きな森、そして高山へ。人と動物が次第に減り、山川草木の雄大さが増していく。
プログラムの解説を書かれた青澤隆明さんが、アルプス交響曲が「ツァラトゥストラ」同様にニーチェの影響を受けた作品であることを強調していたのは、その点で興味深かった。
この曲は単なる描写音楽ではなくて、「山上で生きる」思想を賛美したニーチェの著作『反キリスト』を題材としている。「反キリスト」というそのものずばりの曲名が、スコアの清書直前までつけられていたという。
ずしりと聴きごたえのある、華やかさを抑えた響きを耳にしながら、キリスト教の人間観において、自然という「舞台装置」にはどんな意味があるのだろう、などと考える。
そして、音楽も。いうまでもなく西洋音楽は教会とともに発展したが、教会音楽の中心は言葉をもった聖歌。純器楽はより世俗性がつよい。その器楽が次第に発展して、これほどの大管弦楽になりおおせる。教会の占有物だった巨大なパイプオルガンもコンサートホールに据えられ、楽器の一つとして参加する。
近代オーケストラとは、教会の外に育つ、一つの「大自然」。世俗と呼ばれる自然、実在、権力。
一月十五日(火)若き英雄の肖像
毎日新聞のサイト内に「懐かしの毎日ニュース」というコーナーがある。
そこで五十年前の今日、いわゆるN響事件でN響からボイコットを受けた小澤征爾を励ますために「小沢征爾の音楽を聴く会」が日比谷公会堂で開催されたことを、当時のニュース映画(映画館で劇映画の合間に上映されていたもの)で見ることができるのを、フェイスブック上で教えてもらった。
半世紀前の小澤の周囲の文化人たちなど、短いながらとても示唆に富んだ映像だが、何といっても面白いのは一瞬だけ流れる《未完成》第二楽章の、異様にアグレッシブな怪演。
映像の方は、編成から見て後半のチャイコフスキーの交響曲第五番あたりを重ねてしまっているようだが、こちらもトーサイこと齋藤秀雄の軍楽隊調にミュンシュのダイナミックさを混ぜたような指揮ぶりが面白い(当時の映像と音声は別録りで編集時に重ねるから、こうしたことが当り前に起きる)。
二十七歳のこの熱演を視聴すると、当時『ボクの音楽武者修行』が若い世代からなぜあんなに支持されたのかが、よくわかるような気がする。
「小澤征爾 N響騒動から涙の公演 1963年(懐かしの毎日ニュース)」
http://mainichi.jp/feature/nostalgicnews/news/20130115dog00m040023000c.html
あるいは
http://gyao.yahoo.co.jp/player/01061/v00001/v0000000000000000056/
一月十七日(木)若き獅子たちの時代
十五日に書いた、半世紀前の小澤征爾の映像を見て、感じたこと。
この映像、前の年に結婚したばかりの最初の夫人江戸京子が、かなり頻繁に出てくる。現代ではこのくらいどうということはないが、それまでの「封建的」な日本の夫婦にはなかった、むき出しの仲むつまじさ。リハに立ち会い、演奏会では舞台袖で出迎え、礼状(?)書きを手伝う。「内助の功」に収まらない、あけっぴろげな感じが、かなり欧米風。
このあたりも、当時の小澤が放った新時代、若い戦後世代のイメージにぴったりなのだろう。
で、これを見て思い出したのが、N響事件の一端に、この夫人をめぐる逸話が関わっていたという、安倍寧の『音楽界実力派』(音楽之友社)の記述。
小沢が、N響のあるコンサートで、所用のため遅れてくる京子夫人を、ミキサー室でもなんでもいいからのぞかせてくれと、事務局員に頼んだときのことである。
しかし、NHK側は、演奏中は何人もホールその他に入れないという規則をタテにとり、この小沢の頼みをかなえてやらなかったから、えらいことになった。控え室で、彼は、「ぼくの愛する人に、ぼくの音楽を聞かすことができないというのは、どういうわけだ」とあたり散らしたのである。
この小沢の「ぼくの愛する人……」という発想そのものが、日本的でなく、日本人なら、たとえ、そう思ったにしても口には出さないところだが、それを抑え切れずにぶちまけるあたり、まさに小沢の小沢たるユエンということができる。
さらに運悪く、小沢がわめいたときに、NHKの阿部真之助会長が同室だった。阿部氏は、あたり散らす彼を横目でにらみながら、「なにを、このわがまま小僧め」と思ったらしい。
例のNHK、N響との紛争のおり、阿部氏が、思いのほか小沢に同情的な立場をとらなかったのは、このとき、小沢に対する印象をいちじるしくわるくしたからにほかならない。
この記述の内容が真実かどうかは未確認だが、映像の二人の様子を見ると、なにかとても納得できるものがある。
ちなみに原田三朗の『オーケストラの人びと』(筑摩書房)には、
小沢は同級生のピアニスト、江戸京子と結婚した。のちに離婚したが、N響と契約したのは婚約中だった。若い小沢が、N響の常任指揮者になった裏には、京子の父である三井不動産の経営者、江戸英雄が介在したという話が、そのころの週刊誌をにぎわせた。
自民党の有力者を通じて、NHKに工作し、のちに会長になった専務理事の前田義徳をへて、小沢をN響の指揮者にするよう命令がきたのだという。
という話が出ている。ただしこの中の「常任指揮者」という地位は、当時は広く信じられた噂だが、実際は十二月まで半年の指揮契約を結んだというだけ。
とはいえ、その半年の間、定期演奏会などN響の主催公演や北海道、東南アジアへの演奏旅行はすべて小澤ひとりの指揮だったのだから、実質的には常任、いやそれ以上の頻度での登場になった。
だのに、N響としての待遇は、ただの「指揮者」だった。このあたりに、トップダウンによる問題の難しさが見える。
前田NHK会長といえば佐藤栄作との関係の深さが有名だから、「自民党の有力者」もそのあたりか。
それにしても『ボクの音楽武者修行』の単行本がこの年の四月に出版、六月からN響と契約、その後に江戸京子との結婚と、六二年初夏の小澤は、まさに昇竜の勢いにあったというほかない。
当初は六、七月の二か月の契約だったのに、秋に客演予定のクーベリックがキャンセルした偶然も重なって、十二月まで延長になったのは、NHK上層からの指令だけでなく、小澤の人気が凄かったことの証明だろう。
前述の安倍寧の著書に「NHK交響楽団の公開録音のとき、エフレム・クルツ指揮の演奏が終り、アナウンサーが、次回の指揮者は小沢征爾とつげたとたん、場内からキャーッという、『ウエスタン・カーニバル』そこのけの歓声が上がったことがある」とあるのは、当時の若い聴衆の雰囲気を端的にあらわしている。
半年後、その反動のように起きたN響事件でも、反権威志向の強い当時の週刊誌などは、大半が小澤の味方についた。そしてかれを支持する文化人と若者たちが、あの映像にある特別演奏会を開催して、熱狂的な喝采を贈った。それに対して、小澤もあの《未完成》のようなアグレッシブな大熱演で応える。
時代の気分、そのもの。石原慎太郎と裕次郎の兄弟が突破口を開いて、『何でも見てやろう』の小田実、『太平洋ひとりぼっち』の堀江謙一が続く。『ボクの音楽武者修行』の小澤も、この「若きヒーロー」の一群のなかにいる。
同じ六二年六月開始の『竜馬がゆく』の坂本龍馬が熱狂的に迎えられたのは、この時代の気分を抜きにしては考えられないだろう。
そして、そのやんちゃぶりが、旧制高校的なバンカラ精神や大正リベラリズムを根っこにもつ老齢の実力者たちに愛されるのも、六〇年代前半のヒーローに、多かれ少なかれ共通する特徴といえるかもしれない。小澤を後援した水野成夫や江戸英雄などはその典型だ。
龍馬が松平春嶽や勝海舟に愛されるのは、まさにそれに呼応する。そういえば『竜馬がゆく』が載ったのは、水野成夫の産経新聞だ。
一方、六〇年代半ばから後には、主に創作の世界に限られるが(その理由の想像は、ここではおく)、土方歳三と沖田総司の新撰組や、高倉健のやくざ映画といった、負のヒーロー、敗者の美学を背負った連中も、人気が高まってくる。
司馬遼太郎が凄いのは、こちらのヒーロー像もまた、『燃えよ剣』で見事に描いたこと。
ちなみに自分は司馬作品の愛読者ではあるが、『竜馬がゆく』はいちばん苦手な作品。龍馬とか高杉晋作への憧れを公言する人は、敬して遠ざけたい。
また、「若大将」の加山雄三や「無責任男」の植木等が、この六〇年代のヒーローの光と影の図式にはうまく入らないのが愉快。それだけ東宝映画は、時代を突き抜けて偉大だということで、勘弁してもらおう(笑)。
長嶋も、東宝映画の仲間かも。かれらは「明るい高度成長」そのものの体現者のようでもあり。
なかでも「若大将」は、シリーズそのものは忘れられても、ホイチョイ・プロダクションズに深い影響を与えたのは有名で、たしかにバブル時代の、あの浮薄な気分の原型という気がする。あれが、日本型の消費社会の一つの極楽だったのは否定できないわけで……。
一月十八日(木)この目に
なんとか今年の二月のうちに、見に行こうと思うもの。
・東急東横線渋谷駅の頭端式ホーム(三月一六日に地下化予定。原型は一九二七年開業)
・東急百貨店東横店の東館(三月末で閉店。一九三四年開業)
・上野の同潤会アパート(五月に取り壊し。一九二九年落成。現存する最後の同潤会アパート)
前の二つは、緑が丘に住んでいたころ毎日のように歩いたところなので最後のお別れというだけだが、同潤会アパートはそれと意識して見たことがない。本郷の下宿、本郷館はとうとう現物を目にできないうちに壊されてしまったので、最後の同潤会アパートはなんとか…。
一月十九日(土)メッツマッハーの未完成プロ
サントリーホールで、メッツマッハー&新日フィルの、シューベルトとブルックナーの未完成プロ。
面白かった。特に後者。「宗教の代用品としてのクラシック音楽」の、象徴といってもいいブルックナーの、そうした要素をきっぱりと拒絶していたから。それでいて無機的ではなく、きわめて人間的。まあこれは、意図したものとそうでないものの、両方があいまってのことでもあるけれど。
先週のアルプス交響曲の演奏はこの日記に書いた通り、作品が風景の描写音楽であると同時に、元々はニーチェの『反キリスト』の音楽化として構想されていたという視点に立つと、なるほどと思えるものだった。
その点で、青澤隆明さんの曲目解説はとても示唆に富んでいた。(「交響曲」という名の交響詩だと、割り切っていたのも面白かった。あくまで理念としての交響曲)
脱キリスト教の次は、脱代用品。
一昨年の「666、獣の数字の悲劇」プロと同様、連続性が愉しい、メッツマッハー独特のプログラミング。
両日を通じてメッツマッハーは、陶酔ではなく覚醒を求めてくる。
ブルーノ・ワルターが、ヴァイマール時代のベルリンの精神文化の特徴はあらゆる点で「覚醒」していたことだと語っていたのを、思い出す。
歌う箇所と踊る箇所とを画然と区別して、それぞれの性格を意志的に強調するというメッツマッハーの方法論が、まさにワルターやトスカニーニ、クレンペラーたちの、三〇年代の演奏をはるかな源とするものだからだろう。なだらかにさりげなく、いつのまにか変容していくことをドイツ交響楽の理想としたフルトヴェングラーとは、正反対の思想。
もちろん、覚醒という名の陶酔になっていく危険もあるけれど。
一月二十日(日)小澤のライヴ音源
十七日に書いた小澤征爾話の続き。
N響事件のあと、NHK側の拒否反応がいかに長く続いたかを示す文章を紹介する。
芸術現代社の『小澤征爾の世界』所収の、福永陽一郎の「日本の小澤から世界の小澤へ」という文章から。初出は一九七四年十一月号の「芸術現代」。事件から約十二年後である。
NHKとの話は、もう古い古い昔のことになってしまった。しかし、“戦後”は終わっていない。十月にNHKのFMは、小澤の《第九》のレコードを放送した。これは一部の人々を驚かせた。もう何十枚も名曲のLPが小澤の指揮で発売されているにもかかわらず、NHKのFM放送のレコード番組で小澤のレコードが放送されることは絶対になかったからである。小澤は“アレ”以来、NHKのFM音楽番組に出たことがない。レコードでもそうだから、ナマ演奏などあり得るはずがない。例外があって前に小澤がトロント交響楽団を帯同して来日したとき、フェスティバル協会との契約上、NHKはその演奏会を収録して放送しなければならなかった。NHKは、いま実況録音している演奏会がトロント交響楽団のものであることは何回もアナウンスしながら、その指揮者が小澤征爾であることは、必要の最小限度、つまり一回の放送につき一回しか口にしなかったのである。
私はまだ小学生だったので実感がないが、こうした状況は、周知のことだったのだろうか。これがホントなら、いやほとんどホントなのだろうが、NHKの執念深さは凄い。
ただN響と絶縁、という問題にとどまらず、NHK本体の音楽番組において、十年以上も小澤征爾は存在しなかった、というのだ。
当時のクラシック好きにとって、NHKのラジオの音楽番組がいかに大きな存在だったかは、私などが言う必要もないだろう。
一九六九年四月のトロント響来日公演での、指揮者の名前を「一回の放送につき一回しか口にしなかった」にいたっては、恐るべし。解説なしでアナウンスだけだったのだろうか。指揮者の名をけっして口にせずに、生放送で演奏の解説をしろといわれたら、ものすごく大変だろう。オレなんか絶対に無理(笑)。
まあ、NHKだけでなく、かつての日本の企業体質、組織体質というのが、現代では信じられないくらいに陰湿で小姑根性にねじくれていて、執念深いものだったのは、自分もなんとなく知っている(今でもあるだろうが、もっとムラ社会的で、露骨だったと思う)。
もちろん、NHKも人が替るにつれて態度が軟化したろうし、グラモフォンからボストン響との録音が続々と発売されはじめた七〇年代後半以降は、いくらなんでも無視は不可能になったろう。
一九八六年、LPの末期に出たN響創立六十周年記念の二十五枚組の放送録音集には、小澤征爾が作曲者臨席で日本初演を指揮したことで名高い、六二年のメシアンのトゥーランガリラ交響曲が含められたくらいなのである。
ただしこれは、当初は全曲の予定でサンプル盤もできていたが、小澤側の強い要請で、楽章三つのみの抜粋収録になったそうだ。
これに限らず、小澤の過去の放送録音やライヴ録音は、本人の許可がとれないので、CD化が難しいという。
小澤のライヴ放送で最も伝説的なものは、七二年六月十六日の、旧日フィル最後の定期のマーラーの《復活》だろう。前述の福永の文章でも触れられている。
「この日の《復活》は、特殊な事情のもとにおこなわれたことも手伝って、空前の名演奏となった。それはFM放送を通じて一度ならず放送され、エア・チェックをした熱烈なファンにとっては、発売されたどの《復活》よりも感銘深い演奏記録となって所有されているのである」
この録音のオリジナルが現存していることは複数の関係者から聞いているが、小澤と現在の日フィルとの関係から見ても、発売許可は出そうにない。
しかし、自主制作のLPが存在していたらしい。以前、何かの専門誌の「珍盤自慢」みたいなコーナーで、取りあげている人がいた。
それで存在を知ったのだが、現物は見たことがない。音友ムックの『小澤征爾NOW』、これには小澤のレコードのコンプリート・レビューがついていて、トゥーランガリラの全楽章の録音についても解説しているくらい詳しいものだが、ここにも出ていない。
どうやら、エアチェック・テープなどからつくられた、ブートレグのたぐいだったのではないか。
二十年ほど前、日本のオーケストラの自主制作盤の蒐集で有名な俵孝太郎さんに、「この盤をお持ちじゃないですか」とたずねたことがあった。
すると、それまでの笑顔がにわかにこわばり、「持っていないし、たとえあったとしても名演であるはずがない。名演などというのは作り話でしょう」と、木で鼻をくくったようなご返答。
考えてみれば、産経新聞出身で保守派の論客の俵さんが、旧日フィル末期の労働組合活動を認めるわけがない。
それどころか、あとで日フィル分裂に関する本を読んだら、非組合系の新日フィルを支援する側にお名前が出てきた。
こちらが何も考えず、何も知らずに言っていることが明らかだったから放置してくださったのだろうが、まさしく「虎の尾を踏む」ような質問をしたのだと気づいて、あとで青くなった。
汗顔の至り。「失礼だけが人生だ」
一月二十一日(月)シンフォニスト
サントリーホールで、セゲルスタム指揮の読売日本交響楽団演奏会。
遅刻して前半のモーツァルトのピアノ協奏曲第二十三番(独奏:菊池洋子)は聴けず。後半のマーラーの交響曲第五番のみになったが、見事な演奏だった。
豪快というか豪放というか、とにかくオーケストラが綺麗に轟然と鳴り響く。これぞシンフォニストの作品、シンフォニストの演奏。
一月二十二日(火)オルガンなしとスト
このところ、東京のオーケストラの曲目重複が増えている。
マーラーの交響曲第五番は、昨日聴いたセゲルスタムの前後にインバルと都響が演奏していた。メッツマッハーで聴いたアルプス交響曲は、少し前に大野和士と読響が演奏し、三月末には上岡敏之と日フィルが演奏する(二月十三日付記:さらに六月に、フルシャ指揮都響も演奏するそうだ)
マーラーの《嘆きの歌》は去年から今年にかけ、アルミンク指揮新日フィル、インバル指揮都響、秋山和慶指揮東響の三団体が演奏する。
さらに九月のシーズン開幕には、メッツマッハー指揮新日フィルとインキネン指揮日フィルが同日に《ワルキューレ》第一幕を取りあげる(ともに二日間あるので、聴き較べることが可能)。
話かわって、そのアルプス交響曲。
少し前に出たヤマカズ&日フィルのシリーズ三枚を、先日ようやく聴いた。
一九六九年一月十六日、東京文化会館のライヴ。四十四年前に日本のオケがこの曲をやることがいかに大変だったかを随所に感じるわけだが、特に当日のプログラムに書かれた一言に、深く時代を感じる。
「オルガン カワイ楽器フルスケール電子オルガンC‐一〇〇を使用」。
パイプオルガンがないのだ。東京文化会館だけでなく、当時の主要なコンサートホールは日比谷公会堂も新宿厚生年金会館も、オルガンはなかった。
一九七二年に開場した新しいNHKホールはその設置が自慢だったが、多目的ホールなので正面ではなくサイドに設置する、いま考えるとかなり無理のあるスタイル。コンサート専用で、舞台正面にオルガンが鎮座するホールが当り前になるのは、東京ではバブルへと動き出した一九八六年の、サントリーホール開場以後のこと。
(二月十三日付記:お読みくださった方から、コンサート専用のオルガン付ホールは、一九八二年開場の大阪のザ・シンフォニーホールが最初では、というご指摘をいただいた。おっしゃる通りで、東京の話だからとサントリーホールからにした私の記述は、不正確。東京偏重のクセはいけない。お詫びして訂正し、本文にも「東京では」と加えておきます)
さてこのヤマカズの三枚では、演奏としてはプロコフィエフの交響曲第七番と《サロメの七つのヴェールの踊り》、一九七一年一月二十七日の日比谷公会堂での定期演奏会の二曲が、ハチャメチャのヤマカズ節が炸裂していて気に入った。
それにしてもこの日は、ほかに《亡き子をしのぶ歌》だけで、合計六十五~七十分という、ずいぶん短いプロ。プロコフィエフ、マーラー、シュトラウスという演奏順もちょっと不思議。
ところで日本フィルハーモニー協会編著の『日本フィル物語』(音楽之友社)によると、この公演の十八日後の二月十四日から三日間、日フィルは返還前の那覇の米軍施設で演奏会をすることになっていた。
これは米軍の招聘によるもので、軍人とその家族の慰問、県内の邦人との融和が目的。横田基地から米軍機で往復する予定だったというのだから、まるで進駐軍時代のようだ。
まだ「アメリカがくしゃみをすれば日本が風邪をひく」といわれた時代。返還条約の協議がまもなく大詰めを迎えるこの時期に、財界も米軍も関係の良好さを周囲に宣伝したかったのだろう。
しかし、朝日新聞的な左翼色がきわめて強かった社会風潮のなかで、ヴェトナム戦争の後方拠点へ、まるで戦時中の移動音楽会のような米軍慰問に行かされるのを楽員が嫌ったのは、当然のこと。
結局、直前に基地勤務の労働者(昔風にいえば軍属か)のユニオンが待遇改善を求めるストライキをしたため、混乱を避けるという理由で中止になった。
日フィル自体も、この年の十二月にストライキを行い、翌年の解散、分裂という最終局面を迎えることになる。
ストライキという言葉自体も、懐かしい気がする。この頃までは交通機関の春闘など、ストはごく身近なものだった。現代では、ユーザーの反感を買うことを何よりも恐れてまず行なわれない。現代の労働者は仲間意識よりも、互いに消費者として牽制しあっている。
一月二十三日(水)「友達」の数
フェイスブックなどSNSでは、「友達」というシステムが重要である。
現実社会では、友人の数を日々チェックしている人はごく少ないと思う。年賀状や挨拶状の枚数を数えるときくらいだろう。そのときだって、友人と知人、仕事の上での儀礼的関係、それらの境界はあいまいで、ごちゃ混ぜだ。しかしデジタル世界では「友達」の数が、きっちりと表示されている。
その数は人それぞれで、数人の人もいれば数千人という人もいる。フェイスブックでは五千人が上限らしい。
しかし、その五千人の書き込みを毎日読んで「いいね!」を押してレスを書くなんてことが、生身の人間に可能だろうか。もちろん、アクティブに書き込む人は限られるが、一割でも五百人だ。
自分などにはとても無理だと思って、見知らぬ方のブログなどをのぞくと、どうやらフェイスブックには「エッジランク」というのがあって、つきあいの深い友達二百五十人を選んで、その書き込みだけ表示する仕組みだそうだ(これは初期設定で、望むなら増やせるそうだ)。
その序列を決定するのは、フェイスブック自慢の判定システムによるらしい。
たしかに二百五十人くらいが限界か。とはいえ、自分にはまだ多すぎる。すると、世の中には「ダンバー数」というのがあることを知る。
細かい説明は省くが、要するに人間が全員を認識しあい、理解しあえる集団の上限が百五十人くらい、という研究だそうだ。軍隊でいえば一個中隊(百六十人くらい)にあたる。
そういえば小学校は一学年百二十人、中学は百六十人で、このあたりまではほぼ全員の顔と名前が一致しているが、高校の五百人は自分のクラス+αしかわからないから、個人的にも納得できる数。
これはリアルの、個人差のある人間全員が相互に理解しあえる数だから、もっと多くの仲間と濃密につきあえる人もいるだろうし、複数の集団に属して、それぞれの関係を使い分けることも可能だろう。二百五十人というのは、そうした誤差を加えた数なのかも。
一月二十六日(土)音同ミニOB会
昨年に続き、大学のサークル、音楽同攻会の近い学年によるミニOB会。自分より五年上から三年下まで、九年にわたって計十八名。二次会はOBの経営するバーに押しかける。
今日は参加しなかった三年下の後輩が政経学部の教授になっていると聞いて、びっくり。ごくまれに優秀な人が出る。
一月三十一日(金)渋谷
アルテスの木村さんと、新企画について渋谷で打合せ。
面白いものになりそうな気がする。東横線の地下化を一月半後にひかえ、大きく変る直前の渋谷。
二月二日(土)正春寺と諦聴寺、箒銀杏
新国立劇場の「タンホイザー」に行くが、所用のため一幕のみで失礼。いつものように、甲州街道を四谷まで歩いて帰る。この道程で私がいつも楽しみにする場所を、まだ日があったので撮影。(なおここの説明文の内容は、二〇一〇年四月十八日の日記などと重複している)
まずは、初台交差点から新宿方向へ三百メートル、西参道口交差点のカドに並んで建つ、正春寺と諦聴寺。このあたりも空襲で焼き払われているから戦後の再建だが、いまはうまく古びて、とてもいい感じになっている。
写真は、正春寺脇の墓地から諦聴寺の庫裏を写したところ。建物の雰囲気といい、裏の竹林といい、とても首都高四号線と国道二十号に直に面した寺とは思えないのが、好きな理由。


緑豊かな理由はおそらく、この竹林の裏側が玉川上水であるため。水が豊かなおかげで、武蔵野の気配が残っている。そのせいか、甲州街道を歩くときも、ビルの真下で殺伐と乾いた北側よりも、この南側の歩道の方が空も広く、はるかに気持ちがいい。
もともとは単に景色がよくて気に入ったのだが、調べてみたら四谷周辺地域とも関わりがある。
正春寺は由緒も面白いが長くなるので省いて、この墓地には、大逆事件で刑死した管野スガ(幸徳秋水の愛人)の墓がある。処刑されたのは、例の我家から近い曙橋の近くにあった東京監獄なので、私が関心を持たすにいられない人。
そして諦聴寺の方も、嘉永年間まで四谷にあったのが、ここへ移転してきたのだそうだ。
続いては、そのさらに百メートルほど新宿より、文化服装学院の西側に立つ、箒銀杏(ほうきいちょう)。この愛称はほうきを逆さに立てたような形をしているから、だそうだ。
樹齢二百年、由緒ある古木のほぼすべてが戦災や都市化で失われている渋谷区では、貴重な樹。
大きな木だが、いまは高層マンションのカドに、最低限の場所を与えてもらっているだけ。樹木にとって大切な南と東側は、無情にもコンクリートの壁にふさがれている。切り倒されなかっただけ感謝しろということかも知れないが…。
それでも、何だかこの銀杏はとても温かい。私が甲州街道を歩いて帰るのは、この木に挨拶するためというのが最大の理由。
このあたりは、江戸時代の甲州街道そのままの位置。江戸の切絵図にも「天満宮」として表示されている(根元に小さな天満宮の祠がある)。
たぶん、近藤勇や土方歳三や沖田総司などの連中も多摩方面への武術指南の行き帰り、この銀杏を見上げたはず。そう思うときの、樹を通じて時間を飛び越える感じが嬉しい。
そして、天満宮とくれば太田道灌伝説(笑)。こんな場所にも道灌はちゃんと伝説を残していて、西側の「初台」という地名、これは道灌がこの地域に設けた八つの砦(烽火台)の、最初の一つがあったからだという。古江戸城の陸の連絡路はいまの甲州街道だったはずだから、あながち荒唐無稽ではない。
ということで、ミニサイズの祠に今年初めてお参りして、帰宅。
二月三日(日)鏡花オペラの流行
いまや国産オペラのメッカと化した観のある新国立劇場の中劇場(プレイハウス)で、水野修孝の《天守物語》。
これは旧作の再演。原型は一九七七年作のテレビ用オペラ。新作も去年はここで池辺晋一郎の《高野聖》初演があり、半年後にも香月修の《夜叉ヶ池》初演が予定されているので、日本オペラ界は泉鏡花がブームらしい。
その幻想性と耽美性がオペラの題材に向き、独特の古い口語体が歌詞に使いやすいからか。中劇場も、いっそ《鏡花記念プレイハウス》とか改名してみたら面白いのに。
《天守物語》は、七〇年前後の唐十郎や蜷川幸雄などのアングラ演劇での鏡花の流行を受けて生れたものだろうが、近年のオペラ化の流行は、玉三郎が積極的に鏡花の戯曲を取りあげていることがきっかけにちがいない。そのなかではあと《海神別荘》が未オペラ化だと思う。
鏡花のこうした異界ものには、西洋の幻想小説や映画の影響が濃いから、オペラの劇構造に合うのかも。
日本を舞台にした作品というと、その「日本性」をどのように音楽にとりいれるかが問題になるけれど、近年の作曲家はほとんどが、オペラも含め、西洋音楽の楽器と語法によって作曲している。
一九六〇年代に、やや無理をしながら和楽器を用いるのが流行したのとは、隔世の観がある。生活様式そのものの無国籍化が進んでいることを思えば当然なのだろうが、過去の文学作品を題材にオペラ化しようとしたとき、そこに違和感が生じることになる。
二〇一〇年初演の池部晋一郎の《鹿鳴館》が、まさにそうだった。三島の原作が前半を和風(茶室と着物)、後半を洋風(鹿鳴館とドレス)と、視覚的印象を明白に違えて見せているのに、音楽はそのことに注意を向けさせず、同じような響きでそろえていた。
鹿鳴館への壮士の乱入も、板につかない洋装に対してザンギリ頭の和装、滑稽なもの同士の衝突を象徴する場なのに、音楽も演出もほとんど素通りした。
これでは明治や大正という時代を振り返ってみても、単なる懐古趣味、ノスタルジーにしかならないと思う。三島が鹿鳴館時代と、執筆当時のアメリカナイズが進む戦後日本とを重ね合わせ、そこに精神の危機を見ていたこと(それをどう評価するかは、また別の問題)が、まったく見えてこなくなる。
しかし昨年の《高野聖》には、そうした不満はなかった。人煙まれな峠道を登っていくうちに異界へ入り込んでいく、その雰囲気を音楽はとてもよく出していた。登場人物が着物を着ているからといって、別に邦楽を使う必要は感じなかったし、使ったらむしろ違和感があったろう。鏡花の物語や人物造形に、西洋的なものがかなり混じりこんでいるからではないかと思う。
今日の《天守物語》も同様。さすがに再演を重ねる、鏡花オペラの古典だけのことはある。ただ、天守の異界と地上の人間界、その不気味だが明確な高低の境界(すぐそこに見えているのに、人が手を出せない境界)を、もっと生々しく感じさせる、想像させる舞台装置なら、雰囲気がさらに出ただろう。
鏡花の異界もの、個人的にとても聴いてみたいのは、交響的モノドラマ《高桟敷》。鮫ヶ橋を舞台にした、すぐそこにある異界の、幻想譚。誰かつくってほしい。
二月七日(木)サロネンの歴史認識
三夜連続、サロネンまつり。
初日の今日はオペラシティ。ルトスワフスキの交響曲第四番とベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番(独奏はアンスネス)、そしてベートーヴェンの交響曲第七番。ルトスワフスキもさすがの凄さだったが、今日は何より交響曲第七番。
この作曲家ならではの野性味、野趣をこれほど都会的に、現代的に、鮮烈に聴かせてくれるとは。
ピリオド風に音を素早く減衰させ、強弱長短の変化を俊敏に加えて、一瞬も飽きさせない。そして主に管楽器にあらわれる、突拍子もない音型を鮮やかに浮き上がらせることで、この作曲家の「ぶっ壊れた」魅力、破壊と革新のパワーを、モダン・オーケストラを用いて、いまこのとき、ここに現出させる。
その象徴が、ナチュラル・トランペットの、耳障りなまでに強烈な響き。ナチュラル、この危険な天然野郎(笑)。乱調の美。「永遠の革命児」ベートーヴェンの姿は、こうやらなければ見えてこない。ブリュッヘンが十八世紀オーケストラとやろうとしたことを、恐るべき高水準で止揚してみせる。
サロネンは、古典作品ではモダン楽器との音量のバランスがとれれば、ピリオド楽器を積極的に導入するそうだ。ティンパニも、ピリオドの硬い響きだった。
そしてアンコールの《悲しきワルツ》で、十九世紀初頭とはまるで異なる、二十世紀初頭のオーケストラ音楽の機能的な響きを聴かせることで、ベートーヴェンでの(破綻を含んだ)音楽づくりが完全に意図的なものであることを、これまた鮮やかにわからせてくれた。
ここには、ものすごく正当で深い歴史認識と、その実践がある。サロネンの天才は、古典から現代まで、それぞれがその誕生の瞬間に持っていた鮮烈さを、甦らせてくれることにある。
二年前の幻想交響曲も素晴らしい演奏だったのは承知の上で、正直、こんなベートーヴェンを聴かせてくれるとは思ってもいなかった。反省。
ただしピアノ協奏曲は、自分は曲がどうしても苦手。ベートーヴェンの第三~五番の協奏曲はナマで聴くと、なぜかかならず飽きてくる。美しい瞬間はたくさんあったが、正直にいえば、第二番か第一番が聴きたかった。アンスネスのディスクの第一番もよかったし。だが真面目な音楽好きの多い日本では、三番以降でないと売れないのだろう。
ともあれ、同じ第四番を明日はサントリーで聴くし、日曜日にも期待のリシエツキのピアノで聴けるので、自分のなかで、何かが目覚めることを願うのみ。
二月八日(金)ホールと曲
サロネンまつりの二日目は、サントリーホール。
オペラシティのようなシューボックス型のホールは十九世紀までのオーケストラ音楽に向き、サントリーのようなワインヤード型は二十世紀の複雑な音楽に向くと、音響設計の方にうかがったことがある。昨日と較べて、まさにその通りの差が出た演奏会だった。
つまり、前半のベートーヴェンにはホールが合わない。《シュテファン王》序曲は冒頭の、東洋音楽みたいに揺れる木管群とかっちりした弦楽の対照が面白かったけれど、後半は何かつるりとして、盛りあがらなかった。
じつは「サロネンのベートーヴェンてこんな感じでは?」と昨日の交響曲第七番を聴くまで予想していたものに、きわめて近かった。昨日はその予想を、ものの見事にちゃぶ台返ししてくれたので大感激したのだが、今日はそうはいかず。
続くピアノ協奏曲第四番は、さらにつらかった。昨日は(アンコールのソナタ第二十二番の第二楽章も含めて)ピアノの音に剛毅な強靱さが感じられる瞬間があって、その点がとてもよかったのに、今日は得体の知れない、手応えのない響きに。
私の席が二階正面前列という、特に音響に正体がない場所だったせいもあるのだろうが、こんなに違うのかと、あらためて痛感。せっかくのナチュラル・トランペットも昔風のティンパニも音が散ってしまって、威力半減。
これに対して後半の《巨人》は、さすがにホールに合っていた。小澤征爾の言う通り、ドイツ・ロマン派風のピラミッド型の和声でできた音楽ではない、一種の音のパズル、というよりモビールみたいにユラユラと連動していく音響には、このホールが合っている。
ベルリオーズ~リスト~マーラーという、フランスから入ってきた管弦楽の流れが、ちゃんと感じられるのだ。
いちばん好きなのは第三楽章。コントラバスのソロに始まって、さまざまな楽器が光りと彩りを多種多様に変化させつつ行進していく、その百鬼夜行が愉しかった。終楽章の最後の盛り上げと畳み込みも、見事。
しかし、私にとって啓示的だったのは第一楽章の進行。前半が音型を深くえぐらず、すべてが靄にかすんだように進行して、「?」と思っていたのだが、冒頭に舞台裏で鳴らされたファンファーレが二回目に舞台上で響いた瞬間、響きがまとまって色彩も少しはっきりした。「あれ、これは?」と予感させた通り、三回目に高らかに鳴らされたときには、オーケストラ全体がヴィヴィッドに、明快な肉体を持って、波うつように、大きく動きだした。
音だけ聞こえる~視界に入る~眼前に出現という三段階で、トランペットに先導された凱旋の行進が、やってくる。
これを、単なる音量の増大ではなく、音像そのものの輪郭と色彩が明確化、肉体化する過程として、鮮やかに描きだしてくれた。真の意味での、音のパースペクティブ。
マーラーがそう書いてんだよ、といわれればそれまでだが、こんなにはっきりと聴きとれたことはなかった。マーラーになって用いられたバルブ・トランペットが、モダン・ティンパニとともに、大活躍。
驚きという点では昨日のベートーヴェンの交響曲第七番ほどではないが、やはり得るものの多い《巨人》だった。
二月九日(土)ネコケン、サロネンを語る
サロネンまつり三日目は、横浜のみなとみらいホール。諏訪内晶子を芸術監督としてスタートした、国際音楽祭NIPPONの一環である演奏会。
《シュテファン王》序曲にシベリウスのヴァイオリン協奏曲、交響詩《ポホヨラの娘》、そしてサロネン自作のヴァイオリン協奏曲の日本初演(独奏は二曲とも諏訪内晶子)。
音楽に加え、今日がラッキーだったのは、隣席が金子健志さんだったこと。
「昔、カラヤンの何日間連続とかの来日公演があったけど、それに較べても今回は、曲目にこれだけバラエティがあるのが、素晴らしいよね」に始まって、サロネンの指揮する音楽を、その場でネコケン先生の解説と感想の独占中継つきで味わえる。
嗚呼、音楽乞食をやっていてよかったと心底思う、幸福。
最初の《シュテファン王》、やはりサントリーとはまるで違う、かっちり実体感のある響き。ただ、三日間とも一曲目は暖気運転の気配もあった。
シベリウスでは、後半一曲目の《ポホヨラ》がダイナミックに、俊敏に躍動して、冴えまくり。
さすがですね、と水を向けると、
「この曲をこれだけ振れる人は、いま世界にこの人だけでしょ」
同感。このあと、「サロネンのシベリウスってさ……」とネコケン先生の解説が続いたが、ここは企業秘密(笑)。
そして、サロネン自作の協奏曲。
第三楽章途中で突然中断、指揮者と独奏が袖へ引っ込む。
すると、静寂の客席でネコケン先生、俄然しゃべり始める。無言状態を恐れるラジオ解説者の本能か?
「なんだろ、E線が切れたんじゃない?
バチッと切れなくても、伸びたように切れることがあるから」
「いま、第三楽章のスケルツォだよね。トリオ的な部分へ入るかな、と思ったら止まっちゃったね」
――すいません、いまどこなのか、私まるでわかってませんでした(汗)。サウンド自体はともかく、基本的には古典的な構成だったんですね…。
袖から響くチューニングを耳にして、
「ああ、張りかえてるね。少し時間かかるかも。こうなると、張ってもまた切れたりするんだよね…」
とにかくしゃべってつなぐ。周りのお客さんも安心したことでしょう。
二人が戻ってきて、楽章頭から再開。無事終演。
これは本人以外は、さばくだけで大変な曲ですね、というと、
「うん! とてもしっかり書いてある曲だから、指揮はごまかしようがないね、これは」
「作曲面でこの人に最も影響を与えてるのはルトスワフスキだと思うんだけど、いまの曲はまさにチェインの二番とか、三番とかの感じ。それにシベリウスを合わせ、さらにロスアンジェルスで聞いたラテン系の音楽を加えて、かれのなかにある、すべてを出したような曲なんじゃないのかな」
一昨日、まさにそのルトスワフスキの交響曲第四番から東京公演は始まったんですよ、というと、
「ああ、それならこれは、ものすごくうまく関連してるプログラムだね~」
ルトスワフスキに始まって、ベートーヴェン、マーラー、シベリウスをへて、サロネンへ。その中に三つの協奏曲。
たしかにここに一つのリング、円環があることは私にもよくわかった。サロネンは、見事にそれぞれの時代に応じた様式で演奏していた。
いや、これがチェイン、連鎖なのか。
二百年前の一八一三年にベートーヴェンの第七番が初演され、百年後の一九一三年に《春の祭典》が初演され、ルトスワフスキが生れ、その百年後の今年に、自らの五十歳を意識して書いたというサロネンの曲が日本初演される。この因縁も、チェインなのだろう、きっと。
というわけで自分は、明日池袋で演奏される《春の祭典》は聴けないけれど、ここまででもうまくまとまったように思えたのは、ネコケン先生のおかげ。
サロネンまつり、おしまい。
二月十日(日)リシエツキとネゼ=セガン
ネゼ=セガン&ロッテルダム・フィル@サントリーホール。曲は偶然ながら、七日と八日に続いて三度目となるベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番(独奏リシエツキ)と、ラフマニノフの交響曲第二番。
一曲目にハプニング発生。開演直前にアナウンスが流れ、
「指揮者のネゼ=セガンが体調不良のため、一曲目の協奏曲は、代ってコンサートマスターのマリーケ・ブランケスティンが指揮をします」
この言い方だとわかりにくいが、つまりは指揮者抜きのオーケストラの形態をとり、コンサートマスターがディレクションするということ。
結果的にはケガの功名というか、私にはこれでよかった。
ロッテルダム・フィルは室内オーケストラと違って、指揮者抜きでコンマスのリードで演奏することには慣れてないだろう。それにこの場合はネゼ=セガンの指示を各自が頭に浮かべ、コンマスはそのまとめ役にすぎないから、スタイルはどうしても守備的、消極的になるし、それでも合わない箇所が出る。
だから、オーケストラの表現は微温的なものになった。それなのに、つまらない演奏ではなく、むしろ逆に、七日と八日に二回聴いたアンスネスとサロネン&フィルハーモニア管弦楽団との演奏よりも、はるかに楽しめるものだった。
CDでのショパンやモーツァルトの協奏曲の録音での好演を聴いて、とても楽しみにしていたリシエツキのピアノの軽やかに歌う美音と、控えめなオーケストラという組合せが、作品の性格に適っていると感じられたからだ。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲は、ブラームスやチャイコフスキーのそれとは違う、古典期の作品なのだ。後半の三曲もスケールは大きいが、だからといってモダンピアノでロマン派風に演奏されると、いまの自分には大味にすぎる。ニュアンスを重視したリシエツキの響きは、その点で実に魅力的だった。
アンコールのショパンの「別れのエチュード」では、響きの骨格の弱さを感じたけれど、何しろまだ十七歳(一九九五年生れ)、とにかくこの美音が魅力。グラモフォンからはこの曲を含むショパンの練習曲集が出る予定だそうなので、楽しみにしている。
後半はネゼ=セガンが登場。袖に出てきたときの顔はゲッソリとやつれていたし、楽章間にペットボトルの水をがぶ飲みして、いかにも調子悪そうだったが、演奏自体は大きくうねる美演。昨日までのフィルハーモニアの、精巧な製図器具のように機能的でシャープな演奏と対照的な、オランダのオーケストラらしい、やわらかく明朗な響きに酔った。
二月十一日(月)同潤会と看板建築
藤原歌劇団の《仮面舞踏会》を観に上野へ行くついでに、初夏に取り壊されて建て直すという最後の同潤会アパート、上野下アパートメントを見にいく。
銀座線の稲荷町駅をおりてすぐ。一九二九年落成というから、築八十四年。まさに古色蒼然たる建物で、たしかに貴重だが、これを集合住宅として残せというのはちょっと無理か、と納得。
嬉しい発見だったのは、近くの下谷稲荷付近の個人宅。藤森照信命名の「看板建築」がいくつか現存していた。
看板建築というのは、関東大震災後に店舗兼住宅を再建するときに、普通の木造日本家屋なのに、通りに面した表壁、特にその上階や屋根に、洋風の装飾を施したもの。一九二〇年代の西洋のモダニズムを見よう見まねで採り入れた、その実例がまだ残っていたことに興奮。
二月十二日(火)ムトウ閉店の報に接し
高田馬場駅前のレコード店、ムトウ楽器店が四月三十日で閉店するというニュースを知る。
学生時代に通いつめた店だけに、感慨深し。
銀座の山野楽器やヤマハが夜六時かせいぜい七時で閉店という時代に、夜九時までという、WAVE出現以前は数少ない夜間営業のレコード店だったから、馬場の一次会のあとに酔って入っては、たくさん無駄なLPを買った…(笑)。
こんな愚か者も含め、高田馬場の店は学生をお客に持っているのが強みで、いくつかあった書店もそれぞれに個性があって面白かったが、今やただ春の夜の夢の如し。
ある人によると、高田馬場に増えるのはラーメン屋ばかりとか。物心ついたときからネット環境で育った現代の学生を相手にリアルで商売をするのは、非常に難しいのだろう。飲食店だけはネットですますことができないから、生き残る。
駅前が食い物屋と飲み屋ばかりになるというのは、まるで戦後の闇市の時代に逆行していくようだ。あの時代はほかに売るものがなかったが、いまはほかに売れるものがない。
しかしそれではあまりに味気ない。本や生活雑貨の類は、安いネットで買って配達してもらう前に、店頭で現物を確認するという人も少なくないそうだから、ショッピングサイトと連繋した「ショールーム」的な存在を、リアルでは残していくほかないのかも。
二月十四日(木)歌舞伎役者と神田明神
尾上菊之助と吉右衛門四女の結婚のニュース、何より驚いたのは、式を神田明神であげること。市川宗家ではないのだから、成田不動の天敵の将門の神社であげても、かまわないということか…。
團十郎が生きていたら式には出席したのだろうかとか、余計なことを考える。
それにしても、この夫婦に男の子が三人できたら、菊五郎、吉右衛門、梅幸の三名跡をつぐのかしらん。
二月二十日(水)渋谷の尾根と谷間
瓢箪から駒といった感じで実現した新企画のため、片山杜秀さんたちと渋谷の町を歩き回る。音楽ホールにレコード店(とその跡地)、昭和の大衆教養主義と消費社会の縮図が、尾根と谷間の入り組むこの地形に、刻み込まれている。
けっこううまくいったと思うので、結果を世に問えるときが楽しみ。
二月二十二日(金)二管編成まつり初日
今日から二管編成まつり。第一ヴァイオリンが十一人と十人のオーケストラを三回聴く。
まずはオペラシティで、ミンコフスキとレ・ミュジシャン・デュ・ルーヴル‐グルノーブル(MLG)。シューベルトの《未完成》とモーツァルトのミサ曲ハ短調という当初の二曲のほかに、最初にグルックの《アウリスのイフィゲニア》序曲を追加。
モダン・オケだと厳めしく響くだけでさっぱり面白くないグルックの音楽に、血が通い、肉がつくのはさすが。
続く《未完成》、いきなりオーボエなど木管の音程が不安定。合奏にも乱れが出て、「クラシックにおける世界最高級のビッグバンド」と呼ばずにいられなかった四年前の来日公演のときほどには、今回はメンバーが揃っていないらしい。演奏の難しいピリオド楽器だと、それがいっそう明らかになってしまうのが、つらいところ。
しかし響きの優しさ、息吹に近い自然な変化などはピリオド楽器ならではのもので、安定を捨ててもこの響きをとるという意欲と勇気こそ、自分は大好き。
第二楽章の後半がさらりとしていて、これだと普通の交響曲の緩徐楽章のようで、「次」が聴きたくなるなあと思っていたら、終演後に指揮者は袖に引っ込まずに客席を振り返り、交響曲第三番の終楽章をやると告げて演奏開始。生き生きと愉しい演奏で、見事に締めくくった。
後半のモーツァルトは、合唱団ではなくソリスト十人によって歌われた。スター歌手の独唱とその他大勢の合唱、というロマン派的なスタイルにしないところが素敵。
終演後の喝采のなかで、モーツァルトが妻コンスタンツェのために書いた、長いソロ二曲などを歌った三人のソプラノだけに単独の答礼をさせたのは、ミンコフスキが得意とするオッフェンバックの《ホフマン物語》の三人のヒロインを想起させて、愉快だった。
二月二十三日(土)ナヌート再登場
二管編成まつりの二日目。紀尾井ホールで、アントン・ナヌート指揮の紀尾井シンフォニエッタ。
前半は、ベートーヴェンの《コリオラン》序曲、指揮者と同じスロヴェニア人作曲家、コゴイの弦楽のためのアンダンテ、ワーグナーのジークフリート牧歌。後半はブラームスの交響曲第四番。
八十歳をこえたヴェテラン、ナヌートは二〇〇九年の初登場のさいのベートーヴェン・プロ(チュマチェンコ独奏のヴァイオリン協奏曲と交響曲第五番)が素晴らしかったので、今日も楽しみにしていた。そして期待を裏切らぬ出来。
マタチッチを想わせる、やや粗いが骨太でゴツゴツとした、力強くて味わいの深い音楽。なかでも、ジークフリート牧歌での弦と管の好演と、豊麗な響きが印象に残った。ブラームスの四番も、力んで弦の音が少し硬くなったのは惜しかったが、気合の入った演奏だった。
ゲスト・コンサートマスターがバイエルン放送交響楽団のバラホフスキーだったことも大きい。ボッセが最後に指揮したときも、この人がゲストだった。
それにしても今の自分は、やはりこのくらいの編成が好き。
今日はもちろんモダン奏法で、ホルンの安定した強大な響きは昨日のピリオドとはまるで異なるが、とにかくこの人数でこそ聴こえるものがある。
先々週のフィルハーモニア~ロッテルダムのフルオーケストラ四連発は、とても贅沢な体験ではあるが、最後には自分の耳がバカになってくるというか、感性が麻痺していく気がした。この二日間でリセットできた気がする。
二月二十五日(月)ミンコフスキ二回目
二管編成まつり最終日。東京文化会館でのミンコフスキとMLGのシューベルト・プロ。猛烈に愉しかった。
一曲目の《未完成》は、恐れ入りましたという感じ。三日前に続き二度目なので、木管の不安定さや全体の精度も落ちているのを自分の耳が知っていることを勘定に入れても、今日の方が出来がよかったと思うし、印象も違って聴こえた。
陰影の彫琢を、より深く感じたのだ。第一楽章提示部が反復されたさいの、日がかげったように暗くなった響きなど、その典型。
オペラシティの演奏が、古典派の交響曲の前半二楽章として演奏して、その居心地の悪さを示してみせたような演奏だったのに対し、こちらはもっとロマン派寄り。だから、交響曲第三番の終楽章が今日は演奏されなかったのも、個人的にはとても納得がいった。その必要のない演奏だと、感じたからだ。
実際には、都民劇場公演の終演時間の制約が最大の理由らしく、今日の演奏でもミンコフスキとしては、追加によって影と光のコントラストを明快につけたかったかも知れないが、自分はこのままでも充分だと思った。
古典派とロマン派を隔てる、薄い被膜の上をふらふらと揺れる交響曲。そのことがこの二回の演奏で実感できたのが、何よりも大きな収穫。
なお、吉田光司棟梁のご教示によれば第三番終楽章の追加は、一八六五年の初演のさいにも指揮者ヘルベックが採用した方式だとか。
ただし、ミンコフスキ本人に確認した別の友人によると、その故事を踏襲したわけではなく、調性面の収まりがいいという理由だけで、偶然選んだものだという。むしろその事実を教えられて大喜びしていたというから、なんとも愉しい。
演奏が聴く者に刺激を与え、思考を促し、勝手に詮索してみると、それが演奏者にも驚きをもたらす。
言葉を用いない演奏だからこそ、聴いている方があれこれ詮索する面白さが出る。その詮索の余地がある、勝手に想像させてくれる演奏こそが、私が聴きたいもの。ミンコフスキ&MLGは、まさにその現代最高の例なのだ。
ベートーヴェン同様に、シューベルトの後期作品をピリオド楽器で演奏することには、多くの無理がある。それでも、「やってみる」のが、かれらなのだ。
その後の《グレート》は、完全にロマン派に入った、長大で複雑な書法の巨大作品。その面白さをピリオドならではの柔らかく優しい響きと、軽やかに跳ねるリズムで、生き生きと(木管は本当に大変そうだが)。
特に弦が美しかった。細かい動きが魔術的に、しかし刺激的でなしに浮かびあがる。どこの楽章だったか、ピッツィカートの柔らかいのに明快な響きには、息を呑まずにいられなかった。
合間に聴いた紀尾井シンフォニエッタが、モダン楽器の強大で易々と響きわたる特性を最大限に発揮していたのとは対照的で、どちらも、非常に幸福だった。
ところで、あらためて痛感したのは、東京文化会館がコンサートホールとしてはきわめて優秀だということ。同じ楽団をオペラシティで聴いているだけに、どうなるのだろうと不安だったが、余計な色をつけず、しかし無機的にならずに、ピリオドのオーケストラがちゃんと響いている。指揮者と楽員は音の反射がなくて不安だったそうだが、聴いている方は不満を感じなかった。
もちろん、オペラ公演のために反響板を取り去った場合は、残念ながらこうは響かないが…。
二月二十八日(木)《無口な女》と私
「気になるディスク」にR・シュトラウスの歌劇《無口な女》を取りあげたところ、この作品にはまだ正規の映像ソフトがないことを教えてもらう。
そのようなマイナー作品だが、自分にとっては生れて初めてナマで見たR・シュトラウスのオペラなので、思い入れが深い。
一九八三年二月のウィーン国立歌劇場の公演で、ホルライザー指揮にリッダーブッシュ、オットにモーザー、床屋はカーンズだったかヘルムだったか。
六八年のプレミエという古い舞台だったが、装置と衣装はさらに古く、五九年のザルツブルク音楽祭版(ベームの指揮でCDになった)の流用という、今から考えると貴重なものだった(演出はレンネルト~ホッター~トーマと変遷)。
その翌日も同じ指揮者の《アラベラ》で、なぜか二日連続のホルライザーのR・シュトラウス。いい指揮だったし、オケもさすがの響きだった。
そのあと日本に帰って数か月、代々木のレコード店「ジュピター」に行ったところ、メロドラムのR・シュトラウス・エデイションのLPで、前述のベームのザルツブルク・ライヴが出ていた。
ホッター、ギューデン、ヴンダーリヒにプライという物凄い豪華キャストで、「あれって、こんなメンバーでやるオペラだったのか」とビックリ。
大喜びで買って帰り、解説の舞台写真を見たら、どう見ても自分が見たのと同じ、大きな階段のあるセットと衣装だったので、またビックリ。それくらい、ドイツ語圏でさえ上演機会の少なかった作品ということなのだろう。
三月三日(日)《カルディヤック》
新国立劇場のオペラ研修所修了公演、ヒンデミットの歌劇《カルディヤック》を見る。
日本初演、なかなか実演を見られる作品ではないので、ありがたい。ヒンデミットのオペラは、《画家マチス》といい《世界の調和》といい、芸術家や科学者の、才能と不可分に結びつく孤立性と、市民社会との関係のありように、強くこだわっているらしい。
三月八日(金)上野の山、寛永寺
天気がよいので、現在進行中の仕事、「上野散歩」を単独で予行演習。前回の「渋谷散歩」に続くもの。
渋谷の「山々」とはまるで別種の面白さが、この広大な「山」に満ちていることに、あらためて驚嘆。無駄を恐れず歩いてみることで、初めて気づいたこともいくつか。江戸~明治~大正~昭和~平成のいろんなものが各所に隣りあっているだけでなく、京都、日光、そして「文明開化」のミニチュア、箱庭にもなっている。長大な時間と空間の、パノラマとなっている台地。
たとえば、かつては山一つを有していたのに、いまや北西の一隅に、小さく押し込められてしまった寛永寺。周囲の雰囲気は明らかに、上野というより谷中になっているが、天海僧正ゆかりの川越喜多院から移築されたという本堂には、やはり風格がある。そこで感動したのは、その境内から、国立博物館の表慶館の、西洋式の緑のドーム屋根が見えること。寛永と明治が、江戸と東京が、無数の悲劇と喜劇をのみこんで、鮮やかに一つの「風景」をなしている、青空。
まさに「上野ワールドスクエア」。
もちろん、主目的であるいくつかの音楽ホール(欧化の象徴)もそこに含まれるし、今日は完全に省略した、博物館や美術館の収蔵品、動物園を含めれば、それはさらにさらに多層化、深化する。
前々から憧れていた「国際子ども図書館」こと「帝国図書館」、やっと中へ入れたが、まあなんと豪勢なこと。一九〇六年、国庫が空どころか、借金だらけだった日露戦争直後の完成であることを思えば、構想の四分の一ほどしか実現できなかった、というのもごく当然。
三日後の本番も楽しみ。ただし残念ながら、国際子ども図書館は休館日。
三月十一日(月)二年
東日本大震災から二年。
偶然ながら、上野歩きはこの日。煙霧で空が黄色くなった昨日とはうって変わって、好天に恵まれた。
三月十四日(木)解離性同一性障害
新国立劇場で《アイーダ》を見たあと新宿で、大学時代の後輩と数年ぶりに会って食事。元気そうで何より。
かれの友人の解離性同一性障害、昔でいう多重人格症の人の話を聞く。プライバシーに関わるから細部は書けないが、あまりに苛烈で劣悪な環境が生んだ、生存のための全身全霊の演技とも思えるその症状の、凄まじさ。
人間の思考とは何か、自我とは何かを解いていく、手がかりがそこにあるようにも思えて、深く考えこむ。むろん、そんな安易なものではないに決まっているのだが。
三月十五日(金)『泥だらけの純情』

思春期の思い出のつまった東横線渋谷駅の頭端式ホームも、いよいよ明日でおしまい。そんなときに見たのがこのホームも登場する、一九六三年二月公開の日活映画『泥だらけの純情』。
道玄坂一丁目、いまのマークシティと国道246の中間、大和田町にあった力道山の「リキ・スポーツパレス」が出てくるというので、見てみたもの。
これは三千人収容の大スタジアムにボーリング場、トルコ風呂(リキトルコ)などからなる、九階建ての先駆的な複合スポーツ・ビルで、六一年にオープン、六三年の力道山急逝後すぐに人手に渡って、キャバレーになったという建物。
当時の公式収容人数は、ホールでも野球場でもかなりいい加減だから、三千人収容は大きすぎて怪しいが、ともかく渋谷でこれだけの大ホールは、史上初めての出現だったはず。
映画には短いが、たしかに出てきた。入口の階段やモギリ、それに内部が鮮明なカラー映像で見られるのは嬉しい。
その前後に、六二年当時の東横線渋谷駅ホームが登場するが、これがいまとはまるで違うのが面白い。
眼鏡状の壁面をもつカマボコ型の高い屋根はまだなくて、奥沢や九品仏の駅にあるような、簡単な屋根があるだけ。私の記憶の中の映像でいえば、目蒲線の目黒駅の頭端式ホームみたいな感じ。
車両も、いまはハチ公前にある、昔の緑色の「青虫」だけ――六三年生れの自分は、まだ大井町へ走っていた頃の田園都市線や目蒲線ではこれにさんざん乗ったが、東横線ではまったく記憶がない。
改札やその外の、銀座線への乗り換え階段なども映るが、黒っぽくて色が少ないのが、いかにも昔の駅の内装。
こういう映像を見ると、自分が生れた時代は、もうかなりの大昔なのだと実感せざるをえず、さびしくなったり。
お話は、田園調布に住む大使令嬢役の吉永小百合と、新宿のチンピラやくざ役の浜田光夫の、純愛悲恋物。
身分差のある二人の世界の違いを象徴するものとして、それぞれの東京名所が出てくる。図式的にすぎるけれど、半世紀前の映像なので価値がある。
前者は日比谷公会堂(岩淵龍太郎のプロムジカ弦楽四重奏団も登場)や、完成間もない上野の西洋美術館。対して後者は前述のリキ・スポーツパレスに新宿歌舞伎町の映画館、そしてかれの両親(おやじはバタ屋で母親は淫売宿あがりだ、とは本人の弁)が住む、南千住の火力発電所のお化け煙突が見える、堤防沿いの貧しいバラック群。
鉄ちゃん向けには、昔の国鉄横浜駅東口駅舎や、SL時代の妙高高原駅(当時は田口駅)も貴重。とにかくカラーというのが強み。
映画的にはラスト近く、品川あたりの裸電球だけの安アパートの場面で、浜田光夫がアカペラで歌う『王将』の虚しさが、やたらに印象に残った。
三月十七日(日)マルティノフ!

一月十一日の「気になるディスク」で取りあげた、リスト編曲のベートーヴェンの交響曲第七番と第一番を、一八三七年製のエラールのフォルテピアノで弾いたユーリ・マルティノフのZIGZAG盤、猛烈にオモロい。
精妙なタッチ・コントロールによる音色とリズムの俊敏な変化が、音と音、声部と声部のコントラストと激変を鮮烈に描きだして、素晴らしい遠近感を生む。
自由自在の緩急に加え、強弱の鮮やかな落差は、まさしく言葉の最良の意味での「フォルテピアノ」(笑)。
音が響きすぎる現代のコンサートグランドでは不可能な軽捷さが生む、多彩なる色とリズムの祭典。
音をふわっと抜いてみせる、なんて芸当が、フォルテピアノには可能なのか。この二十年ほどのこの楽器の演奏技術の進歩には、圧倒される。
正直、リスト編曲版の交響曲なんて、轟然と打ち鳴らすトレモロばかりと思っていたのだが、これだけの奥深い可能性が込められていたとは、驚き。
昨年出た第一弾、《田園》&第二番を直前に聴いたときには、第二番は面白いが、《田園》がどうにも曲の長大さをもてあました感じがしたのだが、こっちは段違いに生彩に富んでいる。
あわてて聴きなおしてみると、演奏自体の進歩もあるのだろうが、第一弾では残響多めの録音が、響きと音色をモノトナスにしてしまった感じがする。
惜しい。楽器もスタッフも一緒だが、録音会場が別の教会。
ともあれ、このあとも第二弾と同じ音でつくってくれれば、これは革命的な全集になるはず。楽しみ。
三月十六日(土)インキネン
サントリーホールで、インキネン指揮日本フィルの演奏会。
三回にわけて行なわれるシベリウス・チクルスの一回目で、第一番と第五番。
細部がどうというより、オーケストラの響きっていいなあ、という素朴な感想がなによりもいちばん。
シベリウスの語法がモダン・オーケストラの機能に実にあっていて、インキネンの爽快な指揮が、その幸福感を味あわせてくれる。このあとも楽しみ。
インキネンのシベリウスはニュージーランド交響楽団との録音がナクソスから出ているのだが、これは音質があまりにもアレなので、日フィルの自主製作で出してほしい。ちなみに、すでにチャイコフスキーの第四番とマーラーの《巨人》と第五番が出ている。
三月十八日(月)~二十日(水)ローマへ!
十八日から二十日まで、三日続けて演奏会に通った。
それぞれ独立した無関係の演奏会で、声をかけてくださるままにうかがったものだが、三日目を聴いているときになって、これが周縁から中心へ、音楽史を朔行する流れになっていることに、ようやく気がついた。するとすべてが有機的につながって、さらに輝きを増して感じられて、愉快になった。
・十八日 杉並公会堂小ホール
低音デュオ演奏会 低音デュオ(松平敬:バリトン、橋本晋哉:テューバ、セルパン)
・十九日 杉並公会堂小ホール
エンジョイ!ベートーヴェン第三夜 アテフ・ハリム(ヴァイオリン)高橋望(ピアノ)森明美(お話)
・二十日 石橋メモリアルホール
エンリコ・オノフリ(ヴァイオリン)withチパンゴ・コンソート~すべてのバロック音楽はローマに通ず!?~
現代音楽→ベートーヴェン→バロック音楽。
武蔵国多摩郡下荻窪村→江戸下谷山崎町。
低音デュオはその名の通り、バリトンとテューバのデュオ。
新作の委嘱、初演と再演を積極的に行う点に特徴があり、この日も中川俊郎:《3つのデュオローグ、7つのモノローグと、31の断片》(二〇一二)、近藤譲:《花橘》‐3つの対位法的な歌と2つの間奏(二〇一三)、木下正道:《双子素数Ⅰ》(二〇一一)、《双子素数I‐b》(二〇一三)の、初演や再演がメインになっていた。
私なんぞが無邪気に感想を言える音楽ではないが、中川と木下の作品では「素数」がタイトルのキーワードになっている。一方で木下の曲では「百人一首」、近藤の曲では「千載和歌集」からの和歌が歌詞にとられている。しかしこれらも言葉の意味を情緒的に描こうなどという意志は毛頭なくて、五七五七七という素数でフレーズが構成されていることに意義があるのだろう。
橋本さんの言葉を借りると、「素数マニアにはたまらない演奏会」(笑)。それをデュオという「最小の素数」で。
数理の知性と、息の力という人力の演奏との、合致やらハーモニーやらズレやら矛盾やらが、人声と金管とのそれと重なりながら、脳にいっぱい刺激を受ける演奏会だった。
翌日はベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタから、二、八、九番の三曲。
前夜と同じ会場で聴けるというのが玄妙な偶然。人声に近い自由さで歌うヴァイオリンと、しっかりと構築するピアノの組合せのコントラストが、じつに楽器の特性そのものに則っているのが愉快。
ヴァイオリンがオブリガートから主役へと役割を拡大するうちに、変奏曲という知性と感性の遊戯の、豊かさと可能性がみえてくる。《クロイツェル》の二楽章でそんなことを思った。
三日目は、オノフリと日本のアンサンブルの共演によるバロック音楽。没後三百年、コレッリを柱に、ジェミアーニ、ヘンデル、ヴィヴァルディ、エイヴィソン(原曲はD・スカルラッティ)、バッハの協奏曲。
「合奏すること、一緒に音楽すること」の歓びと愉しさにあふれた、聴いたあと幸福感で心が暖かくなる演奏会。二〇〇九年、一一年、そして今年と、聴くたびにオノフリの音楽が日本の演奏家にも浸透し、一体感が高まっている。
十八人編成、さまざまな楽器が合奏や通奏低音をつとめつつ、一瞬に役割を変えて独奏として現れるときの、パッとスポットライトが当たったかのような、華やかさと明るさ。編成の大きな世俗音楽らしい躍動感と愉悦感。満員のお客も、その生命力を楽しむ。
印象的だったのは、イタリア中心の作曲家のなかで、(イタリアに行かなかった)バッハの音楽の、低音から支える構築性の大きさが、きわだって異質だったこと。
「永遠の都」ローマを拠点にしたコレッリから発して、ドイツという周縁に、やがて巨大な殿堂が築かれる流れが、この一瞬に預言されたかのようだった。
偶然にもヴァチカンの教皇選挙の直後というタイミングが、また玄妙。
もう一点。これは土地因縁の話だが、江戸時代にはたぶん田畑だった土地に建つホールから、同時代には幡随院という大寺(幡随院長兵衛の名前のもと)の、たぶん墓地だった土地に建つホールへ。
今の石橋メモリアルは大きなビルの一角だから、人骨がたとえ残っていたとしても基礎工事の際に撤去されているはずだが、ともあれ、そこにホールが建ち、バロック音楽が生き生きと演奏され、生きている人間たちがそれを楽しむ。
西洋では、突然に寒気がしたときなどに「誰かが私の墓の上で踊った」というそうだ。しかし日本、というか江戸・東京の町人・庶民においては、それは死者を辱めることではなく、生命を受け継いで、やがて受け渡していく、その証。
上野学園のある下谷だけではない。神田も大手町も麹町も四谷も、少なくとも山手線の内側とその東側の地域にはどこも、多かれ少なかれ寺と墓場があった。
市街が拡大するたびに町外れに移転させ、手狭になればさらに遠方へ移して、墓地を町に変える。それを何度もくり返して、その上につくられたのが、東京の街並みなのだ。
先日、市ヶ谷加賀町で発見されたように、縄文期の人骨の上に家を建てて暮らしていても、誰も祟られたりしない。それが、東京。
一方、長く同じ墓に眠る人もいる。
たとえば山の上の上野寛永寺の墓所には、徳川歴代の将軍をはじめとする立派な人々の墓が麗々しく建っていて、墓地から町に変った下谷や、鴬谷のラブホテル街を見下ろしている。
これもまた人の生と死。
「東京・春・音楽祭」が始まって、今日二十二日から来月十四日まで、それ以外もあわせて二十四日間に八回の上野通いになる。ちょうど桜。
桜の樹の下には…。
三月三十一日(日)文化会館の木霊
二十二日から、東京文化会館詣で。
大半は小ホールでの「東京・春・音楽祭」で、二十二日はメゾ・ソプラノのクリスティアーネ・ストーティン、二十九日はアレクサンドル・メルニコフ、三十一日はズッカーマン・チェンバー・プレイヤーズwith原田禎夫。
メルニコフの強大なエネルギーを内包したシューベルトとブラームス。ズッカーマンたちの豊麗な、いかにも北米大陸ふうのグラマラスでエネルギッシュな、ボッケリーニとシューマン、シューベルト。この二つが印象的だった。
ドイツ・ロマン派の音楽を舞台に、旧ソ連のピアニストと、日本を含めた西側諸国の演奏家たちが強大なモダン楽器を用いて豪腕を競うという、東西冷戦下の時代の演奏の、はるかな木霊のようになっていたのが面白かった。もちろん、共産体制下の先輩たちが背負っていた、あの陰鬱で重い影をメルニコフには感じないが、余韻はたしかに残っている。
この「冷戦体制の木霊」のなかでは、オランダ人ストーティンの影が薄くなるのも仕方のないところか。
それよりも初日は、ほとんど闇に近い暗さのなかで、上野公園の桜の樹の下を埋めつくした大勢の人が花見の宴会をしている場面が、なにより記憶に残った。
あまりに早く咲いたため、恒例のぼんぼり型照明が間にあわなかったらしい。闇に浮ぶブルーシートと、遮る人影。
途中の三十日は、大ホールで小澤征爾音楽塾オーケストラ・プロジェクト。
当初の発表では、小澤征爾と同じブザンソンのコンクールで二〇一一年に優勝した垣内悠希の指揮で、ドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲(独奏:三浦文彰)とベートーヴェンの交響曲第七番という曲目。小澤の名前はなかった。
ところが、三日前の京都公演で最後に小澤が登場、《エグモント》序曲を指揮して復帰したというニュースが流れた。東京も当然その再現が予想されて期待が一気に高まり、会場はほんとうに空席のない満員。売切の場合でも空席があるのが普通なのに、座席が人間で埋めつくされているのは壮観だった。
そして実際の演奏会も、その期待を裏切らない、小澤という存在の凄さを見せつけるものになった。
垣内の指揮は響きがやや粗く、雑然とする弱点はあるものの、フレーズの弾力感が魅力的で、会場も盛り上がったのだが、最後に出てきた小澤が指揮した「追加曲」(アンコールではないらしい)の響きは、別格の厚みと骨格をもつ、緊張感にみちたものだった。
特に弦楽パートが、音に深い伸びがあって純度の高い、「桐朋の弦」に一瞬に変ってしまったのには驚いた。
学生主体のオーケストラだから、響きを使いわける余裕など、楽員にはないはずだ。それなのにこれほど立派な響きに一変するのだから、いまさらながらに超一流指揮者の放つマジックに感服。
この一事に、指揮という芸術の不思議さが示されていたが、同時に、小澤が長嶋や裕次郎と同種の、場を一瞬にさらってしまう、どうにもならないスター性の持ち主であることも明らかだった。
場馴れしていない若いコンマスに退場をうながす、小澤のおどけた仕種。そこに、若きヒーローたちが出現した当時の戦後日本の気分――輝かしさというものが、アメリカふうの開放感や明朗さに結びついている――が見える気がした。
ソ連、日本、アメリカ。二十九日から三十一日まで三日間、なぜか昭和後半の気配が木霊する演奏会。
あとで思えば、一九六一年落成、自分が日常的に通うホールでは飛び抜けて古い――あとは八〇年代半ば以降――東京文化会館という場所の、ゲニウス・ロキがなせるわざ、ということか。
いまはずいぶん綺麗になったけれど、サントリーホール開場前、八〇年頃のここの内装はひどく殺風景で、モギリも日比谷サービスのおばちゃんたちで、クロークが稼働していることも少なく、精養軒もひどい味で、すべてがいまとは別物の貧相さだったことも、思い出したり。
懐かしいけれど、戻るにはためらいのある、一億総中流幻想時代の東京。
四月四日(木)マイスタージンガー
東京文化会館でワーグナーの《ニュルンベルクのマイスタージンガー》。
「東京・春・音楽祭」のメイン・イヴェントである、演奏会形式上演。
ヴァイグレの指揮が弾力とメリハリに乏しいとか不満もいくつかあるけれど、フォークトというスター歌手の参加を初めとして、日本でこれだけの演奏を聴かせてくれたのだから、文句はいうまい。
四月七日(日)東京文化会館のステレオ
東京のオーケストラの日程を眺めていたら、五月十七日の夜七時に、ショスタコーヴィチの交響曲第一番が二つの会場で同時に響くことに気づく。サントリーのテミルカーノフ指揮読響と、NHKホールのフェドセーエフ指揮N響。
ほかに今年の秋には《ワルキューレ》第一幕も日フィルと新日フィルの「ステレオ」で立体音楽会。モノラル嫌いの人にはぴったりか。同曲目で日にち違いの「ディレイ」も、マーラーの交響曲第五番があった。アルプス交響曲などは、5・1chサラウンドくらいにある。
「ステレオ」効果といえば、今日の東京文化会館。
小ホールで藍川由美さんの「日本のうた編年体コンサート」の第十回を聴いたが、休憩時にロビーへ出ると、大ホールの「マイスタージンガー」、第三幕の五重唱へのザックスの導入の歌が聴こえてきた。
そのあと客席へ戻って後半、《愛國の花》《愛國行進曲》《海ゆかば》と、一九三七年の日中戦争開始直後の「国民歌謡」が歌われていく瞬間、
――いま、隣では例のドイツ(芸術)讃歌が鳴り響いていることだろう――
と思ったのは、あまりに見事な「脳内ステレオ」効果だった。
それにしても、昭和十一年と十二年の二年間の流行歌には、解説の片山杜秀さんのお話のとおり、単純な戦時一色では片づけられない、雑多な人間感情がちりばめられている。
雑誌とラジオで、都市部を中心に大衆社会が本格的にうまれたところへ、やってきた戦争。友人知人が出征して戦死する状況を、マスコミを介して共有し、消費する社会。《海ゆかば》は、いわゆる軍歌だけれども、まずはラジオを通じて広まった「国民歌謡」だったのだ。
藍川さんの歌は純度と求心性の高いものだけに、前述の三曲はとりわけ見事だった。また、これらでの歌詞と旋律の見事な相乗作用に較べると、前半の古賀メロディというのは言葉が喚起するイメージとの関連をほとんどもたない、言葉が浮遊しているようなメロディであることがよくわかって、とても面白かった。
四月十三日(土)月光と浄闇の音楽
東京文化会館小ホールで「東京・春・音楽祭」の「浄められた夜 ~若き名手たちによる室内楽の極(きわみ)」。
ヴァイオリンの長原幸太と西江辰郎、ヴィオラの鈴木康浩と大島亮、チェロの上森祥平と富岡廉太郎、大フィルの元コンマスに新日のコンマス、読響のヴィオラ首席など、手練の男性ばかり六人の豪華なアンサンブル。去年は聴けなかったが、今年やっと聴けた。
前半のトリオによるモーツァルトのディヴェルティメントK五六三も、この傑作にふさわしい演奏だったが、白眉は後半の《浄夜》。
身の締まった、張りのある、純度と鮮度の高い響きの、澄みきった、月光と浄闇の音楽。
寿司や懐石料理のような、和食の味というか。漠然たる「アジア料理」ではない、日本料理。
先月の三十一日に同じ場所で聴いたズッカーマン・チェンバー・プレイヤーズの艶麗な響きはまさにアメリカふうの高カロリー料理だったが、それとはまるで違う、だけどどちらもすばらしい美味。
この音楽祭、実にいい企画を組むし、お客さんもよく入っていて、しかも真剣に聴く人が多くて、とても心地好い。
四月十四日(日)春の祭典
一か月続いた「東京・春・音楽祭」、いよいよ今日が楽日。
東京文化会館大ホールで、ストラヴィンスキーのバレエ二本立て。ド・バナ振付の《ミューズを率いるアポロ》、ベジャール振付の《春の祭典》。
前者では長岡京アンサンブル、後者ではジャッド指揮東京都交響楽団がナマで伴奏という、この音楽祭らしい、さりげなく豪華版。
《春の祭典》は初演百年ということで今年は自分もいくつか聴く機会がありそうだが、演奏だけでなくバレエつきは、これくらいかも知れない。
ベジャールの振付は数十年も前のものだけれど、生と死の原初的なエネルギーの明快な視覚化という点で優れていて、やはり古典として残るものと感服。ド・バナの《アポロ》が、ブックレットにある設定書きを読まなければ内容が理解できないものだったのとは対照的な、説明不要の肉体と音響の祭り。
東京バレエ団も十八番だけに、さすがに堂に入った踊りぶり。
四月十六日(火)少年いかに生くべきか

久しぶりに、ローズマリー・サトクリフの作品を読む。
イギリスの女性小説家で、一九五四年の『第九軍団のワシ』が出世作。この大傑作を始まりとする「ローマン・ブリテン」、つまりローマ帝国支配下のブリテン島を舞台にしたシリーズの面白さは、以前にこの日記に書いた。
最近、ちくま文庫から「ケルト・ファンタジー」というくくりでサトクリフ作品が二冊出たことに気がついたので、そのうちの『ケルトの白馬/ケルトとローマの息子』の二本立てを読んでみた。
二千年ほど前につくられた「アフィントンの白馬」をテーマとする前者は短めで、後者の『ケルトとローマの息子』はその倍以上ある。
これもローマ帝国時代のブリテン島の話だが、『第九軍団のワシ』の主人公マーカス・アクイラとその子孫たちとは無関係な話なので、ローマン・ブリテン・シリーズには含まれていない。
奥付に一九五五年作とあるから『第九軍団のワシ』に続けて書かれたものだ。なるほど、前作とはまた別の角度でローマ時代のブリテンを眺めてみたものらしいことが、随所にうかがえる。
全世界に身の置き所を失い、心に深い傷を負った少年が、苦難と放浪のすえ、一個の男としての自己と立つべき大地を見出していく辛口の成長譚は、『ともしびをかかげて』や『夜明けの風』と共通する、サトクリフ得意の魅力的な物語。

これでサトクリフ愛が甦って、続いて単行本の『シールド・リング』を購入。
選んだ理由はネタバレになるので書かないが、奥付を見たら一九五六年とあった。偶然にもサトクリフ初期の作品を、『ケルトとローマの息子』と二作続けて読むことになったのが愉快。
こちらはローマ時代から千年をへた、十二世紀初めの湖水地方(イングランド北西部。ピーターラビットやアーサー・ランサムの諸作の舞台として有名)。ヴァイキングとしてこの地に到来、根を下ろしたデーン人が、ブルゴーニュから来たノルマン人の侵略に抵抗する物語。
サトクリフ作品では珍しい女性の主人公は、かつてデーン人と領地争いをしたサクソン人の出身だが、いまはともに侵略を受ける身として、協力して戦う。
これを読むと、サトクリフの関心が、甘美なノスタルジーの対象としての「ケルト」だけにあるのではないことが、よくわかる(面白いことに、彼女の文章にケルトという用語は出てこない。書名などで日本側が用いるだけのようだ)。
現在のイングランドには、初めに褐色の肌をした先住民がいた。かれらは「ケルト」に征服され、その「ケルト」はローマ、ついでサクソンに征服される。そのサクソンの領土の一部はデーンに奪われ、やがては全土が征服王ウィリアムの率いるノルマンにより、征服される。
サトクリフが学校で習った英国史は、もっぱら征服王ウィリアムの「ノルマン・コンクエスト」以降の、光輝ある海外進出の時代に関心を向けていたそうだ。
しかし彼女は栄光の向うに隠れた、勝者が明日には敗者となり続ける、諸行無常のブリテン島二千年の歴史を掘り起こした。それも英雄ではなく、民族盛衰の大波に翻弄され、ただ歴史の波間に埋もれていくばかりの一個人が、そこでいかに生きるかの物語群を紡いだのだ。
それは、ナチス・ドイツによる侵略の記憶と、大英帝国衰退の予感とに、答えていくものでもあったのだろう。
四月十七日(水)ユジャ・ワン
トッパンホールで、ユジャ・ワンのリサイタルを聴く。
凄いが、よくわからず。
四月十九日(金)インキネン第二夜
サントリーホールで、インキネン指揮日フィルによるシベリウス交響曲サイクル二回目、第四番と第二番。純度の高い好演。
四月二十日(土)あの日と今日
サントリーホールで、スダーン指揮東京交響楽団によるモーツァルトの宗教曲二本立て。
《戴冠ミサ》とレクイエム。東響による後者を聴くのは、二年前の三月二十六日、小林研一郎指揮による同じサントリーホールでの演奏会以来。
東日本大震災から十五日後のあの演奏会は、私が震災後、初めて聴いた演奏会だった。家に閉じこもっていても仕方ないと、出かけたのである。
この日、本来はスダーン指揮でベルリオーズのテ・デウムなどをやる予定だったが、原発災害の影響で指揮者が来日不能になった。急遽コバケンが代役を引き受け、ベートーヴェンの《英雄》交響曲の葬送行進曲と、レクイエムのラクリモーサまでを演奏したのだった。開演前に黙祷があり、最後には追悼の意味から、ラクリモーサがアンコールされた。
その日のレクイエムは、東響の東日本大震災チャリティーCDとして自主制作盤になっているから、いまも聴くことができる。小林の引きずるような重い響きが、その日の気分にぴったりと合っていたし、アンコールのラクリモーサの最後では、高々と突きあげられた指揮者の右腕が、泥と灰のなかから高い青空を見ようとするかのようだったことを、憶えている。
今日のスダーンの演奏は、それとはまるで異なるスタイル。ピリオド奏法の速い減衰をとりいれ、澄んだ響きで颯々と進めていく。そしてもちろん全曲演奏。この曲に十九世紀的な物語性とロマンを求めるなら物足りないだろうが、けっして無機的な演奏ではなく、透明な悲しみを感じる。
欧米出身の独唱者のなかに、一人だけテノールの福井敬が参加していたのが感慨深い。福井は二年前、本当はスダーンのもとでベルリオーズを歌うはずだった歌手で、指揮者と曲目が変ったのちもそのまま出演した。
独唱のなかでかれだけが二年前と変わらないのは、そのときの労をねぎらうべく、オーケストラと指揮者があえて選んだのだろう。その存在によって、スタイルも状況もまるで異なる二つのモツレクが、二重写しになっていく。
休憩時、東響の自主制作盤の新譜で、スダーン指揮のブルックナーの交響曲第六番が出ているのを見つける。実演は聴けなかったが、いい演奏のような気がして買って帰る。第一楽章の颯爽とした進行が特に素晴らしく、セッション録音で出た第七番や第八番よりも気に入った。
四月二十三日(火)カピュソン
トッパンホールで、ヴァイオリンのルノー・カピュソンとピアノのダヴィッド・カドゥシュのリサイタル。
ドビュッシー、グリーグ、R・シュトラウスのソナタに聴く、艶麗な響き。
そういえばカピュソンも、二年前の五月、一緒にツアーをするはずだったオーケストラが来日を中止したのに、紀尾井でのリサイタルの予定は変えず、ただ一夜のために日本へ来て、カドゥシュと演奏してくれたのだった。
つとめて冷静に、追悼めいた言葉もなしに演奏しただけなのに、あのときのタイスの瞑想曲の、心にしみる慰撫の響きは、まだ耳に残っている。
二年たって、音楽界のカレンダーはちょうど一回り、というところか。
四月二十五日(木)三十年前の春の夜
ミュージックバードの収録後、半蔵門から四ツ谷駅へ歩いていく途中、新宿通りを南に折れて、平河町の「プリンス通り」を歩く。
戦前は皇族の宏壮な邸宅が並ぶお屋敷町。宮部みゆきの傑作『蒲生邸事件』の舞台。モデルと思しき現在の都市センター、ついで向いの紀尾井町の、かつての赤坂プリンスホテル新館の解体現場へ。
この解体くらい、馬鹿げた無駄という印象を受けるものも少ない。土地を利用しているつもりで、土地に利用されているような。
その一方、旧館の旧李王家邸は邸宅時代に復元して、移築するための工事の最中だった。こちらは新館と違って歴史があるから、新しい高層ビルの住民にとっても、ランドマークやステータス・シンボルになる、ということなのか。
ディズニーランド開園三十周年(一九八三年四月十五日)
赤坂プリンスホテル新館営業開始三十周年(一九八三年三月七日)
この二つがほぼ一緒というのは、なにかものすごく面白い。土地バブルの始まりの頃。春の夜。
四月二十七日(土)インキネンと将門
サントリーホールで、インキネン指揮日フィルのシベリウス交響曲サイクル三回目、第三、六、七番。「交響曲」という概念が拡散する時代に生れた傑作。見通しのいい響きで、心地好し。
歌舞伎座の九月公演で新作『陰陽師』が上演されるというニュース。
主役の安倍晴明を市川染五郎が演じるというのはいいとして、驚いたのは、平将門を市川海老蔵が演じるということ。とうとう、成田屋が将門をやるのか。
この日記で何度も書いたが、将門にとって成田不動は自らを調伏した、憎むべき敵。そしてその成田不動の「化身」が市川團十郎。
そのせいか、歌舞伎で将門そのものがでてくることはまずない。「将門」と通称される芝居でも、出てくるのは娘の滝夜叉姫だけ。それを「将門」と呼んでしまうこと自体、将門の芝居はありえないといっているもののようなわけで。
なにか、菊之助と吉右衛門娘が神田明神で結婚したことといい、歌舞伎界全体が将門の怨霊にとりこまれつつあるような…。
もしかしたら、旧歌舞伎座には将門が封じてあった? それを気づかずに壊したので復活し、さまざまな不幸をまきおこしている? 歌舞伎界滅亡の兆し?
神田明神が皇室に遠慮して将門を祭神からいったん外したのが明治七年。そのあと西南戦争やらなんやらがあって、歌舞伎座ができたのが、十五年後の明治二十二年。
――ということは、将門を封じるために歌舞伎座は新たにつくられた!?
『MMRマガジンミステリー調査班』の読みすぎ。
ああ、陰謀論は密の味。バカな陰謀論や怨霊史観の妄想って、なんと愉しいこと…。
四月三十日(火)コンヴィチュニー
二期会公演のヴェルディ《マクベス》のゲネプロを東京文化会館で見る。ゲネプロなので感想は遠慮。
五月三日(金)ラ・フォル・ジュルネ
東京文化会館小ホールで佐藤久成のヴァイオリン・リサイタルを聴いたあと、東京国際フォーラムへ行き、「ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン」のクラシック・ソムリエをつとめる。
例年は単独だが、今年は高坂はる香さんと二人ソムリエ。いつもは巨大なホールAの公演しか席が残っていないことが多いのだが、今年は他のホールも少しずつ残っている。お客さんにとっては会場で選べるのは楽しいし、薦める立場としてもやりがいがある。
もちろん、営業的には前売だけですべて売切れるのが理想だろうけれど、お祭りには少し余裕というか、こうした「ユルさ」がある方が心地よいと思う。
五月五日(日)ニューラテンクォーター跡地~昭和・平成史の断面(前)
午後、浜離宮朝日ホールでオランダのピアニスト、ユッセン兄弟を聴く。
終演後、新しい歌舞伎座ビルを眺めながら、銀座へ出る。
人は多いが気候が爽やかで気持ちよいので、日比谷の劇場街を抜けて日比谷公園へ。野外音楽堂では九十周年記念のフェスティヴァルをやっている。
霞門の出口を出て、西側の丸ノ内線霞が関駅へ。行く手の丘の上に国会議事堂があるのを見上げて、あそこまで歩いてみようと思いたつ。
太田道灌の時代、日比谷公園あたりは日比谷入江という、銀座と霞が関にはさまれた、海だった。たしかに桜田通りを渡ると、地形は明白な山登りになる。左へ折れて外務省の前を歩き、財務省とのあいだの潮見坂を登る。
坂の上の「財務省上」交差点で後ろを振り返ると、日比谷公会堂の時計塔が下にばっちり見える。潮見とは、あのあたりの入江の干満が見えるということか。
しかしここはまだ山の中腹。国会議事堂の南側の坂をさらに西へ登る。茱萸坂(ぐみざか)と案内板にある。
登りきって「総理官邸前」の交差点に出る。ここがいちばん高い「峠」で、正面の道は下りになる。右、つまり北を見ると国会議事堂と議員会館のあいだを南北に走る道で、これが稜線の尾根道。反対に左手は、前に進むのと同じく下り坂で、降りたところがかつての溜池。その手前に古い首相公邸が見える。
正面へ進んで、総理官邸の北側の道を下る。周囲は警備の警官だらけ。うろうろしている当方を、警官の誰か一人が、目を合わせないようにしながら、つねに視界に収めているのを感じる。
下りきると、東急キャピトルタワー。かつて東京ヒルトンホテル、キャピトル東急ホテルがあったところ。
キャピトル東急は山の上にあるように思いこんでいたが、歩いてみると、東西の山にはさまれた谷間にあることがわかった。
東が国会議事堂と首相官邸のある山、そして西側は、日枝神社の山。
こうしてみると、日枝神社は北の平河町から伸びてきた台地の南端、ミサキにある高い山に位置するから、地形的に縄文以来の聖地にふさわしく、神社になっているのが当然の場所だと納得する。
また、これまでは赤坂見附の側からしか登ったことがなかったので気がつかなかったが、神社の正面は反対の東の、国会議事堂側に向いている。
山を登ってお参りしたあと、西側の稲荷参道という階段道を降る。数十本の小さな赤鳥居が連続して屋根となる、面白い道。(続く)
五月五日(日)ニューラテンクォーター跡地~昭和・平成史の断面(後)
降りたところは、外堀通りに面した大鳥居。右折して外堀通り沿いに北上すると、プルデンシャルタワー。
戦後にはホテルニュージャパンとニューラテンクォーターがあり、戦前には幸楽という料亭が、あったところ。
二・二六事件のとき、叛乱部隊は首相官邸からいまの議員会館のあたりに主力をおき、この幸楽と、南の山王パークタワーのところにあった山王ホテルに一部を配置していたそうだが、これも歩いてみて、その理由がよくわかった。
尾根道、すなわち高地の稜線の手前に本隊が布陣して、西側の青山赤坂方面の台地から、外堀通りの谷へおりて来る鎮圧部隊(かれらの原隊である歩兵一連隊と三連隊)に対峙する形をとる。
そして、山の下の登山道の入口にある幸楽と山王ホテルを前哨部隊が押さえるという、定石通りの配置なのだ。
歩き疲れたので、道路を渡って、向いの喫茶店でコーヒーを飲みながら、幸楽跡地のプルデンシャルタワーを眺める。
日比谷高校を崖上に見上げるこの場所は、二・二六事件だけでなく、それ以後の、近代史の断面のような場所だ。
二・二六事件後の幸楽は大戦末期、撃墜されたB29が落ちて、破壊されたという。
そして戦後は跡地に、ラテンクォーターというナイトクラブができた。
つくったのは、GHQの悪名高き諜報機関、ウィロビー少将率いるキャノン機関のジャック・キャノン少佐。かれが、フィリピン・ギャングの親玉テッド・ルーインと共謀して始めたものだという。
フィリピンというのは唐突な気もするが、太平洋におけるアメリカの植民地であり、マッカーサーはその高等弁務官だったわけだから、かれのスタッフには、現地に巣くったギャングと結託している連中がいた。そのギャングが、進駐軍と一緒に日本の裏社会へ入り込んできた。
フィリピンとの縁の深さは、そのフィリピン生れの歌手ビンボー・ダナオ(淡路恵子の最初の夫)が「ミスター・ラテンクォーター」と呼ばれるスターだったことにあらわれている。
かれ以外にも、日本離れした豪華なショーが売り物だったが、仕込みを担当したのは、キャノン機関出身でルーインの子分のアロンゾ・シャタックと、その協力者でのちにキョードー東京をつくってビートルズを日本に招く、永島達司。
その一方で、秘密のカジノを裏に併設して、ルーイン一家は荒稼ぎをしていたらしい。
この店が幕を閉じたのは、一九五六年九月。「不審火」で全焼したためだが、「運良く」一週間前に一億円の火災保険に入っていた。まさに焼け太り。
占領と朝鮮戦争が終り、不良外人のたまり場、犯罪の温床として警察の監視が厳しくなるなかで、いまが潮時と、足を洗ったのかも知れない。
たとえばこの年の一月、帝国ホテルで宝石強盗を働いたアメリカ人ギャングがラテンクォーターの店内で逮捕され、シャタックとの関係が噂された。また火事の直前には、楽団を率いて出演中のペレス・プラードが、出演料を闇ドルでもらった容疑で、入国管理法と外為法違反で捜査を受ける騒動も起きている。
そのあとこの土地を手に入れたのが、藤山コンツェルンを率いる藤山一郎。
ここにホテルニュージャパンを建てたが、面白いことに同じビルの地下に、ホテルとはまったく別経営の形で、ナイトクラブがつくられた。
その名は、ニューラテンクォーター。
開業四年後の一九六三年、常連客の力道山がヤクザに刺されて死んだことで有名なクラブだが、暴漢だけでなく、政財官のお歴々やマスコミ人、作家、芸能人が常連の、超高級クラブ。
高度成長期の夜の世界、東京アンダーワールドが表世界と同居する場所。
開店当初は、二、三時間飲むだけで大卒初任給の半分近くが飛んだという。しかも、ライヴァル店のコパカバーナや紅馬車は百人がせいぜいなのに、ここは三百人も入れるという巨大クラブ。
このニューラテンクォーターの経営者の後ろ楯になったのが、かの児玉誉士夫の児玉機関。形式的には戦後消滅しているが、裏の組織として残っていた。
じつは、先代のラテンクォーターのときから児玉機関は経営に一枚噛んでいたという。キャノン機関、フィリピン・ギャングに児玉機関の組合せは、まさに類は友を呼ぶ、軍隊裏稼業の日米協力。
おそらくは、ルーイン一家が手を引いたあとも児玉がこの場所の利権を握っていたので、藤山はナイトクラブを児玉機関に完全に委ねることで、引きかえにホテルの建設を納得させたのだろう。
のちにホテルニュージャパンの所有者は藤山から、横井英樹に移る。そして一九八二年、火災で三十三名もの死者を出して廃業するが、ニューラテンクォーターは七年後の八九年まで営業を続けた。上のビルが惨事のときのまま幽霊ビルと化しているのに、地下の高級クラブは営業中とは、なんとも凄まじい景色。
横井の抵抗などもあって、廃墟と化したホテルニュージャパンが解体されたのは、火災から十四年も後の一九九六年。いまのプルデンシャルタワーが建ったのは、二〇〇二年。
もともと、ここにビルを建てようとしたのは千代田生命だったが、中途で同社が経営破綻したため、外資のプルデンシャル生命が買取り、森ビルと協力して建てたのだそうだ。
バブル崩壊後に急伸した外資と、東京再開発の主役までもが顔を出す。まさに昭和・平成の、日米関係の縮図のような土地。B29が墜ちたときから、それは始まったのだ。
二・二六事件の叛乱部隊の拠点だった幸楽と、四十六年後に火災を起すホテルニュージャパンが同じ敷地にあること、近隣にある赤坂プリンスホテルの旧館がもとは旧李王家邸であり、平河町の都市センターホテルと向いあっていること、この一帯のいくつかの地縁をヒントに、宮部みゆきが書いたのが『蒲生邸事件』だった。
とても面白いタイムトラベルものだったが、しかし現実のプルデンシャルタワーの土地には、それ以上に強烈なゲニウス・ロキが宿っている。
背後の崖に、近代史が重層化して連なる、その断面が見えるかのような。
久生十蘭の一九三七年の小説『魔都』の主舞台が、日枝神社下のモダンなマンションだったことも、思い出したり。
あれには二・二六事件を暗示する事件が出てくる。そうか、日枝神社下の建物というのは、迂回しながらそれに結びつくのか…。そういえば、日比谷公園も重要な舞台の一つになっていたっけ。
赤坂見附駅へ出て、丸ノ内線で帰宅。
・参考文献 諸岡寛司『赤坂ナイトクラブの光と影』(講談社)

五月九日(金)インバルのブルックナー
文化会館で、インバル指揮の東京都交響楽団の演奏会。
モーツァルトの《ジュノーム》(ピアノ:児玉桃)とブルックナーの交響曲第九番。ややザラッとした響きながら、さすがの緊迫感。
五月十日(土)『東京暗黒街』のなかの日本

フィリピン・ギャングの根城だったラテンクォーターの話を五日に書いた。その流れで、アメリカ映画『東京暗黒街 竹の家』のDVDを見なおす。
ここに出てくる、東京に巣くうGIくずれのアメリカ人ギャングは、まさにシャタック一味を想わせる。ただしアメリカ風のナイトクラブとカジノではなく、パチンコ屋を根城に金をまきあげているのが、現物とは異なる。そのボス役のロバート・ライアンの縄張りに、一匹狼のロバート・スタックが現れて、ストーリーが動き出す。
サミュエル・フラー監督の本作は、一九五五年一月から四十三日間にわたる大がかりな日本ロケを行い、当時の東京近辺の名所が、鮮明なカラー(シネスコ)で撮られている。
撮影には日本の外務省、警視庁などが全面的に協力したそうだ。ところが、半年後に日本公開されたときの評判は「国辱的」といわれて、散々だった。
たしかに奇妙な点は、数えればキリがない。視覚面では、とりわけハリウッドで行なわれたスタジオ撮影の部分が、予想通り滅茶苦茶。畳ではなくゴザをひいたり、中国や東南アジア風の家の内装。
案内板やノボリの筆書き文字は、和風ではなく中国風。漢字ばかりで平仮名がなく、横書きも右書き。戦後の日本では左書きが進んでいたはずで、中国系の美術スタッフが担当したのだろう。
最大の違和感は目よりも耳で、日本語の発音がおかしい。日本でのロケ部分も含めて、ハリウッドで最新のステレオで吹替えているのが、珍妙なカタコト日本語なのだ。当時の日系二世は戦争の影響か、もうこんなに日本語がしゃべれなかったのかとも思うが、あまりにも変だから、チャイニーズやコリアンも混じっているのだろう。
警視庁の刑事役の早川雪洲も、英語に問題があったためか声を日系人が吹替えており、英語はうまいが日本語が下手という、妙な日本人になっている。
そのなかで、ヒロインを演じるシャーリー山口こと山口淑子だけが、自分で英語もしゃべり、ほぼ唯一、まともな日本語を話している。しかし、役柄そのものはゲイシャのような、欧米人にとって都合がいいだけの日本女性で、「国辱的」なことには変りがない。
また、早川雪洲以外の日本人男性は、ことごとく意気地がない。白人の暴力に手も足も出ず、すぐに気絶してしまう。こういうとき、日本人の自尊心をくすぐるために出てくる「柔よく剛を制す」のジュードーの使い手もいない。ひたすら情けなくて、弱っちい。
貴重な昭和三十年の日本ロケも、日本人が眉をひそめるような描写が、端々に出てくる。監督のフラーがこのB級ギャング映画の背景として望んだのは、フジヤマ・ゲイシャのエキゾチックな、アジアンな日本なのだ。だからギャングが根城にするのも、アメリカ風のナイトクラブではなく、アジア風のパチンコ屋でなければならない。
それはまた、戦前の絵葉書のような日本風景である。冒頭の富士山を背景にした列車強盗の場面では、すでに電車が走っていた路線なのに、わざわざ蒸気機関車を走らせている。ごく少なくなっていた人力車が、まだ東京の道を走っていたりする。和服姿の比率も、実際以上に多いように感じる。
こうした「映画的虚構」を誤解と批判するのは簡単だ。
しかし、この映像を見ていると、それらの虚構とは別に、けっして虚構ではない歴史的事実としての当時の日本、日本人自身があまり見たがらない、振り返りたがらない陰惨な日本の姿があるのも、認めないわけにはいかなくなる。
アンバランスで見すぼらしく、下卑た発展途上国日本の姿が、アメリカ人の意地悪な好奇の視点(原題のハウス・オブ・バンブーなる言葉に象徴される)によって、えぐりだされているのだ。
いまはなき浅草国際劇場の屋上で行なわれている、当時のアメリカ人が大好きだったアヅマカブキ風の、鏡獅子の出てくるカブキダンス。町を歩く、安っぽい薄手の生地の赤や紫のケバケバしい和服を来た婦人たち。毒々しい原色に塗りたくられたパチンコ屋と、新装開店の花輪。くず拾いやチンドン屋の独特の服装。佃島の掘割に密集して浮ぶ汚らしい和船と、貧相な木造の日本家屋。
日本で最もモダンだった尾張町交差点(銀座四丁目)や歌舞伎座も映るが、マンハッタンを知るアメリカ人にとってはどうでもよかったのだろう、カメラの視線は冷たくつき放している。
欧米人も好んだ帝国ホテルの古い建物だけは威風堂々としていて、カメラも敬意を払っていることがわかるが、その威厳が何だか植民地の総督府みたいに見えるのには、苦笑せずにいられない。
近代東京の路地にカラーは合わない。墨絵のようなモノクロの陰影が合う。日本映画の世界的名作の多くがモノクロでカラーが少ないのは、おそらく偶然ではない。モノクロでなら、美しい情緒として感じられたかも知れないものが、ここで醜悪さをむき出しにしている。
なお映画にはこのほか鎌倉の大仏や、五輪塔(上野か谷中か)、そして浅草松屋デパート屋上の遊園地とその水平式観覧車「スカイクルーザー」も登場する。
昭和三十年代への安易なノスタルジーを壊すには、好適な映画。
五月十一日(日)渋谷の谷間の地下
友人と渋谷で飲む。井の頭線のマークシティで待ち合わせなので、副都心線のホームから地下街を抜けて行く。
東横線と直通化して人が増えたこともあって、渋谷地下駅の殺伐とした閉塞感は大しくじりだとあらためて思う。細くねじれた谷間の地下を縫ってつくっているため、地上の狭苦しさがそのまま、いや増幅されて地下に持ち込まれている。
地下でさえ土地の構図は自由でなく、地上と同じ地形の制約を受けてしまうのが、東京の土地利用の限界。
それでも、見せかたで改善できる余地はあるだろう。最近流行りの丸亀製麺の店をデザインした人にでも、広々とした空間の演出法を教わればよかったのに。あそこは味と安さと同じくらい、店舗設計の巧さが客を呼ぶ力なのだから…。
早めについて、大和田のリキ・スポーツパレス跡、現在のヒューマックスビルの周りを見学。谷間からはけっこう登った坂の途中にあり、ビルが少なかった昭和三十年代なら、渋谷の交差点を睥睨するような印象があったのかも知れない。
五月十二日(日)『太陽のない街』


近代の出版業は神保町を中心に隆盛するが、明治末から大正期に、共同印刷や凸版印刷、大日本印刷など(の前身)が中央線沿線の水道橋、飯田橋、市ヶ谷の各駅の北側、文京区と新宿区の低湿地に工場をつくり、中小の印刷所がその周囲にあつまり、印刷街を形成していく。
その初期の様子を描いたものとして、『太陽のない街』という小説を読み、それを原作とする同名映画を観る。
小説は徳永直が一九二九年に発表したもので、一九二六年の共同印刷争議、つまり共同印刷の工場労働者約二千人による大規模なストライキとその敗北を描いた実録小説。盛り上がりかけた労働運動が治安維持法によって潰される時代状況下に書かれた、小林多喜二の『蟹工船』と並ぶプロレタリア文学の代表作。徳永は争議に参加した労働者の一人だった。
舞台は、文京区小石川三丁目にいまも存在する共同印刷の工場と、周囲の労働者の住宅街。南の春日通りと北の小石川植物園、二つの台地にはさまれた谷間の「谷町」で、日照時間の少ない低湿地であることがタイトルの由来。
映画は戦後の一九五四年に独立プロによってつくられた、山本薩夫監督作品。貧乏な独立プロとしては信じがたいことに、今の駒沢公園のあたりに巨大なオープンセットを組み、大正末年の「太陽のない街」を再現しているのが見もの。
あんのじょう撮影中に資金が尽き、日当をもらえないエキストラが怒ってストになりそうなのをなだめすかして、映画のスト場面を撮ったというのが愉快。
五月十五日(水)新宿ブウルヴァル
今日は某企画のために新宿歩き。
数日前、何気なく獅子文六全集の十三巻、初期エッセイのあたりを読みかえしていたら、こんな文章があった。
「こんなノビノビした外国は、滅多にないので、僕はすっかり落ち着いて広場を観察すると、どこかで見覚えあると思ったも道理、まさしく震災一、二年後の新宿駅前そっくりだ。停車場の建物も革命後の新築とみえて、モダンな安普請のところが似ているが、それよりも、馬糞臭い宿場が破壊されて、まだ近代的ブウルヴァルが出来上がらず、ゴッタ返していたあの頃の新宿と瓜二つに、真っ昼間から、薄汚い食物屋台が、列をなしてるので驚いた」
文六が一九三六年にパリからシベリア鉄道で帰国する途中、ソ連のモスクワ駅で降りたときの駅前の様子。
モスクワそのものよりも、大震災直後に「馬糞臭い宿場」から急発展しはじめたころの新宿駅前の雑踏が目に見えるような一文なのが素晴らしいが、なかで特に目に留まったのが「まだ近代的ブウルヴァルが出来上がらず」という一節。
逆にいえば、一九三六年、昭和十一年の新宿には「近代的ブウルヴァル」が出来ていたということだ。
それは、どこか。それは、なにか。
これを考えはじめたとき、それまで読んでいた新宿関係の本では気がつかなかった、いや、そこでバラバラの点になっていたものが、するすると一本の光る線を形成しはじめた。
ブウルヴァル。目抜き通り。
その形成こそが、新宿という街の特性を読み解く鍵ではないか。パリ暮しの経験をもつ文六だからこそ、気づくことのできたもの。私も知っている六〇年代以降の巨大な新宿ばかりを考えると、埋もれてしまう視点。
目からウロコ。新宿の話が出るとは夢にも思わず(他の文章を読むかぎり、新宿が好きではないらしいので)、素晴らしい贈り物をいただく。文六先生万歳。
考えた中身は、この企画が形を成したときのお楽しみ。今日もこれまでの二回同様に話し相手に恵まれて、大いに刺激を受けつつ歩くことができた。
心残りは、新宿歴史博物館の閉館時刻に間にあわず、文六先生が愛惜してやまない「ちんちん電車」に乗り込めなかったこと。近いうちに一人で行って「都電ぐらい、乗り心地のいいものはない」という一節を、偲んでみるつもり。
五月十六日(木)東京クヮルテット
オペラシティコンサートホールで、東京クヮルテットの演奏会。
四十四年の歴史に幕を引く、お別れ演奏会の一つ。ことごとしくお別れムードを盛り上げたりはしないけれど、充実した、見事な演奏。
東京クヮルテットといっても、メンバーの出身地というだけで本拠ではなかったわけだが、終演後のレセプションで創設メンバーの磯村和英さんは、一九六九年にニューヨークのジュリアード音楽院で結成したときにこの名前をつけて、本当によかったと思う、と語っていた。
五月十八日(土)倭琴と海、闇市
昼は東京建物八重洲ホールにて、藍川由美が倭琴を弾き歌う「古代の響き 太古の祈りのうた」コンサート。
特注の倭琴を用い、神楽歌と琴歌譜から、いわゆる雅楽よりも古い奈良時代までのうた。まさに言霊、詞そのものが神事となるうた。
安曇や志賀など、海人族に結びつく地名(日本各地にある)が詞に含まれているのが興味深い。古代日本のうたでは、農業と同時に漁業の重要性も高い。
帰りは八重洲地下街を通る。古い地下街だがゆったりとして、不思議に気分のいい空間で、以前から好きな場所。
そのあと新宿へ行き、三日前に歩けなかった歌舞伎町の名曲喫茶スカラ座があったあたりと、西口の思い出横丁へ。思い出横丁に入るのは四半世紀ぶりだが、戦後の闇市のマーケットがまだそのまま残っているのに、あらためて驚く。
夜は、オペラシティコンサートホールで、大野和士指揮のウィーン交響楽団の演奏会。シューベルトの《未完成》とマーラーの交響曲第五番。残念ながら、指揮者と楽員の息が合わないようだった。
五月二十日(月)高熱と読書
月の初めから風邪が抜けなかったが、とうとう悪化して爆発。三十八度八分という記憶にない高熱で、以後三日間、ただ寝ているのみ。
体温が高いと時間の経過を遅く感じるというが、たしかに進まない。ちょうどいいので、読みそこねていた本数冊を一気に読みおえる。
五月二十四日(金)イベリア
トッパンホールで、岡田博美によるアルベニスの《イベリア》全曲を聴く。技術的にも規模的にも一気に弾くのが大変な曲だが、尻上りに調子をあげていく、素晴らしい演奏だった。
五月二十五日(土)プレトーク
日本フィルの定期演奏会で、プレトークを務めさせていただく。病み上がりで咳が抜けないが、本番になれば忘れるだろうとタカをくくって舞台に出たら、幸いそのとおりになった。
プログラムは高関健さんの指揮で《ジュピター》と《英雄》という、古典派の大傑作交響曲二曲。ピリオド奏法ではないが、自筆譜をもとに高関さん自らがパート譜を用意した演奏。
音符と音色が多く、放っておいても饒舌な後期ロマン派や国民楽派と異なり、抑揚とアクセントに気を払わねばならない古典派作品の演奏を重ねることは、オーケストラにとって財産になるはず。
五月二十九日(水)初期ヴェルディ
新国立劇場で《ナブッコ》。
グラハム・ヴィックの演出は現代の高級ショッピングモールに舞台を設定し、ユダヤ人を物欲にまみれた市民、バビロニア人を左翼的な革命勢力とするもの。うまくやれば説得力のありそうな設定なのだが、舞台がごちゃごちゃと未整理な印象で、感銘にはいたらず。
先月ゲネプロを見たコンヴィチュニー演出の《マクベス》とともに、初期ヴェルディは権力闘争、階級闘争に重きを置くと、断片をつないだだけの筋書の性急さがめだって、人間ドラマも、音楽そのものの魅力も感じにくい気がする。
五月三十一日(金)『虚無への供物』
中井英夫の『虚無への供物』(講談社文庫)を読了。
一九六四年に発表され、「推理小説の墓碑銘」とまで絶賛される小説だが、今まで読むのをさぼっていた。先週、風邪で臥せったときに、よい機会とようやく読み始め、ひきこまれた。
物語そのものの感想はここでは省略。その面白さに加えて自分にこの作品が意味深いのは、時代設定。
一九五四年九月二十六日の洞爺丸遭難事件の翌朝、函館の七重浜から遠望された七色の虹に始まって、一九五五年七月十二日の東京上空にたなびいた夏の日の彩雲まで、二百九十日間に起きた実際の事件や世相が、物語と深く結びつけられていること。
「しかし、この一九五五年、そしてたぶん、これから先もだろうが、無責任な好奇心の創り出すお楽しみだけは君たちのものさ。(略)おれには、なんという凄まじい虚無だろうとしか思えない」
一九五四年から一九五五年までのクラシック音楽をめぐる断片的な物語を書こうとして、四分の三まできて中断したままの自分にとって、強烈な促しの言葉。
そうだ、無責任な好奇心を掲げ、虚無への供物をつくろう。
また、「新装版へのあとがき」で本田正一が引用している、中井の日記の一節が心に残る。
中井が生涯の友人だったB公こと、田中貞夫に先立たれたときの、死の床での問答。
――死んだらどこへ行くのか、Bの最後の問いだった。教えてくれなくちゃ、教える、といった。
「他人の心の中に」だ。
この「他人」は「ひと」と読むそうである。
なきひとは こころのなか
六月一日(土)伊福部昭のバレエ音楽
ミューザ川崎で、広上淳一指揮の東京交響楽団の演奏会「伊福部昭 生誕百年記念プレコンサート」。
来年が生誕百年となる伊福部昭の作品から舞踏音楽を二曲。一九五〇年の《プロメテの火》と一九五一年の《日本の太鼓》。前者は約半世紀ぶりの演奏という珍しい作品。二作とも、伊福部が舞踊家の江口隆哉と共同制作したもの。
伊福部は、日本の作曲家のなかでも例外的にバレエ音楽に情熱を傾けた人で、《サロメ》や《人間釈迦》なども知られている。
バレエ・リュスなどの現代舞踏運動の日本版を目指したもので、人気を博して数多くの再演を重ねた作品もいくつかあるが、出版などはされなかったので、オリジナルの形での演奏は少ない。前述の《サロメ》と《人間釈迦》も、録音で聴けるのはのちに改作された版によるものだし、《プロメテの火》も、これまでは二台ピアノ版しかCDがなかった。
今回は指揮とオーケストラの熱演もあって、伊福部節をたっぷりと、充実した書法で堪能。とくに《プロメテの火》が見事で、バレエ版もいつか観てみたい。
ところで今日は、東日本大震災による損壊の修復後、初めてのミューザ川崎訪問。明快で力のある響きのよさは、幸いにも変ることなく、東響はこのホールでこそ、本領を発揮できる気がした。
六月四日(火)エスファハニと「拝啓ランドフスカ様」
東京文化会館小ホールで、マハン・エスファハニのチェンバロ・リサイタル。
エスファハニは一九八四年生れのイラン系アメリカ人。現在はイギリスを拠点にしているようで、今夜の曲目もウィグモア・ホールと同一だという。
前半がバードの作品だけで十曲、後半はバッハの《音楽の捧げ物》から三曲とリゲティ三曲。十六世紀、十八世紀、二十世紀と、五百年の鍵盤音楽の歴史のなかから三人の作曲家が選ばれ、リゲティではモダン・チェンバロを用いて、楽器の現代性を意識させる。
バードの曲をこんなに面白く、ファンタジー豊かに聴けるとは思わなかった。左手が雄弁で独立性が高いことが、音楽の骨格を確かにし、立体感と奥行をもたらしている。
モダン・チェンバロをピリオドに続けて聴くと、響きが繊細な味わいを失っているのがとてもよくわかるが、そのぶん強靱。いまバードやバッハをこれで聴きたいとは思わないが、リゲティのサイケ風の作品はこの楽器を想定して書いたのだから、これでひくのが正しい。
嬉しかったのは、アンコールにパーセルのハ短調のグラウンドを、ピリオドではなく、あえてモダン楽器で演奏したこと。この人、チェンバロの歴史を本当に深く熟知していると感服した。
この曲の、もっとも印象的な演奏の一つが、チェンバロ復興の最大の功労者、ランドフスカの、モダン楽器によるスケールの大きな録音だからだ。
十九世紀のあいだに、チェンバロはピアノに取ってかわられ、完全に忘れられた。社会の大衆化が進むにつれ、より強く、より大きく、より安定し、より輝かしい響きが求められたのに、構造的に対応できなかったからである。
二十世紀初めにチェンバロの復活が始まったとき、強大な音に慣れた聴衆の意識からあまり遠ざからないように、ピアノ的な剛性がチェンバロにも必要とされたのは、しかたのないことだった。
そして、とにもかくにもそれを用い、この楽器独自の魅力を、ピアノには置き換えられない魅力を、広く知らしめた最初のスターが、ランドフスカなのだ。
エスファハニはとくに何も告げなかったが、この演奏をもって、チェンバロ五百年の歴史をふり返る演奏会の最後を、この楽器の中興の祖であるランドフスカへのオマージュとしたのだ。
――拝啓 ランドフスカ様。
心温まって帰宅。エスファハニ、まだこれというディスクはないようだが、今後は要注目。
六月十一日(火)ウルトラセブンとローマ帝国

本を二冊。まず青山通の『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』(アルテス)。
すでに各所で話題となっている本で、最終回に突如鳴り響くシューマンのピアノ協奏曲をポイントに、テレビ番組をきっかけに音楽の面白さ、奥深さに出会っていく過程を回想したもの。
いまなら「ウルトラセブン 最終回 音楽」とでもキーワードを並べてネットで検索すれば、必要でない情報まで含めて、一瞬に答えが出る。しかし一九六〇年生れの著者の子供時代に、そんな便利なツールは存在しなかった。
何という名の音楽なのか、誰の演奏なのか。謎を解くのに著者は、初放映の一九六八年から中学三年生の七五年まで、七年を要した。
幼年期から思春期、人の個性が確立する時期だ。だが少年の行動範囲などせまいものだから、母親が観ていたテレビ、友人の兄がもっていたLP、そうした偶然の積み重ねで、著者は真実に至る。
このあたりは、二学年下の自分にも似たような経験(大したものではないが)があるから、とても共感がわく。
当時の情報の入手方法はかぎられていて、週刊誌や月刊誌に一度だけ載った記事に出会えるかどうかなどの偶然で、勝負はきまったのだ。偶然性と記憶力だけが頼りで、あとで引用しようにも、確実なソースなど示せるはずもない。
その推理小説じみた謎解きの過程を、じつに面白く読ませる本。

もう一つは南川高志の『新・ローマ帝国衰亡史』(岩波新書)。
著者は京都大学の西洋古代史教授で、特に専門とするのがローマ帝国時代のブリテン。以前にこの日記で紹介した『海のかなたのローマ帝国 ――古代ローマとブリテン島』は、サトクリフのローマン・ブリテン・シリーズの学問的副読本として、多くのことを教えてくれた。
そこでは何よりも、著者が学者としての節度を保ちながらも、『第九軍団のワシ』に深い愛着を抱いていることが、同好の士として頼もしかった。
この本はその著者が、西ローマ帝国全体の滅亡への歴史を、新たな視点で概説したもの。ブリテン島、さらにライン川とドナウ川流域の帝国周辺部の研究が、巧みに活かされている。
ローマ帝国というと、我々は地中海周辺に重きを置きがちだけれども、カエサル以降のローマでは、フランスやスペインなど、アルプスの北側地域の人口や経済力も比重が増していた。三世紀以降には、これらの地域の下層兵士出身の皇帝も登場している。
この世界帝国をまとめたのは、具体的なローマの都よりも、より観念的な「ローマ市民であろうとすること」という意識だった。そして、帝国の内と外の境界は曖昧で、柔軟であったものが、四世紀の後半になると急激に偏狭な「排他的ローマ主義」に変質し、数十年で巨大帝国を内側から崩壊させ、「外敵」ゲルマンの侵攻を許す結果になっていく。
ローマ帝国の歴史叙述の変容に、そのときどきの世界情勢の変化が反映されていることの指摘も面白かった。具体的な比定は避けつつも、日本の将来への危惧も、ここに示唆されている。
夜はサントリーホールで、チョン・キョンファのリサイタル。
六月十四日(金)トリフォノフ!
大野和士が二〇一五年から東京都交響楽団の音楽監督となることが発表され、その記者会見をホテルオークラで聞く。
終了後、オークラ別館の前の道を、南西に進む。泉ガーデンの東側を抜けて、飯倉片町の交差点へ向う、首都高沿いの道に出る。
麻布台一丁目というあたりだが、北半分は我善坊谷と呼ばれた谷町、南半分は台地の飯倉台と、土地の高低が――そして貴賤が――明確に二分されている場所である。
我善坊谷は、Vの字型に二つの坂が行き合う行合坂、その落ち合った交点からYの字の縦線のように下る落合坂、とてもわかりやすい名称の二つの坂を下りたところに始まる、東南へ伸びる谷間。
この谷は、徳川秀忠正室の崇源院を荼毘に付した場所といわれる。将軍家墓所の芝増上寺に近いし、実際に歩いてみると、江戸の火葬場だった四ツ谷千日谷や代々木狼谷と似た、細長い谷になっているから、この伝説は本当なのだろう。いまは確認できないが、谷の奥に水源があれば、葬場としての条件は完璧である。泉鏡花の小説『貧民倶楽部』で華族を乗せた馬車が賤民の不気味な葬列に出くわすのは、この谷間に下りたときだった。
崖の上の飯倉台、旧飯倉町六丁目は対照的な一等地。かつては紀州徳川侯爵の宏大な屋敷で、西北端の麻布小学校のあたりに「音楽の殿様」徳川頼貞が一九一八年(大正八年)に建てた音楽ホール、南葵楽堂があった。二年後の一九二〇年に、日本で初めてパイプオルガンを設置したコンサートホールである(その後このオルガンは上野の奏楽堂へ移転)。
この南葵楽堂の跡地が、同じくオルガンをもつサントリーホールと近く、そのあいだに我善坊谷が沈む。地形の妙。
さらに飯倉台の南側には、狸穴という別の谷間もあるので、そちらにも下りてみる。大きなビルが建ちつつあるが、こちらもまだ普通の住宅が多く、地形がわかりやすいのが嬉しい。
我善坊谷も狸穴も、そのうち森ビルが再開発して、麻布谷町をアークヒルズという「丘」に変えたように、谷間を消してしまうのかも知れない。
夜はオペラシティに移動して、待望のダニール・トリフォノフ独奏会。スクリャービンの二番、リストのロ短調、ショパンの二十四の前奏曲。
アンコールは自作のラフマニノフアーナ組曲五曲と、そして狂気のような、人間凶器のような、アゴースチ編曲によるストラヴィンスキーのバレエ音楽《火の鳥》の〈凶悪な踊り〉。
大爆発。ミュラが騎兵の悪魔なら、今のこの男はピアノの悪魔。目にもとまらぬピンポイント反復横跳び。
しかし、人間離れした俊敏な跳躍力、花咲ける乙女のごとき美しく軽やかな高音の一方で、その鋼のように強靱な低音が、人間の有限への暗鬱の嘆きを告げずにはおかないあたり、今年二十二歳の若き英雄が、たしかにロシア芸術の偉大な伝統の系譜に連なっていることを示す。
人はみな草の如く、されどそれゆえに花が咲く。
いまトリフォノフを聴かずして、何を聴く(笑)。
六月十五日(土)ヘレヴェッヘ登場
ヘレヴェッヘ&読売日本交響楽団によるベートーヴェン演奏会を、東京芸術劇場にて聴く。曲は《コリオラン》序曲、交響曲第一番、後半が第七番。
モーツァルトのオーケストレーションの天才の要諦は管楽器のグラデーションにあるが、対してベートーヴェンの場合は弦楽器のそれにあることを、よくわからせてくれる演奏だった。
第七番終楽章の弦楽器群の「対話」の面白さを教えてくれたのはクレンペラーだったが、ヘレヴェッヘは同じ場所を、各声部が独自性を保ちながらの、響きのグラデーションの遷移として聴かせてくれる。第一番の第二楽章もその白眉。
舞台上手の第二ヴァイオリンと、とりわけヴィオラの存在がきわだっていた。かれらがこんなに体を大きく揺らし、楽しそうに演奏する光景、日本のオーケストラではほとんど見たことがない。
他の楽員も献身的に、そして演奏する歓びを全身にあらわして音楽に没入していたのが素晴らしかった。リハーサルではヘレヴェッヘも、「フランスのオケはこんなに真剣にいうことをきいてはくれない」(笑)と喜んでいたそうだ。
はっきりいって指揮はわかりにくく、コリオランの冒頭など「これでどうやって出るの?」と客席の方が心配になるくらいのものなのに、あやふやにならずにちゃんと出るし、その後も各声部の滑舌が実によく、しゃべるように明快。入念なリハと、楽員の献身あればこそ実現した、生彩あふれるサウンド。
とてもいい感じのコラボレーションだから、今後もこの関係が継続発展してくれることを、切に願う。ひとまずは、来週二十一日のサントリーホールでのシューベルト&シューマン・プロが楽しみ。
昨日のトリフォノフ同様、ミスや完成度の低さを減点法でいいだせばキリはないが、とにかく二日続けて、クラシック音楽を「生きたままで」聴ける歓び。
六月十八日(火)大野の戦争レクイエム
上野の東京文化会館で、大野和士指揮東京交響楽団ほかによる、ブリテンの戦争レクイエム。
十四日の記者会見のとき、大野はこの曲のアニュス・デイでテノールが歌う、砲撃で分断された道路と遺体そのままの場面を、クロアチアのザグレブ・フィルの音楽監督をつとめていた一九九〇年代に、目の当たりにしたと語っていた。
また、それから二十年後の今では、当時の惨禍と憎悪を克服し、かつての交戦相手と融和しようとする、若い音楽家たちの動きがあるという。
戦争レクイエムとオーウェンの詩の描く悲劇は、現代も変ることなく、そしてこれからもくり返されようとしている。
今回の演奏会で、歌手が日中韓の三か国から選ばれていたのには、さまざまな意味が感じられた。
ただし、その意義は意義として認めた上で、芸術本位で考えると、歌手と合唱が、大野とオーケストラの引き締まった響きの水準に及ばなかったのは残念。
六月十九日(水)トゥルノフスキー
大友直人音楽監督の新体制がスタートして、首席客演指揮者なのに三年ぶりにやっと群響にもどってくる、チェコ生れの名匠トゥルノフスキー。
しかも演目は、待望の《わが祖国》全曲。十月の公演がもう売出しになっていたのを忘れていたが、無事購入完了。三年ぶりに高崎音楽センターと旧井上房一郎邸、アントニン・レーモンドが遺した二つの名作をまた眺めに行くつもり。
ちなみに音楽センターは、高崎城址と歩兵第十五連隊の駐屯地跡。こういう場所には、学校か体育館を建てるのが地方都市の通例なのに、ここには音楽ホールがある。老朽化で建てかえる計画も出ているそうだが、私は同じ一九六一年開場の東京文化会館とともに、日本の音楽文化の誇りだと思う。東京ホール歩き企画の、特別編にしたいくらいなのだ。
夜はトッパンホールで、チェロのクレメンス・ハーゲンとピアノの河村尚子によるデュオ・リサイタル。ウェーベルンの二つの小品、シューマンのアダージョとアレグロ、ベートーヴェンのチェロ・ソナタ第五番、そしてラフマニノフのチェロ・ソナタ。河村のピアノは、以前よりもかなりマッチョなスタイルに変ってきているように感じた。大味とはいわないけれど、少し気になる。
六月二十一日(金)ヘレヴェッヘ再び
サントリーホールで、ヘレヴェッヘと読売日本交響楽団のシューベルト&シューマン・プロ。前半は、このホールは十九世紀初めのオーケストラ曲に向かないという懸念があたってしまった。
シューベルトの小ハ長調は先週のベートーヴェンと同じ十四型(十四‐十二‐十‐八‐六)なのに、東京芸術劇場の親密さと明快さが共存した響きと異なる、拡散して芯のない響きしか、二階席では聞こえない。演奏自体は好演なのに、隔靴掻痒の感がうらめしい。
二曲目のシューマンのチェロ協奏曲は十九世紀半ばの音楽だが、編成が小さい(弦は十‐八‐六‐五‐三)ためか、独奏者を引き立てるためか、同様に頼りない響き。クレメンス・ハーゲンの豊かでコクのある独奏は素敵だった。
しかし後半のシューマンの《ライン》は、一転してホールに満ちて、安心感を与える豊穣な響き。楽員の硬さがとれたせいもあるのかも知れないが、それ以上に十九世紀も半ばになると、やはりオーケストラの骨柄が大きいというか、きっちりと肉がつく。弦は同じ数だが、ホルンが四人と倍増、トロンボーン三人が加わったこともあり、厚みが違う。
おかげで、《ライン》はヘレヴェッヘの仕掛けを愉しむことができた。抑揚とアクセントを明快に、波うって色彩と深さを変える音楽。幻想性よりも明朗さを前面に出し、大仰に見得を切ったりはしない。けっして精妙でも立体的ではないけれど、生彩豊か。
いい作品、いい音楽だと素直に感じる演奏。そして今日もヴィオラが大活躍、存在感ひときわだった。
次は偶然、一週間後に同じ会場でハーディングと新日フィルが同じ《ライン》をやるので、聴き較べが楽しみ。
読響の方はその前に名古屋と大阪に行って秋山和慶指揮で演奏会をするが、登場するソリストがなんとコジュヒン。ラフマニノフの二番をやるそうで、これは東京でも聴いてみたかった…。
六月二十二日(土)《悲劇的》の英雄性
ハーディング指揮新日本フィルのマーラー《悲劇的》をトリフォニーで。
ハーディングの《悲劇的》というのがまず魅力的で、客席も満員だったが、個人的にはそれに加え、シューベルトからマーラーへ、十九世紀の交響曲とオーケストラの発展史を丸一日のあいだに(昨夜は十九時開始、今日は十六時に終演)ナマで体験できることが嬉しい。東京という音楽都市のありがたさ。
一八一八年作曲のシューベルトから、一八五一年初演のシューマンをへて、一九〇六年初演のマーラーまで、工業化と国民国家の時代に重なる交響楽の巨大化と怪物化を、ほぼ望み通りに追体験することができたと思う。
古典派と変わらないシューベルトの素朴な二管編成に始まり、ホルンの倍増とトロンボーンを追加したロマン派中期のシューマンを経て、木管は四管、チューバにトランペット六にホルン八、ハープとチェレスタ各二台、そしてあのハンマーを含めて七人の奏者によって奏でられる十三種の打楽器を加えた、まさに国家総動員、総力戦体制のロマン派末期へ。
マーラーの場合、いつも書くようにたくさんのモビールが揺れ動くというか、無数の環虫がもつれあってぐちゃぐちゃ動き回るような響きになるから、ヘレヴェッヘ流のグラデーションでは、処理が難しいだろう。その意味で、輪郭がシャープで見通しがよく、音のモンタージュに長けたハーディングの棒は、オーケストレーションを知るためにもぴったりだった。打楽器群のちょっとした響きも、鮮明に聴きとることができた。
ハーディングの志向が端的に示されたのは、中間楽章を緩徐~スケルツォの順で演奏したこと。
マーラーは当初逆で着想し、初演時にこの順にしたといわれている。オリジナルのスケルツォ~緩徐の順の方が、ベートーヴェンの《合唱》やブルックナーの第八番を引き継いでドラマチックに、物語性豊かな交響詩風になるが、緩徐~スケルツォとすると、古典派交響曲の伝統に則ることになり、あえていえば純音楽的になる。
ハーディングの演奏は緊張感にみちていながらけっして暑苦しいものではないから、たしかにこの古典風の曲順があっていると思った。まあ、終楽章へのつながりは、やはり緩徐楽章のコーダの方が自然だとは思うけれど…。
それにしても、多彩で饒舌な響き。一部のミス、トゥッティの微妙なズレなどはあったけれど、新日本フィルがとても頑張ってくれたおかげで、オーケストラの響きはここまできてしまったのね、といまさら痛感。
そして、オーケストラが巨大で機能的な集団となればなるほど、かれらを率いる作曲家=指揮者という個人が「英雄」となって浮きあがっていくことも思う。
マーラーもR・シュトラウスも、そしてたぶんフルトヴェングラーも(交響曲第三番とか)、そのことを強く意識していたはず。指揮専業の人たちの方がもう少し気楽かもしれない。
作曲家=指揮者の英雄性の悲喜劇を痛感した最後の一人が、バーンスタインだったんじゃないか、あの人の《ミサ曲》は、まさに英雄性への鎮魂歌(英雄への鎮魂歌、ではなく。もともと英雄というのは悲劇的に死ぬものだから、それなら無数に書かれている)だったのじゃないか、なんてことも考えたり。
来週はハーディングの指揮で、シューマンの《ライン》をもう一度聴ける。ヘレヴェッヘでベートーヴェン~シューベルトからの流れで聴いた曲を、今度はマーラーとシベリウスから遡行する形で聴けるとしたら、これもまた東京の音楽会の醍醐味。
マーラー編曲版だったりしたら最高に愉快だが、まさかそれはないだろう。でも《ライン》の五楽章構成が、マーラーの交響曲の多楽章構成に影響を与えている気もして、そのあたりは注意して聴くつもり。
そういえば、むかしヤマカズ&新交響楽団のマーラーの交響曲第七番のプログラムの曲目解説(執筆者は失念)に《悲劇的》は《英雄の生涯》への、第七番は《家庭交響曲》への、R・シュトラウスに対するアンサー・シンフォニーではないかという説が展開されていた。もちろん証明不能の仮説にすぎないだろうが、ふたりの「英雄」の公私を考えると、面白い見立てだとは思う。
六月二十五日(火)夜叉ヶ池
新国立劇場の《夜叉ヶ池》初日。新聞評担当なので詳細はひかえるが、とてもよかった。予想をいい意味で斜め上に裏切り、音楽も演出も、鏡花幻妖譚のロマン世界を見事に現出したのにびっくり。
どうもこのところ、個人的に歌劇公演というものに幻滅が続いていたのだが、こういう舞台を見ると「ようこそ、劇場へ!」と声をかけてくれた気がして、オペラ通いの意欲が戻ってくる。
帰りは、いつものごとく樹齢三百年の甲州街道箒銀杏に、しかし今日はいつも以上に晴々した気分で一礼。
六月二十六日(水)フルシャのアルプス
サントリーホールで、ヤクブ・フルシャ指揮東京都交響楽団の見事な演奏会。
前半のリシエツキ独奏のショパンのピアノ協奏曲第二番は、いつものように軽やかでリリカルなピアノが心地よく、さらにフルシャがこのピアニストのことをとても評価しているのがひしひしと伝わってくるのが嬉しい。
そして後半のアルプス交響曲、しなやかで優艷、しかも雄大な響き。フルシャはR・シュトラウスの音楽語法を完璧に体得している。これはオペラも聴いてみたい。都響もさすがの出来で、二年前に聴いたプラハ・フィルハーモニアよりも相性がいいように思えた。
それにしても、先日の《悲劇的》と似たような大編成なのに、何と響きの異なること! たくさんの楽器がひしめき合い、しばきあい、結局は傷つけあっているかのような《悲劇的》の「痛さ」にくらべて、アルプスのそれは色とりどりの花畑のよう。なかでもカウベルの印象の差が象徴的だった。
マーラーとR・シュトラウス、ハーディングとフルシャ、新日と都響、トリフォニーとサントリー、すべての違いが同じ方向に作用しあって、教えてくれるものの多い結果を生んでいた。
ところで、音が鳴りやむとすぐに後方でカツカツと靴音が響いて気に障ったのだが、終演直前に体調が悪くなって、担架で運ばれた人が二階席にいたらしい。帰宅後に友人に教えてもらいびっくり。
超高齢化社会では、こうしたことが増えるだろう。もし音楽評論家が演奏中に客席で死んだら、本望といえるのだろうか…。
六月二十九日(金)多摩の新日フィル
パルテノン多摩で、ハーディング指揮新日本フィルの演奏会。
曙橋から乗り継ぎを重ねて、多摩センターへ。途中の京王線沿線は緑が多く残っていて、家並みも気持がいい。小田急線も似たような地域を走るのに、周囲の景色がコンクリがつまって殺伐とした、乾いた印象なのとは、ずいぶん違う。
多摩センター駅は受験のときに中央大学の発表を見にきた一九八一年以来だから、三十二年ぶり。あのころは駅しかなかった気がするが、いまは大発展。
ただ、自分が降りた南口は大きくて立派なビルばかりで小さな店舗が見当たらず、人工的で生活臭が少ない気もする。一億総中流幻想時代の一九七〇年代半ばに新たにつくられた駅だから、闇市風の飲食店街が見当たらないのは、当然といえば当然か。
パルテノン多摩は駅の正面、丘陵の中腹に堂々と建っている。背後がそのまま多摩中央公園になって、豊かな緑と水を背負っている。整然として均整がとれ、完成予想図がそのまま立体になったような、まさに絵のような都市計画。
照明が暗めの千四百席のホール、聴衆は三分の二くらいか。しかし東京郊外のホールのクラシックの聴衆に共通する特長として、マナーがよく丁寧な拍手をするので、演奏側の気分は悪くないはず。
シベリウスの交響曲第五番とシューマンの《ライン》はモダンで流線型の、すっきりした演奏。まさに二十世紀的。この人がアバドの弟子なのを思い出す。二曲の合間のヴィトマンの《トイフェル・アモール》は、《悲劇的》の系譜を継ぐような、痛くて苦しい、大編成の響き。
七月二日(火)読書感想文『ウルトラマンが泣いている』

円谷英明『ウルトラマンが泣いている 円谷プロの失敗』(講談社現代新書)を読了。
一九六六年、設立三年目にして不滅のキャラクター、そして不滅の商品、ウルトラマンを生み出した、生み出してしまった円谷プロダクションの栄光と迷走、そして、創業者円谷英二の後継者一族全員が会社から放逐されるまでの半世紀の歴史を、孫の立場から回想。
失敗、怠慢、不和、徒労、挫折、後悔と、読んだこちらが泣けてくる話。
一九六〇年前後に東宝は、俳優や監督などのスター級に次々と個人プロを設立させている。映画産業の黄金期の終りとテレビの隆盛を必然のものと見て、経営のスリム化をはかったのだろう。一九六三年設立の円谷プロも、この流れのなかで黒澤明や三船敏郎のそれととともに生れたものだった。他社でも石原裕次郎、中村錦之助、勝新太郎が続いている。
そうした個人プロには、放漫経営が原因でつぶれたり、縮小したりしたものがいくつかあった。この本を読むかぎり、円谷プロにも早くからその危険がつきまとい、いつ倒産しても不思議ではなかったようだ。
ところが、ウルトラマンという不滅のキャラを生んだことが、存続を可能にしてしまう。困れば誰かが金を貸してくれるし、マーチャンダイズが本業を補って余りあるほどに儲かるからである。
たとえ関係者に不祥事があろうと、架空のキャラに傷はつかず、商品価値が損なわれることはない。それが経営陣の驕りを生み、狂わせていく。
映画以上にテレビの実写の連続ドラマは、集団での共同作業、分担作業の傾向が強い。だから誰も独占できないかわりに、誰もが直接間接に「生みの親」の一人に加わることができる。きわめて高度資本主義的な産物。そして、有能なクリエーターが、有能であればあるほどすりつぶされ、消費される場である。
ここで、音楽というものだけは、ドラマの場合でも特殊で、著作権の独立性が高く、のみこまれにくいことに気づく。
作詞はグループだったりすることもあるけれど、作曲家はまず単独。歌手は、ロイヤリティの恩恵にはあずかれなくても、歌声のイメージ固定による認知度の高さははかりしれない。
そのせいか、この本のなかで音楽著作権に関する言及はほとんどない。そして『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』がある種の「爽やかさ」を維持している要因の一つは、その健全な独立性にあるとも思えてくる。
個人的には、著者が一九五九年生れ、自分の三学年上でほぼ同世代というのも興味深かった。しかも、円谷英二は一九〇一年生れで私の祖父と同い年、その長男で著者の父の一は一九三一年生れで、我が父の一歳上。
三代続けて近いのも、かつて「怠慢な三代目」だった自分(いまは「怠慢なフリーランス」)には、他人事に思えなかったりする。
さらに『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』の青山通が一九六〇年生れ、四月に出ていたがこれから読む『ウルトラマンがいた時代』の小谷野敦が一九六二年生れ。そしてウルトラマン論の嚆矢というべき『怪獣使いと少年』を、二十年前の一九九三年に出した切通理作が、一九六四年生れ。
円谷の孫、そしてウルトラシリーズの作者たちの子供の世代にあたる、一九六〇年前後の人々によるウルトラマン論。
ついでにいえば、創作という形態で円谷特撮へのオマージュを捧げている庵野秀明が一九六〇年生れ。特技監督、映画監督の樋口真嗣が一九六五年生れ。
庵野からの連想で思うのは、アニメというのも共同作業だが、こちらは監督の作家性がきわめて強いジャンルだ。ディズニーも手塚治虫も宮崎駿も富野喜幸も庵野も、円谷英二と円谷プロよりもその点で恵まれている。一方で、作家性を欠いたプロデューサーが強権を有した『宇宙戦艦ヤマト』が、アニメなのに最近までかなり迷走したのは、暗示的だ。
著者が述べるように、かれらとはちがって本来は下請けの制作プロダクションであるはずの円谷プロに、作家性の幻想が生じてしまったことが、間違いの始まりだったのか。
数日後にミュージックバードで『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』を特集した番組の収録をするので、それまでに『怪獣使いと少年』も、久々に読みかえしてみるつもり。
ところで、円谷一族に少し似たワーグナー家がしっかりしているのは、ワーグナー本人の作家性が確立されていることと、ひょっとしたらコジマ以来、ある種の「母権制」(母性社会ではなくて)の一面があったからかも知れない。
そう思って、あらためて考えると、この本での円谷一族の母や妻の存在は、不思議なまでに薄い…。
七月五日(金)「この上、お金までもらえるなんて」
ミュージックバードのザ・クラシックの六時間番組「ウィークエンド・スペシャル」の枠で、「ウルトラセブンと聴くクラシック」を収録。
青山通さんの話題の本、『ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた』(アルテスパブリッシング)の内容に沿って、著者の青山さんと、『ウルトラセブン』の音楽監督である冬木透先生のお話をうかがうもの。
この本については六月十一日の当欄でも少し触れたが、その面白さは、初めは何の曲か、誰の演奏かわからなかった、『ウルトラセブン』最終回の音楽の謎を青山さんという「探偵」が何年もかけて解いていき、ついにその「犯人」である冬木先生と直接「対決」して「真相」をたずねるという、ミステリーのような構成にある。
そこで番組の方は、「間抜けなワトスン」たる私が、探偵と犯人の二人にお話をうかがっていくスタイル。
最終回につかわれたシューマンのピアノ協奏曲の、さまざまな異演の聴き較べを中心に、ウルトラセブンの音楽や、大のクラシック通であるお二人の、おすすめのディスクを紹介した。
謎解きをラジオで再現しつつ、ワトスン役として「謎解き」と「自白」の導入をさせていただくのは、とても愉しかった。ひさびさに「聞き役」の面白さ、充実感を存分に味わった。
お二人と会話をしているとき、まさに「話は仁術」という気がした。
人が二人と書いて「仁」。ようするに仁とは、相異なる人間同士が相手との関係を適切なものにしようとする心持、状態のことだと私は勝手に思っている。それが、会話を通じて具現化した瞬間が、あったような気がしたのだ。
お二人とも初対面なのに、当方の言わんとすること、期待する答えを瞬時に汲み取って、ピンポンのラリーのように、言葉を放ったり受けたり、会話の快感を味わわせてくださった。阿諛追従や巧言令色ではない、心遣いの心地よさ。
こういう会話ができて本当に嬉しく、この世に生きている甲斐があると思ったし、これは独りよがりでなく、きっとリスナーの方にも伝わると信じる。
それにしても冬木先生は、『ウルトラセブン』だけでなく、それ以降の七〇年代のウルトラシリーズの音楽もつくられた方。『帰ってきたウルトラマン』の、あの「ワンダバ」も。
今日はなんと、自分の子供時代の思い出をつくってくれたそのような方から、ピアニストのソロモンの来日公演についてのお話もいただけた。
大不評のため、日本音楽史からほとんど抹殺されている一九五三年のソロモン唯一の来日公演を実際に聴かれて、「みんなはよくないといったけれど、自分はいいと思った」という感想を、誰あろう冬木先生にうかがうことができたのだ。
まさしく「この上、お金までもらえるなんて…」という瞬間。
放送は八月十一日(日)十六時から。再放送は十七日(土)午後十二時から。
七月十二日(金)福岡旅行初日
二泊三日で福岡へ。明日土曜にアクロス福岡で開催される「特別セミナー『トリスタンとイゾルデ』を開く三つの扉」第一回のゲストとして、ナビゲーターの池田卓夫さんと対談するため。
普通なら当日入りだが、博多祇園山笠の祭と重なって航空券代がはねあがるので、生れて初めての九州だし、せっかくなので安い前日に入ることにした。
空港が市の中心に近いのは便利。地下鉄で天神地区のホテルへ。しかしあまりに暑くて日射しが強いため、日中は動く気になれず。平地で歩きやすそうな町並みなのに、残念。夜も天神で食べたが、メインの街路から裏へ入ると屋敷町のような雰囲気が残り、建物をそのまま転用した飲食店なども多く、いい感じ。
どういう理由かわからないが、東京と違ってそうした細い道に車やバイク、自転車の類が、まったく入ってこない。歩きやすくてとても心地よかった。
七月十三日(土)九大フィルの故地
福岡は今日も暑し。橋を渡って西中洲の天神中央公園内にある旧福岡県公会堂貴賓館に行き、ボランティアの方に案内していただく。
一九〇九年完成の洋館で、東京の北の丸公園に現存する旧近衛師団司令部庁舎と、ほぼ同時期の建物。たしかに雰囲気に共通するものがある。
公会堂の裏には、地続きで集会場と呼ばれたホールがあった。残念ながら老朽化で一九八一年に取壊されたが、日本のアマチュア・オケの草分け、九州大学の九大フィルハーモニー初期の演奏会は、このホールで行なわれていたそうだ。
九大フィルは一九〇九年発足というから、奇しくもこの公会堂と同い年。アマチュアといっても、モーツァルトの交響曲第四十番やベートーヴェンの第一番、メンデルスゾーンの《イタリア》などの日本初演を大正年間に行なって、日本の交響楽運動そのものの先駆けとなった、輝かしい歴史を持つ団体である。
運動の中心となったのは、九州帝大医学部教授の榊保三郎。ヴァイオリンをよくし、ドイツ留学のさいにヨアヒムに師事、膨大な楽譜を購入して帰国した。
一九一八年、まだ学習院高等科の学生だった近衞秀麿が、独学でベートーヴェンの交響曲を研究していたときのこと。第一番と《英雄》のスコアは東京音楽学校にあったが、第四番は日本に唯一冊、榊教授が所有するのみと知って、はるばる博多へ訪ねて筆写させてもらった、という話がある。前述のモーツァルトやベートーヴェンが九州で日本初演されたのは、翌年の一九一九年のことだった。
それらの名曲が日本で初めて響いたのは、いまは公園の空地の、ここだったかもという感慨に耽る…といいたいところだが、かんかん照りでそんな余裕なし。
アクロス福岡はこの公園のすぐ対岸、九州交響楽団が本拠地とするのはそのシンフォニーホール。今日の講演は円形ホールという、百三、四十人の会場。
時間があるので、天神の地名の由来となった、水鏡天満宮に参詣。その北に辰野金吾が設計した、東京駅とよく似た赤煉瓦文化館が見えた。これも一九〇九年竣工の歴史的建造物。入ってみたくなったが時間切れで断念。
そのあとの講演は十一月二十日に行なわれる、チョン・ミョンフン指揮東京フィルハーモニー交響楽団の《トリスタンとイゾルデ》演奏会形式公演のための、プレイベントである。満員で、とても熱心に聴いてくださった。
参考に、オリヴィエ・ピィが演出した二〇〇五年チューリヒ劇場での「愛の二重唱」を紹介。独房を思わせる無機的なイゾルデの部屋が、二重唱の進行とともに回り舞台で変化していくもので、水、火、土、風と四大元素が提示され、ドクロがポイントとなる。クライマックスで独房の部屋に戻ってしまうのは、哲学的な愛から即物的な愛(セックス)へと転じたことの象徴だろうか。
夜は中洲で打ち上げ。イカの活き作りが美味。昨日今日と、福岡の食は旨い。ラーメンとか屋台とか、こってり系もいいのだろうけれど、素材の鮮度の高さを活かした料理の方が、自分は好き。
残念ながら、中洲の名高い歓楽街は遠目に見ただけ。町人地の博多、武家地の福岡と、川を境に明快にわかれていて、中間の、江戸期までは畑と湿地しかなかった中洲に歓楽街があるという区分が、話に聞いていたとおりで面白い。
中洲だけでなく博多も地下鉄で通過しただけで町は見なかったが(こういうとき、景色の見えない地下鉄は実につまらない)、福岡の天神周辺の、気取らずに洗練された都市性はとても気に入った。
特に新天町という、入り組んだ回遊式のアーケード街がよかった。昔ながらの小店舗ばかりで、しかも活気がある。アーケード内が街路ごと冷房されていて、過ごしやすいのもこの時期には天国。目的もなくブラブラ歩く楽しさ。
七月十四日(日)太宰府天満宮
福岡三日目。今日は太宰府天満宮へ。このところ、何かと関東の天神社を話題にすることが多い。よい機会なのでお参りをする。晴と雨が頻繁に、極端に交替する、不安定な天気。
西鉄の福岡(天神)駅から大牟田線に乗る。JRは博多、西鉄は福岡と、駅の位置が離れているのがいい。一度乗り換えて四十分ほどで着く。途中に太宰府跡があって、海からかなり遠いのを実感。菅原道真の霊廟跡につくられたという天満宮は背後に山を控えて、いかにも葬祭の地という気配の地形だった。
午後の旅客機で羽田へ。暑くてごく一部しか町を見られず、阿曇族の故地である志賀島にも行けなかった(地元の人によると、とても漢委奴國王印が出土するとは思えないような、何もない場所らしいが)。食べ物も美味だし、いつかまたゆっくり、もう少し楽な季節に来たい。
七月十八日(木)電子書籍のいま
二日の日記の『ウルトラマンが泣いている』の感想を最初にフェイスブックに載せたあと、フェイスブックが閲覧できない中国に赴任中の友人にも読んでもらうべく、ミクシィの日記に転載した(以前にも書いたが、ミクシィは無害と見なされているのか、中国からの閲覧も書込みも自由なのだ)。
すると、その友人からいわれたのが、本そのものもぜひ読みたいけれど、電子書籍になってないね、ということ。
電子書籍に疎い私は、海外在住者にとってはこういうとき、現物よりも電子書籍の方が圧倒的に便利なのだと、初めて気がついた。
さらにもう一つ、新書は意外と電子書籍化されてないらしい、ということ。
薄いものだから簡単に電子化できそうだが、薄い手軽なものだからこそ電子化したくないのか。それとも、たまたまなのか。
電子書籍では、単行本と文庫の区別は意味がなくなる。単に割引率の問題にすぎない。しかし書き下ろし中心の新書はまた別の流れにあるのか。
出版界の人によると、電子書籍化の初期費用と、販売サイトやIT会社などにとられる経費を考えると、低価格の本はよほど数を売らないと、元がとれないそうだ。書き手や出版社よりも「場」の提供者が儲かるという、ネット社会そのものと同じ構造になっているらしい。
だから新書のように、生産~流通~販売のルートが確立され、現在もかなり安定しているものの場合は、ネット業界と海外在住者以外には、電子化のメリットが少ないらしいのである。
それに、たとえ電子化されても、中国国内で買えるものには制限があるのではないだろうか。別の友人が指摘したとおり、『ウルトラマンが泣いている』には中国ビジネスの大失敗のことも最後に書いてあるし…(笑)。
ふっと思ったが、いま日本が国策的に推進しているクール・ジャパン云々というのは、結局、日本全体が円谷プロ化するということなのではあるまいか。すると東宝がアメリカ、バンダイは…。
七月十九日(金)百十万人分の空家
アメリカのデトロイト市が財政破綻して、負債一兆八千億円というニュース。
このニュースもすごいが、それより気になったのが、最盛期には百八十万人を超えたデトロイト市の人口が、いまは役七十万人に減少しているとあったこと。
ということは、百十万人分の住居が空家になり、インフラが放置されているのか。現在の人口の一・五倍もの空家。町の半分以上が空家。
どういう雰囲気なのだろう。当然ながら、治安の悪さは全米でも一、二を争うらしい。中流以上の家庭が郊外のベッドタウンに移住し、中心部が空洞化するのは世界の大都市に共通することだが、デトロイトの減り方は極端すぎる。
クラシック好きにとっては、パレーが指揮したデトロイト交響楽団の本拠地でもある。現在スラットキンを監督に戴く同楽団は、二〇一〇年に減給をめぐってストがあったそうだが、いまはサイトなどを見るかぎり、普通にシーズンを続けているようだ。
七月二十日(土)西陽の闇と夜の輝き
東京タワーの蝋人形館が、九月一日で営業終了というニュース。
最後に行ったのがいつだったか覚えていない(たぶん小学生)くらいだし、閉館前にもう一度行きたいとも思わないのだけれど、それでもなくなるのは残念。
スカイツリーのアンテナが本格稼働して電波放送の収入が減って、来場収入が頼りになった東京タワーとしては、新奇で集客力のある企画で気分一新、というところなのか。
正直、蝋人形というもの自体、東京タワーというよりもかつての浅草っぽい、おどろおどろしい見世物(乱歩的世界)で、いまの日本には合わない気がする。
お台場のマダム・タッソーはどんな雰囲気なのか知らないが、東京タワーのそれは、有名人よりも拷問とか凶悪犯罪とかの再現場面の方が、自分には印象が強かったからだろうが。
そんな場面を思い出していたら、自分の子供時代、つまり昭和四十年代までは遊園地などにも、どこかに暗い影があったことが脳裏に甦ってきた。なにか、江戸の見世物小屋以来の陰惨な雰囲気を引きずっていて、それが乱歩の『押絵と旅する男』に出てくる浅草十二階周辺やサーカス(曲馬団)などの世界と、じつによく親和していたのだ。怪人二十面相の前身がサーカスの曲芸師というのも、いかにも納得させられるのである。
たとえば横浜ドリームランド。おぼろな記憶では、和製ディズニーランドを目指したわりには、そこここの物陰に翳がひそんでいた。
そして、一九八三年開場の浦安のディズニーランドは、何よりもそうした日本の遊園地特有のうらぶれた暗さを、初めて一掃してみせたのが凄かったし、それで消費の新時代を切り拓いた。
あれやそのあとのバブル期の風俗が、明るさや豊かさの日本的典型というものなのだとすると、自分はその方が苦手だけれども(笑)。
かつての日本型遊園地の典型的な場面として記憶にあるのは、西陽に照らされた夕方の、お客の姿がなくなった時間帯の、さびしい景色。
ところが東京ディズニーランドは、夜にエレクトリカルパレードをやって、日暮れ時の遊園地につきものだった終末感を、期待感へと一変させてみせた。ほんとうに革命的な存在だったのだ。
そういえばコンビニもファミレスも、夜遅くに煌々と明るく営業中、というのが魅力の一つだった。いわゆる夜の商売ではない、健全な日常生活に取り込まれた「夜の輝き」こそ、八〇年代消費文化を象徴したものかも知れない。
七月二十二日(月)咳をしても一人
フェイスブックの友達の方が、ある日突然に「これは架空アカウントです。フェイスブックは実名で使用しましょう」と表示されて、ログイン停止になったとのこと。
フェイスブックが実名と顔出し写真を原則としていることは、よく知られている。日本ではそのリスクがかなり過剰にいいたてられているが、匿名ムラ社会になれた人がその拡大を忌み嫌うからだろう。きちんとワキをかためていれば、私はそれほど危険なものだとは思わない。
相手も実名で顔出しで、現実社会に似た社交のマナーが自ずと存在するから、よほど安心感がある。それを見栄や虚礼と思う人もいるが、匿名で本音(ナマの本音というよりは、興味本位で悪意の割合を増幅させたもの)を言い捨てあう環境よりも、私には気持がいい。
だから、架空アカウントが使用停止になること自体は結構なことなのだが、この停止された方の場合は、実名と顔出しで参加されているのだ。ひどい事実誤認としかいいようがない。
ところが、フェイスブックには電話で対応するカスタマーセンターのようなものはないらしい。復旧の依頼や手続きはメールでのやりとりとなったが、相手の応対は機械的で、指示された復旧策もすんなりとはうまくいかず、時間と手間がかかったそうだ。
これと似たようなケースを、又聞きで知ってはいたが、近しい人に起きたとなると、戦慄の度と危機感が違ってくる。
アカウント停止の根拠は教えてもらえず、一切不明というのが怖い。タダだから仕方ないとも思うけれど、仕事のやりとりに使っていたりしたら、大変。
便利なものだけれど、いつなくなってもいい、くらいの心がけは必要か。
原因がただの誤認なのか、それとも何者かの讒訴によるものか。スターリン粛清時代のモスクワにいるつもりくらいでいるほうが、気が楽かも知れない。
さらに、これは偶然だろうが、私がこの顛末をご本人の文章も含めて自分のフェイスブックのウォールに書き込もうとしたら、これまでどんなにたくさん書いても見たことのない、「適正な機能の容量を超えています。節度を保ってご使用ください。このまま続けると機能停止となります」といったような警告が出現、消されてしまった。
ちゃんとチェックされているような気がした。そんなわけはないが(笑)。
しかたないので、簡略化して上記のことを掲載した。すると、それを読まれた別の友達の方から、十億人にサービスを提供しているフェイスブックの場合、生身の人間ではなくシステムがすべて自動で監視して処理するだけだろうから、恣意性はない反面、システムが間違っていても人間が対応してくれる可能性は薄いだろう、というご意見をいただいた。
そして、そのシステムは『一九八四』に出てくるビッグ・ブラザーのようなものではという、示唆に富んだご指摘も。
偉大なるビッグ・ブラザー。非人間。ヒューマンエラーはないがバグはある。
こちらが消されても怒っても抗議しても批判しても、対応するのは、ただのシステム。
――咳をしても一人(尾崎放哉)
七月二十四日(水)LED専用ライト

仕事机に取り付けた二十七ワットツイン蛍光灯のアームライトが壊れた。タッチ式のスイッチの接触が悪くなったか、つけてもすぐ勝手に消える。今の家にくる前後から、十五年ほど働いてくれたものなので、ご苦労さまと感謝するのみ。
というわけで買換え。前のメーカーがツインバードで、長く使ってもアームの間接がゆるんでバカにならず信頼できたので、今回もそこにする。
調べると、もうLEDが主流になっている。壊れた蛍光灯式は、従来の電球式に代って登場してまもない時期に、これは便利と買った記憶があるが、それから十五年、次の段階へ進んでいた。実買価格はLED式も蛍光灯と変わらないし、我が家にはまだLEDがなかったので、ものは験しに購入。LEDアームライトのLE‐H638Bというもの。
使ってみると、いわれているように照明範囲は蛍光灯よりも狭いし、手元の影が多くなった気もするが、これはすぐに慣れるだろう。導光板を用いて点光源を面光源に変換しているので、小さい電球がたくさん、というLEDの旧来のイメージとは異なる。
便利なのは、輝度が五段階で明暗を調節でき、色も昼光色から電球色まで、三段階を手軽に切り換えられること。また蛍光灯よりずっと小型で軽く、そのぶんアームの間接への負荷も小さいから、全体に細くなっているのもいい。蛍光灯にはときどき頭をぶつけて痛い思いをしたが、それもなさそう。
もう一つの相違は、LEDが固定で本体に組み込まれていて、交換できないらしいこと。LEDの寿命が来たら、アームライトそのものを買い換えることになるらしい。
あれっと一瞬思ったが、LEDの定格寿命は四万時間。単純に計算しても、一日十時間使ったとして十一年近くもつものだから、これは電器器具として全体を交換するべき長さに匹敵する。
小型の蛍光灯が開発され、電球と付け替えた経験の延長に、新たな交換品としてLED電球があると、自分などは思っていた。だが、今回のアームライトを使ってみて、LEDは交換用としてより、初めからLED専用の照明器具で使ってこそ、小型軽量化に輝度と色の調節機能などの利点が発揮されるとわかった。この方が、代替品としての不満も少なくすむ気がする。
寝室の蛍光灯式の読書スタンドも、真夏は発熱がきつい。読書時は昼光色で明るく、就寝時は常夜灯として電球色で暗めに、手元ですぐ切り換えられるのは、便利だろうと思う。今度蛍光灯が切れたら、本体ごと買換えよう。
七月二十七日(土)パリのイタリア人たち
カリニャーニ指揮の紀尾井シンフォニエッタの演奏会。
ケルビーニの交響曲とロッシーニのスターバト・マーテル、オペラで鳴らした二人の「パリのイタリア人」の作品を、紀尾井ホールで聴けるのが嬉しい。
ケルビーニの交響曲は幻想曲風というか、一瞬一瞬の感興を楽しむ作品。それだけにとりとめがなく、いささか長く感じられた。
スターバト・マーテルには、四人の独唱と新国立劇場合唱団が加わる。イタリア人独唱者のオペラティックな表情づけと、合唱とオーケストラの澄明で整然とした音楽が異質すぎて調和しない。さらにテノール歌手の不調もあって、途中まではギクシャクと乗りの悪い感じだったが、合唱だけの終盤は、澄んだ響きが美しかった。
七月三十日(火)ホフマン物語
二期会の《ホフマン物語》ゲネプロを新国立劇場のオペラパレスで観る。
あくまでゲネプロだから評の対象とはならないし、お客が入れば違うのかも知れないが、今晩はプラッソンの指揮が生命力に満ちて、見事だった。
プラッソン、十五日にオペラシティで聴いた東響とのフランス・プロはなかなかだったが、数年前の二期会の《ファウストの劫罰》はとにかく眠かったという記憶しかなく、正直あまり期待していなかった。
でも、ことオッフェンバックとなるとこの人、まるで別の輝きを放つ。あらゆる細部に血が通って、優美に、活発に、鳴り響く。この人の中に、オッフェンバックの音楽が血肉化しているかのような自然さ。数日前に、初日のアントニア役の木下美穂子さんにインタビューしたとき、「プラッソンのオッフェンバックへの思い入れは特別」という意味のことをおっしゃっていたけれど、まさにそのとおり。
我が最愛の作曲家、ジャック・オッフェンバック。むかしはこう言っても、ふざけていると思われて本気にされなかったことがあったが、三十年前からこれは変らない。
私のオッフェンバック愛を決定的なものにしてくれたのは、若きプラッソンが一九七〇年代にEMIに録音した《パリ生活》である。
その光輝はいまも色褪せない、まさに不滅の名盤だが、その後の《美しきエレーヌ》や《ラ・ペリコール》はもう一つの出来だったので、あれは偶然の産物だったのか、と思っていた。
でも今夜は違った。これまでオッフェンバックのなかであまり好きでなかった《ホフマン物語》がいかに傑作かということを、初めて知った気がする。
特に、かれの旧作とほぼ同じ語法で書かれている、序幕と第一幕の合唱とオケの絡みには、あの《パリ生活》の演奏を彷彿とさせる輝かしい瞬間がいくつもあって、鳥肌もの。
面白いのは、そして素晴らしいのは、これだけオッフェンバックの音楽のツボを押さえた指揮だからこそ、この作品のキメラのような、ちぐはぐさが露わになってくること。それが、死を前にしたオッフェンバック自身が新たな可能性を求めたからなのか、他人の手が加わってしまったからなのか、そこはまだ私には判然とはしないが、とにかくちぐはぐ。近年一般的な校訂版でもその弱点は消えていないが、さらに今回はプラッソンの希望で古い慣用版が用いられていたので、特にその印象が強かった。
ジュリエッタの幕が、もうまるで不自然なのだ。ホフマンのパートはとてもドラマチックに書かれていて、ドミンゴがいかにもうまく歌いそうな、実際見事に歌っている音楽なのだけれど、その激しさはまるでヴェリズモ。
もちろん、すでに《カルメン》も存在し、音楽の傾向全体が激烈になってきていたことを思えば、オッフェンバック自身が敏感にその流行をとりいれた、と考えて不思議ではないのだが、ただ何か、板についていない感じ。その「感じ」がプラッソンの指揮では見事に浮かびあがる。そうしたことなど、本当に教えられるところの多い演奏だった。
あの有名な六重唱と合唱の絡みも、妙に堂々としすぎていて、とてもオッフェンバックの書くものには思えない。そのあとの、舟歌の旋律にのせて会話でドラマが進行していく結びも、こういうモンタージュみたいな映画的手法は、あまりにも「近代的」すぎる。オッフェンバックはもう少し古いタイプの音楽職人だから、音楽できちんと語らせたがるはず。この幕は腕のたつ人がつくり、構成したことは疑いないが、確実に作曲家本人ではなく、いちばん弱い。
続くアントニアの幕、彼女とミラクル博士の場面に、やはりオッフェンバックの旧作とはかなり異なる手法があるのだけれど、おそらくこれはグノーの《ファウスト》のマルガレーテのいくつかの場面をヒントにしたもので、まったく異質とまではいえない。《ファウスト》の影響を想起させ、ジュリエッタの幕との質の違いを実感させるあたり、本当にプラッソンの演奏は見事で、フランス・オペラの語法を知り尽くしているからこそだろう。
この幕は粟国の演出もわかりやすく、実に冴えていて、アントニア役の高橋絵里の熱唱もあって、ドラマに引きこまれた。各幕のヒロインが女性のさまざまな面を象徴するように、悪もやはり各幕で種々の姿が示されるなかで、このミラクル博士は、外にいる悪ではなく、アントニアやその父の内部にある暗部、ダークサイドを具現化させたものだから、いちばん存在感と説得力がある。
アントニアの、自らを滅ぼす暗い衝動は、すなわち人間の自己表現の衝動、芸術的衝動そのもので、それがホフマンという詩人をも同じく突き動かしている、というこのオペラの骨子はじつにロマン派的、十九世紀的なもの。
オッフェンバックは、こういう、人間の内面の暗い衝動を描いたドラマを生涯の最後に示そうとしたのかと、かれを愛する者として、少し胸が熱くなった。
エピローグもいい音楽だが、ここはふたたびキメラで、ちぐはぐ。ホフマンとアントニアの同類性を示すのに、またドミンゴが必要になるのは妙だ。そのやり口がわかりやすすぎ、あざとすぎて、ちょっとオッフェンバックらしくない。
しかし、そういうことにこれだけ深く気がついたことはなかったので、やはりこのゲネプロは得難い経験だった。
舞台機構の関係もあって新国立劇場になったそうだが、音響的にも視覚的にも東京文化会館より格段に好条件なので、それも大きな力に。
営業的には大変かもしれないが、来てくれたお客を感動させ、次も来ようという気にさせる可能性が高い、つまり将来と未来につながる可能性がより高いことを思えば、できるだけこの新国立劇場でやってほしいと思う。
本番は見られないが、成功を祈る。
七月三十一日(水)一九五六年生れ
某誌の企画で、國土潤一、片桐卓也両氏と鼎談。始まる前の雑談で、一九五六年生れの國土さんが
「自分は敗戦後の貧しい日本を知っている、最後の学年。翌年からは高度成長モードになる」
と言われ、同い年の片桐さんも
「そうそう。五七年生れになると違うんだよね」
とても面白い話だが、その七年後に生れた自分には、何とも判断のしようがない。ただ、たとえば阿久悠の一九五六年の日本を舞台にした小説『最後の楽園』には五五年が「歴史の折り返し点」だったとあり、五六年からマンボ・ブームに「もはや戦後ではない」や太陽族など、戦後の大衆社会の享楽性が一気に増したと、知識としては知っている。
その環境の変化に、生れたときから包まれるのが一九五七年生れから、ということなのだろうか…。
八月一日(木)市民音楽、オラトリオ
先日出た、アーノンクールの《アレクザンダーの饗宴》の拡大版のディスク、後半を始める前に、ある合唱曲を客席に歌わせる場面が入っていて、愉しい。
客席の大半が楽友協会の会員、そして舞台で歌っているのも楽友協会合唱団(ジングフェライン)、この両者が同心円の団体(客席には合唱団OBも少なくないはず)で、かれらのような「市民」が十九世紀以降のクラシック音楽の発展を支えてきたという歴史的事実を、指揮者が踏まえているからこその、楽友協会創立二百年記念演奏会の「客いじり」。
まさに市民音楽としてのオラトリオ。さすがアーノンクール。
八月三日(土)戦後からの脱却
麻生副首相の「ナチス」と「改憲」をからめた発言が世界的な批判を浴びる。
麻生副首相が小泉元首相にならって、生誕二百年記念のバイロイト音楽祭を見に行きたいといったら、ドイツは入れてくれるのだろうか…。
ところで、あらためて思ったのは、現代ドイツにおける「原罪」であり、「絶対悪」であり、使いようによっては「免罪符」ともなるナチズム。麻生発言は、真意がどこにあるかに関わりなく、この危険すぎる言葉に安易に触れたことが問題なのだが、このナチズム、日本の場合は「軍国主義」ということになる。
つまり「悪いのは軍部」。敗戦後の内外の解釈はそうだったはずで、毛沢東もこの解釈を支持していた。
戦力放棄の憲法第九条は、まさにこの歴史解釈によって生れたもの。A級戦犯とは、その犯人のこと。韓国人が旭日旗を忌み嫌うのは、ハーケンクロイツと同様の、原罪の象徴と見なすからだろう。
軍部(とそれに同調した為政者)に責任を負わせ、侵略のための軍隊を放棄することで、国民も、天皇も、ひとまず罪を逃れることができた。だから、再軍備はしない。そのような凶悪なものはもう復活させません。この図式が、平和憲法の原点である。
一方、ドイツでは悪いのはナチズムであって、プロイセン以来の伝統的な軍国主義は少なくとも主犯ではないとされたから、占領が終るとすぐに再軍備した。
しかし、独立国家としてのドイツの再軍備はむしろ当然なことで、つきつめれば軍隊も官僚機構の一つ。つまり近代国家の維持運営に必要不可欠な組織の一つにすぎないのだから、ほんらい存在の可否を問うべきものではない。
軍人の暴走、政治への容喙などの「軍国主義」の欠点に対しては、そのことを抑止すべきなのであって、軍隊そのものをなくすことはできない。ナチズムを否定しても国家運営に支障はないが、軍隊なしでは国家の領土と治安は維持できない。非武装中立は、アメリカの傘の下での、独善的な夢想にすぎない。
ところが日本の場合、この当然の事実を認めると、「悪いのは軍部」という戦後の構図の基盤が、崩れてしまうことになる。責任の所在を、あらためて問い直さねばならなくなる。
しかし、官僚機構には正しいも悪いもない。官僚機構が「悪の組織」になるとしたら、それは社会全体が悪になったときしかないのだ。
だからといって、日本社会全体がナチス党みたいな「永遠の絶対悪」扱いを受け続けるのは困るし、頭を下げて屈従するだけというわけにもいかない。「日本社会=悪」だった過去をどう乗りこえて明日に進むか、どう世界を(中韓だけではなく)納得させるかを、我々も考えなければならない。「悪いのは軍部」のゴマカシは、いろいろな意味で、もはや通用しなくなっている。
軍隊は危ないから放棄します、というのがこれまでの憲法だが、これはアメリカという保護者のついている、子供の憲法。子供が包丁をもてば危ない。危ないけれど必要だから、こうしてコントロールします、と示すのが、一人前の憲法。
「悪いのは軍部」という解釈をそのままに、第九条を改めて再軍備するのは、愚の骨頂だ。「ドイツでナチスを復活させるのと、同じ事をします」と、世界に宣言してしまうことになるのだから。そこまでバカなら仕方がないが(笑)、そうでないのなら、まずは解釈を変えることから始める必要がある。
軍部だけに責任を負わせる戦後日本の解釈を、すなわち「軍部をナチスのようなものと見なす」解釈をやめる覚悟が、再軍備に先立って必要になる。
軍部ではなく、日本社会全体に責任があったと、我々も加害者であったと、解釈しなおすことを宣言する。当然、謝罪と反省は、これまでとは別の位置づけから行う必要がある。
そうしたのち、二度と他民族の独立と尊厳を不当に侵すことのない、新たな社会体制を建設するには、具体的には軍部と結託して政権にしがみつく為政者、軍需で私利を貪る産業界、威勢のいいことを言って人気をとるマスコミと言論人の暴走、そして一時的な気分に流されやすい大衆世論、これらを、言論の自由を守りつつコントロールするには、どうするかを示さねばならない。
そうして初めて、自国の独立と国民の尊厳を自らの手で護ることを、再軍備を世界に宣言できる。ここに、軍部を悪としてきた日本の、ドイツとの違い、困難がある。
課題は軍隊の管理に加えて、その外の方が大きいのだ。「国防軍」と使用目的を限定しておけば充分というものではない。軍隊よりも、その周囲の、社会構造の問題なのだから。そこを抑制して初めて、軍隊は「悪の組織」ではなく、本来そうであるべきところの、ただの官僚機構の一つに復帰することが可能になる。
戦後からの脱却とは、こうした歴史再解釈と、社会再構築の作業にほかならない。それを忘れて、ただ自己満足の、夜郎自大な軍隊ごっこをやるなら、必ずまた破滅することになる。
しかしこの脱却は、安保体制との両立が可能なのだろうか。
八月九日(金)夏は塔上
「夏は塔上、冬は地上」
送電線工事の電工たちの合言葉。高い鉄塔の上は温度も低く風も吹くので、真夏は塔上作業のほうがいい。真冬はもちろん逆。
こう暑いと、自分も山の尾根の上の、百万ボルト送電線のいちばんてっぺんが恋しい。
見上げても、ただ積乱雲。
二十年もむかしの、遥かなる夏の風。
宿舎へ帰ったときの、ビールの美味かったこと。
話かわって、インターハイの高校柔道の百キロ超級の優勝者が、東海大浦安のウルフアロンとニュースで知る。
何者? 駅伝みたいな、どっかからの留学生? と思ったら、米日のハーフらしい。すでに東海大に進んだ一年先輩にも、ベイカー茉秋(ましゅう)というホープがいるそうだ。
柔道界でも、サッカー同様にカタカナ名前がふえてきたのか。日本代表に入るのかどうかまでは知らないが、とにかく活性化してほしい。
八月九日(金)白昼の記憶
真夏の送電線工事現場。もう一つ思い出したので、また昔話。やや納涼系。
二十年ほど前、ある地方都市の自動車メーカーの敷地の隅にある、老朽化した鉄塔を建てなおすことになった。
すぐ脇がテストコースなので、まずは現場の鉄塔の上からコース内が見えないように、目隠しの布を高く張ってから、建て替え開始。
こういう工場内の作業では、正門を通るたびにチェックを受けなければならないので、作業車が何度も出入りするときなど、手間がかかることもある(余談だが、取引業者の場合は、他メーカーの車に乗ってきたら以後の出入り禁止、などということもあるそうだ。我々は外部の業者で直接の関係ではないのでお咎めなしだったが、当時はこうした企業が少なくなく、生コン業者などはどんな工事現場に行っても問題にならないよう、ミキサー車は三社あるメーカーを均等に揃えていると言っていた)。
しかし、うまいことにその現場の場合は、敷地の角に、ふだん使っていない外への出入口があった。大型車も通ることのできる、古い大きな鉄門である。おかげで工場の正門を通らずに作業できた。
それはいいのだが、毎日通っているうちに、この現場、何か妙な一角だなぁ、と思うようになった。
出入口があって便利なのに、ふだんはまったく使っておらず、人けがない。野ざらしにすると塗料がどう変質するかとか、そんな気長な実験のために部品が置いてあったりするだけ。まわりは雑木雑草におおわれ、どことなく湿っぽい。
工事も進んできた、ある日の昼。
現場では昼飯を食べたあと、日陰で昼寝をするのが通例だが、一人の作業員さんと話していたとき、
「寝るときは、あそこの茂みには入らない方がいいよ」
その人が突然、そう言った。
「あそこは、空襲でこの工場がやられたとき、遺体を並べた場所だから」
どうしてそんなことを言いだすのか、理由をきく気にはならなかった――何というか、妙に腑に落ちてしまったから。
この自動車工場は、戦時中には軍用機やそのエンジンをつくっていた。そのため大戦末期に何度も米軍の空襲を受け、大きな被害とともに、多数の犠牲者を出している。
その作業員さんはかなりの年配で、近くの村に住んでいる人だから、そのとき実際に何かを目撃したのかも知れない。
しかしその話を聞いたときには、もっと何か、霊体験的なものだと思った。
なぜなら、たしかにその塀際の茂み、霊感などまるでない自分にも、最初から変に暗く見えて、近づく気になれなかった場所だったからだ。
ただこれだけの話で、何か起きたわけではない。つまらんと思われた方は、ご期待を裏切って申し訳ない。
いまになって思うと、作業用に我々が使わせてもらっていた「ふだん使っていない出入口」は、かなり古そうなものだったし、この工場全体の「不浄門」にあたるものだったのではないか。
現在はどうなっているのだろう。見にいってみたい気もする。
八月十日(土)君よ八月に熱くなれ
夏の甲子園、浦和学院対仙台育英、途中から気がついてテレビで見ていたが、物凄い試合だった。
初回の攻防で一対六と仙台が逆転、三回に浦和が打者十三人の猛攻で八点をとり、六回表まで十対六とリード。しかしその裏に仙台が相手のエラーに乗じて四点とって同点。そして九回裏、二死一塁の場面で、ここまで一人で投げ抜いてきた浦和のエース小島(選抜優勝投手の二年生)が熱中症で足がつって涙の降板、代った山口(アメリカ人とのハーフらしい)が二塁打を打たれて、十対十一で仙台のサヨナラ勝ち。
タイムリーエラーやひとり相撲の押し出しなど、双方にミスの多い乱打戦だったから、高水準の試合とはいえない。いかにも高校生の野球なのだけれど、そうした力みや焦りの凡プレーが、気迫や無心の生む好プレーと表裏一体、一瞬に交替しながらドラマの綾を織りなしていった点で、高校野球だけにしかない醍醐味にあふれたゲームだった。
その最高の例が、八回裏の小島のピッチング。無死満塁で迎えるバッターは四番という、絶体絶命のピンチ。ここから十二球全てストレートの直球勝負で、三者連続三振。まさしく精神力(としかいいようがない)でピンチをしのいだ。
選抜優勝投手の名に恥じぬ、凄まじい投球だったが、おそらくはこの全力投球が次の九回に熱中症で降板することにつながったのだから、勝負の神様は容赦がない。泣くな小島、センバツの花。
ほんとうに、見ているだけの人間は無責任なものだが、こういう試合を現実化させるために甲子園はある、という気がする。君よ八月に熱くなれ。
八月十二日(月)野茂の帰還
十日に行なわれたメジャーリーグで、野茂英雄が古巣ドジャース戦の始球式を行なったというニュースを、ニュースサイトの「スポーツナビ」に掲載された山脇明子さんの記事「ドジャースタジアムから野茂英雄へ――ヒーローに贈られた熱い声援と喝采」で知る。
松井のヤンキーズ引退セレモニーに較べると、日本マスコミの扱いは地味だったし、一日契約のような特別待遇でもないけれども、野茂がドジャースタジアムのマウンドに、再び立っていたのだ。
強引な、横紙破りのドジャース入団だったとはいえ、「日本人でもMLBでスターになれる」ことを初めて証明した功績の大きさははかり知れない(だって、その二十年前には、星飛雄馬のようなあんな非人間的な魔球を投げられないかぎり、大リーグでは通用しないと思われていたのだから)。
この山脇さんの文章も、とてもいい。
現地の雰囲気を感動的にリポートするなかに野茂の経歴をコンパクトに織りこみ、最後は、ドジャースのザック・グリンキー投手の言葉を引用して、プロのスポーツマンシップの継承こそがMLB百年の大きな魅力であることを、野茂がその歴史のなかに立っていることを、示して終る。日本人観客が少ないこと=日本マスコミの関心が低いことを、あまり声高に皮肉ったりしない節度も、お見事。
そのグリンキー投手の言葉、ここにも引用させてもらう。
一九八三年生れのかれは二〇〇八年にロイヤルズで、メジャーでの最後の年を迎えていた野茂と、わずかな期間だけチームメイトになった。
「彼は40歳近い年齢だったのに、2時間にわたる打撃練習でもずっと球拾いをしていた。球拾いをやめて中に入ってはどうかと声を掛けても他の選手と一緒にずっと球拾いをしていた。彼がキャリアでどれだけのことを成し遂げてきたかは誰もが知っていたけれど、彼は決してそれを鼻にかけるようなことはしなかった。ああいう一面を僕も見習いたいと思った」
グリンキーは、翌二〇〇九年にサイ・ヤング賞を獲得。そしてこの日の野茂の始球式の後、先発のマウンドに立ち、見事に勝ち投手となって、今季十勝目を挙げたのである。
八月十四日(水)放蕩亭主の響き
GUILDが出した、一九六〇年のストコフスキーのフィラデルフィア復帰演奏会のトリスタンのシンフォニック・シンセサイズ《愛の音楽》、しばらく前に届いていたのをようやく聴いたが、やっぱものすげぇぇぇぇ。
したたるように官能的な弦の音は、尋常ではない。十九年ぶりに戻ってきた放蕩亭主ストコフスキーとの、音の交合。まさに交響的交合。
驚かされるのは、ここまで官能的なのに異様に響きが澄んでいること。倍音がそろって、スパーンと抜けてホール中に鳴りわたるんだろうということが、不完全なステレオ録音でも、はっきりとわかる物凄さ。そのあとに聴いたブラームスの交響曲第一番の終楽章のクライマックスでも、まさにオルガンのように調和して鳴りきって、度肝を抜かれた。
これが本物の、ストコフスキーのフィラデルフィア・サウンド。まさしくフィラデルフィア・エクスペリメント。
二回の演奏会の完全CD化を切望。この日の、あの《牧神の午後への前奏曲》冒頭のキンケイドのフルートを、きちんと世に出してほしい!
八月十八日(日)佐村河内守の演奏会
ミューザ川崎で、佐村河内守作品の演奏会。《弦楽のためのレクイエム・ヒロシマ》の初演と、交響曲第一番《HIROSHIMA》全楽章版を、大友直人指揮の東京交響楽団で。
交響曲第一番は二〇一〇年四月四日に東京芸術劇場で、同じメンバーによる第一楽章と第三楽章のみの東京初演を聴いて以来だから、三年ぶり。
あのときはまだ、佐村河内の名前は一部の楽壇人と、かなりのマニアにしか知られていなかった。いまのように流行して、「感動物語」が喧伝されている状況だったら、自分のように平凡な人間は、きっと斜に構えて聴かなかったり、バカにしながら聴くにきまっているから、その前に聴くことができて、本当によかったと思っている。
また、初めて聴くには第二楽章抜きの形で正解だったとも思う。それでも約四十分、短いものではなかった。
そして、録音ではなく、ナマで最初に聴けたこともよかった。
とにかく、これくらい轟然と、あるいは深々と、そして立体的また威圧的に、きれいに抜けのいい響きでフルオーケストラを鳴らす才能というのは、日本人作曲家にはあまり類を見ないのではないかと思う。このフルオーケストラの響きの圧力があるから、弦楽が祈りの主題(全楽章に共通する主題)を歌う美しさも、大きな落差のなかで活きてくる。
何がどうより、私にとって佐村河内の真価は、この「落差の凄さ」にある。そしてそれは、ナマでこそよくわかる。
今日の演奏で、その「音圧の落差」を、三年ぶりに味わった。「闘技場の中」という感じのミューザの一階席(闘牛の牛になったような気分なのだ…)だったから、明快さも充分に味わいながら。
闘技場のような周囲の高い壁により、音がちゃんと反射してくるから、けっして響きが頭上をこさずに実体感があり、なおかつ混濁もしないのが、このホールの素晴らしいところ。
さて、第二楽章が入った全楽章版をナマで聴くのは、今日が初めて。ここは、たしかに長い。最初の体験がここ抜きでよかったと思うのはそれが理由だ。とはいえ、この明と暗が交錯し、行きつ戻りつをくり返す、迷走と沈潜の苦しい楽章があって、第三楽章の克服の闘争と光明につながる必然性は、よくわかる。
作曲者には、この「長さ」が必要なのだろう。前半のレクイエムや、他の室内楽作品などがもう一つカタルシスに欠けるのは、かれのドラマトゥルギーには短すぎるからなのではないか。また、前述のようにフルオーケストラ編成も、その長所であると同時に、必需品。あの金管と打楽器の咆哮があるからこそ、弦楽器の祈りに切実さが生れる。
この音楽に「どこかで聴いたような響き」、「誰それのような響き」が出てくることを、弱点と見なす人もいる。しかし、私はこれでよいと思う。
これだけ録音と実演で過去の名作がくり返し響く世の中に、独創のみを求めれば、よほどの天才か狂人でないかぎり、独善の袋小路にはまる。
それよりも、自らが敬愛する音楽を素直に衒いなく「本歌取り」する方が、よほど共感できる。この点は、同じ一九六三年生れとしての、手前勝手な世代的共感でもあるのだが。
大友直人と東響は、レコーディングなどの経験をへて、この長大な音楽を自家薬籠中のものにしつつある、と感じた。特に第一楽章に関しては、構成と構造の把握に確固たるものがあったと思う。
もちろん、東京初演のときの、演奏者も聴衆も全員が手さぐり状態で、そのわけのわからない進行の中から、コーダの光明がわきあがってきて、鐘が高らかに響きわたった瞬間の感動は、どうにも忘れがたいものだが、それは「初聴き」ならではのことだから、あのときかぎりの思い出ということでいい。
今日はとりわけ、金管が素晴らしかった。佐村河内は宗教的な、ブルックナー風のコラール主題ではなく、より世俗的な、バロックの宮廷音楽のような明朗さと快活さを金管に求めることがあるけれど(第二楽章の中間部など)、それも見事に歌われていた。
二回目、長い全楽章版で、しかも思いっきり感動する気でつめかけた聴衆に囲まれてとなると、自分はどう感じるんだろうと、聴く前には不安もあった。しかし、結果的にはそんなこと関係なく、やはりエモーショナルな音楽だった。
(二〇一四年二月八日の附記:この作品は佐村河内守本人の作曲ではなく、作曲家新垣隆が、佐村河内の構成案と指示の下に作曲したことが明らかになった。新垣は健常者であり、ここに書いたことの基礎的事実が崩れたことになるが、当時の私のいつわりのない心境として、原文には手をふれずにおくことにする)
八月十九日(月)眼龍さん、黄金の豚
夏の甲子園、常総学院に眼龍(がんりゅう)という姓の選手がいるのを知る。こんな姓、いままで知らなかった。
佐々木小次郎の厳流とかとは、関係ないのだろうな。あれも雅号なのか流派なのか、よくわからないものだけれど。字も岸柳とか書く場合もあるし。
話かわって、七月三十一日の日記で、一九五六年生れの人が、翌年以降の生れと違って、戦後の貧しさを知っていると語ったということを書いた。
結局、あとに生れた私などはその実感の由来がよくわからないのだが、そんな話を同世代の人とやりとりするなかで、そのちょうど十年後、一九六六年には、前後と確実な差があるという話になる。
一九六六年は丙午(ひのえうま)、気性が激しく夫の命を縮める女性が生れると日本では信じられて、前年の四分の三しか子供が生れていないからだ。
この翌年の六七年から新生児がどんどん増え、団塊ジュニアの世代となる。また、ちょうどこの世代が高校に進むころに学習指導要領が初めて緩和され、つめ込みからゆとり式に変る。いわゆる「ゆとり教育世代」は、小学校からそれを受けた、十歳ほど下の年代以降を指すのだろうが、ともあれ変化は、丙午をきっかけに始まる。
友人によると、こうした干支による出生の増減はヴェトナムにもあるそうだ。「黄金の豚(猪)」と呼ばれる丁亥(ひのとい)がそれで、この年に生れた子供は「財と幸運」に恵まれると信じられ、この干支にあたる二〇〇七年が、ベビーブームになった。
ヴェトナム政府は極端な増減を嫌い、過去のこの干支には偉人が生まれていないという警告まで出したが、歯止めはかからなかったらしい。
面白いのはこの丁亥、前回は一九四七年、つまり日本の団塊世代の頂点の年と重なっていること。
日本の場合はもちろん、終戦による成年男子の復員がこの年の出生数の激増に作用したわけで、別に干支を意識したためではないだろう。
しかし、社会的にも収入的にも社会保障的にも、この年の人が後世の世代より「財と幸運」に恵まれているのは、本当という気がする。偉大な政治家などは出ないようだが、消費集団としては、とても幸福な年代だ。
二〇〇七年生れの日本の「黄金の豚」は、どんな未来を生きるのだろう。
八月二十日(火)百年いろいろ
「気になるディスク」に、一九一二/一三年シーズンからフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督になったネゼ=セガンの、このオーケストラとのディスク第一弾を取りあげる。
ちょうど百年前の一九一二年のストコフスキー就任と、一九一三年初演の《春の祭典》を意識した、うまい選曲になっているものだ。
しかもさらに加えて、最後には伊福部昭のあの有名な自衛隊マーチの「原曲」(?)といわれる、ストラヴィンスキーの《パストラーレ》を、ストコフスキー編曲で聴ける。日本人にとっては、来年の伊福部昭生誕百年にもちなんでいるという(きっとネゼ=セガンは、そんなこと夢にも知らないだろうが…)ほんとうに見事な選曲の一枚。
八月二十一日(水)近代日本の英雄とは
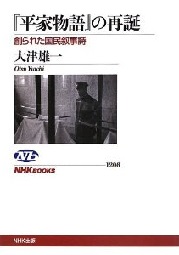
大津雄一の書いた「『平家物語』の再誕」(NHKブックス)を読む。
江戸期から現代まで、『平家物語』はどのように受容されてきたか。
副題に「創られた国民叙事詩」とあるように、いわば「誤読の歴史」としての受容史である。
江戸時代までは立派な史書として扱われてきた『平家物語』は、明治の文明開化で西洋の実証的な歴史学が導入されると、史実面の不備を指弾される。そして史料的価値の低いものとされ、学問としては歴史学ではなく、国文学が扱うべきものとなる。
しかし初期の、つまり明治二十年代の国文学では、『平家物語』の評価は芳しいものではなかった。一つには、江戸以来の国学が日本独自の大和心の発露である『万葉集』や記紀を称揚する代りに、外来の仏教、儒教思想の影響が濃い『平家物語』を軽んじてきた伝統があった。そこへさらに、中世の文化を暗黒時代として軽視する西洋の人文主義的な歴史観が、後押しする形になったからである。
評価が一転するのは、明治三十年代、日清と日露の二つの対外戦争の合間に、国民意識が俄かに高揚した時期である。
「国民」という概念自体、そもそも西洋的なものだが、その卸元の西洋文学においては、国民精神を発揚させるジャンルとして、叙事詩が重要視されていた。
ところが、日本の古典文学には、叙事詩というスタイルがない。これを恥じた知識人たちは、詩ではないはずの『平家物語』を「国民叙事詩」に相当する存在として、称揚しはじめる。
近代西洋の思想、史観を日本文化に強引に当てはめ、日本も西洋風の立派な歴史や文化をもつ、一流国とその国民だと強弁する道具の一つに、『平家物語』が使われだすのだ。「国民叙事詩の創造」である。
そして叙事詩には、主人公となる英雄がいなければならない。惰弱な教養人ではなく、自然児のように素朴で逞しい野性をもった、時代の革新者となる英雄。つまり、国民精神を発揚させる、(やはり西洋風の)ロマン主義的な英雄。
『平家物語』の登場人物のなかで、成立の前後から広汎な人気を独占してきたのは源義経だが、この人はその軍事的天才にもかかわらず、貴種流離譚的な、薄幸の貴公子というイメージの方が強く、叙事詩の英雄にはふさわしくない。
代りに、高山樗牛や山路愛山によって讃えられたのが、平清盛である。
それまでは権勢に奢る、強欲好色の横暴な老人という悪印象が強かったのに、英雄叙事詩の主人公としての清盛は、堕落した貴族社会に終止符を打ち、素朴で健全な武士の世を招来する「高貴な野蛮人」に読みかえられる。
同時に、山国の田舎者と嘲笑されていた木曽義仲も「愛すべき野人」として、そのイメージが生まれ変る。
こうして、明治末期から昭和にかけ、『平家物語』は清盛や義仲など大小の英雄が活躍する群像劇、すなわち国民叙事詩として、読まれるようになっていく。
さらに、急激に右傾化する昭和初期には、武士道精神、日本精神、国民道徳の教科書だと、かなり強引に読まれる。
ここで著者は、当時の国文学者たちの時勢に媚びた醜さを曝露して、痛烈。
そして、戦後になって民主主義の時代になると、かれらが一転して責任を他になすりつけ、口をぬぐってちゃっかり生き残る様子を描くあたりも面白い――もちろんこれは、当時の日本社会のあらゆる場所で起きたことだろうけれど。
しかし、過去を忘却することで大学教員としての地位は保ったとはいえ、さすがにかれらが戦後も学問的な成果をあげることは不可能で、国文学は、歴史学の勢いに引っぱられるかたちになる。
その歴史学とは、石母田正に代表される、マルクス主義の唯物史観。
面白いのは、この見方によって『平家物語』が、再び国民叙事詩に捉えなおされてしまうことだ。
戦後十年ほどの日本共産党は、紆余曲折はあるけれど、プロレタリアート革命が最終目標であることは変りなかった。とりわけ、サンフランシスコ講和条約後には、武力革命によって日本をアメリカの属国から自立させ、民族的独立をかちとることが使命になった。
その後に育った私などの感覚では、右翼的にこそ思える「民族」とか「愛国」とかいった言葉が、左翼勢力によって用いられた時代なのだ(一九五〇年の〈民族独立行動隊の歌〉が、右翼ではなく左翼の運動歌なのは、その象徴)。
この民族独立革命の外国における指導者、英雄が、レーニンでありスターリンであり、毛沢東であり金日成であり、ホーチミンである。
この思想のもとに、唯物史観によって日本歴史を見なおすと、平清盛は、古代的貴族社会に反抗し、中世的な武士の世界を切り拓く、頼朝、義仲、義経たちと同じ階級闘争のリーダー、大英雄の一人ということになる。『平家物語』は、かれらが活躍する日本民族の叙事詩、国民叙事詩となる。
ところがこれは結局、明治の高山樗牛や山路愛山の、ロマン主義的な英雄としての清盛像の焼きなおしにすぎない。
一九五五年の六全協で日本共産党は武装闘争路線を撤回、現実社会では平和共存をうたうことになり、これをきっかけに英雄礼賛も、党の周囲では(やはり口をぬぐって)否定されていく。
だが、ノンポリの大衆社会では、これまで同様の『平家物語』観が残っていくことになる。
その典型が、一九五〇年から五七年に執筆され、大ベストセラーとなって多くの読者に影響を与えた、吉川英治の『新・平家物語』である。
著者はここでの清盛、そして他の登場人物の姿は、「明治以来のイメージで造形されていて新しさはない」とする。私もそのとおりだと思う。
同様の英雄史観は、昨年の大河ドラマ『平清盛』にも、受け継がれていた(あれはマンガじみた薄っぺらい人間造形で、ひどかったが)。
このほか、やはりベストセラーである石母田正の岩波新書『平家物語』の、運命劇としての解釈(その象徴を平知盛にみる)が、西洋哲学の影響によるものであって、国文学としてはより慎重であるべきだと指摘したのも面白い。
著者はそこまで言いきるのを避けているが、これは近代の知識人石母田の、西洋風の「誤読」なのである。
さて、これを読んでつくづく思ったのは、明治維新以来百五十年、変ることなく日本人は、西洋伝来のロマン主義的なヒーロー像、時代の変革者としての「高貴な野蛮人」に、憧れ続けてきたのだなあ、ということ。
それぞれの時期に流行のイデオロギーに染まることはあっても、基本的な人間像にはぶれがない。
清盛だけではない。織田信長が、江戸期までそれほど人気がなかったというのは有名な話だが、とくに昭和以降に大人気になったことの背景には、やはりこの英雄憧憬があるのだろう。清盛の再評価と呼応する。どちらも「高貴な野蛮人」の型に、見事にあてはまったのだ。信長の場合は後半生よりも、吉法師時代の乱暴者の姿にあらわれる。
そしてこのヒーロー像の、高度成長期における最大の新発見が、いうまでもなく『竜馬がゆく』の坂本龍馬だ。
平成においては、小説よりも現実の方が劇場化して、こうしたヒーローが望まれているように思えるが、なかなか…。
ところで、この西洋型英雄像の隆盛と対照的に、義経のような日本古来のスターの人気は、次第に下がっている。
ようするに、仇討物語の主人公。義経記、曽我物語、山椒太夫、忠臣蔵など。美少年美青年が苛められて可哀そう、という嗜虐的な快感の裏返しの物語。
「少年倶楽部」の挿絵などにはそうした嗜虐美が多量に残っていたから、そちらへの憧れは戦後になって薄れてきた、てことか。現代の腐女子のBL趣味は、その変形のようでもあるけれど…。
八月二十九日(木)安曇氏の山野
初日の二十三日に続いて、二十八日に今年二回目のサイトウ・キネン・フェスティバルを松本へ見に行き、一泊。
オペラなのに開演が夜七時と遅かったおかげで、あがたの森公園まで歩いていきながら、どういうわけか昔から大好きな、信濃の夕暮の空をたっぷり味わう。
公園内の旧制松本高校校舎と講堂は、サイトウ・キネンの学生向けの講習に使われていた。

そのあと、会場のまつもと市民芸術館まで歩いたがまだ開演まで時間があったので、会場脇の深志神社へ。
最初の深志城(松本城)主である、小笠原氏が創始したもの。主神は諏訪大明神ことタケミナカタの神だが、なんと天神様も一緒に祀られていて、今年なぜか天神づいている自分には嬉しい偶然。二枚目の写真はその夜景。

翌日は朝から大糸線に乗り、安曇野の美しい山野を眺めつつ、穂高駅でおりて穂高神社へ。ここは、地元の安曇族が主神を祀ったところ。
私は信州の地名が大好きだ。
ホタカ、アヅミノ、タテシナ、ハニシナなど、それを発したときに口に残る余韻が、とても心地よいから。
だから、安曇野という地名の元が同名の氏族であると知って、縁もゆかりもないのに、この氏族に関心を持ってきた。
そして、このアヅミ族というのが、じつは遥か九州は福岡東部の志賀島あたりを発祥の地とする海人族、ワダツミ族であると知ったときは、そのスケールの大きなロマンが、とても嬉しかった。
志賀島というのは、例の「漢委奴国王印」が出たところで、志賀海神社というのがある。ここに祀られる綿津見神(ワタツミノカミ)という海神こそ、アヅミ族の主神。
ここを本拠に天皇家(応神王朝あたりから?)に仕え、海産物をその食膳に供してきた。やがて本土に移住して、海辺の各地に、阿曇・安曇・厚見・厚海・渥美・阿積・泉・熱海・飽海などの地名を残している。
そのかれらが、なぜ最終的には海をはるかに、山に囲まれた安曇野の地を拠点とすることになったのか。
これが、よくわからない。この氏族の有名人は祖先神の阿曇磯良(イソラ)、白村江の戦いで水軍を率いて戦死した安曇比羅夫(ヒラフ)くらいで、その後のヤマト王権の発展の中でかれらがなぜここに来たか、正史には書かれておらず、確実な説明はない。
この「まるでわからない」こと、それも大好きなのだ。
アヅミノ、というじつに美しい響きの地名を残した種族が、九州の志賀島からやってきて、ここにいた。そのため、穂高神社の例大祭、御船祭ではその名のとおり、海などどこにもない山国なのに、船形の山車が出る。そして、白村江の戦いを再現する。
かれらの故地が海であることをしめすもう一つの例証として、長野県では安曇野においてだけ、エゴという海藻の加工品を食べる習慣があるそうだ。山国なのに、わざわざこれを食べている。
そしてこのエゴ、それと同じものを福岡でオキュートと呼んで食べている事実が、かれらが北九州から来たことを証明してもいる。
先日読んだサトクリフの『シールド・オブ・リング』では、海を渡ってイングランドに入ったヴァイキングが、平野を越えて西側の山国、湖水地方に隠れ住んでいた。そして、その族長の館の天井には、昔の誇りを忘れないために、船の船首が飾られている。このあたりを読んだとき、おお、まるで安曇野のワダツミ族そのものじゃないかと、嬉しくなったことがあった。
しかし、日本のワダツミ族がこの緑美しい山間の平野に落ち着くまでには、どんな物語があり、どんな英雄がかれらとともに戦ったのか。何も、わからない。記紀神話から漏れて、いまやすべては忘却のかなた。
それがいい。
有力な説としては、アヅミ族は日本海沿岸の新潟県の糸魚川にたどりついて、姫川沿いに「塩の道」を南下、ここに来たのではないかという。
前述の「エゴ」は、糸魚川あたりでも食べるそうだから、おそらくこの説のとおりなのだろう。
むかし、一度だけ送電線の仕事にかこつけて、大町~白馬~小谷~糸魚川と、車でその「塩の道」国道一四八号を抜けて新潟へ出たことがある。親不知の現場で働く作業員に、給料を手渡しに行ったのだと思う。
崖沿いのシェッドにおおわれた箇所とトンネルを縫う、国道とはいいながら本当に細い、心細い道だった(三桁番号の国道は国道と呼ぶに値しない、といった人がいたが、いい過ぎとはいえない)。
なかでも、小谷の先の県境にある蒲原沢は、少し前の一九九六年十二月に、土石流で十四人が死ぬ災害に襲われたばかりで、そのせいか沢全体が、北斜面ということもあるのだろうが、凄気の漂うような暗さにおおわれていたことは、いまでも忘れられない。
この暗い道を北から抜けて、南に向って平らかに、明るくひらけた安曇野へ入ったとき、アヅミ族の人々は、どんな思いを抱いたことだろう。

今年は偶然、七月に福岡に行く機会があったので(志賀島に回る時間はなかったけれど)、翌月のサイトウ・キネンでは穂高神社へ行こうと、決めていた。アヅミ族の長旅を、カケラだけ再現。
最後の写真はその本殿。伊勢神宮と同様に式年遷宮をするそうなので、木が新しいのが気持ちよい。

しかもここ、境内にはやはり天神様とその牛があった(笑)。「教育県」長野だからこそなのかも知れないが、ここにも福岡との縁があるのが嬉しい。
安曇野、前と変らず空気がきれいで、風が爽やか。昼食は、穂高駅近くの一休庵の、アルプスわさびそば。ワサビの茎がそばにのせられている。
穂高ならワサビだろ、という安易な考えだが、とても美味かった。
ほんとうは、ここで「信濃の夕暮」を見られたら最高なのだが、現世に生きる身としてはそうもいかず、午後のあずさで帰京。

八月三十日(金)ギターフェスタ
Hakujuホールで、Hakujuギターフェスタの初日。
このフェスタは、ギタリストの荘村清志と福田進一を中心に、しかし単なるギターだけのお祭りではなく、声や他楽器との共演で、毎回趣向が凝らしてある。それを、客席わずか三百人という理想的な空間で美しく聴かせてくれるので、普段はほとんどギターに縁のない自分も、毎年楽しみにしている。
今日の前半のテーマは、「中世ルネサンス」。声楽アンサンブルのヴォーカル・アンサンブル・カペラの歌う、ジョスカン・デ・プレやビクトリアのアカペラ曲と、その旋律を転用したギター独奏曲の聴き較べが、涼やかで耳に心地よし。
九月一日(日)あれから三十年
今日が関東大震災から九十年にあたることは知っていたが、同時に大韓航空機撃墜事件から三十年にあたることは、ニュースで知るまで失念していた。
その後の爆破事件とは別の、ソ連のミグ戦闘機が領空侵犯した大韓機を撃墜した事件。レーガン時代、モスクワとロス五輪を米ソ陣営が互いにボイコットしたり、冷戦が最後の緊張状態にあった状況下とはいえ、民間の旅客機を問答無用で撃墜したのだから、本当にひどい話だった(真相については、スパイ行為など陰謀説も流れたが、ありえないだろう)。
個人的な話だが、当時大学三年だった自分は、この事件の少しあと、音楽事務所のジャパンアーツのアルバイトをやってくれ、人を集めてくれ、と先輩から頼まれた。
折悪しく「ロシア・ソビエト芸術祭」を開催することになっており、右翼が公演前から猛烈な抗議をかけているので、会場の警備に学生アルバイトが何十人でも欲しいから、ということだった。
それで、ボリショイ・バレエ団来日公演の神奈川県民会館とNHKホールの公演に、音楽同攻会の仲間を集めた。「こんな赤色踊りを見てはいかん!」とか、会場前では右翼の人がアジっていた。赤色踊り…。
これをきっかけに、ジャパンアーツで数年間バイトすることになった。自分がクラシックの物書きになるのは、これとはまた別の縁によるものだが、いまでもジャパンアーツには当時お世話になった人が、大内社長はじめ何人もおられる。
この悲劇的な事件が、自分にきっかけを与えてくれた。北の空に向って、自分も手を合わせてみる。
午後は、HakujuホールのHakujuギターフェスタの三日目を聴きに行く。
今日は、主要メンバーの荘村清志と福田進一のほかに大萩康司とデヴァイン、そして弦楽四重奏が加わって、ヴィヴァルディ大会。
全体に伸びやかなリラックスした雰囲気のなかで、荘村、福田、大萩のギター三人による編曲版の《調和の霊感》第八番が、緊密性を感じさせて最も印象に残った。アンコールのギター四人によるパッヘルベルの《カノン》も見事。
帰宅後に見た今日の大河ドラマ『八重の桜』は、とりわけて秀逸。
私は坂本龍一のテーマよりも中島ノブユキの劇中音楽の方がいいと思っている方だが、特にあの、賛美歌のコラールみたいな旋律。会津戦争の過酷な状況のなかでも八重の未来を暗示していて、うまいなと思っていたが、今日は弟が死んだ鳥羽伏見の古戦場でそれが響くという、お手本みたいに見事な使いかた。オルガンの響きのなか、死者たちの声が、鬼哭啾々ではなく、促しの言葉となる。
それとなんといっても、降谷建志とオダギリジョー、二人の旧名「斉藤一」が明治後に酒をくみ交わすという、愉しい場面。これサイコー。オダギリジョーがなんだかニヤニヤしているのも、愉快。
九月三日(火)「反・音楽会」
サントリーホールで、カンブルラン&読売日本交響楽団。
ブリテンのラクリメにシンフォニア・ダ・レクイエム、ウストヴォーリスカヤの《怒りの日》、ストラヴィンスキーの詩篇交響曲。
予想を上回る、ヘンな演奏会。
なんたってウストヴォーリカヤで活躍する、立方体の木製の箱。これがハンマーで殴られ小突かれ、ガンガン引っぱたくピアノとギシギシ軋むコントラバス八本と共演。楽器につきものの丸みと曲線を一切もたない四角の箱を象徴として、反・楽器の大会みたいな曲。
この立方体を見て、西洋の楽器はすべて曲線や流線型が基本だということに、あらためて気づく。それがまろやかな反響をつくる。それを拒絶した、立方体。逆説的楽器。
不思議と、マーラーの《悲劇的》のハンマーを想起させるのも面白い。
他の作品も聖書を題材に、近代クラシック音楽の原型としての教会音楽や、十六、七世紀の歌曲が引用され変形され、偏頗な楽器編成で陰気な、アンチ・クライマックスを形成する、美しくも見事な「反・音楽会」。
リハーサルを聴いた人によると、この演奏会のカンブルランのテーマは、「反戦」なのだそうだ。醜い闘争への怒り。
近代のオーケストラの大発展は、軍楽隊の楽器を積極的に導入し、活用することで始まった。反戦と、反・音楽会。
それにしても、夏の音楽祭モードが終って、シーズンしょっぱなの定期演奏会がこれとは、さすがカンブルラン。
サントリーホールにそれなりにお客が入っていて、自分も含めて喝采をしていることそのものが、まるで一種の戯画のようで、愉快。
続けて今週後半に自分が聴くのが《椿姫》や《ワルキューレ》第一幕だというのも、こうなるとまるで、全部ギャグのように思えてくる…。
九月四日(水)サクソンのサイドから

『イングランド王国前史 アングロサクソン七王国物語』(桜井敏彰/吉川弘文館)を読む。
五世紀にローマ帝国がブリテン島から撤退したあと、海を渡って移住し、先住のブリトン人を辺境に押し込めた、ジュート人、サクソン人、アングル人などのゲルマン系部族の諸王国が栄枯盛衰を繰り広げる、五百年の歴史物語。
それはイングランドという統一王国が十世紀に誕生する前、アングロサクソンの七つの王国が覇を競った時代の、いわばイギリス版の戦国時代。
吉川弘文館、と聞くと難しい学術書みたいな気がするが、細部にこだわらず面白さと読みやすさを優先した、読み物風の平易な文章なので、この時代の流れを大きくつかむのにとてもいい。
サトクリフの「ローマン・ブリテン」シリーズの後半は、押しまくられていたブリトン人がアーサー王のもとで一時的に覇権を奪還するも、その死後再び急速に衰微して、ウェールズへ後退する時代を舞台としていたが、そこでは未開野蛮なる勝者として描かれていたサクソン人たちが、ここでは主役になる。
この時代はヘプターキー、つまり七王国時代と呼ばれる。王国自体は大小多数が存在したが、群雄割拠のなかで、他国を圧する存在となった八人の王を特にブレトワルダ(覇王)と呼び、その八人を出した、主要な七つの王国に時代全体を代表させるからである。古代中国の「戦国の七雄」に照応するのが面白い。
といっても、ブレトワルダは自分でそう名乗ったわけではない。八世紀初めに『イングランド人民の教会史』を書いたノーサンブリアの修道士が七人を勝手に選んで名づけ、九世紀末に複数の著者が編纂した『アングロサクソン年代記』がそこに一人を加えたものである。
そのため、ノーサンブリアの王やキリスト教に帰依した王がひいきされる一方で、異教徒の王は、どんなに強盛を誇っても徳のない暴君として排斥されたり、人選は客観性を欠く。逸話にも、宗教因縁話や伝説が無批判に混じるそうだ。
このあたり、古代ローマの理知的な歴史記述に較べ、いかにも暗黒の中世という感じで面白い(本書は怪力乱神を抑えめに、人間の物語として書いている)。
戦場での王の戦死率が非常に高く、ブレトワルダやそれに匹敵する強王さえ、ただ一度の敗戦であっけなく討ち死にするのもまた、いかにも蛮族的。
各国の王、ケントの英主エゼルベルト(サトクリフの『夜明けの風』にも登場した)、ノーサンブリアの冒険者エドウィン、マーシアの勇猛なるベンダとオッファ、など英雄たちの生涯と興亡が、王国ごとに紹介される。大陸のシャルルマーニュが脇役で顔を出すのも楽しい。
ところが九世紀になると、文明化、キリスト教化したアングロサクソン人の王国もまた、新来の野蛮なデーン人、すなわちヴァイキングの攻撃で、次々と滅びていく(ノルマン・コンクエストに至るまで、海外から侵略され、先住民が敗れ続けるのが、イギリスの歴史なのだ)。
そのとき、乾坤一擲の大勝でデーン人を撃破、かつてのアーサー王の再現のように覇権を奪い返したのが、ウェセックスのアルフレッド大王。
その後裔たちの手で、イングランド王国が誕生するまでの歴史が、わかりやすく読める。手頃な日本語の本がなかった時代なので、とても便利。
九月六日(金)息にのせて響きを運ぶ
メッツマッハーと新日本フィル、トリフォニーでの演奏会。
一か月前の下野&霧島祝祭管に始まった《ワルキューレ》第一幕を含む三つの演奏会、「ワル1」シリーズの二回目。字幕がなかったのはちょっと意外。
グッドオールいうところの「ハーモニーが音楽を推進させる」、ワーグナー音楽の要諦をしっかり押えた、辛口のメッツマッハーの指揮がよかった。
しかし、なによりもとにかく耳に残っているのは、ミヒャエラ・カウネの歌った〈一族の男たちが〉での、あまりにも見事なフレージングの妙。
長い旋律線を息にのせて、流れるように運んでゆく、その快感。まさに妙なる呼吸感。
仰々しくテンポを落としたりせず、颯々と素早く進めたのもよかった。残念ながらクライマックスで、彼女の声楽的な限界がその表現意欲を妨げたのは惜しいけれど、それで前半の素晴らしさが失われるわけでない。
じつはこれが、昨夜藤原歌劇団の《椿姫》で、第一幕の大アリアの前半でデヴィーアが披露したものと、きわめてよく似ていた。もちろん、ワーグナーとヴェルディのフレーズ造形の差はあるが、息にのせて運ぶ、という点は一緒。
二夜連続でこうした「息をする響き」に接することができたのは大きかった。
自分にとってはこれがロマン派音楽の魅力だと、あらためて再確認したから。
旋律線を長い呼吸で運ぶこの快感の美は、十八世紀よりも二十世紀よりも、十九世紀音楽の特権的な力だと思う。
三日の、カンブルラン&読響の見事な「反・音楽会」の、美しくも陰鬱な慷慨の響きに接したとき、そのあとに続けて《椿姫》や《ワルキューレ》第一幕なんて「通俗的」な音楽を聴くことは、ギャグなんじゃないかと思った。
それはある程度まで当たったけれど、しかし、デヴィーアとカウネの「妙なる呼吸」には、けっして色褪せることのない、通俗に染まることのない、永遠の何かがある。ヴェルディとワーグナーの音楽が不滅だとしたら、それは、この呼吸感を呼び覚ます要素を多く含んでいるから。他の人は知らないけど、私にとってはそれが理由。
こういう、響きをとおしての呼吸は、百回聴こうと千回聴こうと、飽きたりしない。気持ちよく息をすることは、生物の生命活動そのものだから。たぶん、絶息するその瞬間まで、私はそれを求め続けるはず。
それが舞台に顕現する時間は、ごく短い。昨夜も今夜も、二時間以上あるなかの、数分間。
たったそれだけのあいだ、この世に降りてきた。それで、満足。
ところで、私がヴェルディ全作品の中で偏愛してやまないのは、《ファルスタッフ》でフェントンが歌う、Bocca baciata、という一節。
この短いフレーズには、「息をする響き」が、結晶のようにこもっている。ヴェルディが書いた最も美しい音楽だと、思っている。
なので、スカラ座来日公演の《ファルスタッフ》、素晴らしい上演らしいが、聴けそうにないのが残念。
でも、シーズンの幕開けとしては、今年はかなり愉快。
九月七日(土)あにいもうと
まず紀尾井ホールで、阪哲朗指揮の紀尾井シンフォニエッタの演奏会。
初演となる蒔田尚昊(冬木透)の組曲《歳時》は、忘れて久しい「お正月」の厳粛な気分。「春」の舞い散る桜の景色に鳴り響く、トランペットによる挽歌。そして、R・シュトラウスの《メタモルフォーゼン》やアイヴズを想起させずにはおかない、「終戦記念日」のグロテスクな《君が代》…。忘れがたい響き。
次に「ワル1」シリーズ三回目。サントリーホールでインキネンと日フィル。
響きが拡散して独唱には向かないホールだが、いちばん実力と演技力のある歌手陣(ヴェールゼ!を、「ちゃんと」好き放題に伸ばしたのを三回目でやっと聴けた)に、草書体の流麗な指揮で、これもマル。
三つの演奏会形式、それぞれの上演法の相違やホール音響の差が浮き彫りになって、いろいろと参考になった。
ところで「ワル1」といえば忘れられないのが、新国立劇場での全曲公演でのこと。第一幕後の長い休憩で外に出ようとして耳に入った、隣を歩いていた品のいい老嬢二人の感想。
「でもあの二人って、兄妹なんでしょ」
「そうなのよぉ。やーねぇ」
これが良識だよ、おいわかるか、とつくづく思った(笑)。
九月十四日(土)ロシアと虎ノ門
サントリーホールで、メッツマッハーと新日本フィルのロシア・プロ。コンダクター・イン・レジデンス就任披露演奏会。〈モスクワ川の夜明け〉と《法悦の詩》~チャイコフスキーの第五。いかにも武闘派指揮者らしい、率直でゴツゴツした響きで◎。
ここまで、新日との共演を何度か聴いてなんとなく思ったのは、どうもこのコンビ、初日がいちばん集中力と注意力のある、意欲的な演奏のような気がする。
もちろん、全日聴いているわけではないので、あくまで「なんとなく」の印象なのだが、夜と翌日の午後、というスタイルだと、慣れよりも疲れがオーケストラに出てしまうのかも知れない。
終演後、銀座線で銀座へ。途中、虎ノ門駅で駅名標をながめていたら、ベートーヴェンの「運命の動機」が「トラノモ~ン、トラノモ~ン」と、頭のなかで鳴り出す。
なんかぴったりだなぁと思いながら、ドラえもんとか土左衛門とかブスコパンとかライトバンとかブリーデンとかありえないとか、いろいろ鳴らしてみるが、やっぱり虎ノ門がいちばんの気がする。などと考えるうちに銀座到着。
下手の考え、休むに似たり。
九月十八日(水)平手打ち
高校バレー部の監督が生徒を高速ビンタする場面が動画サイトに投稿され、話題になる。
いっそのこと、次の東京オリンピックに「平手打ち」という新競技を導入したらどうだろう。選手としては大成できなかった体育教師やコーチにも、メダル獲得の道が。
なによりも精神力を競う競技なので、向かいあった二人で叩き合い、どちらかが「まいった」するまで続ける。
ただし、審判が危険と判断した場合は判定とし、姿勢点や気合点、一分間に何発打ったかの速度点なども判断に加味。
なによりも精神力を競う競技なので、ダメージを多く受けた方が「痛みに耐えてよく頑張った、感動した」ということで勝ち。負けるが勝ちという、日本武道の神髄(チガウ)
武道館に選手一万人あつめて日本代表選考会とか、すごそう。そして五輪で見事に金メダルとったら、かじる代りにメダルで平手打ち。
九月十九日(木)歌舞伎役者、不良たち

新書を二冊。
『歌舞伎 家と血と藝』(講談社現代新書)は、クラシックジャーナル編集長としてお世話になっている中川右介さんが書かれたもの。
明治以後の歌舞伎で活躍した主要な役者の家を八つ、團十郎、菊五郎、歌右衛門、仁左衛門、羽左衛門、吉右衛門、幸四郎、勘彌の出自と活動、その一族を、明治から大正、大正から昭和戦前、昭和戦後から平成と、三つの時代にわけて家ごとに述べていくもの。
親子兄弟、師弟、名跡と名跡、門閥と門閥などの入り組んだ相関関係が丁寧に説明され、それぞれの役者が劇界と家系においてどのような位置にあるのかが、代ごとの勢力関係の変化とともによくわかる。
面白いだけでなく、とても便利な本。

『関東連合――六本木アウトローの正体』(ちくま新書)は、久田将義著。
このところ話題の関東連合。ネットには真実なのか興味本位の噂話なのか、部外者には判別のつかない無責任な物語があふれている。『実話ナックルズ』『ダークサイドJAPAN』元編集長の著者なら、いい加減なことは書かないだろうと思って購入。
新書には、前述の中川さんの本のように力を入れてきちんとまとめたものの一方に、とにかく時事ネタを狙ったものがあるが、後者は粗製濫造になりやすい。
残念ながらこの本も、あまり充実した内容とはいえない。現在進行形の問題だけに、遠慮が先に立って、記述の具体性を欠き、曖昧。行間を読む知識も能力もない私には、とてもいまのかれらの「正体」はつかめない。
現時点で、関東連合という反社会的な組織が明確に存在するわけではなく、そのOBが個々に活動するだけだから、書きようがないのか。書きようがないのに書かれてしまうあたりが、量産を義務づけられた新書というジャンルの苦しさなのか。
ただ、関東連合結成の時点からの推移が当事者の談話や著者自身の思い出をもとに、曖昧な部分は多いにせよ、順を追って書かれているのは参考になった。
もともと関東連合とは、複数の暴走族の連合体。暴走族の最盛期は、一九七〇年代から八〇年代初頭にかけてだが、そのさなかの一九七三年に結成された。
暴走族のスタイルは、初めはアメリカのそれの模倣だったが、しだいにグループ名がカタカナから漢字に変り、ファッションもいわゆる特攻服に日の丸など、右翼的なものになり、攻撃性と暴力性が増す。そのきっかけになったのが、国士館高校の生徒が結成した「極悪」。この七〇年代後半は校内暴力の最悪期とも重なって、ツッパリ、ヤンキーのファッションにも影響を与える。
しかし、その勢いは八〇年代半ばに衰える。警察による暴走取締の強化、そして決定的なことに、ツッパリ・スタイルが飽きられたこと。
同じ頃、渋谷にチーマーが出現する。アメカジ・ファッションで、明大中野など同じ高校の生徒によってつくられ、渋谷に集まってはたむろする、いくつかのグループ。
ところが、かれらは一九九〇年前後に世田谷を中心とする不良集団と衝突、駆逐される。世田谷や杉並のいくつかの中学出身者、つまり地縁で結ばれた不良少年たちの方が、団結力と凶暴性で勝っていたからだ。
この不良集団が引き継いだのが「関東連合」という名前だった。といっても、暴走族というより愚連隊に近く、規模も地域も、往年よりはるかに小さい。地縁型がその特徴だという。
渋谷は、かれらが住む田園都市線や井の頭線沿線の終点。そこに集まる不良少年も、抗争後はその影響下におかれる。
やがて、この不良集団のOBが、アダルトビデオで儲けて、クラブ経営に食い込むという「ビジネスモデル」を開発する。これらは旧来の暴力団の手が及んでいなかった新分野で、かれらとの競合もおきなかった。
クラブのつながりで西麻布、六本木、さらに歌舞伎町へと進出し、常連客である芸能界との結びつきも強まっていく、という流れらしい。
そのあたりのこと、背後の悪事がどのようなものなのかということこそ、「六本木アウトローの正体」なのだろうが、前述のようにここは具体性を欠くから、もやもやした読後感。
九月二十一日(土)醜くも美しく燃え
白寿ホールでのエベーヌ四重奏団演奏会の一日目。
モーツァルトのK一三六にバルトークの四番、メンデルスゾーンの六番。期待を裏切らぬ素晴らしさ。
四人がそれぞれのポジションで、鮮烈で不動の存在感を発揮しながら、強い磁力で互いを引っぱりあう。その強靱な張力が生みだす、緊密にして濃厚な、音の立方体。異様な緊張と集中。
面白いのは、どの曲にも「憤り」が感じられること。その苦さが、先日のカンブルランの反・音楽会と共通している。
近頃のフランス人音楽家は、何をこんなに怒っているのか…。ロシア人の暗鬱とも、ドイツ人の気難しさとも異なるもの。とりわけ、バルトークの傑作はもちろん、姉を亡くしたショックのなかで、急逝直前のメンデルスゾーンが書いた六番にもあらわれる、鬱屈と激情、ある種の暴力衝動。そうした醜さが芸術に昇華される、美しくない美しさ。
アンコールはお得意のジャズ・ナンバーから、《ミスティ》と《ミザルー》。甘美な前者と激しい後者、ここにも本プロ同様の「醜い美しさ」がある。
明日はハイドンの《皇帝》とメンデルスゾーンの二番、そして後半がジャズ・ナンバーという、地球上でエベーヌにしかできないプロ。
後者は、二年前にヤマハホールできいたときの衝撃は忘れられない。特殊奏法と見事なコーラス(ナマで聞くと鳥肌ものなのだ、これが)で、音楽家が四人いるだけでどれほど多彩で豊穣な音楽が生れるかを、見せつけてくれるはず。今日を聴いてますます期待。
来月にはエル・システマの生んだ超絶的名手二人、トランペットのパーチョ・フローレスとコントラバスのエディクソン・ルイスも登場する。今年の白寿はほんとうに楽しみ。
九月二十二日(日)メメント・モリ
エベーヌ@白寿二日目。後半のジャズ・ナンバーも期待通りだったが、自分的にぐっと来たのは、二曲目のメンデルスゾーンの第二番。
ベートーヴェンに学んだ、有機的な幻想とロマン、激情。一方に、いかにも十九世紀前半の華麗なヴィルトゥオジティの時代らしい、第一ヴァイオリンの協奏曲的な、というよりもプリマドンナ的な見せ場の多さ。新鮮な響きで、作品と一体化したかと感じられるほどのメンバーの深い洞察と意欲が、びりびりと電撃のように伝わってきた。
さすがのセンスと思ったのは、この曲に限って、ふだんは第二ヴァイオリンのマガデュールが第一ヴァイオリンを担当したこと。正確な理由は知らないが、相棒のコロンブよりも繊細で華やかな音をもつマガデュールのほうが、この曲のストバイにはいいのかも知れないと思う。
今回聴けたメンデルスゾーンの二曲、どちらも啓示的な、というよりも、あえていえば黙示的な名演だった。
柴田克彦さんの曲目解説で教えられたことだが、二番はベートーヴェン、六番は姉ファニー、それぞれの死の直後に、おそらくはその影響のもとにつくられた曲なのだ。まさしくメメント・モリの二曲というか。
そう思うと、エベーヌのディスクが二番と六番の間にファニーの作品を挟んでいることの意味が、わかってくる。面白いので、聴きなおしてみよう。

ジャズ・ナンバーの方は、マイルス・デイヴィスやウェイン・ショーター、チック・コリアなどの新アレンジ入り。来年発売予定というジャズ・ナンバー第二弾に含まれるのだろう。これも楽しみ。
九月二十三日(月)アメリカの日本人

家へ帰って日付が変った深夜、エベーヌのメンデルスゾーンのCDを聴きなおすはずが、なんとなく、届いたばかりの美空ひばりと川田晴久の一九五〇年アメリカ公演ライヴを聴いてしまう。
とても面白いドキュメント。メインのひばりの歌は、いうまでもなくうまい。持ち歌の〈悲しき口笛〉に〈河童ブギウギ〉、それに〈三味線ブギウギ〉に〈唄入り観音経〉など。ただ、後年の大歌手ひばりを知っているから、自分程度の耳でもそう思うだけともいえる。十三歳の少女の巧さは、よくない意味で器用という部分もあるだろう。
でも、ひばりの歌だけなら、デビュー直後の貴重なライヴ、というだけだ。占領下の一九五〇年における、カリフォルニアの日系人相手の公演という録音の意味を痛感させてくれるのは、師にして同行者の、川田晴久。
十二分もその「漫談」が入っているのだが、これが興味深い。戦前の浅草で、レビュー歌手として芸歴を開始した川田が、牧伸二、綾小路きみまろなど、私も知っている一九七〇年代以降の漫談家たちの、まさしく源流の一人だとわかるのも参考になる。だが、それ以上に重要なのは、この漫談が、日本で日本人相手にしゃべっているときそのままみたいだ、ということだ。
あるいは、一月前にハワイでアメリカ公演を始めたときは、もっと「アメリカ向け」を意識していたのではないか。
しかし、それは必要ない。お客である日系の一世二世が聞きたいのは、日本でやるのと同じ、そのままの漫談なのだ。
日系人は日本の情報に飢え、欲している。かれらは、ひばりの出演した映画も他の日本映画同様に、当然のように見ている。その人たちの前だから、川田はまるで普段着のしゃべりをしたのだろう。
一九八〇年代前半くらいまでか、日本の演歌歌手は日系人相手の「アメリカ公演」をよくやっていた。『紅白歌合戦』などのテレビ番組も放映されて、人気が高かったはずだ。
日本を懐かしみ、その流行を共有したいと望む日系人が、その頃までは数多く残っていたからだろう。
その後は世代交代のためか、日本のファンを大挙連れていって「ラスベガス公演」を、なんてスタイルに変るけれど、それ以前の「アメリカ公演」の原型が、この録音のなかにある。
客席の日系人たちはつい五年前まで、太平洋戦争が終るまで、スパイ扱いされて強制収容所に入れられていた。そう疑われた理由の一端は、日本へのかれらの素直で強い関心にあったはずだが、それが戦争をへても失われていないことが、この録音の客席の豊かな反応に、ひしひしと感じられる。
一方でこのアメリカ公演は、二世部隊の記念碑建立のための募金公演だった。
川田は漫談のなかで、ハワイでは第百歩兵大隊の元兵士たちに出迎えられたことを、話している。
アメリカへの揺るぎなき忠誠心を証明すべく、志願して欧州戦線に出征、大損害と引き換えに嚇々たる戦功を挙げた、二世部隊の兵士たちの歓迎。
日本と日本人、日系人の「アメリカ」への愛憎入り組んだ関係の長い歴史が、後ろで渦を巻いているような、ライヴ。
さらに考えさせられるのは、このサクラメント公演が一九五〇年の六月二十四日と二十五日の二回だったという偶然。この録音はおそらく初日ではないかと思うが、二日目の当日は、なんと朝鮮戦争が勃発した、その日なのだ。
「反共の最前線の砦」とアメリカが日本を決定的に位置づけることになり、ふってわいた特需景気で、青息吐息だった日本経済が甦り、高度成長へのきざはしとなる、朝鮮戦争。その入り口の記録。
今回、偶然の結果から奇蹟的に発見されたワイヤー録音には、ひばりと同年の笠置シヅ子、山口淑子(李香蘭)などのサクラメントでのコンサートも入っているという。音質も良好だし、それらも世に出てほしいもの。
九月二十六日(木)復活のエラート?
近日発売のディスク情報で、このところエラート・レーベルが急に元気になったことに気がついた。
フィリップ・ジョルダンとパリ国立オペラ管弦楽団の録音などが出るということで、楽しみではあるのだが、「今頃なぜこのレーベルが?」と思っていた。
今日ある人に教えてもらったところによると、ワーナーが買い取ったEMIクラシックのうち、ヴァージン・レーベルのものを、エラートとして出すことになったのだそうだ。
EMIのロゴがワーナーに変ったのも諸行無常という感じだが、ヴァージン→エラートも意外な展開。
最近はフランス録音が多いから、イギリス起源のヴァージンよりも似合う、ともいえなくはないけれど、エラートは昔風の、より閉鎖的な「おフランス」的イメージなので、違和感のほうが強い。
まあ、旧譜や再発の方に目が行きがちな本家EMIよりも新録音中心だから、より早く慣れる気もする。
発売ペースは以前同様に活発で、面白そうなものが続く。予告ジャケットを見るかぎり、ロゴの色はエラートのオリジナルの見慣れた緑ではなく、紫やオレンジなど、デザインに合わせて何でもありらしい。このあたりは、現場からのささやかな反抗か、という気もするが、どうなのだろう。
九月二十八日(金)中心と周縁
今日はダブルヘッダー。十五時からブロムシュテット&NHK交響楽団@NHKホール、十八時から大友直人&東京交響楽団@サントリーホール。
一九七三年開場、一億総中流幻想まっさかりの前者と、一九八六年、バブル時代の後者。ホールの時代背景の差が、そのまま演奏会の内容にも反映されていたようで、とても面白かった。
NHK交響楽団のプログラムは、ブラームスのヴァイオリン協奏曲(独奏ツィンマーマン)と交響曲第四番。教養というにふさわしい格調高い曲目を、三千六百人の巨大ホールで聴く。しかもチケット売り切れの大人気。これぞ、大衆教養主義。
演奏も正統派、しかし随所に新鮮なバランスや動きをとりいれ、堂々としてかつ鮮度の高い名演。オーケストラに、去年同じ指揮者で聴いたバンベルク響のような自発性があればさらによかったが。
NHKホールで音楽を聴くのは久しぶり。前半の協奏曲では、一階後方の席なので距離的には遠くないのに、音が来ない。二階席だと「遠くて来ない」から矛盾を感じないのだが、不思議な感じ。
しかし、後半の交響曲では音の不足を感じなかった。鳴り出したのか、こちらの耳が慣れたのか。ここの音響しか知らなければ、けっこう納得して聴いてしまうものなのかも知れない。
十七時の終演後、あわただしく移動してサントリーホールへ。
こちらはマクミランの合唱と弦楽オーケストラのためのカンタータ《十字架上のキリストの最後の七つの言葉》と、ホルストの組曲《惑星》という、イギリス・プログラム。
一九五九年生れのスコットランドの作曲家マクミランのカンタータは、一九九三年に作曲され、五年後に大友自ら日本初演したものだという。東響コーラスはいつもながらに暗譜で歌って見事だが、百五、六十人の人数は、弦楽オーケストラ相手にしては少し多すぎる気も。
最後の七つの言葉、それぞれが意味するところは、表面の短い言葉の奥に深い含意があって、今の私の知識ではつかみきれない。
音楽と歌詞を追うだけで精一杯だったが、最後の「父よ、あなたの御手に私の霊をゆだねます」が切れ切れに歌われたあと、弦が細かい音形をくり返し、次第に静かになったところでやっと、この息も絶え絶えの弦が、イエスの生命活動、呼吸と鼓動を示していたことに気づく。
霊と肉、論理と肉体、思惟と行動、そうしたものが合唱と弦楽の関係に込められていたのかも知れず、どこかで聴きなおしてみたいと思う。
そして後半は《惑星》。通俗名曲という趣もあるが、ナマで聴くのは初めて。
レコードで聴きなれた、滑らかでやわらかくブレンドされた音響に対して、今日の演奏はかなりゴツゴツと各パートが存在を主張して、そのオーケストレーションがむき出しになったかのようで、とても刺激になった。
フランス音楽、またパリで流行していたストラヴィンスキーやムソルグスキーなどのロシア音楽の影響が、この管弦楽法には色濃い。その点、イギリス音楽としては異質だが、〈木星〉の有名な中間部の弦の響きだけ、いかにもイギリス風なのが、いろいろな意味で興味深い。
それにしても各種打楽器にオルガンなど、いかにも国家総動員的な大編成。数時間前に聴いたブラームスが、いかにシンプルな編成だったかを、思い知らせるようだった。さらに、N響がいかに男性の多いオーケストラかということも。
九月二十九日(日)二重写し
トッパンホールのハーゲン四重奏団のベートーヴェン演奏会を前半だけで失礼して、東京文化会館小ホールへ移動し、藍川由美さんの「日本のうた編年体コンサート」を聴く。
藍川さんは、現代の我々がなおざりにしがちな日本語の発音にも細心の注意を払い、深みのある美しい響きで、忘れられた歌を甦らせてくれる。
片山杜秀さんの企画構成と解説によるもので、ルルーの《抜刀隊の歌》にはじまる「日本のうた」を、時系列に従って取りあげてきた。第十一回の今日は、昭和十二年から十四年にかけての、「放送軍歌」と「国民歌謡」がテーマ。
昭和初期、ラジオの爆発的な普及で、NHKがつくって放送する「国民歌謡」が、流行歌の一大発信源となった。そこには時代の変化、モダニズムと軍国主義が交差する社会風潮が反映されており、この「日本のうた編年体コンサート」の大きな柱になっている。この国民歌謡、昭和十二年に日中戦争が始まると、戦時色が一気に濃くなっていく。前回四月七日の回では、その始まりの時期の歌が取りあげられていた。
そして、この戦争を受けて別枠で放送開始されたのが「放送軍歌」だった。こちらは銃後ではなく、最前線をおもな題材として扱い、戦場の出来事をトピック的に紹介していくものだったというのが興味深い。
今日歌われたのは、《北支の空》から《南京陥落》までの八曲。自分などはまったく聴いたことがない。忘れられてしまった理由は、こうして聴かせてもらうとよくわかる。「暴支膺懲」など当時の空疎なスローガンがちりばめられた歌詞のせいもあろうが、説明的、語り的に過ぎて、旋律が印象に残らないのだ。
けれど、それはそれとして、激戦の様子や勇敢な戦死者を、ニュースを紹介するように次々と軍歌の題材にしたというのは、いかにも「ラジオの時代」の戦争と納得させられる。
たしか、尾崎秀樹が書いていたと思うのだが、朝日新聞に連載された吉川英治の『宮本武蔵』が、当時の読者をあれほど熱狂させたことの理由の一つに、後半の展開が日中戦争の進捗と、どういうわけか歩調が合っていたからだ、という話を読んだことがある。
日本軍が大戦果を挙げたときは武蔵もはなばなしく勝ち、武蔵が迷いだすと日本軍も停滞するというように、両者の動きは不思議とオーバーラップして、読者は否応なく感情移入した、というのだ。
もちろん偶然の合致だろうが、そんなふうに、時代小説と現実の戦況を重ねて読む読者がいた、戦争。
ラジオ、新聞、ニュース映画など、新しいメディアが肥大した、大衆社会における戦争。例の「百人斬り」を武勇伝に仕立てた新聞記事などは、真実がどこにあるかとは関わりなく、こうした状況から生れてくる。
その一方にかすかに残る、個人的な、モダニズムの音楽。山田一雄の《もう直き春になるだらう》を含む《三つの季節のうた》が、それを示す。
ここまでが前半で、後半は国民歌謡がメインになる。しかしここでも、歌の世界における「公と私」の混在が意識されていて、橋本國彦や信時潔の国粋主義的な曲や、大ヒットとなった《麦と兵隊》《愛馬進軍歌》のあいだに、木下忠司による国民歌謡ではない、個人的な歌曲がはさまる。
好きな歌だがひさびさに聞いた《愛馬進軍歌》は、壮気と情緒をうまく混ぜていて、じつに「少年倶楽部」風というか「キング」風というか、とにかく講談社の本のように、たくみに大衆の心をとらえるものと、あらためて気がつく。
しかし、今回の構成の妙は、この《愛馬進軍歌》で終らせずに、同じ国民歌謡だが軍歌ではない、高木東六の《ヒュッテの夜》を、おしまいにもってきたことにある。
冬の山小屋の夜景を描いた歌で、『日本百名山』で名高い山岳作家、深田久彌の作詞。昭和十四年に発表された。
「雪の青さを透す窓 湯気に凍った花ガラス 温めた指で字を書けば そこから溶けて痕も無く」
に始まり、
「ストーヴの湯も沸いたから お茶を飲み飲み話そうよ」
などと続く、戦争とは無縁の歌詞。
冬山の厳しい自然のなかに、ぽつりと建つヒュッテ。冷気を防ぐ、ガラスとストーヴとお茶。ちっぽけだが、そこには「文明」、すなわち西洋文明が与える、暖かい安息がある。
これを聞いていたら、『きけわだつみのこえ』の主要な戦没学生、中村徳郎の一文を思い出した。
一高の山岳部で活躍したこの人については、この日記の二〇〇八年十一月二十五日に書いたことがある。
かれの一文とは、『きけわだつみのこえ』にある、一兵卒として徴兵された昭和十九年二月の兵営で書いた、四年前の三本槍雪中登攀の思い出だ。
「ストーヴが紅く燃えていた。燻んだ窓硝子を透して、静かなランプの影がこれもまた静かな、雪の舞うのを映していた。食膳に上ったパイナップルと紅茶が私たちの舌をこよなく楽しませた。快い疲れ!
かくて四年前の今宵が暮れていったのを――限りない懐かしさをもって――黄金の夢のように憶い出す。三本槍の登攀を終ったあの日のことを」
冬山登攀の壮挙を遂げた人間を迎え入れる、文明の小さな温もり。
戦争という野蛮な嵐に翻弄される、無力な人間の、理性の光。
「黄金の夢」を描いて印象的なこの一文は、登攀の前の年にラジオから流れた《ヒュッテの夜》をヒントにしているのだろう。作詞者の深田は一高山岳部の大先輩にあたるから、中村とは面識もあったはずだ。
体験した現実と、ラジオの歌詞との、二重写し。前述の『宮本武蔵』と戦況の二重写しと重なる、マスメディアの力。
さらに、勇ましい軍歌にはさまれた平和な歌と、兵営の夜に思い出すヒュッテの幻影の、戦争と平和の二重写し。
けっして単純ではない戦時下の感情。《麦と兵隊》も、軍歌のようなのにやるせない、不思議な詩情の名歌。むかし、満洲経験をもつ祖父が子守歌に歌ってくれたのは、《戦友》とこの歌だった。
九月三十日(月)オルガンとピアノつき
サントリーホールで、チョン・ミョンフン指揮のフランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団の来日公演。
曲はラヴェルの《マ・メール・ロワ》とピアノ協奏曲(独奏:アリス=紗良・オット)、そしてサン=サーンスの交響曲第三番。アンコールに《火の鳥》終結部と、《カルメン》前奏曲。
とにかく響きが美しく輝かしく、上手い。ヤノフスキに薫陶されて以来、「放送局の第二オケ」どころか、フランスでもベストを争う位置にあるオーケストラである。チョン・ミョンフンのダイナミックな指揮のもとで、その力量を存分に発揮してくれた。
ネットのニュースで、韓国公演でもサン=サーンスが演奏されるのだが、韓国にはパイプオルガンをもつコンサートホールがない、という話が流れていた。
一九七三年にNHKホールができる以前の東京と同じだ。東京文化会館や日比谷公会堂では、電子オルガンをもちこむしかなかった。
先日の《惑星》もそうだが、近代の大規模な管弦楽曲ではオルガンが当然のように使用される。ヨーロッパの大都市ではコンサートホールにパイプオルガンを備えつけているのが、十九世紀末には当り前になっていたからだろう。
一八八六年のサン=サーンスのこの曲は、その初期の例ではないか。珍しかったからこそ、「オルガンつき」とあだ名されることになったのだろうし。
そういう視点で見なおすと、ピアノを加えているのも先進的である。金属製のフレームで高い剛性と強大な音量をもつモダン・ピアノが完成したのは、まさに同じ時期だ。それを意識しての起用なのだろう。
古典期までの、通奏低音としてのチェンバロとはまるで違った意味の、いわば新しい鍵盤式打楽器としての導入。チェレスタと同様の意味づけ。
R・シュトラウスやマーラーなどの後期ロマン派、フランスやロシアの近代音楽の、先駆けとなる楽器編成。
十月一日(火)オペラパレスの饗宴
新国立劇場で、文化庁芸術祭オープニング演奏会。すべてイギリス音楽。
尾高忠明指揮東京フィルの演奏で、ディーリアスの《楽園への道》にエルガーの《海の絵》(独唱は加納悦子)、ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》。
新国立劇場オペラ芸術監督である尾高の指揮を新国立劇場で聴くのは、これが初めて。いっぽう、尾高の指揮で《ベルシャザール》を聴くのは、日フィルと東響に続いて三回目。ナマではこの曲、この人以外の指揮で聴いたことがない。
しかし前二回に較べて、この音楽ならではの「神の勝利」の血なまぐさい興奮の味わいは、少なかった。このホールは舞台上にオーケストラを並べると、反響板がないためか音が響かない。サントリーホールで聴いた、これまでの二回に較べて迫力がなかった。肝心の合唱も新国立劇場合唱団が練習不足なのか、発音もアンサンブルも冴えを欠き、残念。
十月四日(金)佐村河内氏インタビュー
某誌の取材で、佐村河内守氏のご自宅でインタビュー。来月に世に出る予定。
十月六日(日)ツィンマーマンのバッハ
トッパンホールにて、フランク・ペーター・ツィンマーマンの独奏によるバッハのヴァイオリン・ソナタ全曲演奏会。ピアノはエンリコ・パーチェ。
二十八日にN響の演奏会で聴いたブラームスの協奏曲もそうだったが、このひとのヴァイオリンにはケレンがなく、言葉の最良の意味で実務的。しっかりと実のある音楽。モダン楽器の抽象的な音色の美しさが、巧まずして活きる。
このソナタ集、第五番までは教会ソナタ形式の緩急緩急の四楽章構成がくり返されるが、最後の六番でルーティンを破り、急緩急緩急の五楽章になる。この構図をしっかりと実感できる演奏だった。
十月八日(火)エル・システマ(一)
ハクジュホールにて、トランペット奏者、フランシスコ(パーチョ)・フローレスの演奏会。
圧倒的なテクニックと輝かしい響き。
十月十一日(金)エル・システマ(二)
ハクジュホールにて、コントラバスのエディクソン・ルイスの演奏会。ピアノ伴奏が小菅優という豪華版。
八日のパーチョとともに、ベネズエラのエル・システマが生んだ俊英。史上最年少でベルリン・フィルに入団した。
重低音が切れのいいリズムで、ブウンと響く。
十月十二日(土)時代の光輝を宿す音楽
東京藝大では「藝大プロジェクト2013 消える昭和~その時、世界は?」という、意欲的なコンサート・シリーズを奏楽堂で行なっている。
その第三回、「テレビと音楽~放送から見える昭和」を聴きに行く。時間の関係で、三部構成のうちの第三部は聞けなかったが、とても面白かった。
演奏だけでなく、ナレーションつき映像に鼎談を入れ子にした、テレビの音楽番組の公開収録のようなスタイルも、今回のテーマに合っている。
一九二五年、ラジオ放送の開始にさいして山田耕筰がつくった《JOAKマーチ》に始まり、一九四七年、占領下の人気ラジオ・ドラマ『鐘の鳴る丘』主題歌《とんがり帽子》が続く。
そしてテレビ時代の幕開け。日本テレビの放送開始・休止時の音楽、深井史郎作曲の《鳩の休日》。
総合司会の片山杜秀さんによれば、この音楽は昭和十九年、戦時下に制作された元寇映画『かくて神風は吹く』の、元の艦隊が登場する場面で用いられたもので、中国風の響きなのはそのためだという。それを深井が転用したのだそうだ。
それにしても、NHKの《君が代》とか日テレのこの音楽など、ブラウン管が砂嵐になる直前の画面を、自分も含めて多くの人が知っているのは、昔は放送終了時刻が早かったからという理由もあろうが、同時に、いかに昭和の日本人が朝から晩までテレビ漬けだったかの、雄弁な証明という気がする。
ゲストで登場した造形作家の山本孝樹さんは一九六四年生れ、私より一歳下でやはりテレビっ子だったそうだが、「テレビのおかげで、週のなかの曜日の感覚が明確になった」という意味の話に、深く同意。
たしかにあのころは、月曜は『水戸黄門』とか、火曜は何、水曜は何と、各曜日を番組で把握していた気がする。いまでは大河のある日曜くらいしか、意識する日はない(余談だが、いまでも日曜だけは朝から晩まで、さまざまなジャンルのおなじみの長寿番組が各局とも並んでいて、日曜を強く意識させる気がする。なぜなのだろう)。
このあとも黛敏郎の《スポーツショー行進曲》や、三木鶏郎、いずみたく、小林亜星のCM音楽、『月光仮面』や『夢であいましょう』などの人気番組、アニメのメドレー、大河の『赤穂浪士』と、もりだくさんに続いていった。
しかし、何よりも強烈に印象的だったのは、二部の最後に演奏された、《東京オリンピックファンファーレ》(今井光也)と《オリンピック・マーチ》(古関裕而)の二曲。
光が満ちてくるような、期待感で高揚させずにおかない、異様な力をもっているのだ。何だかよくわからない、理屈をこえた力。
直接の記憶ではなく間接にだが、一応は知っている一九六四年の東京オリンピックがもっていた、どうにもならない輝き。その一端にここで触れた気がした。
これと似た光輝の力は、初めの《とんがり帽子》にも感じた。
生れる何年も前の放送だから、番組自体は知らない。しかし子供の頃に何かの放送で耳にして、一発で憶えた名曲。この歌もまた、戦後最初の数年間にあったという、新しいよい時代がくるという期待と開放感、それに結びついている。
鶏が先か卵が先か、相関関係はよくわからないが、時代の光輝と熱気を宿す音楽、そういうものがたしかに存在する。
演奏は、松下功指揮の東京藝術大学音楽学部器楽科学生によるウィンドオーケストラと、メゾソプラノの佐藤寛子ほかの独唱とコーラス。取りあげられた曲をリアルタイムでは知るよしもない若い人たちが、じつに真剣に演奏してくれて、心地よし。
後ろ髪を引かれつつ、三部の前に早退けして、藝大奏楽堂からサントリーホールへ移動。
スクロヴァチェフスキ指揮読売日本交響楽団の演奏会で、自作の《パッサカリア・イマジナリア》と、ブルックナーの《ロマンティック》。
気合の入った、辛口で剛毅な、鮮烈な名演。音楽漬けで幸せな一日。
十月十三日(日)スクロヴァチェフスキのベートーヴェン

昨日の演奏会の余韻で、スクロヴァチェフスキと読売日本交響楽団が少し前にSACDで出したベートーヴェンの交響曲集(三~五番)を聴く。
素晴らしい演奏。永遠なる斬新、とでもいうか。
《英雄》は、私がナマで聞いたオペラシティの演奏会の前日、みなとみらいでのライヴで、解釈はもちろん一緒。各声部の音形の動きを克明に描出し、気迫のこもったリズムで生命を込める。
第二楽章後半で見事に浮かびあがらされた、ホルンによる運命動機の出現も、鮮明にとらえられている。
読響との前回の《英雄》よりもはるかに出来がいいし、OEHMS盤とは音質が比較にならない。《英雄》と同日の第一番の録音も残っているし、全集への発展を切望。
十月十三日(日)ノット&東響
サントリーホールで、東京交響楽団の演奏会。指揮は来年音楽監督に就任するジョナサン・ノットで、《四つの最後の歌》(独唱:クリスティーネ・ブリューワー)とアルプス交響曲という、R・シュトラウス・プロ。
このところ、在京の他のオーケストラに較べて、響きの強さや圧力に物足りなさを感じることが少なくなかった東響だが、今日は華麗に鳴り響いて、すばらしかった。ノットとの今後の関係、かなり期待できそう。
十月十九日(土)麹町・赤坂・麻布歩き
今日は片山杜秀さん、アルテスの木村元さんとご一緒に、『帝都クラシック探訪〜音楽都市TOKYOを歩く』のための、四回目の街歩き。
旧町名でいえば麴町區の紀尾井町、平河町、赤坂區の赤坂田町、溜池町、福吉町、榎坂町、麻布區の谷町、市兵衛町一丁目、我善坊町、飯倉六丁目、ついでに狸穴町。明治から現代までの洋楽受容、とくにオーケストラ運動の歴史が、ギュッと濃縮されてつまった地域を歩く。
福吉町では、もしそれが完成していたらサントリーホールが建てられなかったかもしれない、幻のホールの予定地を眺める。続いて谷町のサントリーホールは日フィルの演奏会終了直後だったので、思わず我々も聴きおえた聴衆のような顔をしながら、『超芸術トマソン』の無用煙突の亡霊について、などなど。
日暮れまでに予定地を廻れるか、天気がもつかが不安だったが、幸いにも無事完了。一人で地図片手に妄想を膨らませながら歩くのも面白いが、仲間とわいわい言いながら歩くのは新たな発見があって、また別の愉しさ。路上観察学会のクラシック版、みたいな。
写真は、飯倉六丁目の南葵楽堂跡近くの行合坂にある、ベラルーシ料理店「ミンスクの台所」で、ニガヨモギを食べているところ(そういう冗談は笑えないからよせ)じゃなくて、ウクライナ・ビールを飲みつつ、ベラルーシ料理に舌鼓を打つべく待っているところ。
とても愉快な一日。お二人に感謝。

十月二十三日(水)笑ってプーランク
ある幼なじみが『笑っていいとも!』の後番組は『笑ってる場合ですよ!』の復活じゃないか、と話していた。
むかし『全員集合』が終ったときも、次はクレージーの『出発進行』じゃないかといっていたヤツなので、何年たっても思考パターンに進歩がないと思った。
ひとのことはいえないが。
夜はオペラシティで「没後五十年記念 プーランクの夕べ」。ピアノ曲、歌曲、室内楽、協奏曲に宗教曲、さまざまな編成の代表作を一夜で聴ける、この会場ならではの企画。
十月二十六日(土)講演づくめ
講演づくめの一日。
朝は十時四十分から、東条碩夫さんによる、早稲田大学エクステンションセンターのオペラ総合講座の前期最終回。
午後は十四時から、早稲田大学音楽同攻会・八十周年記念講演会で、大塚修造先輩による「シェークスピアと音楽」。
ここまでは早稲田大学の構内で、夕方は渋谷に移動。十七時からオーチャードホールで、リッカルド・ムーティによる「ムーティ、ヴェルディを語る」。講演に、歌手との《椿姫》ヴィオレッタとジェルモンの二重唱の試演もまじえ、当初一時間半の予定が二時間半に。
ぜんぶ合わせて六時間。大学生に戻ったかのような一日だった。
十月二十八日(月)わかれのギター
ハクジュホールでジョン・ウィリアムスのギター・リサイタル。
年内で演奏活動から引退するため、これが最後の来日公演という。PAを使わない、生音での繊細な響き。
十月二十九日(火)ムーティ・インタビュー
ミュージックバードで、すみだトリフォニーで行なわれる東京・春・音楽祭の特別公演、「ムーティ conducts ヴェルディ」のために来日中のリッカルド・ムーティのインタビューができることになった。
生き生きと、和やかにすすめられたゲネプロのあと、楽屋での三十分間のインタビュー。
ムーティの長年の友人であり、新刊の『リッカルド・ムーティ自伝』(音楽之友社)の訳者であり、そして今回のインタビューの機会をつくってくださった田口道子さんのパワフルな通訳に助けられて、なんとか無事完了。
厳しさと優しさ、大人と子供が同居しているように一瞬に入れ替わる振幅の大きさに、かつてない緊張を味わう。同時に、「世界的存在」の孤独の深さも。
十二月八日の「ウィークエンド・スペシャル」の枠で放送予定。
十月三十日(水)ヴェルディ演奏会
昨日に続いてすみだトリフォニーへ。「ムーティ conducts ヴェルディ」の本番初日。
熱く、引きしまった響き。N響、都響の首席奏者などからなる東京春祭特別オーケストラの演奏にも輝かしい肉体感があって、すばらしかった。合唱の東京オペラシンガーズともども、ムーティの要望なのか、中堅以下の若い世代で構成されていたことも、反応のよさにつながったのだろう。
十月三十一日(木)指揮者の帰還
サントリーホールで、ビエロフラーヴェク指揮のチェコ・フィル演奏会。
グリンカの「ルスランとリュドミラ」序曲、ベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲(独奏はイザベル・ファウスト)、
後半がチャイコフスキーの交響曲第六番《悲愴》。
昨日の東京春祭特別オーケストラの整然としたモダンな響きに較べて、なんと古風に、地方色豊かに鳴るのかとびっくり。同じビエロフラーヴェクでも、前ポストのBBC交響楽団のディスクでは、温かさと現代性を共存させていたが、久しぶりに帰還したチェコ・フィルでは、また違った音楽が生れてくるようだ。
ファウストのキレのいいスタイルとはややズレを感じたけれど、例のピアノ編曲版による、ティンパニつきのカデンツァをナマで見られて、面白かった。
ところで、今回の招聘元はジャパン・アーツ。ビエロフラーヴェクはまだ無名だった一九七〇年代後半、ジャパン・アーツに招かれて日本に長期滞在、安いホテルに泊まりながら、機会を得ては日本のオーケストラに客演して、経験を重ねていったことがあるという。
七〇年代のNHK交響楽団の「第九」八種を集めたボックス中の七九年の録音が、その当時を伝える記録だ。
それから母国チェコで着実に出世、ついにチェコ・フィルの首席指揮者に昇りつめたが内紛で追われ、昨年ようやく、二十年ぶりに復帰。
今回の来日は、いわば凱旋公演のようなものなのだが、華々しく喧伝されたりしないあたりが、いかにもこの指揮者らしくて好ましい。
十一月八日(金)ティーレマンのベートーヴェン
ティーレマンとウィーン・フィルによるベートーヴェン・チクルスの初日を聴きに、サントリーホールへ。
前半が一、二番、後半が《英雄》。どれもさすがウィーン・フィルの美しい響きだが、なかでは力の入った、ときに力みの目立つ《英雄》よりも、自然に演奏された第二番が好ましかった。
十一月九日(土)マーラーの交響曲第七番、ア・ラ・イタリアの道化音楽
今日は某誌の〆切と某誌の〆切の合間に(誤表示 正確には〆切はどちらもとうに過ぎているのに、デッドラインに時間差があることに甘えているだけ)、いやいや合間に、インバル&都響のマーラーの交響曲第七番を東京芸術劇場で。
インバルの手腕にオーケストラの技量があいまって、細部までとてもよくわかる、高水準の演奏。
しかし、それにしても不思議な曲。
この曲は、「ストーリー」がまるで見えない。マーラー自身、何も標題的な説明を残していない。作曲者指揮によるプラハでの初演に立ち会ったワルターも、「マーラーはそのオーケストレーションに完全に満足していた」とか、「純粋に音楽的な、本質的に交響的な作品」などと、書いているだけ。
やはり初演に立ち会い、この曲の最も強烈な録音を残したクレンペラーは「闘争から勝利の喧騒へ」というような説明を若いころに書き残しているが、はたしてそうなのだろうか…。
今日、自分が感じたのは、全部が道化の音楽なのではないか、ということ。暗さも哀しみも、すべて道化のグロテスクなユーモアのそれ。
たしかに、五~七番の三曲はセットになっているのだろう。第五番は、少なくとも両端楽章を較べれば、暗から明へのベートーヴェン的勝利。
一転して第六番は、徹底してペシミスティックで暗い、苦闘と敗北(英雄死)の音楽。
第七番はその第六番を受ける形で、正反対の「明るさ」を目指したのか。モーツァルト風の多楽章の喜遊曲や夜曲を目指したというなら、たしかにワルターのいう通り、純粋音楽なのかも知れない。中間の三つの楽章には、たしかにそんな気配がある。
けれど、終楽章では喜びや愉しさを通りこして(そんなものはもともと存在しないから?)、無理やりな、ヤケクソみたいな狂躁になってしまった。
だから道化。言葉の本来の意味での根暗な、道化。
南欧の、イタリアの、コメディア・デラルテ的な。マンドリンとギターは、いかにもイタリアだし。
と書けば、まさにレオンカヴァッロの歌劇《道化師》の世界。
マーラーは、ウィーン宮廷歌劇場監督としてレオンカヴァッロと交流があり、その《ラ・ボエーム》を駄作と知りつつ指揮したし、自分では振らなかったけれど、《道化師》も上演していた。その内容を熟知していたことは疑いがない。
また、マーラーが死んだ直後にR・シュトラウスは、コメディア・デラルテが登場する《ナクソス島のアリアドネ》を書いている。
そこでの、大仰な歌劇の登場人物を嘲笑する道化師たちが象徴するように、この頃からヨーロッパではロマン主義の肥大化への反動で、古い芸術への関心が高まっていた。マーラーも、バッハの管弦楽組曲を編曲して演奏したりしている。この第七番は、あるいはマーラーなりの新古典主義の表明なのかも知れない。
ディヴェルティメントとセレナードにコメディア・デラルテをまぜて、最後はカーニバルに。
そう、終楽章は一種の、バフチンがいう中世風の「カーニバル」なのかも、なんてことも考える。ぐちゃぐちゃ、ごたまぜの喧騒の大鍋のなかから、第六番で打ち倒された英雄が、再生する。聖杯伝説の元になった、魔法の大鍋のごとき楽章。
第六番の主人公が神話的な英雄なら、こちらの主人公は、トリックスターなのかも。ティル・オイレンシュピーゲルみたいな。
聴きながらこんなことを妄想するうちに、「オーストリア一のナントカ男」とか、植木等風のマーラーが頭に浮かんでしまい、噴き出しそうになって困った。
レオンカヴァッロといえば、トスカニーニがマーラーの第五番のスコアを検討したさい、「ペトレッラとかレオンカヴァッロのようなア・ラ・イタリアのスタイルに、チャイコフスキーの音楽と管弦楽法の大仰さを混ぜ、シュトラウス風の特色を出そうとしているが、あとの二人のようなオリジナリティがない」と批判して、演奏を断念したことを、あとで思い出した。
これはひどい酷評だけれど、ここでトスカニーニがレオンカヴァッロを持ち出したのは、じつに暗示的だ。
トスカニーニの言葉が核心をついているのは、マーラーの音楽がドイツ音楽の伝統とは違う、ということを言外に指摘している点だ。マーラー自身、ヴェルディのオーケストレーションに敬服していることを認めているし、《復活》の終楽章には、「オテロの死」そっくりの部分があったりする。その意味では、レオンカヴァッロと「同根」のものともいえるから、言いがかりというだけでは片づけられない。
レオンカヴァッロのオーケストラはマーラーよりはるかに薄いが、《道化師》の初めで一座が登場するあたりのアンサンブル場面など、七番の終楽章とも似通っている気がする。
いずれにせよ、第七番の評価が難しかったのは、「死の予感にとりつかれた作曲家」という旧来のイメージに、どうにも合わなかったからだろう。前島良雄さんの著作によってこの既成概念が崩れはじめた今なら、別の位置づけが可能かも知れない。
ところでこの七番、同じ日程で新日本フィルも、ハーディングの指揮ですみだトリフォニーで演奏していた。東京のオケのシンクロ現象は今年少なくないが、この曲となると珍しい。そちらは聴けなかったので残念。
十一月十二日(火)コジェナの歌
オペラシティで、マグダレーナ・コジェナ&プリヴァーテ・ムジケによる、バロック歌曲の夕べ。
この時代の楽器のためには、残念ながらホールが大きすぎたよう。コジェナの艶のある声と歌は見事に響くのだが、その響きを保持するために表現が限られてしまい、堂々として立派だが、もう少し遊びが欲しい印象だった。
十一月十四日(木)「字数」感覚の差
先日、ある原稿の校正刷りがあがってきたら、びっくり。
改行が全部なくなって、すべての文章が一つの段落になっている。隙間なく文字がつまって、私が「ヨーカン」と呼んでいる状態に。字数が多すぎて、こうしないと入らなかったらしい。
原因は、担当さんとのコミュニケーションのミス。「字数」の意味が違っていたのだ。ようするに、向うは空白部分も含めた字数で依頼したのに、こっちは空白抜きの実際の字数で書いてしまった。
その背景には「字数」の意味が、二十年前に私がこの仕事を始めたころと、変ってきていることがある。
昔は、四百字詰原稿用紙で何枚、という執筆依頼が大半だった。字数でいうにしても千二百とか千六百とか、四百の倍数が基本だった。支払いのときも、四百字詰め一枚の単価を定め、それに枚数をかける(半分の〇・五枚もあるが)。
そしてこういう依頼では、その字数には空白部分も含まれている。小学校の作文と一緒で、タイトルに筆者名、段落頭の一字下げや行末の空白に行あけ、すべて含まれる。
レイアウトが決まっている場合は、十八字×五十六行とか、そういう指定もある。たとえば日経新聞の評などは、十三×五十三行で書く。
私には、これが見映えを計算して書けるので、いちばんありがたい。適度な改行は、文章に視覚的なリズムをつけて読みやすくさせるだけでなく、内容を強調するための重要な手法、いわゆる「間」やパウゼだが、同時に、行末の空白は少ない方が美しい。
雑誌や新聞の大半は、今でもこの数えかたである。私がメディアに書くようになったのはワープロになってからで、字が汚いので手書きをしないが、書くときの基本にあるのは原稿用紙。
ページ設定をA4の用紙に二十字×四十行を縦書きで二段、つまり四百字詰原稿用紙四枚分にして、使っている。
ところが、CDやDVDのブックレットやパッケージの文章で、字数の意味が違うことが増えてきた。
依頼された字数に、空白を含まないことが多いのだ。生原稿やFAXではなくテキスト・ファイルで入稿すると、PCでは簡単に字数計算できるから、それで数える担当さんが増えたかららしい。
だから、旧来の原稿用紙の感覚で書いて入稿すると、字数が足りない、と文句を言われることが増えた。
人にもよるだろうが、私の場合、空白を含むかどうかで十%くらい変る。項目が多くて行あけが多い場合など、二十%くらいにもなる。そして、この分をごまかしているような感じになるのだ。
初めはワープロソフトの字数計算など頭になかったので、「そんなら改行せずに全部つめて書けというのか。俺はヨーカンつくってるわけじゃねぇぞ」などと腹を立てていたが、そのうち仕方ないと思うようになった。
パソコンの画面上の横書きのテキストしか知らない人に、縦書きの原稿用紙時代の字数感覚など、いってみても始まらない。ソフトに字数計算させてポンなんだし、空白はお前書いてねぇじゃん、といわれれば、お説まことにごもっとも。
そこで、いままでよりも一割増くらいの感覚で書いていって、字数計算で調整することにした。
あくまで印象論だが、ひのえうまより後の年代の人は、空白なしの字数で依頼してくる場合が多い。今回もそのくらいの年齢の方なので、そうだと思い込んだら、意外や原稿用紙の感覚で依頼してくれていた、というわけなのだ。
七千とか、四百で割り切れない字数で依頼する人だと、空白なしの字数だとすぐにわかるのだが、正直、そういう字数はなんか背中がムズムズする(笑)。
しかし聞くところによると、アドベンチャーゲーム用のテキストの量はキロ、つまりキロバイトで量ることがあたりまえだとか。ということは、ライトノベルなどもそうなのかも。
そのうち、ここは9KBで書いてくださいとか、いわれるようになるのだろうか…。
十一月十六日(土)食品偽装騒ぎ
午後はオペラシティで、ケラスによるバッハの無伴奏チェロ組曲全曲演奏会。伸びやかで、多彩に変化する響き。とりわけ第五番と第二番、二つの短調作品での陰影の濃さが印象に残った。
終演後の夕食は、最近ニュースで名前を見た某デパート内にある店だったが、野菜も肉も魚介も、いつも以上に新鮮でみずみずしく、美味しく感じたのは、気のせいなのだろうか(笑)。
少なくとも十一月いっぱいくらいは、ホテルとかでも同じ水準なのではあるまいか。フレッシュジュースとか、きっと(いままで飲んだことがないくらいに)ものすごく新鮮で美味しそうな気が…。
十一月十八日(月)天覧ハルサイ
サントリーホールでラトル指揮ベルリン・フィルの演奏会。
最後のハルサイ、唖然とするような凄まじさ。ベルリン・フィルならこれくらいやるだろうという、予定調和的な前半のシューマンの交響曲第一番に対し、天覧演奏会となった後半のプロコフィエフのヴァイオリン協奏曲とハルサイでは、一気にギアが入った感じだった。
まさにスーパー・オーケストラというか、超絶的な個人技と超高速のパスワークが異様に高い水準で完璧に止揚されていく、トップクラスのサッカーチームみたいなハルサイ。この作品あってこそ、楽団のポテンシャルが十全に発揮されるという。
文化会館のコンセルトヘボウも皇太子ご夫妻臨席だったそうで、個人的にもこのところ演奏会でのロイヤル・ファミリー遭遇率がかなり高くなっている気がするが、どうなのだろう。
皇后陛下と皇太子殿下がかなりのクラシック好きであることは疑いないから、『平成の皇室とクラシック』は、いずれ誰かが本にする気がする。
十一月十九日(木)&二十一日(木)
日経新聞の音楽評のために、アンドリス・ネルソンスとバーミンガム市交響楽団の演奏会へ。十九日はオペラシティ、二十一日は東京芸術劇場。
次代のホープにふさわしい熱演。それにしても、ウィーン・フィル、ベルリン・フィルにコンセルトヘボウが勢ぞろいの東京の音楽シーン。師匠のヤンソンスがコンセルトヘボウといて、バーミンガム市響と縁の深いラトルもベルリン・フィルときている。
十一月二十二日(金)五十年前の今日
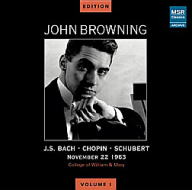
昨日、増えすぎたCDを処分しようとその山をかき分けていたら目について、「そういやこんなディスクをもっていたっけ」と久々に思い出した盤。
今日になってテレビを見ていたら、ケネディ大統領が暗殺されて、ちょうど五十年目だという。こういうシンクロは誰にもある偶然だろうが、面白く感じてあらためて捜索して、聴きなおす。
MSRというレーベルから二〇〇五年に出た、アメリカのピアニストのジョン・ブラウニングが生前に遺したライヴ録音をCD化したものだ。
一九六三年十一月二十二日、JFK暗殺の日の晩に、ブラウニングがバージニア州のウィリアム・アンド・メアリー大学で行なったリサイタル。
舞台に立ったブラウニングは演奏前にスピーチをし、曲目を変更すること、休憩なしで演奏すること、拍手は控えてほしいことの、三つを告げる。そして一曲目は、追悼のために客席の全員に起立を要請し、バッハ/ブゾーニのコラール前奏曲「われ汝を呼ぶ、主イエス・キリストよ」を演奏。
以下、ショパンの幻想曲、シューベルトの即興曲変イ長調、ショパンのマズルカ二曲、そしてソナタ第二番と続く、約五十分。
哀しみや慰撫よりも、強い怒りとその克服への努力のようなものが演奏に感じられるのは、当日の衝撃の大きさのゆえか。特に最後のソナタの、葬送行進曲の後半から終楽章にかけてがすごい。
演奏が終るやいなや、ピアニストは静寂のなか、舞台を去ってゆく。足音。聴衆のセキ。
この日のライヴではほかに、ボストン交響楽団がそのアーカイフをデジタル化したときにつくられた非売品の記念CD‐Rを、関係者の厚意で聴かせてもらったことがある。
演奏会の初めに、暗殺の報を舞台袖で知った指揮のラインスドルフが、客席に悲報を知らせる。大きくあがる悲鳴。そして追悼に急遽演奏される、エロイカの葬送行進曲。
いまは、YouTubeで聴くことができるそうだ。事件発生が東部時間で十三時半で、演奏会は十四時開始だから、客席の聴衆はその瞬間まで本当に知らなかったのだろう。あまりの事態に気もそぞろで、とてもではないが聴衆は、演奏に集中できなかったのではないか…。
ラインスドルフとボストン響のケネディものといえば忘れてはならないのが、翌年のケネディ追悼ミサでの、あの感動的なモーツァルトのレクイエム。
史上初のカトリックの大統領だったからこその、追悼ミサ。事件を記念してアメリカでもようやくCD化されたが、世界初CD化となったRCAの国内盤も、まだ入手可能。
こういうものを、ラインスドルフ最高の名演といっては、いけないのだろうけれど。
十一月二十四日(日)タメスティ!

トッパンホールで、ヴィオラのアントワン・タメスティのリサイタル。
一昨日、『レコード芸術』のためにインタビューして、新譜のヒンデミット作品集のコンセプトを鮮やかに説明してもらい(ディスク専門誌のインタビュアーが語ってほしいのは何かを瞬時に理解して、どんどん語ってくれた。これほどラクなインタビューはなかった)、さらに今日のリサイタルを聴いて、ますますファンになってしまった。
こんな生彩鮮やかなヒンデミットを聴けるのは、驚き。特に、CDでは一曲目に入っている作品十一‐四のソナタ。
インタビューでは、ヒンデミットがドビュッシーを深く敬愛していたこと、このソナタにその反映があることを語り、「だからリサイタルでは、その前にドビュッシーをいれているんです」と、説明してくれた。
その通りというか、実際にはさらに凝っていて、《亜麻色の髪のおとめ》から武満徹《鳥が道へ降りてきた》をへて、ヒンデミットへと続いていく、色彩が光の加減で微妙に変化していくかのような音色の流れは、本当に見事だった。
そしてCDには、それとまた異なる、ヒンデミットのみによる美しい変容がある。五月にビオラスペースで演奏された《白鳥を焼く男》の実演を聴きにいけなかったことを、いまになって後悔。
なお、レコード店のサイトでは「タムスティ」という表記が多いが、本人に確認したところ、トッパンホールの表記どおり「タメスティ」が正しいそうだ。
「日本語で発音すると、ためすてぃ」と、これまたこちらが知りたいポイントを一瞬に理解して、教えてくれた。
十一月二十八日(金)バービィ・ヤールに記念碑はない
ロペス=コボス&都響の演奏会を、サントリーホールで。
いやもう、面白かった。タイムリーであるという意味では、ベルリン・フィルもウィーン・フィルも(聴いていないけれど)コンセルトヘボウも目じゃない、この秋最高の演奏会。
何しろ、特定秘密保護法が制定されようとする今日ただいまの東京で、ショスタコーヴィチの《バビ・ヤール》をやったのだから。詩人エフトゥシェンコのあざといまでの当てこすりが、ギシギシと心にすり込まれる。
プロレタリア独裁のソ連では、社会主義リアリズムを称賛し、資本家や宗教家などの特権階級を非難しているこの歌詞は、建前上は正しい。当局は結局、一部の文言の変更以外は、文句をつけられなかった。
第一楽章、ユダヤ人を虐殺したのは、「正義の、本物のロシア人」ではない、それを騙る贋者の仕業だとして、「本物のロシア人」を讃える。
第二楽章、圧政の下でもけっして死に絶えることのない、不屈のユーモアを讃える。
第三楽章、家事と農業の苦しい労働に耐えてきたロシア婦人たちが、いまは商店に長い行列をつくって並ぶ、その忍耐の美徳を讃える。非難されるのは釣り銭や量をごまかす末端の小悪人だけ。婦人に屈従を強いる、より大きな悪については、一言も語らない。
第四楽章、スターリン流の密告社会の恐怖は遠い過去のものだといい、今は消えたと断言する。
第五楽章、ガリレオなど、過去の科学文化のパイオニアは、特権階級への阿諛追従を拒否して主張を貫いたからこそ不滅の名声を得たと讃えるが、しかし今のソ連でどうすべきかは語らない。
皮肉と反語の大河。ショスタコーヴィチの音楽の陰鬱なユーモアが、その美辞麗句とは裏腹の真意、面従腹背をひたすら暗示し続ける。《森の歌》とは正反対の、恐怖政治下の都市生活者の歌。
タイムリーなのも素晴らしい上に、今日はこの曲以外の選曲がまた、面白かった。トゥリーナの《闘牛士の祈り》とラヴェルのスペイン狂詩曲が前半で、後半に《バビ・ヤール》。
これだけで暗示になっている。一九二五年と一九〇八年作曲の二曲に描かれた「闘牛と祭りの国」スペインが、ショスタコーヴィチと同じ時代、二十世紀後半には、どうなっていたかの。
フランコ独裁。
ソ連に匹敵する、自由なき社会。いやいや、もっといえばショスタコーヴィチのような芸術家すら出てこない、不毛の国。一九四〇年にこの国に生れたロペス=コボスが、そこでどうやって生きたのか、何を考えていたのか、私はまるで知らない。何の説明もない。
ただ、お国ものに続いて、なぜか《バビ・ヤール》が演奏されるだけ。
言わず、語らず。
戦争に勝ったソ連、戦争を回避したスペイン、どちらも二十世紀後半まで全体主義が続いたけれど、日本はこてんぱんに負けたおかげで壊れて、史上空前にしておそらくは絶後の、総中流幻想社会が長く続いた。
そして二十一世紀、「戦争を知らない孫たち」は、何がしたいのか…。
それにしても、都響はショスタコーヴィチに強い。ロペス=コボスの方は典型的な二十世紀後半風の、弾力のない音づくりをする人だから、正直なところ、ラヴェルはまるで面白くないし、形にならなかった。だが《バビ・ヤール》の陰惨さには、バッチリだった。
じつはラヴェルに失望したあまり、仕事もつまっていたので休憩で帰ろうかと思った。ロペス=コボスとショスタコーヴィチというのも、自分の知識では結びつかなかったからだ。ナマで聴く機会がそう多い曲ではないから、聴いていこうと思いなおしただけである。
ところが聴いてみると、フランコ体制下に生きたスペイン人にとって、これくらい共感できる同時代音楽はないのだろうと、骨身に沁みた。とらえどころのない指揮者と思ってきたが、この曲で初めて、かれのパーソナルな部分に触れた気がした。
この曲をナマで聴くのは、数年前に井上道義が日比谷公会堂で、全曲シリーズを敢行したとき以来だが、あのときには遠い国の過去の話としか、感じられなかった。その意味合いが自分のなかで、大きく変っている。
ミッキー、こんどピョンヤンに行ったら、《バビ・ヤール》をぜひやってほしい。いま世界でどこよりもこの曲が似合う、北朝鮮で。
いつか、前半が《バビ・ヤール》で、後半が《森の歌》という演奏会も聴いてみたい。いろいろ皮肉はいったけど、結局はワーッとわいて、歓喜の渦に巻きこまれちゃうんだよね俺たち、みたいな演奏会。
十一月三十日(土)花と呼び戻し
無駄話。先日、あるコンサートの終演後、いつものように拍手のなかで指揮者が舞台袖との往復をして指揮台に戻ってくると、女性ファンが花束を手渡した。
指揮者は微笑みながら受けとったけれど、そのまますぐに、ヴィオラの二列目くらいの女性に渡してしまった。
これを見て思い出したのが、トスカニーニのこと。花束を受けとらない理由をきかれ、答えて曰く。
「花をもらうのは、プリマドンナと死人だけだ。私はそのどちらでもない」
ところで、あの終演後にくり返されるソリストや指揮者の舞台袖との複数回の往復、なんと呼ぶのだろう。いま書いていて、なんで自分はここをもっと簡潔に書けないのか引っかかって、呼びようがないからだと気がついた。業界的にはなんか呼称があるのだろうか。
「一般参賀」みたいに「楽員が引っ込んだあとに指揮者だけ出てきて拍手を受けること」という、特殊な例を指す隠語はあるのに、演奏会につきもののあの往復の呼称は、きいたことがない。
伝記や新聞記事などには「あまりの喝采で、作曲家は十五回も舞台に呼び戻された」などと書いてあることもあるが、「呼び戻し」では、まるで相撲の決まり手だし…。
と、フェイスブックに書いたら、日本の音楽界ではオペラでの呼びかたを転用して、「カーテンコール」と呼んでいることを教えてもらった。また、ドイツやイタリアの言いかたに従えば、ただ「コール」でもよいのではないかとのこと。
「カーテンコール」は、あくまでオペラなどの舞台公演で、カーテンの前で行われるものという意識が自分には強いのだけれど、衣装をつけてなくても「ドレスリハーサル」と呼ぶような感覚なのだろう。
とはいえ、物書きの感覚としては、もう少し一般に広まってからでないと、「緞帳がなくても業界ではこう呼ぶ」と注釈をつけないと誤解を招きやすいので、なかなか使いにくそう。
十二月一日(日)トリノのオペラ
東京文化会館で、トリノ王立歌劇場の《仮面舞踏会》。
いまのイタリアの歌劇場のなかで、黒字経営を維持しているのは、このトリノとヴェネツィアのフェニーチェ劇場、ただ二つだけなのだそうだ。
たしかに、その勢いのよさを感じさせてくれた。その一方で、知人がこの舞台を「ドイツの歌劇場のヴェルディ上演を見ているみたいだ」と言っていたことにも深く同感。合理性と機能性を意識した舞台と上演であるところが、じつにドイツっぽいのだ。
一杯飾り、つまり単一の舞台装置を全幕で使い回した、前回来日時の《椿姫》もそうだったが、とにかく質素にしなければ、今のイタリアの歌劇場はやっていけない。その制限のなかで、できるだけの舞台効果を表出しようとすれば(終景の舞踏会での華やかな赤の色彩とか)、合理性と機能性を意識するほかない。
そのとき参考になるのは、やはりアルプスの北側のシステムなのだろう。舞台装置の雰囲気もそうだし、三幕でも二つの幕を続けて休憩を一回に抑える(二日前の《トスカ》もそうだった)のも、現代ドイツ式だ。トリノが北イタリアの工業都市なのも背景にある気がする。
それにしてもこのオペラ、あらためて大好きな作品。初期の性急さと後期の大仰さ、その中間にあって、軽みと戯れのセンスが勇壮な悲劇と共存、互いを引きたてあうバランスが素晴らしい。
第三幕第一場の、レナートの憤怒と捨鉢、サムエルとトムの執拗な怨念、アメーリアの悔悟と不安が、若いオスカルの軽薄な慢心と交錯して、緊張と弛緩をくり返す。そして悲劇へと緊迫していく場面のドラマの、筆の冴え。指揮も歌手も見事で、聞きほれた。
十二月四日(火)ディアベッリ、麗し
今日はトッパンホールで、シュタイアーのフォルテピアノ独奏会。
ベートーヴェンの六つのバガテルとディアベッリ変奏曲という晩年プログラムの予定に、他の作曲家たちによる《ディアベッリのワルツによる五十の変奏曲》から、十人分の抜粋が直前に追加してされた。
ご承知の通り、ディアベッリのディスクでは、ベートーヴェンの前にこの十人の変奏を組み合わせていた。だから当初の予定になかった方がむしろ不思議な、当然の追加。時間的にも長すぎない。
追加されると知る前は、ひょっとしたらアンコールにもってくるのかと思っていたが、本番を聴いて、ベートーヴェンの完璧で偉大な終止のあとに、同じ主題に基づく変奏を続けることは、とてもできるわけがないと納得。
十人の変奏があって、バガテルがあって、休憩後にディアベッリ変奏曲。
十人の変奏を聴くと、いかにも「作曲法の遊戯」みたいなものだと思わされるのだが――そのなかでも、シューベルトと少年リストが強い個性を発揮しているのは流石だけれど――それと同じ、大したことのない主題を借りて、遊戯を深遠な芸術へと高めるベートーヴェンは、今更ながらにすごい。
変奏芸術の粋をつくしていることといい、要所でフーガを用いたり、第三十二番のソナタの第二楽章を想わせる音型が出てきたり、いかにもベートーヴェンのピアノ曲の総決算。
九月に武蔵野でベートーヴェンのソナタ全曲チクルスを行なったプルーデルマッハーは、プログラムにない「アンコール」として、最後にディアベッリ全曲を弾いてみせたそうだが、それもなるほどと思える。
シュタイアーの演奏がまた、遊戯と芸術の淡い境界を行きつ戻りつしながら、見事に両者を止揚していく。
ここで威力を発揮するのは、作曲と同時代のフォルテピアノの、不揃いな響きと音色が生む多彩さ。モダン・ピアノの均質な音だと、単調で退屈に感じられることもあるこの長大な変奏曲に変化を与えて、飽きさせない。
しかも、どれだけ賛美してもしすぎることがないのは、いびつさを絶対に「未発達」なものとは感じさせない、シュタイアーのコントロール能力の高さ。玩具っぽさが微塵もない。
とにかく、麗しい音色。

話はディスクのことになるが、少し前にアンドラーシュ・シフがECMで出した、二種のディアベッリ変奏曲を収録したディスクも、面白かった。
というのは、わざわざ二種をセットにしたのに、モダンとピリオド、という単純な対照にしていないことだ。
ボンのベートーヴェン・ハウスにある一八二〇年製のブロートマンのフォルテピアノによる録音だけでなく、一九二一年製のベヒシュタインによる録音も、響きにくすみとかげりがあった。ソナタ全集で用いたベーゼンドルファーのモダン・ピアノと、まるで違う音だったのだ。
つまり、モダンとピリオド、それぞれの特性を対照させるためにつくったアルバムではない。モダン・ピアノの高すぎる抽象性と均質性はディアベッリには向かない――ソナタとは違う――という考えが基本にある。
そして、そうではない音をもつ二百年前の楽器と百年前の楽器、どちらにも捨てがたい長所があるので、一つに決めずに、それぞれの音色を聴いてもらおうとしたものなのだろう。
シフは、バッハではチェンバロを用いずに、モダンのコンサートグランドでひく。その抽象性と合理性の高さが作品に合うと考えているからだろう。ベートーヴェンのソナタもそうだ――しかし、ディアベッリは違う。
このあたりの見極めが興味深いし、示唆に富んでいる。
シュタイアーは、ベートーヴェンのソナタをひくのだろうか。
十二月十日(火)プラッソンの怪物
昼は新国立劇場で《ホフマン物語》。
ただし、シャスランの指揮が自分には耐えられず、第二幕までで帰宅。
すべてを聴かなければ判断することはできないのだが、オッフェッバックの仕掛けがことごとく無残に踏みつぶされ、何も中身のない音楽にされるのを聴くのは、オッフェッバック好きの端くれとして、どうにも我慢がならなかった。
ただ、この指揮を聴いたおかげで、七月末に同じ新国立劇場で同じ東フィルが演奏した、二期会公演のゲネプロでのプラッソンの指揮がいかに素晴らしいものだったかがよくわかったのは、収穫。
プラッソンが古い慣用版にこだわるのは、たしかに時代後れだろう。しかし、新版がどんなに取りつくろっても、枯渇しかけていた作曲家の霊感を呼びもどすことまではできない。それに対してプラッソンは、その出がらしの音楽に、自らの情熱で血を通わせていた。
オッフェッバックの音楽法を知りつくした人間ならではの絶妙の語りくちにより、音楽は生き生きと実体化し、躍動したのだ。
そうして、息づいて力強く脈打てば打つほど、その音楽の身体が無理やり縫合された、寄せ集めの「鵺(ぬえ)」であることも、いっそう明白になった。
醜い、「鵺」の姿でしかこの世にとどまれぬ不完全な生命の、脈動。
フランケンシュタインならぬ、プラッソンが生命を与えた「怪物」がそこに生きていた。
この怪物は、今日の新国立劇場の第一幕と第二幕には、影さえ見えなかった。
夜はサントリーホールで、カンブルラン指揮読売日本交響楽団の演奏会。
リゲティの《ロンターノ》、あとはすべてバルトークで、ピアノ協奏曲第三番(独奏:金子三勇士)、ルーマニア民族舞曲、組曲《中国の不思議な役人》という、ハンガリー・プロ。
リゲティはカンブルラン十八番の現代曲だけに、じっくりと精妙に、響きがひろがっていく。じっくり過ぎて、最後のピアニシモで、それよりも大きないびきが各所から聞こえてきたのは、笑いそうになって困った。冬場のホールは暖かすぎる気がする。
バルトークもこの指揮者らしく、華奢な感じの音楽になるのが面白い。アンコールにベルリオーズのラコッツィ行進曲をもってきて、ハンガリーとフランスをつなげたのは、このバルトークのスタイルによく合っていた。
十二月十一日(水)沈降する音
トッパンホールで、シュタイアー・プロジェクトの二回目。
佐藤俊介のヴァイオリンを招いて、モーツァルトのヴァイオリンとフォルテピアノのためのソナタ、変奏曲など。
楽器は一八二六年のグラーフを用いた先週と異なり、さらにさかのぼって一八〇〇年頃のワルターのレプリカ。しかしここでもシュタイアーの、尖ったり濁ったりしないタッチが、絶妙に美しい。
佐藤は、ドイツの名門ピリオド・アンサンブル、コンツェルト・ケルンのコンサートマスターをつとめるなど、モダンとピリオドの奏法をともに身につけて、活躍している。
ただ、自分がどうしても気になったのは、日本人の演奏でときに感じる、音やフレーズの最後が沈んで消える感覚が、佐藤のヴァイオリンにあったこと。
沈降する音。音楽から活力が失せて陰気になるように、私には思えてならないのだが…。
十二月十二日(木)マンガ二冊
今や、マンガをほとんど読んでいないくせに、本屋に行けば新刊コーナーを眺めるクセは抜けない。
久々に、ほんとに久々に、何の予備知識もなしに、表紙と帯だけに惹かれて、大今良時の『聲の形』を買った(そんなことをするのは『海街diary』以来かもしれない…)。

甘酸っぱいラブコメではない。小学校高学年、それまでと変らないはずの日常の、身の回りの、薄皮一枚下の醜悪。まだ一巻だけでは、この物語がどこへ行くのかわからないけれど、強く惹かれた。
それにしても、こんなに深刻で真摯な内容を『少年マガジン』でやってしまうというのは、さすがに講談社。

あと、これは前から読んでいる島本和彦の自伝的マンガ『アオイホノオ』十一巻も購入。
主人公(マンガ内の名前は焔燃)が、『炎の転校生』(連載時に大好きなマンガだった)の原型に取りかかっている大学二年の一九八一年夏、サンデーに『タッチ』が新連載で始まり、大阪芸大の同級生である庵野秀明たちはSF大会(DAICON3)のオープニングアニメで大成功し、世に出る、という、各所でむちゃくちゃ熱い夏が、大阪の暑い夏が、凝縮された巻。
自分より一学年上だけなのに、クリエイターになる人々は、この若さでこんなに真剣に生きている。呆然。
十二月十四日(土)西国分寺にて
朝、二限の時間に早稲田大学エクステンションセンターのオペラ講座で《ウエスト・サイド物語》について話す。
午後は西国分寺に行き、音楽同攻会の創部八十周年記念公演、岡村喬生さんの歌、作詞演出によるモノオペラ二本立て「人情歌物語 松とお秋」に立ち会う。
会場は、音同の大先輩の小俣敏生さんのご自宅。席数八十のハウスコンサート「りとるぷれいミュージック」を、ここで三十年前から続けられている。
小さなステージに、小俣さんが工夫をこらされた、最小限でしかも効果的な装置が映え、現役の学生諸君がスタッフとして照明・音響・道具係で見事に働き、岡村さんの力唱をたすけて、心に響く公演だった。
それにしても、今回の準備のために何度か訪れた西国分寺駅、清々しいほどに周囲に店が少ない。
中央線と武蔵野線の乗換えのために一九七三年に新設された駅だそうだが、乗換え客がどんなにいても、改札の外の発展にまったく寄与しないあたり、西日暮里の駅に似ている。
ここには創建時の武蔵国分寺の史跡があり、一度ついでに寄ってみたかったのだが、その機会を得ず、残念。
十二月十五日(日)ゴーティエ&ユジャ
午後、トッパンホールで、ゴーティエ・カピュソンのチェロとユジャ・ワンのピアノによるデュオ・リサイタル。
強靱。
十二月十九日(木)青ひげ公の城
東京文化会館で、インバル指揮東京都交響楽団。
前回都響を聴いたのは、特定秘密保護法成立を目前にしての《バービイ・ヤール》。今回は、妻の死がきっかけのように絶頂から転落した東京都知事が辞任を発表した日に聴く、《青ひげ公の城》。
バルトーク・プロで、前半もヴァイオリン協奏曲第二番(庄司紗矢香独奏)。
師走といえばベートーヴェンの第九だが、今年は縁がなく、十二月に聴く二回のオーケストラは、十日のカンブルラン&読響と合わせて、なぜかともにバルトーク主体のプロ。頭文字は同じB。
今年亡くなった諸井誠の『ぼくのBBB』――三大Bはバッハ、ベートーヴェン、バルトークだというやつ――とか、戦後まもない日本の「バルトーク・ブーム」では、この作曲家こそが「二十世紀のベートーヴェン」だと目されたこととかが、頭に浮かんだりする。
インバル、カンブルランとは違った意味で、土の匂いのないバルトーク。「第五の扉」の壮大なハ長調のオルガン・サウンドは、舞台下手にバンダを並べ、効果満点。ここは暗く閉鎖的な場面が続くオペラのなかで、恐ろしいほどに広大な空と大地と、権力と栄光が見える瞬間。
数年前にパリ・オペラ座で見たフラ・デルス・バウス演出の舞台は、サル・ガルニエそのものを青ひげ公の城に見立てて、作品内と現実の空間が不可思議に重なっていく快感を味わわせてくれた(何しろここは、『オペラ座の怪人』の住処でもあるのだから)。
そのせいか、今日は一瞬、都庁の幻影が見えた気がしたり。
それにしても、この作品は舞台上演もいいけれど、演奏会形式にはまた別の魅力があることを納得。後半のグロテスクで、血腥くも妖しく美しい「扉の向う」は、オーケストラの幻想的な響きから聴覚だけで想像した方が、その凄絶な光景を肌で実感できる気がする。
ナマで見るのは四回目。二回目(パリ・オペラ座)と三回目(サイトウ・キネン)は舞台上演だが、最初も演奏会形式だったはずと思い出してみたら、同じ都響が、やはり東京文化会館で演奏したものだった。
アダム・フィッシャーの指揮で、シャシュとコヴァーチの歌。
帰宅してネットで調べると、一九八四年三月のことらしい。ほぼ三十年前。当然まだ字幕などなく、予習もしなかったから、細かい部分はよくわからないままだった。
あの頃は、オペラとはそういう無理をして見るものだ、と思っていたっけ。
十二月二十一日(土)UMA年
フェイスブックで、後輩のウォールの年賀状の話題に、
「ウマ年といわずにUMA年にすれば、雪男でも河童でもなんでもありなんじゃねーの」
と書いてから、こういうのって、小学校高学年の思春期小僧が得意気にいいそうだよなぁと、ちょっと落ち込むもうすぐ五十一歳。
十二月二十二日(日)諦観と静謐の第九

ヴェンツァーゴ指揮ベルン響のブルックナーの交響曲第九番、十二月初めに届いていたのを、ようやく聴く。
またまたやってくれたぜ、というほかない、今まで聴いたことのないサウンドの第九番。
なんといっていいのか。ゴブラン織りのような、中世の絵物語のような、独特の静かにうねる、立体感と色彩感。
すみずみまで生命感に富んでいるのに騒々しくなく、威圧的でもなく、不思議な静謐にみちている。中世美術そのもののような、あっちの世界からやってきたような、「安定した非実在感」。
ブルックナー好きが期待する、仰々しいパウゼやダイナミクスの変化を、徹底して引っぱずしてくるのが、清々しいばかり(笑)。だから伽藍ではなく、ゴブラン織り。
ヴェンツァーゴは全集の開始にあたって、ブルックナーの交響曲は金太郎飴ではない、曲ごとに違う響きと世界をもっているんだと高らかに宣言して、たしかにここまでセットごとに(四と七、〇と一、二、三と六)、そのとおりに異なる貌を音にしてくれてきた。
そしてこの第九の、諦観と静謐。終楽章の金管のコラールがこんなに静かに、それなのに高みから響くとは…。
これが第二番同様、カップリングなしに一曲で出てきたのも、骨身に沁みてよく分かる。類似のサウンドの交響曲が他にないからだ。
この全集も、ついにラストスパート。残るは掉尾を飾るにふさわしい、第五と第八。どんな音楽になるのか、今からワクワク。
十二月二十九日(日)一九六〇年の円環
例年よりもインタビュアーの仕事をいただくことの多かった今年。
今日は、その締めくくりにふさわしいお相手だった。
五十三年前の一九六〇年五月二十九日の昼と夜、ウィーン・ムジークフェラインザールでワルター&ウィーン・フィルの「ウィーン告別演奏会」とクレンペラー&フィルハーモニア管弦楽団のベートーヴェン・チクルス初日を、ナマで聴かれた方である。
すなわち、外山雄三さん。
この凄い一日の三か月前の二月には、クナッパーツブッシュ&ウィーン・フィルのブルックナーの三番も聴いておられるし、日本最高のアンコールピース《管弦楽のためのラプソディ》を、この年の夏に書かれている。
いわば、生ける「ウィーン/六〇」。
この話が、ある企画の特典とするために持ち込まれたとき、瞬間的に感じた。
これが、四半世紀前からこだわってきた「一九六〇年のウィーン」の、一つのピリオドになるという予感を、である。
場所は、オペラシティの楽屋。東京フィルのニューイヤー・コンサートのリハーサル後にお邪魔して開始。
マエストロ外山は、一九三一年生れのご高齢とはとても思えぬ、にこやかで鋭敏、饒舌なインタビュイー。脱線が多くて、しかもそれがすべて当時のウィーンと日本楽界に関する楽しい内容なので、進路を保つのは大変だったが(笑)、限られた時間のなかでもポイントは、おおむね聞くことができた。
ワルターとクレンペラーに関しては、演奏会前のウィーンの雰囲気、当日の客席の反応など、居合わせた人ならではの生々しいお話。
ご記憶が鮮明で、たずねればバシッとお答えが返ってくる。そしてお話をされているうちに、映像的、具体的な記憶がどんどん甦ってこられているらしいことが、はっきりとわかった。
クレンペラーの演奏会は売切れで、客席ではなく舞台上の臨時席しか入手できず、その結果、指揮ぶりを正面から見ることになったそうだ。
まさにその目で見られた方にしか再現できない、ほとんど左手しか動かないというクレンペラーの指揮ぶりを真似しながらの「あのエロイカは本当に素晴らしかった」というお言葉を耳にしたとき、私の心は震えた。
「一九六〇年」をめぐる長いクエストが大きな環を描いて、ついに終点に来たと確信したからだ。
二十六年前の一九八七年、クレンペラー&フィルハーモニアの《英雄》と第七番のCDが、チェトラから出た。
演奏の凄さに驚愕すると同時に、前者がワルター&ウィーン・フィルの「ウィーン告別演奏会」と、同じ日の同じ会場のライヴであることに気がつき、これをきっかけにして、この年のライヴ録音を集めはじめた。
その頃、一九六〇年はそれほど遠い昔ではなかった。
単純な年数でいえば、その一九八七年をいま回想するのとほぼ同じ。私にとっては生れる三年前だが、年長の人たちは大概、具体的な記憶をもっていた。
しかし、そうした主観的な「むかしばなし」に頼らず、ライヴ録音と当時の文献を調べていくことで、より複眼的な、立体的な視座から過去を捉えなおせないか、というのが、『ウィーン/六〇』を書くときの方法論だった。
一介の素人で、誰かに話を聞こうにもその伝手がなかったのが、インタビューをさぼる小さくない理由だったけれど、それを逆手にとろうと、思った。
みな、その年をよく知っているつもりでいて、かえって録音も文献もおろそかにしているように、感じたからだ。
これはその後、私が「演奏史譚」と勝手に名づけた書きかたの、基本になっている。
今日、その方法論と正反対に、体験談を直接うかがった。そして出発点となった、《英雄》に戻った。自分の作業が、ぐるりと一つの環になった。
実演から五十三年。CD発売から二十六年。「はんぶる」印刷版開始から十九年。全然キリはよくないが(笑)、二〇一三年の終りこそ、一つの潮時。
そこで、これがピリオドを打つことにあたるのかどうか、よくわからないけれど、とりあえずサイトの『ウィーン/六〇』を、テキストで公開した。
今までは画像で、サイト内の目につきにくいところへ、わざと不親切に置いていたのだが、テキストにして、コピー&ペーストも検索も可能なものにする。
そうして「一九六〇年」を鎖から解き放つと同時に、自分も「一九六〇年」から解き放ってもらう。
いざ、さらば。
二〇一四年には、何をしようぞ。
あ、「一九五四年」から、ちょうど六十年か…。
十二月三十日(月)TOKYO1944

本屋で買ってきた「東京人」二月号。一九四四年の精密な航空写真により、空襲前の「軍都」東京の様子を知ることができる。
昭和初め、もちろん首都高などなく、道が狭く、建物は背が低い、そしてとても緑と土の多い、古き良き帝都、東京。
写真にはこの本らしく丁寧に注釈を入れ、名所旧跡や華族の屋敷などがどこにあるかが、とてもわかりやすい。
当時の日本製の地図では当然ながら詳細を省いてある、連隊の駐屯地などの軍用地や建物の配置がよくわかるのも、とてもありがたい。渋谷の東京陸軍刑務所(いまの渋谷区役所と公会堂)や池袋の東京拘置所(サンシャイン60)の写真に、いちいち「刑場」の位置が表示してあるのも、刑務所好きと思しき担当者の強いこだわりが出ていて、愉快(正直、同病相憐れむ気にもならないではないが…)。
実に素晴らしい写真だが、複雑な思いにさせるのは、これを撮ったのが米軍の偵察機、B‐29に高性能カメラを積んだF‐13だったということ。
この写真により綿密な爆撃計画がたてられ、撮影の直後に、写真の中の風景の大半が焼き払われ、地上から消滅することになる。同時に、各国大使館の多い麻布や、占領後に将校宿舎として接収できそうな洋館の多い麹町や西原などの地域を目標から意図的に除外することも、この精密さなら充分に可能だろう。いわば下手人の、下調べの証拠物件なのだ。
F‐13が東京上空に侵入しはじめたのは、昭和十九年十一月以降のこと。
昼日中にたった一機でくるのだが、高射砲も迎撃機も届かない高々度を飛ぶため、日本側は見上げるのみで、手も足も出なかった。
たしか山田風太郎などだったと記憶するが、当時東京にいた学生の何人かが、秋の高い、雲一つない青空に、銀色にきらめきながら悠然と単機で浮ぶB‐29(F‐13)の幻想的な美しさを、思い出に書いていた。
これらの写真のどこかには、かれらが小さな点となって写っているのかも。
鮮明な偵察写真を撮るのに雲があってはならないからこそ昼の青空を飛んだわけで、それは、災厄をもたらす悪魔の、美しい銀色の使者だった。
日常の暮らしの上空に、こんなものに入り込まれた時点で、もう戦争は完全におしまいなのに、やめられなかった。
「ここで負けを認めれば、死んでいった仲間に申し訳がたたない」というような理屈だとしたら、救いがたい。
そんな軍人同士の「貴様と俺」の理屈とは関係のない無数の一般市民を、巻き添えにする結果になったからだ。
Homeへ