二〇一四年
一月三日(金)有楽町の火事
新幹線、山手線などが朝に起きた有楽町駅前のビル火事による運転見合せ。
品川駅などでの折返し運転ができなかったのは、東京駅の機能が巨大化しすぎたためなのだろうか。
ところで焼けたビル、自分には、高校時代の思い出のある建物だった。
といっても、まるで甘酸っぱいものではない。一九八〇年、同級生六人くらいで『地獄の黙示録』のロードショーを見たあと全員でこのなかのラーメン屋に入り、まったくしゃべる気分にならなかったのでみな無言で食っていたら、店員さんがものすごく気持悪がっていたこと。
また、別の機会にここのゲーセン(ひょっとしたら火元?)で、二人でギャラクシアン(エイリアンに続いて、当時大ヒットしたテレビゲーム)をやったことも、なぜか鮮明に記憶に残っている。
有楽町などよく知らないはずだが、名門でも不良でもない、東京の平凡な量産型高校生にとって、なんとなく入りやすい安心感が、このビルにはあった。駅前の闇市の小店を吸収したマーケットらしい、雑然とした気安さのためだろう。
このビルだけでなく、数年前まで、この付近の雰囲気は「戦前の北アジアのどこかの駅前」のようで好きだった。
東南アジアではないのは、街路の色彩が原色ではなく灰茶色の暗い色で、外が寒くて、狭い店内に湯気と油煙がこもっていそうな雰囲気だから。
新宿の「思い出横丁」や吉祥寺の「ハーモニカ横丁」が、もろに戦後の闇市やマーケットそのものの雰囲気なのに対し(それはそれで大好きだが)、それよりもゴツゴツ、寒々とした、鉄とレンガとモルタルの北アジア。白系ロシア人がいそうな。上野駅周辺みたいに陰惨になりすぎず、適度に整備されているのも、西東京の高校生にとって気楽だった。
再開発でそうした気配がほとんど消えて、古い建物はこの駅前のビルくらいになっていただけに、残念。
これを奇貨として、新しい高層駅ビルが建つことになるのだろう…。
一月八日(水)川奈と伊東
昨日から伊豆の川奈に一泊。旅館は奮発して、「伊東遊季亭 川奈別邸」。部屋に温泉かけ流しの内風呂と露天風呂がついていて、まる一日、温泉に浸かりっぱなし。食事も美味。
翌日はまず川奈ホテルを見学。一九三六年開業、高橋貞太郎設計のしゃれた建物。広々と明るく、東京湾を一望するティールーム。
伊東駅で特急に乗り換えるまで時間があるので、途中下車して市内見学。
これが思わぬ当り。伊東というと、自分の世代には「伊東に行くならハトヤ」の刷り込みが強く、巨大な温泉ホテルしかない気がして、今までは通過するだけだったのだが、どうしてどうして、風情ある景色が残っていた。東海館と湯の花通りである。
昨夜泊まった旅館の大元が伊東市内の東海館という昭和三年創業の老舗で、その木造の本館が、市の文化施設となって保存されているというので、まずそれを見に行った。
途中の駅前大通りは殺風景で面白みがなかったが、東海館そのものは松川という川沿いに建つ、いかにも昔の旅館建築で、いい感じ。隣にも「いなば」(ケイズハウス伊東温泉と改称)という木造旅館が並び、それぞれ特徴のある望楼を備えて、この松川沿いこそ、伊東旅館街のかつての中心的な存在だったらしいことを感じさせる。
その松川をさかのぼった山裾に「伊東に行くならハトヤ」と謳ったハトヤホテルが、大きな姿を見せていた。
そのあと、大通りに戻る気にはならなかったので、並行しているのが見えたアーケード街「キネマ通り」に入るが、ここは閉まっている店も多かった。
しかし、そのまま駅へ続く「湯の花通り」の商店街が、明朗ないい雰囲気。気に入ったので、ここにもう一度ゆっくり来たい。
一月九日(木)異界の起源
これは『アルテス』の「帝都クラシック探訪」次章の「上野篇」にからむ話なのだが、かねて疑問に思っていたのが、鴬谷駅前をびっしりと埋めつくす、あのラブホテル街の起源。
江戸時代の茶屋以来という話もあるけれど、それはあり得ないと思っていた。理由は単純で、そんないかがわしい場所なら、明治の国鉄が駅をあえてつくるはずはない。絶対に駅よりもあと、おそらくは戦後までくだると思っていたら、新刊の『東京最後の異界 鶯谷』(本橋信宏/宝島社)に、地元住人のありがたい証言が載っていた。
それによれば、米軍の空襲で周囲の建物の大半が焼けたあと、わずかに残った駅前の民家が簡易宿泊所となり、繁盛した。焼跡にもそれを真似て類似の宿が建てられ、ドヤ街になった。そしてそれらがいつのまにか、ラブホテルに転業していった、ということらしい。
つまりは小規模店の入る駅の地下街や駅ビル同様に、焼跡闇市時代の落し子なのだ。ラブホテル街は早くても一九五〇年代、おそらくは売妨法施行後の六〇年代からだろう。
東京のラブホテル街の起源は、きちんと書かれていることが少ないけれど、実は意外に歴史が浅い。新大久保も円山町(戦前以来の三業地ではなく、周囲のホテル街のほう)も六〇年代、つまりは売妨法施行のあとに発展している。
後者は、奥飛騨の御母衣ダム建設で水没する村から移住した人々が、花街の衰退に入れ替わる形で始めた。
前者は、売妨法で新宿の赤線(いまの二丁目)と青線(いまのゴールデン街)が廃業して飲み屋街に変ったとき、その代替地として歌舞伎町が急速に一大歓楽街・風俗街と化していくのに並行して、出現した。
六四年の東京オリンピックに先立って移転を余儀なくされた千駄ヶ谷鳩森の連れ込み旅館街――五輪会場近くのこんなものを外国人に見られたらみっともないという発想――が、引越先として目をつけたのが、歌舞伎町に隣接する大久保だった、ということらしい。
大久保も戦前は典型的な山手の住宅地(江藤淳などがここの生れ)だったが、空襲で焼けたあとにドヤ街が出現した。その簡易宿泊所がラブホテルに転業し、周囲の住宅も巻きこむという展開は、鴬谷とまったく一緒。
また、新大久保駅も鴬谷駅も巨大ターミナル駅のすぐ隣の、駅前広場もない地味な駅という位置づけが共通する。
現代の風俗街、いかにも昔からそこにいたような顔をしているが、実はわりと突然に、一軒の出現をきっかけに街を呑み込み、あっという間に定着する。
戦前までの、行政がその境界をある程度コントロールしていた時代とは、そこが違うのが面白い。鴬谷も、そうしてああいう街になった。
それにしてもこの本の表紙、さすが。上野寛永寺の大きな墓地(かつての将軍家墓所)からJRの線路をはさんで、崖下の鴬谷ホテル街を見下ろし、隅田川の向うにスカイツリーを望む。
墓地に崖に線路に風俗街に隅田川、そして塔。荷風が大喜びしそうな風景。
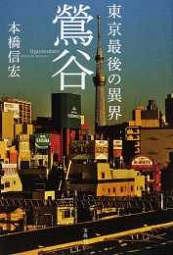
とフェイスブックに書いたあと、川っぺりには風俗街がよくあるというようなやりとりを友達としていて、自分自身の「異界の原風景」を思い出した。
四十年前の子供の頃に最寄りの繁華街だった、自由が丘駅。
南側の九品仏川が暗渠になって緑道になる前は、東横線のガード付近の川沿いに、連れ込みの旅館が数軒並んでいた。なぜこんな住宅地に人が泊まるのか、不思議に思えてならなかったが、母親にたずねても答えは曖昧だった。
そして南口通りからこの旅館街へ、怪しげなスナックの並ぶ、細くて日の入らない路地が通っていた。夕方、人気もなく薄暗いその路地を、自転車で走り抜けるのが面白かった。
普通の町の裏の一角の「異界」。
川が見えなくなってまもなく旅館は立ち退き、路地もふさがれた。南口通りもいまは「マリ・クレール通り」などと呼ばれている。
地価の上昇とともに、昭和五十年代ぐらいから、東急沿線の雰囲気はいまの小じゃれた、しかしとても嘘くさいイメージに変りはじめた。
自分はそれが苦手で、好きになれぬまま今に至っている。昔の雰囲気を今も残しているのは、池上線沿線ぐらいか。
一月九日(木)音が来ない
今年最初の演奏会は、東京芸術劇場でカンブルラン指揮の読売日本交響楽団。
前半はシューマンで《マンフレッド》序曲とピアノ協奏曲(独奏ムラロ)。後半はラヴェルだけで《高雅で感傷的なワルツ》と《スペイン狂詩曲》。
前半、音が身体に届いてこない感じで困惑。二階の正面の席だが、このあたりはこんな音響なのだろうか。演奏に集中できずに終る。後半はカンブルランらしくカラフルで軽やかな響きの演奏を愉しんだが、音響の違和感は消えないまま。
改装後のこのホールの音は気に入っているのだけれど、位置の差とか、気をつけてみる必要がありそう。
一月十一日(土)ヴェデルニコフの洗練
ヴェデルニコフ指揮NHK交響楽団をNHKホールで聴く。
ロシア・プロで、グラズノフの演奏会用ワルツ第一番とチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲(独奏ジェニファー・コー)と《眠りの森の美女》抜粋。
後半の、ヴェデルニコフ自身の選曲による《眠りの森の美女》が、予想以上に素晴らしかった。自分はいわゆる「国民楽派」的な粘っこい曲や演奏が苦手で、チャイコフスキーでも貴族社会向けというか、西欧趣味を意識したファンタジー作品、つまりバレエ音楽とかオペラ《イオランタ》の方が好きである。
この演奏は洗練された味と軽妙さがあって、そうした好みにぴったりだった。《白鳥の湖》や《くるみ割り人形》に較べ「おなじみの旋律」が少ない作品なので、聴く前は不安だったが、むしろそれがよかった。オーケストラも演奏を愉しんでいたように思う。
ところで開演前、チケットの列と席番だけをみて二階席にいくと大失敗。自分の席は一階だった。列と席番の前にまず何階かを確認すること、一階は階段を降りて地下へ行かねばならないこと、というNHKホールの鉄則を忘れていた…。
一月十二日(日)海底王国と海底軍艦

ふと目にした朝日新聞に、復刊ドットコムが出した小松崎茂の絵物語『海底王国』の広告が出ていた。
そこに、この作品こそ東宝映画『海底軍艦』の元ネタ? というようなことが書いてあったので、気になった。
あの映画は、原作とされる押川春浪の大昔の冒険小説と、似ても似つかない。『海底王国』の表紙は映画の敵役のムー帝国の女王を思わせるし、作者の小松崎茂こそ、映画の轟天号のデザインをしたその人ということを考えても、一九五三年から翌年にかけて描かれたこの作品の方が、「原作」よりも近そうだ。
価格が高めなので手が出ないが、ヴェルヌの『海底二万里』やハガードのクォーターメン・シリーズなどの西洋冒険小説の古典と一緒に、「少年倶楽部」に平田晋策とか海野十三が書いた秘密兵器ものの少年小説も下敷にしたような作品なのだろうか。
映画の方は、敗戦によってほとんど封印されてしまった『昭和遊撃隊』などの平田作品に熱狂した世代が、形を変えて戦後にその興奮を復活させようとした気配にみちていて、東宝特撮映画の根っこをあらわにしたような物語だった。
ところで昨年は『海底軍艦』の公開五十周年の記念年。これに『太平洋の翼』に『青島要塞爆撃命令』、同じ年に生れた私の世界観を決めてしまった、一九六三年の東宝映画三本(笑)。
ほかに『マタンゴ』、宮崎駿に影響を与えたとされる『大盗賊』もこの年で、テレビに押されるなかでの、最後の大花火みたいな、東宝大爆発の年だった。
一月十三日(月)大河『徳川家康』
「時代劇専門チャンネル」で一九八三年の大河ドラマ『徳川家康』が始まる。
総集編は放送時に録画してビデオでもっているが、本編を見るのは本放送以来三十一年ぶりなので、とても楽しみ。
滝田栄、武田鉄矢など『草燃える』の脇役で成功した若手を主役級に格上げ、さらに「ほぼ無名の新人」役所広司を信長に抜擢と、配役の妙が光った作品。
脇を固める成田三樹夫の今川義元とか江原真二郎の石川数正とか佐藤慶の武田信玄とか久米明の片桐且元とか辰之助の伊達政宗とかも、大好きだった。
第一回(特別版で二本分の九十分)を見ると、とにかくテンポが速く、まるで総集編のようにシーンが切り替わる。この時代の大河は原作にわりと忠実にやるので、この方法でいかないと文庫二十六冊分の作品を一年でやるのは不可能だったのだろう(以前に『春の坂道』をやったときも、本当はこの作品がやりたかったがスケールが大きすぎて断念し、同じ山岡荘八に新たな原作を書きおろしてもらったそうだ)。まだ時代劇のできる役者――台詞回しがきちんとしていて、声が響く――が残っていたから、それでも形にできるのがすばらしい。
一月十四日(火)三次元のハロルド
カンブルラン指揮の読売日本交響楽団をサントリーホールで聴く。
秋のシーズン開幕のブリテン、ウストヴォーリスカヤ、ストラヴィンスキーというプロに始まり、カンブルラン色をおかまいなしに打ち出した今シーズン。今日もガブリエリ(カンブルラン編)のカンツォーナ、ベリオのフォルマツィオーニ、ベルリオーズの交響曲《イタリアのハロルド》(ヴィオラ独奏:鈴木康浩)と、およそ日本のオケとは思えぬ選曲。
また、選曲とともに特徴として感じるのが、サントリーホールという空間の面白さを、お客に楽しんでもらおうとする意欲の強さ。
ワインヤード形式だからこその音楽、音響だけでなく視覚も併せたパースペクティヴの広がりを、楽しむ。前半のガブリエリとベリオはもちろん、《イタリアのハロルド》まで、最後の最後でシアターピースに変じた。
指揮者の下手の普通の位置でひいていたウィオラが、終楽章でいったん途絶える(殺される?)箇所で、おもむろに袖に引っ込む。
そして、コーダ直前で弦楽四重奏が出る場面。弦楽三人が入場してオルガン席の前につき、ついでヴィオラがP席下手のいちばん下まで降りて、三人+一人+オケで、三段階の高さになる。
天上の弦楽の響きと、中間(煉獄?)の独奏ヴィオラ、そして地上(地獄?)の乱痴気騒ぎとの、「神曲」三部作のごとき、明快な上下の対照の面白さ。オルガン、P席、ステージと、三段階つかえるサントリーホールならでは。
いったんこうされると、オケのコーダがいかにも地の底の悪魔(=人間)の騒ぎみたいに感じられてくる。
演奏の素晴らしさに加えての、ナマだからこそ体験できる空間の面白さ。
そして、あらためて前半からの演奏を思い返すと、そこに見事な一貫性があったことに気がつく。
初めのガブリエリでまず前後の奥行きの対照。ついでベリオでは左右に広い幅を加えた楽器配置の変化を聴かせておいた。ここまでは水平面の動き。
そして後半のベルリオーズは(そういう意味では)普通の配置かと思わせておいて、最後の最後で高さの対照、空間の立体化を、手品のようにやってのけた。
曲ごとに線から面、立体へと広がっていく。この演出の呼吸も、ほんとうに見事だった。
それだけではない。高低の演出によって、終楽章のなかでのあのパッセージの意味が、鮮やかに浮き彫りになった。世俗のなかの聖性。
そこで前半を見なおすと、ガブリエリとベリオが聖と俗の組合せになって《イタリアのハロルド》を予告している。思わず膝を打つような構成だった。
それからもう一つ、嬉しかったこと。
行きは時間短縮優先で銀座線の溜池山王駅、帰りは酔客の混雑を避けて南北線の六本木一丁目駅を使うのだが、六本木一丁目駅、地下二階の殺風景な地下道へおりてから、いったん地下一階の改札まで昇り、最後にまた地下三階のホームまでおりるという昇降のくり返しが、なんとも無駄な気がしていた。
ところが今日行ってみると、「アークヒルズ サウスタワー」の地下一階にアークキッチンなるフード街ができ、そこを抜けると、地下二階へおりずに水平に改札へ行ける。
演奏会と違って通路の無駄な立体化は楽しくないので、これは便利。今日オープンなのだそうで、近いうちに何か食べてみようと思う。
一月十八日(土) つうの愛
日経新聞に公演評を書くために、文化会館で佐藤しのぶの《夕鶴》。満員。
公演そのものについては新聞評に書くので、ここでは作品について。
第一幕が第二幕の倍も長いのは、ドラマのクライマックスまで中断なしに進めたかったからだろうか。
そのクライマックスは、つうが最後の布を織ると決意する瞬間。考えさせられるのは、この決意を促すきっかけについて、きちんと説明されていないこと。
子供のように単純な与ひょう。金銭欲に踊らされて、人間の弱さをむき出しにする。その弱さとそれにつけ込む人間の醜さを、つうは激しく憎む。憎んで、布を織ることを一度は断ったのに、死を覚悟で織ることにする。その転回点がはっきりしないのだ。
そこにあるのは期待ではない。それで得た金で与ひょうが都に行っても、何かを学び、身につけるために行くわけではなく、ただ観光をしてくるだけ。元の木阿弥で、また無学な貧乏に戻るだけ。
最後につうが去ったときでさえ、ただの悲しみ以上の何かをこの男が考えはじめるのかどうか、定かではない。惣どが布を取り上げようとするのを拒み、しっかと抱えこむ姿が何を暗示するのかは、演じ手の演技次第でどうとも変る。
何らかを学んだ登場人物がいるとすれば、運ずだけだろう。悲劇の発端に加担しながら、結局は傍観者にすぎないかれこそ、観客が感情移入できる、唯一の登場人物。
その運ずほどの理解力もない与ひょうを、つうは愛する。論理ではない愛。言葉(歌詞)で説明することのできない、矛盾に満ちて曖昧なもの。
《椿姫》でヴィオレッタが身を引くのは、アルフレードのためを思っての愛だが、つうの愛は、与ひょうのわがままを許すだけで、はたしてかれのためになるものなのか。
言葉にならない、「それを言っちゃあおしまいよ」の愛。言葉でも音楽でも充分には語られていない感情と行動を、どうすれば観客に得心させることができるかは、演じ手にかかっている。
言わず語らず、ヨーロッパ起源のオペラのロゴスの世界では珍しいものをドラマの核心とする、日本のオペラ。
一月二十日(月)郵便切手の消費税
郵便切手を買いに出たが、そういえば久しぶりに消費税がはみ出すから、買いすぎると面倒だと思いなおし、八十円切手を二枚だけ。
四月からは五十二円とか八十二円になり、旧来のはがきや切手には二円切手を新たに貼らないといけない。二十年ほど前、消費税ができたり五パーセントに上がったときにやっていたことが、復活。
新額面の切手は三月三日から発売。
ま、今はコンビニで二十四時間いつでも買えるから、買い置きなどあまり気にしなくてすむが。
夜になって、アバドの訃報をネットで知る。
一月二十二日(水)LINNのCD‐R
イギリスのレーベル、LINNのCDはオーディオメーカーだけある高音質で好きなのだが、タワーレコードのサイトで見ると、SACDハイブリッド以外の普通のCDの最近の新譜は、大半がCD‐Rになっているようだ。
海外はともかく日本の愛好家には拒否反応が強い(そのせいかHMVのサイトではSACD以外の新譜が消えている)けれど、これも時の流れか。
自分は売るときのことを考えて(ああ貧乏はいやだ)、CD‐Rには手を出さない。SACDだけは現状維持でつづけてくれることを期待。
一月二十三日(木)四谷駅の書店全滅
四谷駅近くの本屋、あおい書店の四谷駅前店に、二十八日で閉店の張り紙。
これで、四谷駅付近の書店は全滅。本屋のない街になる。
唯一の店なのに、それでもやっていけなくなったのか。駅からは目につきにくい場所だけれど、立地が原因とは思えない。最後まで店内にお客はけっこういるからで、むしろ地代の安さがメリットになっていたはず。
しかし最近はそのわりに、実際に買っている人が少なかった。思えば、数年前までは三、四人がレジの前に並んで待つ場面をよく見たけれど、そんな光景を目にしなくなって久しい。
かくいう自分がそうだ。毎日のように覗きに行っていたが、重い本、高い本は立読みだけで、ネットで買う癖がついている。だから閉店なんだろう。
本屋がなくなると、その街へ歩きに行く動機づけが消えるので、困る。
四谷三丁目の交差点にあおい書店の別店舗があるからまだいいが、四谷駅の方に行く機会は、確実に減る。
などと書いていて、思い出した。
私が二〇一一年の東日本大震災に遭遇したのは、この四谷駅前店だった。
二階で、一冊の新書を棚からとった瞬間、揺れが始まったのだった。
思わず新書を棚に戻し、他の新書が棚から飛び出してくるのを手で抑えたのを憶えている(人間、とっさに意味のないことを真剣にしますな)。
この店にいると、ときどきその瞬間がフラッシュバックすることがあった。
その場所が消える。
最後にもう一度、その場に立ってみなければ。
一月二十四日(金)本が三冊
本が三冊、家にきた。
まずは「ちゃんと」店で買った本。今までの自分を反省して、あおい書店で買った。なくなる四谷駅前店への手向けにしようかとも思ったが、それよりも未来に投資することを選んで(なんと偉そうな言い方)四谷三丁目店で。
芳賀ひらく『古地図で読み解く江戸東京地形の謎』。
地形本は大流行で各社から類似の本が出ているが、これは自分の知るかぎり、最も面白そうに見える本(まだ立ち読みだけなので)。古地図に手がかりのごとくわずかに残された地名や崖の描写などから地形とその意味を読み解いていく。該当個所の古地図がカラーで、読みやすく拡大されて多数ついているのが眺めて楽しく、素晴らしい。とても楽しみ。

他の二冊は、三十年ほど前に愛読したのに、いつのまにか手元から消えていた本。品切なので中古でネットで購入。

小林孝裕『海軍よもやま物語』。
水兵出身の著者が海軍時代のあれこれをユーモラスに回想したもので、じつに文章がうまい。掲載誌の「丸」は味をしめて、各種の元軍人にさまざまな「よもやま物語」を書かせたが、文章力においてこの一冊に及ぶものはないと思う。ずっと品切だったのがやっと二〇一一年に再販されたのに、もう入手難。

はかま満緒『黙って書いてごめんなさい』。有名人のエピソード集。
フェイスブック友達の渡辺謙太郎さんのところで、力士がまく塩の話が出た。それで「土俵近くに座っていた客のオッサンが、持ち込んだゆで卵にあの塩をつけて食べて、呼出し太郎にものすごく怒られているのを目撃した」という話をむかし読んだのを思い出して書いたが、その本がたしかこれだった。そこで久々に読みかえしたくなった。
川谷拓三の最初の映画出演は、帆船のマストに引っかかっている死体の役だったとか、そんなことばかり延々と書いてある本。
パラパラと読みかえしてみて、以下の話などが可笑しくて、懐かしい。
クラリネットの北村英治さんが日比谷の交差点を渡ろうとすると右折する車に轢かれそうになった。
「その運転手が、バカヤロー、なにぼやぼやしてるんだと怒鳴ったからアタマに来たねェ。車のナンバーと、運転手の人相を目にやきつけると、毎日同じ時間に日比谷の交差点に立ってたんです。見たところ、どこかの自家用運転手。必ず同じ時間にここを通ると思ったんですョ」
北村さんのカンは見事に当たって、一週間後、その車をつかまえた。
運転手をひきずりおろすと、その運転手がまじまじと北村さんを見て言った。
「許してくれ。こんなにヒマな人だとは知らなかったんだ」
一月二十五日(土)クリストのヴィオラ
トッパンホールで、ヴォルフラム・クリストのヴィオラ・リサイタル。伴奏は佐藤卓史。
初めにヴィオラ・ダモーレとフォルテピアノを用いて、生誕三百年のC・P・E・バッハのソナタ ト短調、ダウランドの《ラクリメ》と歌曲〈もしも私のうけた苦しみが、情熱を掻き立てることができるなら〉。続いてモダン楽器に持ちかえて、そのラクリメを原曲とするブリテンの《ラクリメ‐ダウランドの歌曲の投影》。ここまでが前半で、後半はシューマンの《おとぎの絵本》とシューベルトの《アルペジオーネ・ソナタ》。
最後の曲は、昨年十一月にこのホールでタメスティの生気豊かな演奏を聴いた記憶が耳にまだ残っている。それに較べてクリストの演奏は内省的。いかにもヴィオラらしい、つつましい音楽。
アンコールでは五日前に亡くなったアバド(三十年来の友人という)に捧げ、ブラームスのヴィオラ・ソナタ第一番のアダージョが演奏された。
一月二十六日(日)ニューラテンクォーターのライヴ盤
衛星ラジオ「ミュージックバード」のスタジオは、半蔵門のFM東京の四階にある。
数か月前に模様替えがあり、通路にクラシックやジャズの出演アーティストなどの写真がたくさん掲げられた。
そのなかに、モノクロのポスターがあるのが目にとまった。いかにも五〇~六〇年代ジャズの、クロっぽくてクールなポスター。美貌のジャズ歌手として名高いジュリー・ロンドンが写っている。

見たことのないものだが、なんなのだろうと文字に目をこらすと、NEW Latin Quarter、つまりニューラテンクォーター(!)とある。
もちろん、赤坂のナイトクラブ、ニューラテンクォーターに、この歌手が出演したときのものだ。
こういうものが貼ってあるということは、ひょっとしたら当日のライヴ録音のCDでも出たのか。そう思って帰宅してから検索すると、なんとたしかに出ていた。
九月下旬にこのロンドンとパティ・ペイジの二枚が出たばかりで、さらにさかのぼって五月中旬には、サッチモ、ナット・キング・コール、ヘレン・メリルの三点が出ていた。
私がこの可変日記にニューラテンクォーターのことを書いたのは五月五日、まるで知らなかったがその十日ほど後に、そのライヴ盤が出ていたのだ。
こんなものが残っている、世に出ているとは、夢にも思わなかった。これは買わねばと思って調べると、これらだけではなく三年も前の二〇一〇年に、さまざまな歌手を集めたベスト・ライヴ集のような一枚が、アメリカで出ていることもわかった。

このベスト盤、モノクロのポスター風のジャケットの五点とは、セピア色で雰囲気が異なる。そういうものがなぜ国内盤ではなくアメリカで出たのか、どうもよくわからなかったが、初めて聴くには何人も聴ける方が面白いので、とにかく買ってみることにした。
聴いてみると、モノラルながら録音は明快。ソロがオンマイクで強調され、バンドや客席ノイズが遠いのは、条件の悪さを考えれば仕方のないことだろう。しかしメリル以外の前述の四人に加え、ナンシー・ウィルソンやカテリーナ・ヴァレンテ、チャビー・チェッカー、ミルス・ブラザーズ、ハリー・ジェームズ・オーケストラにサミー・デイヴィスJr.など、ポップス界の大物が十三組。日本最高の豪華なショーを売り物にしたこのナイトクラブの伝説的名声を、まさしく実際に耳で確かめることができるものだった。クラブの専属MCとして活躍したE・H・エリックの声も入っている。
しかも、こうしたものは往々にして録音データがいい加減だったりするのに、一九六〇年八月十七日のミルス・ブラザーズから七〇年十月十四日のナンシー・ウィルソンまで、日付もちゃんと入っていたのには驚いた。個人的には、こんなところで一九六〇年ものに出会えるとは思わず、意外な拾い物。解説文も英語と日本語で、きちんと書かれている。
これだけのものがどうして今になって世に出てきたのか、気になってさらに調べると、山本信太郎の『昭和が愛したニューラテンクォーター』というディスクユニオンが出した本に、その経緯が書かれているらしいことがわかった。
著者の山本は創業者の父を継いでこのクラブのオーナーとなった人物。数年前に『東京アンダーナイト』という回想本を出していた。読み物としては営業部長の諸岡寛司の『赤坂ナイトクラブの光と影』の方が面白かったが、オーナーの回想録だけに知名度は『東京アンダーナイト』の方が高く、文庫にもなっている。
新作の『昭和が愛したニューラテンクォーター』は、表紙が前作と同じクラブの外観の写真だったので、てっきり題名を変えて出しなおしたものかと思っていた。しかしそうではなくて、CD発売の顛末と出演アーティストの挿話を中心とする、別の本だったのだ。

この本によると、音源はクラブの音響担当が録音したオープンリールで、山本の家の倉庫に眠っていたもの。前作の出版をきっかけに存在を思い出し、デジタル化したものという。それをアメリカの音楽出版社を経営するジェイ・ワーナーに依頼し、著作権関係をクリアして発売したのだそうだ。
CDには第一集とあるので続きも目論んでいたのだろうが、ワーナーは二〇一二年に亡くなり、企画は中断した。その翌年、新たに歌手別のシリーズがマース・ミュージックから発売開始された、というのが現在の状況らしい。
一月二十八日(金)「君が好きだ」抜き
サントリーホールで、テミルカーノフ指揮サンクトペテルブルク・フィルの演奏会。チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番(独奏ヴィルサラーゼ)、後半はラフマニノフの交響曲第二番。
前世紀後半風の、抑揚やアクセントの弾みを抑えた、平らなフレージング。そのわりに大雑把なアンサンブル。
自分の好きなスタイルではないが、それだけに、ラフマニノフの第三楽章の旋律から歌謡性がなくなり、いつも悩まされる「君が好きだ」(大学時代の友人がこの旋律にあわせて歌っていた歌詞)をまったく連想せず、純粋音楽として楽しめたのは収穫だった。
実演であることを意識してか、最近は聴く機会の少ないカット版だった。
一月三十日(木)読響カレッジ
文京シビックホールで、大井剛史指揮読響の演奏会。
これは読響カレッジと題されたシリーズの一環で、七時半からプレトークがあり、演奏そのものは八時から一時間。今日はドヴォルジャークのスラヴ舞曲三曲と《新世界より》。
このところ名前を聞く機会の増えた大井の指揮、リズムが硬直して弾まなかったのは、初共演による緊張からだろう。次に期待。
ロビーに、ホールの前身である文京公会堂のスタインウェイが置かれていた。
一九五九年の開場から、有名な一九六一年のケンプのベートーヴェンのピアノ・ソナタ連続演奏会などに使われたピアノ。面白いことに、響板には六〇年代のケンプ、ゼルキン、マガロフなどのサインが、大ピアニストたちの来日公演の証言として残されている。
ひとつだけ二〇一一年と新しく、とても目立つ位置に書かれているものがあったので目をこらすと、フジコ・ヘミングのものだった。
一月三十一日(金)バッティストーニ
サントリーホールで、バッティストーニ指揮東フィルの演奏会。
二期会の《ナブッコ》で評判になって以来、聴いてみたかったイタリアの俊英指揮者。曲は《ウエスト・サイド・ストーリー》のシンフォニック・ダンスとマーラーの《巨人》。
熱のこもった指揮でオーケストラをドライヴする一方、つねにコントロールが行きとどいて、響きの骨格がしっかりと崩れない。見事な主観と客観の両立。この人は大器だと思う。
二月五日(水)佐村河内守の事件について
佐村河内守の作品が他人の書いたものだったというニュースが未明に流れる。
本人も認めており、そして夕方には作曲家の新垣隆が、ゴーストライター(コンポーザー)を十八年にわたって務めていたことを自ら公表した。
このような事実を知る由もなく、驚いた。交響曲第一番は大曲だから、何らかの形でアシスタントがいるのかもとは思っていたが、すべて代作だったとは。
具体的な作曲について佐村河内本人の意向がどこまで関わっていたかは、今後の検証で明らかになるだろう。音楽にかぎらず絵画などの芸術、著作や学術研究でも、代作代筆や集団作業など、ゴーストの存在はよく問題となるから、それ自体は珍しいことではない。しかし今回の場合は「耳の聞こえない人が作曲」したことが「物語」の最大のウリであったのに、健常者の作曲となるとすべてが否定され、ペテンだったということになる。
私は、交響曲第一番の二楽章抜きの東京初演を聴いて、弱点を感じつつも最後に感動した。そのときの気持はこの可変日記に素直に書いたし、誰の作品であろうと、いまも変りはない。
そしてこれが縁となり、「レコード芸術」にCDの紹介レビューを書いた。昨年には自宅をたずねて、「CDジャーナル」にインタビュー記事も書いた。
これらの記事が詐欺行為を助長する結果になったことは、すべての読者に対しお詫びする。不明を恥じ、二度とこうしたことに手を貸さぬよう、肝に銘じる。
反省を重ねつつ、同時に、もう少し時間が経ってから、類似と相違を比較考察してみると、日本の西洋音楽受容史として面白いかもしれないと思うもの。
ショスタコーヴィチの《森の歌》の受容と拒絶の歴史と、佐村河内守の交響曲第一番のそれ。国内における大衆層の人気と、教養層の軽視と、そして…。
二月七日(金)新垣隆の記者会見
昨日、新垣隆の記者会見をネットで見る。単純に白黒のつけられない、揺れる心理を誠実に語ったことに共感しつつ、周囲にはまた別の物語がつくられつつある気配を感じる。
二月八日(土)味の継承
自分はまったくグルメではなく、通り道にある「いつもの店」、飽きない味の「いつもの店」がひたすらに好きという人間。そういう私が大好きだったのが、四谷駅近くのしんみち通りにある立ち食いそば「政吉そば」。
店主の「体力の限界」のために昨年夏に閉店して残念だったのが、年をあらためて、店主交替で復活。食べてみないことには味はなんともいえないが、「以前の味を再現しているつもり」との言葉に期待するのみ。
あのツルツルシコシコの麺とダシのきいたツユ(思いっきり凡庸な形容。とんがっているよりも平凡でうまい味の方が好きなので)をふたたび食べられることを祈るのみ。
営業時間が朝~昼だけで夜はないのは以前と同じで、値段は少し上がったが、まだまだリーズナブル。立ち食いといいつつ椅子席あり。ちなみに「まさきち」と読む。
四谷の食べ物屋には、こうした継承が他にもある。新宿通りにあった老舗のとんかつ屋「三金」は元従業員の手で、通りの向い側に復活した。また、しんみち通りの入り口にあって、行列のできる洋食屋として有名だった「エリーゼ」。揚げ物屋に転業したが、コックの一人が調理具を引き継ぎ、荒木町で店名を変えて同じ味を再現している。こういう復活、継承は嬉しい。
二月十一日(火)バーンスタインの遺産
今日はサントリーホールで、アラン・ギルバート&ニューヨーク・フィルハーモニックの演奏会。ソニー音楽財団主催の「10代のためのプレミアム・コンサート」。
前半は副指揮者のジョシュア・ワイラースタインの指揮と小曽根真の司会で、アラン・ギルバートの語りによるブリテン:青少年のための管弦楽入門、福島とニューヨークの子どもたち六人の《ミュージック・フォー・フクシマ》。
後半は音楽監督のアラン・ギルバートが指揮をして、バーンスタイン:「ウエスト・サイド・ストーリー」より《シンフォニック・ダンス》と、小曽根真がピアノをひくガーシュイン:ラプソディ・イン・ブルー。
バーンスタインの「ヤング・ピープルズ・コンサート」の雰囲気を受け継ぐ演奏会。前半が副指揮者の指揮なのも、いかにもバーンスタイン流。
各誌の〆切に佐村河内事件が重なり、最後はひいた風邪をごまかしながら仕事と、気うつな一週間だったので、ゴージャスなサウンドに触れて気が晴れる。
演奏会も三十一日のバッティストーニ&東フィル以来、十一日ぶり。偶然にも「ウエスト・サイド・ストーリー」が重なった。
指揮はバッティストーニの方がシャープな表現意欲にみちて鮮やかだったが、オーケストラの力は段違い。ただ、てろんと流れてしまう感じなのが惜しい。
ガーシュウィンもピアノのアドリブ・ソロが長すぎで、もっと刈り込んだ方が効果が出るのでは。
アンコールの、トロンボーンとベースでの即席ジャズ・トリオは素敵だった。このとき、ガーシュウィンでもほとんど聞こえないのに黙々とひいていたバンジョー奏者が、やはり黙々とリズムを、一人離れた場所でひいていたのが印象的。
二月十三日(木)それはそれ
デッカから「Decca Most Wanted Recitals」という、歌手のリサイタル盤ばかり集めたシリーズが五十枚も出る。
LPのリサイタル盤というのは、初発売時の曲目やジャケットを再発売以降に維持することがとても少ないと思うが、それを目指すという、マニアックを通りこして、かなりマッドなシリーズ。
『レコードはまっすぐに』に出てきたマックラッケンと奥さんとの二重唱集など、初発売以来の復活ではないか。
これを典型として、リサイタル盤というのは純粋に芸術的見地からつくられるとはかぎらないだけに、ローゼンガルテンと歌手の契約上の駆け引きとか、いろいろなドラマが想像できそうで愉しい。
アメリカの歌手をドイツ語圏の歌劇場に次々と売り込んでいたエージェントとタイアップして、プロモーション的につくらせたレコードもありそう。カルショーと現場スタッフのため息が聞こえそうな気もする。
これらの顔ぶれと曲目をながめていて思うのは、レオンティン・プライス&カラヤンのクリスマス・アルバムなどは、こうしたたくさんの「業務録音」の中から、たまたま生れた大ヒット・アルバムだったのかも、ということ。
当時のカラヤンとウィーン・フィルのデッカ盤には、クリスマス・アルバムのほかにも、《惑星》や《ジゼル》のような、「通俗的」な録音がある。
経費とリスクの大きいオペラ全曲録音をやらせてもらうかわりに、デッカが提案したものを録音するというような、バーター契約だったのではないか。
たとえば《惑星》は、レコーディング二か月後の一九六一年十一月にウィーン国立歌劇場のバレエ公演で二回演奏したのが、生涯唯一の実演記録なのだ。演奏会で指揮したことは、一九八一年のベルリン・フィルとの再録音の時期を含め、まったくない。愛着のあった曲とはとても思えないのである。
だが、カラヤンのデッカ盤がなければ《惑星》が現在の知名度を得ることはなかったろう。本人がどんな気持で指揮したかとは無関係に、世界的に売れまくるディスクが生れる。こういうあたり、カラヤンという存在は、指揮者として本当に空前絶後だとあらためて思う。
二月十五日(土)もう会えぬ先達
クリストファ・N・野澤先生を偲ぶ会にうかがう。
昨年八月に八十九歳で亡くなられるまで、日本を代表するレコード・コレクターであられた野澤先生。世界的にも貴重なそのコレクションは、関係各位の尽力で散逸することなく、東京藝大のアーカイヴに収められることになった。
偲ぶ会の会場はご自宅に近く、私もお食事をご一緒させていただいたことのある、中野サンプラザ二十階の、見晴らしのいいレストラン。眼下の真っ白な中野の町と、冬の青空。
野澤先生も、私を先生にご紹介くださった室伏博行さんも、ともに昨年この世を去られた。室伏さんがご紹介くださったもうお一人の「歴史的存在」、ヴァイオリンの松本善三先生も、二〇一〇年に九十九歳で天寿を全うされている。音楽と音盤をこよなく愛された、お三方。残った者は、ただその思い出を語るのみ。
会場でいただいた追悼文集は、野澤先生と一九六〇年代にJRCC、ジャパン・レコード・コレクターズ・クラブなる会でご一緒されていたという俵孝太郎さん、ストリング誌の青木日出男さん、新忠篤さん、片山杜秀さん、クロイツァー涼子さん、幸松肇さん、濱田滋郎さんなどが追悼文を寄せている。
読めば先生の温和な微笑みがあらためて目に浮かぶ、貴重品。
二月十七日(月)弱き人々
NHK大河『徳川家康』を見る毎日。
大河らしい大河とは、出来のいい原作とそれをきちんと尊重した脚本、結局はこれにつきる気がする。まだ性能の低い家庭用受像機を想定しているだけに画面はアップが多く、画面も単純なのに、脚本がちゃんとしていて、それをしゃべれる役者がいれば、それでいい。
山岡荘八の説経くさい天下国家話、あまりにも結果論的な歴史観や人間観、都合の悪い史実の強引な正当化などは、自分も好みではない。
ただこの人、英雄よりも英雄の近くにおかれた凡人の弱さを描くのがうまい。強国の狭間に翻弄される松平広忠、分に過ぎた野望を抱く大賀弥四郎、父に負けまいと力む武田勝頼とそれを諫める老臣の山県昌景と馬場信春など、限られた場面に登場する人々が、大急ぎの展開のなかに、画面外の人生を想像させる。
講談調の台詞の調子も耳に心地よく、あまりいじらずに残した小山内美江子の謙虚さが生きている。
二月十九日(水)「交響曲」綺譚
小学校から中学にかけて耽読したマンガの一つに、松本零士の「戦場まんがシリーズ」があった。一九七四年から七六年ごろである。
第二次世界大戦の日本やドイツの兵士を主人公とする一話完結の短編連作で、最初に読んだのは「少年サンデー」に掲載された、ロケット特攻機「桜花」の操縦士が主人公の『音速雷撃隊』だった。続いて小学館のコミックスを買って、他の作品にも夢中になった。
その第二巻『鉄の墓標』に、『戦場交響曲』という作品があった。
主人公は軍楽隊の兵士、砂津川良助。かれは《戦場交響曲》なる四楽章の大曲を前線で完成し、楽譜を肌身離さず、生還したら自ら指揮する夢を抱いている。戦場でこの男に出会った森山進は、砂津川がフルオーケストラの代りにトランペット一本で吹くこの曲を耳にする。
「しかし、その曲はなぜかおれの胸をうった………男の魂が、歯を食いしばって泣いているような曲だった…無念の涙を流しているような曲だった…」
ところが敵の投げた手榴弾の衝撃で、砂津川は鼓膜を破り、聴力を失う。
かれは森山にトランペットを吹かせ、口にくわえた銃剣を当てて、「わかる…音の振動がくちびるにつたわってくる」「耳が聞こえないベートーベンも、こうやって音をさぐって作曲した。耳が聞こえなくても、あの偉大な第九交響曲を作曲したんだ」と、自らを鼓舞する。
結局、砂津川は楽譜とともに戦場で行方不明。生還した森山は回想する。
「その曲はベートーベンよりも、チャイコフスキーよりも、シューベルトよりもおれの心をうつのだ……なぜならその曲は、砂津川が男の命をかけた交響曲だからだ……おれいがいの人にあの曲が聞こえないのが残念でならない…」
この「戦場まんがシリーズ」から、男のロマンとメカを描く漫画家として松本零士の人気は上昇し、アニメの『宇宙戦艦ヤマト』と『銀河鉄道999』の大ヒットでその名声は不動のものとなる。子供向けと見なされていたSFマンガやアニメに、いい年をした大学生や社会人も夢中になる、オタクの時代の始まり。
自分以外にも、同年代には似たような記憶をもつ人は少なくないはずだ。
さて、ここから本題。
佐村河内守の交響曲第一番につき、聴衆の一人としての立場から、いまの思いと反省を。
二〇一〇年四月四日の東京初演(長すぎるという演奏側の判断により、二楽章抜きの抜粋版)を聴いたときの自分の感想を読みなおして思うのは、音楽が第一といいながら自分も、物語、標題的なものに強くとらわれていること。
私は「演奏史譚」という言葉を用いるように、音楽などの芸術を楽しむ上で物語性を重視する立場だ。しかし、だからといって無批判に物語を信じるのではなく、その存在と介在に自覚的でなければならないと考えている。その意味で、佐村河内守の場合は演奏会に感動したあまり、物語への批判的な姿勢が不足したことは否めない。
ただ、その物語は大きなものではなくて、ごく個人的なものと思っていた。
当日の曲目解説に『ヒロシマの原爆をテーマとした「祈り」の音楽』と書かれてはいたけれども、作品を聴いたあとの感想として、内容とこの言葉に、さして深い結びつきはない、もっと個人的な音楽だと感じた。
本のタイトルと同様、副題なしにただ「交響曲第一番」であることに、大きな物語を避ける作者の節度と態度が表れているとも考えた。
神経症(プログラムによれば重度の抑鬱神経症に不安神経症、頭の中で絶えず轟音が鳴り続ける頭鳴症)を患っている人が、その「心の闇」を音にしたものと思ったのだ。
公開の場に数時間出るためには、その前に数日間にわたり、大量の薬を飲まなければならないほどに重症だとも、プログラムには書いてあった(リハーサルに出ないことの理由づけだったのかも)。
だから、構成が冗長でパッチワーク的なのも、迷いで堂々巡りをする心理を音にしたものだろうと、好意的に考えた。
また、他の名作と似たようなサウンドが出てくるのも、偉大な過去の遺産の集積と情報の洪水のなかに生きる、いまの自分たちの姿なのだろうと思った。
私は「心の病」になったことがない。だから独りよがりな想像でしかないが、「心の闇」とは、こんな感じなのかなと思ったのだ。
心の病に苦しむ人の多い時代、自分もいつそれにかかるかわからない時代に、ぴったりの曲だと感じた。全聾という、自分には想像のつかない状態の障碍ではなく、神経症が生んだ交響曲という点に共感し、最後の祈りと光明に感動した。
だが、すでに多くの人が突っ込みたくなっているだろうと思うが、ほんとうにそんな病に苦しむ人が、音楽など書けるのか。その病を音にしたいと思うのか。つらくて、書けないのではないか。
そこを自分は深く考えなかった。「メンヘルごっこ」と批判されてもしかたない段階で、満足してしまった。
だからこの曲を「中二病的」とか「四畳半的」と批判する方がいることも、今になればよくわかる。自虐的にいえば私は、むしろそうした要素にこそ、感銘を受けたのだ。自分のなかの中二病が、共振したのだともいえる。
ただ、作曲者は心の病に苦しんでいると信じていたから、この響きにウソはないと思っていた。私の知らない、本物の苦しみを音にして、聴かせてくれたものなのだろうと。
かれの本の方は、わざわざ読む気にはなれなかった。ただ、楽譜の書かれたクリーム色の表紙を見た一瞬、なつかしい『戦場交響曲』を三十年ぶりに思い出したことは、いまもおぼえている。
「佐村河内守」という存在をこうした個人的な安易な共感、「小さな物語」でとらえたままだったのは、私の過ちだった。CD発売以後、テレビ番組などでそれとは別の「大きな物語」がどんどんふくらんだことに、私は目を背けた。
障碍をもつ少女のヴァイオリニストとのこと。被災者の少女のこと。テレビ・ドキュメンタリー独特の物語づくりは嫌いだから、まったく見なかった。いまも見ていない。
《HIROSHIMA》という副題が誰の発案かは知らないが、それはCDが発売されたときについた。
CDの裏には、被災地らしき廃墟の写真がある。そして、録音のさなかに起きた東日本大震災。この二つが重なって、「佐村河内守」は大災害という「大きな物語」のなかのものになっていった。
一方で重度の神経症のことは、ほとんど話題にならなくなった。それに苦しんでいる様子は消えた。
「小さな物語」の交響曲などというものは、あり得ないのかも知れない。
ベートーヴェン以来、社会は交響曲に「大きな物語」を求める。このジャンルが衰退したのは、その重さに現代の作曲者が堪えかねるからかも知れない。
巨大性への幻想をもてたのは、マーラーあたりまでか。戦後のショスタコーヴィチは社会主義リアリズムなる「大きな物語」に応えるフリをしながら、「小さな物語」しか書かなかった(「大きな物語」の要求に見事応えたのは《森の歌》だが、それゆえ物語の破綻とともに、意味と光りを失った)。
いまは、まさに中二病的な、独善的な自己肥大としてしか、小を大に重ねることはできない。
今回の発覚により、この交響曲は「大きな物語」の虚妄から解放され、本来の位置を得るのかも知れない。
交響曲の『パノラマ島綺譚』。
作曲家に成りすました依頼者の中二病的な欲望を、本物の才能と職人的技術を持つ作曲家がフルオーケストラのパノラマにしたてた、まさに「中二病の夢」。
現代の日本にしか生まれ得ない、矮小にして巨大なる、畸形の「交響曲」。ハイカルチャーの大芸術ではない、サブカルとしての魅力を持つ「交響曲」。
こんなきれいにまとめるのはウソだ、都合のいい正当化だといわれるかも知れない。たぶん、そのとおり。
しかし私は、自らの中二病ゆえに、現代日本の一つの落し子であるこの「交響曲」を、深い共感をもって、愛しよう。
ただ、小さな物語にかまけて大きな物語から目を背けてはいけないということを、終生の教訓として。
二月二十日(木)もう一つの旅
トッパンホールにて、テノールのクリストフ・プレガルディエンのリート・リサイタル。
「別れ、そして旅立ち」と題して、シューベルトの歌曲を二十四曲。放浪、孤独、憧憬、夜、夢、風のわたる丘、月と星など、ロマンチックなキーワードに満ちた作品をつなぎ合わせ、一つの歌曲集のように再構成したもの。「もう一つの冬の旅」といえるのかも知れない。
このつながりのなかで、《魔王》のような独立したドラマも《ミューズの子》の明朗さも、すべて主人公の詩人の心象風景を映した曲のように互いに結ばれていくのが、まことに心地よい。
これはプレガルディエンとピアノのミヒャエル・ゲースによるプログラムで、二十二年前の一九九二年に、まったく同じ構成でCDを録音している。それ以来熟成を重ねてきたわけだ。
それにしても、人がこれだけあからさまにロマンチックでいられた時代というのは、とても幸福だったと思う。
二月二十二日(土)ハイドン風モーツァルト
紀尾井ホールで、ジョン・ネルソン指揮の紀尾井シンフォニエッタの演奏会。この団体のピリオド・アプローチは大好きだし、シュニトケの《ハイドン風モーツァルト》という愉しい曲を軸にハイドンとモーツァルトを演奏するプログラムも、じつにいい。
と思って聴いていたら、真後ろの席のモーストリークラシックの編集者さんから「これの演奏会評を書いてください」といきなりの依頼。喜んで引き受ける。
二月二十七日(木)春を告げるひと
サントリーホールで、ジャン=クリストフ・スピノジ指揮の新日本フィルの演奏会。楽しみにしていたもの。
前半が《カルメン》の合唱つき抜粋、後半はラヴェル三曲の合間にドビュッシーが二曲。
《カルメン》はサントリーホールが幻想の歌劇場に変ったかのような、鮮やかに躍動する演奏。合唱に細かく役割をふり、パートを分割して応唱させるなど、整然とした顔のない集団から、生き生きとさんざめく群衆に変える。オーケストラもそれに呼応して、有機的に各部が跳ね、対話する。
先日のカンブルランの「三次元のハロルド」といい、フランス人はサントリーホールを用いたシアターピース的演出が巧みなようだ。専門の役者を呼んでナレーションつきオラトリオにしたがりそうなドイツ人とか、セミステージの呪縛から逃れられなさそうなイタリア人とかと違って、ホールのつくりをそのまま活用して、ちょっとした工夫で自然なシアターピースにしてみせるのは、ベルリオーズ以来の伝統のなせる技なのか。
導入や経過句にかなり耳慣れないフレーズや音型が混じったのは、ミンコフスキが用いた版などに近いのだろうか。聴きふるした予定調和でない、かつてこの曲に感じた血湧き肉踊る興奮が甦るような、新鮮な音楽。これで全曲が聴いてみたいと思ったひとは少なくないはず(そういえばミンコフスキも都響に客演して《カルメン》の部分をやるはずだったのに、なくなったようだ。残念)。
後半のラヴェルとドビュッシーも、生命力にみちた演奏。少し前に聴いた、ツェートマイアーとパリ室内管弦楽団のラヴェル&ドビュッシーのディスクに通じるものがあった。
もちろん、フルオーケストラを統率する能力の限界か、たとえば《ボレロ》など、カンブルランが読響から引きだした精妙でカラフル、スリリングでセクスィーな響きと動きに較べると、はるかに荒っぽくて直線的。
だがそれも好き。《牧神の午後への前奏曲》を聴いているとき、前回二年前の客演で《新世界より》を聴いたときの印象を、このところ物忘れの激しい自分がそのままに思い出したのは、とても嬉しかった。
それは、スピノジが「春を告げるひと」だということ。
二年前の三月の《新世界より》に感じた、陽光と発芽と開花の生命の喜び、それが今日の《牧神》にもあった。
春が来る。オオカミではない。
来年も二月末にきてくれるそうで、今度はサン=サーンスの《オルガンつき》だとか。これもまた「春を告げる音楽」になりそうだ。
四年前に初めて客演して素晴らしいハイドン(思わぬアクシデントがあって、交響曲《事故》だったが……)を聴かせたときにはガラガラだった客席が、今日はほぼ満席。これも嬉しいこと。
二月二十八日(金)二つの「英雄」
昨日に続いてサントリーホール。今日は山田和樹指揮の読売日響。《英雄》と《英雄の生涯》。
スピノジと同じコルシカ島出身、やはりイタリア系の名前をもつフランスの英雄を意識して書かれた雄大な曲と、それを念頭において同じ変ホ長調で、巨大オーケストラを引き回す作曲家=指揮者がやや自己肥大気味に書いた曲との、ずいぶんと違う英雄像の、ありそうでない組合せ。
豊麗に、丸い輪郭でたっぷりと鳴らすヤマカズのスタイルは、《英雄の生涯》にじつに合っていた。終演後には、今日で退団する名ホルン奏者、山岸博にも喝采があつまっていた。
《英雄》の方は、一年半前にスクロヴァチェフスキが取りあげたとき、音符の隅々まで彫刻刀で彫りなおすように徹底した新即物主義風のシャープな輪郭がまだ残っていて、ヤマカズの感覚とずれている印象を受けた。
スクロヴァチェフスキが鮮やかにやってのけた葬送行進曲後半での運命動機の強調も再現されたが、もう一つ効果を上げずに終った。
三月一日(土)鎌倉と横浜
朝は音楽同攻会OB会の大先輩にお招きいただき、久しぶりの鎌倉見物。
横須賀線の北鎌倉駅で降りるのは、中学の校外学習で鎌倉史跡めぐりをしたとき以来の気がする。昔のまま、谷筋の細い地形に合わせた小さな駅。
円覚寺と東慶寺、北条時宗夫妻ゆかりの二寺を見学。谷(やつ)の地形に合わせてつくられ、最奥部の山際の斜面に墓地があるのが、千日谷や代々木狼谷などの葬場に似ているのが興味深い。
とりわけ東慶寺の歴代住持の墓は丸い卵形で、まさに「卵塔場」の名にふさわしいものだった。尼寺なのに文人や一高関係の墓が多いのも不思議。
円覚寺の舎利殿は国宝で、鎌倉唯一の室町時代(十五世紀)の建造物。戦乱の多い町だったため、鎌倉にはこれより古い建物は残っていないらしい。源氏政権のわずかな生き証人だった鶴岡八幡宮の大銀杏も四年前に倒れており、鎌倉時代そのままなのは大仏くらいなのだとか。
ところで鎌倉の寺院では、本堂などで室内楽のコンサートを定期的に開いているところも少なくないらしい。ならばそれをまとめて、目白近辺の教会を中心に六年前まで開かれていた、目白バ・ロック音楽祭みたいな古楽音楽祭を鎌倉で開催したらと、夢想してみたり。
昼食後解散して、一人で県道二十一号の谷間の道を歩く。建長寺の前をすぎ、鶴岡八幡宮へ。
途中の家並みに見覚えがあると思ったら、マンガの『とめはねっ!』で見たものだった。いまの自分の鎌倉のイメージは、これと『海街diary』、二つのマンガだけでほぼ出来ている(笑)。
鎌倉駅周辺で時間をつぶしてから、夜は横浜みなとみらいの小ホールで、現代音楽の演奏会「Just Composed」。
バリトン歌手の松平敬をメインに、ピアノ、ヴァイオリン、打楽器のアンサンブルで、川島素晴、中川俊郎、藤倉大、中ザワヒデキ、鶴見幸代、シャルパンティエ、ケージ、アイヴズ、池辺晋一郎、川上統という曲目。日本初演や編作初演も含まれる。
「声る」というテーマを掲げ、松平はプログラムに「声で様々なものを超えることにこだわってみました」と書いている。西洋近代音楽の「歌曲」の枠をこえた、十七世紀から二十一世紀にいたる、声による表現。
人間の声は言葉となって、意味をもてる。楽音と意味との二重存在。最初の川島素晴の《インヴェンション3c》は日常の言葉をわかりやすくパロディ化することで、声のもつ二重性で笑いを誘い、続く曲たちへの入り口となる。
そこからさまざまな響きを聴かせ、おしまいの川上統の《鼻行類について》では、鼻で歩行する架空の動物たち(ヨルハナアルキとか、トビハナアルキとか)の世界を歌い、その生態と動きが、言葉と擬音の複雑なからまりで表現される。
松平の高度な発声技能の万華鏡。
三月二日(日)中劇場と浅草
新国立劇場オペラ研修所公演《ナクソス島のアリアドネ》を、新国立劇場中劇場でみる。
春のオペラ研修所公演は、研修生がしっかりと稽古を重ねた舞台だけに良質な上演が多く、いつも楽しみにしている。今年は特によかった。
上演の成功には、中劇場の空間が大きく寄与している。ハコの大きさが作品に適切なことに加えて、ここは舞台の熱気と輝きが自然に客席にとどくからだ。
どういうわけなのか、同じ新国立劇場でもオペラ劇場の公演は、東条碩夫さんが指摘されているように、舞台にすきま風が吹くことが多くなってしまった。
あれだけ見やすく聴きやすく、豪華な舞台機構をもつ劇場で、歌手も指揮者もオーケストラもスタッフもちゃんとしているのに、全体としては、オペラならではの興奮や熱気があまり感じられない、とても残念な空間になっている。
原因など、部外者の私には想像もつかないが、たぶん、コヴェント・ガーデンにおけるショルティみたいな、強烈にして強力なキャラの芸術監督が劇場の心臓となって、建物と組織の隅々にまで熱い血を送りこんでやらないかぎり、治らない気がする。
ところが中劇場には、劇場空間のオーラが保たれている。ここでは「オペラの喜び」を味わえることが多いのだ。横に広い扇形の客席で内装も簡素、その意味ではけっして「贅沢な空間」ではないのに、貸し小屋の冷たさではない、生きた劇場の温もりがある。あえていってしまえば、ここには「オペラの神」が棲んでいる。
その音響をデッドだと批判する人もいるが、歌劇場はコンサートホールとちがって、歌を明確に聴きとらせるためには残響が少ない方がいいし、デッドでも聴きとれる適切な広さの空間だから、これでよいのだと思う。
この利点をうまく活用して、歌のアンサンブルが明快に、立体的に響いたことで、作品の素晴らしさがいっそう際立った。歌手では特に、作曲家役の今野沙知恵が素晴らしかった。キィキィと叫んでばかりで、ヒステリックで独善的に感じることの多いこの人物を、叫ばずにきちんと歌うことで、この役が知性と豊かな創造の才と、そして愛すべき純粋さの持ち主であると実感させてくれた。
そして、R・シュトラウスが三十六人と人数を指定したオーケストラにとっても、この空間はちょうどよい。
うまいことに、二日前にヤマカズによる極大編成の《英雄の生涯》を聴いていたおかげで、同じ作曲家が十四年後に対照的な少人数でつくりだした響きのマジックの凄さを、あらためて実感できた。
正直にいうと、三浦安浩の演出は幕が開くまで不安だった。これまで見た作品で、なくてもいいような下品な身ぶりの頻用を不快に感じることが多かったからで、今回は題材がバックステージ物だけに、危惧が大きかった。
ところが、意外にもといっては失礼だが、一部を除けば素直にその舞台を楽しむことができた。テノール歌手が女たらしなのは予想通りだったが、かれ以外の不快な描写は抑制され、それぞれの性格づけも、回り舞台による装置転換も、とても納得できるものだった。舞台と舞台裏、まじめとふまじめなど、作品自体が初めから両者の併存をみとめていることがよかったのかも知れない。
最後、アリアドネとバッカスが踏み出した夜空に星が輝くと思いきや、それが劇場のシャンデリアだったのは、表裏の皮膜をうまく表して美しかった。
それにしてもこの作品、次の『帝都クラシック探訪』のために、浅草興行街の歴史をにわか勉強でつめこんでいる最中なので、シリアスなオペラにコメディア・デラルテが主君の希望でつめこまれる展開が、まるで浅草の舞台興行の歴史みたいだ、と考えたりする。
ローシーのまじめな帝劇オペラが、お客の希望で変質して浅草のオペラもどきに変り、さらに震災後にカジノ・フォーリーのレビューへ、ついには戦後のストリップに変る、という日本音楽劇の歴史を重ねる、なんて妄想。
プリマドンナは原信子、ツェルビネッタは梅園龍子、コメディアンたちにはエノケンやロッパやシミキンがいて。作曲家はあえて作家にずらして《葛飾情話》の永井荷風。
ポイントは、テノール歌手を田谷力三ではなく、藤原義江にすること。藤原は浅草と本格的オペラ運動のつなぎ目になった人だから、そうすれば、作品の最後でオペラがオペラとして盛りあがることの理由づけができるだろう。
また谷崎潤一郎、川端康成、高見順、色川武大と、浅草興行街を舞台にした作品を大正から戦後へ、代替りするように書いた作家たちも、舞台裏を出入りする(一九六〇~八〇年代には、その舞台が新宿へ移る。九〇年代は渋谷か)。
三月七日(金)吉村渓さんの訃報
音楽評論家として、NHK・FMの海外音楽番組などでも活躍された吉村渓さんが二月二十六日に亡くなられたとの訃報。学年は違うが、同じ一九六三年生れとして勝手に親近感を抱いてきたので、とても残念。ご冥福を祈る。
三月八日(土)インバルの千人
東京芸術劇場で、インバル指揮東京都交響楽団ほかによる、マーラーの交響曲第八番「千人の交響曲」。
独唱に合唱、パイプオルガンに客席二階のバンダなど、極大編成の作品がインバルのタクトの下、精緻に鳴り響く。テノール独唱の福井敬の声の力と安定感が素晴らしく、全体を引き締めていた。
マーラーはこれだけの編成でも独唱を消さないようにバランスを整えて書いていて、次作《大地の歌》前半の、独唱をかき消すオーケストラの強奏は、やはりわざとなのだとあらためて思う。
このホールのオルガンは改修後、反響板に隠されるようになったので、実際に目にするのは久しぶり。アール・デコ風の外観がマーラーにぴったりなのに感心した。知らなかったが、ここのオルガンのケースは回転式で、曲目の時代にあわせて雰囲気を変える方式なのだそうだ。お金がかかっている。ホールにパイプオルガンがあるのが珍しくない時代になって、さらに付加価値を求めたのだろう。
この曲をナマで聴くのは三十二年ぶりで、前は一九八一年東京文化会館での渡邉暁雄指揮日本フィル、その翌年の早稲田大学記念会堂での岩城宏之指揮早稲田大学交響楽団の二つ。どちらもパイプオルガンのないホールだったのは、まさに隔世の感。
三月十日(月)酒仙投手西村幸生
三重県伊勢市で行なわれたプロ野球オープン戦で、今季創設八十周年を迎える巨人軍と、来季が八十年となる阪神タイガースが、両球団の伊勢市出身のOBにちなんで、巨人が沢村栄治の14番、阪神が西村幸生の19番の背番号を全選手がつけてプレーしたという。
阪神の西村幸生。プロ野球歴は戦前にたった三年しかないにもかかわらず、その強さと、主戦投手ならぬ「酒仙投手」のあだ名で球団史に残る快男児。
その名は自分にとってもなつかしい。もちろん、プレー姿など知るよしもないのだが、中学生のときに読んだ野球雑誌に載っていた短く爽快な評伝で、その存在を知った。
たしか寺内大吉が書いたもので、巨人ファンだから西村は仇役なのに、愛情のこもった、いい文章だった。仲の悪い監督への腹いせに、わざとスリーボールにしてから三振にとるとか、わざと満塁にしてから無得点で切り抜けるとか、たしかそんなことが書いてあったはず。どこまでホントかはともかく、短い絶頂期の傲慢なまでの強さ。
(マンガ『野球狂の詩』の酒仙投手、日ノ本盛にこういうモデルがいたことも、それで知った)
あの一文、また読んでみたいが、こういう短文は、探すのが難しい。
沢村も西村も、同時期に活躍した景浦將も、みな出征して南方で戦死。
三月十一日(金)万世橋駅と新橋停車場、その遺香
震災から三年。
来週の「帝都クラシック探訪」の本所・浅草篇にそなえて下見ののち、時間があまったので、銀座線で神田と新橋へ。
上野篇に書いたことだが、銀座線というのは戦前の下町=南北と、戦後の山の手=東西の繁華街ラインを結ぶ、面白い地下鉄。まずは浅草~上野~神田~日本橋~銀座~新橋と、江戸期から戦前までの南北のライン。そこで方向を転じて、赤坂~青山~渋谷と、戦後の東西のライン上の繁華街を走る。東京という都市の変化を端的に象徴するこの変針を画策したのが、東急の総帥五島慶太だというのがとても面白い。
話を戻して、神田と新橋は、戦前まで主流をなした、南北のライン上の駅。その歴史性を反映するように、明治・大正期の国鉄の重要な、しかし後にその重要性を奪われた駅が近くにある。
万世橋駅と旧新橋駅(汐留駅)で、それぞれに遺構が再現されているのだが、未見だったのでこの機会に見学。
万世橋は、大正初期の東京で、最も繁華な駅前の一つだったことで知られている。一九一二(明治四十五)年から七年間、ここが今の中央線の起終点となっていたことと、近くの須田町が当時の都市交通の大動脈だった路面電車の、主要な乗換地点だったためである。辰野金吾設計の赤煉瓦造りの豪華な駅舎があり、駅前には広瀬中佐の銅像が建っていた。
しかし一九一九年に中央線がようやく東京駅まで伸びると、途中駅になった万世橋駅は乗降客が減り、関東大震災で初代の駅舎も焼失。最終的に一九四三年に運用を休止した。その後はホームだけになっていたのだが、駅舎跡地の交通博物館の閉館を受けて、昨年、新たな商業施設に生れかわった。
訪れてみると、駅舎や駅前広場が再現されたわけではなく、ホームの一部に上がれるだけだから、往時の様子をうかがうには、かなりの知識と想像力がいる。
その意味では面白みがない。しかし、百年前の一九一二年開業時の、地上とホームを結ぶコンクリートの階段を自分の足で踏みしめることができるのには、何ともいえない歴史の重みを感じた。
再び銀座線の神田駅に戻るが、須田町交差点と駅を結ぶ長い地下通路にあったレトロな雰囲気の床屋や帽子屋が、再開発で消えていた。残念。
続いて新橋。汐留駅跡地に建つ汐留シオサイトのなかに、一八七二(明治五)年開業時の駅舎を復元した旧新橋停車場がある。二〇〇三年にできたそうだが、来たことがなかった。
こちらは万世橋駅と対照的な発想で、駅舎やホームの一部が原寸大で復元されている。『八重の桜』にも登場した。
ここが面白いのは、遺構の真上にかさ上げして建てられていて、地下の遺構の一部が見えるようになっていること。
万世橋駅と違って遺構に直接触れることはできないが、往時そっくりの建物を歩き回ることができる。
歴史的な建物というと、以前は現存する建物を他の場所に(明治村とか江戸東京たてもの園とか)まとめて移築保存するのが主流だった。現在はいったん失われたものを、元の場所に復元なり復原なりして、再開発のランドマークにする事例が増えている。
この旧新橋停車場のほか、東京駅や三菱一号館がそうだし、浅草の松屋百貨店も外装を一九三一年開店時の状態に戻した。赤坂プリンスホテル跡地の旧李王家邸も、ホテル以前の姿に復原して活用されるという。
一時期流行した、外壁だけを残して高層ビルに貼りつけておく悪名高き「デスマスク」方式よりは、この方がはるかにいい。
さて旧新橋停車場、東京駅が完成する一九一四年までの四十二年間、つまり明治時代を通じて、帝都の南の玄関口、新橋駅といえばここのことだった。
現在の駅よりも中央通りに近い。神田から南下してきたメイン・ストリートがこの芝口で駅につながり、鉄道で横浜の港へ、さらには船で世界へ。古い南北のラインが世界に通じていたことは、この駅の位置でこそ実感できる気がする(ちなみに戦後型の東西のラインは、新しい東京港から世界に開けるというのが、木村荘八の説)。
それから、知人のSPマニアにすき焼『今朝』の五代目のご主人がおられる。歩いてみると、この店が旧新橋停車場のすぐ近くにあることがよくわかる。駅の八年後の一八九〇年開業、まさにハイカラな地域の牛鍋屋だったわけだ。
三月十二日(水)ペトレンコ(一)
ヴァシリー・ペトレンコ指揮オスロ・フィルを東京芸術劇場で聴く。
この指揮者はCDで聴くばかりだったが、ようやくナマを聴けた。
・ニールセン:歌劇《仮面舞踏会》序曲、グリーグ:ピアノ協奏曲(独奏:アリス=紗良・オット)
・ショスタコーヴィチ:交響曲第五番
特にショスタコーヴィチが鋭利で力強い響きと緊張感で素晴らしかった。ナクソスでロイヤル・リヴァプール・フィルと進行中の全集の好印象を裏切らないもの。オスロ・フィルでの今後も楽しみ。
三月十三日(木)ペトレンコ(二)
ペトレンコ指揮オスロ・フィル、今日の名古屋公演を聴かれた大学時代の先輩から、嬉しいニュース。
ペトレンコはまた来年一月に、もう一つの手兵ロイヤル・リヴァプール・フィルと来日する。名古屋ではなんとショスタコーヴィチの十番、タコ十をやるという。
しかも、もうチケットを売っているというのが驚き。鬼が笑うどこの騒ぎじゃない、しゃちほこの国。東京も楽しみ。
三月十四日(金)松井源水とは違うぞ
ウィスペルウェイのチェロ・リサイタルをトッパンホールで聴く。ピアノは名コンビのジャコメッティ。
・ブラームス:クラリネット・ソナタ第二番、プーランク:チェロ・ソナタ
・ドビュッシー:チェロ・ソナタ、シューベルト(ウィスペルウェイ編):幻想曲(原曲:ピアノとヴァイオリンのための幻想曲ハ長調)
最愛の曲の一つである、シューベルトのヴァイオリンとピアノのための幻想曲のチェロ版が聴きたくて、同時刻の紀尾井のシフのリサイタルをあきらめたが、悔いのない大正解。ウィスペルウェイはこの曲を二〇〇九年のシューベルト作品集ですでに録音していて、ジャコメッティのフォルテピアノとともに見事な演奏が聴けるが、ナマはまた格別。
雄弁、アート・オブ・ユーベン。チェロの雄弁術。プーランクやドビュッシーのソナタをこんなによくしゃべる音楽にできるのはこの人くらいだろうが、最後の幻想曲はそれを超えた。
ショパンが「第二のパガニーニ」と名づけたという技巧派ヴァイオリニストのために、シューベルトが腕によりをかけて書いた曲を、自ら編曲してチェロでひいてのける超絶技巧。
こうすることで、ベートーヴェンの死を意識して書いた、シューベルトの全作品のなかで最もベートーヴェン的なスタイルが、いっそう明快になる。つまり、趣向をこらした変奏曲の面白さと、終曲直前の暗から明への力強い転換と凱歌。
かつてあらえびすは、大仰な言葉で派手に前宣伝されたフォイアマンの超絶技巧を、「松井源水の独楽廻し」のような曲芸かと危惧しながら実演を聴いたら、その気魄と情熱に「これは松井源水とは違うぞ」と思ったそうだ。
ウィスペルウェイのシューベルトもまさしく、曲芸と芸術のきわどい接点で、高らかに奏でられる音楽。ジャコメッティのピアノも素晴らしかった。CDでのフォテピアノと違って普通のモダン・ピアノだが、絶妙のコントロール。
と書いて、思えば松井源水も江戸から何代も続いた浅草の曲芸師。
「帝都クラシック探訪」の取材が終るまで、思いがいきつくのはすべて浅草。わが夢の街…?
三月十五日(土)ラザレフ
ラザレフ指揮日本フィルをサントリーホールで聴く。
・スクリャービン:ピアノ協奏曲(独奏:浜野与志男)
・ショスタコーヴィチ:交響曲第七番《レニングラード》
若いペトレンコとはまた異なる、骨太で大迫力の《レニングラード》。
三月十七日(月)インバル
インバル指揮東京都交響楽団のマーラー:交響曲九番をサントリーホールで。
インバルらしく感情移入をしない、精緻で整然としたマラ九。番号順に進んできた新マーラー・チクルス、このあと夏に第十番(クック版)がある。
三月十八日(火)浅草、ニュー浅草
春一番の吹き荒れるなか、「帝都クラシック探訪」の本所・浅草篇の取材。
鈴木淳史さんとアルテスの木村さん、桑野さんのお二人にお付き合いいただいて、「本所七不思議」の錦糸町からスカイツリーをへて浅草へ。昭和の商店街をそのまま地下に埋めたような浅草地下商店街やら六区興行街あと(R・シュトラウスのサロメ日本初演の地含む)やら、詳細は掲載時のお楽しみ。
しかし今日一番の発見は、貧乏学生が高田馬場や市ヶ谷などで一度はお世話になっている飲み屋、「ニュー浅草」の本店を発見したことかもしれない。「本当に浅草にあったんだ! この名前で!」というわけで、打ち上げはそこにしたたが、やはりとても安かった(笑)。
三月二十二日(土)ハリウッドより
クリスチャン・ヤルヴィ指揮の読売日本交響楽団を東京芸術劇場で。
・ジーン・プリッツカー:「クラウド・アトラス」交響曲から四~六楽章(日本初演)、コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲(独奏:パク・ヘユン)、
・ブラームス(シェーンベルク編):ピアノ四重奏曲第一番(管弦楽版)
テーマはハリウッド=ロスアンジェルスとでもいうのか、ハリウッド映画の音楽を組曲にしたもの、ヴァイオリン協奏曲にしたてたもの、そしてロスにいたシェーンベルクが編曲してクレンペラーが初演を指揮した作品と、弟ヤルヴィが育った西海岸にちなむ音楽。
故郷喪失者の音楽、ともいえるのかも知れない。いろんな、ほんとうにいろんな意味で。
弟ヤルヴィの軽めのフレージングは好きなのだが、響きが雑然ともっさり、安っぽい感じの音楽になったのは残念。
でも、芸術音楽と商業音楽、必ずしも二律背反ではないのにそうなりやすい近代のオーケストラ音楽の問題と、その発信源の一つとなってきたハリウッドという場所を、あらためて考えさせてくれる選曲は、とても面白かった。
特に一九七一年生れのプリッツカー、ヤルヴィ同様に旧共産圏から渡米した音楽家だそうだが、これはミニマル風の、しかしさっぱり面白みのない音楽。
交響曲といっても、ただの映画音楽の組曲。つまりはサブカル的な意味の「交響曲」で、このあたりは「佐村河内守の交響曲第一番」とならべたくなるが、どう考えても後者の方が、音楽によほどキャッチーな魅力があるねと、隣席の鈴木淳史さんと話す。
そしてその源流となった、コルンゴルトとシェーンベルク。
コルンゴルトはいま新国立劇場で《死の都》を上演しているし、交響曲も五月に都響が演奏するし、「東京・春・音楽祭」にもその作品だけをあつめたレクチャーつき演奏会があるし、記念年でもないのにその話題性は、生誕百五十年のR・シュトラウスよりも、日本では上のような気がするのは、なぜ。
三月二十三日(日)駅伝シュトラウス
今日は「東京におけるコルンゴルトにはさまれたR・シュトラウスの日」。
いや、長たらしいのは当方の勝手な都合。「東京・春・音楽祭」の一環で、東京文化会館小ホールでその生涯をふり返るマラソン・コンサート。朝十一時から二十時過ぎまで、五つの演奏会。
昼にも《イノック・アーデン》とか聴いてみたいものがあったが、自分はしぼって十九時からの第五部「辞世のうた‐去りゆく古き良きヨーロッパ」のみ。マラソンではなく勝手に駅伝。
偏愛するのにナマで聴いたことがなかった《メタモルフォーゼン》が目当て。
作曲者の指定は弦楽二十三人だが、ここではレオポルド編曲により、ウェールズ弦楽四重奏団を中心とする七人の縮小版。この編成だと、初めの方が《カプリッチョ》の六重奏に似ていることが露わになるが、やがて、メタモルフォーゼンでしかありえない響きへと、見事にメタモルフォーゼンしていく。
最後近くでコントラバスが、元ネタの《エロイカ》の葬送行進曲を初めてむき出しにひくところ、やはり素敵。スクロヴァチェフスキ&読響の《エロイカ》葬送行進曲後半で、ホルンが運命動機をむき出しに歌うアイディアは、おそらくこれがヒントになっているのだろう。
後半は《四つの最後の歌》など。開演前にお会いした吉田真さんに、「室伏博行さんに最後にあったのは、ちょうど一年前のマラソン・コンサートのときだった」とうかがったこともあって、《四つの最後の歌》を愛された室伏さんのことを思い出しながら聴く。
正直なところ、ピアノだけの伴奏よりもピアノ・トリオなどの編曲があれば、オーケストラ伴奏の響きの雰囲気をもっと出せたかも、と思ったが……。
おしまいは、作曲家の埋葬のときに歌われた《ばらの騎士》の三重唱。失われゆく時代への挽歌。
三月二十四日(月)死の都、生の時
昼は新国立劇場で《死の都》。
主役パウルを歌うケルルが立派。幕切れで歌った〈マリエッタの歌〉のメロディがずっと耳に残る。
キズリンクの指揮は活力と艶に不足して、ダルな印象。
カスパー・ホルテン演出の舞台も、不満が残るもの。亡き妻が、生身の役者が演じる幻影として出ずっぱりなのは、自分はあまり面白いとは思わないけれど、一つのアイディアではある。
しかし、最初から最後まで中央にベッドがあるのは、夢オチのネタ割れでつまらない。シャッターや壁が動いたり割れたりして、その向うが見えたりはするものの、一切は部屋のなかで進行する。本人の夢にすぎないからなのだろうが、オペラとしてワクワクしない。
自分の感覚では、睡眠時の夢はどんなに話や規模が荒唐無稽でも、見ている瞬間には一定の真実味がある。その空間がどんなに歪んでいても、書き割りのように裏がなくても、自分が意識する部分にだけはたしかな触感があり、どんな奥行きも高さも広がりも、自分があると感じたその瞬間に生れるのだ。そのことが、この舞台では否定されている。
第二幕で運河、つまりブルージュの澱んだ荒廃を象徴するもの(『ヴェニスに死す』の疫病の都ヴェネツィアの先駆として)が出てくるのに、前後と同じ室内のまま。全幕を一気に上演するならともかく、休憩つきでこれではつまらない。
先日ゲネプロを見た二期会の《ドン・カルロ》もそうだが、初めから終りまで単一のセットを用いる「一杯飾り」は、登場人物を囲む閉塞状況を表すといえば聞こえはいいけれど、オペラという異世界の時空に接する喜びを半減させる。
場面転換に制約のある特殊なホールでの上演だとか、予算が足りないとか、そういう公演ならともかく、新国立劇場のオペラ劇場ほどの舞台機構なら、もっと想像力を刺激するプロダクションを借りてきてほしいと思った。
夜は片山杜秀さんと新宿でサシ。
まずはクリミア状勢の話から、冷戦終結後ほぼ四半世紀をへて、意外にも勝者と敗者が逆転しつつあること、全面核戦争の現実味が薄れ、金融経済から資源重視の現物主義に移るにつれて、帝国主義時代みたいな古い地政学の論理が復活しつつあること、いきなり世界がこんなにキナ臭くなってしまったことへの驚き、など。
つづいて片山さんのご著書『クラシックの核心』の表紙話。河出書房のムック『文藝別冊』シリーズ掲載の談話をまとめたもので、メジャーな作曲家、演奏家について、さらにそれをサカナにご自身の音楽体験について饒舌に語りまくる片山節を堪能できる一冊で、中身は本当に素晴らしいのだけれど、驚くのが表紙。
昔の廉価盤のドイツ名序曲集とかを想わせる安っぽさなのだ。その内容とも、これまでの片山本ともあまりに異質でかえって印象に残るこの表紙、書店で目にしたときは呆然となったのだが、ご本人も初めて知ったときはやはり固まったそうだ(笑)。
途中まで別のデザイン案だったのに、突然、担当編集者がこれに変えたというから、わざと仕掛けたらしい。その担当者、被差別民の研究で有名な塩見鮮一郎の著作も一手に引き受けている人なのだそうで、いい意味でかなりの曲者。「昔のソノシートのジャケみたいだっていってる人いました」といったら、片山さんバカ受け。
ところでこの本、片山さんの日本では初のハードカバー本なのだとか。日本ではとはどういう意味ですときくと、『未完のファシズム』のハングル版があるのだそう。あの本が韓国で出ているというのは、とても面白い。
佐村河内の話もする。これは二月十九日付の可変日記に私が書いたことなど。
片山さんが慶應の先生になられてから大変なご多忙になったこともあり、サシで飲んだのは五、六年ぶり。しかし以前同様、「この世に生れてきてよかったなあ」と思える、贅沢な時間。
三月二十六日(水)二人フィガロ
小澤征爾音楽塾の《フィガロの結婚》を東京文化会館で。
指揮を小澤征爾とテッド・テイラーが分担する。冒頭からしばらくを小澤が振り、テイラーはレチタティーヴォのチェンバロをひいているが、やがて小澤は下手の舞台袖にひっこみ、テイラーが指揮を代る。テイラーがチェンバロをひいているときに小澤が入場、再び指揮台へ、という方式。
オーケストラの響きは、さすがに小澤が指揮したときにピンと張りが出る。しかし歌手のオペラ的な呼吸は、テイラーのときのほうが伸びやかになるのが面白かった。
昨年CDで出た、ムーティ指揮のメルカダンテのオペラ、《二人のフィガロ》を思い出す。あれはケルビーノがフィガロを名乗る、という話だったが。
三月二十八日(金)三木稔の《春琴抄》
日本オペラ協会の歌劇《春琴抄》を新国立劇場中劇場で。
一九七五年初演の三木稔の最初のオペラで、二十世紀中は再演も多かったが、今世紀は三木が一昨年に没するまで、新作の発表に力を注いだこともあってか、久しぶりの上演という。
オペラとしてはやや平板に感じられたけれど、ヒロイン春琴が三絃(三味線)の師匠という役どころだけに、通常のオーケストラに邦楽器の三絃と二十絃箏を加え、独奏楽器として活躍させたのがききものだった。
三月二十九日(土)肌色、東京交響楽団
銀座線や山手線で、昔の黄や緑のカラーリングを再現した車両が増えたが、東武東上線も開業百年を記念して肌色電車を復活させるというニュース。
すっかり忘れていたが、東武はたしかにむかし「肌色」だった。一九八五年まで使われていたというから、エアコンがない時代の車両だ。
真夏にエアコンなしでラッシュの地下鉄に乗るなど、現代では想像しにくい、したくない情景だが、大学時代の八〇年代前半はエアコンありとなしの車両が混在していたし、日比谷線の恵比寿や六本木などホームに冷房がなく、頭上で羽根が蒸れた空気を回すだけの駅もあった。
復活版はピカピカのきれいなクリーム色だが、オリジナルは色あせてつやのない、正直さえない「肌色」だった。
しかし、乗り入れの関係で東急と営団と東武と三社の車両が走っていた日比谷線では、色はダサいが、腰掛けの奥行きの広さなどから、東武がじつはいちばん乗り心地がいいといわれていた。
そうはいっても、末期はこの色が見えるとエアコンなしだとすぐわかるので、乗るのを避けていた。その点、大井町線などのイモムシ(自分は青ガエルと呼んだ記憶がない)と同じ。
午後はサントリーホールにてスダーン指揮東京交響楽団。二〇〇四年に就任した音楽監督として、東京最後の演奏会。
ベートーヴェンの《皇帝》協奏曲(オピッツ独奏)とシューベルトの交響曲第二番というプロで、これは二〇〇五年にもアファナシエフを独奏にやった選曲だそうだが、隣席の舩木さんによると、そのときはシューベルト~ベートーヴェンという順番だったとか。
いずれにしても、スダーンは作曲年代の近いこの二曲の組合せに、何か必然性や理由を見出しているのだろうが、自分にはよくわからなかった。十七歳のシューベルトがつくった交響曲第二番はスダーンの十八番だけに、曲の天才性を思い知らせてくれるもの。あまり知られてない曲だけど、とても面白い。ハイドンの九〇番台に似た、合奏協奏曲的な独奏の扱いもある。
シューベルトの交響曲の面白さ、とりわけ《未完成》と《グレート》以外の曲の面白さは、ピリオド・スタイルが採り入れられたことで初めて、広く知られたのではないか。日本のオーケストラ運動において、ここでスダーンが果たした役割は大きい。
一方《皇帝》は、なぜかナマで聴くといつも退屈する曲だが、今日もやはり、まったく面白くない。ベートーヴェンが中期で協奏曲の作曲をやめたのは、必然のことだったのかとか、そんなことばかり考えて聴いていた。
シューベルトの天才性に見合うベートーヴェンのピアノ協奏曲は、やはり初期の、第二番や第一番なのではないか。古典派の枠のなかにありながらそれを突き抜けようとしているこの時期の方が、素直に楽しめる気がする。
なぜ《皇帝》がナマではつまらないのか、理由は即断できないけれど、こういうときにグールド&ストコフスキーのあの演奏、「諸君、エロイカのテンポで」というあの録音をあらためて聴きなおすと、何か視野が開けるのかも知れない。
二十世紀半ば、モダン楽器が「響きすぎる」ことにほとんどの人が疑いを抱かなかったときに、早くもそれに疑問を呈したグールドの美意識は素晴らしい。当時のアメリカでは、チャイコフスキーやラフマニノフと同じ感覚で《皇帝》を巨大ホールで演奏するのが、当り前だったはずなのだ。
アンコールは予想通り《ロザムンデ》間奏曲。ただし演奏前に、二十六日に急逝した東響のチェロ奏者、井伊準さんの思い出に捧げる旨を、指揮者がスピーチした。何もなければこの日の舞台にもいたはずという井伊さん、若すぎる。ご冥福を祈る。
三月三十日(日)ブロック経済の音楽
今日はダブルヘッダー。オペラシティでの「メキシコ音楽の祭典」オーケストラ・コンサートと、東京文化会館小ホールでの藍川由美「日本のうた編年体コンサート」第十二回。
たまたま同じ日にあるだけでメキシコと日本の音楽、内容は無関係と思っていたが、聴いてみたらじつは密接に関連していた。こういう驚きは、ほんとうに愉しい。
まずは午後二時から「メキシコ音楽の祭典」オーケストラ・コンサート。
今年は支倉常長がメキシコに上陸して四百年目にあたることから、「日メキシコ交流年」。その一環で開催された。
ホセ・アレアン指揮東京フィル、ヴァイオリンのアドリアン・ユストゥスとピアノのゴンサロ・グティエレスの出演。
曲はレブエルタス:センセマヤ、ポンセ:ヴァイオリン協奏曲、日本初演のチャベス:ピアノ協奏曲、レブエルタス:マヤ族の夜。
メキシコのクラシック音楽を代表する三人の作曲家の作品だが、今日の曲で判断するかぎり、レブエルタスが傑出した天才。ポンセとチャベスは、演奏家には申し訳ないことながら、聴いているうちに何度も意識を失ってしまったが、レブエルタスは鮮烈で強い芳香を放つ、独自の響きの魅力をもち、とても寝るどころではなかった。
短い《センセマヤ》には《春の祭典》のエコーがある。その響きを消化して独自のものとし、そして、バーンスタインの《ウエスト・サイド物語》のオーケストレーションの元ネタになっている。
この《ウエスト・サイド物語》への影響は、おしまいの《マヤ族の夜》でも顕著だった。もちろん、《ウエスト・サイド物語》のオーケストレーションはバーンスタイン本人ではなくアーウィン・コスタルとシド・ラミンだから、直接にはこの二人がレブエルタスを参考にしているのだろうが、バーンスタインも《センセマヤ》の録音を残しているから、まるで無関係とは思えない。
こんなことから、南北アメリカの音楽の関係を思いながらプログラムの浜田滋郎さんによる曲目解説を読んでいたら、気づいたことがひとつ。
今日の四曲とも、作曲年代が近い。オーケストラ曲の作曲は大仕事だから、霊感にまかせてつくるのではなく、演奏してくれるアテがあって書かれるはず。それが近い。レブエルタスは一九三七~三九年、ポンセが一九四三年、チャベスは一九四二年。
そしてチャベスの曲は、アメリカのグッゲンハイム財団が委嘱し、一九四二年一月にカーネギーホールで、ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィルが初演したという。
欧州と極東の国家間の対立が激化し、戦争になっていく時代に、メキシコではオーケストラ曲が書かれ、その一つにアメリカが金を出してやっている。
戦火のなか、平和を維持する南北アメリカ両大陸。想像にすぎないが、当時のアメリカ大陸のブロック経済が、これらの作品の背景にあるのではないか。
先日片山さんと飲んだとき、アメリカが政治経済の両面で衰退するのにともない、次の共和党政権は十九世紀のモンロー主義に戻って、アメリカ大陸に閉じこもる可能性があると教えてもらった。
一九三〇年代、世界恐慌を契機に生れた、ブロック経済の復活である。
するとアメリカは古くて新しい、対外問題であると同時に国内問題でもある、ヒスパニックの存在とまた正面から向き合うことになりますね、などと話したのだが、今日のメキシコ管弦楽曲は、まさにかつてのブロック経済の時代に生れているわけだ。
さらにいえば、コープランドが《エル・サロン・メヒコ》を書くのが一九三六年。ニューヨークでザビア・クガートなどカリブ海のラテン音楽、ルンバやマンボが流行りだすのが、三〇年代から四〇年代にかけて。
偶然かも知れないが、アメリカの音楽界にラテン音楽が大きく採り入れられだすのは、まさに南北アメリカがブロック経済で強く結ばれた時期なのだ。経済と文化の密接な連繋。
そしてバーンスタインは、そのころに成人している。かれには、ラテン音楽が新鮮な生命力にあふれた、まさに新時代の息吹に感じられたのではないか。
などと面白がりながら、上野に移動して、夜七時から藍川由美「日本のうた編年体コンサート」第十二回。
藍川さんが歌い、片山さんが企画構成・解説をつとめるこのシリーズ、編年体の名のとおり、よくある列伝的な作曲家単位ではなく、同時代のさまざまな作品が並列されるのが面白い。
今日は文部省日本國民歌(一九三九)と、日本放送協會國民歌謡(一九三六~四一)がテーマ。
つまり、今度は日本のブロック経済の時代の歌だったのだ。
文部省が上から押しつけて失敗した日本國民歌や、放送軍歌の《南京空爆》、大ヒットした《暁に祈る》《紀元二千六百年》など、ほかではまず聴けない歌と耳になじんだ歌が、同時代という理由でならぶ面白さ。日本版のブロック経済、大東亜共栄圏を象徴する、《南進男兒の歌》なんてのもある。
そしておしまいに、金井喜久子が採譜し編曲した、琉球民謡が琉球語で歌われた。
片山さんの解説によると、琉球音楽などはそれ以前の日本では未開の音楽として、価値を絶対に認められないものだった。しかし、南進論の中継点として沖縄への関心が高まったことが、その文化の独自性への評価も高めることになる。
上から目線で、中央だけでなく辺境の文化の価値も認めてやろうじゃないか、ということになっていく。金井が公表した琉球民謡の歌詞が標準語になっていたり、両者がまじったりしているのは、中央への微妙な意識の表れであるらしい。
このあたり、アメリカとラテン文化の関係も同じ、という気がする。
ブロック経済が生みだす、辺境文化への一定の評価。ソ連でも、アルメニアの民族音楽をとりいれたハチャトゥリアンが活躍したり。一九四〇年前後の、世界の一つの潮流。
いままた、ブロック経済の地政学に逆戻りしそうな現代の世界のなかで、こうした音楽を聴く。
ドゥダメルの存在などは、どのような位置づけになるのだろう。あるいはアジア志向のAKBは、現代の日本版ブロック経済歌謡を目指して、挫折しかけているものなのか?
四月七日(月)アルベリヒの呪い
景気がよくなったのか、サービス業での若年層の人手不足が深刻らしい。行きつけの美容院でも、若い美容師が集まらなくて困っているという。
超高齢化、少子化社会の歪みがいよいよ表面化してきたのか。突然、いくつかの企業が正社員化を進めだしたのは、ある種の囲い込みなのか。
移民を導入せよという意見もあるけれど、大規模な移民は日本の場合、将来的には「ローマ帝国の滅亡」の引き金を引くことになる気もする。それでも、誰も逆らい得ない、歴史の必然ということなのかも知れないが。
夜は「東京・春・音楽祭」の《ラインの黄金》。一昨日の初日の大評判を聞いて楽しみにしていたが、期待が大きすぎたようでもう一つ。《ラインの黄金》というより、楽劇《アルベリヒ》だった。
それくらい、アルベリヒ役のコニエチュニが鮮烈。そのためか、最後はN響の金管までがアルベリヒの呪いで…。
四月十二日(土)紀尾井からNHKへ
今日はダブルヘッダー。まず紀尾井ホールで、紀尾井シンフォニエッタ。
指揮はペーター・チャバ。ハンガリー系のルーマニア人(こう書いただけで、東欧の民族地図の複雑さを感じる)で、三十年前からフランスに移っている。
この楽団はこれまでの印象通り、東欧系指揮者と相性がいい。前半はラヴェルの《マ・メール・ロワ》組曲と《亡き王女のためのパヴァーヌ》、コダーイのガランタ舞曲、後半はシュトラウスの《町人貴族》という、組曲中心プロ。
弦の人数は前半が八六六四二、後半はさらにしぼって三三三四二。ゲストコンサートマスターはパリ管弦楽団の副コンマスの千々岩英一で、在京オケの首席を中心とするいつものメンバーとともに、美しいソロを各所で聴かせてくれた。
ラヴェルやシュトラウスはわりと最近にフル・オーケストラでの演奏も聴いているが、今日の方が断然いい。適切な小編成と適切な広さのホールだからこそ、シャープな輪郭で聴ける幸福。
つよく印象に残ったのは前半。ラヴェルの色彩的な響きの根にある、暗さ。コダーイのハンガリー風(ジプシー風)の導入の旋律も哀しく、舞曲はそれを無理に振り払うかのように、情熱的。
どちらも、音の向うに闇が口をあけているような音楽だった。
夜はNHKホールで、ヤノフスキ指揮N響のブルックナーの交響曲第五番。
月曜日の「アルベリヒの呪い」がまだ效いているのか、今日も金管が悲惨。
紀尾井を聴いた直後だけに、むやみに人数が多ければいいというものではないとつくづく思う。
ヤノフスキも、妙に硬い。この人の根っこにある、一九七〇年代ドイツの無味乾燥な、形骸化した古典主義みたいなものが、露出してしまったような。
この殻を突き破る瞬間があるのが、今のこの人のワーグナーの魅力なのだが、今日はそうはいかない。融通のきかないN響の性格もあり、ブルックナーがワーグナーと違って器楽的な作曲家だということも、あらためて感じる。
舟をこぐ人、いびきをかく人、自分のいびきに驚いて目覚める人、いろんな人が周囲にいたが、自分には逆に、とても寝られるような音楽ではなかった。
四月十四日(月)近代音楽まつり
メシアン~ショスタコーヴィチ~マーラー~ブリテン。
昨日と今日で、プチ近代音楽まつり。生の困難と死の恐怖。
昨日はサントリーホールで、アンドリス・ポーガ指揮新日本フィルの、メシアンの《キリストの昇天》、ショスタコーヴィチの《バビ・ヤール》。
今日はトッパンホールで、イアン・ボストリッジ(テノール)とジュリアス・ドレイク(ピアノ)による、マーラーとブリテンの歌曲。
とにかくマーラーが凄かった。テノールが歌うマーラー歌曲は、意外なくらいに聴いたことが少ない。プレガルディエンも歌うけれど、かれはディースカウに似たバリトナルな声質。ボストリッジはキャラクター・テノールのごとき発声と叫びで、極限的に病んだ、骨と皮だけみたいなマーラーを歌う。
《子どもの魔法の角笛》の三曲、〈少年鼓手〉〈トランペットが美しく鳴りひびくところ〉〈死んだ鼓手〉の、戦争の殺戮とちっぽけな自分の死への、全身的な恐怖。
ドレイクのひく〈少年鼓手〉前奏のピアノの低音が、大地の裂け目から死神が覗いているような響きで、凄かった。オーケストラには不可能な、ピアノの単彩で抽象性の高い響きでこその、歌との緊密な対話。
《さすらう若人の歌》でも、「失恋」というロマン派の主軸をなす伝統的で甘美なテーマが、ボストリッジが歌うと、絶対的な孤独と絶望の自覚への、ただのきっかけにすぎなくなる。
二月に同じホールでプレガルディエンが歌ったシューベルト歌曲の、放浪と憧憬の十九世紀的ロマンチシズムがいかに健康で幸福だったか、あらためて思う。
後半のブリテンも、まず《ジョン・ダンの神聖なソネット》で、ボストリッジ節が炸裂。
隣席の青澤隆明さんが「ジョン・ダンて、ほんと壮絶な人ですよ」とおっしゃっておられたが、そのジョン・ダン(一五七二~一六三一)の、迷いと不安と不信と恐怖と呪詛をすべてそのまま裏返して祈りの言葉に変え、神様に全部おっかぶせたみたいな「神聖なソネット」に、ブリテンが曲をつけたのは終戦直後の一九四五年夏。ベルゲン=ピルゼンの強制収容所を慰問して、そこで見た光景に受けたショックがきっかけ。
続く三曲の民謡編曲、〈サリーの園〉〈おお悲しい〉〈オリヴァー・クロムウェル〉も、悔悟と嘆きと反骨の歌。最後の童謡の「オリヴァー・クロムウェル、くたばって埋められたとさ」(向井大策訳)という歌詞は、我が日本の「見よ東条の禿げ頭」みたいで、いと可笑し。
アンコールはシューベルト三曲。ここでも最後の〈ます〉のおしまい、自由に泳いでいた鱒が漁師にだまされて釣り上げられたあと、ボストリッジはフゥとため息をついた。
ひと晩これだけ歌って叫んで嘆いて、最後の最後が、ため息。
お見事。
全曲通じて、死屍累々。ジョン・ダンが書いた、最後の審判の日に墓から甦る死者たちも、ゾンビのような姿しか想像できない。そして作曲家も詩人もすべて死んで、墓の中。
これほどの凄みと凝集は、昨日のオーケストラ演奏会にはなかったが、プログラムは鏡のように似ている。
メシアンとショスタコーヴィチ、《キリストの昇天》と《バビ・ヤール》は、二十世紀の不安と恐怖から逃れるのに、信仰に頼るか皮肉に頼るかの差でしかない。そしてメシアンの信仰はジョン・ダン=ブリテンのそれに、ショスタコーヴィチの皮肉は、マーラー=シューベルトの寓話に、それぞれ照応する。
ポーガ指揮の演奏は熱くてわかりやすいものだったが、それだけに《バビ・ヤール》は、十一月に聴いたロペス=コボスと都響の演奏の、鉄とコンクリートの乾いた都市生活の硬質の陰惨さ、鉄面皮のユーモアの強烈さは、あまりない。
このあたり、プログラムの歌詞につけられた一柳富美子さんの訳注が、地名や人名などを丁寧に説明して、とてもわかりやすいのだけれど、第四楽章「恐怖」末尾の詩人の自虐とごまかし(粛清時代の密告政治の恐怖がフルシチョフになったらきれいに消えたなんて、誰も信じているはずがない)にまったく理解を示さずに、「エフトゥシェンコはかなり鼻持ちならぬ気取り屋であることがうかがえる」と書く純粋さに、どこか似たものを感じたり。
それにしても、この曲は不思議にタイムリー。十一月は特定秘密保護法制定に重なったし、昨日は第一楽章でアンネ・フランクの悲運に触れているのを見て、図書館の『アンネの日記』のページが破られた事件を思い出す。
四月十六日(水)日帰り仙台墓参り
日帰りで仙台に墓参り。朝早めの新幹線でついて午前中にさっと回り、駅前に戻って、名掛丁アーケードにある牛たん料理「利久」で昼食。美味。
いまや仙台名物の牛たん焼だが、帰省する祖父や父に連れられて頻繁に訪れた四十年ほど前には、そんな料理のことなど聞いたこともなかった(父が話題にしたのはとんかつ大町の「元帥とんかつ」などだった)。
牛肉の輸入自由化で値が下がった一九九一年以降に、急激に流行したものらしい。昼食にしてはそれなりの値段のものだし、同種の店も多いのに、店内は大賑わい。仙台人の食趣味にバッチリ適合して、根を下ろしたのだろう。
たしかに仙台の親戚たちにしても、味つけの好みは東北のイメージに反して、すっきり素直で淡めだった。これが仙台全体の嗜好に通じるのなら、余計な強い味をつけていない牛たんを韓国焼肉などより好むのは、当然なのかも知れない。
自分もいつか暮らしたい町なのだが、クラシックに関わる仕事をしているかぎり、難しそう。
四月十七日(木)ターラ活動停止
ヒストリカル・レーベルのターラが活動を停止することを知る。
二月に主宰者ルネ・トレミヌが急に亡くなったことは聞いていた。ほとんど個人のレーベルだっただけに、長年のパートナーのミリアム・シェルヘン(指揮者の娘)が停止を決めたという。
二十二年間に六百五十五のタイトルを世に出してきたそうだ。著作隣接権の独占期間が二十年から五十年に延び、ヒストリカルの世界でも権利者の許諾が不可欠になったちょうどその頃から、オルフェオとともに大きな足跡を残してきた。
時の経過を実感し、残念ではあるが、マイナー・レーベルはラーメン屋と同様に店主一代限りのほうが、潔くてよいのかも知れない。感謝。
夜はサントリーホールで、カンブルラン指揮読売日本交響楽団の演奏会。
前半がシェーンベルクの《弦楽のためのワルツ》とリスト:ピアノ協奏曲第一番(独奏デミジェンコ)、後半がマーラーの交響曲第四番(独唱エイキン)。
今シーズンのカンブルランの演奏会には、テーマ性が明確に感じられるのが面白い。
今日は、前回一月のガブリエリ、ベリオ、そしてベルリオーズの交響曲《イタリアのハロルド》のプロのテーマの、続篇のように感じられた。
あのときは線~面~体と、音場が広がっていくさまを、鮮やかに実感させてくれた。それはドイツ風の、和声の柱を立てるような「音の建築物」とは異なる、「音の空間」の創造だった。
そしてそのベルリオーズの管弦楽が、リストをへてマーラーにつながる。モビールのように揺れ動いて、ふわふわと浮いて広がる空間。
今日のリストとマーラーは、まさにそのような響きの音楽だった。さらに前者の終楽章のトライアングル、後者の冒頭の鈴の音と、二つの打楽器を照応させている気もする。
冒頭のシェーンベルクの珍しい初期作品も、マーラーの下流に位置づけられるものなのだろう、きっと。
マーラーでは、ひょっとしたら終楽章のソプラノ独唱をまたオルガン席あたりの高さで歌わせるのではと期待したが、これは普通に指揮者の横の位置だった。
四月二十二日(火)現物を見ないから
ヒストリカル・レーベルのURANIAから、トスカニーニの「The Great Live Concerts」という二枚組が昨年出ている。
HMVもタワーもショップサイトにはまともな曲目情報がないので知らずにいたが、数年前にCD‐Rで出た、ニューヨーク・フィルとの一九三五年のブルックナーの交響曲第七番が含まれていることを知った。トスカニーニ唯一のブルックナー録音。アセテートの低音質だからマニア向けとはいえ、初CD化の貴重な音源のはず。CD‐Rも持っているが、「CDなら買うぞ病」が発病。
いままでわからなかったのは、現物を見ていないから。いかに実店舗に行っていないかを反省。
四月十九日(土)新日本フィル
トリフォニーホールで、上岡敏之指揮新日本フィル。シベリウスの四番とベートーヴェンの《田園》。前者が秀逸。
四月二十日(日)ノットと東響
サントリーホールで、ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団の演奏会。武満徹の《セレモニアル‐秋の歌‐》(笙:宮田まゆみ)とマーラーの交響曲第九番。
音楽監督としての船出を、マーラーの第九で始めたノット。秀演。
四月二十三日(水)閉じた瞳の彼方には
今日は二期会の《蝶々夫人》。ルスティオーニ指揮の東京都交響楽団がすばらしかった。歌手の声量などを意識して抑えた部分はあったにせよ、これだけ骨格のしっかりした、澄んだ響きのプッチーニの音楽を聴くのは久しぶり。
この充実したオーケストラ(《蝶々夫人》の実演ではなかなか聴けないもの)を聴いていたら、四半世紀前に一度見たきりの三谷礼二演出の、あれこれの場面がまぶたの裏に甦ってきたのに、自分でびっくり。
冒頭、ゴローが指一本を高々と突き上げると、それを合図に音楽が始まり、人力車が何台もあつまって、蝶々さんの家が組み立てられていったこと。
二幕の間奏曲を、蝶々さんの生涯の回想場面の、伴奏音楽にしてみせたこと。
正月の空に上がる凧(正月といえば凧あげ、というイメージを持てるのが何歳くらいまでなのか知らないが、昭和四十年代まではたしかにそうだった)、長崎名物の龍踊りなどの幼時の思い出に始まり、父の切腹、大雪の日に母に連れられて置屋に芸妓として売られる場面(傘を投げ捨てて抱きつく母親…)などが、まさに走馬灯のように描かれる。
終景間近の太鼓が連打される場面、太鼓を持った武士の幻影が現れて蝶々さんを見下ろし、父の運命と死にざまを思い出させること。
そういった諸々のなかでも、なんといっても鮮明に焼きついているのは、花の二重唱の直前、リンカーン号を発見した蝶々さんの歌のクライマックスで、歌舞伎の振落しの技法を用いて、巨大な豪華客船を舞台背景いっぱいに、一瞬に出現させたこと。音楽のドラマと見事に合致した、そのきっかけの鮮やかさに、客席から思わず喝采が起きたこと。
しかもその船が設定通りの蒸気帆船の軍艦ではなく、ノルマンディー号とかアトランティック号の、カッサンドルのあの有名なアール・デコのポスターの絵そのままだったのが、素晴らしかった。
一九三四年生まれの三谷さんが子供のときに体験したはずの、銀座や横浜に象徴される舶来のモダニズム。そして、惨憺たる敗戦の焼け野原にやってきた、アメリカ文明の輝き。
それらへの憧憬が、この客船の絵ひとつに集約されていた。《蝶々夫人》が百年前の昔話ではなく、開国以来、今もなお続く日本の「西洋化」を描く「神話」であることが、そこに示されていた。
夢を与える一方、日本を踏みにじるアメリカへの、愛と憎しみの「神話」。戦争も安保もTPPも。
三島由紀夫が占領期に急速にアメリカナイズされていく日本社会を見ながら、明治初期を舞台とする『鹿鳴館』を書いたこととの、共通性。
三島は三谷さんより年上だが同じ学習院で戦前のブルジョワ階級で、西洋式生活への親近感と、日本の伝統文化への、直接的でない、西洋式生活の日常からあらためて眺めた、みたいな迂回的な観察とかが、たぶんどこかで似ている。
《蝶々夫人》は日本を舞台にした名作だが、オペラという西洋音楽の形式で、つくったのはプッチーニというイタリア人。その事実こそが、むしろ昭和の日本人の一部には自国の芸術よりも、かえって共感しやすかった不思議。複雑怪奇な「西洋化」の精神を象徴する作品。
などと、オーケストラの響きがこうした過去と現代のイメージをさまざまに喚起するのに対し、目の前にある栗山昌良の「名舞台」は、こんな妄想とは無関係に、音楽の波動ともほとんど無関係に、しかし忠実に筋書きを追い、時代を再現し、絵のように美しい。
そのことに、あらためて感心。
四月二十五日(金)ポルポラとヘンデル
オペラシティで、フィリップ・ジャルスキー&ヴェニス・バロック・オーケストラ。
ロンドンで覇を競った二人のカストラート、ファリネッリとカレスティーニ。この二人のためにポルポラとヘンデルが作曲したオペラのアリアを並べたプログラム。ジャルスキーはファリネッリとカレスティーニをテーマにしたアルバムを一枚ずつ作っている。
ごく大雑把にいえば技巧的なポルポラと劇的なヘンデル、両者を一晩で較べられるのが楽しかった。ジャルスキーの蠱惑的な歌も、オーケストラも見事。
四月二十八日(月)肘掛けは誰のもの
前から気になっていたが、あまりにもどうでもいいので、いままで書かなかった話題を。
演奏会の客席の肘掛けのこと。
隣席に人がいるときは「非武装中立地帯」だと私は思っている。unarmed。armrestだけど。お互いに使わない。トッパンホールは中央が山形になっていて、二人でわけて使いましょうみたいな感じだが、真夏とか男同士で毛深くひじ寄せ合うのも、あれだし。
同様の考えの方が大半だが、しかし四人に一人くらい、占有する人がいる。
そういうとき思い出すのが、むかし久米宏がやっていたラジオを元にした本。
「あの肘掛けは、どう使うのが正しいのか」というリスナーの質問があって、久米宏が学生時代によく行ったという自由が丘の名画座、武蔵野推理劇場(私も近所なので行ったことがある)に電話してきいてみると、支配人か誰かが「列の右半分の人は右側の肘掛けを使い、反対側は左を使う。中央の人だけ、特別に両方使える」と答えた。
「なるほど!」と久米が感心して、そんなきまりがあるんですか! ときくと、「いや今考えついただけです」という返事でガックシ、というオチ。
でも、いいアイディアだと思う。私も列の端の場合、通路側の肘掛けを独占する。内側は隣席の人に喜んで譲るが、問題はこのルールが、駅のエスカレーターの右側をあける不文律のように共有されているわけではないこと。なので、内側の席のときは失礼なヤツと思われたくないから、まったく使わない。
で、思う。隣の、この平然と肘をのっけている人は、ひょっとしたら「通路に近い側の肘掛けはオレの。代りに内側はあけてあるよ」思想の人なのかも知れない、と。ひょっとしたら自分が知らないだけで、コンサートゴーアーにとっては常識なのかも、と。
ならば反対側は本当にあけてあるのだろうかとか、気になりだす。ちらちら横目でうかがってみたり。
で、気がつくと一曲終ってたりする。
冗談はさておいて、このルール、広まればいいのにと本気で思っている。特に席の狭い古いホールなどだと、肘掛けを一つでも占有できると、気分的にはけっこう楽だと思うのだが。
エスカレーターの左右の使いわけだって、日本では自分の知るかぎり、エスカレーターが多くの駅に普及したこの四半世紀ぐらいで広まったマナーで、それ以前はなかったし(一九八三年にロンドンに行ったとき、地下鉄の長いエスカレーターで片側をあけるのが徹底されているのを見て、日本とは違うと感心した記憶があるから、そのころにはなかった)。
追記:エスカレーターの使いわけ、友人から関西では一九七〇年の万博で導入されていたと教えてもらった。
そこから連想したのだが、この使いわけは「動く歩道」の普及がきっかけで始まったのではないか。「動く歩道」はあまり速いものではないから、当初から右側を歩行用に空けるようにと指示があった記憶がある。それまで左右適当に立っていたエスカレーターにも、この指示がなんとなく援用されるようになって、やがて不文律化したのではないだろうか。
万博会場だったかそのための地下鉄だったか忘れたが、「動く歩道」はそのウリの一つだった。東京はどこが最初だったか思い出せないが、もっとあとの八〇年代のはずで、エスカレーターの使いわけと時期が似ているのだ。
四月三十日(水)イザイと再現芸術
トッパンホールで、アリーナ・イブラギモヴァによるイザイの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ全曲。キレキレの超絶技巧による凄演。そして、この六曲のありようを考えさせてくれる演奏だった。
よく知られているように、六曲はそれぞれ同時代の名ヴァイオリニストに捧げられている。その関連は、私などにはわかるようでわからない。ただまちがいないのは、かれらがパガニーニやサラサーテのような、演奏も作曲も同時にこなす十九世紀的ヴィルトゥオーゾではなく、過去の名作の再現を主とする、そうなりはじめた時代に生きる、大ヴァイオリニストたちであること。
わずかな例外のクライスラー同様に、イザイ自身もまた作曲をするけれど、大筋のところでは、過去の偉大すぎる、膨大な遺産を背負わされた「再現芸術家」となりつつあることを、いやというほど自覚しているはず。
イブラギモヴァの演奏が素晴らしかったのは、この六曲が当時の演奏家と過去の名曲の間にある、複雑で苦い関係(今よりももっと重苦しいものだったはず)の戯画でもあることを、その一種自虐的なパロディをむき出しにすることで、明快に示してくれたことだった。
たとえばシゲティに捧げた第一番が見ているのは、いうまでもなく偉大なる大バッハの姿そのもの。この六曲を構想したきっかけは、バッハを奏でるシゲティの演奏という。
ティボーに捧げた第二番はバッハの引用で始まるが、本体はむしろそれを強く否定して逃れようとするかのようで、グレゴリオ聖歌の「怒りの日」が変形されながら浮かびあがる。これはどう考えても、この旋律を終楽章につかったベルリオーズの幻想交響曲が元ネタだろう。あの曲では恋人を示すイデー・フィクスの役割を「怒りの日」が果たすという、意地の悪さ。ただ、いったいどうしてこれがティボーなのかはよくわからない。フランス人だから?
エネスクに捧げた第三番は、《バラード》と副題があってショパン。
クライスラーに捧げた第四番がバロック舞曲なのは、クライスラーが「発掘」して、十八番にしたバロック作品が念頭にあるのだろう。あれらがクライスラーの「偽作」であることに、このときイザイが気づいていたかどうかの詮索は、とても面白い(作曲は一九二三年、クライスラーが偽作を公表したのは一九三五年だが、イザイは同業者として、何らかの事情を知っていたかもしれないし、そうでなかったかも知れない…)。
弟子のクリックボームに捧げた第五番は、その曲想といい標題(曙光、田舎の踊り)といい、ドビュッシー風。イザイが一八九三年に自らの弦楽四重奏団でドビュッシーの弦楽四重奏曲を初演したとき、セコバイがそのクリックボームだったというのだから、いわば自分の鏡像への献呈。二楽章の舞曲の主題は、オーケストラ演奏でたしかに聴いたことがあるのだが、何の曲か思い出せなかった。
スペイン出身のキロガに捧げた第六番は、これはもう、ビゼーの《カルメン》の〈ハバネラ〉を変形させたものにまちがいない(イブラギモヴァは、明らかにそういう風に演奏した)。
演奏家が「再現芸術家」の枠に閉じ込められつつある時代の、白鳥の歌。
今日の演奏は残念ながらミュージックバードでは放送できないそうで、ということは、セッション録音のディスクが近々に登場するのかもしれない。楽しみ。
五月三日(土)二本立ての話(一)
毎年恒例となっているクラシックソムリエ役をラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンの会場でつとめたあと、家でDVDを見る。
最近本屋で買える往年の東宝映画のDVD、戦争映画と喜劇映画の二つのシリーズが別々の会社から出ている。
戦争映画シリーズで四月十五日に出たのが、松山三四三航空隊「剣部隊」の紫電改戦闘機隊の活躍と始末を描いた『太平洋の翼』。一方、五月二日に出た喜劇映画が、森繁久彌の十八番「社長シリーズ」の一本、『社長漫遊記』。
約二週間の差で出たこの二本、一見無関係のようで、関係がある。ともに一九六三年一月三日公開、つまり二本立てで同時に封切られ、正月に交互に上映されていた併映作品なのだ。
こういう偶然、シンクロは面白い。
まず『太平洋の翼』を、テレビ放映以来三十年ぶりくらいに見た。
ちゃんと見るとアラが目立つ。八十一分という短時間につめこんだせいもあってエピソードにまとまりと深さがなく、東宝戦争映画でも同年の『青島要塞爆撃命令』や三年前の『太平洋の嵐』などに較べ、出来がいいとはとてもいえない。
けれど、それでもここに出てくる紫電改のカッコよさと、加山雄三・夏木陽介・佐藤允の三人の飛行隊長が、モデルとなった実在の菅野直・鴛淵孝・林喜重の三人の海軍大尉を彷彿とさせる点(ただし戦死の順番を史実に合わせたためにこうなったようだが、人柄のイメージは加山=鴛淵、夏木=林、佐藤=菅野という感じ)は、数々の欠点を乗りこえて、いまもこちらの心を鷲掴み。
また、この頃までの日本映画の特徴として、帝国海軍の軍人のしぐさが本当に細かく再現されている点があるが、この映画でもやはり徹底されている。たとえば敬礼の仕方は挙手礼一辺倒ではなく、状況や相手の階級に応じて、細かく使い分けられる。また、物資不足の南方の戦場にいるときでさえ、将校だけは兵士とまったく違う、パリッとした清潔な服を着ている。大尉を「だいい」と濁るのも海軍式。
海軍陸戦隊の将校だった監督の松林宗恵はじめ、特攻隊で九死に一生を得た西村晃(髭面の歴戦の上飛曹役。杉田庄一あたりがモデルか)や平田昭彦など、スタッフや俳優に経験者がたくさんいたことに加えて、当時の海上自衛隊、つまりは旧海軍OBの全面的協力があるから、細部の描写が、忙しいスケジュールで量産した時代の映画とは思えぬこだわり方なのだ。ストーリーに弱点があっても印象に残るのは、こうした迫真性が細部に宿っているからだろう。
最強かどうかはともかく、近代日本の「最も美しい組織」だったことはおそらく間違いない帝国海軍の、残影。
潜水艦艦長役の池部良の潜望鏡を覗く姿勢なども、実際を知っている人間にしかできない雰囲気がある。これはどうやら、一九五九年の『潜水艦イー57浮上せず』で潜水艦の艦長役をやったとき、そこで叩き込まれたしぐさを再現したものらしい。ほんのわずかの出演場面なのに、異様にサマになっている。
おお、と思ったのは、源田実役の三船敏郎が海軍のお歴々を相手に新型戦闘機紫電改を説明する場面で、零戦のことを「れいせん」と呼ぶのに対し、戦場から脱出する輸送機のパイロットが、「あ、ゼロせんです!」と叫んだこと。
正式には「れいせん」だが、ハイカラ好きの海軍が現場では戦時中から「ゼロせん」と呼んでいたという話が、さりげなくここに示されている(つまり、戦後になって初めてゼロ戦と呼び出したという話は、本当ではない)。
ただ、三四三航空隊最初の出撃の場面で軍艦マーチが鳴り響くのは、ちょっと趣味が悪い気もする。これはパチンコ屋の店頭でこのマーチをさんざん聞かされてしまった世代の僻目だろうか……。


五月四日(日)二本立ての話(二)
続いて『社長漫遊記』を見る。
森繁に加えて加東大介に小林桂樹に三木のり平にフランキー堺、東宝喜劇映画黄金時代の、いつものあのメンバー。監督は杉江敏男。
日比谷公園近くに本社がある塗料会社が舞台で、そこここに一九六二、三年らしい感じがありあり。
たとえば社長室や会議室は、同時期の日生劇場に通じる、流線型のモダンな内装。森繁演じるアメリカ帰りの社長は、パンアメリカン機で羽田に到着する。そして、当時国際線の旅客機に乗るともれなくもらえた、社名の入った四角いビニール製の小型のバッグ(海外旅行の何よりの証拠で、飛行機好きのコレクターがこれを並べて悦に入っている写真を、当時よく目にした)を抱えている。
ペンキの耐久性を高めるために、アメリカの企業と独占契約を結んで技術供与してもらおう、なんてアメリカ頼みの話が出るのは、いかにも「アメリカがくしゃみすると日本が風邪をひく」時代。
その一方で、一九六二年九月に開通した、当時「東洋一の吊り橋」だった北九州の若戸大橋の開通式が映画のポイントになっていて、東京五輪直前の高度成長期の建設ブームがうかがえる。少しずつ自信を回復しつつある、日本産業界。
和洋の混在と対照は今より強い。銀座のナイトクラブではホステスとツイストを踊っているのに、北九州の若松では料亭の大広間に芸者を呼んで大宴会。
社長室長役の小林桂樹は自宅の茶の間で畳に寝転がり、白黒テレビで力道山のプロレス(白人と闘っている)を見る。
こういう喜劇と、悠然と爆弾を投下するB29の大編隊に向って、「出てけ、日本の空から出てけーッ!」と叫んだ加山雄三が、たった一機の紫電改で体当たりするラストをもつ戦争映画。
日本を爆撃するボーイング社の爆撃機で終る映画と、同社の旅客機で始まる映画が、平然と交互に上映される映画館。
こじつければ、憧れだけど憎い、アメリカの物質文明への昭和日本の感情のダイジェスト版みたいな。
家でその再現ができたのは、とても面白い体験。
私にとっては『太平洋の翼』と『社長漫遊記』、この二本が封切られた二日後にこの世に生を受けたというのは、けっこう運命的な気がする。
なんか、結局オレの中身って、戦争映画と喜劇映画、それだけだよね、という感じ(笑)。いや、それで充分に結構なのだけれども。
鵺のようなこの東宝二本立ての面白さを象徴する人物に、『太平洋の翼』を監督した松林宗恵がいる。『社長漫遊記』は違うが、この人は「社長シリーズ」の育ての親でもあるのだ。
戦争と平和は表裏一体。かっこいいけど悲壮で不幸な前者と、みっともないけど愉快で幸福な後者の、ひとつながり。
戦前と戦後を一種の「断絶」として教わってきた世代の人間にとっては、あらためて勉強になる。
そういえば『社長漫遊記』でも、怪しげな日本語を使う日系三世のフランキー堺にからかわれて怒った森繁が、「おのれ、断固として膺懲してやる」と叫んでいた。暴支膺懲、すなわち「戦後の前にあったもの」を暗示している(たぶんアドリブ)。こういう歴史の連続性が、自分などは長くよくわからなかった。
ところで続編の『続社長漫遊記』は四か月後のGWに公開されているが、そのときの併映作は、黒澤明のあの傑作『天国と地獄』なのだそうな。喜劇と悲劇、明朗と暗澹の二本立て。
今はほとんど消えてしまった、ロードショーの二本立て。我々がテレビで色々な番組を続けてみるように、その場では気分を切り換えてしまうのだろうが、あらためて組み合せをふり返ると、考えさせられる。能と狂言とかオペラ・セリアと幕間喜劇とか、悲喜劇の二本立ては歴史的にもさまざまに存在したわけだし。
近年で有名なのは、いわゆる「トトロの墓」。
一九八八年に『となりのトトロ』が公開されたとき、併映は『火垂るの墓』だった。見にきた親子連れを幸福な気分から一転、どん底へたたき落とすという、強烈で意地悪な二本立て。
五月五日(月)早朝の地震
朝に地震。千代田区は震度五弱とか。
低弦からだんだんクレッシェンドして激しくなり、長くあとに残す感じとか、たしかにゆれ方は久々に気持ち悪いものだった。でも新宿区では震度四もなかったと思う。うちには「CD積み上げ式地震計」が部屋の各所に研究用に立っているのだが、震度三の「上の方の一、二枚が落下する」ですんだ。震度四の「地震計のいくつかが倒壊する」には至らず。
五月九日(金)~十一日(日)また風邪
前回から三か月もたたないうちにまた風邪をひいて三日間寝込む。「ダメだなぁお前」状態。各誌原稿のデッドラインをどうにか越えずにしのぐ。
五月十二日(月)オイストラフと二十世紀重工業音楽
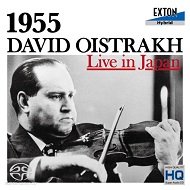
一九五五年オイストラフ初来日の初日のライヴが、オリジナル音源を用いてエクストンからSACD化されるそうだ。
国交回復前のこの来日を成しとげたのは、小谷正一という毎日新聞出身の快男児。伊藤忠のダミー企業(国交がないので、表向きには動くことのできない大商社は、ダミー企業をつくってソ連と貿易していた)に頼んで話をつけた。
しかし当時の吉田茂首相はソ連嫌いのため、親米派の牙城たる外務省が嫌がらせをして、ビザを発給しない。ようやく発給されたのは十二月の吉田政権崩壊のその前日。当初の公演予定の十一月を過ぎたあとなので、外務省としてはせめてものいやがらせだったのだろうが、意外にもソ連当局は、あっさりと日程変更の依頼をのんだ。
理由はおそらく、鳩山新政権との国交回復交渉(これも外務省抜きで、頭越しで進んでいた)に水をさすことをしたくなかったから。日本全国を回るオイストラフ一行は親善と同時に偵察部隊としての役割も負っていたというから、その意味でも中止したくなかったのだろう。
加えて面白いのは、小谷に看板を貸したのが読売新聞だったこと。当時文化人招聘用の外貨枠をもっていたマスコミ四社のうち、NHKも毎日も、朝日さえも「ソ連の音楽家」に尻込みしたのに、反共でなる正力の読売新聞だけが、あえてその企画に乗った。
一九五五年元旦の紙面に掲載された社告でオイストラフ招聘が発表されるが、面白いことにこの日の社告は「アメリカの原子力平和使節団招待」も発表している。前年の第五福竜丸事件を逆に利用して、原子力平和利用(すなわち原発)を押し進めようという動き。毒を薬にしてしまう、正力らしい手法。
さて初日のライヴ、発売元の情報には「いままで、この来日時のライヴ音源が存在する、という噂はありましたが、陽の目を見ることはなく、このたびニッポン放送の倉庫からテープが発見され、六十年の眠りから、遂に目を覚ますことになったのです」とあるが、オイストラフ側が持ち帰ったコピーらしき録音からモスクワ音楽院レーベルですでにCD化されているのは、周知のこと。
残念なのは、モスクワ音楽院盤と同じく、やはり《詩曲》が抜けているらしいこと。とても評判がよかったのだが、じつは演奏中に日比谷公会堂の客席にニッポン放送による実況放送の解説が、アナウンスみたいな感じで流れてしまったのだという。
当日は大阪の新日本放送(小谷正一がかつて所属したラジオ局で、現在の毎日放送)と東京のニッポン放送の二局が中継していたが、生中継の前者に対し、後者は番組開始を少し遅らせていた(録音を流したのだろうか)。タイムラグの関係か、実演中に解説をすることになったのが事故の原因だったらしい。日比谷公会堂にきちんとした実況設備がないからだともいわれた。
ニッポン放送もそこは保存しなかったか(あたりまえか)。ともあれ自分にとっては一九五五年ネタでもあるし、SACD正規発売は嬉しい。
なお小谷正一はこの招聘で大儲けしたそうだし、以後も大きな金脈になると思わなかったはずはないと思うが、これかぎりで共産圏ビジネスから手を引いてしまう。有名な神彰のアートフレンドはその代りに登場する。小谷がなぜ手を引いたのか、ここはいろんな史料を読んでもよくわからない、謎の一つ。
ところで、一九五四年に小谷が来日交渉で通ったのが、いまも狸穴にあるロシア大使館。ただし占領は終っているのに国交もないというので、外務省の建前としてはソ連と戦争状態にあるため、大使館ではなく、「旧ソ連代表部」が不法占拠していることになっていた場所。
ここはこの年の初めにスパイ事件「ラストロヴォフ事件」が起きたばかり。
そのラストロヴォフがシベリアで共産スパイとして育てたという噂のある日本将校のひとりに瀬島龍三がいて、その瀬島は一九五六年に帰国すると、二年後に伊藤忠に入る。そして、オイストラフ招聘の影の立役者である進展実業は、その伊藤忠のダミー企業としてソ連貿易をやっていた。
なんかこう、スパイ小説に仕立てられそうなくらいには、事件と役者がそろっている。左翼ではない小谷が手を引いたのも、こういうドロドロに関わりたくなかったのではないか、とも思う。
夜は東京文化会館へ行き、ツィガーン指揮東京都交響楽団。
ラヴェル:道化師の朝の歌&組曲《クープランの墓》、トゥリーナ:セビーリャ交響曲 、レスピーギ:交響詩《ローマの祭》という、「イマドキの都響」ならではの、只者でないプログラム。
フランス、スペイン、イタリアと、ローマ帝国の末裔三か国のラテン・プロかと思いきや、それだけではすまない。ドイツに交響楽の宝灯を奪われてしまったかつての音楽先進国の、反撃の歌。ラヴェルの二曲は元がピアノ曲だけれど、オーケストレーションはそれぞれ一九一八年と一九一九年、トゥリーナが一九二〇年、レスピーギが一九二八年。つまり第一次世界大戦後の作品を、年代順に演奏していくのがミソ。
いかにもラテン風の哀愁あるメロディも弦を主体に随所に顔を出すが(矢部達哉のソロが美麗)、オーケストレーションはだんだん度を越していって、けたたましく、機械のように非人間的な響きになっていく。
今日は演奏されていないが、このレスピーギの次にくるのは「パリのアメリカ人」の、あの大都市の無機的な喧騒の響きしかないなと思いながら帰宅後に調べてみると、ちゃんと一九二八年発表で、《ローマの祭》のあとになっている(そしていうまでもなく、《ローマの祭》を初演したのはトスカニーニ指揮のニューヨーク・フィル)。
アメリカの「狂騒の二〇年代」と同じ時代、フランの下落でアメリカ人や日本人が、パリに大挙して押し寄せていた時代の音楽。
それにしても、こういう「二十世紀重工業音楽」みたいなものをやらせると都響は圧倒的。アジア最凶、いや失礼、アジア最強なのではないか。
五月十三日(火)三谷幸喜の真田幸村
NHKの再来年の大河、三谷幸喜が再登板して、真田幸村を主役とする『真田丸』をやることが発表される。
これは楽しみ。一年間の大河を書ける脚本家が枯渇するなか、昔の大河への憧れをもつ三谷は最後の希望だった。主役は発表されていないが、堺雅人という噂が根強い。そうなったら素晴らしい。
連戦連勝の朝ドラに対して、不振の大河はどうなるのだろうと思っていた。現代の時間感覚に合わせて半年にする、信長~秀吉~家康の戦国末期に安易に頼るのをやめ、このところ得意の近代史にするとか、何か変えないとダメだろうが、『真田丸』だけは好きにやってくれることを願うのみ。
五月十九日(月)ムーティ記者会見と青山陸軍通り
グランドプリンスホテル新高輪で行なわれた、ムーティとローマ歌劇場の来日公演記者会見に行く。
質疑応答のとき、歌劇場の経営陣が運営と将来についての質問に、教科書通りであまり面白味もなく答えるのをわきで聞いていたムーティが、
「イタリア人に解決策なんかたずねたって無駄ですよ。そんなものあるわけがない。でもいざとなれば、帽子からハトをたくさん出してみせる連中です」
と口を出して笑わせた。
その前の挨拶もちょっと気になった。
「日本にはピンからキリまで、いろんなアーティストが同時に来ている」と、やはり冗談めかしてしゃべったのだが、そこで「AからZまで(アーからゼータまで)」といった。
話の脈絡としてはかなり唐突にこの話題になったので、ちゃんと聞きとっていなかったのだが、あとで「ゼータってのは、なんか意味があるんだろうか……」と疑問がわく。
いや、ちょうど同じ時期にアルベルト・ゼッダが東フィルを指揮したりしていなければ、こんなことまったく気にもならなかったと思うのだが(笑)。
ところで、グランドプリンスホテル高輪に行くのも久しぶり。
四谷三丁目駅から最寄りの高輪台駅までは新橋経由で大回りなので、都営バスを利用してみた。これだと四谷三丁目からホテルの脇まで、一本で行ける。
外苑東通りを南下して西麻布で外苑西通りに合流、天現寺で左折して明治通りを東進、古川橋から魚籃坂を登るまでのコースは、往時の路面電車の四谷三丁目と品川駅を結ぶ七号線の軌道と同じ。
旧青山練兵場だった神宮外苑をすぎると、北青山に陸軍大学校、南青山の第一師団司令部と射的場、歩兵第三連隊兵営と、陸軍施設の跡が北から南へ連なる。
そのため戦前のこの市電の乗客は、陸軍の軍人だらけだったらしい。慶応の教授時代に余丁町や荒木町からこの路線で三田へ通った永井荷風は、『日和下駄』に書いている。
「慶應義塾に通う電車の道すがら、信濃町權田原を経、青山の大通りを横切って三聯隊裏と記した赤い棒の立っている辺りまで、その沿道の大きな建物は尽く陸軍に属するもの、又電車の乗客街上の通行人は兵卒ならざれば士官ばかりという有様に、私はいつも世を挙て悉く陸軍たるが如き感を深くする」
バスから外を眺めると、南青山は東側に公園が二つもある。最初の青葉公園が第一師団司令部、南の都立青山公園は第三連隊兵営の跡。いずれも用地の一部にすぎず、軍隊は土地も物も人も食う。
「世を挙て悉く陸軍たるが如」し。
高輪へ乗り換えなしで行けるのはいいが、四十分近くかかる。乗り物酔いをする自分にはあまり向いていなかった…。懲りて帰りはJRと地下鉄に乗る。
五月二十日(火)《ナブッコ》初日
今週はときならぬオペラ強化週間で、四つを観る予定になっている。初日の今日は東京文化会館でローマ歌劇場の《ナブッコ》。批評を日経新聞に書く(二十八日掲載)。
五月二十二日(木)《アラベラ》
オペラ強化週間二日目。新国立劇場で《アラベラ》。新国立劇場の再演には珍しく、演出家アルロー本人が立ち会っていた。初演よりも水準が上がったように感じたのはその賜物だろう。
ただ、アラベラの青いドレスの腰につけた赤い花は、何とかならないのだろうか。処女性の象徴なのかもしれないが、青と赤の対照が極端すぎ、田舎くさい。ドレスの青が美しいだけに残念。
五月二十三日(金)居酒屋、個室の幻想
最近はマレーシアやヴェトナムで働く現代のハリマオのような友人が増え、SNS経由で、東南アジア各地の空気をリアルタイムで教えてくれる。ヴェトナムの反中暴動は日本の報道のように過熱したものではまったくないとか、タイの軍部のクーデターと戒厳令は年中行事みたいなもので、現地の市民の空気は平静だとか、なるほどと感心。
そのヴェトナムから一時帰国した友人など三人で、新宿で飲む。いま大流行らしい個室居酒屋で飲んだが、中途半端な個室のため、若い男女六人くらいのグループと一緒にされる。これがうるさいのなんの。ハコが小さいだけにキンキン響いて、普通のテーブル席の方がよほどましな環境だった(苦笑)。
五月二十四日(土)ヴェリズモ二本立てと《テ・デウム》
オペラ強化週間三日目。新国立劇場で《キャヴ&パグ》(アメリカ式呼称)。
休憩時に某誌の編集長に遭遇、雑談をしているうちに、今週のオペラ四本の話を書くことになる。ありがたし。
終演後、慌ただしく移動してサントリーホールへ。スダーン指揮東京交響楽団のベルリオーズの《テ・デウム》ほか。
合唱と少年合唱で三百人、オーケストラを合わせて約四百人、パイプオルガンの壮大な響きも加わり、サントリーホールが小さく感じられる大迫力。東響コーラスはいつものごとく暗譜歌唱。立派。
ベルリオーズの巨大作品は教会の大空間のために書かれた。しかし十九世紀後半には、そうした作品まで演奏可能な大型コンサートホールが増えていく。
ところでこの曲は、もともと二〇一一年四月に演奏が予定されていた。しかし東日本大震災による原発公害でスダーンが来日不可能となり、小林研一郎の指揮で曲目変更の上、犠牲者のための追悼演奏会となった。
これは震災後、自分が最初に行く気になった演奏会だった。〈ラクリモーサ〉までを演奏したモーツァルトのレクイエムの最後、天を指し示すようにコバケンの右手が高く掲げられていたことなど、いまもよく憶えている。
春で音楽監督を退任、桂冠指揮者となったスダーンにとって、これは「やり残したこと」だったのだろう。また、その指揮への楽員の反応のよさと自然さに、十年間重ねた歳月の力を実感する。
五月二十五日(日)《シモン》
オペラ強化週間四日目。東京文化会館でローマ歌劇場の《シモン・ボッカネグラ》。素晴らしい公演。
このあと東京文化会館は六月から半年間の改修期間に入る。しばしの別れ。
五月二十六日(月)インタビュアー山崎
来日した某クァルテットにインタビュー。急な日程変更と時間変更に始まり、一、二人しか出てこないかもしれないだの、時間を短めにしてくれだの、事前は「ご機嫌ナナメ」モード全開で心配だったが、ふたを開けたら全員そろっているし、サーヴィス精神全開で愉しくたくさん話してくれるしで、大助かり。さすがはプロ。
しかも最後、「明日のコンサートは同時刻の別のクァルテットのコンサートにいかなければならないので自分は聴けない、とても残念」と話したら、そのクァルテットは友達だから(一部メンバーが共演したCDもある)、四人でメッセージを手書きするから持っていって渡してくれという、ヘンな展開に(笑)。EメールもSNSもある時代に、こういうお遊びに一役買えて愉快。
問題は、全員いてくれたおかげで、あとでテープ起しするときに誰が誰なのやら確認が大変になることだが、とにかく愉しい仕事になった。
今週はインタビューがもう一つ。
「齢五十にしてオシッコちびりそうになった」あの某マエストロ再び。
今回は奥さんの進言でメディアに露出する方向に突然変換したと話に聞いてはいたが、まさかまたこちらにもチャンスがめぐってくるとは思わなかった。あの人は男よりも女性が聞きにいった方が絶対よいと思うのだが。
しかしこのところ、人づきあいの悪い自分には珍しく、人とじかに会って刺激を受けることが続いているので、今回もその一つと信じるのみ。
でも怖えぇんだよあの人…。
五月二十七日(火)メッセンジャー山崎
昨日とは別のクァルテットの演奏会を聴きに行く。終演後のサイン会に混じってメッセージを手渡す。喜んでくれた。
二つの団体はメンデルスゾーンの弦楽八重奏曲を一緒に演奏する企画があるそうで、日本で聴けたら素晴らしい。
五月二十八日(水)「ヴィオラスペース」のイギリス音楽
今井信子を中心に内外の優れたヴィオラ奏者が集う「ヴィオラスペース」。
二十二回目となる今年のテーマは、イギリスの生んだ二人の偉大なヴィオラ奏者、ライオネル・ターティスとウィリアム・プリムローズを讃えて、イギリス音楽の特集。昨年のヒンデミット特集に続いてアントワン・タメスティが選曲構成を担当、会場は石橋メモリアルホール。
昨夜の第一夜も聴きたかったが、あきらめて第二夜のみ。ダウランド、パーセルの編曲も含めて、ヴォーン・ウィリアムズにウォルトン、ブリテンに現代のジョージ・ベンジャミンなど、近代イギリスの作曲家たちの名品がならぶ。
前半はピアノ伴奏などの室内楽で、後半は管弦楽つきの協奏曲的な音楽。前半の最後は急病の篠﨑友美に代ってタメスティが登場、レベッカ・クラークのヴィオラ・ソナタの第三楽章をひいた。再評価されつつある女性作曲家の代表作を聴けたのは、ひろいもの。
後半は原田幸一郎指揮の桐朋学園オーケストラが登場。鈴木学独奏のウォルトンの協奏曲、タメスティ独奏のヴォーン・ウィリアムズの組曲《野の花》(フロス・カンピ)など、ヴィオラのソリストの元祖ターティスゆかりの曲が続いて、その存在の大きさを実感させる。
ウォルトンもよかったが、歌詞のない合唱(上野学園大学合唱団)と小管弦楽という変った編成で、聴く機会の少ない《野の花》を、タメスティの艶やかな響きで聴ける喜び。
ところで、桐朋学園オーケストラの弦楽器と管楽器の女性奏者たちが、ソリストのような色とりどりのドレスで演奏したのは、ちょっと不思議な光景だった。
よくいえば、パステルカラーの花園のようだったけれど……。
五月二十九日(木)「インタビュー・ウィズ・マエストロ」
昨年秋に続いてのリッカルド・ムーティへのインタビュー、無事に完了。
危うく虎の尾を踏みそうになった前回の轍を踏まぬよう、今日は鞄のなかに、お護りを二つ用意していった。
三谷礼二の『オペラのように』と、TIMAClubの「アウレリアーノ・ペルティレ全録音集」CD八枚組。
前者は、一九六九年フィレンツェで新人指揮者による《群盗》を見たという一節があるから。後者は、マエストロの新著『イタリアの心 ヴェルディを語る』のなかで、ペルティレの歌うシェニエの即興詩が絶賛されていたから。
この二つのご加護により、今回はかなり打ち解けて話せた(残念ながら、ペルティレの話までは聞けなかったが)。
場所はNHKホールの楽屋、指揮者控室。
まず、昨日の日経夕刊の《ナブッコ》の拙評のコピーを見せ、これはこいつが書いたと紹介してもらうと、ちょっと驚いたように片眉があがり、
「じゃあこれは、あなたに責任があるんだね」
「そうです。なので私が帰ってから読んでください」
「いや、気に入らなければ後を追いかけていくよ」(笑)
インタビュー開始。いまはなき師(正式の師弟ではないが、親しく謦咳に接して、大きな影響を受けた)の三谷礼二がオペラの演出家だったこと。かれが一九六九年にフィレンツェで若い新進の指揮者が、ヴェルディの《群盗》をみなぎる情熱で指揮するのを見たという話を聞いたこと。
それがマエストロですねというと、パッショーネ(情熱)という言葉を、愛おしむように、過去を懐かしむように自らも口にしたあと、
「あれが私の指揮した最初のヴェルディのオペラだった。ならば我々には、縁があるんだね」
光栄です、と答えるのみ。これはほんとにお護りのおかげ。
そこからはヴェルディについて、饒舌にしゃべってくれた。話が終りそうになると、こっちをパッと見て、次の質問を用意しろと、無言のキュー。このあたりはさすが一流指揮者のタクト(笑)。
リハーサル前の時間を割いてもらったので長くはできず、《シモン・ボッカネグラ》の話を聞けなかったのは心残りだが(とりわけ、ラストの響きがヴェルディのレクイエムそのものだったのは、意図的なものなのかどうかきいてみたかった)、最後に一つだけ、ヴェルディに関係なしに、どうしても聞きたかった質問をできたのは嬉しかった。
いま、新国立劇場でやっている《キャヴ&パグ》。その《道化師》のラストは先日の二期会同様に、初版譜に基づいて「これで喜劇は終りです」をバリトンのトニオが言う形になっている(現在はテノールのカニオがいう)。
新旧二つの録音で、やはりトニオに言わせているマエストロに、どうしてそうするのかを聞いてみたのだ。
突然の質問にもかかわらず、明快に答えてくれた。総譜に続けて出たピアノ譜(ヴォーカル・スコア)で、早くもカニオが言うように変えてあるのも承知の上で、それでも初版譜のほうが、ドラマとして正しいこと。
なぜなら、そこに作曲者がつけた表情の指示は、あくまでトニオが口にするものとして書かれていること。
その指示に基づき、トニオがどんなふうにしゃべって、続いてオーケストラがどう入るべきか。マエストロによる納得の実演は、ミュージックバードで放送するインタビューで(放送は七月予定)。
三谷礼二ばんざい!
ペルティレばんざい!
五月三十日(金)ブルーインパルスの飛行音とコンツェルト・ケルン
夜は紀尾井ホールで、ヨハネッテ・ゾマー(ソプラノ)とコンツェルト・ケルンの演奏会。
出る前に早めの夕飯を食べていると、テレビにブルーインパルスが映る。明日の国立競技場お別れイベントのための予行演習の生中継という。
すると、キーンという爆音が聞こえてきた。家の真上を飛んだのだ。音だけで姿は見られなかったが、金属的でない、なんともワクワクするような美しい飛行音だった。
外に飛び出ていった(笑)山の神は、五機が横一線に飛んで、まっすぐに残したスモークを見て興奮していた。
明日の本番も自分はミューザの帰りだから、間に合いそうもない。
サヨナラ国立。
ゾマーとコンツェルト・ケルンの演奏会も愉しかった。
ゾマーとともにオーボエのズザンネ・レーゲルもソロで活躍、平崎真弓をコンサートマスターとする三三二一一の弦とリュート、チェンバロという編成。ヘンデルのアリアや合奏協奏曲、バッハのオーボエ・ダモーレ協奏曲と結婚カンタータが、交互に演奏された。
「劇場の人と教会の人」という文言がプログラムに載っている。私はむしろ、ハンブルクやローマ、ロンドンと各国の大都市に生きた人と、ドイツの地方都市と宮廷に生きた人との対照を想った。
四月二十五日にオペラシティで聴いたジャルスキーとヴェニス・バロック・オーケストラのコンサートは、ロンドンで覇を競ったヘンデルとポルポラの作品を対照させたものだった。ヘンデルを軸にポルポラとバッハの三角関係(?)を、イタリアとドイツのバロック・オーケストラで聴くことになり、両者の個性の違いが際立って愉快。
五月三十一日(土)伊福部昭生誕百年
今日は伊福部昭百歳の誕生日。
というわけで、ミューザ川崎で開催された、東京交響楽団による生誕百年記念コンサートを聴く。
SF交響ファンタジー第三番、二十絃箏と管弦楽のための交響的エグログ、ピアノと管弦楽のためのリトミカ・オスティナータ、そして交響頌偈《釈迦》という長大なプロ。東響コーラスは一週間前の《テ・デウム》に続き、今回ももちろん暗譜歌唱。
指揮は井上道義が療養のため、大植英次に交替。
六月三日(火)フィラデルフィア管
サントリーホールでネゼ=セガン指揮フィラデルフィア管弦楽団の演奏会。曲は《ジュピター》と《巨人》。日経新聞に評を書く。掲載は十六日。
六月五日(木)自由が丘
小中学校の同級生と飲み会。場所は自由が丘。
新宿三丁目で副都心線に乗りかえるとそのまま、東横線に直通で到着。
一本のチューブの中を押し流されるだけの安楽さ。渋谷駅の雑踏を通らなくてすむのは楽だけれど…。
飲み屋は駅のすぐ脇のビルの三階。
自分が自由が丘と緑が丘のあいだに住んでいたころ、二十年ほど前まではここにイタリアン・レストランがあった。深夜に一人で食べにきたのを思い出す。イタリアンが流行っていた時代の話。
六月七日(土)林隆三の雑賀孫市、オノフリの「趣味の混淆」
林隆三の訃報。ニュースには出世作の『天下御免』が紹介されていた。これも好きだったが、子供心に印象に残るのは大河ドラマ『国盗り物語』の雑賀孫市。
司馬遼太郎の快作『尻啖え孫市』の主人公そのままの、「日本一なんのなにがし」のノボリの、肝心の下の名前がにじんでいて読めないとか、人を喰ったキャラだった。
役者もよかったし、メインの『国盗り物語』だけでは原作として短いので、司馬の他の複数の作品をたくみに組み合わせ、織りあわせて大きなマンダラにしてみせた、大野靖子の脚本の力も大きかった。司馬のそれぞれの原作をうまく使って、秀吉も黒田官兵衛も山内一豊も、それに『梟の城』の葛籠重蔵も、キャラが立っていて魅力的だった。そのなかでも特にキラキラと輝いていたのが、林隆三の孫市だった。
信長と周囲だけでは、雲の上の政治劇になりやすい。中間層の武士から忍者までのさまざまな視点を加えることで、ドラマの構造が立体的になっていた。
五時間の話をダラダラと十倍に引き延ばしただけみたいな、どこかの大河の脚本とは…、いや、いうまいいうまい。
夜は石橋メモリアルホールにて、エンリコ・オノフリのバロック・ヴァイオリン・リサイタル。
バロック・ヴァイオリンの杉田せつ子と鍵盤楽器の鍬形亜樹子が共演。「趣味の混淆」と題して、その題のもととなったF・クープランの曲集から一曲を導入に、ヴィヴァルディ、テレマン、コレッリ、ビーバー、J・S・バッハ、ルクレール、C・P・E・バッハと各地域のさまざまな作品が「音楽の宝箱」をあけたように演奏される。
言葉をしゃべるように、抑揚と響きを多彩に変化させて歌うバロック・ヴァイオリンならではの魅力を堪能。オノフリ自ら独奏用に編曲したバッハの《トッカータとフーガ》は、途中で弦が切れて中断したのは惜しかったが、その雄弁術の真骨頂だった。
共演の二人との息も合っていた。特にテレマンの《ガリヴァー組曲》やC・P・E・バッハのトリオ・ソナタ《陽気と憂鬱》では、二梃のヴァイオリンが極端に対照的なキャラクター描写でかけあいをして、ユーモラスで愉しかった。
六月九日(日)ショーケンの人斬り以蔵
フェイスブックで大河話に花が咲き、ユーチューブを検索したら、『勝海舟』のショーケンの場面が見つかった。人斬り以蔵といえばこの人。
よさこい節を歌う場面が忘れられなかったが、四十年ぶりにみる。この哀しい以蔵はやはり最高。しかし昔のドラマの人間たちは、いやらしくて重厚。武智半平太も、また同じ『勝海舟』からアップされている「龍馬暗殺」の場面で出てくる大久保一蔵、中村半次郎など。役者の声と台詞回しもいい。
藤岡弘の龍馬はきらいではないが、もう少しやせた方がよさそう。
ちなみに、自分が誰よりもいちばん龍馬らしいと思うのは、『花神』の夏八木勲。実物の写真にもよく似ているし、本物は正体のよくわからない人だと思うから、これくらいバッチイほうがいい。いかにもヒーローらしい龍馬は苦手。
それにしても、龍馬暗殺の下手人が人斬り半次郎を初めとする薩摩藩士と匂わせているあたり、さすが彰義隊の孫にして新選組に光をあてた男、子母澤寛の原作のことだけはある。
六月十日(火)コパチンスカヤ
トッパンホールにて、パトリツィア・コパチンスカヤのヴァイオリン・リサイタル。ピアノがコンスタンチン・リフシッツという豪華版。
同じヴァイオリンでも、三日前のオノフリとはまるで別の世界。その気になれば強大で鋭利な響きをいくらでも出せるモダン楽器の威力を見せつける演奏会。
最初がよりによってC・P・E・バッハの幻想曲というのが暗示的。オノフリの《陽気と憂鬱》は、陽気と憂鬱それぞれの性格の二梃のヴァイオリンの対話による寸劇だった。一方コパチンスカヤは幻想曲をヴァイオリンのオブリガートつきピアノ曲と見なして、ピアノの後ろに立つという異例の配置をとった。
演奏後に自ら舞台から説明したところによると、アンドラーシュ・シフの方法にならったもので、ヴァイオリンはピアノの影のような存在となる。内面、もう一人の自分としてのヴァイオリンが、背後から鋭く斬りこむように、衝動的に自己を主張し、ときにピアノによりそう、いわば心理のドラマ。メフィストフェレスのような存在でもあるのか。
オノフリの外向的な対話劇とコパチンスカヤの内攻的な心理劇、いずれもC・P・E・バッハのファンタジーの大きさを示して、興味深い。
続くシマノフスキの《神話》、シェーンベルクの幻想曲、そして後半のプロコフィエフのヴァイオリン・ソナタ第一番では、普通にピアノの前に戻って、猛烈ぶりもいや増すばかり。一種剣舞のようでもあり。
同じ裸足でも、軽やかに跳ねるアリス=紗良・オットとは正反対に、ドシンドシンと歩くのも印象的だった。
六月十二日(木)ヴェルレク
サントリーホールにて、カリニャーニ指揮の読売日本交響楽団と新国立劇場合唱団ほかによる、ヴェルディのレクイエム。
この指揮者らしい、つるりと滑らかでスピード感のある響きが、梅雨の湿気を忘れさせてくれて心地よい。
歌手は指揮者の両脇にいたが、おしまいの《リベラ・メ》のときだけソプラノが下手奥に移動して、合唱との距離を縮めたのは納得の演出。テノールの不調は惜しかった。
六月十七日(火)ネットなしの生活
朝起きてパソコンの電源を入れたら、ネットへの接続ができず、メールのやりとりもできない。プロバイダー側の認証システムの故障だったそうで、結局十五時過ぎまで復旧せず。
原稿のデッドラインの朝などだったら冷汗ものだが(短いものならファックスでいいだろうが、長いものならメモリスティックでも持参するしかない)、幸い急用のない日だったので、パソコン内に残っている仕事を黙々とやる。
何も情報が外からこないのは、仕事がはかどる。常時接続をやめて時間課金制などに戻した方が、自分は真面目に働くような気もする。
あとでプロバイダーのDTIが発表したところによると、
「認証要求数の一時的な急増により処理の滞留が発生し、認証サーバが高負荷な状態となったため、新規の接続要求へのレスポンスが低下し接続障害となりました」とのこと。
大規模な攻撃を受けた、ということなのだろうか。他のプロバイダーやサイトでも、前後してこうしたことが起きたようだった。不気味。
六月十八日(水)チッコリーニの芸
池袋の東京芸術劇場で、アルド・チッコリーニのピアノ・リサイタル。
曲目は前半がブラームスの四つのバラードとグリーグのピアノ・ソナタ。後半がボロディンの小組曲とカステルヌオーヴォ=テデスコの《ピエディグロッタ一九二四、ナポリ狂詩曲》。
並のピアニストではとてもお客を呼べないプログラムだが、満員に近い盛況。池田卓夫さんの言によると、二十年前には東京文化会館の小ホールでさえ一杯にはならなかったそうだ。一九二五年八月生れで八十七歳のチッコリーニ、それが嘘のような人気ぶり。
杖をついて舞台に現れ、足どりはゆっくりとしていたが、ひとたび演奏が始まると、老いの翳を微塵も感じさせない。
暖かく軽妙だが、骨組みのしっかりした甘美な響き。ドイツ、ノルウェー、ロシア、そしてチッコリーニの母国イタリア。さまざまな国の夢幻的な風景のミニチュアが、音によって描かれていく。
終ってみると、実にまとまりのある曲目構成だと納得。
六月二十日(金)神楽歌と伊福部昭
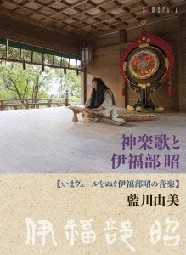
生誕百年ということで伊福部昭のCDがたくさん出ているが、そのなかでも異色作は、藍川由美さんの『神楽歌と伊福部昭』。
今月号の『レコード芸術』でプレビューを依頼されて聴いたが、これがとても面白かった。
ここ数年、藍川さんは琴をひきながら歌う、日本の古代歌謡の研究と実演に力を注いでいる。古代歌謡とは雅楽のなかで国風歌舞(くにぶりのうたまい)とよばれる、記紀などにある日本古来の歌。
ここではその歌と琴により、東宝映画『日本誕生』で伊福部が記紀などの詞につけた曲は、古代歌謡の技法に精通していればこそ生れた音楽だということを、録音と詳細な解説で明らかにしていく。
「大和は國のまほろば」の歌や、ヤマト王権の戦闘歌として名高い《久米歌》の「撃ちてし止まむ」の歌などの伊福部メロディーが、和琴と歌だけで朗々と歌われると、なるほどと思わされる。
神楽歌《阿知女法》(あぢめのわざ)と伊福部昭の映画『モスラ対ゴジラ』の《聖なる泉》を続けて収録、その技法の類似を指摘しているのも興味深い。
門外漢の私にはつかみきれないも部分も多々あるが、それはそれとして、このディスクが日本古代史のさまざまな謎、ミステリーへの入口になっているのが、歴史好きにはとても面白い。
伊福部昭は北海道生れで、アイヌの音楽を研究し、自作にとりいれたことで知られている。しかし祖父の代までは因幡国の一ノ宮、宇倍神社の神官を長くつとめてきた家柄。
伊福部氏は因幡国造をつとめた古代の豪族で、始祖を大己貴(おおなむち)、すなわちオオクニヌシとする古い家系。天津神に国譲りを余儀なくされた、国津神の長の血を引いている。
つまりは敗者の子孫。この意識が滅びゆくアイヌ文化への共感につながったのでは、と藍川さんはみる。
そして、そういう自覚を持って国風歌舞を研究した人物にとって、勝者、征服者であるヤマト王権の歌、《久米歌》などは、どんなふうに思えただろう。
興味深いことに、宇倍神社の祭神は景行から仁徳まで五代の天皇に大臣として仕え、三百六十余歳まで生きたという、武内宿禰なのである。ヤマト王権の有力者が因幡一ノ宮の祭神というのも奇妙な話で、本来は伊福部氏の祖先神を祀っていたのが、武内宿禰に入れ替わったのではないか、とみる説もある。
とすれば、まさしく勝者(進駐軍)の押しつけを敗者が呑まされた形。
ヤマトとイヅモ、その関係の縮図。
また、伊福部昭が参照した神楽歌。この神楽歌のなかには、北九州の志賀島を本拠とする海人(あま)族の歌舞を源流とするものがある。
北九州などではもともと、縄文時代から五絃の和琴が用いられていた。そこで藍川さんは五絃の和琴を復元して用いているのだが、しかし正倉院にある和琴はすべて六絃で、現代の雅楽も六絃しか用いない。
日本の琴を六絃に統一しようとしたのは天智天皇だといわれる。その一方、海人族の歌を含む神楽歌を宮中にとりいれたのは、その弟の天武天皇、すなわち大海人皇子(おおあまのおうじ)。
天智と天武の「兄弟」の関係も、どこまでが本当なのか、謎が多くて面白いところだが、そこに五絃と六絃の和琴の問題と、海人族の話がからむ。
この海人族こそ安曇(あづみ)氏。前述の神楽歌《阿知女法》の阿知女も、安曇氏の祖先神、安曇磯良(あづみのいそら)だとする説がある。
アヅミ氏は日本各地の水辺にその名を地名として残しながら、最後は海のない信濃の国の、安曇野を本拠とする。私の大好きな山野に住む人たち。
ヤマト、イヅモ、アヅミ。
さらにいうと武内宿禰と琴といえば、北九州でかれと神功皇后の目前で亡くなった、仲哀天皇の琴の話を連想せずにはいられない。
解けないからこそ面白い、日本古代史の謎。現代と古代、北海道から九州まで想像が駆けめぐって、想像力と妄想力を刺激してやまないディスク。
六月二十二日(日)アファナシエフ
読売日本交響楽団を東京芸術劇場で。ヴァレリー・アファナシエフのピアノと円光寺雅彦の指揮によるモーツァルト・プロ。
《後宮からの誘拐》序曲とピアノ協奏曲第九番《ジュノム》、後半がピアノ協奏曲第二十七番と交響曲第三十一番《パリ》。
このピアニストと指揮者だから、ピリオド様式とは無縁の、一九七〇~八〇年代風のモーツァルト。モダン楽器が響きすぎて《ジュノム》は居心地が悪かったが、年代の降った第二十七番は、この響きでちゃんと形になるのが面白かった。
日本でのアファナシエフは、一九八〇年代半ばにクレーメルの来日公演の個性的な伴奏者として、その名を知られた。評判が広がってソロ演奏もするようになったのはたしか一九八五年で、そのときもデビュー間もない広上淳一の指揮で、この二十七番の協奏曲をひいた。
直前に師ギレリスが亡くなったため、演奏を故人に捧げる旨のアナウンスがあったと記憶する。それから二十九年たったが、今日の演奏はあの頃とほとんど変化がないように思えた。
六月二十三日(月)ハンガリー国立管
ハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団をサントリーホールで。指揮はゾルタン・コチシュ。
リスト/コチシュの《ゲーテ記念祭の祝祭行進曲》、リストのピアノ協奏曲第一番(金子三勇士独奏)、ブラームスの交響曲第一番。
コチシュの指揮はCDでバルトークやりストを聴いて、ゴツゴツした感じを気に入っていたのだけれど、今日は音楽がなぜかとても生硬で、ブラームスでは管楽器にミスが連発、終楽章は形にならなかった。不思議。
六月二十五日(水)アンデルシェフスキ
東京都交響楽団を東京芸術劇場で。指揮はヤクブ・フルシャ。
オネゲルの《パシフィック231》、バルトークのピアノ協奏曲第三番(ピョートル・アンデルシェフスキ独奏)、ストラヴィンスキーの《春の祭典》。
二十世紀重工業音楽をやらせればピカイチの都響、今日も精度が高く、迫力充分。安心して聴けるのが嬉しい。
バルトークではアンデルシェフスキのピアノが冴えに冴えて素晴らしい出来。喝采に応えて、アンコールを異例にも二曲。バルトークの三つのハンガリー民謡と、バッハのフランス組曲第五番のサラバンド。バルトークで続いた犀利な緊張が、バッハでほどけていく快感。
六月二十八日(土)中野サンプラザ解体~山形交響楽団~HARIKOMI
中野駅前の中野サンプラザを解体・再整備して、二〇二〇年の東京五輪をメドに駅ビルを建てるというニュース。
東京の名所がまたひとつ消える。サンプラザの解体と五輪に、いったい何の関係があるのかよくわからない。老朽化がひどいというのだが、鉄とコンクリでつくったものがたった四十年で老朽化するなんて、欠陥工事じゃないのか。
日本は、なんだかんだと口実をつくっては、土建屋が食いつなぐだけの国になっている気がする。高度成長期のように新たな消費市場の開拓につながるわけでもない。駅ビルができればサンロードやその東側の飲食店街の客を奪って、衰退させるだけだろう。タコが自分の足を食っているような。
それに、資材費も人件費も跳ね上がる五輪前の繁忙期に、なぜ工事しなければいけないのか。五輪の観光客も来ます、という理由づけをしたいからだろうけれど、それは一時のことにすぎない。
五輪後に当然くる不況時への対策にとっておくほうが、公共工事としては正しいあり方なのでは。でもそういう考えかたは評価されないのが、日本の政治行政なのか。勝ち馬に乗るよりも負け戦をきちんとやれる奴のほうが、よほどえらい奴だと思うんだけれども。
夜は山形交響楽団の東京公演をオペラシティで。指揮はもちろん飯森範親。
シューベルトの《未完成》、ドヴィエンヌのフルート協奏曲第七番(南部やすか独奏)、ベートーヴェンの《英雄》。
ホルンやトランペットにピリオド楽器を交えた、モダン楽器による折衷的なスタイル。
既存のオーケストラが古典派以前の作品を演奏するのに、合理的かつ有効な方法だと思う。飯森と山響が早くから積極的に採用しているのは素晴らしいこと。これで演奏にもう少し遊び心があれば、と思う。今日はやや生真面目すぎた。
帰宅後、「週刊文春」が新垣隆氏に作曲を依頼したというニュースをフェイスブックで教えてもらう。作品のタイトルは《交響曲HARIKOMI》、雑誌記者の張り込みの心理状態を描く曲、だそうだ。早くも七月十九日に発表され、ネットのCMのBGMにするというから、題名は交響曲でも短く、フルオーケストラではないものなのか。
どうせなら規模を大きく、《HIROSHIMA》の録音準備を整えながら、あの事件で阻まれて悔しがったというネーメ・ヤルヴィが、あわせて録音できるようなものにしてもらいたい。「つくらされたもの」と「つくったもの」がどのように違うのか、同じ演奏家で較べてみたいから。
六月二十九日(日)フルシャのスーク
東京都交響楽団を東京芸術劇場で。指揮はヤクブ・フルシャ。
フルシャのお国もののスーク・プロ。組曲《おとぎ話》と交響詩《夏の物語》の二曲。昨年絶賛されたアスラエル交響曲を聴けなかったので、今日は楽しみだった。期待を裏切らぬ出来。美しい、澄んだロマンチシズム。
六月三十日(月)大野和士とリヨン
フランス国立リヨン歌劇場管弦楽団の来日公演をオペラシティで。指揮は大野和士。
ルーセルの《バッカスとアリアーヌ》組曲第二番、ラヴェル:ラ・ヴァルスと《ダフニスとクロエ》全曲。おしまいの曲の合唱はフランス国立リヨン歌劇場合唱団。
この指揮者らしい、隅々まで張りつめた緊張感と色彩感。ゲストで参加した上野星矢の首席フルートが鮮やか。
七月一日(火)二十世紀オペラ特集
今日はミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」収録。いつもと少し趣向を変えた特別篇「さらば夏の日~二十世紀オペラ特集」。
この半年くらいに発売されたオペラの全曲録音盤を眺めていたら、バロック・オペラと同じくらいに二十世紀オペラが含まれている。そこでそれをまとめて、この二年ほどの新譜のなかで紹介できていなかった盤もあわせて一週間五日、二十九時間の番組で放送することにした。
放送は八月二十五日(月)~二十九日(金)の十八~二十四時(最終日のみ二十三時まで。翌週深夜に再放送)。
オペラとオペラ的オラトリオ、ミュージカルを計十二本。
・二十五日 ティーレマン指揮《エレクトラ》(DG)、ヴァイグレ指揮《西部の娘》(OEHMS)
・二十六日 レスピーギ作曲《マリー・ヴィクトワール》(CPO)、リリング指揮の《火刑台上のジャンヌ・ダルク》(Hanssler)
・二十七日 カンブルラン指揮《モーゼとアロン》(Hanssler)、フリッツ・レーマン指揮《死の都》(Myto)、コルンゴルト作曲・指揮の《沈黙のセレナード》(ARCHIPEL)
・二十八日 シュレーカー作曲の《烙印を押された人々》(BRIDGE)、ベッドフォード指揮《ピーター・グライムズ》(Signum)
・二十九日 ガーディナー指揮の《エディプス王》(LSO Live)、サロネン指揮《青ひげ公の城》(Signum)、ティルソン・トーマス指揮のミュージカル《ウエスト・サイド・ストーリー》(SFS Media)
一九六〇年以後の作品が入っていないなど、新譜がメインなので選択の幅は限られるが、それなりにヴァラエティがあって、演目の流行や各国のレーベルの動向があらわれていると思う。
七月六日(日)江戸城に本丸御殿を!
江戸城天守閣の再建という話があるらしい。
私は反対。「お城=天守閣」という発想は江戸城の場合、あまりに安易で幼稚に思える。高層ビルだらけの東京に復元しても、ほとんど見えないだろう。どうせやるのなら、金がもっとかかっても本丸御殿の方が面白い。
なぜなら江戸城天守閣は、明暦の大火で焼け落ちたとき、保科正之が再建無用と進言し、以後二度と存在しなかったということ以外、特に事件もない。
松の廊下とか、人気の大奥とその御鈴廊下とかがあった本丸御殿を復元した方が、よほど愉しいではないか。
かつて名古屋城を見て思ったが、天守閣というのは生活感のない建物だから、基本的につまらない。だから、いま本丸御殿の復元工事を名古屋城が長い時間かけてやっている意味は、あの場に立ってみるとよくわかる。人間が生活して仕事して、ドラマが演じられてきたのは本丸御殿なのだ。歴史の息吹を感じさせてくれるのはそれ。
それに江戸の場合、我々がそのよすがを知っている都市のかたちは、明暦の大火を契機とする復興政策以降に形成されたもの。それより前にしか存在しなかった、江戸がもっと小さかった時代の天守閣など、いらない。
江戸城はむしろ、天守閣がないことにこそ意味があった泰平の巨城。保科正之にならって、いまこのときこそ、声を上げて言おう。
「泰平の世に天守閣は無用」。
七月九日(水)インタビュー・ウィズ・バッケッティ・アゲイン
『レコード芸術』のために、ピアニストのアンドレア・バッケッティにインタビュー。
二年前、札幌のPMFに出演して帰国する直前に東京でインタビューして以来二回目。前回は札幌でしか演奏しなかったので実演は聴けず、国内盤もまだ出ていない段階だったが、今回は東京など全国各地で公演、国内盤も出たばかり。このまま順調に知名度と評価が高まってくれれば、ファンとして素直に嬉しい。
相変わらずの機関銃トークだったが、今回の方が落ちついて話を聞けたから、インタビューに活かせる部分が多そう。
部屋にピアノがあったので、途中でにわかに立ち上がると、ゴルトベルク変奏曲のアリアと、モーツァルトのピアノ四重奏曲の初めをひいてくれた。役得。
十四日にトッパンホールで初めて実演を聴ける予定で、それも楽しみ。
七月十一日(金)ラジオとマンガと交響曲
昼間、TBSラジオの「大沢悠里のゆうゆうワイド」でやっていて噴き出してしまった、どなたかの川柳。
「馬鹿息子 ホントに会社の金つかい」
いまのご時世、親に急な穴埋めを頼んでも、すぐには信じてもらえない可能性高し。
さてまたしても(嗚呼、またしても)月誌各誌をデッドラインギリギリでしのぎきり(編集さんゴメンナサイ)、一息ついた今日の宵。
本屋に行ったら、なんと『海街diary』の六巻が出ていた。脇には『アオイホノオ』の十二巻も並んでいた。大喜びで購入。
数日前の「留守と言へ ここには誰も居らぬと言へ」(高橋新吉)状態で電話もメールも一切返事できませんのときにも、抜け出して本屋に行ったら『百鬼夜行抄』の二十三巻が出ていたので、「宿題が終ったら読むこと」で、袋にしまってある(小学生だ)。
今日はその三冊を読む。
だからまた
「留守と言へ ここには誰も居らぬと言へ」
と思っていたら、ネーメ・ヤルヴィがエストニア国立交響楽団の定期演奏会で佐村河内守/新垣隆の交響曲第一番《HIROSHIMA》を取りあげる、というニュースをネットで知る。
来年五月十四日の演奏会で、曲はほかにR・シュトラウスの《日本建国二千六百年祝典曲》とプロコフィエフのピアノ協奏曲第二番(テンクー・アーマド・イルファン独奏)。
パパ・ヤルヴィの弟子の指揮者、徳岡直樹さんにきいた話だが、もともとヤルヴィはこの曲を高く評価していて、録音の準備を進めていたという。ところが四月にNHK交響楽団の客演に来日したさい、事件のために演奏できなくなったことを知り、「作品自体には関係がないじゃないか」と悔しがっていたそうだ。
知名度の低い管弦楽曲に光をあて、積極的に演奏と録音をしてきたパパ・ヤルヴィ、ひるむことなくまず実演にこぎつけたわけだ。作曲者に新垣さんの名前もあるから、手続き上の問題は解決しているということなのだろう。
七月十二日(土)日本のサッカーとは
ネットの「Number Web」に掲載された西川結城のコラム『W杯前の闘莉王の言葉が頭をよぎる。本当の「日本のサッカー」とは何か?』を読んで、生半可なサッカー好きの自分は、とても納得がいった。
「サッカーは何も“殴り勝つ”ことだけが勝利の条件ではない。今回のW杯でも、前からのプレスがかからなければ、少し引いて陣形をコンパクトにしつつ、組織的な守備で対抗してもよかった。4年前の“守り耐えて勝つ”スタイルとまではいかなくても、選手たちがもっと柔軟に、より組織的にプレーすることはできたはずだ」
「世界を相手に、時間帯によってはディフェンシブに振る舞う。それは消極的なスタンスどころか、現時点での強豪国との実力差や日本人の国民性に鑑みれば、自然と自分たちの“耐える力”を発揮できる戦い方だったのではないか」
目指すべきは、分をわきまえ、謙虚に献身的に、耐えがたきを耐え、己れを見失うことなく、最後の最後に勝つサッカー。高倉健&池部良の男の美学。「死んでもらいますサッカー」。
でも、日本にいれば自然な感覚でも、外国に行って戦っている選手には困難なのでは?という気がする。
阿吽の呼吸でグっとこらえるサッカーなんてやっていたら、理解されずにレギュラーをとれないのではないか。個々の選手としてのかれらは、つっぱって自己主張しなければ戦えない。
してみると今回の日本代表は、帰国子女選手が外国人監督のもとで「欧米ではこれがスタンダードなのよ」とか、そんな論理を振りかざして失敗したのか?
でも選手としては魅力的で、ゼニもとれる。ザッケローニ就任後の二年間くらいは、本当にワクワクさせてくれた。
それなら、四年間をわけてチームづくりしたらどうか。アジア杯とW杯のアジア予選は、外国人監督と帰国子女チームで、派手に攻撃的に、思う存分戦う。たぶんそれで間違いなく勝てる。
そしてコンフェデレーションズ杯で木端微塵に負けて、欧米の強豪には通用しないことを確認したのち、W杯では日本人監督に切り換えて、高倉健&池部良のガラパゴスチームを編成、「死んでもらいますサッカー」でベスト4を目指す。
というと、結局はオシム~岡ちゃんのあの流れが理想、ということか?
七月十四日(月)バッケッティ演奏会
CDをほとんど集め、これまで二回もインタビューしながら実演を聴けていなかったイタリアのピアニスト、アンドレア・バッケッティの演奏をようやくトッパンホールで聴く。
「今回の」ゴルトベルク変奏曲はセンツァ・リトルネッロ、一切反復なしの一気呵成ヴァージョン。これまでの三種(DVD+CD、CD)の反復つき、装飾たっぷりのヴァージョンとはまったく違っていて、じつに個性的で面白し。新たなソニーへの録音は、今日と同じ反復なしと反復つきの二種を収録する予定だそうで、これで都合五種のゴルトベルクを世に出したことになる(笑)。
後半はモーツァルト。あまりひいていない作曲家というけれど、軽妙なタッチで戯れるようにひきながら、ニ短調(幻想曲)とハ長調(ソナタ)の暗い影を浮き彫りにしていく、音のドラマ。
そしてアンコール、「今日は後半が少し短いので」と前置きして、今回のツアーの他会場で後半にひくことになっている、アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳からの四曲(フランス組曲第五番を含む)を、ノンストップで全部ひいた。前半のプロをこれで受けなければ、きっと気持が収まらないのだろう。インタビューで「バッハ・プロは、できればゴルトベルクのあと休憩なしで一気にひきたい」といっていたくらいだから。
ここでは前半にあった硬さがとれて、この人の魅力であるリズムの弾みと「憂いをはらんだ祈りの歌」がはっきりと出てきて、以前からのファンとして嬉しい(スタインウェイではなく、かれが「イタリアの誇り」と呼ぶファツィオリで聴いてみたかったけれど、それはまたのお楽しみ)。
さらにアンコール二曲、曲名がよく聞きとれなかった曲(他会場の情報によるとヴィラ・ロボスの《道化師》らしい)と、ショパンの黒鍵のエチュードを一気呵成にひいて、わかせておしまい。
これで神戸と東京の二か所が終って、あとは静岡・名古屋・京都・武蔵野の四公演(京都は協奏曲)。成功を祈る!
七月十七日(木)音楽評論家の生と死
「吉村渓さんのお別れ会」に行く。会場は、杉並区和泉にある室内楽演奏ホールsonorium。
今年二月二十六日、五十歳で成人T細胞白血病のために亡くなられた、音楽評論家の吉村渓さん。一年のつらい闘病のあいだ、生の音楽を聴くことを切望していたという吉村さんのために「故人に捧げるコンサート」に出演してくださったのは、オーボエの古部賢一さん、ヴァイオリンの深山尚久さん、ピアノの三輪郁さん、ハープの吉野直子さんという、豪華なメンバー。
追悼演奏会では拍手はしないのが慣例だが、今日は普通のコンサートのように拍手をと、心のこもった会を企画してくださった実行委員の方から要請あり。吉村さんの遺影と一緒に音楽を聴き、演奏者に感謝の意を込めて拍手をする。
自分のような仕事を東京でやっていると、ナマの音楽を聴けることが当り前になってしまっているのだが、それがいかに恵まれたことかを、素晴らしい演奏を聴きながら、あらためてかみしめる。
そして、その感謝すべき音楽と演奏家に対して勝手なことをいってのける、評論家という因果な稼業を思う。
今日の美しいプログラムに再録された四国新聞掲載の「批評行為の難しさ」という一文に、吉村さんは書いている。
「談笑する輪の中にいて意気投合したつもりでも、評論家という名刺を出した途端に相手の態度が豹変するといった経験は一度や二度ではない」
しかしその先を、つまりアーティストとの実り豊かな関係を構築することも可能なはずで、それには、
『自分の基準となる審美眼を常に磨き、その是非を厳しくチェックし続ける必要がある。「何でもほめる」は、評論家として誠実な態度とは言えない。評論家もまた、対象者と読者の両方から「批評」されるのだから』
素晴らしいアーティストが今日ここで音楽を奏でてくれるのは、吉村さんが誠実な態度をつらぬいたからこそ、。
だが志半ば、まだこれからという年齢で病に倒れねばならなかった。無念の思いに打ち克ち、自分と愛するご家族のために生還しようとした、文字通り命懸けの闘病。それを許さぬ、運命の力。
風船のように生きている自分を叱咤する、生と死。
お会いできた機会はわずかでしたが、本当にありがとうございました。いまはどうぞ、安らかにお休みください。
七月十八日(金)労音と浅野翼の本

長崎励朗の『「つながり」の戦後文化誌 労音、そして宝塚、万博』(河出書房新社)を読む。
副題にあるとおり、労音(勤労者音楽協議会)の盛衰を、その中心的存在だった大阪労音を軸に描いたもの。
労音に関して客観的な資料というのはじつに少ない。同時代のものは左右のイデオロギー対立を反映して色がついていることが普通(『恐るべき労音』など)だし、時代が降れば降るほど、建前の背後にある本音が見えなくなってくる。当時の人が「誰もがわかっているからあえて口にしないこと」が、後世ではわからなくなってしまうのだ。
著者は一九八三年生れだから、物心ついたときには冷戦が終っていたろう。その「冷戦後派」の目で、関係者や機関誌などの一次資料に直接取材して、私などは中途半端にしか知らない、労音の実像にせまっている。日本共産党との関係という、微妙で複雑な「闇」の部分に肉薄しきれなかったのは残念だが、それでも多くのことを教えてくれた。
特に、山崎豊子の小説『仮装集団』の主人公流郷正之のモデル、浅野翼について調べてくれたのは嬉しい。
また、『ミュージックマガジン』をつくったのが、一九六九年に大阪労音を大挙退職した人たち(中心となった中村とうようは別)という記述も面白かった。
七月十九日(土)ひとりよりもふたりが良い ツィンマーマンとベートーヴェン
すみだトリフォニーで新日本フィルの演奏会。インゴ・メンツマッハー指揮。
仕事がぐちゃぐちゃで演奏会など行ける状況ではないのだが、ツィンマーマンの曲の評判が高く、次にいつ聴けるともわからない作品なので、無理して行くことにした。
仕事がぐちゃぐちゃで感想など書ける状況ではないのだが、ものすごく面白くて、頭の中にあふれる言葉を出してしまわないと仕事にならない状況なので(そういうことにして)、書くことにする。
今年のメッツマッハーはベートーヴェンとB・A・ツィンマーマンを組みあわせた演奏会を、四回行なう。現代曲を人気曲でサンドイッチして、幅広い聴衆に聴いてもらうのはメッツマッハーお得意の手法だが、今回の組み合わせは、それ以上に積極的な意味を感じた。
時代も作風も知名度も、ベートーヴェンとツィンマーマンは対照的だけれど、この両者には共通点がある。メッツマッハーはそれを浮き彫りにしようとする。
プログラムの青澤隆明さんの解説にある指揮者の言葉を孫引きすると
「両者とも存在論的な意味で、人生を深刻に思索した。意味を持たぬ音はひとつとしてない。形式はつねに闘争のかたちをとる。背後には作品全体を貫く不屈の意志の力がある」
曲は三つ。ベートーヴェンのバレエ音楽《プロメテウスの創造物》序曲、ツィンマーマンの《私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た》(日本初演)、そしてベートーヴェンの交響曲第五番ハ短調。
再びプログラムから指揮者の言葉。
「3作いずれも超越的な力に対する抵抗を描いている。神であれ、権力や体制であれ、私たちを支配するものに対する英雄的な闘争の音楽だ」
ただし「ベートーヴェンでは光が打ち克ち、ツィンマーマンでは闇が勝つ」
まず《プロメテウスの創造物》序曲が開幕を告げる。中世の迷妄、教会と王権の桎梏を脱して始まる、革命とナポレオンとヘーゲルとベートーヴェンの「エロイカの世紀」、ヨーロッパ近代の火。
ツィンマーマンの《私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た》はどんな作品なのか、今日聴くまで、まったく知らなかった。
旧約聖書の伝道の書にあるソロモン王の言葉と、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」の部分とをつなぎあわせたもので、ツィンマーマンが一九七〇年に自殺する直前に完成した遺作だけに、厭世的な気配が濃い。バス独唱(ローマン・トレーケル)と二人の話者(松原友、多田羅迪夫)がテキストを歌い、語る。
「大審問官」というとボリス・ブラッハーのオラトリオしか知らなかったが、ツィンマーマンも書いていたのだ。
異端審問と宗教戦争の中世、九十歳の大審問官の前にあらわれた、復活したキリスト。何ら力をもたぬ、徒手空拳の強者。すなわち精神の強者。
同じく精神の強者を目指したのに挫折して、自由の重みに耐えられない弱者の群れを束ねる教会の「権力者」となった大審問官にとってキリストは、自らの弱さと矮小を思い知らされる、憎むべき存在でしかない。その孤独と敗北が、ソロモン王晩年の厭世観に重ねられる。
最後のソロモンの言葉。
「ひとりよりもふたりが良い。共に労苦すれば、その報いは良い。倒れれば、ひとりがその友を助け起こす。倒れても起してくれる友のない人は不幸だ」(舩木篤也訳)
このあと、バンダのトロンボーン三本が鳴り響いて「最後の審判」の到来を告げ、バッハのコラール〈事みちたれり〉の断片があらわれ、歪んで終る。
このコラールはベルクの遺作、ヴァイオリン協奏曲にも引用されたもの。バッハとベルクの影。それに「倒れても起してくれる友のない人は不幸だ」という詞は、シラーの「歓喜の歌」の一部分を想起させるから、ベートーヴェンの影もある。
ここまでが前半。後半がベートーヴェンの第五番。
今回と前回の新日定期、ツィンマーマンの好評に較べて、ベートーヴェンはあまり評判がよくないようだが、私にはとても面白かったし、ツィンマーマンのあとを見事に受ける演奏だと思った。
もっと新即物主義風の、筋肉質で強い響きのベートーヴェンかと思っていたがそうではない。ベーレンライター新版による、ピリオドの響きを意識した、音の減衰の早い、澄明度の高い響き。運命動機もアクセントを抑えて早口に奏され、仰々しくならない。
驚いたのは、その音楽の寂しさ。音楽の雄弁法の代名詞みたいに思っていた交響曲第五番が、あちこちで口ごもり、言いよどみ、気まずい沈黙で途切れる。その沈黙の直前に一人残る木管の音色の、なんと孤独で寂しいこと。まるでクレンペラーみたいな木管の強調が、見事な効果を生んでいた。
あの「運命」ではなく、まるでシューベルトの《未完成》のような、疎外感に満ちた、モダンな響き。
三楽章までこの調子で進んで終楽章。どうなるのだろう、嘘の歓喜、マーラーの第七番終楽章のやけくその狂躁みたいになるのかと思ったら、そうではない。ちゃんと輝かしく、力強い。
ただ、例の三楽章からの導入はもったいぶらず、かなり唐突に、凱歌が奏でられた。人間が自分の力でつかんだ勝利というよりも、外から転がり込んできた勝ち星のような。
ここで思ったのが、ベートーヴェンがこの終楽章でトロンボーン三本を投入したこと。かれの交響曲では初めてのトロンボーンで、それを終楽章だけ用いた。
それまで、トロンボーンはおもに教会で用いられ、世俗音楽ではほとんど使われなかった。つまり「神の楽器」。それを世俗音楽に持ちこんだことにベートーヴェンの人間讃歌を普通は見るのだが、今日の演奏はそうではなく、「最後の審判」そのものが突然にきてしまったような、天使の大軍勢が空に現れたような、そんなふうに思えた。
それは、ツィンマーマンの作品の最後のトロンボーン三本のバンダと重なるから。これが、ものすごく面白かった。
終楽章でも木管のソロが出てくると、やはりメッツマッハーは浮きあがらせて強調する。孤独を歌っていた木管が、いまや神と天使と聖人の列に伍しているかのように。
メッツマッハーがいっていた「光が打ち克」つとは、けっして現世的な勝利ではないのだと思う。ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》と同じく、黙示録の世界での、自分が一度死んだあとでの、復讐的な勝利。
そのある種の虚しさが、今日の演奏にははっきりと出ていたように思えた(だからもう少し、終結で沈黙の余韻をかみしめたかったけれど、フライング気味の喝采でかき消されてしまった)。
トロンボーンが三本なのは、演奏上の実用的な意味合いがあるはずだが、同時に三は、三位一体の「神の数字」。
メッツマッハーが新日本フィルに初登場したとき、チャイコフスキー、マーラー、ハルトマンの三つの交響曲第六番を演奏して「666」、「獣の数字」をつくってみせたことを逆に思い出したり。
ツィンマーマン作品のソロも三人。しかし話者は二人。「ひとりよりもふたりが良い」。二こそが「人間の数字」なのか。
人が二人と書いて、人間関係の理想的状態を示す、「仁」という字を思い出したり。
でも、ツィンマーマンもベートーヴェンも、ひとりぼっち。
それを思い知らせてくれる演奏会。感謝。
七月二十一日(月)マーラーの十番
サントリーホールで東京都交響楽団の演奏会。指揮はインバルでマーラーの交響曲第十番(クック補筆)。第一楽章と第三楽章で、マーラーのオーケストレーションが第九番以前よりもさらに進化していることを痛感する。一九一〇年、この時期に華麗に開花したロシアやフランスの同時代音楽からの影響はあるのだろうか。第一楽章クライマックスのきしむ不協和音の咆哮が、爛熟する時代の、滅びゆく恐竜の断末魔の叫びのようでもあり、崩壊の予感のようでもあり、素晴らしかった。
これに較べると、第二、四楽章のオーケストレーションは平凡というか薄いというか、従来のマーラーの響きの範疇にとどまる(補筆だから仕方がない)。それでも、クライマックス以外は第九番によく似た雰囲気の第一楽章で終ってしまうのと、そこから始まるのでは、曲の意味がまるで違う。その意義を教えてくれる演奏。
さらに終楽章は、未完成の不満など忘れさせる凄さ。大太鼓の不気味な強打に始まって、オーケストレーションも鬼気を放つ。
どうにもマーラーらしくない、オペラの一節のように滑らかな、なんというかベルカントな、不思議なメロディ。第六番と第七番の終楽章を混ぜたような、奇妙な悲喜劇も闖入する。喜怒哀楽の感情が入り混じったままクライマックスの弦楽器のグリッサンドに突入して、無重力状態のような浮遊感を味あわせたのち、音楽は一気に収斂して、ブルックナーの第九番終楽章の、あるいはベートーヴェンの三十二番のピアノ・ソナタのラストのごとく、高空へ吸い込まれるようなコーダへ。
この音楽から、頽廃よりも新世紀の澄んで乾いたモダニズムをつねに感じさせたのは、インバルの力。その精緻な指揮と、高い技術と集中で応えた楽員、それぞれに感謝。
七月二十四日(木)川の両岸
芭蕉の『奥の細道』の出発地(矢立初の地)が南千住なのか北千住なのかをめぐって、隅田川両岸の荒川区と足立区が対立しているというニュースをみる。
川を境界線として市町村を区画することから起きる、無益な対立。往時の千住の宿場は、川をはさんで両岸にあった。川を生業の場としている人にとっては、どちらの岸も一つの生活空間として、頻繁に往復するもの。
橋が架かっていない渡しなどは特にそうで、同じように、世田谷区と川崎市の双方に「等々力」という地名があるが、あれも元は両岸あわせて、一つの等々力村。
川の両岸で権利関係が何かと対立しやすいのは事実だから、一つの村とすることで調整を容易にするという古来の知恵の正しさが、この問題で逆に裏付けられている。
荒川区としては、隅田川の手前が江戸で、橋をわたって出発という感覚らしいが、どちらだろうと千住の宿場はもう江戸ではない。だから芭蕉もいちいち書いていないのだろう。まあ、普通に考えれば隅田川を舟でさかのぼってきたら、北岸の足立区側に上陸して、そのまま北上するだろう。
カミソリ堤防で町と川とを遮断した光景しか頭にないから、川が土地と人をつなぐ生活の場だったという発想がなくなるのではあるまいか。
七月二十五日(金)新監督は誰
サッカー日本代表の新監督はアギーレかアギレか。混乱の主因は共同通信がアギレにこだわり、新聞がそれに従うためらしい。クラシックでもおなじみの外国人表記問題。
まあ「アギーレ」と聞くと、どうしても「神の怒り」と応えたくなるが。
七月二十七日(日)「魔法の大釜」
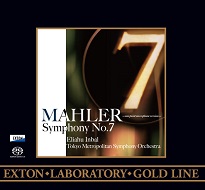
インバル&都響のマーラーの交響曲第七番の高音質ヴァージョン、「エクストン・ラボラトリー・ゴールドライン」。
本当にほれぼれとする、凄い音。鮮明で生々しい響きの定位感と、見通しのよい広がり。指揮者のつぶやきと歌声までバッチリ。
こんな大規模な作品をワンポイント・マイクで録っている。しかも音響の異なる、みなとみらいと東京芸術劇場の二回の演奏会だけが音源だ。
通常盤のSACDももちろんよい音だと思ったけれど、これはさらに上。私がナマで聴いた、芸術劇場での演奏の光景と空気が、眼前に再現されるような凄みがある。
江崎友淑のプロデューサーノートによると、日本ではインバルの旧録音以来、ワンポイント・マイクへの絶大な信頼感があって、これまで「エクストン・ラボラトリー・ゴールドライン」で出た第一番と第五番は、通常盤に匹敵する売り上げを記録していて、ご本人も「驚きを隠せない」そうだ。だがこの第七番の音を聴くと、税別三千八百円はまったく高くないと思う。
このときの演奏で受けた印象は、この日記の二〇一三年十一月九日のところに「ア・ラ・イタリアの道化音楽」として書いた。
道化の、コメディア・デラルテのグロテスクなユーモア。レオンカヴァッロの《道化師》の世界にも通じるもの。そして終楽章の、バフチン的なカーニバル。第六番で敗死した英雄をトリックスターとして再生させる、魔法の大釜(聖杯の原型)。
それを「二十世紀重工業音楽は俺たちにまかせろ」の都響が、ひんやりと醒めた陰惨さをはらんだモダンな響きと、驚異的な技量で音にしていることが、ここに半永久的に記録される。
このディスクもまた「魔法の大釜」。
七月二十七日(日)博士論文からの本
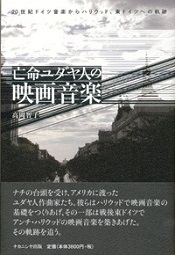
一九五四年と五五年をテーマにした本の原稿、亀の歩みで進めているのだが、いま取りかかっているのは、ハリウッド映画と芸術音楽の関係の話。
一九五四年秋にハイフェッツがカステルヌオーヴォ=テデスコのヴァイオリン協奏曲を録音しているのを「メインディスク」という「話の枕」にして、ハイフェッツがコルンゴルトなどハリウッド映画系の作曲家に委嘱して積極的に録音していたこと、そしてウィーンに帰ったものの、冷淡に扱われて傷ついていたコルンゴルトの交響曲が同時期に放送初演されたことを、組みあわせてみようというものだ。
資料探しをしていたら、こんな本を見つけた。高岡智子の『亡命ユダヤ人の映画音楽~20世紀ドイツ音楽からハリウッド、東ドイツへの軌跡』。
シェーンベルクとコルンゴルトに加えて、ハリウッドを追われたのち東ドイツでアンチ・ハリウッドの映画音楽をつくったアイスラーやデッサウに言及するという、バッチリすぎて怖いくらいの本。
神戸大学大学院の博士論文が元になっているそうだ。そういえば、吉田光司棟梁が教えてくれた森佳子の『オッフェンバックと大衆芸術 パリジャンが愛した夢幻オペレッタ』や、十八日の日記に書いた労音の本など、日本人による面白そうなテーマの音楽関係の本には、最近は博論を元にしたものがけっこうある。
文科省の博士大量生産計画は、小保方事件を象徴として弊害も多そうだが、その結果、著者が採算無視で書いた良書の淵源になりうる点には、大いに感謝。
八月三日(日)都響とミンコフスキ
今日は東京都交響楽団の「作曲家の肖像シリーズ」を芸術劇場で。指揮は初顔合わせのミンコフスキ。
日経新聞に評を載せる(十四日)ので簡単にするが、交響曲《ローマ》におけるメンデルスゾーンの《真夏の夜の夢》的な夢幻的叙情から、《アルルの女》での《カルメン》をこえ、すぐそこに《カヴァレリア・ルスティカーナ》の血と情熱と惨劇の世界が隠れている気配を感じさせる「歌のないオペラ」まで、ビゼーの天才をまざまざと感じさせる、素晴らしい演奏会。都響の演奏も見事だった。
アンコールでは鮮やかな《カルメン》前奏曲に続いて《アルルの女》のファランドールを急遽もう一度演奏、指揮を変えてよりダイナミックな表現を求めたミンコフスキに瞬時に対応して、現在の都響の能力の高さを実感させた。
インバルのマーラーの交響曲十番という記者さんからの提案を、「未来につながるものにしませんか」と、僣越にもこちらに変えてもらった甲斐があったと、まずは一安心。
とはいえ、マーラーの十番も素晴らしかったことは言うまでもない。この二つの対照的な演奏スタイルの演奏会は、並ぶことでさらに互いの効果を高めあう、好一対だった。
八月十三日(水)ブリュッヘンの一枚
フランス・ブリュッヘンの訃報。
ブリュッヘンで忘れられないCDといえば、ベートーヴェンの交響曲第一番。ちょうど三十年前の一九八四年五月のライヴで、翌八五年に、モーツァルトの第四十番との組み合わせで発売された。

一九八一年結成の十八世紀オーケストラのデビュー盤、指揮者ブリュッヘンのキャリアの始まり、そして――私の記憶が正しければ――ピリオド・オーケストラによるベートーヴェンの交響曲の、初のCDだった(LPでは、既にコレギウム・アウレウムの三、七番があった)。
ピリオド楽器による古典派交響曲録音の嚆矢となった、オワゾリールのホグウッドのモーツァルト全集はすでにかなり進んでいたが、ベートーヴェンはコレギウム・アウレウムしかなかった。数年前にその第七番をLPで聴いて、気の抜けたようなゆるい演奏に「古楽器オーケストラのベートーヴェンて、こんなもんなのか」とがっかりした記憶がある。
だから、自分にとってはこのブリュッヘンの第一番の躍動感に満ちた演奏が、ある「時代」の、本当の意味での始まりだった。
モーツァルトとベートーヴェン、年の差は十四歳。ところが「古楽器」の世界はこの十四年の壁を飛び越えるのが、かなり大変だった。モダンの側にも「ベートーヴェンはおれらのもん」みたいな意識が強かった。このディスクはそこに橋を架けた点で、まさに画期的だった。
自分が最初にCDプレイヤーを買ったのも、このディスクの少し前だと思う。まだCDの種類が限られていたころ。いまはなきPHILIPSレーベルで、佐々木節夫さんの日本語解説をつけて三千二百円(もちろん消費税はない)。その一、二年前まで、四千二百円とか三千八百円もしたから、これでもかなり安くなったものだった。
いろいろな「時代」の始まり。CDの登場をきっかけに、自分がなれ親しんだ輸入盤LPの個人店が消え、大型店中心に変っていく、その節目でもある。
およそ物持ちの悪い自分だが(まるでコレクターではない…)、このCDだけは何か特別な気がして、いまも手元にある。しかも、何よりも驚くべきことに、思いついたら探すまでもなく、すぐに目の前に出てきた。
今日はこれを聴いて、ブリュッヘンの追悼に。どうぞ安らかに。
八月二十二日(金)バロック・ギターの魅力
今日から「Hakujuギター・フェスタ2014」。九回めの今年のテーマは「フレンチ・ギターの魅力」。
このシリーズは本公演三回と期待の若手が登場する「旬のギタリストを聴く」の四公演からなっている。本公演は前半がゲスト、後半がホストの荘村清志と福田進一が演奏する構成が基本になっていて、ゲストは初日が古楽系、中日がジャズなど、楽日が海外ギタリストというパターン。狭くなりがちなクラシック・ギターの世界を時空を広げてさまざまに堪能させてくれるので、自分もサイトウ・キネンとともに毎年八月下旬の楽しみにしている。
今年初日のゲストはバロック・ギターの竹内太郎。十八世紀のオリジナルだそうで、細身の胴に五複絃、ガット絃を用いていることもあって音量はモダン・ギターよりもずっと小さいけど、これがじつに繊細でいい音がする。
古楽器は全般に、ナマで聴いてこそその魅力がよくわかる。そよ風のように優しく、慎ましやかに空気を震わす感じというか。まさにアコースティック。
こういう音のそよぎに接すると、不便で不安定な古楽器をあえて愛する音楽家が少なからず存在する理由が納得できる気がする。
録音ではなく、ナマを聴いてもらえれば日本のクラシック好きに多い古楽アレルギーもかなり減少すると思うのだが、およそ大ホール向きではなく、奏者の技量が水準に達しないと弱点ばかりが目だちそうなのが、古楽器の難しいところ。
しかし今日の竹内は素晴らしかった。一曲めのコルベッタのシャコンヌでは、くり返される低音がだんだん足拍子や手拍子に聞こえてきて、かれのまわりで拍子をとり、はやす人々の幻影が見えるようだった。
そして次のド・ヴィゼの組曲ニ短調では、その幻影が実体化したように、客席後方からバロック・ダンスの「市瀬陽子とセーヌ・エ・サロン」の女性八人がロココ風の装束で登場、ギターにあわせて舞い、踊る。
前奏曲、マスカラード、ブーレ、サラバンド、メヌエット、舞曲って舞曲なんだよねという、当り前のことなのにクラシック好きが忘れがちな事実を、思い起こさせてくれる。振付はすべて市瀬陽子が記録に基づいて復元したもの。
「スペインのフォリア」による即興演奏では、象牙でできた十八世紀のカスタネットを鳴らしながら踊る。
コントルダンス「レ・マンシュ・ベルト」のメロディは、有名なグリーンスリーヴス。竹内によるとこの旋律はイギリス起源ではなく、フランスから、その前はイタリアから、さらに最初はポルトガルかスペインからきたものだそう。イギリス風のカントリー・ダンスを原型とするフランスのコントルダンスで、四人ずつでつくる二つの円がきれい。
竹内のギターにもこの「舞いと踊り」のセンスが見事に活きていたが、そのひとつの要因は、かれが立って、動きながらひいたせいなのかも知れない。
というのも、途中で一曲だけ椅子に座ってひいた、クープランの鍵盤音楽を編曲したロンド「修道女モニク」は、ちょっとしゃっちょこばった感じで軽快さに不足したから。でもこれを聴いたとき、よくもわるくも、いかにも「クラシック音楽」っぽいとも思った(笑)。
後半は福田進一と荘村清志のソロ。なかでも福田のサティのグノシエンヌ第一番とジムノペディー第一番が妖しい響きで、魅惑的だった。
二日めは残念ながら行けないが、午後に小暮浩史のリサイタル、夜は前半がジャンゴ・レナール(ラインハルト)のホット・クラブ五重奏団と同じ編成による東京ホット倶楽部バンドの「マヌーシュ・ジャズ」に、後半が鈴木大介の「シャンソン」と、これもとても面白そう。
そして明後日は前半に福田いうところの「革命的ギタリスト」マルシン・ディラが登場し、後半は荘村清志、福田進一、鈴木大介、小暮浩史の四人の「饗宴」で、ローラン・ディアンスの新曲《ハクジュ・パルス》など。
八月二十四日(日)代ゼミ縮小
駿大、河合塾とともに三大予備校と並び称された代々木ゼミナールが、来年三月末で全国二十七つの校舎を七つに縮小し、全国模試を廃止するという。
代ゼミを全国規模に発展させた元理事長の高宮行男(一九一七~二〇〇九)のことは、佐野眞一の『あぶく銭師たちよ!』で読んだことがある。団塊ジュニアを最大の商機ととらえて、鼻息荒く拡大戦略をとる一九九〇年前後の姿が、ほかのバブル紳士たちとともに活写されていたが、それも今はむかし。
ある資料によると、予備校生がいちばん多かった時期、二十万人を超えていた時期というのは意外にも一九七五~八五年、つまり昭和三十年代生れのあたりなのだとか。全体の人数は団塊と団塊ジュニアの狭間で多くなかったのに、受験戦争、いわゆる「教育ママの時代」で、当然といえば当然か。
一九八〇年前後は、日本が豊かになって進学率が倍に急上昇して十年前の団塊時代よりも人数そのものが増えたのに、大学の定員拡大が追いつかなかったのだろう。思い出したが、一九八一年に入った自分の語学クラスは、二十人くらいのうち、現役はほんの数人だった。高校時代の友人も、かなりが浪人していたように思う。高校と大学のあいだに予備校一年をはさむのは、ごく自然だった。
おそらく、ひのえうまで子供が減った一九八五年に、十年続いた志望者と定員の一年のズレを一気に解消し、そのあとの団塊ジュニアには波及しなかったのではないか。
そして、本来なら人数が多いはずの昭和四十年代の団塊ジュニア世代は、やはり商機と見た大学の定員が激増し、あまり浪人せずに現役で入るようになった。この流れは少子化でどんどん強まったろうから、代ゼミのように、超一流の難関よりもその下を狙う受験生が多い予備校だと、特に影響が大きそうだ。
しかし、これだけ受験競争がゆるんでお客さん扱いをずっと受けてきて、生まれて初めて直面する厳しい選抜が就職活動では、そりゃ若い人はきついだろう。「中二病」ならぬいま流行の「大二病」が本当にあるのだとしたら、入試の容易化も深く関係あるのかも。
八月二十五日(月)刮目して見よ

ケント・ナガノ指揮のモントリオール交響楽団による、ベートーヴェンの交響曲第一番と第七番のCDのこと。
ミュージックバードの新譜番組「ニューディスク・ナビ」で取りあげるため、さして期待もせずに(すいません)聴いてみたら、じつにいい演奏だった。モダン楽器による、ピリオド・アプローチをとりいれたベートーヴェン。シリーズの最初の方の何枚か(第五番とか《英雄》とか)は、文学史的な意味では凝ったプログラムだが、音楽面でそれ以上の「サムシング」を感じることはなかった。
ところがこの第一番と第七番には、文学史的な意味づけがない(旅立ち‐理想郷、と副題らしきものがあるだけ)かわりに、演奏が素晴らしい。自然な躍動感と緩急強弱の変化にみちて、音と音が対話し、呼応し、生き生きと飛び跳ねる。第七番の終楽章、音に音が重なって、ぐわっと巨大にふくらむ瞬間なんて、さんざんに聴いてきた曲なのに、あきれるほどに新鮮。ケント・ナガノって、こういう一面ももっていたのか。いつものことながら、先入観にとらわれてはいけないと反省。
どうやらこの一枚が新本拠地でのライヴ録音であることが大きな意味を持っていそうだ。前作の第九がこのホールのこけら落としライヴで、あるいはそこから変ってきたのだろうか。確かめるべく、ちゃんと聴きなおしてみようと思っているが、CD山脈のどこかで遭難中…。
八月二十六日(火)今年も松本
名称変更により「最後」となる、サイトウ・キネン・フェスティバル松本へ。
ルイージ指揮の《ファルスタッフ》。俊敏な音楽に、やはりこの人の本領はイタリア・オペラにこそあると再確認。
八月二十七日(水)ウツボな人々
フェイスブックのフレンドの方の話。拙訳のジョン・カルショー『レコードはまっすぐに』を買おうと思ったが、アマゾンでは品切で、マーケットプレイスではかなりのプレミアムがついていた。この値段では買えないと思ったところ、ジュンク堂のサイトで普通に新品を正価で売っているのを教えてもらえて、無事に購入できたという。
アマゾンのマーケットプレイスにときどきある、本やCDで正価の数倍以上になる値付けは、相場とはまったく関係ないものだと思っている。
旧来の古書店や中古盤店が長年の経験や需給動向のなかでつくった適正な価格と、かけ離れているからだ。
新品や廉価な中古が出払ったとき、どうしてもすぐに欲しい人はそれで買うほかない。本当に入手しにくいものならそれもしかたないが、たまたまアマゾンのサイトで品薄になっただけ、ということもありうる。
「とりあえずアマゾンで見てみる」という、ネットでやりがちなクセ、かくいう自分もその典型だが、その心理を利用した商法らしい。
アマゾンはあくまで数ある販売サイトの中の一つにすぎないのに、あまりに流通量が大きくて手軽で、マーケットプレイスで中古も買えるので、どうかすると市場そのものと錯覚しがち。ここで新品が品切だと、他のサイトにもないような気になったりする。それを利用して、プレミアムをつけるのだ。ところが、まさにこの本のように、別の書店サイトでは普通に新品が残っていたりするのだ(ただし品切で増刷は見込めないので、残り少ないことは確かだ)。
はたして売れるのかどうかわからないが、トンデモ価格だけに間違って一つでも売れれば、いい儲けになる。ウツボのように客をじっと待つ作戦。もっとも、客のほうにも、こうしたプレミアムつきに引っかからずにじっと待って様子をうかがい、たまたま底値におりてきた品を見逃さずにガブッといく「ウツボ買い」をする人も、これまた私を含めて多いのだが(笑)。
ともあれ、市場において寡占はよくないという一つの例だろう。
八月二十九日(金)故人の指揮者三人
ミュージックバードのウィークエンド・スペシャルの六時間枠で、マゼールとブリュッヘンそれぞれの追悼番組を収録(放送予定は十月)。
収録後、一月に亡くなったアバドとあわせて、あらためて思ったこと。
三人はほぼ同世代。マゼールが一九三〇年、アバドが三三年、ブリュッヘンが三四年。しかし、三人のオーケストラとの関わりかたはまさしく三者三様で、それが「オーケストラとは何か」という問題を考える、一つのヒントになっているのが面白い。
ピリオド楽器への態度とも関わるのだけれど、色眼鏡になりがちなそれはいったん外し、純粋に人間の集合体としてのオーケストラのあり方から考えてみる。
十九世紀末から二十世紀前半にかけて完成した、企業としての交響楽団。アメリカのそれを典型として、演奏会の企画と組織の管理運営、ホールや練習場も含めた興行システムになっている。ある意味で、二十世紀の巨大工場やプラントにも似た合理的なシステム。金銭的な利益だけを優先するシステムではないが、資本制の社会に合致した文化集団。
ほぼ、この興行システムのなかだけで生き、喜怒哀楽をともにし、死んでいったのがマゼール。
そこに動脈硬化、時代的限界を感じ、ユースオーケストラの育成、その発展形としての(ピリオド・スタイルを含む)各種の室内オーケストラ、そして臨時編成のルツェルン祝祭管弦楽団と、別の地平を求めていったアバド。
面白いのは、このアバドがけっして挫折者ではないこと。ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、ベルリン・フィルという各ジャンルの頂点を三つとも制覇して、カラヤンでさえなれなかった「覇者」であること。
逆にマゼールは「企業としての交響楽団」の頂点、ベルリン・フィルのトップに昇りつめることはとうとうできなかった。だからこそかれは、最後まで二十世紀風の興行システムのなかに生きようとしたのかも知れない。かれはバーンスタインとはまた違ったところで、典型的なアメリカの指揮者だったのだろう。
そしてブリュッヘン。クラシックのアメリカ化、グローバル化への異見表明という一面ももっていた古楽運動に学生時代から身を投じ、「企業としての交響楽団」とは無縁だった男。四十代半ばまで演奏家で、そのあと指揮者になった男。神童として、生まれながらに交響楽団の指揮者だったマゼールとは対照的。
その十八世紀オーケストラは、音楽家仲間が室内楽をやることの延長に形成される、新たなオーケストラ。歴史的な十八世紀以前のオーケストラがこういう自由な形、二十世紀の市民運動的な意味での個人の自由さを基礎に形成されたとは思えないので「新たな」。
ブリュッヘンの死とともに十八世紀オーケストラはたぶん終るだろうし、アバドの死でモーツァルト管弦楽団やルツェルン祝祭管弦楽団は、なくなりはしないが変化を余儀なくされる。マゼールの死で失われる、あるいは大きく変るオーケストラは、たぶんない。
それぞれのあり方をふり返りつつ、これからオーケストラはどうなっていくのだろう、と考えてみる。
三歩あるくと、もう忘れているが。
八月三十日(土)軍人ふたり
元海軍軍人ふたりの本。海軍兵学校六十八期の同期生、豊田穣と松永市郎。
六十八期というのは一九四〇(昭和十五)年八月に卒業、中尉で開戦を迎えて最前線で戦い、二百八十七名のうち百九十五名が戦死、終戦まで生き残ったのは九十二名だけというクラスである。
どちらの作品も勇ましい軍記物ではない。苛烈な戦場で偶然に生き残った、そのさまをめぐる物語。
豊田穣については四年前に興味を持って、いろいろとその著作を読んだ。この可変日記の二〇一〇年十月のあたりに何度も書いている。
豊田の著作を読んだのは、特殊潜航艇で真珠湾に潜入して「捕虜第一号」となった酒巻和男、三四三航空隊で紫電改に乗って勇戦した鴛淵孝、このふたりの同期で、かれらについて書いている作家ということからだった。
しかし本人も数奇な戦歴の持ち主で、昭和十八年四月に米軍の捕虜となり、酒巻とともにアメリカ本国で、二年の収容所生活を送っている。この「不名誉」な経験が自伝的な著作すべてに暗い翳を投げかけている点に、特徴がある。
読んだのは『漂流記』(三笠書房)と『南十字星の戦場』(文春文庫)。前者は自伝的な連作の一つで、物語の時系列としては、日本での飛行学生時代を描く『海の紋章』と、捕虜時代の『割腹』のあいだに位置する。
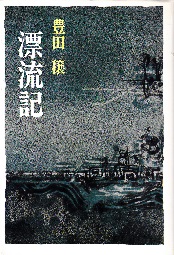
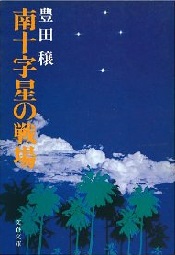
昭和十八年三月中旬、「私」は空母飛鷹の艦爆隊操縦士として、二人乗りの九九式艦爆で九州を出発、トラック島での訓練をへてラバウル島に入り、ガダルカナル島攻撃の「い号作戦」に参加する。
そして四月七日、連合艦隊司令長官山本五十六自らの見送りを受けて出撃するが、攻撃目標のルンガ沖泊地目前で米軍機により撃墜され、海面に不時着。
友軍の不時着基地まで約九キロの距離だったが、櫂のない救命ブイで海流に逆らって近づくことはできなかった。サメにつきまとわれながら同乗の偵察員と二人で七日間漂流、米軍側のガダルカナルに流され、ニュージーランド軍の哨戒艇に発見されて捕虜となる。
その三十年後の一九七三年、オーストリア経由でガダルカナル、ラバウルなどの激戦地と、捕虜生活の初期を送ったニューカレドニアを再訪する旅行記である『南十字星の戦場』に、ラバウルの従軍記者が当時の新聞に書き送った、〇〇中尉こと豊田中尉「戦死」の記事が引用されている。被弾してエンジンの止まった豊田機を上空で援護した、戦闘機操縦士の目撃談である。
「それまで、グッタリしてゐた偵察員が、この時ムックリと頭をあげて僚機を仰ぎ見た。おお、その手には軍艦旗がへんぽんとひるがへつてゐるではないか。伝声管で自爆を決意した二人の爆撃隊員の最期を飾る軍艦旗である。そして〇〇中尉は一瞬、操縦棹から手を放して「天皇陛下万歳」を絶叫したのだらう、両手を高く差しのべた後、再び握った操縦棹でグッと機首を下げ、まつしぐらにソロモンの海面目がけて自爆したのだつた。アツと思はず瞑目した戦闘機の戦友が目を開いた時、海面には飛散した機体の破片が僅かに浮かぶのみ。早や襲つて来た心ないスコールが、それさへまたたく間におほひかくしてしまつた」
じつに勇壮な最期だ。満州事変以後の典型的戦場記事の書きかたなのだろう。豊田も「戦争中の記事であるから、この文章についてとくに言うことはない」として、ウソをなじったりはしない。
軍もこのとおりに自爆戦死と認定し、公報を受けた豊田の父親は、息子の最期を書いた記事を切りぬいて保存し、立派な墓を建てた。ソロモン、ニューギニア方面では六十八期の戦没者の半数近い九十名が戦死したが、豊田も、戦時中はその一人と見なされていたのである。
しかし実際には、操縦席の豊田は自爆ではなく不時着を選択、友軍基地に近づくことに懸命だったし、後席の偵察員は二人乗りのブイに空気を入れて、ふくらませる作業に没頭していた。軍艦旗も天皇陛下万歳も、そんな場面はなかった。
そのあとの漂流中も、敵に捕虜になったときも、かれは自決を選ばなかった。
自分は英雄的な最期など選べる人間ではない、豊田はそのことを不時着から七日間の漂流を通じて、強く自覚していくが、自身の幼いヒロイズムへの懐疑は、それ以前に芽生えていたという。
「中学二年生のときに海軍士官に憧れ、受験を決してから私は相当過度に勉強した。海軍兵学校におけるスパルタ式訓練はその苦業に輪をかけた。私はこの苦しい試練にも堪えたが、海軍兵学校は私が夢みたような理想的な快男児の集う日本の梁山泊ではなかったようである。私の幻滅はその頃から始まっていたといえよう」(『漂流記』)
そうして生き残り、戦記物を得意とする人気作家になり、三十年後に戦場を再訪し、かつて山本五十六が立ってかれを見送った――十一日後に山本も戦死する――ラバウルの飛行場の飛行指揮所の跡が、ただ雑草の繁る丘になっているのを眺める。そしてそこにいた、若くして世を去って永遠に老いることのない死者たち、同期生や先輩の笹井淳一中尉、納富健次郎大尉などの姿を回想する。
若いまま死ぬより、醜くとも長生きした方がいいにきまっていると、わかったようなことをいうのはたやすい。だが、豊田の背負ったものはあまりに重い。


一方、同期の松永市郎の『思い出のネイビーブルー 私の海軍生活記』と『先任将校 軍艦名取短艇隊帰投せり』(ともに光人社NF文庫)は同じ海軍物、しかも後者は『漂流記』と似た漂流体験を扱いながら、読後感は爽やか。
もちろん松永も、敗戦のなかで多数の戦友を失って生き残った人間である痛みを、片時も忘れない。それは著作の随所にうかがえる。それでも、苛烈な時代に青春期をともに過ごした仲間たちへの温かい思いを支えるのは、生きること、生きたことへの肯定である。
これは人柄とともに、松永の軍歴が、豊田よりは恵まれたものだったことが大きいだろう。兵学校卒業時、生徒の大半が花形の飛行機乗りを希望したが、選ばれたのは百名のみ。松永は残りの二百名に属して、通信科の士官となった。
豊田が捕虜となった一九四三年、松永の乗る練習巡洋艦香取は、潜水艦部隊の旗艦としてラバウルの後方の平和な根拠地、トラック島にとどまっていた。そこで九か月のあいだ、同期各科の士官四人で短歌をよんだり、雑誌「東宝」を東京から毎月取り寄せて、宝塚の女優のグラビアを眺めていたというから、まるで戦前の大学生のような生活である。
しかし恵まれた軍歴とは、このように安全な配置だけを指すのではない。
その後の激戦で、松永以外の香取の三人は戦死。松永自身、靖国神社へ行っても何の不思議もなかった。開戦から乗った戦艦榛名~重巡古鷹~巡洋艦香取~軽巡那珂~軽巡名取~空母葛城の六隻のうち、古鷹、那珂、名取、じつに三隻が任務中に撃沈されているのである。
戦死はもちろん、脱出しても捕虜となる可能性があったが――実際に豊田は、アメリカの捕虜収容所で古鷹と名取の乗組員に会っている――そのたびに松永は海を泳いで生還した。
なかでも劇的なのは、昭和十九年八月十八日、フィリピン東方三百マイル(四百八十キロ)で敵潜の雷撃を受けて沈んだ、名取からの帰投航海である。
生き残ったのは、カッター三隻に分乗した二百人。通信長松永大尉は、先任将校としてカッター隊の指揮をとる航海長小林英一大尉を次席将校として助け、昼は帆走、夜は星座で方位を確認しながらオールで十時間漕ぐという原始的な航海を十三日間、毎日乾パン二枚とわずかな水だけで続け、ついにフィリピンにたどり着く。『先任将校』はその顛末を描いたもので、困難な状況下での統率術の模範として、一九八四年に初めて発売されたときはベストセラーになったそうだ。
海で生きぬくことが戦いぬくことに直結した点、松永は豊田より幸運だった。
しかしその松永も、名取に続いて昭和十九年十二月に乗艦を命じられた空母葛城が、百日後に戦艦大和に従って沖縄特攻に参加すると知ったときには、さすがに二十五年の生の証をどうして残すか、自らをもてあましたという。
だが、運良く葛城は、乗せる飛行機もないからと特攻部隊を外れる。続いて、松山航空基地通信長を命じられ、そのまま内地で終戦。
この松山では三四三航空隊の鴛淵孝に再会しているはずだが、そのときの話がないのはちょっと残念。
九月六日(土)《ます》の編成で
ルーテル市ヶ谷で、オウル・ピアノ・クインテットの演奏会。
ヴォーン・ウィリアムズの《グリーンスリーヴス》による幻想曲とピアノ五重奏曲、塩見康史編曲の《日本のうたファンタジー》とシェーファーのピアノ五重奏曲《梟(OWL)》
ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロにコントラバス、アンサンブル鴻巣ヴィルトゥオーゾの四人の弦楽奏者と秩父出身のピアニスト高橋望による、シューベルトの《ます》の編成のピアノ五重奏団。
変則的な編成の《ます》のメンバーで演奏会がやれるように、ヴォーン・ウィリアムズなど何人かの作曲家が曲を書いている。聴く機会の少ないそれらを《ます》抜きでやるのが面白い。ていねいで好感のもてる演奏会。
九月八日(月)マルティヌーのメルヘン
サントリーホールで東京都交響楽団の演奏会。指揮はヤクブ・フルシャ。
マルティヌーの作品二曲という、近年の都響ならではの意欲的なプログラム。交響曲第四番とカンタータ《花束》。交響曲もよかったし、四人の独唱と新国立劇場合唱団が共演した後者はなかなか聴けない作品だけに、優れた演奏で聴けて嬉しい。《子供の魔法の角笛》に似た、ロマン派風の民話的な詩の連作。
九月十一日(木)小型アップライト
新国立劇場で二期会《イドメネオ》のゲネプロ。演出、最初はどうかと思ったが、さすがの才人ミキエレット、進むにつれてなるほどと納得。メルクルのピリオド・アプローチもいい。スダーンに鍛えられただけあって、東響は在京オケのなかでもこういうアプローチが特にうまい。アイディア賞ものなのは、通奏低音のピアノ。モダンのグランドでは強すぎる、フォルテピアノでは大空間に弱すぎるということで、練習室にあったシンメルの小型アップライト。これが古朴な響きでなるほどバッチリ。本番が楽しみ。
九月十三日(土)鎌倉武士団の地
昨日から修善寺に一泊旅行。踊り子号で三島経由。伊豆半島中央部を北流する狩野川流域の田方の平野は、山にはさまれた地形の雰囲気が安曇野に似ている。そういえば南の天城は、安曇野と同じくワサビの名所。
ただ平和な安曇野と違うのは、頼家最期はもちろん北条氏やら仁田氏やら、血なまぐさい鎌倉武士団の生まれた土地であること。頼朝の存在がかれらを歴史の表舞台に押し出し、狂わせたのか。絵画の狩野派の父祖の地もこことは、はじめて知った。
九月十四日(日)王の沓
新国立劇場で二期会《イドメネオ》の本番。
モーツァルトのオーケストレーションの天才を思い知らされる作品だと、あらためて実感。ドラマの動き、心理に結びついた凄まじい能力。
三十日の日経新聞に評を書くので、ここではそこに入らない、瑣末な妄想だけを二点。
まず、最後のエレットラのアリアのとこの演出。本来、オペラではアリアのあいだ時間の進行が停まって、歌手がその内心をくり返し口にするわけだが、今回の演出では原則的に時間は停まらず、周囲の他人への語りかけとして扱われている。アリアの続くオペラ・セリアを飽きさせないためには合理的な方法だと思うが、そのなかで、例外的に明確に時間を停めてみせたのが、最後のエレットラの激怒のアリアだった。
ここでは周囲に主要人物四人がいるのに、いずれも石のように動かず、そっぽを向いたり眠ったりしている。かれらがエレットラを見ても聴いてもいないのと同じように、おそらくエレットラもかれらの姿をもはや見てはいない。
時間を停めるという消極的な意味を超えて、ここはエレットラの時間だけが早く進行しているのではないかと思った。未来の、年老いた孤独と絶望の最後を早回しで見せているのではないか。
かつらを外して禿頭を見せるのは、グルベローヴァが《ロベルト・デヴェリュー》で演じた女王エリザベッタの、あの凄絶な老残の孤独を想わせる。
「王は死せり、新王万歳」の無限の反復による種の継承(利口な女狐の物語みたいな)と、それに対する個人の恐れをテーマにしたこの作品のなかで、記者会見でのミキエレットの説明によると、エレットラはその継承にあくまで反対する存在だという。
身体だけは一人前だが、大人になれない、大人としての責任感も諦観ももち得ない、駄々をこねるだけのなりそこないの大人(今日の大隅さんは、そんな彼女にも愛らしい一面があることをコミカルな演技で示して、人間像に深みを与えていたのがお見事)。
いつまでもたっても「誰かの子供」という楽なポジションで、「誰かの親」にはならない「すべての私たち」(要は私のことです…)の結末が、このエレットラの姿なのだろう。なんとも意地悪なミキエレット野郎(笑)。
それから、舞台全面の土の上に転がる靴。革靴。
これはミキエレットによると「トロイ人の遺体」なのだそうだ。トロイア戦争のすべての犠牲者のむくろ、ということか。そこまでどぎつい発想をせずとも、主なき靴が人のいた証、同時に人がいなくなった証であることは、我々も戦争や事故や災害の現場映像などで、よく知っている。
イリアが途中で集めて祭壇にしたり、アルバーチェやクレタ島の人々が靴をそろえたり持ち帰ったりするのは、死者への弔い、勝者も敗者も等しく運命にもてあそばれていることを暗示しているのだろう。
その靴で連想したのが、天智天皇が暗殺されたという話。日本書紀ではなく扶桑略記という書物にある、山科に遠乗りに出た天智天皇が行方不明となり、ただ沓だけが落ちていたので、そこを天皇陵にしたという、あれ。天武天皇一派による暗殺ではないかと噂される、あれ。
歴代のなかでも強い印象を誇る一代の大王が、それほどの人物が、沓だけを遺して行方不明という虚しさ。
やがて起こる壬申の乱は、その規模において、日本史における最初の大戦争。地中海史における最初の大戦争、トロイア戦争にそれは照応しているし、王位継承がからむのも、イドメネオの物語と通じる。
ただ、敗者の過酷な運命だけでなく勝者も物心両面の荒廃に襲われたことがさまざまに語られるトロイア戦争の物語に対し、日本書紀は勝者の論理だけで書かれたもの。その編纂を命じた天武系と、滅ぼされた天智系(しかし持統は天智の娘。その後の女帝たちも)。
ただ語るのは天智の沓だけ。そんなことを妄想。
九月二十日(土)ナヌート
紀尾井シンフォニエッタの演奏会。
指揮はアントン・ナヌート。力強い響きで素晴らしかった前二回の客演に較べると、今日はもう一つ。前日夜に演奏して翌日午後の二回目というのは、疲れがぬけずに集中しにくいことがあるのかも知れない。
九月二十二日(月)クォ・ヴァディス?
ムーティがローマ歌劇場の終身名誉指揮者を辞任する意向を表明したとのニュース。楽団の資金難、組合闘争などにより、演奏水準が維持できないため。新シーズンの《アイーダ》と《フィガロの結婚》も制作中止らしい。
残念。五~六月の来日公演が最後の共演となった。当時は、政府の助成金がきまって喜んでいると聞いたし、翌シーズン開幕の《アイーダ》についても大乗り気で構想を喜んで話してくれたから、なんとか乗り切れるとまだ思っていたのだろう。その思いが、記者会見での「イタリア人に解決策なんかたずねたって無駄ですよ。そんなものあるわけがない。でもいざとなれば、帽子からハトをたくさん出してみせる連中です」という言葉に込められていたのだと思うが、とうとう我慢できなくなったのか。
「騒々しい《アイーダ》にはなりません」と言っていたので、若いときの情熱的な《アイーダ》とはまた異なる、深みをもった演奏を聴かせてくれることを期待していたのだが。
ノセダが一月前にトリノを辞めているし、ルイゾッティもナポリを離れるとのことで、シャイーとスカラ座がいよいよ最後の砦のような……。
九月二十四日(水)ひぐらしの声
子供の頃は、甲子園が終りかかった頃から一斉に鳴きはじめ、夏休みの宿題にかかれと急かしてくれたツクツクツボウシ(それでもやらないのだが)。
近年は温暖化のせいか、その声を聞くことがほとんどなくなっていたけれど、今年は八月後半に数匹聞くことができ、これくらい涼しくなると出てくるのかと思った。
そして昨日、JRの四ツ谷駅のわきを歩いていると、外堀の土手でツクツクボウシがうるさいくらいに鳴いていた。幼虫はちゃんとどこかにいて、自分たちの気候になれば出てくるものらしい。
ここからはただの思い出話になので、お暇な方だけ。
ツクツクボウシはこうして聞けたが、一方ヒグラシは、もはやまず聞くことがない。東京は暑くなりすぎ。
ヒグラシで忘れられないのは、新潟県北部の胎内市。二十年ほど前の送電線屋時代のこと。七月に自社の仕事がなくなってしまったので、作業員には他社の応援に行ってもらった。お金が切れずにすむので助かったが、土工さんは山形県の尾花沢、電工さんは新潟県の糸魚川と、とんでもなく現場が離れてしまった。それでも月給は現金で現場に届けなければならない。
そこで一日目は車で東北縦貫を北上して仙台、山形を経由して尾花沢(護岸工事していない最上川の美しかったこと)へ、戻る途中の天童で日が暮れかかり、ビジネスホテルに飛び込んで一泊。
翌日は米沢に寄り道して上杉神社に行って謙信公の馬上杯を拝み、米沢牛を食ってから少し北へ戻り、国道百十三号線を走って西の新潟県へ出た。
ヒグラシの山に会ったのは、この国道沿い。
鷹ノ巣温泉をすぎて、荒川沿いの平らな道を走る。気持ちいいので、エアコン入れたまま窓を開ける。左手は一面、広闊な水田。右手の川向こうは低い、緑の山が続く。
その山すべてで、夏の青空と白雲のもと、無数のヒグラシが鳴いていた。
すごい。すごいが、静かで涼やかなのがヒグラシの声。しばらく走っても同じ景色と、ヒグラシの声ばかりが続く。
ついに途中で車を停め、降りて呆然と聞いた。これでは日が暮れてしまうと我にかえったが、あの日以来、芭蕉のあの句の蝉はヒグラシしかありえないと、勝手に思い込んでいる。
あとは主要国道をひたすら新発田、新潟、長岡、柏崎、上越、そして糸魚川。糸魚川の親不知は曇天のもと、やはり陰気で険しい雰囲気だったと記憶するが、それはまた別のときだったか。
帰りは新潟市まで戻って関越で帰ったのだと思うが、それはまったく記憶にない。高速は新幹線同様、目的地の景色しか目に入らない。途中は色も音も匂いもない灰色の時間で、何も残らない。
九月二十五日(木)ヒスパニックの時代とホグウッドの死
サントリーホールでドゥダメル指揮ウィーン・フィルを聴く。
R・シュトラウスの交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》とシベリウスの交響曲第二番。オーケストラがとにかく豊潤に鳴り響く。ウィーン・フィルによる豪華絢爛の美食。
グラマラスでカラフルな響きへのドゥダメルの志向は、経験を重ねてますます強まっているようだ。いかにもアメリカの交響楽団にふさわしいスタイルだと思える。ロス・フィルはうってつけのポジションだろう。
高度成長時代の日本企業のアメリカ進出のシンボルが小沢征爾だったように、アメリカにおけるヒスパニックの時代のシンボルとなるのだろうか。
ホグウッドの逝去を知る。アバド、マゼール、ブリュッヘンに続いて指揮者の訃報が目立つ年。
あらためて経歴を見なおすと、アカデミー・オブ・エンシェント・ミュージック、AAMでモーツァルトの交響曲の録音シリーズを始めたのは、四十歳になったころ。いまの感覚だと意外と年をとっている気もするが、初期のピリオドの音楽家は、畑を耕して広く理解を得るのにそれだけ時間がかかったということ。
だがあのシリーズの成功がなければ、メジャーがピリオド楽器による古典派作品の録音に雪崩を打つことはなかった。ほんとうの功労者。
あのシリーズの評判を知ったのは、代々木の個人レコード店、ジュピターでのことだった。このシリーズは分売せず数枚のボックスにまとめられているのが特徴で、店の新入荷の棚に白いLPボックスがずらりとならんで、とくに初期交響曲集の面白さが評判になっていると聞いたのだった。「レコード芸術」の海外盤試聴記でも絶賛されていたと思う。
私自身は、その響きとリズム感にもう一つなじめず、途中からほとんど聴かなくなってしまったが、LP末期には国内盤も続々と発売される人気となった。
(ところで、国内盤が出る前の「レコード芸術」ではAAMを「イギリス古楽アカデミー」と表記していた。妥当な日本語訳だと思うが、国内盤が出ることになったときに、発売元が「エンシェント室内管弦楽団」という妙な和名を発明してしまった。ASMFをアカデミー室内管弦楽団と訳したのと同じ方式で、いかにも昭和の匂いがする)
そしてCD時代には前述のように、メジャー・レーベルは併設の古楽レーベルも用いて、洪水のようにピリオド系指揮者による古典派作品の新譜を出した。
デッカ=オワゾリールのホグウッド、DG=アルヒーフのガーディナー、テルデック=ダス・アルテ・ヴェルクのアーノンクール、フィリップスのブリュッヘン、EMI=ヴァージンのノリントン、ソニー=ヴィヴァルテのブルーノ・ヴァイル、などなど。
大半の指揮者が自ら結成したオーケストラを率いていており、既成の交響楽団のシステムに乗っていないことに、その大きな特徴があった。
九〇年代後半、CDバブルがはじけてメジャー・レーベルが手を引いたとき、古楽系指揮者たちは、大きな岐路に立たされた。オーケストラという一座を座長として維持しつづけるかどうかの岐路である。
ホグウッドやピノック、ノリントンなどイギリスの指揮者の多くは座頭をおりて、一匹狼の客演指揮者になった。ノリントンは通常の交響楽団のシェフ(雇われ社長)というポストにつき、マイナーとの継続的な録音契約も得ることができたが、あとの二人は旅がらすになった。
二人が離れたあとのAAM(ホグウッドは名誉音楽監督という名誉職へ)とイングリッシュコンサートが、解散せずに新しい座長(雇われ座長らしい)のもとで活動を継続し、自主レーベルかマイナー・レーベルに録音を今も続けていることには、いろいろと考えさせられる。
十月四日(土)ターミナル・シリーズ
天のいと高きところには神に栄光
地には善意の人に平和あれ
御嶽山噴火。
天界に近い高山の頂きで、多くの人が噴火で命を失い、愛する肉親や友人を地上に残していく。わずかの差でながらえた人々も、消えぬ心の傷を負う。
よりによって、紅葉の絶好期の晴天の休日、多くの人が山頂にくつろぐ正午前を狙う。人間の所業なら、そのあまりに残虐な手口をなじらずにはいられまい。しかし天災。天災。
人はもちろんさまざまだけれど、休日に仲間と登山する人は、危険ドラッグにふけって事故を起こしたり、昼間からぶらぶらして女児をさらって殺したりするような連中に較べれば、はるかに善き人だったはず。
なのに……。
「これは何者か。知識もないのに、言葉を重ねて神の経綸を暗くするとは」(ヨブ記)
さて十月は、翌十一月とともに演奏会強化月間。一日から四日まで連日の演奏会はドイツの作曲家ばかりで、しかもその最晩年の作品がその大半。ターミナル・シリーズと勝手に命名。
まずは一日、トッパンホールでアルカント四重奏団。
シューベルトの弦楽五重奏。全曲の巨大なファンタジーのなかでも、コーダの空間が歪むような終りかたに胸をしめつけられる。
七月にメッツマッハーと新日本フィルが日本初演した、ツィンマーマンの《私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た》――このタイトルを私が暗記できる日は、絶対にこない――のラスト、最後の審判のラッパが鳴り響いて、バッハのコラール〈事みちたれり〉の断片があらわれて大団円かと思いきや、音楽が突然に歪んで終ったのを思い出す。
二日、新国立劇場《パルジファル》。
『ビルマの竪琴』の水島上等兵を思い出して「ビルマの土は赤い」と脳内で唱えつつ、そういえば今年は、ワーグナーの著作権の消滅で《パルジファル》のバイロイト独占権が切れ、各地の歌劇場が勝手に上演し始めてから百年、そして第一次世界大戦百年だったと思いだす。
その意味では、同じ飯守さんの指揮でも二期会のグート演出の方が、刺激的で面白かった。あれはまさに、前期の二つの事件が同じ年に起きたことをヒントにして、そこにマンの『魔の山』のサナトリウムをからめ、十九世紀的な市民社会への弔鐘としたものだった。あれこそ、今年上演すべきものだと思う。
三日、すみだトリフォニーでメッツマッハー&新日本フィル。七月に始まったツィンマーマン&ベートーヴェン・シリーズの最終回で、《静寂と反転》とミサ・ソレムニス。
前者は虫の羽音のような、耳鳴りのようなニ音が鳴りつづける。先月二十九日に演奏した《フォトプトシス》と《ユビュ王の晩餐のための音楽》が、過去の名作の引用にあふれ、オマージュなのかパロディなのか、自虐なのかあてつけなのか判然としない騒々しいものだったのに較べ、たしかに「静寂」。
しかし、そのニ音がそのままアタッカでニ長調のミサ・ソレムニスにつなげられたから、ニ音それだけですでにパロディ、ということなのかも知れない。
しかし、ニ音ならニ短調の《合唱》につなげる手もあるだろうし、ここまでメッツマッハーが三、五、七とベートーヴェンの奇数番の交響曲を順番に演奏したことを思えば、むしろその方が自然。
だのにミサ・ソレムニスを選んだのはなぜなのか。あるいは、さきの《私は改めて……》が旧約聖書やドストエフスキーの『大審問官』をテキストにしたことを受けて、カトリック典礼による明快な宗教曲をその鏡像にしたのか。
演奏そのものは「オラトリオとしても演奏可能」というベートーヴェンの言葉通り、教会のミサよりも演奏会のオラトリオとしての、力強くドラマチックなもの。市民音楽としてのヘンデルの《メサイア》に応えるものであり、ただ自国語ではなく、カトリック圏の古い公用語であるラテン語を用いている。市民音楽へとさらに踏みこむため、シラーのドイツ語歌詞を用いたのが《合唱》なのだと、よくわかる。
その劇的なスタイルから、いちばん感興豊かで説得力があったのは、イエスの生涯と受難、復活と審判を歌うクレドの部分だった。
そして四日は、彩の国さいたま芸術劇場でエマールのひくバッハ。
ターミナル・シリーズとしては《フーガの技法》ならバッチリだが、曲は壮年期の平均律クラヴィーア曲集第一巻。
しかしこれはこれで、四日間の締めとしてよかったと、聴きおえて思う。
二十四の調が揃うということは、逆にそのどれでもないということ。
エマールは音と戯れ、ときに口ごもりながら、多彩に描いていく。昨日の新日フィル演奏会は指揮者の強い希望で休憩なしに続けることになったそうだが、今日はピアニストの強い希望で休憩がはさまれることに。その効果か、いま一つノリの悪かった前半に較べ、後半がとくに鮮やかだった。
白眉は終曲、第二十四番ロ短調のフーガ。十二音すべてを用いているため、シェーンベルクが「バッハこそ最初の十二音作曲家」といったというこのフーガ、エマールは音と音、フレーズとフレーズの間を意識してとって、解体直前、関係が崩壊する直前のような、ギリギリの音の連なりにした。
エントロピーの増大。世界の終り。
初めてきた彩の国さいたま芸術劇場、前に「十万石まんじゅう」の店があったので、埼玉ならこれということで、買って帰る。埼京線から見る夜景は、団地各階の通路の照明ばかり。
うちへ帰ってエマールのDG新譜の平均律クラヴィーア曲集第一巻を聴いてみる。あまりに流麗で凹凸がなく、実演とかなり違う……。
十月七日(火)狩られるもの
紀尾井ホールでテツラフ・カルテットの演奏会。テツラフが妹(顔そっくり)のチェロ奏者ターニャ、二人の女性奏者(第二ヴァイオリンはバンベルク響の元コンマス、ヴィオラはチューリヒ歌劇場の現コンマス)と組んだ弦楽四重奏団。辛口で苦い、スーパードライな響き。
後半のベートーヴェンの第十五番は、先週に引き続いてのターミナル・シリーズ。しかしこれら後期の弦四やディアベッリ変奏曲での融通無碍な、音と戯れ、自我と戯れ、ひょっとしたら神とも戯れるような境地は、ツィンマーマンはいうまでもなく、モーツァルトもシューベルトも到達し得なかった、それだけの余生を与えてもらえなかったもの。
そして、この境地に誰よりも憧れたのがマーラーだったのか、などとも考える(交響曲第四番とか第三番とか)。
その前の、ヴィトマンの弦楽四重奏曲第三番《狩りの弦楽四重奏曲》も面白かった。ベートーヴェンの交響曲第七番にも似たシューマンの《蝶々》終曲を引用しながら、四人が一緒に狩に出かけて、走り回り跳ね回り叫び回ったあげく、最後に、他の三人に狩られるのはチェロ奏者だったとわかる、怖い内容。
惨劇の直前、他の三人が楽器をチェロのように持つ。ストバイ、続いてセコバイ、そして対面のヴィオラが「おっ」とうなずいて真似る。後から考えると「今日殺るのはコイツ」と、第一ヴァイオリンが示したわけで、何とも不気味。これは視覚つきの実演でないとわからない。
ヴィトマンは奏法も細かく指示しているそうなので、この動作も作曲家の指定だろう。曲頭では四人で弓を高く掲げ、四回振りおろしてから狩に出発した。最後にも弓を掲げて振りおろすが、そのときは上声の三人のみで、チェロ奏者は断末魔の叫びをあげるという、わかりやすい作品。
それにしても、狩られるのがヴィオラでなくてよかったとも思った。ヴィオラならただのイジメ、少なくとも新しいヴィオラ・ジョークの一つになってしまうだろう。
などと考えたりしたのは、隣席がヴィオラ・ジョークの名手、舩木篤也さんだったからに違いない。
十月九日(木)ブルックナーのヌルテ
サントリーホールでスクロヴァチェフスキ指揮の読売日本交響楽団。
ブルックナーの交響曲第〇番とベートーヴェンの第七番。剛毅、苛烈、驀進。とりわけ前半のブルックナーが鮮烈で、音響の各ブロックを削りなおして骨格を新たに組んだような発見に満ちていた。ワインヤードの拡散型の音響も、時代的にこちらの方があう(ベートーヴェンは開放的な音響のために、集中よりも体育会系の迫力がかちすぎた気がした)。
面白かったのは、金管の輝かしいコラール、ティンパニの豪打(こういう、水島新司の野球漫画でしか見ないような形容を使わずにいられない)、これらがいかにもブルックナーらしいのに対して、スケルツォやフィナーレの第一主題が、ロッシーニのブッファの序曲の旋律みたいな歌謡性とリズムをもっていること。弦の対位法の動きもそれを想わせる。ロッシーニ直接ではなく、何らかの間接的な影響なのだろうが、スクロヴァチェフスキの克明な音づくりだと、それが露出してくる。
来年十二月にミンコフスキが都響に再登場するときにこの曲をルーセルとの組み合わせでやるのは、ひょっとしたらこうした要素に注目したからではないか、などと妄想が膨らむ。同じサントリーだし、そちらも今から楽しみ。
十月十一日(土)不の字の建物
「奈良少年刑務所の重要文化財指定」を求める運動があるというニュースを見て、明治時代の監獄がまだ現存していることを知る。
これは「不」や「木」の字のような形をしていて、中心点の「要」のところから各房の廊下が一斉に監視できる、西洋式の監獄。監獄にしかありえない、独特のスタイル。明治期に日本各地につくられ、五大監獄といわれたが、自分は犬山の明治村に移築された、金沢監獄の中央部分しか見たことがなかった。
奈良少年刑務所の建物は一九〇八(明治四十一)年に奈良監獄として建設されたもので、設計したのは山下洋輔のおじいさん。五大監獄のなかで完全な形で現存する唯一の建物だという。ぜひ保存してほしい。
かつて、我が家から近い新宿区の市ヶ谷台町と富久町(新宿線曙橋駅の北側の台地)にも、このタイプの監獄が二つ、隣りあって存在した。市ヶ谷監獄と東京監獄の二つで、幸徳秋水や毒婦高橋お伝たちが処刑された場所だが、いまはただの住宅地。池袋のサンシャインシティのところにあった巣鴨監獄(のちの巣鴨プリズン)にも、この「不の字」が二つ、向い合せに建っていた。抹消された土地の記憶。
小菅にある現代の東京拘置所は近代的なビル建築だが、形状はやはり「大」や「*」の形。カメラなど設備がどんなに進歩しても、肉眼で死角のできにくい、監視しやすい形がいちばんということなのだろう。
午後はオペラシティで、東京交響楽団の演奏会。飯森範親の指揮で、ファジル・サイ独奏のモーツァルトの二十一番、そしてサイの交響曲 第一番《イスタンブール・シンフォニー》など。
十月十二日(日)八十八分二十五秒
CDの収録時間の話。
ミュージックバードで新譜紹介の番組をやっていると、一回六時間の枠の中に収まるよう計算するために、新譜の収録時間に気をつけるクセがつく。
六十~七十分台のどこか、という盤が大半で、それを五枚か六枚で計三百四十分前後になるように構成する(残りが自分のしゃべり)のだが、もっと長かったり短かったりする盤もある。
最近はとくに、三十年前のCD初期には想像もつかない、超長時間のディスクが増えてきた。
たとえば六月にデッカの外盤で出たビエロフラーヴェク指揮チェコ・フィルのドヴォルジャークの交響曲全集は、六枚組の五枚が八十分を超え、うち二枚は八十三分台。最長七十四分とされた初期よりも十分近く伸びている。
この長さになると、盤質と再生機によっては読み取り不良を起こす可能性もあるはずで、いまだに国内盤が出ない理由の一つにあるのではと思ったりもする。
ところが、今日聴いた『一九一四』と題するGRAMOLA盤。第一次世界大戦中に作曲されたケクランのヴァイオリン・ソナタとヴィエルヌのピアノ小品とピアノ五重奏曲。
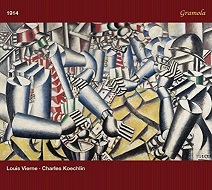
タイミングの関係で「気になるディスク」にあげ損ねたが、この選曲にひかれて買ったもので、特に十七歳で戦死した息子にヴィエルヌが捧げた最後のクインテットは悲痛にして甘美、これは出会えて本当に嬉しい名品。
今年は『一九一七』とか『一九一九』とか『一七九一』とか、特定の年で作品を結びつけたディスクがいくつかあって「気になるディスク」にも紹介したが、紹介し損ねたこの『一九一四』が、いちばん出来がいいようだ。
それはそれとして、プレーヤーの時間表示を見てびっくり。なんと八十八分二十五秒。液晶が壊れたかと思った(笑)が、ついに九十分目前まできた。すっかり「オワコン」扱いのCDだが、まだ進歩を続けている。
九十分弱あれば、一晩のプログラムをそのまま入れられる可能性がより高まるだろうから、これは意味のある進歩。
などとフェイスブックに書いたら、メジャー、マイナーそれぞれのレーベル担当者の方からご意見をいただく。
まず、ソニーには「七十九分五十九秒以上のCDは製造できない」という規定があるらしい。これは海外制作でもそうだろうという話で、たしかに八十分超のCDはDGやデッカなどユニバーサル傘下のレーベルによくあるが、ソニーやRCAでは見たことがないと思う。
続いて、日本のプレス工場では八十分を超すCDはレッドブック違反、規定外ということでプレスできないらしい。
九日に聴いたスクロヴァチェフスキ&読響のブルヌルとベトシチも日本コロムビアが録音していたようだが、八十七分くらいあれば一枚に入る。しかし日本で制作するかぎり、二枚に分けなければ難しそう。
八十分超はたしかに盤質の良否が重要になりそうで、『一九一四』はその点でも非常にしっかりしていて、音質もすばらしかった。
十七時からさいたま芸術劇場でレ・ヴァン・フランセの来日公演。トゥイレ、リムスキー=コルサコフ、カプレ、ルーセル、プーランク。名演。
十月十四日(火)ゲルギエフのタコ八
サントリーホールで、ワレリー・ゲルギエフ指揮マリインスキー歌劇場管弦楽団の来日公演。
前半がブラームスのピアノ協奏曲第二番(ピアノ:ネルソン・フレイレ)、後半がショスタコーヴィチの交響曲第八番という重量級プログラム。タコ八の強い凝集力が印象的。
十月十七日(金)川越カプリース

川越に行ってみる。
ここ数年、江戸東京のなりたちへの興味がますにつれ、太田道灌という存在が大きくなってきた。
道灌は江戸城の築城者として徳川幕府から尊敬されると同時に、文武両道をきわめた忠臣として、幕臣の理想像となった。神に祀られることはなかったが、かれが城内に勧請して崇敬した二つの神社がのちの平河天神と日枝神社となって、間接的に神のような存在になった。
前者の天神社は、もともと道灌時代には江戸城内の梅林坂上にあったという。
平河天神とともに道灌ゆかりの「城のなかの天神」というと、河越城の天神曲輪にある三芳野神社も名高い。江戸城も河越城も、一四五七(長禄元)年に築城されたもの。二十五日に江戸城本丸跡に行く用事があるので、その前に現在の川越城と三芳野神社を見学して、似ているのかどうか確かめようと思った。
東武東上線の川越市駅で降りて、西武新宿線の本川越駅の前をへて北上、観光スポットとして人気の高い「蔵造りの町並み」と「時の鐘」のあたりを歩く。平日の昼なのに観光客多し。
町の中心が駅から離れているのが、いかにも由緒を感じさせる。江戸期から大きかった町はほとんどすべてが、駅と線路を建物が密集する繁華街に近づけることができず、町外れにつくった。いまは時代の変化で駅前に繁栄が移った都市も少なくないが、川越は中心部が観光地となっているために、古い街がまだ衰えていない。
そして、これまで何度か訪れたときに感じたのは、川越の町と住人の人柄に、埼玉県の他のどこにもない都市性と、洗練されて落ち着いたマナーがあること。駅を中心に形成された新興都市とは、商都としての歳月の厚みが違うのだろう。
「蔵造りの町並み」北端の札の辻の交差点で右折して東に進んで、市役所前の交差点へ。ここが江戸期の川越城の西大手門で、その東側が城内となる。堀の大半は埋められ、城内も宅地化されているが、雰囲気はなんとなく残っている。ただしこれは江戸初期の城主、松平伊豆守信綱が拡張整備したもので、戦国時代はこんなに広い城ではなかったらしい。
本丸につく。ここには一八四八(嘉永元)年建築の本丸御殿が現存。「東日本唯一の本丸御殿遺構」なのだという。
三芳野神社は本丸の東南に隣接していた。築城前からあった神社を取りこむ形で城を形成したらしい。そのため神社は天神曲輪という城の一郭となっている。「天神」なので菅原道真が主祭神かと思いきや、氷川神社系の素盞鳴尊。ここはちょっと謎だが、道灌の天神へのこだわりを感じるようでもある。
このあたりは高低がなく平ら。ただ本丸の南北は土地が下がっていて、おそらく道灌時代の河越城は、台地の東端にへそのように突き出していたのだろう。東側は川が流れ、天然の堀となっている。いかにも縄文時代からの聖地、ミサキという地形で、神社が城の前からあったという話も当然に感じられる。
周囲の低地を川がめぐる台地という地形は、いうまでもなく江戸城と似ている(あれより高低差は少ないが)。道灌はこういう地形の城に拠って、東方の敵と対峙する戦法を好んだようだ。そしてそういう場所には神社があるのが通例で、河越も江戸も、そのまま城に取りこんでいる。
本丸の西南端にある、富士見櫓の跡というのも面白かった。櫓といっても建物が高いのではなく、櫓台そのものが尖った小高い山になっていて、登ると見晴らしがよい。
その西隣の三の丸跡は県立川越高校。城跡に公立の名門校があるのも、いかにも古い城下町らしくて好ましい。
南下して喜多院を見、西に進んでクレアモールという商店街に入る。南の川越駅まで、千二百メートルもある長い商店街。二階建てくらいの低い専門店がどこまでも並んで、活気に満ちているのが、実にいい感じだった。
帰宅してからネットを見ると、川越市は川越駅の西口を再開発して、どこにでもあるような大型商業施設を建てたらしい。川越の街の個性と魅力を殺すことにならないといいが、かなり不安。
夜はトッパンホールへ行き、ツェートマイヤーのヴァイオリンで、パガニーニの二十四のカプリース全曲。くすんだ、燻したような響きで華美を取りさって難曲をひききった。感嘆。
十月十九日(日)日本センチュリー響
サントリーホールで、日本センチュリー交響楽団の東京特別演奏会。創立二十五周年を記念するもので、首席指揮者の飯森範親の指揮で、山形交響楽団が共演するマーラーの交響曲第二番《復活》。
このオーケストラは、大阪センチュリー響として一九九〇年に設立されたが、二〇一一年に大阪府からの補助金がカットされ、改組改名して再出発したもの。新たな四半世紀に向けた《復活》。
十月二十日(月)都響イギリス・プロ
サントリーホールで東京都交響楽団の定期演奏会。名古屋フィルの常任指揮者としても活躍中のイギリス人、マーティン・ブラビンズによるお国ものプロ。
ヴォーン・ウィリアムズのノーフォーク狂詩曲第一番、ブリテンのピアノ協奏曲(改訂版、独奏はスティーヴン・オズボーン)、そして後半がウォルトンの交響曲第二番。
ナマで聴く機会の少ないイギリス音楽なので嬉しかったが、そのスタイルに慣れていないせいか、都響のアンサンブルはいつになく大変そうだった。
十月二十一日(火) トリフォノフ…
オペラシティでダニール・トリフォノフのピアノ・リサイタル。
バッハ/リスト編の幻想曲とフーガ、ベートーヴェンの最後のソナタ、リストの超絶技巧練習曲より十曲。
昨年の興奮が忘れられず楽しみにしていたが、もう一つ乗れない。技巧はこれまで同様に見事なのだが、上滑りしている印象が否めなかった。忙しすぎるのではないかとも思ったり。
十月二十三日(火) ネマニャ…
六本木のデザインKホールで行なわれた、ネマニャ・ラドゥロヴィチの「ドイツ・グラモフォン移籍CD発売記念コンヴェンション」に行く。
ショーアップされた、セミクラシック的な方向へと、この躍動感に満ちたヴァイオリニストは進んでいる。演奏スタイルは違うがカンポーリを思い出す。
デザインKホールは、全特六本木ビルという大きなビルの一画。泉ガーデンの南、かつての麻布市兵衛町二丁目。不思議な名前のビルと思ったら、全国特定郵便局長会(現全国郵便局長会)の持ち物だった。
十月二十四日(金)ラザレフのタコ四
サントリーホールで日本フィルの定期演奏会。ラザレフ指揮でショスタコーヴィチの交響曲第四番。長大な難物だが、力強く集中力の高い名演。
ネット・ショッピングの話。
HMVのサイトが「青春クーポン」というクーポンをくれる。五千円以上買うと五百円ひいてくれるクーポン。
なぜこの名前。いまどき五千円もCD買うなんて完全な「大人買い」で、およそ青春とはほど遠い気がするのだが。
何の説明もないので、クーポンをくれる条件もよくわからないが、たぶん大人買いの常習者だからだろう。クレジットカードの青春。
青春とはなんだ。夏木陽介。
そんなとき、主に大正生れのおじいさんたちが大好きだった(日経新聞などに財界人が短文を書くと、しょっちゅう引用されていた)あの詩を思い出す。
「青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ」
サミエル・ウルマンの『青春』という詩。相田みつおの詩やラッセンの絵のようで、自分などは気恥ずかしくなってしまう。
まあ「大人買い」というのも、ある種「心の様相」には違いない。「病膏肓に入る」とか。
というわけで、今日も青春クーポンでお買いもの。
十月二十五日(土)東西音楽三昧
今日は朝から音楽三昧。まずは十時半から、宮内庁楽部による雅楽演奏会。
春と秋に行なわれる定期演奏会だが、一般公開は秋の三日間のみ。無料だがハガキ申込による抽選制。昨年は外れたが今年は当たった。それにしても入場料をとらないのは、木戸銭をとるような地下(じげ)の芸人の興行とは違う、ということなのだろうか。
会場は皇居東御苑、すなわちかつての江戸城本丸にある宮内庁楽部の建物。
平川門から入って、天神堀や梅林坂など太田道灌ゆかりの天神社(半蔵門にある平河天神の大元)にちなむ名を残すあたりを眺めながら本丸へ登り、天守閣あとの石垣の東脇へ。


ここに音楽ホールがある。桃華楽堂。東京の最も中心にあるホール。珍しい八角形のこのホール、一度入ってみたいのだが皇室関係の行事にしか使われず、残念ながら平民には縁がない。


宮内庁楽部はその南隣り。屋内に舞台がしつらえられているが、感じとしては中庭に屋根をかぶせて、手前と左右の回廊を客席としている雰囲気。

三十分前の十時過ぎについたら客席はほぼ満杯。自由席なので、九時半の開場前に行列してないといい席はとれないらしい。白い小石の上を歩いて、小さくて硬い木の椅子に着く。
初めてナマで聴く本格的な雅楽はとても面白かった。初めの三十分は「管絃」で唐楽の器楽合奏。《千秋楽》や《越殿楽》など。休憩十分をはさみ「舞楽」、これは中国系の「左方の舞」と朝鮮系の「右方の舞」。全部で約一時間半。
かなり日本化されているのだろうが、奈良時代あたりに伝来したものとされていて、音響も装束の色彩も形態も、渡来系の雰囲気が本当に濃厚なことを実感。能狂言や日本舞踊、浄瑠璃や長唄の「和風」――あやふやな印象にすぎないけれど――の響きとはまるで違う。いまの日本文化は応仁の乱以降の成立で、それ以前は別物という考え方は、こういうところに由来するのか。
明治維新後、皇族がすぐに西洋風俗をとりいれた素早さの原点は、こうした唐様の導入にあったのかもなどと思う。お雇い外国人の音楽教師に最初に弟子入りを志願したのが、宮内庁楽部の伶人たちだったというのも、かれらがもともと千年前から外国の音楽をやってきたという意識をもっていたからかも、などとも。

舞台奥左右の丸い派手なヤツは太鼓。これが舞楽でボゴン!ボゴン!とリズムをとる大迫力。左方の舞だと下手、右方の舞だと上手の太鼓が鳴って、わかりやすい(笑)。

終って大手町経由でサントリーホールへ行き、日本フィル定期で山野さんによるプレトークを聴く。次回が自分の担当なので参考になる。本番は昨日聴いたので退出。
帰りは赤坂経由で徒歩。大正と明治に赤坂に短期間存在した歌劇場とオーケストラ練習所の跡地の写真を撮ろうとしたが、北側で午後は日陰で暗くてダメ。午前中にでも出直し。
続いて五時から、トッパンホールでモザイク四重奏団。
モーツァルト、シューベルト、ベートーヴェン、十八番のウィーン古典派時代の三曲。ガット弦だがヴィブラートを交える二十世紀的なスタイルで、温雅な響きが心地よい。
少し前に聴いたモダン楽器のアルカントやテツラフは、四人が自己主張しながら濃密な響きでホールを充たしたが、モザイクには楽器とそれが響く空間の双方が存在し、互いを聴きあっている。ベートーヴェンの二番が特に印象に残った。
十月二十七日(月)違う曲でした…
昨日、サントリーホールでメータ指揮イスラエル・フィルの演奏会を聴いた。
ヴィヴァルディ の四つのヴァイオリンのための協奏曲ホ短調作品三‐四RⅤ五五〇、モーツァルトの交響曲第三十六番《リンツ》、チャイコフスキーの交響曲第五番、とプログラムにあった。
ところが今日になって、ヴィヴァルディの曲が違っていたと主催者から連絡がきた。演奏されたのは、四つのヴァイオリンとチェロのための協奏曲ロ短調作品三‐一〇RⅤ五八〇。オーケストラ側から変更の連絡がなかったためにわからなかったという。
お恥ずかしい話だがプログラム記載の調性まで目がいかず、違っていることに気がつかなかった。当日〆切の批評の担当とかでなくて、本当によかった。
たしかにチェロも独奏に参加していたが、指揮者の脇に四人の女性ヴァイオリン奏者が華やかなドレスを着て立ち、指揮者と一緒に舞台に出入りしたので、オケの中に座ったままの男性チェロは、独奏者には含まれないものと思っていた。CDでも取り違えはたまにあるが、ヴィヴァルディの協奏曲はうっかりしやすいので怖い。今後は要注意…。
十一月一日(土)テノール、その一
オーチャードホールで藤原歌劇団の創立八十周年記念公演《ラ・ボエーム》。
昭和九年、日比谷公会堂での旗揚げ公演と同じ演目。一方、主役コンビにフリットリとフィリアノーティが客演という豪華さは、バブル期の五十嵐総監督時代を思い出させてなつかしい。NHKイタリア・オペラと新国立劇場の合間の時期の「主役だけ外国人」方式を担ったのが藤原歌劇団だったことを思い出す。
この作品のカギを握るのはロドルフォ役のテノールの出来なので、そこにフィリアノーティを呼んでくれたことは素晴らしかった。しかし不調で残念。
十一月二日(日)テノール、その二
サントリーホールで新日本フィル。ハーディングの指揮で前半が《子供の魔法の角笛》より、後半が交響曲第四番というマーラー・プロ。
ソプラノのリサ・ミルンが降板して歌手が変更になっていたのだが、面白かったのは前半の歌曲をテノールのアンドリュー・ステイプルズが歌ったこと(交響曲は森麻季が出演)。
テノール歌手がマーラーを歌うことはごく少ない。それもオーケストラ伴奏となると限られる。ボストリッジの実演やプレガルディエンのCDもピアノ伴奏だった。その意味で貴重な体験だったが、声質がリリック・テノールで表現力の幅が限られていたためか、いま一つ。
十一月四日(火)妖怪「会場ちがい」
ティル・フェルナーのリサイタルを聴くべく、いつものように曙橋から都バスで江戸川橋に行き、神田川沿いに一キロ歩いてトッパンホールへ。
ところが着くと、人気がなく暗い。ホールの扉が閉まっている。
ここでやっと、フェルナーは明日の話で、今日は池袋の芸術劇場で都響のイギリス・プロを聴くのを楽しみにしていたことを思い出す。
ひさびさにやられたぜ…妖怪「会場ちがい」。
家へ戻ることも考えたが、江戸川橋まで戻れば有楽町線ですぐに池袋に出られるのを思い出し、「これは行けということなんだろうな」と、再びトボトボ歩いて西へ。
こういうときにかぎって妙に連絡がよく、スイスイと芸術劇場に着いたが時すでに七時十五分。いかにも中途半端。時間をつぶして後半のウォルトンの交響曲第一番だけ。
力演だったのでよかったが、明日またトッパンホールまで歩くのか…。
今日一回往復したんだからハンコもらえんかな。何のハンコか知らないが。
帰宅後、フェイスブックの友人の方たちから、前半はむしろ聴けなくて幸運、みたいななぐさめを受ける。そういえばロビーで会った知り合いに「前半のディーリアスのヴァイオリン協奏曲、どうでした?」と聞いても、みんなムニャムニャいうだけではっきり答えてくれなかったっけ…。
十一月六日(木)オーソドックス
紀尾井ホールにて、ペーター・レーゼルとゲヴァントハウス弦楽四重奏団の演奏会。
前半はクァルテットだけでメンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第六番とシューベルトの《四重奏断章》、後半にレーゼルが加わりブラームスのピアノ五重奏曲。
強い個性が主張されることはないが、オーソドックスでいい音楽。今年は来月にかけてブラームスの作品をさまざまに聴くことになる。そのさきがけ。
十一月八日(土)メディアとオペラ
今年も早稲田大学エクステンションセンターの「オペラ総合講座」の後期「メディアとオペラ」が始まる。
一回目は自分が担当して、草創期の録音メディアに登場した名作オペラの創唱者を中心に、カルーソー、ジーリの登場などを話す。
十一月九日(日)ベジャールの第九
NHKホールにて、ベジャールによるベートーヴェンの「第九」バレエ版。メータ指揮イスラエル・フィルがナマで伴奏する豪華版。終楽章コーダの、同心円の多重旋回の迫力。
十一月十三日(木)演奏会の連環その一
サントリーホールで、ペライアとアカデミー室内管弦楽団の演奏会。メンデルスゾーン、モーツァルト、バッハ、ハイドン。
十一月十四日(金)演奏会の連環その二
サントリーホールで、日フィルの演奏会。インキネン指揮のマーラーの交響曲第七番。明日のプレトークにそなえて予習。終演後にはインキネン自らが登場してアフタートークをしていた。
司会のオヤマダアツシさんによると、インキネンは向うでも慣れているからと喜んで引き受けてくれたそう。イマドキの指揮者にとって、こうしたサーヴィスは当然のことになっているらしい。
十一月十五日(土)パズルの駒
長い一日。
朝は十時四十分から十二時十分まで、早稲田大学エクステンションセンターのオペラ講座、加藤浩子先生の「映像とオペラ」の雑用係。
終って地下鉄を乗り継いでサントリーホールへ移動し、十三時十分から十五分間、日フィル定期演奏会のプレトーク。マーラーの交響曲第七番の「夜の歌」はあくまで通称だが、日本の曲には正真正銘の《夜の歌》があると、尾崎宗吉の同名の曲にも触れる。
終了後ただちに南北線に乗り、永田町まで行って紀尾井ホールへ。この時期の金土は演奏会がたてこんで、どれを選ぶか頭が痛い。ほとんどパズル。インキネンは昨日聴いたので、今日は東京芸術劇場の都響の演奏会でロバート・レヴィンのピアノと指揮も聴いてみたかったが、時間的に間に合いそうもないので、紀尾井シンフォニエッタを選んだ。
オラフ・ヘンツォルトの指揮するブラームス・プロで、ハイドンの主題による変奏曲とセレナード第二番、そしてレーゼル独奏のピアノ協奏曲第一番。
十一月十六日(日)演奏会の連環その三
自分はピリオド楽器の実演が好き。それは、ナチュラルで金属的でないその響きが大好きだからだが、同時に、時系列の関係性を考えるきっかけとなることが多いからでもある。
種々の演奏会を脈絡もなく、連日のように聴き続けるなかにそれがあると、複数の演奏会をつなぐ経路、関連性をふっと見せてくることがあるのだ。
ピリオドの演奏家が歴史性を明確に意識しているためなのか。ともかくそれが入ることで、時系列がなおざりになりかねないモダン楽器の演奏会の羅列のなかからも時代の遠近感というか、歴史のパースペクティヴというか、「時系列の愉悦」みたいなものが味わえるようになることがある。
それは自分のような人間にとって、個々の演奏会の出来不出来を論じるよりもはるかに興味深く、日々を生きる醍醐味といってもいいもの。
石橋メモリアルホールでのエンリコ・オノフリ&チパンゴ・コンソートの演奏会は、まさにそうした「時の要」。
六月に続いて一年に二度も幡随院の跡地でオノフリを聴く幸福。「ヴェネツィア、霧の中の光」と題したオール・ヴィヴァルディ・プロ。
一曲目が先日二十六日のメータ&イスラエル・フィルでくらった「昨日の曲、違ってました攻撃」と同じ、四本のヴァイオリンとチェロのための協奏曲だったのには笑ってしまった。あの日は《調和の霊感》の第十番ロ短調だったが、今日はその第一番ニ長調。
しかしその音楽のなんと異なること!
モダン楽器の艶麗に対して、ピリオド楽器の清冽。ありていにいって、厚化粧の前者よりナチュラルな後者の方がはるかに敏捷で面白く、自分には美しく聞こえた。
さらに、楽器配置がまったく違ったのが面白かった。イスラエル・フィルが指揮者の両脇に四人のヴァイオリンがならぶ普通の協奏曲配置だったのに対し、チパンゴ・コンソートは通常の指揮者の位置にギターがいて、その上手にチェロとヴィオローネ。正面奥にチェンバロとオルガン、その両側に鶴翼の陣形で左右にヴァイオリンとヴィオラ。そしてオノフリを含む四人の独奏者は、正面最奥部の高いひな壇の上にならぶ。その響きには独特の奥行きが生じて、とても魅力的だった。
これを聴きながら脳のなかで重なったのが、十四日に聴いたインキネン指揮日フィルのマーラーの交響曲第七番の第四楽章の、やはり独特の楽器配置。
ここではマンドリンとギターという、普通はオケにない楽器をどこに置くのかが問題で、何度か聴いたナマではオケによって異なっていた。インキネンはそれを、奥の木管楽器の列の下手に置いた。音量の小さい撥弦楽器をずいぶん奥に置くと思ったが、本番では明快に響いた。ならば増幅したのかと思いきや、そうではなくアンプラグド。ひな壇の上にあるのできれいに抜けて響いたらしい。
こうすることでこの楽章を「マンドリンとギターが独奏する楽章」ではなく、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロに木管など、ソロをとるさまざまな楽器にマンドリンとギターも加わって、オーケストラのあちこちからソロが響くという、合奏協奏曲的な楽章にしようとするインキネンの意図が見えたし、これにより、バロック音楽へのマーラーの視線が、より明快に感じられた。楽器配置もまた、重要な演奏表現の一つなのだ。
オノフリに話を戻す。ソロを最後列に配する配置はこの曲かぎりで、一本や二本のヴァイオリンのための協奏曲では前に出てきて、ギターの下手脇の、いかにも協奏曲のソロらしい位置に戻した。一人や二人なら、音量的にも視覚的にもこの方がいい。
チパンゴ・コンソートは年々うまくなっていて、後半の《四季》は五年前の同曲の演奏とは比べ物にならないくらい、自然で自発的な生命力にみちた、愉しく刺激的な演奏だった。
ここで十三日にサントリーで聴いた、ペライア&アカデミー室内管弦楽団のバッハのピアノ協奏曲第七番が、どうにも耳に合わなかったのを思い出す。
バッハの鍵盤楽器作品でも、ソロ曲のピアノ演奏を聴くのは大好きだ。そこには一種の「高度な抽象化」があるから。だが協奏曲では違和感がぬぐえない。通奏低音の一つだったチェンバロを協奏曲で独奏楽器に起用したバッハの炯眼は、たしかに未来を見通したものだが、それでもなお、これはピアノとモダン楽器のための音楽ではないと思う。
そのあとのハイドンの《驚愕》も、自分には合わなかった。通奏低音のチェンバロの入っていないハイドンの交響曲を実演で聴くのは、いったいいつ以来なのか憶えていないが、モダン楽器だけではこんなに硬くて流動感のない音楽になるのかと、あらためて驚いた。
しかし面白いことに、前半のモーツァルトの二十一番のピアノ協奏曲は、上記の不満が問題にならないくらい、本当に素晴らしい音楽だった。これもまた二十世紀半ば風の、完全にオールド・スタイルの演奏なのだが、その時代の優れたモーツァルト演奏がすべてそうであったように、気魄と呼吸感が豊かで、生命力に満ちていた。
ついでにいうとその二日後の十五日、レーゼルと紀尾井シンフォニエッタがアンコールで演奏した二十七番の二楽章もまた、タイプは違うが豊麗な、とても美しいものだった。
どうやら、モーツァルトのなかでも二十番以降のピアノ協奏曲は、ベートーヴェンの交響曲と同様に、ロマン派を、十九世紀を、近代の市民社会の音楽を、預言して準備したものらしい。だから、モダン楽器がぴたりとはまる(もちろん、ピリオド楽器も同様にはまるが)。
この意味で、十五日の芸術劇場のレヴィン&都響の二十番を、フォルテピアノ奏者として名高いレヴィンの弾きぶりだけに聴き較べてみたかったが、サントリーホールでの日フィルのプレトークを終えてからでは間に合いそうもないので断念した。十、十一月の東京の週末は演奏会がたてこみすぎ。
しかし、代りにレーゼルの素晴らしいブラームスの協奏曲第一番が聴けた。レーゼルのシリーズは今年でいったん終了だそうだが、次はぜひモーツァルトの協奏曲シリーズをやってほしい。CDで進行中なのに、むしろないほうが不思議。
十二月四日(木)年忘れ演奏会強化週間
サントリーホールにて、読売日本交響楽団の演奏会。指揮はカンブルラン。
曲は世界初演の酒井 健治の《ブルーコンチェルト》とメシアンのトゥーランガリラ交響曲。
今日から十一日連続で演奏会とオペラへ。まず紀尾井ホールで、萩原麻未とヴォーチェ弦楽四重奏団によるドヴォルジャークとフランクのピアノ五重奏。新国立劇場の《ドン・カルロ》、N響の《ペレアスとメリザンド》、東京文化会館で大野&都響、そしてオペラシティでパーヴォ・ヤルヴィとドイツ・カンマーフィル・ブレーメンのブラームス・チクルス四回と、合間にトッパンホールでフォーレ四重奏団。
十二月六日(土)浅草と田谷力三
早稲田大学エクステンションセンターの「オペラ総合講座」の後期「メディアとオペラ」最終日。
自分がしゃべって、テーマは「メディアとしての浅草オペラ」。メディアというのは媒介、仲介するものという意味なので、西洋の本格的なオペラと日本人を媒介したものとしての、浅草オペラ。
音資料として大いに役立ったのが、ぐらもくらぶというレーベルから今年出た『六区風景 想ひ出の浅草』というCD二枚組。明治末期から昭和二十八年までのSPの復刻盤で、珍しい音源を丹念に集めてあって、じつに面白い。

昭和三十年代以降に東京の西郊に育った子供にとって、浅草ははるか遠い町だった。親に連れられて、最寄りの自由が丘の町よりも遠出するとすれば、有楽町を含めた銀座。テレビなどで浅草を見て話題に出しても、連れて行ってもらえる雰囲気にはけっしてならなかった。関東大震災直前に仙台から東京に出てきた祖父なら最盛期の浅草を知っているはずだが、銀座に較べて、愛着はまったくないようだった。
おそらく、昭和後半に西東京の私鉄沿線に育った子供の大半は、浅草に同様の遠さを感じるのではないかと思う。
いまになって思うと、それはたぶん、戦後の浅草が「ストリップの町」という印象が強まっていたからだと思う。テレビには雷門と仲見世しか映らないから子供にはわからないが、各地の温泉街の、男性向けの下卑た街並みの総本山みたいな雰囲気が、東京西郊からみた浅草にはあったのだ。
もちろん、ストリップは六区興行街の一画にすぎないのだが、それを象徴として、浅草には前時代の見世物小屋風の、猥雑と陰惨の暗い影があった。遊芸人を最下層においてきた江戸期の身分社会の名残であり、このことは一億総中流幻想の時代の気分に、およそそぐわなかったのだろう。
しかしその前の数百年間は、猥雑と陰惨が浅草の魅力そのものとなって、熱気と輝きをはらんでいたのだ。
江戸随一の歓楽街だった時代には浅草寺の西側の奥山という、大道芸人や露店の集まる一帯が繁華の中心だった。明治になって奥山の西に大きな池を堀り、出た土で田圃を埋めて造成されたのが、いわゆる六区だった。
六区はまもなく、西洋風の劇場や寄席が並ぶ興行街となる。日本初の映画常設館たる電気館も浅草に生まれ、昭和初期に東宝が丸の内に劇場街を築くまでは、東京唯一の興行街だった。
その後も、山の手のホワイトカラーを主な客層とする銀座・有楽町に対し、浅草は下町と江東のブルーカラー向けの、庶民的な歓楽街として人を集めた。
昭和五年の浅草には、三十三の興行施設があったという。和洋の映画の封切館や二番館、歌舞伎、新派、新国劇に女剣劇、喜劇、松竹少女歌劇、レビュー、舞踏、安来節、講談、浪花節、落語など、あらゆる大小の出し物がそろっていた。
『六区風景 想ひ出の浅草』は、奥山の見世物にはじまって、六区の浅草オペラ、活動写真、軽演劇の隆盛までを、時代を追ってSPで再現していく。
面白いのは、玉乗りの江川一座の口上のように、口上に加えて開演前の呼び込みや終演後の追い出しの掛け声や囃子も含めて、興行全体の雰囲気を再現しようとしているものがいくつかあること。
活動写真の花形弁士十三人が交代で登場して洋画邦画の名作をダイジェストで語る二枚四面の『想い出の浅草』でも、内容に合わせて変る洋楽邦楽の伴奏や客席での中売りの声などが入り、映画館で一日を過ごす気分を短縮版で味わえるようになっている。
柳家金語楼の『浅草見物』もその名のとおり、北は花屋敷(遊園地)から南の来々軒(中華料理)まで、六区の表通りを歩きながら、途中で見物する活動や安来節などたくさんの出し物を、二面にわたって金語楼が声色で再現して楽しい。六区興行街がどんな楽しい場所か、音で伝えているのだ。再現ものでは吉原芸妓連中の出演で、夜の吉原の街頭音なんて盤もある。吉原も、広い意味では浅草に含まれるのである。
このほか、曽我廼家五九郎一座にエノケンと相棒の二村定一、古川緑波の「笑いの王国」に川田義雄など、浅草歴代の喜劇人の録音もそろって穴がない。松竹少女歌劇のスター、水の江滝子もいる。
昭和初期のエッチな歌詞の歌と柳家三亀松の艶笑漫談があるのは、いかにもエロ・グロ・ナンセンスの時代(わずか数年で軍国主義が隆盛し、戦争へと突っ走ることになるのだが)。
そのなかでも浅草オペラ関係は全三十五トラックのうち十二と、三分の一以上をしめる重要度。浅草からオペラの灯が消えた昭和期の録音も含まれているが、浅草オペラ関係の重要人物の貴重な録音が並んでいる。
清水金太郎と静子夫妻、井上起久子など東京音楽学校出身の歌手にくわえ、楽長として活躍した竹内平吉のピアノも。
原信子の歌う〈いまの歌声は〉の伴奏をしているのが、日本で初めて単独のリサイタル(それまでは複数が交代で出演していた)を開いたピアニスト、澤田柳吉というのも嬉しい。この人は浅草オペラの舞台に印半纏を着て登場、ベートーヴェンの《月光》をひいたことで知られている人だ。
藤原義江も戸山英二郎という芸名で、最初の妻の安藤文子の〈恋はやさし〉に共演している。
なんといっても興奮させられるのは、《女軍出征》の二面にわたる短縮版が含められていること。大正六年に常盤座で初演された伊庭孝作のこの「歌舞劇」こそ、浅草オペラの始まりとなった作品なのである。ここに収められているのは、その翌年に日本館で旗揚げした、東京歌劇座による録音。
音楽は当時の欧米のさまざまな流行歌や舞曲などを勝手に用いたものだったそうで、ここでもその一部、《ティペラリー》や《ダブリン・ベイ》を楽師が演奏しているが、ストーリーはほとんど台詞によって進行される。
こういう、ヴォードヴィル的な公演が大当たりしたので、ならばより本格的なオペラはどうだということになり、帝国劇場では失敗した歌劇部の残党が浅草に招かれて、人気を博したのである。
聴いていくなかで、歌のうまさと存在感できわだってくるのが、田谷力三。
浅草オペラを「オペラ」たらしめたのは、この田谷の存在だったのではないかと思う。
浅草オペラの大衆的な人気の多くは、若い女優たちの肉体的魅力にあったとよくいわれる。そうした要素はどんどん卑俗化して再生産されるから、それゆえに軽演劇やストリップによって、取ってかわられることになったのだろう。
しかし、本物のテノール歌手は、オペラにしか存在しない。ほかのジャンルはテノール抜きでも成り立つが、オペラはそうはいかない。十九世紀後半以降のオペラとはそういうものであり、その意味で、徹底して男性原理の芸術だった(この原理に挑戦した女性は、おそらくマリア・カラスただひとりだ)。
田谷は有史以来、日本に初めて出現したテノール歌手だった。このアルバムに登場する大津賀八郎(声量は田谷以上だが、大酒で身を持ちくずしたという)も藤原義江も、田谷の後ろ姿を追いかけていたにすぎない。
しかし、音楽学校と無縁で、海外に行くこともなく、歌劇団もつくることなくフリーランスの一匹狼で、そしてあまりにも長く歌いつづけた田谷は、それゆえに正統派のクラシック界、オペラ界とは無縁で、きちんと音楽史上に位置づけられていない。本格的な評伝もない。
わかる範囲で田谷を調べて痛感するのは、田谷に憧れて新国劇から浅草オペラに転じた戸山英二郎は、「田谷がやらないこと」をすべてやることで、後世に名を残すテノール歌手藤原義江になったということ。
浅草を抜けてミラノに留学したこと、それで箔をつけて華族やマスコミの人脈を作り、「本格派」に転じたこと。そして座長となって歌劇団をつくったこと。
この二人の対照は面白そう。
十二月十日(水)レギオンとチーム
年忘れ演奏会強化週間の七日目、パーヴォ・ヤルヴィ指揮ドイツ・カンマーフィル・ブレーメン(DKB)のブラームス連続演奏会「ブラームス・シンフォニック・クロノロジー」の初日を、オペラシティで。ピアノ協奏曲第一番(独奏フォークト)と交響曲第一番。
実演で聴く機会の多くないブラームスのピアノ協奏曲第一番だが、珍しいことにこの一か月のあいだに三回目。紀尾井シンフォニエッタ、バイエルン放響、そしてDKB。
今日聴いていて、特に感じたのはヤンソンス&バイエルン放響との違い。とにかく、オケの響きがまったく別物。原因はもちろん楽員の多寡によるのだが、それが単純な音量の大小の問題におさまらず、大げさにいえば「合奏の哲学」の問題にまでつながっているのが、ものすごく面白かった。
今日、始まった瞬間に痛感したのは、バイエルン放響の響きがいかに美しかったか、ということ。澄んでいて、絹のように優美で軽く、性質の異なる管と弦と打の楽器が見事に調和して、音のグラデーションをなしていた。
それにくらべるとDKBの響きは雑然として、しかも鳴らない。弦が力を込めてひくせいか、とりわけ初めの部分がまるで響かないのでびっくりさせられる。ひき進むうちに力みが減るのか鳴り出すのだが、初めは本当にガシャガシャとしている(これは後半の交響曲も同じだった)。バイエルン放響が初めからムラなくきれいに響いたのとまるで違う。そしてDKBは鳴り出したあとも、アンサンブルはかなり粗っぽい。
力量の差があるにしても、そもそも合せることにこだわっていないのだろうと感じた。それはフルオーケストラには許されないこと。フルオケが同じやりかたをしたら大変なことになる。百人近い人間が整然とひき、整然と響かせるためには同じ方向を向いて、ある程度機械的に合せなければならない。
これはバイエルン放響にかぎらず、去年聴いたベルリン・フィルも、タイプこそ違え共通していた。恐ろしく高い技量を持った連中が一糸乱れぬ合奏をする。
それはまさに音のレギオン(軍団)。十九世紀後半から二十世紀にかけて完成された、シンフォニックなオーケストラ芸術の粋。
しかしDKBは違う。意識的に、わざと違う方向を求める。わざと乱しているということではなく、ミスなく合せることを最重要課題とは見なさないということ。ワイワイガヤガヤ、そこから出てくる何か別のものを目指している。
超一流のフルオーケストラが一部上場の伝統企業のチリ一つない大工場だとすれば、かれらは新興の中小企業の町工場たろうとしている。組織化されたレギオンではなく、チーム・プレイの面白さ。
同じドイツのオケなのに、こんなに合奏へのメンタリティが違うのが、ものすごく面白い。これはDKBだけでなく、数年前に聴いたフライブルク・バロック・オーケストラもそうだった。「古楽器のベルリン・フィル」というのがウリ文句だったが、全然そんなものではなかった。あんないい加減な合奏を、ベルリン・フィルの楽員が絶対にやるはずがない(笑)。そしてそれがむしろ、フライブルクの魅力になっていた。
ドイツに室内管弦楽団はたくさんあるから、それぞれにさまざまなポリシーがあるだろうが、全体としては、二十世紀の交響楽運動に対するアンチテーゼなのかと思う。
それは、ピリオド・アプローチやユース・オーケストラ運動など、アメリカ的なグローバリゼーションへの反発という意味合いに加えて、それよりも前の、ナチズムの全体主義への反省もあるのかも知れない。ミュンヒンガーのシュトゥットガルト室内管やリヒターのミュンヘン・バッハ管の活動から、はるかにつながるものがあるのかも知れない。
パーヴォという人は、各国の交響楽団のシェフとして、その特性に合せたレパートリーをやってきた人だけに、このメンタリティの違いをしっかりとわきまえて統率し、さらに意識的に強調している気がした。このコンビの演奏はライヴの方が面白いが、くり返し聴くにはつらいので、セッション録音ではそれを抑え、ライヴ演奏はDVDとしてのみ後に残すのも、違いを意識しているためだろう。
こうした脱レギオン的なアプローチはバロックに始まって、古典派から前期ロマン派まで進み、いまちょうどブラームスが最前線、端境にある。それを今回のチクルスは実感させてくれそうだ。
今日は粗っぽさがかなり目立ったが、よりロマンティックなアプローチも可能な三番や四番でどうなるのか、わざわざクロノロジー、年代記と名うっているだけに楽しみ。四年前のシューマンの交響曲チクルスのときの《ライン》四楽章で響かせた、白い川霧の中に浮かんでは消える大伽藍の幻影のような、あのはかなく幻想的な響き(絶対にマイクには入らないもの)を、今回のどこかでまた聴けることを、自分としては願う。
ただ不安要素としては、前回はもっと技術が高く、間一髪のところできわどく合せることができたものが、崩れていたこと。たとえば前回の《春》は、似たようなピリオド・スタイルでも、あまりにも整然とやってのけるラトル&ベルリン・フィルのつまらなさとは別種のスリルがあったのに、今日はよけきれずに事故になったところが多々あった。
できれば、この力みはブラームス初期の力みを描いたものであって、曲ごとに変えていってほしいと思うが、どうなるのだろう。
十二月十一日(木)肉食系ライヴバンド
パーヴォ&DKB、二日目。ハイドン変奏曲とヴァイオリン協奏曲(独奏テツラフ)、交響曲第二番。
ハイドン変奏曲は直前に飲んだビールが効いて幽体離脱したため、感想パス。
ヴァイオリン協奏曲は昨日に近い、高速度全力ノリ。これはテツラフの望む流儀でもあるのか。音程がズレようがかまわずに気合優先で斬りこむ、ヘンゲルブロック&NDR響とのメンデルスゾーンの時と同じテツラフ・スタイル。
この奔放さが、少し前に聴いたテツラフ・クァルテットのときの、神妙な演奏ぶりとまるで違うのが面白かった。クァルテットのストバイにかかる重圧は、なるほどソリストのときとはまったく別のものなのだろうと納得。
交響曲第二番の第二楽章で、黒くて濃厚な何かが響きの下半分でようやくうごめきはじめたのが、シューマン・チクルスの雰囲気に近づいた感じで、嬉しい。この暗黒物質のようなものが三番四番、それにピアノ協奏曲二番とドッペルでドロドロと増殖してくれると、まさに「クロノロジー」の意味が出てくる。
ただこれが意識的な変化なのかどうかは、後半の二回を聴きおえるまでは何ともいえない。
このコンビはその日の即興的な、ロックなノリにまかせる部分がかなりあるようで、そこが難しい。肉食系ライヴバンドというか。ここが評価と好悪のわかれるところ。
自分は、脱レギオンならそうなるのは自然だと思うし、それをブラームスでやってくれるのは新鮮だから、好きだが。もちろん、どちらが正しいということではなく。
十二月十二日(金)ぶったまげた
フォーレ四重奏団をトッパンホール。
前半がマーラーとR・シュトラウスの作品だということしか憶えておらず、行ってみたら後半がブラームスのピアノ四重奏曲第一番だったので、大笑い。
パーヴォ&DKBの交響曲チクルスの真ん中に、シェーンベルクがオーケストレーションして「交響曲第五番」と遊びでいわれたりする曲の、オリジナルの室内楽を聴くことになるとは。

と曲目で喜んでいたら、演奏を聴いていやもう驚天動地。ぶったまげた。ものすげぇ名演。いままで聴いたCDでは、まったくわからなかった。
俗な言いかたを承知で、私の限られた音楽体験のなかで形容すれば「歌を歌わない、ピアノ四重奏のエベーヌ・クァルテット」。
今日聴くまでは、クァルテットといってもピアノ四重奏、全員ドイツ人なのにフォーレ、フォーレなのにDGデビュー盤はモーツァルトと、なにかちぐはぐな人たちという悪印象があった。
それはソニー第一弾のR・シュトラウス&マーラーのディスクを聴いてもぬぐえなかったのだが、ナマは、それらをすべて引っくり返してしまうものだった。
前半のマーラーとシュトラウスも後期ロマン派の爛熟美にみちていて、CDよりはるかによかったが、後半のブラームスは作品の出来が数段上なだけに、フォーレQの真の実力を耳にたたき込まれることになった。
レギオンとチーム、なんてことをこの数日考えているなかで、この四人を形容するとすれば、ユニット。
常設のピアノ四重奏団は珍しい。普通は弦楽四重奏団‐1+ゲストのピアニストとか、ピアノ・トリオ+ゲストのヴィオラ奏者とか、あるいはソリストばかりの臨時編成とか、そういうものが多いわけだが、かれらは常設。
響きと音色の統一性、ハーモニー、合奏の精度、完璧といっていい高水準。互いを熟知しているから、遠慮がない。確信に満ちて、それが響きに確固たる骨格をもたらす。きわめて濃密。この濃密さが、エベーヌにそっくりなのだ。ピアノ四重奏で、最良の弦楽四重奏団のような緊密で立体的なアンサンブルを構築したことの驚異。
この骨格を基礎とした上で、ブラームスの暗い、内攻的な情熱が随所にほとばしる。ブラームスはやはり激しい。第三楽章の情熱を秘めた歌いあげもすばらしく、そして終楽章のたたみこみのものすごさ。オケ版では絶対に不可能な、超高速全力疾走の強烈な訴求力。四人五足の超高速全力疾走。この一体感こそ、ユニットの快感。
そしてアンコール。これも常設の強みを発揮したものだった。臨時編成の演奏会だと一曲あるかないか、それも大概は本プロのどこかの楽章をくり返すことになるが、かれらは素敵なオリジナルをもっている。
まず《展覧会の絵》の〈卵のからをつけたひなの踊リ〉の自分たちによる編曲版。続いて、フーベルトの〈フォーレ・タンゴ〉という、ピアソラ風の曲。これはまさに「歌わないけどエベーヌ」。
そして最後に、シューマンのピアノ四重奏曲のアンダンテ・カンタービレ。ブラームスの激情の向うにある、シューマンの哀しみ。これも濃密で感動的で、ラストを飾るにふさわしい。
終演後、ソニー・クラシカルの担当者に会ったので「すっばらしかったじゃん!」というと、かれもここまでとは思わなかったか、「ねぇ…」とあきれ顔。
「CDには入ってないね」というと、そこは企業人、けっして同意してくれなかった(ということにしておく)。
「ブラームスとシューマンと、それに《展覧会の絵》ピアノ四重奏版を録音するように本社にいってよ!」と叫んでおいた。
この人たちの本領が、近いうちにディスクでも発揮されることを祈るのみ。いまこれを録らずして、何を録るのかといいたい。
いずれにしてもフォーレ四重奏団、これからは目が離せない。こういう凄腕ユニットをまったく知らなかったとは…。
十二月十三日(土)ちぐはぐ
パーヴォ&DKBのチクルス三日目。大学祝典序曲とピアノ協奏曲第二番(独奏フォークト)、交響曲第三番、一八八〇年代の作品群。
今日はゆったりとした箇所も多く、楽想の移行をなだらかにした。中一日おいての演奏スタイルの変化は顕著で、意図的なものであることが明確になってきた(初日は入れ込みすぎてその意図を超えて、仕掛けた以上に狂燥と焦燥の度がすぎ、悪い意味のカーニヴァルになったのだろうとも思うが)。
たしかにこの頃からオーケストラの楽器の性能が全体に向上して、強く高く安定して響くようになり、モダン・ピッチへと半音上昇する時期も近づいている。当然、歴史上の鳴らし方も堂々としたものに変っていったはず。
全体としてはアグレッシブな、ガリッとした響きの演奏であることは変わらないけれど、暴れ馬のような粗さはかなり減った。ピアノ協奏曲第二番の冒頭付近の弦など、今回のチクルスで初めて「いい音だなあ」と思った。熱情と沈潜の交代が、波動するような流れのなかで行なわれる。第三楽章のチェロ独奏は、首席のターニャ・テツラフがひいた。
四楽章構成の協奏曲という異例の巨大さがチクルスのなかできわだっていたピアノ協奏曲第二番と、隣席のネコケン先生いうところの「巨大な室内楽」の交響曲第三番、効果としては演奏順を逆にしてもいいようにも思えた。ブラームスの作品の大小の奇妙さ、ちぐはぐさ。
十二月十四日(日)身の置きどころ
パーヴォ&DKBのチクルス最終日。悲劇的序曲、ドッペル、交響曲第四番。
今日は一気呵成に突き進めていく。序曲と交響曲では、今チクルスで初めてゼペックがコンマスに登場。ドッペルのソロはテツラフ兄妹。兄はここでも奔放。アンコールのコダーイのデュオの方が、シャープでフォルムがしっかりしていて自分は好き。これは先日のテツラフ・クァルテットの演奏を思い出させた。
交響曲第四番は木管群の弱さが露出。さびしく沈潜する箇所で妙なハーモニーになるために集中をそがれる。しかし、終楽章の悲壮というか悲愴というか悲劇的な、自暴自棄の気配さえ漂うコーダは激しく暗く(どこかスラヴ的)、チクルスのラストをこういう響きでしめくくったのは印象に残る。
全体を支配した悲劇の雰囲気が、アンコールにいつものハンガリー舞曲二曲に加えてパーヴォ恒例の《悲しきワルツ》でしめたことと結びつくのやら、それとも結びつかないのやら。
ともあれブラームスについて、いろいろ考えるきっかけをあたえてくれたことに感謝。
今回のチクルス(と、あいだのフォーレQ)で自分が強く感じのは、ブラームスという作曲家とその作品の「収まりの悪さ」、ちぐはぐさ。ある種のオーパーツとでもいうか。
小さいんだか大きいんだか、激しいんだか穏やかなんだか、あらゆる点でちぐはぐして、収まらない。四つの交響曲も四つの協奏曲も、「オーケストラでやりたくなる」ピアノ四重奏曲第一番も。どうやっても「あるべき位置」にないように感じられて、身の置きどころがない。心を病んだシューマンの音楽の方が、よほど位置がはっきりしている。
この不安定さこそブラームスであり、今回のチクルスはそれを象徴したのかもしれない。ある意味で、真実に肉薄しているのかもしれない。
そして、レギオンとチーム、ユニットのこと。今回のDKBは、木管をはじめとしてアンサンブルがかなり弱体化していたのが意外だった。トップ奏者はまだしも、おしなべて二番以下が弱い。
同年代の仲間が集まってつくった室内オケというチームの場合、ある程度の年齢に達すると、より安定した生活や新環境を求めてまとまった数の退団や移籍が起きて、立てなおしにくくなったりするのだろうか(現代の弦楽四重奏団も同じ問題を抱えている)。
この点でレギオンは組織がしっかりしているだけに、世代交代、消耗品の交換システムが確立されている。たとえばバイエルン放響も、数年前の来日で管楽器がとても不安定なことがあったが、素早く立ちなおっていた。
二十世紀の後半に続々と生まれたチーム、つまり室内オーケストラ(モダンでもピリオドでも)の場合、組織としての維持能力が、課題としてつきまとうのかもれない。これは、エベーヌがヴィオラ交代の転機を迎えているように、ユニットにしても同様だ。
十二月二十日(土)フォーレQのCD
十二日の「フォーレ・ショック」から八日。あの日のことは、日経新聞にほんの少しだけ触れるチャンスをもらえたので嬉しい(二十四日夕刊掲載予定)。
その間、ディスクをかき集めて聴きなおした。ショック前の自分はDGのブラームス(二〇〇七)とSONYのマーラー&シュトラウスを聴いていて、かれらの凄さがまるで聴きとれていなかったわけだが、とにかくそれらもそれ以外も聴きなおしてみようと。
あらためて調べたら、DG契約以前にARS MUSICIというドイツのマイナー・レーベルから三枚出ていた。これなら音はよさそうだし、しかも曲目はなんとあのシューマン全曲とフォーレ。聴かずにいられようか!
残念ながら最初期の二〇〇〇年発売のドヴォルジャークとフォーレの一番は中古が高くていまはウツボ状態(八月二十七日の日記参照)だが、あと二枚はすぐに入手できた。
まず、聴いたことのあった二枚はやはりダメ。ブラームスのスタイルは一緒だから、ナマの響きを頭の中で甦らせるよすがにはなるけれど、ディスクの音自体は近年のDGらしくエッジが甘く平面的で、生々しさと立体感を欠き、響きが濁る。SONYはさらに…以下略(笑)。
新たに聴いたDGのデビュー盤のモーツァルト(二〇〇五)は、演奏がすばらしい上に、ブラームスと違ってかなりいい音質。これは実音を充分にイメージできる。クレジットを見たらスタッフも会場もまったく違うので、これが原因か。モーツァルトのときのエミール・ベルリナー・スタジオという録音会社は、たしかなくなったはず。惜しい。
ブラームスの後に出たメンデルスゾーンと、ロック・ナンバーを編曲した『ポップソング』、それに新作のへルヴィヒ作曲の『ポケットシンフォニーズ』は、注文済ながら未着なので、ここでは触れない。ピアノ四重奏という限られたレパートリーを拡大するために、新作の委嘱にも積極的なのだそうだし、特に編曲集は、実演のアンコールを思い出すと興味がわくが、いまふうのポップス的な音づくりをしそうで、音はかなり不安。
そしてARS MUSICI。これは放送局録音の転用だが、音質はDGよりずっと自然で素直で、好ましい。スークとフォーレの二番の一枚は二〇〇一年の南西ドイツ放送(SWR)、キルヒナーとシューマンの一枚は二〇〇四年の西部ドイツ放送(WDR)。
とりわけ後者がいい。WDR音源のCDの音質はハズレがない。そして曲も。シューマン&クララ、ブラームスのトライアングルの近くに(あるときはそのなかに?)いたキルヒナーもいいが、やっぱりシューマン! あの第三楽章のアンダンテ・カンタービレをもう一度聴けるだけでなく、全曲を聴ける喜び。

音質の好みと曲と演奏の総合点で選ぶなら、キルヒナー&シューマン、次点にモーツァルト、そしてスークとフォーレの二番か。これらをもっと早く聴いていればと思うし、後の発売になるほど音質が不自然になるというのは……。
二十一世紀の盤に「ナマの響きを頭の中で甦らせるよすがにはなる」などと、まるでアコースティック録音の交響曲みたいな感想をいうのは本当に悲しい話だが、あまりにもナマの音とかけ離れている以上、そう形容するほかない(笑)。
合間に、エベーヌが参加したプレスラーの九十歳記念のCD、ドヴォルジャークとシューベルトのピアノ五重奏曲も聴きなおしてみた。
エベーヌもプレスラーもすばらしい音楽家であることはよくわかるが、どうしてもフォーレQの緊密な連繋にくらべると、臨時編成の弱さを感じる(録音がもう一つ冴えないせいもあるが)。ピアノと弦をあわせた室内楽でフォーレQの水準は、ほんとうに貴重だと再確認。
十二月二十二日(月)忘年会余興係
下北沢のアートレッグカフェにて、アルテスパブリッシングの忘年会。
下北沢も久しぶりで、地下駅になってからは通過したことさえなかった。便利だけれど特徴がなくてつまらないのは、いずこの地下駅も同じ。しかし地上の街並みの温かさはやはりいい感じ。
今回は忘年会の余興役を仰せつかっていて、月刊誌「アルテス」(電子版)に連載中の「帝都クラシック探訪」の「赤坂・溜池・飯倉」篇から、赤坂のあたりをゲストの片山杜秀さんとともに実演。
といっても現地には行けないから、地図を拡大してもらって、その前でしゃべる。みなさん、とても熱心に聴いてくださってとても心地よし。お客さんの反応を見ながらしゃべれるのは楽しい。
国会議事堂も日枝神社も、正面が東を向いた山の上。赤坂の町というのは、その反対、裏の崖下の低湿地沿いにある。この地形的条件から、町の性格が見えてくる。そんな話をしゃべる。
十二月二十六日(金)いまどきの第九
今日はNHKホールで、フランソワ・グザヴィエ・ロト指揮N響の第九。
自分としては十四日のパーヴォ&DKBのブラームス・チクルス楽日で今年は店じまいして、内省の日々(?)を過ごすつもりだったが、某誌から批評の依頼がきて、急遽聴きにいくことに。
結果としてはものすごく面白く、今年の締めにふさわしい音楽だった。批評は短いものなので、ここではそこに入らない話をメインに。
ノンヴィブラートで音の減衰の早いピリオド・スタイル。ピリオド・アプローチもいまや形骸化する危険が高くなっているのだが、ロトのつくる音楽には身がつまっていて、初めて聴く、そして教えられるものの多い第九になっていた。
社会主義リアリズムの「闘争と勝利」とか、少年ジャンプの「友情、努力、勝利」みたいなスローガンとは無縁の、単純素朴なドラマトゥルギーはひっぱずした音楽。
しかし無味乾燥ではない。ワーグナー風の雄弁で濃厚な音楽ではなくなっているかわりに、ベルリオーズ風のきらびやかだが軽快で反英雄的な音楽を感じる。合唱つき大交響曲の起源が革命期のフランスにあるという話を思い出したり。
あとでプログラムを読むと、そこでロトは「最終的には歓喜にあふれて、精神性の高いメッセージで締めくくられるにもかかわらず、作品全体は暗いトーンに包まれ謎めいている」と語っている。
さらに「この音楽は作品全体を通して長い旅を経験するように書かれている」とし、「人類への希望、信頼、そして確信といったものに関係しているように思います」といいながらも、これを明快で意志的な闘争と解決への流れ、ドラマと見なすのではなくて、「多くのパラドックスを秘めている」と考えているのが面白い。私が「ベルリオーズ風」と感じたのは、これと結びつくのかもしれない。
そしてこの点が、メッツマッハーと新日本フィルがツィンマーマンと併置することで聴かせてくれた「ひとりぼっちのベートーヴェン」像にうまく重なってくる。エロイカは聴けなかったけれど、第五、第七、ミサ・ソレムニスとメッツマッハーがつくった流れに、偶然にもこの第九は見事に乗っているように思えた。特に、ミサ・ソレムニスとの関係。
ロトの第九では軍楽的な要素、すなわち大太鼓、シンバル、トライアングルがとてもよく聴こえてきた。弦が澄んでいるので、威圧的に響かせることなしに、よく聴こえてくる。終楽章のテノール独唱の威勢のいい行進曲だけでなく、コーダでもかれらは大活躍している。神の軍軍勢の行進。そこではもちろん、天使の楽器トロンボーンが活躍。
一八二〇年代、ナポレオン戦争後の反動的なウィーン体制、厭戦気分、反戦気分が強かった時代に響く軍楽。「戦争の時代」の始まりの一八九四年にハイドンが《軍隊》交響曲で響かせたものの三十年後の後身だが、時代の気分は大きく変っている。
そして、パーヴォ&DKBのブラームスの交響曲第一番の騒々しさにも、やはりどこかでつながっている気がする。
現代を生きる音楽家が、けっして奇をてらうのではなく、渾身で聴かせてくれた、現代を生きる名曲たち。その締めのようだった。
それにしてもフランソワ・グザヴィエ・ロト、ナマは初めて聴いた。指揮するその後ろ姿を見ながら、「おお、たしかにフランシスコ・ザビエルのようだ、頭頂部が」と思った人がいたとか、いなかったとか。
Homeへ