二〇一五年
一月三日(土)フランキー堺の映画から
昨日今日と、昔の邦画を家で二本。
「帝都クラシック探訪」なる連載をやらせていただいていると、東京の興行街と繁華街の歴史への関心がいやおうなく高まる。興行街が浅草一つしかなかった江戸・明治から、浅草~銀座(「~」は前者から後者への主流の遷移でもあり、両極が張りあって往復するエネルギーでもある)の大正・昭和戦前、浅草~銀座~新宿の昭和戦後、そしてテレビがすべてを呑み込む昭和四〇年代以降というのが、大雑把な図式。
最近読んだ高平哲郎の『銀座の学校・新宿の授業』は、一九四七年生れの筆者が戦後の「銀座~新宿」とテレビの時代の体験を回想するもの。一方、小林信彦と萩本欽一の『ふたりの笑タイム』は、「銀座~新宿」とテレビの時代を、忘れられていく浅草の視点から眺めていく面白さ(先月の日経新聞の萩本欽一の「私の履歴書」は、その副読本の役を果たしてくれた)。
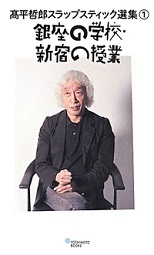

両者で絶賛されているのが、一九六〇年に有楽町の宝塚劇場で上演された東宝ミュージカル『雲の上団五郎一座』。そのなかでも伝説的なのが、切られ与三郎(三木のり平)と蝙蝠安(八波むと志)のコンビで劇中劇として上演される「源氏店」。銀座(有楽町なども含めた、広い概念の地域としての銀座)の絶頂期の象徴。
この『雲の上団五郎一座』、一九六二年に映画化されているのだが、そちらは評判がよくない。高平は完全に無視しているし、小林も「つまんない」で片づけている。
そこで、何がどう「つまんない」のかが気になり、衛星で録画したまま見ていなかったものを見た。
「源氏店」は、かなり短縮された形で入っている。ナマを見た人には物足りなかったんだろうし、小林と萩本が「いちばんおかしかった」と口をそろえる「のり平の草履」の芸も入っていないのだけれど、これだけでも充分面白い。
不思議だったのは、この場面を見た瞬間、自分がこの喜劇版「源氏店」を子供のときに見て大笑いしている、それも時間をおいて何度も見ているのを、思い出したこと。
それはこの映画版ではなく、テレビ。八波むと志は私が一歳の年に亡くなっているから、かれだったはずはない。蝙蝠安を誰か別人に代えて、その後もやっていたのだろうか。
ここは謎。しかしこの謎はすぐに解けそうもないのでここではおくとして、映画の話。
たしかにつまらない。最大の原因は、肝心要ののり平と八波のコンビが最初と最後にちょっと出るだけで、中抜けしていること。そして中間の主要部分で主役となるフランキー堺と水谷良重、この二人がまるで冴えないこと。
自分は二十代くらいまで、フランキー堺が桂小金治やなべおさみとともに、どうも苦手だった。あくまで個人的な好悪だが、わざとらしさが鼻につくように思えたのだ。しかし後年にみた、森繁の社長シリーズなどに脇役として出てくるフランキーは面白いので、何が苦手だったのか忘れていた。
それが、これをみて思い出した。ここにいるのはまさにその苦手な、鼻につくフランキーなのだ。
そこで、フランキー堺ってずっとこうだったのだろうかと、今度はそっちが気になって、代表作の『幕末太陽傳』を、何十年かぶりに見なおした。
これのフランキーはとても魅力的。五年のあいだに、何かが変ったのだろう。しかしその理由の詮索は、作品を見ているうちにどうでもよくなってしまった。
この作品の本当の主役は、かなり忠実に再現されているという品川の旅籠、土蔵相模のセットだ。夜は灯火にさんざめき、昼はけだるく眠る、生き物のような建物。『千と千尋の神隠し』の油屋の描写は、この映画からかなり影響を受けている気がする。
旅籠を舞台にする着想は、戦前の米映画『グランド・ホテル』から得ているのだろうが――死病にとりつかれ、余命いくばくもないことを覚悟した人物がどちらにも出てくるし――現代の目で見るといかにもセット然として薄っぺらいホテルに対して、この土蔵相模は隅々まで血が通い、生気が宿っている。
それから、高杉晋作(石原裕次郎)などの長州の志士たちの描写。オペラ演出家の三谷礼二さんも、秋津礼二という芸名でその一人有吉熊次郎を演じている。かれらは、制作された一九五七年当時の日本の社会に生きる若者たちの、写絵にもなっている。
それは、よくいわれるような太陽族ではない。鬱屈を抱えた志士たちは、一九五六年以後の消費社会、昭和元禄の落し子たる太陽族ではなく、それより古い、日本共産党が武装闘争をおしすすめた五〇年代前半にいた、左翼運動の若き闘士たちを想わせるのだ。だから演技はうまくないのに、妙な実在感がある。
映画のなかで英国公使館を建てようとする幕府は、アメリカに屈従する、当時の自民党政府そのもの。
その動きに反対して、愛国と民族独立(現時点の常識から見ると右翼みたいな主張なのが面白い)を訴える若者たち。ところが、一九五五年の六全協で日共が平和共存路線に転じ、突然ハシゴを外された若者たち。この映画はかれらへの挽歌という一面も、もっているように思える(実際には絶滅するわけではなく、六〇年安保の全学連、大学闘争の全共闘と、反日共の反体制学生運動としてつながっていくが)。
そこで面白く思ったのは、そのちょうど二十年後の一九七七年放映の大河ドラマ『花神』の、中村雅俊の高杉晋作をはじめとする長州の志士たちの描写との関連性。
『花神』の志士の描写には、『幕末太陽傳』を意識しつつ、その後の六〇年代末の新宿の活気と、全共闘運動の残影を重ねているような感じがあった。
思えば七〇年代の大河ドラマでは、幕末はもちろん戦国でも鎌倉でも平安でも元禄でも、つまりどんな時代を扱った場合でも、反体制的な変革者への憧れと高揚感が、その面白さの背後にあった気がする。
ならば、明日から始まる『花燃ゆ』の志士たちには、何を重ねるのだろう。ネトウヨや反原発運動…はまだ難しそう。予告編には、はっきりと「幕末ホームドラマ」と書いてあったっけ。
乙女ゲームを重ねて、さらにその背後にBLを暗示するのは、近年のNHKの腐女子傾向から見て、間違いなさそうな気がするが…。
一月二十五日(日)ゼッダ快演
東京文化会館で、藤原歌劇団によるヴェルディの《ファルスタッフ》。
明朗で軽妙なゼッダの指揮が見事。歌手もそれに乗って好演。以前、同じ指揮者と団体による《フィガロの結婚》をここで聴いたときには、歌もオーケストラもホールの大きさを持てあましている印象があったのに、今日はそんな不満をみじんも感じなかったのが不思議。音楽と指揮者との相性のせいなのか。
一月二十九日(木)NHK移転計画
設立百周年をにらんで、NHKが十年後の移転を計画というニュースを見る。そこには「神宮前の都有地」としか書いていないが、あそこでいまの放送センターに匹敵する広さというと、神宮前五丁目の青山病院跡と、南に隣接する「こどもの城」の合計くらいか(まだ少し狭いように思えるが)。
今年三月の「こどもの城」のかなり強引に思える閉鎖が、この移転を見越してのことだったとすると、とても腑に落ちる(後味はよくない)。すでに空き地となっている青山病院跡だけでは広さが足りず、青山通りに直結しない裏通りの土地になるが、「こどもの城」の用地を足せば状況は一気に好転する。
NHKホールはどうするのか。放送センターが移転して、あれだけ残すとは考えにくい。たとえば紅白や歌番組は国際フォーラムのホールA、N響はサントリーホールへ行くとするなら新たに建てなくてもいいし、それで放送センターだけにしぼれば、神宮前の土地でも足りる。
もうすぐはじまる日比谷公会堂の大改修で、二〇二六年に創立百年となるN響が六十五年ぶりに日比谷へ戻るというのも面白いが、それはないか…。建てなおしたあとの渋谷公会堂、というのもありえるか。
一月三十一日(金)ゴルトベルクの旅
昨日はFBフレンドでもあるピアニスト、高橋望さんのひくゴルトベルク変奏曲の全曲演奏会へ。
ゴルトベルクをナマで聴くのは、昨年七月のバッケッティのトッパンホール以来。しかし、あのときのバッケッティがセンツァ・リトルネッロ、反復一切なしで一気呵成の驀進スタイルだったのとは対照的に、反復を完全に行なうもの。演奏時間はほぼ倍になる。そして各変奏を一つ一つ、しっかりと音にしていく。
偶然、その前にリヒテルのことを仕事で調べていて、かれがモスクワでグールドのリサイタルを聴いたときの一文が印象に残った。
「一九五七年にグールドが来ました。彼が行ったリサイタルのひとつを聴きました。《ゴルトベルク変奏曲》を唖然とさせるやり方で弾きましたが、繰り返しは省きました。それで私の喜びの一部が殺がれてしまいました。作曲家の指定に従わず繰り返しを省略する演奏家(大勢います!)は、口笛を吹いてやじってやればいいと、ずっと思ってきました」
(『リヒテル』ブリューノ・モンサンジョン編/中地義和・鈴木圭介訳/筑摩書房)
あるいは、ルージチコヴァのチェンバロによるゴルトベルクを聴いたあと。
「有難いことに繰り返しを全部やっている(繰り返しをやらなければ、全曲弾かない方がいいくらいだ)」
こうした文に出くわしたあと、ナマで反復ありのゴルトベルク変奏曲を聴くことになる。本の中と外の現実と、過去の偉人と現在の友人と、重なりあってくる面白さ。いまの自分が歴史に求めているのは、まさにこういう多層性の快感だと思う。
高橋さんのバッハは、まずそのピアノの、虚飾のない質素な音色が美しい。ベーゼンドルファーの充実感のある響き。左手の低声の線が確固として響く快感。三十の変奏曲の性格をきちんと描きわけようとするなかで、特に第十五変奏のゆっくりと抑制された祈りの歌が印象的だった。私は第二十三変奏前後の、音楽の自発的な躍動もとても心地よかったのだけれど、演奏後の高橋さんによると、あのあたりは集中力が薄れかかっていたのだという(笑)。ひくものときくものの意識のズレの面白さ。
バッハが趣向をこらしてつくった、三十の多彩な変奏という回遊式庭園。それはピアニストにとって長大な、終りのない旅。リヒテルは一九七五年にこう書いている。
「いつの日か自分も弾いてみたいものだ……最後まで弾き通せるものなら」
リヒテルが公開の場で全曲を弾くことはついになかったが、しかし、道は未知へと、つねに開かれている。
前述のバッケッティのナマは反復なしだったけれど、かれはこれまでに三回反復つきで映像と録音にし、それぞれテンポが違う。そして秋には反復つきと反復なしの二つを合わせたものを録音すると語っていた。ついでにいうと、かれはグールドがわずかな箇所だけ反復をつけたことを「天才的な発想」とたたえつつ、自分は反復をやるかやらないか、どちらかに分けたいと語っていた。
高橋さんの演奏も長い旅。今日を終えて、そしてまた明日。
会場は四谷区民ホールだったので、十五分ほどの歩きで帰宅。この旅は短いほうがラク。
二月十二日(木)若きフォーレ四重奏団
NHKのBSプレミアムで早朝放映された、昨年十二月のトッパンホールでのフォーレ四重奏団の演奏会を録画。本プロのブラームスに、アンコールからフォーレタンゴとシューマン。
マーラーよりもシューマンを選んでくれたのは嬉しい。ブラームスの頭を少し見ただけだが、あのときのただならぬ雰囲気、なにかとんでもないものになりそうな予感──そして本当にそうなる──がちゃんと画面に捉えられているようなので、見るのが楽しみ。
と思っていたら、先日ウツボ買いしたフォーレの一番とドヴォルジャークの二番が無事到着したので、先にこちらを聴く。結成四年目の一九九九年、フライブルクでの録音なので、おそらくこれがデビュー録音。レーベルは他の初期録音と同じARS MUSICI。
二曲とも現在の濃密さとは別の、若々しい爽快さと軽みのある演奏で、これはこれでとても魅力的。中に四人のバイオが入っている。それによるとみな一九七四年か七五年生れで、このとき二十四、五歳なのだから当然か。下の写真は解説内にあったもの。若い若い(笑)。しかし立体的で骨格がしっかりしている点は、このときから変わらない。これが原点か。
バカ高いプレミアム価格で買う必要はないと思うが、ウツボ買いなら絶対に損のない一枚。

二月十四日(土)ゴルトベルクの器
紀尾井シンフォニエッタ東京の定期。
ドミトリー・シトコヴェツキーの指揮で、バッハ/シトコヴェツキー編のゴルトベルク変奏曲(弦楽合奏版)と、チャイコフスキーの弦楽セレナード 。
チャイコフスキーはタクトをもって指揮に専念する普通の形式だが、ゴルトベルクはコンサートマスター席からのひきぶりによる。
シトコヴェツキー編のゴルトベルクは一九八四年の弦楽三重奏版が有名で、一九九二年の弦楽合奏版は聴いたことがなかった。マーラー編のベートーヴェンの弦楽四重奏曲の弦楽合奏版みたいなサウンドを想像して行ったところ、まるで別の凝った編曲で変化に富んで、とても面白かった。
合奏協奏曲的に、各パートのトップがソロをとるだけでなく、変奏によってトップだけの室内楽になったり、低弦伴奏によるヴァイオリン独奏になったり、さまざまに変る。プログラムに載っていた編成の始めだけ引用すると、
アリア:五重奏
第一変奏:全合奏
第二変奏:合奏(ヴァイオリン二部とチェロ)
第三変奏:四重奏(ヴァイオリン二部、チェロとコントラバス)
第四変奏:全合奏
第五変奏:五重奏
第六変奏:全合奏
第七変奏:二重奏(ヴァイオリンとチェロ)
といった感じで、じつに多彩。バッハというよりはヴィヴァルディやコレッリなど、イタリアの弦楽合奏のような明朗な響き。シトコヴェツキーのセンスの冴えと、恣意的な変更なしにこれだけの変容を遂げることのできる、ゴルトベルク変奏曲という作品の器の大きさに驚嘆。
編成はしっかり数えなかったが、たぶん八‐六‐六‐四‐二にチェンバロ。通奏低音以外は弦楽器だけなので響きの均質感は保たれ、なおかつ変化に富むというすばらしさ。第二ヴァイオリンのトップに座ったコンサートマスターの千々岩英一以下、ソロも合奏も高水準。そして同時に、独奏も重奏も合奏もすべてが適切に響く、八百席の紀尾井ホールという空間あっての音楽だった。
発想の源がグールドの一九八一年盤なので、反復は曲によって自由に取捨選択し、長さは約六十分。第十五変奏のあとの、いわゆる「第一部」の終りに間をとった以外は、ほぼ続けて演奏。最後の第三十変奏にいたって、今日初めてといっていいくらいにたっぷりとしたカンタービレをかけて全合奏で歌いあげた大団円の効果は見事なもので、そこから五重奏のアリアへ戻って、幕。
後半のチャイコフスキーも力強い生命力で美しい。そして編成もホールも、まさに適切な規模なのが素敵。最後に曲頭の序奏主題が帰ってくるところはゴルトベルクと同じで、いい組合せ。アンコールにバッハのアリア。
なお今日はライヴ録音が入っていたので(エクストン?)、発売される日が楽しみ。その前に折よくこの弦楽合奏版の新録音がイギリスのブリテン・シンフォニアの演奏で出るので、購入予定。
追記(七月十三日):このときのライヴ録音はマイスターミュージックから六月二十五日にCD化された。(MM-3051)

プログラムの最後に来シーズンの予定が出ており、ライナー・ホーネック指揮でドール独奏のシュトラウスとモーツァルトのホルン協奏曲にメタモルフォーゼンとか、ピノック指揮のフォーレ、ベートーヴェンに太鼓連打とか、来年も面白そう。
個人的に期待するのはバラホフスキーをリーダーに指揮者なしでやるペルト、ブリッジ、ドヴォルジャークの弦楽合奏の回。バイエルン放響の花形コンマスであるバラホフスキーが客演したときの紀尾井シンフォニエッタの弦はすばらしい音がするだけに、ものすごく楽しみ。
二月十六日(月)一九五三年の朝比奈隆とブルックナー事始

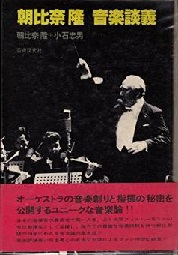
ヒストリカルのトリビア。
クナッパーツブッシュがミュンヘン・フィルを指揮した《英雄》の、一九五三年十二月十七日のミュンヘン、ヘルクレス・ザールでのライヴ。いろいろなレーベルで出ている盤だが、朝比奈隆が客席で聴いていたことに気がつく。といっても、前にどこかでこの話を読んでいると思うが、すっかり忘れていた。
思い出すきっかけは、少し前から読んでいる押尾愛子の『朝比奈隆のオペラの時代』(図書新聞社)。三谷礼二さんの関西での活動に触れているというので買ったのだが、三谷さんが登場する前に別の方向に興味が膨らんで、停まってしまった。
朝比奈が関西歌劇団で武智鉄二の演出と組んだ、いわゆる武智オペラ。これの一つに、一九五四年十一月に《修善寺物語》の初演があるということ。
これがものすごく嬉しかった。私が亀の歩みで進めている一九五四/五五年本につかえないかと思っていた録音に、一九五五年一月の、東京二期会による東京初演の直後にビクターから発売された、この作品の全曲盤がある(『永遠のテナー 柴田睦陸』という三枚組で初めてCD化された)。
これを使って二期会初期の話をしたいと思っていたのだが、押尾本によってさらに朝比奈隆と武智鉄二、そして関西楽壇の話もできることを教えてもらった。そこであわててこの二人の資料を引っぱりだしたり買ったりしている。
朝比奈がオペラにおける演出を重視するようになったきっかけは、一九五三年秋にドイツで、レンネルトやギーレンの仕事ぶりに接したことだという。
それで、朝比奈隆の『音楽談義』(芸術現代社)を読んでみると、この朝比奈初の欧米旅行での音楽体験が細かく回想されている。わかる範囲で演奏記録などと突き合わせ、推測もまじえて時系列で組みなおしてみると、抜粋だけでもとても興味深いラインナップになる。
十一月二十九日 ベルリンでティーチェン指揮ベルリン市立歌劇場の《神々の黄昏》。
十二月六~八日 ベルリンでフルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルのブルックナーの交響曲第五番ほか。
十二月十か十二か二十九日 ミラノ・スカラ座でバーンスタイン指揮カラス主演の《メデア》
十二月十六か十七日 ミュンヘンでクナッパーツブッシュ指揮ミュンヘン・フィルの《英雄》ほか
一月十四日 ニューヨークでセル指揮メトロポリタン歌劇場の《タンホイザー》
一月十五日(?) ニューヨークでワルター指揮ニューヨーク・フィルの《ジュピター》ほか(リハーサルだけの可能性あり)
一月十五日(?) ニューヨークでエレーデ指揮メトロポリタン歌劇場の《ラ・ボエーム》
一月十八日 ニューヨークでコズマ指揮メトロポリタン歌劇場の《カルメン》
このうち、《メデア》《英雄》《タンホイザー》は録音が残っているので、とても嬉しい。
ただし朝比奈の面白いところは、オペラの場合だと指揮者についてはほとんど論じていないこと。メトは誰が指揮していたか覚えていないというし、バーンスタインのことも言及なし。例外はティーチェンだが、これは演出も兼ねていて、リハから見学したからという関係。
それともう一つ面白いのは、一月のニューヨークには吉田秀和と大岡昇平と福田恆存がいて、かれらも連日音楽会通いをしていたのに、朝比奈とはまったく没交渉だったらしいこと。なかでも吉田はワルターと《タンホイザー》の日に会場に行っている。お互いわずかな日本人の音楽関係者だし、顔を合わせなかったとは考えにくいが、ともに言及なし。
吉田と朝比奈の関係は、後年朝比奈が東京でも売れだしたときもふくめて、どうなっていたのだろう。謎。
(つけくわえると、武智鉄二は五〇年代後半に東京で実験工房などとシェーンベルクやケージの上演に関わる。そのときには吉田秀和と近いところにいたはずなのに、これも微妙にねじれていて、よくわからない)
さて、これで朝比奈は《修善寺物語》とクナの章に出せることがわかった。さらに一九五四/五五本の初めの方で《タンホイザー》と《メデア》の話をしているので、そこに朝比奈を新たにからませることができるかどうかも、思案しなければならない。
司馬遼太郎が、史料を読むときのいちばんの醍醐味といっていた「あなたはこんなところにいたのか」という発見、それを少し味わうことができた。
ここまでをフェイスブックに書いたところ、FBフレンドの指揮者徳岡直樹さんから、朝比奈は、フルトヴェングラーのブルックナーの第四番を聴いたと書いていたのではというご指摘を受ける。
鋭いご指摘で、たしかに朝比奈は何度もそう書いている。一九七八年の『音楽談義』も、『この響きの中に』(実業之日本社)所収の一九七三年の「フルトヴェングラー回想」と八七年の「わが音楽人生の「到達点」」などのエッセイもそうだ。しかし、フルトヴェングラーの演奏記録にあるのは第五番。これが第四番に変更されたという話もない。
この相違について周囲が疑問を呈したのか、『朝比奈隆のすべて』(芸術現代社)所収の一九九三年の宇野功芳との対談になると、「『四番』か『五番』を聴いた後に」と、記憶違いの可能性を意識した発言をしている。
それは、少年時代からの夢だったベルリン・フィルとフルトヴェングラーを初めてナマできけたことが「あまりにも強烈すぎる印象であり、ただ身も目も激しく旋回する渦の中にあるよう」で、「強い流れに押し流されるような切れ切れの記憶」しかないせいもあるだろう(「フルトヴェングラー回想」による)。
しかしそれだけでなく、この時点では朝比奈がブルックナーの交響曲を指揮したこともなく、勉強をはじめたばかりだったせいもある。このときの印象について『音楽談義』では、「今そんなことを言ったら笑われますが、ちょっと見当がつかなかったのです」と述べている。朝比奈は帰国後の一九五四年に、オーケストラのレパートリーを広げるべく第九番を指揮することにしていたが、その理由は「後期の三つの作品は、初期のものに比べてスコアを読んで大体見当がつく。スコアが読みやすかったからなんです。大して深い考えもなしに選んだのです」というもので、とにかくブルックナーの音楽については「見当がつかなかった」という形容が数か所で用いられる。
これは朝比奈だけのことではない。ブルックナーが男性専科の人気作曲家となった現代日本のクラシック界では想像しにくいことだが、昭和三十年代まではまるで人気がなかったのだ。朝比奈もこの年第九番と第四番を指揮したものの、周囲からも聴衆からも総スカンをくらい、その後十年はほとんど指揮しなかった。
そして曲の取り違えについては、翌五五年にザルツブルクでクナッパーツブッシュ指揮ウィーン・フィルによる第八番を聴いた吉田秀和が、あれほど吸収力と記憶力に優れた人なのに、第七番と間違って書いたのと、よく似ているのが面白い。吉田もそれほど退屈したのだ。
当時のこの感覚は、柴田南雄の「作曲家には過去の音楽。指揮者、聴衆には未来の音楽」という一九五八年のブルックナー評が、的確に言いあらわしている。
前衛音楽を信奉する当時の作曲家や評論家にとっては古くさく、演奏家と聴衆にとっては見当がつかない。
それが日本人にとってのブルックナーだった。当時の吉田は前者の立場、朝比奈は後者で、対極的に違うが、いずれにしても遠い音楽だったのだ。
朝比奈も吉田も十年ほどのあいだにブルックナー観をあらためるし、一般のファンも次第に増えていく。その背景にはステレオLPの普及もあったろう。
七〇~八〇年代に「宇野功芳のブルックナー観=日本人のブルックナー観」みたいな傾向がとても強かった(例外はもちろんあるが)のは、いかにそれまで日本人がブルックナーを聴いていなかったか、の証明でもあるわけだ。
その価値観が多様化するのは、CD時代になって、ブルックナー好きがさらに増えてからのことである。
と、この話も一九五四/五五本がもとなのだが、いつ世に出せることやら。
二月十七日(火)バッティストーニ
二期会公演《リゴレット》のゲネプロを東京文化会館で。
何度か書いたが、自分はこの作品、ヴェルディが旅興行の小さな歌劇団と劇場向けを意識した印象を持っていて(初演はヴェネツィアのフェニーチェという大劇場だけれど)、大きなハコでやるとどうも違和感がある。小さい場所にギュッと詰めこんだときにこそ真価を発揮する作品、という気がするのだ。
しかしそれはそれとして、ゲネプロの段階から指揮のバッティストーニの放つ生命力は見事。
二月二十日(金)ひとくぎり
サントリーホールで新日本フィルの定期。指揮はジャン=クリストフ・スピノジ。
曲は前半がロッシーニの《チェネレントラ》序曲、シューベルトの交響曲第三番、後半がサン=サーンスの《オルガンつき》。
晩冬にこのコンビを聴くのは三回目。いつも春の到来を感じるのだが、今年ははじけ方が少なく、そこまでは感じなかった。来シーズンは登場しないようで、メッツマッハーの退任とともに、客演陣の顔ぶれが変るらしい。季節の始まりよりも、一つのくぎりを感じる演奏会。
二月二十四日(火)
家猫のフク死す。外で野良猫とケンカしているうちに崖から落ち、運悪く頭を打ったらしい。二歳上のワサビが病死してから二年あまり。よいコンビだったから連れていったのかもしれない。
二月二十五日(水)
フク火葬。これまで同様、哲学堂の動物霊園。帰宅して骨箱をワサビと並べると、まるで二匹が寄り添っているようにサマになる。
二月二十六日(木)銀の祝い
HMVの開店二十五周年を記念して、エソラ池袋にHMVのクラシック売場が四月に復活するというニュース。芸術劇場の帰りに寄ろう。
ところで渋谷店開店二十五周年ということは、自分が「レコード芸術」のHMV広告欄に拙文を紹介してもらいはじめて、同じく四半世紀になる。それが今の稼業の始まり。
まだ、インターネットが一般には遠い世界だった。そんな時代に、不特定多数の人の目に触れる機会を与えられた自分は、つくづく幸運だったと思う。
多謝。
三月一日(日)県立音楽堂の神託
神奈川県立音楽堂でヴィヴァルディのオペラ《メッセニアの神託》。
ヴィヴィカ・ジュノーなどの歌手陣のなかでも、ユリア・レジネヴァの声と歌がきわだっていた。他の歌手が口から声を出すのに、彼女だけ頭全体が共鳴するような、まるで別の豊麗な響きだった。この響きがあって高い技巧も活きる。鳴りのよさそうなおでこを無駄にしていない。ビオンディ指揮のエウローパ・ガランテの演奏もさすがのもので、日本ではなかなか見られない、バロック・オペラの高水準の公演だった。
面白かったのが、ビオンディがヴァイオリンをひきながら指揮台に立っていたこと。コンマスを兼ねていて、手が空くと弓を指揮棒にして拍子をとる。近年はバトンを用いない、素手の指揮者も少なくないが、そのなかで鍵盤楽器出身にくらべて弦楽器出身の指揮者が指揮棒を使うことが多いのは、こうしてみると、もともと持ちなれているからか。
公演とあわせて、自分が見たかったのは、神奈川県立音楽堂の建物。八〇年代にジャパン・アーツでバイトしているころにリヒテルの公演かなにかで来て以来だから、ほぼ三十年ぶり。
ホールとロビーの構造をながめると、群馬音楽センターとよく似ている。
まず、客席が一枚のフラットな斜面になっていて、勾配が高いのでどの席からも舞台が近く、見やすいこと。そしてその斜面の下の空間を利用して、一階のロビーやトイレがあること。
また、外壁の黒い窓枠がコルビジェ風に障子の桟のように細く、窓が広くて外光を大きくとりいれていること。二階へ昇る階段からロビーを斜めに眺めたときの雰囲気など、ほんとうにそっくり。
いうまでもなく、五十四年前の一九六一年開場の群馬音楽センターに対して神奈川県立音楽堂はその七年前の一九五四年(横浜開港百年)完成だから、これは前者を設計したアントニン・レーモンドが、後者の前川國男を参考にしたのだろう。前者の外形の青いザリガニみたいな板の組み合わせは、レーモンド独自のものだが、建物の中は板張りのホールの内装といい、よく似ている。
しかし前川は群馬音楽センターと同じ年の一九六一年、上野の東京文化会館でさらに一歩前に進む。巨大な四角い箱の中に大小二つの六角形の箱を仕込んでホールとし、上野駅の鉄道の音を完全に遮断する、金のかかった方式。
ただ東京文化会館の失敗は、ミュージック・センターという当初の名称を貫徹できず、「文化会館」という、目的のよくわからない名前になったこと。まだ貧しくて戦後民主主義の強い時代、公共の建物で音楽だけに目的を限定した名称では議会の承認をとりにくかったらしい。
そういうなかで「日本で初めての公立による音楽専用ホール」音楽堂をつくった神奈川県の心意気は大したものだし、反対を押しきって「音楽センター」を貫徹した高崎市もえらかった(とはいえ、パイプオルガンをつけるだけの予算は、さすがにどちらもとれなかった)。
ホールには、こうした歴史が蓄積されている。壊されずに保存・活用されていってほしいもの。前川が神奈川県立音楽堂と東京文化会館のあいだにつくった世田谷区民会館も、一九五〇、六〇年代に特別区が続々と建てたホールの、貴重な生き残りの一つ。あれも近いうちに見にいかねば。
ただ神奈川県立音楽堂、惜しいのはこの建物のある掃部山公園と桜木町駅を分断する、広くて殺伐とした、煤と埃の国道十六号線。タンクローリーやダンプの似合うこの高度成長時代のモータリゼーションの残滓だけは、もう少し美しくできないのかと思う。並行する東横線のガード跡の上を遊歩道化する計画があるそうで、これを掃部山に直結できれば、雰囲気が変るかもしれない。
このだだっ広い道路が囲んでいるために、桜木町駅にしても港湾工業地帯の煤けた建物みたいで、外国人居留地に面してつくられた、初代の「横浜駅」という情緒を片鱗も感じることができない。
外国人居留地にあった幕末以来のオペラ上演会場、ゲーテ座の跡も見にいきたかったが、強い雨で断念。
三月二日(月)ミューザへの時空
昨日に続いて、連日の「新橋から東海道線に乗って」シリーズ。
ミューザ川崎で、ソヒエフ指揮のトゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団。ショパンのピアノ協奏曲第一番(独奏アヴデーエワ)とリムスキー=コルサコフの《シェヘラザード》。
客席で会った音友の編集者に「今日も感想書くんですか?」ときかれて「いや書かないと思います」と、〆切時期だけに万引きを見つかった小学生のような返事を思わずしてしまったが、やはり我慢できずに一言。
いやもう、「新橋から東海道線に乗って」これほどに対照的な楽音を、昨日と今日で聴けるとは。
一七三七年に初演の《メッセニアの神託》と一八八八年初演の《シェヘラザード》、百五十年のあいだにどれほどオーケストラが発展し、巨大化したか。まさにチームとレギオン。
強く輝かしい響きが安定して出る、モダン楽器ならではの質と量のスケール。構成員の役割は明確に分化して、指揮者という「大英雄」を頂点に、コンマス初め重要なソロを担当するトップ奏者という「小英雄」が何人かいて、その背後に一糸乱れず従う、精鋭揃いの一般の兵士が居並ぶ。これぞレギオン。
左翼にも右翼にも大きな影響を与えた十九世紀以来の英雄主義(ナポレオン、ベートーヴェン、バイロンなどに始まるもの)が、作曲家や指揮者、大ヴィルトゥオーゾのピアニストやヴァイオリニストの特別化、英雄化の背景にあるのだから、オーケストラも呼応して、英雄を支えるレギオンとして位置づけられる。
二十世紀前半のボストン響やクリーヴランド管の話を読むと、オーケストラ内に明確なカーストがあり、「小英雄」の首席奏者はかれらだけの階層を築き、下っぱとほとんど交流がなかったとある。
現代フランスのオーケストラにそこまでの階層はないだろうが、しかし《シェヘラザード》の華麗な色彩的オーケストレーションと情緒的な旋律美は、そうしたカーストを求め、固定化させるだろうことが、聴いているとよくわかる。
昨日ビオンディがやった、指揮者がコンマスを兼ねるなんてスタイルは、ここでは絶対に不可能。カーストが違うものなのだから(笑)。
そしてホール。駿河の富士川から津軽の外ヶ浜までのあいだで(蝦夷はキタラがあるからのぞく)、おそらく最高の音響をもつ大ホール、ミューザ川崎。
同じオケを九日前にサントリーホールで聴いているが、響きの純度、透明度がまったく違っていた。余計な残響や色をくわえず、自然に花ひらくような、美しい音響。楽員が前回より伸び伸びと、楽しそうにひいているのがよくわかる。
神奈川県立音楽堂から四十四年で、日本はこれだけのホールをもてるほどに発展した。立派なパイプオルガンもある。
だが、だからといって、県立音楽堂がたんなる時代後れのろくでもないホールだとは、思わない。ヴィヴァルディがたんなる時代後れの音楽とは思えないように。ピリオド楽器がたんなる旧式の楽器とは思えないように。
進化の度合いはとても大きいけれど、退化したり失くしたものもある。そしてそこには、積み重なった時間と空間という、かけがえのない歴史がある。
優劣でも好き嫌いでもなく、これほど対照的なものを二日つづけて聴ける、体験できることの面白さ。まさに、めくるめく落差の快感。
こんな快感は、自分が学生だった三十年前には、日本では実演でもLPでも、まず味わえないものだった。
音楽好きには「いまどきの演奏」を嫌う人も少なくない。昔を懐かしむ人がたくさんいる。それはそれでよい。私にとって「いまどきの演奏」、いや「いまどきのクラシック」の快感と醍醐味は、このめくるめく落差、対照、時空の瞬間移動にこそある。こんなものは、少なくとも日本には、かつて存在しなかった。
そして現代の演奏家たちは、モダンであれピリオドであれ、自分がその落差の渦中にあることをはっきりと自覚して、日々演奏している。
それはけっして、関東の演奏会でしか味わえないものではない。ディスクだって、衛星ラジオだって(ここは宣伝が多量に入っている)、味わえる。
その快感に喜びふるえつつ、新橋へ東海道線に乗って。
三月七日(土)中学同期会
六本木にて、中学の同期会。今年はちょうど、入学から四十周年。百六十人のうち約七十人出席というから盛会か。
今は社会的立場もそれなりだろうに、こうして集まると、とたんに統制のとれない中坊集団に戻ってしまうのが面白かった。
三月十四日(土)クンドリーの花
私のように中途半端なランクのフリーランスの悪いクセは、来た仕事を断れないことである。
そのぶんお金が増えるという意味もあるけれど、それ以上に、信頼関係にある編集者さん以外だと、もう二度と頼んでくれないかもしれないという恐怖心があるからだ。
もちろん、売れっ子でもないから大体は適当な量に落ち着くのだが、この二月末から三月中旬にかけては、どういうわけか滅茶苦茶な量をいただいた。出版業界には年度末の予算消化のための工事とかは関係ないはずだが、とにかく多かった。ギリギリ穴を空けずにはすんだけれども、ついに月刊誌のうち二誌で、校了日の日暮れ時に原稿を出す体たらく。
これが編集さん、デザイナーさん、印刷屋さんその他にどれほど迷惑をかけるかはいうまでもないことで、海老名みどり風にいえばまさに「白髪ブタ野郎」状態。一誌ならともかく(ダメ)二誌続けてとなると、かなり凹む。
十二日夕べについに終り、脳内アドレナリンが出まくった興奮状態のまま、日経新聞で評を書く新国立劇場の《マノン・レスコー》を見、ひと晩眠ったが、翌日(昨日)は、自己嫌悪で虚脱状態。
今日は少し持ちなおして、デッドラインの見えてきた確定申告にとりかかり、そのあと十八時から、サントリーホールで東京交響楽団の演奏会。
ジョナサン・ノットの指揮で、ベルクの叙情組曲より三つの小品と、ワーグナーの《パルジファル》抜粋。
叙情組曲は直前にテツラフ四重奏団のCDを試聴記のために聴いたばかりで、そのキレキレの響きが耳にこびりついていたため、あまり強い印象は残らず。でも透明度の高い、美しい演奏だった。
それよりも《パルジファル》がすばらしかった。
かなり珍しい抜粋のしかたで、第一幕の前奏曲、第二幕のパルジファルとクンドリーの二重唱、そして第三幕の「聖金曜日の音楽」(歌抜き)。
グルネマンツ役のバスも連れてくれば「聖金曜日」も歌入りでやれるし、東響コーラスも入れてくれれば第三幕全曲もできるのに、と思ったりもしたが、聴き終わってみれば、これはこれで、とても筋の通った抜粋だとわかった。
単に聞きどころを集めたのではない、筋の通った抜粋なのである。
第一幕のエッセンスは前奏曲につまっているし、第二幕の肝は二重唱だし、第三幕の花は「聖金曜日の音楽」にある。これだけで充分に抜粋がなりたつのだ。第三幕の終曲があった方が、たしかにわかりやすい大団円になるけれど、そこで何が起きるのかは第二幕の最後にパルジファルがすでに預言しているのだから、なくてもいい。
それを省き、さらに歌を第二幕だけにすることで、ここではドラマを「クンドリーの救済」にしぼる、という意志が明快になる。それがとてもよくわかった。だから聖杯騎士団に関わる音楽は前奏曲以外、すべてカットされる。
今日が二日目の公演だからか、二人の歌手は終始よく声が出て、すばらしかった。ヤノフスキの録音で同じ役を歌ったエルスナー(あのシリーズではローゲとミーメも歌う大活躍)はいかにもそれらしい声と響きだし、クンドリーのアレックス・ペンダはさらによかった。
ただペンダ、プログラムを開くまで、これがあのアレクサンドリーナ・ペンダチャンスカのことだとは、夢にも思いませんでした。いつのまにこんなアメリカンな略名に(笑)。
くぐもって力のある声、そして、クレオパトラを思わせる漆黒の長髪と金ラメの絢爛なドレス。これがいかにも、キリストの時代から中世まで、あらゆる場所と時間に生き続ける「アラビアの妖艶な古き魔女」という感じでぴったり。
この第二幕だけが唯一、幕の終りらしく終ったあと(もちろんクリングゾールは出てこないが)、そのまま「聖金曜日の音楽」へ。
ここは、どうしても脳内でグルネマンツが歌ってしまう(それもホッターの声で)が、しかしこれは、やはり歌抜きでこそ意味がある。
これが「クンドリーの物語」だから。第二幕のあの魔の城にあった、色も形も匂いも毒々しい、季節知らずの虚飾の大輪の花が、ここで春の野原に咲く、可憐な花々へ転じる。
これがクンドリーの「救済」なのだ。永遠に死ぬことのできぬ呪われた悪の華から、美しくもはかない、野の花へ。
「花のもとにて春死なむ」
ああ春が来た、と思った。なぜ受難と復活が春の季節にあって、「パルジファル」がこの時期に上演されるのか、こんなに深く実感したことはなかったように思う。
音楽は、そのまま盛りあがらず、場面転換の音楽に入ることなく、すーっと終る。「だがそれがいい」。終景の、あの死と血の臭気と煩悶にみちたモンサルヴァートの陰惨な聖堂に入ることなく、花の咲く広い野っぱらで、ただ青空と雲を見上げるようにして、音が終る。
春が来た。
去年はスピノジと新日本フィルがそれを実感させてくれたけれど、今年はノットと東響が教えてくれた。東響、私が聴いたかぎりでは、ここ数年でも最高クラスの好演だったと思う。
さ、確定申告。
三月十五日(日)メトロとメガロ
東大教養学部の駒場博物館にて、「會舘の時代―中之島に華開いたモダニズムとその後」という特別展が行なわれていることを教えてもらう。大阪中之島のホール、朝日会館(會舘)のモダニズムを紹介するものらしい。
『帝都クラシック探訪』で東京各地の音楽ホールの今と昔を調べていて、あらためて実感するのは、昭和の東京における大阪文化の影響力の大きさ。
それは、京都でつくった呉服を越後屋が江戸日本橋で売っていた江戸時代の力関係と、あまり変っていない。
町人文化は豊かな経済力が育むものだから、いうまでもなく江戸時代は大阪が上だった。大坂と江戸の商人の違いは、大坂は全国規模で商売を考えるが、江戸は江戸の中だけということ。日本橋の魚河岸がどんなに活気があっても、その商売は江戸の住民だけが相手。日本最大の消費地ではあっても、物流の中心にはなりえなかったのである。
この差は維新後も埋まらなかったようで、とりわけ関東大震災で東京社会が壊滅的打撃を蒙ったあとは、大阪起源の新聞社や興行社、すなわち朝日や毎日や東宝や松竹が、東京のそれを併呑して、消費市場の拡大とともに全国へ展開する。
大阪の町そのものも発展、昭和初年には大阪市の人口が東京市を上まわっていた。いわゆる「大大阪」の時代。モダニズムとブルジョワ文化も次第に阪神間、梅田をターミナルとする阪急文化圏に中心を移しながら、文化力を蓄える。阪急以外にも近鉄や南海が私鉄網を張りめぐらし、メトロポリスが形成される。各私鉄はプロ野球の球団を競って所有する。
私鉄各社の球団とともに、大阪中之島の朝日会館は「大大阪」時代の象徴の一つである。「東洋のカーネギーホール」と謳われたと、昔どこかで読んだ記憶がある(対して日比谷公会堂はせいぜい、「東京のカーネギーホール」なのだ)。
この力関係は、敗戦をへて新幹線、東名高速などが出来るたびに徐々に変っていく(新幹線開通こそ大阪財界の終りの始まりだったと、誰かが書いていた)。バブルまでには大阪にあった企業も東京へ拠点を完全に移してしまい、お笑い以外の大半が東京中心になる。
山崎豊子の小説の舞台が次第に関西でなくなっていくのは、その象徴のようでもあり。山崎といえば、大阪労音をヒントにしたと思われる『仮装集団』の敵役のモデルで、大阪労音に対抗する音協の発起人、朝比奈隆の最大の後ろ楯となっていた住友銀行元頭取の鈴木剛が一九八六年に亡くなったことも、財界だけでなく大阪の文化にとって、決定的な損失だったのではないか。
その変化、重心の移転は、ホールのあり方にもあらわれている。
大阪の代表的ホールの特徴の一つは、朝日会館、その地位を受け継ぐフェスティバルホール、ザ・シンフォニーホールと、歴代が朝日新聞系の企業による民営だったことである。
民間活力という点でアメリカ的で、だからこそ「東洋のカーネギーホール」ということができたのだ。対して東京は日比谷公会堂、東京文化会館とも都営、NHKホールも半公営のようなもの。つまり、震災後の東京のコンサートホールはみな、いわば官営だったのだ。
震災前に演奏会場の役割も果たしていた帝国劇場だけは、渋沢栄一を中心とする東京の民間活力によるものだったが、震災後は大阪起源の松竹、最終的に東宝の手に落ちている(ついでにいうと、震災後につくられた丸の内の劇場街も、おもに東宝の手によるものだった)。
官営と民営。これで何が違うかというと、官営のホールは内装もサーヴィスもよくいえば質素、はっきりいってしょぼい。食い物もまずい。
だから、それらすべてがホテル並に豪華なサントリーホールの出現(一九八六年)は革命的で、これは民営だからこそ可能なものだった。そして、そのサントリーも関西の企業というのが、いかにも大阪の活力を吸収し従える、バブル以降のメガロポリス東京の象徴なのである。
もっとも、東京も「メガの時代」だった九〇年代がおそらくピークで、二十一世紀風のギガロポリスやテラポリスにはなりそうもない。
三月二十日(金)低音デュオ
低音デュオ演奏会を聴きに、杉並公会堂の小ホールへ。
松平敬(バリトン)と橋本晋哉(チューバ/セルパン)のデュオは一昨年も聴かせてもらい、楽しんだ。今年は川島素晴、近藤譲、湯浅譲二などの作品が取りあげられ、作曲家たちも列席で豪華。
趣向をこらしたさまざまな音が響くなかにも、低音の音楽にはユーモアと暗い翳、その明暗の対照が宿る。今年は前者が優っていたように感じたけれど、いずれにしてもほかでは聴けない響き。
三月二十一日(土)南の島に雪が降る
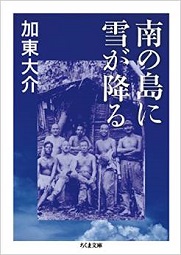
加東大介の『南の島に雪が降る』を読みかえそうと思ったが、室内のどこかの本の山で遭難して、見つからない。
ところが数日前に本屋に行くと、絶版になっていた二十年前のちくま文庫版が復活していたので、これ幸いと買ってきた(最近のちくまは獅子文六作品をいくつか復活させたり、趣味があう)。
ひさびさに読みなおしたが、やはりいい話。悲しい話。
簡単に言えば、戦争中のニューギニアでの飢餓生活のなか、加東大介を分隊長に編成された陸軍の演芸分隊が、マノクワリ歌舞伎座を舞台に慰問活動をし、兵士一万を慰めたという話。
昭和十八年十月、前進座の歌舞伎役者として活動していた三十二歳の加東大介は、十年ぶりに招集されて帝国陸軍の衛生伍長となり、ニューギニア島西部のマノクワリに進出する第二軍二万の将兵の一員となる。
この時期、すでに劣勢が明らかになりつつあったが、日本は東南アジアや南洋諸島など、海を隔てた地域を「絶対国防圏」として、死守を絶対目標とした。
西部ニューギニアのマノクワリもその一角をなしていたが、いざ進出してみたものの、大規模な戦闘は起きなかった。連合軍がかれらを置き捨てにして、フィリピンへの侵攻を「飛び石作戦」でどんどん進めてしまったからだ。
とはいえ平穏なわけではない。マノクワリのすぐ東にあるビアク島は一九四四年五月に米軍の猛襲を受け、一万の部隊が全滅。マノクワリも毎日のように空襲を受けており、米軍がこの先、上陸して来ないという保証はない。
なにより最大の問題は食糧。「絶対国防圏」も何も、制海権を失って補給がこないから自活するしかない。イモを栽培して食いつなぐが、栄養失調が原因で死ぬ兵士が続出する。
この生殺しのような状況下で、兵の心の荒廃を恐れた司令部が、慰問の演芸会を企画する。
といっても物資同様、本土から芸人を連れてこれるはずはないから、これも自給自足。というわけで、病院勤務の加東軍曹(昇進)に命令が下ると、とんとん拍子に話が進んで演芸専門の分隊を編成することが決定され、全部隊から要員が募集される。
スペイン舞踏家に長唄の三味線弾き、田舎芝居の役者、博多仁輪加の得意な僧侶(小林よしのりの祖父)、コロムビアレコード専属の歌手、針金細工のうまい浪曲師に、新宿の「ムーランルージュ」の脚本家、洋服屋にカツラ屋、画家。
みな招集された兵士だから、「地方」(一般社会のことを陸軍はこう呼ぶ)での本職はさまざま。軍事には無縁の才能が、思わぬ形で活躍の場を得る。ついには花道付きの専用の劇場「マノクワリ歌舞伎座」まで建設される。秘蔵の長谷川伸戯曲集を提供してくれる兵士もいて、限られた物資で工夫しつつ、本格的な芝居公演も開始される。
女っ気のまったくない地域(慰安婦を載せた輸送船が入港目前に撃沈されたため、ピー屋すなわち慰安所がマノクワリには存在しなかった)のため、俄か仕立ての女形役が、一種異様な人気と関心を集めてみたり。
クライマックスをなすのは、タイトルになった「南の島に雪が降る」場面。
『関の弥太っぺ』のなかで落下傘の白布で雪景色をつくったら、熱帯に飽きた客席の兵士たちが大喜びしてくれた。ところが、ある日だけは粛然として歓声がない。不思議に思って袖からのぞくと、みな静かに泣いていた。
客席にいたのが東北出身の部隊で、遠い故郷を想い、感情を抑えられなくなったのだった。
以前録画しておいた、映画版の『南の島に雪が降る』も見なおしてみる。
一九六一年の東京映画(東宝系列)製作で、監督は久松靜児。加東大介が本人を演じ、演芸分隊の隊員は有島一郎、西村晃、伴淳三郎、渥美清、桂小金治など強力。
森繁久彌、小林桂樹、三木のり平、フランキー堺といった「社長シリーズ」でおなじみの面々もカメオ出演。加東のためにみな時間を割いたとか。ほかに軍司令官役に志村喬、参謀役に三橋達也。
戦争の悲惨さを原作以上に強調した脚本はちょっとくどいが、これは、憲法改正と再軍備を最終目標とする岸信介政権を打ち倒した「六〇年安保」翌年の作品であることを思うと、時代の気分として仕方がないことかもしれない。
一方、歩兵の行軍のしかた、幕僚や兵士の階級に応じた軍装や挙措動作など、細部が異様にリアルに感じられるのは、この時代の東宝戦争映画に共通する、軍隊経験者だけがもつ迫力。
面白いのは、加東や森繁がマノクワリを旧仮名遣い風に「まのかり」と発音するのに対し、士官学校出の職業軍人役の三橋達也だけが「まのくわり」と読んでいること。撮影上のたんなる不統一かもしれないけれども、軍人描写の細かさからみると、意味を持った使いわけなのかもしれない。気になるところ。
ところで森繁は、二百キロ南方のイドレへ「転進」(退却を陸軍式に言いかえた言葉)する、そしてそこへは永遠にたどり着けないことを承知で出発する、歩兵中隊の指揮官役で出てくる。
これは原作にない映画の脚色だが、ある程度は史実を反映している。マノクワリでの二万人の自活は不可能と考えた司令部が、口減らしのために半分の部隊に徒歩移動を命じたのだった(実際は、この転進は演芸分隊の発足前の出来事で、敵から遠ざかるだけにより生存率が高いと考えられ、むしろ加東など、マノクワリ残留部隊の方が捨て駒にされた気分だったという)。
ところが、地図上の直線距離では三、四日でつくはずの行程は斧入らずのジャングルばかりで、実際には一、二か月を要した。一週間分しか食糧を携行しなかった兵士たちは飢餓と悪疫でバタバタと倒れ、文字通りの「死の行軍」。たどり着いたイドレにも食糧はなく、終戦まで生き残ったのはわずか三千人。あとは弾を撃つこともなく、ただ餓死と病死。
八紘一宇だ、大東亜共栄圏だ、絶対国防圏だと、威勢がいいだけの空虚なスローガンのもとに国民を太平洋の彼方にばらまいたあげく、他人の国を戦場にして荒廃させ、そして縁もゆかりもない天地に、百万の遺骨を野ざらしにする戦争。
ただこの映画、DVDはもちろん、VHSでもソフト化されたことがないらしい。このところ東宝の喜劇や戦争ものがシリーズでDVD化されているので、そこに入るのを期待していたが、前者はすでに完結。後者にも入るかどうか。
原作がこうしてときどき復活するなど愛読者も多く、映画も公開時に好印象をもった観客が多いのに、不思議な話。映画作品としての評価は人それぞれとしても、加東本人が自らを演じているのは何よりの強みなのだ。なにか権利関係の問題なのだろうか。いつか出てほしい。
原作に戻ると、戦後生還した加東大介は長谷川伸を訪ねて、南方でその作品を無断上演したことを詫びた。
すると長谷川伸、答えていわく、
「きみ、そんなことは問題じゃないよ。ぼくの芝居がそんなに役にたったのならけっこうだ」
「しかし、きみは、なんてしあわせな役者なんだろう。そんなにもよろこんでもらえる舞台を踏んだ役者は、めったにあるものじゃない」
「芸とはね、人をたのしませることだよ」
この言葉を受けて、加東は思う。
「いつまでも、人にたのしんでもらえる演技者でありたい。
それが、ニューギニアで死んでいった人たちへのわたしの義務ではないだろうか」
三月二十二日 南の島に『浅草の灯』
昨日触れた『南の島に雪が降る』を読みかえしたくなったのは、マノクワリ歌舞伎座で『浅草の灯』を上演する話がどんなものだったか、確かめたかったからである。
『浅草の灯』とは浅草オペラ全盛時代の大正十(一九二一)年前後の浅草を舞台にした小説。歌劇団の男性歌手と若いコーラス・ガール、オペラファン(ペラゴロと当時呼ばれた)の画家志望の青年の淡い三角関係を軸にして、華やかなりし頃の六区に暮らす人びとのさまざまな生活を活写したもので、何度も映画化されたこともあって、浅草オペラを題材にした小説ではもっとも知名度が高い。
作者は濱本浩(一八九一~一九五九)といい、現在はほぼ忘れられたが、昭和十二(一九三七)年に新聞小説として発表したこの『浅草の灯』で翌年の新潮社文芸賞を受賞、大衆文芸のジャンルで活動した作家だった。
この作品の大きな特徴は、大正十二年の関東大震災によって失われる直前の、つまり十二階こと凌雲閣がそびえていた頃の浅草の風物を、約十五年後に回想して書いていることである。
浅草興行街の繁華とその陰の頽廃は、当時の作家たちにとっても大きな魅力となっていて、川端康成が昭和四年に書きはじめた『浅草紅団』や、高見順の昭和十二年の『如何なる星の下に』、あるいは谷崎潤一郎の大正九年発表の『鮫人』などがよく知られている。
なかでも『鮫人』は浅草オペラを舞台にした点で『浅草の灯』に先行し、谷崎の濃密な描写力が見事で、未完なのがとても惜しい作品だが、いずれにしてもこれら三作は執筆と同時期の浅草の光と影を鮮やかにとらえた反面、『浅草の灯』のような、失われた時代への懐古趣味が惹起する吸引力をもってはいなかった。
そのノスタルジーとわかりやすいストーリーが「絵になる」と思われたからこそ、発表と同じ年にすぐ映画化されたのだろう。
島津保次郎監督の松竹映画で、歌手役は上原謙、コーラス・ガールは新人の高峰三枝子。歌劇団の座長夫人役は杉村春子で、カルメンを歌う場面がある。
これも『南の島に雪が降る』と同じく未DVD化だが、幸いVHSで発売されたことはあり、中古が安価で出ていたので手に入れた。

画面に独特の情緒があるのは、名監督の力か。座長部屋や大部屋などが狭くたてこんだ楽屋裏、裏の射的屋、公演中の客席の樣子など雰囲気があって、十五年前の現実もこんな感じだったかと想わせる。客席のペラゴロが喉を鳴らす独特の声援をするのが面白いが、これもきっと本当にあったことなのだろう。
セットではあるが十二階や興行街、それにひょうたん池の藤棚も登場する。
浅草寺と六区の間にあった、このひょうたん池とその橋の藤棚も、浅草全盛期の象徴である。
正式には大池といい、瓢箪池は東にある別の小さな池なのだが、大池をひょうたん池と呼ぶ人も多く、通称となっていた。ともに明治になって掘られた人造池で、その土で西側の田圃を埋めて造成されたのが、六区興行街だった。
噴水もあり、深くもなくさして美しくもなかったとはいうが、池水とその周囲に緑があったことが、浅草を公園と呼ぶにふさわしい場所にしていた。
しかし戦後、浅草寺は空襲で焼けた本堂の再建費用を捻出するため、池の土地を売却した。そして昭和二十七年から三十四年にかけて順次埋め立てられ、すべて映画館や遊興施設などに変った。
だが、施設が増えて繁盛したかといえばまったく逆で、その後の六区は衰退の一途をたどる。映画の観客減少が直接の原因とはいえ、ひょうたん池をなくしたことが、東京一の繁華街だった六区という場所の魅力を殺したとしか思えない。
話を『浅草の灯』の映画に戻すと、この作品は一九三七年の松竹版以外に、一九五六年の田中重雄監督の大映版、一九六四年の斎藤武市監督の日活版と、計三回も映画化されている。大映版は未見だが、日活版は最近DVD化されたので、見ることができた。

「踊子物語」という副題がつき、吉永小百合と二谷英明、浜田光夫などが出演するカラー版。杉村春子の役は山岡久乃が演じている。吉永が《ボッカチオ》の〈恋はやさし〉を歌っている。
上演場面は、浅草オペラの座長として名高いバリトン歌手の清水金太郎の夫人で、自身もカルメンなどで活躍した清水静子が監修しているが、やや立派すぎる感もないではない。
こちらにももちろん十二階やひょうたん池が出てくるし、カラーなのはありがたいけれども、映画としては全体に泥くさく、松竹版におよばない。
マノクワリ歌舞伎座の上演も、おそらくは島津監督の映画版をもとにしたのだろう。地方での本職は友禅意匠家という装置担当がつくった、藤棚からひょうたん池越しに劇場が並び、後方に十二階がそびえる夜景は、浅草っ子の加東や六区のオペラ館にいた隊員の舌を巻かせ、観客の全支隊を仰天させたという。
雪景色同様、ニューギニアのジャングルにまたたく、はるかなる六区の幻影。
映画版の『南の島に雪が降る』には残念ながらこのシーンはないが、宿舎兼稽古場での台詞合せの場面がある。
そこにあらわれた一般兵士役の小林桂樹が、「お、『浅草の灯』ですか。僕は映画では見たけど、舞台は知らないから嬉しいなあ」というような台詞をしゃべる。それほどによく知られていた名作、ということだろう。

おしまいに『浅草の灯』の原作小説。
手元にあるのは新潮社版の昭和十六年の第八刷。定価一円四十銭、外地定価一円五十四銭とあるのが戦前ならでは。
映画の直接的な視覚の力はないが、浅草の地理の具体的な描写、若者が色濃く染まっていた共産主義的な傾向(回想という形でなら、昭和十二年でもまだそれが書けたのだ)、そして物語の悪役となる、十二階下の私娼窟の酒場の説明などは、映画にはない。
十二階の周囲の下界には、表向きは新聞縦覧所や和洋銘酒屋と名うって、裏では売春をさせる淫売屋が、迷路のような横丁に密集していた。「十二階下」といえばその種の店のことである。
震災で十二階が倒壊したときに私娼窟も壊滅した。警察が再建を許さなかったため、まとまって川向こうに移転、永井荷風の『墨東綺譚』で名高い、玉ノ井の私娼街となる。十二階下もまた「失われた浅草」の風景なのだ。
ところでこの本、題名は『浅草の灯』といいながら、じつは一緒に収められた『人間曲馬団』の方が長い。
なにか乱歩風の猟奇的な作品みたいだがさにあらず、二人の若い女性を主人公に、彼女たちが東中野の駅前で共同経営するバーに出入りする男女のさまざまな人間模様を描いたもの。
これも『浅草の灯』と同じ昭和十二年の作品で、あわせて同年上期の直木賞候補になったものだが、こちらは執筆と同年代の東京を舞台にしている。
浅草にはけっして触れず、銀座に新宿に麻布、十年前に完成したばかりの人造湖村山貯水池とそのほとりの瀟洒な村山ホテルなど、徹底して「モダン都市」東京にこだわっていくのが、『浅草の灯』とは(おそらくかなり意図的に)対照的な構成。
銀座から山の手へと西方に伸びはじめた東京の重心の変化、そのままである。
全体に、ハッピーエンドのハリウッド映画を想わせるストーリーやキャラクターで、モボ・モガの時代からすでに、アメリカの影響力(一方では仮想敵国として、対立もあおられていたのだが)が大きかったことを実感させる。
バーがあるのが中野駅でも高円寺駅でもなく、東中野という設定が気になる。というのも、少し前に読んだ獅子文六の長編小説第一作『金色青春譜』でも、登場人物で東中野のアパートに住んでいるのがいたからだ。
昭和十年前後のモダン東京における、東中野という町の位置づけ。どのようなものなのだろう。
三月二十四日(火)小澤と魔法
東京文化会館で小澤征爾音楽塾。シュトゥッツマン指揮のベートーヴェンの交響曲第二番と、小澤征爾指揮のラヴェルの《子どもと魔法》。
後者は「オペラ・ドラマティコ形式」と名うっていたので演奏会形式的なものかと思ったら、かなりちゃんとした舞台上演。もちろん、二年前の松本のサイトウキネンのローラン・ペリー演出のようなものではなく、旅興行向きの効率重視の装置だが、雰囲気は出ていた。
小澤のこの作品というと、松本での上演で忘れがたいのが、ネコの場面が終って室内から屋外の庭へ出たところの、そのときの音楽。
今日も素晴らしかった。
乾いて埃っぽく動きのない、せまい室内の空気が瞬時に消え、草の湿った匂いが風でそよぐ夜の庭の空気が流れだし、ふわーっと舞台奥へとひろがっていく。
名手揃いのサイトウキネンではない、学生オケではどうなるんだろうと思っていたが、マジックは今日も一緒だった。
正直言って、ふだんは小澤の演奏からイマジネーションや幻想性を感じることはあまりないが(好き嫌いは別にして、小澤の魅力や個性はそれとは別のところにあると思っている)、どういうわけかこの部分は特別。小澤にとって、このオペラが何か特別なものなのではないかと思える理由が、ここ。
ところで、その直前に登場するネコ。室内の場面で登場するのは椅子や時計、壁紙といった無機物ばかりで、オスとメスの二匹のネコだけが例外なのだが、今回のニースの演出では、オスはぬいぐるみ。対してメスは本物の生きたネコで、彼女が無機物ばかりの室内から、動植物と虫、無数の小さな生命が生きる庭へ、主人公の少年を誘い出す。このオスとメスの使い分けは、なるほどと思った。
これで夜桜を見ることができたら最高のコンビネーションだったが、休憩時に覗きにいった上野公園の桜並木は、まだまだ全然だった。
来週、東京・春・音楽祭のメルニコフを聴きにくるあたりが、ちょうど満開になりそうだ。
三月二十九日(火)袈裟と盛遠
新国立劇場中劇場で、日本オペラ協会による石井歡のオペラ『袈裟と盛遠』。
『新・平家物語』で親しんだのと同じ物語によるオペラ。
三月三十一日(火)メルニコフ第一
幡随院跡に建つ上野学園石橋メモリアルホール(お寺の跡がメモリアル、うまくできている)で、メルニコフのひくドビュッシーの前奏曲全曲。
二十九日にショスタコーヴィチの二十四の前奏曲とフーガ(休憩二回を入れて三時間かかるはず)をひき、一日おいてドビュッシーをひき、翌日にショパンの前奏曲全曲とスクリャービンのソナタをひくという、超人的なプログラムをこなしている。
自分は三年前にショスタコーヴィチを浜離宮朝日ホールで聴いていて、素晴らしいのはわかっているのだが、体力的な不安から今回は行かず。
前回は、バッハ風の形式とそれを突き破ろうとするエネルギーとの葛藤が、正味二時間半の全曲のなかでしだいに巨大な「歪み」となるさまが凄かった。
今日のドビュッシーは、時間的には二時間かからないが、難曲であることはいうまでもない。しかしメルニコフは軽々とひいていく。余力も充分のようで、アンコール三曲つき。
全曲を続けて聴くと、第一集の濃厚なロマンティシズムに対して、第二集が皮肉で刹那的でパロディックで、いかにも二十世紀作品らしい晦渋さを増していることがよくわかる。第一次世界大戦の前の作曲なのに、英国国歌やラ・マルセイエーズが聞こえるのは、不吉な預言のようでもあり。
今日の特色は一九一〇年製のプレイエル、つまり作曲当時のピアノを用いていたこと。メカニック的にはかなり現代に近いようだが、響きはモダンのように重く威圧的なものではなく、その軽快さが心地よし。スタインウェイが全金属の単葉戦闘爆撃機とすれば、こちらは布張木製の複葉戦闘機のような。つまりサンダーボルトでなくてスパッドみたいな。
四月一日(水)メルニコフ第二
昨日に続き、メルニコフの前奏曲シリーズ。東京文化会館の小ホールで、前半がショパンの二十四の前奏曲、後半が前奏曲を含むスクリャービン。
昨日とは変って、モダンピアノの高い剛性を活かした演奏と感じたが、本人がどう思っているかはわからない。このあと倉敷に行き、現地にある百年前のピアノでスクリャービンをひくのだとか。それも聴いてみたかった。
四月四日(土)四十六年目の花見
小学校時代の有志で花見。
自分にとっては特別の桜。今から四十六年前の今頃、わが小学校に入学した生徒は全員、桜の苗木をもらった。同じ世田谷区では区立も配ったというから、東京五輪以来の桜植樹運動が広く続いていたのかもしれない。
去年の秋にクラスの男子会をやったとき、ひとりが「奥沢の実家にはまだ桜が残っている」という話をした。
自分もふくめ、桜を現存させている人は他にいなかったから貴重で、ぜひ見にいこうという話になり、今日がその日。
現物を見て驚いた。子供の背丈くらいだった苗木は、二股にわかれて、呆然とするほどに大きく高く。根もごつく張りだして、隣家との塀は持ち上げられて壊れてしまい、柵につけかえたとか。

自分のもらった苗木は、枝を近所の子に折られてすぐに枯れてしまったので、こんなに大きくなるものとは想像もしなかった。我々が住んでいた、昭和四十年代に世田谷、目黒、大田あたりでサラリーマンに買えた家の庭は、ほとんどが申し訳程度の広さだった。育ったけれど始末に負えなくなり、家を改築するときなどに伐ってしまった、という友人が何人かいたのは当然だろう。
この樹を維持してくれた親御さんに感謝。ソメイヨシノは寿命が六十年くらいというから、いま見にきてよかったのかも。
四月七日(火)クールマン登場
東京文化会館で、東京・春・音楽祭の《ワルキューレ》。
このところそのCDにはまっている、エリーザベト・クールマンのフリッカを聴くことができたが、期待に違わぬ素晴らしい歌唱。ひとり飛びぬけた歌を聴かせてくれたし、それによって「いま自分がワーグナーに聴きたいものは何か」を再確認することもできた。
といってもそれは結局、三十年前にメルヒオールの歌うジークフリートのライヴ全曲盤を聴いて、ワーグナーというかオペラそのものの魅力に自分なりに気づいたときから、変っていない。
ようは歌唱の弾力。ワーグナー作品の歌唱パートは、言葉をさばいて音を弾ませ、フレーズを伸縮させることではじめて、その魅力の全貌を私に(あくまで私に)明らかにしてくれる。
しかし、あの大オーケストラ、それも伴奏的に歌唱パートを補助する旋律をほとんど鳴らさない、あの不親切な管弦楽の上を八艘飛びのように飛びこえて、自由自在にそんなことができる歌手は、百年の録音史のなかでも、ほんの一握りしかいない。メルヒオールとか、ロッテ・レーマンとか、ヴァルナイとか、ホッターとかグラインドルとか。
クールマンはそれに近いことをやってくれた。そしてそれは残酷なことに、他の歌手には何ができていないか(より正確には、私が聴きたいものの何を聴かせてくれていないか)を、如実に明らかにすることにもなった。みな東京文化会館を狭く感じさせるくらいの充分な声量をもった人たちで、それだけでも素晴らしいことなのだが、ワーグナー歌唱には、さらにその先に奥義があるのだ。
まず、第一幕に出てきた三人は、旋律を弾ませ、回すことが充分にできない。こうなるとオーケストラも同じようにしか動けないし、音量もセーブしなければならないから、正直この幕はピンとこなかった。
それが第二幕に入ると変った。まずヴォータン役のシリンス。この人の重大な弱点は響きの色にまったく変化がなく強いだけで単調なことで、幕の最後にフンディングに憤怒をぶつけて「行け!」の一言で殺してしまうあたりの無念さとかは、さっぱり出せない。しかしそれはそれとして、この人は言葉をサッサッとさばいて、俊敏に響かすことはできる。
その典型が、ヴォータンの最初の歌詞「Nun zäume dein Ross, reisige Maid! Bald entbrennt brünstiger Streit」のところ。この部分だけで、言葉をさばいて弾ませられるかどうか、なおかつ響かすことができるかどうかは明らかになるが、シリンスはそれができていた。
そしてそのあとに出てくるブリュンヒルデ役のフォスターも、力まかせに歌う人かと思ったらそうではなくて、意外なくらいに叫ばない。逆に、メッツァヴォーチェを揺らさずに、安定してすーっとホールに通す能力をもった人だった。伸縮も色の変化も乏しいけれど、これができることで、あとはオーケストラがニュアンスをおぎなえる。
こうなると、ヤノフスキが速めのもたれない進行のなかで、各パートの強弱の浮沈によって全体を織りなすことで、表情を過不足なく表現しているのがより明らかになって、その美質がきわだってくる。もったいぶった大仰なワーグナーより、私はこの硬骨の方がはるかに好き。
そして二人に続いて出てきたクールマンは、さばきと弾力と伸縮と変化のお手本みたいな、俊敏な歌唱。まさに「ああいえばこういう」、立て板に水の口調と論理でヴォータンをやりこめる。怒れば怒るほど頭がさえて高速回転する、女性にままある恐ろしいタイプ(笑)。
こんな《ローエングリン》の魔女オルトルートみたいなフリッカは初めて聴いた。なるほど、オルトルートが信仰する異教の「古きゲルマンの神々」とは、フリッカのことであったのかと納得。クールマンのオルトルートも聴いてみたいものだ。
さてここで重要なのは、クールマンの歌の響きの立ち上がりがじつに鋭敏なこと。ヤノフスキのつくる音楽ではオーケストラにも新即物主義的な反応の鋭さが求められるのだが、歌唱においてもそれは重要。
その重要さに気づかせてくれたのは、皮肉にもそれができない歌手たち。すなわち、第三幕の八人のワルキューレ。日本人らしい含み声(いわゆるオペラ歌手らしい発声)で、響きがぜんぶ遅れる。遅れまいとすれば金切り声で叫ぶしかないので、なんとも美しくない響きに。
できていないことによって教えてくれた、気づかせてくれたという意味では、第三幕のヴォータンの告別(字幕でいうところの「達者で暮らせ」…)の一番最後、「Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer nie!」。
「わが槍先を恐れる者は、この炎を越えるな!」に応える、金管のファンファーレ。全体に今回は、金管も最後まで本当によく奮闘したが、ここは表情と抑揚がまったく消えてしまっていた。普通は、同じ音型のヴォータンの歌をなぞって歌唱的に響かせるのに、オペラ経験の少なさなのか疲労か、ただ音符をそのまま鳴らすだけになった。
これを聴いたら、そうか、このファンファーレはヴォータンが槍を掲げると同時に、炎となったローゲがまさに火の壁となって高く立ちふさがり、ヴォータンの言葉が成就していることを示す場面であって、歌うヴォータンに金管のローゲが応えている。だから「同じように歌われなければならない」のだと、その大切さにあらためて気がつくことができた。
もう一つ、フリッカの場面が示したこの作品の重要な鍵。
「doch Siegmund verfiel mir als Knecht!」、「ジークムントなんてただの奴隷じゃないの!」という、強烈な差別。ここのクールマンの叫びも見事だったが、そう、有限の人間なんて無限の神に較べれば、すぐ壊れるただのおもちゃ。神族の眼差しや一言で、その生命は終る。
《ワルキューレ》の面白さの一つは、人間と神族、「はかなき者」と「はてなき者」が交錯する、その落差にある。この落差は、《指環》のほかの三作にはない(ジークフリートは半神的な英雄だから、人間というには例外的)。
第二幕の、ブリュンヒルデの死の告知の場は、まさに神と人の出会い。ここはブリュンヒルデ役のフォスターの背の高さと大きさが、「はてなき者」の力と威厳と恐ろしさの肉体化のようで、とても効果的だった。後方の映像が余計な動きをしなかった点でも、第二幕はドラマにいちばん没入できた。
四月十一日(土)十周年
このサイトも本日で開設十周年。皆様のご愛顧のたまもの。
可変日記も十年分がたまった。サイトをつくってよかったと思うのは、自分がある行動をしたのはいつだったか、この十年に限ってすぐ検索できること。
日記を書く習慣のなかったそれ以前は不正確で、まさに有史以前。伝説と歴史の違いがよくわかった気がする。
夜は東京文化会館の小ホールで、クールマンのリサイタル。やはりお見事。とりわけ前半、ワーグナーの音楽の波動を完全にものにしているのが素晴らしい。グルックのアリアも切々と。死と愛と死みたいなプロ。最後のシューベルトは、歌いこめばもっと陰惨さが出そう。
四月十六日(木)クールマンの決意
エリーザベト・クールマンがコンサート、リサイタル、演奏会形式のオペラだけに専念することをきめ、オペラの舞台公演からの引退を自身のサイトで発表した(記事はこちら)。関心が高まっていたところでのニュースに驚く。
徹底していて、発表と同時にすべて降板。ただし言葉通り、フリッカ(ラトル&バイエルン放響の《ラインの黄金》)やクイックリー夫人(ノット&バンベルク響の《ファルスタッフ》)など、演奏会形式の公演は予定通り出演。
ということは音楽面ではなく、他人に演技を強制される、演出に縛られるのがいやになったということか。先日のリサイタルはもちろん、アマルコルド・ウィーンとの共演とか「ムソルグスキー・ディス‐カヴァード」などのCDでの自由な構成を聴くと、彼女がライヴのステージに望むものが、想像できなくもない。
仰々しく「舞台引退公演」をしないということは、機が熟せば戻る可能性もありそう。
日本では、これでむしろ聴ける頻度が高まるかも、と個人的には期待。
四月二十四日(金)大原總一郎が聴いたもの
『大原總一郎随想全集3 ──音楽・美術』(福武書店)
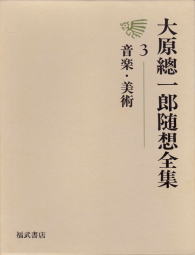
近年は、ネットの検索で古本も広範囲に、容易に入手できるようになった。しかし今世紀が始まったころは、ネット上では種類も流通量も限られていて、古いものなどはとても探しにくかった。
これもその一つで、むかし探して見つからず、そのまま忘れていたもの。先日ふと思い出して検索したら、アマゾンに数百円で出ていたので、この金額なら無駄になってもいいやと購入。
いま読んでいるが、いやいや私などには大当たりのコンコンチキ。ご存じない方のために書くと、大原總一郎(大原総一郎、一九〇九~六八)というのは倉敷紡績(現クラレ)の三代目。倉敷に大原美術館をつくった大原孫三郎の継嗣で、本人は音楽が大好きで、パトロン活動をしたことでも知られている。
一九三〇年代後半にヨーロッパに遊学しているので、きっといろいろ聴いているに違いない、その思い出を書いているかもしれないと期待して買ったが、期待以上どころか、大戦直前のヨーロッパ全域の一流音楽家、団体をこんなにたくさん聴いた日本人は他にいないのではないかというほどのものだった。
「音楽・美術」とあるけれども、本文三百頁ほどのうち二百三十頁、すなわちほとんどが音楽の話。
まず「私のレコード遍歴」には、帝大生時代の一九三〇年前後に日本青年館で近衞秀麿指揮の新響を聴いた話が出てくる。日比谷公会堂に行く前の新交響楽団(NHK交響楽団)は、青山の日本青年館が本拠だった。「その頃の新響では、ティンパニーの音だけが独り高らかに鳴り響いていた」(笑)。
そして山場はなんといっても、一九三六年から三八年まで三年間の音楽体験を記した「欧州楽壇の思い出」。一九五一年から翌年にかけて、「DEMOS」という朝日新聞系の雑誌に書いたもの。感想の長さはそれぞれに違うが、主なものを列挙してみる。
一九三六・六 モントゥー指揮パリ音楽院管、ルービンシュタインのベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番と《展覧会の絵》 ほかにパリでは年月不明で、ヴォルフ指揮パドルー管、ティボー独奏のスペイン交響曲と詩曲、ハバネラも。
一九三六・六・十二 ワルター指揮ウィーン・フィル。
一九三六・六 ウィーン国立歌劇場にてサバタ指揮《オテロ》、フルトヴェングラー指揮《タンホイザー》、ワルター指揮《トリスタン》、ワインガルトナー指揮《ワルキューレ》、クリップス指揮の《ばらの騎士》ほか。すごいのは、有名な《トリスタン》の臭気爆弾事件の現場に居合わせたこと。大原によると薬剤は二硫化炭素だったそうで「人絹製造に必要な薬品なのですぐなんであるかがわかった」。
一九三六・七 バイロイト音楽祭で、フルトヴェングラー指揮《指環》《パルジファル》《ローエングリン》
一九三六・八 ザルツブルク音楽祭でトスカニーニ指揮《マイスタージンガー》とワルター指揮のマーラーの四番。
一九三六・十一 ロンドンでシュトラウス指揮ドレスデン国立歌劇場の《アリアドネ》《ドン・キホーテ》《ティル》。
一九三六 ブレッヒ指揮ベルリン国立歌劇場《アイーダ》。
一九三七 クレメンス・クラウス指揮バイエルン国立歌劇場《ばらの騎士》。
一九三七・五 ロンドンでフルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルの《合唱》
一九三七・六 ボールト指揮BBC響、カザルスのエルガーのチェロ協奏曲。
一九三七・六 トスカニーニ指揮BBC響の《田園》。
一九三七 グラインドボーン音楽祭で、ブッシュ指揮《ドン・ジョヴァンニ》。
一九三七・十一 フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィルの《悲愴》。
一九三七・十 メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウ、独奏クライスラー。
一九三七・十 ロンドンで、フーベルマンとセルのヴァイオリン・リサイタル。
一九三八頃 ローマ歌劇場にて、セラフィン指揮ジーリ主演の《アイーダ》、ローレンツ主演の《ジークフリート》。
一九三八・一 フルトヴェングラー指揮ベルリン・フィル、バックハウスの《皇帝》。
一九三八頃 シューリヒト指揮ベルリン・フィル。
一九三八・四 メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウ、独奏メニューイン。
一九三八・五 メンゲルベルク指揮コンセルトヘボウの《千人の交響曲》。
一九三八・七 パリ郊外にてランドフスカのひくバッハ。
一九三八・九 ミュンヘン会談直前、風前の灯のプラハで、ターリヒ指揮チェコ・フィルの《わが祖国》。
ここには、ライヴ録音が残っている演奏もいくつかある。いつか、一九三〇年代後半の風雲急を告げる世界情勢のなかでの各国のライヴ音源をまとめた演奏史譚をやってみたいと思っているが、大原はその話の狂言回しにぴったり。当日のプログラムを参考にしているようで、あやふやな記憶に頼らず、記録的にもかなりしっかりしている。
このほか、一九六二年のクレンペラー指揮フィルハーモニアの幻想交響曲、一九六五年のザルツブルク音楽祭(アバドの《復活》)、一九五三年来日のギーゼキングとスターン、一九五七年来日のカラヤン&ベルリン・フィル、一九五九年来日のカラヤン&ウィーン・フィル、一九六〇年来日のウィーン・コンツェルトハウス四重奏団などの印象記も。
全体から見えるのは、大原がマーラーを早くからとても好きだったこと。一九六〇年の日本マーラー協会発足を大原が援助した理由の一端が納得できた。
一方でやはりブルックナーは苦手なようで、リストのなかにあるフルトヴェングラーとバックハウスの《皇帝》の日には八番をやったはずなのに言及なし。一九五九年のカラヤン&ウィーン・フィルの八番日本初演にも立ち会って、一応ほめてはいるが行間には苦しさがにじむ。
このあたりの機微を意識して、一九六〇年にコンツェルトハウス四重奏団を接待したときの思い出に、メンバーに「今年はマーラーの百年祭だがと話すと、大抵、顔をしかめる。そのかわり、ブルックナーの大の信者である。日本でマーラー協会を作るくらいなら、なぜブルックナー協会を作らないのかという」とあるのを読むと、その部屋の微妙な空気がよみがえるようで、当時の日本人とオーストリア人の嗜好の差がよくわかって面白い。とにかく貴重な記録。
四月二十六日(日)ジンマン降板
N響に五月客演予定のジンマン降板。代役にデ・ワールト。サイトには以下の発表が。
「二〇一五年五月定期公演B・Cプログラムに出演を予定しておりました指揮者のデーヴィッド・ジンマン氏は、ニューヨークで股関節置換の緊急手術を受けるため、来日が不可能となりました」
今月のN響のプログラム「フィルハーモニー」にジンマンについて書いていたのだが、間の抜けたものになってしまった。白ページにさしかえとか、黒塗りされるとかでないといいが(笑)。
今回の二つのプロ、ジンマンは師のモントゥーへの追慕の念からすべて選曲したのではないか? という視点から書いたもので、私自身、とりわけブラームスの二番(モントゥーはブラームスを深く敬愛したのに、交響曲ではなぜかこの曲しか商業録音しなかった。しかし、三度も録音している)を聴くのを楽しみにしていたので、とても残念。
五月一日(金)新盤の意味
タワーレコードの、没後五十年のクナッパーツブッシュの再発シリーズ。
あるところに書く予定が相手の事情でボツとなり残念なのだが、そこでどうしても書きたかったのが、一九六二年のフィリップス原盤の《パルジファル》。

それは、オリジナルのアナログ・マスターから一九二KHz、二四bitのハイビット・ハイサンプリングの新規マスターというのも魅力なのだが、ある意味で私がそれ以上に評価したかったのが、面の分けかた。
第一幕を二枚にわけ、二、三幕はそれぞれ一枚で四枚組。と書くと当然の分割法に思えるだろうが、これまでのCDはそうではなかったのである。LPの分割を踏襲したのか、一枚目から時間一杯に詰めこんでいったため、どの幕も一枚に収まらずに、二枚にまたがるようになっていた。とくに第三幕の〈聖金曜日の音楽〉の途中で面が変わるのが何とも残念だったのだが、今回は一枚で聴ける。
これは、オペラのディスクではけっこう重要なことだと思う。以前よりCD収録時間が伸び、そして原盤が八十分超の長時間収録に鷹揚なユニバーサル系列というおかげで、今回の再発ではこの六二年盤だけでなく、より演奏の遅い一九五一年盤でも、同じ切りかたをしている。この一点だけでも、この二つの《パルジファル》は買い直す価値あり。
五月三日(日)朝からソムリエ
例年同様、ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンでクラシック・ソムリエ。初日の朝九時からという今までにない時間割だったので、時間中に次第に人が増えてくる樣子がわかって面白い。
五月八日(金)ペヌティエのフォーレ
トッパンホールにて、ペヌティエのひくフォーレのノクターン全曲。やわらかな叙情。
五月九日(土)大英帝国のプライド
イギリスのディスク店クロチェットが閉店することを、吉田光司棟梁に教えてもらう。サイトのほうは、昨夜まではいつものままで注文可能だったが、今朝見たら閉店看板に。
引退する店主はこの商売に五十年以上かかわり、そして二十年近くこの店を経営してきたという。
自分の知るかぎり、イギリスのCD店は個人店でも海外対応がしっかりしている場合が多かった(中古店ではなく、新品を扱う店の場合)。七つの海を支配した「日の沈まぬ帝国」以来の、よき伝統なのだと思う。アメリカの通販は自国の広さに対応するべく発展したものだが、イギリスのそれは、海の外をつねに意識してきた。
それは、他国よりも国外向け送料がおおむね安いことに端的にあらわれているし(各国のアマゾンでもイギリスがいちばん安いことが多い)、発送時やアフターサーヴィスの配慮も細やかで、しっかりしているところが多かった。
むかし、ドイツか日本か、イギリスから雑誌を前払いで取り寄せていた人の国がイギリスと戦争になってしまった。当然郵送は途絶えたが、やがて戦争が終ると、何事もなかったように再び雑誌が送られはじめたという話を読んだことがある。たしかにそれが誇張に思えない、律儀さがかれらにはあった。
製造~卸売~小売と、大英帝国の各業者が消費社会の発達と国際化のなかで確立した、商道徳の末端を担っているというプライドがそこに感じられた。
クロチェットの閉店の挨拶にも、こうしたよき伝統に対する誇りが感じられ、なんとも素敵だし、惜しい。
海外発送は、いうまでもなくコストも手間もかかる。そのため、複数枚のオーダーは全部そろってからまとめて送ってくる店舗が多く、発売遅れが出た場合などはすべて遅れてしまうこともある。
しかしクロチェットは一枚でも入荷次第発送してくれて、その不安のない店だった。だから、自分のように仕事でディスクを扱う者には大助かりだった。
自分にとっては一昨日、五月七日に発送したと連絡のあったオーダーが、予期せぬ最後の購入となる。
ブラックショウのウィグモア・ホールのモーツァルト・リサイタルの第三集、ゼッダの《どろぼうかささぎ》、クレオバリーのひくオルガン曲集の三つ。
十日以内に届くだろうから、心して開封することにしよう。
ジュディとイアン、長いことありがとう。どうぞお元気で。
五月十三日(水)プレガルディエン
新国立劇場の《椿姫》と、トッパンホールでのクリストフ・プレガルディエンのテノール・リサイタルをハシゴ。
テノールでは珍しいマーラーをナマで聴けたのも嬉しかったが、キルマイヤーの《ヘルダーリンの詩による歌曲集》も切実な美しさに満ちて素晴らしかった。
五月十四日(木)最後の荷物、音楽監督の仕事

クロチェットよりの最後の荷物、ついに到着。心なしか、いつもよりさらに梱包がていねいな気もする。
いざ、さらば。
夜はスダーン指揮の東京交響楽団をサントリーホールで。
後半のフランクの交響曲も躍動感のある、好きなタイプの演奏だったけれど、ちょっと雑然とするところがあった。それよりも前半のモーツァルトのパリ交響曲と、フルートとハープのための協奏曲がじつに素敵で、そして色々と考えさせくれる演奏だった。
何より印象的だったのは、小編成の東響の楽員たちが自信を持って、迷いなく自分たちのモーツァルトを奏でたこと。
いま在京のオーケストラはロマン派以降の複雑な大管弦楽作品をやることが多く、それは近代の交響楽団の成り立ちというものを考えればしごく当然のことなのだが、そのぶん、古典派やそれ以前の音楽をきちんとやる機会は多くない。
東響は本拠地ミューザ川崎で「モーツァルト・マチネ」を二〇一〇年から年四回やっていて、すでに二十回を数える。この経験がサントリーホールという、本来は古典派向きでないホールでもしっかりとモーツァルトのサウンドを響かす、今日の成果につながっていると思う。
この「モーツァルト・マチネ」は、スダーンが音楽監督時代に発案したもの。そしてこれまで同様、モダン楽器によるピリオド・スタイル。考えてみると、在京のオーケストラの常任クラスでは、スダーンというのは初めての「歴史主義的指揮者」だったのではないか。
「歴史主義」というのは、作曲年代の楽器の特性を意識しながら反映させるもの。前期ロマン派であれ後期ロマン派であれ二十世紀音楽であれ、それぞれにあった響きと演奏を考えていくもの(といっても、どこまで反映させるかはその人次第)。
スダーンは十年の任期で、モーツァルト演奏の流儀をしっかりと東響に残していった。その深い信頼、楽員の自然な反応のよさはいまも消えていない。
こういうふうに、自分がかくあるべしと思う音楽を、サウンドをオーケストラに残して、その財産としてやる、これが「音楽監督」という存在なのだろう。
「首席指揮者」では、ここまではできない。現音楽監督のノットが次に何を残していくのかも楽しみだし、他の在京オケにも、もっと音楽監督がふえてほしいと、あらためて実感する。
五月十五日(金)アバドの遺産とアンスネス
いままで、オーケストラ・コンサートにベートーヴェンのピアノ協奏曲が何番であれ入っていると、大概はとても退屈な時間であることが多かった。録音では好んで聴いているのに、ナマはなぜか予定調和の雰囲気が強く、飽きるのだ。
今日はわざわざ、それだけが三曲も並ぶ演奏会に行き、そしてあまりの素晴らしさに、腰が抜けるほど驚いた。
アンスネスが独奏と指揮を兼ねてマーラー・チェンバー・オーケストラと共演した「ベートーヴェン・ジャーニー」の初日。オペラシティでベートーヴェンのピアノ協奏曲第二、三、四番。
特に前半二曲目の第三番。古典派の趣を残していた第二番からベートーヴェンがどれほど進化・深化したか、どれほど革命的な音楽をつくってみせたか、横っ面を張り飛ばして教えてくれるような、物凄い演奏。管楽器の増強とティンパニの追加で、どれほど多様なハーモニーの深さとサウンドの変化が生れるか。
五曲のなかでこの曲だけが短調であることを、こんなに意味深く感じたことはなかった。ナチュラル・トランペットと小型ティンパニをまじえたピリオド・スタイルだからこその、響きがダンゴにならず、生き物のように敏捷に動くオーケストラの響き。
そして、抽象美の極致のようなアンスネスのピアノ。オケに頭を突っ込んだ形で、蓋を外して響かせたピアノとオーケストラとのバランスも、まさに完璧。
終った瞬間、客と一緒に楽員がアンスネスに拍手したのも感激的だった。これはなんというか、例のウィーン・フィルの楽員がフルトヴェングラーの指揮で演奏しながらつぶやいたという「このうえさらにお金までもらえるなんて…」の境地に近かったのではないだろうか。
こういう音楽の場に立ち会えるのは、ほんとうに幸福なこと。
後半の第四番は第三番ほどの衝撃はなかったけれど、それはベートーヴェン自身が求めたコントラストであって、誤差を恐れずにいえば運命と田園みたいな関係にあることを、やはり目に見せるようにして教えてくれた。アンコールのバガテルも柔らかい響きがまあ美しい。
少し前に出たCDがよかったので楽しみにはしていたが、これほどとは思いもよらず。今年自分が行ったなかでは、たぶんベスト・コンサート。続く第1番と《皇帝》の日も聴いてみたくなったが、これは断念。
アンスネスは二〇一〇年の三月に同じオペラシティで、ノルウェー室内管とのモーツァルトの協奏曲も聴いているが、もっと、よくも悪くも平凡に美しく幸福な音楽であって、こんなビリビリ電撃が走るようなすごい音楽ではなかった。明日も生きて音楽を聴きつづけたくなる、高貴なる野性の音楽。
それは、オーケストラの各楽員の高い自発性が生んだ、丁々発止の応酬と対話による一体感の面白さだった。こうやらないとベートーヴェンのピアノ協奏曲は面白くならない。
あらためて、ベートーヴェンのピアノ協奏曲は、アメリカで大完成された交響楽団の演奏会システムとは決定的にずれたものなのだろうと思う。それは、チャイコフスキーやラフマニノフのピアノ協奏曲にはぴったりだが、ベートーヴェンには向いていない。
ところが、第三番以降はひきぶりをするには難しくて、規模の大きな協奏曲のようにも見える。このことが誤解を招いて、演奏をハリボテじみたものにしてしまう。チャイコフスキーやラフマニノフのような、モダンのオーケストラとコンサート・グランドが巨砲を撃ちあうような作品ではないのに、そんなふうにやるから間が抜けてしまう。
今日のように、世界中をまわって共演を重ねてきて、完璧な信頼関係ができている小アンサンブルのひきぶりでこそ、その真実の姿が初めて見えた気がする。
とりわけ、第三番の序奏での楽員たちのソロが本当にすごかった。あの一瞬に会場の空気が変った。
八〇年代以降のアバドがいみじくも見抜いた、大交響楽団の限界とオーケストラ運動の変化。その精華が今日のマーラー・チェンバー・オーケストラにあったと思う。
五月十七日(日)不発
サントリーホールで、ベルトラン・ド・ビリー指揮の東京都交響楽団。
ド・ビリーは小粒ながら好きな指揮者なので、都響とのこの共演も楽しみにしていたのだが、残念ながら、息が合わないままだったよう。
一曲目のベートーヴェンの《エグモント》序曲は軽快な進行で期待させたが、モーツァルのフルート協奏曲第一番とシューベルトの交響曲第四番《悲劇的》は音が上滑りしたように響かない。三日前に東響が、同じような小編成で聴かせた活力に満ちた音楽が耳に残っているだけに、さびしかった。
これならオペラシティのアンスネスを聴きに行けばよかったと思ったが、まさしく後の祭り。
五月二十一日(木)エヴォカシオン
王子ホールでサンドリーヌ・ピオーの歌曲リサイタル。翌日に某誌でインタビューする準備をかねてのものだが、愛聴盤である「エヴォカシオン」とほぼ同一の曲目をナマで聴けたのは嬉しかった。
五月二十二日(金)獅子文六の復活
ピオーさんのインタビューを終えたあと、新国立劇場の中劇場で二期会の《ジューリオ・チェーザレ》のゲネプロを後半だけ見学。
帰り道に本屋に寄ると、『七時間半』がちくま文庫で出ていたのでびっくり。獅子文六復活の静かなブーム、ここまで来たか。

『七時間半』とは、一九六〇年執筆当時に東京大阪を結んだ特急「つばめ」の所要時間のこと。すなわち、東京から大阪に向かう特急(作品内では「ちどり」と変えてある)のなかで、七時間半の間に展開する物語。食堂車のコックとウェイトレスの恋物語が主なテーマだが、品川操車場に始まる運行の描写も細かく、昔に興味のある鉄ちゃんは必読の作品。単行本で読んだときの感想は、二〇一一年六月十三日の可変日記に書いている。
舞台は、いまはまずお目にかからない食堂車。しかし自分も子供の頃には、親の実家のある仙台に行くのに当時の特急で五、六時間かかったから、食堂車に一度は行くことになった。そんなに美味しくはなかったけれど、狭苦しくて退屈な客席から解放されて、テーブル席につくあのワクワク感は忘れがたい。
東京駅のレストラン街に、日本食堂の食堂車風の内装の店があるが、あれに惹かれるのは、年代的にはどのあたりなのだろう。数年前に店内を覗いたとき、中高年の白人のグループがものすごく嬉しそうな顔をして席に着いていたのが忘れられないが、あの人たちも食堂車に思い入れがあったのだろうか。
それにしても、獅子文六の名を本屋で見るのは嬉しい。私が個人全集なるものを唯一保有している人だからだ。
他愛ない大衆文芸だけれどストーリーはうまいし、長編デビューの昭和九年から亡くなる四十四年までの、昭和日本の大衆社会の変遷を描くものとして読んでも、じつに面白い。
生前は新聞小説では最高級の人気作家で、作品は次々と映画やテレビドラマになった。『南の島に雪が降る』を紹介した加東大介の代表作も、獅子原作の宇和島出身の株屋を主人公にした『大番』シリーズである。
獅子の小説の最大の読者層は、勤め人(サラリーマン)家庭の、いわゆる中流の人びとだった。これはデビューから死まで、終始一貫している。
この中流層は、昭和初期には東京の山の手などにいるだけの新興階級で、まだそれほど多いものではなかった。ところが日本が豊かになるにつれ、国民の消費生活のスタイル全体が中流的になる。
戦後民主主義は一面では総中流化的社会主義ともいえたから、高度成長期にはついに、誰もが自分は中流だと思う一億総中流幻想が生れる。戦争の前後の昭和で読者層が自然に増え、国民全体に広まるという幸運に、かれは恵まれた。
かれの作品を読んでいると、その過程の中流意識の広がっていくさまを、さまざまな断面で、その時々の流行を巧妙にとりいれながら、教えてくれる。
消費の流行をかぎつけて増幅するその能力は、まさに天才的。それは特急やテレビ、インスタントコーヒー、シューマイやバナナといった消費生活の表層にあるモノの流行だけにとどまらない。
終戦直後の「民主主義的自由」を消費者の視点でとらえた『自由学校』や、焼跡から遠く離れたユートピアを描く『てんやわんや』、高度成長のエコノミック・アニマルの原型のような主人公が登場する『大番』など、社会精神における流行までを、獅子は描いている。
そこには、多くの若者に海軍士官を志願させた傑作『海軍』という、戦時中の作品も含まれる。いってしまえば、軍国主義もまた大衆が消費する「流行」だったということが、そこから見えてくる。
ほんとうに、すごい人なのだ。
戦争は戦前と戦後を断絶させるものであったが、こと大衆消費社会の発展という観点から見れば、すべては一つながりの潮の流れなのだ。獅子の作品は、その重要な証拠なのである。
ただ、獅子の小説は源氏鶏太などと同様に時代と世相に密着しすぎたか、死後十年ほどすると急速に人気が下がり、近年は一部の作品を除いて、ほぼ忘れられた作家になっていた。ところが二年ほど前から俄然、ちくま文庫が復活に力を入れはじめた。
きっかけは、中身は面白くて自分も大好きなのに題名がイマイチで、マイナーなままに終っていた『可否道』を、『コーヒーと恋愛』と改題した上で、初めて文庫化したこと。
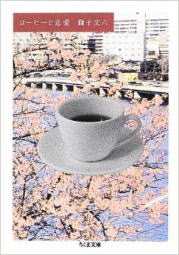
よくこんな企画が通ったものだと思うが、これがヒットしたことで、ちくまの獅子文六シリーズが始まった。
『可否道』も『七時間半』に続けて、四年前の可変日記に感想を書いている。あのときは、数年後にどちらも文庫化されるなどとは夢にも思わなかった。
ちなみに、『七時間半』は『特急にっぽん』、『可否道』は『なんじゃもんじゃ』という題で映画化されている。
川島雄三監督の前者は未見だが、井上和男監督の後者はCSで見た。森光子がヒロインで、あまりいい出来ではないモノクロ映画だが、開局間もない時期の河田町のフジテレビの局内でロケをして、当時のテレビ局や新劇界の雰囲気がうかがえるのが貴重。
五月二十三日(土)オケとヴァイオリン
オペラシティでダブルヘッダー。
まずコンサートホールで、ウルバンスキ指揮東京交響楽団。ルトスワフスキの交響曲第四番、ドヴォルジャークのチェロ協奏曲(独奏はタチアナ・ヴァシリエヴァ)、そしてスメタナの《我が祖国》から前半の三曲。
前半だけというのは珍しいが、ウルバンスキはドヴォルジャークのチェロ協奏曲とこの三曲という組合せがお気に入りらしく、インディアナポリス交響楽団の定期でもズイル・ベイリーを独奏にやっている。テラークからそのライヴ盤が出ていて、収録時間の関係で後半をカットしたのだろうかと思ったら、実演も同じだったので驚いたことがある。
東京交響楽団でも以前に同じプロを組んでいたのに負傷とかで降板、あらためて同じプロを組むのだから、よほど得意にしているらしい(前回代役になった指揮者は、引き受けると同時に曲目を変えてしまった)。自国のルトスワフスキに始まり、シャープで機能的な、土臭さのない演奏。
続いて、ピリオド楽器のメッカというべき近江楽堂で、杉田せつ子のひくバッハの無伴奏ヴァイオリン曲集。ソナタ第一番と第三番、パルティータ第二番の三曲。眼前に聴くバロック・ヴァイオリンの響き、その息吹。
五月二十六日(火)ボルトン&ピオー
ボルトン指揮カメラータ・ザルツブルクの演奏会を東京文化会館で。
ピオーがモーツァルトのアリアを歌ったのがききもの。指揮はやや荒っぽく、会場も大きすぎる感じ。
五月二十九日(金)ダウスゴーのニールセン
レコード芸術の取材で音楽之友社を訪れたのち、サントリーホールのダウスゴー指揮東京都交響楽団の演奏会後半へ。
ニールセンの交響曲第三番《広がりの交響曲》。ダウスゴーらしい雄渾な演奏で飽きさせない。前半のサーリアホのクラリネット協奏曲も聴いてみたかった。
六月五日(金)瑞鶴男
テミルカーノフ&読響のマーラーの交響曲第三番をサントリーホールで。
今月はこのあとショスタコーヴィチの交響曲を八、十、十一と三曲聴くことになる、「交響的白亜紀」シリーズ。別名「六月のタコ」。
今日はその予告編にふさわしい、ショスタコーヴィチ風マーラー。イカれた骨太。鋼鉄の冗談。難曲だけに金管など傷も少なくなかったけれど、すべてのパーツが鉄製のように硬くて重く、腹に応えるマーラー。
合唱をどこで入場させるかは合唱つき交響曲につきまとう問題だが、今日は第四楽章の前で一休みして、入場させた。最初から座らせて、児童合唱団の子供が居眠りしたこともあったというから、妥当な方法か。
ところが、第四楽章で歌うはずのアルト歌手の姿は見えないまま演奏再開。低弦がうなりだしたところで、二階のLA2扉がひらく音が聞こえた。
「おやっ、二階で歌わせるのか?」と思って目を向けると、視界に入ったのは、遅れて勝手に入場した男性客が席に着く場面だった。
あわてて下をみる。すでに歌手はステージ下手のドアから入って、指揮者脇の位置につこうとしていた。
見事な陽動作戦。やるな瑞鶴男。
六月六日(土)「灯台」からの音楽史
ノット指揮東京交響楽団をサントリーホールで。《メタモルフォーゼン》とブルックナーの交響曲第七番。
同じコンビが三月に聴かせてくれた叙情組曲と《パルジファル》抜粋と同様に充実した演奏で、しかも選曲の意味を考えさせてくれる、嬉しい演奏会。
いうまでもなく、この二曲は葬送行進曲でつながる。
前者はエロイカの第二楽章の主題を元ネタにして、第二次世界大戦の戦災で失われたドイツの歌劇場群、ひいてはドイツの精神文化そのものへの挽歌としたもの。シュトラウスは自作《英雄の生涯》の調性をエロイカと同じ変ホ長調にしているくらいで、ベートーヴェンに始まった「英雄の世紀」のはしっこに自分がいることを意識して、ここでその主題を使わずにいられなかったのだろう。
そして後者は第二楽章が葬送行進曲。こうして並べられると、交響曲第七番というのはブルックナーにおける英雄交響曲なのではないか、という見方も不可能ではないことに気がつく。全体の緩急の構成、楽章の時間配分とか、エロイカを下敷きにしたと考えられなくもない。調性はホ長調で、半音異なるけれど。
もちろん、この葬送行進曲がワーグナーという「第二の英雄」を意識したものであることもいうまでもない。つまりワーグナーを中央にして、前にベートーヴェン、後にブルックナー、シュトラウスという歴史の層が見えてくる。
こんなことを考えながらプログラムを読むと、ノットが舩木篤也さんとの対談でバッチリのことをいっている。
「最初のシーズン(二〇一四年度)全体が、ワーグナー・ストラクチャーのなかにあると言っていいでしょう。私自身にとっても、ワーグナーは大変重要な作曲家ですが、彼はそもそも「灯台」のような存在ですね。彼を出発点に、時代的に後に行けるし、前にも行ける」
ドイツ音楽の歴史の、前と後を照らす「灯台」としてのワーグナー。ブルックナーのオーケストラのオルガン・サウンドの原型はワーグナーにあるし、なかでも《パルジファル》の響きはその典型だから、あれが春に演奏されていたのは、前後のブルックナー(昨秋の第三番初稿と今夏の第七番、ともにワーグナーに縁が深い)を光で照らし、しっかりと結びつける意味をもっていたのだ。
シュトラウスとベルクもその光に照らされている。そして今回は演奏されないけれど、灯台の背後にはエロイカ、ドイツ・ロマン派音楽の出現と栄光を高らかに予告した作品の、巨大な影も見える。
面白い。こういうつながりから音を、響きをつくるのがオーケストラのシェフの仕事なのだろう。聴衆を楽しませると同時に、オーケストラを教育する。
面白いといえば、昨夜同じ会場で聴いたテミルカーノフ&読響のマーラー交響曲第三番。すべてのパーツが鋳鉄でできているみたいな、重量感と渋い光沢をもつ響き。そして同時に、ショスタコーヴィチの視点から見なおしたような、ロシア人らしいマーラーだった。
テミルカーノフがこの後に演奏する、ショスタコーヴィチの十番とどう結びついてくるのかが楽しみだし、愉快なことに今月はさらにその前後にラザレフ&日フィルの八番とカエターニ&都響の十一番と、ショスタコーヴィチの重量級の交響曲がならぶ(名づけて「六月のタコ」作戦)。
人為と偶然の関係が綾なしてつくる、さまざまな線のつながり。東京の演奏会シーンは、本当に恵まれている。
マーラーといえば、エロイカとの関係で思い浮かんだのが《悲劇的》。緩徐楽章を第三楽章にした方がロマン派的なドラマトゥルギーに合う気がして、自分はその方が好きだけれど、あれを第二楽章にすると、エロイカの陰画みたいな感じになる。
つまり、エロイカの気高さとは対照的に、主人公の英雄はひたすら苦闘を続けて、第二楽章は挽歌と逆に、わずかな安らぎの時間になる。こんな感じで聴きなおしてみるのはどうか。
六月七日(日)ベートーヴェンの旅へ
先日のアンスネスの「ベートーヴェン・ジャーニー」は、半分しか聴けなかったが素晴らしかった、続いて今日から、ミロ・クァルテットによる新たな「ベートーヴェンの旅」。
サントリーホールのブルーローズで行なわれる室内楽音楽祭「チェンバーミュージック・ガーデン」恒例の企画、弦楽四重奏曲全曲演奏会。
ただし今回は、作曲順というのが面白い。これはかなり異例の方法で、一般的には初期中期後期から一曲くらいずつ選んで一夜のプログラムとし、それを五回か六回続ける。その方が一夜の構成としては自然で、奏者も聴衆も流れに乗りやすい。作曲順となると、後期の大曲が連続する後半での奏者の肉体的、精神的負担は、尋常なものではないはずだ。
実際、「チェンバーミュージック・ガーデン」過去四回の全曲演奏会でも、こんな無謀な曲順を組んだ団体はない。それをあえてやる。その意気やよし。
初日の今日は、作品十八の六曲を一気にひくマラソン・コンサート。十五分の休憩二回入れて三時間四十分の長丁場。
某紙に評を書くので演奏についての感想は述べないが、十年前にやはり六曲をひと晩でひいたときにくらべて、いい意味で歳月の積み重ねを感じるものだった(といっても、あのとき自分は最初の四曲で早退したが)。
ところでかれらのCD。最初の六曲だけが十年前にノンサッチから出たのはよく憶えている。実演同様にパワフルでいい演奏だったのに、不運にも直後にノンサッチがクラシックの新規制作から手を引いてしまい、あとが続かなかった。
だが昨年ラズモフスキー・セットが録音されて出たのは見落としていた。作曲時の年齢に自分たちが近づいたところで録音したいということらしい。
ということは後期の録音は……。これもまた「ベートーヴェンの旅」。

六月八日(月) 神戸・大阪散歩(一)
「みなさま、一泊二日で神戸と大阪へ行ってまいります」
一九七〇年の万博以来、四十五年ぶりの大阪。当時は七歳で親に連れ回されただけなので、今回は自分の意思で初めて行動する阪神地区。もとより表面をなでただけだが、さまざまな発見があり、自分がよく知っているつもりの東京や仙台に関しても類似や相違から見つめなおすことになる、収穫の多い二日間だった。
八日の八時二十二分に新大阪につき、梅田から阪神電車で神戸三宮へ行き、海岸通りと元町を歩いたのち、阪急で西宮北口経由で宝塚へ。大劇場で宙組『王家に捧ぐ歌』第二幕を見てから宝塚線で梅田へ。夜はフェスティバルホールでエリシュカ指揮大フィルのドヴォルジャークの《スターバト・マーテル》を見て、曽根崎のホテル泊。
翌九日はお初天神に詣でてから中之島の中央公会堂などを見学、南下して心斎橋筋~道頓堀~千日前~難波と散歩。南海電車で三国が丘に行き大山陵古墳を半周、次いで中心部に戻って新世界と通天閣を見、天王寺から地下鉄で谷町へ行って大坂城を南北に縦断。いずみホールをながめて京橋から新大阪へ行き、十九時五十分発で二十二時二十三分東京着。
下手くそなピンぼけ写真で、しかも写真映えのしない灰色の曇り空(歩くには楽だった)だが、文章だけよりはわかりやすいと思う。
さて、行きは朝六時発、八時二十二分に新大阪につく「のぞみ1号」。宝くじでもあたりそうな列車名で、その名の通り一日の始まりの新幹線。早朝にもかかわらず、月曜の朝イチで関西に戻ってそのまま出社、という雰囲気のサラリーマンで満杯。
新大阪につくとエスカレーターに乗る人が右立ちで、そうだった、大阪に来たと実感。この人たちも東京駅では当たり前に左立ちだったろうと思うと、ちょっと不思議。JR大阪駅に出てバッグをコインロッカーに入れ、行動開始。阪神梅田から神戸方面へ。

今回の旅行のガイドブックの一つがこれ。
万城目学と門井慶喜の『ぼくらの近代建築デラックス!』。少しでも古い本だと、紹介されたビルがなくなっていたりするので怖いが、これはちょうど一月前に文春文庫版が出たばかりでタイミングがよかった。
東京や横浜、京都、台湾も紹介されているので神戸と大阪の件数は多くないが、当方の日程が二日しかないのでちょうどよし。
午前9時43分

ということで、阪神電車で甲子園球場を車内から眺めながら西に進んで石屋川駅で降り、まずは『ぼくらの近代建築デラックス!』に出ていた御影公会堂(神戸市東灘区御影石町四-四)へ。
一九三三年竣工の公会堂。左右非対称のつくりと、木に隠れているが右角上部の円盤が個性的モダニズム。灘の白鶴酒造の嘉納治兵衛の寄付によるものだそうで、初期の大都市の公会堂は、大阪市中央公会堂(一九一八年)といい日比谷公会堂(一九二九年)といい、富豪の個人的寄付で建設されたケースが多い。
当時はアメリカ的な社会還元の意識が強かったようで、上流階級にキリスト教徒がけっこう多かったことと関係があるような気もする。
戦後は、権限の増した地方自治体が積極的にハコモノ行政をやるようになり、体育館やら公会堂はイの一番につくられるようになって、個人の出る幕はあまりなくなった。
現役の公会堂だがあまり補修されておらず、暗く埃っぽい内部。
午前10時16分

御影公会堂から石屋川駅に戻って、阪神電車で神戸の元町駅へ。これは北側にある兵庫県公館。もとは一九〇二年竣工の兵庫県本庁舎。ハイカラ。
午前10時50分

左が海岸ビル(一九一八年)、右が商船三井ビルディング(一九二二年)。この二つのビルも『ぼくらの近代建築デラックス!』から。海岸通りに建つ、国際港神戸華やかなりし頃の遺産。ただし海岸ビルは外壁だけ残して中を高層ビル化した、いわゆるデスマスク式。
午前11時5分

海岸通りを西に進んで、『ぼくらの近代建築デラックス!』にあった地下鉄のみなと元町駅。もとは東京駅と同じ辰野金吾設計で一九〇八年竣工の第一銀行神戸支店だったが、震災による損傷で、外壁だけを残して地下鉄の入り口に。まるで映画のセットのように中身がない。
北上して、元町通りを歩く。アーケードの商店街。第一印象は「仙台の一番町にそっくりだ」で、この印象は翌日大阪のある場所でも感じることになる。
サントスという古い喫茶店に入ってチョコレート・ケーキ。美味。バニラアイスと生クリームもついてボリューム満点。関西は喫茶店文化が東京よりはまだしっかりと残っている感じ。
このあと南京街という中華街を抜けて大丸百貨店前から居留地跡を通り、三ノ宮へ。同じ港町でも横浜の方がはるかに大きく、権威主義的に感じられる。神戸の方が好き。
午前11時36分

神戸の生田神社に参詣。写真左上に指が写っているのはご愛嬌。源平の一ノ谷合戦の舞台の一つ、生田口とはこのあたりか。それにしてもあの合戦、東の生田口から西の塩屋口まで十キロもあって、人馬しか連絡手段のない時代の戦闘にしては戦場が広すぎると思うが、今回やってきてますます疑問に。
午前11時48分

阪急の三ノ宮駅ホームの時計。デザインといい色使いといい、実にセンスがいい。
ここから神戸線に乗って、西宮北口駅に向かう。
阪神と阪急、自分のイメージは中学生の頃に読んだかんべむさしの『決戦・日本シリーズ』(早川文庫)、阪神と阪急が日本シリーズで戦い、勝った方が相手の線路を走るというSF小説の、次の一節でつくられている。
「たまたま阪急で通勤している人は、阪神をローカル線のように思っています。阪神に乗っている人も、阪急なんてと考えています。傾向として、阪急側が阪神側に対して、優越感を持っているようです。阪急電鉄が創ってきた高級イメージに彼らは乗っかって、それをそのまま武器として、阪急は高級→俺は阪急→俺コーキューという位置づけをするのです。根拠も証明もありません。イメージです。願望です。欲求です。逆に阪神側も、その対抗意識のなかに、腹立たしさ、くやしさ、みじめさが多少なりとも入っています。これもその根拠はありません。相手が自分たちは高級だと言っている。先に言ってしまった。言った者の勝ちです」
こう言って両球団の対決をあおろうとする主人公(スポーツ新聞の企画課員)に対して、「南海がおる。君は、南海が勝てんと言うのか」と南海ファンの取締役が食ってかかるあたりが、電鉄球団さかんなりし良き時代の楽しい短編。
それにしても、「阪急は高級→俺は阪急→俺コーキュー」。登場人物の台詞とはいえ、それから四十年たって、阪神が阪急の子会社となった現代でも、やはり現実に近いのだろうと思った。沿線も乗客も、雰囲気は明確に違う。阪神もJRも車両色は意外にシックで美しいが、阪急にはかなわない。
驚いたのは「みなさま、まもなく…」とやる阪急のアナウンス。必ず「みなさま」がつく。これは翌日に乗った南海でも聞くことができたが、阪神とJRはやっていなかった。
一方、夙川に出るまでの神戸寄りの多くの駅の周囲がすぐに住宅ばかりで、商店がほとんどなさそうなのが不思議だった。まるで箱根登山鉄道の駅みたいな感じだったが、どこか他の場所にあるのだろうか。
そういえば、次の駅名を告げる車内アナウンスで、阪神は阪神バスへの乗り換えを案内するのに、阪急は阪急タクシーの案内をしていて、すげぇぜタクシーか、さすが阪急俺コーキュー、と納得したが、見方を変えると、バス・ターミナルがつくれるような広い駅前がないという意味かもしれない。
とフェイスブックに書いたら、京都在住の方から、やはり阪急はターミナル以外にはデパートや商店街をもつ駅が少ない、と教えていただく。
各駅を人の集まる商業的な拠点とは考えない、というのが面白い。かつては西武もまわりがすぐ建物で、ロータリーもない駅が多かったが、商店だけは線路沿いにわずかにあった。しかし阪急は周りがすぐに住宅だけみたいな感じの駅が多い。阪神や南海では関東の私鉄同様に小規模でも駅前に店舗があったので、阪急はきわだって不思議。
午後12時11分

阪急の西宮北口駅で降りて、兵庫県立芸術文化センターを眺める。二〇〇五年開場で十周年。前日に来てここで野田秀樹演出の《フィガロの結婚》を見ることも考えたが、日程がきつく断念。外から見るだけ。
街の雰囲気は、いかにも郊外の再開発された都市の駅。
午後13時33分

今津線で宝塚南口駅で降り、宝塚ホテルで昼食。一九二六年開業の由緒ある建築だが、もう一つ写真のとりようない、張り合いのない建物だった。取り壊しが発表されたばかりなので、行くことができたことには意義があったが。
写真は宝塚南口駅から宝塚大橋を渡る途中、見えてきた宝塚大劇場。十三時から宙組公演の『王家に捧ぐ歌』のチケットを買ってあるが、一幕後の休憩に入ることにして周辺をウロウロ。
午後13時35分

もう一枚、宝塚大劇場。巨大な建物で大劇場とバウホールのほか、九つのレストランと五つのショップが劇場内外にある。このあたりは歌舞伎座の売場を西洋風に拡大したようで、非日常感があって楽しい。
市街地から離れた郊外の終点駅にこうした劇場があって、お客を集め続けていることが面白い。遊園地なら同様の例が全国の電鉄にあるが、劇場となると珍しい。テーマパーク的なその雰囲気を肌で知りたいというのが、今回の旅行の目的の一つだった。
公演の方はまぁ、マイクを使ってしまうとねぇ、という感じ。大昔にヅカファンだった山の神によると、一九六〇年代までは歌のうまい人と演技・ダンスのうまい人と、役割がある程度分担されていたらしいが、いまは歌は二の次の印象強し。ヴェルディの《アイーダ》の設定とキャラを借りて、自由に翻案したもの。音楽はまったく無関係。フィナーレで大階段が出てきてからは、さすがに見ものだった。
午後13時42分

第一幕が終るまで時間があったので、大劇場斜向いの手塚治虫記念館へ。『アドルフに告ぐ』が二か所で別脚本により舞台上演されることを受けて、生原稿などが展示されていた。
午後19時00分

宝塚から阪急宝塚線で梅田駅に戻り、宿の梅田OSホテル(曽根崎)にチェックインして、フェスティバルホールへ。夜になり、雨もきつくなったので写真は断念。
エリシュカ指揮の大阪フィルによるドヴォルジャークの《スターバト・マーテル》。衒いのない、堂々たる演奏。大フィル合唱団の合唱指揮をFB友達の福島章恭さんがなさっていて、澄んだハーモニー、うねるような呼吸感が見事。終演後にエリシュカが福島さんの仕事ぶりに熱い抱擁で応えたのを見て、こちらまで嬉しくなった。
新しいフェスティバルホールは、ロビーの上が星空みたいでキレイだが、かなり薄暗い。
話題の長大なエスカレーターも暗めだし、客席についたときにステージの明るさをさらに明るく感じてもらおうという演出なのだろうか。ホール左右の壁の高所に、二人がけのボックス席がゴンドラ風にいくつかあるのは面白そうだった。一つ一つ出入り口がついていて、歌舞伎の棧敷席のようなつくりになっている。
六月九日(火) 神戸・大阪散歩(二)
午前10時6分

空けて九日。雨が降りやむのを待ち、午前十時行動開始。しっかり休めたのでよかったかも。まずはホテル裏手のお初天神(露天神社)へ参詣。
午前10時48分

お初天神から御堂筋を南下、昨日と同じ中之島へ。堂島川と土佐堀川に挟まれたこの中州には、重要な公共建築がならぶ。これは一九〇三年竣工の日銀大阪支店。辰野金吾設計。その前には五代友厚の屋敷がここにあったとか。
そういえばこれ、赤レンガではないけれど、中央上部のドームの形は東京駅の復元されたやつとそっくり。同じ辰野設計だけに。
午前10時53分

中之島、東へさかのぼって、これは大阪府立中之島図書館。一九〇四年開館。
午前10時54分

これも中之島図書館。ネオ・バロック様式とか。
午前10時56分

図書館の東、大阪市中央公会堂へ。
午前10時59分

中央公会堂。一九一八年竣工。辰野様式。
株屋の岩本栄之助の寄付でつくられたが、当人は完成前に株で大損して自殺したという。日比谷公会堂の建設費を寄付した安田善次郎も完成を見ずに暗殺されている話とならべると、感慨深い。
大大阪の黄金時代を象徴する建物の一つで、修復されてホール(大集会室)では大フィルの演奏会も行なわれるそう。ホールは使用中で入れなかったが、いつかここで大フィルを聴いてみたい。
午前11時1分

中央公会堂の正面。
午前11時12分

中央公会堂の内部その一。
午前11時16分

中央公会堂の内部その二。
午前11時24分

中之島にあった木村重成の表忠碑。
今年は大阪夏の陣四百年、ワーテルローの戦い二百年。ある時代の終りを告げた大戦闘の記念年。ともに季節は今頃。
午前11時26分

中之島の東にかかる橋、難波橋の南。斜向かいは北浜の大阪取引所。高速で上をふさがれなかったころの東京の日本橋もこんな感じだったのかもと考える。大阪は川を多く残しているのがいいところ。
午前11時28分

難波橋南詰から中之島の岸をながめる。徳川時代には蔵屋敷がならんでいたそうだが、明治以後の中之島は、パリのセーヌ河に浮かぶシテ島を意識して、あんな感じにしたかったんだろうと、このあたりの景色を見て思った。ベルリンやミュンヘンも中州に博物館があるし、その日本版のような。
午前11時37分

難波橋から南下した堺筋にある、高麗橋野村ビルディング(一九二七年)。これも『ぼくらの近代建築デラックス!』で知ったビル。ウェディングケーキのような、アール・デコ風のやわらかい雰囲気。御堂筋が拡幅される前は、むしろこの堺筋がメインストリートだったとか。
午後0時0分

『ぼくらの近代建築デラックス!』で絶賛されているのを読んで、中は無理でも外見だけでもと思ったのがこの綿業会館。御堂筋にあって、大阪の紡績業が日本をリードした時代の記念物。周囲には紡績関係の会社が多い。
外見だけでは品はいいがあまり強い印象はなく、昔のメトロポリタン歌劇場のよう。
午後0時12分

これも指の自撮りになっているがご愛嬌。心斎橋筋の商店街をめざして、本町三丁目駅から心斎橋駅まで一駅だけ地下鉄に乗ろうと思い歩いていたら、心斎橋筋の商店街ははるか北側のこの「せんば心斎橋筋商店街」から始まることに気がつき、そこへ入ろうとしているところ。
午後0時54分

心斎橋の大丸百貨店。一九二二年から三三年にかけてつくられた、ヴォーリズ設計によるアール・デコの建物。神戸といい、関西の百貨店といえば大丸かと実感。
で、これが手前の御堂筋と、向こう側の心斎橋筋の商店街とにはさまれる形になっている。これを見ていたら、妄想がわいてきた。それは次の次の写真で。
午後0時54分

心斎橋の大丸百貨店の下側。
午後0時55分

手前の広い道路が御堂筋、大丸があって、その向うには心斎橋筋のアーケード商店街(左端に少しだけ写っている)。
この、商店街がデパートをはさんで新設の幅の広い自動車道路(並木つき)と並行して長く直線で続く風景をみたとき、仙台の都市設計にそっくりだと感じた。
仙台では、一番町のアーケード商店街に並行したり横切るかたちで、東二番丁通りや青葉通りなど、幅広の自動車道路(戦闘機でも飛ばすのかと揶揄された)が走る。空襲で焼けた戦後につくられたものだが、そのモデルになったのは、おそらくこの昭和初期の大大阪、モダン大阪の都市設計だったに違いない。
これはとても面白い。なぜなら東京にはこういう都市設計がないから。近代商店街の代表である銀座は、広い車道と両側の歩道をもつ直線型の商店街。東京都心部ではこれが原型になっている。
維新前以来の狭い歩行者用の商店街(完全な歩行者専用になったりアーケードになったりしたのは戦後だろうが)と自動車道路を並行させて市街を目抜きでぶち抜く、ようは碁盤の目の隣り合う二本の直線の役割を、歩行者用と自動車用とに分けて特化させるなんてことは、東京都心ではやっていない。
だのに、「銀ブラ」こそが日本のプロムナードの象徴になっている。真似をして大阪では心斎橋筋を歩く「心ブラ」、神戸では元町を歩く「元ブラ」という言葉ができたそうだが、これらは歩行者用の狭い商店街。東京郊外の各地にあった「~銀座」も、歩行者用の商店街。
銀座とはなんだろう、を考えていく、一つの切り口になりそうな気がする。あと、歩行者用と自動車用の道路が並行している繁華街って、東京ではじつは浅草がそういうつくりになっている。仲見世と馬道、新仲見世と雷門通り、六区と国際通り、それぞれ並行させてある。山手線上にない浅草だけ。これも、とても興味深い。
午後0時59分

心斎橋筋商店街に戻る。ここまで「せんば心斎橋筋」「北心斎橋筋」と三つの商店街が続いている。直線で二キロくらい。いまの銀座を歩いても銀ブラをしているという実感や楽しさはさっぱりわかないのに、三つの心斎橋筋や昨日の神戸元町などは、たしかに「ブラ」をした気になる。これも面白い。
なお昼食は北心斎橋筋の「ひなた」という日本料理店。豆腐メインの定食で八百七十円、安いのに細部まで行き届いて美味。というより、東京が高すぎて味が濃すぎるのか。
午後1時5分

そして道頓堀、あまりにも大阪な、夷橋の北話。カニやら餃子やら、心斎橋筋では控えめだった食い物屋が、ここへくると一気に自己主張するのが面白い。グリコは反対側だがみんなが写真を撮っているので、あえて仲間にならないあまのじゃく。
午後1時7分

道頓堀にある大阪松竹座。アジアンな、私の知識の範囲でいうと浅草によく似ている道頓堀の街並みに、いきなりこういう建物が場違いにあるのが面白い。
元は一九二三年、大大阪の時代。道頓堀はもともと六区あるいは有楽街のような劇場・映画館街だったから、こうしたものがある。なんか植民地的、租界的な感じもあるのだけれど、特権的白人ではなく日本人が自分でつくっているあたりが、二十世紀アジアにおける日本の面白さか。
これも外壁だけ昔のを残したデスマスク建築かと思っていたが、東京の歌舞伎座と同じく、外壁をそっくりにして新築したものだと中川右介さんから指摘を受けた。松竹は保存より再現を好むのか。
内部は外壁とまったく無関係な現代風なのだそうだ。いわゆる「看板建築」の現代版ともいえないことはない。
午後1時26分

道頓堀から南の千日前に入り、かつての楽天地の跡であり、大阪歌舞伎座の跡であり、百十八人が焼死した千日デパート(個人的にはこれが強烈な記憶)の跡であるビックカメラを横目に抜けると、いきなり、場違いなまでに堂々たる難波駅が出現。左隣の高島屋デパートと一つながりのデザインなので、これまたモダン。ふり返った極彩色の千日前との対照が面白し。
それにしても、環状線のなかにこれだけ立派な私鉄のターミナル駅があるのも、東京では考えられない。東京のような特権性は大阪のJRにはなく、対等に競争させられている感じ。各私鉄の個性も強く、近鉄南海阪急阪神、それぞれがプロ球団を抱えて張り合った時代の大阪は、『決戦・日本シリーズ』のごとく面白かったろうなと思う。
午後2時10分

南海電車の三国ヶ丘駅で下車、大仙陵古墳、いわゆる仁徳天皇陵を歩く。一周二・八五キロ、馬鹿馬鹿しいまでにでかい(皇居は一周五キロ)。宮内庁が管理するこの土地の脇にラブホテル、というより昔風のモーテルがあるのが愉快。エロスとタナトスか。火曜日で博物館はほとんどが休館日のなか、古墳に隣接する堺市博物館はあいていたので見学。
午後3時59分

百舌鳥駅からJR、長居から地下鉄と乗り継いで動物園前駅について新世界にあがると、もう午後四時。雰囲気はますます浅草っぽい。串かつ屋だらけ。
午後4時6分

新世界から見上げる通天閣。この先は道が三本に分れて、パリの凱旋門の周囲の放射道路を模しているのだとか。中之島をシテ島に見立てるのに較べると、かなり見世物小屋的見立て。
午後4時20分

大阪夏の陣四百年ということで、真田幸村が本陣とした(冬の陣では家康本陣)茶臼山に新世界から行こうとしたが、道を間違って南の大阪市立美術館の前に出る。一九三六年完成の建物。その前には住友家の屋敷があったとか。
午後5時7分

天王寺から地下鉄で谷町四丁目駅へ行き、大坂城を目指す。見えているのは南外堀。
午後5時19分

本丸に入る前に、南の豊国神社に参拝。かつては中之島にあったそうで、シテ島のノートルダム聖堂に相当する見立てだったのに、いまはここに遷座。
午後5時25分

大坂城といえばお約束(?)、旧第四師団司令部庁舎。一九三一年竣工。
午後5時29分

そしてようやく大坂城天守閣。一九三一年再建、これも大大阪時代の一つの象徴。五時過ぎで中には入れず。残念。
午後5時38分

東北の青屋門から天守閣をふり返る。大坂城は大阪の市街の東北にあって、まるで鬼門を守っているかのよう。すると豊国神社が鎮守か。
都市構成としては、このように町外れに城郭がある方が自然で、中心に大いなる空虚としてある東京(江戸はそうではなかった)は、やはり面白い場所。
午後5時50分

青屋門の外にある大坂城ホール。「一万人の第九」でおなじみ。一九八三年に始まって今年は三十三回目だそう。
午後5時54分

最後の訪問地は、大坂城の東北にあるいずみホール。といっても外から覗くだけ。
いずみというから和泉の国にあるのかと思っていたら、住友の屋号である泉屋にちなむものだった。六本木の泉ガーデンも住友家の東京本邸があったところだから、それと同じ命名法。
さてここで十八時。薄暗くなってきたのと帰宅ラッシュ・アワーで動きにくくなることも考え、読売テレビの前を通って京橋駅まで歩き、環状線で大阪駅に出て新大阪。時間をつぶして、十九時五十分発の「のぞみ254号」に乗り、東京二十二時二十三分着。大阪よ、また会う日まで。
六月十六日(火)川瀬賢太郎
よみうり大手町ホールで、川瀬賢太郎指揮読響のモーツァルト演奏会。
今月は「六月のタコ」だけでなく、後期ロマン派から二十世紀前半にかけての大交響曲が在京オケのプロに並ぶ。
十一日間にテミルカーノフ&読響のマーラー三番、ノット&東響のブルックナー七番、ラザレフ&日本フィルのショスタコーヴィチ八番、テミルカーノフ&読響のショスタコーヴィチ十番ときて、リットン&都響のラフマニノフ二番。名づけて「交響的白亜紀の六月」。
旧ソ連経験者二人の指揮による、重くて苦いショスタコーヴィチ二曲のあとにリットンと都響による、まさにハリウッド風、ジョン・ウィリアムズ風の華麗で感傷的なラフマニノフというのは対照的で面白かったが、さすがに大管弦楽に食傷してくるのも事実。
というわけで、今日は五百人のホールでのモーツァルト(フィガロ、ヴァイオリン協奏曲第三番、ジュピター)が聴けるのが楽しみだった。話題の川瀬賢太郎も縁がなくて、いままでナマでは聴けなかったので嬉しい。
読売新聞本社ビルのよみうり大手町ホールも今日が初めて。大企業の本社ビルのホールは多目的なので、味気ない内装も少なくないが、ここは木質の内装も好ましく、残響やステージの広さを目的に応じて変えられるようになっている。
川瀬のモーツァルトは俊敏なピリオド・スタイルで、とにかくアグレッシブ。日本人音楽家にありがちな、フレーズの終りが沈んで停滞する沈降感がなく、ちゃんと跳ねさせて、緩急のメリハリをつけてくる。
微温的なスタイルよりはよほど好ましいが、つねに力一杯に力んでいて、適切な脱力をしないから、音楽が硬くて息づかない。音も濁る。大ホール向けの表現のようで、八六五四二の弦と管でも、音が飽和した感じ。
オーケストラとの意思疎通も充分ではなかったようで、終演後の楽員の表情もいま一つ。特にコンサートマスターの小森谷巧はその態度に不満を露骨に示していて、川瀬と目をあわせず、握手もほんのお義理。小さいホールだとこうしたやりとりが客席からも露わに見えてしまうので、怖い。
こういう経験を重ねて、指揮者は育っていくのだろう。
六月二十二日(月)キリルが来た
朝、キリル・ペトレンコがベルリン・フィル音楽監督を承諾か?という噂。
個人的にはミュージックバードの番組で自分が推した人であり、なってほしいところだが、それはそれとして、ティーレマン、バレンボイム、ネルソンス、ネゼ=セガンにドゥダメルと、今回あがった他の候補のほぼ全員にDGがツバつけてあるなかで、たった一人だけ無関係というのが面白い(レコード産業だけの話でなく、そこに端的にあらわれる、マルチ・メディア戦略全体の話として)し、だからこそあり得そうな話(だからこそきまりにくい話)という気もする。
アメリカのマーケットでいちばん知名度の低い人物、ともいえる。日本でも低いけど、日本のマーケットは雪崩現象を起こすのが得意技(笑)。
いずれにしてもまだ噂話。
夕方、あるコンサートに出かけたが満席で座りようがなく、仕方なく開演前に早退け。八時に帰宅。
メールを見ると八時からベルリン・フィルの緊急記者会見の報が入っている。ちょうどよいと見始めたら、キリル・ペトレンコに決定とのこと。
とにかくこの人はCDが少ない。ベルリン・コーミッシェ・オーパー管のスークの交響詩シリーズ以外は、OEHMSの《パレストリーナ》全曲とウィーン放送響ライヴのブラームスのピアノ協奏曲第一番があるくらい。ブラームスはミュージックバードのベルリン・フィル番組でかけてしまったが、パレストリーナは「ニューディスク・ナビ」でタイミングを逃して取りあげそこねたまま、温存してある。
五月に噂が出てきたので、順調に決まったら、すぐ放送する気で用意してあった。とにかく今からこれを予定にあげよう。早くて八月第一週の「ニューディスク・ナビ」か…。
六月二十三日(火)『名曲決定盤』復刊

あらえびすの『名曲決定盤(上) 器楽・室内楽篇』。
一九八一年に初めて文庫化されたが、三十四年ぶりに改版して再登場。
解説の大役を仰せつかった。上下巻の場合、解説は下巻にしかつかないのが普通だが、今回は上下を一か月ずらして発売するということで、上下の双方に書いた(下巻の方は、初文庫化時の荻昌弘さんの名解説とならぶという畏れ多さ)。
下巻は来月発売。
文庫初版の一九八一年は私が大学に入った年、クラシックをがんがん聴きはじめた年。手元にある昔の『名曲決定盤』もまさにその年に買ったもの。文庫本も書店も、クラシック界も、とりまく状況は大きく変っていて、感慨深し。
六月二十七日(土)キリル雑感
キリル・ペトレンコ決定の報を受けて急遽収録した、ミュージックバード THE CLASSICのウィークエンドスペシャルの「【緊急特集】決定!ベルリン・フィルの次期首席指揮者はキリル・ペトレンコに!!」が放送される。
アリアCDの松本大輔店主のご厚意により、現時点ではかれの貴重な交響曲録音である、RAI国立響との《レニングラード》交響曲のRAI自主制作盤(二〇〇二年ライヴ)を番組内で放送でき、番組の価値を高めることもできた。
以下は番組でしゃべったことをあらためて整理したもの。収録後に、記者会見の前日に最後の楽員総会が行われていたことなどの新事実が発表されており、決定に至る細部の状況もこれからどんどん明らかになるだろう。
しかし、短い時間のなかでペトレンコの経歴やベルリン・フィルがサイトに挙げているインタビューなどを見てみるだけでも、この人のイメージは自分のなかでずいぶん変っていった。
簡単にいえば、ロシアの指揮者、「寒い国から来たシェフ」というレッテルでは、この人は評しきれないこと。
まず、ユダヤ人であること。お父さんがウクライナのリヴィウ出身のヴァイオリニストであること。
おそらくは、お父さんの家族は独ソ戦の戦火を避けて、西シベリアのオムスクに移り住んだのではないか。そこでペトレンコは一九七二年に生れた。同地でピアノを学んだのち、十八歳の一九九〇年に、お父さんがオーストリア西端のボーデン湖に面したフォアアールベルク州の、フェルトキルヒ市のオーケストラに職を得たのに伴い、家族で移住した。そして同市の州立音楽院と、ウィーンの音楽大学で最終的な音楽教育を受けている。
現時点でかれのオーケストラ曲のレパートリーのメインがロシア音楽であることは間違いないけれども、たとえばゲルギエフやソヒエフなどのように、サンクトペテルブルクやモスクワのようなロシア楽壇の中心地で学んだわけではない。
インタビューで、かれは明確な故郷をもたないと語っている。前述のように、オムスクはけっして父祖の地というほどの強い結びつきがあるわけではない。フェルトキルヒもベルリンもミュンヘンも家になりうるというし、イスラエルに住む親戚もいるという。このへん、とてもユダヤ人的だと思う。
もう一つは、そのプロの音楽家としてのキャリア。一九九五年にフォアアールベルクでデビューしたのち、一九九七年にウィーンのフォルクスオーパーのコレペティ、楽長になった。二年後にドイツのマイニンゲンの南テューリンゲン国立劇場の音楽総監督になり、《指環》の上演で名を挙げる。そして二〇〇二年にベルリンのコーミッシェ・オーパーの音楽総監督。二〇〇七年にいったんフリーになって各地の一流歌劇場に客演したのち、二〇一三年からバイエルン国立歌劇場の音楽総監督。バイロイトで《指環》。
指揮者としてのキャリアは、ほんとうに絵に描いたような、ドイツのカペルマイスターのそれなのだ。ロシアはまったく無関係。マーラーやワルター、クレンペラーやクナッパーツブッシュがそうして育ったように、ウィーンの音大を出てからドイツ語圏の歌劇場を遍歴して評価を高めてきた。そしてかれらの多くと同様、四十歳までは独立のシンフォニー・オーケストラに特定のポストを持ったことが一切ない。徹底して、歌劇場のカペルマイスター。
こういう人物を、シンフォニー・オーケストラであるベルリン・フィルが選んだというのが面白い。
ドイツ語圏の諸都市では、歌劇場が音楽生活の中心にあって、最高のオーケストラも歌劇場所属のもの。ベルリン国立歌劇場に勝るとも劣らぬ評価を得てきたベルリン・フィルは例外的な存在で、その点で、シンフォニー・オーケストラが音楽生活の中心にあるアメリカやイギリスの都市のそれを想わせる。ドイツのなかでもプロイセン時代から英米資本主義的な特質を持っているベルリンを、象徴するような存在。
そのようなオーケストラにペトレンコが招かれたのは、どういうことなのか。ペトレンコの中にそれが眠っていることを期待しているのか、それとも。
今回、非公式に名前があがっていた候補のなかで、ペトレンコがありうると私が思った理由の一つは、グラモフォンと無関係な指揮者の名が一人だけ、唐突にあがっていたからだ。あとの指揮者はみんなDGに録音している。
これはどういうことか。ベルリン・フィルがもうCDを重視していないからとお考えの人も多いようだけれども、私が考えたのはそれだけではない。
現在のDGというのが、特殊なブランドだからだ。いま、バーデンバーデンとかルツェルンとかザルツブルクとか、あるいはメトロポリタン歌劇場のような潤沢にお金のある興行団体や、それに関わるマネージメントが、あるアーティストにディスクをつくらせようとするとき、DGを使うことが多い。
二十世紀後半、CD時代にカラヤンやバーンスタインを擁して形成されたDGの栄光のブランド・イメージは、まだ生きている。これはワーナーに吸収されたEMIはもちろん、ソニーやRCAも持っていないブランド力。「あのDG」からCDを出すランクのアーティストなのだと、マネージメント側はそのブランド・イメージを利用する。プロモーションをかねたCDをつくるなら、DGがいちばん効果がある。
DGそのものにはもう、単独でオペラや交響曲全集のような金のかかるディスクをつくる資力は限られているようだ。そうしたディスクは多かれ少なかれ、アーティスト側(マネージメント)との協力によってつくられる。DGにとってもブランド・イメージを維持する上で、これは重要な活動。
つまり、DGから新録音のオーケストラ録音を出せる指揮者の大半は、何らかの形でとても強力なスポンサーをそれぞれに持っている人と考えられる。
これは悪いことではない。入場料収入だけでは成り立たないし、助成金も減る一方のクラシック界で、タニマチをもてることはアーティストの重要な力だ。
ペトレンコは、DGと縁がない。ということは、そうした独自のスポンサーを持っているようには見えない。それなのに、そういう人の名前が一人だけ挙がっていたからこそ、私はありうるのではないかと思った。
これからどうなるのか。あるいはベルリン・フィルがさらに自主性を高め、スポンサーも自らの判断と都合で自由に選びたいから、余計な色のついていないペトレンコを選んだのかもしれない。そのへんは、まださっぱりわからない。
ベルリン・フィル側の思惑は、これから明らかになってくる。ラトルがEMI(現ワーナー)に忠誠を誓っていたことは、かれらのメディア戦略の障碍になっていたような気もする(ラトルがLSOに移ったときにワーナーがどう動くのかも、とても興味深い)。
不安材料は、ペトレンコの慎重さだろう。ベルリン・フィルでと五回招かれたうち二回をキャンセルしている。自分の活動の中心はオペラだという意識が非常に強く、納得できないものは振れなかったのではないか。
オペラの場合はチーム・プレイだからやたらにキャンセルできないが、ホール内のすべての視線が指揮者に集中してくるコンサートの場合、その完璧主義がどうなるのか。なんといってもベルリンのフィルハーモニーは指揮者がホールの中心に立つという、とりわけ特殊な構造でもあるし。
ウィーン国立歌劇場で指揮した《ばらの騎士》はクライバー以来の感激だったという感想を複数の方から聞いているのだが、キャンセル癖もその再来になったりしないといいが(笑)。
あるいは、楽員の選挙でもめたことの一つにそうした不安があったのかもしれない。それでもかれと共演したいと思う人たちが最終的に多数派を占めた、ということなのだろうが。
いずれにしても、楽しみ。
六月二十九日(月)長崎からモスクワへ
新国立劇場で《沈黙》、東京文化会館でカエターニ指揮都響のダブルヘッダー。
二〇一二年の中劇場の上演以来の《沈黙》は、やはり素晴らしいオペラ。
原作ではクライマックスに、黙り続けた主がロドリゴの踏み絵の場面でついに口をひらく。
「踏むがいい。お前の足の痛さをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちに踏まれるため、この世に生れ、お前たちの痛さを分つため十字架を背負ったのだ」
しかしオペラではこの言葉を、ロゴスを切り捨て、松村は音楽だけに委ねる。
言葉を捨てたことにより、オペラでのここの解釈は見るもの、聴くものに委ねられる。言葉の真の意味の沈黙。今回の演出も非常に優れたものだと思いつつ、ここは解釈の一つにすぎない。
前回はこの十一日後にマタイ受難曲をナマで聴き、両者が互いに呼応して、考えさせられたことを思いだした。
スコセッシの映画版はどうなるのだろう。イタリア系アメリカ人は、原作から何を読み取るのか。
そしてマルケヴィチの息子カエターニのショスタコーヴィチの交響曲第十一番《一九〇五年》。前半のブリテンとタンスマンもこの曲と結びついて、うまくできたプログラム。人気ソリストの有名協奏曲を聴くよりもこういうプロの方が面白い。カエターニのつくる響きは、今月聴いたラザレフ、テミルカーノフのショスタコーヴィチよりもシャープでモダンな重工業音楽。二十世紀音楽に強い都響の特長が見事に活かされていた。東京文化会館の乾いた音響も、この作品にぴったり。都響の本領は、このホールでこそ発揮されるのかもしれない。
カトリシズムを批判し否定するマルキシズム、その教則に則っているようでいてそうでないショスタコーヴィチ。日本のキリスト教受容が疑問であるように、ロシアのマルキシズム受容もまた。《沈黙》に続けて聴く面白さ。
そして、一九〇五年の悲劇(日本海海戦の四か月前)と一九五六年の悲劇(ハンガリー動乱)の二重写し。暴力と血の臭い。サディズム。不寛容。
最後に鳴り響く鐘の凄絶。教会の弔鐘なのか。大きめの鐘で、視覚的効果も満点。ミスで滅茶苦茶になって、妙な響きになったらしい。でもそれが異様でよかったという(笑)。
鐘といえば教会ということで《沈黙》にもつながるし、同時に、24日にロト指揮読響で聴いた幻想交響曲(面白かった)にもつながる。あの鐘が、ここまでグロテスクに発達。交響的白亜紀。
暴力装置としての近代交響楽団、そして近代交響曲。いや、ハイドンからか。
七月一日(水)ロトと読響
サントリーホールで、フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮読売日本交響楽団。
ブーレーズの《ノタシオン》五曲、ベルクのヴァイオリン協奏曲(独奏は郷古廉)、そしてハイドンの《十字架上のキリストの最後の七つの言葉》というプログラム。
先月二十四日のベルリオーズとサン=サーンスの演奏会に続き、カンブルランの薫陶宜しきを得て、読響はフランス風の華やかな響きが板についてきているようで、ロトの指揮にも鋭敏に反応。《十字架上のキリストの最後の七つの言葉》も美しかった。
七月三日(金)作品と楽器の共時性
紀尾井ホールでビシュコフ指揮の紀尾井シンフォニエッタ東京演奏会。《フィガロの結婚》序曲、ブラームスのドッペル、ベートーヴェンの七番。
創立二十年、第百回定期を記念して、指揮者だけでなく独奏者も豪華で、ライナー・ホーネックとマキシミリアン・ホルヌングがドッペルのソリスト。
この三人にくわえて、コンマスもバラホフスキーだった。今まで二回この人をリーダーにしたこのオケを聴いたことがあるが(指揮はボッセとナヌート)、いずれもヴァイオリンの響きが段違いに伸びやかでパワフルになっていたから、これは嬉しい驚き。
ウィーン・フィルとバイエルン放響の現役のコンマスが揃い踏み、ホルヌングもバイエルンの元首席チェロ、それにもちろん在京の首席級がならぶ紀尾井シンフォニエッタと、オケマン好きには垂涎ものの組み合わせ。バラホフスキーがダイエットしたのかぐっとスリムになり、ほとんどウェルザー=メストになっていたのにもびっくり。
ビシュコフというと重くて濃厚な音づくりというイメージがあったが、ベートーヴェンでも十‐八‐六‐四‐二のいつもの弦のまま増員することなく、意外にもキビキビした進行。
もっと厚みのある低音がほしいという人もいるだろうが、ベートーヴェンもブラームスも、このくらいの編成で席数八百のこのホールで聴くのが、いまの自分の耳にはいちばんしっくりくる。
紀尾井ホールの大きさでちょうどいいということでは、先週二十七日に聴いたアファナシエフのリサイタル(ベートーヴェンとショパン)もそうだった。モダンのコンサートグランドにも狭すぎず広すぎず、適切な大きさ。
その二日前にトッパンでバッハとシルヴェストロフを聴いたときの窮屈そうな感じがなく、のびのびと鳴らしていた。そのぶん音楽の柄も大きくなって、聴いていてラク。トッパンでは譜面をのぞき込んでいたのに、紀尾井では暗譜でひいていたことも、自然な流れとダイナミクスにつながっていた感じ。
ただ一方で面白かったのは、《悲愴》ソナタとは完全に当時のフォルテピアノのあの音響と機構のためにつくられた作品で、モダンピアノでは間尺があわないという思いを痛感したこと。
短く細かい音の連続はいかにもフォルテピアノの音(というより、その限界にいらついて書きまくった感じ)だし、その限られた音の強さと音量と音階の枠をぶちやぶろうとする、ほんとうに楽器が壊れてしまいそうなスリルが生じてはじめて、ベートーヴェンがこの作品に込めた狂気じみたパッションが音として現代に甦えるように、思えてならなかった。
自分がこの作品がどうも苦手だったのは、剛性の高いモダンピアノでは表現しきれない部分への、その違和感のせいだったのかもしれない。
作品と楽器の関連ということで思い出すのが、最近アンドラーシュ・シフがECMから出した、シューベルト・アルバム。シフはここで一八二〇年製の、シューベルトと同時代のフォルテピアノをひいていて、これがまたいかにも作品との共時性を感じさせるものだった。
このアルバムはシフが寄せた一文もよかった。シフ自身、八〇年代初めにはピリオド楽器に懐疑的だったこと。歴史的なオーセンティシティを押しつけようとする教条主義の尊大さに辟易していたこと。そのころ、大いに皮肉を込めて、シフは言ったという。
「そのうちシューベルトのソナタをグラーフのフォルテピアノで演奏するような時代がくるだろう」と。
それから三十年たって、その預言を自ら成就させてしまったことに、シフはあきれている。三十年前は先入観にとらわれ、知識が足りなかったことを正直に認める。きっかけはモーツァルトの幻想曲ハ短調をモーツァルト自身のヴァルターでひいたとき。音が強すぎるモダンピアノでは抑制が要求されるのに、この楽器ではそんなことがなく、「存分に遠慮無く演奏することができる。モーツァルトはこの曲で鍵盤楽器を限界まで用いた。だからフォルテピアノは、この幻想曲の革命的性格に適した楽器なのである」
《悲愴》ソナタで思い出したのは、まさにこの言葉。楽器の限界に挑んではじめて、この曲の「革命的性格」が生命の輝きを放つ。
そういう《悲愴》を聴いてみたい。ただ、そのときには紀尾井ホールでは大きすぎる。トッパンホールのほうが絶対にいいし、近江楽堂の方がさらにいいかもしれない。
シフ自身も、現代の大きなホールで演奏するときには、これからも現代のピアノを用いつづけるだろうという。しかしそのときでも、オリジナルの楽器の響きを知っておくことは、必須のことだとつけくわえて。
どんなスタイルであれ、演奏が教条主義化、形骸化してしまえば、作品の炎は消えてしまう。
七月五日(日)日生劇場の空間と時間
藤原歌劇団の《ランスへの旅》を日生劇場で見る。
ゼッダの軽快な指揮に乗り、歌手陣も好演。千三百席と小さめの日生劇場の空間もよかった。
無粋で無機的な形態で、しかも大きいという戦後民主主義的な高度成長期の東京のホールのなかで、このホールは珍しく明快な個性を主張している。日本生命の本社が大阪だったことを思い出して、あらためて納得する。戦後の市民文化は関西からやってくる。
隣席が奥田佳道さんだったので、自分の日生劇場の最初の記憶は劇団四季のジョン万次郎のミュージカルを小学校の観劇会で見たことで、開幕に舞台で江戸っ子が「黒船だ、黒船だ」などとうろたえていると、平土間に現れた勝海舟が「ガタガタするんじゃねぇ!」とかいいながら舞台に上がったんですよ、なんて話をしたら、奥田さんもそのミュージカルを憶えているという。
考えてみれば奥田さんは同学年。東京各地の小学校六年生が日生に見に行ったのだろう。大河ドラマが『勝海舟』だったので、内容的に小学生の関心も高かったのだ。思わぬ共時の快感(笑)。
七月八日(水) 悲しき思い出
アルテミス四重奏団のヴィオラ奏者、フリーデマン・ヴァイグレの訃報。
これはほんとうに惜しい。このクァルテットを昨年五月に一時間インタビューさせてもらったことがあるだけだが、落ち着いて魅力的な、まさしく「賢者」という雰囲気を全身にただよわせた人で、強烈に印象に残っている。
「東京には室内楽用のホールがいくつくらいあるんだい?」と逆に質問してきたこと、今回は演奏会を聴けなくて残念といったら「そのメンデルスゾーンのCDを聴いて待っていてくれ」と、突然冗談を飛ばしたこと。そして、終ったあと廊下ですれ違ったら「ヴィーダーゼン」と、にこっと微笑んで、わざわざ手を差し出してくれたこと。
まったく理由もなく、ゆっくりこの人と言葉を交わしてみたいと思わずにいられなかった。指揮者ヴァイグレの弟、そして自分と同学年とは知らなかった。
九月にブラームスの一、三番が出る。ナマを聞くことは永久にかなわぬ夢になったけれど、このCDが出るまで、メンデルスゾーンを聴いて待とう。
ベートーヴェンの死を悼む第二番の前に、姉の死を悼み、自らの死を予感するような第六番。その前に長調の三番を奏でる二枚組。追悼に聴くには預言的でつらい曲目。 合掌。
七月十日(金)ピノックのロ短調ミサ
紀尾井ホールでピノック指揮の紀尾井シンフォニエッタ東京による、ミサ曲ロ短調全曲。清々しく、気持のいい時間。
七月二十日(月)ジャワの獄にて
一九五四/五五の追加エピソードとして、「リリー・クラウスと『戦場のメリークリスマス』」を書き上げる。それはこんな話。
朝比奈隆が一九四四年に上海交響楽団を指揮しているころ、一年前に録音した『ジャワの唄声』のSPが発売された。大東亜共栄圏に属するそのジャワでは、一九四二年からリリー・クラウスとシモン・ゴールドベルクが日本軍に抑留されていた。六年前の一九三六年に来日して人気となり、日本録音も残したデュオ。
終戦で解放されてヨーロッパに戻ったクラウスは、一九五四年二月と三月に、その最高傑作となるモーツァルトのピアノ・ソナタ全集を録音する。
その一九五四年、イギリスの作家ヴァン・デル・ポストは小説『影の獄にて』の第一部を発表した。これはジャワの俘虜収容所を舞台として、映画『戦場のメリークリスマス』の原作となった作品。
この小説全体が完成されたのと同じ一九六三年、クラウスは二十七年ぶりに来日し、以後も来日を重ねる。そしてゴールドベルクも、一九八八年に山根美代子と結婚して、日本で永眠する。
関連する素材が多く入りきるか不安だったが、どうにかつなげられた。ただ、ジャワ統治初期に善政を敷きながら戦犯として投獄された「仁将」今村均大将が、一九五四年にようやく巣鴨プリズンを出所した話は、うまく入らないのでカット。残念。さらに戦後、ジャワを含めたインドネシア独立のために戦った残留日本兵の話にすると、テレビの『快傑ハリマオ』につながるが、それはいくらなんでも無茶なのでやめた。
前半のどこに挿入するかが問題だったが、四話に入れるほかない。残りの完成部分三十五話の番号を順次ずらして、ああ面倒。しかしこれで日本の戦前と戦中の状況に具体的に触れられたので、意味はあるはず。
あと八本(朝比奈隆と武智鉄二の挿入一本と、未完成七本)。必ず今年中になんとかしたい。鞭打て鞭打て。
ところで今回、『影の獄にて』を読むついでに『戦場のメリークリスマス』も見なおしたが、ずいぶん日本化されてしまった映画だと感じる。映画だとよくわからない、説明されていない、あるいは単純化されているものが、原作にはちゃんと書かれている。
なによりも大きいのは、キリスト教的な「赦し」、すなわち愛、それがポイントになるからこそ、話全体がクリスマス説話の一つとなっているはずなのに、映画ではまるで情緒的な、宗教心の薄い平均的日本人にとってのクリスマスにすぎなくなっている…。
七月二十四日(金)引越のラトル
ラトルがLSOライヴのレーベルから十月に《楽園とペリ》を出すと知る。
在ロンドンの友人から、LSOはゲルギエフがあまり登場しないので、ラトルが現時点ですでにLSOのシェフみたいな雰囲気になっていると教えてもらったが、こんなCDが登場すると、さもありなんと思える。
ベルリン・フィルに来てから、ラトルがそれ以外のオケを指揮したディスクはほぼなかった(特にオペラ以外では)はず。なのにこういうものが出てくるということは、すでにいろいろな意味で実質的な引越が進んでいるということなのだろう。
七月二十五日(土)がんばれ日本映画専門チャンネル
三月二十一日の欄で取りあげた久松靜児監督の『南の島に雪が降る』、日本映画専門チャンネルが八月に放映してくれるという、嬉しいニュース。キレイな画質で見るのが楽しみ。
あのとき見返して、この映画でいちばん悲しい場面は、兵隊さんたちが〈酋長の娘〉を歌いながら、「お~ど~れ、お~ど~れ~」と体をゆらすところだと思った。作り手が悲劇性をまったく強調していない、むしろ愉しいつもりでつくってするはずの場面にこそ、こんなところに連れてこられてしまった一般人の運命が浮き彫りになる。
大河の『篤姫』で、誰だったか忘れたけど薩摩の下級武士の結婚式の場面が、みんながゲラゲラ笑って愉しそうだからこそものすごく悲しかったのと一緒。そこにいる連中のほぼ全員がやがて、互いに斬りあったり、戦死したり暗殺されたりして非業に死ぬことになる。この場合は、そのことを作り手が強く意識しながら知らんぷりして、ただただ愉快に仕上げたのが素晴らしかったのだけれど。
それにしてもこのところのCSのテレビ局は攻めていて素敵。『北の国から』とか『まんが日本昔ばなし』とかを、初放映時と同じ曜日と時刻に、週一回しかやらないようにしてるのもいい。まだビデオが普及していなくて、テレビが「曜日」を強く意識させたあの頃を思い出しつつ、一本一本をじっくり見る。
八月には『不毛地帯』の一九七九年テレビ版(平幹二朗主演)も始まる。これは毎日放映だが、見たことがないので楽しみ。
七月三十日(木)ローレル登場
昨日はサントリーホール、今日はミューザ川崎で、ジェレミー・ローレル指揮読売日本交響楽団のメンデルスゾーン・プロを聴く。楽しみにしていた指揮者。初顔合わせだけにまだ手さぐりの部分もあったけれど、爽快さが次第に浸透していたよう。また聴きたい。
八月二十二日(土)一九五五年話から
月の前半は先月来の猛暑で動く気になれず。演奏会は一日に阿部加奈子指揮東京シティ・フィルの「真夏の第九こうとう2015」、五日にサントリーホールで行われた、ゲルギエフと東京交響楽団によるチェスキーナ洋子メモリアル・コンサートに行っただけ。近年の東京では年末だけでなく真夏にも「第九」をやることが増えているらしい。
来週行く予定のセイジオザワフェスの二回を入れても今月は計四回。ここ数年で間違いなく最小。そのぶん、ようやくエンジンが五年ぶりくらいにかかった一九五四/五五本のために、本とCDとDVD三昧。
一九五五年前半にビクターが録音した《修善寺物語》全曲(おそらく日本最初のオペラ全曲録音)の元になっているのが同年一月の二期会によるこの作品の東京初演で、さらにそのもとは前年十一月の大阪の朝日会館での朝比奈隆指揮関西歌劇団による日本初演という話から、このオペラも《夕鶴》もともに大阪朝日会館が日本初演していることを指摘して、当時の大阪の活況を考え、その背景に朝日会館館長の十河巌(大阪労音の発案者らしい)と住友銀行頭取の鈴木剛(大阪音協の発起人でもある)の存在があり、さらに《修善寺物語》の演出は、大阪も東京も武智鉄二が担当しているという話から、昭和二十年代大阪の武智歌舞伎の話になるというのが、まず一本できた。これが第三十五話。

資料にあたるなかで、武智が神のように尊敬していたのが六代目菊五郎とともに義太夫の豊竹山城少掾だと知り、その「息を詰める」極意(よくわからないのだが、横隔膜の支えによる呼吸法のことだと思う)が武智歌舞伎に応用されていると読んで、興味がわいて山城少掾の一九五一年四ツ橋文楽座でのライヴ録音の「絵本太功記 尼崎の段」を買ってきいてみたら、なるほどこれは門外漢が音だけ聴いても引き込まれるくらいに素晴らしい。一九五一年の四ツ橋文楽座といえば、まさに武智歌舞伎が上演されていた場所なので、なんとかこれも《修善寺物語》の話に入れられないかとやってみたが、一話三千二百字の制限のなかに入るはずがない。これは断念。あまりにいいので山城少掾の戦後録音五枚組名演集も新たに買ってしまったが、これはおいおい聴くことに。
ついでに、いろいろ人間関係を調べているうちに、謎だった一九五四年一月のニューヨークでの吉田秀和と朝比奈隆の関係について、なんとなく筋道が見えてきたような気がするのだが、これは完全な推測にすぎない。
次の、マリオ・ランツァとディ・ステファノの生き方から、十九世紀後半以降のオペラと歌劇場におけるスター・テノールの重要性とカラスの関係について考えるという第四十一話にかかろうとしたところで、月刊誌とミュージックバードの仕事が忙しくなってきた。しかしそれで仕方ないと中断してしまうと、またいつまでたっても完成しないことになる。今回は合間を縫って続けようと、まずはランツァの映画『歌劇王カルーソー』を見なおそうと思っていた。
ところが今月の「レコード芸術」九月号に、矢澤孝樹さんがリヒター最後の来日のゴルトベルク変奏曲ライヴの再発盤について突っ込んだ評を書かれていて、出来の悪い変なライナーを十年前に書いた私の名前まで挙げてくださっている。
これを読んでいたら、一九五四/五五本に入れるかどうか迷っていた「一九五五年のカール・リヒター」を、やっぱり入れたいという気になってきて、テノール話の前に取りかかりたくなる。
なぜ迷っているかというと、これをやると全四十八話になってしまうから。今回は仮名手本の四十七話でいくというのが当初からの構想で、これは別に内容に関係あるわけではないので増やしても誰にも文句はいわれないが、自分で決めたことだから崩したくない。
そう思いつつリヒターの録音を調べ直すと、一九五四年のデッカ録音のオルガン曲集(デッカ最初期のステレオ録音の一つ)と、テルデック録音の一九五五年アンスバッハのバッハ音楽祭での一台、二台、三台、四台のチェンバロ協奏曲集のほかに、一九五五年のクリスマス・オラトリオがある(原盤はアルヒーフ)。
そして重要なことは、山根銀二がアンスバッハでこれらの曲の演奏を聴いて、絶賛する文章を残していること。おそらくこれが日本人によるリヒター賛の最初期の文のはずで、一九五四年に吉田秀和がモンテヴェルディを初めて聴いて驚愕した第十五話(吉田は知らなかったが、そのときの演奏家には若き日のアーノンクールが混じっていた)と、この話を対照させる、あるいはそこまでいかなくても、併置させることができるのだ。
(できれば、タワーレコードがようやく初CD化したミュンヒンガーの《四季》の第一回録音も、バロック・ブームの嚆矢として、そこに組み合わせたい)
なんとかならんかなと思って全話の構想表(こんなのものが珍しくあるのだ)をあらためて見る。もしかしたら、第四十二話の「グールド登場」に合わせてしまえるかもしれないと気がつく。
これは一九五五年六月のグールドのゴルトベルク変奏曲と、マイルスの「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」のニューポート・ライヴが近い時期の演奏で、数か月後に同じ三十丁目スタジオでアルバムが録音される話に、プレスリーのRCAデビューが近いことから、「アメリカのメジャー・レーベルに次代のスターがデビューすること」を考える話にする予定だったが、それを適当に短縮して、グールドのゴルトベルク変奏曲とリヒターのアンスバッハ録音が一か月違いであることをポイントにして、二十世紀後半のバッハ演奏をリードして、神のように崇められた二人の演奏家を考えるという内容にしてしまえば、その方が面白いんじゃないか。
こうすれば仮名手本四十七話で収まるし、四十三話に「プラードのカザルス」が来るから、続けて戦前のバッハ演奏に戻る形になってちょうどいいぞ、とほくそえんでいるところだが、はたしてそううまくいくかどうかは、神のみぞ知る。
八月二十六日(水)オペラ講座のこと
毎年晩秋に担当する早稲田大学エクステンションセンターのオペラ講座、今年は「日本オペラ事始」と題して行う。
十/三十一、十一/十四、二十一、二十八、十二/五の全五回、土曜の十時四十分~十二時十分。
去年、一回だけ取りあげた浅草オペラの話が好評だったので、今年は調子に乗って三回に拡大。そしてその前に吉田光司さんの「テノールの歴史と役割」と、池田卓夫さんの「オペラのグレートマザー、ベヴァリー・シルズ物語」。
全体としては、まず欧米のテノール歌手の歴史をとりあげ、オペラにおけるその重要性を。続いて、日本の興行界に大きな影響を与えたアメリカの、そのプリマドンナの典型として、ソプラノ歌手ベヴァリー・シルズの生涯を。後半は前2回を踏まえて、日本にオペラがどのように根づいたかを、幕末横浜の外国人居留地にはじまって、帝国劇場と浅草オペラ、女性歌手の登場、そして日本初のスター・テノール、田谷力三と藤原義江の生涯などから紹介。
アルテス(電子版)に掲載した「帝都クラシック探訪 〜音楽都市TOKYOを歩く」の内容にからめ、横浜、上野、丸の内、赤坂、浅草、日比谷と、オペラが公演される土地の雰囲気をなるべく感じていただけるようにするつもり。
八月二十八日(金)松本の二日間
昨日から松本に来て、セイジ・オザワ松本フェスティバル。
いつもは日程が離れているオペラ公演とオーケストラ・コンサートが、今年は二日続き。そこで松本に二泊。のんびりできるがあいにくの天候で雨がち。
朝は勝手に恒例としている穂高神社参りをして、午後に松本へ戻って丸善の松本店で本さがし。ここは広々とした巨大店舗なので飽きない。東京の大書店と中身は変わらないが、たくさん本があるという、ただそれだけで私には魅力的。
面白そうな本に会って、立ち読みをしているうちに中身に引きこまれ、ふっと我に返ると、自分がどこで何をしていたのか一瞬理解できず、やがて周囲の景色や音とともに再び身体に入ってくる。これは大型書店でこそ味わえる快感。
ところで、丸善なのに陳列が完全にジュンク堂式なのが不思議だったが、いまは両方とも大日本印刷(DNP)傘下なので、文具は丸善式、書籍はジュンク堂式と、双方を組み合わせた店舗なのだ。
さらに三階には別会計のホビー売場があって、元模型少年としては懐かしく楽しいが、ここは文教堂書店系列の店。
むかし、関東各地で通いなじんだロードサイド型書店の文教堂も、いまはやはりDNPの子会社なのだ。丸善にジュンク堂に文教堂、各ブランドの個性と長所を活かす戦略か。キメラのような感じが面白い店。自分などは何時間でも入り浸れる店なので、頑張ってほしいもの。
夕方、これまた恒例のおきな堂で早めの夕食をとる。ここの二階には一昨年あたりまで、一九五二年に来日したフランスのレイモン・ガロワ=モンブラン(ヴァイオリン)とジュヌヴィエーヴ・ジョワ(ピアノ)がここで食事したときの写真が飾ってあった。食後、演奏会へ。
例年、まつもと市民芸術館のオペラには喜んで行くのに、キッセイ文化ホールの演奏会は敬遠しがちだったのは、ホールへの往復に普通の路線バスに乗らねばならず、それがやたらに混んで、何か余裕のない、惨めな気分になったため。
松本駅と信州大学を循環するバスなのだが、今年は前回と逆に、反時計回りの路線に乗ってみた。こちらは座れたし、ルートも広い道路を通るので楽だった。
途中、かつての遊廓・赤線として知られる横田温泉が見えた。そういえば何度も松本に来ながら、赤線跡の横田も青線跡とおぼしき西堀も、花街跡の裏町も、歩いてみたことがない。来年、天気がよかったらまわってみたいもの。
さて演奏会、不完全燃焼に終った昨晩のオペラに較べ、段違いにすごかった。バボラク、タルコヴィ、吉野直子などの名手が大活躍。前半のハイドンの《熊》ではコンマスが竹澤恭子だったが、後半のマーラーは豊嶋泰嗣に交代。大編成の大曲となると、やはりコンマスを本職とする人の方がよいということか。
前半のハイドンの音楽が持つしっかりした骨格に対し、マーラーはより自由。その差が響きに明快に出ていて、昨日の《ベアトリスとベネディクト》の、つまりリストを経由したベルリオーズの音楽からの影響が浮き彫りになる点、偶然なのかどうか知らないが、二日続きに聴く意味のあるプログラムだった。
一方で、自らは演奏するわけではない指揮者という芸術の不思議も痛感した。昨晩のギル・ローズと今夜のルイージ、同じオーケストラが演奏してこれほどの差が出る。今日の方がメンバーが強力で編成も大きかったとはいえ、それだけでは説明のつかない、欲求不満を解消するかのような大熱演。
これだけ鋭敏に反応してくれて、食らいついてくる「楽器」を前にしたルイージは、指揮者冥利につきる思いだったのではないか(あとで聞いた話だと、リハーサルのときにルイージは感激のあまり泣きだして練習が中断したそうだ。本番でもやはり涙を浮かべていたという)。

今年からフェスティバル自主制作のCD販売が始まった。会場では十月の一般発売より一足早く、割引価格で小澤征爾の幻想交響曲(昨年のライヴ。小澤五回めの録音)が売られていた。今日のルイージの演奏も、ぜひ発売してほしい。
帰りは会場で会った大学時代の先輩の車に乗せてもらって宿へ。いくつになっても先輩はありがたきもの。明朝帰京。
九月五日(土)或る音楽状況、パリ
サントリーホールで、山田和樹指揮の日本フィル。自分の音楽シーズンの始まり。曲目がヤマカズならではのひねったものなので、前から楽しみにしていた。
・ミヨー:バレエ音楽《世界の創造》
・ベートーヴェン:交響曲第一番
・イベール:アルト・サクソフォンと十一の楽器のための室内小協奏曲(サクソフォン:上野耕平)
・別宮貞雄:交響曲第一番
日本フィルが委嘱して一九六二年に初演した別宮貞雄の交響曲第一番をメインに、その音楽的基礎というべきベートーヴェン、パリ留学時代に学んだミヨー、その同年代のイベールを前座とすることで、二十世紀日本の西洋音楽受容史の、或るミニチュアのようになっている。
ジャズ色の濃いミヨー、サックスを用いたモダンなイベール、まさにバーンスタインいうところの、二十世紀音楽史においてシェーンベルクの十二音音楽と別の流れを築いたフランス音楽の系譜。十二音やブーレーズ以降の前衛音楽に否定的だった別宮が、パリで学んだもの。
しかしそのパリでさえ、ブーレーズのドメーヌ・ミュジカル運動などが隆盛したのを嫌って、別宮は一九五四年に三年間の留学を打ち切ることにするが、ところがそうして帰りついた祖国は、西洋の学問芸術の流行にものすごく敏感なお国柄だった(これも西洋受容における重要な性格)。前衛音楽にあらずんば現代音楽にあらずという風潮により、以後の別宮は主流を外れてしまうことになる。
しかも別宮にとってショックだったのは、かれの美意識に大きな影響を与えた吉田秀和が、柴田南雄たちと組んで二十世紀音楽研究所の所長となり、前衛音楽の旗振り役になっていたことだった。
別宮は一九五九年の「音楽芸術」に公開質問状を載せて、敗戦直後に出会ったころにはワーグナーさえ否定する厳格な古典主義者(いかにも戦前の教養主義的な)だった吉田の、この「転進」(事の是非はともかくとして、このイカサマな大本営用語をあえて用いたあたり、別宮の失望がいかほどのものだったかがわかる)を批判することになる。
じつは吉田が一九五三年から五四年にかけて米欧を初めて旅行して、パリで別宮に会ったとき、吉田はすでに「転進」していて、現代音楽の動向を現地で知りたいというのが目的の一つとなっていたのだが、なぜかこのときはまだ、両者の対立は表面化しなかったらしい。
このへんの心理的動きが興味深くて、これを一九五四年十二月パリのヴァレーズの《砂漠》世界初演とからめて、「一九五四/五五」本で一話にしたててあるので、まさにその時代に関わる今回のプロが、とても楽しみだった。
しかしヤマカズはもう一枚、さらに上手だった(笑)。それは、別宮と吉田の原点であるベートーヴェン、その交響曲第一番を、倍管十六型の巨大編成で鳴らしてみせたこと。
二十世紀半ば、まさに別宮がいた時代のヨーロッパでは当然だった、ベートーヴェンにおける倍管演奏。精神的な大きさを物理的な大きさで表現しようというロマン派的幻想にもとづくもの。そう、このロマン派的肥大主義に対置されるべきものとして、ミヨーとイベールの小編成のジャズ様式が生れて、同時に並んだのが、この時代のパリ。
別宮がパリにいたころ、毎年秋と春にフルトヴェングラーとベルリン・フィルがやってきては、ドイツ・ロマン派の精髄のような音楽を聴かせたという。吉田と一緒だった一九五四年春にももちろんやってきて、二人はCDにもなった「パリのフルトヴェングラー」を聴いている(吉田はこの直後、パリの音楽では何がよかったかとフランス人にきかれて、パリで聴いた最高のオーケストラはベルリン・フィルだと答えてしまい、いやな顔をされたと書いている)。
その意味で、ヤマカズのこのベートーヴェンは、いわゆるピリオド・スタイルとは正反対だけれども、二十世紀半ばの「或る音楽状況」を再現したという点では、やはりきわめて歴史主義的なものであるということがいえて、ものすごく面白かった。
もちろん、ただの再現ではなく、その大きさを誇示するかのように音を延ばしたり、逆に第二楽章を弦のトップのソロで始めたりと、大と小の落差でスケールを演出したのが、まさにヤマカズ流。
ちょうど某誌のためにタワーレコードの「札響アーカイブ」の紹介記事を書いていて、この曲の一九六一年の第一回定期での荒谷正雄の演奏や、二年後の近衞のライヴを続けて聴いたところだったので、さらに感慨深いものがあった。
一九六一年(くしくも別宮が交響曲第一番を書いた年)の札響は、トラ抜きでは二管編成がやっとだったらしく、演奏会のメインがこの曲。その編成の問題も含めた日本のオケの非力をカバーする目的と、そしてロマン派的肥大主義から、近衞は独自の「近衞版」をつくり、札響と演奏している。
その半世紀後、新ヤマカズによるこの響き。交錯する時間。
九月六日(日)ワーグナーを東京で
サントリーホールで、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団による《トリスタンとイゾルデ》演奏会形式上演。
プログラムと一緒にもらったチラシを見ると、イゾルデ役のクリスティアーネ・イーヴェンが降板、レイチェル・ニコルズが代りに歌うとある。ワーグナーの代役となると、おいそれとは見つかるはずがないので、かなり危惧したが、透明度の高い声が美しく、カンブルランのスタイルに適うものだった。
トリスタン役のエリン・ケイヴスは不調なのか、声がしばしば白っぽく響き、やっとこさっとこの歌いぶり。しかしこれは、ワーグナーがテノールに要求したものがあまりに過大(特に第三幕)なので、こうしたロマン派的肥大に応えられないことに文句をいう気は、最近はまったくなくなっている。
クラウディア・マーンケ(ブランゲーネ)と石野繁生(クルヴェナル)の二人の歌は存在感豊かで気に入る。アッティラ・ユン(マルケ)の歌は大味だが、これだけ雄大に響く声はたしかに希少。
カンブルランの志向する音楽は、精妙で澄明度の高いもの。まさにフランス的ワーグナー。重ったるい演奏にほとんど興味がなくなってしまった自分には、じつに心地よい。
カンブルランはサントリーホールの空間の使い方が、いつもうまい。今回は一幕のバンダと二幕のブランゲーネ、三幕の牧童とコーラングレを舞台背面のオルガン席に配して、劇場公演では不可能な音響をつくり、演奏会形式の面白さを楽しませてくれた。
コーラングレを吹いた北村貴子は、二〇一二年にスクロヴァチェフスキが読響とこの曲のオーケストラル・アドヴェンチャー(管弦楽のみの抜粋)を演奏したときも、恐ろしく見事なソロを奏でていた。今回はこの配置で、その妙技がさらに際立つ。さすがカンブルランはわかっていると、嬉しくなった。
オーケストラ全体もとてもよかった。読響のワーグナー全曲は、二〇一二年の二期会の《パルジファル》以来。あのときは飯守泰次郎の指揮に応え、厚みのある響きをつくっていた(二年後の新国立劇場では同じ指揮者でも、東フィルの響きが薄く説得力を欠いた)が、今回は対照的なサウンドを献身的に生み出した。
この美しい演奏に、トリスタンという音楽の怪物性、「とんでもなさ」をあらためてかみしめつつ、やはりワーグナーでは、オーケストラの重要性が大きいことを思う。
東フィルへの批判を続けて申し訳ないけれども、今日の演奏を聴きながら、二〇一一年正月の新国立劇場の上演が、東フィルの管楽器が事故だらけでさんざんの出来だったのを、思い出さないわけにはいかなかった。いや、問題は個々のミスではない。全体の淡泊な薄さが、あのときも決定的に足を引っぱっていた。
その昔、十年以上前の《指環》では、準メルクルの強い要望を劇場がのんで、《ジークフリート》からはNHK交響楽団が特別にピットに入ったのだった。
資金に余裕があったからといえばそれまでなのかも知れないけれど、ウォーナーの演出とあわせ、あの頃は、劇場というものに不可欠なワクワク感、何が起こるのだろうという期待感があった。
だが今の自分は、この秋の新国立劇場《指環》の第一作《ラインの黄金》を、どうしても見る気になれないでいる。理由は、説明不要だろう。
九月八日(火)日本舞踊と《春の祭典》
サントリーホールで、山田和樹指揮の日本フィル。「日本フィル&サントリーホール とっておき アフタヌーン Vol.2 歌舞伎×オーケストラ」。
前半がチャイコフスキーの《花のワルツ》と《ロメオとジュリエット》。後半はストラヴィンスキーの《春の祭典》。
《春の祭典》には歌舞伎役者の尾上右近の舞踊(尾上菊之丞振付)がつく。ステージ中央に白木の床がしかれ、オーケストラはそれを囲んで半円形に展開。紋服のみで衣裳やかつらをつけない素踊りなのは、これが舞台公演ではなくてセミステージ上演だからか。
第一部は男、第二部は薄地の打掛と仕草で女と、キレのいい動きで踊りわけたのが面白かった。
九月十七日(木)草書体の《英雄》
サントリーホールで、ヘルベルト・ブロムシュテット指揮のNHK交響楽団。
ベートーヴェンの交響曲第一番と第三番《英雄》。一九二七年生れとは思えぬ若々しい音楽に会場がわく。
個人的にはやや流麗すぎて、もう少しメリハリが欲しい。三年前にバンベルク響との来日公演で、同じホールで三番と七番をやったときには、オーケストラが現代風にエネルギッシュな刻みと抑揚をつけていたが、N響はフレージングが草書体なので、昔の新古典主義的なスタイルに近くなる。
十月三日(土)パーヴォの《復活》
NHKホールでNHK交響楽団の定期演奏会。パーヴォ・ヤルヴィの首席指揮者(このポストはN響史上初だとか)就任記念、マーラーの《復活》。
NHKホールの巨大空間を逆手にとった、まさに空間的なマーラー。NHKホールをあえて活用しようとするなんて誇大妄想的な発想こそ、まさにマーラーの交響曲にふさわしい。
レコーディング中のR・シュトラウスはサントリーホールにこだわっているだけに、ひょっとしたら任期中に全曲やるかも、というマーラーは、NHKホールを活かしたものになるのかも、などと妄想してみる。
「空間的なマーラー」という意識は、先月二十九日にサントリーホールで聴いたハイティンク指揮ロンドン交響楽団による交響曲第四番で強く刻みつけられたものだった。弦五部をフラットな床において、管楽器と打楽器をスタンドのように、P席のすぐ下まで高くした中央の雛壇に配置するという、ハイティンク得意の楽器配置で、高低差のあるサウンドをつくりだしてみせた。
床面の弦楽器の描く平穏に、甲高い金管が上方から不意の闖入者となり、不安と緊張を高める。これが、弱音の微細なコントロールによる遠近感の変化と組み合わさっているのが素晴らしかった。
そしてパーヴォの《復活》は、客席後方、外のロビーの左右から「審判のラッパ」を響かせた。
NHKホールのでかさを思うと、あれはステージから、はたしてどのくらい離れていたのか。広大な客席空間の彼方から「審判のラッパ」が聞こえてくる、その距離感の見事な効果。誰もが持てあますはずのNHKホールの巨大空間を逆手にとった、NHKホールでしかありえない、驚くべき活用。ギリギリのクライマックスまで合唱を座らせたまま歌わせたことといい(クレンペラーがミサ曲ロ短調の録音で、合唱に神秘的な響きを求めて座ったまま歌わせたという話を思い出した)、そのサウンドの空間的変化へのこだわりは見事だった。
マーラーの音楽には、緩急大小の変化による時間的なモンタージュだけでなく、巨大な音の全体像のなかに、同時に小さな挿話が書き込まれているような、絵画的なモンタージュがつかわれている。それはいうまでもなく、空間の活用によってこそ明確になるもの。
これからパーヴォは、NHKホールをつかって、それを体感させてくれるのかもしれない。《千人》はその最高の例になるだろうし、声楽なしの作品でも。
NHKホールでクラシックを聴くのが楽しみ、なんてことは今までまったくなかった。できれば他のホールで、としか思わなかった。三十年前の一九八五年のバーンスタイン&イスラエル・フィルの交響曲第九番のように、ホールの広さを忘れさせる密度というものなら、体験したことがあるけれども。
ところが、その絶望的な広さを逆に活用したマーラーという、前代未聞の音楽が、これから数シーズンにわたって、ひょっとしたら聴けるのかもしれない(オルガンだけは、舞台の右外の上空から響くというのが、難しいけれど……)。
頼りにしてまっせ。
十月四日(日)セイジ・オザワ八十歳
ウィーン・フィルのサントリーホール公演初日の、朝の公開リハーサル。全員私服。エッシェンバッハ指揮で、今日の曲目のサワリ(モーツァルトの管楽器のための協奏交響曲、ハイドンのオックスフォード、ベートーヴェンの第一番)が一時間リハーサルされる。
そのあと、再びベトイチの終楽章が響いたかと思うと、そこに《ハッピバースデイ》の音型が混じり、『ウエストサイド物語』の〈アメリカ〉などの部分が接続され、おしまいに全員で「ハッピバースデイ」と叫ぶと、客席から赤いスニーカー姿の小澤征爾登場。
九月一日の八十歳を祝して、ウィーン・フィルが企画したサプライズ。楽団長やエッシェンバッハの祝辞(通訳つき)に続いて、小澤が英語で短く答礼したあと、《エグモント》序曲を指揮。
今やなかなか聴けない、小澤指揮のウィーン・フィル。ぶっつけだろうに、エッシェンバッハのときとは違う、グッと踏みこんだ、緊張感のある深いハーモニーが出てきたのはさすが。
演奏会ではなく公開リハーサルということで、抽選で無料招待された客席(もちろんスタンディングオベーション)に応えるよりも仲間――今日はとりわけ、この場をつくってくれた仲間、音楽を一緒につくる仲間が最優先だ、という姿勢が明確だった――への声がけを優先するあたりが、いかにも小澤。
それにしても今回の来日公演は軽めの曲目と思ったら、十二型の二管編成らしい。一九五六年のヒンデミットとの初来日と同じような人数なのが何か面白い。十六時から本番。
ところで、楽団長はあいさつで、小澤がカラヤンに連れてこられてウィーン・フィルに初めて紹介されたのは、一九六〇年にカラヤンがウィーン国立歌劇場で《フィデリオ》を指揮したときだった、と言っていた。だとすると十一月二十七日、ゴールデンメロドラムからCDが出ている、その晩のはず。
更新を止めている「一九六〇年話」だが、不意打ちで一瞬呼びもどされた。
十月九日(金)ライプツィヒの人々

QUERSTANDというレーベルから第四集まででている「ゲヴァントハウス管弦楽団エディション」のこと。
ゲヴァントハウス管弦楽団は、一九三四年にアーベントロートがカペルマイスターになる以前の録音はほとんど出ていないが(ヴァイマル共和国時代までは、ドイツの商業録音はほぼベルリンでしかやっていないため)、このシリーズには少しだけ入っている。
たとえば第二集。一九二四年から三三年までライプツィヒ歌劇場の音楽総監督をつとめた、グスタフ・ブレッヒャーのほぼ唯一の録音とおぼしき、一九二九年の《魔弾の射手》序曲のパーロフォン盤が入っている。
このブレッヒャーは、若き日のクレンペラーがアウフタクトの重要性を教えてもらったと語っていることで、個人的にとても興味のある人だから、少しでも聴けて嬉しかった。いかにも戦前のドイツの楽長らしく、アンサンブルはかなり大雑把だが、重みのある呼吸感に納得。
最近注文したのは第三集。一九一八年から三九年まで聖トーマス教会のカントルをつとめた、カール・シュトラウベ指揮によるバッハのカンタータ集。
シュトラウベはギュンター・ラミンとカール・リヒターの師で、トーマス・カントルの跡を襲ったのがラミン。リヒターはラミンの一九五六年の急逝後に次のカントルへの就任を要請されるが、すでに自由を求めてミュンヘンに出ていたため、熟慮の末に断る。
というわけで、一九五四/五五本での「一九五五年のリヒター」を考える上ではラミンとシュトラウベの演奏はリヒターと似ているのかどうか、トーマス・カントルの伝統の影響がどこまでリヒターに及んでいるのか、を確認したい。
幸いラミンはライヴも含めてそれなりの量が残っているので、リヒター、特にその初期のスタイルとかなり似ていることはわかった。しかし先代のシュトラウベの方は、商業録音がほとんどない。
しかしこれが二年ほど前に出ていた。
一九三一年から三九年に、シュトラウベがゲヴァントハウスで演奏した、カンタータのラジオ放送用の録音数曲。
シュトラウベについての感想は別の機会にゆずって、このディスクには思わぬ副産物があった。
伴奏のオーケストラがゲヴァントハウス管弦楽団で、首席が何人かソロを担当している。
一九三一年の第九十七番のヴァイオリンはカール・ミュンヒ(Karl Münch)。すなわちコンサートマスターのシャルル・ミュンシュのドイツ名。オーボエは、ルドルフ・ケンペとヴァルター・ハインツェ。
ミュンシュとケンペが共演して、ソロをとっている。これは、先程のブレッヒャーの《魔弾の射手》とともに、二人が在籍した時代の貴重な記録。
ミュンシュはかなり長いソロが入っている。さすがに巧い。ミュンシュは同年の百七十七番にも参加していて、そこでのオルガンはトーマス教会オルガニストのギュンター・ラミン。
このあと、それぞれの場所でそれぞれに名前をのこしていく人々の、一瞬の交差点。まさしく「あなたはこんなところにいたのか」の録音。
十月十五日(木)サヴァリッシュ流?
サントリーホールで、NHK交響楽団の定期演奏会。これもパーヴォの就任記念で、オール・R・シュトラウス。
《ドン・キホーテ》(独奏モルク)、《ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら》に《ばらの騎士》組曲。
春の《英雄の生涯》に続いて、これもソニーがライヴ・レコーディング。やはりNHKホールのマーラーとは違う、豊麗な響きを求めたことがよくわかる。弦のフレージングが流れるような草書体になっているあたり――そのぶんメリハリはつきにくいが――、サヴァリッシュの時代を思い出させたのが面白かった。
録音曲目にR・シュトラウスを選んだ理由として、サヴァリッシュなどのもとで、ドイツ物に伝統のあるオーケストラだからとパーヴォは述べていた。本当にあの時代の演奏を知っているようなのが面白い。
十月十七日(土)南葛散歩

「東京右半分」の代表的なコンサートホールといえば、すみだトリフォニーとティアラこうとうに、かつしかシンフォニーヒルズ。いずれも区営。
かつしかシンフォニーヒルズだけ行ったことがなかったので、今日訪問。
区営ホールはアマチュアが無料演奏会をやるので、そういうときに行けば、ロビーと客席に入って様子を見て、演奏まで聴かせてもらうことができる。今日はミュージック☆スター マンドリンオーケストラの演奏会。
京成線の立石と青砥の中間にあって、ホールのサイトを見ると青砥からがオススメらしいが、あえて手前の立石から。
いま立石は、安い飲み屋と食い物屋のB級グルメの名所だそうだが、自分が興味あったのは赤線と青線の跡。
B級グルメは、おもに駅南側のアーケード街のほうらしい。そちらも歩いてみたが、東西二本あるうちの西側の仲見世通りというのが、狭くていい感じ。
周囲の駅と違って高架化を拒んできたため、駅脇の繁華街に踏切のある、いまとなっては懐かしい感じの風景。
赤線と青線は駅の北側。駅通り商店街から細い路地を左に入れば赤線、右に入れば青線。車の入れない、細い路地がギクシャクと折れ曲がり、見通しがきかない迷宮状になっているのがいかにもで、昔のままの建物が数多く現存しているのがありがたい。車が来ないから、道には猫がたくさんいた。
古いとはいっても戦後の産物で、築六十年超。青線は大正期に浅草の十二階下や観音裏にできた銘酒屋、カフェーが原点で、大震災で焼けたあと玉ノ井と亀戸天神裏に移り、さらに空襲でも焼かれて、前者は鳩の街、後者は立石へと移ったという。立石は売血でも有名で、貧しい労働者や学生が血を売って金に換える、血液銀行があった。
写真の「呑んべ横丁」は青線跡。戦後にマーケットとしてつくられたのが青線になり、売妨法後は飲み屋街に。新宿のゴールデン街と一緒だが、狭くてアーケードになっているので昼は真っ暗。



かつて東急の自由が丘駅にも、南口に一か所だけ、こういう薄暗い路地があったのを思い出した。立石のはH字型で、もっと大きい。
駅の北側は大規模な再開発がきまっているらしいので、いつまで残っているかわからない。見ておけてよかった。
歩いて数分で、かつしかシンフォニーヒルズへ。一九九二年開場、バブル期の設計だがあまりいやらしくなく、好感のもてる建物。とはいえ、有名なモーツァルト像と八百屋の取り合わせはやはり面白い。

演奏のミュージック☆スター マンドリンオーケストラ、プログラムを見ると早稲田大学マンドリン楽部のOBと現役で構成されているのだそう。助演も含めて五十人弱の編成。聴いたのはバンドネオンの啼鵬をゲストに、ピアソラの《三つのタンゴ》と《リベルタンゴ》。マンドリンオーケストラでやるピアソラは世界初じゃないかという話。前者の第二楽章と後者がとてもよかった。
ホールの音響は抜けが悪いのか低音がボンつき、いま一つ。
休憩で失礼して、青砥駅へ歩く。こちらは線路が高架になり、街並も近代化されていて、そのぶん面白みはない。駅ビルを見たら、なぜか宝塚阪急駅を連想。
さいわい空も晴れてきたので、ことのついでに京成線を乗り継いで柴又へ行って、帝釈天に参詣。駅前に寅さんの銅像が建つ。
半世紀東京に住んでいても、生れて初めての南葛飾地域。中川、荒川、隅田川と川を三本もまたいで帰宅。それにしても東京右半分は、やっぱりまっ平ら。

十月二十三日(金)時計を動かして
トッパンホールで、カルミニョーラ&ヴェニス・バロック・オーケストラ。タイミングが合わなくてこれまで聴けてなかったので、初の生カルミニョーラ。
オーケストラだけのジェミニアーニの合奏協奏曲を前座に、二曲めからカルミニョーラが出ずっぱりでヴァイオリン協奏曲。ヴィヴァルディの《お気に入り》(個人的には「ご寵愛」と訳したい)、バッハ三曲と進んで、最後のヴィヴァルディ《ムガール大帝》が圧倒的な出来。
かっちりした建築物みたいだったバッハが終って、《ムガール大帝》に入った瞬間、薫風にはためいて波うちだした色とりどりのカーテンのように、オーケストラの各パートが生き生きと、表情豊かに動き始めたのにびっくり。
そしてカルミニョーラも一気にヴォルテージを上げ、カデンツァ的な長いソロでは、息をのむような妙技を次々と繰り出す。トゥッティとソロが交互に出る終楽章の、華麗なヴィルトゥオジティ。
続くアンコール四曲もすべてヴィヴァルディで、《ムガール大帝》の勢いのまま、凄かった。とりわけ《四季》の夏の第三楽章の、ゾクゾクするようなリズムの奔流。聞きあきたつもりでいたこの曲に、こんな凄い音楽がつまっていた。
しかも、これだけエネルギーに満ちても、けっしてうるさくならない、ピリオド楽器の響きの、空気と戯れるような品のよさ。こういう響きを聴くと、モダン楽器って無粋だよなと思ったりする。トッパンホールの小空間だからこそだが。
カルミニョーラは、一昨日モダン楽器でピアノ伴奏のリサイタルを行なっていた。聴きたかったが、その日は仕事でクレーメル&クレメラータ・バルティカを聴くべく、サントリーホールへ行った。
だが結果的には、クレーメルとカルミニョーラをならべて聴くことになり、面白かった。二つのアンサンブルは、モダンとピリオドの差はあるが、ヴァイオリン・ソロと弦楽合奏、それにリズム楽器という編成の点ではそっくりなのだ。
いってしまえば、どちらもヴィヴァルディの《四季》をやるための編成。二十世紀前半まではほぼ無名だったこの《四季》という曲が、戦後のLP時代に俄かに大人気になり、バロック・ブームを起こした。
そこから、十八世紀で止まっていた時計が動き出した。
そうして、時代をさかのぼる形で、ピリオド楽器と奏法の考証を進めていくなかで出てきたのがヴェニス・バロック・オーケストラで、一方、《四季》を現代化する形で、二十世紀の他の作曲家の同テーマの新作に拡げていくのが、クレメラータ・バルティカ。一昨日はまさにそうしたプログラム。
ベクトルは逆みたいだけれど、しかし時計の針を止めることなく動かし、音楽を博物館に入れてしまわないように、生命の灯を消すまいとしている点では、一緒。これがすごく面白かった。
クレメラータ・バルティカのほうも、最後のピアソラの《ブエノスアイレスの四季》で、いきなり水を得た魚のように鮮やかな演奏をしはじめたところが、今日の《ムガール大帝》に似たところがあって、愉快だった。
ヴェニス・バロック・オーケストラのヴィヴァルディと、クレメラータ・バルティカのピアソラ。いわゆる十八番。
さらに面白いことに、いまちょうどイ・ムジチ合奏団も来日している。半世紀前のバロック・ブームの原点となったアンサンブル。そして明日、サントリーホールで《四季》を演奏する。
かれらとて世代交代をしているから博物館には入っていないはずだけれど、しかしお客の方は何を求めるのか、そこが興味深い。サントリーホールの大空間で《四季》を鳴らすなんて、二十世紀の大衆教養主義のクラシックそのものなのだが、やっぱり半世紀前の「アーヨの演奏みたいなの」が聴きたくて来るのか、どうなのか。行けそうにないのが残念。
十月二十四日(土)二百年の合わせ鏡
NHKホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団。
東京の演奏会の日々というのは、偶然にも勝手に関連したり対照したりというのが醍醐味の一つだが、今日もそう。
カルミニョーラ&ヴェニス・バロック・オーケストラを四百席のトッパンホールで聴きおわって十八時間後、N響を三千六百席のNHKホールで聴く。単純にいって客席九倍のホール。
しかも曲目がまた、見事な合わせ鏡。
ジェミニアーニの合奏協奏曲と、ヴィヴァルディとバッハのヴァイオリン協奏曲だった前夜に対し、今日はエストニアの作曲家トゥールの《アディトゥス》という十分くらいの曲に始まって、ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲第一番(独奏五嶋みどり)と、バルトークの管弦楽のための協奏曲が続く。
追悼曲という《アディトゥス》をつなぎ目に、曲目が鏡像になっている――ものすごく大きく歪んでいるが。
ショスタコーヴィチのヴァイオリン協奏曲は、まさに二十世紀風の大交響楽団(今日は十四型)と、コンサートグランドなみの音が出せるヴァイオリニストのための作品。長大なカデンツァが入るところだけ、昨夜の《ムガール大帝》に似ているのが愉快。
強大で輝かしく、安定した響きを求めて発展した再現芸術の一つの極点が、二十世紀半ばの、ソ連の独奏家とアメリカの交響楽団だった。
だからこの曲の理想的な演奏の一つは、オイストラフとミトロプーロス指揮のニューヨーク・フィルが、二千八百人入るカーネギー・ホールでやった、一九五六年正月のアメリカ初演ライヴ。
五嶋みどりの内攻的で、沈潜していくヴァイオリンは、オイストラフとは異質のものだけれども、息をのませる凝集力の高さはたしかにすばらしい。
続くバルトーク。今日は両端楽章の金管の荒さが気になったけれど、第三楽章の〈悲歌〉にただよう冷やかな神秘性、怪奇性、陰惨さは見事だった。
それにしてもその大編成。昨日のジェミニアーニはストバイ四人の計十四人のオーケストラ(管楽器がないので管弦楽団とはいえないが、たしかにオーケストラ)だったのに、バルトークはストバイだけで十六人いる。さらに木管金管、たくさんの打楽器。
「オーケストラのための協奏曲」は、二百年でこれだけ変化した。NHKホールはさすがにでかすぎるけれど、やれないことはない。やったろうぜ、という気にさせる大編成のモダン楽器軍団。
二百年のときの流れを、二十時間くらいで跳躍する音の旅。最後はニヤニヤ笑いがとまらなかった。
十月二十八日(水)大人買い
「レコード芸術」十二月号取材記事のため、タワーレコード渋谷店にてボックス・セットの大人買い。
十月三十日(金)パールマンの美学
ミュージックバードの番組「ニューディスク・ナビ」で扱う新譜に、パールマンの再発盤と新録音が含まれている。
七十歳記念盤ということだが、パールマンがまだたった七十歳だったことに、むしろ驚く。もっと、ずっと年上のような気がしていたが、じつはクレーメルより二つ年上なだけ、カルミニョーラよりも六歳上、というだけなのだ。
しかしこの二人とは、ヴァイオリニスト、音楽家としての活動領域が、なんと隔たっていることか。パールマンはその後の潮流にお構いなく保守本流、クライスラー~ハイフェッツ~スターンの系譜の「カーネギー・ホールを一杯にする」ヴァイオリニストであり続けてきた。
大オーケストラと張り合い、豊麗で安定した大きな音量を、大ホールの聴衆に届けることを重視する奏法。同時代のアルバン・ベルク四重奏団や東京クヮルテットとも共通する様式。アメリカの音楽家としてブレることなく、徹頭徹尾それを貫いて、時計は止めたまま。
戦後のドイツでは名ヴァイオリニストが払底したとされたのは、当時のこのような美学に適う人がいなかった、という一面が大きいだろう。ムターに至って、ようやくそういう、カラヤン&ベルリン・フィルのような、アメリカ市場にも通用する独奏者が出た。
日本では今も、この美学を懐かしむ声が根強い。ヨーロッパ志向なのに、その点はアメリカ的だ。
十一月四日(水)シベリウス祭り
ハンヌ・リントゥ指揮のフィンランド放送交響楽団のシベリウス演奏会。
《フィンランディア》、ヴァイオリン協奏曲(諏訪内晶子独奏)、交響曲第二番。
二日にすみだトリフォニーで演奏した第七番、第五番を知人が絶賛していたとおり、今日は素晴らしい演奏だった。澄んだ響き、力強いエネルギー。
十一月五日(木) エベーヌ新生
エベーヌ四重奏団を聴きに、ハクジュホールへ。
《クラシック+ジャズ プログラム》と題して、前半がモーツァルトのディヴェルティメントのヘ長調K一三八とベートーヴェンの弦楽四重奏曲第十五番。後半はコルトレーンの《ジャイアント・ステップス》や、ピアソラの《リベルタンゴ》など、このクァルテットの特許的十八番のスタンダード・ナンバー。
とにかくいま、自分がいちばん楽しみにしている弦楽四重奏団。二日の《クラシック・プログラム》も聴きたかったけれど、これは大野和士&都響と重なって聴けず(そして失敗。この組合せの大野は、だんだん「うんとレベルの高い秋山和慶」みたいになっているようで、気がかり)。
今日のプロは、三日午後に聴いたのと同じもの。個人的な事情で前半だけで失礼したが、演奏は今日の方がはるかに好調。三日は前夜にやって翌日の午後というスケジュールだけにコンディションが充分でなかったのか、特にストバイのコロンベの音が硬く、音程が不安定で、全体的に力んで軋むような響きになっていた。しかし、今日はいつもの調子に戻って、見事な脱力で美しく漂うような響きを出す。こうなると全体のハーモニー、共鳴も、本当にほれぼれするほどに美しい(この澄んだ共鳴を聴いたとき、新メンバーのヴィオラのボワソーを三人が選んだ理由も納得できた気がした)。
三日間ひいて、かれらがハクジュホールの音響になじんだことも、大きいのだろう。まあ、ストバイが苦闘すればするほど、ベートーヴェンの後期のクァルテットがいかに至難の曲かということも浮き彫りになるわけで、そのぶん三日の演奏のほうが刺激的で、強烈な演奏に聞こえたという逆説もいえる。
しかし、やはり今日のような、純度の高い上質の響きと、一体感と独立性の奇跡的なバランスこそがエベーヌの魅力。第十五番という作品の「とんでもなさ」も、天上の音楽のような神性のなかで、その魔性がきわだってくる。
ヴィオラが交代して、あのアカペラ歌唱が聴けなくなったのは残念だが、まず基本はクラシック。その期待を感じさせる新メンバー。
さて今日は珍しく食い物の写真。代々木八幡駅前にある「ドリア&グラタン なつめ」の、タルタルから揚げ丼(柚子胡椒味)。

三日のハクジュからの帰りに初めて入って、ドリアとグラタンを食べて、シンプルな調理法と店内の雰囲気のよさにひかれた。どんなほめ言葉よりも、子供連れの家族で店がいっぱいになって、その子たちがみんな幸せそうな顔をして食べていたので、これは間違いなく良店だと感じた。子供だましというなかれ。子供ほど味に正直なものはない。
この、ドリア用の炊き込みご飯の上にサラダとから揚げと、卵のタルタルを乗せた丼、このまるで、まかない飯みたい感じこそが魅力で、五十二歳のオヤジもきっと幸せそうな顔をしているだろう味だった(笑)。
十一月七日(土)「理想の楽器」
今日はダブルヘッダー。
まずは二時からサントリーホールで、インキネン指揮日本フィル。シベリウスの歴史的情景第一番と《ベルシャザールの饗宴》組曲、そしてマーラーの《大地の歌》。
《大地の歌》は、聴く機会の少ないバリトン版が嬉しい。指揮者をはさんでテノールとバリトンが両側に。腐女子風にはBL系《大地の歌》の三角関係か。
この作品はとにかくテノールの声が聞こえないように、かき消すようにマーラーが書いていることが実演だとよくわかるが(録音ではごまかされてしまう)、今日の西村悟は比較的よく聞こえた。少し鼻にかかった、ドイツ風の発声なのが幸いしたのだろう。今はイタリア風のアッペルトな、開けっぴろげな発声が主流だけれど、正面から挑んでもオーケストラに負けてしまう。パツァークみたいな声がいちばんいいのだろうと思う。
同時に、インキネンがオーケストラを巧みに抑えたことも大きい。西村もバリトンの河野克典も強大な声量の持ち主ではないし、歌ううちにさらに響かなくなっていったから、コントロールは大変だったのではないか。このためか、管弦楽の表現の幅が抑制され、全体におとなしく感じられた。
むしろ、思いきりかき消してしまい、終楽章の後半で諦観の境地に至って、ようやく声が管弦楽との調和を見出す、というほうが、この曲らしいのではないかと自分は思っている(そのことは、この日記に前に書いた)。
夜はすみだトリフォニーで、マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ)とアントニオ・メネセス(チェロ)のデュオ・リサイタル。オーケストラホールで聴くにはメネセスの表現が繊細すぎ、ピリスの印象が強く残る。
そして、大空間であるためか、モダン楽器の剛性の高い響きと作品とのズレを感じてならなかった――作曲家の念頭にあるのはこの響きではないのでは、という違和感である。
といっても、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ第三十二番のような曲では違和感なく、曲と演奏の素晴らしさに没入できる。ズレを感じたのは、同じ作曲家のチェロ・ソナタ第二番と第三番である。
後期の作品、ピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲や交響曲では、ベートーヴェンはもはや音の聞こえない世界に生活しながら、この世にない「理想の楽器」のためにつくっていたように思う。そして、その理想に近づくべく発展したのが、モダン楽器なのではないか。本当に同じかどうかは別として、ともあれ違和感がないのは、そのためだろう。
しかし、中期までの室内楽は、それを演奏してくれる音楽家、その楽器の特性を意識しながら、ベートーヴェンはつくっていたのではないか。一人でひくピアノ・ソナタでも、《悲愴》のように、目の前のフォルテピアノの限界にムカムカしながら、それをぶち破ろうとしている曲もある。逆にいえば、ムカムカするくらいにその楽器を意識している。
ピリスは、こうしたことをもちろん熟知しているはずだが、大ホールでひくかぎりは、繊細さを犠牲にしなければならないのだろう。
十一月八日(日)怪談
今日の怪談。
サントリーホールでのハーディング指揮の新日本フィルの本番中、私の椅子を後ろから蹴った人がいた。
しかし、すぐ後ろは通路なのだった。
十一月十一日(水)あれに見えるは鈴ヶ森
グスターボ・ヒメノ指揮コンセルトヘボウ管弦楽団を聴きにミューザ川崎へ。
演奏については日経新聞の評に書くのでそちらにゆずる。ここでは、ちょうど演奏会の最中にJRで起きていた騒動のこと。
演奏会が始まる直前の六時五十分頃、横浜駅手前の東海道線下りの車中で痴漢が捕まり、被害者、目撃者とともに横浜駅で降りたが、ホームから線路に飛び下りて川崎駅方面へ逃走。
その捜索のために付近の電車が停車、あるいは徐行することになったが、すると品川~川崎間の多摩川手前にいた後続の東海道線車両から、乗客が手動でドアをあけて線路に降り、アナウンスが気にくわないからと車掌室に線路上から投石し、その後、駆けつけた運転士と川崎駅まで線路を歩いたところで逮捕。
未確認だが、このほかにも線路に降りた人とか、非常ベルを鳴らして遅延させたりした人がいたらしい。さらに、この状況をうけて品川駅では私鉄の京浜急行に振り替えたところ、乗りきれない乗客が改札外まであふれて、すさまじい混雑になったのだとか。
自分は終演後、九時半近くに駅について新橋まで乗ろうとしたら、「十五分遅れ」の表示はあったがすぐに空いた電車が来て、なんということもなく新橋に到着。ただ車内の電光掲示板に、「京急が混雑のため遅延」と出ていて、「今頃なぜ混雑?」と不審に思ったのだが、こういうことだった。
川崎に行く途中にまき込まれなくて大助かり。やられていたら仕事が一つ吹っ飛ぶところだった(今回はいろいろな意味で保険をかけて、十三日のサントリーホール公演にも行くので、書くには書けるが)。こんな騒動は大いなる無駄。ホームドアがあれば、こういう迷惑な逃亡者も減るのでは。
東海道線のように、首都圏の通勤電車にしては駅間の長い路線は、ラッシュアワーに痴漢が出やすいのだろう。女性専用車両もない。グリーン車があったりトイレがついていたり、長距離仕様の車両だから設定できないのか。
そういえば、行きに東京駅ホームの乗車待ちの列で女性の後ろになったら、その人はちらちらとふり返り、こちらを警戒していた(こういうとき、にじみでる人徳のなさを痛感するが、地下鉄や山手や中央線でそうした警戒に出会うことはないので、やはり特殊だと思う)。
それにしても、複数の乗客が線路に降りたり、非常ベルを鳴らしたというのが本当なら、普段から募っていたイライラが、ここで爆発したのかなと思う。
たしかにラッシュ時の東海道線の混雑はひどい。私も、前にミューザ川崎に行くときにひどい目にあい、それ以来、平日夜の場合はできる限り早めに川崎駅について、そこで夕食をとって時間をつぶす、という形にしている。
駅間が長いだけに、駅の間であの混み方で停まってしまったら、頭に来て降りたくなる気持もわからないではないが、でも実行してはダメ。
痴漢におぞましい体験、恐い記憶をお持ちの女性が多いとは知りつつ、男としてはまず、誤解されたために逃げたという可能性も考えてしまう――今回のは目撃者がいたというから、冤罪ではなく本物の痴漢の可能性が高いが。
二十年くらい前、京浜東北線で品川から大井町に向かっていたとき、そんなに混んでいない車内だったが、斜め前に立っていた女性が突然ふり返り、こちらをキッと睨みつけてきたことがあった。
そのときはなぜ睨まれたのか、見当もつかなかったが、しばらくして、あれは自分を痴漢だと思っていたのに違いないと気がついて、ゾッとなった。
もし彼女が、こちらの腕をつかんで叫びだしたりしていたら、当方は何が起きたのかわからないまま狼狽するだけで、ますます疑われて警察に突き出されていたろう。そして、二十年前には痴漢冤罪なんて話はまだまったくなく、女性が訴えれば、ほぼ百パーセント有罪になった時代だ。あの日突然に、自分の社会的生命を抹殺されていた可能性が高い。
あの日以来、自分は一度死んだ生命を助かって生きていると思っている(大げさ)。そういえば、あれも品川から川崎にかけての海沿いの線路だった。恐い。鈴ヶ森刑場の祟りではないか(笑)。
十一月十四日(土)疎外と連帯
クリスティアン・テツラフのバッハ無伴奏全曲を紀尾井ホールで。
長袖Tシャツのような、恐ろしくラフな服装にモジャモジャの長髪で登場したテツラフは、自由で柔軟、聴く者に過度の緊張を強いることのない、ストレスから解放されたバッハをひく。声高にクライマックスをつくらない、何者かへの対峙を強いることのない、バッハ。
テツラフが協奏曲や室内楽で見せる表情、聴かせる音楽とは、かなり異なるもの。たった一人で舞台に立つ、という、ピアニストにとっては当たり前だがヴァイオリニストにとってはかなり異常な状況で、いまテツラフはこうしたスタイルを選択する。その落差。
聴きながらパリの事件を思う。
大きな疎外、と小さな連帯。
はてしなき孤独、と目の前の仲間。
苦しみ、と悲しみ。
全曲のあと、テツラフは「フォー・オール・フレンズ・オブ・パリス」というような言葉とともに、ソナタ第二番のアンダンテをあらためてひいた。
終演後、後方のお客の声が聞こえた。
「そうだよね、テツラフだったらパリにたくさん友達がいそうだもんね」
うーん、そういう意味で言ったんじゃないと思います(笑)。
十一月十六日(月)ボンカレー
ベトナムで企業経営するセレブ・プレジデントと、某コピーライト関係法人で働くえげつないヤツと、サークルの同級三人で、毒婦高橋お伝、いやただのおでんを食べる。
フクイチの門前に昔は「アトミック寿司」という寿司屋があったとかなかったとか、なんかそんな愚にもつかない話を二時間。
ベトナム・セレブから沖縄みやげにいただいたのがボンカレー。懐かしい松山容子パッケージは、いま沖縄でしか販売されていない。沖縄人がこの味を別して好むため、特別に続けているのだそう。

水原弘と由美かおるのアースの看板と同じ、昭和のにおい。夏休みにどっかの海の家かなんかで「業務用ボンカレー」を食べて以来、三十年くらい食べてないので楽しみ。
十一月二十日(金)どうか全曲を

「レコード芸術」十二月号の特集は、「BOXセット大集合!」。ディスクと実店舗への愛に満ちた特集。
矢澤孝樹さん、片山杜秀さんなど、強力なディスコフィリアの末席を私も汚している。担当した一つが、ウィーン・フィルの「ニューイヤー・コンサート・コンプリート・ワークス」二十三枚組。

ウィーン・フィルが一九三九年大晦日以来のニューイヤー・コンサートで演奏した全三百十七曲を、すべて一九四一年から二〇一五年までのニューイヤー・コンサートのライヴ録音だけで重複なしに収録する(初期に演奏したのみで、録音のない十三曲はわざわざ新録音)というマニアックな企画ボックス。
ライヴの少ないボスコフスキーも、デッカではない六〇年代のORF音源が入ったりしている。何より驚いたのが、正規盤では初出の、一九五四年のクレメンス・クラウス最後のニューイヤー・コンサートのライヴが二曲入っていること。
このコンサート、ORFの保存音源には存在しないという話を聞いたことがある。ただ、全曲がプライヴェート・テープ業界(なんか矛盾した表現だが、やっぱり業界としかいいようがない)では流通したことがあり、そのテープから神戸の「らるご」(だったか)がLP化、さらにオーパス蔵もCD化している。
でも正規音源が残っているなら、その音で聴いてみたい。今回のセットはウィーン・フィルの保存音源も使ったというから、もしかしたらそこにあるのか? いい音だし、全曲のCD化を切望。
十一月二十二日(日)甘き死よ来たれ
昨日の土曜はオペラ講座「日本オペラ事始」の三回目、ここからは自分が担当して、まずは丸の内の帝国劇場の話。
一九一一(明治四十四)年開場のこれが「国立劇場」ではなかったのは、武士階級出身の為政者にそのような発想がなかったためだけれど、民間だからこそ可能になった部分もあった。というより、その主導者である渋沢栄一は、公営ではろくなものにならないという英米式の社会観の持ち主だったから、むしろそれこそが望むところだったろう。
民営と公営の最大の違いは、サービス意識。公営の日比谷公会堂と東京文化会館があれだけ殺風景だったからこそ、民営のサントリーホールが出来たときに、私などはその豪華なサービス、一流ホテルのようなサービスに驚いた。
それにはサントリーという企業が関西起源であることが関係していて、日生劇場も東宝もすべて関西起源であることと似ている。大阪はその点で進んでいて、東京文化会館の三年前にできたフェスティバルホールも、横にホテルがあった。
ところが、このホールとホテルを併設する大本は、じつは関東大震災前の東京にあって、すなわち帝劇と、十一年後に開場した東京会館の関係がそれ。これも本来はホテルにするはずだったが、芝居茶屋の大がかりなものになるのではというお上の杞憂から、宿泊施設にする許可がおりなかった。それでも、東京会館と地下通路でつなぐことにより、幕間や前後に豪華な食事とサービスを提供するという帝劇の構想が実現した。

東京会館(左)と帝国劇場(右) (都立中央図書館所蔵資料 https://www.library.metro.tokyo.jp/portals/0/tokyo/chapter1/22_042.html)
この構想はけっして日本独自のものではなく、もとにあるのはロンドンとシカゴのホテル併設型劇場、とくに前者の、サヴォイ劇場(一八八一)とサヴォイホテル(一八八九)。
最新鋭の設備をもつ劇場と超豪華ホテル(支配人がリッツで、総料理長がエスコフィエだった)の組合せを可能にしたのは、この劇場を本拠とするドイリーカート歌劇団、その専売特許のギルバート&サリヴァンのオペレッタの、圧倒的な人気だった。
とりわけ、ホテルを生むきっかけになっているのは、一八八五年の《ミカド》の大ヒット。ただしこの作品自体は、明治憲法下の日本ではとても上演できない代物。欧米のジャポニズムを考える上でも絶対に避けて通れないのに、いまも日本人が論じたがらない作品。
西洋化を懸命に押し進める近代日本、その象徴のような帝劇と東京会館の、その構想の元ネタを生んだのが、よりによって《ミカド》の劇団という、大いなる皮肉。
そこに近年のアメリカでの「イエローフェイス」問題による上演反対運動をからめると、「アジア人の自己嫌悪」という、鹿鳴館以来の古くて新しい問題がいぶり出されてくるかもしれない。
この問題から目をそむけたまま、いま西洋風の生活をして、西洋のオペラを見ているのは、何か無理がある気がして、ひとまずその原点をふり返ってみようと思っている講座。でもやはりこういう内容は、オペラ好きにはまるで人気がないようだ(笑)。
講座のあと、NHKホールでNHK交響楽団。チョ・ソンジンのショパンについてはここではおいて、後半のフェドセーエフのロシア・プロが、圧倒的に面白かった。
特に《一八一二年》。オーケストラは十八世紀後半に軍楽隊の楽器、金管や打楽器を導入して、壮大さと華麗さを激増させた。つまり近代交響楽は、国民国家の「暴力装置」との関連がいやがおうにも深い。その象徴のような曲。
パリのテロ事件を受けて、数日前に共感と連帯の象徴としてあちこちで歌われた《ラ・マルセイエーズ》が、ここでは敵の侵略の象徴として響く、偶然の相対化の玄妙さ。壮烈なラストではケン・ラッセルの映画『恋人たちの曲』の、あの《一八一二年》の場面が頭の中でオーバーラップ。
そして今日。サントリーホールでノット指揮東京交響楽団。
開場と同時に演奏が始まった、リゲティの《ポエム・サンフォニック》。百台の振り子式メトロノームがさまざまな速度に設定され、騒々しく響いている。しかし、ゼンマイが切れて動かなくなるメトロノームが増え、徐々に音が減っていくうちに、ベルが鳴らずにホールの扉がしまり、オーケストラと指揮者が静かに配置に着き、全停止を待つ。
四台、三台、しだいに音がさびしく単調になっていき、やがて下手に一台だけ残ったが、ついにそれも止む。
一瞬の死の静寂。オーケストラが起動し、ストコフスキー編曲のバッハの《甘き死よ来たれ》が甘美に奏でられる。
これを聴きながら、昨日といい今日といい、二つの演奏会とも「いま」となんと見事にシンクロしてしまったのだろうと思う。曲目が構成された時点では、いちばんシンクロしているのはショパン・コンクール優勝者の登場のはずだったのに、それさえ霞んでしまった。
《甘き死よ来たれ》。まさに偶然の追悼の音楽。舞台上の百台のメトロノームが、ろうそくの祭壇のように見える……などと考えていたら、ホールの扉が一斉に開いて、アサルトライフルをもったテロリストが立つ幻影が、脳内に浮かんでしまって困る。
――どうしたらいいか、とりあえずは伏せて、椅子の下にもぐり込むしかないが、その姿勢のまま射殺されるかな、などと妄想する。
続いて、R・シュトラウスの《ブルレスケ》。安らかに眠って最後の審判を待つ敬虔なキリスト教徒の墓の上で踊る、馬鹿者どもの黒い影。ノットは、本当はマーラーの交響曲第九番のロンド・ブルレスケ楽章みたいなものがやりたいのだろうが、楽章だけ抜くよりはこの方がまとまりがあるという判断か。
休憩があって後半は、ショスタコーヴィチの交響曲第十五番。
昨日、《一八一二年》を聴きながら、この曲くらい大衆を興奮させる、つまりアメリカ人が喜びそうな曲って、《ウィリアム・テル》序曲くらいだよなとか考えていたところだったのに、それが第一楽章で聞こえる快感(笑)。審判のラッパみたいなファンファーレも鳴る。第二楽章は葬送行進曲。終楽章では《神々の黄昏》と《トリスタン》、キリスト教の神のいない世界からの愛と死の音楽が響いて、そして、弦の持続音にのる打楽器が一つまた一つと次第に減っていき、チェレスタの一つの音で終る。
大きな輪っか。永劫回帰みたいな。
とても面白いプログラムだったが、一つだけ困ったのは、後ろの爺さんの規則正しい安らかな寝息。《ブルレスケ》のときには「安らかに眠って最後の審判を待つ敬虔なキリスト教徒」のイメージを与えてくれたからまだしもだが、ショスタコーヴィチのラストにも、やはり見事にシンクロして聞こえてきた。こんなのは永劫回帰しなくてもいいのに。
しかも爺さん、終演後にはショスタコーヴィチの曲の印象を、語る語る。「でもあんた寝てたじゃん」とワキから言いたくなったが、グッと我慢。
たしかに眠りは死ではない。終りに言葉があった。
この語りを聞いたあと、隣席の知人に「ああいう話が聞こえてくるってのも楽しいスね」と言ったら、「でも内容が何の役にもたたないよ」とボソッと言ったのが、ものすごく面白かった。
十一月二十四日(火)夜明けの夢

雑誌も放送も、仕事はそろそろ年末年始モード。毎年恒例の元旦の東京MXの正月クラシック番組、近年は監修のみだったが、来年は四年ぶりに顔出し。
というわけで今日は、首都圏某所にてその収録。MXの正月クラシック番組始まって以来の広いステージ。自社制作で出演者多数。収録時間の長さも画期的だったが(笑)。写真右に小さく見える美人女子アナの隣に九時間も座っていた。役得。
帰宅して深夜。正確には翌日未明。長時間の収録というのはアドレナリンが出てしまい、帰宅しても興奮状態でぜんぜん疲れを感じない。そしてポストをあけると、クナッパーツブッシュの《ローエングリン》が届いていた。
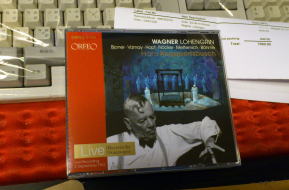
日本のサイトより割高(四千五百四十+四百二十)だが、一週間ほど早く入手できそうだったので、堪えきれず注文。こういうのは往々にして、入荷がおくれてしまって猿知恵に終るのだが、今回は三日遅れくらいでちゃんときた。
みなさん、確かに出ましたぜ。今から聴こうか聴くまいか、それが問題。
そして堪えきれず、第一幕を聴いてしまう いやもう、お腹一杯胸一杯。
一言でいって、こんな「大きな大きなローエングリン」は聴いたことがない。
音は、第一幕に関しては、一九六〇年前後のクナのオペラのモノのライヴを聴いている人ならまったく問題ない(ごく一部、気になる時間帯があるが)。音源は放送局ではなく、バイエルン国立歌劇場のアーカイヴと書いてある。
第一幕は六十二分三十九秒、クナとしては予想したより短い演奏時間だが、そこになんとたくさんのものがつまっていること! 前奏曲だけで幸福感で一杯になるのに、まだその先がある幸せ。
第一幕の歌手では、エルザ役のイングリット・ビョーナーがとりわけ素晴らしい。クナの長い呼吸線のとてつもない波動に、完璧についていっている。録音に恵まれているとはいえない彼女の、嬉しいドキュメント。一九八三年にミュンヘンに行ったとき、この人のイゾルデを聴いて、録音がなくともこんなにいい歌手がいるんだ、と感じたのを思い出した。
三十余年前、フラグスタートとクナ&ウィーン・フィルの「エルザの夢」を聴いて、たった六分間の中に、凡百の指揮者の楽劇一本分以上の「ワーグナーの音楽」を込めてみせた指揮者に驚嘆して、「この人の《ローエングリン》全曲が聴きたい!」と願って以来、ついにかなった私の夢。
いよいよヴァルナイが出てくる第二幕は、明日、目が覚めてから聴こう。
目覚めたらCDが消えてなくなってるなんてこと、ねえだろうなぁ、おい…。やっぱり今のうちに聴いといた方が…。いやいや(笑)。
十一月二十五日(水)マリナーの矛盾
サントリーホールでマリナー指揮NHK交響楽団。
一九二四年生れ、九十一歳なのに足腰もしっかりしていて、驚異的に元気。
しかし、二十世紀で時計の止まった音楽家。ブラームスの交響曲第四番を、十六型の大ホール向け音楽としてガンガン鳴らす。一方でスタイルは、一九七〇年代風の新古典主義の端整なもの。その不思議な矛盾。
十一月二十九日(日)オケの旬
二十六、二十七、二十九と三日間にわたり、オッコ・カム指揮ラハティ交響楽団のシベリウス交響曲チクルスをオペラシティで聴く。
ラハティ響は前任のオスモ・ヴァンスカのもとで驚異的な水準に達していた。私も二〇〇六年の来日公演でラウタヴァーラの交響曲などを聴いて、異様なまでに澄みきって倍音の美しい、芳醇な弦と管の響きに圧倒されたことがある。
カムになって、残念ながらあの精緻をきわめた響きは、かなり失われてしまった。よくいえばおおらか、悪くいえば大まか。とりわけ金管が粗っぽいので一、二、五番のような曲が苦しい。弦主体の他の四曲には往時の片鱗があった。
オーケストラにも旬というものがあるのだろう。いまはリントゥとフィンランド放響か。
十二月二日(水)ゲルギエフの変容
サントリーホールで、ゲルギエフ指揮ミュンヘン・フィルの来日公演。
九月に首席指揮者に就任したばかり、多忙な指揮者ゆえに練習時間もごく限られていたと聞くが、予想はいい方向に裏切られた。日経新聞の評を担当しているので、詳細はそちらで。
十二月四日(金)時は過ぎて
サントリーホールで、ヴァンスカ指揮読響演奏会。シベリウスの交響曲第五~七番の三曲。
カム&ラハティ交響楽団とは大きく異なる、精妙な演奏。日本でヴァンスカはラハティ響を聴きに行ったそうだし、楽員も合間の二十八日の読響演奏会(交響曲第一番など)に行ったらしいが、お互いどんな感想を抱いているのだろう。
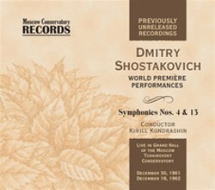
タワーレコードから届いたCD。コンドラシン指揮によるショスタコーヴィチの交響曲第四番と第十三番の世界初演ライヴ。一九六一年と六二年、「雪解け」とその終りが見えた時期に実現した、歴史的意義の大きい演奏会の記録。
第四番は初登場、第十三番は別レーベルからも同年の録音が出ているが、あちらは初演二日後の十二月二十日の録音という表記。こちらは十八日当日という表記で、「未発表録音」と書いてある。
第十三番ははたして本当に別録音か、それとも同じ録音か。ここはショスタコーヴィチ専門家に確認してほしい。このモスクワ音楽院レーベルは、たしかに秘蔵の未発表音源をこれまでにもぽんぽん世に出しているので、本当に初日という可能性もありそうだが。
ところでやっと来たと思ったら、今タワーレコードのサイトは「販売終了」。「二〇一五年十一月一日時点で現地在庫が完売したため、ご予約枚数が弊社初回入荷数に達し次第、販売を終了させていただきます。ご了承くだいませ」と書いてある。日本のタコスキーが爆買いしたということか。
やったぜ「買い逃げ」。
「得々と書いて、自慢ですか?」
はい自慢です(笑)。
マニアとしては卑しい優越感を刺激される事態。ミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」で放送するので、リスナーへのサービスにはなる。
十二月五日(土)浅草から丸の内へ
「浅草から丸の内へ」
これは、昭和前半の時代の芸人たちにとっての、社会的成功を意味する言葉だった。エノケンから渥美清、萩本欣一あたりまで。浅草の松竹系の劇場群とストリップ小屋から、丸の内と有楽街にアミューズメントセンターを築く東宝の、とりわけ日劇へと。それは同時に、映画への進出も意味していた。ブルーカラーから中間層への、ファンの格上げ。地域から全国区への進出。
今日、早大エクステンションセンターのオペラ講座で取りあげた藤原義江もまた、「浅草から丸の内へ」を成功の証しとしたオペラ歌手だった。
浅草オペラにもぐり込んだ日本館をふりだしに、ヨーロッパとアメリカを経由して、日比谷公会堂での藤原歌劇団旗揚げへ。そして戦後の五年間、東宝と組んでの、丸の内の帝国劇場での連日のオペラ公演。かれの後継者たちも、東京文化会館、オーチャード、新国立劇場など、「檜舞台」での活動を維持している。
一方、明白に藤原以上の素質と音楽性をもちながら、大風呂敷をひろげることなく、精神的に「浅草」を生涯離れることのなかった、田谷力三。この二人を主人公とする日本オペラ史、のつもり。
時期が不思議に重なって、一週間ほどのちには『帝都クラシック探訪』の「銀座・丸の内篇」の取材をやる。
この地域の西洋化を急激化させる端緒となった、旧新橋駅舎(それは横浜へ、外国人居留地の劇場ゲーテ座へ、そして横浜港をへて、世界への玄関となっていた)から歩き始めて、銀座、築地、丸の内、日比谷へと歩いてまわる、近代音楽史の旅。片山杜秀さんにおつきあいいただけるので、いったいどんな濃い話になるか(笑)、いまから楽しみ。
もうコースの下見は終っている。普通にただ歩いて一時間、しゃべりながらで二~三時間の、これまでの『帝都クラシック探訪』と同じくらいの距離。東京会館が跡形もない更地になっているのは驚いたが、日比谷公会堂が無期限の長期閉館にならないうちには間に合った。
そしてその前に、約四十年ぶりに犬山の明治村を一人で見に行くつもり。どうしても取材の前に、ライトがつくった旧帝国ホテルの建物を、もう一度見ておきたくなった。お掘端は帝劇も東京会館も鹿鳴館(華族会館)も、昔のままの建物ではない。取材のとき、せめて帝国ホテルだけは昔の玄関を頭に入れて、夢想できるように。さらにその玄関の背後にあった素敵なホール、(ハイフェッツも演奏した)帝国ホテル演芸場を、夢想できるように。明治村が四十年前と、どう変っているのかも楽しみ。
そしてこれらが終ったら、「演奏史譚一九五四/五五」の残り数話を、年内に全力で仕上げる。
と、うまくいったら、いいなあ!
十二月六日(日)私の愛は純粋の愛だ
アーノンクール引退のニュース。予定されていた公演活動をあきらめての引退とのことだから、さぞかし無念だろう。
気になるのは、進行中と伝えられるウィーン・コンツェントゥス・ムジクスとのベートーヴェンの交響曲全集の録音。
収録は全部終っているのだろうか? モダン楽器による折衷的なピリオド・スタイルがベートーヴェン演奏のスタンダードになりつつある(アーノンクール自身もヨーロッパ室内管との録音で先鞭をつけた)現代において、あえて逆行するようにピリオド楽器でやるという挑戦がどのようものになるのか、とても興味があった。完成していてほしいもの。
午後はNHKホールで、デュトワ指揮NHK交響楽団による《サロメ》演奏会形式上演。
昨年のあの《ペレアスとメリザンド》に続いての素晴らしい演奏。歌手もオーケストラも。
ヒロインのバークミンは、ルイーズ・ブルックスそっくりの髪形とメークで、「ファム・ファタール」を体現。七つのヴェールの踊りが終ったところでショールを落として肩を出す。ヘロデ役のキム・ベグリーも、黒い燕尾服姿なのに焦燥する場面で蝶ネクタイを外して襟をくつろげてみたりと、向うの歌手は演奏会形式でも、衣服や細かな演技で役と場面を暗示するのが上手い。
コンサートホールならではの魅力を味わえたのは、完全にサロメが堕落したラストに至って、上手上方のパイプオルガンが二回、ホールの空気を重く震わせたこと。作曲家はただ重低音の響きを求めたに過ぎないのかもしれないが、人間の堕落と神の楽器パイプオルガンという、コントラストの効果が凄かった。通常の歌劇場では難しい効果。
オルガンの操作盤はステージ上に移されて、他の楽器に混じっていた。その意味では「重低音を補強する楽器」というだけの扱い。でも、パーヴォの《復活》コーダで感じたオルガンの、他から遠い距離感が、ここでは不思議な説得力をもってしまう面白さ。その重さと暗さが、悪魔的なものではないのかもしれないという、不思議な説得力(ついでにいうと今回、ハルモニウムの方は指揮者の希望により未使用とのこと)。
そういえば、装置も衣裳もないせいだろう、音楽と歌詞だけで暗示される、この世のどこかにいて、次第に近づきつつあるイエスの存在を、舞台上演よりもいっそう強く、そして暖かい光のように感じることができたのも、思わぬ余得で面白かった。
なるほど、この作品はこうなると、クリスマス前に主の降誕を待つ、アドベントのこの時期にやるのに、まさにふさわしい作品になるのだと納得。
イエスといえば、たまたま山折哲雄の「悪と往生 親鸞を裏切る『歎異抄』」を読みかえしているところだった。
親鸞の奥深く、苦渋に満ちた思想を、『歎異抄』の著者唯円は矮小化してしまっていて、結果的にユダ同様に師を裏切っているのではないかと考察する本(もちろん、唯円が親鸞を物理的に殺したわけではないことを、著者は百も承知の上で書いている)。
唯円とユダ。その関係を著者が考えるきっかけは、太宰治がイエスを売るユダを主人公にして書いた、短編『駈込み訴え』。自分ほど師を深く愛し、理解している人間はいない――その思いが、師を裏切る動機になる。
「私があの人を売ってやる。つらい立場だ。誰がこの私のひたむきの愛の行為を、正当に理解してくれることか。いや、誰に理解されなくてもいいのだ。私の愛は純粋の愛だ。人に理解してもらう為の愛では無い。そんなさもしい愛では無いのだ。私は永遠に、人の憎しみを買うだろう。けれども、この純粋の愛の貪慾のまえには、どんな刑罰も、どんな地獄の業火も問題でない。私は私の生き方を生き抜く」(太宰治『駈込み訴え』)
ヨカナーンへの愛を歌うサロメの最後のモノローグを聞きながら、太宰版ユダのイエスへの愛を想う、アドベント第二主日の日曜日。
十二月八日(火)ブユかブヨかブトか
テレビでノーベル賞の大村さんの番組をやっていた。そこで気になったのが、寄生虫を媒介する「ブユ」なるもの。
ブヨなら知っているが、ブユなんて聞いたことがない。そこでウィキペディアをみたら、こう書いてあった。
「ブユ(蚋、蟆子、Black fly)は、ハエ目(双翅目)カ亜目ブユ科(Simuliidae)に属する昆虫の総称。ヒトなどの哺乳類から吸血する衛生害虫である。関東ではブヨ、関西ではブトとも呼ばれる」
正式にはブユ。驚いたが、しかし、フェイスブックの友達からのコメントを見るかぎり、ブヨもただの関東方言ではなさそうだ。
具体的には、ブヨ六(自分も含む)、ブユ二、ブト二で、ブヨが六割。
ブヨと呼ぶのは北海道、福島、東京、長野、阪神、広島の出身者。ブユはどちらも関東育ち。ブトは鳥取と岡山。
十しかサンプルがないのを承知で強引に結論づけると、学術的にはブユだが、割合としては少数派。ブヨは、北海道から関西まで、広い範囲で使われている。ブトは中国地方だが、広島はブヨ。
少なくとも、「関東ではブヨ、関西ではブトとも呼ばれる」というのは、正確ではない模様。
夜は、トッパンホールでシュタイアーのリサイタル。シューベルトの即興曲二曲で始まってシューマンの幻想小曲集、後半は再びシューベルトの《楽興の時》三曲、そしてブラームスの作品百十八の六つの小品。
タカギクラヴィア所有の一八八七年製ニューヨーク・スタインウェイ。機構が現代と具体的にはどのように異なるのかよくわからないが、響きはかなりフォルテピアノ的で、心地よい。
フォルテピアノの音を嫌う人は日本に多いけれど、もともとコンサートグランドの剛性の高い音に愛着を持てなかった自分には、やわらかくて微妙な変化に富んだ、こうした響きの方が合う。
音量的にもトッパンホールではこれで充分。ブラームスの作品は、この楽器とほぼ同時代。もったいぶらず、率直だが音楽性豊かな演奏を満喫。
十二月十日(木) 犬山明治村散歩
日帰り旅行で明治村。JR東海ツアーズの「日帰り1day明治村」一万七千三百円。
通常だと新幹線のぞみ往復二万七百二十円、名古屋~犬山の名鉄往復千百円、犬山~明治村のバス往復八百四十円、明治村入場料千七百円、村内バス五百円、計二万四千八百六十円の約三割引。ただし出発は固定されていて、品川六時ちょうど発ののぞみ九十九号。
名古屋には七時二十八分到着予定だったが、新富士~静岡間で点検車両が脱輪とのことで遅延、七時五十四分着。同じホームから複数の行先の路線が出る名鉄独特の方式にとまどいつつ、名鉄名古屋駅八時十六分発の急行で犬山に四十九分着。明治村行きのバスが九時三十六分発なので、犬山駅のロッテリアで朝食。駅にはコンビニとロッテリアと、ベーカリーカフェがあるだけで、駅前も何もなし。バスは約二十五分で明治村の南口正門到着。十時開村なのでちょうどよい頃合。
明治村は広く、五区にわかれている。お目当ての帝国ホテルの旧館中央玄関は一番北奥の五区。曇りで夕方からは雨の予報なので、一番先に見ることにして村内バスに乗って五区へ。

一九二三(大正十五)年、関東大震災の当日に開場したライト設計の帝国ホテル。一九六七年に建替えのため解体。中央玄関とロビー部分が一九七六年に明治村に移築保存されている。
むかし、自分が祖父に連れられて来たのは、この帝国ホテルが見たかったからだった。小学六年だと思っていたが、七六年なら中学一、二年のときということになる。いい加減な記憶。そんなに混んでいなかったから、春休みの平日だったと思うが。
それ以来の明治村。三十九年ぶり。さすがに少し黒ずんでいるように見える。厳密にいえば大正の建物だが、日本を代表する名建築として多くの人から愛されていたために、明治村に移築されたときには大きな話題になった。子供の自分もそれを聞いていきたくなったのだった。


中央玄関だけとはいってもかなりの大きさ。

帝国ホテル内部。内外装に今はなき大谷石をふんだんに用いている。インカの神殿風の独特のつくり。大谷石を刻んだ装飾や照明。左下の部分がホテルのフロント。その上が今はカフェになっているが、十二月は平日休みで残念。それにしても天井が意外に低いことに驚く。全体に、いかにも西洋風の威圧感、豪華さがないのが、旧帝劇などと大きく異なる。その、猿真似でない独自性が愛された理由だろう。
写真の正面奥の一階には、日露戦争後のポーツマス講和条約調印に使われた長テーブルがおかれている。


中央玄関を進んだ奥。一階のカーテンの向うには大食堂があった。二階の写真はもちろんライト。大食堂のさらに奥には、八百席の豪華ホール、演芸場などのビルがあった。

このロビー空間の魅力、なんともいえず和む感じは、威圧的な垂直の壁面がないことだろう。どの場所も閉鎖的に四角く区画されることなく、横に少しずつずらして、次の空間へ流れるようにつながっていく。高低も滝のように長い直線の階段を使わず、大小の池がわずかな段差でつなげられていくようなつくり。連想したのは和室の違い棚。互い違いになることで、流れる雲のようにやわらかい流動感が、不思議な親密さと落ち着きをもって生じている。大谷石を使用した以外はさっぱり和風ではないのに、たしかに日本のホテル。
傑作として愛される理由がよくわかるし、玄関だけとはいえこれだけの大きさで保存されていることは、本当に素晴らしい。

二階の右側回廊から、正面のカフェを眺める。天井の低さがよくわかる。しかし周囲に空間が開けていて明るいので、圧迫感でなくて親密さに感じられるのが奇跡的。


往時同様に再現された正面の池から。右側に人がいるので大きさがわかる。大谷石を使用したことは建物を軽くするためにも大きな効果があり、日比谷の軟弱地盤(江戸初期まで海だった)の上に、あまり大がかりな杭打ちをせずに、舟のように各ブロックを浮かべる方式だった。しかしそれゆえに歳月の経過とともに地盤沈下にばらつきが出て廊下に段差が生じ、さらに多孔質の大谷石による雨漏りで傷みが激しく、建替えしかなくなったのだとか。

皇居にあった内閣文庫(中央図書館)。帝国ホテルより雰囲気がよほど「帝国っぽい」のは、さすがに明治政府の官の建物。とはいえ一階と二階の外壁の模様が異なっていたり、じつはけっこう洒落者。

帝国ホテル前から明治村第五区を眺める。左から聖ザビエル天主堂、菊の世酒蔵、金沢監獄中央看守所。とにかくデカイ建物たちを移築して補修、維持していることが素晴らしい。

金沢監獄の模型。右側の「木」の字のようなヒトデ型の建物が監房。中央で監視して、放射状に独房が伸びている。家の近くにあった市ヶ谷監獄や東京監獄も、同様の構造だった。

金沢監獄の中央看守所(左)と、監房(右)。監房は短縮して、五本のうち一本だけ残してある。
 金沢監獄の独房内
金沢監獄の独房内
右が金沢監獄の中央看守所。手前中央の赤レンガは東京駅警備巡査派出所。

金沢監獄の正門。東京監獄もこんな感じだったのだろうか。

どっかの高校生たちが監獄の門をくぐるところ。正面奥は聖ザビエル天主堂。上は教会、下は監獄の妙。

聖ザビエル天主堂越しに入鹿の池を望む。天主堂は一八九〇(明治二十三)年落成、京都市中京区河原町三條にあったカトリック教会。

天主堂の内部。右は正面にあった薔薇窓。
 天主堂内陣。ここはいまでも教会の機能を持ち、結婚式もできるらしい。
天主堂内陣。ここはいまでも教会の機能を持ち、結婚式もできるらしい。
天主堂の内部。立派。

中央は大阪府池田市にあった劇場、呉服座(くれはざ)。一八九二(明治二十五)年落成。

呉服座の内部。回り舞台や奈落を持つ本格的な劇場建築。右側が下桟敷(うづら)、その左が高土間、その左が仮花道で、中央が平土間。桟敷席は二階建てで、下桟敷の上には上桟敷がある。

呉服座の内部(二)。この写真だと平土間が舞台に向かって斜めに掘られていて、傾斜をつけることで後方でも見やすくなっていることがよくわかる。その手前は「追込」という席。畳のヘリで前後三列にわかれる。

呉服座の内部(三)

一九〇九(明治四十二)年の宇治山田郵便局舎。ハイカラ。

郵便局の内部。歴代のポストがずらり。

名古屋城二の丸にあった歩兵第六聯隊兵舎の内部。寝床がとにかく短い。百六十センチ弱くらいしかない感じ。


目黒の西郷山にあった西郷從道邸。和風の本館とは別に建てられた、接客用の洋館。内部は完全な洋式。


京都市下京区河原町通五條にあった聖ヨハネ教会堂。一九〇七年落成のプロテスタント教会。先の聖ザビエル天主堂とは対照的な雰囲気。


幸田露伴住宅「蝸牛庵」。明治初年に東向島に建てられた。今市子のマンガ『百鬼夜行抄』の主人公の家のモデル。

焼津にあった西園寺公望別邸「坐漁荘」。一九二〇年落成。江戸東京たてもの園の高橋是清邸と同様の、高級旅館のような豪邸。こんなのが明治村にはゴロゴロ、六十八もある。
写真は撮り忘れたが、金沢にあった第四高等学校物理化学教室というのも外見は面白みがないが、内部は階段教室があったり、廊下の雰囲気がいい建物だった。一九六五年(今年はちょうど開村五十周年)に明治村をつくる契機となった、東京工業大学教授で建築家の谷口吉郎と、名古屋鉄道株式会社会長の土川元夫はここで机をならべて勉強したそうで、それを記念して二人のレリーフが向かいあわせてこの教室に飾ってある。友情のありがたさ。

ひととおり見終えたので、二時半のバスで犬山駅へ。まだ時間があるので、明治村とは反対の犬山駅の東北にある犬山城へ向かってみる。徒歩二十分くらい。

犬山城の大手へ向かう道には大正~昭和初期の商家の建物がならんでいて、明治村とはまた別のいい感じ。犬山城は山の上なのでまたの機会に。しかし南から行くと犬山城までまっ平なのに、城の東西は崖のような急斜面になり、北へ張りだした岬のようになっている。城にぴったりの地形。
犬山駅にもどり、四時七分の名鉄特急で名古屋駅へ。夕飯を食ったりしてから、五時四十二分ののぞみで帰京。七時二十三分東京着。おつかれ。
さて明治村、名古屋からでも片道一時間強、中もだだっ広くて意外に高低差のある場所だが、大人になってから一度は見ても損しないだろう。中高生のときに来たきり、という人も少なくないようだが、家の周囲と学校の建物しか知らない子供よりも、さまざまな現代の建物を利用したり訪れたりしている大人の方が、建物のそこかしこに人間の姿、境遇(聖職者から囚人まで)を思い浮かべられるから、それぞれの建物の価値と個性を楽しめると思った。
十二月十一日(金)デュトワ
NHKホールで、デュトワ指揮N響のマーラーの交響曲第三番。美麗な響き。金管をはじめ、楽員の真摯で献身的な演奏が今日も素晴らしい。
十二月十二日(土)放談とサイン
ミュージックバード、ザ・クラシック年末恒例の特番「年末クラシック放談二〇一五~クラシック再稼働!」、今年も片山杜秀さん、田中美登里さんと、楽しく収録。
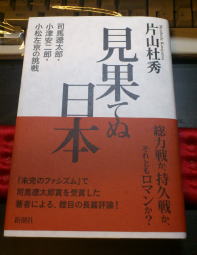
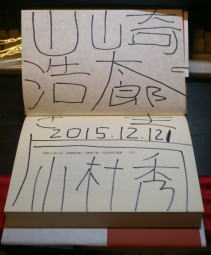
写真は、片山さんの新著『見果てぬ日本』(新潮社)と、いただいたご署名。一昨日みた帝国ホテルのインカ風デザインに、一脈通じるものあり。
小松左京、司馬遼太郎、小津安二郎を題材にした評論集。とりわけ、半分近くを占める司馬遼太郎論が楽しみ。
十二月十四日(月)夢の中で
各方面の仕事が一段落して、たまっていた郵便物をあける。
そのなかに、ソニーからきたサンプルCD‐R。アーノンクール指揮のベートーヴェンの四、五番。
担当の古澤さんによる、いつもながらに心のこもった案内文によれば、これがアーノンクールの「ラスト・レコーディング」とのこと。予定されていた残りの七曲の演奏と録音はキャンセル。
ベートーヴェンの交響曲全集再録音、ピリオド楽器ではアーノンクール初の全集は、二曲のみで幻に。
なぜか、プロ野球選手の大杉勝男の引退の言葉を思い出す。
「あと一本と迫っておりました両リーグ二百号本塁打、この一本をファンの皆様の夢の中で打たして頂きますれば、これにすぐる喜びはございません」
国内先行発売で、来年二月三日リリースとのこと。
夜はある演奏会に出かけたが、満員で座る席が見つからず、開演前に早退け。今年はこれが二回め。自由席の演奏会は難しい。早く行けばよいだけなのだが。
十二月十五日(火)ア・ラ・ロッシーニ
サントリーホールで、ミンコフスキ指揮東京都交響楽団。
ルーセルもよかったが、やはりブルックナーの交響曲第〇番ことブルヌルが、素晴らしいききもの。各声部が息づくように歌いながら、透明度の高い綾をやわらかく織りなしていく美しさ。
そして予想通り、この作品にある不思議なロッシーニ的要素を、ミンコフスキは満喫させてくれた。去年の十月に同じサントリーホールでスクロヴァチェフスキと読響がこの曲を演奏したとき、いかにもスクロヴァらしい剛直な響きのなかから、スケルツォや終楽章の主題が、ロッシーニのオペラ・ブッファの旋律と音型そのものみたいに響いてきたのに驚かされた。
ロッシーニ直接でなくとも、その影響を受けたドイツ音楽、ウィーン音楽がブルヌルに流れ込んでいて、それがブルックナー固有の響きと混じり合っている。作曲者が「無価値」としたのはこの「ア・ラ・ロッシーニ」に、自分で戸惑ってしまったからではないかと自分は思っているが、もしそうだとすると、ブルックナーは「ウィーンの作曲家」として、シューベルトと同じような戸惑いを抱えていることになる。
ロッシーニ歌劇がウィーンを席巻するのを目の当たりにして反発し、ドイツ歌劇、ドイツ人のための歌劇を《フィエラブラス》などで模索しながら、一方でその交響曲、特にその初期の交響曲にロッシーニ的要素が入り込んでいたシューベルト。
むかしのドイツ音楽絶対史観は、こうした非ドイツ的要素を青筋たてて否定してきたわけだが、ヨーロッパという全体の中でそうした交流や影響があるのは、不思議でもなんでもない。
ミンコフスキのブルヌルは、その意味でシューベルト直系。それも、ブッファ部分が浮き上がるのではなくて全体がロッシーニのオペラ・セリアみたいな、言葉のないオペラ・セリアみたいな、劇的交響曲。これだけ緩急強弱を自在につけても響きの骨格がしっかりしている点、たしかに交響曲。面白かった。
それにしても、ブルックナーの交響曲は、第三番からワーグナーの引用を削除するまでは、習作ではないが習作的な、自己を確立する前という意味合いが強いのだろう。ヴェンツァーゴがあの痛快な全集録音で、二番までの三曲に室内管弦楽団を用いたのも、その点を強調したかったからだろう。
第〇番は、着手したのがいつかはともかくとして、ウィーンに移って最初に完成した交響曲であるというのは、さまざまな可能性を想像させてくれる。「音楽の都」ウィーンで流行っていた多国籍の要素が入り込むことは、大いにありえるだろう。
視点をずらしてみることで新たな景色が見える、ピリオド系の指揮者はとりわけ、その奥深い面白さを教えてくれる。
ただ、終った瞬間に響いた、なんとも下品な「ぶらぁぁぁゔぉ」は、どこかの温泉地の歌劇場みたいで、これは残念だった。
十二月十六日(水)オレオレゆずりあい
サントリーホールでデュトワ&N響。コダーイのガランタ、バルトークのマンダリン、サン=サーンスのオルガンつきという、ハンガリー&フランス・プロ。バルトークの血腥さ、サン=サーンスの豪放華麗、N響が真剣な大熱演で、色彩豊かに大盛りあがり。
《オルガンつき》では、コンサートホールのオルガンは向う正面から轟々と響いてこそ、という醍醐味を味合わせてくれた。《サロメ》のあの不思議な響きとの好対照にもなっている面白さ。
それにしても昨年の《ペレアスとメリザンド》といい、今のデュトワとN響の関係は本当に特別なもの。今回も三プロとも素晴らしい演奏で、第九前の十二月前半、アドベントの時期恒例の、大きな楽しみになっている。
ところで、これは昨日に限ったことではないが、終演後の拍手の中で、指揮者が特定の奏者を立たせることがあるが、ああいうとき、「オレ?オレ? 君でしょ? やっぱりオレ? みんなも立とうよ、え、立たないの? じゃあ、しょうがないね」みたいな動き、「オレオレゆずりあい」みたいなのが必ずあるのは、日本のオケの特徴なのだろうか。
外来のオケはああいうとき、指された奏者がためらいなく、誇らしげに立つ気がする。一流指揮者なら職業柄、ああいうときの目線と手ぶりも恐ろしく的確なはずで、誰を指しているかわかりにくいなんてこと絶対にないと思うが、それでも照れてゆずりあう。美徳といえば美徳か。
これはまったく別のオーケストラの話だが、初めて客演した指揮者が指しているのとまるで違う楽員が次々と立ってしまい(二階LC席からでも、指示と違うのが明確にわかった)、指揮者があきらめて全員立たせて、ふり返った瞬間に首をかしげて苦笑いしたことがあった。
本番でアンサンブルがイマイチだった原因はこれかと、あの時は妙に納得できたが(笑)。
十二月十七日(木)ペトリ
ハクジュホールで、ミカラ・ペトリのリコーダーと西山まりえのチェンバロのリサイタル。闊達。しかし都合で前半しか聴けなかったのが残念。
十二月十八日(金)いざ、ピリオド

四日前に触れた、アーノンクール最後の新録音のCD‐Rをようやく聴く。コンツェントゥス・ムジクスとのベートーヴェンの交響曲第四番と第五番。
特に第五番はやりたい放題、猛烈に面白い。バ・ロックなベートーヴェン。そして、ピリオド楽器でなければ不可能なベートーヴェン。これを聴いて、ベルリン・フィルとのシューベルトの録音は、やはりオーケストラが鳴りすぎていたことが、モダン楽器では強すぎたことが、よくわかる。
かつての、ヨーロッパ室内管との全集録音ともまるで異なるもの。はるかに表情が多彩で、戯れの度も深まっている。こういう音楽を、気のおけない、信頼できる仲間たちに、思う存分に演奏してもらえることは、ものすごく幸せなことなのではないか。
もちろん、今回聴いてみても、ベートーヴェンの音楽はピリオド楽器の、同時代の楽器の限界を超えてしまっている部分が多々あって、それはモダン楽器の剛性に委ねるしかないということも、あらためて感じる。
そういう意味では欠点の多い演奏。でも、だからこそ、ベートーヴェンの思いにより肉薄していると、私は思った。それは、六月に紀尾井ホールでアファナシエフのひく《悲愴》ソナタを聴いたときに思ったことの、裏返し。それについて自分は、七月三日の可変日記に、次のように書いた。
ただ一方で面白かったのは、《悲愴》ソナタとは完全に当時のフォルテピアノのあの音響と機構のためにつくられた作品で、モダンピアノでは間尺があわないという思いを痛感したこと。
短く細かい音の連続はいかにもフォルテピアノの音(というより、その限界にいらついて書きまくった感じ)だし、その限られた音の強さと音量と音階の枠をぶちやぶろうとする、ほんとうに楽器が壊れてしまいそうなスリルが生じてはじめて、ベートーヴェンがこの作品に込めた狂気じみたパッションが音として現代に甦えるように、思えてならなかった。
自分がこの作品がどうも苦手だったのは、剛性の高いモダンピアノでは表現しきれない部分への、その違和感のせいだったのかもしれない。
ここに書いた、「ほんとうに楽器が壊れてしまいそうなスリルが生じてはじめて、ベートーヴェンがこの作品に込めた狂気じみたパッションが音として現代に甦える」、これ。
アーノンクールがいわゆる「運命」交響曲で、折衷スタイル(モダン楽器によるピリオド奏法)のベートーヴェン全盛期のいま、あえてピリオド楽器でやろうとしたことは、これに近いものなのではないかと思う。
怒り。身の置きどころのない、怒り。叫び。
楽器の限界への。人間の限界への。人類の限界への。
神の…。
アーノンクールは前世紀までは、モーツァルトの三大交響曲の録音でも、モダン楽器のオーケストラを選んでいた。しかしそれをピリオド楽器で再録音し、ついにベートーヴェンもやり始めた。
ピリオド楽器奏者の水準が上がって、モダンに劣らない技術と音楽性の持ち主(アーノンクールの子や孫のような年代の…)だけで、オーケストラを編成できるようになったからではないかと思う。それでこそ、思いきったアプローチもとれるようになって、「限界に挑むこと」それ自体が、いまなら芸術表現になりうると思ったのではないか。
だからこれは、まさしく現在進行形のベートーヴェン。
この全集が二曲のみで未完に終ったことを、本当に残念に思う。これを完成させなかったのは、取りあげたのは、何者か。いかなる思し召しか。
わからない。ただ、それぞれの夢の中で。(でも、第九だけでもいい、聴いてみたかった!)
正直にいって、自分はモダン楽器のオーケストラを指揮するアーノンクールには、あまり関心がなかった。
ただ、モンテヴェルディの歌劇《ウリッセの帰郷》と《ポッペアの戴冠》のチューリヒでの再録音を三十年ほど前に初めて聴いたときの衝撃、それが忘れられずに、かれの演奏を聴き続けてきた。
そう、《ウリッセ》の序幕、はてなき者たちの気まぐれに翻弄される、はかなき者、人間の宿命の嘆きの歌を聴いたときから。
その旅に、ここでピリオド。
CDは二月三日発売予定。楽しみ。
十二月二十日(日)クリスマスといえば
彩の国さいたま芸術劇場の音楽ホールで、鈴木雅明とBCJによるヘンデルの《メサイア》全曲。難関のナチュラルトランペットも見事に決まって、端整な美しい音楽。六百席のホールで四十人の音楽家を聴く、贅沢な三時間。
十二月二十一日(月)
その一:演奏会形式オペラの隆盛
バッティストーニ指揮の《トゥーランドット》のSACDを聴く。一九二〇年代から、つまり作曲家の生きていた時代から進歩が停まってしまっているプッチーニ演奏に、新たな生命をもたらす、嬉しい演奏(新しいスタイル、とまでは今はいえない。歌唱スタイルに変化が生じたとき初めて、可能性が芽生える)。
これは東フィルの演奏会形式上演。今年はほかにもデュトワ指揮N響の《サロメ》、カンブルラン指揮読響の《トリスタンとイゾルデ》など、オーケストラ主催のすぐれた演奏会形式上演があった。
こういう上演に、実際の舞台を与える劇場として、新国立劇場が機能したら、なんと素敵なことだろうと思う。かれらだけでなく、ノット&東響、上岡&新日本フィル、大野とフルシャ&都響、インキネンとヤマカズ&日本フィルなど、それぞれのオーケストラと指揮者が腕によりをかけたオペラ上演を持ちこんで、舞台化する場としての、新国立劇場。
明確なヴィジョンを主体的に示せないなら、その方がよほど劇場的ワクワク感がある気がするが、もちろん、夢のまた夢。
その二:司馬、小松、小津、ついでに渋沢栄一
片山杜秀さんの『見果てぬ日本』を読む。
小松左京の未来(未来への総力戦)、司馬遼太郎の過去(過去へのロマン)、そして小津安二郎の現在(現在との持久戦)。昭和の語り部三人。
司馬遼太郎賞受賞者なのに、日本に数多いる司馬信者を敵に回すようなことを書いてしまって、大丈夫なのかしらんと気になったりするが、もちろん片山さんは、それを覚悟で書いている。
片山さんは「司馬のロマンは本質的に悲劇である」とする。物語の内容が悲劇というのではなく、かれ自身は気質的に好まないはずの読者たちから愛されてしまうという、悲劇。
「だから司馬の同時代批判はやはりリアリティを欠く。まさにロマンティックなのである。司馬は騎馬民族や坂本龍馬をつぶてにして現代を撃とうとするのだが、撃たれているはずの政治家も財界人も誰も彼もチンギス・ハンや幕末の志士の現代版を気取って喜んでしまう。司馬に励まされたつもりになる。(略)司馬はマイノリティのつもりで実はマジョリティなのではあるまいか」
たしかにマジョリティに愛読されなければ、「国民的作家」にはなれまい。龍馬好きの政治家や実業家にはろくなものがいないという、例のあれ。
自分は司馬ロマンの愛読者、耽読者だけれども(ただし『竜馬がゆく』は初めから苦手で、未だに読みとおせない)、あくまであれはロマンで、現実に応用することの無理はもちろんよくわかる。
自分は最近、日本のクラシック運動にも大きな役割をはたした帝国劇場創建の主導者として、渋沢栄一という人間に興味をもった。調べていくうちに、薩長閥の「官軍の国家主義」と異なる「賊軍の資本主義」の近代日本の象徴として、さまざまに意識するようになったけれど、こういう「資本主義者」は、司馬がまったく好まないもの。ほとんど何も書いていないはずだ。
渋沢栄一には、渋沢成一郎(のちに喜作)という同年輩の親戚がいた。幕末には双子のように行動を共にして、攘夷運動から転じて一橋家家臣、次いで幕臣となったが、栄一が徳川昭武の随員としてフランスに渡ったのが、運命の分かれ目となる。以後の成一郎は彰義隊、函館戦争と転戦して敗北、維新後も種々の事業に手を出すが失敗も多く、そのつど栄一が尻拭いをした。陽のあたる道を歩む栄一に対し、陰となる分身。
この好一対が人のありようとして、とても面白いのだが、それはそれとして、二人とも家は同じような深谷の豪農で、商売もしていた。
司馬は連作小説『幕末』の「彰義隊胸算用」で、成一郎の実家について、武士側からの評価として、こう書いている。
「農家だが、商売もしている。近郷の百姓から藍葉をやすく買いたたき、それで藍玉をつくって江戸の紺屋へ売ってもうける。その金利を高利にまわし、近在の百姓を相手に金貸しもかねていた」
司馬がこうした「百姓のくせに地道に生きず、商売をし、金貸しもする」地主連中に深い嫌悪感を抱いていることが、実によくわかる文章(笑)。
栄一の家も同じで、そしてまさにこうした階層(しかし一方で、国学にかぶれるほどの非常な読書階級でもあった)から出たからこそ、金銭を卑賤のものとする武士とも、卑屈に実利だけを追う商人とも、田畑のことしか頭にない百姓とも異なる、柔軟で高い意識をもって、西洋風の資本主義を日本に移植するという難事に、成功できたはずなのだ。
そのような人物(とその影法師の成一郎)が、「最後の将軍」徳川慶喜の側近にいたことは、大いなる歴史の妙だと、自分は思う。両者の関係の変化を眺めることにより、幕末から明治へと、動乱から革新へと停まらずに連続する社会を、敗者の視点から、関東平野の視点から、追っていくことも可能なように思える。
しかし、こういうことには興味を示さないのが、司馬という小説家だった。同じ関東の豪農出身でも、武士に憧れて戦闘集団を組織し、負け戦を全力で戦いぬいて死ぬ男、新選組副長土方歳三を描くことが、司馬ロマンの魅力なのだ(そして渋沢は、城山三郎が小説にする)。
余談がすぎたのでもとに戻すと、片山さんは小松、司馬、小津の三人を、二十世紀ドイツのキリスト教思想家、パウル・ティリッヒによる社会思想の類型化、過去を根源と、現在を自律と、未来を決断と結びつける理論にあてはめていく。
これはとても面白い分類。さらに私が思ったのは、この差にはそれぞれの世代の違いもあるのでは、ということ。
小津は敗戦の年に四十二歳、司馬は二十二歳、小松は十四歳。つまり、分別盛りの大人として敗戦を迎えた小津と、青年兵士の司馬と、軍国少年の小松。
国破山河在。
その、国破れても在る山河に、三人はそれぞれの時間を視た。
大人として、軍国主義化と敗戦を食い止めることができず、個人の力の限界を思い知っていた小津は、現代だろうが過去だろうが未来だろうが、歴史を動かす大人物などに興味をもたず、戦前と同じように、小市民の日常を描き続けた。
大正デモクラシーと戦後昭和と、中流階級の消費生活はほぼ似たようなものだとかれはわかっていたが、当時は戦前と戦後に大きな断絶を見るのが歴史観の主流だから、黙っていた。口を出せば、大人のくせに亡国を止められなかったのをなじられるだけと、わかっていたから。
その小市民、自律する訥弁の小市民の象徴が笠智衆。片山さんは小津映画のその役名が「平山周吉」だの「平山周平」だの、平々凡々であろうとしていることを指摘している(植木等の東宝サラリーマンものの「平均(たいらひとし)」などとの類似を思った)。
一方、青春真っ盛りの司馬は、兵隊にとられて戦車隊将校を命じられ、本土決戦になれば真っ先に死ぬ覚悟でいた。敗戦のとき、いまの日本はどうしてこんなことになったのかと思い、過去の歴史を考えるようになったと、何かの随筆に書いていたはずだ。亡国体験から民族の根源を求めて、過去のロマンへ。
思春期の小松は、罪悪感など持ちようがない。価値観の逆転をニヒルに受けいれる。敗戦直後の時期は多くのインテリ青年同様、マルクスにかぶれた。イデオロギーとは、方法の選択を決断して理想の未来を求めるもの。ただその根っこには、「少年倶楽部」や「幼年倶楽部」で培った、空想科学でなりたつ強国日本への憧れが、消えていなかったように自分は思う。秘密兵器、最終決戦兵器への憧れ。本土決戦になれば、ひょっこりと出てきたかもしれないもの。しかし現実にそれを用いたのは敵国の方で、結果、本土決戦は起きることがなかった。そして未来へ。
かれが参加した大坂万博は、まさにその敵討ち、弔い合戦のようなものだったのではないか。現実への応用としての、核の平和利用という決断。
しかし小松が想定した核融合実用化の前に、東日本大震災が起きて、核利用への大きな疑問が現実化してしまう。
同じ「少年倶楽部」育ちだが、司馬の根っこにあるのは山中峯太郎の冒険小説なのに対し、小松の根っこは平田晋策の架空戦記。その違いも大きい気がする。敗戦で山中峯太郎的アジア・ロマンが吹っ飛んだことから、司馬のロマンは過去へと向い、その案内人には山路愛山や徳富蘇峰がいた。
不遜を承知で書くと、自分だったら、このように小津~司馬~小松と、世代順に構成したくなるかもしれない。
しかし片山さんは逆に、小松から始めてさかのぼる構成にした。原発が喫緊の問題だという、危機意識からだろう。ときにやや書き急いでいるように感じられるのも、おそらくはこの危機意識から。日本の中枢にも小松と同じ「決断」をした人々がいて、そのまま不動の「国策」となっていることへの、危機意識。
おしまいに、渋沢家の人々のことをつけくわえる。
栄一の妻の兄は尾高惇忠といい、やはり深谷の豪農で、塾を開いて栄一に論語を教えた教養人だった。栄一と成一郎の志士仲間で、賊軍となったが維新後は栄達している。そして、この惇忠と栄一の曾孫が、指揮者の尾高忠明である。
十二月二十二日(火)年忘れ第九(一)
NHKホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団の「第九」。
今年の東京は「第九」の当り年で、例年よりも各オーケストラの指揮者の顔ぶれが豪華、かつ個性的で面白い。インバル&都響、上岡敏之&読響、バッティストーニ&東フィルなど、いずれも全公演が売切か、それに近い状況というから、聴衆の期待もそれに応じて大きい。
パーヴォは、レコーディングにおいては、起用するオーケストラに合わせてレパートリーを選ぶことで知られている。ベートーヴェンの交響曲は室内オケのドイツ・カンマーフィルと、ピリオド・スタイルを採り入れて録音しており、実演も多い。そこで、通常の交響楽団であるN響では、どのような編成にするのか興味津々だった。
答えは、十六型で木管を倍に増強した大編成。合唱も二百人を超す。NHKホールの巨大空間を考えてのことだろう。ただし演奏自体はアンコ型ではなく、すっきりと明快な響きで、快速のテンポで進める、ドイツ・カンマーフィルでの演奏と共通したもの。内声の動きを際立たせながら、ときに木管や金管のソロが、くっきりと浮き上がる。もちろんN響の特性として、あれほどアグレッシヴで、攻撃的なサウンドにはならない。
指揮者の持ち味がいちばん出たのは終楽章だった。大編成の合唱で逞しく、ひた押しに押す力強さ。今年CDで聴いたショスタコーヴィチの《森の歌》の強力なドライヴに通じるもの。
十二月二十四日(木)年忘れ第九(二)
オペラシティで、上岡敏之指揮読売日本交響楽団の「第九」。
パーヴォの第九も一般的な演奏より速いのだが、上岡(と、自分は聴けなかったがバッティストーニ)はそれよりも速く、六十分を切るくらいの快速と独創的な解釈で、すでに話題となっていた。
たしかに面白い。スケルツォの最後の音は、スッと抜いて微笑を誘う。納得したのは十四型の、やや小ぶりな編成だったこと。管楽器とのバランスは、この方が自然だろう。
ここまでサントリーホールや東京芸術劇場など、大きなホールで演奏してきたせいか、オペラシティでは合唱の響きが飽和気味で、これは残念だった。
音楽全体の格調はパーヴォに一歩をゆずるけれど、とても意欲的な演奏。あまりにも多すぎて新鮮味の維持が困難な、日本での第九演奏の難しさも、感じないわけにはいかなかったが。
十二月二十六日(土)タモリと東横沿線

週刊文春を読んだら、「タモリが見た東京 青春編」というインタビュー記事が載っていて、引きこまれた。
なぜ引きこまれたかというと、一九六五(昭和四十)年に早稲田大学へ入学して、福岡から東京に出てきたタモリが最初に下宿したのが、東横線の都立大学駅近くのアパートだとあったから。
早大生の下宿といえば大学周辺か、西武新宿線か東西線~中央線沿線というのが普通なのに、東横線。高校の同級生がいた部屋に居候したため、そんなことになったらしい。
そこは数か月で出てちゃんと部屋を借りたが、それも別の同級生がいたアパートで、これも隣駅の学芸大学駅近くの目黒区中央町。そこには二年も。今の家にも近いそうで「やっぱり結局は戻ってきちゃうんですよ。最初に住んだ都立大、学芸大に」
自分も東急の緑が丘駅近くで育って、三十年以上住んでいたから、一駅二駅で行けるこの地域には親近感がある。都立大学駅は、小中学校のバス通学の乗り換え地点なので、毎日のようにそこで遊んでいた。タモリのいたアパートが「東横線のすぐ横で」、「銭湯の帰りに坂を上がって」、などと書いてあるとどの辺か見当がつくから、読んでいてとても楽しい(ただ、自分が思っていた自由が丘寄りの中根ではなく、学芸大学駅寄りの柿木坂のアパートで、現存だそうだ)。
とはいえ、「こう下りて、線路伝いに行ったら都立大(の駅)。ここにストリップ劇場があった」という、そのストリップ小屋はさすがに知らない(笑)。
ただ、七〇年代前半でもあの地域の街角には、自由が丘の小映画館の映画ポスターや、田園コロシアムの小人プロレスのポスターに混じって、「なんとかOS劇場」みたいなストリップ小屋のポスターが貼られていたのを、おぼろに思い出した。まだ東横沿線のどこかで、営業していたのだろう。
一九六五年ごろは、都立大学駅はすでに高架だったが、学芸大学駅はまだそうではなくて、町に踏切があったという。これも知らない。
「学芸大学は、建物は全部変わってますけど商店街の雰囲気は今も同じですね。高層もないしゴチャゴチャしてる。京王線とか、新しい駅ビルやバスセンターがあって大きなショッピングセンターがあるっていう駅は嫌いなんですよ」
これは同感。
自由が丘駅にもよく行っていて、こじんまりした店が多いので、「いまだに大好き」だそう。自由が丘デパート(という名の、闇市由来のマーケット・ビル)に、エビが入っていないのにエビらしき味がする、エビライスなるものを出す店があったというが、これは知らない。喫茶店の「ら・りるれろ」は、自分もおぼろに憶えている。「揃えがマニアック」という古本屋の文生堂書店は、自分もよく知っているし、現存している。
そして早大へ通うには、この都立大学と学芸大学の下宿から東横線で渋谷に出て、暇なときは渋谷~早大正門のバス、時間がないときは山手線で高田馬場に向かったという。
自分と同じ通学路だったとは。そういえば、『ブラタモリ』の渋谷篇で、坂道の高低差をタモリが面白がるようになったきっかけが、東京に出てきて、渋谷の地上四階のビルの上にある地下鉄銀座線の駅を見たときだと話していたのも、渋谷が通学路だったからかと納得。
渋谷にかぎらず、都立大学や自由が丘の周辺も、やたらと坂が多い。駅が谷底にあるからだ。タモリの坂道好きの原点に、自分が毎日のように自転車で上ったり下りたりした、あれらの坂があるというのは、なにか嬉しい。子供のころは、なんてめんどうくさい町なんだろうとしか、思わなかったが。
次回は早稲田と渋谷を回想するそうなので、これも読まねば。
ということをフェイスブックに書いたところ、友人の方々から示唆に富んだコメントをいただき、やりとりのなかで三十年前の都立大学駅あたりの思い出が、頭に浮かんできた。
大学時代は一プレー五十円のゲーセンの全盛期で、都立大学駅の近くにも何店かあったから、自転車で山を越え――途中に有名野球選手の自宅があった――しょっちゅう通っていた。
ある夜中、改札口前の太い柱に、「いつか人が人を喰う時代がくるであろう」と、誰かが大書していた。これは強烈な記憶で、この駅は東横線では小さい割に田代まさしがつかまったり、駅員が客を殴ったり、東急らしくない印象的な事件の多い場所なのだが、きっとあの預言のせいだろうと、自分は信じている。
少し離れた目黒通りには、中古レコードのハンターがあった。大学入学直後、そこでクナの《指環》の五七年バイロイトのキング盤全曲LPを買った。生涯初の《指環》、生涯初のクナ。一万四千八百円。繁華街から外れているのに、都立大の学生が来るのか、この店にはマニアックな盤もあった。友人に頼まれて、オレ・シュミット指揮のニールセンの交響曲全集を買ったこともある。
昭和五十年代のハンターは、テレビCMを打つなど、東京の中古盤屋では飛び抜けて有名だった。高校の通学路の銀座には、高速下の数寄屋橋ショッピングセンターとソニービルとにあって、両方ともよく通った。
当時の銀座は新譜店も山野ヤマハにハルモニア、モール名盤堂など、お茶の水&秋葉原地区とともに、レコード漁りのパトロールコースだった。中古では、ハンターの方がディスクユニオンより玉石混淆だが安い、という魅力があった。ただ、売る側にまわった場合は、ハンターの買取価格はさらに激安で、泣かされたものだった。
数寄屋橋のハンターの閉店は、ネットで見ると二〇〇一年のことらしい。都立大学の店は、CD時代にはもう消えていた気がするから、八〇年代までか。
十二月二十七日(日)小地震の群れ
江戸時代まで大名屋敷の池の底だった場所にある我が家は、震度一の地震でもはっきり体感できるほど、よく揺れる。揺れかたもさまざまで、それで震源の方向の見当がつくこともある。
昨日は夜十一時過ぎにごく短い振動が数分おきに何度もあって、少し気持悪かった。ネットのヤフーの地震情報ページを見ると、十時台のものを含めて五回。震源が東京湾というのも、あまりないのでヤな感じ。巨大ナマズでも東京湾にきていたのだろうか。
(とフェイスブックに書いたところ、ナマズは淡水魚なので、海には出ませんよとのご指摘をいただいた。お恥ずかしいかぎり…)
二十二時十二分頃 東京湾 震度二
二十三時四分頃 東京湾 震度一
二十三時十六分頃 東京湾 震度一
二十三時十八分頃 東京湾 震度一
二十三時二十一分頃 東京湾 震度二
十二月二十八日(月)ベストプレー・クラシック2015
二〇一五年の演奏会通いが終ったところで、「いちばん凄かった瞬間」を思い起こしてみると、やはりあるオーケストラ演奏会(特に名を秘す)での、《英雄の生涯》コーダ直前。
締めの一音を、水平に置かれたグランカッサがドン! と盛大に決めた次の瞬間、跳ね上がったバチが打楽器奏者の手から離れてしまい、弦楽器の持続音の上を、クルクルと美しく空中を舞った。
息をのむ客席(たぶん指揮者も)。
落ちてきた瞬間、打楽器奏者が必死の形相で、ハッシとばかりにキャッチ! 下に落として派手なノイズをたてたりしたら、全員の数十分間の演奏を台無しにするところだっただけに、本当に凄いファインプレーだった。
どちらかというと「珍プレーにして好プレー集2015」のほう向きか?
しかし見事なリカバリーだったとはいえ、見ていたこちらも、吹き出しそうになるのを必死でこらえて曲が終るのを待たなければならなかったから、ものすごく大変だった(笑)。
毎回あの妙技を決められるパーカッションがいたら、シルク・ドゥ・ソレイユに入団した方がよさそう。
十二月三十日(水)ソウル・フィル
年の瀬、チョン・ミョンフンがソウル・フィルとの芸術監督を、今月末の契約満了をもって退任するというニュース。
数か月前からもめているという話が広まっていて、退任は時間の問題と思っていたが、ギリギリの段階で発表。
二十六日に日韓国交正常化五十周年を記念する第九をソウル・フィルと東京フィルで合同演奏していたから、それが終るまでは表沙汰にしない、という判断だったのだろうか。
Homeへ