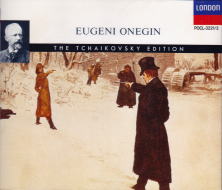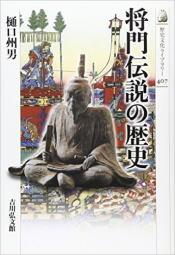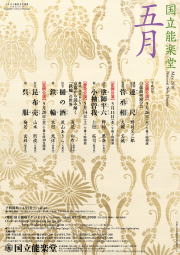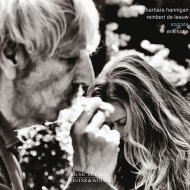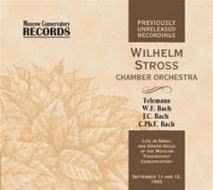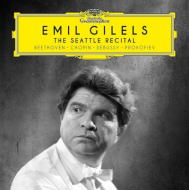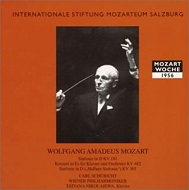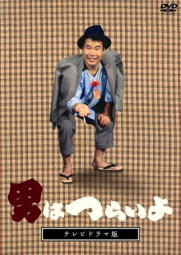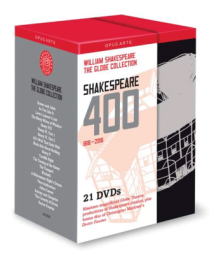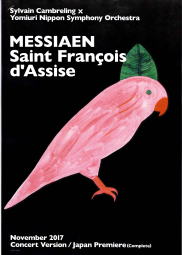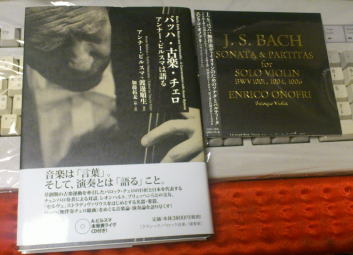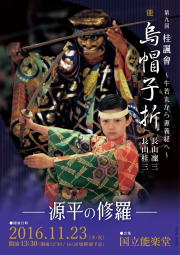Homeへ
一月二日(土)高幡不動

初詣は日野の高幡不動に行く。
日野は土方歳三の出身地で、高幡不動はその菩提寺である。昨年初めて行ったときに、その銅像の写真を撮ってきた。

一月十日(日)ヤマカズと真田丸
二〇一六年の演奏会通いの始まりは、ヤマカズ&N響。ビゼーの《こどもの遊び》、ドビュッシー(カプレ編)の《おもちゃ箱》、ストラヴィンスキーの《ペトルーシカ」(一九一一年版)というパリ初演プログラム。そして、子供と人形のプログラム。
人形遊びの代表的なのは、女の子ならおままごと、男の子なら戦争ごっこ。家事と殺人。
およそ人間の営為というのは、極論すれば、この二つのあいだにすべて収まるのかもしれない。それを、人形が代りに演じる。《おもちゃ箱》はまさにそんなストーリーで、その延長に《ペトルーシカ》があり、前段に《こどもの遊び》がある。さすがヤマカズらしい、よくできたプログラム。
《おもちゃ箱》はナレーションつき。以前、音楽のみをカンブルラン&読響で聴いたことがあるが、取りとめのない長い音楽という印象しかない。ナレーションが入ると、ストーリーと音楽の関連がよくわかって、とても楽しめた。ただ、松嶋菜々子は女優といってもきちんとした修練を重ねた人ではないので、言葉がつかみにくく、情景を想像させるような語りではないのは仕方のないところ。
ヤマカズは、羽毛布団のような優美な響きがきれい。コルトレーン風にいえばウモウブトン・オブ・サウンド。デュトワの置き土産で、実は今のN響は何よりもフランス音楽が上手いという特性を、定期デビューで万全に活用したあたり、さすがに抜かりがない。
そのことは、後半の《ペトルーシカ》で、さらに明らかに。四管編成の一九一一年版は、響きがやわらかく華麗。まるでラベルの音楽のように輝かしく響く、ユニークなストラヴィンスキー。フランス(で初演された)音楽の文脈に位置づけるという意図が明確で、心地よし。
夜は『真田丸』第一回をみる。とても面白くて悲しくて、一年間が楽しみ。
落城で始めて落城で終る、「国破山河在」で始めて「国破山河在」で終る、ということにどうやらなるらしい一年の設計も、さすが三谷。
浅間山の噴火は笑った。人間が必死でやっているときにこそ起きる、滑稽な天のいたずら。そして、山県も馬場も高坂ももういない、甲斐の人、勝頼の孤独。平岳大よかった。ぜひ、内野の家康が三方が原の敗戦を回想するときには、ヒラミキ演じる信玄を見たい(笑)。
燃える新府城、自分は送電線屋をやっていたときに通った韮崎の現場が、まさにあの新府城のあった、釜無川わきの大きな岩の台地の上にあったので、とても懐かしかった。
その前には塩山市に長くいたこともあって、塩山には「心頭滅却すれば火もまた涼し」の恵林寺や、日の丸や孫子の旗が残る雲峰寺があって、昼休みに覗きに行ったことがある。山梨県の武田家関係は華々しいものよりも、滅亡にかかわる故地や遺跡の方が目立つ。強いのは甲斐の外へ攻め出ているときであって、中を守るようになったら駄目。今回の勝頼の諦観には、それが感じられたような。
あと、高嶋の北条氏政もひそかに楽しみ。飯に汁をかけて食っていた場面、汁を二回に分けてかけて父氏康を慨嘆させたという「二度汁」の逸話に引っかけてあるのが愉快。
不作が何年も続いた大河ドラマ、これで延命できそう。ところでNHKの大阪は朝ドラでヒット連発して乗っているけれど、そのうち大河もつくったりするのだろうか。
一月十六日(土)教会と塹壕と
午後にすみだトリフォニーで、ハーディング指揮新日本フィルによる、ブリテンの戦争レクイエム。
ボストリッジの独唱がダントツ。オーウェンの戦争詩の世界を具現化するようだった。バリトンはノルウェー人だそうだが、ブリテンが意図したようなドイツ人が確保できなかった時点で、イギリス人にした方が言葉をもっと明確に歌えたのでは、とも思う。オーケストラと合唱は、もう少しハーディングの棒に明敏に反応できればと思うところも少なくなかったが、まずは好演。
何よりも、コンサート専用ホールならではの構造を活かした、立体的な配置がうまくできていて、その音響が効果的だった。典礼部分を担当するオケと合唱が舞台にいるのは当然として、戦争詩を担当する小オケは、舞台上手前方に固められる。テノールとバリトンは指揮者の左手。ソプラノは二階のオルガン操作盤の脇。そして少年合唱とオルガンが、三階後方のロビーの高みから、はるかに降ってくる。
今まで聴いた小澤&サイトウキネンや大野&都響は、キッセイホールと東京文化会館という、多目的ならぬ無目的ホールが会場だったので、ただ全部を指揮者を扇の要とした形で舞台上に並べることしかできず、のっぺりとしたサウンドでしかなかった。それが今日は空間を活かした立体の響きで、宗教と世俗を、教会と塹壕を入れ子にしたブリテンの独創的な仕掛けを、ようやく体感できた。
〈怒りの日〉が描く「最後の審判」の世界と実際の戦場の、未来と現実が、重なるような重ならないような、揺れるオーバーラップの距離感。
聴きながら思い出していたのが、カルショーの『レコードはまっすぐに』にある、ブリテン自作自演盤の録音時の話。
あのときはキングズウェイホールの床にオーケストラを配置、指揮者の背中側に小オケと男声独唱を置き、合唱とソプラノは二階のバルコニーに置いて高低を離す。少年合唱は脇のバルコニーで、専用マイクをつけずにぼやかして録る。男声と別にされてしまったウィシネフスカヤがその意図を勘違いして怒りだして収録中断、なんて一幕もあった。
この録音の話は、未完のこの自伝のクライマックスに置かれていて、訳しながら思ったのは、これが自伝冒頭の従軍体験と照応している、ということだった。複葉攻撃機ソードフィッシュの航法士として第二次世界大戦に参加、戦友たちの死に直面し、自分も死にかけたことがあるカルショーにとって、戦争レクイエムの世界は自身の体験でもある。
第二次世界大戦の爆撃の惨禍と、第一次世界大戦の塹壕の戦争詩とでは世界が違うのではないか、というかれの戸惑いも、体験者だからこそだろう。
ズレと重なり。過去にして未来という現在。神話化される死。いま。
夜は『演奏史譚一九五四/五五』のカザルスの話を、ようやく書き上げる。
プラードに閉じこもっていたはずのカザルスのところに「アメリカ」が押しかけてきて、押し出されるように一九五五年のカザルスは外界へ出て、シュヴァイツァーとチャップリンに会いに行き、ルツェルンのワーグナーの家とボンのベートーヴェン・ハウスを訪ね、ついには母の故郷、プエルトリコに至る。
天路歴程、いやある種の「胎内めぐり」というか。そこにアレクサンダー・シュナイダーとディースカウとメニューインのプラード体験がからんで、妙にスケールがでかい話でまとまりがつかず、この二週間どうにも書けなかったのが、今日になって突然、三千三百字の中にすとんと収まった。戦争レクイエム効果か。
これで、仮名手本四十七話まで残り三つ。次は一九五五年八月の「バイロイト・オン・ステレオ」(団伊玖磨と吉田秀和と山根銀二のワーグナー体験つき)。そして九~十一月の「二つのベルリン、一つのウィーン」と、十二月の「バイロイトの第九発売」。頼むから停まるな。
一月十七日(日)タイム閉店
高田馬場の中古レコード店「タイム」が閉店して、ネット販売のみにするという。自分と同い年のお店とは知らなかった。カウンターの人がLPを廻しながら白い布巾でキュッと磨いていた光景が懐かしい。ムトウもとうに消えたし……。
一月十八日(月)光はクレージーより
SMAP解散騒動。音楽の一方でコントをやり、それぞれにドラマやヴァラエティに出るのはクレージーがつくってドリフが継いだ方式だから、同様にテレビの冠番組が終ったところで個々に散開、明確な解散はしないのが、一番まるく治まるはず。ナベプロの場合は、派閥抗争が表面化はしなかったわけだが。
一月十九日(火)あなたも共産党員

これから読む(つもりの)新書三冊。今月は久しぶりに、食指の動く歴史関係の新書が並んでいた。
『オペラでわかるヨーロッパ史』はFBフレンドでもある、加藤浩子さんの新著。名作オペラの背景にある史実をわかりやすく説く、ありそうでなかった本。
『戦国の陣形』は、江戸時代の軍学者の張り扇や、明治の参謀本部の机上の空論で適当に語られてきた、戦国時代の軍勢の陣形の実際について考察する本。
立ち読みしたら、「日本の参謀本部の父メッケルは、(まだこの地上に存在しなかった)関が原の布陣図など見られるはずがないので、西軍の勝ちと即座に断じたというのは作り話」と、一刀両断していたのが気に入って、買ってきた。
『70年代オカルト』は、その名のとおりのオカルトブーム検証本。大切な人格形成期に、脊髄にオカルトを注入されてしまった(笑)自分のような世代にとっては、読まずにいられない本。本タイトルの前に、小さく「今を生き抜くための」とついている。
夜は東京文化会館で、ムーティ指揮のシカゴ交響楽団を聴く。
プロコフィエフの古典交響曲、ヒンデミットの弦楽と金管のための協奏音楽、チャイコフスキーの交響曲第四番。
高カロリーの濃厚な音で、技術も世界でも超一級であることは疑いない。しかし、リズムが重くて弾力のない、前世紀のオーケストラの音みたいなのに驚く。フィラデルフィア管やニューヨーク・フィルは若い指揮者の下で、もっと今風のサウンドをつくっていると思うし、ムーティもヨーロッパや日本のオケを振った近年は変ってきたように感じていたのだが、両者が組み合わさると、時間が戻ってしまうのだろうか……。
近年のヨーロッパ、特にドイツのオケは、幼少期からロックを聴いて育ってきた音感覚が、よくも悪くも攻撃的な音づくりにつながっていると思うのだが、今日のシカゴ響にはそうした要素が微塵もなく、純然たるクラシック。
スタインウェイのコンサートグランドをオーケストラ化したら、こんな音になるのだろうか、などとも思う。
そうしたありかたと、弦楽器のアジア系の多さとは関係があるのかないのか、気になるところ。
ムーティは三月にイタリアのユースと日本の混成オケを振るから、可能なら聴き較べてみたい。
東京文化会館の舞台上の天井反響板が斜めになっていることを考慮したのか、管楽器全員がひな壇を使わずに床面にフラットに座っていたのも興味深かった。
ところでチャイコフスキーの交響曲第四番の終楽章、どうしても大学のサークルで先輩があの主題に合わせて歌った、「♪チャイコのよんばん、こ~れがよんばん、な~んどきいてもよんばん」という歌詞が今日も脳内で響いてしまい、追い出すのに一苦労。でも「な~んどきいてもよんばん」というのは、チャイコの音楽の本質をけっこう鋭く衝いている気がしてならない。
とフェイスブックに書いたら、「あなたも共産党員、わたしも共産党員、みーんな共産党員」というのを教えられて、迷惑を蒙っている(笑)という方がおられた。こちらの方がメジャーらしい。確かにぴったり。
一月二十日(水)がんばれ鍾馗
ソヒエフ指揮NHK交響楽団をサントリーホールで聴く。
グリンカのルスラン序曲、ラフマニノフのPコン二番、チャイコフスキーのハクチョウコ(これは書くと正式タイトルの方が短い…)抜粋。
昨日、偶然にもシカゴ響でプロコの古典とチャイ四を聴いているので、東宝争議風にいえば「ショスタコ以外はみんな来た」の、ロシアな二日間。それを日米安保体制二大オケで聴く面白さ。
こうやって続けて聴くと、N響をサントリーホールで聴くという贅沢な体験をさせてもらっているにもかかわらず、とても熱演だったにもかかわらず、やはりシカゴ響がどれほど凄いオケかということを、あらためて思い知らされる。
P‐47サンダーボルトが圧倒的なパワーで爆音と強風を残して飛び抜けた直後を、二式戦鍾馗が追尾しようとしてかえって引き離されていくのを、日の丸ふって応援しているみたいな(笑)感じ。
ラフマニノフの冒頭のピアノの重低音を聴いた瞬間、そう、これをそのまま引き延ばして輝かしく響かせたみたいなのが、昨日のシカゴ響の金管だったと思った。鍵盤を叩けば大きな音が安定して確実にすぐに出る。そういう、機械的結果みたいな響きを、生身の人間が吹いて、当り前みたいにつくることの物凄さ。こういうことを理想とするならば、ピリオド楽器なんて、たしかに馬鹿馬鹿しくて聴いてられないだろうと思う。
ただ、昨日なくて今日あったのは、弦のうねり。しなやかな動き。ソヒエフのつくる音楽も、シカゴ響の音も、ひと言でいえばどちらも「重い」のだけれど、その「重い」の意味が、まったく異なっている面白さ。それはたしかに、ピアノの音はうねるはずがない。
ところで、サントリーホールは久しぶりだった。調べたら先月十六日の同じくN響が最後だったので、ひと月以上のごぶさた。その間に起きたことで残念なのは、アークヒルズの書店丸善が年末で閉店していたこと。ちょっと寄れる本屋、というのが、どんどん行動範囲から消えていく。
さて明日は一転、スクロヴァ&読響のブル八。会場は池袋の芸術劇場。正月からやたらにリキの入ったオーケストラ演奏会が三日間。どれも完売らしいのもすばらしい。
一月二十一日(木)新即物主義の人
スクロヴァチェフスキ指揮の読売日本交響楽団を東京芸術劇場で。ブルックナーの交響曲第八番。
新即物主義の系譜を今に伝える男、ミスターS。左膝が悪いのか、歩くときは足を少し引きずるけれど、指揮台では立ったまま。譜面台にはスコア(隣席の渡辺和彦さんによると、古いプライトコップ版の由)が置かれているが、最後までただそこにあるだけで一度も開かず。
さすがに数年前にくらべてツメの甘さを感じる部分もあったが、緩急強弱とテクスチュアをくっきりとした輪郭でつける剛直スタイルは変わらず。いくつになっても楽譜を再検討して、予想外のデフォルメをするのもこの人の特徴で、二十世紀前半の新即物主義というのがけっして教条主義的な楽譜厳守ではなく、むしろその醍醐味はデフォルメにあるということを、今日も教えてくれた。
情緒に訴えて陶酔に誘うのがロマン主義とすれば、差異を認識させて覚醒に導くのが新即物主義。デフォルメは、差異に気づかせる有効な手法なのだ。
いちばん印象的だったのは、アダージョ冒頭のリズムをバルカローレ(舟歌)のように揺らしたこと。舟歌といえばショパン、スクロヴァが同じポーランド人であることは、関係あるのやらないのやら。でも何か、ほほえましい感じがして嬉しかった。
オケの献身的な熱演も気持よし。
今日の演奏はNHKが放映するとのこと。三十年前のNHKなら、読響がこの世に存在することすら認めたがらなかったんじゃないかと思うが、時代が違う。ジャイアンツのナイターをNHKが中継するみたいなものか。
一月二十四日(日)あとは察せよ
『真田丸』第三回をみる。前回の第二回は脚本と演出の息が合ってない感じを部分的に受けた(特に勝頼最期のあたり)が、今回は快調さが戻って気持よし。
黒木と長澤の女性二人(役名忘れた)の描きわけも楽しいし、なんといっても藤岡弘、の本多平八郎の妙ちきりんさが愉快。たしかに戦場で鬼神のように強い人間なんて、こんな風にどこか壊れているものなのかもしれない。この変な男が娘を通じて真田家の命運に関わってくるのかと思うと、楽しみ。
とにかく三谷の脚本が好き。ここ何年か、龍馬も清盛も官兵衛も苦手だったのは、キャラがとにかく力んで怒鳴ったり泣いたりと感情をむき出しにして、そして自分の感情やら思考やら他人への意見やらを、簡単に現実の言葉として口にしてしまうことだった(『天地人』あたりからひどくなったように思う)。
こういう、まるで含みというもののない、子供っぽい人間像しかつくれないのは、現代の脚本家が幼少期からマンガやアニメの、単調な絵づらをすべてセリフで補うしかない単純な表現で育ってきたことの悪影響のようにも思えるが、当っているかどうかはわからない(微妙な感情表現、表情の移ろいや変化を描けるマンガ家がいることも、知っているし)。
いずれにしても、三谷の人間描写の原型にあるのはそうした薄っぺらい「絵」ではなく、映画であったり演劇であったり、生きた人間(あるいは立体の陰影を持った人形)が演じるもの。だから、性格描写はわかりやすいが、けっして一面的ではなく、含蓄の影と奥行きがある。
今回好きだったのは、大泉洋の信幸の描写。総領息子のつらさ。父はその痛みを、実地で体験させて憶えさせる。そのつらさを総領は誰に話すことも許されない。ひとりで呑みこみ、弟や女たちの後楯になり、すっくと立っていなければならない。そして、そういう兄貴を心から尊敬し、その背中を笑って見つめる弟。
こんな人間関係や、思いや仕掛けを全部口に出して言葉にしたら、安っぽいだけ。「あとは察せよ」のドラマ。
ただし「あとは察せよ」とはいっても曖昧にぼかすことなく、視覚的には明快な表現。三谷の根っこには、フランク・キャプラなど、二十世紀半ばのハリウッド映画もある。この明快さは、サイレントから始めてトーキーに移った映画監督たちの映像表現に由来するのかも。
あらためて考えてみると、武田滅亡から大阪落城まで、このドラマが描く三十五年ほどの歳月のあいだには、父と子の関係がつまっている。偉大な父の影を負う、跡継ぎたちの物語。
まず初めに武田勝頼がそうだし、主人公の信繁と信幸はいうまでもない。上杉景勝と北条氏政も。このあと、信長の息子の信雄や信孝も出てくる。秀頼、秀次に秀秋、豊臣家の人々。そして家康のたくさんの息子たち。秀康や秀忠は信繁とは豊臣家の人質仲間になるし、忠輝もいる。あと、本多正純もいれば、長宗我部盛親も井伊直孝も本多忠朝も。信繁の娘を娶る伊達の家臣、片倉小十郎もやはりその二代目。
「不肖の息子」だらけの、英雄時代の終りの日々。
肝心なのは、そこに、たった一人だけ生き残っている「最後の親父」こそ、徳川家康であること。
私自身が不肖の息子なので、こんなことを強く感じるのかもしれない。ともかく内野の家康、楽しみ。
一月二十九日(金)デッカ、ステレオの旅
「演奏史譚一九五四/五五」の第四十五話、「バイロイト・オン・ステレオ」を、いま書いているところ。デッカがバイロイト音楽祭で初めてバイノーラル(ステレオ)録音した、一九五五年夏の話がメイン。
以下に書くのは本文の下敷きとなる、ものすごくマニアックなデータ整理段階の部分。
史料を調べていくうちに、バラバラに書かれたいくつかの記述がかっちりとかみ合って、立体物のように、まさにオーケストラ・サウンドのようにさまざまな史料がつながり合い、響きあい、ハーモニーとテクスチュアを形成していく瞬間というのは、本文を書くよりもよほど愉しい。史料のオーケストラ、ステレオ・サウンドが生まれる瞬間(笑)。
昨日もそんな時間を味わえた。まとめてみたのが、以下の話。本文ではかなり短縮してしまうことになるので、もったいないからここに残しておく。
この当時のステレオ録音は、デッカでは社外秘扱いで、メインのモノラル用の機材に紛れて、アーティストにばれないようにコソコソと録っていた。
バイノーラルの専門家ロイ・ウォーラスが試験用の機材を完成したのは、一九五四年四月。
翌五月と六月にジュネーヴでのアンセルメ指揮の録音をし、アンセルメにだけ事情を話してプレイバックを聴いてもらい、絶賛をもらえたので、本格的に試験録音を秘密裡に開始。七月ローマ、九月パリ、十月に再びジュネーヴで録って、どの会場でも実用に耐えることを確認。
で、一九五五年には二台目の録音セットをつくって、二グループに分れて、さらに試験録音することになった。初号機はウォーラス、二号機はその弟子のジェームズ・ブラウンが管轄して、メインのモノラル録音チームに混ざってツアーに参加(ウォーラスが「忍び込んだ」のはケネス・ウィルキンソンが率いるモノラル・チームで、入社間もないゴードン・パリーもこちらでステレオの手伝い)。
いくつかの資料を綜合して、その動きと主な録音を再現すると、このような流れになる。
ウォーラス ブラウン
二月 ベオグラード
四月 ウィーン ウィーン
五月 ジュネーヴ ウィーン
六月 パリ ウィーン
七月 バイロイト ローマ
八月 バイロイト
九月 ベオグラード フィレンツェ
十月 ジュネーヴ
十一月 ウィーン
十二月 ウィーン ロンドン
ベオグラード ホヴァンシチーナ、イーゴリ公
ウィーン ベーム、クリップス、クライバーのモーツァルトのオペラ四本
ジュネーヴ 火の鳥
パリ ヴォルフ、ボールト、アルヘンタ指揮パリ音楽院
ローマ 運命の力、トゥーランドット
バイロイト オランダ人、指環
フィレンツェ 愛の妙薬
ベオグラード オネーギン、イワン・スサーニン、雪娘、スペードの女王
ジュネーヴ アンセルメ指揮のフォーレのレクイエム、恋は魔術師、ミュンヒンガー
ウィーン ベーム指揮の影のない女
ロンドン カーゾンの交響的変奏曲
重要な録音拠点のはずのウィーンに初めて行ったのが、試験開始から一年もたってからなのは、噂話の好きなこの町では、本社のあるロンドン以上にバイノーラルの秘匿が難しいと考えたからか。それともメインのプロデューサー、ヴィクター・オロフがステレオ録音にまったく無関心だったためか。
そのロンドンも十二月になってやっと出てくるが、実はデッカが試験録音を開始してから、これが初めての本社での録音。ステレオ機材は大陸の録音でしか稼働していなかった。ジュネーヴより一年半近く遅れたことになる。本社と大陸の連繋の悪さ。
この仲の悪さに嫌気が差したこともあって、一九五三年末にデッカをやめてキャピトルに移っていたのが、ジョン・カルショー。かれがデッカに再び戻ってくるのは、一九五五年八月末。早速、本社でのレコード制作に携わるが、もちろんモノラル録音。
そうこうするうちに十月。ベオグラードに出張していた録音チームにいたゴードン・パリーが、本社に戻ってくる。そしてカルショーと初めて一緒に仕事をして、ブリテンの《小さな煙突掃除人》をモノラルで録る。意気投合して、バイロイトでステレオ録音したばかりのカイルベルトの《指環》などの話をする。
一九五六年末、デッカは来る一九五七年からステレオ録音の秘匿をやめることを決め、アーティストに告知し、ステレオ用の音場づくりに協力してもらうことにする。そして、新たに発足するステレオ録音チームのまとめ役として、パリーが任命された。カルショーとパリーのコンビにより、ショルティとクナのワルキューレ三幕と一幕などが、一九五七年に録音される。
ここから、カルショーとパリーの協同による、《指環》全曲のセッション・ステレオ録音への長い旅が、始まる。
と、こうしてまとめると、どこがどの史料の部分で、どういう風につながっているかは、自分以外にはまるでモノラルのように(笑)わからない。これは論文ではない「読み物」である以上当然のことで、一体感と明快な分離が共存するような、最良のモノラル音響こそ、自分が目指さなければならないもの。
そして、書き散らしただけの冗長なこの文をいかに縮めて他のエピソードと織合わせ、三千三百字にまとめるか。これが何より面倒……。
以上、R・シュトラウス風にいえば、「病んでいる奴の仕事場から」。
ところで、今回の史料のなかで特に気になったのが、一九五五年の二月と九~十月に行なわれた、旧ユーゴのベオグラード国立歌劇場のオペラ録音のこと。共産圏内で孤立した非同盟路線を歩むチトー時代のユーゴと提携した、ロシア・オペラの最初のステレオ録音。
バラノヴィチとダノンが指揮をして、チャンガロヴィチなどを主役に、ロシア・オペラの名作七つを録音(《ボリス・ゴドゥノフ》以外はステレオがある)しているが、今はほぼ忘れられている。LP時代にはハンターなどで、エース・オブ・ダイヤモンドの廉価盤などをよく見かけた記憶があるが、不思議なことに正式なCD化は一度もされたことがない模様なのだ(例外があった。後述)。ドイツのLINEレーベルから三種が板起しでCD‐Rになっているが、《スペードの女王》以外はモノラル音源のようだ。
もはや価値がないと判断されているのか、権利関係に問題があるのか。もったいないと思うのだが…。
一月三十一日(日)一九五五年のベオグラード
風邪気味で家にこもり、楽しみにしていたバッティストーニの講演会は断念。
一昨日のデッカ話をフェイスブックに書いたところ、貴重な情報を教えていただいた。まず森泰彦先生からは、デッカのほぼ完全なディスコグラフィがCHARMというサイトに存在していること。早速ダウンロード。(http://www.charm.rhul.ac.uk/discography/decca.html)
さらに吉田光司棟梁から、ベオグラードでのロシア・オペラのうち、ダノン指揮の《エウゲニ・オネーギン》とバラノヴィチ指揮の《スペードの女王》は、一九九三年にポリドールの日本企画、「ロンドン・チャイコフスキー全集」で出ていたこと。
《オネーギン》だけはすぐに入手できたので、少し聴く。ディスコグラフィにより、一九五五年九月録音と特定できたもの。
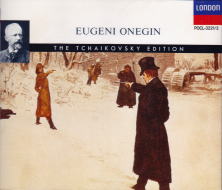
未公刊の本の内容を、こうした場で小出しにすることについては、いろいろな意見があるだろう。しかし私の場合は、励ましと促しになるだけでなく、内容についてさらなる補強と裏付けを得られるのだから、本当にありがたいかぎり。
さて《オネーギン》、モノラルのセッションに三本マイクのデッカ・ツリーを一本、密かに紛れ込ませただけでこの音場を録ったのだから、やはりデッカは凄い。そして、ダノンの指揮と歌手もかなりのクオリティなのに、これと《スペードの女王》しかCDになっていないというのは、本当にもったいないと思う。
ロシア・オペラでは合唱の重要度が高いだけに、ネイティヴに近いクオリティのロシア語で歌える意義は大きい(六〇年代のクリュイタンスやカラヤンの《ボリス》も、合唱だけはソフィアやザグレブの歌劇場合唱団を借りて西側で録音している)。それだけに、ムソルグスキーやボロディン作品のベオグラード録音も正規のクオリティできいてみたい。
当時のユーゴという存在にも、いっそう興味がわく。「一九五四/五五」が扱うのは一九五三年のスターリンの死の直後という時代なので、雪解けが始まった時期のソ連(ショスタコーヴィチなど)とその近隣、ハンガリー(シフラ)、チェコ(ターリヒ)、ポーランド(ショパン・コンクール)、フィンランド(シベリウス)などの話が出てくるが、ユーゴは適当な音楽家がいないと思っていた。しかしこの録音を使えば、スターリンに罵倒されながらチトー統治下で独自路線を歩んだユーゴの話ができる――といっても、話を新たに追加する余裕はないから、「バイロイト・オン・ステレオ」に押し込むしかないが(笑)。
気になるのは、デッカとのつながりのきっかけ。ユーゴの歌手はジュネーヴ国際コンクールを受けたりしているから、スイスでローゼンガルテンとつながった可能性もあるけれど、それよりも、ウィーンつながりの方がパイプとしては太そうだ。デッカのディスコグラフィがベオグラード録音をウィーン録音の章に含めているのも、そんな人脈を思わせる。
一九六五年に行なわれたNHKスラヴ・オペラも、いまあらためて面子を見ると、チャンガロヴィチにダノン、マタチッチにザグレブ国立歌劇場合唱団と、完全にユーゴ勢で構成されている。これもN響事務長の有馬大五郎がもっていた、強力なウィーン人脈が実現させたものに思える。
二月一日(月)華麗なる…
CSで録画した『華麗なる一族』二十六回を、ようやくみおわる。
山崎豊子の小説を原作とするテレビドラマで、一九七四年十月から翌年三月まで放映されたもの。万俵大介が山村聡、息子の鉄平が加山雄三、高須相子と語りが小川真由美など。
映画を完全に圧倒し、カラー化で栄華を極めた時代の、まさに華麗なる民放テレビ局がつくった大作。セットも衣裳も凝っている。二十六回あるので、主役だけでなく脇役の描写もしっかりやって、群像劇になっているのもありがたい。
自分がこういうものをみながら育った世代だからなのだろうが、脇を固めている新劇系の役者たちの演技、とりわけその安定した台詞回しに、なんともいえず安心感をおぼえる。サラリーマンや役人や医者は、やっぱりこうでないと。
とはいえ、一方で労働者を演じるときなどは、左翼芝居みたいに類型化したつまらなさになるのも面白い。こういう、インテリが鼻につく演技に飽きて、やたらに怒鳴りまくる蜷川演出とか、アングラや小劇団が生まれてくるのだろうが、そのため逆に、小市民的なインテリの役ができなくなってしまった。
制作が東京の局ではなく、大阪の毎日放送なのも興味深かった。毎日放送は平幹二朗主演の『不毛地帯』も五年後につくっていて、プロデューサーの財前定生(『白い巨塔』を想起させる名前なのが愉快)と脚本の鈴木尚之などは共通。
『不毛地帯』もその前に放映されたのでみたが、ともに大阪を舞台に始めながら東京に移る話なのが、時代を象徴している。『華麗なる一族』の銀行家は最後に、『不毛地帯』の商社マンは途中で。
高度成長期は、経済の中心が大阪から東京に完全に移行する時代だった。『華麗なる一族』の大介の娘たちの婿や婚約者も、東京で働いている。森繁の社長シリーズの会社が東京なのに、先代社長未亡人の邸宅が芦屋にある設定も、大阪からの移転を示している。
そのおかげか、終盤で日比谷公会堂でのクリスマスの《メサイア》が登場、合唱が舞台にいてオケが下のピット(といっても客席と同じ床面)にいる場面があったのは、思わぬ収穫。そういえば、初期の回では、屋外はみなフィルム撮影になっていて、メインとなるスタジオ内のビデオ映像との差が激しく、合成も不自然だったのが、後半は機材の進歩か、屋外もビデオで撮影している。
二月十二日(金)見立て
昼は新日本フィルの記者会見に行く。上岡次期音楽監督、ドイツ語での記者会見は慣れているが日本語での就任会見は初めて、というのが面白かった。ソロ・コンサートマスターの崔文洙が語った通り、課題は山積しているのだろうが、逆にそれを糧にして、足を地につけて着実に明日を切り拓いてほしい。

写真は、そこでいただいたグッズ。新しいロゴマークの入った箸、ではなくてペンシル。握ってみたかっただけ。
夜はライナー・ホーネックと紀尾井シンフォニエッタ東京の演奏会。
モーツァルト:ディヴェルティメントK一三六
R・シュトラウス:ホルン協奏曲第二番
モーツァルト:ホルン協奏曲第三番
R・シュトラウス:メタモルフォーゼン
モーツァルトとR・シュトラウスだけのプロを聴いて、いまの自分は、これくらいの編成が好きだとあらためて思う。
それまで、今月はブルックナーの交響曲を二つきいて、耳が疲れてしまった。六日にパーヴォ指揮N響の第五番、十日にバレンボイム指揮シュターツカペレ・ベルリンの第二番。前者の金管ギンギンのコラール、後者の純粋な二管編成なのに弦十六型という怪物的な音響バランスなど、その剛強すぎる音が、いまの自分の耳と心にはきつすぎた。
ストバイは八人まで、指揮者もコンマスに入ります、みたいな。遠征じゃなくて遠足、みたいなほうがいい。
シュテファン・ドール独奏の二曲のホルン協奏曲は、さすがに唖然とする見事さ。シュトラウスの二番の協奏曲は、管と打楽器に関してだけはブルックナーの交響曲第二番と同じくらいの人数がいるのがおかしい(そしてかれらの出番は今回、前半のこれ一曲だけ)。
最後は偏愛する曲、メタモルフォーゼン。独奏弦楽器二十三人の、この音。最後にエロイカの葬送行進曲が、その姿をついにあらわにする瞬間、何度聴いてもグッと来る。このエロイカは本人ではなく、その亡霊の嘆きなのだろう(二つのブルックナーのあいだに能をみてきたので、ついこんなことを考える)。
嬉しいことに、来週にはパーヴォ&N響、来月にはツァグロセク&読響と、ひと月のあいだに三回も演奏される。貴重なメタモル強化月間(さらに、四月にもロト&都響がある)。
ところでその能というのは、某誌の編集者の方が国立能楽堂でシテを演じられた『鉢木』。
最小限の小道具による極小の空間の、究極的な見立ての美学。周囲のすべての景色、状況、世界と歴史が、人がそこにいるという、そのことに圧縮されて表現される。
人がそこにいることで宇宙がある。恐るべき見立て。そして、爆発(ビッグバン)を内包している。極小にして極大の時空。室町の大発明。
鼓と大皮と笛と掛け声と、無音の間。ただこれだけでつくられる音響の豊かさにも驚く。よいきっかけと促しをいただいたので、これから、色々と能をみてみるつもり。
内包といえば、今週の『真田丸』は、滝川一益の「もうすぐ戦がなくなる」という、あの唐突なひと言にグッとつかまれた。信長とは何者だったのかが、あのひと言に込められる。知らぬ間に置き去りにされた凡人の運命。
二月十四日(日)夏至の夜の歌
今日は、カンブルラン指揮の読売日本交響楽団を池袋の芸術劇場で。
一昨日の紀尾井シンフォニエッタ、昨日の佐藤俊介のピリオド演奏とあわせ、挑発して刺激して、脳を活性化してくれる三日間だった。まずその曲目。
十二日 モーツァルトとシュトラウス
十三日 メンデルスゾーン姉弟とシューマン夫妻
十四日 モーツァルトとマーラー
それぞれ別の団体による三つのプログラムが、打合せしたみたいにうまくできていた。なぜなら、こうして並べてきくと、マーラーとシュトラウスがモーツァルトを敬愛し、好んで演奏したのに対して、メンデルスゾーンとシューマンとその仲間は、バッハを意識したほどにはモーツァルトを参照していないことを、思い出さずにはいられなくなったから。
(森泰彦先生のご教示によると、若き日にはモーツァルトの影響が強かったメンデルスゾーンは、やがて理想のドイツ音楽と理想のドイツ建国を目指す過程で、その土台にバッハとベートーヴェンを置くようになった。そして我々も学生時代に教え込まれた、ドイツ中心の音楽史が「発明」され、ハイドンとモーツァルトはベートーヴェンの先駆者という、二次的な位置づけになったのだそうだ)。
モーツァルトは没後に忘れ去られたとまではいえないけれど、十九世紀末になって俄かに再評価され、演奏機会が増えたといわれている。マーラーとシュトラウスは、まさにその時代の子。
これまた森先生に教えていただいたことだが、理想とは程遠いがともあれドイツが、プロイセン中心に建国されたあとで、あらためてモーツァルトに目が向いた、ということらしい。マーラーとシュトラウスが、プロイセンではなく、南部のカトリック圏の出身であるのも、モーツァルトへの関心の背景にあるのかもしれない。
十二日の紀尾井シンフォニエッタの曲目は、ホルン協奏曲と弦楽合奏という似た曲種を並べることで、シュトラウスがモーツァルトから得たものと変えた(歪めた?)ものを示してくれた。
そして、その二日後にカンブルラン&読響によるモーツァルトとマーラーをきくと、これもまた、やはり同じことを意識した組合せだということを、はっきりと感じた。いまバレンボイムがやっているように、モーツァルトのピアノ協奏曲とブルックナーの交響曲を一晩に組み合わせることは、どちらもかれの十八番であるという以上の関連性はもっていないだろう。しかし、シュトラウスとマーラーは違う。
アイネ・クライネ・ナハトムジークとマーラーの交響曲第七番は、ナハトムジークつながり。前者がなぜこの曲かといえば、曲目解説にある通り、モーツァルト自身がこの曲をセレナードとはつけずにドイツ語の曲名をつけていて、マーラーがそれをうけるように、第二、四楽章をナハトムジークとしたからだろう。
開演前、オーケストラが入ってきて何より驚いたのは、第二ヴァイオリンが右にいる、対向配置をとったこと。これまでのカンブルランは、いつもピアノ配置だったという記憶しかない。そして、マーラーで人数を八型(八‐八‐六‐四‐三)から十六型に拡大しても、同じ配置をとった。となるとこれは完全に、両者の関連を意識しての配置。
そして演奏。モーツァルトはアクセントと抑揚をはっきりとつけながら、フレーズを膨らませたりしぼませたり、音量の強弱をきちっとコントロールすることで波動をつくり、しなやかに、立体的にうねらせた。第二楽章の速めのテンポでの変なアクセントも面白い。そして、全体に響きがくすんでいて、ほの暗い。たしかにナハトムジーク。
数年前にカンブルランでモーツァルトの交響曲をきいたときは、抑揚もリズムの弾力もなくサラサラと流れてしまい、さっぱり面白くなかった記憶があるが、今回は明らかに違って、生命がこもっている。カンブルランが変ったのか、オケにカンブルランの意図が浸透してきたのか、どちらかわからないけれども、とにかく今日は、音楽が脈打っていた。
この方法論は、マーラーで弦が倍増して四管の管楽器と打楽器が加わっても、変わらなかった。ドイツ音楽らしい明快な句読点づけや、段落分けはしない。論理的な構築はしない。ただ、アクセントと抑揚だけをつけて、澱みなく、流麗に音楽をくねらせていく。
たしかにモーツァルトは、ドイツ風に楷書でかっちり演奏しても面白くない。かえって響きが薄っぺらく感じられることがある。だからこの方法は大いに説得力があるし、その延長にマーラーをとらえることも、ベルリオーズなどフランス音楽との関連と影響で、納得できる(これが唯一の方法とはいわないが)。
そしてマーラーは二、四楽章だけでなく、全体がナハトムジークだった。不思議な静けさが漂っている。マンドリンとギターも、チェロの後方から、静かに、しかし明瞭にきこえてくるだけで、自己主張はしない。管楽器などのソロと同じ扱い。そうしたソロの瞬間には、他の楽器がすべて耳をすましてそれをきいているような雰囲気を、テンポと音量の微妙な操作で形成する。だから静か。
グロテスクではなく、不安感もない。金管の呼びかわしは、近くに仲間がいることを、かれらに囲まれていることを示している。見知らぬ異界ではない、親しく温かい世界としての、夜の空間。
つまり、きいているこちらも魔界の眷属、妖精界の住人であるような、安心できる空間としての夜。三楽章はあきらかに死の舞踏なのに、悲劇性はない。
四楽章まで夜できて、五楽章でいきなり日光の下での乱痴気騒ぎになるのかと思ったら、それさえなかった。《トリスタンとイゾルデ》でトリスタンが憎んでやまない、偽りの世界としての昼になって、あの第三幕の太陽の下、包帯を引きちぎりながら「さあこの血、楽しく流れ出ろ」と笑いながら死んでいく、あの自暴自棄の太陽が出るのかと思ったら、出ない(笑)。
終楽章のあのファンファーレさえ、きらきらしく突出することなく、くすんだ一体感をもって温かく響く。そしてパッチワークのようなチグハグさの代りに、さまざまな連中が顔を出す、夜の歓喜の行進になっている。
ナイト・パレードとしての終楽章。ここで、ヴィーラント・ワーグナーが一九六一年にベルリンで演出したという《アイーダ》の話を思い出した。酷暑のエジプトで、炎天下に行進する馬鹿などいるはずがないという考えの下、ヴィーラントは凱旋の行進を夜の場面にした。まさにそれ。
いやおうなく、これは夏至の日の夜、ミッドサマーズ・ナイトにきくべきものなのではないかと、思わされる。
あの夜の妖精界。シェークスピアや、山岸涼子の『妖精王』の世界。つまりメンデルスゾーンの劇音楽の拡大版のようでもある。そういう、時間の流れのなかの、交響曲というよりは長い幻想曲のような音楽。
まあ、最後は闇の中に深い崖がひそんでいて、そこにみな落ち込んでいくような、レミングの群れみたいな結末も、想起せずにはいられなかったが。
マーラーらしくなくてつまらない、退屈という意見も当然にあるだろうが、私はカンブルランのつくる音世界を、とても楽しんだ。少なくとも、ここには確固たる解釈による、独自の主張をもつ音楽がある。そしてそれは、私の脳を活性化してくれるものだった。
カンブルランがこのような「ドイツ音楽」をきかせてくれるとは思ってもいなかったので、とても嬉しいし、これからも楽しみ。
二月十八日(木)シューマン三夜
確定申告の準備。フリーランス稼業は色々なところから仕事をいただく。源泉徴収票にしたがってその一覧表をつくるのは面倒だが、顧客の数がどのくらいあって、それぞれが収入のうちのどのくらいの割合なのかを知るのは、それなりに面白い。
そういえば、自分はマイナンバーをこれらすべての顧客に教えなくてはならないらしいのだが、そんなことをしていたら、いずれどこかから漏れないほうが、むしろ不思議という気がする。
つくっていて気になったこと。中央公論新社や河出書房新社は、いつまでもこの「新社」をつけているのだろうか。ニュー・フィルハーモニア管弦楽団などはあとでニューをとっているのに。「うちは一度つぶれたことがあるんだぞ」と宣言しているみたい。
調べると、文藝春秋も一九四六年から六六年まで「文藝春秋新社」だったことがあるらしい。二十年後に銀座から紀尾井町に本社を移したときに「新」をとった。とすると、中央公論は読売傘下の新会社になったのが一九九九年、旧会社の清算終了が二〇〇一年。どちらかの二十年後が旧名復帰の目途なのかも。
河出は旧会社が存続していて、業務提携をしているそうだから、吸収合併でもすれば、というところだろうか。
今夜はトッパンホールでパドモア&フェルナーのリート・リサイタル。十三日さいたまの「佐藤俊介の現在」第二回、十七日サントリーのパーヴォ&N響と、いずれもシューマンが入っていたので、三日間の感想をまとめて。
佐藤俊介はヴァイオリンの岡本誠司、ヴィオラの原麻里子、チェロの鈴木秀美にフォルテピアノのスーアン・チャイの五人で、メンデルスゾーン姉弟とシューマン夫妻。ガット弦のピリオド楽器は、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲第六番などでは、この作品の激烈さをモダン楽器に較べて和らげてしまう。
このあたり、ベートーヴェン中期以後の弦楽四重奏曲は、その高い抽象性を響かせるためにはモダン楽器のほうがいいのかもと思う。とはいえ、そのことを知ることができたのはこうして聴けたからこそだし、終楽章の軽快な疾走感はとても素敵。
後半のシューマン夫妻の方が、フォルテピアノが入ったこともあり、ピリオドならではの魅力を満喫。クララがヨアヒムに献呈した《三つのロマンス》の第三曲でのフォルテピアノのアルペッジョの浮遊するような波動は、モダンにはない美しさ。ロベルトのピアノ五重奏曲も、全奏で音がきしむことなく、それぞれが和んで謙虚に、しかし確固として響く愉悦。フォルテピアノの音は、たしかにモダンピアノに慣れた耳には違和感があるのだけれど、弦楽器や人声との親和性がより高く、自然になじむことが、ナマだといっそうよくわかる。六百席の大きさもぴったり。
続いてN響。メタモルフォーゼンは倍弦四十六人。トップがソロをとるところ以外、基本的に一パートを二人でひく。八百席の紀尾井で二十三人で演奏した響きを聴いた直後だけに、サントリーの音響もあって、なんとも大味に感じた。紀尾井では二十三人が独奏楽器となって、1人ずつ譜面台を前にして(開演前に舞台係が二十三のパート譜を正しく並べるのが大変そうだった)、バラバラに演奏するのが聴覚的にも視覚的にも非常に刺激的だったのに、四十六人でやると、ただの弦楽合奏に感じられてしまう。
ブニアティシヴィリ独奏のシューマンのピアノ協奏曲も、サントリーの大きさと音響をもてあましている印象で、ピンと来ず。
しかし後半の《ツァラトゥストラ》は面白かった。パイプオルガンの効果といい壮麗なオーケストレーションといい、やはりサントリーホールはこういう、十六型のフルオーケストラをきくためのホールなのだとあらためて感じる。
たくましく気合の入った進行で、この曲の主人公が、実はティル・オイレンシュピーゲルによく似ていることを知る。永劫に回帰する自然と宇宙の掌の上で、キーキーキャーキャーとやかましく、しかし束の間の時間を生きるだけの人間。最後は自然に対して、そのはかなさを憐れんでくれと懇願するが、まるで無視される。ティルが最後に助命を請う相手はまだしも同じ人間だから、一応対話にはなるが、ここでは永遠の自然が相手だけに、まったく融和の余地がない。
矮小なるかな人類、救いなきかな、人類。
そしてパドモア。日本の不安定な気候もあってか、あまり調子がよくなかった様子。たとえば、アンコール曲にはお得意の、そして確実なものを選ぶはずなのに、今日はそのアンコールのシューマンの《月の夜》で、音をとるのにかなり苦労していた。しかもリート・リサイタルでは珍しく、一曲しか歌わなかった。
とはいえ、シューマン以外はその不調を感じず。前半二つめのツェンダーの《山の空洞の中で》(日本初演)は、あの面白い《冬の旅》の編曲をやった作曲家だけあって、プリペアード・ピアノ的な音が登場。面白いのは、弦に何かを装着してアップルのラップトップと接続し、その操作で音を変えていたこと。プリペアード・ピアノの仕掛けを禁止するホールもあるそうだが、こういう電子的な操作なら反対が少ないのかも。
そして今日の白眉は、ベートーヴェンの《遥かなる恋人に寄す》。第二曲から第六曲までをアタッカで一気呵成に駆けぬけて、雲に乗って空を飛ぶように、遠い恋人への熱い愛を歌で走らせる。こうすると、最後のくどいほどにくり返す凱歌が、まるで《運命》のコーダみたいに感じられてきて愉快。
しかしシューマンは難しい。もっと、フィッシャー=ディースカウ風に上から旋律を抑えつけるような歌い方、音を置くような歌い方が、この作曲家にはあっているのだろう。ベートーヴェンのように、音を弾ませて勢いよく歌いまわす方法はとれない。響きが重くなることで、調子の悪さがむき出しになる。初めの五つの歌曲の《母親の夢》と《兵士》などは、皮肉で意地悪な詩がマーラーの《子供の魔法の角笛》の先取りみたいで、面白かったのだけれども…。
CDでは、シューマンの《詩人の恋》もベートーヴェンも、フォルテピアノのベザイデンホウトと共演している。こういう不調のときこそ、フォルテピアノの軽妙な響きなら、と思ったりするのは、さいたまで聴いたばかりだからこそ。
そういえばベザイデンホウト、十月にイザベル・ファウストとデュオで来日するよし。これもいまから楽しみ。
二月二十一日(日)ドイツのCD
ドイツのショップ、JPCからディスク到着。日本ではまだ予告の出ていないいくつかを注文したもの。
まずは、ペーター・シュタンゲル指揮タッシェンフィルハーモニーによる、マーラーの交響曲第七番。

シェーンベルクの私的演奏協会ふうのマーラーの室内アンサンブル版がこのところ流行している。オリジナルの第四番と《大地の歌》のほか、第九番など新たな編曲もふえているようで、これもそのひとつ。第七番を管八、打三、ギターとマンドリンの持替え一(持替え…)、ハープ一、弦六の十九人だけで演奏してのけたもの。
タッシェンフィルとは、ポケット・フィルハーモニックの意味。ポケット戦艦「アドミラル・グラーフ・シュペー」が好きだった人間としては、ポケットという言葉を目にするだけで心が騒ぐ。ほかにベートーヴェンの七番とかモーツァルトの四十と四十一番のポケット版も出ているが、どうせきくならマラ七。「いつもポケットにマラ七を」
早速きいてみる。やはり十九人で演奏するにはかなり無理が(笑)。ポケット戦艦というよりは、日清戦争のときの三景艦(松島、厳島、橋立。戦艦を買うお金がないので、一門だけ巨砲を積んだ小型艦を三隻そろえて、すばしっこく走りまわらせた)みたいな感じ。終楽章は、接近戦に持ちこんで副砲ポンポン撃ちまくって勝った、黄海海戦みたいな爽快感があるが、やはり戦艦定遠を撃沈するまではいかない。
でも面白かった。ポケット版のマーラー全集を、いつの日か期待。
ほかに、ジョナサン・ノット指揮ユンゲ・ドイツ・フィルによる、グバイドゥーリナのヴィオラ協奏曲(タメスティ独奏)とブルックナーの九番の二〇一五年ライヴ。粗いけれど、若い勢いをノットが大きな呼吸感でまとめていて、かなりいい感じ。
そしてフンガロトンから出た、クリストフ・バラーティのひくヴァイオリン小品集、など。


二月二十四日(水)銀座歩き
今日は久々の帝都クラシック探訪。新橋~銀座~丸の内~日比谷を、右左折をくり返して迷路のようにめぐる、百五十年の洋楽史がギュッとつまった地域。
おつきあいくださった片山杜秀さん、ラジオ番組用に収録してくださったミュージックバードの田中美登里さんたちと。楽しかったが寒かった。

二月二十八日(日)イェヌーファ
新国立劇場で《イェヌーファ》初日。日経新聞の評の担当なので細部は控えるが、みるべき価値のある演目と舞台。
初日がマチネーというのは難しかったのではないかと思うが、本格的にエンジンがかかった二幕以降は、殺風景な白い壁だけの部屋に重なって、自分の頭の中に、「聖母子像」のイメージがずっと浮かんでいた。
みどり児の二重写し。「人の罪」と「赦し」の意味。まるでクリスチャンではない自分にも、キリスト教文化のことを考えさせずにおかない舞台。受難節の時期にぴったりの演目(《サロメ》がアドベントにふさわしかったように)。
一方で、二幕のコステルニチカの決意をきいて、反射的に連想した言葉が「最終的解決」。手前勝手な論理(神様はご存じだ)がもたらす、狂気の飛躍。
そして、最後に断罪を叫ぶ村人の群れは、安全な場所から正義をふりかざす、「ネット正義」の人びとのようだった。キリスト教的な「愛」から、おそらくもっとも遠いもの。
三月五日(土)架空の過去から
オペラシティで、シギスヴァルト・クイケン&ラ・プティット・バンドによるバッハのマタイ受難曲。

今季はマタイの当り年とでもいうか、東京では面白そうな実演がならぶ。自分はそのうち三つ、それぞれスタイルが違うはずの三つの団体の公演をきくつもりだった。
最初は、敬愛する福島章恭さん指揮の一月三十日の目黒パーシモンホールでの公演。目黒パーシモンホールはかつての都立大学の跡地で、自分にとっては小中学校へのバス通学の乗り換え地点として七年ほど毎日通った場所だから、地縁も感じて楽しみにしていたが、仕事で他の公演に行くことになり断念。すばらしい公演だったという評判にかさねて、三月一日のバッハゆかりのライプツィヒ・トーマス教会での公演も大成功だったそうで、まことに悔いが残る。
いきなり計画が狂って、残るは二つ。まずは今日のクイケン。
いうまでもなくピリオド楽器、そしてOVPP(ワン・ヴォイス・パー・パート)、つまり独唱と合唱を一パート一人で兼ねる最小編成の歌で、実演ではどんな響きになるのかが楽しみだった。
オーケストラは十一人(弦六、管四、オルガン)×二の二十二人。声楽は四×二に、ペトロやユダを歌う男性二と女性一の十一人(ただしあとの三人はあくまで補助的役割で、合唱は基本的には四×二だけ)で、計三十三人。
第一群が下手側、第二群が上手側に、鶴翼の陣形(だからこういう軍事用語は使うなというのに)でならぶ。前から歌手、管、弦の三列。オルガンはそれぞれの、客席からみて右端。補助の歌手三人は中央最後部。
面白かったのはクイケンの位置。「指揮者」として中央に立つのではなく、第一群オーケストラのリーダーとしてヴァイオリンをひきながら、いちばん下手、つまり左端の最後列にいる。位置的に第一群の管楽器と歌手は、クイケンのことがほとんど見えない。なので第一群の歌手が通奏低音と管だけでソロを歌う場合は、基本的におまかせ。顔のみえる第二群に対しても、ときどきキッカケと冒頭のテンポを与えるくらい。
コンダクトではなくディレクション、アーティスティック・ディレクションという立場。カペルマイスターは不在。カントルは留守。
カペルマイスター抜きは歴史的なマタイとしては考えにくいスタイル。OVPPにしても、プログラムで磯山雅さんが書かれているように、「ライプチヒにおいてそうであったとは考えにくい」。つまり、バッハがマタイをこの人数で指揮したとは考えにくいわけで、史実に従ったものではない可能性が高い。むしろ、多分にシェーンベルクの私的演奏協会的な「見立ての美学」に則ったスタイル。
これが面白い。カリスマ的な指導者に統率される、優秀なソロと規律のとれた大集団という、国民国家と近代軍隊と重工業の発達とともに広まっていく、「国民音楽としてのオラトリオ」に、あえて背を向けたスタイルだから。
ヘンデルが国民国家の元祖イギリスで育て、ハイドンがオーストリアに、そしてメンデルスゾーンがドイツに持ちこんだ、「国民音楽としてのオラトリオ」。「ドイツ国民音楽、理想のドイツ音楽」の基礎となる「ドイツ中心の音楽史観」を発明するべく、その元祖「音楽の父」にバッハを位置づけようとするならば、マタイ受難曲は「国民音楽としてのオラトリオ」の元祖でなければならない。メンデルスゾーンが初演百年後にこの作品を、教会ではなくコンサートホールで蘇演したときは、おそらくはそのように演奏したはず。
そのような演奏は、壮大な響きと劇的感動にあふれ、自国語で歌うものときくものとを、没入と陶酔のなかでロマンティックに渾然一体とさせうる。すなわち「国民の創生」。幸福であり、危険もはらむもの。
クイケンたちの演奏は、そうした「未来へのバッハ」ではなくて、あえていえば「架空の過去から来たバッハ」のようなものだった。ヴァイマルやケーテンでの若き日の、OVPPによるカンタータ演奏――そういう演奏があったと仮定して――や、あるいはナポリ楽派やヴィヴァルディの、独唱とわずかな重唱だけで合唱ぬきにつくられたオペラとか、そうしたものから出てきた、マタイ受難曲。
けっして大向う受けの効果をねらうことなく、端然と、激情と陶酔を排し、清澄に歌われる受難。ごまかしのきかない演奏法だけに、実演での完璧な演奏は困難だったが、こちらもつねに覚醒した状態で臨める、美しい音楽。
三日前の二日に、タローのひく、まったくドイツ的でないゴルトベルク変奏曲をトッパンホールできいたのに続けて、こうしたマタイをきけたのも意義深かった。ドイツ人がOVPPのマタイをやらない、録音しない理由も、ものすごくよくわかったように思う(笑)。
三月十一日には、トーマス教会合唱団のマタイ受難曲をきく予定。優れたソリストと大編成の合唱を、ゲヴァントハウス管弦楽団が伴奏する、おそらくは現代的な「国民音楽としてのオラトリオ」になるだろう演奏。
私はきくだけの人間だから、どちらか一つを取捨選択する義務も権利もない。ただ、かりそめの世の日々を生きるなかでさまざまな実演と録音に接し、再現芸術の底知れぬ、はてなき深さと広さに歓び、ときに恐れ、そして、音楽家たちに感謝するのみ。
書き忘れたが、ラ・プティット・バンド第一群のトラヴェルソはフランク・トインス、オルガンはバンジャマン・アラールで、さすがに見事な演奏だった。クイケンは一曲だけヴィオラ・ダ・ガンバを演奏。それにしてもアラール、ソロをナマできいてみたい。
三月六日(日)アーノンクール死す
アーノンクールの訃報。
突然の引退発表がさぞかし無念だろうと感じる形だったので、ひょっとしたらと思ってはいたが、残念ながらそのとおりに。
ネットでそのことを知ったのが、夜の九時半頃。私は有名人の訃報にあまり心を動かされるタイプではない。だが、アーノンクールの場合は、中断した、そして未完に終ったベートーヴェンの交響曲全集の計画が、いまのクラシックの状況に深く関わっているもののように感じていたので、さすがに感慨が深い。
すると四十五分ほどして「音楽の友」の編集長からメール。十二時間後の明日朝十時までに、二千四百字で追悼記事を書けないかというもの。
普段書かせてもらっている「レコード芸術」や「モーストリークラシック」なら、校了までまだあと数日あるはずだから、今頃は記事の差替えなどでおおわらわだろうと思っていたが、それより校了の早い「音楽の友」がまだ間に合うとは思わなかった。日曜の夜なので、さすがに印刷所には連絡がつかないとか。
こういう依頼をもらって、ふるい起たない書き手はいない。勇んで引き受け、翌朝、一時間遅れで何とか入稿。
三月十日(金)午の吹奏楽
昼は皇居東御苑、すなわち旧江戸城本丸御殿跡に行き、皇宮警察音楽隊のランチタイムコンサートをきく。

明治末から大正にかけ、日比谷公園で陸海軍の軍楽隊が行なう吹奏楽は、当時の日本人が接することのできた、数少ない大規模な西洋式オーケストラだった。
今回は日比谷公園でも軍楽隊でもないが、かつて正午に午砲(いわゆる「丸の内のドン」)が撃たれていた場所の芝生できく、吹奏楽。周囲の係員が着るウィンドブレーカーの背に英字で「インペリアルガード」とあるのが格好よかった。
夜はサントリーホールで、ツァグロゼク指揮読響。演奏についての感想は評を書くので省いて、ここでは曲目のこと。
ブラームスの悲劇的序曲、シュトラウスのメタモルフォーゼンに、ブラームスの交響曲第一番。
紀尾井、N響に続いて二月から三つ目のメタモルフォーゼンについては、プログラムにはツァグロセクのメッセージとして、東日本大震災の犠牲者追悼のために演奏すると書いてあった。同時に、東京大空襲を重ねることも可能な日付。全体の構成自体も、暗から明へ、という明快なメッセージになっていた。
三月十一日(日)トーマス教会のマタイ
五年目の震災当日の夜は、芸術劇場でトーマス教会合唱団のマタイ受難曲。
トーマス教会のマタイは、二〇一二年二月にもオペラシティできいている。あのときは直前に亡くなったゲルハルト・ボッセ追悼のために、冒頭で第六十二番の合唱曲が、聴衆を起立させて歌われたものだった。それ以来のマタイ。
違うのは、トーマスカントルがビラーからシュヴァルツに交代したこと。平板で緊張感に乏しかった前任者よりも起伏があって、はるかに短く感じられた。
それにしても、五日のラ・プティット・バンド公演とは、何から何まで対照的なのが面白かった。
トーマス教会でのマタイ上演はバッハの死で一世紀ほどのあいだ途絶えて、メンデルスゾーンの蘇演の影響を受けて復活する。このメンデルスゾーン流のコンサートホールでの十九世紀のロマンティックな方式と、教会の慣習的な方式が混合し、そこに二十世紀の考証がくわえられた、あらゆる意味で折衷的な公演。
伴奏のゲヴァントハウス管弦楽団はモダン楽器をメインとし、リュートやガンバ、チェンバロにオルガンなど、通奏低音主体に古楽器を加えた編成。これは二十世紀前半のカントル、シュトラウベあたりで始まって、次のラミンの時代にほぼ完成し、リヒターなどが受け継いだ、トーマス教会のスタイル。
弦は五‐四‐三‐二‐一を二つ、左右に分ける。合唱も四十五人を左右に分けてあるが、通奏低音は共通。歌手もバスが二人いる以外は各声部一人。完全にシンメトリックに二グループあったラ・プティット・バンドとは、別の考えかた。
合唱は教会の伝統に従って、少年と青年のみ。要所要所では劇的に歌う。ユダやペトロなどのソロは後方の合唱から出る。緊張もあって最前列のソロ歌手との力量の差は歴然だけれど、人としての弱さをみせるユダやペトロは全キリスト教徒の代表だから、これはこれでいい。
前回の独唱陣はいかにも普段着的というか、現地で日常的に共演していそうな顔触れだったが、今回は中国、韓国ツアーも兼ねているためか、とても強力。ルーベンスとシャピュイの女声、ドラマチックな福音史家のペッツォルト(本来はもう一人のテノール役だったが、予定のブルンス不調のために福音史家を兼任。じつは四年前も、ゲンツ不調のために独りで歌った)、それにイエスのヘーガーとピラト他のベッシュ。
前回はピラトのバスが不調で、客席より合唱の少年たちがあからさまに退屈そうな表情をしたのが面白かった(まさにかれらは私たちの代表なのだ……)が、今日はベッシュが朗々と歌い、少年たちと客席をひきつけた。
プロのソロと未熟な合唱の対比。ヴァイオリンやフルートがソロをとるときには立ちあがって、オケの集団から際立たされることなど、ソロと集団のヒエラルキーが明快なことが、指揮者すらいなかったラ・プティット・バンド公演との、決定的な違い。
帰宅して、ラ・プティット・バンドのマタイのSACDをききなおす。ディスクでしか知らないときには、ただぬるめの演奏としか思っていなかったけれど、ナマをきいたことでその「ぬるさ」の興趣、意味と意義、価値が、鮮明にききとれるようになってきた。
古楽運動というのが、大交響楽団に象徴される、人間集団の機能的な組織化という産業革命以降の近代史に対するアンチテーゼ、異見表明という一面をもっていることを、あらためて実感。
ところで四年前の不調のバス歌手、あとで調べたら、どうやら今日指揮をしていたシュヴァルツだったらしい……。
あとは、『帝都クラシック探訪』最終話のために、平将門伝説の由来の勉強。樋口州男著の『将門伝説の歴史』(吉川弘文館)。
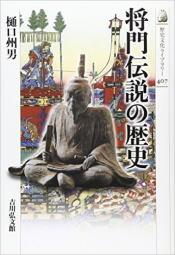
面白いのは、将門を死後すぐに伝説化させていく人びとが、最近の研究ではどうやら、道真を怨霊化させることで自分たちの復権を、少なくとも憂さ晴らしをもくろんだ、道真の不遇の遺児たちと弟子に連なる人脈らしいと、みえてきていること。
左遷されたかれらは、将門が暴れた常陸などの遠国で吏人、つまり事務方をやっていたらしいのだ。中央で身につけた文筆能力をもつかれらが書きとめないかぎり、僻陬の地の反乱者の伝記、すなわち『将門記』などが、きちんとした形で残るはずはなかった。
伝説の裏の、なまなましい現世の人間たちの思いと恨み。
三月十二日(土)タンゴの生命
今日はオペラシティで、「小松亮太 タンゴの歌 featuring バルタール&グラナドス」。

演奏するのはバンドネオンの小松亮太と特別編成のタンゴ・オルケストラ・エスペシアル(総勢二十一人、ただし同時に演奏するのは最大十五人)。
前半はレオナルド・グラナドスの歌と語りで、ピアソラがボルヘスの詩に作曲した組曲「エル・タンゴ」。小松いわくブエノスアイレスの任侠物。弦楽やコーラスが部分的に参加する、ピアソラ自身がアルバムのみでやっている凝った編成を、ナマできかせるのがミソ。
そして後半はアメリータ・バルタールが歌う、ピアソラやガルデルなどの歌。編曲はピアソラの曲はピアソラ自身、他は小松によるもの。ピアソラはバルタールと出会って、オペリーノ《ブエノスアイレスのマリア》の主役に起用して一九六八年に上演と録音、翌年には大ヒット曲《ロコへのバラード》を彼女のために書いた。私生活でも伴侶となり、一九七四年の離婚までピアソラの歌姫をつとめた、伝説的存在(ピアソラがミルバと共演するのはこのあと)。
独特のしゃがれ声に宿る、歌の力。彼女が袖に入って器楽のみで美しく演奏されたガルデルの《首の差で》のあと、舞台に出た途端、「なぜあたしには歌わせないの」とばかりに同じ歌をアカペラで勝手に歌いだしたりと、自然体のステージマナーがなんともカッコいい婆さん。
《ブエノスアイレスのマリア》からの〈受胎告知のミロンガ〉と、《ロコへのバラード》が圧巻だった。ピアソラの音楽とオーケストレーションも冴えに冴えていて、この歌手がかれに与えた霊感の大きさと深さを思い知る。
小松とバルタール、グラナドスは二〇一三年六月にオペラシティで《ブエノスアイレスのマリア》全曲を演奏して、ソニーからライヴ録音も出ているが、自分は他の批評仕事と重なり行けなかった。今日〈受胎告知のミロンガ〉をきいて、ききたかったと悔やまれることしきり。
そして、この《ブエノスアイレスのマリア》は、東日本大震災との結びつきが深い公演でもある。もともと、二〇一一年三月十九日に公演が予定されていたのに(ただし、このときはバルタールは参加しないはずだった)、練習中の三月十六日に公演中止を発表。それから二年後にバルタールも加わって、ようやく実現にこぎつけたものだった。
それから五年、ちょうど一週間前にラ・プティット・バンドのマタイをきいたホールで、今度はタンゴ。冒頭のあいさつで小松は「あれから五年、生きて音楽ができることに感謝」と語った。こちらも「生きて音楽がきけることに感謝」しなければ。
そういえば、第一部の公演中、体調を崩したお客が担架で運び出される事件があった。一階の後方、上手側の壁際の席の方だったので、客席の大半が気づかずにすみ、進行に支障はなかったが、担架が入ったのは二階席からみていてもショッキングだった。大事にならないことを祈るのみ。
生きて音楽がきけることに感謝。
三月十八日(金)三日間、遡る時間
水曜日は上岡敏之指揮新日本フィルでサントリーホールへ行き、木曜日はリッカルド・ムーティ指揮日伊国交樹立150周年記念オーケストラで東京芸術劇場へ行き、金曜日は「附子・小塩」で国立能楽堂へ行った。
ともだちよ これが私の三日間の仕事です テュリャ テュリャ テュリャ テュリャ テュリャ テュリャリャ テュリャ テュリャ テュリャ テュリャリャ~
演奏会の感想というより、そこから連想した、さまざまな時間のこと。
お気に入りらしい焦茶色(?)のテカテカの服を着た上岡のマーラー《巨人》は、この人らしいケレンのきいたもの。随所で弦のグリッサンドというよりもポルタメント、というよりもずりあげさげを多用。二〇一二年に読響でマーラーの交響曲第四番をきいたときも第三楽章でやったことを、より徹底してしかけてきた。そして最後にはホルンとトランペット全員を起立させて強奏。視覚的だけでなく音量的にも目の覚めるような効果。
先月の「レコード芸術」誌のレビューのために、アバド&ベルリン・フィルのラスト・コンサートのディスクを試聴した。映像として、ある意味で本番よりも興味深かったのが、ボーナスのDVDに入っている、一九九〇年の就任時のドキュメンタリー。選挙が行なわれた一九八九年秋にはまだ「ベルリンの壁」が存在していて、そこから就任までの間に、壁の崩壊という大事件が起きる。まさに新しいエポックの始まりという気分を見事にとらえたドキュメンタリーで、最後に就任披露演奏会のための、《巨人》のリハーサルが映る。
そこでアバドは、楽譜通りにコーダでホルンを立たせてみる。しかし演奏者も指揮者も照れたように笑いだし、「大げさだったね」のひと言で断念。ベルアップだけにとどめる。つまり、四半世紀前の一九九〇年にはまだ、この程度でさえおおごとだった。新日本フィルの演奏をみながら、時の推移を実感。
続いてムーティの演奏会では、ボーイトの《メフィストーフェレ》のプロローグ。ナマできくのは初めて。大編成オケにバス独唱と百人の合唱、それに児童合唱にオルガン、十七人のバンダが轟然と鳴り響く、壮大な音響体。《アイーダ》初演の三年前の一八六八年に、〈凱旋の場〉の前に、二十六歳でこういうものを書いたボーイトに、あらためて驚く。
このプロローグの迫力を広く世に知らしめたのは、なんといってもトスカニーニ。録音が残っているものでは、一九四六年のミラノ・スカラ座再建記念演奏会でロッシーニ、ヴェルディ、プッチーニに続いて、この場面を全体の〆に取りあげているし、一九四八年スカラ座でのボーイト没後三十年記念演奏会では、この場面を最初に演奏した。いずれも指揮者とオーケストラが化学反応を起したような爆発的演奏で、後者はトスカニーニ生涯最後の舞台つきオペラ上演ということでも意義深い。
そして、いちばん一般的なのは、RCAがレコード化した、一九五四年三月十四日のNBC響とのカーネギー・ホールでの放送演奏会。
ここからは、しばらくぶりに「一九五四/五五」の話(まだ、モタモタと書き続けている……)。
この日の客席には、吉田秀和がいて、「とても迫真力があって、息苦しい位の熱気があたりに漲り、何か背筋がぞくぞくしてくる」と『音楽紀行』に書いた。
返す返すも残念なのは、一週間前の六日と八日にライナー&シカゴ響のR・シュトラウスの《ツァラトゥストラはかく語りき》と《英雄の生涯》を録音していたRCAのステレオ録音チームが、この公演に間に合わなかったこと。
結局、遅れてきたかれらは一週間後の二十一日の《悲愴》交響曲そのほかと、四月四日のワーグナー演奏会をステレオ録音したが、これらはトスカニーニの衰えが顕著で、リリース不能と判断された(世に出ている録音はその非正規のコピー)。《悲愴》は楽員が「トスカニーニはリハーサルにはちゃんといたんだが、本番にはいなかったんだよ」ともらすような代物で、ワーグナー演奏会はいうまでもなく、記憶障害のために「ラスト・コンサート」となったもの。この二つの演奏会の間の三月二十五日にトスカニーニは引退を最終的に決意し、かねて用意の引退表明文にサインをして、NBC会長宛てに発送している。
ということで、三月十四日の放送演奏会(奇しくもヴィヴァルディ、ヴェルディ、ボーイトという、イタリア・プログラム)は、トスカニーニの生涯最後の、その名に恥じぬ大花火だった。
そして《メフィストーフェレ》のプロローグは、正規にリリースされたもののなかで(そしておそらく、本人が自ら発売を許可したもののなかで)、トスカニーニ生涯最後の演奏となっている。
愛聴盤ではあるが、それがさらに、ステレオ録音されていたら。
覆水盆に帰らず。それから六十二年後の二〇一六年三月十七日、ムーティの指揮でそのナマの響きを耳にする歓び。
十八日の能の「小塩」で、いちばん印象に残った語句(元は漢詩)。
「春宵一刻値千金」(しゅんしょういっこくあたいせんきん)
春が来た。

三月二十二日(火)高遠桜
東京は昨日が開花宣言。家近くの高遠桜は、いつものごとくそれよりも早く、もう満開。

クローンで一斉に咲くソメイヨシノは、東京には五輪前後の高度成長期に大量に植えられたという点もあわせ、昭和の一億総中流幻想に似たところがある。居心地のいいもので大好きだったけれど、そろそろ寿命で、どうするか。次は色々な種類の桜を植えて、バラバラに開花させるのもいいのでは。
三月二十三日(水)千駄ヶ谷と古雑誌
久しぶりに千駄ヶ谷の二期会でインタビューの仕事。終って、近くの鳩森八幡へ。ここは五叉路に面して神社があるのが、いかにも異界の入り口じみて、夜にくるともっと面白げな雰囲気になる。

写真は境内にある一七八九年築造の富士塚。富士山を模した築山。左手にみえる小さい社が里宮。中央の大きな鳥居の左端上の石段の上が山頂で、そこに奥宮がある。写真ではわかりにくいがゴツゴツした火山岩をつみあげたものなので、ほんとうに山っぽいのが愉快。小さいくせに登山道も何本もある。

千駄ヶ谷から外苑西通りを北へ歩くと新宿御苑の東側、大京町交番の先の川跡に「伝 沖田総司逝去の地」なるプレート。このへんに水車があって、脇の植木屋の屋敷で沖田は死んだとされている。
沖田の最期といえば、一九六五~六六年NET放映のテレビ『新選組血風録』(結束信二脚本)が決定版。
沖田役の島田順司と、土方役の栗塚旭の今生の別れのやりとり。
土方「今度生れるときはな、俺は、お前のような人間に生れたいと思っているよ」
沖田「うふっ、困るなあそれじゃ。だって私はね、今度生れ変ってくるときも土方さんと同じような人に、逢いたいと思ってるんですから」
このプレート、前に歩いたときは気がつかなかったと思ったら、二年前につくられたばかり。沖田は浅草裏の今戸の松本良順邸で死んだという説もあって、この説明文はあいまいに濁した書きかた。

家に届いた、「音楽之友」一九五五年と五六年の二十四冊揃いと、「レコード藝術」一九五六年八月号。
当時の「音楽之友」は小ぶりのA5版(文芸誌などは今もこのサイズ)。「レコード藝術」も一九五五年までは同じだったが、この年から今と同じB5版。
東京文化会館の音楽資料室に行けば無料で閲覧できるとはいえ、それではまとまった記事以外を見落としやすい。小さなニュースや、インタビュー記事で聞き手が思わずもらした片言隻句などにあらわれる、当時のホンネの気分(後世になると都合が悪いのか、しばしばなかったことにされてしまうもの)は、手元にあってこそ気がつくことが多いので、買えて嬉しい。
さすがに六十年前の雑誌となると、一年揃っているものは少なく、しかもネット検索だと店頭よりも概ね割高。今回は十二冊そろって五千円と手頃、しかも二年分あったので、ありがたし。『一九五四/五五』のラストスパートに必ず役立つ、……と思いたい。
三月二十五日(金)最近買ったディスク
「気になるディスク」の更新をさぼってばかりいるので、代りに最近購入したディスクをまとめて。
いずれも、ミュージックバードの「ニューディスク・ナビ」で順次紹介の予定。

まずはバロック系。時節柄、受難曲が三つ。
左上はイギリスのダニーデン・コンソートがOVPPでやったマタイ。二〇〇八年の旧譜だが、クイケン以外のOVPPがきいてみたくなったので。
左下はベルニウスのマタイSACD。
中上はヤーコプスのヨハネ。
中下はようやく出た、ルセによる平均律第一巻。
右上はピション指揮アンサンブル・ピグマリオンのアルバム「ラインの娘~シューベルト、シューマン、ブラームス、ワーグナー」。女声合唱によるしゃれた選曲で、メゾのフィンク、ハープのセイソンと共演も豪華。
右下はベイエとリンコニーティによるパッヘルベル作品集。

左上と中上は、バロック・ヴァイオリンのミナーシと鍵盤楽器のエメリャニチェフのディスク。クルレンツィス指揮のモーツァルト・オペラで強烈なフォルテピアノをひいていたエメリャニチェフ、思ったとおりの表舞台登場で、最近はミナーシと仲がいいらしい。左上は両者のモーツァルトのヴァイオリン・ソナタ三曲。
中上はハイドンの協奏曲などを、二人が一枚ずつ指揮した二枚組。オケはミナーシ率いるイル・ポモ・ドーロ。
左下はモルロー指揮シアトル響のアイヴズ作品集。交響曲三番と四番、《答えのない質問》に《宵闇のセントラルパーク》と、お買い得な一枚。
中下は昨日から大はまりのディスクで、フランスの若手チェロ奏者クリスチャン=ピエール・ラ・マルカがピリオド楽器アンサンブルのレサンバサドゥールなどと共演した「CANTUS」。バッハ、フォーレなどの聖歌を、モダン楽器におそらくガット弦のチェロで演奏したもの。やわらかく澄んだ響きと歌いくちがたまらない。トリオ・ダリのメンバーでもあるラ・マルカ、ヨーロッパではバッハの無伴奏全曲とフランス歌曲のチェロ編曲版も出ているので、あわてて注文。兄弟(?)のヴィオラ奏者アドリアン・ラ・マルカもCDに来日公演と活躍中なので、あわせて注目していくつもり。
右上はマイアベーアの歌劇《ディノラ》。チオーフィ主役、マッツォーラ指揮のベルリン・ドイツ・オペラ。
右下はピアノ六重奏の「ストックホルム症候群」アンサンブルのアルバム「移動祝祭日」。ヴォーン・ウィリアムズのピアノ五重奏曲(シューベルトの《ます》と同じ編成)、ラヴェルの《口絵》と《クープランの墓》、ファリャの〈火祭りの踊り〉と、ベルエポック期の作品の選曲とアルバム名、そして、何とも言えないアンサンブル名(笑)にひかれて購入したもの。

左上は、コルトーの弟子のピアニスト、ジル=マルシェックスの録音集。この人は大富豪のバロン薩摩こと薩摩治郎八が大正十四年に日本に招いて、帝国ホテル演芸場で最新のフランス音楽を初紹介したことで有名。獅子文六がその思い出を書いていたはずなので、きくときはあわせて読みなおすつもり。
左下は美空ひばりのラジオ音源のライヴ録音で、一九五八年の歌舞伎座公演のほか、一九五六年に初来日したペレス・プラード楽団と三人娘の浅草国際劇場での共演もあり。ひばりもききたいが、ラテンクォーターのフィリピン・ギャングがつれてきたときのペレス・プラード、というのが興味津々。
中上はヘンデルのオラトリオをメンデルスゾーンが一八三三年に編曲したもの。「国民音楽としてのオラトリオ」の実例になるか。
中下は、昨夜トッパンホールでまた見事な《水車屋の美しい娘》を歌ってくれたクリストフ・プレガルディエンの息子、ユリアン・プレガルディエンの「シューベルティアーデ」。ピアノ伴奏ではなくフルートのアンタイ、ギターのシャビエ・ディアス=ラトーレ、バリトン(楽器)のピエルロというピリオド楽器の名手たちと共演しているのが面白そう。小プレガルディエンは五月のトッパンホール公演も楽しみ。
右上は、コパチンスカヤがホリガーの指揮で演奏したシューマンのヴァイオリン協奏曲。
右下は、エラス=カサド指揮のメンデルスゾーンのスコッチとイタリア。
三月二十六日(土)母校へ
今日はまず、午前中から小学校の創立百四十周年記念式典に行く。
学芸会や卒業式でつかった、千人くらい入る児童館でやるというので、約四十年ぶりにそこへ入ってみたくなった。いまどきオヤジが一人で小学校に行っても変質者扱いで入れてもらえないだろうが、今日は堂々と入れる。
せっかくだから、家からバス通学したときのルートをつかってみたいと思って調べると、幸いまだ同じ路線が残っている。東横線の都立大学駅まで行って、その近くのバス停から乗ることに。バス停のあたりにあったはずの中古レコード店「ハンター」の跡地をさがしてみたが、よくわからず。
正午前に始まった式典、二、三百人くらいだろうか。いちばん上は一九三一年卒業と言っていたような。最後はみんなで歌。団伊玖磨作曲の校歌と、元々はウチの卒業式専用でつくられたが、今はほかの小学校でも歌うという、岩河三郎作曲の《ゴールめざして》など。
小学校のOB会というのもあまり多くないと思うが、結局そのアイデンティティは、「歌の共有」にある気がする。歌があるから、それを歌うために集まる。旧制高校の寮歌祭とかと似ているのかも。
早稲田だって《都の西北》があるからこそ、というかそれ以外のアイデンティティはない気がする(そういえば数年前に高田馬場でサークルのOB会をやって、最後にコンパ恒例の校歌斉唱を始めたら、「歌はやめてください」と店員に注意された。高田馬場の飲み屋で個室借りても校歌が歌えない時代が来たのかと、驚いたことがあったっけ)。
十四時に終って、十五時開始の山田和樹と日本フィルによるマーラー・ツィクルスをきくべく、自由が丘駅経由で渋谷のオーチャードホールへ。小学校と隣の中学の外を歩いていたら時間を食い、1曲目の武満徹の《ノスタルジア》はききそこねる。前々回の《系図》の美演といい、ヤマカズの武満は柔和で美しいもののはずだから、残念。
休憩後に席について、交響曲第六番《悲劇的》。ヤマカズは緩徐楽章を三楽章にすえた。個人的には第二楽章にする古典派交響曲配列のほうがいい気が最近はしているが、これはこれでロマンッチックな劇的構成になる。
マーラーはこの曲で、ロマン派音楽崩壊への一歩を踏み出した。ヤマカズは緩徐楽章の澄んだ悲しさが素晴らしい。西洋的でない、肉食人種的でない響きに、武満の音楽に通じるものを感じる。終楽章はその破綻。英雄の死というよりは、「ある夢の終り」のような。最上段中央で、これ見よかしとばかりに打ちおろされるハンマーの打撃や、三人同時のシンバルなど打楽器の威力を視覚的にも強調したのは面白かったけれど、むしろコーダ直前のトロンボーンによる暗い挽歌が印象に残った。
終って時計をみると十七時十二分、あわてて外へ出てJR渋谷駅に行き、山手線で上野駅、そして東京文化会館の小ホールへ。
十七時五十八分、開演予定の二分前にすべり込んで、東京・春・音楽祭のコンサート「シェイクスピアの時代 ― 文芸の扉を開くイングランド ~シェイクスピアが聴いた音楽」。
没後四百年のシェイクスピア時代のイギリス音楽。一九〇〇年前後のマーラーから、一六〇〇年前後のダウランドへ、三百年の時の遡行。メゾソプラノの波多野睦美、リュートのつのだたかし、リコーダーの浅井愛、それにヴィオラ・ダ・ガンバが福沢宏、坪田一子、譜久島譲、田中孝子の四人という古楽アンサンブルによる、ダウランドそのほか、金管と打楽器が心に突き刺さるような巨大サウンドの直後の、古楽器の慎ましく優しい響きの快感。
シェイクスピアとエリザベス一世の時代のイギリス音楽はこんなにも豊穣で、ファンタジーに満ちていたのに、少しのちのパーセルの死で途絶える不思議。
アンコールは歌入りの《グリーンスリーヴズ》。シェイクスピアの戯曲世界の背景には、こうした歌と旋律があった。
ここにも歌の力。これをいちばんうまく後世に引き継いだのは、ゼッフィレッリの映画版『ロミオとジュリエット』の、あのニーノ・ロータ作曲の歌だろう。それを口ずさみながら帰宅。
以下、母校関係の写真。

都立大学駅の改札口。二つ隣の学芸大学駅同様、大学移転後も駅名だけが残っている駅。三十年前、手前の柱かその奥の柱に「いつか人が人を喰う時代がくるであろう」と大書されていたのが、いまも忘れられない。

都立大学駅脇の八雲堂書店は昔のままだったので、嬉しかった。

校庭のどんぐり山。アスレチック遊具のようなものが置かれている。総合機械の代りか。

バス停をおりて、信号をわたると学校の角。在学中はいつも憂鬱な気分でここを渡った。そのせいか、記憶のなかにあるここの景色は、いつも灰色の空に雨が降っている。

児童館内の式典と懇親会(一)。千人くらい入るはずだが、思いのほか小さい。塗りなおされてはいるけれど、非常口に描かれた、逆三角形のオレンジ色の模様が四十年前と同じなのが懐かしい。舞台袖の照明室なども昔のまま。

児童館内の式典と懇親会(二)。

藤棚と校舎(一)。壁面を補修して、玄関上に赤い三角のオブジェがついているが、基本は昔のまま。

藤棚と校舎(二)。玄関前に座り込んでいるのはヤンキーではない。

昔、総合機械があったところ。きれいに取り払われて、手前の丸いものだけが昔のまま。これは日時計だったと思う(友人の情報で、上の校庭の校舎前に日時計部分は移築されたことが判明)。その脇に昔は噴水の池があったはず。

鬱蒼とした暗い雰囲気だった沼(なんか名前があったはずだが忘れた。友人たちの教えで「藤が池」と判明)は、周囲の木が伐採されて、セメントで護岸されている。カエルの卵はなさそう。その向うは草ぼうぼう。

ついでに附中。下の校庭のサッカーゴール裏から、校舎と旗の台をみる。サッカー部時代はいつもこのあたりの校庭にたむろしていた。右の体育館は、昔のままではない?
四月一日(金)英国音楽史の俯瞰者

ムーティの《メフィストーフェレ》プロローグで開幕して、今年も興味深いコンサートが続く「東京・春・音楽祭」。
今年のテーマの一つは没後四百年のシェイクスピア。そこで今日は、上野学園石橋メモリアルホールで、リチャード・エガー指揮の紀尾井シンフォニエッタ東京、阿部早希子(ソプラノ)と藤木大地(カウンターテナー)による、パーセルとヘンデルの演奏会。
紀尾井シンフォニエッタを紀尾井ホール以外できくのは新鮮。四‐四‐三‐二‐一の弦と木管三、リュートとエガー自身のチェンバロが基本で、ティンパニ、トランペット二とホルン二が曲によって参加。
ノンヴィブラートとはいえ、モダン楽器のパーセルの響きには違和感。響きの剛性が強すぎる上に、エガーの解釈が予想以上にアグレッシヴなものだったこともあり、かなり獰猛な、なんというか、名誉革命期というよりは十九世紀後半の帝国主義的な雰囲気に(笑)。しかしそのぶん活力はあるし、当然ながら金管などは安心してきける。
曲は前半がヘンデルの「シバの女王の入城」に始まって、パーセルの《妖精の女王》 からエガーが編んだ「ソプラノと管弦楽のための大組曲」。後半は全ヘンデルで、やはりエガー編の《水上の音楽》組曲、そしてオペラのアリア四曲と二重唱一曲。
先月二十六日に文化の小で、波多野睦美の歌とつのだたかしのリュートそのほかの「シェイクスピアの時代 ――文芸の扉を開くイングランド」でダウランドをきいて、イギリス音楽の豊かな流れがパーセルで突然に終るのを不思議だなどと書いたが、エガーのプログラムは、わが浅学をたしなめてくれるものだった。
パーセルからヘンデル(イギリス風にハンデルというべきか)への、連続する時の流れ。変化はあるけれど、けっして断絶ではない。ダウランドの内省的な、厭世的で虚無的な(どこか同時代の室町文化に似た)シンプルさから、清教徒革命と王政復古をへて、名誉革命後に旺盛な市民社会が勃興する時代に直面したパーセルとヘンデルの、外向的なバロック歌劇。
大陸の流行をパーセルが島国流に合わせてとりいれたところに、ヘンデルがイタリア直輸入の「本物」のオペラを持ちこんでくる。一九八〇年代日本のファッションが、ドメスティックなDCブランド・ブームからバブル景気が来て、本場のブランド物へとトレンドが移っていった、あんな感じか。
スター歌手の存在をより際だたせ、華やかに歌わせる趣向も、大衆消費社会の原型が生まれた十八世紀前半のロンドンには、ぴったりだったのだろう。
この印象を鮮やかなものにしてくれたのが、カウンターテナーの藤木大地の見事な歌だった。今まできく機会がなかったけれど、この歌手は素晴らしい。息の柱が体内をすぽんと抜けて通って、自然に共鳴するあたりは、日本人離れ。元がテノールで、転向したのが三十歳を過ぎてからというのが、余計な力みのない、この響かせかたにつながっているのだろう。そして、舞台姿に華、花がある。ヘンデルのオペラにはこういうスターがいたから、ロンドンの客を熱狂させたのに違いないと、みていて思った。
そして、あとで曲目をみなおして面白かったのは、エガーがヘンデルのオペラ時代の、イタリア語のアリアしか選んでいないこと。バブルがはじけて、ヘンデルは英語のオラトリオに転向するが、そこでは歌手と同時に、市民参加型の合唱が重要になっていく。国民音楽の創生。
それをやるには大規模な合唱がいなければ、とエガーは考えたのではないだろうか。ここではあくまで、その前の時代まで。
そのエガー、次のディスクはなんと、サリヴァンの《HMSピナフォア》なのだとか。パーセル、ヘンデルときかせてくれて、そしてサリヴァンという、名誉革命後のイギリス舞台音楽の潮流。
ミンコフスキがオッフェンバックを得意とし、アーノンクールもシュトラウスを好んだという文脈なら、イギリス人エガーがサリヴァンに至るのは不思議ではない。そしてその点がガーディナーやピノックたちとは異なっていて、エガーならではのイギリス音楽史への俯瞰的な視点が、あらわれている、
エガー、これまではあまりちゃんときいていなかったのだけれど、この人のイギリス音楽の歴史意識、歴史観はどうやらとても明快で、面白そうな気がする。遅ればせながらこのサリヴァンのほか、いろいろときいてみるつもり。
帰宅後、ヘンデルの英語オラトリオ転向初期の傑作、《エジプトのイスラエル人》のメンデルスゾーン編曲版のCDをきく。ロバート・キングとキングズ・コンソートによる演奏で、一八三三年、デュッセルドルフ上演を復元したもの。メンデルスゾーンが追加した序曲もある。ドイツ国民音楽の確立を模索するなか、十九世紀ドイツの市民社会のために、メンデルスゾーンが蘇演したオラトリオの実例。
この録音、イギリスの音楽家たちがドイツ語で真面目に歌っているのが、不思議にねじくれていて面白い。

四月二日(土)シューベルトの展開
「東京・春・音楽祭」から東京文化会館小ホールで、プレガルディエンが歌う《冬の旅》の室内楽編曲版。木管五重奏とアコーディオンの共演。
編曲者がプログラムに掲載されていなかったが、ネットのサイトにある独唱者インタビューに出ていると、フェイスブック友達から教えていただく。それによれば、同じ編成で二〇〇七年にケベックで録音したCDでオーボエも吹いたフォルジェによるものという。
木管は楽器を持ち替え、また十七曲目(この編曲ではシューベルトのオリジナルではなく、詩人ミュラーが最終的に定めた順番になっている)の宿屋では合唱に転じたり。前半よりも後半、しだいに音が減っていったあたりの編曲がよかった。奏者もフィンランド放響の首席で、来日公演のアンコールでもフィーチャーされたフルートの小山裕幾はじめ、在京オケの首席クラスの若手がそろって、さすがにうまい。
プレガルディエンの歌も見事なもの。テノールの澄度の高さとバリトンの暗さをそなえた声質、ゆるぎない骨格。感情の表出を抑え目にした、苦味。
凝集力という点では原曲のピアノ版に及ばず、やや散漫になるが、しかしこうした、後期ロマン派的な膨張と拡大をもちこみたくなる要素が、たしかにこの曲にはあるのだろう。プレガルディエンもフォルテピアノ、ツェンダー編曲の現代音楽風オーケストラ版、この室内楽版、ピアノと、四つの形態で全曲を録音しているし、さらにギター伴奏で半分の十二曲を歌った録音がある。
ほかに、昔プライが歌ったロマン派風オーケストラ版、シュライヤーが録音した弦楽四重奏版もあった。個人的にはプレガルディエンとホップシュトックとのギター版がいちばん好きなのだが、十二曲しかないのはさすがにギターでは無理があるからか。後世に向って、より広い世界に向って展けているような「ロマン的可能性」が、この曲にはある。
面白いのは、この点が《水車屋の美しい娘》(トッパンホールの日本語題)とは異なること。
《水車屋》には《冬の旅》風の拡大系の編曲はなさそうで、逆に、より簡素なギター版くらい。いわば縮小系。とはいえ、では《水車屋》の可能性がすでに閉じられているかというとそうではない。近年は、シューベルトの友人のアマチュア歌手カール・フォン・シェーンシュタイン男爵が書き残した装飾や変更を元にして、シューベルト時代に歌手がその裁量で原曲に自由に加えたと考えられる装飾歌唱を、再現するスタイルが試されている。つまりピリオド系の展開。
それを最初にきかせてくれたのが、誰あろうプレガルディエンだった。二〇〇九年三月にハクジュホールできいたときには、こういうやりかたがあるのかと度肝をぬかれた。けっしてシェーンシュタイン版の歴史的再現ではなく、それを元にしてピアノのゲースとつくりあげた解釈だそうだが。
今年の来日公演が面白かったのは、三月二十四日にトッパンホールで、このピリオド的可能性を追求した《水車屋》を再びゲースと(冬の旅では客席できいていた)、より力みのとれた、より自由なスタイルで歌ったあとに、それとはベクトルの異なる、ロマン派的《冬の旅》をきかせてくれたこと。
六十歳をこえた歌手が披露する、それぞれの可能性、冒険心。終ることなきクエスト。感謝。
なお、このピリオド的《水車屋》はプレガルディエンの二〇〇八年のDVDできけるが、最近、さらに徹底した形でマルクス・シェーファーがトビアス・コッホのフォルテピアノとの共演でCDにしている。

これはさらに凝っていて、ミュラーの詩集のもとになった、ベルリンの枢密顧問官フォン・シュテーゲマン邸で行なわれていたリーダーシュピール、歌芝居あるいは歌遊びから生まれた、ベルガー作曲の「歌芝居《水車屋の美しい娘》からの歌曲」のうち九曲(半分がミュラーの詩)を先に歌い、続いてシューベルトを録音している。
当時の芸術家が斜に構えて、皮肉や自虐をこめて戯れてつくった「水車屋ごっこ」を、シューベルトの「本気」の向うに見いだそうというもの。歌手が勝手に加えてしまう装飾もまた、そうした戯れのあらわれ。シェーファーとコッホはわざと、やりすぎなくらいにやっている。その倦怠と虚無。虚無との戯れ。
歌そのものとしての魅力はプレガルディエン&ゲースには及ばないが、これもまた、じつに面白いクエスト。
それから、プレガルディエンの息子ユリアンも、先月二十五日の可変日記に紹介した、『シューベルティアーデ』というSACDをミリオスから出している。

シューベルト歌曲のピアノ伴奏パートをフルート、ギター、バリトン(楽器)の古楽器トリオ用に編曲、シューベルトや友人たちの文章の朗読とあわせて、その生の一場面を再現しようとしたもの。しかもフルートがマルク・アンタイ、ギターがシャビエ・ディアス=ラトーレ、バリトンがピエルロと、ドイツ語圏ではなくラテン語圏のピリオド楽器の名手たちとの共演であること――編曲も大半をピエルロが担当――がユリアンの幅広い人脈を感じさせて、とても面白い。
四月七日(木)若きジークフリート!
東京文化会館の東京・春・音楽祭《ジークフリート》に行く。前二作に較べ、ずば抜けて高い満足度。最大の要因は、なんといっても外題役のシャーガー。
まさに、ワーグナーがこの作品に最初につけたタイトル、《若きジークフリート》の具現化。こういうヤング・ジークフリートをきける日がくるとは思いもよらなかったので、嬉しい。
昨日の新国立劇場《ウェルテル》に続けて、独りよがりで、はなはだ傍迷惑なテノールが主人公のオペラを二本みた。ところがこれくらい若さに輝くと、その独善が魅力になってしまう不思議(昨日はそこまではいかなかった)。
プレガルディエンが二つのシューベルト歌曲集できかせてくれたあの若者たちが、「永遠の独善」という名の憧れとロマンをそのまま芸術になりおおせていたのとは異なる、真の瑞々しさ。
第一幕の溶鋼歌と鍛造歌をエンジン全開で歌いきって客席を興奮させ、「素晴らしいが、これで最後までもつのか?」という不安をあざ笑うように、最後まで朗々と歌いきった持久力に唖然。
第三幕で楽譜から目を離せず、それまでのように伸び伸びと歌えなかったのは残念だったとはいえ、ワーグナーが夢に描いたジークフリート歌いは、こんな感じだったのではとさえ思った。ベテランがペース配分をして歌うジークフリート――この役の異常さを考えれば仕方のないことだが――は、短気で無思慮な暴れん坊のくせに、いざとなると妙に狡猾という、なんとも好いたらしくない感じになるのに、シャーガーはまさに「無垢」を感じさせた。聖なる愚者のイメージ。今年四十五歳ときいて驚く。
ワーグナーの音楽はほんとにすげえ、とあらためて感謝したくなる純度の高さを維持したNHK交響楽団も素晴らしかった。この作品後半の複雑精妙な響きをしっかりと音にできるのは、日本ではやはりN響だけだと思った。なかでも第二幕〈森のささやき〉の瑞々しい美しさ。シャーガーの歌とともに、緑と水と光と大気と生命のもたらす歓喜のおののきが、音楽となって鳴り響く、そのとてつもない偉大さ。
ヤノフスキは無敵の中戦車。芝居がかった表情づけを排するスタイルが、いまの自分にはとても好ましい。

ところで写真は、幕間の上野公園。噴水を撮ったつもりだったのだが、こうしてみると日本海海戦の場面みたい……。至近弾があげる水柱。
昔の「レーダー作戦ゲーム」みたい、ともいえる。当たったら赤い火柱、はずれたら白い水柱のピンを立てる、単純だが実に優れたビジュアル。ただし相手からはみえず、自己申告制なので、当たったのに当ってないといったり、途中で軍艦動かしたり、ズルするヤツがいる。人の本性がよく出るゲームだった。
四月九日(土)歌手の開花時期
朝から原稿が書けずにウンウンうなっているうちに、十四時からマリナーとアカデミー室内管弦楽団の演奏会に行く予定だったことを、完全に失念。何げなくフェイスブックをのぞいたら、たくさんのFB友達がオペラシティにいると書いていて、ハッと気がついたが後の祭り。素晴らしい演奏会だったらしい…。
若きジークフリート、シャーガーのこと。一九七一年生れで、つい数年前まで軽いオペレッタを歌っていたときいて驚いたが、同じような芸歴の持ち主に、フラグスタートという素晴らしい先例があったことを思い出した。彼女も四十歳近くなるまで軽いものを歌っていて、国際的にはまったく無名だったのが、ある日突然、二十世紀最高のワーグナー・ソプラノとして、花開いたのだった。
もちろん明るいシャーガーの声質と、地母神的なフラグスタートの声は異なるけれども、素直で伸びのある、鳴りのいい声の出しかたそのものは共通しているように思える。もともと非常にやわらかい、恵まれた声帯をもっていて、若いときにそれが軽すぎたのが、それでも無理に重い声を出すことなくキャリアを送ってきて、肉体の変化とともに開花のときを迎えた、ということなのではないか。
開花後のフラグスタートもまた、クナッパーツブッシュいうところの「戦艦みたいな」無尽蔵のスタミナをもった歌手だった。馬力があるというよりも、のどと身体に負担の少ない、自然な発声だからこその持久力という点で、シャーガーも似ている。フラグスタートと同じように長い活動期間をもってほしいもの。
そういえば、先日きいて感心させられたカウンターテナーの藤木大地もまた、もとはテノールだったのに、三十歳過ぎてからカウンターテナーに転向して、キャリアが開けた人。あの伸びと張りのある、自然なノドの鳴りかたは、余計なものを捨てることで得られたものらしい。
人の声、歌、というものの面白さ。
夜はポリーニをミューザできく。
四月十一日(月)新田一族と母系の力

田中大喜著『新田一族の中世』吉川弘文館刊を読む。同族の足利氏にくらべて不遇な新田氏とその分流の話。
中世の武士は、独立自尊では生きられない。それぞれが自営業者でありつつ、京都の公家や寺社、近隣の同業者と親分子分の関係を結び、縦の系列と横の連繋でネットワークを形成、利用しあう。婚姻は関係づくりの最も有効な手段。
ただ板東の場合は、京都の諸権力があまりに遠く、親分とするのはさまざまな意味で不合理。だから、地域密着型で権力構造が一元化された鎌倉幕府が待望され、歓迎される。しかし幕府内も権力闘争が激しく、流動的で不安定。
やくざやテキヤの小さな組が集まり、盃などで上下と水平の関係を形成、ピラミッド型の巨大組織をつくりつつも、代替りに混乱するのと似ている。
新田氏は、八幡太郎義家の四男、義国の長男が初代という源氏の名門なのに、幕府創建期の激動の波に乗りそこねる。分家の里見氏や山名氏(日本史に名を残すこの二家の名の由来が、もとは高崎市付近の小さな地名というのが楽しい)は新田の本家を早々に見かぎって、世渡りの巧い親戚の足利氏に接近、その子分になる。宗家も結局、足利の一門のような境遇になる(足利家三代目の義氏以降にならって、名の最後が「氏」になる)。新たな分家の世良田氏(その支流が得川、つまり徳川)や岩松氏に対しても、強いリーダーシップは発揮できない。
本書では強調されないが、二〇〇九年十一月十四日の当日記に感想を書いた高橋昌明の『平家の群像』(岩波新書)で教えてもらった、平安期の公家や武家における母系の力をポイントにすると、新田氏不遇の一因がみえてきそう。
兄弟関係は母が異なる場合、長幼の序よりも母の実家の人脈がものをいう。長男の母は身分が低いことが少なくない。身分があっても、先に亡くなっていたりする。そうした場合、あとからきた「正妻」の子が本家の跡継ぎ、惣領に選ばれることが多い。父の長男よりも母の長男、父太郎よりも母太郎の方が強いのだ。
新田氏初代の義重よりも、異母弟の足利氏初代義康が恵まれたのはおそらくそのためだろうし、義重の長子が里見氏、次子が山名氏として分家するのも、母の実家が京都の公家につながる異母弟の吉兼が継いだ方が、勢力拡大に有利だったからだろう。この中央とのコネがあるために、義重は頼朝に対抗意識を抱いて出遅れた。ところが、その孫の里見義成や子の山名義範は肉親の義重を見限り、地元政権の頼朝を早くから担いでしまう。
また、悪源太義平の未亡人となった義重の娘に、義平の異母弟たる頼朝が懸想して、それを拒否した義重を頼朝が冷遇したという吾妻鏡の記述にも、異母兄弟の複雑な関係がみえる。
それに対して足利義康は、頼朝の母方のいとこを妻としている。その間に生まれて二代目を継いだ義兼(新田氏二代目となぜか同名)は早くから頼朝に接近、かれ以降は北条得宗家と婚姻を重ねて、幕府内に強固な基盤を築く。
そのため本家を継いで惣領となるのは必ず正妻の北条氏を母とする母太郎。父にとっては次男か三男にあたる。庶子の兄たちは分家をつくる。
矢田(細川と仁木の祖)、畠山、桃井、吉良(今川はその支流)、斯波といった、室町から戦国にかけて盛名を轟かす足利一門は、みなそうした庶兄がつくった分家(弟がつくった一色氏もある)。かれらが新田氏と違って、本家を主と仰いで結束が固かったことが、南北朝の戦いでは大きな力となった。
一門には前述のように山名氏など、新田氏の分家も加わっている。結局は足利宗家こそ義国流源氏の嫡流、一族の惣領という認識を、初めからかれらも共有していたのかもしれない。かれらが独立を画策した新田義重を見限って頼朝を担いだのも、惣領の足利義兼の意志に従っただけ、ということなのかも。
こうして生い茂った足利一門のなかに埋もれていた新田義貞が脚光を浴びることができたのは、鎌倉攻略の功績を後醍醐天皇の周囲に高く評価され、引き立てられたからこそ。結局、板東に下ろした根は狭く限られ、中央とのコネだけを頼りに畿内を中心に戦い、北陸で死ぬ。
初代義重といい義貞といい、中央とのコネという幻影に踊らされるのが、新田一族の宿命なのか。
それにしても、こうして具体的な一族の系譜の動きとして読んでいくと、鎌倉期までの分割相続制というのが、庶兄の分家独立を伴う、一種の末子相続制、正確には「母太郎相続制」のことであるというのが、よくわかってくる。でなければ、なぜ分割相続なんて馬鹿なことをするのか、意味がわからない。庶兄の分家は未開の土地に行き、父親たちに手伝ってもらいながら開墾して、新たな領地を得ることができたから、本拠は嫡弟に譲っても問題がなかった。この点が遊牧民族の末子相続に似ている。
たとえば桓武平氏の一つ、秩父氏から畠山、河越、江戸、豊島などの庶流諸氏が分家してそれぞれの土地を開拓して発展、さらに江戸氏から木田見(喜多見)、丸子、六郷といった多摩川沿い、さらに渋谷、飯倉などの庶家が枝分かれする、というのは、一族の拡大発展の理想的な模式図だろう。
ところが、鎌倉期も中盤になって社会が安定すると、未開の土地などやたらにはなくなり、本当の分割相続になって、衰退の危機を招くようになる。そのため室町期になると、庶子だろうが何だろうが「父太郎」に財産を一括相続させる単独相続制に変化する。このことは、家族制度における母権の変化とも深くかかわっていく。後世の我々は単独相続に慣れているが(戦後はまた分割相続だが)、それで眺めてしまうと、鎌倉までの武士の感覚を見誤ることになる。面白い。
四月十七日(日)演奏会一週間
The show must go on.
音楽家は楽を奏でる。私はきく。
今月はアカデミー室内管弦楽団に行きそびれて、外来オケはひとつもきかず、「特集:日本のオーケストラ」月間。
以下、自分としては一つながりのものなので、一気に。
まず十二日火曜、ロト指揮の都響を東京文化会館で。ストラヴィンスキーの《ペトルーシュカ》と《火の鳥》全曲。ともに初演直後の版による演奏。二十世紀重工業音楽を得意とする都響と、ピリオド楽器による録音で愉しませたロトとの組合せに期待したが、残念ながら互いの方向性が合わなかったか。弾力を欠いて流れの悪いブツ切れの進行、ザラザラして潤いのない、鳴りの悪い響き。
いままできいたN響や読響でのロトはこんな感じではなかったから、やはりこれは相性か。前にド・ビリーが振ったときもこんな感じの、しらけた音楽だったことを思い出す。互いの弱点を強調しあうような結果になったのが残念。先週の《メタモルフォーゼン》とエロイカをきいておきたかった。
続いて十四日から十七日は、四つのオケと指揮者が趣向をこらし、次にナマできけるのはいつの日か、というような作品で競演した。
十四日はサントリーホール。月に十二~十五回ほどの演奏会という数はいつもと同じなのに、サントリーホールは先月十六日の上岡&新日以来、一月ぶり。
下野竜也指揮の読売日本交響楽団。池辺晋一郎の《多年生のプレリュード》、ベートーヴェンの交響曲第二番、そしてフィンジの《霊魂不滅の啓示》。
池辺の曲は「多年生」というから植物的な曲かと思ったら、とても動物的な、活発な音楽。ベートーヴェンは端正だがふくらみと余裕のない、角張った日本風の新古典主義的演奏。
しかしフィンジは期待通りのききものだった。ヘンデル以来のイギリスの国民音楽たる、管弦楽つき合唱音楽の伝統。内省からときに噴出する外向。ウォルトンの《ベルシャザールの饗宴》の、あの黙示録に基づく血と復讐の快感の音楽が一瞬にはしゃぐ、危うい心のバランス。
諦観を望んで諦観に至らず。自然を愛しつつ、時の移ろいと同様に、その裏切りを恐れ、揺れる心。
帰宅して、東京で九時過ぎに一瞬の縦揺れがあり、さらに熊本で震度七の大地震があったことを知る。
十六日。未明からの熊本の震災を横目にダブルヘッダー。まずはオペラシティでノット指揮東京交響楽団。
この人の選曲構成はいつも面白い。リゲティの《アトモスフェール》《ロンターノ》《サンフランシスコ・ポリフォニー》の三曲のあいだに、ヴィオラ・ダ・ガンバ四重奏によるパーセルのファンタジアを、二曲ずつ計四曲。すべて拍手なしに連続して演奏される。
細かすぎてポリフォニーとは判別しがたいリゲティのうなるような響きと、声部は明快だが同種の楽器による単色の響きのパーセルとの対照。数年前にエスファハニが、ヒストリカルのチェンバロでバードとバッハをひき、ついでモダン楽器に乗りかえてリゲティをひいた、見事なリサイタルを思い出す。
ヴィオラ・ダ・ガンバ(神戸愉樹美ヴィオラ・ダ・ガンバ合奏団)は二階正面オルガン席の下手側にいて、かれらが演奏するときは舞台照明が落とされ、オーケストラは闇のなかに沈む。リゲティの複雑な響きにも明瞭さを保つのは、さすがノット。
一転して後半はわかりやすく、R・シュトラウスの交響詩《ツァラトゥストラはかく語りき》。もちろん《アトモスフェール》とは『2001年宇宙の旅』つながり。雄渾で艶麗、しっかりした呼吸で肉体感があって、きかせ上手。
そしてここでも、最後に人間は自然から拒否され、突き放される。
続いてNHKホールに行き、スラットキン指揮NHK交響楽団。前半にバッハ作品のオーケストラ編曲数曲をまとめて 十八世紀と二十世紀を対照させ、後半にプロコフィエフの交響曲第五番という人気曲をおくところが、東響のプロと似ていて面白い工夫。
はじめは、バッハの無伴奏ヴァイオリンのパルティータ第三番の前奏曲が三回くり返される。まずコンサートマスターの伊藤亮太郎が原曲を独奏。スラットキンは脇に立ってきいている。続いてバッハ自身がカンタータ第二十九番《神よ、あなたに感謝をささげます》のシンフォニアに転用した、オルガンとオーケストラによる編曲。そしてヘンリー・ウッドによる、ロマン派風の華麗な編曲。
あと、バルビローリ編曲のカンタータ第二百八番《狩りだけが私の喜び》の〈羊は安らかに草を食み〉、オーマンディ編曲のカンタータ第百四十七番《心と口と行ないと命》の〈主よ、人の望みの喜びよ〉と続き、おしまいにストコフスキー編曲のトッカータとフーガ、ニ短調。
英米のバッハ受容に大きな役割をはたした、ロマン派的オーケストラ編曲。四人の編曲をならべてきくと、やはりストコフスキーの才能がきわだつ。ウッドのドンガラガッシャン、パンパカン的な華麗さも、バルビローリの木管の美しい歌も、オーマンディの穏当も、ストコフスキーの強烈な魔性とはレベルが違う。
パイプオルガンの色彩と威力、壮大な「鳴り」を、ストコフスキーは見事に写し取って、フルオーケストラの特徴を活用し、生き物のように躍動させる。スラットキンの演奏も見事。ただしこうなると、この曲のあまりに劇的でロマン派的な「正体」がみえてくるようで、これではバッハ以外の別人の作という説が出るのも当然に感じられたりする(笑)。
後半のプロコフィエフも、ダイナミックでゴージャスな、まさにアメリカ風プロコフィエフ。この作品のオーケストレーションがバーンスタインやジョン・ウィリアムズなど、二十世紀後半のブロードウェイ&ハリウッド音楽に大きな影響を与えていることを、あらためて実感。
スラットキンは月末に、バーンスタイン作品とマーラーの交響曲第四番をならべたBプログラムも振る。プロコフィエフからブロードウェイにつながり、そしてニューヨーク・フィルの指揮者として力を入れたマーラーへ。音楽的ルーツと作曲、そして再現芸術家としての十八番へと続く、「バーンスタインの道」。
そして十七日はパスカル・ヴェロ指揮仙台フィルをサントリーホールで。
東日本大震災で損害を受けたオーケストラの、定期三百回記念の東京公演。天皇皇后両陛下ご来臨の予定だったが、九州の震災のためにご欠席。
曲目は幻想交響曲と《レリオ》という意欲的な組合せ。ヴェロ自ら演出して、幻想交響曲の時点からシアターピースのようになっている。
舞台には開演前から楽員が三々五々と席についていて、近くの席から「アメリカン・スタイルだね」という声も聞こえたが、これも演出の一部ということが、あとでわかった。《レリオ》の最後がリハーサル場面なのを利用して、全体をオーケストラ・リハーサルに見立てたものなのだ。だから指揮者も初めから舞台にいて楽員と立ち話をし、作曲家の分身レリオ役の渡部ギュウもあらわれて楽員に挨拶、金管の脇の仕事机につく。
そして幻想交響曲は、リハーサルをききながらのレリオの回想として進んでいく。第四楽章の最後で自殺を試み、終楽章は席に突っ伏したまま。曲の終りで暗転のうちに指揮者とレリオが退場、休憩後も暗転で始まって、点灯したときには二人が元の位置にいる。
レリオの語りは日本語、歌は原語。自分を主人公にした音楽とは、なんたる自己肥大。なんたる自己顕示。二十代のベルリオーズの登場とともに、時代は突如としてロマン派まっさかり。
ヴェロはじっくりと、克明に表情を描きだそうとする。オーケストラも弦の合奏精度と響きの量感には不足するが、きれいな音色で応える。
《レリオ》では、シェイクスピアへの賛嘆と熱い共感がくり返し語られる。これがシェイクスピア没後四百年という記念年を意識した選曲だということに、いまさらながら気がつく。
シェイクスピア作品のヒロインへの憧れと、オフィーリアを演じたハリエット・スミッソンへのかなわぬ恋がごっちゃになった、熱い自分語り。ロマンティック!
四月二十一日(木)海軍大尉宮野善治郎

神立尚紀著『零戦隊長 宮野善治郎の生涯』(光人社NF文庫) を読む。
鈴木亮平を連想させる面差しの表紙が目につき、これに惹かれて買った。
一九一五年生まれ、海兵六十五期。大尉として太平洋戦争開戦と同時に零戦に乗ってフィリピン攻撃に参加したのが、初の実戦。オーストラリアを対岸に望むジャワのチモール島まで一気呵成に進出したところで翌一九四二年三月に内地に帰還、第六航空隊新編に従事。六月のアリューシャン作戦に参加。
そして十月、ラバウルを経て前哨基地ブインに進出、ソロモン諸島のガダルカナル攻防戦に参加。翌月、六空は二〇四空と改称。ガ島撤退後の一九四三年二月にラバウルに移動。その実質的な飛行隊長となる。指揮官機が真っ先に狙われる空中戦で率先垂範、身をさらして戦う。
練度が高く経験豊富な部下たちといえども、連日の空戦は次々とかれらの生命を奪う。交替は許されず、戦死か病気か重傷でなければ内地には帰れない。補充要員は経験不足で、数も足りない。
四月には、部下の六機が護衛してブイン視察に出た山本五十六を乗せた一式陸攻が撃墜される(宮野は出撃せず)。
そのような苦戦でも部下を鼓舞し、慕われ、不死身のように生還し、ラバウルに宮野ありと謳われた男。内心では日本の必敗を予感しつつ、全力で生きた。六月十六日のルンガ沖航空戦で未帰還。戦死の状況は不明。二十七歳。
のちに三四三航空隊の飛行隊長をつとめる三人のうちの二人、鴛淵孝と林喜重は、二〇四空とともにラバウルにいた二五一空の分隊長として、宮野と同じ戦場で戦い、薫陶を受けている。
とりわけ鴛淵は「戦上手の理想的な戦闘機指揮官の範」として、帰国後も宮野を絶賛していたという。
この鴛淵や豊田穣などの六十八期にとっては、六十五期の宮野は入校時の最上級生、「鬼の一号生徒」として厳しく鍛えてくれた先輩にあたる。そうした交流が描かれているのかどうかも、この本を読んだ理由の一つだったが、兵学校での宮野があまり目立たない存在だったせいか、六十八期の後輩の回想はない。
文庫本で七百頁をこす大作で、宮野その人だけでなく、周囲で戦った上官、部下の証言や動向、生死にも多くが割かれている。戦場での宮野に関する記述はそれほど多くない。宮野はラバウルで詳細な手記をつけており、遺品として実家に帰ったが、敗戦の衝撃で兄が書簡とともに焼いてしまい、残されていない。
著者の神立尚紀は一九六三年生れ。宮部の出た大阪の八尾中学の後身、八尾高校の後輩にあたる。生存者の証言を丁寧にあつめて、戦争という巨大な状況のなかで自らの生死を全うする兵士の姿を、つとめて冷静に描きだしている。
それにしても戦果確認の難しさ(実際の撃墜数の二倍、三倍が普通)、艦爆のすさまじい損耗率の高さが印象に残る。
四月二十二日(金)前説の予習
明日は午後一時十分からサントリーホールで、日本フィルの定期演奏会の開演前にプレトークをする。サントリーホールの舞台にたったひとりで下手のあの扉から出て、十五分間しゃべるのは、恐ろしいと同時に快感でもある。
熊本を念頭に、五年前の三月十二日の土曜午後二時にも、同じようにここで日本フィルの演奏会があったことをかみしめつつ、話すつもり。
というわけで今日は予習のために、七時からインキネン指揮の日本フィルの定期演奏会。曲はもちろん明日と同じ、ブリテンのヴァイオリン協奏曲(庄司紗矢香独奏)とホルストの《惑星》。
終演後には楽員たち、アフタートーク後にはインキネンもホワイエに立って、熊本のための募金を呼びかけていた。
プレトークは「いまからきく公演」の話をするものなので、それがどんなものになるのか、事前に知っておけるのは本当に助かる。ネタバレしないようにしつつ、あとで「ああ、あの話はこのことだったのね」と思ってもらえるような中身にできるかどうかがキモ。

写真の左下のCDは、会場で購入してきた日本フィル自主制作盤。ヤマカズ指揮の山本直純の《えんそく》、三善晃の《連祷富士》、グローフェの《グランド・キャニオン》の三曲。すべて杉並公会堂でのライヴ。
ミュージックバードの番組「ニューディスク・ナビ」で紹介するのに、今月エクストンから出た同じヤマカズ指揮の信時潔の《海道東征》(右下)と組み合わせるのがいいか、同じ日本フィルのラザレフのタコ八がいいか、思案中。
奇しくも《海道東征》は二〇一四年の熊本県立劇場ライヴというのが、感慨深し。ちなみに湯浅卓雄指揮藝大のナクソス盤に続けて、同じ曲が二週連続でかかる。いままでステレオ録音はオーケストラ・ニッポニカ盤しかなかったのに…。
四月二十三日(土)ポケット・マーラー
日本フィルのプレトークから、ピノック指揮紀尾井シンフォニエッタ東京の演奏会へ。感想はあらためて書くが、おっと思ったのは紀尾井のプログラムに書かれていた、翌シーズンの予定のこと。
結成二十年をひとくぎりとして、これまでの九月から翌年八月までというシーズン日程を変更して、日本式の四月から翌年三月という年度制にあらためる。そこで、今年八月から来年三月までは移行準備期間として定期を休み、来年四月から再開するとのこと。
一瞬不安がよぎったが、年五回の定期は維持するとのこと。今日、八百席のホールで八‐七‐六‐四‐二の弦でベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番のじつに「適切」な演奏をきいて、作品に合った「適正」な規模で演奏する、きく、というのがいかに大事かということを痛感させられたばかりだけに、頑張ってほしいもの。
秋から半年の「移行準備期間」には、定期の代りに「紀尾井シンフォニエッタ東京のメンバーによる室内楽公演」を三回開催。三回とも面白そうだが、なかでも個人的には十一月の第二回、パリ管弦楽団と紀尾井シンフォニエッタ東京の名手たちによる、室内楽版のマーラーの交響曲第四番ほかにひかれる。
いまヨーロッパで流行の室内アンサンブル編曲版、いわゆるポケットオーケストラ版。なぜ流行るのかを考えるためにも、ポケット・マーラーは一度ナマできいてみたいと思っていたので、嬉しい。
四月二十四日(日)内戦から黙示録へ
金曜から日曜の三つのオーケストラ演奏会。ときどきあるように、まるで別の演奏会が玄妙にからみあって、時間を行きつ戻りつ、人と音楽の歴史を考えさせる三日間。
まずは二十二日サントリーホールのインキネン指揮日本フィルによる、ブリテンのヴァイオリン協奏曲(庄司紗矢香独奏)とホルストの《惑星》。インキネンの指揮は透明度の高い響きとニュアンスを求めるもの。
とりわけきく機会の多くないブリテンが嬉しい。一九三九年に作曲され、翌年ニューヨークでスペイン出身のヴァイオリニスト、ブローサを独奏に初演された曲。ブリテンは三年前の一九三六年にブローサとバルセロナの現代音楽祭に参加、2人でヴァイオリンとピアノのための組曲を演奏したが、そのとき私淑するベルクのヴァイオリン協奏曲の世界初演をきき、大きな感銘を受けた。おそらくはそのエコーがこの作品にあるということを、プログラムの曲目解説に書いた。
煩雑になるので当時の世界情勢についてはほとんど書かなかったのだけれど、驚かされたのは当日の庄司のアンコール。自身で編曲したという、スペイン内戦時の軍歌《アビレスへの道》をひいたのだった。
そう、一九三六年と三九年の間には、スペイン内戦がある。スペイン人に初演を任せている以上、作曲者ブリテンがそのことをまったく意識しなかったとは考えにくい。良心的兵役拒否者としてアメリカに移住していたくらいだし。こうなると、それについて曲解で触れなかったのは失敗。
しかし幸い、翌日にプレトークをすることになっている。そこで、スペイン内戦の説明をすることにした。もちろん、アンコールの中身について触れるわけにはいかないので、内戦との共時性の話だけ。日によってアンコールの曲を変えるソリストもいるので、変えられたら意味がなくなるが、この曲の選択に限っては変えまいと考えた(あとでサントリーホールのサイトで確認したらやはりそうだったので、一安心)。
プレトークのあとは急いで紀尾井ホールに移動し、ピノック指揮紀尾井シンフォニエッタ東京の定期。
まずはフォーレ晩年の《マスクとベルガマスク》の組曲。偶然にも《惑星》とほぼ同じ、第一次世界大戦直後の作品。ただしこちらは擬バロック、新古典主義の時代の始まりに位置していて、古楽出身の指揮者がモダンの室内オケを振るにはふさわしい作風。爽快。
続いて、イモジェン・クーパーを独奏とするベートーヴェンのピアノ協奏曲第四番。これは実に「適切」な演奏。理由は八百席のホールで八‐七‐六‐四‐二の弦という、ホールの大きさと演奏者の数が、作品にぴったりの「適正」な規模だから。二千人級のホールだと大味で予定調和の退屈な作品にきこえることが多いベートーヴェンのピアノ協奏曲が、快活に、新鮮な音楽として鳴りひびく。
クーパーのピアノはレガート主体の柔和な響きだが、音が濁らず水っぽくならない。ホールの明快な残響のたまもの。オケも歯切れよく、しかし過度に攻撃的にはならない。終楽章のピアノの裏でうなる首席チェロのソロの響きも効果的。
後半は、ハイドンの交響曲第一〇三番《太鼓連打》。これもホールと人数の規模が適正で、きいていて気持がいい。
一七九五年にこの曲がロンドンで初演されたとき、イギリスはフランス共和国と戦争の最中だった。ここからナポレオン戦争の時代を通じて、オーケストラのなかで打楽器や管楽器など、軍楽隊のつかう楽器の比重が増していく。ショスタコーヴィチまで続く、「疑似戦場」としての大交響曲の時代の始まり。この曲の冒頭のドラムロールも、軍楽隊の影響そのもの。
そして二十四日は、サントリーホールでノット指揮東京交響楽団。やはりノットならではプログラムで、前半がシェーンベルクの《ワルシャワの生き残り》とベルクの《ルル》組曲、後半がブラームスのドイツ・レクイエム。
前半の新ウィーン楽派の師弟による二曲は、相似と相違が明確なのが面白い。似ているのは、ともにきわめて映画的であること。映画音楽みたいという意味ではなく、映画という新たな芸術分野が出現して発展しはじめた時代に生きている芸術家の作品、ということ。
《ワルシャワの生き残り》は映画の一場面のように強烈に視覚的で、直接的に訴える。フラッシュバックして、唐突に切り取られた場面。アメリカで初演された作品なのに、英語だけでなくドイツ語とヘブライ語がつかわれる。それらは言葉の論理ではなく、つまり意味ではなく、響きの表情の力で、皮膚感覚に訴えかけてくる。異文化の摩擦。不寛容。
厳しく凝縮された、大戦争と大虐殺の体験直後につくられたこの作品に対し、両大戦間の《ルル》組曲は、はるかにのんびりとして、耽美的で頽廃的。死すら頽廃的。いきりたつトーキーではない、古き良きサイレント映画。これが違い。
同時に、一昨日きいたブリテンに影響を与えた作曲家の音楽。
そして、ドイツ・レクイエム。
今回きいて、ああ、これこそがメンデルスゾーンからシューマンに続いた「ドイツ国民音楽としてのオラトリオ」の系譜における、最も成功した、最もドイツ市民の心をとらえてきた作品なのだと、気がついた。
国民意識。ハイドン晩年のナポレオン戦争が契機となって、ヨーロッパ諸国にもたらされたもの。
そして生まれた、ドイツの、ドイツ人による、ドイツ人のためのレクイエム。
ルター訳のドイツ語聖書の言葉を、自由に用いた歌詞。聖書に密着することで教皇と教会の典礼から離れ、コンサートホールのためにかかれた音楽。そのコンサートホールにはオルガンがある。教会に代わる市民の場としての、コンサートホール。
百五十人の東響コーラス。個人的な好みとしては、もっと少人数でキビキビと鋭くやってほしい。しかし、「国民音楽としてのオラトリオ」としては、アマチュアの大合唱団が、たっぷりと壮大に響かせる解釈こそふさわしい。これこそ国民音楽。
同時に、鋭角的な抑揚ではなく、丸めにつけられたオーケストラの響きの輪郭が、その耽美的ロマン性において、さきほどのベルクに似てくるのも愉快。もちろん、ベルクがブラームスから学んだもの。
メンデルスゾーンもシェーンベルクもベルクも、ドイツ国民文化の担い手の一員になることを望み、そして、ユダヤ人としてはじかれてゆく。
(ブラームスは?)
ドイツ・レクイエムの歌詞は、新約聖書だけでなく旧約聖書からもとられている。いうまでもなく、もとはユダヤ教徒だけの聖典だったもの。シェーンベルクは《ワルシャワの生き残り》で、旧約聖書の一節をヘブライ語で歌わせる。
奪還? そうではなく……
ドイツ・レクイエムの結び、第六曲の後半と第七曲は、ヨハネ黙示録からとられている。
黙示録の主題は、最後の審判。
《ワルシャワの生き残り》の主人公もドイツ兵も虐殺されたユダヤ人も、ルルもその仲間も切り裂きジャックも、すべての死者が甦って受ける審判。
D・H・ロレンスが『黙示録論』で喝破した、ヨハネ黙示録の最後の審判にひそむ、弱者による富者への怨嗟と嫉妬、神の正義の名による復讐の快感。
インターネット上の「正義」に、よく似たもの。最終的には、富者も弱者も、誰もが傷ついてゆく世界。
ブラームスは、その部分は避けているけれど…。
とりあえずは、この三日間の音楽家と関係者に感謝。
とここまでをフェイスブックに書いたところ、江森一夫さんから、今回の隠れテーマがロレンスとすれば、前回十六日のリゲティ/パーセル+シュトラウスのプロには、キューブリックつながりという表層の裏にバフチンのポリフォニーとニーチェの超人思想があるのではという、ものすごく面白いご指摘をいただく。
ケンブリッジ出の教養人ノットなら、そんな暗喩を密かに面白がっているのかも知れない…。
五月三日(火)N響世界旅行
ひさびさに一九六〇年話。自分のなかでの「一九六〇年」というテーマは、クレンペラー&フィルハーモニアのウィーンでのベートーヴェン・チクルスに関して、外山雄三さんにインタビューしたときにピリオドが打たれたと思っていた。二〇一三年十二月二十九日の可変日記に書いている。
『まさにその目で見られた方にしか再現できない、ほとんど左手しか動かないというクレンペラーの指揮ぶりを真似しながらの「あのエロイカは本当に素晴らしかった」というお言葉を耳にしたとき、私の心は震えた。
「一九六〇年」をめぐる長いクエストが大きな環を描いて、ついに終点に来たと確信したからだ』
その指揮真似は、お腹の脇でひろげた左の手のひらをグウッとねじる、丸いハンドルを閉めるような動きだった。その動作をみて、「一九六〇年」という円環が、始点と終点をくっつけて、完全な環になって閉じたような気がした。
その翌日からもうすっぱりと離れた気がしていたのだが、それから二年半たって、また戻ってきた。
N響の一九六〇年世界一周演奏旅行のライヴを、キングが八枚組でCD化するから、八千~一万字くらいでエピソードを書いてくれという。外山雄三の《ラプソディ》が強烈に大成功した、あのツアー。今回は岩城、外山、シュヒターの三人それぞれの指揮で《ラプソディ》ききくらべつき。
幸い、このツアーについては福原信夫と細野達也、二人のNHK局員が詳細な紀行を書いているので、それを基本にして、さまざまな回想を織り込み、オーケストラ・サウンドのように多声部のものに仕立てていく。史料から史料へと飛び回り、十二カ国二十四都市、六十八日間の日程を再現する作業には、回転の悪い頭を激しく消耗させられたが、とても懐かしく、愉しいものだった。
実際の音はまったくきいていないのでアレだが(笑)、けっこう面白いセットになりそうと、期待している。
キングの紹介文には自分の解説が一万六千字と書いてくれているが、このうち四千字はツアー全体の日程、曲目と楽員名簿(宇宿允人が山口治という元の名前でトロンボーンを吹いている)。
外山さん、コントラバスの田中雅彦さん(ワセオケの永久名誉顧問)、中村さん、堤さんなど、参加した人に思い出話をきくところまでいきたかったが、それは次の機会に。
ところでこの八枚組、同じツアーの録音なのに《ラプソディ》と《君が代》くらいしか曲が重複しない、というのが凄いところだ。しかもモスクワでチャイコフスキー、プラハでドヴォルジャーク、ウィーンでワルツ、パリでラヴェルと、敬意を表するつもりでお国ものをわざわざやるという、「恐れを知らぬ」武者修行ぶりが、いかにも躍進の時代。
ウィーンで《美しく青きドナウ》をアンコールで始めたときには、お客が驚いてヒソヒソザワザワしはじめ、指揮していた岩城のタクトが思わずガクガクふるえたそうで、今回はその録音をきけるのが、とても楽しみ。
五月五日(木)高き所より

今年もラ・フォル・ジュルネのソムリエカウンター、無事終了。来てくださった方々、ありがとうございました。
写真は七階からの眺め。この仕事の役得で、アーティストラウンジなる出演者用の食堂で昼を食べられる。担当を終えてから音楽をきかせてもらい、メシを食い、眺め、また音楽をききにいく。この大空間の上下左右の隅々に、さまざまな音楽がつまっている。
私の仕事場も写っている。左下の方、白い長方形の区画のなか。その右下隅に小さく、数時間前は自分が座っていた。
半年前に会ったばかりの小中学校の同級生の、その突然の訃報を知って、とりあえずいま生きてこの世にあることのありがたさを思いつつ。
しかし高所恐怖症の方には申し訳ない写真。昔、送電線鉄塔の高い所にばかりいたもので、こういうところにいるときの方が、生きている実感がある(笑)。
五月十一日(水)交響曲と能狂言
月刊誌の原稿をようやく終えて、今日はダブルヘッダー。
今回の感想は時間をさかのぼる形で、まず夜のラトル&ベルリン・フィルのベートーヴェン・チクルス第一夜、交響曲第一番と《英雄》から。
まず目につくのは編成が小さいこと。第一番は十‐八‐六‐五‐三の低弦厚めの十型、《英雄》は十二‐一〇‐八‐六‐五の十二型。昨年DVDでみたイヴァン・フィッシャー指揮のコンセルトヘボウのツィクルスも十一型(十一‐十‐八‐六‐五、ただし第九だけ十四型)、ヒメノが指揮した来日公演の《田園》も十二型だったから、これくらいの編成が交響楽団でもいまの主流らしい。自分はきけないが、今後のツィクルスでどう拡大していくのかも面白いところ。
二管編成のバランスは、やはりこのくらいの弦がいい(それにしても、二月のバレンボイムのブル二の二管編成十六型は、いかにブルックナーとはいえナイトメアなものだった…)。そしてベルリン・フィルだけに、十型でも弦は充分に響く。
前半の第一番は、数年前の来日できいたシューマンの《春》に似た、予想通りのアグレッシブでダイナミックで意欲的で積極的で精力的な、同じような形容詞をいくつも重ねたくなる、元気一杯の演奏。ただ自分にはどうも単調に思えてしまうが、おっと思ったのがメヌエットのトリオの終りで、木管がやや不安定に浮かびあがって、異様に現代的な雰囲気になった箇所。これはなんだろうと思っていたら、《英雄》ではまさにこの響きがポイントになった。
その《英雄》、第一楽章は第一番と似た、積極的なスタイル。ここは客席でずっとアラームを鳴らした人がいて、静かになるとそれが耳について困るので、たしかににぎやかなほうがよかった。
それがはっきりと変わったのは第二楽章。さいわいアラームも停まって、ベルリン・フィルの弱音の表現力の豊かさが前面に出てきた。力みも消え、サントリーホールの音響にもなれて、十二型という編成により、木管がしっかりと浮き上がってくる。その寂寥。まさに「せきをしてもひとり」的な寂寥感。
これによく似たベートーヴェンをたしかにきいたことがあるが、それはいつだったかと、ききながら考えた。そして、二〇一四年七月のメッツマッハー指揮新日本フィルの演奏会、ツィンマーマンの遺作、《私は改めて、太陽の下に行われる虐げのすべてを見た》の日本初演と組み合わされた「運命」だったと、思い出した。
その日の可変日記に書いている。
「驚いたのは、その音楽の寂しさ。音楽の雄弁法の代名詞みたいに思っていた交響曲第五番が、あちこちで口ごもり、言いよどみ、気まずい沈黙で途切れる。その沈黙の直前に一人残る木管の音色の、なんと孤独で寂しいこと。まるでクレンペラーみたいな木管の強調が、見事な効果を生んでいた。
あの「運命」ではなく、まるでシューベルトの《未完成》のような、疎外感に満ちた、モダンな響き」
今回のラトル&ベルリン・フィルのベートーヴェンのポイントもまた「寂しさ」にあるのではないか。ひとりぼっちのベートーヴェン。しかしその寂寥から、あの「歓喜の歌」をつかみだし、世界に与えるベートーヴェン。
今回のツィクルスには、その過程が描かれていきそうな気がするけれど、自分は今日だけなので、あとはCDできいてみるつもり。
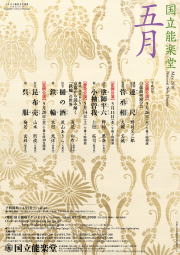
その前の昼は、国立能楽堂で狂言「塗師平六(ぬしへいろく)」と能「小袖曽我(こそでそが)」。
これもあとの能「小袖曽我」の話から。簡単に言えば、曽我兄弟が仇討に行く前に母に別れを告げにくる話。
歌舞伎でもお馴染みの、仇討物語の原点。昔の日本人が大好きだった仇討話。しかし考えてみると、その原点の『曽我物語』の成立は鎌倉期以降で、わりに新しい。記紀の神話や王朝説話に、仇討の話はあるのだろうか。
古代は知らず、平安期には御霊信仰、怨霊話があった。恨みを抱いて死んだ人間が霊となって復讐する話。仇討というのは、その霊の代りに現世の子孫が復讐するもの。つまり現実的で、怨霊というものを信じない武士階級の感覚として、出てきたものなのか。
その前にみたのが狂言「塗師平六」。今日みたなかで、もっとも印象に残ったものなので、最後に。
まず塗師の師匠(アド/野村万作)が登場。京の都では最近仕事がなく困っている。弟子の平六(シテ/野村萬斎)は腕は未熟だが、一乗に移って繁盛している。「仕事がないときは来てください」という弟子の言葉を頼りに、一乗の平六の店を訪れる。
平六の妻(小アド/深田博治)が出迎えるが、腕のいい師匠があらわれたのでは拙い平六の仕事をとられてしまうと考え、平六は死んだと嘘をつく。そこに平六があらわれ、師匠の姿をみて喜んで会おうとするが、妻に止められる。「自分に恥をかかせるなら離縁する」と妻に脅され、しかたなく幽霊のふりをして師匠の前に出る。
という話なのだが、一度みたかぎりでは、かなり不思議なものになっている。ここまでの前半は普通の狂言なのに、平六がニセ幽霊となる後半は、能のスタイルになる。地謡や囃子が加わり、セリフではなく謠と舞で進行される。平六の装束も能の怨霊風。
何よりも、オチらしいオチがない。解説をみると、平六の最後の謠の「塗籠他行」という詞が、ニセ幽霊だよと打ち明ける、種明しの言葉なのだそうだが、正体をあらわす明快な仕種があるわけではなく、師匠も妻も反応しない。そのまま終ってしまう。わかりやすく笑えるような結末は何もない(あえていえば、最後の詞のあたりで平六が師匠の間近に迫ったのが、何らかの意味があるようで、気になったといえば気になったが)。
種明しというより、自虐的な告白、仄めかしにすぎないようにさえ思えた。
この話はなんなんだろう、と腑に落ちないまま、ラトルのベートーヴェンをききながら、いろいろ考えた。
この話は、まがいもの、鳥なき里のこうもり、キッチュなものに満ちている。まず平六の腕前がそう。そして「一乗」なる地名。北陸の朝倉氏の本拠、一乗谷に決まっている。応仁の乱で荒廃した京都を逃れた公家たちにより、ここは「北の京」と呼ばれる栄華を一時的にみた。一乗谷も京のまがいもの。仕事がないというのは、戦乱による京の荒廃を意味しているともとれる。
そして、平六による幽霊のフリ。これは完全に能のパロディ、まがいもの。萬斎のキレのいい動き。能では許されないような動きもわざとまじえた、能のようで能でない、狂言師の舞。萬斎という、狂言師にとどまらない優れた才能の持ち主、しかし絶対に能楽師にはなれない、大きな才能による、仮装芝居。
多層的な虚実の入り交じりの面白さ。そういえば地謡も舞台上手の地謡座ではなく、正面奥の囃子方の後ろ、後見座に座って、能ではないことを示していた。
ひょっとしたら、生きているつもりの平六は、本物の幽霊になっているのではないか。信長に敗れて破壊され、廃墟と化した一乗谷に出る、幽霊なのではあるまいか。
などと考えたのはサントリーホールにきてからだったけれども、萬斎のキレのいい「ニセの能」をみたあと、能の「小袖曽我」の舞がいささかくすんでみえたのは、確かだった。能よりも狂言に考え込まされる、逆転の公演。
五月十二日(木)小さな「プラハの春」

今日五月十二日はスメタナの命日で、チェコの「プラハの春」音楽祭恒例の開幕日。今年の《わが祖国》はパーヴォ・ヤルヴィが指揮するそうだ。
その開幕の八時間前に広尾のチェコ大使館で行なわれた、ミニチュア版「プラハの春」。稲島早織さんと大石真裕さんによる、ピアノ連弾版の《わが祖国》をきく。日本には輸入されていない習慣なので、面白し。
大石さんのご両親は、私の大学の同級生が一九八三年のバイロイト音楽祭で知り合った、古い友人。一九八四年に夫妻で大阪フェスティバル・ホールにテンシュテット指揮のロンドン・フィルのマーラーの交響曲第五番をききにいったら、妊娠中のお母さんのお腹のなかで動いていたというのが、大石さん。いまはその人がこんな立派なピアノをひいている。
そのときのテンシュテットのマーラーはTOKYO FMでCD化されているので、きくたびに不思議な感じがする。
五月十五日(日)現在と、或る過去と

ラトル&ベルリン・フィルの新譜、ベートーヴェンの交響曲全集をブルーレイ・オーディオのハイレゾできく。演奏会ごと(日本ツィクルスと同じ組合せ)のCDと違って番号順の収録で、第七番まできいたところ。
ナマできいた第一番&《英雄》とは、音も演奏もかなり違う。はっきり言ってディスクのほうが全然いい。何より弦の音。ふわっと力を抜いて、軽く漂わせるような響き。このベルリンのホールで音をつくっているオーケストラなのだと、つくづく思う。
サントリーホールの一階後方できいた音ははるかに力んでいて、きつい、混濁した響きだった。こちらは自然な弾力があって横揺れし、よくうねって歌うのにびっくり。こういう要素は、これまでのラトルにきいたことのないものだった。見事な脱力。
これらの要素はラトル本人よりも、オーケストラ側から出てきたもののように思える。一九九〇年頃から顕著になる、ユースオーケストラやピリオド・オーケストラの相次ぐ誕生など、前任のアバドがその意味を逸早く賢明に見抜いた、ヨーロッパのオーケストラ運動の潮流の大きな変化を、ラトルがうまくくみ取ったものではないか。
一、二番が十型で三~八番が十二型という、室内管弦楽団に近い編成をとっているのも、楽員の自発性を活かし、響きの明快さを保つのに最適な規模だからだろう。とりわけ名人揃いの管楽器のソロの、個人技とチームプレーのギリギリの両立の見事さは、充実しながら軽いという、現代のベルリン・フィルでこそ可能な響きのなかで、鮮明に浮きあがったり透明に重なったり、素晴らしい威力を発揮する。
元気な音で満たされているようで、しかし音の響きを無言できく沈黙も、その脇にいる。そこに際だつ、ベートーヴェンの孤独。第二番の溌剌と《田園》の静寂の好対照。
日本のクラシック好き、オーケストラ好きは「カリスマ指揮者と、一糸乱れず翼賛する大軍団」みたいな組合せへの郷愁が強いから、こうしたベートーヴェン像は、なかなか受けいれようとしないかもしれない。十九世紀後半以降の複雑な大規模作品はともかく、それ以前のこうした二管編成くらいの作品に関しては、また別のアプローチもあると思う。
自戒を込めて思うが、先入観で好き嫌いをいうだけで、目の前にいる相手が何をしようとしているかをひとまず考えてみる習慣をもたない人は、さびしい。
これはまさに現代においてこそ可能な名演、名盤だと感じながら、一方で、指揮者とオケのこれとはまったく別の関係による、ほぼ百年前から評価を得るようになった、過去のベートーヴェン演奏との不思議な類似を思う。
それは、トスカニーニのベートーヴェン。それも一九四〇年代までの、できればNBC響ではないオーケストラの、あまり力まない演奏のもの。疾走するスピード感、高い運動性と軽妙な弾力、カンタービレといった要素が、似ている。いわゆる「ドイツ的」な演奏ではない(ここではひとまず、一九四九年にスカラ座管とヴェネツィアで演奏した《田園》をきいてみて、見当外れではないことを確認した)。
もちろん、カリスマ的独裁者が猛練習で楽員をねじ上げて叩き込んだ音楽と、楽員の自発性を活かして生まれてきた音楽とで、淵源も結果もかなり違う。
ラトルの演奏にトスカニーニの影響があるとは思わない。ムーティやシャイーが受けたような影響はラトルにはなかったと思うし、何よりも今までのかれの演奏が違いすぎる。そうではなく、ビリオド・スタイルを意識しながらモダン楽器によるベートーヴェンを模索していくなかで、結果として百年前の、トスカニーニの「新即物主義」に似たものに至ったんじゃないか、という気がする。
似ている点と、違う点と、それを検討していくことで、百年の演奏史のある一面を、立体的に削りだすことができるかもしれない。ラトルとトスカニーニの共通点と相違点なんて、これまでは考えてみようとも思わなかった。それが、現在と過去から、まったく別の時間と空間から姿をあらわして出会い、互いを見つめる、その面白さ。
考える足がかりに、自分が十年前に書いたトスカニーニについての小文を引っぱりだして、さっきから眺めている。
演奏史の現在と過去が出会い、互いの姿を照らしあう場所で、自分もついでに過去の自分と、会ってみる。
「トスカニーニは間違っているか」 (二〇〇六年七月八日)
――わたしは間違っていないと確信する。もしどうしても間違っているというなら、誰のどんな「正しい」演奏より、わたしはトスカニーニの「間違った」演奏を聴きたいと思う。(フリッツ・クライスラー)
一九二〇年のこと、トスカニーニはミラノ・スカラ座管弦楽団を率いてアメリカ演奏旅行を行なった。
上の言葉は、かれらのニューヨークの演奏会にいあわせ、その《運命》交響曲を聴いた不世出の名ヴァイオリニスト、クライスラーが言ったものである。
ウィーン生まれのクライスラーは、ドイツの友人たちから、イタリア人トスカニーニのベートーヴェンの解釈は「間違っている」と、さんざん聞かされていたらしい。それならさて、どんなものだろうと聴きに来て、もらした感想が、こうだったのである。
クライスラーの友人たちは、いったい何が「間違っている」と思ったのか。
ドイツ人のベートーヴェン観の一例を、『フルトヴェングラーの手記』(芦津丈夫、石井不二雄共訳、白水社)にみることができる。一九三〇年、トスカニーニとニューヨーク・フィルがベルリンを訪れて演奏した《エロイカ》を聴いたフルトヴェングラーは、次のように手帳に書いた。
「ベートーヴェンの音楽の本来の内容を決定するすべてのもの、すなわち有機的なものとか、ひとつのものが別のものに移行する経過とかは、トスカニーニにとって存在しない」
「トゥッティかアリアか、この二つの要素に、ベートーヴェンの音楽の限りなく豊かなニュアンスのすべてが分解されてしまう。まことに驚くほど単純な操作である」
「ソナタの――それはそのすべての代表者を通じてドイツの産物であるが――本質と意味に対する無理解がまさしくイタリア音楽の特徴となっていることを思い起こす」
有機的な関連がなく、アリアとトゥッティ、つまり歌うところと全合奏と、この二つの明確な対照があるだけ。その間をなだらかに移行させ、結びつけることがない。それでは「ドイツの」ソナタ形式が表現できない。フルトヴェングラーはそう言いたいらしい。
わたしのような音楽の素人にはよくわからないが、たぶん、フルトヴェングラーは正しいのだろう。
トスカニーニはほのめかしたり、暗示したりはしない。その音楽は常に鮮烈で、俊敏だ。ドイツ音楽の本質からは、遠いのかもしれない。
しかし、生き生きとしている。
真の意味の「コン・ブリオ」がある。わたしがトスカニーニに惹かれるのはまさにこの活力ゆえだし、クライスラーが賞賛したのもまた、その点なのではないか。(後略)
その後、第九をきいた。この曲だけは倍管十六型の編成を採用して、よりロマンティックな(あえていえばメンデルスゾーン的な)祝典音楽を指向している。凝集的ではなく拡散的。これは、トスカニーニとはまったく似ていない音楽。終楽章の雑然としたつくりも、あえてそのまま提示される。
そして、思いっきり残る、未達成感、未完成感。レオノーレ序曲の三番でなくて、二番のような。
大団円ではない。まだ先がある。作品にまだ先があるのか、演奏にまだ先があるのか(世界ツアーはこれからだ)、どちらともつかない結末。
いやな人はいやだろう。でも自分は、終楽章で見渡すかぎりに未開の原野が拡がってしまったみたいなこの感覚、けっして間違ってはいない気がする。
ここから、ロマン派が展開していくのだから。
五月十九日(木)文楽
国立劇場小劇場で、文楽鑑賞教室『曽根崎心中』をみる。
能狂言の俄かファンになって、文楽もあらためて観たくなったのだが、本公演は歌舞伎同様に四時間近くかかって、いかにも長すぎる。鑑賞教室の『曽根崎心中』なら解説を含めて二時間強とのことなので、行くことにした。NHKのドラマ『ちかえもん』(面白かった)で、初演の再現場面をみたばかりというのもありがたい。
若い人がメインで、一般売りは最後列のみだから、舞台が遠い。ドラマではもっと狭い小屋だった。心中も生々しく描かれていたが、かなりソフトになっている。一個の人形を三人で操作し、義太夫語りと三味線も次々と交替するなど、小さいわりに人間がたくさん必要で、これを現代の商業ベースにのせるのはたしかに難しそう。
五月二十六日(木)踏み台の人
午後、紀尾井シンフォニエッタ東京の今後に関する記者会見に行く。
聴衆の立場からの大きな変更は、
・「紀尾井ホール室内管弦楽団」への改称。
・首席指揮者にライナー・ホーネックが就任、年五回の定期のうち三回を担当する。二〇一七年四月から二〇二〇年三月までの三年契約。
・既発表の通り、九月から来年の三月までは移行期間として、定期を休止。
個人的な感想は色々あるが、とにかく決まったことなので、頑張ってほしい。
フォルクスオーパーの《メリー・ウィドウ》初日。とても楽しかったのでフェイスブックに感想を書こうと思い、帰宅してPCを起動したら、本番中にメールで「音楽の友」から批評依頼がきていたので感想はパス。綱渡り人生(笑)。
なので、一点だけ。
こういう、「ちゃんとした本場もの」の音をナマできくと、この作品の各所の音楽がいかにオッフェンバックのオペレッタのそれをうまく換骨奪胎しているかがよくわかり、とても面白かった。それも《美しきエレーヌ》や《ペリコール》あたりのオッフェンバック。
舞台がパリだから、原作がオッフェンバックの重要な台本作者だったアンリ・メイヤックだから、というのが理由なのだろうが、それが現代では元ネタをこえた、圧倒的な知名度を獲得してしまっているあたりが、歴史の皮肉。
ビゼーが《カルメン》で、シュトラウスが《こうもり》で、それぞれのやりかたでオッフェンバックを超えていったこと、そうして不朽の傑作を生み出したことを、連想したり。
いや、そういう踏み台のような芸術家をこそ、私は、大好きで大好きでたまらないのだけれど。
五月二十七日(金)涅槃交響曲
下野竜也&新日本フィルをすみだトリフォニーで。三善晃の管弦楽のための協奏曲、矢代秋雄のピアノ協奏曲、黛敏郎の涅槃交響曲、という素晴らしいプロ。
涅槃交響曲ではバンダを三階席などではなく、一階席を前後にわける中央の通路に配置。珍しい形だが、ホールの構造上これしかないのかも。自分は上手側の柵の後の二列目だったので、木管群と鉄琴の後ろできくことに。下手はホルン、チューバ類だったから、それよりはよかった。しかも下手にはモニターテレビがおかれて、指揮者の正面の姿が映っていたから、あちらはまさしく「錦糸町にいながらにしてサントリーホールP席にご招待」状態だったはず。
そして、下野さんが登場してオーケストラを立たせると、バンダの人たちも起立。隣席の知人も、思わず一緒に立ちそうになっていた。豊富な舞台経験のたまものか。
しかも開演直前、少し離れた席にいた大学の先輩(特に名を秘す)が、「おやじ、涅槃で待ってる」とか突然口走ったため、当時たけしが『オールナイトニッポン』でしゃべっていた「おとうさん、ねはんですよ」(桃屋のCMののり平の口調で)とか、「ネハンデルタール人」といったしょうもないギャグが、頭の中で猛然と甦り、我を失いそうになる。
さて演奏、矢代秋雄のピアノ協奏曲が白眉。独奏のトーマス・ヘルのピアノはタッチのやわらかさといい響きの絶妙のコントロールといい、日本人にはなかなか真似できない響きで、この作品の国際性を示してくれた。
しかし、涅槃交響曲の合唱(藝大合唱団)や鐘の響きまでが完全に西洋風だったのは、二十一世紀の国際化を思えばしかたのないこととはいえ、この作品の衝撃性を薄れさせていたような。お寺の経営がどこも苦しいというのも今の日本では当然だよなぁ、などと考える。
五月三十一日(火)ヴィオラスペース

上野学園石橋メモリアルホールで『ヴィオラスペース2016』初日。
二十五回記念の今回は「ヴィオラの誕生! バロックへの回帰」と題し、初日がテレマンやヴィヴァルディ、第二日がバッハ。
初めにテレマンの《六つのカノン風ソナタ》から第一番と第四番。ヴィオラ奏者四人が客席に登場、前方中央の客席を正方形に囲んで通路に立つ。合計で六つ楽章があるので、四人のうち二人ずつ、上下左右の辺と二つの対角で演奏していくという趣向。二十七日の涅槃と違い、自分の席が正方形のなかにあったので、今回は響きに囲まれるような面白さを味わえた。こういう差が出るのは難しい。
続いてアントワン・タメスティが舞台に立ち、今回はガット弦とバロック弓を用い、ピッチも低めにして演奏すると説明。今月は強めの響きをきくことが多くて、辟易気味だったのでありがたい。
そのあとヴィオラ・ダ・スパッラ(肩掛けのチェロ)や、ヴィオラ・ダ・ガンバ、ヴィオラ・ダモーレなど、ヴィオラと名のつく古楽器もまじえて、室内楽や協奏曲。それぞれに楽しんだが、タメスティがひくビーバーの《パッサカリア》が印象に残る。舞台を暗くし、ひきながら舞台袖に現れ、中央に歩いていく。心臓の鼓動とリズムとの、不可欠の連関。
明日のバッハもききたくなったが、新国立劇場の《ローエングリン》を先に入れていたのでムリ。残念。
六月一日(水)世の憂き人に伝ふべし

十三時から国立能楽堂の定例公演(狂言『腰祈』と能『羽衣』)、十七時から新国立劇場《ローエングリン》の、国立劇場系ダブルヘッダー。
四月から国立能楽堂の公演をみるようになって、少しずつ慣れてきた。能楽堂の定例公演は長さが二時間前後(狂言三十分で休憩二十分、能一時間前後)と、クラシックのコンサートとほぼ同じ。一回四時間とドイツ・オペラ並に長い歌舞伎や文楽よりも、みやすい長さ。狂言の開放と能の集中の、相異なる組合せも気持いい。
今日は佐藤友彦(和泉流)の狂言『腰祈』に続いて、藤井雅之(宝生流)の能『羽衣』。
『羽衣』はよく知られた名作で、駿河の三保の松原の浜に、天人(天女)がおりて水浴しているところに居合わせた漁師が、松にかけられた羽衣を奪う。天人は地上では長くは生きられない。早くも死の徴、「天人五衰」が現れる。哀れに思った漁師は、舞をみせてもらうかわりに羽衣を返すことにする。羽衣をきて天を舞い、やがて高空に消え、月の宮に帰る天人。
今回は、盤渉(ばんしき)という小書(こがき。特殊演出)による。徹底した先例主義の伝統芸能にも、流派の違いに加えて、種々の小書の採用によって変化が生じる。序ノ舞の途中で笛の調子が高くなるのが主な変更点、とあり、太鼓も加わって囃子は華やか。
しかし自分にとってこの演出が印象的だったのは、結びのところ。
本来はシテの天人が舞台で舞を留めて終るが、この小書ではシテは橋懸を通って幕に入り、見送ったワキの漁師が、舞台で留め拍子を踏んで終る形となる(脇留、というそうだ)。
その、シテが舞台から離れていく動きが、「天の羽衣。浦風にたなびきたなびく。三保の松原、浮島が雲の。愛鷹山や富士の高嶺。かすかになりて。天つ御空の。霞にまぎれて。失せにけり。」という謡の、天人が舞いながら松の高さ、愛鷹山の高さ、富士の高さへと次第に天に昇り、霞のなかに遠くなっていく光景を暗示する。
そして橋懸の途中で、袖を振る。その回る袖そのものが、高空で嬉しげに舞う天女の、遠い小さな姿のようにみえた。
やがて点になって、空に吸い込まれ、消える。
もはや何もない。一場の夢の終りに残った、現世の果てしなき青空。ただ見上げ続ける男。
しかしこの男は、そのあとも夕霞の空を見上げるたびに、天女が舞う美しい幻影を、はるかな高みに見ることだろう。その平凡な人生の、限りある生命のつきるまで。舞を始める前、天人は言った。「世の憂き人に伝ふべし」。世を憂い、嘆く人に、我が舞を伝えよと。
こういうイメージを与えてもらえるから、自分は舞台をみにいくのだと思う。
大がかりなもの、広いもの、激しいものを凝縮して、小さく狭く静かな空間に映す、見立ての美。年々歳々、獰猛なものについていけなくなっている身には、まことに心地よきもの。
和漢の古典を巧みに採り入れた、詞章の美しさも大きな魅力。日本語をちゃんと勉強しなければ、と今更ながら思う。
それにしても、能舞台の「橋懸」は、客席の只中を通って、客と一体化するためにある歌舞伎の「花道」とは、まったく違うものなのだと痛感。
異界への架け橋。
そのあとは《ローエングリン》。この世ならぬものが高空からおりてきて、一瞬だけ現世の人間と交わるというところが『羽衣』に似ているので、我ながら乙な組合せだと思ったのだが…。
イメージを与えてくれるのではなく、人のものまで壊してまわるような演出だったと、四年ぶりに骨身に沁みた。
ただ、プログラムで歌人の須永朝彦さんがルートヴィヒ二世について書いた一文を、以下のご自身の歌で結んでいるのが嬉しかった。
「白鳥に五衰はありや たとふれば美しかりしバヴァリアの王」
六月十一日(土)ドイツからの荷物

写真は昨日届いたディスク。CPOはドイツのJPCで買う方が断然早くて安い。上がヴェンツァーゴのブルックナー全集(メーキングDVDつき)、下がシラー原作のフィビヒの歌劇《メッシーナの花嫁》(キンボー・イシイ指揮マクデブルク劇場)、右がシルマー指揮のレハールの《ジュディッタ》(これは大期待)、左は男声合唱のレーゲンスブルク・レンナー・アンサンブルによる「フランツ・リストとその時代」。
JPCではノット指揮バンベルクのマーラー全集SACD十二枚組(TUDOR)がEUR50.41(送料別)という安さで出るので楽しみにしていたが、七月八日発売になってしまったので、しばしおあずけ。
ヴェンツァーゴは箱になったのは便利だが、初出分売時のそれぞれ色調の違うジャケも大好きなので、結局はどちらも手元に置いておくことになりそう。
六月十二日(日)宇野功芳さんの訃報
ネットに宇野功芳さんの訃報。
思い出は少なからずあるが、初めてお目にかかったときにご相伴に預かった、二十年ものの赤ワインの濃厚芳醇な味わいが、笑顔とともに脳裏に甦る。
いまはただ深く感謝し、ご冥福を心よりお祈りするのみ。
六月十三日(月)三十夜から
さぼりっぱなしだった演奏会の感想。
いまふりかえると、五月一日から六月十日までの四十日間に、三十の演奏会やオペラや能狂言に通った。もともと人より脳の容量が小さいのに完全なオーバーフローで、毎日きくだけで精一杯。これでは演者に対しても失礼で、次からは少し考えねばと反省。「お仕事」や義理ではなく、ききたいからききに行ったものばかりなのだが。
そのなかで、特に印象に残っている事柄をいくつか。
まずは五月二十八日、サントリーホールでウルバンスキ指揮東京交響楽団。これは演奏会よりも、来年三月のNDR響との来日公演のための、本番前のインタビュー仕事がメイン。まだ日本ではサイトも立ちあがっていないが、NDR響のサイトなどには情報がすでに出ている。
ウルバンスキはまだ三十三歳だが、昨年からNDR響の首席客演指揮者に就任しており、ベルリン・フィルにもデビューするなど、まさに昇竜の勢いにある。早くもかなり忙しくなってきているようで、NDRとの公演前の来日は今回が最後のチャンス。来年三月の話だがここでインタビューということになった。
先方が指定してきたのは、ゲネプロ終了十五分後から本番三十分前までの四十五分間。いくら先方の指定とはいえ、本番直前の貴重な四十五分に、まともに話などしてもらえるのだろうかと不安だったが、これがにこやかに、立て板に水。四百字詰め原稿用紙十五枚分なんて絶対に無理だよと思っていたが、とれた。
ポーランドという、現代の音楽シーンでは辺境ともいうべき国から出てきて、これから世界をつかんでやろうという若者の野心と意欲は、むしろ清々しいくらいほどだった。
そのあとの本番のチャイコフスキーの交響曲第四番も素晴らしかった。この四十日間で何よりも食傷したのは、モダンのピアノとロシア音楽の、弾力がなくて獰猛な、打楽器的なサウンドの要素だったのだが、ここにはその代りに、爽快なしなやかさがあった。前回の来日よりも明らかに成長していたし、これから世界屈指のオケとの経験を重ねて、さらに伸びるのだろう。まさしくライジング・スター。ちなみにNDR響と最初のディスクであるルトスワフスキもいい演奏。その後の発売予定も教えてもらった。
次は六月四日の「ウィーン・フィル トップメンバーによる室内楽の夕べ」を東京文化会館小ホールで。ダナイローヴァ(ピアノ)、トバイアス・リー(ヴィオラ)、カール=ハインツ・シュッツ(フルート)。ピアノが入らないこの三人によるベートーヴェンのセレナードの綾なす響きの妙が、その前のピアノとの一人ずつの共演では、消えていたことに考えさせられる。ピアノの強い響きに張りあって、押し込むような弾力のないリズムと、濁った音色になっていた。
ピアノの発展があればこそ、十九世紀後半から二十世紀のクラシック音楽の名作の大半が生まれているのだけれど、その剛性のあまりの高さが、音楽から奪ったものも少なくない、などと考える(この時期がロシア音楽の黄金期と重なるのも、おそらく偶然ではない)。
二日後、再び文化小で、フォークトの歌う《美しい水車小屋の娘》。歌いあげる、張りあげるということを避ける歌唱法なので、どうしても旋律の呼吸感が小さくなる。いかにもコレペティのピアノらしい、アウトラインは押さえているけれど、きちんとひいてはいないピアノも気になる。

七日、サントリーホールでクレーメルとリュカ・ドゥバルグのデュオ。
これは驚いた。ピアノへの懐疑が高まっていたときだけに、このドゥバルグは啓示のようだった。
ピアノの可能性を信じさせる演奏。叩かない、繊細な軽めの音なのに、広大なサントリーホールの空間に、凛と鳴りわたる。水面に波紋が次々とあらわれるような横の広がりと、深い水底までみえるような透明な奥行きをもつ、美しい《夜のガスパール》。デュオの曲でも、ヴァイオリンの音をつぶしたり、煽ったりすることなく、完璧に共存させる。
この人はあまりピアノをひかずに、楽譜を読むことで音楽をイメージしていくそうだが、もしかしたら、自らの楽器、すなわちピアノの音への深い懐疑と嫌悪という、グールドのそれと似たようなセンスをもっているのではないか。だからこそ、ピアノという楽器の限界を超えていこうとしているように思える。
すごく楽しみだし、クレーメルが自分で連絡して共演を依頼したという話も納得。そして、プログラムの最後にクレーメルの近年のECM盤の広告がでていたのだが、それをあらためてみると、ブニアティシヴィリにトリフォノフと、個性は異なるけれども、いずれも只者ではない音感覚をもった若手ピアニストを、クレーメルが起用し続けていることに気がつく。
そういえば八〇年代、アファナシエフが本当の意味で日本の聴衆にその存在を知られたのは、クレーメルが伴奏者として連れてきた、一九八三年の来日公演が始まりだった。八六年、二回目の来日できいた(そのときはもう、ヴァイオリン・リサイタルではなくデュオ・リサイタルと名うたれていた)、この二人がガラガラの東京文化会館でひいたシューベルトのファンタジーの心揺るがす音楽は、いまも耳に残っている。
あれからちょうど三十年、クレーメルはドゥバルグをつれてきた。ミュージックバードの番組「ウィークエンド・スペシャル」で、「クレーメルのピアノ ~クレーメルと若手ピアニストたち」なんて番組がつくれそうだと、考え始める。(たぶん九月放送)
おしまいに、十日オペラシティリサイタルホールでの、水戸博之指揮オーケストラ・トリプティークによる「黛敏郎個展」。涅槃交響曲までの過程ということで、戦後から五〇年代までの作品。戦後の時代精神と音楽の関わりとを考えさせる、とても面白い選曲。
アメリカ文化の洪水のような流入。進駐軍の慰問演奏で、懐の暖かい音楽家たち。ジャズを採り入れた《オール・デゥーブル》。
しかし日本の教養人は、アメリカそのままよりも、そのジャズがフランス近代音楽に採り入れられたことに注目して、そこにヨーロッパとのつながりを見いだそうとする。一九四八年、十九歳の黛が作曲したディヴェルティメントは、まさにフランス近代音楽風の明朗なユーモアで、戦後民主主義が輝いた三年間を象徴するような作品。
ところが、黛はISCM(国際現代音楽協会)の音楽祭にこの曲で応募したのに、落選してしまう。一九五一年、黛はついに入選して国際的知名度を高める。しかしその曲は、一転してアジア音楽をとりいれた《スフェノグラム》。
欧米人のエキゾチシズムに媚びたように感じられなくもないこの曲、面白いことに黛が使ったアジア音楽の歌詞と旋律は、じつは戦時中につくられた「東亜の音楽」という、大東亜共栄圏思想によるSPから、自分の耳で採譜したものだった。「近代の超克」の影。
五〇年代になると黛は、十二音による《六重奏曲》や、電子音楽など、国際的な流行を敏感に採り入れていく。「名誉白人」的音楽。しかしそこから、日本的な要素へ。涅槃交響曲は、黒船からGHQにいたる、圧倒的な西洋との遭遇の歴史が生み出したもの。
黛の音楽的彷徨を端的に示すような作品を、特殊な編成だけに演奏されにくい作品を、実際に音できけてとてもありがたかった。
では、一九五八年に涅槃交響曲で一つのクライマックスを迎えた黛は、そこからどこへ進んだのだろう。これは、演奏会が私に突きつけてくれた疑問。
六月十四日(火)ソニービルのハンター
銀座のソニービル解体のニュース。
ソニービルといえば地下のハンターと音の出る階段だろ、なんていうのは、年季の入ったクラヲタだけ。
六月十五日(水)カウベル鳴らせば
秋田県の山中で四人の遺体が次々と発見され、本来は人を襲わないはずのツキノワグマが、人肉の味を覚えてしまったのではないかというニュース。
二十五年ほど前、送電線工事の仕事で山梨県塩山市の宿舎にいたころ、その工事現場は機材をヘリで運ぶような山の上ばかりだった。人間は車で行けるところまで行き、現場まで山道を四十分も登って、毎日通う。
そういう現場で、私の仕事は単独行動が多かった。そのため欠かせなかったのが、ナップザックにカウベルをぶら下げること。歩く振動でこれをガラガラ鳴らすことで、クマに人間の存在を遠くから教えてやる。そうすれば怖がって逃げていくので、それによって、不意に遭遇することを防ごうとする工夫だ。
なので、今でもマーラーやシュトラウスの曲でカウベルをきくと、反射的に山梨の誰もいない山道の光景が脳裏に甦ったりする(笑)。
ところが、こういうふうに「人間は食べ物」(なんか「カレーは飲み物」みたいだ…)と思っているツキノワグマが出てきたとなると、むしろカウベルはそれを呼び寄せる「破滅の鐘」になってしまうことになる。恐ろしい。
近いうちに、襲われる場面を夢に見そうな気がする(北海道出身の電工さんなどは、なんたってヒグマの出没する現場で仕事してきただけに、比較にならないその恐怖を、昼休みなどによく話してくれたものだった…)。
連想したのは、東宝映画『サンダ対ガイラ』の一場面。初めのうちはガイラが光を嫌うというので建物の照明をつけることが奨励されるけれども、頭のいいガイラはそこに人間がいることを覚えて襲うようになるので、逆に消すことが指示される。ところが次に襲ってきたとき、その指示が徹底しきれてなくて、明かりをつけてしまう人もあちこちにいる。それをみて登場人物たちが「困ったな」と頭を抱える場面。
こういうところ、昔の脚本はディテールが妙にしっかりしていて、それが全体のリアリティにつながっていた。
話を電気屋時代の現場に戻すと、いちばん山の上の現場で仕事していたときには、作業員さんのなかに元は青森の山の炭焼きだったというおじいさんがいて、何百メートルも離れた場所に湧き水を見つけて、そこまでゴムホースをはって水道をつけてくれたりしたものだった。
山上でゴシゴシ顔や手を洗ったり、熱いお茶を沸かしたりできるのは、本当にありがたかった。水がどのへんにありそうか、素人にはまるでわからない――現に、別の作業班がその前に半年以上かけてそこで作業していたのに、誰も湧き水の存在など気がつかなかった――が、地形などから長年の経験で見当がつくらしい。当然キノコの種類や判別にも詳しくて、晩秋になればキノコ入りのインスタントラーメンとかみんなでつくって、冷たい弁当と一緒に食べたものだった。
ああいう人のいいおじいさんみたいな人たちが襲われたのだろうか……。人もクマも、どちらにとっても不幸。
六月十六日(木)ハニガンのサティ
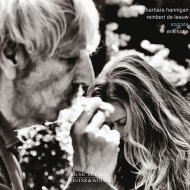
少し前に買ったまま、きけていなかったCDをようやくきいている。
バーバラ・ハニガンがラインベルト・デ・レーウのピアノで歌う、生誕百五十年のサティ作曲の交響的ドラマ《ソクラテス》と歌曲七曲。とくれば悪いわけない。そのとおり。何をか謂わんや。
素敵。妖しく息づき、ささやいて揺れる、青白き炎の如き歌曲。無垢の少年が語るかのような、ソクラテスの死。
六月十九日(金)音楽の大使
ようやく『演奏史譚一九五四/五五』の四十六話の執筆が佳境に。
「二つのベルリン、一つのウィーン」と題して、一九五五年秋に十年ぶりに再建されたベルリン国立歌劇場とウィーン国立歌劇場、それぞれの状況を中心に。
分断されたベルリンでは、東ベルリンの廃墟ウンター・デン・リンデンに再開された前者が、西ベルリンの芸術週間の祝祭の日々(カラス&カラヤンのルチアなど)と競う。
一方、統一して独立したウィーンではベームのもと、ユダヤ人ワルター、ハンガリー人ライナー、チェコ人クーベリック、ドイツ人クナッパーツブッシュをあつめて、往年の多民族国家ハプスブルク帝国の栄華の夢を追うけれど、そこにもひたひたと忍び寄る、カラヤンと世界歌劇場の影。
両方の再建記念公演をみた山根銀二を狂言回しにしようという章(少し遅れてベルリンに入った、『ビルマの竪琴』の竹山道雄のことも少し)だが、その下準備のときに気になったのが、ヴィルヘルム・シュトロス室内管弦楽団が一九五五年九月、ベルリン芸術週間の最中にモスクワで行なった演奏会のライヴ盤。
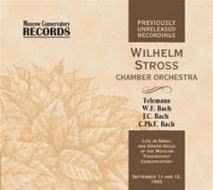
分断が既成事実化して、西ドイツとソ連がものすごく仲悪そうな時期に、なぜロシアを訪れたのかが不思議だった。
中公新書の『アデナウアー』を読んでいたらわかった。九月八日に西ドイツ首相アデナウアーはモスクワを初訪問、国交樹立と引換えに、戦時捕虜と抑留者三万人の解放を約束させた。
交渉旅行にアデナウアーが「音楽の大使」、親善使節として帯同したのが、シュトロス室内管弦楽団だったというわけらしい。チェロ独奏はシュトロス弦楽四重奏団でチェロをひいていた、盟友のルドルフ・メッツマッハー、つまり指揮者インゴの父。
当時のロシアには室内管弦楽団という概念そのものが存在しなかったので、かれらのバロック演奏は大きな衝撃をもたらした。感激したバルシャイが直後に設立したのが、モスクワ室内管弦楽団なのだそうな。
そしてこの交渉の結果、やっと十年以上ぶりに帰国できた捕虜のなかに、敵機撃墜の世界記録保持者、三百五十二機撃墜のエーリヒ・ハルトマン少佐がいた、という話までは、さすがに『一九五四/五五』には入れないつもり。
六月二十一日(火)景清の太陽
演奏会と能の感想。
今日は、トッパンホールでケラス。
・ラッヘンマン:プレッション
・黛 敏郎:BUNRAKU
・コダーイ:無伴奏チェロ・ソナタ
・細川俊夫:線Ⅱ
・藤倉 大:osm~無伴奏チェロのための(トッパンホール十五周年委嘱作品/世界初演)
・ブーレーズ:メサージェスキス(七本のチェロのための)
すべて近現代、チェロ六人と共演する最後のブーレーズ以外はチェロ一挺という、トッパンホールでしかありえないようなプロ。しかも完売。どの曲でも特殊奏法、特殊調弦が多用されるが、せせこましくなることなく、ケラスは伸び伸びと多彩な空間をつくる。
モダンピアノの伴奏しない弦楽器は、自由闊達でいいなあと、ピアニストに殴られそうなことを考える。もちろん、ケラスの豊潤な音楽性と構成力あっての話だが。でもやはり、バロックまでの「通奏低音」とロマン派の「ピアノ伴奏」とは、どうしてああも意味合いが違うのだろう。だからこそ「西洋芸術音楽」が十九世紀に成立したのではあるけれども。
十九日は池袋でカンブルラン指揮の読響、十八日は紀尾井シンフォニエッタのこの名称での最後の演奏会。
前者は《火の鳥》組曲、後者はペルトの《タブラ・ラサ》が特に印象に残る。ここでのプリペアド・ピアノはほとんど鐘の音。反復のなか少しずつ変化して、拡がっていく波紋。
それにしても、コンマスと独奏をかねたバラホフスキーと奥さんの第二ヴァイオリンのミンニエヴァ、顔がそっくりなのが愉しい。きっとバラホフスキーのお母さんも同じ顔をしてるのではないか。

十七日は国立能楽堂へ。狂言『太刀奪(たちばい)』大藏彌太郎(大蔵流)と能『景清(かげきよ)』塩津哲生(喜多流)。
勇猛で知られた平家の部将、悪七兵衞景清。平家滅亡後は日向に流され、盲目の乞食と落ちぶれている。鎌倉から訪ねてきた娘の人丸の前で、屋島合戦での自らの戦いぶりを回想し、物語る。そしてこれを今生の別れとして、早く鎌倉に帰って自分を弔ってくれと、娘を出発させる。杖を頼りに、ゆっくりと去る景清。
追憶として語られる、屋島の戦いの鮮やかさ。赤旗の平家の舟が浮かぶ青い海と、白旗の源氏の騎馬が並ぶ白い砂浜。陽光にきらめく鎧武者の華やかな色彩。回想の冒頭に登場する平家随一の猛将、能登守教経の逞しい立ち姿。
そして合戦。上陸した景清が、逃げる敵の三保谷十郎を追う。相手の兜の後ろの錏(しころ)をつかんで引けば、錏がちぎれて三保谷は一目散。離れたところでふりかえり、「お前の力は強いなあ」と感心すると、「なんの。お前の首こそ強いなあ」と景清がにっこり破顔する。男と男の、戦場の会話。生命が輝いた瞬間の、屋島の太陽。盲いた景清が、再び見ることのないもの。
こういう場面が現実ではなく、過去の追憶として、そのイメージが能の舞台に甦える。平家物語が好きで読んでいて、しかし不思議だったのは、その文章以上のもの、もっと明快で生々しいイメージを、過去の読者たちがもっているらしいことだった。能のにわかファンになり、それは能の舞台化によるものではないかという気がしてきた。
その特徴として、長い物語全体を舞台化するのではなく、名場面を少しずつ切り取る。それだから無理が少ない。観客は物語全体を知っているから、わずかな言葉や小さい場面や動きから、全体へのつながりを想像できる。たとえば「能登守教経」と名前が出るだけで、勇猛ぶりが目に浮かぶ。これもまた「見立て」。
ほかにどんな名作があるのか、ゆっくりと味わいつつ学んでいこうと思う。
今日はこれまでの正面ではなく、脇正面の席を買ってみた。横目で橋懸をみることになるし、舞台も舞台袖からみているような印象。それだけに後見の動きなどはよくわかるが、一度正面からみて、作品の姿そのものに正対してからの方がよさそう。
驚いたのは、景清が人丸と親子の情愛を交わす場面で、シテのセリフがしどろもどろになったこと。後見が助け船を何度か出していたが、なかなか戻らず、しばし字幕も停まったまま。字幕のために素人にもわかってしまうのが怖い。
あと、世阿彌よりも少しあとの時代のシェイクスピアにもニワカな興味がわいていて、あの時代のロンドンの演劇も装置がなくて舞台も狭く、ほとんど見立てだったらしいと知る。女性もいない。
そこからの歴史の差。
六月二十二日(水)ずんだ餅
『真田丸』第二十四回「滅亡」をみる。小田原攻めと開城、後北条氏の滅亡。そして三成版「のぼうの城」。
地生えの戦国大名たちの悲哀。三谷ドラマでは人間の「役割」が常に明確で、時代劇の場合はそこに「歴史的位置」が加わってくる。役割と位置がずれたりねじれたりてしまい、「身の置き所のなくなったヤツ」への視点がつねに温かいのが、この脚本の魅力。ここではもちろん北条氏政(高嶋政伸)。最後の最後まで「二度汁」をつらぬく男(笑)。そして真田父も家康も景勝も、このズレとどう折り合いをつけるか、それぞれに苦しんでいる。
そこへ闖入する伊達政宗。東北という僻遠の「場所」に生まれたがために「時代」に遅れた男。信繁と同い年とは失念していた。治世向きの第二世代のなか、ひとりだけ乱世向きの英雄おとこ。しかし自らを韜晦する賢さをもっている。私の亡父が仙台人で、ずんだ餅に異様な郷愁と愛着を持っていて、しばしば周りから迷惑がられたこと(好き嫌いがはっきり分れる味だから)を思い出して、個人的にも餅つきの場面は楽しかった。
政宗役の長谷川朝晴、自分は知らない人だったが、餅つきの場面での甲高くて軽い声と、あとで信繁にあったときの低めの声と、声を使いわける工夫をしていたのが好き。やはり声の演技は大切。
役者の工夫といえば、内野の家康。山の神が「森繁風にしている」と言い出した。よくみるとたしかに、いままでよりも眉毛の端を伸ばして下へ丸くさげて、あの傑作ドラマ『関ヶ原』で森繁がやった家康の老人顔に、ちょっと似させてきている。まだ髪は黒いけれど。
内野は『風林火山』のときも映画の三船を連想させる演技をいれたり、ちょっとした遊びをする人なので、これからどうなるのか、楽しみ。
幸村ではなく信繁という、史実どおりとはいえ馴染みの薄い名前を採用した意味も、だんだんみえてきた。「幸村」には既成のイメージがつきすぎている。最後には十勇士がいなければ納得できないだろうし。ここにいる信繁は私たちがみたことのない、新鮮な魅力をもった男。
一年の構成も、新府城落城で始めて、中央に小田原落城をおき、最後に大阪落城をおく。とりわけこの小田原落城のエピソードと人間模様(こんなに何回もかけるとは思わなかった。それだけ重要ということか)は、最後の大阪落城と、さまざまな対照をなすように三谷は仕掛けてくるのではないか。小田原は身の置き所のない氏政がひとり腹を切ればそれで済んだが、大阪はそうはいかない。
大阪の陣では、身の置き所がないのは豊臣家の人間だけでなく、入城した牢人衆もみな同じ。小田原落城をその目で見ていた信繁は、大阪の日々をどう生き、死ぬのか。
あと、この話のなかでひとりだけ大阪弁しゃべっている千利休の「死の商人」ぶりも好き。もうすぐ出てくるという、松本幸四郎演じる呂宋助左衛門(黄金の日々!)と、どうからむのやら。期待。
六月二十三日(木)消えた街の気配

夕方から、「音楽の友」のために音楽之友社でジャン=ギアン・ケラスにインタビュー。とても一九六七年生れとは思えない、永遠の好青年。
今回のさまざまなプログラムには、ピアノ伴奏のリサイタルが一度も含まれていない。その意味は? とピアニストに殴られそうなことをたずねると、バッチリとわかりやすく、その意味と意義を説明してくれた。ほかに「音楽的な父」というブーレーズのこと、その指揮で《メサージェスキス》を演奏・録音したときの思い出など。明日の読響とのデュティユーの協奏曲も楽しみ。
そのあと、歩いてトッパンホールへ。ベルリン古楽アカデミーの第一夜、J・S・バッハとC・P・E・バッハ。服装や髪型など、見た目のなんともいえない野暮ったい雰囲気に、一九八三年にみた東ベルリンの街角をとっさに連想する。あの空気。あの人びと。
この団体が、一九八二年に共産圏の東ベルリンで結成されたピリオド・アンサンブルだという気配は、三十年以上の歳月をへても、まだ残っていると感じる。あるいは、隣席の舩木篤也さんがいっていたように、北ドイツ的というべきなのか。サウンドにもその地域性は濃厚。
機能性追求のために、構造的にグローバル化せざるを得ないモダン楽器演奏とのコントラスト。アンチテーゼとしての一面。
二十七日の第二夜では、どんな「ヴェネツィアの休日」をきかせてくれるのか、楽しみ。たぶん、昨年十月にきいたカルミニョーラとヴェニス・バロック・オーケストラの「ヴェネツィア」とは、まるで違う景色のはず。
六月二十六日(日)英国離脱とポンド安
LSOライヴのレーベルから出る、ゲルギエフ指揮のベルリオーズの《ロメオとジュリエット》。この指揮者、レパートリーによるところはあるが、数年間にサントリーホールでやった《トロイアの人びと》がよかったし、ことベルリオーズに関してはききのがしたくない。
なので、SACDだし買うことは間違いないのだが、気になるのがこのPRESTO CLASSICALでの値段。金曜日までは日本円表示で千五百八十円だったのが、土曜には千四百十円。英国のEC離脱決定のポンド安で一気に百七十円下がった。では、週明けにはどうなるのやら。
他のサイトみたいに発送時に課金する方式だと、そのときのレートできまるのでじたばたしてもしょうがないが、この店は注文時のレートで金額が決まる。なので、もう少し待ちたい気もする。
などといっても、自分の場合は変動幅が電車の初乗り料金程度の話なので、単に気分の問題にすぎないが(じつにみみっちい)、商売で大きな金額動かす人は大変だろう…。
六月二十七日(金)イタリアへ
トッパンホールのベルリン古楽アカデミー二日目「ヴェネツィアの休日」。テッサリーニ、ヴィヴァルディ、カルダーラ、マルチェッロ、アルビノーニの序曲や協奏曲。
四日前のバッハよりもずっと出来がよく、本領発揮の日。四日前は日本の梅雨の多湿に人も楽器もとまどったか(コンマスは何度も弦を切った)、さらに編成が変わるたびにマイクの位置を動かしに出てくるNHKのスタッフの、気の利かない動きが奏者の集中を奪ったようにも思え、結果として二人のバッハの厳粛で野暮ったい要素が強調されて、私に一九八三年の東ベルリンの空気を思い出させてくれた。
しかし今日は違う。少しくすんだ響きとかっちりした骨格は北ドイツ風ではあるけれど、旧共産圏の抑圧と疎外の空気までは思い出さない。とりわけ後半の二曲目のヴィヴァルディからは、仮面を外したように快活に弾けた、ジャズ・コンボのようなソロと合奏との対話の快感。これこそバロック音楽の愉悦。
四日前のあのバッハが収録され、こちらは虚空に消える。音楽って、しばしばそういうもの。
アンコールの、ベネデット・マルチェッロの協奏曲イ長調のアダージョでは、舞台上のオーボエと、下手後方の客席扉から入ったヴァイオリンが響きを交わして、素敵だった。
ベネデット(オーボエ協奏曲で有名なのはアレッサンドロで、その弟)の音楽には、たしかにこういう空間性が感じられて面白い。バッケッティのひくイタリア・バロック・シリーズでも、飛び抜けて面白いのがこの人の作品集。もっといろいろな作品をききたい。
隣席の朝日新聞の吉田記者から、ベルリン古楽アカデミーの新譜、《水上の音楽》が素晴らしいと教えてもらう。期待しただけに初日は少しがっかりしたが、今日は満足したそう。自分はそのディスクをきいていないので、早速購入。
六月三十日(木)仏独音楽ぴんぽん
今日はサントリーホールで、スラットキンとリヨン国立管弦楽団。新聞評をやるので細かい感想は控えるが、さすがのエンターテイナーぶりで愉しかった。ところでリヨンのティンパニはカンブルランの弟なのだとか。
そして、昨日まではそのカンブルランと読響の三回シリーズ。スラットキンも(ツアーなのに)アンコールまで含めて筋道を立てた構成が見事だったが、カンブルランも見事。
十九日はベートーヴェンをストラヴィンスキーで挟む曲目。十九世紀初めの革命児と二十世紀初めの革命児のコントラスト。前半はスペインとピアノ、後半は超自然的な「炎」がキーワード。これらのキーワードはすべて「破壊的なまでの支配力」という点で共通する。ただ、カンブルランがベートーヴェンから引き出そうとしている古典性が、自分の力ではまだよく読みとれない。現時点ではストラヴィンスキーが突出した印象。
二十四日と二十九日は、連携するプログラム。隠されたキーワードは「ワーグナー」。新ドイツ楽派の主柱ワーグナーの源泉の一つはベルリオーズであり、リストがヴァイマルにその影響を持ちこむことで、ドイツ音楽になる。そしてそこから流れ出ていく、ブルックナーとマーラー、そしてデュティユー。ワーグナーだけを抜いた形でつくられた、一枚抜けたジグソーパズルのような、見事な二日間のプログラム。
二十四日は、ベルリオーズの《宗教裁判官》序曲。これは後半の金管のコラールを、そしてその背後のカトリシズムの教会を、ブルックナーに引っかけたいのではないか。
続いてデュティユーのチェロ協奏曲。これはボードレールの『悪の華』から副題が採られている。ボードレールはなんといってもフランスのワグネリアンの元祖。その意味で、ブルックナーの交響曲第三番《ワーグナー》と、独仏ワグネリアン大会のような作品。このチェロ協奏曲は十二月だったか、ノットと東響も取りあげるが、そのときはトリスタンの前奏曲から中断なしに続ける趣向らしい。これも実にノットらしい構成で、「判じ物」的なカンブルランの選曲とは対照的な直球勝負。
二十九日は、リストのピアノ協奏曲第二番とマーラーの交響曲第五番。ベルリオーズとリストの、はっきりいって散漫な構成が、ブルックナーとマーラーにいたって長大な交響曲(きわめてドイツ的概念)になっていくという流れを耳できくことができて、とても面白い。五番は前回の七番同様に発見にみちた演奏で、第三楽章が猛烈に面白かった。あえていえば、きわめてフランス的な、明晰な演奏。
クラシックはとかく、十九世紀のナショナリズム、というよりもショービニズムの文脈で語られやすいけれども、フランスとドイツの文化は、ライン川をはさんでピンポンのように影響を与えあってきた。それを明快に音にしてくれた二日間で、とても面白かった(ブルックナーとマーラーでアンサンブルがなぜか不安定だったのは残念だったが)。
では、イギリスは? これからどうする? それは、東響のジョナサン・ノットに読み解いてもらいたい(笑)。
それから『真田丸』第二十五回。
利休の呪い。愛するものをすべて死に追いやる茶々という存在。しかしその大元には、秀吉のこれまでの所業が、かれに殺された、追い落とされた怨霊たちがいる。「身の置き所」を、何もないところからつくりあげてきた男の、暗い影。
七月一日(金)墨田千人ベルリオーズ
ハーディング&新日本フィルの《千人の交響曲》を、すみだトリフォニーで。
カンブルラン&読響の独仏親善、新ドイツ楽派の流れをより大きく俯瞰したEU楽派(?)シリーズの、その続篇、完結篇のようにも思えるのが、毎度ながらに東京の演奏会の日々の面白さ。ただし指揮はイギリス人。
カンブルランのおかげで、この曲こそドイツ音楽の伝統よりも、ベルリオーズからの流れで考えた方がつかみやすいと思った。
「交響曲」とマーラーが名づけている以上、第一部と第二部は続けて演奏されるのだが、両者の肌合いはまるで違う。
ラテン語の聖歌の第一部と、ゲーテの『ファウスト』終景の第二部という組合せは、ベルリオーズのレクイエムと劇的交響曲を、一遍につなげたようなものなのだろう。第一部は合唱も独唱も基本的にトゥッティなのに、第二部はそれぞれが独立して動き、オーケストラだけの部分も少なくない。これはまさに劇的交響曲の方法論。
ハーディングもよく心得ていて、第一部ではステージ手前からオケ、独唱、合唱と並べるミサ曲スタイルの配置を一切動かさなかったのに(児童合唱は二階のオルガン席上手、下手にバンダ)、第二部は「法悦の教父」と「瞑想する教父」だけにステージ最前列で歌わせたり、栄光の聖母を二階オルガン席下手で歌わせるといった、まさにカンブルランが得意とする、シアターピース的な空間活用を効果的に行なった。
もちろん、《ファウストの劫罰》とゲーテのテクストそのままとでは、ずいぶん違う。ベルリオーズという人は、敬愛するシェイクスピアともゲーテとも母国語が違っていたからこそ、あれほど自由にロマンを音楽で飛翔させることができたのかも、なんてことを考える。「ここではないどこか」への憧れこそ、ロマンチシズムの源泉なのだから(すると、西洋芸術に憧れる日本人というのもきわめてロマン的な存在なのだが、現代の日本人の場合は、それ以前にいま自分のいる「ここ」がそもそも、どこだかわからなくなっている気もする)。
ゲーテのオリジナルに拠ったのは、マーラーがドイツ語圏の人だからこそ。しかし方法論はベルリオーズ。この点で、同じ終景を用いたシューマンの《ゲーテの『ファウスト』からの情景》とは、まるで違う。この曲のハーディングのCDがあったのでききなおしてみたが、これはヘンデル&バッハ~メンデルスゾーンに至る国民音楽的オラトリオの流れを、ロマン的に展開したものだと思う。ドイツ音楽の、二つの大きな流れ。
初日ということもあってか、オーケストラと合唱の技術的限界を意識し、本当のピアニッシモとか急激なギアチェンジなど破綻を招きかねないギリギリの表現をさけた慎重な演奏とはいえ、ハーディングらしいシャープな緊張感は、随所にきくことができた。オーケストラも中盤までよく集中力を保っていた。
新日本フィルも、これで「スター指揮者の時代」が一段落して、上岡との新しいサイクルへ。
カンブルラン&読響がサントリーホールでこの曲をやったら、どんな演奏とどんな演出をするのだろう。それもいつかきいてみたし。
話は変るが、「法悦の教父」と「瞑想する教父」という役名は、この曲をミュージックバードのナレーションで紹介するときに、いつも困る言葉である。
なぜなら、どうしても「法悦の恐怖」と「瞑想する恐怖」との抑揚の区別がつけられない。なにか悪魔の種類を説明しているような感じになる。ただリスナーの方の善意にすがるのみなのだ(笑)。
七月七日(木)禁断症状
仕事がグッチャグッチャになっている今、自分でも思いもよらないことに、能の禁断症状が出ている。
瞬きをした瞬間のまぶたの裏とか、何気なく横をみた瞬間の暗い隅とかに、能装束の人が片膝立ちの姿勢でいて、能管と鼓の音がきこえたりする(もちろん、全然怖くない)。
最後にみた『景清』が先月十七日で、それからほぼ三週間。明後日の『巴』まで少しの我慢。月刊誌もあとひとやま。
七月九日(土)君の名残をいかにせん
国立能楽堂の普及公演に行く。普及公演では、最初に識者による解説がある。スーツ姿だが、本舞台なので白足袋。
解説・能楽あんない「義仲を追い続ける巴」表きよし(国士舘大学教授)
狂言『蚊相撲』佐藤友彦(和泉流)
能『巴』櫻間右陣(金春流)
『巴』は禁断症状を起しながら待った甲斐のある、いや余りある美しい公演だった。木曽義仲の便女(びんじょ)、巴を主人公とする修羅物。国立能楽堂がこのシーズンの隠れテーマにしているらしい、平家物語シリーズの一つ。
国立能楽堂に通い出してまだ数か月、あせらずのんびりと能楽の魅力に接していこうと思っている。つまり、あわてて名作を全部観てやろう、映像や本で勉強しよう、各地の能楽堂を見に行こうなどとせずに、過ぎる季節のなかで、国立能楽堂にかかる演目にまかせて、接していくつもり。
自分がいつまで健康かは誰にもわからないけれど、それでも五年十年あれば、一通りの名作はみられるだろう。四座一流の違いとか、個々の能楽師の巧拙や個人的な好き嫌いは、もともと何も知らないのだから、その過程で、自然にわかるようになっていきたいと思う。
だから、まずは作品を観る、知る。これが今の最大の目的だが、今日はそれと同時に、シテの魅力に惹きつけられた。この数回のなかで、シテ個人の芸に、これほど惹かれたことはなかった。
それは、巴を演じた櫻間右陣(さくらま うじん)。斯界で、また能楽好きのあいだで、どのように評価されているのかはまったく知らない。帰宅後にネットで検索してみても、超大物というわけではないらしい。だから、自分がこれから書くのは素人の早とちりかもしれない。でも、感じたままを書く。
まず、舞姿の美しさ。澱みなく、すーっと流れるような動き。静止したときの緊張感。仕種一つ一つが関連しあい、必然性をもっているようにみえる(演者によっては、ただ段取りを踏んでいるだけのようにみえたこともあるのだ)。
そして、恵まれた容姿。頭と手が小さい。本当に女性の手のようにみえるし、面を顔に載せているのではなくて、面そのものが顔のようにみえる。ブレのない手と身体の動きとあいまって、文楽の人形のようにみえる瞬間さえある。
写真は、プログラムに掲載されていたもの(前島吉裕提供)。後ジテの、鎧姿(もちろん見立て)の巴。均整の美と姿勢の美、そして凛とした緊張感は、ここからでも充分に伝わると思う。

さて、作者不明の『巴』。木曽育ちの僧(ワキ)が都へ旅する途中、近江粟津の木曽義仲を祀った神社で女が泣いている。これこそ義仲の女武者、巴の霊。粟津での義仲敗死のとき、女を連れていてはみっともないと、伴を許されずに木曽に帰されてしまったことを悔いている。
と、ここまでの義仲の最期については平家物語の原作にしたがっているのだけれど、この作品では巴の霊の妄執に、さらにもう一つの原因をくわえている。これが面白い。
『景清』のときも書いたが、平家物語の世界は能になることでより生々しく、五感に強く訴えるものになっているのではないかという予感、これは今日も当った。一部分を取り出して舞台化し、ふくらませる。そしてそれは、けっして改変ではない。原作に対して、ある種の批評精神をもってふくらませることで、より奥深いものにする。
平家物語での木曽義仲の最期は、はっきりいってカッコ悪い。名もない雑兵に討たれるよりは自害しようと、人のいない場所を馬で目指す途中、深田にはまって動けなくなり、そこを矢で射られて首をとられてしまう。自害させるために敵を引きつけていた乳母子、今井四郎兼平の必死の奮戦も、無駄に終る。
これは、義仲の従者たちにとって、あまりに口悔しいこと。だから巴の霊は、義仲の最期はそうではなかったと言い出す。義仲が深田にはまったとき、自分が助け出し、そして群がる敵を自分が薙刀を振るって追い払っているあいだに、義仲は見事に自害したのだと。
つまり、最後まで伴をできなかったこと、それゆえに主君が雑兵に討ち取られたこと、この二つのために巴は死んでも死にきれない。その執心を弔ってくれ、と僧に乞う。「涙と巴はただ一人、落ち行きし後ろめたさの、執心を弔ひて賜び給へ、執心を弔ひて賜び給へ」
この『巴』の物語構成が素敵なのは、平家物語そのままの義仲の最期も、途中でアイが説明していること。そしてそれとは異なる巴の霊の説明が真相なのか、それとも妄執が高じたあまりの作り話なのか、どちらにもとれるようにしてあること。こういう深さが、本当にたまらない魅力。
そしてどちらであれ、義仲の死骸をそのままに、木曽に落ちていく巴の無念。この場面が素晴らしい。シテ独りの演技だけで、状況も周囲の景色も、そして義仲の遺骸も、すべてが何もない能舞台に描き出されていく。「死骸に御暇申しつつ、行けども悲しや行きやらぬ。君の名残をいかにせん」
君の名残をいかにせん。
なるほどと思ったのは、ここでの巴は義仲と夫婦などではなく、今井兼平の妹でもない。平家物語にある通りの、ただの従者。男女の情愛はあるにしても、ともかく主従の関係のなかだけで、巴は行動する。
巴は甲冑を脱ぎ捨て、白装束となって笠を被り、形見の品を抱いて木曽へ落ちていく。
「所はここぞ近江なる、信楽笠を木曽の里に」
近江の信楽の笠を被って木曽にいく、と地謡は歌うが、巴は最後にこの詞と異なる行動をする。笠を地面に投げ捨て、さめざめと泣いて、そのまま去る。笠を自身の身代わりに、主君の最期の地に残して、去る(信楽笠置きその里に、という意味なのか?)。
笠を舞台に捨てた瞬間の「バシッ」という響きに、すべての無念がこもる。
ここのところ、恥ずかしながら涙が出そうになった。舞台をみながら泣きそうになるなんて、いつ以来のことやら。
次は二十八日、『竹生島』。
七月十二日(火)ギレリスと三谷礼二
今年はギレリス生誕百年で、DGから一九六四年十二月六日のシアトル・リサイタルの発売予告が出ている。
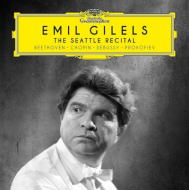
三谷礼二さんが、最初のアメリカ旅行の強烈な思い出の一つとして熱く語ってくれたのが、一九六四年のギレリスのカーネギー・ホール・リサイタルだった。
狂熱的な演奏で、ワルトシュタイン・ソナタのコーダのグリッサンドのところで、ギレリスがブワーッと鍵盤を走り抜けた瞬間、興奮した聴衆がうおーっと、ウェーブを起こすように一斉に立ち上がってしまった場面が忘れられないと、目を輝かせながら話してくれた。
このシアトル・ライヴのワルトシュタインに、似たものが入っていることを祈るのみ(数年後のフランス・ライヴがCD化されたが、それはさほどではなかった)。三谷さんはシューベルトの《楽興の時》の素晴らしさもあげていたが、曲目が違うのか入っていない。しかし難技巧の作品ばかりで、当時のギレリスの流儀がうかがい知れそう。どんな音質なのかわからないが、DGなのだからそれなりのクオリティではあるはず。
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第二十一番《ワルトシュタイン》、ショパン:モーツァルトの《ドン・ジョヴァンニ》の〈お手をどうぞ〉による変奏曲、プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第三番、ドビュッシー:《映像》第一集、プロコフィエフ:《束の間の幻影》から六曲、ラヴェル:道化師の朝の歌、ストラヴィンスキー:《ペトルーシュカ》からの三楽章から〈ロシアの踊り〉、バッハ(シロティ編曲):前奏曲ロ短調(原曲:ホ短調)
と書いていて、連鎖的にもう一つ思い出した、三谷礼二の語るギレリスの思い出その二、題して「昨日のハイドシェック」。
みなさん故人なので、実名で。
一九七二年に来日したギレリスのリサイタルのときのこと。そのときのギレリスのスタイルは一九六四年のカーネギー・ホールとはまったく反対の、ひたすら凝縮していくものだった。
(四月二十二日の東京文化会館大ホールのリサイタルだとすると、モーツァルト :ソナタ変ロ長調K二八一、シューベルト:楽興の時、リスト:ソナタ ロ短調というプログラム)
そのあまりの美しさに、終演後のロビーで三谷さんと若杉弘さんが呆然としていると、そこに遠山一行さんがあらわれて、「ヒドイねぇ…」という。
えっ、と驚いた二人が呆然としていると、「昨日のハイドシェック、よかったよ~」といって消えてしまった。
やはり二人が呆然としていると、居合わせた別の知人(名前忘れた)が、「あいつ何いってんだ。頭に来た。おい、送ってってやるから俺の車に乗れ!」と強引に誘う。
車中、その人が怒るの怒らないの。
「何が『昨日のハイドシェック』だ! 馬鹿野郎!」
以来、「昨日のハイドシェック」という言葉が仲間うちで流行ったそうだ。
東京文化会館のサイトのアーカイヴを調べると、たしかに前日の二十一日に、ハイドシェックが同じ場所でリサイタルやっている。
・昨日のハイドシェック
モーツァルト:幻想曲ハ短調K四七五、ピアノ・ソナタ ハ短調K四五七、ベートーヴェン:エロイカの主題による変奏曲とフーガ、ドビュッシー:六つの前奏曲(前奏曲集第二巻から)、ルーセル:ソナチネ。
この話のおかげで、ハイドシェックときいて私の頭に浮かぶのは宇野功芳さんではなく、まず遠山一行さんなのだ。もちろん、「昨日の」と枕詞つきで。
七月十六日(土)ニコラス・ナボコフ
今週と来週は演奏会も最低限で我慢して、『一九五四/五五』の四十六話「二つのベルリン、一つのウィーン」の仕上げに没頭。
冷戦時代の東西ベルリンは、竹山道雄が「人生の實存的不安とそれの中での主體性を、ここほどはっきりと生きている人間はいない。これこそ現代の精神的狀況の象徴である。西ベルリン人こそはまことの現代人である」と語った通り、本当に二十世紀後半の世界を象徴する街だった。
竹山や山根銀二、そして西ベルリンにほれこんだ吉田秀和の言葉を読んでいたら、たしかに一九八三年に自分が通過した(ほんとに通過しただけ)ヨーロッパの都市の中で、あれほどヒリヒリしていやな気分の、しかしあれほど魅力的だった街がほかになかったことを、まざまざと思い出した。
というわけで、これまでの各話の字数制限をここだけぶっ壊して、好きなだけ書くことにしたのだが、そこで大きくなってきたのがニコラス・ナボコフ(一九〇三~七八)という、作曲家・文化人。小説『ロリータ』を書いたウラジーミル・ナボコフのいとこで、ロシアに生まれて革命でベルリンに移住。ナチス時代はアメリカへ。そして戦後はベルリンで、米軍の非ナチ化政策に関わり、フルトヴェングラーの活動再開に尽力(これ以上延ばすとソ連地域の東ベルリンだけが活動許可を出し、ベルリン国立歌劇場にとられてしまう可能性が高まったため、急いだそうだが)し、一九五〇年に文化自由会議を創立、その事務長となる。
この文化自由会議は圧政から文化の自由を守る、簡単に言えば反共組織。『一九五四/五五』を書いていると、このナボコフが東京、ローマ、ベルリン、冷戦の最前線に何度も顔を出してきて、そして吉田秀和や山根銀二、竹山道雄たちと直接間接に関わっている。
こうなると、何かちゃんとした資料がないとまずいと思っていたら、うまいことに昨年、アメリカでヴィンセント・ジロー著の評伝が出ていた。腑に落ちることばかりで助かったが、驚いたのは、フィルハーモニア・フンガリカとの関係。
一九五六年のハンガリー動乱で逃げた若手ハンガリー人音楽家が、ウィーン近郊に集まってオーケストラをつくりたいとナボコフに連絡してきた。これほど文化自由会議の目的にふさわしい活動はないので、ナボコフはメニューインと組んでオーケストラ設立に奔走する。そしてフォード財団とロックフェラー財団(どちらも反共文化活動の大資金源)に資金を出してもらい、一九五七年四月にウィーンで最初の演奏会を行なう。発起人の指揮者ロジュナイが指揮、メニューインがひくバルトークの二番の協奏曲など。
ところがここで、楽員からロジュナイの力量不足への不満の声があがる。ちょうどスキャンダルで仕事がないグーセンスを紹介したが、うまくいかない。そこで担ぎだしたのがドラティ。その年の秋から無給で音楽監督を引き受けてくれ、さらにフィリップスに話をつけ、LP二枚を録音した。
そのあとはマーキュリーにステレオ録音しはじめるが、今度はドラティと常任指揮者ロジュナイの間が険悪に。ナボコフは間を取り持ちつつ、新たな本拠地を探してボンやミルウォーキーに断られたあげく、西ドイツのマールを見つけてくる。一九五九年秋にはアメリカ・ツアーをドラティの指揮で実現し(赤字は文化自由会議が補填)、ロジュナイにはアメリカでの仕事を見つけてやって、最終的にオーケストラから離れさせる。
こういう話を読むと、当然この時期の録音がききたくなる。最初の、一九五七年フィリップス録音とはさてなんぞやと探したら、タワーレコード限定のコンセルトヘボウとのバルトーク作品集二枚組に、特別収録されているヴァイネルのハンガリー民俗舞曲のことだと判明。

LPではバルトークのディヴェルティメントもあるらしいが、こちらは未CD化のよう。しかしともかくありがたい。一九五七年は『一九五四/五五』のエピローグになる部分なので、そこでバッチリと話にケリをつけられることになるから、本当にありがたい。
あと、フンガリカの初期録音で入手容易なのは、一九五八年六月の一連のマーキュリーのステレオ録音シリーズ(レスピーギとか、ウィンナ・ワルツとか)なのだが、そのなかでも早く録音されたのが、コダーイのガランタ舞曲とマロシュセーク舞曲。これは、CDではミネアポリス交響楽団の《ハーリ・ヤーノシュ》などと組み合わされている。

それでそのCDも入手したが、よくみると、メインの《ハーリ・ヤーノシュ》やバルトークの曲のデータにも、引っかかるものがある。ニューヨークからわざわざツィンバロンをミネアポリスまで運んで録音したというこのハンガリー作品集、日付が一九五六年十一月十七日。十月二十三日にハンガリー動乱が始まって、ソ連軍の戦車がブダペストを蹂躙し、大量の難民がオーストリア国境を越えて亡命してくる、その真っ最中。
何らかのプロテストの意味をこめての録音としか、考えにくい。
今年はハンガリー動乱六十周年。ミュージックバードの番組で、シフラとフンガリカの亡命前後特集がやれるかも、なんてことを考え始める(シフラとロジュナイは、動乱直前の風通しがよくなったブダペストで、一緒にラプソディ・イン・ブルーを録音したりしている)。
こんなふうに横道へそれて、どんどんと膨らんでいくので、いつまでたっても『一九五四/五五』は終らないのだが、こんな調べ物をしているときが何より楽しいのも、また事実。
七月十八日(月)真田丸の日々
『真田丸』二十八回「受難」をみた。
とにかく『黄金の日々』ラヴにあふれた回。
助左衛門役の幸四郎が出てくる直前、あのオープニングそっくりの夕日と雲が出てきたのもよかったが、個人的には最初の方の、まずあの壺だけが助左衛門という名前とともに出てきたところでツボにはまる。『黄金の日々』で利休(鶴田浩二)がとんでもない値段をつけて、秀吉(緒形拳)に命懸けの勝負を挑んだあの壺にわざとそっくりにつくってある。利休と秀吉がにらみ合うドアップの場面とか、あそこで安国寺恵瓊(神山繁。この人は『関ヶ原』でも安国寺役で、人呼んで日本一の安国寺役者)がうつ芝居とか、いろんなものが一気にフラッシュバック。
鈴木京香の寧が一人だけ尾張弁しゃべっているのは、『黄金の日々』の同役の十朱幸代の、舌っ足らずの尾張弁がとてもキュートだったことへのオマージュだったのかと、いまさら気がつく。
そして秀次の娘たかが口にする「ぱあどれ」という言葉。『黄金の日々』屈指の名場面の一つ、追放されるフロイスに助左が「パードレ!」と声をかけ、フロイスが権力者の無常を語り、「助左、何も恐れることはない」と諭す場面につながって、それが、今回の助左衛門のあの力強い反権力のセリフの背後を支えているような(今回の利休はまるで違う人間だったが)。
ひとつだけ、「受難」という言葉をここでつかっていいのかどうかは、キリスト者ではない自分でさえ、ちょっと引っかかったが。
オマージュではないオリジナルの部分では、信幸の人物描写がどんどん魅力的に。前回の、惣領たるべしとして自分を厳しく律しているくせに、官位のことでヘソを曲げたりするというのは、いかにも妙なとこでプライドが高い、坊ちゃん育ちの長男ならではの描写で絶妙だったし、今回は、じつはとても女に恵まれている、支えてもらえる男だということが次第にみえてきた。そして先を思えば悲しい、兄弟愛。
ついに出てきた妙な秀忠と、しっかりした正純もとても楽しみ。この物語はほんとに「二代目の大河」になっていく。秀康や忠輝がどう描かれるのかも期待。
『真田丸』の大きな魅力は、『黄金の日々』など、黄金時代の大河をみて育った人間がつくる大河だからこそ、「昔はよかった、それにくらべて今どきの若い者は…」と必ずいわれるだろうことを逆手にとって、「二代目たちの物語」にしてみせたことだと思う。
最後にもう一度オマージュに戻って、今回は締めの「真田丸紀行」もよくできていた。秋田県由利本庄市、羽後亀田。
この地名をきけば、だれもがあのセリフをいいたくなるはず。
「カメダは変りありませんか」
あの人情警官役が『黄金の日々』の秀吉と同じ役者だということを意識しているのか。それとも、大谷刑部の病気に、『砂の器』を意識させようというのか。
七月二十日(水)カラヤン帝国
『演奏史譚一九五四/五五』の四十六話「二つのベルリン、一つのウィーン」をようやく書きおえる。この話はこのディスクのことだったのか、このライヴがこのセッション録音につながるのか、などと発見して喜んでいるうちに、結局通常の一話の六本分、一万九千八百字になってしまった。実質的な最終話にふさわしいボリュームと中身になったので、エピローグの「一九五七年」はごく短くすることに変更(こういうところはいい加減)。あとは四十七話「『バイロイトの第九』発売」のみ。

さて気分転換に、今日届いた海外盤。meloclassicが出した、カラヤン指揮リンツ帝国ブルックナー管弦楽団の弦楽セクションによるバッハの《フーガの技法》抜粋。十二曲、四十五分。
もちろん、完全初出の驚きの音源。一九四四年十二月十四日、リンツの市立劇場での放送録音。ヒトラーが育った町にゲルハルト・ボッセなど優秀な若手を集めてつくった、第三帝国のエリート・オーケストラ。大戦末期のカラヤンはゲオルク・ルートヴィヒ・ヨッフムを追い出してこのオケのシェフになりたいと熱望していたが、ヨッフムに泣きつかれたフルトヴェングラーの介入で阻止されたという。この《フーガの技法》を指揮していたことは知られていたけれど、録音が現存していたとはビックリ。
今月の「モーストリークラシック」の「カラヤン企画」に、このディスクを注文したことまでは書いたが、それがついに到着。聴きはじめたところ。モノラルですがちゃんとした音質。カラヤン流のレガートと、行進曲風の推進力の共存。
七月二十四日(日)千葉から来た復活
今日の午後は、すみだトリフォニーにて、千葉フィルの第二十八回サマーコンサート。音楽監督兼常任指揮者の金子建志指揮で、マーラーの《復活》をメインとする演奏会。
ネコケン先生と千葉フィルは一度聴きたいと思いながらも、普段の会場が津田沼の習志野文化ホールで、川を四本も渡るのをおっくうがって、機会を得なかった。しかし今回は金子さん直々の「面白くなりそう」とのお言葉と、そして会場が隅田川をこすだけの「すみだトリフォニー」ということで、喜んで参上。期待を上回る、刺激に満ちた時間となった。

前半は実演つきレクチャー。金子さんがバーンスタイン風に、指揮台上でマイクをもって語り、ふりかえって指揮をする。まずグレゴリオ聖歌の〈怒りの日〉の主題を、ベルリオーズの幻想交響曲終楽章から実演し、続いてそれより早いシューベルトの未完成交響曲第一楽章初めの弦の刻みにその変形をきき、さらにサン=サーンスの《オルガンつき》終楽章の輝かしい長調版、そして《復活》第一楽章と終楽章からその引用を。「死のイメージ」としてあらわれるこの音型を、マーラーはあからさまに「最後の審判」の情景に響かせた。
自分が思ったのは、これを共有するのはフランスとオーストリア、やはりカトリック圏だということ。プロテスタント圏はあまりこだわってなさそう。
次にマーラーの親友で、夭折したハンス・ロットの交響曲のファンファーレ。マーラーはこれを《巨人》と《復活》のスケルツォで引用している。第三楽章で華々しく登場したのち、一転して暗く沈んで、最後に死のイメージへ。
続いてメンデルスゾーンの無言歌集から、作品六十二‐三の《葬送行進曲》。これは《夏の夜の夢》の結婚行進曲を短調に変えたようなもので、冒頭のタタタターンというフォンファーレ音型は、マーラーの交響曲第五番第一楽章の元ネタと考えられるという。
そこでこのピアノ曲を、金子さんがまずメンデルスゾーン風に、続いてマーラー風にオーケストレーションしたものを演奏。後者は全曲。これは一方ではベルリオーズ風の響きにもなり、また、山田一雄の怪作《おほむたから》(おおんたから)にも通じてくるのがとても愉快。マーラーをはさんで、その原型のメンデルスゾーンと、その変形のヤマカズが出会う面白さ。
二十世紀風の芸術観というか、何となくわれわれは独立自尊、突然変異みたいな天才を偉大な英雄とみなし、芸術における影響や継承をかつては軽侮しがちだったと思うが、いまはそこにこそ、生きた人間の姿をみるようになっている。
休憩をはさみ、いよいよメインの《復活》。金子さんの指揮は拍節感を重視しつつ、杓子定規にならない。響きはつねに明快。独善的な熱演ではなく、作品の姿をきちんと示そうというもの。しかし一方で、マーラーがこの作品に仕掛けたハッタリ、ケレンといった要素もやはりきちんと示してくるのが、好感度高し。
第一楽章が終って指揮者はいったん退場、その間にステージ奥の合唱団が入場して着席。ここまでが第一部で、あとが第二部であることが明確になる。
第三楽章の演奏中に、アルト歌手が二階のオルガン席下手につく。余計な拍手を防ぐには好手。途中のトランペット・ソロは三階客席の上手側から吹かれて、全体から浮き上がる。そしてアタッカで第四楽章に入り、そのまま終楽章へ。
ここで、プロセニアムアーチのない、オープンステージの特性を活かした、空間活用が全開。トランペットによる審判のラッパは、三階の上手と下手、四か所から響きわたる。
オケが盛り上がるところで、ステージ奥の合唱が起立(一部拒否したお爺さんたちあり)。さらに二階オルガン席の上手下手にソプラノ独唱、女声合唱と児童合唱団が入場。
この作品では、声楽の入場の仕方次第で集中が途切れる可能性があるが、じつに巧妙で、納得させられるものだった。
そして金管の空間活用と児童合唱の参加は、この作品がベルリオーズと、のちの《千人の交響曲》(先日同じ会場できいたばかり)の、架け橋となっているのだということを実感させてくれる。さらに男声合唱主体にした導入部は、《パルジファル》のようだった。
オーケストラも頑張っていたし、大編成の合唱の響きの安定感も素晴らしかった。はっきりいって、同じホールで聴いた涅槃交響曲の藝大合唱団、千人の栗友会合唱団より、よほど声の力を感じた。
そして独唱を含めて全体が鳴りひびくコーダでも響きが混濁せず、たしかな見通しできれいに鳴りわたったのは、金子さんの手腕のたしかさ。
今日は全席自由なので、新日本フィルではいつも一階席だから上の方、大編成だからいっそと思って三階正面を選んだが、大正解だった。
アマオケがこうした大編成作品をやるのは、芸術面以上に金銭面、実務面で大変だと思う。しかしその成果は充分以上のもの。この大曲の構造、本質を確かに感じさせてくれた点では、私がこれまで聴いたいくつかのプロオケの実演を、はるかに上回っていたと思う。
この演奏会に関わられたすべての方に対し、心より感謝。
七月三十日(土)戦時のストックホルム
NHKが『百合子さんの絵本 ~陸軍武官・小野寺夫婦の戦争~』というテレビドラマを放送する。
ドイツ降伏から三か月後にソ連が対日参戦するという、日本の敗北を決定づけるヤルタ会談の密約を日本の諜報員がキャッチしていたのに、自分たちの予想がはずれてメンツがつぶれるのを恐れた大本営の一部が、その報告をすべて握りつぶしていた。そのため、負けると決まった戦争が三か月長引き、原爆投下はもちろん、死ななくてもよかった人々の生命が、両軍ともに大量に失われた。
その情報を中立国スウェーデンのストックホルムから送っていた小野寺信の夫人が、ムーミンものを翻訳した人だとは知らなかった。あらためて調べると、私が大好きな『名探偵カッレくん』シリーズを訳した尾崎義という人も、外交官としてスウェーデンにいた人なのだそう。子供の自分が何気なく読んでいた北欧の児童文学の背後にある、時代。
戦時下の中立地、謀略渦巻くストックホルム。この中立国を訪れたフルトヴェングラーやウィーン・フィルの録音も印象的。
というわけで見た。ストックホルムもきれいだし、確かになかなかの出来だった。戦前だけでなく、一九七七年頃のホールの客席や街角の歩行者たちの服装まで、きちんと再現してあるこだわりも、いかにもNHK。
ただし終戦、戦後までのテンポのよさにくらべて、回想シーンを交えるなど老後が間延びしていたのは、本当はここでもう少し責任問題を突っ込みたかったのに、カットして残りを引き延ばしたのでは? などと邪推。
大島駐独大使は名を変えて出てきたけど、瀬島龍三はそれらしき人物が新聞写真にあるだけ。現実には戦後、抑留から帰還して就職した瀬島が小野寺に会いに来たという話があるのに、それをあえて出さなかった。最後に少し出てきた佐野史郎あたりに瀬島をやらせてみればドラマとして面白かったのに、という気が。
もちろん、情報を握りつぶしたのは、特定の個人の人格の問題などではない。そうしたエリート、スタッフとその「アガリ」としてのサラリーマン経営者を次々と生み出す日本型組織の問題であり、それは今も続発する企業の不祥事にまでつながるのだから、ひとりのせいにしても仕方がない。ただ、日本型無恥無責任の典型として、「参謀たちの戦後」がどのようなものであったかを少しでも描いてほしかったのに、やりたくてもやれなかったのかなと。
印象的だったのは、戦後の闇市をあるく元軍人たちが、軍服やベルト類を着崩さずにきちんと着用していたこと。横浜野毛の闇市を小学生のときに歩いたという方から、実際も軍人の服装は敗戦後もそれなりにきちんとしていて、矜恃を感じさせたと、フェイスブックで教えていただく。NHKの時代考証はさすが。
八月四日(木)龍神様と弁天様


写真は、四日前に矢来能楽堂にかかっていた、ポケモンGO禁止の看板。矢来町の新潮社別館近くのこの能楽堂、音楽之友社から西に「牛込保健センター前」のバス停へと歩く途中にある。友社に行くには地下鉄よりこのバスの方が簡単で速いと、十五年ぐらいたってやっと気づいた。
ミニリュウならぬこの龍神は能の『竹生島』に登場するもの。先月二十八日にこの作品を国立能楽堂でみたばかりだったので、ご縁を感じて嬉しい。というわけでここからその二十八日の能の感想。
箏曲『竹生島』山勢松韻
能『竹生島』(小書「女体」)種田道一(金剛流)
間狂言『道者』野村萬斎(和泉流)
『竹生島』は能のなかでも「脇能」と呼ばれる、神様が出てきて衆生済度と国土鎮護を誓う、単純でおめでたい筋書のものの代表作。最初は竹生島へ琵琶湖を渡る船からの景色。「緑樹影沈んで魚木に登る気色あり。月海上に浮かんでは兎も波を奔るか。面白の島の景色や」の詞が有名。
気がつくと、参拝者に女性が混じっている。竹生島は女人禁制ときいたがとワキがたずねると、竹生島の神は弁財天、女神にして天女の形をとるものなれば、「女人とて隔てなし。唯知らぬ人の言葉なり」とやりこめられる(いつも常識的なことを口にしてシテにやりこめられるのが、ワキの役割である)。そしてその女性は弁財天に変じ、やがて海から龍神もあらわれ、二柱の神が舞う。龍神は頭の飾りといい、雅楽的というかアジア風というか、舞も豪快で男性的で、弁財天の女性的な舞とは好対照。華やかな締めくくり。
この日は公演全体も「女人とて隔てなし。唯知らぬ人の言葉なり」で、前半は山勢松韻など、女性三人をメインとする箏曲『竹生島』。
さらに、能の中間に演じられる間狂言『道者』も、竹生島に参詣する夫婦たちの話。かれらが拝むご本尊の弁財天は、頭に宇賀神という男性神(蛇身でとぐろを巻いている。ここから能での龍神の出現につながるらしい)をのせている。では、我らもこれにあやかろうと、妻二人が夫を肩車したまま橋懸から退場する、アクロバティックな締め。
これはきわめて珍しいヴァージョンだそうで、わけのわからないシュールな展開が実に愉快。舞台に残った萬斎のいたずらっぽい表情がいい。
続いて今日四日は
狂言『仏師』小笠原匡(和泉流)
能『通小町』山階彌右衛門(観世流)
小野小町と深草少将の霊が相次いで登場する『通小町』は作り物(大道具)などなく、演出もとても地味。いまの自分にとっての能の魅力である「見立て」がほとんど活用されていない(歌舞伎のように派手にやってほしいというのではなくて、最小限にして最大限の、落差の舞台美というか)。なんというか、ドラマが抜け落ちているような素っ気ない感じから、とても古いものなのではと思ったら、やはり観阿弥の時代よりも前の、現存最古に近い作品なのだそうだ。
こういう作品になると、観客が想像の翼を得られるかどうかは、演じ手の発するオーラだけにかかってくる。正直、今の自分にはそれを感じることができなかった。素人なので軽々しい批判は控えるが、もしこれを初めに見ていたら、自分は能楽に関心を抱くことはなかったろうな、という気がする。
出会いは大切。どういうわけか、観世流一門とはまだうまく出会えていない。これからいろいろ見てみねば。
八月十一日(木)《ハフナー》三種
先月二十四日の、ネコケン先生の《復活》を最後に、クラシックの演奏会はほぼひと月のご無沙汰。その間に観るのは能とシェイクスピアのみ。そして黙々と『一九五四/五五』を進めている。
今は最後の第四十七話「バイロイトの第九」の準備。「バイロイトの第九」って一九五一年の録音だろうというご指摘をいただくだろうが、LPが最初に出たのは一九五五年十一月、フルトヴェングラー一周忌のとき。つまり一九五五年の締めくくりの時期で、そして「死せるフルトヴェングラー、生けるファンを走らす」の、ほぼ最初の一枚だった。という話。「過去を録音に聴くこと」という、いわばこの原稿全体のテーマにかかわるものなので、そこへうまくつながるといいがと思っているところ。
さてそれはそれとして、ここではその前の「二つのベルリン、一つのウィーン」に出てくるディスクの話から。
ひと月ほど前、むかし手放したまま、再会する機会を逸していたCDを、手頃な値段で手に入れることができた。それは、シューリヒトが一九五六年一月にザルツブルクのモーツァルト週間でウィーン・フィルを指揮した、モーツァルトの交響曲第二十三番と第三十五番《ハフナー》、ピアノ協奏曲第二十二番(独奏ニコラーエワ)のライヴ。モーツァルテウムの自主制作盤。交響曲第二十三番以外は他レーベルでもコピー盤みたいなもののが出ているが、できればオリジナルが欲しかった。
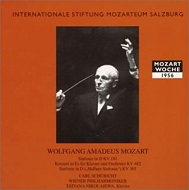
前はあまり意識せずにきいていたが、じつはこれ、色々な意味で面白いライヴだった。
まず、山根銀二が客席できいていたこと。拙稿では山根銀二の『音楽の旅』は種本の一つである。この本は、なにしろ左翼の評論家がスターリン批判もハンガリー動乱も起きる前の「欧州・ソヴェト・中国」の紀行文を岩波から出したものだから、バリバリの社会主義リアリズムに則って書かれていて、その後復刊されることもなく、現在ではほぼ忘れられている。たしかに、「いやその考えかたは偏っているのでは」みたいな部分も、特に後半の共産圏紀行でたくさん出てくるが、一方ではやはりたしかな耳をもっていて、素直な感想とあるべき主義との間で齟齬を来したりすることがあって、その本人の困りようが面白かったりする。
前も書いたが、カール・リヒターの凄さを一九五五年の時点で気がつくことができていた日本人は、たぶん山根だけだろう。シューリヒトもまたそうで、上の演奏会について絶賛している。
「もう七十歳をこえる老指揮者だが、その鋭く音楽的な棒のさばきには感激せざるを得ない。それはたしかに私がヨーロッパで聴いた最優秀の演奏の一つであった」とまで、書いている。このとき、カラスが歌っているスカラ座やベルリン芸術週間、ウィーン国立歌劇場再建記念公演などを回ってきたばかりなのだ。
《ハフナー》については「これも素晴らしい。どの音符も生きてピチピチとはねかえり、われわれを突き刺してくる。あの剛毅なテーマの颯爽たる弾きぶり。もう一度ウィーン・フィルの優れた性能に心うたれる」。
当時の日本でシューリヒトは、まだほとんど評価されていなかったはず。このあと、三月にベルリン・フィルとの《英雄》をきいて、「独特の鋭さと強さでやる。これにはまいってしまった。この爺さんただものではない。なぜ、あまりもてはやされないのであろうか」と書いている。
その評価のきっかけになった一月二十六日のザルツブルク演奏会、ウィーン・フィルにとっても大きな意味を持つものになった。
というのは、翌日のモーツァルト二百歳の誕生日に大クライバーが急逝したからだ。ウィーン・フィルは秋の全米旅行をクライバーに帯同してもらう予定だったので、代役が突然必要になった。そこで思い出したのが、前日の演奏会の素晴らしさ。のちに楽団長となるシュトラッサーは、神の思し召しのようにまで感じたという。そこでシューリヒトに、クリュイタンスとともにアメリカ・ツアーに帯同してもらうことになった。

で、十二月十日にニューヨークの国連で「世界人権デー」に演奏したのが、ARCHIPHONが出したライヴ。このときはハンガリー動乱の直後ということで、ソ連の暴虐に抗議する人々が国連を取り巻いていたというが、ここでもやはり《ハフナー》をやっている。
シューリヒトといえば《ハフナー》だという思いを、ウィーン・フィルが強くもっていたためなのだろう。

さらに、この一月と十二月の二つのかれらの《ハフナー》のちょうど真ん中の六月に、もう一つ《ハフナー》の録音がある。唯一のセッション、ステレオのデッカ盤。アメリカにシューリヒトと行くと決まって、この《ハフナー》を《未完成》と一緒に訪米記念盤に録音したものらしい。
ところがこの録音には、強烈な、悪夢のような思い出をもつ人がいた。
ジョン・カルショー。デッカのチーフ・プロデューサーだったオロフが突然EMIに移籍したため、ウィーン・フィルの録音を急遽担当することになり、右も左もわからぬまま、楽員の白い目にさらされながら最初に録音したのが、このシューリヒトのセッションだった。
しかしシューリヒトは《未完成》の冒頭のテンポが決められずに十一回もやりなおし、楽員とスタッフをうんざりさせた。オーケストラはカルショーの力不足が原因ときめつけ、デッカ上層部に直接文句をつけて、カルショーを辞職寸前に追い込む。
その後、カルショーは徐々にウィーン・フィルの信頼を得ていくが、よほど懲りたのか、シューリヒトを二度とゾフィエンザールに呼ばなかった。結局、シューリヒトとウィーン・フィルはオロフの移ったEMIで、五年後からブルックナーの交響曲集を録音することになる。
と、三つの《ハフナー》録音がつないでいく人と場所。
八月十四日(日)一九六九年の寅さん
同世代のフェイスブックの友達の方々が、次々と映画『シン・ゴジラ』を観て絶賛。我遅れじと、テレビ版『男はつらいよ』のDVDを借りてみる。
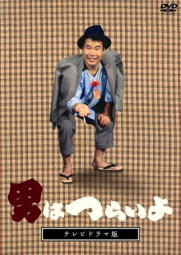
映画版の元になったモノクロの連続ドラマで、一九六八年十月から一九六九年三月まで半年間放送されたうち、第一回と最終回(第二十六回)のみ現存。当時としては必ずしも視聴率が高くなく、映画が「国民的映画」になったからこそ後世に知られたテレビ版だが、自分は最終回の本放送を観たのをよく憶えている。
寅さんが失恋して柴又を出て、奄美大島に行ってハブにかまれて唐突に死んでしまう場面が、子供心に衝撃的だったからだ。幼稚園の年長組の後半、小学校入学直前の三月末だったのか。フジで木曜十時からの放映だったという。その前の『泣いてたまるか』もみているので、ウチは渥美清が早くから好きだったらしい(ただしこちらは、自分の記憶にある画面は数年後の再放送時の記憶で上書きされている)。
その後、『男はつらいよ』は再放送もみたことがないので、四十七年ぶりの再会。さくらとおばちゃんに寅さんの死を告げに来た佐藤蛾次郎の泣き顔は、記憶の中にあるものとたしかに一緒だった。
あらためて観ると、この最終回は寅さんだけでなく、一つの時代への挽歌になっている。
帝釈天前の団子屋は時流に合わなくなって人手に渡り、取り壊されて跡地にはしゃれた喫茶店が建つ。おいちゃんとおばちゃんはすることもなく、朝から晩までテレビをみているだけの毎日。
妊娠したさくらは団地に住んでいて、金魚屋の声がきこえて、「あら、最近珍しい」なんて言っているところへ、蛾次郎がやってくる。寅の死を信じようとしなかったさくらは、その夜に寅の幻影をみてようやく納得するが、その幻影があらわれるのは団地の玄関の鉄製の扉の前であり、そして団地の前の公園の鉄製の遊具の脇を通って、コンクリと鉄の世界から消えていく。
『男はつらいよ』の原型となっている東映やくざ映画でも、主人公たちは必ず「自分たちみたいな古い人間の時代はおしまいだ」みたいなことを言うが、寅さんも同じ。昭和四十年代の高度成長期の日本から置き去りにされていく男。テレビドラマでも最末期のモノクロでつくられているのも象徴的。
自分のいた東京の反対側の区部郊外の住宅地でも、どぶが消えて暗渠になり、バキュームカーもみなくなって街の匂いが清潔になったのは、これから数年のうち。同時に、隣駅で夏に見かけた風鈴屋のリヤカーにも、二度と出会うことはなかった。
そのまま、映画第一作も観た。跡形もないはずの団子屋は元通りに、そして寅さんは三日目ならぬ五か月後に甦り、カラーの大画面の上で、そのまま二度と死なない。さくらとおばちゃんは別人に代わっている。
映画のヒットとともに柴又の門前町も観光地として残り、そして翌年からの国鉄のディスカバー・ジャパンに合わせるように、寅さんは日本各地の古い木造の街並みを訪れて映像に残し、滅亡寸前の日本映画界をたった一人で支え、生き残らせていく。

夜は東京芸術劇場のシアターイーストで、オックスフォード大学演劇協会(OUDS)による、シェイクスピアの『夏の夜の夢』。
能が好きになって、あらためてその二百年後のシェイクスピアもみたいと思った。できればピリオド風(笑)の、ロンドンのグローブ座みたいなオープンステージの小舞台・少人数の上演を、原語でナマで観たいとさがしたら、ちょうどこれがあった。オックスフォードの学生たちによる上演は現代風に超スピーディ(全五幕を休憩一回で本編百十五分)で、露骨で饒舌、けたたましいものだったけれど、これはこれで狂乱の一夜の夢にふさわしい。大道具なし、照明の変化すらない、見立てだけの舞台は、まさに自分の望んでいたもの。
作品の設定は夏至前夜ではなく五月祭(メーデー)前夜だとか、妖精王オベロンとはアルベリヒのことだとか(するとミーメにはローゲ同様に、パックのような性格づけもありうるのだろうか)、シェイクスピアの活躍した一六〇〇年前後は同時にイタリアでオペラが誕生した時期でもあるとか、ついでにいくつかのトリビアを知った。
小舞台でのシェイクスピア、もっと色々みてみたい。本家グローブ座の公演十九本を集めた没後四百年記念DVDボックスが、気になっている(アマゾンUKだと送料込みで一万円しないので、心が揺れている…)。
とりあえずは、そのグローブのレーベル第一弾、サム・ワナメーカー・プレイハウスでのボストリッジとシューフェイ・ヤンのリサイタルCD「ソングス・フロム・アワ・アンセスターズ」は買うつもり。
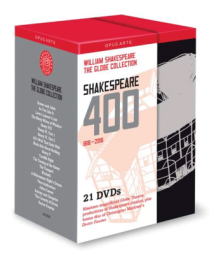

トリビアとして、一九六九年のこと。
『男はつらいよ』の映画版、『サザエさん』のアニメ版、『ドラえもん』のマンガ版、すべて一九六九(昭和四十四)年開始。『ゴルゴ13』も『ビッグコミック』一九六九年一月号から連載開始(実際の発売は前年)。
どれも「最終回」をもたない、主人公の死なない、終りなき物語。他人がつくった幻の最終回はある。そのなかで『男はつらいよ』のテレビ版だけが主人公の死を描く。そして復活。
世界史的なビッグイヤーは「一九六八年」だが、その翌年。自分が小学校に入った年なので、ちょっと感慨あり。あと三年で半世紀。
八月二十二日(月)丸子橋の呉爾羅
同世代のフェイスブックの友達の方々が、次々と映画『シン・ゴジラ』を観て絶賛。我遅れじと、松本市内唯一の映画館、シネマライツ8で観る。
多くの方と同様、とても面白かった。あくまで娯楽作品としてゾクゾクさせつつ、今の日本を活写した映画。一九五四年の第一作は水爆の恐怖と東京大空襲の記憶を重ねたものだったのに対し、こちらは原発と津波の記憶。
しかし怪獣映画というより、『日本沈没』のようなパニック映画の正統な後継者だと思った。正確にはパニック映画というよりも『日本のいちばん長い日』や『激動の昭和史 沖縄決戦』(いずれも岡本喜八監督)とか、『日蓮と蒙古大襲来』などを含む、国難映画の系譜。一九七三年の石油ショックにノストラダムスなど、オカルトと世界破滅の予感を思春期に刷り込まれた、自分たちの年代が共有する歴史感覚でもある。
スクラップ&ビルドでやっていく国、日本というセリフ。炎に飛び込んで自らの身を焼き、甦える不死鳥のような国。日本は、というよりも明暦の大火以来の江戸・東京は、というべきかも。
不死鳥といえば「死すら超越した」ゴジラそのものがそうであり、同時に東京に劫火をもたらす地獄の天使でもある。手塚治虫の『火の鳥』のグロテスクな変形でもあるような(すると、ラストの永井豪風のあの尻尾は…)。
「日本」と言わずに「この国」という司馬遼太郎式の呼び方はかなりしつこいが、古舘伊知郎風に皮肉をこめて突き放すわけでなく、愛憎入り混ざるなかでも少しだけ前者が勝った呼びかたらしい。
日米安保信奉とか、中国市場に売る気がないらしいとか、いかなる時にも「忠良無私の公僕」であり続ける自衛隊は、海軍善玉論における帝国海軍の「サイレント・ネイビー神話」みたいだとか(科学技術館に設置されたヤシオリ作戦の指揮所、誰がみたって日本海海戦の旗艦三笠の艦橋だし。それならZ旗は掲げないの?と思っていたら、ここぞというところで鳴り響いた伊福部マーチがその代役を見事に果たして、心のなかで大喝采。たしかに東宝怪獣映画では、Z旗でもなく軍艦マーチでもなく、このマーチこそが「皇国の興廃此の一戦に在り」の昂揚に誘うのだ)、政治的立場は明快。無邪気な日本礼賛も気になるが、それだけ今の日本が疲れているということか。「ピンチはチャンス」的な、復活のための国難待望論であるあたりが、来なかった本土決戦の劫火の代りに「日本沈没」を夢想した小松左京の、正統なる後継者。
これがいかにも国難映画であるのは、東宝怪獣映画が戦前の「少年倶楽部」から伝統的に引き継いだ秘密兵器、決戦兵器の類を、まったく出さなかったことにも如実にあらわれている(ゴジラへの凝固剤は、薬品であって兵器ではない)。
二〇一一年にフクイチの冷却が喫緊の問題になったとき、「映画秘宝」は「冷凍砲さえあれば原発処理はすぐ済むぞ!」と書いた。たしかに東宝怪獣映画の傑作の一つ、『海底軍艦』轟天号の冷線砲さえあれば一撃で片づいたろうが、現実は自衛隊のヘリからの投下水と、高層階向けポンプ車の放水だった。この映画でも、轟天号はもちろんスーパーXさえお呼びでない。決戦兵器的なものはすべて米軍の実在兵器で、自衛隊はあくまで通常兵器と工事車両、在来線などを使って戦う。「ありもの」の応用で戦い抜くのが、国難映画の醍醐味だからこそ。
そしてここでの皇居は、ロラン・バルトの言うような、空虚な、何もない巨大な穴。
ラスト、皇居に正対して建てられた東京駅から皇居に向う行幸通りに、彫像のように立つゴジラと、少し離れた科学技術館の間には、石垣しかない江戸城本丸跡があり、その南には聖なる、則天去私の森がある。
あとは個人的な話。ゴジラの暴れる場面は、個人的に自分の知っている、生まれ育ってきた地域と風景だというのが感慨深し。
一九五四年の第一作で破壊されたのは銀座や隅田川沿岸の、広義の下町地域。そこには関東大震災や東京大空襲の大被害の記憶が反映されているし、一九五四年における「東京」というものも、そのあたりのことだったのだろう。しかし今回は東海道をはさんで反対の西側の、山手南部。
とりわけ、丸子橋防衛戦までは、目黒区緑が丘に育って、大田区雪ヶ谷や世田谷区東玉川などに住む友人たちと自転車で走り回ってきた自分にとって、原風景みたいな場所ばかり。
まず呑川。こんな川、流域の住民以外はその存在すら知っている人は限られるのでは。サザエさんの桜新町を水源とするこの川は、世田谷区深沢の母校の小中学校の近くを通り、通学バスの乗りかえ地点としてなじみが深い東横線都立大学駅の脇を流れる。そこに注ぐ支流の一つが、かつての我が家のすぐ近くを流れる九品仏川。合流したその先は友人の住む雪ヶ谷、そして馴染みの模型屋があった久ヶ原と蒲田を通って、東京湾に注ぐ。
今回、あらためて思ったが、渋谷以外の自分の子供時代の行動範囲は概ね、三区にまたがるこの川の流域だったといっても過言ではない。
ただし、ウチのあたりから上流は一九七〇年代半ばに暗渠になり、緑道公園になった。それまでは汚い川で、周囲はいかにも低湿地という雰囲気を残していたのが、緑道化によって「山手っぽく」オシャレで乾いた風景に変身した(自由が丘などその典型)。地価もそれをきっかけに高騰したはずで、私がそれ以降の故郷の姿を、どうにも嘘くさく感じる原因の一つでもある。
しかしその呑川、家から少し行った緑が丘駅のすぐ先で姿を現し、大田区では昔のままの川の姿を残している。そして海に近づくにつれ周囲の家は古く、密集していて、いわば「山手側、東京左半分における下町」。地震防災マップで火災や倒壊の危険度の高いこの地域に最初にくるというあたり、ゴジラの原像が天災だということを示すのだろう。ゴジラはたぶん、緑道公園には関心がない。
そして中原街道の丸子橋防衛戦。これこそ、本当にたまらない景色。丸子橋とは、多摩川のあのあたりでは唯一、上部に二つのアーチをもつ、美しいローゼ橋型。戦争映画『遠すぎた橋』(オランダのアーネムとかナイメーヘンとか)や、『レマゲン鉄橋』に出てくる鉄橋に似ていて、子供の頃はあの橋をみるたびに、それらの映画の戦闘場面の幻をそこに重ねて楽しんでいた。
そしてその丸子橋を見渡すのに最適なのが、北側の浅間神社の山上の見晴台。あそこに指揮所をおき、そして『コンバット』などでおなじみのカモフラージュネットをかぶせるって、もう子供の想像そのまま(ゴジラに対して迷彩がきくのかどうかなどは、このさい関係ない。野戦指揮所には、ネットとテントがなければならないからだ。その点が、三笠の露天艦橋とは違わなければならない)。
映画には出て来ないが、神社の北側にある多摩川台公園。戦争ごっこをするには夢のような、さまざまな高低差のある地形やトーチカみたいな人工物などをもつ、素晴らしい公園だった。それも踏まえて丸子橋を選んだ人は、ものすごくよく分かっているとしかいいようがない。河川敷に戦車隊が展開するのも、まさに子供が現実の景色を戦場に見立てて遊ぶときの、一場面。
自分の原風景が戦場になる。現実化したら悲劇以外の何物でもないが、子供の想像と映画の夢のなかでは、ゾクゾクするような見立ての快感。東京駅近くの無数の線路を一斉に走る無人在来線爆弾の光景も、最高の見立ての快感。
と書いて、二〇一四年十二月に久々に丸子橋へ行き、浅間神社の展望台(まさにあの野戦指揮所が置かれたところ)から写真を撮ったのを思い出した。

昔は橋を見下ろし、『遠すぎた橋』のナイメーヘンのワール河渡河作戦で、ロバート・レッドフォードが対岸からきたシャーマン戦車と連絡するべく、橋を走っていく場面を思い浮かべつつ(橋を渡る車と歩行者を勝手にそれに見立てるのだ)、自分はそれを遠くから双眼鏡で眺めるドイツ軍将校(ナントカ中佐)になりきり、「今だ、爆破!」と叫ぶと、隣の友達が何度も起爆装置のT型ハンドル(のつもり)を押し込むが、なぜか起爆せず、橋は破壊できない。
「なぜだ! アーンエムまであと十マイルしかない!」などと、映画の場面を再現して喜んでいたのだが(バカ)、次に行くときは、武蔵小杉の高層ビルの影からあらわれるゴジラと、河川敷の陸自戦車隊の幻影が見えることだろう(笑)。
八月二十三日(火)浅間神社、浅間温泉
シン・ゴジラさんでおもったこと、付け足し。
長谷川博己の「次のリーダーがすぐに決まるのはこの国のいいところだな」というようなセリフ、よかった。日本型組織のリーダーというのは「資質」の問題ではなくて、よくもわるくも単なる「役割」「役目」だから、組織の構成員がつとまるくらいの社会適応性があれば、誰にでもできる(その向うに万世一系の天皇制があるのかどうかは、賢明にも沈黙していたが)。
組織そのものがもつ強靱な再生能力。あのゴジラにもよく似ている。たぶん頭を吹っ飛ばされても、すぐに再生させるだろう。必要があれば尻尾の先からも光線出せるくらいだから(あんなこともできるのかとか、長谷川博己だったかが感心してた)。やはりこの作品は庵野版の『火の鳥』のような。熱核攻撃だけは、両者を滅ぼせるようだが。

そう考えると、あのヤシオリ作戦の、三笠を想わせる露天の指揮所。
浅間神社の見晴台がそのまま使われたように、きっと科学技術館にはあの物干し台みたいなものがあるのだろう。いつか確かめにいきたい。
たしかにマストもないし、防弾用のカンバスもないが、作戦直前に長谷川博己が「指揮官は身をさらすべし」というようなセリフを言ったので、お、アドミラル・トーゴーみたいだと思った。それで物干し台みたいな平らな場所にみんなで並んだので、これは決まりだと(ところで作戦開始のとき「始めてください」と言ったのは、『硫黄島からの手紙』で渡辺謙の栗林中将が、上陸した米海兵隊への砲撃開始のときに言った同じセリフへのオマージュか)。
もしこの指揮所が全滅しても、作戦は途切れることなく粛々と遂行されるという確信があるから、あそこにかれらは平然と立っているのだろう。
逆算すると、日本海海戦の三笠の露天艦橋に東郷が立ち続けたのも、同じ理由だったのだろう。しかし戦史を思うと、それは凄い判断。直前の黄海海戦でロシア旅順艦隊は、旗艦の艦橋を砲弾に直撃され、司令官以下が戦死して艦隊運動が混乱したために敗れている。連合艦隊は当の対戦相手だから、自分たちが勝つことができた理由を、いやというほどによく知っている。
それでなお、東郷は露天艦橋に立つ。「死ぬときは死ぬ」という、江戸期三百年の武士道教育が練成した薩摩武士の覚悟でもあるのだろうが、同時にしたたかな現実派でもある薩摩藩士だから、自分たちが旅順艦隊の轍を踏むことはないとわかっていたのだろう。たとえ司令部が全滅しても各戦隊、各艦は混乱せずに粛々と任務を遂行するだろうこと、そして上村彦之丞なり誰なり、生き残ったうちの先任者が遅滞なく次のリーダーになることがわかっていての、あの立ち位置。
シン・ゴジラさん、勉強になるなあ。

ところで、二十一~二十二日は松本旅行。『シン・ゴジラ』が目的ではなく、セイジ・オザワ・フェスをきくため。演奏会の感想は他に書く。ここでの主な話題は、九回目にして初めて松本市街ではなく、浅間温泉に泊まったこと。
今年のフェスはコンサートのみで、キッセイ文化ホールで二日連続。ここは市内からだとバスかタクシーなので、往復が面倒。松本駅から五キロ東の浅間温泉は、ホールと女鳥羽川(めとばがわ)をはさんだ東隣りで、歩ける距離にある。そこでコンサートではこちらに泊まりたいと思っていたが、古い温泉地で旅館ばかりで、どの宿も二人部屋二食付きというようなプランしかない。一人で素泊まりできる宿がわからなかったが、今年は香蘭荘という旅館を見つけることができた。六畳一間、バス・トイレ(和式!)別の古い旅館だが、源泉かけ流しで二十四時間入り放題。
松本は川沿いの平野にある平らな町だが、浅間温泉は山の入口で、奥に行くほど高くなっていく。
正直、街はかなりさびれていて、かつては小沢征爾が毎年通ったというそば屋もすでに閉店しているし、ほかもやっていない店だらけで、わずかな飲み屋とみやげ物屋以外は、そば屋とコンビニとインドカレー屋、各一軒くらいしか営業していない。
昔は、旧制松本高校生がここに下宿していたという。松本は学都でもあり、戦後の学制改革で信州大学となる松本高校は、その象徴。北杜夫の傑作『どくとるマンボウ青春記』に、松高での古き良きバンカラ生活が活写されており、旧校舎も一部が「あがたの森文化会館」として現存。ここは浅間温泉からは数キロあるが、かつては松本電鉄浅間線という路面電車が走っていたので、バスだけの今よりもずっと便利だったらしい。
浅間温泉にいた松本高生のなかで有名なのが、北の仲間だった辻邦生。辻邦生というとパリに住む作家、というイメージが強いが、そういう人が自我を確立する旧制高校時代に、この山裾の温泉地のどこかの一間で炬燵に入っていたと思うと、その果てしない距離感が面白い。
残念ながらその下宿がどのあたりかは調べなかったが、その代りのように、初日にキッセイ文化ホールへ歩く途中に偶然発見して驚いたのが、「川島芳子旧宅跡」という看板をもつ家。
なんでも「東洋のマタ・ハリ」川島芳子の養父、川島浪速は松本生れで、旅順で清朝の王女を養女にしたあと東京へ移り、やがて故郷に帰り、浅間温泉に住んだ。そして芳子はここから松本高等女学校まで、馬に乗って通学していたのだという。成人して世に出て、上海、新京、天津などでの活動ののち、北京で処刑。引き取られた遺骨は松本の浪速の元に届き、墓所も松本市内にあるのだとか。
昭和初期の中国大陸を股にかけた活動の原点、少女時代が、やはりこの温泉地の一隅から。辻邦生と同じく、こういう時空の距離感は想像を絶するものがあって、実に愉快。ただ空を見上げる。かんかん照りで暑い。
二日目は台風で雨のはずが曇りだけで一滴もふらず、拍子抜け。車を借りて南松本まで行ってシン・ゴジラをみて、そのあと安曇野を北上、毎年恒例となっている穂高神社参り。今までよりも柏手が響いた気がするのは、能楽の囃子をきいて、その間が身体に入ってきたからじゃないかと、勝手な自画自賛。
松本市内に戻り、これも恒例の「おきな堂」で遅めの昼食。一九三三年開業、「時代遅れの洋食屋」を自認するだけあって、メニューは進化しつつも、行くたびに何とも言えない幸福感に包まれる。「祝福された当たり前の場所」というのは理屈を超えた感覚で、説明不能だけれど、そうとしか言いようがない。「ガーリックライス・カツカレー」という、字面だけでも旨そうな特別メニューを食べる。期待を裏切らぬ美味。たった千円。
近くの「まるも」という珈琲店も古びて好きだが、昔風の喫茶店のため、煙草常習者がいるので残念ながら敬遠。
浅間温泉に帰ってひとっ風呂浴びて、再びキッセイ文化ホール。世界的名手も加わったオーケストラの演奏会が終り、夜の女鳥羽川を渡り、コンビニ以外は灯の消えた温泉街を通って、暗い旅館に戻って、明るい六畳間に座る。
大きな空と小さな部屋。宇宙と一隅。闇と灯。頭の中でゴジラの伊福部の音楽が鳴り、暗闇の東京で、ゴジラが放った青く光る熱線(なんとも心の痛い場面だった)の残像が、まぶたに。
九月五日(月)ヤマカズ、真田丸と能
土曜は山田和樹指揮日本フィルをサントリーホールで。シュトラウスの《四つの最後の歌》もエルガーの交響曲第一番も、艶麗や重厚というようなそれぞれの既存のイメージにおぼれず、流動的にその構造を立体化させる手腕が光る。とりわけ生誕百年・没後二十年の柴田南雄の《コンソート・オブ・オーケストラ》が興味深く聴けた。一九七三年作曲というのに納得。六〇年代の前衛真っ盛りの熱狂でもなく、八〇年代の飽食でもなく、どことなく白けて醒めていて、方向性が見えず、しかし嫌味のない、謙虚で手堅い七〇年代。その時代精神そのもののような、都会的な音楽。いかにもピアノから生まれたサウンド。昭和後期の日本を写す鏡としての柴田南雄。その典型というべき交響曲《ゆく河の流れは絶えずして》を含む、十一月のこのコンビによる記念演奏会も、とても楽しみ。
『真田丸』はついに犬伏の別れ。成長をみせた信幸。巣立ち。
犬伏は栃木県佐野市だったのか。送電線工事をやっていたころは佐野に資材置場と宿舎があったのでしょっちゅう通っていたが、駅をはさんで反対側の犬伏には行ったことがなかった。佐野は終戦直前、司馬遼太郎が戦車小隊長として本土決戦に備えていた地であり、渡良瀬川の対岸の西は、足利氏発祥の地の足利荘。
いまから思えば、故地だけでなく地勢も含めて踏査しておけばよかったと思うが、なにしろ戦車戦や騎馬戦をやるのに最適のだだっぴろい関東平野で、そのわりに視界に爽快感がなくて道が迷路じみた、どうにも親しみのわかない地形だったから、平面ではなく点と線でしか、把握していない。ちなみに能の『鉢木』の舞台の佐野というのは、ここではなくて群馬県高崎の南部の小地名らしい。
それにしても『真田丸』後半は、秀吉キッズの物語ともなっている。秀吉のもとで育って、その魅力に心底ほれこんでしまった、たらし込まれてしまった若者たちの物語。秀次、宇喜多秀家、三成、清正、片桐且元、そして信繁。このなかではいちばん恩顧が薄いのに、切ないほどに秀吉を慕う信繁の思い。
残念ながらキッズは互いに誰一人として息が合わず、理解しあえない。それゆえに一人ずつ滅び、家康に各個撃破されていく。みんな寂しい(今回の島左近は本多忠勝と同類の、ただの勇猛な侍大将というだけなので、なるほどこれでは秀吉が言うとおり、三成は「寂しい奴」。『草燃える』での、弁慶がでてこない義経が、あまりにも孤独な人物だったのを思い出す。対して後藤又兵衛は、かなり妙ないくさ人のようだ)。
かれらが頼りにする、頼りになるはずと思っている人たちが、じつは秀吉を嫌い、仇敵のように憎んでいる悲劇。金吾中納言秀秋、そして誰よりも茶々。秀吉好きキッズには、かれらの心情がまったく想像もできない。秀頼はどのように描かれるのか。
友情の人というより、最後の働き場所を与えてくれたことに感謝して三成に味方する大谷刑部。偉大なる不識庵謙信に憧れ、義の人を気取ってはみたものの、やっぱり貫徹できそうにない上杉景勝。偉大なる法性院信玄に憧れ、元亀天正の戦国乱世を夢見続ける真田昌幸(たしかにいま思い出すと、本能寺の変以後の謀略戦のころは、なんと人間がみな生き生きとしていたことか)。
家康(信長への思いと同じく、秀吉を愛しつつ憎んでいる男)も含めて、それぞれが勝手なことを考えて生き、慶長の日本のそれぞれの場所に足跡を残す。三谷幸喜の好む「グランドホテル方式」のようなドラマ。
ところで先日、フェイスブック友達の方から「長澤まさみ演じる『きり』こそ実は霧隠才蔵である」という説を教えていただいたが、今回をみるとますますその感つよし(笑)。炎に包まれた包囲下の細川邸に難なく忍び込んでいるし、佐助と行動をともにしているし。とすると残りの真田十勇士も、既に何らかの形で物語に入り込んでいるのかも。由利鎌之介や海野六郎は、どこにいる?
おしまいに能の話。このドラマの秀吉は、武将でも公家でもなく、能装束をアレンジしたような衣装を着ていた。今、表章と天野文雄著の『岩波講座 能・狂言〈一〉能楽の歴史』というのを読んでいる。三十年前の本だから最新ではないが、全体の流れとしては基本的な解説書のようだ。
これによると、秀吉の能好きは史実でも大したものだったが、これは戦国武将全般に共通するものであり、さらには江戸期の大名、室町の守護大名たちも同様だった。怨霊というものを基本的に信じない武士が、怨霊だらけの能を好んで演じ、みている面白さ。
能というと「幽玄」の名のもとに、嫉妬や恨みのジメジメと湿った、うじうじしたものに思われがちなのではないか。少なくとも、自分は多分にそう誤解していた。そうした要素ももちろんあるし、深さに通じるのだろうけれど、もっと開放的な、カラリと乾いた要素もある。
能に興味を持ちだして調べると、室町時代や足利将軍家へのイメージもかなり変ってきた。今後さらにどのように変っていくか、楽しみ。明後日は『敦盛』。
九月六日(火)能の妄想、仏公武の三界
以下は前日の日記をフェイスブックに書いたところ、コメントをくださった方とのやりとりから。とりとめなく、随想風に。
戦国時代や武士と幕府、鎌倉と江戸、などが雄々しいイメージなのに対し、室町時代や公家と宮廷、京の都などが女々しいイメージでくくられる、そういう、歴史観以前の安易な二元論、そのなかで能楽が誤解されているのではないか、という気がしている。
ただ単に自分だけが気づいていなかっただけかもしれないが、能がこれほどに平家物語を重視していることと、王朝文化だけでなく同時に武家文化(足利~豊臣~徳川)と結びついていることは、もっと積極的に考えていい気がする。
足利義満など、『一休さん』のために白塗りのキンキラキンの「まろ」な人というイメージが強いが、同時に武家の棟梁でもある。公武が混じり合った状況で能が大成されるというのは、いろいろと考えさせてくれそうで、面白い。
能は幕藩体制の武家文化と深く結びついていたゆえに、明治維新後は生き残るのが大変だった。その強い仏教性も廃仏毀釈の時代には否定の対象となる。大名が華族になり、行き過ぎた旧秩序破壊への揺り戻しが起きる西南戦争以後から、ようやく復活するが、それでも評価しにくい要素が残っていたのではないか。
半可通の推測だが、明治になって西洋近代の芸術観、社会観が新たな価値観となるなかで、武家や寺社の「御用芸術」だったという位置は、苦しかったろう。
近代西洋の芸術観は芸術家の独立性、個人性、さらにいえば変革者としての英雄性を重視する。それまで一般には忘れられていた世阿弥という個人の存在が急激にクローズアップされてくるのは、そうした新しい美学の要求に応えられそうだったからではないか。ベートーヴェンやシェイクスピアのような、英雄的個人芸術家としての「能聖」。
一介の芸人であるにもかかわらず、二条良基や足利義満のような公武の頂点に立つ人物にその才能を認められる。しかし最後は将軍義教に嫌われて佐渡に流される。反権力の英雄的芸術家。戦前の世阿弥像が大きすぎたのを戦後の学問は修正するようになったそうだが、世間的なイメージはいまも残っている。
江戸時代における京の能のこと。江戸幕府の「式楽」として強力な庇護を受けながらも、京が江戸と並ぶ能楽の中心であることは変わらなかったらしい。
江戸時代の京というと、幕末になって俄然政争の中心になるまではほとんど話題にならないが、それ以前の、文化首都としての京は、どういう存在だったのだろうか(大坂が経済首都として町人文化を育んだのは、金があったからと簡単に理解できるが、江戸期の京の宮廷や寺社や民衆は、どんな存在だったのか?)
京の能は寺社と商人が最大のスポンサーなのだろうが、一方で、加賀前田や仙台伊達といった雄藩も、領地に能役者を置くと同時に京都の役者も抱えていた。これはどういう役割なのか。江戸期に大名が京都に行くことは可能だったのだろうか。参勤の途中に通る藩はともかく、仙台伊達とか、どうだったのだろう。
そんな基本的なことさえ知らないことに、能に興味を持って初めて気づいて、驚いている。おそらくは、気ままには行けなかったろう。それなのに京に役者を抱えている。祝事に領地に招いたり、情報をもらうことで、文化首都とのコネクションを保つという目的の他に、ひょっとしたら室町以来の「国持大名としての義務、プライド」のようなものが地方の雄藩にはあって、京に金を出しつづけているのかもしれない。
室町~戦国~江戸と体制は変化しながら、確固として継続している武家文化の流れ。そういうものが能楽を通じて、だんだん見えてくる気がする。
その前の戦国時代、戦国大名と能楽との関係では、京が戦乱で衰えた時期に、地方の大名家に寄寓した座がいくつかある。宝生が小田原北条氏というのはいかにもだけれど、観世が永楽年間に徳川家康のところにいた、という話が面白い。
家康が今川から独立して織田と結び、元康から家康に改名、三河守に正式に任ぜられるために姓を松平から徳川に変えて、参州岡崎から遠州浜松に本拠を移した時期。一連のこうした動きと、観世宗家を保護するという行為を合わせると、けっして織田の准家臣ではなく、独立した戦国大名として、京へ独自のルートを持っていたことが見えてくる。
家康が能好きだったからこそで、能が幕府式楽となる原点がここに。
それから、金春流から分れた大蔵流の太夫は、甲斐の武田信玄を頼った。ところが跡取りの息子二人は能役者をやめて武士となり、土屋姓となる。おそらくは信玄の寵童になったのだろうが、兄は長篠の合戦で死に、弟は亡国ののち家康に拾われ、改名して大久保長安となる。長安の前身が能役者だったというのは知識として知ってはいたが、逆方向から、つまり能役者が長安になると考えると、また違った景色がみえて、面白い。
これを拡大していくと、ときの権力者を間近にいた能楽師から見る、室町以降六百年間の通史的な歴史小説がつくれるのではないか。秀吉の能楽師だった暮松新九郎のことは奥山景布子の『太閤の能楽師』がすでに小説化したそうだが、それ以前の足利義満~義教と世阿弥に始まり、ずっとつながる。義教~義政と音阿弥、信長・光秀と梅若家、信玄・家康と大久保長安、秀忠・家光・伊達政宗と北七太夫、綱吉・家宣と間部詮房、岩倉具視と梅若実、などなど。
武家社会の変転と、猿楽芸術の継続。
現在の歴史研究における室町幕府観を概説として知りたいと思って、岩波新書の『室町幕府と地方の社会』(榎原雅治著)を読んだ。
簒奪者がつくった利己主義的で惰弱な幕府、という前時代の皇国史観的なイメージとは離れた足利政権像を学ぶことができたが、面白かったのは、一般民衆の歴史知識の多くは『平家物語』から得たものであり、古代中国に関しても、『平家物語』のなかで言及されたそれであったと指摘されていたことだ。そのように平家物語を普及させたのは、室町後期には琵琶法師よりも、世阿弥などがそれを舞台化した能楽だったのではないか。
『平家物語』の受容史、特に明治維新から現代までのそれは「『平家物語』の再誕」という本に、わかりやすく書かれている。その感想は二〇一三年八月二十一日の可変日記に書いた。
維新直後、史学からは史実でないとはじかれ、国文学からは外来の仏教思想に染まった、中世の迷妄そのものみたいな書物と蔑視された平家物語が、明治三十年代になって急速に再評価され始める。
その理由は、『イーリアス』や『ローランの歌』やアーサー王伝説のような、西洋風の国民叙事詩が日本にないかと求められるなかで、『平家物語』がその役割を新たに担わされることになり、積極的に「誤読」されていったため。
面白いのはこの動きと、能の復興期とが重なるのに、ほとんど無関係のように感じられること。当時の学問独特のピューリタニズムが、シンプルなものこそオリジナルで価値が高いと見なしたがるとき、他者の手が多く加わったものを評価するわけにはいかなかったのか。
しかし、その原典主義の背後で、テキストにより生々しいイメージを与えていたのは、能とその謡曲だったように、自分には思える。そこにはけっして幼稚な大衆化ではなく、原作への批評的精神をもって、より深く、より生々しい物語の可能性が提示されている。
世阿弥がいた室町期の京は、武家と公家と寺社が並立する、三つの権力というより三つの社会精神の境界のような場所だった。その反映のように、そこで生まれた能の名作の世界もまた、仏公武の精神が混じりあう境界にある。そして、世阿弥が多くの自作の原作とした『平家物語』は、仏公武の三つの精神の境界から生まれた、最初の傑作文学だったといえないか。
これは「国民叙事詩という誤読」ではない、別の位置づけになりうると思うのだが、ともあれその「境界の芸術」を引き継ぐ形で、世阿弥がいる。
そのかれをみることで、『平家物語』の真の姿と、日本中世の精神的基礎にある「成仏」とは何かを考えられるかもしれない、などと妄想している。
九月七日(水)夢の世なれば驚きて

国立能楽堂で能楽。
狂言『口真似婿』井上松次郎(和泉流)
能『敦盛』観世喜正(観世流)。
『口真似婿』は、国立能楽堂の主催公演三十三年目で初上演という稀曲だそうだが、それが不思議なほどにわかりやすく、愉快な作品。役者もノっていた。
そして世阿弥の名曲『敦盛』。一ノ谷の合戦で討ち取られた十六歳の平無官太夫敦盛と、自分の息子と同い年の少年の首をとったことに武者稼業の虚しさを感じて出家した、熊谷次郎直実の話。
さすがに格調高く、詞章も生き生きとして美しい。一ノ谷合戦の古戦場の須磨に、出家して蓮生法師となった直実(ワキ)が弔いのためにやってくる。
通常の夢幻能では、ワキの法師は無名の存在でいわば「現在」を象徴し、そのかれが幽霊という「過去」の人間と出会うことで「過去」が「現在」となり、生々しく甦えるという二重構造の時間が大きな魅力なのだが、ここでは直実が出家したという史実を基礎にしているので、すべてが過去の時間の流れということになる。そのぶん、当事者同士の物語となるので、互いの縁の深さは格別で、ドラマはそこにポイントを置く。
「夢の世なれば驚きて、夢の世なれば驚きて。捨つるや現なるらん」
現世をはかなんで出家した法師の最初のこの詞からして、なんと美しいこと。
途中で法師は里人に、地元に伝わる敦盛の最期を語らせる(本人の癖に意地が悪い)のだが、その描写が不思議にエロティックなのが、とても印象に残った。
花のような美少年を荒武者が組み敷いて討ち取ろうとするものの、美貌と年若を惜しんで助けることにし、抱きかかえて馬に乗せてやる。ところが、折悪しく友軍(わざわざそれが「梶原」だと一言説明するのが愉快。梶原といえば佞人と決まっているから)が現れる。裏切りだと疑われそうなので、しかたなくもう一度馬から引きずり下ろし、首をとる。
人形のように、されるがままの美少年を玩ぶような一連の動きの説明が、どうにも稚児遊びを暗示しているように思えて、このアイの語りの後に出現する敦盛(シテ)の霊の艶やかな鎧姿の舞に、痛々しくも美しい影を負わせる。こういう隠れたBL的エロティシズムも、能の魅力なのだろう。
「いかに蓮生、敦盛こそ参りて候え」
「不思議やな鳬鐘を鳴らし法事をなして、まどろむ隙もなきところに、敦盛の来たり給うぞや。さては夢にてあるやらん」
「何しに夢にてあるべきぞ。現の因果を晴らさんために、これまで現れ来たりたり」
敦盛の霊は、私が気づいたところでは都合三度、脇座にいる蓮生法師に接近する。最初は前半の、草刈男に身をやつしていたとき。二度目は霊として姿を現してから。この二回は仇まであと一歩の所まで近づき、動きをとめ、凝視する。その、無限の動をはらんだ静止の緊張感の素晴らしさ。ワキがただ通りかかった法師ではなく、待ち続けた仇敵本人だからこその、緊張感。
そして三度目は最後、身が触れるまで近づき、座り込む蓮生法師を見下ろして立ち、引き抜いた刀を仇に降り降ろそうとする。
「因果はめぐり逢いたり敵はこれぞと討たんとするに、仇をば恩にて、法事の念仏して弔わるれば、終には共に、生まるべき同じ蓮の蓮生法師。敵にてはなかりけり。跡弔いて。賜び給え。跡弔いて賜び給え」
「終には共に生まるべき同じ蓮の蓮生法師。敵にてはなかりけり」が素敵。
シテの敦盛は観世喜正。声もよく、舞もキレがあって、さすが。ようやく観世流の真骨頂にふれられたような。
そして今回は、一九七〇年生れで今が盛りのこの喜正を、大ヴェテランが囲んでいたのも印象的だった。ワキが福王茂十郎、囃子方も七十歳前後で、後見には喜正の父の喜之。そして地謡のリーダーである地頭に観世流シテ方の重鎮、梅若玄祥。
重鎮たちが打ち揃って次代を担う喜正を支え、同時に舞台全体のありかたを身をもって示しているような感じがして、とても気持がよかった。とりわけ、梅若玄祥率いる地謡は、アンサンブルも音程も、これまでみた能公演のなかでも最高水準だった。初めの方のソットヴォーチェのコントロールなんて、本当に見事。このあたり、弟子が多いだけに観世流のシテ方の層の厚さの力か、とも思う。
九月八日(木)鏡像のマーラー
NHKホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団ほかの《千人の交響曲》。昨日の国立能楽堂に比して、ホールの大きさも入場者も出演者も段違いなのが愉快。昨日の出演者は二十三人だったが今日は四百五十人だとか。二十倍。
完売、休憩なしということで開演前の男子トイレは大行列。千人行列。八王子千人同心にちなんで、オリンパスホール八王子でこの曲をやるのはどうだろうとか、下らないことを考えつつ本番。
剛毅、コワモテな演奏で、第一部や第二部終曲の〈神秘の合唱〉にはぴったりだったと思うけれども、第二部はもっとメリハリと脱力がほしいと感じた。シーンの広がりや変化に鮮度がなく、単調。ミサ曲と劇的交響曲を、宗教音楽と十九世紀を強引に一体化させる、そのコントラストの面白さが出ていなかった。濁らない響きのコントロールはさすがだし、舞台上のひな壇にずらりと並んだマスのパワーは凄いけれど、NHKホールの空間の活用にも、あまり工夫がなかった。このあたりはハーディング&新日本フィルのすみだトリフォニー公演の方がよほどうまくできていた(弱点も多い演奏ではあったが)。いずれにせよ、一日だけの公演はもったいない。
カンブルラン&読響でサントリーホールの空間を存分に活用した《千人》をいつか体験したいと、あらためて感じた。
それにしてもこの夏はハーディングの《千人》、ネコケン先生の《復活》、ルイージの《復活》、パーヴォの《千人》と、マーラー鏡合せのうちに過ぎた。
続いてメンデルスゾーンの《エリヤ》にベルリオーズの《ファウストの劫罰》と、その源流への旅の予定。
九月九日(金)海鳴りのトリスタン

第一次世界大戦の後半、ドイツの戦局が悪化するなかで、ある歌劇場の支配人がリヒャルト・シュトラウスにこんなことを言った。
「お客が入らない。《トリスタン》のような作品はもう上演できない」
シュトラウス答えて曰く、
「それなら、なおのこと《トリスタン》の上演を続けなさい。続けなさい、お客が最後の一人になるまで。その人こそ、最後のドイツ人なのだから」
今日は午後から、東京文化会館で二期会の《トリスタンとイゾルデ》のゲネを見学。
ゲネのとき、見学者は一階中央より後ろ、石垣より後ろに座ることになっている。しかし今日は二階でみてもいいと許可をいただいたので、二階正面で鑑賞。
ここからだと、見下ろしても客席にはほとんど人が見えない。照明が落ちて、ピットから前奏曲が流れだしたとき、たった一人できかせてもらっているような贅沢な気分になって、そして、前述のシュトラウスの逸話を思い出して、「《トリスタン》をみる最後の日本人」になったような幻を追う。
最近は三間四方の能舞台ばかりみているものだから、オペラのステージの広大さ、そしてそこに人間がたった二人しかいなかったりすることに、今さらながらに感心(笑)。
しかし、それを埋めてなおあふれ出る《トリスタン》の音楽の凄いこと。
まさしく魔に魅入られたような音楽。いつか、たとえ自分がオペラから、大規模なオーケストラの響きから遠ざかることがあったとしても、この音楽だけは遠い海鳴りのように自分を呼びにきて、また連れ去っていくに違いない。
ナマで聴くのは、ちょうど一年前に同じ読響の演奏会形式上演を聴いて以来。一年に一度この音楽を聴けるなど、かつての東京では考えられないことだった。
二幕の〈愛の二重唱〉、「こうして私たちは死んだのです」に始まるトリスタンの歌。その響き。
そして事が露顕して、マルケ王の嘆きが終ったあとの、「これからトリスタンが行くところに、イゾルデ、あなたもついてきてくれますか」に始まる歌。
すべてが闇に包まれて、黄泉の国へと流れる川の、その黒々と光る川辺に立っているような、そんな音楽。
何しろ《トリスタン》だから、本番二日前のゲネで、歌手はどこまで歌ってくれるのだろう、昨日の別キャストのゲネから本番まで、四日連続で全曲をひくオケは、いったいどこまでやってくれるのだろうと心配だったが、かなり本気でやってくれた。きいたところでは、昨日のトリスタンはほとんど歌わずに身振りだけ、歌はスタンドインがカゲウタでやっていたそうだから、しっかり歌ってくれた今日の福井敬さんに感謝。
しかし仕事で七時からサントリーホールに行かねばならず、残念ながら第三幕途中で退出。後はみていないので、演出についての感想は述べない。
そしてサントリーホールでは、上岡敏之指揮新日本フィルのシュトラウス・プロ。よりによってシュトラウス、それも初めがニーチェ原作の《ツァラ》というあたりが、東京の演奏会の玄妙さ。直前の昨夜もマーラーの《千人》だし。
ところが明日は、いきなり《カプレーティとモンテッキ》。こういう唐突さも楽しい。
九月十日(土)もっとベルカントを!

ベッリーニの歌劇《カプレーティ家とモンテッキ家》。藤原歌劇団による新国立劇場での公演。
前々日、前日に千人~トリスタン~ツァラ&英雄の生涯と、ドイツ後期ロマン派の重厚濃密な響きをたっぷりと聴いてきた耳にとっては、まさに一服の清涼剤(死語)のように、その爽快なオケと声の響きが心地よい。
少し驚いたのは、山下一史指揮東京フィルのオケの良さ。ピシッと骨格のしっかりした、シンフォニックな響きで、序曲が鳴り出した瞬間、ああこれはいい上演になるぞと感じた予感は、そのまま裏切られなかった。
たしかに硬質の響きで、オペラ的な崩しはなかったから、終演後の指揮者への拍手が意外に熱くなかったのはそのせいかもしれないが、けっして杓子定規ではなく、歌手の呼吸も尊重しながら品格と推進力を保って、気持がよかった。
松本重孝演出の舞台も手堅く、雰囲気のあるもの。東京文化会館はもちろん、日生劇場などとくらべても、新国立劇場くらいにオペラ上演に適した空間は東京にないと、あらためて感じる。
ロメオの向野由美子、ジュリエッタの高橋薫子、テバルドの笛田博昭、みなよかった。ロメオはメゾのためのパートながら、こうしてきいてみるとテノール的な、開放的な歌い回しを求めているところが多くて、五十年前にアバドが指揮したとき、テノールのアラガルに歌わせているのも納得。ロッシーニのズボン役のような強い響きの声の方がいいのかも。向野の響きはより少年的で、テバルドとの対決などでは不利だったが、終幕の場では透明な叙情が効果を発揮した。
ベッリーニとドニゼッティのシリアスなオペラは、日本人歌手に合うと思う。もうカラスやサザランドの幻影を追う必要はない。十九世紀前半にはそれにふさわしい別のスタイルがあるし、史劇としての興味も、昔より現代の方がもってもらえるはず。どんどんやってほしい。
九月十一日(日)《エリヤ》の毒(前)
メンデルスゾーンのオラトリオ《エリヤ》。大井剛史の日本フィル&日本フィルハーモニー協会合唱団ほかによる東京芸術劇場での公演。日本フィル創立六十周年記念の大作。
死の一年前に初演されたこの作品が、その劇的な書法の充実、漲る生命力において、疑いなくメンデルスゾーンの代表作であると納得できる公演だった。そのわりに日本できかれる機会が少なく、人気も高くないのは、演奏会用オラトリオという、日本では不人気の形式に原因があるのに違いない。
かつてのような純粋器楽派のクラシック好きによる、オペラに対する半可通的な偏見はかなり少なくなったけれど、オラトリオはまだ軽視されがち。宗教的な題材が多いのも敬遠の理由の一つか。
しかし、近代西欧の音楽界を考える上で、市民社会との関わりを考える上で、演奏会用オラトリオの重要性は高いと考える。少数の王侯貴族や教会ではなく、富裕層を中心とする市民社会が音楽家の活動と生活を支えるようになったとき、人気を得たのが演奏会用オラトリオだった。産業革命でイギリス各地の都市が発展し、市民社会が拡散するなかで、ヘンデルはそのパイオニアになった。
イタリア語という外国語ではない自国語の英語で、アマチュアの合唱がプロのオケ、歌手と、同じ舞台で歌う。市民がスポンサーであり聴衆であり、自身や家族が出演者になりうる音楽。
教会ではなくコンサートホールで歌われるものながら、題材は聖書が中心。聖書の物語は市民共通の教養であって、良識的市民と家庭の道徳性にかなう。不倫や姦淫や殺人なども出てくるが、勧善懲悪的なストーリーづけで正当化される。
ドイツ語圏でも市民社会の発展とともに半世紀近く遅れて、モーツァルトがヘンデルの管弦楽を拡大したり、ハイドンが《天地創造》と《四季》をつくるなどこの動きを採り入れる。しかし中央集権のカトリック国家、そして多言語の十八世紀オーストリアよりも、言語は一つなのに小国に別れている十九世紀ドイツのプロテスタント社会の方が、市民音楽、ひいては国民音楽としての演奏会用オラトリオが重要性をもつ可能性があった。
メンデルスゾーンはまさに中心人物。ドイツ語による演奏会用オラトリオとしてバッハのマタイ受難曲を復活させ、さらにヘンデルのオラトリオを取りあげて再評価を促し、そして、《聖パウル》と《エリヤ》を書く。
昨日の日本フィルハーモニー協会合唱団は二百人超のアマチュア、まさに市民合唱団。大人数ゆえに響きが不明瞭になったり、ドイツ語が聞きとりにくかったりはしたが、迫力は素晴らしい。十四型のオーケストラ、四+八人のソリスト、パイプオルガンを併せて統率し、壮大に響かせた大井剛史をみていると、まさにこの仕事はコミュニティの指揮者なのだと感じた。
いまでもドイツの地方都市では、音楽総監督という職務が歌劇場だけでなく、歌劇場を包含した都市全体のそれであることがある。大規模な演奏会用オラトリオはその最大の見せ場。ライプツィヒでのメンデルスゾーンはまさにそうした、音楽コミュニティの長(音楽総監督という職名ではなかったが)。
そして思うのは、二日前にきいたワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》と、これはなんと遠く隔たった位置でつくられた音楽なのだろうということ。
オラトリオとは別の流れで、イタリア語ではないドイツ・オペラの確立を模索する人々もいて、ウェーバーが道を開いて、ワーグナーが出現する。《エリヤ》が一八四六年にイギリスのバーミンガムで英語訳詞により初演され、翌年にハンブルクでドイツ初演されるころ、ワーグナーは《タンホイザー》までのオペラを書き上げ、ドレスデン宮廷管弦楽団の楽長をしていた。
そしてこの年メンデルスゾーンは三十八歳で死に、翌々年にワーグナーはドイツ革命に加担して亡命、以後はコミュニティの長ではなく、独立した英雄的芸術家としての道をゆく。
その道程で生みだしたのが《トリスタン》。こうして翌々日に《エリヤ》をきくと、あれがなんと反市民社会的な、ロマン派的な、不道徳な、孤独な、そして反キリスト教的な作品だったかということを痛感する。キリスト教到来以前の異教世界を描く音楽。
そしてなんといっても、そこには素人=市民が参加する余地がまったくない。超人的な能力を要求される二人の歌手以下、徹底して玄人のための、それも特別の玄人にしか手を出せない、芸術作品。
しかしそれだからこそ、現代社会の日本の聴衆である自分にとっては、《トリスタン》の方がより理解しやすく、共感しやすい。《エリヤ》では壮大な音響に圧倒され、これは素晴らしい傑作だと再確認しながら、同時に、鳥肌がたつような嫌悪感を覚えずにいられなかった。
このところ通いつめている能には、物語の骨子に神仏習合の仏教思想がある。妄執から成仏できない霊が僧に弔いを希う。諸行無常。草木国土悉皆成仏。箸を使ったり、家に上がるとき靴を脱いだりする以外は、すっかり似非西洋人のような生活をしている自分でも、この感覚はすんなり身体に入ってくる。
キリスト教は、そうはいかない。しかし、西洋音楽を聴き、語るときにその存在を無視してしまうことはできない。宗教曲でなくて器楽曲なら気にしなくていいという人もいるだろうが、たとえばベートーヴェンの弦楽四重奏曲第十五番の第三楽章「病より癒えたる者の神への聖なる感謝の歌」の「神」を、日本の神道の神と同一視したら間違いだろう。フランス料理を食べたりワインを飲んだり、欧州に観光旅行に行くのと同じように、音楽を嗜好品として楽しむだけならそれでもいいが、何か考えようとするなら、そうはいかない。
結局はわかりっこないにしても、わかろうと努め、間違えながら語っていくしかないと思っている。聖書を題材とするオラトリオは、その端的な例。
で、《エリヤ》。エリヤというのは旧約聖書に登場するユダヤの預言者で、モーセに次いで偉大な存在とされる。
メンデルスゾーンは、オラトリオ第一作では新約聖書のイエスの使徒パウロを主人公に《パウロ》(グレン・グールドが、自分はベートーヴェンのミサ・ソレムニスよりも《パウロ》をききたがる唯一の人間らしい、とほめていることで有名)を書き、続いて旧約聖書から《エリヤ》を書いた。第三作は《キリスト》そのものだったが、未完に終っている。
詞の構成はメンデルスゾーン自身で、ルター訳の聖書から言葉を集め、一部を自ら創作した。
しかしこの旧約聖書の預言者というのが強烈な、不寛容の権化。特に第一部。イスラエルの民が、シリア出身の王妃イゼベルに従って異教の神バアル(のちに悪魔ベールゼブブに変形される)を信じるのをみて、天罰として何年も旱魃が続くことを預言する。死者を蘇生して自らが神の意に沿う者であることを証明したあと、バアルの預言者たちをあつめて、どちらが火を呼び起こせるかを競い、対決する。
懸命に、しかし無駄にバアルに何度も祈る預言者たちを、エリヤは、お前たちの神は忙しいのか、あるいは居眠りでもしているんだろうと嘲笑う。
「バアルよ! バアルよ! お答えください! ご覧ください、敵どもが私たちをあざ笑っています!」
エリヤはイスラエルの民を集め、その前で祈って火を起こし勝利を決定づけ、かれらを味方にして、叫ぶ。
「バアルの預言者どもを捕らえよ、一人も逃がしてはならない。キション川に連れて行き、そこで彼らを殺すのだ!」
――皆殺し。鏖殺。
そこで主の声。
「私に背いたから、彼らは滅びる」
エリヤが神に祈ると、豪雨となって旱魃が終る。主への民の感謝の歌。
これらをメンデルスゾーンは実に見事に、劇的に音化する。
一神教の毒、というか。異教への憎悪と徹底的な不寛容。エリヤは非常に危険な煽動者だとしか自分には思えなかったけれど、これは現代日本人の感覚でみてしまうからなのだろう。
旧約聖書は元々ユダヤ教の聖典で、キリスト教が受け継ぎ、さらにイスラム教もここから分れる。エリヤはこの三つの宗教で偉大な預言者となっている。
九月十二日(日)《エリヤ》の毒(後)
前作《パウロ》は、キリスト教徒を迫害していたユダヤ教徒サウロがイエスの声を聞いて回心し、使徒となり、殉教を覚悟してエルサレムに向う話。愛と寛容。音楽もより叙情的で優しく、自分の知っているメンデルスゾーンのイメージに近い。中世説話的、とでもいうか。
《エリヤ》はそこから旧約聖書に立ち返って、より古代的で荒々しく好戦的な、感情むき出しのユダヤ教の世界を描いていく。作品の最後にキリストの出現を予告しているので、三部作の最後の《キリスト》がジンテーゼとなって、命題をアウフヘーベンする予定だったのかもしれない。
その前に、キリスト教徒のユダヤ人メンデルスゾーンは死んでしまった。音楽技法的にはさらに進歩して充実して劇的に壮大に、異教徒から見れば独善としか言いようのない、不寛容で暴力的な、血なまぐさい人物を賛美したまま。
この作品が「一八四八年」の直前、革命と英雄の時代に生まれたのは、ある意味で必然的だったのかも。エリヤは神の名の下に革命を行ない、悪王を王座から引きずりおろす英雄なのだ。
第二部の最後、火の馬が牽く火の戦車に乗ってエリヤが昇天したあと、エリヤとキリストと主を賛美して壮大に終る部分は、不思議なくらいに三日前にきいた《千人の交響曲》のラストの、ファウストの昇天と壮大な締めくくりに照応するものがあって、ものすごく面白かった。
ファウストを引きて昇らしむのは、異教的なマリア信仰、母性信仰で、エリヤを昇天させる男性原理、父性信仰のユダヤ教とは正反対なのに、メンデルスゾーンはここで『ファウスト』を、ゲーテを意識したように、感じられてならなかった。あえて裏返しにした感じというか。
大規模声楽作品は、実演で声と音響の洪水に身を浸してこそ、真価が実感できる。ハッタリ、ケレン、こけおどしも含めて十九世紀西欧的な、黒船的な強大なエネルギーと、直面できる。
千人、トリスタン、エリヤ。居ながらにして続けて体験する機会を与えられたことに感謝(誰に対して?…)。
九月十三日(火)CDと雑誌

一枚目の写真は、数日前にドイツのJPCから届いたディスク。ORFEOの二点は九日発売だが、到着まで一週間くらいかかるのを考慮してか、発売前に発送してくれたので発売日前後に届いた。こういうのはありがたい。
上はバイロイト音楽祭ものから、一九六一年のケンペ指揮の《指環》。これは前年よりケンペの指揮が安定したといわれているのと、なんといっても《ジークフリート》のさすらい人役でこの年デビュー、ホッターの次を担う未来の偉大なワーグナー歌手と評判をとった、三十四歳のカナダ人ジェイムズ・ミリガンがききもの。将来を嘱望されながら四か月後にバーゼル歌劇場でリハーサル中に急逝した人。状態の悪いテープでしかきいたことがないので、正規発売は楽しみ。
右下はザルツブルク音楽祭シリーズから、故アーノンクール指揮ウィーン・フィルのベートーヴェンの一&七番の二〇〇三年ライヴ。祝祭大劇場かと思ったらフェルゼンライトシューレでの演奏会。
左下はヴェンツァーゴ指揮ベルン響のオネゲル作品集で、交響曲第三&五番と《ラグビー》。二〇一二年と一五年の録音。ジャケットはラグビーの絵。

続いて二枚目は、能と狂言総合誌「花もよ」。出版不況の中、果敢にも二年前に創刊された隔月間誌の二十六号。私が能楽の深みにはまるきっかけを下さった方が、病膏肓に入るのを見かねて、こういうものがあると送って下さった。
七百円で二十四頁と薄いが、毎号CD(CD‐RではなくプレスCD)がついていて、貴重録音がきけるのが魅力。また別売のCDシリーズには、一九六〇年代の筑摩書房のフォノシートを復刻した能・狂言の音源も出ているようで、応援したくなる。
二十六号の附録は明治三十六~四十四年の、海外レーベルによる「出張録音」のSP復刻。当時の日本にはまだ録音と製造技術がなかったので、海外から技師を招いて録音、本国でプレスしてもらって輸入するという、大変な経費と手間のかかることをやっていた。そこまでしても、自国の文化と西洋の科学を組み合わせようとした人たちがいたのが、明治後半という時代。維新の荒波からようやく復興した時期の名手たちの歴史的遺産。
こういう録音にこだわる方は、やはりどこの世界にもいる。やみくもに過去をありがたがるのではなく、現在をよく知って味わうために、能でもやはりこの世界に深入りすることになりそう(笑)。
九月十五日(木)ハーゲンとパーヴォ
九月の声を聞くと同時に、演奏会強化月間が始まっている。
昨日はオペラシティでハーゲン・クァルテット、今日はサントリーホールでパーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団。二つの演奏会を勝手につなぐと、テーマは「変容(メタモルフォーゼン)」。
まずハーゲンは「フーガの芸術~宇宙への旅路」と名うたれて、
バッハ:フーガの技法よりコントラプンクトゥス一~四
ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲第八番
ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第十三番(終楽章は大フーガ)
前半のバッハとショスタコーヴィチは続けて演奏。プログラムにセコバイのシュミットの言葉が引用されていて、両者はテンポも雰囲気も同じように始まるとあったが、そのとおり。BACHとDSCH、自らの名の音型。
ショスタコーヴィチがバッハの「平均律」に触発されて「二十四の前奏曲とフーガ」を書いたのを想起させる。あれと同じように、バッハの鏡像が陰惨に歪められていくような感じ。変容。あちらは一九五〇年のライプツィヒ訪問、こちらは一九六〇年のドレスデン訪問が契機。戦争の惨禍という公的な理由の影に、共産党入党という私的な苦しみがあったとされる曲。スターリン時代に発表したら一発で粛清されるだろう陰鬱さ。
ハーゲンの響きは、金属的直線ではなく、木質のたわんだような感じが独特。しかしユーモアや遊びはかけらもない。
後半はベートーヴェン。前半よりも明らかに響きの音圧が弱い。数年前のトッパンホールのツィクルスでの演奏の、あの強靱な響きとは違う。しかしあのときは、ストバイのルーカスだけが不調でうわずっているように感じられたが、今回はその一人旅感はない。音圧を弱めてルーカスを助けているのかどうかはわからないが、聴くほうも息をひそめて集中しなければならない感じだったので、この表現こそトッパンホール、せめて紀尾井ホールで聴きたかった。終楽章は大フーガでなければならないというだけに、そこに山をおいた表現。
そして今日はパーヴォとN響。メインのムソルグスキー三曲の間に武満二曲が挿入されたプロ。
ムソルグスキーの三曲は、オーケストレーションの変容を示していて、じつに面白かった。最初の交響詩《はげ山の一夜》はあえて原典版で、垢抜けない響きと散漫な構成。武満をはさんで後半の、歌劇《ホヴァンシチナ》の第四幕第二場への間奏曲〈ゴリツィン公の流刑〉はリムスキー・コルサコフ編曲。組曲《展覧会の絵》は、いうまでもなくラヴェル編曲。
本人~リムスキー・コルサコフ~ラヴェルと華麗に壮大に、色彩にあふれた、そして洗練されたユーモアをもつ響きへと次第に変容していく。このオーケストラという音響体の変容を、パーヴォはN響の機能性を活かして、鮮やかな手腕でさばいてみせた。骨っぽく、しかも明晰で鋭利。
サントリーホールできくN響の音はときに濁った感じがして、NHKホールのデッドな響きに馴れすぎた音の出し方をしているのではと思うこともあるが、今日は(二日目ということもあってか)そんなことを微塵も感じさせない。
強烈だったのが《展覧会の絵》コーダの鐘。「のど自慢」で使うみたいな小さいやつではなく、『道成寺』で使いそうな(それは大げさ)、幻想交響曲用か何かの大きな鐘を、まさに耳を聾するばかりの音量でぶっ叩いてくれた。
これをきいた瞬間、《はげ山の一夜》が原典版でなければならなかった、もう一つの理由が頭に響いた。
原典版にはコーダの教会の鐘がない。中途半端に終り、そのまま魔界の祝宴が続いたのだ。《展覧会の絵》のコーダ、演奏会全体のコーダに至って鐘が鳴りひびき、やっと夜が明けて魔は去るのだ。
すると武満は、はるばる日本からロシアの百鬼夜行にやってきた魔属なのか。
美しい憂いに満ちて、《ホヴァンシチナ》間奏曲の響かせた宿命的な暗さとはなんと異なる、はかなさか。
「音響体」としてのオーケストラの面白さを、満喫させてくれた演奏会。ソニーがCD用に録音していたので、世に出る日が楽しみ。
九月十六日(金)黒塚、暗い部屋
十六日は国立能楽堂の九月定例公演。
狂言『萩大名』石田幸雄(和泉流)
能『黒塚 雷鳴ノ出』髙橋忍(金春流)
作者不明の『黒塚』は、安達ヶ原の鬼婆の話。しかし、単なる怪異譚に終ることなく、自分が最近気にかかっている現代日本の問題にもからんでいるようで、深く考えさせられた。
それについてはあとで述べるとして、物語は那智の山伏、東光坊祐慶(ワキ)と同行の山伏(ワキツレ)が安達ヶ原で行き暮れて一夜の宿を借りると、心安く泊めてくれた老婆の正体は鬼女。しかし祐慶の祈祷の力で退散するというもの。
後半は正体を現した鬼女と山伏との、派手な動きの対決になるが、それよりもそこまでの物語に惹きつけられた。
自分は、鬼女はこれまでの犠牲者同様に、山伏を殺して食うつもりで泊めたのだろうと思い込んでいたのだが、この話はそうではないのだ。
徳の高い仏僧が来たことで、鬼女は自分も成仏の機縁を得られるかもしれないと喜んで、本心からもてなしている。老婆の姿で糸繰り車を廻しながら、成仏できぬまま、徒(あだ)に長らえる自らを嘆く。
「およそ人間の、徒なる事を案ずるに人さらに若きことなしついには老いとなるものを、かほど儚き夢の世をなどやいとはざる我ながら、徒なる心こそ恨みてもかひなかりけれ」
「長き命のつれなさを、思い明石の浦千鳥、音をのみひとり鳴き明かす」
「人さらに若きことなし」、人は若くなっていくことはない、ただ老いて、長き命のつれなさを泣き明かすと歌ったあと、夜が更けると寒くなるので、山に登って薪を採ってこようという。
これは解説によると、釈迦が聖人から法華経を伝授してもらうべく、薪を採って仕えた故事になぞらえているのだそうで、老婆の仏心を象徴している。
しかし、老婆は家を出るとき、自分の閨(寝所)は覗かないでくれ、と言わずにいられない。この余計な一言に、さすがに山伏も「さように人の閨などを見る山伏にてはなく候」と、人を見て物を言えとばかりに答える。
そしてこのやりとりが、脇で見ていた能力(山伏の従者)の心に、不審の火をつけてしまう。この能力は狂言役者(竹山悠樹)が演じる、おどけ役。子供のころから、人からやるなと言われるとやりたくなり、見るなと言われると見たくなる性分だという能力は、主人が寝たのを見計らっては何度も閨を覗こうとし、その度に気配に気づいた山伏にたしなめられる。この動きで笑いを誘ったのち、三度目にしてついに成功するが、そうして見たものは、人の死骸の山。
驚いて主人に報告、「自分は先に行って宿を探して参ります」と、体よく先に逃げてしまう(ここがまた可笑しい)。
笑いと恐怖が交互にあらわれるうちに緊迫感を高めていくという展開が、じつにうまくできている。十五世紀半ばにはすでに成立していた作品に、こうした劇的効果がある。
そして激しい太鼓を交えた、嵐のような囃子のなか、二人の山伏は能力と同じ光景を見る。そこの詞がまた凄い迫力。
「人の死骸は数知らず、軒と等しく積み置きたり、膿血たちまち融滴し、臭穢は満ちて膨脹し、膚腑ことごとく爛壊せり」
中世人が好んで描いた、地獄絵に通じる強烈な字面。
山伏は肝をつぶし、あてもなくひたすら走って逃げる。この逃げるさまを、舞台を走り回るのではなく、二人が脇座に斜めに立って、足先を少し浮かせるだけであらわし、あとは激しい囃子だけで想像させるあたりが、見事な見立て。
そして、正体を知られたことに気がついた老婆は薪を投げ捨て、鬼の姿となって追ってくる。山伏は手に持った数珠を鳴らして懸命の祈祷をはじめ、ついに鬼女を折伏する。
正直、ここのところはとても難しいと思った。前に見た『巴』や『景清』のようなシテ単独の舞ではなく、ワキとの二人の動きになるので、わかりやすいけれども、それだけ安っぽいチャンバラになりかねない。こうした多人数の派手な殺陣が歌舞伎につながるのだろう。しかし歌舞伎の場合は様式化された軽業に仕立てているからいいけれども、能はより激しい内面の怨みを、そこに籠めなければならないから難しい。こうした作品を世阿弥ではなく、より大衆性を求めた後世の人が書いたとされるのも納得。
しかしそれはそれとして、鬼女の悲しさ、あさましさ。人間は誰でも人に見せられない、「暗い部屋」を心の中にもっている。黒塚、黒い墓、というタイトルは、それを象徴しているようでもある。
なぜ老婆が人食い鬼になりはてたか、その由来を、この能が一切説明しないのもいい。それは個人的事情にすぎず、暗闇はより普遍的なもの。
そしてそれがここでは、「人さらに若きことなし」という老いの問題、「長き命」という長寿の問題にからめてあることが、私を考えさせた。
最近、友人知人、フェイスブックでの知り合いも含めて、老親を介護されている方が、たくさんおられる。
さまざまにご苦労なさっているようだが、なかで私が気になるのが、昔はけっして見せなかった一面を、老親が見せるようになった、ということ。
心遣いの細やかな、優しい親だった人が、身勝手で意地悪な人になる。食べ物の味に絶対に文句をいわなかった人が、悪態をつくようになる、などなど。
それは生まれついてのもの、本性なのだろうか。物心つくうちに、親に教えられ、自分で学んで、隠すようになった、克己の対象としての本性、「暗い部屋」なのだろうか。
性悪説に立てばそうなる。誰しもが生まれながらに抱えている闇、妄執。赤子がそうなのは当然のことで、親や祖父母はそれを克服する術を、身をもって教えていく。
そうして「立派な大人」になった人が年老いて、本性に戻っていく。子にとっての「生きる手本」から、「厄介な生き物」となって。
長く生きる以上、それは避けられないことなのか。親の見たくない姿を見る子も、やがて年老いて、同じことをくり返すのか。それが長寿時代の人の一生か。
老婆は、糸車を廻しながら、はてなき輪廻の苦しみを歌っていた。
「生死に輪廻し、五道六道にめぐることただ一心の迷ひなり」
「かほど儚き夢の世をなどやいとはざる我ながら、徒なる心こそ恨みてもかひなかりけれ」
鬼女は最後、成仏することなく、浅ましい我が姿を恥じて、激しい夜風の音にまぎれて、ただ身を隠して消える。
再び現れるのか、どうか。
九月二十一日(水)お別れの会


九段下のホテルグランドパレス(金大中事件が起きたホテル、と書くのも古いか)にて「宇野功芳先生お別れの会」。出席者三百人で盛大にお別れ。このような会にこれだけの人数が集まるクラシックの音楽評論家は、先生が最後だろう。いただいたのは「宇野功芳御用達」のあられ。
昨年の八月、先生からの最後のお葉書(ミュージックバードで共演させていただいた番組についてのご感想など)が、長年ご愛用の青インクではなく、黒インクであることにちょっとさびしい思いをしたことなどを思い出す。
会場に行く途中には、咲きかけた彼岸花(写真撮らず)。

九月二十二日(木)五重奏オーケストラ

今月書いた月刊誌が出揃ったので、まとめてご紹介。
左の「モーストリー・クラシック」、巨匠名盤の連載はデ・サバタ。特集のなかで幻のカリスマ・オーケストラと題して、NBC響やコロンビア響など。
右の「音楽の友」は、ジャン・ギアン・ケラスのインタビュー、特集の弦楽四重奏団紹介をいくつか、それにセイジ・オザワ・フェスティバル松本の公演レポート。
中央の「レコード芸術」は、特集「人生の五十枚」。くり返し聴いてきたディスクを五十枚挙げて紹介するもので、喜多尾道冬さん、満津岡信育さん、相場ひろさん、舩木篤也さん、矢澤孝樹さんという濃いメンツの末席に。担当モトヒロ氏は「みなさんマニアのつくりかたという感じで面白いです」と言っていたが、私のは「道の踏みはずしかた」というほうが正しい。しかし書いていて楽しかった記事。CD初期の盤など五十枚のデータとジャケをそろえるのには手間がかかったが。
今になって最後に能楽を一枚入れて、新たな冥府魔道の行く先を示しておけばよかったと思っているが、今回は過去の盤もクラシックだけに絞ったことを考えれば、これでヨシ。
そして今日は、青葉台のフィリアホールでベルリン・フィルハーモニー弦楽五重奏団。五百席と編成にぴったりの大きさなので、とても気持よかった。
弦楽五重奏というと、弦楽四重奏にヴィオラ、あるいはチェロを足すのが一般的だが、かれらはコントラバスを加えている。つまりオーケストラの弦五部の各一人版。だからモーツァルトやブラームスの「弦楽五重奏曲」を演奏したりはしない。モーツァルトでも《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》とか《アダージョとフーガ》、それにバルトークの《ルーマニア民俗舞曲》など、弦楽オーケストラのレパートリーをひく。
メンバーはヴァイオリンのルイス・フェリペ・コエーリョとロマーノ・トマシーニ、ヴィオラのヴォルフガング・ターリツ、チェロのダヴィッド・リニカー、
コントラバスのヤーヌシュ・ヴィジク。
一人ずつしかいなくても、計五人しかいなくても、これは狭い意味での「室内楽」ではなくて、ミニ・オーケストラなのだと納得させられる響き。それはとりわけ、一人をソロに仕立てて残りの四人がバックをつとめる協奏曲スタイルの曲で、強烈に感じさせられた。
ヴィオラがソロのウェーバーの《アンダンテとハンガリー風ロンド》、チェロとセコバイがリードするアンコールのチャイコフスキーの《エフゲニー・オネーギン》のレンスキーのアリア、ストバイがソロのサン=サーンスの《序奏とロンド・カプリチオーソ》、アンコールのバッツィーニの《妖精の踊り》、そしてコントラバスも、アンコールのボッテジーニの《「夢遊病の女」による幻想曲》で活躍。
今回のメンバーには各セクションの首席奏者は含まれていないようだが、上手い人が多い。コントラバスのヤーヌシュ・ヴィジクはNDR響の首席だったというように、他のオケなら首席級の奏者が二列目以降にもゴロゴロいるのがベルリン・フィルなのだということを、耳に叩き込んでくれる(笑)。
なんといっても、ピアノがいないのがよかった。前述のケラスのインタビューで、「今回の来日ではピアノを連れてきていないのはなぜか」ときいたら、「ロマン派ではハーモニックな音楽が重視されたから、ピアノが重用された。しかしピアノの響きはあまりに支配的、拘束的だ。音の出しかたが弦楽器と違いすぎ、単色すぎる」という意味のことを即座に答えてくれて、ロマン派以外のレパートリーばかり持ってきた理由を説明してくれた。
今回も、ピアノがいたらいかにもロマン派の室内楽になってしまったろうけれど、弦楽だけだからより自由に呼吸し、跳ね、まさにミニマムのオーケストラとして躍動する。ピアソラの五曲の編曲版も素敵だった(どの曲も編曲者の表記がプログラムになかったが、おそらくは作曲家、編曲者としても活躍するチェロのダヴィッド・リニカーが担当)。
そして、五人の生き生きと自発的な音楽を聴いていて、これをそのままフル・オーケストラにしたのが現代のベルリン・フィルなのだと、あらためて実感。
室内楽的という意味ではなく、五人であれ百人であれ、ソリストが合奏する集団、オーケストラ。巨大なゾリステン。ラトルとのベートーヴェン全集は、まさにそうした、奏者の自発性が見事に生きた音楽だった。好き嫌いは別れるだろうが、私は多大の刺激を受けた。
九月二十四日(土)ファウストたち
スダーン指揮東京交響楽団の《ファウストの劫罰》をサントリーホールで。
サントリーホールでベルリオーズというと、四月に聴いたヴェロ指揮仙台フィルの幻想交響曲&《レリオ》の記憶がまだ鮮明。あれは二曲をあわせて、作曲家立会いのもとで行われたオーケストラ・リハーサルに見立てる、というヴェロの演出が面白かった。
二十代のベルリオーズがつくった《レリオ》は、「偉大なシェイクスピアを好きな偉大な俺様」といわんばかりの、独善的な自己肥大にみちていた。それに対して《ファウストの劫罰》は四十代の作品だから、自己顕示欲は抑制されたが、しかし自由な改変による「俺様無双」な作品。テキストもストーリーも尊重してないのは、ゲーテの作品をフランス語訳で読んでいるからか。
今年は《千人の交響曲》を二回、その前にボーイトの《メフィストーフェレ》のプロローグと、『ファウスト』にちなんだ作品をまとめて聴けて嬉しい年(前日にさらにもう一曲。後述)だが、ベルリオーズくらい原作を自由に読みかえた人はいない。
それにしてもこの作品とメンデルスゾーンの《エリヤ》が同じ一八四六年初演と気がついて、愉しくなってしまった。あの旧約聖書のユダヤ世界と、中世から近世へと遷移するヨーロッパとを時代背景とする、二つの対照的な大作。エリヤの昇天とマルグリートの昇天と(つけ加えれば《千人の交響曲》のファウストの昇天と)、なんと異なる思想と音楽であることか。
マルグリートの昇天の直前、ファウストの地獄落ちを喜ぶ魔界の合唱が「恐怖の神秘は成し遂げられたり」と、原作第二部の「神秘の合唱」をもじって歌う、ベルリオーズの悪意(笑)。
エリヤに皆殺しにされた人々が信じ、そして裏切られた神はバアル。そのバアルがキリスト教では悪魔ベールゼブブになる。同じ悪魔でも後世に創作され、より近代人的な性格をもつメフィストフェレス。両者の差。
何より信じることを求める教会と、あまりに容赦なく訪れる死と災厄を前に、刹那的に生を謳歌する猥雑な俗世間との二面性。ベルリオーズはいかにも中世的なこの聖俗の両面を音で描く(マルグリートの家の隣が兵営なのが象徴的)。その狭間で苦悩して愛を求め、悪魔につけ込まれるファウスト。その昇天をベルリオーズは許さない。
そして、今回はナマで聴く機会を得ないが、シューマンの《ゲーテのファウストからの情景》も一八四四年から五三年にかけて作曲と、ほぼ同時期。こちらはゲーテのテキストそのまま、重要場面を抜粋して音楽をつけたもの。
劇的物語とオラトリオ、そして曲種指定のないシューマン。自由に変形していく大規模声楽作品たち。
マーラーはシューマン同様にテキストを尊重しつつ、ベルリオーズ流の雄弁なオーケストラを採用した。ベルリオーズとシューマンのジンテーゼとしての「交響曲」を目指したのか。
ワーグナーが同じ時期に、前半生の歌劇時代の締めくくりとなる《ローエングリン》の作曲に取りかかっていたというのも、面白い符合。
その歌劇時代は、キリスト教の規範への懐疑がテーマだった。神を呪うオランダ人。戒律を破るタンホイザー。愛する者をより深く知ろう、求めようと禁断の質問を発するエルザ。
呪詛は破戒をへて好奇心に変化し、科学と芸術の発展の種子となる(同時に破滅の危険に満ちた)人間の知識欲へと、深まる可能性をみせる。そこに悪魔はいない。いるとしたら人の心の中。
後半生、教会以前の世界を志向しはじめたワーグナーが、より一般的な喜劇をつくろうとしたとき、中心に教会のある中世の町ニュルンベルクと、聖と俗が混在するその世界に戻っていき、奇跡も悪魔も描かなかったことの意味。
もう一つのファウストの音楽というのは、二十三日に杉並公会堂で聴いた「安達朋博ピアノリサイタル2016」。
安達はクロアチアの作曲家の紹介に力を入れている。二十世紀前半の女性作曲家ドラ・ペヤチェヴィッチのピアノ・ソナタ第一番、ダヴォリン・ケンプの《光の蝶よ》といった珍しいクロアチア作品に加えて、ラフマニノフのピアノ・ソナタ第一番など。やわらかいタッチの持ち主で、ラフマニノフも打楽器的な響きではなく、ききやすい。
このラフマニノフのソナタは、元々はゲーテの『ファウスト』に基づいて、第一楽章がファウスト、第二楽章がグレートヒェン、第三楽章がメフィストフェレスという、リストのファウスト交響曲そっくりの構想だった。標題はのちに破棄されたが、楽想には雰囲気が多分に残っている。そういう音楽を《ファウストの劫罰》の前日に聴く、偶然の愉しさ。
九月二十五日(日)肉弾相撃つ
NHKホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団。フォークト独奏のモーツァルトのピアノ協奏曲第二十七番とブルックナーの交響曲第二番。
モーツァルトのこの曲というと、初秋の高い空、というイメージを勝手にもっているのだが、今日の演奏は硬派で、晩秋から冬にかけての雰囲気。冬の室内のような緩徐楽章の温もり。
ブルックナーも筋肉質で気迫のこもった、逞しい響き。こちらも緩徐楽章の不思議な静けさが印象に残る。他の楽章では久々に音の格闘技を味わう。交響的プロレス。黒パンツ一丁の男たちが組んずほぐれつ、投げたり叩きつけたりするような、音の肉弾戦。
九月二十六日(月)生き証人
サントリーホールで、ロジェストヴェンスキー指揮バルチック艦隊、じゃない読売日本交響楽団(お約束)のショスタコーヴィチ演奏会。
ショスタコーヴィチのバレエ組曲《黄金時代》 、ピアノ協奏曲第一番(独奏ポストニコワ)、交響曲第十番。
ありていに言って「〆切の将棋倒し」が起きかねない瀬戸際的状況なので、演奏会に行っている場合かと考えたが、それでも行くことにした。『演奏史譚一九五四/五五』の原稿を七年遅れで(…)ようやく送ったその日に、タコ十があるというのは、じつに素晴らしい符合だったから。
この原稿は、トスカニーニが引退してフルトヴェングラーが死に、カラヤンやカラスやグールドが台頭してくる、まさにその時期のヨーロッパと、そこに居合わせた吉田秀和や山根銀二たちの音楽体験が主軸なのだけれど、同時に、スターリン没後の共産主義圏の変化の中を生きる音楽家たちと、まだ左翼が圧倒的にインテリ層を支配していた日本にも頁を割いた。
ショスタコーヴィチの交響曲第十番はまさに、この時期に生まれた作品なのである。一九五三年十二月十七日にムラヴィンスキー指揮のレニングラード・フィルによって初演され、社会的リアリズムにふさわしい作品かどうか議論が巻き起こったが、翌年四月の会議はうやむやに終ってその価値が認められ、ただちに初演者の演奏で初録音される。
ロジェストウェンスキーはゆったりしたテンポでたっぷりと鳴らし、疎外と陰惨を呵々大笑するようなユーモアで包んでいった。当時を知る生き証人。一九五七年夏のボリショイバレエ初来日の指揮者として帯同してから、五十九年め。
九月二十七日(火)日本フィル新世紀
サントリーホールで、日本フィル創立六十周年記念、ピエタリ・インキネン首席指揮者就任披露演奏会。
曲はワーグナーの《ジークフリート》と《神々の黄昏》の抜粋。前日の同じホールでのロジェストヴェンスキー演奏会に続いて、今日も約二時間半(休憩十五分)の終演九時半の大演奏会。
ブリュンヒルデとジークフリートの出会いから終焉までの愛の物語に的を絞った、楽劇「ジークフリートとブリュンヒルデ」というような構成に納得(《ジークフリート》終幕の二重唱だけは半分に縮めてほしいといつも思うけれど…)。
インキネンの演奏は、「ワーグナーの毒」が薄めなのがよくも悪くも特徴で、それでも重い長丁場だけにオーケストラも大変そうだったが、最後、すべての妄執と欲望を焼きつくし、流しつくした炎と水がおさまったあと、長く引き延ばされた終結音が澄んで美しく、台風一過の青空のよう。
就任披露に《神々の黄昏》ってどうなの(笑)と思ったが、なるほどこれは新たな世紀の始まり。幸あれかし。
九月三十日(金)メシアン、紅葉狩
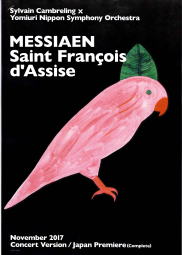
東京芸術劇場にて、読売日本交響楽団の二〇一七年度プログラム発表記者会見。
目玉は十一月のメシアンの歌劇《アッシジの聖フランチェスコ》の演奏会形式による全曲日本初演。十九日と二十六日にサントリーホール、合間の二十三日にびわ湖ホール。
カンブルランでは四月十五日の東京芸術劇場、メシアンの《忘れられた捧げもの》、ドビュッシーの《聖セバスティアンの殉教》交響的断章、バルトークの歌劇《青ひげ公の城》(演奏会形式)というプロもとても面白そうで、楽しみ。
なお読響は来年二~八月のサントリーホール改修期間は東京芸術劇場を使うそうで、これは距離的に助かる。
それにしても、こうして在京各オケが定期演奏会での演奏会形式オペラの上演に非常に力を入れている現況を見ると、以前にも言ったことだが、新国立劇場がこれにうまく協力することはできないのだろうか、と思う(メシアンにびわ湖ホールが関っているのを見て、いっそう思う)。新国立劇場の現状の興業システムでは、よほどのことがない限りジリ貧だと思われるのだから。
もちろん舞台上演でなくて、演奏会形式でいい。演出に関して先進的な層と保守的な層とで深い断裂がある日本の現状では、むしろそのほうが広く支持される上演ができそうな気がする。
サントリーホールよりキャパが小さくて収入減となる弱点は、オケと新国立劇場が責任を分担しあって二回公演を三回公演に増やすとか。サントリーホールの音響は独唱を聴くには最適ではないだけに、新国立劇場の舞台がもっと活用されてほしい。もちろん、本格的な反響板とか、演奏会形式のための音響設備は必要だろうが。
演技つきの上演は、これも前にも書いたことながら、中劇場で簡素な装置とオケで演技メインの、親密な上演。大歌手は必要なく、むしろ座付の日本人が望ましい。《ボエーム》とか《フィガロ》とか《リゴレット》とかは、そうした規模でこそ真の魅力を放つ作品だろう。

夜は国立能楽堂で、能楽協会主催の「第十三回ユネスコ記念能」。
能の「五番立」の神・男・女・狂・鬼の各作品を、金剛・金春・宝生・喜多・観世の五流の若手が分担する。
といっても五作品を完全上演すると一日がかりになるので、前の四つは仕舞、つまりクライマックスのシテの舞だけを面や装束をつけずに地謡で舞うもの。自分のように元の舞台をみたことのない人間には雰囲気しかわからないが、神・男・女・狂の違いはなんとなく感じる。続けて大蔵流の狂言『鴈礫』があって、休憩後に観世流の『紅葉狩 鬼揃』だけが完全な形で上演される。
紅葉狩りの季節、美女に化けた戸隠山の鬼が退治されるチャンバラもの。深みはないけれど艶やかで賑やか。「鬼揃」という小書は、シテの鬼女以外に五人も女が登場し、紅葉模様の打掛で揃えて、華やかに舞う。鬼と変じた後半も、紅葉の枝を振り回して闘う。
グッと引きこまれたのは、美女が怪しい素振りを見せはじめる、中の舞が急の舞に変わる瞬間。囃子も舞も、一瞬に緊迫していく。こういうゾクゾクする瞬間を存分に味わうために、全体が存在するような気もする。
そういえば戸隠は、中学二、三年の林間学校の行き先だった。それ以来行ったことがない。
十月二日(日)サナダマン
『真田丸』をみる。早くも九度山編の終り。次回からの大坂の陣編の予告を見て、なるほど幸村伝説の始まりと期待が膨らむ。
それまでの信繁の人生は、偉大な父の名声の陰に隠れてきた。真田家においても豊臣家においても、ただの脇役。その男が昌幸の名をとって「幸村」と名を変えて、初めて人生の主役、真田丸の主人となって、戦国最後の夏の夕空に大花火を揚げてみせる。
脱皮、羽化。ここまで本編ではけっして見せなかった「赤備え」は、芋虫が蝶に、より正確にはサナギマンがイナズマンに変身したようなものなのか。そこには、家康を震撼させた三方が原の父の雄姿、そして信玄の軍勢が重なるのか。
大河ドラマは、忠臣蔵もの以外は最後が陰惨になることが多いが、今回は九か月に及ぶ幼虫時代をへて、最後に羽ばたいて光を放つらしい。楽しみ。そして、幸村が自らの人生をようやく謳歌する部分だからこそ、十勇士は要らないのかもしれない、とも思う。
一方で、父の雄姿という言葉で思い出したのが、信繁の母、薫の最後の登場場面。若いころの昌幸は凛々しかった、というセリフで終ったけれど、ほんとはあれ、あのあとに昌幸の若いときそっくりの若武者があらわれ、薫が驚くというような展開だったんじゃないか。それはもちろん信之の息子役の、高畑裕太。そこをカットして、あのセリフだけが残ったような気がする…。
それから、呂宋帰りのたかが真田紐のヒントを持ってくるという味付け、最後まで『黄金の日々』ラヴがあふれて、素敵。助左もいつもこんなふうに商売のヒントを見つけていたような。
赤備えが戦国の夕焼けを意味しているのなら、『黄金の日々』タイトルバックのあの落日の光景にも重なるのか?
十月五日(水)再会フォーレ四重奏団
月頭からの演奏会他の感想まとめ。
一日はまず十四時から紀尾井ホールで「紀尾井シンフォニエッタ東京メンバーによるアンサンブルⅠ ~小菅優とともに贈る楽しい室内楽」。ショパンのピアノ協奏曲第一番(弦楽五重奏版)に、サン=サーンスの動物の謝肉祭のオリジナル版。こういう編成の良質の演奏をこのホールで聴けるのは嬉しい。ただ、弦楽はとりわけ、もっと自発性を発揮してほしい。それが室内楽の醍醐味なのだし。そのあとに十八時からトッパンホールでフォーレ四重奏団をきいたので、その思いが特に強まってしまった。
そのフォーレ四重奏団。本当に度肝をぬかれた二〇一四年十二月の同じホールの演奏会から、二年弱での再会。あのときの印象が間違いではなかったことを確められた。
今回は一日トッパンホール、五日みなとみらい小ホールと二回聴けた。前者はブラームスのピアノ四重奏曲第二番で、この演奏効果を上げにくい曲から見事に充実した時間をもたらしてくれたが、本領発揮の面白さでは断然五日の方(ただし、同じ約四百席という席数でも、音響に関してはトッパンホールが断然優れていた)。
その五日、最初のブラームスのピアノ四重奏曲第一番は、二年前に驚愕の名演を聴かせてくれた曲。かれらの名刺代りの十八番だと、今日もあらためて納得。圧倒的な終楽章はもちろん、第三楽章中盤で、ピアノがファンファーレのように鳴りひびき、弦の三人が答えていった瞬間、こういうものを聴きたくて自分は音楽を聴き続けているのだと、嬉しさで涙が出そうになった。泣きそうになるなんて、櫻間右陣の『巴』以来。
この四人は本当に息が合う。二十年一緒にやってきて、今も互いの演奏を、音を本当によく聴きあって、答えあっている。四人とも、飽きずに毎日を新たに楽しむ達人なのかも。その術を知らなければ、レパートリーの少ないピアノ四重奏を続けるのは難しいかも。
だが、四人というのはなんと充実した人数なのだろう。以前、初めて生でエベーヌを聴いたときと同じことを思う。ヴィオラがいるぶん、ピアノ・トリオよりも厚いハーモニーがあり、「弦楽四重奏+ピアノ」になりやすいピアノ五重奏よりも、それぞれの個性が際だつ。本当にギリギリの、少なすぎず、多すぎない、これしかない編成。
しかし同時に、これはやはり、ピアノのディルク・モメルツがアンサンブルの鍵、扇の要なのだということも、今回聴いてよくわかった。この人の絶対に濁らない、澄んだ響きには、よい意味での隙間があり、そこに弦の三人がそれぞれの居場所をみつけている。モダン・ピアノなのに、奇跡のように出しゃばらない。この人が、四人のつくる音楽に広がりと奥行きを与えている。ケラスが言っていたような、ピアノならではの強大な拘束力と支配力をもちながら、それを絶妙にコントロールしている。四人がそれぞれの音を響かせるだけの空間を確保し、しかし離れることなく、親密に結ばれあっている。
その意味で、エベーヌのオリジナル・メンバーだったヴィオラのマチュー・ヘルツォークと、同じような存在なのかもしれないと思った。マチューはリード・ヴォーカルという役割も大きかったけれど、新メンバーに変わった昨年の来日公演では、それ以上に四人のつくるリングの大きさ、互いに離れようとしながら互いに牽引しあう強烈な作用と反作用のような、緊密なのに豊かな遠近感、それが失われていた。
それと同じで、モメルツがもし若いピアニストに代わってしまったら、いかに新入りが腕利きであっても、アンサンブルの密度と広がりを再構築するには、大変な苦労と時間を要するに違いない。
偶然に出会った四人が、いつか別れる日までのほんの束の間、奏でてくれる、かけがえのない音楽。それが鳴り響く場に立ち会えた幸運。
それは、後半のピアノ四重奏版の《展覧会の絵》(フォーレ四重奏団&グリゴリー・グルツマンによる編曲)でも明らかに。
ムソルグスキー原曲のピアノ独奏の響きを、きかせどころで活かしつつ、ラヴェルのあの天才的なオーケストレーションを巧みにピアノ四重奏にリダクションして、色彩とハーモニーを加えていく。重要なのは、オーケストラ版では薄れた土俗的なグロテスクさや陰惨さを、より残してあること。まさしくピアノ独奏版とオーケストラ版の中間、ポテン・ヒットのように、ピアノ四重奏しか入れない隙間のフィールドに、新しい響きが生まれていく。
二年前のアンコールで〈卵のからをつけたひなの踊リ〉を聴いたときから願っていた全曲をついに聴けて、とても嬉しかった。
こういうものがまだディスクになっていないこと、そしてブラームスのピアノ四重奏曲第一番を最低の音質でDGが出してしまったことなど、レコード会社は何をやっているのかと、強く思う。
順序が前後したが、後半の最初に演奏された細川俊夫の新作《レテ(忘却)の水》も、彼岸に誘う流れのように、こちらを漂わせ、ときに深みに引きこむ、音でつくられた淵。
生者はつねに悩み、死者はもはや悩まない。
聴くのが二回目、ということもあったと思うが、五日の方がよりこなれていたようで、安心して音に身を委ねることができた。
書き忘れたが、ヴァイオリンのエリカ・ゲルトゼッツァー孃は一日の本番後にホテルで転んで、靱帯を痛めたとか。ギプスで固めて翌日の西宮公演をこなし、三日からは横浜で三連続。その間、舞台以外は車椅子の生活だったそう。舞台では松葉杖と片足移動。それでも普段と変わらぬ演奏を披露してくれた、そのプロ意識に感謝。
十月九日(日)キは霧隠のキ
『真田丸』第四十回。ついに名前が出た「なんとか官兵衛さん」。大笑い。もちろん如水。しかしあっちは、とてもではないがそこまでライバル視するほどの作品水準ではなかったと自分は思うけれど、つくり手の心理としてはそうはいかないのだろうか。
大坂城を出た片桐且元が入城を誘いにくる、という仕掛けはさすが。信繁が三成以下の秀吉大好きキッズの最後の生き残り、まったく目立たないけど本気の生き残りであることを知っているのは、現在の大坂城内では、茶々以外は且元ただ一人のはずだから。
すごく素敵な回で、この一回の信繁の心理を描くためにそれまでの三十九回があったような、というのがじつに贅沢。
それはきりの、あの促しの言葉。あれはこの一年間の物語の、ターニングポイントとなるセリフだった。
『江』や『花燃ゆ』のあの最悪のヒロインたちの、かなり嫌味なパロディなのではないかといわれてきた、長澤まさみ演じるきり。今回のセリフで、そうではないことを証明した。彼女は賢しらな傍観者(けっして実現されない正しい意見の持ち主、結果から逆算して捏造された預言者)ではなく、平穏無事を最優先する家庭的な女でもない。
『花燃ゆ』がどうにもならなかったのは、「幕末男子の育て方」といいつつ、女性の脚本家たちが吉田松陰や久坂玄瑞などの志士たちの思いと行動に対して、一片の愛着も理解も持てなかったこと。だから、松陰も久坂も家族の平穏な日常を壊す、傍迷惑な独善的テロリストにすぎず、それを忘れさせるほどの魅力がなかった。それでは結局、跳ねかえってヒロインもまた魅力と個性を失ってしまうことに、気がつかなかったらしい。
蛤御門の変の直前に椋梨藤太の妻が、お前の夫は藩全体を災厄に巻きこむ愚か者だとヒロインをやりこめたが、あのドラマではどうみても、その意見の方が正しいとしか思えなかった(そのくせ久坂は、京に女つくって子供まで産ませる、共感しようのないダメ人間だった)。
きりは違う。平穏な余生を捨て、才を振るって歴史に名を残せと促す、英雄を召喚する女神になった。仕方ないといいつつ促してくれる、男にとって都合のいい、ロマンチックな存在かもしれない。都合のいい母親のような存在であるけれど、ともかくも本物の「戦国男子の育て方」をやってのけた。これはやはり脚本家が男だからか、という気がする。だからこそ自分も共感してしまうが(笑)。
私が胸を焦がした、若い頃の源次郎さまはどこへ行ったの、というようなセリフも意味深かった。
これまでを思い返すと、ひょっとしたら、最初の上田の合戦で、「敵も味方も最小限の犠牲に抑える」と梅(黒木華)に教えられ、そしてその梅を死なせたときから、源次郎の才覚は消えたのかもしれない。つまらない無名の脇役、戦嫌いの人生を送ることになったのかもしれない。九度山は、そのゴールだったのかもしれない。
きり、この話ではどうやら霧隠才蔵の暗喩らしいきりは、ついにその呪縛を解いたか。死者には勝てないと春(松岡茉優)にいわしめた、死者の呪いを解いたか。それとも、生きていたら梅がそう言っただろう促し、もう口にはできない促しを、代りに言っただけなのか。
さらにあるいは、まったく女神などではなく、茶々の呪いを成就させる魔女だったのか。
それらの答えはこれからの、英雄真田幸村の大坂での生きざまと死にざまが、示してくれることだろう。
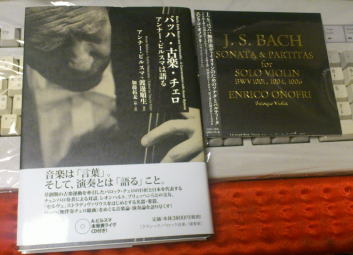
写真は、一枚目がビルスマの本とオノフリのCD。コンセルトヘボウ管のチェロ奏者だったビルスマがピリオドに目覚めていく過程などが、渡辺順生との対話で語られていく。二人の一九九九年のライヴCD(佐々木節夫メモリアルコンサート)がついているのも魅力。まもなく実演に再会できるオノフリは、バッハの無伴奏のソナタ一番とパルティータ二、三番の三曲。

二枚目はポンド安で買いまくっているイギリスのCD店の購入物から、まだ日本で発売予告が出ていないもの二点。ネゼ=セガン指揮シュターツカペレ・ドレスデンによるブルックナーの交響曲第三番初稿(二〇〇八年ライヴ)と、フランスのヴァイオリン奏者ジュリアン・ショーヴァンが二〇一五年に結成したピリオド・オーケストラ、ル・コンセール・ド・ラ・ローグによるハイドンの《王妃》など十八世紀作品。ローレルと組んでル・セルクル・ドゥラルモニーをやっているショーヴァン、これはコンマス席から指揮。ピオーがゲスト参加。
十月十五日(土)雪解けと自由
イザベル・ファウストをサントリーホールで、ノット指揮東京交響楽団とのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を聴く。素晴らしい出来。
同じサントリーホールでは一週間ほど前、アンネ=ゾフィー・ムターが大ホールで三回の演奏会を開いていた。ファウストとムターは同じドイツの女性ヴァイオリニストながら、本当に対照的な存在なのが面白い。
ムターはまさに二十世紀後半の美学を引き継ぐ、二千人級のホールいっぱいに艶麗な響きを鳴りわたらせることが出来る人。アメリカのマーケットにも通用する、大衆教養主義的な、カラヤンが偏愛したのがよくわかるスタイル。
ファウストは違う。細身の響きで、言葉を語らせるようにヴァイオリンを歌わせる人。その音楽は、注意深く聴きこむことを聴衆に求める。バロック・ヴァイオリンと弓(チェンバロとのソナタでは緩急の楽章で二本を使いわけた)を用いた、チェンバロのベザイデンホウトとの彩の国さいたま芸術劇場での十日のバッハ演奏会でもその魅力を堪能したが、サントリーホールに登場した今日は、その個性と特徴がより明確になった。
ここで彼女のベートーヴェンを聴くのは二回目で、最初は三年前の二〇一三年十月にビエロフラーヴェク指揮チェコ・フィル。ピアノ版に基づくティンパニ伴奏付きカデンツァも同じだったが、今日の方が断然個性が際立って、素晴らしかった。前回はよくいえば伝承的な、雰囲気に任せた曖昧なスタイルのオーケストラだったから、線の細い独奏が一人で色々やっている、という孤立感があった。
今日は違う。ちょうどCDの新旧の録音(ビエロフラーヴェク&チェコ・フィルとアバド&モーツァルト管)が違うのと同じように。
弦が十二型の対向配置(コントラバスが中央最後列だったのは、後半がショスタコーヴィチの交響曲第十番なのでロシアのオケの伝統的配置に倣ったのか、それとも古い配置ということで採用したのか、その両方か)で、ナチュラル・トランペットに小型ティンパニを用いた、ピリオドを意識したスタイル。
アクセントを明快にした歯切れのいいオーケストラの歌いかたが、ファウストの奏法にぴったりで、彼女をけっして埋没させない。互いに音を聴きあい、聴衆にも耳をそばだてさせ、対話して、鮮度の高い音楽が生まれる。
東響がスダーンの置き土産でモーツァルト・マチネをやっている甲斐が出ている、と思った。
ところで、サントリーホールでの十二型のベートーヴェンは、実は昨日も聴いている。カンブルラン指揮読響による交響曲第八番。今回のカンブルランの三回シリーズは、シューベルトを軸にしてウィーンとパリの音楽を聴く、というようなテーマのようで、昨日は他にロザムンデ数曲とベルリオーズの《夏の夜》。すべてを十二型で、純度の高い響きで爽快に鳴らした。強い特徴をもつ演奏ではなかったけれど、これだけきれいにホールに響くというのは、聴衆だけでなく、楽員にとっても気持ちのいいことなのではないかと思った。
ヨーロッパでは、ラトルもイヴァン・フィッシャーもベートーヴェンの交響曲(第九以外)を十型や十二型でやっていて、モダン楽器もこのくらいの編成が当然になりつつあるらしい。
それを受けるように、今日も十二型。協奏曲なので編成を小さめにしただけかもしれないが、ノットが今後もセミ・ピリオドで古典派をやってくれるなら、大いに楽しみ。来シーズンには《英雄》と八番、それにハイドンとモーツァルトが凝ったカップリングで含まれている。
後半は、ショスタコーヴィチの交響曲第十番。こちらは十六型。前述したようにコントラバスを中央最後列に並べる、ロシアン・スタイル。
今日は、昼十二時からマリインスキーの《エフゲニー・オネーギン》だった。十二日の《ドン・カルロ》のさえない演奏とは段違いの、まさに水を得た魚のようにオケも歌手も合唱も舞台も、すべてが生き生きした上演。帝政ロシアの雰囲気を味わったあとで、ソ連の「雪解け」の交響曲。
先月二十六日にきいたロジェストヴェンスキー指揮読響の演奏は、悠然としたテンポでオーケストラをたっぷりと鳴らし、なんとも陰惨なユーモアをたたえたものだった。前半がロシア・アヴァンギャルド時代の作品、後半がスターリンの死を契機に完成・初演されたこの交響曲という組合せを、ソ連時代の生き証人みたいな老巨匠が読響の高い能力を活かして、盛大に鳴りひびかせていた。
ノット&東響の演奏は対照的。二楽章など限界に挑むように速い。みなぎる焦燥。古典派を得意とする一方でこのオケの弱点は、星飛雄馬の球質の軽いボールのように、響きの重量感に不足する点だが、この場合はこれでいいと思う。ロジェヴェンが恐竜なら、ノットは疾走する小動物。スターリンの粛清と果てしない人間疎外から、必死で逃げる。
ところで、在京オケで明快なテーマをもった曲目構成をするのは、カンブルランとこのノット。今日の二曲も何らかの関連があるはず。
ひとつ思ったのは、アンダンテから終楽章のアレグロへの加速。十九世紀のベートーヴェンは勇壮で激励的だけれど、二十世紀のショスタコーヴィチは、とてもそうではない。その対照と落差を聴けということなのか? と勝手に想像。
そこから連想。この曲を六十二年前の一九五四年十一月に日本初演したのは、上田仁指揮のこの東響だった。同日に演奏されたケンプ独奏の《皇帝》第一楽章は録音が現存してCD化されているが、タコ十は不評だったこともあるのか、残っていないらしい。演奏もうまくいかなかったとか(《皇帝》を組み合わせるという発想は、今日と似ている)。
同年の四月、同じコンビが《森の歌》をフルサイズ初演(前年京都での日本初演は、オケ四十人の縮小編成)して、聴衆から圧倒的な支持を得て、日本独特の《森の歌》ブームの始まりになったのと対照的に、十番はあまりに暗かったか。
社会主義リアリズムは明るくわかりやすく、対して「雪解け」は暗く難解。それが「自由」というもの。
話の続きは来年出る『演奏史譚一九五四/五五』で、とさりげなく宣伝。
十月二十一日(金)バッハまたバッハ
トッパンホールでフライブルク・バロック・オーケストラ(FBO)第一夜。
昨日までムックの仕事でカール・リヒター漬け。リヒターのマタイ受難曲とミサ曲ロ短調とクリスマス・オラトリオの全録音を聴き較べるという、骨の折れる仕事。
マタイの一九七九年盤は単に不出来というよりも、今ききなおすと一九八〇年前後の世界的な演奏様式の潮流にきちんと乗っていたものでもあるとか、一九五八年盤の「げにこの人は神の子なりき」の合唱は、何度聴いても奇跡としかいいようがないくらいに物凄い(本当に、天から光が降り注いでくるような響き)とか、あらためて発見は多かったけれど、ものすごく疲れた。
それに続いて今日は、別のムックの仕事で、ラトルのマタイとヨハネの映像をみなおす。ピーター・セラーズ演出のこのシアターピース版はとても面白いし、いつかサントリーホールなどで体験してみたいものだけど、やっぱり疲れた。
もうバッハはいいス、といいながら、しかし実演までバッハ(笑)。
ただしFBOのプロは一捻りしてあって、休憩をはさんで前半後半をそれぞれ三曲のブロックとして構成してある。ヴィヴァルディの序曲、バッハの協奏曲、ヘンデルかコレッリの合奏協奏曲という、三曲のひとつながり。
今回は弦楽とチェンバロのみで十五人という、FBOの最もシンプルな編成なので、楽器の多彩さではなく、響きのグラデーションと独奏合奏のバランスの変化だけできかせる。トッパンホールの大きさだから可能なこと。そのなかでバッハが、他の偉大な作曲家にはさまれて相対化されていく、肩こりがほぐれていくような快感。二十四日も同様の曲目構成なので、また楽しみ。
十月二十三日(日)我は一過性全健忘
人生で初の入院。一晩で済んだが。
病名は「一過性全健忘」。
自分でかかって初めて知ったが、数時間分の記憶がスッポリと抜ける病気なのだそうだ。ただ、その最中の自分の感覚でいうと、その間、十分ほどで記憶がリセット、上書きされて、その前のものが消えるのをくり返す感じ。その間、一応そつのない対応や行動を、ほとんどただの反射行動として行なっているが、長時間一緒にいる人は異常に気がつく。
結果として後からふりかえると、数時間分の記憶がスッポリと抜けていて、その間は断片的な映像や音声のデータが、幼時の遠い記憶のように残っている、という感じ。
原因は不明で、ある日突然、誰にでも起こり、そして一度きりで再発しないという、不思議な脳の現象。
昨日は十八時から親しい方がたと新宿で飲み会、だったらしい(笑)。会場に向うべく家を出て、銀行で金をおろして出てきたら、二人のフェイスブック友達の方が声をかけてくださった。偶然、お仲間と近くで集まっておられたらしい。「よかったらお茶でも」と誘ってくださったのに「いまから飲み会なんです」と断らざるをえなかった。
正直、このあたりから世界と自分の間に距離を感じるというか、長い管を通して外界を眺めているような「妙に遠い、視界の狭い感覚」があった。
地下鉄に乗り、新宿駅ホームの後ろ側の階段だな、出たらサブナードに入って歌舞伎町の方だな、と思いながら、店の前までついたことまでは、前述の狭い視界の映像とともに記憶があるのだが、ただ、映画の移動シーンのように、途切れ途切れにカットが飛ぶような感覚があった。すでに間歇的な夢遊病状態に入っていたのだろう。
そして店に入り、ジャケットを脱いで椅子の背にかけた映像を最後に、数時間の記憶が飛ぶ。あとは断片的な映像と音声データがメモリーにあるだけで、気がつくと山の神に連れられて、慶応病院の救急外来に座っていた。
あとで飲み会の参加者の方にお話を聞くと、途中まではいつも通りに話していて、何の異常も感じなかったが、二時間ほどしたとき、トイレに行くような感じでジャケットをおいたまま、席を立ったそうだ。
ところが長時間戻らないので不審に思い、近辺を手分けして探したが見つからない。しかたなく私の部屋の留守電にメッセージを入れたら、帰宅した私から返電があった。置いていったジャケットを最寄駅まで届けてくださることになり、自分は改札で受け取ったのだそうだ。だが知っているはずのことを忘れ、無意味な質問をしたりしたため、どうも様子がおかしいと感じられたそうだ。(飲み会はこうして私の勝手な行動のために、後味の悪い終りとなった。飲み代も払っていない。本当に申し訳なし)。
一方の私。九時頃に帰宅して、山の神に声をかけたという。悪酔いして頭打った、財布を無くしたのでカード会社に電話して止める、などと言ったという。どうやら財布を持っていないので地下鉄に乗れず、三、四十分の道を歩いて帰ったが、途中で注意力がよほど散漫になっていたのか、階段か坂道かで仰向けに転んで、頭と肘を軽く打った模様(車に跳ねられたりしなかったのは、不幸中の幸いだった)。
そのあとしばらくして「店の人が届けてくれたので駅まで行ってきた」(友人の方がわざわざ届けてくれたのに、なぜかそんな言い方をした。もう忘れかかっていたのだろう)とまた山の神に声をかけ、「あれ、さっきも自分は声をかけたっけ?」と言い出したので、こりゃおかしいと山の神が動き出した。見ると、頭頂部の後ろに傷がある。これで頭をやられたかと、病院へ。
普通に歩けるのでタクシーで病院に行くことにし、それなら保険証を用意すると言って自分の部屋に探しに行き、山の神に渡している。その場その場の応対はきちんとできるのに、十分ほどで記憶が上書きされる状態。コンピューターでいえば、メモリー媒体へのアクセスエラーが起きているみたいな感じで、何度も同じ質問をし、何度も謝ったという。星新一のショートショートに出てくるロボットとかにありそうな性能(笑)。
CTスキャンやMRI検査の結果、脳梗塞などはないので、典型的な一過性全健忘と診断され、一晩入院。生まれて初めての病院食を朝と昼。言われている通り、今の病院食は充分に美味しい。
数時間で回復するとされる通り、自分の記憶はMRI検査のあたりからはっきりして、後はつながる。八時間くらいでメモリーへのアクセスが通常に復帰したらしい。翌日午後に退院して、帰宅。
この飲み会の前々日の木曜まで、ムックのカール・リヒターの文章が遅れに遅れ、ようやく仕上げたところだった。マタイ受難曲とミサ曲ロ短調とクリスマス・オラトリオのリヒターの全録音を聴き較べるという仕事。
そのあと、別の媒体のために二十五枚ほどの原稿を土曜昼まで一日半で大急ぎで仕上げるはずが、先方の方針転換で、急遽中止。
この病気はストレスが原因ともいうけれど、執筆中止は収入減に直結するとはいえ、同時多発でもしない限り、ストレスにはならない。自分の場合はむしろ、予定にぽっかりと穴があいて気が緩んだために、こんな病気が出たのかも。
あるいは、五十歳代になって急激に衰えた、リヒターの呪いか(笑)。行きつ戻りつする一九七九年最後の来日時のゴルトベルク変奏曲の、あの痛ましくも夢幻能のような世界に、自分はワキとなって囚われたのか。
さらに妄想すれば、今年は春に能楽に俄かに興味がわいて国立能楽堂に通うようになった。山の神は千駄ヶ谷の東京体育館の屋内プールにウォーキングに通っている。慶応病院まで加わって、よほど千駄ヶ谷~信濃町に縁がある年。
このあたりの土地の神(シテ)が、俺も「帝都クラシック探訪」に加えて弔えといっているだろうか。それは場所的に無理だと思うが。
再発はないとはいいながら、一応、今週中に再度のMRIと脳波の検査を受ける予定。
それにしても、もし怪我もせずに帰って、山の神に気づかれずに一晩寝ていたら、あれ、昨日のこと憶えてないぞ、酒のせいか、くらいで済ませて病気に気がつかず、無断で帰宅したことを後で聞いて驚き、ただあやまるだけだった可能性が高い。
(一過性全健忘については、松田脳神経外科クリニックの以下のページの説明を参考にした)
http://www.matsudaclinic.jp/disease/409/
十月二十四日(月)影法師、大いに騙る
昨夜の一過性全健忘の最中の飲み会、途中の録音が残っていたそうで、参加者の方がデータを送ってくれた。
参加者の一人が片山さんだったので、ICレコーダーに、その面白いお話(シン・ゴシラなどのお話)のついでに、一過性全健忘の発症最中の、自分の話も録音されているというわけ。
こんな録音がありますと、その内容が書かれたメールを見た瞬間、片山さんのお話の内容の最初の部分の音声と、机の上に置かれたICレコーダーという画像が、脳内で突如としてアクセス可能になって、甦ってきた。お話をうかがいながら自分も言いたいことを思いつき、それを脳内でまとめながら、切り出す適切なタイミングをうかがうという、能動的、企図的思考をしていたので、簡単に戻ってきたのだろう。
それに対して、相槌を打つのに近い、単に反射的な反応や言動を自分がした部分は、やはりまだ記憶が戻らない。
自分が無断で店外へ出ていく前後も録音されているそうなので、その前に「我がドッペルゲンガー」がどんな言動をしているのか、知るのは楽しみのようでもあり、怖いようでもあり。一過性全健忘では、発症中の記憶は戻らないものらしいが、もしかすると、それですべてを思い出すこともありうるかもしれない。
時間ができたら、聞いてみるつもり。
夜のフライブルク・バロック・オーケストラ第二夜は、MRIの再検査もあって断念。
十月二十八日(金) 全健忘一過
一過性全健忘のことをフェイスブックに書いたところ、たくさんの方からお見舞いの言葉とイイネをいただく。本当に心強い。御陰様でその後は異常なし。
退院二日後の火曜日は、朝のミュージックバードの番組収録に始まって、「レコード芸術」編集部で「名盤鑑定団」最終回に参加、そして夜は上野で、ウィーン国立歌劇場の《ナクソス島のアリアドネ》初日。朝から晩まで出っ放しなのはきつかったが、偶然にもそれぞれの場所で、土曜夜に直接間接にご心配をかけた方々のほぼ全員に次々とお会いすることができ、間を置かずに直にお詫びを言うことができたのは、何者のお導きなのかわからないが、ありがたいこと。
他にも、友人知人の方々が各所で次々と声をかけてくださって、こんなに人気者だったことはないというほど(笑)。嬉しかった。
そして今日は慶応病院で脳波の検査。眠って結構ですといわれたのに完全には眠らず、半睡の中で、三十年前のかつての家近くの奥沢のゲームセンターと、そこで友人と深夜に遊んでから帰る動作を突如として思い出して、想いを馳せる。
そのあと、病院内の帝国ホテルのレストランで昼食。ここは十一階で見晴らしがよく、眼下には南の国立競技場の建替え現場が。一枚目はその写真。工事はあまり進んでいない。左奥の盛り上がった斜面が、戦前の神宮競技場以来の、地形を利用したスタンド部分の名残なのか。

写真の二枚目は今日届いた、ポンド安万歳のディスクから。左上はアラルコン指揮のミレニアム・オーケストラが、一七八三年ウィーンでのモーツァルト主催の演奏会を再現した二枚組。

右上はサラステ指揮ケルンWDR響のブルックナーの交響曲第八番。骨太な指揮が魅力なだけに楽しみ。
右下は、エロイーズ・ガイヤール率いるアンサンブル・アマリリスによるペルゴレージのスターバト・マーテル。ヨンチェヴァとカリーヌ・デエの独唱。
そして左下は、コパチンスカヤとセント・ポール室内管の『死と乙女』。弦楽合奏に編曲し、楽章の合間にダウランドやジェズアルド、クルタークの曲が挿入されるという、コパチンスカヤならではのアルバム。ほかに室内アンサンブル版の幻想交響曲とか、CD界はまだまだ意気盛ん。
十月二十九日(土)刊行決定
中川さんから、『演奏史譚一九五四/五五』の刊行が正式に決まったとの連絡あり。エピローグやディスクのデータ、まえがき、あとがきなど追加部分に取りかかる。
十一月六日(日)憧れと哀しみと

二か月近く前の話だが、デアゴスティーニから出ている「東宝・新東宝戦争映画DVDコレクション」。九月十三日に出た七十号でついに完結となった。その最終号が一九四三年三月公開の『音楽大進軍』。その名のとおり、戦争映画ではない、戦意高揚でもない、音楽慰問映画というべきもの。
南方の占領地の、それまでアメリカ映画を見ていた層の住民を教導するためにつくられた音楽映画、ということなのだが、はっきり言うとそれを口実にして、戦前から日本人も憧れていたハリウッド風、そのままの娯楽音楽映画をつくってしまったものに思える。
東宝映画、その親会社の阪急と小林一三のもつ洗練された欧米趣味、モダニズムが、戦前と戦後のあいだの戦乱期にもちゃんと生きていたことがよくわかる。その意味で面白く、哀しい(その憧れの相手と戦争やっているのだ)画面。
とにかく、日本にも西洋風のしゃれたコンクリの建物や景色や音楽があるということを、これでもかとばかりに強調してくる。このシリーズの常で解説がしっかりしていて、制作の経緯やロケ現場もきちんと説明してくれるので、本当にありがたい。
主人公の古川緑波は銀座の楽器店の社員で、かれが南方向けの音楽大慰問団を思いつき、実現させるまでのコメディ。その楽器店はヤマハか山野のロケかと思えば、これがそうではなく、一九三五年増築の日本橋三越本店の中央ホールを借り切って、楽器店に仕立てている。なぜかといえば、ここの名物、一九三〇年製ウーリッツァー社のパイプオルガン(まだ日本に数台しかなかった)の演奏シーンを入れるため。
さらに西洋風の高原をバスが進む場面は、伊豆の十国峠。見晴らしのいい、気持ちのいい景色を走る自動車道路は、すでに戦前に整備されていたのだ。
そして、伊豆のホテルで傷病兵のための慰問音楽会が行われるのだが、これは大倉財閥がつくった名門、川奈ホテル。現存する一九三六年完成のあのしゃれた建物、半円形の明るいラウンジと大階段の前に、ずらりと傷病兵が並ぶ不思議な画面(この傷病兵たちは撮影のために伊豆の療養所から連れてきた、本物なのだそうだ)。この表紙写真の右側、上から二枚目の写真の奥に見えるのが、その川奈ホテル。
東宝撮影所正門も登場するが、わざわざマット合成で豪華なビルを描き足して「東洋のハリウッド」ぽくしてある。消えてしまった西洋風景観として、丸ビル周辺や旧帝国劇場も映る。
音楽家は辻久子、平岡養一、桜井潔などが実名で登場して演奏。楽しいのは藤原義江の場面で、箱根の山中牧場で乳牛に囲まれながら、《トスカ》第一幕の二重唱を歌う。
戦況が本格的に悪くなる前の一九四二年末に撮影して国内公開にこぎつけたものの、本来の目的の南方での公開は行なわれなかった。こんな「アメリカ臭」のある映画の輸出はまかりならんと、検閲に引っかかったらしいのだとか。
西洋から入ってきた文明の利器を用いて西洋と戦争している、その日本精神の不思議と不條理を、実感させる映画。
偶然にもこの映画のあと、山の神がテレビで録画した小津の『晩春』をみた。『音楽大進軍』のわずか六年後の一九四九年、占領下の傑作。
鎌倉と京都、空襲を免れた古い日本建築と風景の美を強調しながら、復興しつつある銀座や洋館など洋風の風景も映して、対照させる。この映画では染井能舞台での梅若万三郎による能の『杜若』の場面も有名だが、その前には巌本真理の東京劇場での演奏会シーン(音は聞こえるが本人は映らない)があって、やはり対照させられる。主人公の笠智衆はつねに日本風景のなかにいるが、娘の原節子が父と離れて単独で行動する場面は洋風の景色。
なぜか、唐と戦った白村江とか、元と戦った太宰府とか、そんな景色と精神に想像が飛ぶ。
十一月七日(月)百年、八百年
今夜はサントリーホールで「柴田南雄生誕百年・没後二十年記念演奏会 山田和樹が次代につなぐ~ゆく河の流れは絶えずして」。
いや面白かった。オープンステージ型のホールだからこその、シアターピースの響きの快感。全周から人の声が包み、揺れ動く。傑作《追分節考》と、音楽の歴史と西洋受容の自分史を重ね合わせた音楽絵巻のような交響曲《ゆく河の流れは絶えずして》。この作品を大正教養主義の精華だと称えたのは、片山さんだった。それにしても今年は、鴨長明没後八百年の記念年だったのか。
脳と耳に刺激を受ける演奏会ということでは、今年のクラシックではいちばんだったかも。
柴田さんがユーロポイドからモンゴロイドに音楽活動を転換した、つまりアジア音楽に目を向けたのは五十三歳の年だったと、プログラムにある。自分と同い年だという事実に、何か励まされるような感覚。もちろん、こんな「知の巨人」と自分ではまるで比較にならないが。
脳に刺激を受けるといえば、今日は一階席だったのだが、前半終了後の拍手のなか、二階LC席から袋が降ってきて、斜め後ろの女性客に命中。中にCDが入っていたそうで、大事に至らなかったのは不幸中の幸い。自分だったら頭に当って、また健忘症になるところだった。
あとで若い男性が取りにきたとき、謝るより先に「ぼくのCDどこですか」と言ったというので、後列のご婦人方が怒っていた。LC最前列だと一階席とそれほど高低差がないからまだしもだが、二階正面からの落下だったらと思うと、ちょっとゾッとする。
そういえば、先日の一過性全健忘を起した飲み会の席で、初めてお会いして名刺を交換したのに、私があっぱらぴーになって忘れてしまった方が、今日の演奏会後に「初めまして」と声をかけてくださった(笑)。面白いもので、お顔を拝見した瞬間に、あれ、たしかにこのお顔は前に見たことがある、と記憶がうずいた。脳の不思議。
十一月九日(水)ポケット・マーラー5
能を一か月も見に行けていない。そろそろ禁断症状。今月は平家物を中心に三回行く予定なので、あと少し我慢。
『元老 ──近代日本の真の指導者たち』(伊藤之雄/中公新書)という本を読む。日本の大衆の民度を信用せず、首相を自分たちで選任していた維新以来の元老たち。ポピュリズムはどこへ行く。

ドイツのJPCから、クラウス・ジモン指揮ホルスト・シンフォニエッタのマーラーの交響曲第五番の室内アンサンブル版のCDが到着。ジモンは近年のポケット・マーラー運動の仕掛人の一人として第九番や第四番、第一番(これは未録音)の新規編曲を手がけている人だが、不思議と自身の率いるホルスト・シンフォニエッタでのディスクはなかった。第五番でようやく登場。十八人編成。
シェーンベルクが主催した私的演奏協会版に較べると編成が大きい。響きの薄さという弱点はかなり解消するものの、それならオリジナルのフルサイズを聴けば充分では、という問題も生じる。
それを承知で、二十人前後という、室内オーケストラよりも小さいバロック・オーケストラみたいな編成で、かれらは何をしようというのか、マーラーはあくまでそのレパートリーの「売れ線」の一つにすぎないのだろうが、ともあれ巨大交響楽団の維持が難しくなるかもしれない近未来に対して、かれらが模索しているものが、自分にはとても興味深い。
物は段ボールの箱の中にCDとブックレットと録音時の写真とマーラーの写真が入った、手作り風ボックス。ハイレゾがダウンロードできるコードも手書きで同封。五番なのにジャケに大きく「3」と書いてあるのは、発売元のbastille musiqueの三種目のCDということらしい。
ポケット・マーラーのCDも、別人の編曲も交えてこれで四、五、七、九と四曲。ほかにシェーンベルク時代の四番と《大地の歌》。
十一月十日(木)柴田南雄とグレツキ
ジンマン指揮NHK交響楽団をサントリーホールで。
東京の連日の演奏会の玄妙さ、まったく無関係に企画された複数の演奏会が偶然に結びつきあって、さながら統一テーマのツィクルス、音楽祭をなしてしまう面白さは、私がいつも書いていることだが、今回もそれが起きた。
私が今日の前に聴いた演奏会は、三日前の同じサントリーホールの、山田和樹指揮日本フィルによる「柴田南雄生誕百年・没後二十年記念演奏会」だった。
この結果、私は柴田南雄の交響曲《ゆく河の流れは絶えずして》と、グレツキの交響曲第三番《悲歌のシンフォニー》を連続で聴くことになった。
面白くてたまらないのは、この二曲がまるで腹違いの兄弟のようであること。
前者は一九七五年、後者は一九七六年作曲の一年違い。どちらも石油ショックのあと、六〇年代の前衛音楽の熱狂、社会全体の熱狂が収まって、世界に閉塞感が広がった時代に、新たな道を求めてつくられた。
共通するのは歴史への視点。中世の音楽とその歌謡性への注目、声楽の導入、そして軽侮されていた「交響曲」というジャンルの復活。バックボーンにはマーラー(グレツキの場合はショスタコーヴィチを間に挟んでいるかもしれない)。
それぞれの国と言葉の歴史から、歌詞が選択される。柴田は鴨長明の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」をメインに「無常」を歌い、グレツキは中世の聖歌、アウシュヴィッツの少女の言葉、そして民謡を用いて、母が子に先立たれる嘆きという「喪失」を歌う。
未来を求めて走ってきて、つまずいて止まった二人の作曲家が、一九七〇年代半ばに歌入りの交響曲をつくったとき、それぞれに選んだテーマが、「無常」と「喪失」。これを連続して聴ける、今の東京を生きる快感。
そしてこの「無常と喪失」、今の自分の興味の対象へ思いっきり我田引水するが、能の名作の重要なテーマそのものでもある。修羅能の多くが原作とする『平家物語』は、無常観の総本山みたいな作品だ。母が子の死を嘆く作品といえば、なんといっても傑作『隅田川』がある。つまりはどちらも「もののあはれ」。
グレツキを聴きながら、この人は『隅田川』か、それを原作とするブリテンの《カーリュー・リヴァー》を意識しているのではないかと考えていた。
第二楽章の「お母さま、どうか泣かないでください。天のいと清らかな女王さま。どうかいつも私を助けてくださるよう。アヴェ・マリア、恵みに満ちた方」と、子供が母に対して歌うところは、子の幽霊が「南無阿弥陀仏」と唱えながら現れて、母がその手を取ろうにも幻ゆえに触れることのできない、『隅田川』の悲しいクライマックスを想起せずにはいられない。
印象的なのは第一楽章の開始と終結。弦五部の各パートをさらに二つに分割、コントラバスに始まって第一ヴァイオリンまで、十の声部が順繰りに登場して音を高め、母の歌を引き出し、その後は順繰りに下がっていく。水底から出て水面に現れ、そして水底へと沈む、幻のような母の祈り。音楽的にはこの第一楽章がいちばん面白かった。

ところでいま、中村真一郎の『王朝物語』というのを読んでいる。竹取物語に始まって源氏物語で絶頂を迎える王朝~鎌倉期の物語群を、西洋の物語、小説と照応させながら解説するという面白い作品。まず西洋的教養の中で育った旧制高校出身のインテリが、後天的に和漢のアジア文化に興味を持って語るという図式は、柴田南雄の創作活動にも重なっていて愉しい(柴田が二歳年上の同世代)。
中村によると、「無常」という感覚は平家の全盛と滅亡を体験したあとの、鴨長明や定家の時代において顕著になるもので、それ以前の紫式部とそのあとの二世紀ほどは、無常ではなく世代交代による反復があるだけで、藤原氏全盛の社会がずっと続くように考えられていた。
こういう王朝時代と鎌倉期では、源氏物語のとらえ方も、かつては繰り返しの参考書だったのが、失われた黄金期への憧憬の書へと意味づけが変ってきて、その亜流物語の世界観にも変化が生じる。鎌倉時代の京と公家の生活をどう考えるかは、中村の本が書かれた一九九〇年前後と現在の研究では変化がありそうだけれども、刺激される箇所多し。
十一月十二日(土)困った共時性
同日同時刻の演奏会の重複というのは頭の痛い問題、東京だからこその贅沢な悩みなのだが、今とりわけ困っているのが、十二月一日の木曜日夜七時。
オーチャードのゼッダ指揮藤原歌劇団のロッシーニ演奏会、トッパンホールのタメスティの無伴奏、そして浜離宮のドゥバルグ・リサイタル。どれも行きたい。週末ならともかく、どうして平日にこんなに重なるのか。しかも休日なら午後と夜とかに時間がずれてハシゴできる可能性もあるが、平日だから全部夜七時。そして、どれもこの日一回しかない。
ドゥバルグは、ほとんど離れかけていたピアノという楽器への関心を引き戻してくれた人だし、今回は曲目もとてもいい。タメスティも前から好きなヴィオラ奏者で、聴いて損するはずがない。
とはいえ、ゼッダが指揮するロッシーニのカンタータ《テーティとペレーオの結婚》なんて、とてもではないが日本でもう一度聴けるとは思えない。あとの二人は若いからこれからも何かと聴く機会があるだろうから、やはりこれか。しかしもったいない…。
十一月十四日(月)日本一のつわもの!
昨日能に行って見られなかった『真田丸』の「完封」を録画で見る。
真田信繁、いや幸村一世一代の晴れ舞台、真田丸合戦。息子大介の謡曲高砂の陽動作戦に始まる戦術全体が第一次上田合戦の再現になっていて、やはり昌幸のあの合戦が、この二代目の原点であることが描かれる。それを日本中の武士が集まった大坂で、よりスケールを大きく、そして華やかに。かっこよかった。
一方で、籠城と決まった時点で勝利はないとみて、あとは終らせ方次第と考えていることが妻との会話で明らかに。そのためには局地戦での勝利がいる。山本五十六の、あの「やれと言われれば一年や一年半は存分に暴れてみせる」という言葉を思い出したり。
そしてきり。とうとう茶々の侍女になった。ということは、落城の日の山里曲輪にまで彼女は立ち会うのだろう。そこで茶々や秀頼や大介、あるいは毛利勝永に彼女が何を語り、行動するのか、今から大いに楽しみ。
それにしても、これだけ直感的な人間観察が鋭いのに、自分を必要としてくれる人間に対してはけっして好き嫌いでは進退せず、真摯に応接する女性というのは、じつに面白い。自分を必要とする素振りをおよそ見せない信繁への、あてつけがこの「歴史立会人」の原動力なのだろうか。
しかし、「あの赤備えは井伊直孝。井伊直政の息子。かれらにもここまでの物語があるのだろう」「いつか聞いてみたいものですな」とかいう問答は笑った。官兵衛にはきついが『おんな城主直虎』にはエール。そういや井伊直政も、ここまで一回も出さなかったような気が。
能は、金春会定期能を国立能楽堂で。櫻間右陣の『経正』で始め、野村万作の狂言『樋の酒』、佐藤俊之の『葛城』、山井綱雄の『一角仙人』。
『巴』があまりに見事で俄かファンになった右陣が出る、それも平家物、というので行くことにしたもの。
『経正』は、敦盛の兄で琵琶の名手だった平経正をシテとする修羅能。ただし筋立てが単純すぎ、人間造形にも陰影を欠くので、『巴』のような感動はない。しかし小柄な右陣の舞はやはり美しい。来年一月はこの会で『羽衣』をやるそうなので、これは見なければ。
『葛城』はシテの葛城の女神の装束が美しかった。歌舞伎の『鳴神』の原型らしい『一角仙人』は、最後に登場する子方二人の演じる龍神が可愛い。一角仙人を籠絡する旋陀夫人とのやりとりを、直接的な色仕掛けとしてではなく、両者の舞の足拍子の変化で暗示してしまうところは、さすがに能らしい想像にゆだねた仕掛け。ここはまた見てみたい。
十一月は温度が下がって能に向いた時期なのか、国立能楽堂ではほぼ連日誰かが公演している。そのせいかどうか、ワキ方や囃子方が疲れているようで、全体にいま一つ緊張感を欠いたのが残念。
十一月十八日(金)武智鉄二の遺産

写真は能と狂言専門誌「花もよ」から発売された『武智鉄二 古典は消えて行く、されど……』二十枚組CD付。
武智鉄二(一九一二~八八)という存在は、私などはその後半生の、妙なポルノ映画を作る人というイメージが強いのだが、前半生においては有名な武智歌舞伎をはじめ、歌舞伎、能狂言、オペラ、さらにそれらを横断した前衛諸芸術などの演出に手腕を発揮した、まさに鬼才としかいいようのない存在だった。
一九五五年を境とする、大坂での前半生と東京での後半生の大きな断絶(本人の中では繋がっていたのだろうが)が、没後二十八年となる現在でも、その評価と位置づけを難しくしている。
自分は『演奏史譚一九五四/五五』のなかで、一九五五年の朝比奈隆指揮関西歌劇団のオペラ《修善寺物語》初演の演出者として関心を持ち、さらに能に興味が出たことで、この人物の邦楽方面での業績へと興味が膨らんでいた。
そんなときに絶好のタイミングで出たのが、このセット。武智は元々、大金持ちの御曹司の評論家として活動をはじめた人で、邦楽や現代音楽のSPの大コレクターでもあった。その武智が一九七五年から七七年にかけ、鎌倉書林発行の月刊誌「78」(seven eightと読むらしい)に二十回連載したのが、義太夫と歌舞伎を中心に往時の名人のSP録音を紹介するエッセイ「古典は消えて行く、されど……」。
このセットはこの連載を一冊にまとめて詳細な注と解説をつけ、紹介された全録音をCD二十枚に復刻して、武智の文と実際の音を即座に、立体的に参照しあえるようにした、とても便利なもの。
武智所蔵のSPは現在早稲田大学文学部に寄贈されているそうで、その音源を主体に、足りない盤、痛んでいる盤は個人蔵で補うという、徹底したもの(それでも大隅太夫の『鰻谷の段』十面目だけがどうしても見つからなかったそうで、情報を募集している)。
いま、とりあえず一枚目の大隅太夫と鶴沢道八の「逆艪の段」と「松波琵琶の段」を聴いている。素人が聴いても惹きこまれる。音も聴きやすく、義太夫も三味線も生々しい、いい音。
ブックレットがCDサイズだと、収蔵には便利だけど老眼には読みづらくて読まない、ということになりがちだが、これは本がB5版なので読みやすい。セットで一万円という定期購読者向け価格も素晴らしい。
(12月27日追記) 目出たいことに、平成28年度(第71回)文化庁芸術祭賞のレコード部門の大賞を、見事受賞したとのこと
中身の詳細はここ。http://hanamoyo.heteml.jp/takechi.html
全体の紹介はここから。http://www.hanamoyo.info/
amazonで買うことも可能。
十一月十九日(土)闇を呪うよりも
早稲田大学エクステンションセンターのオペラ講座「オペラと現代の名指揮者たち」の二回目。
前回の加藤浩子さんのクルレンツィスに続き、今日は矢澤孝樹さんのウィリアム・クリスティ。オペラの視野を拡げてくれる老若二人の指揮者、熱のこもったお話がどちらも好評でうれしい限り。例年一枠の慶応枠を二枠にした甲斐があった。次回からは早稲田三枠で、パッパーノ、バッティストーニと遊軍。
そして今日は終了後の昼食の場で、矢澤さんと『真田丸』話で盛り上がる。こういう、普段は全然別の場所で生活している人間同士が「共有感」を味わえるのは、大河の、テレビのありがたさ。メディアの力。
クラシックではレコードでさえ、そうした共有感を味わいにくくなっているのが残念。東京とそれ以外で、空間だけでなく時間の差も広がりつつあるような。衛星ラジオのミュージックバードの新譜紹介では、少しでもその差を埋めたいと思っているが、これは思い上がりもいいところ。

家に帰ると、内外から購入品が届いていて、また嬉しくなる。写真の一枚目は本。左と中の二冊は、室町ものの選書。能のおかげで、すっかり室町野郎になってしまった。政治的には大混乱なのに、エネルギーに満ちた時代のような。
左は『「怪異」の政治社会学 室町人の思考をさぐる』。怪異、迷信に対し室町の組織や人がどう考え、反応したか。
中は『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』。今年のサントリー学芸賞〈芸術・文学部門〉を受賞した話題作。白拍子とは女性の舞手のことではなく、或るリズムのことを本来指していて、それが乱拍子というもう一つのリズムとともに、能楽に流れ込んでいく。
室町期の研究は、イデオロギー的呪縛をようやく離れてどんどん進んでいるようで、どちらも楽しみ。
そして右はBBCミュージックマガジン。これはとにかく附録のCDが聴きたかった。チェンバロのエスファハニがエンシェント室内管弦楽団(笑)、すなわちアカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックとともにバッハの《フーガの技法》を演奏したものとなれば、聴かないわけに行かない。今年の来日公演は聞き逃したけれど、エスファハニは、今いちばん楽しみなチェンバロ奏者の一人。

二つ目の写真はCDばかり。上左はフルシャ指揮バンベルクの《我が祖国》SACD。フルシャがシェフになっての第一弾。
その右も同じくシェフ第一弾、エラス=カサド指揮セントルークス管弦楽団の《冬の日の幻想》。エラス=カサドがチャイコフスキーをやるとは驚き。
下の右はヘンゲルブロック指揮の《エリヤ》。自分が不寛容の毒気にあてられたばかりのこのオラトリオをヘンゲルブロックが録音して発売するなんて、なんと素晴らしいタイミングか。
そして下の左は、これも現在の状況にあっているかもしれない、マリアン・アンダーソンの一九三九年、ワシントンのリンカーン記念堂でのライヴのレストア盤。アメリカの婦人団体がアンダーソンが黒人であることを理由にホールの使用を断ったことに端を発し、ときの合衆国大統領夫人エレノア・ルーズベルトの提唱によってリンカーン記念堂で野外演奏会が開かれた、そのときのライヴ。
ちなみに、誰か(忘れた)がエレノア・ルーズベルトを評した言葉、「闇を呪うより、闇に灯をともすことを選ぶ人だった」は、私の大好きな言葉。もとはどこかの諺らしい。そんなふうに清く正しくはとても生きられないが、いつかの目標。
十一月二十日(日)ラクリモーサで…
午後はすみだトリフォニーで、ハンスイェルク・シェレンベルガー指揮カメラータ・ザルツブルクと岡山バッハカンタータ協会による、モーツァルトの交響曲第四十番とレクイエム(バイヤー版)。
六‐五‐四‐三‐二の弦、モダン楽器による折衷的ピリオド・スタイル。ヴィブラートを抑えて音の減衰を速めに。今の自分にはこの規模とスタイルのモーツァルトが曲をいちばん楽しめて、しっくりくる。
指揮者も演奏者も肩肘張らず、緩めるときはふわっと抜いて、脱力することが音楽に余裕と奥行きをもたらす。日本の音楽家も、古典派以前をやるときはこの脱力法をもっと身につけてほしいと思ったり。
レクイエムではナチュラル・トランペットとバロック・ティンパニが参加。八十人強の岡山バッハカンタータ協会はピリオド・スタイルに慣れているようで、滑舌よく、がならずに美しい響き。
しかし面白かったのは、レクイエムのラクリモーサが終った瞬間、そそくさと客席を出ていくおじさんがいたこと。
これを見ていて、そうだ、昔の日本の清教徒的なモーツァルト好き(ピリオド以前の、新古典主義バリバリの時代)には、ラクリモーサまでしか聴かずにLPの針を上げちゃう人とかが、けっこういたということを思い出した。あのおじさんはその残党だったのだろうか。単に待ち合わせとか電車の時間とか、WCダッシュだったのかもしれないが、ラクリモーサまで聴いて、というのがいかにも意味深だった。
雷雨の中、自宅でLPを聴いていたら落雷、停電した瞬間が偶然にもモーツァルト絶筆のラクリモーサの八小節目だったという、ほとんどオカルトみたいな話を書いていた音楽学者もいたような…。
まあたしかに、その後は霊感が一気に失せたように音楽の魅力が減退することは、客席で聴いていても実感。モーツァルトはもういない。アンコールに《アヴェ・ヴェルム・コルプス》をやることでバランスをとる人もいるが、今日はやらず。
十一月二十一日(月)砲弾
『真田丸』四十六回「砲弾」みた。
真田信伊かっこいい~。かつて、兄を陰から支える自分に憧れた信繁に「ワシのようになるな」と忠告した信伊。まっすぐに生きる甥への満足と、ある種の痛み。途中からは真田本家と距離をおいて生きてきた男の、言葉にならない心の底。
もう一つの長い伏線、茶々と信繁の悲恋物語、大坂城物語も、次第に形を明快に。きりの表情だけが示す二人の関係。きりと、そして茶々の妹お初だけが、女として茶々の心を見抜いている(大蔵卿は入ってない?)。
そして、大きなテーマである「二代目はつらいよ」。秀頼も秀忠も信之も、みんなつらいよ。ところで星野源の声、誰かに似ていると思ったら岡本信人の声に似ている。いや、岡本信人は自分は好きな役者なので(『草燃える』の藤原定家とか最高だった)、これはほめてるつもりだが。
土曜に畏友矢澤孝樹さんと『真田丸』話でもりあがったとき、「結局、この物語の最大の謎は、なぜ大坂城にいるのか自分でもよくわからないという、信繁の心そのものなんじゃないか」という矢澤さんのご指摘がものすごく面白かった。
それについて自分でも考えていたら、なんと最終回は副題なし、だという。これこそ、信繁の心そのもの、なのかも。
そういえば砲弾。今回の『真田丸』のは破壊的な一撃。
昔の『風神の門』での、天守閣の屋根をぶち抜いてから長い階段をガッコンガッコンと落ちていき、最後に御殿の廊下をゴロゴロとボーリングのボールのように走って、大野修理の眼の前まで転がってくるという、あの演出もブラックで面白かった。しかも伊丹十三演じる大野修理の存在感が強烈で……などとやりだすと、昔話が停まらない(笑)。
十一月二十三日(水)少年神牛若丸
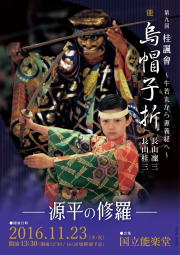
午後は国立能楽堂で、観世流シテ方長山桂三主催の「第九回 桂諷會 ~牛若丸から源義経へ~」。
最後にメインの『烏帽子折』を置き、前半は源平合戦の人々を題材とする七作品、『経正』『敦盛』『船弁慶』『奈須与市語』『碇潜』『清経』『景清』の仕舞や一調、語といった抜粋(オペラの扮装をせずに、タキシード姿でピアノ伴奏のアリアだけ歌うような感じ)が、観世銕之丞や野村四郎などの重鎮も交えて演じられる。
とりあえずは平家物語を軸に能に親しんでいこうとしている自分にとっては、素晴らしいご馳走。このような形の抜粋は、オペラ全曲の舞台上演とアリア・コンサートよりも大きな差があって、原曲を知らないと味わいにくいのだが、ともあれ壇の浦での平新中納言知盛の奮戦と入水を描いた『碇潜(いかりかづき)』みたいに、見る機会の少なそうなものが見られたのはありがたい。
そして後半の『烏帽子折』。鞍馬山から逃げた牛若丸が商人の金売り吉次の一行に混じって平泉に下る途中、美濃で大盗賊の熊坂長範の一味に襲われるが、たった一人で数十人を切り伏せ、最後に熊坂を討ち取って撃退するという話。
牛若丸はとにかく強い。絶対に強い。なぜ少年がこんなに強いのか。鞍馬山の天狗に秘術を習い(鞍馬天狗)、五条の橋で弁慶を倒し(橋弁慶)、ここで熊坂一味を全滅と、能やその原作では、牛若丸は滅多やたらに強い。不思議なのは成人後の判官義経が敏捷なだけで、貧弱で非力な存在になっていることだが、その理由は誰も説明してくれない。
これが日本古来の少年神信仰と関わっているのではないかとみるのは堂本正樹の『男色演劇史』だが、たしかにそうかもしれない。能では声変り前の子方(子役)を、さまざまな作品で一種独特に有効活用する。
ここで牛若丸を演じるのは長山桂三の息子の小学五年生、長山凜三。長山桂三は前シテで烏帽子屋ノ亭主、後シテで熊坂長範と、牛若丸を助ける役と敵役の二役を演じる。
ところで、熊坂長範が出てくる能の名作は二つあり、もう一つはその名も『熊坂』。これも先月国立能楽堂で見ることができた。こちらは幽玄能の形式で、薙刀を持った熊坂の幽霊があらわれ、一人きりで牛若丸との戦いを再現する。対して『烏帽子折』は現実能、すなわち熊坂の奮戦がいま目の前で展開されるもの。
こういう、同じ題材の二種の能が裏と表のように存在しているのが面白く、しかもそれを二か月のあいだに比較鑑賞できる愉しさ。
さらに今回の『烏帽子折』は、とにかくにぎやかに人を大勢出して、シテとワキ二人だけの『熊坂』との違いを、思いっきり見せてくれた。なにしろ、登場する役は計二十二に及ぶ。もちろん入れ代り立ち代りだが、最後の襲撃場面だけで熊坂とその一味十一人、あわせて十二人が橋懸に並ぶのは壮観。地謡八人より多い人数が立って一斉に声を出すから、その謡の迫力も凄い。
たった一人で、三間四方の舞台に壮大な時空を出現させるのも能なら、これだけの人数を小空間に詰めこみ、まさに犇かせてみせるのも、やはり能の醍醐味。
最後は十二人を一人か二人ずつ牛若丸が倒していく(闇夜を風のように移動して、少しずつ倒しているという暗示か)大チャンバラ。これが子供だましにならずに、ちゃんと緊張感があって面白かった。刀を振るう盗賊の中に、薙刀を持つ法師もいれば、五尺三寸と号する野太刀をもつ熊坂もいて、殺陣は変化に富む。
能のチャンバラについて、白州正子は『謡曲平家物語』で『正尊』という作品のそれについて、こんなことを書いた。
『後シテは斬り合いの場面ばかりで、まったくのチャンバラに終始する。幽玄を旨とする能の理想からははずれるが、それもまた「当座の一興」で、上手な人々が演じるとまことに面白い。が、今の専門家たちは、まともに斬り合いなど訓練する人はいないようで、つまらなくなったのも事実である。トンボ返りや仏倒し(まっすぐ後ろへ倒れる)、時には橋掛りの欄干や白洲から、舞台へ飛び移るといったような離れ業まで、昔はやってのけたものである。むろん斬り合いには決まった型などはない。歌舞伎のタテ師がやるように、若い人々が面白がって、難しい業を工夫して見物を喜ばせた。それは私が子供の頃のことで、今思い出しても血湧き肉躍る心地がする。お能にはそういう大衆的な一面もある。そこではじめて本格的な幽玄も生きて来るのである。専門家も、見物人もそのことを忘れてほしくないと思う』
この本が出たのは一九八二年。それから三十四年後の今日の『烏帽子折』の斬られ役は「トンボ返りや仏倒し」を次々とやり、アイの盗人役の野村万蔵は「橋掛りの欄干」から舞台に飛び移ってみせた。まさしく「若い人々が面白がって、難しい業を工夫して見物を喜ばせた」。
こうして思いきり楽しませて、「はじめて本格的な幽玄も生きて来る」。
十一月二十九日(火)指揮者の位置
この十日ほど「さがさないで下さい」の潜伏状態。〆切の将棋倒し(それどころか最後は表層雪崩みたいになった)でお天道様に顔向けできない状態に。
しかし暗くなるとゴソゴソ動き出して演奏会に行く。夜の闇こそ我が友。着いたホールは明るいので、なるべく物陰に(だが席が編集者の隣だったりすると、さすがに観念するしか…)。というわけで少し前の感想。
二十八日、サントリーホールでヤンソンス指揮バイエルン放響。これは日経に評を書くので省略。
二十九日、紀尾井ホールで紀尾井シンフォニエッタ東京メンバーによるアンサンブル。パリ管弦楽団の副コンサートマスターも務める千々岩英一を要に、両団体の名手十二人が、シェーンベルクの私的演奏協会で演奏された、オーケストラ曲の室内楽編曲版四曲。
ザックス編曲の《牧神の午後への前奏曲》、シェーンベルク編曲の皇帝円舞曲と《南国のバラ》、シュタイン編曲のマーラーの交響曲第四番。ナマで聴く機会の少ないものなので嬉しい。それぞれに編成の規模が違うのがまた面白く、ほとんどピアノ五重奏に近いシェーンベルク編の二曲は、音が少ないからこそ編曲者の才気と個性と工夫が前面に出て、独創性の高さを感じさせるのがさすが。
しかし考えさせられたのはマーラー。オーケストラ音楽における指揮者の役割とは何か。十二人+歌手だと指揮者なしで充分で、千々岩がコンサートマスターとしてまとめればよい。コンダクトではなくディレクト。ヨーロッパでは古典派以前の作品ではこうしたスタイルが当り前になっていて、専業の指揮者がいる場合も、そのことを意識するようになっている(ベルリン・フィルのベートーヴェンにおけるラトルなどがそうだろう)。近代的な「権威的専業指揮者」への憧れが、日本でもアメリカでも未だに根強いが、それとは異なるスタイル。この意識の変化は、ヨーロッパにおけるピリオド演奏の隆盛と不可分に結びついていて、いまも広がり続けている。
アーノンクールなどはこの運動のまさに始まりにいて、ガンバをひきながらのディレクトから始めて、コンダクトも兼ねた人だけれど、最後にピリオド楽器でベートーヴェンの交響曲を演奏し始めたとき、かれには、どちらの意識が強かったのだろうか。
この運動をマーラーなど後期ロマン派でもやろうとすると、オリジナルではさすがに厳しく、縮小することになる。シュタイン版の復活や、より人数の多いクラウス・ジモン編曲版は、だからこそ必要なのか。二十人前後のジモン版ではさすがに専業指揮者が必要だが、その役割はやはり、ディレクトに近い調整役のはず(これはいつか確かめてみたい)。
オーケストラ曲やピアノ曲に較べて、室内楽の人気が日本でおおむね低いのは、指揮者なりピアニストなりといった、カリスマ的個人が見当たらず、感情移入しにくいというのも一因なのかも。
そういう存在のない紀尾井ホールのマーラー、息をあわせて合奏し、ソロをとりあう楽員たちだけのマーラー、当然ながら個性は強くないのに、しかしとても魅力的な時間だった。
前日に都響が大野和士の指揮でこの曲のオリジナルを演奏していたのに、聴き較べそこねたのが、なんとも残念。「勝手に東京ツィクルス」の醍醐味を活かせずじまい。
十二月一日(木)ブルボン家の作曲家

ドゥバルグとタメスティをあきらめ、オーチャードホールの「アルベルト・ゼッダ スペシャルコンサート」に。
ゼッダの八十八歳を祝う、藤原歌劇団主催の演奏会。プログラムにゼッダの謝辞があり、「私の米寿に際して」とあるので、隣の原文ではどうなっているのだろうとワクワクしながら見ると、「l'augurale omaggio del Beiju」とあった(少しがっかり)。
二十九日の紀尾井では指揮者の存在意義に疑念を抱いていたくせに、ゼッダの指揮する東京フィルの軽やかで明朗な、澄んだ響きを聞いた途端、こういう響きはよい指揮者の存在なしでは絶対に出てこないと、思わず手を合わせたくなる。指揮者なる存在の不思議。
曲目はゼッダがその復活に心血を注いできたロッシーニ。名アリア大会ではなく、カンタータ《テーティとペレーオの結婚》と《スターバト・マーテル》の二曲という、日本ではゼッダしか客を集められないだろうプログラム。
王族の結婚祝賀、子孫の誕生と繁栄を祈る「喜」の音楽と、子の死を嘆く聖母マリアという「哀」の音楽を並べる好対照。ハロウィンがすぎるやクリスマス一色になった東京の町中に「聖母の嘆き」が響く、まさにメメント・モリ(笑)。
同時に、ロッシーニという芸術家のありかたをオペラ抜きで浮き彫りにする、面白い曲目でもあった。
水谷彰良さんの丁寧な解説によると、《テーティとペレーオの結婚》は一八一六年、ナポリ王フェルディナンド四世の孫娘と、ルイ十六世の甥との結婚を祝うためにつくられたもの。ロッシーニは前年に二十三歳でナポリのサンカルロ劇場の音楽監督に就任したばかりだった。
この機会音楽の誕生が示すように、ロッシーニの芸歴は、ヨーロッパで滅びゆく王制との関わりが深い。
スペイン・ブルボン家出身のフェルディナンド四世の王妃は、オーストリア・ハプスブルク家出身のマリーア・カロリーナ(マリー・アントワネットの姉)。このマリーア・カロリーナは、惰弱な夫に代わって政治の前面に出て、王制を打倒し、妹を殺したフランス革命軍と戦った人物。一八〇〇年頃にはローマも支配した。《トスカ》の世界では、悪役スカルピア(これは架空の人物だが)を使ってローマに恐怖政治を敷いた悪女。
しかしその後は破竹の勢いのナポレオンにナポリを追われ、シチリアに逼塞していた。代りにナポレオンがナポリ王としたのが、信頼する部下で妹婿のミュラ元帥。この人、騎兵の悪魔みたいな傑出した戦闘指揮官だったが、知性はさっぱり。落ち目の義兄を見限って旧体制の仲間入りをしようとしたものの、裏切は認められずに退位、銃殺。
そして一八一五年六月のワーテルローの戦いの前後に、フェルディナンド四世夫妻はナポリに返り咲くと、ロッシーニがサンカルロに招かれる。そして夫妻の孫のためにこのカンタータを書く。機会音楽だから、旧作をあちこちに流用、クライマックスには《セビリアの理髪師》終幕のアルマヴィーヴァの大アリアを女声用にして転用。これはさらに《ラ・チェネレントラ》でも再使用(同じ日に新国立劇場では理髪師をやっていたので、東京の二会場で同じ旋律が響いた)。
ロッシーニは、ナポリだけでなくその後はフランスのブルボン家と縁が深く、一八二五年にはシャルル十世の即位に際して、記念オペラ・カンタータ《ランスへの旅》をつくり、王に献呈。そして一八三〇年の七月革命でシャルル十世が退位して、支流オルレアン家のルイ=フィリップに変ると、契約が無効になったためにオペラ作曲の道を絶たれる。まるでそのオペラ歴は、ブルボン家の浮沈とともにあったよう。王の作曲家。
しかし、十九世紀が英雄的個人、独立自尊の作家性に価値をおき、御用芸術家を認めない時代となったことは、ロッシーニもよくわかっていたのではないか。《テーティとペレーオの結婚》も《ランスへの旅》も、再演をせずに封印されることになった(それらを忘却の淵から甦えらせたのが、ゼッダなのだ)。
圧政反対と闘争のシンボル、英雄ギョーム・テルの作曲家として記憶される方がよい、と思っていたのかもしれない。一八四一年の《スターバト・マーテル》完成の経緯、他者に任せた部分を自分で作曲しなおして出版したという話は、後半生のロッシーニがいかに自身の芸術家としての作家性、個人性を重視していたかを物語る。「王のための音楽」にそれを求めることは不可能。だから、封印しなければならない。
その意味でも対照的な二作品を、ゼッダは並べてみせた。
かれが指揮する《スターバト・マーテル》は、澄んだ悲しみに満ちていた。同時に、ヴェルディのレクイエム(原型はロッシーニ追悼のために書かれたもの)と《アイーダ》が、いかにこの音楽から多くを得ているかを、教えてくれるような演奏だった。ゼッダがかつて指揮した《ファルスタッフ》の素晴らしい軽妙さを思い出しつつ、「王の作曲家」ロッシーニと「国民作曲家」ヴェルディとの、見えにくかった関連を思う。
十二月三日(土)ワグネリアンたち
ノット指揮東京交響楽団をサントリーホールで。前半のメインはデュティユーのチェロ協奏曲。生誕百年とはいえ、この曲を一年で二回東京で聴くとは驚き。しかもケラスとヨハネス・モーザー、いまが盛りのチェリスト二人の競演で。
さらにいうと、指揮がカンブルランとノット。現在の東京のオケでも、最もテーマ性豊かなプログラムを組む首席二人だけに、カップリングも面白い。
どちらも、このチェロ協奏曲の各楽章の副題がボードレールの『悪の華』から採られたことに目をつけた。
そしてボードレールといえばフランスの熱狂的ワグネリアンの元祖。ということでワーグナーに結びつけた(『ワーグナー変貌』という本に載っていた、パリでワーグナー指揮の演奏会を聴いたボードレールが書いた《ローエングリン》前奏曲への熱烈な賛辞は自分も耽読して、今なおこの作品を偏愛する、大きな理由となっている)。
六月に読響を指揮したカンブルランの場合は、自分もフランス人だけに一捻りしたくなったのか、ブルックナーの交響曲第三番《ワーグナー》を演奏して、仏墺ワグネリアン大会みたいな組合せに。
対してノットは、イギリス人だからか直球勝負で、ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》前奏曲(愛の死はなし)。
この曲から、中断なしでチェロ協奏曲に進むアイディアは素晴らしい。しかも唸らされたのは、モーザーが最初から登壇して、チェロのパートをオケと一緒に演奏したこと。対向配置でチェロ群はちょうどモーザーの背後にいるので、モーザーがトップを取るような格好になる。
冒頭付近でチェロだけの部分があるなど、この曲でのチェロ・パートの存在の大きさに気づかされていくうちに、デュティユーのチェロ協奏曲につながる。
そのデュティユー、ケラスのときにはその耽美的な響きに何度か夢の世界に誘われかけたが、よりえぐいモーザーの響きは、むしろ覚醒を導く。しかしやはり美しい音楽。
後半はシューマンの交響曲第二番。これもノットだから、前半と結びついているはず。あえていえば、シューマンがワーグナーと同じドレスデンに住んでいた時代につくられた作品、ということか? 二楽章と四楽章の快速にはさまれた、三楽章の漂うような憂愁が印象に残る。
十二月八日(木)今日は
先日、フェイスブックにある方が「手帖に酔って書いた字が読めません。なんと書いてあるか読めますか? 十二月八日に誰か私と約束した人おられます?」というようなことを書かれていたので、「先輩、そりゃ『ニイタカヤマノボレ』に決まってるでしょ。十二月八日なんだから」と突っ込もうと思ったが、マニアックすぎて誰にもわかってもらえないかもしれないと思い、やめておいた件。
十二月十一日(日)カルメンと青の洞窟
NHKホールで、デュトワ指揮N響の《カルメン》。
演奏会形式による、純音楽的な《カルメン》。ギローによるレチタティーヴォつき。第一幕は舞台がないことに無理を感じたが、第二幕以降は音楽が暗示する力でもっていく。音楽にこういうドラマとパースペクティヴを突然変異的に持ち込んだという点において、このオペラはやはり大傑作。
この作品でこれだけ高水準のオーケストラ・パートの演奏は、日本ではまず聴けないもの。明澄。
二回目の休憩で外に出ると、NHKホール前の代々木公園の並木道が、夜空に青いイルミネーション。幻想的で冬らしくきれい。「青の洞窟」というらしい。


十二月十二日(月)お人好し信繁
『真田丸』四十九回「前夜」をみた。
「四十九回お待たせしました」の信繁初めての本格的ラヴシーンがついに出て、きりちゃんよかったねの巻。
それはともかく、台所方の大角与左衛門、史実通りなら善人であるはずがないので最後はどうするのかなと思っていたら、なんと『真田丸』最強の「草」だった。こういう忍びを疑うことなく信じきってしまい、してやられる信繁の人間観の甘さ。三成とはまた違ったお人好し。善の存在を信じたい男。
対してこの大角といい、「眠りの弥八郎」(?)こと本多佐渡といい、乱世生き残りの老人どもが、ここ一番に発揮する凄さ、悪どさ。要領の悪い世渡り下手ばかりが集まった大阪方牢人衆が、かなうわきゃない。次々と討死に(木村長門は、本当は井伊の赤備えにやられるのだが、やはりその姿は見せなかった)。
しかし、信繁のその純粋な善人ぶり、お人好しのまっすぐな生きざまが眩しくてたまらない、己を韜晦して戦国最後の日々を生きる武将たち。景勝、家康、政宗、信之、信伊。それは「からっぽ」の裸身の放つ眩しさなのか。反応は人それぞれ。
山岡荘八の『徳川家康』に出てくる真田幸村は、「この世から戦は無くならない」と信じて、つまり人間を信じないがゆえに最後の最後まで戦い抜く男だけれど、『真田丸』の信繁は、人間を信じたいがゆえに最後まで戦う男。
それにしても、「ずんだもちが好きな人間に悪いヤツはいない」みたいな伊達政宗と片倉小十郎の思い込みが、仙台人を父に持つ人間として愉しかった。政宗登場の回にも書いたけれど、三谷幸喜は古い仙台人のこの嗜好を、どこで学んだのだろう。
思えば、各地の人間が出てきたこの大河のなかで、その土地の色、お国柄を明快に持っていたのは、「ずんだ好きの仙台人」政宗と、「人間不信にさせられるほど腹黒い京都人」小野お通の、この二人だけだったんじゃないか(笑)。ここまで風土の特色を背負った人物はほかにいなかった。
さあ、いよいよその前夜。いまこの時こそもう一度みるネットの特別篇、『ダメ田十勇士』。
「ワシは怖ない。真田の殿様に、これを貰ろうたから」
十二月十八日(日)最終回
さわやかな、信繁の見なかったものには一切触れないラスト。ダメ田十勇士がちゃんと出てきたのにも快哉(Mrオクレがいなかったのは残念)。
とはいえ最後、まさか『新選組!』の第一回につながるとは、夢にも思わなんだ(笑)。
石坂浩二の佐久間象山、「げんさいのげんは、どう書くんだ?」だったか、虫の息で下手人の人斬り彦斎に名前の書き方を質問する最期だけ、とりあえず思い出す。
真田の赤備えを見たあとは、サッカーのクラブワールドカップ決勝、鹿島の赤備えの奮闘に勇気づけられる。二点取って延長戦に持ち込むなんてビックリ。
まさしく三谷幸喜いうところの、「もしかしたら勝っちゃうんじゃないか」というところまで、あと一歩まで、エル・ブランコすなわち白い巨人(巨人だが読売ではない)を追いつめてみせた。かれらのこのあとの成長が楽しみ。
ここから夜明けまで自分も遅れた仕事(ダメ)、がんばらねば。赤い服を着ようと思ったが持っていない。赤いマフラーでも巻こう。
「赤いマフラー」といえば、自分的には白黒のアニメ『サイボーグ009』の主題歌。ヤマトの「真っ赤なスカーフ」もあるが、こちらはどうも苦手。それにしても、あらためてきくと二曲ともロシア民謡風、うたごえ喫茶風なのは、やはり時代か。
十二月二十日(火)剣をとる者は
今年は第九なしにしたので、十七日のデュトワ&N響が二〇一六年の演奏会通い仕舞い。
ブリテン、プロコフィエフ、ラヴェルにオネゲルと、デュトワ十八番の近代音楽プロだから、鳴りと音色は文句なしに見事。ただ、オネゲルの交響曲第二番だけは室内オケ向きで、十六型でやるのは無理があるように思った。
そういうことを気にせず、二千人以上の大ホール向きのサウンドが基本というのが、大交響楽団と生きてきたデュトワの思想なのだろうが、響きが濁る。
前にパーヴォがメタモルフォーゼンを倍弦四十六人でやったときと似た感じ。あのときは残響の多いサントリーホールだからかと思ったが、この日はNHKホール。このあたりはN響の弱点なのだろうか?

今月の能。今年は能楽師・作者の観世信光の没後五百年の記念年で、国立能楽堂では年の後半にその特集を組んだ。その信光作の能の名作を二本。
七日の『遊行柳』は、今の自分には静寂すぎて、味わえるようになるにはまだまだ時間がかかりそうな作品だが、柳の枯木が僧に弔いを求めるという話は、いかにも日本仏教独特の「草木国土悉皆成仏」思想に拠っていて興味深い。永正十一(一五一四)年三月十九日、京の新黒谷で初演と、作者どころか初演日と場所まで判明している、きわめて珍しい能なのだとか。
続く十六日の『船弁慶』は、自分などにもわかりやすく、楽しめる人気作。信光は本来、上演効果の高い作品を得意としたとされる。宝生流の辰巳満次郎がシテ、そして「後之出留之伝」という小書による上演。
兄頼朝との不和が決定的になり、摂津の大物浦から船出して西国へ逃れようとする義経一行。前半は、ここで義経と別れることになった静御前(前シテ)の舞。後半は船出した一行が平知盛の怨霊(後シテ)に襲われる場面。一人のシテが婦人と男の怨霊という、前半後半でまったく別の役柄を演じるもの。
義経役は、大人の役をあえて声変り前の子方に演じさせる。これは、『烏帽子折』や『橋弁慶』の牛若丸を子方が演じるのとは、まったく意味が違う。牛若丸は若々しい生命力に満ちた無敵の少年神だが、『船弁慶』や『安宅』の義経を演じる子方は非力で、人が守らねばならない聖なる存在を意味する。
屋内での別れの愁嘆場が終って、浜辺の船出の場面へと移り変わるときの囃子の調子の変化、一気に高まる緊迫感が見事。静から動への、こういう一瞬の落差が、能の大きな魅力。
新中納言知盛卿とくれば、孔明、正成や幸村などに通じる、敗軍のなかに輝く智将の美学に彩られた存在だが、ここで義経一行の船に襲いかかる知盛の霊は、そうした生前の人格とは別の、怨みと憎しみだけの存在。敗れて海に沈められた平家一門の代表、我等は「桓武天皇九代の後胤」だ、と喚くだけの怨霊。
夢幻能における幽霊の場合は、霊を弔う僧(ワキ)が夢うつつのおぼろな境界で出会う存在だから、僧がその人に抱いている生前の美しいイメージが反映されて、生前の性格を引き継いでいる。だが怨霊が現実世界に姿を現しているこの場合は、そうではない。生身の人間とは交感も共感も不可能な妖怪(あやかし)、化物。
狩衣の両袖をからげた、平家の怨霊の装束が面とともに印象的。
この悪霊を相手に「その時義経少しも騒がず」、剣をとって戦おうとするのを「打ち物業にて敵ふまじ」と弁慶が間に入って止め、折伏しようとするのが面白い。悪霊が相手では人間は敵わないからなのか、非力な義経では敵わないからなのか。どちらの意味でもあるのだろう。「剣をとる者はみな剣で滅びる」というイエスの言葉を連想したり。
そして、さらに面白かったのはそのあと。弁慶の祈りで悪霊が退散する、というようにきれいにまとめたあらすじを自分はどこかで読んだ気がするが、実際に舞台と詞章を体験すると、ここはそんな単純な勝利の終りではない。
弁慶の祈りで悪霊の力は弱まるが、退散させられるほどではない。そもそも荒法師弁慶の法力なんて、高僧のように強いもんじゃないだろう。祈りでちょっと引き離して時を稼ぎ、船頭を手伝って、必死で船を浜辺に漕ぎ戻そうとする。それを悪霊が追ってくるのを祈って遠ざけて、とうとう船は浜辺にたどりつく。
すると、折よく引き潮になったので、水を離れることができないらしい水死者の霊は、沖に退るほかない。やがて、白波の間に消えていく。
「弁慶船子に力を合はせ、お船を漕ぎ退け汀に寄すればなお怨霊は慕ひ来るを、追っ払ひ祈り退け、また引く汐に揺られ流れ、また引く汐に揺られ流れて、跡白波とぞ、なりにける」
つまり、義経一行の船は平家の怨霊に妨害されて沖に出られず、浜に戻されてしまった。命からがら、どうにか海中に引きずり込まれずにすんだ、というだけのことであって、渡航そのものは無残な失敗。
こうして、義経一行は海から山へ、吉野に潜伏することになるという、史実をちゃんと踏まえての作劇。
「剣をとる者はみな剣で滅びる」
十二月二十七日(火)めでたし
平成二十八年度(第七十一回)文化庁芸術祭賞のレコード部門、大賞は「花もよ編集室」のCD二十枚組ブック『武智鉄二「古典は消えて行く、されど・・・」』。
おめでとうございます!
素晴らしい仕事が評価されるのは本当に嬉しいこと。
http://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/pdf/2016122701_besshi.pdf
さらに優秀賞の一つは、キングインターナショナルの『N響世界一周演奏旅行1960』。この企画の末席に連なった者として、一年の締めくくりにこのニュースを聞いて、素直にとても嬉しい。
人生のある時期に「一九六〇年」にこだわり続けたのは、無駄なことばかりではなかったと励みになった。
どちらも新録音ではないことには、いろいろな意見があるだろう。しかし、間違いなく言えるのは、どちらも過去の貴重な録音遺産を現代のききてに楽しんでもらう、味わってもらうにはどうすればいいかをユーザーの目線で考え、とても丁寧につくってある品物だということ。「過去の再現」に関わる仕事をする者として、多くのことを教えられた。
また音楽部門の大賞は、十一月七日サントリーホールの山田和樹指揮「柴田南雄生誕百年・没後二十年記念演奏会」。これも忘れがたい演奏会、音響空間の体験だったから、我が事のように嬉しい。
十二月二十八日(火)
『演奏史譚一九五四/五五』の残りの原稿、参考文献リストなどを送る。
十二月三十一日(土)大つごもり
大晦日。二〇一六年の終り。今年も色々あった。
最後の仕事は『一九五四/五五』のまえがきとあとがき。まえがきはできた。その、結びのところ。
一九五四年と五五年。二十世紀の半ばを過ぎたばかりのこの二年間には、過去を締めくくり、未来を予告する、つまり百年間の過去と未来を凝縮した「現在」がある。
この二年間を、これから吉田や山根たちとともに旅していきたい。物語は一九五三年の大晦日、吉田秀和が「二十世紀の首都」ニューヨークで新年を迎える晩から、始まる。
それから六十三年後の、今日大晦日。
本年も大変お世話になりました。
みなさま、よいお年をお迎えください。
Homeへ