二〇一八年
一月一日(月)謹賀新年

聴き初めは、来年が生誕二百年となるオッフェンバックの序曲集(元旦から来年にそなえる男)。ダレル・アン指揮のリール国立管。
しかし、いくら同じ十九世紀後半のパリつながりとはいえ、オッフェンバックの《地獄のオルフェ》序曲のジャケにモローが描いたオルペウスの絵は、ものすごく無理があると思う(笑)。
一月二日(火)今年の初荷は。

初詣は例年同様、地元の鎮守様の須賀神社。映画『君の名は。』のヒットの影響で、去年から若い参拝者がぐんと増えた。階段の上からキービジュアルと同アングルの写真を撮る若者多数。
昔はこの階段、二時間ドラマの殺人現場(もみ合っているうちに転落して頭を打って死ぬというお決まりのパターン)の名所だったが、変れば変るもの。
今年最初の宅配便もくる。到着したのはHMVからのCD。

年の瀬に注文したが取り寄せだから、松の内には来ないと思っていた。だが大晦日に出荷してくれて、今日届く。
問題は中身。能のCD二枚。ともに観世銕之亟家のもので観世寿夫の謡曲『藤戸』と、七、八、九世と三代の銕之亟と寿夫が顔を揃える番囃子『隅田川』。
どちらも曲も演者もよく楽しみではあるのだが、ともに母親が我が子に先立たれたことを嘆き、涙する話。いかに名作とはいえ、どうにも松の内にふさわしい話ではないので、しばらく我慢。わざわざ届けてくれたのに、申し訳ない…。
一月七日(日)今年の国立能楽堂
年明けの恒例で、国立能楽堂の四月からの二〇一八年度のスケジュールが発表になる。現物を観たかった能がいくつも並んで今年も嬉しい。安いし、字幕がついているし、凸凹が少ないし。
嬉しいが頭が痛いのが、九月の「開場三十五周年記念公演」シリーズ。各流派の重鎮がずらり並んで名作連発。前半三回は各日とも能二番。まあ、五回全部買っても、ベルリン・フィルのS券一枚くらいですむのはありがたいが。
十二月と一月には『明治一五〇年記念「苦難を乗り越えた能楽」』で、『道成寺』二連発がある。武家社会崩壊とともに滅亡の瀬戸際にあった明治の能楽を再興した功労者、梅若実と宝生九郎の、それぞれの継承者がシテというのが妙味。
梅若玄祥(この頃には梅若実)の『道成寺』、この後は観られるのかどうか。
一月十日(水)つまづかせるもの
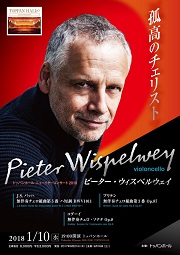
夜はトッパンホールで、ピーター・ウィスペルウェイによる無伴奏のチェロ・リサイタル。バッハの無伴奏チェロ組曲第五番、ブリテンの無伴奏チェロ組曲第三番、コダーイの無伴奏チェロ・ソナタの三曲。思索するチェロ。バッハは低くうなるように踊る。
白眉はブリテン。ここだけ全曲の演奏に先立ってマイクをもち、マーチや舟歌など、各部分の頭をひきながらレクチャー。舟歌は『ヴェニスに死す』、つまりマンの小説、ヴィスコンティの映画、ブリテン自身の遺作のオペラを想起させるという。ほかにも全体を通じて流れる、死のイメージ。終曲のパッサカリアの締めに、三つのロシア民謡(チャイコフスキーが編曲したもの)に続いて、ギリシャ正教の死者のための聖歌の旋律が姿を現す。これにより、全曲が何らかの形でこのレクイエムの主題の変奏であったことが明らかになる。
ウィスペルウェイの説明はここまでだが、葬送の歌から引用された主題が最後の最後に初めて明確に鳴り響くなんて、シュトラウスの《メタモルフォーゼン》みたいで面白い。
この曲はロストロポーヴィチの演奏するバッハの無伴奏に触発されて書いた三つの組曲の最後の作品で、一九七一年に完成したが三年後にオールドバラでロストロポーヴィチにより初演された。初演者とショスタコーヴィチに献呈されているという。一九七五年と翌年に、相次いで亡くなるショスタコーヴィチとブリテン。鉄のカーテンをはさみ、大チェリストを媒介に交感する、二人の作曲家。
年表を見なおしてみると、ロストロポーヴィチがソルジェニーツィンを擁護して出国を禁止されたのが一九七〇年。西側の働きかけで出国できたのが一九七四年。ブリテンの作品は軟禁中に書かれ、その出国により初演されたことになる。一方、そうした状況を見つめつつ、ブリテンと同じように七〇年代に入ると、弦楽四重奏曲第十五番やヴィオラ・ソナタなど、遠からぬ死を見つめる作品を書いていたショスタコーヴィチ。かれはこの曲を知ることができたのだろうか。
ロストロポーヴィチは被献呈者にもかかわらず、ブリテンの三つの無伴奏チェロ組曲のうち、この曲だけ録音していない。なぜなのか。レクチャーと演奏をきっかけに、広がっていく興味。
その前の午後には、国立能楽堂で新国立劇場主催の『能とオペラ ─「松風」をめぐって─」。二月の細川俊夫のオペラ《松風》日本初演に向けての催し。まず原作となった能の『松風』から、汐汲みと狂瀾の場だけを舞囃子形式で 観世銕之丞が演じ、その後に細川、銕之丞、柿木伸之、司会宮本圭造による座談会。
座談会で海外の作曲家も能を題材にオペラをつくっていることに対し、細川が「ほとんどがとんでもない誤解をしている」と述べたところは、さらに細かい説明と理由を聞きたかった。外国人が能というものをどのように受け取っているのか、それに対して細川は何が不満で、自分では能をどう考えてオペラにしているのか、そしてそれに対して銕之丞はどう感じるかなど、いろいろな可能性が眠っていそうな発言だった。
銕之丞が芸術の一般論として、分かりやすさを安易に求める風潮に媚びることはないのでは、と話したのも同感。
我田引水になるが、文章だってそうだろうと思う。先日、ある原稿に「その国の音楽は豊かな稔りの時代を迎え」というようなことを書いたら、担当さんから「稔り」を「実り」にできないかといわれた。しかしここは、果実の実りではなく、穀物が広い大地に稔っている雰囲気を「みのり」という言葉の背後に込めたいので、ママにしてくれと頼んだ。すると、ルビを振るかもしれないとのこと。
ルビを振ってもらえるなら、自分としては大歓迎だ。ところがいつのまにか、ルビはできるだけ振らない風潮になっている。たとえば日経新聞などだと、私のように外部の人間が署名原稿に書く場合にはしかたなしに許されるが、社内の記者の文章ではルビは原則禁止、つまり、ルビなしで誰にでもそのまま読めるような語句で書くことになっているという。
愚かしいことだと、私は思っている。外来文字である漢字と日本語の複雑な関係を思えば、読めない字があるのは誰だって当然で、恥ずかしいことではない。むしろ面白いことなのだ。子供時代の私は、自分の常識ではそうは読めないようなルビが振ってあると、かえってその文字が印象に残って憶えたり、ときには調べたりした。そこから、知識が広がっていったりした。同じ音の言葉に違う漢字をあてるだけで意味を少しずらしたり、深めたり、重ねたり(掛詞の元祖みたいなもの)することができる日本語を、面白いと思うようになった。平仮名にひらくことも、カタカナにすることも、やはりそうした工夫のなかに入る。
ルビがないと「稔り」が読めないという人がいるなら、なぜ「みのり」にこういう字をあてるのかを、そこで初めて考えてくれればいい。難しい字があると投げ出すような人は、もともとそんな文章は読まないだろう。「実り」に変えれば誰でもすぐに読めるのかもしれないが、それでは語句の想像力が失われる。印象にも残るまい。こんな些細なことでも引っかかって、つまづいてもらえたら、それこそ幸いなのだ。
つまりルビとは、わかりやすくするためにあるのではない。むしろつまづかせるためにある。だから、ルビがいらない文章は「わかりやすい」のだ。そうすると水は低きに流れるで、程度はどんどん下がる。愚民化のための文章作法。だがネットのテキストはルビが振りにくいので、ますますルビ文化は衰退か…。
不安なのは、ルビなしの時代に育った世代の人が、かなり変な読みを勝手にしているように感じられる時があること。
何が言いたいかというと、ウィスペルウェイのブリテン作品についての短いレクチャーは、まさにルビのようなものだった、ということ。読みかたならぬ聴きかたを示すことで、作品につまづかせ、考えさせる、賢者の音楽。
一月十一日(木)芸術監督大野和士
新国立劇場の「2018/2019シーズン ラインアップ説明会」(百四十人の大盛況)で、オペラ部門の新芸術監督、大野和士の談話に感じたこと。
・二〇〇九年に若杉弘が没して以来、久しぶりに明確なビジョンをもった、本物の芸術監督がきたことを、とても心強く感じた。「新国立劇場最後の切り札」といわれるのもむべなるかな。
・あくまで芸術監督であって音楽監督ではないこと。十本のうち自らが振るのは二本だけ、しかも一本は東京文化会館との共同制作による「オペラ夏の祭典」の《トゥーランドット》だから、純粋な主催公演は新作の《紫苑物語》のみ。再演は振らず、またオーケストラも前者はバルセロナ交響楽団、後者は東京都交響楽団と、自身が音楽監督をつとめて気心の知れた団体のみ。近衛を率いて陣頭に立つのは最小限にし、帷幄で策戦を練って指示を出す、諸葛孔明型。これはこれでありだと思う。劇場に自前のオーケストラがあれば、また話は違ったろうが。
・一シーズン十本のうち、新制作をこれまでの三本から四本に増やすこと。これはレパートリー公演に使える作品が少なくなってきていて、早晩足らなくなることへの対策。新制作を次に再演するのが三年後というサイクルで考えると、レパートリーが三年分必要になる。ところが近年の新制作は他の劇場から一度だけ借りてきたプロダクションが多く、これらは再演できない。そのためにレパートリーが足らなくなる。共同制作でも新国立劇場発、日本発のプロダクションを増やす。借りてきた場合もできるだけ上演権を買い取り、装置や衣裳を自前にして、再演可能にする。
・日本人作曲家への委嘱作品シリーズの開始。隔年で新作。日本人のオペラは独唱が多く、重唱や合唱を交えたアンサンブルなど、オペラ本来の魅力を発揮できるものが少ないから、そこを変えたい。
(この発言はとてもおもしろかった。始まりの山田耕筰からそうだと言えるが、戦後になるとさらに《ペレアスとメリザンド》原理主義みたいなものが強くなった。戯曲の詩をそのまま楽劇化するという理想にとらわれすぎたこと、もっといえば、イタリア・オペラをよくわからないままに軽侮してきたこと)
・一幕物二本の「ダブル・ビル」と、バロック・オペラを一年交替で取りあげること。一幕物は研修所公演で事前に取りあげるなど連携もはかる。バロックものはピリオド楽器ではなく、モダン楽器にガット弦を張るなどして対応する。
(一幕物は二十世紀以降に多いし、バロックはいうまでもなく十八世紀以前。これまでの十九世紀に偏ったレパートリーを拡充することは大賛成。モダン・オーケストラの起用は、中劇場ではなくオペラパレスでやることを意識してか。日本人作品もバロックものも、これまでは主に中劇場でやってきたけれど、すべてオペラパレスでやるつもりらしい)
・自身のネットワークを活かして、旬の演出家、歌手を呼ぶこと。
・バレエ部門や演劇部門との連携。来年のダンスに「Summer/night/dream」、演劇に『オレステイア』という演目があるのを見て、オペラでも前者にブリテンの《夏の夜の夢》、後者に《エレクトラ》を組み合わせるなんてことができると思う。
(同じ劇場内にオペラ&バレエと演劇が同居しているケースは西欧ではドイツ以外では珍しいのだから、せっかくの利点を活かさないのはもったいない。まあこれは、三部門全体を統轄する芸術監督がその上にいないと、並列のままでは調整が難しいだろうが)
構想が明快で、じつに頼もしい。しかしいうまでもなく、新構想の最大の問題は予算。額が劇的に増えたり、大スポンサーがついたりしているのでもないかぎり、どこかを締めてやりくりするほかない。どうなっていくのか。
そのなかで「オペラ夏の祭典」は、都の東京文化会館と共同制作し、びわ湖や札幌とも連携することで予算規模を拡大し、公演の水準を上げようという、大野ならではの雄大な構想。東京の西と南を新国立劇場が、東と北を東京文化会館が(おそらくハコの大きさに応じて代金も上下させながら)分担するのも面白い。
ともあれ、幕を開けたときが楽しみ。組織全体が活性化されることを願う。
一月十三日(土)土蜘蛛の吐く糸
今年の能の最初は国立能楽堂公演。
・狂言『伯母ヶ酒(おばがさけ)』善竹富太郎(大蔵流)
・能『土蜘蛛』廣田幸稔(金剛流)
『土蜘蛛』は芝居風味の強い派手な作品として人気の高いもの。前場は源頼光の屋敷で、病床の頼光を僧に化けた妖怪土蜘蛛が襲うが、頼光は刀を振るって撃退する。後場は駆けつけた頼光の家臣独武者(ひとりむしゃ)が、妖怪の残した血の跡を追って葛城山の塚に行き着き、塚を崩すと土蜘蛛が出現。激闘となるが見事に土蜘蛛の首を落として帰京する。
シテが土蜘蛛なので、『大江山』などと同様に、王土に身の置き所のない鬼の無念に同情したくなるが、物語としてはあくまでワキの演じる独武者がヒーローで、悪を平らげてめでたしめでたしという展開。ワキの福王和幸は長身でハンサムなので、こうした役にはぴったり。今の時代はその点でとても恵まれている。
この能の人気の高さの最大の理由は、土蜘蛛が投げる紙製の蜘蛛の糸。ぶわっと広がって中空に放物線を描いた瞬間、見所(客席)から思わず嘆声があがる。
江戸時代まではもっと地味なものだったそうで、明治初期に金剛流宗家の金剛唯一が現在の糸を工夫して、各流派に広がった。今では歌舞伎などでもおなじみだが、三間四方の狭い能舞台だと、本当に空間を埋めつくすような感じになるので、じつに効果的。しかも終われば、きれいさっぱり片づけられて、何もない能舞台に戻るのが、気持ちがいい。
最後、討たれたシテが通常の橋懸からではなく上手奥の切戸から退場したのに驚く。ツレ、ワキやアイならいつものことだが、主役であるシテが、あえていってしまえばコソコソと消えてしまう。あとで詳しい方に聞くと、『土蜘蛛』では珍しくないやり方だとか。演能後に普通に橋懸から退場することもあるが、討たれたことを示すために切戸から出るらしい。ワキの独武者こそが正義のヒーローだということがより強調される終り。
一月十八日(木)東京文化会館のトゥーランガリラ
東京文化会館で東京都交響楽団の定期演奏会。大野和士指揮。
・ミュライユ:告別の鐘と微笑み~メシアンの追憶に(ピアノ・ソロ)
・メシアン:トゥーランガリラ交響曲
(ピアノ:ヤン・ミヒールス、オンドマルトノ:原田節)

メシアンのサウンドを聴くのは昨年十一月サントリーホールの読響の《アッシジ》以来。しかし、その響きのなんと違うこと。カンブルランの柔らかくてしなやかに跳ねる、輪郭が丸くて華麗な響きとはまるで別の、硬質で明確な、強い響きと拍子。
二十世紀重工業音楽に無類に強い都響のカラーと大野の指揮、そして東京文化会館の残響の少ない音響があいまって生れた、むき出しな響き。
でもこの曲は、これくらいに獰猛な、バーバリックなものであっても不思議でないと納得。四十歳の若いメシアンがつくった、トリスタン伝説に基づく、挑戦的なエネルギーに満ちた曲。ガムランの響きを模した異教的、異郷的サウンドが説く愛は、カトリックの規範の内にとどまるものなのか。ときに響く、捨て鉢な哄笑やシニカルな笑い。トロンボーン主体の「彫像の主題」は、幻想交響曲などでおなじみのグレゴリオ聖歌の「怒りの日」を想起させて、宿命の到来のよう。
トリスタン伝説に基づく以上は悲恋のはずなのに、しかし不思議に明るく、肯定的で力強い。来世の明るさなのか。あるいはここにあるアグレッシブさは、第二次世界大戦終了まもない時代そのものの明るさなのか。バーンスタインがボストンで世界初演したという歴史的事実があるからか、この作品のオーケストレーションに、当時の西側世界を覆いつくした、アメリカ的な旺盛な消費への欲望と工業力を強く感じたりする。
聴きながら、この曲が日本初演されたのは、まさにこの東京文化会館の大ホールだったという事実を思い出す。五十六年前の一九六二年七月四日、小澤征爾指揮のNHK交響楽団(アメリカの独立記念日だったのはただの偶然だろうが、なにか面白い)。そのときは、どんな風に響いたのだろう。前衛音楽全盛の、当時の東京の音楽界に。そしてその晩には、この客席のどこかに、メシアン本人も座っていたはず。
それから二十四年後の一九八六年三月に、小澤は新日本フィルを指揮して《アッシジ》の抜粋版初演をした。会場は東京カテドラル聖マリア大聖堂。あの頃、東京にはない残響の多いホールに音楽ファンは憧れて、東京カテドラルにその幻を追った。少し前には朝比奈隆のブルックナーの連続演奏会もあった。《アッシジ》の七か月後にサントリーホールが開場して、その幻は形をとる。
カンブルランの《アッシジ》がサントリーホールだったのと、大野のトゥーランガリラが東京文化会館だったのは、作品の音響にぴったりだったのかも。カンブルランのトゥーランガリラも二〇一四年にサントリーホールで聴いているが、今日の方が、作品と音響が心身に食い込んできた。
それにしても、今日のトゥーランガリラは獰猛ではあったが、けっして脂ぎった肉食系ではなく、あくまで硬質な響きだった。
大野の求めるものとその動き、東京文化会館の内装、そして空気に、不思議なくらい各所の能楽堂とその公演に似たもの(ある種の聖域的な清浄さ、とでもいうか)を感じたのは、面白かった。
能に行きだして初めて気がつく、東京文化会館の特異性。
こういうホールは、その後はもちろんのこと、前にもない気がする。たとえば日比谷公会堂にはない。昭和後半の「或る時代精神」を象徴する場としての、東京文化会館。
一月十九日(金)和歌と言葉が遺すもの
国立能楽堂公演。
・狂言『鬼継子(おにのままこ)』石田幸雄(和泉流)
・能『忠度』佐野登(宝生流)

『忠度』は修羅能の代表作の一つで、世阿弥の自信作。いつものごとく、さもありなんと納得。
武人を主役とする修羅能に、萬葉集以来の和歌の伝統と、花の中の花というべき桜をからめ、互いに彫りを深めあう。詞章も格調が高い。
平清盛の腹違いの末弟、薩摩守忠度がなぜ昔から日本人に愛されてきたか、それはもちろん平家物語が原点だが、その人気を決定的に不滅のものとしたのは、この世阿弥の能なのだろう。
成仏できずに一ノ谷の古戦場に留まっている妄執の第一の理由は、勅撰集の千載和歌集に自分の歌がせっかく載ったのに、勅勘の身であるために「詠み人知らず」とされ、名が伝わっていないことだと、忠度の霊は告げる。
古今和歌集に始まる勅撰集に歌が採用されること、それは歌人としての最高の名誉だった。このことは王朝時代に始まって、世阿弥が生きた室町時代前半まで続いた伝統で、公家や僧侶だけでなく、武家も強く意識したことだった。だから和歌にも武芸にも秀でた薩摩守忠度という文武両道の存在は、歌を嗜む教養ある室町武士にとって一つの理想、憧れだったのだろう。世阿弥はその姿を能に留めてみせたのだ。
ここで忠度の生を再現するために何よりのよすがとなるのも、やはり和歌である。忠度の「行き暮れて木の下陰を宿とせば、花や今宵の主ならまし」と、能には出てこないが、背景に暗示される「さざ波や志賀の都はあれにしを、昔ながらの山桜かな」という、本人の歌なのだ。
歌が忠度の幻に生命を吹きこむ。自分の名で歌が記録されることを中世人が熱望する理由が、ここに端的に示される。
歌が残れば作者も永遠に残る。肉体は儚い。名前もそれだけでは識別記号にすぎない。業績も人柄を伝えるとはかぎらない。しかし歌と結びつけられれば、その人となりと息づかいが、その魂が後世に残される。それが芸術の力なのだ。
和歌は文字が使われる前から、口承で作者の存在を言葉で伝えてきた。短歌は暗誦もたやすいので、広い範囲の人に、そして長く、世に伝わる。
黙読ではなく、口に出して詠むのが本来の姿ということは、能の謡と相性がいいということ。だからこそ、能の名作は名歌を採り入れて詞章に味わいと深みを加え、登場人物の造型をより立体的にする。私が知った範疇では、この和歌の借用と活用が誰よりもうまいのが、世阿弥なのである。
時空を超越する言葉の力を、言霊を、世阿弥は能楽師のなかで誰よりもよく知り、よく用いることができる。そしてその言葉なるものへの信頼、願いを、作品として結晶化させる。『鵺』に登場する源三位頼政がそうであり、『忠度』もそうだ。とりわけ『忠度』は修羅能でありながら、死者の妄執が合戦にではなく和歌という芸術に向けられている点で、世阿弥の思想が明確になっている。だからこその自信作なのだろう。
世阿弥は言葉にこだわった。文字に書き残すことにもこだわった。世阿弥が芸術論を書き残さなければ、草創期の能がどのようなものであったかの現場からの証言は、決定的に不足した。同時代人にとってはわざわざ文章にする必要もない常識的な知識も、時が過ぎれば虚しく忘れられるという真理を知っていた。
そして何よりも、その言葉と文字は、本来は「詠み人知らず」の集団芸能であった猿楽において、世阿弥という個人の存在を、芸術家の存在を際立たせることになった。かれは自らの名を後世に向けて刻印し、不滅のものとすることに成功した。それは、和歌という芸術のありようから学んだものにちがいない。
『忠度』の後場では、一ノ谷合戦での敗死の様子が再現される。誰とも知らずに忠度を討ち取った岡部六弥太は、遺骸の箙に短冊がつけられていて「行き暮れて木の下陰を宿とせば、花や今宵の主ならまし 忠度」とあるのを発見する。
武将として勇ましく名乗りを上げることを慎み、歌人として後世に名が残ることをこそ願った男。
能では箙の代りに、矢に短冊をつけている。その一方で、修羅能らしい、武士の凄まじさと生々しさを暗示する動作もちゃんとある。
剛力の忠度は六弥太をいったんは組み伏せるのだが、駆けつけた六弥太の郎党に右腕を切り落とされて、ついに討たれる。その右腕の落下を、右手の扇子をぽとりと落すことで暗示するのだ。
佐野登が毅然と舞ったシテによるこの動作、落ちる扇が肉体の儚さと虚しさを象徴しているかのようで、見事だった。
一月二十一日(日)カンブルランの態度
今月三回目となるカンブルラン指揮読売日本交響楽団の演奏会。
七日芸術劇場のニューイヤーはウィンナ・ワルツとフランスの小品名曲集。華やかに盛りあげて、アンコールで三浦文彰独奏の『真田丸』テーマ曲をカンブルランの指揮で聴けたのが楽しかった。
十三日サントリーホールは、イェルク・ヴィトマン自作自演のクラリネット協奏曲《エコー=フラグメンテ》日本初演が目当てだったが、モダンとバロックの二種のオーケストラを並列するという試みが、同じオケのなかではあまりうまくいかなかったのが残念。別にBCJでも呼んでいたら違っていたのだろうか。
そして今日はみなとみらい。
・ブラームス:ヴァイオリン協奏曲(独奏イザベル・ファウスト)
・バッハ(マーラー編):管弦楽組曲から第二、三、四曲
・ベートーヴェン:交響曲第五番
昨年十一月の《アッシジ》の初日後に「音楽の友」のためにインタヴューしたさい、任期最後のシーズンの抱負をたずねると、「最後のシーズンは、大きな弓のようなものになるでしょう。二百五十年に及ぶ音楽の歴史をカバーするものです。バロック時代のラモーに始まり、ロマン派をへて現代の作曲家、ゲオルク・ハースまで。それは、オーケストラとの八年間で成し遂げたものを、そして数多い経験の後に私たちが今どこにいるのかを、示すものになるでしょう」との答えだった。たしかに四、九、三月の三か月の公演には、二百五十年間のさまざまな時期と国の作品が(意外とチャイコフスキーに力を入れつつ)選ばれている。
今回の「三大B」プロはその予告編のようなもの。ブラームスにブゾーニ(第四のB?)のカデンツァが用いられ、バッハはマーラー編曲版なので、二十世紀初めにまで足を踏み入れている。
「音楽史」に対するカンブルランの姿勢が明快に表れていたのは、マーラー編のバッハだった。この版を使う理由をたずねてみると、「ラモーやバッハなど、バロック音楽も取りあげたいと思っている。マーラー版は、伝統的な大交響楽団のために書かれていて、古楽器演奏とはちがうところが面白い。マーラーのような指揮者がどのように表現したかをやってみたい。バッハそのままではなく、組み合わせを変えて別の作品のようになっている。これを現代の指揮者とオーケストラが鳴らせば、ロマンティックなものとクラシックなものとモダンなもの、三つが重なることになる」という答えだった。
実際に聴いて感じたポイントは、マーラーの演奏を再現することを目指してはいなかった、ということ。マーラーが一九〇九年にニューヨークで演奏したときには、歴史的チェンバロではなくスタインウェイのピアノを改造した「チェンバロもどき」を使ったことが有名だが、カンブルランは一般的な歴史的チェンバロを使った。演奏スタイルも二十世紀前半のドイツ語圏のバッハ演奏に多かった、リズムを引きずった過度に荘重なものではなく、新古典主義的にすっきりしたもの。マーラーは、たとえば「シャルクが改訂したブルックナー」のようにオーケストレーションまでロマン派風に塗りたてたわけではなく、あくまでバッハのオリジナルをモダン楽器で演奏するために補筆したにすぎない。カンブルランはそれを素直に音にした。
カンブルランはあくまで「スコアから読み取れるもの」に集中して、それを現代の楽器と演奏法で鳴らせば、スコアそのものが歴史を、作品の時代性を語りだすはず、と考えているように思える。現代の楽器の安定性と機能性を信頼し、活用することが基本。作曲当時の楽器の性能や演奏法といった「スコア外のこと」にはかかわらない。
ただしそれは、なんでもかんでも十六型の大編成でやるというような姿勢でもない。バッハは八‐八‐六‐四‐三、ブラームスとベートーヴェンは十四型。響きのバランスと規模も、スコアから自ずと読み取れると考えているよう。
実際、ここではスコアそのものが作品それぞれの時代を語っていたと感じた。ベートーヴェンは力強く、ときに豪快なユーモアを交えながら、端正で明快な、古典的な響き。対してブラームスは何かぐずぐずとして夢見がちで、粘るようにリズムの腰が重くなる。
イザベル・ファウストはカンブルランとは対照的に、歴史意識を強くもった音楽家で、楽器も奏法も作品の時代に合わせて変える人だから、モダンに近づいたロマン派のブラームスで共演したのは、ちょうどいいところだったと思う。バッハやベートーヴェンだったら響きの様式がズレていたかもしれない。いつもながらに見事な脱力で、しゃべるように多彩な、やわらかく力みのない響き。ティンパニと共演し、最後には弦楽まで加わってくる第一楽章のブゾーニ作のカデンツァも愉快。アンコールにバッハをひかずに、クルタークの「サイン、ゲームとメッセージ」からドロローソをもってきたのも、「ブラームスのあと」を響かせるという意味でこの演奏会の趣旨にぴたりと合っていて、さすがのセンス。
カンブルランの歴史への態度は筋が通っていて、現代の交響楽団の指揮者として納得させられるもの。同時に、ファウストの高い歴史意識も現代の音楽家として尊敬しているものだけに、翌日の文化会館小ホールでのバッハの無伴奏を聴き較べ、勝手にツィクルスにしてみたかったが、大雪で断念。残念。
一月二十六日(金)三十三年ぶり
一昨日から東京に低温注意報。一九八五年一月以来三十三年ぶりとか。一九八五年一月といえば自分は大学四年。そういえば東京に何度も雪がたくさん降った記憶がある。でも特別に寒かったという記憶がほとんどないのは、やはり若かったからか(笑)。
それよりもこの時は学費値上げ反対闘争で、後期テストを学生がボイコット、全学部でレポートに切り換えたということのほうが印象深い。早稲田の試験中止は六〇年代後半の学園闘争時代以来という事件だった。革マルが自治会を牛耳るなか、法学部だけは民青で対立関係にあり、早稲田祭に参加せずに法学部祭を期日を変えて独自に行うような状況だったが、このときだけは共闘したらしく、法学部もボイコットに参加した。
大多数を占めるノンポリ学生まで珍しく賛同したことに味をしめたのか、自治会はこのあとも九〇年代前半まで試験ボイコットを何度か仕掛けたらしい。この大暴れが、革マルの大資金源だった早稲田祭が一九九七年から二〇〇一年まで中止に追い込まれ、自治会が弱体化される原因の一つになったのかも。法学部祭もいつのまにかなくなったらしい。
その後、学費はどんどん高くなっていった。
一月二十七日(土)兵営の女
あるレコード会社がインフルエンザ蔓延のため閉鎖になり、原稿執筆に必要な資料が来月一日にならないと用意できないと聞かされる。それでも間に合うからいいが、学級閉鎖ならぬ職場閉鎖。今年は深刻なよう。
今日はオペラと演奏会のはしご。現代音楽系の集まりではないのにどちらにも日本初演が入っているという、珍しいケース。後半のウンジャン指揮NHK交響楽団はまたの機会にゆずるとして、ここではオペラ。
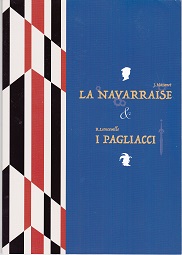
東京文化会館で藤原歌劇団による、マスネの《ナヴァラの娘》とレオンカヴァッロの《道化師》、一幕物二本立て。
前者が日本初演。近年は中小のオペラ団体がかなり珍しい作品まで果敢に日本初演を試みているなかで、藤原歌劇団クラスが日本初演とは珍しい気がする。《カヴァレリア・ルスティカーナ》や《道化師》の大ヒットの影響を受けてマスネが一八九四年に書いた、唯一のヴェリズモ風フランス歌劇。
世話物からグランド・オペラ風、ワーグナー風まで、作品ごとに作風が変り、すべてきちんとした水準で書いたマスネは、ヨーロッパ中からあらゆる情報が集まり、洗練され、流行となって発信される「十九世紀の首都」パリそのものみたいな作曲家だったのかもしれない。キャッチーなアリアこそないとはいえ、声楽も管弦楽の扱いもドラマの磨き方も、レオンカヴァッロとは段違い。
一八七四年、スペインの王位継承戦争(カルリスタ戦争)の時代の、バスクのビルバオ近くの最前線の村。下士官アラキル(テノールの小山陽二郎)が属する立憲君主派の部隊がビルバオ奪還に失敗し、将校が全員戦死するほどの大損害を出して村に退却してくる。そのアラキルを恋人のアニタ(ソプラノの小林厚子)が訪ねてくる。ところがそこにアラキルの父も現れ、ナバラの貧しい孤児の娘に息子はやれぬ、結婚したければ持参金を持ってこいという。
窮したアニタは、敵将を殺せば大金をやるという指揮官の呼びかけに応じ、敵陣に忍んで、首尾よく仕留めて帰り、報奨金を得る。しかしアラキルは戦闘で重傷を負って帰陣し、アニタが敵将の情婦となって金をもらったと誤解したまま死ぬ。悲しみのあまり、狂気にとらわれるアニタ。
西洋で敵将を暗殺する女性といえば、旧約聖書の寡婦ユディト。自らが住む町を包囲したアッシリアの将軍ホロフェルネスの陣営を訪ねて誘惑し、大酒させて寝首をかき、侍女に首を持たせて町へ凱旋する。絵画やオラトリオの題材としても有名な物語。
 クリストファーノ・アッローリ 『ホロフェルネスの首を持つユディト』(英国王室コレクション)
クリストファーノ・アッローリ 『ホロフェルネスの首を持つユディト』(英国王室コレクション)美女と敵将の間に寝所で何があったのか、「後家」という意味ありげな設定と合わせて、そこにはさまざまに下衆の勘繰りが働く余地があるわけだが、そのヒロインに恋人がいたとして、彼女を信じることができなかった場合に何が起きるかをドラマにしたのが、この《ナヴァラの娘》。
プログラムの岸純信さんの文章によると、原作のケーンの短編『煙草』はまったく違う話で、孤児育ちのアラキルが恋敵を毒殺して死刑になるという筋書だそうで、いったいそれがどうするとこういうオペラになるのか、不思議としか言いようがない(笑)。この改作は作家本人が台本作者と共同で行なったという。
登場する女性はアニタただ一人で、あとは軍人とアラキルの父の男性ばかりという、思いきった設定のオペラ。いろいろと書きたくなりそうなところをバッサリ切り詰めて、五十分強の短い話と音楽にまとめてある。
ガンディーニの演出は、西部劇の騎兵隊の砦のような、板塀に囲まれた兵営を舞台とするもの。後半の《道化師》も、舞台は同じで板塀に囲まれている。そして男たちはやはり軍服姿のみ。この演出は、兵営の村に平和が訪れたあと、道化師一座がやってくるという設定も可能性に含めている。
男たちが兵士ばかりという設定は、ヴェリズモの魁でもある《カルメン》第一幕を想起させる。幕開けの、ホセを訪ねてきて兵士にからかわれるミカエラ。
あの場面の延長にアニタも《道化師》のネッダもいる。ガンディーニの演出ノートには「今回の両作品では、共に男性社会にいる唯一の女性を主人公としています」とある。
アニタもネッダも孤児だから、家族も帰るべき故郷もない。兵営という男性社会に、居場所を見出すしかないのだ。
たしかに《道化師》も笛田博昭演じるカニオの力強い歌唱にもかかわらず、カニオ、トニオ、そして希望のようでありながら苦悩の種でもあるシルヴィオと、三人の男に追いつめられるネッダ(砂川涼子)が、いちばん印象的だった。
この作品ではネッダが出ずっぱりに近く、カニオは主役といいながら要所にしか登場しない、三人の男の中の一人にすぎないことに、あらためて気がつく。最後の場面も、観客の視点がネッダの死体に抱きつく舞台下手のカニオにだけでなく、中央奥のトニオと上手のシルヴィオを合わせて三角形に分散するように、うまくつくってあった。
お定まりの《カヴァレリア・ルスティカーナ》とではない組み合わせ、どうなのだろうと思ったけれど、じつにうまく出来ていた。二本立て、ダブルビルは、演出の工夫でじつに面白いツィクルスになりうる。新国立劇場の来年からのダブルビル・シリーズも、そんなことを意図しているのだとしたら、とても楽しみ。
二月三日(土)ドイツの文脈
すみだトリフォニーで新日本フィル。指揮はマルクス・シュテンツ。
・ハイドン:交響曲第二十二番《哲学者》、交響曲第九十四番《驚愕》
・ヘンツェ:交響曲第七番
新日本フィルのハイドンといえば、自分には二〇〇九年にブリュッヘンとこのホールでやったロンドン・セット四回のシリーズが懐かしいし、さらに歴史をひもとけば、一九八八~九一年にカザルスホールでやった百七曲の全交響曲の三十四回シリーズもある、縁の深い作曲家。今回は一月にジャッド指揮で《軍隊》をやり、さらに二月中旬にも鈴木雅明指揮で《ロンドン》が予定されているから、久しぶりのハイドン・シリーズ。
そして後半のヘンツェは、二〇一四年にメッツマッハーが集中的に、ヘンツェと同じ二十世紀ドイツの作曲家ベルント・アロイス・ツィンマーマンを取り上げていたことを思い出させる。メッツマッハーはあのときベートーヴェンと組み合わせることで、ツィンマーマンや自分たちドイツの音楽家が背負っているものを喜びと苦しみの両面から示してみせた。対してシュテンツは、十八世紀のハイドンと組み合わせることで、ドイツ交響音楽の発展史に仕立ててきた。八日には十九世紀のワーグナーとベートーヴェンを演奏して間を埋めるようになっている。
 NJPのフェイスブックから
NJPのフェイスブックからさて本番。ハイドンの二曲からして、一七六四年と九一年、バロックから古典派への過渡期を示す好対照。まず弦楽の配置が面白い。十一‐十一‐八‐六‐四のヴァイオリン二部を両翼に配するのは当然として、ヴィオラを中央に置き、チェロとコントラバスは半数ずつその左右に分け、ヴァイオリンの裏に置く、シンメトリックな配置。上手側にはチェンバロが入って、いかにも初期古典派。
そして《哲学者》の第一楽章、ファゴットはいつもの中央弦楽裏に座るが、ホルン二人は下手側の端、コーラングレ二人は上手端に離れて立ち、演奏開始(上の写真)。コーラングレが入るだけでも珍しいのに、目立つ位置にくることで視覚的にも音響的にも存在が際立つ。そして、ホルンとコーラングレは混ざることなく、交互に、呼び交わすようにハイドンが書いていることも、これでよくわかる。さらには、ホルンが吹くときは反対側の上手のコントラバスが休み、コーラングレが吹くときは下手のチェロとコントラバスが休んで、響きのバランスの変化をさらに明快に。
こういう、空間を意識した音響の発想は、いかにも現代音楽に精通した指揮者らしいもので、とても面白い。第二楽章からは普通に管楽器席について演奏。
二曲目の《驚愕》。弦は人数も配置もそのままで、管楽器は通常の二管編成となり、トランペットとティンパニが加わり、代りにチェンバロは退場。フランス革命を合図に沸騰し始めるヨーロッパの市民社会、オーケストラは軍楽隊の楽器を加えて豪放華麗に、そして貴族の楽器チェンバロは退場。
弦の配置は《哲学者》のまま。こうして中低音の弦が横一線に広がって響くと、第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンのかけあいが、より明確に響く。シュテンツの工夫に納得。第二楽章ではティンパニの居眠りに気づいた下手側のコントラバス奏者が駆けつけ、代りにドンと叩いて奏者を起こす小芝居つき(笑)。カンブルランのニューイヤーでも《雷鳴と電光》で若い楽員たちが傘をもって踊っていたし、最近の楽員さんはいろいろ大変。
キビキビととんがっていて、演奏も面白い。一月のジャッドの《軍隊》が「アンサンブルのおけいこ」的な、きっちりした一九七〇年代の新古典主義的演奏だったのとは好対照(ジャッドにインタヴューしたとき、ジョージ・セルを引き合いに出して、古典派はアンサンブルの基礎をつくるために不可欠だと話していた。まさにそのとおりの演奏だった)。
そして後半は、ヘンツェの交響曲第七番。弦は十六型でピアノ配置、四管編成で打楽器六人、ピアノとチェレスタも加わる、ティラノサウルス的巨大編成。ハイドンから始まった拡大傾向の極点の一つ。一九八四年、ベルリン・フィル創立百年を記念する委嘱作だったというのが象徴的。石川亮子のプログラム解説から孫引きすると「私は常にベートーヴェンの伝統というものに魅力を感じてきた。第七番はドイツ的な交響曲であり、ドイツ的なるものについての交響曲である」と作曲家は述べているという。
ベートーヴェンの交響曲の伝統を背負う。その意味で、ヘンツェもシュテンツも、ツィンマーマンとメッツマッハーと同じ歴史的文脈のなかにいる。
しかもその「ドイツ的な交響曲」が、ベートーヴェンと同じ一七七〇年に生まれて、同じ革命の時代の空気を吸いながら、やがて狂気にとらわれ、心を病んでいった詩人、ヘルダーリンの生涯とその詩に基づいているというあたり、ヘンツェの複雑な心情が象徴されているよう。美しい悪夢のような音楽。
「ハイドンとヘンツェのあいだ」の十九世紀作品も楽しみだし、鈴木雅明のブラームス、ハイドン、メンデルスゾーンも、また違った文脈を提示してくれそうで、大いに楽しみ。
二月七日(水)頼政
国立能楽堂公演。
・狂言「無布施経(ふせないきょう)」野村万作(和泉流)
・能『頼政(よりまさ)』塩津哲生(喜多流)
二月八日(木)シュテンツ二回目
シュテンツ指揮新日本フィルをサントリーホールで。
・ワーグナー:歌劇《ニュルンベルクのマイスタージンガー》第一幕の前奏曲
・ヘンツェ:ラ・セルヴァ・インカンタータ
・ベートーヴェン:交響曲第三番 《英雄》
キビキビと俊敏に、刺激的に運ばれる《英雄》がとても面白かった。五日前のハイドンと同じく、ヴィオラを中央にチェロとバスを左右対称に分割して配置。だからこそ明快になる、ハイドンからの革命的変化。饒舌と情熱。一方で、前半の肥大した響きとも対照的。
新日本フィルとはかなり相性がよさそうなので、これからも呼んでほしい。
二月十日(土)東北
横浜能楽堂にて大槻文藏の能『東北』を観る。
二月十四日(水)合奏の時代

JPCの荷物到着。左はシュタンゲル率いるタッシェンフィルハーモニー(ポケット・フィルハーモニック)のベートーヴェンの交響曲全集。弦は各一人の十二~十六人の室内交響曲サイズで第一~八番を演奏し、第九だけは二十六人に増強して合唱とバランスをとる。
いうまでもなく、ポケット化といってもベートーヴェンの場合はマーラーなどに較べてオーケストレーションの変更に無理が少ない。それで、すでに三番と七番は出ていたが、わざわざ聴くまでもないかと思っていた。しかし交響曲全集、史上初の室内交響曲版全集にまとめたとなると、聴いてみたくなった。
聴いてみると、これが意外な拾い物。演奏そのものが正攻法で、リズムの弾力を自然に出したのが、とても魅力的。弦の厚みでごまかしてしまうような大味なベートーヴェン演奏よりも、見通しの良さと呼吸感があることで、よほど曲の面白みと偉大さが素直に出てくる。revisited、「ベートーヴェン再考」を謳うだけのことはある中身。
「英雄的存在」としてのカリスマ指揮者の「解釈」にたよらない、二十一世紀のアンサンブルの時代、合奏の時代にふさわしい、小気味のいいポケット・ベートーヴェン。
右下は日本でも発売予定の、ラトル&LSOのハイドン。「空想のオーケストラの旅」と題された名曲集で愉しそう。
右上は、『モンティ・パイソンのスパマロット』。史上最も優れたアーサー王映画という人さえいる(?)『モンティ・パイソン・アンド・ザ・ホーリー・グレイル』の、ミュージカル版。ザルツブルク州立劇場(LANDESTHEATERだから、これはまさしく州立劇場)でのドイツ語版ライヴ。ドレスデン国立オペレッタの『ワンダフル・タウン』がとてもよかったので、味をしめて買ってみたもの。オリジナルの映画版は大好きなのでこれも楽しみ。
二月十五日(木)パーヴォ語る
代官山(生れてから三十七年も東横線沿線に住んでいたのに、降りて改札を通ったのはせいぜい三度目)のライブハウス「晴れ豆」(晴れたら空に豆まいて)にて湯山玲子さん主宰の「爆クラ!」。 「指揮者パーヴォ・ヤルヴィと語る、バーンスタイン・ラヴ!!!」
 「晴れ豆」のサイトから
「晴れ豆」のサイトから現代のオーケストラの三種類のありかたとか、ウィーン・フィルとベルリン・フィルの二十一世紀における進路の違いとか、パーヴォもやはりそう考えているのかという話も多く、濃密な三時間。
バーンスタインがテーマのはずが、後半はマーラー、シュトラウス、シェーンベルクの比較論になり、その方がメインになってしまった気も(笑)。
しかしあとでふり返ると、パーヴォが途中で語った、WSSの成功で「キング・オブ・ライト・ミュージック」になったバーンスタインが得られなかった、劣等感の原因になった「シリアスな音楽における成功」とはどのようなものなのかが、三者の比較論のなかに暗示されていたとも考えられるわけで、こういうあたりは、さすがに頭脳明晰。
それ以外にもいろいろと示唆に富んでいた。そのなかで「なるほど」と思ったのは、マーラーの第七番の冒頭のあの揺れるような動機を、銃殺刑執行前の小太鼓の連打音だと、パーヴォがとらえていたこと。
十一日のN響で聴いた演奏のあそこのテンポは、それであんなに速かったのかと納得。そうなれば、全体もそれに引っ張られて当然に速くなる。そこには含まれていない小太鼓の音を、オーケストラの響き全体が暗示していく、ということかも。先日の快速テンポの理由と解釈の一端が、見えてくるような。
二月十六日(金)離郷の歌、望郷の歌
十一時から「ラ・フォル・ジュルネTOKYO2018」の記者会見。会場が例年の東京国際フォーラムではなく東池袋の豊島区役所(新しい)なのは、今年から東京国際フォーラムと東京芸術劇場の二か所開催となったため。北国街道沿いの滋賀、金沢、新潟での開催が終了して、名称も「オ・ジャポン」から「TOKYO」に。
大野和士の「オペラ夏の祭典」も新国立劇場と東京文化会館の共催で双方の会場で上演される。東京を分割して都内のホールが共存共栄をはかるスタイルが、今後は流行するのかも。高校野球の東西地域分割みたいな感じか。神奈川や埼玉のホールを含めた連携もありえそう。
テーマは「UN MONDE NOUVEAU ‐モンド・ヌーヴォー 新しい世界へ」。ルネ・マルタンによると当初は「exile(亡命)」だったが、亡命という訳語の語感を嫌って変更したのだとか。「exileは、語源的には移住といった意味も含まれる」と説明。
テーマそのものも四年前に決めたときには欧州で難民問題がこれほど大きくなるとは予想もしておらず、今となっては政治的色彩を帯びかねないので変更も検討したが、企画がすでに進行していたのでそのままにしたとのこと。
 公式サイトから
公式サイトからフェスの内容の紹介はまた別の機会にして、十四~十六日は出郷というか離郷というか、そのテーマを想起させていくものに遭遇する機会が多かった。
十四日はサントリーホールでクレーメルとクレメラータ・バルティカ。ソ連時代のラトビアに生れて、一九八〇年に亡命。一九九七年にバルト三国の若手を集めて結成したのがクレメラータ・バルティカ。今年は第一次世界大戦終結百年、つまり近代国家としてのバルト三国独立百年。クレメラータ・バルティカは「祝バルト三国独立百周年文化大使」に選ばれているそうで、客席には皇太子殿下夫妻を初めとして三国の大使関係者が顔をそろえる。エストニア出身のパーヴォ・ヤルヴィもいた。
曲はベートーヴェンとモーツァルト。《セリオーソ》の弦楽合奏版に始まり、文字どおりシリアスに演奏が進むが、最後の《セレナータ・ノットゥルナ》終楽章のカデンツァでソロ四人が次々と遊び始めて、懐かしいロッケンハウス音楽祭のノリに。亡命翌年にクレーメルがはじめたロッケンハウス音楽祭でのライヴ盤は、一流音楽家が冗談音楽を本気で手がける面白さを、私に初めて教えてくれたものだった。あれはクレーメルの「新しい世界」での存在証明だったのだろう。これも「合奏の時代」の一つ。
翌十五日、指揮者テミルカーノフにインタヴュー。やはりバルト海沿岸にあるサンクトペテルブルク=レニングラードで、旧ソ連時代から生き抜いてきた指揮者。ちょうど回顧録が出たばかりで、父親が侵攻してきたドイツ軍に銃殺されていたこと、その直前にプロコフィエフと交流があったことなどを知った。十一月の来日公演に向けたインタヴューで、そのときはラフマニノフの交響曲第二番とプロコフィエフの《イワン雷帝》を演奏する。「ラフマニノフは亡命してそのまま死んだのに、プロコフィエフはソ連に帰りました。二人の違いはどこにあると思われますか?」などの質問をしてみたので、返答は記事になったときに。
その夜は「晴れ豆」の「爆クラ!」でパーヴォのトークイベント。『ウエスト・サイド・ストーリー』との出会いは、私も含めた大半の日本人と同様に映画版だったという湯山玲子さんの「あの映画を初めて見たのはいつですか?」という質問に、パーヴォは「自分は十八歳までソ連にいたので、それまでは見ることができませんでした」と答えた。
日常的な会話のなかに、過去の異常な世界が突然顔を出す。いや、日本にいる自分にとって「異常」なだけで、同い年のパーヴォにはそれが日常だった。父ネーメが西側で買ってくるレコード、《ミサ》などを通じてバーンスタインの音楽に出会ったという。それから父に従ってアメリカに行き、そこで成人した人。
翌十六日、LFJの記者会見のあと、すみだトリフォニーへ移動して十四時から鈴木雅明指揮の新日本フィル演奏会。気迫のこもった、集中力に満ちた、背筋の伸びるような名演。ロンドンに行って新たな創作環境を得たハイドン、キリスト教世界にユダヤ人として生きたメンデルスゾーン。
続いて千駄ヶ谷に移動し、十八時半から国立能楽堂で能の『熊野』。平家全盛の時代、熊野(ゆや、と読む)は、駿河の池田の宿から京に平宗盛に連れてこられて愛妾となっている女性。病身の老母を見舞う帰郷を願い出るが、花見に随行させたい宗盛は許さない。今生の別れにもう一度と願う母の手紙が来て、熊野がそれを宗盛に読ませても許されず、花見に連れて行かれる。
牛車に揺られながら、京の東山を南に進む熊野。牛車の窓から覗き見る六道珍皇寺や清水寺の春爛漫の風物を謡で描きながら、牛車の中の暗がりに沈み、母の無事を祈る熊野の心と対照させていく、言葉のマジック。
わずか三間四方の空間に、都の春の風景の広がりと人の心象の深さが浮かび上がる。これはなるほど、傑作中の傑作。
花見の宴で求められて、熊野は舞う。突如降りはじめ、花を散らす村雨。
「春雨の、降るは涙か、降るは涙か桜花、散るを惜しまぬ、人やある」
五七調で口になじむ詞章。諸行無常。この雨に霊感を得て、熊野は歌を書き留める。
「いかにせん都の春も惜しけれど、馴れし東の花や散るらん」
時宜を得た歌の出来ばえに感服した宗盛、一転して熊野の暇乞いを許す。喜色満面、宗盛の気が変わらぬうちにと、取るものもとりあえず帰郷を急ぐ熊野。
ここでポイントになるのは、権力者の奢れる心をも動かす和歌の力。時宜を得た歌がもつ、その力の大きさ。
能は、萬葉集以来の日本独特のこの原理、言霊の原理を舞台化したという一面ももっている。『忠度』との共通点。
私は、その日本に暮らしていられるけれど。
二月十八日(日)熊野松風

能では「熊野松風に米の飯」という。
ご飯と同じく『熊野』と『松風』は毎日食べてもけっして飽きのこない、味わいのつきない名作だという意味。
十六日に『熊野』を初めてナマで観てなるほどその通りと思い、二日後に《松風》を見て、やはりその通りと思う。後者は細川俊夫のオペラ版だが(笑)。
音楽も演出も舞台も、能という芸術の抽象化された外形を真似るのではなく、その内奥に切り込み、『松風』の宇宙をオペラという芸術に換骨奪胎している。
より生々しく肉体の存在を実感させ、残滓がこびりつく。枯れ枝。日本語ではなくドイツ語であること。生命。髪。
それにしても『松風』の世界は、とにかくすべてが「るす」。ただし高橋新吉の詩は「いるのにいない」が、『松風』の場合は「いないのにいる」。
死んで魂魄だけがとどまっている松風村雨の姉妹がそうだし、姉妹を残して帰京、そこで死んだ在原行平も、烏帽子と狩衣という装束だけが遺っている。そしてこの行平は伊勢物語の在原業平の兄。業平本人ではないのに、そこにはどうしても美男子業平、「昔男」のイメージが重なってくる。舞台が明石となれば、源氏物語の光の君の残像も。それにキーワードとなる行平の「立ち別れ」の歌も、因幡の国に赴任したときのもので、須磨ではない。「それじゃない」ものがいくつも物語世界の背後に影を重ねる、「いないのにいる」話。
松風と村雨という、行平が姉妹に名づけた名前からして、後者が『熊野』で効果的に用いられたように、世の無常を実感させる自然現象のこと。
舞台公演というものも、一夜明けてしまえばすべては、その場にいた人の心の中に留まるだけ、「いないのにいる」だけのもの。立ち会った者がみな「ワキ」となって、それを語り継ぐ。
能そのものの面白さも、「いないのにいる」にある。言葉が、象徴化された身ぶりや装束や作り物をよすがにして、三間四方にそれを現出させる。公演が終るのは囃子が止んだ瞬間ではない。登場人物だけでなく囃し方も地謡もすべて舞台を去り、作り物も片づけられて、初めと同じ何もない空間に戻って、そこで終わる。いないのにいた。
昨日のオペラはそういうことを真似はしないけれど、「いないのにいた」感じは新たに鮮烈。そこが素敵。
二月二十一日(水)白鳥の騎士に米の飯

二期会の《ローエングリン》初日。日経新聞に評を書くので感想はパス。
ゲネプロと二回見て、深作演出の要点は自分なりに理解できたと思う(自分は舞台から受ける印象がすべてと思っているので、演出家の言葉などは、すくなくとも公演以前には目にしないようにしている)。一回だけだと、自分程度の知能や知識では誤読したかもしれない。
これからご覧になる方のために、ネタバレなしで一言アドヴァイスするなら、字幕で意味ありげにカタカナ表示される「ハイル」や「フューラー」といった単語には、とらわれない方がいい。
これはナチスとの関係を暗示する、言葉遊びとしては面白い語句だと私も思うが、あくまで副次的なものであって、今回の演出が表現したいこととは、ほとんど関係がないと私は思う。
それにしても《ローエングリン》第一幕の音楽は、私にとっては熊野松風と同じく米の飯。これと《美しきエレーヌ》があれば、とりあえず生きていける。
もちろん、日によって焚き加減が違って硬軟の好き嫌いがでたり、米が古くて味がなかったりもするが、そんな出来不出来もひっくるめて、毎日食べられる。
ふたを開けた瞬間に米がキラキラと光り輝いていて、口に含むとそのあまりの甘みに泣きそうになった、なんていうご飯には半世紀で数回しか出会ったことがないが、その思い出だけで明日も食べてみようと思えるのが、米の飯と《ローエングリン》第一幕というもの(笑)。
この春は二期会のゲネプロと本番、そしてさらに東京・春・音楽祭と、三回も食べられる予定なので、幸せ。
ところでプログラムに、公演監督の大野徹也さんが一文を寄せている。二期会での《ローエングリン》は一九七九年以来、三十九年ぶり二度目の公演だそう。大野さんは前回の公演(若杉弘指揮、西澤敬一演出)に、四人のブラバントの貴族の一人として参加していたとある。
私の知り合いでもこの公演に出演していた人がいる。その人によるとローエングリン役のテノール(特に名を秘す)、肝心要の登場の場面で声が裏返ってしまったとか。その師にあたる総監督の中山悌一は頭をかかえてしまい、第一幕終了と同時に家に帰ってしまったという。
それに較べると福井敬さん、朗々と響く安定した発声で、本当にありがたし。
二月二十二日(木)映画版復元
サントリーホールでパーヴォ&N響の武満&ワーグナー。《指環》抜粋は、最後の《ラインの黄金》の〈ワルハラへの神々の入場〉での、ラインの乙女の声部を吹いた木管の美しさに心奪われる。
今月のパーヴォ&N響のBプロとCプロ、その前のライナー・ホーネック&紀尾井ホール室内管の定期と計三回、目が覚めるように鮮やかで美しい木管のソロがオーケストラからスパンと抜けて響いてきてハッと驚くと、そこにいるのはいつもオーボエの吉井瑞穂さんという、恐るべき事実。まさしくワールドクラス。
 公式サイトから
公式サイトから佐渡裕の指揮で「ウエスト・サイド物語」シネマティック・フルオーケストラ・コンサートが行なわれるという。オリジナルの歌と効果音を残して、オーケストラ部分だけ最新技術で分離、カットしてあるそうだ。映像に合わせるアテブリが大変そう。
ハリウッド映画版のオーケストレーションはブロードウェイ版とはまったく別物の、ハデハデ華麗ヴァージョン。シャルク改訂版のブルックナーの五番みたいで、個人的にはブロードウェイ版のシンプルな響きが好きだが、それでも映画版のオーケストレーションが復元されてナマで響くことには、興味津々。
「映画製作時の演奏で使われたオリジナルの編曲資料は全てなくなってしまっていたが、レナード・バーンスタイン事務所のエレノア・サンドレスキーによる14か月に及ぶ調査の結果、アメリカ中の図書館のアーカイブや個人のコレクションの中に宝物ともいうべき資料が数多く見つかった。また、映画版の編曲を担当したシド・ラミン、指揮者・音楽監督のジョニー・グリーン、監督のロバート・ワイズ、プロデューサーのウォルター・ミリッシュの個人所蔵アーカイブからも数々の資料が発見され、サンドレスキーは映画版の全スコアを完成させるのに必要な素材の端々を揃えることができた」
二月二十七日(火)スコットランドより

オペラシティでミンコフスキとルーヴル宮音楽隊のメンデルスゾーン演奏会。フィンガル~イタリア~スコッチ。初期稿使用により慣用版では耳慣れない響きがあちこちに。ピリオド楽器すてき。十二月のデュトワ&N響のモダン楽器十六型では、美しいけれど大味でつまらない音響としか聴こえなかったスコッチが、多彩で緊張感に満ちた音楽に変身。
特に強烈に印象に残ったのは、冒頭で木管群がバグパイプそのもののような響きを出してみせたこと。あの響きの玄妙さは、たぶん一生耳に残るだろう。
二月二十八日(水)龍宮より
千駄ヶ谷でひさびさのプール能。狂言『浦島』と海幸彦の伝説を扱った能『玉井』の二番だけに、今日泳がずしていつ泳ぐ。
・復曲狂言 『浦島(うらしま)』野村又三郎
・能『玉井(たまのい) 龍宮城』梅若紀彰、梅若玄祥(観世流)

豊玉姫と玉依姫、龍宮の姫二人の連舞の艶やかさ。青木繁の『わだつみのいろこの宮』の絵、海の底なのになぜ樹上にいるのかと思っていたが、この『玉井』の設定によるものだったとは。姫二人の他に海神(玄祥)、アイで四人の貝の精も出る、いかにも観世信光作の賑やかな能。ただ、視覚的に賑やかなことがかえって想像力の羽ばたきを奪ってしまう部分もあり、潮の満干を自在に操る豪快さと天地の広大さを想像させる喚起力は、七月に観た『鵜羽』の方が見事だった。このあたりが信光と世阿弥の違いか。
三月三日(土)タツヤの神曲
サントリーホールで日本フィル定期。指揮は下野竜也。今シーズンの日本フィルの曲目は、幕末の薩摩藩なみに攻めたててくる。企画をしているのが益満休之助のご子孫だから当然か。今回も益満子孫と下野コンビの面目躍如たる、普通はありえないような曲目。
・スッペ:喜歌劇《詩人と農夫》序曲
・尹伊桑(ユン・イサン):チェロ協奏曲(チェロ:ルイジ・ピオヴァノ)
・マクミラン:イゾベル・ゴーディの告白
・ブルックナー(スクロヴァチェフスキ編曲):弦楽五重奏より「アダージョ」

あとの三曲のつながりはなんとなくわかるが、最初のスッペの意図が読めなかった。すると本番、この曲のあとの配置転換の時間に下野本人が舞台から説明してくれた。日本統治時代の一九一七年に朝鮮で生れたユン・イサンは十八の年に大阪に来てチェロと作曲を学んでいる。それからどんな生涯になるのか、どんな作風になるのか、本人もまったく予想できなかったろう若き日に、かれが聴いたかもしれない作品として、チェロ独奏をもつこの曲を選んだとのこと。たしかに昭和十年代の日本なら、この曲は今よりも広く聴かれていたろう。近衞秀麿指揮新交響楽団のSP(チェロは齋藤秀雄)があることも有名だ。
この明朗な、純粋無垢な若き日を出発点に、ダンテならぬ「タツヤの神曲」が始まる。地獄~煉獄~天国。あるいは冥界~人界~天界。
ユン・イサンの作品は、韓国諜報機関KCIAによる拘束と拷問、スパイ容疑での死刑判決と特赦による釈放を経験してきた作曲家の自伝的作品。ひたすらに苦しく、寒くてとげとげしく痛い、救いの光も見えない音楽。地獄。
続くマクミランの作品は、十七世紀魔女狩りの時代に魔女であることを自白したスコットランドの女性を題材とするもの。魔女狩りというと無実の女性が罠にはめられ拷問で無理に自白させられて火刑に、みたいな展開を想像するが、この人は訴えられてもいないのにわざわざ自分から告白してきたというし、話は荒唐無稽で裁判の判決も不明というから、一種の誇大妄想の気配が濃い。そのためかこの作品は、人の心の中の善と悪、正気と狂気、祈りと呪いの、激しく不断の交代と葛藤を音にした心理劇のようになっている。最後に強烈な音響で満たされ、目がくらむほどの輝く光に包まれたように感じられたのは、救いの暗示なのだろうか。としたら煉獄。
そしてブルックナー。弦楽合奏なので交響曲のアダージョほど疑似宗教的な大仰さがないのが安らかで心地よし。
天界は見えたか。
三月七日(水)千手の恋、無音の音楽
昼は国立能楽堂定例公演。
・狂言『音曲聟(おんぎょくむこ)』茂山逸平(大蔵流)
・能『千手(せんじゅ)』髙橋忍(金春流)

『千手』は平家物語を題材とする能なので、前から見たかったもの。一ノ谷で捕虜となり、鎌倉に移送されてきた平清盛の五男、本三位中将重衡卿がシテ。史実では平家一門を代表する文武両道の指揮官だったらしいが、平家物語では文弱のイメージが強く損をしている。
治承の乱で南都奈良を攻めたさい、東大寺大仏殿や興福寺など堂塔をことごとく焼き払う結果を招き、大罪人として僧俗の憎悪の的となった。そのため鎌倉から南都に引き渡されて斬首されることになる、その鎌倉を出る前夜の話。
栄華の日々は夢のごとくなり、敗残の身を嘆く重衡。出家を願い出るが朝敵ゆえに許されない。その境遇を慰めるために頼朝に仕える女性、千手の前が遣わされる。菅原道真の詩を朗詠し、琴をひいて重衡の琵琶に和する。宴と恋情の一夜が明け、重衡は出立していく。
情感のあるいい話だし、千手のキャラクターも素敵だが、詞章が説明的で卑俗なのが残念。知名度の高さに比して名作とはいわれないのは、このためか。最後の地謡が「げに重衡の有様、目も当てられぬ気色かな」では、俗っぽすぎて興が醒める。近年は『重衡』という別の復曲能があって、それを浅見真州や大槻文藏が演じているのは、『千手』にあきたらないからかも(これも見てみたいと思っているが機会を得ない。昨年は大槻文藏がゆかりの奈良で演じたのに、日程の都合がつかなかった)。
能楽師について偉そうなことは言えないけれど、地謡がずっと口ごもっているようで意気あがらないのは気になった。もっと元気があってもいいのでは。
夜はトッパンホールでダニエル・ゼペックによる無伴奏のヴァイオリン・リサイタル。
・テレマン:十二のファンタジーより第九番
・ベリオ:セクエンツァ 第八
・ビーバー:《ロザリオのソナタ》より 第十六曲〈パッサカリア〉
・ボッソベ(アカ・ピグミー族の音楽)
・ライヒ:ヴァイオリン・フェイズ
・バッハ:無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第二番

バロックと二十世紀の作品が交互に。ライヒの作品は、録音されたアフリカの民族音楽からそのまま開始。舞台にスピーカーが設置され、事前に録音されたゼペック自身の演奏と生演奏が重なり、反復と追奏をくり返していく。バッハのシャコンヌも低音部は執拗な反復。
反復を重ね、聴く側の時間感覚が曖昧になってきたとき、音が突然に止む。その瞬間、無音の瞬間にそれまでのすべての音と時間が圧縮されて詰め込まれたような、不思議で圧倒的な感覚を味わう。
「永遠の一瞬」の背中がちょっとだけ見えたような、そんな気持。
三月八日(木)ヤマカズ版《白鳥の湖》
フェイスブック友達の方が何人か行かれて、いずれも絶賛している、東京シティ・バレエ団の《白鳥の湖》。
大野和士指揮の都響がピットに入り、昭和二十一年の旧帝国劇場での「日本初の全幕上演」で用いられた、藤田嗣治の舞台装置を再現しているというのも大きな話題。自分は見られなくて残念。
帝劇公演ときいて思い出したが、このときは山田一雄が指揮しただけでなく、全部自分でオーケストレーションしたという、伝説的な上演だった。
やると決めたはいいが、日本にはピアノ・スコアしかないことが判明(笑)、敗戦直後の状況では海外から取り寄せることもできず、しかたなく三か月かけてオーケストレーションしたという。
自伝を読むかぎり、元のオーケストラの響きを山田は知らないまま(断片的には録音もあったろうが)、好きなようにやったらしい。
藤田の原画も散逸しているというし、当時のバレエ公演のスコアの管理とか本当にいい加減だから、山田版のリ・オーケストレーション、おそらくは失われているのだろうが、藝大に寄贈された山田一雄の遺品コレクションの中に眠っていたりしたら、面白そう。
三月十日(土)平和祈念
今日の「すみだ平和祈念コンサート2018《すみだ×広島》」のコンサートのプログラムに、以下の文章を寄せた。自分の備忘録として載せておく。
・ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲(独奏:大江馨)
・ブラームス:交響曲第一番
上岡敏之(指揮)新日本フィルハーモニー交響楽団
明治生まれの私の祖父は、故郷の仙台から勉強のために東京に出てきていた二十二歳のとき、関東大震災に遭遇した。
水道橋駅の線路脇の土手に逃げて、様子をうかがったという。一週間後、汽車を乗り継いで生家の最寄り駅までようやく帰り着くと、駅員さんから、君のお母さんは昨日まで毎日、君が無事帰ってくるかどうかを心配して、朝から晩までそこの改札口で待っていたんだよと教えられ、初めて本当の意味で、親心のありがたさを知ったという。
それから二十二年後の夏、当時十三歳の父は、仙台近くの工場に徴用されて働いていたが、中心部が大空襲にあったため、翌朝に帰宅させられた。通りかかった仙台の町は一面の焼け野原、見たくないものまでたくさん目にしながら、郊外の家まで歩いて帰ったという。東京大空襲からちょうど四か月後の、昭和二十年七月十日のことである。
どちらも、私にとっては間接的な体験にすぎない。祖父も父も、とうの昔にこの世を去っている。しかし、これらの話を聞かせてくれたときの口ぶり、表情は、いまもありありと思い出すことができる。そして、何よりも二人がそのときに生き残ってくれたおかげで、いま私はここにいて、こんな文章を書いている。
今日ドヴォルザークのヴァイオリン協奏曲で独奏をつとめる大江馨は一九九四年仙台生まれ。東日本大震災の数年前、高校入学と同時に横浜に移っていたそうだが、震災後にはがれき処理のボランティアをし、また数々の復興支援コンサートにも、積極的に参加してきたという。
若い大江さんはきっと、その体験を音楽活動に活かし、明日につなげてくれるだろう。戦災も天災も、罪なき人々に大きな苦しみを残す点では、同じである。今日の演奏会では、平和と平穏への思いを、どのように込めてくれるだろうか。
そして後半、上岡敏之と新日本フィルが演奏するブラームスの交響曲第一番。これは「暗から明へ」というベートーヴェン的な構成で、多くの人に愛される作品だ。ティンパニの連打で、苦しみや葛藤を示すように始まる第一楽章。その後にほの暗く、気分の晴れない二つの楽章をはさんで、終楽章の初めでは葛藤が回帰するが、アルペンホルンの響きを想わせるメロディが登場して、景色は一気にひらけていく。前へ、明日へ進もうとする、強い意志と信念。言葉にすると嘘くさくなりやすい思いが、そうはならないのが、音楽というものの不思議な魅力である。
三月十二日(月)ルノーのヴァイオリン
トッパンホールでルノー・カピュソン(ヴァイオリン)と 児玉桃(ピアノ)のリサイタル。
・ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ(遺作)
・フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第一番
・メシアン:主題と変奏
・サン=サーンス:ヴァイオリン・ソナタ第一番
・ラヴェル:ツィガーヌ

さらにアンコールでドビュッシーのヴァイオリン・ソナタの第三楽章とマスネの《タイス》の瞑想曲という、近代フランス音楽史総まくりみたいなプロ。
香気豊かに始まり、後半のサン=サーンスとラヴェルでのスケールの大きな、凄まじいばかりのヴィルトゥオジティにただただ圧倒される。ここまでひきぬいても無機的にならないのがすごい。
三月十五日(木)夜の博物館

今年も「東京・春・音楽祭」開幕。今日はそのプレ・イヴェント、〈ナイトミュージアム〉コンサート。
自分みたいなクラオタは、この音楽祭でもメイン会場の東京文化会館の大ホールと小ホール、特に後者にばかり行ってしまいがちだが、この音楽祭の大きな特徴は、上野の森に複数ある博物館と美術館でも、その講堂やエントランスで演奏会をたくさん行うこと。
なかでも行ってみたかったのが、一昨年から国立科学博物館で始まった、この〈ナイトミュージアム〉コンサート。地球館の常設展示室でやるという以外、どんなものなのかさっぱりわからずに行ったのだが、とても楽しかった。

十九時からの二時間、写真のタイムテーブルの通りに、地上三階地下三階の博物館の展示室で、五組の演奏家が同時多発で短いコンサートをくり返している。お客は広い博物館内を自由に回遊しながら、それを聴く(聴かなくてもいい)。かすかに流れてくる楽音を聴きながら、隣室の展示物を見て回るのも自由。
二階にあるラバウルで引き揚げられた複座式の現地改造ゼロ戦の前ではクラリネットがピアノと演奏し、地下一階のティラノサウルスの前でヴァイオリン。三階では剥製の動物に囲まれて二十絃箏。地下二階の古代の巨大なウミガメの骨格の下ではバンドネオン、といった感じ。
しかもワンドリンクつきなので、食堂に行って飲み物をもらって別売りの軽食を買い、おしゃべりしていてもいい。
つまりはいわゆる学園祭ノリ。ラ・フォル・ジュルネのもっと気楽な博物館版というか(しかも音響が意外にいい)。
そして、何といっても嬉しいのが、普段は入れない夜間の博物館をウロウロできるという、やってはいけないイタズラをやっている、あの不思議にゾクゾクする感じ。
ほかに人もたくさんいるし、照明はいつも通りだし、窓はないので夜空が見えるわけでもないし、違法なことをしているわけでもないのだが、子供時代の夢がかなったような、不思議な快感。
それにしても中学以来おそらく四十年ぶりの国立科学博物館、かなり垢抜けた展示法になっていた。その前に行ってみた東京国立博物館が相変わらず地味だったのとは、対照的。
 ピアノの向うに、ゼロ戦を現地で2機つなげてつくった偵察用の複座式。
ピアノの向うに、ゼロ戦を現地で2機つなげてつくった偵察用の複座式。 なぜか座り込んでいるティラノサウルス。演奏中は撮影禁止なので、ヴァイオリンの演奏終了後に撮影。
なぜか座り込んでいるティラノサウルス。演奏中は撮影禁止なので、ヴァイオリンの演奏終了後に撮影。 でかい魚竜。尻尾の方にウミガメがいる。左端に写ってるのは地上最大の哺乳類パラケラテリウム。たしかに馬鹿みたいにでかい。
でかい魚竜。尻尾の方にウミガメがいる。左端に写ってるのは地上最大の哺乳類パラケラテリウム。たしかに馬鹿みたいにでかい。 なんかこう、ナイトミュージアムな感じの写真(笑)。
なんかこう、ナイトミュージアムな感じの写真(笑)。 ハワイの日系コレクターが寄附したという、大量の物言わぬ剥製群。昔見たタローとジローはいなかったが、別の階にパンダのホワンホワンがいた。
ハワイの日系コレクターが寄附したという、大量の物言わぬ剥製群。昔見たタローとジローはいなかったが、別の階にパンダのホワンホワンがいた。
三月十六日(金)一人の女と二人の男
オペラと能をはしご。国立オペラ能。
十四時から新国立劇場でドニゼッティの歌劇《愛の妙薬》、十八時半から国立能楽堂で能『求塚』。
・狂言『太刀奪(たちばい)』善竹忠一郎(大蔵流)
・能『求塚(もとめづか)』観世清和(観世流)

西洋の喜劇と日本の悲劇。他はあらゆる点で違うのに、一人の女と二人の男の三角関係という構図だけ共通しているのが面白い。
《愛の妙薬》は人間の負の側面には目を向けない、執着とは無縁の話。二人目の男は、もともと惹かれあっている男女の仲を成就させる触媒として登場するだけで、結婚直前までいった女に振られても、あっさりと納得してあきらめる。
『求塚』は逆に、強すぎる執着がもたらす破滅。二人の男が一人の女に同時に懸想し、互いに譲らない。女はどちらと決めることができずに死を選び、絶望した男たちも刺し違えて死に、女の墓の左右に葬られる。
これは萬葉集と大和物語にある菟名日処女(うないおとめ)の伝説を元にして観阿弥が書いた作品を、世阿弥が改作したと考えられている。
成仏できずに地獄に落され、死後も求婚者たちにさいなまれ続けなければならない女の苦しみを強調したのは、伝説を下敷きにした能独自の作劇法。
前場の春の菜摘の乙女たちの清らかにみなぎる生命力に対し、後場ではすべてを逆転させる。妄執を捨てられぬ死者を示す「痩女」の面をつけ、地獄の闇と炎をおどろおどろしく語るシテ。いかにも室町前半、怪異好みの中世の産物。
三月十七日(土)高遠桜
高須松平(容保の実家)庭あとの策の池の高遠桜、今年もいち早く見頃。

三月十九日(月)ピアノ五重奏
アンデルシェフスキにインタビュー。
終了後の雑談で「ベルチャ四重奏団との新録音が出るんだってね」と言うと、
「そう、ショスタコーヴィチ。知ってるのかい? 自分はどんなジャケかも知らないんだよ。もう出たの?」とご本人。
「まだだけど、ひと月以内だと思うよ」
「ベルチャは日本に来ないのか? 自分が知るかぎり最高の弦楽四重奏団だ。ベートーヴェンの全集とか素晴らしい」
「ぜひ日本でもあなたとの共演を聴いてみたい」
「やりたいねぇ」
なんてやりとりをしているうちに、カジモトの人がスマホで探してくれて、ご本人にみせた。
「なんてこった。俺写ってない……」
というオチになったのがこの盤。何はともあれ発売がとても楽しみ(笑)。

三月二十日(火)ピアノな二日間


昨日からピアノな二日間。アンデルシェフスキ(演奏聴かずにインタビュー~ベザイデンホウト(演奏聴いてインタ)~タロー(演奏聴いてインタなし)。
三人とも音楽観も音楽性も大きく異なっていたが、共通したのは鋭敏な芸術家であることと、そして、たった一人で舞台に出て虚無と対峙するという強烈な孤独感、あえていえば死神のようなものを引き連れて、それでも自我を保とうとしている人たちということだった。
これは他の楽器や指揮者や歌手にインタビューしているときには、ほとんど感じることのない感覚。(自分がいちばん苦手なガンガンバリバリひくタイプのピアニストたちも、同種の恐怖から逃れようとしてああいう演奏をするのかもしれないと、ふと思った)
それをはっきり言葉として語ってくれたのはベザイデンホウトだけだったが、アンデルシェフスキの韜晦するような言葉にも、タローの軽やかで麗しく、しかしなぜか酒場の爛れた空気と酒精分がほのかに漂う演奏にも、そしてベザイデンホウトのスカルラッティのように快活に始まり光を放ちながら、やがてメランコリーの暗い影が姿を現していくモーツァルト演奏にも、それは確かにあった。
得たものがけっこう大きかったピアノな二日間。それにしてもタローの演奏、同じトッパンホールでの先日のカピュソンのフランス・ヴァイオリン音楽史と好一対の、パリ・ピアノ音楽史。
三月二十五日(日)作曲家とその時代
「春雁我に似たり 我雁に似たり 洛陽城裏 花に背いて帰る」とは、直江兼続の漢詩。
今日はさながら「上野山内 花に背いて音楽」。
パンダと花見で大混雑のJR上野駅公演口を抜け、どちらにも背を向け、東京文化会館へまっしぐら。

まず十三時から小ホールで東京・春・音楽祭の「東京春祭マラソン・コンサートvol.8」へ。テーマは「ロッシーニとその時代(没後150年記念)」。十一時から二十時まで計五部のコンサートでロッシーニの生涯をたどるマラソンの第Ⅱ部だけ聴く。勝手に駅伝。ナポレオン戦争後のナポリ時代の話。
《オテッロ》序曲の弦楽四重奏版とか《セビリアの理髪師》序曲と同じ旋律が歌われる《イングランドの女王エリザベッタ》の〈心からの感謝を捧げ〉とか、ナマではなかなか聴けない曲が並んで嬉しい。
十四時ちょうどに終演。外に出る気になれないので四階の音楽資料室で能関係の本を眺め、十五時前に大ホールに行き小澤征爾音楽塾オペラ・プロジェクトXVI。前半の《ジャンニ・スキッキ》をみるつもりだったが、小沢征爾降板の余波で曲順変更、《子供と魔法》をみる。
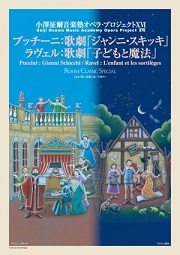
十五時、JRに乗って飯田橋へ行き、トッパンホールで十六時開演の「シュニトケ&ショスタコーヴィチ プロジェクトⅡ ―チェンバー・オーケストラ」。
井上道義指揮の特別編成の弦楽オーケストラ(六‐六‐四‐四‐二)、山根一仁とアビゲイル・ヤングのヴァイオリンに北村朋幹のピアノとチェンバロ、長谷川智之のトランペット。
・シュニトケ:コンチェルト・グロッソ第一番(一九七六~七七)
・ペルト:タブラ・ラサ(一九七七)
・シュニトケ:モーツ‐アルト・ア・ラ・ハイドン(一九七七)
・ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第一番(一九三三)

ヘビーだが刺激的なプロ。全体を聴き終えて頭に浮かんだのは「ショスタコーヴィチ・イズ・デッド」というテーマ。
ショスタコーヴィチは死んだ。
シュニトケとペルトの三曲は、ショスタコーヴィチが一九七五年に死んで、その二年後に完成されたものばかり。しかしその内容は、スターリン圧政時代の社会主義リアリズムの音楽とは程遠いという意味で、四十年以上前のショスタコーヴィチのピアノ協奏曲第一番と照応する。とりわけシュニトケはそのパロディ性において。ジャズとタンゴの借用。
スターリンが死に、そしてヴェトナム戦争も終ると、中心も目的も消滅し、形骸化するソ連の全体主義。ショスタコーヴィチが死んだとき、かれがそのなかを生き抜こうとした社会体制もまた、脳死状態になっている。
「その死後」を生きるシュニトケとペルト。隣席の柴田克彦さんが喝破されたように、この四曲はすべてコンチェルト・グロッソ、二重協奏曲のようなスタイルになっている。小編成だからこそ透けて見えてくるその構造。
ショスタコーヴィチとその時代。そういえばシュニトケもペルトも、一九八〇年に亡命したクレーメルによって西側に伝えられ、広められた音楽。伝道者クレーメル。その意味と役割は?
三月三十一日(土)喜多流の『道成寺』
喜多能楽堂にて「佐藤寛泰独立記念 披キ 道成寺」。喜多流の若きシテ方、佐藤寛泰の主催公演。
・舞囃子『枕慈童』佐藤章雄
・狂言『箕被』山本東次郎
・仕舞『八島』友枝昭世
・仕舞『野守』塩津哲生
・能『道成寺』佐藤寛泰

喜多流らしいキレのいい動きが気持ちよし。喜多流では鐘を橋懸から運び込むところからすでに能が始まっている。鐘は黒川能よりは重そうだが、宝生流よりもかなり軽め。そのせいか出演者たちのヒリヒリするような緊張感は少なめ。
四月三日(火) 抽象の海、具象の島

靖国神社の「奉納夜桜能」へ。
・舞囃子『柏崎』小倉敏克
・狂言『水掛聟』野村万作・野村萬斎
・能『綾鼓』田崎隆三

いわゆる薪能。
靖国神社の能舞台は都内最古の能舞台の一つ。元は一八八一(明治十四)年に芝公園の紅葉館の隣につくられた芝能楽堂にあった。一九〇二年に靖国神社に移設された。能楽復興のシンボルだった芝能楽堂は屋内型の能楽堂の元祖で、靖国神社でも当初は能楽堂式だったが、三十六年後に現在地に移築されてからは能舞台のみで客席は露天式のパイプ椅子。
現代の薪能は鎌倉の観世流シテ方中森晶三が戦後に創始して、全国に広まったもの。屋外のかがり火の下で(もちろんそれだけでは光量が足らないので、舞台には照明が入っている)鑑賞するというのが受けて、いまも人気が高い。
今年二十六回目の「奉納夜桜能」はフジテレビ主催で毎年三日間。明治の能楽復興の功労者で、芝能楽堂と縁が深かった宝生流宗家と観世流の梅若家、この二家が毎年出演している。今日は初日で宝生流の田崎隆三がシテ。田崎はこの夜桜能の発案・企画者でもある。
都心は薪能の機会が少なく、自分は今回が初体験。席が遠いので姿も声も小さく、能楽堂公演より条件は悪いが、頭上を吹き抜ける風の爽快感は格別。野球で東京ドームより神宮球場で観るほうが、ナイターの快感を味わえるのと同じ。
例年なら満開の桜の下で観られるそうだが、異例の早咲きの今年はそうはいかない。近くのお客さんが「これじゃ葉桜能だ」と、うまいことを言う。
開演前に火入れ式。これが薪能では重要で、人気のある行事らしい。松明を持った裃姿の偉い人たちが、能管の伴奏に乗って進み、薪に点灯する。現代を代表する名手一噌幸弘が、厳粛げな儀式なのになぜか松任谷由実の〈春よ、来い〉の旋律を吹いているのが楽しい。
野村万作と萬斎父子による『水掛聟』は元気よくわかせる。野外の大観客向けということで能楽堂公演より身ぶりが派手で大きい気もするが、気のせいか。
さて『綾鼓』。これは、古典芸術のあり方とか現代の解釈とか、さまざまなことを考えさせてくれる演能だった。それはクラシック演奏、再現芸術を考えていくときにも、ヒントになりそうだ。
宮殿の庭掃きとして使われている老人が、偶然に美しい女御の姿を垣間見て、身分も年の差も忘れて恋心を抱く。そのことを知った廷臣が老人に、庭の桂の木にかけた鼓を鳴らせば、女御が姿を見せてくれると伝える。たやすいことと喜び勇んだ老人は鼓を叩くが、どんなに力を入れても鳴らない。皮の代りに綾布が張ってあったからである。からかわれたことを覚った老人は深く傷つき、女御を恨みながら池水に身を沈めて死ぬ。ここまでが前場。
後場は、老人の死を知った女御が池のほとりに出る。すると池の波の音が鼓の音に聞こえ、老人の霊が鬼となって現れる。鳴らせるものなら鼓を鳴らしてみろと笞を振るい、ひとしきり女御を責め苛んで、再び池の中に消えていく。
この能の話は去年の可変日記で何度か触れている。初心者の自分は同じ能を見比べるより、二百本以上ある未見の作品を観ることが最優先なのだが、この能だけは例外的に三回目である。
・一月三十日 浅見真州(観世流)
・五月二十五日 香川靖嗣(喜多流)
さらに、この作品を世阿弥が改作したといわれる『恋重荷』も観た。
・四月十四日 野村四郎(観世流)
何度も観た理由は、それぞれにかなり違うことがはっきりわかり、その相違が非常に興味深いからである。
能は五つある流派で上演作品に異同があり、同じ能でも詞章や演出、ときには題名も異なっている。『綾鼓』はとりわけ、私のような初心者が観てもわかるくらいに性格が違う。江戸以来の伝統的な詞章と演出の宝生版に対し、他の二つには現代人の手が入っているからだ。
まず喜多版は十五世宗家の喜多実が国語学者の土岐善麿の協力を得て一九五二年に初演したもの。物語の大筋は一緒だが詞章は大きく改変され、演出もあわせて心理描写はかなり現代風。
続いて浅見真州版は、二〇一五年に浅見の節付と演出で復曲上演したもの。詞章は宝生版によく似ているようだが、演出はかなり異なる。老人の憤怒と復讐がより写実的に演じられる。
なぜこうなったかというと、喜多流と観世流では『綾鼓』が長く廃曲になっていたため、復曲するしかなかったのだ。
喜多版では老人を結果として死に至らしめた女御の罪の意識がより表に出る。浅見版では独りよがりな老人の暴走、ストーカー的な性格が強調される。それぞれの感想は当日の可変日記に書いたので参照してほしいが、いずれにしても人間の悪意と恨み、どろどろとした負の側面を明確に感じることができる。
これに対し、今日観た宝生版は、よくも悪くも「能らしい能」。生々しい演技はほとんど切り捨てられる。後悔や怨恨の表現は抑制され、抽象化される。女御役のツレはわずかしか動かない。シテの老人も、前場で鳴らない鼓を強打する一瞬の自暴自棄の表現を除くと、その動きはゆるやかで、具象性を欠く。鬼になってからも女御にはほとんど触れない。
詞章が耳から暗示するものを、視覚面はきわめて簡素に様式化し、想像力にゆだねる。老人と女御の感情がどのようなものなのかは、見物人一人一人の憶測にまかされている。
具象的、写実的な動作を加えてドラマをより明確に描き出した二つの復曲が現代的なのに対して、宝生版は古典的だ。現代劇や歌舞伎よりも写実性が稀薄でドラマの風化が進み、舞と歌の様式美を純化しているという意味での、古典的。
宝生の『綾鼓』はあまりにお行儀がよすぎて食い足りなさが残る点で、昨年観た観世の『恋重荷』とよく似ていた。古いものだから仕方ないのかも知れない。それが古典なのかも知れない。
ところが問題は、ではこの宝生版が作品の生まれた時代の上演に近いのかとなると、そうはいいきれないことだ。
『綾鼓』も『恋重荷』も、室町時代には人気の高い曲だったらしいのに、戦国時代から江戸初期にかけてのどこかで上演が全ての流派で途絶し、江戸時代前半には廃曲となっていた。
復活はどちらも江戸期の半ば、将軍吉宗時代の享保年間(一七一六~三六)になってからである。宝生が『綾鼓』を、観世が『恋重荷』を復曲した。
しかしこの復曲は原曲そのままであったのかどうか。『恋重荷』に関しては詞章と演出の異なる一五九八年の「妙佐本仕舞付」が発見されている。現行版よりも老人の復讐が劇的で生々しく、現在はこの古演出を復活させることもたびたび試みられている。現行版を物足りないと感じるからだろう。
現行版は、復古と質素倹約を旨として堅苦しさが求められた吉宗時代の精神の反映とも思える。「武家の式楽」の儀式性にふさわしい荘重な様式美。シテ独りが目立つ印象も強まる。武士は食わねど高楊枝、やせ我慢の美学に則った演能。
江戸後期のこの「伝統」が、室町時代はもちろん、家康から家宣までの時代の猿楽の精神と同じであるとはいえない。大衆性では歌舞伎や文楽に勝てなくなった時代の、高尚化。
『綾鼓』も江戸後期風に改変された可能性が残る。喜多や浅見は現代化と同時に、幻の室町版の精神に迫ろうとしたともいえる。少なくともかれらの曲の方がより示唆に富み、現代に通じるテーマを見出しやすいと自分は感じた。
復曲や新作にも力を注ぐシテは、型を守るだけでなく、闊達に能の精神を伝えようと望んでいるのかも知れない(このあたりが、現代のクラシックのピリオド演奏にも通じる)。浅見や梅若実、大槻文藏など、故観世寿夫の薫陶を受けた世代にはその気配が濃い。
もちろん、写実一辺倒では能にならない。現代劇はいうまでもなく、歌舞伎にもかなわない。抽象と様式美こそが能の骨格だ。しかしそこへ写実、具象をわずかに交えることで息が通い、想像の翼が広がる。抽象の海に浮かぶ具象。その対照と落差が立体感、深さと奥行を生み、人の生を象徴する一瞬となる。
そしてその一瞬は、復曲や新作にしかないものではない。古典の名作のなかにも存在する。たとえば、薩摩守忠度が最期に落す扇子のように。
抽象海上の具象。その共存の瞬間を求めて、自分は能を観つづける気がする。

四月四日(水)『鞍馬天狗』予告篇
昨日の薪能に続き、今日は屋内の国立能楽堂で定例公演。
・狂言『口真似(くちまね)』山本則孝(大蔵流)
・能『鞍馬天狗(くらまてんぐ)』出雲康雅(喜多流)

『鞍馬天狗』は能における牛若丸物語の出発点。平治の源義朝敗死後、鞍馬山に稚児として預けられた沙那王こと、かつての牛若丸(子方の大島伊織)。鞍馬山の大天狗(シテの出雲康雅)に出会って、平家打倒のための兵法を授けられるという話。
春の鞍馬山の花見が舞台なので、桜の時期に上演される。最大の特徴は子方がたくさん登場すること。沙那王以外に平家一門の稚児四人、合わせて五人が着飾ってチョコチョコと橋懸を歩いてくる。数が必要なので年少の子も女児も、シテ方以外の子も混じる。大概の能楽師はこれが初舞台になるそう。今回も女児二人とワキ方一人が含まれ、最年少は二〇一三年生れ。みな父か祖父がワキツレや後見か地謡で同じ舞台で見守っている。
花見なのに桜木の作り物はない。観ていて明白なのは子方五人を春の桜そのものに見立てて、愛でる作品であること。
このことや沙那王と大天狗の微妙な関係など、中世の稚児文化というものが気になってくる。参考文献をいくつか集めて読んでみて、それから『鞍馬天狗』をあらためて考えてみることにする。
四月五日(木)きかなくてもすむ名前

上野で東京・春・音楽祭の《ローエングリン》。総体的には充実した上演だったが、オーケストラは二期会でのメルクル&都響の方がニュアンス豊かだった。
とりわけわが「米の飯」(笑)、第一幕のノリがイマイチだったのが残念。演奏会形式ではドラマの視覚的表出は歌手の演技力、それも扮装も大きな身ぶりもない状態での、表情とわずかな動作の表現力にすべてがかかる。エルザ役のレジーネ・ハングラーにそれがないのが痛かった。エルザの苦境がはっきり出てこないと、白鳥の騎士出現のありがたみも半減することがよくわかった。
でも何をいおうと、安定して歌ってくれるローエングリン役の歌手が中心にいるのは、本当にありがたいこと。
生れて初めて見た一九八三年ベルリン・ドイツ・オペラの公演(装置と衣裳、演出の原型はヴィーラント・ワーグナーのバイロイト演出そのままだった。指揮は若き日のヤノフスキ)でも、翌年のハンブルク国立歌劇場来日公演(ネルソン指揮、エファーディング演出)でも、一九九三年のベルリン・ドイツ・オペラ来日公演(指揮の若きティーレマンと演出のゲッツ・フリードリヒとアームストロングのエルザと合唱は素晴らしかった)でも、二〇〇七年のアルミンク&新日本フィルのセミ・ステージ上演でも、こういってはなんだが、ローエングリンの偽者みたいなものばかり聴かされた。名前を思い出したくない歌手たち。
よいヘルデンテノールが払底した時代だったからだろうが、それに加え、二十世紀後半の日本の興行主も観客もオペラにおけるテノール歌手の決定的な重要性を理解しておらず、お金をかけなかったために、あんな状況が続いたのではないか、という気もしないでもない(カラスが遺した誤解、ともいえそう)。
舞台ではまともなローエングリンは一生聴けないのだろうと思っていた二〇一一年、バイエルン国立歌劇場来日公演でカウフマンの代役となったボータを聴いて、ローエングリンを歌えるテノールが本当にこの世にいたと、初めて納得できた。以後はフォークトの数回、そして福井敬と、ちゃんとしたローエングリンを聴ける巡り合わせになっている。


ところで、ボータがその前年に歌ったプッチーニの《外套》のド・ビリー指揮のCDが最近出た。少し時期がずれて、同じド・ビリーの指揮でツェムリンスキーの《フィレンツェの悲劇》も出た。
現物を手元で並べて気がついたが、これらは二〇一〇年五月二十日にコンツェルトハウスで行なわれたダブルビル、一幕物二本立ての演奏会形式上演である。
なるほど二本の話には共通点がある。どちらもソプラノの妻がテノールの間男と不倫して、それを知ったバリトンの夫が間男を殺し、妻に見せつける話だ。ただし《外套》はそれで終りだが、《フィレンツェの悲劇》は夫の強さに妻がほれなおすという急展開。ここでは夫役を二本ともヴォルフガング・コッホが歌う。
さらに面白いのが、どちらも第一次世界大戦中の一九一六年に完成された「同い年」のオペラだということ。
こういうダブルビルは、相似と相違が互いの彫琢を深くして、じつに効果的。ということで、ミュージックバードのニューディスク・ナビでこの二本立てを再現する形で五月に放送することにした。順番はCD番号に従ってツェムリンスキー~プッチーニにしたが、あとでみたコンツェルトハウスの公演記録のサイトでもそのようになっている。
先日の藤原歌劇団の《ナヴァラの娘》&《道化師》もそうだが、ダブルビルは組み合わせの妙が生命。ちなみに大野和士の新国立劇場では二〇一九年に《フィレンツェの悲劇》を、《外套》とではなく同じプッチーニの《ジャンニ・スキッキ》と組み合わせる。こちらの共通点はフィレンツェが舞台であること。これもどうなるのか、楽しみだ。
四月七日(土)実演の予感、録音の継承
東京芸術劇場でカンブルラン指揮読売日本交響楽団。カンブルランのラスト・シーズンの開幕演奏会。
ラモーのダルダニュス組曲、モーツァルトの《トルコ風》、ベートーヴェンの七番というプロは、今月の他の二つのプロと関連づけられているはずなので、三つ聴いてから。ほかは一つが《くるみ割り人形》組曲にモーツァルトのクラリネット協奏曲と《春の祭典》、もう一つはアイヴズの《ニューイングランドの三つの場所》とマーラーの九番。
パッと見えるのは三世紀にわたる舞曲の変遷、ラモー~ベト七~くるみ割り~ハルサイだが、今月のプログラムの解説を読むと、その舞曲のなかでも、とりわけて「ロンドの変容」がテーマではないかと思えてきた。
ラモーとモーツァルトのロンド楽章、くるみ割りの行進曲、ハルサイの春のロンド、マラ九のロンド・ブルレスケ…。
「ロンド二百年の変容」はこれからの二回で確認していくとして、とにかく今日感じたのは、カンブルランの意図がオケの隅々に徹底してきたということ。ベト七は就任早々に取りあげた曲なので、その間の発展を聴いてほしいといっていた。たしかに前はときに上滑り、空転していた表現が、今はかっちりとギアがはまって、無駄なく伝わっているように思える。今シーズンのこのコンビは本当に聴きのがせない予感。

レコード店のサイトで、「レナード・バーンスタイン~ザ・ピアニスト」十一枚組の廉価版ボックスが発売され、「ジェニー・トゥーレル&バーンスタイン・アット・カーネギー・ホール」が含まれていることを知る。
一九六九年ライヴのこれはバーンスタインの録音のなかでも最もマイナーなLPの一つで、初めてCD化されたのはようやく二年前のこと。四十三枚組の「グレート・モーメンツ・アット・カーネギー・ホール」で世界初CD化されたのだが、四十三枚組で必要ないものも多いし馬鹿でかいデザインがなんかアレ(笑)ということで買っていなかった。これは十一枚組で無駄がなく買いやすい。
このライヴは我が師、三谷礼二さんが愛惜してやまなかったLP。なかでも、なんといっても、 オッフェンバックの《ラ・ペリコール》の「手紙の歌」!
自分は三谷さんと出会う前からオッフェンバックが大好きだったが、そんな半端な知識を飛び越えて、こういうものを知っていて、それを惜しみなく若造に教えてくれる人がいて、しかもそういう人が自分と親しく口をきいてくれると知って、本当に嬉しかった。
その後、吉田秀和の『音楽紀行』で、一九五四年ニューヨークのトゥーレルのリサイタルを聴いて絶賛していることを知った。学生時代の三谷さんはこれをむさぼり読んでトゥーレルへの興味をかきたてられたにちがいないとも確信した。その思いがこのレコードを通じて、後世の自分たちにも伝えられる。そういう、思いのバトン・リレーみたいな感覚。これもなんだか、とても嬉しかった。
これは『演奏史譚一九五四/五五』には、個人的すぎて書かなかった話。
四月八日(日)児姿は幽玄の本風なり
能楽と稚児の勉強。
・細川涼一『逸脱の日本中世』(ちくま学芸文庫)
・松岡心平『宴の身体―バサラから世阿弥へ』(岩波現代文庫)
細川は一九五四年生れで中世史、松岡は一九五五年生れで中世文学の研究者。


稚児とは元服前の子供のことだが、中世の寺院では、寺に預けられ、高位の僧の身の回りの世話をしつつ礼儀作法や基礎教養を学ぶ童形の少年たちを指した。公家や武士など上中流の子弟がその中心だが、身分は卑しくても見目麗しく利発な少年が混じることもあった。
当時は女犯戒があるため、僧にとって紅顔の美少年は女性の代用品(より高貴な代用品)の意味合いをもった。法会などで、着飾って舞や歌を披露する稚児たちは、位の低い一般の僧にとっては、手の届かぬ憧れのアイドルだった。一方、稚児を預かる立場の僧にとっては、少年愛や男色など性欲の対象となった。
この稚児寵愛の風習が、僧侶から公家へ、さらに戦場の男性社会に生死する武士にも広まったのが中世という時代。
稚児を寵愛した僧の例として、『逸脱の日本中世』では、南都興福寺の大乗院門跡尋尊(一四三〇~一五〇八)が挙げられている。
呉座勇一のベストセラー『応仁の乱』の主役の一人として私にも親しい存在となったこの尋尊には、愛千代丸と愛満丸という二人の寵童がいたのだ。
愛千代丸は武士の子で、十四歳から元服する十九歳まで尋尊に仕えた。愛満丸は猿楽の鼓打ちの子で、尋尊に親権を買い取られ、十五歳から二十六歳まで稚児姿で寵愛された。その後に出家(厳密には遁世)したが二年後に自殺している。長く稚児のままだったことが心を病ませたのだろうと推測されている。
卑賤の猿楽の者が、稚児になることによって貴人に近づき、愛されるというのは世阿弥の少年時代を想わせる。そのとおり松岡によると、世阿弥もまた、ある寺院に稚児として召し置かれていた可能性があるという。そこで上流階級に交われる基礎教養を身につけて、足利義満や二条良基にその才と容姿を愛されたのではないかというのだ。
さらに松岡によると、世阿弥本人の用いる「幽玄」とは、私などが安易にイメージする「わびさび」風の、質素で枯淡なものではない。童形の少年の、瑞々しく伸びやかな官能美、「清冽可憐なエロス」のことを指す。「児姿は幽玄の本風なり」と世阿弥は『二曲三体人形図』で断じている。桜花と同様に短い盛りを迎えて散る「幽艷」の美。
思春期の少年の花。稚児たちを満開の桜に見立てる能の『鞍馬天狗』は、この美学の舞台化。なかでも敗残落魄の境遇にめげることなく、けなげに復讐と源氏の再興を誓う沙那王は、その張りつめた脆さ、ときにみせる気弱さゆえに、大人の男にとってはたまらなく愛おしい。
その愛おしさの感情を純粋ととるか、下劣ととるかは、観る人次第。
弱い沙那王を強い大天狗が憐れんで、というだけの単純な話になっていないのもいい。天狗は山伏に化けて人間たちの花見の宴を脇で楽しもうと思ったのに、不審者に気づいた僧たちはこれ見よがしに場所を変えてしまう。親疎貴賤の隔てなどないはずなのに、仏法の慈悲の心はどこに行ったのだと、人の中の魔物としての孤独を嘆く天狗。ところがそこに、独りで残った稚児が親切に声をかける。平家の中の源氏としての孤独を生きる沙那王。花の下で二人だけの心の交歓が始まる。ここで地謡は「人にひと夜を馴れ初めて(略)馴れは増さらで恋の増さらん悔しさよ」と『閑吟集』にある恋の歌を謡いだして、友情と恋情を重ねあわせる。その初々しい妖しさ。
後場は翌日、大天狗が正体を現して兵法を授ける場面。詞章では供に全国各地の天狗を六人ぐらい引き連れているとあって、天狗界の大立者であることが示されるのだが、出てくるのはシテだけ。あとは想像にまかされている。
兵法を授けおえた天狗が去ろうとすると、また独りになることを嫌った沙那王が駆けより、袂にすがる。思わず見せた少年の幼さに、天狗はいったん戻ってくる。このあたりもどこか艶っぽい。
面白いのは、そこで沙那王を励ます天狗が、大丈夫だ、西海で平家を打倒するときには影ながら助ける、とだけ言うこと。つまり、宿願を果たすまで助けると言っていて、その後のことは触れない。平家を滅ぼした後の義経の運命の急転落が暗示されているかのよう。
稚児と山伏の関係では、昨年九月に観た『大江山』の鬼、酒呑童子も興味深い存在だった。討伐に来た武士たちが山伏に変装して近づくと、酒呑童子は悪鬼とは思えないほどに他愛もなく山伏と信じきり、親切に宿を貸してやり、酒宴でもてなす。そしてかれらに対し不思議な馴れと媚態を示すのだが、それは酒呑童子がかつて叡山の稚児であったから。
今は大江山の鬼と成り果てた者の、皆から慕われ、憧れられる人気者の美童だった時代の、遠く甘美な記憶。それに酔ったところを猛々しい武士たちにつけ込まれ、あえなく討たれる。稚児の知識が増えたところで、もう一度観てみたい。
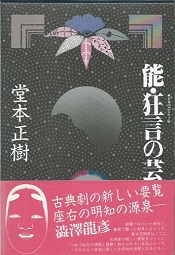
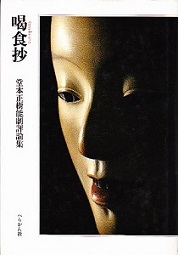
合わせて、堂本正樹の本も二冊読む。
・堂本正樹『能・狂言の芸』東京書籍
・堂本正樹『喝食抄―堂本正樹能劇評論集』ぺりかん社
堂本は一九三三年生れの劇作家、演出家、劇評家。在野の演劇人として能楽を論じている。学者に較べて直感と推測に頼っていく傾向が強いが、それだけに鋭利でテンポよく、面白く読める。前者は一九八三年、後者は一九九三年刊。
十五歳で三島由紀夫と親交を結び、映画『憂国』では監督をつとめた。堂本の『回想 回転扉の三島由紀夫』(文春新書)は出て早々に自分も読み、二〇〇五年十一月二十日と、翌年の七月十三日の可変日記で触れている。
これもついでに読みなおしてみると、能に関する部分がいくつかあった。初めて読んだ頃は能など何の興味もなく、十三年後の自分が能に入れ込むなど夢にも思っていない。能の話は読みとばしたはずで、日記でもまったく触れていない。これも昔の日記を読む面白さ(笑)。
『喝食抄』の喝食(かつじき)とは、禅宗寺院の稚児のことである。この本の副題を「能劇評論集」としたように、堂本は能を劇として考えている。今では当たり前のことのようだが、昭和三十年代まではむしろ異端思想だったらしい。一九五九年に出した『古典劇との対決―能・歌舞伎・僕達の責任』でこのことを主張したとき、能は演劇ではない、能は能だ、日本独特のものだという批判や非難にさらされたという。
しかし、劇としての緊張感が抑圧されたのは江戸期に「武家の式楽」となって以降のことで、中世にはもっと闊達で、ドラマ性が豊かだったと堂本は考える。
これは戦後の能楽研究を牽引した大学者たち、横道萬里雄(一九一六~二〇一二)や表章(一九二七~二〇一〇)などの学説に沿ったもの。実践面では八世観世銕之丞や梅若実、浅見真州、大槻文藏など、観世寿夫の薫陶を受けた観世流のシテ方が学問的成果を採り入れて、家元制度との兼ね合いのなかで、中世以来の復曲や古い詞章、古い演出の復活に一九八〇年代から力を注いだ。堂本もそこに関わっているようだ。
このような八〇年代以降の能のとらえ方や演能の潮流の変化――一九八三年の国立能楽堂開場も関係あるのだろう――が『喝食抄』にうかがえる。『鵜羽』が江戸時代に廃曲になったのは、足利義教が暗殺されたときに演じられていた能であることを徳川将軍家が忌んだためという推測も、堂本が広めたものらしい。
演劇性を重視する堂本には、宝生流のシテがいちばん歯がゆいというのも面白かった。江戸の式楽的性格を最も濃厚に残す宝生流では「戯曲面が退化して抽象舞踊に徹せざるを得ぬ」からである。
堂本より十一歳年上で、戦後昭和を代表する能評家だった大河内俊輝(一九二二~二〇一〇)が、名手野口兼資(一八七九~一九五三)以降の宝生流シテ方に肩入れし、対して復曲や古い詞章の復活を嫌ったのとは、見事なまでに対照的。
その後がどうなっているのかは、これから学んでいくつもり。宝生流でも若い宗家の室生英照(一九五八~二〇一〇)は思いきった表現で、変化が生じつつあると当時の堂本は書いているが、英照は早世して、今は息子の和英(一九八六年生れ)の代となっている。
四月九日(月)渡世をいとなまば
国立能楽堂で観世流の久習会の演能。
・一管『惣神楽(そうかぐら)』一噌幸弘
・独吟『和布刈(めかり)』橋岡伸明
・狂言『横座(よこざ)』善竹十郎
・能『善知鳥(うとう)』荒木亮

初めは現代を代表する名手、一噌幸弘による笛の独奏。
独吟の橋岡伸明は、観世流シテ方の職分、故橋岡久馬の三男。謡のあと、舞台右手奥の切戸口から出るのに、いったん反対の左手奥まで行き、そこからダッシュして勢いをつけ、野球のスライディングを思わせる姿勢で足から滑り出ていったのにびっくり。こういう退場の仕方の例があるのだろう。
能は橋岡久馬に学んだ荒木亮のシテ。『善知鳥』と書いて、うとうと読む。当時の日本の北端と考えられていた青森市北部の海岸、外ヶ浜に棲む鳥の名前。喜多流では同じ能を『烏頭』と呼び、この方が元の字だろうが、なぜか喜多流以外はこの字をあてる。
親鳥が「うとう」と鳴くと、雛が「やすかた」と答えて居場所を知らせる習性をもつので、猟師は親鳥の鳴き真似をして雛を捕らえる。こうして殺生を生業とした人間は、地獄に堕ちなければならない。人の業の深さを描く悲劇。
能楽は仏教思想が支配した中世の産物である。神仏の加護で離ればなれになっていた親子が再会できるとか、護法神が降臨して悪魔を退治するといった、現代人からみればご都合主義に思える奇蹟譚も少なくない。
しかし一部に、ハッピーエンドを拒否した作品がある。仏法の光は、地獄や修羅に堕ちて苦しむ人間の姿を照らしだすだけ。それでも、誰にも知られぬままに無明の闇の中に沈んでいるよりは、光が照らして、存在を気づかれるだけマシなのだ。『善知鳥』はその代表的な名作。
前ジテは、越中立山の地獄谷(死者が堕ちる立山地獄)で修行中の僧(ワキ:福王和幸)が出会う老人。じつは外ヶ浜の猟師の霊で、故郷の妻子への伝言を僧に頼み、妻への証拠に、自らの衣の片袖を託す。その伝言は、家にある蓑笠を供養に手向けてほしいというものだった。
この問答のあいだ、遥かな外ヶ浜にいるはずの妻子が先に舞台に出ていて、脇座にじっと座っているのが面白い。
いうまでもなく、富山県から青森県までは本州の半分を縦断することになるほどの遠距離だが、能舞台の上では物理的な距離を超越して、立山の地獄と外ヶ浜の賤家が隣りあっているのだ。
松岡心平の『宴の身体』によると、修行僧が立山地獄で会った少女が、近江の蒲生で亡くなった霊で、その遺族に会いに行ったという話が今昔物語にあるそうで、『善知鳥』はその話を借りて設定を変え、日本の北のさいはて、外ヶ浜と結んだものらしい。
立山も外ヶ浜も、生身の人間が行ける限界。ともに人外の世界との境界の場所である。生前は外ヶ浜、死後は立山と、人間の限界地にあることを余儀なくされているのが、猟師とその霊なのだ。
僧が外ヶ浜の妻子を訪ね、片袖を示して確かめさせ(片袖幽霊譚という伝説の一つの形らしい)ると、妻は蓑笠を供えて、僧と供養を行なう。すると、現世への懸け橋がつながったか、後ジテの猟師の霊があらわれる。
妻子を懐かしみ、子の髪をなでようとするが、殺生の罪を負う霊なので家の中に入ることができない。そのもどかしさに、猟師は自分が殺してきた雛たちの親鳥がどのような気持だったかを思う。
ここから猟師は生前の所業を再現していく。「渡世をいとなまば、士農工商の家にも生れず。又は琴碁書画をたしなむ身ともならず。ただ明けても暮れても殺生をいとなみ」という詞の迫力(ただ、世阿弥の甥の音阿弥が得意とした能だから、作者不詳ながら古いことが間違いないのに、「士農工商」という江戸時代風の用語は意外だった)。
シテは蓑笠を雛鳥に見立てる。橋懸から舞台の目付に向かって笠をくるくると放り投げ、鳥の飛ぶ姿を暗示する。そして笠に近づいて杖で突き、鳥を獲る。ゲームに夢中になるような、殺戮の快感。
雛をとられた親鳥は悲しんで、血の涙を降らせる。猟師は笠を被ってそれを防ぐ。そのために、家に遺した蓑笠を手向けてくれと頼んだのだ。
一転して、猟師は地獄での悲惨さを語る。無力な親鳥は鉄のくちばしと銅の爪の怪鳥に変じ、身動きできぬ亡者を襲い目をえぐる。狩られる者の苦しみ。「助けてたべや、御僧助けてたべや、御僧」と悲鳴をあげて消える。無明の闇へ。
このように生活のために殺生をする人でも浄土へ行けると説いたことが、法然や親鸞の浄土教の革命的な新しさと魅力だったのだろうと、今さらながら実感。しかしその救済の思想はここにはない。
四月十三日(金)ロンドと生贄
カンブルラン指揮読売日本交響楽団を聴きにサントリーホールへ。
サントリーホールは久しぶりと思って調べると、三月三日の日本フィル以来、なんと四十一日ぶり。この間にクラシックの演奏会とオペラに十六回(あと能に六回)行ったのに一つもサントリーホールがないというレアなケース。「東京・春・音楽祭」効果。
この間の大きな変化として、アークヒルズのレストラン街がようやく改装を終えて再オープンしたのを友人のフェイスブックで知り、開演前に覗きに行く。
さて演奏会。カンブルランの「ロンド二百年の変容」(勝手に命名)シリーズの二回目。
・チャイコフスキー:バレエ音楽《くるみ割り人形》から
・モーツァルト:クラリネット協奏曲
・ドビュッシー:クラリネットと管弦楽のための第一狂詩曲(クラリネット独奏はともにポール・メイエ)
・ストラヴィンスキー:《春の祭典》

《くるみ割り人形》の行進曲がいきなりロンド形式。この元気の良さをグロテスクに、ヤケクソ風にするとマーラーの第九番のロンド・ブルレスケになりそう(二十日のこの曲が楽しみ)。
続いてモーツァルトのクラリネット協奏曲の終楽章のロンド。前回の《トルコ風》の終楽章もやはりロンドだった。二つとも春風駘蕩というか、自然に眠気を誘い、最後に自然に減速して、終るともなく終る。この催眠効果、《春の祭典》の〈春のロンド〉前半の、眠りに落ちるような雰囲気に通じるようにも思える。
そして《春の祭典》。これはたしかに先週聴いたラモーの《ダルダニュス》組曲の、遥かな遥かな末裔(チャイコフスキーを経由した)にちがいない。ラモーがあそこで使った一本のプロヴァンス太鼓は、いまや多数の打楽器の強烈なサウンドに進化している。
それにしても感服するのは、指揮者と楽員の関係の見事な成熟。数年前までは上滑りして表面をなでるだけだったような響きが、今はその透明な表面の裏側で、何かが有機的にうごめいているところまで聴かせてくれる。「洗練された血の臭いのする音楽」としてのハルサイ。
この「血の臭い」は、もちろん生贄が流す血の臭いだ。これは今回の「ロンド強化月間」(勝手に命名)とは別に、一年前の演奏会にもつながっていると気がつく。一年前の四月十五日、東京芸術劇場でのカンブルランと読響。
・メシアン:忘れられた捧げもの
・ドビュッシー:《聖セバスティアンの殉教》交響的断章
・バルトーク:歌劇《青ひげ公の城》
当日の日記に書いたように、すべて生贄、聖なる犠牲を扱う音楽だった。カンブルランにとって春とは、尊き生贄により万物が再生する季節なのか。
このうちドビュッシーとバルトークはともに一九一一年作曲。《春の祭典》は一九一三年完成。ドビュッシーの狂詩曲の原曲(ピアノ伴奏版)は一九一〇年完成。この曲と雰囲気がよく似た《牧神の午後への前奏曲》をバレエ・リュッスでニジンスキーが踊ったのは一九一二年。
来週のアイヴズの《ニューイングランドの三つの場所》は大半が一九〇八~一四年に書かれていて、マーラーの交響曲第九番は一九一〇年完成。
第一次世界大戦直前の時代精神が生んだ「生贄の音楽」たち。蜘蛛の巣のように張りめぐらされた、それぞれの関係。
マーラーとアイヴズはいったい何を、何に対して、犠牲に捧げるのだろう。そのとき、ロンドはどう響く。
来週もすごく楽しみ。
四月十四日(土)オリンピックと音楽
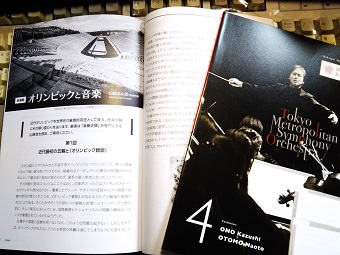
宣伝。今月から東京都交響楽団の演奏会プログラム「月刊都響」に「オリンピックと音楽」という連載を書いている。
オリンピックに関わりのある音楽を二年間、二十回にわたり紹介する予定。第一回は「近代最初の五輪と《オリンピック賛歌》」。《オリンピック賛歌》の作曲者スピロス・サマロス(一八六一~一九一七)の話。
話がきたときは正直、「行進曲と賛歌の話ばかりで二十回なんてもつのだろうか」と思ったが、調べるとこれが出てくる出てくる。司馬遼太郎いうところの、歴史の調べ物の最大の快感「あなたはこんなところにいたのか」を何度も味わえることになり、楽しくなった。縦横さまざまにつながって広がり、近代史と音楽史の一側面をふり返る物語にできそうな気配もある。
今回のサマロスも、じつはギリシャ人初のイタリア・オペラの作曲家で、《オリンピック賛歌》の旋律はそのまま一九〇八年フィレンツェ初演の歌劇《リア》に流用されていて、というような話。
来月の第二回は「一九二四年パリ・オリンピックと映画『炎のランナー』」。
四月十五日(日)春の一段落
東京・春・音楽祭の楽日。スペランツァ・スカップッチ指揮の東京都交響楽団そのほかによる、モーツァルトの交響曲第二十五番とロッシーニのスターバト・マーテル。前者はカラヤン風の重いレガートでもたれたが、後者は緊張感とスケールがあって大満足。
四月十七日(火)アイーダ
新国立劇場で《アイーダ》。アムネリス役のセメンチュクが体調不良で降板、急遽カバーの森山京子が代役など、歌手陣は完璧ではなかったが、ゼッフィレッリの大規模な舞台は今もなお、創立二十周年の新国立劇場を代表する演出と再確認。初台駅のホームに凱旋行進曲が流れることの意味を、あらためて納得。
四月十九日(木)童貞力で行こう
 写真は「音楽の友」のフェイスブック・ページから
写真は「音楽の友」のフェイスブック・ページから代官山「晴れ豆」でのイベント「爆クラ!」、無事に終了。来てくださったみなさまに感謝。
湯山さんからのテーマが『童貞力をクラシックで追求してみた!』で、一体どうなるんだ、お客さんいるんだろうかと本人がいちばん不安だったが、ふたを開けてみると常連のお客様主体にたくさんの方が席を埋めていて、嬉しいかぎり。しかもとても反応がよく熱心に聴いてくれたので、話していて心強いかぎりだった。湯山さんの進行もさすがに絶妙。話の穂をうまくつないでくれるので、とてもやりやすかった。
写真は「童貞クラオタ独特の肩のもみかた」を説明しているところではなく、たぶんグールドの話をしているところ。
四月二十日(金)昨日と明日

サントリーホールで読売日本交響楽団演奏会。指揮はカンブルラン。曲はアイヴズの《ニューイングランドの三つの場所》とマーラーの交響曲第九番。
もやもやした雰囲気に終始することが多いアイヴズが、明快なフォルムをもって響くのがカンブルランならでは。
情緒に流れず、きっちりと明確に振られたマーラーも同様。ロマン派の時代の終り、一区切りという告別の感覚と、次の時代への橋懸りとなる要素の共存。ロンド・ブルレスケのキレも期待通り。
四月二十一日(土)チェリビダッケ邂逅
この録音が再発売になったからには、紹介しないわけにはいかない。
一九六六年一月、チェリビダッケが東ベルリンを訪れてシュターツカペレ・ベルリンを指揮した演奏会のライヴ録音。
・ヒンデミット:ウェーバーの主題による交響的変容
・プロコフィエフ:スキタイ組曲
・ブラームス:交響曲第四番
・ドヴォルザーク:スラヴ舞曲第八番

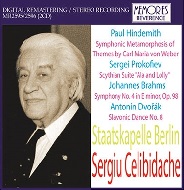
自分が持っているのは一九九七年にAUDIORからAUDSE‐514‐515として発売された二枚組CD。あの当時のチェリビダッケ物の海賊盤の通例として録音年月の表記はないが、後述する理由で自分は一九六六年一月に違いないと知っていた。この時代の東独ライヴとしては異例なほどの鮮明なステレオ録音なので、事情を知らない人なら七〇年代後半と思っても何の不思議もないほどに高いクオリティ。
それが「イタリア」(ということになっている。真相は知らない…)のMEMORIESから四月十四日に突然出た。もう隣接権は切れているので、海賊盤ではない公有盤。
なぜこれを一九六六年一月のライヴだとAUDIOR時代から知っていたかといえば、旧師の三谷礼二さんがこの演奏を実際に会場で聴き、その思い出を書き遺しているから。一九八六年のミュンヘン・フィルの来日公演プログラムに掲載された『「劇場」のチェリビダッケ』は遺稿集『オペラのように』(筑摩書房)に転載されて読むことができる。

『“感動”の原点というものが、ある。
私にとって「指揮者とオーケストラの結びつき」の原点は、一九六六年一月十八日、東ベルリン・シュターツオパーにおける、セルジュ・チェリビダッケとシュターツカペレ・オーケストラの演奏会である』
一九六四年七月から六六年五月まで、三谷さんはアメリカとヨーロッパを回って、念願の劇場勉強旅行をした。その間に六百ものステージに接したという。
そのなかで、気にかかっていたのがチェリビダッケという存在だった。福原信夫と園田高広の著作で、レコードを録音しない凄い指揮者がいると知り、渡欧してからその名をさがしつづけたが、ウィーン、ロンドン、パリなどでは見つからなかった。インターネットなど想像もつかない六〇年代半ばには、偶然に出くわすしか見つける方法はないのだった。
しかし東ベルリンで、ついにその名を見つけたのである。まだ廃墟のようだったウンター・デン・リンデンの、夜の暗闇の中にほの暗く浮かぶベルリン国立歌劇場で、その演奏会のチラシを見つけたのだった。
そして待望の本番。チェリビダッケが登場すると、
『満員の客席はさんざめき、いつもは地味な東の客たちとは思えない湧き立つような熱気がたちこめた。実は私があまり好きでないヒンデミットの「ウェーバーの主題による交響的変容」も、精妙な響きと、構成を考え抜いてあるのだろう、次から次ヘと興趣を盛り上げていく演出上手で、プロコフィエフの「スキタイ組曲」は、これが東のオケ? と思わせるリズムの鋭さとシャープな音色で、私はまずすっかり驚倒してしまった。
しかし、ここまではあくまで前座だった。
休憩のあと、ブラームスの四番の、おなじみのフレーズがゆったりと流れだすと、私は実に不思議な気分がしてきた。もちろんそれはたっぷり過ぎるくらい叙情的で、かなり大きな表情がついていたが、それ以上に何かそこには“時の流れ”のようなものが漂っていたのである。オーケストラは前二曲とはまるで違った音色を出し、それは私たちが、かなり昔、勝手にイメージしていた戦前のドイツのオーケストラのイメージだったのである。
コンサート・マスターと副コンサート・マスターの喰い入るような眼つきと、真剣そのものの頬の緊張も、西側のオーケストラ、つまりベルリン・フィルの、単に職業的な表情とはまるで違っていた。もっとも私は、のちにフルトヴェングラー=ベルリン・フィルのヴィデオで、これと同じ没入の表情を見ることになるのだが……。
とにかく、さんざん聴き馴れたブラームスの四番シンフォニーが、はじめて耳にするようだった。中でも第四楽章のパッサカリアの劇的な立体性と、甘美さ、荘厳さ、いやすべてのことばが色あせる不可思議玄妙な進行は、時の流れを、ある時は遠い過去へつなげ、あるいは夢のような未来へとつなげた。ブラームスが、バッハをも、ベートーヴェンをも超える神業を達成しつつある、あくまで時の流れとともに感動しながら、私は人間の歩んできた歴史と、切実な現在と、無限の未来への信頼の気持でいっぱいになってしまった。
曲が終わると、聴衆は総立ちになって、いつまでもつづく喝采を浴びせた。私は実は最前列の中央にいたのだが、ふと横を見ると、白髪の老女が、むせぶように泣いていた。私も眼が曇ってしまった。チェリビダッケは何回目かに指揮台へもどって来た時、涙ぐむドイツの老婆と東洋人の私をじっと見つめ、わずかな微笑とともに、しばらく眼を離さなかった。私がお節介に、人に音楽の素晴らしさを説きつづけるのは、こういう原点たり得る音楽を聴くことができたからである。私は若いから未来を見たが、老女は過去のドイツ、過去のベルリンの栄光を見たのであろう。ドイツ人の戦前の誇りを一瞬呼び戻し得る霊媒のような指揮者、と、私は日本の友人たちへの手紙に書いた』
五十二年前の東ベルリンで三谷さんが聴いた演奏が、私の前で鳴りひびく。
自分がチェリビダッケを生れて初めてナマで聴いたのは一九八三年二月、ミュンヘンのヘルクレスザールでの演奏会だった。自分も最前列中央で、指揮者の尻が揺れるのを見上げながら聴いた。前半のハイドンが終り、後半のブラームスの一番が始まるとき、前半の笑顔とはうって変った恐ろしい形相で指揮者が入場してきたのを、強烈に憶えている。
そして、終楽章のアルペンホルンが大きな間をとって、時が止まらんばかりの遅さで朗々と鳴りわたったあと、そこからコーダへ向かって、巨大な驀進が始まったことも。
二十歳の自分が友人に連れられて三谷さんのお宅を初めて訪れたのは、日本に帰った、その直後のこと。
だから、三谷さんが亡くなった翌年の一九九二年に出た『オペラのように』でこの一節を読んだとき、不思議な縁を感じた。とはいえ、亡くなられる数年前に自分は個人的事情で、裏切るような形で三谷さんの元を離れていたから、正直そのときは、素直にその不思議な感情に浸ることはできなかった。
しかし、その五年後にAUDIOR盤を店頭で見かけたとき――今はなき六本木のWAVEだったと思う――オーケストラと曲目からみて、これは三谷さんが書いた演奏に違いないと直感した。
そうして、買って帰って聴いたときにわき上がってきた感情については、今はまだ書くまい。いや、書くべきものではない。
それから二十一年たって、また聴く。CDには十五日とあって三谷さんが書く十八日とは違うが、どちらかの誤記で、おそらくは同じ演奏だろう。
なんといっても、四番の冒頭の響き。身悶えるように、耐えきれずにあげたうめき声のようなヴァイオリンの響きは、恐ろしく印象的だ。そこから重ねられていく変転。第二楽章の魔術的な変容。そして終楽章のパッサカリア。
他の指揮者やチェリビダッケの他の録音にくらべてどうだとか、自分もナマで聴いた一九八六年、三谷さんがプログラムに書いたときの同じ曲の実演と較べてどうだとか、言おうと思えば言える。
だが、そのような比較は虚しい。どの一回も、かけがえのない体験だからだ。
この音楽が生れた瞬間の三谷さんの体験、それを追いかけた自分の、文章と録音と実演によるいくつかの体験。それらの記憶は鮮やかなままに折り重なり、目の前のこのディスクとともにある。
四月二十五日(水)式楽としての能

銀座の観世能楽堂で「開場一周年記念 音阿弥生誕六百二十年特別記念公演」と題された「古式謡初式」を観に行く。
進取の気風少なきたちゆえ、新築の観世能楽堂に行くのはこれが初めて。地下鉄の駅から地上に出ることなく行けるのは、気候や天候に左右されないのでありがたい。ビルの地下二階というのはセルリアンタワーの能楽堂に似ている。現在はこのような形でしか、東京では民間の能楽堂の新築は難しいのだろう。
しかし、さすがにセルリアンタワーよりも内装ははるかに風趣があるし、観世宗家の本拠として、宝生や喜多のそれと同じように、次第に舞台に神が宿っていくのだろう。
「古式謡初式」とは徳川時代、毎年の正月に江戸城本丸の大広間で将軍、御三家、諸大名が列座して行われた幕府の公式行事、謡初(うたいぞめ)を再現したもの。「幕府の式楽」、幕府公式音楽としての能を象徴する儀式で、明治維新後も観世宗家が上野寛永寺で最近まで続けてきたという。
江戸期は観世、喜多の両太夫と、他の三座から毎年交代で一座の太夫が出演するきまりだったが、今回は観世清和、宝生和英、金剛永謹の家元三人。各人が各流派の重鎮ばかりの地謡を引き連れて登場。侍烏帽子に素袍という武士の正装。
幕府の奏者が出座して進行を取りしきる。奏者役は茂木七左衞門。「うたいませ」と声をかけると、観世が『高砂』の一節、四海波を単独で謡う(小謡)。続いてワキの森常好と囃子方がやはり正装で登場し、居囃子(座ったまま囃子にあわせて謡う)で観世が『老松』、宝生が『東北』、金剛が『高砂』を謡う。祝いごとにふさわしいものばかりで、つねにこれらに固定されていたという。
奏者が時服(表が白、裏が紅の絹服)を三宗家に渡し、三者はそれを着て、舞囃子で「弓矢立合」。それぞれの流儀で同時に謡い、舞うのが面白い。
「弓矢立合」を舞う由来は、三方ヶ原合戦後に浜松城に逃げ帰った家康が疲れて眠って目覚めてみると、武田勢が城を襲わずに撤退していた。それを喜んで何か舞えと命じられた側近の観世太夫が、これを舞ったことだという。
この頃、観世太夫は京の荒廃を避けて家康の庇護を受け、側近にまでなっていた。このことが、後年の徳川将軍家と観世の緊密な関係の出発点となった。
著作権とか、そういった近代的な概念を超越して存在し続ける、家元制度。能の場合は足利、豊臣、徳川と、歴代の武家の権力者が権威づけたことが、今もその権威の原点となっている。その象徴としての古式謡初式。
四月二十六日(木)ワキの人西行
国立能楽堂の企画公演「特集・西行 生誕九百年記念」の第一日。
・仕舞『実方(さねかた)』キリ 梅若実
・狂言『鳴子遣子(なるこやるこ)』茂山七五三(大蔵流)
・能『西行桜(さいぎょうざくら)』梅若万三郎(観世流)
西行(一一一八~一一九〇)は、在原業平とともに、能によく登場する人物。業平と違うのは、業平がシテの演じる霊だったり、あるいは恋人の霊や植物の精などシテが慕う存在として間接的に出てきたりするのに対し、西行はワキとして霊や精の夢を見るのが多いこと。本人が出家だからだろう。松尾芭蕉や夏目漱石など、自らをワキの位置において人と事物を眺める文学者の、始祖的存在か。今日の『実方』と『西行桜』も、西行がワキとなってシテと夢で会う複式夢幻能。
特に後者は西行ものの代表作。世阿弥あるいは金春禅竹の作で、前場の花見客の喧騒と、後場の孤独な春の宵、桜の老木の精の舞を見る夢幻劇との対照の見事さ。感服しつつも、自分はまだまだ初心者で、ゆっくりした静かな舞が楽しめない。後場では何か、どんよりした重苦しさを感じてしまった。機会をあらためてまた観たい。
四月二十七日(金)クレオパトラの死
紀尾井ホール室内管弦楽団の演奏会。
パオロ・カリニャーニの指揮、コンマスは千々岩さん。
・ケルビーニ:歌劇《アリババ》序曲
・マルトゥッチ:夜想曲(管弦楽版)
・レスピーギ:組曲《鳥》
・ドビュッシー(クロエ&カプレ編曲):ベルガマスク組曲
・ベルリオーズ:クレオパトラの死(メゾソプラノ:リリー・ヨルシュター)
普段の定期よりも金管や打楽器が増強され、ナマではあまり聴けない曲ばかりでありがたかった。なかでも最後のベルリオーズの《クレオパトラの死》が飛び抜けた出来。この曲が近年録音される機会が多い理由を納得させてくれる、鮮やかな演奏。
この劇性豊かな音楽になったとたん、オペラ指揮者カリニャーニの指揮が水を得た魚のように生彩豊かになる。ヨルシュターが楽譜を使わず、前奏から厳しい顔つきとなってクレオパトラの運命のドラマに没入したことも、大きなプラス。
シェイクスピアの戯曲を意識の下におき、イタリア風の劇的なソロ・カンタータの伝統を受け継ぎながら、オーケストラをより雄弁に、劇的に語らせ、情景を描き出すベルリオーズ。《トロイアの人々》のカサンドルとディドンの先駆けとなり、さらには〈ブリュンヒルデの自己犠牲〉のあの音楽までも予感させる、クレオパトラの自決のドラマ。バーンと盛り上げずに死の静寂で終るラストは、むしろよりモダンであったり。
しかしそれでもなお、オーケストラの規模(十型)も歌手の様式も、あくまで一八二九年という時点にふさわしい響きなのが嬉しい。歌もオーケストラもヴェリズモ風に、大柄にやることも可能だろうが、そうしていない。このへんは紀尾井ならではのありがたさ。
ロシア南部出身のヨルシュターはペーザロやミラノで学んだ、細身の美女(プロフィール写真の時点よりも段違いに垢抜けている)。ロッシーニ歌唱を基礎にしてベルリオーズに挑むという、歴史的に正しい選択。
四月二十九日(日)思へば仮の宿
二十六日に続き、国立能楽堂の企画公演「特集・西行 生誕九百年記念」の第二日。
・舞囃子『松山天狗(まつやまてんぐ)三段之楽(さんだんのがく)』金剛龍謹(金剛流)
・狂言『花折(はなおり)』小笠原匡(和泉流)
・能『江口(えぐち)』金剛永謹(金剛流)
『松山天狗』は、保元の乱に敗れ、讃岐松山に流されて崩御した崇徳上皇の御陵に西行が詣でて、上皇の霊と夢で会う話。現在は金剛と観世の二流しか取りあげないが、源平騒乱の原点みたいな能なので一度観たかった。舞囃子の一部分とはいえ嬉しい。
西行がはるばる来てくれたことに感謝して、墓所を鳴動させながら上皇の霊が出現、往時の栄華を偲んで舞うが、やがて敗北と配流の悔しさを思い出し、形相を一変させて怒りにふるえる。
すると雷雲の中から相模坊なる天狗が眷属を引き連れて現れ、逆臣どもを皆殺しにしてご覧に入れようといい、上皇を喜ばせる。
ではと天狗たちが都へ飛翔していく瞬間、夜が明けてその姿は消える。ただの一場の夢なのか、真実なのか。自分は前者に思えた。上皇の霊が頼もしい臣下に助けられ、復讐を果たすことができるのは、ただ夜の夢の中でのみ。
狂言『花折』は『西行桜』のパロディになっているのが楽しい。
『江口』は観阿弥の作を世阿弥が改作したという。西行その人は登場せず、西行を慕う後世の旅の僧が、淀川沿岸の江口の里を訪ね、西行と歌を交わした遊女の霊に出会うという話。
俗世の垢にまみれて苦界に生きる遊女が、自分たちや浮世(仮の宿)のことなど気に留めるな、執着を捨てよと僧に説く。じつは普賢菩薩の化身で、最後は正体を現し、西の空に去っていく。
出家に覚悟を求めると同時に、自分は苦悩の旧里に生きて死ぬという諦観、それが菩薩行、なのだろうか。
これも解釈はさまざまにありそうで、長くつきあっていくつもり。
五月五日(土)有楽町と池袋
東京国際フォーラムの「ラ・フォル・ジュルネTOKYO」に行く。
今年から池袋の東京芸術劇場と二か所開催となり、体制も変化したということで、二〇〇六年から続いたクラシック・ソムリエもお役御免。気楽な立場でコンサートを二本聴く。有楽町線に乗って池袋の会場ものぞく。池袋をターミナルとする各線の沿線には、潜在的なクラシック需要が眠っていそうな気がする。
五月九日(水)武士と仇討
国立能楽堂の定例公演。
・狂言『水掛聟(みずかけむこ)』能村晶人(和泉流)
・能『放下僧(ほうかぞう)』山階彌右衛門(観世流)

『放下僧』は仇討物。父を殺した仇に兄弟二人が放下(芸人)に変装して近づき、すきをみて首尾よく討つ。
兄弟二人が舞うのかと思っていたが、芸を見せるのは出家の兄(シテ)のみだった。ちょっと拍子抜け。
仇討物語は、鎌倉時代から昭和期まで約七百年、日本人が最も好む物語だったといってよいだろう。その原点が曽我兄弟で、頂点はもちろん忠臣蔵。
能には曽我兄弟物が何作もあるし――それらをつなげて一つの物語にする試みも、去年セルリアンタワー能楽堂で行なわれていた――他にもこの『放下僧』や『望月』がある。
歌舞伎でも江戸期の正月興行は曽我兄弟物と決まっていて、助六のように強引にその変形とされた狂言もある。忠臣蔵は群像劇だけに最高の材料になった。浪士が町人や遊び人に身をやつして仇を油断させ、隙をさぐるという筋書きの原型が、『放下僧』や『望月』なのだろう。
王朝物語には仇討という発想はなさそうだし、平家物語は仏教的な因果応報の色が濃いし、太平記は怨霊譚。縁起や怨霊の力に頼らない、自助努力的な仇討物語は、京や奈良のような先進地域よりも東国などの地方武士が好んで、発展させたものか。『放下僧』も舞台は東国。
権力が確立されて秩序が安定している時代なら、復讐の連鎖を生みやすい仇討は本来なら歓迎されないものだろう。しかし江戸幕府がこれを法制化していたというのは、仇討が武士の証明、権利と義務と見なされていたということか。
五月十二日(土)弱くても負けず
国立能楽堂の普及公演。
・解説・能楽あんない「足摺する俊寛、しない俊寛」佐伯真一(青山学院大学教授)
・狂言『茶壺(ちゃつぼ)』茂山宗彦(大蔵流)
・能『俊寛(しゅんかん)』宇髙通成(金剛流)
『俊寛』は、平家打倒の陰謀が発覚して、二人の仲間とともに鬼界島に流罪となった俊寛僧都をシテとする現在能。
赦免使の舟が到着するが、赦免状には他の二人の名があるのに、俊寛の名だけはない。都に戻る二人を乗せた舟にすがりつくが、力づくで引きはがされ、島におきざりとなる。
同名の歌舞伎の原型だが、歌舞伎よりもはるかにみっともなく、往生際の悪い俊寛。中世において鬼界島は日本の西端と考えられていた。先月九日に観た『善知鳥』の舞台奥州外ヶ浜が東の端と見なされていたのと、ちょうど反対。
当時は日本の範囲を示す決まり文句に「鬼界島から外ヶ浜まで」というものがあった。この世の両端といっていい場所で展開される能二本を観た。共通するのは、弱い人間の悲惨な姿。
十一日から二十日までは能やら演奏会やらオペラやら、連日の公演通い。GW明けの中旬は毎年公演がたてこむ時期。しかし去年は一週間の入院で、公演をいくつもあきらめたことを思い出した。
ちょうど一年前の今日は、慶応病院で副鼻腔炎の手術を受けた日。その夜はさすがにいろいろと苦しく、眠りにくかった。おかげさまで翌日には高い熱以外ほぼ平常に戻り、点滴も外れて、昼から普通に食べることができたが。
あのころは自覚症状もあまりなく、何のための手術かと思っていたが、一年たってみるとたしかにさまざまに快適。
慶応病院とは幸い縁遠くなって、同じ中央線の線路沿いの東京都体育館と国立能楽堂に通う日々。
ところで公演関係の最近の話題といえば、八日サントリーホールでの東京フィルの《フィデリオ》での事件。音楽に先立って俳優の篠井英介がストーリーを説明していたら、最前列の客が「早く演奏はじめろよ」などと怒鳴ったという。
私はこの公演には行っていないので、すべての情報は伝聞のみ。怒鳴ったのがある音楽評論家だという話もあるが、確認がとれているわけではないので、それには触れない。噂話や憶測だけで決めつけるのは中世の魔女狩りを想起して気持が悪いので、自分は控える。
確実なのは、怒鳴った人がいたということ。じつは自分も少し前に同じような場面に遭遇したばかりなので、これは大いにありうると思う。
それは三月十五日、「東京・春・音楽祭」のプレ・イヴェント、国立科学博物館での〈ナイトミュージアム〉コンサート。クラリネットの金子平さんが一曲目のあとに話をしていたら、「話なんかやめて演奏しろ! それが当然だ!」というようなことを、お年を召した男性の方がお怒鳴りになられた。
周囲は凍りついた。金子さんは顔を歪ませながらなんとか話を締めて、演奏につなげた。自分は情けないことにこのマナー違反に驚くばかりで、何も対処することができなかった。
あまりに不快な体験だったので、フェイスブックや可変日記でイベントを紹介したときには、あえて触れなかった。
ただ、今になっても、あのとき自分がどう行動するのが正しいのかはわからない。「お前の方がうるさいよ! 何様のつもりだ!」と怒鳴りかえすのも、無言で殴りつけるのも、場の雰囲気をさらに壊してしまう可能性が高い。終演後に金子さんに声をかけるのが唯一可能なことだったと思うが、後方にいたのでこれもやりそこねた。
最近は演奏会場で客同士がケンカになるなど、些細なことでキレるケースが増えていると聞く。
静粛にするのがマナーとなっている空間で怒鳴り声をあげる迷惑行為も、おそらくはそのあらわれ。短気で独善的な人間は、高齢化とともにますます増えてくる。前後左右のどの客がそうなるかわからない。自分だってなる可能性がある。ゾンビみたいなもの。
博物館のときは一度かぎりの交通事故みたいなものだろうとあきらめるつもりだったが、短期間に二回あったらしいのだから、きっとこれからもある。そのときそのときに下手人を血祭りにあげて排除しても、おそらくキリがない。次から次へと、ある日突然にわいて出ると思った方がいい。そんな相手と正面からケンカして会場を殺伐とした空気にしたら、その場では勝った気になったとしても、客を迎える立場としては大敗北だ。
自分も人前で話す機会があるので、そんなときにどう対処するか。その場を丸くおさめるには、自分の心を平静に保つには、どんな心構えが必要か。とりあえずはそれを考えていこうと思う。
五月十三日(日)矢来能楽堂初体験
矢来能楽堂で観世九皐会定例会。
この能楽堂は地下鉄神楽坂駅の近くにある。観世流の職分家で、銕之丞家から分かれた矢来観世の本拠地。
現在の能楽堂は一九五二年の再建で、都内では古いもの。二百三十七席と小ぶりで、一九七〇年以降に建った喜多や宝生、国立などがコンクリートのビルの中にあるのに対し、これは木造モルタルの和風建築。白く平らな壁面はしっとりとした落ち着きがあるし、欄間などの木彫りの装飾も粋で凝っていて、現代建築ではもはやお目にかかれないもの。
小津安二郎の一九四九年の映画、『晩春』に出てくる染井能楽堂の雰囲気を想わせて――畳に正座の当時とは違って、矢来は椅子式だが――気持がいい。
席は中正面奥に仕切られた座敷席。ここは靴を脱いであがる。畳に椅子を置いて、後方が次第に高くなるように椅子の高さが調節してある。


・能『実盛』長山禮三郎
・狂言『口真似』大藏彌弥右衛門
・仕舞三番
・能『皇帝』観世喜正
長山禮三郎は一九四三年生れで九皐会の重鎮。息子の耕三と桂三も観世流のシテ方。『実盛』の老武者役はぴったり。最後の敵郎党の首をかき切る仕種が扇を小刀のように使って、これまで観たものよりもリアルだった。
『皇帝』のシテ、鍾馗を舞うのは矢来観世の当主喜之の嫡男、喜正。
唐の玄宗皇帝(ワキ:福王和幸)の寵姫、楊貴妃(子方:喜正の娘の和歌)が重い病にかかる。玄宗が案じていると、正体不明の老人が現れ、自分は鍾馗の霊だと明かし、明王鏡という鏡を献じて、貴妃の枕元に置けば助けに現れると告げて消える。
その言葉に従って玄宗が鏡を置くと、病鬼(ツレ:小島英明)の姿が映しだされる。玄宗は剣を抜いて斬りかかるが、鬼は柱の陰に隠れる(茶色の幕をかぶって、隠れたことにする)。そこに馬に乗った鍾馗が颯爽と登場、鏡で鬼を照らし出し、追いつめる。逃げ回る病鬼は最後に柱をよじ登ろうとするが、鍾馗に引きずり下ろされてとどめをさされる。よじ登る姿勢を、橋懸の端の揚げ幕のところで片足をあげて暗示するのが愉しい。
宮殿や寝所を示す一畳台が二つ置かれたり、ワキの皇帝にも見せ場があったりと、いかにもスペクタクルな能を得意とした観世小次郎信光らしい作品。
玄宗はハンサムな福王和幸にははまり役。ところが病鬼と戦う場面で剣がうまく抜けなかったのか折れたのか、とっさに鞘を振るって戦うハプニング。終り近くで後見が刃を拾いに舞台中央に出てきて、笛座前にいた福王の握ったままの鞘と取りかえさせていたけれど、手筈が狂ったことを演能中に客席にわからせるのは、どうなのだろう。ごまかすよりも、一刻も早く正規に戻すのが能では基本なのだろうか。
矢来能楽堂、観客の雰囲気も含めて、上品でいい感じ。古くて良質なものが簡単に失われてしまうのが現代の東京なので、なるべく多く訪れたい場所。
五月十五日(火)オーケストラ=バンド
昨日はホルンのアレッシオ・アレグリーニにインタビューし、サントリーホールでヴァシリー・ペトレンコ&ロイヤル・リヴァプール・フィルを聴く。今日は紀尾井ホールで、コントラルトのシュトゥッツマンが率いるピリオド・オーケストラ、オルフェオ55による、イタリア古典歌曲集の原曲復元演奏会。
アレグリーニはアバドとのモーツァルトのホルン協奏曲集での名技で有名。この録音とアバドの思い出をたずねたら、文字どおり話が止まらなくなった。翌日の東京シティ・フィルとの演奏会で、指揮も兼ねて同じ曲を演奏する。
しかし残念なことに自分は行けず、同時刻に代りに行ったのがシュトゥッツマンの演奏会。


歌手が歌いながら指揮者も兼業するなんて、二十世紀の一般常識としてのクラシックのあり方からすれば、おそろしく面妖なもの。指揮棒を手に客席にお尻を向けて指揮台の上に君臨する指揮者と、客席に向かって歌う歌手は、まったく別のスペシャリストであるはずという、強固な思い込みがあるから。
しかしバロック作品を四‐三‐二‐二‐一の小さなピリオド楽器のオケで八百席の紀尾井ホールでやるときは、さほどに無理はない。シュトゥッツマンと楽員たちが一緒につくっていく音楽。オーケストラというバンド。
分業制、専業制は、十九世紀末以降の巨大化したオーケストラを大ホールに鳴り響かせるために、必要不可欠になったもの。その時期の大作のための特殊なあり方を、すべての時代に共通するもののように思い込ませたのが、常設の交響楽団による定期演奏会というシステム。
「英雄的なカリスマ指揮者と、最新型の巨大音響工場としてのオーケストラ」だけがクラシック音楽のあり方ではなくなることをいち早く予見、実践したのがアバドの後半生であり、その蒔いた種が、アレグリーニやシュトゥッツマンの活動となって花開いている。
それに立ち会える幸福。
五月十六日(水)音楽に言葉がついて
映画館で《カルメン》を観る。英国ロイヤル・オペラ・ハウス二〇一七/一八シネマシーズンの一つ。松竹がやっているメトのライヴビューイングにくらべると、東宝東和のこれはやる気が足りないのかわかっている人がいないのか、情報がつかみにくいのが困りもの。
しかし今ヨーロッパで大活躍のバリー・コスキーの演出でフルシャの指揮だということを知り、観に行くことにした。
ロイヤル・オペラ『カルメン』
演出:バリー・コスキー、指揮:ヤクブ・フルシャ
出演:アンナ・ゴリャチョーヴァ(カルメン)、フランチェスコ・メーリ(ホセ)、コスタス・スモリギナス(エスカミーリョ)、クリスティナ・ムヒタリアン(ミカエラ)
演出は、二〇一六年にフランクフルトで初演されたプロダクションをROHにもってきたもの。ROHほどの大歌劇場が、これほどポピュラーな作品であえて純粋な新制作ではなく他劇場の「お古」を使うのだから、よほど優れたものに違いないと期待したが、その通り、ワクワクする時間を体験させてくれた。
演出と舞台は後述するとして、まず面白いのが音楽。現行版、慣用版とは大幅に異なる、ビゼーが初演時に書いたスコアを復元していて、かなり長く複雑なものになっている。
たとえば〈ハバネラ〉の後半の長い部分。これは初演時のカルメン役の要求でカットされたものだという。ホセとエスカミーリョの決闘場面も長く、ケンカ慣れした闘牛士が素人をもてあそぶ描写があり、ホセの凡人ぶりが強調される。この幕の最後、エスカミーリョの歌が遠くから聞こえる場面でも、ホセとミカエラの歌も別方向から聞こえてきて交錯し、舞台に残るカルメンをいらつかせる。
そして、これは使用したスコアのせいか指揮のせいか録音のせいか、ヴィオラ・パートがとてもよく聞こえる。それで声部の絡み合い、ハーモニーが奥深くなり、響きの雰囲気がかなりワーグナー風になっているのが面白かった。ヴェリズモ・オペラ風に激烈に単純化された現行版よりもオッフェンバック的であると同時に、ワーグナー的でもあるという、非常に興味深い音楽。
こうして、ビゼーの音楽を新鮮に、最大限に活用するのとは対照的に、セリフはばっさりカットして事前に録音されたカルメンのモノローグで物語をつなぐ。このあたりは映画的。衣裳の雰囲気が一九二〇~三〇年代の夜の社会を感じさせることといい、トーキー初期の映画を想わせる。
 公式サイトから。(C) ROH.Photo by Bill Cooper
公式サイトから。(C) ROH.Photo by Bill Cooper舞台装置は、レビューのフィナーレ風の大階段があるだけ。装飾も何もない、暗灰色の階段。なぜ階段かといえば、多人数の動きと位置関係を客席からわかりやすく見せるため。それ以外は何の意味も持たないという点では、平らな能舞台によく似ている。具象性を徹底して奪うことで、人の動きと表情、素のドラマに集中させる。
独唱と合唱に加えてダンサー数人が出ずっぱりで踊り、音楽に合わせて目まぐるしく移動する。ビゼーの音楽が、まるでバレエ音楽のように、肉体の動きとリズムで表現されつくす面白さ。
その肉体の躍動のなかから、感情がリズムとメロディを持つ言葉、すなわち歌となってあらわれてくる。ここでは言葉に音楽がついて歌になるのではなく、音楽に言葉がついて歌になる。だから、ただのしゃべり言葉、説明するだけのセリフはいらないのだ。
登場人物のなかではミカエラの性格づけがもっとも鮮烈で、彼女との対比によってカルメンもホセも、盗賊たちも際立ってくる。
ダサくてウザい田舎者の女。純粋だが独りよがり。大人の女の身体をもちながら、少女のような格好でそれを隠して、もてあましている。ホセは彼女にまったく関心がなく、母親のメッセンジャーとしか思っていない。全曲中でもっとも魅惑的な旋律の一つである第一幕の二人の二重唱が、感情の完全なすれ違いを露わにしつつ、しかしきわめて美しく歌われるという、痛烈な皮肉。
孤児でありながらホセの母に愛されて育ったミカエラ。そのことがカルメンや盗賊たち、幸せな家庭環境だったとはとても思えないジプシーたちをいらつかせる。ホセもしょせんはその同類。腕一本で名声と富をなし、派手な服を着て華やかに生きるエスカミーリョの方が自分たちに近く、憧れたくなる存在。
肝心なのは、キャラクターの性格と動きが音楽にうまく合わせて、つまりとても音楽的に肉体化されていること。この点こそがコスキーが評価されるゆえんなのだろう。ビゼーの音楽を愛するからこそ、最大限に活用する。
それが端的にあらわれたのが、ホセの〈花の歌〉だった。ここはいかにもアリアらしく、完全に時間の進行が停まり、ホセとカルメンだけの宇宙になる。ホセのなかから突然に湧きだしてきた、あまりに美しい詩と旋律。
ここはもう、歌の力にすべてをゆだねるだけ。この歌の突然の出現ゆえに、ホセもカルメンも破滅を運命づけられる。ドラマの中にあるのと同時に、ドラマの外からドラマを決定してしまう、名曲。ホセ役のメーリが見事な歌。全体に歌手も指揮も充実していて、心地よし。

Anna Goryachova as Carmen in Carmen, The Royal Opera Season 2017/18 © ROH 2017. Photograph by Bill Cooper.
五月十九日(土)地上の夫、冥界の夫

サントリーホールで日本フィルの演奏会。ラザレフ指揮でストラヴィンスキーの《ペルセフォーヌ》日本初演。
イダ・ルビンシュタインの委嘱で、一九三四年に彼女が主演したメロドラマ、音楽劇。台本がアンドレ・ジッドというあたりが、ルビンシュタインならではの豪華な作詞作曲コンビ。
自らの宿命を従容と受け入れつつ、しかし地上と冥界、どちらの夫にも従属することなく、主体性を保って二つの世界にうららかな光をもたらすヒロイン。
五月二十日(日)拍手しながらブー

新国立劇場の《フィデリオ》初日。
カタリーナ・ワーグナーの演出、面白かった。なんというか、ブーを叫ばずにはいられない、今年最高の舞台(笑)。
これはブーイングしなければ演出家に失礼な気がして、カーテンコールの最後近くまで引っ張ってやっと姿を見せた演出家に、思わず拍手しながらブーイングした。こんなこと生れて初めて。
今の日本の状況にぴったりの舞台。クラシックに予定調和の感動を求める人は身震いして嫌うだろう演出。でも、ナチス時代のドイツで《フィデリオ》を盛んに上演することに、それを熱狂してみることに大いなる矛盾と愚かしさを感じたトーマス・マンの精神には、きちんと則っている演出。いまどき、レオノーレの三番を終幕前にやるなんてと思ったけれど、これならバッチリ。
何の予備知識もなく、一度見ただけで書いているので、舞台上の出来事について誤認や見落としが多々あるかも知れないが、ご容赦のほどを。
カタリーナ・ワーグナーの演出の肝は「女傑の存在など信じない」ということにあったと思う。
暴力が支配する状況において、いかに女性が無力であるか、あってきたかを、これ見よがしなまでに見せつける。男性の演出家がやったら、おそらく女性蔑視として非難される演出。女性演出家でなければ許されない演出ではないか。
伏線をあちこちに張りながらも定石通りに第一幕を終えたワーグナーは、第二幕にいたってその毒を物語に注ぎ込む。
レオノーラは男装しているときしか、強い英雄的存在であることができない。第二幕でフロレスタンの地下牢に到達したとき、鉄柵を次々と引き抜いて見せるが、これはフィデリオとして男装しているからこそ。
そのあとでロッコが誤ってレオノーラのカツラを剥がしてしまい、下から女性らしい長髪が現れたとたん、彼女は狼狽し、ロッコの視界から逃れようと隅に逃げ、追いつめられる。ロッコが不審に思いながらも深く考えずにカツラを戻してやると、再び力を取り戻して(英雄サムソンの長髪とは逆の効果)、フロレスタンの墓を掘ることを手伝い始める。
そのあとピツァロが現れ、ナイフを取り出してフロレスタンを亡き者にしようとする。暗がりから現れ、そのナイフを奪うレオノーラ。形成逆転、ピツァロを刺そうとする。
だがピツァロ、パワハラとセクハラ、権力濫用が服を着て歩いているみたいなこの男は、相手がフロレスタンの妻、すなわちスカートをはいた弱い女であるとわかった瞬間から、おそらく自分の勝利を確信している。すばやくナイフを奪い返し、男の力でレオノーラを床に叩きつける。
そのとき、フロレスタンは何をしていたか。
見事なまでに、手をこまねいて見ていただけ。そして再びナイフを手に迫るピツァロをあきらめたように見つめ、無抵抗に刺されて倒れる。
この男は最初から暗い虚無にとらわれていて、何の希望も持っていなかったことが、ここにいたってよくわかる。
自分をこのつまらない現世から救い出してくれる天使、死の天使を待ち焦がれているだけだったのだ。第一幕、下層にあるこの男の牢獄には、上階から光が差し込むことがある。そのとき見えるのはマルツェリーネ(ピンクの部屋とお花畑に暮らしてお人形遊びをやめられない、夢見がちな女の子女の子した少女)の長髪の影。
その影に死の天使の幻を見たかのように、フロレスタンは壁に白墨で長髪の女の絵を描く(第二幕でそれを発見したロッコは、その長髪の姿がカツラのとれたフィデリオとそっくりなことを不思議がる)。そして第二幕のアリアを歌いながら女の絵に天使の翼を描き加え、床石を剥がして、墓穴を自分で掘っている。
虚無にとらわれたこの男は、妻が一人で助けに来たくらいでは、どうにもならないと思っているのだ。その意味ではこの男も女性を蔑視している。力を合わせれば何とかなったかも知れないのに、女の敗北を当然の結果と納得し、自分より強い男に刺される。
ここで、大臣の到着が上階から告げられて二重唱になる。勝利の二重唱ではなく、この演出では、あきらめないレオノーラが傷ついたフロレスタンを励ます二重唱に意味が変わる。フロレスタンの手を引いて逃げようとするレオノーラ。
だが、再び姿を現して立ちはだかり、勝ち誇るピツァロ。
絶望。ここでよりにもよって、その名も高き「レオノーレ」序曲第三番が始まる。レオノーラはピツァロに抱きすくめられ、口づけされ、ナイフで刺される。妻が蹂躙される脇で、茫然と座り込んでいるフロレスタン。ピツァロは手下と協力して、地下牢の入り口をブロックで封鎖し、脱出不能にする。
そのあとピツァロはフロレスタンのコートを奪い、さらにはレオノーラが自分の部屋の妻だか愛人だかの肖像によく似ているのに気がつき、ほくそえむ(友人たちの意見に従うと、もともとレオノーラに横恋慕していたから、肖像も彼女を描いたものらしい)。この男はその地位と力にふさわしい能力、フロレスタンとは比較にならない狡猾な生存能力と執念深さをもっている。フィデリオの部屋に入り、レオノーラのワンピースを奪い、そこにあるフロレスタンの肖像を眺め、容姿をもう一度頭に入れる。
そうして終景。ピツァロと愛人(一瞬マルツェリーネかと思ったが、そうではないらしい)はフロレスタンとレオノーラに化け、見事に逃げおおせる。そればかりか、解放されたはずの囚人たちをその妻たちもろとも、再び地下牢に閉じ込めてしまう。
一網打尽。そして大臣に対し、傲然と胸を張って対抗する。そのころ、本物のフロレスタンとレオノーラは出口のない地下牢で、ラダメスとアイーダのように愛を讃えながら死を待っている。
こうして書いていても、まあ何といやな話。よくもまあこんな意地悪な展開を思いつくものだと、ブーを叫ばずにはいられない(笑)。
だが、折よく大臣が現れて、その大臣が正義の味方で危機を救ってくれる、そんなうまい話があるのだろうか。正直に努力すれば、神様が幸運をもたらしてくれるものなのか。上位の権力者が寸前に気まぐれな憐憫を与えてくれることを、期待していていいのだろうか。「デウス・エクス・マキナ」は、お話のなかだけのことじゃないだろうか。
カタリーナ・ワーグナーがこの演出で何をいいたいのかは知らない。オペラなんだから、これ以上は観客の想像と感想にまかせているに違いない。
私が思うのは、暴力が支配する状況、暴力だけが尺度となる状況においては、女性や力の弱い者は、ひたすら虐げられるだけということ。男に化けて暴力で対抗してみても、勝てるはずがないこと。女傑など、女豪傑など、存在しない。いたとしても単に幸運な例外。
そうではない社会、暴力や圧力(物理的なものであれ、精神的なものであれ)が理性によって封じ込められる社会でしか、女性や弱者が強者と平等の権利をもって生きることはできない。現世はろくでもないものだが、古代や中世はいうまでもなく、半世紀前と較べても、その点では少しずつ進歩しているし、それを手放すことがないように、あきらめてはならない。
《フィデリオ》のト書きとは何も関係がないといわれれば、その通り。だから私はブーイングをする。だが私は、そこに積極的なメッセージを感じるから、同時に拍手を送る。
続けて観た、コスキーのカルメン、ジッドのペルセフォーヌ、カタリーナのレオノーラ。男の身勝手な欲望と暴力が支配する世界を生きる、三人の女。
五月二十二日(火)いつまでも若く
サントリーホールで東京都交響楽団の定期演奏会。指揮は下野竜也。
メンデルスゾーン:交響曲第三番《スコットランド》
コリリアーノ:ミスター・タンブリンマン ─ボブ・ディランの七つの詩(二〇〇三)(日本初演、ソプラノ独唱ヒラ・プリットマン)

端麗辛口のスコッチもよかったが、やはり日本初演の後者がききもの。ボブ・ディランの歌の歌詞に音楽をつけたものだが、面白いのは今年八十歳、ディランより三歳年上のコリリアーノがディランの歌をまったく聴いたことがなく、その詩が喚起するイメージだけで音楽をつけたということ。つまりディランの旋律のアレンジやヴァリエーションではない新規の作曲。オリジナルのピアノ伴奏版は二〇〇〇年作曲。今回のオーケストラ版は二〇〇三年完成で、同年に初演したのが今日歌うプリットマン。
選ばれた詩は「ミスター・タンブリンマン」「物干し」「風に吹かれて」「戦争の親玉」「見張塔からずっと」「自由の鐘」「いつまでも若く」の七つ。プログラムに引用されたコリリアーノ自身の説明によると、
『空想的で華麗なプロローグ「ミスター・タンブリンマン」に続いて、5つの鋭敏で内省的なモノローグが作品の中心部分を形成する。そしてエピローグの「いつまでも若く」は一種のフォーク・ソング的ベネディクトゥス(祝祷)であり、これが作品を締めくくる。5つの歌は、感情の成熟、市民が成熟していく旅をドラマティックに辿る。無邪気な「物干し」に始まり、広い世界があることに気づき始め(「風に吹かれて」)、「戦争の親玉」では政治に対する怒りを覚え、この世の終わりを予感し(「見張塔からずっと」)、思想の勝利というヴィジョンに到達する(「自由の鐘」)』(飯田有抄訳)
六〇年代につくられた詩(「いつまでも若く」のみは一九七三年)による、市民の感情が成熟していく物語。いうまでもなくそれはアメリカの六〇年代を生きた市民の成熟。しかしそれは個人のものであると同時に、アメリカ国民の、アメリカの成熟の物語でもあると思えた。
回想であると同時に、このように成熟してほしいという希望の物語。アメリカ人の、愛する国家への思い。「風に吹かれて」の「何回弾丸の雨がふったなら 武器は永遠に禁止されるのか?」(歌詞はすべて片桐ユズル訳)なんてのを読むと、五十年たってもその希望は実現していないように思える。
というより、その「望ましい姿」は、実現したと思った次の一瞬に消えてしまう、一歩進んだと思えば一歩下がる、それを永遠に繰り返して、幻のように明滅し続けているものなのだろう。
最後の「いつまでも若く」に歌われるのは、なかでも切実な願い。
「つねに勇気をもち 立って筋をとおし強く いつまでも若くありますように」
人は永遠に若くあることはできない。しかし国家は、そうあることができるかも知れないし、そうあってほしい。
ここに至って、下野さんは今のアメリカへの願いを込めて、この曲を選曲したのではないかという気がしてきた。
どうしてコリリアーノの前にメンデルスゾーンがあるのかよくわからなかったのだが、後がアメリカなら、前は二〇一四年の独立投票で揺れたスコットランドということなのか。その二年後、大統領選挙にブレクジット、スマホ時代のポピュリズムの行方を考えさせられた二〇一六年。ディランがノーベル文学賞をもらったのはこの年なのだ。
プリットマンが歌った「いつまでも若く」の祈りは美しかった。はかなく、もろい願い、現実に対してはひどく虚しく思える願いが、歌われ、奏でられているあいだだけはこの世に、少なくともサントリーホールの空間に、出現して光を放っていた。
はかなく、もろい願い。
ここで、新国立劇場の《フィデリオ》で虚しく砕け散った希望、辱められるレオノーラのことを思い出す。
あの瞬間、残酷に響き出すレオノーレ序曲第三番。
あの瞬間まで、希望は残っていた。フロレスタンは傷ついたが、外へ出て、大臣に会えさえすれば。
そのとき、立ちはだかるピツァロ。
まるで『民衆を導く自由の女神』が凌辱されていくかのような、あの絶望感。信じていたものの崩壊。
私は男だから思う──おいフロレスタン、それでいいのか。
客席の人間にはどうすることもできない。手をこまねいて見ているしかない。
その痛みは今も忘れがたい。あまりに痛すぎて、快感に似てきさえする。
原作無視でも、冒涜でも、無茶でも、支離滅裂でも、このさいなんでもいい。
こういう絶望の瞬間を出現させ、記憶に刻みつけさせるために劇場は存在すると、私は思う。
「いつまでも若く」の美しき希望を降臨させるために劇場は存在すると私が思うのと、同じように。
五月二十六日(土)動かざること
山梨英和大学メイプルカレッジ『“クラシック音楽”って、何?』で、「ヴィルヘルム・フルトヴェングラー ドイツ音楽に生き、ドイツ精神に殉ず」。

の、はずが、九時三十分新宿発の特急かいじ号は、国分寺駅~西国分寺駅間の信号機故障で、ずっと新宿駅のホームに停まったまま。発車したのは三時間後。十一時に山梨市駅に着いて、昼をゆっくり食べて十三時三十分の開講の予定が、会場に着いたのは開講一時間後。
この講義シリーズの中心人物で、今日は聞き役だったはずの矢澤孝樹さんに、急遽一時間をつないでいただくことに。大変なご迷惑をかけたが、矢澤さんがいてくださったのは不幸中の幸い。単独の講義だったらどうなっていたことか。
山梨版「川中島の戦い」というか、キツツキの戦法が見事に大失敗、戦場に遅刻したけど矢澤信玄がつないでくれて、最後はどうにか勝てたみたいな展開。
二時間しゃべるところを半分の一時間だけで済ましたのに、エネルギーを一気に放出したからか、終わったら心身ともにクタクタ。帰りのかいじが、わずか十分程度の遅れで通常運行しているという復旧能力に感心しつつも、夜に参加するはずだった中学の同窓会二次会はキャンセルして帰宅。
停まった電車に座りっぱなしだったためか胃が萎縮して食欲もわかず、それでも何か栄養はとらなければと思って、矢澤さんからお土産にいただいたほうとうを食べる。
麺をドロドロッと煮込んだほうとうはこういう身体にこそぴったりで、とても美味で驚き。食べだしたらスルスルと胃に入る。さすが信玄の戦陣食、疲れた人間でも食べられるようにできていると、その効用に感服。
五月三十日(水)バーンスタインの世紀
サントリーホールで読売日本交響楽団演奏会。指揮はイラン・ヴォルコフ。
・プロコフィエフ:アメリカ序曲
・バーンスタイン:交響曲第二番《不安の時代》(ピアノ=河村尚子)
・ショスタコーヴィチ:交響曲第五番
交響曲二曲は、バーンスタインがニューヨーク・フィルと一九五九年にヨーロッパ・ツアーを行ない、ソ連まで訪れたときと同じ組み合わせ。
ソ連では作曲者臨席でこの曲を演奏しただけでなく、父をボストンから連れてきて、ソ連に残っていた父の兄に再会させた。しかし半世紀ぶりに会った兄弟は会話がほとんど成立しなかったらしい。

帰国後すぐに、ショスタコーヴィチの五番を訪問記念としてセッション録音したとき、このときにかぎってニューヨークではなく、ライバルRCA専属のボストン響の本拠地、ボストンのシンフォニーホールで録音したいとバーンスタインが言い出し、コロンビアのスタッフを困らせたという話がある。音響上の理由だと本人は言ったが、移民という父の選択の結果、自分がこの町に生まれたことを再確認したかったのにちがいない。
イスラエル人ヴォルコフの指揮は、CDで聴いていた通りのコクのある響きと骨太の音楽づくりが魅力的だった。
六月四日(水)イタリアを望んで

サントリーホールで東京都交響楽団。指揮はダニエーレ・ルスティオーニ。
・モーツァルト:《フィガロの結婚》序曲
・ヴォルフ=フェラーリ:ヴァイオリン協奏曲(独奏フランチェスカ・デゴ)
・R・シュトラウス:交響的幻想曲《イタリアより》
一ひねりして、イタリアを意識したドイツ音楽というプロ。まずイタリア語台本に曲をつけたモーツァルト。
次にドイツとイタリアのハーフで、後半生をミュンヘンで過ごしたヴォルフ=フェラーリ晩年の作品。閨秀ヴァイオリニストのブスタボ(バスタボ)のために書いた、ソロの名技をひたすら盛り立てる長大な曲。パガニーニの二十世紀版のよう(と思ったら、今日の夫妻コンビはDGに二曲を合わせて録音していた)。
そして、イタリアへ行くことで古典派好みの父の影響を離れ、ワーグナー風のサウンドをためらいなく採り入れた、若きシュトラウスの出発点のような曲。それぞれの特徴を出した指揮と演奏。
六月六日(水)演奏会のフルコース

サントリーホールで、ヴェルザー=メスト&クリーヴランド管弦楽団のベートーヴェン・ツィクルス「プロメテウス・プロジェクト」第四日。自分は二日めに行けなかったので三回め。
おそろしく高水準なツィクルス。とにかくオーケストラが上手い。メストの最高の楽器。まろやかにブレンドされた、羽毛のようにやわらかな響き。十七型倍管の巨大編成が信じられないような透明度の高さ。譜面台にヴォリュームコントローラーがついていると思いたくなるくらい、滑らかに、微妙に変化していく強弱。その強弱と見事に連携した加減速によって生まれる、しなやかな流動性。カラヤンの水平的なレガートとは異なる、くねりながら流れるレガート。
これみよがしな劇性を排した、二十一世紀の「移行の芸術」とでもいうか。トスカニーニの「対照の芸術」とは正反対だが、かといってフルトヴェングラー流の「移行の芸術」とも異なる、古くて新しいもの。十二~十四型の編成が主流の現代のヨーロッパ式ベートーヴェンとは異なる、しかもアメリカのなかでも独自の境地に達したもの。
昨日の第八番第二楽章も、明滅する木管のソロをはじめとして妖精の国みたいな超絶的な美しさだったが、今日の《田園》第二楽章も凄かった。そして終楽章の水たまりに照り映える太陽のような、響きの瑞厳(きらきら)しさ。
そして、ここまで演奏してきた八曲の声楽なし交響曲の最後にあえて《田園》をもってくることの意味。そのあとに舞台外からの印象的なファンファーレ(このトランペットがまた巧かった)をもつレオノーレ序曲第三番がきたことを考えたとき、今日は全体が「第九」の第三楽章みたいだと思えてきた。
一回の曲目構成はパターン化されていて、前半のオードヴル(序曲)とポワソン(軽めの交響曲)が十四型、後半のヴィアンド(メインの交響曲)が十七型倍管と、コース料理のようになっている。
それと同時に、全体が巨大な「第九」に見立てられているように思えるのだ。初日の一&三が第一楽章アレグロ、三日めの八&五が第二楽章スケルツォ、四日めの二&六が第三楽章アダージョ、楽日の九番が終楽章という感じ(聴けなかった二日めは一楽章と二楽章の中間か)。
六月九日(土)凝集と拡大、苦悩と歓喜

アルテミス・カルテットの男性二人にインタヴュー。嬉しいことに、四年前にも自分がインタヴューしたことを場所も含めてきちんと憶えていてくれた。前回は翌日の演奏会を聴くことができなかったが、今回は前日の演奏会を聴いていたので、話が進めやすい。
ただしあのとき、私が本番を聴けないのを悔しがると、「次に来るときまで、そのメンデルスゾーンのCDを聴いて待っていてくれ(笑)」と冗談を飛ばしたフリーデマン・ヴァイグレ(読響の次期首席セバスティアンの弟)は、もうこの世にいない。しかしその思い出がこの二人の中にまだ鮮烈に生きていることを、きっとその隣に今も座っていることを、話を聞きながらひしひしと感じる。
四年前に聴けなかった理由は、同時刻のカザルス弦楽四重奏団に行くことになっていたためだったが、不思議なことに今回もこの二つの弦楽四重奏団が同時に東京にいる。カザルスはサントリーの小ホールで七日から十日まで、四日間六回のシリーズでベートーヴェンの弦楽四重奏曲全曲。夜に第四回を聴きに行く。

七日までサントリーホールでクリーヴランド管弦楽団の十七と十八型の倍管ベートーヴェンを聴いてきた身には、三百八十席の小空間での弦楽四人の演奏が、あまりに親密に聴こえすぎて(笑)不思議に感じられる。アルテミスは八百席の紀尾井ホールなのでそれほど差を感じなかったが、ここでは演奏直前に四人が合わせる息づかいの音まではっきり聴こえるし、人間が身体を動かすことで音が出るのだということもはっきりわかり、直接音が耳に迫ってくる。
あらためて、クリーヴランド管弦楽団の演奏が二千席の大空間に響きわたらせるために練り上げられてきたものだったことを、実感する。カザルスSQの演奏があまりシステマチックな、緻密に構築するものではないだけに、とりわけその差がきわだつ。宇宙と小宇宙の対比が禅的というか室町文化風で、愉快。
四人が初日に演奏した大フーガを、クリーヴランドの十八‐十五‐十一‐十一‐九の六十四人合奏版と聴きくらべてみたかった。しかしどちらも七日の夜七時からの演奏会で、大ホールと小ホールで隣り合って演奏されていたので、物理的にそれは困難――曲目の最初と最後で位置は違ったので、大ホールの《合唱》をあきらめれば聴けるが――なのだった。
クリーヴランドの大フーガは、メストがプログラムに「ベートーヴェンが残した最も斬新で先駆的な作品の一つ」で、「それらはまるで、二十世紀に書かれたかのごとく響く」と書いた通り、非常にモダンで洗練された響きのものだった。
その先駆性と近代性は、実存主義を強く感じさせた。オリジナル版、たとえば昨年十月にエベーヌがハクジュでやった凄演などだと、実存主義が個人の孤独と不安につながり、心の奥の超越的な存在(宗教と呼んでいいのかどうかはわからない。あるいは超人なのかもしれない)に向かっていくようなものになるのに対し、弦楽合奏版はその孤独を、人間の集団すなわち社会で共有していく、つまり実存主義を社会が包み込んでいく(実存主義が社会を、でもいい)ような感じ。それに続いて《合唱》のシラーの賛歌がくるのは、少なくともその瞬間においては、とても納得がいく。
その《合唱》、予想通り第三楽章が神がかった美しさ。停まることなく次々と消えていく、息づく美しい瞬間。最後の弦のピツィカートの甘くまろやかな、小さな波紋のような震えも素晴らしかったが、圧倒的なのはやはり木管。第四楽章で前の三つを回想して否定する場面でも、第三楽章の回想は極度に耽美的で、人をそこから離れがたくするものだった。
それに続く終楽章の完成度の高さもあきれるほどのもの。ベートーヴェンがここで投入する軍楽的要素、シンバルなどの打楽器群までドルチェに、他の楽器と調和して響くのが凄い。
そしてまた木管。独唱の背後で伴奏的に動く木管があまりに美しすぎて、声よりもそちらに耳がいってしまう。リズムを保持しているだけでひたすらに美しいなんて、ソロモンの大公トリオ第三楽章のピアノみたいなことは、お願いだからやめて。たまらなくなるから(笑)。
前日のレオノーレ序曲第三番から《合唱》にかけて顕現した、調和と理想主義の美は、カタリーナ・ワーグナーのまがまがしい毒を洗い流し、清めてくれるもの。「苦悩を通じての歓喜」とは、そうかこういうことなのかと思う。
両者の関係は、単なる勝ち負けの話ではない。私のように鈍い人間は、邪なものがあってこそ聖なるものの尊さに気がつくことができる。メストの理想主義を今の自分が素直に受け入れられるのも、カタリーナの演出あってこそ。
舞台清祓祝典劇ならぬ、演奏会清祓祝典音楽。何と見事な「東京勝手にツィクルス」。
(舞台清祓祝典劇とは、高木卓が《パルジファル》のビューネンヴァイフェストシュピールの訳語としたもの。舞台神聖祝典劇という一般的な訳よりも、清めはらうという力と作用を込めたこちらの方が、私は好きだ)
六月十二日(火)天狗とハルサイ

この日から三日連続で観能三昧。まずは午後に国立能楽堂で「第十六回青翔会(能楽研修発表会)」。
国立能楽堂の研修所で学んだ三役(ワキ方・囃子方・狂言方)などの新人を中心に、若手による会。
・舞囃子『忠度』狩野祐一(喜多流)
・舞囃子『巻絹 惣神楽』村岡聖美(金春流)
・舞囃子『絃上(けんじょう)』亀井雄二(宝生流)
・狂言『 清水』河野佑紀(和泉流)
・能『善界(ぜがい)』安藤貴康(観世流)
能『善界』は、中国の仏教界を堕落させた天狗、善界坊が次に日本に目をつけて比叡山の僧正を襲うが、僧正が祈ると不動明王、さらに山王権現や石清水八幡などの日本の神々も護法神となって現れて善界坊に攻めかかる。こてんぱんに懲らしめられた善界坊は、二度と日本には手を出さぬと逃げていくという、スケールの大きな話。元寇のさいに諸神社が主張した、祈祷による異敵調伏の功徳を天狗相手に置きかえたような話で、大映映画の『妖怪大戦争』も思い出す。
ただ、実際に舞台で舞うのはシテの善界坊だけなので、その場面を一人で現出させなければならないという、いかにも能ならではの難しさとやりがいがありそうな作品。
能界でも女性の増加は必然の流れで、今日もシテ、小鼓、太鼓に女性が加わっていた。能の場合、謡で声を出すシテや地謡はもちろんのこと、囃子方も洋楽器と違って掛け声が重要なので、笛以外は耳からも性別がはっきりとわかる。
アルトで男性風に出すのが現在の形だが、違う発想もありうるのではないかと堂本正樹が書いていたのを思い出す。シテが生身の女性の役の場合は、直面でやる可能性だってあるだろう。そうして新たなスターが出てくる未来もありえる。

夜はオペラシティでロト&レ・シエクル。本当に素晴らしかった。日本でこの一公演だけなのはもったいない。
二~七日に聴いたメスト&クリーヴランド管弦楽団と対比すると面白い。どちらも恐ろしく優秀なオーケストラだけれども、基盤が好対照。
クリーヴランド管は十九世紀末から二十世紀にかけて完成された「交響楽団」という興行システムの、一つの理想的な形。言葉の最良の意味での「音の巨大工場」。完璧にシステム化され、品質管理された最新のプラント。指揮者であると同時に有能な工場長メストのもと、楽員は芸術家であると同時に誇り高き工場労務者。
対してレ・シエクルは、ロトという親方が中心の「大型の音楽工房」。専門職の職人たちが仕事の種類と規模に応じて集まる。システマチックではないが、親方のもとで協力しあって完璧なアンサンブル仕事をする。
いうまでもなく後者は十九世紀以前のフランス風。親方個人の一座という気配が濃く、組織は流動的で不安定。油断すれば演奏水準はすぐ下がる。クリーヴランド管は二十世紀資本主義型。組織がしっかりしているので短期的に水準が激しく変動するようなことはない。安定と信頼のブランド。
様式的にも歴史的にも、音楽工房がベートーヴェンをやり、音楽工場がハルサイをやるのが合っているのに、今回はそれが逆になっているのも面白い。
ストコフスキーがフィラデルフィア管の首席になったのが一九一二年、ハルサイ初演が一九一三年というのは時代の転換点として暗示的な符合だけれど、そのハルサイを音楽工房がやってのけてしまう、ものすごい演奏を聴かせてしまうというのが、二十一世紀の面白さ。
この恐るべき音楽工房の経営的基盤、資金面のバックボーンはどういうものなのだろうというのは、気になるところ。ロト&レ・シエクルとクルレンツィス&ムジカエテルナが、フランスとロシアから出てきているということも、考えさせられるところ。
六月十三日(水)『正尊』を観る


夜に国立能楽堂で、能楽の囃子方が年四回主催している、東京能楽囃子科協議会定式能。
・舞囃子『当麻』武田孝史(宝生流)
・舞囃子『玉葛』櫻間右陣(金春流)
・一調『雲林院』坂口貴信(観世流)
・狂言『千鳥』山本則俊(大蔵流)
・能『正尊(しょうぞん) 起請文・翔入』観世清和(観世流)
新人や若手に続けて重鎮たちの芸に接すると、私のような素人でも、やはりまるで説得力が違うと感じる。シテも三役も、適切な脱力によって緩急強弱に自然な変化をつけている。前にこの会を観に来たときには、初めから終りまで妙に意気があがらず、不思議だったのだが、今日はピシッと締まっている感じ。
『正尊』は『烏帽子折』とともに能の大チャンバラ、多人数が斬りあう「斬り組み」ものとして知られる作品。
作者の観世弥次郎長俊は十六世紀前半の戦国時代前期に活躍した人で、後世の歌舞伎につながるような大スペクタクル劇を得意とした。正尊と弁慶のどちらがシテなのかはっきりせず、観世・宝生・喜多は前者を、金春・金剛は後者をシテと、流派によって別れるのも、大人数作品だからこそ。今回は観世流。
平家を滅ぼした後、頼朝に疎まれて京にいる義経。刺客として鎌倉から派遣された土佐正尊(土佐坊昌俊)の軍勢が襲いかかるが、企みを見破った義経主従に返り討ちとなるという「堀川夜討」話。
登場の人数が凄い。義経に弁慶に静御前に江田源三と熊井太郎と、義経方が五人。正尊とその手勢が合わせて十二人。合計十七人のチャンバラ。江田と熊井が十人を斬り、弁慶が一人を斬る。最後は正尊が義経と静(子方が演じる彼女も刀を抜いて戦うのだ)と戦っているところに弁慶が駆けつけ、薙刀同士の戦いに。正尊が倒されたところを江田と熊井が縛り上げ、生け捕りにしておしまい。
この十七人のほかに囃子方四人、地謡八人、後見三人がいるので、計三十二人が能舞台と橋懸に、文字どおり犇(ひしめ)いている。中入には狂言方のアイも出るので、総勢三十三人。
しかもシテの正尊が二十六世観世宗家の観世清和だからか、義経が銕之丞家の淳夫、地謡に矢来観世の喜正と、分家も一挙登場のにぎやかさ。
義経の生涯最後の勝ち戦にふさわしいスペクタクル。このあとは大物浦(舟弁慶)、吉野(吉野静)、安宅(安宅)、衣川(錦戸)など、流亡を重ねて敗死することになる。
六月十四日(木)関根祥丸の能


昼に銀座の観世能楽堂で、観世会の荒磯能。
・能『西王母』関根祥丸
・狂言『不腹立』三宅右矩
・能『玉鬘」武田文志
観世能楽堂の客席は縦長であることに特徴があり、橋懸が短め。国立能楽堂から続けてだと、なおさらそう感じる。
荒磯能は観世宗家の若手の弟子が出演する会。シテは二人とも昨日の『正尊』に切られ役で出ていて、忙しそう。他に何人も地謡で出ているし、清和も『西王母』の後見にいる。さらにワキの王(周の穆王)役の森常太郎が降板して、昨夜弁慶役だった森常好が代役で登場。
目当ては『西王母』を舞う関根祥丸。一九九三年生れ、今年二十五歳のこの人(名はよしまると読む)がシテ方の「希望の星」として将来を嘱望される存在だと、門外漢の自分の耳にまで、あちこちから届いてきたからである。平日昼の公演なのに完売。
昨年亡くなった観世シテ方の重鎮、関根祥雪の孫で、この祖父と八年前に早世した父祥人の二人をシテにして、二〇〇四年に子方として義経を演じた『烏帽子折』のDVDも出ている。その頃から期待されていたらしい。
単なる印象としてしか語ることはできないけれど、凛とした姿と舞の美しさ、明快に響く謡。そして何よりも、私にはしばしば退屈な、弛緩したものに感じられるゆっくりした女舞が、手先まで張りつめた集中力で間然するところがなく、眠くならずに見続けることができただけでも、驚くべきこと。
まだこれからのところもたくさんあるのだろうが、期待を集める理由が納得できた気がする。チケットの入手が次第に大変になりそうな気配。近い将来に『道成寺』を披くときには争奪戦かも?
六月十六日(土)夢幻能の世紀
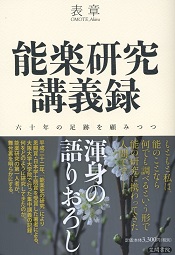
表章(おもてあきら)の『能楽研究講義録―六十年の足跡を顧みつつ』(笠間書院)を読む。
表章(一九二七~二〇一〇)は、昭和後半~平成期を代表する能楽研究者。東京文理科大学(現在の筑波大学)で能勢朝次(一八九四~一九五五)に学び、一九五二年から九八年まで野上記念法政大学能楽研究所の助手・所員・所長をつとめ、法政大学文学部の専任講師・助教授・教授を兼ね、その後は名誉教授。
この本は二〇〇七年に大阪大学で行なった、四日間十二時限の集中講義を活字化したもの。戦後の実証的な能楽研究の発展をリードした人だから、六十年間の活動の回想が、二十世紀後半の能楽研究史そのもののようになっている。
戦前の泰斗だった能勢朝次や野上豊一郎(一八八三~一九五〇)の印象に始まり、在野の英文学者ながら世阿弥研究で革新的業績を残した香西精(一九〇二~七九)との交流などのなかに、妙に依怙地な先輩学者などの話が混じって、学者の世界の狭さが描かれるのが楽しい。
面白いのは、当初は能そのものはあまり好きではなかったということ。関心はあっても感動はしなかったのが、二歳年上の観世寿夫(一九二五~七八)の能に接して感動することが増えてから、だんだん好きになったという。「研究対象としての関心ではなく、現代に生きる古典演劇としての能の面白さを感じさせてくれたのが寿夫でした」とある。
また、「夢幻能こそが能を代表する作品であるとの戦後の能界・学界、そしてマスコミ社会の共通認識の形成に、寿夫が大きく貢献していた」という。その例として『井筒』を挙げ、能の代表作として評価されるようになったのは、寿夫が『葵上』に次いでこれを得意としたからで、戦前はそこまでの評価はなかったそうだ。明治初年の頃はむしろ現在能の演能頻度が圧倒的に高く、夢幻能は少なかった。芝居的な志向が強かったのだ。
六月二十二日(金)新世界三連発
明後日からのサントリーホール、外来オケで三夜連続の《新世界より》。人気曲で間違いなく売れるとはいえ…。よほど工夫しないと、どんどん旧世界になるような。
二十四日 オンドレイ・レナルト指揮プラハ放送交響楽団
スメタナ:《モルダウ》
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第二番
ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》
二十五日 レオシュ・スワロフスキー指揮スロヴァキア・フィル
スメタナ:《モルダウ》
ドヴォルザーク:チェロ協奏曲
ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》
二十六日 ヤクブ・フルシャ指揮バンベルク交響楽団
ブラームス:ピアノ協奏曲第一番
ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》
六月二十三日(土)平成音楽史
平成最後の夏ということで、「レコード芸術」八月号とラジオで平成三十年間をふり返る仕事。今日はミュージックバードの番組「ウィークエンド・スペシャル」で、片山杜秀さんと「平成音楽史」を収録。
話していてとにかく面白かった、楽しかった、としかいいようのない番組。
片山さんが佐藤優さんと出した『平成史』(これも抜群に面白い)のクラシック音楽版をやろうというわけで、佐藤さんのインテリジェンスには及びもつかないけれど、不肖私めが相手役を仰せつかった次第。
簡単に言えば、毎年末に放送してご好評をいただいている「クラシック放談」の平成史版という感じだが、三十年間の流れの中で事象を追うかたちにすると、それぞれの関係がより立体的に結びあって、うごめいていく。
マーラー、ブルックナー~オウム~東日本大震災~佐村河内などなど。


その楽しさは、いうまでもなく片山さんが話し上手なのが第一だが、同時に無類の聞き上手でもあること。言葉をやりとりする快感がある。言葉のキャッチボールをしていくうちに、受けとったボールがだんだん違うものに変形して、熱くなったり冷たくなったり、大きくなったり小さくなったり、青くなったり赤くなったりする。ときに変化球や魔送球も飛んでくる。
あえて書くが、私がいちばん苦手な話し相手は、「ていうか…」と答えて、つねに人の話をとりあえず否定する人。こういう人が、ではどんな予想外の話を聞かせてくれるかというと、そのあとにくる返事はただ用語を言い換えているだけで、論旨は変わらなかったりする場合がほとんど。発展性皆無。
片山さんはそれを絶対にやらない。こっちの用語を捕球して、そのまま、しかし微妙に動かし、ふくらませながら返球してくる。
そうするとこっちは、何か気の利いた言葉を使ったような気になってきて、ワクワクしてボールを返すと、片山さんはまた変化させながら、しかし、こちらのグラブにしっかりと気持ちよく、スパンと収まるボールを投げてくる。
こういう、言葉のキャッチボールの希少な快感を味あわせてもらえる頭脳と、四時間番組で存分に会話できる喜び。
ほんとに、文字どおりの、「こんな体験をさせてもらって、さらにお金までもらっていいんですか」といいたくなる仕事、パフォーマンス。
その面白さは独りよがりなものではなく、リスナーにも伝わると信じる。
本放送は八月十九日(日)二〇:〇〇~二四:〇〇で、再放送は二十五日(土)一二:〇〇~一六:〇〇。『平成史』のリスナー・プレゼントもあるので、ぜひお聞きあれ!
・ウィークエンド・スペシャル
8月19日/夏休み自由研究~平成音楽史
「平成」の終わりが刻々と近づいています!1989年1月8日から始まった「平成」が、来年2019年4月30日で幕を閉じる予定です。夏休み自由研究として約30年の「平成音楽史」を改めて振り返り、来るべき時代の到来を展望します。出演はお馴染み演奏史譚の山崎浩太郎さんと、音楽評論、政治思想史研究の片山杜秀さんです。ベルリンの壁崩壊、阪神淡路大震災、オウム事件、東日本大震災・・・。平成の時代を象徴する音楽とは一体何か?(出演:山崎浩太郎、片山杜秀 司会:田中美登里)
六月二十五日(月)奈良、能と律宗

松岡心平の『能 大和の世界』(山川出版社)を読む。副題に「物語の舞台を歩く」とあるように、能作品に描かれた奈良各地を紹介するもの。
松岡は一九五四年生れで東京大学総合文化研究科教授。能楽研究では現代を代表する人物の一人。表章ほかの先達に加え、網野史学なども当然参照している。
猿楽と賤民や仏教との関わりを意識して、民俗学的な仮説や推定もどんどん書くあたりは、表章との世代の差か。
徳川秀忠の時代に新設された喜多流以外の、観世・宝生・金春・金剛の能の四つの流派は、すべて奈良を故郷としている。ところが面白いことに、現行曲で奈良を舞台にした作品は、世阿弥より前の世代には意外に多くないらしい。
世阿弥にしても、若い頃は京に較べて生地奈良を田舎と軽侮していたらしく、六十歳までの作品(と推定されるもの)に奈良を舞台とするものは一つもない。しかし、奈良に戻った六十代以降は『井筒』『野守』『当麻』など、奈良の寺社と関係の深い名作が量産される。その影響で、後継世代の長男元雅が『重衡』、娘婿の金春禅竹が『玉葛』『龍田』『春日龍神』『三輪』などを書いた、と松岡は推定している。
それらの舞台となった地域を紹介するこの本、「奈良坂」の章には、中世にここにあった北山宿という非人宿が登場する。ここは「強大な勢力を持って大和一帯の乞食・非人・芸能者たちを支配していた。この北山宿から、声聞師とよばれる芸能を主体とする人びとが独立し、(略)このなかに世阿弥たち猿楽芸能者も所属していた。奈良坂は、芸能者の故郷だったのである」という。京にも東山の清水坂に非人宿があり、北山宿と勢力争いをしたそうだ。坂、高低差のある場所に住むと決まっていたのだろうか。
中世の非人には、癩者や不具者など重病人や身体障碍者も含まれていた。都市社会の下層階級であるこの非人たちと深く関わり、救済につとめたのが、西大寺の叡尊(一二〇一~九〇)や唐招提寺の覚盛(一一九四~一二四九)など、南都の律宗の僧たちだった。「叡尊や道御たち南都律宗が行った運動は、北山宿に代表される非人宿を歴史の主役に引きあげるような運動であり、それはまた芸能者を含む非人階層を歴史の表舞台に強く押し出すような運動であった」と松岡は書く。宇治橋などの架橋や寺社の再建のような社会事業も担った律宗の僧は、そのための募金活動である「勧進」を通して芸能者とも深く関わる。
自分には、南北朝以後の民衆宗教といえば浄土教や禅宗、日蓮宗といった鎌倉仏教のイメージが強かったから、能もそれらと関係するのだろうと漠然と思っていたが、それら新仏教が勢力を拡大するのはもう少しあとで、鎌倉時代から南北朝にかけては、南都北嶺の旧仏教の改革運動として登場した律宗、とりわけ西大寺流が広く支持されていた。かれらのシンボルは十三重の石塔で、奈良坂に近い般若寺や摂津の兵庫津、宇治浮島などにあるそれは、非人救済、遊女救済、漁民救済の意味をそれぞれに持つモニュメントであったろうという。
世阿弥前後の能の大成期は、律宗から鎌倉仏教へと新仏教の主役が移っていく時代に重なる。夢幻能で死者の霊を弔う僧には、遊行上人などの浄土教や修験者とともに、戒律重視を旨とし、死者の穢れを厭うことなく弔う、律宗の僧が含まれているということか。能は興福寺など南都の旧仏教と縁が深いから、旧仏教が警戒した鎌倉仏教よりも律宗とつながる方がたしかに自然だ。『蝉丸』や『弱法師』など、非人に属すると思しき弱者が主人公の能もある。物狂や狂女と呼ばれる人びとも、そうなのではないか。
戦後民主主義の時代には体制迎合的として軽視されがちだった律宗への再評価は、松岡などが活躍を始めた、一九八〇年代以降に進んだことらしい。自分はよく知らないままだったが、俄然興味がわく。何か読んでみなければ。松尾剛次という研究者の新書がいくつかあるようなので、買ってみる。
六月二十七日(水)真に感動的な芸術
毎年この時期は山岸凉子の『妖精王』を読み返しつつ、日本は梅雨のせいでミッドサマーズ・ナイトがはっきりしなくてつまらないとか言っているのだが、今年は梅雨が消滅したような好天続き。夏至の時期にこんなふうに晴れていると、日が高くて陽差しが強くて、たまったものではないことを思い知らされる。
CDの話。最近面白かったのが、SWRの「ミヒャエル・ギーレン・エディション第七集」。放送録音を集めたこのシリーズ、古典派から近代まですでに六集五十三枚(!)出ているが、個人的には今回の第七集八枚組がいちばん面白い。

テーマは二十世紀初頭の近代音楽。ヤナーチェク、ラッグルズにアイヴズ、ドビュッシー、ブゾーニにレーガー、シュレーカーにヒンデミット、シュトラウスにプッチーニ、ラヴェルにスクリャービン。国も様式もバラバラの作品群を横断的に並べて、ギーレンの鋭利で精妙な響きで鳴らすと、それぞれの響きの同時代性が、透けて浮かびあがってくる感じ。
とりわけ好きなのは六枚目、「キッチュ・オア・アート・オン・TV」に収録された《蝶々夫人》抜粋。一九九七年のテレビ番組『キッチュ、クンスト、…オーダー?』の音声。「キッチュか偉大な芸術になるかは解釈次第」というギーレンによると、《蝶々夫人》は、お涙頂戴の安手の異国趣味にみえるが、プッチーニの作曲は素晴らしいという。
「小さな歌劇場で《蝶々夫人》を観たときには、まるでオペレッタだった。しかしミトロプーロスがウィーン国立歌劇場でこの作品を上演したとき、かれはこれを偉大な、真に感動的な芸術に変えた。〈ある晴れた日に〉のアリアで、蝶々さんは夫の帰還を信じ込もうとして歌うけれど、その悲しい音楽は、彼女がすでに気がついていることを物語っている」
ミトロプーロスがウィーン国立歌劇場で一九五七年にこの作品の新制作初演を指揮したとき、ギーレンはここの楽長の一人で、演出は父のヨーゼフ・ギーレンだった。ミトロプーロスの《蝶々夫人》のウィーンでの録音は残っていないが、一九五六年にメトでアルバネーゼを主役に演奏した圧倒的な演奏のライヴ盤は、わが「無人島の一枚」。だからこの言葉はとても嬉しい。
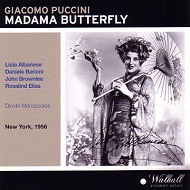
ギーレンは〈ある晴れた日に〉とともに〈花の二重唱〉と二幕終りの音楽も、響きが匂うように精妙に演奏している。
そしてその前に《ばらの騎士》の「銀のばらの献呈の場面」を演奏して「女声二人による花の歌」という共通点をプッチーニとシュトラウスの歌劇に見出し、音にして見せる。
こういうやりかた、ふるいつきたくなるくらいに好き(笑)。
六月三十日(土)能のモダナイズ

世田谷パブリックシアターで「狂言劇場 特別版―能『鷹姫』」をみる。
『鷹姫』の原作は、アイルランドの詩人イェーツが能の影響を受けて一九一六年にロンドンで初演した戯曲、『鷹の井戸』。横道萬里雄がこれを翻案して一九四九年に新作能『鷹の泉』として初演、一九六七年に『鷹姫』に改作した。
西洋の戯曲と日本の能が交わる作品ということもあってか、近年は梅若実や野村萬斎の手で上演される機会が多い。今回は萬斎が主演・演出。
鷹姫(片山九郎右衛門)が守る、岩に囲まれた涸れた泉。不死の水が湧く瞬間を、数十年もじっと待っている老人(大槻文藏)の前に、若き王子、空賦麟(くうふりん。野村萬斎)が水を求めてやってくる。問答をするうちに鷹姫が舞いながら去り、泉が湧きだすが、老人は眠りこけて前回と同じ失敗をし、空賦麟も女を追ってしまい、飲みそこねる。再び涸れた泉の前で老人は岩と化し、空賦麟も老人の姿そっくりになっていく。
不死と永遠を求める人間の業の、虚しい反復を描いたものか。ただし空賦麟が老人の運命を受け継ぐのに対し、原作はクー・フーリンが鷹姫との戦いを求めて去り、老人が残されるラストだという。
想像だが、第一次世界大戦とアイルランド独立闘争の時期に書かれた原作と、敗戦後まもなく初演、ベトナム戦争の時代に改作された能との違いなのかも。
能舞台の制約を離れ、劇場の舞台に写実的な舞台装置をおき、地謡も岩のように舞台を動くのが面白い。シテ方と狂言方の二群の地謡がエコーのようにずれて謡う響きの斬新さ。
空賦麟はワキ方にもやれそうだが、一九六七年の改作初演で萬斎の父万作が演じたという。父から子へ受け継がれる、けっして手に入らぬ物を求める能。
七月一日(日)遁世僧と夢幻能
松尾剛次の仏教関係の新書を四冊。
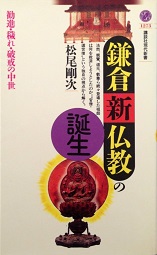



『鎌倉新仏教の誕生 勧進・穢れ・破戒の中世』(講談社現代新書、一九九五)
『太平記 鎮魂と救済の史書』(中公新書、二〇〇一)
『破戒と男色の仏教史』(平凡社新書、二〇〇八)
『葬式仏教の誕生 中世の仏教革命』(平凡社新書、二〇一一)
松尾は一九五四年長崎県生れ、東大卒で山形大学人文学部教授。各書のテーマはそれぞれに異なるが、共通して大きな役割を果たす人びとがいる。
中世に教団を形成した「遁世僧(とんせいそう)」だ。国家の正規の僧である「官僧」を離脱した僧のことである。
官僧とは「天皇から国家鎮護の祈祷の資格を認められた僧団で、僧正・僧都・律師といった僧官と、法印・法眼・法橋といった僧位を有する僧のことである。また、官僧たちが着る袈裟の色は、役職や地位によって相違はあるが、一二世紀には、基本的には白であった」(『葬式仏教の誕生)という。
奈良や叡山などの大寺に属する官僧が現代の僧侶とまったく異なる点は、葬式をしないこと。鎮護国家の祈祷に加わるには穢れを避け、身を清浄に保たねばならない。死者に触れれば穢れるから葬式はしない。法衣が白衣なのも清浄を象徴する。神仏習合の時代だけに、穢れを嫌う神道の流儀が混じったように思える。
官僧は出家とはいいながら、大寺の上層部は王家や摂関家など名門の次男三男が占めており、父や兄との血縁を通じて宮廷政治に関係し、巨大組織となった寺の内外の欲得づくの権力闘争とも無縁ではいられない。一方で、稚児愛など男色はもちろん、妻帯して子供をなす僧までいて(弟子になった実子を真弟子と呼んだという)、破戒が日常化した、俗世と変わらぬ世界だった。この状況が『破戒と男色の仏教史』に活写されている。
遁世僧とは、こうした世俗的な官僧の世界を離脱して、鎮護国家の前に諸人救済を旨とした僧たちである。正規の得度を経ずに自分で僧になった奈良~平安期の私度僧に似ているが、遁世僧はいったん官僧となった上で、自らの意思で離脱している点に特徴がある。
いわゆる鎌倉仏教の宗祖たち、法然、親鸞、道元、栄西、日蓮が、さらに旧仏教の改革者として、奈良の明恵や叡尊、叡山の恵鎮などの律僧がそれにあたり、『鎌倉新仏教の誕生』はかれらを描く。
遁世僧は穢れを恐れず、黒衣や墨染めの衣に身を包んだ。そして死者の葬式を積極的に行う。寺といえば墓地がつきもので、そこに黒衣の僧がいるという現代のイメージは、官僧ではなくて、遁世僧のそれなのである。
鎌倉時代から南北朝の頃は、旧仏教の改革者となった律宗の教団の方が、浄土教や禅宗よりも勢力が大きかった。
律宗はその名の通り、戒律を復興して厳格に守っている身なので、穢れることがないという信念のもとに行動した。葬式や勧進など官僧が嫌う「汚れ役」を引き受けることで、官僧と対立せずに発展できたのである(だからこそ、古代から中世への橋渡し役にとどまって、近世の始まりとともに浄土教などに圧倒され、衰滅したのかも知れないが)。松岡は、とりわけ叡尊の西大寺系の律宗教団に重点を置く研究者である。
これらの遁世僧の教団が、それ以前から葬送に従事していた非人集団と関わりをもち、葬送と供養をセットにして、組織的に行うようになる。穢れを嫌っていた寺の境内にも、墓地がつくられる。
それまで人間は死ぬと、火葬される王族貴族以外は位の高い官僧でも、京なら東の鳥辺野、北の蓮台野、西の化野に運ばれ、埋めずに風葬になるのが一般的だった。さらに貧しい者の場合は、河原や道端に野ざらしにされていたという。
それが平安時代の後期から鎌倉期にかけて、土葬が一般化していく。この変化に大きな役割を果たすのが遁世僧だと考えるのが、『葬式仏教の誕生』だ。
死者を埋葬し、目印として墓を建て、供養する――現代では当然になり、仏教の主な役割だと我々が思い込んでいるそれらは、鎌倉時代以降のものなのだ。
そうしてみると、ここからが私の関心の中心である能楽の話になるが、世阿弥によって大成された複式夢幻能、死者の霊が現れて遁世僧に弔いを求めるという形式は、当時としては最新流行の、ようやく一般にまで広まった葬式の概念に基づくものだということに気がつく。
供養や鎮魂といった儀式は、怨霊の存在を前提としている。弔ってもらえないと執着が消えず、この世に魄がとどまってしまう。
これは個人的な感覚だが、風葬で野ざらしの場合、死者は自然に還って、動物に生れ変ることもあると、抵抗なく感じるのではないか。それが墓への埋葬になると、死者は生前の姿のまま、地獄や餓鬼や修羅に生れ変る感じになる。墓はその救済のよすがとなる。亡者の生前の姿が甦る夢幻能も、同様に供養と鎮魂のよすがとなる。
平安時代までは、崇道天皇や菅原道真のような、国家そのものに祟りをなすような怨霊は神として神社に祀られてきたが、鎌倉期には鎮魂の役目を仏教が果たすようになる。
兵藤裕巳の『平家物語の読み方』(ちくま学芸文庫)によると、滅亡直後に大地震を起こした平家一門の怨霊を鎮魂する役割を担ったのは、叡山の天台座主慈圓(九条兼実の弟)だった。平清盛の鎮魂のために平家物語の原型を創造したのも、慈圓の周囲の人びとだとする説が現在は有力だという。そこには同時に、源平両氏が交代で「朝家の御まもり」たるべしという、鎮護国家の願望が史観として込められている。
これが太平記になると、叛服常ならぬ混沌とした五十年間の争乱を描いて、儒教的道義論や仏教的因果応報論を軸としながら、後半では前半の登場人物が怨霊となって僧たちの夢に出現し、世を乱すことを告げる。夢幻能の後場そのものなのだ。こうした宗教性や怨霊の話は迷信として目をそむけておくのが、近代から戦後民主主義時代の「科学的」態度だったが、近年は当時の人間心理を浮き彫りにするものとして、注目するようになっている。人の心の問題は過去も現在も変わることのない、永遠の謎だからだ。
太平記の原型を書いたのは叡山系の律僧である恵鎮とその教団(小島法師も含む)であり、目的は有名無名の無数の戦死者の鎮魂だったと考えるのが、『太平記 鎮魂と救済の史書』。
能の現行曲の題材は平家物語が多く、南北朝の争乱は扱われていない(かつては存在したが、廃曲になった)ため、太平記にはあまり興味がなかったのだが、怨霊鎮魂という時代精神においては、やはり同時代のものとして、創作の基盤に共通するものが多そうだ。いずれきちんと読まねばならない……。
七月四日(水)地獄の曲舞、元雅と南朝

国立能楽堂で『月間特集・能のふるさと・越路』公演。
・狂言『金津(かなづ)』茂山千五郎(大蔵流)
・能『歌占(うたうら)』上野朝義(観世流)
能『歌占』は世阿弥の息子、観世元雅の作。加賀国の霊山、白山の麓を舞台とする父子の再会物。父(シテ)は伊勢の神官だったが、諸国遍歴に出たところ人事不省となり、三日後に総白髪で蘇生して占師となっている。地獄の凄惨な様子を謡う「地獄の曲舞」が有名な作品。地獄を恐れつつも、阿鼻叫喚のさまに興味津々というホラー趣味がいかにも中世的だ。ただしこれは、別人の古い人気曲をここに転用したもの。
元雅は代表作『隅田川』など、人間心理の暗い襞に触れる「現代性」をもった能作者だが、これはハッピーエンド。シテの総白髪に親近感がわく(笑)。
ところで元雅、先月二十五日に紹介した松岡心平の『能 大和の世界』では、その孫が「越智観世」と呼ばれていることから、大和国南部で南朝について戦った越智氏との関連が指摘されていた。
将軍足利義教の命令で、観世太夫の座を従兄弟の音阿弥元重に奪われる不遇のなか、南朝方に接近したのではないか、それが原因で伊勢安濃津(ここも南朝方の拠点)で若くして客死することになったのではないか、という推測だった。
状況証拠しかなくて(世阿弥のように自ら書き残さないかぎり、猿楽師の心の内など歴史から消えてしまう)、小説的な想像ではあるが、面白い説。
七月七日(土)千石フルトヴェングラー
千石にて、フルトヴェングラー・センターのレクチャー・コンサートを聴く。
指揮者の徳岡直樹さんによる、指揮者ならではの視点によるフルトヴェングラーのリハーサル分析や一九五一年バイロイト盤の編集痕解明など。続いて徳岡さんの夫人シュー・スーランさんによる、フルトヴェングラーのヴァイオリン・ソナタ第一楽章の実演。CDで聴くよりもこの曲の濃密さ、室内楽の器に収まらない後期ロマン派的恐竜性が直に伝わってきて、貴重な体験。
七月十二日(木)史劇の快感

新国立劇場にて《トスカ》。話題のロレンツォ・ヴィオッティの指揮。新鮮で見通しのよいプッチーニ・サウンドが心地よし。ディアツ演出の舞台は、ゼッフィレッリの《アイーダ》やツェドニクの《こうもり》とともに、この劇場で最も安定度の高いもの。
マリー・アントワネットの姉で、妹を殺して王制を倒したフランス革命勢力を不倶戴天の仇と憎むナポリ王妃、マリーア・カロリーナが第一幕の最後に仰々しく登場するところは、本当にうまくできている。史劇ならではの快感(チラシもその場面)。その意味で、やはりこのオペラは読み替えが難しい作品か。
七月十四日(土)エントロピー増大


午後はすみだトリフォニーでシモーヌ・ヤング指揮新日本フィル。《ロマンティック》交響曲の初稿。予定調和にならない、アイディアがあふれて未整理のままの音楽の瑞々しさの快感。
長くクラシックを聴き続けてくると、法則通りエントロピーが増大した音楽の方に惹かれるようになる。交通整理が行き届かない段階の方が鮮度が高いように感じられてくるのだ。レオノーレの三番に飽きて二番に惹かれだす、みたいな。
夜はサントリーホールで「ゲロ夢」こと《ゲロンティアスの夢》。
毎度のことながら、合唱つきの大曲はナマで聴いてこそ真価がわかる。録音だとつかみどころがないように聴こえる響きが、神秘的な奥行きと広がりに。東響合唱団はいつもながらの暗譜で見事。大友直人の下でも前にやっているはずだから二回目か。その大友は九月に高崎で群響と、同じエルガーの《神の国》をやるので、これも楽しみ。
七月十五日(日)虚空に

観世能楽堂で、大槻文藏の『卒塔婆小町』。垢じみた百歳の老婆となった小野小町に、かつて彼女に懸想して死んだ深草少将が憑依してくる瞬間、大きく声がふるえる、狂気の発現の恐ろしさ。
大詰めで「悟りの道に入らうよ」と物狂いが鎮まって祈りに転じたあと、大鼓の亀井忠雄と小鼓の大倉源次郎が息を合わせてかすかに鳴らした、虚空に吸い込まれて消えるような終結の音の、聴く者が息をのむ美しさ。こういう瞬間こそ、能の快感。
ワキの高僧が福王茂十郎、ワキツレが福王和幸、地頭が観世銕之丞、笛が杉市和など、当代のトップクラスが顔をそろえた演能。
七月十六日(月)巨人ハイブリッド
サントリーホールで、東京都交響楽団のアラン・ギルバート首席客演指揮者就任披露演奏会。これくらい相性のいい指揮者とオケのコンビというのもなかなかない。翌日の記者会見で語られた「ケミストリー」、化学反応という言葉がまさにぴったり。
《巨人》では、「クピーク新校訂全集版」が用いられた。いわゆるハンブルク第一稿の音詩版と、現行譜との中間にあるようなヴァージョン。ヘンゲルブロックや山田和樹なども用いて、このところ聴く機会の多い版だが、十四日の《ロマンティック》初稿にあったような発展途上の瑞々しさは、少し薄まっている。
記者会見でギルバートはこれと現行譜とのいいとこどりをしたハイブリッド版をやりたいと言っていたけれど、この版自体が既にかなりハイブリッドな感じである。「エントロピー増大派」(笑)としては、ハンブルク第一稿をきちんとナマで聴いてみたい。
七月十八日(水)甲府の仇と二つの木曾
午後は朝日カルチャーセンター新宿教室で「名指揮者の歴史的名演奏」第一回のフルトヴェングラー。
先月の山梨では電車遅延戦法に巻き込まれて半分しか話せなかったので、「甲府の仇を新宿でとる」ような形に。酷暑にもかかわらず、熱心に聴いてくださってやりやすい。来月にカラヤンをやるのが楽しみ。
夜は国立能楽堂。
・仕舞『花筐(はながたみ) クルイ』梅若紀彰(観世流)
・狂言『鏡男(かがみおとこ)』大藏彌太郎(大蔵流)
・能『木曽(きそ) 願書(がんしょ)』観世銕之丞(観世流)
能の『木曽』は、倶利伽羅峠の戦いの直前、勝利を八幡社に祈願する木曽義仲主従。去年十一月に見た黒川能の『木曽願書』とは、後半がまったく違うのが面白い。黒川能版は源平両軍の派手なチャンバラなのに、観世流はシテの男舞だけで見せる形式。前半も、願書を詠みあげるシテが、黒川能は義仲、観世は義仲の右筆の大夫坊覚明となっている。
農民能の黒川能の方が古い形を残している、と一概に言い切ることはできないらしいが、シテ一人の芸にすべてが収斂される観世版の方がシンプル。
七月二十日(金)昭和は遠く

フェイスブックでの山田治生さんのご投稿がきっかけになって、音楽ライターや関係者のあいだで最近はやっているのが、ビスコ(笑)。
自分は徳用の大袋で大人買い。「発酵バター仕立て」のバニラとカフェオレの二種入りで、なかなかいける。一パックが二枚入りで、ちょこちょこ食べるのに便利。
大学生の頃は「なにビスケットォ? カッコつけたってどうせお前なんかビスコだろ」とか馬鹿にするときのものだったのに、それから三十五年たって、自分で金払って買って食べる日が来るとは、昭和は遠くなりにけり。
七月二十一日(土)西洋より
六月下旬のサントリーホール《新世界より》三連発は結局一つも行かなかったが、驚いたことに七月も昨日と今日で二連発があって、それを聴く。《新世界より》にはチャイコフスキーの交響曲とならんで、今も昔も圧倒的な集客力があるらしい。
連発といっても、会場はサントリーホールと東京芸術劇場の組み合わせに変わる。しかし普通は後半のメインディッシュにあるこの曲が、池袋では珍しく先頭に置かれたため、もろに二つ続けて聴くかたちになった。

まず昨日二十日はサントリーホールでベトナム国立交響楽団。本名徹次指揮。
・チョン・バン:交響詩《幸せを私たちに運んでくれた人》
・ドヴォルザーク:チェロ協奏曲(独奏:宮田大)
・ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》

今日は東京芸術劇場(久しぶりと思ったら、GWのフォル・ジュルネ後からずっと改修工事だったそう)で、東京都交響楽団。指揮はアラン・ギルバート。
・ドヴォルザーク:交響曲第九番《新世界より》
・バーンスタイン:『ウエスト・サイド・ストーリー』より「シンフォニック・ダンス」
・ガーシュウィン:パリのアメリカ人
昨日は「日越外交関係樹立45周年」と銘打たれて、壁面には両国国旗が飾られ、冒頭には両国国歌という、昔懐かしい始まり。チェロ以外の楽員、客席の大半が起立する。ホーチミンを讃えるお国の曲に始まって、ドヴォルザークの名作二曲。後半は天皇皇后両陛下ご鑑賞の、天覧新世界。
今日の都響の都会的で国際的な、モダンな高水準の演奏に較べるまでもなく、ベトナム国立響はまだ発展途上。しかしそれは歴史的推移を考えればむしろ当然のことで、日本のオーケストラもたどってきた道程。
アジア諸国の歴史の中の日本の特殊性や、その幸福と不幸と功績と罪悪なんてことを考えたりするのは、そうしたことを誰よりも深く意識し、一身に背負う方が、同じ客席空間におわすからか。西日本豪雨の被災者のことを意識されてか、黒系のお召しだったことが強烈に印象に残る。
そしてベトナムも日本も、アメリカと戦った国。
二つの《新世界より》を通って、アメリカ音楽のバーンスタインとガーシュウィンへ。
家へ帰ってから、毒を食らわば皿までとばかりに、CDを取り出して三つめの《新世界より》を聴く。

少なくともこの十年間で、おそらく最もキテレツな、破天荒な演奏の《新世界より》。マレク・シュトリンツル指揮のピリオド・オーケストラ、ムジカ・フロレアによるライヴ録音。
このコンビはドヴォルザークの交響曲をすでに四曲、ピリオド楽器で録音しているけれど、響きはともかく演奏そのものは二十世紀の新古典主義風で、あまり面白いものではなかった。ところが昨年九月のこの《新世界より》に至って、突然に大噴火した。
変幻自在の緩急と強弱の連動、ポルタメントにテンポ・ルバート、前代未聞のバランスとアクセント、なぜか最後に何度も叩かれるシンバル(笑)、メンゲルベルク以前に遡行したような、奔放きわまりない演奏。
シュトリンツル自らが解説に書いている。「現在の『正統的解釈』に従ったたくさんのドヴォルザークの権威たちが、かれらには思いもよらない、かつて存在したが忘れられた効果に驚くだろうことは、疑いなし」
かれが目指したのは十九世紀までの激烈でロマンティックなスタイルの蘇生。それが正確かどうかはわからない。肝心なのは、そうであろうとしたこと。
二十世紀のグローバル化された合理的解釈と演奏スタイルよりも古い、クラシックがヨーロッパ内で多国籍化しつつもその外には出ない、つまりそのアジア・アフリカ・南アメリカのAAA植民地には伝わらない、せいぜい新興のアメリカ合衆国が懸命に採り入れようとしだしたくらいの頃の、ヨーロッパ・ローカルだった時代の音楽演奏への、遡行の試み。それを、チェコ人たちがやる。
十九世紀的なスタイルの復元とは、音楽そのものが求めていることを思いきって外に露出させる、極端に激しくやってみる、ということだろう。
そういうとき、チェコ人ならば戻れるルーツ、音の基本を外さずにできる、という部分があるように思える。シベリアまで行ってしまうと少し不安になってくるし(笑)、アメリカやアジアになると独りよがりになってしまう可能性が高くなる。そこから独自の展開をする、という道はもちろんあるだろうし、そうしないといけないのだろうが、その見極めは簡単ではない。
もちろん、チェコ人とて安易に血統とか血の問題に寄りかかってはいけないわけで、それが何に拠っているのか、ということを客観的に位置づける努力は忘れてはならない。しかしそうして分析できたとしてもなお、外国人がそれを身につけるのは簡単なことではないだろう。
しかも、それが必ずしも不可欠かどうかはわからない。もっと普遍的な価値もありうる。日本人やベトナム人が一生懸命に西洋のクラシックを学び、演奏する意味は、何なのだろう。
今回続けて聴いた実演とCDの三つの《新世界より》は、それを考えるきっかけになりそうだ。これらが同じ時空に存在してくれる面白さ。聞き飽きたと思っていた音楽が別の鏡に映しだされて、未知の異なる相貌を見せる、面白さ。
七月三十一日(火)奥志賀より

トッパンホールで、小澤国際室内楽アカデミー奥志賀の演奏会。若者たちの弦楽四重奏や五重奏がメインで、最後の講師も交えた全員の合奏の二曲目に小澤征爾が登場、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲第十六番の第三楽章を指揮した。
小澤の実演をみるのは昨年九月の松本での内田光子とのベートーヴェンの協奏曲三番以来、一年ぶり。
 (C)大窪道治 写真は小澤国際アカデミー奥志賀のサイトより。
(C)大窪道治 写真は小澤国際アカデミー奥志賀のサイトより。 八月一日(水)生贄の魔性

オペラシティでミンコフスキの《ペレアスとメリザンド》。戦場帰り、第1次世界大戦で心の一部を破壊されてしまったようなゴロー。焦燥が官能につながっていくようなこの舞台においては、ペレアスは心を病んだゴローが分裂させた、別の人格のようにも思える。若くて情熱的で素直な、戦場の塹壕の泥水の中に置いてきてしまった、もう一人の自分。憎くて、消滅させずにはいられないもの。
ミンコフスキ指揮のドビュッシーは、不思議なほどバルトークに似ている。去年の四月にカンブルラン指揮読響で二人の作品を続けて聴いたときに感じた印象を、ふたたび味わう。
そう、この《ペレアス》というか「ゴローとメリザンド」は、男の心と精神の内奥に入っていくという意味で、《青ひげ公の城》に似ている。メリザンドとユディットの人格は似ていないが、ともに生贄であるという点で似ている。メリザンドは生贄を逃れようとして、戦場をさまようゴローに会ったのではないか。
そして結局はゴローの生贄となりかけるが、同時に彼女はファムファタール、無意識的な魔性の女でもある。ゴローもその分身ペレアスも、父アルケルも、その魅力に翻弄される。三つの死から生まれ出る、新たな魂。男ではなく女。
八月二日(木)かれは弱虫か

国立能楽堂で『通盛』。
一ノ谷合戦の前夜、戦場に愛妻の小宰相を呼び寄せる、越前三位通盛。敗死の予感と恐怖のなかで女を愛さずにいられない男の弱さは、《ペレアス》の荒れ果てた王国に通じる。
若いころの自分は、通盛の弟で平家随一の勇将、能登守教経のファンだったから、逢引の最中にその教経に怒鳴り込まれてしょげかえり、あわてて妻を本陣に帰す通盛の弱虫ぶりが情けなくて、大嫌いだった。
しかしもちろん今となると、少し違う思いがある。翌日、鵯越を下った義経軍の奇襲で平家方は総崩れ、通盛は逃げそこね、あえなく討たれる。その夜、敗残の平家の船団にいた小宰相は夫の死を知り、世をはかなんで海に身を投げる。
はてなく深い水もまた、《ペレアス》と平家物語をつなぐもの。
八月四日(土)映画版の実演

東京国際フォーラムAで「ウエスト・サイド物語シネマティック・フルオーケストラ・コンサート」。
ここ数年、大会場で上映する映画に合わせてオーケストラ・パートをナマ演奏する、ライヴ・シネマコンサートが夏の定番となってきている。これもその一環で、ハリウッド映画版の『ウエスト・サイド物語』に合わせて、佐渡裕指揮東京フィルが伴奏するもの。サウンドトラックからセリフと歌、効果音を残して管弦楽パートだけを消去し、あらためてナマで演奏するスタイル。
最新デジタル技術によるオケ・パートの除去は、かなりうまくできていた。ただ指揮は、プレトークで佐渡裕が「もうテレビゲームで百点目指しているみたいな感じで、バーンスタイン本人だったら引き受けなかったに違いない」と語っていた通り、自分の音楽を殺して、音ゲー的にひたすらタイミングをシンクロさせることに専念しなければならない。
それでもずれる箇所もあるわけで、わざわざやる意味があるのかと言っている知人もいたけれど、オリジナルのブロードウェイ版とは大きく異なる映画用オーケストレーションをナマで聴けたのは、自分としては収穫。オリジナルにはないヴィオラ・パートが加えられて弦五部になる。そして十六型約百人の大編成(一部変更はあるが、ハリウッドのスタジオ・オーケストラも同様の大編成だったらしい)だと、分厚い弦がパーカッションよりもよく鳴り、オリジナルより壮麗でシンフォニックな、ハリウッド風の響きになっていることもよくわかった。
去年シアター・オーブでみたブロードウェイ・オリジナルに近い小編成から、三月のパーヴォ&N響の拡大型ブロードウェイ版をへて、ついにここに至る。生誕百年ならではのありがたさ。
それに、大画面でこの傑作をじっくりと見られたのは、やはり貴重な体験だった。音楽的にはオリジナル・サウンド・トラック盤のジョニー・グリーンの呼吸感のない指揮がどうも苦手(ブロードウェイ盤のゴーバーマンの方がはるかに上手い)で、それに合わせる佐渡も大変だなあと思っていたが、今回あらためて見てみて、トニー役の吹き替え歌唱をやったジム・ブライアントの歌にも問題があると強く思う。
悪い意味の英語らしい、のっぺりして言葉のカドが立たない響きの歌なので、バーンスタインとソンドハイムが仕掛けた、リズムとフレージングの緩急によるスピード感がなくなっている。だからトニーのソロやマリアとのデュオが冴えない。〈サムフェア〉がクライマックスではなくリプライズみたいに聞こえる(オリジナルがすでにあったかのような、もどかしいほどのあっけなさ)のは、ブロードウェイ版の女声ソロとそれに続くバレエ・シークエンスをとってしまったせいだけでなくて、ブライアントの歌う言葉に魅力がないから(これもブロードウェイ盤のラリー・カートの方がバーンスタインの直接指導を受けているだけに、はるかに上手い)。
それにしても〈サムフェア〉は、やはりブロードウェイ版の長いヴァージョンの方が、ミュージカルらしくていい。トニーとマリアがベッドでみる夢の場面だから、映画ではストーリー上の緊迫感を維持するためにカットしたのだろうが、ジェローム・ロビンズが途中でクビにならずに全曲の振付をやれていたら、この「最初からリプライズみたいな」やり方に納得していたろうか。
ロビンズが振付と演出を担当した〈プロローグ〉〈アメリカ〉〈クール〉は、いま見ても本当にすごい出来。映画だからこそ可能なスピードとキレ、そしてスタミナなので、これしか知らないお客が舞台版オリジナルの振り付けを見ると、生ぬるく感じてしまうという弊害はあるけれど(笑)。M・ジャクソンの《スリラー》の振付は、この〈クール〉の直系の子孫だと気がつく。〈トゥナイト〉のクインテットも、ロビンズがやっていたらまるで違ったものだったろう。ここは音楽的にもドラマの肝だけに、残念。
ラスト。歌もオケも沈黙したからこそ革新的な傑作になっているのだが、やはり作曲家としては「負け」だろう。このために、音楽のみの演奏会形式だと、どうにもしまりのないものになる。
それはともかく、ここで愚連隊の連中がトニーの遺体を持ちあげて運ぶ場面、キリストの「十字架降下」がモチーフになっていると気がつく。もちろんマリアは悲しみの聖母になぞらえられる。
シェイクスピアに逆らってマリアを生き残らせたことがこうして意味を持つ。ひょっとしたらマリアは懐胎しているのではないか、とも想像したくなる。そしてあらためて、聖母マリアが一切出てこないバーンスタインの《ミサ曲》にただよう苦渋を、思う。
続くエンドロールで、オーケストラは単独で長く演奏する機会を、タイトルロール以来久しぶりに与えられる。実演だとここで帰りだす客はいないから、じっくり見られる。
八月五日(日)バレ・イマジネール

ミューザ川崎で、ミンコフスキ指揮東京都交響楽団による《くるみ割り人形》全曲の演奏会形式。
バレエというのも他者のタイミングに奉仕することを指揮者が求められる音ゲー的なものだが、演奏会形式ならそんな制約はない。といっても、ミンコフスキが器楽的で硬い音楽になるわけがなく、自由なアクセントに緩急のリズムで音楽の自律性を前面に出した、音そのものが踊る音楽。フランス的な軽妙さが出てくるのが嬉しい。
ラモーのバレエ曲を自由につなぎ合わせたミンコフスキ編曲の「サンフォニー・イマジネール」、あの架空の管弦楽曲のチャイコフスキー版を聴いているような、新鮮な快感。バレ・イマジネール。
『ウエスト・サイド物語』に続けて、普段は音ゲーではない音楽が音ゲーになり、音ゲー的音楽が音ゲーから解放される、示唆に富んだ二日間。
八月七日(火)シェイクスピアいくつか

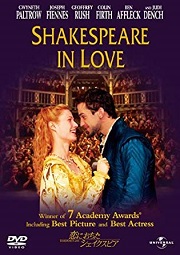


酷暑の八月は能閑期なので、能は九月まで一休み。かわりにシェイクスピア。
池袋の東京芸術劇場のシアターウエストで、オックスフォード大学演劇協会の「オックスフォード・シェイクスピア・プレイヤーズ」による喜劇『十二夜』。
この団体は二年前に来日したときにも『夏の夜の夢』をみて楽しませてもらった。大学生のサークル公演とはいえ天下のオックスフォードだし、廉価(二千五百円)で原語上演を、二百七十席の小さいハコでみられるのが魅力。
今回は衣裳を一九六〇年代に設定してあったけれど、前回同様に装置はほとんどなく、小舞台の演技と想像喚起力だけで勝負する。この能狂言的なスタイルこそ、自分には落ちつけるもの。舞台転換に時間を食ったりしたら作品のリズムが死んでしまう。さすがの傑作だし、シェイクスピアの英語台詞って、すべてを聞きとれなくてもその響きを聴いているだけで心地よい。
初演は一六〇一年頃で、関ヶ原合戦の翌年、猿楽が秀吉~家康の庇護で隆盛を迎えていた時代。フィレンツェでオペラが生れた時期。
これをきっかけにシェイクスピア時代の円形の劇場と張り出し舞台での上演を再現した映画がみたくなり、『十二夜』が最後に登場する『恋に落ちたシェイクスピア』と、『もうひとりのシェイクスピア』のDVDを引っぱりだす。後者の劇中劇『ヘンリー五世』の、観客が舞台と一体化していく場面をみたら、さらにローレンス・オリヴィエの映画版『ヘンリー五世』がみたくなる。
オリヴィエが製作・監督・主演を兼ねた一九四四年の『ヘンリー五世』は、ウォルトンが音楽を担当したカラー大作映画。バトル・オブ・ブリテンの激闘を経て大陸反攻に向う時期の作品だけに愛国的・戦意高揚的な色彩も強いが、シェイクスピアへの絶対的な敬意を忘れない。
とても面白いのは、そのような時代状況での製作にもかかわらず、メタフィクション的要素を持ち込んでいること。
単なる映画化ではなく、初めはシェイクスピア時代のグローブ座での上演の再現ドラマにして、出番前の舞台裏の役者たちの様子も写しながら進んでいく。開幕前に舞台に出る解説役(コロス)が、小さな舞台から巨大な場面を想像してほしいと告げることを利用したもの。
もちろん、映画なら観客のイマジネーションを大規模に補助することができる(そのぶん観客を栄養過多の肥満児のようにしてしまい、自分の想像力や考える力を減退させる危険もはらむが)。途中から通常のスタジオ撮影になり、クライマックスのアジャンクールの戦いでは、大規模なロケーション撮影になり、雄大な緑野と青空が視界に拡がる。
そのあとスタジオに戻ってのラスト近く、アップで写る役者のメーキャップが突然派手になったと思ったら、これが最初の舞台用の化粧に戻ったという合図。ロングで引くと、グローブ座の小さな舞台に変わっている。
これは、劇場でよい上演に接したときの、ドラマの中に半分入り込んで、虚構と現実のあいだを行き来する、没入と覚醒をくり返す私たちの感覚を、画面に再現したもの。オリヴィエが映画オンリーではない、すぐれた劇場人だったからこその手法。
舞台でしかできないことへの賛歌であると同時に、映画でしかできないことへの賛歌でもあるのが、まことにお見事なメタ映画。
八月八日(水)綜合指揮者カラヤン
朝日カルチャーセンター新宿教室で、「名指揮者の歴史的名演奏」の第二回、カラヤン。
前回の精神性豊かなフルトヴェングラーに対して商業主義的なカラヤンというような、ありきたりの論法でとらえるのはつまらないし、そんなものではわざわざ来てくださった方に申し訳ない。
四人の先輩指揮者、フルトヴェングラー、トスカニーニ、クレメンス・クラウス、ストコフスキー。それぞれが得意とした相異なるフィールド、つまりベルリン・フィル、イタリアの歌劇場、ドイツの歌劇場、レコード、それぞれでの四人のあり方のいいとこ取りをして、「指揮者」というイメージの、二十世紀的な綜合をやってのけたのがカラヤンではないか、という視点から話をしてみる。
ワーグナーの綜合芸術ならぬ、「綜合指揮者」としてのカラヤン。その聖地としての、ザルツブルク・イースター音楽祭。
この視点はなかなか面白そうな気がするので、機会があったら、さらにふくらませてみたいところ。
八月十三日(月)世界最古の長編アニメ
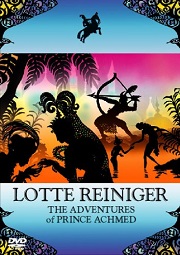
代官山の「晴れ豆」でアニメ映画『アクメッド王子の冒険』をみる。
サイレント時代の一九二六年製作、現存する世界最古の長編アニメ。ドイツの女性監督ロッテ・ライニガーによる、千夜一夜物語を原作にしたアニメ。影絵の動きが幻想的で、懐かしく美しい。
サイレント時代のドイツ映画は映像表現だけでなく音においても世界に先んじていて、映画館でオーケストラが伴奏するための専用スコアが書かれていた。いま手に入るこの映画のDVDも、ウォルフガング・ツェラー作曲の当時のスコアによる演奏がついている。サウンドトラックに代わって音楽を生演奏する現代流行のフィルム・コンサートは、ある意味でサイレント時代の大劇場上映への原点回帰なのだ。
しかし今回はそれと違い、弁士の片岡一郎がしゃべり、菊地成孔がDJ形式で即興的に音楽をつけるという、戦前日本独特の特殊なスタイルを現代に再現してくれたもの。
いくつもの声色で役柄を演じわける台詞を聞きながら、声優というものが大発展、やや畸形的に大発展した日本アニメの原点が、この弁士文化だったのだな、などと考える。
世界のフィルム・コンサートと日本の声優の故郷として考える、サイレント映画。
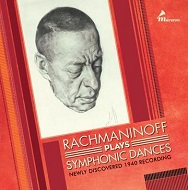
マーストンがピアニスト、ラフマニノフの未発表音源のリリースを発表。
一九四〇年十二月二十一日、交響的舞曲の初演二週間前、初演の指揮者オーマンディの邸と思しき場所でピアノで演奏して聞かせたときの抜粋録音。
思いつくままに各所を演奏した未編集版と、曲順通りにまとめたもの(約二十七分)と、二種のヴァージョン入り。
同曲のミトロプーロス&NYPによる全曲の一九四二年ライヴ(作曲者臨席)と交響曲第三番(一九四一年)、一九四三年四月二日、ラフマニノフ没後五日目にオーマンディ&フィラデルフィアが行なった《死の島》の追悼演奏(スピーチつき)など初CD化音源てんこもりの、さすがマーストンとしかいいようのない三枚組。
八月三十一日(金)レトロサンドと、プラスチック製パセリの記憶

毎年恒例のセイジ・オザワ・フェスティバル松本に泊まりがけで行く。
写真は、行きに新宿駅で買った日本食堂のサンドウィッチ。外装のデザインは昔風だが、中身は三分の一日分の緑黄色野菜サンドと今風。
日本食堂(現在の日本レストランエンタプライズ)の創業八十周年を記念して七月に復活させたレトロパッケージとのことで、何とも魅力的。
そういえば、自分が子供の頃はこういうサンドウィッチなどに、プラスチック製のパセリ・モドキ(もちろん食べられない)が入っていたのが忘れられない。弁当箱の「ばらん」という緑色の仕切りと同じような感じのプラスチック製で、もっと立体的なパセリの形だった。日本人がほとんど生野菜を食べなかった時代の名残で、パセリを食べずに残す状況では、本物よりプラスチックの方が割安だった、ということなのだろうか。
残念なことにそれは再現されていないが――あたりまえだ――、葉っぱと茎が別パーツで、人間の手ではめてある、手間がかかったタイプもあったはず。
今ではむしろあんな面倒で無駄なものをつけたことの方が不思議だが、あの頃はそれが当然と思っていた。しかしいつのまにか消え、忘れられている。ネットでざっと調べても出てこないが、話題にもならないものなのだろうか?
到着後、夜はキッセイ文化ホールで秋山和慶指揮のサイトウ・キネン・オーケストラ。これは日経新聞に評を書く。

九月一日(土)毎年同じ行動
翌朝は雨がそぼ降るなか、恒例の穂高神社参拝。拝殿前がいつのまにかアンツーカーみたいになっていて、こういう天候のときは楽だが、ちょっと味気ない。

食事はこれも毎年パターン化。初日の開演前は、おきな堂で安曇野ポークのステーキ(きわめて美味。写真なし)を食べ、翌日昼はそば。いつもは穂高神社近くの「一休」だが、今年は早めに松本に戻ることにして、駅脇で舞茸天ざる。

松本駅前にある三角柱のモニュメント。上はセイコーの時計。下に小澤征爾書の「樂都」。小澤の「樂都」の裏には誰かの「岳都」の字。もう一面には「学都」とあって、松本の三つの顔。


ここで時間を過ごすのも松本恒例の楽しみのひとつ。丸善と文教堂というDNP(大日本印刷)系列の書店が一緒に入っているが、前者は文具と書籍、後者は模型などホビーに特化。

書籍は丸善の名称ながら、配置は同じDNP系列のジュンク堂式で地下一階から地上二階まで。三階に文教堂書店。
東京より人が少なくて、広い店内でたくさんの本を眺めることができる。松本に来始めたころは大型書店の閉店直後とかで本屋が少なくてつまらなかったが、三年ほど前にここができて、必ず一時間以上入りびたる。
ここから歩いて市民芸術館に行き、十四時から小澤征爾音楽塾の《ジャンニ・スキッキ》を観る。キッセイ文化ホールより市民芸術館の方が市街に近く便利なのに、なぜか演奏会はここではやらず、オペラのみ。サイトウ・キネンがピットに入ったのは2015年が最後なので、近年は音楽塾公演でしか市民芸術館に行く機会がないのが残念。
終演後、「スーパーあずさ」で帰京。やっぱりただの「あずさ」に較べてふわふわ揺れ、乗り心地悪し。
九月二日(日)訃報 藤田六郎兵衛
能管(笛)の藤田流宗家、藤田六郎兵衛(ふじたろくろびょうえ)さんが八月二十八日に六十四歳で亡くなられた。
現代を代表する能管の名手の一人で、二年前に見始めたばかりの自分も、結構な数の舞台で聴かせてもらった。どこか不思議なユーモアの漂う笛で、末期癌と闘いながらの出演とは思いもよらず。
その笛を聴いたのは三月の国立能楽堂『求塚』がたぶん最後。七月の大槻文藏の『卒都婆小町』など、このところ病気休演の知らせが続いていたので気になっていたが、まさか亡くなられるとは…。ご冥福をお祈りするのみ。
九月五日(水)《三部作》の環

杉並某所で山田和樹さんにインタヴューしたのち、新国立劇場で二期会公演のプッチーニ《三部作》のゲネプロへ。
ゲネプロだから歌唱については触れない。演出と指揮の話だけ。それが、ミキエレットの演出とド・ビリーの指揮が、素晴らしかった。
三部作相互を有機的に連関させる大小の仕掛けがじつにうまい。《外套》のジョルジェッタと《修道女》のアンジェリカ、《外套》のミケーレと《スキッキ》のスキッキを同じ歌手に歌わせたことがそれを暗示する。
死体と生者が織りなす三つのドラマのなか、子供、すなわち子孫を残すことを象徴するものへの人の思いが、その行動に大きな意味を持ってくる。種の保存という、動物の根源的な本能が、貧富善悪さまざまな人間が暮らす社会とその喜怒哀楽において、もつ意味。
そして、ド・ビリーの指揮。うるさくなりがちなこの時代のプッチーニのオーケストラを、気品と情感を保って、劇性豊かに響かせる。いままで日本のオケとはどうも相性がよくない感じがしていたド・ビリーだが、ピットに入ったことで本領発揮。《修道女アンジェリカ》がこんなにも美しくて充実した音楽だったとを、初めて知る。
それに、やっぱりオペラをやるハコ、みるハコとして、新国立劇場には東京文化会館とは比較にならない利点がある。
本番は明日から九日まで四日間。今年の日本のオペラ公演のなかでも、この初演百年記念公演は観る価値がとても高いものだと思う。
九月八日(土)国立能楽堂開場記念公演
まだまだ暑いが街路の影はずいぶん長くなり、秋の気配。天災の夏として記憶されそうな平成最後の夏、東京はいまのところ無事。
九月の声を聞いてまもなく、演奏会シーズンの開始。四日はサントリーホールでオラモ指揮ストックホルム・フィルの「第九」。五日は新国立劇場で二期会の三部作GP、六日はサントリーホールでヴィト指揮都響(前半だけ)、七日はサントリーホールで山田和樹指揮日本フィル、八日は昼に国立能楽堂で能楽、夜にサントリーホールでマイスキー一家の七十歳記念リサイタル。
サントリーホールは七月二十日以来、ちょうど小中学学生の夏休みのように六週間ぶりだったが、行きだすと五日間で四回。向かいのオーバカナルが今月一杯で閉店と知る。カフェの方はときどき使っていたので残念。
ドイツ語圏、北欧、イタリア、ポーランド、フランス、日本、ロシアの音楽と舞台。それぞれに啓発されたなかで、とりわけ語らずにいられないのは、国立能楽堂の能。
今月は開場三十五周年記念の特別公演が四回。八日は行けなかった初日五日の「翁、井筒、乱」に続く、第二回。

・能『安宅』武田孝史(宝生流)
・狂言『栗焼』茂山七五三(大蔵流)
・能『砧』野村四郎(観世流)
国立能楽堂の通常の公演は能一番狂言一番の二曲だが、特別公演で能二番狂言一番。囃子方や地謡は、普段はつけない肩衣をつけた裃姿の礼装。
演目もシテも選りすぐりに加え、各流派や家が競って総力をあげた配置で、出演者全員に隙がない。その威力を見せつけられるような公演だった。
まずは『安宅』。いわずとしれた歌舞伎『勧進帳』の原作。わかりやすく劇的に仕上げられた『勧進帳』に対して暗示的で抽象性が高いぶん、親しみにくいものだが、その抽象性の高さゆえの魅力を教えてくれるような演能。
シテの弁慶は武田孝史。一九五四年生れの六十代、心技体のバランスのとれたベテラン。後見に回った宗家の若い宝生和英(一九八六年生れ)に代って、開場記念シリーズで宝生流を代表する存在に選ばれただけあって、重厚で存在感がある。同行の山伏(略して同山と呼ぶ)八人が武田より年下の若手、地謡八人が年上の老練たちとはっきり分けられているあたりも、総力でシテを盛り立て、よい演能にするという流派の意志の、明確なあらわれ。
弁慶が錦絵風の英雄豪傑になっている歌舞伎版に対し、能の弁慶はより人間的で冷静沈着、血気に逸る味方と血に酔った関守、両軍の気勢をがっしりと受けとめ、豪胆にその力を利用したりいなしたりしながら虎口を脱する役柄だから、武田の落ちつきは納得のいくもの。
自分がこれまでみた二回の『安宅』のシテはいずれも「被き」、すなわち初挑戦だった。大役中の大役だけに意欲と気迫と積極性に満ちながらも、それがともすれば力みや空回りといった硬さにつながるのは仕方のないところだった。二人とも顔の汗がとまらず、後見などに何度もぬぐってもらっていたことがそれを象徴していたが、今回は違う。力まず、澱みなく、波動するようにシテが進めることで舞台が落ちつき、緩急強弱の自然な変化によって緊張感が維持される。
なるほど、と思わされたのは関所をどうにか抜けて、弁慶が義経に無礼を詫びたあとの場面。平家を滅ぼしながら讒言によって陥れられた悲運の境遇への嘆きが、地謡によって謡われていく。ここで義経主従は動きも表情も殺し、一切感情を出さずに座っているだけ。一幅の絵と化したように停止する。
この部分がこれまではとても長く、正直退屈に感じられたが、今日は違った。字幕つきで地謡の歌詞がよくわかるおかげもあり、動きのない場面ゆえに、その向こうの世界に思いを馳せたくなる。
見事に切り抜けられたからこそ、そこまでして切り抜けねばならない主君の境遇の不運を思う。感情と行動が激発した関所抜けの場面から、無言の回顧と内省へ。激動から静止へ、有から無への変化と対照にこそ、能の醍醐味がある。直前の義経の詞「げにや現在の果を見て過去未来を知るという事」を受けて、ここでは時間の進行が止まって、来し方行く末の無限の時空とつながっている。
そのあと、歌舞伎のようにいきなり富樫某が追いついてくるのではなく、舞台から離れた橋懸の上で、関所に残っている富樫が太刀持に声をかけ、追いかけろと命じる場面が一瞬挿入されるのも、能の面白さ。追いかけたりするのは小者の役目だという主従関係、人間関係の不文律を描くためだろうが、それが映画のモンタージュみたいな手法を舞台上に生むことになり、離れた空間を一瞬につなげる効果になる。そうして、この瞬間にドラマは現在の場所に帰ってきて、止まっていた時間と場面がふたたび動き出す。こういう跳躍の瞬間も能の悦楽。
そうして結びの弁慶の「男舞」。その場にいる人びとすべての長命を願い、言祝ぐ舞。これも叡山出身の遊僧である弁慶の過ぎし日々と、そして行く手の陸奥に待つ日々とを、つなぐ舞。ここでは舞という動きによって、富樫をだましとおすという現在と、過去と未来の運命がつながれる。
あと全体に、同山の動きが観世流と違うのも面白かった。とりわけ、関守に迫って弁慶に押しとどめられるところで、全員が順番にぴょんぴょん飛び跳ねる動きの楽しさ。
休憩ののち狂言『栗焼』。シテの太郎冠者が茂山七五三(一九四七年生れ)、アドの主が茂山千作(一九四五年生)と茂山家の重鎮二人が顔をそろえるのも、記念公演ならではのことか。太郎冠者が栗を焼いて食べてしまう場面が以前にみた和泉流の野村家よりもはるかに長く、ほとんど落語と化しているのが愉しい。
最後に、野村四郎の能『砧』。これも充実した演能だった。 『砧』は世阿弥の名作の一つだが、これまで接する機会なく、今日が初鑑賞。
シテ(野村四郎)は北九州の芦屋を拠点とする武士の妻。夫の芦屋某(ワキ:森常好)は訴訟のために京に行き、三年も帰っていない。妻を心配した夫は「今年の暮には必ず帰る」という伝言を、侍女の夕霧(ツレ:長山桂三)に託して帰郷させる。
到着した夕霧の顔を見るや、妻は何も音信がなかったことをなじり、花盛りの都の楽しさに浮かれていたのだろうと非難し、田舎の秋の孤閨の淋しさを嘆く。
そこへ聞こえてくる、砧の音。妻の砧を打つ音が遠く離れた夫の夢に聞こえたという中国の故事を思い出した妻は、夕霧に用意をさせて自分も砧を打つ。
そのさまを見ていた夕霧は、しかし突如として告げる。
「いかに申し候、殿はこの秋も御下りあるまじきにて候」
暮に帰るというのだから、たしかに秋には帰らないにしても、なぜこんな意地の悪い、傷つける言いかたを夕霧はするのか。夕霧こそが夫の妾だからでは、と考える人もいる。自分はそうは思わない(妾なら夫は手元から離すまい)が、いずれにしても奇妙な、妄想をはたらかせずにはいられないセリフ。
じつはこの詞は古い時代のものと考えられていて、室町後期から江戸中期まで二百年も上演が絶えた後に復活した現行版では、「いかに申し候、都より人の参りて候ふが、此年の暮にも御下あるまじきにて候」と、夫が暮にも帰れないことを、自分よりも後に到着した使者が報せてきたと教える、論理に矛盾がない形に改められている。
今回はあえて昔の、謎を残す形。この方が想像の余地があって面白い。
ともあれ、この一言で夫が心変りしたに違いないと思い込んだ妻は絶望し、病の床につき、やがて亡くなる。
ここまでが前場。シテとツレが退場したあと、下人役のアイが進み出て、ここまでの話をふり返り、妻の死を知った芦屋某が急いで帰国し、砧を手向けて法華経で弔うことになったと告げる。中堅以下がやればいいこの役を、大蔵流山本家の当主で人間国宝の山本東次郎(一九三七年生れ)がつとめるあたりは、記念公演ならではの豪華さか。
さて後場。長く帰らぬ夫を待ちわびて死ぬ女、それを象徴する砧の音、とくると、私は小林正樹の映画『怪談』の「黒髪」を思い浮かべてしまう。
のこのこ帰ってきた夫が妻に迎えられるが、一夜明けるとそれは黒髪が残る屍だった、という展開。『砧』も同様に男の愚かさ、浅はかさが責められる話かと思っていたら、そうではないのに驚く。
罰を受けるのは夫ではなく、妻の方。供養の開始とともに現れた妻の霊は亡者と化し、地獄に落ちて責め苛まれ、苦しんでいる。なぜかといえば、「邪淫の業深き」がゆえだという。無実の夫に浮気の疑いをかけ、砧に恨みを込めて妄執にとらわれたまま死んだから、ということらしいのだが、そんな猜疑心から孤閨を恨んだ程度で「邪淫」とまでいえるのかどうか、自分には納得がいかない。
ほかに何かがあったのか、そうでないのか、そのあたりの想像や解釈を、観る人なりにどうとでもできるように抽象化の隙をつくってあるのが、能の魅力。
このままでは六道の輪廻を繰り返し、成仏できない妻は、孤閨の淋しさの恨みを口にする。
「君いかなれば旅枕夜寒の衣うつつとも、夢ともせめてなど思ひ知らずや怨めしや」
しかしここで供養の効果が出て、妻は成仏に向かう。
「法華読誦の力にて、幽霊正に成仏の、道明らかになりにけり、これも思へば仮初めに、擣ちし砧の声の中、開くる法の花心、菩提の種となりにけり」
ここには「女人成仏」の思想が込められている。女性は罪業深き存在だから仏にはなれないという初期仏教の考え方を否定して、女人も成仏できると解釈できる経典が、法華経。
それをとなえて供養することで、芦屋の妻の霊も地獄から救われ、成仏することができる。鎌倉仏教の新しい考え方が採り入れられている。夫を慕って打った砧の音のうちにその種があったという発想が面白い。
それにしても、世阿弥の詞章のうつくしいこと! 『安宅』のあとに聞くと、いっそうその芸術性の高さが際立ってくる。中国の故事や詩句をこれみよがしにひいてくるあたりはかなりペダンチックなんだけれども(三島由紀夫的で若い時代の作品かと思ったら、逆に晩年の作品とされているそう)、その言葉が織りなす綾は、字面も響きも壮麗。
たとえば、シテとツレが砧を打つ場面の詞。
「牡鹿の声も心凄く、見ぬ山里を送り来て、梢はいづれひと葉散る、空すさましき月影の、軒の忍に映ろひて」
「かの七夕の契りには、ひと夜ばかりの狩衣、天の川波立ち隔て、逢瀬かひなき浮舟の、梶の葉もろき露涙、ふたつの袖や萎るらん、水蔭草ならば、波うち寄せよ泡沫」
地謡の技巧も、『安宅』とは比較にならない難しさ。
観世流銕之丞家の銕仙会の面々ががっしりと支える舞台での、シテの野村四郎がすばらしかった。一九三六年生れの人間国宝。自分がこれまで観たものはおとなしすぎる感じがしていたが、今日はその静かなたたずまいのまま、エネルギーが放射してくる。
夫の帰郷が遅れることを知らされたあと、うつむいた姿勢のうなじにこもる、はかりしれぬ悲しみと怨み。静止した悲しみ。静止の絶望。
後場の霊の苦しみの緊張感も深い。最後の静かな救済。
三十五周年というのは記念年としては半端だが、国立能楽堂にとっては、今年に記念能をやることに大きな意味と意義があるらしい。それが何なのかは私にはわからないけれど、能楽師たちも総力をあげて協力するだけの、それだけの価値があるものらしい。
普段より倍以上の料金設定だが、それを上回る充実が舞台にみなぎっている。一か月ぶりの観能ということもあるだろうが、能はいいなあ、大好きだなあと、心から納得し、嬉しくなる公演だった。
来週の記念公演三回目「嵐山、定家」も買ってあるので、大いに楽しみ。
九月十五日(土)金春禅鳳と禅竹
国立能楽堂で「九月開場三十五周年記念公演 嵐山・猿聟・定家」。
・能『嵐山 白頭働キ入リ(はくとうはたらきいり)』金春安明(金春流)
間狂言『猿聟(さるむこ)』野村万之丞(和泉流)
・能『定家(ていか)』浅見真州(観世流)
『嵐山』は金春禅鳳(一四五四~一五三二?)、『定家』はその祖父で世阿弥の娘婿の金春禅竹(一四〇五~七一頃)と、ともに室町時代の金春太夫の作品。
ただし作風は時代の変化を象徴するように対照的。禅鳳は「鳳」の名にふさわしく派手で華やか、にぎやかで色とりどりで、歌舞伎を予告する。『嵐山』は、吉野から嵐山に移植された桜林を、吉野の神々が祝福するというもの。金春流の前宗家の安明がシテ、現宗家の憲和がツレ、憲和の長女初音が子方と、金春ファミリー能。
中間に挿入される間狂言『猿聟』は、吉野山に住む猿の婿が嵐山の舅を訪ね、キャッキャキャッキャと祝宴する話。こちらは野村万蔵ファミリー。
一方、禅竹は舅の世阿弥の影響を受けた教養人で、その能は暗く思索的。『定家』は後白河帝の皇女、式子内親王がシテ。藤原定家と秘密の恋仲だったという伝説によるもの。
式子が薨じた四十年後に定家が亡くなると、式子の墓の石塔に葛がからみついて繁りはじめた。払っても払っても生えてきて石塔にからみつく葛は、死してなお式子を欲する定家の愛執をあらわし、定家葛と呼ばれるようになった。
絡みあう草木のツタが妄執と男女の愛欲をあらわすあたりが、禅竹の特徴だとか。先週世阿弥の傑作『砧』を聴いた直後だけに、あの美しさに比べると詞が理屈っぽくてわかりにくいと感じるが、イマジネーションはやはり豊か。
「御法の雨のしたたり、皆潤ひて、草木国土、悉皆成仏の機を得ぬれば、定家葛もかかる涙も、ほろほろと解け広ごれば」と、ワキの僧の読経によって定家葛は成仏しかけ(草木も成仏するという本覚思想)、石塔の縛めがほどけて、中から式子の霊(後シテ)があらわれる。
ところが面白いのは、そのまま成仏するハッピーエンドではないこと。定家葛の執念は凄まじく、ふたたび石塔にからみつき、式子の霊もその中に埋もれて、消えてしまう。
「夜の契りの、夢の中にと、ありつる所に帰るは葛の葉の、故の如く、這ひ纏はるるや定家葛」
ここまできて「夜の契り」なんて生々しい言葉が出てきてしまい、救われないというのがすごい。
救いなき愛欲。妄執のツタ。少し前にみた『玉鬘』でも、ツタのようにからむ女の黒髪が愛欲の象徴として用いられていた。こうした、暗く湿った植物的エロティシズムが、「竹」の禅竹ならではのものらしい。そしてそれが、草木国土悉皆成仏の思想と表裏一体になっているのが素敵。
先週に続き、今回の記念公演の柱となっている観世流の銕仙会。シテの浅見真州は野村四郎とともにその重鎮。『砧』と同じく「痩女」の能面が示す、妄執のはてなき苦しみ。その裏の、陶酔のはてなき喜び。
九月十九日(水)四十年ぶり
小中学校の同級生四人と、自由が丘で飲み会。
うちの小学校は変っていて、百二十人を三組に分け、六年間ずっとクラス替えなし。だから違う組の子とは少し精神的な距離がある。中学へ進むと新規に四十人を加えて四組にシャッフル、さらに一年終了時にクラス替えがある。
今夜の四人は小学校では自分とは違う組で、うち三人と中学で二年間一緒の組になった。だから小学校での「分離」と中学での「混合」、その二層構造というか、最後だけ一緒にねじって結んである三本の棒というか、過去の記憶についてある種のネジレが生じているのが、話していて面白い。
小学校の同じ組の友人は六年間一緒なだけに、特別な紐帯の強さを感じるが、それとはまた異種の濃密な連帯感。九年間の時空を共にしているのに、ねじれている快感。
思い出話の一方で印象に残ったのは、中学卒業以来四十年ぶりに会った、航空自衛隊の元戦闘機乗りの体験談。
冷戦時代は小松基地でファントムに乗ってスクランブル発進にそなえる日常で系三千時間を飛び、続いてヘリに転じて千時間、その後は長く教官生活をやってきたという。
海上で操縦不能になって機を放棄、脱出して洋上を漂ったこと、他機と衝突しかけたこと、そして同僚や教官時代の教え子の数人が殉職していることなど、安穏な自分とはまるで別の、命懸けの緊張のなかに生きてきた人間と四十年ぶりに会って話をする、その愉快。
かれの組の担任が少し前に亡くなったことも教えてもらう。
九月二十日(木)肉から骨へ
オペラとピアノ連弾をはしご。
まずは上野で十五時から、ローマ歌劇場公演《マノン・レスコー》。デ・グリュー役のグレゴリー・クンデが最大のお目当て。タッカー、シコフという「アメリカのデ・グリュー歌い」の系譜に連なる、イタリア語の語感を大切にした響きとフレージング、歌いあげの効果。指揮者がもっとそれを活かせるとよかったけれど。
終演後、銀座線と大江戸線を乗り継いであわてて浜離宮朝日ホールに移動し、「ジョス・ファン・インマゼール+伊藤綾子 連弾の夕べ」。

・サティ:梨の形をした三つの小品
・ラヴェル:スペイン狂詩曲(ラヴェル自身による編曲)
・ドビュッシー:《夜想曲》より〈雲〉と〈祭〉(ラヴェルによる編曲)
・ドビュッシー:管弦楽のための《映像》より〈祭りの日の朝〉(アンドレ・カプレによる編曲)
・ラヴェル:ボレロ(ラヴェル自身による編曲)
一八七七年製エラールを用いているのが魅力。仕事は別として、個人的には現代のコンサートグランドの剛性の高すぎる、重い響きを聴くのが億劫になっている人間にとっては、軽快で、響きすぎない響きがなんとも耳に心地よい。インマゼールはスペイン狂詩曲だけ高音側、あとは弟子の伊藤綾子が担当。
ラヴェルが編曲した自作とドビュッシーは、オーケストラの響きの骨格が透けるような書きかた。カプレ編曲版のドビュッシーの方がよほどピアニスティックで、ピアノの独自性を活用している。その差が面白い。
《ボレロ》は先月二十七日に「落合陽一×日本フィル プロジェクトVol.2《変態する音楽会》」でみた、新たな「楽器」として映像装置を加えたヴァージョン、三十一日に秋山和慶&サイトウ・キネン・オーケストラの圧倒的高水準の演奏に続くピアノ連弾版。肉から骨へと、みたいな三つの変容。
アンコールはブラームスのハンガリー舞曲第一番で、これはピアノこそがオリジナルだとよくわかるつくりの響き。
九月二十一日(金)N響のクレルヴォ
NHKホールで、パーヴォ・ヤルヴィ指揮NHK交響楽団による、エストニア国立男声合唱団を招いてのシベリウスの合唱つき作品プログラム。

・レンミンケイネンの歌
・サンデルス
・交響詩《フィンランディア》
・クレルヴォ交響曲(ソプラノ:ヨハンナ・ルサネン、バリトン:ヴィッレ・ルサネン)
クレルヴォの骨太な表現が素晴らしかった。合唱はもちろん、オーケストラがとても雄弁で力強い。パーヴォ自身の音楽語法との特別な親和を感じる。
九月二十二日(土)スダーンの置き土産
オーケストラをはしご。
十四時から東京芸術劇場で、ローレンス・レネス指揮東京都交響楽団。ナッセン死去により指揮が交代、一曲目が追悼のためにナッセン作品に変更された。
・ナッセン:フローリッシュ・ウィズ・ファイヤーワークス
・武満 徹:オリオンとプレアデス(チェロ:ジャン=ギアン・ケラス)
・ホルスト:組曲《惑星》(女声合唱:ヴォクスマーナ、女声合唱団 暁)
十八時からサントリーホールで、ユベール・スダーン指揮東京交響楽団のウィーン古典派プログラム。

・ハイドン:交響曲第百番《軍隊》
・モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第四番(ヴァイオリン:堀米ゆず子)
・ベートーヴェン:《田園》交響曲
スダーンが音楽監督時代に創設したモーツァルト・マチネの成果で、東響は小編成のピリオド・スタイルによる古典派を得意とする。その賜物のような、澄明な美しい演奏。
九月二十三日(日)群馬の《神の国》

大友直人指揮群馬交響楽団による、エルガーのオラトリオ《神の国》演奏会を高崎の群馬音楽センターで。
一九〇六年初演で、《使徒たち》に続く、イエスの十二使徒の物語。イエスの昇天後の、ペンテコスト(精霊降臨)の場面がクライマックスとなるが、ここの音楽が神秘体験というよりも、心の内部に根をおろす確信として描いているのが印象的だった。深い宗教体験とは、そのようなものなのかも知れない。
ノット指揮東京交響楽団の《ゲロンティアスの夢》と同様だったのは、字幕なしでテキストはプログラムに記載されているのに、前半の客電が暗すぎて読めなかったこと。後半は少し明るくなったので助かった。
ここからは群響ゆかりの高崎の街のアルバム。
群馬交響楽団とその創立者丸山勝廣、そしてかれらをモデルとする映画『ここに泉あり』の話は、二〇〇九年から翌年にかけて、拙サイトの「可変日記」に書いたことがある。
二〇〇九年十月十六日「今井正と戦後民主主義」、十七日「丸山勝廣と周囲の人々」、十一月六日「ルーヴル宮音楽隊!」、二〇一〇年二月二十一日「群響と指揮者たち」と書いたのち、同年十一月二十日に初めて群馬音楽センターを訪れ、群響をその本拠地で聴いた。
このときの紀行は当日の日記に「高崎で群響を聴く」としてまとめていて、自分の高崎訪問記としてはこれで充分なのだが、心残りは、まだカメラなしのガラケーしか持っていない時期だったので、写真を撮らなかったこと。下手くそな写真でも文字だけよりもイメージが伝わるので、八年ぶりに群響を聴くのを機に、それらの場所を撮ることにした。
来年度には新たな群響の本拠として、高崎駅東口に高崎芸術劇場のオープンが予定されており、群馬音楽センターがその後どうなるのかもわからないので、今のうちに再訪できたのは幸いだった。

当日のプログラムとチケット

高崎駅前。ペデストリアンデッキがあって、ミニ仙台駅という感じ。新宿を十四時二十分に出る湘南新宿ラインで、十六時二分に到着。これについては、二〇一〇年の日記から。
「新幹線に乗らないのはコスト節約の意味もあるが、時間はどうせたっぷりあるし、また、車で行ったとき、高速道路しか使わなかったために、落下傘でいきなり目的地に降りるようなもので、そこまでの景色の変化や、東京からの距離の感覚を肌で知ることができなかった、という反省があるからだ。
新幹線も高速道と同じで、やはり落下傘になる。遠距離ならともかく、高崎なら在来線の急行でも片道二時間弱。そこで、『ここに泉あり』の時代と、ほぼ同じ経路を体験してみることにした。
行きは新宿から、湘南新宿ライン経由の直通なので、乗り換えもなく簡単。午後に出て三時頃に高崎に着き、夜の演奏会までに街を見てまわる計画」

高崎市美術館に併設された、井上房一郎邸。井上は高崎を代表する企業だった井上工業の二代目で、群響初期の会長。これも群馬音楽センターを設計したアントニン・レーモンドによるもの。思想は共通している。以下日記から。
『駅前のワシントン・ホテルの角を右に曲がって南下、八島町交差点にある高崎市美術館へ。
目的はこの美術館の隣にある、旧井上房一郎邸。美術館経由で見学できるようになっている。
この邸宅は、建築家アントニン・レーモンド(一八八八~一九七六)の事務所兼自宅「笄町の自邸」のデザインを写して、アレンジをくわえたものである。
レーモンドはチェコ生れのアメリカ人で、帝国ホテル建設の際に有名なライトの助手として来日、その後独立して、戦時中をのぞく四十年間、日本を拠点に活動した。東京文化会館の設計者、前川國男もその下で働いた経験があるという。そのレーモンドが一九五一年に麻布笄町に建てたのが「笄町の自邸」で、その原型は臨時の現場事務所だったという、木造平屋建ての簡素なものである。
翌年、自宅を火事で失った井上房一郎は、レーモンド邸の無駄のない、美しいデザインにほれ込んだ。それを写し、和風の生活様式に合せてアレンジして、自邸を建てなおした。
日本建築の美点を西洋建築にとりいれたレーモンドのモダニズムは、曲線のない、直線と斜線だけで構成されている。華美な装飾は一切なく、細い丸太で組んだむき出しの柱と梁に板を張りつけた、「小屋」と呼びたくなるような、単純な質素さ。窓とガラス戸が壁面の大部分を占め、非常に風通しがいい。西洋風に自然を遮断するのではなく、自然とともにある、優しい建物。窓やガラス戸の棧がとても細くて繊細に感じられるのも、印象的だ。
井上は、桂離宮の「発見者」として名高いブルーノ・タウトを高崎に招き、庇護したことで知られるが、この家の質素と繊細の美学は、まさしくタウトのそれに通じているのだろう。
もちろんそれはいうまでもなく、贅を極めた者の質素である」

井上房一郎邸

井上邸内部

井上邸内部。コルビジェや前川國男と共通する、細い線からなる質素なつくり。素敵だが、高崎の冬にはかなり寒そう。

井上邸内部。ほかに畳敷の和室もある。

高崎の通りはこんな感じ。途中に横浜銀行の支店があったのは意外だったが、明治期の生糸輸出の関係で、高崎と横浜が結ばれていたのかも。

高崎城址にある、歩兵第十五連隊の碑。戦前の高崎は軍都でもあった。

十五連隊の碑を通って、一九六一年開場の群馬音楽センターへ。以下日記から。
『市街の中心部は駅の西、烏川との間にある、高崎城址の周辺に広がっている。現代では前橋が県行政の中心、高崎が県経済の中心というイメージが固定しているが、高崎城は江戸初期に井伊直政が築いた由緒をもつ立派なもので、戦前は陸軍第十五連隊の駐屯地、戦後は市役所などの公共施設がある場所となっている。
今夜の演奏会場である音楽センターはそこにあるのだから、市中の主要な場所を与えられているわけで、高崎市における群響の重要性がよくわかる』

「群馬音楽センター」の碑。右奥が音楽センターだが、なぜか今は草木が視界をふさいでいるために、わかりにくい位置にある。

その碑の背面にある、「昭和三十六年ときの高崎市民之を建つ」の言葉。以下日記から。
『一九六一年に音楽センターが開場したとき、丸山が言葉を選んだという「昭和三十六年ときの高崎市民之を建つ」の碑が前庭に建てられた。
その建設費が、当時の市の年間予算八億の四割を超す、三億三千万という巨額なものであり、市民の賛同と募金活動なくしては、不可能なものだったからである。前庭が公園化されたためか、碑はあまり目立たない、木の陰にあった』
『そんな町が、楽員が二、三十人程度しかいないオーケストラのために、演奏会を主な用途とする二千人収容のホールをいきなりつくった。『ここに泉あり』の成功と好評がなかったら、ありえなかったに違いない。
市議会では、音楽ホールよりも体育館の方が先だという、ごく当然の意見も根強かった。
そこで両者を兼ねるような構造で、五千人収容の大公会堂という折衷案も出たが、多目的ではどっちつかずでよくないという丸山の意見を採用した住谷啓三郎市長が押し切って、「音楽センター」という、当時の公共建築では異例の、限定的名称をもつホールが誕生した。
ほぼ同時期に、東京都が上野に「ミュージックセンター」を建てる計画を立てていたから、あるいは名称のヒントは、そこから得たのかも、という気がする。
しかし、日本の首都と人口十万の地方都市とでは、文化を取りまく状況がまるで異なるのだから、その意気の高さは見上げたものだ。しかも東京さえ、結局は「東京文化会館」という曖昧な名前になったのに、高崎は「音楽センター」で貫徹したのだから、すばらしい』

高崎中心部にあるアーケード商店街「たかさき中央ぎんざ」。

日曜の夕方にしてはさびしい感じ。

アーケード街の中程にある、映画館「オリオン座」の廃墟。

喫茶店「ラ・メーゾン」。以下日記から。
『音楽センターへ行く前に、まずは群響発祥の地である、ラメーゾンという喫茶店に向かう。それは市の北部、田町北交差点の南西角にある。
かつての中山道とおぼしき古い国道沿いの、大きなビルなどない町並みだが、丸山勝広の『この泉は涸れず』(本田書房)によると、戦前には高崎の目抜き通りだったそうだ。
だが敗戦直後の一九四六年初めには、戦前に高級店として知られた山徳呉服店のショーウィンドウに、高価な着物や帯の代りにゴム長が干してあるほど、物のない状況になっていた。
その山徳呉服店の向いに、「市内最大のデパートであった」熊井呉服店の一棟があった。戦時中は疎開した肥料会社が借りていたが、東京に引き上げて空いたのを、戦前のように品物が豊富な時代はもう二度とこないだろうからと、呉服店の熊井社長が、群響に気前よく貸してくれたのだそうだ。
建物は三階建てで、二階を高崎市民オーケストラ(群馬フィルハーモニーオーケストラと改称。通称群響)の練習場、三階を和室の集会所(楽団のプロ化後は県外から来た楽員の合宿所)とし、一階を、楽団長となった井上工業社長、井上房一郎の提案で、喫茶店とした。
その喫茶店が、ラメーゾンである。正式には、フランス帰りの井上の命名で、「ラ・メーゾン・ド・ラ・ミュージック(音楽の家)」という。
開店は、同店のホームページによると一九四七年九月一日とあり、丸山の回想では一九四六年十月だという。どちらが正しいのか私には判断できないが、その草創期の印象を、丸山が活写している。
「この店ができたときにはすばらしかった。けい光灯の間接照明だが電球がなく東京まで買いに行った。お客さんがドアの外からのぞいていて中に入ってこない。戸まどいしているのである。まだまだ世間は混乱状態で町はよごれていた。当時のラ・メイゾンのもつふん囲気は町の中できわだっていた。(略)二十一年から二十二年にかけてとにかくこの建物の二階からはオーケストラが、階下の喫茶店ではクワルテットや、芝居までが演じられたのである。
そして町の空気とはそぐわない明るい灯の下で、コーヒーなどをすすりながら毎晩十時十一時まで、文化人といわれるような人が集まって、だべっていた。
『パリではこんなふうにしているうちに夜が明けてくるんだよ』と井上さんのいった言葉が耳に残っている」
――パリではこんなふうにしているうちに夜が明けてくるんだよ。
この井上の言葉は、私にはとても印象的に響く。この店を、地方にはそぐわないほどの、洗練された都市文化の灯にしようとしたのは、誰よりも井上房一郎だったのだ。その思いがこの一言に、痛いほどに込められている。
ラメーゾンでの最初期の活動には、楽団指揮者の山本直忠を院長に附属音楽院を開設、歌とピアノなどを教えたり、教養講座と名打って、井上自身が講師役となってフランス絵画の講義をするなど、まずは畑を耕し、底辺を拡大しようとする動きが含まれていた。
のちの高崎哲学堂運動に通じる、こうした啓蒙活動こそが井上の考えていたもので、楽団をプロ化して性急に拡大をはかる丸山の、多分に誇大妄想的な目標とは、ずれていたのである。
その後、プロ化によってアマチュア楽員が手を引いたとき、井上がかれらとともに別楽団をつくる動きまで起きた。結局は分裂にいたらず、井上は群響の会長に戻ったが、丸山と井上の齟齬という火種は、その後もくすぶり続け、一九六三年の訣別に至ることになるのである。
しかし、井上なしでは、つまり丸山だけでは、今日の群響はありえなかった。そのことは、これから高崎市街を回るにつれて、強く感じるようになる』

昔の「ラ・メーゾン」は西側、右隣のこのビルの位置にあったらしい。以下日記から。
『熊井社長の予想に反し、東西冷戦のおかげで戦後経済の回復は急激だった。
熊井呉服店も売場を拡張することになり、楽団の練習場は一九五四年頃に移転を余儀なくされ、いまの音楽センターの付近にあった、旧十五連隊の兵舎に移った。指揮者が足に力を入れると、床が抜けてしまうボロ家だったそうだ。
ラメーゾンは田町に残った。
といっても、残念ながら当時の場所にはない。群響がいた元の建物は西隣、いまの近藤ビルの位置にあったという。一九六二年に現在の地に移転、建物は一九八八年に改装したものだそうだ。
そのラメーゾンに到着。奥の喫茶部に入って、コーヒーとケーキを注文。喫茶部はあまり大きくなく、持ち帰り用の販売がメインのようだが、老舗らしく落ち着いた雰囲気が心地よい。
『ここに泉あり』に出てくる喫茶店、「ラララ」とその建物は、ラメーゾンをそっくり再現していたというから、それを頭に描きつつ、元の用地を眺める。
周囲は、小規模な商店ばかり。戦前に高崎市で一、二を競ったという熊井呉服店も山徳呉服店も、見当たらない。ネットで調べたくらいでは、現存するのかどうかよくわからない

八年前にはなかったもので、今回の嬉しい発見がこのカフェ「あすなろ」。一九八二年まで存在した名曲喫茶「あすなろ」は、「ラ・メーゾン」同様に群響の歴史と関係の深い店だった。『ここに泉あり』に感動したオーナーが二年後の一九五七年にわざわざ高崎に移住してきて、芸術文化の拠点として開業した店。
その店が二〇一三年に高崎経済大の支援で復活していたのである(場所が同じかどうかは不明)。
せっかくだからと、開演前にここでパスタを食べていくことにした。そこで席で待っていると、突然に渡辺和彦さんに声をかけられる。二〇〇一年から群響のプログラム解説とプレトークをしている渡辺さん、電車が早めについてしまうので、登場までここで時間をつぶすつもりだったとのこと。
群響の歴史を知る者なら、やはりここに来てしまうのだろう(笑)。十八時くらいまで、しばし歓談。

「あすなろ」を出るともう日が暮れている。城跡脇のお堀沿いの道は暗い。そこにある地元群馬の百貨店「スズラン」。以下日記から。
『まだ五時過ぎで、かなりの店が閉まっている。この早さは、やはり地方都市らしい。昼はそれなりに賑わっていたアーケード街も、人通りがなくさびしい。
北へ抜けて西側、柳川町のあたりはスナックやパブが密集する飲み屋街のようだが、その種の店はまだ開店前で、酔客のための運転代行業の車がポツポツ停まっている以外は、やはり人気がない。
昼の街と夜の街の隙間の時刻の、無人の闇。
柳川町の西を南へ戻ると、道は城跡と市街の境界をなす、三の丸跡の水堀に沿う形になる。街灯しか明りのない、堀脇の道を進む。
八階建ての百貨店スズランが、夜空に大きな黒い影をつくっていた。
少し人恋しくなって中に入ると、内部はとても明るく、広い。外と内の落差の大きさに、ちょっと呆然。このデパートは窓が少なく、外に光をもらさないようになっているのだ』
以下日記から。
『(スズランの)店内を抜けて南に出る。また、無人の夜のさびしい闇に包まれる。
ところが、少し歩くと右前方に、闇の中にひときわ明るく、内部の光を外に放射している建物が、見えてきた。
そして、どこから出てきたのかというほどの数の人々が、そこへ向かって、歩いている。
群馬音楽センターだった。

闇の中の灯。
この鮮やかな効果には、驚いた。
霊感や宗教心などまったくない私でさえ、ここが祝福された場所、何者かが嘉みするホールだと、感じないわけにはいかないくらい、効果的な光景だった。
冷静に、その明るさの理由を考えてみる。一階と二階のロビーの正面全部がガラス窓になっていて、中の照明の光が、そのまま素通しで外を照らすためだ。
窓の広さと、そして、その細い桟。
曲線を用いず、多数の直線と平面を組みあわせて構成する、立体物。精巧な折紙細工、折鶴のような、繊細な立体物。専門的には折板構造というのだそうだ。
ああ、これもアントニン・レーモンドが設計したものなのだと、いま初めて思う。昼にはわからなかったその魅力が、旧井上房一郎邸を見た経験を通して、夜の闇の中で、初めてわかってきた』

『チケットを取り出し、ホールへ入場。モギリが扉のところではなく、いったんロビーに入って、左右の二か所に別れているのが面白い。この方が、人の流れをスムーズにできるのだろう』

二階の天井。以下日記から。
『階段をあがって二階へ。この階段はうねるような曲線で、たくさんの丸穴があき、直線の建物の中でコントラストをつくっている。アルミなどの軽い建材が普及する以前だからなのか、素材の重量感と繊細さの同居が、じつに面白い。
二階ロビーは天井が高く、広々。昼にはガラス面から、外光がたっぷり入るのだろう』

二階のホール入口の壁面。以下日記から。
『客席との間の壁面には、レーモンド自身の手になるという、個性的でカラフルな抽象的模様が描かれている。
私が子供のころ、一九六〇年代には、あちこちでこういう模様を見かけた。今となってみると古い印象だが、しかし暗い外に向かって、鮮やかな色彩を放射していたのは、他ならぬこの壁面である。その効果は、夜の闇にこそ映える』

何度来ても、やはり強烈に印象的。力強い。

一階の正面奥、客席斜面と1階床面のあいだにつくられた、ホール事務所。急勾配の客席斜面との隙間を利用するこのやり方は、一九五五年開場の前川國男の神奈川県立音楽堂のトイレと同じ。
 群馬交響楽団のフェイスブックのページから
群馬交響楽団のフェイスブックのページから以下日記から。
『椅子は古い劇場だけに小さいが、前の席との高低差があるので、舞台は見やすい。後方をふりかえると、客席は二段に別れておらず、かなりの勾配をつけた、一つの斜面にしてある。
二段にしないのは、二千人級の日本の大型ホールとしては、かなり珍しい構造だろう。横も扇形に広がっているから、これならどの席からでも、舞台はとても見やすく、近く感じられるのではないだろうか。新国立劇場を連想する。
そしてその斜面の下に生じる空間を利用して、ロビーの一階奥に事務所やトイレなどを設置している。この無駄のなさが、レーモンド流なのだ。
たしかに、あとで演奏を聴いた印象では、残響の少ないドライな音響で、これは音楽ホールとしては弱点だ。しかし、これほどの見やすさ(前席に無神経な大男が座っているときの不快感は、平らなホールでは誰もが味わっているはずだ)をもち、舞台と客席に近接感のあるホールは、多くない』

やはり今回も、音響がどうだろうと設備がどうだろうと、そんなこととは無関係に、ここは何者かに「祝福された場所」だとしか思えなかった。この幸福感が、群響を支えてきたのだと冗談抜きに思う。以下日記から。
『終演後、人込みにまじって外に出て、いま一度、闇に浮かぶ音楽センターの姿を、眺める。
この建物を実現した最大の功労者は、疑いなく丸山勝広だ。
かれの情熱、それを支えた高崎市民、そして高崎市長住谷啓三郎の実行力がなければ、画餅に終ったにちがいない。
しかし、こうしてその場所を体験してみると、設計者のレーモンド、そしてかれを強力に推薦した井上房一郎の功績もまた、非常に大きなものであることが痛感される。
私の手元にある丸山の回顧録二冊は、いずれも井上と最終的に決裂した一九六三年より、あとに書かれたものである。
だから、ギクシャクはしながらも、政治経済の両面で事務長の丸山の後ろ楯だったはずの会長、井上の寄与が、実際よりも軽く書かれている可能性が高い。
音楽センターの構想も、丸山は一人で思いついたように書いているのだが、そうではないと、感じられてならない。
旧井上房一郎邸に掲示されていた井上の経歴には、一九五四年秋頃から井上が音楽センター建設を提唱した、というように書いてあった。
たぶん、どちらか一人の考案ではないのだろう。言い出しっぺが誰であるにしても、関係者間でダベっているうちに、具体的になっていったのではないか。
音楽センターは、最終的には二千人収容のホールのみに落ち着いたが、当初の構想では、複数の施設からなる、音楽文化の総合的な「センター」だった。
「でき得る限り大勢の人を収容し、ひとりひとりの負担額を少なくしなければならない。芸術家をそのつど宿にとめては経費がかさむ。宿泊施設ももちたいものだ。県下の先生方がそこに自由に寝泊まりし、研究できるような資料室やレコード鑑賞室も必要だ。各国大・公使館を通じ、その国独自の民族的な楽器を寄贈してもらい、生徒たちにみせる音楽博物館的な要素もほしい」(この泉は涸れず/本田書房)
こんな構想を、丸山は自分の頭の中で考えついたという。
だが、結局それは、群響が終戦直後に熊井呉服店の一棟を借りて始めた、「ラ・メーゾン・ド・ラ・ミュージック」での啓蒙活動を、より大規模に焼き直したもの、といえるのだ。
そしてそのころ、中心にいたのは丸山ではなく、井上だったはずである。
闇の中の灯。
闇に明るく光を放つ、群馬音楽センター。その姿に、敗戦間もない高崎の暗い夜に煌々と輝く、ラメーゾンのまばゆい照明が、私の頭の中で二重写しになる。
もちろん、独断専行型の丸山が無謬のマネージャーではなかったように、県下有数の建設会社を引き継いで、何不自由なく育った井上も、完全無欠の聖人君子ではなかったろう。批判の余地はそれぞれ大いにあったろうと思う。
だが、金儲けのためではなしに、文化活動に注いだ情熱の熱さと強さは、どちらも本物。その何よりの証が群馬交響楽団であり、群馬音楽センターである。
二人のうちどちらが欠けても、高崎のオーケストラ運動は少なくとも数十年、遅くなっていたにちがいない。
ホール建替の話があるという。絶好の立地だけに、再開発もしたくなるのだろう。土木工事で富を地方に再分配してきた、「土建屋の国」戦後日本らしい、いかにもな発想ではあるのだけれど…』

ホール前にある、コントラバス型の公衆電話ボックス。今は貴重な電話ボックス、この形だからこそ撤去されないのかも。

新幹線のホーム。今回は時間節約で大宮まで新幹線に乗って帰ったが、前回は帰路も高崎線だった。以下日記から。
『シンフォニーロードを歩き、高崎駅に着く。事故があったとかで、高崎線は遅れていたが、特に混んでもおらず、発車後は順調に走ってくれた。夜の埼玉を抜け、東京へ、東京へ。
面白かった。
ラメーゾン、旧井上房一郎邸、群馬音楽センター、演奏会。そしてその合間に歩いた、昼と夜の高崎の町と道。
気ままな散歩だったのに、どれもがそれぞれのメロディを奏で、見事なコントラストとハーモニーをなし、軽やかなリズムで交響して、楽しませてくれた。
高崎交響楽。今日はおしまい』
九月二十四日(月)池田卓夫さん独立
「音楽の友」のために、「トリトン晴れた海のオーケストラ」のメンバー、矢部達哉さん、山本裕康さん、小池郁江さん、高橋敦さんによる座談会の司会。
終了後、池田卓夫さんの「音楽ジャーナリスト@いけたく本舗・誕生記念ガラコンサート」の後半、パーティの終り近くに顔を出す。大学のサークル、音楽同攻会の先輩である池田さんは、私に日本経済新聞の批評を担当するように声をかけてくださった恩人。九月一杯で日経新聞を定年退社、独立の第一歩を記念する催し。百人近い音楽関係者が集まる。
その新たな活動拠点となるのが、インターネットのサイト「音楽ジャーナリスト@いけたく本舗」である。
九月二十八日(金)ラトルとLSO

みなとみらいでラトル指揮ロンドン交響楽団によるマーラーの交響曲第九番。
二十世紀のころはこの作品というだけで異様な緊張感が舞台と客席を包んだものだが、いまはかなり日常的な雰囲気になった。ラトルとオーケストラの親密度の高さを感じる演奏。
九月二十九日(土)カニサレス

めぐろパーシモンホールで、カニサレス・フラメンコ・クインテットを聴く。門外漢の自分も惹きこまれる、見事なコンサート。ソロにセカンド・ギター、歌と踊りに打楽器を適宜加えて、編成の変化で飽きさせない。
私のすぐ後ろの席のスペイン男性が絶妙のタイミングで「オーレ!」などと掛け声をかけてくれる。客席はもちろん、演奏者もやりやすいに違いない。
十月一日(月)フォーレQ強化週間

フォーレ四重奏団強化週間、トッパンホール初日。モーツァルト、メンデルスゾーン、シューマン。四年前にアンコールでアンダンテ楽章を聴いて以来、ついに聴けたシューマン全曲。濃厚なるロマンチシズム。この人たちはどうしてこんなに、もうさんざんひいてきただろう音楽に深い愛情を込め、ナマな命を引き出すことができるのか。音程が少し甘かったとか、そんなことはまさしく些事。
来日最初の三十日の神戸女学院小ホール公演が台風で中止となり、到着した関空からそのまま成田経由で移動してきたとか。東京も一日早ければ危なかった。
十月二日(火)ヴィキングル
ミュージックバードの番組収録後にトッパンホールへ行き、マスタークラス前のフォーレ四重奏団にインタビュー。まさに役得の仕事。しかしただのファン丸だしになってしまい、あまりいいインタビューにならなかった(笑)。
ただ、四人の性格が垣間見えたのは収穫。いちばん気遣いが細やかなのは、やはりというかピアノのモメルツだった。弦三人とはただひとりまるで違う楽器をひいているのだから、当然か。終了後、少し離れた場所で、機を逸して見せそこねちゃったなあなどと思いつつ、かれらが二〇〇〇年に録音したフォーレの一番他のCDをしまおうとしていたら、目ざとく見つけて「それ持ってるのかい、今はドイツでも手に入らないんだよ」とわざわざ話しかけてくれたのがモメルツだった。勇気を得て「やっと手に入れたんだ。これが最初のCDなの?」ときいたら「そうだよ」と嬉しそうで、個人的にはこの問答だけでも満足(笑)。
写真は終了後、飯田橋の珈琲館でミックスサンド(玉子入り)を食っているところ。その脇にあるのが、そのフォーレのCD。十八年前から音楽への基本的な姿勢がまったく変っていないことが、よくわかるCD。

そのあと紀尾井ホールに行き、ヴィキングル・オラフソンのピアノ・リサイタルを聴く。


かれのDG二枚目のCD「バッハ・カレイドスコープ」の、まさしく萬華鏡のようにきらめいて、多彩に千変万化するバッハ演奏を聴いて以来、聴くのを楽しみにしていた人。前半がバッハ小品集、後半がベートーヴェンの一番と《悲愴》(三十二番の予定だったが残念ながら変更)。
バッハもベートーヴェンも、今ここにあるモダンピアノのために作品を書いたわけではない。音符は同じでも、モダンピアノを用いたその瞬間に、どちらも一種の編曲になる。そのことを意識して、ではどうすればモダンピアノでこれらの音楽を美しく響かせることができるのかを、考え、そして実践したピアノ演奏。
タッチとペダル操作の繊細な動き。鋭敏な感性と音への想像力を具現化するための、敏捷で若々しい肉体。霊と肉との幸福な、(永遠の時から思えば)束の間のものにすぎない結合。バッハのファンタジー、ベートーヴェンの天空を跳ねまわるエネルギー。モダンピアノでやるとただ騒々しく、せせこましいものになりやすい《悲愴》から、ただ抽象化されたマグマだけを取り出してくる、絶妙のコントロール。
こうなると、第三十二番とかどうなるのかと、聴けなかったのがいっそう残念になるが、「まだ聴くべきもの」が明日に残っているのは、人間にとって最高の幸福なのだと、思うことにしよう。
十月五日(金)晴海からトッパンへ
 トリトンアーツのフェイスブック・ページから。
トリトンアーツのフェイスブック・ページから。ゴゴイチで晴海の第一生命ホールへ。「トリトン晴れた海のオーケストラ」のリハーサルを聴く。ベートーヴェン・ツィクルスの第一回。今月出る「音楽の友」のために、コンマスの矢部達哉さんほか四人の座談会の司会をした関係で、翌日の本番を聴けないのでリハに入れてもらったもの。ホール関係者と三人しかいない客席で、少数精鋭の豪華メンバーによる第一番の通し演奏を聴かせてもらうとか、とても贅沢な体験。
矢部さんはリーダーとしてメンバー全員の音に注意を払い、大忙しのはずなのに、リハのちょっとした隙間に客席にいた当方を見つけて、休憩のときに舞台をおりて、わざわざ挨拶にきてくれる。こういう人たちは人間としても只者ではないんだということに、今さらながら気がつかされる。
指揮者なし、六‐五‐四‐三‐二の小編成で聴いていると、中央に座るオーボエ、いつもは指揮者の陰になるオーボエが、アンサンブルの扇の要になるようにベートーヴェンが書いていることに、あらためて気がつく。
練習終了後、オーボエの広田さんにそんな話をすると、「でも今回は、いつもの半分くらいの音量でしか吹いていないんですよ」とのこと。この編成とホールならそれで充分。だからニュアンスが込められる。
矢部さんがこのオーケストラの目標として、指揮者がいないぶん他の奏者の音を聴きやすくなるのは当然。次の段階として、自分の音がどうなっているのかを考えるところへ、という意味のことをいっていたのが、ここで腑に落ちる。十四型、十六型では聞こえにくくなる他者と自分の関係を、ここでなら突きつめていきやすくなる、ということらしい。次回十二月の第二回は、本番を聴きたい。
その夜は今週三度目のトッパンホールで、フォーレ四重奏団第二夜。ラフマニノフ、これもついにナマで聴けた「フォーレのフォーレ」、そして代名詞というべきブラームスの一番。この曲は自分ももう三度目だから、二〇一四年に何も知らずに初めて聴いたときの「ぶったまげる」驚きはない。しかしそれでもなお圧倒される、奔流のようなエネルギー。
アンコールは二日と同様に《展覧会の絵》から二曲だったが、今日は〈キエフの大門〉をやらなかった。この「また今度ね」感が大好き(笑)。
十月六日(土)新国立劇場開幕

新国立劇場の《魔笛》へ。大野和士音楽監督時代の幕開けとなる公演。具体的な出来については日経新聞に評を書くのでここでは控える。あえて自ら振らなかった大野が目指すもの、新国立劇場のオペラ公演のありかたというものが、しっかりとみえる開幕だと思った。
大野が振れば、よくも悪くも関心はそこに集中して、お祭りになるだろう。それを避け、堅実だがけっして守旧的ではない公演を出した。地味とはいえるが、良質の演出による、基盤づくりになるような公演。こうしたものでシーズンを構成しつつ、そこに「オペラ夏の祭典」や新作初演のような、大野自身の指揮による祝祭を載っけていこう、ということのように思えた。
個々の部分の揚げ足取りはいくらでもできるだろうが、表層で踊らされずに、自分はじっくりと見ていきたい。ケントリッジの演出がまさにそのような、多層的な価値観を提示して、含蓄のある、考えさせられるものだったのだから。
ひとつだけいえば、タミーノが他の登場人物とは完全に異質な、猛獣狩りのハンターの服装をしていた(しかし銃は手にしていない)のも、この演出のポイントのひとつなのだろう。
ああ、ト書きには、タミーノは日本の「狩衣」を着ているとあるんだっけと、思い出してニヤリ。
一日から、かけがえのない芸術家たちの音と言葉と映像から、さまざまに教わってばかりの一週間。
「君は何をするの」
「とりあえず原稿」
十月十二日(金)古歌の力

宝生能楽堂で、銕仙会定期公演。
・能『龍田(たつた) 移神楽』鵜澤久
・狂言『鳴子遣子(なるこやるこ)』善竹十郎
・能『項羽(こうう)』浅見慈一
興味の重心は『項羽』。秦の滅亡から楚漢戦争にかけての英雄、項羽をシテとする修羅能。垓下の戦いでの四面楚歌から死に至る英雄的な最期の話は自分も好きなので、どのように能にしてあるかを知りたかった。
結論をいうと、おそらく世阿弥よりも後世の人が、複式夢幻能の確立されたパターン通りに、項羽の物語をあてはめたもの。ワキが刈った草をかついだ草刈男なのが面白いが、古代中国の話に仏僧は合わないから変えた、というだけかも知れない。
川で渡し舟に乗ろうとしたところ、不思議な渡し守の老人に会い、これが実は項羽の霊、というお決まりの展開。中入でアイにそれは項羽の霊だから、僧でなくともいいから弔ってやってくれと言われ、ただの草刈男なのに経を読んで弔いを始めるというのは、かなり強引。
しかしこれは重要な問題ではない。なにより残念なのは、後場の項羽の回想が虞美人との別れから死に至るストーリーを単になぞるだけで、「力は山を抜き、気は世を蓋う」に始まる有名な垓下の歌を、うまく使えていないこと。古歌の力を活用してドラマを重層化させ、奥行きを与えるのが世阿弥の真骨頂なのに、そこはさすがに真似できなかったらしい。
こういう凡作がたくさんあるなかに、珠玉の名品がわずかに混じるのが創作活動というもの、なのだろうけれど。
・垓下の歌
力は山を抜き 気は世を蓋う
時利あらず 騅逝かず
騅逝かざるを 奈何すべき
虞や虞や 汝を奈何せん
十月十三日(土)心地よい時間
新宿の「どん底」で、片山杜秀さんとサシで呑む。
ミュージックバードの年末番組などではご一緒しているとはいえ、サシで呑むのは何年ぶりか。なにしろ片山さんが忙しすぎて、ずっとやれなかった。
以下は酒席の与太話なので、どの話題も深い意味はない。
出たばかりの「中央公論」十一月号の特集「クラシックに未来はあるか」で、片山さんは指揮者の大友直人と「マエストロと考える危機の乗り越え方」という対談をされている。その話から、大友直人、井上道義、外山雄三という、ある共通点をもつ指揮者たちの話(その共通点が何かはひみつ)。
昭和の初めの日本のインテリたちにとって共産主義が魅力的に思えた理由の一つは、それを使えばキリスト教抜きに西洋文明を科学として理解できる、という幻想を与えてくれたからじゃないか、なんて話。戦国時代のキリシタンのなかにも、科学としての西洋文明に惹かれたからキリシタンになったが、しかし最後にはどうしても神を否定できないイエズス会から離れ、むしろ弾圧に回った日本人がいたなんて話が出て、そのへん精神構造として似てるのかも、なんて話。
キリスト教を規範とする十九世紀の市民社会と同様、共産主義は音楽が人民の情操教育に役立つと考えた、資本主義が損得や生産性しか考えないなら、教養としてのクラシックなんて不要ですね、なんて話。
衰えの目立つポリーニの話になり、あの完璧なテクニックにおいて、昭和の大衆教養主義の時代にぴったりのピアニストだったのかもしれませんね、ホロヴィッツはその時代にはあまり合っていませんでしたね、そうすると吉田秀和がポリーニを高く評価し、ホロヴィッツにはそうではなかったのは、ポリーニを考える上でも吉田秀和の位置を考える上でも、けっこう象徴的なことなのかも、なんて話。そこから、ポリーニ好きのある人はグールドがダメらしいと進み、グールドの場合は大衆教養主義の次の、セゾン文化の時代にぴったりだったからでは、なんて話。
そうして、片山さんが観てきたばかりの新国立劇場の《魔笛》の話になる。自分は六日に観た。片山さんも自分もそれぞれ別の新聞に批評を書くことになっているから、あまり情報交換をしてしまうのはよくないのだが(笑)、やはりしゃべらずにはいられない。それくらい考えさせる上演だった。
二時間があっという間に過ぎ、仕事を山のように抱える片山さんが帰らなければいけないので、ここでお開き。楽しかった、また近々やりましょうと別れる。
しかし次はいつのことやら(笑)。可変日記を読みかえすと、前にサシで呑んだのは二〇一四年。そのときも五、六年ぶりだったと書いてあるから、次も早くて四年後か。ほとんどオリンピックか、「こち亀」の日暮熟睡男か(笑)。
まあそうならず次は早くやりたいが、もし、たとえこのままやれなかったとしても、心地よい時間の記憶は、自分のなかにずっと残っていくのだろうと思う。
それにしても「どん底」、数年前に来たときにはそんなに混んでいる感じでもなかったのだが、土曜の今夜は若い層を中心に、外まで人が並ぶ人気ぶり。
十月十六日(火)祥丸とアントニーニ
六月までは千駄ヶ谷の東京体育館のプールを利用していたので、泳いでからそのまま同じ千駄ヶ谷の国立能楽堂へ行って(もちろん水着は着替えて行く)能を観る「プール能」ができたのだが、東京五輪に向けた改装工事で閉鎖されてしまったため、今は四ツ谷で泳いでいる。
そこで今日は泳いでからポールでモーニングを食って国立能楽堂へ行き、さらにサントリーホールへ向かう、「プールポール能クラシック」(別につなげなくてもいいのだが)。

能は十三時から「青翔会」。国立能楽堂で学ぶ若手能楽師を中心とする、能楽研修発表会。発表会とはいえ、千五百~七百円で本格的な狂言と能が一本ずつ見られる。未見の作品ばかりの自分にはありがたいもの。
しかも今回は観世流シテ方若手のホープ、関根祥丸が舞囃子(能のクライマックス部分だけを、装束をつけずに地謡と囃子をバックに舞うもの)に登場するという楽しみがあった。
・舞囃子『田村(たむら)』田崎甫(宝生流)
・舞囃子『胡蝶(こちょう)』関根祥丸(観世流)
・舞囃子『野守(のもり)』友枝雄太郎(喜多流)
・狂言『 蝸牛(かぎゅう)』河野佑紀(和泉流)
・能『花月(かげつ))柏崎真由子(金春流)
関根祥丸の舞、期待に違わぬ美しさ。素人の観客にとって、女舞の能のゆったりした舞はいちばんの難関で、あまりに動きが少ないので眠くなることが多い。『胡蝶』の舞もそうしたもの。ところがなぜか名手がやると、静止がただの静止ではなくなり、動きの緩さも消えて、麗しき流れとなる。
今日もそうだった。肩甲骨から頸にかけての肉体にみなぎる、静かで凛とした緊張感。腕から指先への弧が放つ、なんともいえぬ色気。中空に浮かんでいるかのように、すーっと平行移動する見事なすり足。声もいい。張りがあって発声が明快で、しかも潤いがある。この人は、能を知らない人をも能に惹きこむ力を持っているのではないか。あるいは少なくとも、持つことになるのではないか。
続く友枝雄太郎の『野守』もよいものだった。優雅な蝶の舞とは対照的に、宇宙を映しだす魔鏡を手にした鬼神の踊りで、いかにも喜多流らしいキレのいい足さばき、鋭く力強い足拍子が、とても気持よし。名人友枝昭世の孫、ということは将来喜多流を背負って立つべきこの人もまだ二十二歳、関根の三歳年下。
能の『花月』は、まず作品がみたかった。遊芸の民、寺社と芸能、人さらい、天狗、稚児愛など、日本中世の社会と、その精神世界の光と影がつまっているような作品。しかしこれについて書くと長くなるので、十九日に観る予定の『自然居士』も似たような世界を持っているらしいから、それと合わせて考えてみる。
続いて夜はサントリーホールで、読売日本交響楽団の演奏会。ジョヴァンニ・アントニーニの指揮。
・ハイドン:歌劇《無人島》序曲
・ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲(独奏:ヴィクトリア・ムローヴァ)
・ベートーヴェン:交響曲第二番

イル・ジャルディーノ・アルモニコを率いて、イタリアの古楽アンサンブルといえば「ゴリゴリ系」、という印象を確立させたアントニーニ。ゴリゴリ感が強すぎてかつては苦手だったが、近年はバーゼル室内管とのハイドンなど、肩の力の抜けた、より自然な演奏を聴かせてくれるように感じていたので、二十年ぶりという今回の来日が楽しみだった。
十‐十‐六‐五‐三の編成による、キビキビとした進行と澄んだ響きのピリオド・スタイルも期待通りだったし、ムローヴァの独奏の美音もよかったが、それよりも何よりも感心したのは、オーケストラの「鳴り」がいいこと。
古楽系指揮者が既成の交響楽団を指揮すると、音がグシャッとして響かないことがよくある。そういうとき、シンフォニーオーケストラを鳴らす指揮能力というのは、音楽性の有無とはまた別の特殊技能なのだろうと思わされるのだが、意外にも(失礼)アントニーニの指揮は響きのフォルムがしっかりしている。だから澄んで、よく鳴りわたる。大きなサントリーホールの空間に、日本のオケが十型の小編成でこれだけよく鳴る、音が通るなんて、あまりないことではないか。
いうまでもなく、ただ強くてデカイ音と、よく鳴って通る音は違う。前者は興味のない人にはただの騒音だが、後者はそうならない。
その点でアントニーニの響きと、関根祥丸の謡には共通するものがあった。
二十日と二十一日には池袋の東京芸術劇場でヴィヴァルディとバッハとハイドンを演奏する予定だが、今日のように鳴るなら、ホールが大きすぎるとは感じないはず。リコーダー協奏曲では自らが吹くというのも楽しみ。
十月十九日(金)自然居士と梅若

国立能楽堂で《開場三十五周年記念 月間特集・所縁の能・狂言》
・狂言『右近左近 (おこさこ)』善竹十郎(大蔵流)
・おはなし 松岡心平(東京大学教授)
・能『自然居士 (じねんこじ) 古式(こしき)』観世清和(観世流)
能にはシテが「芸づくし」をする物がいくつかある。曲舞やら小歌やらササラやら羯鼓やら、中世の芸能をたて続けに演じて、ワキに見せるというもの。
シテの役柄は今風にいえば芸人だが、中世においてはそれが居士とか放下僧とか、半僧半俗の形をとっている点に、この時代の特徴がある。芸はあくまで勧進(寺院や橋梁の造営や修繕のための募金活動)のため、つまり宗教活動の一環であるとすることで、一定の身分の保証を得ている。
国家鎮護を旨として一般世間とは関わりを持たず、穢れを嫌って白衣を着た正規の寺社の僧たちと、家族や自身の現在と死後の安寧を求める民衆の素朴な信仰心とをつなぐ、聖と俗とをつなぐ存在。穢れた俗世に身を置くために、墨染や黒衣を着た人びと。
かれらの芸能や説法は、物狂や狂言綺語などと卑しめられつつ、まさにその狂の力で聖と俗をつないでみせる方便。
能、当時の言葉で猿楽も、やはり狂言綺語のひとつ。将軍足利義満が稚児の藤若、のちの世阿弥を寵愛して祭見物の桟敷に同席させたことを、ある公家が日記で「猿楽ハ乞食ノ所業」だと批判した。芸の作用で尊卑貴賤がつながれる。
この『自然居士』は世阿弥の父、観阿弥の代表作で「芸づくし」の典型。
前半の舞台は京都東山、現在の高台寺の付近にあった雲居寺(うんごじ)。応仁の乱で焼亡するまでは、八丈(二十四メートル)の高さの大仏があり、隆盛をきわめたという。
自然居士はここで、雲居寺造営のための説法をしている。かれのマネージャー的存在であるらしい「門前の者」が、聴衆が集まったところで自然居士を呼び出す。造営のための御札を買ってくれ、と触れながら現れる自然居士。
居士とは出家していない、在俗の禅者のこと。つまり正規の僧ではなく、雲居寺に所属しているわけでもない。「門前の者」というのも、門前町に勝手に住みついて、勧進興行をやっている俗人だから、寺の者ではない。このあたりがいかにも当時の半聖半俗。
居士だから有髪なのは当然としても、「喝食(かつじき)」の面をつけているのが面白い。喝食とは、禅寺の稚児のこと。つまりここでの主人公は十代の美少年なのである。自然居士は鎌倉時代後期の実在の人物らしいが、ササラをすりながら歌い舞い、説教をして、世を惑わすものとして京を追放されたという以外には、その生涯や行跡はわずかしか伝わっていない。その人を中年ではなく、美しい稚児に設定している。
シテの観世清和が今回つけたのは、観世宗家秘蔵の竜右衛門(たつえもん)作の面。世阿弥が面打の名手として讃えている人なので、観阿弥や世阿弥の時代から、じつに六百五十年の歳月を超えて使われている面ということになる。
話を戻すと、その美少年が説法を始めると、小袖を捧げた幼女が登場。その小袖を奉納して父母の供養をし、自分もともに極楽浄土に往きたいと願う。その孝心に居士が墨染の衣の袖を濡らすところに、奥州の人商人(ひとあきんど)が現れ、幼女を連れ去ってしまう。
さては幼女は自らの身を売って、その金で小袖を買ったのかと覚った居士は、琵琶湖の畔まで追いかけて、漕ぎ出でようとする人買い舟を呼びとめ、小袖を返すから幼女を解放しろと交渉する。解放しなければ自分も奥州までついていくという居士が面倒になった人買いは、舞を見せるなら解放してやるという。そこで居士の「芸づくし」が展開され、ついに幼女を取り戻すという物語。
居士と人買い、門前の者などとの対話が生き生きとしていて面白い。ややシニカルな、醒めた人間観もあって、このあたりは狂言の人間観に通じる。観阿弥はこうした対話劇を得意としたらしい。相手に対してすごむような大声や仕種をするのは、歌舞伎の見得の原型のようにも思える。
世阿弥はこれを純化、芸術性を高めた夢幻能に結晶化させ、息子の世代もそれを引き継ぐが、そのあとの観世信光たちの能は、観阿弥の芝居的要素を復活させて、派手にしたものなのかも知れない。
今回は「古式」という小書で、世阿弥が削除した詞章を復活させている。ここは居士が自らの生い立ちを語る長大な部分で、元は寺にいて、隠遁して修行しようとしたが、「山に入りてもなほ心の水の水上は求め難う、市に交はりても、同じ流れの水なれば、真如の月などか澄まざらん、かやうに思ひしより自然心得、いまは山深きすみかを出で、かかる物狂ひとなり。花洛の塵に交はり(略)法のためなれば、身を捨つる」という。
深山にこもって独善的に修行するよりも、俗世の巷の塵にまみれることで悟りを目指そうという、いかにも大乗仏教的な、煩悩即菩提的な発想。だからこそ、幼女を救うために身も誇りも捨て、卑賤の芸で俗人の関心を惹くことができるのだ。
じつによい部分で、ここをなぜ世阿弥が削除したのかは、ちょっと不可解。居士が若年のはずなのに、豊かな人生経験を持っていそうな内容なのが矛盾するから、という解釈もあるらしい。
解釈はさまざまなのだろうけれど、ネットで調べると、この居士の生い立ちの部分は、物語の舞台となっている雲居寺に八丈の大仏を建てたという、瞻西(せんせい、又はせんさい)という天台僧を意識したものではないかと思えてきた。
瞻西は比叡山延暦寺の僧で、後半生を雲居寺で送り、院政期の一一五七年に没した。ここに大仏を建立し、「迎講」という、臨終の際に阿弥陀如来が迎えに来て浄土へ導く「来迎図」を再現する劇を行ない、僧俗貴賤を問わずに広く人気を博したという。声明の名手で、説法も上手だったらしい。芸よりも説法が得意という能の自然居士の人間像には、雲居寺ゆかりのこの瞻西のイメージが重ねられているのではないか。
さらにこの瞻西という人は、南北朝時代に書かれた『秋夜長物語(あきのよのながものがたり)』という物語の、主人公にされた人でもあるのである。
秋夜長物語は稚児物語の代表作とされる。白洲正子の『両性具有の美』の紹介によると、比叡山の律師桂海は、ふと見かけた三井寺の美しい稚児、梅若に恋をし、ついに一夜を共にする。しかしこれが原因となって比叡山と三井寺の激しい抗争に発展し、三井寺は焼き払われてしまう。自責の念にかられた梅若は琵琶湖の淵に入水して死ぬ。桂海はその美しい水死体を必死で探し出し、悲しみに暮れる。そして山にこもって梅若を弔い、徳を積んで瞻西と名を変える。
瞻西はそのまま深山に孤独のうちに果てたが、弟子たちはその遺志を継いで京の東山に寺を建て、衆生を済度することにつとめた。これこそが雲居寺である、という話なのだそうだ。

美少年、美青年という自然居士のイメージと、瞻西と梅若の悲恋物語。能における美少年自然居士は、まるで秋夜長物語の瞻西の遺志の化身のようだ。心は瞻西、体は梅若とすれば、豊かな人生経験と若々しい容姿の両立も不思議はない。
ところで梅若といえば観阿弥の孫、元雅の名作『隅田川』の、人買いにさらわれて川のほとりで死んだ少年の名でもある。そして現在は観世流の職分となっている梅若六郎家は、元は丹波を拠点に独立の一座を組んでいで、信長や光秀に贔屓されたシテ方だが、堂本正樹によるとこの家は子方が活躍する能を得意としてきた形跡があるという。美少年梅若という意識が能に及ぼした影響は、意外と大きいのかも知れない。
もとよりそれぞれの話の前後関係、因果関係もわからない(簡単にいえば、観阿弥が秋夜長物語を知っていたかどうかはわからない)。すべては想像にすぎないけれど、こうしたさまざまなイメージが折り重なり、思いの淵をなして、その水面に浮かびあがる、『自然居士』の喝食の面。
こういう深さと広がりが、中世物の面白さか。
十月二十一日(日)アントニーニ週間
アントニーニ週間。読売日本交響楽団に招かれたジョヴァンニ・アントニーニを、十六日にサントリーホール、二十一日に東京芸術劇場で聴き、その間の十八日に「音楽の友」でインタビュー。
こういうインタビューは本当に役得で嬉しいが、読響の練習所のある小田急多摩線黒川駅は半端でなく遠く、さびしい場所だった(笑)。練習所が駅の真ん前だからまだよかったが。
二十一日の演奏会はヴィヴァルディとバッハ、ハイドンという、現代の日本の交響楽団とは思えないような斬新なプログラム。個人的には、十六型の大編成ばかり聴いていると耳と感性がバカになってくる気がする。こういうほうが脳を刺激してくれて嬉しい。

・ヴィヴァルディ:ドレスデンの楽団のための協奏曲ト短調RⅤ五七七
・ヴィヴァルディ:マンドリン協奏曲ハ長調RⅤ四二五
・J・S・バッハ:マンドリン協奏曲ニ短調BWⅤ一〇五二(マンドリン:アヴィ・アヴィタル)
・ヴィヴァルディ:リコーダー協奏曲ハ長調RⅤ四四三(リコーダー:ジョヴァンニ・アントニーニ)
・ハイドン:交響曲第百番《軍隊》
ヴィヴァルディとバッハは六‐五‐四‐三‐一。チェンバロとテオルボを加えた、折衷型のピリオド・スタイル。
ピリオド嫌いの人にはよく、ピリオド派とは「正しさ」を押しつけてくる教条主義だと思っている人がいるけれど、それは三十年前の、体育会でうさぎ跳びとかやっていたころの話。いまは、作曲当時の楽器や奏法がどんなものだったかを意識する、つまり歴史意識をしっかりと持つのは当然のこととして、それをどこまで現場の状況に合わせていくかの話になっている。理想と現実の落しどころ。モダン楽器でも歴史意識を持つのは当然のことで、でなければ古典音楽、クラシックを現代にやっている意味はないだろう。あとは、それをどこまで実践に移すかという、それだけの話。
アントニーニの歴史意識が見事に出たのは、一曲目のRⅤ577の第二楽章。この作品ではフルート、オーボエ、ファゴット各二が、コンマスの日下紗矢子とともに最前列に立って、合奏協奏曲的に演奏した。
その第二楽章で、アントニーニは指揮台をおりて日下の脇に立ち、なんと指揮をやめてしまった。そしてオーボエとファゴットだけの二重奏に、耳を傾けているだけ。
先日のインタビューのとき、指揮棒を使わない理由をたずねたら、いくつかあげてくれたなかに、「権力の象徴のように思えるから」というのがあった。軍団の将軍ではない、アンサンブルのリーダーとしての指揮者。指揮者という存在の位置づけも、歴史意識の深化とともに変ってきている。
そのかれがソロに耳を傾ける。客席の我々も耳を傾ける。耳をすます。大きな音に慣れると、忘れてしまうこと。
こうすると急緩急の三楽章構成の中央にある「緩」の静けさのもつ魅力がきわだってきて、活力にあふれた両端楽章との鮮やかなコントラストになる。ヴィヴァルディの音楽の構成はバッハに比べるとはるかに単純だが、だからこそそこに工夫を込められる「余地」がある。その魅力。イタリア人アントニーニは、その可能性をよく知っている。
続く二曲のアヴィタルの鮮やかなマンドリン。セゴビアがリズム楽器だったギターを二十世紀の大ホール向けのソロ楽器に改良するまでは、マンドリンこそが撥弦楽器の花形だったという話を思い出す(だから明大マンドリンオーケストラとかが流行った)。
後半一曲目のソロはアントニーニ自らのリコーダー。まことに鮮烈。
そしてハイドン。バロック期のオーケストラを拡大しただけでなく、打楽器とトランペットという軍楽隊の楽器を大活躍させて、ナポレオン戦争の時代にふさわしい、イギリスの市民社会に向けた作品。息づくようなフレーズの呼応が美しい。しかしこうして聴くと、十六日のベートーヴェンの交響曲第二番がいかに革命的な、ロマン派の扉を足でぶちやぶるような作品だったかも、鮮やかにわかってくる(編成がどちらも十‐一〇‐六‐五‐三だったので、いっそう)。
アントニーニのインタビューのベートーヴェン論もすごく面白かった(イタリア人らしくよくしゃべってくれた)。これは一月号に掲載される。
いま出ている十一月号にはベートーヴェン・ツィクルスを進行中の「トリトン晴れた海のオーケストラ」のメンバー四人の座談会の司会と、マルク・アンドレーエとハンスイェルク・シェレンベルガ―のインタビューなどが載っている。
祖父も指揮者だったアンドレーエ、オーボエ奏者から指揮にも力を入れるシェレンベルガー、同じ指揮者でもそれぞれの立場の違いが面白かった。特に後者、指揮者であると同時にベルリン・フィルの首席オーボエとしての、ベルリン・フィルの指揮者たちの印象。
字数がかぎられていたのでかなり省略せざるを得なかったのが残念だが、ヴァントの感想などは面白かったので、なんとか含めた。ご興味ある方は書店で。

十月二十六日(金)バッハへの遡行
東京都交響楽団と読売日本交響楽団の定期演奏会。歌でつながるドイツ音楽史の一断面、とでもいうか。
まずは一昨日の二十四日、東京文化会館で大野和士指揮の東京都交響楽団。
・シュレーカー:室内交響曲
・ツェムリンスキー:抒情交響曲(ソプラノ:アウシュリネ・ストゥンディーテ 、バリトン:アルマス・スヴィルパ)

ドイツ後期ロマン派の残照のような、ウィーンゆかりの二つの「交響曲」。編成は小と大で対照的だが、ともにチェレスタとハルモニウムが入っているのが面白い。世紀末ウィーンのアンサンブルには欠かせぬ楽器、響きだったのか。
まず一九一六年作曲のシュレーカー。四楽章の伝統的な構成を変形して単一楽章にまとめた、らしいのだが、とにかくぬるぬるとつかみどころのない音楽。うねっているだけで歌いようのない旋律。
二十五分くらいも長さがあるのに、耽美的な響き、という以外に特徴をまったく言葉にしようのない、じつにシュレーカーらしい音楽。ただ、今月のプログラム掲載の「オリンピックと音楽」が、シュレーカーの弟子であるヘルベルト・ヴィントが音楽を担当した映画『オリンピア』の話だったのに、本筋からそれるからと師のシュレーカーの話をしなかったのは、ちょっと失敗。
続いてツェムリンスキー。シューベルト、シューマン、マーラーと続く、ドイツ・ロマン派伝統の「失恋して悲劇の主人公な俺」の歌曲集を、大オーケストラに伴奏させた作品。音の発想がいかにもモダンピアノ的で、バンバンガンガンうるさい。
対訳を読めるくらいに客電を明るくしてくれたのはよかったが、ストゥンディーテのドイツ語は、どこを歌っているのかさっぱりわからなかった。でも、遠目には黒いトレンチコートみたいに見えるドレスはかっこよかった。
終演は早く、八時四十分くらいに出られる。夜の上野はこのくらいの時刻の方がラク。ロマン派の自己肥大の伝統を継ぐツェムリンスキーと、肥大しすぎて自己が融解したみたいなシュレーカー。
サントリーホールでの今日の鈴木雅明指揮の読売日本交響楽団は、時代をさかのぼって、古典派と前期ロマン派。
・J・M・クラウス:教会のためのシンフォニア ニ長調ⅤB一四六
・モーツァルト:交響曲第三十九番
・メンデルスゾーン:オラトリオ《キリスト》
・メンデルスゾーン:詩篇第四十二番《鹿が谷の水を慕うように》

前半は、先週のアントニーニのあまりに鳴りのいい響きが耳に残っていたために、ちょっと損をした感じ。しかし細身の響きながらモーツァルトは生き生きと響いて、飽きさせない。
そして、RIAS室内合唱団を加えたメンデルスゾーン。これが何より聴きたかった。四十人弱くらいだったが、流れと鳴りの豊かな合唱の響きがほれぼれするほどに美しく、音楽にぐんと広がりが加わる。
いつも思うが、大規模声楽曲はナマを体験しないと真価がわかりにくい。今日のメンデルスゾーンもそう。何よりも痛感したのは、オラトリオでも詩篇でも、メンデルスゾーンが意識しているのはバッハよりもヘンデルだ、ということ。
ともにライプツィヒで活動し、マタイ受難曲の蘇演も手がけているだけに、メンデルスゾーンがバッハを深く敬愛していたことはもちろん疑いない。しかし、近代的な国民国家のための国民音楽の代表たるオラトリオ、十九世紀の市民社会にふさわしいオラトリオの、理想の姿を提示していたのは、イギリスにおけるヘンデルだったのだ。
自国語による市民音楽、キリスト教を倫理の規範とするコミュニティ用の、教会ではない公会堂でのオラトリオという道を示した、ヘンデル。ただかれはあくまでイギリス人のために活動したから、ドイツ人の、ドイツ人による、ドイツ人のための市民音楽はないのかとメンデルスゾーンが考えたとき、見つかったのがバッハの受難曲だったのだろう。
メンデルスゾーンは、ヘンデルとバッハのいいとこ取りをしようとした。前者の華やかで肯定的な、健全な市民のための音楽と、後者のルター訳の聖書を精神基盤とする、善良なドイツ人のための音楽(それをユダヤ人がやろうとする、歴史の皮肉)。
その特徴が今日の二曲には、とてもよく出ていた。
そして、最後に今日の演奏会をさらに味わい深いものにしてくれたのは、アンコールとして合唱のみで一曲、鈴木が指揮して歌ったこと。
響きだした瞬間、擬ヘンデル風ではなく、バッハ的なものと感じた。厳粛さ、心の奥底から響いて、天の高みを見上げるような、はてしない深さ。
メンデルスゾーンがバッハを模倣してこれを書けたのならすごいが、そうではあるまいと思った。演奏会後に確認すると、やはりバッハのモテットとのこと。
これは厳粛さにおいて教会に由来し、教会のあの空間から生まれ出るものでなければならないのだろうと思った。
近代国家の市民社会のものというよりは、三十年戦争よりも前の、ある種中世的な時代精神と論理から、生れてきた音楽。二日間の演奏会で聴いた古典派以降の五人の作曲家とは異質なものをもつ、異形とさえいいたくなるような、底知れぬ音楽。
来月二日のオペラシティでのRIAS室内合唱団の演奏会では、このバッハのモテットを三つ、より完全な形で、そしてメンデルスゾーンの詩篇とブルックナーのモテットを交えて聴くことができるので、そこでどんな感想を抱くことができるのか、とても楽しみ。
蛇足な補足。モーツァルトの三十九番のカーテンコールのとき、指揮の鈴木が楽員をパートごとに立たせていった。
順繰りに来て、面白かったのはティンパニとトランペットを一緒に立たせたこと。「音楽の友」のトリトンオケの座談会で、トランペットの高橋敦さんが「古典派交響曲だとトランペットはティンパニの補強をしているだけの役なので、ひまです」と言っていたなと思い出し、なるほどそれでこうなるのねとおかしかった。ここでのトランペットはいわば、パーカッションの一種なのだ。
これが明快に変わるのはエロイカだけれど、先日のアントニーニの《軍隊》でも、トランペットがファンファーレを吹き鳴らしてから、打楽器群が活躍し始める場面があった。軍楽隊の楽器を加えることで、十九世紀以降の交響曲世界の可能性が大きく拡がるとき、トランペットも変身するのだなと納得。
十月二十七日(土)仲道郁代と一八四二年製のプレイエル

東京文化会館小ホールで、仲道郁代のショパン・リサイタル。
「プレイエルの響き、スタインウェイの輝き」と題して、一日に二つの演奏会があり、第一部は一八四二年製のプレイエル、第二部は現代のスタインウェイをひく。時間の都合で第一部だけを聴く。
二十四の前奏曲と四つのバラード。やわらかく濁りのないピリオド・ピアノの響きが美しい。普段は演奏会の一部分でひくだけで、まるまるプレイエルを用いるのは珍しいそうだが、演奏経験を重ねているだけに、見事なコントロールで楽器特有の謙虚な詩情を聴かせてくれた。
十月三十一日(水)あとは自分たちで
サントリーホールで、ティーレマン指揮シュターツカペレ・ドレスデン(SKD)の演奏会。二日間でシューマンの交響曲四曲を演奏するツィクルスから、第一夜の第一番《春》と第二番を聴く。
アインザッツは大まかで楽員にまかせているが、さしものSKDでも合わせきれない。サウンドにも統一感がなく、雑然とした音楽。楽員が前半と後半でかなり交代し、後半の方がぐっとまとまったが、それくらいに楽員の技量次第の指揮のように思える。
これでいいのだろうかと思う反面、ドイツ語圏のオーケストラの楽員からティーレマンはかなりの支持を得ているようだし、日本の高名なオケマンからも、ティーレマンの指揮は室内楽のツボをしっかりと心得たものだという話を聞いた。聴く立場と演奏する立場では、受けとるものが違う指揮者なのかも知れない。
十一月三日(土)世界音楽としての

サントリーホールでノット指揮東京交響楽団の演奏会。
・ブラームス:ピアノ協奏曲第二番(ピアノ:ヒンリッヒ・アルパース)
・ラフマニノフ:交響曲第二番
ラフマニノフが超絶的名演。高純度で濁りのない、世界音楽としてのラフマニノフ。ノットだから前半のブラームスとの組み合わせにも理由があるはずだが、つかみきれなかった。あえていえば、ピアノのついた交響曲としてのブラームスと、ピアノのない協奏曲としてのラフマニノフ、みたいな対照なのだろうか。アルパースの(大柄な体格からは想像もつかない)小音量の繊細なピアノを起用したことには、そうした意味があったような気もするが……。
十一月五日(月)彼も酔狂、我も酔狂
午後はサントリーホールのブルーローズで、ベルリン・フィル・レコーディングスの新譜発表の記者会見に参加。
ベルリン・フィルの責任者である首席チェロのマニンガーたちによるラトルの《悲劇的》の紹介、内田光子自身が語るベートーヴェンのピアノ協奏曲全集という、豪華な内容が会場を沸かせたあと、中川右介さんと二人で登壇して、フルトヴェングラーおたく漫才をする。
紹介したのは十二月発売予定の、フルトヴェングラーの一九三九年から四五年までの放送録音を集めた二十二枚組。
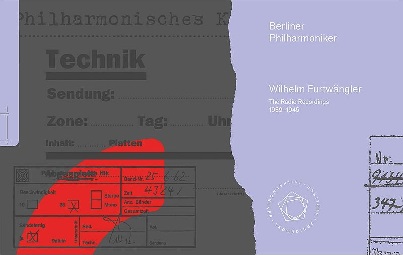
一九九一年の返還以来、ほぼ誰も手をつけようとしなかった(唯一の例外はテスタメントから出た、ブルックナーの交響曲第五番だそう)、権利切れの音源を手間隙かけてマスタリングし、SACDで発売する理由はなんなのか?
それは「酔狂」以外の何物でもないだろう。粗悪なコピーならネットでタダでいくらでも聴けてしまう時代に、よき音を目指し、オリジナルに一歩でも半歩でも近づくことを目指して、手間をかけて安くない商品にする人たちなのだ。それを買う我々もまた酔狂。
でも音楽のような芸術も、つきつめれば酔狂。功利主義で生存し、種の保存だけを目指すなら、みな無駄。
酔狂をするからこそ人間。
このセットには、そういう酔狂が詰まっている。肉親や友人知人が戦場で生命のやりとりをしているさなか、空襲の危険のもとでホールまで行き、音楽を演奏したり聴いたりすることぐらいに酔狂なことがあるだろうか。
彼も酔狂、我も酔狂。
能や狂言の背後には「煩悩即菩提」とか「狂言綺語」といった思想がある。そこにあるのも酔狂。人が現代よりも簡単に死んでしまう当時の世の中で、酔狂心を宗教心とからめて先鋭化させていたのが中世の人びとだったように、自分には思えてきている。
「ベルリンは現代史の鏡のような街」と途中で口走ったことがきっかけで、それならベルリン・フィルはクラシック史の、オーケストラ史の鏡のようなオーケストラなのかも、 などと考えはじめている。
十一月七日(水)「能のデパート」
国立能楽堂の定例公演。
・狂言『千鳥(ちどり)』野村万禄(和泉流)
・能『三井寺(みいでら)』粟谷能夫(喜多流)
能には、生き別れになった親子が仏恩により寺院でめでたく再会を遂げるという展開の名作がいくつもある。『花月』『弱法師』『百万』『柏崎』などがそうで、こうした物語が観客からも、御利益の高さの宣伝になる寺院側からも、大いに歓迎されたらしい。
舞台となるのは小さな寺ではなく、清水寺とか四天王寺とか清涼寺とか善光寺とか、名の知れた大寺である。勧進が目的でつくられたのだろうし、系列の寺社で上演するのに好都合だったのだろう。今日の『三井寺』もその一つ。
初めの場面は京の清水寺。シテは駿河の国の清見が関に住む女だが、行方不明になった息子千満を探すため、清水寺に参籠している。すると三井寺(園城寺)へ行けという霊夢を見、急行する。
シテが退場し、場面は三井寺に移る。三井寺の住僧(ワキ:宝生欣哉)が、僧三人と稚児一人(子方)を引き連れ、八月十五夜の名月を眺めようと登場する。この稚児はどこからともなく現れたが、非常に利発なので弟子にしたと語る。
シテが女物狂いとなって登場。琵琶湖の湖面に映る月を愛でる。能力(アイ)が鐘楼の鐘を撞くのを見て、自分にも撞かせろと強情を張り、撞きはじめる。月光の下に韻々と響きわたる鐘の音。
そこで、物狂いと稚児は互いに母子であることに気がつき、名乗りあう。再会を果たし、手に手を取って帰国する。
作者も成立時期も不明らしいが、古典詩歌をちりばめてあるだけでなく、能の名作へのオマージュなど、さまざまな要素からなる集大成を目指したような雰囲気を感じた。
和漢の詩句をよく知り、中世の稚児崇拝(住僧は弟子であるはずの稚児をとても大切にしている)とか、女人成仏思想(三井寺の鐘は藤原秀郷が龍宮から持ち帰ったもので、法華経の龍女成仏に結びつくから、その鐘をつくことで自分も五障を離れて真如の月を眺めたいとシテは主張する)とか、ぜんぶ詰め込んで「能のデパート」みたいにしているのだ。
始まりの場面をわざわざ興福寺系の清水寺にしているのは、南都と寺門派、どちらにも受けがいいように、という配慮なのか。清水寺といえば『花月』の舞台で、主人公の花月は天狗にかどわかされてそこにたどりついた。『三井寺』の稚児の場合は人商人(ひとあきんど)にさらわれたという。『自然居士』や『隅田川』の子方を想起させる設定。
母親については、鐘と女人の能といえば『道成寺』。鐘に執心する姿はそれを想わせるし、「山寺の春の夕べを来てみれば入相の鐘に、花の散るらん」とそのままの引用も出てくる。ただ『道成寺』の鐘は煩悩の象徴、愛欲の象徴だが『三井寺』のそれは、撞いて響かせることで煩悩を消し去っていくもの。
最大の違いは、『道成寺』の鐘が巨大で間近なものなのに対し、『三井寺』では専用の、遠景に見える小さな鐘楼の作り物になっていること。
鐘の音が鳴りわたっていく、三井寺内外の大きな風景をイメージさせるのと同時に、この鐘がより観念的な存在であるのを示しているようにも思える。
よくできた話なのだが、しかし感動はあまりなかった。プログラムの解説には「謡・三井寺、能・松風」なる言葉が紹介されていて、これが『松風』とならぶ名曲であると書かれている。
たしかに、凝った語句を用いた詞章は多彩多様で美しい。美しいけれども、不思議と心に響いてこなかった。詞章と能のドラマとの、母親の真情との、結びつきに必然性を感じにくかったからだ。世阿弥作の能での、言葉と状況がからみあい、歴史と現在がからみあって生れる心の戦きのようなもの、それがない。何か理屈で納得させようとするように感じられる。先の言葉も、謡としては名曲だが能としてはどうか、ということを指摘しているようにも思える。
 写真は銕仙会のサイトから
写真は銕仙会のサイトから十一月九日(金)稚児酒呑童子
銕仙会の定期公演。
・能『夕顔 山ノ端之出』大槻文藏
・狂言『鈍根草』能村晶人
・能『大江山 替之型』観世銕之丞

光源氏の思い人で、「なにがしの院」こと源融の六条河原院の跡(原作ではぼかしてあるが、能ではここだと断言している)で、逢引中に怪異に襲われて急死した夕顔の君の霊をシテとする『夕顔』も美しかったけれど、長くなるのでここでは『大江山』に話をしぼる。
能楽を通じて日本中世文化に興味をもつようになって、次第に関心が大きくなってきたのが、稚児崇拝のこと。下ネタ的な男色趣味といった浅薄な好奇心ではなく、もっと広い意味で、一つの美学として中世社会に根づいていて、能そのものの美意識にも大きく影響を及ぼしているように、感じられはじめた。
女犯を禁じられた僧侶が、成人男子のうちの一定の比率、とりわけ読書階級、識字階級でかなり大きな割合を占めた時代。稚児はかれらにとって現代のアイドルのような存在だった。性と聖、両方がない交ぜになった憧れの対象。十二~十八歳くらいに限定された、中性的魅力。当時は二次性徴が遅かったから、声変わりするあたりまでに限定された少年美。
三島由紀夫は『禁色』の主人公に「日本の中世で、欧羅巴の中世の聖母崇拝に相当するもの」として「稚児崇拝」をあげさせている。小説の登場人物の言葉とはいえ、これはけっこう的を射た言葉のように思える。
世阿弥が使うときの「幽玄」とは、おぼろで渋いもの、という現代のイメージとは違って、少年の稚々しい肢体とその動きを指しているという。「児姿は幽玄の本風なり」と世阿弥は『二曲三体人形図』で述べている。稚児の美学。それを成人してからでもいかに再現してみせるかが、シテの目指すところの一つ。
こうしたことを知ると、『大江山』のシテ、酒呑童子は、単なる鬼神ではなく稚児の美学の体現者、そのために滅びる存在であると思えてくる。前に観たときはまだそうした知識が充分ではなかったので、あらためて観てみたいと思っていたところに折よくあったのが、銕仙会の当主銕之丞がシテとなる、この公演。
「替之型」という小書のついた今回の演能は、銕仙会らしくドラマの表現に重点を置いたものなので、当方の思いを大いに満足させてくれるものだった。
まず、訪れた山伏(討手の源頼光主従が変装したもの)を屋敷に招じ入れるさい、酒呑童子は二人の稚児(子方)に先導されて登場する。自らも稚児のなりをしている上に、さらに稚児にかしずかれているあたり、かなりの「稚児趣味」の持ち主らしいことが示される。
 写真は銕仙会のサイトから
写真は銕仙会のサイトからそして稚児であるがゆえに、山伏たちに甘える。居場所を知られたからには魔力が失われた、といって童子が手にした鹿杖(かせづえ。能では鬼神の武器と決まっている)を取り落とすと、自分たちは出家の身だ、人には言わないから心配するな、と山伏たちは誓ってくれる。
そうだあなたたちは出家、自分は山育ちの稚児だと狎れる酒呑童子。山とは比叡山のこと。「一稚児二山王」、山王権現よりも稚児の方が大事、という比叡山の稚児崇拝をあらわす有名な語句が、ここで出てくる。稚児は僧から崇拝され、愛される存在。山伏も自分と同じ美意識を共有していることを、童子は信じて疑わない。それは往古の甘美な思い出に直結しているのだろう。
気持ちよく酔った酒呑童子が寝所に入るや、このときを待っていた武士たちは変装を解いて刀を抜き、襲いかかる。
「情けなしとよ客僧達。偽りあらじといいつるに。鬼神に横道なきものを」
鬼神は嘘をつかないのに、人は裏切るのか。白い布団を引っ被って顔を隠したまま、童子がいう恨み言が哀しい。
そうして現わす正体は、身の丈二丈(六メートル)の恐ろしくも醜い、赤髪の鬼。怒り狂って闘うも多勢に無勢、武器もなく、あえなく頼光に討たれる。
鬼の首に見立てて掲げられる赤頭。
可憐な稚児の姿は、幻術でそう見せていただけ。稚児の美学に憧れ、酔い、それゆえに人間に討たれる、哀れな鬼神。
 写真は銕仙会のサイトから
写真は銕仙会のサイトから十一月十日(土)校長先生と生徒
サントリーホールで今日から十五日にかけ、六日間に四回のロシア音楽シリーズ。まずは十日、ラザレフ指揮の日本フィル。
・グラズノフ:交響曲第八番
・ショスタコーヴィチ:交響曲第十二番《一九一七年》

二人の作曲家の違いがはっきりと出ていた。いかにも音楽院の院長らしい、構成も響きも謹厳実直で無茶をしないグラズノフ。トロンボーンの扱いなど、個々のパートの動きは細かいが、その個が突出して聞こえることはなく、オーケストラ全体でハーモニーをつくる。個に抑制を求める学校的な集団芸術。パリ音楽院院長のデュボワの作品を連想する。
五十五年後のショスタコーヴィチのオーケストレーションは、まるで別物。あちこちで羽目を外す。個々の楽器、声部のキャラクターが明快で、しばしば放り出されたような、あえていえば疎外されたような独自性をもって響く。表現主義的といえばそうだろうし、大音量にもかかわらず、室内アンサンブルをそのまま巨大化させたかのような、独特の隙間風が吹いている。
終楽章の強迫的な凱歌の響きが、交響曲第五番の終楽章を想わせるのは、もちろん故意にそうしたのだろう。曲の調性も同じニ短調だ。暴力装置のような交響曲。そうした要素をむき出しにさせたラザレフの指揮が強烈。
十一月十二日(月)本物(たぶん)
今日から二日連続でサンクトペテルブルグ・フィル。テミルカーノフ降板で、代ってアレクセーエフが指揮。
・シベリウス:ヴァイオリン協奏曲(独奏:庄司紗矢香)
・ラフマニノフ:交響曲第二番

開演直前の客席では、背中に「私はアレクセーエフ」と大書したデュトワがいきなり出てきたらどうしよう、などと愚かな会話が交わされていたが、もちろんそんなことはなく、本物(たぶん)のアレクセーエフが登場。艶のある響きと強い凝集力が見事な庄司の独奏。アレクセーエフの指揮は、音楽を大づかみに呼吸させるやりかた。
十一月十三日(火)栄光と迷妄
・プロコフィエフ:オラトリオ《イワン雷帝》
語り:ニコライ・ブロフ
合唱:東京音楽大学合唱団

曲の始めと終り、ジャーン!と鳴りわたる総奏の響きを聴いて、ジョン・ウィリアムズの『スターウォーズ』冒頭の元ネタはこのあたりか、と思う。プロコフィエフのオーケストレーションはジョン・ウィリアムズだけでなく、バーンスタインなどにも大きな影響を与えている。
テミルカーノフにインタビューしたとき、ラフマニノフはロシアの憂愁を音にし、ショスタコーヴィチは交響曲を通じてソ連社会のプロフィールを描いたが、プロコフィエフの音楽は世界に向けられていて、身近なことにはとらわれていない。まさに天才の作品で、二十世紀で最も偉大な、特別な作曲家だ、と言っていたことを思い出し、納得する。
これはたしかにロシア音楽の枠を超えた、世界音楽なのだろう。アメリカとフランスを肌で知るその響きは洗練されていると同時に、オーケストレーションも音楽そのものも、人間の内面の暗部、陰惨と狂気に深く踏みこんでいる。
テミルカーノフは、イワン雷帝とスターリンはともに殺人鬼である点が共通しているが、プロコフィエフの音楽にそうした要素はなく、大好きな音楽だから取りあげると言っていた。しかし、人間の栄光と迷妄の両面性は、このスタセーヴィチ編のオラトリオにもある。
スターリンの秘密警察GPUそのもののような、オプリーチニキ(親衛隊)の男声による盲信的な忠誠の歌と、女声による聖歌〈神よ汝の民を救いたまえ〉(チャイコフスキーの《一八一二年》に引用された有名な旋律)が唱応し、次第に重なっていく、狂信と信仰の二重写しの場面など、恐ろしく効果的だった。
イワン雷帝は歴史上の人物だが、権力者の孤独と狂気と恐怖政治の物語は、時代を超越した「神話」なのだろう。歴史上のどの時点においても、つねに過去であり現在であり未来であるのが、神話。その世界性。
十一月十五日(木)ラフマニノフの音
「サントリーホールで勝手にロシア音楽シリーズ」の続き。ノセダ指揮NHK交響楽団。
・レスピーギ:リュートのための古風な舞曲とアリア 第一組曲
・ハイドン:チェロ協奏曲第一番ハ長調(ナレク・アフナジャリャン)
・ラフマニノフ:交響的舞曲

前半二曲は八型の小編成で、演奏スタイルは二十世紀中葉の新古典主義風。つまり響きは端整だがリズムが重い。一九一七年のレスピーギはともかく、一七六〇年頃のハイドンにはちょっとアレなのだが、ハイドンも二百年後の一九六一年に発見されてロストロポーヴィチが愛奏した曲という印象が強いので、こういうスタイルが不思議にはまる(笑)。
その意味では、二十世紀の、ものすごく大雑把な意味での擬古典主義風の三曲のプロ、ともいえるのかも。
といってもラフマニノフは別にバロック風を意識していないのだろうが、舞曲という点でなんとなくつながる。ロシア時代にバレエ音楽を書かなかった作曲家が、欧米のバレエ~ダンスの隆盛のなかで、アメリカで生涯最後に書いた作品。「ラフマニノフは亡命して帰らなかったが、プロコフィエフは帰った」とも、テミルカーノフは言っていた。
それにしても交響曲第二番ばかり聴いていた耳には、ラフマニノフのオーケストレーションの進歩に驚かされる。交響曲第二番は日本フィルで聴いたグラズノフの八番とほぼ同時期の作曲で、語法としても似ていたのに、それから三十三年たって、はるかに多種多彩な響きと動きに変わっている。
第一次世界大戦と革命をへて、西側に出てきたラフマニノフが体験したのは、自動車と飛行機が大衆化され、劇映画が大発展してトーキーになり、さらにカラーになりつつあり、ラジオ放送が出現して家庭生活のなかに入り込んでいく、三十年間だった。
そのなかでオーケストラの響きも演奏技術も大進歩した。その象徴がアメリカの三大オーケストラ。ラフマニノフはまさにそのサウンドのために書いたのだということを実感。
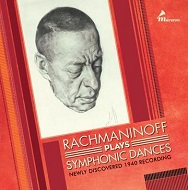
家に帰って、入手しながら聴いていなかったマーストンの新譜、「ラフマニノフ、交響的舞曲をひく」を聴く。時間がとれなかったせいもあるが、ナマで聴いてからにしたいというのも、ここまで聴かなかった理由の一つ。
ラフマニノフが一九四〇年十二月二十一日に、十二日後の初演の指揮者オーマンディのためにひいてみせたというビアノ版の録音、欠落もあるが、響きも音楽もスケールが大きい。広くて深い。さすがとしかいいようがないし、昔の自作ではなく、いま頭の中にある新作を音にしているというのは、自作自演のなかでもとりわけ意味深いものだろう。
これは、三枚組の一枚目の最初に作品の順序通りに編集したもの、三枚目の最後に無編集でひいたままに収録したものと二種が入っているが、興に乗ってひきまくっていくような後者の方が、話し声などのノイズも含めてライヴな感じで、面白い。
ラフマニノフのRCAの正規録音は、正直にいって生気に欠け、あまり面白くない。何か抑圧感がある。ラジオを拒んだことが示すように、時空を超えるものに対しては心を許せなかったのだろう。
ところがここでは、霊感が湧きでるようで、大きくうねりながら各部が自然につながって呼応しあい、変化しながら流れていく感興が素晴らしい。本人のなかに滞留していたマグマが噴き出してくるかのようだ。気のおけない、親密な環境でのびのびと、躊躇なくひいている。公衆の前、マイクの前では、おそらく決して見せなかった顔。「ゲーテとの対話」のピアノ版という趣きさえある。
無編集版の、一楽章四十八小節から始まって二百六十三小節まで行って中断、三楽章に移って八小節目から二百十四小節までで録音が消え、二楽章に戻って全部ひき(百七十七小節から百八十二小節途中まで録音欠落)、最後に一楽章冒頭を四十一小節までひくという流れが妙に自然に感じられるのも、録音の前後や途中にどれくらいの「演奏はしたが録音なし」があるのかはわからないが、作曲者=演奏者の感興と思考の赴くさまがそのままとらえられているからだろう。
曲順通りの編集版とそうでない無編集版、両方をディスクにいれたマーストンのセンスは、さすが。
一枚目にはそれに続いてミトロプーロス指揮のニューヨーク・フィルによる、この曲の一九四二年十二月二十日のライヴが入っている。これがまた素晴らしい演奏。リズムが息づいてうねり、艶やかで官能的。
アメリカのオーケストラの最良の特性が発揮されているというだけでなく、重要なのは、まさにこうした、妖しいまでに美麗なサウンドのためにラフマニノフはこの曲を書いたのだということを、痛感させてくれること(ラフマニノフ自身の演奏を聴いた直後だけに、いっそう納得させられる)。色と空気を再現する、マーストンの復刻がまた圧倒的な出来。
名曲がこの世に生れ出る、その瞬間の作曲者と再現者の共通理解、時代と場所の空気がとらえられているという点で、このアルバムの価値ははかりしれない。
感慨深いのは、このニューヨーク・フィルの演奏会の場に、ラフマニノフ本人が臨席していること。そしてさらに面白いのは、十二月の十七、十八、二十日と三日間カーネギー・ホールで行なわれたこのときの定期を調べると、最初の二日間は自らパガニーニ狂詩曲の独奏で出演したのに、ラジオ中継のあるこの三日目にかぎって出演しなかったこと。
初めからラジオでの演奏を拒んでいたために、その貴重な演奏が録音されることはなかったのだ(二十日だけ、クシェネクの変奏曲に差し替えた模様)。
ところで本人演奏のカーネギー・ホールでのパガニーニ狂詩曲と読んで思い出したが、これはジョン・カルショーが自伝で述べていた、イギリス海軍に入隊してアメリカで訓練を受けていたとき、憧れのラフマニノフをナマで聴けるとチケットを買ってこの日を楽しみにしていたら、直前に転属命令が出てしまい、ついに聴けなかったという、まさにそのときの演奏会でもあるのだった(こういう発見はほんと、あなたはこんなところにいたのかという、司馬遼太郎いうところの歴史の快感)。
もう一つミトロプーロスの指揮で入っている、一九四一年十二月二十一日の交響曲第三番のときも、十八、十九日の定期ではなんと自作のビアノ協奏曲第二番のソリストとして出演していたのに、二十一日はやはり出演しないで、ダイアモンドの交響曲第一番が代りに演奏され、放送されている(ミトロプーロスが嫌がらせみたいに正体不明の新作にいちいち変えるのが愉しい。この頃はまだ一介の客演指揮者にすぎないのだが)。
そのほか、舞台袖で盗み録りしたみたいな、ベル研究所による一九三一年録音のあまりにもひどい音とか、面白いものばかりだけれど、これらは私より詳しい人がきちんと書いてくれるだろうから、以下省略。
十一月二十三日(金)桂諷會の能(前)
国立能楽堂で第十一回桂諷會を観る。観世流銕仙会所属のシテ方長山桂三が、毎年十一月下旬に行うこの自主公演に来るのは早三回目。
今年は独立十五周年記念の拡大版で、三代能。すなわち父の禮三郎と子息の凜三を加えて、一番ずつ能を舞う。七十五歳と四十三歳、そして十三歳と、三世代それぞれの芸を楽しめるもの。
三役の顔ぶれも壮観。ワキ方は宝生流が、狂言方は大蔵流山本東次郎家が固めて、囃子方も小鼓の大倉源次郎など名手揃い。地頭も浅見真州、山本順之、野村四郎と、観世寿夫の薫陶を受けた銕仙会の重鎮が交代でつとめる。
さらに今日は、全員が肩衣をつけた裃姿。九月の国立能楽堂開場記念公演もそうだったが、肩衣だと舞台にいっそうの気合が込められた雰囲気になる。
・能『花月』長山凜三
・狂言『成上り』山本東次郎
・能『羽衣 彩色之伝』長山禮三郎
・能『道成寺 赤頭・中之段数躙・無躙之崩』長山桂三


まず仕舞二番。桂三の兄、長山耕三の『嵐山』と銕之丞の嗣子、観世淳夫による『田村』キリ。この『田村』から『花月』、狂言『成上』までは、すべて清水寺を舞台とする一貫性がある。
さてその『花月』。かげつと表記するが、能では最後のつを呑みこんではっきりと発音せず、「かげ」と「かげっ」の中間くらいに聞こえる。花月とはシテが演じる少年の名前。
ワキ(殿田謙吉)は、九州筑紫の彦山(英彦山)の麓に住む僧。元は在俗だったが、七歳の息子がある日行方不明となり、それを契機に出家した。親も子もない無住漂泊の旅を続けて、行き着いたのが京の清水寺。
清水寺門前ノ者(アイ:山本凜太郎)に、何か面白いものはないかとたずねると、門前ノ者は花月という喝食が面白い芸を見せるという。花月が登場して名乗り、小歌を謡い、舞う。その姿を見た僧は自分の子ではないかと思い、過去をたずねると、七つの年に彦山に登ったときに天狗にさらわれ、諸国をめぐってきたという。二人の顔を見比べた門前ノ者も「瓜を二つに割った」ようにそっくりだといい、親子は再会を果たす。
羯鼓を叩きながら、天狗に連れられて眺めた山々の悲しい日々を回想し、僧と出会った喜びを謡った花月は、手にしたささらを棄て、連れだって修行の旅に出る、という話。
芸づくしものとしては、先月十九日の『自然居士』と共通し、親子再会ものとしては七日の『三井寺』と同じジャンルに属している。短く明朗な作品なので若手が演じることも多く、長山桂三が初めてシテを演じたのもこの能で、思い入れがあるという。だからこそ、十三歳の凜三には「時期尚早かとも思いましたが」選曲したという。
そのときの写真もプログラムに載っているが、桂三は通例どおり、美少年を表す「喝食」の面をつけている。これは先月十六日の「青翔会」で観た柏崎真由子(金春流)も同様だった。
しかし能では、十代の少年がシテを演じるときには、原則として面をつけずに直面(ひためん)でやる。凜三もそうしていて、実はこれこそ今日を楽しみにした理由の一つなのだった。


公演プログラムから フェイスブックの「世田谷 長山能舞台 『桂諷會』長山桂三」のページから。(撮影:駒井壮介)
面をつけることで、自己と異なる存在(年齢、性別、生死や人間の境を超え)になりきるのが能の魅力だが、少年が素顔で少年を演じる、まさに「時分の花」が咲くのにまかせた能、「幽玄の本風」の能も、一度は観たかったのだ。単なる事実と演劇的迫真性が別のものであることはいうまでもないが、といって、両者はけっして重ならないわけではない。
軽快な手の動きと足さばき、涼やかな表情。美声が長所(やけくそ気味に調子っぱずれに声を張りあげる子方も少なくないのだ)の凜三だが、声変りが始まっているのか、さすがにシテとなると負担が大きいのか、謡は大変そうだったが、颯々とした印象には、原初の猿楽の持つ魅力の一端が現れていると思えた。
先月十六日の金春流の『花月』では、門前ノ者が花月を紹介するときに「自然居士の弟子」と言っていたのだが、観世流ではこの詞がない。しかし花月が雲居寺から清水寺に来たという詞は共通していて、ともに「喝食」の面の美少年による芸づくしであることといい、自然居士と花月の相似点は多い。天狗にさらわれた花月を救ったのは自然居士なのかも、などという想像もできる。
この能の詞章には暗示的な要素が多々あって、花月と門前ノ者のやりとりには同性愛的関係が匂わされているとか、天狗との山行を回想する最後の謡いは、悪山伏にさらわれて慰み者とされ、日本各地の山々で体験してきた陰惨な過去を仄めかしているという解釈もある。堂本正樹の『男色演劇史』でそれは読めるし、シテ方のサイトにもそれに触れたものがあるようだ。
中世の暗部というべきそれは、しかし詞の裏の、能の影の部分。能舞台で目の当たりにする快活な謡と舞の光と一対をなして、味わいを深くしている。
来年二月には八十二歳の野村四郎が、八十一歳の山本東次郎を門前ノ者として『花月』を銕仙会でやるそうなので、これもぜひ観にいきたい。
狂言『成上り』は山本東次郎がシテ、アドに山本泰太郎と山本則俊。東次郎と則俊の兄弟共演に接するのは、二〇一六年三月の『附子』と一八年六月の『蜘盗人』に続いて三回目。
にわかに能楽に興味がわき、生れて初めて国立能楽堂の定期公演のチケットを買い、まったくわからないままに最初に観たのが『附子』だった。息のあったベテラン二人の快演が、慣れない空間での不安半分の気持を吹き飛ばしてくれた。そして昨年の蝋燭能での『蜘盗人』は、これまでの能楽堂体験で、最も忘れがたい感動を与えてくれたものの一つ。
『成上り』では則俊の登場部分はわずかで、居眠りする東次郎から刀を盗んでいくだけ。言葉は交わさないのだが、動きだけでやはり絶妙の呼吸。この二人の狂言には、人間が人間としてこの世にあることの喜びがつまっていると思う。いま、自分ができるかぎりナマで見ておきたいと思っているもの。なので、今日はそれだけでも嬉しい。
続いて桂三の父禮三郎の『羽衣』。頭に白蓮の飾りをいただき、さらに特別のものというだけあって、月光のように輝く美しい装束。『花月』の若さの舞とは対照的な、ゆったりとした時間。
 フェイスブックの「世田谷 長山能舞台 『桂諷會』長山桂三」のページから。(撮影:駒井壮介)
フェイスブックの「世田谷 長山能舞台 『桂諷會』長山桂三」のページから。(撮影:駒井壮介)『花月』と続けて観てみて面白かったのは、結びの視点の交錯。『羽衣』の有名な末尾は、天女が橋懸で舞いつつ、
「天の羽衣。浦風にたなびきたなびく。三保乃松原浮島が雲の。愛鷹山や富士の高嶺。かすかになりて、天つ御空の、霞に紛れて、失せにけり」
三保の松原の上の雲から愛鷹山、富士山へと、天女の舞う姿が高く遠くなっていき、やがて人の目には見えなくなる。これに対して『花月』の結びは、
「山上大峰釈迦の嶽。富士の高嶺にあがりつつ、雲に起き臥す時もあり。かやうに狂ひめぐり心乱るるこのささら。さらさらさらさらとすつては謡ひ舞うては数へ。山々嶺々里々をめぐりめぐりてあの僧に、逢ひ奉る嬉しさよ」
天狗と空を飛んで富士の頂上にまで行き、雲上に生活することもあった。狂いめぐって心乱れて、ささらをする。
下界を見下ろす人外の視点と、浜辺から富士を仰ぐ人間の視点の交錯。天を翔ける魔人の陶酔と、地に暮らす凡人の幸福。
三十分休憩の後、仕舞二番。野村四郎の『砧 後』と観世銕之丞の『船橋』。前者の『砧』は九月の国立能楽堂開場記念公演で素晴らしい演能を観たばかりなので、面と装束をつけないとこんな感じになるのかとまた納得。仕舞はやはり、元の能を一度でも観ているかどうかで、私のような素人の場合は理解度に大きく差が出る。
十一月二十三日(金)桂諷會の能(後)
いよいよ『道成寺』。
この能は宝生流、喜多流、準じるものとして黒川能の『鐘巻』を観ているが、観世流は初めて。
これまでの印象では、作り物の鐘は、重い方が舞台に緊張感、緊迫感があっていいと思う。各流で最も重いといわれる宝生流の九十キロの鐘は、狂言方がつとめる狂言鐘後見が四人がかり(鐘の竜頭の穴に通した太い竹竿を四人で担ぐ)で運んできて、いかにも重そうな綱を上方の滑車にかけて吊り上げたときから、何ともただならぬ空気が舞台を支配した。
それに比べ、二人でそれほどの苦労もなさそうに運んできた喜多流と黒川能の鐘は、いかに能では想像力が大事といっても、その想像力の翼をはためかせるためのきっかけ、そのものが失われているように感じてしまった(喜多流ではアイ二人が重い重いと演技しながら運んでくるのだけれど、そうは見えなかった)。
観世流の鐘は、二人で担いでいるから宝生流よりは軽そうだが、喜多流よりはるかに重いらしいことは、担ぎ手の本当につらそうな表情からわかる(一切演技ではない)。吊り綱も重そうで、これをけっして若くない(婉曲表現)山本東次郎と則俊が滑車に通し、シテ方の鐘後見が渾身の力で吊り上げる。
この、しなくてもよさそうな危険をあえてやるからこそ、『道成寺』の舞台はシテを中心に全員が生命を懸けているような、非日常の空間となっていくのだと思う。『三井寺』の遠い鐘楼ではない、生々しく人にのしかかり、禍々しくも見つめずにはいられない、巨大な鐘。
いよいよ始まり。シテ方にとっては通例三十代半ばで『道成寺』を披く(初演する)ことが一人前の証明、通過儀礼となるそうだが、大変なものだけに再演の機会はなかなか得られないらしい。長山桂三も九年ぶりの再演とある。
揚げ幕が上がって少し間をあけて、静かに緊張感をはらんでいた囃子がわずかの間だけ騒がしくなり、まるで森がザワザワと風で騒いだ、川面の波がザザと騒いだ、そんな瞬間にトトトトッ、と白拍子の女が橋懸に入っている。
このとき、我々は舞台のアイ(能力)と視点を共有している。視界の端に小さく、しかし明らかに不吉な存在がいつのまにか入っているような、そんな感覚。だんだん近づいてくる。


フェイスブックの「世田谷 長山能舞台 『桂諷會』長山桂三」のページから。(撮影:駒井壮介)
催眠術にかかったように、あっけなくアイは白拍子を鐘に近づけてしまう。
乱拍子。ここは何度観ても聴いても、こんなものを考えついた作者(不明)は本当に凄い。無音の緊張、それを破る裂帛の気合と足拍子だけの十五分間。速度を速め、溜めに溜めたエネルギーを一気に開放する急の舞から、鐘入りへ。降りてくる鐘に向かって上へ跳ねるという、きわめて危険な動きが見事に決まる。
今回の小書は「赤頭」のほかに「中之段数躙(なかのだん・かずびょうし)・無躙之崩(ひょうしなしのくずし)」。ネットでみるとあとの二種は乱拍子の踏み方の変化らしいが、私のような初心者にはもちろん判別できない。
しかし赤頭はわかる。鐘の中で蛇身に変じたとき、赤髪の鬘をかぶるのだ。通常だと黒髪のままで、まだ女性の思いが残っているように感じられるのだが、赤頭だと完全に怪物化した印象になる。白拍子のときの装束も、九年前の披きのときとは違っていた。前回は若い娘で、今回の方が臈長けているような感じ、ということか(違うかも知れない)。
人の執心、その醜さと凄まじさ。そのあらわれである蛇体。その姿をどうとらえるか、解釈するかは、観るたびに、考えるたびに変わるだろう。その奥行きが能の面白さ。


フェイスブックの「世田谷 長山能舞台 『桂諷會』長山桂三」のページから。(撮影:駒井壮介)
十三時から十八時過ぎまで、五時間超の長丁場ながら、飽きることなく楽しんだ。桂諷會、来年は桂三の『屋島』と凜三の『菊慈童』の予定だとか。これも今から楽しみ。
それにしても能には、舞台芸術としては異例の六百五十年もの歳月を生き抜いてきた凄味がある。年とともに錆びついた自分の好奇心や想像力の刃を、研ぎなおしてくれるような興奮に出会えるが、同時に自分の人生経験と知識の深浅が露わになる恐さもある。面白くて、語らずにはいられないけれど、恐いもの。
十一月二十五日(日)国民楽派を笑え
この一週間の演奏会。
十九日と二十四日はサントリーホールでウィーン・フィル。初日は楽員たちによる室内楽スペシャル「ウィーン・フィル オペラを謳う」。二十四日はウェルザー=メスト指揮でドヴォルジャーク、ブラームス、ワーグナー。

演奏の感想云々の前に、初日は交代しながら五十人くらいの楽員が登場したのに、女性はハープひとりだけという、現代まれに見る頑なさに驚く。二十四日に見ても、フルートとオーボエの二番、十六型のヴァイオリン群の最後列に、申し訳程度に数人いるだけ。
このことが象徴するわけではないが、音色と音響、指揮者との関係など、「ウィーン・フィル」は、二十世紀に発展・確立されたシンフォニー・オーケストラというシステム(同じメストの指揮で六月に聴いたクリーヴランド管弦楽団を一つの典型として)とは、まるで異質の音楽集団であり続ける楽団だという思いを、いっそう強くする。これは来年一月からの朝日カルチャーセンターの講座に向け、実感として大いに参考になる。

二十日はみなとみらいホールでバッティストーニ指揮東京フィルによる「魅惑のオペラ・アリア・コンサート」。ヴェルディ、プッチーニ、チレア、マスカーニ、(アンコールの)ロッシーニと並ぶなかで、この指揮者とプッチーニとの格別の相性のよさを感じる。ただ、この人を聴き始めたころに感じた、世阿弥いうところの「離見の見」の凄味、自分の背中を自分で見ているかのようなコントロール能力の凄味は、薄まってきているような。

二十二日は浜離宮朝日ホールで、サヴァールとエスペリオンXXI。十六世紀スペインの王カルロス五世とフェリペ二世、ドン・カルロスの祖父と父の時代の音楽。これは掛け値なしに素晴らしい。歌なしの五人の器楽アンサンブルで、まったく飽きさせない深さと広がり、芳醇さ。リズムの反復の中から浮かびあがる短い旋律の多彩さにおいて、九月に聴いたカニサレス率いるフラメンコ・クインテットともどこか似ていた。手間のかかる、面倒な五百年前の楽器をあえて用いるからこその、酔狂が放つ魅力。
ウィーン・フィルとはまた違った形での、グローバリズムへの異見表明としてのヨーロッパの古楽運動。そのなかでグリーンスリーヴズをあえてやっているのが面白かった。この旋律、実はイギリス起源ではなく、その前はフランス、その前はイタリア、さらに大元はイベリア半島のものなのだそう。
そして今日はNHKホールで、広上淳一指揮NHK交響楽団の演奏会。
・バーバー:シェリーによる一場面のための音楽
・コープランド:オルガンと管弦楽のための交響曲(鈴木優人独奏)
・アイヴズ:交響曲第二番
外来オケでは不可能な、定期ならではの、広上ならではのアメリカン・プログラム(会場に来るまでプーランクのオルガン、弦楽とティンパニの協奏曲だと思い込んでいたのは、ひみつ)。
一九三三年初演のバーバーのベタベタにロマンティックな陶酔的旋律美に始まり、一九二五年初演のコープランド、一九〇二年完成、一九五一年初演のアイヴズへと、時代を遡るにしたがって音楽がサイケデリックになっていく面白さ。
コープランドは、オルガンがなんともサイケ。ビャー、ビャーと鳴りまくる。サントリーホールや東京芸術劇場と違って、パイプオルガンが上手の壁面上方にあってオーケストラと響きが完全に分離するから、面白さがきわだったのかも。ここは鍵盤だけを分割して舞台に置くこともできるはずだが、演奏者と楽器の響きは離れないほうが自然だろう。
さらに面白かったのは、アンコールにひかれたバッハの《目を覚ませと呼ぶ声が聞こえ》のほうが、オルガンという楽器の多彩なサウンドの可能性をはるかに活かしていたこと。コープランドはとにかく力任せで、パワー・ビッグスとかしか思いださなかった(笑)。
なおコープランドは四年後にこの曲からオルガン・パートを抜いて、交響曲第一番に改作したという。アメリカのオーケストラホールでオルガンがあるところが限られていたからだろうが、あまり面白くなさそう。しかしその交響曲第一番を、オリジナルのオルガンの初演者であるナディア・ブーランジェに、お詫びのように献呈しているというのは面白い。
そしてアイヴズ。LP時代からファーバーマン指揮の交響曲全集などで愛聴してきた曲とはいえ(ファーバーマンの少しどんくさい演奏がこの曲にはすごく合っていた)、実演で聴くのは生れて初めて。ホルンが四人指定されている以外はオーソドックスな二管編成で、三人いるトロンボーンもほとんどは二人だけ、テューバや大太鼓、小太鼓は終楽章にわずかに参加するだけという、とてもシンプルな響きだったりすることは、ナマでこそよくわかる。
独特なのはメロディへの感覚。冒頭、まるでメロディの後半のフレーズだけを演奏しているみたいに唐突に鳴り出させ、それでポリフォニーを形成してしまえるあたりが、この人の才能。《コロンビア、大洋の宝》から《草競馬》まで、さまざまなホピュラー曲を引用するのだけれど、メロディまでいかないような、音形やフレーズの断片が多い。バーバーの長く引っぱった旋律とは好対照。
まあとにかく独創的な才能の持ち主だけれど、この人の交響曲についての原イメージは、チャイコフスキーやドヴォルザークの「国民楽派」のそれにあるのだな、というのは強く感じた。チャイコフスキーがカーネギー・ホールのこけら落としを指揮したのが一八九一年、ドヴォルザークがニューヨークの音楽院の院長になるのが翌年。
アイヴズがこの曲に着手するのは一八九七年で、当時のアメリカでは土くさく民謡的な旋律をこれ見よがしにたっぷりと歌い、金管が輝かしくも煽情的にファンファーレを奏で、ティンパニがドカンと決める国民楽派の交響曲が、大流行していたに違いない。《新世界より》なんて、同時代のアメリカ人には嬉しくてたまらない交響曲だったろう。
この交響曲はそれらへの、それらを大喜びで聴いている聴衆への、パロディのように思えた。編成もこれらの作品とほとんど同じ。イヤミが露骨すぎるのは、二十代の若書きだからだろう。どこかで聞いたような音形が頻出し、しかしたっぷりとは味わえないうちに消え、ファンファーレが響きわたりそうになると断ち切られる。最後くらいはすなおに盛りあげるのかと思ったら、あの終止(笑)。
十一月二十八日(水)中折れ帽の時代
サントリーホールで、読売日本交響楽団の定期演奏会。指揮はデニス・ラッセル・デイヴィス。
・スクロヴァチェフスキ:ミュージック・アット・ナイト
・モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲(フルート:エマニュエル・パユ、ハープ:マリー=ピエール・ラングラメ)
・アダムズ:シティ・ノワール

二十世紀の夜をイメージさせる二曲のあいだにモーツァルト。とくればセレナードがよさそうなのに、なぜかフルートとハープのための協奏曲。
よくわからないが、ともあれメインのアダムズの《シティ・ノワール》がききものだった。題材にしたのは一九四七年頃のロサンジェルス。スクロヴァチェフスキのミュージック・アット・ナイトはまさにその時代、一九四九年にパリで初版が書かれた音楽だが、アダムズのは六十年ほど後に、ドゥダメルのロス・フィル音楽監督就任を記念して二〇〇九年に書かれたもの。
戦争が終って平和と繁栄を謳歌し、東西冷戦もまだ表面化していない時代のアメリカ。しかし戦場帰りの若い世代は暗い衝動を抱え、不安と焦燥を隠し、犯罪も多発する。そんな街の夜の官能、というところか。サックスとパーカッションが活躍し、全編にジャズのムードがただよい、モノクロのフィルム・ノワールの世界のようで、最後はサルサのリズムで熱狂する。
ジャズ、映画(暗黒街もの)、ラテン音楽とくれば、一九三〇~四〇年代のアメリカを象徴するもの。ロックンロールが隆盛する直前、最後のロックなしの時代の音楽。いいかえれば十代の若者という新しい巨大な消費層が隆起する直前、アダルトな世界の終りへのオマージュ。紫煙ただよう酒場、男性が中折れ帽をかぶり、スーツとトレンチを着て歩いていた時代へのオマージュ。
アダムズは一九四七年生まれだから、幼時に少しだけ雰囲気を知っている、というところか。自分はやったことがないのだが、この曲と同時期につくられて二〇一一年に発売されたテレビゲーム『L.A.ノワール』は、やはり一九四七年のロスを舞台にした、警官が主人公の犯罪物で、映画のように美麗なグラフィックスで当時を再現していることで話題になった。十年前ほどのアメリカには、なにか懐古的な気分があったのだろうか。
ドゥダメルという、現代アメリカにおけるヒスパニック社会の影響力を象徴するような人物のために、こういう懐かしきアメリカを追想するような音楽を書いた、というのが面白い。一方で、ラヴェルが、自分は見たこともない一八五五年のウィーン宮廷の舞踏会を幻視して書いた《ラ・ヴァルス》に通じるものがあるような気もする。
日本のオケにとっては演奏機会の少ないタイプの音楽だからか、演奏は初めこそまとまりがなく雑然とした感じだったが、途中から調子が出てきて、最後は大きく盛りあがった。
《シティ・ノワール》のことを考えていると、バーンスタインの《ウエスト・サイド物語》に思いがいく。
ジャズとラテンの効果的な使用という点で、《ウエスト・サイド物語》は《シティ・ノワール》の先祖みたいなもの。しかし扱っている時代は十年後にずれて一九五七年、主人公もアダルトではなく十代の少年たち。
だがこのズレにこそ《ウエスト・サイド物語》がヒットする要因があったのかも、と考えてみる。
この時期の少年なら、むしろぴったりなのは一九五五年の映画『暴力教室』の主題歌、ビル・ヘイリーの《ロック・アラウンド・ザ・クロック》みたいな音楽だろう。しかしバーンスタインはそれより少し前の一九三〇~四〇年代、自分が思春期~青春期を過ごした時代に興隆したジャズとラテンをもってきた。
これらは、ミュージカルではまだあまり多用されていなかったもの(前例はあるにしても大ヒットはしていない)。オペレッタの延長にあるロジャース&ハマースタインの優美な音楽が主流だった時代に、バーンスタインはそれを持ち込んで革命的成功をするけれども、本当のティーンの音楽であるロックンロールまでは進まなかった。たぶん、この時点でそれをやっても革新的すぎて、聴衆は受けいれなかったろう。流行には少し遅れているけれどもミュージカルではまだやっていない、「半歩だけ進んだ」音楽だったからこそ、そこに架け橋をかけたからこそ、バーンスタインは偉大なのかも。
そういえば《ウエスト・サイド物語》の原型の「イースト・サイド物語」をジェローム・ロビンズが思いついてバーンスタインたちに最初に話を持ちかけたのは、一九四〇年代後半だったはず。
そのときはアイリッシュとユダヤの移民間の対立劇(ケネディとバーンスタインの出来の悪い親戚がケンカするような話)で、しかも大人を含めた対立劇(シェークスピアそのまま)だった。まだアダルト主流の時代。父祖の音楽としてのアイルランド民謡とユダヤ聖歌、現代の音楽としてジャズとラテンが混じる、なんて音楽だったのだろうか。
実際の制作までに時間がかかっているうちに不良少年問題が表面化し、豊かな社会の中でティーン層という、情熱的で巨大な消費集団が出現する。プエルトリカンの問題も出てくる。そこに登場人物を集約させるという、天才的転換。しかし音楽はそこまで進ませなかった。その絶妙のバランス。
ロックンロール以降はなちよりも電気楽器、というのがクラシックのオーケストラになじみにくい難しさか。バーンスタインもアダムズもそこを心得て、「一九四七年」で止めているのかも。
すると、その先へ進もうとしたバーンスタインの《ミサ》は…、ということになってくるが、それはまたいずれ。
十一月三十日(金)稚児のために
国立能楽堂で、一年半ぶりの蝋燭能。野外の薪能だと、外は暗くても舞台内は明るく照明がついていることが多いけれど、これは本当に蝋燭の灯だけにして、舞台が薄暗いのが特徴。


・狂言『石神(いしがみ)』茂山忠三郎(大蔵流)
・能『調伏曽我(ちょうぶくそが)』大坪喜美雄(宝生流)
前回の狂言『蜘盗人』と能『融』が、本当に「中世の夜」の幻影が目の前にあるみたいな、あまりにも素晴らしいものだっただけに、今回はちょっと期待が大きすぎたか、楽しみきれず残念。英語版のポスターみたいな、密教的鬼気(不動明王だけど)を期待したが…。
調伏、禅師、小袖、夜討と四番ある曽我兄弟ものの能の一つ。弟の五郎が箱王と呼ばれる、箱根権現の別当の稚児だった時代を扱っていて、子方が箱王を演じる。仇の工藤祐経(前シテ)を襲おうとする箱王を別当(ワキ)が押しとどめ、箱王のために悪魔降伏の祈祷をしてやると、不動明王(後シテ)が現れて祐経の形代の首を切り、本願成就が約束されるという話。仇討という、中世から近世までの日本の物語の根幹をなす要素があるとはいえ、そのために調伏をしてもらえるくらいに、稚児は師の別当から大切に扱われている。ここにも稚児崇拝。
前場に出る頼朝の家臣が五人、後場の別当の従僧も五人。いうまでもなく元々は同じ役者が装束だけ変えて出るようになっていたのだろうが、シテ方とワキ方が厳格に区別された徳川幕府以来、現在では五人ずつ必要になる。封建制の身分固定は安定を生むが、無駄も増やす。こういうことが上演を難しくする上に、しかも大勢力を持つ観世流では廃曲となっていて、他の四流にしかない。珍しい作品をみられたのはよかった。
ところで能の前半、橋懸の上で子方と謡い交わしていたシテが絶句、つまり詞を忘れてつまったのはドッキリ。
後見が詞の頭の句を口にして助け船を出すが、三回ほど繰り返されても、気まずい沈黙。橋懸の上は後見の位置からだと見えないので、身を乗り出して覗き込んだところで、ようやく復帰した。
身を乗り出した後見は子方のお父さんらしい。何が起きているのか、心配だったことだろう。子方のかれは動揺なく、しっかりとその後も役を務めていたが。絶句は自分が観た範囲では、同じように前半の少し過ぎたぐらいのところで起きることが多い。集中がゆるみやすいところなのか。
十二月一日(土)指揮者なし
晴海の第一生命ホールで、「トリトン晴れた海のオーケストラ」によるベートーヴェン・チクルスⅡ、交響曲第二番と第五番を聴く。
コンサートマスターの矢部達哉を中心に、都響をはじめとする名手が集う、六‐五‐四‐三‐二の室内オーケストラ。互いの音を聴きあい、反応する面白さ。筋肉質の、活力に満ちた音楽。なかでも第五番は、演奏経験を各自が積んでいるからか、思いきった動きが面白かった。
十二月五日(水)見立ての快感

午後一時から国立能楽堂で能楽。
・狂言『文蔵(ぶんぞう)』茂山千三郎(大蔵流)
・能『芭蕉(ばしょう)』大槻文藏(観世流)
狂言が『文蔵』なのは、能のシテが大槻文藏だからなのだろうか(笑)。国立能楽堂近くの飲み屋に「文蔵」というのがあることを思い出す。
金春禅竹作の『芭蕉』は、禅竹の特色があらゆる面で発揮されている曲。芭蕉の精が女人の姿で僧の前に現れ、草木国土悉皆成仏や女人成仏など、法華経の思想をきわめて難解な詞章で謡う。
大槻文藏の舞う姿、居ずまいはいつもながらに美しく、芭蕉の葉を想わせる緑の装束とあわせて見ほれ、独特の枯れた声の色気に聴きほれるが、作品そのものはあまりに長大で深遠すぎて、自分が楽しめるようになるにはまだまだ時間がかかりそう。植物の精が女で、それが僧に近づくという、禅竹独特の湿り気のある艶っぽさは面白いのだが…。
禅竹が公家や僧など、同時代の最高級のインテリに囲まれていて、かれらに向けて書いた能なのだろうな、ということは、ひとまずよくわかった。

夜は紀尾井ホールで「紀尾井ホール室内管弦楽団によるアンサンブルコンサート3 バラホフスキーとともにバイエルン放送交響楽団の名手たちを迎えてブルックナー交響曲第七番(室内楽版)」
・マーラー(シェーンベルク編曲):さすらう若人の歌(バリトン:萩原潤)
・ブルックナー(アイスラー、シュタイン、ランクル編曲):交響曲第七番
アントン・バラホフスキー、ダフィト・ファン・ダイク(ヴァイオリン)、ベン・ヘイムズ(ヴィオラ)、伊東裕(チェロ)、吉田秀(コントラバス)、野口みお(フルート)、金子平(クラリネット)、カーステン・ダフィン(ホルン)、武藤 厚志(打楽器)、西沢央子(ハルモニウム)、北村朋幹、中桐 望(ピアノ)
シェーンベルクの私的演奏協会のために、室内アンサンブル用に編曲された二曲。マーラーはシェーンベルク自身がやり、ブルックナーは三人の弟子が分担。
紀尾井ホール室内管は二〇一六年にもマーラーの交響曲第四番とウィンナ・ワルツ二曲の私的演奏協会版を演奏していて、それも素敵だったが、充実度は今回の、特にブルックナーが上回った(マーラーの歌曲は歌手の音程がぶら下がっていて、合わなかったのが残念)。バイエルン放送交響楽団の四人が加わって、日本の名手たちもそれに引っぱられるように、振幅の大きな表現と立体的で堅固な骨格を聴かせてくれる。一楽章と四楽章の長大な呼吸線によるクライマックスへの長い山登りなど、十一人しかいないとはとても思えない壮大さ。
一人一人の音が聴こえる、いわば「その顔が見える」室内アンサンブルを巨大な交響楽団に見立てるという、その無理が無理でなくなるイリュージョンの快感は、まさに優れた能に似ている。シェーンベルクが一九二〇年代初頭に模索した「室内楽化」の試みが、百年後に花開いているような。
十二月八日(土)音、果しなき流れの
国立歌劇場一月公演のあぜくら会会員向けの売出し日。休日の土曜ということもあって、開場三十五周年記念の『道成寺』は、文字どおりの瞬殺で売り切れ。体調の都合でシテの梅若実は観世銕之丞に交代したが、超豪華メンバーなのは変わらないから、当然か。端に近い席になったが、とにかく買えてよかった。

午後、NHKホールでのヘンゲルブロック指揮N響のバッハ演奏会は、五日の紀尾井ホールとともに、見事な東京勝手にチクルスになるものだった。
しかも、一日のプログラムとしても、ノットかカンブルランかというくらいにコンテクストをよく考えた、知的なゲームのような組み立てだった。
・組曲第四番ニ長調BWⅤ一〇六九
・(シェーンベルク編曲):前奏曲とフーガ 変ホ長調BWV552《聖アン》
・マニフィカト ニ長調 BWV243(クリスマス用挿入曲つき)(合唱:バルタザール・ノイマン合唱団)
まずは十型、ノンヴィブラートによる管弦楽組曲。モダン楽器によるピリオド・スタイル。つまり、大ホールの空間や放送用に求められる安定度に適合する形で、できるだけ作品本来の響きを求めたもの。ノンヴィブラートだとごまかしがきかないので、初めは音程や縦の線のブレとズレが気になったけれど、次第に揃ってくる。
それから、オルガン曲をシェーンベルクが大管弦楽に編曲したもの。十六型でヴィブラートも用いる。十八世紀から二十世紀へのオーケストラの発展がここで示される。同時に、八百席の紀尾井ホールでは、後期ロマン派の肥大した音楽を「茶室化」していたシェーンベルクが、三千八百席のNHKホールでオルガンを大交響楽団に恐竜的に拡大する、ベクトルの逆転も提示される。
前回、同じホールでの広上指揮N響で聴いた、鈴木優人のオルガン・ソロによるバッハの響きがまだ耳に残っているから、脳内で比較するのが愉しい。ストコフスキーの、演奏効果満点の編曲(二年前の四月にスラットキンがここで聴かせてくれた)にくらべると、もっと真面目に、オルガン曲の音の構造を、オーケストラという音響組織(まさしくorgan)に移しかえようとしたもの。地味だけれど凝っていて面白い。
これは私的演奏協会より五、六年後の一九二八年の編曲。その二年前からシェーンベルクは、十二音技法による最初のオーケストラ作品である《管弦楽のための変奏曲》に取りかかり、この年に完成初演させたところだった。この曲ではBACH音型が用いられていて、十二音技法の始まりにあたってシェーンベルクがドイツ音楽の父バッハを意識したことが露わになっている。その流れで生まれたのが、この《聖アン》のオーケストラ編曲。
ここでヘンゲルブロックが、ドイツ音楽史に二百年を隔てて新時代を画した二人、バッハとシェーンベルクを歴史上の二つのポイントに設定して、その流れを考えていることがわかる。ちなみに《管弦楽のための変奏曲》も《聖アン》も、初演したのがフルトヴェングラー指揮ベルリン・フィル(一九二八年と二九年)だというのが、歴史のポイントとしてまた面白い。
(そしてここで、一年前の十月にノット&東響が《管弦楽のための変奏曲》を取りあげ、リスト、ラフマニノフ、ラヴェルという、一見無関係な三人の作品と組み合わせて、蜘蛛の巣のように複雑な、見事なコンテクストを張りめぐらしてくれたことを思い出す。これについては可変日記参照のこと)
休憩をはさんで、オーケストラは最初の折衷式ピリオド・スタイルに戻り、三十人のバルタザール・ノイマン合唱団を加えて、バッハのマニフィカトの「クリスマス用挿入曲つき」。
クリスマスに演奏するために、バッハが四つの曲を加えたものだが、そのうち二つはドイツ語。しかも最初の一つがルター作のコラール《髙き天より》だというのが、バッハよりさらに前のドイツ音楽の原点にルターがいることを示しているようで、それがラテン語のカトリック由来の音楽に入り込む。
合唱が入ったことで、ヘンゲルブロックの音楽のフォルムがしっかりと決まってくる。N響の管楽器のソロも美しく、技量の高さを再確認させられる。
終了後「ヘンゲルブロック氏の希望により、ヨーロッパのクリスマスでの演奏習慣に従い」、バッハの《クリスマス・オラトリオ》から第五十九曲 コラール〈われらはここ馬槽のかたえ、汝がみ側に立つ〉が歌われる。
面白いのは、前半はオーケストラが伴奏していたのに、後半は合唱だけのアカペラになること。バルタザール・ノイマン合唱団がとてもうまくて、響きの純度が高いだけに、これによって、教会音楽家バッハの根っこはやっぱり、無伴奏合唱のポリフォニー音楽なんだろうと実感させる。
しかも、それだけで終らない。ヘンゲルブロックはさらにアンコールをくわえて、『バッハよりシェーンベルヒ』とは逆の、シェーンベルクからバッハへと遡る流れの奥の、さらに源流へと向かってみせる。
それが十五世紀フランスの聖歌〈久しく待ちにし、主よとく来たりて〉(ヒッレルード編)。無伴奏の、澄んだポリフォニーの美しさ。西洋音楽の原点。
ただのバッハ・プログラムに見せかけて、バッハを軸にして西洋音楽六百年の歴史――作品だけでなく、演奏様式まで含めた――を行ったり来たりしながら、二時間で俯瞰してみせるという、壮大な仕掛けなのだった。
自分が音楽を聴き続けるのは、こういう、自在に時空を翔けまわるような精神的冒険に接したいからだと、あらためて思う。しかもそれを、いちいち言葉で説明したりしないのが、ものすごく好き。
つけくわえると、この日の選曲の素晴らしさは、すべてがクリスマスにつながるものから選ばれていること。組曲第四番は、序曲がクリスマス向けのカンタータ百十番《われらの口を笑いで満たし》の第一曲に転用されている。《聖アン》とは聖母マリアの母アンのことで、妊娠の守護者としてのイメージが出産、クリスマスにつながってくる。マニフィカトとアンコールはいうまでもなし。
すべてをクリスマスという、キリスト教世界の原点の中の原点、原点オブ原点に結びつけながら、西洋音楽の歴史を音で俯瞰させる。まことにお見事。
十二月九日(日)俊敏のフィガロ

サントリーホールで、ノット指揮東京交響楽団による《フィガロの結婚》。
素晴らしかった。舞台中央に六‐六‐四‐三‐二のオーケストラを置き、歌手は主に舞台の前縁で歌う。演奏会形式とはいっても、歌手は現代風の衣装を着て舞台公演同様の演技をする。装置としては椅子や洋服掛けなどがわずかに使われるだけ。
恩師の三谷礼二さんが生前、「装置も衣装もなしで、一か月充分に稽古して上演してみたい」と言っていたとおり、このオペラは人間の演技だけによる方が、その本質的な魅力と不朽性が露わになる部分がある。
これはモーツァルトのオペラでも《フィガロの結婚》だけの特質ではないか。あとのオペラはそれぞれに、何らかの視覚的主柱があったほうがいいように思う(ドン・ジョヴァンニならば騎士長の石像、コジならナポリの青い海と空、魔笛となると視覚面のシンボルが多すぎて、演奏会形式など想像もつかない)。
同じホールで二〇〇八年から一〇年まで、ホールオペラとしてルイゾッティの指揮でダ・ポンテ三部作を上演したときも、いちばんよかったのは初年度の《フィガロの結婚》だった。とはいえ、あのときのガブリエーレ・ラヴィアの演出は照明の明暗を効果的に用いて、より舞台公演に近づけていた(第四幕の夜の庭園の簡素で美しい明滅の効果とか、いまも記憶に残っている)が、今回は夜の場面でも照明は明るいままで、すべてを見立てにまかせてくるあたり、より能などに近い。三谷さんが思い描いたものにも近いのかも、などと思いながら楽しむ。
そして、《フィガロの結婚》に端役はいない、という誰かの言葉が今回も心に刻まれる。主役の言葉を受けるだけみたいな相手役、端役はここにはいない。全員がそれぞれの人生を生き、ドラマに関わっている。第一幕の村娘が歌う場面、フィガロがその合唱を指揮していたらバジリオも指揮しだしてフィガロと小競り合いになるとか、なるほどと思った。バジリオは音楽教師なのだ。
そしてそのことを、隅々まで水準の高い歌手陣が証明する。ロッシーニ歌いとして鳴らしたベテランのジェニファー・ラーモアが歯切れのいいイタリア語でマルチェリーナを歌うとか、日本オペラ界の状況としては反則に近い(笑)。
十年前のルイゾッティ公演では期待の若手として見事に伯爵役を歌ったマルクス・ヴェルバが今回はフィガロなのも、感慨深し。
そして、なんといってもノット指揮のオーケストラの見事さ。よく歌いよく弾み、よく跳ねる、生命力に満ちた爽快なモーツァルト。ノットは自らハンマーフリューゲルもひいて大活躍。
同時に、ノットの前任の音楽監督、スダーンが残した財産の大きさを思う。ノンヴィブラート、ビリオド楽器のホルンとトランペットを用いたピリオド・スタイルが、純度の高さと爽やかさを生んでいる。
ピリオド様式の採用はスダーンがいたからこそで、かれが始めたモーツァルト・マチネーにより、いまの東響は在京のオーケストラのなかでも、古典派の演奏に関していちばん豊かな経験をもっている。二十一世紀ヨーロッパの演奏スタイルの潮流をスダーンが導入してくれていたから、ノットがそれを見事に活用できているのだ。
首席指揮者ではない、音楽監督ならではの重み。
十二月十四日(金)大船から池袋まで
今週はしゃべる仕事が続いた。
十一日は大船で、一九一八年徳島の板東俘虜収容所での日本初の第九の話。
映画『バルトの楽園』と加東大介原作の映画『南の島に雪が降る』を一緒に取りあげて、ドイツ人の捕虜が徳島に連れてこられて第九を演奏するのと、ニューギニアに置き捨てられた日本兵が歌舞伎座を作って『瞼の母』を上演し、つくりものの雪を見て涙する話を並べて、望郷の思いの共通点など。つづいて映画『ここに泉あり』の第九の演奏場面を取りあげ、そこでは加東大介がティンパニを叩いているので、話としてはうまくつながったのではないかと思う。
十二日は新宿の朝日カルチャーセンターで、カルロス・クライバーの最終回。「生の横溢」としかいいようがない《こうもり》のドゥイドゥ・ワルツから、最後の正規映像である一九九六年の演奏会まで。
十三日はミュージックバード来年からの新番組「夜ばなし演奏史譚」の二月放送分から二回を収録。英デッカのステレオ録音開始と、一九五五年の「ステレオの旅」。二時間番組の流れをどうつくるか、少しつかめてきた感じ。
十四日は「音楽の友」の恒例企画、コンサート・ベストテンの座談会に初参加。自分の投票した演奏会のいくつかが上位に来ていたので、そうピント外れでもなかったと一安心(笑)。

並行して、夜はコンサート。十二日はオペラシティでパーヴォ指揮ドイツ・カンマーフィル。ヒラリー・ハーンのヴァイオリンは、言葉の真の意味で「親密」としかいいようのないもの。媚びず、声高な自己主張をせず、謙虚に自らを厳しく律し、愛をもってそこにある音楽。クライスラーのヴァイオリンを想起する。パーヴォのグレートは、ブラームスの獰猛さとは異なり、音の減衰を早めに、あくまで古典派的な軽快さをもった響き。スケルツォのトリオの管の歌いくちが素敵だった。
十三日はサントリーホールで、フェドセーエフ&N響の《くるみ割り人形》全曲。ゆったり、たっぷりとした交響詩のような演奏で、夏に聴いたミンコフスキ&都響とはまるで別の作品みたいに聴こえる。どちらにも説得力があるのが、作品の器の大きさか。
十四日は東京芸術劇場でフィルハーモニクス。都合で前半だけ。芸能人との結婚で話題のヴィオラが欠席で六人編成。しかし編曲をどう変えたのか、初めから六人だったみたいに演奏しているのが不思議。べつにヴィオラはいなくてもすむのか。まるで、よくできたヴィオラジョークのような……(あとできいた話によると、メンバーが不眠不休で六人版に編曲したそう)。

『海街diary』の完結編、第九巻「行ってくる」が出ているのを本屋で見つけて、大喜びで買う。本編の結びもよかったが、最後に番外編としてついている、主人公すずの義理の弟、和樹の話がとても印象に残る。
本編よりも何年もあと、すずの父の十三回忌の年の話で、和樹は二十歳の若者になっている。やるせない現実がのしかかるなかにも、瑞々しくきらめく夏の光と水と緑。
すずの父の死で始まる連載の開始が二〇〇六年だったから、この話はまさにそれから十二年後の、現在の話ということになる。そのあいだに本編は二年ぐらいしか進まなかった。作中のキャラの時間と、現実の作者と読者の時間の経過のズレを、一気に解消しているのが素敵。
『海街diary』の世界が一九九五~六年の『ラヴァーズ・キス』から分かれたように、和樹の周囲の人物の物語も、あるいはスピンオフになる可能性がありそうな。
十二月十五日(土)音楽の白亜紀


新国立劇場の《ファルスタッフ》、サントリーホールでノット指揮東京交響楽団演奏会をはしご。どちらも、九日のノットの《フィガロの結婚》の素晴らしい記憶に結びついていく。
《ファルスタッフ》は、それまで屋内で展開されていた欲と誤解のドラマが、終幕についに屋外へ出て、夜の自然のなかで衝突が解消されて宥和し、最後に人間賛歌となる展開がフィガロとそっくりだと、あらためて思う。夜の空気と植物の持つ力。
アルベルト・ゼッダが日本で聴かせてくれたロッシーニ以外のオペラが、やはりこの二本だったことを思い出す。二〇一二年と一五年。どちらも優美で軽やかな響きのなかに豊かなニュアンスが込められた、見事な指揮だった。
ノット&東響はヴァレーズの《アメリカ》とシュトラウスの《英雄の生涯》がメイン。管楽器と打楽器の人数がめったやたらに多く、十六型の弦が舞台からこぼれ落ちんばかり。六型二管編成の《フィガロの結婚》とは、音響もスタイルも極端に対照的。その落差の大きさ。白亜紀の巨大な恐竜を想わせる、洪水のように過剰なサウンド。
十二月十六日(日)年末特番

十一日からのしゃべくり週間の仕上げは、ミュージックバードのザ・クラシック年末恒例、片山杜秀さんとの四時間特別番組の収録。タイトルは「この世はもうじきおしまいだ!?」。
今年は飛び入りゲストに「ハイレゾ・クラシック by e‐onkyo music」でおなじみの原典子さん、アルテス・パブリッシングの木村元さんも登場して、にぎやかに。
放送は二十三日夜八時、平成最後の天皇誕生日。
十二月十八日(火)百川、海に学んで
年が明けて少したつと誕生日が来て、五十六歳になる。山崎五十六。たぶん一生に一度のチャンスだから、来年一年間だけこのペンネームにしようかなどと考えるのは、愚かで楽しい。

夜はトッパンホールで、アンドレアス・シュタイアーのチェンバロ・リサイタル。
バッハの平均律クラヴィーア曲集全曲の演奏会はやるつもりがないというシュタイアーが、そのなかから七曲を選んで(当然のごとく調律は「平均律」ではない)、バッハ以前を中心に七人の作曲家の作品をあわせて演奏し、バッハがさまざまな様式を巧みに採り入れ、創作に結びつけていったことを示す、じつに刺激に満ちた選曲。
「百川、海に学んで海に至る。丘陵は山に学んで山に至らず」なんて言葉を連想する。
バッハがクラヴィーア曲集という四十八曲からなる大河を生むために、どれほど多種多様な河川をそこにひき込んでいるかが、示されていく。他者の作品が流れてくると、続いてそれと共通性をもつバッハの前奏曲が「合流点」として示される。
プログラムに掲載された那須田務さんの解説はその仕掛けを見事に解きあかしていて、大いに参考になる。というか、これを読まずに演奏だけを漫然と聴いていても、ほとんど何もつかめない。
十六世紀イギリスのヴァージナル音楽が、フランドルに移住したジョン・ブルによって大陸に移植される。スウェーリンクがそれを学び、ベームなど北ドイツ・オルガン楽派に伝達し、その弟子であるバッハにつながる。これがバッハへの大きな源流。さらに楽譜やドイツを訪れた楽員などを通して、バッハはフランスとイタリアの音楽を学ぶ。そこには幻想様式や多感様式も混じっている。最後を結ぶ哀歌は、情緒に訴える長い旋律線が、ロマン派音楽を予感させる。
音楽の父ではない、大成者としての、流れゆく大河としてのバッハ。
肝心なのはオルガンではなくチェンバロなど、弦鳴楽器の鍵盤音楽であること。教会で神に捧げるためではなく、家で孤独にひくための音楽。内省の音楽。
イギリスのヴァージナリストに発してスウェーリンクを経てバッハへ、というその流れを思うと、グレン・グールドの名が浮かんでくる。バードやスウェーリンクを音楽史の年表中の人名ではなく、生きた音楽として聴かせてくれたのはまずグールドだった。内省する鍵盤音楽の変遷を見通した、その歴史眼の確かさを思う。それはブラームスをへて、シェーンベルクやベルクへつながっていく。
多彩な情報を、外国に行かずにドイツ語圏内だけで入手して、自らの芸術に結びつけたという点で、バッハは北の辺境にいようとしたグールドの先駆者なのかもしれない。自らは丘陵のように動かないが、情報にメディアを介して来てもらうことで、川をつくる。まさにインターネット時代の情報活用の先駆けとして、バッハもグールドもいる。
シュタイアーの指先から生まれる音楽がもたらす、想像力の飛翔。知的刺激に満ちたコンサート。
すべての全音と半音をとおして ~バッハと先駆者たち~
アンドレアス・シュタイアー(チェンバロ)
プログラム
ジョン・ブル:ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ
幻想様式
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 第7番 変ホ長調 BWV852
ベーム:前奏曲、フーガと後奏曲 ト短調
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866
“イタリア風に…”
ヴィヴァルディ(チェンバロへの編曲:J.S.バッハ):協奏曲 ト短調 BWV975/RV316より〈ジーグ〉
ヴィヴァルディ(チェンバロへの編曲:J.S.バッハ):協奏曲 ト長調 BWV973/RV299より〈ラルゴ〉
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻 第4番 嬰ハ短調 BWV873
半音階的幻想
スウェーリンク:半音階的幻想曲 SwWV258
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻 第20番 イ短調 BWV889
“フランス様式で…”
クープラン:クラヴサン曲集第2巻 第8組曲より〈女流画家〉〈ガヴォット〉
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV882
“その他のギャラントな音楽も…”
W.F.バッハ:12のポロネーズより ヘ長調/へ短調
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881
死を思え
フローベルガー:トッカータ ニ短調 FbWV102/組曲第20番より《瞑想~来るべきわが死を想って》FbWV611a
J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻 第24番 ロ短調 BWV869
十二月二十三日(日)国立演芸場の落語
国立劇場、国立能楽堂に続き、国立演芸場に初見参。隼町の国立劇場の敷地内だがその裏側にあり、永田町駅側に入口がある。近代的なビルだが入口にお囃子が響いて、いかにも寄席な雰囲気。聴くのは落語だけの会。


・十二月特別企画「円丈の『茶の湯』を聴く会」
落語「あま噛み」 三遊亭めぐろ
落語「座席なき戦い」 三遊亭白鳥
落語「首ったけ」 柳家喬太郎
落語「鉄の男」 柳家小ゑん
―仲入り―
落語「つばさ」 林家彦いち
落語「茶の湯」 三遊亭円丈
円丈が古典落語を年末に語るのが国立演芸場の恒例だそうで、還暦の年から十四年続いているそう。十三時に始まって三時間、笑いっぱなしであっという間。
古典二本に新作四本、前の噺家の噺をさっと採り入れるアドリブの上手さ、面白さとか、人前で話す者として大いに参考になる。先頭を切っためぐろが、公演中の楽屋ではテレビを観ているという話をしておいてから、続く五人がテレビを観るどころか、全員が互いの噺をきちんと聴いていることを示すあたり、なるほどという感じ。とにかく、野暮にならないように全員が心がけているのが気持ちよかった。
小ゑんの「鉄の男」はクラシックのライターにもなぜかとても多い鉄ちゃん、鉄道マニアが主人公の噺。
五十分近くかかる「茶の湯」は、随所で円生直伝ということが素人にもよくわかって、楽しかった。
ナマの落語を聴くのは十年ぶりくらいだが、やはりナマでこその魅力がある。これを機に少しずつ通うつもり。
十二月二十五日(水)百五十五+三十八

今年のコンサート納めは、東京芸術劇場でのマッシモ・ザネッティ指揮読売日本交響楽団の「第九」。
いかにもイタリア・オペラの指揮者らしい演奏で、句読点をしっかりつけるドイツ風の論理的演奏ではなく、ダイナミクスの変化などに即興性と流動性を感じさせるもの(もちろん、本当の即興ではない)。
隣席のベテラン同業者の方から、秋山和慶&東京の「第九と四季」にも行きたかったが、チケットが手に入らなかったという話を聞く。一九七八年に始まったこのコンビの最後の演奏で、二回しかないだけに人気爆発だったらしい。東響にはぜひ、四十一回すべての第九を収めたCD四十一枚組を発売してもらいたい。
ところで、「音楽の友」のアンケートのために昨年十二月から今年十一月までに行ったコンサート&オペラを集計したら、百五十五回だった。ほかに能楽に三十八回。今年もよく通った。すべての出演者と関係者に感謝。
十二月二十六日(水)漫才から漫談へ
先日、朝日カルチャーセンターの新宿教室での拙講座の終了後のこと。
受講者の方が「ベルリン・フィルの記者会見でのフルトヴェングラー漫才、自分も聞きたかったです」と言ってくださったのを朝日カルチャーセンターの担当者さんが脇で聞いていて、「それ面白そうじゃないですか、やりましょうよ」ということで、急遽一回だけの講座を二月二十七日に追加で行なうことになる。中川右介さんとの漫才から漫談へ
ひょうたんから駒、現物も未着で情報も変化している段階(当初の四百三十八ヘルツに統一、という話はなくなったらしい)だが、もうこうなれば、こちらも酔狂(笑)で突き進むしかない、ということで。
十二月二十八日(金)平行弦ピアノ
今日は朝に泳ぎ納め、昼に番組収録納め。意外にも午後の方が風が出て寒くなったので、朝に泳いでおいてよかった。番組は来年の「夜ばなし演奏史譚」の第一話「ステレオ録音の夜明け」その六の「デッカとジョン・カルショー」。
一九五五年晩夏に米キャピトルから英デッカに戻ったカルショーは、同年十二月に英デッカのロンドンでの最初のステレオ録音(フランクの交響的変奏曲)を担当し、翌一九五六年五月にはパリでクナッパーツブッシュ指揮パリ音楽院のシュトラウスを録る。すると、チーフ・プロデューサー格のヴィクター・オロフがHMVに引き抜かれたため、急遽ウィーンに移動して、シューリヒト指揮の《未完成》と《ハフナー》を録る。しかし三十二歳の若造のプロデュースをウィーン・フィルが嫌い、現場は混乱。どうにか終えたところに、EMIのキャピトル買収を怒った米RCAがデッカと新たに提携することになり、RCA専属のライナーとモントゥーがデッカに録音することになる。ライナーからは「出来が悪ければ帰るぞ」と脅かされ、モントゥーからは「パリのだらしないオーケストラなんて二度と振りたくない」と愚痴られながら仕事を重ね、その間にステレオ録音の音質はどんどん進歩していく。同時にレコード会社の意向で、スタジオではヴァイオリンのピアノ配置が進む、なんて内容を、ディスクとあわせてしゃべる。

写真の下にあるのはその台本、というよりただの曲目表。
そしてその上にあるのは、この数日はまっているCD。はまりすぎて、某誌のオーディオ企画にも持っていった。
没後百年のドビュッシー記念年の、個人的には最大の収穫となるCD。一九八三年に《ペレアスとメリザンド》の交響曲版をつくったことで知られるマリウス・コンスタンが、続いて一九九二年にピアノ連弾と六人の歌手のために編曲した《ペレアスの印象》が、二枚組のメインとなっている。編成だけでなく音楽も刈り込み、百五十分の全曲を百分弱に短縮してある。
最近は小編成化、室内アンサンブル化が大好きで、あれこれ聴いている自分だが、ピアノ編曲版だけは躊躇することが多い。声楽とも管楽器とも弦楽器とも、まったく異なる打楽器的な音の出しかたをするモダン・ピアノの強すぎる響きが、他の楽器や声と、どうにも調和しないように思えてならないからだ。
ところがこのヤン・ミヒールスとイング・スピネットによる連弾は、クリス・マーネ制作の平行弦ピアノを用いることで、交差弦を用いたモダン・ピアノ特有の音の濁りを解消し、十九世紀以前のピアノに近い、人間の声となじみやすい澄んだ響きを出している。
これがこのディスクの強烈な魅力。その響きがドビュッシーの音楽に、恐ろしいくらいに合う。《ペレアスの印象》の前後に加えられた《牧神の午後への前奏曲》と《白と黒で》の連弾版の、ふわーっとした音の拡がりとからみあいの、透明な幻想性がたまらない。そして《ペレアスの印象》では、歌声との絶妙のバランス。それによってきわだつ、歌手の言葉の響きと旋律の繊細な美しさ。
面白いのは、このスタイルでは作品のもつ《パルジファル》からの影響の深さがさらに露わになってくること。冬の到来と死滅の絶望を目前にして、動かぬ身体で空しくあがく昆虫のように、他者の温もりを求める男たち。死と風化の予感。アンフォルタスの痛みと苦しみの、その延長にある世界の音楽。
オールド・ピアノの響きとモダンの効率的メカニズムをもつ平行弦ピアノ、バレンボイムが使ったことで有名になったけれど(未聴だがCDも出ている)、フランス語圏では次第に他の奏者も使い始めているようで、ほかにもいくつかCDが出ている。
モダン・ピアノの響きに何の疑問ももたない人にとってはどうでもいい楽器だろうが、自分みたいにその独善にうんざりすることが多い人間にとっては、福音かも。ほかの盤も聴いてみるつもり。
夕方。フルトヴェングラーのセットを役得で他の方より少しだけ早くゲット。予定通り年内発売。まだ眺めているだけだが、中身が軍装品ぽいカラーリングなのは、戦時録音だからなのか(笑)。思わずトーチカみたいな形に組んでみる。嬉しいがその代り、これのおかげで年末年始も休まず働くことになる。時期が時期だから、やっぱり第九から聴くか。

ともあれ、大姑小姑が手ぐすね引いて待つ(笑)年の瀬の日本へようこそ! 幸多からんことを!
Homeへ