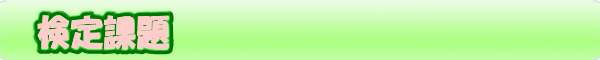
毎月本部から提出課題が出されています。
この課題の紹介と、管理人の日々の奮戦記を載せました。
臨書(真似て書く)が課題ですが、全くの真似ではなく、作品として強弱の変化、場合によっては字体にも変化を
与えて全体のバランス構成を考えて書くことが重要です。
しかし課題本から読み取れる作者の本意を汲みながら書かなければ「臨書」とは言えないでしょう。
ここが大変難しい所ですし、勉強のし甲斐のある所なんでしょう。
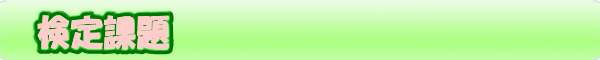
毎月本部から提出課題が出されています。
この課題の紹介と、管理人の日々の奮戦記を載せました。
臨書(真似て書く)が課題ですが、全くの真似ではなく、作品として強弱の変化、場合によっては字体にも変化を
与えて全体のバランス構成を考えて書くことが重要です。
しかし課題本から読み取れる作者の本意を汲みながら書かなければ「臨書」とは言えないでしょう。
ここが大変難しい所ですし、勉強のし甲斐のある所なんでしょう。
| 月度 | 課 題 | 出典 | 釈文 | 読み方 | 意味 | 備 考 |
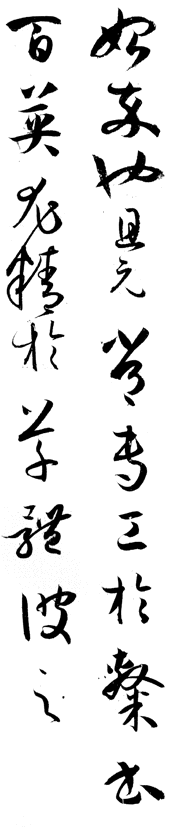 |
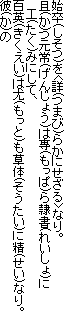 |
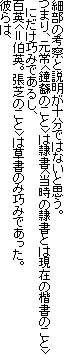 |
●今月も孫過庭の「書譜」の第二紙から引用したもの。先月の続き。 今月の墨付けは、「始」「常」「隷」「英」「草」とする予定。 「始卒」「且元」「於隷」「尤精於」などは連続して書きたい ●今月は「始」「卒」「也」「常」「専」「隷」「尤」「精」「草」「體」「彼」と 難しそうな文字が多い。 また「且」「工」も書きにくそう。 |
|||
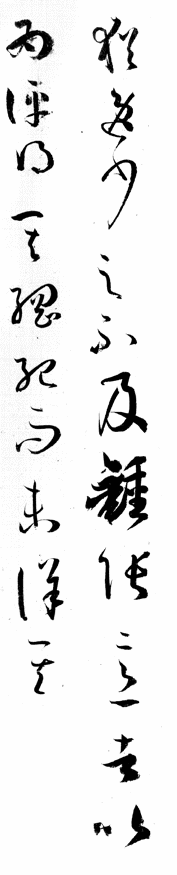 |
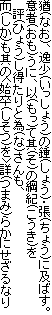 |
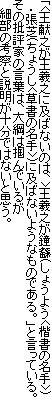 |
●今月も孫過庭の「書譜」の第二紙から引用したもの。 今月の墨付けは、「猶」「及」「者」「評」「未」とする予定。 通常とは異なるが「猶逸少」「之不」「鍾張」「其綱」「紀而」「詳其」は 連続して書きたい為。 通常ならば「紀」のところを墨付けとしたいが、一行目の「及」と 墨付け文字が並んでしまうので、これで進めてみる。 ●今月の難しそうな文字は 「鍾」「意」「為」「評」「得」「綱」「而」あたりか。 「宮」「者」「及」なども侮れない。 |
|||
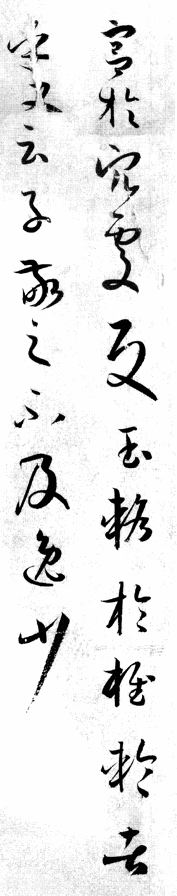 |
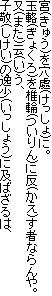 |
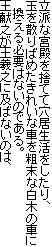 |
●今月から孫過庭の「書譜」の第二紙から引用したもの。 今月の墨付けは、「宮」「反」「椎」「又」「不」とする予定。 ●孫過庭の草書は独特な筆の運びと美しさがある。 書き方の難しそうな文字は 「處」「輅」「椎」「輪」「敬」「逸」あたりだが、 「宮」「者」「乎」「及」なども侮れない。 |
|||
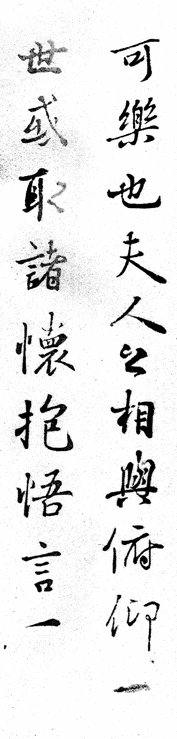 |
![楽しむ可(か)き也(なり)。
夫(そ)れ、人之相与(ひとのそうよ)に
一世(いっせい)に俯仰(ふぎょう)するや、
或いは諸を懐抱(かいほう)に取りて
一[室之内]に悟言(ごげん)し、](vimgtext433.gif) |
![楽しく愉快である。
およそ人と人が、一緒に過ごす時、
或る人々は[同じ部屋の中で]互いに向き合って、
自己の思いを述べ合い、](vimgtext522.gif) |
●今月も王羲之の「蘭亭叙」からの引用 今月の墨付けは、「可」「人」「俯」「或」「抱」の4文字ごとする。 ●今月の注目する文字は 「楽」「與」「仰」「或」あたりだが、 「也」「之」「世」「取」もしんどそう。 「一」が2度現れるし、「俯」や「懐」は先月号にも有ったが、 王羲之らしく字体を変えてあり、これまた要注意。 |
|||
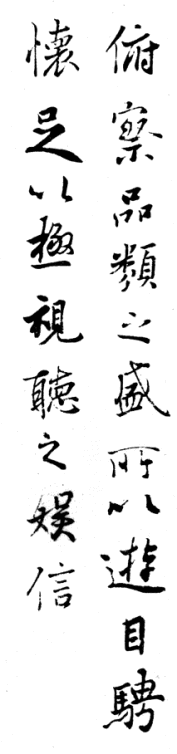 |
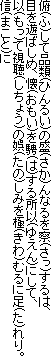 |
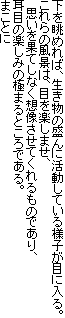 |
●今月も王羲之の「蘭亭叙」からの引用 今月の墨付けは、「俯」「類(または「之」)「遊」「足」「聽」とする。 「類」にするか「之」にするかは書いてみて決める。もしくは「盛」もあり得る。 ●今月は注目する文字は 「類」「所」「遊」「騁」「娯」あたりだが、 二つの「以」や「之」及び「足」なども書きにくそう。 |
|||
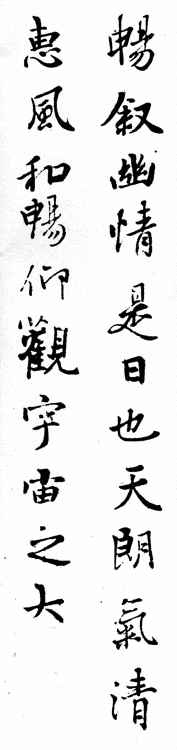 |
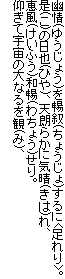 |
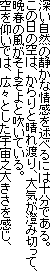 |
●今月から王羲之の「蘭亭叙」に戻った。 今月の墨付けは、「暢」「是」「朗」「風」「觀」とする。 ●行書なので取り分け書きにくいという文字はないのだが、 「幽」「是」「仰」「觀」などは注意が必要だし、「朗」「宇」も油断できない。 |
|||
| |
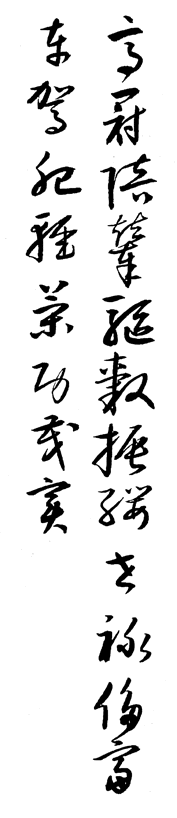 |
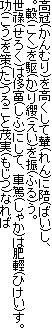 |
![重臣の人々が冠をそびえさせて、天子の輦(こし)[天子の乗る手引き車]の
前後随従して車を駆れば、冠のひもがゆらゆらと振り動く。
代々、受け継いだ俸禄(ほうろく)[支給された報酬]は富み栄え、
肥えた馬や軽車に乗ることが出来る。
勲功をたて、その勲功が大きく盛んなれば、](vimgtext244.gif) |
●今月も木村卜堂の草書千字文。 今月の墨付けは、「高」「驅」「世」「車」「策」とする。 課題の最後が途切れているが、 続きは「勒碑刻銘(クコクシンエイ)」となる。 意味は「碑に勲功を刻み、銘に記して後世にたたえた」。 ●今月はほとんどが難しそうな文字ばかりである。 中でも 「輦」、「驅」、「轂」、「纓」、「輕」などは特に難しそうだ。 ●課題を見ると1行目が12文字、2行目が8文字である。 これは今までとは異なっている。やはり1行目は11文字として進める。 |
||
| |
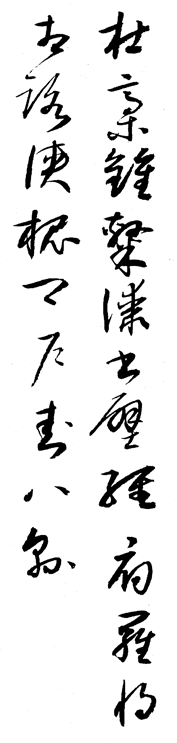 |
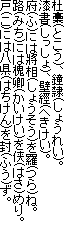 |
![杜度(とど)[後漢の人。杜操(とそう)とも]は草書を得意とし、
鐘?(しょうよう)[後漢から三国・魏の人]は隷書の名手であった。
漆で書いた書物、壁中から出た経書がある。
役所には将軍や宰相らが聚屯し、
道を隔てて公卿たちの邸宅が連なり建てられている。
諸侯は、封ぜられて八県の租税を収入と為し、](vimgtext619.gif) |
●今月も木村卜堂の草書千字文。 今月の墨付けは、「杜」「漆」「府」「路」「戸」とする。 課題では2行目最初の「相」と「路」が繋がっているが、墨付けの関係で切り離す。 ●書き方の難しそうなのは 「槀」、「隸」、「漆」、「壁」、「經」、「羅」、「路」、「封」、「縣」と多いが、 更には「將」、「相」、「侠」、「槐」、「戸」なども要注意だろう。 「卿」はカタカナの「マ」にも見えて簡単そうだが、文字の大きさや筆の強弱などで 意外と苦心するかも。 |
||
| |
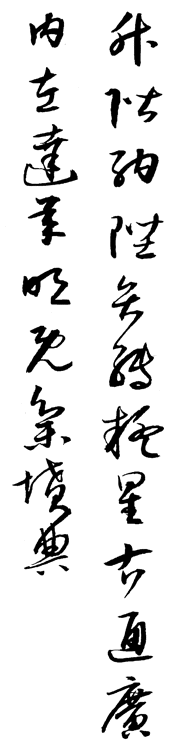 |
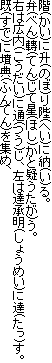 |
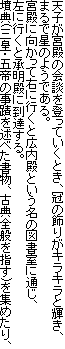 |
●今月から木村卜堂先生の千字文草書。 「升」「弁」「右」「左」「既」の4文字文毎に墨付けとする。 ●今月も注意すべき文字は多々ある、というよりほとんど全部。 その中でも、「升」「階」「陛」「疑」「既」「集」などは苦労しそう。 ●今月は「既集墳典」で終わっているが、この後は 「亦聚羣英(エキシュウグンエイ)」と続く。 意味は「承明殿には学識才能ある人々を集めた。」となる。 |
||
| |
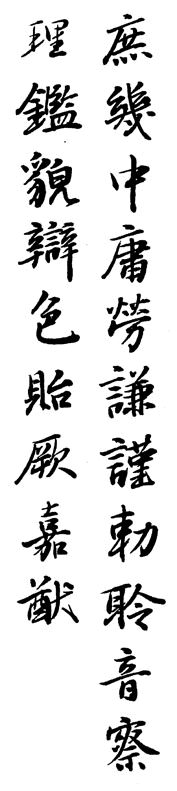 |
|
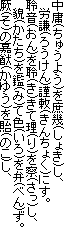 |
![人として正しい道を志す者は
中庸[かたよらず常に変わらないこと]の道を極めることを
願い、勤労しなければいけない。
また人に接する時は、へりくだり、つつしんで、
常に正しい行いをするように心がけなければいけない。
人の言葉を聴いて、その道理を察し、
また人の容貌を見てその喜怒をわきまえよ。](vimgtext429.gif) |
●今月も木村卜堂先生の千字文行書。 「庶」「勞」「聆」「鑑」「貽」の4文字文毎に墨付けとする。 ●今月の注意すべき文字は 「庸」「聆」「辨」「厥」「猷」あたりが難しそう。 その他にも「幾」「勞」「敕」「察」「鑑」「貌」「嘉」なども注意が必要。 ●尚、今月は「貽厥嘉猷」で終わっているが、 本来は「勉其祗植(ベンキシショク)」と続き完結文となる。 |
|
| |
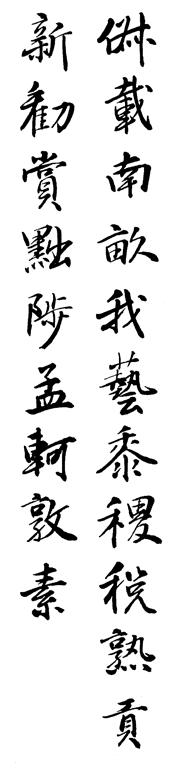 |
|
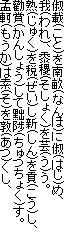 |
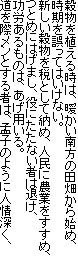 |
●今月も木村卜堂先生の千字文行書。 「俶」「我」「税」「勸」「孟」の4文字毎に墨付けとする。 ●今月の注意すべき文字は 「俶」「藝」「黜」「軻」が目につくが、「黍」「畝」「勸」「陟」「敦」「素」あたりも侮れない。 ●先月は「治本於農」で終わったのに、今月は、「俶載南畝」から始まった。 千字文ではこの間の「務茲稼穡(むしかしょく)」が抜けている。 先月号と続けると「治本於農。俶載南畝。」であり、その意味は 『国を治める根本は農業である。種をまき収穫するまでこれに努めることだ。』 となる。 尚、今月の終わりは「孟軻敦素」となったが、 この後に「史魚秉直(シギョハイチョク)」。が続いて完結文となる。 |
|
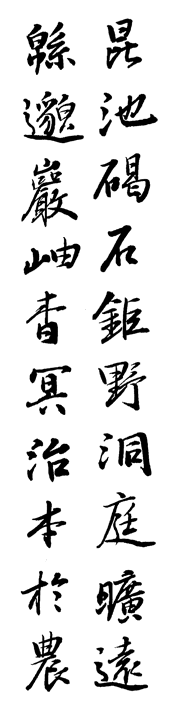 |
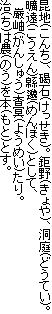 |
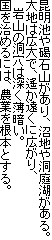 |
●今月から木村卜堂先生の千字文行書に戻った。 今月は2列共10文字である。 「昆」「鉅」「曠」「巌」「治」と4文字毎に墨付けとする。 ●今月の注意すべき文字は 「碣」「鉅」「曠」「遠」「緜」「巌」「農」あたりか 特に、2行目の「邈」や「巌」は文字が大きくなりやすい。 今月は2行共10文字なので、2行目の終わりが少し短くなるように注意したい。 |
|||
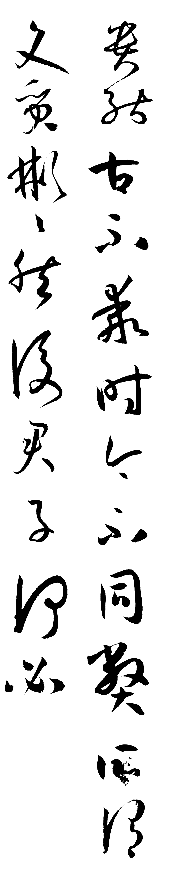 |
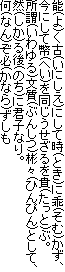 |
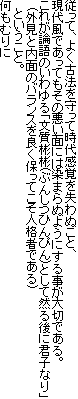 |
●今月も孫過庭の「書譜」の続き。 今月は2文字、1行目は12文字もあり文字の大きさにも注意が必要。 「貴」「乖」「幣」「質」「君」を墨付けとするつもり。 本来は「君子」をつなげたいが、文字の流れからして「後君」が繋がっているが、 ここを断ち切り「君」を墨付けとしてみる。 ●今月の注意すべき文字は 「貴」「能」「乖」「幣」「所」「謂」「質」「然」「何」あたりか? |
|||
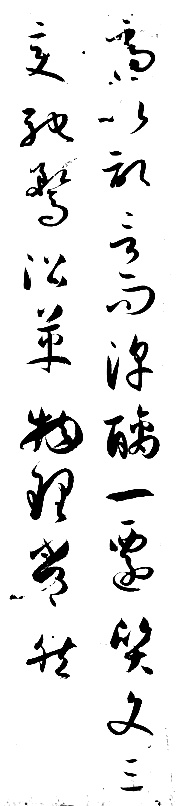 |
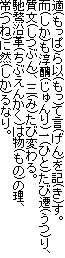 |
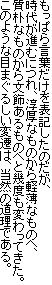 |
●今月も孫過庭の「書譜」の続き。 今月は21文字。文章の区切れにこだわらず、文字の配列や 書き方のつながりからして 「適」「淳」「質」「馳」「物」を墨付けとする。 ●今月は読み方も書き方も難しい文字が多い。 「適」「言」「而」「淳」「鶩」「遷」「變」「馳」「鶩」「常」などは、難儀しそうだが、 「文」「三」「沿」「革」「理」「然」なども見た目以上に書きにくい。 ●今月の出題文を読むと、言葉だけでも時代の流れでどんどん変わっていくと 嘆いているのは興味深い。 近代や現代において、言葉の変遷が激しいと忠告する輩も少なくない。 でも、この時代(7世紀)から、現代と同じようなことが言われていたとは 驚きである。言葉の進化はずっと昔から続いていたのですね。 これからも、時代と共にどんどん変化していくのでしょう。 でも自分は、段々と時代に取り残されていくんでしょうね。 |
|||
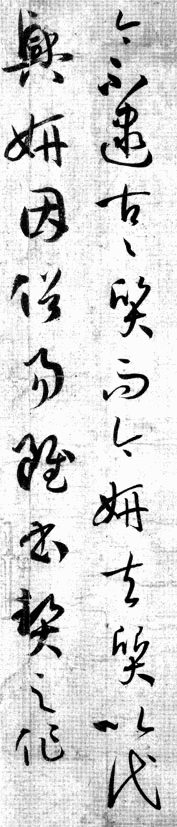 |
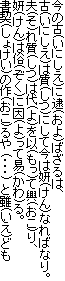 |
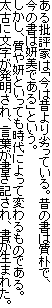 |
●今月から孫過庭の「書譜」。久しぶりの草書となる。 今月は23文字と多い。文章の区切れにこだわらず、文字の配列や 書き方のつながりからして 「今」「質」「質」「妍」「雖」を墨付けとする。 ●今月は「今」「古」「質」「妍」が2回現れている。 「古」は連続しているので、一方を「ゝ」が使われており、 実質3文字が2回現れている。 ●「逮」「質」「而」「興」「易」「雖」「作」など書き方の難しそうなのも多い。 「不」と「逮」、「古」と「ゝ」、「而」と「今」、「以」と「代」、「俗」と「易」は繋がった 書き方となる。 |
|||
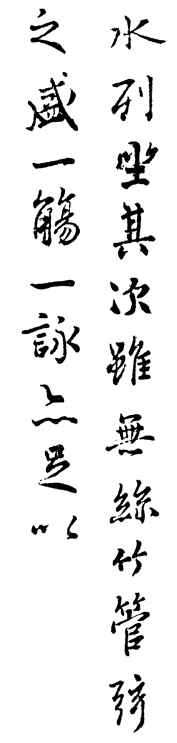 |
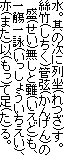 |
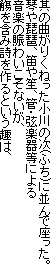 |
●今月も王羲之の「蘭亭叙」。 今月も単純に四文字毎の「水」「次」「竹」「盛」「詠」を墨付けとする。 ●今月は難しい文字はないが、 書き方では「雖」「無」「絲」「弦」「詠」「足」あたりが書きにくいと思われる。 ●「觴」は先月にも出ているし、「之」も今まで何度も出てきた。 しかし王羲之の特徴でもある「同じ文字でも同じ字体ではない」ことからも 工夫が必要。「一」も2度現れるが同じことだろう。 |
|||
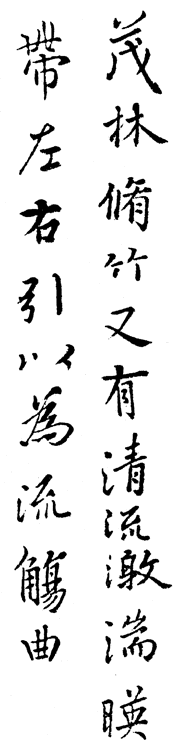 |
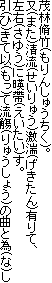 |
![生い茂った林や長く伸びた竹があり、
また清らかな水の流れや激しい瀬があって、
色や景色が左右に映り合っている。
この流れを引いてきて、觴(さかずき)を流す曲がりくねった
[小川]をつくり、](vimgtext238.gif) |
●今月も王羲之の「蘭亭叙」。 今月は単純に「茂」「又」「激」「左」「為」を墨付けとしてみる。 ●行書は筆運びをしっかりすることが大事。 今月は 「激」「帯」「觴」「為」などがやっかいな文字と思われる。 ●今月は「流」が2カ所、「さんずい」が5文字もあり、それぞれ少し書き方を 工夫したい。。 |
|||
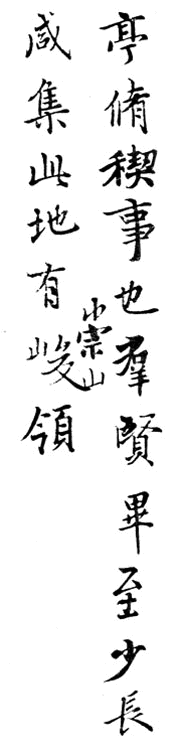 |
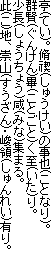 |
![[蘭]亭において。禊(みそ)ぎを行った。
多くの賢者が畢(ことごと)く至れり、年少の者も歳をとった者も
咸(みな)集まった。
此の地には、高い山や険しい嶺があり、](vimgtext614.gif) |
●今月からは王羲之の「蘭亭叙」に戻った。 文章からして、今月は「亭」「群」「少」「此」「崇」あたりを墨付けとしてみる。 ●今月は行書だが、中でも 「禊」「群」「畢」「崇」などがやっかいになるか?。 ●釈文の「禊」は「しめすへん」だが、実筆では「のぎへん」となっている。 また、「群」の実筆では「君」と「羊」が上下に書かれていることに注意要。 「峻」も同様に「山」が左上に寄っている、でもこの書き方も悪くない。 |
|||
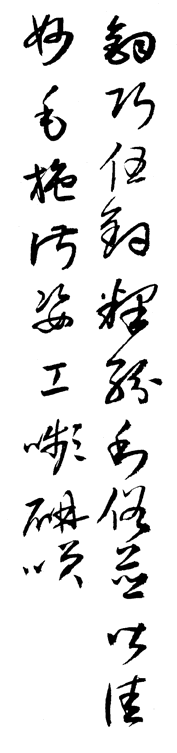 |
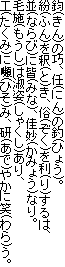 |
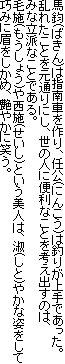 |
●今月も木村卜堂の草書千字文。 今月の墨付けは、「鈞」「釋」「並」「毛」「工」。 この中で「俗」と「並」が繋がって書かれている様に見えるので、 ここは成り行き次第となるだろう。「皆佳妙」と3文字が一区切りとなるかも。 ●釈文の最後の文字「笑」は、原文では「咲」である。 課題文では「咲」で書かれている。 ●書き方の難しそうなのは 「鈞」「釣」「釋」「紛」「俗」「並」「皆」「妙」「施」「淑」「嚬」「笑」等と多い。 ●中に出てくる人物を調べてみた。 ・「馬鈞」=三国時代の学者・発明家。足踏み式水車を発明した他、諸葛亮孔明 の作った連弩(れんど=連射または一度に多数本の矢が撃てる)や、 発石車(=カタパルト)など改良したことでも有名。生没年は不明 ・「任公」=? 釣り名人であった様だ。 |
|||
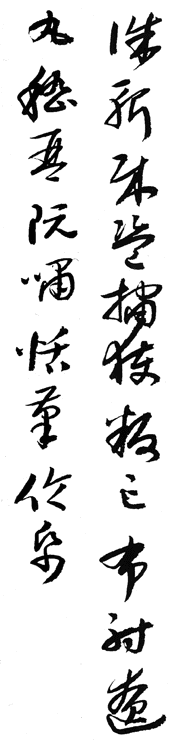 |
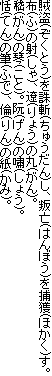 |
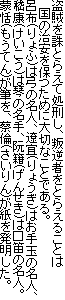 |
●今月も木村卜堂の草書千字文。 今月の墨付けは、「誅」「捕」「布」「嵇」「恬」。 ●今月も難しい文字は多い 特に「斬」「賊」「捕」「獲」「叛」「遼」「嘯」「筆」などは苦戦しそう。 ●この中に出てくる人物を調べてみた。 ・「呂布(りょふ)=?~198」:三国志では豪傑の武将として有名。弓のみならず 馬術にも率い出た才をもつと言われ「飛将」とも呼ばれた。 ・「遼宜(りょうぎ)=宜遼(ぎりょう)?」:春秋時代の楚の武人で、玉を弄ぶ技の 名人だった。(人を手玉に取る妙手という説もある) ・「嵇康(けいこう)=223頃~263頃」:三国時代の魏の文人で、竹林の七賢の 一人でもある。告発された親友の弁をとったことで死罪となる。 ・「阮籍(げんせき)=210~263」:嵇康と同じく竹林の七賢の一人。 詩では「詠懐詩」82首が有名。偽善と詐術が横行する世間を嫌っていた。 ・「蒙恬(もうてん)=?~BC210」:文官で訴訟。裁判に関わっていたが、家柄か ら秦の将軍となり斉を滅ぼし匈奴を追い払う実績も持つ。 蒙恬が獣の毛を集めて作ったものが筆の始まりと言われたが、この説は 近年覆された。 ・「蔡倫(さいりん)=50?~121?」:後漢代の宦官で、製紙法を改良し実用的な 紙製造に大きく貢献した。 |
|||
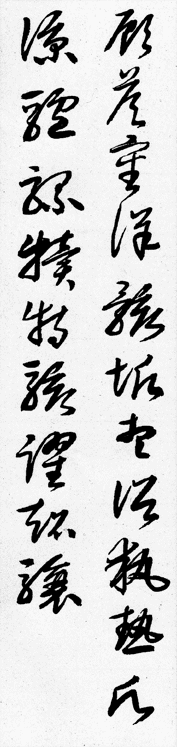 |
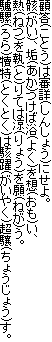 |
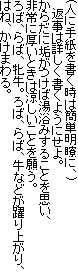 |
●今月から木村卜堂の草書千字文。 今月の墨付けは、「顧」「骸」「執」「驢」「駭」。 ●今月はどの文字も複雑で難しい。 特に「骸」「願」「躍」「超」などは苦戦しそう。 ●馬へんが目立つ。 「驢(ろ)」=ロバ[驢馬、馿馬] 「騾(ら)」=ラバ[騾馬](雄馬と牝ロバの交配種) 「駭(がい)」=おどろく「駭く、驚く、愕く」と同じ 「驤(じょう)」=おどりあがるという意 (馬が走るときに首がふりあがる) |