広重「名所江戸百景」めぐり21目黒コース
10月29日(水)晴れ
爽やかな秋晴れに恵まれた一日を、JASS(日本セカンドライフ協会)のイベント「広重・名所江戸百景めぐり」第21目黒コースに参加してきた。
企画・運営委員の日紫喜さんをはじめ、ガイドをして下さる東京シティガイド江戸百景グループの松島さん、アシスタントの国保さん他、総勢26名(内女性2名)が参加した。
コースは、東急東横線・代官山駅を皮切りに⇒元富士跡(第25景「目黒元富士」)⇒新富士跡(第24景「目黒新富士」)⇒茶屋坂⇒爺々が茶屋跡(第84景「目黒爺々が茶屋」)⇒千代ヶ池跡(第23景「目黒千代ヶ池」)⇒目黒駅アトレ⇒大円寺⇒太鼓橋(目黒川)(第111景「目黒太鼓橋夕日の丘」)⇒五百羅漢寺⇒目黒不動⇒青木昆陽墓所で流れ解散となった。
気温が22度位まで上がって、歩いていると汗ばむほどだった。
目黒駅から目黒不動にかけては、目黒不動前に約15年住んでいたことがあるので、流石にどの道も懐かしい記憶を辿ることができた。
11:40に我が家を出発して、バスで新宿駅まで行き、山手線の渋谷駅で東急東横線に乗換えて、集合場所の「代官山駅」に12:20に到着した。

集合場所の代官山駅
予定通り、12:30に代官山駅を出発した。
今回は、先ず目黒台地に富士眺望ルートを辿るところから始まった。
江戸の住民にとって、富士は広く親しまれた存在だったようで、西に開けた高台ではどこでも富士が望めたに違いない。
最近では、国土交通省が、景観を活かした地域振興の観点から、「富士山の見えるまちづくり」として、「関東の富士見百景」を2004年と2005年に合わせて128景選定したそうで、その内、東京都内には30地点が選ばれているという。
富士講が信仰の拠点としたのが富士塚である。 小型の富士山を神社、寺院などに築き、頂上までの登山道や各種の石碑を設け、毎年夏には山開きを行い、8月下旬には山納めの火祭りを開催するなど、山岳信仰として、ご神体の富士山と同じ行事を行なっていたという。
そして、富士講で富士登山に行くたびに、富士の溶岩を持ち帰り、富士塚に積み上げていたそうである。
そして、広重も「名所江戸百景」で、富士山を19景描いている。
東京都内にある富士塚は60ヶ所以上といわれ、その内3ヶ所(豊島長崎富士、江古田富士、下谷坂本富士)が、国の重要文化財に指定されているという。
先ずは、上目黒のマンション「キングホームス」の敷地内にあったという「目黒元富士」跡を訪れた。
この富士塚は、文化9年(1812年)に築かれ、高さは12mあったそうである。 文政2年(1819年)に、中目黒2丁目に新しく富士が築かれ、それを新富士と呼ぶようになってから、ここの富士は元富士といわれるようになったという。



第25景「目黒元不二」 富士塚跡に建つマンション 富士塚からの眺望
第25景「目黒元不二」では、近景に松の生え茂る富士塚、中景は富士塚下、茶店の床机と憩う人々が描かれている。 遠景は目黒川を隔てた田畑、その向うに丹沢山塊が描かれている。
目黒区と渋谷区の境の狭い道を進み、中目黒2丁目のマンション「テラス恵比寿の丘」にある「目黒新富士」跡に向かった。
この富士塚は、文政2年(1819年)に、蝦夷地探検で知られる近藤重蔵が別邸内に築造したもので、元富士より7年遅かったため、新富士と呼ばれたそうである。
高さ15mの新富士は、昭和34年(1959年)に、旧KDD研究所工事に際して取り壊され、山腹にあった3つの石碑(「南無阿弥陀仏」、「小御嶽」、「文化二年吉日戌申」の銘がある)は、別所坂児童遊園に移設されている。

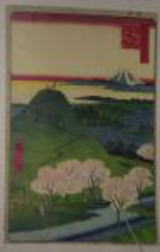
新富士にあったという3つの石碑 第24景「目黒新富士」
第24景「目黒新富士」では、中央に富士塚がそびえ、麓の水流は三田用水である。 用水の畔の桜は満開であり、藤棚の下に床机が並んでいる。
富士塚の中腹に、身禄を祀った祠と石碑が見える。 中景には水を張った田圃が拡がる。 田圃の脇には林があり、屋根が望める。
遠景の富士山は春浅く、多量の残雪が望める。
防衛研究所に向かう道端には、馬頭観音や道しるべを見かけた。 江戸中期に建てられたこの道しるべは、中央に南無阿弥陀仏、その左側にゆうてん寺道、右側には不動尊みちと書いてある。


途中で見かけた「馬頭観音」と「道しるべ」
防衛研究所の正面入口や艦船艤装所などを眺めながら、茶屋坂に向かった。


防衛研究所入口と戦艦大和も入ったという艦船艤装所
目黒は、将軍一行の鷹狩りや遊猟が盛んに行なわれた土地で、今でも鷹番という町名が残っている。
「茶屋坂」は目黒区三田2丁目にあり、目黒清掃工場に向かって下がる坂である。 百姓彦四郎の茶屋に、家光や吉宗が鷹狩りの際にしばしば立ち寄り、彦四郎を「爺、爺」と呼んだところから、「爺々が茶屋」になったという。


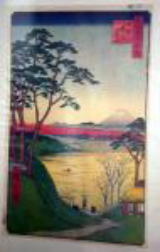
茶屋坂の標識と坂の風景 第84景「目黒爺々が茶屋」
第84景「目黒爺々が茶屋」では、急な下り坂の下に広がる田圃は黄金色で、稲刈りを待っている。
中景の緑の林と建物は、疑いなく目黒不動である。
遠景は富士山の手前に見える丹沢の山々も正確に表現されており、左端は大山である。
真っ白な富士山を眺める人物が、左の高台、坂の途中に描かれている。
茶屋坂を降り、田道小学校の前を通り、目黒1丁目にある「千代ヶ池跡」へ向かった。
目黒駅から恵比寿ガーデンプレース辺りまでの目黒川に沿った台地を「千代ヶ崎」と呼び、富士をはじめ、花鳥風月を楽しむ名所になっていたそうである。
「千代ヶ池」の由来は、南北朝時代の正平13年(1358年)、新田義興(義貞の次男)が、足利基氏、畠山国清に謀られて多摩川の矢口渡で殺され、義興の妻であった千代は「死ねば義興のそばに行ける」と考え、池に身を投げた。 その千代の心情を哀れんだ人々がその池を千代ヶ池と呼ぶようになったという。

第23景「目黒千代ヶ池」
第23景「目黒千代ヶ池」では、千代ヶ崎の斜面途中にあった池を描いている。
段をなして落下する滝が、斜面の急勾配を表している。 池の近くには桜の数珠があり、花の盛りである。
板を渡って小島に渡ったのは、身なりから察して商家の奥さんと娘、手前に佇む女はお供の女中のようである。
桜と針葉樹が水面に影を落としているが、こうした技法は西洋画の影響を浮世絵師が受け、18世紀にはよく使われていたようである。
しかし、広重はあまり好まず、名所江戸百景でも3景にしか現れていない。
「夕日の岡」は、目黒駅西側の台地の上で、今でも「夕陽丘町会」がある。 千代ヶ崎の南端に当たり、西に開けていて楓樹美しく、夕日の景色が良いことから名付けられたという。
「目黒駅アトレ」でトイレ休憩を取った後、「行人坂」(ぎょうにんざか)を下りて行った。
目黒駅から目黒川に下る道は、権之助坂と行人坂がある。 今は、権之助坂が目黒通りとなり、車の往来が激しいが、江戸時代には行人坂が目黒不動への参詣道として賑わっていたそうである。
行人坂は、今でも東京で有数の急坂で、自動車は上りの一方通行になっている。
行人坂の中程の左手に、「天台宗大円寺」がある。 この寺は、江戸の初期、寛永年間(1624~1643年)に、湯殿山の行人、大海法印が建てた大日如来堂に始まると伝えられている。
山門を入ると先ず目に付くのが、境内左手の崖に沿い、幾段にも並ぶ石仏群である。
釈迦像三体、五百羅漢像などからなる五百二十体の石仏像は、昭和45年(1970年)に都有形文化財に指定されている。
振袖火事、車町火事と並んで江戸三大火の一つである、明和9年(1772年)の行人坂火事は、この大円寺が火元といわれている。
火は、折からの強風により、たちまち白金から神田、湯島、下谷、浅草まで江戸八百八町のうち六百二十八町を焼き尽くす大火となった。
特に、城中のやぐらまでも延焼したので、大円寺は、以後76年間も再建を許されなかったという。



大円寺とその石仏群


大円寺の金箔貼りの薬師如来 大円寺の水子地蔵
目黒川に架かる「太鼓橋」は、両岸から石を畳み出して建設され、横から見ると太鼓の胴のように見えるところから太鼓橋と呼ばれたようだ。
江戸には珍しい石造アーチ橋であったが、大正9年(1920年)9月の水害で流失した。 現在の橋は、昭和6年(1931年)竣工で、橋の袂には橋名を取った「太鼓鰻」がある。
橋を渡り、真っ直ぐ進むと目黒不動までは500mである。 江戸から日帰りの行楽に多くの人が訪れるため、丈夫な石橋を架けたのであろうと思われる。



太鼓橋 太鼓橋からの目黒川の眺め


太鼓橋脇の太鼓鰻 第111景「目黒太鼓橋夕日の岡」
第111景「目黒太鼓橋夕日の岡」では、石造アーチ橋、太鼓橋の左は行人坂、右は目黒不動道である。
画面奥が目黒川の下流になる。 左側の斜面は、夕日の岡、現在は雅叙園の位置で、当時は熊本藩細川家の下屋敷であった。
道行く人々の蓑、傘や笠には雪が付着している。 近景遠景を問わず、木立も田畑も雪に覆われている。 上空からしんしんと雪が降り続く。 用紙の白色が効果的に使われている。
山手通りを越えて、「五百羅漢寺」を訪れた。
本所五つ目(現江東区大島)にあった羅漢寺は、寺域4千坪の大寺院だったそうである。五百羅漢は、死んだ人が恋しい時に「らかんさん」に会いに行くと必ず似た顔があるとして人気があったそうである。
安政の江戸地震で被害を受けてから寺運が傾き、本所を経て明治41年(1908年)、目黒不動の隣地に移転してきた。
536体作られた五百羅漢像も少しずつ失われ、現在は305体が東京都重要文化財に指定されて、羅漢堂に安置されている。


五百羅漢寺
目黒不動尊への参道にある「たこ薬師」にも寄って行った。これを撫でて祈願するとイボなどが取れるという、お撫で石(1500円)が売られていた。

たこ薬師
さらに、参道を進み、うなぎの「にしむら」の前を通り、目黒不動の直前の「比翼塚」</span>にも立寄った。
これは、処刑された愛人白井権八と、彼の墓前で自害した遊女小紫の悲話を伝えている。
その悲話は、”後追い心中”として歌舞伎などで有名だが、この比翼塚は、二人の来世での幸せを祈り建てられたという。


権八・小紫の悲話を伝える比翼塚
「目黒不動」は、天台宗泰叡山瀧泉寺といい、寛永寺の末寺だそうである。
江戸時代に入り、三代将軍家光は、深く目黒不動に帰依していたので、寛永11年(1634年)堂宇を造営した。
当時は、元和元年(1615年)の火災で仮本堂しかなかったため、本堂を再建し、鐘楼・観音堂・仁王門を修造、また種々の仏像・宝物を寄進した。
さらに目黒筋に遊猟の際、駕籠を寄せるために御殿を新設するなどして、広壮華麗な寺になったという。
以来、幕府の保護が厚く、江戸近郊における最も有名な参詣行楽地になり、門前町もにぎわった。
江戸の三富と呼ばれた富くじが行なわれたことも、目黒不動繁栄の一因となった。


10月28日に甘藷まつりと縁日が終わったばかりの目黒不動
本堂の奥に「昆陽青木先生之碑」がある。
青木昆陽は、日本橋魚河岸の魚問屋に生まれ、八丁堀に私塾を開いたが、地主の南町奉行所与力とじっ魂になり、奉行大岡越前守忠相に推挙される。
その際に、飢饉時の対策としてサツマイモの普及を説いた「蕃薯考」を提出し、八代将軍吉宗に認められた。
後に蘭学も学んで、前野良沢等にオランダ語を教え、解体新書の翻訳につながっていく。
「甘藷先生墓」の墓碑銘は、生前に自書して刻ませ、自宅に置いていたという。

青木昆陽の墓
青木昆陽の墓で、16:00に流れ解散となり、山手通りに出て、大鳥神社を経由して、権之助坂を上り、JR目黒駅から山手線で新宿駅に出て、ヨドバシカメラで買物をして、17:20に帰宅した。
歩行距離:自宅から約9.3km(歩数計で14,400歩)
費用:参加費(五百羅漢の入場料込みで1400円)、交通費(800円)、合計2,200円