仠PLL IC偺曄慗
PLL IC偲偄偊偽丄僷儔儗儖愝掕偺MC145163偑億僺儏儔乕偱偁偭偨偑丄攑昳庬偲側傝丄揦摢嵼屔昳偼丄崅摣偟偰偄傞傛偆偩丅
戝検惗嶻捠怣婡婍偵偼丄僔儕傾儖愝掕PLL偺傎偆偑埑搢揑偵巊偄堈偔丄僷儔儗儖愝掕IC偑徚偊偰峴偔偺偼乭惙幰昁悐偺棳傟乭偐偲傕偝傃偟偔姶偢傞
乽桞堦偦偺栚揑梡搑偺PLL丂VFO偑惢嶌偱偒傟偽廫暘側傾儅僠儏傾偵偼丄僷儔儗儖愝掕IC偺傎偆偑埖偄傗偡偄乿偲埲慜偼巚偭偰偄偨丅
偑丄嵟嬤偼儚儞僠僢僾PIC偺棙梡傕梕堈偵側傝丄偦偺慻傒崌傢偣偱姶摦乮姰摦乯偡傞偲丄僷儔儗儖愝掕IC偼巊偆婥偑偟側偔側傞丅帠幚丄1屄攦抲偒偟偰偄偨MC145163偼晄椙嵼屔偲側偭偰偟傑偭偨丅
僔儕傾儖愝掕僾儘僌儔儉傕堦搙嶌傟偽丄偦偺儖乕僠儞偼嫟捠儕僜乕僗偲偟偰孞傝曉偟巊偊傞偟丄壗偲尵偭偰傕3杮偺怣崋慄偱帺桼偵墦妘愝掕偑偱偒丄暘廃斾傪偐偊傞偺傕僜僼僩偺曄峏偺傒偱嵪傓儊儕僢僩偼戝偒偄丅
仠搶幣PLL IC TC9256P
奜廃婍偼丄16P-DIP偱丄PIC16F84傛傝2僺儞憡摉暘偩偗彫偝偄丅
僨乕僞僔乕僩偼丄
搶幣偺HP傛傝僟僂儞儘乕僪偱偒傞丅
擖庤偼
宧惤偱峸擖偟偨丅
仠TC9256P偺摿挜
埲壓偼丄幚嵺偵巊偭偰傒偨婡擻傪巹側傝偵欚殣偟偰婰擖偟偰偁傞偙偲傪抐偭偰偍偔丅幚嵺偺巊梡偵摉偨偭偰偼丄搶幣HP偺僨乕僞僔乕僩傪嶲徠偝傟偨偄丅
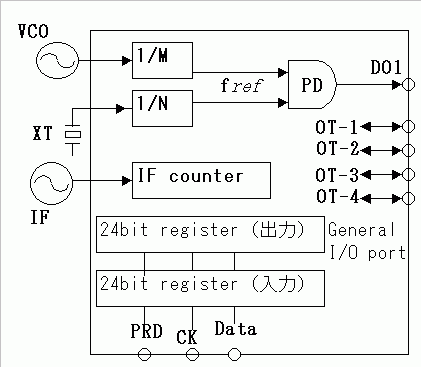
撪晹峔憿偺奣梫傪嵍偵帵偡丅
丒VCO偺暘廃斾俵偼丄
528乣65535乮僷儖僗僗儚儘乕曽幃乯丄
傑偨偼16乣4095乮捈愙暘廃曽幃乯偑慖傋傞丅
丒VCO偐傜偺擖椡廃攇悢偼丄10(*)乣130MHz乮僷儖僗僗儚儘乕曽幃乯*;僇僞儘僌抣偺壓尷偼30MHz
丒XT偺暘廃斾俶偼丄師崁偵婰嵹偡傞丅
丒撪晹偵斈梡僇僂儞僞乕傪帩偮丅IF廃攇悢傪撉傒庢傝丄Lo偐傜偺堷偒嶼傪偟丄僿僥儘僟僀儞昞帵偡傞傛偆側応崌偵桳梡偱偁傞丅
丒僎乕僩僞僀儉偼丄XT傪3.6MHz,4.5MHz,7.2MHz,10.8MHz偲偟偰偄傞偲偒偵丄1,4,16,64msec傛傝慖戰偱偒傞丅
丒斈梡擖弌椡億乕僩偲偟偰丄OT-1,2,3偺3億乕僩偑偁傞丅懠偺IF擖椡億乕僩傕斈梡億乕僩偵曄峏偱偒嵟戝6億乕僩偑巊偊傞丅
丒
仠XT偺暘廃斾俶
丒XT偺暘廃斾俶偼丄偁傑傝帺桼搙偼側偄偑丄埲壓傛傝慖傋傞丅
21600,14400,10800,9000,7200,4500,4320,3600,3456,2880,2400,2304,2160,1800,1500,1440,
1200,1152,1080,900,864,800,720,576,500,450,432,400,360,
288,216,180,144,108,90,72,45,36
丒XT傪丂3.6MHz,丂4.5MHz,丂7.2MHz,丂10.8MHz偲偟偨帪偵丄斾妑廃攇悢丂fref 偑丄5kHz,10kHz,15kHz,50kHz摍偺妱偺傛偄廃攇悢傪慖傋傞傛偆偵側偭偰偄傞丅
丒fref亖10kHz偲偟偨偄偲偒偵偼丄忋婰偺暘廃斾傪10攞偟偨偺偑XT偺敪怳廃攇悢(kHz)偲側傝丄12MHz,丂9MHz,丂8MHz,丂5MHz傕巊梡偱偒傞丅
丒摨條偵fref亖12.8kHz偲偟偨偄偲偒偺XT偼丄10.24MHz,丂9.216MHz,丂5.76MHz偑巊梡偱偒傞丅
丒fref亖12.5kHz乮GH倸VCO傪俉暘廃偟偰100kHz偍偒偵儘僢僋偝偣傞帪乯偲偟偨偄偲偒偺XT偼丄10MHz,丂9MHz,丂5MHz偑巊梡偱偒傞丅
偙傟傜偺暘廃斾偼捈愙擖椡偡傞偺偱偼側偔丄XT偺廃攇悢偲斾妑廃攇悢偱僙僢僩偡傞丅
椺偊偽丄N=800傪慖傇偲偒偼丄埲壓偺愝掕傪偡傞丅
XT=7.2MHz fref=9kHz 亪N=7200/9=800
幚嵺偺僔儕傾儖僨乕僞偼丄傾僪儗僗倓08倛偵堷偒懕偒憲弌偡傞24倐倝倲傪
d0h+仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩+R0+R1+R2+R3+仩仩+OSC1+OSC2
d0h+仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩仩+ 1+ 0+ 0+ 1+仩仩+ 0+ 1
僔儕傾儖僨乕僞
| R0 | R1 | R2 | R3 | fref | | R0 | R1 | R2 | R3 | fref | | | OSC1 | OSC2 | XT(MHz) |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5kHz | | 0 | 0 | 0 | 1 | *7.8125kHz | | | 0 | 0 | 3.6(MHz) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1kHz | | 1 | 0 | 0 | 1 | 9kHz | | | 1 | 0 | 4.5(MHz) |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5kHz | | 0 | 1 | 0 | 1 | 10kHz | | | 0 | 1 | 7.2(MHz) |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3kHz | | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.5kHz | | | 1 | 1 | 10.8(MHz) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3.125kHz 丂 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 25kHz | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | *3.90625kHz | | 1 | 0 | 1 | 1 | 50kHz | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5kHz | | 0 | 1 | 1 | 1 | 100kHz | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 6.25kHz | | | | | | | | | | | |
*報偼丄倃俿亖4.5俵俫倸偺帪偺傒桳岠丅
側偍丄XT偺曐徹摦嶌廃攇悢偼丄3.6MH倸乣10.8MH倸偱偁傞丅
仠巊梡夞楬椺
丒 巊梡夞楬椺傪帵偡丅埵憡斾妑婍乮PD)偺Amp偼奜晹偵暿抲偒偡傞丅2SK30A(Y)-2SC1815偺LPF傾儞僾偲偟偰偄傞丅
丒2SC1815偺儀乕僗僶僀傾僗乮偡側傢偪丄2SK30A偺僜乕僗掞峈乯傪0.4乣0.6V偺斖埻偵挷惍偡傞揰偵棷堄偡傞丅
丒PD偺僩儔僀僗僥乕僩弌椡抂巕乮DO1乯偼丄埵憡嵎偺僷儖僗偑弌椡偝傟傞丅僷儖僗偑側偄偲偒偼丄2SC1815偼僆乕僾儞偲側傝俠乮僐儗僋僞乯偼Vdd揹埵傊丄媡偵僷儖僗偑弌椡偝傟偨偲偒偼2SC1815偼僋儘乕僘偲側傝丄俠偼GRD揹埵偲側傞傛偆側僶僀傾僗偵挷惍偡傞丅
丒2SK30A(Y)偼倄儔儞僋傪巊偄丄僜乕僗掞峈傪300兌偲偡傞偲丄Idss偑3mA側偺偱偦偺摿惈傛傝丄柍怣崋帪栺0.5V偲側傞丅
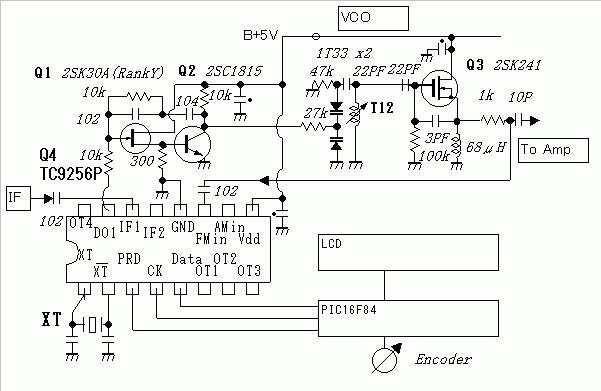
仠惂屼怣崋
怣崋偼丄儗僕僗僞乕傾僪儗僗傪昞偡8bit僨乕僞偵堷偒懕偒24bit僨乕僞傪PIC傛傝憲弌乮庴怣乯偡傞偙偲偵傛傝姰寢偡傞丅
擖椡儗僕僗僞乕傊偺彂崬傒
丒VCO暘廃斾俵偺愝掕
丂32bit=傾僪儗僗d0h + 16bit(M偺暘廃斾乯+8bit(N偺暘廃斾偲XT偺廃攇悢乯
丒斈梡僇僂儞僞乕婲摦偍傛傃斈梡I/O億乕僩偺愝掕
丂32bit=傾僪儗僗d2h + 24bit(斈梡僇僂儞僞乕僎乕僩丄斈梡I/O億乕僩偺愝掕摍乯
弌椡儗僕僗僞乕偺撉傒弌偟
丒斈梡僇僂儞僞乕應掕抣偺撉傒弌偟
丂32bit=傾僪儗僗d1h + 24bit(斈梡僇僂儞僞乕僨乕僞偺撉傒偙傒丟TC9256P仺PIC乯
丒俹俴俴偺儘僢僋忬懺摍偺撉傒弌偟
丂32bit=傾僪儗僗d3h + 24bit(PLL偺儘僢僋忬懺丄IO億乕僩偺抣偺撉傒弌偟丟TC9256P仺PIC乯
仠DDS_PLL VCO偺峔憐
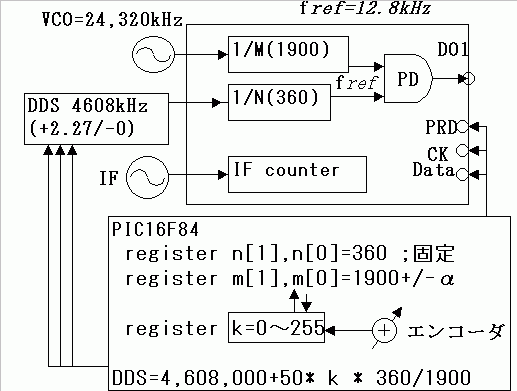
奜晹偵愙懕偡傞XT偼丄捠忢偼屌掕xtal osc丂偱偁傞偑丄偙傟偵戙傢傝DDS怣崋傪擖傟偰丄PIC偱DDS廃攇悢傪惂屼偡傟偽丄DDS_PLL_VCO偑弌棃忋偑傞丅
偙偺惂屼儘僕僢僋峔憐偺堦椺傪帵偡丅
IF=10.17MH倸丄14.15MHz傪up hetro偱庴怣偡傞応崌丄Lo亖10.17+14.15亖24.32MH倸
TC9256P偺愝掕偼丄XT=4.5MH倸丄fref=12.5kHz偲偟偰偍偔丅偡側傢偪N亖360
PIC偺撪晹儗僕僗僞乕傪師偺偲偍傝掕媊偡傞丅
k; 8bit 僇僂儞僞乕偱 僄儞僐乕僟偵傛傝憹尭偡傞丅
丂丂丂僄儞僐乕僟乕偺1step傪50Hz偲偡傞偲丂0乣255step 偡側傢偪0-12.8kHz偺曄壔傪婰榐偡傞丅
丂 m[0],m[1]; 儗僕僗僞乕k丂偺忋埵僇僂儞僞乕 偱弶婜抣亖1900偲偡傞丅
丂丂丂丂丂丂丂偙傟偼丄忋恾偺VCO暘廃斾丟M偺抣偦偺傕偺偲側傞丅丂
丂 n[0],n[1];=360丂XT偺暘廃斾
DDS偐傜偺怣崋廃攇悢弶婜抣亖4608kHz丂乮佹4500*12.8/12.5乯丅k=0
丂
TC9256P偵暘廃斾丂m亖1900丂偺僔儕傾儖怣崋傪擖傟傞偲
丂
儘僢僋廃攇悢偼丄24,320,000Hz (佹4608/N *M=4608/360 *1900=24,320)--嘆
偙偺帪丄僄儞僐乕僟傪100step=5000Hz摦偐偡偲丂k=k+100=100
DDS廃攇悢亖4,608,000丂+50*k丂*丂N/M 偺寁嶼傪偝偣丄
DDS=4,608,000+50*100 * 360/1900 =4,608,947Hz 傪摼傞
PLL偺儘僢僋廃攇悢偼丄4,608,947/360丂*1900亖24,324,998Hz--嘇
偙傟偼丄嘆偺廃攇悢偵懳偟偰4,998Hz憹壛偟偰偄傞丅2Hz偼丄傗傓傪偊側偄岆嵎偲偡傞丅
仠惂屼僾儘僌儔儉
惂屼僾儘僌儔儉偼丄幚嵺偺惢嶌婰帠傪弴師岞奐偟偰偄偔偺偱偦傟傪嶲徠捀偒偨偄丅
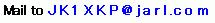
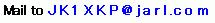
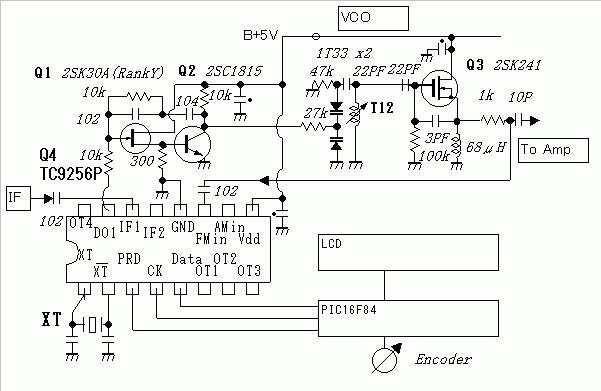
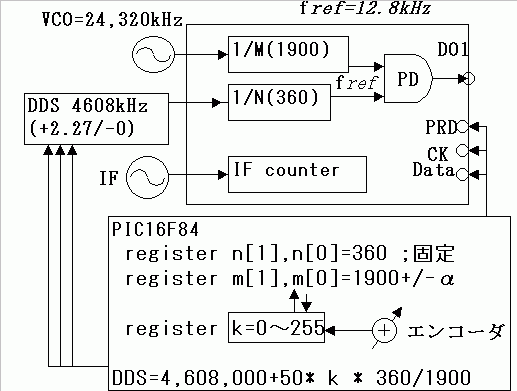 奜晹偵愙懕偡傞XT偼丄捠忢偼屌掕xtal osc丂偱偁傞偑丄偙傟偵戙傢傝DDS怣崋傪擖傟偰丄PIC偱DDS廃攇悢傪惂屼偡傟偽丄DDS_PLL_VCO偑弌棃忋偑傞丅
奜晹偵愙懕偡傞XT偼丄捠忢偼屌掕xtal osc丂偱偁傞偑丄偙傟偵戙傢傝DDS怣崋傪擖傟偰丄PIC偱DDS廃攇悢傪惂屼偡傟偽丄DDS_PLL_VCO偑弌棃忋偑傞丅