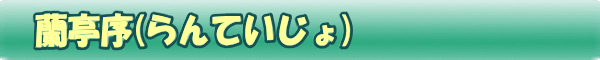| 本文 |
釈文 |
日本語訳 |
| 永和九年歳在癸丑暮春之初會干會稽山陰之蘭亭脩禊事也 |
|
永和九年、歳(とし)は癸丑(きちゅう)に在り、暮春(ぼしゅん)の(之)初め會稽山陰の蘭亭に會す。禊事(けいじ)を脩(しゅう)するなり。
|
永和九年(三五三)癸努丑の歳、三月初めに、会稽山のかたわらにある「蘭亭」で筆会をひらきました。心身を清めるのが目的の催しです。
|
| 郡賢畢至少長威集此地有崇山峻嶺茂林脩竹又有 |
|
郡賢畢(ことごと)く至り、少長威集まる。 此地、崇山峻嶺(すうさんしゅんれい)茂林脩竹(もりんしゅうちく)有り。
|
大勢の知識人、それも年配者から若い人までみんな来てくれました。さて、ここは神秘的な山、峻険な嶺に囲まれているところで、生い茂った林、そして見事にのびた竹があります。
|
| 清流激湍暎帯左右引以為流觴曲水列坐其次 |
|
清流激(せいりゅうげき)湍ありて、左右に暎帯(えいたい)せり。引きて以(も)ちて流觴(りゅうしょう)の曲水(きょくすい)と為(な)し、其の次(かたはら)に列坐す。
|
また、激しい水しぶきをあげている渓川の景観があって、左右に映えています。その水を引いて觴を流すための「曲水」をつくり一同まわりに座りました。
|
| 雖無絲竹管絃之盛一觴一詠亦足以暢叙幽情是日也 |
|
絲竹管絃(しちくかんげん)之(の)盛(せい)無しと雖(いへど)一觴(しょう)一詠(えい)。亦(また)以ちて幽情(ゆうじょう)を暢叙(ちょうじょ)するに足る是(こ)の日也。
|
楽団が控えていて音楽を奏でるような華やかさこそありませんが、觴がめぐってくる間に詩を詠ずるというこの催しには、心の奥を述べあうに足だけのすばらしさがあるのです。
|
| 天朗気清恵風和暢仰観宇宙之大俯察品類之盛 |
|
天朗(あきらか)に気清(すみ)、恵風和暢(けいふうわちょう)せり。仰いでは、宇宙の(之)大を観、俯(ふ)しては品類(ひんるい)の(之)盛(さかん)なるを察(み)る。
|
この日、空は晴れわたり空気は澄み、春風がのびやかにながれていました。
我々は、宇宙の大きさを仰ぎみるとともに、地上すべてのものの生命のすばらしさを思いやりました。
|
| 所以遊目騁懐足以極視聴之娯信可楽也 |
|
目を遊ばしめ、懐(おも)いを騁(は)する所以(しょえん)にして、以ちて視聴(しちょう)の(之)娯(たの)しみを極むるに足る。信(まこと)に楽しむ可きなり(也)。
|
なぜ我々が、目の保養をはかるのか、また、心を開いてのべ合おうとするのか、そのわけは其処あるのであって、見聞の楽しみの究極といえます。本当に楽しいことです。
|
| 夫人之相興俯仰一世或取諸懐抱悟言一室之内 |
|
夫(そ)れ人の(之)相興(あいとも)に一世に俯仰(ふぎょう)するや、或は諸(これ)を懐抱(かいほう)に取りて一室の(之)内に悟言(かんげん)し、
|
そもそも人間が、同じこの世で生きるうえにおいて、ある人は心中の見識こそいちばん大切だとして、部屋の内にこもり、うちとけて、
|
| 或因寄所託放浪形骸之外 |
|
或いは寄(よ)するに、託(たく)する所に因(よ)りて、形骸之外(けいがいのそと)に放浪(ほうろう)せり。
|
人々と相対して語り合おうとし、ある人は、言外の意こそすべての因だとして、肉体の外面を重んじ、自由に生きようとします。
|
| 雖趣舎萬殊静躁不同當其欣於所遇得於己 |
|
趣舎(しゅしゃ)萬殊(ばんしゅ)にして静躁(せいそう)同じからずと雖も、其の遇(あ)う所を(於)欣(よろこ)び、く己れに(於)得るに當りては |
どれをとりどれを捨てるかといっても、みな違いますし、有りさまも同じではありませんが、それぞれ合致すればよろこび合いますし、 |
| 怏然自足不知老之將至及其所之既倦情随事遷 |
|
怏然(おうぜん)として自ら足り、老いの(之)至らんと將(す)るを知らず。其の之(ゆ)く所、既に倦むに及びては、情事(じょうこと)に随ひて遷(うつ)り |
わずかの間でも、自分自身に納得するところがあると、
こころよく満ち足りてしまい年をとるのも忘れてしまうものです。
自分の進んでいた道が、もはやあきてしまったようなときには、感情はことごとく変わりますし、胸のうちも左右されてしまいます |
| 感慨係之矣向之所欣俛仰之閒以為陳迹 |
|
感慨之(これ)に係(かか)れり(矣)。向(さき)の(之)欣(よろこ)びし所は、俛仰(ふぎょう)の(之)間に、以(すで)に陳迹(ちんせき)と為る。
|
以前あれほど喜んでいたことでも、しばらくたつともはや過去の事跡となることもあります。
|
| 猶不能不以之興懐况脩短随化終期於盡 |
|
猶、之(これ)を以ちて、懐(おも)いを興(おこ)さざる能はず。
况(いはむ)や、脩短(しゅうたん)、化(か)に随(したが)い、終(つい)に(於)盡くるに期するをや。
|
だからこそおもしろいと、思わないわけにはいかないのです。
まして、ものごとの長所・短所は変化するものであってやがては終わりになってしまうのはどうしようもありません。
|
| 古人云死生亦大矣豈不痛哉毎攬昔人興感之由 |
|
古人も、死生亦(また)大なりと云う(矣)。豈、痛ましからず哉(や)。毎(つね)に昔人(せきじん)感を興(きょう)ずるの(之)由を攬(み)るに |
昔の人も死生こそ大きな問題だといっています。これほど痛ましいことはありません。昔の人は、いつも何に感激していたか、そのさまをみていると、
|
| 若合一契未嘗不臨文嗟悼不能喩之於懐固知一死生為虚誕 |
|
一契を合はすが若(ごと)し。嘗(かつ)て、文に臨みて嗟悼(さとう)せんずばあらず(未)。之を(於)懐(こころ)に喩(さと)す能はず。固(まこと)に死生を一にするは、虚誕(きょたん)たり |
割り符を合わせるようにきまっていました。
いまだかって、文を作るとき、なげき悲しまないでできたためしはなく、それを心に言いきかせるすべはありませんでした。実際に死生は一つだなどというのはでたらめです。 |
| 齊彭殤為妄作後之視今亦由今之視昔 |
|
彭殤(ほうしょう)を齊(ひと)しくするは妄作(もうさく)たるを知る。
後の(之)今を視(み)ること、亦由(なお)、今の(之)昔を視るがごとし。
|
長命も短命も同じなどというのは無知そのものです。後世の人が今日をどうみるか、きっと今の人が昔をみるようなものでしょう。
|
| 悲夫故列叙時人録其所述雖世殊事異所以興懐其致一也 |
|
悲しい夫(かな)。故に時の人を列叙(れつじょ)し、其の述ぶる所を録(ろく)す。世、殊に事、異なると雖(いえど)も、懐(おも)い興す所以は、其の致(むね)一也(なり)。
|
悲しいではありませんか。こんなわけで今日参会した方々の名を並記し、それぞれ述べたところを記録したわけです。
世の中がかわり、事物が異なったとしても、心に深く感ずるということの根拠は、たいてい一つにつながることです |
| 後之攬者亦將有感於斯文 |
|
後の(之)攬る者も、亦(また)、將(まさ)に(於)斯の文に感ずる有るらむ。
|
後々の世にこれを手にとって見てくれる人は、きっとこの文章に何かを感じてくれるにちがいないと信ずる次第です。
|