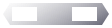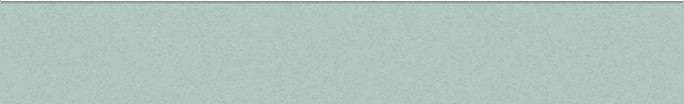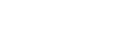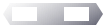茶道を楽しむ 表千家不白流 清風会師範 石原宗牛
C 動機不純な入門
入門当時の私の心を振り返る
「茶の湯の講演会を聴講していた かの岡本太郎画伯が立ち上がり、
なぜ、小難しく作法をするのか? お茶を飲むのだから、人それぞれ好きに飲めば良いはず、なぜだ、と詰め寄った・・・」
こんな場面を本で目にしました。私もその通りだと思っておりました。

動機不純なれど、お茶室の主菓子は美味しいものです。ですが、お茶室で頂く主菓子だから美味しいのです。むさ苦しい私の居間ではダメなのだと気付くに時間はかかりません。
お部屋に入り込む時の座して襖を引き開く作法、静かな足の運びなど何と優雅なものか。私には、馬子にも衣装ならぬ馬子にも茶道です。
夜咄し(yobanashi)の茶事を教室で催して頂くと、湯桶から汲んだお焦げ湯と香の物で、使った茶碗を洗い、洗った湯を飲み干す場面は、忌み嫌った遠い昔の食事の場面を思い出しこれが作法かとビックリ仰天するやら、お茶碗を差し出し二膝躙った時点で両者のその時の関わりが切れるとした狭い茶室空間での賢明な心遣いとか、いちいち刮目する次第です。

その点 西洋建築のドアの何と機能的でスマートな事かなどと眺める中、洋文化に浸り込んで今日に至りました。
だが、歳のせいなのかそもそも欧米文化の限界なのか、洋文化に飽きて和の文化が恋しくて仕方が無くなって参りました。だから、教室の門を叩いたのでしょう。

茶の湯の席は、物理的にも心理的にも日本文化の全てが伺える場と考える様になりました。
茶の湯の世界にある諸流派には、永年の経験の中で会得されたお茶を楽しむ美しい手順や振舞い、更には気遣いの具体的な方法として、作法が伝わっています。
お茶を頂くのですから、日頃いただくようにすれば良いのですが、一人で勝手に頂くのと違い、人が集い何らかの思いを醸し出そうとする場−お茶事−では、お互いが見せ、見られる場であり「お互いがどう振舞ったら美しく見えるか」が課題となります。これが茶道の教えと理解する様になりました。
室町時代の芸能世界の言葉で、演者と観客が共に一体となり、舞台だけで無くその場全体を芸能として完成させる事を意味する「一座建立」という言葉に通じます。
茶室での「一座建立」の方法は、人それぞれです。美しい振舞いを追求する茶の湯は詰まる所は物の芸術・心の美学です。美の価値観が人の数だけあるように、茶の湯の形は諸流派の数以上にあります。この、人それぞれの心得が最大公約数的に束ねられたものとして、諸流派が作法を現代に伝えています。
これは、人間社会に生きるに必要な日本の道徳や倫理なのでしょう。日本人の美しき知恵なのだと感じ入る次第です。

かように思い巡らしても悲しいかな、老いて踏み込んだ茶道の故か、和菓子ばかりが頭に残ります。
平成二十年六月 一日
宗牛