| ������ �M�҂́g���]�u�z�K�����q : ���e�̃��@�C�I���j�X�g���̌��I���U : 1920-2012�v�ƁA �����炭�����\�̎�������̍l�@�h�Ƃ��������^�C�g���̕��͂̒��ŁA�x�������̖��B�����g�ق̎Q�����ł������]���j��̃G�s�\�[�h���Љ���B�i������Q�Ƃ��������j �b�̎�|�͍]���͐펞���A��h�C�c�ŁA�Â�����̖��H�̍�̃��@�C�I�����i�⑰�̕��̘b�ł̓X�g���f�B���@���E�X�j���w�����A�����{�̔ނ̂��Ƃɓ͂���ꂽ�Ƃ������ƁA�X�g�����f�B���@���E�X��z�K�����q�ɑ��悷��悤�ɃQ�b�y���X��`���ɐi�������͎̂����ł������Ƃ����咣�ł���B �����͑�萳��́u�y���Ȃ�l�ԕ��i�v�����p�������A���̗��t�������͖����B������鉹�y�]�_�Ƃ̂���� �u�i�]���́j��������̃X�g���f�B���@���E�X�H�@���Ȃ��Ƃ�����̑��݂̉\�����ʔ������ł��B �������łɁA�I�[���h�E�C�^���A���̖���̌ːЂƏ��݂͂قڂ��ׂĂ����炩�ŁA������g�����������̃X�g���f�B���@���E�X�h�̉\���͂Ȃ������͂��B�v �Ƃ����A�������B�g�����������̃X�g���f�B���@���E�X�h�Ƃ͖ʔ����\���ƈ�l���S�������A�܂�]���̂��͖̂{���ł͂Ȃ��ł��낤�Ƃ����������A���@�C�I�����̖�O���ł���M�҂����������͂ɒ��J�ɃR�����g���������A���ӂɊ����Ȃ��B ���������̂悤�Ȃ��Ƃ����Ƃ����]���j��Ƃ́A�ǂ̂悤�Ȑl���ł������̂ł��낤�H�ƕM�҂̍D��S���������A�������s�����B ����萳��̉�z�^�� �܂���̑��̖{�ɂ́A�M�҂͏Љ�Ȃ��������A�]���̃��@�C�I�����̐^��ɂ��āA���̌�̓^����������Ă���B �]���͂܂��Ȃ����Ď������ɓ���邽�߂ɁA���̃��@�C�I��������������ӂ������B�|��̋����ŁANHK�������̃h�C�c�l�������������āA�Ӓ菑�̐M�҂傤�����A���ۂɎ������y������t���邱�Ƃɂ���Ċm���߂悤�Ƃ����B���ʂ̃��@�C�I�����ł̓z�[���̉��ʼn��������ĕ������Ȃ��̂ɁA�]������̊y��͖��Ăɉ����͂����B����ł�NHK�́i�{���ƔF�߂鎖���j�a�����̂ŁA�w���̘b�͕s���ɏI������悤�ł������B �܂��N�������āA�i�P�X�S�V�N�N���H�j�����V���Љ�̃x�e�����L�ғ��c�N���������������B���������̘b�͐V���̓ǂ݂��̂ɂȂ�Ȃ������B�Ӓ菑�̓��e���m���߂�藧�Ă��Ȃ���������ł������B�����Ă��̌���́A�]���Ɖ�@��͂Ȃ������B�����V���Ђ̃x�e�����̓��c�L�҂̑��݂́A�M�҂��l�b�g�Œ��ׂ�����ł͊m�F�ł��Ȃ��B �܂�^���͈ł̂܂܂Ƃ������A��͂肩�Ȃ�����Ȋ����̂���^��_���ł���B ������������ �p�X�|�[�g�ɋL���ꂽ���ɂ��ݓƖ��B�����g�َQ�����]���j��́A�P�W�X�U�N�P�P���P�T�����܂�ŁA�{�Ђ͉��R���ł���B���A�u���[���P�����v��|�P�X�U�U�N�ɏo�ł���Ă���B�����̎��g�ɂ�鏘������A�������������������m�邱�Ƃ��o����B �]���͉��R���̑�Z�����w�Z�ɒʂ��B���̎��n���̉��y��ŁA���[���b�p����A���ĊԂ��Ȃ��R�c�k��̉̂��B���̒��Ƀh�C�c�̃��}����`���l���[���P�̉̂��������B�R�c�� �u���h�C�c�ł́A���[���P�l�C�̓Q�[�e�𗽂����̂�����A���y��ōł��̂���̂͂��̎��ł���v�Ƙb�����B ���ꂪ���@�ƂȂ��āA�]���̓��[���P�ɋ��������悤�ɂȂ����B�������P�X�Q�R�N�ɓ���@�w���𑲋Ƃ���ƁA�����Ŋւɋ߁A���R���[���P����������������B ���̌�嗤�ɂ͖��B�����a�����A�P�X�R�V�N�V���P���t���Ńn���s�����ʎs�̎����ɏA���Ă���B��Ƀh�C�c�Ŕނ̏�i�ƂȂ�C�镶�͂��̎��ʉ��Ȃ̏Ȓ��ł���B ���h�C�c�ց� �i�`�X�h�C�c�����B�������F�����̂͂P�X�R�W�N�Q���Q�O���ł���B�q�g���[������ʼn��������B���Ɛݗ�����R�N�����o�߂��Ă����B�h�C�c�͓`���I�ɋ��͊W�ɂ���R���ږ�Ȃǂ������Ă�����������A���{�ւƗF�D�����ւ����B ����Ɋ�Â��A�����ԂŊO���g�߂��������邱�ƂɂȂ�B�P�X�R�W�N�P�O���Q���A�_�˂��o�`�����������ɁA�]����̖��B���W�҂���荞�B �Ԃ��Ȃ��x�������Ɍ��g�فA�n���u���N�s�ɂ����Ă͉��B�ɂ�����ŏ��ŗB��̑��̎��ق��J�݂��ꂽ�B�x���������g�قɃi���o�[�Q�ł���Q�����Ƃ��Ă���ė����̂��A�]���ł������B ���B���M�l�̎����͏��Ȃ����A�n���u���N���̎��قɋΖ��������{�E���̈⑰���ۗL����ʐ^�ɍ]�����ʂ��Ă���B�����Ȑl���ł���B�܂����{�̌�����I���Ɋ��o�Ȏ҂̏��ɂ��]���̒B�M���c����Ă���B  �P�[�j�b�q�X�x���N(���v���V���j�s�ɂ����閞�B�����{�s���J�ËL�O�B�e�@�o�b�N�̃{�[�h�ɂ́u���B���@�L���̍��v�Ə�����Ă���B�����ψ����@���{�E���@�ʐ^�������l�ڐ��{�A�O�䕨�Y�n���u���N�x�X�g�c�x�X���@�@�����E�������]���Q���� 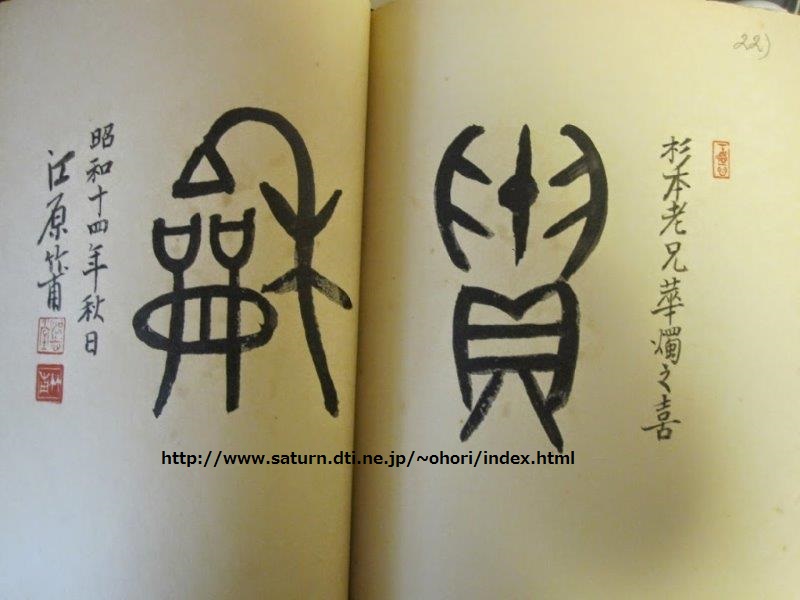 ���{�E���̌����ɍۂ��āB�]���̏��@�E�Ɂu���{�V�Z�ؐC�V��v�Ɠǂ߂�B�i�Q���Ƃ����{����j �P�X�R�X�N�X���A���B�ɐ푈���n�܂�A���{�l�w���q�͋}����A������B���̍ۏ�D���������ۂ̏�D����ɂ́A�Ȑ��q�ƂS�l�̎q���̖��O���ɏo�Ă���B�~�A���A�b�A���Ƃ����C�悤�Ȗ��O�ł��邪�A�q�������͐����Ă���W�O��㔼�ł��낤���B ���G�h�D�A���g�E���[���P�� ���܂���{�ł͓���݂̂Ȃ����l�̖��O�ł��邪�A�]���́g��P�̂����h�Ń��[���P�ƍĉ��B����Ƃ����̂̓x�������ł͋�P�x����ƁA�F�n�����ɔ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��B��������P�������͓ۋC�Ȃ��̂ł������Ƃ����B�P���Ԃ��n�����ɂڂ��肵�Ă���̂͑ދ��Ŏd�����Ȃ��B�����ō]���́A�n�����ɉ���邽�тɁA���[���P�������g���čs���A��т��|��������B ����Ŏ��l�ւ̋������Č����A���̌�͎蓖���莟��Ƀ��[���P�Ɋւ��镶�����W�߂�B�V���g�D�b�g�K���g�̃��[���P�̂��Ă̏Z�Ƃƕ�n��K��A���{�ɂQ�T�N���؍݂����O���f���g�A�n���u���N��w�w�������X�̏��������B�{�i�I�Ȍ����Ƃ̈�ɓ������ƌ����悤�B �Ȃ����̃O���f���g�w���ƍ]���̊ԂŌ��킳�ꂽ�莆�́A���݃n���u���N��w��Herbert Worm���m�̎�ŕۊǂ���A�M�҂͑�O�҂���ăR�s�[�������������B �i�Q�O�P�U�N�X���P�V���@�lj��j �����y�t�@���@�P�� ���A�]���͉��y�G���ɁA�펞���̉��B�ł̉��y�̌��̋L���������Ă���B�M�҂����������̂� �P�@���M ���v���N�̕Жe /�i���R�[�h�|�p�j �Q�@���q�A���g�E�V���g���E�X���̑z���o�i���R�[�h���y�j �R�@�y�����[�c�A���g��K�˂�--���[���b�p�Œ��������[�c�A���g�̉��y-1-�i���R�[�h���y�j �̂R�{�ł���B �����̕��͂���]���̐펞���̉��y�Ƃ̂������������Ă݂�B�܂�����̓h�C�c�̌�����}���h���\�����ȉƂ̂ЂƂ�A���q�����g�E�V���g���E�X�Ɛe������F�W������ł����B�]���͂��̎��V�O��㔼�ł������V���g���E�X���g���h�Ɛe�����ɏ����Ă���B�����Ď��̂悤�ȃG�s�\�[�h���Љ��Ă���B ���鎞�V���g���E�X���̓i�`�X�����̕v�l�����ŁA�x�������ɂ���ė��āA��`��b�Q�b�y���X�̒���ɍ]���Ƌ��ɎQ�����Ă����B�Q�b�y���X�ƃC�^���A��g�����_���l���ɂ��ċc�_���n�߂��̂ŁA�]���͂��̃O���[�v�ɓ����Ă���ƁA���͒m��ʊԂɉ��������グ�Ă��܂����B �����ł͍]�����g���A�Q�b�y���X�Ƃ̌�F������Ă���B�܂����y�ɑ��鑢�w�̐[�����������킹��B�ނ��u���鎞�A�����̃p�[�e�B�[�ŁA�Q�b�y���X��`���̎p������ƁA���ɋ߂Â��Ĉ��A�����킷�Ȃ�A�����q�ɃX�g���f�B���@���E�X�悵�����o�����B�v�Ƃ������̋L�q���e���A�����b�A�p�[�e�B�[�g�[�N�Ƃ��Ă͂��������Ɛ��������B �܂��P�X�S�R�N�U���Ɏ���㉉�̂��߂Ƀx�������ɗ����ہA�V���g���E�X���͏]�҂�A��A�P�O�����܂���O���[�l�����g�̍]���̎��@�ɐ��������Ƃ����B�V��ȉƂ̐M���Ă����؍��ł��낤�B�܂��Q�����Ƃ��āA���Ȃ�L���Ƃɍ]���͏Z��ł����̂ł��낤�B �����������Ƃ���V���g���E�X�͍]���Ɂu�I���Q�U�O�O�N�̏j�T�y�v�ƃI�y���u�J�v���`�I�v�̃X�P�b�`�u�b�N�� �u����Ȃ��̂ł����A�L�O�ɂ�����ĉ�����ł��傤���H�v�Ɛu�ˁA�]���� �u����Ă��������ł��v�Ɠ������B ����ɍ]���̓h�C�c�؍ݒ��A�V���g���E�X�̌��������߁A�E�B�[���A�~�����w���A�U���c�u���N�ɏo�����A�܂����N�̂悤�ɃU���c�u���N�ƁA�o�C���C�g�̉��y�Ղɏo�Ȃ����Ƃ����B���܂�O���̎��̂̂Ȃ����B���̎Q�����䂦�A���̂悤�Ɋe�n�ɏo���̖��ڂŏo�����A���y�����Ƃ��o�����̂ł��낤�B ���͍]���̃X�g���X���@���E�X�Ɋւ��u��h�C�c�ŊӒ菑�t���̃X�g���f�B�o���E�X�����v�Ə������A�������ɕp�ɂɓ�h�C�c�ɏo�|�����悤���B��������͍]�����g�̋L�q�ɂ����̂ł��邪�A���̍ۂ̂ǂ����ŁA������̃��@�C�I�������w���������Ƃ��l������B �����y�t�@���@�Q�� ���������]���̉��y�̎����b�������B�P�X�S�P�N�̓��[�c�A���g�v��P�T�O�N�̔N�ł������B���̔N�̂P�P��������P�Q���ɂ����āA�U���c�u���N�ŋL�O�Ղ��J�Â��ꂽ�B �Ō�̔ӂ̔ӂ����̓E�B�[���̃K�E���C�^�[�A�i��Nj�w���ҁj�ł���V�[���b�n�v�Ȃ̎�ÂŁA�V�O�O�������҂��ꂽ�B���Ȃ���}���A�E�e���W�A�̐������Č������l�ł������ƍ]���͉�z����B�����ł͍]���͒����H��̃V�[���b�n�v�l�ׂ̗ɐЂ�^����ꂽ���A�����e�[�u���ɂ͎w���҃t���g�x���O���[�������B ���̋L�O�Ղɂ͑哇�_���Ƒ�g���Ȃ�A��ďo�Ȃ������A���{�̎Q��߂��ŁA���߂Ƀx�������ɖ߂��Ă���B �܂��P�X�X�S�S�N�U���A��N�̂��Ƃ��o�C���C�g���y�ՂɎ�Î҃��[�O�i�[�v�l�̏��҂����]���́A���{�ł̔ӎ`��ɏo�Ȃ��A���̌�ōL�Ԃɒʂ��ꂽ�B�����ɂ͂S�l�̌��ْc�����ă����o�[�͑S���A���B�ɂ̍����ȑt�҂ł������B�����Ă�������͍̂]���Ɛ��s��W�N�A���Ƃ͎�l���̂P�O�l���炸�ł������Ƃ����B �����������ʂȑҋ������̂́A���B���̎Q�����̂��A����Ƃ��{�l�̉��y�ɑ����M�̂��H�����炭���҂ł��낤�B�]���͉��B�ɒ��݂������{�l�̒��ŁA�ō����x���̉��y�ɍł������ڂ����ƌ����悤�B����ɂ��Ă����������L���̒��ɁA�𗬂��������Ƃ����z�K�����q�̘b���o�Ă��Ȃ��͉̂��̂ł��낤�H ���Ⴂ�O�����̍]������ �P�X�S�R�N�Q���P�P���A�E�B�[���ň��v��Ȃ́u���B���t�@���^�W�[�v���㉉�����B���t�̓E�B�[���E�t�B���n�[���j�[�ł���B�E�B�[���̐V���́A���̃R���T�[�g�͓��{�̋I���Q�U�O�R�N�ƁA���B���Ƃ̗F�D���L�O���ĂƏ����Ă���B�Q���P�P���͓��{�͋I���߁i�����L�O���j�ł������B���ꂪ���߂Ƀx�������̓��{��g�ق���͌��o��Y�Q�����ƁA���B�����g�ق̍]�����Q���B ���{����t�����X�Ɍ������r���̊O������̍����ۂ́A���R�]���Ɖ�����ۂ̈�ۂ���L�ɏ����c���Ă���B �u�]�����ɂ͎��ɔ������Z�M���̐e���݂��������B�i�����j�Ⴂ���I�����藧�ĂāA�������F������������Ă����v �]���͊O�����Ƃ������A�|�p���̐l�Ԃł��������Ƃ�������B �i�Q�O�P�U�N�P�Q���P�P���lj��j �������g���� �h�C�c�̕���ɔ����A���{�l�̓h�C�c�����邱�ƂɂȂ�B���B���W�҂̈�s�̓x�����������R�T�L���̃O���f�n�C���ɑa�J���A�\�A�R�ɂ��ی��҂����B�����Ĕނ�̎�Ŗ��B�ɑ����邪�A��s�̃��[�_�[�͍]���ł������B�O���ȊO���j���قɔނ�̈����g���̋L�^���c����Ă���B ���a20�N7��12�� �ݖ��@�R�c��g�@�@������b�@�� �ݓƍ]�����F���Q�����y��s���g����Ɋւ��錏 �ݑh��g�ق��G�ɑh�A�o�R���g����ݓƖ��F���]���Q������s11���A�h�C�c������胂�X�N�����̈��g��p�i����A�H���A�ו��^�������j�\�A����萿�����肽��ɂ��A�A�A�i�ȉ��ȗ��j�v �\�A�̎�ɂ���ĖM�l�͓��{�ɑ���ꂽ���A���̔�p�͓��{���ɐ�������A�Ō�͌l���S�Ƃ������ł������B �]���͖��B�������ł���������A���̂܂ܓ��{�ɂ͖߂炸���B�ɗ��܂�A�����ŏI����}�����͂��ł���B�������I��̗��N�̃N���X�}�X�ɂ͓��{�ɂ���̂ŁA�\�A�R�̎�ɂ��}���̑O�ɓ��{�ɔ��ł����̂��A�������͂P�N���炢�̗}���ł���ł���B ����い �h�C�c���g�ł������C�X���͖��B�l�́A���܂��Ȃ��A�����ŏ��Y�����B������{�l�ł������]���ɑ��Ă̂���߂͂Ȃ������悤���B �����Đ��ٌ͕�m�Ƃ��Ċ���B�@�w�����ƂƂ��Ă���Ζ{�Ƃł��낤�B����ٌ�m��V��̐��̒��S�����o�[�̈�l�ƂȂ��Ă���B�u���F��̗��j�Ǝ��v�@�i�ٌ�m ������j�ɂ͍]���̖��O�������ɓo�ꂷ��B�Ⴆ�Έȉ��̂悤���B �\�L��搶��i�������l�B��O�n��������g���Ă����R�c���A�]���j��搶�炪���S�ƂȂ�A��㏉��̖@���Ȑl���i��ǒ��ƂȂ����厺����搶���i���ٌ�m��j��ɐ����������䓪�����B �\���R��ى����ׂ��l���Ƃ��Ă��̎R�c���A�]���j��Y���搶�̍����w���͑�ς�����ċ���A�A�A ����ɍ]���̊�������͍L����B���{�L���X�g������Ԃ��Ȃ��A�]���̂����肷��ɍۂ��A�̎��M��҂Ƃ��Ė��O���������Ă���B�܂������Ɍ��ꂽ�@���v�z�ƌ����^�C�g���ŕ��͂��G���u���R�Ɛ��`�v�ɏ����Ă���B�h�i�ȃL���X�g���k�ł������̂�������Ȃ��B �����čŌ�͊w������ɖ�����ꂽ�A���[���P�����̏o�łł���B���Ƃ��ƂP�X�T�S�N�ɏo�ł����\��ł��������A�v�悪�y�d��ŕ���A�P�X�U�U�N�P�O���ɏo�łƂȂ�B ���I���Ɂ� ���̂悤�ɁA�]���͊O�����A�ٌ�m�A���[���P�̐��ƁA�|��ƁA�]���̖̂|��҂Ɨl�X�Ȋ�������Ƃ����������B �M�҂̒����ł��ŏ��̖{�l�������������@�C�I�����̋^��ɑ��Ă̓����ɂ͂Ȃ�Ȃ����A�풆���ɂ����ă}���`�^�����g��������l�̐l�ԑ��������яオ��B���̂悤�ȏT�x�Q���ł͂Ȃ�����ɁA�ǂ̂悤�Ɏ��Ԃ��˂�o�����̂ł��낤���H ��Ɉ��p��������̉�z�ɂ��� �u�R�c�搶�̂��Ƃ̉���Ƃ��ẮA�]���j��搶���O�ڂ̌���Ƃ���ł��������A�s�K�ɂ��ď��a�S�S�N�P�Q���P�S�����S�v�Ƃ���̂ŁA�P�X�U�X�N�ɂV�R�ŖS���Ȃ�B �I��� �i�Q�O�P�T�N�U���P�T���j �������l�@�]���� �����܂ł̕��͂����J��������A�u�ߑ��Ɠ��{���v�{��������i�ق݂�������j�̒��́u���B�T���L�v�@��F���i�R���D�D�x���������݈��j�ɍ]�����o�ꂵ�Ă���ƁA�����ؑ��m����ɋ����Ă����������B���̖{�͂ƂĂ������[���̂ł��邪�A�����ł͍]���ɂ��Ă̂ݏ����B �܂���ɏq�ׂ����V���g���E�X�����P�O�������܂����Ƃ����A�]���̏Z�܂��ɂ��ďڂ����L�q������B �u�]������͕����l���B�O���[�l�����g�̌ΐ��ɖʂ��郔�B�����ꌬ��Ă����邪�A��ɒ��X����鐔�{���ԏ���ʂ��āA�Â��ɕ��䂭���ʂɒނ肷�鏬�M�A�ΐ��̌������͂܂��ԏ��сB �T�����ɂ͐����@�́h��h�Ƃ����r�����Ȃ������ꎚ�̝G�z��������A�I�ɂ͈��āA����A����A�����A���{�̓��A�x�߁A���{�̊G�{���A�m�����A�V�l�̉f�ʋ@���Ɠ������Ă��āA�������j����������Ă��Ȃ��B��X�͂������̉ƂƌĂ�ł���B�i�����j ���玪�G�����A�p�i�ɂȂ����\�ʂ��ė��āA�A�A�B�v�]���͌Ó��������ē��m���p���W�߂Ă����B ���ō]���̐R����̍����ɂ��Č����B �u�ʕ���ʂƂ���ɐR����̍����������A����͌c����w������p�j��U�̂��߁A���n�n�w���̎牮�i����j���������S���Ă���B�v �����ē����h�C�c�ɂ͑����̓��{�����o����Ă������A���̂قƂ�ǂ͂R���ȉ��̂܂������ł������B���������B�����g�قɔ����݂�����A�]��������ōw���������́A���Ƃł������R���Ԏ�āA���ߕ�炵��,��_�̔�̌�����Ȃ��A���q����̖��H�A�g�[�̍�Łu�@��o�������̌@��o�����v�Ƒ�͏����B ��͍]�����x�^�J�߂��Ă���B��������]���̓X�g���f�B���@���E�X�Ə̂���郔�@�C�I�����Ɋւ��Ă��A�����ĕςȕ��Ɏ���o���͂����Ȃ��Ƒz�������B �i�Q�O�P�T�N�U���Q�W���j �������l�@�]���@�Q�� �]���ɂ��āA�܌��J���ł��邪�A���낢��Ǝj����������B���x�͏��������퐶�q�̋L�q����ł���B �P�X�R�W�N�P�O���S���A�����ۂʼn��B�Ɍ������D��ō]���ƈ����B�]���͖��B���Q�����Ƃ��ăx�������ɕ��C����r��ł������B ���̌�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ�����āA���N�V���Q�W���A���v�Ȃ̓x�������ɒ����B�h���͓��{�l���ǂ����p�����z�e���E�G���N�\���ł������B�����ė��V���Q�X���ɂ� �u���B���̍]�����̌}���̎ԂāA��������z��������Ƃ����i���B���́j�������Ɍ������B�v�ƍĉ�Ă���B�]���͂��̊Ԃ��łɂɃx�������ł̐������m�����Ă����B �V���R�O���A �u�R�����A�]���v�Ȃ̌}�����A�w�����Z���������ɍs���B���́i�x�������j�I�����s�b�N�̉^����B �|�c�_���ɎԂ��삯��A���@���[�[�̍]�����̉ẲƖK��B���@���[�[�̐��ɓY�����X��A�y�n�́A�x�������̎s���ɂȂ��h���h������������B��ɉԂ�Ύ��ɏ[�����O��������A����ɓY���Č��T������̂̕ʑ��n�͔������B�]�����̎�Ă���ĂɉƂ͂��̈�ŁA���̕ʑ��n�̑������Ƃ����B�v ���̕ʑ��͐�ɏЉ���O���[�l�����g�̕ʑ��Ɠ������̂ł���B �����łW���P�� �u���C�}�[���s���B�]�����̃r���[�C�b�N�i�A�����J�̎ԁ\�M�ҁj�ŏo�|����B�]���v�ȁA�J���i�g�Y�j���B����Ɏ��B�v�ƘA���ʓ|������B ����ɂW���Q�� �u�]��������̓d�b�ŁA�A�����ʂ�̂��Ƃ֎f���B��ɂ���ĒJ���������A�����Ă������y���ɂȂ�B�]�������@��o�����h�g�r�f�h�̔\���i����傫���J���A�ڂ��яo���悤�Ɍ��J�����A�_�̂������ʁ\�M�ҁj�����āA�ނ̎B���������i�W�~���f���ł��낤�[�M�ҁj������B�v �]���͕ʑ��̑��ɁA�s���ɉƂ������Ă������Ƃ�������B�܂��\�ʁA�����f��͑O�ɏЉ����̕��͂ɂ��o�ꂷ��B�]���͒N�����F�߂镗���l�ł������B ���̃��C�}�[�����s�Ɋւ��ẮA������l�̓��s�ҒJ���g�Y�������u�����炬���L�v�ɏ����Ă���B �������͒��H���Ƃ邽�߂ɊX�̏��������X�g�����ɓ������B�X�̓��ӂȗ������Ƃ������𒍕�����ƁA���������B���̂��ƁA�]���v�l�����Q���ꂽ�u�̂芪���v��H�ׂȂ���A�̍��̖�����������ł���ƁA�����l�����A�ɏo�ė����̂ŁA���H�������߂�B��������ɓ���A��Ŗ����ᖡ����ƁA�ڂ��ۂ����āu�f�G���v�Ɠ�����B �i�u�����炬���L�v�͂Q�O�P�U�N�X���V���lj��j ����ɖ��v�Ȃ��p���Ɉړ�������̂W���P�R�� �u�����炨������i�v�̂��Ɓ\�M�ҁj�͍]���v�Ȃ����[�u���Ɉē�����B�v�Ƃ���A�����͍]���̏��҂ŁA�I�y����K�₵�Ă���B�s���̑D�ł��܂��܈ꏏ�ɂȂ��������ŁA�����܂Ŗʓ|������Ƃ͎v���Ȃ��B���Ƃƍ]���Ƃ͓��{�ł��q���肪�������̂ł��낤�B �܂��퐶�q�̕v�L��Y�͔\�ʂ̌����Ƃł������B�����ăx�������̖��������قɂ���\�ʂ�������A �u����i�����ق̔\�ʁj�ɔ�ׂ�ƁA�]���N���x�������̂��鍜�����̓X��Ō����Ĕ����ċA�����h�g�r�f�h�͌����ȍ�ł������B�����]���N�̉Ƃ֍s�������A���̃g�r�f�͌ÐV���ɕ�܂�Ă����܂����o���ꂽ���A���͂��̋s�҂���Ă����Ƃ悭�ۑ�����悤�ɒ��������B�v�Ɩ퐶�q���������g�r�f�̑f���炵���������Ă���B �i�w�\�ʘ_�l�x�@1944�N�@���j ���v�Ȃ̕��͂����Ă��A�]���̕�������ڂ̊m�������m�F�ł����B���ꂾ�������̏����Ȃ���A��̃X�g���f�B���@���E�X�Ɋւ���L�q���ˑR�o�Ă��Ȃ��̂��c�O�ł���B �i�Q�O�P�T�N�V���Q�O���j <�]���j��ƃ��q�����g�E�V���g���E�X�̃X�P�b�`�u�b�N> ������ ���B���Q�����]���j��́A�펞���̃x�������ŁA��ȉƌ��w���҃��q�����g�E�V���g���E�X�Ɛe��������ł������͂��łɏ������B �����W�O�߂��V���g���E�X�͂P�X�S�R�N�U���A����㉉�̂��߂Ƀx�������ɗ����ہA�]�҂�A��P�O�����܂���O���[�l�����g�̍]���̎��@�ɐ��������Ƃ����B�V��ȉƂ̐M���Ă����؍��ł��낤�B�܂��Q�����Ƃ��āA�]���͂��Ȃ藧�h�ȉƂɏZ��ł��������z�������B �����������Ƃ���V���g���E�X�͍]���Ɂu�I���Q�U�O�O�N�̏j�T�y�v�ƃI�y���u�J�v���`�I�v�̃X�P�b�`�u�b�N�� �u����Ȃ��̂ł����A�L�O�ɂ�����ĉ�����ł��傤���H�v�ƍT���߂ɐu�˂��B�]���́u����Ă��������ł��v�Ɠ������B ����ƃV���g���E�X�͂��̏�ő���̎�����������āA�]���ɓn�����̂ł������B�u�]�����ɕ�����v�ƌ����悤�ɏ������܂ꂽ�̂ł��낤�B�O�҂�1940�N�A���{���I���Q�U�O�O�N���}����̂��L�O���č��ꂽ�nj��y�Ȃł���B�V���g���E�X�̍�i�̒��ł����炭�ł����t����Ȃ���i�Ƃ̎��ł��邪�A�i�`�X�̎���Əd�Ȃ邱�Ƃ����̈���ł��낤�B ��҃J�v���b�`���͂P�X�S�Q�N�P�O���Q�W���A�o�C�G���������̌���ŏ������ꂽ�B ���X�P�b�`�u�b�N�� �]���ɑ��悵���u�X�P�b�`�u�b�N�v�ł��邪�A�V���g���E�X�ɂƂ��ăX�P�b�`�u�b�N�Ƃ͂ǂ̂悤�ȕ��Ȃ̂ł��낤���H�{�l�̌��t�ɂ��A �u�U�����Ă���ԁA�h���C�u���A���H���Ă���Ƃ��A�Ƃɂ��Ă��O�o���ł��A���͂ǂ��ɂ��Ă���Ȃ��Ă���B���X�����z�e���A���̒�A��Ԃ̒��A�����X�P�b�`����g�ɂ��Ă��āA�v������ ���@���ɂ���ɏ������߂�v�Ƃ��Ă���B�i�u���q�����g�E�X�g���E�X�̎����v���j �܂��V���g���E�X�Ɛe������������{��ƁA�V���e�t�@���E�c���@�C�N�͎����̒��ŁA�V���g���E�X�̐E�l�I�Ȏd���̎d���Ƃ��� �u�����X���Ɋ��̑O�ɍ���A�O���I������Ƃ��납��A�K���I�ɉ��M�ōŏ��̃X�P�b�`�������A������C���N�Ńs�A�m���ɂ��Ă����v�Ə����Ă���B�i�gDie Welt von Gestern�g���j ���́g�ŏ��̉��M�����̃X�P�b�`�h���A�O�q�̃X�P�b�`�u�b�N���w���Ă��悤�B �߂�V���g���E�X�̃X�P�b�`�u�b�N�͍�i�̌��ƂȂ���̂ŁA�̌��ł͕���C���[�W��������Ă����Ǝv����B ���X�P�b�`�u�b�N�T���� ���y�����ƂɂƂ��Ă��M�d�Ȏ����̂悤�� �A�����J�̂��鉹�y���j�Ƃ���M�҂ɃR���^�N�g���������B�ނ͂܂��Ƀ��q�����g�E�V���g���E�X�̌��������Ă���A�P�X�W�U�N�V���g���E�X�̑��q�̖��S�l�A���[�`�F���h�C�c�ɖK�₵���ہA�]���ɓn�����X�P�b�`�u�b�N�̃R�s�[�������Ƃ����̂��B �u�N���]���̊W�҂��A�ޏ��ɑ������̂ł��낤�A�I���W�i���͍����]���̊W�҂ɂ���͂����v�Ƃ����̂��A�ނ̐����ł������B �M�҂͔ނ̐��ɂ�������A�X�P�b�`�u�b�N�̌��{��T�����Ƃ����B�����č]���̐e���̕����l�T���o���A�����Ă݂��� �u�I��Ń\�A�A���B���o�R���Ĉ����g���Ă���ۂ́A�g��ŁA�h�C�c����̂��͉̂��������A���ė��Ȃ������ƕ����Ă��܂��v�Ƃ̎��ł������B�c�O�ł��邪�A����ȏ�͕����o���Ȃ��B �ډ��W�҂̌��ɂȂ����͊ԈႢ�Ȃ��̂ł��낤���A�h�C�c����S�����������A��Ȃ������Ƃ����͎̂����ł��낤���H�O�q�̂悤�ɉ��y���j�Ƃ��A���̃R�s�[�������Ƃ����،�������B �]���̓h�C�c����ɂ��낢��W�߂����Ƃ́u�����l�@�]���v�ɏ������B�ނ� �h�C�c�̎��l�G�h�D�A���g�E�t���[�h���q�E���[���P�̃t�@���ł�����A���̕������W�߂Ă���B���W�̏��ŁA���łȂǂł���B �h�C�c�؍ݒ��̓��[���P�̖Â��~�����w���ɒT���o���A���[���P�̎����A���e���̑��̋L�O�i����ɓ���鎖���o�����B������ �u�i�����́j�������ЂŎ����Đ��Ɏc�O�Ȃ��Ƃ��������A���Ŏ��l�̈��p�����ዾ������(�����A��)�A������ɕۑ����Ă���v(���G�Q��)�v�Ə����Ă���B���[���P�̊ዾ���������\�A�̌��{�A�v����������A���{�Ɏ����A�������͊m���ł���B�i�w���[���P�����x�]���j���@�������j �܂��]���ɂ͎��̂悤�ȃG�s�\�[�h������B �ނ͓�h�C�c�ŊӒ菑�t���̃��@�C�I�����i�X�g���f�B���@���E�X�H�j����肵�����A�x�������Ɋ�@������ƁA�������X�G�[�f���̉��������قɂ��̕ۊǂ𗊂B�����Đ��]���X�G�[�f�����疳���ɓ��{�̍]���̌��ɖ߂����Ƃ����B�܂�x�������ח��ŁA���{�ɑ��҂����O�ɁA�M�d�i����[�X�G�[�f���ɗa���A��㖳���Ɏ���i������Ă���̂ł���B�����ɃX�P�b�`�u�b�N���܂܂�Ȃ��������H �t��������Ƃ��̃��@�C�I�������]���͎藣�����Ƃ����B��ɋ������e���̕��ɂ��ƁA����̓X�g���f�B���@���E�X�ŁA����������͗��w���钼�O�́A�������o�����́A�Ⴂ�������@�C�I���j�X�g�ł������B�������ޏ��͊Ԃ��Ȃ��S���Ȃ�A���̌�̖���̏����͕s���Ƃ̎��ł���B �X�P�b�`�u�b�N�͈�x�́A���{�ɓ͂����̂ł͂Ȃ��낤���H�����Ă��̌�A�N���ق��̐l�̎�ɓn�����̂ł͂Ȃ����B�����炭���{�l�ł��낤�B�����A�Ђ�����苣���ɂł��o�i�����̂ł��낤���H (�Q�O�P�U�N�R���Q�V��) �M�҂̏��Ђ̂��ē��������� �w����E��퉺�̉��B�M�l(�h�C�c�E�X�C�X)�x�������� 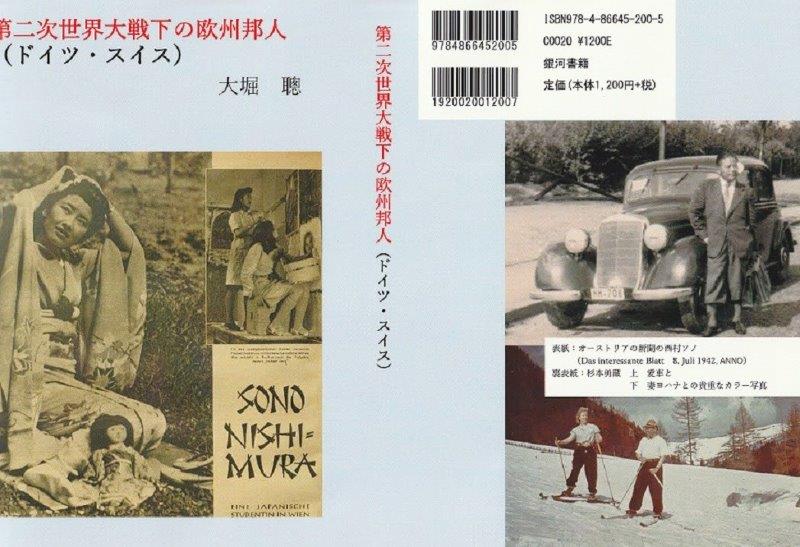 |