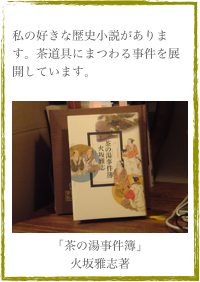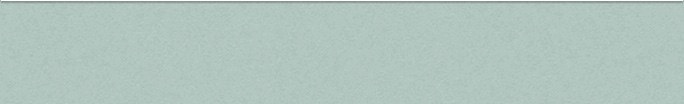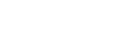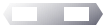茶道を楽しむ 表千家不白流 清風会師範 石原宗牛
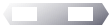


B 抹茶を頂こう
表千家不白流とは
川上不白の登場
如心斎という表千家七代宗家がいました。表千家では、中興の祖と敬っています。時代は、関ヶ原の戦から百五十年を経て商工経済が発展し町人文化が成長。如心斎は武家の文化であった茶道を江戸に広めんと図ります。
この大任を負うたのが、如心斎から千家茶道の奥義まで伝授されていた川上不白(江戸千家の祖)なる若き(三十二歳)高弟でした。

江戸の武家階級は武家茶道の石州流が良く普及しており、京の千家茶道は中々浸透しなかった様ですが町人階級への交流も力を入れたことで広く浸透するようになり、江戸千家と呼ばれるようになります。
この間、興味ある事件があります。
如心斎が四十七歳の若さで死にます。如心斎の後継は八歳の宗員。不白は京に戻り四年かけて宗員に茶道を教え込み宗家を継がせます。
また、江戸の豪商、材木商の冬木屋に、千家が探しに探していた「利休辞世の偈(rikyu-jisei-no-ge)」を不白が発見し、京の如心斎に届けます。如心斎から冬木屋に返礼として、利休が古田織部に宛てた「武蔵鐙の文(musasi-abumi-no-fumi)」を届けます。この手紙の中で触れている、小田原の陣にあった利休が自ら作ったと云う「園城寺竹花入れ」も冬木屋は所蔵していましたから、この手紙は園城寺花入れの利休自らの添え書きと成ったのです。
(2010/10 石原宗牛。 参考資料イ;「川上不白茶中茶外」寺本界雄、 参考資料ロ;「茶の湯事件簿」火坂雅志、 参考資料ハ;三千家各HP)