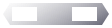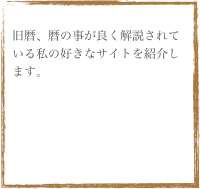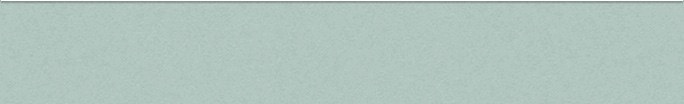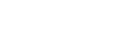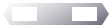茶道を楽しむ 表千家不白流 清風会師範 石原宗牛
E 茶道徒然草
半夏生(hangesyou)
太陽と孫と共に起きて朝の散歩に出ると、農道に面した土手の草の中に不思議なものを見つけました。撮影したこの写真、何が写っているのか分かりますか。

「カラスビシャク」が写っています。見えますかな。
茶花の花材にあるウラシマソウの様な構造をしています。
暦に二十四節気(sekki)、そして各節気の中にそれぞれ三つの候(kou)が設けられた七十二候があります。六月末の頃の暦には、夏至(夏至の日とは区別)という節気の期間中の三つ目の候に、
半夏生hangesyou ( はんげが、しょうずる。)
があります。「半夏」が野に現れる頃である、の意です。中国で開発された七十二候ですから半夏は中国名。この日本名がカラスビシャクという訳です。
半夏が生ずる頃とは夏至の日から約十一日経過した頃で、農家では田植えを終えてしまう事になっているそうな。四国では松明を持ち錬り歩き悪い虫を追い出す「虫送り」行事、小麦の収穫時期である事からうどんとか小麦の餅を食すとか、蛸を食すとかの風習がある地方もあるのです。
ところで茶花として使われる「半夏生」という和名の野草があります。この半夏生という野草は、やはり、七十二候の半夏生のころ花咲くので名付けられたもので先のカラスビシャクとは姿も生い立ちも全く異なるものです。
二十四節気、七十二候は、太陽暦から出来ていますので日本の旧暦と違って時のズレ無く季節を映し出してくれて私は重宝しております。(宗牛 2011/7/4)