戦後初の渡欧者を求めて
Visiting Europe of Japanese right after the war.
大堀 聰
<序> 1945年8月の日本の敗戦で、欧米の在留邦人は原則、全員が日本に引き揚げた。そして1951年9月8日、日本は米国など48カ国とサンフランシスコ条約を締結して、戦争状態を終結させることが出来た。海外には再び日本の大使館が設置された。これ以降、海外渡航が再び可能になったと言える。もちろん厳しい外貨の持ち出し制限は残る ではその戦後の渡航はどのようであったか?たとえば作家遠藤周作は、1950年6月4日 フランス船 マルセイエーズ号で横浜を出発し、7月5日マルセーユに到着する。そして書物には“戦後初のフランス留学生”と書かれている。 一方アメリカには戦後「フルブライト交流事業」が出来て、今日まで続いている。この事業の前身として、当初はガリオア・プログラムがあり、1949年から1951年まで、約1,000名の日本人が米国へ留学したという。(フルブライト交流事業ウェッブサイトより) 現在年間50人程度に対し、3年で1000人というのはずいぶんと多い印象だが、やはりサンフランシスコ条約加入と前後して、留学生がフランス、アメリカに再び出始めたと言えよう。 よってこの時期もしくは以前に海外に欧州に渡航した日本人がいたとすれば、かなり例外的である。本編ではこうした特異な邦人の欧州への渡航の経緯を追う。またアメリカへの渡航者は姉妹編「石垣綾子日記に見る、終戦直後の渡米日本人」を参照ください。 <西村伊作の娘ヨネ> 文化学院の創設者西村伊作は独自の教育観を持ち9人の子供を育てたが、そのうち4人の娘が、今回のテーマである1950年以前に海外に渡っている。(付け加えれば残りの2人の娘は戦前に留学している。) まずは3女西村ヨネである。彼女は戦前の1935年7月、戦後NHKの英語講師を務める松本亨等と共にシアトルに向かい、第2回日米学生会議に出席する。そして日本に滞在するスエーデン人カール・リーベルと終戦間際の1944年12月18日に結婚式を挙げた。 1946年1月、終戦から5か月しか経たない時に、彼女はアメリカの病院船で夫と共にシアトルに向かう。しかも出産間近であった。そして2月15日、シアトルの病院で、長女マリアンを出産した。 ヨネがこの時期に渡欧できたのは、スエーデンのパスポートを持っていたためであった。戦時中もアメリカに留まった松本亮は「自分の知る限りでは、戦時中は日本にいた日本人で、戦後最初にアメリカに来たのは西村ヨネ」と書いている。 同年4月、スエーデンの客船グリップス・ホルム号(the Gripsholm)で夫妻はストックホルムに着く。戦後初めて日本から帰国した若夫婦は、四方から質問攻めにあったという。ヨネは後に書いている。 「私たちがスエーデンに到着したのは4月15日で、北の国にもやっと春が訪れたときでした。」(「真夜中に太陽の照る国」より) スエーデンでは日本の敗戦後も中立国に留まっていた、外交官、軍人らにマッカーサーの帰国命令が出て、同年1月20日に岡本季正公使以下全員が、引揚船の出るナポリに向かって旅立った。その3か月後の事であった。戦後最初の渡欧日本人で間違いなかろう。 なお他の3人の娘はアメリカに向かっているので、こちらを参照されたい。 <スイス> スイスの公文書館に「日本人の入国1946年〜1959年」という史料が残っている。 もっぱらフランス語で書かれているのが、筆者には難物である。これからスイスへの入国者について読み解いていく。 最初に出てくるのは”Akira SUEKUNI”で1946年3月18日に申請をしている。彼が戦時中、スイスの公使館に勤務していた末国章であることはすぐにわかった。 スイスにおいて邦人が日本に引き揚げたのは、同年1月24日の事であった。末国は妻(ジルベルテ)子供二人(アキコ,レイジ)と共に、加瀬俊一公使らと船の出るナポリまで向かったが、病気のため、帰国船には乗らなかった。そこからスイスへの入国申請となったのだが、書類には「異議なし」と書かれているので、晴れて入国第一号となった。 次の申請は”Morido INAGAKI”で1946年8月26日の申請である。終戦からわずか1年後である。生まれは1923年で大学生、住まいは長野県軽井沢と書かれている。苗字は“稲垣”と分かるが、名前の考察は後程行う。 終戦時軽井沢に住んでいたとすれば、上記西村家のような相当な富裕層か、外国人と結婚した人物が想定される。そして日本のスイス公使館に直接申請したのであろうか? ネットで調べたところ、ソーシャル・ネットワーキング・サービスである“LinkedIn”にまさにMorido INAGAKIの名前が登録されて、写真と共に英語で自分の研究歴を紹介している。要約すると以下のようだ。 1935年から1939年までジュネーブのカルヴァン単科大学で学び、戦後1949年〜1950年はアメリカBowdoin Collegeで奨学金を受けて学ぶ。 そして「ジュネーブに戻ることに決めた」とあり、ジュネーブ大学で1951年から1957年まで学び、多くの資格を取得している。彼は2000年代に入っても活躍している。 このネット上の人物と同一人物であることは間違いない。1946年にスイス入国を申請し一旦入国するが、すぐにアメリカに渡り、1951年にまたスイスに戻った可能性が高い。敗戦直後の日本人が、まるでアクロバットの様な海外渡航が出来たのは驚きだ。 <稲垣守克> スイスのリストには、間に数名入るが、1949年9月6日には” Morikatu INAGAKI”の名前の申請がある。1893年生まれで住居は東京である。もう一人稲垣姓の人間が、スイスの入国を申請している。こちらは稲垣守克で間違いない。 ジュネーブの国際連盟で日本の常任代表を務めていた稲垣守克は1939年、欧州戦争勃発前に日本に引き揚げた。そして彼の働きかけにより1948年、尾崎行雄を代表、協同組合の父・賀川豊彦を副代表という布陣で、日本における世界連邦運動が発動することになった。また遡って1922年には、来日したアインシュタインの通訳をしている。アインシュタイン夫人と守克のドイツ生まれのトニー夫人は、その際に多く行動を共にしている。 そして1949年8月26日の朝日新聞に「(稲垣守克らは)9月、ストックホルムで開かれる世界連邦国際運動大会に出席のため、8月23日東京を出発した」という記事が出ている。先に述べたスイスの入国申請の時期と一致しているので、この後スイスに寄ったのであろう。タイミングからして空路による渡欧でないか。スイスでは、名前の知られた守克であるから許可はすぐ下りたであろう。 <稲垣守働> 子供が親の名前の一字を取ることは、よくあることである。守克(Morikatu)は先のMoridoより30年前に生まれている。そこから先述のMorido INAGAKIは稲垣守働であることを探し当てた。 守働は“World”という戦後の民主化の中で生まれ、間もなく消えた雑誌に「スイス通信:第一報」、「横浜からスイスまで:ヨーロッパ留学記」という2つの記事を書いている。 記事の冒頭の説明には「世界連邦同盟理事長を父に、幼児からカレッジ4年までの青年時代の初期をスイスで育った。その後東大理学部に入り、戦後初のヨーロッパへの留学生」と紹介されている。外国での教育が長くて、東大に入れたという事は、帰国子女枠の様なものが当時もあったのであろうか? 雑誌によれば彼が最初の留学生である。1948年10月12日オランダ船 ラングリースコツト号でジュネーブに向かったのだが、この船にはイギリスの入国ビザを持つ2人の日本人が同船していたという。 そして「私はジュネーブに帰ってきた。懐かしのスイスよ」と書いている。当時の人からすると“日本人離れした“背景を持つ人が、まず海外に出たといえよう。渡航費用を含めた留学費用をすべて自分でまかなったのであろうか? その解として筆者が見つけたのは、父守克の名前が「スイスの休眠口座」として2001年にスイスが公表したリストに挙がっていることだ。戦後長らく放置されてきたのであろうが、戦前にスイスに残してきた資産ゆえに、敗戦直後で円の価値が紙切れ同然になったにもかかわらず、守働のスイス留学が可能となったのであろう。 守働の入ったジュネーブ大学には、聖書学者の前田護郎が終戦後も講師として留まっていた。時期は重なっているが、2人とも相手について書いてはいない。付け加えればジュネーブの前田は1948年9月から10月、イギリスのオックスフォードのマンスフィールド・カレッジに招かれて同地に滞在している。招待があると日本人もかなり移動できたようだ。 さらに付け加えると稲垣守臣という牧師が軽井沢追分教会におり、2013年に亡くなっている。彼は1911年11月11日、7人兄弟の末っ子として軽井沢596に生まれている。軽井沢のつながりからして、彼も守克の子供であろう。 なお戦後初めてアメリカを訪問した日本で2番目の女性牧師植村環は、アメリカ滞在中の1946年下半期から1947年3月ごろまでの間に、ジュネーブを訪問している。彼女が戦後初の日本からの訪問者であろう。 (スイスの入国申請書類に名前がないのは、アメリカのミッションの一員として訪問したためか?) その後、バルバラ・シンチンゲルによる戦時下の軽井沢の回想の中に、守働の名前を見つけた。こちら <ヘンリー玉置> 1948年にはもう一人スイスに留学をしている。ヘンリー玉置は父親が日本人で母親がドイツ人である。終戦直後横浜のセントジョゼフで2年間学んだ後、スイスのサンクトガレン大学に留学する。そして1950年、チューリッヒのアメリカ大使館(領事館?)でアメリカ大学入学試験を受けて、合格して一旦日本に帰国後アメリカに向かう。 先の稲垣守働もおそらく同じ試験を受けスイスからアメリカに向かったのであろう。しかしあまりにもスイス滞在が短いのは、何か事情があったためと思われる。 改めて伺ったところ、ヘンリーは6月にセントジョゼフを卒業し、10月にスイスに向かった。父親が良く知るスイス人のジョゼフ神父が推薦状を書いてくれた。スイス大使館には手続きに行かなかった。 今は存在しないパンアメリカン航空の飛行機に乗り込んだが、まだ夜間は飛べない機体だったので、上海、カルカッタ、イスタンブールで宿泊してブリュッセルに着き、そこからスイスエアーでスイスに向かった。 守働は同じ10月の出発だが船である。つまり到着ベースでは戦後初の欧州留学生はヘンリー玉置と言えそうだ。なおヘンリー玉置も戦争中は軽井沢で過ごしている。また二人とも母親がドイツ人で、戦前の欧州に暮らし、とても似た境遇だ。 (2020年4月7日) <片山哲(日本社会党初代書記長)> 片山は1949年5月に、急にMRA(道徳再武装)世界大会へ行ってはどうだという勧めを受けた。その話が進行して、5月31日、妻と上原蕃と3人、着のみ着のままで羽田を飛び出すことになった。費用はMRAが引き受けた。 (MRAのホームページでは「片山哲夫妻、毎日新聞 高橋編集長、藤本外信部長参加」となっている。またその時の写真には4人の男性と2人の女性が写っている。) 大会は6月4日からスイスのコー(Caux)で行われる。アメリカ経由で3日の晩までにはスイスのジュネーブに着くという予定であった。当時としては格段のスピードである。なお片山もジュネーブ大学を訪問している。この時は稲垣守働が留学中であった。 なお同氏の書いた「青い鳥を求めて」には、他にも以下のような興味深い記述がある。 7月7日 西ドイツ ルール重工業の中心部デュッセルドルフ、デュイスブルグ、エッセン地方に向かう。戦後来訪した最初の日本人一行ということで、歓待を受け、ぶっ通しの会合続きであった。 パリでは長くパリで絵の研究をしている萩須高徳君の案内により見学。ロンドンで在留同胞50数氏の招待を受けたのは嬉しかった。殊にグラスゴー行きの汽車弁当に貰ったお寿司は、久しぶりの日本飯で、一同舌鼓を打った。 ニューヨークでは、日本料理「都」の主人公特別の骨折りで、盛大な歓迎会を開いてくれた。 なお翌1950年は、中曽根康弘ら国会議員7名・広島市長・長崎市長、石坂泰三・本田親男ら経済人、労働組合代表など何と72名がMRA国際チームの招待で、スイス・コーを始め独・仏・英を歴訪する。 吉田茂首相は「1870年日本の代表が西欧に行き、日本の歴史を変えた。今回の日本の代表がコーに行くことによって、新しい日本を築くことになろう」と述べた。 そしてその際に日本人で初めて同時通訳ブースで国際会議の通訳を担当したのが、尾崎行雄とテオドラの次女相馬雪香と、同時通訳の先駆者とされる西山千であったという。 <随行員としてのスイス入り> 占領下の日本では、国際会議には連合軍総司令部(GHQ)のメンバーが日本の代表として出席し、日本人が随員として合わせて参加している。 「来る4月21日からジュネーブで開かれる『戦争犠牲者保護の国際規定確立会議』に出席する総司令部アルヴァー・カーペンター法律局長、ジョージ・へーガン氏及び日本人随員浅海 鮎沢両氏の一行は来る4月12日、東京発空路カルカッタ経由でスイスへ向かう。」 (読売新聞 1949年3月30日) ここに登場する鮎沢氏とは鮎沢巌のことであろう。コロンビア大学卒業後、ジュネーブのILO本部に1934年まで勤務している。 「スイスのチューリッヒで開催される国際技術会議に出席するため総司令部ロバート・ヒッカソンと日本人3名、16日夜空路東京を出発。」 (読売新聞 1949年5月18日) <その他の申請> その他にスイスに申請した人物には小笹 Augustin Hideichiがいる。1949年4月1日フリーブール大学で神学の勉強のためと申請した。日本に滞在するフランス人のアグリ神父(Albert Haegli) の推薦であった。アグリ神父は横浜のミッション系スクール、セント・ジョセフの校長である。小笹は同校の卒業生であろうか? また藤田喜太郎は1951年4月11日に申請を行っている。彼は戦時中、書記生として公使館に勤務しており、私的要件のための入国を希望した。 外交官北原秀雄は1951年10月21日にロンドンのスイス大使館(公使館?)で申請を行った。彼もまた戦時中スイスに滞在していた。萩原徹がスイス公使として、前任地パリからベルンに到着したのが1952年6月24日である。 <フランスへ 遠藤周作> 冒頭に触れた作家遠藤周作は、「作家の日記」という題名でフランス時代の日記を公開している。まずそれを掲載している遠藤周作全集の解説文からである。 「1950年6月4日GHQの占領下にあった日本からの最初のフランス留学生として三雲夏生・昴兄弟とともに横浜港を出港。 この留学はザビヌル日本渡来400年の1949年に上智大学の数人の教授が計画し、フランスのカトリック教会とネラン家等の一部の篤志家の支援によって実現。 同じ船倉で寝起きする四等先客に、フランスのカルメル会修道院で修行を目指す井上洋治がいた。敗戦国の日本人ゆえマニラやシンガポールなどの寄港地では上陸を許されなかった。」 フランス船ラ・マルセイエーズ号には何人かの日本人が乗船していた。また当時の渡欧には資金等でカトリック教会の援助が大きかったことが分かる。 乗船者の一人は女子画学生、毛利眞美(後に画家・堂本尚郎夫人)であった。お嬢さん育ち、わがままいっぱいの眞美は戦前の女らしさ教育に大反発しての渡仏であった。彼女も教会の援助であった。 <作家の日記> 次いでその遠藤の「作家の日記から」である。そこから当時どのような邦人がフランスにいたのか、知ることが出来る。 「1950年7月8日 朝、パリに着いた。 再びタクシーをつかまえてド・ラ・サンテ通り45番地の片岡美智を訪ねる。突然の訪問であったが、久しぶりに話す日本語ゆえ何ともいえずたのしい。」 片岡は戦前の1939年、日本女性初のフランス政府招聘留学生としてパリに渡り、連合国によるフランス解放時もパリに留まる。そして1952年まで滞在した。つまり彼女は戦後の渡航者ではない、フランス滞在の猛者ともいえる女性である。ジュネーブの前田護郎同様、学問の世界には戦争の勝者、敗者は関係なく、そのまま留まることが出来たようだ。 「1950年8月2日 古沢夫人、兄貴に手紙をしたたむ。10月14日 滝沢敬一老を訪問する。よくしゃべる元気な老人である。」 古沢はソプラノ歌手古沢淑子で戦争中のパリ滞在を経て、終戦直前よりスイスに滞在していた。彼女に関しては筆者の「スイス国境目指して」参照。1949年フランスのラジオ番組出演のオーディションを受けると言うことで、古沢にフランス入国のビザが発給された。そしてオーディションンに合格して、念願のパリへの里帰りをものにする。 滝沢も残留派であった。彼に関しても筆者は「敗戦ドイツの首都に残る」で紹介している。遠藤は懐かしさからか、それとも儀礼上か、残留日本人とだいぶ接触したようだ。 「9月25日 リヨンに日本人来る。プラットホームに入ると岩瀬孝が青い顔をして、立っていた。」 岩瀬 孝はフランス文学者で1950年アンジェー・カトリック大学に留学し、パリ大学文学部博士課程第1年度を修了する。 「1951年6月12日 在外設置事務所の萩原氏に会う。」 萩原氏とは外務省の萩原徹である。彼は1950年10月、パリ在外事務所長に任ぜられている。大使館が開設される前、こうした形で外交官は海外に出て、再開に備えた。まだ外交官としての地位、特権は所持していない。 「7月18日 野村教授がリヨンにやって来られた。 11月16日 12月上旬パリに行くことにした。 会うべき人 : 片岡美智、森有正、木下氏、萩原氏」 後の哲学者で評論家森有正も留学生である。だいぶ日本人も増えたようだ。 別題の「渡仏日記」は1952年9月から1953年1月までの日記である。そこには 「1952年11月19日 マイヤーと食事をした。日本レストランに連れて行く約束をしたのだ。」とある。 すでに日本食レストランが出来ている。有名であったぼたん屋の再開であろうか?また日本食レストランがあるという事は日本人が増えた証左でもある。 遠藤周作の妻、旧姓岡田順子は、別稿「終戦直後の渡米日本人」で紹介した西村クワと文化学院で同級生であった。遠藤周作も同学院で講師をしたことがある。 <パリ在外事務所> 遠藤が書いたパリ在外事務所には次のような方がいた。まず萩原所長と共に外務省の高橋覚、通産省から佐藤清一と松永信雄が着任する。翌年6月に戦時中在外研究生としてフランスにいた井川克一と田村豊もやって来る。二人の旅券にフランス政府はカジ・ディプロマティック(準外交査証)を発給する。(『フランス今昔』) 同じ時期、ブリュッセルの在外事務所には与謝野透が赴任している。 <川石酒造之介(かわいしみきすけ)> 川石は名前からも推測できるように、造り酒屋の家の五男として生まれ、1935年にパリで日仏柔道倶楽部を創立する。連合国がパリに迫るの状況で、1944年8月 パリを去りベルリン経由、満州から日本に引き揚げる。パリに根を下ろしていた川石であったが、 「私がパリに残ったらどうする、と弟子共に聞いたら、あなたの様に強い人はすぐに殺すと言われたので日本へ帰るのだと言っていた。」とパリに残留した画家坂東敏雄は回想する。 そして1948年にはフランス柔道連盟の技術指導に就任する。従って再渡仏はこの時点であろう。フランスは戦後間もなくから柔道に力を注いだ。また川石の助手として粟津正蔵が、1950年に神戸港を出港し約1月の航海を経てマルセイユに到着する。さらには安部一郎が、1951年10月に横浜港からラ・マルセエーズ号で出航し、トゥールーズで柔道の指導に当たる。(ウィキペディア) 川石は「フランス柔道の父」と呼ばれたが、生家のある姫路市は2020年の東京オリンピックでフランス柔道代表チームの事前合宿地となる。 (2020年4月26日) <給費留学生> 1950年8月、横浜港からラ・マルセイエーズ号に乗船した給費留学生は次の通りだ。 ラ・マルセイエーズ号は遠藤周作の次の航海になる。 秋山光和 東京国立博物館研究員 北本治 東京帝国大学助教授 森有正 同上 八木国夫 名古屋大学助教授 吉阪隆正 早稲田大学助教授 田中希代子 ピアニスト 男性は皆30歳くらいの年齢であったが、唯一の女性である田中希代子は18歳であった。さらに田中は1952年秋、ジュネーヴ国際コンクールで最高位(1位なしの2位)を獲得する。1953年6月25日付けの朝日新聞には 「昨秋(希代子の)母親が渡仏したのも、送ってきた写真がやせていたので心配して出かけたという。」と載っている。経済的にもかなり恵まれていた事を想像させる。 また翌1951年には加藤周一が給費留学生として渡仏する。 (2017年1月6日追加) 芹澤光治良が1951年にパリに向かった時に空港で迎えた一人の桶谷繁雄(東大助手)は 1949年にフランス政府の招きで2度目の留学をした。おそらく敗戦後最初の留学生であったろうと芹澤は書いている。これまで見て来たように1950年頃には多くの留学生が、様々なルートからパリに来ていて、誰が一番であったかは判断がつきにくい。(2020年6月10日追加) <スランス大使館再開> 日本ペンクラブが戦後、国際ペン大会に代表を送ることが出来たのは1950年8月、イギリス大会であった。翌1951年にはスイス、ローザンヌで開かれたが、そこには芹沢光治良が石川達三派遣され、池島信平がオブザーバーとして参加した。 芹沢はパリを訪問した時のことを書いている。 「1951年7月14日 この日、日本人に忘れられないことは、アベニュー・オッシュにあった日本の大使官邸が日本に返って、萩原事務所長があばら家になっていた官邸の一部に手を入れて、ここにパリにいる日本人を集めてカクテル・パーティーを催したことである。日本が戦後初めてパリに腰をおろしたような喜びであった。集まった日本人は5,60人もあった。 画家の佐野繁次郎さん、文学者の森(有正)さん、彫刻家の高田(博厚)さん、声楽家の古澤女史、などにも会った。こんなに日本人がいるのかと驚きもした。」(『芹沢光治良文学館 エッセイ 文学と人生 1』より) (2017年6月6日追加) <チェルビ菊枝> 幼少のころからパリにあこがれたチェルビ(加藤)菊枝は、戦時中もパリに留まり、終戦後初のフランスからの個人の引き揚げ者であると同時に、最初の渡仏者であった。 1947年年3月28日、菊江はマルセイユでフランス郵船シャンポリオン号に乗り、ベトナムのサイゴン(今のホーチミン市)に着く。そこから香港に向かいさらにジェネラル・ゴルドン号で横浜に着く。 それから一年もしないうちに、 「いずれ日本人もどんどん、渡仏するようになるだろう。私が本当にしたいのは、そういうフランスで、日本人の為に役立つ仕事をする事だ。」と考え、横浜のフランス領事館を訪問する。領事は 「戦後、入国ヴィザの申請にこられたのは、あなたが初めてですよ。そいうえば、戦後、フランスから単独で、初めて帰ってこられたのもあなたでしたね。」と語り、 「ヴィザは、まだ普通の形式では難しい。だから渡航目的の欄にパリにいる婚約者と結婚するためと書き入れる」方法をアドバイスした。すると1ヶ月半でヴィザは下りた。その後GHQ外事課で日本の出国許可もらう。ここでも「前例のないことだ」と言われた。 1948年8月30日、羽田空港からノースウエストに乗る。日本とGHQ両方の出国検査を受けたが、フランス人に同行するパスポートも持たない日本人旅行者である菊枝に、係官はちょっと驚いた表情をしていた。 9月2日、フランス郵船のアンドレ・ルボン号が上海を出る予定であったが、船はやってこないことになった。そこで香港まで飛んで、そこからアンドレ・ルボン号に乗る。1948年10月15日にマルセイユに着く。行きも帰りも自分で道を切り開く渡航であった。 (2017年5月12日追加 『おてんばキクちゃん巴里に生きる』より) <フランスへの”帰国”> 戦前、多くの日本人を惹きつけたフランスへは、終戦直後から渡航者が多かった。多くはかつての滞在者である。日本人画家として戦後初めてフランス入国を許可されたのは荻須高徳であった。1940年に日本に引き揚げた荻須は1948年、再び渡仏する。著名な藤田嗣二は、戦争協力に対する批判に嫌気がさし1949年、住み慣れたパリに向かう。アメリカ経由であった。 画家では他に筆者が直接会って話を聞いて紹介した関口俊吾が1951年、40歳で再びフランスに向かう。同年1月27日発行のパスポートには 「関口俊吾は美術研究のためフランスに行く目的で、(中略)連合国最高司令官によって許可された日本国民である」と記されている。関口は戦後の渡仏者の内、画家としては萩須高徳、藤田嗣治についで3人目であったと言う。本人の証言もあるので、この時期、他に渡仏した画家はいなかったと判断できる。 またフランス文学者の朝吹登水子は1950年5月、本人の弁によれば”自活するために職を身につけよう”と、神戸からフランス船ル・ファレーズ号で戦前に続いて再度パリに向かう。物理学者湯浅年子(1949年2月)に次ぐフランスへの私費留学生であった。朝吹は”軽井沢派”の代表的存在である。一方湯浅もフランスへは再渡航である。 1951年春、戦後初めての日本人として、東和映画の川喜田長政がカンヌ映画祭に出席した際には、朝吹は萩原在外局長のお伴として参加する。 妻子をスイスに残してきたジャーナリスト笹本駿二は1948年日本に戻るが1950年2月、デンマーク船に乗り込む。 戻った笹本はいきなり占領下の窮屈な日本が耐えられなくなった。またジャーナリストとして頭の中のヨーロッパの知識は、数ヶ月もすると使い物にならないと感じた。そしてフランスに住む妻の親戚筋の世話で、同国に向かう。 (2016年10月11日追加) 高野耀子(こうのようこ)は画家高野三三男(みさお)の長女として1931年パリに生まれる。1940年パリが陥落する際に家族で帰国する。 1946年、東京音楽学校に入学するが、パリへの思いがやみがたく途中で退学する。個人で煩雑な手続きを一切を達成、莫大な費用も調達して1949年、8月1日空路渡仏する。そしてパリ音楽院に入学を果たす。 (なお高野について、「田中希世子」の中で萩谷由紀子は戦後初の渡仏者として時期を1947年と書く。またウィキペディアは1948年である。しかし朝日新聞の記事(1949年7月26日)から1949年が正しいと思われる。 (2017年1月6日追加) 2018年3月26日の日本経済新聞の電子版に 『高野耀子という生き方 輝き続ける87歳のピアニスト - NIKKEI STYLE』という記事が載りました。 リンクはこちら。 <高田市太郎の「風雲の欧米を見る」> 第二次大戦後、最初に海外渡航を許された日本の現役報道人として、1948年10月より欧米を6ヶ月間訪ねた毎日新聞の高田は、先述の題名の著書に、ロンドン、パリの残留邦人について書いている。それによるとイギリスは次のようだ。 「イギリスに住んでいる日本人は、現在全部で100人程度、そのうち80名位がロンドンにいます。大部分昔から住んでいた商船や貨物船の船員で、今はほとんどが50歳から6,70歳にかけての老人です。 他の数名は、戦前日本大使館とか、大倉商社に勤めていた人であります。また戦争中(ドイツの)爆撃の犠牲になって死んだ日本人は、わずか1名であったそう。 ロンドン大学には日本語科がある。永らく日本にいたF・T・ダニエルさんがその主任を担当、5人の日本人がその下で助手を務めている。」 高田の書く「昔から住んでいた船員」というのは、多くは第一次世界大戦中に渡英した船員で、そのまま帰国せずに現地の船会社に雇われ働いた。そして第二次世界大戦が始まると、マン島の抑留された。 続いてパリである。 「フランスに残っている日本人は、現在パリに約30人、マルセイユ、リヨン、ニース、その他の地に25人、合計50人あまりである。インフレと就職難にさいなまれて、いずれも相当な耐乏生活で頑張っているようである。」 ここに遠藤の書いた片岡、瀧沢などが含まれるが、「愛すべきパリは死んでも離れない」と、戦争中を通じて留まった邦人も少なからずいた。高田は筆者の知りたかったことを、ずばり書いてくれている。 <制限付き海外旅行> 1948年4月2日付け朝日新聞によると、この時から日本人の制限付海外旅行が認められるようになる。 「三牧牧師が渡英。制限付海外旅行の第一陣 八代斌助、柳原貞次郎、蒔田誠の三牧師。カンタベリー大僧正に招かれて行く。日本人の制限付海外旅行計画の第一歩をなすもの。政治的なものでない限り、文化的あるいは科学的またはこれに関連したものは今後全て許可されるであろう。」 彼らは5月12日夜羽田空港出発、ニューヨーク経由でイギリスに向かう。 これは日本を占領統治するGHQ総司令部の発表に基づく記事である。こうしてこの頃から渡欧者が新聞記事に登場するようになる。 <高峰秀子> 6歳で子役としてデビューした高峰秀子は1951年6月、パリへ旅立つ。27歳であった。女優が個人で海外に出る時代になったともいえるが、そのために高峰は自宅を売却した。日本人にとって海外旅行は、とてつもない費用がかかる代物であった。 彼女は先に芹沢の書いた大使館の再開レセプションに参加し、それについても書いている。 「パリ祭 夜、雨もあがって、日本の在外事務所が昔の大使館に移ったレセプションがあるとのこと。大使館へ向かう。お客様は100人ばかり、思いの外たくさんの日本人に会って、何となくマゴマゴしてしまいました。(中略)その後、石川達三さん、藤山愛一郎さん、佐野繁次郎さんたちと郊外で食事。」 藤山愛一郎はユネスコの総会に出席するためであった。先述のペンクラブ大会同様、日本人も再び国際会議に招待されるようになった。 彼女は半年余りのこの旅行について『巴里ひとりある記』というエッセイ風の本を書いているが、そこには多くの日本人が登場する。もうパリ在住日本人は固有名詞で語るほど、珍しい存在ではなくなったといえそうだ。また戦後、日本人が欧州で最初に向かった国はフランスであった。これまでに紹介していない名前を以下に挙げてみる。 中原淳一 (画家) 高英雄 (シャンソン歌手) 高橋豊子 (女優) 黛敏郎 (音楽家) 宇野千代 (小説家 ブリュッセル滞在) 砂原美智子 (ソプラノ歌手) 木下惠介 (映画監督) 毛利マミ (若い画伯) マドモアゼル山崎 (フランス人のお母さんと日本人のお父さんを持ったお嬢さん) 小平さんの奥さん (?) (2017年6月11日追加) <ドイツ 1> ドイツに残留した邦人については筆者はすでに発表している。(「敗戦ドイツの首都に残る」参照) その敗戦国ドイツへの最初の渡航は 、「(1949年)7月7日 西ドイツ ルール重工業の中心部デュッセルドルフ、デュイスブルグ、エッセン地方に向かう。戦後来訪した最初の日本人一行ということで、歓待を受けた。」とスイスの片山哲の欄で書いた。 しかし前年11月7日の読売新聞には次のように報じられる。 「スイスのコー市で開かれたM.R.A訓練大会に14カ国の代表とともに参加した 一行9名の内三井高雄氏、同英子夫人、同令嬢直子さん、相馬恵胤氏、同雪香氏 尾崎行雄氏三女、(リーダースダイジェスト編集員)ら7名ドイツ政府の招待を受け平和の”善き道”を携えた一行230名と共に日本人として初めてドイツに入った。 6台の大型バスでスイスの国境の村テンゲンドルフかドイツに入りウルムやミュンヘンの生々しい破壊の跡を見て回った。」 先の片山哲らの一行は初のルール地方の訪問と理解すべきであろう。 1949年3月中国の天津からサーカス団員澤田豊が、ドイツ人夫人らとともに戻ったのが最初の個人最初であろうか?(筆者の「オデッセイア」参照) 日本と同様敗戦国ゆえ、日本からドイツへの渡航はアメリカやフランスに比べれば遅かった。留学生は1953年6月、9名の留学生の名前が発表されたのが最初のようである。 <ドイツ 2> 「ドイツにおける三井物産の歩み」という本には「戦後初のドイツへの旅行者」という記述がある。 1950年ドイツのユーザーの要求で遠州織機の大倉技師が技術指導のために、渡欧することになり、たまたま三上良臣に同行を求めてきた。第一物産(敗戦による解散後の三井物産の主体)はこれを快諾した。三上は三井物産の戦前のドイツ駐在者であった。 「三上氏は取得したパスポートも米軍司令部の発行のものであったが、戦後ドイツへの日本人旅行者としては三上氏たちが第一号であったという。」と同書に書かれている。 1952年4月27日、寺岡洪平(元ハンガリー公使)当時の首都ボンの在外事務所長として朝日新聞に紹介されている。寺岡は1950年4月から、初代ニューヨーク在外事務所長を務めている。 またベルリンにはドイツ人俳優デ・コーヴァと結婚していた田中路子が、終戦後もそのまま残り、まだ大使館の無い時代に日本から来た訪問者の面倒を見たという。 1952年1月から2月、イギリス政府の招きで渡欧した奥むめお(女権運動家、主婦連会長)は、戦後のベルリンに最も早く現れた日本人の一人であった。奥はその思い出を次のように書いている。 「ベルリン飛行場の関門で質問を受けて、ドイツ語のわからぬ私がまごまごしていると、出迎え人のたまりから田中路子さんがとび出してきた。さっとざわめきが起こって衆目が集まったので、路子さんが有名人であることを、感知することが出来た。」 (ミチコ・タナカ 「男たちへの讃歌」より) 戦争中、ベルリンの日本大使館に嘱託として勤務した野原駒吉は、ドイツの崩壊で日本に送還されるが、モスクワに残留し、1946年4月、そこからベルリンに戻った。彼が戦後最初のドイツに入った日本人のようだ。(野原についてはこちら参照) <浅井一彦−渡航の試み> 当時はどのように渡航許可を得たのであろうか? 終戦まで満州重工業のベルリン駐在員であった浅井一彦は、ドイツ人妻と子供を残し、ソ連軍の手で半ば強制的に日本に戻された。 終戦後1年たっても状況がわからなかった妻子について、あちこち手を尽くした結果、国際赤十字を通じて、当時の東ドイツでの生存を確認し、ドイツに赴いて救出することを決意した。 周りから不可能といわれた米占領軍からの出国許可をとるべく、1947年9月18日、連合国最高司令官マッカーサー元帥に直訴状を書いた。そしてマッカーサー元帥の元を訪れる。本人には会えなかったものの強硬にねばり、直訴状を副官に言付けたところ、3日後に出国査証発行の許可が下りた。 当時の渡航許可はマッカーサー司令官によってのみだされたのであろう。 付け加えると浅井はなんとか旅券を作成してもらったが、ドイツに向かう交通手段がままならず、3ヶ月アメリカの貨物船を待つ間に、スイス国際赤十字社から妻子は無事にスイスへ救出され貨物船で日本へ向かったとの電報が届く。 (「マッカーサーへの手紙」より) 同書では 「昭和60年(1985年)9月10日、早くも秋の気配が忍び寄る高原の軽井沢。草花が生い茂る広い庭に建てられたスイス風木造の別荘のベランダで、浅井エリカに会った。」とも書かれている。 浅井家も軽井沢に縁があった。 なお他にユニークな渡欧者をご存知の方がいたら、次のコンタクトからお教えいただけると幸いである。コンタクト (2016年8月13日) <スエーデン> 冒頭に1946年4月に西村ヨネがストックホルムに入ったと紹介したが1947年7月、スエーデン赤十字ベルナドッテ社長から、1948年8月20日から30日まで10日間開催される第17回赤十字国際会議への招請状が日本赤十字社に届く。 しかしGHQは日本独自の出席を認めず、オブザーバーとしてミルトン・エバンス氏を派遣、その技術顧問として社長島津忠承、外事部長工藤忠夫、嘱託渥美鉄三が同行することに同意した。 会議ではオブザーバーのオブザーバーともいえる日本には発言権も、議決権もなく、会場には日の丸も掲げられなかった。しかしながらこれが戦後最初の国際会議への参加であろうか? ベルナドッテ社長は1945年4月親衛隊隊長ハインリヒ・ヒムラーと会見し、ドイツの休戦・降伏交渉に関与するが、不成功に終わっている。 付け加えると4年後の1952年、第18回大会はカナダのトロントで開催された。サンフランシスコ条約調印後初の国際会議への参加と「日本赤十字社社史稿 昭和21年〜昭和30年」に記されている。 外事部から工藤部長と太田成美部員、政府からはカナダ在勤の成田勝四郎公使が出席した。 (2016年11月18日) <イタリア> 日本画家でカトリック美術家の長谷川路可(はせがわろか)は1950年、聖年(ローマ巡礼者に特別の赦しを与える年)に際してバチカンを訪れた。同年の8月、既に金山政英駐バチカン代理公使の紹介で、松風誠人を介して、ローマ近郊チヴィタヴェッキア市の日本聖殉教者教会の壁画制作を依頼されており、翌年の年頭から下絵の制作に取りかかった。 1954年10月、コンスタンティーニ枢機卿を迎えて、壁画完成の祝別式が挙行され、路可はチヴィタヴェッキア市名誉市民に列せられた。 戦後間もなくの渡欧、渡米者にカトリック関係者の多いのは、彼らは戦争中は軍国主義と無縁であったことでGHQが許可を出した、そして受け入れ国のカトリック組織が経済的サポート等をしたからであろう。 金山政英は左記に登場するカトリック信徒の外交官として、1941年3月から1952年6月までの11年間を家族と共にバチカンで過ごした。ドイツ崩壊後も、バチカンは日本の外交官の退去を求めなかったようだ。欧州にそのまま留まった数少ない日本人の一人である。 (2016年12月1日) 1950年4月25日の朝日新聞に 「ローマ法王に謁見 聖年祭の報道のためローマに滞在中の記者(黒住特派員)は22日午前10時半、ヴァティカン宮でピオ12世に謁見した。」という記事が出る。彼は先述の金山政英に伴われての謁見であった。 (聖年はキリスト生誕以来25年目ごとに巡ってくる”良き年”のこと) (2019年8月25日) 湘南の片瀬教会のホームページには「片瀬教会と長谷川路可」という項目がある。 1939年3月19日、同教会献堂式の時の集合写真と、20名ほどの招待客と思われる記念写真に長谷川路可が写っている。 (2025年3月14日追加) <岩元梶子> 六本木の伝説的イタリアレストラン『キャンティ』の創始者川添(旧姓岩元)梶子は『キャンティ物語』によれば 1947年にイタリアに彫刻の勉強のために留学する。父が亡くなり遺産が入ったことも理由のひとつであった。 「マニラに長姉が嫁いでいたのでひとまずフィリピンに飛び、そこからパリ行きの飛行機に乗った。」と珍しい経路であった。 ただし渡航の時期については、もう少し遅いのではないかと筆者は考える。梶子は先ずパリに入るが、そこではまずシャンソン歌手石井好子を訪問すると書かれているが、石井がパリに渡ったのは1952年である。 また『南十字星 : シンガポール日本人社会の歩み』という本には 「篠崎氏が1951年”信洋丸”に乗って当地へ来られた時、当局によって上陸を拒否された。戦前戦中、同地に住んでいた人は入国禁止であった。 次にこられたのは、戦前の三井銀行上海支店長の末娘の岩元梶子さんであった。彼女は当時は 22 才ぐらいで、日本では有名な彫刻家だった。彼女は東京から飛行機でこられ、シンガポールから船でローマへ行かれる予定だった。」とこちらも梶子の渡欧が1952年頃であったことをうかがわせる。 (2018年3月21日追加) 筆者の書籍の案内はこちら 『第二次世界大戦下の欧州邦人(ドイツ・スイス)』はこちら 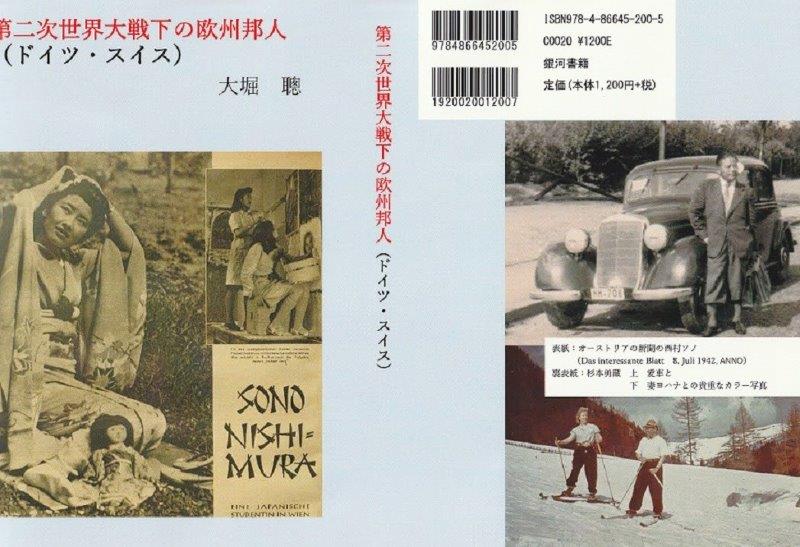 |